前に重なり合う面白さをよく考えていた。オーバーラップすることで、それまでは交わることが無かったモノ同士が重なり合えば、それだけで様々な可能性が広がる。きっかけをつくることがデザインになれば面白いと思っていた。
重なりはモノ同士が物理的につくるものだが、最近はモノは独立していて、物理的な重なり合いは無いが、モノの内部にある一部分がつながり合うことがあり、そのとき、様々な可能性が生まれれば面白いと考えるようになった。

建築でも何でもモノがそこにあれば、それは自立してそこにある。しかし、何かしらそのまわりとモノとの関係も生まれてしまう。そのときに自立することとモノ同士の関係性を対比させて考えることには少し違和感がある。
なぜならば、そのときは関係性がモノの自立があってはじめて現れてくると考えられるからで、そこに違和感があり、はじめから関係性のあるところに自立したモノが置かれるということもあり得ると考えられるから。
ただ、もしそうならば、自立は関係性という地の上に成り立つものであり、自立だけを抜き出して考えることができなくなる。さらには、関係性がモノに先立つことで、自立自体がおかしくなる。
ならば、まわりとの何かしらの関係は、モノ自体の内部から起こると考えれば、全てがうまくいくような気もする。
いちいち考えたりしないから気楽に楽しみたいのが本音で、空間もそこでの瞬間的な気持ちよさ、居心地のよさが大切、でもそれはつくる方も瞬間を意識するのか。
瞬間の連続が時をつくると考えると、こう見せたいやこうしたいと作者側が考え、その情景やシーンを分解するときに一緒に時も分解して瞬間にしている。そのときには、瞬間は細切れの連続で作者側の意図をくむ。だから、ひとつの瞬間と瞬間の間にはつながりがあるとしているし、それが大前提になっている。
そのつながりを疑ってみることにした。昔、たくさん写真を撮りまくっていたころのファインダー越しの情景を思い出した。フレームが瞬間のつながりを強制的に断ってくれる。そして、並べられた写真は独立した瞬間を見せていた。
流れと捉えることはよくある。流れを読むとか、時の流れとか、空気の流れとか。流体力学なんて響きもなんとなくカッコいい。流れはすなわち、つながりともいえる。つながりがあるから流れになる。バラバラであったものがつながり動きだす、そのときの航跡が流れとしてみえる。だから、流れの前提はつながりがあることである。では、つながりが無ければ、それはただのバラバラな点の集まりである。たくさんの点が同時に存在しているだけのことである。
ちょっとおもう、この現実世界は流れでもあり、バラバラな点の集まりでもあると。つながりを見だせば流れだが、つながりを解く、別のつながりを設定する、新たなつながりをつくれば、今までの流れがバラバラな点の集合でしかなくなる。
要するに、流れとはつながりを保つ行為であり、別にバラバラでもよければ簡単に消滅するし、バラバラな点の状態の方がいろいろな流れを形成する可能性を秘めており、その方が多様で面白そうだ。そんなバラバラな点の状態のようなモノをつくりたい。
時の流れというけれども、たしかに時間はつながっており、時間に切断面は存在しないようにおもえる。
しかし、今この瞬間からみたら過去も未来も流れではなく、ひとつの止まった切断面にしかみえず、しかも、それは現在も同じで、それら3つの切断面が合わさって今この瞬間がつくられているようにおもえる。
そうすると、時は流れではなく、今この瞬間のひとつの要素として過去、現在、未来があり、それらが今この瞬間を多様にしてくれているだけで、次の瞬間にはまた別の過去、現在、未来が存在して多様にしてくれる。時間は流れではなく、今この瞬間を多様にしてくれる単なるアイテムでしかないのかもしれない。
ならば、過去のモノを今この瞬間にいかすことも、ことさら過去という時制には意味がなく、そのモノがどういうモノかということの方が重要なのかもしれない。
今現在から過去や未来を考えることは、実際の過去や未来とはちがう。今という時間にポーンと投げ入れられたとしたならば、そこにはすでに過去や未来はあり、ただその過去や未来は自分が都合よくつくったものであり、だからこそ、歴史は勝者によって捻じ曲がり、未来も方向づけられてしまう。
しかし、そうなると、実際の過去や未来にはいつまでたっても出会えないし、もしかしたら、実際の過去や未来など無くて、あるのは現在がより複雑で多様なだけなのかもしれない。
そう考えると、過去のものを未来に残そうとか、現在が過去から未来への流れの一地点とは思えなくなる。あるのは今この時の現在だけで、過去も未来も今この時のためのパーツでしかない。だから、今が大事ということか。
そこに建築があることは、そこにいる人に依存しているように思えるが、そこにいる人が抱いているその建築へのイメージより越えたモノ、それがその建築の真の姿、にするには、その建築がそこにいる人に依存しないで独立している必要がある。さらに言えば、建築が自律しているとはまさにこういうことである。
ただ、そこにある建築がどういう存在であるかは、そこにいる人自身の中にしかない。それはどういうことかというと、そこにある建築が自分の中に存在している人にしかその建築を見ている意識がないからである。
だから、そこにある建築はそこいる人の中にしか存在していないが、その建築自体はそこにいる人に依存しない方がいいとおもう。
建築をしていると全体を構築するので、構築された全体からどのような影響をあたえることができるのかを考えはじめてしまうが、そうした実在的な全体から影響をうけることがほんとうにあるだろうかなどとも考えてしまう。
つくる方は構築していく上で全体から細部へと考えが流れていき、それを実在的なこととして考えるのは仕方がないが、受けとる方は全体的な視点をもてるとは限らず、実在的な細部ばかりに目がいくことも多い。そして、その細部の実在的なモノに触発されて、全体を感覚的に捉えようとするのではないだろうか。
目の前の手の届くモノは、その場で見ることもできるので、ほんとうに存在しているとなるが、全体は目の前のモノの性質から類推し感じているに過ぎないのではないか。ならば、つくる方が向き合うのは全体ではなく細部の性質であり、全体は細部の彼方に見える蜃気楼でしかない。
自分が見ている物がその物のすべてでは無く、自分の都合とは関係無いところで、他の物との関係の中でその物が成り立っている部分があり、そこは自分では見ることができない、とハイデガーはいう。
物をつくるとき、たしかに、すべてを見せたいと考えることは無い。むしろ核心は隠したいと考える。そうしないと、建築が使えないような気がするからで、どこか核心の部分、すなわち、その建築の存在理由のようなものが見てわかるようだといやらしい、そう使えと命令しているようで。
建築が使うためにある物で、それが唯一、建築だと見える理由だと考えているならば、使い方をこちらの思い通りにコントロールしたいところだろう。ただ逆に、想定した使い方以外を見てみたいと完成後は考えてしまう。すなわち、それがハイデガーの見ることができない部分であり、見ることができない物を見たい欲求ほど強いものは無い。
たとえば窓があると、陽をいれる、風をとおす、外をみる、などの窓でできることにそって行動する。窓は行動のきっかけをくれる存在である。だから、窓と何かを紐付けることで行動をコントロールできるかもしれない。建築は人の行動をコントロールするものとしたら、窓は大事なファクターである。
窓は空間を制限する。窓の大きさは空間に特性をあたえる。窓には2種類ある。人が通る窓と人が通らない窓。人が通る窓の方がコントロールできることがたくさん増えるような気がする。ひとつの住宅に人が通ることができる窓は案外少ない。だから、より人が通る窓は大切である。ただ単に出入りするだけではもったいない。そこはデザインしがいのある領域である。
部材はもつ、といつもおもう。建築はスクラップアンドビルドが基本、最近はそうでもないが、真っさらにしてハイ次どうするか。
それについての良し悪しには興味はないが、物の行方には興味がある。生産され、加工され、形を与えられ、そして朽ちていく。スクラップアンドビルトは形を与えられて終わってしまう。形あるものいつかは朽ちるのに、朽ちることをさせない。みな、省エネもはじめの生産ばかりに注力してる。身近で誰でもできることは朽ちさせることではないかといつもおもう。
建築がスクラップになるとき、すべてが必要なくなるわけではないの真っさらにしてしまう。部材はつかえる。部材に新たなに形を与えればいい。そうしたら、また朽ちさせることができる。
地と図にわけて考えてみると、図は感覚的な対象としてとらえることができるが、地は埋没していてすぐにはとれえ所がないかもしれない。別のいい方をすれば、図は直接あつかうことができるが、地は直接にはあつかえない。だから、一所懸命、図についてあれこれと考えるのだが、図は地があって浮かび上がるものと考えれば、地についても同じかそれ以上の注力が必要だろう。
地の中で一般的なもののひとつに環境がある。建築の場合、環境はどうにも動かせないもの、どうにも触れられないものとして与えられることが多い。ただ、すべては無理だとしても、ある特定の状況を設定するなどすれば、限定的だが環境について触ることもできるかもしれない。その状況の設定は建築をつくる側でできる。ある特定の状況設定には良し悪しがありそうだが、そこで社会に対しても貢献できる可能性を秘めている。
シンボルツリーという言葉があり、象徴的なものとして外構の目立つところに木を配置し、それを中心的にまつりあげて展開するやり方がある。意外とどこでも見かける。ここでいつも面白いと思うのは、シンボルツリーの存在というより、そのシンボルツリーがどこからどのように見えるか、ということ。シンボルであるのは見られるからであり、ならば、どこからどのように見えるかに関心をもつとシンボルツリーがまた違って見える。
どこから見えるか、どのように見えるかがシンボルツリーそのものの存在に何か影響を与えるだろうか。先にどこから見えるか、どのように見えるかを決めてしまってからシンボルツリーを配置しようとしたら、先にシンボルツリーがある場合と比べて何かが変わるだろうか。関心は広がる。
新しい道具は新しい着想を生むだろうか。日常的に使う道具を新しくしてみた。正確にいうと、前に使ってはいたが、訳あって使うのをやめたもののバージョンアップ版に変えてみた。だから、完全に新しいわけではないが、今まで使っていたものとは操作感が全くちがう。
昔慣れ親しんだものを、バージョンアップ版とはいえ、また手にすると感覚がよみがえる。だから、変な違和感がなく、すんなりと移行できた。ただ、これは良いことなのだろうか。もしかしたら、新しいものに対する違和感のような変な感覚が新しいものを生みだす原動力になるのではないだろうか。
だから、今度は以前とは使い方を変えようと考えている。使い方を変えることで、全く新しい道具を使いだす時と同じような違和感をつくりだし、新しい着想の手助けになればとおもう。
昔ながらの旧家にはいると、薄暗いけれど、この暑い時期などは冷んやりしていて気持ちよかったりする。薄暗さは時に不安をあおるが、状況が変われば快適にもなる。
旧家の床下はだいたい土間である。夏の冷んやりさは土間だからという理由もあるし、軒が深いことにより日射を遮り陰をつくることも影響が大きい。土間はそもそも土であり、土はある程度の厚みがあると熱容量が大きいので、外気に直接触れることがなければ外気温の影響をあまり受けないので、冬は暖かく夏は涼しい、とされている。
さらに、熱容量が大きれば蓄熱体として利用できる。昼間に蓄熱体に日射を直接あてて熱をためれば、夜には蓄熱体から熱が放出される。現代の住宅に土の土間をつくることは現実的ではないような気がするので、土のかわりにコンクリートをつかうことが多い。ただ、コンクリートを蓄熱体として利用している例はまだまだ少ないので、その点でいろいろと可能性があるような気がする。
ルールははじめから決められていると窮屈なときもある。たぶんそれは現状とあっていないから違和感を感じているのだろう。ただ、ルール自体はほしい。ないと困る。厄介である。もしかしたら、ルールの内容が問題なのではなく、ルールを決めるタイミングが悪いのかもしれない。
はじめに決めるとモレもでるだろう。モレが違和感の原因かもしれない。想定外のことも起きるだろう。普段ならば想定外のことがあっても、それはそれでおもしろいがルール上は困る。ならば、あとからルール自体を修正や編集ができるようにすればいいのだが、修正や編集ができないこともあるかもしれない。
あとからルールを決めてみる。最初にはルールがない。思いつきの連続である。はじめから、辻褄があわない、おかしい、きちんとしないかもしれない。ただ、ルールがないから、辻褄があわないのか、おかしいのか、きちんとしていないのかがわからない。あとで、最後にすべてを包括するようにルールを決めてやれば、辻褄があっていて、おかしくなく、きちんとしていたことになる。それに、はじめの思いつきの連続がたのしそう。
外にいるのか内にいるのかを迷うのは意識の中でズレがあるからで、建築の見え方が意識とズレている証拠である。本来は意識のズレを修正するべきなのだろうが、そのズレをマイナスととらえずに、そのズレをプラスに利用してみようとおもう。
外か内かの意識のズレはふつうにおこることである。たとえば、大きな建築のなかで連続して空間移動しているときなど、知らないうちに外へ出ていたり、内なのにあまりにも天井が高くて外だと感じたりして、意識にズレが生じる。
そのズレは意識の混乱を招くかもしれないが、同時に意識に引っかかりをつくることにもなる。建築を構想する側はこの引っかかりこそ一番求めていることである。それは言葉が先に思い浮かぶ建築ではムリなことかもしれない。
外から帰ってきてとホッとするのは自分の家だから。この当たりまえのことの中に「内」のおもしろさがあるとおもう。建築の外か内かのちがいに人の意識が対応している。たぶん、人の意識の中では、外と内の建築にちがいを感じている。ただし、その建築のちがいは、建築自体のちがいでは無いとおもう。たとえ、建築自体が外も内も全く同じ仕上げで同じように見えたとしても、人の意識は外と内を区別し、建築にちがいを感じるだろう。
この場合、外よりも「内」に可能性を感じる。内に対する人の意識が2つ同時に存在し、そこに暮らしが重なる。現代建築が苦手とする生活感が人の2つの意識を通して建築と絡む。2つの意識は建築でありきで存在するからデザインで影響を与えることもできるだろう。生活感とのちょうどいい距離がとれそうな気がする。
窓は建築の中につくるフレームで、建築は環境の中につくるフレームだと考えると、窓も環境の中につくるフレームだとすることもできる。窓が無い建築は基本的に人がいる場所とは考えられないので、建築には窓が必要である。
環境によって窓の位置や仕様、性格が決まるといってもいい。では逆に、窓から建築、さらには環境が決まることはあるだろうか。何となく、窓が先にあり、それに合わせて建築をつくることは想像できそうである。窓のフレームが建築のフレームをつくる。
では環境はどうだろうか。窓のフレームが環境に何か影響を及ぼすだろうか。それは窓のフレームが何を意味するのかにも関係するかもしれない。もし窓のフレームがアクティビティを意味するのだとしたら、そのアクティビティが及ぼす影響から環境をつくることもできそうな気がする。
時間は重なり合うことができるのか、とかんがえてしまう。過去と現在とは時間でつながっているけれど、建築では分断されることが多い。リノベーションなどにより、全てが解体されない場合も増えたけれども、またまだスクラップアンドビルドが多い。
過去の時間を記憶に変換し、新しい建築にいかすことはよくみられる。端的にいえば、記憶をモノにうつし、そのモノをデザインのパーツにしてしまう。それは視覚的にわかりやすく、時間を途切れさすことなくつなげようとする意図もよくわかり、過去と現在が重なり合い同居できる。
ただ、時間という目に見えないモノを見えるようにすることで、様々な解釈ができる多様性をもひとつだけに具体化してしまっているようにもおもえる。もう少し解釈の余地を残した時間の重なり合いを目指したい。
重なり合うことは見た目だけでない。見た目で重なり合えば、オーバーラップしていることは一目瞭然である。他の部分とのちがいも明確である。視覚情報は優位だが、他の感覚によって重なり合いがわかることもある。
重なり合いは、常に自分たちの生活に影響を与えてくる。スマホひとつとっても、そこにたくさんの情報の重なり合いがあり、それは見ればわかる。スマホというデバイスを通した重なり合いだが、デバイスが無くても情報の重なり合いはわかるだろうか。
きっとそれは炙りだされるように、他の部分での他の感覚がデバイスが示す重なり合いの無さを表現してしまう。あるモノの存在の有無は、他のモノが認識されることにより実感されることもある。
空間という言葉は20世紀の産物であり、それまで空間という概念自体が無かった。今ではかんがえられないが、言葉が無い以上、空間を認識していなかったのだろう。
空間は床壁天井でかこわれた領域を指すとしたならば、ハイデガー的には、人がいてはじめて空間は認識される、となるのだろう。どうしても人間主義に傾いてしまうが、人をかんがえずに空間や建築をイメージできない。
人は何世紀にも渡って生活様式や日常の習慣を変えながら生きてきた。建築もいろいろな様式をとりながら変わってきたが、空間が床壁天井でかこわれた領域であることは変わりがない。
人と空間の関係性はそのような表面的な時代性や建築様式には影響されないもっと違ったところで影響し合っているのだろう。それがどういうことなのかをかんがえるのがまた楽しい。
緑は人をつなぐ役目をするとかんがえてみた。緑は本来、相対するもの、眺めるもので、鑑賞物である。だがもし、人と何かをつなぐ物、媒介する物だとしたら、今までの緑の配され方とはちがってくるだろう。
緑を鑑賞することが目的ではなくなるのだから、建築でいえば、緑は構成要素のひとつになる。今まで外回りの要素のひとつとして眺めてきた。しかし、建築と何かをつなぐためにある存在、すなわち、建築がそこにある必要性を緑が担保してくれる。この流れから室内に植栽を配するという発想も生まれたのだろう。ただ、ちょっと虫嫌いにはつらい。
緑がつなぐ物はどこかで、人であって欲しい、とおもってしまう。だから、人と緑が並列に存在し、そのスペースを緑が構成する、そのような建築を構想してみたい。
ひとつの自律したものをつくりたいという欲求は、ものをつくる人ならば誰でも根源的に持っているだろう。それは建築やデザイナーといった作品をつくる人たちだけでなく、民芸品のような日常に必要な道具をつくる人たちも同じだろう。
ただ同時に、単なる自律したものではもの足りない、ともおもってしまう。単に自律したものは、まわりとの断絶をおこし、孤立する。孤立からくる、その場だけ良い、ようなことはしたくない。だが、孤立を起こさないようにつながりを求めると、自律の良さのひとつである強度が失われていくような気がする。
だから、複数の自律したものを考えてみることにした。複数あれば孤立を避けることができ、かつ自律の強度も担保されるかもしれない。さらに、複数あれば、ひとつの自律が持っている象徴性が分散され和らぎ、複数での象徴性は新たな場面を生むかもしれない。
振り返ると、つくることが目的だった。つくったものを並べて改めて見直してみて、もし、つくることを手段としたら、では目的は何だったのだろうか、と考えてみた。
正直、すぐには思いつかない。目的、すなわち、つくることによって何をしたかったのか。ひとつひとつには、その時々の条件や要望といった固有のコンテクストがあり、それに応えてきた。だから、何か共通の目的を意識はしていなかった。もちろん、デザインに関しての通底する考えはあるが、その実現が目的かというと、ちょっとちがう気がした。
いま一度、目的をちょっとだけ深く考えてみようと思う。そうすることで、この先のものづくりに対してよりクリアな態度でのぞめるような気がする。
できるならば、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。きっとおかしく見えるかもしれない。あんなことやこんなことをしてる、などと笑うかもしれない。初期の携帯電話を知ってる人は、今、その当時を見れば、あまりにも滑稽で、肩から担いでるよ、などとその大きさに呆れるだろう。
ただ、今、一所懸命に未来を描こうと考えることは、例えば、肩から携帯電話を担ぎながら、この電話をもっと小さく軽く、と考えることではない。それは大きいけれど、この電話を使って何ができるか、だとおもう。なのに、ほとんどの人が、もっと小さく軽く、と考える。
一度未来へ行った気になってみる。もしかしたらスマホは無いだろうから、コミュニケーション用のデバイスがあればいいが、無い場合どうするのだろうかと考えてみる。その時できるのは、今考えることができる手段の範疇でしかないから、それは未来ではなくて、今に役立つことになるかもしれない。
結局、未来は現在の延長でしか考えられないので、描く未来像は今である。だから、そこから脱してみたいので、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。
いくつか同時にモノがあるときに、どうしてそこにあるのかを考えてみることに興味が湧く。偶然といえば、そうなので、今度は偶然性に興味が湧く。九鬼周造の『偶然性の問題』をポチッとしてみた。
あと、同時にいくつかあるということは、ひとつひとつが周りから独立している。独立していることは、別の見方をすれば、つながりが切断している、ともいえる。やはり、オブジェクト指向存在論が頭に思い浮かぶ。
偶然性と切断、この2つをつなげる何かを考えたら、面白そうな展開がありそうで、ただ、誰かがすでに考えているだろうから、もう少し枠を狭めて、限定した中で考えてみる。そうすると、その枠から外れたモノも取り込めるようなコトをしてみたくなる。
意図的にやると、やり過ぎて失敗するときがある。そういうときは、そもそも意図的にやるのが失敗のもとだったりする。ではと、そのときに学び、意図的さを排除するためにはどうするかと次に考える、普通は。
もしかしたら、失敗することを避けること自体が失敗のもとだったりしないだろうか。禅問答のようだが、やり過ぎて失敗した様は、そこだけ見れば、もとの意図をすでに反映していない。失敗した後のものには意図的さが消え、違うものに見えていないだろうか。その違うものは最初に目指したものではないが、最初の意図の別バージョンではないだろうか。ならば、失敗は新しいものを生成する要素として、避けるのではなく、つくるものではないだろうか。
自然な様はつくり出すことができるだろうか、という問いには何と答えるか。自然の様は自然そのものではないから、意図的に人工的につくり出すことはできるだろう、と言葉上はそういう回答になるかもしれない。
ただし、実際に意図的に人工的につくり出したものが自然の様に見えるかどうかはわからない。どこかでやはり意図的で人工的だと思ってしまったら、自然の様ではない。結局、自然な様も何もしないで放ったらかしにすることでしか、つくり出すことができないのかもしれない。ならば、自然そのものと同じではないか、となる。
だから、自然そのものの生成過程を真似て、その生成過程を意図的に人工的につくり出し、あとは何もしないで放ったらかしにする。そうしたら、やがて自然の様になる。
時はかかるものである。でも、時はかけれないから失敗する。そして、同じ失敗をたくさん繰り返す。その失敗の山はもしかしたら、自然の山に近い見え方を一瞬するかもしれない。
2つあって、はじめて一人前のような関係性は、どちらも単独では弱いので、チカラを合わせましょうということかもしれないが、それで上手くいくには、チカラの合わせ方をどうするか、という問題もある。
2つの良いところがそのまま失われずに共存できればいいが、打ち消しあっては元も子もない。せめて打ち消しあうのが悪いところならば、良いところが共存できなくても、チカラを合わせる意味はある。
理想は合わさることで、良いところは相乗効果でより良く、悪いところは打ち消し合いなくなることか。ニコイチはきっとこの理想に近いことかもしれない。
もしかしたら、意図的にニコイチを形成することで、単独行為の結果を意図して超えることができるかもしれない。きっとその時には、意図しない複雑性を身につけているだろう。
大きなものを、塊のままにするか、バラバラにするか、結構まよう。例えば、大きな肉の塊があったら、なるべく大きなまま調理して食べたいし、どんな肉でも塊であれば、ひき肉にしてハンバーグにするのはもったいない、とおもう。
やはり、一度バラバラにしてしまったら、元にはもどせないし、バラバラにするのはいつでもできるから、まずは塊のままでどうにかかんがえたい。ただ、塊のままだと、扱いづらく、お持て余しそうだし、使い道も限定されるような気がする。だから、バラバラにしたい誘惑にかられる。
塊のよさってなんだろう。中間をとって、所々をバラす、という手もあるが、扱いづらく持て余しそうということは、それだけポテンシャルを秘めているとも解釈できる。扱いづらいのは魅力的だ。
その昔、フィルムカメラで撮影するおもしろさから、同じフィルムカメラを中古で複数買いし、人にお願いして、部品取りし一台の完動するフィルムカメラをつくったりした。それをニコイチ、サンコイチ、ヨンコイチなどと呼んでいた。だいたいは完動品にしたいカメラがあり、そのための部分取り用として動かないジャンク品の中から探してくる。そのジャンク品探しもまたおもしろい。
ニコイチ、サンコイチされたことは、カメラの外観からはわからない。ほとんどが分解しないとわからない見えない所に部品が使われる。全体として変化はないが、その部材がないと機能しない。ただし、その部材は他から来ている。
ひとつのものとして独立して存在していながら、他との強い関わりが内在されている。きっと、そこにおもしろさを感じ、ニコイチ、サンコイチして遊んでいたんだとおもう。
コラージュという技法が昔から好きで、ただいつもおもうのは、全体的なルールをつくってしまったらコラージュにはならない、ということで、知らず知らずのうちにおちいる。たぶんこれは、全体的なルールをつくることからはじめることに馴らされてしまったせいだろう。
全体的なルールに陥らないために、重なる部分に注目してみた。全体的なルールは整列する方向に向かう。それを避けるためには、整えない、よく見せようと意図しないなど、作為しないことだ。その作為があらわれるのが重なる部分だとおもった。ちょうどよく、綺麗に見えるように、無意識に重ねる。だから、重なりに、むしろ違和感があるくらいに、何もしない。これは、何もしない、という意図ではなくて、本当に何もしない。
スタッキングチェアがある。重ねることができると部屋を広く使いたいときには助かる。ただ、スタッキングできるチェアの場合、背もたれがあるので、ちょっとずつ前のめりにズレていくから、何脚もスタッキングできない場合があるし、その分場所もとる。その点、スツール は背もたれがない分、ズレずに真上にスタッキングできるから、何脚も天井につくまで重ねることができるし、省スペースにもなる。
身近にある重ねることができるものを探したら、スタッキングチェアが目についた。打合せスペースには大人数に対応できるように、スツール がスタッキングされている。スタッキングされたスツール は、高層ビルのように、真上に向かって層を成している。その層、すなわち、スツール は入れ替え可能だ、まるでメタボリズム的。
ただ、面白いのはチェアの方で、スタッキングされていくと、だんだんと偏心されて、背もたれ分前にズレていく。だから、背もたれがスタッキングの鍵をにぎる。背もたれのデザインがスタッキングチェアの生命線だとふんだ。
建築での層の重なりに背もたれ的なものは存在しない。ならばあえて、背もたれ的なものを用意し、スタッキングさせ、偏心させることをかんがえてみても面白いかもしれない。ほとんどの建築は層を成しているのだから。
その土地には過去、現在、未来とその時々で必要なものが現れる。土地自体は不動だが、その時々で必要なものは時間的に過去、現在、未来とつながりをつくらない場合が多い。もしスタッキングチェアのごとく、過去、現在、未来とつながりを重ねつつ、その時々で必要なものがあったら、どうなるだろうか。
日本のようにスクラップアンドビルドではなく、ヨーロッパのように何百年もリフォームしながら使う石の建築でも中を変えるので過去、現在、未来のつながりは断たれる。ただ、都市的には風景は変わらないので過去、現在、未来のつながりは保たれる。そこがヨーロッパの都市の良さなのだろう。
変わらないという価値は素晴らしいが、否応なしに変える必要があったときには困る。変わらないという方法でつながりを保つのではなく、変わるからつながりが生まれる方法をかんがえてみる。
生まれ育った家は、たぶん、築70年以上だろう。増改築を何度も繰り返して、一番最初の外観はどこにもない。もちろん、一番最初の建物を見たことはないが、生前の父親から聞いて当時の平面図はおこしてあり、現在の平面図と比べることはできる。
昔の家は和室が連なったプランであり、壁が極端に少ない。襖や障子の開閉により、部屋の大きさを可変することができ、同じ部屋にいくつかの用途が、例えば、寝室とダイニングのように、重ねられており、家具や寝具も固定ではなくて、収納や移動が可能だった。
あきらかに、今と昔では、空間のあり方や秩序がちがう。それの一番の原因は、生活様式の変化だろう。座敷から椅子になり、寝室とダイニングは分離された。
だから、そこでモノの扱いも変わった。そのモノの扱いのちがいが空間のあり方や秩序に事後的に影響する。それをいまの建築の中に移植することで、前の建築からのつながりは保たれる。主題にすべきは移植の仕方だろう。
入れ子構造というと、ロシアのマトリョーシカ人形を思いだす。マトリョーシカ人形は大家族を連想させる縁起物らしい。大小でつながり、同じ場所でつながり、同じようにつながる、からだろうか。たぶんに建築的である。
建築でも入れ子構造になっているプランは昔から多い。大事な空間を包むように外の空間があったり、大きな空間の中にいくつもの空間が内包されていたりなどする。そうして見ていくと、入れ子構造は空間に関する秩序的なものであり、マトリョーシカ人形も空間の外形ともいえる。だから、マトリョーシカ人形はモノと空間の両方の特徴を合わせもつ、ともいえる。
ただ、この入れ子構造という秩序には、空間の内容は関係ない。もちろん、建築として構成する場合は、空間の機能や目的といった内容によって、入れ子内の配置やつながりが決まるだろうが、入れ子構造だけでかんがえれば、空間の内容はどうでもよく、秩序だけを扱うことができる。それは面白いとおもった。
完結した空間があるならば、それはひとつとして、空間がある目的のためだけにあることかもしれない。その空間の存在理由が明確で、そこで行われるアクティビティも明確で曖昧さが無く、変わることも無い。
一方、不完全な空間ならば、空間が存在する理由に目的が無く、アクティビティも定かでは無く、ただ、その空間はなくてはならないもので、何か足されると、完結した空間に変わるようなものかもしれない。
きっと、完結した空間が圧倒的に多く、不完全な空間は昔と比べて少なくなってきている感じがする。ただ、今さらすべてを不完全な空間にするのには無理があるし、その必要性も感じない。しかし、完結した空間ですべてを覆いつくすのにも息がつまる。
ミックスした状態、例えば、完結した空間にバラバラと不完全な空間が現れるようなものがいいかもしれない。ちりばめられた無目的な感じは気持ちいいとおもう。
空間の中の家具に注目してみた。家具には造り付けのモノと置くモノがある。造り付けのモノは空間と一体化する。だから、造り付けのモノは完結した空間をつくる手助けをする。置くモノは交換が可能だから、空間の中での位置は比較的自由である。だから、空間は置くモノの位置に左右される可能性があるので、不完全な空間になりやすい。
どちらが良いわけではない。完結した空間ならば、何もかんがえる必要はないから、ただそこに居るだけでも良い。不完全な空間ならば、何かをしなければならないが、そこに自由意志が入り込む余地がある。この余地に心地良さを感じる人もいるだろう。どちらかというと、自由さが欲しく、完結さは息苦しく感じるたちである。
プランを考える手が止まる。空間をどうしようか、と考えることが苦痛になるときがある。
20代の頃、フィンランドへアアルトの建築を見にいった。そのときのことを思いかえすと、詳細なエレメントがまず浮かぶ。壁のタイルやレンガ、開口部の形状や光、階段のディテール、手すりの感触など。空間は、そのようなエレメント越しに、意識しないと思いかえせない。すごく近視眼的な把握の仕方だけど、人が建築と対峙するとき、自分と同スケールのエレメントに、まず自然と意識がいくのだとおもう。
なのに、空間から考えている。考えてみれば、はじめからねじれているのかもしれない。アアルトは、空間ではなく、エレメントから着想し、エレメントを浮かび上がらせるために、空間を必要としたのではないかと、その当時も考えたことを思いだした。
建築において20世紀最大の発見が空間だという。空間を表現するためにエレメントは省略されてきた。プランニングを線でおこなうのも、空間を考えるときに都合が良いからだ。でも、苦痛を感じるならば、線ではなくて、他のことで、エレメントを省略せずに、建築を考えてみようとおもった。
なにかを構成する部分は全体の一部、という関係性は普通に日常にある。このときには、全体というものに対する信頼が前提としてあり、また、全体に従う部分があるという関係性にも信頼をおいている。この場合、全体だけ、部分だけで成り立つとは考えていない。
部分だけで成り立つとは、部分同士の関係性にルールはなく、部分だけで独立していて、部分同士はルール無用である。ルールがある時点で全体が生まれてしまうから、部分そのものに信頼があるのが前提になる。
全体だけで成り立つとは、部分がどうであるかに依存せず、全体だけで独立していて、全体に絶対的な信頼があるのが前提になる。
ならば、全体だけと部分だけがあわされば、ルールの無い独立した部分同士と、部分に依存しない全体が、同時にあることなる。それは、なかなかない組合せかもしれない。それで、建築をつくることができるかもしれない。全体と部分の間にちがうなにかが生まれるかもしれない。
「うっかりミスを少なく」 2023.04.16
ときどきか、たまにか、参ったな、なんて思うときは、案外、あきらめもついて、後にはのこらないが、もしかしたら、うまくいったのにとか、思うときは、なかなか、後をひきづる。頻度は、たぶん、参ったなは少ないが、もしかしたらは、それなりにあるかもしれない。それは、うっかりミス、というやつである。
うっかりミスは大体、わかっていたけど、という言葉がさきにくる。頭のなかにはあったけれど、それがうまく表にだせなかったときで、やっぱり、それは一番くやしいし、落ちこむ。
頭のなかにあったけれど、うまくだせないことは、忘れていたことと同じらしい。だからつねに、思いだす、と意識すればいいそうな。それで、うっかりミスが少なくなるか、ためしてみよう。
全体を見ずに部分的なところばかりを見ていては、うまくいかない、と考えるのは、全体と部分には整合性があるものであり、整合性がないといけないから、整合させようとするのはいいこと、だという前提があるからだろう。
ならば、前提を逆にすれば、部分的なところばかりを見ることがいい、となる。この場合、全体と部分に整合性がなくてもいいことが前提になるが、場合によってはそれも可能性としてはある。ただ、単に逆にしただけでは、あまりに単純で反動的なので、ちょっとひねりを入れる。
部分はそれぞれ独立してありながら、全体はひとつにまとまっていて、ただ全体と部分には整合性はない、としてみる。この場合も可能性としてはありえるだろう。部分的なところだけを見て、単独で成り立たせることをだけを考えても、そこに何かつながる細い糸を見つけることができれば、それでいいとなるから。
何かを出現させようとしたとき、まず、つくることを考えるが、選んでいるだけではないか、とおもった。つくるときには、何かしらのベースがあるもので、そこから、いくつも枝わかれした予測が存在する。その予測は無意識に行っている場合もあり、その予測の中から選んでいるだけなのに、つくっていると錯覚をしてしまうかもしれない。
そこで、予測の中から選んでしまっているのならば、いま一度、つくることを意識し直すことで、よい物を出現させようとするのと、どうせ選ぶことになるのならば、選ぶことで済まして、他のことでよい物にしようとするのと、2つの方向性が考えられる。
どちらも有りだとおもうが、イノベーションを起こせるのどちらだろうか。きっと前者だという人が多いだろう。ならば、後者で考えてみる。理由はつくるより選ぶ方が早いからで、スピードがないとイノベーションは起きない、と考えるから。
つねに壁にかこまれていると感じたら窮屈だろうな、とおもうのだが、どうなのだろうか。むかしの城郭都市やゲーテッドコミュニティなどは壁に囲まれた街だが、その壁の存在をふだんの暮らしの中で感じることがあるのか興味がある。あんがい、日常的なこととして、壁の存在などは何も感じないようになっているのかもしれない。
実在している物理的な壁だけでなく、意識的な存在の壁というのもあるだろう。「壁がある」などと物事に対する障害をあらわしたり、「バカの壁」というのもある。「バカの壁」の場合は、その壁の存在に気づいていないから「バカの壁」なのだろう。
壁に気づいている場合は、その壁に対処したり、その壁の向こう側に何かあると、わかっているからいい。ただ、壁に気づいていない場合は問題かもしれない。壁の内側だけなのに、それが全てだとおもってしまうことになるから、それではちとかなしい。だから、壁にかこまれている窮屈さは、貴重なサインなのかもしれない。
時間が蓄積された物が壊されて無くなることはよくある。その物の価値には関係無く、全く無にしない、ことを選択したならば、ただそのままでは残せない。残すためにはどうするか。
時間が蓄積されているということは、そこに何らかの意味も付着し、記憶となっている。記憶を喚起する物としてアイテム化し、部分的に残すことはよくある。ただ、それではまるで標本のようである。標本として残す価値がある物はいいが、価値が無ければ、無くなる運命をたどるのは同じである。
むしろ、記憶や意味、時間を剥ぎとり、物そのものを再構成することで、価値に関係なく、残す方法があるのではないか、とおもった。要するに、配置の仕方しだいで、どのような物にも活きる場があるだろう、としてみた。
できる物ばかりを想像してまうと、脈絡のない妄想ばかりがつづく。時間には制限があるから、この妄想もいったんやめて、まとめようとするのだが、案外、妄想にはバリエーションがなくて簡単にまとまる。はじめから想像できる結果は、どこかで、前に、もしかしたら、妄想したり、チラッと思い浮かんだりしたことだったり、結局は、今までかんがえていた範疇から抜けだすことができないので、妄想にバリエーションが生まれないから、簡単にまとまるのかもしれない。
ただ、この簡単にまとまる、バリエーションのなさ、がつまらなく感じる。だから、結果を生みだす過程をつくることからはじめよう、とおもった。過程をかえれば、たとえ今までかんがえていた範疇から抜けだすことができなくても、結果にバリエーションが生まれ、今までとちがった物になるかもしれないし、過程からつくることで、べつのかんがえ方が生まれるかもしれない。なにより、毎回過程からかんがえることが、面白そうだとおもった。
ポツリとポツリと物を置いていく。物同士につながりはなく、だから何でもいい、脈絡はなくてもいい。ただ自然と、近い遠いのちがい、はできる。置かれている物はそれ自体で完結しているが、近くにある物とは何かをつくる。その何かはコントロールする必要はなく、自然に生まれてくる。
実際、建築は囲うことでつくっていく。そのための順序手順が決まっているし、それは建築のはじまりのひとつの説でもある。ただ、建築が物から派生したものならば、囲うことより、無作為にある物が他の物と合わさって建築になることもかんがえられる。
もし、囲うこと以外で、建築ができるならば、きっと、完結した物同士が近いところからより集まって建築の体をなす、こともあり得るだろう。
物が散乱している情景は、物にもよるが、なんとも様にならないようにおもえる。きっとなにも脈略もなくそこにあるから、様にならないのだろう。ブリコラージュのように、なにかにむかって収束していくのならば、ちょっとは様になるかもしれない。全体的になにかルールをもつことは、まとめるためにはよく、このまとめることが、なにか意図をもつ時には重要だが、それぞれの物がそれぞれのルールで完結してありながら、なおもバラバラにみえれば、それはそれで様になるだろう、ともかんがえた。
全体にひとつのルールでは窮屈におもえる。ひとつのルールで様なるようにしたら、なにか無理矢理におさめようとして、取りこぼすものがでてくるだろう。無理にひとつのルールでまとめようとするのではなく、個々にルールをもち完結すればよく、それでもバラバラにならないためには、近い距離感が必要なのだろう。ただ、近いというだけでまとめる、ルールではなく距離感でまとめる。距離が遠ければ他者ということである。
目に見えないものはアテにならない、としてみる。感じ、雰囲気や気分を直接あつかわない。空間、それ自体は目に見えない。目に見えているのは、空間を囲っている物であり、その物から推測して、そこにどのような空間があるのかを察しているだけだとしてみる。
そうすると、空間を察することは直接できずに、そこには察する側の思惑が、物を通して加味される。だから、思惑が入るので、空間はこれだと、確かにいうことはできないので、空間はアテにならないし、そもそも、そこには空間がある、という一種当たり前のことですら、アテにならなくなる。
では、目に見える物だけをアテにしてみる。確かにそこには物があり、その物をあつかい、その物の中に入る自分がいて、そこで暮らして、生きている。その物に相対しているときだけ、その物から影響を受け、影響を受けることで、物がそこにあることがわかる。この関係の中には空間は必要ない。また、物同士の関係もどうあるかは必要ない。独立して物があり、そこに人がいるだけ。それで建築はできてしまう、となる。
最初におもいつくアイデアはいつも妄想ではないか、とおもってみた。だいたい、好き勝手なことをおもい巡らす。それは、いつも、現実的ではないかもしれない。その時間はとても楽しいが、それではまとまらないから、現実に合わせる。その合わせ方に焦点をあててみる。
妄想ともおもえる初期のアイデアを分解してみる。複数の要素にわかれるだろう。その要素ごとに独立してかんがえ、現実に合わせるために、要素を入れかえたり、変化させたりする。各要素ひとつだけで全体を表すことはないが、すべての要素があつまれば、全体がみえてくる。
だから、各要素ごとに変えたり、変えなかったり、どのように変えるかで全体をコントロールしていく。そうすることで、妄想のおもしろは残しつつ、実際に立ちあがる建築が生まれる。
強い考えがあって、それにそって、何かを決めていく。きっと、そうしたい、と思い、全てをひとつの強い考えで満たしたい、と思う。それは、芯があって、理想的なことかもしれない。別の言い方をすれば、それは、型、かもしれない。
強い型をもつことは、何にでも有効だろう。それにそうだけでいいから。ただ、そもそも型とは、決まったひとつのことに対応するためのものだから、強くなればなるほど、ちょっとの変化にも対応できなくなる。
最近思うのは、強い型では対応できないことが多いのではないか、ということ。型にはまればいいが、そんな、ひとつのことで済む、ような場面はなかなか無い。
だから、ひとつに対応するための型よりは、強くなくてもいいから、複数に柔軟に対応できる方がいい。それはもはや、型、と言えるような全体性は有しないかもしれない。もっと、個別の、その中では完結しているけれど、決してそれは全体を表すことでは無いような、そして、それが複数あることによってはじめて、全体がわるような、そのようなものがあれば、その方がいいような気がする。
ひとつの世界観で表現できるような、きらびやかな世界がユートピアであり、それは憧れであり、よく見聞きした建築は、みな、そのようなユートピアだった。だから、ユートピア的な建築をつくりたい、とおもう気持ちはいつもどこかにある。しかし、それは妄想だろう、という気持ちもいつもどこかにある。
ひとつの世界観でスパッときれるほど、この世界は単純ではない。やはり妄想でしかない建築のイメージをどうしたら現実の世界にフィットさせることができるのか。
フィットさせるためには、どこかで妄想を切り離し、別のものとつなげる必要がある。その別のものはひとつではなく、複数かもしれない。複数のものがそれぞれ別の世界観をもち、かつ同時に共存するような状況が、妄想ではなくなる瞬間かもしれない。
スクラップ、アンド、ビルトにより成り立つ建設業界なので、街を歩けば、結構な頻度で、建物を解体をしているところに出会う。そのたびに、建築はモノだな、壊すのは簡単だな、とかおもい、解体しているときにしか見ることができない建築の姿をながめる。
伊勢神宮の式年遷宮のように、解体しても、またその部材を他で再利用するならば、解体することに対する罪悪感みたいなものは生まれないのかもしれないが、解体は、それまでの記憶や、積み重ねた時間や、見慣れた風景を切断して、膨大な廃棄物に変えるだけである。
ただ、見ようによっては、解体される建築には、さまざまな記憶や時間、風景がつまっていることになるので、それは貴重な財産である。活かしかたがわかれば、解体するより利用することを皆えらぶだろう。
体験によってすべてをとらえようとするのは、経験主義かもしれないが、あらゆる要素を、体験をとおすことで、ひとつの土俵の上にのせることができる、のは面白いかもしれない。
体験でわかることは、けっこう、たくさんある。例えば、赤い花、があれば、「花」という物も、「赤い」という色も、また、赤い花を見ている「自分」も、体験という土俵の上にのせることができる。
あとは、その土俵をどうするのか。はじめから、どういう土俵かを設定するのか、あとから設定するのか、そもそも「土俵」自体を物としてみて、「花」や「赤い」や「自分」と同じようにあつかうのか。
体験をとおすことで、あらゆる物のつながりを切断することができ、さらに、新たなつながりをつくることができる。そこも面白いところかもしれない。
都市部に暮らしていると、たまに自然の中にいきたくなる。都市の中にも自然はあるから、そこへいけば、気がすむかといえば、そうでもない。自然の中にいくことと、自然があることは、一緒のようで、ちがうということかもしれない。
建築をつくっていると、自然がある、という物質的なことをかんがえる。どこに木を植えるのか、どこに緑をもってくるのか、建築と自然をどのように融合させるのか、親和的にするのか、などをかんがえる。そこをかんがえれば、とりあえず、緑を取り入れ、建築と自然をとりまく諸問題を解決できた、となる。
ただ、さきほどの、自然の中にいきたくなることを、直接解決することになるのだろうか。やはり、自然があることとは別のこととして、かんがえるべきなのだろう。
空間があっても、その空間は自分にまとわりついているもので、はじめからそこにあり、意識することがない。しかし、空間をつくろうとすると、囲うことをかんがえ、そこではじめて空間を塊として量で意識する。
塊として量で意識しないと、建築化できないから、囲うための壁や床、天井をかんがえる。ここで、空間をつくることと建築化は、同じことのようにおもえるが、ちがう。
空間をつくることは、空間を認識としてとらえることであり、それは空間という無色透明な水みたいな存在を、何か入れものにいれて、わかるようにすることである。また、建築化とは、壁や床、天井といったエレメントを先に構築し、囲われることにより、空間の形を出現させることである。
どちらも結果的に空間があらわれるが、空間をつくることは内向きで心的なことであり、建築化は物質的である。どちらかというと、心的な空間のとらえ方に共感をおぼえるが、心的なとらえ方をしたあとに、物質的な表現に焦点があうので、建築としての空間には両方の要素が必要で、そこのバランスのとり方やズラしかたが主題になるのだろう、とおもった。
こうしたい、ああしたいと、こうする必要がある、こうしなければいけないを、まとめてすべて満たした物が最終の成果物になるのが一般的であるが、それでは、だれがやっても、大体、にたような物にしかならない。
だから、すべて満たした物の先にある、別の物をつくり、あたかも、はじめから目指していた物はこれですよね、と示し、満たすべき物もそもそもこれですよね、と逆に定義しなおすのが、現代建築ではよくあることである。ただ、満たすべき物を変えることができる場合はいいが、もしかしたら、それは珍しいことかもしれない。
別のやり方として、満たすべき物をすべて満たした建築に、さらに手をくわえる。それは、満たすべき物を強調するためであり、それによって、手を加える前と後とでは、満たすべき物がより浮かび上がる。より浮かび上がった状態は、もしかしたら不自然かもしれない。その不自然さが、にたようは物にはならずにさせ、ちがいを生む。ただ、そのちがいの素は、満たすべき物であるから、そのちがいは受けいれやすいだろう。
これがいい、という確かさをえるには、これでいい、という一般的な了解が必要になるけれど、そもそも、その一般的な了解などが妄想、だということをよくきく。だから、その一般的な了解など存在しないから、それを根拠にして、何かをつくったり、かんがえたりすること自体がおかしいと。
その妄想を、たとえば「ブランディング」というべつの言葉にしたら、わかりやすいかもしれない。ブランディングは、新たにつくる一般的な了解であり、そもそもはじめには何もない、まさに妄想である。ただ、そのブランディングによって、これでいい、という一般的な了解が植えつけられ、これがいい、となる。
具体的に何かが生まれるときには、この一般的な了解は、その生まれたものを受けとる側には必要だろう。ただあまりにも、その一般的な了解が前面にでてくると、その生まれたものがまったくのウソにみえる。
ただ、ウソにみえてもいいもの、みえた方がいいものもある。逆に、ウソはダメなものもある。そのちがいは、一般的な了解のだし方で調整することだろう。受けとる側がいて成立するものならば、調整することが、つくることの一部になる。
建築には、細くて目立たないがしなやかで強い、一般的な了解が必要だとかんがえている。弱いと、建築自体がさまざまなつながりの中で消滅してしまい、ただ強いだけど、建築の存在がウソになる。
かんがえたり、イメージしたりするなかで、妄想はよくしてしまうし、妄想がなにかのヒントになることはよくあるが、妄想の世界をつくり出すことには、まったく面白さを感じない。
妄想の世界は、極端にいえば、何でもありである。この何でもありが、妄想の世界の良し悪しでもあるが、何でもありだから、自由にしていい、何をつくっても、それは妄想だから許される、となってしまうことがつまらない。ようするに、現実的な裏付けがない妄想の世界には興味がわかない、のである。
妄想を別のことばにしたら、非日常的、詩的、観念的などになるかもしれない。非日常的で、詩的で、観念的で、それだけのものならば、興味はわからない。ただ、もし詩的で、観念的でも、日常的であれば、それは現実的な裏付けがある妄想の世界になり、グーッと興味がわいてくる。
ここでしか成り立たないこと、にはあまり意味がなく、もう少し引いて、全体を俯瞰して、何か抽象的な全体像や仕組み、イメージをもち、それへ向かって整列するように、ものごとを決めていくことが大事だとおもっていた。
ただちょっと振りかえると、そのような全体像や仕組みやイメージは、妄想にすぎないのではないか、観念的に、詩的に、そういう全体像などをつくり出して、それに酔っているだけではないか、とおもうようになった。
俯瞰せずに、地に足をつけて、平行目線で、間近なものを、周辺をボカシながら、中心にくるものだけをしっかり捉えてみる。そうすると、あまりにも限定的な部分しか相手にできないが、それらは妄想ではなく、それらが複数集まれば、相当の規模にはなるし、ただ、限定的な部分の寄せ集めなので、決して完璧な全体像は表現できないが、それが現実的でいい、とおもった。
部分の寄せ集めと、全体像はちがう。部分の寄せ集めによってできる全体は、俯瞰してわかる全体ともちがう。どちらかというと、部分の寄せ集めによってできる全体は、ここでしかできないことに近いかもしれない。ここでしかできないこと、の方に、ちょっと可能性がみえてきた。
白くて明るい空間がすきだが、一番すきな空間は、人目につかない暗い場所になる。白いのは壁や天井であり、明るさは大きな開口部が満たしてくれる。この白い空間は全てのものに光があたるから、影などなく、全てが見わたせる。この清いくらいの白さと明るさが、生活の中には必要である。
ただ、同じくらいか、それ以上に、人目につかない暗い場所も必要になる。全てが見わたせる白くて明るい空間では、こぼれ落ちてしまうもの、のために人目につかない暗い場所がいる。
いままで、メインは白さと明るさであり、サブとして秘密の暗部で人目につかなさがあった。この関係性を逆転するのもいいかもしれない。秘密の暗部をメインにするのは、あまりにも外の世界が開かれすぎていると感じるからで、逆にそれを感じられなくなるのがこわいので、自分が日ごろ引きこもる場所は、秘密の暗部がいいとおもってしまう。
つながりはつくりたい、けど、個としていたい、という、いっけん矛盾したこと、は言葉ではいえても、形にはできない、とかんがえてしまう。形にはすぐにむすびつかないけれど、いえてしまうのが言葉のおもしろさ、だとおもう、四角い丸、のような。
ただ、じっさい、四角い丸、をつくれるかもしれない。円柱を横からみればよい。きっと、そのようなことは、誰でもおもいつくが、最初に、言葉があるから、かんがえはじめる。どうでもいいことでも、いっけん有りそうもないこと、をかんがえてみることには価値があり、その時の言葉にも価値がある。
だから、「つながりはつくりたい、けど、個としていたい」も、たとえば、「つながり」がまわりを切断して「個」をつくり出す状況にすればよい。これも言葉だからいえることかもしれないが、少しは形になりそうな雰囲気にはなってきた。
建築は時間がたつと、劣化していくし、25年したら価値がゼロになる。かんせいした瞬間からものとしての価値がさがることになる。ただ、時間がたつことで使用者にとっての価値は上づみされていく。それを愛着といっていいかもしれない。いまのシステムでは、この愛着をすくいとることができない。愛着には価値がないとされる。愛着に価値を見いだすには、愛着に価値があるとかんがえる人がひつようになる。
愛着に価値をみいだし、ただ、それをそのまま表現したのでは誰にもつたわらない。誰にでもわかる形に愛着を変換するか、変換した愛着とのつながり方を調整するひつようがある。
愛着というと、なかなか、実体がないものだから、形にしづらいが、愛着をなにかしらのエレメントに変換するか、あるいは、変換したエレメント同士のつながり方で表現するのが、ひとつの方法だとおもう。
ボディが壊れて、赤絵の蓋だけ、がのこりました。きれいな蓋、では、また、似せて、ボディだけをつくりますか。いや、全く別のボディをあわせちまいしょう。
なんて、そういうやりとりかどうかは知らないが、鉄の燗鍋に赤絵の蓋がついている、のをみた。燗鍋は懐石でもちいる酒つぎのこと。もとは、燗鍋に、共材の鉄の蓋、がついていたのを、赤絵の蓋、にすえ替えたか、赤絵の蓋だけが先にあり、それにあわせて制作されたのか。どちらにしても、茶人のあそび心はおもしろい。
とくに、赤絵の蓋にあわせて、別のボディをつくるのはおもしろい。使用じょうは、蓋の役目さえすればいいから、燗鍋いがいでも、なんでもいいし、元の赤絵の蓋のボディとは、全くちがうもの、にして、落差があって、元のボディが想像できないくらいのほうが、余計におもしろい。
建築でも、ふるい建物の一部分をのこして、新たにつけくわえ、全く別の用途にかえる、ことはよくある。ただ、ここまで、変化のはば、が大きいものはない、ような気がする。どこまでいっても、空間の範疇、建築の範疇から、ぬけ出ることはできないから。ふるい建物の一部分をのこして、空間以外、建築以外、にするのならば、この燗鍋と同じくらい、におもしろいけれど。
そういえば、むかし『北の国から』というドラマで、自動車のスクラップ部品や、古い電話ボックスなど、をつかって、家をつくっていたシーンがあったけれど、あれなどは、この燗鍋と同じ、ようなつくられ方かもしれない。
もちいられるエレメント同士のつながり方や、そこから生まれる全体としてのオブジェクトが、元のエレメントが属していたオブジェクトやつながり方と、全くちがうことでしか表現できない世界があるな、とおもった。
サードプレイス、という言葉がある。家でもなく、職場でもない場所。そのサードプレイスの重要性や必要性をよくきいた。たしかに、場所の量でいえば、圧倒的に、家や職場よりも多いし、無限に存在するといっていいかもしれない。しかし、その場所にいる時間は、ふつうに生活していたら、家や職場より、圧倒的に少なくなる。サードプレイスが無い人も多いだろう。
サードプレイスが必要で重要な理由は、有限な時間を、より有意義にするため、ときいた。家や職場での時間だけでは、なにかが損なわれてしまうと、感じるからだろう。サードプレイスがあることで、有意義、を担保している。ただそれでは、なにかが損なわれること自体が、かわることはないともおもう。なにも損なわれず、有意義でいること、はできないか。
サードプレイスをつくるにしても、家や職場と並ぶような、別々の扱いもいいけれど、サードプレイスの特色はそのままにして、家や職場とからめてみたらどうだろうか。そうすると、場所の量は、限定的になり、有限になるが、そこにいる時間の量が圧倒的に増える可能性がある。サードプレイスのつくり方によっては、なにも損なわれなくなる可能性すらあるかもしれない。
ふつうに、反動的に、逆張りをするのはおもしろいけれど、ちょっと、たんじゅんすぎて、それでは何もうまれない、とおもった。
なにか、つくろうとしたときに、できれば、よく見るものとか、よくあるもの以外のものを、つくりたいとおもう。そのとき、たんなる逆張りをすると、まったくちがったもの、に見えるけれど、それはたんに裏表の関係にすぎず、けっきょくは亜流でしかない。
いちど切断するひつようがある。よく見るもの、よくあるものが外してしまっていることを見つけ、それをメインにすえる。それは、一見、逆張りのようにおもえるが、同じようなことで近くにあっても、外していることもあり、結果的に、すごくわすがな差にしか見えが、よくあるものではなくなる場合もある。
まわりからめいかくに区分けされている状況は、それだけが特殊であるが、それが、特殊ではなく普通で通常である、ということがありえるのか、とかんがえてみた。
かんがえるきっかけは、まわりとの違いがめいかくにあらわれている建築を、普通で通常なものとして、つくりたいからである。特殊なものをつくることは、あんがい簡単、なのであり、それはのぞまれないことが多い。
きっとありえるとしたら、一見普通のかっこうをして、まわりとはいっさい関係をもたない、ようにすればよい。一見普通、というのは、よくみれば普通ではないときがあり、つねに普通ではない、普通でいる時間が限られていることで、普通ではないときには、まわりとの関係が切断している。断続的に関係の切断がおこるならば、めいかくにまわりから区分けされる。
ただの線だとおもっていたものに、太さをかんじると、それはただの線ではなくなり、太さの中に、さらに別のものをみることができる。
壁をえがいた単線に、太さをかんじると、もっと太く、もっと幅をひろげて、その中になにか入れたくなる。そうすると、線は複数になり、そこに間ができる。そしてまた、線に太さをかんじると、そのくり返しで、間ができていく。そうしてうまれた、いくつかの間は、分割してできた間とちがい、もとは単線だから、つらなり、である。
そのつらなりは同時に、もとは単線だから、なにかを分割することにもなる。それは、つながりが切断した状態をつくりだす、ことである。なんとも、みりょく的なこと、だとおもった。
境をこえることは、建築ではなかなかできない。いろいろな境があるけれど、土地の境も、隣りとの境としての壁、床、天井も、あたり前だけど、こえられない。ただ、それでおわり、ではなくて、なにかないか、なにか方法はないか、とかんがえてみる。
かんたんにいえば、建築は決められた境の中でしかつくれない。しかも、境は条件として、はじめに与えられるものだから、選べないし、あとから変えられない。もし、境をこえることができれば、なにかちがう表現が可能になるはずだ。
現実的には、境をこえることはできないが、境をこえたような意識や気分、にはさせることができるかもしれない、とおもった。それをかんがえるきっかけになった、因州中井窯のお皿からアナロジーをえよう、とずっとながめていた。
お約束ごとがわかると、いちいち説明がなくても、理解できたり、行動できたりする。そのお約束ごとのひとつが記号かもしれない。記号はそれだけでシンプルな意味をまとうから、つかう方も受けとる方も、よけいな物事をはぶくことができ、わかりやすくなる。もしかしたら、記号だけで、かなりのことが表現できるかもしれない。
先日、お能の舞台をみていて、音で展開がなんとなくわかった。この音がした時はこうなる、こうなる前にはこの音がする、など音が記号の役割をして、展開が約束されていた。
建築でもデザイン手法として記号があつかわれていた時期があった。意味をまとう記号をデザインの主題にしていた。ただその後、記号をあつかうことがすたれたのは、記号がまとう意味のつたえ方まで意識されておらず、意味にともなう行動までをデザインの範疇にできていなかったから、と記憶している。お能をみていて、そのことをおもい出した。
できるだけ省き、最小限の動き、音、言葉で、意味をつたえるのが、お能、だという。毎回、お能を鑑賞するたびに、気づくことがあり、ちょっとずつ、うすくだけど、かさね塗りするように、自分なりに、お能の理解がすすむ。
省くことで意味をつたえる、というのがおもしろい、とおもう。建築からの視点でかんがえると、モダニズム建築も省くことをおこなった。ただし、それは、それまでの建築が装飾をまとうことで、意味をつたえていたから、建築は意味をつたえるものではない、として装飾を省いた。だから、省くことで意味をつたえるお能はおもしろいと、とくに欧米のひとは、そうおもうかもしれない。
ただ、日本人にとっては、省くことで意味をつたえることは、なんとく感じでも、理解しやすいかもしれない。茶道にしても、花道にしても、道がつく世界では、省いて最小限にして表現することは良い、とされているようにおもうから。
ただ、いつから、省いて最小限にして表現することは良い、となったのだろうか。少なくとも、縄文式土器をみると、装飾することで意味をつたえていた、ようにおもう。その反動からか、弥生式土器には装飾がなくなったが、最小限の良さ、を表現しているのだろうか。たしか、岡本太郎や磯崎新が、縄文式土器と伊勢神宮、弥生式土器と桂離宮を関連づけていた。帰ってからしらべてみよう、っと。
それぞれが中心になれるような人たちが、たくさん寄せあつまると、うまくいくのだろうか。ふつうにかんがえると、それぞれが自己主張をして、バラバラ、になり、うまくいかないようにおもってしまう。だから、バラバラにならないようにするか、そもそも、中心になれるような人だけでなく、脇役や、うまくまとめるような人もまぜる。
ただもし、バラバラでも、うまくいく方法があるとしたら、なんだろうか。バラバラにも利点がある、とおもう。ひとりひとりが中心になれるくらいの能力があるのならば、まとまったひとつの集団より、バラバラであるがゆえに、迅速に細かくうごけるから、より広範囲に、よりふかく、ものごとに対処できる、のではないだろうか。
そして、それによってできる、バラバラな人たち同士の関係性が、無形の財産、として価値があるものになるような気がする。きっと、これは、建築でも同じで、そこに関係性に価値がある所以があるのだろう。
見通しがわるい、ところは不安だから、見通しよくしようとしても、そもそも、どこを見ればいいのか、わからない時って、あるような気がする。見通しをたてる前に、見る方向をさだめたい。
あんがい、見る方向をさだめるほうがむずかしい、とおもう。勘ちがいしたり、まちがったりしてしまう。見通しがわるいのは、見る方向がまちがっている、からかもしれない。
見る方向をさだめるには、さいきんは、つながりを意識している。見る方向をさだめることは、他と切断することになるが、切断したあとは、ちがうつながりができていく。このちがうつながりが、連鎖して生まれるかどうか、が手がかりになる、とおもう。
住宅も同じ、新しく建てることは切断を生む。しかしそのあと、ちがうつながりが連鎖して生まれる、ようにすることで、住宅として成り立つ。そんな連鎖をたくさん起こしたくてはじまったプロジェクトは、切断のあとのつながりが、いたについてきた。
いつも期待は無限にあるように感じてしまう。どこまでもつづくとか、かならずあるとか、ずっととおくまでを範囲に感じる。でも、あたり前だが、無限などありえず、なんでも有限である。
無限だと感じるからできること、を有限だと切りかえたら、でもそこで、今まで、そこまで意識していなかったことに、気づくかもしれない。
なんでも有限、限りがある、としたら、かならず、つきる時がくる。今まで、つきること、を意識してなかったから、そのものの成り立ちなど、どうでもよかったが、つきてしまう、限りがある、有限だとわかったら、とたんに、そのもの自体のこと、が気になりだす。
けっこう、なんでも、有限だとおもうと、なにもしなくても、自然と、いろいろなことに気づいたり、そのものに集中できたり、するのかもしれない。
建築のようなオブジェクトも、有限だとわかっていながら、無限にあるもの、だとおもってしまう。有限をもっと意識したら、関係性などのような、どこまでも無限につづく幻想が、気にならなくなるかもしれない。そもそも、人がつくることができるオブジェクト、は有限だから。
日頃から、ひとつのことだけで無く、他のばしょを持つこと、が面白さにつながる、とおもっている。ひとつのことだけをコツコツやる、ことは大事だが、それが2つ以上、たくさんあれば、それ同士の相乗効果も生まれ、ひとつだけでは出せいこと、に遭遇できる。
ひとつひとつには、そのままでは、その内側に、見ることができない部分、があるとおもう。その見ることができない部分は、その内側にいるから、見ることができないのであり、外側に出れば、見ることができる。
だから、他のばしょ、が必要なのであり、その見ることができない部分が、ほんとうは、じぶんがいちばん必要なこと、だったりする。ただ、その場合、他のばしょ、にも同じくらいの比重が必要で、きっと他中心的になるのだろう。
この住宅には、たくさんの、他のばしょ、をつくり、中心をたくさんつくれる、ようにしてみた。そうしたら、暮らしがアクティブになった、とよろこんでる。
ただ、ただ、形をいじりながら、形のみが、うまくいくように、うまくおさまる、ように置いてみる。その時点で、形は安定して、そこにある。こんどは、そこから、それが置かれるまでに、何をしたか、をかんがえてみる。これを何回かくり返すと、共通のプロセスがうかぶ。
まったくの思いつきで、プロセスをはじめにきめてみる。置かれるものは、同じプロセスならば、まったく同じ形、なるばずである。もし、ちがう形、になるならば、プロセスを調整する。
この2つ、前者は、実践から理論をつくるこころみで、後者は、理論から実践をつくるこころみである。どちらも創造にはなるが、どちらが良いかはなく、創造されるものが実践か理論のちがいである。
今までをかんがえると、実践が先にくるから、創造されるものは、実践してつくられたもの、になるだろう。やはり、実践が先のほうがしっくるくるし、後からの理論づくりは、自分にたいする、気づきにもなる。
まったく周りから切り離された、そこだけにしかない、建築、はあるだろうか、とかんがえてみた。まわりの環境、となじむことが、良し、とされるから、なかなか、周りから切り離された建築、をイメージできないし、見あたらない。
ただ、森のなかにぽつんとある建築とか、周りが自然だと、あり得るかもしれない。周りが建築と相対するものであれば、可能性はある。
あとは、建築自体が、周りから突出して存在している場合、もかんがえられる。その場合は、都市部のなかでもありえるが、シンボリックで単体、の建築がすぐにイメージできる。
面白そうなのは、都市部のなかで、シンボリックではなく、なおかつ、単体ではなく、周りから切り離されて突出している建築であり、単体ではないとしたら、それは多中心的なものか。いずれにしろ、ちょっと、横にスライドして、かんがえてみる。
時間がつながっている、ことと、空間が途ぎれていること、この2つが重要だとおもう。
建築では、とくに、建替えでは、過去そこにあったもの、とは断絶したものができあがり、ただ、そのときの周辺環境、とはつながっている。だから、前とはまったくちがった風景がとつぜん出現する。前そこに、何があったかが思いだせない。
ずっと同じではこまるが、定期的にまったくちがった風景がとつぜん出現するのもこまる。それに、これをくりかえしていくと、どこをみても同じ、というような風景に収束していく。
だから、時間的なつながりは残し、さらに空間が周辺環境とは関係ないところできまるならば、時間は過去現在未来とつながりながら、多様な風景がくりかえし生成されていく。
たのしい街は、あんがい、勝手きままな建築、だらけだ。
目のまえにある木と、そこに何かをつくろうとしている人が、関係することで、何かが生まれる、とすると、生まれたものは、木と人の関係性の産物だが、生まれたもの自体は、それはそれで、その関係性とは別のところにいる。
ちがう言い方をすれば、つくるプロセスでは、木と人の関係が必要だが、できて出現してしまえば、関係性が無くても、そこにいることができる。
これが建築の場合、エコロジーの観点からすると、問題になる。できてしまえば、木という自然が無視できるから、建築が調和をくずす要因になりえる。
ただ、そこでおもうのは、そもそもそこに調和があるのか、ということと、建築がそこで関係性を無視してあった方が良いのではないか、ということ。
木と人の関係性は反映されているわけだから、木と人以外の別のものが出現することで、何か新しいものを捉える可能性が生まれるし、それには、調和の無さ、あるいは、緩さが必要だから、そもそも調和など幻想だったのではないか。
もう少し、建築を関係性ではなく、建築自体が持つ新しいものを捉える可能性というポテンシャルの面をみると、よりエコフレンドリーになるのでは、とおもう。
常にかわるかもしれない、とおもうと、おちおち安心もしてられない。できれば、かわらない方がいい、とおもう人も、多いかもしれない。ただ、自然をみてると、かわらないもの、などない。常に一定の均衡状況を保つことなど無い、ようにおもう。かわることが日常、のようにみえる。たがら、自然をとり入れたい、とおもうことの、本音は、かわりたい、かもしれない。
人も自然のいちぶ、という話には、はんぶん賛成、はんぶん反対。自然のなかに人をくみ入れることで、自然は守るべきもの、になるが、自然と人をおなじようにあつかうと、自然は人によってどうにでもできるもの、にもつながる。
自然のかわりようをみながら、人は人でかわるのがいいのでは。自然はとり入れるもの、ではなくて、そばにあって、いろいろなかわり方、をみせてくれるものでいい。
時がたつのがはやい、あっという間、というけれど、おもいかえすと、はやい時と、おそい時が、あるようにおもう。
はやい時は、なにをしていたか、ぜんぜん、おもい出せない。ただ、その当時、どんな状況だったかと、俯瞰して、かんがえると、なにも自分からすすんでしてなかった、ようにおもう。やらされていた訳ではないが、かといって、自分がほんとうに望んでいたこと、ともちがう状況だった、ような気がする。
おそい時は、逆に、したことを、たくさん、おもい出せる。あれもやった、これもやった、と。上手くいかないことも、よくやったことも、両方あるけれど、とにかく、たくさん、おもい出せる。こうおもい出しているだけでも、時間がかかり、おそく感じる。ちがいは、自分から状況をつくっていたからか。
そうだとしかたら、時間の量はみな同じ、でも、時間の感じかたはみな違う。だから、感じかた、ようするに、状況を自分からつくり出せば、時間をコントロールできる。でも、なかなか難しい。ただ、自分の家の中ならば、だれでもできる。だから、家づくりはおもしろい。
つながり、は大事だと、知らず知らずのうちに、すりこまれている。たしかに、大事だとおもう。ただ、どこかで、切断、もおこさないと、つながり、がにごる、とおもう。
切断、には勇気がいるけど、切断したい願望、はきっと、せんざい的にはある。切断、によって、いまのなにかを変化させたい、という気持ちだろうか。
ただ、じふんでは、切断、をおこすのは難しい。だから、だれか他の人に、切断、をしてほしい、と願ってしまうのは、しごくとうぜんかもしれない。
切断、をテーマに、この住宅をみると、切断面がいたるところに現れる。切断したおかげで、このクライアントは、新たな生活を手に入れた。それは、今までの日常の延長でも、切断という行為で、前の住宅と今の住宅のちがいを、感じとりながら、ちがう気持ちで暮らしてる。
外にながれでるように、外へむかって、つながり、をつくろうとしたら、自身はどんどん、希薄なもの、になりやしないか。自身というものが、つねに、外とのつながりで、決まるから、自身単体では、成立、しない。その成立のしなさは、あいまいなものへ、そして、希薄なものへ、かえていく、とおもう。
外へながれでる、のを止めて、その場で自律、してみるのはどうだろうか。その自律する部分が複数あったら、その自律する部分同士で、ながれでるような、つながりをつくれば、自律したまま、外へのつながりも、つくれないだろうか。
これは、人にも当てはまるし、建築にも当てはまる、とおもう。複数の自律、きっとこれは、今進行中のプロジェクトに当てはめて、かんがるとおもしろいかもしれない、とおもった。
なにか、ムダ、をつくりたくて、きっと、じかには役には立たないけれど、そのおかげで、豊かなきもち、になれるような状況をつくりだしたい。余分なもの、というか、余計なもの、といか、とかく、コスパや効率、ばかりが聞こえてくるので、豊かなきもちになれない。コスパや効率とは、対峙するもの、でも、それがあるおかげで、豊かさが成立するようなものをつくりたい。
きっとそのムダは、感覚的で、わかりづらい。だから、コスパや効率のそとにある。しかし、感覚的で、わかりづらいから、とくに、なにかを、はっきりとさせる必要もなく、あいまいで、ゆるい。この、ゆるさ、が今ひつようだと感じる。
そんな、ゆるさ、を肯定できるには、何があればいいのか、どうなればいいのか。かんがえるに値することだとおもう。
この住宅がきっかけで、ゆるさ、を意識しはじめた。クライアントの人柄が、そうさせたのかもしれない。
意味がある、とか、意味がない、とか、とかく意味という言葉は、価値あるもの、のたとえになる。だけれども、何ごとにも、意味を見いだしていたら、つかれて、しょうがない。意味がつきまとうときは、直感をはたらかせる、ことができない。
建築に意味を見いだしたら、キリがない、ようにおもえる。かんがえてみれば、建築は、意味のかたまり、にもみえる。建築に意味をもとめることが、それこそ、意味がないときもあったし、建築に意味をもとめようとして、おかしな建築ばかり、がでてきたときもあった。意味のかたまり、とは建築を部材に、還元していけば、それぞれの部材は、なにかしらの意味をもち、設計する側は、その意味から、部材の集積をかんがえる。
でも、あんがい、さいごの部分は、直感だったりするから、意味が不明確だったり、それがおもしろい。この建築も直感にしたがった。
時はながれる、あたりまえだけど、10年前をおもうと、この10年で30年分は生きたような気がする。いろいろとみつかるものだ。たぶん、10年前には想像もしてなかったことを、たくさんみつけた。この10年で、みつけ方もたくさん試したので、またまだ、これから、未知のものが、たくさん、みつかるだろう。
日々のなかで、暮らしと直結するもののひとつが、建築、だとおもっている。だから、どうしても、どう考えても、人をとおして建築を考えてしまう。建築が人に与える影響から考えてしまう。これからもそうだろう。
これらの住宅も、発端はすべて、人にどのような影響を与えるか、だった。この、どのような、の部分がこれからさらに、掘りさげていくところで、またまだ、未知のものが、たくさん、ありそうな気がしている。
いかにして、ボーダーラインをこえるか、をつねにかんがえているような気がする。建築の場合は、つねに、なにかしらのボーダーライン、がつきまとう。それが、目にみえる、場合もあるし、目にみえない、場合もある。予算や、敷地境界線や、絶対にこえられないもの、もある。
なかには、ボーダーラインをこえあう関係性、もあるかもしれない。片方がこえても、もう片方もこえれば、バランスがとれて、問題にはならない、ような。そのようなボーダーラインは、意識すること、でみえてくる場合もある。その場合、ボーダーラインをこえてること、に気づかないこともある。
なにかで、ボーダーラインをこえてる、ことを気づかせることができたら、お互いにボーダーラインをこえあうこと、に抵抗もなくなるだろう。きっと気づかせるきっけに建築は役立つとおもう。この住宅は、そんなボーダーラインに気づかせてくれる。
スクラップブックのように、いろいろと貼りつけて、そこには、ルールもなく、好きなようにできる空間、ってあるとしたら、どんなだろう、とそうぞうしてみた。
そのときに、その空間をつくる側か、みる側か、でちがうかもしれない。つくる側は、どうやってつくるか、をかんがえるし、みる側は、どうやってみるか、をかんがえる。ひとによって、ちがうだろうが、じぶんは、つくる側でかんがえてしまう。
現実的に、スクラップブックのような空間みたいな、ありえそうもないことを、簡単にできるようにかんがえる。そうすることで、いろいろなひとを、巻きこみやすいし、みる側のひとたちも、現実感をもちやすくなる。みる側のひとたちは、クライアントだ。
この住宅は、好きなように部屋の範囲をかえることができる。ルールはない。あるとしたら、スクラップブックで紙の大きさがきまってる、ように広さに制限があること。
あんがい、スクラップブックのように、はじめにルールはなく、あとから自分しだいで、好きなようにやるための何かを持ちこみたい、と他でもおもう。それが、つくる側のおもしろさ、であり、みる側ではできないこと。好きなようにやるための何か、はみる側をもハッピーにする。
ちょっとでも、日常とはちがう体験、が日常の中にあれば、そこから、さまざまな連鎖がおこる、とおもう。たとえば、その連鎖は、ふだん行かないような所、に行こうとか、なかなか会えない人、に会おうとか、またちがう体験をよぶ。体験すること、でしか、人はまんぞくできない、とどこかでおもってるから、日常の中のちがう体験はたいせつにしたい。
その、日常とはちがう体験、は非日常なことではない。たぶん、日常的にしている体験のみえない部分、だろう。それは、あえてみようとしないと、みえない部分だとおもう。そのためには、ちょっとした技術、も必要かもしれない。
きっと建築はその、日常とはちがう体験、をつくり出せるもの、だとおもう。そのためには、やはり、ちょっとした技術、が必要だろう。ただ、建築で、それをやる価値は、またちがう体験をよぶ、のならば十二分にある、とおもう。
この住宅では、密集地という立地から、空にちかづくこと、で地上の生活に、変化をつけた。人は、地面ではなく、空とむきあう。地面に接地していては、みえない部分、がそこにはあった。
ズレていると、気になるし、引っかかりができてしまう。これは、ぶつり的なものにでもおこるし、言葉のような、目にみえないもの、に対してもおこる。この引っかかりが、良いものならば、引っかかったら、たのしいし、悪いものならば、気になるだけで、やっかいだ。
ものをつくることを、別のみかた、をすると、この引っかかりをつくること、といえるかもしれない。引っかかりは、意図して、つくることができ、先にふれたように、人の意識に作用し、たのしい気分にさせることもできる。
たのしい気分になって、といわれても、なかなか、たのしい気分にもなれるものでもないし、そこには、なり方はひとまかせ、のような感じもする。それよりは、たのしい引っかかりを、たくさんつくってあげることで、いわなくても、自然とたのしくなる。それが理想だと、いつも、おもう。
この住宅は、そんなことをかんがえながら、そうしたら、こどもも、おとなも、いろいろなところに引っかかりながら、たのしそうだったし、いろいろと、どのように引っかかるのか、発見があった。
つながりや、関係性でかんがえる建築が、いちじ、はやったような気がしてた。たぶん、いまは、それは、当たり前のこと、になり、そして、関心は、モノじたい、にうつって、久しいのだろう。
こう、モノのねだん、が上がると、おもうように、使いたいモノ、がつかえない。だからか、はがしたまま、あらわしのまま、なんて、途中のすがた、が仕上りになってるのを、多くみる。
ただ、いまはいいけど、それを良しとして、放置しておくと、つくり手のイメージに、あらたな本質的なモノを召喚するチカラ、がなくなっていくような気がする。
その時代のかたまりつつある状況から、一歩ふみこむ、ことが、次をつくりだす。途中でよしが通用するのは、最初だけ、だとおもう。
なにがいいのだろう、なにが正解なの、手さぐりのときの気持ち。きっと、これって、そうそうこれこれ、とおもいたいし、どこかで、損したくない、得したいと、無意識にでも、おもってる。あんがい、たくさん、あって選べない。こんなとき、どうするかな、と最近、かんがえることが多い。
ネットには、たくさん、ある。ただ、たくさん、ありすぎるのも、こまる。だから、これが、いいじゃないの、などと、交通整理、してくれる人が、あらわれる。その人もまた、ネットには、たくさん、いる。もう、よけい、わからなくなる。さいごは、直感、にでもたよるしかないのかな。
けっきょくは、なにかに、だれかに、決めることになるのだが、それで納得してしまう理由、をさがしてる。なかなか、その理由を、うまく、しめせてる人は少ない、ような気がする。納得する理由って、あんがい、理屈じゃなくて、ささいなこと、たとえば、それ前からしってたとか、いちどは試そうとしたとか、なんか、じぶんと少しだけの関係があること。この、少しだけがミソ、かなと最近、おもってる。この住宅のクライアントも、そんなワタシとの少しだけの関係を、たぐりよせた、らしい。少しだけだから、気楽だった、と。
何か意味がありそうなもの、が目のまえにあったら、何だろう、とおもうだろう。そのとき、触れられるならば、触れたいし、あつかえるならば、あつかいたい。ようは、何かつながり、をつくりたい。
それは、その場が、どうであれ、いつも可能なこと、だろうか、いや、それを、いつも可能なことにする、場が必要だろう、とかんがえた。その場のひとつが、建築、になり得る。
いわば、建築が、媒介するもの、となる。媒介するものは、いつでも、中間にある。中間にあるから、何にでもつながる、ことができる。だから、媒介するものが、実際にあれば、あとは、そこに、つながりをきずきたいもの、を放りこめばよいだけである。
そのときの、媒介するものは、たしかな、存在、をそこで得ることができる。建築としては、いい、あり方のような気がした。この住宅も、はじまりは、そのような、中間にいる建築をめざした。
めのまえに、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、自然の感じ、をとても簡単にいえば、そうなるとおもった。そうすると、めのまえで、その時間に、自分のしらないことは、全て自然のできごと、といえるかもしれない。かんがえてみれば、自然という言葉を、木や緑などの自然と、自分が関知しないことの、2通りのつかいかた、をするが、もとをたどれば、同じなのかもしれない。
自然を感じたい、とおもうと、森や海に、いこうとする。つねに、まわりに、森や海があればいいが、都市部だと、そうもいかない。海はムリだとしても、都市部で、少ない木で、森を感じるには、どうしたらいいのか、をかんがえている。
まずはきっと、先にした、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、ような状況をつくりだせばよい、とおもった。その状況を、今度は、建築が媒介となり、そこにいる人につたえる。つたわった人は、そこに自然をみる、だろう。こんなことをかんがえた。
デザイン、には注意がむけられるが、そのデザインを伝えること、には注意がむけられていない、とかんじた。大事なことは、伝えること、である。伝えることは、コミニケーションの際の伝達手段であり、それ自体がデザインの核心である、とかんがえた。
伝達手段は、コミニケーションの両端のつなぎ、の部分になる。つなぎ方によって、デザインの意味も、役割もかわる。だから、伝達手段も含めてデザインである、と同時に、伝達手段がデザインの核心になる。
建築には伝達手段も含まれる。いや、もしかしたら、建築とは伝達手段そのもので、伝達手段がカタチになったもの、かもしれない。そうすると、建築=メディア、ともいえる。
この住宅では、たくさんの意味をつめこんだ。その意味をつかみやすくするために、建築がそんざいしている、とかんがえた。
そんなもの、存在しないよ、とどこかで、おもいながらも、期待していること、って意外とありませんか。それは、だいだいが、カタチがないものであったり、目にみえないものであったりする。ちょっと、べつ角度から、カタチがあって、目にみえてるものが、全てかという、てつがく的なことにもつながるかな。ただ、そんなむすがしいことではなくて、何か、期待をもちたい、だけだとおもう。それが、全てのはじまり、全てのきっかけ、のような気がする。
建築の設計って、目にみえるモノをあつかいながら、目にみえないコトをかんがえる、ことかもしれない。だから、いつも、期待すること、でいっぱいになる、どこかで、そんなもの、存在しないよ、とおもいながら。ただ、設計者しだいで、存在させること、ができるコトはふえる。
この住宅には、居場所をみつけて、と想いをこめた。ただのイエでなく、特別な場所、としてのイエ。べつの言い方で、イエらしいイエ。イエがじぶんたちのものならば、それをもっとふかいところで、想ってほしかった。そのためのコトは、設計者しだいで、たくさんできる。
こもる、ことに対して、建築は、とかく、ひはん的なような気がする。うちにこもる、すなわち、閉じた箱的な建築、はこのまれない。都市部では、眺望などに、きたいできないから、閉じて、こもり、必要な光をとりいれるだけ、とかんがえることは、ひとつの方法として、あってもよいはずである。
問題は、こもることで、社会とのつながり、がおろそかになる、のではという、建築だでなく、人にも当てはまること。ただ、オープンであればいいのか、閉じたなかでの、社会とのつながり、を建築として、つくり出すことに、可能性をみいだせば、よいだけだと、それはむずかしいことだが、おもう。ちょっと、それは、建築として、いま的なこととして、かんがえる価値はある。もしかしたら、閉じると開くの中間あたり、に落ちつくことも、ありえる。
これら2棟の住宅は、2つでひとつ、とかんがえ、互いにたいしては開き、外に対しては閉じた。きっと、このように、開くと閉じるが同時に存在し、その割合のちがいが、建築の存在のちがい、になることも、ありえる。
実利、なんて言葉を、ことさらかんがえる。コスパとか、損得とか、にたような言葉があり、コスパより損得には、なんか、ちょっと、計算たかさ、がつきまとう感じがする。コスパも、損得も、その言葉じたい、きらいな人もいるだろうし、べつに、ビジネスや生活の中では、当たり前のこと、だよねとうけとめる人もいるだろう。私は、コスパも、損得も、どちらにも、かんしんがない。
ただ、実利はかんがえる。コスパも、損得も、比較するときにつかう言葉だから、比較にはきょうみがないので、かんしんがない。実利は、比較ではなく、利そのものだから、何がえられるのか、とか、何がかわるのか、とかには、かんしんがある。
だから、実利から、デザインをかんがえる、こともある。ちょうど、いまよんでる本に、1世紀まえの建築家ロースの、空間構成をかんがえるきっかけが実利だった、との記載があった。実利からデザインをかんがえることが、犯罪ではない、としり、ちょっとよかった、この住宅は実利だらけだから。
かんがえを、まとめようとして、手がとまる。クライアントからヒアリングしたこと、にはいつもヒントが、かくされている。かくされているとは、直接語っていないからで、語った言葉のうらの、その言葉を語らせる何かに、気がつこうとする。たいがいは、何かは、言葉でつかみとるが、最初は、イメージや場面で、でてくる。
そのイメージや場面には、人が登場するばあいと、人が登場しないばあいがある。手がとまるときは、人が登場しない。だから、人が登場するまで、待つ。人もクライアントのばあいだけでなく、だれだが特定できないばあいや、クライアント以外の特定の人のばあいもある。これも、クライアントが登場するまで、待つ。
この住宅は、いちばん最初から、イメージや場面に、クライアントが登場した。そのようなことは珍しい。とうぜんのように、ファーストプランで、はなしはきまった。
きまった形式、から自由になりたいとしたら、また新たな自由になれる形式、をつくるのだろうか。それとも、形式から離れること、で自由になるのだろうか。
こうして、言葉にしてみると、形式から離れない、と自由になれないような気がするが、あんがい、自由になれる新たな形式、をつくろうというかんがえに、いたることが、おおいような気がする。
きっとその方が、都合の良い自由、がつくれると無意識に、おもっているのだろう。自由といっても、無秩序ではこまる。自由でいながら、ある程度の秩序、大外しはしないルール、はあってほしい、とおもうのだろう。でもそれは、形式をつくること、だろうか。かえって、きゅうくつな自由、になりそう。それは、自由とはいえない、気がする。
そんなことを、ずっと、かんがえながら、この住宅をつくったこと、おもい出した。
ふしぎと、今まで、当たり前にしてきたこと、にたいして、違和感があるようになった。階ごとで、かんがえること。もちろん、半階ずらすなどは、よくある。しかしそれも、階ごとでかんがえる、範疇になる。
そもそも、建築の構造が、階ごとで、かんがえるのが基本。だから、おのずと、計画だんかいから、階ごと、になる。階ごとは、水平しこう、である。もうすこし、水平しこうではなくて、垂直しこうへ、もっていきたい。
高さのちがいが、連続するような場所を、自然のなかで、想像してみる。その場合、高さがちがう、合わないことにたいして、不自然さは無く、段差をつくるという意識にはならない、気がする。
階段が、階段として、みえてしまうと、たんに、段差があるだけの場所、になるだけかもしれない。階段としては存在せずに、垂直方向に展開するような場所、がりそうとして、ありえる。
この住宅では、階段が、階段として、みえる。この階段がなくなれば、いいのかもしれない。
なにかを感じるとき、そのモノの、審美てきなぶぶん、にアプローチができている。そして、そのときの、感じるきっかけは、気分による感情、に左右される。気分がよければ、よくみえ、気分がわるければ、わるくみえる。モノと気分は直接、関係しながら、モノはある。
そうなると、モノ自体がどうか、はあまり関係がなくなる。そしてそれは、気分がかわれば、モノの審美てきなぶぶん、にたいするアプローチ、もかわることもいみする。モノの美しさは気分しだい、たんてきにはそうなり、モノ自体を、はっきりと、なにかこうである、とつかめない。
建築で、かんがえれば、気分によって、みえ方がかわる、ということでもある。ならば、気分にうったえるようなもの、をたくさんはいすると、みえ方をコントロール、できるかもしれない。さらには、そうすることで、モノ自体がどうか、というところに、たちかえること、ができる。
この住宅では、動きと連動する建築のぶぶん、に気分による感情を、ゆさぶるデザインを、ちりばめた。気分のよしあしが、建築のみえ方だけでなく、動き、にもえいきょうする。気分が身体を感じる、きっかけになる、こともあわせた。
ひっかかるもの、があると、きっと、印象にのこる。よく建築をみてまわっていたころは、さいしょに、ひっかかるもの、をさがした。作者の意図、と合う合わない、は関係なしに、そのひっかかるものが、最初のいとぐちで、なぜひっかかるのか、をかんがえる、ところから、スタートした。もし、ひっかかるもの、が無ければ、その場でしゅうりょう。
たいがいは、ひっかかるもの、があるので、そこから先は、建築とのたいわの時間。つくる方と、しようする方を、いったり、きたりしてから、いっぽひいて、みる。いっぽひくのは、建築を、もの自体、として、世界のがわからみるため。
この建築では、意図して、ひっかかるもの、をたくさん、ちりばめた。ひっかかるものが、たくさんあることによって、かえって気をちらし、べつのもの、をイメージさせたかった。それは、いぜんにみた建築、からの学びだった。
ものから、感じることは、人によって、ちがう。それが、当たり前だと、おもうけれど、案外、おなじだと、みんな、かんがえている。だから、感じたうえでの、最終的な、ものや、かたちを、提示してくるし、つくろうとする。
ちょっと、その前で、とどめてみようかな、とおもう。最終的な、もののかたちや、イメージを、感じる人に、ゆだねる。いろいろな、感じかたができるもの、があり、その時々で、そのなかから、感じる人の、つごうにあわせて、感じとる。感じとりかた、がちがえば、最終的に、見えるもののかたちも、イメージも、ちがうはずだ。
その当時は、そこまではかんがえていなかったが、この住宅では、いろいろな、感じかた、ができるもの、をちりばめた。どこを、感じるかによって、ちがうものが、現れただろう。
せつだんと、せつぞくの繰り返し。集合住宅にたいして、ちがう見方をしたら、そうなるかと、おもった。各住戸が壁で、せつだんされながら、せつぞくされている。さらに、各住戸が、外にたいしても、内にたいしても、せつだんされながら、せつぞくされ、つながる。
集合住宅のれきしは、このせつだんと、せつぞくのれきし、だとおもう。どのように、せつだん、すなわち、分割し、どのように、せつぞく、すなわち、つなげるか。
分割は、はじめから、部分があるのではなく、全体計画のなかから、ちがい、をつくり出すことで、わかれていく。そのわかれた部分が、また、つながることで、全体が形成される。しかし、全体は、部分の、総和には、ならない。その差を、どのように、つくり出すかが、集合住宅のデザインのキモ、だとおもった。
れんぞく的に、流れるように、すすめたいが、なかなか、おもうようには、いかないことが多い。ときどき、よそ見、をしたくなり、立ちどまる、気になるから。気になることは、わるいことではない。だから、立ちどまる前後が、うまくつながれば、いいとおもう。
かんがえてみると、案外、すなおには、ながれていかないものだと。これは、空間のはなし。あちこちに、注意をひくもの、がたくさんあるから。それらを、全部、なくすわけにも、いかないし、なくせない。だから、注意をひかれてもいいもの、ばかりにすれば、立ちどまってもいい、ことになり、立ちどまる前後に、いい影響しかあたえない。
注意をひかれてもいいもの、ばかりにするには、それらを、きちんと、おさめる場所がひつよう。この住宅では、通路をかねるスペースに、注意をひかれてもいいものを、おけるようにし、そこで、じゅうぶんに、ひたって、もらう。ここはワーク&スタディスペース。
がわと、中身を、ぶんりして、かんがえると、中身のあり方、がいつもと、違って、おもえる。建築のがわは外壁で、中身はインテリア。中身だけで、成立させることができるので、外壁がうけもつことから、解放されて、インテリアを、かんがえることができる。さらには、インテリアとして、がわ、もあつかうこと、ができる。
この場合、いわゆる、入れ子、のじょうたいに、にているが、入れ子の場合は、相似の関係、であるから、入れ子、ではない。
もしかしたら、ふつうの、階層のつみかさね、にならされている、のではないか、とおもった。層があることに、もっと、かのう性をみいだしたい。そのために、がわと中身をぶんりをした。
以前につくった住宅でも、がわと中身のぶんり、のいしきはあった。ただ、今回は、より中身で、かんけつする、ようにかんがえている。
何かを、かんじることで、建築が、うかび上がる。そのことは、とても、大切だと、おもっている。そのことが、今度は、まわりと、どのようにつがるのか。そこで、つながりが無ければ、単なる、ひとりよがりの建築、でおわる。
まず、建築とかかわる人が、かんじることで、建築として、形になり、うかび上がる。形になるとは、もともと、そこに建築は、あるけれど、何もかんじ無ければ、無いのと、同じだから。形となり、うかび上がった建築が、今度は、まわりとのつながり、を持ちはじめる。
このように、しゅつげんした、建築が、どんどん、まわりと、つながるイメージ、をしていた。ただ、さいきん、これは逆では、とおもいはじめている。
たしかに、何かを、かんじることで、建築が、うかび上がるのは、それはそうだとおもう。だが、はじめにあるのは、まわりとのつながり、の方であり、まわりとのつながり方、のちがいが、生みだされることで、個々の建築を、かんじること、ができるようになるのではないか。建築のちがいは、単に、まわりとの、つながりのちがいだけ、ではないか。
この住宅は、まわりとのつながり方を、かえてみた。建物の四周に、ウッドデッキをしいた。たった、それだけのことで、たしかに、建築が、うかび上がった。
ひかくてき、安定してるモノを、いつも見るから、そこにある、とおもう。これが、ときどきにしか、見なかったら、無いも同じかもしれない。存在感のはなしで、内容もだいじだが、頻度がだいじ、だとしたら、どうなるか。
存在感は、なんにでも、つきまとうが、建築での存在感は、よりじゅうような気がする。建築は、いつも、安定して、そこにあり、いつも、見るから、存在感があるはずである。しかし、存在感がない、建築もおおい、ような気がする。そのちがいは、どこから、くるのだろうか。
同じ、だからではないだろうか、差異、がない。いつも、そこにあるのに、存在感がないのは、ひかくするものと、同じ、だから。この場合、ひかくするものは、まわりの風景、まわりの建築。まわりと、ひかくして、同じならば、存在感がない、のも当たり前。この場合、存在感をだすには、まわりとの差異、がひつよう。この住宅は、外観のみで差異をつくり、存在感をだした。
じっくりと、モノをみることを、最近、してない、とおもった。スマホやタブレット、パソコン、本もモノだが、これらは、モノというより、情報を、みてるだけ。だから、モノを、対象として、じっくりと、みることがほとんどない。ただたんに、モノを、感じてるだけ、のほうがおおい、かもしれない。あんがい、みんなそうではないか。
もちろん、しごとで、モノをじっくりと、みることはある。だが、それは、しごとをしてるだけ。自ら、すすんで、すきで、モノをみてるわけではない。だから、話はべつ。
モノって、みるより、感じてる、ほうがおおい、かもしれない。そのことを、もうちょっと、意識してみよかな、とおもった。感じることで、モノがどういうものか、浮かびあがってくる。そうだとしたら、モノのつくりかたもかわる。
この住宅は、そもそも、ほぼ同素材で、空間をつくることにより、どこか、特定の部分に、焦点があたらないようにした。そのことで、じっくりとみるより、全体的に、ふかん的に、空間を感じてほしい。感じるから、モノがわかる。
いい天気だな、あおぞら、は気持ちいい。このかんじを、いつも、持ちこみたい。くもりぞら、が多いちいきには、住めない、だから、気持ちいい、ものにしたい、となれば、このあおぞらを持ちこむ、つまり、みえるようにすればいい。
ただ、あおぞらが、単に、みえるだけでは、気持ちよくは、ならないとおもう。あおぞらなんて、みようとおもえば、どこからでも、みえるから、あおぞらと自分をつなぐ、回路のようなものを、つくるひつようがある。
その回路が感性だと、かんがえるが、ただの感性ではなく、汎用性がたかい感性。それは、たとえば、あおぞら、のぶるーを、いろいろなものと、むすびつけてしまう。きっと、その汎用性のたかさは、あおぞらの、みせ方によるのだろう。
空間は、けいそくするから、おおきさを意識してしまうが、そもそも、空間を、どのようにとらえるかは、あくまでも、感性てきなこと、だとおもう。ひろさも感性であり、あかるさも、心地よさも、天井のたかさも、感性である。感性てきなことが、あつまって、そこに、そのような空間があることが、わかる。なにも、感性てきなことが、なければ、そこには、なにもない。
このように、かんがえれば、モノに左右されない。モノがいいかわるいか、たかいか安いか、は関係なくなる。そうすれば、そこに、たくさんデザインできるよちが生まれ、感性てきなことを、生むために、よりデザインが、じゅうようになる。
この住宅は、せまいけれど、そのせまさをかんじさせないように、感性てきなことを生む、デザインをちりばめた。あつさ、さむさも、空間をとらえるための、感性である。だから、モノだけでは、解決しない。
あれはこれ、これはあれ、と何かと、分けたがるひとがいる。分けるには、ちしき、が必要。だから、分けることによって、ちしきをみせているのだろう。ただ、分けることと、それをりかいすることは、違う、とおもう。分けることなど、実際には、りかいする上では、どうでもよいこと。むしろ、分けがたいことが、たくさん、浮かぶくらいでないと、りかいしている、とは言えない、とおもう。
さいきん、気になるのは、部分に分けたものを、たんじゅんに、ぜんぶ足しても、もとの全体には、ならないだろう、ということ。どちらかというと、いったん、分けたものを、またぜんぶ足すと、もとより増えるか、大きくなる、とおもう。
それは、分けることで、何かよけいなものを、纏うからだろう。そういういみでいうと、りかいを、わざと、困難にするために、分ける、というのはありで、おもしろいかもしれない。
なかなか、素直にはわからない、ちょっと違ったかんじがする、ような空間を、つくりたければ、さまざまな分けかた、をするのもいい。分けかたは、デザインだから、さまざまなデザインができる。ちょっと素直にはわからない空間って、日常には必要かもしれない、とおもう。そのほうが、たのしい毎日になる、よかんがする。
としが明けた、てんきもいい、はれやかな気分、ぼんやりした時間がつづく。ぼーっと積読ほんをながめる。なんで、そのほんを買ったかは、いまはもう、おぼえてない。かさなったタイトルで、れんそうゲームなどしてみる。そういえばと、他のほんを、さがしにいく。読みたいときに、かぎって、そのほんだけない。ふだんの、不せいりのたまものを、正月そうそう、なげいても仕方ない。とにかく、一冊のほんに手をのばす。
そのうち、そういえばと、また他のほんを、さがす。そしてまた、そういえば、となり、そしてまた、そういえば、となる。まるで、グラスホッパーか、はしご酒か。けっきょく、読みちらかした、残がいをながめて、おわったいち日。
その寄せあつめの、残がいを、よく日もながめる。あたまの中には、何ものこってない。ただ、タイトルれいそうゲームには、ちょうどいい。そうか、なるほど、などと、思いつくこともある。なかには『無根拠からの〜』など、というタイトルのほんもある。寄せあつめからおもうことと、それぞれのほんのタイトルからおもうことは、ちがう。
見つからなかった、ほんのおかげで、寄せあつめの山ができた。でも、それは、そのときどきの、読みたい気分、を足したもの、とはちがう山になった。どちらかというと、この、無根拠な、寄せあつめの、山のほうが、すきだ。無根拠でも、あつまれば、根拠ができる。それには、偶然のおもしろさ、がある。そういえば、いつも、このような、つくり方を、してきたかもしれない、住宅にたいして。
飾りが、ぎらぎらとあっても、こころが晴れたりはしないだろう。そのぎゃくに、何もかも、ムダだとして、さいしょう限にしても、たのしくもない。やはり、ものがある良さ、というのがある。
ちょうど良いものがない。最近、おもうのは、ものにあわせる、しかないこと。ほんとうは、こうあればとか、ほんとうは、こうあって欲しい、などとおもいながら、手にすることが多い。どうして、ちょうど良いものがないのだろうか。いっそのこと、自分でつくるしか、ないのか、などともおもう。
きっと、決まりきった型が、はんらん、してるからだろう。ちょうど良いものはあるが、それを探しだすのに、苦労する。ひにくなもので、ネットで、何でもアクセスできるけど、ちょうど良いものに、たどりつくのに、時間がかかる。そのぶん、時間をかければいいのだが、時間がかかるものには、価値がないとされ、ゆえに、よけいに、ちょうど良いものの需要がなくなり、ひとしれず、きえていき、決まりきった型だけが、いきのこる。
もっと、時間をかけることに、価値がある、となれば、型などはんらんしない。時間をかけることがムダ、だとしてるから、ちょうど良いものが、なくなっていく。
この住宅は、時間をかけることが、ゆるされた。決まりきった型は、はじめから、もとめられなかった。もとめられたのは、住宅というもの、によって、ぎらぎらな飾りではない、実際のじぶんたちの生活にそった形、としての空間だった。
じぶんの身体を、とおして、はあくできることが、建築、とりわけ、住宅には、だいじだと、何がきっかけか、わかいころから、おもっていた。ただ、ただ、身体をとおして、かんじること、でしか、建築というもの、をはあくすることは、できないと。
身体をとおして、かんじるとは、見ることからはじまり、手足でふれ、移動することで、身体に、建築を、記憶として、きざむこと、かもしれない。
きっと、痛いおもいをしたほうが、建築をマジマジと、見て、ここはこうなってるのか、などと、こまかいところまで、はあくするはず。
そのときに、たよりになるのは、じぶんの身体だから、住宅はこうあるべきとか、建築はこうあるべきとか、カタチは、などと、じぶんのはいごで、いわれても、関係ない。
よしあしは、身体にきいてくれ、とばかりに、むしろ、身体でかんじるほうが、そのときに見える、住宅にたいして、すなおだとおもうし、それが、じふんの世界としての住宅をつくる、ことになるとおもう。
そんなことをかんがえながら、この住宅は、ちょっと上り、ちょっと下る、そして、また移動するようにしてみた。きっと、ここでの生活では、記憶のなかに、身体のかんじが、きざまれ、それによって、記憶がよりふかく、よりせんめいになるだろう。それって、ここで、生活してるじふんが、いとおしくなることだと、きっと。
場あたりてきに、ということばは、何か、いんしょうがわるい。
何か、カタチをかんがえたり、ものづくりをしようとしたとき、まったく、何もないところから、かんがえたり、つくったりはできず、はいごに、これはこういうもの、というかんがえ、みたいなものが、存在すると、いしき的にも、むいしき的にも、かんがえるのではないか。
きっと、何か、ぜったい的なものにした、そのはいごにあるものにそって、つくろうとする。ただ、もっと、目のまえのものに、しょうてんを当てることもでき、そんなはいごのもの、など無いといえる、場あたりてきな、つくり方もあり、だとおもうし、その方が、あますところなく、何か、表現できるような、気がする。
この住宅では、ただ、きびしい敷地じょうけん、と向きあうことで、ここでしかできない、空間をつくろう、とした。そのとき、敷地にたいして、目にみえるもの、以外のものは、無いもの、とした。
さいきん、南部鉄瓶を手にいれた。もくてきは、鉄分ほきゅう。まいあさ、コーヒーをいれるので、そのお湯をわかすのに、南部鉄瓶をつかえば、いっしょに、鉄分ほきゅうもできる、とかんがえた。
どうせなら、気に入ったものをとおもい、北欧のデザイナーもの、南部鉄瓶なのに、にほんには、なかなかないカタチ、すきなカタチ、のものにした。
もともともっていた、南部鉄瓶のイメージとはちがう、鉄瓶というより、ケトルということばで、表現したほうがいい、カタチをしてる。鉄分ほきゅうが目的だから、南部鉄瓶らしくなくてもよい。
さいしょは、南部鉄瓶がほしい、とおもったから、もっていた南部鉄瓶のイメージ、とのズレがうまれた。だから、手にいれたものに、そのイメージのズレ、が上乗せされた。そのズレも、カタチからくる印象のひとつになり、カタチをつくる要素のひとつになった。
もしかしたら、何かものがあるとき、そのものが実際にどうかより、そのものがどういうものか、とあぶり出すようなこと、でしか、そのものを捉えることができないのでは、とおもった。
目のまえにある木を、みている時は、きっと、過去にみた木と、むいしきのうちに、比べているのではないか、とおもった。
木は、いたるところにあるけれど、いしきしてみるときは、特別なとき、である。たとえば、自然のなかにいったときとか、木におもいいれがあるときとか。いずれにしても、木との、特別なかかわりあいが、すでにあるから、比べてみることになるのだろう。その特別なかかわりあいを、記憶というのかもしれない。
もしかしたら、記憶なしに、目のまえのものをみることは、できないのかもしれない。ならば、そのときに、記憶をひきだしてくるものは、目のまえのものの、なんだろうか。
この住宅では、たとえばそれは、空をみたときの、あおさ、だったり、くものしろさ、だったり、太陽のまぶしさ、などの、ひとの感性にうったえてくるもの、だとおもい、空をとりこみ、記憶をかっせいか化し、暮らしと空を、つなげた。
ひとはつごう良く、ものを見わける。見わけることを、知覚、というのかもしれない。知覚は、もの、にたいしてだけ、おこるらしく、もの、をじふんのつごうで、かいしゃくして、次に、そのかいしゃくを、ものに、当てはめる。だから、じふんの中には、知覚は、のこらず、すべて、もの、に知覚がつくらしい。
ものは、そのような、連続したひとの知覚、の集合でできている。だから、もののじったいは、ひとによってかわり、つねに、一定ではないだろう。流行るものもあれば、すたるものもある、のもうなずける。
ただ、ひとの知覚が、ものをつくる、ことにはかわりがない。だとすれば、ひとの知覚に、はたらきかける建築を、構想することは、ありえる。
この住宅は、壁とのキョリが、知覚にえいきょうを、あたえることをかんがえた。遠くからみたばあいと、近くからみたばあいで、みえ方がちがう。画像は、遠くからみたばあいだが、近くではみえるものが、この画像では、みることができない。このみえ方の差が、知覚のズレをうみ、壁に、ちがった意味をあたえ、ここだけの壁のそんざい、につながる。それは、この住宅に、とくべつ感をあたえる。
あたりまえのように、仕切りがある、ことに、いわかんを覚えたので、ペンを手にしながら、フリーズしてしまった。いつものように、スケッチを、くりかえしたところで、いきつく先が、あるていど、想像できてしまうので、この想像できてしまうこと、も重要で、だから時間とお金が、よめるのだけれど、いわかんの元が、気になった。
時間とお金が大事、ならば、フリーズしている場合、ではないが、いわかんを、とりのぞく方が、もっと、価値あるもの、を手にいれる、ことができそうだとおもった。
いわかん、の正体は、いぜんにも、かんじたことで、何もギモンをもたずに、壁をつくることで、そのときは、壁をなくしたり、床を半階ズラす、などして、仕切るのではなく、領域をめいかくにした。
ただ同じことはしたくないので、いま、これからかんがえることは、ばくぜんとしてるけど、空間の流用、かなとおもう。
よこにひろがっていく、水平しせんと、たてにひろがっていく、垂直しせんがあり、水平しせんは、広さを、垂直しせんは、高さをかんじる。斜めのしせんは、広さと高さの両方をかんじる。
さらに、広さは、つながりへ、高さは、ふかさへ、となるとおもう。つながりも、ふかさも、両方とも、だいじだから、斜めのしせん、斜めのうごき、が必要になる。だから、建築の部位で、階段は重要だとおもう。
この建築では、階段をしょうちょう的にみせた。階段はいつも、わきやく、ただの通過する場所だけど、斜めのしせん、うごき、とすれば、それはとても、重要な場所であり、人のうごきは、人のしこうと、直接つながるから、階段がどうあるかは、人にかなりの影響を、あたえるでしょう。
これはこうだと、知らないうちに、きめつけたりしてしまう。あんがい、それが、あたっている、とおもいたいけど、本当は、きめつけない方がよかった、と後でこうかい、しないですか?わたしは、こうかい、します。
もし、きめつけないで、ありのまま、受けとめたら、きっと、ちがう世界が、ひらけた、かもしれない。
でもね、いま、見方をかえれば、大丈夫、とおもうのですよ。建築は見方のかたまり。いま、そこにいる住宅の見方を、かえれば、暮らしが、かわる。
この住宅は、暮らしをかえたい建主のために、見方をかえてもらいたい、とねがいました。そのために、まわりを囲まれているのに、とにかく、明るい空間をつくりました。
どこまでも、あかるく、そして、あかるく。どこでも、あかるいから、それりゃ、いままでと、ちがうから、かわりますよね、それも、あかるくだから、良いほうに。不思議と、わらい顔が、かわるんですよね。
すべてが、まる見えだと、こまるけれど、かと言って、壁にかこまれるのも、きゅうくつになる。何か、じふんがおよぶ範囲を、きめたくなるから、壁がひつようになる。そうやって、いまの居場所を、たしかめている。きっと、あんしん、したいのだろう。
ならば、あんしん、できれば、壁はいらなくなる。どうすれば、あんしん、できるのか。見えなければ、あんしん、できるのであれば、壁のかわり、をつくればよい。
柔軟性を、かくとくするために、かんがえる、ひつようがあった。柔軟性は、固定しないこと、どうにでもなるさま、それが、部屋の仕切りに、ひつようだった、この住宅では。
だから、壁を技術的に、開閉できる、ようにした。ここでは、開閉できることが、あんしん、だった。ときに、じぶんがおよぶ範囲を、きめる方法が、きちんと、固定すること、ではなく、どうにでもなることが、じふんのせかい、をつくると、この建主からまなんだ。
目のまえにあるものを、どんどん、否定していく、それはいらない、それはなくてもいい、それはあっても役にたたない、それはむだ、などとやっていくと、じぶんのカラダすら、無くてもよくなり、最終的には、そうやって、否定してる、じぶんのこと、しかのこらなくなる、これがデカルトの『われおもう、ゆえに、われあり』らしい。
これって、断捨離のまつろかな、ミニマリストのまつろかな、みんな、デカルトに、なりたかったんだ、カラダもいらないんだ、そうか、捨てるじぶん、なくすじぶん、だけのこればいいのか、なんか、たいじなものまで、なくしそう。
ものがあふれてる、ものに囲まれてる、状態はよくないのかな、整理というか、どこに何があるか、わかれば、それでいいのでは。好奇心おうせいならば、ものでも、なんでも、あふれるよ。好奇心のほうが、まさるとおもう、なくすより、捨てるより、デカルトより。だって、そのほうが、単純に、おもしろい。
この住宅は、ものがあふれる、といいように、つくってみた。そのほうが、生活感がでる。生活感だけが、ゆういつの、じぶんの、せかいを、しる方法だし、いまを、いきてる感じがする。
この木をみてるとき、きっと、あの木のことを、かんがえている。だれでも、よくあるとおもう、目のまえのものではなくて、他のもののことをかんがえていること。こころ、ここにあらず、状態のまま、ただ、ぼんやりと、目のまえのものを、みてる。
それは、集中力がない、などといわれそうだけど、きっと、脳が、こうそくで、目のまえのものと、ほかの何かを、むすびつけようと、しているにちがいない。それは、脳の暴走かもしれないが、しばし、その暴走に、つきあって、ぼんやりと、するのもわるくない。
だから、ぼんやりとできる場所、がひつよう。ただ、どこでも、いいわけではない。脳だって、ひとならぬ、場をみる。脳がぼんやりするいえ、っていいな。ひとではなく、脳がぼんやり。この住宅は、そんな、脳がぼんやりして、まったりしてくれたら、とおもう。
森のなかに、自然のなかに、すみたい、とつねひごろから、おもってるので、いま、都市にすんでる身としては、かんたんに、かいけつするならば、田舎へ、いけばいいのだが、あるいは、二拠点、多拠点とふやして、都市と田舎の、りょうほうにすめばいい、いっぱん的には、そうなるのだろうけれど、なにか、しっくりとこない。
田舎へ、拠点をふやしたところで、かいけつしないだろうと、おもってしまうのは、自然のなかで暮らす、多拠点で暮らす、ぎじ体験は、いくらでも、できるので、なんどか、トライしてみたけれど、ただたんに、自然の中に、拠点をかえればいい、というものでもなかった。
たぶん、もとめていたのは、ながれる時間への感覚、だったのかもしれない。なにをしていてもいい、寝ていても、食べていても、さんぽしていても、ボーっとしていても、たとえ、しごとをしていてもいい、ながれている時間が、自分ではどうしようもない、自分とはかんけいないところで勝手にながれてる、そんな感覚、じぶんでは操作できない、もうそれでいいじゃないか、とおもえる感覚。
どうしても、時間を管理できる、とおもってしまう。ただ、自然にたいしては、すなおに、自分では、どうしようもできない、そんな、どうしようもできないものに、囲まれれば、きっと、じぶんの時間感覚も、かわるだろう、という期待から。
こう書きながら、しっくりこなかったことが、整理されてくる。ならば、いまでも、ここでも、できるような気にもなる。
この部屋は、そんな、あたまを、整理する時間と場所を、ご主人のために、住宅内離れ、としてつくった。
キッチンのまえの窓をあけると、おとなりの木がみえる。さいきんは、さむいのでしないが、毎朝、窓をぜんかいにして、空気のいれかえをしながら、ながめていた。ただ、窓をあけなくても、窓ごしにはみえるから、葉っぱのいろの変化はかんじることができる、さいきんは赤茶いろ。
他の窓ごしには、うちのオリーブの木がみえる。いつもあおあおとしていて、葉っぱのいろに変化はないけど、成長がはやいな、といつもおもう。
両方とも、室内から木をみる、ということはおなじ、でも、かんじ方、いみがちがう。キッチンからみる木は、おとなりの木、だから、おとなりさんも毎日みてるだろうし、こちらも、みてる、かんじ。うちのオリーブの木も、また、ちがうおとなりさんが、毎日みてるだろうし、こちらは、みられてる、かんじ。
あたりまえだけど、あきらかに、ちがう。でも、この、あたりまえだけど、あきらかに、ちがうかんじを、つくるのが、空間づくり、だとおもう。この住宅は、たくさんの、あたりまえのちがい、をしこんでみた。
自然をかんじる、っていつも、ふしぎだとおもう。山や海にいけば、自然しかないから、自然をかんじるが、きっとそこに住めば、自然があるのが、あたりまえになり、だんだんと、自然をかんじなくなる。
都市部にいると、せっきょくてきに、緑をとりいれること、条例などもあり、パラパラと緑をみかける。パラパラの緑では、自然をかんじるまではいかないが、自然をせっきょくてきに、かんじよう、とする姿勢にはなる。
けっか、自然にかこまれて、住むより、都市部のパラパラの緑のなかで、くらしたほうが、自然を日々かんじるのでないかな。そんなことをかんがえて、パラパラの緑でも、パラパラの緑なりに、くふうをすると、どこでも、自然ゆたかにくらせるよね。
たまたま、偶然、そうなっただけ、べつの可能性は、あったし、いつまた、変化するか、わからない、としたら、たしかなもの、ってないな、と。
ものをつくるって、たしかなもの、をつくろうとする。ものをつくる仕事に、忠実になろうとすれば、あるいは、いいものをつくろうとすれば、たしかなものを、目指すことになる。それがないとなると。
逆に、たしかなものって、あるのか、とかんがえると、何がたしかなものなの、となる。
いずれも、仮に、かんがえているだけ、だけど、たしかなものって、何か、あいまいだな、とおもう。
きっと、そんなことが、根底に、あったのかもしれない。この住宅では、部屋の仕切りが、あいまいで、それが、要望だった。そう、ここでは、あいまいなことが、たしかなものだった。
けはいを感じるように、ひとは、何かのこんせきを、感じるのうりょくがある。これって、いつもおもうけれど、すばらしい、こと。もとあったもの、なくなっていくもの、ちっていくもの、に何かを感じることができる。たとえば、ちりゆく紅葉に、たとえば、しずみゆく太陽に、たとえば、かわりゆく季節に。きっと、そのとき、ひとは、じぶんのえんちょうとして、じぶんの一部として、あるいは分身として、そのものを感じている。
だから、きっと、逆もある。あたらしく、うまれゆくものにも、けはいをかんじる、ことができるはず。そんな、無意識とも、よべるようなもの、へのけはい、それをきたい、と言うのかもしれない。それもまた、ひとにとって、じぶんのえんちょうや、一部や、分身で、それを、カタチにしたい、といつもおもう。
この住宅では、でてくる言葉とは、まったく、かんけいがないところで、カタチが、きまっていった。それは、なにをきたいしているのか、ひとは、じぶんでは、わからないもので、それをカタチに、翻訳するやくめ、をしたけっか、そうなった。
なにかを感じるから、そこにいるのがわかる。そこにいないと、わからないことを、感じるから、そこにいる価値がある。価値があるとおもえるばしょは、そこだけでしか、感じることができないものがある。いずれも、感じるひとがひつようで、ひととばしょを、感じることがつなぎ、価値をつくる
建築のばあい、感じることは、ものをかいする。ものがどうあるかで、感じることがかわり、価値もかわる。すべてを、感じることに、かんげんさせることで、価値をみちびきだすことができる。
この住宅では、明るさを感じることが、価値になった。1階でも、陽のひかりがさしこみ、明るくくらせる、そんなふつうなことを、価値にした。それは、そんなふつうなことを、えられる環境、ではなかったから。
1階から空がみえるようにした。やったことは、それだけ。ものとして、2階のゆかと、やねをガラスにしただけ。1階のダイニングテーブルにすわり、空を感じることが、できるようにしただけで、この住宅に価値がうまれた。
あぁ、あとから、きづくことって、じぶんでは、なぜだか、理解できていなかったけど、ほかのことをしてるときに、たとえば、つぎのプロジェクト、たとえば、本をよんでいるとき、ふと、うかぶ。いったん、あたまからだして、それをカタチにして、ながめてみたから、きっと、きづくことになった。もし、カタチにしてなかったら、えいえんに、きづかない。
はじめから、そうしようと、してなかった。時間差があったから、ひとつつくって、また、つぎどうするか、だった。だから、この2棟の住宅に、共通点はない。しいていえば、外壁をおなじにしたくらい。ただ、ゆいいつ、玄関だけはむかいあわせ、にすることだけは、決めて、あいだに、通路をそうていした。あとは、まったく、共通点はいらないと。
そうしないと、おなじような住宅がならぶ、ふしぎな風景をつくってしまう。けっきょく、そのときは、きづかなかったけど、あとからおもう、おなじようなものにしたくない、ことをしたかったと。
つながり方には、4種類、せっするか、かさなるか、はなれてるか、ズレているか、がある。つながる、ということだから、最低、2つのものがある。4種類のうち、ただひとつだけ、かさなるだけが、同時に、あらたなものを生成する可能性がある。かさなった部分が、あらたなものになる可能性。ぎゃくに、かさなりからみれば、そこから2つのものが、生成される、ともいえる。
だから、2つのものの、つながり方をかんがえるより、かさなる部分をさきに、かんがえることで、2つのもの、さらには、ぜんたいの構成がみえてくる、とおもった。
それを、いまのプロジェクトにいかしながら、同時に、かこのプロジェクトを再解釈してみる。そうすると、じぶんのなかで、たくさんの、かさなる部分が、うまれた。
カラダとココロが、ばらばらに、気分はいいけど、カラダがつかれてるな、そのぎゃくも、ただ、つい、カラダとココロをべつに、してしまうが、行動に、ちゅうもくすると、カラダもココロもひとつ、行動してるか、してないか、じぶんからうごくか、いわれてうごくか、だけのような気がする。
きっと、行動してるとき、ふぐざつなバランスのなかで、けっか的に、うまくいくように、するだろう。だから、じぶんからうごこうとすれば、けっか的に、そのとき、いちばんいいものになる。ならば、時間をみかたにして、じぶんからうごくことに、たくさんの時間を、かけることができるじょうきょうを、つくりたいものだ。
そんなことをかんがえながら、手をうごしていると、ふくざつなからみあいが、解けて、視界がクリアになった。やっと、まとまりそうだ。おいしいものでもたべて、またあした。
いま、みているものは、きっと、1年後には、ない。いま、みているものは、いま、このときにあわせて、偶然そうなっただけ、かりに、1年前に、いま、みているものを、予測できても、いま、このときにあわせて、用意はできないだろうから、1年後にも、ないだろう。あたり前のことだけど、この偶然そうなっただけ、ということが大事だと、おもった。
偶然そうなっただけ、ならば、たまたま、そうなっただけで、ちがうものになる、可能性もあった。ならば、いま、みているものが、いつまでも同じ、でいる保障もなく、ちがうものに、いつかまた変化するかもしれない。
そう、だから、なにをつくっても、同じでいつづけることは、ないだろうから、絶対なものはないはず。すべては、変化する、ということになるが、そうすると、なにをつくっても、同じ、いみが無い、となりそうだが、なにをつくっても、変化する、という運動に、ちゃくもくすると、ものをつくることって、この運動を、かそくさせることで、そのときの燃料は、言葉、すなわち、いま、みているものが、偶然だと、絶対ではないと、わからせること、だとおもった。
だから、いまつくっているものは、時間の流れが、運動として、仕込まれていて、燃料となる言葉は、プランとかたちに変換して、はいちしている。
うまくできそうだと、おもうのは、カンだけど、そのカンは、いままでの経験から、くるのかな。ただ、経験では、たどりつかない、ようなことが、おこるほうが、おもしろい、ともおもう。だから、経験はあてにはならない、とおもうほうが、おもしろいかもしれない。
経験が、あてにはならない、としたら、どうするか。てきとうに、言葉を、放りこむしかない。それは、思いつくかぎりの、言葉をだし、ならべ、かたっぱしから、ためす。ためした結果は、経験をこえるだろう、とおもえた。
さらにいえば、思いつくかぎりの、言葉をだしたときに、すでに、経験からくるカンは、ふ必要で、むいみになる。その言葉におうじたことが、現実に、てんかいされる、のだから、カンをあてにして、うまくいくかいかないか、をかんがえる、必要がない。
この住宅では、そもそも、経験したことがない、ことばかりした。だから、それをするためには、思いつくかぎりの、必要な言葉をだし、ならべ、ためす、ための素をつくった。素は、ときには図面、ときには素材、ときには職人、ときには感情だった。
けっか、経験したことがないから、うまくやる、こともできなかったが、言葉からつくった素、がおもしろさと、完成度を、たんぽしてくれた。
みたいように、みているから、好きなようにみえる、こうみたいと、話しかけているように。でも、そこに、誰かが、こうだよ、これはどう、これがいいんじゃない、とか、ヨコヤリをいれる。ヨコヤリは、みたことがない、そうはみえなかった世界だった。そのとたん、いままで、みてみたい、とおもっていたものが、かわる、そっちのほうが、よかったと。
きっと、これが、りそうかな、とおもう、なにかをつくるときは。じぶんがヨコヤリのそんざいでいたい。
この住宅は、ヨコヤリをしてみた。リビングのまんなかに、まるみえの階段、その階段が、リビングを、3つのゾーンにわけて、空間はつながりながら、回遊でき、みんなすき勝手に、すごしている。それが2階からも、わかる。この空間のおかげで、なにかと、かおをあわせる、ようもないのに、話したくなる。空間が、なにをしたらいいのか、おしえてくれた。
サボり、っていけないこと、だけど、サボるときは、だいだい、大事なことを、しているときだから、ぎゃくに、大事なことがわかる。べつに、大したことをしてないときは、サボりにならないし。
大事なことは、変化につながること、だから、ひとは、変化がきらい、だから、サボる。ならば、サボるときにすることを、べつの大事なこと、にすれば、べつの大事なことは、おおいにはかどった。
そんなちょうしで、この住宅では、サボれる場所を、たくさん、つくって、あちこちで、サボれるようにした。
サボって、大事なことをする、って、うしろめたさ、とヤッた感が、ダブルでくるから、甘塩っぱいものを、食べてる感、けっこう、クセになるかも、おいしいかも。
なにかと、あいまいにしたい、のだが、建築の境界の話、なかなか、それがゆるされないから、なやむことも多い。いろいろな境界が、建築には、あるけれど、壁もそのひとつ。境界として、外壁をみれば、いくらでも、あいまいにはできるけれど、たとえば、うごくようにするとか、壁を厚くして、外でも内でもない場所をつくるとか、ただしかし、きちっと、境界はきめなくては、いけない。それによって、法令順守と事業担保がはかられる。それはあたり前に大事なこと。
そのうえで、境界をあいまいにしたいのは、ものごとは、揺れうごくでしょ、そんなに、キチッとしてないでしょ、それは建築もおなじ、バッファーゾーンのようなものがあり、そのあいだだったら、揺れうごいてもいい、とすると、建築の決めかたも、できあがる建築も、かわるだろう。あたり前である、前提がかわるのだから、などと妄想してみて、バッファーゾーンがあると、いいなとおもう。
なにかと決まっていることがおおいので、なるべく、決まっていることはせず、そうすると、決まっていることがあいまいになり、そのまま、あいまいなまま、決まらないかな、そんなことはないのに。でも、この住宅は、クライアントに理解があって、あいまいのまま、けっこうギリギリまで、すすめて、アドリブもおおかった。それがよいか、わるいか、は別にして、決めるということを、見直す、キッカケにはなった。
行きつけの呑み屋、をつくったり、いつも同じものを、かったりたべたり、かならず通る場所とか、べつに、それでなくてもいいはずなのに、変えずに、同じをくりかえす。それで、あんしん感はあるし、よけいなことを、かんがえなくても、すむからいいのかもしれないが、ほんとうに、そのままで、いいのか、とギモンにおもわない、のだろうか。
たぶん、おもっても、変えられない、のだろう。変えるすべを、しらない。そんなときは、人まかせにすればいいのに。あいては、まかされて、喜ぶ、とおもうし。
けっか、おもいつけば、いいけれど、そんなこと、自分では、おもいもつかない。さいきん、はじめた、パンづくり、むずかしくて、時間がかかると、おもっていたけれど、レンチンで、15分あれば、できる。そのやり方を、ぐうぜん、SNSでしった。しろうとは、レンチンでパン、なんてできるんだ、と新鮮だったけど、プロにしたら、かんたんなこと、なんだろうな。
たったひとつ、大事なものがあれば、それだけで、なっとくしてもらえるのでは、といつも、かんがえ、プレゼンする。いつも、そうやって、そのときどきで、ちがうけれど、決め手は、いつも、ようぼうの奥にあった。
たったひとつの部屋を、よぶんにつくったり、まったく、常識とは、ぎゃくのことをしたり、いちどは誰でも、おもいつくがやらないことを、やったりした。
ここでは、たったひとりになれる居場所を、いつでも、つながることができるところに、つくった。空間とのかんけいは、使用者とながめる人にわかれるが、使用者とながめる人とのかんけい性がなかったので、トビラをあけることで、つなげてみた。このことで、おこったことは、いままでの暮らしにはなかった、かぞくの時間が、ながれはじめたこと。
はっきりと、こうしよう、と決まるのは、だいたい、動きだしたあとだが、動きだすまえに、なんとなく、こうならないかな、とか、こうならないとイヤだな、とかは、決めてみる。けっこう、いつも、この決めてみる、でどうするかな、となる。
せけんでは、はやい方がよく、こうりつよく、が良いとされ、とりあえず、あいまいでも、はやく動け、となる。ひじょうに、自分みたいなタイプはこまる。はやく動くのは、いくらでもできるが、そのまえに、決めてみる、をしたい。それがないと、いくら早くても、まちがった方向にいきそうになる。
それを言うと、まちがったら、引きかえして、またやり直せばいい、その方がはやいと。ちがう、ちがう、またやり直しても、たぶん、またまちがうか、さいあく、まちがいを無いものにしてしまうかもしれない、早くやるために。けっきょく、最初に、決めてみる、をした方が、けっか、早いし、良いとおもうのだが。
などと書いたのは、いま、そういうじょうきょうだからで、もうちょっと、じかんを下さい、とだれかにつたえたい、気持ちのあらわれでした。
だいたい、あんぜんな方へ、かわらない方へ、いこうとする、本能だろうか。でも、かえるのが、スキだから、何ごとも、いまに定着しない、ようにする。けっきょく、いまいいのは、すぐに、あきるか、だめになる。何かをすこし、かえるぐらいで、ちょうどいい、といつも、おもう。
かといって、何年もおなじことを、し続けている。ふしぎだ。続けていることは、なかなか、うまくいかないこと。続けるコツは、うまくやらないこと、だったりして。
建築も、なかなか、うまくできない、もっと何とか、とおもうから、続いているのだろう。きっと、それがなかったら、うまれないことばかり。この画像の住宅は、いちだん、ギアチェンジしてみた。こまかいことの、精度をあげた。とたんに、うまくできないことばかり、になったけど、その次は、この精度がスタンダード、になって、また、ギアチェンジした。
境界について、きになることが、よくあるなとおもった。きっと、さかいとか、別々とか、はなれているとか、違いがはっきりしている、ことになにか、ていこう、があるのかもしれない。できるだけ、さかいをつくらずに、別々にならずに、はなれずに、できないものか、とかんがえる傾向があるかもしれない。
なに事にも、さかいはある。建築にもある。ただ、そのさかいは、たまたま偶然、そうなっただけとか、はじめからあったとか、便宜上そうなっただけとか、一時的とか、かならずしも、それである必要がなかったり、それだと決めつけなくても、なんとかなることもありそうな気がする。
そうおもうと、さかいを曖昧にしたい、となる。建築で、いちばん影響をうけるさかいは、敷地のさかい、だろう。このさかいだけは、なにがあっても、越えることができないし、曖昧にもできない。
ただ、さかいに、あらがいたい、それが、もしかしたら、設計するうえで、いちばんむすがしく、かつ、いろいろなことに、よい影響を、あたえること、かもしれないと、いまかんがえている。
前に、画像のように、建物の四周と塀とのあいだに、デッキを敷いた。デッキにより、室内空間が、敷地いっぱいまで広がり、その広がりは、敷地の外まで、拡張する意識、をつくりだす、とかんがえた。ただ、デッキによって、敷地のさかい、をよけい強調するけっか、にもなった。
いまは、さかいを別のしゅほうで、曖昧にすることを、かんがえている。
なんとなく、気になる建築や空間を、おもいうかべながら、あれって、かたちだけ残して、あとはぜんぶ替えてみたら、どうなるのかな、とか、平面のプランはおなじだけど、かべの高さをかえてみると、とか、いちぶだけ、大きさをかえてみたら、どうなるかなど、あれこれ、妄想してみる。
そうすると、やっぱり、もとがいい、とか、あれっ、もしかして、なんてことを、また連想する。それで、じっさいに、かたちにしたら、オマージュとか、リスペクトとか、になるのだろうか。
ただ、そうかんがえると、無意識に、なにかしらに、影響をうけているから、もとネタはわからないが、いままでつくったものは、もしかしたら、すべてが、オマージュとか、リスペクトとか、になるのかもしれない。
それは、たくさんの建築にかんすることを、みききしてきたからで、いまこうして着想していることが、なにとつながるか、たどってみると、あんがい、面白いはっけんがあった。あした、その本をさがして、よんでみよう。
カタがあると、それをだれかがくずし、またカタができる、そして、また、だれかがくずす。この一連のながれのなかで、どこに、いちばん、興味があるだろうか、とおもった。
はじめのカタがあること、そのくずし方、くずした後のカタのつくり方、また同じくずし方をするのか、など、ちゃくもくする点は、いろいろと、かんがえることができる。
きっと、自分は、また同じくずし方をするのか、に興味がある。カタなど、なにか主流のものがあれば、それとは真逆のものが、うまれる。そのときの、うまれ方、すなわち、カタのくずし方は、カタを相対化する方法をとる。
歴史はくりかえす、という。相対化する方法も、歴史をみればわかる。だから、また同じくずし方をするだろうことも予想はできる。しかし、それが、いつはじまり、だれがはじめて、どこではじまる、のかは、後になって、歴史になって、わかることで、同時代的には、なかなか、わからないこと、だとおもう。
ということは、また同じくずし方をするのか、に興味をもち、観察することは、いまをいきる、ことにつながる、とおもうし、そうすれば、いまがたいせつ、になる。いちばんは、いまかな、とおもう、きょうこのごろ。
見なれない、だから、すぐに理解できない、ふしぎなものと、見なれてはいるけれど、なにかが違う、とかんじるもの、どちらにも興味があり、じっさいに、りょうほうとも、この目で見てみたくなる。
では、じっさいに、自分がつくるとき、どちらのものをつくりたい、とおもうか。
見なれてはいるけれど、なにかが違うものは、いままであったものを、進化、あるいは、より洗練させた、ものだろう。見なれない、すぐに理解できないものは、いままでと、アプローチがちがう、あるいは、そもそも出発点がちがう、ものだろう。
いつもおもう、いままでに見たことがないもの、をつくりたい、と。だから、見なれない、すぐに理解できないもの、をつくることにひかれる。きっと、そういものは、画像では、すぐに、理解はできないけれど、じっさいに見れば、すぐに、なっとくするものだろう。
どんな形にしようかな、と最初は、かんがえていたのに、いつのまにか、どうやって形にしようかな、とかんがえている。
条件や要望を、形にしていくときに、ばくぜんと、かんがえているあいだは、手がかりがおおすぎて、まよい、形をむげんの海から、引っ張ってくるかんじ。そのうち、どうやって形にしようかな、と自然にかんがえているときには、あるていど、方向性がしぼれているしょうこ。
どうやって、って、まほうのことば、だとおもう。そうかんがえた瞬間に、形にむかって、すすみだし、形になる。
この階段は、ひかりが差しこむ、ところにある。だから、ひかりをさえぎりたくない。かといって、ガラスの階段では、ひかりが差しこむところに、あるいみがない。この階段があることで、ひかりの粒がみえればいい、これで、形のどうやって、のぶぶんができた。
あんがい、どうやってのぶぶんは、そのものとは、直接かんけいない、ところからふってくる。
まいにち、つづけて、それでいて、変化していくようなこと、きっと、暮らしはそういうものだ。
暮らしがおさまる器として、と住宅をかんがえるひとも、いるだろう。それで、いいとおもう。暮らし、という日常的につかわれる言葉で、住宅を表現することは、ひとつ、大切なこと、だとおもう。
ちがう言いかたをすれば、暮らし、という誰にでも、わかる言葉で、住宅をかたることの大切さ、住宅をかたることができるひとの大切さがある。
いっぽうで、ひとがいれば、自然と暮らしはおこる。大切なのは、そこに、ひとがどのようにいるか。暮らしは、たまたまそうなっただけ、として、住宅は、たんに、ひとがいる場所、にすぎない。
これは、もともと、暮らしは、その場所にあったのであり、たまたま、そこにきたひとと、むすびついただけ。暮らしは、つくりだすものではなく、環境にさゆうされる、都市の暮らし、山の暮らし、といったぐあいに。だから、ひとが歳をとるように、ひととむすびついた暮らしも、まいにち、変化していく。
このように、住宅と暮らし、を切り離してみると、もっと、根っこの、いま、そこに、ひとがいることを、形にする必要がある。それが、住宅のほんらいの姿、だとおもう。
つながる、ってキョリの遠近とは、関係ないな、と電車にのりながら、いつも、おもう。となりの席のひとのこと、ではなくて、となりの電車のひとのこと。並走する電車のひとは、ちかいけど、まったく、つながることがないひと。たぶん、二度とあうこともない、かもしれない、あたりまえだけど。どんなに、キョリがちかくても、ふれることもできない、レールがまじわることがないから。
この関係性に、ひとてま、加えたら、たとえば、まじわることができれば、けっこう、りそう的な関係、になるかもしれない、とおもった。
ここでは、住宅が2棟、親族どうしで、ならんでいる。あいだに、きょうつうの、通路をもうけた。電車でいえば、同じレールをつかっている。それ以外は、まったくべつのもの、まったくべつの電車。ただ、ときどき、ぐうぜん、であうだけ、ふれることもできる、かわすこともできる。それが、お互いにとって、ここでは、ほどよいキョリかな、とおもった。
建築みたいに、おおきくて、うごかないもの、に偶然性をおこすのは、むずかしい、と書こうとして、そんなこともないか、とおもいなおした。
建築ないぶに、偶然なにかが、おこるようにすることは、いくらでも、かんがえることはできる。が、建築じたいに偶然性を、まとうことが、できるだろうか。
すぐに、うごかないし、おおきいし、偶然性をまとうのは、むりかな、とおもった。偶然性をまとうとは、変化すること、例えば、太陽のひかりで、みえ方がかわるとか、になるのかな、それならば、とおもい、偶然もありうるか、とおもいなおした。
ただ、形がかわるようなことは、ないよな、やっぱり、うごかないものだし、ここでの偶然性は、形にかんして、言いたかった。可変って、建築にとって、やっかいかなこと。可変する機構をもりこむと、建築ではなく、機械になり、機械というメタファーをもちだしてくるのは、ふるくさい。
などと、ダラダラとかんがえながら、可変する、可動間仕切りを、よくつかっているな、すきなんだな、とおもった。
斜めがすきじゃない、まっすぐで、垂直で、四角がすき、だといつもスケッチしながら、おもう。だからか、坂道もすきじゃない、水平線がすき、地平線がすき。スロープよりも、階段がすき。円も、丸も、すきじゃない。べつに、こじんのすききらいなど、どうでもいいけれど、やっぱり、いままで、つくったものには、振り返ると、えいきょうがあるようだ。
だから、斜めや円、丸などは、いしきして、つかうようにしている。いしきするとは、なにか、意味をもたせたり、アクセントにしたり、そこをみて、というポイントにしたり。
ただ、いきなり、斜めや円、丸などをつかっても、こうかがないから、まっすぐや垂直、四角と対比させてつかう。この対比がうむこうかを、かんがえるのが、デザインのひとつかな、とおもう。
べつに、そこまでする必要は、ないんだけど、とおもうときって、余計なことを、してると、かんがえているんだな、きっと。だけど、その余計なことが、ほんらい、じぶんがやりたかったこと、といまになって、気づく。
たいがい、余計なことは、オーダーには、ないこと。勝手におもいつき、勝手にやること。そのことで、1円ももらえない。これって、いつもおもう、経営者として、しっかくだな、と。
この住宅では、内装仕上げに、よくある下地材をつかった。どうやって、みせるか、がもんだい。ただ、つかうだけでは、芸がない。色をぬって、ごまかしたくもない、その予算もない。
板をつなぐ、ことにした。そのつなぎ方を、デザインする。そうすることで、つかう板が、なにかは、関係なくなる。
どちらにせよ、板をはることは同じ、つなぐことがおこるのも同じ、だから、つなぎ方のデザインは、余計なことになるかもしれないが、つなぎ方をデザインすることで、つかう板、つかう素材、素材の良し悪しが、どうでもよくなる、素材にいぞんしなくなる。これが、やりたかったこと、だった。
じつは、このことで、もっと余計なことをしてる。のちに、大工さんから、ゆめにうなされた、といわれた。画像には、うつらない、実物をみれば、すぐわかること、いままで、じふんも、ほかではみたことがないこと、ほんとうは、これの方が、やりたかったこと、かもしれない。
あちこち、みてしまうのは、集中力がないしょうこ、おちつきがない、とよくいわれたものだった。ものは、注意をひくために、できている、これをアフォーダンス、という。そもそも、興味をひかないものは、そこにないのと同じ、だから、アフォーダンスは、けっして、わるいことではなく、だから、おちつきがない、こともわるくない、とおもう。
この家では、みんな、行動がバラバラ、おもいおもいに、すごしていた。だから、いる場所がちがっても、お互いどこかで、つながってる感がほしかった。
なにげない日常の中で、なれ親しんでも、つながり続けるためには、興味をひきつけあう位置かんけいがひつようだ。チラッとみえる、かんけいは、お互いをじゃましない。
画像は、キッチンでの、奥さん目線。2階のひと、奥のひと、庭のひと、この家のひとの行動がチラみできる。きっと、チラみだから、なんか気になる、なんか興味がわく、そんなかんけいだらけの家が、いいとおもう。
どうでもいい、どっちつかず、あいまい、はネガティブなことで、なるべく、さけたいとおもうかもしれない。こうりつとか、はやくとか、を求めるときは、はいじょされる。
ただ、さいきん、このあいまいとか、どっちつかずの領域も、ひとつのかたち、になるとおもっている。
この住宅では、可動の間仕切りで、領域をつくるだけ。その領域が、そのときの必要におうじて、ついたり、わかれたりして、領域の大きさがかわる。
領域がきまっていないことは、こうりつの観点からいえば、非こうりつに、つながる。あらかじめ、きめられた、限定した領域の中で、うごくほうが、こうりつを追求しやすいから。
ただ、この住宅では、あいまいな領域があるから、いろいろな暮らしの可能性、それは、この住宅をじゅうぶんにいかしきる、という点で、こうりつより勝る、とかんがえた。
色がついているものと、ついていないもの、をくらべると、色がついている分だけ、ひとつ特長がふえて、いいようにおもう反面、色がついていない、透明だから、さまざまなものを、そのまま鮮明に、映しだすことができるよさが、あるともおもう、ガラスのはなし。
ガラスを、色つきか、透明か、さいきんのなやみ、大したことがないなやみだけど、けっこうな時間をかんがえている。色つきだと、とうぜん、その色がガラスごしにつくので、鮮明にはみえないが、ガラスの微細な凹凸を、色が増長してくれる。ぎゃくに、透明だと、色による作用がないから、鮮明にみえ、ガラス特有の映り込みが、よりはっきりみえる。
この住宅では、透明にしてみた。日々の暮らしで、そのつどかわる色を、映すことで、さまざまな、暮らしの重なりが、壁の模様になる。それは、この住宅特有の、色になる。
きょうかい線、って、いろいろなものにあるけれど、さいきん、おもうのは、ちょっとでもはみ出したら、許されない感じが、つよい。建築のきょうかい線は、敷地のまわりにあり、たしかに、ぜったいに越えてはならないが、枝や葉が、空中を越えているのは、よく目にする。
それでいいとは、いわないが、うちもおとなりに越えているので、敷地のきょうかいが厳密なぶん、それぐらいのゆるさがあっても、いいような気もする、おとなりのかた、すみません。
いかに、きょうかいを厳密にまもりつつも、空中のような、いつでも、引きかえすことができるかたちで、越えていくか、って、実際にやるかどうかは、べつにして、一度はかんがえてみたほうが、いいことだとおもう、意識だけでも。
あんがい、なぜ、きょかいをまもるのか、の意味がわかり、そうすると、いままでと違った、きょうかいのまもり方ができるかもしれない。この住宅のように、おとなりの人と、かくしんはん的につながろうと、するかもしれない。
ちょっとでも多く、という心理、なるほど、よくわかるから、ロフトなるものをかんがえてみる。そもそも、あまりの空間をどうりようしようか、という発想のたまもの、だから、そこは、すなおに、あまりの空間さがしをしてみる。
ゆかした、やねうら、階段のおどりば、あとは、たかいところ、人がいきたがらない、ような、あまりはたくさんある。いっぱん的には、そのあたりが、ロフトや収納になる。
あまりの空間だから、いとてきに、空間をつくるのはNGらしい。あくまでも、空間のゆうこうりよう、ということらしい。だから、空間さがし、宝さがしみたいだ。
ふとおもう、宝さがしする空間は、はじめから存在していたのか?いや、つくったはずだ。ならば、ロフトを、さきにつくってから、空間のなかにうめこんでしまい、宝あったどぉ、なんて、やらせ?をしてもいいだろうか??
こどものころは、外からかえると、勝手口からあがり、そこには台所があり、そこでなにかをしてる母親に、ただいま、とこえをかけた。むかしは、なんでも、手づくりだったから、つくるところを、みているのが、おもしろかった。
いまのほうが、家事は、だいぶ楽にはなっただろう。せんたくものは、干さなくてもいいし、レンチンで、おいしいものはたべれるし、ロボットが、そうじしてくれる。
もはやキッチンも、作業するところではなく、コミニケーションするところ、にかわった。家族といっしょにすごしながら、家事をする。もしかしたら、ゆっくりと、家族がすごせる場所がキッチン、ってのもわるくない。
家の外で、家族といっしょにすごすこと以外のことは、全部、みたすことができる。だから、家の中にいる目的は、家族といっしょにすごすことだけ。
この家には、コミニケーションするために、壁が、ひつようとされなかった。風呂とトイレ以外、壁がなくても、暮らせるんだ、とわかると、おもしろいことに、家の外と中のさかいの壁も、パブリックとプライベートのさかいも、なしにできそうな気になる。
建築が複数あれば、関係がうまれる。関係がうまれれば、にぎわいができる可能性がある。だから、建築によって関係がうまれると、にぎあいをつくるためには、どうすれば、いいのか、をかんがえるようにしている。
よくあるのは、人のアクティビティを、建築同士の関係性に、からめること。複数ではなくても、例えば、建築によってつくられた、アトリウムなどの、大空間でもおなじだが、場所があり、人がいれば、かならず勝手に、あるいは、そこになにか、イベントのようなものをたすことで、にぎわいはできるだろう、というようなかんがえ。りくつで、人のことをかんがえ、あとは任せっぱなし、のじょうたい。
それでは、にぎわいはできないだろう。それで、にぎわうのであれば、せまい、路地の、呑み屋に人はあつまらない。
きっと、雰囲気だと、おもう。人がにぎわう雰囲気。それって、新規の建築計画が、いちばん苦手、とするところ、だとおもう。そこに、模範解答はなく、正解はなく、読めない。人のことを読めない、のとおなじ。
だから、ここでは、人のアクティビティを、建築同士の関係性にからめているが、建築が先ではなくて、人のアクティビティ、すなわち、人のからまり方を先にきめてから、建築をきめた。
人がからまり、にぎわうためには、その敷地の、どの場所に、どれくらいの形と広さが、あればいいのか。けつろんは、スープの冷めない距離感だった。それは、内部の部屋の構成にも、影響をあたえた。
光のつぶ、というけれど、光がつぶで、みえるはずがない、とおもうが。
こんな話をきいたことがある、むかしは、雨つぶの存在が、みえなかった。むかしの西洋絵画には、雨がえがかれていない、地面はぬれているのに、というのだ。すなわち、それは当時のヒトには、雨つぶが、みえなかった。しかし、広重が線で、雨を表現したことで、雨つぶの存在にきづき、みえるようになった、というのだ。
真偽はわからないが、いままで、表現できなかったものが、表現できるようになると、それまで、きづかなかったものに、きづくようにはなるだろう。だから、もしかしたら、まだ、光のつぶを、表現できていないから、光のつぶが、みえないのかもしれない。
ここでは、階段をりようして、光をつぶで、とらえようとした。階段の段板と踊り場の床に、無数の穴をあけた。その穴をとおして、ふりそそぐ光は、無数の穴の輪郭を鮮明にし、つぶ状になる、とかんがえた。
じぶんが10年以上まえに、やったことを、いまだれかがやっていると、それはつかい古されたものか、それが当たり前になったのか、それとも、けっしてそのようなことは、ないとはおもうが、じぶんが早かったのか、などとかんがえる。
いずれにせよ、いま他のだれかがやっているのだから、それをいま、またじぶんが、やってもいいだろう、というおもいと、一度やり、いま他のヒトがやっているのだから、もうやる必要がない、ヒトとおなじことはしない、というおもいの、2つがうかぶ。
楽なのは、またやってもいいだろうだ。まえにやっているから、かんたんにできるし、失敗がない、それでいて、いっていの評価はもらえる。ただ、それだと、じぶんが満足できないだろう。いや、しごとだからと、割り切って、失敗がない、のがせいかいかもしれない。
10年以上まえのときも、ヒトとおなじことはしない、としてやったけっか、失敗しなかった。はじめてだから、しんちょうにもなり、いまだにきれいにのこっている。
さっきまで、あたまのなかを、グルグルとめぐっていたけれど、こうして書きながら、せいりされた。やっぱり、ヒトとおなじことはしない。そうしないと、このさき10年ごにこうかいしそうだ。
おおきなものに、包まれる感じは、あんしんする。包まれるものにもよるけど、おおきなものは、ときにはヒトかもしれない。あんしんしていられるヒトは、包むのがうまい。
包まれるあんしん感は、あんぜん地帯にもなる。ヒトにとって、あんぜん地帯はひつようで、その場所は日常のなかにあったほうがいい。
家って、あんぜん地帯になりえるもの。へやにいると、その包まれ感があんしんする。だから、この家では、その包まれ感をみた目で感じてもらうために、家のかたちのなかに、家のかたちをつくった。
いまいる空間を、見た目で感じてもらうことで、いまいる空間がわかる。あんしん感のみなもとは、きっと、このわかる感覚、ヒトもわかりやすいほうがあんしんするでしょ。
大事なものは、捨てられない。だから、いっぱいものが、たまるのかもしれない。みてると、たまるものは、行き先ふめいのものだ。ものがかえっていく所が、きまっていれば、たまらない。たまるというのは、目にみえて、あふれているからで、おさまっていれば、たまっているようには、みえない。
おさめ方がいいと、大事なものは、またちがった価値をうむ。大事なものは、ただあるだけよりは、自分とつながったもの、でいてほしい。
その木は、クライアントのお父さんが、なくなったときに、自然と道路ぎわに、生えてきたらしい。だから、のこしたい、それが最初の希望だった。そのまま道路ぎわより、きちんとおさまる場所をつくり、どこからでも、みえるようにした。
おさまる場所を、つくることじたいが、大事なものとつながることだから、あふれていてもいいものは、もしかしたら、なくてもいいものかもしれない。
昼のかおと、夜のかおがあると、なんとなく、どちらがほんと、なんか疑わしい、などとなるかもしれない。どちらもほんとで、どちらがいいか、わるいかはなく、二面性があっていい、とおもうが、ハッキリしないものには、無意識に、しろくろをハッキリさせたい、となるから、じぶんにとって、都合のいいほうをしんじるようになる。
二面性は、いつも意識する。ふたつの間をいったりきたりしながら、片方をみると、よーくみえるものがあるから、それがなにかのヒントになる。
建築にも、昼のかおと、夜のかおがある。昼ははくじつのもと、すべてをさらけ出す。夜はそうさできる。夜は都合のいいところだけを、みせることができる。だから、昼のかおと、夜のかおをくらべて、変化しているところが、かくしたいところ、すなわち、その建築にとって、いちばんみせたくないところか、もしかしたら、いちばん重要なところ、かもしれない。
それができても、できなくても、たいしてかわりがないのに、やろうとすることは、気がつかないうちに起こりそう。たいがい、そういうときは、やること自体がいい、とされてきたことだから、そのことにギモンを持たないし、持てない。
へやはヒトがたまるところだけど、けっして滞在するところではないこともある。ヒトが通っていくところに、ひっかかるモノがあり、そこにヒトがたまる。しかし、それは一時的であり、またヒトはうごいていく。
そのくり返しでへやが成り立つならば、ヒトは滞在せずに、たまりながら、また次へ、うごいていく。このばあい、へやは廊下のようであり、ならば、廊下をめぐらせてから、その廊下をへやにすることを考えてみた。
はじめから、へやをつくることが当たり前だから、それにたいして、ギモンを持たないし、持てない。しかし、へやイコール建築ではないので、へや以外のところをプランニングすることで、へやをつくりだす試みをしてみた。
こわいもの見たさ、高いところがこわいのに、高いところにいきたくなる。不思議なもので、高いところから、上を見あげたくなる。きっと、好奇心が、こわさにかつのだろう。
四層吹き抜けの、らせん階段をつくったら、ぐるぐると上を見上げながら、のぼるかな、と想像して、計画してみた。らせん階段は、いちばんコンパクトな階段、だから、省スペースのためにもいい。
すける段板は、最上階からのひかりを、拡散させながら、1階までとどかせるため、あと、上を見上げたときに、先まで見せるため。らせん階段は、ふつうの階段より、視線が上にいきやすく、上へのいしきがつよくなる。だから、好奇心をそそるしかけとしても、すける段板はいい。
階段をのぼることに、なにか他のことをたすことで、ひとの動きに、変化をもたらす。その変化は、空間の感じ方に、影響をあたえ、好奇心を刺激する。階段が、単なるのぼり下りのそうち、ではなくなる。
かわってしまうことに、抵抗があるのは、としのせいかな。ただ、むかしから、そうだったような気もする。ものはなんでも、最初はあたらしくて、だんだん古くなっていく。できれば、古くなってほしくないとおもってしまう。だんだんあたらしくなることがあれば、それがいいけれど。だから、なんとか、古くならないようにしようとする。でも、どうしても、古くなるから、古くてもいい、もっというと、古くなるほどに新鮮、という矛盾するようなことが、できないかなとおもってしまう。
古くなるほどに新鮮なさまは、年月をへてもかわらないのではなくて、年月をへてかわることによって、最初とはちがうものになり、それがあたしいみえ方になる、のだろうと考えた。
そこで、年月をへてかわる材料として、木をえらんだ。木を素地のままで、室内につかうと、くちはてることなく、焼けたり、変色して、のこりやすくなる。木の素地のままだから、焼けや変色がめだつが、それがかわったあたらしいみえ方、になるというストーリーをえがいてみた。
何十年後、生きているかわからないが、かわったところをみてみたい、いまが新鮮か、と。
その場所にたったとたんに、なんかスイッチがはいったように、急になにかをしだしたり、考えたり、おもったり、することはないだろうか。それがいいことでも、わるいことでも、なんでだろうとおもう。
美術館には、ひとの評判より、たんにおもしろそうだな、という理由だけでいく。たいがい、ウイークデイで、すいていて、人もあまりいなさそうな時間にいく。しずかにみたいのと、逆走するので。いちばん最初に出口までいき、全体をパッとみて、みたいところだけに、時間をかける。そうしないと、途中であきてしまう。人がいないと、逆走しやすくていい。そんなことするの美術館だけ、美術館だけのうごき。
きっと、うごきって、場所できまる、とおもった。広いところへいけば、のびのび、自由にするだろうし、狭いところへいけば、うごきが自然と制限される。ならば、細長いところへいけば、どうなるか。
細長い通路をとおって、家につく、そういう土地のかたち。この細長い通路をとおるとき、どうするか、自然と、視線は家にむきそう。きっと、この家で、いちばん最初にみえる部分が、いちばん時間をかけて、みるところになる。なにをみるか、夜ならば灯りかな。
窓の灯りが、この家のかたちになる。細長い通路と窓だけが対峙する。そのとき、昼の家のかたちはない。窓の灯りに、なにをみるか、なにがみえるか、なにをみたいか、それがこの家のかちになる、とおもった。
やわらかくて、かたいもの、そんなものはあるはずがないのに、言葉ではいえてしまう。壁もそうかもしれない。かたくて動かないから、壁を困難や問題にたとえたりする。でも、困難や問題も、ずっと変化しないわけではないから、壁もどこかで、やわらかくて、動くもの、とひそかにおもっていたりする。
じっさいに、壁が動いたらたのしいな、忍者やしきじゃないけれど、壁が反転したら、べつのへやがあって、そこには金銀ざいほうとか、なんかあったりして、ぬけ道があったりして、そう動く壁って、いまの暮らしにないものがでてくるにちがいない、とおもえる。
だから、将来がわからないとき、壁は固定しないで、動かしてしまおうと考える。壁があつくなれば、ものがはいる家具になる。家具ならば、自由に動かしてもいい。ときにふさげば壁になる。動く壁は、空間も将来も、なにも固定しない。なにも固定しないから、やわらかい壁なのである。
あたり前のことのようにみえても、しらないところで、いろいろ工夫しているのがプロかな、とおもう。たとえば、おすしのにぎり方にも、しらないところで、とうぜん工夫があるだろうし、なにげない動作にすべていみがあり、目のまえにでてきたおすしは、同じようにみえてもみなちがうし、そのちがいが味にでるとおもう。
窓をつければ、よほどとなりがすぐ建物でなければ、陽ははいってくる。ただ窓って、なんのために必要かな、っておもう。べつになくてもいいか、と考えると、いや必要だとおもう。では、陽がはいれば、それでいいか、と。
さいきんは、窓があったら、空がみたいとおもう。きっと、空がみえると、室内が気持ちよく感じるのではないかな。なぜ?きっと、空と室内をくらべるから。もちろん、空のほうがキレイだけど、空とくらべることで、室内のちょっとよいところをさがしたり、あるいは、ちょっと片づけしてよくしたり、なんてことがおこるような気がする。気持ちいいものをみると、自分もなんかしたくなるものだとおもう。
晴れだけでなく、くもり、ゆきでも、またちがった空にであえば、こちらの気分もかわるし、室内もかわる。これは窓だけができる暮らしのなかのはなし。そのために、となりの屋根のうえに、窓いっぱいの空をつかまえた。
少ないことはいいことだ、少ないことは退屈だ、きっと両方ともあるのだとおもう。よく、少なくすることはいいことだと、ミニマリストにあこがれる人もおおいけれど、できやしない、好きなものがたくさんあるからしかたない。それに、少なくするのは余分なもので、大切なものは少なくしてはいけないし、むしろ、ふやしたい。だから、バランスなんだと、少なくできない自分をいつもなぐさめている。
できるだけ部材は少なくしたい、できれば壁から板だけがでているような階段にしたい、と最初はおもった。ただ、それだと、いくら鉄をつかってもできなかった。ならば最低限、ほそい丸棒で上下の板をつなけば、そこで計算して丸棒の本数をだした。
ほんとは、たての丸棒と丸棒をつなぐように、間にななめの丸棒が必要とされたけど、つくって、いざ現場に設置してから、なくても大丈夫、ない方がきれい、だとおもいとった。
計算してふやし、現物をみて少なくした。いいことと退屈の差は、ほんとうは紙一重で、そこのせまい巾での判断に、少ないはもはや関係がないこと。少ないかおおいかなんて、けっきょく、どうでもいいことなんだとおもった。
ないものは、自分でつくりたくなるもので、あるとき味噌がきれて、これってつくれないかな、とおもった。ただ、おもっただけで、まあそんなことを言っても、とおもいながら、いつもたべている味噌をそのときはまた買った。
ところがしばらくして、知人が自分で味噌をつくっているときいた。せっかくだから、体験してみたい、でもいつもの味噌になれ親しんでるからどうしよう、大概こういうとき、つくることにしてる。コーヒー豆もそう、自分で焙煎してみた、コーヒー好きとしては体験してみたい。
つくりたいのと、あと既製品はいやだ、というおもいがあり、つくれるのならば自分の手で、身の回りのものは、なんでもつくたい。漆のお椀も自分でデザインしてつくった。
ここにあう換気扇がなかった。せっかくの特注キッチンだから、換気扇もあわせたい。ただ、換気扇にはスポットライトを仕込みたいし、仕上げもゼブラ調の木目、形も、などとやってると、もう自分でデザインして、つくるしかない。それから、換気扇は自分でデザインしてつくることがスタンダードになった、味噌も。
リバーシブルとが、一粒で二度おいしいとか、反転できるとか、そういったものによわく、すき。効率がいいからとか、お得だからだけではなくて、ひとつのことに対して、二面性があることが面白いとおもう。
何でもひとつではないと普段からおもっている。答えはひとつではないとおもえば、いろいろなことができる楽しさがあるはず、そこが面白いとおもう。
コンパンクに暮らしたいとおもうときがある。十分な広さがとれないとき、でも暮らしは充実させたい。あと、とうぜん広さには限界があるけれど、人は欲ばりだったりして、あれもこれもとなる。
そんなとき、よくやることは壁を固定しないこと。壁を固定してしまうと、そこでひとつに限定されてしまう。壁をなくすこともできるが、最低限の壁が必要なときもある。壁を固定しないで可動させる。たったそれだけのことで、同じ場所でいろいろなことができるようになる。
壁を固定しないことで、とじこもっていた人の動きが流れでる。そのとき、流れでた先でいろいろな科学反応がおこればいいなとおもうし、それがその家だけでおこるイベントになるはず。きっとそれはその家の人にとって、よかったな、とおもうことにぜったいになる。
好きな形ってだれにでもあるでしょう。こどものころ、らくがき帳にずっと渦まき模様をかいていた記憶がある。なぜかいていたかは覚えていないけれども、大人になった今ではかきたいとも思わないから、きっとテレビかなにかでみて、それをマネしていたのかもしれない。
大人になったら、こんどは三角形をよくかく、屋根の形として。屋根の形はなんでもよくて、半円でも、フラットでもいいのに、三角形にしたくなる。木造の屋根としては、三角形が一番おさまりがいいから、それはそれでいいのだが、別に三角形でなくてもいいのだから、ちょっとそれにこだわる理由をかんがえるときもある。でも、自分のことながら、よくわからない。
ただ、2階の天井だけは意識して三角形にする。屋根の三角形の形を天井にも表して、いまいる場所は屋根に近い、すなわち、空に近いですよ、と思わせたい。
いまいる場所はどういうところなのかを形で表すことは大切で、とくに家はこころの安全地帯なようなものだから、自分がいたい場所といまいる場所を意識しないでも合わせることができるのが重要、安心感が生まれる。そのための形、そのための三角形ということです。
なるべく手ぶらで歩くのが好きで、携帯だけあればいい。どうしても携帯以外で必要なものがあるとき、秋から春にかけてはジャケットやコートがカバンがわりになる。
とにかくバラバラと何かを持ち歩くのが嫌い、なるべくまとめて少なくするか、目立たないようにして存在を消すか、別のものに置き換えて全く別の何かに見せたい。
空間の中でいつも心がけているのは、天井をスッキリさせること。天井には何も設けないか、最低限の小さな照明だけと決めている。頭の上にごちゃごちゃあると落ち着かないし、空間が煩雑にみえる。その分、壁にものが移動してくるが、壁には元々いろいろなもの、たとえば、家具などがくるから、うまく処理すれば目立たず、むしろ特徴にすることもできる。
壁に取り付ける予定だったものは、スピーカー、エアコンの吹き出し口、給気口、照明器具だった。それぞれバラバラの形や色をしている。そのまま取り付けては機能的かもしれないが、煩雑な壁がただ出現するだけ、何かできないか。
共通なのはすべて「穴」だということ。穴があればそこに仕込めばいい。穴がたくさんあっても、要素は壁面と穴だけになり、煩雑さを避けることができ、うまくみせれば、特徴的な壁になる。天井はスッキリ、壁には穴があるだけ、空間に手ぶらの良さが生まれる。
そもそも暮らしは煩雑さとのせめぎ合い、人間が煩雑な存在なのだから仕方がない。だから、その煩雑さをうまく使って、暮らし自体を面白くしたいといつも思う。
せまいより広い方がいいに決まってる。すべてを広くできれば一番いい。ただ、広さには限界がある。だから、どこを広くして、どこをせまくするかもデザインのうち。広いリビングがほしいとの話はよくあり、できるだけ、それにこたえるようにしている。広いという表現は曖昧だから、それをどうあつかうか。
領地の奪い合いではないけれど、極端に差がつけば広いと感じるのではないかと思った。広さには限界があり感覚的だから、数値で置き換えても意味がなく、比較の中で広さを感じてもらうのが一番わかりやすい。
リビングの横に広さを比較できる小さいものをつくった。それは本来は大きくしたいが、小さくても事足りるものがいいと思い、小さい浴室にした。浴室が小さい分、となりのリビングが広くなっているということが視覚的にも、また頭でも理解できれば「うちのリビングは広い」と感覚的に思う。
本来、広さは何かをするときに必要な分だけあればいい。その分だけ確保できれば、あとは感覚的な広さをつくり出す。そのときにもデザインが力になる。
2つの言葉「バラバラ」「つながりがない」はどちらかと言うと否定的な言葉、あまりいい意味では使われないし、言わない。それでも案外使ったり思ったりする機会は多いような気がする。
ただ、バラバラだけど、つながりがあれば、それはいいような気がする。しかし、まとまりがあっても、つながりがないと、それはダメなような気がする。
そうすると、「つながり」のありなしが大事ということになるし、もっと言えば「つながり」があれば、何らかのものにはなるかもしれない。何らかのものとはいいもの。
ならば、何とつながりをつくるか、と考えるだろう、普通は。それにはなぜか違和感がある。「つながり」自体はそこらじゅうにあるし、いくらでもつくることはできるから、意図的にやろうとする、ただそれは不自然な「つながり」になるような気がする、「つながり」があれば何でもいいという訳ではない。
そうではなくて、「つながり」自体が括弧になっているようなものをつくることが大事かなと思った。括弧になっているとは、「つながり」自体はすでに含まれていて、「つながり」自体を考える必要がない状態になっていること。むずかしいけれど、括弧つながりでないと本当の「つながり」はつくれないと思った。
出会うってたのしいなと思う。男女の話だけでなく、出会う人はどんな人でも、自分の知らないことを連れてきてくれると思っている。旧知の人でも、たとえば、街中でとつぜん出会ったりすると、その人のいままで知らなかった一面をみることになる。もちろん、良いことばかりとは限らないけれど、いつも同じ人、同じことのくり返しよりは、なんか可能性を感じることができて、いいなと思う。
だから、出会いをつくり出すことが場づくりの基本だと考えている、それは住宅も同じ。家族や同居人とも出会うような感じがあれば日々の暮らしにもメリハリや、よりたのしむ感じが生まれるでしょ。
それぞれの居場所はきちんとつくる、落ち着く場所を。その上で移動したとき、たとえば、階段の上り下りによって、お互いの姿がみえ隠れするような、オープンとクローズドのバランスのとり方をデザインしてみた。完全にひとりではなく、かといって、いつも一緒でもなく、その中間をたくさん用意し、ひとつの住宅のなかに毎日出会いがある。
そろそろもう必要がないかな、と思う間にあるアクリル板、あるのが普通だとない方が不自然な感じにもなる。アクリル板をなくすかわりに、なんかちがったことで、アクリル板があった方がよい、となることはないかな、と考えるときもある。
壁なんかない方がいいと思うとき、私は床もと思う。壁は人のこころのキョリ感をはかる言葉してつかわれるけれど、床も同じように考えれば、床はこころの上下か階層のキョリ感か。
昔、斜面地で斜めの床を計画しボツにはなったけれど、斜めの床で上下階がつながり階層なくなるなら、それは斜面地という場所を最大限にいかすことになり、また階層がある当たり前の計画に対するちがった提案にもなるから、それはそれでいいのではと思ったことがある。
ささやかな上下の階層をなくすこころみとして、2階の廊下の床の一部を透明ガラスにした。そこを通らないと2階の各部屋には入れないようにして、そのガラスの床は1階のダイニングテーブルの真上にある。
あきらかに上にはあるけれど、下からも丸見え、上下の関係性が微妙にゆがむことで、暮らしにちょっとだけ他にはない体験をはさむことができ、外より家の方が面白いとなれば、をつくってみた。
ものはこうして欲しいとうったえる。だから、何も知らなくても、押してしまうし、触ってしまうし、にぎってしまう。その形が何を意味するか、自然にわかる。TVリモコンがあれば、赤いボタンをとりあえず押す、それが電源のonoffたがら、まじまじと見なくてもそう思う。それをアフォーダンスという。ものが誘惑する、そうしてと。
小さな窓ひとつ、あとドアがあるだけの外壁面、色違いのラインがランダムに入る。そこに、うすい1m弱の出っ張りが端から端まである。
何か出っ張りがあれば、雨露しのげて、日差しをさえぎることができるから、まわりに何もなければ自然とその下にいく。大きな木の下へいくのと同じような感じかもしれない。
外壁の素材はよくある金属板、だから安い。そのままふつうに使えば、よくある住宅で馴染みがあるかもしれないが、そのような住宅があふれる中では金属板である意味がない。金属板でできる表現のうちで、もっとも住宅らしくない使い方をして、まわりの住宅とのちがいを出し、しかし、住宅とは人が集まるところとするならば、他の要素を重ね合わせて人を自然に集める。
見た目の住宅感を装飾してつくりだすのではなくて、人が自然と集まる場所としての住宅感をだしたかった。そうすることで、人と住宅のつながり、人ともののつながりが自然にでき、それが愛着にならないかな。
いつもいっしょでなくても、あそこにいるというのがわかれば、とくべつ意識しなくても、安心した気持ちでいられる。つながったり、離れたり、何ごとにも関係性はできる。人にたいしてだけでなく、でも人かな一番は。さっき宅急便が指定時間よりおくれてきた。大事な荷物だったから、でも今どこかにあるのかわからなかったので、来なかったらどうしよう、などと思ってしまった。
小さい家でも、いや小さい家だから工夫しないと、それぞれ自分だけの場所をつくって閉じこもるような気がした。だから、少しでいいからお互いに今いることがわかるような工夫をしてみた。
階段を上り下りするときにチラッとみえたり、室内の窓から顔がみえたり、半階ズラして同じ場所にいても自分の場所ができるように。
いつも、まったく壁がないときと壁だらけのときの間のどのあたりがちょうどよいのかをさぐってみる。それは、いろいろなつながりが壁の量にあらわれるからで、壁の量が暮らしをつくりだすと思えば、暮らしや空間を壁ではかることができる。壁のあるなしが気になるのは人でも空間でも同じだなぁ
となりは何気にみえてしまうから気になり、「隣の芝生は青い」ことになるのはよくあるでしょう。となりは良くみえるものと、わかっていてもなんか落ち着かない。ならば、一緒に何かをしてしまえば、「なんだあ」と相手をよく知ることができて、落ち着いたりする。
前に、兄妹クライアントの住宅を別々につくった。そのときはひとつの敷地を半分にして、となり同士に建てる計画、要望はまったくちがったが、全くつながりがない住宅を並列に建てるのは、なんかよくないと思った。そもそもつながりがある同士だから、住宅にも何かつながりをつくりたい。
ただ、もともとつながりがある同士だからゆえに、離れていることも大切、だとは思っていた。そこで、玄関にいたるアプローチだけを共有にした。となりの敷地までお互いにつかうことで、倍のはばの通路がとれ、そこはお互いの家族の遊び場にもなる。
要望がまったくちがったので、住宅の大きさも外形もちがうが、外壁の仕上げだけは同じにして、つながりがあるもの同士だと表現し、アプローチに面する窓もお互いにズラしながらも、窓越しにコミュニケーションできるようにした。
アプローチだけを一緒にすることで、別々だけどまったく別ではなく、かと言って、よくある建売住宅の並びのような同じさにはならない。このバランスならば、「隣の芝生は青い」ことにもならないでしょ。
遠くからみえる屋根が郷愁をさそうことは、たとえ実際に体験したことがなくても、なっとくしてしまう人がいると思う。むかし、合掌造りの集落を訪れたとき、だんだんとみえてきた三角屋根は、はじめてみるものでしたが、どこか前から知っているように感じた。なぜだかわからないけど、子供に家の絵を描かせると三角屋根になる。屋根にはそれだけイメージや感情とむすびついた何かがある。別の言い方をしたら、アイコンのようなもので、屋根は人の意識の一部に常にあるのかもしれない。
屋根の形にはいつも悩んでしまう。意識の一部にある屋根は誰でもイメージしやすいものとして常にスタンバイしているから、形はわかりやすく、イメージしやすいものがいい。ただ、それではアイコンとしては弱い。数あるアイコンとしての屋根がならぶ風景の中で自分のアイコンだとわからなくてはいけない、自分の家だから。
前につくった住宅は三方向から遠景としてみることができた。だから、三方向の全てでみえる屋根の形を変えた。屋根の形を考えるとき、まわりの屋根と比べることがある。それは高さや形がアイコンとしてふさわしいかどうかをみる場合、まわりのアイコンとちがいを出したいから。ただ、このときは比べる相手を三方向の屋根の形同士にした。
みる方向によって屋根の形がちがうことで、無意識に家と自分の位置関係を感じる。それは屋根の形を、単なるアイコンではなく、家と自分をもっと深く強くむすびつけるものにし、より愛着がわくようになる、家に、そして自分に。
たくさんの器、昔のものも今のものも、古染付や古九谷、民藝など1日でたくさんみることができた。器にくわしくはないけれど、器は大すき。ふだんの暮らしの中で何をつかうのか、どの器に盛ろうかな、どの器で飲もうかな、と迷うのがすき。
いろいろみて思ったのがつくる側とつかう側、みる側と言ってもいいかもしれないけれど、お互いにちがうところが気になる。つくる側にはつくる側の動機があり、つかう側にはつかう側の流儀がある。みる側はその両方を合わせ持つのかもしれない。
ときに、そのつくる側とつかう側のズレがおもしろい。つくる側の精緻さの具合いによって、生まれるものの良し悪しは決まるが、つかう側はその精緻さの具合いまで含めて迷う。
ふだんの暮らしにはその人の趣味趣向がでる。趣味趣向はその人の考えや想いのあらわれ。ただ、人は気分にも左右される。かっちりしたいときは精密なものを、おおらかにしたいときは緩いものを、というように精緻さの具合いまで趣味趣向の範疇になる。
そうすると、つかう側からみて、緩いもの意識してまじめにつくってほしくなる。そうなると余計おもしろい。今度はその緩さの具合いに良し悪しがあらわれてくる。ただ、つくる側は大変、緩さを精緻につくろうとするのだから。
どちらを向くかってけっこう大事だなと思いながら、ついよそ見をするクセが。よそ見はいつでも向けるからという余裕かもしれないけれど。
東西を電車と道に挟まれた場所ではどちらを向いても空いているが、どちらを向いても視線が気になる。元の家は暗くて寒い。ただ、南と北は建物が接近している。一般的には南に開くのがよくあるパターンだけれども、空いている方に開く方が将来的に周辺環境に左右されない。電車にちょっとだけ開く、道にちょっとだけ開く、あと空にちょっとだけ開く。
開くはそちらの方へ向くことだが、ちょっとだけ開きながら背を向けることもできる。そうすると案外、外から見てもわからない。ちょっとだけ開き背を向けるとは中から見て視界の半分までの窓をつくること。経験上、半分までは窓にしても中外どちらからも気にならない。よそ見もいいいけれど、きちんと向いた方が今までのことを一旦保留にできて、新しい機会が増えるような気がする。
ほとんど車に乗らないのに持ってはいるので、たまにバッテリーが上がらないように用もなく走り回る。2台とも小さい、軽トラと古いミニクーパー。やはりないと困るときがあるので、あと愛着。もともとあまり車に興味がなく、必要に応じて軽トラと、あのときなんかほしかったミニクーパー、すでに27年がたつ。小さくても全く乗り心地がちがう2台、ミニから軽トラに乗り換えると、軽トラが広くただ走りは鈍く感じる。やはり自分はミニの小ささと軽快な走りが大好きなんだと毎回気づく。
前は狭小住宅の依頼がけっこうあったので、小さいなりの工夫をしていた。小さいなりの工夫とは、効率よく機能的にして省スペース化を実現する、ことではなくて「小さい」から「大きい」にはできないことをして「大きい」よりも「小さい」方がいいだろうという顔をするということ。
小さいが故に実現できることを探し出せば、大小のちがいをいったん保留にできる。そうした上でクライアントの暮らしに合わせていけば、まだ見ぬ空間ができあがるかもしれない。
前につくった住宅はあまりに小さくて必要な広さの空間がとれない。どうしてもひとつの空間に複数の行為が重なる、例えば、朝に顔を洗う横で目玉焼きをつくり洗濯をしているとか。一見それは乱雑な空間のように感じるが、それがクライアントの朝の習慣で、細長い空間の中で順番にできたら、クライアントにとっては快適で、さらにその空間がまだ誰も見たことがない景色になる可能性を小さいが故に実現したことになる。
「小さい」ということは制約だが、それは「大きい」も同じで別の制約がある。大小はひとつの条件にすぎず、可能性に差はないとミニに乗るたびに思う。
着ている服が変わっただけで、たとえば安もののスーツでも、ふだん着ていない人が着るとよく見えたり、別人に見えたりする。中身が変わったわけではないけれど、中身まで別人のようで、案外本人も知らないうちにふるまいが変わる。そう自分もはじめて着物を着たときにそれを感じた、それは別の自分の発見にもなった。だから、たまにいつもとはちがうことを、それも他人から言われた方がいいかもしれない、自分の思いつきだとまた同じになるから。
ある時、前につくった住宅の屋根にあがるときがあった。たしかクライアントから何かを見てほしいとたのまれてのことだった。その住宅にはトップライトがあり、2階の床がガラス張りだから1階まで屋根から見える。トップライトの真下はダイニングテーブル、テーブルの上にはいろいろなものが置かれ、人が座ったり立ったり動いているのが見えた。いつもとはちがう見え方、日常では見ることができない風景、四角いトップライトが切り取るある家族の日常を記録映像風に見ているようだった。
設計しているときにはこのイメージはなく、むしろダイニングテーブルから見上げる空のイメージしかなかった。他からトップライト越しに室内を覗かれることはないので、見ることだけで見られることは考えていなかった。
ただ、この風景を見てからトップライト越しに見上げる空が身近に感じるようになった。うまくは言えないけど、一方通行の関係が双方向になったような。どんな風景でもこちらも見られていると思うと見せ方は変わるだろう。ならば見られることを身近に親近感を持って感じた方がいい。そうして生まれた別視点が新たなもの、例えば新たな自分、新たな暮らし、新たな空間を生みだすかもしれない。
昔のツァイスレンズをデジタルで使いたくてカメラを手に入れた。ものは久しぶり、最近は形がないものに、と思ったら最近マグカップが増えた、毎朝のコーヒーのために。ツァイスレンズは15年くらい前に手に入れたもの、ずっと防湿庫に閉じこもっていたけれど、最近写したいものができたので防湿庫の鍵を開けることにした。せっかくカメラを手に入れても飽きたらどうしようとも思ったが、それならば飽きたという経験ができるからいいかなと。
時々、自分ではやらないが面白そうなオーダーを受ける。前につくった住宅ではすべり台がほしいという。ずっとマンション暮らしだったから、2階建ての住宅に住んだことがなく、階段の上り下りが面倒くさい、だからすべり台とのこと。
そもそも広い住宅ではないから、すべり台のスペースがもったいないし、たぶんまちがいなく飽きると思ったので、クライアントに正直にやめた方がいいと言って思った、見方をかえれば、下りの時は1階と2階の区別はなくなり1階と2階はつながる。
結果この住宅は、そもそも2階にある個室に壁がなく戸で仕切るだけ、1階はワンルームのキッチン、ダイニング、リビングだったので、2階からみれば全てがつながって感じられ、逆に1階からみれば階段があることでちがいが出て壁がない2階のプライベート感が増し、個室に壁がないことがよりよくなる。
試しにやってみて飽きたらその時考えればいいかな、いくらでもやりようはある。飽きたらすべり台に下から本を並べれば、階段が図書室に、積読にはもってこい、読みたいところに座ればいい。
空気を感じる、というと何か人間関係や場の雰囲気など目に見えないものをわかることを指すけれど、それを建築に当てはめてみることもできそうな。
建物があると人がいて、その建物と人との間には空気が充満している。空気は見えないけれど、もし空気に色をつけるならば、建物の外の空気と中の空気はちがう気がする。
その中の空気のことをボリュームといえば、ちょっとふわふわなやわらかい透明なマシュマロを思わず想像してしまう。人のまわりにある透明なふわふわマシュマロをどのようにあつかえばいいか。壁を建てないと流れ出てしまうが、壁の建て方によってはふわふわマシュマロでもみたされない場所ができそうな、きっとそういう所は人がいなくてもいい場所か、ひとりになれる場所になるのかな。
空気とすると冷たい空気、温かい空気などそれはそれでなんか良し悪しがあって窮屈だが、マシュマロだと思えばなんか笑えてくる、甘そうで、甘いものに弱いから誘惑されそう。日曜だからとぼんやり妄想してみたら、案外ヒントになったりして。
キョリという言葉をすぐとなりの人にも、実際にはすぐとなりだから離れていないのに「心の距離がある」などとつかう。キョリというものは実際に目に見えること以上に多様な使われ方をする。
建築においてキョリは図面上の表現になる。その表現にさまざまな意図をのせるが、その意図はキョリと密接に関係しながら、読み取らないとすぐにはわからないときも多い。
例えば、壁を間に建てればお互いに遮断しているとわかるが、壁を建てたくないときは、間を離してキョリを取る。壁があれば目で見て遮断はわかるが、キョリを取ったときは他のものとのつながりも同時に見ないと遮断してるのか、つながりは保とうしているのか、どちらなのかがすぐにはわからない。表現がより複雑になる。
前につくった住宅で個室の壁を無くした。そのかわりに引戸で仕切り、個室状の空間を数珠つなぎにつなげた。各個室状の空間は大きさが微妙にちがう。誰がどの空間を使うかは大きさとお互いの離れ、すなわちキョリで決める。別に固定する必要もない。家族の成長に合わせてキョリも調整すれば良い。キョリの多様な使われ方を利用してみた。
緑に包まれたい、ただ見るだけでなく緑に抱かれるような感じで過ごしたい。緑の多い場所、山や森や林に行きたい時はきっとそう思うのでは、私はそう思う。ただ見るだけならば、ちょっと緑の多い場所、都市のちょっと大きな公園などでも、それではもの足りないから自分のとなりに緑があるくらいの近さがほしい。そうすると、自分と緑との間にどのくらいの空間があるといいのかなどと思ってしまう。
自分は建築の中にいるとしたら、建築と緑との間にどのくらいの空間があるのがいいのか。建築の中に緑があったとしても自分との間に空間はできる。ようするに緑との接近度、親密度を間にある空間の大きさ具合ではかろうということ。
緑は自然、建築は人工、自然と人工の対立は昔からある話で、くっきり分けるのではなく自然と人工を混ぜたような状態も考えられるが、いずれにせよそこには人がいて、人は本来自然の方のはずだが、人と自然という対立になる。そうするとややこしくなるので、間にある空間を扱って人と自然をどのようにつなげるかをめぐらしてみると、案外単純な話にならないかな。
家を建てると皆んな緑を置きたくなる。プランターを外に置く人、家の中に置く人、大小いろいろだけど何かしら緑を増やす。それを勝手に自然の中で暮らしていた名残りではないだろうかと思ってる。
人間は大昔自然の中にいて最小限の自分を囲う小屋や巣のような場所で暮らしていた。それは身を守るため、ほかの大部分は自然だった。それがいまでは逆転し大部分が自然ではない人工のものになった。それで大昔のような危険はなくなり身を守る必要はなくなったが、今度はあまりにも自然がなくなりすぎて、それでは身が休まらないと本能的に感じているのかもしれない。人工のもの、すなわち建築がわるいという訳ではないが、人間という生物が生きて行くには自然と人工のバランスがあり、都市部ではバランスがわるいということだろう。
敷地の中に10本の木を植えようと計画している。なぜ10本かは10家族が暮らす予定だから、ひと家族1本、それによって暮らしにいつも木をまとわせる。だから、建築もはじめから木をまとうので、木のまとわせ方が建築を決めていく。それは木の方から建築をみることになるので、建築がじゃまならば建築が木に合わせることになる。
なんか大変そうだな、はじめての打合せで感じたことを貴重なヒントだと思って気にとめてみた。これから建物をつくろう、住宅を建てようとする人はどこかいつも勇ましくみえる。新しいことをするとき、思い切るとき、ちがったことをするとき不安をかき消すためにちょっと背伸びしたくなる、そのぶん見栄えがよくなるのかな。
ときに住宅だと家族のつながり具合がプランに影響を与えるときがある。余程ちがいを感じないかぎりはそのようなことはしないが、できれば感じたことをうまく建築的な要素として取り込み、ちょっと他にはないものを提案したい。
先ほどの「なんか大変そうだな」は以前につくった住宅のご主人、こちらまで息がつまりそうな気になった。プレッシャーを抱え込む感じ、それだけ家族を大事にしようと。初回の提案からひとつの住宅の中に離れをつくった。簡単に言えば外部であるバルコニーを通ってしか行けない部屋。ただし、その部屋は内向きに窓があり開けるとリビングからもお互いの存在がわかる。ご主人がひとりになれて好きなときに家族とつながることができる、ご主人しだいのご主人だけの場所。
昔から部屋の並びには序列があり、一番奥の部屋ほどプライベートで閉鎖的につくられていて重要な場所だとされてきた。その序列はときに有効だが、ときに住宅の規模くらいの建築だと序列を誘導し助長してしまう。ワンルームにして序列を全くなくしてしまうこともできるが、奥の場所と手前の場所につながりをつくり出すことができれば、部屋の並びは残しつつ序列は排除できる。この方がより建築としては望ましい方へ行けるだろう。
高所恐怖症なのに高いところが好き、高層ビルでも屋内ならどれだけ高くても平気、むしろ行きたくなるのに、生身の身体がさらされているところは2階くらいの高さでも怖いから足場の上にはできるだけ行きたくないのに。ただ不思議なことにいまはないWTCの屋上は外に出れたが怖くなかった。あそこまで高いと地上から離れすぎているからかな。
2階くらいの高さでも屋上は貴重な外とつながる場所だと思い計画することがある。建設中何度も見に行くので慣れれば怖くない、むしろ地上とはちがう楽しみを発見する。見渡すと案外上空をうまく使っていない家ばかりなので、地上の庭よりプライバシーが守られて広大な空に近いから解放感があり快適な場所になる。
ただ、だんだんと使わなくなるときく。たぶんそれは屋上というスペースをとってあるだけだから、とくに使わなくてもいいから。強制的に使わせようとしてもダメだが、ないと困るというか、あるから良いとなるような工夫が必要。
前につくった家では屋上で遊ぶ姿が直下のリビングから見えるようにした。人が集まることができる場所、戯れる場所を分散することで家中いたるところがリビングのようになる。たまたま屋上が外のリビングになればいい。きっとこの「たまたま」な感覚が大事で強制はされないがあれば楽しめる場所になる。
曇り空がきらい、雨の日は雨音が癒やしてくれるのでまだいいけれど、朝起きて晴れているだけで一日中気分がよく、特にいまの季節の秋晴れは気候もいいので窓を開け放して過ごしたくなってしまう。
いま住んでいる家は築50年、10年前くらいにある住宅メーカーが建てた家を購入し手を入れた。道路から奥まりまわりは建物に囲まれて1階にあったキッチンとリビングは日当たりが悪かったので、1階と2階の部屋を逆転して、キッチンとリビングを2階にした。おかげで晴れの日は一日中陽が適度にあたるのでずっと快適に過ごしていられる。
まわりを建物に囲まれることは住宅地以外でも、例えば商店街などは道路側以外はとなりの建物が接近している。そういう場合でも上階にはオーナーが住む場合があり、時には住宅地よりも日当たりが悪い。
日当たりが悪いことを別の言い方で「眺望が悪い」「閉鎖的」とも言えると思う。南側に窓がなくても他の方位に窓があればあまり日当たりが悪いとは思わないだろう。だから一番避けたいことは眺望がなく閉鎖的であること。
空は地上の事情とは関係なしに平等な存在。そんな空とつなげることが眺望を得て開放的になれ、そして、いまいる地上の状況を相対的に良くしてくれる。上を見上げれば良こともある。
小さいものが時に魅力的で、その魅力はどこからくるのだろうか。1995年に新車で購入したミニクーパーにまだ乗っている。その小ささが特徴的ではじめて生産された時の技術は素晴らしいものだったらしい。
今でも変わらず新鮮なままの体験が運転している時の感覚で、この感覚が実に楽しい。きっとそれは小ささに由来しているのではないか。小さい車体にエンジンやギアボックスなどを収めるために様々な工夫をし無駄な物を排除しているから、実に運転感覚がシンプルでアナログ。なかなかアナログな道具が減ってきている時に私にとっては貴重なストレス解消アイテムだ。
小さい住宅はいくつかつくった。あまり大小にこだわりはないが、小さい住宅の方が工夫しがいがあるから結果的に楽しい設計になる。室内では何かの存在自体を根本から見直ししないと入り切らないから、新しいことを考えるきっかけにもなる。
それは屋外でも同じで、小さい住宅というのはそもそも敷地も小さいので、余すところなく土地を使い切りたい。以前つくった住宅では敷地境界線までの距離を少し余計にとり、建物の周り四周に敷地境界線までウッドデッキを敷いた。普通に建てると敷地境界線と建物との間に普段使われることがない場所ができてしまう。その場所を室内と連続させることにより、小さい住宅の室内を少しでも広く感じさせることができた。
結果的に小さい住宅の方が敷地全体を余すところなく使い切ることになった。それは小ささに由来している。小さいということを積極的に捉えると大きいものでは獲得できない魅力に出会える。
木は土の地面から生えている、だから何も見ないで木の絵を描いたら普通に地面には土を描くだろう。地面が土ではなかったらとは誰もイメージしない。だから、木と土の地面はセットであり、土の地面がないと木もないと思う。
突然木が目の前に現れた感じがした。そこは地面が砂利敷き、駐車場から続いた場所だった。砂利から木の幹だけが生えている、もっと言うと、どこかで伐採した丸太を持って来て、そこに立てて並べているようにしか見えなかった。
地面に土ではなく砂利を敷いたことで、地面と木がつながらなくなった、まるで別のもの同士、全く関係ないもの同士の組み合わせに見え、そうすると、木自体も木に見えなくなった。
今までの木とはこういうものという既成概念から抜け出た。そこで改めて木について考えると、例えば枝同士に渡して屋根をつくれば木は柱にしか見えなくなるなど、木が多様に変化しはじめるような気がした。
木が木に見えない、ならば木がある場が必ずしも屋外である必要がなくなる、あるいは、木がある場を屋内的な使い方をしても違和感がなくなる。既成概念を抜け出せれば、思いのままに木がある場を新たな空間にできる。
先日の何もしない庭をつくった話のつづき、今は何かする庭をつくろうとしている。そこには1本の木を植えたい。むしろ木を植えたいから庭をつくろうとしている、と書いてふと思った、室内に木を植えたらどうなるだろうか、いややめよう、それも面白いが今は収拾がつかなくなる。
ただ1本の木を植えるだけでは庭にならない。その木があるからどうなの、ないとどうなの、庭の形は、庭のとなりに何がくるのなど、木を植える庭があると暮らしの中で何が変わるの?
以前に1本の木を植えた庭つきの住宅をつくった。その木はクライアントのお父さんが亡くなった頃から自然に敷地内に生えてきたらしく、残したいということで移設して庭の真ん中に持ってきた。その木はキッチンからもリビングからも眺めることができる、それが要望だった。
木が見えるということが家族のつながりを無意識に象徴することになった。庭は木のためだけにあるようなものだが、その庭がないとプランは完結しない。何もしない庭も同じだが、庭はあることでつながりをつくり出す、つながりがなければ庭はいらない。
たくさんの小鳥が木にとまり茂った葉の中で鳴いているのを何度か見た。ちょっと怖い風景でもあり、どうしてその木にと思う。小鳥に好かれている木は他と何がちがうのかと観察してみてもよくわからない。たまたまその木だったのか?
人にも好かれる木と好かれない木があるのだろうか。都市部にいると木が少ないからそもそも木の好き嫌いを思うことがなく、樹種にかかわらず大括弧で木としか思わない。でも、たくさんの木がある場所に行ったら自然と人が集まってくる木はありそうな気がする。
たくさんある木のうち、ちょっと根元に腰掛けやすそうだな、寄りかかりやすそうだな、張り出した枝の下は木陰になっていて涼しそうだなとか、人とのつながり方がイメージできそうだと自然と集まりそう。そうすると、小鳥には小鳥なりの人間にはわからないつながり方をしているということか。
悩ましいのはいつも屋根のかたち、意外と屋根は目立つ。近くで見上げるとあまり見えないが、ちょっと離れると屋根がよく見える。なぜ目立つのか、たぶんそれは一番空に近いから、屋根の形がそのまま反転して空のかたちになるから。
2階の部屋は屋根のすぐ下にあるから、空に一番近い部屋となる。だから、それを表すために天井は屋根の裏の形をそのまま見せることが多い。無意識にここは空に一番近い場所だと、地面からは離れた場所だとわかってもらうために。
時たま天井をフラットにして空を意識させないようにする。そういう場合は2階にいながら地面を意識させたい時でだいたい広い庭か中庭がある。だから、狭小住宅の場合は必ずと言っていいほど2階の天井は屋根の裏を見せて、上へ空へ意識が抜けて少しでも広さを感じるようにする。
階段が好き、そう言うと階段に好き嫌いがあるのかと思われるかもしれないが、過去に1人だけ出会った階段好きに。妙に話が合い、その人はローマのスイペン階段が一番すきだと言っていた。私より若く学生だった彼の口から「スペイン階段」という言葉が出てきたのがちょっと意外で、でも納得してしまった。
よく階段に座りたくなる。2段分にかけて腰掛けるとちょうど椅子の高さと同じくらいになるから、階段を見ると休憩場所だと思うクセがある。スペイン階段もまさに腰掛けだ。
階段はいろいろなバリエーションをつくってきた。階段好きもあるが、階段はひとつの見せ場だといつも思う。階段を上がることは舞台に上がるようなもので、別の世界に運んでくれる。だから、上がった先には何かを用意したいし、上がっている途中も何かを感じさせたい。
別の場所へ行くために、時には休み、時には何かを感じ考え、時には下り、時には上がる。階段はいろいろと例えることができる。それはまるで何かのようでもあり、だから好きなのかな。
まず外と内というような分け方をします、家の話なのですが、案外他のことにも当てはまるかもです。領域というかテリトリーというか、自分たちの安全地帯をつくるように壁を建てて室内をつくります。
その室内に一緒にいる人たちは家族や仲間だから安心、でもお互いに隠したいことはあるからまた壁を建てて囲います。そうやって家はできます、古来より簡単なんです、家づくりは。
ただ、壁のバリエーションはいろいろです。それは人とのつながり方と同じです。何度も会い本当に親しい人から一度きりの人までいて、人によって会った時の感じがちがうようにです。
前に建てた住宅で壁が必要ありませんでした。1階は家族が集まるスペース、2階は各自のスペース、その2階に壁がありません。正確に言うと、引戸があるだけ、必要に応じて仕切るだけ、でもそれは壁ではないです。ご夫婦とお嬢さん2人のご家族、壁がなくてもいい暮らしができることをうらやましく思いながら設計してたな。
壁が必要だと、壁で囲うのが当たり前だと思うことで人のつながり方まで決めつけていたようです、壁はなくなった方が面白い空間ができるのに。
庭つき一戸建て、なんて言葉があるようには庭と家はセットだった、一昔前までは。今ではマンション暮らしの人も多いし、一戸建てを建てる人も庭などはじめからない場合も多い。マンションだから、敷地が狭いからと理由はあるだろうが、そもそも庭が必要ないのだろう。
前に建てた住宅は1階のリビングと同じ大きさの庭をつくった。その庭にはウッドデッキを全面に敷いて室内のリビングの床と同じ高さにした、リビングの延長として広く見せるためとリビングに光を取り入れるために。だから、はじめから庭に出ることは考えていなかった。それで十分で、それで豊かな生活になるだろうと思った。
その庭はリビングが十分に広くて日当たりが良ければなくてもよく、ただリビングとつながって見えるようにするためにウッドデッキを敷いた。そうしないとその空間が生きないから、生かすためにリビングの暮らしと関連づけて何もしない空間をつくった。
10年後その住宅に訪れるとウッドデッキは多少古びたが完成当時と変わらずに何もしない空間があった、まるでそこの空間だけ時間が止まっているように。きっとそう見えたのも何もしない空間だから、でもそれがよかったのである。何もしなくても庭はあった方が日々の生活が豊かになると、室内を見渡して、ご家族を見て思った。
空って当たり前のようにいつもあるけど、うまく使えていない。窓越しに空は見えるけど景色の一部、天気を気にするくらい。使うという表現がいいかどうかわからないが、空だけがみんなに平等に与えられた自然のような気がするから、うまくいかさないともったいないとつい思ってしまった。
自然には他にも緑、木や水辺の川、海、地形として山や谷などがあるけれど、場所によっては身近にはない。だけど空だけは見上げれば誰の上にもある。
建築で空をいかそうと天井をガラス張りにした家を見たことがある。誰でも一度は考えることだ。ただそうすると、夏は暑過ぎて、冬は凍るように寒く、人が住める場所ではない。
空を使うって案外むずかしい。それに空を使わなくても建築はできてしまう。だから誰も真剣には考えないのだろう。ちょっとは空を使ってみてはどうなの、と秋空が教えてくれたような気がする。
コールスローをつくろうとしたら冷蔵庫にマヨネーズがなかった。普段マヨネーズを使うのはあと玉子サンドをつくる時くらいで、それもあまりつくる訳てはないから大体使い切らずに消費期限を過ぎてしまう。キャベツの千切りを別の食べ方にしようかとも考えたが、
ふとマヨネーズをつくろうかと思った。
ネットで調べたら、材料は全て家にあった。卵、酢、オリーブオイル、塩を混ぜればいい。卵は平飼いのもの、取り入れる油はオーガニックエキストラバージンオリーブオイルかグラスフェッド無塩バターだけと決めている。少し高いが他のものは使わないのでかえって安上がりだ。
10分後、オリーブオイルを使うからちょっと苦めのゆるい出来立てのマヨネーズはそれだけで贅沢なソースに変身した。あと茹でた野菜やパンがあれば、ヨーロッパでは平日の立派なディナーだろう。
結局、もうマヨネーズは買わない。
その分、冷蔵庫のスペースは空くし、余計な出費もなくなり、贅沢な気分にもなる。ちょっとしたことである。
ないから足すのではなくても、自作しても、ものを減らしてミニマリストにしても、あるいは、余分なものを削ぎ落としてレスイズモアなミニマムデザインな建築にしても時につまらないことがある。きっとその原因は結果的に新しい価値を獲得していないからである。マヨネーズで言えば、自作するが市販のマヨネーズの代替品でしかない時である。
そうそう関係ないが一昨日見たリヒターの作品は当たり前のように巨匠の域であったが、
マヨネーズ工場のようにも見えた。
現代建築と和風建築を続けて見る機会があり、見た目は全く違う建築だが、繊細さやクオリティの面では共にハイレベルなので、建築について考えるきっかけとなりとても面白ろく、両方共に内部と外部をつなげるような空間構成だが、共に線が目立つ建築だった。
現代建築の方は築20年近く経ち、完成当初から何度か見に行ったが、今回は端部や継ぎ目の線が気になった。劣化もあるだろうが、今つくろうとするとシームレスにでできることが当時の技術的限界でできなかったのだろうと感じた。
和風建築の方はそもそも線材を多用し、線材によって領域を分割していく。故に線が目立つのだが、現代建築と比べることで線材が結界になっている感じがした。
"Compare modern and Japanese style"
I have the opportunity to see contemporary architecture and Japanese-style architecture in succession, and although they look completely different, they are both high-level in terms of delicacy and quality, so it is very interesting as an opportunity to think about architecture, and both are spaces that connect the inside and the outside. Although it was composed, both were buildings with conspicuous lines.
The modern architecture is almost 20 years old, and I went to see it several times from the beginning, but this time I was worried about the edges and seams. There may be some deterioration, but I felt that what I could do seamlessly when I tried to make it now was not possible due to the technical limitations of that time.
Japanese-style architecture uses a lot of wire rods in the first place, and the area is divided by the wire rods. Therefore, the lines stand out, but I felt that the wires were a barrier compared to modern architecture.
建替えの歴史を重ねてみた。増改築を繰り返した今ある建築を一度全て壊して新たに建替える。その増改築の記録と新たなに建築する場合の標準的なプランを重ね合わせてみた。標準的なプランは建築士の設計製図試験の模範解答のようなものであり、それで一般解としての担保とした。
重ねてみることで、重なりの密度が濃い所と薄い所ができる。単に壁量の違いにも見えるが、それが人々のアクティビティの痕跡にも見える。
アクティビティの痕跡だとしたら、アクティビティを入れ替えて重なりの密度の違いに全く違った意味を持たせることができるのではないかと思い、それは新たなプランに記憶の継承という影響を与えると考えた。
"Accumulating memories"
I tried to repeat the history of rebuilding. All the existing buildings that have been repeatedly expanded and renovated will be destroyed and rebuilt. I tried to superimpose the record of the extension and renovation and the standard plan for new construction. The standard plan was like a model answer for an architect's blueprint test, so it was collateralized as a general solution.
By stacking them, you can create a place where the overlap density is high and a place where the overlap density is low. It looks like a difference in the amount of walls, but it also looks like a trace of people's activities.
If it is a trace of activity, I thought that it would be possible to replace the activities and give a completely different meaning to the difference in the density of overlap, and I thought that it would affect the new plan by inheriting memory.
都市の一部分としての建築という見方をしてしまうと、都市が持っている利便性や効率性を担うものになってしまう。利便性や効率性は都市にとって最大の利点であるから否定をする必要はないが、あまり行き過ぎると息が詰まるので、適度な利便性や効率性に調整をしたく、そのためには都市の一部分としての建築から脱したいと考えている。
都市の利便性や効率性を担っているものはむしろ建築以外のものが多く、それらに任せて建築は利便性や効率性を担うのを止めるのは乱暴過ぎるだろうか。
建築は都市の中でも圧倒的に多いものなので、その影響力は計り知れないが、だから利便性や効率性を手放したいと考えてしまう。
"Let's give up convenience"
If you look at architecture as a part of a city, it will bear the convenience and efficiency of the city. Convenience and efficiency are the biggest advantages for the city, so there is no need to deny it, but if you go too far, you will be choked, so you want to adjust to moderate convenience and efficiency, so as a part of the city. I want to get out of the architecture of.
There are many things other than architecture that are responsible for the convenience and efficiency of the city, and is it too violent to leave it to them and stop the architecture from being responsible for the convenience and efficiency?
Architecture is by far the most abundant in the city, so its influence is immeasurable, but it makes us want to let go of convenience and efficiency.
自由に創作するためにわざと制約を設ける。全くの自由では次にすることは制約を求めることだから創作に向かわなくなる。制約から自由になるために創作に意識が向く。創作のコツは制約を設定することであり、制約を別の言い方をすれば、常識、慣習、課題かもしれない。要するに全くの自由な創作というのはそもそも成り得ないということであり、それを逆の状況から言えば、常に創作の種となる制約は身近にある訳だから、捉え方しだいで創作がいつでもできるということである。
"Create"
Constraints are intentionally set to create freely. With total freedom, the next thing to do is to seek constraints, so you will not be able to create. Being conscious of creation to be free from restrictions. The knack of creation is to set constraints, which in other words may be common sense, customs, or challenges. In short, completely free creation is impossible in the first place, and from the opposite situation, there are always restrictions that are the seeds of creation, so you can always create depending on how you think about it. That is.
人の内面が現れるような場をつくりたいと常に思っており、それが内部空間ならば、人の内面の発露を誘発するようなものをデザインしたいと考える。
それは外部空間でも同じだが、外部空間の場合は周辺環境への影響、周辺環境からの影響を考慮する必要もあるので、人の内面の発露を誘発するより、周辺環境に働きかけ、周辺環境が人の内面の発露を誘発するようにしたい。
"Inner dew"
I always want to create a place where the inside of a person appears, and if it is an interior space, I want to design something that induces the exposure of the inside of a person.
The same is true for the external space, but in the case of the external space, it is necessary to consider the influence on the surrounding environment and the influence from the surrounding environment. I want to induce the dew on the inside of the.
きっかけがある訳でもないのに、遠くに見えている、ぼんやりだけれども、何かそこにある、段々と近づくにつれてハッキリと輪郭が立ってくる。はじめからそこにあると意識していたようにピンポイントで見つけたような、まわりはボヤけてピントが合っていないけれど、そこにあるのは遠くからピントが合ってわかっていた。
きっとこれらは自分の何かが対象物と結びついた結果で起こる現象だろう。もともと関心があること、探していたもの、興味があったものであれば、結びつきはわかりやすい。その結びつきを予測して、そこにそっと置くだけで良い。ただ、そうすると、もともとの関心や興味などが無ければ何も起こらない。
何も無いところに何かが起こることもあると仮定してみると、そこに置くものはどのようなものが良いのだろうか。目立つものか、奇抜なものか、これらは一瞬は意識するかもしれないが、見慣れたらただ普通に風景に溶け込み、結果何も起こらないような気がする。
もしかしたら、はじめの見え方としては引っ掛かりも無く、意識することも無く、ただそこにある位からはじまるのが良いのかもしれない。
"How to see at the beginning"
It's not a trigger, but it's visible in the distance, it's vague, but something is there, and as it gets closer and closer, the outline becomes clearer. I found it pinpoint as if I was aware that it was there from the beginning, but the surroundings were out of focus, but I knew that it was in focus from a distance.
I'm sure these are phenomena that occur as a result of something of your own being associated with an object. If you're originally interested in, what you're looking for, or what you're interested in, the connection is easy to understand. All you have to do is predict the connection and gently place it there. However, if you do so, nothing will happen if you do not have the original interests and interests.
Assuming that something can happen where there is nothing, what is the best thing to put there? Whether it's conspicuous or wacky, you may be conscious of these for a moment, but once you get used to it, it just blends into the landscape normally, and as a result, nothing happens.
Perhaps the first appearance is that there is no catch, no consciousness, and it is better to just start from there.
何者かになりたいことと、何者でもないことのギャップに苦しむ人が多いと最近思った。
意外と誰でも何者かになりたいと思うのだろう、FacebookなどのSNSを見ているとよくわかる、何者かになりたいと思う時点で残念なのだが、何者にもなれない。
この瞬間に、手を動かして、誰かの、自分の、隣の人を喜ばせればいいのに、それをしない。それが一番難しいことで、誰も簡単にできない。
"The most difficult thing"
I recently thought that many people suffer from the gap between wanting to be someone and being nothing.
Surprisingly everyone wants to be someone, you can see well by looking at SNS such as Facebook, unfortunately when you want to be someone, but you can not be anyone.
At this moment, you can move your hand to please someone, your own, or your neighbor, but you don't. That's the most difficult thing, and no one can easily do it.
モノだらけは断捨離とは真逆で捨てられずに貯めるだけ貯めて整理もできていない状況で何かと弊害があるように思うが、先人が何を大事にしていたかがよくわかる。
捨てられないとはいえ、その人にとって不要なモノは捨ててはいるはずだから、残っているモノはその人なりに偏る。
古い地図と古い名簿がたくさん残されていた。地図好きは知っていたが、伊能忠敬に興味を持っていたから、今は用をなさない名簿にはいろいろな繋がりを感じる。
断捨離をするとしたら、真っ先に捨てられるモノばかりである。ただ、捨てて捨てて最小限の暮らしと、偏った不要なモノに囲まれた暮らしと、どちらが、いやどちらかを選択する話ではないと思った。
"Throw away, don't throw away"
It's the opposite of decluttering, and it seems that there is something wrong with the situation where you can't just store and organize things without throwing them away, but you can see what the ancestors valued.
Although it cannot be thrown away, things that are unnecessary for that person should have been thrown away, so the remaining things are biased toward that person.
A lot of old maps and old rosters were left behind. I knew that I liked maps, but I was interested in Ino Tadataka, so I feel various connections to the now useless list.
If you want to cut it off, it's all the things that are thrown away first. However, I thought that it was not a matter of choosing between a minimal life that was thrown away and thrown away, and a life that was surrounded by unbalanced and unnecessary things.
時は様々なものを蓄積させる。記憶としての思い出の蓄積だけでなく、もの自体も勝手に蓄積する。
30年使用した事務所を退去し移転することになった。普段は見えない所に過去の仕事の痕跡がたくさんあり、自分も含めて誰も整理をしてこなかったので、ここ2、3ヶ月は30年分の仕事の痕跡を取捨選択し、何を残すのか、何を捨てるのかがずっと頭の片隅にあった。
結局、過去の仕事は自分が生み出した分身のようなものだと思い、すでに自分の手からは離れているが、生み出すまでの過程が記された線一本までが愛おしく、ほとんど捨てることができなかった。自分が生きている間は伴にするものだと覚悟してパッケージした。
今までものに溢れていた事務所が空になった。事務所の空間自体には特に思い入れはなく、郷愁に駆られることはないが、ものが溢れていた状態から空になった状態への変化が全てを表しているような気がしてスマホで写真を撮った。
自分好みに制作した建具越しに2部屋を撮影した。この事務所の空間に自分が手を加えたのはこの建具だけであり、この建具で自分が実現したい見え方をつくり出した。
"When moving out"
Time accumulates various things. Not only the accumulation of memories as memories, but also the things themselves are accumulated without permission.
It was decided to move out of the office that had been used for 30 years. There are many traces of past work in places that are not normally visible, and no one, including myself, has organized them, so for the past few months, I have selected the traces of work for 30 years and left what to leave. I was always in the corner of my head about what to throw away.
After all, I think his past work is like an alter ego that he created, and although he is already out of his hands, he loves even one line that describes the process of creating it, and almost throws it away. I couldn't. She was prepared to accompany her for the rest of her life and packaged it.
The office, which was full of things, has been emptied. I don't have any particular feelings about the office space itself, and I'm not driven by nostalgia, but I feel that the change from an overflowing state to an empty state represents everything on my smartphone. I took a picture.
She photographed two rooms through the fittings she made to her liking. This fitting was the only one I modified in the space of this office, and I created the look I wanted to achieve with this fitting.
外壁と内壁の違いは周りの環境のコンテクストを表しているので、見た目にも外壁と内壁には違いが出る。時には外壁と内壁の違いが今いる場所の手掛かりになる。
ならば、擬似的に外壁と内壁の区別を変化させることにより、周りの環境のコンテクストを書き換えてみる。書き換えるための指針は自らをコンテクストにすることで、それは自律的建築へとつながる。
最初に周りの環境のコンテクスト通りに外壁と内壁をプランニングし、次の段階で自らのコンテクストによって外壁と内壁の区別を変化させ、周りの環境のコンテクストを書き換える。
これにより、周りの環境の中に新たな環境を入れ子状に築くことになり、それは周りの環境のコンテクストに影響を受けるという他律的な状況から自律的な建築を生み出すことができ、周りの環境の中で、都市の中で、違和感がなく自律的建築が納まることになる。
"Rewrite the context"
Since the difference between the outer wall and the inner wall represents the context of the surrounding environment, there is a difference in appearance between the outer wall and the inner wall. Sometimes the difference between the outer and inner walls is a clue as to where you are.
Then, try rewriting the context of the surrounding environment by changing the distinction between the outer wall and the inner wall in a pseudo manner. The guideline for rewriting is to make oneself a context, which leads to autonomous architecture.
First, plan the outer wall and inner wall according to the context of the surrounding environment, and in the next stage, change the distinction between the outer wall and inner wall according to your own context, and rewrite the context of the surrounding environment.
This creates a new environment nested within the surrounding environment, which can create autonomous architecture from the heteronomous situation of being influenced by the context of the surrounding environment. In the environment, in the city, autonomous architecture will be settled without any discomfort.
対立するものがうまく溶け合うような解決策を探している。設計をしていると終始解決策を探しているようだ。
頭に浮かぶイメージには必ず実現困難なことが纏っている。最初から何もかも無理が無くすんなりと実現するようなことは無い。そもそも焼き回しのようなことはしないから、その都度新しい要素を加える分、不確実なことも増える。
不確実であるから、わからないから、興味も湧き、様々な事に関心を持つようになる。
実は空間の不確実性は必要かどうかを考えていた。何もかもが手に取るようにわかる空間は果たして魅力的かどうか。優等生的には確実性の産物が建築なのだろうが、建築を使う人が建築の全てを把握することはないので、確実性に富んだ建築にしたところで意味が無い。
では魅力的な建築や空間ではどうだろうか、「魅力的」という言葉も曖昧で不確実だが、少なくとも設計する側は不確実性を無くそうとする。それが設計だと言わんばかりに曖昧さを無くそうとする。だから、解決策を考える。ただ、ふと不確実な様には惹かれ心動かされてしまう。その惹かれる心と魅力的な空間に魅了される心は同じような気もする、根が同じような。
結果的には不確実だった、確実性を高めた結果の産物が、そうでなければ、ただいい加減な建築が増えるだけである。意図して不確実な建築をつくる、それが良さそうだと考えた。
"Uncertainty"
I'm looking for a solution that blends well with the conflict. It seems that he is always looking for a solution when he is designing.
The image that comes to mind always has something that is difficult to realize. From the beginning, everything is not unreasonable and can be realized smoothly. In the first place, we don't do things like burning, so adding new elements each time increases uncertainties.
Because it is uncertain, I don't know, so I get interested and become interested in various things.
Actually, I was wondering if spatial uncertainty was necessary. Is the space where you can grasp everything in your hands really attractive? As an honor student, the product of certainty is probably architecture, but since the person who uses the architecture does not know everything about the architecture, it is meaningless to make it a highly reliable architecture.
What about attractive architecture and spaces? The word "attractive" is vague and uncertain, but at least the designers try to eliminate the uncertainty. It tries to disambiguate as if it were a design. So think of a solution. However, I am attracted and moved by the uncertainties. The fascinated heart and the fascinated heart of the attractive space feel the same, the roots are the same.
The result is uncertain, the result of increased certainty, otherwise there will only be more sloppy architecture. I thought it would be good to intentionally create an uncertain architecture.
2020年は今見ている風景が全てではないと思い知らされ、2021年は今見ている風景がさらにもっと全てではないと思うかもしれない。
いろいろな価値観が変わったが、自分が移動することで直に見ていたものを、移動せずに目の前で、しかしデバイスを通して見るようになった。きっと直に見ることで無意識に感じとっていたことが、デバイス越しにはカットされ無意識には届いていないだろうと思いながら、そうせざるを得ない状況に可能性を見出すならば、直が大事なことなど案外少ないとわかったことかもしれない。
今この時を少しでもポジティブに考えるならば、2021年はより大事なことだけが明確になるだろう。その時どうするか、他を捨てる心構えをしておく。
"2020 → 2021"
You may realize that 2020 isn't everything you're looking at, and 2021 isn't all that you're looking at.
Many values have changed, but now I can see what I was seeing directly as I moved, in front of me, but through the device, without moving. If you think that what you felt unconsciously by looking directly at it will be cut through the device and not reach you unconsciously, but you find the possibility in a situation where you have to do so, then Nao is important. You may have found that there are few things unexpectedly.
If you think about this time a little positively, 2021 will only clarify what is more important. At that time, be prepared to throw away the others.
「選択する」というアクティビティが人と建築をつなぐ。その時に選択するものは何か、それは「感情」を選択することにしようと考えている。
人の感情は目に見えるものではないので、それを目で見える形に置き換えてやる必要がある。その置き換えを建築的に考えると、感情によって居場所を選ぶことにする。
はじめは居場所を選ぶというアクティビティが人と建築をつなぐ。居場所を選ぶ時の基準が感情であり、それを繰り返していくと居場所に感情が紐づけられて、居場所を選ぶことが感情を選ぶことに変化する。
例えば、「嬉しい」気分になりたいからあそこへ行こうなど、感情を引き出したり、コントロールしたりするようになり、それによって居場所が決まるから建築の見え方もそれによって変化する。
「感情的になる」という言葉があるように、感情によって左右されることは良くないように思われるかもしれないが、人は理性で行動しているようで、実はその理性が感情に支配されていることが多く、社会を見渡しても個人の感情を現実の中で受け止めるような受け皿がない。その受け皿に建築がなるのは「衣食住」という言葉があるように人の基本的な拠り所に建築がなるので必然的だと考えている。
"Choose emotions"
The activity of "selecting" connects people and architecture. What to choose at that time, I'm thinking of choosing "emotion".
Human emotions are not visible, so we need to replace them with visible ones. Architecturally considering the replacement, I decide to choose a place based on emotions.
At first, the activity of choosing a place connects people and architecture. Emotions are the standard when choosing a place of residence, and by repeating this, emotions are linked to the place of residence, and choosing a place of residence changes to choosing emotions.
For example, if you want to feel "happy" and want to go there, you will be able to elicit and control your emotions, which will determine your whereabouts and thus change the way you look at architecture.
It may seem that it is not good to be influenced by emotions, as the word "become emotional" is, but it seems that people are acting with reason, and that reason is actually dominated by emotions. Even if you look around the society, there is no saucer that can accept individual feelings in reality. I think that it is inevitable that architecture will be built on the saucer because it will be built on the basic basis of people as the word "clothing, food and housing" is used.
今日はずっと滞っていた案件が少し動いた。まだまだだけど、やっと面倒くさいことを精度高くやってくれそうな人たちに巡り会った感じで、そのことに少し確信めいたものを確認できた。
やはり、実際にお会いして、こちらのやりたいことを目の前で顔を突き合わせながら、アクリル板越しでも、自分の声で伝えないと、いくらメールでPDFの図面をやり取りしても、相手との間合いとか、表情とか、仕草とかを感じ取りながら創造しないと、難易度が上がれば上がるほど、精度を高めることができない。
できないことはできないとしながらも、それでも何とかできる方法を考えようとする姿勢だから時間はかかるが、まさにそれを、それが普通だとは思うのだが、望んでいたので打合せをしていて楽しく、また、この機会に詰められることは可能な限り詰めておきたかったので、次の予定の時間にくい込んでしまった。
いずれにしても、これからの仕事では開口部の精度を高めることができる。そのことが非常に嬉しいし、創造の及ぶ範囲も広がった。
"How to do it"
The matter that had been delayed for a long time moved a little today. It's still a long way to go, but I finally met people who seemed to do the troublesome things with high accuracy, and I was able to confirm what I was a little convinced of.
After all, if you do not actually meet and tell what you want to do with your face in front of you, even through the acrylic board, with your own voice, no matter how much you exchange PDF drawings by e-mail, with the other party If you do not create while feeling the time, facial expressions, gestures, etc., the higher the difficulty level, the more accurate you cannot improve.
Although I can't do what I can't do, it takes time because I'm trying to figure out how to do it, but I think it's normal, but I wanted it, so it's fun to have a meeting again. , I wanted to pack as much as possible on this occasion, so I was busy with the next scheduled time.
In any case, the accuracy of the opening can be improved in the future work. I'm very happy about that, and the range of creativity has expanded.
建築の内容が気になり、どうしても建築は素材があって形になると考えてしまうが、形は空間の輪郭で、その空間にある「内容」に興味がある。
内容となると物から離れていくように感じるが、建築は物そのものの代表的な存在だから、それだけ物としては強度があるから、内容に焦点を合わせても物としての建築の部分は必ず残る。
この場合、内容とは建築を使う人が織りなすことで、人の感情や気分などが建築に作用することであり、素材と形という対概念において、両方を上手くとりなし、人の感情や気分がその都度、空間をつくるものである。
"Material, shape and content"
I'm curious about the contents of architecture, and I think that architecture has materials and forms, but the shape is the outline of the space, and I'm interested in the "contents" in that space.
When it comes to content, it feels like it's moving away from things, but since architecture is a representative of the thing itself, it's strong as a thing, so even if you focus on the content, the part of architecture as a thing always remains.
In this case, the content is weaved by the person who uses the architecture, and the emotions and moods of the person act on the architecture. In the opposite concept of material and shape, both are well handled, and the emotions and moods of the person It creates a space each time.
先日のプレゼンは建主がとても喜んでくれて実現に向けて動き出しそうでちょっと安堵した。なかなか直接お会いできなかったので、A3シート1枚に計画案をまとめ、それに自筆の言葉を添えて、あと3Dプリンターの模型も一緒にお届けした。
今ここで、この環境で何を実現したらいいのか、設計する側の考えや想いをきちんと込めて、それを簡潔に伝えようとしたが、それがどのような反応になって返ってくるのか、その反応でしか評価できないから安堵した。
ここのところ、いくつかの計画案の素案をSNSにあげてみている。その中で反応をみて、自分でも気に入っているものをA3シート1枚にまとめて提出した。
SNSの反応が全てでは無いし、むしろSNSの役割は情報伝達でそれ以上でもそれ以下でも無く、現実を超えようとするべきでは無く、超えようと考えると現実が壊れていくと考えていて、だから、実現する前のそれも素案に近い計画案という現実では無い情報をさらすにはちょうどいいと思っている。別にそれがダメでもまた考えればいいし、ただアウトプットにはなるから、頭のモヤモヤは整理される。それを見せられる方は迷惑な時もあるかもしれないが、それがSNSの情報の作法だと心得ていれば気にもならないだろうし、気になってもすておける。
"Information that is not the reality of drafts"
The other day's presentation was a little relieved because the owner was very pleased and seemed to move toward realization. I couldn't meet him directly, so I put together a plan on one A3 sheet, added my own words, and delivered a 3D printer model together.
Now, I tried to convey what I should achieve in this environment, the thoughts and feelings of the designer properly, and briefly convey it, but what kind of reaction will it return? I was relieved because I could only evaluate the reaction.
I've been posting some draft plans for SNS recently. After seeing the reaction, I submitted the ones I liked as a single A3 sheet.
The reaction of SNS is not all, and rather the role of SNS is not more than or less than information transmission, and we should not try to exceed the reality, and thinking that it will break the reality, Therefore, I think that it is just right to expose unrealistic information such as a plan that is close to the draft before it is realized. Even if it's useless, it's good to think about it, and it's just an output, so the stuffy mind is organized. It may be annoying for those who can show it, but if you know that it is the manner of information on SNS, it will not bother you, and you can save it.
たまっていく風景が重なり合って、前後左右、時系列がごちゃごちゃになって合成され、記憶も微妙に都合よく書き換えられたり、心に浮かぶ風景はいつも何かと紐づいている。
それを心象風景とか、原風景とかいうのだろうか。
よく原風景が建築に与える影響を聴く。原風景というと、子供の頃の記憶であることも多いだろうが、原風景というと、その時点で答えの範囲が決まっているように思う。
きっとその答えの範囲はその時代その時代で違うだろうが、大概は郷愁を誘うものが期待されるので、その時代に合わせて無意識に書き換えられているのだろう。
だから、もしかしたら原風景など存在せず、あるのはその時代に合わせたフィルターか合成装置かもしれない。
予算からすると10坪が限界のようだ。どのようなお店でも10坪以上あれば何とかなるだろう、10坪未満のお店だってたくさんある。飲食店兼料理教室で10坪平屋の建築、家ならば10坪は狭いが、お店ならば、ただ厨房の割合が大きくなる。
10坪の中で厨房とホールをキッチリと分けたら、例え、オープンキッチンでもどうだろうか、せせこましくなるのではないだろうか。それに中途半端な、厨房も、ホールも、広さになりそう。ホールも狭かったり、席数がとれなけば、カウンターだけにするが、ラーメン屋さんのように、何かもったいない、せっかくの10坪をテナントとして入るのではなくて、平屋で建てるのだから、他にやりようがある気がした。
例えば、10坪全てが厨房というのはどうだろうか。お店として考えたら10坪は中途半端な広さ、特色もないように思えるが、厨房として考えたら10坪は広い、料理教室も兼ねるならば、厨房は広い方がいい。
厨房の中にお客さんがいて、厨房の中で料理教室をして、全てがシェフズテーブルになる。
ただ、保健所で問題になりそうな気がするが、厨房とホールは明確に分かれていないといけないから、小まめに分けて、何とか方法はありそうな気がするが、手洗いだらけになったり、このご時世それでも構わない気もする。
そして、厨房の中には大きなひとつながりのカウンターをつくり、その中に厨房機器、設備を仕込む。カウンター上で料理がつくられ、お客さんに供され、料理教室が開かれる。
屋根はそのカウンターを雨露からしのぐためにつくられる。
その大きなカウンターが人と人、人と料理、料理と料理をつなぐ。
気分でどこで食べてもいい、どこで料理をしてもいい、そのカウンターは外まではみ出してつながっていて、外の人や街の風景もつなぐ、鉄道高架の立ち退きによってできた変形地、これから街が変わる、風景が変わる、その時に何かつなぐ役目が飲食店のカウンターというのも悪くないし、結構、食べ物につられて、だから、カウンターは変形している、変形していれば周長が長くなり、人がより集えるし、直線だらけの風景に味が出る。
こういう計画もまたよしだと思った。
感情や気分をそのまま受け止めるような建築を考えようとしている。やはり、建築は人を包み込むようにできているもので、もしそうでなければ、工作物、土木構築物だから、それでは建築ではないから、ならば、人と建築の関わりの中で考えると、主体は人になり、それに合わせて建築が変化する方が自然のような気がする。
そうすると、人は日々の生活の中で何に一番左右されるのか、良くも悪くも感情や気分だと思う。少なくとも、感情や気分の変化無しに1日を過ごすことはないだろう。
だから、建築を計画する上で、人の感情や気分を扱うことには妥当性がある。程度の差こそあれ、感情や気分に左右される人を包み込む建築はどうあるべきかは重要な問いだと思う。
一方で、そのような言葉による問いから導き出された建築は本当に妥当性があるのだろうかとも考えてしまう。ちょっと窮屈な思いもある。
何もしなくても湧き上がってくる感情や気分があり、それが意図せずとも見方に影響を与え、その影響が何も介することなしに建築化されたようなものにしたく、それは何か固定化されたイメージの建築ではないことだけは確かなので、つくりながら、後追いでできあがったものに言葉をつけてみようと思う。それが例え的外れだとしても、できあがったものにはその時の感情や気分がダイレクトに反映されるだろうし、少なくとも窮屈な思いはない。
らしさを形にする時、どこにでもあるような、特徴のない形になってしまうことは避けたい。たぶん、らしさを形にする時、そこが一番抵抗を感じるところだと思います。誰も見たことが無いものをつくりたい、新しいものをつくりたいと考える。その考え自体は良いと思います、そうでないと新しいものは生まれないから。
ただしかし、新しいかどうか、誰も見たことが無いかどうかは誰が判断して、誰のためになるのでしょうか。新しくて、誰も見たことが無いものをつくるのは案外簡単なのです。人に受け入れられることを考えなくても良ければ、誰でもできる。
らしさを形にする最大の目的は、人に受け入れられやすくするためです。独創とは、人の上に成り立ち、尚且つ、滅私したところに存在すると思うのです。滅私、すなわち、それはらしさを纏うこと、その上で、誰にもできないものをつくり出す、精度を高めて、外しズラして。
だから、外すズラし方の指南は「人に受け入れやすくするために行う」です。それだけでイメージが湧いてくるはず、難解に見せる、面白く見せるためでは無くて、外しズラした方がより人が良いと思い受け入れる、そして、それが独創になる。この場合の人は、特定の個人、クライアントでもいいですし、不特定多数の人、社会に生きる全ての人でもいい、用途により、それは違うでしょう。
らしさを形にすることが、実は独創につながる、これを理解できている人は案外少ないかもしれないです。
らしさを形で出そうと考えています。素材もあると思いますが、瞬時の印象で一番残るのは形だろうと思います。
本当に小さな建築になる、だから、外形を一目で把握できてしまう。その形に好き嫌いの感情が伴うこともあるでしょう。全く好き嫌いの感情を外して成り立つことは考えにくいので、好き嫌いを超えた形をつくりたいと考えています。
好き嫌いを超越するには、やはり「らしさ」が必要になるのではないでしょうか。誰もが連想できる形、それが「らしさ」だとしたら、「らしさ」があれば、好き嫌いの感情がそもそも起きにくいのではないかと思います。
「らしさ」を別の言い方をすれば「馴染みやすさ」になるかもしれません。それが安心感を呼び、その安心感がその形を受け入れやすくする。ただそうなると、案外、どこにでもあるような、特徴のない形になってしまう可能性もあります。それが「らしさ」を形にする時に注意をしなくてはいけないところでしょう。
だから、「らしさ」を形にしながら、それが特徴にもなることを同時に考えなくてはなりません。
あとここが良くなればいいのに、あとここがこうなっていれば手に入れようと思うのに、ということがよくある。そういう時は大抵、自分の中でははっきりとはしていないが、なんとなくこういう物が欲しいことはわかっていて、でも具体的なイメージをまだ考えていない。
違和感を感じている状態ともいえるが、そこからよく考えると、あとここがという部分になかなか答えが見つからない、それはわかっていないからか、知識がないからか、技術がないから。
それと、その違和感は同時に、普通すぎて、よく見かけるし、ありきたりで、つまらないから、何とかした方がもっと良くなるという想いも伴う。
だから、あとここが良くなればいいのに、あとここがこうなっていれば、という想いをたくさん拾い集めるだけでも、コロナで家にいてはできない体験だなと思っていた。
窓は面白い存在だなといつも思う。建築の仕事の場では窓とはいわずに「開口部」という。窓を開口部というとプロっぽい。「開口部」だから、開いている部分ということになり、建築の設計においては窓の機能以上のことを負わせる。
光を入れる、風の出し入れは窓の機能ですぐに思い付くことで、それ以外にも熱の交換、光も入れるだけでなく、光の演出も、これは結構重要だと思っており、設計を志したキッカケでもあり、その他にも開口部をどのようにつくるかによって、窓とは感じさせない、壁の一部として取り扱うこともできるし、その開口部の納まりも枠なしに、ガラスだけとか、そうすると、ガラスが無いように見せることができたり、開口部を見るとその設計者の技量がわかる。
今、窓は、開口部は、専門的にいうと、都内だと防火設備の規定があり、防火設備とは隣家に近いと火に強くしないといくけないという法律で決まっており、鉄製だと自作ができるが、アルミ製だと簡単にいうと自作ができない、でも世の中、アルミ製がほとんどであり、それはメーカーが既製品として安価につくりやすいから、ただ、設計者として設計と共につくりたい開口部があるのに、アルミ製では少数ロットではつくれないし、防火設備として認定するのは難しいし、鉄製のサッシでは高価だし。
建築を実務ではじめた頃、不思議だった、建築基準法ではアルミは鉄ではない、世の中の窓はほとんどがアルミ製なのに、無理矢理、建築基準法に合わせるためにアルミ製のために許認可を求めている、ならば、いっそのことアルミを鉄と同等に扱えばいいのに、利権が絡むのだろう。
そのようなことはどうでも良いが、設計者としては窓の、開口部の、創作を自由にしたい、設計者に全責任を負わせてもいいから、開口部を自由に自作したい。
ここにきて、面白いもので、鉄製で自由にサッシを自作できる機会を得ている。もし上手くいけば、今後つくる建築の精度が上がる、今一番ワクワクすることは、つくることの精度が上がること。
空間を感じる瞬間というのがあると思うのです。それは壁や天井で囲まれていればいいという訳ではなくて、それでは単に室内にいるという感じだから、空間を感じさせる何かに出会うといった方がわかりやすいかもしれない。
空間を感じさせる何か、それはいろいろあるかもしれない、もしかしたら、人によっても違うかもしれない。
そこに人がいれば、あるいは、椅子のような物が置いてあれば、その比較によって空間を感じるかもしれない。ただ、それは空間の大きさを感じるのであって、空間そのものを感じている訳ではない。
そう考えていくと、私が今思いつくのは光しかない。
光は太陽からの自然光と照明による人工光に分けられるが、どちらの光でも、光が当たっているから空間を認識して、空間そのものを感じることができる。真っ暗ならば空間を感じるだろうか。
ただ、ふと思った、真っ暗でも、もしかしたら空間を感じるかもしれない。そうすると、空間を感じることには2通りあるかもしれない。
実際の空間を感じることと、人の意識の中にある空間、それは過去にどこかで経験している記憶の中の空間ともいえるが、真っ暗になった時に人の意識の中にある空間を感じるようになるかもしれない。
ということは、普段、空間を感じている時、人は実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせているのかもしれないと思った。
そして、それは建築を建て替える時に、その時、その場所、その人特有の空間の感じ方をつくることができると思えた。
真っ新な土地にして、まず基礎工事からはじめるのが実際の住宅の工事手順ですが、その前にどのような家にするのか、どのような家にしたいのかを工事ができるように具体的なものにするのが設計です。
その設計をまず最初から家の性能や指標や数値で考えていくやり方があります。例えば、高気密高断熱の家などのように、年間を通して快適な室内温度を保つことを目的に、具体的な計算式を使い、間取りから材料の選定や設備機器までを決めていく。
他に材料にこだわり、家づくりを進めていくやり方もあります。例えば、木の家であることを強調し、無垢の木を室内にたくさん使うことを大事にするなど。
最初にどのような家にしたいかのイメージが無い場合やどのような家にしたいかがわからない場合は、性能や指標や数値で考えたり、材料にこだわりを持つところから家づくりに入る方がわかりやすいかもしれませんが、流行りすたりがあります。
材料や設備などはどんどん進化しますが、家は一度建てたら、簡単に材料や設備を更新できません。だから、材料や設備などは年月が経ても価値が変わらない定番をおさえれば良いと考えています。
家の性能や指標や数値は計算式を知っていれば、誰でも年間を通して快適な室内温度を保つ設計はできます。
ただ、本来どのような家が良いかは住人によって一人一人ちがいます。材料や設備だけでは決まりません。その一人一人のちがいを考え、イメージし、合わせていき、家として具体的な形にして、工事ができるようにするのが本来の設計で、一人一人がイメージしやすいように手助けするのが設計者だと思います。
設計も工事も実際の家が完成するためのプロセスですが、工事は設計したものを実際の家にすることですから、その前の設計段階でどのような家かが決まります。
その設計を何度も経験する住人はいないでしょう。ならば、わからないことが多いけれど、その設計というプロセスを楽しみながら、今一度、一生に一度かもしれませんが、自分はどういう家に住みたいのかを想ってみるのもいいかもしれません。設計というプロセスは楽しいですよ。
東京アラートが発令されて、都庁とレインボーブリッジのライトアップが赤色に変化しましたが、色や照明で何かを抽象的に伝えるという手法は、言葉で直接わかるように伝えようと試みるより、深く印象的に伝わるように思います。
言葉だと字義通りの解釈しかできず、言葉使いや言い方、表現の仕方によっても、受け手の印象が変わり、場合によっては拒否反応が起こる可能性がありますが、色や照明のような抽象的な表現だと、それを見る人が自分の都合のいいように読み取り解釈することになるので、拒否反応が起こりにくく、読み取った解釈がより深く意識に入り込むのだと思います。
よく、窓明かりがもれるように、それが道路から見えるようにします。外灯ではなく、窓の明かりだと、その家の住人ならば、直感的に誰かいる、もっというと、誰がいるかまでわかるはずです。
それは夜帰ってきた時の喜びや嬉しさや安心感につながるような、それは人それぞれ解釈の仕方は違うかもしれませんが、少なくともわるくはない、ちょっとホッとするようなことかなと思いまして。
会社でもない、家でもない場所、別に会社にいたくない訳ではなくて、別に家に帰りたくない訳でもなくて、ただ、会社か家かという2つに1つ、二者択一的な生活はずっと続くとちょっとぐらいの変化を求めたくなるかもしれない。
それは決して悪いことではないけれど、こうするべき的な思いにとりつかれると、まっすぐ家に帰ろう、寄り道なんてせず、となると日々の生活が不自由なものに感じられるようになってくるかもしれない。
要領のいい人は行きつけの飲食店などを見つけて、顔馴染みになり、会社の人でもない、家族でもない、友達でもない、そんな人のつながりをつくり、上手に気持ちを受け流し整理して、家路につくのだろうが、なかなかそれもできない人が多そうな気がする。
だから、ちょっと家の中に、家でもないような場所をつくり、ひとりになれる時間をつくってあげることができたら、少しは違うのかなという想いから、離れをつくったり、部屋ではないが廊下にしては広いような場所をつくり、そこが街の中の広場や通りのような雰囲気をかもし出せば、家の中で気分も切り替り、家族との時間もより楽しめるのではと思ったりして設計した。
そういうこともありますよね、それもありですよね、ポイントを押さえれば案外いろいろな考え方ができそうで、ただ、ポイントを外すと単なるデタラメになってしまう。
足を伸ばして湯船に浸かりたい、普通にそう思いますよね、そうなると体を洗う洗い場も欲しい、当たり前ですよね、ただ、できる限り広いリビングやダイニングも欲しくて、そこで家族と一緒に過ごしたい、大体、住宅全体の広さは敷地の大きさで決まるので、はじめに数値でわかる。
だから、広さとか狭さを数値でいっても意味がなくて、敷地が急に広がらない限り変わらないので、数値ではなくて、広く感じるのか、狭く感じるのかの感覚で考えていく。ただ、感覚的なことは人による違いが大きいので、自分の感覚を押し付けるようなことはせずに、当たり前だが自分の感覚で設計はせずに、そこに理屈があり、あとはクライアントの感覚に合わせていく。
最大限リビングやダイニングの広さを確保するために、お風呂場をコンパクトに、それもただコンパクトにするだけでなく、お風呂場の形状もリビングやダイニングの広さを確保するために細長くし、それで足を伸ばして湯船に浸かり、体を洗うのにも支障がなく、クライアントは狭く感じない。
ちなみに、横に細長い窓の先はリビング、湯船に浸かりながらも、リビングともつながるように。
よくその人だけの居場所をつくったりする。そういう場合は大抵クライアントからの直接的な要望ではなくて、お会いしていろいろとお話を伺う中で頭の中に急に浮かんできたりする。家と人をつなげたいというか、そういう居場所があってはじめて自分の家だと思うような気がしているから。
お子さんがまだ赤ちゃんの時から将来この子に勉強を教えるのが楽しみですと雑談の中で語っていた。たぶんその時はダイニングテーブルで子供が学校の宿題や勉強をしている横で、自分は本でも読みながら、子供の勉強を見るようなイメージだったと思う。
クライアントも本を読むのが好きで、ただ書斎をつくる程のスペースは取れなかった。そこで各個室に行く廊下を少し広げ、そこに本棚と長机を造り付けにしスタディスペースとして、書斎とお子さんもそこで一緒に勉強をする場所とした。
そもそも機能上は廊下だから家族みんなが通る。だから、そこで本を読んだり勉強をしていても、部屋に籠るのとは違って、家族がお互いに何をしているのがわかり、それでいて自分の居場所でもある。
クライアントとの雑談の中で、形として明確ではないけれど、これからの暮らしの中で欲しいのはこのようなスタディスペースではないだろうかと思い、提案し実現した。
隣の家とのすき間はなんとかならないか、中途半端に空いていて、敷地が広ければいいが、狭い敷地だったら勿体ないし利用したいとずっと思っていた。
ちなみに、民法上は境界線から50cmは空けなければならない、だから、必ずすき間ができる。
もちろん、そのすき間が無ければ、作業スペースが取れないから家自体を建てることができない。ただ、そのすき間がもっと狭くても、50cm未満でも建てようとすればできなくもない。
旗竿状の敷地というのがある。敷地の形状を上から見たら竿にたなびく旗のように見えるからそう呼ばれる。敷地というのは建築基準法上、道路に2m以上は接していなければならないと決められている。だから、道路に2m以上接していない敷地には法律上、家を建てることができない。
旗竿状の敷地は竿の部分の巾が2mで、そのままの巾で道路に接していることが多く、これは大きさな敷地を道路に対して手前と奥で分割する際に、奥の敷地に法律上、家を建てることができるようにするための苦肉の策である。そして、その竿の部分には巾が狭すぎるため建物を建てることはほとんどしない、大体、車や自転車の置き場所になり、建物を建てるのは敷地の旗の部分になる。
その竿の部分が20m以上ある旗竿状の敷地が住宅の計画地になった。敷地面積には当然、竿の部分の面積も含まれるから、竿の部分が長くなればなるほど、建物を建てる旗の部分の敷地面積が狭くなり、竿の部分が20m以上もあれば、旗の部分は狭小地と呼べるくらいに狭い。
クライアントの要望はただ1つ「家の周りにメンテナンス用のスペースを取って欲しい」だった。建て替えだったが前の家では家の周りのスペースが狭すぎてメンテナンスに苦労したようだ。
敷地の旗の部分がただでさえ狭いのに、メンテナンス用のスペースを取ったら、余計に狭くなり、家自体も狭くなる。だから、家の周りのメンテナンス用のスペースをなるべく小さく狭くして、家自体の広さを確保することを考える、これが常套集団だろう。
ただ、それではメンテナンスという、家が建っている間に何回も必要にはならないことのためにスペースを空けておくのは勿体ないし、もっと積極的にクライアントの要望に応えたかった。
だから、家の周り四周に、民法上必要なスペースの倍の巾のスペースを取り、それはクライアントの要望のメンテナンス用のスペースとしては余りあるぐらいの広さであり、そして、その家の周り四周にウッドデッキを敷き、その高さは1階の室内の床の高さと同じにして、1階にあるリビングダイニングスペースが敷地いっぱいまで広がっているような感覚をつくり出し、敷地の狭さ、家の狭さを視覚的にも和らげようとし、尚且つ、積極的に敷地いっぱいを住環境スペースとして利用することを試みた。
建築をどうやって認識するかなんて考えたことが無い人がほとんどだろう、どうやって利用するかは考えるだろうけれども。
建築をつくる側にいると、この建築はどのように見えるのだろうか、どのように感じるのだろうか、この空間に入った時、光の見え方はどうだろうか、視線がどのように抜けていくだろうか、歩きながら目線が連続的に変化していく中で、何を感じ、何を見て、どのように思うだろうか、時には歩き、時には座り、時には立ち止まる、そうやって、設計時から抱いていたイメージと現実を擦り合わせし、住宅ならば、ここでこれから暮らしをはじめるクライアントに想いを馳せ、修正した方がいいと思えば、その場で変更を加えたりもする。
まず最初に建築をどうやって認識するかから入る。それは建築を学びはじめた時から当たり前のように行ってきたことだが、クライアント側に立てば、決してそれは当たり前のことでは無くて、広さや大きさや使い勝手などが一番最初に大事なことになり、それは建築そのものの建築的な価値を見るというよりは、不動産としての建築の価値を見るようである。
建築には事業という側面もあるのだから、不動産としての価値が大事なのも当たり前ではあり、それを第一に持ってくるのは仕方が無い場合もあるが、それでは立つ場所や予算や広さ、大きさで優劣が決まってしまうかもしれない、それは惜しい。
建築をどうやって利用するかは少し抑えめにして、建築そのものをどうやって感じて、どのように認識するのがいいのだろうか、暮らしのためには、という考え方もあるかもしれないと思って欲しい。
"What you want the architecture to think about"
Most people haven't thought about how to recognize architecture, though they will wonder how to use it.
If you are on the side of building architecture, what does this building look like, how do you feel it, how does the light look when you enter this space, how do you gaze? What do you feel, what you see and what do you think, while your eyes are changing continuously while walking, sometimes walking, sometimes sitting, sometimes stopping, so from the time of designing If you think it is better to revise the image you were embracing and the reality, to think about the housing you are living in here, and make corrections, you can make changes on the spot.
First of all, we start by how to recognize architecture. It's been a matter of course since I started to learn architecture, but on the client side, it's not a matter of course, but the size, size, and usability are the most important things. It seems to see the value of architecture as real estate, rather than the architectural value of architecture itself.
Since there is also a business aspect to construction, it is natural that the value as real estate is important, and it may be unavoidable to bring it first, but then, where it stands, budget and area, It might be decided that the size is superior or inferior, which is a shame.
I think that there may be a way of thinking about how to use architecture, how it should be felt and how it should be perceived, while limiting how it is used.
人はどこの辺りで認識をするのが一番心地よく感じるのだろうかと考えていた。
今現在の日常より良くなると認識できれば、当然心地よく感じるだろうが、今現在の日常より悪くなると認識したならば不快になるだろうし、今現在の日常と変わらず同じでも不快では無いかもしれないが、ただ心地よいとも思わないだろう。
では、今現在の日常より良くなるとして、今現在の状況からは想像できないくらいに良くなるとしたら、それはどうだろうか、想像できないくらいに良くなるのだから、凄く心地よくなるのだろうか。
もしかしたら、それはそれで不快かもしれない。自分が想像できないくらいのことは、例え凄く良くなることがわかっていても、想像できないことで不安や心配が湧き上がってきて、それは自己防衛本能が働くからか、素直に心地よくはなれないかもしれない。
結局、人は自分が想像できる範囲で良くなることが一番心地よく、それは今現在の位置より自分の手が届く所くらいまでの前進で良いのかもしれない。
これはあくまでも建築やデザインやものづくりのはじめの目標設定の話だが、今現在の状況に照らし合わせても、それは完全にコロナが終息する状況が早く訪れることが一番良いのだが、それに対して誰も明確な答えを出すことができないのならば、人が想像しやすい時間の単位毎に、例えば1週間毎に、今現在までの状況分析からのリスク説明を伴う出口戦略を示してもらえれば、ただStay Homeしているよりもこの時間を使って、今現在も行ってはいるが、より少しでも良くなる手段を自分たちでも考え創意工夫できて、精神衛生上もより良くなるし、今現在より少しは心地よくなれると思うのだが、いかがなものでしょうか。
"It's okay to think ahead"
I was wondering where people would feel most comfortable to recognize.
If you recognize that it will be better than your present day, you will naturally feel comfortable, but if you recognize that it will be worse than your present day, it will be uncomfortable, and even if it is the same as your present day, it may not be unpleasant. I don't think it's just comfortable.
So, if it's better than today's daily life, and it's better than you can imagine now, what's that, and it's better than you can imagine, so it's really comfortable.
Maybe it's offensive. Even if you know that things that you can not imagine can be greatly improved, anxiety and anxiety will rise because you can not imagine, maybe because your self-defense instinct works, you may not be comfortable comfortably .
After all, it is most comfortable for a person to be as good as they can imagine, and maybe it's better to move from where he is now to where he can reach.
This is only about setting goals for the beginning of architecture, design, and manufacturing, but in light of the current situation, it is best that the situation where the corona will completely end soon will come, but to whom If you can not give a clear answer, if you can show the exit strategy with risk explanation from the situation analysis up to now, for each unit of time that people can easily imagine, for example, every week, However, I am spending this time rather than staying home, and I am still doing it now, but I can think and devise ways to improve even a little, I am better in mental health, and now I am I think it will be a little more comfortable, but how is it?
ふと思い出していた「しょがねぇあ」という口癖を。私の両親は千葉東部の出で、今でも父親の実家は残っており、その口癖は伯母がよく言っていた。
いつも優しい伯母はよく会話の最後に「しょがねぇあ」とつけ加えて吐き捨てるように言う。普通に会話をしていて、自分ではどうしようも無いことや、ちょっとでもできないことや、無理なことになるとその口癖で終わる。
言葉だけを字にして見ると、諦めてしまうネガティブな印象を受けるが、実際にその言葉を声として聴くと、なぜか心地よく、癒される。
自分ではどうしようもできないことは無理をせずに「しょがねぇあ」と言って手放し、できることだけをやる。そんな無理のない生活を田舎でずっとしてきて、何事も乗り越えてきた人にしか出せない声のトーンが耳についていて、ときどき無意識に自分でも「しょがねぇあ」と言ってしまう。
ただ、その一言で切り替わり乗り越える強さを、都会に住む人では到底身に付かないしなやかな強さを感じるからこそ、真似して「しょがねぇあ」と唱えたくなる。
"Shogane"
I suddenly remembered the habit of "shoganaea". My parents were from eastern Chiba, and my father's parents' home is still there, and my aunt often said that.
A gentle aunt always adds "Shoganeea" at the end of a conversation and tells her to throw it away. When I have a normal conversation, I end up with that habit when I can't help myself, what I can't do at all, or when it becomes impossible.
Looking at only the words in a word gives the negative impression of giving up, but when I actually hear the words as a voice, it feels comfortable and healed for some reason.
Don't overdo things you can't do without saying anything, let go, let go, and just do what you can. I have lived such a comfortable life in the country all the time, and I hear the tone of voice that only people who have overcome anything can hear, and sometimes I unconsciously say "I don't know."
However, it is tempting to imitate the strength of switching over with just one word, because it feels supple enough that people living in the city can't get it.
建築や建築家が日常や暮らしと結びついた存在ならば、今この状況の中で対処療法的に不自由さと向き合いつつ、アフターコロナの日常や暮らしを考えて、そこに焦点を合わせているだろう。
日常や暮らしと結びついていない建築や建築家の方々もたくさんいるだろうし、過ぎ去れば何も変わらない日々がまた訪れるから、今は巣篭もりしていればいいと割り切れる人たちもたくさんいて、それとは対照的に巣篭もりしたくてもできない人たちもたくさんいる。
どの社会的立場、別の言い方をすれば、どの階層から見るかによって、アフターコロナが違う。
別にわざわざ変える必要性も無いと思うかもしれないし、周りが変われば変わらざるを得ないと思っているかもしれないし、積極的に、あるいは生き残るために変えていこうと考えるかもしれない。
今までも何度か、この後の世界は変わるだろうと言われたが、何も変わらなかった。それ程、過去から未来への時間軸の流れは強固であり、人の営みはそんなに柔ではないし、建築は自身では変える能力を持たず、哲学的や社会的な変容を必要とするので、リニアには変わらない。
しかし、今回はどうだろうか。人の営みは生まれて最後は死ぬという絶対真理と時間軸の流れの掛け合わせで決まるが、その最後の死を今、毎日見せつけられて、毎日考えさせられるこの状況で、変わらずにいられるのだろうか、それとも風化して何事も無かったように戻るのだろうか、などとちょっと考えてみたくなった。
"After"
If architecture and architects are connected to daily life and daily life, they will be facing the inconvenience of coping therapy in this situation, thinking about everyday life and life of after-corona and focusing on it. .
There may be many architecture and architects who are not connected with everyday life and life, and when they pass by, the days when nothing changes will come again, so now there are many people who can divide that it should be a nest, and that. In contrast, there are many people who want to keep their nest but cannot do it.
The after-corona differs depending on which social position, or in other words, from which level you are looking.
You may not think there is a need to change it, you may be forced to change if your surroundings change, and you may think positively or change to survive.
I was told several times that the world after this would change, but nothing changed. To that extent, the flow of time from the past to the future is strong, human activities are not so soft, and architecture does not have the ability to change by itself, and it requires philosophical and social transformation, so it is linear. Does not change.
But what about this time? People's activities are decided by the combination of the absolute truth of being born and finally dying and the flow of time, but in this situation where the last death is shown every day and made me think everyday, I can remain unchanged I wondered if it would be weathered or would it return as if nothing had happened.
良くもなく、悪くもなく、普通というと、何となくそれは悪い部類に含まれるような気がして、少なくとも良い部類では無いように思う。たまに、普通が一番、という言葉を耳にするが、それも当たり障りが無いから、飽きることが無いなど、決して良い訳では無いが、かと言って極端に悪い訳でも無い、ちょっと良いか、ちょっと悪いかが許容範囲くらいのことで、それはそれくらいで収めるのが丁度良いということなのだろう。
ただ、その普通の内容がいつも同じであるということは無く、その時代、その時々で変わる。例えば今ならば、制限の多い暮らしを送っているので、普通にできることも制限されるから、コロナ以前の普通がとても良いもの、素晴らしいことに感じる、その時はそれが普通だったのに、そう思うとストレスになる。
アフターコロナでは普通が変わる。今が普通で、コロナ以前の普通が飛び切り素晴らしいことに格上げされるから、アフターコロナではコロナ以前に戻るだけでも、普通の日常が、暮らしがより豊かに感じるようになるのではないか、同じなのに。
普通に注目して、以前と今、今と以後を比べてみたら、こうして家に篭っている状況が、アフターコロナの飛び切り素晴らしい普通の日常や暮らしを楽しむためには必要なこと、その準備のためとは思えないだろうか。
"A wonderful normal is waiting"
It's good, it's good, it's normal, and it feels like it's part of the bad category, at least not the good category. Occasionally, I hear the word "ordinary is the best", but it's also not disturbing, so I'm not tired of it, but it's not a good reason, but it's not an extremely bad thing, a little good or a little What is bad is about the acceptable range, and it means that it is just good to put in that amount.
However, the usual contents are not always the same, and they change from time to time. For example, now that I am living a limited life, I am also limited in what I can do, so I feel that the normal before Corona is very good, it feels great, I think it was normal at that time, I think Becomes stressful.
Ordinary changes in after corona. It's normal now, and the pre-Corona normal is jumped up to a wonderful level, so even after returning to the pre-Corona after-corona, it seems that normal everyday life will make your life richer. .
If you pay attention to normal, and compare before and now, and after that, the situation of staying in the house like this is necessary for enjoying the wonderful ordinary everyday life and life of after corona, the preparation of it. Don't you think it is worthwhile?
距離を取る、ソーシャルディスタンスなんて聞き慣れない言葉が普通になった。こんな単純なことがウイルスに対して本当に効果的だったのかは後になってわかるだろうが、とにかく得体の知れないものには近づかない方が良いだろうと、場当たり的な対応でも、しておいた方が安全第一でいいと思うのだが、こんな単純な、距離を取る、という対処方法が全てを一変させてしまった。
人と一切会わないでできることはほとんど無いとわかり、距離を取るにしても、手が届く範囲でないとどうしようもなく、それではソーシャルディスタンスが保てず、声が届く範囲で良ければ、わざわざ会う必要もない。
イヤらしい位に心理をもてあそび、アクティビティを封じるウイルスに対して、どうしたものか、リモートやデリバリーで済むならばまだ良いが、直接人と会わないとどうしようもないことも当然ある。
ヒアリングができない。ヒアリングの目的は、相手の話を聴くことでは無い、相手の状況を把握することでは無い、相手の情報を共有することでは無い、それらは全てインタビューであり、直接会わなくても、リモートでも、文書でもできる。
ヒアリングの真の目的は、相手と信頼関係を築くことである。そのためには、飛沫がかかる距離、パーソナルディスタンスに入り込む必要も出てくる。
ウイルスが人の命を奪うこと、これが一番怖くて問題であり、どうしても避けたところだが、それと同じ位に怖くて問題なのが、人との信頼関係が築けずに縁が途切れること、むしろこちらの方が対処が難しいかもしれない、ソーシャルディスタンスを保つ状況では。そして、それが社会の様々な場面でボディブローのように効いてくるだろう。だから、どのような状況になっても信頼関係だけは失わないように気をつけるしかない。
"Keeping trust with social distance"
Unfamiliar words such as social distance and distance have become commonplace. I'll see later if such a simple thing was really effective against viruses, but I also made an ad hoc response that it would be better not to come close to something strange. I think it's better to put safety first, but such a simple way to deal with distance has changed everything.
It turns out that there is almost nothing you can do without meeting people, and even if you take a distance, you can't do it unless you can reach it. Nor.
It would be good if I could remote or deliver it to the virus that blocks the activity and play with the psychology to the extent that it seems to be unpleasant, but of course there is no way I can do without meeting people directly.
I can't hear. The purpose of the hearing is not to listen to the other person's story, not to understand the other person's situation, not to share the other person's information, they are all interviews, even if you do not meet directly or remotely. You can do it with documents.
The true purpose of hearings is to build trust with the other person. For that purpose, it will be necessary to enter the distance where the droplets are splashed and the personal distance.
It is the most scary and problematic thing that a virus takes a person's life, and I avoided it by all means, but the same fear and problem is that the relationship is broken without building a trust relationship with a person, rather here May be more difficult to deal with, in situations where you maintain a social distance. And it will act like a body blow in various scenes of society. Therefore, no matter what kind of situation, you have to be careful not to lose trust.
たくさんの物が目の前にある。お目当ての物はすぐ手の届くところにある、そこにしかない。その前に気になる物もある。ちょっと前に存在を知った。できれば両方手に入れたい。
ただ、両手を目一杯伸ばしても、両方を同時に手にすることはできない、となると、どちらかを先に、どちらかを後に、そこにはたくさんの人がいる、誰かが同じ物を欲しがるかもしれない、先に手にしないと、どちらがより欲しいか、それはお目当ての物だが、その前に気になる物の方が近くにある。
全ての物を360度俯瞰して把握する。全ての物を1つ1つ詳細にじっくりと理解する時間は無いから、その中から気になる物に焦点を当てる。気になるのは、瞬間的に引っ掛かりがあるからで、その引っ掛かりの正体は焦点を当ててからわかる。
近づく、引っ掛かりの正体に惹かれるか、惹かれ度合いのレベルが高いか、とにかく引っ掛かりの正体が何だかわからないが、とにかく惹かれてしまうのか、その時は考えるまでもない、素直に手におさまる。
きっとそれは自分に必要な物だから、気になり、惹かれるのだと、そもそも気がつかない物は、どんなに素晴らしい物でも、見えないのと同じ、存在しないのと同じ、だから、自分が気づいて、手におさめた物はずっと大切にしたい。
"I notice because I need it"
There are many things in front of you. The item you are looking for is within easy reach. There are also things to worry about before that. I knew that there was a while ago. I want to get both if possible.
However, even if both hands are stretched out, you cannot have both at the same time. Then, there is a lot of people there, one after the other, someone wants the same thing. Maybe, if you don't get it first, which one you want is the one you want, but there is something closer to you before that.
Get a 360-degree overview of everything. I don't have time to understand all the details in detail one by one, so I will focus on the ones I care about. I'm worried because there is a momentary catch, and I can tell the identity of the catch after focusing.
I am attracted to the nature of the approach, the degree of attraction, or the level of the degree of attraction is high, or I do not know what the identity of the catch is anyway, but I do not have to think about whether it is attracted anyway.
Surely it's something that you need, and you're bothered and attracted. What you don't notice is the same as you can't see, it's the same as it doesn't exist. I want to cherish the things I put in.
料理を自分でつくって食べることは自分の家でしかできない、この際の自分の家は別荘、別宅を含み、キャンプは入れない。
だから、料理をつくり、それを食べることは、自分の家での主要な生活活動になる。よく考えてみると、その他の生活活動は、別に自分の家でなくても、寝ること、お風呂に入ること、家族と一緒に過ごすことでさえも、できる。
では、自分で料理をつくらない人は、自分の家はいらないのかというと、別になくても、それこそ、余計にお金はかかるかもしれないが、ホテル暮らしをしている方が良いかもしれない。ただ、それで安全地帯にいるような安心感が得られるかどうかは別の話だが。
お腹が空くのは生理現象だから、そのために何か食べ物を用意しなければならないことは誰でも同じ、ならば、極端なことを言えば、自分でつくる人にとって、自分の家=キッチン、と言っても差し支えないだろう。
私は家で仕事をしているが、寝る時以外は、ダイニングにずっといる。仕事部屋はあるのだが、今や資料や本の置き場で、ダイニングテーブルで仕事をする。
大した料理をする訳ではないが、このスタイルになったのは、豆を煮るようになってから、途中経過が気になって仕方がなかったのと、豆を煮ている時の匂いが大好きだったので、近くで仕事をするようになり、今ではキッチンの真横が定位置、冷蔵庫も近いし、コーヒーも豆から挽いていれるから、都合がよくて。
だから、1日の家での居場所の分布図をつくったら、とても狭い範囲におさまるだろう。ならば、規模を小さくして、キッチンで暮らせば良いと思っていて、その分空いた所は庭か何かにして、隣家との距離をより多く取り、窓からより多く陽の光を取り入れたいと考える。
"Kitchen life"
You can only cook and eat your own food at your own home. Your home includes villas and homes, and you cannot enter camp.
So cooking and eating is a major activity at home. If you think about it, you can do other life activities, even if you are not in your own home, sleeping, taking a bath, or even spending time with your family.
So if you don't cook yourself, you don't need your own house, even if you don't need it, it might cost more, but you might want to live in a hotel . However, it is a different story whether it will give you a sense of security as if you were in a safe zone.
Hungry is a physiological phenomenon, so everyone has to prepare food for that, so if you say the extreme, for those who make it, your home = kitchen It would be safe.
I work from home but stay in the dining room except when I sleep. Although there is a work room, I now work at a dining table in the storage of documents and books.
I didn't cook a lot, but this style was because I started cooking boiled beans, and I couldn't help thinking about the progress, and the smell of cooking beans I loved it, so I started working nearby, and now it is convenient because the kitchen is in place, the refrigerator is close, and coffee can be ground from beans.
So, if you make a map of whereabouts at home in a day, it will fit in a very narrow area. If so, I thought it would be nice to make it smaller and live in the kitchen, and make that space a garden or something, take more distance from the neighbor and take in more sunlight from the windows I want to.
「さてと、何をつくればいいのか?」と考えてみる。
何かポーンっと、お題を与えられれば、案外自動的に、ポーンっと出てくるのだが、そればかりではつまらないから、その自動的な中身をよくよく見つめ直してみようと試みる。
そこで、2つの分かれ道に出会う。
1つは行き先を決めないで、その時、その時を積み上げていく道と、もう1つは行き先を決め、ただひたすら、そこに向かって進む道と。
どちらかの道が正解で、どちらかの道が不正確、ということは無く、ただ、道によって、辿り着く場所は違う。
ちょっと、行き先を決めて進むやり方はずっとしてきたし、仕事ならば尚更で、行き先を決めないと何も計画通りには進まないので、ただ、何ができれば満足するのだろうかと考えてみると、まず行き先を決めてしまうと、重い道のりになり、それは、できあがるものに良い影響を与えないだろうから、行き先を決めるのは止めて、進む道中のことを、如何にしたら、道中が楽しみになるかな、そのためには、どうするかなと考えてみる。
つくりたいものの理想は持ちつつ、毎日、何をつくろうかな、どうやってつくろかな、と考えること自体から楽しい状況がいい。
そうすると、つくり方が楽しいものでないと、ただ、つくり方ほど、決まっているものは無い。その都度、つくり方が変わっていたら、広まらないし、効率が悪いから、ただ、楽しむためには。
ということで、つくり方から考え直す試みをはじめていて、久しぶりに夜のKinko'sに来たのでした。
"Rethink"
Think about "What should we make?"
If you are given a pawn and a title, it will come out automatically, but it will not be enough, so I will try to take a good look at its automatic contents.
So we meet two forks.
One is to decide where to go, and then to build up that time, and the other is to decide where you want to go and just go to that.
Neither road is correct or one is incorrect, but the place to reach depends on the road.
I've been doing a lot of ways to decide where to go, and if it's a job, it's much more so if I don't decide where to go, nothing will go according to plan. First of all, if you decide where to go, it will be a heavy road, and it won't have a positive effect on what you'll get, so stop deciding where you want to go, and how you look forward Kana, think about what to do for that.
Having the ideal of what you want to make, it's a fun situation to think about what to make and how to make it every day.
Then, if the method of making is not fun, there is nothing as fixed as the method of making. If the way of making changes each time, it won't spread and it's inefficient, so just enjoy it.
So, I started an attempt to reconsider how to make it and came to Kinko's at night after a long time.
光の移り変わり具合をずっと眺めたことがあるだろうか。影でも同じ、ひとつの所に留まって、じっと何時間も光や影を眺めたことがあるだろうか。
やろうと思えばできなくはない。簡単にやるならば、自分の家でできる。窓から差し込む光の軌跡を追えばよい。ただ、ボーッとして眺めているだけでいい。
でもやる人はいないだろう。そこまで暇な人がいないし、そもそも飽きてしまって見ていられない。
名建築といわれる所に泊まることができても、朝日を浴びるくらいしかできない。1日中いることはできない。
ただ、設計する側はその光の移り変わり具合を計算していたりする。どこに開口部を取るかを考える時に想像している光を。
はじめて見学した建築家の作品は安藤忠雄「光の教会」である。建築の俗名にもあるように、光の十字架が特徴的な建築で、コンクリート打放しの壁に十字状にスリットが入っている。その時に、その十字架の光の移り変わり具合を午前中から夕方、暗くなるまで眺めていた。打放しの壁に十字状にスリットが入っているだけのシンプルな建築なのに、その光の移り変わり具合の豊かさに感動し、それが設計をはじめるキッカケだった。
光は誰にでも平等に手に入る。その光に十字架の形を与えてしまうのは建築家の力量だと、その時素直に思い、こういう仕事がしたいと思った。そして、その時にいつも目にしている光の可能性に気づき、それ以降も光を意識するようになった。
今まで意識していなかったことを意識付けされ、しかもそれに感動したから、建築というものが強く印象付けられてしまった。
"light"
Have you ever watched the transition of light? Have you ever stayed in the same place with shadows and looked at light and shadows for hours?
If you want to do it, you can't do it. If you do it easily, you can do it in your own home. What is necessary is just to follow the trace of the light which injects from a window. You just have to watch it.
But no one will do it. There aren't many people out there, and I'm tired in the first place.
Even if you can stay in a place that is said to be a famous building, you can only take the sun. I can't stay all day.
However, the designing side calculates the degree of change of the light. The light you are imagining when you think about where to take openings.
The first architect to visit is Tadao Ando's "Church of Light". As is known in the name of architecture, it is a structure with a cross of light, and there are slits in the shape of a cross on the concrete wall. At that time, I watched the light transition of the cross from morning till evening until it became dark. Even though it was a simple structure with slits on the wall, it was impressed by the richness of the light transition, and that was the beginning of the design.
Light is available to everyone equally. I thought that it was the architect's ability to give the light a cross shape, and at that time I wanted to do this kind of work. At that time, I realized the possibility of the light that I was always seeing, and after that I became aware of the light.
I was impressed with what I hadn't been aware of before, and I was impressed with it, so I was impressed with architecture.
軽井沢にある篠原一男のTanikawa Houseでのお茶会後、名残惜しく、その地を離れる前に、もう一度、建物の周りを巡って、斜面を登り、南側から見た時だった、今までの様相とは違う表情が見え、ハッとし、思わず「いい」と呟いてしまった。
その時すぐに写真に納めたが、それをお見せできないのは残念だが、それまで強い建築の形式故に、その形式の強さが先導して、この建築はこう理解するのがよろしいという指示の元、確かにそれが素晴らしく、感動してはいたので、満足していたが、その瞬間、形式を超え、建築が周りの空気と同化したような、一瞬建築が消えたような、周りの自然と同化したような、考えてみれば、自然ほどそのルールに則った形式の強いものは無く、その自然の形式に建築の形式が同化した、いや、そのものになったような錯覚が起こった。
そのような感覚を覚えたのはじめだった。この感覚を味わっただけでもここに来て良かったと思ったが、それも一瞬だった。
建築の形式が強いことが時には権威的と批判されることもあり、いかに弱めるかがデザインの暗黙の了解である時もあるが、いや、もしかしたら、形式の強さには別の可能性があるのかもしれない、何故なら、やはり形式の強さには惹かれてしまうから。
"Illusion of the moment"
After the tea party at Tanikawa House by Shinohara Kazuo in Karuizawa, before leaving the place, once again around the building, climbing the slope and looking from the south side, the situation until now I saw a different expression, and was relieved and unintentionally screamed "good".
I immediately put it in the photograph at that time, but I am sorry that I can't show it, but because of the strong form of architecture until then, the strength of that form leads, and I am instructed to understand this architecture like this Sure, it was wonderful and impressed, so I was satisfied, but at that moment, beyond the form, the architecture was assimilated with the surrounding air, the architecture disappeared for a moment, the surrounding nature and If you think of it assimilated, there are no strong forms that follow the rules of nature, and there is an illusion that the form of architecture has become assimilated into that natural form.
It was the beginning of learning such a feeling. I thought it would be good to come here just by tasting this feeling, but it was also an instant.
The strong form of architecture is sometimes criticized as authoritative, and how to weaken it is sometimes an implicit understanding of the design, but maybe there is another possibility for the strength of the form It may be because it is attracted by the strength of the form.
その建築は森の中で凛々しく光り輝いていた。
軽井沢にある篠原一男のTanikawa Houseでのお茶会に参加した。個人の邸宅ということもあり、長らく未公開の建築で、一般公開されたのは竣工以来今回がはじめてらしく、あまり使われていない時期もあり、竣工当時のそのままの姿で現存しているという。
説明によると、Tanikawa Houseとは、1974年、谷川俊太郎氏が一編の詩を建築家篠原一男氏に託して建てられた北軽井沢の別宅、とのこと。
この住宅の特徴は、斜面地に建築され、その斜面がそのまま住宅内に連続して現れたような傾斜した土間を持っていること。その土間は、南北に9mの幅で、1.2mの落差を持ち、火山灰が一面敷き詰められている。この土間で谷川俊太郎は様々なイベントを行うことを想定していたらしい。
さらに、その土間には、45度の方杖が付いた太い柱が、存在を強調するように配されていた。
また、屋根が地面から1m位の高さから45度の角度ではじまるので、斜面に屋根だけが載っている印象になり、外観の印象は全てが屋根で、その屋根の材質がシルバーに着色された亜鉛鉄板なので、森の中で光り輝き、その輝きは鈍く、時として、落ち葉なのか、錆なのか、わからない経年劣化が周りの木立と絶妙な調和をはかっていた。
全体の印象としては、斜面地にシルバーの屋根が架り、それを太い柱が支え、壁が外部と内部を仕切り、斜面がそのまま室内の土間に露出して、これらの建築の架構要素が強調されることによって、建築の形式が強く打ち出され、建築が初源的な姿で、凛々しく自然の中に鎮座していた。
ところが不思議なもので、その強い建築の形式が自然の中で存在感を出しながら、うまく自然と馴染んでいた。
何故だかわからないが、その強い建築形式にとても惹かれた。
(その場での写真撮影は可でしたが、SNS等での建築写真の投稿は不可でした)
"Tanikawa House Autumn Tea Party"
The architecture shone brilliantly in the forest.
I participated in a tea party at Tanikawa House by Kazuo Shinohara in Karuizawa. It may be a private mansion, and it has been unpublished for a long time, and it has been open to the public since it was first completed, and there are times when it has not been used so much.
According to the explanation, Tanikawa House is a separate house in Kita Karuizawa, built in 1974 by Shuntaro Tanikawa entrusting a single poem to architect Kazuo Shinohara.
The feature of this house is that it is built on a sloping ground and has a sloping soil where the slope appears continuously in the house. The soil is 9m wide from north to south, has a drop of 1.2m, and is covered with volcanic ash. It seems that Shuntaro Tanikawa was supposed to hold various events in the space.
In addition, a thick pillar with a 45-degree cane was placed between them to emphasize its existence.
Also, since the roof starts at an angle of 45 degrees from a height of about 1 m from the ground, it becomes the impression that only the roof is on the slope, all the appearance impression is the roof, the material of the roof is colored silver Because it was a galvanized iron plate, it shone in the woods, and its brightness was slow.
The overall impression is that a silver roof is built on the slope, a thick pillar supports it, the wall partitions the exterior and interior, and the slope is exposed as it is between the indoor soils, emphasizing the structural elements of these buildings As a result, the form of the architecture was strongly launched, and the architecture was in its original form and was majestically settled in nature.
However, it was mysterious, and its strong architectural form made a presence in nature, and it was well adapted to nature.
I don't know why, but I was very attracted to its strong architectural style.
(Photographing on the spot was allowed, but posting of architectural photos on SNS etc. was not possible)
「〜らしい」とか、「〜らしく」とか、「〜風」は結局、「〜」では無いということなのに、それは当たり前だけれども、「〜」だと勘違いをついしてしまう。
例えば、「建築家らしい」振る舞いとか、「建築家らしく」行動するとか、何の職業や肩書きでも良いが、その人はその職業や肩書きでは無いから、あるいは、無いと思うから、そう考えるのだろう。
例えば、「和風」料理は、和食風味の料理ということであり、和食では無いし、「欧風」料理も、かなりアバウトだが、フランス料理っぽいとか、イタリア料理っぽいもので、フランス料理でも、イタリア料理でも無い。
「自分らしい」とか「自分らしく」も同じ、そう言っている時点で、自分では無い。
そもそも「〜らしい」「〜らしく」「〜風」などとなると、曖昧になり、その曖昧さを求めているならば良いのだが、案外言っている本人はその曖昧さを求めてはおらず、しっかりカッチリしたものをイメージしていて、ただ、そのものズバリを言い当てる言葉を持ち合わせていないか、頭の中がクリアでは無いのか、自信が無いのかもしれない。
それに「〜らしい」「〜らしく」「〜風」などは全て、外からの決めつけみたいなもの、慣習であったり、常識と言われて範囲のことであったりして、社会的な識別には役に立つかもしれないが、その人であったり、そのもの自体は、それとは別に存在していて、それとは別に成り立ちがあるのだから、何か中身のなる人なりものなりにしたければ、どうでも良いようなことだと思う。
なんて、当たり前のことだろう、なのに自分に対して「〜らしい」とか、「〜らしく」とか、普通に思ってしまうから、それを取り除いた先をイメージしてみようと。
"Like"
Although it seems to be "~", "~ like", or "~ wind" is not "~", it is natural, but it is misunderstood.
For example, you may behave as an "architect" or "behave as an architect", any occupation or title, but because that person is not or does not have that occupation or title, think so. Let 's go.
For example, "Japanese-style" cuisine is a Japanese-flavored dish, not Japanese, and "European-style" dishes are quite about, but they look like French or Italian food. It's not cooking.
The same is true of "Like me" or "Like me".
In the first place, when it becomes "~", "~" or "~", it becomes ambiguous and it is good if you are seeking the ambiguity, but the person who says unexpectedly does not seek that ambiguity, firmly You may be imagining something that is cluttered, but you may not be confident that you don't have words to tell you exactly, or that your head is not clear.
In addition, "~", "~" and "~ wind" are all things that seem to be determined from the outside, such as customary or common sense, and range. It may be useful, but the person itself, or itself, exists separately from it, and it has a separate origin, so if you want to be something inside you don't care I think that's true.
I don't think it's normal, but I usually think of myself as "~" or "~", so I'd like to imagine where it was removed.
最近出会って、ハッとした文章から、
『考えてみれば、とくに自己表現なんかしなくたって人は普通に、当たり前に生きていけます。しかし、にもかかわらず、あなたは何かを表現したいと願う。そういう「にもかかわらず」という自然な文脈の中で、僕らは意外に自分の本来の姿を目にするかもしれません。』
ある人から、だいぶ前に、村上春樹の『職業としての小説家』は面白いから、文章だけでは無く、何かをつくる人は読んだ方が良いから、と言われた。前に『走ることについて語るときに僕が語ること』は読んだことがあり、ただ実は、村上春樹の小説を読んだことが無く、興味も無かったので、人から言われてもすぐには読まなかった。
そうしたら、また最近、ちがう人から、同じことを言われたので、それならばと読みはじめ、冒頭の文章に出会った。
普通につくれば、人はそれだけで喜んでくれるし、感謝もしてくれる、それで生活もできる訳だから、こんな良いことはないとは思うし、それで当たり前に生きていけるけれど、つくっている本人は、出来上がったものに物足りなさを感じる、出来上がったものがつまらないと感じる、「にもかかわらず」そう思うから、だから、何かをしたくなる、何かを変えたくなる。
そう思うことの中身を抽出して、そう思わないようにしてやれば良い。とてもシンプルで単純な話だ。
ところが、そこをあれこれやり過ぎて、結局は不自然な方向へ行き、不自然なことをしはじめる。今度は、そのとてもシンプルで単純なことをやることに物足りなさを感じるから、何か自分なりの表現を意図して持たないといけないと考えてしまうから、それが作家性であり、作品性につながると考えてしまうから。
「にもかかわらず」という問いかけは、自己表現することが、とてもシンプルで単純な話であることを思い出させてくれた。
"in spite of"
Recently met, from a surprised sentence,
"If you think about it, people can live normally, especially if they don't do self-expression. But nevertheless you want to express something. In such a natural context of "in spite of that", we may be surprised to see our original appearance. ]
A long time ago, Haruki Murakami's "Novel as a profession" was interesting, so it was better to read not only the text but also the person who made something. I've read "What I say when I talk about running" before, but in fact, I've never read a novel by Haruki Murakami and I wasn't interested in it. I didn't read it.
Then, recently, another person told me the same thing, so I started reading and met the first sentence.
If you make it normally, people will be pleased with it alone, thank you, and you can live with it, so I think that there is no such good thing, so you can live naturally, but the person who is making it, I feel unsatisfactory with what I'm finished with, I feel like it's boring, I think "even though", so I want to do something, I want to change something.
You can extract the contents of what you think so that you do not think so. It's a very simple and simple story.
However, if you do too much, you will eventually go in an unnatural direction and begin to do unnatural things. This time, I feel unsatisfactory in doing that very simple and simple thing, and I think that I have to have something of my own expression. Because it thinks that it is connected.
The question "Despite" reminded me that expressing myself was a very simple and simple story.
台風が去った後、翌朝の澄んだ青空を気持ち良く迎えることができ、雨戸を開け、家の周りを点検し、本当に幸いにも何も被害が無く、また普段の生活に戻ることができたが、被害に遭われた方々のことを思うと胸が痛く、Facebook上では、ラグビーの歓喜と、被害の状況が、交互に映り出されて、そうなると、自分からそれらの事実がどんどん遠ざかるような気がして、どちらも現実で、どちらも大変なことだが、あまりにも両極端な出来事過ぎて、現実感が追いついていかない。
その現実感が追いついていかない様は、あの強烈な台風の最中にも感じていて、あまりにも雨風が酷くて、でも何もできない、ただじっと耐えるしかない状況で、ことさら不安にならないようにするためには、これは現実では無く、フィクションで、映画のセットの中に迷い込んでしまった位に思わないと、対応できない位だった。
だから、それが翌朝の青空でリセットされ、喉元過ぎれば熱さ忘れる、になるかと思ったが、そうは簡単には行かずに、続きがあり、あまりにも自分の状況とは違う被害状況に戸惑い、それは同じ台風に自分も晒されたからで、なぜか落ち着かない、ソワソワ感が止まらない。
ただ、それでも、明日はどうしようかな、何をしなくてはいけないのかなと考えるのだから、それは今日と明日を違うものにしようという意欲ととらえれば、きっと、その、落ち着きの無さやソワソワ感は、現実を脳か身体か心が消化しようとしているサインかもしれないと受け止めることにした。
"Reality"
After the typhoon left, I was able to greet the clear blue sky comfortably the next morning, opened the shutters, inspected the house, and fortunately there was no damage and I was able to return to my normal life. When I think about the victims, my heart hurts, and on Facebook, the joy of rugby and the situation of the damage are reflected alternately, and then I feel that those facts are moving away from me. However, both are real and both are tough, but both extreme events are too much to keep up with reality.
I don't want to be overwhelmed by the fact that the strong typhoon feels that the reality is not catching up, the rain and wind are too severe, but I can't do anything, I just have to endure it. For this reason, this was not a reality, it was a fiction that could only be dealt with if you didn't think you got lost in the movie set.
So, I thought that it would be reset in the blue sky the next morning and forget about the heat if it is too close to my throat, but it will not go so easily, there is a continuation, and I am confused by the damage situation that is different from my situation, That was because I was also exposed to the same typhoon, so I couldn't calm down.
However, I still think what I should do tomorrow and what I have to do, so if I think that it is a willingness to make today and tomorrow different, I'm sure the calmness and feeling of sorrow I decided to take reality as a sign that my brain, body, or mind is trying to digest it.
先の台風でもそうでしたが、被害に遭われた方々のことを想うと胸が痛みます。例え、対策をし尽くしたとしても、それを上回る自然の力の前にはなす術がない。きっと大昔の人は、特に日本人は、抗うより、受け入れることで、こういう状況を乗り越えてきたのでしょう。だから、昔よりは、それでも治水に関しては良くなったと、子供の頃はよく神田川が氾濫していたのが無くなったり、賛否があってもダムが今回の台風による被害を軽減させたらしい。
水と食料が当たり前にあるから、それが無くなることを想像できない、できても想像力が及ぶ範囲が狭い。今回、自分がいる地域は断水も停電もしなかったが、それはたまたまで、あの強烈な雨風の中、家にいて、いつ停電しても、いつ断水しても、おかしくない状況だと思っていた。
対策はしていて、バッテリー、ソーラーパネル、カセットコンロ、食料、水は貯められるだけ貯めて、ただ、実際に停電や断水になった場合、これで何日持つか、何日持たせれば復旧するかもわからないのに、対策をするのは難しかった。
当たり前の物だから、余計に実感が湧かない、無くなることを、それは豊かの代償かもしれないが、対策をして電源、食料、水が十分にあったとしても、いざ停電や断水になったら不安は消えないだろう。
強烈な雨風の中で一番思っていたのは、普段通りに生活を、時間を、送ること。特別に対策をし過ぎると、かえって不安が消えないし、疲れてしまう。
だから、今、停電や断水を経験している方々には、電源、食料、水がもちろん大事だが、早く普段通りの生活や時間の送り方ができるようになって欲しい。ライフラインや住む所の復旧には時間がかかるかもしれないが、それでも、生活や時間のリズムが普段通りに戻すことができれば、精神的にはだいぶ落ち着き、疲れなくなるだろうし、そのためには自然の力は受け入れて対応するしかできない。
"Power of nature"
As with the previous typhoon, my chest hurts when I think of the people who have suffered the damage. Even if you take all the measures, there is no way to do it before the power of nature that exceeds it. Surely people in the past, especially Japanese, have overcome this situation by accepting rather than resisting. Therefore, it seems that the flood control has improved from the past, and it seems that the Kanda River was often flooded when I was a child, and even if there were pros and cons, the dam reduced the damage caused by this typhoon.
Since water and food are commonplace, we cannot imagine that it will be lost, but if possible, the range of imagination is narrow. This time, the area I was in had no water outages or power outages, but it just happened that I was at home in the intense rain and wind, and I thought it would be a strange situation even if there was a power outage or a water outage. .
Measures are taken, batteries, solar panels, cassette stoves, food and water are stored as much as they can be stored, but if there is actually a power outage or water outage, how many days will it last, and how many days it will recover I didn't know, but it was difficult to take measures.
Because it is a natural thing, it may be a price for richness that it will not feel real or disappear, but it may be a price for richness, but even if there is enough power, food, water, it will be uneasy if it becomes a power outage or water cut Will not disappear.
What I thought most about the intense wind and rain was to spend my life and time as usual. If you take too many special measures, your anxiety will not disappear and you will get tired.
So, for people who are experiencing power outages and water outages, it is important to have power, food, and water, but I want them to be able to live and live as usual as soon as possible. It may take some time to restore your lifeline and place of residence, but if you can restore your life and time rhythms to normal, you will be much more calm and tired. Power can only accept and respond.
家はつくづく、シェルター、だと思う。
台風の対策を、ここまでしたのははじめて、全部の雨戸を、閉めたのもはじめて、3日前から、対策したのもはじめて。
今回は事前から、恐いくらいに、台風の影響を気にして、はじめて、停電した、断水した、その後どうするとして準備した。
今までは、何とかなる、だった。仮に、停電しても、断水しても、何とかる、何とかしてくれる、だった。
千葉の人たちが、大変な思いを、されているのもあるし、それを自分に、置き換えて、水と食料、いつも食べているものを、蓄えた。
で、最後は、家である。いくら、水と食料があっても、家が持たないと、何の意味も無い。
しかし、対策は限られる。簡単に言えば、窓をどうするかだけ、その他は、そもそもの家の、ポテンシャルの問題。
だから、頑丈に、つくりましょう、と言いたいのではなくて、この台風の機会に、余裕がない機会に、家は、シェルター、それも、心のシェルター、だとつくづく思う。
家のつくり、がどうのこうのでは無くて、家という囲われた安全地帯のありがたさ、中では、外とは、全く関係なしに、過ごせるありがたさ、それがある安心感、家がもし必要だとしたら、それが一番だと。
乱暴に言えば、家で行う機能は、全て、外で賄える。食べることも、寝ることも、その他のことも、全て、賄えないのが、安心感。安全地帯という、心の持ちよう。
それを、心底経験すると、家に対する想い、が変わる。
"Shelter of the heart"
I think the house is a shelter.
This is the first time I have taken countermeasures against a typhoon, the first time that all shutters have been closed, and the first three days before that.
This time, I was prepared for the first time because I was worried about the effects of the typhoon, and after a power outage, water cut off, and then what to do.
Until now, it was going to be somehow. Even if there was a power outage or water outage, it managed to manage it.
Some people in Chiba had a great feeling, replaced it with themselves, and stored water and food, what they always eat.
And the last is a house. No matter how much water and food you have, if you don't have a house, it has no meaning.
However, measures are limited. Simply put, what to do with the windows, the other is the potential problem of the house.
So, I don't want to say that I should make it sturdy, but I think that the house is a shelter, a heart shelter.
It's not like how a house is built, but the appreciation of the enclosed safety zone of the house, inside, thank you for being able to spend it without having anything to do with the outside, if there is a sense of security, if the house needs it, Is the best.
Roughly speaking, everything you do at home can be done outside. I can't afford to eat, sleep, or anything else. Let's have a safety zone.
If you experience it, your feelings for the house will change.
前に何度か行った本屋の前をたまたま通りかかり、目的地に行く途中、後で時間があったらと思いながら、前に行った時はどうだったかと思い返し、デザインや建築の書籍専門で、何だったか前に購入したようなと思いつつ、思い出せない。
そこは1年1度くらいしかいかない通り、近くに役所があるからそこら辺にはよく行くけれど、なかなか雰囲気のある通りで、地元の商店ばかり、肉屋、魚屋、八百屋があり、スーパーがない、夕方には惣菜目当ての買い物客が溢れはしないが適度にいて、触れ合いもありつつ、若い人が好きなようにお店をしている、飲食だけでなく、雑貨屋なども、ちょっと裏通りに入ったら、前によく見たドラマの舞台になったお店も発見、表の通りのお店のバリエーションがおしゃれから下町風まで、車もあまり通らないし、住みたい街、その通り沿いにある本屋へ用事の帰りに寄った。
本が綺麗に飾ってあり、雰囲気からしてデザイン本を扱っているのがわかる。規模は小さいので、たくさんは無いがチョイスに特徴がある本が並ぶ。
ただ、自分の趣味とは合わなかったし、建築に関する本もあまり無かった。ひと回り、適当に手に取り、パラパラと、またパラパラと、だけど、この時間は結構楽しい、大型書店とはまた別の、人の趣味をのぞき見しているような、それでいて、そう共感できるものがあると、妙に親近感がわく。
赤い函に入った大冊2冊組が目に止まる。パウル・クレーの『造形の思考』、上下巻あり、クレーのことはあまり知らず、バウハウスで教鞭を取っていたことぐらいで、もちろん、作品もその本のことも知らなかった。
手に取ったのはタイトルに惹かれたから、「造形」しかも「思考」と来たら何が書いてあるのかな、けど、そこまで期待せず、赤い函に黒いタイトル文字が何となくカッコよかったし、それまで、パラパラと流しながら本を眺めていたので、ちょっとじっくりと目を通してみようかなと。
クレーのこと、この『造形の思考』のことは、人からも聴いたことが無かったし、私の周りで話題にのぼることも無かった、それがどうしてと不思議に思うくらい、パッと適当に広げたページから引き込まれた。
造形に関することが言葉と図解で論理的に展開されている、その一つ一つを見て行くと、造形の初源的なことの成り立ちを解説していて、これほど造形に関することをわかりやすく、それも的確に教えているテキストに初めて出会った。
そこに出るくるワードが普段自分が設計する時に念頭に置く言葉であったり、ただ、そこまでストレートに図解に組み込み説明しているテキストには今まで出会わなかった。もう当然気になるし、もっとじっくり読みたくなる。Amazonばかりだけど、本屋へ行くのはこれがあるから、もう当然手に、となるのは必然でした。
"The book I met"
I happened to pass in front of a bookstore that I had visited several times before, and I thought that there was time later on my way to my destination, but I thought back how I was before, specializing in design and architecture books, I can't remember what I thought it was before.
There is a government office nearby because it only goes about once a year, but it is a street with a lot of atmosphere, there are only local shops, butchers, fish shops, greengrocers, there is no supermarket, In the evening, shoppers for sugar beets are not overflowing, but they are moderate, there is also a touch, and shops are opened as young people like. Then, I found a shop that was the stage of the drama I saw before, the variations of the shop as shown in the table, from fashionable to downtown style, not much cars, and the city where you want to live, to the bookstore along that street I stopped by the errand.
The book is beautifully decorated, and you can see that it handles the design book from the atmosphere. Since the scale is small, there aren't many books, but there are many books that are unique to choice.
However, it did not match my hobby and there were not many books on architecture. I picked up and picked it up a little, and it was a lot of fun, but this time was quite fun, something different from a large bookstore, like looking at people's hobbies, yet something that I can sympathize with There is strangely a sense of affinity.
Two large books in a red box catch your eyes. Paul Klee's "Thinking of modeling" has upper and lower volumes, and I didn't know much about Clay, I was teaching at Bauhaus, and of course I didn't know the work or the book.
I was attracted to the title because I was attracted by the title, so what was written if it came to `` modeling '' and `` thinking '', but I did not expect so much, the black title letter was somewhat cool in the red box, Until then, I was watching the book while playing with it, so I would like to take a closer look.
I didn't even hear about Clay and this "Thinking of Thinking", and I did n't get to talk about anything around me. I was drawn from the page that I expanded.
When you look at each of the things that are logically developed in terms of words and illustrations, it explains the origins of modeling, and it's so easy to understand It was the first time I met a text that taught me exactly.
The words that come out there are words that I usually keep in mind when I design, but I have never met texts that are straightforwardly embedded in illustrations. Naturally, I'm curious and I want to read more carefully. Although it is only Amazon, there is this to go to the bookstore, so it was inevitable that it was already in hand.
今読んでいる本に、日々の生活の中でそれまで当たり前だと思っていたささいなことに気を止めてみて、それを問い直し、自分なりの言葉にしてみる、それが正しいか間違いかはどうでもよくて、そのプロセス自体を無償で愛することが「哲学する」ことだと書いてある。
自分が当たり前だと思って、特に気にも止めていなかったことが、ある日突然、たまたま目にした、耳にした、言葉や映像などによって、気になり出すと同時に、そのことについてもっと深く知りたくて仕方がなくなり、いつしかその当たり前の意識だったものが大きく変わってしまう、そのようなことを起こす言葉や映像などを投げかけることができたら、それが建築でできたら面白いと常々思っている。
日々の生活の中にはまだ気づいていない宝物がたくさんあると思っていて、ただ、それを自分の力だけで気づくのは難しく、自分以外からの手助けも必要で、設計はその手助けをすることだと昔から考えており、それを「宝物探し」に例え、自分はトレジャーハンターだと、探し出したお宝を、それを見せることによって、それまで気づかなかった、当たり前だと思っていた意識が変わってくれれば、動き出したらいいなと、昔ある人にそのことを言ったら失笑されたけれど、今でも同じように考えていて、では宝物とは何だと、その本には
「本当の宝物は、誰でも見えるところに落ちているから、むしろ見つけにくい。そして誰にでも手に入れられるから、自分だけの所有にすることはできない。」(堀畑裕之『言葉の服』より)
とあり、宝物だと思うと、特別なもの、見えないところにあるもの、自分だけのものと思っていたが、自分の目で見ているものと、そのもの自体の性質は違う時があるから、なるほどと宝物に対する意識が変わった。
自分なりの言葉にしようと、宝物とは何だと、一所懸命に考えたのに、この本の言葉に出会って、すーっと腑に落ちた、そして、自分が建築でやっていることを逆の立場から経験した。
「哲学する」その無償に愛するプロセスに浸りながら、自分以外からの手助けも受け、また「哲学する」、この入れ子状のプロセスが心地よく、この入れ子がたくさんできればできるほど、日常が豊かに、自分なりの日常を獲得できるような気がした。
"Philosophy"
In the book you are reading now, stop thinking about the trivial thoughts you have taken for granted in your daily life, re-question it, and try your own words. It doesn't matter, and it is written to love the process itself for free.
What I thought was taken for granted and that I didn't care about suddenly one day suddenly happened to happen, I heard it, heard it, words and images, etc. If you can throw a word or video that causes such things to change, something that is the natural consciousness will change greatly, I always think that it will be interesting if it can be done in architecture .
I think that there are a lot of treasures that I haven't noticed in my daily life, but it is difficult to notice it with my own power, and I need help from other than myself, and design helps I have thought of it for a long time, and compared it to "treasure hunting", and if I was a treasure hunter, showing the treasure that I found out changed my consciousness that I had never noticed before. If you tell me that I should start moving, I was laughed if I told a person in the past, but I still think the same way, so what is a treasure,
"The real treasure is so easy to find that anyone can see it, and it's hard to find it, and anyone can get it, so you can't make it your own." (From Hiroyuki Horibata's "Language Clothes" )
When I thought it was a treasure, I thought it was a special thing, something that was invisible, or something that was unique to me, but there were times when the nature of the thing itself was different from what I was seeing with my own eyes. I see, my awareness of treasure has changed.
I thought hard about what the treasure was, whether it was my own words, but I met the words in this book and fell into a trap quickly, and I reversed what I was doing in architecture Experienced from the standpoint of.
"Philosophy" Soak yourself in the process of loving yourself and receive help from other than yourself. Also, "Philosophy", this nesting process is comfortable, the more you can make this nesting, the more everyday you will be I felt like I could acquire everyday life.
そーっと、仕舞い込んでおくことにして、大事かどうだかはわからないけれど、いつか役に立つかもしれないし、何より面白い話だったから。
頭の片隅にその時感じたこと、その時考えたことと一緒に、そう村上春樹が言うところの頭の中の抽斗に仕舞っておこう。
久しぶりに楽しくて、興味深い話だった。普段から見て、いろいろと考えたり、感じたりしていることを科学的検知と歴史的認識と設計的思考で、いろいろな角度から論じた話は、今までにない思考を生んで、頭の中に新たな回路ができたような感じだった。
はじめから人に教えてもらう方が楽だし、自分自身が考えることはすでにわかっていることの先からで良いとするならば、本を読み、人にきき、ネットなどで調べて、それから考えはじめれば良いけれど、それではつまらない、もしかしたら、はじめから人とは違うことが思い付いたりして、そうしたら絶対にその方が良いし、その方が楽しい。
だから、今日のことは頭の中の抽斗に仕舞っておいて、結論を出さずに仕舞っておいて、いつか必要な場面が来たら抽斗を開けて、また考えることにしよう。その時には今とは違う自分がいるから、また違った展開が待っているかもしれないし、それを楽しみにして。
"drawer"
Softly, I don't know if it's important or not, but it might be useful someday and it was an interesting story.
Along with what you felt at that time in the corner of your head and what you thought of at that time, let's finish the drawing in the head that Haruki Murakami says.
It was a fun and interesting story after a long time. Talking from a variety of perspectives, using scientific detection, historical recognition, and design thinking to think about and feel various things from a normal perspective, gives rise to unprecedented thoughts, It felt like a new circuit was created inside.
If it's easier to get people to teach from the beginning, and if you want to think beyond what you already know, you can read a book, ask people, search on the net, and then start thinking It's good, but it's boring, or maybe you've come up with something different from a person from the beginning, and that's definitely better and it's more fun.
So, for today, let's finish the drawer in my head, finish it without making any conclusions, open the drawer when someday comes, and think again. At that time, I have a different myself, so I may be waiting for a different development, and look forward to it.
形が歪んだ、緑の彩色が施された器を見ると織部焼か、織部焼を真似た作品だとわかるくらい特徴的な器、作者の古田織部は最期、切腹させれた。そうすると、罪人の作品は一斉に無くなる、消えて無かったことになるらしい。
それまで端正で大振りだった茶碗が歪みはじめた。歪みや丸味を排し、黒々とした、無骨で武士が好みそうな姿をしていた茶碗から、丸味を帯び、歪み、彩色を施されたものが生まれた。
黒くて無骨で大振りな、きっと武士にふさわしい茶碗が大勢を占めると、それは権威と同等の価値が与えられるようになったのだろう。
そうなると、創造性豊かな人物ほど、その権威的なものを壊したくなる、それまで捨てられて相手にされなかったものの価値に気づき、注目する。
丸味や歪みの中に、端正で無骨以上の茶碗としての価値、茶の湯の道に沿い、より際立たせる姿を見出したのだろう。
その道程を計り知ることは難しいが、今現在も見ることができるその時代の織部焼は、ただ単に形が歪んで面白いとは違い、その形や彩色の中に見え隠れする端正で無骨なものから生まれた強さを感じるし、温和で柔らかいな印象の中にも黒くて大振りなものをも飲み込んでしまう海のような深さ、怖くもあるが、をも感じる。
器ひとつで人が亡くなる時代から残っていた物の凄み、それを今見て、そこに美とは何たるか、作品性とは、と振り返ることによって、今の人の意識を揺さぶることが素晴らしい。
"Workability"
The distorted shape of the vessel with a green color, and the distinctive vessel that can be seen as a work imitating Oribe Yaki or Oribe Yaki, the author's Furuta Oribe, was finally cut off. Then, it seems that sinner's works disappeared all at once, and disappeared.
Bowl it was up to a neat roundhouse began distortion. From a bowl that is black, rugged, and samurai-like, with distortion and roundness removed, it was born rounded, distorted and colored.
Black rustic, a roundhouse, when surely accounts for the many bowl worthy of the samurai, it probably came to be given the equivalent of the value and authority.
Sonaruto, as the rich person creativity, and want to break the authoritarian ones, aware of the value of those not in discarded opponent until then, attention.
In the rounded or distortion, value of as rugged more bowl neat, along the way of the tea ceremony, probably it found a more accentuate appearance.
It is difficult to measure and know the path, but the Oribe ware of that era, which can still be seen today, is not just distorted and interesting, but from the neat and rugged thing that appears and hides in its shape and color. I feel the strength that I was born in, and the depth and depth of the ocean that swallows black and big things in a mild and soft impression.
It is wonderful to shake the consciousness of the present person by looking at the amazing things left from the time when people died in one vessel, looking at it now, what is beauty there, and what is workability.
知りたいことを調べるのはほんと簡単で、スマホですぐに手に入る。だからか、知っていることが当たり前というか、知っていて当然というか、知らないと恥ずかしいと思う人が多いような気がする。
スマホで手に入る情報が本当に価値があるかはどうかは別として、それが知識なのかは別にして、例えば、財布を忘れるより、スマホを忘れた方が困るくらい、スマホは今や肌身離さずに持っているのが当たり前になった。
だから逆に思うのは、スマホで調べられる情報は、必要な時に必要なだけすぐに調べてわかることができるから、スマホで調べられる情報は、知らなくてもよいと、知らない方がよいと。
かなりのことがスマホで調べようと思えばできるはずで、そうすると、かなりのことを知らなくてもよい。
スマホではわからない、それでいて自分にとってはとても大事な知識だけ、それだけに集中して日常を送ることができる環境が今あると考えることができる。スマホやインターネットが無かった時代には考えられないくらい、自分にとって大事で、重要で、好きなことだけに集中できる環境が今ある。
今だに知っていることに価値を見出している人は、もしかしたら、情報の内容には関心が無くて、ただカタログを集めて遠くから眺めていることが好きな人なのかもしれない。それはそれで楽しいが、スマホでは手に入らない情報に直に触れようとした方が、日常がより豊かになると思うのだが。
"You don't have to know"
Finding what you want to know is really easy and you can get it right on your smartphone. That's why there are many people who know that it is natural to know, that it is natural to know, or that it is embarrassing if they do not know.
Regardless of whether the information you get on your smartphone is really worth it or not, whether it's knowledge, for example, it's harder to forget your smartphone than to forget your wallet. It has become natural to have.
So, conversely, the information that can be checked with a smartphone can be understood as soon as necessary when you need it, so if you do not need to know the information that you can check with a smartphone .
You should be able to do a lot of things on your smartphone, and then you don't have to know a lot.
It can be thought that there is now an environment that you can't understand on your smartphone, and that you can concentrate on your daily life with only knowledge that is very important to you. There is now an environment where you can concentrate only on what you like, important and important to you as you wouldn't have thought before in the days when there was no smartphone or internet.
People who still find value in what they know may be those who are not interested in the content of the information and just like collecting catalogs and looking at them from a distance. That's fun, but I think it would be richer to try to touch information that isn't available on a smartphone.
複雑なことを複雑なままにしておけるということは、同時に存在することが許されていること、それを別の言い方をすると、多様性が認められていること。
多様な状態は、一歩引いて俯瞰して見ると、違いだけが、差異だけが乱立している状態で、その差異に特徴があり、その差異に価値があり、その差異を表現しても良い状況ができている。
だから、多様な状態では、その差異で優劣が決まるから、元々の出自は関係が無くなる。実際には、出自が土台としてあって差異が生まれるから、出自は重要だが、多様な状態では差異に焦点が当たり、出自が見えなくなるから関係が無くなる。
単純な状態はその逆で、差異はむしろ余計なもので、出自で優劣が決まり、差異は関係が無い。そもそも、単純な状態は全てが可視化できていないと単純とはみなされないから、差異に焦点が当たると、複雑になり過ぎて全てが可視化できなくなるから、差異には焦点を当てずに、出自でグルーピングして優劣を判断する、その方が簡単でわかりやすく、管理がしやすいから。
多様な状態でも、単純な状態でも、どちらでも良いのかもしれないけれど、差異に価値がある方が創造性があるというか、工夫のしがいがあるから、ものづくりをしている人は多様な状態の方に興味が湧くと思うのだが、意外とそうでも無い。
"Diversified states"
Being able to leave a complex thing complicated means that it is allowed to exist at the same time, and in other words, diversity is recognized.
A variety of states, when viewed from a bird's-eye view, only the difference is a state where only the difference is random, the difference is characteristic, the difference is valuable, and the difference may be expressed The situation is ready.
Therefore, in various states, the difference is determined by superiority or inferiority, so the original origin disappears. Actually, the origin is important because it is based on the origin, but the origin is important, but in various situations, the difference is focused on and the relationship disappears because the origin is invisible.
The simple state is the opposite, the difference is rather superfluous, the superiority and inferiority are determined by the origin, and the difference is irrelevant. In the first place, simple states are not considered simple unless they are all visible, so when focusing on differences, they become too complex to be fully visualized. Group and judge superiority or inferiority because it is easier, easier to understand, and easier to manage.
It may be either a variety of situations or a simple situation, but people who are making things are in a variety of situations because the difference is worth the creativity or the ingenuity I think it will be interesting to you, but not surprisingly.
やったらダメと言われると余計にやりたくなり、さらにダメと言われるとやってしまう。やったらダメだとわかっていても、やっても大丈夫、問題無いと思うのと両方天秤にかけて、行ったり来たりしながら、2つの相反することが個人の中で同居している。
料理研究家の土井善晴さんの記事を読んだ。朝食に赤福と味噌汁で「これでええやん」と「家の中の多様性」を大事に、急速に多様化では無く単純化していく社会を嘆いていた。
人は皆違うと頭ではわかっていても、その違いを容認できずに、自分との違いを攻撃してしまう人をFacebookでもよく見かける。他人どころか自分でさえも一貫した考え方などできずに揺れ動いて違いが生まれるのだから、むしろ、揺れ動き、定まらず、今何をしたら良いのだろうかと考えてしまうことがある自分に気がついて、それで良いと自分に理解があれば、他人との違いなど気にならないし、寛容にもなれる、それが「多様化」の第一歩かな。
そもそも今の自分に理解があり認めている人は、他人との違いをむしろ面白く興味深く見ていて、そちらの方が良ければサッサと自分の考えなんて変えてしまうのだから、何事も流転する、だから、今の自分と未来の自分は違うと考えられると思っているようで。
そうなると、多様性とは物事を流転させる原動力になり、未来を明るくするには、どのような多様性を持ち得るか、多様性の質が鍵になるということか。
やっぱり、赤福に味噌汁は、毎日食べたいとは思わないけれど、赤福をお土産に貰ったら一度は試してみたい、たぶん、合うと思うし、それが朝食でも別にいいし。
"Sweet and miso soup"
If you say no, you will want to do more, and if you say no, you will. Even if you know that it's not good, you can do it. It's okay to do it, and you'll have no problem.
I read an article by cooking researcher Yoshiharu Doi. He was lamenting the society that rapidly simplified, not diversified, with the importance of "this is Eyan" and "diversity in the house" with Akafuku and miso soup for breakfast.
Even if you know that people are different, you can't tolerate the difference, and people often attack Facebook on Facebook. Rather than someone else, even myself can not make a consistent way of thinking and shakes to make a difference, but rather, I am aware of myself who sometimes thinks what to do now without shaking, uncertain, and that is OK If you understand yourself, you will not be concerned about the differences with others and you will be tolerant. This is the first step in "diversification".
In the first place, people who understand and acknowledge themselves now look at the differences from others rather interesting and interesting, and if they are better, Sassa and their thoughts will change, so everything will flow. It seems that I think that I am different from myself in the future.
In that case, diversity is the driving force for diverting things, and what kind of diversity can be possessed and the quality of diversity is the key to brightening the future.
After all, I don't want to eat miso soup for Akafuku every day, but if I buy Akafuku as a souvenir, I would like to try it once.
単純であることと複雑であることが同時に成り立つことは矛盾しているが、単純に見えて実は複雑、複雑に見えて実は単純、となれば同時に成り立つことは可能になる。
複雑に見えて実は単純より、単純に見えて実は複雑の方に惹かれる。質素で、シンプルで、でも本質はとても豊かであり、趣深いものが良いと思ってしまう。
それは日本人だからだろうか、日本の文化、例えば、料理にしても、建築にしても、和食にしても、数寄屋建築にしても、素材を大事にして、一見、質素で、シンプルだが、でも味わうと、とても滋味深く、豊潤で、奥深さに感心してしまう。
それは海外から見た日本のイメージでもあるかもしれない。日本人のデザイナーが海外で仕事をする時に、暗黙的に求められることらしく、ただ、意識しなくても、シンプルだが奥深い、単純に見えて実は複雑なデザインに見えるらしい。
複雑に見えて実は単純の場合は、見た目はデザインされ綺麗に見えるけれど、実は中身が無く、内容が無いということもあるが、複雑なことを複雑なまま見せている、とも言える。
複雑なことを整理して、何らかの解法を与えて、単純に見せれば、それが、単純に見えて実は複雑だが、複雑なことをそのままではなくて、複雑なまま成り立つような解法を与えて、複雑に見せれば、複雑に見えて実は単純になる。
それが、複雑に見えて実は複雑、とならないのは、実は何とは差分だから、最初からどのくらい変化したかの量が少なければ単純、多ければ複雑、となる。
ただ、複雑なことを複雑なまま見せる、ということに可能性を感じる。それは、何も無いところから1から何かをつくろうとした場合は、単純に見えて実は複雑、な状態を作りやすいが、何かあらかじめすでに存在している状態があった場合、すでにその時点で複雑になっている可能性があり、それを単純にするのは難しく、むしろ、複雑なものを整理して複雑なまま表現した方がやり易く、元々の状態とも馴染みが良いはずだから。
都市計画で失敗する例はまさに、複雑なことを無理矢理単純にしてしまうから、元々の状態と馴染めず違和感が出ることが原因で、複雑なことをそのまま複雑に解ければ、失敗する確率も減るだろう。
都市計画以外にも、建築でも、複雑なことを複雑なまま見せることで、日常がより豊かになるならば、その方が汎用性があり、可能性があるのではないかと思っている。
"Simple and complex"
There is a contradiction between being simple and complicated at the same time, but it looks simple and actually complex, and when it looks complicated and simple, it is possible to hold at the same time.
It looks more complex and actually attracts people who look simple and actually more complex than simple. It is simple, simple, but very rich in essence, and I think it is good.
I wonder if it is Japanese, or Japanese culture, such as cooking, architecture, Japanese food, sukiya architecture, cherish the material, seemingly simple, simple, but taste I am impressed by the depth and depth of the food.
It may also be a Japanese image seen from abroad. When Japanese designers work overseas, it seems that they are required implicitly. However, even if they are not conscious, they seem to be simple but profound, simple and actually look complex.
If it looks complicated and actually simple, it looks and looks beautiful, but in fact it may not have any content and may not have any content, but it can be said that it shows complex things as complex.
If you sort out complicated things, give some solution, and show it simply, it looks simple and it is actually complicated, but it does not leave the complicated things as they are, but gives a solution that can remain complex, If it looks complicated, it looks complicated and actually simple.
The reason why it looks complicated and does not become complicated is actually what is the difference, so it is simple if the amount of change from the beginning is small and complex if it is large.
However, I feel the possibility to show complicated things as they are. If you try to make something from scratch from scratch, it's easy to create a complex state that looks simple, but if something already exists, It may be complicated, and it is difficult to simplify it. Rather, it is easier to organize and express complex things as they are, and it should be familiar with the original state.
The example of failing in urban planning is simply complicating the complicated things, and because it is unfamiliar with the original state, if you solve the complicated things as they are, the probability of failure will also decrease right.
In addition to city planning, I think that in architecture, if the daily life becomes richer by showing complex things as they are, it will be more versatile and possible.
禅宗の修行で「夜坐」と呼ばれる夕食後に寝るまでの間で行う坐禅があると聞いたことがある。
1日を振り返る時間なのか、心を静かに落ち着ける時間なのか、いずれにせよ、日が落ちた後は行動的にならず、心身共に休める時間にするということだろう。
人は一日のうちでいつが一番活動的になるのかが遺伝で決まっているようで、朝の人、昼の人、夜、夜中とタイプがあるらしく、自分は朝から昼にかけての時間帯が一番活動的で集中力が増す。
なので、大半の仕事や大事な活動は朝から昼にかけて行い、夕方以降はおまけの時間、大事なことはしないで、静かに過ごすように、また明日、日が昇ってスイッチが入るまでの休憩時間だと思っている。
だだ、もちろん、夜に仕事をする時もあるし、人と会ったり、外食したりする時もあるが、それでも寝るまでの間をどう過ごすか、大事なことはしないが、明日のためには一番大事な時間帯で、家にいる時は、朝から昼の時間帯は特に意識しなくても良いが、寝るまでの間の時間帯は意識して、深い眠りができるような工夫をしないと、明日が気持ち良く過ごせないので、一日のうちで一番過ごし方を大事にしている時間帯になる。
だから、「夜坐」の心の有り様に興味があり、たぶん、収束するように心を落ち着かせるのだろうが、そうすると眠くならないのか、坐禅中に寝ることはできないので、どうするのか、眠たいのに寝られない状況程辛いことはないから、それが修行ということか、ならば、修行ではないから、もう寝よう。
"An important time"
I have heard that there is a Zen zazen called "Yoza" in Zen training, which is performed after dinner until sleeping.
Whether it's time to look back on the day or calm down, it's time to rest after both the day and the day.
It seems that people are genetically determined when it becomes most active during the day, and there are types of people in the morning, noon, night, midnight, and I am the time from morning to noon The belt is the most active and the concentration is increased.
So, most of the work and important activities are done from morning to noon, and after that evening, extra time, don't do anything important, be quiet, and tomorrow, rest time until the sun rises and switches on I think.
Of course, there are times when I work at night, sometimes I meet people and eat out, but it doesn't matter how I spend my time until I go to bed, but for tomorrow Is the most important time zone. When you are at home, you do not need to be aware of the time zone from morning to noon, but you should be aware of the time zone until you go to sleep so that you can sleep deeply. If you don't, you won't be able to spend tomorrow comfortably, so it will be a time of day when you spend most of your day.
So I'm interested in the way of the night-sitting mind, maybe calming my mind to converge, but if I don't get sleepy then I can't sleep during zazen, so I want to sleep It 's not as painful as a situation where you ca n't sleep, so it 's training.
実家は蛇口をひねると井戸水が出る。子供の頃は家の中に手押しのポンプもあり、そういえば、五右衛門風呂だった。端切れの木がたくさんあったから、そういえば、毎朝、作業場に行くと、大工さんが小型の斧で薪をつくっていた、風呂焚きの薪にするため、その薪を風呂焚きに使うと、風呂釜の中で木炭になる、その木炭を今度は火鉢に移して、夕餉の煮炊きに使う、冬はお餅を焼いたり、釜炊きのご飯も、それは台所から続く土間で行い、もちろん、外に持ち出して、これからの時期だと秋刀魚を焼いたりしていた。
土間に風呂焚きの薪を投入するところ、SLの薪を投入する口の小さいような所があった。そこに井戸も、手押しポンプもあり、そういえば、風呂炊きの煙突も、昔のお風呂屋は薪で沸かしていたから結構高い煙突があったが、そこまでではないが、風呂屋の煙突の小型版があり、そういえば、子供の頃は定期的に煙突掃除のおじさん、眼鏡をかけていて、帰る時はその眼鏡の部分だけが肌色だった、よく遊んでもらったような、風呂は板を沈めて入っていて、板無しで入ってそこに足がつくと火傷すると思い込んでおり、板があっても手で縁につかまって足を一所懸命に浮かしていたような気がする。
今は井戸水以外何も無い。
全て電気が無くても良く、時間と手間はかかるが、質素だが、無駄が無かった。今ではスイッチを押すだけ、あとは自動で済む、電気があれば。
子供の頃に戻りたいとは思わないし、家事労働が軽減されることは良いことだから、スイッチひとつで済む方が良い。ご飯だって、魚だって、子供の頃の方がスイッチひとつより美味しくできるかもしれないけれど、手間と時間の方が貴重、日常では、家庭では、スイッチひとつで十分。
ならば、井戸水だって、上水道があるし、井戸水用のポンプ、下水道料金もかかる、そういえば、ポンプを動かすのに電気も必要、でも井戸水だけは両親が残したのは、きっと、井戸水に愛着があったからだろう。
日常的に飲み、煮炊きに使い、洗濯や体を洗うのに使っていた、何があっても365日井戸水だけは確保されていた安心感、あるいは、それが浸透した生活感は何にも代え難いものだったのかもしれない。なぜそれがわかるかというと、井戸水と上水道の2つの蛇口が並んだシステムキッチンに立つと、井戸水の蛇口が正面の使いやすい位置にあり、いつでもその蛇口の水を使えるようにしてあったから。
それだけでも生活感というか、昔の人は生活することを生身で感じていたことがわかる。今とは感覚的に違う、それが災害になり、電気も無く、水も無くなったら、途端に生身で生活することを強いられる。今、その生活をしろと言われても無理だと思う、いくら備蓄して食料、飲み水があっても、山道具や、キャンプ道具があっても、遊びと生活は違うから、支障なく生活を送る術は、やはり、そう思うと、井戸水の存在は有り難い。
"water"
When the parents turn the faucet, well water comes out. When I was a kid there was a hand pump in my house, so it was Goemon bath. There were a lot of pieces of wood, so if you go to the workplace every morning, the carpenter was making a firewood with a small ax, and using that firewood for bathing, It becomes charcoal in the wood, this time the charcoal is transferred to a brazier and used for cooking the evening sun. In the winter, the rice cake is cooked in the soil that continues from the kitchen. In the coming season, I was grilling sword fish.
There was a place with a small mouth to put a bath jar between the soil and a bath jar. There are also wells and hand pumps. Speaking of the chimneys for cooking the baths, the old bathhouses were boiled with firewood, so there were quite high chimneys. Speaking of that, when I was a kid, I was wearing a chimney sweep regularly, wearing glasses, and when I went home, only the eyeglasses were skin-colored. I thought that if I entered without a board and got a foot there, I would burn myself, and even if there was a board, I felt like I was holding the edge with my hand and floating my feet hard.
There is nothing except well water now.
There was no need for electricity, and it took time and effort, but it was simple, but there was no waste. Now you just have to push the switch and the rest is automatic.
I don't want to go back to my childhood, and it's good that housework is alleviated, so it's better to have a single switch. Even rice, fish, and childhood may be better than a single switch, but both time and time are more valuable. In everyday life, a single switch is sufficient.
Well water has a water supply, well water pumps, and sewerage fees. In other words, electricity is needed to operate the pumps, but the parents left only well water. Probably because there was.
I used it for daily drinking, cooking and washing, washing my body, and the feeling of security that only well water was secured 365 days a day, or the feeling of life that permeated it was replaced by anything. It may have been difficult. The reason for this is that when standing in a system kitchen with two faucets, one for well water and one for waterworks, the faucet faucet was in an easy-to-use position on the front, and the faucet water was always available.
That alone is a sense of life, and it turns out that the old people felt that they were living. When it becomes a disaster, no electricity, no water, you will be forced to live live. I think it's impossible to live that life now, no matter how much you have to stock up, food, drinking water, mountain equipment, camping equipment, etc. After all, I think that there is well water.
川の流れの中に関をつくれば、流れが乱れ、関によって流れの影響が多少弱まる所ができる。
人の動きを流れに例え、関を建築の壁だとしたら、壁によって人の動きに影響が出て、立ち止まらなくていけない所に椅子やテーブルを置けば、そこが居場所かもしれない。
時間の経過を流れに例え、関を予定だとしたら、予定によって時間の経過に影響が出て、時間を費やさなければならない時に向き合えば、それが経験かもしれない。
空間の移ろいを流れに例え、関を人だとしたら、人の動きによって空間の移ろいに影響が出て、空間の移ろいがゆっくりとなる所を定めれば、そこが人が集まる場所かもしれない。
空間の移ろいは、例えば、車窓の景色かもしれない。それが、ゆっくりとなる場所は、そこに留まっている時、そして、そこに時間を費やしている時、そして、そこに壁をつくれば居場所になる。
人、時間、空間が相互に関係し合いながら、自然と居場所は決まるものなのだろう。そう考えると、居場所をつくることは、流れの中にいながら、流れを乱す行為、ただし、乱し過ぎて、流れが変わってしまったら元も子もない、そのバランス加減が技術かな。
"Technology for creating a place to stay"
If you relate to the flow of the river, the flow will be disturbed, and there will be a place where the influence of the flow will be somewhat weakened.
If you compare the movement of people to the flow, and Seki is an architectural wall, if you place a chair or table in a place where the movement of the person is affected by the wall and you have to stop, that may be your place.
If the passage of time is compared to the flow, and Seki is scheduled, it may be an experience if the schedule affects the passage of time and faces time when time must be spent.
If the movement of the space is compared to the flow, and Seki is a person, if the movement of the space is influenced by the movement of the person and the place of the movement of the space is determined slowly, that may be the place where people gather. .
The transition of the space may be, for example, the scenery of the car window. The place where it slows down becomes a place when you stay there, spend time there, and make a wall there.
People, time, and space are interrelated and nature and whereabouts are determined. When thinking so, creating a place is an act of disturbing the flow while in the flow, but if the flow changes too much, there is no original or child, and the balance adjustment is technology.
建築をずっとやってきているから、建築性が強い、別の言い方をすれば、作品性が強い建築に興味が湧く。
それは普通ではつまらない、街中によくあるもの、よく見るものなんて論外、何も考えていないし、綺麗に見せるだけならば誰でもできるし、もっと未知なもの、もっと既視感の無いものが見たい欲求があるからだが、建築に関わりが無い人からすれば、違和感があるというか、ちょっと理解ができない可能性もあり、それは建築をつくる側と使う側のズレ、というか、そこに断層が存在するような感じもある。
そもそも建築空間単体では成り立たないと思うが、人がいなければ成り立たないと思うが、建築空間単体で成り立つ自律性を欲してしまう、そこが作品性につながるのだが、それは人が無用という問題をはらんでいて、さらには、建築空間と認識するのは人ではないかという問題も含んでいる。
人が建築空間と認識するから、建築空間として存在しているのであって、人がいなければ、そもそも建築空間自体が存在しないことになるとハイデッカーは唱え、人自体が無用とされれば、建築は単に芸術作品としての価値のみしかなくなるが、それでも良いから、建築性が強い建築をつくりたいし、見てみたい。
ところが、そのような建築性の強い建築が日常を豊かにすると夢見ている。
日常は人がつくり出すものなのに、人自体を無用とした建築が日常を豊かにすると、本気で考えている。
この一見矛盾するつながりを解くことが今の課題であり、次への足掛かり、なぜか、それを考えるのがまた楽しい。
"Everyday and Architecture"
Since I've been doing architecture for a long time, I am interested in architecture with strong workability.
It's usually boring, things that are common in the city, things that you see often are out of the question, anyone can do it if you don't think about it, just show it cleanly, and you want to see something that is unknown or that is less visible However, if you are a person who is not involved in architecture, you may feel uncomfortable, or you may not be able to understand it a little. There is a fault between the side that makes the architecture and the side that uses it. There is also a feeling.
In the first place I think that it does not hold in a single building space, but I do not think that it does not hold if there is no person, but I want the autonomy that stands in a building space alone, that leads to workability, but that is the problem that people are useless In addition, there is a problem that it is human beings who recognize it as an architectural space.
Since people recognize it as an architectural space, it exists as an architectural space, and if there are no people, Hydecker advocates that the architectural space itself does not exist in the first place. It's just a value as a work of art, but it's still good, so I want to make a building with a strong architecture and see it.
However, I dream that such a strong architecture will enrich my daily life.
Even though everyday life is something that people create, I am seriously thinking that architecture that makes people useless will enrich their daily life.
Solving this seemingly contradictory connection is the current challenge, and it is fun to think about it as a foothold for the next.
遠くから見ているのと、実際に近くへ行って見るのとでは、見ているものは同じでも違うはずだと頭のどこか片隅ではわかっていても、両方を見比べて、違いを理解する、感じることはなかなかしないかもしれない。
遠くから見て思い込む、それも大体自分にとって都合良く思い込む、あるいは、過去の経験から、この程度のことだろうと判断する。いちいち、これは何だろうと興味を持っていたら、頭がパンクしてしまうから、そうして見切りをつけて、本当に大事なことだけに意識が集中するように、人の脳の構造がそうなっているのだろう。
ただ、その判断がその人にとって、正しいか間違っているか、良いか悪いかは別問題のような気がする、というか、とりあえず、そこで判断を一旦下すことが重要で、近づいてみたら、実はなんて、意外なことが待っていたりして、嬉しいサプライズが起こる場合もあるし、悲しく嫌なことになったり、逆に素晴らしい体験をしたりする。
そのような、見ることで意識的な変化が起こるデザインを、仕上げを考えているけれど、遠くから見たら感じないのに、近づくと装飾があるような、それを単純シンプルな方法で実現することを。
壁の仕上げをラーチ合板にして、鍋ビスで留めていった。ビスを使ったのは、合板の反り留めになるし、ならば、リベット打ちされた鋼板の木のバージョンをイメージして、頭がリベットのように丸い鍋ビスを使い、それも、鍋ビスの大きさ、色、鍋ビスのピッチを何種類も検討し、遠景、近景の見え方の違い、遠くから見た時はラーチ合板の木目だけが感じられ、近づくと鍋ビスの存在がたくさんの点となって装飾に感じるように、ラーチ合板を鍋ビスで留める、この単純でシンプルな方法に行き着く。ただ、それを見る人は無意識に感じてくれればいい、その方が、あまり意識的に引っ掛かりがあると、うるさいというか、空間に添加物が加わるようで不自然だと考えていた。
やはり、遠くと近くとでは違う、近くに行かないとわからないことも多いはず、それはもしかしたら無意識にもどかしさを、いや、もどかしい。
"I have to go nearby"
Whether you are looking from a distance or actually going to the near, what you are looking at should be the same or different, even if you know at some corner of your head, compare both to understand the difference , You may not feel it easily.
Thinking from a distance, thinking that it is usually convenient for me, or judging from past experience. If you're curious about what this is, your head will puncture, so you give up and give up, so that your mind's structure is so focused that it's really important. There will be.
However, for the person, whether the judgment is right or wrong, whether it is good or bad feels like another problem, or for the time being, it is important to make a judgment once there, What a surprise, sometimes a happy surprise, sometimes sad, disgusting, or a wonderful experience.
To realize such a design that changes consciously by seeing it, but I am thinking about finishing, but I can not feel it when seen from a distance, but there is a decoration when approaching, in a simple and simple way A.
The wall finish was made of larch plywood and fastened with pan screws. The screw was used to warp the plywood, and if it was an image of a wood version of a riveted steel plate, a round pan screw with a head like a rivet was used. Considering the various sizes, colors, and pan-screw pitches, the difference in how the distant and near-fields look, and when viewed from a distance, only the grain of the plywood can be felt. To make it feel like a decoration, we end up in this simple and simple way to fasten the larch plywood with a pan screw. However, the person who sees it should just feel unconscious, and if that person was caught too consciously, he thought it was noisy or seemed unnatural as an additive was added to the space.
After all, there are many things that are different between the distance and the vicinity, and there are many things that you do not know if you do not go nearby, which is probably unconsciously frustrated, noisy.
答えが溢れている、何かわからないことや疑問など、もうすでに世の中には存在しないくらいに、誰かが考え、その答えを用意していてくれて、また、その答えも誰かが出したものを元にしたものだったりするから、調べればわからないことなど無いと言える。
答えは時代とともに変わり、常に更新されていき、その状況は昔と、例えば、30年前と変わらないかもしれないが、昔、30年前のネットが無い時代は、その答えになかなかアクセスできなかったので、今ほど答えが溢れている感覚は無く、もしろ、もっと答えに飢えていて、どうやったら答えに辿り着けるのか、まず調べる手段を考えるところからはじめていたような気がする。
その調べる手段の1つが本を読むだった。簡単なことでも、尋ねる人が見つからない時など、とりあえず、近くの本屋へ、Amazonも当然無いし、昔は近所に本屋がたくさんあったから、本を探すのも、どの本を見れば答えを導き出すことができるのだろうかと、その時点で答えへ至る思考がはじまっていたように思う。
だから、答えを得た時も、そこまでに徐々に思考の積み重ねがあったから、そのまますぐに受け取るよりも、すでに少しは自分色に染まった答えになっていて、自分のものとして遜色なく、すぐに使えたような気がする。
前に聞いた話で、元プロ野球選手のイチローは本を一切読まないらしい。目に悪いからという理由の他に、本には必ず答えがあるから、それが嫌だと。何か自分に問われた時、本を読んで答えを得ても、知ったような気になっているだけで、その答えは自分で切磋琢磨して出したものではないから使えないし、意味が無いと。
思考すること無く、すぐに答えを得ることができる。それは、すでに明白な答えが存在するのに、いちいちそのことについて思考するだけ時間の無駄であり、わかっていることの先にある未知なる部分に早く取り掛かった方が効率的だという考えからすれば便利なことだろう。
しかし、その明白な答えをはじめから導き出すことと、未知なる部分の答えを導き出すことは、同じ思考能力を必要とするはず、ならば、その明白かもしれない答えを導き出すところから自分で切磋琢磨して、自分なりの思考能力を身に付けることが大事で、そうしないと、未知なる部分の答えも導き出すことはできないだろう。
だから、時には遮断、ネットを遮断、本を遮断、人の考えを遮断、答え探しをやめて、バカになって、ゆっくり自分なりに考えや思いを巡らすだけでも、休みの日には楽しいかも。
"answer"
Someone thinks and prepares the answer to the extent that the answers are overflowing, something unknown or questions no longer exist in the world, and the answer is based on something that someone gave It can be said that there is nothing that you do not understand if you examine it.
Answers change with the times and are constantly updated, and the situation may be the same as in the past, for example, 30 years ago, but in the past, when there was no internet 30 years ago, it is difficult to access the answer So, I don't feel like I'm full of answers, and I feel like I was starting to think about how to find out how to get to the answers.
One way to find out was to read a book. Even if it's simple, if you can't find the person you want to ask, for the time being, there are no Amazons in the vicinity, there is no Amazon, and there used to be a lot of bookstores in the neighborhood. I think that I could start thinking at that point in time.
So, when I got the answer, there was a gradual accumulation of thought so far, rather than receiving it as it is, it is already an answer that is a little dyed in my own color, and it is not inferior as my own, immediately I feel like I was able to use it.
As I heard before, former professional baseball player Ichiro seems not to read any books. I don't like it because it's bad for my eyes. When you ask yourself something, even if you read a book and get an answer, you just feel like you know it. Without it.
Get answers quickly without thinking. That is because there is already an obvious answer, but it is a waste of time to think about that one by one, and it is more efficient to start with the unknown part ahead of what you already know. It will be convenient.
However, deriving the obvious answer from the beginning and deriving the unknown part of the answer should require the same thinking ability. It is important to acquire your own thinking ability, otherwise you will not be able to derive answers to the unknown.
So, sometimes it's fun on a day off, just blocking, blocking the net, blocking books, blocking people's thoughts, stopping looking for answers, becoming stupid and slowly thinking and thinking.
何かがちょっとだけ変わるような出来事につながればよいと思い、想い描ければ。
直接的に物と関わり合うので、建築は、どうしても物の価値だとか、物の良し悪しだとか、物の金額が最初にきて、それが中心になってしまう傾向が強いが、並列して、それまでの慣習や思い込みや生活パターンなどがちょっとだけ良い方へ動くようなことも必要ではないかと思う。
新しく建築することが、それまでのことを新しく生まれ変わらせる、刷新するようなことに思ってしまうかもしれないが、どうしても、それまでの延長線でしたか考えられないと、結局、ただ建物が新しくなるだけで終わることも多い。
変化させたくない、保守的になる気持ちはわかるし、無理して変える必要も無いし、それまでと同じでも構わないと思うが、「もしよかったら」という形で、なるべく、接した中でこうすると、ちょっとだけ日常が豊かになるようなことをクライアントへの提案の際に添えるようにしている。
そうして7年前に添えたことを今実らせて、新しい壁を挿入中、7年前に目一杯想像力を発揮して、その想像の範囲内には今のところはおさまっているが、これからは想像の範囲外、どうなるか楽しみがまた1つ増える。
"If it's fine"
I hope it will lead to an event that changes something a little, and I want to draw my thoughts.
Because it is directly related to things, architecture is inevitably the value of things, the quality of things, the amount of goods comes first, and it tends to be the center, but in parallel , I think that it is necessary that the conventional customs, assumptions, and life patterns move slightly better.
You may think that building a new building will reinvent and renovate it, but if you can't think it was an extension of it, it will be just a new building. It often ends just as it is.
I don't want to change it, I understand the feeling of being conservative, I don't have to change it forcibly, I don't mind changing it as before, In doing so, I try to add something that makes my life a little richer when making proposals to clients.
So, now that I've added it seven years ago, while inserting a new wall, I showed my imagination to the fullest seven years ago. From now on, it's out of the imagination, and one more pleasure will happen.
ふるいの目、ざるの目、網の目、ふるいにかける物によって目の密度が決まっているようで、そこまで詳しくないが、料理でも、建築だと左官屋さんが使っている。
必要な物を選別したり、不要な物を残したり、精製するためにふるいにかけるから、目的に応じて目の密度の違うふるいを用意するのだが、その目の違いを使い分けるのにも技があるような気がする。
別の言い方をすると、フィルターにかける。物だけでなく、事柄にも言える話で、どの目を使い選別するのか、精製するのかによって、最初は同じ状態、状況でも、ふるいにかけた後は違ってくる。
このふるいにかける作業は人によって違うはずで、このふるいのかけ方が個性であり、それによって状態、状況が各人違ってくるはず。
ただ、このふるいのかけ方に一定のルールがあるものもあるかもしれない。それは例えば、学問とか、学術的なこと、それは歴史が重なってつくられたふるいのかけ方だから、個人のふるいのかけ方を優先はできないが、そこの差異を埋めるのが研究することなのかもしれないが、その差異を把握して上手く研究に結びつけるのにも、ふるいのかけ方同様、技が必要な気がする。
どちらかというと、ふるい自体に興味があり、どのようなふるいが世の中に存在するのか、料理するより料理道具が好きで、料理道具を使いたいから料理をするようなものだが、たくさんのふるい集めをしたくなる。
"sieve"
The density of the eyes seems to be determined by the sieving eyes, the squirrel eyes, the mesh eyes, and the objects to be sifted.
Screening for necessary items, leaving unnecessary items, and sifting for purification, we prepare sieves with different eye densities according to the purpose. I feel like there is.
In other words, it filters. It can be said not only for things but also for matters, depending on which eye is used for selection or purification, even in the same state and situation, it will differ after sieving.
The process of sieving should be different for each person, and the way of sieving is individuality, and the state and situation should be different for each person.
However, there may be some rules for how to apply this sieve. That is, for example, academic or academic, because it is a way of sieving created by overlapping history, it is not possible to prioritize personal sieving, but it may be researching to fill in the differences I don't think, but I feel that skill is necessary to grasp the difference and to connect it well to research, as well as how to sift.
If anything, I'm interested in the sieve itself, what kind of sieves exist in the world, I like cooking utensils rather than cooking, I like cooking utensils, but it is like cooking, but collecting a lot of sieves I want to
日々、芽が出てくる、新芽がまるで枯木に花咲くように出てくる。
自宅の塀を覆っていた蔦をだいぶ整理してリセット、一部を室内で育てはじめ、最初は枝の切れ端を水につけ、植物活力素も投入、まずは新しい気根が出て長く伸びるまでと思っていたが、白い気根が何本か見えた途端に新芽がムクムクと。
朝と夕で違いがわかるくらい、伸びるのが早い、生命力が強いのか、環境に慣れてきたのか、蔦は何か絡みつくものがあってはじめて取り付くように伸びていくそうなので、室内だと横に広がるだけらしい。
ただ、その伸びる様を見ているのが面白くて、キッチンに置いているのだが、キッチンに立つ度に見入ってしまう。成長していく様が楽しい。植物を育てる楽しみとはこういうものかと、この歳にして初めて思うなんて。
枯らすのが得意だったから小学生の頃、朝顔も何も花が咲いたことがなく、興味もなかったのに。
日々変わるものは見ていて楽しいし、飽きないな、そこは建築に似ている。工事中は当然毎日出来上がっていくから、その様を見ているのは設計者として至福の時だし、完成してから、そう設計者は一所懸命に心血注いでつくっても、自分では住めない、使うことはない、それが、きっと楽しいんだろな、いいんだろうな、なんて思いながら引き渡すのだが、その後見に行くと、住む人色、使う人色に染まって、自分の想像していた変化とは違っていたりすると、またそれが、その様を見るのが楽しい。
自分の想像では、部屋中、蔦だらけになり、蔦に埋もれて、蔦の間で寝て、蔦からひょっこりと顔を出す予定なのだが、どうなることやら。
"Salmon, Mukumuku, Sprout"
Every day, buds come out, and new shoots come out like flowers in dead trees.
Organize and reset the cocoons that covered the cocoons at home, start growing some of them indoors, first put a piece of branch into the water, add plant vitality, first think that new air roots will come out and grow long However, as soon as some white air roots were seen, the shoots were muffled.
As you can see the difference between morning and evening, it grows fast, it is strong life force, whether you have become accustomed to the environment, it seems that it grows as if it is tangled up for the first time, so it is next to the room It just seems to spread.
However, it is interesting to see how it grows, and I put it in the kitchen, but I see it every time I stand in the kitchen. It 's fun to grow up. It 's the first time I 've ever thought that plant fun is like this.
I was good at withering, so when I was in elementary school, I had no flower in the morning glory and I was not interested.
It's fun to see things that change every day, and I'm never bored. It's like architecture. Of course, it is completed every day during the construction, so it's blissful as a designer who sees it like that, and even after it is completed, the designer can not live on his own even if he works hard and makes it I don't use it, but I'm sure it's fun, I'm glad I hand it over, but when I went to see it, I was dyed by the color of the people who lived and the people I used, I imagined If it is different from change, it is fun to see it again.
In my imagination, I'm going to be full of cocoons in my room, buried in cocoons, sleep between cocoons, and sneak out of my niece, but what happens.
目に見えるものは不思議だ。視野の範囲にはたくさんのものがあっても、そのうち覚えられるのはいくつもない、意識がそこに向いていないと正確には覚えられない。
何となくぼんやりと眺めていると、何となくしか覚えていないし、何となくしか記憶に残らない。
ただたぶん、目から入る情報は脳には全て残っていて、意識を向けていようが、何となく見ていようが、そのようなことには関係がなく、情報量としては同じだけはあり、例えば、写真のようにフレームにおさまっているものは全て写るように、あとはその情報に対して、どのように扱うのか、どのようにアプローチするのか、何もしなければ、残ってはいるが、永遠に陽の目を見ることはない、もしそうならば、脳は相当な容量があることになる、一生分の情報を貯めておけるのだから。
意識して覚えようとしても記憶に残らないのに、大したことでもないのに、何となくずっと覚えていることもある。
衝撃的なことがあった時はもちろん、それを覚えているが、サプライズもそう、忘れない、忘れられないが、日常で思い出すことは、どうでもよかったりすることも多い。
どちらかというと、たまに思い出すことより、日常的に思い出すことの方が大切というか、日常を豊かにしてくるように思う。
もしかしたら、それは毎日見る風景が元の情報になっていて、そこから感情や行動が結びついて、ふと思い出すのではないか。
そう考えると、日常的に毎日見る風景がどれ程大切さかがわかる。
"Daily scenery"
What is visible is strange. Even if there are many things in the field of vision, there aren't many that can be remembered, and it can't be remembered accurately if consciousness is not there.
If you look vaguely somehow, you will only remember and you will remember it.
However, all the information that enters from the eyes remains in the brain, whether it is conscious or whether it is seen somehow, it has nothing to do with such things, there is only the same amount of information, for example, It looks like everything in the frame like a photo, and after that, how to handle that information, how to approach it, if nothing is done, it remains, but forever You don't see the sun's eyes, if so, your brain will have a lot of capacity, because you can store information for a lifetime.
Even if you try to remember it, you don't remember it, but it's not a big deal, but you somehow remember it.
Of course, I remember that when there was a shocking thing, but I do not forget, I can't forget about surprises, but remembering in everyday life is often irrelevant.
If anything, I think that it is more important to remember on a daily basis than to remember occasionally, or to enrich the daily life.
Perhaps it seems that the scenery you see every day is the original information, and emotions and actions are linked from there, and you suddenly remember it.
When you think so, you can see how important the scenery you see every day is important.
物が場を規定してしまう、確か、ハイデッカーがそのようなことを言っていたような気がするが、その物が持つ暗黙のイメージみたいなことが、その物の見方だけでなく、その物を扱う人の印象、その物が置かれた場所の雰囲気まで決めてしまう。
前にお願いしていた輪島塗のカップ&ソーサーが届いた。同じ塗師さんの所で、フリーカップを木地から製作中だが、塗りを決めるための参考として、普段使いしようと思い、前に塗師さんの所にお伺いした時に、その場にあったカップ&ソーサーを購入、その色違いを注文していた。
塗りの色は一般的な黒と朱だが、色を反転させ、塗りにも、ぼかしや、艶を出すために油が混ぜてあったり、艶が無かったりと、1つのカップ&ソーサーにいくつもの塗りの技法が使われているので、日常の中で使いながら、フリーカップに使う塗りをどうするか、考えるつもり。
形は至ってシンプル、よくある形、だが綺麗な形、色も漆らしい色、だがきちんと工程を踏み、きちんとした材料を使った本物の塗り物、物は木地でできているから軽いが、見た目には、謂わゆる漆物、重厚なイメージになるかもしれない。
まだ、カップ&ソーサーだから、御重などに比べたら、漆物として日常使いしやすいし、受け入れやすい。
そう、漆物には受け入れにくいイメージ、それはもしかしたら高級なイメージもあり、だから、相反するイメージで受け入れにくい、扱いが難しいイメージもあるかもしれない。
もしかしたら、先のように、漆物があるだけで場が規定されてしまうかもしれない。それを上手く利用できれば良いのだが、後継者がいないらしい、後継者がいないということは、その産業が衰退していること、暗黙のイメージを上手く利用できていない証、万年筆の仕上げにしたり、箸は昔からあるが、漆物の良さを生かしきれていない。
もっと、今までとは違った、漆だから、漆物だから実現できる日常の生活の一部を、漆物は製品として万能で優秀、特に輪島塗は丈夫で普段使いにはとても良く、使えば使うほど味が出る。しかし、それは前の時代の価値観、その価値観だと他のものにとって代わられる、別に漆物でなくても良いとなる。
漆の特性、漆物の特性に特化した、それでいて技術が無いとつくれないような物をつくれば、後継者も育つのだが、その答えを形にできるのは人だから、やはり、物より人が先で、人が物や場を規定することに気がつくと、糸口が見つかるような気がする。
"People first"
The thing defines the place. Certainly, I feel like a high decker said such a thing, but the thing that the thing has an implicit image is not only how to see the thing, but the thing The impression of the person who handles it, and the atmosphere of the place where the thing is placed.
I received the Wajima Lacquer Cup & Saucer I had requested before. A free cup is being made from the wood at the same painter's place, but as a reference for deciding the paint, I would like to use it everyday, and when I visited the painter's place before, the cup & that was there I bought a saucer and ordered a different color.
The colors of the painting are common black and vermilion, but the colors are reversed, the paint is also blurred, oil is mixed to give luster, and there is no luster, many in one cup & saucer Since the painting technique is used, I will think about what to use for the free cup while using it in my daily life.
The shape is very simple, common shape, but beautiful shape, the color is also lacquered color, but the process is neat and the real coating using the proper material, the material is made of wood, it is light, but it looks May become a so-called loose lacquer, profound image.
Because it is still a cup and saucer, it is easy to use and accept as a lacquer everyday compared to Megumi.
Yes, there are images that are difficult to accept in lacquer, and possibly high-quality images, so there may be images that are difficult to accept and difficult to handle with conflicting images.
Perhaps, as before, the place may be defined only by the presence of lacquer. It would be good if you could use it well, but it seems that there is no successor, that there is no successor, that the industry has declined, proof that the implicit image has not been used well, fountain pen finishing, chopsticks Although it has been around for a long time, it does not take full advantage of the goodness of lacquer.
In addition, unlike lacquer, lacquer is a versatile and excellent product, especially Wajima Lacquer is durable and very good for everyday use. Taste comes out. However, it is not necessary to use lacquer separately, because it replaces the values of the previous period and those values.
Successor grows up if we make thing which we cannot make without technical skill that we specialized in characteristic of lacquer, characteristic of lacquer, but person can shape the answer, but after all person But first, if you notice that people define things and places, you will find clues.
マチスのダンスだったり、アンディ・ウォーホールのキャンベルスープ缶だったり、リキテンシュタインの漫画チックな絵だったり、ジャクソン・ポラックのアクションペイントだったり、時代もイズムも全く違うけれども、平面的な絵が好きでそればかりを見ていて、あと、ジャスパー・ジョーンズのフラッグ、東山魁夷の絵は全部好きで、展覧会があると必ず、前は国立近代美術館で常設されていたし、唐招提寺の襖絵は圧巻だった。
作品自体が好きな場合もあるし、作家自体が好きな場合もあるけれど、総じて、大きな括りとしては「平面性」を感じる絵画に惹かれた。
初めて平面的な絵画に触れたのはMOMAで常設されていた、先にも出たウォーホールのキャンベルスープ缶で、最初の印象が「これが絵なの、作品なの」というサプライズに、人はサプライズに弱い、記憶や印象の深い所に残る、だから、虜になる。
そうなると、不思議なことに、平面性を獲得するために排除したはずの精神性が見る側に芽生えてくる。
建築と絵画はよく比較されて、現代では建築と絵画は別々で、多種多様なイズムや思想が成り立っているが、元々は現代の建築も絵画も「モダニズム」運動とも呼べるイズムが発端で、その後の動きは相同的であり、建築を通して絵画を見たり、絵画を通して建築を見たりすると、より時代やイズムや思想を把握しやすくなる。
だからではなく、たまたまだったが、最初にモダニズムに触れたのは建築よりも絵画が先で、先のキャンベルスープ缶で、だから「平面性」の虜になった者からしてみれば、順当にモダニズム建築にも惹かれることになる。
ただ、モダニズム建築は平面的というよりは幾何学的な印象ではあるけれども、装飾を排除し、装飾に伴う精神性も排除し、純粋に自律を目指した点では建築と絵画は同じであり、平面的や幾何学的な元にある、その「純粋性」に惹かれて虜になっていたのかもしれない。
"Pure Prisoner"
It 's a Mathis dance, Andy Warhol 's Campbell soup can, Richenstein 's cartoon chic painting, Jackson Pollack 's action paint, even though it 's completely different in age and ism, but I like flat paintings I liked all of Jasper Jones's flag and Higashiyama Kaoru, and there was always a permanent exhibition at the National Museum of Modern Art. Was a masterpiece.
Sometimes I like the work itself, and sometimes I like the artist itself, but as a whole, I was attracted to paintings that feel "flatness" as a big conclusion.
The first time I touched a two-dimensional painting was a Campbell soup can from Warhol that was permanently installed at MOMA. The first impression was a surprise that "This is a picture, a work", and people are vulnerable to surprise It will remain in a place with a deep memory and impression, so you will be captivated.
Then, mysteriously, the spirituality that should have been excluded to acquire flatness will start to grow.
Architecture and paintings are often compared, and in modern times architecture and paintings are different, and a wide variety of isms and thoughts have been established. Originally, modern architecture and paintings originated from an ism that can be called the "modernism" movement, and then The movements are homologous, and if you look at paintings through architecture, or see architecture through paintings, it will be easier to understand the times, isms, and thoughts.
It wasn't, but it was still happening, but the first thing that touched modernism was the painting before the architecture, and the previous Campbell soup can, so if you were a prisoner of "flatness" Attracted to modernist architecture.
However, although modernist architecture is a geometrical impression rather than flat, architecture and painting are the same in terms of eliminating decoration, eliminating the spirituality associated with decoration, and pursuing pure autonomy. It may have been captivated by the "pureness" of the original and geometrical origin.
雨のやんだ空のような青さが青磁の色としては素晴らしいらしい、青磁の極み、浙江省龍泉窯のものを見せていただく機会があった。
青磁の良し悪しは色で決まるらしい、色の綺麗さ、くすみがなく、澄んだ青さが良く、また、塗りもぼてっというくらいに厚い方が良いとのこと。勝手な青磁のイメージだと薄塗りで繊細なものだが、この青磁の器はそうではなくて、物として重厚な存在感があった。
日常使いされていたかどうかは定かではないが、使われていたらしい。使われていた状況を想像すると、物としての存在感が波紋のように広がっていくようで、それにより、いろいろなことが明らかになるような気がした。
この青磁の器に何を盛るのか、それによって、盛った物がどのように見えて、どのように感じるのか。
この青磁の器をどこに置くか、それによって、その置いた辺りの空間がどのように変わり、どのような雰囲気になるのか。
この青磁の器を誰が扱うのか、それによって、扱う人の心や感情や意識がどのようになるのか、どのように変化するのか。
そして、もう1つ、この青磁の器がそこから無くなったら、どのようになるのか、何が変わるのか。
物に注釈して、極みまで行き、そこから引き返してくる時には、きっと違う風景が見えていることが、物の醍醐味だと思う。
"Ripple-like presence"
There was an opportunity to show me the extreme of celadon porcelain, the one of Longquan in Zhejiang Province.
The quality of the celadon seems to be determined by the color. The color is beautiful, there is no dullness, clear blue is good, and it is better to thicken the paint. The image of a celadon porcelain is thin and delicate, but this celadon porcelain was not so and had a profound presence as an object.
I'm not sure if it was used everyday, but it seems to have been used. Imagine the situation that was being used, and the presence as a thing seemed to spread like a ripple, and I felt that various things became clear.
What is put on this celadon porcelain, how does it appear and how does it feel?
Where will this celadon vessel be placed, how will the surrounding space change and what will it feel like?
Who will handle this celadon porcelain, and how will it change the mind, emotions and consciousness of the person who handles it?
And one more thing, what will change if this celadon vessel disappears from it?
Annotating things, going to the extreme, and returning from there, I think that the best part of things is that you can see a different landscape.
うーん、気分がどうも優れないなー、天気が優れないからかなー、曇っているからかなー、なんて思うと、どんどん、天気に左右される、曇りの方が涼しい時もあるから、別に構わないのだけれども、ようするに、気分なんだなと。
建築は動くことができないから外部環境に左右される、というか、外部環境によってほぼ全てが決まると言って過言ではない。
例えば、規模は、敷地の大きさと、その場所の法規、建ぺい率や容積率、高さ制限で決まる、もちろん、予算もあり、あまりにも広い敷地の場合は目一杯の規模まで建てることはないが、都市部ではそのような広い敷地はなかなかないので、大体、目一杯の規模まで利用することになる。
用途も外部環境に左右される。繁華街のど真ん中に専用住宅をつくることはほぼないし、郊外にオフィスビルをわざわざつくることもない。
また、外部環境によって室内環境も左右される。周りが建物に囲まれている、幹線道路に面している、隣が公園、閑静な住宅街など、外部環境に対して何か対策をしたり、逆に外部環境を生かして室内環境を良くしたりする。
ただ、これだけ外部環境に左右されても、建築の優劣が外部環境で決まることはない。
規模が大きければ良い訳ではないし、建築にとって用途は何が良いかはもちろんないし、室内環境は対策や生かし方しだいでどうにでもなる。
だから、天気が曇りでも雨でも晴れでも、それで気分が変わっても、別にいいなと、曇りだからできることをしようと。
"Because it is cloudy"
Well, I do n't feel good, maybe because the weather is n't good, maybe because it 's cloudy, it 's more and more depending on the weather. However, I feel like I do.
It is not an exaggeration to say that architecture depends on the external environment because it cannot move, and that almost everything is determined by the external environment.
For example, the scale is determined by the size of the site, the regulations of the site, the building coverage ratio, floor area ratio, and height restrictions. Of course, there is also a budget, and if the site is too large, it will not be built to the full scale. In urban areas, there are not many such large sites, so they will be used to the fullest.
Applications are also affected by the external environment. There is almost no private housing in the middle of the downtown area, and there is no need to create an office building in the suburbs.
Also, the indoor environment depends on the external environment. Take measures against the outside environment, such as the surroundings surrounded by buildings, facing the main road, the park next to the park, and a quiet residential area, or conversely improve the indoor environment by taking advantage of the outside environment To do.
However, even if it depends on the external environment, the superiority or inferiority of the architecture is not determined by the external environment.
It doesn't mean that the scale is large, not to mention what the purpose is good for architecture, and the indoor environment depends on measures and how to make use of it.
So, even if the weather is cloudy, rainy or sunny, even if you change your mood, it's fine to try something you can do because it is cloudy.
「あるじゃん」今朝の第一声、「なんだよ」今朝の第二声、声に出した感情が今朝のはじまり、今日からまた新しいプロジェクトがはじまり、そのための段取りを1ヶ月くらい前から具体的にやりはじめた結果の今朝の声。
結構綿密に段取りして、3日前にはほぼほぼ段取りが完了し、初日の朝を迎えたはずが、人に言われて、そういえば、と思い見てみたら、在庫があり、購入する必要が無いものを一所懸命に揃え、まあ、これは新しいものを使った方が良いからと自ら慰めたのだが、さすがに数量を間違えたのには、指摘されるまで全く気付かなかったことが、指摘されたらすぐにわかるという、ここの所で記憶に無いくらいの落ち込みよう、さすがに嫌になり、ちょっと逃避行でもして気分転換するかと頭によぎったが、そうもいかず、いつも通りの行動をこなしていたら、平常には戻ったが、もうなんで間違えたかわからない。
結局、段取りが甘いということだろうが、これがまた、初日にこうことも起きるだろうというパターンに対しても、一応段取りはしており、だから、自分が落ち込んだだけで、プロジェクト自体は何も問題が無く、順調に進んだ1日だったので、そうすると、結果的には段取りの成果かなと自らに甘く、自らを慰め、これで良いだろうとした。しかし、また在庫が増えた増えた。
"Don't get depressed"
"There is" the first voice of this morning, "What 's the second voice of this morning", the emotions in the voice started this morning, a new project started again today, and the preparations for that will be done from about a month ago This morning's voice of the results I started.
It was quite carefully set up, almost 3 days ago it was almost completed, and it should have reached the morning of the first day, but people told me that if I think so, it is in stock and it is necessary to purchase I tried hard to arrange the ones that were not there, and I comforted myself because it was better to use the new ones, but I did not notice at all until I pointed out that I mistaken the quantity as expected As soon as I was pointed out, I knew that I couldn't remember this place, so I couldn't remember it. If you did, you returned to normal, but you don't know why you made a mistake.
After all, it may be that the setup is sweet, but this is also happening for the pattern that this will happen on the first day as well, so I'm just depressed and the project itself is nothing There was no problem, and it was a smooth day. So, as a result, it was sweet to myself that it was the result of the setup, and comforted myself, and I thought it would be good. But again the stock increased.
つながりの妙みたいなものがあって、決して強いつながりではないけれど、かと言って弱くもない、そんなつながりからいろいろと生まれたりする。
これは人の話で、ただネット上の話では無くて、直に触れ合う人間関係の時のみで、ネット上のつながりだと、ほんとに弱すぎて、それでもつながっているのが不思議なくらい、ところが、それが心地良い時もあるからまた不思議で、家族のような強いつながり、ネットのようなごく弱いつながり、その中間に2つくらい強さの違うつながりがあるような気がする。
今まで仕事をしたり、仕事を紹介してくれたりした人で圧倒的に多いのは、その中間くらいの強さのつながりの人で、それは人によって違うかもしれないが、最初はごく弱いつながりがはじまり、そのまま、ごく弱いままだと何も起こらないが、それが少し強くなると、もちろん、全員ではないが、仕事の話になる場合がある。
ただ、強くなり過ぎると何も起こらない。もちろん、これも人によって違うはずで、だから、仕事の場合の人とのつながりの強さはいつも気を使うところで、強くなり過ぎてはダメだと思うが、そこは難しくて苦手なところ。
"connection"
There is something strange about the connection, and it is not a strong connection, but it is not weak.
This is a story about people, not just a story on the internet, but only when people are in direct contact with each other. A connection on the internet is so weak that it is still strange that it is still connected. It is also strange because it is sometimes comfortable, and I feel that there is a strong connection like a family, a very weak connection like a net, and two connections with different strengths between them.
The overwhelming majority of people who have worked or introduced their work so far are those with intermediate strength, which may vary from person to person, but at first it is a very weak connection It starts and nothing happens if it remains very weak, but if it becomes a little stronger, of course, it may be a story about work, not everyone.
However, nothing happens when it gets too strong. Of course, this should be different from person to person, so the strength of the connection with people in the case of work is always a concern, and I think that it should not be too strong, but it is difficult and weak.
もっと早くそこを教えて、とか、はじめからそれがわかっていればな、なんて、誰にでもあるのかはわからないけれど、子供の頃から、全体を俯瞰して把握するのは苦手で、そもそも、わからないことをわかるようにすること自体が上手くできなくて、今ならば、手軽にネットを使えばわかってしまうが、その信憑性は置いておいても、その差は大きいというか、だから、それが自分でわかっていたから、設計事務所に入社した頃は、当時、パソコンもネット無い、今この目の前のわからないことに対して、どうやって答えを出せば、仕事として問題が無いのか、ばかりを考えていた。
入社して1年目位は、まだ入ったばかりだし、わからないこどが多くても、なんて言っていられるような状況ではなかったし、パンクしていた。
それがちょっとだけ楽になったのが、担当者として1つの仕事を初期段階の打合せから設計、工事監理、完成までを通しで行なった後から、よく1年目の新人を担当者にするものだなと思ったけれど、図面も、先輩が手伝ってくれて、とりあえず納めて、現場も先輩にききながら、なんとか納めて、1通りやると、つながりが見えてくる、そうすると、仕事の内容が変わっても応用が効くから、どのような内容の仕事にも対応ができるようになった。
このつながりが、わかる人にはすぐわかるらしい、それを認知力と言うのだろうが、このつながりがわからない。
どこと、どこが、こうつながるから、のどこは、それがどういうことかはよくわかるのだが、というか、調べれば誰でもわかると思うが、つながり、要するに、関係性を把握するのが苦手かもしれないと、最近また思うようになった。
で、昔習ったノートの取り方で、マインドマップをまた使いはじめた。昔は何か面倒くさいなと思ったのが、その階層構造のおかげで全体の関係性がわかりやすくなり、認知力がアップした感じで、昔面倒だなと思ったことが今はジャストフィットということは、と思いながら、スマホでマインドマップを描く日々。
"Cognitive power of connection"
I don't know if anyone can know it from the beginning, or if I knew it from the beginning, but since I was a child, I'm not good at understanding the whole, and I don't know it in the first place. I couldn't do it well, so now I can easily understand it by using the Internet, but the difference is large even if I put the credibility, so that is Because I knew it myself, when I joined the design office, I was only thinking about how to give an answer to what I didn't know right before I had no personal computer at the time. It was.
In the first year after joining the company, I had just entered, and even if there were many children I didn't understand, I wasn't in a situation to say, and I was punctured.
What made it a little easier is that after a job as a person in charge, from initial meetings to design, construction supervision, and completion, the first year's newcomer is often in charge. I thought it was, but my senior helped me, and I paid it for the time being. Can be applied to any kind of work.
Those who understand this connection seem to know it right away. This is called cognitive power, but I do not understand this connection.
Everyone knows what it is and what it is because it is connected to where and where it is, but I think anyone can understand if you examine it, but it may be weak at grasping the connection, in short, the relationship I haven't had it recently.
So I started using Mind Maps again with the notes I learned a long time ago. In the past, I thought that something was troublesome, but thanks to its hierarchical structure, the overall relationship became easier to understand, the feeling of improved cognitive power, what I thought was troublesome in the past is now just fit Thinking of a day, I draw mind maps on my smartphone.
アリストテレスがね、古代の哲学者がね、物とは何ぞやと言って、自ら問いを立てて、自ら物はね、4つに分解して考えるのだよ、と言っているのですよ。
それは、物をつくるための素材と、物の形と、それをつくる人と技術、それをつくる目的だと。
物がね、どのようにしてそこにあるか、と考えたならば、素材があって、その素材を使って形をつくる、その形は、つくる目的があるから、その目的にそって、それをつくることができる技術を持った人が、それを形つくるのだけれども、古代では、なぜか、つくられた後のことはどうでもよいらしい。
古代では物は完成した時点で終わりを迎えるらしい。
それはそれで清い、物は完成した瞬間が、つくった人、この場合、つくる技術を持った人が1番満足できる状態で、1番気持ちよく、1番美しい、だから、さあ、次のことと考えられるのかもしれない。
今日行った料理屋さんで、締めに2種類のご飯と3種類のおかずの組合せ、計6種類のご飯を食べた、おかわりしたから8杯食べた。
料理も物、料理をつくる人は完成したフォトジェニックを求めているのではなく、
「いやー、そんな締めに、そんな美味しそうな物を出さないでよ、それまで散々食べたのに、呑んだのに、お腹いっぱいで入らないよ、もう」
というセリフと顔を楽しみにしているにちがいない。なんて、なんて、それにあがらい、8杯食べる、でも、まだ腹八分目。
物の終わりは消費してなくなる時、もしかしたら、消費という言葉にはあまり良いイメージはないかもしれないけれど、次の物を創作するには、今あるものを無くさないと、手放さないと、消費しないと、できないと思う、それこそ、消費より嫌いな言葉、断捨離か。
きっと古代には美味しい物が無かったのだろう、だから、アリストテレスは8杯のご飯なんて、そんなことより、「このものをこのものとしてかく有らしめているのは何か?」なんて問うて、四原因か答えはうふふ、なんて、腹の足しにもならない。
"8 cups of rice"
Aristotle, an ancient philosopher, asks what the thing is, asks himself, says that he thinks that the thing is broken down into four.
It is the material for making things, the shape of the thing, the people and technology that make it, and the purpose of making it.
If you think about how things are there, there is a material, and you use that material to make a shape. The shape has the purpose of making it. The person who has the technology that can make it forms it, but in ancient times, it seems that it doesn't matter what it was after.
In ancient times, things seem to end when they are completed.
It is clean and the moment when the product is completed, the person who made it, in this case, the person who has the skill to make it is the most satisfied, the most comfortable and the most beautiful, so it seems that Maybe.
At the restaurant we went to today, we had a combination of 2 types of rice and 3 types of side dishes, a total of 6 types of rice.
Cooking is a thing, people who make dishes are not looking for a finished photogenic,
"No, don't bring out such a tasty food to the end of it, I've eaten up until then, but I'm confused but I'm not full."
You must be looking forward to the line and the face. How, why don't you just eat it and eat 8 cups?
When the end of a thing is no longer consumed, perhaps the word "consumption" may not have a very good image, but to create the next thing, you have to lose what you have, If you don't, you think you can't do that.
Surely there were no delicious foods in the ancient times, so Aristotle said, "What is it that makes this thing like this?" The cause or answer is Ufufu.
今この瞬間を生きていることをなかなか意識できないのに、明日とか、来週の予定を考える、それは明日も来週も生きていることを意識していることになるのが何ともな話。
時代は変化するし、社会も変わるから、極端な話、過去には1日で変わった事もあったから、明日も、来週も、何も保証されていないのに、何故か、全てがこのまま、良いことも悪いことも変わらないことが前提になる。
普遍的な真理など、そうは無く、太陽は東から昇って西に沈む的な絶対的に普遍な真理など、そうは無いのに、思い込みも含めて、普遍的で本質的な事柄を追い求めてしまう。
時代性や社会性と絡めて普遍的な真理を説こうとすれば、必ずボロが出るから、そのまま放っておけばよいが、時代や社会は変化する、でも、そのようなこととは別に普遍的な法則は存在する、それが科学かもしれないし、哲学かもしれないが、必ず存在するとなると厄介だ、どう考えても、時代によって科学も哲学も変化してきたと思うし、対象を分析することには変わりが無いが、分析結果は常に時代や社会を反映してしまい、変化してきたと思うが、だから、あるのはポジショニングで、どの立場を取るのかを選択するだけだと思うのだが。
もし、そうならば、論理よりも実践が大事で、その立場において、どのように実践して、どのような結果になったのかだけが重要ということになると思うのだが、そう論理は必要だが、実践の手段にすぎない。
なかなか社会や時代の枠組みが定まりにくい現代だけれども、それでもモデルを仮定して、枠組みを定めれば、社会的な問題も浮き彫りになり、その解決策がその時代の論理であり、実践の手段、ただ、モデルは常に変化するのではないか、そう考えると、この時代や社会を根底から成立させている本質的で普遍的なことなど無いことになるのだが、あるとしたら思い込みか。
"Logic and Practice"
Even though I am not conscious of being alive at this moment, I am thinking of tomorrow or next week's schedule, and that is conscious of being alive tomorrow and next week.
Because times have changed, societies have changed, extreme talks, and in the past, things have changed in a day, so tomorrow and next week, nothing is guaranteed, but why everything is as it is The premise is that things will not change.
There is no such thing as a universal truth, but there is no such thing as an absolute universal truth that the sun rises from the east and sinks into the west, but it pursues universal and essential things, including assumptions. End up.
If you try to explain universal truths in relation to the times and societies, you will always get out of touch, so you can leave them as they are, but the times and societies will change, but apart from that, universal There is a general law, it may be science, it may be philosophy, but it will be troublesome if it always exists. I think that both science and philosophy have changed with the times, and to analyze the object Although there is no change, I think that the results of analysis have always changed, reflecting the times and society, so I think that there is only a choice of the position to be taken in positioning.
If so, I think that practice is more important than logic, and in that position, I think that it is only important how it is practiced and what kind of result is achieved, but such logic is necessary, It is only a means of practice.
Although it is difficult to determine the framework of society and the times, it is still difficult to determine the framework, and if the framework is defined, social issues will be highlighted, and the solution is the logic of that era, the means of practice, However, if the model is constantly changing, there will be no essential and universal things that have fundamentally established this era and society.
支えがあると、それを伝わって、どんどん伸びる、どんどん成長する、どんどん太くなるのに、単独だと、ぜんぜん伸びもしないし、ぜんぜん成長もしないし、ぜんぜん大きくならないという。
うちには某建築家の「母の家」から拝借してきた蔦が地植えしてある。もう20年もので、一度転居した時も連れてきて、二度くらい、あまりにも成長したので伐採してもらい、それでも塀を覆いつくし、日々の手入れでは追いつかないので、今日また何年振りかに伐採してもらった。
完全に無くなるのは忍びがなく、その話をしたら欲しいという人もいたので、かなり伐採して、また生えてくるのか心配なくらいまで綺麗さっぱりになったが、室内で観葉植物として育ててみようということになり、少しだけ確保して水挿ししてあり、他にも、外の植木鉢に移し替えたり、よく見たら地植えしたものも葉が残っていた。
で、植木屋さんに尋ねたら、先の回答、植物には疎いので、ならば、最初から室内で観葉植物として育てればとも思いつつ、蔦は外を覆い尽くすあの感じが良いと、20世紀のモダニズムの建築家は蔦好きだからなと思いつつ、支えがあると成長するという話が面白い、確かに塀に這っている蔦はとても太いのに、観葉植物としての蔦は、ネットの画像を見たが、細い。
観葉植物の蔦には荒々しさが無く、か弱い感じ、そこが良いのかもしれないが、支えが無くても、どんどん成長して、支えが無ければ、横に這ってでも、何か掴まるものを見つけて、あの荒々しい、何にでも絡みつく感じになるのかと思っていたし、イメージは「母の家」の蔦なので、外壁にも這っていく生命力と思いきや、外壁があるから生命力を発揮できたのか、支えがある無しでこの違い。
ずっと、モダニズム建築の蔦は、場所性を捨てた建築に、場所性を取り戻す役目を負わせるために、わざと後から生えてくるように、建築家がしていたのだろうと勝手な解釈をしていたが、蔦の方も格好の餌食が如く建築を利用しており、むしろ、都合よく使われるフリをして、モダニズム建築を覆い尽くしてしまおう、場所に埋没させてしまえと野望を燃やしていたり。
やっぱり、蔦は貴重だから、大事にしよ、また塀を覆い尽くすかな。
"Twentieth Century Trap"
If there is support, it is transmitted and it grows steadily, grows steadily, it gets thicker, but when it is alone, it does not grow at all, it does not grow at all, and it does not grow at all.
Inside, there is a cocoon planted from the "mother's house" by a cocoon architect. It's already 20 years, I brought it when I moved, and it was grown too twice, so I felled it, but it still covered the firewood and I can not catch up with daily care, so it is the first time in several years today I was cut down.
There was no shinobi that completely disappeared, and there was a person who wanted to talk about it, so it fell pretty clean and I was worried whether it would grow again, but I tried to grow it as a houseplant in the room As a result, a small amount was secured and water was inserted, and there were also leaves that were transferred to outside flower pots or planted on the ground if looked closely.
Then, when I asked the gardener, the previous answer, I am not familiar with the plant, so if I think that I should grow it as a houseplant indoors from the beginning, the feeling that the moths cover the outside is good, 20th century I think that modernist architects love cocoon, but it is interesting to hear that it grows when it is supported. I saw it but it was thin.
The foliage of the foliage plant is not rough, it feels weak, and it may be good, but even if there is no support, it grows steadily, if there is no support, you can grab something even if you crawl sideways I found something and thought that it would feel like that rough, tangled with anything, and the image is the "mother's house" trap, so I think that it is the vitality that hits the outer wall, because there is an outer wall This difference without support, whether you have been able to demonstrate the vitality.
For a long time, modernist architecture traps interpreted the architects as if they were to grow up on purpose in order to restore the place to a place where place was abandoned. However, the samurai also uses architecture like a prey, but rather, pretend to be used conveniently and cover modernism architecture, even if it is buried in the place and burns ambitions. Or
After all, moths are precious, so take care of them and cover them again.
日常の何でもない、ごくありふれた、いつも行っていることがちょっとだけ、単純なことをしただけで、何かよくなって、そうしたら、今までとは、たったこれだけのことで、違った感情になったり、違った気分になったり、違った風景が見えたりして、日常が豊かになる、あくまでも日常の中の出来事が大事というか、非日常をつくりだすのは案外たやすいことで、ただ、その中にずっとはいられないし、非日常は楽しいかもしれないけれど、本当に満足したい場所は日常の中にあるのでは、日常の中にしかないのでは、で、これは氷山の一角であり、それを実現するための裾野は海面の下にあり、そこは日常からは見えないし、見せないが、そこには様々な技術や様々な考えがあり、それを磨きつつ、実践と論理のせめぎ合いをし、そのバランスにいつも気を使い、複雑で絡まったならば、解き、単純にわかりやすく、誰にでもすぐに理解できる論理を構築し、実践へと進むようなイメージでいつもものづくりをしている。
で結果、出来上がった物に対して相手が、この場合、相手は不特定多数の場合もあるし、個人の場合もあるが、愛着を持ってくれるのか、共感をしてくれるのかが大事で、それは物としての対外的な評価よりも上回り、相手が愛着を持ち、共感をしてくれたならば、それがつくる側から言えば、極上の喜びになる。
ポリシーについて考える機会があったので、今までと現在進行形の仕事を俯瞰して、そこから共通して言えることだけを抽出し、まとめてみたら、その時々は、その場面場面に合わせて、結構いろいろと考えているのに、普段自分が何気なく自分のためにしようとしていることだった。
"What is a policy?"
Everything you do in everyday life, something that is common, just doing something simple, just doing something simple, something better, and then you're just feeling this different feeling It makes you feel different, feel different scenery, enrich your daily life, it's easy to create an extraordinary life, or it's unexpected. I can't stay in it for a long time, and the extraordinary life may be fun, but the place I really want to be satisfied is in the daily life, only in the daily life, so this is the tip of the iceberg, The base for realizing it is under the sea surface, which is not visible or visible from everyday life, but there are various technologies and various ideas, and while practicing it, it is a struggle between practice and logic. ,That Lance to always use care, if tangled complex, solved, simply understandable, who built a logic that can be immediately understood even in, are always making things in images, such as the process goes to practice.
As a result, the other party may be unspecified number of people or individuals, but it is important whether you have attachment or sympathy. That exceeds the external evaluation as a thing, and if the other party has attachment and sympathy, it will be the supreme pleasure from the side of the creation.
I had an opportunity to think about the policy, so I looked down on the current and ongoing work, extracted only what I could say in common, and put it together. Even though I was thinking a lot, I was casually trying to do it for myself.
「流れるプール」と一声かかると一斉に同じ方向に動き出す群れ、そのうち、水の流れができて、その流れが全身に纏わりつき、その流れがある間は、流れのままに流されていく、泳げなかった自分はその時だけ泳げたような気分になり、中学になり泳げるになったのも、その時の感覚を身体が覚えていたから。
よく思い出すことで、一旦流れができてしまえば、あとはそれに乗るだけ、だけど、1人では流れができないから、はて、どうしたものかと。これは他人を巻き込んだり、何かを利用したりすれば、流れができるが、自分で動き出し、継続しなければいけなかいから、この場合、流れを習慣と言い換えてみて、他の言葉でも良いけれど、それが、流れができるまでの間で、止めてしまい流れができないことがよくある。
一旦流れができてしまえば、もう何も意識して動く必要が無いから、流れができるまでの我慢と思っても、我慢と思った瞬間に続かなくなるから、それは自分だけかもしれないけれど、きちんとした大人は我慢するのだろうが、だから、我慢しないでできることだけ、我慢と思ったら止めて、我慢しないやり方を考えて、そうすると、なかなか進まない、片付かないが、一旦我慢しないでできるようになると、それが習慣になり、例え、その習慣を後に止めたり、変えたりしても、その習慣になるまでの考え方や感覚は共有できるかなと思い、流れをつくるために、本当は動くのは好きではないのだけれども、その時点で我慢だから、流れができるまではいつも我慢とのせめぎ合い。
なんて、片付かない部屋を見て、あれこれ考えて、片付け本読んで利用しようとしても、だから、最近は究極の片付けを、もう片付けない、にしようかと、その時間で他のことをするという流れをつくろうかと、あとは片付かない部屋に我慢しないで済むかどうか。
"I can not stand it"
Swarms that start to move in the same direction when you say a `` flowing pool '', of which water flows, the flow gathers all over the body, and while it is flowing, it keeps flowing while flowing, swim I did not feel like I was able to swim only at that time, and I became junior high school so I could swim because my body remembered the feeling at that time.
Remember, once you have a flow, you can just ride it, but you can't do it alone. This can flow if you involve other people or use something, but you have to move and continue on your own, so in this case, try to rephrase the flow as a habit and use other words. Often, it stops and cannot flow until it can flow.
Once the flow has been made, there is no need to move consciously anymore, so even if it is patience until the flow is made, it will not continue to the moment when it was thought, so it may be only myself, but it is Adults will endure, but only stop what you can do without patience, stop if you think patience, think about how to endure, and then do not progress, do not clear up, but once you can do without patience , It becomes a habit, even if you stop or change the habit later, I think I can share the way of thinking and feeling until it becomes habit, and I do not really like to move to create a flow However, because I am patient at that time, I always fight with patience until I can flow.
How about looking at a room that is not cleaned up, thinking about everything, reading and using a cleanup book, so recently, the flow of doing other things at that time, whether to make the ultimate cleanup no longer cleanup Whether to make it or not to put up with a room that doesn't get cleaned up.
7年経つとさすがに人は変わるだろうか、7年前から今でも続いていることがもちろんあるけれど、その何倍も、7年前にはしていた、あったことが今は無い。
それが当たり前かもしれないが、逆に7年前と全てが同じだっだら、そちらの方がおかしいというか、それは進歩も退歩も無いことで、実際、肉体は変わるから、成長か老化かが、それだけで必ず変化があるはず、それに本人が気づいていない、周りは案外変わったな、なんて思っていて、老けたなんて、でも中身は変わらないな、とか。
建築は完成した段階から、成長と老化が同時にはじまる。完成した時はまだ、借り物の服を着ているような、自分たちに馴染んでいない、人に例えると、赤ん坊、それが住んでいくと、段々と自分たちの生活色に染まって、完成した当時の建築に彩りが加わる、それが成長。
ところが、建築を物としてみた場合、完成した当時が1番綺麗で、段々と劣化していく、劣化のスピードは物の材質によるが、劣化するのは止められない、これが老化。
ただ、劣化が上手くできれば味になり、完成した当時の建築に彩りと、さらに味が加わり、完成した当時の建築よりも良くなる、本来内在していたポテンシャルが解放されたような、建築として成熟した姿は実に素晴らしく、完成した当時よりも、少し年月を重ねた方が良い、というか、そうなるように設計している。
今、7年前に完成した住宅に関わっている。完成した当時赤ん坊だったお子さんが小学生になり、兄妹で使用していた部屋に間仕切壁をつくり、部屋を分ける工事、同時に劣化した部分を修復する。
人と建築の成長がシンクロし、7年経って彩りと味が加わった姿を見ているのは何とも楽しいもので、今回をきっかけに久しぶりにお会いする人もいて、見た目が変わってもあいかわらずだな、なんて内心お互い思いながら、また仕事をするようになるかもしれず、それはそれで、進歩だか退歩だか現状維持だかはわからないが、そういうこととは違う尺度でものづくりができていることが、7年前とは1番違うことかもしれない。
"7 years ago and now"
People will change over the course of 7 years, but of course there are things that have continued since 7 years ago, but many times that has been done 7 years ago.
It may be natural, but conversely, if everything is the same as 7 years ago, it is stranger, that is, there is no progress or retreat, in fact the body changes, whether it is growth or aging, There should be a change, and the person himself / herself is unaware of it, the surroundings have changed unexpectedly, and they think they are old, but the contents are not changed.
From the stage of construction completion, growth and aging begin at the same time. When it is completed, it is still unfamiliar to them, such as wearing clothes for rent, like a baby, when it lives, it is dyed gradually to their life color and completed Color is added to the architecture at that time, and it grows.
However, when looking at architecture as an object, it was the most beautiful when it was completed, and gradually deteriorated. The speed of deterioration depends on the material of the object, but the deterioration cannot be stopped.
However, if the deterioration can be made well, it will become a taste, and it will be colored, and the taste will be added, and the taste will be added, and it will be better than the architecture at the time when it was completed. The appearance is really wonderful, and it is better to spend a little more time than when it was completed.
I am involved in a house that was completed seven years ago. The child, who was a baby at the time of completion, becomes an elementary school student, creates a partition wall in the room used by his brother and sister, works to divide the room, and simultaneously repairs the deteriorated part.
It's a lot of fun to see the growth of people and architecture synchronize, and the addition of color and taste after seven years. Some people have met for the first time in a while after this time, even if the appearance changes I think I may start working again while thinking inside my heart, and I don't know if it's progressing, stepping back, or maintaining the status quo, but it's been 7 years that we have been able to make things on a different scale. It may be the most different from the previous one.
子供の頃から4色ボールペンをよく使っていて、いつからか、たぶん、中学くらいからか、使いはじめたのは、アンダーラインを引くために、色分けして、周りも結構使っていて、なぜかレポート提出で、色にもマイルールがあり、赤は重要、青は最重要、緑は余談、黒は普通としていて、人に聞くとやはりその人なりのルールがあって運用しているようだった。
前に、3色ボールペンを使った読書法の本が出版された時、パラパラと見て、同じと思い、前から本にも4色で、爪痕を残すような感じで、4色以外にも大事なページには付箋紙を貼り、その付箋紙も4色にし、ただ黒の代わりに黄で、黄の意味は青より重要な時、あとページの角を折ったり、その本を読み解くためにしていたのだが、本はノート、という教えも聞いたことがあったので、紙の本にいろいろしていた。
ただ、それは手段で、目的は本やノートの内容を頭に入れることなのに、4色を使い分けることがいつしか目的になっており、それはノートも同じで、いつしかノートを取ることが目的になっていた。
それに気づいたのは、今年になって手書きのノートを止めて、全てiPad にApple Pencilで記述するようになってから。やっていることは手書きのノートと変わらないけれど、デジタルノートには自分で制御できないルールがあり、例えば、色を変えるにも、その操作法は決められていで、手書きならば、ある程度自由に、4色ボールペンを使おうが、色鉛筆を使おうが、マーカーでも選べて、その使い方、運用の仕方も自分しだいだが、その不自由さが、それが手段ならば、そこまで感じないだろうが、目的だからとても不自由に感じた。
では止めればいい、デジタルノートを、と思うかもしれないが、同期していろいろなデバイスで見ることができ、修正も同期により反映できると、繰り返し見たりするのが便利になり、より頭に入りやすく、そのために4色を使い分けていたと、繰り返し見ないと頭に入らないと、認知の問題だけれども、それは手段だと再認識するためにデジタルノートにしたような状況に。
"4 colors"
I have been using four-color ballpoint pens a lot since I was a kid, and I started using them sometime, perhaps from junior high school. In the submission, there are also my rules in color, red is important, blue is the most important, green is a digression, black is normal, and when you ask people, it seems that they have their own rules and they are operating .
Before, when a book on reading methods using a three-color ballpoint pen was published, I thought that it was the same as a flip book, with four colors on the book from the front, feeling like leaving a nail mark, other than four colors Place sticky notes on important pages, and make the sticky notes four colors, just yellow instead of black, and when the meaning of yellow is more important than blue, you can fold the corner of the page or read the book I had heard that the book was a notebook, so I used it as a paper book.
However, it was a means, and the purpose was to put the contents of books and notebooks in mind, but the purpose was to use the four colors differently.
I noticed that this year, I stopped writing notes and started writing everything in Apple Pencil on the iPad. What you are doing is not different from handwritten notes, but digital notes have rules that you cannot control yourself, for example, even if you change the color, the operation method is decided, and if you are handwritten, you can freely to some extent, Whether you use a 4-color ballpoint pen or a colored pencil, you can choose a marker, and how you use it, how you use it, but you can't feel that inconvenience if it is a means. I felt very inconvenient.
You may think that you should stop, but you can think of digital notes, but if you can see them on various devices in sync, and you can also reflect your corrections in sync, it will be convenient to see them repeatedly, and it will be more clever. It was easy, and if you used the four colors properly, it would be a problem of cognition if you didn't come to mind unless you look at it repeatedly.
最近、時間が長く感じる。時間があっという間に過ぎるのは、楽しいことをしていたり、自分が好きなことをしている時にそうなるか、あとは、焦っていたりする時で、長く感じるのはつまらない時や、ただ、何かに没頭している時には2通りあるような気がする。
時間が、気がついたら、いつのまにかすごく経っていた、あるいは、集中して没頭して何かをして、かなりの量をこなしたのに、大して時間が掛からなかった、の2通りで、時間が進むスピード感が早いか遅いか。
実際に、時間の進むスピードが変わることは無いので、そう感じるだけだが、できれば、時間の進むスピードが遅く、時間が長く感じられる方が良く、ただ、つまらないのは嫌だな、となると、どうやって時間を使えば、スピードが遅く、時間が長く感じられるのかと考えてみたら、自分が好きなことや、やりたいことをたくさん用意し、制限時間を決めて、たくさんこなしてみると、好きなことをしているから、時間が早く経つような気がするけれども、制限時間より多くの時間を使うことが無く、それでいて、好きことをたくさんできるので良いのでは。
結局、好きことを効率良くたくさんやれば、時間を長くゆっくり使える感じになる、というなんか当たり前のことに落ち着いた。
"Long and slow"
Recently I feel that time is long. Time passes quickly when you are doing fun things, when you are doing what you like, or when you are impatient, and when it feels boring for a long time, just When I'm immersed in something, I feel that there are two ways.
When I noticed the time, I went through a lot of time, or I was focused and absorbed, did something, did a lot, but it didn't take much time. Is it fast or slow?
Actually, the speed of time does not change, so it just feels like that, but if possible, it is better that the speed of time is slow and it feels longer, but I don't want to be boring. If you think that if you use time, the speed is slow and you feel that time is long, prepare a lot of things you like and want to do, decide the time limit and do a lot, what you like I feel like it's going to be early, but I don't spend more time than the time limit, and I can do many things I like.
In the end, I settled on the natural idea that if I did a lot of things I liked efficiently, I felt that I could use my time slowly and slowly.
道具の話ですが、道具に何を求めるか、やはり、その道具を使うことによって、自分がどうなるか、を求めてしまう。
求めるものは2つで、どちらかが満たされていれば、その道具を使います。それは、自分の気分を高揚させてくれるものか、自分の時間をつくり出してくれるもの。
気分を高揚させてくれるものは人によって違うでしょうから、ただ、なかなか無いので、この時にとりあえずは無し、見つからないからとか、面倒だからとか、この程度でいいやは無し、その程度のものしかできません、その道具では。その道具を使いながら、自分の気分が高揚したら、そんな楽しい時間はないし、きっと良い時間になるでしょ。
例えば、車を移動するための道具だとしたら、動けば何でも良いよりは、気に入ったものに、ただ移動するだけで気分が高揚したら、それだけで素晴らしい時間に。
よく聞く話で、1日24時間は誰でも一緒、同じ、だから、自分の時間をつくり出してくれる道具は有り難い。例えば、ルンバ、掃除から解放されて、他のことをする時間をつくってくれる、ただ、うちのルンバは古いのか、家具に結構強く当たる、それが、家具は収納道具なので、お気に入りの家具しか置きたくないので、それにガンガン当たるのは、最新のものはそんなことはないのでしょうか。
もう模型つくりから解放されて、何でも自分でやりたいので、ただ、模型をつくる時間があったら、その分、プロジェクトを深める時間に使いたい、3Dプリンタがフル稼動です。
最初のスタディ模型はバリエーションを多く、とにかくたくさんつくりたいので、3Dプリンタで模型をつくっている間に、前の模型を検討し、新たな模型作成用データをつくり、模型ができあがってきたら、またそのデータを3Dプリンタにかけ、できあがった模型をまた検討し、新たにまた模型作成用データをつくる、これの繰り返しができるのが心地よく、楽しい時間。
そう考えると、どちらも、つくり出すのはもちろん、高揚させるのも、道具というのは時間を扱うものだと改めて思う。
"Time with tools"
It's a story about tools, but what you want from a tool is what you want to do by using that tool.
There are two things you want, and if either is satisfied, use that tool. It's something that raises your mood or creates your own time.
The things that make you feel uplifted will vary from person to person, so there aren't many, so at this time there is nothing for the time being, it can not be found, it is troublesome, this level is okay, there is only that level With that tool. If you feel better while using these tools, you will not have such a good time and it will be a good time.
For example, if it 's a tool for moving a car, it 's a great time if you just move and feel better than just moving.
The story I often hear is that everyone is the same 24 hours a day, so I appreciate a tool that can create my time. For example, rumba frees you from cleaning and takes time to do other things, but your rumba is old or hits the furniture quite a bit, because it is a storage tool, so you only place your favorite furniture I don't want it, so isn't the latest one that hits it?
Now that I'm free from modeling, I want to do everything myself, so if I have time to make a model, the 3D printer that I want to use to deepen my project is fully operational.
The first study model has many variations, and I want to make a lot anyway. So, while making a model with a 3D printer, consider the previous model, create new model creation data, and when the model is completed, It is a pleasant and fun time to repeat the process of applying the data to a 3D printer, examining the completed model again, and creating new model creation data.
When thinking so, I think again that both tools are not only made up, but also uplifting, tools are things that deal with time.
『全体と部分』
大きな視点から、その一点を見ると、相互の位置関係や様子がわかりやすく、大体、どの辺にいるのかがわかりやすいが、その一点から大きな視点を見ようとすると、そもそも全体像が把握できないから、その一点が全てであるような錯覚にとらわれることがある。
最近、知りたいことがあり、2つの講習を受けてみた。どちらの講習も、受講者同士のディスカッションの時間があったり、質問を元に講習が進めらたりと、話し手と受け手という関係性だけでは無い講習の形をとっていた。
ただ、受講者の知識にレベル差があるから、その差を埋めなかければ、ディスカッションは成り立たないし、質問も噛み合わない。そのため、片方の講習は受講前に、事前動画と称して、基礎的な知識を習得するための動画を自ら前もって見て、アウトプットをすることが要求され、そのアウトプットが参加証代わりになっていて、実際の講習では、最初から質問ではじまり、質問に答える形で講習が進む。
もう片方は講習の中で基礎的な知識を網羅して、それを受けてディスカッションし、自ら行いたいことを明確にしていく。
どちらの講習も、基礎的な知識の全体像を把握してから進むのは同じだが、片方は事前動画を別の日に自ら前もって見るから、講習当日の質問は、どうしても事前動画の内容とはあまり関係が無いというか、今その時の自分の問題にだけ収斂して、質問内容だけが独り歩きし、それが全体を表しているかのような錯覚におちいる。
もう片方はその場での基礎的な知識を網羅してから、自らの考えをまとめるので、全体の中での立ち位置が理解しやすく、より正確に何をするべきかがわかる。
どちらの講習のやり方が良いか、というのは無いとは思うし、目的によって使い分ければ良いと思うが、実際に、講習の内容が記憶に残り続け、忘れないのは、事前動画を見た方で、講習が完結するまで長い時間がかかり、それなのに、講習当日は全体性が無い質問ばかりで、事前動画を想起しながら質問や回答を理解しなければならず、それが頭に残るのだろう。
"Whole and part"
If you look at one point from a large viewpoint, it is easy to understand the mutual positional relationship and appearance, and it is easy to understand which side you are in, but if you try to look at a large viewpoint from that one point, you cannot grasp the whole picture in the first place. You may be caught in the illusion that one point is everything.
Recently, there was something I wanted to know and I took two courses. Both courses took the form of courses that were not just about the relationship between the speaker and the receiver, such as having time for discussion between students, or proceeding with the course based on questions.
However, since there is a difference in the level of knowledge of the students, if the difference is not filled, the discussion will not be possible and the questions will not engage. Therefore, before taking the course, one class is called a pre-video, and it is required to look at the video to acquire basic knowledge in advance and output it. In the actual course, the course starts from the beginning and answers the questions.
The other covers the basic knowledge in the course, discusses it, and clarifies what you want to do.
In both classes, it is the same to proceed after grasping the whole picture of basic knowledge, but one side sees the advance video in advance on another day, so the question on the day of the course is inevitably the content of the advance video It seems that there is not much relation, or it converges only on my problem at that time, and only the content of the question walks alone, and it feels as if it represents the whole.
The other side covers basic knowledge on the spot and then summarizes its thoughts, so it is easy to understand the standing position in the whole and know what to do more accurately.
I don't think there's a better way to do the course, and I think it's better to use it properly depending on the purpose. On the other hand, it takes a long time to complete the course, but on the day of the course, there are only incomplete questions, and you have to understand the questions and answers while recalling the pre-video, which remains in mind Let's go.
そっと口をつけても熱くない、この季節、エアコンをつけない室内に置いてあるだけでも、何でも熱くなり、陶磁器でも、何も注いでいないのに熱い。
手で触るもの、口につけるもの、その手触り、口の感触、そこまで、どうしようかな、この触り心地、触れるだけで心地よい、など、今の季節だと、冷んやりしているとありがたい。
感触の中でも、温度には、案外気がつかないうちに敏感になる。きっと触り心地より、まず温度で判断して、不思議なもので、肌にかかったら大火傷をするような熱湯でも、口の中に、冷ましながらだが、入れることができてしまう。
だから、案外、温度に対しては、無意識に反応して、対応するから、その温度について鈍感になるというか、いちいち気に止めることがない、しかし、冷ましながら、とかしている訳だから、何らかの影響を人に与えていて、料理では、その温度や温度差が美味しさのうちというのは当たり前なのに、それを入れる器は温度に鈍感で、器に接触するものの温度をそのまま伝えるしか能がなく、温度を全く持って器自身のデザインに生かせていない。
その温度と人を媒介するのが器なのに、器はただボーっとしているだけ、そこに一工夫、そこにデザインが関与すれば、その体験がより素晴らしくなるのでは。
だから、飲み口の厚みを変えてみた、温度に器が対応するように、人の好みや気分によって飲み口の位置を変える、そうすると、器の形も変わって見える、いつでも、毎日、気分で。
温度をデザインに取り入れたかった、そのためには熱湯を注いでも、程良く、人肌くらいの温度になる器でないと、熱くて持てない器では、そもそも温度をデザインに取り入れた使いこなしができない、それでいて、まるで口づけをしているような感触が欲しかった。
それが唯一できる素材は、陶磁器ではない、硝子の器でもない、もちろん金属の器でもない、漆器だけだった。まだ漆塗のサンプルができあがってこない、木地を眺めながら、納める箱をデザインしている。
"The vessel that can do that"
It's not hot even if you put your mouth softly. Even if it's left in a room without an air conditioner this season, everything will be hot, and even if it's ceramic, it's still hot.
I feel grateful that it is cool in this season, such as touching by hand, touching by mouth, touching by touch, touching by mouth, how to do it, this touching comfort, just touching.
Even in the touch, it becomes sensitive to the temperature without notice. Surely, it's a strange thing to touch, rather than touch, so even hot water that can cause severe burns when applied to the skin can be put into the mouth, although it cools.
So, unexpectedly, it reacts unconsciously to the temperature and responds, so it will not be insensitive about that temperature, but it will not stop at all, but because it is cooling down, it has some influence In cooking, it is natural that the temperature and temperature difference are delicious, but the vessel that puts it in is insensitive to temperature, and it can only communicate the temperature of what touches the vessel as it is, It has no temperature and is not used in the design of the vessel itself.
Even though it is a vessel that mediates the temperature and the person, the vessel is just a buzz, but if it is devised there and the design is involved there, the experience will be more wonderful.
So, when I changed the thickness of the mouth, I changed the position of the mouth according to the taste and mood of the person so that the container responded to the temperature, and then the shape of the container changed, every day, every day.
I wanted to incorporate the temperature into the design.To that end, even if I poured hot water, it was not a device that would be moderately warmer than human skin. I wanted the feeling of kissing.
The only material that could do that was lacquerware, not ceramic, glass, or of course, metal. I am designing a box to put in a lacquered sample while looking at the wood.
誤魔化していると、それなりに満足感が得られるから、ついつい同じことを繰り返し、それがクセになり、今度は誤魔化している自覚さえも、そもそも誤魔化していると思っていないから、それで満足感が得られるから、ドーピングをしているようなもの、結果に満足してしまうと、それが大事か誤魔化しているのか、脳はそこまで区別できないらしい、だから、自己暗示もできるし、誤魔化しも止められなくなり、何とか欲は、例えば、物欲や食欲や性欲などは、誤魔化す元をオブラートに包んでいるだけで、今が一番大事、がキーワードらしい。
一昨年、福井の永平寺で少しだけ坐禅体験をした。永平寺は曹洞宗の大本山であり、曹洞宗の坐禅は壁に向かって行うのたが、雲水と呼ばれる修行僧が行う坐禅の真似事を、そこだけ、まるで、パラシュートでいきなり中心地に降り立つような感じでやってみた。
それは、大阪から北陸へ行く用事があり、途中の福井で下車し、日本酒の黒龍を楽しんだ翌朝の出来事、前々から、永平寺で坐禅修行をしたい希望があったが、その時の季節は真冬、たまたま大雪が降った直後、とりあえず、早朝に向かったが、驚くほど移動手段が限られ、結局坐禅の時間に僧堂にいたのは私一人だけ、案内役の雲水さんとマンツーマン、座るだけのためにここまで来たかと思うと、とても貴重な時間に思えたが、坐禅をしながら、なぜここにいるのか、と考えていたことも思い出した。
別に、その時に答えが出た訳ではないが、何か一枚一枚剥ぎ取り、その時はすでに誤魔化すのが上手くなっていたから、欲が身体の外へ出ていくような感じがした。
ほんとは誤魔化さない方が良いのに誤魔化すのは、ほんとは食べてはいけないのに食べるようなもので、その方が気持ち良く、満足してしまうからだが、その満足感が虚しいと思いはじめていた時の坐禅は、静寂で誤魔化しようが無い、誤魔化すことができない張り詰めた空気を感じるための時間だったような気がする、おかさまで。
"I can't be deceived"
If you are deceived, you will get satisfaction as it is, so you repeat the same thing, it becomes a habit, and even now, even the awareness of being deceived does not think that you are deceiving in the first place, so you get satisfaction So, if you are satisfied with the result of doping, or if you are satisfied with the result, it seems that the brain can not distinguish so much whether it is important or misleading, so you can also suggest self-implied and it will not stop Somehow, for example, greed, appetite, sexual desire, etc. are the keywords that are the most important now, just by wrapping the elements that become deceptive in oblates.
Last year, I had a little zazen experience at Eiheiji Temple in Fukui. Eiheiji Temple is the main head of the Soto sect, and the zazen of the Soto sect is directed toward the wall, but the imitation of the zazen performed by a monk called Unsui is just like a parachute and suddenly descends to the center. I tried it.
There was a business going from Osaka to Hokuriku, getting off at Fukui on the way, enjoying the sake dragon of the next morning, there was a hope to practice Zazen at Eiheiji Temple, but the season at that time was midwinter, Immediately after the heavy snowfall, I headed early in the morning, but surprisingly the means of transportation were limited, and I was the only one who was in the monastery at the time of zazen, as a guide, Unsui-san and one-on-one, just to sit It seemed like a precious time when I came here, but I also remembered why I was here while doing zazen.
Apart from that, I didn't get an answer at that time, but I felt like my greed was going out of my body because I had already peeled something off one by one and at that time I was already good at becoming a demon.
It's better not to be deceptive, but it's like eating when you really shouldn't eat it, because it makes you feel more comfortable and satisfied, but when you start thinking that the satisfaction is empty Zazen is quiet and can't be deceived, it feels like it was time to feel the tight air that can't be deceived.
おわぁ、何、何、これ、ちょっと間があって、わかった新聞の切り抜き、Amazonで古書を購入したら挟まっていた。
昭和61年の切り抜き、この本の初版が昭和60年だから、新品で購入した前の所有者が挟み、そのまま、装丁も綺麗なので、本棚にあったか、書店にあったか、黄ばんではいるが、のり掛けしたようにピシッとした紙面、天声人語だから、朝日新聞か、そう言えば昔、毎日、天声人語を読まさられたことを、なぜか辛い思い出。
同じ本で、紙か電子かを選べるならば、必ず電子書籍を選ぶ、紙の書籍を購入する時は電子版が無いから仕方がない時で、知り合いの作家さんならば別だけれども、好んで紙の書籍を収集するような、全集を欲しがるような趣味は元々無いので、すぐに携帯で読めて、すぐに知りたい内容がわかり、どこへでも何冊でも持ち歩けて、見たい時にどこでも見られるから、いつでも読み返したい本や重要な内容の本や建築雑誌、座右の書なんてもう一冊購入して、背表紙を裁断し、自らスキャンしてでも、携帯に取り込んで持ち歩いている。
昔は本の間に新聞の切り抜き、その本が掲載されていた新聞広告を切り抜いて書店で探したりして、それを栞がわりに、昔はAmazonどころかネットすらない訳だから、もしかしたら、その当時の切り抜きがうちの書棚の本にもあるかもしれない。
この感覚、前の所有者はこの本を大事だと思っていたのかもしれない、切り抜きも几帳面に挟んである、内容ももちろん大事だが、本は単なる印刷物を超えて、本自体を大事にする感覚が昔はあった、今でもあるだろうが、紙としての実体の無い方が都合が良く、寿命の短い本が多くなってしまった。
単なるデータ、単なる文字情報の集合体が本と言えばそれまでだが、執筆途中はそれこそ今はデータだが、昔の作家の原稿が売られていたり、旧家の蔵から昔の原稿用紙が出て来たりなど聞くと、建築でも今は図面はデータだが、昔の手書きの図面が美術館の収蔵品になっているくらい、制作途中にも作家の痕跡があり、その痕跡自体が作品の一部であり、それが感じられたから、本を、紙の本を所有する喜びもあったのかもしれない。
断捨離なんて言わずに、一度大事にした本は一生持っていたいものだ、紙の本として、それが生きる喜びだと思う。
"An important book"
Wow, what, what, this was a little bit, I found out a newspaper clipping, and I got stuck when I bought an old book on Amazon.
The cut-out of 1986, the first edition of this book was 1985, so the owner before buying it with a new one was sandwiched, and the binding was also beautiful, so it was on the bookshelf, in the bookstore, it was yellow, but it was glued Because it 's so crisp, the Asahi Shimbun, the Asahi Shimbun, or so to speak, once a day, every day, I read the Tenshin Mandoku for a long time.
If you can choose between paper and electronic for the same book, be sure to choose an electronic book. When you buy a paper book, there is no way because there is no electronic version. There are no hobbies like collecting paper books or wanting the whole collection, so you can read it right away on your mobile phone, know what you want to know, take it with you wherever you want it, and take it anywhere you want to see it. Because I can see it, I buy another book I want to read back at any time, a book with important contents, an architectural magazine, and a book on the right, cut the back cover, scan it myself, and carry it on my phone.
I used to cut out newspapers between books, cut out newspaper advertisements where the books were published, and look for them in bookstores. There may also be a cutout in my bookcase book.
This feeling, the previous owner may have thought this book is important, the clipping is sandwiched between notebooks, the content is of course important, but the book goes beyond mere printed matter and takes care of the book itself Although there was a sense in the past, it will still exist, but it is more convenient to have no physical substance as paper, and there are many books with short lives.
Speaking of books, a collection of mere data and simple text information is up to that point, but in the middle of writing it is now data, but old writers of old authors are sold, old manuscript papers come out from old storehouses When you ask, the drawings are now data even in architecture, but there are traces of the artist in the middle of the production so that old handwritten drawings are a collection of museums, and the traces themselves are part of the work Yes, it may have been a pleasure to own a book, a paper book because it was felt.
I don't say that I don't want to divide the book, but once I have cherished it, I want to have it for a lifetime. As a paper book, I think it's a pleasure to live.
こういうものが欲しいのだけれども、どこを探しても無い、そもそも見ない、全てを知っている訳では無いし、全てを探し切った訳でも無いけれど、そうなると、全く知らない世界のことなのに、つくりたくなる、それは十二分な動機で、つくりたい時には無知ゆえの無謀な過信もあり、例えば、ツテがあったり、知り合いがもしかしたら関係者かも、関係しているかもしれない、そうしたら、つくるのはもしかしたら簡単になるかもしれないけれど、それは利用しない。
今、頭の中にあるモヤモヤとした形にならない、でも形にしたいものをつくろうとした時に、それをつくっている専門家や専門の職人と直に繋がりたく、間に専門外の人を介在させたくなく、そして、その専門家や専門の職人と一期一会で、点と点のような初めの接点があり、お互いがお互いのことを全く知らず、こちらはもうそれを形にしたくて仕方がなく、この訳のわからない、どこのどいつだかわからない奴をものをつくるという一点だけで受け入れてくれて、真剣に話を聴いてくれて、真剣につくってくれる人に出会わないと、こちらも本気でものづくりができないし、本物ができないような気がしているので、いつも無防備で、何も持たずに現地へ行き、1から関係をつくり、本当にこういうのを「類は友を呼ぶ」というのだと思う、似たような考えの人と出会い、そうすると、その人が実は、ということになり、いつしかクオリティが高いことがやれている、建築の職人も似たような感じで出会う、そういう運は昔からあるようだ。
いつも点と点、それが線や面にはならないのだが、大概、皆んな、難題を喜ぶ人ばかり、喜んでいるように見える人ばかり、点の存在、類は友を呼ぶ。
"Points and points"
I want something like this, but I can't find it anywhere, I don't see it in the first place, I don't know everything, I don't know everything, but it's a world that I don't know at all. If you want to make it, there is also a reckless overconfidence due to ignorance, for example, there may be a fool, a person you know may be related, or you may be involved, if you make it It might be easier, but don't use it.
Now, when you try to make something that you don't want to have in your head, but want to make it into a shape, you want to connect directly with the experts and craftsmen who make it. I don't want to do it, and I meet with the experts and professional craftsmen, and there is a point-to-point initial contact. They don't know each other at all, and I can't help making it anymore. If you don't know this translation, accept who you don't know where and when, just make a thing, listen seriously and meet someone who makes it seriously. I can't, and I feel like I can't do the real thing, so I'm always defenseless, go to the local area without anything, make a relationship from scratch, and really say this kind of thing is called "friends" think I met a person with a similar idea, and then, that person was actually, and I was able to do something of high quality sometime, and the craftsmen of the architecture also met with a similar feeling, such luck has long been There seems to be.
The point, the point, it doesn't always become a line or a face, but in general, all the people who are pleased with the difficult problem, the people who seem to be happy, the existence of the point, the kind calls friends.
一度ほどいたら、元に戻らなくなってしまった、たぶんそうなるだろと思って、ほどく前の写真を撮っておいたのけれど、諦めた。
桐箱の紐の結び目をほどく、躊躇したのだけれど、中身が見たい衝動を抑え切れず、紐の折り目のクセを頼りに、試行錯誤、その折り目の向きだと、いや反対になる、輪にならない、何をしてるのかと、紐と戯れただけの時間だった。
目がショボショボとしてきたので、立って歩きながら、難しい本は難しいことが難しく書いてあるから、座って読んでいると、眠くなるから、動きながら、運動しながら読むことにしていて、リビングの中をグルグル、ぐるぐる、決して外では危なくて難しい本は読めない体質になってしまった。
ただ、難しい本が助かるのは、案外、論文チックに、起承転結がはっきりしているから、結論がすぐにどこに書いてあるかがわかる、だから、そこしか読まないのだが、眠くて眠くて、さすがに歩きながらは寝ないので、言葉がわからなくても、参照文献を知らなくても、どんどん読み進めると、突然、視界がひらける、パキッと目が覚める、モヤモヤした謎がほどけた瞬間、その難しい本を開いてよかったと思う。
ほどけたものは、また結ぶ必要が無いので、そのままにして、また次の本を読み進める、その喜びや面白さは格別だが、結びが難しい姿は案外美しくて、手が届かない存在として、そのままにしておくのも良かったかもしれない。
"Knot"
Once I had unwound it, I couldn't get it back. I thought it would be so, I took a picture of it before, but I gave up.
The knot of the paulownia box was untied and hesitated, but the impulse that the contents wanted to see could not be suppressed, relying on the habit of the fold of the string, trial and error, the direction of the fold would be the opposite, It was just time I had fun playing with the strings and what I was doing.
Since my eyes have been changed, it is difficult to read difficult books while standing and walking, so when I sit and read, I get sleepy, so I decided to read while exercising while moving, in the living room The book has become a constitution that can never read books that are dangerous and difficult outside.
However, the difficult book is saved, unexpectedly, because the paper tic is clear, the settlement is clear, so you can see where the conclusion is written immediately, so you can only read there, but it is sleepy and sleepy, as expected Even if you do not sleep while walking, even if you do not understand the language, even if you do not know the reference literature, as you read more and more, suddenly the view opens, suddenly wakes up, the moment when the mysterious mystery has unraveled, it is difficult I'm glad I opened the book.
There is no need to tie the unraveled thing again, so continue reading the next book, its joy and fun are exceptional, but the figure that is difficult to tie is unexpectedly beautiful and unreachable It may have been good to leave.
静かにしていられない、立ち止まっていられない、動きたくて動きたくて仕方がない、カッカする、身体がアツイ、じっとしていられない。
無農薬のにんにくをいただいたのでペペロンチーノを作りつつ、にんにくのオリーブオイル漬けをつくりつつ、ひとかけら、ほんのひとかけらを口に含んで噛む、なんてことはない身体は正直だな、汗が止まらない、エアコンの風を浴びていても汗、汗、汗。
聞いた話によると、にんにくは生のままだとカビやすく、農薬の溜まりにポトンするらしい市販の物は、だから、いただいた無農薬のにんにくも乾燥をさせてあるらしいのだが、普段にんにくを食べも何ともないのに、それを使ったペペロンチーノは絶品、自分で言うのも何だけど、だから余計、汗が、汗が、汗が。
いや動きたくて動きたくて、じっとしていられないのは建築で慣れているのだけれども、普通、建築はじっとして見るものだと思われているけど、違うのですよ建築は動いて見るもの、動いて止まり、また動く、ストップアンドゴー、で、適当な所でとぐろを巻く、動かずにはいられないパワーをくれるもの、建築家は結構そういう想像をしながら設計している。さながら無農薬のにんにくですな、無農薬のにんにくをつくって食べた人をじっとしていられないようにする。
市販のにんにくは、よく見る建築は、何てことはない、じっとしていられるのですよ。
"Pesticide-free"
I can't keep quiet, I can't stop, I want to move and I can't help it, I can't help it, I can't stay still.
I received pesticide-free garlic, so I made peperoncino, made garlic soaked in olive oil, chewed with a single piece, just a single piece in my mouth, my body is honest, sweat doesn't stop, Sweat, sweat, sweat even in the wind of an air conditioner.
According to the story I heard, garlic is easy to mold when it is raw, and it seems that the pesticide-free garlic is dried, so I usually eat garlic. Even though there is nothing, Peperoncino using it is exquisite, what you say by yourself, so extra sweat, sweat, sweat.
I'm used to architecture because I want to move and want to move, but I'm accustomed to architecture, but it is usually thought that architecture is something to see, but it's different. Architects are imagining things like things that move, stop, move, stop and go, wind up the appropriate places, and give you the power you can't move. It 's like pesticide-free garlic, so make sure you ca n't keep people who ate and eat pesticide-free garlic.
On the market garlic, the architecture you often look at is nothing but still standing still.
掃除するのは苦手ではないけれど、片付けるのは苦手かもしれない。掃除は回数を重ねれば、やることは同じになってくるから、大した労力も使わないように、パターン化していて、時間も読めるし、やらないとホコリが溜まるし、汚れるから、ルーティン化してやれば良いだけだが、片付けの基本は元に戻すこと、だから、元に戻すのは掃除と一緒にやるから良いのだが、そもそも元に戻しても、なんか片付いたように感じない。
設計打合せで必ずと言って良いほど、話題に上がるのは収納のこと、収納を多くして欲しいという人に限って、なぜか、部屋を広くして欲しいと矛盾したことを言う。
そもそも収納や部屋の広さが一番重要になることは無く、どういう考え方で設計したかを提案して、そこで収納や部屋の広さの話になるので、ちょっとでも多く広くという人に対しては、何をどこにどれ位収納するのか、1日の行動パターンから活動範囲がどれ位か、など事細かに聴き、大概、必要十分な量と広さを確保でき、尚かつ、そこにピタリと納まるようになる。
今住んでいる所はリノベーションした家だが、収納に関しては元からあった物を再利用して、それでは足りない場合も考えて増やした。さらに、移り住む前に使っていた収納家具と移り住んでから購入した収納家具も置けるようにして、収納が結構たくさんある。
もちろん、何をどこにどれ位収納するかを一応考えたが、確かに、そこに全て納まるのだが、そもそも、片付けるのが苦手なのに、片付けるための収納が多過ぎた。
片付けるのが苦手だから、収納を増やせば、何とかなる、隠せるし、部屋の広さを犠牲にしてでも、収納を多く取れば、その分、部屋はすっきりするだろうが間違いだった。
かえって片付ける手間が増えることになる。いくら見えないからと言って、片付けして整理整頓しておかないと、いざ使う時に探したりして時間がかかり、そうならないためには片付けをしなくてはならず、収納が多いと、片付けがさらに多くなり、それが苦手なのだから、元も子もない。
本来は片付けを一度もしないで済むのが理想なので、収納が無ければ、片付けなくて済む、ならば、収納を全部無くそう、収納が無くても生活できるようにしよう、でも、捨てる物などはじめから無い、全部大事、ならば、収納を極力使わないようにして、物を出して飾ろう、飾ってある物を掃除するのは苦手ではないから、飾れない物だけ収納して、それで片付けしない。
"Do not clean up"
I'm not good at cleaning, but I'm not good at cleaning up. If you do a lot of cleaning, the work will be the same, so you do not use much effort, it is patterned, you can read the time, otherwise dust will accumulate and it will become dirty, so it will be a routine It's all you need to do, but the basics of tidying up is to restore it, so it's good to do it with cleaning, but even if you put it back to the original, it doesn't feel like it was tidy up.
The only thing that can be said in a design meeting is that storage is the only topic of discussion, and only people who want more storage say that they contradicted that they wanted a larger room.
In the first place, storage and the size of the room are not the most important, so we suggest what kind of idea you designed and then talk about the size of the storage and room, so for those who are a little larger Can listen to details such as what is stored where and how much, the range of activities from the daily behavior pattern, and in general, it can secure the necessary and sufficient amount and space, but it fits in there It becomes like this.
The place where I live now is a renovated house, but with regard to storage, I reused the original thing and increased it considering that it was not enough. In addition, there is quite a lot of storage so that the storage furniture used before moving and the storage furniture purchased after moving can also be placed.
Of course, I thought about where and how much to store, but it certainly fits in there, but in the first place I was not good at cleaning up, but there was too much storage for cleaning up.
It's not easy to get rid of, so if you add more storage, you can manage to hide it. Even if you sacrifice the space of the room, if you take a lot of storage, the room will be cleaner.
On the other hand, the time and effort to clear up will increase. Just because you can't see it, if you don't clean it up and keep it organized, it takes time to search for it when you use it. If you don't, you have to clean it up. Since there are more and it is not good at it, there is neither a former nor a child.
Originally, it is ideal that you do not need to clean up, so if you do not have storage, you do not need to clean up, so if you do not have all storage, you can live without storage, but things to throw away etc. If everything is important, if you don't use the storage as much as possible, let's put out and decorate things, and it's not a good idea to clean the things that are decorated, so store only the things you can't decorate and don't put away .
結構家にいると独り言を言っていて、それを自覚している、というか、誰かと想定の会話をしていて、それは側から見たらアブナイ人かも、今は亡き猫とは、まだ生きていた時も、亡くなってからも話し掛けているから、ほんとヤバイ人かも、もちろん、外では声に出して言わないが、 頭の中では常に何か会話をしているかもしれない。
昔、大学生の頃、友達と旅行をしていて、一緒に泊まった時に、シャワーを浴びて出てきたら大笑いされたことがあり、どうもずっとシャワーを浴びながら何かをしゃべっていたらしく、誰かが他にいるように、その時、確か手紙を出そうとして、その文面を考えいて、その文面を唱えていた。
今考えていることを、独りでいる時に、家や車の中では、普通に声に出してしゃべっていて、想定問答をしたり、自分で自分に向かって実況中継したり、例えば、計画中の建築のコンセプトをクライアントに伝えるという設定で、その場面を一人二役で演じて、コンセプトの良し悪しを考えたり、ダメ出ししたり、読んだ本の内容を自分で自分に向かって討論したり、自分なりの勝手な解釈で解説したり、別にもっと他のことでも、些細なことでも声に出してしゃべっている。
良く言えば、自分なりに腑に落ちやすいように、自分の言葉に変換して、それを頭だけでなく、口と耳を使って、自分のものにしようとしている、悪く言えば、いつまでも頭が切り替わらずに、ずっと頭に留めておくから、黙っていられずに、何かしゃべって外に出さないと、頭がパンクする寸前とも。
ただ、そうやって独り言を言って、口と耳と頭が連動した場合の事は結構記憶に残っていて、また、そういう状況が来て、独り言の通りにしゃべる事は結構ある。
"Solo Word"
I'm telling myself that I'm quite at home, and I'm aware of it, or I'm talking to someone and it's an Abnai from the side, but now the dead cat is still alive I'm talking to him even when he died, so he's really a bad guy. Of course, he doesn't say aloud outside, but he might always have a conversation in his head.
When I was a college student, I used to travel with friends, stayed together, and when I came out taking a shower, I was laughed out. At that time, he was surely trying to write a letter, thinking about the text, and chanting the text.
When you are alone, when you are alone, at home or in the car, you are speaking out normally, answering assumptions, relaying yourself to yourself, for example, planning In a setting to convey the architectural concept of the client to the client, play the scene in one and two roles, think about the quality of the concept, put out a bad idea, discuss the contents of the book you read to yourself , I explain it with my own interpretation, and speak aloud other things and even minor things.
In other words, I am trying to convert it into my own words so that I can easily fall into the trap and make it my own not only with my head but also with my mouth and ears. I will keep it in my head without switching, so I can't be silent, just talk and do not go out, just before my head punctures.
However, if you speak to yourself and the mouth, ears, and head work together, you still have a lot of memories, and it is quite possible that such a situation will come and you will speak as you say.
どうしよう、どうしよう、どうしようかな、なんていう状況に追い込まれるのは、大概は想定外のことが起こった時で、それが日常の些細な事でも、仕事でも、程度の差こそあれ、困る時で、それは時間を管理して、スケジュールをこなす場合は極力無くしたい。
だから、最大限の想像力を発揮して、これから起こる事を予測して、スムーズに進行するように準備をするのだが、まあ未来の状況を全て把握できる訳が無いから、その対策としてバッファを持たせて、これなら大丈夫だろうと、万全、なんて時ほど、斜め後方の死角からパンチが来るような、それは衝撃的な、やはり、人との関わりの中で、人って、ほんと多種多様で、自分も含めて、他人には理解できない部分が必ずあるから、でも、そこを理解し合えると関係性が良くなるので、とにかく聴く、傾聴しかないと、言いたい衝動を1/3位に抑えて聴くと、これがなかなか、自分ではわからない所で上手く作用する場合があり、人が何に反応するかも、また、わからない、謎な部分なので、そうなると、返しはカウンターパンチしかなく、あの一言が残ることは自分でも思い返せばあるので、何かの一言が作用して上手く行くか行かないかが決まる。
人は感情の動物だから、理性を発揮していても、その一言で決まる。では、どうやったら上手くいくカウンターパンチ、一言を出せるのか、ヒントはいつも相手の言葉使いの中にあると思っている。
"A word"
What happens, how, what to do is usually driven when something unexpected happens, whether it's a trivial thing in everyday life or a job, to some degree Sometimes it's time to keep track of time and to lose as much as you can to schedule.
So, make the best use of your imagination, predict what will happen, and prepare to proceed smoothly, but since there is no reason to understand all future situations, it has a buffer as a countermeasure. Let 's say that it 's okay, it 's perfect. How about a punch coming from behind the blind spot. It 's shocking. After all, in the relationship with people, people are really diverse. There is always a part that other people can't understand, including myself, but if you can understand it, the relationship will be better, so if you listen to it, there is only listening, if you listen to the impulse you want to say to 1/3 , This may work well in places that I do not understand, it is a mysterious part that I do not know what the person reacts to, so when it happens, the return is only a counter punch, Since that word is left in there if I recall myself, or something of a word is not going go work in action is determined.
Because people are emotional animals, even if they are demonstrating reason, they are determined by that word. Then, I always think that there is a hint in the opponent's vocabulary about how to make counter punches and how to make a word.
伸び縮みするような時間の感覚が人の感情と結びついて面白いと思う時に、何をしているのかなと考えると、大体、何かに追われて焦っているか、楽しくて仕方がない時か、今この時を何とかしたい時か、だったりする。よくあることに、楽しいことをしていて、あっという間に時間が過ぎる時があるかと思うと、締切が決まっていて、あっという間にその時間になってしまう時や、逆に、なかなか進まない時間をなんとか自分の手で秒針を動かしたくなるような講義や研修などは座っているだけでも辛い時で、基本的には時間の量は同じだとしたら、気分次第で時間は伸びたり縮んだりするように感じ、ならば、時間を有効活用できる術がそこにはあるのではないかと考えてしまう。
自分の感情をコントロールしてしまえば、時間をコントロールできる、時間を制することができるのではないか、と考えてみる。
例えば、常に楽しいことばかりで、あるいは、楽しい感情に包まれていたら、時間はあっという間に過ぎてしまうので、楽しいから良いが、その時間の使い方は有効活用しているとは言えずに、浪費しているとも言える。
何かに追われて焦っている時も、時間はあっという間に過ぎてしまうが、まだ追われている分だけ、その時に何かを一所懸命にやっているので、効率的ではないかもしれないが、時間を有効活用している部類に入るかもしれない。ただ、焦るのは精神衛生上、良くは無いので、何とかしたいとなる。
辛い時は本当に何とかしたくなるが、考えようによっては、余りある時間がそこには存在していることにはなるので、ただ、辛さを楽しさに変えてしまうと、せっかくの余りある時間が颯爽とスピードアップをして逃げて行ってしまうので、辛さはそのままいじらずに、辛いまま、辛い時にしかできない時間の有効活用をすれば良い。
少し時間が経てば、人には「慣れる」という特技があるので、辛いまま、辛い感情に慣れてしまえば、じっくりと、余りある時間に向き合えるのではないかと考えてみて、「慣れる」の「慣」は習慣の「慣」でもあると気がつくと、だから、トップアスリートは気分に左右されて成績がブレないように、ルーティン化を習慣としているのかと至った。
"Get used to"
When the feeling of time that stretches and shrinks is connected with human emotions and is interesting, when you think about what you are doing, it is roughly when you are chased by something or when you have fun and can not help , Or when I want to manage this time now. Often, if you're doing something fun and you think there's a time when it's too much time, the deadline is fixed and it's time to go, or on the contrary Lectures and training that make you want to move the second hand somehow with your own hands are difficult when you are sitting, basically if the amount of time is the same, the time will grow or shrink depending on your mood If it feels like it's going to happen, then I think that there is a way to make the most of time.
If you control your feelings, think that you can control time and control time.
For example, if you always have fun, or if you are wrapped in fun emotions, the time will pass in no time, so it 's fun, but you ca n't say that you 're using it effectively. It can be said that it is wasted.
Even if you are chased by something, the time will pass quickly, but because you are still chased, you are doing something hard at that time, so it may not be efficient It may not be, but it may enter into the category using time effectively. However, it is not good for mental health to be impatient, so I want to do something.
When you have a hard time, you really want to do something, but depending on your thoughts, there will be a lot of time there, but if you change the hotness into fun, you have a lot of time. However, you can speed up and run away, so you don't need to change the spiciness.
After a little time, people have a special skill of "getting used", so if you get used to painful emotions while staying painful, think carefully that you can face a certain amount of time. I realized that "Inertia" is also the "Industry" of habits, so I came to the question that top athletes are routinely employed so that their performance is not affected by their mood.
知らず知らずのうちにできてしまう、なんてことがあったりする、それは何でも、別に結果を出そうとしていた訳でも無く、何かを意識していた訳でも無く、目の前のことに一所懸命になっていたら、できるようになった、などという経験は誰にでもあるだろう。
知識に関してはどうだろうか。知らず知らずのうちにできるようになることは、どちらかというと、身体を動かしたり、経験をして身につけるようなことだと考えてしまい、知識に関してはそのようなことは無いだろうと思ってしまう。
身体が覚えるように、無意識の動作で何かが、知らず知らずのうちにできてしまう、としたら、知識は頭で覚えることで、頭は身体の一部だから、無意識に知識を得てしまうこともあるのではないか。
本から得られる知識は、その本が専門的であればあるほど、その本自体を読まないと得られないと考えてしまう。確かに、その通りだと思うが、その本自体を読まなくても、もちろん、その本についての解説を読まなくても、いつのまにか、その専門的な本の内容を知っている場合がある。
それは、その専門的な本を発展させたり、派生させたりした本を読んだ時で、元となった本の内容をベースとして書かれているから、元の本の内容まで知ることになる。もちろん、発展させたり、派生させたりした本は著者のフィルターを一度通しているので、元の本の印象が操作される可能性があるが、元の本の根幹の内容はそのままわかるだろう。
このことは、本以外のことでも、デザインとか、アイデアでも同じで、元ネタからの発展、派生を見ていたら、元ネタの考え方まで自然に頭に入っていた、もちろん、元ネタに直接接触することが大事で、時には深く遡ることも必要だが、研究者でない限り、そこまでする必要もない場合もあり、しない方が良い場合もあり、その見極めも必要になる。
"I get"
There is something that can happen without you knowing, it is not something that you were trying to produce a result, and you weren't conscious of anything. Anyone will have the experience of being able to do it.
What about knowledge? I think that something that can be done without knowing is rather like moving the body or gaining experience, and I think that there will be no such thing about knowledge End up.
As if the body remembers, something can be done unknowingly without knowing, if knowledge is remembered with the head, because the head is part of the body, the knowledge is obtained unconsciously There may be.
The more specialized a book is, the more knowledge it can get from a book. Certainly, I think that is true, but without knowing the book itself, of course, without reading the explanation of the book, you may know the contents of the specialized book.
That is, when you read a book that was developed or derived from that specialized book, it is written based on the content of the original book, so you will know the content of the original book. Of course, books that have been developed or derived have passed the author's filter once, so the impression of the original book may be manipulated, but you will still understand the basic content of the original book.
This is the same for things other than books, design, and ideas. If you were looking at the development and derivation of the original material, you naturally came up with the idea of the original material. Of course, you were in direct contact with the original material. It is important to do this, and sometimes it is necessary to go back deeply. However, unless you are a researcher, you may or may not need to go that far.
結果から逆算して今何をするのか、今何が問題かを考えるなんて、当たり前のことで誰でも行っていると思うのだけれども、その時に、解像度というか、どこまで細かく予測できるかで全然違うようだ。
クライアントとの打合せの時に感じることがある、その解像度の違いを、ただそれは、 その違いが生業としている人の所以でもあるのだが、そこに違いがあるということがわかっている人と、わかっていない人では、打合せの深度が違ってくる、なかなか深まらずに、浅いところでウロウロしてしまう。
本当はもっと詰めたところまで、そこより深いところに侵入したいのに、そこに行くまでに時間がかかってしまう。
反対の立場だったら、まず、要望、疑問、問題を伝えるだろう、それで青写真なり、方向性なり、全体像がはっきりしてくるから、そこまでどうやって行くかは詳しい人が考えればよいのでは、そもそも、そのようにできる人に依頼をするのでは、なんて思うのだが、深くない知識や自意識のために、それが粗い解像度の原因なのだが、引っ掛かりが多くなってしまって、何とも勿体ない。
そこにヒントが隠されている場合もあるから、そこを上手くやるのも建築の範囲としているのだけれども、何とも勿体ない。解像度が粗いならば、思いっきり粗くしてしまえばよいのに、自覚が無いと中途半端だと、と我が身を振り返る。
"resolution"
I think that everyone is doing what is right now, thinking what to do now and what to do now by calculating backwards from the results, but at that time it is completely different depending on resolution or how much you can predict It seems.
The difference in resolution that you may feel when meeting with a client is just because you know that there is a difference, but that is also the reason for the person who is doing business. If you don't have it, the depth of the meeting will be different.
I really want to go deeper and deeper, but it takes time to get there.
If you are in the opposite position, you will first convey your requests, questions, and problems, so the blueprint, direction, and overall picture will be clear, so a detailed person should consider how to get there. In the first place, I don't want to ask someone who can do that, but because of my deep knowledge and self-consciousness, it's the cause of the poor resolution, but there are so many catches that I can't help it.
There are cases where hints are hidden there, so doing it well is also within the scope of architecture, but it's useless. If the resolution is rough, you can make it rough. However, if you don't realize it, you're halfway.
合わせるのか、へり下るのか、主張するのか、意外と判断が難しい、相手が何かにもよるから、一概には言えないが、当たり前の回答だろう。
これはデザインの話。注文していたコーヒーカップが届いた。出来合いの輪島塗のコーヒーカップを以前購入したのだが、使い勝手がよかったので、もう1客注文したら在庫切れで、新たなに製作をするというので、ならば、今の黒と朱色の組み合わせを反転して欲しいとお願いしていたもの。
コーヒーカップだが、同型で湯呑もあり、取っ手があるか無いかだけの違い、まず湯呑をつくり、その後に取っ手をつけコーヒーカップにしたのだろう。
元があって、そこに付け足す、建築で言えば、増築みたいなものか。新たに注文していたカップは色違い、だから取っ手は同じ形状のはずが、届いたカップは違う、取っ手の形状が違っていた、付け足すものが変わっていた。
もしはじめからコーヒーカップをデザインするならば、当然、取っ手だけを後から付け足すようなことはしない。取っ手を含めて全体でどうデザインをするのかと考える。ただ、コーヒーカップをデザインすることを想像してみると、取っ手は厄介な存在、無い方がデザインとしては完成度が高くなるような気がする、それか片方だけではなく、両側に付けるか、それもおかしいが、スープカップになってしまうが、非対称の形は良いのだが、取っ手の存在感が大きいので、取っ手の形状が全体のデザインに与える影響が大きい。
それで取っ手を意識しすぎると、カップ全体のデザインがおかしくなる。今までコーヒーカップを見て綺麗なデザインだなと思ったことがほとんどなく、取っ手が無い方がよいのに、取っ手の形状がな、と思うことが多い。それだけコーヒーカップのデザインは難しいのだろう。
毎朝コーヒーを飲むので、コーヒーカップをいくつか所有しているが、無い、無いに等しい、いいデザインのものが、だから、つくりたくなる。
"Handle"
It's hard to judge whether to match, hail down, or argue. The answer depends on what the other party is.
This is a story about design. I received the coffee cup I had ordered. I bought a freshly made Wajima-painted coffee cup in the past, but it was easy to use, so if I ordered another customer, it would be out of stock and a new one would be made. What I had asked for.
It was a coffee cup, but it was the same type and had a tea cup. The only difference was whether or not there was a handle.
Is there something like an extension in terms of architecture? The newly ordered cups were different in color, so the handle should have the same shape, but the cup that arrived was different, the shape of the handle was different, and the additions had changed.
If you're designing a coffee cup from the beginning, of course, don't just add the handle later. Think about how to design the entire design including the handle. However, if you imagine designing a coffee cup, the handle is a nuisance, and if you don't have the feeling that it will be more complete as a design, you can attach it to both sides, Although it is strange, it becomes a soup cup, but the asymmetric shape is good, but the presence of the handle is large, so the shape of the handle has a great influence on the overall design.
So if you are too conscious of the handle, the whole cup design will go wrong. I have never thought that it was a beautiful design by looking at a coffee cup until now, and I often think that the shape of the handle is good, even though it is better not to have a handle. That's how difficult it is to design a coffee cup.
I drink coffee every morning, so I have a few coffee cups, but none, no, good design, so I want to make one.
なんか夏休み、気分は、暑いし、事務所にこもる日々だからいいけれど、今週夏休みの人もいるだろから、やっと動き出したプロジェクトが、動き出す時はなぜか同時に複数だったりして、盆休み前にとりあえず青写真は描けそう。
まったくの王道から外れた、というか、今までカップのデザインはしてこなかった、というか、建築以外はほとんどデザインをしたことがなく、昔、飲食店の設計をした時に、お品書き、箸袋、楊枝入れなどなど、をデザインしたことはあったが、ほぼ素人に近く、塗りを一から調べたり、古い文献にあたったり、カップは昔から好きなので、陶磁器、硝子、それこそ、塗り物も家にはあり、造形に関しては博物館へ縄文式土器を見に行ったりもした。
輪島塗のフリーカップをつくろうとしたキッカケは置いておいても、何回輪島に通っても、いろいろと輪島塗について深掘りをして知り、デザインを考えても、自分で素人感が否めない。
建築の打合せをしていて、クライアントが自分で描いたプランを持ってくることがある、手書きでも、プリンとアウトしたものでも、それはどこまで行っても出来は素人であり、それだったら変な先入観ができるから、要望を伝えて、あとはプロに任せればいいのに、自分では上手くできていると思っていそうだと、無碍にもできなくて、つらい。
それは料理でも同じで、素人が死ぬほど頑張ってもプロの料理人には敵わないだろう、例え、同じレシピで、設備も場所も同じでも素人はプロには敵わない、知識、技術、感覚の全てが足元にも及ばない、その違いがプロたる所以、建築も同じ。
それをプロ側で経験しているから、塗師にスケッチを見せて、フリーカップについて説明する時は、素人感満載なんだろうなと思っていた。
ただ、この素人感満載でものづくりを、デザインを考えているのが実に楽しい、楽しくて仕方がない。ましてや、職人集団は日本で最高レベル、漆器で日本で最高ならば、世界的にも最高レベルだろう。
自分でデザインしたものを最高の職人集団が形にしてくれる、建築でも同じだが、これほど楽しいことは無く、ましてや、この素人感がのびのびとして楽しくさせてくれる、何かに縛られることもなく、何かに忖度することもなく、考えてみれば、建築をやりはじめた時も同じだった。
何か歴史の中でポジションが決まっていて、そのポジションは複数あるが、外れた所には無く、そのポジションを得るために勉強し、知識を得て、実務を経験し、素人からプロに成長し、そのポジションの枠の中でのみ、プロとして全うする。
その大変さと難しさと、当然面白さ、楽しさもあるだろうが、ものづくりの楽しさは、そのポジショニングとは別次元の所に存在していて、ポジショニングとは全く関係が無い。だから、ものづくりの楽しさを得るために、プロも素人も関係が無く、純粋にデザインだけに向き合えるし、そもそも建築以外のことなので、素直にプロ感を捨てられた。
確かに、素人はプロには敵わないが、素人がプロには思いつかない価値を生み出すことは可能だと思う。ただそれは先の話のポジションの枠の外になるから、プロの世界では相手にもされない。しかし、確実に新しい可能性がそこにはあり、新しい楽しさもそこにはある。
"amateur"
Somehow summer vacation, mood is hot and it's hot days in the office, but there are people who are summer vacation this week, so when the project finally started moving, there were several simultaneously at the same time, for the time being before the Bon vacation I can draw a blueprint.
I haven't designed the cup until now, or I haven't designed a cup until now, I have never designed anything other than architecture. I have designed, such as toothpick holders, but it is almost like an amateur, I studied paint from scratch, hit old literature, I like cups from a long time ago, ceramics, glass, that is also the paint home I went to the museum to see the Jomon pottery.
No matter how many times you go to Wajima Lacquer, you can't deny the feeling of an amateur by yourself, no matter how many times you visit Wajima Lacquer.
I have an architectural meeting and the client may come up with a plan that I drew, whether it is handwritten or printed out, it can be an amateur no matter how far it goes, and then a strange preconception I can tell you what I want to do and then leave it to a professional, but if you think that you are doing well, you can't make it instinctively.
It's the same in cooking, even if you do your best to the extent that an amateur dies, it won't match a professional chef, for example, with the same recipe, the same equipment and location, but an amateur is not comparable to a professional, knowledge, technology, The architecture is the same because all of the sensations do not reach the feet and the differences are professional.
I experienced it on the professional side, so when I showed my sketch to the painter and explained about the free cup, I thought it was full of amateurism.
However, it is really fun, fun, and unavoidable to think about design with this amateur-packed design. Moreover, if the craftsman group is the highest level in Japan, and the highest level of lacquerware in Japan, it will be the highest level in the world.
The best craftsman group forms what you designed yourself, the same with architecture, but there is nothing so much fun, let alone this amateur feeling freely and fun, without being bound by anything, If you think about it, it was the same when you started building.
There are several positions in history, and there are multiple positions, but they are not out of place, studying to acquire that position, gaining knowledge, experiencing business, growing from amateur to professional However, I will be a professional only within the frame of that position.
The difficulty and difficulty, and of course, the fun and the fun, but the fun of manufacturing exists in a different dimension from the positioning and has nothing to do with the positioning. So, in order to get the fun of manufacturing, there is no relationship between professionals and amateurs, they can face purely design, and since it is something other than architecture in the first place, I was abandoned professionally.
Certainly, amateurs are not competitive with professionals, but I think it is possible for amateurs to create value that professionals cannot think of. However, since it falls outside the frame of the position of the previous story, it is not made a partner in the professional world. But there are certainly new possibilities and new fun there.
ひとにとってはどーでもよいことでも、本人はいたってまじめに取り組んでいて、いつも同じことをしていて、意味不明で、まわりの人は同じものがたくさんあっても仕方ないじゃない、本人はひとつひとつのちがいが、違うでしょ、と思いながら、どうでもいいことには価値を見出さないかと、
お店の人も、それは全部イギリスのアンティークです、毎回説明してくれるけど、毎回新鮮におどろく、毎回聞いていないのだな、どこのものか、年代が古いとか、価値基準がはっきりしていて、値札も相応なのか、ただ、欲する側はそこを見ていなくて、形とか、大きさとか、厚みや小口の手触り、材質が醸し出す雰囲気なんかを頼りに選り分けて、
今日は何本ですね、と言われながら所望し、目黒と恵比寿の間に1,2ヶ月毎に3回ばかり通っている中華屋さんへと続く道の途中に誘惑されるアンティークショップがあり、カトラリー好きのスプーンフェチなので、まっすぐそこへ、スプーンめがけて行くのははばかるから、好きものは一番最後に食べるので、他のものが気になりつつ、たまたまスプーンを見つけて見入ってます体なのだが、3回目ともなると、この前もスプーンでしたねとバレバレなので、次回はまっすぐスプーンめがけて、ただ、そこのスプーンは全て穴が空くぐらい見てしまったので新鮮味がもうないかも。
たぶん縄文人も木のスプーンを使っていただろうぐらいに、原始的な道具、変わりばえしない機能、だから、何でもあり、どうにでもなるからか、意外と形も大きさも厚みなどにバリエーションがあり、バリエーションをつくりやすいのか、
1番のフェチポイントは柄の厚み、ここの厚みが変化していたり、薄く一定だったり、微妙に曲がっていたり、カトラリーをつくる時はわざと微妙に柄の部分を曲げてみようかな、何の意味もなく、ただ、こういうのは曲げれば、意味は後付けで見つけるもので、それが道具として手放せないものになるところだったり、こういう製作時の自然な、許せる、有りなブレみたいところが今のカトラリーには無い、道具に愛着は必要なのに、そこが愛着ポイントになるのに。
"attachment"
For the people, whatever they are, they are always working seriously, always doing the same thing, meaningless, and it is no wonder if there are many same people around them, each one is one person While thinking that they are different, they may not find value in any kind of thing,
The shop staff are all British antiques, but I will explain them every time, but I am always fresh and shocking, I have not heard each time, where are they, what is the age, and the value standard is clear The price tag is also appropriate, but only the side that wants it is not looking there, depending on the shape, the size, the thickness, the texture of the small part, the atmosphere that the material brings out, and so on,
There is an antique shop that is seduced on the way to the Chinese restaurant, which goes about 3 times every 1 to 2 months between Meguro and Ebisu. Because it is a spoon fetish like a cutlery, it is not good to go straight there or to go with a spoon, so the last thing you like is, so while you care about other things, it happens that you find a spoon and you're on the body As it was the third time, I used to use a spoon last time, so I took a straight spoon on the next time, but I just saw all the spoons there are holes, so there may be no fresh taste.
Perhaps as much as the Jomon people would use a wooden spoon, there are variations in shapes, sizes, thickness, etc., surprisingly, because they are primitive tools, functions that do not change, and so anything, because they do anything. Is it easy to make variations?
The first fetish point is the thickness of the handle, the thickness here is changing, it is thin and constant, or it is slightly bent, or when making the cutlery, let's try to slightly bend the portion of the handle intentionally, what it means No, but if this is bent, the meaning will be found later, and it will be something that can not be released as a tool, or such a natural, forgiving, kind of blurry place like this at the time of production will be the cutlery of today There is no need to attach to a tool, but it becomes an attachment point.
あーあ、とか、どうしようかな、とか、いやになるな、なんて時は何もする気が起きないな、でも、やることはたくさんあるし、困るな、という時でもお腹が空くから、やる気はないくせに、お腹いっぱいご飯を、また食べたら気分も変わるだろうと思うのだけれど、気分も変わらずに、あーあ、どうしようかな、いやになるなの連発を、どうやったら、気分が落ち込んでいる時は、でも、気分が良い時はこの逆だから、結局気分しだいなんだよな、ご飯たくさん食べられるし。
何をつくるか、今しかつくれないものをつくる、ならば、全ての気分をひっくるめて、つくることに生かそうと考えて。
気分であそこにしよう、ここにしようと、自分が身体を動かして選択することはよくあるから、何かをつくるプロセスには気分が関わっていることが当たり前だと思うのだけれども、気分で変わることがネガティブに捉えられる時も。
だから、使う人の気分も拝借してしまえば、プロセスに気分が入り込もうが良いだろうと考え、気分つながりということで、よくわからないが、飲み物があって、飲む人がいて、飲む人の気分が揃ってはじめて成り立つデザインを考えたのが輪島塗のフリーカップ、ようやく塗りのサンプルが出来上がってくるメドがついた。
"As you feel"
Oh, I do, I don't care, I don't feel like doing anything at all, but I have a lot of things to do, and I'm hungry because I'm hungry, so I'm not motivated I think I will change my mind if I eat a lot of rice and eat it again, but I feel the same, oh yeah, how to do it, how I do a barrage of irritating, how I do, when I feel depressed But, when I feel good, the opposite is true, so I feel like I can eat a lot of food.
What to make, to make something that will not be done now, if it is, enliven all the mood, thinking that it will be useful for making.
Because there is a feeling that it is natural to move the body to make a choice, let's feel it here or there, so I think that it is natural that the mood is involved in the process of creating something, but it changes with the mood Even when it is caught in the negative.
So, if you borrow the mood of the person who uses it, I think that it would be better to get in the process, and I'm not sure about the mood connection, but there is a drink, there are people who drink, and the people who drink Wajima-Nuri's free cup was the first to think of a design that could only hold true, and a med's finally came with a sample of the paint.
何年か前、週に一度早朝に臨済宗の僧侶の指導の元、坐禅をしていた。臨済宗の坐禅の特徴は、最中に禅問答のお題を与えられ、その答えを考えながら坐禅をし、坐禅の後、禅問答をする。その時に教えてもらった禅語で
応無所住 而生其心
(おうむじょじゅう にしょうごしん)
がある。「応(まさ)に住(じゅう)する所無くして、而(しか)も其の心を生ずべし」と読みくだすらしい。
住する所とは、自分が留まる所、執着する所で、それが無いから、「応無所住」とは執着しないこと。其の心とは、自分の心で、生ずべしとは、自由自在に働かせることなので、「而生其心」とは自分の心を自由自在に働かせること。
「応無所住而生其心」とは、自分の心を自由自在に働かせるためには、何事にも執着しないこと。
ただ、何事にも執着しない方が良いからと言って、何もしないのではなくて、何かをして執着することがたくさんある方が、その執着の振れ幅が大きい方が人生は豊かになるから、どんどんたくさん執着をすれば良いのだが、どんなにブレても必ず元に戻るということ、執着した心をそのままにしない、元の何事にも執着しない心に戻りなさい、ということ。そうすれば、心を自由自在に働かせることができる。
要するに、何があろうとも、心を常にニュートラルな状態を保つことで、様々なことに対して、自分も含めて、心の機微に触れることができ、本来の自分でいられるということ。
執着することの方が、執着する誘惑が多いから簡単だし、執着している状態は満足感が得られるから、ついついそこが自分の居場所だと勘違いしてしまうが、元に戻りましょう、本来の自分が居るべき場所はどこですか、という気づきの禅語でした。
"Do not attach"
Several years ago, once a week early in the morning, under the guidance of the priests of the Rinzai sect, he was sitting. The feature of the Rinzai sect's zodiac is given the title of a torture question in the midst, and the zodiac is considered while thinking the answer, and the torture question is made after the zodiac. In the shame language taught at that time
Non-Resident Housing
(Study in English)
There is. It says, "If there is no place to live in Masaki, Shiro also produces the heart of Sagi."
A place where you live is a place where you stay, where you attach, and because there is no such thing, don't attach to "non-residential residence". Since the heart of a wolf is one's own mind, and the birth is to work freely, the "Gyusei's heart" is to work one's mind freely.
In order to make your mind work freely, you must not stick to anything.
However, saying that it is better not to attach to anything, it does not do anything, but if there is a lot of attachment to attach something, life is richer if the amplitude of attachment is larger Therefore, it is good to attach a lot more and more, but be sure to return to the original no matter how much the blur, not to leave the obsessed mind as it is, to return to the mind that does not attach to anything of the original. Then you can work your mind freely.
In short, no matter what, by always keeping the mind in a neutral state, you can touch the subtleties of the mind, including yourself, to various things, and be able to be yourself.
Attaching is easy because there is a lot of temptation to attach, and the state of attachment gives you a sense of satisfaction, so you may misunderstand that it is your own place, but let's go back to the original, originally It was a jargon of awareness that where I should be.
眠いと頭が働かなくなる、ボーっとしてもうろうとしてくると、寝落ちしかける寸前あたりで、何かしらのイメージが頭に広がる時がある。
それは、それまで考えたり、思ったりしていたことの延長線である場合もあるし、全く関係が無い場合もあるが、現実とイメージ、それは夢かもしれないが、区別がつかず、連続的に展開される時があり、それも変な、ありえないような、面白いものであったり。
夢と現実の境界が無くなる、無意識と顕在意識の境の扉が開いた状態になるのだろう。
イメージとしては理路整然として秩序だった顕在意識に、無秩序でごちゃまぜになっている無意識が扉から進入して来て掻き乱すような、寝ている時に見る夢が荒唐無稽なのは、この顕在意識と無意識の境が無くなっている状態で、顕在意識よりも膨大な量の無意識が顕在意識を侵食して、無意識ワールドを展開しているから。
だから、眠くて眠くて仕方が無く、でも寝ることが許されない状態の寝落ち寸前の時に、例えば、ただ聞くだけのつまらない講義の時などは、面白い映像がたくさん見られると思うことにしている。
"Interesting picture"
When I'm sleepy, my head stops working, and I'm trying to get down, there's a time when an image of something comes to my head just before I fall asleep.
It may be an extension of what you have been thinking or thinking before, and there may be no connection at all, but reality and image, it may be a dream, but it is indistinguishable, continuous There is a time when it is deployed, and it is strange, impossible, and interesting.
The boundary between the dream and the reality disappears, and the door of the border between the unconscious and the conscious mind will be open.
As the image, in a sense that orderly and orderly in a logical way, an unconscious that is disordered and messed up comes in from the door and comes to a stir, the dream that you see while sleeping is insane, this unconscious In the state where the border of the unconscious is gone, a huge amount of unconscious that is more obvious than the unconscious consciously erodes the unconscious and develops the unconscious world.
So, when I am just asleep in a state of being sleepy, sleepy, unavoidable but I can not sleep, I think that, for example, in the case of a boring lecture that I just listen, I can see many interesting images.
目をつぶってじっとしていて、でも眠らない状態を維持するのは案外難しい。
目をつぶってじっとしていること自体、人によっては苦痛で、何もイメージしない、何も考えたりしないことができず、何かしらイメージしたり、何かしら考えたりしてしまう。その時に暗闇に慣れていない人は、変なイメージや考え、思いが頭をめぐり、目をつぶってじっとしていることができない。
仮に、何もイメージしない、何も考えたりしないことができても、眠気が襲ってくる。眠いのに寝てはいけない状況ほど辛いものは無い。
何年か前、週に一度早朝に坐禅をある所でしていた。ある所とはお寺ではないが、臨済宗の僧侶が出張して約1時間くらい座禅をし、警策もあり、時間は20分ずつ2回で短めだが、場所以外は本格的な坐禅だった。
臨済宗の坐禅の特徴は、最中に禅問答の公案を思索するところ。公案とは問題のことで、禅問答のお題を与えられ、その答えを考えながら坐禅をする。
だから、目をつぶってじっとしていることができる。答えを考えることに意識を集中することになるから、眠くはならないし、変なイメージや考え、思いが頭をめぐることは無いし、余計な雑念も排除しやすく、それでいて、目をつぶって視覚情報が入らないから、頭の中ではかなりクリアに考え事ができる。
今でも時々、坐禅の真似事を自宅でも、椅子に座りながらでもするが、お題を自分に出して、何でも、何食べようかなでも、こういうことは慣れだから、瞬時にスイッチが入って頭が回り出す感じが面白く、実際の公案の答えには正解があるようだが、何よりも自分なりの答えが愛おしく、尊く思えてくる。
"Kouan"
It is surprisingly difficult to keep your eyes closed and still sleepless.
Being blinded and standing still is painful for some people, can not imagine anything, can not think of anything, can imagine something or think about something. Those who are not accustomed to darkness at that time can not have strange images, thoughts, thoughts moving around their heads and closing their eyes.
Even if you can not think of anything or think about anything, you may feel sleepy. There is nothing as painful as it is not to sleep in a sleepy situation.
Some years ago, once a week, I had a sitting area early in the morning. A certain place is not a temple, but a Buddhist priest from Rinzai sects on a business trip for about an hour, and there is a security measure, and although the time is twice as short as 20 minutes each, it was a full-fledged zazen other than the place.
The feature of the Rinzai sect's Zazen is where you think about the torture and answer plan during the process. A public draft is a problem, given the title of torture, and sitting down while thinking about the answer.
So you can close your eyes and stay still. You will not be sleepy, you will not be weird images and thoughts, your mind will not go around your mind, and it will be easy to eliminate extra clutter, because you will concentrate on thinking the answers I can think about things fairly clearly in my head because no information is included.
Even now, sometimes I do imitations of zazen at home or while sitting in a chair, but I give myself the subject, whatever I am, whatever I eat, these things get used to it, so the switch turns on and the head turns The feeling of going out is interesting, and it seems that there is a correct answer in the actual answer of the draft, but more than anything, the answer of one's own love and seems to be precious.
最近知った言葉を思い出した。
「冷え枯れる」
室町中期の茶人、村田珠光の言葉、名言を残した人。
ひえかれる、年を重ねて成熟してくること、と知った時は解釈した。「枯れる」から成熟はあまりイメージできなかったので、だから印象に残っていたのかもしれない。
ひえかれる、には一言でいうと、衰退のイメージしかない。ただ、それは反対の言葉、例えば「熱し盛る」などが豪華絢爛で、それが良いということが前提でのイメージであり、珠光は「冷え枯れる」を良いこと、そこに美意識がある、としてこの言葉を残したのだろうから、改めて「冷え枯れる」を読み味わってみる。
ひえかれる、澄んで凛とした冷たい空気が張り詰めて、そこには豪奢なものは何も無く、あるものは必然的に存在するものだけ、そこにあることが定めのようなものだけ。
ひえかれる、真の成熟の姿が一言で表されているような気がした。
"Mature"
I remembered the words I learned recently.
"Cold and dry"
A man from the middle of the Muromachi tea ceremony, the words of Murata Tamaki, and quotes.
When I learned that it would be held, matured by age, I interpreted it. Because I could not imagine much maturity from "withered", it may have left an impression.
In a nutshell, there is only an image of decline. However, it is an image based on the premise that the opposite term, for example, "Heat up" is luxurious, and that it is good, and the light is "cold and dry" is good, there is a sense of beauty, and this word I will read and taste "Cold and dry" again.
There is a clear, cool, cold air filled, there is nothing arrogant, there is only a certain thing that is necessarily present, only something that is there to be.
I felt as if the figure of true maturity to be held is expressed in one word.
最近知った言葉を思い出した。
「我が心を師にするな、心は師に導かれる」
室町中期の茶人、村田珠光の言葉、名言を残した人。
いろいろな解釈ができそうだが、規範は自分の中には置かず、外に求めるとも読め、その規範は自分の都合とは関係が無く、時には自分とは真逆のことも。
思い込みを捨てよ。思い込みを解くには自分の外に耳を傾けて、素直に従うこととも。
自分がわかる範囲などたかが知れている。外に向かって自分を解放し、広い視野を求めなさいとも。
師は我が心がつくるのではなく、師が我が心をつくるとも。
いずれにせよ、自分という者に重きを置くな、自分を疑え、自分の間違いに気づけ、そして、自分を常に空っぽにしておくことが大事だと解釈をした。
"empty"
I remembered the words I learned recently.
"Do not master my heart, my heart will be guided by him"
A man from the middle of the Muromachi tea ceremony, the words of Murata Tamaki, and quotes.
Although it seems that various interpretations can be made, the norm does not exist in oneself, and it can be read as it seeks out, and the norm has nothing to do with one's convenience, and sometimes it is the opposite of oneself.
Discard your beliefs. You can listen outside of yourself and follow obediently to get rid of your assumptions.
It is known how much I can understand. Free yourself out and seek a broad vision.
The teacher does not make my heart, but the teacher makes my heart.
Anyway, I did not put a weight on the person I called, I doubted myself, noticed my mistakes, and interpreted that it was important to keep myself empty.
意識をして何かに取り込むことは、ああ、楽しいな、面白いな、きっと、見ているだけとか、食べているだけとか、よりも良いと思ってしまう。
だから、何でも自分でやろうとしてしまい、余計に時間がかかってしまい、どうしたらいいかな、と悩む時もあるけれど、そこがまた楽しかったりする。
結局、そこの部分が無いと毎日の生活が楽しくない、日常の出来事に満足できないのだと思うが、よくよく振り返ったり、細かく見ていくと、そのものズバリ、今取り組むべきことよりも、その周辺の整理することが多かったり、そこに気をとられていたりして、そこから抜け出せないでいることも多い。
前は、その周辺のことにヒントや学ぶことも多く、そこも大事というか、そこの方が大事だと思っていたけれど、それは、そのものズバリ、今取り組むべきことから逃避しているに過ぎないので、最近は気にも止めないようにしているが、なかなか、素直に向き合うのも、いろいろ試行錯誤があって、変化があって、ヒントも学ぶこともある。
"Facing"
Being conscious and taking something into something is a lot more fun, interesting, surely, better than just looking, eating, and so on.
So I try to do everything myself, it takes extra time, and sometimes I wonder how to do it, but I enjoy it again.
After all, I think I can not enjoy my daily life without my part, but I am not satisfied with my daily events, but if I look back on it carefully or look in detail, it's better than things I should work on now. There are a lot of things to be organized and taken care of there, and in many cases they can not get out of there.
I used to think that there were a lot of hints and lessons in the surrounding area, and that was important, but I thought that there was more important, but it is only a escape from things that should be tackled now. So, I try not to stop my mind these days, but there are many trials and errors in facing honestly, there are changes, and there are also hints and lessons.
なかなかできないことをどうしてできないのだろうか、と考えていたら、まず、できることはどうしてできるのだろかと考えてみた、行き着いた答えは、全てをパターン化できて、ルーティン化していることだった。
単純な作業や簡単な家事は全てパターン化していて、ルーティン化している、それは特にそうしようと思った訳ではなくて、毎日のことだから自然とパターン化され、ルーティン化した、意識した訳ではない、だからか、自分の都合の良いように、楽なように、何も考えないでできるように、やりながら他のことを考えることができるようにそうしただけ。
できなかったことを意識してパターン化してルーティン化してみようと思う。本当にそれだけで、今まで上手くできなかったことが、上手くできるようになるのだろうか。
そのためには、全てに正解があると意識して、全てに制限時間を設ける必要があるかもしれない、それは日々の単純な作業や簡単な家事をこなすのと一緒と思えば大したことはないか、それで余白が頭の中にたくさんできればいい。
"Patterning routineization"
If I was wondering why I could not do something I could not do, I thought first of all I could do what I could do, the answer I came to was that I could pattern everything and make it routine.
Simple tasks and simple chores are all patterned and routine, not specifically intended to be so daily, so they are naturally patterned, routine, not conscious So, as it is convenient for me, just as easy, as I can think without doing anything, just as I can think of other things while doing.
I will try to make it into a routine and make it conscious of what I could not do. Does it really make it possible to do things that could not be done well until now?
To that end, you need to be aware that everything has the correct answer, and you need to set a time limit for everything, which is not a big deal with daily simple tasks and simple chores. Or, I wish I could make a lot of margins in my head.
間違った方向に進んでしまうのは地図を持たずに行動してしまうからで、そんなことをする訳がないだろうと思うが、案外そういう人は多いような気がする。だって、普通に、とりあえず即行動しよう、なんてことを言う人が多いし、そのようなことをうたっている本も多いし、とりあえず即行動して、行動することは良いことで、あとは動きながら考えれば良い、考える前に直感を信じて行動しなさい、そうしないと機会を失う、なんて具合に。
地図の効用は、目的地までのルートがわかることで、ルートがわかるから、きちんと目的地に着ける。
では、地図を手にするには、まずその前に、目的地がそこで良いのかの方が重要で、そこを直感で決めている時点で、根拠のないギャンブルをしているようで、ギャンブルだから当たることもあるかもしれないが、1度きりでリスクの無いことならば良いが、この先何度もあり、リスクもあることならば、きちんと根拠は必要だし、それも論理的な根拠で、根拠があるならば直感に頼る必要もない。
目的地を決め、地図を手にするにも、事前の情報収集や検討に時間を割かないと、それも徹底的にやらないと、リスクにも対応できない。
地図を持たずに即行動なんて、例えると、東京駅に着いて新宿駅が目的地だとして、どのルートで新宿駅まで行ったら良いのかわからないから、片っ端から東京駅に着いた電車に乗るようなもの、たまたま偶然、中央線や山手線に乗ることができれば良いが、そもそも、そのようなことはしないだろうに、路線図を見るか、人に尋ねるだろうに、直感で行動しないでしょう。
即行動をして良い場合は、目的地がはっきりしていて、地図を持っている時だけ、逆に言えば、目的地がはっきりして、地図があれば、行動するなど容易いこと、自戒を込めて。
"Do not act immediately"
I'm going to go wrong because I'm acting without a map, so I think I'm not going to do that, but I feel like there are a lot of people like that. Because there are many people who usually say, let's act immediately and for the time being, there are many books that sing such a thing, and it is good to act immediately and act for the time being, and while it is moving If you think about it, act on your intuition before thinking about it, otherwise you lose the opportunity.
The utility of the map is that if you know the route to the destination, you can know the route, so you can reach the destination properly.
So, first of all, to get a map, it is more important that the destination is good there, and it seems that you are doing gambling without base at the time you are deciding with that intuition, and gambling It may be hit, but it is good if there is no risk at one time only, but if there are many more and there are risks in the future, a proper basis is necessary, and it is a rational basis, it is a basis There is no need to rely on intuition if there is.
Even if you decide on a destination and get a map, you have to spend time in advance gathering and examining information, or you can not cope with risks unless you do it thoroughly.
If you take immediate action without having a map, for example, if you arrive at Tokyo Station and Shinjuku Station is the destination, you do not know which route to go to Shinjuku Station, so take a train that arrived at Tokyo Station from the other end It would be nice if I could get on the Chuo Line or Yamanote Line by accident, but I would not act with intuition to see the route map or ask people if I would not do such things in the first place.
If you are willing to act immediately, only when the destination is clear and have a map, conversely, if the destination is clear, if there is a map, it is easy to act, and self discipline Please.
見る者と見られる者がいるという関係性が成り立つのが普通のことだと仮定したら、それが、見る者と見られる物でも良いのだが、その関係性自体が近代以降のことかもしれないが、外形には何かしらの意味を持たせることになるだろう。
外形とは、人ならば外身、物ならば外観で、もっと簡略化すれば、双方とも輪郭といえる。
その輪郭の意味を、見られる側は意図してつくるだろうし、見る側は都合よくつくるだろう。
別に意味など無くても良いと思うのだが、見る側が勝手に意味づけをしてしまう、それはたぶん、人の脳の構造の問題だと思うのだが、意味づけ、すなわち、認知することで、自分の周りの環境を把握し、自分の身の安全を保つのだろう。
だから、見られる側はその脳の構造を利用して、意図した意味づけをする、もちろん、その意図通りに見る側が意味をくみ取ってくるないこともあるだろうが、よくある話で、それが成り立つのも、見る者と見られる者がいるという関係性が前提になるから、要するに、見る側見られる側の関係性と輪郭の意味づけは共謀関係になる。
輪郭は様々な分野にあるが、最近、アンジェロ・マンジャロッティがデザインした置時計「セクティコン」を手に入れた。6年程前に復刻されたものではなく、60年前に船室用置時計としてデザイン・製造されたプラスチックの一体成型のオリジナルのもの。
その赤い丸みを帯びたフォルムは見る者に様々な想像を強いる。見られる側、すなわち、デザインした方の意図は計り知れないが、人を模したように、頭があり身体があるように見えなくもなく、水面からひょっこり顔を出したタコのようにも見えたり、もちろん、そのフォルムからミッドセンチュリーの雰囲気が漂ってきて、この時計を部屋に置いておくだけでもいい。
もし、見る側に誰もいなかったら、この時計自体の存在価値はあるのだろうかとさえ思ってしまう。
だから、見られると思って、見られることを意識してデザインする、当たり前だが、逆に言えば、見る側がいて、見る行為が無かったら、デザイン自体が無くても良いことになる。
デザインもまた、見る側見られる側の関係と共謀関係にあり、だから、見る側の目も引きたくなる。
などと、セクティコンを手にして思いながら、だから、既視感が無いことが重要だと改めて思う。
"Secticon"
Assuming that it is usual that the relationship between the viewer and the viewer is satisfied, it may be the one seen by the viewer, but the relationship itself may be after modern times , The external form will have some meaning.
The outer shape is the appearance of a person if it is a person and the appearance if it is a thing, and if it is more simplified, both of them can be said to be a contour.
The meaning of the contour will be purposefully created by the visible side, and conveniently by the viewing side.
I think it doesn't matter if I have no other meaning, but I think that the viewers make their own meaning, maybe it's a problem with the structure of the human brain, but by making meaning, that is, recognizing, Understand the environment around and keep your own safety.
So, the side to be seen uses the structure of the brain to make the intended meaning, and of course the side that looks as intended may not come to understand the meaning, but it is a common story. Since it is premised that there is a relationship between the viewer and the viewer, the relationship between the viewer and the viewer and the meaning of the contour become conspiracy, in short.
The outline is in various fields, but recently I got a table clock "Secticon" designed by Angelo Manjarotti. It is not reprinted about six years ago, but is an original plastic integrally molded and designed and manufactured as a cabinet clock 60 years ago.
The red rounded form forces the viewer to imagine various things. The side that can be seen, that is, the intention of the person who designed it, is immeasurable, but as a person imitating, it looks like a octopus with a head and a body, not as invisible as a head, and a face coming out of the water surface Or, of course, the atmosphere of mid-century comes from the form, and it is good to leave this watch in the room.
If there is no one on the side of the viewer, it even wonders if the watch itself is worthwhile.
So, I think that I can see it and design it consciously to be seen. It is a matter of course, but on the contrary, if there is no act to see, there is no need for the design itself.
The design is also in contradiction with the relationship between the viewer and the viewer, so the viewer's eyes also want to pull.
And while thinking about having a secticon, I think that it is important that there is no sense of sight.
「星に願いを」、七夕の夜、ルーシー・リーの白釉皿に翡翠色した和菓子を思い出しながら、別の情景が広がる。
突然の雨、粒がはじける大きな音が足元からしはじめ、人の賑わいが雨音に変わったことに気づく。
曇りではあったが、陽の光が薄い半透明な膜を張り、ぼんやりと辺りを包み込んで、人が観光地らしさを辛うじて保っていたが、いつの間にか、人と入れ替わり、雨粒が周りから見えないように薄暗い幕を築く。
時々差す陽が水面を差し、返しの白い筋が尾を引き、目に水面の翡翠色を感じさせていたが、今は空からの粒によって真の翡翠を見せる、まるで、それを見せるために、ひとりここにいた。
雨は天からも地からも降る。
そして、翡翠はまた水面に溶けていった。
"Jade"
"I wish for the stars", another scene is spread out, remembering the Japanese-style confectionery colored in the white plate of Lucy Lee on Tanabata night.
Sudden rain, the loud noise that starts to pop up starts at the foot, and notices that the liveliness of people has changed to the rain noise.
Although it was cloudy, the sun's light covered a thin translucent film, and it surrounded the area dimly, keeping people like a tourist destination barely, but in time, people replaced with people and raindrops could not be seen from the surroundings So make a dim curtain.
The occasional yang came to the water surface, the back white streaks pulled the tail, and the eyes felt the amber color of the water surface, but now the particles from the sky show a true moth, as if to show it , I was here alone.
Rain falls from above and from above.
And the cocoon melted in the water again.
モダニズムでの絵画は、モチーフの陰影が消え、そのモチーフ自体も輪郭線だけになり、二次元化する。それは一目見るだけで、全体を把握しやすくし、視覚以外の感覚は排除して、本質に迫ろうとした。実際には絵画に触れることができないが、質感としてあるのは、キャンバスと絵の具だけだった。
この絵画は、モダニズムより前の時代の反動だが、一方、日本には、岩絵具を使い、陰影など無い二次元化された絵画があった。
そこには、岩絵具としての質感は勿論あるし、和紙の質感もあるのだが、それらの質感が前面に感じることは無く、モチーフとなるものに沿うように発色し、しっとりとした印象を与えることに寄与していた。二次元化が決してモチーフを視覚で捉えやすくするためでは無く、むしろ、視覚以外の感覚を誘発し、それを岩絵具の顔料としての質感と発色が後押しし、見る側に様々な事を想起させ、モチーフをよりリアルに感じさせた。
いわゆる洋画は表現された事を、見る側はそのまま受け取るだけに設定され、その設定がモダニズムであったり、時代性だったりした。
いわゆる日本画は何かが不足しているか、何かが実物の見た目と違う、それが二次元化、そこを補うことを、見る側が想起する、無意識のうちに、その想起する余地が、同じ二次元化された絵画でも違う所で、感じるリアルさが違う所で、概念より目の前に全てがあり、それをどう感じるか、時代の反動では無い方が絵画として、モチーフの本質に迫ることができるだろうし、破綻もしないし、絵画としてだけ相対することができるから、それは素晴らしいことではないか、この文化圏に目を向けることが。
"Recollection"
In modernism paintings, the shade of the motif disappears, and the motif itself becomes only an outline, and it becomes two-dimensional. At a glance it made it easy to grasp the whole, excluding senses other than vision and trying to approach the essence. Actually I can not touch the painting, but only the canvas and the paint have the texture.
This painting is a reaction of the days before modernism, while in Japan there was a two-dimensionalized painting that used rock paint and had no shadows.
There is, of course, the texture as a rock paint and the texture of Japanese paper, but the texture does not feel on the front, and it colors in accordance with the motif and gives a moist impression Contributed to the Two-dimensionalization is by no means to make the motif easy to see visually, but rather, it induces a sense other than visual sense, and it is inspired by the texture and color of the paint as a pigment, and evokes various things on the viewing side , I made the motif feel more realistic.
The so-called foreign film was set to just receive what was expressed, and the viewer was set to just receive it, and the setting was modernism or it was historical.
The so-called Japanese paintings lack something or something is different from the real appearance, it is two-dimensional, making up for that, the viewer recalls, unconsciously, the same room for recalling the same Even in a two-dimensionalized picture, in a different place, in a place where the feeling is different, there is everything in front of the concept and how it feels, one who is not a reaction of the times approaches the essence of the motif as a painting You will be able to do it, you will not fall apart, and you will only be able to confront each other as a painting, so it's not a great thing to look at this culture.
とても乱暴に大雑把に言えば、モダニズムとは他の感覚を全部削ぎ落として視覚に特化し、触れること無しに本質に迫ろうとしたことで、モダニズム以後はその反動でしかない。
モダニズムでは、他の感覚、触覚や嗅覚、味覚、聴覚で把握できる情報を全て視覚に変換し、それが可能なのは、人間の知覚構造の特色かもしれない、視覚から8割の情報を得ているからで、一目で本質を把握できるようにし、それを写真に収め、ネットの無い時代に写真という身軽な伝達方法に載せた。
だから、視覚以外の感覚に関連することは全部消えていく。
絵画では、モチーフの陰影は消え、そのモチーフ自体も輪郭線だけになり、やがてモチーフ自体も消える。建築でも形自体に意味があると、空間を視覚的に一目で把握できなくなるから、意味を持たせないように余分な線は消え、根源的な幾何学形態になり、それは仕上げについても同じで、白くなり、絵画同様、空間も輪郭線だけになり、やがて空間自体もどこまでが空間かわからなくなる。
そこでは人間も必要で無くなる、人間を意識してしまうと、触覚や嗅覚、味覚、聴覚が現れてくるから。だから、建築では生活感が必要では無くなった。
モダニズム以後はその反動、視覚以外の感覚が復活し、触れることで得られる感覚も通して、本質に迫り、人もそこに介在する。写真以外の伝達方法も発達したから、生活感も必要になり、それが現代まで続くが、人がやることだから、人が介在するのが当たり前なのだが、そのモダニズムも、モダニズム以前の反動でしかない。
古美術の茶碗を触れる機会があった。なかなか滅多に見られるものでは無いから、箱や箱書きから茶碗まで、写真を撮りまくった。それは記録に残して後から見返すこともできるためだが、自分の手の中に留めておきたいという衝動にかられ、そのためにはまず、写真を撮ろうとしてしまう、ただ触らずにはいられない。
見るだけで、感触までわかろうと思えばわかるが、触ることでしか得られない情報があるだろうし、耳から入る知識も重要だが、一番大事なのは持った時の感触、持って見て触った時に自分がどう思うか。
だから、ひとつひとつ丹念に触った。散々触った後に、ふと、モダニズムはあったのだろうか茶碗に、と思った。
"touch"
Roughly speaking roughly, modernism is nothing more than repercussions after modernism, as it attempts to immerse itself in the essence without scraping it and touching all other senses.
In modernism, information that can be grasped by other senses, tactile sense, olfactory sense, taste sense, and auditory sense is all converted into vision, and it is possible to obtain features of 80% of information from vision, which may be characteristic of human perceptual structure So I made it possible to grasp the essence at a glance, put it in a picture, and put it in a light communication method called a picture when there was no internet.
So everything related to senses other than visual disappears.
In paintings, the shade of the motif disappears, the motif itself becomes only the outline, and eventually the motif disappears. Even in architecture, when the form itself makes sense, the space can not be grasped visually at a glance, so the extra lines disappear so as not to make sense, and it becomes the basic geometric form, which is the same for finishing as well. It becomes white, and like paintings, the space is only an outline, and eventually the space itself does not know how far it is.
There is no need for human beings, because when you are conscious of human beings, touch, smell, taste and hearing will appear. So, in architecture, a sense of life was not necessary.
After modernism, its reaction, the senses other than vision revives, and through the senses obtained by touching, the essence approaches and the person also intervenes there. Since communication methods other than photography have also been developed, a sense of life is also required, and so does the present, but because people do it, it is natural for people to intervene, but its modernism is only a reaction before modernism. Absent.
I had the opportunity to touch the teacup of the old art. It is not something that is rarely seen, so I took pictures from boxes and boxes to teacups. It is possible to leave it in the record and to look back later, but because of the urge to keep it in your own hands, you can not help but just try to take a picture first.
If you just look, you will understand if you feel the touch, but there will be information that can only be obtained by touching and knowledge that can be heard from the ear is important, but the most important thing is the feel when holding it, holding it and touching it What do you think sometimes?
So I touched it one by one. After touching it a bit, I thought it was a teacup, probably there was modernism.
建築に対する考え方やアプローチの仕方やコンセプトは素晴らしいのに、どこかで見たような、既視感に襲われるようなことがある。
建築を言葉からイメージしようとすると、言葉から実際の建築や空間に変換する時の能力が問われる。引き出しがたくさんあるのか、レシピをいっぱい知っているのか、どこまで知覚できるのか、などなど。どうしても、今まで見てきた建築や空間が頭を過る、それは意識して先人の建築から何か学ぼうとすればする程、そうなる。
よく聞くのが、後付けでコンセプトを考えること。与条件に対応して設計した建築に対して、後から考えを整理してまとめること。案外多く、後付けだから、コンセプトに対して実際に出来上がった建築や空間が破綻していない、当たり前だけど。案外その方が既視感も無かったりする。
だから、はじめから既視感が無いものをつくろうとし、後からそこに至る考え方をまとめても良いだろうし、その方が、既視感が無いことは新しいことでもあるので、言葉より建築空間生成が先になり良いのではないだろうか。
"Before words"
Though the way of thinking and approach to architecture and the concept and concept are wonderful, there are times when they are struck by a sense of devil as seen elsewhere.
When trying to image architecture from words, the ability to convert words into actual architecture and space is questioned. Whether you have a lot of drawers, you know a lot of recipes, how far you can perceive, etc. Anyway, the architecture and space I have seen so far have a head, which is the more I consciously try to learn something from my predecessor architecture.
I often ask you to think about the concept later. Organize and organize your ideas later for the buildings designed in response to the conditions. Unexpectedly, because it is retrofit, it is natural that the architecture and space actually completed for the concept have not collapsed. Unexpectedly there is also no sense of sight.
Therefore, it is possible to try to create something that has no sense of sight from the beginning, and to organize ideas that lead to that later, and it is also a new thing that there is no sense of sight, so building space generation rather than words Aren't you good at first?
既視感が襲ってくるのは、見た瞬間の表象化の段階、いろいろなこと、見た目では無い、隠れた部分を感じ取る過程でのこと、そこで見たことがあるかどうか。
「既視感が無い」状態が人間の知覚において、どこで起こるのかを考えていた。
今は当たり前になったが、コンクリート打放しにモルタル薄塗りをかけ、コンクリート打放しはすでによくある仕上げで見慣れているので、同じような色味、同じような質感、でも違う、既視感が無い仕上げに、コンクリート打放しの上に更にモルタルを塗り、それを仕上げにすることは無かったので、コンクリート打放しを何か別の仕上げにするためにモルタルを下地として塗ることは普通に行うが、それを見た時にはじめて既視感ということを意識した。
どうしても、新しい建築、新しく見える建築に惹かれるので、「既視感が無い」とそれだけで新しい建築に思えたので、既視感とはどういうことかを考えたくなった。
"Opportunity to explore the feeling of the sight"
A sense of prejudice comes at the stage of the rendition of the moment of seeing, various things, things that are not visible, in the process of feeling hidden parts, and whether they have been seen there.
I was thinking where in the human perception, the "no sense of sight" condition would occur.
Now it has become commonplace, but put a thin coat of mortar on concrete release, and concrete release is already familiar with a common finish, so similar colors, similar texture, but different, no visible finish It was common practice to paint the mortar as a foundation to make the concrete release some other finish, as there was no need to further coat the mortar on top of the concrete release and finish it. It was the first time I was aware of the feeling of being visible.
I was attracted to new architecture and new-looking architecture, so I thought it was a new architecture with only "no sense of sight", so I wanted to think about what it was like.
既視感が無い建築や空間をつくりたいとしたら、どうするか。既視感とは、見たことがあるという感覚のこと。では、全く見たことが無いような奇抜な建築や空間にすれば既視感が無いものになるような気がするが、そうでは無くて、見たことがありそうで無い、今までありそうなのによく考えたら無い、位の度合いでないと、既視感が無い状態とは言えない。
既視感が無い状態だと「そうなるのか」「それは今まで考えたことが無かったな」「それは盲点だったな」「なるほど、それも有りだよね」などという感想が出てくる。
単に奇抜な建築や空間は「変わっているね」の一言で済まされる。それはぱっと見で理解できないからで、既視感が無い状態は、全く理解ができない訳では無くて、理解はできるけれど「今まで見た物の中には無かったな」「見たことが無いな」という感じ。
新しい建築をつくりたいとしたら、2通りある。奇抜なものか、オルタナティブなもの。
奇抜なものとは、それまでの文脈とは外れて存在するもの、だから、すぐに理解ができない。オルタナティブなものとは、それまでの文脈に則り、既存のものの代替案として存在するもの、だから、理解はしやすいが、新しくて見たことが無いものになる。
既視感が無い建築や空間はオルタナティブなもの、そして、それが新しい建築となる。新しい建築を見てみたいから、既視感が無い建築や空間をつくりたい。
"There is no sense of sight"
What if you want to create an architecture or space without a sense of sight? A sense of sight is the sense of having seen it. Then, I feel that if you look at a quaint architecture or space that you have never seen, you feel that there is no sense of sight, but it is not so, it is unlikely to have been seen, until now If you do not think so well though, you can not say that there is no sense of sight unless it is a degree.
If you don't have a feeling of prejudice, you will come up with comments such as, "Do you think so?" "I never thought about it before", "It was a blind spot," "Oh, that's true too."
The weird architecture and space are just finished with a single word, "I'm changing." It is because I can not understand it at first glance, and I can not understand it at all when I do not have a sense of prejudice, but I can understand it, but I have never seen anything I've seen so far. I feel like that.
If you want to create a new architecture, there are two ways. Or something strange or alternative.
Odd things are things that exist outside of the context so far, so we can not immediately understand them. An alternative is something that exists as an alternative to the existing one in the context of that, so it is easy to understand, but new and never seen.
Architecture and space without a sense of sight are alternative things, and that becomes a new architecture. I would like to see new architecture, so I would like to create an architecture and space with no sense of sight.
ひとつひとつバラバラなものをそのままバラバラなままの状態で表すにはどうしたらよいか。
大きな容れ物の中に、ひとつひとつバラバラのまま、そのままの状態で納める。大きな容れ物が環境を守る役目をし、ひとつひとつバラバラなものの関係性は維持され、バラバラなままの状態で表すことができる。そして、大きな容れ物という、そのバラバラなままの状態で納める容れ物が、そのバラバラな状態を表す名称になる。
例えば、美術館や博物館がそうだろう。大きな美術館や博物館といった容れ物の中に、作品や展示物がバラバラなままの状態で納められ、ひとつひとつバラバラなものの関係性は維持され、バラバラなままの状態で表しており、その状態が、まさに美術館や博物館と呼ぶ。よくある手法だ。
他には、ひとつひとつバラバラなものを、ひとつひとつバラバラな関係性はそのまま維持して、別の事で新しく表すこと。この場合は、その関係性が、そのバラバラな状態を表す名称になる。
例えば、先程の美術館や博物館だとすると、ひとつひとつバラバラなものは、作品や展示物であり、その作品や展示物中から、あるいは、他の美術館や博物館から借りてきた作品や展示物を加えて、新たな関係性をくくり、展覧会をする。その展覧会の名称が、新たなにくくった関係性であり、それが「〜展」になる。
だから、ひとつひとつバラバラなものをそのままバラバラなままの状態で表す方法は、大まかに分けて2通りあり、1つは大きな容れ物を用意する、もう1つは新たなくくるための関係性を用意する。
前者は建築的な解釈にもなり親和性があるが、興味があるのは後者、言わば、関係性をデザインすることであり、それは建築以外でも役立つ手法であり、関係性を建築で実際の空間としてつくりたい。
"Relationships in space"
What should I do to represent things separately one by one as they are separately?
In a big container, put it as it is, one by one. Large containers serve to protect the environment, and the relationships of disjointed things are maintained and can be represented in disjointed states. And, the big container, the container which is stored in the broken state, is the name representing the broken state.
For example, museums and so on. Works and exhibits are stored in pieces in a large museum or museum space, and the relationship between pieces is kept one by one, and they are represented in a broken state, and that state is I call it a museum or a museum. It is a common technique.
The other thing is to keep things broken apart one by one, keep the broken relationships one by one, and express new things in another. In this case, the relationship is a name representing the disjointed state.
For example, in the case of the previous art museums and museums, things that fall apart one by one are works and exhibits, and by adding works and exhibits borrowed from those works and exhibits or borrowed from other art museums and museums, new items Hold a relationship and exhibit. The name of the exhibition is a new difficult relationship, which becomes "-exhibition".
Therefore, there are roughly two ways to represent things separately one by one as they are separately, one is to prepare a big container, the other is to prepare a new connection .
The former is also an architectural interpretation and has an affinity, but the latter is interesting, so to say, to design relationships, which is a useful method other than architecture, and to build relationships with actual space I want to make it.
内部でもよいし、外部にもなる、それは場面場面で変えることもできるし、ずっと外部でもよいし、時々気分でそうしてもよいし、普通にずっと内部でもよい。そのような空間ができたならば、きっと見た目も、その選択、内部か外部かで違うだろうし、そこを使う人、住む人によって、全く違った空間が出現するかもしれない。
それが集合住宅だったら、住む人の数だけ、空間の選択に違いができるし、それがそのまま外観に現れる。まさに、集合住宅でしか実現できないことになる。
そのようなプランにたどり着き、ただそのプランはとても単純で、決して言葉だけが先行した空間ではなくて、実空間として、使い方として成立をしている。
答えを探さずに、ずっと解明したかったことに対して、情報収集して、整理して、丹念につながりを解きほぐすことを繰り返し行っていた。そうすると、誰も手を付けていない領域がわかり、そこが本来自分が建築の中心に据えたいことだと理解できた。
ただ、あまりにも単純すぎて、それはよいことだと思いつつ、何か付け足ししたくなるし、何かがまだ足りないので、さらに、要するに、問題を設定したくなる、終わり時に迷う。
"End time"
It can be internal or external, it can be changed in the scene, it can be external, sometimes it can be in the mood sometimes, it can be internal as usual. If such a space is made, the appearance will be different depending on the choice, whether it is inside or outside, and a completely different space may appear depending on the person who uses it or the person who lives there.
If it is a collective housing, the choice of space can differ by the number of people living, and it will appear in the appearance as it is. Indeed, it can only be realized in an apartment complex.
Having reached such a plan, the plan is so simple that it is not a space where only words first preceded, but is established as a usage as a real space.
Without searching for an answer, I have been collecting information, organizing it, and breaking up connections carefully in order to solve what I wanted to clarify. Then I understood the area that no one had put in hand, and I understood that I would like to put it at the center of the architecture.
But it's too simple, I think it's a good thing, I want to add something, and I'm still missing something, I mean, I want to set a problem, I get lost at the end.
中途半端なんだよね、何でも中途半端に見えてしまう、中途半端って良くないイメージがあるけれど、結構本気で「類は友を呼ぶ」ということわざが大事で、自分の周りにいる人を見れば、本当の自分、心の奥底にいる自分がわかると考えていて、たがら、何でも中途半端に、人が見えてしまうのは、自分が中途半端な人なのかなと考えてしまう。
まだまだ詰められる余地がある、よくある話だが、どうしたらできるかではなくて、こうだからできないと、できない理由ばかりを説明する人に出会うとげんなりする。
そんな人、本当にいるのかと言われそうだけど、で、ところで、本題に入ろうか、どうしたらいいの、ここがこうなったら、全てが上手くいき、皆んながとりあえずハッピーになれるから、話は単純、そこを何とか実現できる方法を考えよう、それは専門の人が絞り込むことなのに、専門外の人が簡単にトリガーポイントを指摘したらまずい、職務怠慢だよね、プロでしょ、とまでは言わないし、言いたくはないので、そこに気づいて欲しいのだけれども、言葉が通じない、おかしな日本語同士でしゃべっているよね、こんな時、昔は現場でも怒鳴り散らしていたような気がするけれど、それは誰のためにもならないから、最近はそういうことが無いように、まず自分が怒鳴り散らすことが無い人と仕事をするようにしている、「類は友を呼ぶ」だから。
"Incomplete"
It's half-baked, there's an image of something half-baked and bad, but everything looks like it's halfway, but if you look at the people around you, it's important to say that the kind "calls kind" is serious. I think that I know that I am true, I am in my heart, and I think that I can see someone who is half-hearted, if only I am a half-hearted person.
It's a common story that still has room to be packed, but it's not how you can do it, and if you can't do it this way, you will meet people who just explain why you can't do it.
Such a person seems to be really there, but, by the way, how to get into the main subject, what should I do, if all this goes, everything goes well and everyone can be happy anyway, so the story is simple, there Let's think of a way to somehow realize that it is a narrowing down of specialists, but it would be bad if a non-specialist could easily point out a trigger point, it would be a delusion of duty, not to say professional, not to say So I want you to be aware of it, but you can't speak words, you're talking with strange Japanese people, At this time, it feels like you used to scream at the scene, but it's for everyone In order not to have such a thing recently, I am trying to work with a person who never screams, "kinds call "So.
なぜ建築をやりはじめたのか。父親は大工、神社仏閣もやっていたから、皆んなは宮大工と呼んでいた。祖父も大工、父親と一緒に千葉から戦後東京に出てきて、商売を、工務店をはじめた。だから、3代目、子供の記憶では、まだ、幼稚園に上がる前、父親の軽トラに乗って現場回りをしていた。もうひとり、住み込みの大工さん見習いがいた、その人と一緒に3人、なぜ、幼稚園に上がる前の自分がそこにいるのかわからないけれど、たぶん、連れて行けとただをこねたのだらう。
大昔は、建築現場で出るゴミは埋めていた、確か記憶が正しければ、多摩川を越えた川崎の山の中に行ったような、そこに一緒にトラックに乗っていたんだよね、そうそう、昔は現場で出たおがくずなんかは、区の清掃工場に捨てに行き、まだ子供ながらにして、こわいんだよ、清掃工事の中に入ったこと無いでしょ、大きな、大きな、ゴミを捨てる穴があって、そこに荷台からスコップで捨てるのだけど、まだ子供だから、危ないから、トラックの外に出してもらえず、車内の窓越しに見るしかなかったが、その底なし沼のような清掃工事の穴の恐怖心は忘れられない。
なぜそんな怖い場面がありながら、父親について行ったかと言うと、その後の唯一の楽しみが有り、多摩川の土手で、昔は売店があり、そこで好きなパンを買ってもらい、父親と住み込みの見習いと一緒に食べるのが楽しみだった、それは姉には内緒で、母親は薄々勘付いていたけれど、しょうがないと見逃してくれていたこと。
そこには、建築のケの字も、デザインのデの字もないけれど、幼い頃から刷り込まれた建築がある訳で、それは学校や社会で教えてもらった建築とは違う訳で、それはそれを経験した人にしかわからない世界がある訳で、後発の建築経験と合わせて、自分にしかできない建築を表現したいし、表現しないと死に切れないと思うのは、この歳になり、豊かな社会を見て、余計に思うこと。
"Permanently to do"
Why did you start building? His father also worked as a carpenter and shrine and temple, so everyone was called a shrine carpenter. My grandfather also came out of Chiba from postwar Tokyo with my carpenter and my father, and started to work as a builder. So, in my third generation, in my memory of my child, I was still riding around my father's light tiger before going to kindergarten. There was another carpenter apprentice who lived in, three with him, I don't know why I was there before I went to kindergarten, but maybe I got rid of them and take them alone.
A long time ago, the garbage from the construction site was buried, and if I remember correctly, I went to the mountain of Kawasaki over the Tama River, and I was on the track together there, yes, in the old days I went to the district's cleaning plant to throw away the sawdust that came out on the site, and I was scared as a child, and I'm scared, I've never entered the cleaning work, big, big, there is a hole to throw away trash , But there is a scoop from the loading platform, but because it is still a child, because it is dangerous, I could not get it out of the truck and had to look over the window inside the car, but the fear of the hole of the cleaning work like a bottomless swamp I can not forget my heart.
If you say why you went to the father while having such a scary scene, there is only one pleasure after that, there is a shop on the banks of the Tama River in the old days, you have bought the bread you like there, and the father and the resident apprenticeship I was looking forward to eating it together, which was secret to my sister, and my mother was thinly aware, but missed it.
There are no architectural characters or design characters, but there is an architecture that has been imprinted from an early age, which is different from an architecture taught in schools and in society. There is a world that is understood only by those who have experienced, and together with the late-stage construction experience, I want to express architecture that can only be done by myself, and I think that I can not die without expression, it is this age, rich society Looking at and thinking extra.
建築は、全てを規定しなければならないから、哲学や社会学などに規範を求めるのだろう。
建築を規定するために使う言語は、哲学や社会学だけではない、人の感覚も使う、しかし、感覚だから言葉にならない、言葉で説明できないこともある。それでもなお、規定しようと試みる。
言葉で全てを規定しようとする人のことを理論家と呼ぶのだろう。言葉で規定てきない所は無い、だから、何でも言葉が必要だ。この場合の言葉は知識と言い換えることができる。
知識で目の前に出現した空間を規定する、それがどういう態度でも関係がない、的を得ていても、的外れでも、こじつけでも、規定することが大事だから。
実現をしたいのは、人の心を揺さぶる未知の空間であり、知識で規定するとかしないとかとは、全く関係がない所に浮遊している事柄に思えるのだが、では、人の心を揺さぶる所まで、未知の所まで、空間を求めて行く乗り物は何か、感覚か、才能か、経験か、諦めないことか、それともやはり知識か、または、これら全てか、そこは誰も教えてくれないし、誰も教えられない、なぜなら、未知だから。
盲目になれば、たやすく未知も、心を揺さぶることも手に入る、ただ、それは求めている未知ではない。しかし、全てを知り尽くした上での未知を求める姿勢は、砂漠の中で一杯の水を求めているようなもので、心が揺さぶられない。だから、知識がある、知っている、わかっている先に、心が揺さぶられる未知はない。
知らないことへの恐怖心からくる知識には価値がなく、それを素とした空間には、未知もなく、心も揺さぶられないのではないか。今、思い出すのは、過去に心を揺さぶれた未知の建築空間、その時は未熟な時だった。
今が成熟しているかどうかは別として、未熟と盲目は同じか違うのか。書きながら考えて、考えながら書いている、これが未熟で、そもそも書かない、考えないのが盲目かな。
だから、知識を受けようとして動いていては、人の心を揺さぶる未知の空間をつくることはできず、自分で試行錯誤することでしか、人の心を揺さぶることはできないし、未知に到達しないのではないか、それが的外れでも、未知だから、それが的外れかどうかも判断てきないし、ただ、やはり、そうなると、諦めないことが重要だけど、今度はそれができる人はなかなかいない、知識を受ける方が無知の恐怖心が和らぐし、誰も無知だと思われたくはないだろうから。
"Unknown wall shaking hearts"
Since architecture must define everything, it will seek norms from philosophy, sociology, etc.
The language used to define architecture is not only philosophical or sociological; it also uses human senses, but sometimes it can not be words because senses can not be explained in words. Still, I try to define it.
People who try to define everything in words will be called theorists. There is no place where there is no provision in words, so everything needs words. The words in this case can be reworded as knowledge.
It is important to define the space that appears in front of the eyes with knowledge, regardless of attitude, whether it is a target, a target, a target, a target or a stigma.
What we want to realize is an unknown space that shakes people's mind, and it seems that it is a matter floating in a place that has nothing to do with whether or not it is defined by knowledge, but then it shakes the mind of people To the place, to the unknown, the vehicle that seeks space, sense, talent, experience, not giving up, or even knowledge, or all these, there is no one to tell me No, no one can teach, because it is unknown.
If you get blind, you can easily get the unknown and the heart shaking, but it's not the unknown you're looking for. However, the attitude of seeking unknown after knowing everything is like seeking full water in the desert, and the mind can not be shaken. So there is no unknown that the mind is shaken before you know, know and know.
There is no value in the knowledge that comes from fear of unknown things, and in the space that is based on that, there is no unknown, and the heart may not be shaken. What I remember now is an unknown architectural space that has shaken my mind in the past, and that time was immature.
Aside from whether they are now mature, are immature and blind the same or different? I think while writing, I write while thinking, this is immature, not write in the first place, it is blind not to think.
Therefore, if you are moving to receive knowledge, you can not create an unknown space that shakes the mind of a person, you can only shake the mind of a person by trial and error yourself, and you reach an unknown Even if it is out of place, it is unknown, but it is not determined whether it is out of place, but it is important not to give up if it is so, but there are not many people who can do it this time. But the fear of ignorance will be relieved, and no one will want to be considered ignorant.
建築は決まり事の集積で成り立っているので、偶然にそうなるとか、結果的にそうなった、ということは基本的には無い。
基本的には、と付けたのは、新築ならば、更地から計画をしていくので、土地に何か、例えば、地盤が軟弱であったり、地中に何か埋まっていたり、文化財など、があったとしても、それを含めての計画になるのだが、リフォームの場合は、手を付ける部分が限定されるので、手を付ける部分以外の所が影響して予想外の出来事が起こることもある。
だから、新築の場合に限って言えば、偶然や予想外は無い。
そうなると、余白としての空間をつくる場合も、その余白で起こることを全て予想してコントロールした上での余白としての空間が成り立たないといけない。
余白となると、どうにでもなる、何が起こるかはその時にならないとわからない、気分で変わる、などの要素を加味したいのだが、そうもいかないのか。
そこが、言葉だけが先行した建築とそうでない建築の分かれ道か。
"Diversion"
Since architecture consists of a collection of routine things, there is basically no such thing that happens by accident or as a result.
Basically, if it is a new construction, we will start from a land area, so something on the land, for example, the ground is soft, something is buried in the ground, or a cultural property And so, even if there is, it will be a plan including it, but in the case of renovation, the part to be touched is limited, so the unexpected event is affected by the parts other than the part to be touched It can happen.
So, just in case of new construction, there is no chance or unexpected.
In that case, even when creating a space as a margin, it is necessary to have a space as a margin with anticipation and control of everything that happens in that margin.
When it comes to the margins, I would like to add elements such as how to do anything, I don't know what will happen at that time, the mood changes, etc.
Is there a branch between the architecture where only words preceded and the architecture where not so?
余白を余白としてつくるのではなくて、プリントアウトする時の余白の設定のように数値でここから余白と決めるのではなくて、気がついたら、それが余白とか、じわりじわり余白になっていくとか、気分で今日は余白とか、現れたり消えたり、または、感じる時と感じない時があるとか、余白が何かと何かをつなぐものだとしても、常に見える必要はない。
建築は空間の範囲を規定しなければならない。その際は、壁であったり、床や天井であったり、敷地境界線かもしれないし、地面かもしれない、解釈によっては空もあり得るかもしれないが、かならず、範囲が決まる。だから、余白として建築空間をつくることは、どうやって範囲を決めるか、その際はどうなるのかを決めること。
ただ、何となく余白は範囲が決まっているようで決まっていない感じがあるので、そこの自分の中での認識の差をどうやって埋めるのか、どうしたものか、余白を考えながらプランをつくること自体に何か違和感がある。
"Plan called margin"
Instead of creating a margin as a margin, instead of using this as a numerical setting for setting a margin when printing out, you decide not to use it as a margin, but if you notice it, it will become a margin, a beginning margin, etc. So today you don't have to always see the margin, even if it appears or disappears, or if you feel or don't feel it, or if the margin connects something to something.
Architecture must define the scope of space. In that case, it may be a wall, a floor or a ceiling, a site boundary, a ground, and depending on the interpretation, it may be empty, but the scope is definitely determined. So, to create an architectural space as a margin is to decide how to determine the scope and what to do in that case.
However, there is a feeling that the margin seems to be fixed and the range is somehow decided, so how to fill in the difference in recognition in oneself there and what to do, it is in making the plan while thinking about the margin itself I have something wrong.
つい選択できることに価値があると考えてしまう、その方が楽しいし。
ここ2,3ヶ月のうちに2回行った飲食店への道の途中にアンティークショップがあり、覗くとつい銀のスプーンに目が行ってしまう。カトラリーが大好きで、スプーン、ホーク、ナイフなど、いいなと思うものを見つけると、つい購入し、バターナイフも、セットではなくてバラバラでも、引き出しをあけると、カトラリー専用、見てるだけでも楽しい気分になるけれど、何か食事をする度に、どれにしようかな、と選ぶ楽しさ、コーヒーカップも毎朝選ぶ楽しさがある。
別に大したスプーンではないけれど、自分が気に入って、そこには自分の審美眼も入ってくるし、それを毎日、その時の気分でも、その時の器に合うものは、その時の料理に合うものは、と選ぶことが生活する上でとても大事、今生きていることを大事にしているような気がして、毎日変化するし、毎日自分は変化していくし、それが成長かもしれないし、老いかもしれないけれど、そこに沿うためには選択肢がある状態の方が良いだろうと。
選択肢がたくさんある、たくさん用意されている状態は、結局何ひとつ決まっておらず、全てが流動的で、どうにでもなる状態であり、ひとつのことに決めれば、他の選択肢は必要無くなるので、無駄やその無駄を容認できる余地、余白を抱えている状態とも言える。
だから、余白に価値があり、余白に可能性を感じ、余白をどうやったらつくり出すことができるだろうか、と自然に考えてしまう。
それは建築に対しても同じで、きっちりと決められた建築家の審美眼による空間は素晴らしいし、そこに建築としての価値があるのだけれども、その空間を使う側の気分みたいな流動的な部分を引き受ける余白にも同じくらいの価値があり、そこもデザインの範疇だと考え、今はその余白が極まるとどうなるのだろうかに関心がある。
"Margins of choice"
I think it's worthwhile to be able to make choices, it's more fun.
There is an antique shop on the way to the restaurant that I visited twice in the past couple of months, and when I look around my eyes go to the silver spoon. I love cutlery, find something that I like like spoons, hawks, knives, etc., I just buy, buy butter knives, even if it's not a set, even if it's loose, open drawers, cutlery only, it's fun just looking However, every time you eat something, it's fun to choose which to use, and coffee cups every morning.
It's not a big spoon, but I like it and my beauty goes into it, and every day, even if it feels like that, what suits the vessel at that time, what suits the cuisine at that time, I think it's very important to choose life, I feel like I take care of being alive now, I change every day, I change myself every day, it may grow, I am old It might be, but it would be better to have a choice to follow along.
There are a lot of options, a lot of prepared states, after all there is no decision, everything is fluid, it is a state that can be done, and if you decide on one thing, the other options will not be necessary. It can be said that there is a room where the waste and the waste can be tolerated, and a margin.
So it is natural to think that there is value in the margin, the possibility of the margin, and how you can create the margin.
The same is true for architecture, and the well-defined space of the architect's aesthetics is wonderful, and although there is architectural value there, a fluid part like the mood of the side using that space Undertaking margins is equally valuable, and I think that it is a category of design, and now I'm interested in what happens when the margins are full.
最近、余白のことを考えている。余地とか、遊びとかと言うかもしれない。余分なもの、どうでもよいもの、ただ、無いと困るもの、なくてはならないもの。
きりきりで、きれきれで、きつきつで、きっちりしている完全なものに憧れたりする。美しいものや綺麗
なものは大抵完全なものを備えていて、そこに惹かれる。
ただ、完全なものはあまりにも完璧すぎてなじまなく、触れると、拒みたくなる。
余白が主役の長谷川等伯の松林図屏風、これは余白を描いていて、その余白が見るものの感受性を刺激し、あらゆる創造を意識の中で強いる。たがら、見ていると松林の余白の中に、霧や風やその先の景色を感じ、松林が浮かび上がってくる。
余白には何も描かれていない。人によっては未完成に見えるかもしれない。そういう意味で言うと不完全である、この長谷川等伯の松林図屏風は。
ただ、その不完全さがこの松林図屏風に動きや情景を与える。
等伯は松林を墨で描きながら、余白を丹念にあぶり出したように見えた。
"See the margins"
Recently, I'm thinking about margins. It may be called room or play. Extra things, things you don't care, just things you don't need, things you have to do.
I'm drowning in perfect things that are crisp, clean, tight and tight. Beautiful things and beautiful
Things are usually complete and are attracted to it.
However, perfect things are too perfect and unfriendly, and touching them makes them want to refuse.
The margin is the leading figure of Matsubayashi Hasegawa, which draws the margin, stimulates the sensitivity of what the margin sees, and forces all creation in consciousness. When I look at it, in the margin of the pine forest, I feel the mist, the wind, and the scenery beyond that, and the pine forest comes up.
Nothing is drawn in the margin. Some people may seem unfinished. In that sense, it is incomplete, this Hasegawa and other pine forest sketch screen.
However, the imperfection gives movement and a scene to this Matsubayashi maple wind.
It appears that Togashi has carefully drawn out the margin while drawing Matsubayashi with ink.
暑いのか、肌寒いのか、最近よくわからない。寒暖の感覚がおかしくなっているようで、夜暑いと思って窓を開けたら、そのうち肌寒くなって、かと思うと、昼間の風は涼しくないから、エアコンをかけると肌寒くて喉が痛くなったり、寝る時は朝方肌寒くなるかもしれないと思い、着込んで寝ると、無意識に暑かったのだろう、いつの間か脱いでいるし。
そんな感覚なんかいい加減なものだなと、それに付き合って振り回されているのも結構面白い。
感覚に言葉をつけたり、言葉を感覚で表現したり、感覚と言葉の間を行ったり来たり、そこに造形が入ってくるから、ややこしく、さらに、経験が幅を利かせてくるから、悪魔のささやきが聞こえてくるから、もうその辺が落とし所じゃないのと。
そう何事にも〆切があるから、まとめることが大事、ただ、まとめることはいつでもできるからと、そうすると相手に伝えることが疎かになる、一番自分にストレスが無いバランスをその都度見つけるのが苦手だなと、いつも思う。
"Not good"
I do not know well lately whether it is hot or chilly. When I open the window when I think it's hot at night, it feels chilly when I think it's hot in the daytime, so the wind in the daytime doesn't cool, so it's chilly and throat hurts when I turn on the air conditioner, I think it might get chilly in the morning when I go to bed, and when I got in and go to bed, I might have been unconsciously hot, and I'm taking off for some time.
It is also quite interesting that it is being swayed along with it that such feeling is kind of sloppy.
Because words are added to the senses, words are expressed with the senses, and back and forth between the senses and the words, there are shapes coming in there, so it is complicated, and because the experience brings in the width, the devil's I hear a whisper, so that area is no longer a dropout place.
So there is a limit to everything, so it's important to put it together, just because you can always put it together and you don't know how to tell it to others, it's not good to find the most stress free balance for yourself each time I always think.
考え続けていると、突然「ひらめき」があるもので、点と点が繋がり、それもここに線ができるのか、となる。
単純なことなのに気がつかない、でも、気がつくと納得して、腑に落ち、そうそう、それをやりたかった、となるから面白い。
ただ、困ることに、それは追い込まれないと、そうはならない、と思っているだけで、もともと考える量が足りていなくて、量が満たされれば、自然と「ひらめき」に行くのではないかと思い、「ひらめき」を形にするのに、また労力を要するし、時間もかかるので、また〆切間際の慌てぶりを晒すことになる。
準備だけはしていて、バックアップ体制は万全だから、もうちょっと余裕があればと思うのだが、その余裕すらも使い考え尽くそうとする。どうしたものだろうか。
"In the corner"
If you keep thinking, there is a sudden "inspiration", and the points and points are connected, which will also be a line here.
I do not notice it is simple, but I am convinced when I notice it and I fall into the trap, so I want to do it, so it is interesting.
However, it is thought that it will not be forced if it is not driven in to be troubled, and the quantity to think originally is not enough, and if the quantity is satisfied, it will naturally go to "inspiration" Because it takes time and effort to form "inspiration", it will also expose the blazing just before the deadline.
I'm just preparing and I have a backup system, so I think I'll have a little more room, but I'll try to use up even the room. What is it?
言葉をイメージより先にしている、それはイメージは既知のものしかできないような気がして。
どうしても、無意識のうちに、過去に見た建築に類型化してしまう。
「これは、あの建築の考え方の延長にあるな」
「この建築は面白いけれど、プランはあの建築にそっくりだな」
「明らかに、真似しているよね」
などなど、結構、類型化するのは案外簡単なこと。
ただ、そのおかげで、自分で計画中に真似を意識してしまう。
建築の設計をしている最大の理由は、未知の空間を見たいから、瞬時にあの建築と同じはできない。
そのイメージを乗り越える手段として言葉を利用している。言葉はイメージを伴わなくても表現できると勝手に思い込んでいるのと、言葉に引っ張られてイメージが出てくると考えているから。
ただ、ここに来て、言葉に引っ張られてイメージは出てくるのだが、現実が伴わない。イメージ通りの空間に到達しないのだ、未知だから仕方がないのかもしれないが、どうしたものか。
"Let's pull out the unknown with words"
I have words before the image, it feels like the image can only be known.
By any means, they unknowingly typify the architecture seen in the past.
"This is an extension of that architectural idea."
"This architecture is interesting, but the plan is just like that."
"Obviously, you are imitating"
And so on, it is quite easy to type out.
However, thanks to that, you will be aware of imitation while planning on your own.
The biggest reason I'm designing architecture is because I want to see an unknown space, so I can't do the same with that architecture in an instant.
I use words as a means to overcome that image. I believe that words can be expressed without an image, and I think that an image will be drawn by the words.
However, I came here, pulled by words, and an image came out, but reality does not accompany it. It does not reach the space as the image, it may not be possible because it is unknown, but what happened?
思考が行き詰まったときには、本来どうあるべきかをもう一度問い直してみることが大切、今日一日、何度も唱えた言葉。
はじめに戻って、そもそも何を考えてはじめたか、いつのまにか違う所を歩いていたりするので、軌道修正をする。
変な先入観や知識がズレを生むのかもしれない。
明確な道筋を立ててはじめていても、はじめの問いが後にブレたりする。意外とそれがあり、何度も本来どうあるべきかを問い直している。
難しいのは、本来どうあるべきかを指向しながら、でも途中で、未だに空白の部分、誰も答えを出していない部分を見つけると、それを行いたくなり、最初の指向とうまく調和調整できないかと試みて、なかなか難解なことになってくるのでブレる。
いずれにせよ、はじめの問いに対しては面白く、そこは未開の地なので、解くことに熱中している。
"question"
When thinking gets stuck, it's important to ask again what it should have been, a word that you have recited several times a day today.
I will go back to the beginning, what I started thinking about, I will walk around a different place before long, so I will correct the trajectory.
A strange preconception or knowledge may cause a gap.
Even if you are starting to make a clear path, the first question will be blurred later. Unexpectedly, there is it, and it is asking again how many things should be.
The hard part is pointing to what it should be, but if you find a blank part, a part where nobody gives an answer, along the way, you will want to do it, and it will not be harmoniously adjusted with the first one. I try, it blurs because it becomes quite difficult.
Anyway, it is interesting for the first question, and it's an unexplored land, so I'm passionate about solving it.
自分の感覚を建築化することの難しさに直面している。今まで、建築を言葉で説明する、言葉を元に建築にする、どちかが難しいか、建築を言葉で説明する方が難しいと考えていた。
建築は言葉だけでは説明できない感覚まで含めたことを形にしているので、そこまで、いくら言葉を駆使しても説明するのは無理だろう、逆に、言葉で表せることは、その時点で咀嚼され曖昧さがかなり無くなってきたものだろうから、それを建築にすることは十二分に可能だろうと。
だから、自分の感覚を言葉で表せれば、十二分に建築化することは可能だろうと考え、言葉を用意した。
ところが、そもそも、そのような建築は見たことが無いので途方に暮れる。安易にイメージしようと思えば、過去の建築に当てはめて、いくらでもできるのだが、これが何らかの試験で、制限時間内に解答を求められていたら、そうするのだが、無限に時間がある訳では無いけれど、自分の感覚をきちんと建築化したいので、だからどうしようとなる。ほんとどうしようか。
"Architecturalization"
I am faced with the difficulties of building my senses. Until now, I thought it was more difficult to explain architecture in words, to explain architecture in words, to build on the basis of words, or which one is difficult.
Architecture is a form that includes the sense that can not be explained by words alone, so it may be impossible to explain even if you make full use of words, and conversely, being able to express in words is at that time And because the ambiguity would be quite gone, it would be possible enough to make it architectural.
So I thought that it would be possible to build enough if I could express my senses in words, and prepared the words.
However, since such an architecture has never been seen in the first place, it is overwhelmed. If you want to imagine easily, you can apply it to the past architecture, and you can do as many as you like, but if this is a test and you are asked for an answer within the time limit, you do, but it does not mean that you have infinite time Because I want to build my own sense properly, so what to do. What should I do?
着地点がかすかに見えてきたのに、そこに行くまでの手段もたぶんこれかなとあるのに、全体のイメージがはっきりしない、霧がかかったよう。
見たことが無いので、見聞きしたことは全て排除して、残されているであろう、目指したい空白部分に向かってダイブをしているのだが、そこに床がたぶんあるはず、もしかしたら透明なガラスの床だから、まだ見えないのかも、光が当たれば反射してわかるはずだけれども。
トライアンドエラーの繰り返しで、時間がもうそんなに残されてはいないから、中途半端でも良ければ、いつでもまとめ上げる自信はあるけれど、それはできないので、自分で良しと思える所まで行けるかどうか、では無く、ここで書きながら、もう一度意識をし直す、着地点を。
"Destination point"
The landing point was faintly visible, but the means to get there were probably mist, although the whole image was unclear.
As I have never seen it, I have removed everything I saw and heard, and I'm going to dive, I'm diving towards the blank area I want to aim, but there should probably be a floor there, maybe transparent Because it's a glass floor, you can see if it's still visible if it's exposed to light.
I don't have much time left by repeated trial and error, so I'm confident I will always put it together if I can be halfway, but I can't do it, so I can't go to a place where I feel good. While writing here, I re-conscious again, the landing point.
「解決がむずかしいと分かっているがどうしてもやり
たいと思う場合は、やみくもにトライするのではなく、問題を何段階かに分解したうえで、ぎりぎり到達可能な目標を設定するのがよいだろう。」
きっと誰にでも身に覚えがある。無理を承知でやって玉砕をすることを。
大人になって、経験を積んで、賢くなると、無理だとはじめに思うことに手を出さなくなる。その判断は概ね正しくて、そのままの自分が普通にやったら、絶対に上手くいかない。 家族もいれば、それは無理だろう。
ただ、自分には無理な出来事はそもそも現実には起こらない、そう考えるならば、一番賢明な判断は、どうしたら、それができるだろうか、と考えることだろう。
そして、そこが分かれ道だと、などと、考えずに、当たり前に進む人にしか、それができない、と今日思い、今、どうしたらできるだろうかと考えている。
きっと、このように考えることに無しに、達成してきたのだろう、過去の人は、だから何も考えずに、新しい自分を見るために続けようと。
"now"
"I know that the solution is difficult but
If you want to do so, instead of trying blindly, it may be better to break down the problem into several stages and then set goals that can only be reached. "
Surely everyone remembers. I know that you can not break the ball.
As an adult, gaining experience and becoming smart, you will not get out of the way of thinking it is impossible at first. The judgment is generally correct, and it will not go well if the person doing it as usual is normal. If there is a family, that would not be possible.
However, events that are impossible for me do not occur in the first place. If you think so, the most wise decision is to think about how you can do it.
And if there is a split road, etc., I think today that only the person who goes forward can do it without thinking, and I wonder if I can do it now.
Surely, without thinking in this way, I would have achieved, the people of the past, so without thinking, try to continue to see a new self.
とても小さな種に気づくところからはじめて、空間はそこら中にあるので、というか、ただ街を歩いていても、そこは都市空間なので、そもそも空間から逃れることができないので、電車で立って外を見ているだけでも、あれとこれ何だろうと思う。
そんな小さな種がずっと頭から離れなかったり、そのうち忘れるのだが、何かのきっかけで、また頭に浮かんだり、そうすると、携帯にメモをして、ブログのネタにする時もあるし、創作のヒントのヒントになったり、そこから新たなことが頭に浮かんで来たり。
電車に乗って外を眺めていると、時々電車がすれ違う、その時、すれ違う電車に乗っている人が見える、出入口のドア付近に立っていたならば、とても近くに、その人のディテールまでがよく見えるくらいに、そばにいるように、ただ、とても遠い人であり、お互い全く意識もしていないし、気にもならないし、見えてもいないし、記憶にも残らない。
空間の中で、とても近い人なのに、全く存在感が無い、この状態は何だろう、が小さな種で、そこからはじめてみたいと何となく思った。
"Small seeds"
You can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space from the beginning. I think that's what it would be like.
Such a small seed will not leave the head for a long time, but I will forget it later, but when something happens or floats in my mind, then I sometimes make notes on my cell phone and use it as a material for blogs. Become a hint of, or something new comes to mind.
When I look at the outside of the train, sometimes the train passes by. At that time, people on the passing train can be seen. If I was standing near the door of the entrance, very close to that person's details. As you can see, as you are by your side, you are just a very distant person, and you are not conscious of each other at all, do not care, do not see, and do not remain in memory.
In the space, although it is a very close person, there is no presence at all, what is this state, but it is a small species and I somehow thought that I would like to start from there.
「分かっていること」と「分かっていないこと」を書き出してメモしてみると、「分かっていないこと」がほとんど出てこない。「分かっていること」を「分かること」、「分かっていないこと」を「分からないこと」と変えても同じ、「分かっていないこと」が何かが分からないのだ。
スタート地点に戻した、今計画中のプロジェクトの話。
「本来どうあるべきか」をもう一度問い直してみようと、着想の記憶に立ち返り、収集した情報をもう一度見返し、読み返し、もう一度自分なりの言葉でメモをしているのだが、「分かっていないこと」がほとんど出てこないということは、別の見方をすると、今計画中のプロジェクトに新しさがほとんど無いということで、既存の、今ある考えを組み合わせているに過ぎないということ。
だから、計画中のプロジェクトに対して、しっくりきておらず、何かが違う、何かが足りない、と思うのだろう。
「分かっていないこと」を明確に意識して分かるためにはどうするか、もう少し収集した情報を読み込んでみるしかないのか。
「分かっていないこと」が分かり、それを解くことにより、計画中のプロジェクトに新しさが加わり、それでどうかを見たいところだが。
"I do not know what I do not understand"
When I write out and write down "I know" and "I don't know", I hardly see "I don't understand." If you change "understood" to "understood" or "ununderstood" to "ununderstood", you do not understand something the same as "ununderstood".
The story of the project currently being planned that has returned to the starting point.
I'm going back to the idea's memory, looking back at the information I've collected, reading it back and making notes in my own words, but I'm "I don't know." The fact that it hardly comes out means, from another point of view, that the project being planned is hardly new, so it is merely combining existing ideas.
So for the project you are planning, you think that something is not right, something is different, something is missing.
What can you do to clearly and consciously understand what you do not understand, or do you have to read in a little more collected information?
You know what you don't know, and solving it adds newness to the project you're planning, and that's where you want to see.
白い箱は、建築では何か象徴的な存在。なぜか、ファッションでは、黒と並んで、ドレス度が高い色。
白い箱は建築的には、抽象度が高い色、白は何色にでも染まる色、だから、建築家は具体的に暮らしとか、生活とかを嫌うから、みんな白にすることにより、住宅なのに、暮らし関係ない、生活関係ないと主張している、潔くないが、それで作品性を確保しようとする。要するに、抽象度を高くして、建築性、建築家としての主張を確保したいのだ。
本当はもっと主義主張があり、そこを理解して欲しいのだが、なかなか、理解されないし、そこはまた別の訓練が必要だし、そこを頑張っても営業には繋がるが、生活していくために必要なのだが、そこに注力を躊躇する、うん、建築家のさがかもしれない。
ただ、今の建築家は暮らしや生活を包括して、自分の主張をできる人ばかりだから、希望をこめて、脱白い箱の人が多い。
白い箱はバリア、建築家が建築家らしくいるための隠蓑が白色、最近はグレー。
建築家がもっと社会的に認められる存在になるならば、それはクライアントの要望を全て受け入れて、クライアント色に染まり、それでも尚且つ、建築家としての主義主張をできる場合、それは高度、それをできる人を日本では見たことが無い。
"White"
The white box is something symbolic in architecture. For some reason, in fashion, along with black, the color with high degree of dress.
White boxes are architecturally high color abstract, white is dyed in any color, so architects specifically hate living and living, so everyone is white by making it a house, It does not relate to living, claims that it does not relate to living, and innocence, but it tries to secure the work property with it. In short, I want to increase the level of abstraction and secure the claim of architecturalness and architect.
There is really a principle claim, I want you to understand there, but it is not understood easily, there is another training required, and if you try there you will be connected to sales, but it is necessary for you to live However, there is a possibility that there is no architect who is focusing on that.
However, since now architects are only people who can comprehend living and living, and can make their own claims, there are many people with white boxes with hope.
White boxes are barriers, metaphors for architects to be architects white, and recently gray.
If the architect becomes a more socially recognized entity, it accepts all of the client's needs and becomes client-colored, yet, if it is able to claim the principle as an architect, it is a person who can do it I have never seen in Japan.
スタート地点に戻した、今計画中のプロジェクトの話。ずっと、ある程度まで完成していたが、これでいいのかと考えていた。考えていたということは、しっくりきておらず、何かが違う、何かが足りない、でもそれが分かっていないから、分からないから、しまいには、何が分からないのかが分からなくなってきたので、最初に戻した。
「本来どうあるべきか」をもう一度問い直してみようと、着想の記憶に立ち返り、収集した情報を見返す所からはじめた。もう一度見返し、読み返し、もう一度自分なりの言葉でメモしている。
メモの整理の仕方を変えた。面白いもので、何か違和感がある、ということは、まだ、もっと違った何かが出てくるかもしれない。
"Return"
The story of the project currently being planned that has returned to the starting point. It had been completed to some extent, but I was thinking that this would be fine. I didn't know what I was thinking about because I wasn't quite right, something was wrong, something wasn't good, but I didn't understand it, so I didn't know, so in the end I didn't know what I didn't know So back to the beginning.
I started from the place where I went back to the memory of the idea, and looked back at the collected information, in order to re-examine the question "what should I do?" I look back again, read back, and write down my own words again.
I changed the way of organizing notes. If something is interesting and something is wrong, there may still be something different.
記録に残すかどうかと考える時がある。
知識として使いたい時は記録を残すことにしており、知恵として使いたい時は記録を取らないことにしてきた。
知識として使いたい場合は、見聞きした内容をそのまま使えば良い場合が多いので記録して、何度も再利用するつもりで、ただ、知識の賞味期限もあるから、そのうち使えなくなり、記録もどこかに無くなってしまう。
知恵として使いたい場合は、見聞きした内容をそのまま使うことは無く、応用させたり、変形させたり、エッセンスだけを生かしたりするし、それは頭の中で無意識に行っていたりする場合が多いから、かえって頭の中以外に記録してしまうと、それができなくなるような気がして、記録をはじめから取らずに、頭だけで覚えようとする。当然、時間が経つと忘れることもあるのだが、どんなに時間が経っても忘れないことはあり、それが知恵として生かせるので、時間が経って忘れることが良い選別になっているように思う。
知識はネットでその都度調べれば良いとすれば、記録を取って残す必要が無くなるし、知恵として使う場合は記録すら取らないので、はじめから記録すること自体が必要無くなる。
だから、最近は紙ベースの記録媒体を持ち歩くことは無いのだが、それでも記録したい、メモしたいことがあれば、それが今の自分にとって本当に必要なことだと判断がつくし、今それを行えば良いという行動規範にもなる。
では建築を見に行った場合はどうするか。
知識と知恵を見分けて、知識の部分はネット調べることが可能だが、折角目の前にあるのだから、写真やスケッチを残し、知恵の部分は、写真撮影やスケッチをしたことで無意識に建築が印象付けられているので、ただ目の前の建築を考えながら感じるだけにしている。
"Do you want to record?"
Sometimes I wonder if I keep it in the record.
When we want to use it as knowledge we keep records, and when we want to use it as wisdom we keep no records.
If you want to use it as knowledge, there are many cases where you just need to use what you see and hear as it is, so I will record it and try to reuse it many times. It will be lost.
If you want to use it as wisdom, you will not use what you have heard or heard as it is, and you may apply or deform it, or use only the essence, which is often performed unconsciously in your head. I feel that I will not be able to do this if I record in my head, and I will try to learn with my head, not taking the record from the beginning. Of course, I sometimes forget as time goes by, but I do not forget how much time goes by, and I can use it as wisdom, so I think that it is a good sort to forget over time.
If knowledge should be checked each time on the Internet, there is no need to keep a record, and if it is used as wisdom it will not even take a record, so there is no need to record from the beginning itself.
So I don't carry paper-based recording media these days, but I still want to record, if I want to make notes, I can judge that it is really necessary for me now and I should do it now It also becomes a code of conduct.
But what if you go to see architecture?
Although it is possible to identify knowledge and wisdom, the part of knowledge can be searched on the net, but because it is in front of a corner, leaving a picture or a sketch, the part of wisdom unconsciously architecture by having taken a picture or sketch As I am impressed, I only feel while thinking about the architecture in front of my eyes.
好きな物に囲まれて生活がしたいから、家の中は物で溢れている。好きな物だから、捨てるなんてとんでもない。一生使うものとして、大事にしているものばかり。
捨てる、断捨離と聞くと、その言葉が一般的には、暗黙の了解として、良い意味で使われているのがわかる。どんどん不要な物は捨てて、物は少ない方が良いと、世間的には当たり前のように思われている。
だから、断捨離と言うと良い行いであり、断捨離ができないとダメ人間なような印象もある。
よくあることだと思うのだが、断捨離はあくまでも手段であり、断捨離をした結果、日常生活が豊かにならなければ意味が無い。断捨離をして、物が無くなり、スッキリするだろうが、それは一過性のことで、頭の中がスッキリ、すなわち、整理整頓され、次の行いにつながらなくては、また結局は元通りになり、断捨離した意味が無くなる。断捨離が目的になっているから。
日常生活を豊かにする方法はいくらでもあると思うが、自分の好きな物で、案外それが無くても困らない物だったりするのだが、囲まれている状態、やっぱり、普段ものづくりをしているから、お気に入りの食器がたくさんあって毎日気分で使う食器を選びたいし、お気に入りの椅子がたくさんあって毎日気分で座る椅子を選びたいし、などと考えてしまう。
頭の中が、思考がスッキリして、整理整頓されていれば良いだけの話で、頭の中を断捨離すれば良いだけで、考えが明解で、自分の感性を刺激してくれる物に、不要な物も含めて、たくさん囲まれていた方が日常生活が楽しくて、豊かになる。
仕事、生活ともに、スケジュールも、情報も、メモも、スマホとタブレットとPCで同期させながら、本もデジタル化で、管理し、終われば、必要が無くなれば、データを捨てる、消して、必要なことだけを残し頭に入れて考える。
程度は別として、考え続けることが多いから、考えるための材料はいつでもすぐに簡単に見られるようにしておきたいし、手ぶらで行動することも多いので、スマホに集約させている。断捨離はそれだけで必要十分。
"I do not want to abandon"
I want to live surrounded by my favorite things, so the house is full of things. It's a favorite thing, so it's not ridiculous to throw it away. As something to be used for the rest of my life, I only use what I cherish.
When you throw it away and ask for it, you can see that the word is generally used in a good sense as an implicit consent. It seems that it is natural for the world to throw away unnecessary things and keep things small.
So it's a good thing to say that it's an end, and there's an impression that you're not good if you can't.
I think that it is a common practice, but abandonment is a means to the last, as a result of abandonment, there is no meaning unless everyday life becomes rich. You will get rid of it, you will lose things, and it will be refreshing, but it is transient, and your mind will be clean, that is, it will be organized and you should be connected to the next thing, and eventually it will be the original It becomes a street and there is no sense of abandonment. Because the purpose is to break away.
I think that there are many ways to enrich my daily life, but I like what I like and I can't be bothered by the surprise, but I am always making things in an enclosed state. I think there are a lot of favorite dishes and I want to choose dishes that I use every day, and I have a lot of favorite chairs and I want to choose a chair that I can sit every day.
It is only a good story if the mind is clean and organized, and all you have to do is just throw away your mind, it's a clear mind and something that stimulates your sensibility. However, people who are surrounded a lot, including unnecessary things, will enjoy and enrich their daily lives.
Work, life, schedule, information, memos, while syncing with smartphones, tablets, and PCs, books are also digitalized, managed, and when finished, if there is no need, throw away data, delete it, need it I just leave things and think in my head.
Aside from the degree, I often keep thinking, so I want to make it easy to see the materials for thinking immediately and always, so I often make them act by hand, so I'm concentrating them on my smartphone. Necessity alone is sufficient enough.
あらゆる無限の事柄の中から何を選択するか、一方、あらゆる無限の事柄の中から何が正解かを見つけ出す、どちらも最終的には1つのことに絞るのだが、プロセスが全く違う。
前提として、何か問題があり、その問題を解決しなければならない。
はじめの態度として、その問題を解決するための方法はたくさんあるだろうと予測して、そのたくさんある解決方法の中から何を選択すれば良いかと考え出すか、一方、その問題を解決するための方法は1つしかなく、そのたった1つの正解を導き出そうとして考え出すか。
たった1つの正解を導き出そうとするのは、いわゆる学校の試験勉強や資格試験の勉強で、たくさんある解決方法の中から何を選択するかは、創造的なことをする時に使う。
この、たった1つの正解を導き出す考え方が苦手で、これは訓練で養うものなのだが、その訓練をすること自体が苦痛だった。
今はもう、そのような訓練をする必要が無し、若い時にサボって、いろいろと妄想していたことが今役立つから良いが、このたった1つの正解を導き出す考え方は今だに苦手で、正解という言葉自体も嫌いだ。
"No correct"
The idea is to choose what out of all infinite things, while finding out what is the correct answer out of all infinite things, both ultimately narrow to one thing, but the process is completely different.
As a premise, there is something wrong, and you have to solve it.
As a starting point, predict that there will be many ways to solve the problem, and figure out what to choose from among the many solutions, while ways to solve the problem There is only one, do you come up with the idea of trying to derive that only one correct answer?
It is the study of the so-called school exams and qualification exams that seeks to derive only one correct answer, and it is used when doing creative things what to choose among many solutions.
I'm not good at thinking about this one single correct answer, and although this is what I cultivate by training, it was painful for me to do the training itself.
Now, there is no need to do such training, and it is good because it is useful to have been variously delusions when I was young, but the way of thinking to derive this single correct answer is still poor and it is said that it is correct I also dislike the words themselves.
言葉が先か、感じることが先か。
感じて、それを言葉にする、のが順序としては正しいような気がするが、そもそも感じる時に、先入観として言葉があるような気もする。
全く先入観無しに感じることなど、不可能のような気がするから、言葉が先のように思うが、ならば、感じることが全て言葉に支配されているか、コントロールされているかというと、どうだろうか。
要は、言葉が先でも、感じることが先でも、どちらが先でも良いのだが、ただ、どちらか一方が、どちらかを制限することになると困る。
だが、考えようによっては、言葉によって制限された感じ方、感じ方によって制限された言葉は、それだけで簡潔に物事を多面的に表現していることになり、深い読み解きになっていたりする。
"Feeding with words"
Is the word ahead, or is it the first to feel?
I feel that I make it into words, but I feel that the order is correct, but when I feel in the first place, I feel that I have words as a preconception.
It feels like it is impossible to feel without prejudice at all, so I think the words are ahead, but if you feel that everything is controlled by the words, how is it? Hm?
The point is that the words may come first, the words may come first, or both may go first, but it will be a problem if one or the other restricts one or the other.
However, depending on the idea, the feeling limited by words and the words limited by feelings may be expressed simply and multilaterally by itself, resulting in deep reading and interpretation.
7年が経ち、赤ちゃんが小学生になり、兄妹別々の部屋に、想定していた間仕切壁工事を行うお声掛けをいただいた。
打合せをしていると、7年前が鮮明に蘇る。7年前の自分に会うようだ。
そういえば、7年前に意図したことがあった、それが今どうなったか、きちんと形になって日々の暮らしに浸透している様を見ると嬉しくなる。
7年前と比べて周りの風景が変わったけれど、ピカピカよりは、こなれてきて、よい感じ。
この住宅が良いか悪いかは別にして、この住宅以前と以後では、明らかに変化があった。毎回、そのような変化が起こるように仕事をするだけ、その度、新しい自分に出会うのだ。
"I am seven years ago"
Seven years have passed, the baby has become a primary school student, and my brother and sister had separate voices in the room to carry out the partition wall construction that I was expecting.
When I have a meeting, seven years ago come back clearly. It seems to meet myself seven years ago.
Speaking of which, when I had intended seven years ago, I would be glad to see how it has become, now properly shaped and pervading everyday life.
The scenery around us has changed compared to seven years ago, but it's better than shiny, it feels good.
Apart from whether this house is good or bad, there has been a clear change before and after this house. Every time I work to make such changes happen, I meet new ones each time.
全く違う場面だが、人が、高い技術でつくり出した、一切の余地をはさむことができない、極めて完成度が高く、極めて繊細なもの、それは、何かしらのものづくりに携わる人ならば、一応に目指すところかもしれないが、それが本当に良いものなのだろうか、と最近よく考える。
ものをつくるということで、もの単体に焦点を当てて考えるならば、完成度と繊細さを極めることは良いことに決まっている。
つくる人がいれば、それを受ける人もいる。もの単体に焦点を当てることに、受ける人は入っていない。
極めて高い完成度、繊細さの極地が、受ける人にどう伝わるかは関係ないのだろうか。
受ける人に、完成度と繊細さの極地を伝えようとした時、もしかしたら、もの単体で極地をつくりだすのとは、何か、プロセスか、完成度か、繊細さが違うのではないだろうか。
一切の余地をはさむことができない、極めて完成度が高く、極めて繊細なものよりは、受ける人の想像力や感受性や能力に委ねる部分、もしかしたら、それは完成度や繊細さの度合いが下がることかもしれないが、余白のような不完全な部分があった方が、かえって完成度の高さや繊細さの極地であることが伝わるのではないだろうか。
そのようなことを考えながら、庭園を、欧米のものと日本のもので比べながら、欧米の庭園は繊細さを完成度高くつくり出すのに対して、日本の庭園はうつろいゆく自然の中に繊細さを見つけ出すことに思いを馳せた。
"The degree of perfection and delicacy"
It's a completely different scene, but when people bring in high technology, they can not cut any room, they are extremely complete and extremely fine, and if they are involved in the manufacturing of something, it is intended for a while I don't know when or when, but I think it's really good nowadays.
In terms of making things, it is good to have perfection and delicacy if you focus on single things.
If there is a person who makes it, there are those who receive it. There are no recipients in focusing on a single entity.
It does not matter how the extremely high degree of perfection and delicacy pole is transmitted to the recipient.
When trying to convey the pole of perfection and delicacy to the recipient, what if it were to create a pole by itself alone would it be different in something, process, perfection or delicacy? .
More than perfection, extremely delicate things that can not be divided into any room, parts that delegate to the recipient's imagination, sensitivity and ability, etc., but it does not decrease the degree of perfection and delicacy If there is an incomplete part such as a blank space, it might rather be transmitted that it is a pole of high degree of completion and delicacy.
While thinking about such things, comparing gardens with those of Western and Japanese ones, while Western gardens create delicacy to a high degree of perfection, Japanese gardens delicacy in the beautiful nature I felt lost in finding it.
技巧を尽くし完成度と繊細さを極めて、その極地まで来たとする。その場所はとても素晴らしく、全ては完全で完璧であり、全く隙も無い。感嘆の声がもれる。溜息が出る。
頭の中はさぞ脳内物質が分泌されて、恍惚の極み、気持ち良くて仕方がないだろう。この世の極みである。この時を待っていました。
しかし、実際は頭の中が混乱し、素晴らしさはわかるが、気持ち良いどころか、楽しめない。これでもか、これでもかと繊細で完全完璧なものが迫ってくる。どうしたら良いのか、わからなくなる。
すなわち、辿り着いた極地は未知の場所であり、すでに極めた既知の場所では無い。既知の場所であれば、それはすでに到達している場所であるから、極みとは思わず、単なる通過点にしか思わないだろう。
未知の場所だから、混乱し、楽しむ余裕など無く、どうしたら良いのか、わからなくなるのが当たり前であり、それは受け手の問題では無い。
そこで、2つの選択肢がある。
受け手が混乱しても、完成度と繊細さを極めて、その極地を提供するのか、受け手の感度にあわせて、完成度と繊細さを調整、すなわち、バランスをとるのか、中庸とも言うかもしれない。
一番難易度が高いのは、技巧を尽くし完成度と繊細さを極めて、その極地まで行き、それが中庸であるとも言えることか。一見、この矛盾することが解けた時、次の新しい扉が開くような気がする。
そのためには、自律だけではなく、他律でもいる必要があり、自律と他律のバランスが中庸であれば良いと思う。
"Moderate"
It is said that it has done its craftsmanship and has achieved perfection and delicacy, and that it has reached its extreme. The place is very nice, everything is perfect, perfect and completely free. There is a voice of exclamation. I get a sigh.
The substance in the brain is secreted in the head, and the limit of the acupuncture, it will be pleasant and can not be helped. It is the limit of this world. I was waiting for this time.
However, in reality, my mind is confused and I know the splendor, but I can not enjoy it. Even here, something delicate and completely perfect is approaching. I don't know what to do.
That is, the polar land reached is an unknown place, not a well-known place already. If it is a known place, it is a place that has already been reached, so it will not be considered as extreme, but only as a passing point.
Because it is an unknown place, it is confusing, there is no time to enjoy it, it is natural to lose track of what to do, and it is not a problem of the receiver.
So there are two options.
Even if the recipient is confused, it may be said that the perfection and delicacy are adjusted, that is, whether the perfection and delicacy are adjusted according to the sensitivity of the recipient, that is, whether it provides a pole or perfection. .
The highest level of difficulty is that you must be skilled and extremely complete and delicate, and go to that extreme and say that it is a middle class. At first glance, when this contradiction is solved, it feels like the next new door opens.
For that purpose, it is necessary to be not only autonomy but also other laws, and I think that it is good if the balance between autonomy and other laws is moderate.
京都近代美術館で開催されている「陶工・河井寛次郎」展の河井寛次郎の言葉より、
「一度も見た事のない私が沢山ゐる」
「すきなものの中には必ず私はゐる」
「私は習慣から身をねじる、未だ見ぬ私が見度いから」
の部分に惹かれた。自分の好きなものを自分で作ってみる、それは、まだ見たことがない自分、新しい自分を見たいから、と言っているのではないかと解釈した。
まだまだ未知の自分が存在し、それを仕事を通して見つけ出す、そのためには「習慣から身をねじる」、それは日常の中で少し見方を変えてやることか。
新しい自分と出会いたい、だから仕事する。
"I have not seen it yet"
From the words of Kawai Hirojiro at the "Poster / Kawai Hirojiro" exhibition held at the Museum of Modern Art Kyoto,
"A lot of me who I have never seen before"
"I always sing in my favorite things"
"I twist myself from the habit, because I have not seen it yet"
I was attracted to the part. I tried to make something that I liked, I interpreted it as saying that I had never seen it, I wanted to see a new one.
There is still an unknown self, who finds it through work, for that purpose, "twists from habits", does it change the way of thinking a little in everyday life?
I want to meet new myself, so I work.
京都近代美術館で開催されている「陶工・河井寛次郎」展では、河井寛次郎の言葉にも惹かれた。河井寛次郎が言葉を紡ぎ出す人とは思ってもいなかったので、その中でも
「表現されるぎりぎりの自分が、同時に、他人のもの」
「ぎりぎりの我に到達した時に初めて、ぎりぎりの他にも到達」
「自他のない世界が、ほんとうの仕事の世界」
の部分に惹かれた。自分の好きなものを自分で作ってみようとすると、独りよがりになり、結果、自分以外の他を排除するものしかできないように思ってしまうが、河井はそうではなくて、自分の好きなものをとことん突き詰めて、自分で作り得る最上級のぎりぎりのものは、自分以外の他にとっても最上級のぎりぎりのものであり、それは自分とか他とかを超越したところに存在するものであり、それが本当の仕事だという。
ぎりぎりの我について、その後、思いを巡らしたのは言うまでもない。
"I at last"
At the "Poster / Kawai Kanjiro" exhibition held at the Museum of Modern Art, Kyoto, I was also attracted by Kawai Kanjiro's words. As Kawai Kanjiro did not think that he was the person who spun words,
"At the same time, the only thing being expressed is that of others"
"The first time you get to the last thing, the last to reach the last"
"The world without oneself is the real world of work"
I was attracted to the part. If you try to make your own favorite thing, you become selfish and, as a result, you think that you can only exclude something other than yourself, but Kawai is not so, it is your own favorite thing The best stuff that you can make yourself, in a nutshell, is the best stuff you have for others, and it is something that transcends you, or something else, that's true It is a job of
It is needless to say that I went over the mind about the last of me.
もっとニュートラルに物事を見てみたい。
自分の都合の良いように世の中を見る、都合の悪いものは目に入らない、嫌だと思うものが気になるのは、嫌だと思うものが自分にとって都合が良いから。
車で大通りを流していて、ビルとビルの間の僅かな隙間から一瞬、良いなあの建築、と見えたものが、何ヶ月後かに建築雑誌に掲載されていたり。
隔たる、ともいうべきか、それが個性かもしれないけれど、たくさんの可能性を捨てているようにも思うし、そこに気がつくと、今、とにかく行動するなんてことはマイナスしか無いと思えてくる。
物事にはタイミングがあると思う。タイミングを見計らうには、ニュートラルな状態でいないと、そして、タイミングを合わせるためには、静止状態からではすぐに動き出せないから、予備動作というか、細かな動きは常にして、その細かな動きが知見を深めることにもなると思っている。
"Fine movement"
I would like to see things more neutral.
Seeing the world as it is convenient, inconvenient things do not come into your eyes, and things that you do not like are bothered because things that you dislike are convenient for you.
You're driving along a boulevard, and from what appears to be a good building, for a moment from the slight gap between buildings, it will be published in architectural magazines in months.
Though it may be different, it may be an individuality, but I think it seems to throw away a lot of possibilities, and if you notice it, it seems that there is only a negative thing to act now anyway .
I think things have timing. In order to look at the timing, if you are not in neutral state, and you are not able to move out immediately from the state of rest in order to adjust the timing, the preliminary movement or fine movement will always be that fine movement I think that will also deepen the knowledge.
事業計画の中で1住戸の大きさと戸数を決め、それを満たせば、あとは自由にデザインしようと思い、集合住宅の計画をはじめるが、できれば最大戸数が欲しくなるので、そうすると、自由度が無くなってくる。
だから、事業計画から入らずに、デザインの方向性、コンセプトや、建築に対する考えから入れば、少しは自由度が上がるというか、デザインできる余地を最大化したいだけだが、そうして見積りすると、予算の2倍とか3倍になるし、収支計画に支障きたす。
なんてことを今さらながらに、つらつらと考えながら、スケッチしていると、迷いが無駄な線になって現れるので、当然消すのだが、iPadだと線に触れるだけで消えるから便利、手書きだと消しゴムカスの山、その前に刷毛が必要だが、おかげでいくらでも迷える。
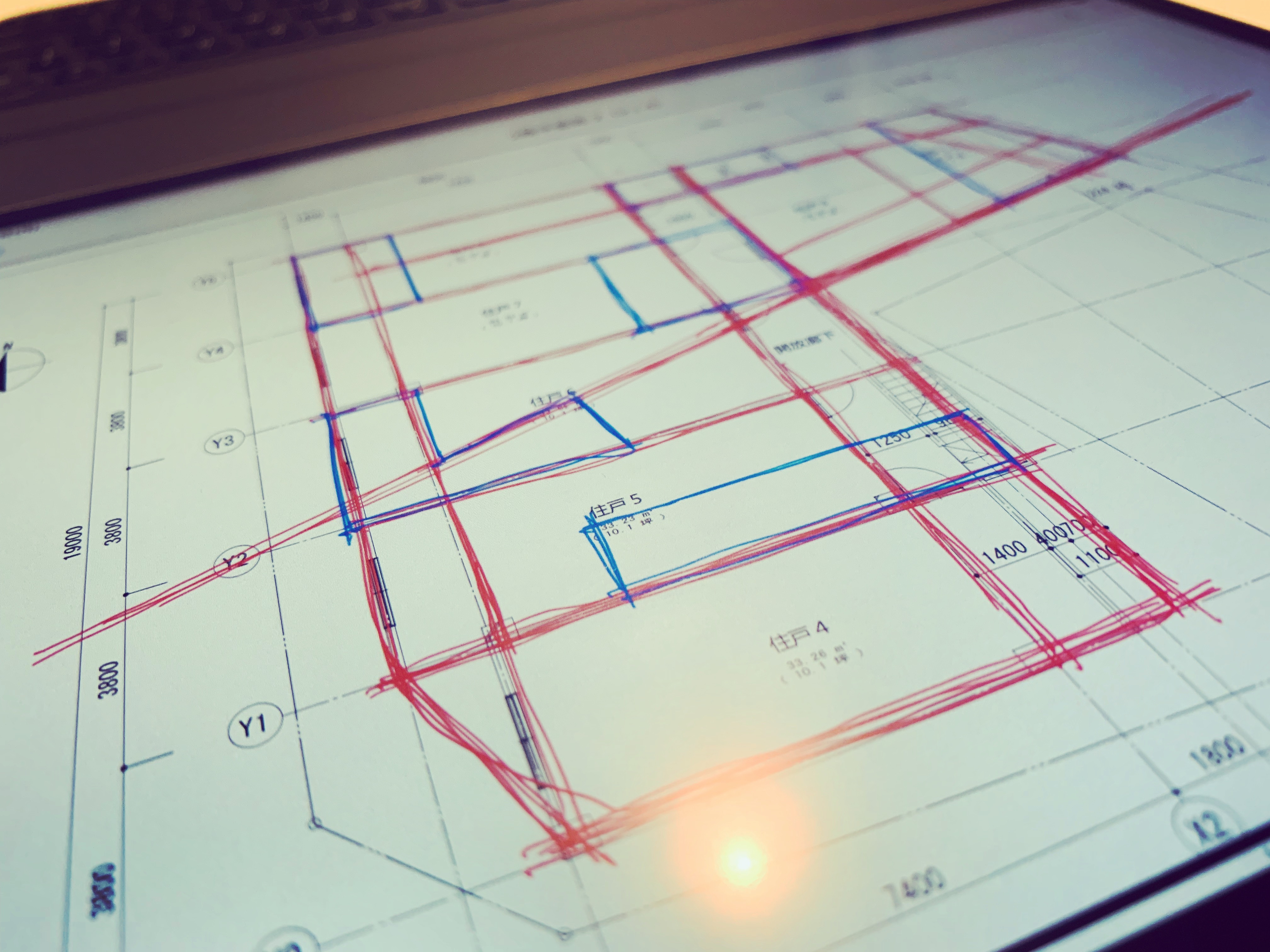
"Most digitization"
If you decide the size and number of units in one business plan and meet it, you will try to design freely and start planning of multi-family housing, but you will want the maximum number of homes if you can, so there is no freedom Come.
So, without entering the business plan, from the direction of design, the concept, and the idea of architecture, I just want to increase the degree of freedom, or just maximize the design space, but if I estimate it, the budget It doubles or triples, and it interferes with budget planning.
If you are sketching while thinking about what you're doing now, you will lose the lines because the stray lines will become useless lines, but of course it will disappear when you touch the lines if it is an iPad, it will be useful, it will be handwritten I need a brush in front of the pile of rubber waste, but I can get lost as much as I can.
なぜか今、ニューヨークに行きたくて、行きたくて仕方がない。
今、barでニューヨークの話をしたからかもしれないが、若い頃、学生の頃は夏休み、春休みが長くて、勉強しない代わりに、チケットが安くて、往復5.6万位で行けたから、ソーホーに友達の知り合いがいたので、泊めてもらいながら、ニューヨーク中の美術館や博物館やギャラリーを見まくっていた。
ニューヨーク近代美術館には建築や家具やプロダクトデザインのコーナーがあり、ミースの図面やライトの落水荘の模型、コルビュジエや倉俣史朗や柳宗理の椅子やスツールをはじめてそこで見て、建築やデザインの本物にはじめて触れた感じがして、全てが私の先生だった。
それが25年前、あの頃は治安がとても悪かったけれど、今は良くなったと聞く。
見るもの、聞くもの全てが血となり肉となった、あの時の感覚を時々思い出すが、その時の感覚をまた味わいたくて行きたいのでは無いのは確かだ。むしろ、普通に淡々といたいと思う。
"A little old story"
For some reason now, I want to go to New York and I can not help going.
It might be because I talked about New York at the bar now, but when I was young, when I was a student, summer vacation, spring vacation was long, instead of studying, tickets were cheap and I could go in 560,000 round trip, so my friend to Soho Because I had an acquaintance of, I was looking at museums and museums throughout New York while staying.
The Museum of Modern Art in New York has a corner of architecture, furniture and product design, and it is the first time to see the first drawing of Mies's drawings and models of Lochuisou of light, Corbusier, Shiro Kuramata, and chairs and stools of Yanagi Soran for the first time in architecture and design I felt touched and everything was my teacher.
That was 25 years ago, but at that time security was very bad, but now I hear that it has improved.
Everything I see and hear listens to blood and flesh, I sometimes remember the feeling of that time, but I certainly do not want to go to taste the feeling of that time again. Rather, I usually want to be naive.
GWは亡父の姉の葬儀に参列するために、何年かぶりに亡父の生まれ故郷に行った。
千葉の外れ、周りは田んぼや畑、街道沿いだけはどこにでもあるチェーン店の街並み、赤紫の○○○モールの看板、それでも夜は真っ暗なのにコンビ二のまわりはだけは青白い。
昔の銀座通りはシャッター街、駅は綺麗に建て替わって、道も整備されているが、コーヒー1杯飲むお店も無く、賑わいも無く、同じ賑わいが無くても、なぜかシャッター街の方は郷愁を誘い、ちょっと離れれば、家の1区画が比較的大きく、高い建物も無く、心地よい風が吹きわたる。
最近ずっと、自閉しないで生活感がオープンになる建築ばかりを考えているせいか、目が行くのは、生活感の伝わり方がどうかということ。
賑わいが無ければ、家の1区画が大きければ、高い建物が無ければ、周りが田畑ならば、誰の目も気にする必要が無いのだから、オープンに、生活感が溢れ出ても良さそうだろうに、自閉している、それは都市よりも強固。
そういう姿を見ると、建築だけでは解決できない、人の心理や人間関係が影響を与えている、もちろん、それは当たり前だが、都市にいると意外と思い違いをしてしまう、そういう心理や人間関係の上に社会が形成され、その社会を建築が反映してしまうことを、その逆の、都市は賑わいに慣れ、人間関係が希薄だから、建築が社会を規定できると、その思い違いから計画がスタートする。
ただ、建築の歴史を辿ると、建築が社会を規定できるというところからスタートするから新しい建築が生まても来た。建築が社会を反映するならば、そのスタートは社会を追認することだから、そこでは見慣れた風景の建築は生まれても、新しさは生まれない。
そう考えると、若い人が都会に出たがるのもわかる気がした。
"Strong more self-confident"
GW went to the hometown of his late father for the first time in several years to attend the funeral of his late father's sister.
Outside of Chiba, around rice fields and fields, the streets of chain stores where there is only along the highway, the signboard of the red-purple ○○○ mall, but it is still dark at night, but only around Combi is pale.
The old Ginza Street is a shutter town, the station is beautifully rebuilt, and the road is well maintained, but there is no shop to drink a cup of coffee, there is no bustling, and even if there is no bustling, people in shutter town somehow Nostalgic, inviting a little away, a section of the house is relatively large, there are no tall buildings, and a pleasant wind blows.
The reason why people are thinking about architecture that will open their sense of life without having a sense of autism all the time has come to see how the sense of life is transmitted.
If there is no bustling, if one section of the house is large, if there is no tall building, if there is a surrounding field, there is no need to worry about anyone's eyes, so it seems good to have a sense of openness It is self-closing, it is stronger than the city.
If you look at such a figure, it can not be solved only by architecture, but it is natural that people's psychology and human relationships are influenced, but it is natural, but if you are in a city, you unexpectedly misunderstand, such psychology or human relationships The opposite is that cities are used to the bustle and that human relationships are weak, and that planning can start from that misconception that architecture can define society, as a society is formed and that architecture reflects that society.
However, since the history of architecture starts from the point where architecture can define society, new architecture has come to be born. If architecture reflects society, the start is to recognize society, so there will be no newness, although architecture of familiar landscapes will be born.
When I thought so, I felt that I also wanted to see young people going to the city.
すれ違う電車同士、お互い近くに乗客が見える、案外近い、しかし、距離の近さとは逆に、当たり前だが接点は無く、もう二度会うことが無い人たち、実際はもうしかしたら、どこかで会っているかもしれないが、元々関心が無いので覚えていない、お互いに丸見えなのに見ていない、見えていない状態。
こちらの電車も向こうの電車も違う活動をしているから、全く別世界にいるように接点が無い。だから、違う電車に対しては意識もしない。
これが同じ電車内ならば、例え、もう二度会うことが無い人たちでも、とりあえず、同じ空間にいるので意識はしてしまう。
同じ電車内ではオープンにできないが、違う電車に対してはオープンにできる気がする。
さらに、違う電車同士に挟まれた場所ならば、誰も関心を持たない、誰も意識しない、空白地帯が出現する。電車ならば、人を乗せたまま電車自体が動き、活動するので、この空白地帯をつくり出すのは容易だが、動かない建築では、この空白地帯はオープンなパーソナルスペースにできるのだが、なかなか難しい。
まず、活動すなわちアクティビティーを建築で発生させなければならない。このアクティビティーは人がする。不完全性を利用して、完全になろうとする働き、この場合は心の働きになるだろう、を発生させる、これが建築でのアクティビティー、このアクティビティーを複数、異なるものを発生させれば、その間に空白地帯ができ、そこがオープンなパーソナルスペースになる。
この考えのもと、スタディを延々と繰り返すも、いつでもまとめようと思えばできそうなのだが、時間があるせいか、余計なことまでしてしまう。
"Blank zone"
Trains passing each other, passengers can be seen near each other, unexpectedly close, but, contrary to the closeness of the distance, people who have no contact but have never met again, in fact, probably met somewhere It may be, but I do not remember because I am not interested in originally, I can not see each other even though I can see each other, I can not see it.
Because this train and the other train are doing different activities, there is no contact as if you were in another world. So I am not conscious of different trains.
If this is in the same train, even people who never meet again will be conscious because they are in the same space for the time being.
I can not open it on the same train, but I can open it to another train.
Furthermore, if it is a place between different trains, a blank zone will appear where nobody is interested or conscious. If it is a train, it will be easy to create this blank area, as the train itself will move with activity and it will be easy to create this blank zone, but in a static architecture this blank zone can be an open personal space, but it is quite difficult.
First, the activity or activity must be generated in the building. This activity is done by people. Taking advantage of imperfections to create a work that will try to be complete, in this case it will be a work of the mind, if this is an architectural activity, and if this activity generates several different ones, There is a blank zone in the area, which will be an open personal space.
Based on this idea, it is possible to repeat the study endlessly, but if you try to put it together all the time, it will do more than necessary because of the time.
接点の無い異なる複数のアクティビティー同士に囲まれた空間がオープンなパーソナルスペースになり、表層の不完全性により、アクティビティーは表層の外、建築の外で発生させるとし、表層の不完全性は敷地のコンテクスト/文脈からつくる、とした。
以前にも書いたが、不完全性のつくり方には、何かを足せる状態か、完全性が乱れたり崩れた状態の2つある。何かを足せる状態とは、例えると、茶会の度に設えを整える前の茶室であり、それは空っぽの状態と言っても良く、完全性が乱れたり崩れた状態とは、同じく茶室で例えると、シンメトリーが崩れた違い棚てあり、その崩れ方、乱れ方が見る者の心に働きかけてくる、心を動かす。
どちらの不完全性もアクティビティーが発生するので、2つの方法を使い分けたり、組合せることも可能だと思うが、見る者の心に働きかける方に興味がそそられ、シンメトリーが崩れり乱れた状態をつくり出すデザインをすることになるだろうが、デザインの完成が目的では無くて、その先の人の心に働きかけることが目的であるという所が、本来、デザインとはそういうもので、デザインが手段であるのがいい。
"Design of means"
The space surrounded by different activities without contact becomes an open personal space, and the imperfection of the surface causes the activity to occur outside the surface and outside the building, and the imperfection of the surface is the site It was made from context / context.
As I wrote before, there are two ways of creating imperfections: adding something, or breaking or breaking integrity. A state in which something can be added is, for example, a tea room before setting up for a tea ceremony, which may be said to be empty, and a state in which the integrity is broken or broken is similarly compared in the tea room The symmetry is broken into a different shelf, and how it collapses and disturbs works on the mind of the viewer, moving the mind.
Since both imperfections generate activity, I think it is possible to use or combine the two methods, but it is intriguing to work on the mind of the viewer and the symmetry is broken down The design will be created, but the place where the goal is not to finish the design but to work on the mind of the person ahead is basically such design, and the design is the means I hope there is.
「表層と中身」の話をした。
中身に制限は無いが、プライバシーを守るために閉じたくなる、中身を見られたくない、という心理が働くのは当たり前だが、その閉じたくなる心理をなんとかしたい、無くしたい。
オープンにできた方が気持ちがいいだろう、天気が良い日には窓を開け放って青空をのぞみたいし、ふんだんに心地よい風を取り込みたい、
そういう生活がしたいが、なかなか、自然の中ならば可能だが、都会の中では難しい、というか、心の中で勝手に無理だと決めつけてしまう。
その障壁みたいなものを昔から、それこそ、建築を学びはじめた学生の頃から取り除きたいと考えている。
住み手が特殊な人で、自分みたいに、周りは何も無かったことにできる人ならば、人に見られようと、どうしようと関係ないから、開け放つことは可能だが、普通はそれは無理だから、周りと干渉しないように、太陽の位置を時刻によって計算し、あと、クライアントの生活習慣を考慮しながら、開口部を厳選してオープンにしていくのだが、その行為は言わば、敷地の欠点を何とか補う行為で、対処療法であるから、本来持っている敷地のポテンシャルを発揮しているとは言えず、でも、暮らしの中で、自閉せず、開いていくのだが、根本的には、それは不健康なような気がして、異なるアクティビティーを発生させ、オープンなパーソナルスペースをつくろうと、どうしても考えたくなる。
"I want to solve autism"
We talked about "surface and content".
There is no limit to the contents, but it is natural that the mind works like closing to protect the privacy and not wanting to see the contents works, but I want to manage or eliminate that closing mind.
It would be nice if you could do it openly, open the window to see the blue sky when the weather is fine, and want to take in plenty of pleasant wind,
I want to live that kind of life, but it is possible if it is in nature, but it is difficult in a city, or rather it is decided that it is impossible in the heart.
I would like to remove something like the barrier from the old days, that is when I was a student who started to learn architecture.
If a person is a special person who can do something like himself and nothing around it, it is possible to open it up regardless of how it is seen by people, but it is usually impossible. The position of the sun is calculated according to the time so as not to interfere with the surroundings, and after taking into account the client's lifestyle habits, the opening is carefully selected and opened, but the act is, as it were, a fault of the site. Because it is a coping therapy, it can not be said that it actually exerts the potential of the site that it has originally, but it will not open itself in the living without being closed, but it is fundamentally It feels like it's unhealthy, generates different activities, and wants to think about creating an open personal space.
異なるアクティビティー同士の間にオープンなパーソナルスペースができると考えている。ちょうどそこが空白地帯というか、真空状態というか、誰も関心を持たない、誰にも干渉されないスペースができると考えている。
例えば、行き交う電車と電車の間とか、そこに普通はいないから、わからないと思うかもしれないが、電車に乗っている人はそこに目もくれない。
だから、オープンにできる。
オープンにできれば、生活が溢れ出すじゃないか。
都市がつまらない時は、街がつまらない時は、肩肘張って、虚勢を張って、繕って、虚飾にまみれている時、生活が溢れ出し、日常まみれの場所は、親近感が湧くし、ほっとするし、自分が素になれて、ストレスが無く、精神衛生上良く、楽しい、長生きするよ。
だから、オープンなパーソナルスペースのつくり方を一般解として解きたい。そのような空間を意図的につくりたい、そのような意図的な空間を見たことないが無いでしょ。
だから、考える意味があるし、トライする意味がある。
"Let's overflow the life"
I think that there is an open personal space between different activities. I think that there is a space where there is no gap with nobody, or nobody's interested, or just a vacuum zone.
For example, you may think that you don't know because you are not in the usual place, such as between trains that go and go, but those on the train will not see you there.
So you can be open.
Life would overflow if it could be open.
When the city is boring, when the city is boring, shoulders, elbows, vignettes, crawling, when covered in a vanity, life overflows, everyday places are covered with a sense of closeness and a sense of intimacy I will be a part of myself, stress free, good in mental health, enjoyable, live longer.
So I want to solve the way of creating an open personal space as a general solution. I would like to create such a space intentionally, I have never seen such an intentional space.
So it makes sense to think and to make a try.
建築を1から構想する時は、何か手がかりのようなものがあってはじめる。全く何も無く、プランが出来上がることは無い。
その手がかりは、建築論であったり、自身の建築に対する想いであったり、クライアントの要望であったり、周辺環境からもあるだろうし、建築性能としての温熱環境を満たすことであったりなど、あと、これらが複合する場合もあるだろう。
いずれにせよ、何を手がかりにするのかを選択し、構想を進めていくのだが、まず手がかりを考えるのが面白いし、悩むところ、最初の方向性だから、面白い場面や、やり甲斐を感じる時や、達成感がある場面はこの後に何度もあるが、全体の方向性を考える時は最初だけで、あとはその都度確認をするが、この方向性を間違うと、後で修正もできないし、途中をいくら頑張っても、報われない結果になる、建築としてのレベルの高さがここで決まるといか。
だから、時間をかけたくなるし、安易に決められないし、ともなるが、面白いもので、大体一番最初に思い付いたことや手がかりが、結局それを出発点として、時間をかけてそれで良いという証明を自分にしながら、構想を進めていったりする。
"clue"
When I envision building from scratch, I begin to have something like a clue. There is nothing at all and there is no plan coming up.
The clue is architecture theory, thought of one's own architecture, the request of the client, there is also from the surrounding environment, it is to meet the thermal environment as the building performance, etc. There may be cases where these are combined.
In any case, we choose what to use as a clue, and proceed with the concept, but it is interesting to think of a clue first, and to be troubled, because it is the first directionality, when you feel an interesting scene or practice There are many occasions after which there is a sense of accomplishment, but when thinking about the overall directionality, it is only the first and every time after that, it is confirmed each time, but if this directionality is wrong, correction can not be made later, No matter how hard you work on the way, it will result in no reward, if the height of the architectural level is decided here.
So it's tempting to spend time, not easy to decide, but it's also fun, and it's mostly about the first things you come up with and clues that prove it's good over time, taking it as a starting point While promoting the concept.
箱や包装も考えた方が良い、と言われた。
輪島塗のフリーカップを製作中だが、そのことを先日お会いした京都の古美術店の店主の方に話をしたら、そう言われた。
箱が良いか、包装が良いか、何か別のやり方もあるかもしれないが、どう見せるか、どう見せたいか、相手に手渡す時のことも考えないと。
そこまでは考えていなかった、フリーカップをつくることしか頭に無く、人に手渡す時のことまで考えていなかった。
店主に言わせると、そこまで考えるのが当たり前のことで、それがものをつくるということだと伝えたかったのかもしれない。
"When handing to people"
It was said that it would be better to think about boxes and packaging.
I was making a free cup of Wajima-Nuri, but when I talked to the shopkeeper of the old art shop in Kyoto that I met the other day, I was told that.
There may be other ways, such as whether the box is good, the packaging is good, but I don't think about how to show it or how I want to show it or when handing it to the other party.
I had not thought about it until then, I was only thinking about making a free cup, and I was not thinking about handing it to people.
If you ask the storekeeper, you might have wanted to tell that thinking so far is a matter of course and making things.
『使うということ』
器は使ってなんぼ、とう言葉を何度も使っていた、古美術店の店主の方とお話ししている時に。
魯山人のお椀、博物館級のもの、それも料理を盛った形跡がある。魯山人は使うために器を、料理を盛るために器を、観賞用では無く。
使う、盛るが最初にあるから、器の形、厚みなどが決まる、それは民藝と同じなのだが、なぜか民藝は丈夫さが優先され、分厚くなる、武骨になる。
使う、盛るが最初にあるからと言って、壊れない、丈夫である必要は無い、それはまた別の話。普段使いだから、壊れない、丈夫さが必要だと、だから分厚くても良い、分厚い方が良いという考えは、使うということがわかっていない人の考え。
使うということは、自分の手先になって、自分の分身のように、自分の性質がそこに出る、美意識も。そうすると、壊れない丈夫で分厚い美意識もあるという人がいるが、それは意図して分厚くしているのでは無くて、単に丈夫さを求めた結果として分厚くなったに過ぎず、そこには美意識のかけらも無い。
使うということは、自分の美意識もセンスも生活レベルも問われているということ。
例えば、細く薄く繊細に見せるために、わざと、太く厚く武骨な部分をつくり、対比によって細く薄く繊細に見せる場合もあり、それはその武骨な部分が必要で、丈夫さを求めた結果では無くて、結果的に丈夫にはなるかもしれないが、たった1回使ったら終わりでも良い訳で、大事なのは器を使った時に、料理を盛った時に、どのように料理と調和を図るかということで、丈夫さを求めるのは単に効率、コストを優先しているに過ぎず、民藝はその意識が強いから民藝になるとも言え、民藝にするために丈夫さを求めるとも言えてしまい、それだと民藝の素の部分が現代の何事も効率を求める精神と同じになり、均一化された工業製品と相対する民藝の精神が、実は均一化された工業製品と素は一緒という、何とも皮肉な、そこに気が付かない民藝の器に料理を盛っても、というか、盛りたくない。
"Use"
When we are talking with the old art shop owner who used the bowl and used the language many times.
There is a trace of a dish of Mioyama-san, a museum-like one, and that also contains a dish. Aoi Yamato is not used for cooking, but for cooking.
Because it is used first, the shape and thickness of the bowl are decided because it is the same as the folk song, but somehow the folk song has strength and becomes thick, it becomes a samurai bone.
It doesn't have to be broken or durable just because you use it first, but it's another story. It's a regular use, so it's not broken, it needs to be strong, so it's good to be thick, the idea that thick is better is the idea of people who don't know to use it.
To use it is your own hand, like your own self, your nature comes out there, also the sense of beauty. Then, there are those who are strong and have a thick aesthetic sense that does not break, but it is not intended to be thick as intended, but merely thick as a result of seeking for toughness, and there is a fragment of aesthetics There is also no.
To use it means that one's sense of beauty, sense and life level are also questioned.
For example, in order to make it look thin, thin and delicate, it is possible to make thick, thick and thick parts intentionally, and to make it look thin, thin and thin by contrast. As a result, it may become strong, but it is good if you use it only once, but the important thing is how to keep the dish in harmony with the dish when you use it. Therefore, seeking robustness is merely giving priority to efficiency and cost, and it can be said that a folk song will be a folk song because its awareness is strong, and it can be said that it seeks robustness to become a folk song. Then, the original part of the folk song will be the same as the modern day's spirit for efficiency, and the spirit of the folk song against the uniformed industrial products and the opposite, but in fact the uniformed industrial products and the element are together Of course, ironically, you notice it Even if the dishes are served in the bowl of a good folk song, I do not want to do it.
京都の古美術店で店主の方と話し込んだ、前にカトラリーを購入したお店。
伊万里焼を見ていたら、久しぶりに伊万里を取り扱っている、と話し掛けられた。父親の代までは伊万里の専門店だったが止めたと。
今でも東京で一度は行ったり、見聞きしたことのあるお料理屋さんに器を下ろしていて、ただ、誰かに言われた訳では無いが、自分で気づいたそうで、
伊万里焼の器はお料理屋さんでは使わない。
当然理由を聞いてみたくなり、その他にも、魯山人の漆器、博物館級のものを触りながら、今ここでは書けない話などを聞いた、随分と長いことお話しをさせてもらった、掛け軸の話も、熊谷守一の、これはまだだれにも見せてない、来年のお茶会の待ち合いで、これもまだここには書けない、そんな話ばかり。
伊万里は武骨だから、お料理に合わない。その理由を聞いて、実はずっと思っていたことがあり、やっぱりと納得した、民藝の話で。
"Judging judgment"
A shop where I bought a cutlery before, talking with the shop owner at an old art shop in Kyoto.
When I watched Imari, I was told that Imari was handled after a long time. It was an Imari specialty store until his father's day, but he stopped.
Even now, I went to a restaurant in Tokyo once and dropped the dish to a restaurant that I had seen and heard, but it wasn't that he was told by someone, but I noticed that I myself.
Imari pottery is not used in the restaurant.
Naturally, I would like to ask why, and while touching the lacquerware of the Sasayama people and museum-class things, I heard a story that I can not write here, etc., a story of a long time, let me talk about the axis Well, that's not yet shown to anyone, Kumagai Moriichi's next year's tea ceremony meeting, this can not be written here yet, such a story.
As Imari is a bone, it doesn't suit you. Hearing the reason, in fact I had always thought, after all I was convinced, in the story of the folk song.
コルビュジエは絵画上で「幾何学的な秩序」と「人間と自然の調和」をはかっていたのか、いや、「幾何学的な秩序」が人間のことで、「幾何学的な秩序」と「自然の調和」をはかっていたのかもしれない、とした。
人は不変ではない、いつか死ぬし、老いるし。
ただ、20世紀の「人間」という概念は不変と規定し、コルビュジエは「人間」を「幾何学的な秩序」の一部として表現していた、それがモデュロール。
人間を幾何学的な秩序とすることで建築の中に人間を取り込み、空間と一体化することをめざした、それは不変を標榜したモダニズム建築と折り合いをつけるために。
結局、人間も空間も建築も不変であるはずが無く、歪みが出るのだが、人はみな不変をなぜか求めてしまう、アンチエイジングもそう、絶対的で不変なものが好きな心理があるのか、それとも、モダニズム的な建築のデザインがやりやすいのか、今だにモダニズム建築の系譜は続いており、何かと折り合いをつけることになる。
モダニズム建築が近現代建築の基礎的なデザインなので、その系譜から逃れることはできないのかもしれないが、建築関係者の中だけで暗黙の了解的なデザインが存在するのも確かだから、全く違うデザインをイメージしたく、それはイメージの中にいたら難しいから、言葉に頼ることになる。
"Start with words"
Corbusier did "geometrical order" and "harmony of human beings and nature" in the picture, or "geometrical order" means human being, "geometrical order" and "geometrical order" It may be that he was trying to harmonize nature.
People are not constant, someday die and they grow old.
However, the concept of "human" in the 20th century is defined as immutable, and Corbusier expressed "human" as part of "geometrical order", which is modulol.
In order to bring human into architecture and unite with space by making human geometrically ordered, it is in order to reconcile with modernist architecture which insisted on invariance.
After all, human beings and space and architecture can not be invariant, and distortions occur, but all people seek for invariance somehow, like anti-aging, do they have a mind that likes absolute and invariant things Or is it easy to design modernist architecture, the genealogy of modernist architecture still continues, and we will get along with something.
Because modernist architecture is a basic design of modern and contemporary architecture, it may not be possible to escape from its genealogy, but it is also true that there is an implicit intelligible design within the building personnel alone, so a totally different design Because it is difficult if it is in the image, it will rely on words.
光をものとして扱うために粒としてイメージし、その粒の集め方、扱い方が建築の造形のヒントになる、とした。
集合住宅を考えている。その建築性を考えている。
集まって住むことでしかつくることができない空間や建築をつくりたいと思っている。
光をものとして扱おうとしているのは、光を媒介にして、その日の気分の変化を建築で感じて欲しいから。そうすれば、その日の気分によって建築の見え方も変わるだろうから。
それが住人の数だけ起これば、その建築はなんて多様で複雑で、ちょっとだけ浪漫が、と妄想するも、そこに集まって住むから、という理由づけしたいのだが、なかなか上手いこといがず、ここ数日ずっと考えている。
"Because we gather and live"
In order to treat light as a grain, it was imagined as a grain, and how to collect and handle the grains is a hint for building the architecture.
I am considering multi-family houses. I am considering its architectural nature.
I would like to create space and architecture that can only be created by gathering and living.
I 'm trying to treat light as things because I want you to feel the change in the mood of the day through architecture through light. That way, the appearance of the building will change according to the mood of the day.
If it happens as many as the number of residents, I'd like to rationalize that the architecture is so diverse and complicated, a little bit romantic, but also live and gather there, but it is quite something good, I have been thinking over the last few days.
建築には空間に差し込む光を利用でき、光はゼンマイ仕掛けのように変化し、そこに差異を見出せる気がする、とした。
ずっと、建築が見る人の気分によって見え方が変わるにはどうすれば良いのかを考えている。
なぜか、建築は今まで不変と考えられて来たから。当たり前だが、建築物が変化しないから不変という訳ではなくて、建築は時代や社会によって捉えられ方が変化してきた、デザインも、流行があるということ。しかし、それを受け止める建築自体は確かなもので変わらないものだから、そこに時代性や社会性を投影できた、建築自体は常にブレが無く不変が前提だった。それは経済的にも重要で、不変だから、不動産と称する事業性を含んだ建築が生まれた。
ただ、建築もものならば、不変という捉え方には無理があるだろう、もちろん、耐久性の話ではなくて、建築以外のものは、簡単に動かすことができ、使う側が取捨選択できることもあるが、ものとしてそこに気分や感情を投影することが容易にでき、それがそのものの存在価値と直結している。
例えば、毎朝飲むコーヒーを淹れるカップを気分で選ぶ、など、その日の気分がコーヒーカップの存在価値を決め、それがそのコーヒーカップのその日の見え方を決める。
だから、建築にもそのようなことが起こる、不変ではないものにしたく、そうすれば、その建築での日常は楽しいことになるのではないか、という考え方のつながり。
"Aiming for Constancy Not Constant"
In the building we can use the light to be inserted into the space, the light changed like a springmaking gimmick, and it seems to be able to find a difference there.
I'm thinking about how to see how the appearance changes depending on the mood of the building.
For some reason, architecture has been considered immutable until now. Naturally, it is not a change that the building does not change so it is not a change, the way that architecture is caught by the times and society has changed, the design also has a fashion. However, since the architecture itself which accepts this is a sure thing, it does not change, so we could project periodicity and sociality there, the building itself was always premised without blurring. Since it is economically important and unchanged, a construction including a business property called real estate was born.
However, if construction is also things, it seems impossible to understand that it is immutable, of course, it is not a story of durability, but things other than buildings can be easily moved, sometimes the use side can sort it out However, it is easy to project moods and emotions there as things, which is directly linked to the existence value of itself.
For example, the mood of the day decides the existence value of the coffee cup, such as choosing a cup to make a drink coffee every morning, which determines how to see that coffee cup that day.
So, if you want to make such things happen in architecture, do not make it immutable, so that the daily life in that architecture will be fun.
民藝には繊細さが無い、とした。
その辺、柳宗理ディレクションは民藝に繊細な部分を持ち込もうとした痕跡があり、端々に厚みを消す処理を施しているように思える。
繊細さは美術品のようであり、民藝品は美術品の対極にあり、繊細さを求めることは美術品を目指すことであり、民藝にとってはタブーなのだろう。
厚みの厚さは民藝の象徴であり、そこに、丈夫で、毎日の生活の中での使用に何十年と耐える、そこにものとしての価値と美がある、ことを現している。
だから、民藝品の美と美術品の美は違う、という解釈が、民藝に携わる人には成り立つし、成り立たないと都合が悪いのだろう、使う我々にとっては関係ないところで。
美は美で、美の根本は同じで、民藝品とか、美術品とか、の違いは一部のつくり手と売り手が意識しているだけの話。
あとちょっと、ほんのちょっと繊細ならば完璧、端が、先が、あと1mm、いやあと、0.5mm薄ければ、細ければ、言うことないものばかり。
それを学んだのは、柳宗理の作品を見て、日常使いしているからなんだけどなと、場末の呑み屋でホッピー呑みながら想う。
"Delicacy in folk art"
It is said that folk art has no delicacy.
In that area, Yanagi Sorihi has traces of trying to bring delicate parts into folk arts, and seems to be applying treatment to eliminate the thickness.
Delicateness seems to be a work of art, folk art is on the opposite side of artworks, seeking delicacy is aiming at art objects, and for folk arts it is taboo.
The thickness of the thickness is a symbol of folk art, and it is strong, it shows that there are values and beauty there as it can withstand decades for use in everyday life.
Therefore, the interpretation that the beauty of a folk art and the beauty of a work article are different for a person engaged in folk arts, and it is not convenient if it does not make it, it is not related to us.
Beauty is beauty, the fundamentals of beauty are the same, the difference between folk art items and art goods is only the story of some making mind and seller conscious.
After a while, perfect if slightly delicate, end, tip, 1 mm afterward, no more, 0.5 mm thin, if it is thin, nothing to say.
I learned it because I see Mr. Yoshinori's works and I use it everyday, but I think while swallowing Hoppy at the sweet shop at the end.
手づくりでも、手仕事の痕跡を残さずにものをつくることは可能だろう。繊細なものをつくろとすればする程、手仕事の痕跡は消したくなる。痕跡があると、そこに意識の引っ掛かりができ、繊細に見せたいのに、仕上げに余計な意味が生まれ、さらりと流れなくなる。
厚みが無いところには痕跡は残せないし、繊細に薄く見せたいとしたら、表面の仕上げに凹凸が無い方が良い。
そうなると、手仕事の痕跡を残すと繊細なものにはならないし、
そうすると、繊細なものには、その日の気分を投影できるような余地は無いことになる。
勝手なイメージだが、民藝品は、厚くて、凹凸があり、繊細では無い。
繊細だけれども、余地・余白があり、中庸であり、その日の気分を投影できるものは、やはり、仏像のお顔がすぐに思い浮かぶ。
ちょっと民藝とは違うところに、可能性が眠っているような気がしてきた。
"Feeling of delicacy"
Even with handmade it would be possible to make things without leaving traces of manual work. The more you make the delicate things, the more you want to erase the trace of handwork. If there is a trace, you can get stuck with consciousness there, and you want to show it delicately, an extra meaning is born in the finish, it will not flow any further.
Traces can not be left in places without thickness, and if you want to show delicately thinly, it is better that the surface finish has no irregularities.
Then, leaving traces of handicrafts will not be delicate,
Then, there is no room for delicate things to be able to project the mood of the day.
Though it is a selfish image, folk art is thick, has irregularities, it is not delicate.
Though it is delicate, there is room / margin, moderate, those that can project the mood of the day, the face of the Buddha statue immediately comes to mind.
In a place a bit different from folk art, the possibility seems to be asleep.
民藝に新たな可能性を感じる、とした。
ずっと玉子焼き器を眺めている、なぜこれが良いのか。ずっとコーヒーカップを眺めている、なぜこれにその日の気分を投影できるのか。
不揃いで、一定ではなく、たぶん意味があるのだろうが、それが装飾になる処理など、そのきちんとしていない様に惹かれるからか。
京都の北村一男さん作の銅製の玉子焼き器が良いのは、形と大きさ、スケールという幾何学的な秩序に、デザインと民藝の手仕事の痕跡があるから、もっと突き詰めると、形の比率、縦横の比率のバランスの良さ、全体の大きさがこれよりも大きくてもダメ、小さくてめダメ、絶妙な大きさで、縁の補強?リベット?のデザインが、シルバーと銅色のコントラストがアクセントで良く、持ち手が丸鋼で細くて良いが、もう少し幅が狭い方が全体の形が綺麗になるし、使いやすいのではと思うが、これはもしかしたら、実際に狭くしたら、わからない、これで良いのかもしれない。
この玉子焼き器に手仕事の痕跡が無くて、角とか、端々がきちんと綺麗に整形されていても良いと感じるのだろうか、手仕事の痕跡が無くても、その日の気分を投影できるのか。
手仕事の痕跡が無くても、大まかな幾何学的な秩序やデザインは変わらない、手仕事の痕跡もデザインの内と捉えることもできるが、手仕事の痕跡のみが幾何学的な秩序をほんのちょっとだけ乱し、この乱し具合が絶妙で、そこがその日の気分を投影できる余地かもしれない。
計算して手仕事の痕跡をつくることはできないかもしれないが、全く無くても成り立たないとしたら、ものづくりとは厄介なものだと、改めて思う。
"Traces of handicrafts"
He felt new possibilities for folk art.
I have been looking at the egg oven for a long time, why is this good? I am looking at a coffee cup all the time, why can I project the mood of the day to this?
It is irregular, not constant, probably meaningful, because it is attracted to not being properly decorated, such as processing to become decorative?
Kimoto's Kitamura Kazuo's worked egg baked goods is good because there are signs of design and folk handicrafts in the geometric order of shape and size, scale, so if you make a further break, shape Ratio, good balance of vertical and horizontal ratio, even if the size of the whole is larger than this, it is not good, it is not small, is not it exaggerated size, reinforcing the edge? rivet? Although the design of silver, copper contrast is good with accent, the handle can be thin with round steel, but the one with a slightly narrower width will make the whole shape beautiful and I think that it is easy to use, but this Perhaps, if actually narrowing down, I do not know, perhaps this is fine.
Is there any trace of handwork on this egg grill and does it feel that the corners or the edges are shaped properly neatly? Even if there is no trace of handwork, can you project the mood of the day?
Even without the trace of manual work, rough geometric order and design does not change, traces of manual work can be regarded as design, but only the trace of handicraft is merely a geometrical order It is just a bit disturbed, this disturbance is exquisite, and there may be room to be able to project the mood of that day.
Although it may not be possible to calculate and make traces of handicrafts, if it does not exist at all even without it, I think again that manufacturing is troublesome.
その人の気分を投影する余地をつくるには、ちょっとだけ幾何学的な秩序をつくり手が、無意識にでも、いじれば良い、それは民藝的なつくり方、とした。
毎朝、豆から挽いてコーヒーを淹れるのが日課で、コーヒーカップをその日の気分で選んでいる。
きっかけは、柳宗理がディレクションした因州中井窯と出西窯のコーヒーカップを複数手に入れたこと。色や形が違うカップだけれども、同じ色・形でも、微妙に大きさが違ったり、釉薬の乗りの違いから来る微妙な色の差に、その日の自分の気分を乗せて、毎朝、どれにしようかと楽しみながら選んでいる。
そして、偶然にも、この因州中井窯と出西窯は民藝を代表する陶器の窯元である。
その日の気分によって違って見える建築をつくれないかと考えはじめるきっかけは、この毎朝のコーヒーカップ選び、
そして、民藝は、以前話題にしたブリコラージュにもつながる。はじめと終わりが見事につながり、新たに民藝に興味が湧いた。
今、民藝品を見ようとするならば、まずは駒場にある日本民藝館に行くが、ガラスケースに入った民藝品は美術品のようで、なんかしっくりとこない。
日本民藝館で前に、あまりにも形と大きさが秀逸だったので、銅製の玉子焼き器を購入したことがあるが、それはいわゆる民藝品の域を超えた、しかし、美術品では無く実用品としての美しさがあった。
今、民藝に可能性を感じるのは、そもそも当たり前のことかもしれないけれど、まだまだ掘り下げる余地があることがわかった。
"I feel new possibilities in folk art"
In order to create room for projecting the mood of that person, we made a little geometric order, hands, unconsciously, even if we do not know how to make it a folk artistic way.
Every morning, it is the daily routine to grind coffee from the beans and chose a coffee cup for the day 's mood.
The trigger was that you got multiple coffee cups of Genju Nakai kiln and Izuno kiln that Mr. Yanagi directed. Even though it is a cup with different colors and shapes, even in the same color and shape, it is slightly different in size and slight difference in color that comes from the difference in riding glaze, putting your own mood on the day, every morning I am picking it while having fun.
And, by chance, this Nazu Nakai kiln and Izune kiln are pottery pottery representing the folk art.
The chance to start thinking about whether you can create a building that looks different by the mood of the day is to choose this morning coffee cup,
And folk art also leads to bricolage which was talked about before. Beginning and end were connected beautifully, and new interests appeared in folk art.
Now, if you are going to see the folk art, I will go to the Japanese art museum in Komaba first, but the items in the glass case are like works of art, they do not come nicely.
Before the Nippon Municipal Hall, the form and size were too excellent, I purchased a copper egg oven, which is beyond the area of so-called folk art, but it is not a work of art There was beauty as a practical item.
Now, feeling the possibility of folk art may be a matter of course in the first place, but I found that there is still room to dig down.
去年、東京ドームで開催されたテーブル・ウェア フェスティバルの有田焼ブースで購入した急須、急須好きな私が今一番日常使いしている急須で、その時、湯呑をなぜセットで購入しなかったかと悔いる日々を送っていたが、
先日、今年のテーブル・ウェア フェスティバル、まず最初に有田焼ブースに行き、その同じ急須を見つけ、湯呑を探したが無い、近くにいた窯元の方に尋ねたら、今年は持って来ていない、とのこと。
「去年、急須を買おうかどうか悩まれており、でも最後に買われて行った方ですよね」
挙動不審だったのか、完全に顔を覚えられている。
ただ、そうなると、話が早い、こちらの熱意は伝わるかもしれないので、
「どうにか湯呑を購入する方法はないですか、そちらの窯元のHPを見ても、この商品は掲載されていないようなので」
と食い下がると、この窯元の方、とても良い方で、フェスティバル終了後、メールで画像を送ってくれて、茶托もあるので、気に入れば、購入して下さい、と対応してくれた。少量なのに、ありがたい話です。
連絡先を教えるために名刺交換をすると、窯元の社長さん、また、有田に行く時は、窯元を見学させて下さい、とお願いしたら、快く受け入れてくれました。
去年は茶托を見ていませんが、画像だけで気に入ってしまい、組みで購入、打合せ時にクライアントへ淹れるお茶は、この湯呑と茶托で出そう。
今年もテーブルウェア・フェスティバルに行ってみた。器やカトラリーが大好きなので、行くと陶磁器、漆器、ガラス食器、銀食器などやアンティークも、主に日本のものだが、海外のものも見られるので、知り合いもいるし、入場券も3回分もらったし、東京ドームで大好きなもの浸れるので、1日時間を取って出掛けてみた。
去年も行ったが、毎年この時期に行われるイベントで、出店しているお店も場所も去年とほとんど変わらなかったので、去年ほど時間がかからずに見て回ることができた、というか、去年行ってもう一度行ってみたいお店だけ、また去年は購入しなかったものを今年購入するために、そうしたら、挙動不審だったのか、顔を覚えられていて、その場に品物は無かったが、後で連絡をくれることを約束して名刺交換、その窯元に機会があれば見学しに行くことになった。
販売するためのお店がたくさん出店しているが、メインイベントの1つにテーブルウェア・コーディネート、テーブルウェア、器のコンテストがある。公募型のコンテストで、テーブルウェアという広い縛りなので、その表現に使用する素材は、陶磁器、漆器、ガラス食器、木や銀の食器など様々で、それを見に行くだけでも面白いし、たくさんの人が興味を持って見ていたが、ひとつ不思議というか、腑に落ちない点があった、触れないのだ。
展示に触れないのは当たり前なのかもしれないが、テーブルウェアは食卓に食べ物や飲み物などを供するための食器類なので、実際に食べ物や飲み物を供する必要は無いのかもしれないが、食器やコーディネートを触らないでわかるのだろうか、いやわかるはずが無い、というストーリーにしようと思っていたのだが、そう言えば、建築のコンペではまだ影も形もなく、プレゼン資料だけで判断するな、もっと言えば、普段の建築設計の場でも、クライアントに説明する時だってそうだなと思い、困った。
手触りなどの感触だってデザインの一部で大事ではないか、だから、触れないのはおかしい、と結ぶはずができなくなった。
ただ、建築は規模も大きくお金もかかるので、そう簡単には実物をつくれないから、やむを得ないと言い訳をした上で、審査の時にどうだかはわからないが、テーブルウェアくらいの大きさであれば、手で持った時の感触や唇に当てた時の感触などは、とても重要な気がするし、もしかしたら、その感触だけで1つのテーブルウェアがデザインでき、つくれるかもしれない。
展示されているテーブルウェアに触れなければ、見た目で判断するしかなく、それでは感触が大事だと考える作者がいたら、自分の作品の良さが伝わらない。
展示だからにせよ、触れないのは、作者にとっても、見る側にとってもつまらなくて不幸なことのように思うし、見た目やデザインの魅力の裏には感触があり、それがわかることも見る側の技量の1つなので、見る側もそれで問われていることになる。
"Touch that does not touch"
I went to the tableware festival again this year. As I love vessels and cutlery, when I go there, I go to china, lacquerware, glass dishes, silverware and antiques, mainly in Japan, but also overseas, so I got acquainted and I got three admission tickets Then, I will immerse my favorite things at the Tokyo Dome, so I took a day to go and went out.
Although I went last year, it is an event to be held at this time every year, the shops and places that are open are almost the same as last year, so I was able to look around without last time as much as last year , Only the shops that I would like to visit last year and want to visit again last year, in order to buy things I did not buy this year, if I did so, I was remembered my behavior, so I did not have any items on the spot I promised to contact you later, I exchanged business cards, I decided to visit the pottery if I had opportunity.
There are many stores open for sale, but one of the main events is tableware coordination, tableware, container contest. Because it is a public contest contest, because it is a wide binding of table wear, the material used for that expression is various such as ceramics, lacquerware, glassware, glassware, wood and silver dishes etc, it is interesting only to go to see it, Although I was watching with interest, it was one wonder, or there was a point that I could not understand, I did not touch it.
Although it may be natural to not touch the exhibition, tableware is a tableware to serve food and drinks etc at the table, so it may not be necessary to actually supply food and drink, but dishes and coordination I was planning to make it a story that I can understand without touching it, but if you say so, in the competition of architecture, there is no shadow and shape, do not judge only with presentation materials, say more I was in trouble because I thought it was the case even in the usual architectural design places, even when explaining to clients.
Even feeling such as feeling is important in a part of the design, so it is strange not to touch, it can not be connected with.
However, since construction costs large scale money, it is not easy to make real thing so easily, so I do not know how it is at the time of appraisal after excusing it is inevitable, but if it is about table wear, I feel that when I hold it with my hand and the touch when I touch the lips, it feels very important and perhaps I can design one tableware with that feel alone and make it.
If you do not touch the exhibited tableware, you only have to judge by appearance, then if the author thinks that the feel is important, the goodness of one's work will not be conveyed.
Whatever the exhibit, I do not touch it, it seems like boring and unfortunate for both the author and the viewer, there is a feeling behind the attractiveness of the appearance and design, and also the things that you can see As it is one of the skills, the viewer is also asked by that.
ちょっと気になる言葉がある「建築性」。それが建築たる所以みたいなものと捉えているが、ついその「建築性」が疎かになってしまうような気がする。
おかしな話だが、建築性が無くても建築は成り立つ。極端に言えば、機能を満たし、法規を守れば、建築はできてしまう、そのような建築がほとんどだ。
例えば、建築性とは「不完全性とアクティビティー」「気分と感触」がいま、あるのではないかと考えている。
無くても良いとは思えず、あった方が良いの当たり前のことと捉えている、それが人にとって。
この建築性を磨き、建築として実存させることにいま一番時間を割いている。
"Time now"
There is a word which is a bit a little "Building property". It seems that it is like the thing that it is built, but it seems that its "architecturality" becomes unclear.
Although it is a funny story, building is established even if there is no building ability. In extreme terms, buildings can be built if they satisfy the function and keeping the regulations, such constructions are mostly.
For example, I believe that "building imperfections" have "imperfections and activities", "moods and feelings", and so on.
I do not think that it is not necessary, and I think that there was better being a good one, that is for people.
I am taking the most time to refine this architectural nature and make it exist as a building.
ボリュームチェックをする。それはその敷地にどのくらいの規模のものが建築できるのかを確認するためだが、同時にそれは集合住宅の場合、最大戸数を確認する、収支計画を立案する、ための元資料にもなる。
昔いた設計事務所では、もう25年くらい前の話だが、不動産屋から敷地図がfaxで送られてくると、社長がボリュームチェックをして、その敷地に対する計画案を作成し、それは収支計画用の計画案なので、最大戸数を確保したものをまた送り返していた。
その場合、建築基準法や条例などを法規を満たすのは当たり前のことだが、とにかく知りたい情報はその敷地にどれだけの規模の、戸数の集合住宅ができるか、だったので、デザインは二の次、付け足すもの扱いで、とりあえず、平面図だけあればよく、それで収支計画が立案できるので、実際に計画がスタートして外観を考える時にデザインが入ってくるようだった。
そのデザインや計画案作成の態度にはなじめず、でも大概の設計事務所はそうなのだろうと想像しながら、私が設計担当した最初の建築は、その社長が作成した計画案からはじまった集合住宅だった。だから、私が担当としてデザインできる範疇は外観くらいしかなく、それはそれで重要なのだが、プランから考えなければ、外観だけ考えても意味は無いのでは、と思いながら仕事をしていたのを思い出した。
なぜ思い出したかというと、今、そうだから、とりあえず、収支計画用の最大戸数を確保した計画案を作成し、これからどう進めていくかと考えているところだから。
ただ違うのは、この計画案はあくまでも収支計画用で、ボリュームチェック用で、アタリの図面で、ここから全く違うものをはじめからデザインしはじめる。
ところが、この計画案が結構強力で、引きづられてしまう、自分で作成したのだが、厄介なしろものだ。
"Volume check"
Perform volume check. It is to confirm how much can be built on the premises, but at the same time it is also the original source for planning the income and expenditure plan to confirm the maximum number of houses in the case of multi-family houses.
In the former design office, about 25 years ago, when the real estate agent sent the site map at fax, the president made a volume check and created a plan for the site, which is a balance plan It was a plan for use, so I sent back the one that secured the maximum number.
In that case, it is natural to satisfy the Building Standards Law and ordinances etc, but since the information that you want to know is just how large, multi-united housing can be built on the premises, design is secondary, It is treated as a thing to add, in the meantime, it is only necessary to have a plan view, so you can plan the income and expenditure plan, so it seems that the design will come in when you plan the actual planning and consider the appearance.
While imagining the design and the planning draft attitude, but imagining that most of the design office would be, the first building I was in charge of designing was a collective housing that started with the plan drafted by the president was. So, the category that I can design as a responsible person is only about the appearance, which is important, so I thought that if I did not think about it from the plan, I thought that it was meaningless to think only about the exterior, I remembered that I was working .
I remember why I remember now that I am thinking about how to proceed from now on, because I am planning a plan that secures the maximum number of households for income and expenditure planning.
The only difference is that this plan is for balance planning only, for volume checks, Atari's drawings, beginning to design completely different things from here.
However, this plan was quite powerful and attracted, created by myself, but a troublesome one.
以前に、建築に感触を取り込みために「見立て」を考え、建築に気分を取り込むために「追従する」建築で差異を考えた。いずれも、納得して建築に取り込める手法だと考えていたが、違う角度から再度、感触や気分を建築に取り込む方法を考えてみたいと思った。
そのきっかけは、今制作中の輪島塗のフリーカップ。もの自体が感触と気分を取り込む媒介になるのならば、建築でも可能なのではないか、と思ったから。
建築を空間として扱うから全体のボリュームが最重要になるが、建築を細部のものの集合体として扱えば、まず細部のもの自体がどうあるか、からはじまるので、感触やその時の人の気分を反映しやすく、その感触や気分を伴ったまま、最終的に空間が出来上がるのではないか、と考えた。
人を中心に据えて、人に密着した周辺からはじまり、その時々の人の気分を反映することが可能なものを細部から感触を含めつくり出しながら、どんどん同心円状に広がっていき、空間に仕立てていくイメージ。
イメージがまずできないと、実際のものづくりはできない、全てのイメージでなくても良いが、はじめの取っ掛かりや、大まかで良いから骨子みたいなものは欲しいが、それが段々と揃ってきたような気がする。
"Image to tailor the space"
In the past, I thought about differences in architecture "to follow" in order to capture the mood in buildings, considering "looking" to incorporate the feeling into architecture. Both thought that it was a method that I could consent to incorporate into architecture, but from another angle I wanted to think about a way to incorporate feel and mood into architecture again.
The trigger is a free cup of Wajima coat under construction now. Because I thought that it might be possible in architecture as long as things themselves become intermediaries for taking in feel and mood.
The whole volume becomes the most important because it treats architecture as space, but when treating the building as a collection of details, it first starts from how the detail itself is, so reflects the feel and the mood of the person at that time I thought that it would be easy to do, with the feel and mood accompanied, the space would eventually be finished.
Starting from the periphery that is close to people, starting from the surroundings close to people, reflecting the feeling of the people from time to time, create things including details from the details, spread more and more concentrically and tailor it to the space Some image.
If you can not do an image first, you can not make actual manufacturing, not all images, but I want something like a gist of a first bargain, because it is rough and good, but it seems that it has gotten step by step I will do.
内側からボコボコと必要な場所を広げていく感じで、人を中心に、人の周辺からはじめていくという空間のつくり方があると思う。
今日行ったオープンハウスでの説明によると、2階建ての2階の個室の天井の形を決めて、その形のまま屋根したとのこと。屋根を決めて天井が決めるのでは無くて、室内の天井の形を先にデザインし決めてから、その形の裏返しが屋根の形になる。外から見ると屋根の形で室内の天井の形がわかる。室内の天井をデザインしたら、同時に外観の屋根と室内空間もデザインされる、室内天井をデザインする時は当然、人から派生する事柄を手掛りにするだろうから、そこに人も絡んでくる、とても秀逸だと思った。
ボリュームチェックがあり、そこから細部に向かっていくやり方、ボリュームを決めれば、同時に空間や細部まで決まり、人が絡んでくる手法もあるだろうし、それはそれで素晴らしいと思うが、どうしても人が最後というか、例え最後ではなく途中に人が絡んでくることもあるが、人からはじまる感じが、人の周辺からはじめていく空間のつくり方よりは薄いような気がする。
どうして、人を中心に、人の周辺からはじめていく空間のつくり方が気になるのかと言うと、建築にもっと感触とか、気分とかを取り込みたいから。人を中心に据えてはじめた方がより感触や気分を建築に取り込めるのではないか、という勘からです。
"There are people, I feel, I have a feel"
I think that there is a way to create a space where people start from the periphery of people, with the feeling of spreading the necessary places with Bocoboko from the inside.
According to the explanation in the open house that I went today, I decided the shape of the ceiling of the 2nd floor upstairs private room, and said that he roofed in that shape. It is not to decide the roof and the ceiling to be decided, after designing and determining the shape of the ceiling in the room, the flip of that shape becomes the shape of the roof. When seen from the outside, you can see the shape of the ceiling in the room in the form of a roof. When designing the ceiling in the room, the roof of the exterior and the interior space are also designed at the same time, when designing the indoor ceiling, naturally it will clue the things derived from people, so people will also get involved there I thought it was excellent.
There is a volume check, there is a way that people decide at the same time as much as space and details, if there is a way to go to the details from there, deciding the volume, there is also a method involving people, and that is wonderful, but I guess the person is the last Even though some people are involved on the way instead of the last one, I feel that the feeling that people start with is thinner than the way I start from people's surroundings.
Why do you care about how to create a space to start from people's surroundings, mainly because people want to capture more feel and feelings in architecture. It is from the intuition that people who started putting them mainly can get more feel and mood in building.
以前に、人がいて、体を覆う衣服があり、体を支える椅子があり、食事をするためのテーブルがあり、テーブルの上には人が使う食器やカトラリーがあり、そのテーブルを照らす灯りがあり、そのテーブルや椅子や人を囲むように、床や壁や天井があり空間ができ、それが部屋と呼ばれ、部屋がいくつも連なり、家という建築ができる、ようなつくり方がしてみたい、とした。
たぶん、今の設計に対する違和感は全てここに集約されるような気がする。そう思うと、とてもすっきりとした気分になった。
ただ、果たして、このようなつくり方が現実実際にできるのだろうか。
どうしても、実際に敷地に建築を設計しはじめる時にはボリュームチェックから入る。ボリュームチェックとは、その敷地にかかる法規を調査し、どのくらいの規模まで建築可能かをみること。
ボリューム、イコール、空間では無いが、空間の大枠を決めることから考えはじめてしまうし、そこが無いと最初の事業計画が立案できないだろう。
だから、ボリュームチェックまではして、そこから、人の周辺から広げていくやり方をすれば良いのかもしれないが、その時に結局、最終的にはボリュームチェックの結果に引きづられてしまうような気がして、はじめの一歩が踏み出せないでいる。
"Hajime no Ippo"
There used to be people, there are clothes that cover the body, there is a chair that supports the body, there is a table to eat, there are tableware and cutlery used by people on the table, the light that illuminates the table There is a floor, a wall and a ceiling so that it surrounds the table, the chair, and the person, and a space is made, it is called a room, a number of rooms are connected, we want to try to make such a way that we can build a house did.
Perhaps, I feel that all the discomfort to the current design is concentrated here. I thought so, I felt very refreshing.
But I wonder if we can actually do this in reality.
By all means, when you actually start to design the building on the premises, you enter through the volume check. Volume check is to investigate the laws concerning the premises and see how big it can be built.
Although it is not volume, equal, space, I will start thinking about deciding on the space of space and if there is not there, I can not plan the first business plan.
So it may be good to do a volume check and then spread from people's surroundings, but at the time it will eventually end up with the result of the volume check I feel like I can not take the first steps.
デザインするのが好きで、ものをつくるのが好きだから、それを死ぬまでやり続けたいと、その環境づくりも含めて、今、奔走しているところで、輪島塗のフリーカップづくりは、塗りの見本待ちで、それが楽しみでしょうがなく、ここまで来ると、何をデザインするか、何をつくりたいか、また、どうしたら出来上がるのか、が明確になっているので楽しくて、待ち遠しくて、早くそのカップでコーヒーが飲みたくて仕方がない。
建築ももちろん、ものづくりなのだが、建築と建築以外では同じものづくりでも違うような感覚がある。
端的に言うと、ものそのものをつくるのか、空間をつくるのか、の違いか。建築でも細部に至る時はものそのものに向き合い、ものそのものをつくるが、最初は空間から考えるのが一般的で、大きな入れ物から考えはじめて、段々と中身に何を入れようか、中身のつくりをどうしようかと考えて細部に至る。それはインテリアデザインでも同じだが、建築はそのインテリアデザインをする空間そのものも一から考えるので、より空間をつくる思考が強くなる。
もっと違う言い方をすると、人がデザインされたものを全て操れるのか、人がデザインの一部なのか、の違いか。建築では、空間は人を包み込み、人はその空間の一部という扱いになるが、建築以外では、人から離れたところにものが実存し、そのものを人が全て操るようにデザインされる。
輪島塗のフリーカップづくりをはじめてから、この当たり前のような違いが、とても大きな違いのように感じるようになっており、それは、もしかしたら自分が指向している建築のつくり方は、空間からはじめるのでは無くて、ものそのものからはじめることではないか、とちょっとどこかで思うようになっている。
人がいて、体を覆う衣服があり、体を支える椅子があり、食事をするためのテーブルがあり、テーブルの上には人が使う食器やカトラリーがあり、そのテーブルを照らす灯りがあり、そのテーブルや椅子や人を囲むように、床や壁や天井があり空間ができ、それが部屋と呼ばれ、部屋がいくつも連なり、家という建築ができる、ようなつくり方がしてみたい。
考えてみれば、衣服以外は今すぐにでもつくることができる。
"How to make architecture"
I like to design and I like to make things, so I want to keep doing it until I die, and now I'm busy making the environment, Wajima painted free cup making is waiting for samples of paint So, it can not be helped fun, and as soon as you come this far, it's fun to see what you design, what you want to make, and how to make it, so it's fun, I can hardly wait, in that cup There is no point in wanting to drink coffee.
Not only building but also manufacturing, but there is a different feeling in building the same thing outside of architecture and architecture.
To put it briefly, is it the difference between making things themselves or creating space? Even in architecture, when it reaches the details, it faces the thing itself and makes things themselves, but at first it is common to think from the space, starting with thinking from a big container, what should we put in contents, and how to make contents I think to it and it comes down to details. Although it is the same in interior design, architecture thinks space itself to do its interior design from scratch, so thinking to create more space becomes stronger.
Writing in a different way of speaking, is it different whether people can manipulate everything that was designed or whether people are parts of design. In architecture, space envelops people, treats a person as a part of the space, but outside the building, things are existed far away from people and designed to manipulate them all.
The difference like this is beginning to feel like a very big difference since I started making a free cup of Wajima coat, which is probably how I'm pointing my way of building a building from the space It is not at all, it is supposed to start somewhere somewhere, starting with things themselves.
There are people, there are clothes that cover the body, there is a chair that supports the body, there is a table to eat, there are tableware and cutlery for people to use on the table, there is a light that illuminates the table There is a floor, a wall, a ceiling and surrounding a table, a chair and a person, a space is made, it is called a room, a number of rooms are connected, we want to try to make such a construction that a house can be done.
If I think about it, I can make anything but clothes right now.
気分というのはいい加減なもので、さっきまでイライラしていても、誰かと話すとすっかり忘れて元に戻ったり、落ち込んでいても、美味しいものを食べたら、ちょっとだけ前向きになれたり、ダラダラなのがシャワーを浴びたら、何かやる気になったり、逆に、朝起きて天気が良いと、それだけで楽しい気分になったり。
気分がコロコロ変わることに対しては良いイメージは無く、気分に左右されないようにして、きちんとしなきゃ、なんて思ったりする。
コロコロ変わるところを言えば、確かに、気分とはいい加減なものだが、その気分を感じる裏には、その気分にさせる、もしかしたら自分でもはっきりと認識できていない、何か要因がある訳で、そう考えると、気分はもしかしたら、その人自身が持っている膨大なデータベースに基づいたシグナルかもしれない。
そうなると、気分がコロコロ変わるということは、場面場面に応じて、自身が持っているデータベースを活かしていることになり、かえって気分がコロコロ変わる方が自然なことのような気がするし、決して悪いことでは無いような気がする。
むしろ、気分に変化が無い方がその場その場にきちんと対応していないような気がして、それでも良いのかもしれないが、何かもったいないというか、今生きていることを肯定していないような気がして。
だからか、なるべく気分の変化みたいなことをそのまま生活の中に取り込みたいと思っていて、簡単なことでも、毎朝飲むコーヒーを淹れるカップをその日の気分で選んだりすることでも、とても大事なことのように思っている。
気分の変化に建築は応えてくれるのかな、と気がつくと考えている。建築は強固だ。
室内の模様変えなんてことを気分ですれば、見える範囲の室内の景色は変わるから、まあ、それで。でも、建築が変わる訳では無いから、固いし、動かないし、動かせないから、気分の変化に対応できない建築はつまらないなと、コーヒーカップは気分の変化に応えてくれるのに。
"Corochoric mood"
Feeling is sloppy, even if you are irritated a while ago, if you talk to someone you forgot to completely forgotten and return to the original, even if you are depressed, if you eat delicious things, you can get a little forward or you are dull When I take a shower, I feel motivated something, on the contrary, when I get up in the morning and the weather is good, it makes me feel happy alone.
There is no good image for the change in the mood, so I try not to be influenced by the mood, and I do not think it is proper.
Corocoro When speaking of the place to change, indeed, the mood is irresponsible, but behind the feeling of that feeling makes me feel that, perhaps because I do not recognize myself clearly, there are some factors, If you think so, the mood may be a signal based on the huge database that person himself possesses.
Then, the fact that the mood changes, depending on the situation scene, it makes use of the database that it owns, and it seems that it is more natural that the person who changes mood is more natural, and it is never bad It seems that it is not a thing.
Rather, it seems that people who do not have a change in their mood properly correspond to the spot on the spot, but it may still be good, but something is a waste or I am not affirming that I am alive now Like I thought.
So, I think that I want to incorporate things like a change of mood as much as possible into life, and even if it is easy, even if you choose a cup that makes coffee to drink every morning by the mood of the day, it is very important thing I think like.
I believe that architecture will respond to the change of mood. Architecture is solid.
If I feel like changing indoor patterns, the scenery in the room in the visible range will change, well, so. But, because the construction is not a translation, it is hard, does not move, can not move, so the architecture that can not respond to the change of mood is boring, the coffee cup will respond to the change of mood.
その日の気分で変えたいのです。その日の気分に左右されたい。
毎朝、豆から挽いてコーヒーを淹れますが、コーヒー豆は、コーヒーの味は、お気に入りがあるので、酸味が強くて、苦味が少ない、しっかりした味が好みなので、豆は決まってしまうが、コーヒーカップは毎朝気分で違うものを選びたいのです。
ゲン担ぎはしないので、今日は絶対結果を出したい日だから、このコーヒーカップにするとか、そんなことはしないけれど、食器棚を開け閉めしながら、今朝はどれにしようかな、今日の気分はこれかな、とやりたい。
コーヒーカップは、人より小さいし、簡単に動かせるし、いくつも用意することができるから、気分で選ぶことが容易にできる。
建築は、コーヒーカップと真逆、人より大きいし、絶対に動かないし、いくつも用意できないから、その日の気分で、今朝はどれにしようかな、今日の気分はこれかな、とできない、できないはず、できる人もいるか、大体の人には無理。
建築自体は動かせないから、変えられないから、選べないならば、その中で人が気分で動いて場所を変えればよいか。都市の中では、よくあることで、今朝はこのカフェ、昨日はあそこだったとか。大きな建築ならば、それも可能。
例えば、狭小の敷地で、ペンシル状に10階建て位のビルを建て、各階1部屋で、そうすると、1階と10階では見える景色が全然違い、各階それぞれでも景色が違うはずたがら、その日の気分で、今日は3階、昨日は5階にしたな、週末は10階にするか、なんて選べたら、何かいい、昔、このような計画をした人がいて、何て素敵な考え方なんだと感心したことがあった。
気分で場所を変えるのは、都市の中でも、建築の中でも可能だから、それでも十分に気分に左右されるのだが、ちょっと、もうちょっと、コーヒーカップを気分で選ぶように、建築に気分を持ち込み、気分で建築が変わらないかな。
"Bring your mood"
I want to change it in the mood of the day. I want to be influenced by the mood of the day.
Every morning, we grind coffee from beans, but coffee beans, coffee taste has favorite, so we prefer sour taste, little bitterness, firm taste, so beans will be decided, I want to choose a different coffee cup every morning.
Because I do not carry gen, so today is absolutely a day I want to put out a result, I do not do such a coffee cup, I do not do such a thing, but I will do this morning while opening and closing the cupboard, I feel like this today I want to do it.
Coffee cups are smaller than people and can be moved easily, and as many can be prepared, it is easy to choose by mood.
Architecture is bigger than a cup of coffee, is bigger than a person, absolutely does not move and can not prepare anything, so I feel like that day, I will do this morning, I can not do today, I can not, can not be, Some people can do it, impossible for most people.
Since the building itself can not be moved, it can not be changed, so if you can not choose it, why should a person move in a mood and change places? It is common in the city that this cafe this morning, yesterday was over there. If it is a big building it is also possible.
For example, in a small site, building a ten-story building in a pencil shape, in each room one floor, then the view that can be seen on the first floor and the tenth floor is totally different, the scenery must be different on each floor, the mood of the day So, if you could choose the third floor today, yesterday to the 5th floor, weekend to the 10th floor, whatever you choose, something good, there was a person who had done such a plan in the past, what a wonderful way of thinking I was impressed.
Changing the place by mood is possible even in the city and in the architecture, so still it depends on the mood enough, but a little more, just a little bit more, to bring the mood to the building to bring the mood like a coffee cup feeling, feeling I guess the architecture will not change.
道はコンテクストか。直接道を扱うのは気が引ける。
法規制も敷地のコンテクストならば、すでにボリュームチェックで道を直接的に扱っているから、ただ、道はまず永遠に道のままだろう、そこには惹かれる。
空地ということであれば、道も空地、子供の頃、空地がたくさんあり、勝手に入って遊び場としていたが、ある日突然に柵ができ入れなくてなり、子供ながらにそんなことは予測していて、ここがだめになったから、あっちの空地とか、今日はここで、ちょっと遠征してあそことか、流れのように転々とするのが遊びのセンスみたいなことだったから、ある日突然使えなくなっても何とも思わなかったが、常に空いていること、隙間、子供は隙間好きだから、が無性に惹かれた。
だから、道は延々と続く遊び場だった。あの道、この道、あそこの道と道の違いが遊びの違いだった、この遊びをするならば、この広さが無いと、車があまり来ない所でないと、あそこの道は疲れたら居心地のいい階段があるとか。
道をコンテクストと扱いたい。扱うとしたらどうするか、空か、空間か、坂道の方が角度があるから特長があるな、とか。
そもそも建築を行う敷地は道路に接していなければならない。これを改めて考えてみると面白いかもしれない。敷地単体では存在できないということ、必ず道路とセットになる、その道路には手をつけることができない。そして、その道路は延々と続き、常にからっぽの空間のままである。
道は上を塞いだら道でなくなるのか、道たる所以の逆がパーソナルスペースか。道の上を木の枝で塞いだだけで素敵な空間にはなるけれど。
"Way is attracted"
Is the road a context? It is not easy to handle direct roads.
If the regulation is also the context of the premises, we already deal directly with the road by volume check, so the road will remain forever for the first time, we will be attracted to it.
If it is an open space, the road was also open space, when I was a child, there were plenty of open spaces, and I decided to make it a playground without permission, but one day I suddenly did not have a fence, and while I am a kid I predicted such a thing So, as this place was useless, it was like a sense of play to topple like flowing over there a little expedition here and today, sometimes it is not possible to use it suddenly I also did not think anything, but I was always attracted because it is always vacant, gaps, children like gaps.
That's why the road was an endless playground. That road, the road, the difference between the road and the road there was a difference in play, if you play this, if there is not this area, if the car does not come so often, if the road over there is comfortable There are good stairs of the place.
I want to treat the road as a context. If it is dealt with, what to do, sky, space, on the slope are angles, so there are features, for example.
In the first place the site to be built must be in contact with the road. It may be fun to think about this again. It can not exist on the site alone, it will definitely become a set with the road, you can not put a hand on that road. And the road continues indefinitely, always being an empty space.
Will the road get out of the way after closing the top, or the reverse of the way is a personal space? Although it becomes a nice space just by closing the top of the way with branches of trees.
敷地の文脈/コンテクストとして、敷地周辺の秩序を取り出して考えたいとしたら、秩序とは何なのか?
周辺の建物の高さ、外壁の色、窓の位置、屋根の形、建物の向き、敷地の大きさ、建物の大きさ、混沌具合、玄関の位置、匂い、法規制など、目で見て確認できるものや五感で感じることなどか。
これらは長年、敷地周辺の地域で形成されてきた暗黙のコード、ルールみたいなものか。
これらのコンテクストと呼ばれる秩序の中から、不完全性をつくるために、実体としても、概念としても、必要なものを都合よく抽出してきて、組み合わせるのか、秩序を明示し、ただそれは、その敷地周辺の地域で完全に整っている秩序だと思われるものでないと。
まず完全なものがあり、それを崩すことで不完全性を得ようとするならば、その敷地周辺の地域で完全に整っている秩序を抽出しないといけない。
そうすれば、実体としての不完全性を獲得するのは容易にできそうな気がする。完全な秩序と対比して目で見てはっきりと不完全とわかるようにすれば良いのだから。
概念としての不完全性は、人が頭の中で想うこと、感じることだとして、それは、その敷地周辺の完全な秩序を頭の中でわかっていることが前提、暗黙知と言うべきものか、なので、誰もが認識している秩序を抽出しないと、これがこじつけで、わかりづらいとだめかもしれない、アクティビティーを生むことができないかもしれない。
いまひとつスッキリしないのは、まず完全なものがあり、それを崩すことで不完全性を得ることで、本当にアクティビティーが発生するかということ。
まず完全なものから入るのは、わかりやすくて、やりやすいのだが、不完全なものをはじめからつくり出していくことができるのではないか、その方がアクティビティーがより発生しやすいのではないか、と頭の片隅で思ってしまう。
"Perfect Order"
If we wanted to consider the order around the site as the context / context of the site, what is order?
The height of the surrounding building, the color of the exterior wall, the position of the window, the shape of the roof, the direction of the building, the size of the site, the size of the building, the state of chaotic, the position of the entrance, the smell, regulations etc Do you know what you can check and feel with five senses?
These are like an implicit code or rule that has been formed in the area around the site for many years.
From the order called these contexts, in order to create incompleteness, as an entity as well as a concept, we conveniently extract what we need and combine, explicitly state the order, but that is only around the site I think that it seems to be an order that is perfectly arranged in the region of.
First of all, if there is perfect thing and trying to get imperfections by breaking it, we need to extract the order that is perfectly arranged in the area around the site.
Then, it seems easy to obtain incompleteness as entity. Because it is good to see clearly incomplete by visually contrasting with perfect order.
As incompleteness as a concept is what people think and feel in their minds, it is based on the premise that the complete order around the site is known in the mind, is it to say as tacit knowledge , So if you do not extract the order that everyone is aware of, this may be difficult to understand, it may not be easy to understand, it may not be able to produce an activity.
The thing that is not refreshing at first is that there is perfect thing first, and getting incompleteness by breaking it is really how the activity will occur.
It is easy to understand and easy to enter from the perfect one, but it seems that whether incomplete things can be created from the beginning, that the activity is more likely to occur, I think at one corner of my head.
ずっと、集まって住むことと、敷地の文脈/コンテクストと、アクティビティーと、秩序と、パーソナルスペースについて考えている。
ひとりでは無くて、家族だけでは無くて、シェアする訳でも無くて、ただ集まって住む、要するに、集合住宅が良いところや、その暮らしの方が楽しいと思えることや、事業者側のメリットではなくて、住む側からのメリットというべきことなのか、
それが敷地の文脈/コンテクストと関連して、そこでしかできない集住の仕方や、敷地の文脈のありようみたいなものが直接集住の仕方を決めてしまうようなことが起きて、
その時に自然発生的にアクティビティーが生まれ、そのアクティビティーに複雑さがあるから、
そのおかげでオープンなパーソナルスペースが容易にあちこちに形成され、
そのオープンな感じが、ゆるやかで、おおらかな秩序を建築に与え、
その建築があるおかげで、その周りが何となくいい雰囲気になる、
ようなことになるためには、
とここまで書いて、ひとつの建築が思い浮かんだ。
やはり、あの建築は名作だ。
"Architectural aiming aim aim vol.1"
I'm thinking about living and living together, the context / context of the site, activities, order and personal space.
It is not alone, it is not just a family, it is not a reason to share it, I just gather and live, in short, it is not a merit of the business side that things that collective houses are good and those who think that their living is fun Whether it is a merit from the living side,
As it relates to the context / context of the premises, what kind of collections can only be done there and things like what seems to be the context of the premises decide how to collect dwells,
At that time spontaneous activity is born and its activity is complex,
Thanks to that, an open personal space is easily formed here and there,
The open feeling gives the building a gentle and extraordinary order,
Thanks to its architecture, its surroundings become somewhat nice atmosphere,
In order to be like this,
And I wrote so far, one architecture came to mind.
After all, that architecture is a masterpiece.
なるほど、混在した街、カオスの方が賑わうは、ただ単にたくさんのアクティビティーが発生するだけでなく、オープンなパーソナルスペースが形成できるからにもよる。
そうすると、治安やゴミやインフラなどの問題が解決できれば、カオス状態の都市の方がいろいろなアクティビティーがあって楽しいだろう。
ただ、そういう都市は自然とは対極になるので、いくら公園などをつくり自然を持ち込んでも、それはつくられた自然だから、人工物と大差無い。
そうしたカオス状態の都市は面白いかもしれないが、私などは自然の中にいるよりも落ち着くと思うが、やはり、自然の真っ只中に行きたい人もいるだろう。
都市が一極集中してカオス状態になれば、当然その反動で、自然の中に行きたくなる。その時は、過疎化した地域をうまく利用すれば良い。
過疎化した地域は、すなわち、人がいないということ、都市から抜け出して行きたい場所はそういう人がいない所だと思うから、そういう場所へ、例えば、週末だけとか、仕事が許せば、週単位で行けるといいな。
移動手段と通信インフラと滞在できる場所さえ確保できればいいのだから、都市の一極集中化と地方の過疎化をセットで考えれば、費用面でも解決策がありそう。
要は、一極集中化した都市に無い所と、過疎化した地域に足りない物を補い合えば良いだけ。過疎化した地域も移動手段が増えれば喜ぶし。
そうなれば、都市の一極集中化も地方の過疎化も決して悪いことでは無く、むしろその方がお互い都合が良くなる。
人生100年時代を迎え、元気な中高年が増えるのだから、自分もそうだけど、そういう人たちの行動欲を手軽に満たしてあげれば、少子化して市場自体が縮小しても、人が流動的になり、あちこちでお金も落とすしね。
多地域移動居住。
そうなると、生活自体も、家族といても、ひとりでいても、楽しそう。やはり、たくさんのアクティビティーが用意されていて、それを手軽に選択することが可能な状態がいい、精神衛生的にもいい。
こういうことを考えている人はたくさんいるだろうけど、そこに税金を投入すれば、割と簡単に解決しそうだと思うのだが、それで、みんなが楽しく暮らせそうだと思うのだが、いかがなものか。
"Multilateral moving residence"
Indeed, mixed cities and chaos are crowded, not only because there are so many activities but also because of the ability to form an open personal space.
Then, if problems such as security, garbage and infrastructure can be solved, the city in chaotic state will be more fun with various activities.
However, since such cities will be opposite to nature, no matter how much they make parks and bring in nature, it is the natural nature created, so it is not much different from artifacts.
Such a chaotic city may be interesting, but I think that I will settle down rather than being in nature, but again, some people would like to go in the midst of nature.
If the city concentrates and becomes chaotic, of course it will be a reaction and it makes me want to go to nature. At that time, you can use the depopulated area well.
I think that the depopulated area, that is, that there is no person, the place where I want to get out of the city is such a place where there are no such people, so to such a place, for example only on the weekend, if the work allows weekly I hope to go.
It would be nice if we could secure transportation means and communication infrastructure and even a place where we could stay, so it seems to be a solution in terms of cost, considering the centralization of urban areas and depopulation of rural areas.
In short, it is only necessary to complement a place that is not in a centralized city and a missing one in a depopulated area. It will be pleased if the means of transportation also increases in depopulated areas.
If so, city centralization and local depopulation is not a bad thing, rather it will be more convenient for you.
As the longevity of a century celebrates the era of energetic and lively mature age, even if I am also so, if I can easily satisfy those behaviors of those people, even if the birthrate declines and the market itself shrinks, Then, I also drop money here and there.
Multiple area moving residence.
In that case, it seems fun to live itself, family, or alone. After all, a lot of activities are prepared, it is good to select it easily, it is good for mental hygiene.
There seems to be a lot of people thinking about this, but I think that it would be easy to solve it if you put in taxes there, but I think that everyone seems to be able to live happily, but what is it like .
その場所でしか実現できない空間をつくること。
その場所で無くてもいい空間ではなくて、
その場所だからいい空間になるとしたい。
場所性を意識するから、いい空間が生まれる、
という図式に魅力を感じる。
場所性を意識することを宝探しに例え、
建築家はトレジャーハンター。
良くも悪くも、その場所には、何か眠っている。
それに気づき、それを活かすのは建築家しだい。
ほとんどの建築が、場所性よりも経済性を重んじていて、決して経済性を重んじることが悪い訳では無く、建築行為は経済活動そのものという側面もあるから、
ただ、場所性がないがしろにされているならば、建築の持つ魅力や素晴らしさや、それを引き出すことができる建築家の能力が必要とされていないということになるので、それでは現代の建築が、風景が荒廃していく。
自分たちの住む街が、街の風景が、他の街と、他の都市と同じで、どこかで見たような、どこでも見るような風景で、安心したくはない。
"What is important is placeability"
To create a space that can only be realized at that place.
It is not a space you do not need in that place,
I'd like to be a nice place because it's that place.
Because we are conscious about the location, good space is born,
I feel charm in the scheme.
Comparing the awareness of the place to a treasure hunt,
The architect is a treasure hunter.
Between good and bad, in that place, I sleep something.
It is up to the architect to realize it and make use of it.
Most of the buildings place importance on economy rather than placeability, it is not a bad thing to value economic efficiency, and building acts are aspects of economic activity itself,
However, if the place is undestroyed, it means that the charm and excellence of the architecture and the ability of the architect who can draw it out are not required, so then the modern architecture is a landscape It is devastating.
I do not want to worry about the city where I live, the landscape of the city is the same as other cities and other cities, as if I saw it anywhere, anywhere.
敷地の文脈/コンテクストを意識するきっかけは、大学1年の時の建築概論で教わったコルビュジエのサヴォア邸かもしれない。
近代建築の五原則(ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由な立面)の全てが実現されているサヴォア邸は、1931年完成の20世紀の近代建築を代表する住宅で、そもそも近代建築とは、敷地の文脈/コンテクストから自立して世界中のどこに建てても成り立つ建築を標榜するものだった。
だから、近代建築は敷地の文脈/コンテクストとは無縁の存在であり、敷地の文脈/コンテクストが重視されるようになったきっかけも近代建築への反動からだった。
私が、建築概論の授業でサヴォア邸を教わった時、印象に残ったのは、近代建築の五原則が実現されていることや20世紀の近代建築を代表する建築だということでは無くて、車でアプローチしてきて、そのまま住宅の内部に駐車して、住宅の中で車から乗り降りをし、また車で外出していくように計画されていたこと。
これを20世紀のモータリゼーションの具現化だというのが定説のようだったが、私は1階の平面図にUの字状の車路が計画されているのが面白くて、その車路を見た時に敷地の中を車が走り抜けて街につながっていくイメージができて、そうしたら、この住宅はどういう場所に建っているのだろうか、車で入って来て車で出て行くことができる土地って相当広いよな、とか、建築より敷地の方が気になって仕方がなかった。
このサヴォア邸の計画は、その敷地ありきで、建築だけが自立して存在するなんて到底思えなかった。
"The chance to be conscious of the site"
The chance of consciousness of the context / context of the site may be Colbusier's Savoya residence taught in the architectural overview of the university.
Savoya residence where all five principles of modern architecture (piloti, rooftop garden, free flat, horizontal continuous windows, free elevation) are realized is a house representative of the 20th century modern architecture completed in 1931, In the first place, modern architecture was the proclamation of architecture which can stand independent from the context / context of the premises wherever it is built in the world.
Therefore, modern architecture is not related to the context / context of the premises, and the reason that the context / context of the site began to emphasize was also a reaction from modern architecture.
When I taught Savoya 's house in the class of construction theory, the impression remained in the fact that the Five Principles of modern architecture are realized and that it is the architecture representing the modern architecture of the 20th century, It was planned to approach by car, park inside the house as it is, get on and off from the car in the house, and go out with a car.
It seemed to be an established theory of motorization in the 20th century, but it seems to me that it is interesting that a U-shaped roadway is planned on the first floor plan view, seeing that road When the image runs through the premises running through the premises and connecting to the city, if so, what kind of place is this housing built in, you can come in by car and leave by car The land was quite large, and there was nothing it was worrisome about the site rather than the architecture.
This Savoya's plan is that there is the site, and it seemed that there was no self-sustaining existence only in architecture.
桜の木がある。
道路の反対側の小さな公園にある。
春になると満開の花が舞う。
北側だから日中は陽を浴びて浮かび上がる綺麗な桜が部屋から見られるだろう。
今計画中の敷地の文脈/コンテクストを読み取ろうとすると、最初にその桜の木が目に入る。その敷地の良い所、特徴的な所、生かしたい所はどこかとまず探してしまう。
ちょうど敷地に対して、道路の反対側の正面にあるから、設計者ならば誰でもそれを室内から愛でるようにする計画をパッと思い描くだろう。
1年のうちで桜を楽しめるのはせいぜい2週間位、その2週間を楽しむための計画。敷地の道路に面する以外の3面は隣家に囲まれているから、余計に桜の木に目が行く。
桜が部屋からよく見えるように、桜に向かって大開口を設けるのが常套手段か。大開口を開けても北側で道路側だから、日射もプライバシーも問題無いだろう。
この敷地はまだ良い方なのか、敷地周辺が混沌としていたり、例えば、分譲地だったり、都市のど真ん中だったりすると、尊重すべき文脈が無い場合もある。
ただね、桜の木に注目して、それを愛でる計画でいいのだろうか。桜の木が枯れてしまったら、桜の木が切られてしまったら、どうするんだ。それでも建築計画が成り立つ強度があるのか。
桜の木に焦点を当てて、敷地の文脈を読み取ったと思うのが甘いのではないか。
桜の木があるということは、そこに都市のスケールとしては空地、空間が存在するということではないか、その桜の木はその空間に変化を与えるパラメーターとして扱えば良い、だって1年の内で2週間しか影響を与えないのだから。
その空間に対して、何ができるのが設計者の優劣が問われる所か。
桜の木が見えるように大開口を設ければ、その後にどうなろうとも保身ははかれるのに、それでは納得がいかない。
どうする。
それは建築家として、技量が問われるところだ。
"Sakura blooms"
There is a cherry tree.
It is in a small park on the other side of the road.
Flowers in full bloom will dance in the spring.
Because it is on the north side, beautiful cherry blossoms that will emerge in the sun during the day will be seen from the room.
When trying to read the context / context of the site under planning, the cherry tree comes first to the eyes. I will first find something where the good place, the characteristic place, the place I want to make use of that site.
Just in front of the premises in front of the other side of the road, we will imagine a plan to make everyone as a designer to love it from the room.
We can enjoy cherry blossoms within a year for at most two weeks, plan to enjoy the two weeks. Three sides other than facing the road on the premises are surrounded by the neighboring house, so the eyes go unnecessarily to the cherry blossoms.
Is it a usual way to set up a large opening towards the cherry blossoms so that cherry blossoms can be seen well from the room? Even if you open a large opening, you will not have solar radiation and privacy as it is on the roadside in the north.
Does this site is still better, such of, or has been the site around the chaos, for example, or was a subdivision, and or was right in the middle of the city, in some cases context should respect there is no.
But I wonder if you can pay attention to cherry trees and plan to love it. If the cherry tree withers, what will you do if the cherry tree is cut. Still there is the strength that the building plan is established?
Is not it sweet to think that reading the context of the site, focusing on cherry trees?
The fact that there is a cherry tree, there in open areas as the scale of the city, or does not mean that space is present, the tree of the cherry blossoms may be handled as a parameter that changes in the space, because of the year 2 It only affects weeks.
What can be done about the space where the superiority or inferiority of the designer is questioned.
If you set up a large opening so that the cherry blossoms can be seen, then whatever you do can protect you from anything, then it is not convincing.
what will you do.
As an architect, the skill is questioned.
スーッと閉まる感じがよくて、毎朝、珈琲缶を開け閉めするのが楽しくて、使いたくなる、触りたくなる茶筒。外蓋が載せただけで、精巧なつくりゆえに、自然にスーッとゆっくり落ちて、ピッタリと寸分狂わずに閉まる。その感じがたまらなくよいのである。
京都の開化堂の茶筒を使いはじめて1年が過ぎた頃、京都に行く用事があり、Kaikado Caféに立ち寄った。三十三間堂に行った帰り、夕方の新幹線に乗るまでの間、コーヒーが飲みたくて。
少し疲れていたので、コーヒー1杯で長居をしてしまい、そろそろお店を出ようかと、その前にトイレでも、と思い帰ってきたら、
「今からTVの取材が入りますが、いいですか?」と店主に言われ、あまりに突然でいいも悪いもなく「は、はい」と答えたら、すぐにどばどばと人やカメラが入ってきて、目の前で取材がはじまった。
あまりにも目の前で、映るのは構わないが、顔を上げて取材の様子を見ていたら、もろに映りそうだったので、さすがにうつむき加減で、耳だけで取材の様子を伺っていた。
タレントの方が茶筒について質問をしているらしく、何を質問したかは聞き取れなかったが、店主の答えだけが聞こえてきて、
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
ちょっと意外だった。音を意識することが無かったから。確かに、茶筒を開けた時の感触は、毎朝のことだから覚えていて、とても気持ちのいいものだとわかるが、音は、まあ、音も感触のうちのような。
と同時に、この店主の答えを聞いて、自分の中ではハッとするものがあった。音が良ければ大切な物を入れてくれるかもしれない、なんて、なんて素敵なんだと。確かにそうだな、感触がいいとそれを大事にしなくてはと思うよな。
てっきり開化堂の茶筒は、外蓋が載せただけ自然にスーッと閉まるのを売りにしているのかと思っていた。その精巧さは海外でも有名らしく、私がお店に行った時も中国の方が1人で買いに来ていて「中国でも有名だ」と店員と英語で話していた。
だから、私が購入したもの中に外蓋が自然に閉まらないものがあり、手直ししてもらったこともあった。後で考えてみれば、茶筒は金属だから、冬と夏で伸び縮みするだろう。冬に製作したら、夏には、例え0.1ミリでも伸びたら、閉まらなくなるはず、製作時にどうしているのだろう、とききたくなった。
取材中、もう帰ろうかと思っていたので、コーヒーも無く、水も無く、30分くらい、あまりにも目の前なので席を立つ訳にもいかず、どうしたものかと思っていたけれど、店主の
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
という話が聞けて、京都に来た甲斐があったと思った。大切な物を入れてもらうために茶筒をつくる、そのために音、すなわち感触を良くするために自分たちの技術と知識を使う。
音が良ければ大切な物を入れてくれるだろう、なんて本当に素敵な考え方だ、素晴らしい。
建築に例えるとどうなるのだろう、帰りの新幹線でずっと考えていた。
"Lovely way of thinking"
It feels good to close with Su, and every morning, it is fun to open and close the coffee can, and you want to use it, you want to touch it. Just by placing the outer lid, because it is elaborate making, it falls naturally and suddenly, it closes perfectly and not crazy. That feeling is unbearably good.
I used a tea ceremony in Kyoto's Kaidokudo for the first time after a year, I had something to go to Kyoto, stopped by Kaikado Café. I went to Sanjusangendo on the way home and wanted to drink coffee until I got on the Shinkansen in the evening.
Because I was a bit tired, I made a long cookie with a cup of coffee, so I decided to leave the shop soon, I thought of going to the restroom before that,
The shopkeeper told me that "TV interviews are coming in from now," but the shopkeeper told me that, if it is too sudden and there is neither good nor bad, and answering "Yes, yes", people and cameras will soon I came in and interview started in front of my eyes.
I do not mind seeing it in front of my eyes, but as I looked at the state of the interview with raising my face, it seemed to be revealed as well, so I was asking about the state of the interview with just my ears .
The talent seemed to be asking questions about the tea ceremony, I could not catch what you asked, but I heard only the shopkeeper's answer,
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
It was a bit surprising. Because I was not conscious of the sound. Certainly, as I remember the feeling when I opened the tea chestnut, as I remember it every morning, I remember it is a very pleasant feeling, but the sound, well, the sound is like a feeling.
At the same time, there was something that made me feel relieved in listening to this shopkeeper's answer. It is wonderful how wonderful it might be to put important things if sound is good. Sure it is, I think that you must take care of it if the feel is nice.
I definitely thought that the tea ceremony of the Kanjido is selling that it closes naturally only with the outer lid on it. Its elaborateness is famous abroad, and when I went to a shop, the Chinese came to buy alone and was talking to a clerk in English with a clerk, "It is famous in China."
So, there were things that I did not close naturally in what I bought, and there were things I had to rework. After considering it, the tea ceremony is metal, so it will expand and shrink in winter and summer. If I make it in winter, in the summer, if it grows even by 0.1 mm, it will not close, I want to hear what you are doing in the making.
Because I thought that I would go home already, I did not have any coffee, there was no water, about 30 minutes or so, because I was in front of my eyes so I could not translate into a seat and I thought what was wrong,
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
I thought that it was worth to come to Kyoto to hear the story. To make precious things to be put in, make a tea ceremony pipe, therefore use their skills and knowledge to improve the sound, that is, feel.
If sound is good it will put important things, what a really wonderful way of thinking is wonderful.
I wonder what happens if you compare it to architecture, I have been thinking about it on the returning Shinkansen.
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
京都へ行くと必ず寄るカフェがあり、そこでの出来事。三十三間堂を見て、東京へ帰る前に、どこかでお茶でもと思い、少し歩いて「Kaikado Café」に来た。
ここは京都で長年、茶筒を制作している「開化堂」が出しているカフェ。京都で路面電車が走っていた時の車両基地だった所を改装したらしく、洋風な建物で、室内は天井が高く明るくて、とても居心地が良いので、京都へ来ると1度は立ち寄る場所。
ちなみに、うちには開化堂の茶筒が大小7つある。ブリキ製4つ、真鍮製3つ、うち1つは毎朝飲むコーヒーの豆を入れる真鍮の珈琲缶。ここの茶筒が好きで、ちょっとずつ買い足していった。一番最初に真鍮製の珈琲缶を買い、やっぱりブリキ製も欲しくなり、違う大きさも必要だなとなり。
なぜここの茶筒か、経年変化するのが面白くて。ブリキ製は真っ黒になるし、真鍮製は赤味か黄味を帯びてくる。あと、私は持っていないが銅製の茶筒もあり、こちらは渋く茶色になっていく。
購入した時はピカピカ、ブリキ製は光沢のあるシルバー、真鍮製も光沢のあるゴールド。共に、塗装を施していない生地だから、使い込むうちに、擦れたり、手の油などが付着して、自然と色が変わるそうです。
買った時にお店の人から「最初の1週間はよく手で全体をまんべんなく触って下さい。そうすると色の変化が綺麗に早く出るようになりますよ」と言われたので、毎朝愛おしくスリスリしていた。
銅製は買わなかった。銅製が一番早く色が変わるそうで、早く経年変化を楽しみたいならば、銅製かもしれないので、それも良かったが、買ったのは真鍮製とブリキ製。
真鍮製は使う人の手の油によって、その人が普段何を食べいるのか、肉なのか魚なのかで、赤味を帯びるか、黄味を帯びるか、が違ってくるらしく、人によって経年変化した結果が違うところが面白いと思った。ただ少なくともその結果がわかるのは10年後、段々と変化していくので、赤味か黄味かは2、3年したらわかるかもしれないけれど、まだ1年なのでわからない。
ブリキ製はもっとかかる。ピカピカのシルバーが真っ黒になるには40年、私はもう生きていないかもしれない。それでも、次の世代になってもその茶筒が受け継がれ、真っ黒になった茶筒が日常生活で使われていたなら、なんて素敵なことなんだろう、と思い、そのためには今買わないと。
塗装で擬似的にその風合いを出すことは可能かもしれないが、本物の生地が変化した風合いには敵わないだろう。時間かかるのだよ本物は、がいい、ブリキ製はそこがいい。次の世代に受け継ぐ物ができた。
経年変化にはとても興味をそそられた。経年変化することは、もしかしたら現代では製品として否定的に捉えられてしまうことかもしれないが、自然の素材や生地の物を使えば、経年変化するのは当たり前のことで、それを手入れをしながら使い、また、自然の素材や生地だから手直しもできるので、長い年月に渡って、次の世代にも受け継ぐことができる。
使い捨てでは無い、物としての本来の在り方がそこにあるような気がした。
それでもうひとつ、この茶筒いいなと毎朝楽しみにしていることがある。
"Real things change"
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
There is a cafe where you will go to Kyoto without fail, and there happens there. When I saw Sanjusangen-do, before I came back to Tokyo, I thought that it was tea somewhere, came a little "Kaikado Café".
This is a cafe that Kyoto has been producing "tea ceremony" for many years. It seems that it was refurbished where the tram was running in Kyoto, it is a western style building, the ceiling is bright and the interior is bright and very comfortable, so when you come to Kyoto it is a place to stop by once.
By the way, there are seven large and small tea cranes in the Kaiden-do. Four tinplate, three brass, one of which is a brass coffee can that puts coffee beans to drink every morning. I liked the tea ceremony here, and I bought it a little at a time. I bought a brass coffee can at the very beginning, I wanted a tinplate as well, and it became necessary to have a different size.
Why is it a tea ceremony here, it's fun to change over time. Tinplate will be black and brass will be reddish or yellowish. Also, although I do not have a copper tea cupboard, it is browned with astringency.
Shiny when purchasing, glossy silver in tinplate, shiny gold in brass. Both of them are fabrics that have not been painted, so it rubs, oils of hands adhere, and so on, it seems that the color changes with nature, as it is used.
When I bought it I was told from the store people "Please touch the whole thoroughly with your hand well in the first week, so that color changes will come out cleanly and quickly" It was.
I did not buy copper. It seems that copper changes most quickly, so if you want to enjoy secular change quickly, it may be made of copper, so it was also good, but I bought it made of brass and tin.
The brass made by the oil of the person who uses it, seems to be reddish or yellow depending on what you usually eat usually, fish or meat, it seems different, I thought that the difference between the changed results is interesting. However, at least the result will be known 10 years later, so it will gradually change, so it may be known in a couple of years whether red or yellow taste, but I do not know as it is still a year.
Tinplate takes more. It has been 40 years for shiny silver to become black, I may not be alive anymore. Even then, even if it comes to the next generation, if the tea ceremony was handed down and it was used in everyday life, it seems that it is a wonderful thing if a black tea chestnut was used in daily life, and for that I have to buy it.
Although it may be possible to produce the texture in a pseudo manner by painting, it will not be enemy to the texture where real fabrics have changed. It is time consuming, genuine article is good, Tin tin is good there. There was a thing to hand down to the next generation.
I was intrigued by the secular change. It is likely that it will be caught negatively as a product in modern times, but it is commonplace to change over time if you use natural materials or fabric items, so that it will change over time While using it, because it is also natural materials and fabrics can be reworked, over the years can be passed down to the next generation.
I felt there was the original way of things, not disposable.
And another thing, I have looked forward to this morning that this tea cup is nice.
先日「仲村さんのところは、3DプリンタとかVR機材とか夢の機材がありますので、アジトみたいで楽しいです」と言われたり、事務所へ行きたいという人が増えた。普段、事務所にはいないので、それに合わせて事務所にいるようにして、来る人拒まず、大歓迎、話し込んでしまう。
そう言えば「どこに向かっているんですか」とも言われた。意外では無いけれど、気恥ずかしくて一瞬間を置いて小声で「自作自演」と思わず言ってしまった。
VRもBIMも3Dプリンターも自作自演を支えるためのツール。VRからはじまり、最初はただVRでの建築の見え方が凄い、これを設計に使いたいと思っただけ、そこから、BIMに興味を持ち、25年近く使用したCADからRevitに変え、Revitのモデルには拡張性があるので、人から勧められてCGソフトを入れ、リアルなパースや動画をつくりはじめ、前から欲しかった3Dプリンターでモデルを出力して模型や部材もつくるようになり、気がつくと、設計だけでなく施工の領域にまで踏み込んで自作自演できる環境が整ってしまった。
別にこれらのツールが無くても自作自演はできるが、意識せずに、これをはじめたからこれもできるようになるな、とか、これがあるからこれもできないかな、とか、前からこれに興味があったのだけれどもできるかな、と人にきいたりして、気がついたら自分で何でも自らの手で簡単に対してそんなに労力なしに生み出せるようになっていた。根底には、道具は大事、道具しだいで変わることがたくさんある、と思っているからだろうけど、意識せずに整ってしまったことが本当は求めていたことなのかもしれない。
自作自演とは、自分の思考だけで完結でき、その評価を誰に求めるのでも無く、自分で自分に評価を下すことで、好きなことをするよりも、楽しいことをするよりも、自作自演を大事にしている。好きや楽しくても、自分の判断だけで決定できないと、どこかで迎合することになり、精神衛生上よくない。仕事として建築デザインを行いつつ、自作自演できる場があると、自分の能力を確認し、鍛え、高めることができ、相乗作用があれば、いずれ自作自演だけになるかもしれない。
このように設計環境を再構築したおかげで、どこにいても設計ができ、1人でやりくりして完結できるようになったので、もっとひとつのことに対して思考を深めることができるようになり、それが自作自演の場で自分の能力を高めることに繋がっている。
例えば、輪島塗のフリーカップづくり。これは完全に自作自演、しかし、自分から出て来たとは信じられないようなデザインに発展しており、自分の能力を確認し、鍛え、高めることができていると思う。
これからもっと自作自演をしていくことになるだろう。それを継続してずっと行っていく環境が今整いつつある。
"Self-made performances"
The other day, "Nakamura's place has 3D printers, VR equipment and dream equipment, so it's fun like an honor" and more people said they wanted to go to the office. I usually do not stay in the office, so I will stay in the office accordingly, I will not refuse to come, welcome, I will talk.
As I said, 'Where are you heading?' Although it is not surprising, I was embarrassed and sprang one moment and in a low voice I said without thinking "self-made performance".
Both VR, BIM and 3D printers are tools to support self-made performances. Beginning with VR, at first it is just how VR's architecture looks awesome, I just wanted to use it for design, from there I got interested in BIM, changed from CAD used for nearly 25 years to Revit, from Revit's As the model has extensibility, I recommend CG software from people, start making realistic perspectives and animations, outputting models with a 3D printer I wanted from before to make models and members, I noticed And, not only the design, but also the environment where we can stepping in to the field of construction and making self-made performances has been set up.
Apart from these tools I can do my own self-performance but without consciousness, since I started this I can also do this, I can not do this because there is this, I've been interested in this for some time I listened to someone that he could do it, but when I realized I could create whatever I could with my own hands without much effort by my own hands. Basically, tools are important, because they think that there are lots of things to change depending on the tool, but it may be that what you really wanted is that you did not realize it without being conscious.
Self-made performances are self-made performances rather than doing something more fun than doing anything they like by doing self-evaluation on themselves without asking anyone to evaluate themselves, being able to complete with their own thoughts alone I am cherished. Even if you like or have fun, if you can not decide just by your own judgment, you will be somewhere to meet up and it is not good for mental health. If you have a place to do your own self-made work while doing architectural design as a work, you can check your ability, train and enhance, if there is a synergistic effect, it may be only your own self-made performance.
Thanks to the rebuilding of the design environment like this, I can design anywhere, I can finish it by one person, so I can deepen my thought on one more thing, It leads to enhancing my skills at home for self-made performances.
For example, making a free cup of Wajima coat. This is completely self-made, but I am developing into a design that I can not believe that I came out of myself, I think that I have been able to confirm my skills, train and enhance.
I will be doing more self-made performances from now. The environment where we continue to do it all the time is coming.
VRを建築設計途中の検討用ツールとして使いたいならば、BIM(ビム)とは関係無しに、現状Autndesk社のRevit(レビット)を導入するしかない。ならば、BIMにもっと興味を持ってみよう、がBIMをはじめるキッカケだった。
VRの説明会では最初にBIMの話から入った。BIMの基本概念からはじまり、BIMが今後主流になるだろう、特に施工現場ではすでに導入され機能しているなど。その中で特に興味を持った話は、Revitを導入してBIMをはじめた場合の拡張性だった。
建築設計する場合、今までは2次元の図面をつくり、それを元に3次元のパースや模型を制作していたが、Revitを導入してBIMをはじめると、最初から3次元のモデルと称する実際の建物をソフト内で構築し、必要な情報、例えば、図面などを後でモデルから取り出すことになる。
このRevitのモデルには拡張性があり、VRはそのモデルデータを変換して使用するのだけれども、このモデルを構造設計事務所に渡すと、建物の骨組みをモデルに入力して返してくれるので、Revit上で意匠設計と構造設計の整合性を見ることができ、確認申請機関にはRevitのモデルをそのまま提出すれば、ペーパーレスで確認申請の審査を受けることができ、このモデルデータはそのままで他のCGソフトに読み込ますこともできるので、よりリアルなパース画像や動画も簡単に作成することができ、また、このモデルデータを変換して使用すれば3Dプリンタで出力でき、スチレンボードで白い模型をつくる必要が無くなる。
私は1人で設計から施工管理まで行うので、設計時にRevitでモデルデータを作成することが、自分が実際に動くことによる労力や時間を大幅に削減でき、設計を大幅にサポートするだけでなく、1人だからよりRevitのモデルから拡張されたこれらのことを上手く連携させ、レスポンスよく進めることができ、設計の質を直接高めていくことができるのではないかと考えるようになった。
また、この拡張性のおかげで、どこでも場所を選ばずに、動くことなく、ノートPCとネットの環境があれば設計ができるようになる。VR装備一式も持ち運べ、最低2m角位の場所があれば良い。3Dプリンタを置く場所だけは限定されるが、一度プリントアウトの作業をすればずっとその場にいなくてよく、モデルデータだけを送信してその作業だけを誰かに頼むこともできるだろう。そうすると、事務所もいらなくなる。
BIMとは、最低限ここまで拡張性があってはじめて成り立つのではないだろうか。
そう考えると、メインのOSをMacからWindowsに変えることも、より拡張性を高め、よりクリエィティブな建築を生む可能性も高めることになる。また、Autodesk社のRevitはBIMソフトとして世界中でメインで使われるようになるので、モデルを作成すれば、それが共通言語となり、モデルを渡すだけでプレゼンから施工までできてしまう可能性も秘めていた。
ここまで順に考えてきてやっと、25年近く使用して習熟しているCADソフトを捨て、愛着のあるOSも変え、Revitを導入してBIMをはじめることに決心がついた。
これは、この先まだ15年以上は設計をして、よりいい建築を生む出したいと考えていたので、そのためには、今、設計環境を再構築する必要があるのでは、という想いもどこかにあったから決断できたのかもしれない。
"Bim's silence"
If you would like to use VR as a tool for examination in the middle of building design, you can only introduce Revit (Revit) from Autndesk, regardless of BIM (Bim). Let's be more interested in BIM, but it was a challenge to start BIM.
At the briefing session of VR, we entered from the story of BIM for the first time. Starting with the basic concept of BIM, BIM will be mainstream in the future, especially already installed and functioning at the construction site. Among them, the story that was particularly interesting was the extensibility when I introduced Revit and started BIM.
In the case of architectural design, until now, we have created a two-dimensional drawing, and based on that we created a three-dimensional perspective or a model, but if we introduce Revit and start BIM, we will call it a three-dimensional model from the beginning We will build the actual building in software and retrieve the necessary information, such as drawings etc later from the model.
This Revit's model is extensible, and VR converts its model data and uses it, but if you pass this model to the Structural Design Office, you will enter and return the framework of the building to the model , You can see the consistency of design design and structural design on Revit and you can receive the examination of confirmation application paperless if you submit Revit's model as it is to the confirmation application agency and keep this model data as it is Since it can also be loaded into other CG software, more realistic perspective images and moving images can be easily created, and if this model data is converted and used, it can be outputted with a 3D printer, and it is white with a styrene board There is no need to make a model.
Since I do it from design to construction control, creating revit model data at design time can greatly reduce labor and time due to my actual movement, not only to greatly support the design Since I was one, I began to think that I could collaborate these things extended from the model of Revit well and proceed with a good response, so that the quality of design can be improved directly.
Also, thanks to this extensibility, designing will be possible if there are laptop and net environments, without moving anywhere, without moving anywhere. You can also carry a complete set of VR equipment, as long as there is a place at least 2 m square. Although only the place to place the 3D printer is limited, once you print out, you do not have to stay there for a long time, you can send only the model data and ask someone to do just that work. Then you will not need an office.
Will not it be possible to have BIM for the first time with scalability so far?
If you think so, changing the main OS from Mac to Windows will also increase the possibilities of increasing scalability and creating more creative architecture. Also, Autodesk's Revit will be used mainly as a BIM software all over the world, so if you create a model, it will become a common language and you can also possibly be able to do from presentation to construction simply by passing a model It was.
After considering it so far, I decided to throw away the CAD software that I've been using and using for nearly 25 years, changed the OS with attachment, introduce Revit and start BIM.
This is because I was thinking that I wanted to design more than 15 years and to produce better buildings, so for that I think that it is now necessary to reconstruct the design environment somewhere It may have been decided because it was in.
VRを導入することを決めたが、問題はVRのデータをどうやって作成するか、外注か自前か。
外注すればデータを作成する毎に費用がかかるし、データを自分で変更できないので、少し変更するだけでもまた外注に出さなければならず、費用と時間が余計にはかかるが、VRデータを作成するために何かを特別に覚える必要が無く、設備投資も無く、忙しくても外注に投げてしまえばいいのは良い。
自前でVRデータを作成しようとすると、新たなにソフトを導入しなければならず、ソフトを習熟する時間と労力が必要になる、もちろん新しいソフトを導入する費用も。ただ、自前でVRデータを自由に作成できれば、VRで検討して、すぐ修正し、またそれをVRですぐ確認できる。
VRを建主用の説明ツールとしてだけではなくて、建築設計途中の検討用ツールとしても使おうと考えると、いちいちVRデータの作成を外注に出していては費用と時間と、あと検討のレスポンスが悪くなるので現実的では無い。建築設計途中の検討用ツールとして使おうと考えると必然的に新たなソフトを導入して、自前でVRデータを作成するしかない。
VRデータを作成するソフトとして勧められたのがAutodesk Revit(レビット)というBIM(ビム)のソフト。
BIMとは、Building Information Modeling(ビルディング インフォメーション モデリング)の略称で、建築設計する時に、今までは2次元の図面をつくり、それを元に3次元のパースや模型を制作していたのを、最初から3次元のモデルと称する実際の建物をソフト内で構築し、必要な情報、例えば、図面などを後でモデルから取り出すことを総称してBIMという。
これからBIMは、建築では当たり前に行われるようになるといわれ、現状、大手ゼネコンには一通りRevitが行き渡ったらしく、まずは施工現場から一般的にBIMが行われるようになりつつあるという。
VRデータは、そのRevitで作成した3次元のモデルのデータを変換して作成する。いずれ住宅設計でもBIMが一般的に行われることが予想はされていたが、私としてはその当時BIMを行うことまでは考えておらず、当時はVectorworks(ベクターワークス)という図面を描くCADソフトを使用していて、ソフト上でシームレスに2次元と3次元を行ったり来たりできたし、必要であればそのソフトでも簡易的にBIMができたので、それで十分だと思っていた。
ただ、VRを建築設計途中の検討用ツールとして使いたいならば、BIMとは関係無しに、現状Revitを導入するしかない。
ここは即断できず躊躇した。なぜかというと、Revitを導入することはVectorworksから乗り換えるということで、25年近く使って習熟しているCADソフトを捨てて、全く新しいソフトを1から覚えなくてはいけないのと、Vectorworksの前身のMini CAD(ミニキャド)から使っていたが、その当時はMac版しかなく、そのためずっとメインのOSはMacだったが、RevitはWindowsでしか動かないので、Revitに変えたらメインのOSも変更しなくてはならないし、また半年前に新しいMacBook Proを導入したばかりだった。
やはり、OSとしてMacに愛着があり、クリエィティブを刺激するものを感じ、Windowsにはそれが無かった。あと偏見かもしれないが、Autodeskの製品にも同じ感じだった。だから、Revitを導入するということは、私にとって今までの設計環境を根底から全く違うものに変えるのと等しいことだった。
"Barriers to VR"
I decided to introduce VR, but the problem is how to create VR data, outsource or self?
Since it costs expenses every time data is created, it can not be changed by yourself, so even if you make a slight change, you have to submit it to outsourcing, which will add extra cost and time, but create VR data In order to do something, I do not need to memorize something specially, there is no capital investment and it is good to throw it to outsource even if I am busy.
If you try to create VR data yourself, you will have to introduce new software, you will need time and effort to learn the software, as well as the cost of introducing new software. However, if you can create VR data freely on your own, you can review it immediately with VR, and immediately check it with VR.
Considering that VR is not only used as an explanatory tool for the owner but also as a tool for consideration in the middle of architectural design, if the creation of VR data is outsourced every time, the cost and time, and the responses after consideration It is not realistic because it gets worse. It is inevitable to introduce new software and create VR data on its own by considering it as a tool for consideration in the middle of building design.
Authorized as software to create VR data, Autodesk Revit (Bit) software called Bim (Levit).
BIM is an abbreviation of Building Information Modeling. When designing a building, until now, it has created a two-dimensional drawing, and based on that it was producing a three-dimensional parse and a model, at first From the viewpoint of constructing an actual building called a three-dimensional model in software and extracting necessary information, such as drawings from the model later, is collectively called BIM.
From now on, it is said that BIM will come to be taken as a matter of course in the current situation, Revit seems to have spread all the way to major general contractors, and it is said that BIM is generally beginning to be done from the construction site first.
The VR data is created by converting the data of the three-dimensional model created by the Revit. Although it was anticipated that BIM would be commonly done in residential design, as I was not thinking of doing BIM at that time, at that time we had CAD software drawing Vectorworks (VectorWorks) drawing I was using it, I was able to seamlessly go back and forth between two dimensions and three dimensions on software and I thought that it was enough that BIM could be easily done with that software if necessary.
However, if you want to use VR as a tool for consideration in the middle of building design, you can only introduce Revit as it is without relation to BIM.
I hesitated because I could not make it immediately. For the reason, introducing Revit means switching from Vectorworks, so I have to abandon CAD software that I have been using for nearly 25 years and I have to remember completely new software from 1, and the predecessor of Vectorworks Although I was using it from Mini CAD (mini-caddy) of that time, at that time there was only Mac version, so the main OS was Mac all the time, but Revit only works on Windows, so change to the main OS if I change to Revit I had to get it and I just introduced a new MacBook Pro six months ago.
After all, there was attachment to the Mac as OS, I felt something that stimulated the creative, Windows did not have it. Moreover, although it may be prejudiced, it felt the same for Autodesk's products. So introducing Revit was equivalent to changing my existing design environment from the very bottom to completely different things for me.
はじめから、今回輪島に行って、フリーカップの漆塗りをどうするかは決まらないだろう、と思っていた。
漆塗りを人肌の感触にしようと考えついた時点で、見本塗りを作成し、その感触が本当に人肌なのかを確かめないと、フリーカップの塗りを発注できないと思っていたから、見本塗りを作成するには、その場ではできずに、それなりの日数が掛かるし。
ただ、見本塗りをしてもらうにしても、どうしたら人肌の感触が実現できるのか何ひとつ技術的なことがわからなかったので、輪島まで行って打合せになるのか、全くできる可能性が無かったら、など考えていた。
だから、石目乾漆の手触りには驚いた。塗師の所の見本場には、お盆とお膳の2種類の石目乾漆があったが、特にお盆の方は人肌のしっとり感に似た感触をあったから、メールや電話では感触までは打合せできない、輪島まで来た甲斐があったと思った。
塗師の方が打合せ中に連絡を取り合って石目乾漆についていろいろときいていた呂色職人が実際に塗師の見本場までやって来て、さらに感触の話が深くなる。実際に手を動かして、この石目乾漆を仕上げた人だから、こちらの説明「人肌の感触にしたくて塗師の方にご相談したら石目乾漆を見せて頂いて」と話したら、若干の驚きとともに興味を持ったみたいで、どうやって制作するのか、その難しさや乾漆の撒き方などを一所懸命に説明してくれた。
途中で「前に京都で出来合いのお椀の木地に漆塗りだけをデザインして制作してもらったのですが、満足できる出来では無かったので、今度は木地から漆器をつくりたいと思いまして」などと話したら、
呂色職人「何をされている方ですか?」
京都でとか、今輪島にいるし、不思議に思ったらしく、
私「建築です、一応、建築家をしてまして」
呂色職人「私も昔、建築をやっておったですわ」
一気に距離が縮まった。
ここで仕上げの方向性は、石目乾漆に決まったようなものだったので、あとは色をどうするのか、もっと人肌の感触に近づけるにはどうするのか、という細かい技術的な話になったところで、見本塗りをお願いしてみることにした。どんなに細く打合せをしても、最終的な仕上げがどうなるのかを手で触り、その感触を確かめないと先の工程に進めないと思っていたから。
私の申し出に塗師も呂色職人も納得したように、すんなりと見本塗りをすることが決まった。今ちょうど呂色職人の所で石目乾漆を制作中とのことだったので、後で工房を見せてもらい、そこで更に細かい打合せをすることにした。
ここまでだけでも私は嬉しくて、こんなにすんなりと、何よりも塗師の方も呂色職人の方も、私が言い出した「人肌の感触」に真剣に向き合ってくれて、技術的にも克服できそうで、自分が考えたカップが実際に本当に実現するかもしれないという喜びで十二分に満たされていた。
"Joy"
From the beginning, I thought that I will go to Wajima this time and decide how to lacquer the free cup.
When I thought about making the lacquer coat feel as human skin, I created a sample paint and I thought that it was impossible to place a free cup painting unless I confirmed that the feel was really human skin, so I created a sample paint You can not do it on the spot, it will take a certain number of days.
However, even if you ask a sample paint, how can you realize the feel of human skin? Because I could not understand one technical thing, I wonder if I will go to Wajima and meet up, if there is no possibility at all , And so on.
So I was surprised at the feel of the stone eye lacquer. There were two types of stone eye lacquer at the painter's place in the place, Obon and the meal, but in particular the tray had a feel similar to the moist skin feeling, so we discussed up to feeling by e-mail or telephone I thought that it was worthwhile to come to Wajima.
Painter will keep in touch with each other during the meeting and Lu color craftworker who actually heard about the stone eye lacquer went to the painter 's trade fair, and the story of the feel became deeper. Actually moving the hand and finishing this stone eye lacquer, if we talk about this explanation "If you want to make it to the skin feel and talk to the painter and see the stone eye dry lacquer," a little She seemed to be interested with surprises, and explained her difficulty and how to sprinkle dry lacquer very hard, how to make it.
On the way, "I was designing just the lacquer coating on the wooden bowl that I could make in Kyoto before, but it was not satisfactory, so now I wanted to make lacquerware from the woodland If you talk to them,
Lu color craftsman "What are you doing?"
In Kyoto, I am in Imajima now and seemed to wonder,
I "It's architecture, once you are an architect"
Lu color craftsman "I used to do architecture a long time ago"
The distance shrunk at a stretch.
The direction of finishing here was like a stone eye lacquer, so after that it became a detailed technical story about what to do with the color and how to do it more closely to the feel of the human skin , I decided to ask the sample painting. No matter how narrow a meeting I thought I would not be able to proceed to the previous process unless I touched the final finish with the hand and confirmed that feeling.
As painters and Lu color craftsmen agreed with my offer, I decided to paint samples sweepily. It was just now that Lu Lu color craftworker was making a stone eye lacquer, so I asked him to show me the workshop later and decided to make further meetings there.
Even so far, I am happy, I am glad that all the painters and Lu color craftsmen are seriously facing the "feel of human skin" I mentioned, so that they can overcome technically Well, I was fully satisfied with the joy that the cup I thought might actually come true.
「色をどうするかより、持った時の感触を人肌の感じにしたいんです。漆塗りの感触に違ってあるのですか?」
輪島の塗師の方にお会いして、一番最初にこう切り出した。とにかくやりたいことははっきりとしていたが、それがどうしたらできるのかがわからないので、とにかく塗師の方にこちらがしたいことを明確に伝えるしかなかった。
塗師の方の事務所は、塗師屋造りという輪島独特の住宅形式、道路側に住居、奥に仕事場、をした建物を住居部分に事務所、仕事場部分を見本場という展示スペースにして利用しており、毎回、見本場に通されて打合せをする。
「きっともっとザラついている方が人肌の感じに近くなるんじゃないかと思うんですが」と普通?の輪島塗のコーヒーカップを手で触りながら塗師に伝えたら、見本場から呂色のお盆を見せてくれた。
呂色とは、上塗りの上に施す仕上げのことで、いろいろな色の乾漆と呼ばれる粒状のものを均一に撒いたり、不均質に撒いたりして、それを磨いて細かい粒状の凹凸ができるように仕上げる。
見せてくれたお盆は乾漆を均一撒いた仕上げで、確かにザラつきは出たが、人肌のしっとりな感じはなく、乾いた感触で、人肌とは全く違った感触だった。
次に塗師の方が同じく呂色だが、今度は石目乾漆(画像のものは磨く前)という技法のお盆を見せてくれた。粒状の乾漆を今度は不均質に撒き、乾漆がのる部分と乾漆がない部分の面積が均一に撒くより大きくなり、それを磨くと乾漆がのった部分が平らになり、手で持った時に少し密着感が出て、感触がしっとりしてくる。
この感触の延長線に人肌の感触があるのではないか、直感で。塗師は皮膚を拡大するとこんな模様ですねと言う。
いろいろ石目乾漆についてききたい、どうやるのか、好きな色を出すのにどうするのか、もっと密着感を出すことはできるのか、立て続けに塗師に質問したら、突然、携帯で電話しはじめた。電話の相手は呂色職人のようだ。輪島塗の工程は全て分業制、それぞれに専門の職人がいる。
右手で右耳に携帯を押し当てている塗師に対して、左耳にききたいことを話し掛けていた。ここが重要だと思ったから、今日ここまで朝2時に起きて輪島に来るまでずっと、漆塗りで人肌の感触を出すことが本当にできるのだろうか、技術的な糸口が何ひとつなかったので、やっと糸口を掴んだ、必死で離すものか、という気持ちだった。
電話を切った塗師は
「いま、職人が来るから、ききたいことをきいた方がよいよ」と私に告げた。塗師の声だけは聞こえていたからわかるが、その呂色職人は自ら説明しに来ると言ったようだった。もしかしたら人肌の感触ができるかもしれない、可能性が出てきた嬉しい瞬間。
"Grasp the clue"
"I'd like to feel the feeling of my skin when I had it, rather than what to do with color, is it different from the feel of lacquer painting?"
We met the painter of Wajima and cut out like this at the very beginning. Anyway I wanted to do what I wanted to do but I did not know how to do it, so anyway I had to tell the painter what I wanted to do clearly.
The office of the painter is using the building space unique to Wajima called Painter's House Building, the building which did the residence on the roadside, the workplace in the back, as the exhibition space of the office in the residential part and the main part looking at the workplace part Every time, I will go through a sample place and meet.
"I think that it is more likely that people with more roughness will be closer to the feeling of human skin" and normal? I touched the Wajima-covered coffee cup with my hands and handed it to the painter, who showed us a Lu color tray from the exhibition ground.
Lu color is the finishing to be applied on the top coat so that granular items called various lacquer lacquers are spread uniformly or sprinkled inhomogeneously to polish it so that finely granular irregularities can be formed Finish.
The tray that showed me was a finely sprinkled dry lacquer, certainly with zara, but there was no moist skin feeling moist, with a dry feeling, it was totally different feeling from human skin.
Next, the painter is also Lu color, but this time it showed us the tray of the technique called the stone eye dry lacquer (the thing of the image before polishing). This time the granular dry lacquer is spread inhomogeneously and the area of the part where the lacquer is lined and the part which does not have lacquer is larger than it spreads evenly and when polishing it the part with dried lacquer was flat and it was held by hand Sometimes a bit of a close feeling comes out, the feel is moist.
It is intuition whether there is a feeling of human skin on the extension line of this feeling. The painter says when he enlarges his skin it looks like this.
About various stone eyes dry lacquer, I want to hear, how to do, how to do what I like to put out a favorite color, how can I get a more close feeling? If you question the painter after you in a row, suddenly I started calling on the mobile phone. The other party of the telephone seems to be Lu color craftsman. All processes of Wajima coat are divided into division of labor, each has a specialized craftsman.
I was talking to the left ear about the things I wanted to hear against a painter who was pressing a cell phone against my right ear with my right ear. Because I thought that this was important, I wonder if I could get up at 2 o'clock in the morning so far, until I came to Wajima, I could actually feel the human skin with lacquer painting, since there was not any technical clue, Finally I caught a clue, was feeling I was desperate to release.
Painter who hung up
"Since craftsmen are coming now, I should tell me that you should listen to what I want to ask." I heard that only the painter 's voice was heard, but that Lu color craftsman seemed to say that he would come to explain himself. Perhaps it may be the feeling of human skin, a happy moment when the possibility comes out.
「鯖あるけど」
カウンターにいたもう1人の客が帰ってすぐに大将が唐突に声を掛けてきた。
私「えっ」
大将「鯖があるけど」
間髪入れず、被せ気味に
私「ください」
大将はニコニコしながら急に話し掛けてきた。
昼間、塗師の方がそのお店のおススメを教えてくれた。今だったら香箱蟹、鱈の白子。それに加えて、輪島のふぐ刺し、白海老の天ぷら、酢牡蠣も注文、生ビールを少し呑んでから、輪島の地酒も。
香箱蟹の内子、外子で地酒をゆっくりとなんて思ったが、その旨さにかぶりつき、最後は甲羅に地酒を入れて、きれいに食べていたのを見ていたのかもしれない、全然話し掛ける雰囲気が無い大将が何の前ぶれもなく「鯖あるけど」だったので。
鱈の子付け、のどくろ、それとメニューになかった鯖の刺身を食べ比べながら、鯖が一番旨く、大将にお礼をと思い、
「鯖美味いですね」と言ったら
ニコッとしながら
「鯖はね」と一言、また黙々と大根の皮むき、仕込みか、この無理のない、ほっとかれ感がちょうど良い。
この大将に塗師の方を紹介してもらったから、輪島塗のフリーカップ制作がはじまった。
「仕事?」また唐突に一言、
私「いや、仕事というか、漆器をつくりたくて、というか、以前大将に塗師の方の連絡先をきいて、それから、以前に木地をつくり、今日塗りの打合せをしてきたんですよ」
カウンターの入口近くの端の席を指して
大将「あこの席にいたよな」
やはり、覚えていてくれたらしい。何か嬉しかった。
それから、どんなカップをつくっているのか、携帯の画像を見せながら、木地はこうしてあーして、塗りはこんな感じにしたくて、それで今日、こんなことがあって、こーなったなどと、大将に話したら、作業中の手を止めて、店で使っているカップの漆器を出してくれて、これいいだろという感じでカウンターに並べはじめた。そこから漆器談義、はじめてこのお店に来た時もそうだった。
漆器の話からはじまって旅行の話まで、大将が人懐っこく話し掛けてくる間でゆったりとしていたら4時間位いたかな、大将の言葉で一番印象に残っているのは、
「儲ける商売の仕方は客が離れるが、儲かった商売の仕方は客が支えてくれる」
輪島の塗師や職人は皆なこの「儲かった商売の仕方」で、まずは技術的な話、お金の話は二の次という様子で、だから、こちらも実現したいことをどういう技術を使って、どうつくるかの話に専念しやすい、だから、打合せをしていて楽しい、実現していく実感が直に得られるから。
最後に釜飯まで食べて、気持ちよく、お腹パンパンで、真っ暗な中、月を見ながらホテルまで、カウンター越しにしか見送らない大将がわざわざ出てきてくれて、ニコニコしながら、また来年来ますと告げて帰った輪島の夜でした。
"Reunion"
"There are mackerels"
As soon as the first customer returned to the counter, the general came suddenly.
I "Eh"
Admiral "There are mackerels"
Do not put on your hair,
I "Please"
The general suddenly spoke to us while smiling.
In the daytime, the painter taught me the recommendation of the shop. If it is now, it is a barakaba crab, cod white matter. Besides that, we also ordered Wajima's blowfish, tempura of white shrimp, vinegar oysters, drinking a bit of draft beer, also local sake from Wajima.
I thought slowly the sake as a baby crab crab and a foreign boy, but I hung on to that effect and at last it might have been seeing the local sake in the shell and eating cleanly, the atmosphere of speaking at all Because no generals were "no sausagi" without any precaution.
Mackerel was the most satisfactory while thinking of eating the cod attachment, the skull and the mackerel of the mackerel which was not in the menu, mackerel was the best,
When saying "Mackerel is delicious"
While making it nice
One word saying "Mackerel", silently peeled the radish, put it in, it is reasonable, feeling relieved is just right.
Since this general was introduced to the Painter, the Wajima-coat free cup production began.
"Work?" In addition,
I: "No, I wanted to make a lacquerware, I asked the general of the contact address of the Painter before, I made a woodland before and we had a meeting of painting today."
Point at the end seat near the entrance of the counter
Admiral "You were in the seat of ako"
After all, it seems that he remembered. I was pleased.
Then, while showing the picture of the cell, what kind of cups are making, the woodlands do like this and I want to paint like this, so today, this is the case, Talking to, I stopped the work in operation, put out the lacquerware of the cup used in the shop, and started to line up at the counter with feeling like this. It was also when I came to this shop for the first time about lacquer ware handling.
From the story of lacquerware to the story of the trip, it seems that if I was relaxing while the general caught friendly and spoken, it would have been around 4 hours, the most impressive thing in the generals'
"The way customers make money, how to make money is profitable, but customers will support the way of profitable business"
Wajima's painter and craftsman are all "how to make a profitable business", first of all technical story, the story of money is a secondary story, so the situation is like secondary story, so what kind of technology will be used for what we want to realize and how to make it Because it is easy to concentrate on the story, so that you can get a sense of fulfillment, realizing that you are having fun meeting.
Finally eating up to Kamoro, feeling good, with a stomach bumper, while looking at the moon, while seeing the moon, the general who only watches over the counter comes out of their way, noticing that I will come next year, while smiling next year It was the night of Wajima that I returned.
漆の色は黒、朱以外にも、金、銀、赤、青、緑、紫、黄、橙など、色の名前は違っても色味としては大体好みのものを選ぶことができるが、白だけはない。正確に言うと、白漆は存在するのだが、色は真っ白ではなくベージュのような色味。
以前、京都でできあいの木地に白漆と銀漆を使って塗りだけ特注して制作したお椀が画像にあるもの。
そのことを輪島の塗師の方に尋ねたところ、理由はよくわからないが、色粉は真っ白でも、漆に混ぜると真っ白にはならないらしい。
輪島塗のフリーカップ制作は木地までできて、次は漆塗の段階、本当ははじめから漆塗までを想定して制作をしていくのがよいのだろうが、漆器を木地から制作するのは初めてのことなので勝手がわからないのと、自分がつくりたい漆器を自分でつくるのが目的なので、予定調和的に進める必要がないから、まず木地、すなわち形だけを考えて、その中で漆塗のことまで考えることができたならば、それはそれでよいと思っていた。
実際は形を考えるので精一杯で、塗のことまで頭が回らずにいたが、形を考える中で人の気分もデザインとして取り入れようとしていたので、ただ漆の色だけをどうするかを考えるのではなくて、違う何かを元に考えたいと思っていた。それに漆の色だけを取り出して考えることは、木地のデザインの時に形だけを取り出して考えるのと同じで、単に恣意的操作をして、別に漆器でなくてもいいようなことに終始しそうで嫌だった。できれば漆器特有の何かを持ち込みたかった。
艶も操作できる。艶をより出すには、輪島の塗師から教わった話によると、漆に油を入れる、最終工程として鹿の角の粉末で磨くなどがあるそうで、普通の上塗りならば、マットな仕上げで、使い込んで行くうちに自然と艶が出てくるそうです。ただ塗師は人工的に出す艶は好みではないようだった。
手掛けの窪んだ部分だけを最終工程で磨いてもらって艶を出し、その他の部分は普通の上塗りにして、艶の差が形を強調するようにするか、あるいはその逆にして、手掛けの部分だけ普通の上塗りにして、一番手の当たる部分だから、使い込んで艶が出て、同じ艶ありでも他の部分の艶とどういう違いが出るのか見るというのもある。
色と艶をどうするか、これを最終的にどうするか、どう見せるかによって、例えば、溜塗などという透明な漆を塗って仕上げる技法もあるらしい。
ちなみに、輪島塗には木地に寒冷紗などを貼る「布着せ」と言われる工程があるのが特徴で、山中塗のような下地の木地を見せる漆の塗り方はできない。ただ、布着せをすることで、より丈夫になり耐久性が上がり、また割れても補修がきく。
色と艶をどうするかをずっと考えているが結論が出ない。というか、色と艶に関して考えれば考える程、どんどん興味を失っていく、どうでもよくなっていく。
色と艶を考えている時点で、当たり前だが、漆を塗るのが前提だから、器の木地に漆を塗る=漆器という図式の中にいることになり、それがどうもつまらない。それは、漆器にするために漆を塗る、ということになり、そこに違和感を感じてしまう。
器として、こうしたいから、こういうものにしたいから、たがら漆でないと駄目なんだ、だから漆を塗って器をつくるのだ、という考えのもとで塗りについて、またはじめから考え直してみたいと思うようになった。
"Oddness"
Besides black and vermillion, the color of lacquer can be chosen pretty much as color taste even if the color names are different, such as gold, silver, red, blue, green, purple, yellow, orange, There is not only white. To be accurate, white lacquer exists, but the color is not pure white but it looks like a beige.
Previously, in the image there is a bowl made by using white lacquer and silver lacquer on the finished wooden ground in Kyoto, custom made only for painting.
I asked the painter of Wajima about that fact, I do not know the reason well, but it seems that even if the color powder is pure white, it will not become white when mixed in lacquer.
Wajima coat free cup production can be made to wood, and next time it is better to produce lacquerware at the stage of lacquering, in fact from the start assuming lacquer coating, but to produce lacquerware from woodland Since it is the first thing, I do not understand selfishly, because I want to make lacquerware I want to make myself, so there is no need to proceed harmonizedly, so first of all consider the wooden area, that is, the shape, the lacquer If I could think about painting, I thought that would be fine.
Actually I was thinking about shapes so it was all they could and my head did not turn until the painting, but as I was trying to incorporate the mood of people as a design in thinking of shapes, just thinking about how to do just the lacquer color I wanted to think based on something different without it. Also, taking out only the color of the lacquer is the same as thinking only by taking out the shape at the time of designing the wood land, just doing arbitrary operation and seeming to start doing something that does not have to be a separate lacquerware I hated it. I wanted to bring something specific to lacquer ware if possible.
You can also operate gloss. According to the story taught from the painter of Wajima, according to the story taught from the painter of Wajima, it is said that there is an oil in the lacquer, as a final process there is polishing with powder of deer horn, if it is ordinary top coat, with a mat finish, It seems that nature and gloss come out while using it. Just a painter seemed not to like taste artificially.
Only the depressed portion of the hand is polished in the final process to give a gloss and the other parts are ordinary top coat so that the gloss difference emphasizes the shape or vice versa, Since it is an ordinary top coat, since it is the part where the hand is hit the first time, gloss comes out and gloss comes out, and there is also a case to see what difference is made with gloss of other parts even if there is the same gloss.
There seems to be a technique to finish by painting transparent lacquer such as sand coat depending on how to color and gloss, how to finally do this and how to show it.
Incidentally, Wajima Coating is characterized by having a process called "clothing" that affixes cheesecloth and the like to wooden plants, it is not possible to paint the lacquer showing the woodland of the underlying like Yamanaka painting. However, clothing makes it more durable, durability rises, and even if it cracks, it will be repairable.
I have thought about how to color and gloss forever, but I can not draw a conclusion. Or, if you think about color and luster, you think about it, you lose interest more and more, no matter how it goes.
At the time of thinking about color and gloss, it is natural, but because it is a premise to paint lacquer, it will be inside a diagram called lacquer wrapping lacquer on the wooden piece of a vessel, which is really boring. It means that it is painting lacquer to make it a lacquer ware, and it makes me feel uncomfortable there.
As a container, I want to do this, because I want to do this, it is useless unless it is lacquer lacquer, so I would like to try painting under the idea of painting lacquer to make a vessel, and thinking from the beginning Became.
出来上がった木地は、私にとってまるで縄文式土器のように思えた。
輪島塗のフリーカップの形をどうしようかと考えている時に最初、縄文式土器を参照した。その形は素晴らしいものだが、私が求めている形ではなかったので、ただ、その精神性は引き継ぎたいとは思っていた、と出来上がった木地を見ながら思い出した。それまで、そのことを完全に忘れていたが、無意識にその精神性を大事にしていたのかもしれない。
フリーカップの木地を見て、縄文人のDNAから湧き上がってきたような唯一無二の精神性を感じる縄文式土器のように思えたことは、この木地の形が私の根源的な精神性を表現することができたのではないかと思い嬉しかった。
輪島の塗師から朴(ほう)木地職人が制作した木地が送られてきた時、木地を見るのは楽しみではあったが、信頼してお願いしたとはいえ、正直不安もあった。スケッチには絵として起こしていたが、こちらの意図をくみ取ってくれるだろうか、曲線の具合や角の仕上がりなど。
そもそも、自分が欲しい形をスケッチにはしていたが、実際の形になった時にはまた違うはず、ズレが生じるはずで、そのズレが許容できるものか。本当ならば、試作を繰り返したいのだが、そうもいかず、例えば、私の好きなデザイナーの柳宗理は石膏で試作を繰り返したそうだが、その技術も装備もないので、考えていたのは、出来上がってきた木地を修正をすることぐらい。
このこともあり、後に3Dプリンターを導入した。これで完全とはいかないまでも、ある程度繰り返し試作ができるようになった。
全くの杞憂だったというか、私自身が朴木地職人の伝統技術を失礼なことに過小評価していたのかもしれない。偏心させて、窪ませて、非対称の形にしたこの複雑な形を見事に木地として仕上げてくれた。スケッチから形を完璧に理解し、こちらの意図をきちんとくみ取って、スケッチでは表現しきれていない所まで、実に痒い所に手が届くが如く、こちらがこうして欲しいと思っていたことがきちんと出来ていた。
飲み口の厚みが雲形に不連続に変化するように滑らかな曲線を描き、カップの側面の手掛けとして窪ませた部分も同じように滑らかな曲線を描くようにしたかったが、スケッチでは側面の窪ませた部分の形状をわかりやすく、基準となる数値を入れるために、どうしても曲線の滑らかさを表現しきれていないような気がしていた。ただ、このスケッチの通りに制作していくと、自然と滑らかな曲線になるだろうから、もし滑らかさが足りなければ、後で修正してもらおうと思っていた。
これが全くの見当違いだった。当たり前のように、私がして欲しかったことがきちんとできていた。本当に腕のよい職人と仕事をした後はいつもこうで、私の心を見透かしているのではないかと思うくらいに、そうするのが当然が如くに仕上がっており、輪島の朴木地職人の伝統技術の底力にただただ敬服するしかなかった。
"Underlying power of craftsman"
The finished wood land seemed to me like a Jomon style pottery for me.
When I was thinking about what to do with Wajima-covered free cup shape, I first saw Jomon style pottery. Its shape is wonderful, but because I was not in the shape I was looking for, I remembered watching the finished woodland that he wanted to take over the spirituality. Until then, I had completely forgotten about that, but I may have unwittingly taken care of that spirituality.
It seemed like a Jomon style pottery that felt the only spirituality that seemed to have risen from the Jomon people's DNA, looking at the free cup wooden ground, this woodland shape is my fundamental I was happy that I thought that I was able to express my spirituality.
When the woodland produced by the painter of Wajima was sent from the painter, it was pleasure to see the woodland, but I was honestly worried even though I trusted him. I woke up as a picture in the sketch, will it take away the intention of this, such as the condition of the curve and the finish of the corner.
In the first place, I was sketching the shape that I wanted, but when it comes to actual shape it should be different again, it will cause a gap, is the gap acceptable? If it is true, I would like to repeat the prototype, but I do not think so, for example, Mr. Yori Yanagi of my favorite designer repeated prototyping with plaster, but because there is neither that technology nor equipment, I was thinking about it It is about correcting the wood land.
As a result of this, we introduced 3D printers later. With this it is possible to prototype it to some extent even if it is not perfect.
Perhaps it was a totally unfounded situation, or maybe I myself underestimated the rude traditional techniques of Park Jukdo. It was eccentric, concave, finished as an asymmetrical shaped splendidly as a woodland. I understand the shape perfectly from the sketch, properly take out the intention of this, properly reaching the itchy place until it can not be expressed in the sketch, as I thought that I wanted this to be done properly It was.
I wanted to draw a smooth curve so that the thickness of the drinking mouth changes discontinuously in a cloud shape, so that the depressed portion as a handrail on the side of the cup also draws a smooth curve in the same way, but in the sketch, It was easy to understand the shape of the part that was not, and I felt that I could not express the smoothness of the curve by all means in order to put the reference numerical value. However, as I make it according to this sketch, it will be naturally smooth curves, so if I'm not smooth enough I thought I would correct it later.
This was absolutely wrong. As it is natural, what I wanted was done properly. After working with a truly skilled craftsman, this is always like this, it seems natural to think that it seems to me to see my mind, so it is natural that it is done, traditional techniques of Parkjik place craftworkers in Wajima I just had to admire the bottom power of the.
輪島で塗師に出会うきっかけをくれたのは、輪島の割烹料理屋の大将だった。はじめて輪島に行った時にたまたま行ったお店の大将で、カウンター越しにいろいろな話をしていたら、漆器の話になり、そっと内緒で塗師の連絡先を教えてくれた。
そのおかげで、今こうして木地を手にし、塗りのことを考える機会を得ているので、輪島に行く時は必ずそのお店を予約して行こうと思い、来週輪島に行く予定なので、すでにお店には予約を入れてある。
前回、木地のスケッチを持って輪島に行った時も夜に予約して行った。はじめて行った時は輪島塗のカウンターの大将の前だったが、この時はカウンターでも大将から一番遠い所、大将の前は常連らしき人が座っていた。ただ、大将はカウンター内で黙々と調理しており、目の前の常連さんとも話をしていない様子だった。
入って行った時に大将と目が合い、軽く挨拶をして通された席に座ったが、3ヶ月ぶり位に行ったので、覚えてくれているのかいないのか。見たことあるかないか位かなと思い、席だけの予約だったので、アラカルトで何か注文しようとメニューを見て、
のどぐろの刺身、焼き白子、白海老の天ぷらなどを肴に、輪島の地酒を呑んだ。
お店に来るまでは、大将に会ったら何を話そうかな、あの時から今日までのこと、本当に漆器をつくろうとしていることに驚くかな、そもそも覚えているかな、などいろいろ考えてはいたが、
いざお店に来て、お酒を呑みはじめると、特に無理をして大将と話そうとはしなかった。忙しく調理していたし、自然に話す機会があればいいし、無ければ無くてもいいしという感じだった。こうして、また輪島に来て、また大将のお店に来る、というのだけで充分だという想いになっていたから。
今日のことに思いをはせ、明日のことに気を配り、そろそろ酔いも程よく回ってきたので、結局大将と話す機会は無かったが、ホテルへ帰ろうと、カウンターを立ち、大将の前で、ごちそうさまでしたと軽く会釈をしたら、大将は目線も合わせず、何も言わず、ただただ満面の笑みだった。
その時に、この大将はそういう人なんだな、きっと前のことを全部覚えていて、また来てくれた、と思っているに違いない、その笑顔を見てそういう気がした。
"Communicate"
What gave me the chance to meet a painter in Wajima was the general of a cooking restaurant in Wajima. When I went to Wajima Island by chance at the store who happened to happen by chance, if I had talked a lot through the counter, I was talking about lacquerware and gently taught me the contact address of the painter.
Thanks to that, now I have the opportunity to grab the wood land and think about painting, so whenever I go to Wajima I definitely want to book the shop and I will go to Wajima next week There are reservations in stores.
Last time I went to Wajima with a sketch of wood land and even booked it at night. When I went for the first time, it was before the general of the Wajima coat counter, but at this time the counter was also the most distant from the general, before the general was a regular seeming person sitting. However, the general was cooking silently in the counter and it seemed that he was not talking to regulars in front of his eyes.
When I entered, the eyes met with the general, I greeted lightly and sat in the seated seat, but I went to the first time in 3 months, so do not you remember? Because I thought that there was something I had seen, because it was a reservation only for the seat, watching the menu to order something in an à la carte,
I drank local sake from Wajima with a fridge sashimi, baked baki, tempura of white shrimp and so on.
Until I came to the shop, I was thinking about various things, such as what I should talk about when I meet the general, from that time to today, whether I am surprised that it really is making lacquerware,
When I came to the shop and started drinking alcohol, I did not try to talk to the general general, in particular. I was busy cooking and had the opportunity to talk naturally, and it was feeling that it would not have been necessary if there was nothing. In this way, I came back to Wajima again and I was feeling that it was sufficient to just come to the general shop.
Taking a thought on today, I was careful about tomorrow, so I got better sickness soon, so I had no chance to speak with the general after all, but I set up a counter to go back to the hotel, in front of the general, When bowed lightly as if it was a feast, the general did not match his eyes, did not say anything, it was just a full smile.
At that time, this general is such a person, I surely remembered all of the previous things, I think that I came again, I felt like seeing that smile.
価格の話は一切していない、期間もいつまでという制限もない。塗師のご主人からは少し時間を下さいと言われただけ。持参したスケッチの通りに木地をつくって欲しい、私の要望はこれだけ。
私にとって塗師のご主人、朴(ほう)木地職人を信頼して任せるとはそういうことだった。自由度を最大限に高くすること、拘束する部分を最小限にすること、私が誰かを信頼して任せる時に気をつけていることはこれで、私の要望が満たされるならば、あとのやり方は全て相手本位、私はそれに合わせるだけ。
なぜそうするか、私はその人の技術を信頼して任せる訳だから、その人が自分の技術を一番発揮しやすい環境をつくるのが私の仕事だと思っているから。
ただこれは考えようによっては一番厳しい条件を突きつけているのと同じかもしれない。だって、やり方もお金も時間も全てあなたの希望をのみますから、あなたが持っている技術をフルに発揮して完璧なものをつくって下さい、言い訳はできませんよ、半端は許しませんよ、ということを暗に言っているようなものだから。そのことは一流の職人になればなるほどわかるはずで、ただ、技術の高い職人はそのようなことは当たり前のことで、それを精神的なプレッシャーだと感じる人はいない。
だから、こちらも承知の上で、肝心なところだけ確認して、朴木地職人との打合せは10分で済み、余計なことを言わずに朴木地屋さんをあとにした。
後から振り返れば、もう少し伝えたいことも正直あった。スケッチとして絵としては渡してきたが、行間というか、ニュアンスというか、意図をうまくくんで欲しいところは言葉で補足した方がこちらは安心する。
ただ、いつもそう考えているのだが、信頼して任せている関係で、自分が安心したいから、何かを確認する、伝える、指示することは絶対にしないようにしている。意図をうまくくんでくれる人だと信頼している人なのだから、任せた以上は余計な手出しをしない。例え一時的にうまくいかなくても、自分の心配を消すために行動しない。そこで行動してしまうと、信頼して任せている関係が崩れるから。ただ、伝える、確認することもコミュニケーションとして必要な時もあるから、この判断は難しいところで、それにうまく意図をくんでくれない場合もあるかもしれないから、その時は自分が責任を負うつもりで、そうなってもいいような最低限の準備はしておく。これを貫かないと、信頼して任せられる人にいつまでたっても巡り合わない。
ちなみに、最低限の準備をリスクヘッジという人がいるかもしれないけど、それは違う。リスクヘッジとは、リスクがあることが前提で、何かトラブルが起こることが前提だが、私はそもそもノーリスクなことしかしない。信頼して任せられる人がいれば、チャレンジしてもはじめからリスクなど存在しない。だから、リスクヘッジをするからリスクを呼び込みトラブルになる。リスクヘッジをすればする程、失敗する確率が高くなる。
塗師のご主人から輪島塗のフリーカップの木地が届いたのは2ヶ月後だった。木地を触りながら、眺めながら、塗りをどうするかずっと考えていた。
"Entrust"
I do not talk about prices at all, there is no restriction that the term is also how long. It was said that the painter's husband told us to spare some time. I want you to make a wooden street according to the sketch I brought, my request is this alone.
That was the case for me to trust the painter's owner, Park Hui woodland craftworker. To maximize degrees of freedom, to minimize the restraint part, to be careful when I trust someone is this, if my request is satisfied, All ways are opponent, I just adjust it.
Because I think that it is my job to create an environment where people can best demonstrate their skills because I am going to trust that person's technology.
However, this may be the same as thinking the most stringent condition depending on thinking. Because, as well as the way, money and time all hope for you only, make full use of the technology you have and make perfect things, excuses you can not, he says it will not forgive you It seems to be said that it implies things. The more it becomes a first-class craftsman, the better it is, the higher craftworker of technology is such a thing, it is natural that no one feels that it is spiritual pressure.
Therefore, after consenting to this, we confirmed only the essential point and we had a meeting with Park Hwa craftmen in 10 minutes, and we left Park Hokkaido without saying anything extra.
Looking backwards, I also honestly wanted to tell a bit more. Although I handed it as a picture as a sketch, I'm relieved here if you supplement it with words, where you want the intention to succeed, whether it is between lines or nuance.
However, although I always think so, I do not absolutely do not confirm, tell, or instruct something because I want to be relieved with the relationship I trust to leave. It is a person who trusts that he is an intelligent person, so do not extra handouts beyond what I leave. Even if it temporarily fails, I will not act to put out my concern. If you do act there, trust and leave the relationship that you trust. However, there are times when it is necessary to communicate, to tell, to confirm, because this judgment is a difficult place, there may be times when it does not make it well for it, so at that time I will assume the responsibility, so Prepare minimum necessary for it to be good. If you do not go through this, you will never meet a trustworthy person forever.
By the way, there may be some people called risk hedging as a minimum preparation, but that is not the case. Risk hedging is a prerequisite that something will happen on the premise that there is a risk, but I do nothing but a noisy thing in the first place. If there are people trusted, there are no risks from the beginning even if you challenge. Therefore, he risks hesitating and calls for risk and becomes trouble. The more you risk hedge, the higher the probability of failure.
It was two months after the painter's husband arrived the Wajima-covered free cup wooden land. While touching the woods, I was thinking about how to paint while watching.
見てすぐに理解したようだった。横からこのスケッチに描かれている非対称の形を詳しく説明しようとしたけれど、朴(ほう)木地職人の様子を見て、すぐに簡単な説明に切り替えた。すでにどうやったらこの非対称の形をつくることができるのかを考えているようだったので、横から話し掛けるのをすぐに止めた方がよいと思ったから。
段々と深く深く考えが沈んでいく様子がわかった。白い紙にメモ書き程度のスケッチを描きながら考えている。こうやればいい、いや、それではできない、ならこうするか、手の動きがそう語っている。横で見ている方は嬉しい、真剣に考えてくれて。
それにしても、このスケッチ、自分で言うのもなんだけど、必要な寸法は全て書き込みをしてあるけれど、拙い。なのに、私が求めている形を瞬時に頭の中にイメージできているようで、全く補足説明がいらない。それよりも、どうしたらこの形がつくれるのかが最大の関心事になっており、それが解決するまで、誰も話し掛けられない、黙っているしかない雰囲気が作業場に流れていて、私も塗師のご主人も一言もしゃべらずに、朴木地職人が次に発する言葉を待っていた。そこには緊張感があり、でも私はこの時間が愛おしく思えた。だって、自分が考えたデザインが立ち上がろうとしている、それも一流の職人の手で。デザイナーにとって、これ程の喜びはないのではないのだろうか。心血注いでひねり出したものが実際に現実に形になるのだから。
スケッチの非対称の形を半分にして、木の塊からその半分の形を削り出し、最終的に2つをひとつにして、底に蓋をする。
木の塊から削り出す、それは確かに可能だけれども、そんなことをするんだと、それは技術力があるが故の力技かもしれないけど、そこまでしないとやはりこの非対称の形がつくれないのか、 1個しかつくれないな、量産は無理だな、元々量産するつもりはないけれど、あと2個ほど制作して、知人にあげようと思っていたので、ただ黙って受け入れて、とにかくこの形が実現することが嬉しくて、朴木地屋さんを後にすることにしたけれど、
滞在時間はわすが10分、この10分の間にこの非対称を解決した朴木地職人の技術力にただただ感嘆するしかなかった。それもこのスケッチの肝を抑えていて、一番見せたい所をここでしょと見抜いていた。なぜそれがわかったかというと、飲み口の厚みについて話をした時に、一番薄い所が2mmになる、ただしそれは一点だけたがら、2mmでも成り立ちますよね、と話した時、それをみなまで言わないまでもわかったから。
他の人はどうだかは知らないけれど、自分が描いたスケッチ、それがそのまま実現するのだから、これ程嬉しいことはない。
"Craftsman"
It seemed to understand immediately as I saw it. I attempted to explain in detail the asymmetric shape drawn on this sketch from the side, but I immediately switched to a brief explanation as I looked at the state of the craftsmen of Park. It seemed like how I could already make this asymmetrical shape, so I thought that it would be better to stop talking from the side immediately.
I learned that the idea sank down deeply and deeply. I'm thinking while drawing sketches of notes on white paper. No need to do this, no, if you can not do it, do it like this, the movement of the hand says so. Those who are watching by side are happy, they think seriously.
Even so, this sketch, what I say on my own, but I have written all the dimensions I need but it is awkward. However, I seem to be able to instantly image the shape I am seeking in my head, so I do not need any supplementary explanation at all. More than that, how to make this shape is the biggest concern, until the solution is resolved, nobody can talk to it, there is only an atmosphere that is silent is flowing to the workplace, I am a painter Your husband also did not speak a word, and waiting for the words that Park Mokuchi craftsman would give next. There was a feeling of tension there, but I think this time was lovely. Because, the design I thought is going to stand up, it is also handed by first-rate craftsmen. I wonder if there is not such pleasure for designers. Because what actually threw out with heartblood pouring actually forms in reality.
Halve the asymmetrical shape of the sketch, cut out the half shape from the wood chunk, finally make one in one and cover the bottom.
Although it is certainly possible to do it, although it is certainly possible, if it does such a thing, it may be a power skill of the late although there is a technological power, but if we do not do it we can not make this asymmetrical shape again , I can make only one, mass production is impossible, I do not intend to mass-produce, but since I was thinking about making two more pieces and giving to acquaintance, just accept it silently, anyway this shape is I am happy to realize it, I decided to leave Park Parkya,
The staying time was merely 10 minutes, I just had to admire the technical power of Park Jukdo craftmen who solved this asymmetry in the last 10 minutes. It kept the liver of this sketch down, and I thought that the place I wanted to show the most was here. When I talk about the thickness of the drinking mouth, the reason why I found out is that the thinnest part will be 2 mm, although it only holds one point, it will be true even if it is only 2 mm, I will not tell it all Because I understood it.
I do not know how other people are, but there is nothing I'm happy about as this is the sketch that I draw, that will be realized as it is.
椀木地職人との打合せでも、やはり問題になったのが非対称の形だった。輪島塗フリーカップ制作のおいて、まずは木地の形をどうするか、これに関しては自分なりに満足のできるデザインの所までは行った。建築の場合もそうだけれど、イメージや構想を設計やデザインやスケッチとしてまとめ上げるのはかなりの労力を要するが、それで終わりではなく、むしろここからが本番で、この設計やデザインやスケッチを実現するために、誰に声を掛け、誰と話し、誰につくってもらうかを考えて、だから、こう準備して、こう伝えて、それにどう関わるかが重要になる。実現する段階でこれらひとつでも間違うと、せっかくまとめ上げた設計やデザインやスケッチ通りのものができず、残念な結果になる。
それだけは避けたかった、本当にこの木地のデザインが気に入っていたから。ただ、今回は全く誰もツテがない所からはじめて、お会いする人全てがはじめての方ばかりで、短時間で関係づくりからはじめるので、実際に実現することを全くと言ってよい程コントロールができない、ぶっつけ本番のようなものだった。
こういう場合、今までの経験上、依頼を請けてくれる職人の方の意識が高く、腕がよくないと、うまくいかない。そこはもう輪島の職人の方々を信頼するしかなかった。
椀木地制作の過程でも、全体の形が対称のもので厚みが違うだけならば、回転する木材にノミの角度を変えて入れてやればできるとのことで、実際にそれは今までに行ったことがあるそうで、見本(画像のもの)も見せてもらった。
ただ、それはあくまでも全体の形が対称ならばの話で、私が持って行ったスケッチを眺めながら、塗師のご主人、椀木地職人、私とで、どうしたらこの非対称の形をつくり出すことができるのかを一緒になって考えていた。
もともと回転する木材にノミを入れて成形するやり方だと、対称の形はつくりやすく、非対称の形は無理なのではないかと思っていた。私の木地職人の作業の仕方に対する勝手なイメージが椀木地制作の要領だったので、スケッチを描きはじめた当初から、この非対称の形が本当にできるのかどうか半信半疑だったが、それでも厚みを変えることができるのだからと、いろいろと考えて提案してみた。
例えば、2個1にするなど。左右別々に対称形のものをつくり、縦に半分にして、左右それぞれ別のものを組み合わせて1つのものをつくるなど。これは塗師のご主人も私もできるような気がしたが、椀木地職人はできることとは思わなかったようだった。
できるかもしれないという勘みたいなものが働く時は大抵、例えすんなりとはいかなくても、できるもので、できることとは思わない時には、全くと言ってよいほど、かもしれないすら思わない。それは長年の経験からくる勘だと思うが、できない時にはハッキリと「できません」と言ってくれた方がむしろありがたい。
この人ができない、やめた方がよいと言うならば、素直にやめようと思える人と一緒に仕事がしたい、といつも思っているので、塗師のご主人や椀木地職人の方には、素直にそう思えたので、椀木地職人が「うちではできないですね」と言った時には素直に従えた。
あとは塗師のご主人に任せるしかない。ご主人には他にアテがあるらしく、ここでは断念して、他の木地屋さんに行くことになった。
ただ、この椀木地職人の方には、プロとしての気構えと、意識と技術の高さを感じて、とても気持ちのいい打合せができ、この椀木地屋さんで過ごした時間は短くも楽しいものだった。
"Leave it to trust"
Even with a meeting with a bowl of woodland craftsman, what was still a problem was asymmetrical form. In Wajima coat free cup production, we first went to the place of design that can satisfy ourselves as to how to shape the wood land. Even in the case of architecture, it takes considerable effort to design images, concepts and design as a design, sketch, but it is not the end of it, rather it is real from here, in order to realize this design, design and sketch So, who is talking to, talking to whom and talking to whom, thinking about who to make it, so prepare this, tell them how it is important to know how to do that. If you mistake one of these at the stage of realization, you can not do the design, design or sketch that you gathered together, which is disappointing.
I wanted to avoid that much, because I really liked the design of this woodland. However, this time for the first time since nobody gets tired, it is only the first time for all of you to meet up, so we start with relationship creation in a short time, so we can not control as much as we actually can realize , It was like a batting turnaround.
In such cases, experience is that if the consciousness of the craftworker who undertakes the request is high and the skill is not good, it will not work. There was no other choice but to trust the artisans of Wajima.
Even in the course of producing bowls and woods, if the entire shape is symmetrical and the thicknesses are different only if you change the angle of the fleas to the rotating wood and you can do it actually I heard that there was something I had and a sample (image one) was shown.
However, that is only a story if the whole shape is symmetrical, while seeing the sketch that I brought, with the painter's owner, a bowl of woodland craftsmen, and me, how to create this asymmetric shape I was thinking about what I could do.
I thought that it is easy to make a symmetrical shape and not an asymmetrical shape if it is a way to insert fleas into rotating wood. Since the arbitrary image of how my woodland craftsman worked was the way of making bowls and woodlands, from the very beginning I began drawing sketches, I was dubious about whether this asymmetric shape could really be done, but still change the thickness Because I can do it, I thought variously and made a suggestion.
For example, 2 to 1 and so on. Make symmetrical ones separately on the left and right, half in length and combine different ones on the left and right to make one thing. Although I felt that my husband and master of a painter could do it, it seemed that bowl of woodland craftworker did not think that I could do it.
When something intrinsic that it might be possible works, most of the time, even if you do not get rushed up, you can do it, even when you do not think you can do it, I do not even think that it might be totally. I think that it is an intuition that comes from many years of experience, but it would be much appreciated by those who told me that it can not be "clear" when it can not be done.
If this person can not do, saying that it is better to quit, I always think that I want to work with someone who seems to stop obediently, so if you are a painter's owner or a bowl of woodland craftworker, So I thought obediently when a bowl of woodland craftworker said "You can not do it at home."
The rest is left to the master of the painter. Your husband seems to have other attes, so we abandoned here and decided to go to another wooden store.
However, for this bowl of woodland craftworker, feeling as professional, feeling the height of consciousness and technology, I was able to make a very pleasant meeting and the time spent at this bowl of the wooden store was short but fun It was.
輪島塗のフリーカップ制作は輪島での木地制作の段階になり、塗師のご主人に新幹線の中で描き上げたスケッチを見せながら、このフリーカップの非対称な形についてわかってもらおうといろいろと説明した。その時には、どうしてこの形なのか、自分の考えていたことは何も説明しなかった。
今まで木地制作の経験がなく、どこまで制作可能かがわからなかったので、書き上げたスケッチの通りに木地が制作できる確信が持てなかったから、とにかく、この非対称な形について説明し、できれば、その場で制作は可能のような言葉が聞きたかったのかもしれない。
そもそも制作不可ならば、どうしてこの形なのかも、自分の考えていたことも、どうでもよいことになるので。
ご主人には事前に木地屋さんを見学したいとお願いしていたので、とりあえず、スケッチを持ってご主人と一緒に木地屋さんへ行き、木地職人の方をまじえて話をすることになった。
移動の車中、この状況はいつもと同じだな、と思いながら、ご主人と世間話をしていた。既視感のないものや空間をつくりたいと思っているので、毎回今まで設計したこととは違うことをするから、必ずと言っていいほど、実際に手を動かす職人をまじえて、どう施工するかを打合せする。
ただ建築の場合だと、どこまで施工可能かはわかるので、そもそも全く施工不可なことはやろうとしないので、たまに羽交い締めされるように待ったがかかることはあるが、ここで今自分が考えていることやしたいことを素直に話す方が一緒に打合せしている人たちの士気を高め、話の道筋もはっきりするので、ではこうしよう、あーしようと意見も出てきやすくなるし、そもそも、はじめからできないと言わずに、できる方法をいろいろと考えてくれる人たちと仕事をしているので、尚更のこと、今自分が考えていることやしたいことを素直に話す方がよいと思っている。
ちなみに、私の勝手な思い込みだが、腕のよい職人ほど、はじめにできないとは言わずに、こうすればできるかもしれないと、柔軟にできる方法を考えてくれる。はじめにできないと言う職人は単に技術がないか、自分の技術に自信がないのだ。
漆器の木地屋さんには4種類あるらしい。お椀などをつくる椀木地、お盆などをつくる曲物木地、お重などをつくる指物木地、仏具などをつくる朴(ほう)木地。
最初に行ったのは椀木地屋さん。ここでは回転する木材にノミのような刃物を当て、あっという間にお椀の形に仕上げていく。その時にお椀の形を決めるのが型板。代々伝わっているもので、椀木地屋さんによって、この型板の曲線の曲率が違うとのこと。この型板をお椀に押し当てて、ピタリと合うまで成形するそうです。
最初にお椀づくりの実演を見させてもらってから打合せに入った。この椀木地職人の方とお会いするのははじめてでしたけど、これから打合せをするのが楽しみになるくらい、よい雰囲気を持った職人の方でした。
"Beginning of production"
Wajima-covered free cup production was at the stage of woodland production in Wajima, while showing the sketch drawn in the Shinkansen to the master of the painter while explaining various asymmetric shapes of this free cup . At that time, I did not explain why I was thinking about this form.
Until now I have not had experience of wood land production and I was not sure how far I could produce it so I could not produce the woodland as I did in the sketch I wrote so anyway I could explain this asymmetrical shape, Perhaps he wanted to hear words like production that could be produced in the field.
In the first place, if it is impossible to produce it, why is this form, what you were thinking is nothing to do.
As my husband asked me to visit the wooden store in advance, I decided to go skating and going to the lumber store with my husband and talking with a woodland craftsman.
While thinking that this situation is the same as usual in the moving car, I was talking with the husband over the matter. Since I'd like to create something with no sense of dead vision or space, I do different things from what I have designed so far, so it is always certain that I can not say how much it is practiced by craftsmen who actually move their hands I will meet up with you.
However, in the case of construction, since we know how far it can be constructed, we will not do anything that is impossible at all in the first place, so we sometimes have to wait for feathers to be squeezed but something that we are thinking right now Those who speak frankly talk about what they want to do are raising the morale of the people who are meeting together and the path of the talk is also clear, so let's try it, it will make it easier to comment, and in the first place you can not do it from the very beginning And without saying, I work with people who think about various ways, so I think that it is better to speak frankly what I am thinking and what I'm thinking now or more.
By the way, although I am selfish thought, I do not say that a skilled craftsman can do it at first, but I think how to do it flexibly if I do this way. A craftsman who says not to be able to do it at first can not have confidence in technology or just technology.
There seem to be 4 kinds of lacquerware wooden store. Bowls making bowls and the like Birch wood lining, Bon festival curved woodlands, things to make heavyweight woodlands, Buddhist wooden buildings, etc.
The first thing I went was a wooden bamboo shop. Here, we apply a flea-like blade to rotating wood and finish it in the shape of a bowl in a blink of an eye. It is the template that decides the shape of the bowl at that time. It is said that the curvature of the curve of this template is different depending on the bowl of the wooden store. It is said to press this template against a bowl and mold it until it fits perfectly.
I first got to see the demonstration of bowl making and then started meeting. It was my first visit to this bowl of woodland craftsman, but it was a craftworker with a nice atmosphere as much as I look forward to meeting up now.
輪島塗のフリーカップは木地までできていて、今、塗りをどうするか考えている段階。
カップの木地の形を決める上で一番難航したのが、飲み口から手で持つ部分までの大きさの絞り方。飲み口の直径85mmは手で持つには大きくすぎる。だから、手で持てる大きさまで形を絞らなくてはならない。
まず最初の手かがりとして、手で持つ部分の直径をいくつ位にするか?本当は最初、形の絞り方ばかり考えていた、どのような絞り方をすればいいのかと。でも全然決まらない。考えれば考えるほど、気に入らないものになっていく。たぶん、それは見た目の形をどうすれば美しくできるのかだけを考えていて、単なる形態操作になり、恣意的な作業ばかりをしていたからかもしれない。
最終的に美しさを纏った形にしたいが、それは形をどうするかだけの話ではないと思う。
このフリーカップをどういうものしようかと考えはじめた時、一番最初に参照したのが縄文式土器。岡本太郎が昔から好きで、特に作品よりも考えやものの見方が好きで、岡本太郎は縄文式土器の造形美を参照し、自身の作品の創作に生かしていたので、そのことが一番最初に頭に浮かび、資料を見たり、実際に博物館へ縄文式土器を見に行ったりした。
縄文式土器を見ていくと、一見実用とはかけ離れた装飾性を感じ、形態操作だけをしているように思うが、そこには縄文人のDNAから沸き起こってくるような唯一無二の確固たる精神性を感じてしまう。きっと造形美とは、形態操作の果てにあるのではなくて、そこに込めるつくり手の精神性からしか生まれないのではないかと思った。
それもあり、単なる恣意的な形態操作はしたくなく、徹底的にそれを排除しようとしていたので、飲み口から手で持つ部分までの大きさの絞り方に難航した。絞り方を考えることは単に形態操作になってしまうから。
恣意的な形態操作を避けるため、手で持つために絞るという目的以外に、何か別のことを重ね合わせたかった。それがカップ全体の存在を決めるようなことであれば尚よいのだが、それがなかなか思いつかずに難航した。
結局、輪島の塗師に見せる木地のスケッチを書き上げたのは、金沢行きの新幹線の中だった。
"What is beauty"
Wajima-covered free cup is made up of wood, and now we are thinking what to paint.
The most difficult way to decide the shape of the wooden cup is to narrow down the size from the drinking mouth to the part that it holds by hand. The diameter of the drinking mouth of 85 mm is too large to hold by hand. So you have to shape down to the size you can hold with your hands.
First of all, how much is the diameter of the part held by hand as the first hand crawl? In fact, initially, I was thinking about how to narrow down the shape, what kind of diaphragm should I do? But not at all. The more you think about it, the less you like it. Maybe it is because I was just thinking about how to make it look beautiful, it was just a morphological manipulation and I was only doing arbitrary tasks.
I would like to eventually shape beauty, but I think that is not the only story about how to shape.
When I started thinking about what to do with this free cup, I first referred to Jomon style pottery. Okamoto Taro liked from long ago, especially liked the view of ideas and things than works, Taro Okamoto used the beauty of the Jomon style pottery and used it to create his own work, so that was the first time I went to the head, watched materials, and actually went to the museum to see Jomon style pottery.
As I look at the Jomon style pottery, I think that it seems to be decorativeness far apart from practical use, I only think that it is only manipulating the form, but there is a unique and unique firm that seems to be boiling from the DNA of the Jomon people I feel spirituality. Surely beauty of formality is not at the end of morphological manipulation, but I thought that it could be born only from the spirituality of the making hands that can fit in there.
There was also it, I did not want to do mere arbitrary form manipulation, I tried to eliminate it thoroughly, so I faced difficulty in narrowing down the size from the drinking mouth to the hand holding it. Because thinking about throttling is merely a form manipulation.
In order to avoid arbitrary form manipulation, I wanted to superimpose something else besides the purpose of squeezing it for holding with hand. It would be even better if it was like deciding the presence of the whole cup, but it seemed difficult to think hard.
In the end, it was in the Shinkansen to Kanazawa that I wrote the sketch of the woodland that I showed to the painter of Wajima.
住空間で見えるもの全てが建築だという考えから、何でも制作するし、もちろん、それらの物が大好きだから、どこでどのような物を手に入れることができるか、大体は頭に入っているが、
専門は建築なので、まだ、漆器を木地からつくったことが無く、漆器を木地からつくりたいと思っても、何のツテもなかった。
今年1月、金沢に行く予定ができたので、ならば輪島まで足を伸ばして行ってみようと思った。輪島に行き、有名な朝市にでも行き、そこに出ている漆器のお店に一軒一軒当たれば、どこかしら相手にしてくれるだろうと漠然と考えて。
輪島に着いたのは夕方だったので、当たりはすでに暗く、お店は飲食店しか開いていなさそうだったので、土地勘も無いし、明日に備えて何か美味しいものでも食べようと思い、ビジネスホテルから近い割烹料理屋さんを予約して行った。
一見無愛想にも見える大将が忙しく動き回っているカウンターに腰掛ける。地物の肴をあてにひとりゆったりと地酒を呑んでいた。金沢には随分前に一度来たけれど、能登ははじめて、ホテルの周りには何も無く、その割烹のお店があるだけだから、辺りは真っ暗、でもこのお店の灯りが和ませてくれた。
だいぶホロ酔いになり、地酒をあと1合呑もうかどうしようか、と思っている時に、お店の忙しさのピークが過ぎたのだろうか、ビールが入ったグラスを右手に持った大将が頬を緩めながら、カウンター越しに目の前に立ち、
「どこから来たの?」
と話しかけてきた。
その口調はやわらく、人懐っこく、さっきまでの無愛想な感じとは全く違っていた。だって、今までほとんどしゃべらないし、いらっしゃいませもなかった。
唯一、〆鯖を注文した時に、
「今日は鯖が無いんだ」と言われ
「じゃあ、仕方ないですね」と返したら
後で、鯵のぬたを
「〆鯖出せなかったから、これサービス」と言って出してくれたくらい。
普通に「東京です」から話はそれにそれて、大将がここで店を開くまでの由来、流れの板前で、包丁だけを持って全国を回ったとか、本当は引退しようと思っていたけれど、どうしてもと請われ、今のお店をはじめたなどなど。
そんな話をしながら、流れで漆器はいいですね、なんて話をしたら、大将がカウンターにお店で使っている漆器を並べはじめた。
自分も輪島出身で漆器が好きだからと、特注でつくったものや、食洗機に入れてだいぶ漆の光沢がなくなったものと塗り直しやつを見比べたり。
「特注でつくってくれるんですね」
なんて言いながら、漆器を木地からつくりたくて、と自分の話をしてみた。ツテがないから、どこか漆器屋さんに入って、つくってくれるところを探そうかと。
「つくってくれますかねぇ」と大将に尋ねたら
「それはあんたの想いをぶつけることだね」と。
自分がつくりたい漆器は1つか2つくらい、大体、木地から特注で、となるとある程度数を頼まないとつくってくれないだろう、大将はお店で使うから数もあるから特注できたのでは、と思っていたので、意外な返答だった。
「その特注の漆器をつくった所を教えてください」
と思いつきで言ってみた。勘が働いた。
ところが大将はいいとも、悪いとも言わず、どこかに行ってしまった。お客とはいえ、見ず知らずの人間に、そう簡単に教える訳ないか、と思い、またひとりで呑みはじめ、明日のこと、どこの漆器屋さんに行こうか、と酔いがまわる頭で考えていた。
しばらくしたら、お店の女性の方が、たぶん女将だと、小さい紙切れを渡してくれた。何かと思い見ると、そこに電話番号と漆器屋さんの名前が、大将からだと。
また大将がビール片手に寄ってきて、
「漆器関係の人ばかりだから、この町は、お店の中も」
画像はその漆器屋さんの塗師の所でつくってもらった木地。その漆器屋さんは輪島の中でも有力な所だったので、私の想いをきちんと形にしてくれました。
来月は3度目の来輪、毎度大将のお店で呑みます。
"The feeling becomes a form"
From the idea that everything visible in the living space is an architecture, I make everything, and of course I love those things, so I'm pretty sure what kind of things I can get and where,
Since the specialty is architecture, I have never made lacquer ware from wood, and even though I wanted to make lacquerware from wood, I had no point.
I was planning to go to Kanazawa this January, so I thought I'd better go to Wajima if I could go. If you go to Wajima, go to famous morning market, and hit one lacquerware shop out there, think vaguely that it will be some opportunity.
Because the evening was already arrived at Wajima, the hit was already dark, so it seemed that only the restaurant was open, so there is no habit of the land, I thought about eating something delicious for tomorrow, I made a reservation for a nearby restaurant from a business hotel.
The general who seemingly unfaithfully seats at the counter busy moving around. He was drinking relaxing sake along with the relish of the feature. It came to Kanazawa once long ago, but Noto was the first time since there was nothing around the hotel, there was only a shop for that cuisine, so the neighborhood was dark, but the light of this shop made me relax .
When I was thinking about how to get a bottle of local sake after one more hollowing, I wonder if the peak of the busyness of the store has passed, the general who held the glass containing beer on his right cheeks Loosen while standing in front of you through the counter,
"Where are you from?"
I was talking to him.
That tone is soft, friendly, and it was completely different from the impatient feeling until a while ago. Because, I have hardly talked to you until now, and never came.
The only time when ordering late server,
It is said that "There is no mackerel today."
"Well, if it returns,"
Later on, the paddle
"Because I could not get out of the server, this service was said to be out and it was about to show out.
Normally it is from "Tokyo is the story" And the story to that, it originally thought that the general came around the country, only the kitchen knife in front of the flow, whether it was to open the shop here, or really, I wanted to retire, but inevitably I was planning to retire I was asked to start shop now.
While talking about such a thing, lacquerware is nice in the stream, after talking, the general took the lacquerware that the shop is using at the counter.
Because I am also Wajima and I like lacquerware, I compare what I made custom-made and what I paint in a dishwasher and what the luster of lacquer is not much.
"We make it custom-made"
I said, I wanted to talk about myself, trying to make lacquerware from wood. Since I do not have any sheen, I should go into a lacquer store somewhere and find a place to make it.
If you ask the general to "Do you make it?"
"It's going to hit your thoughts,"
About one or two lacquer ware you want to make, roughly custom-made from wood land, would not make it unless you ask a certain number to a certain extent, since the general is used in the shop, so it can be custom-made Because I thought, it was an unexpected reply.
"Please tell me the place where you made the special lacquerware"
I tried to think on purpose. My intuition worked.
However, the general is good, I did not say it was bad, I went somewhere. Although I was a guest, I thought with a head that got drunk, thinking that it would be easy to teach a stranger to teach, so I started to drink alone, tomorrow, where I went to a lacquer warehouse.
After a while, the lady of the store was probably a general lady, and handed out small pieces of paper. When I think of something, there is a phone number and the name of a lacquer ware store from the general.
The general also came down to a beer with one hand,
"Because there are only people related to lacquerware, this town is also in the shop."
The image is a woodland that was made at the lacquer store's painter. That lacquer warehouse was a powerful place in Wajima, so I shaped my thought properly.
Next month is my third visit, I swallow at the general shop every time.
今、輪島塗のカップを制作中です。
以前、京都で知り合いになった五条の陶器店のご主人に、漆のお椀が欲しくて、いろいろ探したが、気に入ったものが無い、と伝えたら、お店の上階に漆器の見本場があるからと案内され、そこでお椀を製作したことがある。
その時は、お椀の木地があらかじめ何種類か用意されていて、その中から選び、漆の塗りだけは好きにお願いできた。
黒漆や朱はもちろん、金や銀の漆や白漆まであった。
当然お椀の形をいじることはできないので、木地の中から2種類選び、漆の色の付け方だけを自由に考えた。
気に入った形のお椀は無かったが、漆の色の付け方を工夫できるので、その形を利用して、上手く漆の色の分け方を考えれば、最後に仕上がった時には満足できるものになるだろう、と思っていた。
ところが、これが思いの外、難航した。
頭の中でイメージしながら、漆の色の付け方や分け方を考えてみても、それがどうやってもしっくりこないのだ。
今まで経験の無いことだから無理もないのかもしれないけれど、経験とは関係なしに、お椀の形をいじることができないのが原因だった。
建築の場合に当てはめると、漆の色の付け方を考えることは、外壁の色をどうするかを考えることに置き換えることができると思うが、私の場合、外壁の色だけを抜き出して考えることは無く、建築のプランと立面を交互に行き来しながら、建築の形を考え、同時に外壁の素材や色も考えている。
だから、漆の色の付け方だけを考えることは、単に塗り絵をしているに等しく、物足りず、どうしても気に入らない木地の形を何とか補う作業になってしまい、
それは自分が欲しい漆のお椀をつくることから、段々とかけ離れて行って、だから、いくら考えてもしっくりいかないものになってしまった。
画像にあるお椀が出来上がったものですが、結果的には、その時できることは全てやったという思いはあったので、満足できる範囲のものには仕上がりましたが、やはり何か物足りず、次回は木地から漆器をつくりたい、という想いが芽生え、段々と強くなって行き、今、輪島へ直接行って、塗師に輪島塗のカップを木地の制作からお願いしている。
それで、来月、また輪島の塗師の所へ行くことにして、3度目の訪問、塗りについて相談してくる予定でいて、今、塗りついていろいろ思案中。
"Making from wood land"
I am working on a cup of Wajima coat now.
When I told that my husband of Gojo pottery store I met in Kyoto wanted a lacquer bowl, I looked for something, but there was not anything I liked, the lacquer warehouse on the upper floor of the shop There was something I made a bowl there, guided by being there.
At that time, several types of wooden bowls were prepared in advance, we chose from among them and asked only for lacquer painting.
Black lacquer and vermillion as well as gold and silver lacquer and white lacquer were found.
Of course you can not touch the shape of the bowl, so I chose two from the woodland and thought about how to color the lacquer freely.
I did not have a bowl that I liked, but I can devise how to color the lacquer, so if you think about how to distinguish the color of the lacquer well using that shape, it will be satisfactory when finally finished , I thought.
However, this was a difficult flight unexpectedly.
Even though you imagine in the head, considering how to color and divide lacquer, it does not come nicely in any way.
It may be impossible for us to have experience so far but it was caused by being unable to fiddle the shape of the bowl without relation to experience.
When applying to the case of architecture, I think that thinking about how to color the lacquer can be replaced with thinking what to do with the color of the exterior wall, but in my case, I do not think about extracting only the color of the exterior wall While alternating between plan and erection of architecture, thinking about the shape of architecture, at the same time thinking about the material and color of the outer wall.
Therefore, considering only the way of coloring lacquer is equal to just painting, it is not enough, it becomes a work that supplements somehow the shape of the wooden which I do not like,
Because it makes a bowl of lacquer which I want, it is going far apart, so it has become something I can not make it even if I think about how much.
Although the bowl in the image was completed, as a result, there was a desire to do all that can be done at that time, so it was finished in a satisfactory range, but something was not enough in the next time The feeling of wanting to make lacquerware from wood land grows steadily and gradually becomes stronger. I am going directly to Wajima now and asking the painter a cup of Wajima from the creation of woodland.
So, I plan to go to Wakajima's painter next month and plan to consult about my third visit and painting, now I'm sticking and thinking a lot.
ローバーミニにはシガーソケットが純正では付いておらず、新車で1995年から23年乗っていて禁煙車ですが、やはりiPhoneの充電には必要で、ここに来て取り付けることに。。。
去年暮れ、エンジンがアイドリング中にストンと止まるようになり、22年間ミニの整備をお願いしていた、社用車の整備を全てお願いしている自動車屋さんでは、部品が無く修理することができず、紹介してもらったミニ専門の修理工場へ持ち込んだ経緯から、その修理工場にシガーソケット取り付けを問い合わせしたところ「面倒くさい」と。
見るとダッシュボードのパネルの中にシガーソケットを組み込めそうなスペースがあらかじめあるのです。いかにも後付けですという感じの取付けは嫌だったので、そこに取付けたいとその修理工場に伝えたら、ほとんどの人がお金もかかるので、両面テープでソケットだけを足元に取付けます、とのこと。それがいかにも後付けな感じだから嫌なので。
やはり同じことを考える人はいるもので、そのダッシュボードのパネルの位置にシガーソケットを取付けするミニ専門の整備工場がネットで検索したら出てきて、家から30分位の所、メールで問い合わせしたら、心良く、当たり前のように、普通に引き受けてくれて、1泊2日でミニを預けることに。
(画像1枚目:緑枠で取付け(整備工場ブログより))
その整備工場でシガーソケットの実物を見たら、緑の枠がソケット口に付いている。ダッシュボードのパネルは黒色なのて、その緑が不自然に目立ち、ダッシュボードと馴染まない。
私「その枠の緑、他の色は無いんですか?」
整備士「無いんです、この緑色だけです」
私「その緑の枠を取ることはできませんか?」
整備士「この緑の枠が無いとダッシュボードにしっかりと収まらないんです」
ここでたぶん整備士の人は気がついたみたいです、なぜ私が緑の枠のことを言っているのか。
整備士「後でハゲるかもしれませんが、この緑の枠を黒く塗りましょうか?そうすれば、ダッシュボードも黒なのでおかしくないし」
私「お願いします、黒く塗ってください。何を塗るんですか?」
整備士「塗料の食いつきをよくするために、緑の枠にペーパーで傷を付けてから、スプレーします」
私「じゃ、ハゲたら、油性マジックで塗ればいいですね」
整備士「そうですね」
(画像2枚目:取付け完成後)
純正にこだわる訳では無いのですが、余計な物を付けたく無い、購入した当時の雰囲気、感じが好きだから、そのまま乗りたい、余計な手を入れたくない、消耗劣化品だけ取替える。
カーナビも無い、ETCも無い、CDも無い、あるのはカセットとラジオ。携帯のナビソフトを使えばいいし、ETCカードを料金所で差し出せばいいし、音楽は携帯から聞けばいい。でもだから、携帯充電用にシガーソケットだけはどうしても必要、ただ取付けるならば、元々はじめからそこにあったように見えないと。
今後、修理も車検も「面倒くさい」と言った修理工場には頼まないでしょう。
シガーソケットひとつにしても、おろそかにせずに考えるのが、大事な物を大事に扱う人の考え方で、それがわかり、それにきちんと当たり前のように対応できるのがプロだと思うから、私もものづくりをしているので、そういう人たちと付き合いたい、そういう人たちにお願いしたい。
"Cigar Socket"
Rover Mini does not have genuine cigar socket, it is a non-smoking car riding 23 years since 1995 with a new car, but still needed to charge the iPhone, to come here to install. . .
Last year, at the car shop asking for maintenance of all the company cars that had been requesting maintenance of mini for 22 years, engine stopped with Ston while idling, it was possible to repair without parts However, from the circumstances that I brought it to the mini specialty repair factory that I was introduced, when I contacted the repair shop to install the cigar socket, it was "troublesome".
There is space beforehand looking into the panel of the dashboard so that cigar socket can be incorporated. Since it is disgusting how to install it feeling that it is a retrofit everything, since most people take money, if you tell the repair shop that you want to install there, we will install only the socket with feet on the feet. Because it is disgusting because it is indeed a post-attachment feeling.
After all, there are those who think the same thing, if a mini specialized maintenance factory that installs cigar socket at the position of the panel of the dashboard comes out when searching on the net, if you inquire by email about 30 minutes from home As a matter of course, as ordinary, ordinary underwriting, to leave the mini in 2 days 1 night.
(Image 1st sheet: Installed with a green frame (from maintenance plant blog))
When seeing the real thing of the cigar socket at the maintenance factory, a green frame is attached to the socket mouth. Since the panel of the dashboard is black, its green is conspicuously unnatural, and it does not become familiar with the dashboard.
I "Green of that frame, are there no other colors?"
The mechanic "There is nothing, this green only"
I "Can not you take that green frame?"
Maintenanceist "If there is no green frame there will not fit firmly on the dashboard."
Perhaps the mechanic's person seemed to notice, why am I talking about the green frame?
Maintenance mechanic "Maybe later you will paint this green frame black, and if so, the dashboard is black, so it's not strange"
I "Please, please paint black, what do you paint?"
Maintenanceist "To scratch the paint, scratch the green frame with a paper and spray it."
I "Well, if you're bald, you can paint with oily magic,"
Maintenance professional "That's right"
(2nd image: After installation completed)
Although I am not stuck with genuine, I do not want to add extra items, I like the feeling at the time I purchased, I want to ride, I want to ride, I do not want to put extra hands, replace only consumable deterioration items.
There is no car navigation, no ETC, no CD, what is a cassette and radio. You only need to use the mobile navigation software, just give out the ETC card at the tollgate and listen to the music from the mobile. But, it is necessary just for cigar socket for mobile charging, if only installing it, it seems as if there was there originally from there.
From now on, we will not ask the repair shop to say that repair or vehicle inspection "is troublesome".
Even if it is one cigar socket, thinking without negotiating is to think that it is the idea of a person treating an important thing carefully, I understand it, I think that it is professional that we can properly deal with it properly like normal, so also I Because I am doing, I would like to ask those people who want to go out with those people.
Instagramをご覧ください。
ヤネで決まる。
プランのよしあしは屋根で決まるかもしれない。
いつも時間をかけるところのひとつ。
屋根のかけ方のセオリーはあるが、
それが必ずしもよいとは限らない。
破掟しないのは当たり前。
今回は見える方向がたくさんあるので、
どこから見ても建築の表情がちがうことを意識している。
そして、それがより深く
プランやコストやメンテナンスやデザインとうまく調和するように。。。
いい感じ。いい感じ。
祭りの前の静けさ。

今年から地元の神社の世話人に。
手作りに近い祭りだから夜店のテント設営も自分たちで。
幼稚園もここだったので記憶が幾重にも重なる。
人にとって思い出深い場所はたくさんあるかもしれないけど、大切な場所はそうはないと思う。
人の縁を大切にするように、記憶との縁も大切に風通しよくしておきたい。
記憶を紡ぎながら暮らす生活が本来大切で、一番贅沢なことだと最近想うから。
だから・・・
田舎がある人は帰りましょ!
きっと秋祭りですよ。
「動いて流されてぶつかって・・・
だから感じることができる」
先日、あるお寺の住職さんと禅問答をしました。
禅問答は
雲水(見習いのお坊さん)に対して行うもので
秘儀とされ
本もあったり、一般の人に対して行ったりもしますが、
それは本当の禅問答ではないらしいです。
今回、
その住職さんが
秘儀に近いかたちで
あえてわかりやすく行っていただきました。
その時に
昨日のブログの五重塔の心柱の話がでてきました。
「あなたの心の柱は何ですか?」
お題です。
しばし考えてみてください。
私は・・・
「情」
と答えました。
お題をいただいてすぐに
頭の中に「情」の文字が浮かびました。
愛情
人情
友情
の「情」です。
「それがどうした?」
「その程度で・・・」
大きなお寺に行くと、
よく五重塔や三重塔を見かけます。
中には千年以上も前に創建されたものも。
その間、台風や地震などの自然災害にも耐えて。
建築の構造の話を少ししますと、
五重塔や三重塔の真ん中には
心柱という太い柱が
大体、根元から頂部近くまで通っています。
そして、
その心柱は固定されていません。
周りの屋根の部分とも繋がっていません。
心柱だけが
ゆらゆら揺れるようになっています。
刺さっているだけ。
普通ちょっと考えると・・・
台風や地震に耐えるためにも
しっかりと根元も地面に固定されていて、
他の部分もしっかり繋がっていて、
何があっても動かないぞ!
とばかりに頑丈にできてないと・・・
と思いますよね。
それではじめて台風や地震に耐えられると。
逆なんです。
台風による強風、
地震による強い揺れ、
と一緒になって心柱も揺れる。
一緒になって揺れることにより
台風や地震による揺れを吸収し、
周りの屋根の部分には伝わらないようにしているのです。
もちろん、
周りの屋根の部分は
その部分だけで揺れますが、
心柱とは切り離されているので、
強風の揺れは心柱には伝わらずにおさまり
建物全体に影響はあまり与えず、
地震の揺れは心柱があるおかげで
地面から直接伝わりません。
そして、
揺れた心柱、
揺れた屋根は
揺れがおさまると
また元の位置にもどります。
現代でいうと、制震構造です。
もっとわかりやすくいうと、
大きな木を想像してみてください。
太い幹があって
その周りに枝葉がある。
その太い幹と周りの枝葉が切り離されているイメージです。
どんなに揺れても
太い幹が折れることはありません。
強風で折れるのは
太い幹と枝葉が繋がっていて、
少しも揺れないぞ!と
頑張っているから
限界を越えた時にポッキと折れるのです。
どんなに揺れても
一緒になって揺れていたら
揺れの力が分散されます。
そして、
また元の位置に戻る。
どんなに揺れても
また戻るべき位置にきちんと戻る。
その位置が
家の存在であったら・・・
外で何があっても
帰るべき
安心できる場所がある。
私の
家に対する
理想のイメージのひとつです。
「水鏡に映るその姿が・・・」
桜の季節ももう終わり。
でも、この桜吹雪舞う時期が結構好きです。
水際にある桜の木。
水面に映る桜の花。
舞う桜の花びら。
水面一面が桜色。
好きなシーン。
私の春のイメージです。
桜を見上げないで
水面に映る桜ばかり見てしまいます。
なぜか
そのものを見るより
他に映る姿の方が好きになります。
鏡に映る姿だったり。
その感覚は
もしかしたら日本人独特の感性かも。
日本庭園の借景や
わざと池に月を映してみたり。
床の間の一輪挿し。
自然の美を感じさせるのに
何かひと手間入れた方が
その美の本質があぶり出されるかのように。
あるいは
もうひとつ、美に意味を加えるように。
水面の桜の花びらの流れに
郷愁やはかなさ
を感じるように。
それを演出というのかもしれませんが、
人のこころに響く
には必要かもしれません。
「・・・」
「独坐大雄峰」
「どくざだいゆうほう」と読みます。
仕事柄、自分の居場所についてよく考えます。
よくボーッとしながら。
静かで外の喧噪がうそのような
緑豊かで
爽やかな風が吹き抜け
ゆるやかな光が頭上から落ちてくるような。
暖かくやわらかな陽射し下、
海を見ながら、それも横になりながら・・・
遠くの山をぼんやり
見晴らしのいい
晴天の下
草木や花の匂いがしてきて
雲がゆっくりすぎていく
妄想してます。
たぶん、
その時は呼吸も穏やかで
落ち着いて
リラックスしている時だと思います。
先の「独坐大雄峰」は禅語です。
ただ坐り、深くお腹で呼吸する。
何回か呼吸しているうちに
気持ちも落ち着いてくる。
その心が落ち着く立ち位置が
安心していられる居場所「大雄峰」
という意味です。
実は
妄想していられるその居場所が「大雄峰」
自分の居場所とは、
現実の目に見える世界の場所とは限らない。
だから、
私はいつもクライアントに質問します。
「あなたの大雄峰は?」
「これ、これ」
「これが好きなの」
先日のお酒のイベントに、私が持ち込んだお酒は
どぶろく
でした。
山形のどぶろく
「PINDOBU(ピンどぶ)」
赤色清酒酵母を使ったピンク色のどぶろくです。
味は冷蔵で寝かせるとどんどん
苺をすり潰したような酸味と甘みがでてきて
爽やかフルーティで濃厚芳醇です。
冷蔵で2ヵ月ほど寝かせましたが、
最初はお酢を飲んでるかのようでした。
発酵の力はおもしろいですね。
なぜ、どぶろく?
私の飲み物遍歴を紐解くと
子供の頃から普通にジュースを飲み
大人になってビールから入り、
焼酎、日本酒、ワインなどなどと
たぶん、誰でも通る道順できてるかもしれませんが、
唯一ちがうのが
子供の頃から、物心ついた時から
甘酒が大好きで、
今でも自分で酒粕からつくるほど好きです。
うちのお袋の影響です。
お袋が大好きでいつも冬になると常備されていたので。
だから、
日本酒の入りも最初は濁り酒から。
見た目が似てるからきっと美味しいだろうという理由で。
でも、
見た目が似てても味は非なるもので・・・
でも、
甘酒好きとしては
どうしても
濁り酒で美味いものを探したい、自分好みのものを見つけたい
となるわけでして・・・
結果、見つけたのが
先の「PINDOBU(ピンどぶ)」
ともう1つ
三重県伊勢の伊勢萬という酒蔵所がだしている
「おかげさま 限定にごり酒」
の2つ。
特に「おかげさま 限定にごり酒」は甘酒そのものでして・・・
どぶろくの方が珍しいと思って
イベントには「PINDOBU(ピンどぶ)」を持っていきました。
子供の頃にヒントが。
自分の好みは案外子供の頃につくられます。好きな空間も。
子供の頃よくいた部屋が、その空間が
大人になっても案外ここちよかったりします。
子供の頃を想い出すと・・・
あの部屋のあの場所のあの匂い。
案外覚えているものです、ここちよい場所は。
私は
母方の田舎の西日の当たる部屋でした。
鮮明に覚えています。
幼いその記憶だけで
自分にとって、ここちよい
自分だけの居場所をつくることができます。
想い当たらない人は
忘れているだけ。
誰かに見つけてもらいましょう。
「おっ、そこ?!」
「そこにあるんだ」
先日、お酒のイベントに参加しました。
各自がオススメのお酒を持ち寄り、
試飲しながら、
お酒のことを語るイベント。
私は、お酒は呑むのですが、
その場の雰囲気が好きで
お酒自体を楽しむことがなかったので、
何か新たな楽しみの発見になればいいなと。
なので、
お酒を語る言葉を持ち合わせていないのですが・・・
日本酒好きな方は多いと思います。
私も好きです。
ただ銘柄とかは特に気にしないで呑んでました。
それこそ、お店のオススメとか。
そのイベントで
お米の話になりました。
日本酒の原料はお米。
多くは「山田錦」という品種のお米でできている。
そのイベントで
自分に合う好きな日本酒に出会いました。
「風の森」
奈良の日本酒です。
味は甘くて軽く爽やかで、私にはメロンの味がしました。
『日本酒をお米しばりで呑む』
「風の森」は「雄町」という品種のお米でできているそうです。
「雄町」米をつかうと
甘めのお酒ができるとか。
今回たくさんのお酒、
日本酒をはじめ
スパークリングワイン、シャンパン
赤ワイン、白ワイン
どぶろく
などなど
を呑んで、自分の好みは甘めでスッキリ軽くフルーティな味とわかりました。
先の日本酒「風の森」がぴったりでした。
そうすると、
「風の森」という銘柄にいこうかと思っていましたが・・・
イベント主催者から
「日本酒をお米しばりで呑むという手もありますよね」
『なるほど!』
今後は「雄町」米しばりで日本酒を楽しんでみよう。
ほんと意外な発見でした。
日本酒の原料のお米に注目して、自分好みのお酒を探し出すとは。
お酒のことがわかっている人にしか出てこない発想です。
実は
意外なところに
自分の好みを探し出す手段があるものです。
ただ、それは自分ではなかなか気がつかない。
その道のエキスパートでないと探し出せない、見い出せない。
それが案外自分にとっての核心だったりするから困りものです。
誰に委ねるか?
私はカンです。直感。
ただそれだと
はっきりしないので、
もうちょっと、その直感の中身を紐解くと、
『可能性』です。
その人に、経験値からくる可能性を
「何か導いてくれるかもしれない良い方向に」
と感じたときに委ねます。
先の「雄町」米しばりの日本酒を早速発見。
ただやはり人気があり、
なかなか手に入りにくそうです。
「この扉があけば・・・」
先日、万年筆を買いました。
LAMY2000
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、
40年以上前にデザインされて発売されたドイツのメーカーのもの。
バウハウスデザインの流れをくむもの。
自分へのご褒美で、仕事で望んでいた結果が出たので。
きちんとした万年筆を使うのははじめてです。
きちんとしてないというか、おもちゃみたいのは使いましたが、
すぐに使わなくなってしまいました。
特に、ことさらその万年筆でないと、という理由がなかったから。。。
「弘法筆を選ばず」といいますが、普通の人は弘法大師ではないので選びます。
『道具7割。残り1割。全部で8割できれば上出来』
私が何か新しくはじめる時に最初に頭に浮かぶ言葉です。
自分に合った道具を手に入れた瞬間、
自由に表現する扉が開かれたようなもの。
道具を探す行為は表現の扉をノックすることです。
あとは、
その場で普段の自分を出すだけで、人からは秀でたものに見えます。
道具の力を借りてどうする?!
道具が優秀なだけじゃない!
そんな声が聞こえてきそうですが、
どんなに優秀な道具であっても使う人がいなければ、ただの道具。
その道具を使って結果が出たのであれば、
それはその道具を使っている人の実力です。
先のLAMY2000、手に入れてから、
無性に文字が書きたくて仕方がありません。
結果こうしてブログを投稿してます。
だから、
私は道具を選ぶ時には徹底的にこだわります。
何にこだわるか?
1、自分に合うか?
2、今の自分が手に入れることができる範囲で最高のものか?
1、はお話した通り。
2、は最高のものとは金額とは限りません。
むしろ金額より、
道具にもつくり手がいます。
その人やその企業の
想いだったり、能力だったり、技量だったりが
きちんと道具に反映されていて、質の高いものになっているか。
そういう質は伝染します、道具を使う人に。そして、道具を使って出す結果に。
だから、
私は道具にこだわります。
自分が出す結果にこだわるから。
暮らしにおける道具の一つは家です。
自分に合う
今の自分が手に入れることができる範囲で最高のもの
を手に入れた途端、暮らしの質が変わります。
あとは残り1割。
普段の自分で生活すればいいのです。
それだけで今までより豊かな暮らしになります。
家づくりは、こころ豊かな自由な暮らしの扉をノックすること。
「長いと思うか」
「短いと思うか」
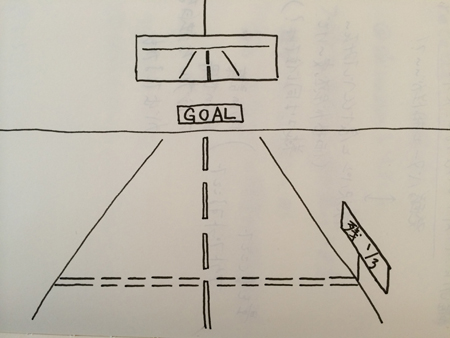
人生を80年とすると、
80年 × 365日 = 29,200日
自分はだいたい、とりあえず70年とすると、
70年 × 365日 = 25,550日
44年間生きてきたので、
44年 × 365日 = 16,060日
残り
25,550日 − 16,060日 = 9,490日・・・あと1/3
「あと1/3もある」
「でも9,490日しかない」
という感じでしょうか、私は。
建築の工程でいえば、骨組みと下地ができて、造作と仕上げの時期に入るところ。
仕上げをイメージして、
骨組みと下地をつくってきて・・・
さあ!これからイメージした空間が出現していく。
あとどれだけ
あと何棟
数にはこだわりはありませんが、
こだわりの家を実現できるか。
もうムダにできる時間はありませんね。
超久々の更新です m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2013春夏」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

今号も
「お住まい拝見レポート」に掲載されてます。
毎号言いますが!
正直・・・他とは・・・ちがう・・・。
自信作です。
これ!
お客さまの想いをカタチにしました。 o(^^o)
「だから、仲村さんにお願いした」と・・・。
どうぞお楽しみください m(_ _)m
新年あけまして
おめでとうございます
2012年ご縁があった方々に
改めまして
感謝を申し上げます
私にとって2012年は
いろいろとあり過ぎて
4〜5年分の出来事を
ぎゅっと凝縮して
1年で体験したような年でした
崩れるくらい
大泣きしたことも
あったし
逆に
アゴが外れそうなほど
大笑いして
次の日
ノドが痛くて
声が出なかったことも
不思議と
怒る時は静かだったような
そう
喜怒哀楽の激しさが
印象に残り
その時一緒にいた人達との
思い出がたくさんある
そんな2012年でした
だから
人の縁に恵まれた年だったと
改めて想います
だぶん
2012年は一生記憶に残る年
さて
あけて2013年の今年は
変化の年になる予感が・・
それはそれで
愉しく
活きます!
うちの飼い猫のカーンも
あけおめ
よろニャン
と面倒くさそうに
迎えてくれてました

だから(?)
きっと
良い年になるでしょう
そして
日本全国や海外にもいる
私とご縁のある方々の
益々のご開運を
心から願っております。
皆様
また遊んでくださいm(_ _)m
たくさんやりましょう!
久々の更新です m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2013冬春」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

前号からはじめた、記事の大幅変更!
私、仲村和泰とお客さまとの関わりを中心に誌面を構成しています。
ポイントは・・・
見たことがない建築を
見たことがない住宅を
見たことがない家を
つくりたい方必見ですよ!!
そして、
聴いたことない、
見たことがない打合せを体感したい方は・・・。
どうぞお楽しみください m(_ _)m
スマートフォンサイトのdesignを変更しました。
色をPCサイトと合わせただけですが・・・
かなり印象が違うと思います(^_^)

色を変えるだけで
相手に与える印象が全然違います!
だから、
住宅でも色使いが大事なんですよ!!
それに・・・
家の色を楽しみたいものです。。。
超々久々の更新です m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2012秋冬」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

今号から記事を大幅に変更!
私、仲村和泰とお客さまとの関わりを中心に誌面を構成してみました。
見たことがない建築を
見たことがない住宅を
見たことがない家を
つくりたい方必見ですよ!!
どうぞお楽しみください m(_ _)m
スマートフォンサイトが公開されました。
サイトデザインは
これから自分で手を入れていく予定です。
ご期待ください(^_^)

超久々の更新です m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2012夏秋」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)
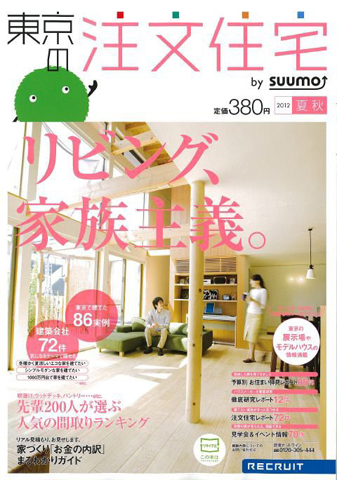
今号も
「お住まい拝見レポート」に掲載されてます。
毎号言いますが!
正直・・・他とは・・・ちがう・・・。
自信作です。
これ!
お客さまの想いをカタチにしました。 o(^^o)
「だから、仲村さんにお願いした」と・・・。
どうぞお楽しみください m(_ _)m
久々の更新です m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2012春夏」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)
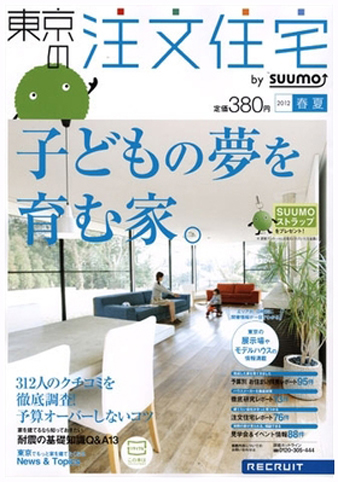
今号から
「お住まい拝見レポート」
にも掲載されます。
正直・・・他とは・・・ちがう・・・
自信作です。
どうぞお楽しみください m(_ _)m
当初、2012年2月11日(土)も完成見学会を予定していましたが、
ご予約でいっぱいになってしまいました。
感謝、感謝です。ありがとうございます。 m(_ _)m
従いまして、
私ひとりでしかご対応ができませんので・・・
1日限定の完成見学会に変更させていただきます。
2012年2月12日(日)にSE構法の家の完成見学会を1日限定で開催!

仲村建築店ではオープンハウス(完成見学会)を下記の日程で開催します!!
1日限定『わたしの居場所』オープンハウス
場 所 東京都杉並区永福 永福T-house
日 時 2012年2月12日(日) 9:00 ~ 15:00
内 容 『わたしの居場所』のイメージが現実に・・・。
建 物 SE構法 木造2階建て
約 束 売り込み&訪問販売は一切致しません。安心してお越し下さい。
予 約 必要ありませんが、日時をご予約した方がゆっくりとお話ができます。
是非お申し込みください。
特 徴 デザイン住宅を建てたいとお考えの女性の方必見!!!
建築家がたくさんの想いをつめ込んでつくった『わたしの居場所』です。私たち仲村建築店が想う住空間を見てください。きっと今までの住空間のイメージが変わります。今まで聞いたことがない話も聞ける。絶対に後悔させません!お気軽にお越しください。
2012年2月11日(土)・12日(日)にSE構法の家の完成見学会を開催!

仲村建築店ではオープンハウス(完成見学会)を下記の日程で開催します!!
『わたしの居場所』オープンハウス
場 所 東京都杉並区永福 永福T-house
日 時 2012年2月11日(土)・12日(日) 9:00 ~ 17:00
内 容 『わたしの居場所』のイメージが現実に・・・。
建 物 SE構法 木造2階建て
約 束 売り込み&訪問販売は一切致しません。安心してお越し下さい。
予 約 必要ありませんが、日時をご予約した方がゆっくりとお話ができます。
是非お申し込みください。
特 徴 デザイン住宅を建てたいとお考えの女性の方必見!!!
建築家がたくさんの想いをつめ込んでつくった『わたしの居場所』です。私たち仲村建築店が想う住空間を見てください。きっと今までの住空間のイメージが変わります。今まで聞いたことがない話も聞ける。絶対に後悔させません!お気軽にお越しください。
T様、外れましたよ、足場が。。。

もう見られましたか?
結構いいですね(^_^)
渾身の作品です。
本日発売の
「東京の注文住宅 2012冬春」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

いま、
皆さまのおかげで
デザインに格闘させていただいています。
おかげさまで
ありがとうございます m(_ _)m
だから、
こんなに忙しい今を、
さらなる自分磨きを大切に・・・
それが、
お客さまのためになると想うから。。。
なので、
今後は
いろいろな展開を考えています。
どうぞお楽しみに m(_ _)m
ただいま格闘中(^_^)

自分自身、完成を楽しみにしてます!
来年1月に見学会予定。
ちょっと・・・見てもらいたいです。。。
切ない気分になるのは
私だけでしょうか?(^_^;

街はすっかりクリスマス。
先日、
2ヶ月に一度の中古カメラの会が新宿でありました。
ご存知の方はいるかもしれませんが・・・
私、写真が趣味なんです。
それも
クラシックのフィルムカメラでの撮影が好きなんです。
そんな同じ趣味同志が集まって
自慢のカメラを見せ合う会です。
ちなみに、
毎回違うカメラを持参しなくてはならないのですが・・・
私はもうネタ切れで何も持参せず、
まわりの方々は
私の父親位の歳の方ばかり、
質と量でかないません(^_^;
楽しい会でしたが、
外に出ると・・・
なんか切ない、
なんか寂しい、、
そんなのもいい、、、
冬の寒い夜でした。。。
皆さま、大変お久しぶりです m(_ _)m
決して寝ていた訳ではありません・・・(^_^;
大変ありがたいことに、
仕事が集中してしまい
ブログまで手が回りませんでした。。。
お客さまに感謝、感謝です。
ありがとうございます m(_ _)m
それでやっと、この環境にも慣れてきまして、
落ち着いてきました・・・仕事量は変わらないのですが。
今後は、
こまめにブログを更新していきますので・・・
また、
皆様、お時間がある時に訪れてください。
よろしくお願いいたします m(_ _)m
本日発売の
「東京の注文住宅 2011秋冬」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

このところ、
皆さまのおかげで、
大変忙しくお仕事をさせていただいていまして、
もうすぐ、来週には上棟を迎える現場もあります。
おかげさまで、
ありがとうございます。m(_ _)m
そして、
その合間に
研修やセミナーなどを受けに出張しています。
忙しい時だからこそ、
さらなる自分磨きを大切に・・・
それが、
お客さまのためになると想うから。。。
なので・・・ブログがかなり疎かに(^^;)ゞ
今後は、
出張紀行などをできる限り書いていきます。
なので・・・皆さま、見捨てずに
このブログにまた、
ご訪問ください。m(_ _)m
「デザイン住宅に住みたいという方が増えたなあ」
ということ。
もちろん、
デザイン住宅をつくっているのだから、
それを求めるお客さまから
お問い合わせがあるのは当たり前ですけど。。。
そう実感するのは、
自分なり想うことは、
きっと、
私が、
ただ見栄えだけがいいデザイン住宅をつくっている訳ではない、
ということがわかっていただける
目の肥えたお客さまが増えた、
ということ。
それだけ、
住宅のみならず、
デザインに対する意識が
世間一般、社会で高い、
ということ。
だから、
当社HPにもあるように
デザイン住宅は『モノではなくコト』
なんです。
要するに、
デザインによって
今までの体験をブラッシュアップ
するんです。
一度、
体験する価値あり
だと想います。。。
一生に一度の家づくり
ですから、
デザインの世界を。
8月というのに
涼しくて過ごしやすい日でした。

きょうは、
午後から地鎮祭、よかったです。
T様、おめでとうございます m(_ _)m
毎回、
地鎮祭の時は
気持ちが引き締まります。
工事期間は、
その後のここでの生活の期間を考えれば短いものです。
しかし・・・
その後の生活を左右するかもしれません。
だから・・・。
完成まで全力でいきます。
きょうは、
さらに
近隣の方々への挨拶まわりを
T様と一緒に行い、
その後、
会社に帰り、
新たなお客様とお会いし、
たくさんの人とのご縁がある日でした。
とても
皆様に
感謝感謝の一日でした。
おかげさまで
ありがとうございます。
そして、
あらためまして
T様、おめでとうございます m(_ _)m
こんな物たちに囲まれています(^_^)
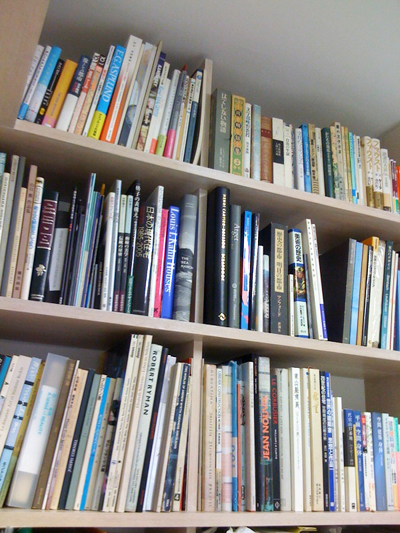
合間に・・・、
息に抜きに・・・。
結構、
名著だったりします。
歴史から学ぶこと、
多いです。
いま一番ほしいもの・・・やすみ。
というわけで、
世間とはズレています・・・感謝、感謝です m(_ _)m
待って下さっている方に・・・感謝、感謝です m(_ _)m
ところが、
やすみがなくても、
おかげさまで・・・毎日たのしく過ごせています。
感謝、感謝です m(_ _)m
ひとくち目を・・・思い出します。
先日の京都、
祇園の一力茶屋近くのお店で
お昼を食べた時です。

定食に付いてきた、厚焼き卵。
たぶん・・・
見た目からは想像できない味です。
何気なくひとくち、
衝撃が走りました。
なんと上品な・・・。
うなり、ました。
例えるならば、
とても上等なお出汁を使った
茶碗蒸しを食べているよう・・・。
とくに、
ふつうのお店です。
忘れられない味が
ひとつできました。
きっと、
人の感覚は
こういうことの
積み重ね
だと
あらためて想う。。。
先日所用で行った京都で・・・
くずきり
を食べに行こう、と京都をよく知る人から誘われました。
それが
鍵善。
祇園の四条通に面した、
前から知ってました、入りづらそうなお店だな〜という感じの
言わば、
京都らしい店構え。
ただ、奥に喫茶室があり、
入ると、知っていると普通に行けそうな
それこそ、
京都らしい雰囲気。
いい場所知りました。
そこのくずきり。
漆の器で出てきます。

京都らしい。
この器ほしい!

この仕掛け。
なんか作法がありそう!
まわりをキョロキョロ (^_^;

氷水に浮かんだ
くずきり
を黒蜜でいただく。
暑い夏、
まず
京都らしい雰囲気を感じ、
涼しみ。
目で見て楽しみ、
涼しみ。
食べておいしく、
涼しみ。
ただ単に、
くずきり
をいただく中にも
たくさんのコトを含んでいる。
それが
一番、
京都らしい。
先日、所用で京都に行きました。
夏の京都は、はじめて。
やはり、暑かったです (^_^;
なにか、お土産と思い、人からのオススメで、
鍵善のお干菓子を購入。

包装。

木箱でのし。

「園の賑わい」という名のお干菓子。
むかし祇園祭に
あでやかな女人たちが、
それぞれに装いをこらした
行列「園の賑わい」がありました。
その、うつくしかりし
面影をしのんで、
ゆたかな四季の花ばなを
映し出した京のお干菓子。
だそうです。
〜らしさ、という言葉がありますが、
我が家はいまだに一時、
京の風が心地よく流れます。
きょうから8月。
毎年、
夏の本番が暦の上でもはじまったな、と思います。
というのも、8月1日は
毎年、実家のお墓がある近くのお寺の御施餓鬼法要があるからです。
御施餓鬼は「おせがき」と読みます。
簡単にいうと、お寺のお祭り、だそうです。

法要の前の説法によると、
直接のご先祖様のご供養は、何回忌ということで、ご法要を執り行いますが、
御施餓鬼法要とは、
あの世で餓鬼道(がきどう)に落ちてしまった人々を供養するための法要で
その法要に参加された人には徳が返ってくる、
ということだそうです。
じつは、
今回はじめて知りました (^_^;
さらに詳しいことはネットで検索願います。
このお寺には、
実家のお墓があり、また、
本堂の改修、庫裏の増築、水屋の建築など、
普段からお寺全体の建築工事に携わらせていただいて、
尚かつ、社長が総代ということもあって、
毎年8月1日は、社員一同でお手伝いをしております。
わたしは、
法要に参加しているのですが、
法要前の説法を真近で聴いたのは
今回がはじめてでした。
特に今年は、
東日本大震災で犠牲になった方々へのご供養、
という意味もあります。
改めて想います。
「無常」
常に同じ状態は無い。
これも説法の中でのお話です。
悪いこともいいことも
ずっと続くわけではない。
だから、
いまこの時を大切に。。。
夏の少しためになる日、でした。
毎日・・・言いたくはないですけど・・・暑いですね (^_^;
この時期、
上棟前の現場は日陰がなくて、、、
電柱の陰にも入ったりします (-_-;
きょうは、
来月の着工をめざして計画中の物件の
地盤調査でした。

地盤の10年保証を取得するための調査です。
(ジャパンホームシールド㈱(JHS)の地盤サポートシステム)
この物件のお客さまは
土地探しの段階からお声を掛けていただき、
サポートさせていただきました。
私が考える
土地探しの一番大事なポイントは、
資産ですから、
地盤のいい場所を手に入れること。
建物の基礎にもお金をかけないで済みますし、
その分、他の予算にお金を回せますし、
次の世代にもきちんとしたものを残せます。
では、
地盤のいい場所を探すコツは・・・
結構あるんですよ。
不動屋さんは、
地盤の良し悪しはあまり・・・。
で、
今回の地盤調査の結果は、
まだこれから、解析して、数値できちんと報告書が出ますが、
現場で調査をした技術者の方曰く、
「安定した良好な地盤ですね。」
とのこと。
ほっと!
調査する前から、
たぶん良好な地盤だろう、とは考えてはいましたが。
よかったですね、T様!(^_^)
7月5日、石巻に入りました。
目的は、被災地を感じとることと買い物支援。

この写真から何を感じますか?
わたしは
・・・
何も感じとることができませんでした。
・・・頭の中が空白でした。こんな体験はじめてです。
・・・東京にいたら、わかりません。
行き先を決めないで、ここまで来たけど・・・。
やっぱり来てよかった。
不謹慎かもしれないけど・・・大事なことかもしれない。
6月21日(火)発売の
「東京の注文住宅 2011夏秋」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

実は、出張で大阪にいて、
発売されたのを忘れていました。(^^;)ゞ
このところ、
皆さまのおかげで、
大変忙しくお仕事をさせていただいています。
おかげさまで、
ありがとうございます。m(_ _)m
その合間に、
研修やセミナーなどを受けに出張しています。
先月、今月と結構行きました。
忙しい時だからこそ、
さらに自分を磨き、
将来もっと皆さまのお役に立てるようになりたい、と考えています。
なので・・・ブログがかなり疎かに(^^;)ゞ
まだ、
今後も出張の予定がありますが・・・
ブログの更新はなるべく(?)していくつもりです。
自分でも
出張紀行を書けばいい、と思うのですが・・・
遊びに行っている訳ではないので、
そんなに・・・ネタができないんですよねぇ。
ホテルでもパソコンで仕事しているし・・・(^_^;
なので・・・皆さま、見捨てずに
このブログにまた、
ご訪問ください。m(_ _)m
軽く見られがち・・・そんな感じを時々受けます。。。
21日、T様と設計契約をしました。
T様ありがとうござます。最後まで全力でがんばります。
T様は逆で、
設計こそ大事と考えらている方です。
だから、私も限界ギリギリまで・・・。
HPにもありますが、
自分にとって、家族にとって
いい家をつくろうとするならば、
存分に設計者に設計してもらいましょう!
いい家を建てる一番のコツかもしれません。
ただし、
設計者を誰にするか・・・。
想いを叶えてくれる人を見つけてください。
都市計画は、役人と学者の世界。
街づくりは、市民の世界。
どちらからも建築家は相手にされていない。
だから復興に必要とされていない。
これが建築家の社会的立場の現実。
まずは、
現地で体を使ってみれば、遠くから頭を使ってないで。。。
赤富士です。

静岡のセミナー会場から見えました。
なかなか見られないそうで・・・静岡の人も携帯で写真を撮ってました。
縁起がいい \(^_^)/
『仲村さんのつくった家のデザインが好きなんです』
『仲村さんのセンスで設計してください』
と言われることが多くなったこと。
もうこれは・・・
飛び上がるほど、うれしい!!!
と同時に、
そう言っていただける方々に
感謝、感謝、感謝です。
おかげさまで、ありがとうございます。
私は、
このように皆さんから言われて、
仕事ができることを
目標にしていましたので、
いまはとても充実した毎日を送っています。
なので、、、
忙しさを言い訳にするつもりはありませんが、
ブログがおろそかに・・・。
来月からは
もっとブログを更新していくつもりでいますので、
今まで以上にご愛好のほどを・・・
と、今月2度目のお願いでした。。。m(_ _)m
my ペットのネコたちです。

手前がキジトラで名前が「トラ子」。
奥がアメショーで「カーン」。
トラ子は奥さんの連れネコで、
カーンはペットショップで売れ残ってるのを見つけました。
最初ガリガリで小さかったのに・・・カーンとはいつも一緒に寝てます(^_^)
今では家族の一員です!
東北の被災地でもペットと一緒に津波から逃げて、
避難所で生活している方々がいるそうです。
ただ、避難所にはペットが苦手な方もいて・・・。
そんなペットたちを一時的に無料で預かる支援をしている方々がいる、
というニュースを聞きました。
頭が下がります。
でも、
行政は日頃から津波に対する避難訓練の時に、
ペットも一緒に連れて逃げてください、
とアナウンスしていたそうです。
ただし、避難所での混乱は想定していなかったと・・・。
『想定外の悪い事が起こっても、被害を最小限に食い止める想定はできる。』
今回の震災で一番学んだことではないでしょうか。
ブログの更新が・・・。
実は理由があるのですが、
その理由は、またの機会に。。。
別にもったいぶるつもりはありませんが、
ただ、今はまだ言えない感じです。。。
そんな大した理由ではないので、
いつも見てくださる方々、
今後はもっとブログを更新していくつもりでいますので、
今まで以上にご愛好のほどを。。。
ここ最近、珍しく夜の街に出かけることが多い。。。
新橋、渋谷、新宿・・・
渋谷の街、めったに行きませんが、
あんなに暗い渋谷ははじめて。
渋谷駅前のスクランブル交差点なんて、
ここどこ?
と言うくらい、違って感じます。
ある意味貴重な体験かもしれません。
まるで海外の街のよう、
雰囲気があっていい。
夜なんだから、
昼間のように
照明でコウコウと照らす必要なんてないんです。
夜には、夜の街の表情がある。
これは住宅も同じ。
私は今ぐらいの明るさで調度いいです。
それに、いつもと変わらないくらい人がいますよ。
原発なくて、
節電して、
計画停電なければ・・・
このままでいいのでは。。。
3月19日(土)発売の
「東京の注文住宅 2011春夏」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)
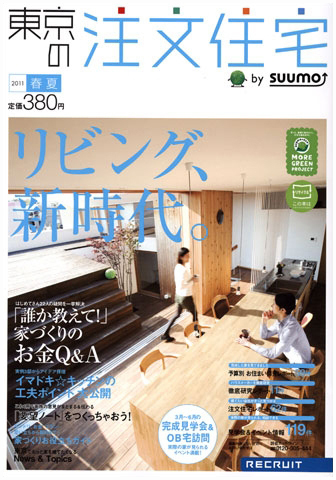
実は、発売されたのをすっかり忘れていました。(^^;)ゞ
リクルートの担当者から電話をもらい、気がつきました。。。
このところの震災、それに伴う原発の騒ぎに
そちらの方に気が取られていたのかもしれません。
毎日考えることは、
今できることを全力で・・・。
こんな時だから、
家族の暮らしを真剣に考える時なのかもしれません。
そんな方に
仲村建築店の誌面を
ホームページを
見ていただきたい、、、です。
先ほど、メールで
八戸の知り合いの工務店の方と震災後はじめて連絡がとれました。
本当に良かった。。。
その方が
被災し、不自由な生活を強いられ、
とても辛い状況にいるにもかかわらず、
『笑っていられる・・・・・生きてるだけ絶好調です♪v(^^)v』
と・・・。
涙でそう。。。
頭ではわかっていることかもしれません。
でも、実感というか、、、
心で意外とわかってないというか、、、
普段、知らず知らずのうちに、忘れてしまう。
この震災で失ったものがたくさんあり過ぎますが、
その分、何か・・・。
『Mさん、今度お会いするときは、笑って飲みましょう!!』
ある人のツイートです。
『たとえ津波がまちやむらを根こそぎ奪い去っても、暮らしの記憶まで海の藻くずにはさせない。暮らしの記憶、生活に根ざした歴史、すなわち、「場所の力」を顕在化させるのが私たちの仕事。』
今後、どうするべきか?
建築をやっている人間として、指針になる理念です。
この言葉に感動し、奮い立ちました。
心配をして、連絡を下さった方々へ
ありがとうございます。m(_ _)m
家族も含めて「無事です。」
ただ、実家の屋根瓦がグチャグチャになりました。

はじめての、経験したことがない揺れ。。。
「無事でよかった!」
改めて思います、、、決して、大げさではありません。
栃木や茨城の知り合いの方とメールで連絡がとれた時、
「無事でよかった!」
ホッとしました。
東北の知り合いの方とは、まだ連絡がとれません。
「無事でいてほしい!」
とても心配です。。。
自分にできることは・・・
メールやツイッターで知り合いに情報を送る、
節電をする、
そして、、、
OBのお客さまを回って、建物確認。
それぐらいしか・・・。
雑誌「TVホスピタル 3月号」の「編集部のお勧め」というコーナーで
当社を紹介してくれました。

この雑誌は、
全国の総合病院に無料で置かれるフリーペーパー、
だそうです。
早ければ、
今日あたりから置かれる、とのこと。
見かけたら、
ちょっと手にとってみてください。
今週の月曜・火曜の2日間、
今の自分に一番欠けている所を補うための研修 part4、最終回。
銀座で受けてきました。 o(^^o)
研修内容は・・・。
わたしは、この研修を過去に受講したことがあり、
今回は、再受講で、、、お手伝いで、、、という形で参加してました。
この研修、ほぼ全国から集まった
工務店を経営している、言わば、同業者の方々が
自分をパワーアップさせるために受けるもの。
だから、
同じ業種で、同じ目的で研修を受けるので
心と心の結びつきが強くなります。
特に今回は、非常にみんな仲良くなり
途中から、
家族や友だちにも普段話さないようなことを語り合う
仲間になりました。
わたしも
東京に居ながら、
銀座にお泊まり(^^;
今回は最終回なので、日曜の夜から2泊(^^;
これは、
毎回、初日の夜は懇親会で
銀座の夜をみんなで仲良く遅くまで過ごすため。
さらに、
今回は前泊して
浅草に集合、、、。

それが楽しくて。。。
もちろん、昼間は真剣そのもの、、、笑いもありますが(^^;

写真は、
月曜日の夜の銀座。
懇親会の後、お店の外。
銀座の雪、、、はじめて見ました。。。
今回は、
研修修了前夜祭と称し、
また、
過去の受講生が参加しての同窓会と
たくさんの人が集まり、
わたしにとっては、
今回の仲間だけでなく
過去の研修で一緒だった人との再会もあり、、、
泣けるほど楽しい夜でした(^^)
もちろん、この後
まだまだ、、、
つづきが、、、ありましたけど。。。
次の日、眠い。。。
でも、
いつでもみんな真剣に研修受けてましたよ。
だから、
みんないい顔になりました。
自分も、、、
相当パワーアップ。
3年後の自分に見通しが立ちました(^^v
実は、
絵を描くのも趣味なんです。。。
ただ、、、

写真は、趣味仲間、、、というとおこがましいですが、
普段から良くしていただいているお客さま(右の方)が描いた絵です。
用事があってご訪問すると、
決まって絵の話になり、
いつも半日ぐらいお邪魔してしまいます。(^^;
そのお客さまから
グループ展に出品した、とのご連絡をいただいたので
先日、早速うちの奥さんと一緒に三鷹まで見に行きました。
結構、レベルの高い展覧会でした。。。
実は、、、私も絵を描くのが趣味と書きましたが、、、
一応、
20代の頃に
美術学校を修了していまして、
建築設計をやっていく上で、
美術の勉強も必要では、と考え
主に、油絵を勉強してました。
今でも、
その時の仲間と
わたしもグループ展をしています。
今年は、、、
11/3〜 武蔵野市立吉祥寺美術館で開催する予定です。
今は、
油絵ではなく、アクリルで描いています。。。
先ほどの「ただ、、、」というのは、
普段は絵を描くことがなく、
展覧会に合わせて
出品用に制作に入るので、、、
趣味と言っていいのか?
ただ、、、
絵を描くのはホントなので、、、
一応、趣味と言ってます。(^^;
建築はデザインの領域。
絵画はアートの領域。
美術学校で学んだおかげで、
わたしの視界は広がりました。
普段描かなくても、、、
自然と、、、
アートを意識してます。
だから、
自然と、、、
デザインにも意識がいきます。
椅子が大好き(^^v
以前のブログで「椅子が趣味」だと書きましたが、、、
今発売中のBRUTUSで椅子特集をしてるのをコンビニで発見。
思わず立ち読み、即購入。
「椅子が趣味」と聞いて驚く人も多いです。。。
でも、椅子の世界は結構奥が深い。
それだけで一晩は余裕で語れます(^^;
宣伝をする訳ではありませんが、
BRUTUSの椅子特集・・・
いいです、、、写真が、、、取り扱う椅子が、、、焦点の当て方が。
訳わからん、という人・・・立ち読みススメます(^^;
わたしは、
デザインと座り心地などの機能性に、、、
椅子は単純な用途ですよね、、、
でも、いろいろな椅子がある。
まず、それがおもしろい!
次に、
空間に椅子が1つあれば、
それだけで空間に変化が生まれる。
2つあれば、
新たな空間がそこだけにできる。
椅子は最小の空間をつくり出すモノであり、
最小のコトも生み出す。
そこに様々なデザインがあり、
単純な用途だけに
そのデザイン性が直に影響する。
だからか、椅子に惹かれます。。。
惹かれるとなると、
当然欲しくなる、、、欲しい椅子がたくさん!
ところが、椅子高いんです、、、結構いい値段、、、欲しい椅子は(^^)
だから、なかなか買えず、
ミニチュアもあるんです・・・
でも、それも結構、普通に市販されている椅子より高かったりする。
でも、ミニチュアで我慢してたんです。
やはり、
人が座れる椅子でないと、、、「椅子が趣味」とは堂々と言えません。
まあ、「ミニチュアの椅子集めが趣味」というのでも、、、そういう人もいますが。
本来は、
人が座れる椅子が好きな訳ですから、、、あまり趣味とは言いませんでした。
しかし、
引っ越しを機に、
リビングダイニングに椅子が増えました(^^v
当然、どんなモノでもいい訳ではないので、、、
奥さんも椅子好きなので、、、
許せる範囲で買えるモノをチョイス。
で、気がつくと
20脚くらいになったので、、、
そろそろ「椅子が趣味」と公言しはじめました。
中には、結構歴史的に貴重な椅子もあるんです。
いずれまた、このブログで紹介していきます。。。
本当は、
引っ越しを機にソファが欲しかった・・・
でも、欲しいソファは高くて手がでません・・・LC2
(わからない人は「LC2」で検索してみてください)
ソファはLC2、と決めているので
買えるまで、ソファ無しです、、、いつ買えるのか(^^;
かわりに、
カリモク60のベンチシートを購入。
てな感じで、、、
欲しい椅子がたぁくさん!!!
満たされる日がくるのかぁ(^^;
空からふわふわ、、、
白い粒がふわふわ。

昨日、昼間
小雪がちらちらと。
写真には写らない。
でも、人の目には見える。
その希薄さが好きです。
最近、、、
問い合わせが多いんです。。。(^^)
結構、資料発送に、、、対応に、、、忙しいです。
「東京の注文住宅」の反響のおかげか、、、二次的効果か、、、。
うれしいことです、、、皆様に感謝感謝です。 m(_ _)m
それに、、、
プロからの問い合わせも多いんです。。。
それも、、、
うちの会社の作品を見て、デザインの指向が合うから、
という理由で来る方が多い。。。
少しづつ、、、デザインのつながりが増えていく。
なんか、いい感じのつながりです、、、今後に確実につながります。(^^)
先日、ある方から
「感動しました。」とお手紙をいただきました。
何に感動されたのか?
年賀状です。
その方の
心の琴線に触れたのかもしれません。
「たのしい毎日がくる」
わたしはこの言葉が大好き。
この言葉、、、たくさんの人に届けたい。。。
きょうが仕事はじめ。 o(^^o)
皆様、
ブログでの私を
今年も宜しくお願いいたします。m(_ _)m
きょうは、新年のあいさつ回り。
でも、、、途中のお宅で話し込んでしまい、、、
すべてのお宅を回りきれず、、、また明日です。。。
でも、
おかげさまで
いくつかお仕事をいただきました。
中には、新築のお話も、、、
新年早々、とても感謝を申し上げます。m(_ _)m
やはり、
一度ご縁を持たせていただいた方々ばかりですので
最近どうなのだろうか、
お元気なのだろうか、
などなど、気に掛かりますので
こうして、
必ず毎年、新年にお会いすると
ほっとする、と言いますか、
何かたのしく、うれしい気分になり、
ついつい長居してしまいます。。。(^^;)ゞ
この時期は日が暮れるのも早いので、、、
また明日、あいさつ回りのつづきをします。 (^-^ )
ところで、
今年のお正月は、、、
の〜んびり
とはいきませんでした。
2日から仕事してました。。。
「東京の注文住宅」の反響はスゴいですね。
うれしいことです。
なので、
お正月気分は元日だけ。

写真は、
元旦の光。

我が家のおせちです。
普段飲まないシャンパンなどを。。。

で、
毎年恒例の浅草・浅草寺への初詣。 o(^^o)
ただし、今年は行く暇がなく、、、
きょう夜に行きました。
20時ころ。。。
浅草寺初詣のたのしみの1つが
食べること、、、だったりするのですが、、、
着いたのが遅くて、、、お正月なので、、、
お店がやってない、、、ちょっとガッカリ。
でも、
お腹いっぱい食べましたけど。(^-^ )
そんなお正月でした(?)
今年も良い年に!
たのしい毎日がくる。

あけまして
おめでとうございます。
皆様の新年が
たのしい毎日でありますように。
仲村建築店 仲村和泰
追伸:
もう初詣に行ってきました。
毎年恒例で、近くの鎮守神社へ。
午前0時前から並び
今年は110番目、うちの奥さんは111番目。
1がたくさんで縁起がいいですね。
何番目かわかるのは、
確か200番目まではお箸をいただけて
そこに何番と書いてあるからです。
このお箸、長寿箸と言いまして、
伊勢神宮の式年遷宮で出た古材でつくったものだと
先日、宮司さんから伺いました。
縁起のいいお箸なので、お正月に使います。
一年の感謝を込めて、ごあいさつです。
今年は「変化のはじまり」の年でした。
目立つ所で言いますと、
会社のホームページを新たに立ち上げ、
携帯サイト、ブログをはじめました。
そのお蔭で、たくさんの人との出会いがありました。
結果、仕事に結び付きましたし、
新たな縁や深い縁ができました。
この場をお借りして、
そんな皆様方に感謝の意味を込めまして、
お礼を申し上げます。
「お陰さまで、ありがとうございました。」
また、
目立たない所で言いますと、
新たな縁や深い縁が
わたし自身にたくさんの気づきをもたらしてくれました。
結果、少しですが
成長と言いますか、
変化することができました。
その気づきは、
わたし自身の人生観に及ぶこともありましたし、
建築に対する考え方、
家づくりに対する考え方にも大いに影響を与えました。
よく
このブログを見ている方から、
「今やっている仕事のことをブログに書いた方がいい。」
と言われます。
それは、その方が
これから家を建てようと考えている人にアピールになる、
という理由からです。
しかし、わたしは
今やっている仕事の内容はブログには書かない、
というルールを自分で決めました。
理由は3つ。
ひとつは、このブログを通して、わたしの人間性を見てもらいたいから。
一言一言、一文一文から
わたしがどういう人間なのかを感じてもらいたい。
仕事の内容を書くと
そちらの方に目が行ってしまうから。。。
最終的には、
家づくりは人対人です。
一緒に家づくりができる人かどうかを判断してもらいたいからです。
ふたつ目は、
家づくりは、実際の現場も大事ですが、そこに至る考え方の方がもっと大事だから。
この家づくりに対する考え方は、なかなか具体的に表に出てきません。
実際の仕事の影に隠れている、抽象的な場合が多いです。
例えば、『いい家をつくる』『すばらしいデザインの家』などなど。
具体的にわからない場合が多い。
だから、そこに焦点を当てるために
今やっている仕事の内容を書くよりも
もっと広く家づくりについて普段考えていることを
事例を通して具体的に紹介したい、と考えています。
これも
一緒に家づくりができる人かどうかを判断してもらいたいからです。
最後は、
わたし自身が
建築に対して
住宅に対して
家づくりに対して
いろいろと気づきたいから。。。
仕事の内容をそのまま書くと
気づきも何もありません。
しかし、
なかなか言葉にできないコトを
書こうとすると、
自分でも想いもしなかった言葉が出てきます。
それが、自分自身への気づきになります。
そして、
その気づきが
次の仕事に生かせます。
少しの成長、変化になります。。。
このブログを
定期的に見てくださる方、
気が向いた時に少しでも見てくださる方、
あるいは、
今回はじめて見ていただいた方、
すべての方に感謝を申し上げます。
「お陰さまで、ありがとうございました。」m(_ _)m
来年も少しずつ成長、変化したいと思います。
見守ってくださいますと、とてもありがたいです。
来年もどうか
宜しくお願い申し上げます。
それでは、
皆様方の幸せをお祈りいたしております。
よいお年をお迎えください。
フォトシネマをYouTubeにアップして、
ホームページのトップページで見られるようにしてみました。 o(^^o)
『家族の「コト」を形にする。』
「コト」をイメージしてもらいたい、、、
「コト」のことをわかってもらいたい、、、
「コト」が一番大事だと。
また、
ちがった角度から「コト」を、、、お見せします。 (^-^ )
冬期休業は 12/30 (木) 〜 1/4 (火) です。
お正月に何しようかな?
わたしは
家での〜んびり、というより
どこかに行くこと
何か好きなことをすること
でストレス解消やリラックスし
癒されるタイプなので、、、
だから、
中古フィルムカメラを持って
街を散歩するのが趣味なんです。 o(^^o)
でも、
今年は、、、仕事するかも。。。( ̄□ ̄;)
それだけ、
「東京の注文住宅」の影響は大なんだなぁ。。。 (^-^ )
本日発売の
「東京の注文住宅 2011冬春」(リクルート)
に当社が掲載されました。 o(^^o)

コンビニで立ち読みしてみました、、、
改めて
誌面を見ますと、
少し、、、照れます。。。(^^;)ゞ
たくさんの人に
仲村建築店がやっているコトを知ってもらいたい、、、です。
今週は、
今の自分に一番欠けている所を補うための研修 part2。
銀座で受けてきました。
研修内容は・・・。
別の機会にまたお話しします。
かなりパワーアップして帰ってきました。。。
帰りに、銀座みやげを。

ここでしか買えないものを
感謝したい人の顔を想い浮かべながら購入。
物で釣る訳ではありませんが、、、なかなか素直になれないもので。。。
結果は、、、
また、すぐに1つ食べてました。。。
これ、マカロン。本場フランスのお店らしい。
おみやげにオススメ。
美味しいのは、もちろん。
東京だと、
日本橋か銀座の三越でしか買えないので希少価値がある。
色が鮮やかで見た目に楽しいし、
色ごとに味がちがうので
「これ、なに味?」
などと会話もはずむ。。。
普段なかなか会えない人へ、
話がしたいのになかなかうまく話せない人へ、
それから、
感謝している人へ。
たまには、贈り物も。
毎年行きます。この時期の楽しみのひとつ。
世田谷ボロ市。
毎年12月の15・16日、1月の15・16日。

子供の頃から、ほぼ毎年。
何がいいかって?
師走気分になれる、、、季節感を味わえる。
最近はテレビでも大きく取り上げられるので、人がいっぱい。
ボロはありません、、、近いのはあるけど。。。
骨董品、お正月の準備品、植木、衣類、、、あと食べ物などなど。
ふつうの縁日の夜店とはちがう店揃い。
ここでしか見られないお店も、、、神棚のお店、鉱物のお店、何だか分からないお店。
もちろん、、、中古カメラのお店も、、、買いませんよぉ。
子供の頃は、バナナの叩き売りをここで初めて見ました。
食べるもの、見に行くお店は、ほぼ毎年同じ。
というのも、毎年同じ所に同じお店。
でも行きたい。
だから行きたい。
朝からソワソワ。。。
ほんとは昼間に行ってみたい。
でも昼間はお仕事なのでガマン。。。
今年も十分堪能してきました。
で、
今年は帰りにボロ市会場近くのベトナム料理屋へ。

ここは普段からよく行くお店。
ベトナムビールと生春巻き。
定番だけど、旨い!フォーもいい。
ここカレーも旨いんです。もちろん、いただきました。
ボロ市行って、ベトナム料理食べて、、、ほろ酔い気分で世田谷線乗って。。。
いや〜、楽しい!
お披露目といっても、カメラの話。
今週、平日の夜。
2ヶ月に一度の趣味の会。
中古カメラ好きが
毎回違うフィルムカメラを持ち寄り、
新宿のレストランでカメラ談義。

先日のブログ「買ってしまった!」に出てきたカメラのお披露目です。
(写真左下のカメラ)
う〜ん、デカくて重い!
新宿まで持って行くだけで肩が痛い。。。
でも、シャッター音がいいんです!
『ヴァスゥッ』って感じ、、、バズーカーを撃つ感じ、、、撃ったことないけどぉ(^^;
「撮ったぁ、、、撮ったぞ、、、撮ってやったぞ!」
という満足感が味わえるカメラです。
先日、深大寺で試し取り。
光漏れもなく、快調でした。
結構いい写真が撮れました、、、
しかし、会の人には「堅い写真だね〜」と。
「適当に露出を決めてるもので、、、そこはあまり気にしないんです。」
「撮って、自分で楽しむ世界ですから。。。」と言い訳。
でも、本人はいい写真だと思うんだけどなぁ〜
これ持って、、、次はどこ行こうかな(^o^)
お正月だなぁ。
腕がパンパンになるけどね。。。
とりあえず、終了。
引っ越しました。

でも、
まだまだ荷物だらけ、段ボールだらけ。。。
まだまだ続くのです、、、ひとり片付け。
年末の大掃除の前倒しだと思うのです。。。
いずれ片付いたら、
写真撮影して、
みなさまにお見せします。
明日、引っ越しです。。。

リノベーションの詳しい内容は、また別の機会にお伝えしますが、
かなり気に入っています。
快適な生活が待っていると思うと、ワクワクです!
でもその前に、、、荷造りしなきゃ。。。。
きょうは誕生日。
だれの?・・・私。
えっ!何才だっけ?まわりに聞きました(^^;
というわけで(?)
バースデイディナー・・・というほど大げさではありませんが、、、
前から気になっていた
ちょっと洒落たお店に。。。

前菜。
自家製無農薬のルッコラのサラダと
ほうれん草とじゃがいものポタージュ。

で、シメ?のエスプレッソ。。。
メインを撮るのを忘れました(^^;
ちなみに、メインは
ガーリックステーキライス。
すべて旨かったぁ。。。
お店全体を写せないのが残念です。
とてもくつろげる場所で
ゆったりした幸せな時間でした。
この時間を感じたい方は、
個別にお問い合わせください。。。
今の自分に一番欠けている所を補うために
銀座で研修を受けてきました。
研修内容は・・・。
別の機会にまたお話しします。
帰りに、銀座みやげを。

ここでしか買えないものを
喜ばせたい人の顔を想い浮かべながら購入。
結果は、、、
すぐに1つ食べてました。。。
撮影会の帰りに、
横須賀のハードオフへ。。。
行きに目を付けておきました(^-^;
中古フィルムカメラ好きにとっては、
ハードオフは穴場。
でも、
買う気は無かったんです。
本当です。。。(誰に言い訳!?)
しかし、
見ちゃいました、、、
前から欲しかったカメラがすごく安く出ているのを。。。
今までで最安値です。
たぶん、お店の人はこのカメラの価値がわかっていない。
(だから穴場なんです。)
即決!!
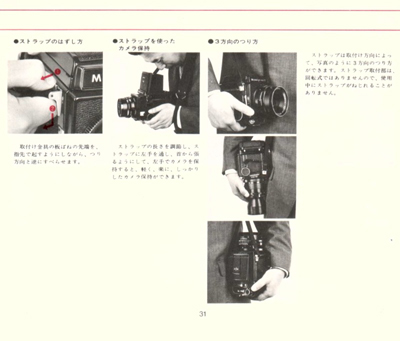
マミヤ RB67 ProS + 90mmレンズ
(実物はまたの機会に、、、)
プロ用のカメラです。
電池がいらないフィルムカメラ。
写真館などで使われていました。
でも今はデジタル時代。
昔は何十万としたフィルムカメラが二束三文に。
かなり大きく重たい、、、でもそれがいい!!
・・・どこに隠すか。。。
15年以上前から、、、できた当時から、、、
行きたかった博物館です。
三重県鳥羽にある「海の博物館」。
建築家の内藤廣の作品です。

なかなか行く機会がなく、
先の関西出張の途中に寄りました。
なぜ行きたかったか?
理由は2つ。
1つは、
この博物館建築は、絶対的な美を求めて設計されました。
しかし、
それがある方向で、ある限界点を超えると
昇華され、人とアートをも巻き込み、違った展開をみせる。
この博物館はそんな状況をつくり出しているのではないか?
それを体験してみたかったのです。
もう1つの理由は、
この建築のモノとしての完成度を見てみたかった。。。
この博物館が完成し開館したのは、バブル景気崩壊後でしたが、
計画立案・設計の時期は、ちょうどバブル景気の最中。
その頃の建築家は公共建築、とくに地方の公共建築などには見向きもぜず、
東京などの大都市で、溢れる予算を使い民間の建築を設計していました。
ポストモダニズムと称し、
時代の最先端の建築だと言いながら皆やってました。
しかし、
バブルが弾けたとたんに、
今では多少の振り返りはありますが、
ポストモダニズムの建築=悪みたいな風潮に変わりました。
一部の建築家が好き勝手にやり過ぎたのでしょう。
今でも残骸を時々見かけますが、、、
もちろん、その時代、建築家だけでなく、
全ての人が浮かれていましたから、、、何でもアリでした。
この博物館は、もともと予算があまり無かったようです。
バブルの最中です。
建築家のモチベーションは上がりますか?
今なら、上がります!
でも、その当時は難しかったのでは。。。
なのに、
建築家は粛々とできることの限界を見極めながら、
建築のモノとしての作品に昇華していった。
その結果、
バブル崩壊後に、賞賛を受けました。
今では、その姿勢がスタンダードに。
だから、
この建築のモノとしての完成度を見てみたかった。。。

木の架構。
使っている材料は、
決して高いものではありません。
納まりを工夫して、デザインして見せている。
その工夫は、他にも随所に見れます。

コストコントロールの賜物だと思います。
余分なものを無くし、
構造そのものをデザインして見せる。
ちなみに、
この木構造を住宅に応用したものがSE構法です。

プレキャストコンクリート版の架構。
コンクリート版を工場で製作し、
コストと精度とデザインの両立を計り、
木の架構同様、
余分なものを無くし、
構造そのものをデザインして見せる。
感銘を受けました。
建築家の誠実さと言いますか、志の高さに。
すばらしいと思うと同時に、
自分が普段考えている方向性に間違いはない、、、
志も技量も、、、と確認できました。
そして、
何よりいいのが、
ここを訪れた人が
「ね、ここいいでしょ。
前に来た時よかったから、一度連れて来たかったの!」
と家族に言っていたこと。
やはり、
建築はモノとしての絶対的な美を求めつつ、
最終的には、
そこを訪れる人やそこに置かれているアートなり何かを巻き込んで
どんな想い、衝動、感情をいだかせるか、が大事だと思います。
それは、どんな建築でも、住宅でも。
そして、
一番身近で大切な人とその想いを一緒に味わえる。。。
そんな建築を、住宅をつくり出さなくては、、、。
人とアートと建築の関係を一番表している場所は、、、
美術館です。
先週末、台風の中、横須賀美術館に行きました。
建築家の山本理顕の作品です。

美術館というと、
展示室の白い壁、白い部屋、白い箱の連続で
建築はそれだけを用意すればいい、
あとは、絵の作家が主人公、というのが一般的かもしれません。
しかし、
そこに、人とアートと建築の相対的な関係性を持ち込むと
違った展開が、、、
関係性が昇華するというか。。。
人とアートと建築は、
バラバラな存在ではなく、
独立しながら、補完し合って、
違った世界をつくり上げる。
金沢21世紀美術館。
その、人とアートと建築の相対的な関係性を持ち込んだ美術館。
美術館のレベルは、その国の文化レベルの指標です。
わたしは、
日本の美術館建築は世界レベルの作品が多い、と思っています。
その中でも、金沢21世紀美術館は群を抜いていいです。
その良さは、人とアートと建築の相対的な関係性の良さ。
子供が、大人がみんな笑顔で楽しそう。
難しい顔をしている人はいません。
これは、体験してみないとわからない。
ちょっとでもアートか建築か住宅に興味がある方ならば、
是非一度、行かれることをオススメします。
わたしは、、、ちょっと衝撃でした。。。
で、横須賀美術館です。
すばらしい美術館建築だと思います。

ただ、
人とアートと建築の相対的な関係性は、視覚的なことだけではありません。
現代のわれわれが設計する時、
やはり、
相対的な関係性の部分に手を付けないと
進歩がない、、、20世紀の建築とは決別しないと。。。
そんなことを感じ、考えながら台風の中帰路に。
つながり方、結び方、関係性、関わり方。
どれも何かと何かの相対性を言い表す言葉です。
アートは、
絵画でも、彫刻でも、絶対的な美を求めます。
絶対的な美とは、絵そのものの美しさ。
しかし、
それを見る人との間のつながり方、結び方、関係性、関わり方を
アートと呼ぶことができると思います。
それが、相対的な美。
相対的な美とは、
例えば、絵を見た時にいつもと違う気分になったならば、
その違う気分が絵で表現したかった美であり、
絵と人がいて、はじめて美が成り立つ。
建築は、、、絶対的な美を求めてきました。
それは歴史が証明しています。
建築そのものの美しさ。
しかし、
建築を人との関係の中で考えた時、
相対的な美も存在するだろう。
建築と人がいて、はじめて美が成り立つ。
これが、現代建築の美の根本です。
ちなみに、
アートの相対的な美が、現代アートの美の根本です。
難解な現代アート、
なんでこれが作品なの、、、と思うこと多いですよね。
でも、
その気持ち、、、それがその作品で表現したかったことです。
変なの、、、その思いがその作品で表現したかったことです。
そう考えると、難解な現代アートも気楽に楽しく見れませんか。
解読しなくていいんです。
現代建築の美の話、
ちょっと難しい言い方になったところもありますが、
住宅で言えば、
家としてのモノそのものの美しさもあるけど、
そこに住む人の想いなど、
家と人とのつながりの中で考えても
いいモノ、美しいモノはできる、ということです。
だから、
予算がいくらだから、
こんなモノしかできない、などと考えるよりも
こんなコトしたい、あんなコトしたいと
想いをたくさんふくらませた方がいい、ということです。
予算と想いの調整は、設計でプロがしますから。
そこに、技とコツがあります。
だた、想いの形に固執しないことが大事です。
どんな形でも、想いは一緒だから。。。
木造の耐火構造の住宅がつくれます。

きょうは、講習会に行きました。
(社)日本木造住宅産業協会が実施する
「木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル講習会」。
今現在、この講習会を修了した者だけが
大臣認定による
木造軸組工法の耐火建築物がつくれます。
今まで防火地域での木造3階建てはできませんでした。
3階建て以上にする時は、
鉄筋コンクリート造か鉄骨造でした。
(高層ビルだと、鉄骨鉄筋コンクリート造もある)
これからは
防火地域でも4階建てまでならば、
木造にできます。
最近、木造耐火による住宅の需要が増えています。
防火地域に指定されている所は、
都心か都心に近い
大抵、駅前商店街などの密集地やその近くの利便性の高い場所が多く、
土地を探す場合でも
そういう場所を好んで探している人もいます。
しかし、そういう場所は密集地が故に
防火上、法令で木造の建築物が建てられませんでした。
したがって、鉄筋コンクリート造か鉄骨造の住宅にするしかない。
ところが、
この大臣認定により、木造が普通に可能に。
簡単に言いますと、
どこでも木造3階建ての住宅が建てれる、ということです。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造よりは、
木造の方が建築費が安く済みますから
需要があるのです。
これは
住宅をつくる時の選択肢が増えた、ということです。
参考にしてください。
毎年のことです。
9・10日はもう1つの地元の神社、
勝利八幡神社の例大祭。

そのご寄付の札貼りのお役目に
毎年弊社が指名されます。

神社の総代の方にお客さまが多くいらっしゃる、
というご縁もありまして、
毎年ご協力させて頂いています。
去年は、
神社の神楽殿の新築事業にも携わらせて頂きました。
この八幡様、
字の通り「しょうりはちまん」。
なので、
受験シーズンになると、
わざわざ、
この八幡様を訪ねてくる学生がいる、とのこと。
その気持ち、
私は非常にわかります。。。
なんか、、、切なくなります。
京都の夜のイメージ。
関西出張で夜の京都を散策。

先斗町です。
在り来たりかもしれません。
でもこの感じ。
ちょっと味わいたくて。
ちょうど、
京都の暑い夏の終わりかけ。
一度、
見てみたかった、
体験したかった。
川床。

納涼床って言うんですね。
鴨川の納涼床。
うーん、京都って感じ。

今回は、納涼床には上がりませんでしたが、
鴨川の橋から土手に下りてみました。
風がほんと心地よい。
たぶん、
納涼床でも気持ちいいはず。
次回のお楽しみです。
暑い京都の夏を
京都らしく、
粋にのり切る知恵。
川は都市のスケール。
納涼床は建築のスケール。
そこでの粋な行為は生活のスケール。
都市と建築と生活のスケールが一体になって地域性を出す。
まさに理想的なコト。
あらゆるコトの基本です。
最近のお気に入りです。

自宅で使うつもりで先日購入。
でも今は、
デザインオフィスのアトリエで使用中。
中古の無名のイス。
たぶん30年位前のもの。
かな〜り安く手に入れました。
プライウッドの感じと
鋳物の肘掛けと足の感じが
たまらなくいい。
無名とは言え、
デザインのレベルの高さを感じます。
座り心地も抜群。
実は私、イスも趣味。
たくさん欲しいイスがあります。
ちょこちょこと増えてます。
あまりに高くて手が出ないイスは、
まずミニチュアから。
ここでおいおい紹介していきます。

iittala(イッタラ)のマグカップです。
Kaj Franck(カイ・フランク)のデザイン。
自宅と事務所で使ってます。
色はターコイズ。
見た瞬間、即決。
色がいいし、
形とスケール感もいい。
使いやすいし、
コーヒーがおいしく感じますよ。
これを使ってるだけで
楽しい気分に。
見渡すと
iittalaのKaj Franckのデザインのものが結構ある。
ガラスコップなど。
色違いで。
昔と今はガラスの厚みが違います。
昔は厚かった。
昔の厚いガラスの方がいい。
デザインもののアンティークのお店に行くと探します、
Kaj Franckの厚い方のガラスコップを。
実は、
イスもマグカップも
同じ所で購入。
気になる人は、
Googleで「ロングライフデザイン」と
検索してみてください。
一番目の所。
一度でいいから
中に入りたい、体験したい。
金閣寺のあと、
まだ時間があったので
歩いて行ける大徳寺に行ってみました。
大徳寺といえば、小堀遠州の孤篷庵(こほうあん)。
孤篷庵といえば、遠州好みの茶室・忘筌(ぼうせん)。
ほのかな期待とともに、ダメもとで行きました。

案の定、「拝観謝絶」の札。
ま、当たり前といえば、当たり前。
仕方なく、門の所から、中を伺う。
ちょっと変な人?!

ただ、この石畳、見事です。
さすが、遠州。
この石の配列、目に、脳に焼き付けてきました。
本物の質。
こういうモノに触れないと、
人は絶対にいいモノを生み出せません。

関西出張最初の泊まりは京都。
駅前のビジネルホテルに泊まりました。
(写真の京都タワーホテルではありませんよ)
夜遅く京都に着いたのですが、
夕食探しにフラフラと外出。
京都は7、8年ぶりです。

京都駅。
私が確か設計事務所に就職して2年目位の時に
駅舎建替えのための国際指名コンペがあったと思います。
そのコンペで
日本人の建築家、原広司の設計案が選ばれました。
今でも覚えているのは、
その当時話題になったからです。
高さ論争。
京都の街並みを考える時、
いつも建築の高さが問題になります。
東寺の五重塔を超えない高さ。
原広司の設計案が選ばれたのも
応募案の中で建築の高さが一番低かったから。
60m。
もちろん、それだけで選ばれた訳ではないでしょうが。
応募案の中には、高さ120mの建築も。
確かに、
京都の街並みを考えた場合、
東寺の五重塔や大文字焼きが見渡せる、
というのは大事なこと。
建築の高さを論議するのは、
大切なことで至極当然のこと。
ただ、
コンペの審査員でイタリア人の世界的建築家、レンゾ・ピアノは、
日本人の建築家、安藤忠雄の応募案、
羅生門をモチーフにした建築をイチ押ししてました。
高さは、確か120mくらいあったと思います。
イタリアも歴史的建造物の街並みが多い国。
そんな国の建築家なのに。
大事なことは、
建築の高さではないのでは。
1000年以上前にできた東寺は、
その当時の最先端の建築、現代建築でした。
それは、清水寺も金閣寺も。
京都という街は、
江戸時代までは現代建築の街だった。
明治維新後、現在に至るまで、
大きな建造物建立の機会がなかっただけで。
だから、
今、京都にふさわしい建築は現代建築だと。
たとえ、
東寺の五重塔を超えようとも。
ピアノが言いたかったこと。
京都の街並みの本質だったのかも。

現在の京都駅。
私は個人的に好きなデザインではありません。
でも1つだけ。
夜の暗さがいい。
照明の明かりが
月明かりのようなんです。
京都の雰囲気に合ってる。
それは建築家の設計でないと実現しなかったでしょう。
だって、
よく目にするのは
白色蛍光灯の昼間のような駅舎ばかりだから。
毎年のことです。
22・23日は地元の神社、
六所神社の例大祭。
きょう、23日は大人神輿が出ます。
その大人神輿の巡幸の途中の休憩所に
毎年弊社が指名されます。
我が家・当社の氏神様、というご縁もありますし、
私が通った幼稚園が六所神社付属の幼稚園だったこともあり、
毎年ご協力させて頂いています。

もう20年以上、
休憩所のお役目をしていますが、
思いつく限り、
天気はいつも晴れか曇りで
今年のように
朝から土砂降りの雨というのは
はじめてでした。
いつもは休憩用に
お酒やジュース、お菓子などを
外に台を設置して並べるのですが、

今年は、
あまりに雨がひどく、
また気温も低いので
下小屋(作業場)に
お酒やジュース、お菓子などを並べて、
屋内で休憩してもらいました。
下小屋には、
いつもは多くても4、5人位で作業していますので、
たまに、
現場でできなくて
ここで上棟式を行うことはありますが、
こんなに人が入ったのははじめてです。
入れば入るもんです。
なんかイベントでもできるなぁ。。。
それにしても、
この雨の中で御神輿を担ぐのは
端から見てると大変そうだけど、
担いでる人たちは楽しんだろうなぁ。。。
最近、ブログの更新をしばらくしていませんでした。
今月は2回程、
大きく間が空きましたが、
別にサボっていた訳ではありません。
出張していました。
関西に。
目的は、
同業者の話を聞きに行ったり、
現場を見せてもらったり。
それと、
見たい建築、
行きたい展覧会へと足を運びました。
東京にいれば、
大概のことはできそうですが、
その考えがキケンです。
ちがう場所での
ちがう考え方に触れることが
一番勉強になります。
今回は、
和歌山の同業者の方が
自身の仕事の仕方を披露して頂ける、とのことで
この機会にいろいろと関西を回ってきました。

なかなか同業者の
仕事の仕方や現場を見ることはできませんので、
とても参考になったと同時に
自社の足りない部分もわかり、
非常に勉強になりました。
和歌山まで行った価値がありました。
今後、
このブログで
関西出張での見聞を書いていきます。
私と同じ年です。
日本最初の超高層ビルは、霞が関ビルディングでした。

先日の夜、仲間との食事会で行きました。
霞が関ビルディングの足元は、
今はこんな風になってます。
霞が関ビルディングより
高いビルがたくさんできたので、
存在感が薄れましたね。
日本最初の超高層ビルだと
知らない人も多そう。
東京スカイツリーは
東京タワーの約2倍の高さ。
ということは、
40〜50年後には
東京スカイツリーの倍の高さの超高層ビルが立つかも。
でもすでに
ドバイのブルジュ・ハリファは828mだから、
東京スカイツリーの倍の高さといっても1268m、
10年以内に中国あたりでできそうですね。
高さ競争に興味はありませんが、
学生の時に、
高さ1000mの超超高層ビル計画が
21世紀に向けた先端研究だったのを思い出すと、
すごく時の流れを感じてしまう、
つまり、
年取ったなぁ。
皇居を見下ろす。

前川國男という建築家がいました。
その建築家は、35年位前に
皇居の脇に地上32階、高さ130メートルの日本最初の超高層ビルを構想していました。
しかし、「美観論争」に巻き込まれ
また「皇居を見下ろすとはけしからん」という非難から
結局、高さを100m以下に下げるという設計変更を行い建設するになりました。
そのビルは今でもあります。
ただ、その周りには
もっと高いビルがひしめいてます。
私は、先日セミナーで
皇居・大手門の脇の超高層ビルに行きました。
普通に皇居を見下ろしてます。
私も皇居を見下ろす位の
高い建築は建てるべきではない、と思います。
やはり美観上の問題があるので。
ただそれならば、徹底して欲しい。
時代が変われば、
当然変わるルールもあるでしょう。
しかし、美観に関しては
時代に関係なく、
ルールは徹底されるべきだと思います。
でないと、
先人たちの想い、努力が無駄になってしまうし、
未来の人々に想いを伝えられない。
美観は一度壊れると、
なかなか元には戻りません。
継承が大事です。
経済性と美観
天秤にかける話ではありません。
夜の姿ですか?

浅草・浅草寺の夜景です。
ライトアップどう思いますか?
ライトアップされるのは、大抵の場合、建築。
夜には夜の建築の姿がある。
夜の暗闇で見えないのも、建築のある一面の姿だと思います。
特に歴史的建造物は、
夜は暗くなり、見えなくなるのが、昔からの真の姿。
それがいい、それでいい、と思います。
だから、
夕暮れのはかなさなどが
人の心を打ち、
俳句や短歌に読まれ、詠い継がれるのです。
それを昼間のように
はっきりくっきり見せてしまっては、
趣きも何もあったものではありません。
大事なのは、建築の真の姿を見せること。
付け加えの作為はいりません。
リアリティのある夜景が見たい。
月明かりだけでもいいじゃないですか。
それがたとえ暗くて何も見えなくても。
昨日は一日中研修。
SE構法の設計・営業研修で
赤坂のNCN東京本社に行きました。
ここ赤坂の景色は、
子供の頃から首都高よりよく眺めていました。
両親の田舎が千葉なので、
里帰り時にいつも首都高を利用。
子供ながらに、
車窓から緑の多いお堀端の景色をボーッと見てる、
そんな映像と印象が強くあります。
その頃は、赤坂プリンスの高層棟はありませんでした。

それが今は、その高層棟が壊される、という。
月日が経つのが早いのか?
高層ビルを簡単に壊しすぎるのか?
ただ自分が年をとったのか?
「ニューヨークの高層ビルは、ずっと建ってるじゃないか。」
「歴史になってる。」
「なんで日本では?」
建築に対する理念の問題でしょうか?
それとも経済性重視?
答えは、『理念なき経済性重視』
そろそろ止めませんか、
スクラップアンドビルド。
仲村建築店では
完全予約制のオープンハウス(完成見学会)を下記の日程で開催!!

『わたしの居場所』リノベーション オープンハウス開催
場 所 東京都世田谷区赤堤5丁目 N邸
日 時 2010年9月25日(土)・26日(日) 10:00 ~ 18:00
内 容 『わたしの居場所』のイメージ、フライハウススペック披露!!
建 物 木造2階建て
約 束 売り込み&訪問販売は一切致しません。安心してお越し下さい。
予 約 完全予約制。ご予約はお早めに!
特 徴 新築住宅、リノベーションをお考えの女性の方必見!
当社女性デザイナーがたくさんの想いをつめ込んで、築30年の家を改修してつくった『わたしの居場所』です。
私たち仲村建築店が想う住空間、フライハウスの標準仕様の一部を見てください。
きっと今までの住空間のイメージが変わります。
具体的ないい情報、得する情報、今まで聞いたことがない話も聞ける。
絶対に後悔させません!お気軽にお越しください。
![]()
「フライハウス / flyhouse」
仲村建築店の家づくりのコンセプトを
自然素材を使って実現するブランドを設立しました。
「フライ」の由来は、、、HPを見てください。
今後、新しい展開をしていきます。
更なる追求のはじまりです。

2ヶ月に一度の趣味の会。
中古カメラ好きが
毎回違うフィルムカメラを持ち寄り、
新宿のレストランでカメラ談義。
私は正確に言うと、
古いフィルムカメラを持って
街を散策しながらの写真撮影
が趣味。
だから、
カメラの収集自体が趣味ではないので
そんなに数は持っていません。
なので、段々とネタ切れになりつつあります。。。
同じ趣向の人が年齢に関係なく集まり、
(たぶん私が最年少で、一番年上の方は70代)
話をして盛り上がる。
趣向が同じというのは、それだけで気が合います。
だから、話をしていると
とても気が休まり、リラックスできます。
2ヶ月に一度のこころの洗濯日です。
「夏の風景」と言われたら、何をイメージしますか?
私は、
陽炎が立つくらい暑い晴天の真昼で
遠くに山が見え、近くに畑や田んぼがあり、
土の匂いがモワッとしてくるような風景です。
まさに、そんな場所。

栃木県の粟野
という所に
盆休みに行きました。
目的は、お蕎麦を食べるため。
粟野は
お蕎麦では、
知る人ぞ知る場所らしいです。
何軒も蕎麦屋がありました。
なのに、
混んでいて
入れませんでした。。。
仕方なく、
近くのハーブ園へ行くと、

綺麗なハーブの葉を見つけ、
山の尾根まで上がると、

綺麗な空に出会い、
蕎麦より
美味しい想いを。
「夏の風景」を探しに行く、
ただそれだけでいい。

スイス天然漆喰を施工中。
マイハウスのリノベーション。
玄関の壁に使いました。
いいですね。
風合い、質感。

左官屋さんもいいと。
コテで扱いやすいし、
綺麗に仕上がる。
自然素材ですから、
健康にもいい。
完成見学会という程大げさではありませんが、
みなさんにも見て頂きたい、
と思っています。
他にも工夫がありますから。

きょう、調布市花火大会に行きました。
何度も行ってますが、
今回は4、5年ぶりでした。
いつも狛江駅からバスで
多摩川の土手まで行き、
適当な所で見物。
帰りは狛江駅まで歩き。
この行き方だと、
行き帰りほとんど混みません。
それに狛江駅まで車で行けば、
公共の駐車場がありますから、
さらに気軽に見物できます。
花火大会となると、
見たいけど、
行き帰りの混雑が、、、
という方にオススメです。
いつも川原に
ビニールシートを敷いて見物。
きょうは
適度に風があり、
暑くなく、
とっても気持ちよく
なんかの〜んびりと花火を見てました。
夏だなぁ〜。
たくさんの見物客。
歓声。
大輪。
歓声。
川風。
夏だなぁ〜。
大輪。
歓声。
夏の風物詩
何はともあれ味わう。
幸せなり。
きょうはこんな心境!?

スキな空間です。
透ける光。
反転した影。
曖昧な境界。
こんな建築空間をつくりたい。。。
前々から、
知人にススメられていた場所がありました。
東村山・正福寺。東京都唯一の国宝建造物があります。
そして、
東村山と言えば、うどん。
前々から行きたいうどん屋がありました。
ネットで調べると、
なんと、正福寺のすぐ裏に、目指すうどん屋が。。。
コレは、、、ということで
一昨日の日曜日に行ってきました、東村山。
昼ごろ、車で東村山に到着。
腹が減っては国宝に失礼(?)と、
まず、うどん屋に直行。
野口製麺所。

突然、畑の中に出現。
民家の庭先にありました。
讃岐うどん風で、
「しょうゆうどん」を食す。
茹でたうどんを水で締め、
大根おろしがのり、
好みでだし醤油をかける。
薬味は、ねぎ・しょうが。
(画像はありません。想像を!)
本場の讃岐うどんを食べたことがありませんが、
きっとこんな感じだと思わせるくらい、
おいしかったです。
また、ロケーションものどかで、
ここ東京?、と思うくらい。
ちょっとした、小旅行気分に。
で、国宝。

(山門の中に見えるお堂)
千体地蔵堂です。
誰もいません。
時より、お墓参りの人が。
静かに、国宝と対峙。

綺麗です、屋根の反り。
室町時代に建立。
禅宗様仏殿の代表作の一つ、だそうです。

ということは、このお堂、
室町時代の最先端の現代建築、
ということ。
なかなかこれだけ綺麗な屋根の反りは見られません。
寺社好きでなくても一見の価値あり。
室町の建築でも、
フォルムは
平成の現代でも通用するデザイン。
「古くても新鮮」
昔、美術学校の先生に言われた言葉です。
例えば、
モネの「睡蓮」は、描かれたのは今から100年前ですが、
この現代でも絵画の世界に影響を与え続け、
そして、見る人に感動を与える。
今、影響と感動を与える。
だから「新鮮」。
この正福寺千体地蔵堂も「古くても新鮮」。
国宝と一緒にする気はさらさらありませんが、
私が目指す
そうありたい建築の像です。
『古くても新鮮』

くもりの日、暑いです。
西新宿の超高層ビル街も暑い。
でもこの辺り、樹木が比較的多いです。
高層粗密。
東京の都市再開発の基本的な考え方で、
低層密集の街を、建物をまとめて高層化し、空いたスペースを緑地化する。
六本木ヒルズもミッドタウンも皆この考え方が基本。
だから、超高層ビル街で比較的多い樹木です。
この考え方は、20世紀の建築家の巨匠、ル・コルビュジエが
「300万人の現代都市(1922年)」計画で提唱したものです。
本当は、この考えにより、
街路を整備して自動車道と歩道を完全分離し、
都市問題の解決を図ることが狙いでした。
つまり、人と車を完全に分けて、
人が暮らす場所に車を入れないことにより、
排ガスなどの環境悪化がなく、
樹木や緑地がある住み良い環境にする。
ここがこの考えの目指すところで、
これを都市の広範囲で行う。
でも現実は、狭い地域だけのことで、
都市としては
自動車道と歩道の完全分離はなされず、
もともと、住み良い環境を目指している、というより
結果的に樹木や緑地がある環境になった、というところ。
要するに、狭い地域で
「建物をまとめて高層化」するという
ル・コルビュジエの考えの都合の良いところだけを使い、
再開発の道具にしているだけに過ぎない。
私は六本木ヒルズもミッドタウンも
東京の都市のあり方としてはちがうと想います。
そこには経済優先で、人が置き去り。
ただ、みんな気がつきません。
人も再開発の道具にされていることを。
みんなが気づく、東京の都市のあり方?
お手本は、きっとみなさんの近くにあります。

近くの幼稚園の大きな桜の木。
その枝が覆いかぶさり、空間をつくる。
自然の空間。
建築の空間は人工。
自然と人工。永遠のテーマです。
どのように折り合いをつけるのか?
「自然に寄りそう人工」
私が考える、自然と人工の関係です。
最近、自分の立ち位置をよく考えます。
仕事のことで言えば、何をするべきか。
自分が人より優れている部分は何か?
自分が人のためにできることは何か?
自分にしかできないことは何か?
などなど、、、
ホームページにある言葉は
そんなことを考えながら、
やっとの想いでつむぎ出した言葉であり、願いです。
家づくりについて、
真剣に考えている人たちと日々対しているから。。。

きょうの夕焼け。
夕焼け見ますか?
自然の色、毎日ちがう色。

昼に西新宿で散歩。
もちろん仕事で来て、
昼休み中に。
高層ビルの谷間、
癒しの場発見。
とくに見るべきものはないです。
ふつうです。
でも人が集まっています。
よく観察します。
道路レベルより一段下がっているので、
囲われ感があり落ち着く。
噴水池の水辺が清涼感を生む。
植樹が目に優しい。
座れる場所がある。
人の通り抜けの途中にあり、
たまりやすい。
外気に直接触れられ、
空が見える。
などなど、
人が集まる要因はあります。
でも、、、
これらの条件が全てそろっていたら
人が集まるかと言えば、
そうとは限りません。
よく見かけます。
誰も座らないベンチ。
誰も立ち止まらない池。
見向きもしない植樹。
人が集まる、、、
人に行動を起こさせるには、
上っ面の要因ではダメです。
もっと深いところで人の価値観に訴えなくては。
人を癒す場をつくるヒトは、
そこが問われているのだと思います。
家でも。
私は
それがデザインの本質だと思います。

歴史の1ページを見ているのかもしれません。
見えそうな所へ行くと探します。
東京スカイツリー。
写真では小さいです。
でも、
中間の第1展望台の所まで建ち上がったみたい。
ということは、あと1/3くらい。
やはり、景色の中で頭1つ出ますね。
東京スカイツリーは
架構の組み方がいい。
タワーの水平方向の断面の形状が
地面真上では正三角形で、
高くなるほど丸みをおびた三角形となり
地上約320mで円となるそうです。
これは、
外観のシルエットに
日本の伝統的建築物などにみられる
「そり」や「むくり」の曲線を
意識しているため、とのこと。
かなりの精度を要求される仕事でしょうが、
きっと完成したら、
見る角度や場所によって
タワーの姿がちがうでしょう。
すーっと、細身の姿だったり、
「そり」の曲線がきれいな姿だったり、
丸みをおびた姿だったり。
そこがデザイン的にみて一番おもしろい。
単純ではなく、
見る人まかせの複雑さ。
タワーの色は「スカイツリーホワイト」とのこと。
これは
日本の伝統色、
最も薄い藍染の色である「藍白(あいじろ)」
をベースにしたオリジナルカラーで、
青みがかった白だそうです。
私は
白を選択したということに
内心「スゴくいいな」と。
白は
日本の伝統的建築物では基調色であり、
例えば、漆喰の色として使われます。
また、白は
ヨーロッパで発祥した
20世紀初頭から続くモダニズム建築でも
基調色として使われていて、
数々の白の名建築が生まれています。
白の中にもいろいろな白色があり
黄みがかった白、
赤みがかった白、
灰みがかった白、
青みがかった白などなど。
日本の伝統から発想し、
それがインターナショナルな意味あいにも通ずる。
ここにも単純ではなく、
複雑さがあります。
ただ白って、
一般的に言うと、
汚れやすい、などと
建物の外観や室内の色に使うのを
敬遠されたりすることがあります。
実は正反対です。
汚れやすさは、
どの色でも同じ。
要するに、
汚れが
目立つか目立たないか。
白は、
数ある色の中で一番、
光の反射率が高い色なので、
少しくらいの汚れならば、
光の反射で白が強調され、
目立たないのです。
例えば、近くに
外壁に白いタイルを使った家があるのですが、
その家は築30年くらい経っていますが、
外壁の汚れがほとんど目立ちません。
ただし、近寄ってよーく見ると、
年相当の汚れはあります。
ただ、そこまでじーっと見る人はいません。
汚れなどと言わずに、白を使って欲しい。
白は
単純ではなく、
複雑で奥が深い色
だから。

散歩好きです。
よく行く街は、上野・浅草あたり。
写真は、上野不忍池。
昨日の日曜日に行きました。
もう少しすると、
池の水面が見えなくなるほど
蓮でいっぱいに。
花が咲きます。
夏の早朝、
蓮の花を見ながらの池のまわりの散歩
気持ちいいです。
その後、
秋から冬にかけて、
蓮が枯れ、
また水面が現れます。
見える景色が極端に変わります。
大都市のど真ん中で
これだけ大きな水面があり、
そして、
四季の変化が感じられる。
なんと贅沢なコトでしょう。
ここはいつ行っても
私を癒してくれます。

先日、国立のギャラリーに行きました。
美術学校時代の仲間、Oさんがグループ展を開催、
それを見に行きました。
仲間と言いましても、私よりずっと年上の方。
写真中央のシルエットの方。
私の趣味の写真でも時々ご一緒させて頂いています。
Oさんの絵はいつも思慮深く、
私の知らない世界への入口です。
私も昨年まで毎年、
Oさんもご一緒の他のグループ展に出展していました。
私のは、アートとデザインが融合したような絵。
絵画はアートの領域。
建築はデザインの領域。
その両方をのぞいて見たくて、美術学校に行きました。
建築デザインの仕事に少なからず影響を与えてます。
今日は、
本来終日にわたる予定が入っていたのですが、
先日キャンセルになり、
ほぼ丸1日全く予定のない日に。。。
こんな日は久しぶり!
朝少し現場に立ち会い、
あとはデザインオフィスのアトリエにずっといました。
やらなくてはならない事はたくさんありますが、
こういう時は、
時間に制限を設けず、考え事をするに限ります。
ということで、
先日現場調査に伺ったお客さまの建替え案を計画していました。
計画案を考えている時は、思いついたら、
いたる所でいたる所にスケッチするのがクセなのですが、
今日はそれらをもとに、さらに具現化。
まだまだこれから、計画中ですが、
アレコレと考えているこの時間がおもしろく、
私にとっては貴重な時間。
もっと、もっとです!
GWにお客さまとお会いしました。
自宅の建替えをお考えとのこと。
設計のご要望をお聴きするなかで
ペットと一緒の時間を大切にする空間づくりが話題に。

飼われているのは、ボーダーコリーとのこと。
(写真はお客さまの飼われているボーダーコリーではありません。)
私も猫を2匹飼っていますので、
ペットと一緒にいる時間がとても癒されます。
もう家族です。
家族の居心地の良さを空間プロデュース、
ペットの居心地の良さも当然です。
今日からブログをはじめる。
何事も「はじまり」は期待感と不安感がありますが、
今回は期待感と楽しみでいっぱい。
想いを、気づきを書いていきます。