前に重なり合う面白さをよく考えていた。オーバーラップすることで、それまでは交わることが無かったモノ同士が重なり合えば、それだけで様々な可能性が広がる。きっかけをつくることがデザインになれば面白いと思っていた。
重なりはモノ同士が物理的につくるものだが、最近はモノは独立していて、物理的な重なり合いは無いが、モノの内部にある一部分がつながり合うことがあり、そのとき、様々な可能性が生まれれば面白いと考えるようになった。

建築でも何でもモノがそこにあれば、それは自立してそこにある。しかし、何かしらそのまわりとモノとの関係も生まれてしまう。そのときに自立することとモノ同士の関係性を対比させて考えることには少し違和感がある。
なぜならば、そのときは関係性がモノの自立があってはじめて現れてくると考えられるからで、そこに違和感があり、はじめから関係性のあるところに自立したモノが置かれるということもあり得ると考えられるから。
ただ、もしそうならば、自立は関係性という地の上に成り立つものであり、自立だけを抜き出して考えることができなくなる。さらには、関係性がモノに先立つことで、自立自体がおかしくなる。
ならば、まわりとの何かしらの関係は、モノ自体の内部から起こると考えれば、全てがうまくいくような気もする。
いちいち考えたりしないから気楽に楽しみたいのが本音で、空間もそこでの瞬間的な気持ちよさ、居心地のよさが大切、でもそれはつくる方も瞬間を意識するのか。
瞬間の連続が時をつくると考えると、こう見せたいやこうしたいと作者側が考え、その情景やシーンを分解するときに一緒に時も分解して瞬間にしている。そのときには、瞬間は細切れの連続で作者側の意図をくむ。だから、ひとつの瞬間と瞬間の間にはつながりがあるとしているし、それが大前提になっている。
そのつながりを疑ってみることにした。昔、たくさん写真を撮りまくっていたころのファインダー越しの情景を思い出した。フレームが瞬間のつながりを強制的に断ってくれる。そして、並べられた写真は独立した瞬間を見せていた。
流れと捉えることはよくある。流れを読むとか、時の流れとか、空気の流れとか。流体力学なんて響きもなんとなくカッコいい。流れはすなわち、つながりともいえる。つながりがあるから流れになる。バラバラであったものがつながり動きだす、そのときの航跡が流れとしてみえる。だから、流れの前提はつながりがあることである。では、つながりが無ければ、それはただのバラバラな点の集まりである。たくさんの点が同時に存在しているだけのことである。
ちょっとおもう、この現実世界は流れでもあり、バラバラな点の集まりでもあると。つながりを見だせば流れだが、つながりを解く、別のつながりを設定する、新たなつながりをつくれば、今までの流れがバラバラな点の集合でしかなくなる。
要するに、流れとはつながりを保つ行為であり、別にバラバラでもよければ簡単に消滅するし、バラバラな点の状態の方がいろいろな流れを形成する可能性を秘めており、その方が多様で面白そうだ。そんなバラバラな点の状態のようなモノをつくりたい。
時の流れというけれども、たしかに時間はつながっており、時間に切断面は存在しないようにおもえる。
しかし、今この瞬間からみたら過去も未来も流れではなく、ひとつの止まった切断面にしかみえず、しかも、それは現在も同じで、それら3つの切断面が合わさって今この瞬間がつくられているようにおもえる。
そうすると、時は流れではなく、今この瞬間のひとつの要素として過去、現在、未来があり、それらが今この瞬間を多様にしてくれているだけで、次の瞬間にはまた別の過去、現在、未来が存在して多様にしてくれる。時間は流れではなく、今この瞬間を多様にしてくれる単なるアイテムでしかないのかもしれない。
ならば、過去のモノを今この瞬間にいかすことも、ことさら過去という時制には意味がなく、そのモノがどういうモノかということの方が重要なのかもしれない。
今現在から過去や未来を考えることは、実際の過去や未来とはちがう。今という時間にポーンと投げ入れられたとしたならば、そこにはすでに過去や未来はあり、ただその過去や未来は自分が都合よくつくったものであり、だからこそ、歴史は勝者によって捻じ曲がり、未来も方向づけられてしまう。
しかし、そうなると、実際の過去や未来にはいつまでたっても出会えないし、もしかしたら、実際の過去や未来など無くて、あるのは現在がより複雑で多様なだけなのかもしれない。
そう考えると、過去のものを未来に残そうとか、現在が過去から未来への流れの一地点とは思えなくなる。あるのは今この時の現在だけで、過去も未来も今この時のためのパーツでしかない。だから、今が大事ということか。
そこに建築があることは、そこにいる人に依存しているように思えるが、そこにいる人が抱いているその建築へのイメージより越えたモノ、それがその建築の真の姿、にするには、その建築がそこにいる人に依存しないで独立している必要がある。さらに言えば、建築が自律しているとはまさにこういうことである。
ただ、そこにある建築がどういう存在であるかは、そこにいる人自身の中にしかない。それはどういうことかというと、そこにある建築が自分の中に存在している人にしかその建築を見ている意識がないからである。
だから、そこにある建築はそこいる人の中にしか存在していないが、その建築自体はそこにいる人に依存しない方がいいとおもう。
建築をしていると全体を構築するので、構築された全体からどのような影響をあたえることができるのかを考えはじめてしまうが、そうした実在的な全体から影響をうけることがほんとうにあるだろうかなどとも考えてしまう。
つくる方は構築していく上で全体から細部へと考えが流れていき、それを実在的なこととして考えるのは仕方がないが、受けとる方は全体的な視点をもてるとは限らず、実在的な細部ばかりに目がいくことも多い。そして、その細部の実在的なモノに触発されて、全体を感覚的に捉えようとするのではないだろうか。
目の前の手の届くモノは、その場で見ることもできるので、ほんとうに存在しているとなるが、全体は目の前のモノの性質から類推し感じているに過ぎないのではないか。ならば、つくる方が向き合うのは全体ではなく細部の性質であり、全体は細部の彼方に見える蜃気楼でしかない。
自分が見ている物がその物のすべてでは無く、自分の都合とは関係無いところで、他の物との関係の中でその物が成り立っている部分があり、そこは自分では見ることができない、とハイデガーはいう。
物をつくるとき、たしかに、すべてを見せたいと考えることは無い。むしろ核心は隠したいと考える。そうしないと、建築が使えないような気がするからで、どこか核心の部分、すなわち、その建築の存在理由のようなものが見てわかるようだといやらしい、そう使えと命令しているようで。
建築が使うためにある物で、それが唯一、建築だと見える理由だと考えているならば、使い方をこちらの思い通りにコントロールしたいところだろう。ただ逆に、想定した使い方以外を見てみたいと完成後は考えてしまう。すなわち、それがハイデガーの見ることができない部分であり、見ることができない物を見たい欲求ほど強いものは無い。
たとえば窓があると、陽をいれる、風をとおす、外をみる、などの窓でできることにそって行動する。窓は行動のきっかけをくれる存在である。だから、窓と何かを紐付けることで行動をコントロールできるかもしれない。建築は人の行動をコントロールするものとしたら、窓は大事なファクターである。
窓は空間を制限する。窓の大きさは空間に特性をあたえる。窓には2種類ある。人が通る窓と人が通らない窓。人が通る窓の方がコントロールできることがたくさん増えるような気がする。ひとつの住宅に人が通ることができる窓は案外少ない。だから、より人が通る窓は大切である。ただ単に出入りするだけではもったいない。そこはデザインしがいのある領域である。
部材はもつ、といつもおもう。建築はスクラップアンドビルドが基本、最近はそうでもないが、真っさらにしてハイ次どうするか。
それについての良し悪しには興味はないが、物の行方には興味がある。生産され、加工され、形を与えられ、そして朽ちていく。スクラップアンドビルトは形を与えられて終わってしまう。形あるものいつかは朽ちるのに、朽ちることをさせない。みな、省エネもはじめの生産ばかりに注力してる。身近で誰でもできることは朽ちさせることではないかといつもおもう。
建築がスクラップになるとき、すべてが必要なくなるわけではないの真っさらにしてしまう。部材はつかえる。部材に新たなに形を与えればいい。そうしたら、また朽ちさせることができる。
地と図にわけて考えてみると、図は感覚的な対象としてとらえることができるが、地は埋没していてすぐにはとれえ所がないかもしれない。別のいい方をすれば、図は直接あつかうことができるが、地は直接にはあつかえない。だから、一所懸命、図についてあれこれと考えるのだが、図は地があって浮かび上がるものと考えれば、地についても同じかそれ以上の注力が必要だろう。
地の中で一般的なもののひとつに環境がある。建築の場合、環境はどうにも動かせないもの、どうにも触れられないものとして与えられることが多い。ただ、すべては無理だとしても、ある特定の状況を設定するなどすれば、限定的だが環境について触ることもできるかもしれない。その状況の設定は建築をつくる側でできる。ある特定の状況設定には良し悪しがありそうだが、そこで社会に対しても貢献できる可能性を秘めている。
シンボルツリーという言葉があり、象徴的なものとして外構の目立つところに木を配置し、それを中心的にまつりあげて展開するやり方がある。意外とどこでも見かける。ここでいつも面白いと思うのは、シンボルツリーの存在というより、そのシンボルツリーがどこからどのように見えるか、ということ。シンボルであるのは見られるからであり、ならば、どこからどのように見えるかに関心をもつとシンボルツリーがまた違って見える。
どこから見えるか、どのように見えるかがシンボルツリーそのものの存在に何か影響を与えるだろうか。先にどこから見えるか、どのように見えるかを決めてしまってからシンボルツリーを配置しようとしたら、先にシンボルツリーがある場合と比べて何かが変わるだろうか。関心は広がる。
新しい道具は新しい着想を生むだろうか。日常的に使う道具を新しくしてみた。正確にいうと、前に使ってはいたが、訳あって使うのをやめたもののバージョンアップ版に変えてみた。だから、完全に新しいわけではないが、今まで使っていたものとは操作感が全くちがう。
昔慣れ親しんだものを、バージョンアップ版とはいえ、また手にすると感覚がよみがえる。だから、変な違和感がなく、すんなりと移行できた。ただ、これは良いことなのだろうか。もしかしたら、新しいものに対する違和感のような変な感覚が新しいものを生みだす原動力になるのではないだろうか。
だから、今度は以前とは使い方を変えようと考えている。使い方を変えることで、全く新しい道具を使いだす時と同じような違和感をつくりだし、新しい着想の手助けになればとおもう。
昔ながらの旧家にはいると、薄暗いけれど、この暑い時期などは冷んやりしていて気持ちよかったりする。薄暗さは時に不安をあおるが、状況が変われば快適にもなる。
旧家の床下はだいたい土間である。夏の冷んやりさは土間だからという理由もあるし、軒が深いことにより日射を遮り陰をつくることも影響が大きい。土間はそもそも土であり、土はある程度の厚みがあると熱容量が大きいので、外気に直接触れることがなければ外気温の影響をあまり受けないので、冬は暖かく夏は涼しい、とされている。
さらに、熱容量が大きれば蓄熱体として利用できる。昼間に蓄熱体に日射を直接あてて熱をためれば、夜には蓄熱体から熱が放出される。現代の住宅に土の土間をつくることは現実的ではないような気がするので、土のかわりにコンクリートをつかうことが多い。ただ、コンクリートを蓄熱体として利用している例はまだまだ少ないので、その点でいろいろと可能性があるような気がする。
ルールははじめから決められていると窮屈なときもある。たぶんそれは現状とあっていないから違和感を感じているのだろう。ただ、ルール自体はほしい。ないと困る。厄介である。もしかしたら、ルールの内容が問題なのではなく、ルールを決めるタイミングが悪いのかもしれない。
はじめに決めるとモレもでるだろう。モレが違和感の原因かもしれない。想定外のことも起きるだろう。普段ならば想定外のことがあっても、それはそれでおもしろいがルール上は困る。ならば、あとからルール自体を修正や編集ができるようにすればいいのだが、修正や編集ができないこともあるかもしれない。
あとからルールを決めてみる。最初にはルールがない。思いつきの連続である。はじめから、辻褄があわない、おかしい、きちんとしないかもしれない。ただ、ルールがないから、辻褄があわないのか、おかしいのか、きちんとしていないのかがわからない。あとで、最後にすべてを包括するようにルールを決めてやれば、辻褄があっていて、おかしくなく、きちんとしていたことになる。それに、はじめの思いつきの連続がたのしそう。
外にいるのか内にいるのかを迷うのは意識の中でズレがあるからで、建築の見え方が意識とズレている証拠である。本来は意識のズレを修正するべきなのだろうが、そのズレをマイナスととらえずに、そのズレをプラスに利用してみようとおもう。
外か内かの意識のズレはふつうにおこることである。たとえば、大きな建築のなかで連続して空間移動しているときなど、知らないうちに外へ出ていたり、内なのにあまりにも天井が高くて外だと感じたりして、意識にズレが生じる。
そのズレは意識の混乱を招くかもしれないが、同時に意識に引っかかりをつくることにもなる。建築を構想する側はこの引っかかりこそ一番求めていることである。それは言葉が先に思い浮かぶ建築ではムリなことかもしれない。
外から帰ってきてとホッとするのは自分の家だから。この当たりまえのことの中に「内」のおもしろさがあるとおもう。建築の外か内かのちがいに人の意識が対応している。たぶん、人の意識の中では、外と内の建築にちがいを感じている。ただし、その建築のちがいは、建築自体のちがいでは無いとおもう。たとえ、建築自体が外も内も全く同じ仕上げで同じように見えたとしても、人の意識は外と内を区別し、建築にちがいを感じるだろう。
この場合、外よりも「内」に可能性を感じる。内に対する人の意識が2つ同時に存在し、そこに暮らしが重なる。現代建築が苦手とする生活感が人の2つの意識を通して建築と絡む。2つの意識は建築でありきで存在するからデザインで影響を与えることもできるだろう。生活感とのちょうどいい距離がとれそうな気がする。
窓は建築の中につくるフレームで、建築は環境の中につくるフレームだと考えると、窓も環境の中につくるフレームだとすることもできる。窓が無い建築は基本的に人がいる場所とは考えられないので、建築には窓が必要である。
環境によって窓の位置や仕様、性格が決まるといってもいい。では逆に、窓から建築、さらには環境が決まることはあるだろうか。何となく、窓が先にあり、それに合わせて建築をつくることは想像できそうである。窓のフレームが建築のフレームをつくる。
では環境はどうだろうか。窓のフレームが環境に何か影響を及ぼすだろうか。それは窓のフレームが何を意味するのかにも関係するかもしれない。もし窓のフレームがアクティビティを意味するのだとしたら、そのアクティビティが及ぼす影響から環境をつくることもできそうな気がする。
時間は重なり合うことができるのか、とかんがえてしまう。過去と現在とは時間でつながっているけれど、建築では分断されることが多い。リノベーションなどにより、全てが解体されない場合も増えたけれども、またまだスクラップアンドビルドが多い。
過去の時間を記憶に変換し、新しい建築にいかすことはよくみられる。端的にいえば、記憶をモノにうつし、そのモノをデザインのパーツにしてしまう。それは視覚的にわかりやすく、時間を途切れさすことなくつなげようとする意図もよくわかり、過去と現在が重なり合い同居できる。
ただ、時間という目に見えないモノを見えるようにすることで、様々な解釈ができる多様性をもひとつだけに具体化してしまっているようにもおもえる。もう少し解釈の余地を残した時間の重なり合いを目指したい。
重なり合うことは見た目だけでない。見た目で重なり合えば、オーバーラップしていることは一目瞭然である。他の部分とのちがいも明確である。視覚情報は優位だが、他の感覚によって重なり合いがわかることもある。
重なり合いは、常に自分たちの生活に影響を与えてくる。スマホひとつとっても、そこにたくさんの情報の重なり合いがあり、それは見ればわかる。スマホというデバイスを通した重なり合いだが、デバイスが無くても情報の重なり合いはわかるだろうか。
きっとそれは炙りだされるように、他の部分での他の感覚がデバイスが示す重なり合いの無さを表現してしまう。あるモノの存在の有無は、他のモノが認識されることにより実感されることもある。
空間という言葉は20世紀の産物であり、それまで空間という概念自体が無かった。今ではかんがえられないが、言葉が無い以上、空間を認識していなかったのだろう。
空間は床壁天井でかこわれた領域を指すとしたならば、ハイデガー的には、人がいてはじめて空間は認識される、となるのだろう。どうしても人間主義に傾いてしまうが、人をかんがえずに空間や建築をイメージできない。
人は何世紀にも渡って生活様式や日常の習慣を変えながら生きてきた。建築もいろいろな様式をとりながら変わってきたが、空間が床壁天井でかこわれた領域であることは変わりがない。
人と空間の関係性はそのような表面的な時代性や建築様式には影響されないもっと違ったところで影響し合っているのだろう。それがどういうことなのかをかんがえるのがまた楽しい。
緑は人をつなぐ役目をするとかんがえてみた。緑は本来、相対するもの、眺めるもので、鑑賞物である。だがもし、人と何かをつなぐ物、媒介する物だとしたら、今までの緑の配され方とはちがってくるだろう。
緑を鑑賞することが目的ではなくなるのだから、建築でいえば、緑は構成要素のひとつになる。今まで外回りの要素のひとつとして眺めてきた。しかし、建築と何かをつなぐためにある存在、すなわち、建築がそこにある必要性を緑が担保してくれる。この流れから室内に植栽を配するという発想も生まれたのだろう。ただ、ちょっと虫嫌いにはつらい。
緑がつなぐ物はどこかで、人であって欲しい、とおもってしまう。だから、人と緑が並列に存在し、そのスペースを緑が構成する、そのような建築を構想してみたい。
ひとつの自律したものをつくりたいという欲求は、ものをつくる人ならば誰でも根源的に持っているだろう。それは建築やデザイナーといった作品をつくる人たちだけでなく、民芸品のような日常に必要な道具をつくる人たちも同じだろう。
ただ同時に、単なる自律したものではもの足りない、ともおもってしまう。単に自律したものは、まわりとの断絶をおこし、孤立する。孤立からくる、その場だけ良い、ようなことはしたくない。だが、孤立を起こさないようにつながりを求めると、自律の良さのひとつである強度が失われていくような気がする。
だから、複数の自律したものを考えてみることにした。複数あれば孤立を避けることができ、かつ自律の強度も担保されるかもしれない。さらに、複数あれば、ひとつの自律が持っている象徴性が分散され和らぎ、複数での象徴性は新たな場面を生むかもしれない。
振り返ると、つくることが目的だった。つくったものを並べて改めて見直してみて、もし、つくることを手段としたら、では目的は何だったのだろうか、と考えてみた。
正直、すぐには思いつかない。目的、すなわち、つくることによって何をしたかったのか。ひとつひとつには、その時々の条件や要望といった固有のコンテクストがあり、それに応えてきた。だから、何か共通の目的を意識はしていなかった。もちろん、デザインに関しての通底する考えはあるが、その実現が目的かというと、ちょっとちがう気がした。
いま一度、目的をちょっとだけ深く考えてみようと思う。そうすることで、この先のものづくりに対してよりクリアな態度でのぞめるような気がする。
できるならば、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。きっとおかしく見えるかもしれない。あんなことやこんなことをしてる、などと笑うかもしれない。初期の携帯電話を知ってる人は、今、その当時を見れば、あまりにも滑稽で、肩から担いでるよ、などとその大きさに呆れるだろう。
ただ、今、一所懸命に未来を描こうと考えることは、例えば、肩から携帯電話を担ぎながら、この電話をもっと小さく軽く、と考えることではない。それは大きいけれど、この電話を使って何ができるか、だとおもう。なのに、ほとんどの人が、もっと小さく軽く、と考える。
一度未来へ行った気になってみる。もしかしたらスマホは無いだろうから、コミュニケーション用のデバイスがあればいいが、無い場合どうするのだろうかと考えてみる。その時できるのは、今考えることができる手段の範疇でしかないから、それは未来ではなくて、今に役立つことになるかもしれない。
結局、未来は現在の延長でしか考えられないので、描く未来像は今である。だから、そこから脱してみたいので、一度未来にいき、そこから今をながめてみたい。
いくつか同時にモノがあるときに、どうしてそこにあるのかを考えてみることに興味が湧く。偶然といえば、そうなので、今度は偶然性に興味が湧く。九鬼周造の『偶然性の問題』をポチッとしてみた。
あと、同時にいくつかあるということは、ひとつひとつが周りから独立している。独立していることは、別の見方をすれば、つながりが切断している、ともいえる。やはり、オブジェクト指向存在論が頭に思い浮かぶ。
偶然性と切断、この2つをつなげる何かを考えたら、面白そうな展開がありそうで、ただ、誰かがすでに考えているだろうから、もう少し枠を狭めて、限定した中で考えてみる。そうすると、その枠から外れたモノも取り込めるようなコトをしてみたくなる。
意図的にやると、やり過ぎて失敗するときがある。そういうときは、そもそも意図的にやるのが失敗のもとだったりする。ではと、そのときに学び、意図的さを排除するためにはどうするかと次に考える、普通は。
もしかしたら、失敗することを避けること自体が失敗のもとだったりしないだろうか。禅問答のようだが、やり過ぎて失敗した様は、そこだけ見れば、もとの意図をすでに反映していない。失敗した後のものには意図的さが消え、違うものに見えていないだろうか。その違うものは最初に目指したものではないが、最初の意図の別バージョンではないだろうか。ならば、失敗は新しいものを生成する要素として、避けるのではなく、つくるものではないだろうか。
自然な様はつくり出すことができるだろうか、という問いには何と答えるか。自然の様は自然そのものではないから、意図的に人工的につくり出すことはできるだろう、と言葉上はそういう回答になるかもしれない。
ただし、実際に意図的に人工的につくり出したものが自然の様に見えるかどうかはわからない。どこかでやはり意図的で人工的だと思ってしまったら、自然の様ではない。結局、自然な様も何もしないで放ったらかしにすることでしか、つくり出すことができないのかもしれない。ならば、自然そのものと同じではないか、となる。
だから、自然そのものの生成過程を真似て、その生成過程を意図的に人工的につくり出し、あとは何もしないで放ったらかしにする。そうしたら、やがて自然の様になる。
時はかかるものである。でも、時はかけれないから失敗する。そして、同じ失敗をたくさん繰り返す。その失敗の山はもしかしたら、自然の山に近い見え方を一瞬するかもしれない。
2つあって、はじめて一人前のような関係性は、どちらも単独では弱いので、チカラを合わせましょうということかもしれないが、それで上手くいくには、チカラの合わせ方をどうするか、という問題もある。
2つの良いところがそのまま失われずに共存できればいいが、打ち消しあっては元も子もない。せめて打ち消しあうのが悪いところならば、良いところが共存できなくても、チカラを合わせる意味はある。
理想は合わさることで、良いところは相乗効果でより良く、悪いところは打ち消し合いなくなることか。ニコイチはきっとこの理想に近いことかもしれない。
もしかしたら、意図的にニコイチを形成することで、単独行為の結果を意図して超えることができるかもしれない。きっとその時には、意図しない複雑性を身につけているだろう。
大きなものを、塊のままにするか、バラバラにするか、結構まよう。例えば、大きな肉の塊があったら、なるべく大きなまま調理して食べたいし、どんな肉でも塊であれば、ひき肉にしてハンバーグにするのはもったいない、とおもう。
やはり、一度バラバラにしてしまったら、元にはもどせないし、バラバラにするのはいつでもできるから、まずは塊のままでどうにかかんがえたい。ただ、塊のままだと、扱いづらく、お持て余しそうだし、使い道も限定されるような気がする。だから、バラバラにしたい誘惑にかられる。
塊のよさってなんだろう。中間をとって、所々をバラす、という手もあるが、扱いづらく持て余しそうということは、それだけポテンシャルを秘めているとも解釈できる。扱いづらいのは魅力的だ。
その昔、フィルムカメラで撮影するおもしろさから、同じフィルムカメラを中古で複数買いし、人にお願いして、部品取りし一台の完動するフィルムカメラをつくったりした。それをニコイチ、サンコイチ、ヨンコイチなどと呼んでいた。だいたいは完動品にしたいカメラがあり、そのための部分取り用として動かないジャンク品の中から探してくる。そのジャンク品探しもまたおもしろい。
ニコイチ、サンコイチされたことは、カメラの外観からはわからない。ほとんどが分解しないとわからない見えない所に部品が使われる。全体として変化はないが、その部材がないと機能しない。ただし、その部材は他から来ている。
ひとつのものとして独立して存在していながら、他との強い関わりが内在されている。きっと、そこにおもしろさを感じ、ニコイチ、サンコイチして遊んでいたんだとおもう。
コラージュという技法が昔から好きで、ただいつもおもうのは、全体的なルールをつくってしまったらコラージュにはならない、ということで、知らず知らずのうちにおちいる。たぶんこれは、全体的なルールをつくることからはじめることに馴らされてしまったせいだろう。
全体的なルールに陥らないために、重なる部分に注目してみた。全体的なルールは整列する方向に向かう。それを避けるためには、整えない、よく見せようと意図しないなど、作為しないことだ。その作為があらわれるのが重なる部分だとおもった。ちょうどよく、綺麗に見えるように、無意識に重ねる。だから、重なりに、むしろ違和感があるくらいに、何もしない。これは、何もしない、という意図ではなくて、本当に何もしない。
スタッキングチェアがある。重ねることができると部屋を広く使いたいときには助かる。ただ、スタッキングできるチェアの場合、背もたれがあるので、ちょっとずつ前のめりにズレていくから、何脚もスタッキングできない場合があるし、その分場所もとる。その点、スツール は背もたれがない分、ズレずに真上にスタッキングできるから、何脚も天井につくまで重ねることができるし、省スペースにもなる。
身近にある重ねることができるものを探したら、スタッキングチェアが目についた。打合せスペースには大人数に対応できるように、スツール がスタッキングされている。スタッキングされたスツール は、高層ビルのように、真上に向かって層を成している。その層、すなわち、スツール は入れ替え可能だ、まるでメタボリズム的。
ただ、面白いのはチェアの方で、スタッキングされていくと、だんだんと偏心されて、背もたれ分前にズレていく。だから、背もたれがスタッキングの鍵をにぎる。背もたれのデザインがスタッキングチェアの生命線だとふんだ。
建築での層の重なりに背もたれ的なものは存在しない。ならばあえて、背もたれ的なものを用意し、スタッキングさせ、偏心させることをかんがえてみても面白いかもしれない。ほとんどの建築は層を成しているのだから。
その土地には過去、現在、未来とその時々で必要なものが現れる。土地自体は不動だが、その時々で必要なものは時間的に過去、現在、未来とつながりをつくらない場合が多い。もしスタッキングチェアのごとく、過去、現在、未来とつながりを重ねつつ、その時々で必要なものがあったら、どうなるだろうか。
日本のようにスクラップアンドビルドではなく、ヨーロッパのように何百年もリフォームしながら使う石の建築でも中を変えるので過去、現在、未来のつながりは断たれる。ただ、都市的には風景は変わらないので過去、現在、未来のつながりは保たれる。そこがヨーロッパの都市の良さなのだろう。
変わらないという価値は素晴らしいが、否応なしに変える必要があったときには困る。変わらないという方法でつながりを保つのではなく、変わるからつながりが生まれる方法をかんがえてみる。
生まれ育った家は、たぶん、築70年以上だろう。増改築を何度も繰り返して、一番最初の外観はどこにもない。もちろん、一番最初の建物を見たことはないが、生前の父親から聞いて当時の平面図はおこしてあり、現在の平面図と比べることはできる。
昔の家は和室が連なったプランであり、壁が極端に少ない。襖や障子の開閉により、部屋の大きさを可変することができ、同じ部屋にいくつかの用途が、例えば、寝室とダイニングのように、重ねられており、家具や寝具も固定ではなくて、収納や移動が可能だった。
あきらかに、今と昔では、空間のあり方や秩序がちがう。それの一番の原因は、生活様式の変化だろう。座敷から椅子になり、寝室とダイニングは分離された。
だから、そこでモノの扱いも変わった。そのモノの扱いのちがいが空間のあり方や秩序に事後的に影響する。それをいまの建築の中に移植することで、前の建築からのつながりは保たれる。主題にすべきは移植の仕方だろう。
入れ子構造というと、ロシアのマトリョーシカ人形を思いだす。マトリョーシカ人形は大家族を連想させる縁起物らしい。大小でつながり、同じ場所でつながり、同じようにつながる、からだろうか。たぶんに建築的である。
建築でも入れ子構造になっているプランは昔から多い。大事な空間を包むように外の空間があったり、大きな空間の中にいくつもの空間が内包されていたりなどする。そうして見ていくと、入れ子構造は空間に関する秩序的なものであり、マトリョーシカ人形も空間の外形ともいえる。だから、マトリョーシカ人形はモノと空間の両方の特徴を合わせもつ、ともいえる。
ただ、この入れ子構造という秩序には、空間の内容は関係ない。もちろん、建築として構成する場合は、空間の機能や目的といった内容によって、入れ子内の配置やつながりが決まるだろうが、入れ子構造だけでかんがえれば、空間の内容はどうでもよく、秩序だけを扱うことができる。それは面白いとおもった。
完結した空間があるならば、それはひとつとして、空間がある目的のためだけにあることかもしれない。その空間の存在理由が明確で、そこで行われるアクティビティも明確で曖昧さが無く、変わることも無い。
一方、不完全な空間ならば、空間が存在する理由に目的が無く、アクティビティも定かでは無く、ただ、その空間はなくてはならないもので、何か足されると、完結した空間に変わるようなものかもしれない。
きっと、完結した空間が圧倒的に多く、不完全な空間は昔と比べて少なくなってきている感じがする。ただ、今さらすべてを不完全な空間にするのには無理があるし、その必要性も感じない。しかし、完結した空間ですべてを覆いつくすのにも息がつまる。
ミックスした状態、例えば、完結した空間にバラバラと不完全な空間が現れるようなものがいいかもしれない。ちりばめられた無目的な感じは気持ちいいとおもう。
空間の中の家具に注目してみた。家具には造り付けのモノと置くモノがある。造り付けのモノは空間と一体化する。だから、造り付けのモノは完結した空間をつくる手助けをする。置くモノは交換が可能だから、空間の中での位置は比較的自由である。だから、空間は置くモノの位置に左右される可能性があるので、不完全な空間になりやすい。
どちらが良いわけではない。完結した空間ならば、何もかんがえる必要はないから、ただそこに居るだけでも良い。不完全な空間ならば、何かをしなければならないが、そこに自由意志が入り込む余地がある。この余地に心地良さを感じる人もいるだろう。どちらかというと、自由さが欲しく、完結さは息苦しく感じるたちである。
プランを考える手が止まる。空間をどうしようか、と考えることが苦痛になるときがある。
20代の頃、フィンランドへアアルトの建築を見にいった。そのときのことを思いかえすと、詳細なエレメントがまず浮かぶ。壁のタイルやレンガ、開口部の形状や光、階段のディテール、手すりの感触など。空間は、そのようなエレメント越しに、意識しないと思いかえせない。すごく近視眼的な把握の仕方だけど、人が建築と対峙するとき、自分と同スケールのエレメントに、まず自然と意識がいくのだとおもう。
なのに、空間から考えている。考えてみれば、はじめからねじれているのかもしれない。アアルトは、空間ではなく、エレメントから着想し、エレメントを浮かび上がらせるために、空間を必要としたのではないかと、その当時も考えたことを思いだした。
建築において20世紀最大の発見が空間だという。空間を表現するためにエレメントは省略されてきた。プランニングを線でおこなうのも、空間を考えるときに都合が良いからだ。でも、苦痛を感じるならば、線ではなくて、他のことで、エレメントを省略せずに、建築を考えてみようとおもった。
なにかを構成する部分は全体の一部、という関係性は普通に日常にある。このときには、全体というものに対する信頼が前提としてあり、また、全体に従う部分があるという関係性にも信頼をおいている。この場合、全体だけ、部分だけで成り立つとは考えていない。
部分だけで成り立つとは、部分同士の関係性にルールはなく、部分だけで独立していて、部分同士はルール無用である。ルールがある時点で全体が生まれてしまうから、部分そのものに信頼があるのが前提になる。
全体だけで成り立つとは、部分がどうであるかに依存せず、全体だけで独立していて、全体に絶対的な信頼があるのが前提になる。
ならば、全体だけと部分だけがあわされば、ルールの無い独立した部分同士と、部分に依存しない全体が、同時にあることなる。それは、なかなかない組合せかもしれない。それで、建築をつくることができるかもしれない。全体と部分の間にちがうなにかが生まれるかもしれない。
「うっかりミスを少なく」 2023.04.16
ときどきか、たまにか、参ったな、なんて思うときは、案外、あきらめもついて、後にはのこらないが、もしかしたら、うまくいったのにとか、思うときは、なかなか、後をひきづる。頻度は、たぶん、参ったなは少ないが、もしかしたらは、それなりにあるかもしれない。それは、うっかりミス、というやつである。
うっかりミスは大体、わかっていたけど、という言葉がさきにくる。頭のなかにはあったけれど、それがうまく表にだせなかったときで、やっぱり、それは一番くやしいし、落ちこむ。
頭のなかにあったけれど、うまくだせないことは、忘れていたことと同じらしい。だからつねに、思いだす、と意識すればいいそうな。それで、うっかりミスが少なくなるか、ためしてみよう。
全体を見ずに部分的なところばかりを見ていては、うまくいかない、と考えるのは、全体と部分には整合性があるものであり、整合性がないといけないから、整合させようとするのはいいこと、だという前提があるからだろう。
ならば、前提を逆にすれば、部分的なところばかりを見ることがいい、となる。この場合、全体と部分に整合性がなくてもいいことが前提になるが、場合によってはそれも可能性としてはある。ただ、単に逆にしただけでは、あまりに単純で反動的なので、ちょっとひねりを入れる。
部分はそれぞれ独立してありながら、全体はひとつにまとまっていて、ただ全体と部分には整合性はない、としてみる。この場合も可能性としてはありえるだろう。部分的なところだけを見て、単独で成り立たせることをだけを考えても、そこに何かつながる細い糸を見つけることができれば、それでいいとなるから。
何かを出現させようとしたとき、まず、つくることを考えるが、選んでいるだけではないか、とおもった。つくるときには、何かしらのベースがあるもので、そこから、いくつも枝わかれした予測が存在する。その予測は無意識に行っている場合もあり、その予測の中から選んでいるだけなのに、つくっていると錯覚をしてしまうかもしれない。
そこで、予測の中から選んでしまっているのならば、いま一度、つくることを意識し直すことで、よい物を出現させようとするのと、どうせ選ぶことになるのならば、選ぶことで済まして、他のことでよい物にしようとするのと、2つの方向性が考えられる。
どちらも有りだとおもうが、イノベーションを起こせるのどちらだろうか。きっと前者だという人が多いだろう。ならば、後者で考えてみる。理由はつくるより選ぶ方が早いからで、スピードがないとイノベーションは起きない、と考えるから。
つねに壁にかこまれていると感じたら窮屈だろうな、とおもうのだが、どうなのだろうか。むかしの城郭都市やゲーテッドコミュニティなどは壁に囲まれた街だが、その壁の存在をふだんの暮らしの中で感じることがあるのか興味がある。あんがい、日常的なこととして、壁の存在などは何も感じないようになっているのかもしれない。
実在している物理的な壁だけでなく、意識的な存在の壁というのもあるだろう。「壁がある」などと物事に対する障害をあらわしたり、「バカの壁」というのもある。「バカの壁」の場合は、その壁の存在に気づいていないから「バカの壁」なのだろう。
壁に気づいている場合は、その壁に対処したり、その壁の向こう側に何かあると、わかっているからいい。ただ、壁に気づいていない場合は問題かもしれない。壁の内側だけなのに、それが全てだとおもってしまうことになるから、それではちとかなしい。だから、壁にかこまれている窮屈さは、貴重なサインなのかもしれない。
時間が蓄積された物が壊されて無くなることはよくある。その物の価値には関係無く、全く無にしない、ことを選択したならば、ただそのままでは残せない。残すためにはどうするか。
時間が蓄積されているということは、そこに何らかの意味も付着し、記憶となっている。記憶を喚起する物としてアイテム化し、部分的に残すことはよくある。ただ、それではまるで標本のようである。標本として残す価値がある物はいいが、価値が無ければ、無くなる運命をたどるのは同じである。
むしろ、記憶や意味、時間を剥ぎとり、物そのものを再構成することで、価値に関係なく、残す方法があるのではないか、とおもった。要するに、配置の仕方しだいで、どのような物にも活きる場があるだろう、としてみた。
できる物ばかりを想像してまうと、脈絡のない妄想ばかりがつづく。時間には制限があるから、この妄想もいったんやめて、まとめようとするのだが、案外、妄想にはバリエーションがなくて簡単にまとまる。はじめから想像できる結果は、どこかで、前に、もしかしたら、妄想したり、チラッと思い浮かんだりしたことだったり、結局は、今までかんがえていた範疇から抜けだすことができないので、妄想にバリエーションが生まれないから、簡単にまとまるのかもしれない。
ただ、この簡単にまとまる、バリエーションのなさ、がつまらなく感じる。だから、結果を生みだす過程をつくることからはじめよう、とおもった。過程をかえれば、たとえ今までかんがえていた範疇から抜けだすことができなくても、結果にバリエーションが生まれ、今までとちがった物になるかもしれないし、過程からつくることで、べつのかんがえ方が生まれるかもしれない。なにより、毎回過程からかんがえることが、面白そうだとおもった。
ポツリとポツリと物を置いていく。物同士につながりはなく、だから何でもいい、脈絡はなくてもいい。ただ自然と、近い遠いのちがい、はできる。置かれている物はそれ自体で完結しているが、近くにある物とは何かをつくる。その何かはコントロールする必要はなく、自然に生まれてくる。
実際、建築は囲うことでつくっていく。そのための順序手順が決まっているし、それは建築のはじまりのひとつの説でもある。ただ、建築が物から派生したものならば、囲うことより、無作為にある物が他の物と合わさって建築になることもかんがえられる。
もし、囲うこと以外で、建築ができるならば、きっと、完結した物同士が近いところからより集まって建築の体をなす、こともあり得るだろう。
物が散乱している情景は、物にもよるが、なんとも様にならないようにおもえる。きっとなにも脈略もなくそこにあるから、様にならないのだろう。ブリコラージュのように、なにかにむかって収束していくのならば、ちょっとは様になるかもしれない。全体的になにかルールをもつことは、まとめるためにはよく、このまとめることが、なにか意図をもつ時には重要だが、それぞれの物がそれぞれのルールで完結してありながら、なおもバラバラにみえれば、それはそれで様になるだろう、ともかんがえた。
全体にひとつのルールでは窮屈におもえる。ひとつのルールで様なるようにしたら、なにか無理矢理におさめようとして、取りこぼすものがでてくるだろう。無理にひとつのルールでまとめようとするのではなく、個々にルールをもち完結すればよく、それでもバラバラにならないためには、近い距離感が必要なのだろう。ただ、近いというだけでまとめる、ルールではなく距離感でまとめる。距離が遠ければ他者ということである。
目に見えないものはアテにならない、としてみる。感じ、雰囲気や気分を直接あつかわない。空間、それ自体は目に見えない。目に見えているのは、空間を囲っている物であり、その物から推測して、そこにどのような空間があるのかを察しているだけだとしてみる。
そうすると、空間を察することは直接できずに、そこには察する側の思惑が、物を通して加味される。だから、思惑が入るので、空間はこれだと、確かにいうことはできないので、空間はアテにならないし、そもそも、そこには空間がある、という一種当たり前のことですら、アテにならなくなる。
では、目に見える物だけをアテにしてみる。確かにそこには物があり、その物をあつかい、その物の中に入る自分がいて、そこで暮らして、生きている。その物に相対しているときだけ、その物から影響を受け、影響を受けることで、物がそこにあることがわかる。この関係の中には空間は必要ない。また、物同士の関係もどうあるかは必要ない。独立して物があり、そこに人がいるだけ。それで建築はできてしまう、となる。
最初におもいつくアイデアはいつも妄想ではないか、とおもってみた。だいたい、好き勝手なことをおもい巡らす。それは、いつも、現実的ではないかもしれない。その時間はとても楽しいが、それではまとまらないから、現実に合わせる。その合わせ方に焦点をあててみる。
妄想ともおもえる初期のアイデアを分解してみる。複数の要素にわかれるだろう。その要素ごとに独立してかんがえ、現実に合わせるために、要素を入れかえたり、変化させたりする。各要素ひとつだけで全体を表すことはないが、すべての要素があつまれば、全体がみえてくる。
だから、各要素ごとに変えたり、変えなかったり、どのように変えるかで全体をコントロールしていく。そうすることで、妄想のおもしろは残しつつ、実際に立ちあがる建築が生まれる。
強い考えがあって、それにそって、何かを決めていく。きっと、そうしたい、と思い、全てをひとつの強い考えで満たしたい、と思う。それは、芯があって、理想的なことかもしれない。別の言い方をすれば、それは、型、かもしれない。
強い型をもつことは、何にでも有効だろう。それにそうだけでいいから。ただ、そもそも型とは、決まったひとつのことに対応するためのものだから、強くなればなるほど、ちょっとの変化にも対応できなくなる。
最近思うのは、強い型では対応できないことが多いのではないか、ということ。型にはまればいいが、そんな、ひとつのことで済む、ような場面はなかなか無い。
だから、ひとつに対応するための型よりは、強くなくてもいいから、複数に柔軟に対応できる方がいい。それはもはや、型、と言えるような全体性は有しないかもしれない。もっと、個別の、その中では完結しているけれど、決してそれは全体を表すことでは無いような、そして、それが複数あることによってはじめて、全体がわるような、そのようなものがあれば、その方がいいような気がする。
ひとつの世界観で表現できるような、きらびやかな世界がユートピアであり、それは憧れであり、よく見聞きした建築は、みな、そのようなユートピアだった。だから、ユートピア的な建築をつくりたい、とおもう気持ちはいつもどこかにある。しかし、それは妄想だろう、という気持ちもいつもどこかにある。
ひとつの世界観でスパッときれるほど、この世界は単純ではない。やはり妄想でしかない建築のイメージをどうしたら現実の世界にフィットさせることができるのか。
フィットさせるためには、どこかで妄想を切り離し、別のものとつなげる必要がある。その別のものはひとつではなく、複数かもしれない。複数のものがそれぞれ別の世界観をもち、かつ同時に共存するような状況が、妄想ではなくなる瞬間かもしれない。
スクラップ、アンド、ビルトにより成り立つ建設業界なので、街を歩けば、結構な頻度で、建物を解体をしているところに出会う。そのたびに、建築はモノだな、壊すのは簡単だな、とかおもい、解体しているときにしか見ることができない建築の姿をながめる。
伊勢神宮の式年遷宮のように、解体しても、またその部材を他で再利用するならば、解体することに対する罪悪感みたいなものは生まれないのかもしれないが、解体は、それまでの記憶や、積み重ねた時間や、見慣れた風景を切断して、膨大な廃棄物に変えるだけである。
ただ、見ようによっては、解体される建築には、さまざまな記憶や時間、風景がつまっていることになるので、それは貴重な財産である。活かしかたがわかれば、解体するより利用することを皆えらぶだろう。
体験によってすべてをとらえようとするのは、経験主義かもしれないが、あらゆる要素を、体験をとおすことで、ひとつの土俵の上にのせることができる、のは面白いかもしれない。
体験でわかることは、けっこう、たくさんある。例えば、赤い花、があれば、「花」という物も、「赤い」という色も、また、赤い花を見ている「自分」も、体験という土俵の上にのせることができる。
あとは、その土俵をどうするのか。はじめから、どういう土俵かを設定するのか、あとから設定するのか、そもそも「土俵」自体を物としてみて、「花」や「赤い」や「自分」と同じようにあつかうのか。
体験をとおすことで、あらゆる物のつながりを切断することができ、さらに、新たなつながりをつくることができる。そこも面白いところかもしれない。
都市部に暮らしていると、たまに自然の中にいきたくなる。都市の中にも自然はあるから、そこへいけば、気がすむかといえば、そうでもない。自然の中にいくことと、自然があることは、一緒のようで、ちがうということかもしれない。
建築をつくっていると、自然がある、という物質的なことをかんがえる。どこに木を植えるのか、どこに緑をもってくるのか、建築と自然をどのように融合させるのか、親和的にするのか、などをかんがえる。そこをかんがえれば、とりあえず、緑を取り入れ、建築と自然をとりまく諸問題を解決できた、となる。
ただ、さきほどの、自然の中にいきたくなることを、直接解決することになるのだろうか。やはり、自然があることとは別のこととして、かんがえるべきなのだろう。
空間があっても、その空間は自分にまとわりついているもので、はじめからそこにあり、意識することがない。しかし、空間をつくろうとすると、囲うことをかんがえ、そこではじめて空間を塊として量で意識する。
塊として量で意識しないと、建築化できないから、囲うための壁や床、天井をかんがえる。ここで、空間をつくることと建築化は、同じことのようにおもえるが、ちがう。
空間をつくることは、空間を認識としてとらえることであり、それは空間という無色透明な水みたいな存在を、何か入れものにいれて、わかるようにすることである。また、建築化とは、壁や床、天井といったエレメントを先に構築し、囲われることにより、空間の形を出現させることである。
どちらも結果的に空間があらわれるが、空間をつくることは内向きで心的なことであり、建築化は物質的である。どちらかというと、心的な空間のとらえ方に共感をおぼえるが、心的なとらえ方をしたあとに、物質的な表現に焦点があうので、建築としての空間には両方の要素が必要で、そこのバランスのとり方やズラしかたが主題になるのだろう、とおもった。
こうしたい、ああしたいと、こうする必要がある、こうしなければいけないを、まとめてすべて満たした物が最終の成果物になるのが一般的であるが、それでは、だれがやっても、大体、にたような物にしかならない。
だから、すべて満たした物の先にある、別の物をつくり、あたかも、はじめから目指していた物はこれですよね、と示し、満たすべき物もそもそもこれですよね、と逆に定義しなおすのが、現代建築ではよくあることである。ただ、満たすべき物を変えることができる場合はいいが、もしかしたら、それは珍しいことかもしれない。
別のやり方として、満たすべき物をすべて満たした建築に、さらに手をくわえる。それは、満たすべき物を強調するためであり、それによって、手を加える前と後とでは、満たすべき物がより浮かび上がる。より浮かび上がった状態は、もしかしたら不自然かもしれない。その不自然さが、にたようは物にはならずにさせ、ちがいを生む。ただ、そのちがいの素は、満たすべき物であるから、そのちがいは受けいれやすいだろう。
これがいい、という確かさをえるには、これでいい、という一般的な了解が必要になるけれど、そもそも、その一般的な了解などが妄想、だということをよくきく。だから、その一般的な了解など存在しないから、それを根拠にして、何かをつくったり、かんがえたりすること自体がおかしいと。
その妄想を、たとえば「ブランディング」というべつの言葉にしたら、わかりやすいかもしれない。ブランディングは、新たにつくる一般的な了解であり、そもそもはじめには何もない、まさに妄想である。ただ、そのブランディングによって、これでいい、という一般的な了解が植えつけられ、これがいい、となる。
具体的に何かが生まれるときには、この一般的な了解は、その生まれたものを受けとる側には必要だろう。ただあまりにも、その一般的な了解が前面にでてくると、その生まれたものがまったくのウソにみえる。
ただ、ウソにみえてもいいもの、みえた方がいいものもある。逆に、ウソはダメなものもある。そのちがいは、一般的な了解のだし方で調整することだろう。受けとる側がいて成立するものならば、調整することが、つくることの一部になる。
建築には、細くて目立たないがしなやかで強い、一般的な了解が必要だとかんがえている。弱いと、建築自体がさまざまなつながりの中で消滅してしまい、ただ強いだけど、建築の存在がウソになる。
かんがえたり、イメージしたりするなかで、妄想はよくしてしまうし、妄想がなにかのヒントになることはよくあるが、妄想の世界をつくり出すことには、まったく面白さを感じない。
妄想の世界は、極端にいえば、何でもありである。この何でもありが、妄想の世界の良し悪しでもあるが、何でもありだから、自由にしていい、何をつくっても、それは妄想だから許される、となってしまうことがつまらない。ようするに、現実的な裏付けがない妄想の世界には興味がわかない、のである。
妄想を別のことばにしたら、非日常的、詩的、観念的などになるかもしれない。非日常的で、詩的で、観念的で、それだけのものならば、興味はわからない。ただ、もし詩的で、観念的でも、日常的であれば、それは現実的な裏付けがある妄想の世界になり、グーッと興味がわいてくる。
ここでしか成り立たないこと、にはあまり意味がなく、もう少し引いて、全体を俯瞰して、何か抽象的な全体像や仕組み、イメージをもち、それへ向かって整列するように、ものごとを決めていくことが大事だとおもっていた。
ただちょっと振りかえると、そのような全体像や仕組みやイメージは、妄想にすぎないのではないか、観念的に、詩的に、そういう全体像などをつくり出して、それに酔っているだけではないか、とおもうようになった。
俯瞰せずに、地に足をつけて、平行目線で、間近なものを、周辺をボカシながら、中心にくるものだけをしっかり捉えてみる。そうすると、あまりにも限定的な部分しか相手にできないが、それらは妄想ではなく、それらが複数集まれば、相当の規模にはなるし、ただ、限定的な部分の寄せ集めなので、決して完璧な全体像は表現できないが、それが現実的でいい、とおもった。
部分の寄せ集めと、全体像はちがう。部分の寄せ集めによってできる全体は、俯瞰してわかる全体ともちがう。どちらかというと、部分の寄せ集めによってできる全体は、ここでしかできないことに近いかもしれない。ここでしかできないこと、の方に、ちょっと可能性がみえてきた。
白くて明るい空間がすきだが、一番すきな空間は、人目につかない暗い場所になる。白いのは壁や天井であり、明るさは大きな開口部が満たしてくれる。この白い空間は全てのものに光があたるから、影などなく、全てが見わたせる。この清いくらいの白さと明るさが、生活の中には必要である。
ただ、同じくらいか、それ以上に、人目につかない暗い場所も必要になる。全てが見わたせる白くて明るい空間では、こぼれ落ちてしまうもの、のために人目につかない暗い場所がいる。
いままで、メインは白さと明るさであり、サブとして秘密の暗部で人目につかなさがあった。この関係性を逆転するのもいいかもしれない。秘密の暗部をメインにするのは、あまりにも外の世界が開かれすぎていると感じるからで、逆にそれを感じられなくなるのがこわいので、自分が日ごろ引きこもる場所は、秘密の暗部がいいとおもってしまう。
つながりはつくりたい、けど、個としていたい、という、いっけん矛盾したこと、は言葉ではいえても、形にはできない、とかんがえてしまう。形にはすぐにむすびつかないけれど、いえてしまうのが言葉のおもしろさ、だとおもう、四角い丸、のような。
ただ、じっさい、四角い丸、をつくれるかもしれない。円柱を横からみればよい。きっと、そのようなことは、誰でもおもいつくが、最初に、言葉があるから、かんがえはじめる。どうでもいいことでも、いっけん有りそうもないこと、をかんがえてみることには価値があり、その時の言葉にも価値がある。
だから、「つながりはつくりたい、けど、個としていたい」も、たとえば、「つながり」がまわりを切断して「個」をつくり出す状況にすればよい。これも言葉だからいえることかもしれないが、少しは形になりそうな雰囲気にはなってきた。
建築は時間がたつと、劣化していくし、25年したら価値がゼロになる。かんせいした瞬間からものとしての価値がさがることになる。ただ、時間がたつことで使用者にとっての価値は上づみされていく。それを愛着といっていいかもしれない。いまのシステムでは、この愛着をすくいとることができない。愛着には価値がないとされる。愛着に価値を見いだすには、愛着に価値があるとかんがえる人がひつようになる。
愛着に価値をみいだし、ただ、それをそのまま表現したのでは誰にもつたわらない。誰にでもわかる形に愛着を変換するか、変換した愛着とのつながり方を調整するひつようがある。
愛着というと、なかなか、実体がないものだから、形にしづらいが、愛着をなにかしらのエレメントに変換するか、あるいは、変換したエレメント同士のつながり方で表現するのが、ひとつの方法だとおもう。
ボディが壊れて、赤絵の蓋だけ、がのこりました。きれいな蓋、では、また、似せて、ボディだけをつくりますか。いや、全く別のボディをあわせちまいしょう。
なんて、そういうやりとりかどうかは知らないが、鉄の燗鍋に赤絵の蓋がついている、のをみた。燗鍋は懐石でもちいる酒つぎのこと。もとは、燗鍋に、共材の鉄の蓋、がついていたのを、赤絵の蓋、にすえ替えたか、赤絵の蓋だけが先にあり、それにあわせて制作されたのか。どちらにしても、茶人のあそび心はおもしろい。
とくに、赤絵の蓋にあわせて、別のボディをつくるのはおもしろい。使用じょうは、蓋の役目さえすればいいから、燗鍋いがいでも、なんでもいいし、元の赤絵の蓋のボディとは、全くちがうもの、にして、落差があって、元のボディが想像できないくらいのほうが、余計におもしろい。
建築でも、ふるい建物の一部分をのこして、新たにつけくわえ、全く別の用途にかえる、ことはよくある。ただ、ここまで、変化のはば、が大きいものはない、ような気がする。どこまでいっても、空間の範疇、建築の範疇から、ぬけ出ることはできないから。ふるい建物の一部分をのこして、空間以外、建築以外、にするのならば、この燗鍋と同じくらい、におもしろいけれど。
そういえば、むかし『北の国から』というドラマで、自動車のスクラップ部品や、古い電話ボックスなど、をつかって、家をつくっていたシーンがあったけれど、あれなどは、この燗鍋と同じ、ようなつくられ方かもしれない。
もちいられるエレメント同士のつながり方や、そこから生まれる全体としてのオブジェクトが、元のエレメントが属していたオブジェクトやつながり方と、全くちがうことでしか表現できない世界があるな、とおもった。
サードプレイス、という言葉がある。家でもなく、職場でもない場所。そのサードプレイスの重要性や必要性をよくきいた。たしかに、場所の量でいえば、圧倒的に、家や職場よりも多いし、無限に存在するといっていいかもしれない。しかし、その場所にいる時間は、ふつうに生活していたら、家や職場より、圧倒的に少なくなる。サードプレイスが無い人も多いだろう。
サードプレイスが必要で重要な理由は、有限な時間を、より有意義にするため、ときいた。家や職場での時間だけでは、なにかが損なわれてしまうと、感じるからだろう。サードプレイスがあることで、有意義、を担保している。ただそれでは、なにかが損なわれること自体が、かわることはないともおもう。なにも損なわれず、有意義でいること、はできないか。
サードプレイスをつくるにしても、家や職場と並ぶような、別々の扱いもいいけれど、サードプレイスの特色はそのままにして、家や職場とからめてみたらどうだろうか。そうすると、場所の量は、限定的になり、有限になるが、そこにいる時間の量が圧倒的に増える可能性がある。サードプレイスのつくり方によっては、なにも損なわれなくなる可能性すらあるかもしれない。
ふつうに、反動的に、逆張りをするのはおもしろいけれど、ちょっと、たんじゅんすぎて、それでは何もうまれない、とおもった。
なにか、つくろうとしたときに、できれば、よく見るものとか、よくあるもの以外のものを、つくりたいとおもう。そのとき、たんなる逆張りをすると、まったくちがったもの、に見えるけれど、それはたんに裏表の関係にすぎず、けっきょくは亜流でしかない。
いちど切断するひつようがある。よく見るもの、よくあるものが外してしまっていることを見つけ、それをメインにすえる。それは、一見、逆張りのようにおもえるが、同じようなことで近くにあっても、外していることもあり、結果的に、すごくわすがな差にしか見えが、よくあるものではなくなる場合もある。
まわりからめいかくに区分けされている状況は、それだけが特殊であるが、それが、特殊ではなく普通で通常である、ということがありえるのか、とかんがえてみた。
かんがえるきっかけは、まわりとの違いがめいかくにあらわれている建築を、普通で通常なものとして、つくりたいからである。特殊なものをつくることは、あんがい簡単、なのであり、それはのぞまれないことが多い。
きっとありえるとしたら、一見普通のかっこうをして、まわりとはいっさい関係をもたない、ようにすればよい。一見普通、というのは、よくみれば普通ではないときがあり、つねに普通ではない、普通でいる時間が限られていることで、普通ではないときには、まわりとの関係が切断している。断続的に関係の切断がおこるならば、めいかくにまわりから区分けされる。
ただの線だとおもっていたものに、太さをかんじると、それはただの線ではなくなり、太さの中に、さらに別のものをみることができる。
壁をえがいた単線に、太さをかんじると、もっと太く、もっと幅をひろげて、その中になにか入れたくなる。そうすると、線は複数になり、そこに間ができる。そしてまた、線に太さをかんじると、そのくり返しで、間ができていく。そうしてうまれた、いくつかの間は、分割してできた間とちがい、もとは単線だから、つらなり、である。
そのつらなりは同時に、もとは単線だから、なにかを分割することにもなる。それは、つながりが切断した状態をつくりだす、ことである。なんとも、みりょく的なこと、だとおもった。
そこに境目があることで、別々であり、別のものだということがわかる。しかし、境目は便宜上ひつようで、そのようにみえてるだけで、実はつながりがあり、重なっていたとしたら、むしろ、境目はつながりを形成しているものになる。
たとえば、壁は部屋と部屋を切断して、別々なものにわける。ところが、別のみ方をすれば、部屋と部屋をつなげている存在とみることもできる。あたり前だが、壁がなければ、2つの部屋は存在しない。しかし、壁が2つの部屋をつないでいる、とみることもできる。そのつないでいるときの壁は、またちがった性質をみせはじめるような気がする。
ちょっと壁についてみ方を変えてかんがえてみる。きっと、つなぐ役目の壁は切断しておわりの壁とはちがうはずだ。
境をこえることは、建築ではなかなかできない。いろいろな境があるけれど、土地の境も、隣りとの境としての壁、床、天井も、あたり前だけど、こえられない。ただ、それでおわり、ではなくて、なにかないか、なにか方法はないか、とかんがえてみる。
かんたんにいえば、建築は決められた境の中でしかつくれない。しかも、境は条件として、はじめに与えられるものだから、選べないし、あとから変えられない。もし、境をこえることができれば、なにかちがう表現が可能になるはずだ。
現実的には、境をこえることはできないが、境をこえたような意識や気分、にはさせることができるかもしれない、とおもった。それをかんがえるきっかけになった、因州中井窯のお皿からアナロジーをえよう、とずっとながめていた。
お約束ごとがわかると、いちいち説明がなくても、理解できたり、行動できたりする。そのお約束ごとのひとつが記号かもしれない。記号はそれだけでシンプルな意味をまとうから、つかう方も受けとる方も、よけいな物事をはぶくことができ、わかりやすくなる。もしかしたら、記号だけで、かなりのことが表現できるかもしれない。
先日、お能の舞台をみていて、音で展開がなんとなくわかった。この音がした時はこうなる、こうなる前にはこの音がする、など音が記号の役割をして、展開が約束されていた。
建築でもデザイン手法として記号があつかわれていた時期があった。意味をまとう記号をデザインの主題にしていた。ただその後、記号をあつかうことがすたれたのは、記号がまとう意味のつたえ方まで意識されておらず、意味にともなう行動までをデザインの範疇にできていなかったから、と記憶している。お能をみていて、そのことをおもい出した。
できるだけ省き、最小限の動き、音、言葉で、意味をつたえるのが、お能、だという。毎回、お能を鑑賞するたびに、気づくことがあり、ちょっとずつ、うすくだけど、かさね塗りするように、自分なりに、お能の理解がすすむ。
省くことで意味をつたえる、というのがおもしろい、とおもう。建築からの視点でかんがえると、モダニズム建築も省くことをおこなった。ただし、それは、それまでの建築が装飾をまとうことで、意味をつたえていたから、建築は意味をつたえるものではない、として装飾を省いた。だから、省くことで意味をつたえるお能はおもしろいと、とくに欧米のひとは、そうおもうかもしれない。
ただ、日本人にとっては、省くことで意味をつたえることは、なんとく感じでも、理解しやすいかもしれない。茶道にしても、花道にしても、道がつく世界では、省いて最小限にして表現することは良い、とされているようにおもうから。
ただ、いつから、省いて最小限にして表現することは良い、となったのだろうか。少なくとも、縄文式土器をみると、装飾することで意味をつたえていた、ようにおもう。その反動からか、弥生式土器には装飾がなくなったが、最小限の良さ、を表現しているのだろうか。たしか、岡本太郎や磯崎新が、縄文式土器と伊勢神宮、弥生式土器と桂離宮を関連づけていた。帰ってからしらべてみよう、っと。
それぞれが中心になれるような人たちが、たくさん寄せあつまると、うまくいくのだろうか。ふつうにかんがえると、それぞれが自己主張をして、バラバラ、になり、うまくいかないようにおもってしまう。だから、バラバラにならないようにするか、そもそも、中心になれるような人だけでなく、脇役や、うまくまとめるような人もまぜる。
ただもし、バラバラでも、うまくいく方法があるとしたら、なんだろうか。バラバラにも利点がある、とおもう。ひとりひとりが中心になれるくらいの能力があるのならば、まとまったひとつの集団より、バラバラであるがゆえに、迅速に細かくうごけるから、より広範囲に、よりふかく、ものごとに対処できる、のではないだろうか。
そして、それによってできる、バラバラな人たち同士の関係性が、無形の財産、として価値があるものになるような気がする。きっと、これは、建築でも同じで、そこに関係性に価値がある所以があるのだろう。
見通しがわるい、ところは不安だから、見通しよくしようとしても、そもそも、どこを見ればいいのか、わからない時って、あるような気がする。見通しをたてる前に、見る方向をさだめたい。
あんがい、見る方向をさだめるほうがむずかしい、とおもう。勘ちがいしたり、まちがったりしてしまう。見通しがわるいのは、見る方向がまちがっている、からかもしれない。
見る方向をさだめるには、さいきんは、つながりを意識している。見る方向をさだめることは、他と切断することになるが、切断したあとは、ちがうつながりができていく。このちがうつながりが、連鎖して生まれるかどうか、が手がかりになる、とおもう。
住宅も同じ、新しく建てることは切断を生む。しかしそのあと、ちがうつながりが連鎖して生まれる、ようにすることで、住宅として成り立つ。そんな連鎖をたくさん起こしたくてはじまったプロジェクトは、切断のあとのつながりが、いたについてきた。
いつも期待は無限にあるように感じてしまう。どこまでもつづくとか、かならずあるとか、ずっととおくまでを範囲に感じる。でも、あたり前だが、無限などありえず、なんでも有限である。
無限だと感じるからできること、を有限だと切りかえたら、でもそこで、今まで、そこまで意識していなかったことに、気づくかもしれない。
なんでも有限、限りがある、としたら、かならず、つきる時がくる。今まで、つきること、を意識してなかったから、そのものの成り立ちなど、どうでもよかったが、つきてしまう、限りがある、有限だとわかったら、とたんに、そのもの自体のこと、が気になりだす。
けっこう、なんでも、有限だとおもうと、なにもしなくても、自然と、いろいろなことに気づいたり、そのものに集中できたり、するのかもしれない。
建築のようなオブジェクトも、有限だとわかっていながら、無限にあるもの、だとおもってしまう。有限をもっと意識したら、関係性などのような、どこまでも無限につづく幻想が、気にならなくなるかもしれない。そもそも、人がつくることができるオブジェクト、は有限だから。
日頃から、ひとつのことだけで無く、他のばしょを持つこと、が面白さにつながる、とおもっている。ひとつのことだけをコツコツやる、ことは大事だが、それが2つ以上、たくさんあれば、それ同士の相乗効果も生まれ、ひとつだけでは出せいこと、に遭遇できる。
ひとつひとつには、そのままでは、その内側に、見ることができない部分、があるとおもう。その見ることができない部分は、その内側にいるから、見ることができないのであり、外側に出れば、見ることができる。
だから、他のばしょ、が必要なのであり、その見ることができない部分が、ほんとうは、じぶんがいちばん必要なこと、だったりする。ただ、その場合、他のばしょ、にも同じくらいの比重が必要で、きっと他中心的になるのだろう。
この住宅には、たくさんの、他のばしょ、をつくり、中心をたくさんつくれる、ようにしてみた。そうしたら、暮らしがアクティブになった、とよろこんでる。
ただ、ただ、形をいじりながら、形のみが、うまくいくように、うまくおさまる、ように置いてみる。その時点で、形は安定して、そこにある。こんどは、そこから、それが置かれるまでに、何をしたか、をかんがえてみる。これを何回かくり返すと、共通のプロセスがうかぶ。
まったくの思いつきで、プロセスをはじめにきめてみる。置かれるものは、同じプロセスならば、まったく同じ形、なるばずである。もし、ちがう形、になるならば、プロセスを調整する。
この2つ、前者は、実践から理論をつくるこころみで、後者は、理論から実践をつくるこころみである。どちらも創造にはなるが、どちらが良いかはなく、創造されるものが実践か理論のちがいである。
今までをかんがえると、実践が先にくるから、創造されるものは、実践してつくられたもの、になるだろう。やはり、実践が先のほうがしっくるくるし、後からの理論づくりは、自分にたいする、気づきにもなる。
まったく周りから切り離された、そこだけにしかない、建築、はあるだろうか、とかんがえてみた。まわりの環境、となじむことが、良し、とされるから、なかなか、周りから切り離された建築、をイメージできないし、見あたらない。
ただ、森のなかにぽつんとある建築とか、周りが自然だと、あり得るかもしれない。周りが建築と相対するものであれば、可能性はある。
あとは、建築自体が、周りから突出して存在している場合、もかんがえられる。その場合は、都市部のなかでもありえるが、シンボリックで単体、の建築がすぐにイメージできる。
面白そうなのは、都市部のなかで、シンボリックではなく、なおかつ、単体ではなく、周りから切り離されて突出している建築であり、単体ではないとしたら、それは多中心的なものか。いずれにしろ、ちょっと、横にスライドして、かんがえてみる。
時間がつながっている、ことと、空間が途ぎれていること、この2つが重要だとおもう。
建築では、とくに、建替えでは、過去そこにあったもの、とは断絶したものができあがり、ただ、そのときの周辺環境、とはつながっている。だから、前とはまったくちがった風景がとつぜん出現する。前そこに、何があったかが思いだせない。
ずっと同じではこまるが、定期的にまったくちがった風景がとつぜん出現するのもこまる。それに、これをくりかえしていくと、どこをみても同じ、というような風景に収束していく。
だから、時間的なつながりは残し、さらに空間が周辺環境とは関係ないところできまるならば、時間は過去現在未来とつながりながら、多様な風景がくりかえし生成されていく。
たのしい街は、あんがい、勝手きままな建築、だらけだ。
目のまえにある木と、そこに何かをつくろうとしている人が、関係することで、何かが生まれる、とすると、生まれたものは、木と人の関係性の産物だが、生まれたもの自体は、それはそれで、その関係性とは別のところにいる。
ちがう言い方をすれば、つくるプロセスでは、木と人の関係が必要だが、できて出現してしまえば、関係性が無くても、そこにいることができる。
これが建築の場合、エコロジーの観点からすると、問題になる。できてしまえば、木という自然が無視できるから、建築が調和をくずす要因になりえる。
ただ、そこでおもうのは、そもそもそこに調和があるのか、ということと、建築がそこで関係性を無視してあった方が良いのではないか、ということ。
木と人の関係性は反映されているわけだから、木と人以外の別のものが出現することで、何か新しいものを捉える可能性が生まれるし、それには、調和の無さ、あるいは、緩さが必要だから、そもそも調和など幻想だったのではないか。
もう少し、建築を関係性ではなく、建築自体が持つ新しいものを捉える可能性というポテンシャルの面をみると、よりエコフレンドリーになるのでは、とおもう。
常にかわるかもしれない、とおもうと、おちおち安心もしてられない。できれば、かわらない方がいい、とおもう人も、多いかもしれない。ただ、自然をみてると、かわらないもの、などない。常に一定の均衡状況を保つことなど無い、ようにおもう。かわることが日常、のようにみえる。たがら、自然をとり入れたい、とおもうことの、本音は、かわりたい、かもしれない。
人も自然のいちぶ、という話には、はんぶん賛成、はんぶん反対。自然のなかに人をくみ入れることで、自然は守るべきもの、になるが、自然と人をおなじようにあつかうと、自然は人によってどうにでもできるもの、にもつながる。
自然のかわりようをみながら、人は人でかわるのがいいのでは。自然はとり入れるもの、ではなくて、そばにあって、いろいろなかわり方、をみせてくれるものでいい。
時がたつのがはやい、あっという間、というけれど、おもいかえすと、はやい時と、おそい時が、あるようにおもう。
はやい時は、なにをしていたか、ぜんぜん、おもい出せない。ただ、その当時、どんな状況だったかと、俯瞰して、かんがえると、なにも自分からすすんでしてなかった、ようにおもう。やらされていた訳ではないが、かといって、自分がほんとうに望んでいたこと、ともちがう状況だった、ような気がする。
おそい時は、逆に、したことを、たくさん、おもい出せる。あれもやった、これもやった、と。上手くいかないことも、よくやったことも、両方あるけれど、とにかく、たくさん、おもい出せる。こうおもい出しているだけでも、時間がかかり、おそく感じる。ちがいは、自分から状況をつくっていたからか。
そうだとしかたら、時間の量はみな同じ、でも、時間の感じかたはみな違う。だから、感じかた、ようするに、状況を自分からつくり出せば、時間をコントロールできる。でも、なかなか難しい。ただ、自分の家の中ならば、だれでもできる。だから、家づくりはおもしろい。
つながり、は大事だと、知らず知らずのうちに、すりこまれている。たしかに、大事だとおもう。ただ、どこかで、切断、もおこさないと、つながり、がにごる、とおもう。
切断、には勇気がいるけど、切断したい願望、はきっと、せんざい的にはある。切断、によって、いまのなにかを変化させたい、という気持ちだろうか。
ただ、じふんでは、切断、をおこすのは難しい。だから、だれか他の人に、切断、をしてほしい、と願ってしまうのは、しごくとうぜんかもしれない。
切断、をテーマに、この住宅をみると、切断面がいたるところに現れる。切断したおかげで、このクライアントは、新たな生活を手に入れた。それは、今までの日常の延長でも、切断という行為で、前の住宅と今の住宅のちがいを、感じとりながら、ちがう気持ちで暮らしてる。
外にながれでるように、外へむかって、つながり、をつくろうとしたら、自身はどんどん、希薄なもの、になりやしないか。自身というものが、つねに、外とのつながりで、決まるから、自身単体では、成立、しない。その成立のしなさは、あいまいなものへ、そして、希薄なものへ、かえていく、とおもう。
外へながれでる、のを止めて、その場で自律、してみるのはどうだろうか。その自律する部分が複数あったら、その自律する部分同士で、ながれでるような、つながりをつくれば、自律したまま、外へのつながりも、つくれないだろうか。
これは、人にも当てはまるし、建築にも当てはまる、とおもう。複数の自律、きっとこれは、今進行中のプロジェクトに当てはめて、かんがるとおもしろいかもしれない、とおもった。
なにか、ムダ、をつくりたくて、きっと、じかには役には立たないけれど、そのおかげで、豊かなきもち、になれるような状況をつくりだしたい。余分なもの、というか、余計なもの、といか、とかく、コスパや効率、ばかりが聞こえてくるので、豊かなきもちになれない。コスパや効率とは、対峙するもの、でも、それがあるおかげで、豊かさが成立するようなものをつくりたい。
きっとそのムダは、感覚的で、わかりづらい。だから、コスパや効率のそとにある。しかし、感覚的で、わかりづらいから、とくに、なにかを、はっきりとさせる必要もなく、あいまいで、ゆるい。この、ゆるさ、が今ひつようだと感じる。
そんな、ゆるさ、を肯定できるには、何があればいいのか、どうなればいいのか。かんがえるに値することだとおもう。
この住宅がきっかけで、ゆるさ、を意識しはじめた。クライアントの人柄が、そうさせたのかもしれない。
意味がある、とか、意味がない、とか、とかく意味という言葉は、価値あるもの、のたとえになる。だけれども、何ごとにも、意味を見いだしていたら、つかれて、しょうがない。意味がつきまとうときは、直感をはたらかせる、ことができない。
建築に意味を見いだしたら、キリがない、ようにおもえる。かんがえてみれば、建築は、意味のかたまり、にもみえる。建築に意味をもとめることが、それこそ、意味がないときもあったし、建築に意味をもとめようとして、おかしな建築ばかり、がでてきたときもあった。意味のかたまり、とは建築を部材に、還元していけば、それぞれの部材は、なにかしらの意味をもち、設計する側は、その意味から、部材の集積をかんがえる。
でも、あんがい、さいごの部分は、直感だったりするから、意味が不明確だったり、それがおもしろい。この建築も直感にしたがった。
時はながれる、あたりまえだけど、10年前をおもうと、この10年で30年分は生きたような気がする。いろいろとみつかるものだ。たぶん、10年前には想像もしてなかったことを、たくさんみつけた。この10年で、みつけ方もたくさん試したので、またまだ、これから、未知のものが、たくさん、みつかるだろう。
日々のなかで、暮らしと直結するもののひとつが、建築、だとおもっている。だから、どうしても、どう考えても、人をとおして建築を考えてしまう。建築が人に与える影響から考えてしまう。これからもそうだろう。
これらの住宅も、発端はすべて、人にどのような影響を与えるか、だった。この、どのような、の部分がこれからさらに、掘りさげていくところで、またまだ、未知のものが、たくさん、ありそうな気がしている。
いかにして、ボーダーラインをこえるか、をつねにかんがえているような気がする。建築の場合は、つねに、なにかしらのボーダーライン、がつきまとう。それが、目にみえる、場合もあるし、目にみえない、場合もある。予算や、敷地境界線や、絶対にこえられないもの、もある。
なかには、ボーダーラインをこえあう関係性、もあるかもしれない。片方がこえても、もう片方もこえれば、バランスがとれて、問題にはならない、ような。そのようなボーダーラインは、意識すること、でみえてくる場合もある。その場合、ボーダーラインをこえてること、に気づかないこともある。
なにかで、ボーダーラインをこえてる、ことを気づかせることができたら、お互いにボーダーラインをこえあうこと、に抵抗もなくなるだろう。きっと気づかせるきっけに建築は役立つとおもう。この住宅は、そんなボーダーラインに気づかせてくれる。
スクラップブックのように、いろいろと貼りつけて、そこには、ルールもなく、好きなようにできる空間、ってあるとしたら、どんなだろう、とそうぞうしてみた。
そのときに、その空間をつくる側か、みる側か、でちがうかもしれない。つくる側は、どうやってつくるか、をかんがえるし、みる側は、どうやってみるか、をかんがえる。ひとによって、ちがうだろうが、じぶんは、つくる側でかんがえてしまう。
現実的に、スクラップブックのような空間みたいな、ありえそうもないことを、簡単にできるようにかんがえる。そうすることで、いろいろなひとを、巻きこみやすいし、みる側のひとたちも、現実感をもちやすくなる。みる側のひとたちは、クライアントだ。
この住宅は、好きなように部屋の範囲をかえることができる。ルールはない。あるとしたら、スクラップブックで紙の大きさがきまってる、ように広さに制限があること。
あんがい、スクラップブックのように、はじめにルールはなく、あとから自分しだいで、好きなようにやるための何かを持ちこみたい、と他でもおもう。それが、つくる側のおもしろさ、であり、みる側ではできないこと。好きなようにやるための何か、はみる側をもハッピーにする。
ちょっとでも、日常とはちがう体験、が日常の中にあれば、そこから、さまざまな連鎖がおこる、とおもう。たとえば、その連鎖は、ふだん行かないような所、に行こうとか、なかなか会えない人、に会おうとか、またちがう体験をよぶ。体験すること、でしか、人はまんぞくできない、とどこかでおもってるから、日常の中のちがう体験はたいせつにしたい。
その、日常とはちがう体験、は非日常なことではない。たぶん、日常的にしている体験のみえない部分、だろう。それは、あえてみようとしないと、みえない部分だとおもう。そのためには、ちょっとした技術、も必要かもしれない。
きっと建築はその、日常とはちがう体験、をつくり出せるもの、だとおもう。そのためには、やはり、ちょっとした技術、が必要だろう。ただ、建築で、それをやる価値は、またちがう体験をよぶ、のならば十二分にある、とおもう。
この住宅では、密集地という立地から、空にちかづくこと、で地上の生活に、変化をつけた。人は、地面ではなく、空とむきあう。地面に接地していては、みえない部分、がそこにはあった。
ズレていると、気になるし、引っかかりができてしまう。これは、ぶつり的なものにでもおこるし、言葉のような、目にみえないもの、に対してもおこる。この引っかかりが、良いものならば、引っかかったら、たのしいし、悪いものならば、気になるだけで、やっかいだ。
ものをつくることを、別のみかた、をすると、この引っかかりをつくること、といえるかもしれない。引っかかりは、意図して、つくることができ、先にふれたように、人の意識に作用し、たのしい気分にさせることもできる。
たのしい気分になって、といわれても、なかなか、たのしい気分にもなれるものでもないし、そこには、なり方はひとまかせ、のような感じもする。それよりは、たのしい引っかかりを、たくさんつくってあげることで、いわなくても、自然とたのしくなる。それが理想だと、いつも、おもう。
この住宅は、そんなことをかんがえながら、そうしたら、こどもも、おとなも、いろいろなところに引っかかりながら、たのしそうだったし、いろいろと、どのように引っかかるのか、発見があった。
つながりや、関係性でかんがえる建築が、いちじ、はやったような気がしてた。たぶん、いまは、それは、当たり前のこと、になり、そして、関心は、モノじたい、にうつって、久しいのだろう。
こう、モノのねだん、が上がると、おもうように、使いたいモノ、がつかえない。だからか、はがしたまま、あらわしのまま、なんて、途中のすがた、が仕上りになってるのを、多くみる。
ただ、いまはいいけど、それを良しとして、放置しておくと、つくり手のイメージに、あらたな本質的なモノを召喚するチカラ、がなくなっていくような気がする。
その時代のかたまりつつある状況から、一歩ふみこむ、ことが、次をつくりだす。途中でよしが通用するのは、最初だけ、だとおもう。
なにがいいのだろう、なにが正解なの、手さぐりのときの気持ち。きっと、これって、そうそうこれこれ、とおもいたいし、どこかで、損したくない、得したいと、無意識にでも、おもってる。あんがい、たくさん、あって選べない。こんなとき、どうするかな、と最近、かんがえることが多い。
ネットには、たくさん、ある。ただ、たくさん、ありすぎるのも、こまる。だから、これが、いいじゃないの、などと、交通整理、してくれる人が、あらわれる。その人もまた、ネットには、たくさん、いる。もう、よけい、わからなくなる。さいごは、直感、にでもたよるしかないのかな。
けっきょくは、なにかに、だれかに、決めることになるのだが、それで納得してしまう理由、をさがしてる。なかなか、その理由を、うまく、しめせてる人は少ない、ような気がする。納得する理由って、あんがい、理屈じゃなくて、ささいなこと、たとえば、それ前からしってたとか、いちどは試そうとしたとか、なんか、じぶんと少しだけの関係があること。この、少しだけがミソ、かなと最近、おもってる。この住宅のクライアントも、そんなワタシとの少しだけの関係を、たぐりよせた、らしい。少しだけだから、気楽だった、と。
何か意味がありそうなもの、が目のまえにあったら、何だろう、とおもうだろう。そのとき、触れられるならば、触れたいし、あつかえるならば、あつかいたい。ようは、何かつながり、をつくりたい。
それは、その場が、どうであれ、いつも可能なこと、だろうか、いや、それを、いつも可能なことにする、場が必要だろう、とかんがえた。その場のひとつが、建築、になり得る。
いわば、建築が、媒介するもの、となる。媒介するものは、いつでも、中間にある。中間にあるから、何にでもつながる、ことができる。だから、媒介するものが、実際にあれば、あとは、そこに、つながりをきずきたいもの、を放りこめばよいだけである。
そのときの、媒介するものは、たしかな、存在、をそこで得ることができる。建築としては、いい、あり方のような気がした。この住宅も、はじまりは、そのような、中間にいる建築をめざした。
めのまえに、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、自然の感じ、をとても簡単にいえば、そうなるとおもった。そうすると、めのまえで、その時間に、自分のしらないことは、全て自然のできごと、といえるかもしれない。かんがえてみれば、自然という言葉を、木や緑などの自然と、自分が関知しないことの、2通りのつかいかた、をするが、もとをたどれば、同じなのかもしれない。
自然を感じたい、とおもうと、森や海に、いこうとする。つねに、まわりに、森や海があればいいが、都市部だと、そうもいかない。海はムリだとしても、都市部で、少ない木で、森を感じるには、どうしたらいいのか、をかんがえている。
まずはきっと、先にした、木はあるが、それが自分のしらないところで、変化をしていく、ような状況をつくりだせばよい、とおもった。その状況を、今度は、建築が媒介となり、そこにいる人につたえる。つたわった人は、そこに自然をみる、だろう。こんなことをかんがえた。
デザイン、には注意がむけられるが、そのデザインを伝えること、には注意がむけられていない、とかんじた。大事なことは、伝えること、である。伝えることは、コミニケーションの際の伝達手段であり、それ自体がデザインの核心である、とかんがえた。
伝達手段は、コミニケーションの両端のつなぎ、の部分になる。つなぎ方によって、デザインの意味も、役割もかわる。だから、伝達手段も含めてデザインである、と同時に、伝達手段がデザインの核心になる。
建築には伝達手段も含まれる。いや、もしかしたら、建築とは伝達手段そのもので、伝達手段がカタチになったもの、かもしれない。そうすると、建築=メディア、ともいえる。
この住宅では、たくさんの意味をつめこんだ。その意味をつかみやすくするために、建築がそんざいしている、とかんがえた。
そんなもの、存在しないよ、とどこかで、おもいながらも、期待していること、って意外とありませんか。それは、だいだいが、カタチがないものであったり、目にみえないものであったりする。ちょっと、べつ角度から、カタチがあって、目にみえてるものが、全てかという、てつがく的なことにもつながるかな。ただ、そんなむすがしいことではなくて、何か、期待をもちたい、だけだとおもう。それが、全てのはじまり、全てのきっかけ、のような気がする。
建築の設計って、目にみえるモノをあつかいながら、目にみえないコトをかんがえる、ことかもしれない。だから、いつも、期待すること、でいっぱいになる、どこかで、そんなもの、存在しないよ、とおもいながら。ただ、設計者しだいで、存在させること、ができるコトはふえる。
この住宅には、居場所をみつけて、と想いをこめた。ただのイエでなく、特別な場所、としてのイエ。べつの言い方で、イエらしいイエ。イエがじぶんたちのものならば、それをもっとふかいところで、想ってほしかった。そのためのコトは、設計者しだいで、たくさんできる。
こもる、ことに対して、建築は、とかく、ひはん的なような気がする。うちにこもる、すなわち、閉じた箱的な建築、はこのまれない。都市部では、眺望などに、きたいできないから、閉じて、こもり、必要な光をとりいれるだけ、とかんがえることは、ひとつの方法として、あってもよいはずである。
問題は、こもることで、社会とのつながり、がおろそかになる、のではという、建築だでなく、人にも当てはまること。ただ、オープンであればいいのか、閉じたなかでの、社会とのつながり、を建築として、つくり出すことに、可能性をみいだせば、よいだけだと、それはむずかしいことだが、おもう。ちょっと、それは、建築として、いま的なこととして、かんがえる価値はある。もしかしたら、閉じると開くの中間あたり、に落ちつくことも、ありえる。
これら2棟の住宅は、2つでひとつ、とかんがえ、互いにたいしては開き、外に対しては閉じた。きっと、このように、開くと閉じるが同時に存在し、その割合のちがいが、建築の存在のちがい、になることも、ありえる。
実利、なんて言葉を、ことさらかんがえる。コスパとか、損得とか、にたような言葉があり、コスパより損得には、なんか、ちょっと、計算たかさ、がつきまとう感じがする。コスパも、損得も、その言葉じたい、きらいな人もいるだろうし、べつに、ビジネスや生活の中では、当たり前のこと、だよねとうけとめる人もいるだろう。私は、コスパも、損得も、どちらにも、かんしんがない。
ただ、実利はかんがえる。コスパも、損得も、比較するときにつかう言葉だから、比較にはきょうみがないので、かんしんがない。実利は、比較ではなく、利そのものだから、何がえられるのか、とか、何がかわるのか、とかには、かんしんがある。
だから、実利から、デザインをかんがえる、こともある。ちょうど、いまよんでる本に、1世紀まえの建築家ロースの、空間構成をかんがえるきっかけが実利だった、との記載があった。実利からデザインをかんがえることが、犯罪ではない、としり、ちょっとよかった、この住宅は実利だらけだから。
かんがえを、まとめようとして、手がとまる。クライアントからヒアリングしたこと、にはいつもヒントが、かくされている。かくされているとは、直接語っていないからで、語った言葉のうらの、その言葉を語らせる何かに、気がつこうとする。たいがいは、何かは、言葉でつかみとるが、最初は、イメージや場面で、でてくる。
そのイメージや場面には、人が登場するばあいと、人が登場しないばあいがある。手がとまるときは、人が登場しない。だから、人が登場するまで、待つ。人もクライアントのばあいだけでなく、だれだが特定できないばあいや、クライアント以外の特定の人のばあいもある。これも、クライアントが登場するまで、待つ。
この住宅は、いちばん最初から、イメージや場面に、クライアントが登場した。そのようなことは珍しい。とうぜんのように、ファーストプランで、はなしはきまった。
きまった形式、から自由になりたいとしたら、また新たな自由になれる形式、をつくるのだろうか。それとも、形式から離れること、で自由になるのだろうか。
こうして、言葉にしてみると、形式から離れない、と自由になれないような気がするが、あんがい、自由になれる新たな形式、をつくろうというかんがえに、いたることが、おおいような気がする。
きっとその方が、都合の良い自由、がつくれると無意識に、おもっているのだろう。自由といっても、無秩序ではこまる。自由でいながら、ある程度の秩序、大外しはしないルール、はあってほしい、とおもうのだろう。でもそれは、形式をつくること、だろうか。かえって、きゅうくつな自由、になりそう。それは、自由とはいえない、気がする。
そんなことを、ずっと、かんがえながら、この住宅をつくったこと、おもい出した。
ふしぎと、今まで、当たり前にしてきたこと、にたいして、違和感があるようになった。階ごとで、かんがえること。もちろん、半階ずらすなどは、よくある。しかしそれも、階ごとでかんがえる、範疇になる。
そもそも、建築の構造が、階ごとで、かんがえるのが基本。だから、おのずと、計画だんかいから、階ごと、になる。階ごとは、水平しこう、である。もうすこし、水平しこうではなくて、垂直しこうへ、もっていきたい。
高さのちがいが、連続するような場所を、自然のなかで、想像してみる。その場合、高さがちがう、合わないことにたいして、不自然さは無く、段差をつくるという意識にはならない、気がする。
階段が、階段として、みえてしまうと、たんに、段差があるだけの場所、になるだけかもしれない。階段としては存在せずに、垂直方向に展開するような場所、がりそうとして、ありえる。
この住宅では、階段が、階段として、みえる。この階段がなくなれば、いいのかもしれない。
なにかを感じるとき、そのモノの、審美てきなぶぶん、にアプローチができている。そして、そのときの、感じるきっかけは、気分による感情、に左右される。気分がよければ、よくみえ、気分がわるければ、わるくみえる。モノと気分は直接、関係しながら、モノはある。
そうなると、モノ自体がどうか、はあまり関係がなくなる。そしてそれは、気分がかわれば、モノの審美てきなぶぶん、にたいするアプローチ、もかわることもいみする。モノの美しさは気分しだい、たんてきにはそうなり、モノ自体を、はっきりと、なにかこうである、とつかめない。
建築で、かんがえれば、気分によって、みえ方がかわる、ということでもある。ならば、気分にうったえるようなもの、をたくさんはいすると、みえ方をコントロール、できるかもしれない。さらには、そうすることで、モノ自体がどうか、というところに、たちかえること、ができる。
この住宅では、動きと連動する建築のぶぶん、に気分による感情を、ゆさぶるデザインを、ちりばめた。気分のよしあしが、建築のみえ方だけでなく、動き、にもえいきょうする。気分が身体を感じる、きっかけになる、こともあわせた。
ひっかかるもの、があると、きっと、印象にのこる。よく建築をみてまわっていたころは、さいしょに、ひっかかるもの、をさがした。作者の意図、と合う合わない、は関係なしに、そのひっかかるものが、最初のいとぐちで、なぜひっかかるのか、をかんがえる、ところから、スタートした。もし、ひっかかるもの、が無ければ、その場でしゅうりょう。
たいがいは、ひっかかるもの、があるので、そこから先は、建築とのたいわの時間。つくる方と、しようする方を、いったり、きたりしてから、いっぽひいて、みる。いっぽひくのは、建築を、もの自体、として、世界のがわからみるため。
この建築では、意図して、ひっかかるもの、をたくさん、ちりばめた。ひっかかるものが、たくさんあることによって、かえって気をちらし、べつのもの、をイメージさせたかった。それは、いぜんにみた建築、からの学びだった。
ものから、感じることは、人によって、ちがう。それが、当たり前だと、おもうけれど、案外、おなじだと、みんな、かんがえている。だから、感じたうえでの、最終的な、ものや、かたちを、提示してくるし、つくろうとする。
ちょっと、その前で、とどめてみようかな、とおもう。最終的な、もののかたちや、イメージを、感じる人に、ゆだねる。いろいろな、感じかたができるもの、があり、その時々で、そのなかから、感じる人の、つごうにあわせて、感じとる。感じとりかた、がちがえば、最終的に、見えるもののかたちも、イメージも、ちがうはずだ。
その当時は、そこまではかんがえていなかったが、この住宅では、いろいろな、感じかた、ができるもの、をちりばめた。どこを、感じるかによって、ちがうものが、現れただろう。
せつだんと、せつぞくの繰り返し。集合住宅にたいして、ちがう見方をしたら、そうなるかと、おもった。各住戸が壁で、せつだんされながら、せつぞくされている。さらに、各住戸が、外にたいしても、内にたいしても、せつだんされながら、せつぞくされ、つながる。
集合住宅のれきしは、このせつだんと、せつぞくのれきし、だとおもう。どのように、せつだん、すなわち、分割し、どのように、せつぞく、すなわち、つなげるか。
分割は、はじめから、部分があるのではなく、全体計画のなかから、ちがい、をつくり出すことで、わかれていく。そのわかれた部分が、また、つながることで、全体が形成される。しかし、全体は、部分の、総和には、ならない。その差を、どのように、つくり出すかが、集合住宅のデザインのキモ、だとおもった。
れんぞく的に、流れるように、すすめたいが、なかなか、おもうようには、いかないことが多い。ときどき、よそ見、をしたくなり、立ちどまる、気になるから。気になることは、わるいことではない。だから、立ちどまる前後が、うまくつながれば、いいとおもう。
かんがえてみると、案外、すなおには、ながれていかないものだと。これは、空間のはなし。あちこちに、注意をひくもの、がたくさんあるから。それらを、全部、なくすわけにも、いかないし、なくせない。だから、注意をひかれてもいいもの、ばかりにすれば、立ちどまってもいい、ことになり、立ちどまる前後に、いい影響しかあたえない。
注意をひかれてもいいもの、ばかりにするには、それらを、きちんと、おさめる場所がひつよう。この住宅では、通路をかねるスペースに、注意をひかれてもいいものを、おけるようにし、そこで、じゅうぶんに、ひたって、もらう。ここはワーク&スタディスペース。
がわと、中身を、ぶんりして、かんがえると、中身のあり方、がいつもと、違って、おもえる。建築のがわは外壁で、中身はインテリア。中身だけで、成立させることができるので、外壁がうけもつことから、解放されて、インテリアを、かんがえることができる。さらには、インテリアとして、がわ、もあつかうこと、ができる。
この場合、いわゆる、入れ子、のじょうたいに、にているが、入れ子の場合は、相似の関係、であるから、入れ子、ではない。
もしかしたら、ふつうの、階層のつみかさね、にならされている、のではないか、とおもった。層があることに、もっと、かのう性をみいだしたい。そのために、がわと中身をぶんりをした。
以前につくった住宅でも、がわと中身のぶんり、のいしきはあった。ただ、今回は、より中身で、かんけつする、ようにかんがえている。
何かを、かんじることで、建築が、うかび上がる。そのことは、とても、大切だと、おもっている。そのことが、今度は、まわりと、どのようにつがるのか。そこで、つながりが無ければ、単なる、ひとりよがりの建築、でおわる。
まず、建築とかかわる人が、かんじることで、建築として、形になり、うかび上がる。形になるとは、もともと、そこに建築は、あるけれど、何もかんじ無ければ、無いのと、同じだから。形となり、うかび上がった建築が、今度は、まわりとのつながり、を持ちはじめる。
このように、しゅつげんした、建築が、どんどん、まわりと、つながるイメージ、をしていた。ただ、さいきん、これは逆では、とおもいはじめている。
たしかに、何かを、かんじることで、建築が、うかび上がるのは、それはそうだとおもう。だが、はじめにあるのは、まわりとのつながり、の方であり、まわりとのつながり方、のちがいが、生みだされることで、個々の建築を、かんじること、ができるようになるのではないか。建築のちがいは、単に、まわりとの、つながりのちがいだけ、ではないか。
この住宅は、まわりとのつながり方を、かえてみた。建物の四周に、ウッドデッキをしいた。たった、それだけのことで、たしかに、建築が、うかび上がった。
ひかくてき、安定してるモノを、いつも見るから、そこにある、とおもう。これが、ときどきにしか、見なかったら、無いも同じかもしれない。存在感のはなしで、内容もだいじだが、頻度がだいじ、だとしたら、どうなるか。
存在感は、なんにでも、つきまとうが、建築での存在感は、よりじゅうような気がする。建築は、いつも、安定して、そこにあり、いつも、見るから、存在感があるはずである。しかし、存在感がない、建築もおおい、ような気がする。そのちがいは、どこから、くるのだろうか。
同じ、だからではないだろうか、差異、がない。いつも、そこにあるのに、存在感がないのは、ひかくするものと、同じ、だから。この場合、ひかくするものは、まわりの風景、まわりの建築。まわりと、ひかくして、同じならば、存在感がない、のも当たり前。この場合、存在感をだすには、まわりとの差異、がひつよう。この住宅は、外観のみで差異をつくり、存在感をだした。
じっくりと、モノをみることを、最近、してない、とおもった。スマホやタブレット、パソコン、本もモノだが、これらは、モノというより、情報を、みてるだけ。だから、モノを、対象として、じっくりと、みることがほとんどない。ただたんに、モノを、感じてるだけ、のほうがおおい、かもしれない。あんがい、みんなそうではないか。
もちろん、しごとで、モノをじっくりと、みることはある。だが、それは、しごとをしてるだけ。自ら、すすんで、すきで、モノをみてるわけではない。だから、話はべつ。
モノって、みるより、感じてる、ほうがおおい、かもしれない。そのことを、もうちょっと、意識してみよかな、とおもった。感じることで、モノがどういうものか、浮かびあがってくる。そうだとしたら、モノのつくりかたもかわる。
この住宅は、そもそも、ほぼ同素材で、空間をつくることにより、どこか、特定の部分に、焦点があたらないようにした。そのことで、じっくりとみるより、全体的に、ふかん的に、空間を感じてほしい。感じるから、モノがわかる。
いい天気だな、あおぞら、は気持ちいい。このかんじを、いつも、持ちこみたい。くもりぞら、が多いちいきには、住めない、だから、気持ちいい、ものにしたい、となれば、このあおぞらを持ちこむ、つまり、みえるようにすればいい。
ただ、あおぞらが、単に、みえるだけでは、気持ちよくは、ならないとおもう。あおぞらなんて、みようとおもえば、どこからでも、みえるから、あおぞらと自分をつなぐ、回路のようなものを、つくるひつようがある。
その回路が感性だと、かんがえるが、ただの感性ではなく、汎用性がたかい感性。それは、たとえば、あおぞら、のぶるーを、いろいろなものと、むすびつけてしまう。きっと、その汎用性のたかさは、あおぞらの、みせ方によるのだろう。
空間は、けいそくするから、おおきさを意識してしまうが、そもそも、空間を、どのようにとらえるかは、あくまでも、感性てきなこと、だとおもう。ひろさも感性であり、あかるさも、心地よさも、天井のたかさも、感性である。感性てきなことが、あつまって、そこに、そのような空間があることが、わかる。なにも、感性てきなことが、なければ、そこには、なにもない。
このように、かんがえれば、モノに左右されない。モノがいいかわるいか、たかいか安いか、は関係なくなる。そうすれば、そこに、たくさんデザインできるよちが生まれ、感性てきなことを、生むために、よりデザインが、じゅうようになる。
この住宅は、せまいけれど、そのせまさをかんじさせないように、感性てきなことを生む、デザインをちりばめた。あつさ、さむさも、空間をとらえるための、感性である。だから、モノだけでは、解決しない。
あれはこれ、これはあれ、と何かと、分けたがるひとがいる。分けるには、ちしき、が必要。だから、分けることによって、ちしきをみせているのだろう。ただ、分けることと、それをりかいすることは、違う、とおもう。分けることなど、実際には、りかいする上では、どうでもよいこと。むしろ、分けがたいことが、たくさん、浮かぶくらいでないと、りかいしている、とは言えない、とおもう。
さいきん、気になるのは、部分に分けたものを、たんじゅんに、ぜんぶ足しても、もとの全体には、ならないだろう、ということ。どちらかというと、いったん、分けたものを、またぜんぶ足すと、もとより増えるか、大きくなる、とおもう。
それは、分けることで、何かよけいなものを、纏うからだろう。そういういみでいうと、りかいを、わざと、困難にするために、分ける、というのはありで、おもしろいかもしれない。
なかなか、素直にはわからない、ちょっと違ったかんじがする、ような空間を、つくりたければ、さまざまな分けかた、をするのもいい。分けかたは、デザインだから、さまざまなデザインができる。ちょっと素直にはわからない空間って、日常には必要かもしれない、とおもう。そのほうが、たのしい毎日になる、よかんがする。
としが明けた、てんきもいい、はれやかな気分、ぼんやりした時間がつづく。ぼーっと積読ほんをながめる。なんで、そのほんを買ったかは、いまはもう、おぼえてない。かさなったタイトルで、れんそうゲームなどしてみる。そういえばと、他のほんを、さがしにいく。読みたいときに、かぎって、そのほんだけない。ふだんの、不せいりのたまものを、正月そうそう、なげいても仕方ない。とにかく、一冊のほんに手をのばす。
そのうち、そういえばと、また他のほんを、さがす。そしてまた、そういえば、となり、そしてまた、そういえば、となる。まるで、グラスホッパーか、はしご酒か。けっきょく、読みちらかした、残がいをながめて、おわったいち日。
その寄せあつめの、残がいを、よく日もながめる。あたまの中には、何ものこってない。ただ、タイトルれいそうゲームには、ちょうどいい。そうか、なるほど、などと、思いつくこともある。なかには『無根拠からの〜』など、というタイトルのほんもある。寄せあつめからおもうことと、それぞれのほんのタイトルからおもうことは、ちがう。
見つからなかった、ほんのおかげで、寄せあつめの山ができた。でも、それは、そのときどきの、読みたい気分、を足したもの、とはちがう山になった。どちらかというと、この、無根拠な、寄せあつめの、山のほうが、すきだ。無根拠でも、あつまれば、根拠ができる。それには、偶然のおもしろさ、がある。そういえば、いつも、このような、つくり方を、してきたかもしれない、住宅にたいして。
飾りが、ぎらぎらとあっても、こころが晴れたりはしないだろう。そのぎゃくに、何もかも、ムダだとして、さいしょう限にしても、たのしくもない。やはり、ものがある良さ、というのがある。
ちょうど良いものがない。最近、おもうのは、ものにあわせる、しかないこと。ほんとうは、こうあればとか、ほんとうは、こうあって欲しい、などとおもいながら、手にすることが多い。どうして、ちょうど良いものがないのだろうか。いっそのこと、自分でつくるしか、ないのか、などともおもう。
きっと、決まりきった型が、はんらん、してるからだろう。ちょうど良いものはあるが、それを探しだすのに、苦労する。ひにくなもので、ネットで、何でもアクセスできるけど、ちょうど良いものに、たどりつくのに、時間がかかる。そのぶん、時間をかければいいのだが、時間がかかるものには、価値がないとされ、ゆえに、よけいに、ちょうど良いものの需要がなくなり、ひとしれず、きえていき、決まりきった型だけが、いきのこる。
もっと、時間をかけることに、価値がある、となれば、型などはんらんしない。時間をかけることがムダ、だとしてるから、ちょうど良いものが、なくなっていく。
この住宅は、時間をかけることが、ゆるされた。決まりきった型は、はじめから、もとめられなかった。もとめられたのは、住宅というもの、によって、ぎらぎらな飾りではない、実際のじぶんたちの生活にそった形、としての空間だった。
じぶんの身体を、とおして、はあくできることが、建築、とりわけ、住宅には、だいじだと、何がきっかけか、わかいころから、おもっていた。ただ、ただ、身体をとおして、かんじること、でしか、建築というもの、をはあくすることは、できないと。
身体をとおして、かんじるとは、見ることからはじまり、手足でふれ、移動することで、身体に、建築を、記憶として、きざむこと、かもしれない。
きっと、痛いおもいをしたほうが、建築をマジマジと、見て、ここはこうなってるのか、などと、こまかいところまで、はあくするはず。
そのときに、たよりになるのは、じぶんの身体だから、住宅はこうあるべきとか、建築はこうあるべきとか、カタチは、などと、じぶんのはいごで、いわれても、関係ない。
よしあしは、身体にきいてくれ、とばかりに、むしろ、身体でかんじるほうが、そのときに見える、住宅にたいして、すなおだとおもうし、それが、じふんの世界としての住宅をつくる、ことになるとおもう。
そんなことをかんがえながら、この住宅は、ちょっと上り、ちょっと下る、そして、また移動するようにしてみた。きっと、ここでの生活では、記憶のなかに、身体のかんじが、きざまれ、それによって、記憶がよりふかく、よりせんめいになるだろう。それって、ここで、生活してるじふんが、いとおしくなることだと、きっと。
場あたりてきに、ということばは、何か、いんしょうがわるい。
何か、カタチをかんがえたり、ものづくりをしようとしたとき、まったく、何もないところから、かんがえたり、つくったりはできず、はいごに、これはこういうもの、というかんがえ、みたいなものが、存在すると、いしき的にも、むいしき的にも、かんがえるのではないか。
きっと、何か、ぜったい的なものにした、そのはいごにあるものにそって、つくろうとする。ただ、もっと、目のまえのものに、しょうてんを当てることもでき、そんなはいごのもの、など無いといえる、場あたりてきな、つくり方もあり、だとおもうし、その方が、あますところなく、何か、表現できるような、気がする。
この住宅では、ただ、きびしい敷地じょうけん、と向きあうことで、ここでしかできない、空間をつくろう、とした。そのとき、敷地にたいして、目にみえるもの、以外のものは、無いもの、とした。
さいきん、南部鉄瓶を手にいれた。もくてきは、鉄分ほきゅう。まいあさ、コーヒーをいれるので、そのお湯をわかすのに、南部鉄瓶をつかえば、いっしょに、鉄分ほきゅうもできる、とかんがえた。
どうせなら、気に入ったものをとおもい、北欧のデザイナーもの、南部鉄瓶なのに、にほんには、なかなかないカタチ、すきなカタチ、のものにした。
もともともっていた、南部鉄瓶のイメージとはちがう、鉄瓶というより、ケトルということばで、表現したほうがいい、カタチをしてる。鉄分ほきゅうが目的だから、南部鉄瓶らしくなくてもよい。
さいしょは、南部鉄瓶がほしい、とおもったから、もっていた南部鉄瓶のイメージ、とのズレがうまれた。だから、手にいれたものに、そのイメージのズレ、が上乗せされた。そのズレも、カタチからくる印象のひとつになり、カタチをつくる要素のひとつになった。
もしかしたら、何かものがあるとき、そのものが実際にどうかより、そのものがどういうものか、とあぶり出すようなこと、でしか、そのものを捉えることができないのでは、とおもった。
目のまえにある木を、みている時は、きっと、過去にみた木と、むいしきのうちに、比べているのではないか、とおもった。
木は、いたるところにあるけれど、いしきしてみるときは、特別なとき、である。たとえば、自然のなかにいったときとか、木におもいいれがあるときとか。いずれにしても、木との、特別なかかわりあいが、すでにあるから、比べてみることになるのだろう。その特別なかかわりあいを、記憶というのかもしれない。
もしかしたら、記憶なしに、目のまえのものをみることは、できないのかもしれない。ならば、そのときに、記憶をひきだしてくるものは、目のまえのものの、なんだろうか。
この住宅では、たとえばそれは、空をみたときの、あおさ、だったり、くものしろさ、だったり、太陽のまぶしさ、などの、ひとの感性にうったえてくるもの、だとおもい、空をとりこみ、記憶をかっせいか化し、暮らしと空を、つなげた。
ひとはつごう良く、ものを見わける。見わけることを、知覚、というのかもしれない。知覚は、もの、にたいしてだけ、おこるらしく、もの、をじふんのつごうで、かいしゃくして、次に、そのかいしゃくを、ものに、当てはめる。だから、じふんの中には、知覚は、のこらず、すべて、もの、に知覚がつくらしい。
ものは、そのような、連続したひとの知覚、の集合でできている。だから、もののじったいは、ひとによってかわり、つねに、一定ではないだろう。流行るものもあれば、すたるものもある、のもうなずける。
ただ、ひとの知覚が、ものをつくる、ことにはかわりがない。だとすれば、ひとの知覚に、はたらきかける建築を、構想することは、ありえる。
この住宅は、壁とのキョリが、知覚にえいきょうを、あたえることをかんがえた。遠くからみたばあいと、近くからみたばあいで、みえ方がちがう。画像は、遠くからみたばあいだが、近くではみえるものが、この画像では、みることができない。このみえ方の差が、知覚のズレをうみ、壁に、ちがった意味をあたえ、ここだけの壁のそんざい、につながる。それは、この住宅に、とくべつ感をあたえる。
あたりまえのように、仕切りがある、ことに、いわかんを覚えたので、ペンを手にしながら、フリーズしてしまった。いつものように、スケッチを、くりかえしたところで、いきつく先が、あるていど、想像できてしまうので、この想像できてしまうこと、も重要で、だから時間とお金が、よめるのだけれど、いわかんの元が、気になった。
時間とお金が大事、ならば、フリーズしている場合、ではないが、いわかんを、とりのぞく方が、もっと、価値あるもの、を手にいれる、ことができそうだとおもった。
いわかん、の正体は、いぜんにも、かんじたことで、何もギモンをもたずに、壁をつくることで、そのときは、壁をなくしたり、床を半階ズラす、などして、仕切るのではなく、領域をめいかくにした。
ただ同じことはしたくないので、いま、これからかんがえることは、ばくぜんとしてるけど、空間の流用、かなとおもう。
よこにひろがっていく、水平しせんと、たてにひろがっていく、垂直しせんがあり、水平しせんは、広さを、垂直しせんは、高さをかんじる。斜めのしせんは、広さと高さの両方をかんじる。
さらに、広さは、つながりへ、高さは、ふかさへ、となるとおもう。つながりも、ふかさも、両方とも、だいじだから、斜めのしせん、斜めのうごき、が必要になる。だから、建築の部位で、階段は重要だとおもう。
この建築では、階段をしょうちょう的にみせた。階段はいつも、わきやく、ただの通過する場所だけど、斜めのしせん、うごき、とすれば、それはとても、重要な場所であり、人のうごきは、人のしこうと、直接つながるから、階段がどうあるかは、人にかなりの影響を、あたえるでしょう。
これはこうだと、知らないうちに、きめつけたりしてしまう。あんがい、それが、あたっている、とおもいたいけど、本当は、きめつけない方がよかった、と後でこうかい、しないですか?わたしは、こうかい、します。
もし、きめつけないで、ありのまま、受けとめたら、きっと、ちがう世界が、ひらけた、かもしれない。
でもね、いま、見方をかえれば、大丈夫、とおもうのですよ。建築は見方のかたまり。いま、そこにいる住宅の見方を、かえれば、暮らしが、かわる。
この住宅は、暮らしをかえたい建主のために、見方をかえてもらいたい、とねがいました。そのために、まわりを囲まれているのに、とにかく、明るい空間をつくりました。
どこまでも、あかるく、そして、あかるく。どこでも、あかるいから、それりゃ、いままでと、ちがうから、かわりますよね、それも、あかるくだから、良いほうに。不思議と、わらい顔が、かわるんですよね。
カタチには、ココロで感じとるものと、カラダで感じとるものがある。ココロにうかぶカタチ、というもので、すきなカタチや、きらいなカタチも、ココロからくるものだろう。スロープのような斜めのカタチ、階段のようなギザギザなカタチは、カラダで感じとるもので、うごきをカラダで、感じとる。
そうすると、ぎゃくもありえる。カタチがココロをうごかす、カタチがカラダをうごかす。ココロをうごかすとは、カタチがなにかを、想起させる。カラダをうごかすとは、カタチがなにかを、決起させる。
よくかんがえてみると、建築は、ココロのカタチと、カラダのカタチで、できている。なにかを想起させるか、なにかを決起させるか。
この住宅では、我が家であること、じふんの居場所であることを、想起させ、その家の中を、すきに居場所を、えらんで、かえるように、決起させる、ようなカタチを、たくさん、ちりばめた。家とココロとカラダが、つながる感じが、ここでいちばん、大切にしたかった。
すべてが、まる見えだと、こまるけれど、かと言って、壁にかこまれるのも、きゅうくつになる。何か、じふんがおよぶ範囲を、きめたくなるから、壁がひつようになる。そうやって、いまの居場所を、たしかめている。きっと、あんしん、したいのだろう。
ならば、あんしん、できれば、壁はいらなくなる。どうすれば、あんしん、できるのか。見えなければ、あんしん、できるのであれば、壁のかわり、をつくればよい。
柔軟性を、かくとくするために、かんがえる、ひつようがあった。柔軟性は、固定しないこと、どうにでもなるさま、それが、部屋の仕切りに、ひつようだった、この住宅では。
だから、壁を技術的に、開閉できる、ようにした。ここでは、開閉できることが、あんしん、だった。ときに、じぶんがおよぶ範囲を、きめる方法が、きちんと、固定すること、ではなく、どうにでもなることが、じふんのせかい、をつくると、この建主からまなんだ。
目のまえにあるものを、どんどん、否定していく、それはいらない、それはなくてもいい、それはあっても役にたたない、それはむだ、などとやっていくと、じぶんのカラダすら、無くてもよくなり、最終的には、そうやって、否定してる、じぶんのこと、しかのこらなくなる、これがデカルトの『われおもう、ゆえに、われあり』らしい。
これって、断捨離のまつろかな、ミニマリストのまつろかな、みんな、デカルトに、なりたかったんだ、カラダもいらないんだ、そうか、捨てるじぶん、なくすじぶん、だけのこればいいのか、なんか、たいじなものまで、なくしそう。
ものがあふれてる、ものに囲まれてる、状態はよくないのかな、整理というか、どこに何があるか、わかれば、それでいいのでは。好奇心おうせいならば、ものでも、なんでも、あふれるよ。好奇心のほうが、まさるとおもう、なくすより、捨てるより、デカルトより。だって、そのほうが、単純に、おもしろい。
この住宅は、ものがあふれる、といいように、つくってみた。そのほうが、生活感がでる。生活感だけが、ゆういつの、じぶんの、せかいを、しる方法だし、いまを、いきてる感じがする。
この木をみてるとき、きっと、あの木のことを、かんがえている。だれでも、よくあるとおもう、目のまえのものではなくて、他のもののことをかんがえていること。こころ、ここにあらず、状態のまま、ただ、ぼんやりと、目のまえのものを、みてる。
それは、集中力がない、などといわれそうだけど、きっと、脳が、こうそくで、目のまえのものと、ほかの何かを、むすびつけようと、しているにちがいない。それは、脳の暴走かもしれないが、しばし、その暴走に、つきあって、ぼんやりと、するのもわるくない。
だから、ぼんやりとできる場所、がひつよう。ただ、どこでも、いいわけではない。脳だって、ひとならぬ、場をみる。脳がぼんやりするいえ、っていいな。ひとではなく、脳がぼんやり。この住宅は、そんな、脳がぼんやりして、まったりしてくれたら、とおもう。
森のなかに、自然のなかに、すみたい、とつねひごろから、おもってるので、いま、都市にすんでる身としては、かんたんに、かいけつするならば、田舎へ、いけばいいのだが、あるいは、二拠点、多拠点とふやして、都市と田舎の、りょうほうにすめばいい、いっぱん的には、そうなるのだろうけれど、なにか、しっくりとこない。
田舎へ、拠点をふやしたところで、かいけつしないだろうと、おもってしまうのは、自然のなかで暮らす、多拠点で暮らす、ぎじ体験は、いくらでも、できるので、なんどか、トライしてみたけれど、ただたんに、自然の中に、拠点をかえればいい、というものでもなかった。
たぶん、もとめていたのは、ながれる時間への感覚、だったのかもしれない。なにをしていてもいい、寝ていても、食べていても、さんぽしていても、ボーっとしていても、たとえ、しごとをしていてもいい、ながれている時間が、自分ではどうしようもない、自分とはかんけいないところで勝手にながれてる、そんな感覚、じぶんでは操作できない、もうそれでいいじゃないか、とおもえる感覚。
どうしても、時間を管理できる、とおもってしまう。ただ、自然にたいしては、すなおに、自分では、どうしようもできない、そんな、どうしようもできないものに、囲まれれば、きっと、じぶんの時間感覚も、かわるだろう、という期待から。
こう書きながら、しっくりこなかったことが、整理されてくる。ならば、いまでも、ここでも、できるような気にもなる。
この部屋は、そんな、あたまを、整理する時間と場所を、ご主人のために、住宅内離れ、としてつくった。
キッチンのまえの窓をあけると、おとなりの木がみえる。さいきんは、さむいのでしないが、毎朝、窓をぜんかいにして、空気のいれかえをしながら、ながめていた。ただ、窓をあけなくても、窓ごしにはみえるから、葉っぱのいろの変化はかんじることができる、さいきんは赤茶いろ。
他の窓ごしには、うちのオリーブの木がみえる。いつもあおあおとしていて、葉っぱのいろに変化はないけど、成長がはやいな、といつもおもう。
両方とも、室内から木をみる、ということはおなじ、でも、かんじ方、いみがちがう。キッチンからみる木は、おとなりの木、だから、おとなりさんも毎日みてるだろうし、こちらも、みてる、かんじ。うちのオリーブの木も、また、ちがうおとなりさんが、毎日みてるだろうし、こちらは、みられてる、かんじ。
あたりまえだけど、あきらかに、ちがう。でも、この、あたりまえだけど、あきらかに、ちがうかんじを、つくるのが、空間づくり、だとおもう。この住宅は、たくさんの、あたりまえのちがい、をしこんでみた。
自然をかんじる、っていつも、ふしぎだとおもう。山や海にいけば、自然しかないから、自然をかんじるが、きっとそこに住めば、自然があるのが、あたりまえになり、だんだんと、自然をかんじなくなる。
都市部にいると、せっきょくてきに、緑をとりいれること、条例などもあり、パラパラと緑をみかける。パラパラの緑では、自然をかんじるまではいかないが、自然をせっきょくてきに、かんじよう、とする姿勢にはなる。
けっか、自然にかこまれて、住むより、都市部のパラパラの緑のなかで、くらしたほうが、自然を日々かんじるのでないかな。そんなことをかんがえて、パラパラの緑でも、パラパラの緑なりに、くふうをすると、どこでも、自然ゆたかにくらせるよね。
たまたま、偶然、そうなっただけ、べつの可能性は、あったし、いつまた、変化するか、わからない、としたら、たしかなもの、ってないな、と。
ものをつくるって、たしかなもの、をつくろうとする。ものをつくる仕事に、忠実になろうとすれば、あるいは、いいものをつくろうとすれば、たしかなものを、目指すことになる。それがないとなると。
逆に、たしかなものって、あるのか、とかんがえると、何がたしかなものなの、となる。
いずれも、仮に、かんがえているだけ、だけど、たしかなものって、何か、あいまいだな、とおもう。
きっと、そんなことが、根底に、あったのかもしれない。この住宅では、部屋の仕切りが、あいまいで、それが、要望だった。そう、ここでは、あいまいなことが、たしかなものだった。
けはいを感じるように、ひとは、何かのこんせきを、感じるのうりょくがある。これって、いつもおもうけれど、すばらしい、こと。もとあったもの、なくなっていくもの、ちっていくもの、に何かを感じることができる。たとえば、ちりゆく紅葉に、たとえば、しずみゆく太陽に、たとえば、かわりゆく季節に。きっと、そのとき、ひとは、じぶんのえんちょうとして、じぶんの一部として、あるいは分身として、そのものを感じている。
だから、きっと、逆もある。あたらしく、うまれゆくものにも、けはいをかんじる、ことができるはず。そんな、無意識とも、よべるようなもの、へのけはい、それをきたい、と言うのかもしれない。それもまた、ひとにとって、じぶんのえんちょうや、一部や、分身で、それを、カタチにしたい、といつもおもう。
この住宅では、でてくる言葉とは、まったく、かんけいがないところで、カタチが、きまっていった。それは、なにをきたいしているのか、ひとは、じぶんでは、わからないもので、それをカタチに、翻訳するやくめ、をしたけっか、そうなった。
なにかを感じるから、そこにいるのがわかる。そこにいないと、わからないことを、感じるから、そこにいる価値がある。価値があるとおもえるばしょは、そこだけでしか、感じることができないものがある。いずれも、感じるひとがひつようで、ひととばしょを、感じることがつなぎ、価値をつくる
建築のばあい、感じることは、ものをかいする。ものがどうあるかで、感じることがかわり、価値もかわる。すべてを、感じることに、かんげんさせることで、価値をみちびきだすことができる。
この住宅では、明るさを感じることが、価値になった。1階でも、陽のひかりがさしこみ、明るくくらせる、そんなふつうなことを、価値にした。それは、そんなふつうなことを、えられる環境、ではなかったから。
1階から空がみえるようにした。やったことは、それだけ。ものとして、2階のゆかと、やねをガラスにしただけ。1階のダイニングテーブルにすわり、空を感じることが、できるようにしただけで、この住宅に価値がうまれた。
あぁ、あとから、きづくことって、じぶんでは、なぜだか、理解できていなかったけど、ほかのことをしてるときに、たとえば、つぎのプロジェクト、たとえば、本をよんでいるとき、ふと、うかぶ。いったん、あたまからだして、それをカタチにして、ながめてみたから、きっと、きづくことになった。もし、カタチにしてなかったら、えいえんに、きづかない。
はじめから、そうしようと、してなかった。時間差があったから、ひとつつくって、また、つぎどうするか、だった。だから、この2棟の住宅に、共通点はない。しいていえば、外壁をおなじにしたくらい。ただ、ゆいいつ、玄関だけはむかいあわせ、にすることだけは、決めて、あいだに、通路をそうていした。あとは、まったく、共通点はいらないと。
そうしないと、おなじような住宅がならぶ、ふしぎな風景をつくってしまう。けっきょく、そのときは、きづかなかったけど、あとからおもう、おなじようなものにしたくない、ことをしたかったと。
つながり方には、4種類、せっするか、かさなるか、はなれてるか、ズレているか、がある。つながる、ということだから、最低、2つのものがある。4種類のうち、ただひとつだけ、かさなるだけが、同時に、あらたなものを生成する可能性がある。かさなった部分が、あらたなものになる可能性。ぎゃくに、かさなりからみれば、そこから2つのものが、生成される、ともいえる。
だから、2つのものの、つながり方をかんがえるより、かさなる部分をさきに、かんがえることで、2つのもの、さらには、ぜんたいの構成がみえてくる、とおもった。
それを、いまのプロジェクトにいかしながら、同時に、かこのプロジェクトを再解釈してみる。そうすると、じぶんのなかで、たくさんの、かさなる部分が、うまれた。
カラダとココロが、ばらばらに、気分はいいけど、カラダがつかれてるな、そのぎゃくも、ただ、つい、カラダとココロをべつに、してしまうが、行動に、ちゅうもくすると、カラダもココロもひとつ、行動してるか、してないか、じぶんからうごくか、いわれてうごくか、だけのような気がする。
きっと、行動してるとき、ふぐざつなバランスのなかで、けっか的に、うまくいくように、するだろう。だから、じぶんからうごこうとすれば、けっか的に、そのとき、いちばんいいものになる。ならば、時間をみかたにして、じぶんからうごくことに、たくさんの時間を、かけることができるじょうきょうを、つくりたいものだ。
そんなことをかんがえながら、手をうごしていると、ふくざつなからみあいが、解けて、視界がクリアになった。やっと、まとまりそうだ。おいしいものでもたべて、またあした。
いま、みているものは、きっと、1年後には、ない。いま、みているものは、いま、このときにあわせて、偶然そうなっただけ、かりに、1年前に、いま、みているものを、予測できても、いま、このときにあわせて、用意はできないだろうから、1年後にも、ないだろう。あたり前のことだけど、この偶然そうなっただけ、ということが大事だと、おもった。
偶然そうなっただけ、ならば、たまたま、そうなっただけで、ちがうものになる、可能性もあった。ならば、いま、みているものが、いつまでも同じ、でいる保障もなく、ちがうものに、いつかまた変化するかもしれない。
そう、だから、なにをつくっても、同じでいつづけることは、ないだろうから、絶対なものはないはず。すべては、変化する、ということになるが、そうすると、なにをつくっても、同じ、いみが無い、となりそうだが、なにをつくっても、変化する、という運動に、ちゃくもくすると、ものをつくることって、この運動を、かそくさせることで、そのときの燃料は、言葉、すなわち、いま、みているものが、偶然だと、絶対ではないと、わからせること、だとおもった。
だから、いまつくっているものは、時間の流れが、運動として、仕込まれていて、燃料となる言葉は、プランとかたちに変換して、はいちしている。
うまくできそうだと、おもうのは、カンだけど、そのカンは、いままでの経験から、くるのかな。ただ、経験では、たどりつかない、ようなことが、おこるほうが、おもしろい、ともおもう。だから、経験はあてにはならない、とおもうほうが、おもしろいかもしれない。
経験が、あてにはならない、としたら、どうするか。てきとうに、言葉を、放りこむしかない。それは、思いつくかぎりの、言葉をだし、ならべ、かたっぱしから、ためす。ためした結果は、経験をこえるだろう、とおもえた。
さらにいえば、思いつくかぎりの、言葉をだしたときに、すでに、経験からくるカンは、ふ必要で、むいみになる。その言葉におうじたことが、現実に、てんかいされる、のだから、カンをあてにして、うまくいくかいかないか、をかんがえる、必要がない。
この住宅では、そもそも、経験したことがない、ことばかりした。だから、それをするためには、思いつくかぎりの、必要な言葉をだし、ならべ、ためす、ための素をつくった。素は、ときには図面、ときには素材、ときには職人、ときには感情だった。
けっか、経験したことがないから、うまくやる、こともできなかったが、言葉からつくった素、がおもしろさと、完成度を、たんぽしてくれた。
みたいように、みているから、好きなようにみえる、こうみたいと、話しかけているように。でも、そこに、誰かが、こうだよ、これはどう、これがいいんじゃない、とか、ヨコヤリをいれる。ヨコヤリは、みたことがない、そうはみえなかった世界だった。そのとたん、いままで、みてみたい、とおもっていたものが、かわる、そっちのほうが、よかったと。
きっと、これが、りそうかな、とおもう、なにかをつくるときは。じぶんがヨコヤリのそんざいでいたい。
この住宅は、ヨコヤリをしてみた。リビングのまんなかに、まるみえの階段、その階段が、リビングを、3つのゾーンにわけて、空間はつながりながら、回遊でき、みんなすき勝手に、すごしている。それが2階からも、わかる。この空間のおかげで、なにかと、かおをあわせる、ようもないのに、話したくなる。空間が、なにをしたらいいのか、おしえてくれた。
サボり、っていけないこと、だけど、サボるときは、だいだい、大事なことを、しているときだから、ぎゃくに、大事なことがわかる。べつに、大したことをしてないときは、サボりにならないし。
大事なことは、変化につながること、だから、ひとは、変化がきらい、だから、サボる。ならば、サボるときにすることを、べつの大事なこと、にすれば、べつの大事なことは、おおいにはかどった。
そんなちょうしで、この住宅では、サボれる場所を、たくさん、つくって、あちこちで、サボれるようにした。
サボって、大事なことをする、って、うしろめたさ、とヤッた感が、ダブルでくるから、甘塩っぱいものを、食べてる感、けっこう、クセになるかも、おいしいかも。
なにかと、あいまいにしたい、のだが、建築の境界の話、なかなか、それがゆるされないから、なやむことも多い。いろいろな境界が、建築には、あるけれど、壁もそのひとつ。境界として、外壁をみれば、いくらでも、あいまいにはできるけれど、たとえば、うごくようにするとか、壁を厚くして、外でも内でもない場所をつくるとか、ただしかし、きちっと、境界はきめなくては、いけない。それによって、法令順守と事業担保がはかられる。それはあたり前に大事なこと。
そのうえで、境界をあいまいにしたいのは、ものごとは、揺れうごくでしょ、そんなに、キチッとしてないでしょ、それは建築もおなじ、バッファーゾーンのようなものがあり、そのあいだだったら、揺れうごいてもいい、とすると、建築の決めかたも、できあがる建築も、かわるだろう。あたり前である、前提がかわるのだから、などと妄想してみて、バッファーゾーンがあると、いいなとおもう。
なにかと決まっていることがおおいので、なるべく、決まっていることはせず、そうすると、決まっていることがあいまいになり、そのまま、あいまいなまま、決まらないかな、そんなことはないのに。でも、この住宅は、クライアントに理解があって、あいまいのまま、けっこうギリギリまで、すすめて、アドリブもおおかった。それがよいか、わるいか、は別にして、決めるということを、見直す、キッカケにはなった。
行きつけの呑み屋、をつくったり、いつも同じものを、かったりたべたり、かならず通る場所とか、べつに、それでなくてもいいはずなのに、変えずに、同じをくりかえす。それで、あんしん感はあるし、よけいなことを、かんがえなくても、すむからいいのかもしれないが、ほんとうに、そのままで、いいのか、とギモンにおもわない、のだろうか。
たぶん、おもっても、変えられない、のだろう。変えるすべを、しらない。そんなときは、人まかせにすればいいのに。あいては、まかされて、喜ぶ、とおもうし。
けっか、おもいつけば、いいけれど、そんなこと、自分では、おもいもつかない。さいきん、はじめた、パンづくり、むずかしくて、時間がかかると、おもっていたけれど、レンチンで、15分あれば、できる。そのやり方を、ぐうぜん、SNSでしった。しろうとは、レンチンでパン、なんてできるんだ、と新鮮だったけど、プロにしたら、かんたんなこと、なんだろうな。
たったひとつ、大事なものがあれば、それだけで、なっとくしてもらえるのでは、といつも、かんがえ、プレゼンする。いつも、そうやって、そのときどきで、ちがうけれど、決め手は、いつも、ようぼうの奥にあった。
たったひとつの部屋を、よぶんにつくったり、まったく、常識とは、ぎゃくのことをしたり、いちどは誰でも、おもいつくがやらないことを、やったりした。
ここでは、たったひとりになれる居場所を、いつでも、つながることができるところに、つくった。空間とのかんけいは、使用者とながめる人にわかれるが、使用者とながめる人とのかんけい性がなかったので、トビラをあけることで、つなげてみた。このことで、おこったことは、いままでの暮らしにはなかった、かぞくの時間が、ながれはじめたこと。
はっきりと、こうしよう、と決まるのは、だいたい、動きだしたあとだが、動きだすまえに、なんとなく、こうならないかな、とか、こうならないとイヤだな、とかは、決めてみる。けっこう、いつも、この決めてみる、でどうするかな、となる。
せけんでは、はやい方がよく、こうりつよく、が良いとされ、とりあえず、あいまいでも、はやく動け、となる。ひじょうに、自分みたいなタイプはこまる。はやく動くのは、いくらでもできるが、そのまえに、決めてみる、をしたい。それがないと、いくら早くても、まちがった方向にいきそうになる。
それを言うと、まちがったら、引きかえして、またやり直せばいい、その方がはやいと。ちがう、ちがう、またやり直しても、たぶん、またまちがうか、さいあく、まちがいを無いものにしてしまうかもしれない、早くやるために。けっきょく、最初に、決めてみる、をした方が、けっか、早いし、良いとおもうのだが。
などと書いたのは、いま、そういうじょうきょうだからで、もうちょっと、じかんを下さい、とだれかにつたえたい、気持ちのあらわれでした。
だいたい、あんぜんな方へ、かわらない方へ、いこうとする、本能だろうか。でも、かえるのが、スキだから、何ごとも、いまに定着しない、ようにする。けっきょく、いまいいのは、すぐに、あきるか、だめになる。何かをすこし、かえるぐらいで、ちょうどいい、といつも、おもう。
かといって、何年もおなじことを、し続けている。ふしぎだ。続けていることは、なかなか、うまくいかないこと。続けるコツは、うまくやらないこと、だったりして。
建築も、なかなか、うまくできない、もっと何とか、とおもうから、続いているのだろう。きっと、それがなかったら、うまれないことばかり。この画像の住宅は、いちだん、ギアチェンジしてみた。こまかいことの、精度をあげた。とたんに、うまくできないことばかり、になったけど、その次は、この精度がスタンダード、になって、また、ギアチェンジした。
境界について、きになることが、よくあるなとおもった。きっと、さかいとか、別々とか、はなれているとか、違いがはっきりしている、ことになにか、ていこう、があるのかもしれない。できるだけ、さかいをつくらずに、別々にならずに、はなれずに、できないものか、とかんがえる傾向があるかもしれない。
なに事にも、さかいはある。建築にもある。ただ、そのさかいは、たまたま偶然、そうなっただけとか、はじめからあったとか、便宜上そうなっただけとか、一時的とか、かならずしも、それである必要がなかったり、それだと決めつけなくても、なんとかなることもありそうな気がする。
そうおもうと、さかいを曖昧にしたい、となる。建築で、いちばん影響をうけるさかいは、敷地のさかい、だろう。このさかいだけは、なにがあっても、越えることができないし、曖昧にもできない。
ただ、さかいに、あらがいたい、それが、もしかしたら、設計するうえで、いちばんむすがしく、かつ、いろいろなことに、よい影響を、あたえること、かもしれないと、いまかんがえている。
前に、画像のように、建物の四周と塀とのあいだに、デッキを敷いた。デッキにより、室内空間が、敷地いっぱいまで広がり、その広がりは、敷地の外まで、拡張する意識、をつくりだす、とかんがえた。ただ、デッキによって、敷地のさかい、をよけい強調するけっか、にもなった。
いまは、さかいを別のしゅほうで、曖昧にすることを、かんがえている。
なんとなく、気になる建築や空間を、おもいうかべながら、あれって、かたちだけ残して、あとはぜんぶ替えてみたら、どうなるのかな、とか、平面のプランはおなじだけど、かべの高さをかえてみると、とか、いちぶだけ、大きさをかえてみたら、どうなるかなど、あれこれ、妄想してみる。
そうすると、やっぱり、もとがいい、とか、あれっ、もしかして、なんてことを、また連想する。それで、じっさいに、かたちにしたら、オマージュとか、リスペクトとか、になるのだろうか。
ただ、そうかんがえると、無意識に、なにかしらに、影響をうけているから、もとネタはわからないが、いままでつくったものは、もしかしたら、すべてが、オマージュとか、リスペクトとか、になるのかもしれない。
それは、たくさんの建築にかんすることを、みききしてきたからで、いまこうして着想していることが、なにとつながるか、たどってみると、あんがい、面白いはっけんがあった。あした、その本をさがして、よんでみよう。
カタがあると、それをだれかがくずし、またカタができる、そして、また、だれかがくずす。この一連のながれのなかで、どこに、いちばん、興味があるだろうか、とおもった。
はじめのカタがあること、そのくずし方、くずした後のカタのつくり方、また同じくずし方をするのか、など、ちゃくもくする点は、いろいろと、かんがえることができる。
きっと、自分は、また同じくずし方をするのか、に興味がある。カタなど、なにか主流のものがあれば、それとは真逆のものが、うまれる。そのときの、うまれ方、すなわち、カタのくずし方は、カタを相対化する方法をとる。
歴史はくりかえす、という。相対化する方法も、歴史をみればわかる。だから、また同じくずし方をするだろうことも予想はできる。しかし、それが、いつはじまり、だれがはじめて、どこではじまる、のかは、後になって、歴史になって、わかることで、同時代的には、なかなか、わからないこと、だとおもう。
ということは、また同じくずし方をするのか、に興味をもち、観察することは、いまをいきる、ことにつながる、とおもうし、そうすれば、いまがたいせつ、になる。いちばんは、いまかな、とおもう、きょうこのごろ。
見なれない、だから、すぐに理解できない、ふしぎなものと、見なれてはいるけれど、なにかが違う、とかんじるもの、どちらにも興味があり、じっさいに、りょうほうとも、この目で見てみたくなる。
では、じっさいに、自分がつくるとき、どちらのものをつくりたい、とおもうか。
見なれてはいるけれど、なにかが違うものは、いままであったものを、進化、あるいは、より洗練させた、ものだろう。見なれない、すぐに理解できないものは、いままでと、アプローチがちがう、あるいは、そもそも出発点がちがう、ものだろう。
いつもおもう、いままでに見たことがないもの、をつくりたい、と。だから、見なれない、すぐに理解できないもの、をつくることにひかれる。きっと、そういものは、画像では、すぐに、理解はできないけれど、じっさいに見れば、すぐに、なっとくするものだろう。
どんな形にしようかな、と最初は、かんがえていたのに、いつのまにか、どうやって形にしようかな、とかんがえている。
条件や要望を、形にしていくときに、ばくぜんと、かんがえているあいだは、手がかりがおおすぎて、まよい、形をむげんの海から、引っ張ってくるかんじ。そのうち、どうやって形にしようかな、と自然にかんがえているときには、あるていど、方向性がしぼれているしょうこ。
どうやって、って、まほうのことば、だとおもう。そうかんがえた瞬間に、形にむかって、すすみだし、形になる。
この階段は、ひかりが差しこむ、ところにある。だから、ひかりをさえぎりたくない。かといって、ガラスの階段では、ひかりが差しこむところに、あるいみがない。この階段があることで、ひかりの粒がみえればいい、これで、形のどうやって、のぶぶんができた。
あんがい、どうやってのぶぶんは、そのものとは、直接かんけいない、ところからふってくる。
まいにち、つづけて、それでいて、変化していくようなこと、きっと、暮らしはそういうものだ。
暮らしがおさまる器として、と住宅をかんがえるひとも、いるだろう。それで、いいとおもう。暮らし、という日常的につかわれる言葉で、住宅を表現することは、ひとつ、大切なこと、だとおもう。
ちがう言いかたをすれば、暮らし、という誰にでも、わかる言葉で、住宅をかたることの大切さ、住宅をかたることができるひとの大切さがある。
いっぽうで、ひとがいれば、自然と暮らしはおこる。大切なのは、そこに、ひとがどのようにいるか。暮らしは、たまたまそうなっただけ、として、住宅は、たんに、ひとがいる場所、にすぎない。
これは、もともと、暮らしは、その場所にあったのであり、たまたま、そこにきたひとと、むすびついただけ。暮らしは、つくりだすものではなく、環境にさゆうされる、都市の暮らし、山の暮らし、といったぐあいに。だから、ひとが歳をとるように、ひととむすびついた暮らしも、まいにち、変化していく。
このように、住宅と暮らし、を切り離してみると、もっと、根っこの、いま、そこに、ひとがいることを、形にする必要がある。それが、住宅のほんらいの姿、だとおもう。
つながる、ってキョリの遠近とは、関係ないな、と電車にのりながら、いつも、おもう。となりの席のひとのこと、ではなくて、となりの電車のひとのこと。並走する電車のひとは、ちかいけど、まったく、つながることがないひと。たぶん、二度とあうこともない、かもしれない、あたりまえだけど。どんなに、キョリがちかくても、ふれることもできない、レールがまじわることがないから。
この関係性に、ひとてま、加えたら、たとえば、まじわることができれば、けっこう、りそう的な関係、になるかもしれない、とおもった。
ここでは、住宅が2棟、親族どうしで、ならんでいる。あいだに、きょうつうの、通路をもうけた。電車でいえば、同じレールをつかっている。それ以外は、まったくべつのもの、まったくべつの電車。ただ、ときどき、ぐうぜん、であうだけ、ふれることもできる、かわすこともできる。それが、お互いにとって、ここでは、ほどよいキョリかな、とおもった。
建築みたいに、おおきくて、うごかないもの、に偶然性をおこすのは、むずかしい、と書こうとして、そんなこともないか、とおもいなおした。
建築ないぶに、偶然なにかが、おこるようにすることは、いくらでも、かんがえることはできる。が、建築じたいに偶然性を、まとうことが、できるだろうか。
すぐに、うごかないし、おおきいし、偶然性をまとうのは、むりかな、とおもった。偶然性をまとうとは、変化すること、例えば、太陽のひかりで、みえ方がかわるとか、になるのかな、それならば、とおもい、偶然もありうるか、とおもいなおした。
ただ、形がかわるようなことは、ないよな、やっぱり、うごかないものだし、ここでの偶然性は、形にかんして、言いたかった。可変って、建築にとって、やっかいかなこと。可変する機構をもりこむと、建築ではなく、機械になり、機械というメタファーをもちだしてくるのは、ふるくさい。
などと、ダラダラとかんがえながら、可変する、可動間仕切りを、よくつかっているな、すきなんだな、とおもった。
斜めがすきじゃない、まっすぐで、垂直で、四角がすき、だといつもスケッチしながら、おもう。だからか、坂道もすきじゃない、水平線がすき、地平線がすき。スロープよりも、階段がすき。円も、丸も、すきじゃない。べつに、こじんのすききらいなど、どうでもいいけれど、やっぱり、いままで、つくったものには、振り返ると、えいきょうがあるようだ。
だから、斜めや円、丸などは、いしきして、つかうようにしている。いしきするとは、なにか、意味をもたせたり、アクセントにしたり、そこをみて、というポイントにしたり。
ただ、いきなり、斜めや円、丸などをつかっても、こうかがないから、まっすぐや垂直、四角と対比させてつかう。この対比がうむこうかを、かんがえるのが、デザインのひとつかな、とおもう。
かんじんなことは、いつも、後まわし、それで、他のことは、用意周到、なんてこと、よくありませんか?けっきょく、かんじんなことを、大事にとっておく、いや、面倒だから、やらない、なんてことになるかもしれない。
ただ、まわりから、決めていく、という考えも、あるかもしれない。かんじんなことは、いずれ、やらなくてはいけないことだから、先に、関係ないことをやる、のはいいとおもう。もしかしたら、まわりから、決めたことで、また、べつの展開が、みえたりして。
まわりのもの、たとえば、住宅では洗面かも。どこでもいい、訳ではないけど、かといって、そんなに。だからか、いつも、なぜか、場所を工夫することに。けっきょく、洗面のような、まわりを飾るものの場所が、反転して、かんじんな場所が、決まるような、気もする。
べつに、そこまでする必要は、ないんだけど、とおもうときって、余計なことを、してると、かんがえているんだな、きっと。だけど、その余計なことが、ほんらい、じぶんがやりたかったこと、といまになって、気づく。
たいがい、余計なことは、オーダーには、ないこと。勝手におもいつき、勝手にやること。そのことで、1円ももらえない。これって、いつもおもう、経営者として、しっかくだな、と。
この住宅では、内装仕上げに、よくある下地材をつかった。どうやって、みせるか、がもんだい。ただ、つかうだけでは、芸がない。色をぬって、ごまかしたくもない、その予算もない。
板をつなぐ、ことにした。そのつなぎ方を、デザインする。そうすることで、つかう板が、なにかは、関係なくなる。
どちらにせよ、板をはることは同じ、つなぐことがおこるのも同じ、だから、つなぎ方のデザインは、余計なことになるかもしれないが、つなぎ方をデザインすることで、つかう板、つかう素材、素材の良し悪しが、どうでもよくなる、素材にいぞんしなくなる。これが、やりたかったこと、だった。
じつは、このことで、もっと余計なことをしてる。のちに、大工さんから、ゆめにうなされた、といわれた。画像には、うつらない、実物をみれば、すぐわかること、いままで、じふんも、ほかではみたことがないこと、ほんとうは、これの方が、やりたかったこと、かもしれない。
あちこち、みてしまうのは、集中力がないしょうこ、おちつきがない、とよくいわれたものだった。ものは、注意をひくために、できている、これをアフォーダンス、という。そもそも、興味をひかないものは、そこにないのと同じ、だから、アフォーダンスは、けっして、わるいことではなく、だから、おちつきがない、こともわるくない、とおもう。
この家では、みんな、行動がバラバラ、おもいおもいに、すごしていた。だから、いる場所がちがっても、お互いどこかで、つながってる感がほしかった。
なにげない日常の中で、なれ親しんでも、つながり続けるためには、興味をひきつけあう位置かんけいがひつようだ。チラッとみえる、かんけいは、お互いをじゃましない。
画像は、キッチンでの、奥さん目線。2階のひと、奥のひと、庭のひと、この家のひとの行動がチラみできる。きっと、チラみだから、なんか気になる、なんか興味がわく、そんなかんけいだらけの家が、いいとおもう。
どうでもいい、どっちつかず、あいまい、はネガティブなことで、なるべく、さけたいとおもうかもしれない。こうりつとか、はやくとか、を求めるときは、はいじょされる。
ただ、さいきん、このあいまいとか、どっちつかずの領域も、ひとつのかたち、になるとおもっている。
この住宅では、可動の間仕切りで、領域をつくるだけ。その領域が、そのときの必要におうじて、ついたり、わかれたりして、領域の大きさがかわる。
領域がきまっていないことは、こうりつの観点からいえば、非こうりつに、つながる。あらかじめ、きめられた、限定した領域の中で、うごくほうが、こうりつを追求しやすいから。
ただ、この住宅では、あいまいな領域があるから、いろいろな暮らしの可能性、それは、この住宅をじゅうぶんにいかしきる、という点で、こうりつより勝る、とかんがえた。
色がついているものと、ついていないもの、をくらべると、色がついている分だけ、ひとつ特長がふえて、いいようにおもう反面、色がついていない、透明だから、さまざまなものを、そのまま鮮明に、映しだすことができるよさが、あるともおもう、ガラスのはなし。
ガラスを、色つきか、透明か、さいきんのなやみ、大したことがないなやみだけど、けっこうな時間をかんがえている。色つきだと、とうぜん、その色がガラスごしにつくので、鮮明にはみえないが、ガラスの微細な凹凸を、色が増長してくれる。ぎゃくに、透明だと、色による作用がないから、鮮明にみえ、ガラス特有の映り込みが、よりはっきりみえる。
この住宅では、透明にしてみた。日々の暮らしで、そのつどかわる色を、映すことで、さまざまな、暮らしの重なりが、壁の模様になる。それは、この住宅特有の、色になる。
きょうかい線、って、いろいろなものにあるけれど、さいきん、おもうのは、ちょっとでもはみ出したら、許されない感じが、つよい。建築のきょうかい線は、敷地のまわりにあり、たしかに、ぜったいに越えてはならないが、枝や葉が、空中を越えているのは、よく目にする。
それでいいとは、いわないが、うちもおとなりに越えているので、敷地のきょうかいが厳密なぶん、それぐらいのゆるさがあっても、いいような気もする、おとなりのかた、すみません。
いかに、きょうかいを厳密にまもりつつも、空中のような、いつでも、引きかえすことができるかたちで、越えていくか、って、実際にやるかどうかは、べつにして、一度はかんがえてみたほうが、いいことだとおもう、意識だけでも。
あんがい、なぜ、きょかいをまもるのか、の意味がわかり、そうすると、いままでと違った、きょうかいのまもり方ができるかもしれない。この住宅のように、おとなりの人と、かくしんはん的につながろうと、するかもしれない。
ちょっとでも多く、という心理、なるほど、よくわかるから、ロフトなるものをかんがえてみる。そもそも、あまりの空間をどうりようしようか、という発想のたまもの、だから、そこは、すなおに、あまりの空間さがしをしてみる。
ゆかした、やねうら、階段のおどりば、あとは、たかいところ、人がいきたがらない、ような、あまりはたくさんある。いっぱん的には、そのあたりが、ロフトや収納になる。
あまりの空間だから、いとてきに、空間をつくるのはNGらしい。あくまでも、空間のゆうこうりよう、ということらしい。だから、空間さがし、宝さがしみたいだ。
ふとおもう、宝さがしする空間は、はじめから存在していたのか?いや、つくったはずだ。ならば、ロフトを、さきにつくってから、空間のなかにうめこんでしまい、宝あったどぉ、なんて、やらせ?をしてもいいだろうか??
こどものころは、外からかえると、勝手口からあがり、そこには台所があり、そこでなにかをしてる母親に、ただいま、とこえをかけた。むかしは、なんでも、手づくりだったから、つくるところを、みているのが、おもしろかった。
いまのほうが、家事は、だいぶ楽にはなっただろう。せんたくものは、干さなくてもいいし、レンチンで、おいしいものはたべれるし、ロボットが、そうじしてくれる。
もはやキッチンも、作業するところではなく、コミニケーションするところ、にかわった。家族といっしょにすごしながら、家事をする。もしかしたら、ゆっくりと、家族がすごせる場所がキッチン、ってのもわるくない。
家の外で、家族といっしょにすごすこと以外のことは、全部、みたすことができる。だから、家の中にいる目的は、家族といっしょにすごすことだけ。
この家には、コミニケーションするために、壁が、ひつようとされなかった。風呂とトイレ以外、壁がなくても、暮らせるんだ、とわかると、おもしろいことに、家の外と中のさかいの壁も、パブリックとプライベートのさかいも、なしにできそうな気になる。
建築が複数あれば、関係がうまれる。関係がうまれれば、にぎわいができる可能性がある。だから、建築によって関係がうまれると、にぎあいをつくるためには、どうすれば、いいのか、をかんがえるようにしている。
よくあるのは、人のアクティビティを、建築同士の関係性に、からめること。複数ではなくても、例えば、建築によってつくられた、アトリウムなどの、大空間でもおなじだが、場所があり、人がいれば、かならず勝手に、あるいは、そこになにか、イベントのようなものをたすことで、にぎわいはできるだろう、というようなかんがえ。りくつで、人のことをかんがえ、あとは任せっぱなし、のじょうたい。
それでは、にぎわいはできないだろう。それで、にぎわうのであれば、せまい、路地の、呑み屋に人はあつまらない。
きっと、雰囲気だと、おもう。人がにぎわう雰囲気。それって、新規の建築計画が、いちばん苦手、とするところ、だとおもう。そこに、模範解答はなく、正解はなく、読めない。人のことを読めない、のとおなじ。
だから、ここでは、人のアクティビティを、建築同士の関係性にからめているが、建築が先ではなくて、人のアクティビティ、すなわち、人のからまり方を先にきめてから、建築をきめた。
人がからまり、にぎわうためには、その敷地の、どの場所に、どれくらいの形と広さが、あればいいのか。けつろんは、スープの冷めない距離感だった。それは、内部の部屋の構成にも、影響をあたえた。
光のつぶ、というけれど、光がつぶで、みえるはずがない、とおもうが。
こんな話をきいたことがある、むかしは、雨つぶの存在が、みえなかった。むかしの西洋絵画には、雨がえがかれていない、地面はぬれているのに、というのだ。すなわち、それは当時のヒトには、雨つぶが、みえなかった。しかし、広重が線で、雨を表現したことで、雨つぶの存在にきづき、みえるようになった、というのだ。
真偽はわからないが、いままで、表現できなかったものが、表現できるようになると、それまで、きづかなかったものに、きづくようにはなるだろう。だから、もしかしたら、まだ、光のつぶを、表現できていないから、光のつぶが、みえないのかもしれない。
ここでは、階段をりようして、光をつぶで、とらえようとした。階段の段板と踊り場の床に、無数の穴をあけた。その穴をとおして、ふりそそぐ光は、無数の穴の輪郭を鮮明にし、つぶ状になる、とかんがえた。
じぶんが10年以上まえに、やったことを、いまだれかがやっていると、それはつかい古されたものか、それが当たり前になったのか、それとも、けっしてそのようなことは、ないとはおもうが、じぶんが早かったのか、などとかんがえる。
いずれにせよ、いま他のだれかがやっているのだから、それをいま、またじぶんが、やってもいいだろう、というおもいと、一度やり、いま他のヒトがやっているのだから、もうやる必要がない、ヒトとおなじことはしない、というおもいの、2つがうかぶ。
楽なのは、またやってもいいだろうだ。まえにやっているから、かんたんにできるし、失敗がない、それでいて、いっていの評価はもらえる。ただ、それだと、じぶんが満足できないだろう。いや、しごとだからと、割り切って、失敗がない、のがせいかいかもしれない。
10年以上まえのときも、ヒトとおなじことはしない、としてやったけっか、失敗しなかった。はじめてだから、しんちょうにもなり、いまだにきれいにのこっている。
さっきまで、あたまのなかを、グルグルとめぐっていたけれど、こうして書きながら、せいりされた。やっぱり、ヒトとおなじことはしない。そうしないと、このさき10年ごにこうかいしそうだ。
いつもおなじが落ちつく、いつもおなじことには価値がある、とおもわない。いつもおなじと、いつも変わらない、はちがう。いつもおなじは、いちもおなじにしようとする。いつも変わらないは、いつもちょっとずつ変えて、変わらないようにしている。いつも変わらないほうが、あたしいことを受け入れるよちがあり、好奇心をはっきできる。好奇心は、価値のみなもと、だとおもう。
よくランダムにする。それは、そろえることが、いつもとおなじことをすることであり、ランダムにすることが、いつもと変わらないにようにすること、だとおもうから。
この建築では、かべの空調の吹き出し口やスピーカー、照明をとりつける穴をランダムにした。ランダムに変えたことで、機能は変わらないが、壁の穴にデザイン性がうまれ、ひとつあたしい価値がプラスされた。いつも変わらないには、あたらしい価値をうむ可能性がある。
おおきなものに、包まれる感じは、あんしんする。包まれるものにもよるけど、おおきなものは、ときにはヒトかもしれない。あんしんしていられるヒトは、包むのがうまい。
包まれるあんしん感は、あんぜん地帯にもなる。ヒトにとって、あんぜん地帯はひつようで、その場所は日常のなかにあったほうがいい。
家って、あんぜん地帯になりえるもの。へやにいると、その包まれ感があんしんする。だから、この家では、その包まれ感をみた目で感じてもらうために、家のかたちのなかに、家のかたちをつくった。
いまいる空間を、見た目で感じてもらうことで、いまいる空間がわかる。あんしん感のみなもとは、きっと、このわかる感覚、ヒトもわかりやすいほうがあんしんするでしょ。
大事なものは、捨てられない。だから、いっぱいものが、たまるのかもしれない。みてると、たまるものは、行き先ふめいのものだ。ものがかえっていく所が、きまっていれば、たまらない。たまるというのは、目にみえて、あふれているからで、おさまっていれば、たまっているようには、みえない。
おさめ方がいいと、大事なものは、またちがった価値をうむ。大事なものは、ただあるだけよりは、自分とつながったもの、でいてほしい。
その木は、クライアントのお父さんが、なくなったときに、自然と道路ぎわに、生えてきたらしい。だから、のこしたい、それが最初の希望だった。そのまま道路ぎわより、きちんとおさまる場所をつくり、どこからでも、みえるようにした。
おさまる場所を、つくることじたいが、大事なものとつながることだから、あふれていてもいいものは、もしかしたら、なくてもいいものかもしれない。
昼のかおと、夜のかおがあると、なんとなく、どちらがほんと、なんか疑わしい、などとなるかもしれない。どちらもほんとで、どちらがいいか、わるいかはなく、二面性があっていい、とおもうが、ハッキリしないものには、無意識に、しろくろをハッキリさせたい、となるから、じぶんにとって、都合のいいほうをしんじるようになる。
二面性は、いつも意識する。ふたつの間をいったりきたりしながら、片方をみると、よーくみえるものがあるから、それがなにかのヒントになる。
建築にも、昼のかおと、夜のかおがある。昼ははくじつのもと、すべてをさらけ出す。夜はそうさできる。夜は都合のいいところだけを、みせることができる。だから、昼のかおと、夜のかおをくらべて、変化しているところが、かくしたいところ、すなわち、その建築にとって、いちばんみせたくないところか、もしかしたら、いちばん重要なところ、かもしれない。
それができても、できなくても、たいしてかわりがないのに、やろうとすることは、気がつかないうちに起こりそう。たいがい、そういうときは、やること自体がいい、とされてきたことだから、そのことにギモンを持たないし、持てない。
へやはヒトがたまるところだけど、けっして滞在するところではないこともある。ヒトが通っていくところに、ひっかかるモノがあり、そこにヒトがたまる。しかし、それは一時的であり、またヒトはうごいていく。
そのくり返しでへやが成り立つならば、ヒトは滞在せずに、たまりながら、また次へ、うごいていく。このばあい、へやは廊下のようであり、ならば、廊下をめぐらせてから、その廊下をへやにすることを考えてみた。
はじめから、へやをつくることが当たり前だから、それにたいして、ギモンを持たないし、持てない。しかし、へやイコール建築ではないので、へや以外のところをプランニングすることで、へやをつくりだす試みをしてみた。
こわいもの見たさ、高いところがこわいのに、高いところにいきたくなる。不思議なもので、高いところから、上を見あげたくなる。きっと、好奇心が、こわさにかつのだろう。
四層吹き抜けの、らせん階段をつくったら、ぐるぐると上を見上げながら、のぼるかな、と想像して、計画してみた。らせん階段は、いちばんコンパクトな階段、だから、省スペースのためにもいい。
すける段板は、最上階からのひかりを、拡散させながら、1階までとどかせるため、あと、上を見上げたときに、先まで見せるため。らせん階段は、ふつうの階段より、視線が上にいきやすく、上へのいしきがつよくなる。だから、好奇心をそそるしかけとしても、すける段板はいい。
階段をのぼることに、なにか他のことをたすことで、ひとの動きに、変化をもたらす。その変化は、空間の感じ方に、影響をあたえ、好奇心を刺激する。階段が、単なるのぼり下りのそうち、ではなくなる。
かわってしまうことに、抵抗があるのは、としのせいかな。ただ、むかしから、そうだったような気もする。ものはなんでも、最初はあたらしくて、だんだん古くなっていく。できれば、古くなってほしくないとおもってしまう。だんだんあたらしくなることがあれば、それがいいけれど。だから、なんとか、古くならないようにしようとする。でも、どうしても、古くなるから、古くてもいい、もっというと、古くなるほどに新鮮、という矛盾するようなことが、できないかなとおもってしまう。
古くなるほどに新鮮なさまは、年月をへてもかわらないのではなくて、年月をへてかわることによって、最初とはちがうものになり、それがあたしいみえ方になる、のだろうと考えた。
そこで、年月をへてかわる材料として、木をえらんだ。木を素地のままで、室内につかうと、くちはてることなく、焼けたり、変色して、のこりやすくなる。木の素地のままだから、焼けや変色がめだつが、それがかわったあたらしいみえ方、になるというストーリーをえがいてみた。
何十年後、生きているかわからないが、かわったところをみてみたい、いまが新鮮か、と。
その場所にたったとたんに、なんかスイッチがはいったように、急になにかをしだしたり、考えたり、おもったり、することはないだろうか。それがいいことでも、わるいことでも、なんでだろうとおもう。
美術館には、ひとの評判より、たんにおもしろそうだな、という理由だけでいく。たいがい、ウイークデイで、すいていて、人もあまりいなさそうな時間にいく。しずかにみたいのと、逆走するので。いちばん最初に出口までいき、全体をパッとみて、みたいところだけに、時間をかける。そうしないと、途中であきてしまう。人がいないと、逆走しやすくていい。そんなことするの美術館だけ、美術館だけのうごき。
きっと、うごきって、場所できまる、とおもった。広いところへいけば、のびのび、自由にするだろうし、狭いところへいけば、うごきが自然と制限される。ならば、細長いところへいけば、どうなるか。
細長い通路をとおって、家につく、そういう土地のかたち。この細長い通路をとおるとき、どうするか、自然と、視線は家にむきそう。きっと、この家で、いちばん最初にみえる部分が、いちばん時間をかけて、みるところになる。なにをみるか、夜ならば灯りかな。
窓の灯りが、この家のかたちになる。細長い通路と窓だけが対峙する。そのとき、昼の家のかたちはない。窓の灯りに、なにをみるか、なにがみえるか、なにをみたいか、それがこの家のかちになる、とおもった。
やわらかくて、かたいもの、そんなものはあるはずがないのに、言葉ではいえてしまう。壁もそうかもしれない。かたくて動かないから、壁を困難や問題にたとえたりする。でも、困難や問題も、ずっと変化しないわけではないから、壁もどこかで、やわらかくて、動くもの、とひそかにおもっていたりする。
じっさいに、壁が動いたらたのしいな、忍者やしきじゃないけれど、壁が反転したら、べつのへやがあって、そこには金銀ざいほうとか、なんかあったりして、ぬけ道があったりして、そう動く壁って、いまの暮らしにないものがでてくるにちがいない、とおもえる。
だから、将来がわからないとき、壁は固定しないで、動かしてしまおうと考える。壁があつくなれば、ものがはいる家具になる。家具ならば、自由に動かしてもいい。ときにふさげば壁になる。動く壁は、空間も将来も、なにも固定しない。なにも固定しないから、やわらかい壁なのである。
あたり前のことのようにみえても、しらないところで、いろいろ工夫しているのがプロかな、とおもう。たとえば、おすしのにぎり方にも、しらないところで、とうぜん工夫があるだろうし、なにげない動作にすべていみがあり、目のまえにでてきたおすしは、同じようにみえてもみなちがうし、そのちがいが味にでるとおもう。
窓をつければ、よほどとなりがすぐ建物でなければ、陽ははいってくる。ただ窓って、なんのために必要かな、っておもう。べつになくてもいいか、と考えると、いや必要だとおもう。では、陽がはいれば、それでいいか、と。
さいきんは、窓があったら、空がみたいとおもう。きっと、空がみえると、室内が気持ちよく感じるのではないかな。なぜ?きっと、空と室内をくらべるから。もちろん、空のほうがキレイだけど、空とくらべることで、室内のちょっとよいところをさがしたり、あるいは、ちょっと片づけしてよくしたり、なんてことがおこるような気がする。気持ちいいものをみると、自分もなんかしたくなるものだとおもう。
晴れだけでなく、くもり、ゆきでも、またちがった空にであえば、こちらの気分もかわるし、室内もかわる。これは窓だけができる暮らしのなかのはなし。そのために、となりの屋根のうえに、窓いっぱいの空をつかまえた。
少ないことはいいことだ、少ないことは退屈だ、きっと両方ともあるのだとおもう。よく、少なくすることはいいことだと、ミニマリストにあこがれる人もおおいけれど、できやしない、好きなものがたくさんあるからしかたない。それに、少なくするのは余分なもので、大切なものは少なくしてはいけないし、むしろ、ふやしたい。だから、バランスなんだと、少なくできない自分をいつもなぐさめている。
できるだけ部材は少なくしたい、できれば壁から板だけがでているような階段にしたい、と最初はおもった。ただ、それだと、いくら鉄をつかってもできなかった。ならば最低限、ほそい丸棒で上下の板をつなけば、そこで計算して丸棒の本数をだした。
ほんとは、たての丸棒と丸棒をつなぐように、間にななめの丸棒が必要とされたけど、つくって、いざ現場に設置してから、なくても大丈夫、ない方がきれい、だとおもいとった。
計算してふやし、現物をみて少なくした。いいことと退屈の差は、ほんとうは紙一重で、そこのせまい巾での判断に、少ないはもはや関係がないこと。少ないかおおいかなんて、けっきょく、どうでもいいことなんだとおもった。
ないものは、自分でつくりたくなるもので、あるとき味噌がきれて、これってつくれないかな、とおもった。ただ、おもっただけで、まあそんなことを言っても、とおもいながら、いつもたべている味噌をそのときはまた買った。
ところがしばらくして、知人が自分で味噌をつくっているときいた。せっかくだから、体験してみたい、でもいつもの味噌になれ親しんでるからどうしよう、大概こういうとき、つくることにしてる。コーヒー豆もそう、自分で焙煎してみた、コーヒー好きとしては体験してみたい。
つくりたいのと、あと既製品はいやだ、というおもいがあり、つくれるのならば自分の手で、身の回りのものは、なんでもつくたい。漆のお椀も自分でデザインしてつくった。
ここにあう換気扇がなかった。せっかくの特注キッチンだから、換気扇もあわせたい。ただ、換気扇にはスポットライトを仕込みたいし、仕上げもゼブラ調の木目、形も、などとやってると、もう自分でデザインして、つくるしかない。それから、換気扇は自分でデザインしてつくることがスタンダードになった、味噌も。
リバーシブルとが、一粒で二度おいしいとか、反転できるとか、そういったものによわく、すき。効率がいいからとか、お得だからだけではなくて、ひとつのことに対して、二面性があることが面白いとおもう。
何でもひとつではないと普段からおもっている。答えはひとつではないとおもえば、いろいろなことができる楽しさがあるはず、そこが面白いとおもう。
コンパンクに暮らしたいとおもうときがある。十分な広さがとれないとき、でも暮らしは充実させたい。あと、とうぜん広さには限界があるけれど、人は欲ばりだったりして、あれもこれもとなる。
そんなとき、よくやることは壁を固定しないこと。壁を固定してしまうと、そこでひとつに限定されてしまう。壁をなくすこともできるが、最低限の壁が必要なときもある。壁を固定しないで可動させる。たったそれだけのことで、同じ場所でいろいろなことができるようになる。
壁を固定しないことで、とじこもっていた人の動きが流れでる。そのとき、流れでた先でいろいろな科学反応がおこればいいなとおもうし、それがその家だけでおこるイベントになるはず。きっとそれはその家の人にとって、よかったな、とおもうことにぜったいになる。
好きな形ってだれにでもあるでしょう。こどものころ、らくがき帳にずっと渦まき模様をかいていた記憶がある。なぜかいていたかは覚えていないけれども、大人になった今ではかきたいとも思わないから、きっとテレビかなにかでみて、それをマネしていたのかもしれない。
大人になったら、こんどは三角形をよくかく、屋根の形として。屋根の形はなんでもよくて、半円でも、フラットでもいいのに、三角形にしたくなる。木造の屋根としては、三角形が一番おさまりがいいから、それはそれでいいのだが、別に三角形でなくてもいいのだから、ちょっとそれにこだわる理由をかんがえるときもある。でも、自分のことながら、よくわからない。
ただ、2階の天井だけは意識して三角形にする。屋根の三角形の形を天井にも表して、いまいる場所は屋根に近い、すなわち、空に近いですよ、と思わせたい。
いまいる場所はどういうところなのかを形で表すことは大切で、とくに家はこころの安全地帯なようなものだから、自分がいたい場所といまいる場所を意識しないでも合わせることができるのが重要、安心感が生まれる。そのための形、そのための三角形ということです。
なるべく手ぶらで歩くのが好きで、携帯だけあればいい。どうしても携帯以外で必要なものがあるとき、秋から春にかけてはジャケットやコートがカバンがわりになる。
とにかくバラバラと何かを持ち歩くのが嫌い、なるべくまとめて少なくするか、目立たないようにして存在を消すか、別のものに置き換えて全く別の何かに見せたい。
空間の中でいつも心がけているのは、天井をスッキリさせること。天井には何も設けないか、最低限の小さな照明だけと決めている。頭の上にごちゃごちゃあると落ち着かないし、空間が煩雑にみえる。その分、壁にものが移動してくるが、壁には元々いろいろなもの、たとえば、家具などがくるから、うまく処理すれば目立たず、むしろ特徴にすることもできる。
壁に取り付ける予定だったものは、スピーカー、エアコンの吹き出し口、給気口、照明器具だった。それぞれバラバラの形や色をしている。そのまま取り付けては機能的かもしれないが、煩雑な壁がただ出現するだけ、何かできないか。
共通なのはすべて「穴」だということ。穴があればそこに仕込めばいい。穴がたくさんあっても、要素は壁面と穴だけになり、煩雑さを避けることができ、うまくみせれば、特徴的な壁になる。天井はスッキリ、壁には穴があるだけ、空間に手ぶらの良さが生まれる。
そもそも暮らしは煩雑さとのせめぎ合い、人間が煩雑な存在なのだから仕方がない。だから、その煩雑さをうまく使って、暮らし自体を面白くしたいといつも思う。
せまいより広い方がいいに決まってる。すべてを広くできれば一番いい。ただ、広さには限界がある。だから、どこを広くして、どこをせまくするかもデザインのうち。広いリビングがほしいとの話はよくあり、できるだけ、それにこたえるようにしている。広いという表現は曖昧だから、それをどうあつかうか。
領地の奪い合いではないけれど、極端に差がつけば広いと感じるのではないかと思った。広さには限界があり感覚的だから、数値で置き換えても意味がなく、比較の中で広さを感じてもらうのが一番わかりやすい。
リビングの横に広さを比較できる小さいものをつくった。それは本来は大きくしたいが、小さくても事足りるものがいいと思い、小さい浴室にした。浴室が小さい分、となりのリビングが広くなっているということが視覚的にも、また頭でも理解できれば「うちのリビングは広い」と感覚的に思う。
本来、広さは何かをするときに必要な分だけあればいい。その分だけ確保できれば、あとは感覚的な広さをつくり出す。そのときにもデザインが力になる。
2つの言葉「バラバラ」「つながりがない」はどちらかと言うと否定的な言葉、あまりいい意味では使われないし、言わない。それでも案外使ったり思ったりする機会は多いような気がする。
ただ、バラバラだけど、つながりがあれば、それはいいような気がする。しかし、まとまりがあっても、つながりがないと、それはダメなような気がする。
そうすると、「つながり」のありなしが大事ということになるし、もっと言えば「つながり」があれば、何らかのものにはなるかもしれない。何らかのものとはいいもの。
ならば、何とつながりをつくるか、と考えるだろう、普通は。それにはなぜか違和感がある。「つながり」自体はそこらじゅうにあるし、いくらでもつくることはできるから、意図的にやろうとする、ただそれは不自然な「つながり」になるような気がする、「つながり」があれば何でもいいという訳ではない。
そうではなくて、「つながり」自体が括弧になっているようなものをつくることが大事かなと思った。括弧になっているとは、「つながり」自体はすでに含まれていて、「つながり」自体を考える必要がない状態になっていること。むずかしいけれど、括弧つながりでないと本当の「つながり」はつくれないと思った。
出会うってたのしいなと思う。男女の話だけでなく、出会う人はどんな人でも、自分の知らないことを連れてきてくれると思っている。旧知の人でも、たとえば、街中でとつぜん出会ったりすると、その人のいままで知らなかった一面をみることになる。もちろん、良いことばかりとは限らないけれど、いつも同じ人、同じことのくり返しよりは、なんか可能性を感じることができて、いいなと思う。
だから、出会いをつくり出すことが場づくりの基本だと考えている、それは住宅も同じ。家族や同居人とも出会うような感じがあれば日々の暮らしにもメリハリや、よりたのしむ感じが生まれるでしょ。
それぞれの居場所はきちんとつくる、落ち着く場所を。その上で移動したとき、たとえば、階段の上り下りによって、お互いの姿がみえ隠れするような、オープンとクローズドのバランスのとり方をデザインしてみた。完全にひとりではなく、かといって、いつも一緒でもなく、その中間をたくさん用意し、ひとつの住宅のなかに毎日出会いがある。
そろそろもう必要がないかな、と思う間にあるアクリル板、あるのが普通だとない方が不自然な感じにもなる。アクリル板をなくすかわりに、なんかちがったことで、アクリル板があった方がよい、となることはないかな、と考えるときもある。
壁なんかない方がいいと思うとき、私は床もと思う。壁は人のこころのキョリ感をはかる言葉してつかわれるけれど、床も同じように考えれば、床はこころの上下か階層のキョリ感か。
昔、斜面地で斜めの床を計画しボツにはなったけれど、斜めの床で上下階がつながり階層なくなるなら、それは斜面地という場所を最大限にいかすことになり、また階層がある当たり前の計画に対するちがった提案にもなるから、それはそれでいいのではと思ったことがある。
ささやかな上下の階層をなくすこころみとして、2階の廊下の床の一部を透明ガラスにした。そこを通らないと2階の各部屋には入れないようにして、そのガラスの床は1階のダイニングテーブルの真上にある。
あきらかに上にはあるけれど、下からも丸見え、上下の関係性が微妙にゆがむことで、暮らしにちょっとだけ他にはない体験をはさむことができ、外より家の方が面白いとなれば、をつくってみた。
ものはこうして欲しいとうったえる。だから、何も知らなくても、押してしまうし、触ってしまうし、にぎってしまう。その形が何を意味するか、自然にわかる。TVリモコンがあれば、赤いボタンをとりあえず押す、それが電源のonoffたがら、まじまじと見なくてもそう思う。それをアフォーダンスという。ものが誘惑する、そうしてと。
小さな窓ひとつ、あとドアがあるだけの外壁面、色違いのラインがランダムに入る。そこに、うすい1m弱の出っ張りが端から端まである。
何か出っ張りがあれば、雨露しのげて、日差しをさえぎることができるから、まわりに何もなければ自然とその下にいく。大きな木の下へいくのと同じような感じかもしれない。
外壁の素材はよくある金属板、だから安い。そのままふつうに使えば、よくある住宅で馴染みがあるかもしれないが、そのような住宅があふれる中では金属板である意味がない。金属板でできる表現のうちで、もっとも住宅らしくない使い方をして、まわりの住宅とのちがいを出し、しかし、住宅とは人が集まるところとするならば、他の要素を重ね合わせて人を自然に集める。
見た目の住宅感を装飾してつくりだすのではなくて、人が自然と集まる場所としての住宅感をだしたかった。そうすることで、人と住宅のつながり、人ともののつながりが自然にでき、それが愛着にならないかな。
いつもいっしょでなくても、あそこにいるというのがわかれば、とくべつ意識しなくても、安心した気持ちでいられる。つながったり、離れたり、何ごとにも関係性はできる。人にたいしてだけでなく、でも人かな一番は。さっき宅急便が指定時間よりおくれてきた。大事な荷物だったから、でも今どこかにあるのかわからなかったので、来なかったらどうしよう、などと思ってしまった。
小さい家でも、いや小さい家だから工夫しないと、それぞれ自分だけの場所をつくって閉じこもるような気がした。だから、少しでいいからお互いに今いることがわかるような工夫をしてみた。
階段を上り下りするときにチラッとみえたり、室内の窓から顔がみえたり、半階ズラして同じ場所にいても自分の場所ができるように。
いつも、まったく壁がないときと壁だらけのときの間のどのあたりがちょうどよいのかをさぐってみる。それは、いろいろなつながりが壁の量にあらわれるからで、壁の量が暮らしをつくりだすと思えば、暮らしや空間を壁ではかることができる。壁のあるなしが気になるのは人でも空間でも同じだなぁ
となりは何気にみえてしまうから気になり、「隣の芝生は青い」ことになるのはよくあるでしょう。となりは良くみえるものと、わかっていてもなんか落ち着かない。ならば、一緒に何かをしてしまえば、「なんだあ」と相手をよく知ることができて、落ち着いたりする。
前に、兄妹クライアントの住宅を別々につくった。そのときはひとつの敷地を半分にして、となり同士に建てる計画、要望はまったくちがったが、全くつながりがない住宅を並列に建てるのは、なんかよくないと思った。そもそもつながりがある同士だから、住宅にも何かつながりをつくりたい。
ただ、もともとつながりがある同士だからゆえに、離れていることも大切、だとは思っていた。そこで、玄関にいたるアプローチだけを共有にした。となりの敷地までお互いにつかうことで、倍のはばの通路がとれ、そこはお互いの家族の遊び場にもなる。
要望がまったくちがったので、住宅の大きさも外形もちがうが、外壁の仕上げだけは同じにして、つながりがあるもの同士だと表現し、アプローチに面する窓もお互いにズラしながらも、窓越しにコミュニケーションできるようにした。
アプローチだけを一緒にすることで、別々だけどまったく別ではなく、かと言って、よくある建売住宅の並びのような同じさにはならない。このバランスならば、「隣の芝生は青い」ことにもならないでしょ。
遠くからみえる屋根が郷愁をさそうことは、たとえ実際に体験したことがなくても、なっとくしてしまう人がいると思う。むかし、合掌造りの集落を訪れたとき、だんだんとみえてきた三角屋根は、はじめてみるものでしたが、どこか前から知っているように感じた。なぜだかわからないけど、子供に家の絵を描かせると三角屋根になる。屋根にはそれだけイメージや感情とむすびついた何かがある。別の言い方をしたら、アイコンのようなもので、屋根は人の意識の一部に常にあるのかもしれない。
屋根の形にはいつも悩んでしまう。意識の一部にある屋根は誰でもイメージしやすいものとして常にスタンバイしているから、形はわかりやすく、イメージしやすいものがいい。ただ、それではアイコンとしては弱い。数あるアイコンとしての屋根がならぶ風景の中で自分のアイコンだとわからなくてはいけない、自分の家だから。
前につくった住宅は三方向から遠景としてみることができた。だから、三方向の全てでみえる屋根の形を変えた。屋根の形を考えるとき、まわりの屋根と比べることがある。それは高さや形がアイコンとしてふさわしいかどうかをみる場合、まわりのアイコンとちがいを出したいから。ただ、このときは比べる相手を三方向の屋根の形同士にした。
みる方向によって屋根の形がちがうことで、無意識に家と自分の位置関係を感じる。それは屋根の形を、単なるアイコンではなく、家と自分をもっと深く強くむすびつけるものにし、より愛着がわくようになる、家に、そして自分に。
たくさんの器、昔のものも今のものも、古染付や古九谷、民藝など1日でたくさんみることができた。器にくわしくはないけれど、器は大すき。ふだんの暮らしの中で何をつかうのか、どの器に盛ろうかな、どの器で飲もうかな、と迷うのがすき。
いろいろみて思ったのがつくる側とつかう側、みる側と言ってもいいかもしれないけれど、お互いにちがうところが気になる。つくる側にはつくる側の動機があり、つかう側にはつかう側の流儀がある。みる側はその両方を合わせ持つのかもしれない。
ときに、そのつくる側とつかう側のズレがおもしろい。つくる側の精緻さの具合いによって、生まれるものの良し悪しは決まるが、つかう側はその精緻さの具合いまで含めて迷う。
ふだんの暮らしにはその人の趣味趣向がでる。趣味趣向はその人の考えや想いのあらわれ。ただ、人は気分にも左右される。かっちりしたいときは精密なものを、おおらかにしたいときは緩いものを、というように精緻さの具合いまで趣味趣向の範疇になる。
そうすると、つかう側からみて、緩いもの意識してまじめにつくってほしくなる。そうなると余計おもしろい。今度はその緩さの具合いに良し悪しがあらわれてくる。ただ、つくる側は大変、緩さを精緻につくろうとするのだから。
どちらを向くかってけっこう大事だなと思いながら、ついよそ見をするクセが。よそ見はいつでも向けるからという余裕かもしれないけれど。
東西を電車と道に挟まれた場所ではどちらを向いても空いているが、どちらを向いても視線が気になる。元の家は暗くて寒い。ただ、南と北は建物が接近している。一般的には南に開くのがよくあるパターンだけれども、空いている方に開く方が将来的に周辺環境に左右されない。電車にちょっとだけ開く、道にちょっとだけ開く、あと空にちょっとだけ開く。
開くはそちらの方へ向くことだが、ちょっとだけ開きながら背を向けることもできる。そうすると案外、外から見てもわからない。ちょっとだけ開き背を向けるとは中から見て視界の半分までの窓をつくること。経験上、半分までは窓にしても中外どちらからも気にならない。よそ見もいいいけれど、きちんと向いた方が今までのことを一旦保留にできて、新しい機会が増えるような気がする。
ほとんど車に乗らないのに持ってはいるので、たまにバッテリーが上がらないように用もなく走り回る。2台とも小さい、軽トラと古いミニクーパー。やはりないと困るときがあるので、あと愛着。もともとあまり車に興味がなく、必要に応じて軽トラと、あのときなんかほしかったミニクーパー、すでに27年がたつ。小さくても全く乗り心地がちがう2台、ミニから軽トラに乗り換えると、軽トラが広くただ走りは鈍く感じる。やはり自分はミニの小ささと軽快な走りが大好きなんだと毎回気づく。
前は狭小住宅の依頼がけっこうあったので、小さいなりの工夫をしていた。小さいなりの工夫とは、効率よく機能的にして省スペース化を実現する、ことではなくて「小さい」から「大きい」にはできないことをして「大きい」よりも「小さい」方がいいだろうという顔をするということ。
小さいが故に実現できることを探し出せば、大小のちがいをいったん保留にできる。そうした上でクライアントの暮らしに合わせていけば、まだ見ぬ空間ができあがるかもしれない。
前につくった住宅はあまりに小さくて必要な広さの空間がとれない。どうしてもひとつの空間に複数の行為が重なる、例えば、朝に顔を洗う横で目玉焼きをつくり洗濯をしているとか。一見それは乱雑な空間のように感じるが、それがクライアントの朝の習慣で、細長い空間の中で順番にできたら、クライアントにとっては快適で、さらにその空間がまだ誰も見たことがない景色になる可能性を小さいが故に実現したことになる。
「小さい」ということは制約だが、それは「大きい」も同じで別の制約がある。大小はひとつの条件にすぎず、可能性に差はないとミニに乗るたびに思う。
着ている服が変わっただけで、たとえば安もののスーツでも、ふだん着ていない人が着るとよく見えたり、別人に見えたりする。中身が変わったわけではないけれど、中身まで別人のようで、案外本人も知らないうちにふるまいが変わる。そう自分もはじめて着物を着たときにそれを感じた、それは別の自分の発見にもなった。だから、たまにいつもとはちがうことを、それも他人から言われた方がいいかもしれない、自分の思いつきだとまた同じになるから。
ある時、前につくった住宅の屋根にあがるときがあった。たしかクライアントから何かを見てほしいとたのまれてのことだった。その住宅にはトップライトがあり、2階の床がガラス張りだから1階まで屋根から見える。トップライトの真下はダイニングテーブル、テーブルの上にはいろいろなものが置かれ、人が座ったり立ったり動いているのが見えた。いつもとはちがう見え方、日常では見ることができない風景、四角いトップライトが切り取るある家族の日常を記録映像風に見ているようだった。
設計しているときにはこのイメージはなく、むしろダイニングテーブルから見上げる空のイメージしかなかった。他からトップライト越しに室内を覗かれることはないので、見ることだけで見られることは考えていなかった。
ただ、この風景を見てからトップライト越しに見上げる空が身近に感じるようになった。うまくは言えないけど、一方通行の関係が双方向になったような。どんな風景でもこちらも見られていると思うと見せ方は変わるだろう。ならば見られることを身近に親近感を持って感じた方がいい。そうして生まれた別視点が新たなもの、例えば新たな自分、新たな暮らし、新たな空間を生みだすかもしれない。
昔のツァイスレンズをデジタルで使いたくてカメラを手に入れた。ものは久しぶり、最近は形がないものに、と思ったら最近マグカップが増えた、毎朝のコーヒーのために。ツァイスレンズは15年くらい前に手に入れたもの、ずっと防湿庫に閉じこもっていたけれど、最近写したいものができたので防湿庫の鍵を開けることにした。せっかくカメラを手に入れても飽きたらどうしようとも思ったが、それならば飽きたという経験ができるからいいかなと。
時々、自分ではやらないが面白そうなオーダーを受ける。前につくった住宅ではすべり台がほしいという。ずっとマンション暮らしだったから、2階建ての住宅に住んだことがなく、階段の上り下りが面倒くさい、だからすべり台とのこと。
そもそも広い住宅ではないから、すべり台のスペースがもったいないし、たぶんまちがいなく飽きると思ったので、クライアントに正直にやめた方がいいと言って思った、見方をかえれば、下りの時は1階と2階の区別はなくなり1階と2階はつながる。
結果この住宅は、そもそも2階にある個室に壁がなく戸で仕切るだけ、1階はワンルームのキッチン、ダイニング、リビングだったので、2階からみれば全てがつながって感じられ、逆に1階からみれば階段があることでちがいが出て壁がない2階のプライベート感が増し、個室に壁がないことがよりよくなる。
試しにやってみて飽きたらその時考えればいいかな、いくらでもやりようはある。飽きたらすべり台に下から本を並べれば、階段が図書室に、積読にはもってこい、読みたいところに座ればいい。
空気を感じる、というと何か人間関係や場の雰囲気など目に見えないものをわかることを指すけれど、それを建築に当てはめてみることもできそうな。
建物があると人がいて、その建物と人との間には空気が充満している。空気は見えないけれど、もし空気に色をつけるならば、建物の外の空気と中の空気はちがう気がする。
その中の空気のことをボリュームといえば、ちょっとふわふわなやわらかい透明なマシュマロを思わず想像してしまう。人のまわりにある透明なふわふわマシュマロをどのようにあつかえばいいか。壁を建てないと流れ出てしまうが、壁の建て方によってはふわふわマシュマロでもみたされない場所ができそうな、きっとそういう所は人がいなくてもいい場所か、ひとりになれる場所になるのかな。
空気とすると冷たい空気、温かい空気などそれはそれでなんか良し悪しがあって窮屈だが、マシュマロだと思えばなんか笑えてくる、甘そうで、甘いものに弱いから誘惑されそう。日曜だからとぼんやり妄想してみたら、案外ヒントになったりして。
キョリという言葉をすぐとなりの人にも、実際にはすぐとなりだから離れていないのに「心の距離がある」などとつかう。キョリというものは実際に目に見えること以上に多様な使われ方をする。
建築においてキョリは図面上の表現になる。その表現にさまざまな意図をのせるが、その意図はキョリと密接に関係しながら、読み取らないとすぐにはわからないときも多い。
例えば、壁を間に建てればお互いに遮断しているとわかるが、壁を建てたくないときは、間を離してキョリを取る。壁があれば目で見て遮断はわかるが、キョリを取ったときは他のものとのつながりも同時に見ないと遮断してるのか、つながりは保とうしているのか、どちらなのかがすぐにはわからない。表現がより複雑になる。
前につくった住宅で個室の壁を無くした。そのかわりに引戸で仕切り、個室状の空間を数珠つなぎにつなげた。各個室状の空間は大きさが微妙にちがう。誰がどの空間を使うかは大きさとお互いの離れ、すなわちキョリで決める。別に固定する必要もない。家族の成長に合わせてキョリも調整すれば良い。キョリの多様な使われ方を利用してみた。
緑に包まれたい、ただ見るだけでなく緑に抱かれるような感じで過ごしたい。緑の多い場所、山や森や林に行きたい時はきっとそう思うのでは、私はそう思う。ただ見るだけならば、ちょっと緑の多い場所、都市のちょっと大きな公園などでも、それではもの足りないから自分のとなりに緑があるくらいの近さがほしい。そうすると、自分と緑との間にどのくらいの空間があるといいのかなどと思ってしまう。
自分は建築の中にいるとしたら、建築と緑との間にどのくらいの空間があるのがいいのか。建築の中に緑があったとしても自分との間に空間はできる。ようするに緑との接近度、親密度を間にある空間の大きさ具合ではかろうということ。
緑は自然、建築は人工、自然と人工の対立は昔からある話で、くっきり分けるのではなく自然と人工を混ぜたような状態も考えられるが、いずれにせよそこには人がいて、人は本来自然の方のはずだが、人と自然という対立になる。そうするとややこしくなるので、間にある空間を扱って人と自然をどのようにつなげるかをめぐらしてみると、案外単純な話にならないかな。
家を建てると皆んな緑を置きたくなる。プランターを外に置く人、家の中に置く人、大小いろいろだけど何かしら緑を増やす。それを勝手に自然の中で暮らしていた名残りではないだろうかと思ってる。
人間は大昔自然の中にいて最小限の自分を囲う小屋や巣のような場所で暮らしていた。それは身を守るため、ほかの大部分は自然だった。それがいまでは逆転し大部分が自然ではない人工のものになった。それで大昔のような危険はなくなり身を守る必要はなくなったが、今度はあまりにも自然がなくなりすぎて、それでは身が休まらないと本能的に感じているのかもしれない。人工のもの、すなわち建築がわるいという訳ではないが、人間という生物が生きて行くには自然と人工のバランスがあり、都市部ではバランスがわるいということだろう。
敷地の中に10本の木を植えようと計画している。なぜ10本かは10家族が暮らす予定だから、ひと家族1本、それによって暮らしにいつも木をまとわせる。だから、建築もはじめから木をまとうので、木のまとわせ方が建築を決めていく。それは木の方から建築をみることになるので、建築がじゃまならば建築が木に合わせることになる。
なんか大変そうだな、はじめての打合せで感じたことを貴重なヒントだと思って気にとめてみた。これから建物をつくろう、住宅を建てようとする人はどこかいつも勇ましくみえる。新しいことをするとき、思い切るとき、ちがったことをするとき不安をかき消すためにちょっと背伸びしたくなる、そのぶん見栄えがよくなるのかな。
ときに住宅だと家族のつながり具合がプランに影響を与えるときがある。余程ちがいを感じないかぎりはそのようなことはしないが、できれば感じたことをうまく建築的な要素として取り込み、ちょっと他にはないものを提案したい。
先ほどの「なんか大変そうだな」は以前につくった住宅のご主人、こちらまで息がつまりそうな気になった。プレッシャーを抱え込む感じ、それだけ家族を大事にしようと。初回の提案からひとつの住宅の中に離れをつくった。簡単に言えば外部であるバルコニーを通ってしか行けない部屋。ただし、その部屋は内向きに窓があり開けるとリビングからもお互いの存在がわかる。ご主人がひとりになれて好きなときに家族とつながることができる、ご主人しだいのご主人だけの場所。
昔から部屋の並びには序列があり、一番奥の部屋ほどプライベートで閉鎖的につくられていて重要な場所だとされてきた。その序列はときに有効だが、ときに住宅の規模くらいの建築だと序列を誘導し助長してしまう。ワンルームにして序列を全くなくしてしまうこともできるが、奥の場所と手前の場所につながりをつくり出すことができれば、部屋の並びは残しつつ序列は排除できる。この方がより建築としては望ましい方へ行けるだろう。
高所恐怖症なのに高いところが好き、高層ビルでも屋内ならどれだけ高くても平気、むしろ行きたくなるのに、生身の身体がさらされているところは2階くらいの高さでも怖いから足場の上にはできるだけ行きたくないのに。ただ不思議なことにいまはないWTCの屋上は外に出れたが怖くなかった。あそこまで高いと地上から離れすぎているからかな。
2階くらいの高さでも屋上は貴重な外とつながる場所だと思い計画することがある。建設中何度も見に行くので慣れれば怖くない、むしろ地上とはちがう楽しみを発見する。見渡すと案外上空をうまく使っていない家ばかりなので、地上の庭よりプライバシーが守られて広大な空に近いから解放感があり快適な場所になる。
ただ、だんだんと使わなくなるときく。たぶんそれは屋上というスペースをとってあるだけだから、とくに使わなくてもいいから。強制的に使わせようとしてもダメだが、ないと困るというか、あるから良いとなるような工夫が必要。
前につくった家では屋上で遊ぶ姿が直下のリビングから見えるようにした。人が集まることができる場所、戯れる場所を分散することで家中いたるところがリビングのようになる。たまたま屋上が外のリビングになればいい。きっとこの「たまたま」な感覚が大事で強制はされないがあれば楽しめる場所になる。
曇り空がきらい、雨の日は雨音が癒やしてくれるのでまだいいけれど、朝起きて晴れているだけで一日中気分がよく、特にいまの季節の秋晴れは気候もいいので窓を開け放して過ごしたくなってしまう。
いま住んでいる家は築50年、10年前くらいにある住宅メーカーが建てた家を購入し手を入れた。道路から奥まりまわりは建物に囲まれて1階にあったキッチンとリビングは日当たりが悪かったので、1階と2階の部屋を逆転して、キッチンとリビングを2階にした。おかげで晴れの日は一日中陽が適度にあたるのでずっと快適に過ごしていられる。
まわりを建物に囲まれることは住宅地以外でも、例えば商店街などは道路側以外はとなりの建物が接近している。そういう場合でも上階にはオーナーが住む場合があり、時には住宅地よりも日当たりが悪い。
日当たりが悪いことを別の言い方で「眺望が悪い」「閉鎖的」とも言えると思う。南側に窓がなくても他の方位に窓があればあまり日当たりが悪いとは思わないだろう。だから一番避けたいことは眺望がなく閉鎖的であること。
空は地上の事情とは関係なしに平等な存在。そんな空とつなげることが眺望を得て開放的になれ、そして、いまいる地上の状況を相対的に良くしてくれる。上を見上げれば良こともある。
小さいものが時に魅力的で、その魅力はどこからくるのだろうか。1995年に新車で購入したミニクーパーにまだ乗っている。その小ささが特徴的ではじめて生産された時の技術は素晴らしいものだったらしい。
今でも変わらず新鮮なままの体験が運転している時の感覚で、この感覚が実に楽しい。きっとそれは小ささに由来しているのではないか。小さい車体にエンジンやギアボックスなどを収めるために様々な工夫をし無駄な物を排除しているから、実に運転感覚がシンプルでアナログ。なかなかアナログな道具が減ってきている時に私にとっては貴重なストレス解消アイテムだ。
小さい住宅はいくつかつくった。あまり大小にこだわりはないが、小さい住宅の方が工夫しがいがあるから結果的に楽しい設計になる。室内では何かの存在自体を根本から見直ししないと入り切らないから、新しいことを考えるきっかけにもなる。
それは屋外でも同じで、小さい住宅というのはそもそも敷地も小さいので、余すところなく土地を使い切りたい。以前つくった住宅では敷地境界線までの距離を少し余計にとり、建物の周り四周に敷地境界線までウッドデッキを敷いた。普通に建てると敷地境界線と建物との間に普段使われることがない場所ができてしまう。その場所を室内と連続させることにより、小さい住宅の室内を少しでも広く感じさせることができた。
結果的に小さい住宅の方が敷地全体を余すところなく使い切ることになった。それは小ささに由来している。小さいということを積極的に捉えると大きいものでは獲得できない魅力に出会える。
木は土の地面から生えている、だから何も見ないで木の絵を描いたら普通に地面には土を描くだろう。地面が土ではなかったらとは誰もイメージしない。だから、木と土の地面はセットであり、土の地面がないと木もないと思う。
突然木が目の前に現れた感じがした。そこは地面が砂利敷き、駐車場から続いた場所だった。砂利から木の幹だけが生えている、もっと言うと、どこかで伐採した丸太を持って来て、そこに立てて並べているようにしか見えなかった。
地面に土ではなく砂利を敷いたことで、地面と木がつながらなくなった、まるで別のもの同士、全く関係ないもの同士の組み合わせに見え、そうすると、木自体も木に見えなくなった。
今までの木とはこういうものという既成概念から抜け出た。そこで改めて木について考えると、例えば枝同士に渡して屋根をつくれば木は柱にしか見えなくなるなど、木が多様に変化しはじめるような気がした。
木が木に見えない、ならば木がある場が必ずしも屋外である必要がなくなる、あるいは、木がある場を屋内的な使い方をしても違和感がなくなる。既成概念を抜け出せれば、思いのままに木がある場を新たな空間にできる。
先日の何もしない庭をつくった話のつづき、今は何かする庭をつくろうとしている。そこには1本の木を植えたい。むしろ木を植えたいから庭をつくろうとしている、と書いてふと思った、室内に木を植えたらどうなるだろうか、いややめよう、それも面白いが今は収拾がつかなくなる。
ただ1本の木を植えるだけでは庭にならない。その木があるからどうなの、ないとどうなの、庭の形は、庭のとなりに何がくるのなど、木を植える庭があると暮らしの中で何が変わるの?
以前に1本の木を植えた庭つきの住宅をつくった。その木はクライアントのお父さんが亡くなった頃から自然に敷地内に生えてきたらしく、残したいということで移設して庭の真ん中に持ってきた。その木はキッチンからもリビングからも眺めることができる、それが要望だった。
木が見えるということが家族のつながりを無意識に象徴することになった。庭は木のためだけにあるようなものだが、その庭がないとプランは完結しない。何もしない庭も同じだが、庭はあることでつながりをつくり出す、つながりがなければ庭はいらない。
たくさんの小鳥が木にとまり茂った葉の中で鳴いているのを何度か見た。ちょっと怖い風景でもあり、どうしてその木にと思う。小鳥に好かれている木は他と何がちがうのかと観察してみてもよくわからない。たまたまその木だったのか?
人にも好かれる木と好かれない木があるのだろうか。都市部にいると木が少ないからそもそも木の好き嫌いを思うことがなく、樹種にかかわらず大括弧で木としか思わない。でも、たくさんの木がある場所に行ったら自然と人が集まってくる木はありそうな気がする。
たくさんある木のうち、ちょっと根元に腰掛けやすそうだな、寄りかかりやすそうだな、張り出した枝の下は木陰になっていて涼しそうだなとか、人とのつながり方がイメージできそうだと自然と集まりそう。そうすると、小鳥には小鳥なりの人間にはわからないつながり方をしているということか。
悩ましいのはいつも屋根のかたち、意外と屋根は目立つ。近くで見上げるとあまり見えないが、ちょっと離れると屋根がよく見える。なぜ目立つのか、たぶんそれは一番空に近いから、屋根の形がそのまま反転して空のかたちになるから。
2階の部屋は屋根のすぐ下にあるから、空に一番近い部屋となる。だから、それを表すために天井は屋根の裏の形をそのまま見せることが多い。無意識にここは空に一番近い場所だと、地面からは離れた場所だとわかってもらうために。
時たま天井をフラットにして空を意識させないようにする。そういう場合は2階にいながら地面を意識させたい時でだいたい広い庭か中庭がある。だから、狭小住宅の場合は必ずと言っていいほど2階の天井は屋根の裏を見せて、上へ空へ意識が抜けて少しでも広さを感じるようにする。
階段が好き、そう言うと階段に好き嫌いがあるのかと思われるかもしれないが、過去に1人だけ出会った階段好きに。妙に話が合い、その人はローマのスイペン階段が一番すきだと言っていた。私より若く学生だった彼の口から「スペイン階段」という言葉が出てきたのがちょっと意外で、でも納得してしまった。
よく階段に座りたくなる。2段分にかけて腰掛けるとちょうど椅子の高さと同じくらいになるから、階段を見ると休憩場所だと思うクセがある。スペイン階段もまさに腰掛けだ。
階段はいろいろなバリエーションをつくってきた。階段好きもあるが、階段はひとつの見せ場だといつも思う。階段を上がることは舞台に上がるようなもので、別の世界に運んでくれる。だから、上がった先には何かを用意したいし、上がっている途中も何かを感じさせたい。
別の場所へ行くために、時には休み、時には何かを感じ考え、時には下り、時には上がる。階段はいろいろと例えることができる。それはまるで何かのようでもあり、だから好きなのかな。
まず外と内というような分け方をします、家の話なのですが、案外他のことにも当てはまるかもです。領域というかテリトリーというか、自分たちの安全地帯をつくるように壁を建てて室内をつくります。
その室内に一緒にいる人たちは家族や仲間だから安心、でもお互いに隠したいことはあるからまた壁を建てて囲います。そうやって家はできます、古来より簡単なんです、家づくりは。
ただ、壁のバリエーションはいろいろです。それは人とのつながり方と同じです。何度も会い本当に親しい人から一度きりの人までいて、人によって会った時の感じがちがうようにです。
前に建てた住宅で壁が必要ありませんでした。1階は家族が集まるスペース、2階は各自のスペース、その2階に壁がありません。正確に言うと、引戸があるだけ、必要に応じて仕切るだけ、でもそれは壁ではないです。ご夫婦とお嬢さん2人のご家族、壁がなくてもいい暮らしができることをうらやましく思いながら設計してたな。
壁が必要だと、壁で囲うのが当たり前だと思うことで人のつながり方まで決めつけていたようです、壁はなくなった方が面白い空間ができるのに。
庭つき一戸建て、なんて言葉があるようには庭と家はセットだった、一昔前までは。今ではマンション暮らしの人も多いし、一戸建てを建てる人も庭などはじめからない場合も多い。マンションだから、敷地が狭いからと理由はあるだろうが、そもそも庭が必要ないのだろう。
前に建てた住宅は1階のリビングと同じ大きさの庭をつくった。その庭にはウッドデッキを全面に敷いて室内のリビングの床と同じ高さにした、リビングの延長として広く見せるためとリビングに光を取り入れるために。だから、はじめから庭に出ることは考えていなかった。それで十分で、それで豊かな生活になるだろうと思った。
その庭はリビングが十分に広くて日当たりが良ければなくてもよく、ただリビングとつながって見えるようにするためにウッドデッキを敷いた。そうしないとその空間が生きないから、生かすためにリビングの暮らしと関連づけて何もしない空間をつくった。
10年後その住宅に訪れるとウッドデッキは多少古びたが完成当時と変わらずに何もしない空間があった、まるでそこの空間だけ時間が止まっているように。きっとそう見えたのも何もしない空間だから、でもそれがよかったのである。何もしなくても庭はあった方が日々の生活が豊かになると、室内を見渡して、ご家族を見て思った。
空って当たり前のようにいつもあるけど、うまく使えていない。窓越しに空は見えるけど景色の一部、天気を気にするくらい。使うという表現がいいかどうかわからないが、空だけがみんなに平等に与えられた自然のような気がするから、うまくいかさないともったいないとつい思ってしまった。
自然には他にも緑、木や水辺の川、海、地形として山や谷などがあるけれど、場所によっては身近にはない。だけど空だけは見上げれば誰の上にもある。
建築で空をいかそうと天井をガラス張りにした家を見たことがある。誰でも一度は考えることだ。ただそうすると、夏は暑過ぎて、冬は凍るように寒く、人が住める場所ではない。
空を使うって案外むずかしい。それに空を使わなくても建築はできてしまう。だから誰も真剣には考えないのだろう。ちょっとは空を使ってみてはどうなの、と秋空が教えてくれたような気がする。
コールスローをつくろうとしたら冷蔵庫にマヨネーズがなかった。普段マヨネーズを使うのはあと玉子サンドをつくる時くらいで、それもあまりつくる訳てはないから大体使い切らずに消費期限を過ぎてしまう。キャベツの千切りを別の食べ方にしようかとも考えたが、
ふとマヨネーズをつくろうかと思った。
ネットで調べたら、材料は全て家にあった。卵、酢、オリーブオイル、塩を混ぜればいい。卵は平飼いのもの、取り入れる油はオーガニックエキストラバージンオリーブオイルかグラスフェッド無塩バターだけと決めている。少し高いが他のものは使わないのでかえって安上がりだ。
10分後、オリーブオイルを使うからちょっと苦めのゆるい出来立てのマヨネーズはそれだけで贅沢なソースに変身した。あと茹でた野菜やパンがあれば、ヨーロッパでは平日の立派なディナーだろう。
結局、もうマヨネーズは買わない。
その分、冷蔵庫のスペースは空くし、余計な出費もなくなり、贅沢な気分にもなる。ちょっとしたことである。
ないから足すのではなくても、自作しても、ものを減らしてミニマリストにしても、あるいは、余分なものを削ぎ落としてレスイズモアなミニマムデザインな建築にしても時につまらないことがある。きっとその原因は結果的に新しい価値を獲得していないからである。マヨネーズで言えば、自作するが市販のマヨネーズの代替品でしかない時である。
そうそう関係ないが一昨日見たリヒターの作品は当たり前のように巨匠の域であったが、
マヨネーズ工場のようにも見えた。
森の中で暮らすにはどうするかと考えながら設計をしているのだが、敷地が東京の区部でそれを実現するには広大な土地が必要になり無理だな、とぼんやり赤坂の迎賓館あたりを見下ろしながら考えていた。
森の中にいる感じを木の量で実現しようとすれば広大な土地が必要になる、当たり前である。では量でしか森を感じることはできないのか、探究のはじまりである。
1本の木で森を感じることはできないか。
普通に考えたら、というかそもそもおかしな問いの立て方である。1本の木が森になる、小学生の時に習ったはずである国語の時間に、木が2つあって「林」、木がたくさんあって「森」という漢字になると。まともな捉え方では解決しない。
ちょっと別視点から、その木は誰ものか。
自宅の玄関脇に1本のオリーブの木がある。最初は親指ほどの幹が今では私の太腿より大きい。毎年実をつけ、どんどん成長していくので自分で手入れをしている。また、2階のキッチンの窓からはお隣の木を見下ろすことができる。こちらは何の木だかはわからないが常緑で小鳥もよくやってきて鳴いているので、毎朝窓を開けてコーヒーを飲みながら眺めている。
どちらがより森にいる感じに近いか。
どちらも森にいる感じではないと言われればそうだが、強いて言えば、お隣の木を眺める方ではないかと思った。
そこで所有が鍵にならないかと考えた。
森を感じる時に自分のものであるかどうかは最初から頭にない。当たり前である、森の木と自分との間には何も関係性が無いから。関係性が無いから自分勝手に想いを抱き、そこに癒しを求めることができる。
長屋計画である。各長屋の中庭に1本の木を植える。ただし、その中庭は外部からアクセス可能であり木も共有である。長屋の数だけ木がある。10戸近く長屋があれば木もそれなりに目立つ、ただし、自分の木ではない。この感じは森に近いのではないか、そして、各長屋では木に接近した暮らしが実現できる。
日本では敷地の中で建築は北側に配置し、南側に庭を取るのが一般的である。その一番の理由は日当たりを確保することで、四季がある日本では季節により太陽高度が違い、その差が室内環境に大きく影響を与えるから、太陽高度の知識が無くても慣習的に建築の北側配置、南側に庭というパターンが昔から定着しているのだろう。ただ当然、人の暮らしや生活は太陽高度だけで決まる訳ではないから、このパターンとは違うことを考え比較する。その時にいつも思うのが建築は北、庭は南というパターンの説得力の強さである。それだけ人の暮らしや生活を慣習以外の視点で捉えることが難しいということである。だが同時にそこにデザインのヒントがあるとも思う。
"A Perspective Outside of Convention"
In Japan, it is common to place the building on the north side of the site and take the garden on the south side. The main reason for this is to ensure sufficient sunlight. In Japan, which has four seasons, the altitude of the sun varies depending on the season, and this difference greatly affects the indoor environment. The pattern of arranging on the north side and the garden on the south side seems to have been established for a long time. However, of course, people's lives and lifestyles are not determined only by the sun's altitude, so I will compare things that are different from this pattern. At that time, I always think about the strength of the persuasive power of the pattern that the architecture is in the north and the garden is in the south. This means that it is difficult to understand people's lifestyles and lifestyles from a perspective other than customs. But at the same time, I think there are design hints.
SNSはすべてのことを時系列で並列にしてしまう。それはSNSを見ているだけで勝手にすべての物事が時系列で相対化されることである。下から上に向かって相対化された物事が勝手に羅列されて積み上がっていく様は考えることを放棄させる。本来物事の相対化が考えることであり、SNSを見ていると何も考えていないのに考えているような錯覚に陥る。それはSNSを使って何かを仕掛ける側にとってはパラダイスなプラットフォームなのだが、享受する側にとっては頭の向きを自身で変えることができないように固定されているようなものだとSNSを眺めながら思った。
"While looking at SNS"
SNS makes everything chronological and parallel. It is that all things are relativized in chronological order just by looking at SNS. The way things that are relativized from the bottom to the top are arbitrarily listed and piled up make me abandon thinking. Originally, thinking is to relativize things, and when you look at SNS, you fall into the illusion that you are thinking even though you are not thinking about anything. Looking at SNS, I thought that it was a paradise platform for those who used SNS to set things up, but for those who enjoyed it, it was like being fixed so that they could not change the direction of their heads. .
住宅街の中で大きな敷地があると分割されるケースが多いが、分割せずに一塊の建築にしようとすると必ず奥の部分ができる。奥の部分とは道路から一番遠い場所である。一般的に建築の場合、道路側から順に奥へ向かってパブリックなスペースからプライベートなスペースへと変わっていく。だから、プライベートなスペースをつくりたい場合、奥にあるということだけでプライベートなスペースだと認識されてしまうので、建築としては特に何もする必要が無くなる。これは人の認識を利用する訳だが、大きな敷地の場合、それだけ建築の配置計画が重要であることを示している。
"Private space in the back"
In many cases, when there is a large site in a residential area, it is divided, but if you try to build a single building without dividing it, there will always be a back part. The back part is the farthest part from the road. Generally speaking, in the case of architecture, from the road side to the back, the public space changes to the private space. Therefore, if you want to create a private space, it will be recognized as a private space just because it is in the back, so there is no need to do anything in terms of architecture. This is based on human recognition, but in the case of a large site, it shows that the architectural layout plan is that much more important.
雑多な要素が日常には溢れる。それを入れる器として住宅を考えるならば、雑多な要素を物理的に見えなくしてしまうか、見えている要素を意識させなくするか、あるいは雑多な要素を美しいものに変換させるかが必要だろう。それらを端的に言うと、見えなくするには収納を多くする、意識させなくするにはより強い強度のもので雑多な要素を覆う、例えば、大屋根や高い天井で覆う、そして美しいものに変換するには雑多な要素を主役にして室内風景の一部あるいは室内風景を構成する一要素としてしまうことである。
このうち美しいものに変換することに興味があり、雑多な要素を主役にすることは外部における見え方である景観にも使える。雑多な要素を風景の一構成要素にする場合、雑多な要素の中での共通事項を取り出して構成するのが良く、その共通要素は形だと考えている。
"Composing shapes to create landscapes"
Miscellaneous elements overflow in everyday life. If we think of a house as a container for it, we must either make the miscellaneous elements physically invisible, make the visible elements invisible, or transform the miscellaneous elements into something beautiful. . To put it simply, to make it invisible, we need more storage, to make it invisible, we cover miscellaneous elements with something stronger and stronger, for example, cover it with a large roof or high ceiling, and transform it into something beautiful. To do so, it is necessary to make miscellaneous elements the leading role and make them a part of the interior scenery or an element that composes the interior scenery.
Of these, I am interested in transforming them into something beautiful, and making the miscellaneous elements the main characters can also be used for the landscape, which is how it looks on the outside. When using miscellaneous elements as a constituent element of a landscape, it is better to take out common items among the miscellaneous elements and compose them, and I think that the common element is the shape.
中庭を持つコートハウスを設計しようとすると、自然と中庭に何か意味を持たせてしまう。特に意味を持たせないでただ空間があるだけ、誰も利用できない、ただ眺めるだけで、空白地帯のように扱ってもいいのに空間を隅々まで無駄なく使おうとしてしまう。それはもしかすると空間の可能性に気づけなくする行為かもしれない。ただ空間があるだけ、それをどう使おうかと考えることも暮らしなのではないか。それこそその方が自分にとっての暮らしとは何なのかと考えるキッカケになり、自分の暮らしの可能性を広げることにもなるのではないかと考えるクライアントでありたい。
"There's just space"
When you try to design a courthouse with a courtyard, you naturally give the courtyard some meaning. It's just a space without any particular meaning, no one can use it, you can just look at it and treat it like a blank area, but you try to use every corner of the space without waste. It may be an act that makes us unaware of the possibilities of space. Just because there is space, isn't it part of life to think about how to use it? I would like to be a client who thinks that it will be an opportunity to think about what life is for him and that it will also expand the possibilities of his life.
建築空間を生み出す時に予め楽しいだろう暮らしを想定しないことで新たな建築の価値が生まれるだろうと考えた。あらゆる種類の建築空間を実際に見聞きしてくると、空間とその空間を使うことでの楽しさがリニアにつながり、それが建築全体の枠組みと化してしまう。この建築全体での枠組みが建築を見慣れたものにしてしまう。いわゆる既視感である。既視感には安心感はあるかもしれないが、新たな建築の価値は生まない。
"I don't expect a happy life"
I thought that a new architectural value would be created by not assuming an enjoyable life in advance when creating an architectural space. When you actually see and hear all kinds of architectural spaces, the space and the enjoyment of using that space are connected linearly, and it becomes the framework of the whole architecture. This framework of architecture as a whole makes the architecture familiar. This is the so-called déjà vu. A sense of déjà vu may provide a sense of security, but it does not create new architectural value.
外の空間の話。水平方向の連続した壁があり、それは木造であったりRC造であったりして、その壁同士の間に木がある、あるいは木と木の間に壁がある。そこには何も関係性は無く、あるのは壁の連続性と木の点在である。はじめから何かそこに意味付けをしたくなく、不規則に変化する木を利用し、木が成長していけば壁との関係が、さらには建築まで含めた関係性がその都度変わり、そこに住人のアクティビティも加わり、当初の思惑とは違うことになるだろう。コントロールすることでできる関係性がつくる空間は予想に反した驚きが生まれない。また、その壁が室内にも対となり現れる。室内から外へではなく、外から室内へとつなげることにより住空間にも木を利用した予想外のことが生まれる可能性がある。それは建築の存在に木が深く関わることを意味する。
"use wood"
Talk about the outside space. There are continuous horizontal walls, which may be wooden or reinforced concrete, with trees between them, or walls between trees. There is no relationship there, just the continuity of the walls and the scattering of trees. I didn't want to attach any meaning to it from the beginning, so I used a tree that changes irregularly. Residents' activities will also be added to this, and it will be different from the initial speculation. A space created by a relationship that can be controlled does not create unexpected surprises. The walls also appear in pairs in the room. By connecting the outside to the inside instead of the inside to the outside, there is a possibility that unexpected things will be born using wood in the living space. It means that trees are deeply involved in the existence of architecture.
外が連続して室内に至る、また逆に室内が連続して外に至る。外と室内の関係性をきっちりと分け隔てるのでななく混在させようとしたら、連続的にレイヤードさせようと考えるだろう。レイヤーというと垂直方向の層の積み重ねをイメージするが、水平方向にも適用できる。垂直方向ならば床をレイヤーとするが、水平方向ならばレイヤーは壁になる。壁が連続的に配されていく様である。水平方向のレイヤードは人をプライベート空間からパブリック空間までシームレスにかつ不連続につなげることを可能にする。さらに壁には様々な機能を組込むことが可能であり、エコや環境に配慮するために外と室内を分断することに対して外と室内の連続性を担保しつつエコや環境に配慮することができる。
"Horizontal Layered"
The outside reaches the interior continuously, and conversely, the interior reaches the exterior continuously. If you try to mix the relationship between the outside and the inside instead of separating them, you will probably think of layering them continuously. When we think of layers, we imagine stacking layers vertically, but they can also be applied horizontally. If it is vertical, the floor is the layer, but if it is horizontal, the layer is the wall. It seems that the walls are arranged continuously. Horizontal layering makes it possible to seamlessly and discontinuously connect people from private spaces to public spaces. In addition, it is possible to incorporate various functions into the wall, and in consideration of ecology and the environment, it is possible to separate the outside and the interior, while ensuring the continuity between the exterior and the interior while considering ecology and the environment. can be done.
外装だけを抜き出して考えてしまう。外装は外部環境と内部空間の間に一皮一枚だけ存在し、建築に一枚の布を被せるようなイメージである。その布はその時々で変化する。それはまるでTPOに合わせて変える服のようである。今回はどのような服を纏わせるかと考える。その服は装飾的で目立たせる場合もあるし、周辺環境に馴染ませようとする場合もあるし、馴染ませつつ違った形で映えようとする場合もある。いずれにせよ判断基準はその場所での相対的な立ち位置をどこにするかであり、その外装の存在が周囲に対して批評性を帯び、それがクライアントの所有欲を満たすことにつながることを目指し、引いてはそれがよくある住宅への批評性を帯びると考えている。
"Criticality of Exterior"
I pull out only the exterior and think about it. Exteriors exist as a single layer between the external environment and the internal space, giving the impression of covering a building with a single sheet of cloth. The cloth changes from time to time. It's like clothes that change according to TPO. Think about what kind of clothes to wear this time. Sometimes the clothes are decorative and stand out, sometimes they try to blend in with their surroundings, and sometimes they try to blend in and look different. In any case, the criterion for judging is where the relative standing position in the place is, and the existence of the exterior is critical of the surroundings, aiming to satisfy the client's desire to own. , and by extension I think it takes on a critique of ordinary housing.
コートハウスの中庭は室内と一体的に使おうと考える場合が多いかもしれない。屋外の緑、光や風といった自然を取り込むことを目的として積極的に活用しようとする。今までもいくつかコートハウスを手がけてきた。その際にクライアントからの要望もあったがどちらかというとこちら側からの提案でコートハウスにする場合が多かった。その場合、中庭は積極的に空白、無の場所にしようとした。大概ウッドデッキを室内と同じ床高さで中庭全面に敷いた。室内と同じように続く空間として表現し、しかし、何も目的を与えなかった。何も目的を与えないことでただ室内から眺めるだけの空間になる。同じ床高さであるだけに積極的な空白、無の場所となり、室内の煩雑になりがちな暮らしの対比として中和してくれる。住宅ではそのような場所が必要だと思う。
"The courtyard is a blank place"
In many cases, it may be thought that the courtyard of the courthouse should be used integrally with the interior. We try to actively use it for the purpose of incorporating nature such as outdoor greenery, light and wind. I have worked on several courthouses. At that time, there were requests from the client, but in many cases it was a proposal from our side to make it a court house. In that case, I actively tried to make the courtyard a blank, empty place. A wooden deck was generally laid on the entire courtyard at the same floor height as the room. It was expressed as a continuous space like the interior, but without giving it any purpose. By giving no purpose, it becomes a space that can only be viewed from inside the room. As the floor height is the same, it becomes a place of positive blankness and nothingness, and neutralizes it as a contrast to the life that tends to be complicated indoors. I think you need a place like that in your home.
コートハウスの中庭は外なのか中なのか。どちらにでもなり得る。関連付けをどうするかの問題である。では選択肢は外と中だけだろうか、と考えたくなる。
コートハウスは世界中で環境や地域を問わずに見られる形式であり、それだけコートハウスという形式には普遍性があるのだろう。しかし、皆同じという訳では無い。中庭の役割が環境や地域によって違う。中庭に何を求めるか、何を関連付けるかに依る。何を求め、何を関連付けか次第で外でも中でも無い、あるいは外でも中でもある、そのような二面性、両義性、あるいは渾然一体となった中庸な場所ができると考えてみた。
"What is the courtyard?"
Is the Courthouse courtyard outside or inside? It can be either. The problem is how to make the association. Then I want to wonder if the only options are outside and inside.
The courthouse is a form that can be seen all over the world regardless of the environment or region, and that is why the form of the courthouse has universality. However, they are not all the same. The role of the courtyard differs depending on the environment and region. Depends on what you want and what you associate with the courtyard. Depending on what you are looking for and what you associate with it, I thought that you could create a moderate place where there is such a duality, ambiguity, or a harmonious unity between outside and inside, or outside and inside.
2階建てや平屋でも屋根直下の部屋の天井は、屋根形状なりに仕上げることが多かった。それは天井の上はすぐ屋根で空があることを表現したかったのかもしれない。あるいは、その部屋が空に近い、空と隣り合わせということを暗示したかったのかもしれない。そうすることで空間に変化をつけ暮らしに影響を与えようという意図がわかる。
別の見方をすると、天井を屋根形状なりに仕上げることでその部屋が存在するための具体的な証拠を得ようとしたのかもしれない。生活空間と考えれば具体的な何かが欲しくなる。ならば、生活空間と考えなければ具体性は必要なくなり、抽象度を高めるために天井を屋根形状とは関係なくつくることことになるかもしれない。どちらにせよ用途が住宅ならば生活空間にはなる訳だから、天井を屋根形状とは関係なくつくり、抽象度を高めた生活空間を試みる方が面白そうだ。
"Creating a living space with a high degree of abstraction"
Even in two-story or one-story houses, the ceiling of the room directly under the roof was often finished according to the shape of the roof. It may be that he wanted to express that there is a roof right above the ceiling and there is a sky. Or maybe he wanted to imply that the room was close to the sky, next to it. By doing so, you can understand the intention to change the space and influence the living.
From another point of view, the ceiling may have been finished in the shape of a roof in an attempt to obtain concrete evidence for the existence of the room. If you think of it as a living space, you want something concrete. If so, if we don't think of it as a living space, there is no need for concreteness, and in order to raise the degree of abstraction, we may end up making the ceiling regardless of the shape of the roof. In any case, if the purpose is a residence, it will be a living space, so it seems more interesting to create a living space with a higher degree of abstraction by making the ceiling independent of the shape of the roof.
建築を配置した残りの場所を緑化することはよくある。まず建築の位置を決める場合がほとんどだろう。ただそれでは自然の中に住むようにはならない。自然の中に住むことをイメージした場合、森がありその中に建築を建てることを思い浮かべる。ならば、先に木を植える場所を決めてしまおう。それもその敷地の中でどこに植えればその場所が、森とは言わずとも、緑が溢れる自然の中にいるイメージになるかと考えてみる。そうすると一番環境が良い、一番目立つ、大概は建築を配置することになる場所になる。建築はその木を避ければいいだけと考える。
"Determine the location of the tree first"
Greening the rest of the building is common. In most cases, the location of the building will be determined first. But that doesn't make it possible to live in nature. When I imagine living in nature, I think of building a building in a forest. Then decide where to plant the tree first. Think about where you should plant them on the site to give the place an image of being in a natural environment full of greenery, not just a forest. Then, it will be the place with the best environment, the most conspicuous, and most likely where the architecture will be placed. I think architecture should just avoid that tree.
敷地の中のどこに建築を置くのかを考えてみる。緑を多くして自然の中にいるようにしたい。地面に近い所で暮らせるメリットは外の自然と対峙できて取り込むことができることである。ただ、敷地の中のどこに緑を配するかで敷地の中の場所に優劣ができる可能性がある。敷地の中での場所の優劣はそこでの暮らしや生活に直結しやすいから避けたい。なぜなら建築としてそこで何かをする必要が無くなるからである。
"Green place"
Think about where to place the building on the site. I want to be in nature with a lot of greenery. The advantage of living close to the ground is that you can confront and take in the nature outside. However, there is a possibility that the place in the site can be superior or inferior depending on where the greenery is arranged in the site. I want to avoid the superiority and inferiority of the place in the site because it is directly connected to the living and living there. This is because there is no need to do anything there as architecture.
二層の住宅を考えている。二階建てとは言わずに二層としているのは、一階、二階という表記には生活や暮らしや住空間に関する慣習が染み付いていて、それには良し悪しがあり、一度別視点から住宅を眺めたいからである。二層とすれば、一階は外部空間とのつながり、ニ階は屋根や空とのつながり、さらに一階とニ階のつながりなどの関係性から自由になれて、単に層の積み重ねとして見ることができる。そうして二層と考えると、なぜ二層なのか、二層の必要があるのか、何とも二層は中途半端だと思うようになった。二層にするのは単に積み重ねることができ、敷地の広さに対して要求していることが多いだけのように思える。もし要求していることを最小限にし、それでも二層が必要か、必要ならばなぜ二層かを考えることにした。
"A two-story building is half-finished"
I am thinking of building a two storey house. The reason why I say two stories instead of two stories is that the notation of first floor and second floor is ingrained in customs related to life, living and living space, and there are good and bad in it, and I want to see the house from a different point of view. It is from. If there are two floors, the first floor is connected to the outside space, the second floor is connected to the roof and the sky, and the connection between the first floor and the second floor can be freed from the relationship, and it can be viewed simply as a stack of layers. can be done. When I thought about the two layers, I came to think that the two layers were half-baked, as to why the two layers were necessary and why they were necessary. It seems that making two layers simply means that they can be stacked on top of each other, and that there are many demands on the size of the site. If I minimized what I was asking for, I decided to think about whether I still needed two layers, and if so, why two layers.
窓があるから建築だとわかる。窓が無ければ単なる建造物で人の存在もない。窓は人を表す。普通は窓によって人のアクティビティが想像でき、暮らしが垣間見える。だから、窓は人を表し、尚且つ、暮らしを表す。ところがデザインをする上では窓の存在を消したい。もっと正確に言うと、窓枠の存在を消し、壁に穴を開けたような感じを消し、窓と壁の境目を無くして窓は透明な壁として扱い、窓が持つ特別感を消したい。その時建築は暮らしから自由になれるような気がする。
"A window is a transparent wall"
You can tell it's architecture because it has windows. If there are no windows, it is just a building and there is no human existence. Windows represent people. Normally, people's activities can be imagined through windows, and people's lives can be glimpsed. Therefore, windows represent people, and they also represent lives. However, when designing, I want to eliminate the existence of windows. More precisely, I want to eliminate the presence of the window frame, eliminate the feeling of opening a hole in the wall, eliminate the border between the window and the wall, treat the window as a transparent wall, and eliminate the special feeling that the window has. At that time, I feel that architecture can be free from life.
窓は大きく取りたいと考える。特に南側の窓はできるだけ大きく取りたい。昔の日本家屋は南側の窓が他の方位の窓に比べて極端に大きかった。昨今では環境問題からCO2排出抑制を目指した省エネ基準により断熱性能が重視され窓は小さくなるばかりである。
断熱を考える時、窓が最大のウィークポイントである。壁や屋根の断熱性能は断熱材の性能や厚みでいくらでも対応できるが、窓はガラス自体の断熱性能が元々低くく極端に上げようがない。だから、窓を小さくしようとする。
断熱性能の向上だけを考えるならば、小さい窓は有効である。しかし、住環境の快適性は断熱性能だけで決まる訳ではなく、断熱性能から紐解けば暑さ寒さの体感が重要である。冬暖かくて夏は涼しい住環境を実現するには南側の窓を大きく取るしかない。
冬の南側の窓はストーブ並の熱源であり、この熱を室内に蓄積すればエネルギーを使わずに室内を暖かくすることができ、夏は日射を遮り日影をつくる工夫をすれば良い。窓を小さくすることは省エネとは逆の発想である。
"Small windows are not energy efficient"
I would like to make the windows bigger. In particular, I want to make the windows on the south side as large as possible. In old Japanese houses, windows on the south side were extremely large compared to windows on other directions. In recent years, due to environmental issues, energy-saving standards aimed at reducing CO2 emissions have emphasized insulation performance, and windows are becoming smaller.
When considering insulation, windows are the biggest weak point. The heat insulation performance of walls and roofs can be handled as much as you want depending on the performance and thickness of the insulation material, but the heat insulation performance of the glass itself is originally low and cannot be increased extremely. So try to make the windows smaller.
Small windows are effective if only the improvement of thermal insulation performance is considered. However, the comfort of the living environment is not determined only by the insulation performance. The only way to create a living environment that is warm in the winter and cool in the summer is to have large south-facing windows.
In winter, the windows on the south side are a heat source similar to that of a stove, and if this heat is accumulated in the room, it is possible to keep the room warm without using energy. Reducing the size of windows is the opposite of energy saving.
周辺の建築にスケールを合わせることで街並みに上手く建築を挿入するが、建築自体の寸法の取り方を変えることで周辺の建築とは違う空間を生み出そうと考えた。寸法の取り方とは距離を変えることであり、建築において距離は機能上からも大体この位というのが暗黙の了解である。例えば、部屋の端から端まで、天井の高さなどで、一般的に押さえるべき数値の範囲があるが必ずしもそれにする必要はない。その数値の部分をデザインしてみようと考えた。
"Design distance"
By matching the scale to the surrounding architecture, the architecture can be skillfully inserted into the townscape, but by changing the way the dimensions of the architecture itself are taken, we wanted to create a space that is different from the surrounding architecture. The way to take dimensions is to change the distance, and it is tacitly understood that the distance in architecture is about this degree from the functional point of view. For example, there is a range of numerical values that should generally be held, such as from one end of the room to the other, the height of the ceiling, etc., but it is not necessary. I decided to design the numerical part.
分節は周辺環境のスケールに合わせるためである。一塊が示すスケールは周辺にある建築のスケールと齟齬を起こす。だから、周辺の建築のスケールに合わせるように分節するのが常套手段で、その分節の仕方をデザインすることは良いとなる。ここには周辺のスケールと合わないことは駄目であり、スケールを合わせることは望ましいという前提がある。その前提を横展開してみる。スケールを合わせることは望ましいのだが、分節の仕方まで周辺の建築に合わせる必要はなく、周辺の建築ができない分節をしてみたらどうなるかをみてみる。もしかしたら、スケールを合わせることで街並みには素直に挿入されるがその場所だけの風景が生まれ、街並みに合いながら、街並みとは違う空間を持つという二面性を持ち合わせた建築が生まれ、上手く良い方向に街並みを改変できるかもしれない。
"Duality that changes the cityscape"
The segmentation is to match the scale of the surrounding environment. The scale indicated by the mass is inconsistent with the scale of the surrounding architecture. Therefore, it is common practice to segment a building to match the scale of the surrounding architecture, and it is good to design the way of segmentation. There is a premise here that it is not good if the scale does not match the surrounding scale, and that it is desirable to match the scale. Let's expand on that premise. It is desirable to match the scale, but it is not necessary to match the way of articulation to the surrounding architecture. Perhaps, by matching the scale, it will be inserted obediently into the townscape, but it will create a landscape that is unique to that place, and it will create an architecture that has the duality of having a space that is different from the townscape while matching the townscape. You may be able to change the cityscape in the direction.
分節の仕方を考えるのも面白い。大きな一塊の建築をつくる予定だったのが、10個に分節した塊になることになりそうな気配に。それはそれで分節の仕方によっては、地と図の関係のように、敷地の中に面白い形の外部空間をつくることも可能になり、また内部空間にも様々な外部空間とのつながりをつくることもできる。なかなか分節した塊をつくる経験もできないので、早速スタディしてみた。計算上は10個に分節できるが無理があるのがわかる。敷地は割合きれいな形をしていてプランニングは素直にできるから、何とか10個に分節してみたい。きっとそこが今回の計画で一番難しくて、一番面白いところだろう。
"Creating segmented masses"
It is also interesting to think about how to segment. I was planning to create a large block of architecture, but it seems that it will be a block divided into 10 pieces. Depending on how it is segmented, it is possible to create interesting external spaces within the site, like the relationship between ground and figure, and it is also possible to create connections between internal spaces and various external spaces. can. I didn't have the experience of making a segmented mass, so I immediately tried to study it. Although it can be segmented into 10 pieces in terms of calculation, it is understood that it is unreasonable. The site has a relatively clean shape and the planning can be straightforward, so I would like to somehow divide it into 10 pieces. This is probably the most difficult and most interesting part of this project.
住宅街の中で建築のスケールが突出しそうな時にどうするか、広い敷地に建築を建てようとすると、住宅街ならばどうしても周辺の建築とのスケールの違いが生まれ、街並みが乱れることになる。程度の問題かもしれないが、できれば既存の街並みを良くする方向で建築を街並みの中に挿入したい。そのような時は建築のヴォリュームを分節する。1つの建築だが、建築の部分によって高さを変えたり、屋根形状を変えたりして周辺の建築のスケールに合うようにし、一塊としての建築ではないように見せる。
"Fit scale to surroundings"
What to do when the scale of architecture is likely to protrude in a residential area, and if you try to build a building on a large site, you will inevitably create a difference in scale with the surrounding buildings in a residential area, and the cityscape will be disturbed. It may be a matter of degree, but if possible, I would like to insert architecture into the townscape in the direction of improving the existing townscape. In such a case, the architectural volume is segmented. Although it is one building, the height is changed depending on the building part, and the roof shape is changed to match the scale of the surrounding building, making it look like it is not a single building.
全体を通して一貫性がある方が良いされ、全体から部分へ、subjectからobjectへという流れで計画を立てることが多い、というかそのように教えられることが多かった。それは効率的であり、ストーリーも立てやすいから説得力と信頼を築きやすい。ただいつも思っていた、一番興味があるのはobjectで、さらに言うとobjectの中身ではなくobject同士のつながりだと。だから、subjectの存在を どうでも良いとまではいわないが、objectから subjectを見て考えるだけで済むと思う。
"from object to subject"
It is said that it is better to be consistent throughout, and we often plan from the whole to the parts, from the subject to the object, or rather, we were often taught that way. It is efficient and easy to create a story, so it is easy to build persuasiveness and trust. However, I always thought that what I was most interested in was objects, and even more so, the connections between objects, not the contents of objects. Therefore, I can't say that he doesn't care about the existence of the subject, but I think it's enough to think about the subject from the perspective of the object.
「どこにでもある」のに「ここにしかない」という分裂を意図してつくり出しスタバは特別感を生んでいるという記事を見た。「どこにでもある」は安心感、信頼感を生むが、それだけでは人はいずれ興味を無くすし飽きる。「ここにしかない」は希少性を生み、もしかしたら良い意味での反社会性を帯びて大事にされるかもしれないが、そこにしかない不便さは大多数の支持を得られないだろう。「どこにでもある」安心感と「ここにしかない」希少性は本来矛盾して両立はしないはずである。それが両立している背景を考えてみる。
「どこにでもある」は店舗数の多さで実現できる。「ここにしかない」は本来ならばここでしかできない体験が必要になるだろう。それにはイメージも伴うのかもしれない。元々スタバは「サードプレイス」がコンセプトだから「ここにしかない」という希少性を演出できていないと「サードプレイス」として認識されない。だから、スタバは「安心の希少性」というものを演出してつくり出していることになる。確かに「安心の希少性」はなかなかつくり出せないから差別化にはなり、店舗数も増やすことができるという好循環が生まる。
ただ「安心の希少性」は下手をすると中途半端な甘いものになる可能性があるような気がする。それは「安心の希少性」が両極端のものの組合せで中和され角が取れて丸くなったような状態だからである。しかし、この丸くなった状態が丁度良く、たくさんの人に支持される理由にもつながるとも言えるのだろう。
"Everywhere, only here"
I saw an article saying that Starbucks creates a sense of specialness by intentionally creating a division that "it's everywhere" but "it's only here". "Everywhere" creates a sense of security and trust, but people eventually lose interest and get bored with it. "Only here" creates a rarity, and maybe it's anti-social in a good sense, and it may be cherished, but the inconvenience that it's only there won't get the support of the majority.
"Everywhere" can be realized with a large number of stores. "Only here" would require an experience that can only be done here. Originally Starbucks is not recognized as a "third place" unless it can produce the rarity of "only here". Therefore, Starbucks is producing and creating something called "safe rarity".
However, I feel that "reliable rarity" may become a half-hearted sweetness if done poorly. This is because the "rarity of peace of mind" is neutralized by the combination of extremes, and the corners have been removed and rounded. However, it can be said that this rounded shape is just right and is also the reason why it is supported by many people.
あるものの存在を捉えようとする時、いくつかの関係性を見つけ出し、その関係性を二面性を持つように極端化してみる。あるものの存在はそのいくつかの極端化された関係性の重なりの部分に現れる。ただし、その重なりの部分はその時たまたまそうなっただけで、たまたま仮にその形になっているだけで、いつまた変化するかわからない。だから、時間の要素を含んだ関係性を見つけ出すことにより、時間的な猶予を獲得する。ただ、いくつかの関係性の重なりでは、あるものの存在をそのままズバリ完璧に全て捉えることは難しい。どちらかというと捉え方のイメージは、完璧には捉えることができないものをいくつかの関係性の重なりによりあぶり出す感じである。
"Duality that can be utilized in how to perceive"
When trying to grasp the existence of a certain thing, I find some relationships and try to make the relationships extreme so that they have two sides. The existence of a thing appears in the overlap of its extreme relations. However, the overlapping part just happened to be that way at that time, and it just happens to be in that shape, and you don't know when it will change again. Therefore, by finding a relationship that includes the element of time, we acquire time grace. However, due to the overlap of several relationships, it is difficult to completely capture the existence of a certain thing as it is. If anything, the image of how to capture it is a feeling of revealing something that cannot be captured perfectly by overlapping several relationships.
あるものの存在を捉えようとする時、これはこうで、あれはこれで、このようになっていると、仮にでもひとつのことに収束するように結論を出す。だから、建築として形になり、そして、その存在の在り方をズラしていくことで存在の捉え方自体をアップデートすることもできる。その際に矛盾しないように捉えようとするが、それをやめて矛盾をつくり出して矛盾したままで結論を出してみようと考えた。矛盾した状態は二面性であり、二面性がつくり出す建築空間の方がより社会性を帯び、人に受け入れられやすいのではないかと考えた。
"Duality is easy to accept"
When you try to grasp the existence of something, this is this, that is this, and that is this, and even if it's this way, you come to a conclusion to converge on one thing. Therefore, it takes shape as architecture, and by shifting its way of existence, it is also possible to update the way we perceive existence itself. At that time, I try to capture it so as not to contradict it, but I decided to stop doing that and create a contradiction and try to reach a conclusion while remaining contradictory. The contradictory state is duality, and I thought that the architectural space created by duality would be more social and more acceptable to people.
最近、二面性について考えており、二面性の捉え方は創作のヒントになるかもしれない。二面性は両極端のもの、あるいは矛盾するようなものが同時に存在している様だが、関係性として捉えてみると、関係性が極端化して1つには納まりきらない姿とも言えるかもしれない。両極端のもの、あるいは矛盾するものには各々のもの同士の関係性が存在しているが、その関係性自体はつながりがあり破綻しなければ安定して存在し、実際に現れるのはどちらか1つで済むはずである。ところが2つのものが同時に存在してしまうということは安定した関係性が破綻してしまった様、それが極端化であり、その極端化が起こった様である。
"How to Perceive Duality"
Recently, I've been thinking about duality, and how to capture duality may be a hint for creation. Dichotomy seems to exist at the same time as extremes or contradictions, but if you look at it as a relationship, it may be said that the relationship has become extreme and can not be contained in one. . There is a relationship between each of the extremes or contradictory things, but the relationship itself is connected and stable if it does not break down, and one of them actually appears. should be enough. However, the fact that two things exist at the same time is like a stable relationship has broken down, that is extreme, and it seems that extreme has occurred.
表と裏、明と暗、陽と陰、オンとオフなどの言葉が示すように両極端の状態があり、そのどちらに立つのか、あるいは2つの状態の間のどこに立つのか、真ん中ならば中庸だが、どららかの影響が強い状態で間に立つこともある。ただこれは両極端の状態が線状につながり音量の調整のように両極端をミックスしてどこかで1つの状態で立つということが前提の場合である。両極端のことが同時に成り立つ場合もあるだろう。二面性である。中庸と二面性は違う。中庸はミックスされた状態だが、二面性はミックスされていない。両極端、すなわち矛盾した状態が同時に成り立つ様には創作の種があるような気がする。
"Duality"
As the words front and back, light and dark, yang and yin, on and off indicate, there are two extreme states. , may stand in between with some strong influence. However, this is based on the premise that the two extreme states are linearly connected, and that the two extremes are mixed like volume adjustment and stand in one state somewhere. Both extremes can occur at the same time. It is two-faced. There is a difference between moderation and duality. Moderation is a mixed state, but duality is not. I feel that there is a seed of creation in the way that two extremes, that is, a contradictory state, is established at the same time.
建築は常にねじれていると思った。建築はスケールが大きいので目立ちやすく、単体での存在感が際立つ。しかし、同時にスケールが大きいので周りへ影響を与えるし、影響を与えられもして、周りとの関わりの中で存在することを余儀なくされる。単体で存在しながら周りとの関わりもあるので、建築を一概にこういう存在だと決めつけることは難しい。ただ、そこが建築の魅力のような気がする。建築を単体で見た時の完結的な形や空間に対して、印象はそこにいる人によって様々であり、建築の形や空間の存在だけに左右される訳ではない。この存在のねじれ加減をコントロールしてみるのも面白い。
"distortion"
I thought architecture was always twisted. The architecture is large in scale, so it stands out easily, and the presence of a single building stands out. However, at the same time, because the scale is large, it affects the surroundings, and it is also influenced by the surroundings, and it is forced to exist in the relationship with the surroundings. It is difficult to categorically define architecture as such because it exists on its own but also has a relationship with its surroundings. However, I feel that this is the charm of architecture. In contrast to the complete form and space when looking at a single building, the impression varies depending on the person who is there, and is not only influenced by the shape of the building or the existence of the space. It is also interesting to try to control the degree of twist of this existence.
ちょうどさっき、そう言えば昔やり残したことがあったと思い出した。別に今更と思えれば賢いのだろうけど、一度頭の中に広がると何とも引っ掛かる。今からこの歳からやることも可能だが重く感じる。でも今一度やろうとしてみると、何とも方法がわからない。想いだけは重層し塊としてあることには気づいたが、できれば手間を掛けずにできないかと考えてしまう。もし誰かが代わりにお膳立てしてくれたらなどと妄想してしまう。中途半端なモヤモヤがあるが、別の見方をすればここから新たなモチベーションをつくれたら、今後も同じようなことに活かせるなとも思った。
"Noticing Moyamoya"
Just now, speaking of which, I remembered that there was something left unfinished in the past. It's probably clever if you think it's too late, but once it spreads in your head, it's hard to get caught. It is possible to do it from this age, but it feels heavy. But when I try to do it again, I can't figure out how to do it. I noticed that my thoughts are multi-layered and lumped, but I wonder if it's possible to do it without taking much effort. I fantasize about what if someone else arranged it for me. There is a half-hearted feeling, but from a different point of view, I thought that if I could create new motivation from here, I could use it for similar things in the future.
関係性には2つあると思った。周辺環境と結びつこうとする関係性と自らの内あるものとの関係性である。建築は規模が大きいため周辺環境に与える影響は大きく、また規模が大きい故に周りから受ける影響も大きい。よって必然的に周りとの関係性が生まれてしまう。また建築自体の内側にも関係性はあり、その建築が生まれる前と後のつながりである。例えば建替えならば以前の建築との関係性である。ほとんどの場合、以前の建築とは断絶し新しい建築が生まれる。建替えにはそれ相応の理由があり、大概は以前の建築が使えないから建替えるので断絶が必然的に起こる。面白いもので新しい建築が生まれる時、必然的に周りとの関係性は生まれ、必然的に以前の建築とは断絶が起きる。この必然的という言葉には積極性は無いので、関係性が生まれたところでそれを活かす訳でも無く、断絶があったところでそれを回避しようとはしない。ただ中には必然的に生まれる周りとの関係性を利用し、断絶を回避しようとする動きもある。しかし、それは新しい建築が生まれるには断絶は避けられないので、そのための償いとして周りとの関係性を利用しようと捉えることもできる。ならば一番的確なことは断絶を起こさないで新しい建築をつくることではないかと考えた。
"Creating a new architecture that does not cause discontinuity"
I think there are two relationships. The relationship that tries to connect with the surrounding environment and the relationship with what is inside oneself. Since the scale of the building is large, it has a large impact on the surrounding environment. This inevitably creates a relationship. There is also a relationship within the architecture itself, a connection between before and after the architecture was born. For example, in the case of rebuilding, it is the relationship with the previous architecture. In most cases, new architecture is born, breaking away from the previous architecture. There is a reasonable reason for rebuilding, and in most cases it is rebuilding because the previous building cannot be used, so a discontinuity will inevitably occur. When interesting new architecture is born, it inevitably creates a relationship with the surroundings, and inevitably causes a discontinuity with the previous architecture. This word "inevitable" does not have positiveness, so even if a relationship is born, it will not be used, and if there is a discontinuity, it will not be avoided. However, there are also moves to avoid severance by taking advantage of the relationships that inevitably arise with those around them. However, since discontinuity is inevitable for the birth of new architecture, it can also be considered to use the relationship with the surroundings as compensation for that. Then, I thought that the most accurate thing would be to create a new architecture without causing a discontinuity.
たまたま偶然そこにいるだけ。人は突き詰めていくと今の居場所はたまたま偶然そこであっただけである。例えば隣であっても大差はない訳で、別に今の居場所でなくでも良い訳である。今の居場所には必然性が無いとしたら、強固な他者との関係性でつくられずっと変化することが無い建築に居ることに違和感がある。建築はたまたま偶然そうなっただけの瞬間を形にしただけで今の姿に必然性は無いものであれば良い。結局、街も似たようなもので今の姿に必然的が無ければ、もう少し柔軟に必要で無いものを配して、どうでもいいような間をつくり、もっと街がおおらかになり、街を構成する建築もおおらかにできると考えてみた。
"Generous City, Architecture"
I just happen to be there by chance. When it comes down to it, people just happened to be where they are now by chance. For example, it doesn't matter if it's next door, so it doesn't have to be where you are now. If there is no inevitability in the place where I am now, I feel a sense of incongruity in being in an architecture that has been created in a strong relationship with others and has never changed. Architecture should just be a form of a moment that happened by chance, and there is no inevitability in its current form. In the end, if the city is similar and there is no necessity in its current form, we will be a little more flexible in arranging things that are not necessary, creating spaces that do not matter, making the city more generous, and improving the city. I tried to think that the architecture that composes can also be generous.
建築計画学的に考えると敷地から一番効率の良いプランは導き出せる。特に建築の用途が集合住宅やテナントビルなどのように床面積の大小が事業計画に直結するものは特にそうである。規模や戸数だけで考えれば大体似たり寄ったりのプランに収束していく。ところが実際は設計者の数だけ違ったプランが存在するはずである。すなわちそれは規模や戸数の効率だけで建築は決まる訳ではないということであり、おそらく世の中にある建築で戸建て住宅の次に多いのは集合住宅かテナントビルだと思われるので、何かそこでできることを見つけてアウトプットすることは社会的に意義あることだと感じた瞬間があった。
"Efficiency alone is not enough"
From an architectural planning perspective, the most efficient plan can be derived from the site. This is especially the case when the size of the floor area is directly linked to the business plan, such as a collective housing or a tenant building. Considering only the scale and the number of units, it will converge to a plan that is roughly similar. However, in reality, there should be as many different plans as there are designers. In other words, it means that architecture is not determined only by the scale and efficiency of the number of units, and probably the next most common construction in the world after detached houses is collective housing or tenant buildings, so what can be done there. There was a moment when I felt that finding and outputting is socially meaningful.
どこにでもあるマンションの形式はどこでも大体一緒である。そもそもマンションは効率良く人口密度を上げるための形式だから、どこでも一緒になるのが当たり前である。むしろ、効率を廃した形式ではマンションにする意味が無い。この効率の果てのマンション形式は事業側のメリットと住む側のメリットの合致点のバランスが取りやすいから当たり前のように繰り返される。ただ効率で決まるような形式は否定したい気持ちが強いからこのマンション形式をなんとかしたいと思う。その時考えられる方法はこの形式の効率性に着目し、一旦非効率にし再構成するか、効率をさらに推し進めて別の何かを引き出すことで効率の枠から外れるか。前者はよくある方法で再構成したものを見かけるが元の形式の亜種でしかない場合が多い。可能性を感じるのは後者の方で効率というものそのものを結果的に解体して再構成することなのかもしれない。
"Out of bounds of efficiency"
The format of the condominiums that are everywhere is almost the same everywhere. In the first place, condominiums are a format for efficiently increasing population density, so it is natural for them to be together everywhere. Rather, there is no meaning in making it an apartment in a form that has lost efficiency. This condominium format, which is the end of efficiency, is repeated as a matter of course because it is easy to balance the points of coincidence between the merits of the business side and the merits of the living side. However, I have a strong desire to reject a format that is determined by efficiency, so I would like to do something about this apartment format. At that time, the method that can be considered is to focus on the efficiency of this form, and either make it inefficient and reconfigure it, or push the efficiency further and draw something else out of the framework of efficiency. The former can be seen reconstructed in a common way, but in many cases it is only a subspecies of the original format. What I feel is possible is the latter, which may result in the dismantling and reconstruction of efficiency itself.
この程度だろうという予想を越えるために、既存の関係を結びつきから解きほぐして、新たなに結び直す作業をしている。建築が建て替わる際のエネルギーは相当なものだといつも思う。0から構想するエネルギーもそうだが、現状を一旦0にするにも相当なエネルギーが必要だし、0から完成させるのにも相当なエネルギーがいる。また、元あった建築は決して単体で成り立っていた訳では無く、周辺との関係も簡単に切れないほど結びついている。だから、0にするために相当なエネルギーが必要なのだが、新たに完成後もただ新しくなっただけでは元の関係は戻らないどころかエネルギーが必要だった分、新旧でアンバランスになる。新しくするということは新しい結び目をつくることであり、それは今までの関係性の延長には無いものだと考えた。
"New Knot"
In order to exceed the expectation that it will be at this level, we are working to untie the existing relationships and reconnect them to new ones. I always think that the energy when a building is rebuilt is considerable. It's the same with the energy to envision from 0, but it takes a lot of energy to turn the current situation into 0, and it takes a lot of energy to complete it from 0. In addition, the original architecture never stood alone, and the relationship with the surroundings was so connected that it could not be easily cut off. Therefore, a considerable amount of energy is required to bring it to 0, but even if it is newly completed, simply renewing it will not restore the original relationship, and the energy required will create an imbalance between the old and the new. To renew means to create a new knot, and I thought that it was not an extension of the existing relationship.
この季節は雑草との闘いを何度かする。最近は諦めていて邪魔にならなければいいと思っている。庭木も剪定しないと伸び放題、特にオリーブの木は成長が早いから、今年も見事な実をたくさんつけた。全部集めて搾ったらいいオリーブオイルができそうだ。草木と戯れていると案外楽しくて、面倒くさいし暑いから滅多にやらないが、やると夢中になって一日中戯れていても苦にならないし、雑草取りや剪定をやった後はマジマジと見てしまう。ほんと緑は不思議なもので、雑草が伸び放題だが目に優しいというか、緑が溢れる姿はなんとなく好きで、そんなにきちんとする必要がないというかそのままがいいと思ってしまう。だからか草木に侵食されたような建築は好きなのだが、はじめからそのような建築をデザインしたいと思わない。緑や自然はコントロールできない存在で、建築はあくまでもその緑や自然に負ける存在で、デザインすることは自然をコントロールしようとする行為だから、唯一できるのは緑や自然から邪魔な存在だと虐げられるようにするくらいである。
"Existence oppressed by green"
This season has several battles with weeds. Lately, I've given up on it and hope it doesn't get in the way. If you don't prune the trees in your garden, they grow as much as you want, especially the olive trees, which grow very quickly, so they produced a lot of wonderful fruits this year as well. It looks like you can make good olive oil if you collect all of them and squeeze them. Playing with the plants is unexpectedly fun, but it's annoying and it's hot, so I rarely do it, but when I do, I can be absorbed in playing with it all day long, and after weeding and pruning, people stare at me seriously. . The greenery is really strange, and the weeds grow as much as you want, but it's easy on the eyes. Maybe that's why I like architecture that looks like it's been eroded by plants, but I don't want to design that kind of architecture from the beginning. Greenery and nature are entities that cannot be controlled, and architecture is an entity that is defeated by greenery and nature. Designing is an act of trying to control nature. It's about to.
普段意識していないことは見えないと考えると、その時々にはほとんどのことが見えていないと思った。目の前にあったとしても何気なくそれを見ているだけでは見えていない。見えていないものを見えるようにするには認識を変えるしかないのかもしれない。認識は自分が勝手につくり出したものであれば、自分で変えることができる。その時に人は知識が必要だと言い、本を読む必要があると言う。認識を変えるには知識を増やすしかないと言う。本を読む目的はアウトプットのためだと考えている。先にアウトプットが無く本を読んでいたら、増える知識に比例して満たされない想いだけが募るばかりであり、それで認識が変わることは無く、結局は見えないままである。
"To See the Unseen"
When I thought that I couldn't see things that I wasn't usually conscious of, I thought that most of the things I couldn't see at that time. Even if it's right in front of you, you can't see it if you just look at it casually. Perhaps the only way to make the invisible visible is to change our perception. Perceptions can be changed by oneself if they are created by oneself. Then people say they need knowledge, they say they need to read books. He says that the only way to change perceptions is to increase knowledge. I think the purpose of reading books is for output. If you read a book without any output first, only unsatisfied feelings will arise in proportion to your increasing knowledge, and your perception will not change, and in the end you will remain invisible.
自邸は実験の場だと学んだのはアアルトの夏の家で中庭の外壁を見た時である。様々なタイプのレンガが見本のように張られていた。もちろんただ張られているだけでなく、窓と合わせてコラージュされていた。それははじめからそのようなデザインを目指しそこに至ったように思える程印象的なものだった。でもたぶんクライアントの建築に対してはやらないだろう、やってもいいとは思うが。普段できないことをしようと考えるのはアイデアがあってもなかなか実現できないからかもしれないが、もしかしたら、そもそも普段のデザインとは違うところで考えていたのかもしれない。思いつく限りのレンガを並べて使い、一度使えば勝手知る材料になり、未知の部分に惑わされることが無くなるから、レンガ以外の素材へと意識が向くようになる。25年前、夏の家の中庭に立ち様々なタイプのレンガが張られた外壁を見ながら想っていたのは前年見たコルビュジエ のインドでの建築の荒々しい打放しの肌だった。
"Home for experimentation"
It was when I saw the outer courtyard of Aalto's summer house that I learned that my house was a place of experimentation. Various types of bricks were stretched like samples. Of course, it wasn't just stretched, it was collaged with the windows. It was so impressive that it seemed that he had aimed for such a design from the beginning and had arrived there. But I probably wouldn't do it for a client's architecture, although I think it's okay. The reason why I try to do things that I can't usually do may be because I can't easily realize even if I have an idea, but maybe I was thinking in a different way from my usual design in the first place. As many bricks as you can think of can be used side by side, and once you use them, they become familiar materials. Twenty-five years ago, standing in the courtyard of a summer house and looking at the outer wall covered with various types of bricks, what I thought was the rough, exposed skin of Le Corbusier's architecture in India that I had seen the previous year.
細かさを極めて繊細につくるのはいくらでもできてしまうが実際に繊細に見えるかどうかはまた別な話のような気がする。精巧に精緻に繊細に綺麗につくり込むことは技術だから熟練すればある程度のレベルのものはつくれる。ただ、そうやってつくり込んだものが実際に精巧で精緻で繊細で綺麗に見えるとは限らない。見え方は相対的な判断になるから精巧で精緻で繊細で綺麗に見えるようにするには、精巧で精緻で繊細で綺麗でない部分が必要になる。全てが精巧で精緻で繊細で綺麗なものは全てが精巧で精緻で繊細で綺麗では無い。
"Sophisticated, precise, delicate and beautiful"
It is possible to make the details extremely delicate, but I feel that whether or not it actually looks delicate is a different story. Since it is a skill to create something exquisitely, precisely, delicately and beautifully, if you are skilled, you can make something of a certain level. However, it is not always the case that things that are created in that way actually look elaborate, delicate, and beautiful. Since the appearance is a relative judgment, in order to make it look elaborate, delicate, delicate, and beautiful, it is necessary to have an elaborate, precise, delicate, and not beautiful part. Everything is elaborate, exquisite, delicate, and beautiful, but not everything is exquisite, exquisite, delicate, and beautiful.
よくデザイン案を考える時は極端化をする。極端化は最大限に逸脱することだが、何を極端化するかというと、当たり前だと考えられていることの影に隠れていて日の目を見ないがもしそれが表に出てきたら最大限の違和感を感じる、あるいは表に出ることが想像できないものである。表に出てきて尚且つ主役になるように、主役にするには最大限の違和感から逸脱する極端化が必要で、その一連の極端化が成り立つ説明がつくようにすることがデザインだと考えている。
"Departure from discomfort"
When I often think about design proposals, I go to extremes. Extremization is to deviate to the maximum extent, but what is extreme is that it is hidden in the shadow of what is taken for granted and does not see the light of day, but if it comes to the surface, it will be maximized. I can't imagine feeling uncomfortable or coming out. In order to appear on the surface and become the leading role, in order to make it the leading role, it is necessary to go to extremes that deviate from the maximum sense of incompatibility, and I believe that design is to provide an explanation that makes this series of extremes possible. ing.
なぜそうなるのだろうか、と改めて疑問に思えるか。当たり前のことは実は見えていない。見えていないから疑問にも思わない。見えていないというのはもしかしたら知識の無さか、鈍いのか、考えたくないのか。改めて疑問に思うと、人はわからないことを埋めたくなる、理解したくなる。事実が先にあり、その事実を自分自身に説明し納得するために仮説を考える。この説明するための仮説が創造であり、創造とはこうして生まれるのではないかと今日読んだ本に書いてあった。
"Hypothesis to explain"
Do you ever wonder why this is the case? I can't really see the obvious. I can't see it, so I don't doubt it. If you can't see it, maybe it's lack of knowledge, dullness, or you don't want to think about it. Asking questions again makes people want to fill in what they don't understand and want to understand. Facts come first, and we come up with hypotheses to explain and convince ourselves of the facts. The hypothesis to explain this is creation, and the book I read today says that creation is born in this way.
土地が広いから緑化をする必要があり、そもそも自然の中で暮らしたいという希望だから、緑化面積を満たすために隙間を緑で埋めるのでなく、もっと積極的に緑と一体になった建築を考えてみる。が、しかし、何事にも限界はあり、木々に埋もれるような建築は現実的にはできない。今考えているのは最小限の緑で自然の中に建つような建築はできないかということである。言い換えれば、緑は少ないがその緑によって建築が決まっているように見えないか。そうすれば、自然の中に建つ建築と同等のものになり、限定的かもしれないが自然の中で暮す感じをつくることができるかもしれないと仮説を立ててみた。
"Architecture in Nature"
Since the land is large, it is necessary to plant trees, and in the first place, people want to live in nature. View. However, there is a limit to everything, and it is not realistic to build a building that is buried under trees. What I'm thinking about now is whether it's possible to create a building that stands in the midst of nature with minimal greenery. In other words, although there is little greenery, it seems that the architecture is determined by the greenery. I hypothesized that if I did that, it would be equivalent to architecture built in nature, and I might be able to create a feeling of living in nature, albeit in a limited way.
周辺環境のスケールに合わせなければならないと考えてしまう。街並みということを意識すると突出したスケールは悪だと考えてしまう。ただ東京だと至る所で突出したスケールが現れる。せめて住宅街ではスケールを周辺環境と合わせることで住環境が少しでも良くなるように貢献しようと考えてしまう。確かに、街並みのスケールから逸脱している建築は良くも悪くも目立つし、周辺環境に貢献しようと意識してデザインされた建築は少ないから、突出したスケールの建築に好印象がない。ただ、周辺環境に貢献することを意識してデザインすれば突出したスケールの建築にも好印象を抱くかもしれない。スケールとは関係無しにデザインの良し悪しがある、そこに注視したい。
"Design without Scale"
You think you have to match the scale of the surrounding environment. If you are conscious of the cityscape, you will think that the projecting scale is evil. However, in Tokyo, a prominent scale appears everywhere. At least in the residential area, I think that I will contribute to improving the living environment by matching the scale with the surrounding environment. Certainly, buildings that deviate from the scale of the townscape stand out for better or worse, and there are few buildings that are designed with the intention of contributing to the surrounding environment, so buildings with a prominent scale do not give a good impression. However, if you are conscious of contributing to the surrounding environment when designing, you may have a good impression of the outstanding scale of the building. I would like to focus on the good and bad of design regardless of scale.
建築は一度つくれば動かないし、大きいし、ずっと残り続けるから、たまたま偶然そうなっただけでいつまた価値が変化してしまうかわからない様では困る。だから、建築には時間という尺度を持ち込み、時間を建築の価値に加える必要がある。時間をどのように扱い建築の価値として加えるかには様々な方法が思い浮かぶが、時間と関連する記憶を建築に刻みたいと考えた。記憶は建築と人の相対的な関係性から生まれるもので、それを建築に刻むためには記憶を形の情報を持ったものに変換する必要がある。この変換の作業が建築と人の関係性の極端化につながり、関係性の曖昧な部分が排除され、時間を取り込みつつ自律的な建築を生む手助けになる。
"Capturing Time"
Once a building is built, it does not move, is large, and will remain forever. Therefore, it is necessary to bring the measure of time into architecture and add time to the value of architecture. Various methods come to mind as to how to handle time and add value to architecture, but I wanted to engrave memories related to time into architecture. Memory is born from the relative relationship between architecture and people, and in order to engrave it in architecture, it is necessary to convert memory into something with shape information. This work of conversion leads to the extremeness of the relationship between architecture and people, eliminates the ambiguous part of the relationship, and helps to create an autonomous architecture while taking in time.
結果の全ては関係性の重なりの果て偶然そうなっただけのものであり、それ自体はすぐまた変化するかもしれない可能性があるが、結果として現れた時点ではとても強い強度を持ち自律している。建築とはそういうものだと仮定してみると、結果に執着すること無く、関係性に焦点をあて構築するというプロセスを重視したくなる。それはとても自然な流れだが、関係性をそのまま当てはめて重なりをつくったところで他律的な建築の域から脱することはできない。関係性をそのままではなく、極端化して関係性から曖昧な部分を排除することにより、他律か抱える相対性が薄れ、自律に欠かせない絶対性が増す。そうすることで他律的な関係性の重なりの向こうに自律的な建築が見える。
"It just happened to happen"
All of the results are just a coincidence at the end of the overlapping relationships and may change again soon, but at the time they appear as a result they are very strong and autonomous. There is. Assuming that architecture is such a thing, we want to emphasize the process of building with a focus on relationships without being obsessed with the results. It's a very natural process, but you can't get out of the heteronomous architecture by applying the relationships as they are and creating overlaps. By excluding the ambiguous part from the relationship by making it extreme rather than keeping the relationship as it is, the relativeity of heteronomy is diminished, and the absoluteness that is indispensable for autonomy increases. By doing so, autonomous architecture can be seen beyond the overlap of heteronomous relationships.
既存の繰り返しから新しいものが生まれるだろうか。いくら積み重ねても今までの考え方ややり方からは新しいものは生まれないような気がする。やり方を熟練させたり、効率を上げて早くできるようになり誰にもできない成果を上げることができてもそれは新しくない。新しいものははじめから新しいのだと思う。だから、新しいものは最初違和感があるし、その違和感故に消えてしまう。本当に新しいものとして実感され残るものはギリギリ受け入れることができるくらいの違和感にコントロールされたものであり、それははじめから新しくて徐々にコントロールされ、ギリギリ受け入れられて残りながら新しいと認識されていくと仮定してみた。そうなると、はじめから新しさが必要で、それは必ず既存からの逸脱になり、それも予定調和的な逸脱では新しくないので、研究者など既存のつながりから思考することが必要な場合、新しさを求めるのは困難になるかもしれない。
"New"
Will new things be born from existing repetitions? No matter how much I accumulate, I feel that new things will not be born from the way of thinking and methods so far. It's not new if you can master the method, improve efficiency and do it faster, and achieve results that no one else can. I think new things are new from the beginning. Therefore, new things have a sense of incongruity at first, and they disappear because of the sense of incongruity. It is assumed that what is truly new and remains is controlled to a sense of discomfort that can be accepted at the last minute, and that it is new and gradually controlled from the beginning, and that it is accepted at the last minute and is recognized as new while remaining. I tried it. In that case, newness is necessary from the beginning, and it will always be a deviation from the existing, and it is not new with a planned harmonious deviation, so if it is necessary to think from the existing connection such as a researcher, seek newness. May be difficult.
たくさんの他律的な関係性が重なり合うところに自律した建築は成り立つが他律的な関係性から生まれる自律は偶然の姿であり、いつまた変化するかわからないと考えた。その時、その場所でしか偶然成立せず、いつまた変化してしまうかわからない自律的建築は本来望まれないものである。たくさんの他律的な関係性を受け入れて、それによって成り立つ自律的建築は望まれるが、いつまた変化してしまうかわからないという時間を担保にできない様は建築では困る。だから、時間における関係性をつくり出し関係性の重なりの中に加えるしかない。関係性に時制は無いので、いくらでも関係性をつくり出すことはできる。
"Adding relationships in time"
Autonomous architecture is established where many heteronomous relationships overlap, but the autonomy created by heteronomous relationships is a coincidence, and I thought that I would not know when it would change again. At that time, an autonomous architecture that happens only in that place and does not know when it will change again is not originally desired. It is desirable to have an autonomous architecture that accepts a lot of heteronomous relationships and is built on it, but it is a problem in architecture if we cannot secure the time when we do not know when it will change again. Therefore, there is no choice but to create relationships in time and add them to the overlap of relationships. There is no tense in relationships, so you can create as many relationships as you like.
たくさんの関係性が重なり合うところに自律した建築が成り立つのではないかと考えた。関係性から生まれる建築は他律的である。関係性はどこまでいっても切ることができないとするならば、他律の中に自律が存在するしかないし、他律の中でしか自律は存在できない。自律だけ存在しているように見えるのは、関係性がフラットでは無く主従があり、主にだけスポットライトを当てているからである。重なり合う他律的な関係性の全体にスポットライトを当てれば他律の中に自律が見える。そして、他律的な関係性から生まれる自律は偶然の姿であり、いつまた変化するかわからない。その時、その場所でしか成立しないのが自律的なものとなる。そう考えるとオブジェクト指向実在論のように複数の自律が同時に成り立つことが考えられだが、オブジェクト指向実在論の場合は関係性が二次的なものだから、他律の中に存在する自律的なものとは違う。だから、他律的な関係性をどのようにつくり出すかが自律的な建築のデザインになる。その時一番に考慮するべき他律的な関係性となる素材は時間だと仮定してみようと思っている。
"Autonomy can be seen in heteronomy"
I thought that an autonomous architecture would be established where many relationships overlap. Architecture born from relationships is heteronomous. If the relationship cannot be broken no matter how far, autonomy can only exist in heteronomy, and autonomy can exist only in heteronomy. It seems that only autonomy exists because the relationship is not flat, but there is a master-slave, and only the main spotlight is on. If you shine a spotlight on the whole of overlapping heteronomous relationships, you can see autonomy in the heteronomy. And the autonomy that arises from heteronomous relationships is a coincidence, and we do not know when it will change again. At that time, it becomes autonomous that it is established only in that place. If you think so, it is conceivable that multiple autonomy can be established at the same time like the object-oriented realism, but in the case of the object-oriented realism, the relationship is secondary, so the autonomous thing that exists in other laws. Is different. Therefore, how to create heteronomous relationships becomes an autonomous architectural design. At that time, I will assume that time is the material that has the heteronomous relationship that should be considered first.
リノベーションは主に内部空間について行われる手法であり、外観には関しては従前の姿をそのまま引き継ぐか、補完するデザインで終わるか、全く新しい仕上げでパッケージングし直すかである。もしリノベーションの手法を新築に応用した場合は外観は時の流れをどのように継続すれば良いのだろうか。外観はそもそも周りとの環境の中で決まる部分もある。ただ、個人的な様も都市の色になり得るので、むしろ個人的なことを時の流れにのせてつなげてみたいと考えた。建替えとなると全く新しい仕上げでパッケージングし直すことになるがそれでは断絶するだけであり、時をつなげるには建替え後の外観が従前とのつながりで決定されれば良い。つなげるために従前の建築から何を抽出するか。スクラップアンドビルドにおいて他者になるものは何だろうか。
"Scrap and Build Others"
Renovation is a technique that is mainly performed on the interior space, and in terms of appearance, it is either to inherit the previous appearance, to end with a complementary design, or to repackage with a completely new finish. If the renovation method is applied to new construction, how should the appearance continue the passage of time? In the first place, the appearance is determined by the environment with the surroundings. However, personality can also be the color of the city, so I wanted to connect personal things with the passage of time. When it comes to rebuilding, it will be repackaged with a completely new finish, but that will only break it, and in order to connect the time, the appearance after rebuilding should be determined by the connection with the past. What to extract from traditional architecture to connect. What makes you another in scrap and build?
建替えによるその場所での時の流れの断絶は避けたいと考えた場合、何を引き継げばいいのか。記憶は時の流れが断絶した状態のものであり、時の流れをつなげたい場合には使えないかもしれない。建替えはそれまでの建築の必要性が無くなったからなので引き継ぐものは何も無いと思ったが、もしあるとしたらならば何があるかと考えみる。元々の建築のプランは少なくとも完成時にはその場所での最適解のひとつではあったとみなしても良いのではないかとすると、プランの何かは使えるかもしれないし、元々のプランを有効活用することは効率が良い。ただし、使えるのはプランの機能に関する以外のことだろう。機能に関しては時の流れによる変化があり、現実的に今取り入れるのは難しい。よく考えたらこれはリノベーションの手法であり、リノベーションはむしろ断絶することの方が不可能に近く、強制的に時の流れのつながりができる。
"Renovation that connects time"
What should I take over if I want to avoid the disruption of the passage of time at that location due to rebuilding? Memories are in a state where the flow of time is cut off, and may not be usable when you want to connect the flow of time. I thought that there was nothing to take over because the rebuilding was because the need for construction had disappeared, but if there was, I wondered what it would be. Given that the original architectural plan could be considered to have been one of the optimal solutions for the location, at least when it was completed, something in the plan could be used and it would be efficient to make good use of the original plan. Is good. However, you can use it for anything other than the features of the plan. As for the function, it is difficult to incorporate it now because it changes with the passage of time. If you think about it, this is a method of renovation, and it is almost impossible to break the renovation, and you can forcibly connect the passage of time.
緑も輪郭があるようで無い、特定の輪郭を持たない。たまたま偶然にそうなっただけ、またいつ変化するかわからない。特定の輪郭を持たない様を建築として表現するには密度や濃淡の差異を利用する。特定の輪郭を持たない建築は特定の輪郭を持たない緑と親和性がある。特定の輪郭を持たない建築をつくるために記憶を利用すれば、記憶と緑がつながる。
"Connecting memory and green"
Green also doesn't seem to have a contour, it doesn't have a specific contour. It just happened to happen, and I don't know when it will change. The difference in density and shade is used to express the appearance without a specific contour as an architecture. Architecture without a specific contour has an affinity for green without a specific contour. If you use memory to create an architecture that does not have a specific contour, memory and green are connected.
記憶にも密度があるかもしれないと思った。建築には指標によって様々な密度が存在し数値で表すことができる。実際には記憶はイメージで実体が無いから数値化はできないかもしれないが、ある特定の記憶だけが濃くてあとは薄い場合があるだろう。だから記憶を濃淡では表すことができる。濃淡も密度の一種である。逆に建築を濃淡で表すことはできるだろうか。何についての濃淡かによるが建築を平面絵画的に捉えれば可能である。平面絵画は奥行きに濃淡をつける。それは西洋絵画も日本画も同じである。建築を平面絵画的に捉えるにはヴォリュームを消す必要があり、そのためにはヴォリュームの輪郭を消去する必要があるだろう。輪郭を消去するには2通りあり、そもそも輪郭線を描かないか、特定の輪郭を持たないようにする。建築に応用するならば、実体としてオブジェクトは存在してしまうので、特定の輪郭を持たないようにすることだろう。特定の輪郭を持たないためにはオブジェクトの密度の疎密の差異を利用する。すなわちそれが濃淡でもある。だから、オブジェクトの密度の疎密をつくる出すものを元として建築を表現することができる。
"Shadow creates architecture"
I thought there might be a density in my memory. There are various densities in architecture depending on the index, and they can be expressed numerically. In reality, memory is an image and has no substance, so it may not be possible to quantify it, but there may be cases where only a specific memory is strong and the rest is light. Therefore, the memory can be expressed in shades. Shading is also a type of density. On the contrary, is it possible to express architecture in shades? It depends on what the shade is, but it is possible if you think of the architecture as a two-dimensional painting. Planar paintings add shades to the depth. It is the same for Western paintings and Japanese paintings. In order to capture the architecture as a two-dimensional painting, it is necessary to erase the volume, and for that purpose, it will be necessary to erase the outline of the volume. There are two ways to erase the contour, either not to draw the contour line in the first place or to have no specific contour. If it is applied to architecture, the object will exist as an entity, so it would be better not to have a specific outline. In order not to have a specific contour, the difference in the density of objects is used. That is, it is also a shade. Therefore, it is possible to express architecture based on what creates the density of objects.
記憶はつながりを示すものと考えがちだが、記憶は断絶の上に成り立つと思う。記憶を示す時はつながりが絶たれた時である。一旦つながりが絶たれた後に持ち出してくる過去のことが記憶である。だから、記憶自体には現在とのつながりが無く、時間軸としては過去だが、つながりが無い状態では過去のことでも、現在のことでも、未来のことでも皆同じであるから入れ替えが可能で、過去の記憶と未来の想像を等価に扱い自由に組み替えて考えることもできる。
"Recombining memory and imagination"
It is easy to think that memory is a connection, but I think that memory is based on disconnection. The time to show memory is when the connection is broken. I remember the past that I brought out after the connection was broken. Therefore, the memory itself has no connection with the present, and the time axis is the past, but if there is no connection, the past, the present, and the future are all the same, so they can be replaced. It is also possible to treat the memory of the future and the imagination of the future equally and freely rearrange them.
見方や捉え方の奥底、先にある建築の存在自体には手が届かないのかもしれない。ただもし手が届くと仮定しみたら何によって建築の存在自体を表現できるだろか。メイヤスーは数学でもの自体を捉えることができるとしたが、それは偶然そうなっただけであり、いつまた変化するかわからないという。一番簡単なことは建築の存在自体に踏み込まずに建築の見方や捉え方をデザインすることである。記憶をつなげるにはどうするかも捉え方のデザインである。ただその捉え方も一筋縄ではいかない。それを主題にしても考えることはたくさんある。記憶には時間の概念も含むから変化するものを捉えることが可能かもしれない。あらかじめ変化しそうなところまでを囲い込むように捉えることができればいい。認識や現象を捉えるより先のものの存在自体を捉える試みは例え無駄でもそれによって新しい認識を生むような気もする。
"Attempt to catch"
It may be out of reach of the depth of perspective and perspective, and the existence of the architecture ahead. But if we assume that it is within reach, what can we express the existence of architecture itself? Meillasso said he could capture itself in mathematics, but that was just a coincidence and he didn't know when it would change again. The simplest thing is to design a way of looking at and understanding architecture without stepping into the existence of architecture itself. It is also a design of how to grasp how to connect memories. However, the way of thinking is not straightforward. There are many things to think about even if it is the subject. Since memory includes the concept of time, it may be possible to capture things that change. It would be nice if we could capture the areas that are likely to change in advance. Even if it is useless, it seems that an attempt to capture the existence of something before it captures the perception or phenomenon will create a new perception.
建築の存在は実体として捉えようとしても捉えられないのかと思った。建築はこういうものだとという見方があるだけで、たくさんの見方の重なりが濃いか薄いかだけの違いに思えてきた。見方には正解は無く、間違いは有るかもしれないが、どの見方を選択するかだけの違いかもしれない。だから、創作するのは建築という実体では無くて捉え方であり見方である。ただそのなると他律的に存在する建築はイメージしやすいが自律的に存在する建築がイメージしにくい。自律的な建築は捉え方や見方という外からの指標とは無縁だと考えてしまうので、純粋な自律的建築は存在しないように思える。
"There is only a point of view"
I wondered if the existence of architecture could not be grasped even if I tried to grasp it as an entity. There is only a view that architecture is like this, and it seems that the difference is whether the overlap of many views is strong or light. There is no correct answer in the view, and there may be mistakes, but it may only be the difference in which view you choose. Therefore, it is not the substance of architecture that is created, but the way of thinking and the way of looking at it. However, in that case, it is easy to imagine an architecture that exists heteronomously, but it is difficult to imagine an architecture that exists autonomously. It seems that there is no purely autonomous architecture, because we think that autonomous architecture has nothing to do with external indicators such as perspectives and perspectives.
言葉以外で記憶を表現しようした時、建築において数値が端的に表現された寸法を用いる。言葉と違って数値だけが解釈によって変わらずに記憶を表現できると言ってもよい。ではその寸法はいつも同じだろうか。決してそのようなことはない。その場所で偶然そうなっただけである。だから、他の場所へ行けば当たり前だがいくらでも寸法は変化をする。ならば、寸法にその場所だけの固有性があり記憶として表現されるならば、その記憶としての寸法を引き継ぐことは建築として必然の行為ではないだろうか。
例えば、過去のプランがあり、そこに固有の寸法を見つけ出したならば、それをパターン化し判子のように転写を繰り返して新しいプラン、新しいエレベーションをつくってはどうだろうか。固有の寸法がまた違ったものになる、それも判子という効率を具現化したようなアイテムによって。
記憶という効率を考える上で排除されるようなもの、すなわち、他者性を帯びたものがパターン化し判子として転写されることでより活きるのであれば、効率の先に多様なモノがみえる。
数値は効率のために用いるものなのに、効率によって排除された記憶を表現するものになるところが面白いと思った。
"Past plan stamp"
When trying to express memory with something other than words, we use dimensions that express numerical values in architecture. It can be said that, unlike words, only numerical values can express memories without change depending on the interpretation. So are the dimensions always the same? That is never the case. It just happened to happen at that place. Therefore, if you go to another place, it is natural, but the dimensions will change as much as you like. Then, if the dimension has the uniqueness of the place and is expressed as a memory, it would be an inevitable act as an architecture to inherit the dimension as the memory.
For example, if you have a plan in the past and find a unique dimension in it, why not pattern it and repeat the transfer like a stamp to create a new plan or a new elevation? The unique dimensions will be different again, depending on the item that embodies the efficiency of a stamp.
If something that is excluded when considering the efficiency of memory, that is, something that has otherness, is patterned and transcribed as a stamp, it will be more useful, then various things can be seen beyond the efficiency.
I found it interesting that the numerical values are used for efficiency, but they express the memories excluded by efficiency.
言葉では表現できない記憶というものがある。建築における記憶もどんなに言葉を駆使しても全てを表現できない。モノとしてモチーフとして表現できる記憶は言葉でも表現できてしまう。だから、わざわざ建築として表現する必要性は無いかもしれないし、表現されたところでわざとらしくくどい。言葉以外で記憶を表現しようした時には数値を用いたらいいかもしれないとメイヤスーから着想した。数値は建築において絶対的な尺度である。数値でしか建築は表現できないと言っても過言ではない。建築において数値が端的に表現されているものは寸法であり、その寸法によって成り立っているのはプラン、セクション、エレベーション、そしてディテールである。さらに、寸法は建築の内外の関係性をも表現している。
"Dimensions are expressions other than words"
There is a memory that cannot be expressed in words. No matter how much words I use, I can't express everything in the memory of architecture. Memories that can be expressed as motifs as things can also be expressed in words. Therefore, it may not be necessary to express it as an architecture, and it is intentionally awkward when it is expressed. Meillasso came up with the idea that when trying to express memory with something other than words, it might be better to use numerical values. Numerical values are an absolute measure of architecture. It is no exaggeration to say that architecture can only be expressed numerically. In architecture, the simple representation of a number is a dimension, which is made up of plans, sections, elevations, and details. Furthermore, the dimensions also express the relationship between the inside and outside of the building.
暮らしや情緒という言葉は本来建築とは無縁である。そう言うと不思議な感じを受けるかもしれない。建築によって暮らしは営まれるし、建築による趣きや感性を刺激することが情緒につながる。ただ、建築自体はモノであり、暮らしや情緒はモノに従属するもので、人がいてはじめて発揮されるコトである。だから、コトが無くてもモノとしての建築は成立するし、先に暮らしや情緒を求められると建築の話ができなくなる人も中にはいる。暮らしや情緒はコトとして後付けだから、建築自体がモノとして、モノだけで成立できる。建築のプランもモノとしてだけ見れば、単に壁のパターンだけであり、壁の位置の違いはそこでの機能によるアクティビティの違いである。よって、壁の位置が密か疎かも機能によるアクティビティの違いを意味するし、空間の中での壁の見え方は人の視覚に影響を与え、記憶として残る可能性が高い。ただ、記憶として残る場合は壁にコト、すなわち、暮らしや情緒が付着している。それは壁と暮らしや情緒が相互に関係性があるとも言え、壁の見え方が暮らしや情緒を想起させると考えることもできるだろう。だから、その建築特有の壁の見え方を過去のプランから抽出し、それはできればパターンを見つけ出し、そのパターンを定規として用いて新しいプランを考えれば、記憶として暮らしや情緒をつなぐようなモノができやしないかと考えている。
"Making a ruler from the past"
The words life and emotion have nothing to do with architecture. That may make you feel strange. Living is carried out by architecture, and stimulating the taste and sensibility of architecture leads to emotions. However, architecture itself is a thing, and life and emotions are subordinate to things, and it is something that can only be demonstrated when there are people. Therefore, architecture as a thing can be established without things, and some people cannot talk about architecture if they are asked for their living and emotions first. Since life and emotions are retrofitted as things, architecture itself can be established as a thing, only with things. If you look at the architectural plan only as a thing, it is just the pattern of the wall, and the difference in the position of the wall is the difference in the activity depending on the function there. Therefore, whether the position of the wall is dense or sparse also means the difference in activity depending on the function, and the appearance of the wall in the space affects the human vision and is likely to remain as a memory. However, if it remains as a memory, things, that is, living and emotions, are attached to the wall. It can be said that the wall and the life and emotions are related to each other, and it can be thought that the appearance of the wall is reminiscent of the life and emotions. Therefore, if you extract the appearance of the wall peculiar to the architecture from the past plan, find a pattern if possible, and use that pattern as a ruler to think of a new plan, you can create something that connects your life and emotions as a memory. I'm thinking about it.
記憶は建築の外側にあるものであり、記憶から建築が導き出される。そして、プランは建築の内側にあるものであり、プランから建築は出来上がる。また、記憶の源はプランから派生した見え方である。記憶とプランと建築は相互に内外混じり合いながら関係性を持つ。過去のプランは記憶そのものであり、過去のプランから派生した見え方やそれに伴う暮らしの情緒が記憶の中身になる。見え方を通した暮らしの情緒は誰でも郷愁を誘うがそれは個人的なことであるから他人にはわからないかもしれない。しかし、そうして除外されていることで個人的な暮らしの情緒が他者性を帯び、それが建築として具現化された時には情緒を除外させたもの、たぶんそれは効率であり、効率か非効率かの脱構築として個人的な暮らしの情緒が使え、それが都市に対する関係性を築くきっかけにもなる。だから、過去のプランから個人的な暮らしの情緒につながるものを抽出して新しい建築に活かす。
"Emotions that connect the city and life"
Memory is outside of architecture, and architecture is derived from memory. And the plan is inside the architecture, and the architecture is completed from the plan. Also, the source of memory is the appearance derived from the plan. Memories, plans, and architecture have a relationship that mixes internally and externally. The past plan is the memory itself, and the appearance derived from the past plan and the emotion of life that accompanies it become the contents of the memory. Anyone can feel nostalgia for the emotion of living through the way they see it, but since it is a personal matter, others may not understand it. However, such exclusion makes the emotions of personal life alien, and when it is embodied as architecture, it excludes emotions, perhaps it is efficiency, efficiency or inefficiency. The emotion of personal life can be used as a deconstruction, and it also becomes an opportunity to build a relationship with the city. Therefore, we will extract things that lead to the emotions of personal life from past plans and utilize them in new architecture.
その敷地においての過去のプランは記憶や過去との時間のつながりを形成する上で大事な素材であり、新たな建築に活かすことでできるつながりは都市の色になる。過去のプランはアクティビティを示す。過去のプランがいくつか存在するならば重ねてみることでアクティビティの密度がわかる。密度の高低により空間をデザインできる。
"Density of activity"
The past plan on the site is an important material for forming the memory and the connection of time with the past, and the connection that can be made by utilizing it in the new architecture becomes the color of the city. Past plans show activity. If there are several past plans, you can see the density of activities by stacking them. Space can be designed by increasing or decreasing the density.
記憶として残るものには様々なものがあるが、記憶をイメージと結びつける時に建築が手助けすることができるとしたら、そのひとつは視覚に派生するもの、例えば、壁や天井、床といった部位の見え方だろう。部位の見え方が記憶を呼び起こすと言っても良いかもしれない。そのような部位の見え方を引き継いでいくような建築は記憶や過去との時間のつながりを持ったものと言える。では、部位の見え方を決めるおおもとのものは何だろうか。たったひとつのことで全ての部位の見え方をコントロールしているのはプランである。プランによって見え方をコントロールし、それは記憶をもコントロールしている。だから、過去のプランは記憶や過去との時間のつながりを形成する上での大事な素材である。
"Plan is a material of memory"
There are many things that remain in memory, but one of the things that architecture can help in connecting memory to images is something that is visually derived, such as how parts such as walls, ceilings, and floors look. right. It may be said that the appearance of the part evokes memory. It can be said that the architecture that inherits the appearance of such parts has a memory and a connection with the past. So what is the basis for determining how the parts look? It is the plan that controls the appearance of all parts with just one thing. The plan controls the appearance, which also controls the memory. Therefore, the plan of the past is an important material for forming the memory and the connection of time with the past.
建替えることで全く新しい建築ができる。それは一旦リセットされることである。ただ、建替える前にはそこに建築があった。そこにあった建築はただそこにあった訳ではなく、その場所で生まれた時には最適な解であった。きっと時間の経過によって建築自体の耐用年数を超えただけで建築としての最適解は今でも有効かもしれない。ならば有効な部分は引き継ぎ今に活かすことは必然であり、もっと引いて都市的視点で考えれば、建替えによる断絶より過去からのつながりが残った方が都市としては時間的な重みが増し、時間の経過による記憶が都市の色となるのではないかと考えた。
"City color"
A completely new building can be created by rebuilding. It is to be reset once. However, there was an architecture there before it was rebuilt. The architecture that was there wasn't just there, it was the best solution when it was born there. I'm sure that the optimal solution as an architecture may still be effective just because the useful life of the architecture itself has been exceeded over time. If so, it is inevitable that the effective part will be taken over and utilized now, and if we take it further and think from an urban perspective, it will be more time-consuming for the city if the connection from the past remains rather than the disconnection due to rebuilding. I thought that the memory of the passage of time would be the color of the city.
記憶の中から何を抽出して建築デザインに活かすかを考えている。建築デザインに活かすには形になる情報を含んでいる必要がある。エコが直接的に建築デザインに結びつかないのは、エコには形の情報が無いからであり、エコを建築デザインに活かせるものに変換をしなければならない。例えば、最適な室温を保つために電力をたくさん使うのでは無く、日射や風などの自然の力を使うことを目指して、開口部の大きさや位置、庇や屋根形状などをデザインするように、建築の部位の形に直接影響を与えるように記憶の中から何かに焦点を絞る必要がある。
"From memory"
I am thinking about what to extract from my memory and utilize it in architectural design. It is necessary to include information that can be used in architectural design. The reason why eco is not directly linked to architectural design is that eco has no information on its shape, and it is necessary to convert eco into something that can be utilized in architectural design. For example, instead of using a lot of electricity to maintain the optimum room temperature, design the size and position of the opening, eaves, roof shape, etc. with the aim of using natural forces such as solar radiation and wind. It is necessary to focus on something in the memory so that it directly affects the shape of the part of the building.
関係性を記憶として捉え直してみると面白いと考えた。記憶は過去との関係性が現れたものとすれば、記憶と関係性が時間を媒介にしてつながることになる。過去と現在が記憶で関係性ができる。関係性のデザインだけが効率との両立が可能だと考えていて、関係性の並置と断絶が効率と都市性をつなげることができる。
"Memory is a relationship"
I thought it would be interesting to reconsider the relationship as a memory. Assuming that the memory has a relationship with the past, the memory and the relationship are connected through time. The past and the present can be related by memory. We believe that only the design of relationships can be compatible with efficiency, and the juxtaposition and disconnection of relationships can connect efficiency and urbanity.
効率的に空間配置をすることは集合住宅では特に求められることである。効率的な空間配置を目指すと事業性が上がる経済的メリットとプランに妥当性と納得感が生まれる。通常はここまでで終わる。それ以上は考える必要がない。しかし、様々な関係性も同時に生まれるので、本来はその関係性こそがデザインをする対象として最も重要だと考えている。
"Relationship is important"
Efficient spatial arrangement is especially required in apartment buildings. Aiming for efficient space layout will increase business feasibility. The economic merit and plan will be valid and convincing. Usually it ends here. You don't have to think any further. However, since various relationships are created at the same time, I think that these relationships are the most important objects to design.
効率の良さと関係性の並置に関連性があるかどうかを考えている。集合住宅の計画において効率の良さは事業性にもつながるので大事だが、効率ばかりを追い求めていると人の住む空間ではなくなってしまう。だから程よい効率を求めたいのだが、その際に効率とのバランスを保つために関係性に注目した。
関係性には3つあり、住戸内の関係性と住戸間の関係性、そして外部環境との関係性である。どれも各々の関係性は存在しつつも、壁や床などの部位で各々の関係性には断絶が起こるので、関係性が並置された状態になり、一塊の建築の中に複数の関係性が共存している状態ができる。その状態が都市のようであり、関係性に注目すると建築に都市を内包することができる。
そこで、効率は関係性の断絶の繰り返しだと考えれば、関係性を媒介にして効率に都市性を発見できるかもしれないと考えてみた。効率に都市性を発見できれば、やり方しだいで効率と人の住む空間を上手に結びつけることができるかもしれない。
"Including the city in architecture"
We are considering whether there is a relationship between efficiency and juxtaposition of relationships. Efficiency is important in planning an apartment building because it also leads to business feasibility, but if you pursue only efficiency, it will not be a space where people live. Therefore, I would like to seek moderate efficiency, but at that time I focused on the relationship in order to maintain a balance with efficiency.
There are three relationships: the relationship within the dwelling unit, the relationship between the dwelling units, and the relationship with the external environment. Although each relationship exists, each relationship is interrupted at parts such as walls and floors, so the relationships are juxtaposed, and there are multiple relationships in a block of architecture. Can coexist. The state is like a city, and if we focus on the relationship, we can include the city in architecture.
Therefore, if we think that efficiency is a repetition of the disconnection of relationships, we thought that we might be able to discover urbanity efficiently through relationships. If we can discover urbanity efficiently, we may be able to successfully connect efficiency with the space where people live, depending on the method.
関係性を並置してみるとまた違ったコトになると考えた。関係性から判断する時にはどうしてもヒエラルキーをつくってしまう。強引に言ってしまえば、関係性とはヒエラルキーである。大小、強弱など関係性に差異をつける。関係性を判断する時に差異を意識しないとわからないからかもしれないが、関係性の差異の塊が建築では古典的過ぎるので、差異を平すために、関係性を並置してみることにした。関係性を並置するとは関係性にヒエラルキーが生じても全体としての塊である建築には全く影響を与えない様である。関係性が有りながら、関係性自体が断絶して連続しない様とも言える。たがら、並置できる。
"Parallelization of relationships"
I thought that if the relationships were juxtaposed, it would be different. When judging from the relationship, it inevitably creates a hierarchy. Forcibly speaking, relationships are a hierarchy. Make a difference in relationships such as size and strength. It may be because you have to be aware of the difference when judging the relationship, but since the mass of the difference in the relationship is too classic in architecture, I decided to juxtapose the relationship in order to flatten the difference. The juxtaposition of relationships does not seem to affect the architecture, which is a mass as a whole, even if a hierarchy occurs in the relationships. It can be said that although there is a relationship, the relationship itself is broken and not continuous. However, it can be juxtaposed.
全てをはっきりと、白黒とつけたくなる。全てを1mm単位で数値に落とすので曖昧さを許容できなくなる。曖昧に決めた数値だとしても、数値が一人歩きし決して曖昧とはならない。ただ、そこまで厳密に行うことがいいのかと、必要なのかと思った。それで良くなるのであればいくらでも厳密にできる。きっちりと何もかもが決まったものが果たして良いものとして受け入れられるのだろうか。よく遊びが必要だと言われるが、遊びが緩さではなく、遊びという厳密と同じ属性の行為になってしまってはつまらない。結局は厳密と曖昧のバランスを取ることが必要であり、それはあえて何も手を加えないで保留にできるかどうかではないかと考えた。
"Dare to put it on hold"
I want to put everything clearly in black and white. Ambiguity cannot be tolerated because everything is reduced to numerical values in 1 mm increments. Even if the numerical value is decided vaguely, the numerical value walks alone and never becomes ambiguous. However, I wondered if it was necessary or necessary to do so strictly. If that makes it better, you can do it exactly as much as you want. Is it acceptable that something that has been decided exactly is really good? It is often said that play is necessary, but it is boring if play is not loose and it becomes an act with exactly the same attributes as play. In the end, it was necessary to strike a balance between strictness and ambiguity, and I wondered if it could be put on hold without any modification.
記憶が断絶している建築ばかりでは都市は形成されない。記憶が個人的なものであったとしても断絶せずにつながりがあることで都市に時の流れによる積み重ねが生まれ特色が出る。だから、建築を更新する時には時の流れを断絶させずに記憶をいかに積み重ねていくかが重要だが、それが観念的な手法では単なる妄想の中の積み重ねで終わる。具体的に記憶を何らかの形あるモノで表現し、それを用いることで記憶をつなぐことができればよい。
"To connect memories"
A city cannot be formed only by architecture whose memories are cut off. Even if the memory is personal, the connection without interruption creates the accumulation of time in the city, which gives it a distinctive character. Therefore, when renewing architecture, it is important how to accumulate memories without interrupting the passage of time, but with the ideal method, it ends up being simply accumulation in delusions. Specifically, it is only necessary to express memory in some form and use it to connect memories.
建築を都市とつなげようとした時、特別な意味づけとして時間によって蓄積された記憶が必要だとした。その記憶は決して特別なものである必要はない。むしろその場所だけの、個人的で構わない、その局所的な記憶の重なりが都市をつくり、都市に魅力を出す。その記憶を皆が理解できなくてもいい。その記憶がその場所をつくり、その連なりが都市を形成し、建築と都市をつなげることになる。
"A series of memories is a city"
When trying to connect architecture to the city, he said that he needed a memory accumulated over time as a special meaning. The memory does not have to be special. Rather, the overlap of local memories, which can be personal and only in that place, creates a city and makes it attractive. It doesn't have to be that everyone can understand the memory. The memory creates the place, the chain forms the city, and connects the architecture and the city.
建築を都市とつなげようとするならば、外部空間をつなげようとするよりも時間によって蓄積された記憶をつなげていく方が効果があるのではないかと考えた。外部空間をつなげる場合、敷地境界線という壁がある。公共建築の場合はその壁が管理区分でもあるから管理の仕方次第で都市とつなげることは可能で、公共建築、あるいは公共性の高い建築は外部空間を積極的につなげるべきである。しかし、外部空間のつながりは単に公共の外部空間が広がるだけに過ぎず、そこに特別な意味づけがなければ建築と都市がつながるとは言えないのではないか。それは公共空間以外であれば尚更で、観念的なつながりに過ぎない。その特別な意味づけに当たる部分が時間によって蓄積された記憶だと考えている。
"To connect architecture and cities"
When trying to connect architecture to a city, I thought that it would be more effective to connect the memories accumulated over time than to connect the external space. When connecting external spaces, there is a wall called the site boundary line. In the case of public buildings, the walls are also management divisions, so it is possible to connect to cities depending on the management method, and public buildings or highly public buildings should actively connect external spaces. However, the connection of the external space is merely the expansion of the public external space, and if there is no special meaning there, it cannot be said that the architecture and the city are connected. It's even more so except in public spaces, it's just an ideological connection. I think that the part that corresponds to that special meaning is the memory accumulated over time.
立体街区のようなプランが多く、集合住宅では住戸内部のプランに他との明確な差異を見つけることができないのか、建築計画上効率を優先し不特定多数に支持されるものにするにはある程度住戸内部のプランをニュートラルにせざるを得ないのか、住戸以外の廊下や階段といった動線空間をデザインしてまとめ上げる事例をよく見る。集合住宅のメリットである効率性を活かしつつデザインするには最善の方法にも見えるがちょっと無理を感じる時もある。敷地境界線を越えていく難しさとでも言うか、なかなか境界線を越えてつなげることは妄想の中でしかないケースも多い。
"Beyond the border"
There are many plans such as three-dimensional districts, and it is not possible to find a clear difference in the plan inside the dwelling unit in the apartment house, or it is to some extent to prioritize efficiency in the architectural plan and make it supported by the general public. I often see cases where the plan inside the dwelling unit has to be neutral, and the flow line space such as corridors and stairs other than the dwelling unit is designed and put together. It may seem like the best way to design while taking advantage of the efficiency of an apartment building, but sometimes it feels a little impossible. It may be said that it is difficult to cross the boundary line of the site, but there are many cases where connecting beyond the boundary line is only a delusion.
関係性が時制の中で変化することはよくあることであり、過去の関係性と現在の関係性は途中で断絶することが無ければつながるが、過去の関係性は記憶と言い換えて、記憶を何らかの形で抽出し、同じ方法で現在から抽出したものと合わせ、その差異を現在のプランに刻み込む。そうすれば、関係性が時制というフィルターを通して残り、さらにその手法は未来へと受け渡すことができる。このようにプロセスからデザインする必要をいつも感じる。
"Design from process"
Relationships often change in tense, and past relationships and present relationships are connected if they are not interrupted in the middle, but past relationships are paraphrased as memories, and memories are remembered. Extract it in some way, combine it with the one extracted from the present in the same way, and imprint the difference in the current plan. Then the relationship remains through the tense filter, and the method can be passed on to the future. I always feel the need to design from the process like this.
効率か非効率かを置き換えてシークエンスかランダムかにしてみると、建築計画上でプランニングとの関係性がわかりやすくなる。この関係性に含まれないものはひとつに時間だろう。時間という概念が無くてもシークエンスかランダムかはとりあえず考えることができる、今だけを見ればいいのだから。ただ、時間すなわち過去現在未来の時制に焦点を当ててみると、シークエンスかランダムかはプランニング上では棚上げになり大した問題ではなくなるのではないかと考えた。
"Tense and efficiency"
By substituting efficiency or inefficiency for sequence or random, it becomes easier to understand the relationship with planning in architectural planning. One thing that is not included in this relationship is time. Even if you don't have the concept of time, you can think about sequence or random for the time being, because you only have to look at it now. However, when I focused on time, that is, the tense of the past, present, and future, I thought that sequence or random would be shelved in planning and would not be a big problem.
関係性があるから個別の存在が浮き上がるともいえる。個別の存在そのものを知覚することはできない、関係性という現象を通してのみ個別の存在がわかると、カントへの理解はその程度だが、人も含めた物には必ず他者が存在するから物そのものを知覚できないし、そもそも知覚できないということから他者が存在する。そうすると、他者を置くことは永遠に物そのものに到達できないことになる。建築を考えていると物そのものに思いをはせてしまう。だから、物の素材性や触覚性に走るのだろう、それは自分の手で確かめることができる唯一の物それ自体かもしれないから。ただ、それはある種の慰めでしかない。一度は無理を承知で物そのものに迫る建築行為をしてみたい。
"I want to get closer to the thing itself"
It can be said that individual existence emerges because of the relationship. If we can understand the individual existence only through the phenomenon of relationship, which cannot perceive the individual existence itself, we can understand Kant to that extent, but since there are always others in things including people, we can understand the thing itself. Others exist because they cannot be perceived and cannot be perceived in the first place. Then, putting others will never reach the thing itself. When I think about architecture, I think of the thing itself. Therefore, it may be the material and tactile nature of the thing, because it may be the only thing that can be confirmed by one's own hands. But that's just some kind of comfort. I would like to do a building act that approaches the thing itself, knowing that it is impossible once.
関係性は二次的で個別には存在している、まさによくある集合住宅のことだと思った。個別に存在することは二次的で関係性がまずあるのがシェアハウスか。個別に存在することよりも関係性に注目すれば、形の有無に関わらず、何かをつくる時のヒントになるのだが、それよりも関係性と個別の存在の外側に何かあるだろうかが今の関心事である。
"Relationship and individual outside"
I thought that the relationship was a very common apartment house that was secondary and existed individually. Is it a share house that exists individually is secondary and has a relationship first? Focusing on relationships rather than being individual is a hint when creating something, with or without shape, but is there anything outside of relationships and individual beings? Is the current concern.
効率の良さを目指すことは同時に効率よく余分なものを排除することでもあり、排除する時の基準は制御できるかどうかであり、制御できないものは効率の外に置くことになる。効率の良さを測る指標は数値であり、制御できないものは数値化できない。それでは、効率の良いものと数値化できないものを組合せるとどうなるだろうか。普通に考えれば効率が悪くなると考えるだろう。だから、数値化できないものは、徹底的に数値化しようと試みるか排除しようとする。しかし、効率の良いものと数値化できないものを組合せても効率が悪くないらないどころか効率が良くなることがあるとしたら、それはどのような場合だろうかと考えてみると面白い。
"Combination of efficiency and things that cannot be quantified"
Aiming for efficiency is also to efficiently eliminate excess, and the criterion for exclusion is whether or not it can be controlled, and what cannot be controlled is placed outside of efficiency. The index for measuring efficiency is a numerical value, and what cannot be controlled cannot be quantified. So what happens when you combine something that is efficient and something that cannot be quantified? If you think about it normally, you will think that it will be inefficient. So, if you can't quantify it, try to quantify it thoroughly or try to eliminate it. However, it is interesting to think about what kind of case it would be if the combination of efficient and non-quantifiable ones would not be inefficient but would be more efficient.
建築計画上効率によって排除される多様な関係性に当たるものには何があるかを考えてみた。あるいは、排除される多様な関係性を誘発するものは何か。例えば、集合住宅は建築計画上効率を追求する最たるもののひとつであり、効率によって同一的なプランの連続になる。そもそも集合住宅にするのは効率によって集積し高密度にする目的だから、同一的になることが目指すところではあるがそれによって排除されるものが気になる。集合住宅において多様な関係性、あるいはそれを誘発するものは何だろうか。たぶん、住戸内部にはない。あるとしたら住戸の外部だろうが、住戸間の関係性や住戸の外部である周辺環境との関係性以外にはないのかを考えてみたい。
"Think about what is excluded"
I thought about what are the various relationships that are excluded by efficiency in building planning. Or what induces the diverse relationships that are excluded? For example, an apartment house is one of the most pursuing efficiency in architectural planning, and efficiency makes a series of identical plans. In the first place, the purpose of making an apartment house is to concentrate and increase the density by efficiency, so the goal is to be the same, but I am concerned about what is excluded by it. What are the various relationships or triggers in an apartment building? Probably not inside the dwelling unit. If there is, it may be outside the dwelling unit, but I would like to consider whether there is anything other than the relationship between the dwelling units and the surrounding environment outside the dwelling unit.
建築計画上効率的なプランニングや配置とは、ある指標に対して一番無駄がなく動かしようのないものだが、それは同時に関係性の面からみたら多様性を排除している。効率を求めれば多様な関係性は築けない。効率を何か目的を達成するための手段と考えることができれば、代わりに多様な関係性が手段となり同じ目的を達成できればいい。排除された多様な関係性を主題に据える。ただ一度は効率を追い求めているので、排除された多様な関係性は効率とバランスが取れるように極端化することができ、効率と齟齬を起こさない新たな多様な関係性を築くことができる。
"From efficiency to diverse relationships"
Efficient planning and placement in architectural planning is the least wasteful and immovable for a given indicator, but it also eliminates diversity in terms of relationships. If you seek efficiency, you cannot build diverse relationships. If efficiency can be thought of as a means to achieve some purpose, then it would be good if various relationships could be used as a means to achieve the same purpose. The subject is the diverse relationships that have been excluded. Since we are pursuing efficiency only once, the diverse relationships that have been excluded can be extremed to balance efficiency, and new diverse relationships that do not conflict with efficiency can be built.
建築計画上効率的にプランニングや配置をされてたことにより排除されるものは何かを考えてみた。効率的なプランニングや配置は建築計画にとって重要なひとつの目指すべきことであり、それのみで建築計画を完了しても文句はないかもしれない。ただし、それと引き換えに何かが排除され、その排除されたことの方が重要な場合、効率的なプランニングや配置は存在意義を失くす。
"Eliminating efficiency"
I thought about what would be excluded by efficient planning and placement in the building plan. Efficient planning and placement is one of the important goals of a building plan, and it may not be a complaint to complete the building plan by itself. However, if something is excluded in exchange and the exclusion is more important, efficient planning and placement loses its raison d'etre.
関係性を取り扱う時の時制は現在の今この瞬間か、少なくとも過去なり未来なりに合わせるだろう。時制がズレていては関係性を計る上で時間という余計な要素が加わる。時間は状態を変化させ、当然関係性にも影響を与えるので、関係性に時間による補正を加える必要が出てくる。だから、時制をズラすことは正解な関係性を計れなくする。しかし、関係性をデザインの発露にする場合は時制をズラすことで時間という要素をデザインに取り入れることができ、その取り入れ方次第でデザイン上の差異を生むことができる。
"Sliding the tense of relationships"
The tense when dealing with relationships will match the present moment, or at least the past or the future. If the tense is off, an extra element of time is added to measure the relationship. Since time changes the state and naturally affects the relationship, it is necessary to correct the relationship with time. Therefore, shifting the tense makes it impossible to measure the correct relationship. However, when the relationship is exposed to the design, the element of time can be incorporated into the design by shifting the tense, and depending on how it is incorporated, a difference in design can be made.
過去から未来へ流れる時間の中でのある点で切り取ったものが建築だと考えるならば、どこに焦点を合わせて切り取るかが問題になる。別に必ずしも現在に焦点を合わせる必要は無く、未来でも過去でもいい。未来に焦点を合わせることはよくあることだが、過去に焦点を合わせることはあまり無いかもしれない。時間の流れを考えれば必ず未来へ向かうので未来に焦点を合わせることは自然で、過去に焦点を合わせることは時間の流れに逆行するので違和感がある。ただ、現在を過去の集積と考えるならば、過去に焦点を当てて未来に向かう建築をつくることはできるような気がする。
"Focus on the past"
If you think that architecture is cut out at a certain point in the time that flows from the past to the future, the question is where to focus and cut out. You don't necessarily have to focus on the present, it can be in the future or in the past. Focusing on the future is common, but focusing on the past may not be very common. Considering the flow of time, it is natural to focus on the future because it always goes to the future, and focusing on the past goes against the flow of time, so it feels strange. However, if we think of the present as an accumulation of the past, I feel that we can focus on the past and create architecture that faces the future.
現在を過去の集積だと考えた場合の他者は偶然性である。ならば偶然性を主題にして、現在を過去の集積とは考えずに、現在は単なる偶然の産物と考えてみる。そうなると現在はたまたまそうなっただけとなる。たまたまそうなっただけの存在にはもしかしたら意味など全く無いかもしれないし、たまたまそうなっただけならば、いつかまた変化してしまうかもしれない。いつかまた変化してしまうものに価値を見出すとしたら、その瞬間の姿を焼き付けて記録し、変化したらその差異を楽しむしかないし、そもそも変化することが前提ならば、変化せずに残るのは差異だけである。
"All that remains is the difference"
Others who think of the present as an accumulation of the past are accidental. Then, with the theme of contingency, instead of thinking of the present as an accumulation of the past, think of the present as a mere product of chance. Then it just happened to happen now. The existence that just happened to happen may have no meaning at all, and if it just happened to happen, it might change again someday. If you want to find value in something that will change again someday, you have to burn and record the appearance of that moment, and if it changes, you have to enjoy the difference, and if it is supposed to change in the first place, the difference remains unchanged. Only.
他者を見極め徹底的に他者を全うする一貫性が素晴らしかった。東京都現代美術館で開催中の吉阪隆正展での感想である。昔からから不連続統一体に興味があり、ただ今回はあまり詳しく不連続統一体に触れる展示は無く、最後の展示で都市計画に表れていた。以前から不連続統一体はコルビジェのオブジェクトの配置の発展したものと捉えていたので、その辺りを展示の中で見たかったのだが、それよりも面白い他者性に触れることができ有意義な時間だった。
"Consistency of others"
The consistency of identifying and thoroughly fulfilling others was wonderful. This is my impression of the Takamasa Yoshizaka exhibition being held at the Museum of Contemporary Art Tokyo. I have been interested in discontinuities for a long time, but this time there was no exhibition that touched on discontinuities in detail, and it appeared in city planning at the last exhibition. I've always thought that the discontinuous unification was an evolution of the arrangement of Corbusier's objects, so I wanted to see that area in the exhibition, but it was a meaningful time to be able to experience more interesting otherness. was.
美学的な素晴らしさがあり、それがモノの存在や関係性と結びついて表現されているならば更に興味深いモノになるのだが、両方が満たされているものはなかなか見当たらない。それは美学的な素晴らしさも、モノの存在や関係性もそれぞれ単独で成り立たせることができるから、それぞれを単独で追求する人はいるが両方を満たそうとする人はなかなかいないし、いてもバランスが悪い。モノの存在や関係性に意識的にならないと美学的な素晴らしさは引き出せないし、美学的な素晴らしさに目を向けないとモノの存在や関係性に意義を見出せないと考えている。だから、両方満たすために新たな他者的な視点が必要かもしれない。
"Another perspective that satisfies both"
It would be even more interesting if there was aesthetic splendor and it was expressed in connection with the existence and relationships of things, but it is hard to find anything that satisfies both. It is aesthetically pleasing, and the existence and relationships of things can be established independently, so there are people who pursue each independently, but there are few people who try to satisfy both, and even if they are balanced. bad. I think that aesthetic splendor cannot be brought out unless one is conscious of the existence and relationship of things, and that the existence and relationship of things cannot be found to be meaningful unless one pays attention to the aesthetic splendor. Therefore, a new perspective of others may be needed to satisfy both.
建替えによって時間と記憶が断絶される。この断絶には功罪がある。ただ、断絶か継承かの二者択一では無く、断絶では無いがかと言って継承でも無いような、断絶か継承かを棚上げするような他者が見つかれば、別の建替えの表現ができると考えた。
繋がりながらも一部は途切れているような関係性を時間や記憶と形成したい。時間や記憶をデザインの話として扱う時には関係性に注目すると捉えやすいかもしれない。
"Disruption or inheritance of relationships or others"
Rebuilding cuts off time and memory. There are merits and demerits in this disconnection. However, if you find someone else who shelves whether it is a break or a succession, it is not a choice between a break and a succession, and it is not a break or a succession, you can express another rebuilding. I thought.
I want to form a relationship with time and memory that is connected but partially interrupted. When treating time and memory as a design story, it may be easier to understand by focusing on relationships.
記憶の継承を外部からの関係性か内部からの関係性かを考えた場合、排除されている他者は何だろうか。外部からは周辺環境のコンテクストを含むものであり、内部からは実際の物によって記憶を対象化できる。だから、この時の他者は、記憶の継承は周辺環境のコンテクストと実際の物から成り立っているということ以外である。ただ、外部からでも無く内部からでも無いもので見当がつくものは無いが、外部か内部かという考えから外れた他者は思い当たるものはある。それは外部からの関係性や内部からの関係性のみを抽出し、その関係性を組み替えたものである。組み替えることで他者性を獲得する。ただし、この時の組み替えは記憶を編集するものでなければならない。
"Others who edit memory"
When considering whether the inheritance of memory is an external relationship or an internal relationship, what are the others excluded? From the outside, it contains the context of the surrounding environment, and from the inside, the memory can be targeted by the actual object. So, the others at this time are other than that the inheritance of memory consists of the context of the surrounding environment and the real thing. However, there is nothing that can be guessed from the outside or the inside, but there are things that others who deviate from the idea of whether it is the outside or the inside can think of it. It extracts only the relationships from the outside and the relationships from the inside, and rearranges the relationships. Acquire otherness by rearranging. However, the rearrangement at this time must edit the memory.
その場所の記憶の継承を考えた場合、内部からと外部からの2通りある。内部からは空間の変遷が及ぼす関係性を記憶と重ねることができ、外部からは周辺の影響の変遷が及ぼす関係性を記憶と重ねることができる。一般的にはどちらかを選択することになり、どちらを選択しても記憶の継承はできる。ただ、内部か外部かだけでは無いという立脚点に立ち別の可能性を考えてみる価値はあるかもしれないと考えてみた。
"Internal or external or otherwise"
When considering the inheritance of the memory of the place, there are two ways, from the inside and from the outside. From the inside, the relationship exerted by the transition of space can be superimposed on the memory, and from the outside, the relationship exerted by the transition of the influence of the surroundings can be superimposed on the memory. Generally, either one is selected, and the memory can be inherited regardless of which one is selected. However, I thought that it might be worth considering the possibility of another from the standpoint that it is not only inside or outside.
建替えで排除されるものは過去からの時間であり、記憶など時間によって蓄積されたものが一旦リセットされるのが一般的である。リセットされることで未来への新しい展開が生まれるが、それと同時に記憶など蓄積されたものは何か特別な施しをしない限り消滅する。そこでリセットしないで建替えをすれば良いと考えれば記憶など蓄積されたものは消滅しないが、それと引き換えに未来への新しい展開が制約を受けるかもしれない。そうなると建替えのプロセスの中で記憶など蓄積されたものを含む何かをプラン作成のアイテムとすれば、未来への新しい展開が制約を受けることはないかもしれないと考えた。
"Item of memory"
What is excluded by rebuilding is the time from the past, and what is accumulated by time such as memory is generally reset once. By being reset, a new development for the future will be born, but at the same time, the accumulated things such as memories will disappear unless some special treatment is given. Therefore, if you think that you should rebuild without resetting, the accumulated things such as memories will not disappear, but in exchange for that, new developments in the future may be restricted. In that case, I thought that if something including the accumulated things such as memories in the rebuilding process was made an item for making a plan, new development to the future might not be restricted.
記憶は自分の中に他者をつくる。記憶の重なりが無ければ今の自分だけであり、そこには他者は無い。どのような記憶であれ完全に消えることは無いので必ず自分の中に他者は存在する。だから、建替えで記憶を継承しないことには無理があり、例え形が無くなったとしても記憶は消えないので、何らかの形で記憶を紡ぐ必要はあると考える。結果的にモノとして記憶を継承することを目指すがむしろ継承の仕方、プロセスに目を向けてみることで他者をより意識できる。
"Spinning memory"
Memory creates others in you. If there is no overlap of memories, I am the only one I am now, and there is no other person there. No matter what kind of memory you have, it will never disappear completely, so there will always be others in you. Therefore, it is impossible not to inherit the memory by rebuilding, and even if the shape disappears, the memory will not disappear, so I think it is necessary to spin the memory in some way. As a result, we aim to inherit the memory as a thing, but rather we can be more aware of others by looking at the inheritance method and process.
無意識な自分が他者というのは現代思想の礎だが、今だに無意識な自分を他者と捉えてもいいかもしれない。自分の中に他者を内包するのは自然なことだと思うがそれを受け入れられない人が多いかもしれない。自分の中にいる他者と対話することはそれだけで新たな発見があるのだがそれを社会と結びつけないとつまらない。もし自分の中にいる他者が暴走したらと考えて受け入れらないのならば他者の背中に乗れば今まで見たことが無い世界を概観できるだろうに。
"Riding on others"
It is the cornerstone of modern thought that the unconscious self is another person, but it may still be possible to regard the unconscious self as another person. I think it's natural to include others in yourself, but many people may not accept it. Dialogue with others within you is a new discovery, but it's boring if you don't connect it to society. If you don't accept the runaway of others in you, you can get an overview of a world you've never seen before by riding on their backs.
訳がわからない、わからないと言えるモノを探してみようと考えた。どこまでも考えても、どこまでも塗りつぶしても塗れない部分、考えても結論が出ない部分がある。それは能力の問題なのかもしれないが能力が高くても空白と呼べるような部分は残る。きっとそれが自分にとっての他者なのだろう。自分にとっての他者と社会にとっての他者にはきっとズレがある。そのズレがデザインのヒントになる。だから、自分にとっての他者は大切な基準になる。
"Others for me"
I thought I'd try to find something that I couldn't understand or could say I didn't understand. There are parts that cannot be painted even if you think about it, and parts that you cannot reach a conclusion even if you think about it. It may be a matter of ability, but even if the ability is high, there remains a part that can be called a blank. I'm sure it's someone else for me. There is surely a gap between others for me and others for society. The deviation becomes a design hint. Therefore, others are an important standard for me.
建替えを計画する時、時の流れを建築の存在に込めることはできないかと考えてしまう。
建築が時の流れを止めてしまうのでは無く、時の流れを繋ぐような存在にしたいという想いがあるからだが、もうひとつの想いは建築という物自体の存在を捕まえたいという欲求が働くからでもある。
だがたぶん捕まえることはできないだろうという想いも同時にある。
"I want to catch architecture"
When planning a rebuild, I wonder if the passage of time can be incorporated into the existence of architecture.
This is because architecture does not stop the flow of time, but wants to be something that connects the flow of time, but another desire is that the desire to capture the existence of architecture itself works. be.
But at the same time, I have the feeling that I probably won't be able to catch it.
自分が認識している範囲が全てでは無いのでその外側に意識を向けようとするのは至極当然の行為だが、その外側でさえ認識の範囲だから外側に意識を向ける事自体が無意味である。結局は全てを認識できることは無く、全てをコントロールしようという考え方自体が虚しい。その時々の出来事は共時的偶然なのだからコントロールしようが無い。唯一できるのは出来事の確率を高めることだけであり、確率を高めるにはコントロールすることとは真逆のコントロールできないことを受け入れる姿勢にある。これは建築の話であり、偶然性がデザインの鍵になるということである。
"Contingency is the key"
It is quite natural to try to turn your consciousness to the outside because the range you are aware of is not all, but it is meaningless to turn your consciousness to the outside because even the outside is the range of recognition. In the end, it is not possible to recognize everything, and the idea of controlling everything is empty. The events at that time are synchronic coincidences, so there is no way to control them. The only thing that can be done is to increase the probability of an event, and to increase the probability, we are willing to accept that we cannot control the opposite of controlling. This is an architectural story, and contingency is the key to design.
バラバラな条件をひとつにまとめようとするのがモノづくりの典型的なパターンだろう。ただ、まとめるという行為はイレギュラーなものを排除することにもなる。
バラバラな条件をさらにバラバラにし、個々の条件が際立った状態でそのまま全体をひとまとめにするさらに上位の条件を設定すれば、イレギュラーなものまで含んだモノをつくることができる。その上位の条件はただ個々の条件のつながりだけを設定するようなものかもしれない。
"Make it even more disjointed"
A typical pattern of manufacturing is to try to combine disparate conditions into one. However, the act of putting together also eliminates irregular things.
By further disassembling the disjointed conditions and setting higher-level conditions that put the whole together in a state where the individual conditions stand out, it is possible to create a product that includes even irregular ones. The higher-level conditions may be like setting only the connection of individual conditions.
何かを極端に扱う時には何かを排除しなければならない。それは極端に扱うものに焦点を当て、極端に扱ったものを中心に据えるから他が排除されるが、排除されるものを知りたくて一時的に極端な扱いをすることもあるかもしれない。
排除されるものは今その瞬間には必要がないかもしれないが見方や焦点の当て方をかえれば再び必要とされるものである。だから、再び必要とされる見方や焦点の当て方を考えれば、それがすなわち新しい展開へと通じる。
"How to make a new development"
When dealing with something extreme, something must be excluded. It focuses on the extreme treatments and puts the extreme treatments at the center, so others are excluded, but there may be temporary extreme treatments to know what is excluded.
What is excluded may not be needed at that moment, but it is needed again from a different perspective and focus. So, if you think about the perspective and focus that you need again, that leads to new developments.
建築は全て一時的なものだと捉えるならば、建築に対する距離の取り方も変わる。建築を考える時、その存在に対してどこか相対的になることが多い。それは建築の経済的影響のせいか、はたまたスケールの大きさのせいか、建築を絶対的なものとすることに何故か躊躇する。しかし、一時的なものだと捉えるならば、建築を絶対的なものだとしてもいいような気になる。絶対的な建築を想起できれば、そこからこぼれ落ちる他者が明確になる。そのこぼれ落ちた他者が絶対的な建築に代わる新たな建築をつくる。
"Spilled others"
If you think of architecture as temporary, it also changes the way you distance yourself from architecture. When thinking about architecture, it is often somewhere relative to its existence. Perhaps because of the economic impact of architecture, or because of the size of the scale, I hesitate to make architecture absolute. However, if you think of it as temporary, I feel that architecture can be considered absolute. If you can recall the absolute architecture, the others who spill from it become clear. The spilled others create a new architecture that replaces the absolute architecture.
全ては一時的なものと捉えるならば、はじまりも終わりも無意味なものになる。それは着想も無意味であり、結論も無意味である。そうなると建築は成り立たない。全ては一時的なものだろうか。
建築もいつかは無くなる。ならば一時的であり、はじまりも終わりもないとなる。その様が建築のデザインに現れないことにいつも違和感を感じていた。ならば、その回答としてメタボリズムのような新陳代謝を繰り返す建築を想起すればいいのだろうか。今、中銀カプセルタワーは解体中である。
一時的な姿をスクリーンショットのように捉え実現化する、その繰り返しで良く、さらに建築はその大きさと不動故に経年変化をデザインに取り込まないといけないと思うがそこの部分に知恵を絞る事例は皆無に近い。
"Everything is a temporary end"
If everything is considered temporary, the beginning and the end will be meaningless. The idea is meaningless, and the conclusion is meaningless. If that happens, architecture will not be possible. Is everything temporary?
Architecture will disappear someday. If so, it is temporary and has no beginning or end. I always felt uncomfortable that such a thing did not appear in the architectural design. Then, as an answer, should we think of architecture that repeats metabolism such as Metabolism? The Nakagin Capsule Tower is currently being dismantled.
It's okay to capture and realize a temporary figure like a screenshot, and it's okay to repeat it, and because of its size and immobility, I think that secular variation must be incorporated into the design, but there are no cases where wisdom is narrowed down to that part. Close to.
両義的な意味を考えることができれば、他者として隠れていることに焦点を当てることができる。
単純に物事を捉えれば何かが抜け落ちる。抜け落ちたものは単純化する際には不要なものと見なされたが、単純化が何かの弊害を生む場合、解決するには抜け落ちたものの中に答えがある。
抜け落ちたものが他者であり、単純化の際には暗黙の了解で隠れていてすぐには把握できない。そこで、単純化した物事を再度両極端な状況で成り立つような両義的な状態を仮定することで隠れていた他者を炙り出すことができる。その時には最初から両義的な状態を仮定した場合とは違う他者が現れるかもしれず、よりクリティカルな他者になる可能性がある。
だから、他者を見つけ出すために一旦極端な単純化をすることは有効かもしれない。
"Burning others"
If you can think of ambivalent meanings, you can focus on hiding as others.
If you simply catch things, something will fall out. The omissions were considered unnecessary in the simplification, but if the simplifications do something wrong, there is an answer in the omissions to solve.
What is missing is another person, and when it is simplified, it is hidden by an implicit understanding and cannot be grasped immediately. Therefore, by assuming an ambivalent state in which simplified things are once again established in extreme situations, it is possible to expose others who have been hidden. At that time, another person may appear different from the one assuming an ambiguous state from the beginning, and it may become a more critical person.
So it may be useful to make some extreme simplifications to find others.
関係性を誘発する建築は自律していると言ってもいいだろうと考えた。関係性の中から生まれる建築は関係性から影響を受けているので自律しているとは言い難いがその建築があることで関係性が生まれる場合は関係性を生成する元であり関係性からの影響を受けていないので自律していることになる。
関係性からつくる建築でも関係性を生成する元であれば自律でき、関係性からの影響で歪むことも無い。
"Autonomy created from relationships"
I thought it could be said that the architecture that induces relationships is autonomous. It is hard to say that the architecture born from the relationship is autonomous because it is influenced by the relationship, but when the relationship is created by the existence of the building, it is the source of the relationship and is the source of the relationship. It is autonomous because it is not affected.
Even architecture created from relationships can be autonomous as long as it is the source of the relationships, and it will not be distorted by the influence of the relationships.
オブジェクト自体が自律して存在するには関係性を否定する必要があるかもしれない。ただ、関係性を否定してオブジェクトが成り立つことがなかなか想像できない。それは関係性を常に創作のヒントにしてきたからだろう。
関係性を断ち建築というオブジェクトを自律させる必要性は感じる。それは関係性に引っ張られて建築の在り方が歪んでいると思う時があるからである。関係性を尊重するあまりに建築が醜いものになる。それは関係性を尊重すること自体が悪い訳ではないが、度を超えていることを示している。
"Architecture distorted by relationships"
It may be necessary to deny the relationship for the object itself to exist autonomously. However, it is hard to imagine that an object would be established by denying the relationship. That's because relationships have always been a hint of creation.
I feel the need to break the relationship and make the object of architecture autonomous. This is because there are times when I think that the way architecture is distorted due to relationships. Architecture becomes too ugly to respect relationships. It's not that respecting relationships is bad in itself, but it shows that it's overkill.
バラバラに分断して配置したものの次の展開はどうなるのだろうか。バラバラに分断したのだから次は統合へ向かうのが普通に考えれば順当な流れかもしれない。ただその場合、バラバラに分断する前の統合の状態に戻らないし、戻さない。
あと、統合かバラバラかの話の中でどこに焦点を当てるかもある。統合かバラバラかはオブジェクトの関係性の問題だが、その場合関係性があることが前提になっている。関係性が無い場合はそもそもバラバラか統合かの話にはならないからだが、関係性の話をした時に気になるのは関係が前提になっていること。関係性はたくさんの拠り所にできるから、まず関係性をみるクセが身に付いているが、それはオブジェクトが関係性で成り立つことが前提である。その場合、おざなりにされているのはオブジェクト自体であり、関係性など無しにオブジェクト自体は存在できることを全く否定している。
"Affirmation of relationship, denial of existence"
What will happen to the next development of what is divided and arranged separately? Since it was divided into pieces, it may be a reasonable flow to move to integration next time. However, in that case, it does not return to the state of integration before it was divided into pieces, and it does not return.
Also, where may we focus on the story of integration or disparity? Whether it is integrated or disjointed is a matter of object relationships, but in that case it is assumed that they are related. If there is no relationship, it is not a matter of disjointness or integration in the first place, but when talking about relationships, what is worrisome is that relationships are a prerequisite. Since relationships can be based on many sources, we first have a habit of looking at relationships, but it is premised that objects are made up of relationships. In that case, it is the object itself that is being neglected, and it completely denies that the object itself can exist without any relationship.
無意識で当たり前のように行っていた階数による配置、重ね合わせることについて考えてみた。階段やスロープ、エレベーター、吹抜けなどで上下階をつなぎ重ね合わせし配置をするがそれらによってつながる以外は上下が床で分断されている。だから、上下階を別々のものとして考えることができるのだが、もう少し上下が混じり合うようなことができないかと思った。
その際にどうしても床で分断されることは避けられないから床全体を傾斜させて上下階の区別自体を無くす方法は今までたくさん試みられてきた手法で、それ自体は魅力的な空間ができあがるが、分断に対する対処の仕方がつながること以外にはないのか。
もしかしたら、さらに分断を進める、あるいは別の分断を持ち込むことにより分断自体から自由になれて上下が混じり合うような手法がないかと考えている。
"Mix the top and bottom"
I thought about arranging and superimposing by the number of floors, which was unconsciously done as a matter of course. The upper and lower floors are connected and arranged by stairs, slopes, elevators, stairwells, etc., but the upper and lower floors are separated by the floor except that they are connected by them. Therefore, I can think of the upper and lower floors as separate things, but I wondered if the upper and lower floors could be mixed a little more.
At that time, it is inevitable that the floor will be divided, so the method of tilting the entire floor to eliminate the distinction between the upper and lower floors is a method that has been tried many times, and it itself creates an attractive space. Isn't there anything other than connecting how to deal with the division?
Perhaps, I think there is a method that allows us to be free from the division itself and mix the top and bottom by further dividing or bringing in another division.
型が無い世界と型が有る世界、両極端を味わいたくて茶道を習いはじめたのかもしれない。生業としている建築の世界は型が無い。これについては異論があるかもしれないが、一定基準のレベルを満たしていれば何でも有りの創造の世界だと考えている。一方、茶道の世界は今のところ型が有り、その型の中での創造性はある一定の基準以上のレベルまで行けばあるのかもしれないが、その型は崩せない。だから、型の有無でいえば、建築と茶道は真逆の世界であり、一方から真逆の片方を眺めることで気づくことがたくさんある。
"Presence or absence of mold"
Perhaps he started learning the tea ceremony because he wanted to experience the extremes of a world without a mold and a world with a mold. The world of architecture, which is a living business, has no pattern. There may be some disagreements about this, but I think it's a world of creation where anything meets a certain standard level. On the other hand, the world of tea ceremony has a pattern so far, and the creativity in that pattern may be reached to a level above a certain standard, but that pattern cannot be broken. Therefore, in terms of the presence or absence of molds, architecture and tea ceremony are the opposite worlds, and there are many things that can be noticed by looking at one of the opposites.
コントロールできるものとコントロールできないものがあり、コントロールされたものとコントロールされないものがある。コントロール自体を主題にするのは全てをコントロールしたい欲望かもしれず、この世界は全てコントロールされているのが良いとする考えが前提かもしれない。それに対しては反論したくなり、コントロールから逃れる所にクリエイティブなことを見つけたくなる。
ただ結果的に良いものが出来上がれば、それがコントロールされていようが、偶然であろうがどちらでも構わない。要は良いものを生み出すプロセスを考えていく中で偶然とコントロールのバランスを最適にとりたいのである。
"Balance of control"
Some are controllable and some are uncontrollable, some are controlled and some are uncontrolled. The subject of control itself may be the desire to control everything, and the premise that this world should be all controlled. I want to argue against it, and I want to find something creative where I can escape control.
However, if the result is a good one, it doesn't matter whether it is controlled or accidental. In short, I want to optimally balance control by chance while thinking about the process of producing good things.
偶然に生まれたものはコントロールされたものではないから評価に値しないだろうか。何かが生まれる仕組みの中に偶然性を盛り込めば、それは確かに偶然生まれたものとなるが、その仕組み自体はコントローされたものだがら、少し引いて見てみればそこには偶然という名のプロセスパーツがあるだけになる。
だから極端なことを言えば、サイコロを振るという仕組みを決めてしまえば、サイコロの目が何になろうと、結果は全てコントロールされたものであり、偶然性という作為ゼロのことまでコントロールされたものの範疇に含めることができる。
"Control zero action"
Isn't it worthy of evaluation because what was born by chance is not controlled? If you include contingency in the mechanism by which something is born, it will certainly be born by chance, but the mechanism itself is controlled, but if you look at it a little, there is a process called chance. There are only parts.
So, to put it in the extreme, if you decide on a mechanism to roll the dice, no matter what the dice roll, the result is all controlled, and even the zero act of chance is controlled. Can be included in.
不安定でコロコロと変わるものは捕まえようが無いがもし捕まえようとしたら、こちらも不安定で不確実な手段を用いて、どこかの瞬間に共鳴して捕まえることができるかもしれない。
不安定で不確実な手段とは、別の言い方をすれば偶然性を伴う手段であり、それは全てをコントロールできない手段である。その手段をデザインしてみたら、不確実なものがデザインの範疇におさまるかもしれない。
"Catch unstable things"
There is no way to catch something that is unstable and changes, but if you try to catch it, you may be able to resonate and catch it at some moment using unstable and uncertain means.
Unstable and uncertain means, in other words, means with contingency, which is a means out of control of everything. If you try to design the means, uncertainties may fall into the category of design.
他者性に埋没して見える世界は青い海か赤い海か。きっと青い海だから他者性になるのだろうが、あらゆる可能性を掘り起こした後の痕跡だらけではすぐに青い海には結びつかない。
きっと他者性の獲得にはもう一段階の捻りなり展開が必要かもしれない、簡単に考えれば、それは新しい組合せになるだろう。
"Creating otherness"
Is the world buried in otherness the blue sea or the red sea? I'm sure it will be a stranger because it is a blue sea, but if it is full of traces after digging up all the possibilities, it will not immediately lead to the blue sea.
I'm sure that the acquisition of otherness may require another twist and development, in a nutshell, it will be a new combination.
効率から生まれるものは無駄が無いものになるが、無駄を効率的に配置したら、それはそれで効率的ではないのかと思った。
地である効率と図である無駄を反転させたような話だが、図である無駄を効率的に配置すれば、地か図か、効率か無駄かの話が棚上げになり、別の視点が持てるのではないかと考えた。
"Efficiency or waste"
What is born from efficiency will be lean, but if waste is arranged efficiently, I wondered if it would be efficient.
It's a story that reverses the efficiency of the ground and the waste of the figure, but if the waste of the figure is arranged efficiently, the story of the ground or the figure, efficiency or waste will be shelved, and another perspective will be given. I thought I could have it.
さらに効率を推し進めるとむしろ効率から離れることができるのではないかと考えた。効率的になる部分を増やしてより効率化すると、それまで効率について考える必要があったことが無くなり、効率自体を考える必要が無くなる。その結果、効率から自由になれる。
だとすれば、さらに効率化する時の手段を固有のものにすれば、効率化を推し進めながら固有のものが生まれ、生まれたものは効率とは無縁のものにできる。
"Free from efficiency"
I thought that it would be possible to move away from efficiency by further promoting efficiency. If we increase the efficiency and make it more efficient, we no longer have to think about efficiency, and we don't have to think about efficiency itself. As a result, you are free from efficiency.
If that is the case, if the means for further efficiency improvement are made unique, unique things will be born while promoting efficiency improvement, and the born things can be unrelated to efficiency.
ひとつの決まり事をつくり、その決まり事はそこでの固有のものだが、その決まり事をハンコのように繰り返しながら、しかしその時々でハンコのどの部分を押さえるのかを偶然的に決めようと考えた。
ハンコは効率的なもの、ただ、押し方を偶然性に頼ったら予想もしなかったものが現れるかもしれない。効率は担保しながら自分でも予想していないようなものを見てみたい。
"A coincidental stamp"
I made a rule, and the rule is unique to it, but I thought about repeating the rule like a stamp, but accidentally deciding which part of the stamp to hold at that time.
Hanko is efficient, but if you rely on chance to push it, you may find something unexpected. I want to see something that I didn't expect while guaranteeing efficiency.
内部から詰めるか、外部から詰めるか、この内部と外部という両義な問題はいつも頭にある。たぶんそれはどちらかを決めて、そのスタンスではじめれば良いのだろうが、その時その時でこの内部と外部の両義のどちらに振るかを決めていたので、その選択が重要になった。
ちょっと進めて内部も外部もお互いに依存しあうような切り口があるかどうかを考えてみる。内部を決める時に外部を必要とする、あるいは外部を決める時に内部を必要とする、そのような関係性がある切り口で建築が部分から全体ができあがればいい。
それは内部と外部の関係性をリフレーミングするようなことかもしれないが、新たな自由と秩序が手に入るような気がする。
"Depending on each other"
Whether to pack from the inside or from the outside, this ambiguity between the inside and the outside is always in my head. Maybe it's better to decide which one to start with, but at that time I was deciding whether to swing inside or outside, so that choice became important.
Let's go a little further and consider whether there is a way to depend on each other both inside and outside. It would be good if the whole building could be completed from the part with such a related cut that needs the outside when deciding the inside, or needs the inside when deciding the outside.
It may be like reframing the relationship between the inside and the outside, but I feel like I have new freedom and order.
プロセスは効率的なことをさらに進めて行うが、結果的には効率的なプロセスから導き出されるものから一番遠い所に着地したいと考えている。
効率にもバリエーションがあるとしたら、その場所での一番効率的なことを選択し、その結果出てくるものはその場所固有のものであり、もしかしたら他の場所では効率的ではないかもしれない。それはちょっと引いて見れば、結果的には効率的なプロセスから導き出されたものから一番遠いものになるかもしれない。
"The farthest thing"
The process goes a step further in efficiency, but in the end we want to land farthest from what is derived from the efficient process.
If there are variations in efficiency, choose the most efficient one at that location, and the resulting results are specific to that location and may not be efficient elsewhere. not. At a glance, it may end up being the furthest from what was derived from an efficient process.
先日見たある絵画は桜を題材にしたものだった。ポロックのアクションペインティングの指向性を高めて、青空に映える桜というモチーフを表現していた。どこまでが具象でどこまでが抽象かがわからない、作者本人も語っていたが、具象と抽象をつなぎ行ったり来たりする。
面白いことに絵画から距離を取りある一点から見ると実際の花が咲き乱れる自然の桜のように見えるが、間近で見ると単なる抽象絵画になってしまう。
距離が近ければ絵画と自分との間に差し挟むものは何も無く直接的に対峙することになるからそのままの絵画としての桜が目の前に出現する。距離を取り絵画から離れれば絵画と自分との間に別の要素が入り込み、絵画としての桜はその別の要素を通して間接的に出現する。別の要素が入り込むということが絵画の桜を自然の桜のように見せるのだろう。
自然の桜はどこから見ても、近くても遠くても、自然の桜に見える。細密に描いた桜の絵画はどこから見ても絵画の桜で自然の桜のようには見えない。
具象度を落とし遠くなることで実物との差異が生まれる。その差異が自身が持っている桜に対する感性と共鳴し増幅され、無意識のうちに増幅された実物との差異を埋める作用が起こり、自然の桜に浸るような感覚に包まれる。だから絵画との距離は人によって違う。
"Is it far or near?"
One of the paintings I saw the other day was about cherry blossoms. By increasing the directivity of Pollock's action painting, he expressed the motif of cherry blossoms that shine in the blue sky. The author himself said that he didn't know how much concrete and how abstract he was, but he goes back and forth between concrete and abstract.
Interestingly, when viewed from a certain point away from the painting, it looks like a natural cherry blossom in full bloom, but when viewed up close, it becomes just an abstract painting.
If the distance is short, there is nothing to put between the painting and myself, and they will face each other directly, so the cherry blossoms as the painting will appear in front of me. If you take a distance and move away from the painting, another element will enter between you and yourself, and the cherry blossoms as a painting will indirectly appear through that other element. The inclusion of another element may make the cherry blossoms in the painting look like natural cherry blossoms.
Natural cherry blossoms look like natural cherry blossoms no matter where you look, whether they are near or far. The detailed painting of cherry blossoms is a painting of cherry blossoms and does not look like a natural cherry blossom from any angle.
By reducing the degree of concreteness and getting far away, a difference from the real thing is created. The difference resonates with one's own sensibility for cherry blossoms and is amplified, and the action of filling the difference with the amplified real thing occurs unknowingly, and it is wrapped in the feeling of being immersed in natural cherry blossoms. Therefore, the distance from the painting varies from person to person.
時間が切断されるものをつなげようとすると無理が生じるかもしれないが、そのままにしておくと時間に張り付いている記憶が消滅してしまう。きっと切断を繰り返すことが当たり前になっているから記憶の消滅を何とも感じないようになっているのかもしれない。
切断してしまう方が楽でつなげる方は労力がいる。切断し新しい時を刻むようにつくり替えてしまえば、切断した時点がスタートになるので全てがリセットされ身軽になるが、つなげる方はそれまでの記憶を継承するのではじめから記憶との関わりが伴い対処を迫られる。
ただ、記憶とのつながりはその人、その場所、そのものの固有のものだから消滅してしまうことには抵抗感があり、いつもこの抵抗感との兼ね合いが建築デザインには伴う。
"Resistance to the disappearance of memory"
If you try to connect something that cuts time, it may be impossible, but if you leave it as it is, the memory stuck to time will disappear. I'm sure it's normal to repeat disconnection, so it may be that I don't feel the disappearance of my memory at all.
It is easier to disconnect and it is more laborious to connect. If you disconnect and remake it so that it ticks a new time, everything will be reset and lighter because the point of disconnection will be the start, but the person who connects will inherit the memory so far, so it will be dealt with from the beginning. Is pressed.
However, since the connection with memory is unique to the person, the place, and itself, there is a sense of resistance to disappearing, and the balance with this sense of resistance always accompanies architectural design.
ある一点を見つめていると周りはボヤけてくる。まさにある一点を見つめることがものづくりかもしれない。次のことを考えているつもりでも、ある一点を見つめる範疇から逃れることができておらず、周りがボヤけている様を自身の投影に利用する。ある一点を見つめることは他の部分を捨てて断絶しているように見えるが、一点に集約して周りを引き連れようとしているようにも見える。解釈のちがいは断絶か連続かだが、断絶せずに次のことを考えていても何も変わらない、連続では何も変わらない。次のことを何かを変えたいならば、一点を見つめながらボヤけている周りに他者を投影したい、それで断絶できる。
"Projection of others"
When I stare at a certain point, the surroundings become blurred. It may be manufacturing to look at exactly one point. Even if I think about the following things, I haven't been able to escape from the category of staring at a certain point, and I use the appearance that the surroundings are blurred for my own projection. Looking at one point seems to be cut off by throwing away the other parts, but it also seems to be trying to consolidate into one point and take the surroundings. The difference in interpretation is whether it is discontinuous or continuous, but nothing changes even if you think about the following without discontinuity, and nothing changes in continuous. If you want to change something to the next thing, you want to project another person around the blur while staring at one point, and you can cut it off.
全体があり部分が決まるような流れから脱したいとしたならば、ひとつの方法としてはその流れを切断するように偶然性を取り入れる。何の疑いもなく全体から部分を考えていると全てが予定調和の範疇におさまってしまう。
ひとつサイコロを振ることにしよう、たったそれだけで予定調和が切断され、面白いことに結果が気になりだす。
サイコロは不真面目かもしれない、しかし、予定調和も真面目とはいえない。予定調和は何も考える必要がないだけで、むしろサイコロを導入しようと考えるだけでも現状に何かを変化を、そうしたらもっと良くなるかもと考えるだけ大真面目である。
"Roll the dice seriously"
If you want to get out of a flow that is whole and part-determined, one way is to take in chance to cut off that flow. If you think about the part from the whole without any doubt, everything falls into the category of planned harmony.
Let's roll one dice, and that alone will break the planned harmony, and interestingly the result will be worrisome.
The dice may be unscrupulous, but the planned harmony is not. Scheduled harmony doesn't just have to think about anything, but rather just thinking about introducing dice is serious enough to think about something that will change the status quo and that it will be even better.
偶然性をコントロールできないかと考えている。偶然性をコントロールするとは一見矛盾することの組み合わせだが、全てが偶然である必要はないし、全てをコントロールする必要もないと考えれば、一見矛盾することに妥協点は見出せる。
コントロールし、ある枠内で偶然性が起こる。偶然の結果で現れるものが最終結果になれば、それは偶然性を帯びたものと呼べるだろう。
偶然性をコントロールすることはプロセスデザインでもあり、結果を手放し、結果をコントロールしないことをデザインすることでもあり、結果に収束していく流れを切断することでもある。
何を持って決定するかとした時の基準が偶然性に委ねられることはものづくりの世界ではタブーかもしれないがアートの世界では当たり前である。ならば、一考の余地はあるかもしれないと思った。
"Leave it to chance"
I'm wondering if I can control the contingency. Controlling contingency is a combination of seemingly contradictory things, but if you think that everything doesn't have to be accidental and you don't have to control everything, you can find a compromise in seemingly contradictory.
Control and chance happens within a certain frame. If what appears as a result of chance is the final result, it can be called contingent.
Controlling contingency is also process design, letting go of the result, designing not to control the result, and cutting off the flow of convergence to the result.
It may be taboo in the world of manufacturing that the criteria for deciding what to have is left to chance, but it is commonplace in the world of art. Then, I thought there might be room for consideration.
カルサイトという石がある。必ず菱形に割れるその石は半透明なのでかざすと文字や線が透けて見えるが、石の性質上必ずブレて見える。
自分の目と線や文字の間に何も無く直接的に見ることができるならば、ブレることなくはっきりと見えるが、自分の目と線や文字の間にカルサイトが入ると見え方はカルサイトの性質に依存し間接的に見ることになる。それはカルサイトの分だけ距離が遠くなったとも言える。
日常の中ではカルサイトが間に入るように距離を遠くして間接的な見方をしていることが多く、本来はブレて見えているはずだが、自分の目が自動補正しブレずに見せていると思う。
だから、直接的に見ないとダメとかという話では無くて、むしろ日常の中では直接的に見ることは不可能だから、カルサイトに当たるものを意識して入れ替えながら見て、その時のブレの見え方の差異を面白がる方が良いのでは。
"Interesting blur"
There is a stone called calcite. The stone, which always breaks into a rhombus, is translucent, so when you hold it over, you can see through the letters and lines, but due to the nature of the stone, it always looks blurry.
If you can see directly without anything between your eyes and lines or letters, you can see clearly without blurring, but if you put calcite between your eyes and lines or letters, you will see it. It depends on the nature of calcite and will be seen indirectly. It can be said that the distance has increased by the amount of calcite.
In everyday life, I often take an indirect view by increasing the distance so that calcite is in between, and although it should look blurry, my eyes automatically correct it and show it without blurring. I think it is.
Therefore, it is not a story that you have to look directly, but rather it is impossible to see it directly in everyday life, so look at it while consciously replacing what hits calcite, and how the blur looks at that time. I think it's better to be amused by the difference.
何事も遠くなればブレや行き違いなどの差異が生まれ誤解が生じるが、誤解や行き違いをネガティブではなくポジティブに捉えれば、良し悪しも無いどっちつかずの状態になり、それはひとつの側に固定されていない状態だから、そこからどのようにでも変化させることができる。
逆に近いと相当正解に言い当てることができてしまうが故に差異が生まれずにかえって融通が利かなくなるとも言える。
遠くでもなく近くでもないバランスをとることができれば一番良いのだがそうもいかないので、差異をポジティブに捉え主題にし拡張してみると、バランスを取らない方が良い結果が生まれるかもと思い、遠いか近いかの距離感の見方がちょっと変わった。
"Is it far or near?"
If everything goes far away, differences such as blurring and misunderstandings will occur and misunderstandings will occur, but if you catch misunderstandings and misunderstandings positively instead of negatively, you will be in a state of neither good nor bad, and it is fixed to one side. Since it is not in a state, it can be changed in any way from there.
If it is close to the opposite, it can be said that the answer is quite correct, so there is no difference and it is rather inflexible.
It would be best if we could balance neither far nor near, but that is not the case, so if we take the difference positively and expand it to the subject, I think that it is better not to balance, so it is far. The view of the sense of distance, whether close or near, has changed a little.
時が流れれば必ず変化していく、それは人も物も同じだが、時による変化が絶対的なことと捉えれば、時の変化自体が人や物の何か固有なことを絶対的に表現してしまうと考えることもできる。
その時問題になるのが切断か継承かであり、時の流れを切断することで固有なことまで切断し無いことにするか、時の流れをつなげることで固有なことを継承するか、モダニズムの考えは切断を選んできた。
ポストモダニズム以降はいかに切断されたものをつなげるかの歴史であるが、今だに切断が優位である。切断する方が資本主義経済と同調しやすくメリットがあるからだろう。中には時の流れをつなげるという見せかけまで存在させて切断する。
切断されるものは放っておいて、つなげることができるものだけでもつなげていくのが固有なことを継承する現実的手段だと思うが、どうも頷けない。それは切断に可能性が見出せないのかと思ってしまうからである。
"Is there a possibility of disconnection?"
It always changes as time goes by, which is the same for people and things, but if we consider that the change with time is absolute, the change in time itself absolutely expresses something unique to people and things. You can think that it will be done.
At that time, the problem is disconnection or inheritance, and whether to cut off the flow of time so that it does not cut off the unique things, or to connect the flow of time to inherit the unique things, or to inherit the unique things of modernism. The idea has chosen to disconnect.
Since postmodernism, it is a history of how to connect cut things, but cutting is still dominant. This is probably because disconnecting is easier to align with the capitalist economy and has the advantage. There is even a pretense that connects the flow of time inside and cuts.
I think it's a realistic way to inherit the uniqueness of leaving things that are cut off and connecting them only with things that can be connected, but I can't nod. That is because I wonder if there is a possibility of disconnection.
普通にいったら効率に飲み込まれてしまうところを別の効率を持ち出してきて違う結果を生み出せないかと考えている。
最近、効率的=同一的=全体的という図式から逃れてたくて、非効率、不同一、部分について考えたりするが、反対を考えても結局は同じ文脈で考えていることになるので、度を超す位に効率的=同一的=全体的を推し進めたらどうなるかを考えてみている。
例えば、絶対と呼べるような効率的な状態は不安定になるのではないか。絶対的な効率は少しでもバランスを崩したら非効率に転じるのではないか。それは結果的に効率から逃れてまた別の状態をつくることができるのではないか。
"Is absolute efficiency inefficient?"
I'm wondering if I can bring out another efficiency and produce different results where it would normally be swallowed by efficiency.
Recently, I've been thinking about inefficiencies, inconsistencies, and parts because I want to escape from the scheme of efficiency = identity = overall, but even if I think about the opposite, I end up thinking in the same context. I'm thinking about what would happen if I pushed forward with efficiency = identity = overall to the extent that it exceeds.
For example, an efficient state that can be called absolute may become unstable. Absolute efficiency may turn into inefficiency if the balance is lost even a little. As a result, it may be possible to escape from efficiency and create another state.
偶然的に生まれることははじめから全体を持たないことであり、部分の生成が最初にあり、いくつか部分が増えていった時に部分同士の関係性が生まれ全体が見えてくる。
ただ存在としての全体ははじめには無いが、コントロールをしようとした時には指針のようなものが必要になるだろう。だがその前にコントロールする必要があるのかということもある。コントロールすればそこに偶然が生まれるのかという疑問もあるが、何かを生み出す場合にコントロールがそもそも必要か。
決定できれば良いのだから、コントロールせずに決定できる方法か、そもそも決定しないことを受け入れる曖昧な状態が最終的な全体の状態で良いとなればいいのか。ならば、時間を持ち出してきて、ある時間で切断した状態、その時間の偶然性による結果が最終で良いともいえるか。
"A coincidence by time"
Being born by chance means not having the whole from the beginning, the generation of the part is first, and when some parts increase, the relationship between the parts is born and the whole becomes visible.
It's not the whole thing at first, but when you try to control it, you'll need something like a guideline. But before that, it may be necessary to control it. There is a question as to whether control will create a coincidence, but is control necessary in the first place when creating something?
Since it is only necessary to make a decision, is it a method that can be decided without control, or is it good if the ambiguous state that accepts not making a decision in the first place is good in the final overall state? If so, can it be said that the final result is the state of taking out the time, disconnecting at a certain time, and the accidental result of that time?
建築がつくられていく上で必然的にそうなったのではなくて偶然的にそうなったようにできないかと考えている。必然的とは建築計画学的な積み重ねや暗黙の了解も含めた同時代的な表現であり、偶然的とはそれらの意図が及ばないところで決定されることである。
建築計画学的な積み重ねや暗黙の了解も含めた同時代的な表現は全体的に同一なものを生み出す方向に力が働く。それに対して偶然的は同一なものを生み出す力とは断絶して、とてもフラットな状態で何にでもなるし、何にでも変化する。それ故に偶然的は目の前の事柄を重視し、全体的な関係性は二の次になる。
だから、偶然的ははじめから全体的な結果を生み出すことはできず、目の前の事柄に対して個別に結果を生み出しながら、ある時全体が現れるの待つ。
"Wait by chance"
I'm wondering if it could happen by chance, not inevitably in the construction of architecture. Inevitable is a contemporary expression that includes architectural planning accumulation and implicit understanding, and accidental is determined where those intentions do not reach.
Contemporaneous expressions, including architectural planning accumulations and implicit understandings, work in the direction of producing the same thing as a whole. On the other hand, by chance, the power to produce the same thing is cut off, and it becomes anything in a very flat state, and it changes to anything. Therefore, by chance, the matter in front of us is emphasized, and the overall relationship is secondary.
Therefore, by chance, it is not possible to produce an overall result from the beginning, and while producing an individual result for the matter in front of us, we wait for the whole to appear at a certain time.
効率的でありたいと思うのと同時に遊びたいし効率的じゃないことも必要かなと思ってしまう。効率的か非効率的か、非効率的という言葉の響きにはネガティブな印象しかないが、どちらも効率を扱う上での立ち位置の違いだけなような気もする。
ちょっと角度を変えて、効率をさらに進めたらどうなるだろうか。効率というとムダを省きシンプルにするようなイメージもあるが、進め方や進んだ先は1つではないだろう。様々な効率のバリエーションがあった場合、どれもが効率的ではある訳だから、どれを選んでも良いとして、何を判断基準として選ぶかと考えてみた。それを考えることが効率ということに対するささやかな遊びになるような気がして。
"For efficiency"
At the same time as I want to be efficient, I also want to play and I think it is necessary to be inefficient. There is only a negative impression on the sound of the words efficient, inefficient, and inefficient, but I feel that both are just different positions in dealing with efficiency.
What if we change the angle a little and further improve efficiency? When it comes to efficiency, there is an image of eliminating waste and simplifying it, but there is probably more than one way to proceed and where to go. When there are various efficiency variations, all of them are efficient, so I thought about what to choose as a criterion. I feel that thinking about it is a small play for efficiency.
一貫性が大事だなと思うことがよくある。それはコントロール感と言い換えてもいいと思うが、自分で制御しながらある範囲内で物事が行える感覚を保ちたいと思う。一貫性やコントロール感などと思うと、何か目標がありそこに向かうようなことをイメージするかもしれない。最近も何を目指しているのと言われたことがあるが、目の前の個々に起きる複数のこと、それぞれに関連性があってもなくてもいいのだが、に対しての態度のようなものが一貫性やコントロール感で、具体的な目標が無くても、むしろ無い方がいいくらい、もし目標を持つとしたら抽象的で捉えどころが無い方が様々な工夫をする余地があっていいと思う。
"Multiple things"
I often think that consistency is important. It can be rephrased as a sense of control, but I want to maintain a sense of being able to do things within a certain range while controlling myself. When you think about consistency and control, you might imagine that you have a goal and you are heading for it. I've been told what I'm aiming for lately, but it seems to be an attitude toward multiple things that happen individually in front of me, whether they are related or not. What is consistency and control, even if there is no concrete goal, it is better not to have it, and if there is a goal, there is room for various ingenuity if it is abstract and elusive. I think
自身を確立する、あるいは違いを生み出すにはそれまでの流れとは違うものを生み出さなくてはならない。それはとてもビジネス的だが、それも飲み込まなくては先には進めないと人は言い、確かにと頷く。
その場合2通りある、ひとつはそれまでの流れに対してアンチテーゼを示すことであり、それはよくあり、大概はそれで自身を確立しようとする。それは今までの流れと関連性を持たせることができるから安心安全最大限のリスクヘッジをして自身を確立しようとできるだろう。ただし、それでは大きな流れ、うねりはつくれない。
断絶を狙う、自身を確立するもうひとつの方法である。断絶を起こす、それは新しい流れを自らつくることである。ただし、それは今までの流れを全否定するのでは無く、今までの流れをさらに度を超える位に推し進めることだと気がついた今日。
"Making a break"
In order to establish yourself or make a difference, you have to create something different from the previous flow. It's very business-like, but people say that if you don't swallow it, you can't move on, and nods.
In that case, there are two ways, one is to show antithesis to the previous flow, which is common and usually tries to establish itself with it. Since it can be related to the current flow, it will be possible to try to establish itself by performing maximum risk hedging for safety and security. However, that does not create a big flow or swell.
Another way to establish yourself, aiming for a break. To cause a break, it is to create a new flow by oneself. However, today I realized that it is not to completely deny the flow so far, but to push the flow so far to a higher level.
何かをデザインする時に効率をどのように扱うかを考える場合がある。効率を別の言い方をすれば無駄を省くことなのでレス イズ モアと考えて、より洗練させていく方向でデザインすることができる。また、逆にレス イズ ボアと考えて、効率をデザイン上で考慮することは避けたいと考えることもできる。この場合は効率と非効率を天秤にかけるのだが、非効率も効率の範疇だとしたら、効率や非効率に対して超効率のような普通の効率とは違う絶対的な効率を考えれば、それは初源のような状態かもしれないし、飽和状態にあり何も省くことができない状態かもしれないが、効率だけで何かを規定してしまう力を持ち、逆に効率以外のことが入り込む余地が生まれると考えてみた。
"Thinking about super efficiency"
Sometimes we think about how to handle efficiency when designing something. In other words, efficiency can be considered as less is more because it eliminates waste, and it can be designed in the direction of further refinement. On the contrary, it is possible to think of it as a less bore and avoid considering efficiency in the design. In this case, efficiency and inefficiency are weighed, but if inefficiency is also a category of efficiency, considering the absolute efficiency that is different from ordinary efficiency such as super efficiency with respect to efficiency and inefficiency, It may be a state like the first source, or it may be in a saturated state and nothing can be omitted, but it has the power to define something only by efficiency, and conversely there is room for things other than efficiency to enter. I thought that would be born.
良し悪しは別として逆張りをしたくなる。大概のことには王道と呼ばれるような大多数が支持するものがあり、その逆の少数支持のものも存在する。通常の逆張りはその少数支持のものを祭り上げることだが、もう少し引いて考えて、この大多数対少数という構図自体に対して逆張りをしたくなる。この構図からこぼれ落ちるものに焦点を当てたくなる。そもそもの前提にこのこぼれ落ちるものを含む可能性が無いからで、こぼれ落ちるものに焦点を当てることで前提自体を変えてしまえば新しい構図をつくることができる。
"Creating a new composition"
Regardless of whether it is good or bad, I want to make a contrarian. Most of them are supported by the majority, which is called the royal road, and vice versa. The usual contrarian is to celebrate the minority support, but with a little more thought, I want to contradict the composition of majority vs. minority itself. I want to focus on what spills out of this composition. There is no possibility that this spilling thing is included in the premise in the first place, so if you change the premise itself by focusing on the spilling thing, you can create a new composition.
ちょっと思うことは周りを見渡せば他者性なるものに溢れているのにちっとも他者性を感じないことである。それは他者性なるものにもネットやSNSなどの受け皿があり、他者性なるものをいちいち祭り上げる必要がないからかもしれない。ただ、そうなると結局は全てが同じ地平の上にいて、いる場所が違うだけになっていき、他者性という単なるアドレスを持っているに過ぎなくなる。
だから、さらにちょっと思うことは未来がそのように全て同じ地平に収束していく方向ならば、過去を見て記憶と結びつけて収束の過程にノイズを起こして他者性なるものをつくり出したらどうか。
"Make noise in memory"
What I think for a moment is that if you look around, you will find that you are full of other things, but you do not feel other things at all. It may be because there is a saucer for other things such as the Internet and SNS, and it is not necessary to raise the festival for other things one by one. However, in the end, everything is on the same horizon, and the place where they are is different, and they just have the address of otherness.
So, what I think a little more is that if the future is all in the direction of converging on the same horizon, why not look at the past and connect it with memory to create noise in the process of convergence and create something else.
全体を全て同列に扱うことは中々難しいが、仮に全てを同列に扱うことができたとしたら、そこからこぼれ落ちるものは何かを考えみた。集合住宅の話である。個別に同列に扱えば、個別の関係性は全てイコールになるはずだがそのようなことはあり得ない気がする。
関係性がイコールにならない要因がこぼれ落ちていることかもしれない。ならば、今度はこぼれ落ちるものを主体に全体を考えようとする。そうするとたぶん全体を全て同列に扱えなくなるが、同列に扱おうとする前の状態とは違うものが生まれるだろう。
"Try changing the subject"
It's difficult to treat everything in the same line, but if I could handle everything in the same line, I wondered what would spill out of it. It is a story of an apartment house. If treated individually in the same line, all individual relationships should be equal, but I feel that such a thing is impossible.
It may be that the factor that the relationship is not equal is spilling out. Then, this time, I will try to think about the whole, focusing on what spills. Then you probably won't be able to treat the whole thing in the same row, but you'll end up with something different than before you tried to treat it in the same row.
全体としての統一感は求めていないが個々のつながりがそれぞれで違いながらもあるようにデザインしたいと考えている。集合住宅の話であり、効率的にプランニングしたいと考えるのが常套手段であるが、その効率性は建築計画上だけでそれが事業性の高さに通じるからだが、事業性の高さは別の手段で担保すれば良い。
そもそも全体を考えることを止めることができないかと考えている。集合住宅以外でも建築は全体から部分へと考察が流れていくが全体と部分という分け方では無くて、全てが同列に扱われその間の関係性を考察するように設計ができないかと考えている。
"Same line, not the whole"
I don't want a sense of unity as a whole, but I want to design it so that each connection is different. It is a story of an apartment house, and it is a common practice to want to plan efficiently, but the efficiency is only in terms of architectural planning and it leads to high business feasibility, but high business feasibility is different. It should be secured by the means of.
I'm wondering if I can stop thinking about the whole thing in the first place. Even if it is not an apartment house, the consideration of architecture flows from the whole to the part, but it is not a way of dividing the whole and the part, but I think that it can be designed so that everything is treated in the same line and the relationship between them is considered.
全く見過ごされて外されてしまっていることはあるルールの中での話であり、別のルールを設定することにより見過ごされ外されていることに焦点を当てることができる。そもそものルールを変える話だが、揺れ動く関係性が何にでもどこにでもあると考えることができれば、絶対的なことなどは存在せずに常に状況は入れ替えて考えることができ、それを考えでは終わらせずに実践さえすれば目の前の状況やことやものも変わり、違った状況やことやものをつくり出せる。それはデザイン行為であり、別のルールを設定することもデザインの範疇になる。
"Set another rule"
What is totally overlooked and missed is a story within one rule, and by setting another rule we can focus on what is overlooked and missed. It's a story that changes the rules in the first place, but if you can think that the swaying relationship is everywhere, you can always think about the situation by changing the situation without absolute things, and end it with thinking. If you practice it without doing it, the situation, things and things in front of you will change, and you can create different situations and things. It is a design act, and setting different rules is also a category of design.
アクティビティが空間に与える影響を考えている。アクティビティは機能より発生すると考えれば、機能が空間に与える影響と読み替えてもいいが、それでは当たり前過ぎて面白くない。
アクティビティを限定したり、制限したりしたら空間は何か変わるだろうか。アクティビティがダイレクトに空間になる場合、例えば、スロープ状の動線空間などは当たり前だがスロープを上るとうアクティビティに限定していることになる。これは単一のアクティビティで1つの空間をつくることは可能だということだが、制限された範囲での複数のアクティビティによる空間を考えた場合はどうなるだろか。空間は単なる受け皿にしかならないだろうか。
"Space with limited activities"
I am thinking about the impact of activities on space. If you think that activity occurs more than function, you can read it as the effect that function has on space, but that is too obvious and not interesting.
Will limiting or limiting activities change anything in space? When the activity becomes a space directly, for example, a slope-shaped flow line space is natural, but it is limited to an activity that goes up the slope. This means that it is possible to create one space with a single activity, but what if we consider a space with multiple activities within a limited range? Is the space just a saucer?
何かを生み出すプロセスに目を向けている。ものづくりの場合、完成した物が成果品として価値を持つので、どうしても結果にフォーカスすることになるが、結果を変えようとするならばプロセスを変えなければ何も変わらない。
同じプロセスでは、コンセプトや考え方を変えても結果は今までの範疇に収まってしまう。だから逆に考えると、結果をあと少し変えたい時やもう少しで目指す結果に辿り着きそうな時はプロセスを変えない方が良い。プロセスに目を向けることで、直接的に結果をデザインしようとするのでは無く、プロセスをデザインすることで自ずと結果が変わってくる。
最近よく考えるのは結果の一貫性では無く、プロセスの一貫性である。それは常に同じプロセスを踏むということでは無くて、常にプロセスに手を入れて、今求めたい結果を出すためのプロセスに最適化していくことだと考えている。
"Process optimization"
We are looking at the process of creating something. In the case of manufacturing, the finished product has value as a deliverable, so the focus is always on the result, but if you want to change the result, nothing will change unless you change the process.
In the same process, even if you change the concept or way of thinking, the result will be in the same category as before. So, if you think about it the other way around, it's better not to change the process when you want to change the result a little more or when you are about to reach the desired result. By looking at the process, rather than trying to design the result directly, designing the process naturally changes the result.
What I often think about these days is not the consistency of the results, but the consistency of the process. I think that it is not always the same process, but always working on the process and optimizing it to the process that produces the desired result.
意識に物が現れそして消えていく、これを繰り返すのが広告だとしたら、それは建築でも同じだと思った。日常的に建築と広告をたくさん目にするが明確に意識して覚えているものは数少ない。脳の記憶容量には限界があり全てを覚えていたら脳がパンクしてしまうから、目にはするが無意識にほとんどを覚えないようにしてしまうのだろう。
ただ、これは人の感性に訴えてくる広告や建築に対して起こることである。特に広告は人の感性を刺激して記憶に残すことを広告効果のひとつにしているから、意識の取捨選択の対象になりやすく、ほとんどの広告が現れては消えるを繰り返す。
もし建築や広告が人の感性に訴える量の度が超えて、人の感性が働かなくなるくらいに一度にたくさんの影響を与えることになったとしたら、意識の取捨選択の対象から外れて建築や広告そのものと直に対峙せざるを得なくなるだろう。その時建築と広告は風景の一部になってしまうのか、それとも対峙する人が建築や広告の一部になってしまうのか。
"Will it be a part?"
If it was advertising that things would appear and disappear in consciousness, and this would be repeated, I thought it was the same in architecture. I see a lot of architecture and advertisements on a daily basis, but few of them are clearly conscious and remembered. There is a limit to the memory capacity of the brain, and if you remember everything, your brain will puncture, so you may unknowingly try not to remember most of it.
However, this happens to advertisements and architecture that appeal to human sensibilities. In particular, since advertising stimulates human sensibilities and leaves it in memory as one of the advertising effects, it is easy to be the target of consciousness selection, and most advertisements appear and disappear repeatedly.
If architecture and advertising exceed the amount that appeals to human sensibilities and have so many effects at once that human sensibilities do not work, then architecture and advertising are out of the scope of consciousness selection. You will have to face it directly. Will architecture and advertising then become part of the landscape, or will the confronting person become part of architecture and advertising?
建築は常に目の前に現象としてあり続けているが、受け取る側の都合でその現象が意識されたりされなかったり、受け取る側の感性に影響を与えたり与えなかったりする。
建築は現象として常にある訳で、それに対して厚さが所々で違う感性のベールをかけて現象を感じ取っているようなものだと考えている。その感性のベールを全て透かして、受け取る側が現象としての建築を全て意識できるようになれば、建築は感性から自由になりただ単に物だけの存在になる。物だけの存在になった建築は今度は根源な物、例えば、光や影、木や岩などといった意図を感じない自然物と同化していき風景になる。
感性のベールが全て透けた状態を無感性状態といい、無感性状態をデザインでつくり出そうと考えている。その際に参考になるのが広告で、その過激性は受け取る側を無感性状態にする。ただ、広告の過激性をそのまま建築に応用するのではなくて、応用した例は新宿辺りに行けばよく見られるが、建築と受け取る側との関係性の中に広告が過激になる際のルールを抽出して持ち込もうと考えている。
"Extract and bring in advertising rules"
Architecture always exists as a phenomenon in front of us, but for the convenience of the recipient, the phenomenon may or may not be conscious, or it may or may not affect the sensibility of the recipient.
Architecture is always a phenomenon, and I think it's like feeling the phenomenon by putting a veil of different sensibilities on it in places. If the recipient can be aware of all the architecture as a phenomenon by seeing through all the veil of that sensibility, the architecture will be free from the sensibilities and become merely an existence. Architecture, which has become an existence of only things, is now assimilated with the original things, such as light and shadow, trees and rocks, which do not feel the intention, and become a landscape.
The state in which all the sensibility veils are transparent is called the insensitivity state, and we are thinking of creating an insensitivity state by design. Advertising is helpful at that time, and its radicality makes the recipient insensitive. However, instead of applying the radicality of advertising to architecture as it is, examples of applying it are often seen around Shinjuku, but the rules when advertising becomes radical in the relationship between architecture and the recipient I'm thinking of extracting and bringing it in.
建築を届ける側と受け取る側に分けて考えた場合、受け取る側がどのように感じるのかに興味がある。受け取る側は建築を現象として何を感じるかを無意識のうちに取り扱っていて、それを感性という。
感性が豊かという言葉があるように、感じることを微細に受け取ることはいいがそれが行き過ぎると逆に感性が鈍く空回りする無感性の状態になる。
無感性の状態はよく広告の世界ではあり得ることで、広告の過激性が問題になることがあるが、見方を変えれば、建築に広告の過激性のような感性が鈍く空回りしてしまう状態、無感性の状態まで人の感性を刺激する力があれば、建築において感性のベールが透けて、建築が本来持っている空間性や素材性や時間性などが現れるのではないかと考えた。
普段、建築は人の感性のベールに包まれており、それが良くも悪くも建築の姿を歪めているように思えてならない。
"Veil of sensitivity"
I am interested in how the recipient feels when considering the architecture on the delivery side and the receiving side separately. The recipient unknowingly deals with what he feels as a phenomenon of architecture, which is called sensibility.
Just as there is a word that the sensibility is rich, it is good to receive the feeling finely, but if it goes too far, the sensibility becomes dull and the state of insensitivity becomes idle.
The state of insensitivity can often be in the world of advertising, and the radicality of advertising can be a problem, but from a different point of view, the state of architecture that is dull and idle like the radicalness of advertising. I thought that if there is a power to stimulate human sensibilities to the state of insensitivity, the sensibility veil can be seen through in architecture, and the spatiality, materiality, and temporality that architecture originally has will appear.
Architecture is usually wrapped in a veil of human sensibility, which, for better or for worse, must not seem to distort the appearance of architecture.
その場所固有のことを建築計画の軸にしようと考えている。都市部では特殊なロケーションでもなければ、なかなかその場所固有のことはないかもしれない。もちろん、その場所の特徴的なことはある。例えば、角地であったり、前面道路が広いなど、ただそれは別に他の場所でもあることである。
その場所固有のことを計画の軸にしようとした理由は時間の流れを計画に取り込みたかったからである。一過性の点で計画に関わるのではなく、過去から未来への時間の流れの中に建築を自然な形で埋め込みたいと考えた。
そのためには過去からの時間が蓄積されて形成されたその土地固有のことを軸にして建築計画をする必要があると考えた。
"The accumulated time from the past"
I'm thinking of making the place-specific thing the axis of the architectural plan. If it is not a special location in an urban area, it may not be unique to that location. Of course, there are some characteristics of the place. For example, it is a corner lot, the front road is wide, etc., but it is also another place.
The reason I tried to make the place-specific thing the axis of the plan was because I wanted to incorporate the flow of time into the plan. I wanted to embed architecture in a natural way in the flow of time from the past to the future, rather than being involved in planning in terms of transients.
For that purpose, I thought that it was necessary to make an architectural plan centering on the land-specific things that were formed by accumulating time from the past.
無感性的な状態が感性が行き過ぎた状態かまだ感性のはじまりの状態だとすれば、無感性的な状態では感性というベールが透けてしまうか無い状態で物事を見ることができるので、何かを理解しようとする時には望ましい状態かもしれない。
この無感性的な状態と感性的な状態の境界をつくり出すことができたら、その境界を行ったり来たりしながらものづくりをすると面白いかもしれない。
"Crossing the boundaries of sensibility"
If the insensitive state is a state in which the sensibility has gone too far or is still the beginning of the sensibility, in the insensitive state, things can be seen with or without the veil of sensibility, so something It may be a desirable state when trying to understand.
If we can create the boundary between this insensitive state and the emotional state, it may be interesting to make things while going back and forth between the boundaries.
感性的とは感性が豊かになることがひとつの状態で、その状態になりたくて綺麗なものを見たり、美しい音を聴いたりとアクティビティを起こす。また逆にひどく悪いものを見たり、悲しいことがあった場合にも感性的になる。
さらに良くても悪くても感性的な状態の度が進むと、今度は感性が麻酔を打ったような状態になり無感性的になる。無感性的な状態は決して極端なことではなく、あまりにも素晴らしい、逆にあまりにも悪いことが続くとその状態に慣れ、それが普通になり、無感性的な状態になる。無感性的な状態は感性が無い状態ではなく、感性が麻酔を打ったような状態なっているだけだから感性は働いているので、今目の前で起こっている現象は受け入れている。
この無感性的な状態では全ての現象を感性で計ることなく受け入れてしまう状態かもしれないので、この状態を意図的につくることができたら、万人に受け入れられるものができるかもしれない。しかし、感性は麻酔を打ったような状態なので、そのものの良し悪しを感性では判断できずに現象として理解するのみになってしまうかもしれないが、かえってそのものを理解するには良いかもしれない。
"Understanding insensitively"
Sensitivity is a state in which the sensibilities are enriched, and activities are triggered by seeing beautiful things and listening to beautiful sounds that one wants to be in that state. On the contrary, if you see something bad or sad, you will be sensitive.
As the degree of sensibility progresses, whether better or worse, the sensibilities become anesthetized and insensitive. The insensitive state is by no means extreme, and if it continues to be too great, or too bad, it becomes accustomed to it and becomes normal and insensitive. The insensitive state is not a state without sensibility, but a state in which the sensibility is just like anesthesia, so the sensibility is working, so I accept the phenomenon that is happening in front of me.
In this insensitive state, all phenomena may be accepted without being measured by sensibility, so if this state can be intentionally created, it may be possible for everyone to accept it. However, since sensibility is a state of being anesthetized, it may not be possible to judge whether it is good or bad by sensibility, and it may only be understood as a phenomenon, but it may be better to understand it.
何かを見て、見たままに捉えるのではなく、心の中で意識したことで捉えてみると必ず偏重が起こるだろう。偏重とは何かを見た時に人によって受け取り方が違うということであり、偏重が起こることは当たり前のような気がするが、案外そうでもないかもしれない。
ある所へ急いで歩いていたら途中で藤の花が咲き乱れる家を見つけた。普段よく通る所だが何故か今まで気がつかなかった。藤の花が綺麗だったが、それ以上に関心を引いたのはその家だった。藤の花に朽ちられていて、そのやられ感が妙に良かった。
きっと多くの人は綺麗な藤の花に目がいくのかもしれないし、自分ももしかしたら今までは藤の花にしか目がいかなかったのかもしれない。しかし、今回は急いでいたこともあり、視野も意識も拡散せずに集中していた。集中していたことにより全体像ではなく部分的な像しか見えず、綺麗な藤の花と朽ちた家の一部のコントラストしか目に入らず、そこで違和感を覚え、意識の中で何か反応してしまったようだった。
意識での偏重がアクティビティと絡んで起こることはあり得るかもしれない。
"When consciousness is overweight"
If you look at something and catch it by consciousness in your mind instead of catching it as you see it, there will always be a bias. When you see what is overweight, it means that people receive it differently, and it seems natural that overweight occurs, but it may not be surprising.
When I was walking to a certain place in a hurry, I found a house where wisteria flowers were in full bloom on the way. It's a place I usually go to, but for some reason I didn't notice it until now. The wisteria flowers were beautiful, but it was the house that attracted more attention. It was decayed by wisteria flowers, and the feeling of being damaged was strangely good.
I'm sure many people will be interested in beautiful wisteria flowers, and maybe I've only been interested in wisteria flowers until now. However, because I was in a hurry this time, I was concentrating without spreading my horizons and consciousness. Due to my concentration, I could see only a partial image, not the whole image, and I could only see the contrast between the beautiful wisteria flowers and a part of the decayed house. It seemed like I had done it.
Conscious bias may occur in connection with activity.
過去の記憶や体験が「地」となり、今目の前で起こっていることを「図」として浮かび上がらせて認識する。この場合、地も図も現象になるのだろうが、同じような現象では図が浮かび上がらず、図として認識されない。
空間認識もこれと同じで、地としての記憶や空間体験が今目の前にある図として空間の認識に影響を与えることになる。地は認識する個人により違うので、図の認識のされ方も個人により違ってくるが、個人の地でも他の個人と共通な領域があるから、その領域にある図としての空間は浮かび上がらず、図として認識されず印象にも残らない。
印象に残すためには、個人の地の共通な領域にある記憶や空間体験とは違う図としての空間をつくる必要があり、そのためにはどうすればいいかを考えている。
ひとつの方法として、見た目でわかるくらいな共通領域にある地との違いを出すことだが、それはよくあるつくり方で、時に違和感という印象が図に伴うことがあり、必ずしも良い方法ではない場合がある。
"Impression of the figure"
The memories and experiences of the past become the "earth", and what is happening in front of us now emerges as a "figure" and is recognized. In this case, both the ground and the figure will be phenomena, but in the same phenomenon, the figure does not emerge and is not recognized as a figure.
Spatial cognition is the same as this, and memory as the earth and spatial experience will affect the perception of space as a figure in front of us. Since the ground differs depending on the individual who recognizes it, the way the figure is recognized also differs depending on the individual, but since there is an area in common with other individuals even in the individual land, the space as a figure in that area does not emerge. It is not recognized as a figure and does not leave an impression.
In order to leave an impression, it is necessary to create a space as a diagram that is different from the memory and spatial experience in the common area of the individual's land, and I am thinking about what to do for that.
One way is to make a difference from the ground that is in a common area that you can see visually, but it is a common way of making, and sometimes the impression of discomfort accompanies the figure, so it may not always be a good method. ..
人の感性に最も影響を与えるものは何か、外部から持たされるもので何が一番影響を与えるのか。素直に考えれば、視覚を通して入ってきたものが一番影響を与えるように思うが、果たして本当にそうなのだろうか。
建築でいえば空間認識の仕方が人の感性に影響を与えるルートになるだろう。空間認識はどのようにして起こるのか。例えば、目を閉じて視覚からの情報をシャットアウトしたら空間認識できないのだろうか。視覚を奪えば確かに空間の詳細な様子はわからなくなるかもしれないが、空間の中にいるという感じは得られ、これを空間認識といっても良いだろう。
ではどうして視覚が無い状態でも空間認識をすることができるのだろうかと考えてみる。
"Can you recognize space?"
What has the greatest impact on human sensibilities, and what has the greatest impact on external sensibilities? To be honest, I think that what comes in through vision has the most impact, but is that really the case?
Speaking of architecture, the way of recognizing space will be the route that affects people's sensibilities. How does spatial cognition occur? For example, if you close your eyes and shut out the information from your eyes, can you not recognize the space? If you deprive yourself of your eyesight, you may not be able to see the details of the space, but you can get the feeling that you are in the space, and this can be called spatial recognition.
Then, let us wonder why it is possible to recognize space even without vision.
標準プランの繰り返しだけは避けたいと考えていて、それは一見効率的では無いが、効率性は違うことで担保すれば良いとすれば、標準プランの繰り返しを避けることは可能だと考えた。標準プランはプロセスの簡素化が一番の効用だから、違うことでプロセスの簡素化を行えば良い。例えばひとつとして、プロセスを決めるルールをつくっておけば標準プランをつくらなくてもプロセスを簡素化でき、尚かつプロセス自体が毎回違う可能性が生まれ、その結果自ずからプランにもバリエーションができ、効率で決まる標準プランとは違う効率的なものができる。
"Making process rules"
I wanted to avoid repeating the standard plan, which is not efficient at first glance, but I thought it would be possible to avoid repeating the standard plan if I could guarantee that the efficiency would be different. The standard plan is most useful for process simplification, so you can simplify the process by doing something different. For example, if you create a rule that determines the process, you can simplify the process without creating a standard plan, and there is a possibility that the process itself will be different each time. You can create an efficient one that is different from the standard plan that is decided.
感性が生まれる時を演出したいと思う。それがデザインであって欲しい。デザインが社会性を帯びてきた初期には感性がないがしろにされてきたように思う。デザインが感性を刺激することを忘れた世の中はつまらない。
なぜデザインをしているのか、それは人の感性を刺激したいから、人に影響を与えたいから。
なぜ感性をないがしろにするのか。感性を刺激するデザインを主題にしたら、これほど楽しい社会はないだろう。もうちょっと不真面目になろうよ。
"Let's be unscrupulous"
I want to produce a time when sensibility is born. I want it to be a design. In the early days when design became social, I think it was neglected because it had no sensibility. The world where design forgets to stimulate sensibilities is boring.
The reason why I design is because I want to stimulate people's sensibilities and I want to influence people.
Why do you neglect your sensibility? If the theme is design that stimulates sensibilities, there would be no more enjoyable society. Let's be a little more serious.
建替えをする時、できれば何かしらを次に引き継ぎたいと考える。その何かは思い出が染み付いた物や記憶にあることを物として残したい。よくやったのは、旧家では今はもう生産されないようなガラスを使っていることが多いので、そのガラスを再利用し建具などに組み込んでいた。それはそれで面白いと思うのだが、もっと根本的な部分で過去から未来へ引き継げることはないかと考えた。
その土地固有の何かを探し出し、次に引き継ぎたい。もし建替えが何度か行われているのならば、あるいは増改築を繰り返しているのならば、その時々のプランを重ねてみたらどうなるだろうかと考えてみた。プランはその土地固有のものであり、重なりに偏重が見られるだろうから、それを何かの尺度で拾い集めれば次に引き継ぐ物が姿を現すかもしれない。
"What to take over"
When rebuilding, I would like to take over something next if possible. I want to leave something that is ingrained in memories and that is in my memory. What I often did was to use glass that is no longer produced in old houses, so I reused that glass and incorporated it into fittings. I think that's interesting, but I wondered if there was a more fundamental part that could be passed on from the past to the future.
I want to find something unique to the land and then take over. If the rebuilding has been done several times, or if the expansion and renovation are repeated, I wondered what would happen if I repeated the plans from time to time. The plan is unique to the land, and there will be a bias in the overlap, so if you pick it up on some scale, the next one may appear.
装飾は人の感性に影響を与える。装飾以外にも人の感性に影響を与えるものはあるが、装飾というモダニズムが排除してきたものを用いることにより建築に対するアプローチやつくる上でのプロセスが変わるだろうと考えた。
ただ、近代のモダニズム建築の中にも今から振り返れば装飾を纏っているといえるものもあると考えていて、例えばアアルト流の装飾といえるものもあり、装飾の中に住むことで感性に影響を受けることを意図した建築もあると考えた。
装飾の中に住むことを考えるならば、装飾をもっと構築的な観点で捉え直すことにもなるので面白い。
"Living in decoration"
Decoration affects human sensibilities. There are other things that affect people's sensibilities besides decoration, but I thought that using decoration, which modernism has eliminated, would change the approach to architecture and the process of making it.
However, I think that some modern modernist architecture can be said to be wearing decorations from now on. For example, there are some Aalto-style decorations, and living in the decorations affects sensibility. I thought that some buildings were intended to receive.
If you think about living in a decoration, it's interesting because it also gives you a more constructive view of the decoration.
効率を求めることによってどこかで見たようなものに収束してしまうことを避けようと考え、プロセスに注目した。
どこかで見たようなものになるのは予測可能なことばかりでプロセスが形成されているからであり、そこに予測不可能なプロセスが挿入されれば、思いも寄らない結果が生まれ、どこか見たようなものにはならなくなる。
予測不可能なプロセスとは偶然性を取り入れることであり、その偶然性の源をその場所やそのものの成り立ちなど求めれば、生まれる結果はより固有のものになる。
"Unpredictable process"
I focused on the process, trying to avoid converging on something I saw somewhere by seeking efficiency.
It looks like you've seen it somewhere because the process is formed by only predictable things, and if an unpredictable process is inserted there, unexpected results will be produced and where. It doesn't look like you saw it.
An unpredictable process is the incorporation of contingency, and if the source of the contingency is sought, such as its location or its origin, the resulting result will be more unique.
効率から逃れるためにはどうしたらいいのかとずっと考えてきた。効率を求めるあまり同じようなものばかりになってしまう。効率は目に見えない物の構造にまで及んでいるので、目に見える部分をいくらいじっても何も意味が無い。効率は結果だけで無くプロセスから効率を求めるために起こる結果であるので、効率から逃れるには結果では無くプロセスに目を向けて、効率から脱却をしなければならない。
間違ってはいけないのは、効率を求めることが良くないのでは無く、効率を求めた結果が皆同じようになってしまうことが良くないのである。だから、プロセスを見直すことにより同じになることを避けて違う結果を求め、その結果がはじめからプロセスを含めて効率を求めた物と違うが同じ位に効率的であれば良い。
"Escape from efficiency"
I've been wondering what to do to escape efficiency. The demand for efficiency is so similar. Efficiency extends to the structure of invisible objects, so there is no point in tinkering with the visible parts. Efficiency is not only the result, but the result of seeking efficiency from the process, so in order to escape from efficiency, we must look at the process, not the result, and break away from efficiency.
Don't get me wrong, it's not that it's not good to ask for efficiency, it's not good that all the results of looking for efficiency are the same. Therefore, by reviewing the process, we avoid the same thing and seek different results, and the result is different from the one that asked for efficiency including the process from the beginning, but it should be as efficient as it is.
記憶に残るものは何だろうか。例えば小さい頃の記憶として今は無い母方の実家で残っているのは、夏の夕暮れのオレンジ色の西日がさす部屋である。あるいは急な階段、2階の窓から見える景色であり、身体の動きと一緒に目が覚えており、匂いも同時にしてくる。それらは何でもないことであり、特別なことではないが他では体験できないことであった。身体に目がついているという当たり前のことを記憶が教えてくれる、鼻もそうであり、五感を改めて身体を通した記憶で感じる。
五感を通した記憶から何を抽出するかを考える。抽出したものから形をつくることで記憶を継承していくことが可能になると考えた。記憶という形が無いものに形を与えるためには、形につながる情報が必要であるが、最終的に形になるものを装飾として限定することにより抽出する情報の抽象度を上げることができ、様々な要素を使えるようになるのではないかと考えた。
"Extraction from memory"
What is memorable? For example, what I remember when I was little is the room where the orange west sun shines at dusk in the summer, which remains in my mother's parents' house. Or the steep stairs, the view from the window on the second floor, the eyes remember with the movement of the body, and the smell comes at the same time. They were nothing, not something special, but something that couldn't be experienced anywhere else. The memory tells us that the eyes are on the body, and so is the nose, and the five senses are felt through the body again.
Think about what to extract from the memory through the five senses. I thought that it would be possible to inherit the memory by creating a shape from the extracted material. In order to give shape to something that does not have the shape of memory, information that leads to the shape is necessary, but by limiting what will eventually become the shape as decoration, the degree of abstraction of the information to be extracted can be increased. I thought that I could use various elements.
記憶を継承しようとする時、何をつないでいくかを考えている。建築の場合、形として物が存在しているので、形の輪郭をトレースするように継承することはひとつの方法かもしれない。
景色の違いに気がつく時は、まずぼんやりと視界に入ってきた物の輪郭の違いにわかるのではないだろうか。人は見ている物全てをはっきりと記憶していたら簡単に脳の記憶容量を超えてしまうので、自身の身の安全を図る上で最低限のことだけを記憶しておく。だから、輪郭だけで十分であり、その違いには気がつき、何かしらの影響を人に与える。
今までそこに動かずにずっとあり、常日頃から見ていたりする物、ただし意識して見たりはしていない物でも、無くなったり変化したりすると違和感を感じる。だから、輪郭を継承することは十二分に記憶の継承につながると考えた。
"Inheritance of contour"
When I try to inherit my memory, I am thinking about what to connect. In the case of architecture, things exist as shapes, so it may be one way to inherit to trace the outline of the shape.
When you notice the difference in the scenery, you may first notice the difference in the contours of the objects that are vaguely in sight. If a person clearly remembers everything he sees, he or she can easily exceed the memory capacity of the brain, so remember only the minimum for personal safety. So contours are enough, and you'll notice the difference and have some impact on people.
I haven't moved there for a long time, and I feel uncomfortable when things that I see on a regular basis, but things that I haven't consciously seen, disappear or change. Therefore, I thought that inheriting the contour would lead to the inheritance of memory more than enough.
装飾に感じる可能性は、装飾には人の感性に直接影響を与える力があることであり、その装飾が最大ボリュームから成るのであれば、最大ヴォリュームが人の感性に直接影響を与えるということである。またデザインも人に影響を与えるものだとすれば、最大ヴォリュームをつくることはデザインだとしてもいい。
装飾にもいろいろあるが、まずは模様に注目した。なぜ模様かは装飾をパラフレージングしてみた結果であり、模様ではあれば平面的にも立体的にも捉えることができ、建築とも相性が良い。
模様を扱うことで最大ヴォリュームが得られるプロセスは何か、そのプロセスが構築できれば、同時に人の感性に影響を与えるものもできる。
"Volume consisting of patterns"
The possibility of feeling a decoration is that the decoration has the power to directly influence the human sensibility, and if the decoration consists of the maximum volume, the maximum volume directly affects the human sensibility. be. Also, if design also affects people, it can be said that creating the maximum volume is design.
There are various decorations, but first I focused on the pattern. The reason for the pattern is the result of paraphrasing the decoration, and if it is a pattern, it can be grasped both two-dimensionally and three-dimensionally, and it is compatible with architecture.
What is the process that can obtain the maximum volume by handling patterns, and if that process can be constructed, it can also affect human sensibilities at the same time.
事業性を考えた時、建築の最大ヴォリュームを確保することは必要な要件になってくるが、最大ヴォリュームのおかげでプランやデザインに余裕が無くなり、遊びもできず、つまらない建築になる可能性がある。
そこで最大ヴォリュームだからできることはないかと考えてみた。ひとつの考え方として全く関係性が無いことをつなげてみることにした。それは「装飾」である。ヴォリュームが塊の量としての表現ならば、装飾はサーフェスとしての表現であり、直接的な関係性は無いがヴォリュームも装飾も見え方という共通項で括ることができると考えた。
つなげて言えば「最大ヴォリュームが装飾になる」であり、そこに何か可能性を感じるのである。
"Volume is decoration"
When considering business feasibility, securing the maximum volume of architecture is a necessary requirement, but thanks to the maximum volume, there is no room in the plan and design, there is no play, and there is a possibility that the architecture will be boring. be.
So I thought about what I could do because it was the maximum volume. As one way of thinking, I decided to connect things that have nothing to do with each other. It is "decoration". If the volume is expressed as a quantity of lumps, the decoration is an expression as a surface, and although there is no direct relationship, I thought that both the volume and the decoration can be summarized by the common term of appearance.
In short, "the maximum volume becomes a decoration", and I feel something possible there.
過去の体験を予測に利用し感情が生まれ行動するとのことだが、過去に体験したことが無いことでは感情による行動は起こらないのだろうか。何かしらを頼りに予測し感情を生み行動するのではないだろうか。その何かしらは現実に今体験していることでもいいのではないだろうか。
体験と感情と行動がほぼ同時に起こる。体験は行動でもあるので、感情と行動が過去とは切り離されてほぼ同時に現実に今起こる。その時の感情と行動は新しい結びつき、新しい回路で形成される。それが初めて体験するということだろうが、何かしらの過去の体験からの予測も無意識に起こり介入してくるかもしれず、それをコントロールすることができないだろうから、予測を起こさせない仕掛けが必要になる。
もし予測を起こさせない仕掛けを建築デザインで行うことができたら、建築が感情と行動をほぼ同時に生むことができ、それが初めてのこととして記憶されることになる。それは建築体験の新しい可能性になるだろう。
"New possibilities for architectural experience"
It is said that emotions are born and act by using past experiences for prediction, but isn't emotional behavior occurring if you have never experienced it in the past? Perhaps they rely on something to predict, generate emotions, and act. I think it's okay if something is actually being experienced now.
Experiences, emotions and actions occur almost at the same time. Since experiences are also actions, emotions and actions are separated from the past and occur almost at the same time in reality. The emotions and actions at that time are formed by new connections and new circuits. It may be the first experience, but predictions from some past experience may unknowingly occur and intervene, and you will not be able to control it, so you need a mechanism that does not make predictions. ..
If architectural design can do something unpredictable, architecture can produce emotions and actions at about the same time, which will be remembered for the first time. It will be a new possibility for the architectural experience.
感情による行動を脳科学的に解くと予測が行動のきっかけになるとのこと。視覚を通して入ってきた情報に対して過去の似たような体験を頼りにその後に起こることを予測し対処するために感情を発動し行動するのだろう。
恐いから行動する場合は、それが恐いということを過去の体験より予測するから、恐いという感情が生まれ行動に結びつくとのこと。過去の体験が現在の感情の源になる。
もしかしたら、過去の体験は規範やルール、秩序といった言葉に置き換えることが可能かもしれないと考えた。予測に過去の体験を使うということは、その人にとって過去の体験が行動の規範になっている。ならば、過去の体験以外のことを規範として利用し、感情による行動を促すことが可能かもしれないと思った。
"Promote emotional behavior"
It is said that prediction will be the trigger for behavior if the behavior due to emotions is solved by brain science. They will act by invoking emotions to anticipate and deal with what will happen afterwards, relying on similar experiences in the past for information that comes in through vision.
When acting from fear, it predicts that it is scary from past experiences, so feelings of fear are born and lead to behavior. Past experiences are the source of current emotions.
I thought it might be possible to replace past experiences with words such as norms, rules, and order. Using past experiences for prediction means that past experiences are the norm of behavior for the person. If so, I thought that it might be possible to encourage emotional behavior by using things other than past experiences as norms.
最大のヴォリュームを得ようと計画することがよくある。制限がある中でギリギリまで大きくする。事業性が高い建築、例えば、集合住宅では当たり前に行うことである。その敷地に対してどれだけのヴォリュームのものが建つかは算定ソフトでも出すことができ、数値上の話で終始する。
ただ、他に可能性はないのかと思った。最大のヴォリュームがもたらすものは事業性の高さだけだろうか。ヴォリュームというものに注目すれば、それだけで人に影響を与えることもある。どのようなヴォリュームがどのように人に影響を与えるのか。ただ、それではまだチャンクが大きい。もう少しチャンクダウンして、例えば、ヴォリュームの構成や配列が人の感性に影響を与えるか、もし影響を与えるならば結果的に得られる感性が人のアクティビティに変化もたらすか、などまだまだヴォリュームという言葉から派生することはありそうだと考えている。
"Influence of Volume"
Often we plan to get the maximum volume. Make it as large as possible while there are restrictions. This is a matter of course in highly business-friendly buildings, such as apartment buildings. How many volumes can be built for the site can be calculated with calculation software, and it is a numerical story from beginning to end.
However, I wondered if there was any other possibility. Is the only thing that the largest volume brings is high business feasibility? If you focus on the volume, it can affect people by itself. What kind of volume affects people and how. However, the chunks are still large. Chunk down a little more, for example, whether the composition and arrangement of the volume influences the human sensibility, and if so, whether the resulting sensibility changes the human activity, etc. I think it is likely to be derived.
なぜもっとより深みに目を向けないのだろうかと魯山人が乾山に対して嘆いたとのこと。深みに目を向けるには何かを変える必要がある。きっと無意識のうちに変える行為に抵抗してしまうのだろう、だから変わらない、より深みに目を向けない。別に変えなくても生きていけるが、変えないと満たされない、そのような人が結構多いかもしれない。
着物を選ぶのは楽しい。いろいろな組み合わせの中から絞る時点で面白さに没頭している、色の深みにはまる。柄の違いがわかるかわからない位のところで見栄えに影響する。
より深みに目を向けやすくするひとつの方法は細部の見過ごしていたことに注目し、そこに自分なりのやり方を見出すことだが、そもそも気がつかないフリをしているから見過ごすので、自身のフリを振り払うには第三者からの言葉が必要かもしれない。
"To the depths"
Rosanjin lamented Kenzan as to why he didn't look deeper. Something needs to change to look at the depths. I'm sure they will resist the act of changing unknowingly, so don't change, don't look deeper. There may be quite a lot of such people who can live without changing, but are not satisfied without changing.
Choosing a kimono is fun. At the time of squeezing from various combinations, I am absorbed in the fun, and I am absorbed in the depth of color. It affects the appearance where you do not know the difference in pattern.
One way to make it easier to look deeper is to focus on the details that you have overlooked and find your own way, but since you are pretending to be unaware in the first place, you will overlook it, so shake off your own pretense. May need words from a third party.
人の感性が極端に振れるような影響を与えたいと思うから建築のデザインをしているので、極端に振れるような可能性が無いことはなるべくやりたくはない。感性が振れるとはどういう状態なのか、逆に全く振れないとはどういう状態なのか、さらには感性が全く振れない状態は感性が無い状態なのかに興味がある。ここでは感性を振り子のようだと考えているので、感性が振れる振れないと表現しているが、それ自体が違う可能性もある。振り子だと一定の円弧上を移動するが、もしかしたら点から点への移動かもしれない。あるいは、円弧移動と点移動のミックスも考えられる。感性についてはまだまだわからないことが多い。
"Sensitivity swing"
I'm designing architecture because I want to have an influence that makes people's sensibilities shake extremely, so I don't want to do as much as possible without the possibility of shaking extremely. I am interested in what kind of state it is when the sensibility swings, what kind of state it is when it does not swing at all, and whether it is a state where there is no sensibility at all. Here, I think that the sensibility is like a pendulum, so I express that the sensibility does not swing, but it may be different in itself. A pendulum moves on a certain arc, but it may move from point to point. Alternatively, a mix of arc movement and point movement can be considered. There are still many things I don't understand about sensibilities.
ヴォリュームに対して大小の尺度で考えるのが建築では当たり前である。建築は人を内包することで定義されるようなものだから、人がどのように内包されるかの尺度のひとつがヴォリュームで、スケール感という言葉があるように大小をみる。
ヴォリュームの大小は当然数値に影響を与えるが、それだけではなく人の感性にも影響を与える。建築に限らず人の尺度を超えるヴォリュームのものを目の前にした時、人はそのヴォリュームに対して感性が動く。その時の感性は畏敬の念かもしれないし、崇高かもしれないし、驚きかもしれない。自身のヴォリュームとの差を埋める何かを感性でつくり出す。
"Volume creates sensibility"
It is natural in architecture to think about the volume on a large or small scale. Architecture is something that is defined by the inclusion of people, so one of the measures of how people are included is volume, and we look at the size as if there is a word of scale.
The size of the volume naturally affects the numerical value, but it also affects the human sensibility. People move their sensibilities to the volume when they see something in front of them that exceeds the scale of human beings, not limited to architecture. The sensibility at that time may be awe, sublime, or surprise. Create something with sensibility that fills the gap with your own volume.
プロジェクトをはじめる時、最初に探すのはわからないこと。全てをわかる範囲内でプロジェクトをおさめることは勿論可能だが、それでは今までの焼き増しに過ぎず、焼き増しの段階で全てが古いもので価値が半減している。また、自身のモチベーションも上がらない。
わからないということは自身にとっては新しいことであり、毎回何か新しい要素が入り込むから創意工夫も生まれる。
わからないことをわかるようにすることで新しいことが生まれるならば、それがクリエイティブであり、わからないこと探しがクリエイティブのはじまりになる。
"Beginning of creative"
When you start a project, you don't know what to look for first. Of course, it is possible to complete the project within the range where everything can be understood, but that is just a reprint so far, and at the reprint stage, everything is old and the value is halved. Also, my motivation does not rise.
Not knowing is new to me, and every time something new is introduced, ingenuity is born.
If something new is born by making people understand what they don't understand, it is creative, and searching for something they don't understand is the beginning of creative.
綺麗な模様が並んだ中に見過ごしてしまそうな位に小さな点を見つけた時に、それを綺麗な模様を乱す点と思うか、綺麗な模様にアクセントを加えてくれる点と思うかで模様の浮かび上がり方が違うと思った。
完全さを求めるならば綺麗な模様を乱す点になるだろうが、不完全さを許容するならばアクセントになり得る。
どちらが良いかでは無いと思うが、不完全さを許容する方が外からの要因によって変化する可能性があり不確実性が増す。不確実性は捉えようによっては不安要素だが、未知なことを含んだ伸び代として魅力的でもある。
"Unknown charm"
When you find a small dot in a line of beautiful patterns that you might overlook, you can either think that it disturbs the beautiful pattern or that it adds an accent to the beautiful pattern. I thought the way it emerged was different.
If you want perfection, it will disturb the beautiful pattern, but if you allow imperfections, it can be an accent.
I don't think which is better, but allowing imperfections can change due to external factors and increases uncertainty. Uncertainty is an anxiety factor depending on how you capture it, but it is also attractive as a growth margin that includes unknown things.
昨夜、猫背矯正ベルトに目が止まりポチり、去年の健康診断の身長測定で1cmも縮み、何度試しても、背伸びしても、背筋伸ばしても、数ミリかかとを上げても変わらず、測定してくれた女性の半笑いの「歳とると誰でも縮むのよ」の慰めが今だに聞こえ、今年はそれでも1年間無理して背伸びし続けた結果か5mmを取り戻し、あと5mmの来年に向けて早いデリバリーのおかげでランチには矯正ベルトを装着、なかなか、これで無理して背伸びしなくていいかもしれないと。
先日、ミニクーパーを車検に出した。乗り始めて27年、外装の輝きが無くなってきたので、そろそろボディ磨きをしてみてはの誘いに一旦は乗ってみたのだが、一晩考えて、27年間の垢が落ちてピカピカのボディになったとしてそれが良いのかと、新車当時の輝きより27年経った今のくすみの方が価値あるだろうと思い、ボディ磨きは取りやめてワックス掛けだけしたら余計に外装のくすみがマダラで浮かび上がったなと。
年月は無用なあがきと変な納得を生むけれど、また次の機会まで楽しみができたなとも思う。
"Height is small"
Last night, my eyes stopped on the stoop straightening belt, and I shrank by 1 cm in the height measurement of last year's health check. I can still hear the comfort of the half-laughing woman who measured me, "Everyone shrinks when I get older." Thanks to the quick delivery, I put on a straightening belt for lunch, and I thought that I might not have to stretch myself with this.
The other day, I sent a mini cooper to an automobile inspection. It's been 27 years since I started riding, and the exterior has lost its brilliance, so I tried to polish the body and tried to ride it once, but after thinking about it overnight, the dirt from 27 years was removed and it became a shiny body. I wondered if that was a good idea, and I thought that the dullness of the current 27 years after the brilliance of the new car would be more valuable, so if I stopped polishing the body and just waxed it, the dullness of the exterior emerged with Madara. When.
The years have given rise to useless postcards and strange convictions, but I think I was able to enjoy it until the next opportunity.
何かを見ることは対象物からの誘いに乗ることだとしたら、誘いに乗る前は無感性な状態、例えば、ボーっとしていたり、麻酔をかけられていたりするような、意識はあるが反応しないような状態であり、誘いに乗った後は感性が満ちていく状態になる。
感性に満ちている状態は対象物に焦点を合わせ見ている状態だが、興味があるのは無感性な状態での対象物からの誘いに乗る瞬間で、誘いに乗る時の決め手は何になるのかである。
ひとつの推測としては違和感ではないか。無感性なボーっとしている状態でも意識はあるので何かを受け止めている。その受け止めた中に何か違和感があれば、そこに焦点を合わせる。その違和感はギャプかもしれないし、不足や不完全かもしれないし、驚きや賞賛かもしれない。いずれにせよ、意識の地平の中に出現する異物なのだろう。
そうなると、少なくとも異物になる可能性を秘めたものをつくらないと人から見られることは無いと言えるかもしれない。
"To be seen by people"
If seeing something is to ride an invitation from an object, you may be conscious but react to an insensitive state, such as being drowsy or anesthetized, before riding the invitation. It is a state where you do not, and after you get on the invitation, you will be in a state where your sensibilities are full.
The state of being full of sensibility is the state of focusing on the object, but what is of interest is the moment of riding the invitation from the object in the insensitive state, and what is the decisive factor when riding the invitation? Is it?
Isn't it strange as one guess? I am accepting something because I am conscious even in a state of insensitivity. If there is something wrong with that, focus on it. The discomfort may be a gap, a shortage or an incompleteness, a surprise or an admiration. In any case, it is a foreign substance that appears in the horizon of consciousness.
In that case, it may be said that people will not be able to see it unless they make something that has the potential to become a foreign substance.
何かを見る、凝視する直前には散漫な状態があり、散漫でボーっとしている時には視野の中にたくさんのものが同列で優劣なく存在している。まず人はこの散漫でボーっとしている状態を瞬時に無意識につくるが、意識的に長くつくることもできる。
この次の段階で何に焦点を合わせて凝視するかを決めるのだが、散漫な視野の中にあるたくさんのものからの誘いに乗ることで決めていると考えることもできる。それは散漫な視野の中にものを置く時点で誘いを誘発しているとも考えられる。
そうすると「見る」ことは焦点を合わせて凝視する段階ではじまるのではなくて、その以前、目を開けて視野を形成している時点にはすでに凝視するものは捉えていて「見る」ことははじまっていると考えることができるかもしれず、初期のボーっとしている状態はまだ誘いに乗る前で何かを「見る」上で実は一番素直にものを見ている状態かもしれない。
"Seeing is an invitation"
Immediately before seeing or staring at something, there is a distracted state, and when distracted and drowsy, many things are present in the same line in the field of vision. First of all, people instantly and unconsciously create this distracted and dull state, but they can also consciously create it for a long time.
At this next stage, you decide what to focus on and stare at, but you can also think of it as taking the invitation from many things in a distracted field of view. It is also thought that it induces an invitation when it puts something in a distracted field of view.
Then, "seeing" does not start at the stage of focusing and staring, but before that, when the eyes are opened and the field of view is formed, the person who is staring at is already caught and "seeing" begins. You may think that you are, and the initial dull state may be the state where you are actually looking at something most honestly in "seeing" something before you take the invitation.
曖昧な言い回しや曖昧な事柄は何かがハッキリとせずわかりにくいので、そのわかりにくさを自分で補おうとして余計に印象に残ることがある。全てが曖昧だと全体がボヤけてしまうので、何を曖昧にするかが重要になる。また、曖昧なこととハッキリとしていることの境目を意識することも重要である。
このことを建築空間の中で考える時、ハッキリしたことと曖昧なことをボーダーレスで重ねることがある。これは目に見える実体があるものだからできることで、特に建築のようなスケールが大きく人を内包できるものには有効な表現方法になる。
"Ambiguity and clarity"
Ambiguous phrases and ambiguous things are unclear and difficult to understand, so it can be even more impressive to try to make up for the incomprehensibleness. If everything is ambiguous, the whole thing will be blurred, so what is important is what makes it ambiguous. It is also important to be aware of the boundary between what is ambiguous and what is clear.
When thinking about this in an architectural space, there are times when clear and ambiguous things are overlapped borderlessly. This can be done because there is a visible substance, and it is an effective expression method especially for things such as architecture that have a large scale and can contain people.
何かを見ている時、その対象物以外の周辺のものは、視界の中には入っているがボヤけていて、感じてはいるがハッキリと感じていない状態である。ハッキリしている対象物とボヤけている周辺部の境目もまたハッキリとしない。それで境目を意識して見ようとすると、今度は焦点が合い境目は消える。
人の目の構造がそうさせるのだろうが、「見る」ことをそこまで意識しない時は無意識に自動的に周辺部のボケをつくり対象物に焦点を合わせる。それは目の動きで起こるが、人は無意識に自分の感性がなせることと錯覚するのではないだろうか。
「見る」ことに重点を置く時、対象物がどのように見えるかを感じとろうとする。その際の目の動きも感性の一部と考える。ボヤけている周辺部は感じとれていないと思うところで、その部分が無感性としてダイレクトに人の感性に影響を与える部分になるのではないだろうかと考えてみた。
"Parts that affect sensitivity"
When I'm looking at something, things around me other than the object are in my field of vision, but they're blurry, and I feel it, but I don't feel it clearly. The boundary between a clear object and a blurred peripheral area is also not clear. So when I try to look at the boundary, the focus is on and the boundary disappears.
The structure of the human eye may make it so, but when you are not so conscious of "seeing", you unconsciously automatically create a blur in the peripheral part and focus on the object. It happens with the movement of the eyes, but people may unconsciously think that they can make their own sensibilities.
When we focus on "seeing", we try to get a feel for what the object looks like. I think that the movement of the eyes at that time is also a part of the sensibility. I don't think I can feel the blurred peripheral area, so I thought that it might be a part that directly affects people's sensibilities as insensitivity.
人の行為をデザインすることが建築や時間をデザインすることにつながるのならば、人が何かを知覚することをデザインすることで建築空間と時間の流れができあがると考えた。
人が何かの行為を行う場合、同時に何かを知覚し、同時に空間を感じ、同時に時間が流れていく。人が何かの行為を行うことによって、知覚と空間と時間が生まれる。ならば、あとは人の行為をデザインするだけで知覚と空間と時間をコントロールできる。
"Controlling Perception, Space and Time"
If designing human actions leads to designing architecture and time, I thought that designing what people perceive would create an architectural space and the flow of time.
When a person does something, he perceives something at the same time, feels space at the same time, and time flows at the same time. Perception, space and time are born when a person does something. Then, you can control perception, space, and time just by designing human actions.
人が見るという行為が時間という概念をつくり出すことは面白く、それができるのが建築の特徴かもしれない。
建築の中で人が何かの行為をする場合は時間や時間差が生じ、その人の行為に対して建築が応答するものと考えると、建築と時間は人の行為によって結びついていると考えることができる。
ならば、人の行為によって建築と時間の関係性が変わることもあり得る。それは、人の行為をデザインすることが建築をデザインすることにつながり、同時に時間もデザインすることになる。
"Designing human actions"
It is interesting that the act of seeing people creates the concept of time, and it may be a feature of architecture that it can be done.
Considering that when a person does something in architecture, there is a time or time lag, and the architecture responds to that person's actions, it is considered that architecture and time are connected by the person's actions. Can be done.
Then, the relationship between architecture and time may change depending on the actions of people. It means that designing human actions leads to designing architecture, and at the same time designing time.
建築を見る時に歩き回ることでしか建築は知覚できないと信じているところがある。
建築が人を内包するスケールで歩き回ることができるということが歩き回りながら建築を知覚することを可能にしているのだが、建築は一点から全てを把握することが困難な場合が多いので必然的に歩き回ることになるのは自然なことだとずっと思ってきた。
歩き回りながら見るということは視点が常に移動しているので、シームレスな視点の連続性が、まるでパノラマ写真のように、建築空間を把握するにはいいと考えてきたが、もしかしたら移動することで前の視点をリセットし続けていくとも考えらないかと思った。
もしそうならば、歩き回りながら建築を見る行為は常に新しい視点を得る行為であり、その建築の中に常に新しい発見をする行為であり、それは建築の中に時間の概念を人が自らつくり出す行為になると考えてみた。
"Time created by people"
Some believe that architecture can only be perceived by walking around when looking at it.
The fact that architecture can walk around on a scale that embraces people makes it possible to perceive architecture while walking around, but it is often difficult to grasp everything from one point, so it is inevitable to walk around. I've always thought it was natural.
Looking around while walking is always moving the viewpoint, so I thought that seamless continuity of viewpoints would be good for grasping the architectural space like a panoramic photograph, but maybe by moving I thought I would continue to reset the previous viewpoint.
If so, the act of looking around the architecture is always the act of gaining a new perspective, the act of constantly making new discoveries in the architecture, and the act of creating the concept of time in the architecture by oneself. I thought it would be.
「見る」という知覚に興味があり、「見る」ことがデザインに与える影響が気になる。デザインを考える時に当然「見る」という知覚を意識するが、それは自分が対象物を見ていることを考える。
他の可能性として、対象物が見られている状態を考えることもデザインには必要である。対象物がどのように見られているかを知覚するには同時に全方位から見られることを意識の中で自分の目を感じながら行うが、それは同時に対象物が周りからどのように存在しているのかを考察することにもなる。
"Perception being seen"
I am interested in the perception of "seeing", and I am concerned about the effect of "seeing" on design. When thinking about design, of course, we are conscious of the perception of "seeing", but we think that we are looking at the object.
Another possibility is that the design also needs to consider the state in which the object is being viewed. To perceive how an object is viewed, at the same time, consciously feel that it is seen from all directions, but at the same time, how the object exists from the surroundings. It will also be considered.
何かを見ている時、周辺視野はぼやけて見ているようで見ていない。デザインの時、その周辺視野が存在していることは考慮しないのが普通で、ぼやけて見えない部分はそもそも存在していないことにして、全てが均等に見えることが前提である。
もし周辺視野のぼやけをデザインに組み込むとしたらどうなるだろうか。それは人の視覚の特性をデザインにいかすことでもある。そのように考えると、デザインをする時に人の視覚の特性が無視されていることがわかる。
"Making use of visual characteristics"
When I'm looking at something, the peripheral vision seems to be blurry and I'm not looking. At the time of design, it is normal not to consider the existence of the peripheral vision, and it is assumed that the part that cannot be seen blurry does not exist in the first place, and that everything looks even.
What if you wanted to incorporate peripheral vision blur into your design? It is also about utilizing the characteristics of human vision in design. Thinking that way, we can see that the characteristics of human vision are ignored when designing.
普通に知覚できる以上のことがバーチャルやメディアで予め流れているので、実際に目の前で起こることに対して、それがどれだけ自分にとって素晴らしいことでも、無感動、無関心、無感性になりやすいかもしれない。
それは一見否定的なことかもしれないが、考えようによっては新たな感性を生む土台になるかもしれない。だから、あえて無感性になってみようと考えてみた。
無感性は身体が麻痺したような状態であり、自分の周りで何があっても他人事のような感覚である。もしそこに別の新たな感性を挿入でき知覚できれば、今までにないもの生み出すための感性を会得できるかもしれない。
"Acquisition of new sensibilities"
Beyond what you can normally perceive, it's pre-flowing in virtual and media, so it's easy to be insensitive, indifferent, and insensitive to what actually happens in front of you, no matter how great it is to you. Maybe.
It may seem negative at first glance, but depending on how you think about it, it may be the basis for creating new sensibilities. So, I dared to try to be insensitive.
Sensitivity is a paralyzed state of the body, which feels like someone else's affairs no matter what happens around you. If we can insert and perceive another new sensibility there, we may be able to acquire sensibilities to create something that has never existed before.
見ることと見られることは同じかもしれないと考えると、実際に目で見ることと意識の中で見ることは同じになるかもしれないと思った。
対象物を見ることは対象物が見られる状態をつくることであり、同時に発生する訳だから、引いて状況を観察すれば同じ枠組みの中のことだといえるかもしれない。
対象物を見ることは実際に目で見ることであり、対象物が見られる状態を把握することは意識の中で見られる状態を想像することである。それらが同じ枠組みとして捉えることができるならば、人の意識にアクセスできれば、実際とは違うことを見せることができるかもしれない。
"Show different things"
Given that what you see and what you see may be the same, I thought that what you actually see with your eyes and what you see in your consciousness may be the same.
Seeing an object creates a state in which the object can be seen, and it occurs at the same time, so it may be said that it is within the same framework if the situation is observed by pulling it.
To see an object is to actually see it, and to grasp the state in which an object is seen is to imagine the state to be seen in consciousness. If they can be seen as the same framework, it may be possible to show something different if we can access human consciousness.
スルーしていくことでしか見えないことがあるような気がする。スルーしてやり過ごすことでそれがどういうことだったのかが後でわかる。後でわかることに対して損得勘定が働くからスルーできない。後でわかることを受け入れてしまえば簡単にスルーできる。受け入れるためにはスルーすることでしか最大限の成果は得られないようにすれば良く、それがスルーしていくことでしか見えないことになる。
デザインも同じで全てをデザインする必要はなく、最低限の範囲でデザインできれば最大限の成果を得られる領域を見つけることができれば、デザインをスルーすることもできる。
デザインをスルーすることでもっと初源的なものの在り方を考えるキッカケができるような気がする。
"Through design"
I feel that there are things that can only be seen by going through. You can see what it was like by going through it. You can't go through because the profit and loss account works for what you will find out later. If you accept what you will find out later, you can easily go through it. In order to accept it, the maximum result should be obtained only by passing through, and it can only be seen by passing through.
The design is the same and it is not necessary to design everything, and if you can find the area where you can get the maximum result if you can design in the minimum range, you can go through the design.
By going through the design, I feel that I can think about what the original things should be.
感性的に物事を捉えようとすると、いちいち気になるところで引っ掛かりができる。気になるところはその物事の表面上の帰納するところである場合も多いので、無視することもできずにいちいち考え込んでしまうが、結局は表面上のことなので捉え方によってはまた別の解釈も成り立つかもしれないから、引っ掛かりが自分にとって無駄な時間で終わる可能性もある。
だから、感性的に物事を捉えようとしつつ、無感性的な状態に意識してなり、表面上の引っ掛かりを回避して、本当に気になるところに着地したいと思うのだが、それがなかなか難しい。
"Insensitive landing"
When I try to grasp things sensuously, I can get caught in every place I care about. In many cases, the place of concern is the induction on the surface of the thing, so I can not ignore it and think about it one by one, but in the end it is on the surface, so another interpretation holds depending on the way of thinking. Maybe that's why the catch can end up in wasted time for you.
So, while trying to capture things sensuously, I want to be conscious of the insensitive state, avoid getting caught on the surface, and land where I really care, but that is quite difficult.
仮に慣れ親しんだものをリセットしようとしてもなかなかできないもので、それは何かを変えようとしても守りに入る人間の本能が関係しているかもしれない。
例えば、片付けなどはまず何かを捨てようとすると失うことへの損得感情が働き、結局失うことに対して守りに入るから捨てられなくなる。だから、まず捨てて片付けしようとするのでは無くて、まず何を残すのかを考えてから片付けをする。絶対に残したい物を選ぶことは損得勘定が働いて守りに入ってもできるから、絶対に残したい物以外を捨てて片付けをすればいい。
それでいけば、リセットしようとしても全てを変える訳では無いので、まず絶対に変えないことを決めてからそれ以外を変えれば、守りに入る人間の本能の影響を最小限に抑えてリセットができるのではないかと考えた。
"First decide not to change"
Even if you try to reset something you're used to, it's hard to do, and it may be related to the human instinct that protects you even if you try to change something.
For example, in the case of tidying up, if you try to throw away something, you will have a feeling of loss and gain, and in the end you will be protected against losing, so you will not be able to throw it away. So, instead of throwing it away and trying to get rid of it, first think about what to leave and then get rid of it. You can choose what you absolutely want to keep even if the profit and loss account works and you can protect it, so you can throw away the things you absolutely want to keep and put them away.
If that is the case, even if you try to reset it, it will not change everything, so if you first decide not to change it and then change everything else, you can reset it with the minimum influence of the human instinct that enters the defense. I thought it might be.
慣れ親しんだことをリセットして、別の状態にしようとした時に何からはじめればいいのかを考えてみた。
慣れ親しんだことは継続した積み重ねとなり、それはリソースとして武器にできるが、同時にそれは他の新しいことに目を向けなくなる原因にもなる。常に何か新しい要素を少しでもいいからプロジェクトには持ち込みたい。
リセットする時のヒントは好奇心であり、慣れ親しんだこと以外の好奇心が湧くことから手をつければ、自然とリセットできるかもしれない。
"reset"
I reset what I was used to and thought about what to start with when trying to change to another state.
Familiarity becomes a continuous buildup, which can be a weapon as a resource, but at the same time it also causes you to lose sight of other new things. I always want to bring some new elements into the project, even if only a little.
The hint when resetting is curiosity, and if you start with curiosity other than what you are used to, you may be able to reset it naturally.
いつものこと、いつもの状況、いつもの素材、いつもの場面など、いつもと変わらないことが揃っている中で、何かを変えれば新しい成果が生まれだろうかと考えてみた。
例えば、いつもの素材でも組合せを少し変えれば成果は違うし、いつもの状況でも時間を少しズラせば成果は変わるだろうし、いつものことでも途中のプロセスを少し変えれば成果に違いが生まれるだろう。
どれもこれも少しの工夫で済むかもしれない。そう思えれば、いつもと変わらないことに可能性が生まれる。
"Always the potential"
With all the things that are the same as usual, the usual situation, the usual materials, the usual scenes, etc., I wondered if something could be changed to produce new results.
For example, even with the usual materials, if you change the combination a little, the result will be different, even in the usual situation, if you shift the time a little, the result will change, and even if you change the process in the middle a little, the result will be different. ..
All of this may be a little ingenuity. If you think so, there are possibilities for things that are the same as usual.
タイル張りなのにタイル張りに見えない。前川國男の打ち込みタイルにはいつもハッとしてしまう。よくある通常のタイル張りの外壁は正直好きではない。重厚さが出るような厚みのあるタイルを使い、端部やコーナー部の納まりも詳細につめて精緻につくり込むことができればいいのだが、そこまでいいタイルを使い施工できている建築はほとんど見ない、それほど安直なタイル張りが多い。
打ち込みタイルは通常のタイル張りとは施工方法が違う。そこにひとつタイル張りに見えない所以があるのだろう。もちろん、見た目で違いがわかるのだから、通常のタイル張りに見えないのは当たり前なのだが、関心があるのは同じ素材を使ってもつくり方を変えれば見え方が変わる所である。
見え方をコントロールしようとする時、見えているそのもののデザインや素材に焦点を当てることが多いが、つくり方を変えるだけで見え方をコントロールできるとなれば、見え方のデザインにより可能性を感じることができる。
"Just change the way you make it"
It's tiled, but it doesn't look like tiled. Kunio Maekawa's driving tiles are always a surprise. I honestly don't like the usual tiled exterior walls that are common. It would be nice if we could use thick tiles that would give a heavy impression, and make the edges and corners fit in detail, but we can see most of the buildings that can be constructed using such good tiles. No, there are many tiles that are so easy.
The construction method of driving tiles is different from that of normal tiles. There may be one reason why it doesn't look like tile. Of course, it's natural that it doesn't look like normal tiles because you can tell the difference by appearance, but what I'm interested in is that even if you use the same material, the appearance will change if you change the way you make it.
When trying to control the appearance, we often focus on the design and material of what we see, but if we can control the appearance just by changing the way we make it, we feel the possibility of designing the appearance. be able to.
イメージを実現化していく時にあまり考え過ぎてしまったり、スケッチを何度も繰り返していると、当初の新鮮でスッキリしたイメージがいつの間にか鈍重で安全なイメージになってしまうことがある。
それはそれで良いのかもしれないし、たくさんの人に安心を与えるかもしれないが、当初のイメージが頭をチラつきモヤモヤする。
ある程度鮮明なイメージができたらすぐに図面に手をつけることにしている、イメージを焼き付けておくために。
"Image to burn"
If you think too much when you realize the image, or if you repeat the sketch many times, the original fresh and refreshing image may become a dull and safe image before you know it.
That may be fine, and it may reassure a lot of people, but the original image is flickering and moody.
As soon as I get a clear image to some extent, I will start working on the drawing, in order to print the image.
妄想との対話が続く。常に妄想が語りかけてくる。妄想がいろいろとアイデアやヒントをくれる。ほとんどを聞き流し気にもとめないが中には引っ掛かり頭にずっと残るものがある。妄想は現実ではないが現実と区別がつかなくなった時、ずっと頭に残っていたものが意識に上る。
意識化されたアイデアやヒントには逆らえないからそのまま受け入れるが、役に立たなければ容赦なく捨てる。そうしないと妄想に振り回されて意に反したものをデザインしてしまう。
"From delusion"
Dialogue with delusions continues. Delusions always speak. Delusions give us various ideas and hints. I don't care about most of them, but some of them get caught and stay in my head forever. Delusions are not reality, but when they become indistinguishable from reality, what remains in my mind comes to my consciousness.
I can't go against the conscious ideas and hints, so I accept them as they are, but if they don't help, I mercilessly throw them away. If you don't do that, you'll be swayed by delusions and design something that goes against your will.
物の質感をデザインする時にはじめは意識していないが後から考えると記憶の中にある質感からヒントやアイデアをもらっていることがある。
例えば、木の質感は子供の頃からまわりに材木があふれていて遊び道具だったので素手で触ることが多く、当然ざらつきや棘が刺さり痛い思いをしてきて、それが木の質感としては当たり前のように触感として身体に刻まれているので、木の面はなるべく塗装などで覆いたくは無く、ざらつきを残し、視覚的にもざらつきや凹凸感や立体感を出したくなる。
記憶の中には当然今の自分を形づくる要素がたくさん存在しているが、はじめから記憶を拠り所にするのでは無く、気がついたらあの記憶と結びついていたと思う位の方が自然と自己とのつながりの中で創作でき、また自分にしかできないものを登場させることができるような気がする。
"Connection with memory"
When designing the texture of an object, I wasn't aware of it at first, but when I think about it later, I sometimes get hints and ideas from the texture in my memory.
For example, since I was a kid, the texture of wood has been a plaything because it has been a plaything, so I often touch it with my bare hands. Since it is carved on the body as a tactile sensation, I do not want to cover the surface of the wood with paint as much as possible, leaving a rough surface, and I want to visually give it a rough, uneven or three-dimensional effect.
Of course, there are many elements that shape oneself in memory, but it is better to think that it was connected to that memory when you noticed it, rather than relying on it from the beginning. I feel like I can create something that only I can create in my memory.
設計において階段は特別な存在だという意識がある。昇降するためのものだからその機能を満たすだけで良いのだが、空間において何か異質の存在のような、機能などどうでも良い、むしろ昇降しない、ただそこにあるだけための階段をつくりたいとも思う。
だから、昇降する機能は当たり前のこととして、設計する時に考えることは空間の中でどのような在り方をするのか、どのようなつながりをつくるのか、どのように見せるのか、そして、昇降する機能が無くなっても存在価値があるのかということ。
"The stairs are foreign"
There is a consciousness that stairs are special in design. Since it is for going up and down, it is only necessary to satisfy that function, but I do not care about the function, such as the existence of something different in the space, rather I would like to create a staircase that does not go up and down, just to be there. ..
Therefore, the function to move up and down is a matter of course, and when designing, what to think about in the space, what kind of connection to make, how to show it, and the function to move up and down are lost. But is it worth the existence?
想起によって誘発するアクションは消費へ直接向かわずに何かのつながりをつくる方向へ持っていきたい。
想起によるアクションの誘発は広告が最も得意とするところだが、消費が大前提になる。ただ消費することだけでは想起のもととなる記憶が脚色されてしまう。
つながりをつくる方向に持っていければ、記憶が今この瞬間とつながり、その人なりのアクションが生まれる。そのアクションには消費も含まれるかもしれないが、つながりのおかげで多様なものになる可能性がある。
"Action to make a connection"
I want to take actions triggered by recollection in the direction of making some connection without going directly to consumption.
Advertising is best at inducing actions by recall, but consumption is a major premise. Just consuming it will dramatize the memory that is the source of the recollection.
If you take the direction of making a connection, your memory will be connected to this moment and your own action will be born. The action may include consumption, but it can be diverse thanks to the connections.
アクションを誘発するには、ひとつに想起させることである。何かを想起させることができれば、その何かに関連することのアクションを起こすかもしれない。
想起には人の意識の中にある記憶や思い込みや常識を利用する。一般的なこと、よくあること、普通なことを排除して、それでも残ることに注目する。
常識的なことも一般的なことと特定の範囲で通用するものとある。一般的なことは排除して、特定の範囲で通用するものを利用する。特定の範囲で通用するものを掴むことはすでに誘発のヒントを獲得したことになる。
"Induction of action"
To provoke an action, remind one of them. If you can remind yourself of something, you may take action related to that something.
For recall, we use memories, beliefs, and common sense in human consciousness. Focus on eliminating the common, common, and ordinary things and still remaining.
Common sense is also common and can be applied to a specific range. Exclude the general ones and use the ones that are valid in a specific range. Grabbing something that works in a certain range has already acquired a hint of triggering.
壁が隔てる目的以外に存在する理由があるとしたら、ひとつに人の視覚を通して何かを伝え、人にアクションを起こさせることである。
一番わかりやすい例は、壁にあるものは全て含むとしたら看板であり、その広告性は人のアクションを誘発するために存在する。
広告以外でも壁がアクションを誘発することが可能だとしたら、隔てるためのデザインとは違ったものになるだろうし、そもそも壁の見え方が違うだろうから、アクションを誘発する壁を考える時点で何か違う空間を生み出す可能性を孕む。
"Inducing wall"
If there is a reason other than the purpose of separating the walls, one is to convey something through human vision and make people take action.
The most obvious example is a signboard, if anything on the wall, to provoke human action.
If a wall could induce action other than advertising, it would be different from the design for separating, and the appearance of the wall would be different in the first place, so when thinking about the wall that induces action It has the potential to create something different.
薄っぺらい平らな面に何を施せば奥行き感が出るのだろうかと考えてみた。もちろん、厚みを持たせれば奥行きはつくれるかもしれないが、ここで意図したいことは奥行きがある感じである。厚みを持たせても奥行き感が出せるとは限らない。しばしば目の錯覚で奥行き感が出たり、消失したりすることがある。その時実際には奥行き自体は無い。
薄っぺらさはそれだけでひとつの表現を指向することになる。そこから脱却したい時、厚みを増すことでは無く、目の前の物を違った表現にすれば脱却し別の物にできることに興味がある。
"A sense of depth"
I wondered what to do on a thin, flat surface to give it a sense of depth. Of course, if you give it thickness, you may be able to create depth, but what I want to do here is to have depth. Even if it is thick, it does not always give a sense of depth. Often, the optical illusion may cause a sense of depth or disappear. At that time, there is actually no depth itself.
Flimthiness alone directs one expression. When I want to break away from that, I'm interested in being able to break away and make something else by expressing the thing in front of me in a different way, rather than increasing the thickness.
空間は人に従属するものだろうかと、その逆の人が空間に従属することはあるのだろうかと考えてみた。人が空間に従属することは空間が人を選ぶことでもある。さらに空間は物だから、物が人を選ぶことと言い換えることもできるかもしれない。
物が人を選ぶとしたら、物の機能や使用感、例えば、快適性などに注意を払う必要が無くなる。物は合う人だけと関係ができれば良いとなる。
そうなると、極端に物の価値が限定されるように思えてしまうが、人側から物の魅力の深度みたいなことを考えてみると、機能や使用感が消失して物と同一化しても良いくらいに合わせたいと思えれば、それはその人とって物の価値は最大化しており、結局ものづくりをしている人にとってはそこが最終目的地なのではないかと思ってしまう。
"Things choose people"
I wondered if space is subordinate to humans, and vice versa. The fact that a person is subordinate to space also means that space chooses a person. Furthermore, since space is a thing, it may be rephrased as a thing choosing a person.
If an object chooses a person, it is not necessary to pay attention to the function and usability of the object, for example, comfort. Things only need to be able to relate to people who fit.
In that case, it seems that the value of the thing is extremely limited, but considering the depth of the attractiveness of the thing from the human side, the function and usability may be lost and it may be identified with the thing. If you want to match it, it maximizes the value of things for that person, and after all, for those who are making things, I think that is the final destination.
トリップしたいのは非日常を味わいたいから、いつもと違う体験がしたいからだと思うが、案外にも日常の延長でしか考えない場合も多いかもしれない。
非日常とは言えあまりにも日常とかけ離れていては現実味が無くなるから、かえって楽しめなくなるのかもしれない。
非日常の加減、度合いが大事になるが、それは今ここにいる自分をどれだけ想像できるかによると思う。今ここにいる自分とは、今ここにいることに自分とつながりがあり、そのつながりが自分のことのように思えるかである。
建築ならば、今いる空間につながっている自分を現実感を持って見ることができるかであり、そのつながり加減、度合いを調整することもデザインの範疇だと考えている。
"The connection that is here now is design"
I think that I want to trip because I want to experience extraordinary things, and I want to experience something different from usual, but unexpectedly, I may think only as an extension of my daily life.
Even if it is extraordinary, if it is too far from everyday life, it will be unrealistic, so it may not be enjoyable.
The degree of extraordinary adjustment is important, but I think it depends on how much you can imagine yourself here. I am here now, and I have a connection with myself to be here now, and that connection seems to be me.
In the case of architecture, it is possible to see yourself connected to the space you are in with a sense of reality, and I think that adjusting the degree and degree of that connection is also a category of design.
視覚の中にメタファーを持ち込むことにより、時間に空白という間をつくり、今ここには無いことまで意識させ、目の前の空間だけでは無いことまでデザインしたいと考えた。
メタファーという暗示は、明示のような瞬時のわかりやすさは無く、わかるまでに時間の空白ができ、その空白がより深い理解と意識を別の所へ運ぶ。
ここでデザインしたいのは人の意識の行き先である。
"Consciousness carried by metaphor"
By bringing a metaphor into the visual sense, I wanted to create a gap in time, make people aware of what is not here now, and design not only the space in front of them.
The suggestion of metaphor is not instantly understandable like explicit, but there is a time gap before it is understood, and that gap carries a deeper understanding and consciousness to another place.
What I want to design here is the destination of human consciousness.
視覚の中に時間の要素を持ち込みたいと考えている。
時間の要素とは時間の幅のようなもので、例えば、何かを見ている時に目の前にある物の今この瞬間を捉えているが、その物が過去から未来へと時間の流れの中でどのように存在してきたが伝わるようにしたい。
もしかしたら、それは瞬時にでは無くて少しの間があり、少しわかりづらい状況をあえてつくることになるかもしれない。
"Visually the width of time"
I want to bring an element of time into my vision.
The element of time is like the width of time, for example, when you are looking at something, you capture the moment of the thing in front of you, but that thing is the flow of time from the past to the future. I want to convey how it has existed in the world.
Perhaps it's not an instant, but a short time, and it may dare to create a situation that is a little confusing.
視覚の中で曖昧な部分をつくることにより瞬時にわかることを避けて、そこに時間の空白をつくろうとした。
人は空白を感じると何かで埋めようとする。時間の空白は視覚で得た情報に余分な意味づけをする機会を与える。その意味づけの内容は見る人によって違う。
同じものを見ていても見る人によって受け取り方が変わる可能性がより広がり多様になる。
"The gap in time creates variety"
I tried to create a time gap there, avoiding instant understanding by creating an ambiguous part in the visual sense.
When a person feels a blank, he tries to fill it with something. The time gap gives the visual information an opportunity to give extra meaning. The content of the meaning differs depending on the viewer.
Even if you are looking at the same thing, the possibility that the way you receive it will change depending on the person who sees it will become more widespread and diverse.
視覚で感じたことの中にある意味が明示ならば瞬時に全体を把握することができ、それがわかりやすさや自律性の高さにつながる。
わかりやすさは何かを相手に伝える時には非常に大事なことだが、相手に深い印象を残すことを意図した場合には必ずしも大事なことでは無い。深い印象を残したければ明示より暗示、すなわちメタファーを活用する方が良い。
視覚で感じるメタファーにより、瞬間の把握では無くほんの少しのタイムラグが生じる。このタイムラグが深い印象へとつながる。
"Create a time lag visually"
If the meaning in what you feel visually is clear, you can instantly grasp the whole thing, which leads to easy understanding and high autonomy.
Clarity is very important when telling something to the other person, but it is not always important when the intention is to leave a deep impression on the other person. If you want to leave a deep impression, it is better to use suggestion, that is, metaphor, rather than explicit.
The visual metaphor creates a slight time lag rather than a momentary grasp. This time lag leads to a deep impression.
素材からの連想を意識することはメタファーにアクセスしていくことを意識する必要があると考えた。
メタファーは建築において使い古された言葉と思ってしまうが今だに主題になり得る言葉であり、あえて特別に扱う必要が無く一般的な言葉になったと解釈している。建築以外の分野ではメタファーは当たり前に意識されているので、建築でも特殊なことを一般解として扱いたい時には手段として使える。
"Aware of metaphor"
I thought that it is necessary to be aware of accessing the metaphor to be aware of the association from the material.
I think that metaphor is a word that has been used up in architecture, but it is still a word that can be the subject, and I interpret it as a general word that does not need to be treated specially. Metaphors are taken for granted in fields other than architecture, so they can be used as a means when you want to treat special things as general solutions in architecture as well.
素材から連想する建築もあるだろう。例えば、木組みを見たら和風の建築や和に関係する空間や建築を連想する。素材に意味がついている。あと、素材の見せ方や素材感にも意味がついていて連想を助けている。それは素材を扱う時に考慮しなければいけないところであり、別の考え方をすれば、素材の扱い方を変えればついている意味を操作できることでもある。
木組みは和風という素直な連想を利用することが重要な時もあるが、少し素材の扱いを変えて、木組みに和風以外の意味を付け加えた時にどうなかるかを考えるのもデザインの範疇である。
"Designing associations from materials"
Some architecture may be associated with the material. For example, when you look at the wooden structure, you think of Japanese-style architecture and spaces and architecture related to Japanese. The material has a meaning. Also, the way the material is shown and the texture of the material have meaning, which helps the association. That is something that must be taken into consideration when dealing with materials, and if you think about it differently, you can manipulate the meaning that comes with it by changing the way you handle materials.
Sometimes it is important to use the straightforward association of Japanese style for woodwork, but it is also a category of design to think about what happens when you add a meaning other than Japanese style to woodwork by slightly changing the treatment of materials. ..
素材感だけを抜き出して眺めてみると、素材の違いに関係無く全て同じに見える場合がかる。
例えば、木製の仕上げがされていても、そこにクリアな厚い塗装がかけられていたら、木製に見せかけたプリントと素材感は似たようになる。何かでコートすることにより汚れや傷みから守ろうとするのはわかるが、それならばそもそも木を使わなければ良い。
素材の違いより素材感の違いに注目すると見た目以上に素材の持つ空間への影響を感じ取ることができる。
"Effect of texture"
If you take out only the texture and look at it, it may look the same regardless of the difference in the material.
For example, even if it has a wooden finish, if it is painted with a clear thick paint, the texture will be similar to the print that looks like wood. I know that you can coat it with something to protect it from dirt and damage, but then you shouldn't use wood in the first place.
If you pay attention to the difference in texture rather than the difference in material, you can feel the influence of the material on the space more than it looks.
物そのものでは無くて物に付随すること、例えば、見せ方についていろいろ考えてみた。モジュールやパターンで物を見せようとした時に何が起こるだろうか。
物そのものの存在もあるが、物とは関係するが離れたパターンやモジュールといった規則性、それを秩序と言い換えてもいいと思うが、その秩序を直接扱うことになる。それは物そのものでは無いが付随することを直接扱うことになり、それが物そのものにどのような影響を与えるのか気になる。
"The impact of order"
I thought about things that accompany things, not the things themselves, such as how to show them. What happens when you try to show things in modules or patterns?
There is the existence of the thing itself, but the regularity such as patterns and modules that are related to the thing but separated from each other, which can be rephrased as order, but the order is dealt with directly. It is not the thing itself, but it deals directly with the accompanying things, and I am wondering how it affects the thing itself.
物に付随していることを扱う方が直接物を扱うより可能性があると考えている。
物を直接扱う場合は物の質を問うことになり、質の良し悪しが物の直接的な価値を決めることになる。質の悪い物をつくる気は無いつし、質の悪い物でいい訳では無く、質の良い物をつくろうとするが、質に焦点を当てると価値判断にコストが付き纏い、コストが直接的に価値を決める場面が出てくる。
しかし、物に付随していること、例えば、物の見せ方に焦点を当たれば、価値判断をコストで左右されにくく、別の要素が価値を決めるようにできる。
"Attachment determines value"
I think it is more possible to deal with things that accompany things than to deal with things directly.
When dealing with things directly, the quality of the things is questioned, and the quality of the things determines the direct value of the things. I have no intention of making poor quality products, and I am not good at making poor quality products, but I try to make good quality products, but if I focus on quality, the cost is attached to the value judgment, and the cost is direct. There will be a scene where the value is decided.
However, if we focus on what is attached to an object, for example, how it looks, the value judgment can be less cost-sensitive and another factor can determine the value.
見え方をデザインすることは見えているものをデザインすることとは違う。見え方を変えれば、見ているものが同じでも、違うものに見えるかもしれない。
見ているものをデザインすることは物を直接扱うことになるが、見え方をデザインすることは物を間接的に捉えることになり、直接扱うのは物に付随していることである。
付随していることは有形無形いろいろあるが、今ここにあることに直結していることで、物の存在に直に関わることだと考えている。
"Attachment"
Designing what you see is not the same as designing what you see. If you change the way you look, it may look different even if you are looking at the same thing.
Designing what you are looking at deals with things directly, but designing how you see them indirectly captures things, and dealing directly with things is attached to them.
There are various tangible and intangible things that accompany it, but I think that being directly connected to what is here now is directly related to the existence of things.
どう見せるかを考える時にそのまま物を見せるより、物が見える現象に注目して、その物の見え方をコントロールしたいと考えた。物がそこにあることと物が見えることは等しいことでは無く、そこにあることをデザインすることと見え方をデザインすることも違う。
見え方に注目してみた。その物がどうであるかより、どう見えるかを扱った方が物そのものの存在に迫れるような気がしている。
"The thing itself"
Rather than showing things as they are when thinking about how to show them, I wanted to focus on the phenomenon of seeing things and control how they look. It is not the same that an object is there and an object is visible, and designing what is there is also different from designing how it looks.
I paid attention to how it looked. I feel that it is closer to the existence of the thing itself when dealing with what it looks like rather than what it looks like.
何を美しいと思うのだろうか。美しいという基準は人から植え付けられる。いま一度、赤子に戻り美しさを問い直すと疑問が湧く。美しさの常識が嘘に思える。ここで分かれ道です、どうするか、美しさの常識に乗る方が安心でき、確実で、破綻しない。ただ、自分の中にある美しさと一致しないかもしれない。破綻が怖い人が多いだろう、積み上げが無になるから。積み上げが無い人にとっては自分の中にある美しさが尊い。
"What is beautiful"
What do you think is beautiful? The standard of beauty is planted by humans. When I go back to the baby and ask the beauty again, I have doubts. The common sense of beauty seems to be a lie. This is a fork in the road, and it's safer, more reliable, and unbreakable to follow the common sense of beauty. However, it may not match the beauty within me. Many people are afraid of bankruptcy, because there will be no stacking. For those who do not have a stack, the beauty within them is precious.
何かを見せるにしても、そのまま見せることに興味が湧かない。どれだけ美しいものでも美しさを前面に出すだけではつまらない。絶対的な美しさは素晴らしいが飽きる。飽きないためには常に変化する要素が必要である。常に変化する要素を得るために相対的な美しさを求める。相対的とは比較であり、美しさも比較する対象があって成り立つ。比較する対象を必要とすることは、比較する対象によって美しさが変化するということである。
"Changing beauty"
Even if I show something, I'm not interested in showing it as it is. No matter how beautiful it is, it's boring just to bring it to the fore. Absolute beauty is wonderful but tired. In order not to get bored, we need elements that are constantly changing. Seeking relative beauty to get the ever-changing elements. Relative is a comparison, and beauty also has an object to be compared. The need for an object to be compared is that the beauty changes depending on the object to be compared.
現状をブレークスルーには、違和感のような小さなフラストレーションに目を向け、それを解消することに好奇心を持つといいかもしれない。
似たり寄ったり当たり前のことに違和感を持つことが多く、似たり寄ったりがたくさんあることはそれがその業界の今の正解かもしれないが、たくさんあることに違和感を持ち、そもそも似たり寄ったりと思う時点で自分には興味の無いものになっている。
当時者が気づかない違和感を持つことができれば、それだけでブレークスルーの種はできたかもしれない。
"Seeds of breakthrough"
To break through the status quo, it may be good to look at small frustrations such as discomfort and be curious about eliminating them.
There are many things that are similar or close to each other, and it may be the correct answer in the industry that there are many similarities, but it is strange that there are many things that are similar to each other in the first place. At the time I think about it, I'm not interested in it.
If the person at that time could have a sense of incongruity that he did not notice, that alone might have created a breakthrough seed.
人が影響を与える空間では人の根源的な欲望を刺激する必要がある。人が影響を与えるには、人がアクティビティをする必要があり、アクティビティのきっかけが必要になる。そのきっかけが根源的な欲望を刺激されることであり、空間が人の根源的な欲望を刺激する存在である必要がある。
根源的な欲望は好奇心と言い換えてもいいかもしれない。好奇心にもいろいろと種類があり、人により違うかもしれないが、わかりやすいのは未知の体験に対する好奇心である。知らないものを知りたいという知識欲と相まって未知の体験は好奇心を刺激する。
"Space needs an unknown experience"
In a space where people influence, it is necessary to stimulate the person's fundamental desires. In order for a person to influence, a person needs to do an activity, and an opportunity for the activity is needed. The trigger is to stimulate the fundamental desires, and the space needs to be the existence that stimulates the fundamental desires of human beings.
Primitive desire may be rephrased as curiosity. There are many types of curiosity, which may vary from person to person, but what is easy to understand is curiosity about an unknown experience. An unknown experience, coupled with a desire to know what you don't know, stimulates curiosity.
常に空間に囲まれている。建築を考える時、空間に注目するか、物に注目するかの2通りある。
それは建築を空間として捉えるか、物として捉えるかの違いであり、空間として捉える場合は建築内部に空虚な部分があり、その空虚な部分が人を内包できる位に大きいので、建築は人の影響を受けるという考え方である。
一方、物として捉える場合は建築はひとつの塊として捉え、その塊をどのようにつくるか、どのように置くかが重要であり、それによって周りの環境や人にどのような影響を与えるかが主題になる。
どちらが良いかではなく、時代によって流行り廃りはあるが、基本的には歴史上どちらかが優位になることを繰り返してきた。
別の言い方をすると、人が影響を与えるか、人に影響を与えるかの違いである。良い建築を見て感動する場合は人に影響を与えることになるので、物としての建築が優位になり魅力的に見えるが、人無しで成立するものは建築以外でも、工作物でも、美術品でもあり得るので、人が影響を与える建築、すなわち空間として捉える方が建築独自のものが表現できると考えている。
"Space is unique to architecture"
Always surrounded by space. When thinking about architecture, there are two ways to focus on space and things.
It is the difference between perceiving architecture as a space or as an object. When perceiving it as a space, there is an empty part inside the building, and the empty part is large enough to contain people, so architecture is influenced by people. The idea is to receive.
On the other hand, when considering it as an object, architecture is regarded as one mass, and how to make the mass and how to place it are important, and how it affects the surrounding environment and people. Become a subject.
It is not which one is better, but it has become fashionable and obsolete depending on the times, but basically, it has been repeated that either one has an advantage in history.
In other words, it is the difference between a person's influence and a person's influence. If you are impressed by seeing a good architecture, it will affect people, so architecture as a thing will be superior and look attractive, but what can be established without people is not only architecture, but also works of art. However, since it is possible, I think that it is possible to express something unique to architecture by considering it as an architecture that people influence, that is, a space.
狭い空間では求められる機能を頼りにデザインをしていたら似たり寄ったりになる。
機能を頼りにデザインをすることはデザインに明確な根拠を与え、恣意的という批判を安易にかわすことができるので多用されやすい。しかし、狭い空間では機能が限定されバリエーションが無くなるので似たり寄ったりを招く。
だから、むしろ機能とは関係が無いところでデザインをする。それはもしかしたら人の内面に直接働きかけることになり、人のウォンツを引き出すかもしれない。
"Don't rely on features"
In a small space, if you rely on the required functions for designing, they will look similar.
Designing by relying on function gives a clear basis to the design, and it is easy to avoid criticism that it is arbitrary, so it is easy to be used frequently. However, in a narrow space, the functions are limited and there are no variations, which leads to similarities.
Therefore, rather, design in a place that has nothing to do with the function. It may work directly on the inside of the person and may bring out the wants of the person.
時を経て前の建築とつながろうとする時に齟齬が起きそうなところに注目してみようと考えた。
前の建築とこれから現れる建築は同じ場所に建つので同じような特徴を持つが同時に全く違う要素も持ち合わせる。全く違う要素は齟齬を起こすが、その場所での可能性につながると考えた。
定まらないから全く違う要素になるのであり、定まらないことに可能性を感じる。
"Possibilities that cannot be determined"
I decided to pay attention to the place where a discrepancy might occur when trying to connect with the previous architecture over time.
The previous architecture and the one that will appear in the future will be built in the same place, so they have similar characteristics but at the same time have completely different elements. A completely different element causes a discrepancy, but I thought it would lead to possibilities in that place.
Since it is not decided, it will be a completely different element, and I feel the possibility of not being decided.
時を経て前の建築とつながることで魅力的な空間ができないかと考えている。現在これから魅力的な空間をつくろうとする時に前の建築とつながる必要は無いから、スクラップアンドビルドが普通に行われるが、それでは時間と記憶と愛着の断絶が起こってしまう。
時間と記憶と愛着をつなぐのが建築の役割であって欲しいので、つなぐための手法をいろいろと考えている。
"The role of connecting"
I am wondering if it will be possible to create an attractive space by connecting with the previous architecture over time. Nowadays, when trying to create an attractive space, it is not necessary to connect with the previous architecture, so scrap and build is usually done, but that causes a break in time, memory and attachment.
I want architecture to play a role in connecting time, memory, and attachment, so I am thinking of various methods for connecting them.
抽出するのは密度であり、抽出したものは単なる模様として意味を剥奪し、全く違った意味を付着させる。
時がズレており決して交わることが無かったプラン同士を重ねてみた時、そこにつながりを見つけるために重なりの密度に着目し、そこから俯瞰して模様として全体を見ることにした。
模様として全体を俯瞰することは元々の意味を無いことにし、新たな意味で捉え直すことであり、その新たな意味が新たな空間を生むだろう。
"A new space with a new meaning"
It is the density that is extracted, and what is extracted deprives the meaning as a mere pattern and attaches a completely different meaning.
When I tried to stack plans that never intersected due to the time lag, I focused on the density of overlap in order to find a connection there, and decided to take a bird's-eye view of the whole as a pattern.
Taking a bird's-eye view of the whole as a pattern has no original meaning and is to be reconsidered in a new meaning, and that new meaning will create a new space.
現在の建築のプランと前回の建築のプランを重ねてみた。何度か増改築を繰り返しているので柱の位置が同じ所もあり、また重ねたことにより壁の密度の差がよりはっきりと出た。
壁の密度が高い所は細かく仕切られた空間が集まっており、密度が低い所は仕切られていない空間の集まりである。
重ねることでより顕著になる壁の密度の差は、その場所での建ち方の傾向を表現している。
"Tendency of how to build"
I tried to overlap the current architectural plan and the previous architectural plan. Since the pillars have been expanded and remodeled several times, the pillars are in the same position, and the difference in the density of the walls became clearer due to the overlapping.
Where the wall density is high, the spaces that are finely divided are gathered, and where the density is low, the spaces that are not partitioned are gathered.
The difference in wall density, which becomes more noticeable when stacked, expresses the tendency of how to build at that location.
現在の建築があり、そして、次の建築を用意する。そこに何か現在と次の建築の間につながりをつくりたいと考えた。
全く無いことにして次の建築を計画することが普通になっているが、それでは様々な断絶が繰り返し起こるだけであり、断絶は積み重ねたものを無にしてしまい、しかもその原因を建築がつくっていることになる。
建築は人を内包する規模のものであるから影響力がある。だから、断絶しない、つながりをつくることが様々なことに良い影響を与えると考えている。
"Make a connection without breaking"
There is a current building, and the next one is ready. I wanted to make a connection there between the present and the next architecture.
It is common to plan the next building with nothing at all, but then various breaks will only occur repeatedly, and the breaks will eliminate the piled up things, and the cause will be created by the architecture. Will be there.
Architecture is influential because it is of a scale that embraces people. Therefore, I think that making connections without breaking has a positive effect on various things.
建築において目には見えない規範のようなものは何かと考えてみると、モジュールやグリッドやスパンなどの一定の決まった尺度の繰り返しであったり、その土地固有のルール、例えば、敷地に対する建ち方や仕上げの素材などの環境からの影響や、建築に具体的にはわかりやすく現れてこないかもしれない慣習などがある。
さらに、それらの規範にはその元となる建築へのモラルや期待感なども含まれるかもしれないし、過去へ遡ってつながりを紡ぐことも必要かもしれない。
何かひとつの規範を抽出したら、建築に関係する全ての事柄を絡め取るようなことができないかと考えている。
"The norm entwines everything"
Thinking about what kind of invisible norms in architecture are the repetition of certain fixed scales such as modules, grids and spans, and the land-specific rules, such as how to build on the site. There are environmental influences such as finishing materials, and customs that may not appear in architecture in an easy-to-understand manner.
In addition, those norms may include morals and expectations for the underlying architecture, and it may be necessary to go back in time and create connections.
I'm wondering if I could extract all the norms and get involved with all the things related to architecture.
永遠に残すことができるものは何かと考えていくと、経年劣化しないものであり、実体があるものというよりは概念や枠組みやルール、それを秩序と言い換えてもいいが、目には見えない規範のようなものをイメージした。
建築に吸着している記憶や愛着は、建築自体が無くなれば消滅してしまうかもしれないが、建築が持っていた規範のようなものが抽出され残るならば、記憶や愛着も元々は目に見えないものだけに相性が良く、記憶や愛着のエッセンスだけ残り、また新たな肉付けが記憶や愛着にされるのではないかと考えた。
"Extraction of norms"
Thinking about what can be left forever, it does not deteriorate over time, and it can be rephrased as a concept, framework, rule, or order rather than a substance, but an invisible norm. I imagined something like.
The memories and attachments that are attached to the architecture may disappear if the architecture itself disappears, but if the norms that the architecture had are extracted and remain, the memories and attachments are originally visible. I thought that it would go well with only the invisible things, leaving only the essence of memory and attachment, and that new flesh would be made into memory and attachment.
記憶や愛着が吸着するモノは、よく見ていたモノか、よく触れていたモノであり、人の五感、特に視覚や触覚と結びついていたモノである。だから、建築には記憶や愛着が吸着しやすいかもしれない。
吸着した記憶や愛着は建築の形や空間や場面として残る。だから、建築の形や空間や場面がそのまま記憶や愛着となる。よって、建築の形や空間や場面をそのまま永遠に残すことができれば、記憶や愛着は途切れることが無いが、永遠に残すことなどはできない。
ならば、永遠に残すことが可能なモノを建築の形や空間や場面の中から抽出して残せば良いのではないか。
"Extract and leave forever"
The things that memories and attachments adsorb are the things that you have often seen or touched, and the things that are associated with the five senses of human beings, especially the sense of sight and touch. Therefore, it may be easy for memories and attachments to stick to architecture.
The adsorbed memories and attachments remain as the shape, space, and scene of the architecture. Therefore, the shape, space, and scene of the architecture become memories and attachments as they are. Therefore, if the shape, space, and scene of architecture can be preserved forever, memories and attachments will not be interrupted, but they cannot be preserved forever.
Then, it would be better to extract and leave things that can be left forever from the shapes, spaces, and scenes of architecture.
記憶や愛着などの自体が無いものを形にするには、記憶や愛着が投影されているモノを探し、そのモノをどのように扱えば記憶や愛着が前面に出てくるのか、表現できるのかを考える。
記憶や愛着が投影されているモノは必ず時のサイクルを経ても残っているモノであり、ただそのままでは時のサイクルにより無くなるモノであり、投影されているモノを探し出したら、時のサイクルに流されないように変えてやる必要がある。
"Searching for projected objects"
In order to shape something that has no memory or attachment, look for a thing on which memory or attachment is projected, and how to handle that thing to express how the memory or attachment comes to the fore. think of.
Things on which memories and attachments are projected are always things that remain even after the cycle of time, but things that disappear by the cycle of time as they are, and if you find the thing that is projected, it will flow into the cycle of time. It is necessary to change it so that it will not be done.
今は見えない、かつてあったものに思いを馳せて、つながりを持ちたいと考えた時に何に注目し、そこから何を抽出すればいいのだろうか。
無くなる建築、建て替わる建築、それらは時のサイクルだとしたら仕方は無いが、それでも何かつながりを持てれば無くなった建築から未来に向けて何か残すことができるかもしれない。
建築には記憶や愛着が宿る。記憶や愛着をつなぎたい。記憶や愛着はそれ自体実体が無い。自体が無いものを形にするには、何かに変換する必要がある。
"Connect, convert"
What should we focus on and extract from what we once had, which we can't see now, and when we want to make a connection?
It can't be helped if it's a cycle of time, architecture that disappears, architecture that rebuilds, but even so, if we have some connection, we may be able to leave something from the lost architecture to the future.
Architecture has memories and attachments. I want to connect my memories and attachments. Memories and attachments have no substance in themselves. In order to make something that doesn't exist, it needs to be converted into something.
実物を目の前にして、ただそれを見せるだけでデザインするのはつまらないと思った。どれだけ素晴らしいモノでも、どれだけ精緻に加工しても、そのまま痕跡を残すようなことをしたら、そのモノと対峙して内在している良さを引き出せたことにはならない。
そのモノの存在自体からデザインしたいと考えた。今見ている実像とは違う虚像をつくり出し、実像に内在しているそのモノだけでは納まり切らない関係性をデザインし、全く違うが関連性のあるコトをイメージさせたい。
例えば、存在しているのかしていないのかというような状態をつくり出せれば、虚実が入り乱れ内在している関係性が浮かび上がるかもしれない。その時の虚実の入り乱れ方をデザインすることで、全く違うが関連性のあるコトのイメージをコントロールできるかもしれない。
"The mess of truth"
I thought it would be boring to design by just showing the real thing in front of me. No matter how wonderful a thing or how finely it is processed, if you do something that leaves a trace as it is, it does not mean that you can bring out the inherent goodness by confronting the thing.
I wanted to design from the existence of the thing itself. I want to create a virtual image that is different from the real image I'm looking at, design a relationship that isn't completely contained in the real image, and imagine something that is completely different but related.
For example, if we can create a state of existence or non-existence, the relationship between the truth and the immanence may emerge. By designing how the truth is mixed up at that time, it may be possible to control the image of things that are completely different but related.
見ることでしか実感ができないのであれば全てが虚像だと思った。触覚を除いた視覚でのみモノを把握しようとした時、モノは目を通した像が脳内で処理され認識するので、脳というフィルターを通している時点で実像とは違うものになっており虚像である。
そうすると、いつまで経っても視覚のみでは実像にたどり着くことはできない。人間に手足があるのは触覚により実像を把握するためともいえるかもしれない。
しかし、手足で触れることができるモノは限られる。
だから、モノは視覚のみで把握されると限定した上で虚像としてのモノについて考察したりデザインをする方がモノの本質に迫ることができるような気がした。
"Things are virtual images"
If I could only feel it by looking at it, I thought it was a virtual image. When trying to grasp an object only by sight excluding the sense of touch, the image through the eye is processed and recognized in the brain, so when it is passed through a filter called the brain, it is different from the real image and it is a virtual image. be.
Then, it is impossible to reach the real image only by sight, no matter how long it passes. It may be said that humans have limbs because they can grasp the real image by touch.
However, the things that can be touched with limbs are limited.
Therefore, I felt that it would be possible to get closer to the essence of things by considering and designing things as virtual images after limiting things to things that can only be grasped visually.
半透明の膜を通して見ることと直接見ることの違いについて、言い換えると虚と実について考えるきっかけがあり、虚をつくり出すことで実の存在を超えるようなものにしたいと思った。
虚は実との関係で成り立ち、実があるから虚が存在できるが、極端なことを言えば虚が実をつくり出すようなことができないかと考えている。
例えば、虚が大枠や輪郭を定めることにより実が浮かび上がるようなことができないか。その場に虚と実が同時に存在している必要はないから、虚だけが見せることができる像から実がイメージできればいい。
"Bringing fruit from the emptiness"
There was an opportunity to think about the difference between seeing through a translucent film and seeing directly, in other words, imagination and reality, and I wanted to create something that goes beyond the existence of reality.
The emptiness is based on the relationship with the fruit, and since there is a fruit, the emptiness can exist, but to put it in the extreme, I wonder if the emptiness can create the fruit.
For example, is it possible for the imaginary to emerge by defining the outline and outline? It is not necessary for the imaginary and the real to exist at the same time, so it is only necessary to be able to imagine the real from the image that only the imaginary can show.
線材で文節される空間領域を持つ和風建築を引き継いでいく時に、時が経ち形が無くなったとしても線材による空間領域の輪郭は残せるのではないかと思った。
その場所における空間領域の輪郭はその場所固有のものであり、その場所においては時が積み重なった価値あるもので、別の言い方をすれば記憶や愛着の輪郭である。
輪郭を引き継ぐことは建築ならば受け入れやすく実践しやすいことかもしれない。
"Take over the contour"
When taking over the Japanese-style architecture that has a space area that is sung by the wire, I thought that the outline of the space area by the wire could be left even if the shape disappeared over time.
The contours of the spatial area at that location are unique to that location, and at that location are valuable as time accumulates, in other words, the contours of memory and attachment.
Taking over the contours may be easy to accept and practice in architecture.
和風建築をよく見ると緩やかに段階的な結界で領域をつくりながら空間が展開していく。その様は現代建築や西洋建築とも違う。
和風建築の空間はつながり連続していくが決して全てがオープンでは無い。節目があり、越えられない線が存在し、領域分けを覆い被せるように天井や屋根が架けられる。
だから、いかに越えられない線を扱い、巧みに配置するかが和風建築のプランニングの肝であり、それは現代建築にいかすことができる。
"Japanese-style liver"
If you look closely at Japanese-style architecture, the space develops while creating areas with gentle stepwise barriers. That is different from modern architecture and Western architecture.
The spaces of Japanese-style architecture are connected and continuous, but not all are open. There are knots, there are lines that cannot be crossed, and ceilings and roofs are erected to cover the area division.
Therefore, how to handle the lines that cannot be crossed and arrange them skillfully is the key to planning Japanese-style architecture, which can be applied to modern architecture.
数寄屋建築のような和風建築で大広間があるものは障子や襖を開け放てば外部空間と一体的にシームレス につながる。その場合、大広間から外部空間までの間でいくつかの線材により区切られる。
線材とは例えば、敷居や鴨居であったり、框などの段差の見切りであったり、天井の仕上げの変わり目や見切り縁であったりする。
機能上必要だから線材を入れるのだが、見せ方として線に見せないこともできるはずであり、意図的に何かの意味を持たせるために線としているのだろう。線材が無ければよりシームレスに一体的に外部空間と大広間がつながる。しかし、和風建築はそこは意図しておらず、大広間から外部空間まで見通せるが外部空間は別の領域としたい。
そこで、外部空間までの間にいくつか線材を入れて段階的に結界をつくっているのだろう。だから、和風建築は決して開放的では無い。
"Japanese style that is not open"
Japanese-style architecture such as Sukiya-zukuri, which has a large hall, can be seamlessly connected to the external space by opening the shoji and sliding doors. In that case, it is separated by several wires from the hall to the external space.
The wire rod may be, for example, a sill or a lintel, a parting line of a step such as a stile, or a transition or a parting edge of a ceiling finish.
I put in a wire because it is functionally necessary, but it should be possible not to show it as a line as a way of showing it, and it seems that it is intentionally made into a line to have some meaning. If there is no wire, the exterior space and the hall will be connected more seamlessly and integrally. However, Japanese-style architecture is not intended there, and although you can see from the hall to the exterior space, you want to make the exterior space a different area.
Therefore, it seems that some wires are inserted between the exterior space and the barrier is created step by step. Therefore, Japanese-style architecture is by no means open.
全ての敷地のコンテクストには歪みやノイズが必ずあり、その歪みやノイズを均一にしてしまうような計画で建てること、すなわち、どこで建てても同じになる建築には魅力を全く感じない。
この場合の均一化は、均一に均すというより、均一な枠組みに無理矢理嵌め込むようなイメージであり、枠組みがあった方が管理しやすく、再現性があるから良いという理屈になり、それは効率化へつながる。
では歪みやノイズをいかしながら、管理の良さと再現性を求めてみたることはできるだろうかと考えみた時、中和が有効手段だと思った。一旦ニュートラルな状態にする中和は、一見均一化に似ているが、元々あるモノとのつながりを断絶せずに維持する点で相違がある。
中和は歪みやノイズを一旦ニュートラルにするが、その過程では最大の歪みやノイズを発生し新しいモノを生むことができる。だから、効率化されたモノとは全く違うモノになる。
"Making use of distortion and noise"
There is always distortion and noise in the context of every site, and I am not attracted to building with a plan that evens out the distortion and noise, that is, the same architecture no matter where it is built.
Uniformization in this case is more like forcibly fitting into a uniform framework rather than evening it evenly, and it is the theory that it is better to have a framework because it is easier to manage and reproducible, which is efficiency. It leads to reproducibility.
Then, when I wondered if it would be possible to seek good management and reproducibility while taking advantage of distortion and noise, I thought that neutralization was an effective means. Neutralization, once neutralized, is similar to homogenization at first glance, except that it maintains an unbroken connection to the original thing.
Neutralization makes distortion and noise neutral once, but in the process, the maximum distortion and noise can be generated and new things can be created. Therefore, it will be a completely different product from the one that has been streamlined.
中和は元があって成り立つから、既存の改修やリノベーションの際にデザインのヒントになりかもしれないが、元が無くても、元を仮想的につくれば良く、一旦イメージの中でもいいから構築し、それに対して中和を試みことは全てのものづくりに対してできることであり、有効だと考えている。
結果的にできあがるモノに中和の影響が色濃く表れることで元のつながりがわかる。
中和することは一旦ニュートラルな状態になることであるから、例えば、その土地のコンテクストや人のアクティビティが素直に読み取れるはずであり、それは効率化を超えた状態がつくれるのではないかと考えた。
"Neutralization beyond efficiency"
Neutralization is based on the origin, so it may be a hint for design when renovating or renovating an existing one, but even if there is no origin, you can create the original virtually and build it once in the image. However, trying to neutralize it is something that can be done for all manufacturing, and I think it is effective.
The original connection can be understood by the strong effect of neutralization on the resulting product.
Since neutralization is to become a neutral state once, for example, the context of the land and the activity of people should be able to be read honestly, and I thought that it could create a state beyond efficiency.
中和しようとする試みは全く逆のアクティビティを発生させる必要があるかもしれないので、プランに大きく影響を与えるが、逆という関係性を意識することでつながりはできる。
ただ、面白いのは中和という混ぜ合わせるような試みをした結果が全く逆の新しいもの、違ったものを生み出すかもしれないということである。元があるものに対して強調することは新しい試みでも何でも無く、同じことの繰り返しでしかない。
"The fun of neutralization"
Attempts to neutralize may need to generate the exact opposite activity, which can have a significant impact on the plan, but you can make a connection by being aware of the opposite relationship.
What is interesting, however, is that the result of a mixed attempt of neutralization may produce something completely opposite, something different. Emphasizing the original is not a new attempt or anything, it is just a repetition of the same thing.
時間のサイクルを建替えの歴史で表現できると思い、時代毎のプランを重ねてみた。そこに現れるのは時間のサイクルがもたらした記憶の痕跡の重なりであり、痕跡はそのまま愛着と結びつくかもしれない。
時間がサイクルしても記憶や愛着をつなげるためにプランの重なりの中から何を抽出するか。重なり具合の違いや密度の違いは、その場所で生活した人達特有のものであり、固有のアクティビティとも読み取れる。
プランの重なりにさらに新しいプランを重ねてみる。その時に重なり具合の違いや密度の違いをより強調するのか、中和するのか。強調する方が時間がサイクルしても記憶や愛着をつなぐことにはなるが、重なり具合の違いや密度の違いに呼応したことにより中和が行われるのであれば、新しいプランは今までとは全く違うものになりつつもつながりはつくることになり、それならば中和する方が面白いかもしれないと考えた。
"Attempt to neutralize memory"
I thought that the cycle of time could be expressed in the history of rebuilding, so I tried to repeat the plans for each era. What appears there is an overlap of the traces of memory brought about by the cycle of time, and the traces may be directly linked to attachment.
What to extract from the overlap of plans to connect memories and attachments even if time cycles. The difference in the degree of overlap and the difference in density are peculiar to the people who lived in the place, and can be read as a peculiar activity.
Try to add new plans to the overlap of plans. At that time, whether to emphasize or neutralize the difference in the degree of overlap and the difference in density. It is better to emphasize it to connect memories and attachments even if the time cycle, but if neutralization is done by responding to the difference in the degree of overlap and the difference in density, the new plan is different from the past. I thought it might be more interesting to neutralize it, because it would be a completely different thing but a connection would be made.
建替えの歴史を重ねてみた。増改築を繰り返した今ある建築を一度全て壊して新たに建替える。その増改築の記録と新たなに建築する場合の標準的なプランを重ね合わせてみた。標準的なプランは建築士の設計製図試験の模範解答のようなものであり、それで一般解としての担保とした。
重ねてみることで、重なりの密度が濃い所と薄い所ができる。単に壁量の違いにも見えるが、それが人々のアクティビティの痕跡にも見える。
アクティビティの痕跡だとしたら、アクティビティを入れ替えて重なりの密度の違いに全く違った意味を持たせることができるのではないかと思い、それは新たなプランに記憶の継承という影響を与えると考えた。
"Accumulating memories"
I tried to repeat the history of rebuilding. All the existing buildings that have been repeatedly expanded and renovated will be destroyed and rebuilt. I tried to superimpose the record of the extension and renovation and the standard plan for new construction. The standard plan was like a model answer for an architect's blueprint test, so it was collateralized as a general solution.
By stacking them, you can create a place where the overlap density is high and a place where the overlap density is low. It looks like a difference in the amount of walls, but it also looks like a trace of people's activities.
If it is a trace of activity, I thought that it would be possible to replace the activities and give a completely different meaning to the difference in the density of overlap, and I thought that it would affect the new plan by inheriting memory.
全てを単なる模様だとする見方はモダニズムが捨てたものを拾うことになるから面白いと思った。削ぎ落とした末に辿り着いたモダニズムはまた削ぎ落としたものを拾いはじめ、それは歴史が証明しているが、また拾う時は同じ扱い方をせずに意味付けを変える。
模様も元々は装飾だから削ぎ落としたのだが、拾う時は装飾ではなく何かを識別するための記号とみなすことにした。記号であれば意味付けを容易に操作して創作できる。
究極まで削ぎ落としたモダニズムは一緒に創作できる余地まで削ぎ落としてしまい、全てが一様でつまらないモノになってしまった。そこから脱却するために一度削ぎ落としたものを拾う必要があった。
"Pick up what you scraped off"
The view that everything is just a pattern is interesting because it picks up what modernism has thrown away. Modernism, which arrived at the end of the scraping, began to pick up the scraped one again, which history proves, but when it is picked up again, it changes its meaning without the same treatment.
The pattern was originally a decoration, so I scraped it off, but when I picked it up, I decided to consider it as a symbol for identifying something rather than a decoration. If it is a symbol, you can easily manipulate the meaning and create it.
The modernism that was scraped down to the ultimate was scraped off to the point where it could be created together, and everything became uniform and boring. In order to get out of there, I had to pick up what I had scraped off.
時間がサイクルし、スクラップアンドビルドが繰り返される。そのサイクルから逃れることもできるが、そもそも人がサイクルする時間に身を投じているので、サイクルすることで生まれるモノに価値を見出そうとした。
価値を生むモノは何かと考えてみると、サイクルの終わりと始まりをつなぐものではないかと思った。サイクルの終わりと始まりで断絶を起こすことが多く、そこが問題になるので、つなぐものがあればそれ自体に価値があるし、さらに言えば、つながれたサイクルに新しい価値が生まれる。
サイクルを波とすれば、つながれたサイクルは波長が長くなる訳ではなく、始まりから終わりまでの振動数が増えることになり、それだけ影響を与える機会が増えることになる。
"More opportunities"
Time cycles and scrap and build is repeated. It is possible to escape from that cycle, but since people are devoting themselves to the cycle time in the first place, I tried to find value in the things created by cycling.
When I thought about what creates value, I thought it might connect the end and the beginning of the cycle. Often there is a break at the end and beginning of the cycle, which is a problem, so if there is something to connect, it is worth it, and for that matter, new value is created in the connected cycle.
If the cycle is a wave, the connected cycle does not have a longer wavelength, but the frequency from the beginning to the end increases, and the chances of influencing it increase accordingly.
なかなか進まない時は何かに引っ掛かりがある時だと思い、うまく説明ができない得体の知れない引っ掛かりを炙り出そうとあれこれ考えてみる。大概は同じパターンの繰り返しで、同じようなことが原因になるのだが、進まない事がきっかけで全く違った角度から気づくこともあり、新たな展開が生まれることもある。
それを期待する訳では無いが、途中で手を止めてみるのもひとつの方法だと思う。特に今までの経験値だけではどうにもならないようなことは部分に焦点を当て過ぎている場合があるので、途中で手を止めて全体を再度見回すようにしてみる、自戒を込めて。
"Try to stop your hand"
When it's hard to make progress, I think it's time to get caught in something, and I think about trying to get rid of mysterious catches that I can't explain well. Most of the time, the same pattern is repeated, and the same thing is the cause, but sometimes you notice from a completely different angle because of the fact that you do not proceed, and new developments may be born.
I don't expect that, but I think one way is to stop halfway through. In particular, things that cannot be helped by the experience points so far may be over-focused on the part, so stop in the middle and try to look around the whole again, with your own caution.
全てを模様として眺め、そこからできるだけ削ぎ落としていくと四角形や三角形、円といった幾何学図形に還元できる。幾何学図形はもうこれ以上省くことができないくらい簡素化されているので、初源的な魅力はあるが、何かを付け加えたくなる。
本来であれば、還元した先にあるのが幾何学図形だから、還元の途中で止めれば過不足ない幾何学図形が現れるはずである。ところが、途中で止めることができず、揺れ戻りのように何か付け加えるようになることは歴史が証明している。
ならば、はじめから還元の途中で止めることを念頭に置いたプロセスのルールをデザインし、それ自体に再現性があれば一般解となり得るモノになるだろう。
"Design of rules to stop in the middle"
If you look at everything as a pattern and scrape it off as much as possible, you can reduce it to geometric figures such as rectangles, triangles, and circles. Geometric shapes are so simple that they can't be omitted anymore, so they have a primitive appeal, but I want to add something.
Originally, the geometric figure is at the destination of the reduction, so if you stop in the middle of the reduction, a geometric figure that is just right should appear. However, history proves that it cannot be stopped in the middle and something is added like a swing back.
If so, it will be a general solution if the rules of the process are designed with the intention of stopping in the middle of the reduction from the beginning and if it is reproducible in itself.
単なる模様だと思い見てみる時、ぼんやりと解像度を落としてみたら、密度の違いのみが浮かび上がった。さらに再度解像度を上げてみると、今度は密度の違いが地と図の関係にも見えてきて、そこに記号、そして新たな意味づけが浮かび上がる。
新たな意味づけは元のモノとのつながりが保持されたものだから、意味が何であれ他にはない唯一無二のモノになり、それが次への足掛かりとなる。
"The difference in density is a stepping stone"
When I thought it was just a pattern, I vaguely lowered the resolution, and only the difference in density emerged. When the resolution is increased again, the difference in density can be seen in the relationship between the ground and the figure, and symbols and new meanings emerge there.
Since the new meaning is that the connection with the original thing is maintained, it becomes a unique thing that has no other meaning, and it becomes a stepping stone to the next.
単なる模様だと見れば、全てのモノが一様になり、模様に意味付けしているだけに過ぎないと理解できる。
単なる模様だと見れば、相互にできるつながりは単に模様の柄だけのつながりであり、それ以上のコトは無い。
単なる模様だと見れば、元々のモノが持っている性質や性能や機能など、模様以外のことは全て消失する。
模様として捉え直せば、拘束した枠組みから自由になれ、展開できる範囲が広がり、汎用性が増すことになる。
"Simply pattern"
If you look at it as a mere pattern, you can understand that all things are uniform and just give meaning to the pattern.
If you look at it as a mere pattern, the connections that can be made to each other are just the patterns of the patterns, and there is nothing more than that.
If you look at it as a mere pattern, everything other than the pattern, such as the properties, performance, and functions of the original thing, disappears.
If you reconsider it as a pattern, you will be free from the restrained framework, the range that can be expanded will be expanded, and the versatility will increase.
模様は記号に変換でき、記号は意味を持ち、意味は一人歩きする。一人歩きした意味は元の模様とはつながらなくなる。つながらなくなった意味は模様に別の記号を与える。そして記号はまた意味を持ち、また一人歩きする。そしてと、段々と模様に意味が重層的になる。
模様であれば、そこら中に存在する。模様が模様で無くなる時が意味を見出した時とも言えるかもしれない。まず模様だと意識するところからはじめてみる。
"From pattern to meaning"
The pattern can be converted into a sign, the sign has meaning, and the meaning walks alone. The meaning of walking alone does not connect with the original pattern. The meaning that is not connected gives another symbol to the pattern. And the sign also has meaning and walks alone again. And then, the meaning of the pattern gradually becomes multi-layered.
If it is a pattern, it is everywhere. It may be said that the time when the pattern disappears from the pattern is the time when the meaning is found. Let's start from the point of being aware that it is a pattern.
汎用性を引き継ぐと考えた場合、建築において何が汎用性になり、何を次に引き継ぐか。
全く何も無くしてしまい、新たにつくることを想定する。今後の建築の流れとしてはリノベーションを範疇に入れることが現実的かもしれないが、今までのスクラップアンドビルドの中で解決をしておかなくてはいけないことを扱う方が今後の建築の流れに役立ち、また本質を突くものだと考えた。
スクラップアンドビルドでは前後の時間の流れに断絶が起こる。前後のつながりをつくる必要が無い場合もあるが、前後のつながりをつくる必要があるにも関わらず、つながりをつくらない場合も多い。デザイン手法が無いことが原因であり、つながりをつくることに一般的な価値を見出せないことも原因である。
スクラップアンドビルドでの前後の時間の流れにつながりをつくる試みは建築における主題になり得るものだと考えている。
"Scrap and Build Connection"
If you think that you will take over the versatility, what will be the versatility in architecture and what will you take over next?
It is assumed that nothing will be lost and a new one will be created. It may be realistic to include renovation in the category of future architectural flow, but it is better to deal with what must be solved in the scrap and build so far in the future architectural flow. I thought it was useful and piercing the essence.
In scrap and build, there is a break in the flow of time before and after. In some cases, it is not necessary to make a front-to-back connection, but in many cases, it is not necessary to make a front-to-back connection. The cause is the lack of design methods, and the lack of general value in making connections.
We believe that attempts to connect the flow of time before and after scrap and build can be a subject in architecture.
経過していく時間の内容は人によって違うかもしれないが、経過していく時間がサイクルすることは同じではないかと考えた。時間のサイクルとは、はじまりがあり、終わりがあり、途中ではピークを迎える時があるということであり、時の経過と共に変化することであり、それは全ての人に訪れる。
時間がサイクルするということに建築の有り様を重ね合わせようと考えた。建築も時の経過、時間のサイクルから逃れることはできない。そこには記憶と愛着が詰まっている。もしかしたら時間のサイクルを通して見る建築の有り様は記憶と愛着そのものかもしれない。
さらに、全ての人に訪れる時間のサイクルを通して見る建築の有り様には個人の記憶や愛着を超えた汎用性が内在しているかもしれない。その汎用性を抽出し次に引き継ぐ。そうすれば、建築が新陳代謝を繰り返してもつなげることができる、記憶も愛着も。
"Take over versatility"
The content of the elapsed time may differ from person to person, but I thought that the cycle of the elapsed time would be the same. A cycle of time means that there is a beginning, an end, and a peak in the middle, which changes over time, which is visited by everyone.
I thought about superimposing the state of architecture on the cycle of time. Architecture cannot escape from the passage of time and the cycle of time. It is full of memories and attachments. Perhaps the state of architecture seen through the cycle of time may be memory and attachment itself.
Furthermore, the state of architecture seen through the cycle of time that all people visit may have versatility that goes beyond personal memory and attachment. Extract its versatility and take over next. That way, architecture can be repeatedly metabolized and connected, both in memory and attachment.
記憶をつなぐことはできるのだろうか。記憶を愛着と言い換えてもよい。愛着をつなぐことはできるのだろうか。個人の記憶や愛着の中に汎用的な要素を見つけ出すことができれば、それを手掛かりにデザインして一般解として受け渡し、つなぐことができるかもしれない。
それでは、個人の記憶や愛着のどこに着目し、汎用的な要素を抽出すればいいのか、と考えてみる。記憶は時間の経過が記録されたものである。ならば時間の経過の中で汎用的な要素につながるものを見つけ出そうとしてみる。ただ、単に時間の経過だけでは人によって違うので汎用的な要素を見つけ出すのは難しいかもしれない。しかし、時間はサイクルするということ自体は誰でも同じなので汎用性があるはずである。
次は時間のサイクルから汎用的な要素を見つけ出してみようと思う。
"To connect memories"
Is it possible to connect memories? Memory may be paraphrased as attachment. Is it possible to connect attachments? If we can find a general-purpose element in personal memory and attachment, we may be able to design it as a clue, pass it as a general solution, and connect it.
Then, let's think about where to focus on personal memory and attachment and extract general-purpose elements. Memory is a record of the passage of time. Then, over time, try to find something that leads to a general-purpose element. However, it may be difficult to find a general-purpose element because it varies from person to person simply by the passage of time. However, the fact that time cycles is the same for everyone, so it should be versatile.
Next, I will try to find a general-purpose element from the cycle of time.
ラップに包んだモノは、ラップが透明でも、直に見るモノとは違って見える。そこには透明なラップが見えているのであり、中身のモノが見えている訳ではなく、中身のモノがラップの模様のようになっている。
どこに焦点を当てるかで違いがあり、ラップに焦点を当てれば見えているのは透明なラップであり、中身のモノに焦点を当てれば透明なラップを透して中身のモノが見えていることになる。
別の見方をすれば、2つの焦点による違いを同時に成り立たせることができ、状況により焦点をいつでも切り替えることができるモノになっているとも言える。透明性を孕んだモノの面白さはこの焦点の切り替えができることである。
"The fun of things with transparency"
Things wrapped in plastic wrap look different from what you see directly, even if the wrap is transparent. You can see the transparent wrap there, not the things inside, but the things inside are like the pattern of the wrap.
There is a difference depending on where you focus, if you focus on the wrap you can see the transparent wrap, if you focus on the things inside you can see the things inside through the transparent wrap become.
From another point of view, it can be said that the difference between the two focal points can be established at the same time, and the focal point can be switched at any time depending on the situation. The fun of things with transparency is that this focus can be switched.
覆われていたモノを透明にすれば隠れていたモノが姿を露わす。ただし、姿を露わしたモノは透明とは言え何かに覆われているので直に見るのとは違うモノになる。そこに新たな価値を見出せないかと考えている。
初期のiMacのようなスケルトンは、複雑になりブラックボックス化してしまったものを露わにすることに価値を見出した。
そうではなくて、姿を露わしたがそのモノ自体ではなく、そこにまだ覆われているモノがあり、覆われているモノを透して見えていることに価値が生まれないかと考えている。
"Value to reveal"
If you make the covered object transparent, the hidden object will be revealed. However, although the exposed object is transparent, it is covered with something, so it is different from what you see directly. I am wondering if I can find new value there.
Early iMac-like skeletons found value in revealing what had become complex and black-boxed.
Instead, I'm wondering if there is something that is still covered, not the thing itself, that has been revealed, and that it is worth seeing through the covered thing. ..
精度を高めることでつながりをつくろうと考えている。それまで曖昧だったものの精度が高めれば、自然とつながりが生まれるだろう。
つながりをつくるために形式を設定する。その形式の精度を高めようという試みである。形式の精度を高めていく場合、制度やルールなどを厳格に細かく決めるのがひとつの手段だが、そうではなくて、曖昧なことを曖昧だとハッキリさせることも精度を高めることになり、つながりをつくることができる。
つまり、曖昧のままでよいとする形式であり、そのために曖昧だから生まれる不足しているような部分を補うようにつながりが生まれる。
"Ambiguous form"
I'm thinking of making a connection by improving the accuracy. If the accuracy of what was vague until then is improved, a connection will be created with nature.
Set the format to make a connection. It is an attempt to improve the accuracy of the format. If you want to improve the accuracy of the format, one way is to make strict and detailed decisions on the system and rules, but instead, making it clear that ambiguous things are ambiguous will also improve the accuracy and connect. Can be made.
In other words, it is a form that can remain ambiguous, and for that reason, a connection is created to make up for the lacking part that is created because of the ambiguity.
「集まってしまった」ような予測不可能な雰囲気を醸し出す空間をつくるためには、その根底になる形式が必要なのかもしれないと思った。
ただ何となく自然発生的に人が集まるような場所や空間をたまに見ることがあるが、その場合結果的にそうなったようで、元々何も形式がない。例えば、カオスはカオスという形式が存在していると考えているので、「集まってしまった」ような予測不可能な雰囲気を醸し出す空間にも形式が必要である。
ただその場合の形式は建築的な形式というよりは、人と人とがつながるような形式、例えば言葉だけの形式でもいいかもしれない。
"Connected format"
In order to create a space that creates an unpredictable atmosphere like "getting together", I thought that the underlying format might be necessary.
However, I sometimes see places and spaces where people gather spontaneously, but in that case, it seems that it has happened, and there is no form in the first place. For example, chaos thinks that there is a form of chaos, so it is necessary to have a form in a space that creates an unpredictable atmosphere such as "gathering".
However, the form in that case may not be an architectural form, but a form that connects people, for example, a form with only words.
集まらなくてもいいのに集まってしまった状態が理想的ではないかと考えている。そこには自発的な意志だけでなく、何かの影響が働いていてアクティビティを自分だけでコントロールできていない様がうかがえる。
「集まる」ではなくて「集まってしまった」ということを形にしたいと考えている。「集まる」を形にすることは予測できるので建築計画学が得意とするところだが、「集まってしまった」を形にすることは予測不可能な要素が加わるので、建築計画学プラスアルファの要素が必要になってくる。
そのプラスアルファを考えるところが面白く、プラスアルファの部分はデザインの範疇になる。
"Adding unpredictable elements"
I think that it is ideal to have gathered even though it is not necessary to gather. It seems that not only the voluntary will but also the influence of something is working and the activity cannot be controlled by oneself.
I want to make it a form of "getting together" instead of "getting together". Architectural planning is good at forming "gathering" because it can be predicted, but it adds an unpredictable element to forming "gathering", so it is an element of architectural planning plus alpha. Will be needed.
It is interesting to think about the plus alpha, and the plus alpha part is in the category of design.
移動するということはその土地の場所性から切り離されることであり、場所が持つ固有のものが意味のないものになり、移動する側からすれば固有の場所性は今どこにいるのかという確認程度のものになる。
逆に固有の場所性をいかすならば移動しない方がよく、移動できない建築だからできることでもある。
移動しながら固有の場所性をいかすことはできないものかと考えている、それをモノとして。きっとそのモノは日常の延長ではなく、日常の中に現れる固有の場所性とは相対して混じり合わないモノであり、だから固有の場所性を結果的にいかすことになるのだろうと考えてみた。
"How to make the most of the location of movement"
Moving means being separated from the location of the land, and the uniqueness of the place becomes meaningless, and from the perspective of the moving side, it is only a confirmation of where the unique location is now. Become a thing.
On the contrary, it is better not to move if you take advantage of the unique location, and it is also possible because the architecture cannot move.
I'm wondering if it's possible to take advantage of the unique location while moving, as a thing. I'm sure that thing is not an extension of everyday life, but something that does not mix with the unique placeness that appears in everyday life, so I thought that it would eventually make use of the unique placeness. ..
人との接触を制限されたことが新型コロナによる一番の影響だが、それでわかったことは接触を制限されてもある程度の社会生活は送れるということと、それでも人は接触を求めてしまうということである。
人が接触を求めてしまうことを表現すると「集まる」というよりは「集まった」というすでに起こってしまった、それも無計画なニュアンスを醸し出す状態が似合うような気がした。
新型コロナが引き起こした無計画に起こってしまった状態に翻弄された約2年間だったが、「集まった」状態は人の心理や行動のコアな部分に新たな領域をつくったような気がする。
"collected"
The biggest impact of the new Corona is that contact with people is restricted, but what I found out is that even if contact is restricted, people can live a certain degree of social life, and people still seek contact. Is.
When I express that people want contact, I feel that the state of "gathering" rather than "gathering" has already happened, and that it also suits the state of creating unplanned nuances.
It's been about two years since I was at the mercy of the unplanned situation caused by the new Corona, but I feel that the "gathered" state has created a new area in the core of human psychology and behavior. do.
ずーっと考えているのは、どこまで人は知覚できるのだろうか、ということ。当たり前の言葉で到達できる感じはすでに使い古されている。それでも尚当たり前の言葉を使い続けるのは、使う本人が知覚しようとする範囲を狭めている。言葉にできないかもしれないけれど、少なくとも知覚はできることをぼんやりとでもいいのでイメージできないと、形にすることと言葉にすることは同じだから、新しいものはつくれない。どこまで知覚するのか、言葉は使い古されていないか、新年に想うこと。
"How far do you perceive?"
I've always been thinking about how far people can perceive. The feeling that can be reached with ordinary words has already been used up. Even so, continuing to use the usual words narrows the range that the person who uses them tries to perceive. It may not be possible to put it into words, but at least if you can't imagine what you can perceive, you can't make a new one because it's the same as putting it into words. Think about how much you perceive and whether the words are used up in the New Year.
何度も行ったことがある場所でも乗り物が変われば、手段が変われば、全く違ったことに気づくし、全く違う行動をする。
年末に両親の田舎へコロナ後はじめて先祖のお墓参りに行った。何度ももう数え切れない程通った場所なのに、今回ははじめてキャンピングカーで行ってみた。
車中泊する場所はどこにするか、食事はどうするか、なるべくだったら車内で食べてのんびり過ごしたいから、どこで調達するか、温泉にも入りたいし、できれば景色を見ながら、などといろいろと思いを巡らし、現地で過ごしてみると、こんな場所あったのか知らなかったというはじめての所ばかりを訪れる結果になり、キャンピングカーだから車内からいい景色を見ながらコーヒーを飲みたいとなり、海を見下ろせる無料駐車場を見つけたりなど、はじめての行動ばかりで、行動が変われば当然行き先も変わる面白さを、子供の頃から通って知る場所なのに新しい発見をたくさんした。
改めて見方を変えただけでいつものものが違って見える面白さを体験できてよかったし、見方変えるきっかけをつくるにはどうすればよいのかを考える機会になった。
"To change your perspective"
Even in places where I have been to many times, if the vehicle changes, if the means change, I notice that it is completely different and act completely differently.
At the end of the year, he went to his parents' countryside for the first time after Corona to visit his ancestor's grave. It's a place I've visited countless times, but this time I went with a camper for the first time.
Where to stay in the car, what to eat, if possible, I want to eat and relax in the car, so where to procure, I want to take a hot spring, if possible, while watching the scenery, etc. When I went around and spent time there, I ended up visiting only the first place I didn't know if there was such a place, and because it was a camper, I wanted to drink coffee while looking at the nice view from inside the car, and a free parking lot overlooking the sea I made a lot of new discoveries even though it was a place I've been to since I was a kid, and I've learned that it's just the first time I've been doing something, and if the behavior changes, the destination will naturally change.
I'm glad that I was able to experience the fun of making things look different just by changing my perspective, and it was an opportunity to think about how to create an opportunity to change my perspective.
キャンピングカーは移動できるが狭い、だから「可変」が求められる。逆に建築は移動できないがキャンピングカー程は狭くなく広いので「可変」は必ずしも必要では無い。
建築では「可変」を標榜した時代もあったが、結局建築のスケールでは可変は容易ではなく、可変性を担保しながらそのまま何もしない状況になる。
建築における「可変」を捉え直してみようと思う。物理的な可変以外にも「可変」という概念や意識は持てるのではないかと考えている。
"Variable recapture"
Campers can move but are narrow, so "variable" is required. On the contrary, the building cannot be moved, but it is not as narrow and wide as a camper, so "variable" is not always necessary.
There was a time when architecture advocated "variable", but in the end it was not easy to change on the scale of architecture, and it became a situation where nothing was done as it was while ensuring variability.
I would like to reconsider the "variable" in architecture. I think that we can have the concept and consciousness of "variable" other than physical variable.
キャンピングカーはある意味、建築以上に建築らしかった。狭い故に、余計なものは削ぎ落として、使いやすさと機能的に特化している。しかも、断熱性と遮音性もよく、20年位前の住宅より性能がよい。いまの建築が大衆から求められている全てのものが過不足なく詰められている。
これを同じベクトルの中で越えようとしたら、もっとお金を掛けて豪華にするか、あえて不便な所をつくるか、ミスマッチなもの、例えば、フェラーリをキャンピングカーに改造する、ようなことをするしかないと思う。
いずれにしてもそれでよいのかと思う、そこには創造力が必要ないから。いま思うのは「移動」が加われば、新たな価値を創造できるだろうということ。たぶんベクトルはそれで合っている。
"Movement creates new value"
The camper was, in a sense, more like architecture than architecture. Due to its small size, it is specialized in ease of use and functionality by scraping off unnecessary items. Moreover, it has good heat insulation and sound insulation, and has better performance than a house about 20 years ago. Everything that the public demands for today's architecture is packed in just the right amount.
If you try to overcome this in the same vector, you have to spend more money to make it luxurious, dare to create an inconvenience, or do something mismatched, such as converting Ferrari into a camper. I think.
I wonder if that's okay anyway, because it doesn't require creativity. What I think now is that if "movement" is added, new value can be created. Maybe the vector fits that.
モノもコトも移動することで変化する。だから、移動できない建築はモノやコトに関してその分影響と制限を受けるかもしれないが、移動できないということを建築の特色にすればよいといつも考えている。
コロナにより移動を制限されモノやコトに影響が出だが、移動できない建築も大いに影響を受けた。そうすると、アフターコロナでは移動の可否は関係無いことになるが、移動を別の側面から紐解けばアフターコロナとの関連性が生まれると考えた。
そのきっかけがキャンピングカーだが、移動できるキャンピングカーの中にいると、移動できない建築との差異が明確になり、移動できないこととアフターコロナを結びつける要素として「可変」というキーワードを掴んだ。
"The goodness of not being able to move"
Things and things change as they move. Therefore, architecture that cannot be moved may be affected and restricted by that amount in terms of things and things, but I always think that it is good to make the feature of architecture that it cannot be moved.
The movement was restricted by the corona, which affected things and things, but the architecture that could not be moved was also greatly affected. Then, it doesn't matter whether or not the movement is possible in the after corona, but I thought that if the movement was unraveled from another aspect, the relationship with the after corona would be created.
The reason for this was a camper, but when I was in a movable camper, the difference from a non-movable building became clear, and I grasped the keyword "variable" as an element that connects immovability and after-corona.
移動する建築はちょっと範疇から外れていた。そもそも建築は動かないから、動く住空間は建築では無いという認識だった。
コロナの影響でキャンピングカーがバブルを迎えているらしい。移動をしていれば走行充電するので電気の心配はいらない。ガソリンを補給できれば寒さもFFヒーターで凌げる。駐車する場はトイレさえあれば良く、食料は最悪コンビニでもいいとすればどこでも手に入る。
環境は必要最低限のものはきちんとあるのでそれで十分だとすれば、あとは自分しだいで様々な体験をクリエイティブできる。
余計なモノコトに気を取られている日常から抜け出して、自分がしたいコト、自分がしなければいけないモノにきちんと向き合うにはキャンピングカーはいいかもしれないし、本来建築はそのような状況をつくり出すモノである。
移動するかしないかということに拘らなければ、キャンピングカーは建築である。
"Camper is architecture"
Moving architecture was a bit out of the category. In the first place, architecture does not move, so it was recognized that moving living spaces are not architecture.
It seems that the camper is in a bubble due to the influence of corona. If you are on the move, you will be charged while driving, so you don't have to worry about electricity. If you can replenish gasoline, you can overcome the cold with an FF heater. All you need is a toilet to park, and you can get food anywhere if you can go to a convenience store at worst.
The environment is the minimum necessary, so if that's enough, then you can create various experiences on your own.
A camper may be a good way to get out of the daily life of being distracted by extra things, and to properly deal with what you want to do and what you have to do, and architecture is originally a thing that creates such a situation. be.
A camper is an architecture, regardless of whether it moves or not.
モノかコトに分けて考えるよりも、モノとコトを混ぜて新たにモノかコトを構築する方が面白いと考えた。
モノやコトがそれ自体で成り立つことがモノコトの話の根幹だが、モノもコトもそれ自体で成り立たないような場合の方が多い。モノにコトが付着していたり、コトにモノが付着していたりする。
だから、モノとコトを混ぜ合わせ、それまでとは違うモノやコトを新たに構築し直すことの方が自然な成り立ちで面白い。
"Mixing things and things"
I thought it would be more interesting to build a new thing or thing by mixing things and things, rather than thinking separately about things or things.
It is the basis of the story of monokoto that things and things are established by themselves, but there are many cases where neither things nor things are established by themselves. Things are stuck to things, or things are stuck to things.
Therefore, it is more natural and interesting to mix things and things and reconstruct new things and things that are different from the previous ones.
民藝活動はナショナルではなくインターナショナルだと、『民藝の100年』展でわかったことは民藝活動はメディアによってつくられた、メディアを活用して仕掛けた活動であり、それは建築におけるモダニズム活動と同じでおり、モダニズムが世界に広がったのはインターナショナルな要素を含んでいたからであり、民藝もインターナショナルな要素を含んでいるからメディアに載ったのであり、民藝がナショナル的なリジョーナルなものと考えものづくりをしている人たちは、誤解を恐れずに言えば、単に粗悪な精度の低いものをつくっていることに気がつかず、民藝が持つ真の良さを表現していない。
民藝は朝鮮に憧れる。それがインターナショナルな民藝を表しているのであり、民藝は地方の、リジョーナルなものではない。だから、あらゆる人々の心に染み渡り、世代を超えて惹かれ合うのである。
鳥取砂丘が民藝の聖地だとはじめて知った。砂丘にはいつでも惹かれ、民藝に触れた後にはいつも砂丘を訪れたくなる理由がわかったような気がする。砂の粒には拠り所がなくいつでも場所を変えることができるインターナショナル的な要素を持つものだから、砂の集合体である砂丘は民藝のメタファーなのかもしれない。
見方を変えるきっかけは民藝がメディアに載せるための工夫を知ったことであり、そのつながりとしてデザインとの融合が柳宗理によって行われたことであり、民藝そのものがインターナショナルなものだと解釈するきっかけにもなった。
"Folk art is international"
It was found in the "100 Years of Folklore" exhibition that folk art activities are international rather than national, and that folk art activities were created by the media and set up using the media, which is modernist activity in architecture. It is the same as, and modernism spread to the world because it contained an international element, and because folk art also contained an international element, it appeared in the media, and folk art is a national regional thing. Those who think and make things, without fear of misunderstanding, simply do not notice that they are making inferior and low-precision products, and do not express the true goodness of folk art.
Folk art longs for Korea. It represents an international folk art, and the folk art is not a local, regional one. That is why they permeate the hearts of all people and are attracted to each other across generations.
I learned for the first time that the Tottori Sand Dunes are a sacred place for folk art. I'm always attracted to the dunes, and I feel like I understand why I always want to visit the dunes after touching the folk art. The dunes, which are aggregates of sand, may be a metaphor for folk art, because the grains of sand have an international element that can be relocated at any time without any reliance.
The reason for changing the view was that Minge knew how to put it on the media, and that the fusion with design was done by Sori Yanagi as a connection, and it was an opportunity to interpret that Minge itself is international. It also became.
決定プロセスを経た場合、結果は重要ではなくなる。
決定プロセスとは決定に至るまでの道筋をはっきりとさせるためのものであり、それはとても細かく、その道筋通り順序よく行えば、ある一定のレベル以上で結果を出すことができる。
しかし、結果が出る時点で結果はたまたまそれになっただけに過ぎず、むしろ決定プロセスを紐解く方が重要になる。
"Unraveling the process"
After going through the decision process, the results are not important.
The decision-making process is about clarifying the path to a decision, which is very detailed and, if done in order, can produce results above a certain level.
However, when the results come out, the results just happen to happen, and it is more important to unravel the decision-making process.
プロセスに目を向けることが多くなった。最終的な結果を得たいのだが、そのためには結果を生み出すプロセスをつくることが必要であり、それを習慣にできればいいが、それが難しくなかなかできないのだ。
モノをつくる時のプロセスは積み上げになる。コトをつくる時のプロセスは変換になる。積み上げとは段階を踏むことでの連続性であり、変換とは言い換えなどのようにプロセスに変化と断絶をつくることであり、モノとコトのプロセスは正反対の性質になる。
プロセスの性質はそのまま結果の性質になる。だから、プロセスをつくることは結果をつくることにつながり、結果を直接扱う訳ではないから、試行錯誤がしやすくシミレーション回数が増え、結果的に最終的な精度が上がる。
"Process of things and things"
I've become more focused on the process. I want to get the final result, but to do that, I need to create a process that produces the result, and I wish I could make it a habit, but that is difficult and difficult.
The process of making things is cumulative. The process of making things is conversion. Stacking is the continuity of steps, and conversion is the creation of changes and breaks in the process, such as paraphrasing, and the process of things and things has the opposite nature.
The nature of the process becomes the nature of the result. Therefore, creating a process leads to creating a result, and since the result is not handled directly, trial and error is easy and the number of simulations increases, and as a result, the final accuracy increases.
コトとモノが同時発生的に現れる瞬間があるのだろうか。コトが先か、モノが先か、どちらかが先のように思えるし、それが自然なような気がする。
もしそうならば、コトとモノが同時発生的に現れる瞬間は不自然なことであるから、不自然なつながりや不自然な状況をわざとつくり出そうとするプロセスがコトとモノを同時発生させる装置になるかもしれない。
"Simultaneous occurrence of things and things"
Is there a moment when things and things appear at the same time? It seems that either things come first or things come first, and that seems natural.
If so, the moment when things and things appear at the same time is unnatural, so the process of intentionally creating unnatural connections and unnatural situations is a device that causes things and things to occur at the same time. May become.
形とコトには関係性があるだろうか。モノと形は形があってモノとなるから、モノ=形といえるかもしれないが、コトにはそもそも形が無いので、コトを形にする時は何を手掛かりにするのだろうか。
形になる手掛かりは幾何学的な要素を持っているか、幾何学的な要素につながるかであり、コトの中にそのような要素を見出すことができればいいのだが、無い場合は幾何学的な要素と無理矢理にでも結びつける必要がある。
コトはコトのまま形を与えなければ、それはそれで建築以外ならば成り立つが、建築にするにはコトを形にする必要がある。だから、形とコトの関係性を考えることは建築行為そのものといえる。
"Relationship between shape and things"
Is there a relationship between shape and things? Since things and shapes have shapes and become things, it may be said that things = shapes, but since things have no shape in the first place, what is the clue when making things into shapes?
The clue to the shape is whether it has a geometric element or it leads to a geometric element, and it would be nice if such an element could be found in the thing, but if not, it is geometric. It is necessary to forcibly connect the elements.
If you don't give a shape as it is, it will work except for architecture, but to make it architecture, you need to shape it. Therefore, it can be said that thinking about the relationship between shape and things is the act of building itself.
プロセスの中にはそのまま表に出した方が良いモノもある。隠蔽していた訳ではないが表に出す必要が無かったモノであり、結果的に隠蔽されていたモノである。
表に出すには新たな価値を纏う必要がある。プロセスの中に隠蔽されていたのは表に出す価値が無かったからであり、モノとしては表に出せるが表にする必要性がなかったモノである。
新たな価値はコトがつくり出してくれる。コトのひとつには機能がある。機能ならば建築と相性が良いのでいくらでもコトを用いてモノを表に出してくることができる。
"What is called function"
Some processes should be exposed as they are. It wasn't hidden, but it didn't need to be exposed, and as a result, it was hidden.
It is necessary to wear new value to bring it to the table. It was hidden in the process because it wasn't worth exposing, and it was something that could be exposed but didn't need to be exposed.
Things create new value. One of the things is the function. If it is a function, it goes well with architecture, so you can use as many things as you like to bring things out.
見えていなかったものが露わになり隠蔽が解かれた時、本来見せるものではないモノを見せることになる。それはプロセスであり、隠蔽されていた理由である。
隠蔽を解くことはプロセスを見せることにつながる。だから、今までの見せ方では通用しない。プロセスを結果にする訳だから、本来結果ではないモノを結果に仕立て上げる訳だから、当然見せ方にも工夫が必要になり、そこにはコトを重ね合わせる必要が出てくる。
"What to reveal"
When something that wasn't visible is revealed and the concealment is lifted, you'll be showing something that you shouldn't be able to see. It's a process and why it was hidden.
Breaking the concealment leads to showing the process. Therefore, the conventional way of showing does not work. Since the process is the result, the thing that is not the result is made into the result, so naturally it is necessary to devise the way of showing, and it is necessary to overlap the things there.
今まで見えなかったモノが見えるようになるきっかけはコトによるだろう。コトはいつでもきっかけになる。
建築は最終的にはモノとして表現するからモノ主体になりがちだが、建築を使う人はコトにより動かされることが多いので、コトを積み重ねていく途中でモノが入り込み、最終的にはコトとモノが入り混じって区別がつかない状態で成立している建築が理想だと考えている。
コトとモノが入り混じって区別がつかない状態とは、例えば、隠蔽されていたモノが主体となって表現されているような状態である。そこにはコトが介在し隠蔽されていたモノが表に出てくる。この状態ではモノだけでは成り立たないし、コトだけでも成り立たない。モノとコトが両方合わさってひとつになることで成立する。だから、隠れているモノを探すことがデザインのひとつのプロセスになる。
"A mixture of things and things"
The reason why you can see things that you couldn't see before is probably due to things. Things are always a trigger.
Architecture tends to be mainly things because it is expressed as things in the end, but people who use architecture are often moved by things, so things get in while stacking things, and finally things and things. I think that the ideal architecture is one that is indistinguishable from each other.
A state in which things and things are mixed and indistinguishable is, for example, a state in which hidden things are mainly expressed. Things that were hidden by the intervention of things appear on the surface. In this state, things alone do not hold, and things alone do not hold. It is established when both things and things are combined into one. Therefore, finding hidden things is one of the design processes.
今まで見えなかったものが見えるようになるということはどういうことか、機能的に考えてみる。見えなかったものが見えるようになって機能的に何か変わるだろうか、変わるとしたらどのような場合か。
今まで見えなかったものとは隠蔽されていたものであり、その隠蔽が解かれる場合は、覆っていたものが不必要になったか、表現として見せるかであり、覆っていたものが必要になった場合は隠蔽されていたものに新たな機能が付加されたことになる。
その機能にはデザイン的な必要性、すなわち隠蔽されていたものに新たな価値を見出した場合も含む。隠蔽されていたものを見せるという仮定になって考えると新たな価値に気づくかもしれない。
"Uncovering"
Think functionally about what it means to be able to see what you couldn't see before. Will something that I couldn't see become visible and something functionally change, and if so, when?
What was not visible until now is something that was concealed, and when the concealment is broken, it is either unnecessary or expressed as an expression, and what was covered is necessary. In that case, a new function has been added to what was hidden.
Its function includes design needs, that is, finding new value in what was hidden. You may find new value when you think about it on the assumption that you will show what was hidden.
変化を許容するものづくりをしているだろうか。
変化を許容しないのが自律、変化を許容するのが他律、そういう分け方を建築ではする。自律と他律のどちらがいいのか、どちらに属するのか、どちらが可能性があるのか、どちらにでもなれるがそれよりも自律でもなく他律でもない状態をつくれないかと考えている。
変化することは時の流れに呼応すると考えており、時の流れに何事も逆らえない、建築も、時の流れを含んだものをクリエイティブすることが求められていると思う、現在の建築ではそこが不十分である。
今までの建築家が皆挑み、皆散っている、中銀カプセルタワーのように。建築という巨大で環境に与える影響が大きいものが時の流れに対応できるようになれば、世界が何か変わるように思えるのは私だけだろうか。
"Can we tolerate change?"
Are you making things that allow change?
In architecture, it is autonomy that does not tolerate change, and heteronomy that allows change. I am wondering whether autonomous or heteronomy is better, which one belongs to, which one is possible, and whether it is possible to create a state that is neither autonomous nor heteronomous.
I think that change responds to the passage of time, and I think that it is necessary to create something that includes the passage of time in architecture, which cannot resist the passage of time. Is inadequate.
Like the Nakagin Capsule Tower, where all the architects up until now have challenged and scattered. Am I the only one who seems to change something in the world if architecture, which is huge and has a great impact on the environment, can keep up with the passage of time?
狭い空間になればなる程、何かひとつのことに収束させないとどこにでもある汎用的な空間になってしまう。何に収束させるか、収束は他のものを切り捨てることにもなるから、圧倒的な強度を持って他のものを切り捨てたい。
バランスを必要とするならば、圧倒的な強度は邪魔になる。だから、圧倒的に無難なものと織り交ぜる。圧倒的な強度は圧倒的に無難なものと表裏一体だから相性がいいだろう。
"Overwhelming strength"
The narrower the space, the more general-purpose space you can find anywhere unless you converge on one thing. What to converge, convergence also cuts off other things, so I want to cut off other things with overwhelming strength.
If you need balance, overwhelming strength is a hindrance. Therefore, it interweaves with overwhelmingly safe things. The overwhelming strength is inextricably linked to the overwhelmingly safe one, so it will be a good match.
高架のための立ち退きで出現した延々と続く更地はいつか埋まってしまうが、晴れの日は遮るものがないのでその明るさに翻弄され暗闇に入ると何も見えなくなる。都市だから生まれた明るさは都市だからやがて無くなる。
このままで何もない方が、見慣れた風景にもなったので、良いのではないかと勝手に思ってしまうが、それは許されない。都市では何も無い状態は許されない。何も無い状態は都市では無い。
"Not a city"
The endless vacant lot that appeared due to the eviction for the overpass will be filled up someday, but since there is nothing to block on a sunny day, nothing can be seen when entering the darkness at the mercy of its brightness. The brightness that was born because it is a city will soon disappear because it is a city.
It would be nice to have nothing as it is, because it would be a familiar landscape, but that is not allowed. Nothing is allowed in the city. An empty state is not a city.
なかなか着地点が見えない時に予め予測しながら向かい、いい着地点を見つけたと思っても他の障害が現れたりして、なかなか着地できない。簡単に済ませればいいのだが、それでは足りないと思ってしまう。
こういう時は、着地を忘れ浮遊し続けて燃料切れで自然に着地するか、どこでもいいから強制着地するか、着地点自体を自分でつくってしまうか。着地点自体を自分でつくる方が予測もつきやすいし、いいかもしれない。
"Creating a landing point"
When I couldn't see the landing point, I headed for it while predicting it in advance, and even if I thought I found a good landing point, other obstacles appeared and I couldn't land easily. It should be easy, but I think that is not enough.
In such a case, do you forget to land and continue to float and land naturally due to lack of fuel, or do you force landing anywhere, or do you make the landing point yourself? It is easier to predict and it may be better to create the landing point itself.
形を決めるプロセスにおいて、形が配置される周辺の何もない空間は何か影響を与えることはあるだろうかと考えてみた。何も影響を与えないと考えることは簡単だが仮に何か影響を与えることがあるとしたら何があるだろうか。
周辺の何もない空間は形において金型の雄雌のような関係であるともいえる。ならば、周辺の何もない空間の形から考えるということもあり得るかもしれない。
"Relationship like a mold"
In the process of determining the shape, I wondered if the empty space around the shape could have any effect. It's easy to think that it has no effect, but what if it could have any effect?
It can be said that the empty space around the space is like a male and female mold. Then, it may be possible to think from the shape of the empty space around.
自由な形で配置していいとしたら、どのような形を置くだろうか。自由な形といっても建築の場合、案外と制約があると思ってしまうのは自ら可能性を潰しているような気がする。
形に妥当性があれば、どのような形でもつくることができる環境にいる訳だから、毎度同じような形にする必要が無く、毎度全く違うものを構想するので、形は何によって決まるのかという決定プロセスをデザインしている。
"Design of decision process"
If it were possible to arrange it in any shape, what kind of shape would it be? In the case of architecture, even if it is a free form, I feel that it is crushing the possibility of thinking that there are unexpected restrictions.
If the shape is valid, we are in an environment where we can make any shape, so we don't have to make the same shape every time, and we think of something completely different every time, so what determines the shape? Designing the decision process.
何かする空間で構成するのが建築だとしたら、何もしない空間は建築以外の空間になる。工作物は除くとして建築以外の空間を都市空間の中で探すと、やはり同じ敷地内での余白の空間というか建築以外の外部空間を指すことになるだろう。
いつも思うことだが、敷地内での建築以外の外部空間
をどのように扱うによって建築の見え方に差が出る。もしかしたら、何もしない空間として外部空間を捉え直してみると何か違った見え方が現れるかもしれない。
"A space where nothing is done outside"
If architecture is composed of a space that does something, a space that does nothing is a space other than architecture. If you look for a space other than architecture in the urban space, excluding the works, you will probably refer to the space in the margin on the same site or the external space other than architecture.
As I always think, the exterior space other than the architecture on the premises
There is a difference in the appearance of architecture depending on how you handle it. Perhaps, if you reconsider the external space as a space that does nothing, something different may appear.
隙間を空けるように何もしない空間をつくりたいと考えている。建築は基本的に何かをする空間の集合であり、何もしない空間はない。何もしない空間とは無駄な空間ではなく、何もしなくていい空間であり、何かをする空間を切断するように配置することにより、何かをする空間の複雑性を上げることになる。
何かをする空間だけだと全体が常に動的であり、人はそこまで動的であり続けることはできないので、適度に静的な何もしない空間を必要とする。
静的な何もしない空間は時間の流れとは関係なく存在し、時間の流れと呼応する何かする空間と対局になるが、日常の中で起きる時間感覚の歪みを矯正してくれる。
"A space that does nothing"
I want to create a space that does nothing so as to leave a gap. Architecture is basically a collection of spaces that do something, and there is no space that does nothing. A space that does nothing is not a wasteful space, but a space that does not need to do anything, and by arranging it so as to cut off the space that does something, the complexity of the space that does something increases.
The whole thing is always dynamic if it's just a space to do something, and people can't stay that dynamic, so we need a reasonably static space to do nothing.
A static space that does nothing exists regardless of the flow of time, and it plays against a space that does something in response to the flow of time, but it corrects the distortion of the sense of time that occurs in everyday life.
スケール感と何かを組み合わせたら、もっと違った見え方が生まれるかもしれないと探っている。
建築の大きさに対して敷地が大きく、その敷地の中に複数の建築を建てる場合、建築同士のスケール感の取り合いが自然に生まれる。ただ、その建築のスケール感は取り合いを優先して決めることがなかなかできない。様々な与条件を満たした上でのスケール感になる場合が多いから、何かスケール感以外のものと組み合わせて、スケール感を優先してコントロールし、見え方に影響を与えたい。
スケール感は感覚であり目で見ることができず意識しないとわからないという側面もあるから、組み合わせるものは意識せずとも見えるものがいいかもしれない。さらに全く逆のものや一見あり得ないようなものを組み合わせた方が何か新しい見え方が生まれるかもしれない。
"What to combine with a sense of scale"
I'm exploring that if I combine something with a sense of scale, a different look may be created.
The site is large compared to the size of the building, and when multiple buildings are built on the site, a sense of scale between the buildings is naturally created. However, it is difficult to prioritize the scale of the architecture. In many cases, the feeling of scale will be obtained after satisfying various given conditions, so I would like to combine it with something other than the feeling of scale to prioritize control of the feeling of scale and affect the appearance.
The sense of scale is a sensation, and there is also the aspect that it cannot be seen with the eyes and cannot be understood without consciousness, so it may be better to combine things that can be seen without being conscious. Furthermore, a new look may be created by combining the completely opposite or seemingly impossible.
重さとスケールに関係はあるだろうか。建築は重いが見た目を重厚や軽快に見せることで重さのイメージをコントロールできる。スケールに密度というものがあるならば、密度を濃くすれば重く、密度を薄くすれば軽く感じるかもしれない。
それでは、建築の見た目を重厚にしてスケールの密度を薄くしたらどうなるだろうか。あるいは、建築の見た目を軽快にしてスケールの密度を濃くしたらどうなるだろうか。
建築はそもそも重くて動かないが、重さとスケールの関係に注目して見た目の重量感をコントロールしスケール感を操れば、建築の見せ方にバリエーションを築くことができ、その見せ方によって建築の周りの空間に様々な影響を与えることができる。
"Relationship between weight and scale"
Is there a relationship between weight and scale? Although the architecture is heavy, the image of weight can be controlled by making it look heavy and light. If the scale has a density, it may feel heavier at higher densities and lighter at lower densities.
So what if the architecture looks heavy and the scale density is low? Or what if the architecture looks lighter and the scale is denser?
Architecture is heavy and does not move in the first place, but if you pay attention to the relationship between weight and scale and control the appearance of weight and manipulate the scale, you can create variations in the way the architecture looks, and depending on the way you look around the architecture. It can have various influences on the space of.
大小のスケールの組み合わせで建築をつくることにより、建築の周りの空間までスケールによって巻き込み、つながりをつくることができるのではないかと考えている。
建築として自律するだけでなく、周りをも巻き込んで建築空間の一部としたい。そのためには何かつながりが必要で、ただ物理的なつながりはなかなかつくれないからスケールで巻き込もうとした。
周りをスケールで巻き込もうとしたら少なくとも2つの建築が必要である。ちょっと磁場をイメージした。N極とS極があることで磁力線が発生するように、2つの建築が影響し合いその場だけのスケールが発生し、周りに影響を与える。その影響はきっとその場の雰囲気を変えるだけの力を持つだろう。
"Effect of scale"
I think that by creating an architecture with a combination of large and small scales, it is possible to involve the space around the architecture with the scale and create a connection.
I want to not only be autonomous as an architecture, but also to involve the surroundings and make it a part of the architectural space. To do that, I needed some kind of connection, but I couldn't get a physical connection, so I tried to get involved on a scale.
If you want to get around on a scale, you need at least two buildings. I imagined a magnetic field for a moment. Just as the presence of N and S poles produces magnetic lines of force, the two buildings affect each other, creating an in-situ scale that affects the surroundings. The influence will surely have the power to change the atmosphere of the place.
モジュールやパターンの反復には何故か一昔前の事のような感じがある。それは同じことの反復が大量生産や工場や伝統といったワードと結びつくと勝手に思い込んでいるからかもしれない。
現代でもモジュールやパターンの反復は至る所にある。しかし一昔前とは違い、反復されるの枠組みだけで、その中身には多様性があるのではないかと考えている。
一昔前は全てが反復され、反復されること自体に意味があり目的だった。それは情報伝達の速度が遅く鈍かったので反復の強度のみが唯一確かなものだったからで、現代のように一瞬で情報が広まる状況では反復に意味はなく、反復しているとその分他のものを伝えることができなくなる。
ただ、情報伝達の枠組みだけは使い回され反復される。その枠組みだけが唯一確かなものとして、中身はどうでもよく、好き勝手な多様性が乱舞し、それに一喜一憂する人達がたくさんいる。だから、枠組みをつくる側にいたいと思う。
"The side that creates the framework"
For some reason, the repetition of modules and patterns feels like it was a long time ago. It may be because they arbitrarily assume that the repetition of the same thing is combined with words such as mass production, factories and traditions.
Even in modern times, module and pattern iterations are everywhere. However, unlike a long time ago, I think that there is diversity in the contents only by the framework of repetition.
A long time ago, everything was repeated, and the fact that it was repeated was meaningful and purposeful. Because the speed of information transmission was slow and slow, only the strength of the repetition was certain, and in the situation where information spreads in an instant like in the present age, the repetition is meaningless, and if it is repeated, it is something else. Can no longer be communicated.
However, only the framework of information transmission is reused and repeated. The only certainty is that the framework is irrelevant, and there are a lot of people who are happy and sad about the variety that they like. Therefore, I would like to be on the side of creating the framework.
モジュールの反復で何かを描けるか、今3つのピースがあり、それを使ったデザインを考えている。挿入したい空間と比べたらとても小さいピースを生かすには、ピースの外形をひとつのモジュールとして、そのモジュールで空間を組み立てることを思いついた。が、しかし、そこからイメージが膨らまず2日、何かが足りないのだろう。もうひとつ何かモジュールの反復という発想にスパイス的なものを加えたい。
考えられるのは何かを重ね合わすこと。全くの異物を重ね合わせることで3つのピースを浮かび上がらせたい。
"Module Iteration"
I have three pieces now, and I'm thinking of designing using them, whether I can draw something by repeating the module. To make the best use of the piece, which is very small compared to the space I want to insert, I came up with the idea of using the outer shape of the piece as one module and assembling the space with that module. However, it seems that something is missing for two days without the image expanding from there. I want to add something spicy to the idea of repeating modules.
The idea is to superimpose something. I want to make three pieces stand out by superimposing completely foreign substances.
問題解決によるプロセスで生み出される新しさは、はじめから求めて生み出される新しさとは違う。問題を解決することにより、角が取れ丸みを帯びるように、結果が大衆化される。だから、新しいがたくさんの人達に受け入れられやすい結果になる。
新しいことは最初に反発を招くことがあるが、問題解決によるプロセスが反発を和らげる。だから、ちょっと無理なくらい新しいことを思いついた時は問題解決のプロセスを重ねると実現しやすくなる。
"Newness to be popularized"
The newness created by the process of problem solving is different from the newness created from the beginning. By solving the problem, the result is popularized so that the corners are rounded off. Therefore, the result is that the new one is easily accepted by many people.
New things can lead to repulsion in the first place, but the problem-solving process softens the repulsion. Therefore, when you come up with something new that is a little unreasonable, it will be easier to realize it by repeating the problem-solving process.
新しい見え方をつくる方法は2通りある。ひとつは意識して新しいことをする、もうひとつは結果的に新しいことにたどり着く。
結果的にたどり着く場合は、はじめから新しいことをしようとしていたのではなくて、何かの問題を解決しようした結果、何か新しい解決方法を生み出さなくてはいけなくなり、その解決方法が結果的に新しい見え方になる。
意識して新しいことをしようとすると、まず何が新しいかをわかっている必要があるが、問題解決を糸口にすれば、既存の方法では解決できないから問題になっているので、新しいことがわからなくても解決のプロセス自体が新しいことを生み出すプロセスになる。
まず意識して問題を持つことが新しい見え方への第一歩である。
"Process to create newness"
There are two ways to create a new look. One is consciously doing new things, and the other is eventually reaching new things.
If you arrive at the end, you're not trying to do something new from the beginning, you're trying to solve a problem, and you have to come up with a new solution. It will look new.
When you consciously try to do something new, you first need to know what is new, but if you use problem solving as a clue, it is a problem because it can not be solved by existing methods, so you can understand new things. Even without it, the solution process itself becomes a process that creates new things.
Being conscious and having problems is the first step toward a new perspective.
建築は人が入ることができる空間を内包するので表と裏の両方の見え方がある。いわゆる外観と内観だが、どちらが表か裏かは定かではなく、外観と内観の見え方の一致不一致もあり、外か内かの違い以上に様々な見え方が存在するが、それを表か裏かで考えてみようと思う。
表か裏かと思う時は真逆の面のつながりが確認できる時だろう。面がそのままつながっていれば、多少ねじれていたとしても表か裏かとは思わない。
真逆の面を持つのは建築の特徴のひとつだろう。真逆の面を持っていてもどちらかが見えなければ、表か裏かを意識することがない。それで言えば、どちらが表か裏かは人が見ている方が表で、その反対側が裏とした方が自然だろう。
表から裏の存在を意識する時はどういう時だろうか。外か内かを持ち込んで考えてみると、外から表を見る時に裏を意識する場合は内が見える時であり、内から表を見る時に裏を意識する場合は空間の形状がそのまま外観となっているかもしれないと意識する時だろう。
表も裏も意識できる建築を透明性が高いと考えても良いのではないだろうか。
"Highly transparent architecture"
Since architecture contains a space where people can enter, there are both front and back views. It is so-called appearance and introspection, but it is not clear which is the front or the back, and there is a mismatch between the appearance and the inside, and there are more various appearances than the difference between the outside and the inside, but it is the front or the back. I will think about it.
When you think it's front or back, it's time to confirm the connection on the opposite side. If the faces are connected as they are, even if they are twisted a little, I don't think they are front or back.
Having the opposite side is one of the characteristics of architecture. Even if you have the opposite side, if you can't see either side, you don't have to be aware of whether it is the front side or the back side. With that said, it would be more natural for people to see which is the front or the back, and the other side is the back.
What kind of time is it when you are aware of the existence from the front to the back? When you bring in the outside or the inside, when you are conscious of the back when you look at the front from the outside, it is when you can see the inside, and when you are conscious of the back when you look at the front from the inside, the shape of the space is the appearance as it is. It's time to realize that it may be.
It may be considered that architecture that can be conscious of both front and back is highly transparent.
大きさが醸し出すスケール感はデザインを上回る。スケールもデザインのうちだと思っているが、あえて別々にすると、デザインの成否はスケールで決まると言っても過言ではない。
では大きさというスケール感の丁度良さはどこからくるのだろうか。スケール感は感覚だから、感覚にズレがなければ良いスケール感だとなる。ただ感覚だとしたら人によって違いが出るはずである。人によって違いが出てしまったらスケール感をデザインの良し悪しの判断に使えない。
それでは感覚でも人によって違いが出ないスケール感がもし存在するとしたら、そのスケール感は何によって決まるのだろうか。
ひとつの仮説として、形によって観念的にスケールが存在しているのではないか、ということで、この形に対しては潜在的にこの位のスケールが丁度良い、と認識してしまうということである。
スケールでデザインの成否が決まるならば、すなわちそれは形でデザインの成否が決まるという当たり前の結論だが、形をデザインする際のヒントになるだろう。
"Hint of shape"
The sense of scale created by the size exceeds the design. I think that the scale is also part of the design, but if you dare to separate it, it is no exaggeration to say that the success or failure of the design is determined by the scale.
So where does the scale of size come from? The sense of scale is a sense, so if there is no discrepancy in the sense, it will be a good sense of scale. If it's just a feeling, it should make a difference from person to person. If there is a difference between people, the sense of scale cannot be used to judge whether the design is good or bad.
Then, if there is a sense of scale that does not make a difference between people, what determines that sense of scale?
One hypothesis is that the scale may exist conceptually depending on the shape, and it is recognized that this scale is potentially just right for this shape. be.
If scale determines the success or failure of a design, that is, it is a natural conclusion that the success or failure of a design is determined by the shape, but it will be a hint when designing the shape.
異なるスケールを組合せてつくるスケールは、ひとつのスケールに収束するのだろうか、それとも別々のスケールを認識するのだろうか、それとも新たなスケールの感覚を生むのか。
たくさんのスケールを兼ね備えている方が見え方に変化が生まれるだろう。空間であれば囲われるスケールで、物体であれば大きさのスケールで様々な異なるスケールを組合せてみようと考えている。
東京という都市は様々な異なるスケールで形成されている。だから、大きさのスケールで様々な異なるものを挿入しても違和感なく馴染むし、逆にスケールしだいで突出させることもできる。それはスケールを建築で扱う面白さでもある。
"Combination of scales"
Will scales created by combining different scales converge to one scale, will they recognize different scales, or will they create a new sense of scale?
Those who have many scales will change the way they look. I'm thinking of combining various different scales with a scale that surrounds space and a scale of size if it's an object.
The city of Tokyo is formed on various different scales. Therefore, even if you insert various different things on the scale of the size, it will fit comfortably, and conversely, it can be projected depending on the scale. It is also the fun of dealing with scale in architecture.
スケールには惑わされる。写真と実物で極端にスケールの印象が違う時がある。写真で見たらバランスがいいのに、実物を見るとスケールアウトしていて、各部位、各パーツが大きく見える。ものには適切なスケールがあり、それよりも大きくても小さくても違和感を感じる。
スケールには惑わされる。それまで別に気にも留めなかったのに、急にある角度から見た瞬間に見え方が変わり気になりだすことがある。それがスケールによるものなのか、たぶん角度が変わることによって微妙に大きさが変わって見えるからだろう。ある意味ズルい、翻弄されている。
"Deceived scale"
I'm confused by the scale. There are times when the impression of scale is extremely different between the photo and the real thing. The balance is good when you look at the photo, but when you look at the real thing, it is scaled out, and each part and each part looks big. Things have an appropriate scale, and it feels strange whether it is larger or smaller.
I'm confused by the scale. I didn't pay attention to it until then, but when I suddenly saw it from a certain angle, the appearance changed and I started to worry about it. Perhaps it is due to the scale, probably because the size changes slightly as the angle changes. In a sense, it's sloppy and at the mercy.
スケールが違うだけで同じ形でも見え方が違う。たぶん、そこには観念が入り込む余地があるからだろう。
人はどうしても観念的にものを見てしまう。昔、美術学校のデッサンの授業で観念的なものの見方は良くないと教わった。例えば、人物デッサンをしている時、顔は顔だと思って、胸は胸だと思ってデッサンをしてはいけない、単なるそういう形だとして構造を見て描くようにと教わった。
だから、デッサンを通してものの成り立ちが解像度高くわかるようになるのだろうが、その時同時に思っていたのは観念的にものを見ることによって、例えば、顔ならば顔だと思ってデッサンすることにより、普段人が顔だと認識することによって生まれる生々しい像を描けるのではないか、その方がよっぽどリアルなデッサンになるのではないかということだった。
実際は観念がものの成り立ちを左右する。だから逆に考えて、観念に左右させるネタをあらかじめ用意しておくのもデザインの手法であり、そのひとつして使えるのがスケールで、意図的にスケールを操作することにより見る者の意識に問いかけることができる。
"Ideal scale"
The appearance is different even if the shape is the same, only the scale is different. Maybe it's because there's room for ideas.
People inevitably see things conceptually. A long time ago, I was taught in a drawing class at an art school that the idea was not good. For example, when I was drawing a person, I was taught to look at the structure as if it were just such a shape, not to think that the face is the face and the chest is the chest.
Therefore, it will be possible to understand the origin of things with high resolution through drawing, but at the same time, I was thinking by looking at things conceptually, for example, by thinking that a face is a face and drawing. It was possible to draw a vivid image created by recognizing a person as a face, and that it would be a more realistic drawing.
In reality, ideas influence the formation of things. Therefore, thinking the other way around, it is also a design method to prepare in advance the material that influences the idea, and one of them can be used as a scale, which asks the viewer's consciousness by intentionally manipulating the scale. be able to.
足したものが目に見えないことにより、よりシンプルになる。今まで見てきた中で足すことの可能性を感じたのは、足し算をすることで引き算になり、よりシンプルになりながら足された状態であるものだった。
一見矛盾することだが足し算の可能性はここにあると思った。足すことにより、それまでの違和感が無くなり、より滑らかになるような感じで、滑らかになるということは一体感を招き、それは結果的には何か引かれて滑らかになったように感じる。
足したものがあからさまにわかることは違和感でしかない。一旦違和感をつくり、その後に違和感を消しながら一体感をつくるという方法もあるかもしれないが、足すことでの違和感は即不快感につながるおそれがあるので、足したものはなるべくわからないようにした方がいい。
"Resolving the discomfort of adding"
It's simpler because you can't see what you've added. What I've seen so far and felt the possibility of adding was that adding was subtracting, making it simpler and adding.
At first glance it is a contradiction, but I thought the possibility of addition was here. By adding it, the feeling of strangeness that has been used up to that point disappears, and it feels smoother. Being smoother creates a sense of unity, and as a result, it feels like something has been pulled and smoothed.
It's just a sense of incongruity to know what you've added. There may be a way to create a sense of discomfort once and then create a sense of unity while eliminating the discomfort, but the discomfort caused by adding it may immediately lead to discomfort, so those who try not to understand what they have added. Is good.
足し算の可能性、何を足すか、全く関係がないものを足すことを考えるよりは何かつながりがあるものの方がいいのか、足すものの基準はあるのだろうか、などと考えている。
案外答えはシンプルですぐそばにあるような気がする。足りないものが無いと思うのはそこまで思考が及んでいないからと決めつければ何か見えてくるかもしれない。
何かを足すと考えるより、何かを組み合わせると考えた方が現状とつながりやすい。組合せを考えるならば、全く真逆のものも候補に上がり、その中庸をとるようなことも範疇になる。
中庸というと中途半端なイメージがあるかもしれないが、全ての要素が入り込み尚且つ成り立つのだから、一番望まれる状態かもしれない。
一番望まれる状態はそこに他者性も含まれるので、自分だけでは気づけなかったことに気づく可能性もある。結局はいいものができあがる可能性が一番高まる手段を選択しようとしている。
"Means of possibility"
I'm wondering about the possibility of addition, what to add, whether it's better to have something connected than to think about adding something that has nothing to do with it, or is there a standard for what to add?
The unexpected answer is simple and I feel like it's right around the corner. If you decide that there is nothing missing because you haven't thought so much, you may see something.
It is easier to connect with the current situation by thinking of combining something rather than adding something. If you think about the combination, the exact opposite is also a candidate, and it is also a category to take the middle of it.
There may be a half-hearted image when it comes to moderate, but it may be the most desirable state because all the elements are intricate and valid.
The most desired state includes otherness, so you may find that you didn't notice it on your own. In the end, I'm trying to choose the means that is most likely to produce good things.
引き算の美学だと日本文化のことをいうが、確かに建築でいえば数寄屋造、料理でいえば寿司などは引き算だといえる。ただ現実の生活の中では引き算よりむしろ圧倒的に足し算か多いのではないかと考えている。そもそもプリミティブやミニマムなところからはじめて段階的に足していくことになることが多い。
しかし、もしはじめから引き算をする場合は予め存在しているものを変える時だろう。改革な革新などを行う時は大体が飽和状態なのでまず引き算をして余白をつくり、その余白で新しいことを行う。片付けや整理整頓も同じでまず捨てる必要がある。
ただ、決して足し算が悪い訳ではない。結局はできあがったもので判断をする訳だから、足すことにより引くことよりも良いものをつくればいいだけで、引き算の文化だといわれているならば、余計に足し算による可能性を追求した方が良いものや見たことがないものをつくれるかもしれない。
"Possibility of addition"
The aesthetics of subtraction refers to Japanese culture, but it is true that Sukiya-zukuri in terms of architecture and sushi in terms of cooking are subtraction. However, in real life, I think that addition is overwhelmingly more than subtraction. In the first place, it is often the case that you start with primitives and minimums and add them step by step.
However, if you want to subtract from the beginning, it's time to change what is already there. When making reforms and innovations, it is usually saturated, so first subtract to create a margin, and then do something new with that margin. The same is true for tidying up and tidying up, so you need to throw it away first.
However, the addition is not bad at all. In the end, the decision is made based on the finished product, so if it is said that it is a culture of subtraction, it is better to pursue the possibility of addition more than just adding and subtracting. You may be able to make something good or something you have never seen.
プレーンという言葉について、プレーンという言葉からどのような特性や機能が思い浮かぶかというと、一様な、純白、素、途中、初源的な、可変可能などがあり、そこから更に連想すると、食べ物で言えば豆腐が思い浮かんだ。
プレーンを建築的には現代から振り返って言えばモダニズムかもしれない。だからモダニズムは「四角い豆腐」とすることもできる。
四角い豆腐に対して、いろいろな味付けをしたのがポストモダニズムで、その後やっぱり豆腐自体の味を良くする必要があるよね、その後やっぱり豆腐自体が美味しくても飽きるしどうしようかと変わっていかながら、豆腐をつくる時の素材である大豆と水に拘ることもするようになった。だから、もう一歩進めて豆腐の原形が無くなったても良いから料理の味付けとして使うことを考えている。
"Square tofu"
Regarding the word plain, what kind of characteristics and functions come to mind from the word plain are uniform, pure white, plain, intermediate, primitive, variable, etc., and if you associate it further, food Speaking of which, tofu came to my mind.
Architecturally, looking back on the plane from the present age, it may be modernism. So modernism can also be called "square tofu".
Postmodernism is a variety of seasonings for square tofu, and after that it is necessary to improve the taste of the tofu itself. After that, even if the tofu itself is delicious, I get tired of it. I also started to stick to soybeans and water, which are the ingredients when making tofu. Therefore, I'm thinking of using it as a seasoning for cooking because it's okay to go one step further and lose the original form of tofu.
つくり手はハーフポーションもコースも同じようなクオリティでつくることができるのだろうかといつも思う。
量の違いは建築で言えばスケールであり、ふさわしいスケールというものがある。建築以外のオブジェクトを扱うものも概ね一緒だと思うが、形にふさわしいスケール、ピッタリと合う大きさがあり、それが数ミリずれただけで印象がガラリと変わり、クオリティが落ちる。
だから、ふさわしいスケールを探しだすことは、ものづくりやデザインにとって重要なことなのだ。ハーフポーションにしたら少なくとも見た目のバランスは崩れる。見た目も味のうちならばクオリティはそれだけで落ちるはずだ。
"Potions and Courses"
I always wonder if the creator can make half potions and courses with the same quality.
The difference in quantity is scale in terms of architecture, and there is a suitable scale. I think that things that deal with objects other than architecture are almost the same, but there is a scale that fits the shape, a size that fits perfectly, and even if it is off by a few millimeters, the impression will change completely and the quality will drop.
Therefore, finding the right scale is important for manufacturing and design. If you make a half potion, at least the appearance will be out of balance. If it looks and tastes good, the quality should be reduced by itself.
不足の中に可能性を感じるのは不足という中途半端な状態を見慣れていないからでもあるが、不足という過程の状態はそこからどのようにでも変化できるという変化量の多さに可能性を感じることができる。
だから、可能性を追求するならば、わざと中途半端に留めておくことのもひとつの方法である。
"Possibility of shortage"
I feel the possibility in the shortage because I am not accustomed to the halfway state of the shortage, but I feel the possibility of the large amount of change that the state of the process of the shortage can be changed in any way from there. be able to.
So, if you're looking for possibilities, it's a good idea to keep it halfway.
世の中にはありとあらゆる形が存在していて、作為を持って作為が無いものをつくろうと意識している人もいて、これまでもたくさんの形を見てきたが、まだまだ見ぬ形や形の可能性や気づいていない形の見方や捉え方もあると感じることができた貴重な2年に一度の鳥取でした。
きっと永遠に終わりがないのだろう。追求しつづけていくことでしか形を見ることができない。追求するのはいつか完璧な形を見出したいからで、しかし、追求することで形の不足が見えてしまう。だから、終わりがない。
"Pursuit of shape"
There are all kinds of shapes in the world, and some people are conscious of making things that have no intentions, and I have seen many shapes, but there are still possibilities for shapes and shapes that I have not seen yet. It was a precious once-in-a-two-year Tottori that I could feel that there was a way of seeing and understanding the sexuality and the shape that I didn't notice.
I'm sure there will be no end forever. You can only see the shape by continuing to pursue it. I pursue it because I want to find the perfect shape someday, but by pursuing it, I can see the lack of shape. So there is no end.
ちょっと何かが足りないこと、ちょっと何かが過ぎることに可能性を感じた。いつもと違う見え方、それは何かが足りない、何が過剰であり、その足りない部分、過剰な部分を頭の中で補い省き処理することでその人だけの像が頭の中にできあがる。完璧の良さは十二分にわかるが、それとは違う良さが過不足にはある。もしかしたら、完璧の良さを上回る可能性すらある。I am crazy about lack and excess.
"Insufficient and excessively engrossed"
I felt the possibility that something was missing or something was going too far. It looks different from usual, it is something missing, what is excessive, and by compensating for the missing part and excess part in the head and processing it, an image of that person alone is created in the head. I can fully understand the goodness of perfection, but there is a different goodness in excess and deficiency. Maybe it even exceeds the goodness of perfection.
つながることが中庸を生む手段だと砂丘の風紋を見ながら思った。一面の砂な中に凸凹ができることにより周りとは違い場所を生み出す。しかし、その場所は同じ砂の中であるから全くの異質ではない。中庸とは、間を取り上手く調整することではなくて、周りと同じだが違う状態を生み出すことであり、そのためにはまずつながりをつくり、その中で違いをつくること、すなわち、それは創造と同じ結果を生み出すのではないかと考えみた。
"Medium = Creation"
Looking at the wind patterns of the dunes, I thought that connecting was the means to create a golden mean. By creating irregularities in the sand on one side, it creates a place different from the surroundings. However, the place is not completely different because it is in the same sand. Moderate is not about adjusting the interval well, but about creating the same but different state as the surroundings, for which you first make a connection and then make a difference in it, that is, it has the same result as creation. I thought that it might produce.
対比と同化を使い分けて色を考えることを建築では行わない。現在の建築において色を扱うことは主題ではない。色自体に意味を持たすことが建築の自律性を高めることにはなるが、自律性を高めることが時代にそぐわないし、仮に自律性を高めたとしてもその手段に色を使うことを躊躇する。
それは多分、コルビュジエ やデ・ステイルが100年前に色で自律性を高める表現行為をしており、他の手段、例えばフォルムで自律性を高める手段が技術の発達でより可能になり、その可能性を追求する方が魅力を感じるからだろう。
ただ逆に言えば、色が持つ可能性はまだまだ未開拓な部分があり可能性があると言える。
"Color is undeveloped"
In architecture, we do not think about colors by using contrast and assimilation properly. Dealing with color in modern architecture is not the subject. Having meaning in the color itself enhances the autonomy of architecture, but increasing autonomy is not suitable for the times, and even if it enhances autonomy, hesitate to use color as a means of doing so.
Perhaps Le Corbusier and De Stijl were 100 years ago in the act of expressing autonomy with color, and other means, such as the means of increasing autonomy with form, became more possible with the development of technology. Perhaps it is more attractive to pursue sex.
However, to put it the other way around, it can be said that the possibilities of color are still undeveloped.
建築の輪郭について意識してみようと考えた。輪郭がはっきりと主張を持つような自律した建築はいかにも建築らしい建築で好きなのだが、輪郭が周りに馴染み、輪郭があまり感じられないような建築もまた好きであり、それは主張しないということではなくて、周りと馴染むという主張をしていると考えた。
むしろ輪郭が消え去るような状態をつくりたいと考えており、消え去るためのひとつの方法がバックグラウンドまで含めて建築にし、バックグラウンドと輪郭の差異を無くすことである。
そのためには屋根の形状を利用してバックグラウンドをつくり、消失するような輪郭をつくり出せないかと考えている。
"Disappearing contour"
I thought about the outline of the architecture. I like autonomous architecture that has a clear outline, but I also like architecture that has contours that are familiar to the surroundings and the contours are not so noticeable, which is not to say that I do not claim it. I thought that I was insisting that I would be familiar with the people around me.
Rather, he wants to create a state where the contour disappears, and one way to eliminate it is to build the building including the background and eliminate the difference between the background and the contour.
To that end, he wonders if the shape of the roof could be used to create a background that would disappear.
輪郭がはっきりしない様を輪郭の中につくれば良いと思った。はっきりしない輪郭はバックグラウンドとの差異の少なさでつくることができる。
ただ、建築のような大きなものになるとバックグラウンドは風景くらいのスケールになり、なかなかそこまでコントロールできない。
だから、バックグラウンドを建築の一部にしてはっきりしない輪郭をつくろうと考えた。
"How to make an unclear outline"
I thought it would be good to make the outline in the outline so that it is not clear. Unclear contours can be created with little difference from the background.
However, when it comes to big things like architecture, the background becomes a landscape-like scale, and it's hard to control that much.
So I decided to make the background a part of the architecture and create an unclear outline.
輪郭が凸凹したり、ランダムに歪む、反転するなど単なる直線や曲線ではなく不規則に変化する様は、はっきりとしない輪郭を余計に浮かび上がらせる効果があり、それは輪郭がはっきりとすることにつながる。
輪郭を輪郭らしくしないようにいじればいじる程、輪郭が目立つ。むしろ幾何学的な輪郭の方が輪郭が消失するかもしれない。ただ純粋な方向に持っていく方が良いとすると、それは輪郭を単なる直線や曲線にする方が良いとすると、もうそれ以上輪郭について考えることをしないようになるのでそれは避けたい。
"Not a pure contour"
Random changes in contours, such as unevenness, random distortion, and inversion, rather than just straight lines or curves, have the effect of making unclear contours stand out more, which leads to sharper contours.
The more you mess with the contours so that they don't look like contours, the more noticeable the contours will be. Rather, geometric contours may lose their contours. If it's better to just take it in the pure direction, it's better to make the contour just a straight line or a curve, and I don't want to think about it anymore because I don't think about it anymore.
輪郭を動かしてぼかすような効果をつくり出せないかと考えていたら、見ようによっては輪郭がはっきりとしないかもしれないものに出会った。
そのもの自体はとても固く、ピン角の輪郭ならばぼけるようなことはない。ただ、輪郭がランダムに歪んでいる、凸凹している。そうすると、はっきりとしない輪郭がはっきりと見える。
はっきりしないこと、ぼかすことはものづくりにおいては同じことだとしてもよいと考えてみた。
"Unclear contour"
When I was wondering if I could move the contours to create a blurry effect, I came across something that might not be clear depending on how I looked at it.
The itself is very hard, and the contour of the pin angle will not be blurred. However, the contour is randomly distorted and uneven. Then you can clearly see the unclear outline.
I thought that uncertainties and blurring could be the same in manufacturing.
輪郭がはっきりとしないものは存在するのだろうかと考えみた。どんなにゆらゆらとするものでも輪郭は動くがはっきりとしている。
ゆらゆらと像が映り込む様子は輪郭ははっきりとしつつもうつろう。うつろうとゆらゆらは違うかもしれないが輪郭は動く。輪郭がはっきりとしない様を輪郭が動くと読み替えてみたらどうなるかを考えてみることにした。
"The outline moves"
I wondered if there was something whose outline was not clear. No matter how swaying it is, the contours move but are clear.
The appearance of the image reflected swayingly will be clear while the outline is clear. Depression and swaying may be different, but the contours move. I decided to think about what would happen if I read that the outline is not clear when the outline moves.
すりガラス越しに見るように形をぼかすことが建築おいてできるかどうかを考えている。すりガラスの表面の凸凹に光か当たり乱反射して形の輪郭がはっきりしない様なのだが、目と建築の間にすりガラスを置くわけにはいかないし、建築をすりガラスで囲うことはできるが今のプロジェクトでは現実的ではない。
輪郭がはっきりしない様を意図的につくり出せば良いのだが、建築においてはバックとの差異がなく同じようになれば意図的につくり出せるかもしれない。バックとの差異がない状態は色ならば可能か、空の色と同じように、ちょっと安直すぎるかもしれない。
"To blur the outline"
I'm wondering if it's possible in architecture to blur the shape as seen through frosted glass. It seems that the outline of the shape is not clear due to light hitting the unevenness of the surface of the frosted glass and the outline of the shape is not clear, but it is not possible to put the frosted glass between the eyes and the building, and it is possible to surround the building with frosted glass, but in the current project Not realistic.
It is good to intentionally create something that does not have a clear outline, but in architecture it may be possible to intentionally create it if there is no difference from the back and it becomes the same. It may be possible for the color to be the same as the back, or it may be a little too easy, just like the color of the sky.
色には濃度の差がある。濃度の差は相対的指標なので、単純に濃度の差と言っても、色は明度と彩度の組み合わせで決まるから、場合によっては薄い色だが濃く感じさせることができる。
同じように不透明な色だが透明な色に見せることもできる。
色は生き物のように色同士で関係性を持ち影響し合う。例えば、補色対比や明度対比などがそれにあたるがより複雑な組合せによって見た目の空間の歪みさえもつくり出すことができる。
"Distorted by color"
There is a difference in density between colors. Since the difference in density is a relative index, even if it is simply called the difference in density, the color is determined by the combination of lightness and saturation, so in some cases it is a light color but it can be made to feel dark.
It's also an opaque color, but it can also look transparent.
Colors have a relationship and influence each other like living things. For example, complementary color contrast and lightness contrast correspond to it, but even more complicated combinations can create distortion of the apparent space.
色は光を通して目で認識され、違う色同士も組合せて新たな色をつくり出す。それは無意識に行われて脳に刻まれる。実際には無い色を脳でつくり出す。それは広い面積であればより顕著になる。だから、建築のような人のスケールよりも大きいものは色の影響を受けやすいし、影響を与えやすい。建築ではまだまだ色が持つ様々な影響について可能性が残されていると感じており、今手掛けているプロジェクトでいろいろと試してみたいと考えている。
"Try colors"
Colors are recognized by the eyes through light, and different colors are combined to create new colors. It is done unconsciously and is engraved in the brain. The brain creates colors that do not actually exist. It becomes more noticeable in large areas. Therefore, things that are larger than a person's scale, such as architecture, are susceptible to and easily influenced by color. I feel that there are still possibilities in architecture for the various effects of color, and I would like to try various things in the project I am currently working on.
物体を色のみで識別すると全て不透明な色として認識することになるのだろうか、色のみで建築同士の関係性を表現できるのだろうか、などと考えている。
不透明な色として全て認識してしまうかどうかは、単体のみで見れば全てを不透明な色として認識するだろうが、複数の物体が存在しているならば、それらの関係性の中で透明な色として認識させることはできるだろう。
少なくとも、不透明な色の物体の中で透明な色を認識させようとした時には物体同士の関係性は使えそうである。ならば建築同士の関係性の中でも同じことはできそうである。
"Transparency in relationships"
I wonder if all objects will be recognized as opaque colors if they are identified only by color, or if the relationship between buildings can be expressed only by color.
Whether or not to recognize all as opaque colors will be recognized as opaque colors when viewed alone, but if multiple objects exist, they are transparent in their relationship. It can be recognized as a color.
At least, it seems that the relationship between objects can be used when trying to recognize a transparent color among objects of opaque color. Then, it seems that the same thing can be done in the relationship between buildings.
2つの建築が別々に近接して存在していた時に、その間に生まれる関係性には様々あるだろうが、その関係性の中に偶然性はあるだろうか。
偶然性は停滞せずに常に動いているから起こることだと思っていたが、もし停滞していても偶然性が発動されるようなことがあれば、近接した2つの建築との間でも偶然性がある。
窓に映る景色なども偶然性によるところもあるが、単体の建築におけることではなくて、建築同士の関係性の中で偶然性を探している。もしかしたら、イメージの中で2つの建築が生み出す中庸の産物が偶然性を帯びると解釈すればよいかもしれない。
"Interpretation of contingency"
When two buildings existed separately and in close proximity, there may be various relationships that arise between them, but is there any chance in those relationships?
I thought that contingency happens because it is always moving without stagnation, but if it happens even if it is stagnant, there is a contingency between two buildings in close proximity. ..
The scenery reflected in the window is also due to chance, but I am looking for chance not in a single building but in the relationship between buildings. Perhaps it may be interpreted that the moderate products produced by the two architectures are contingent in the image.
偶有の産物によるリアルさは、ミニマルなリアルさではなく、ダイバースなリアルさになる。偶有という一時的に偶然に備えた性質がリアルさを醸し出すのは何かに触れた時であり、その何かが偶然性をより複雑にしてくれる。
建築は動かないから偶然性は建築に必ず必要な要素だと考えている。偶然性がリアルな建築の姿を浮かび上がらせる。ただ、それは自然によってもたらされるような陳腐なものではない。建築同士の関係性の中で生まれる偶然性である。
"Needs chance"
The reality of accidental products is not a minimal reality, but a diversity reality. It is when you touch something that the temporary accidental nature of contingency creates reality, and that something complicates contingency.
Since architecture does not move, I think that chance is an essential element of architecture. Contingency brings out the appearance of real architecture. But it's not as stale as it comes from nature. It is a contingency that arises in the relationship between buildings.
偶然の産物をつくり出すためにはどうするかを考えている。建築は可能な限り予定調和を目指す。全てにおいて限りがあるので、有効活用するには予測通りに事が起こるようにする必要があり、そのための技術であり、安全性である。
しかし、それだけではつまらない。予測の不可能なものを差し込むことにより、偶然が生み出す偶有性を備えたものが出来上がり、それは本質的ではないかもしれないが、今そこに建っているというリアルさは表現できる。
"Accidental product"
I'm thinking about what to do to create a product of chance. Architecture aims for planned harmony as much as possible. Everything is limited, so in order to make effective use of it, it is necessary to make things happen as expected, and it is a technology and safety for that purpose.
But that alone is boring. By plugging in something unpredictable, you end up with something with contingency created by chance, which may not be essential, but it can express the reality of being there now.
中庸である状態を目指すことはするが、中庸の強度まで範疇にすることはないだろう。強度を問題にしないと中庸に対して中途半端になる。中庸の深遠とでも言うだろうか、そのような言葉や概念があるかどうかはわからないが、中庸の度合いを吟味しないと、陳腐で意味がない中庸が出来上がる。
中庸が大事な社会だと思う。情報が氾濫し、様々な情報や知識が入手しやすく、そのおかげで極端なことも増えた。極端なことに人はつい惹かれてしまう。ただ、人は極端な状況に身を置き続けると自身を失う。意識して中庸を見定める必要があり、それで自身の身も守ることができる。
"Become moderate"
We will aim for a moderate state, but we will not fall into the category of moderate strength. If strength is not an issue, it will be halfway to the middle. I don't know if there is such a word or concept, but if you don't examine the degree of the golden mean, you will end up with a stale and meaningless golden mean.
I think the golden mean is an important society. Information was flooded, and various information and knowledge were easily available, which increased the number of extremes. At the extreme, people are attracted to it. However, people lose themselves if they continue to be in extreme situations. You need to be conscious of the golden mean, and you can protect yourself.
中庸は何かと何かの間を片寄ることなく上手くとることで成立するとするならば、真逆の何か2つを探し出してくれば良いのだが、その何かが主題では中庸は単に中途半端な産物に成りはしないかと考えてしまう。
中庸は上手くミックスすることで成り立ち、それが強度を持つ状態だが、中途半端な産物では強度が出ない。
強度を出すために主題となるようなものの中庸をとるのではなくて、主題になるかどうかわからない、偶然の産物のような、その瞬間だけ現れるようなもの同士の中庸を考えてみる。偶然の産物だとしたら中庸の強度にバラつきが出るかもしれないが、予測不可能なだけに突き抜けたような強度が出るかもしれない。
突き抜けたような中庸、一見矛盾するような言葉の組み合わせだが、それだけに可能性を感じる。
"Medium strength"
If the golden mean can be achieved by getting it right without shifting between something, then you can find two things that are the exact opposite, but if that something is the subject, the golden mean is simply a half-finished product. I wonder if it will be possible.
Moderate is made by mixing well, and it has strength, but half-finished products do not have strength.
Instead of taking the middle of something that is the subject for strength, think of the middle of things that appear only at that moment, such as accidental products that you do not know whether or not they will be the subject. If it is a product of chance, the strength of the golden mean may vary, but the strength may be unpredictable and piercing.
It's a combination of words that seem to be piercing, moderate, and seemingly contradictory, but I feel the possibility.
つながりには結界が必要だ。おかしな話だが、全くのオープンなつながりはつながりにはならない。どのような要素にも境界は存在し、要素同士のつながりをつくる時は境界を無くすのではなく、境界は残しつつ、その境界の一部分を薄くして接するようなイメージでつなぐ。境界が無くなってしまうと要素同士が混ざり合い一体となってしまい、つながりでは無くなる。
人間関係も同じかもしれないが、境界が無くなり要素の個性が無くなってしまったら、つながりをつくる意味さえなくなる。だから、絶対に相容れない境界である結界は必要になる。
"To be connected"
A barrier is needed to connect. Oddly enough, a totally open connection is not a connection. Boundaries exist in every element, and when making a connection between elements, instead of eliminating the boundaries, we connect them with the image of thinning a part of the boundaries while leaving the boundaries. When the boundary disappears, the elements are mixed and integrated, and it is no longer a connection.
Relationships may be the same, but if the boundaries disappear and the individuality of the elements disappears, there is no point in making connections. Therefore, a barrier, which is an absolutely incompatible boundary, is necessary.
要素を拡散させて、異なった結びつきをいかにたくさんつくるか。ただ、要素同士をケンカさせるように結びつけるのは意味がない。例え要素同士が真逆のことでも中庸を取り、両方の要素を融合させることで異なった新しい結びつきをつくることができる。
新しいアイデアは新しい結びつきである。新しい結びつきは今までの結びつきのクリティカルになる。だから、全く関係が無い異なった要素同士を見つけてくることが大事であり、それだけで新しい結びつき、すなわち新しいアイデアを喚起することになる。
"Inspire new ideas"
How to spread the elements and make many different connections. However, there is no point in connecting the elements so that they fight each other. Even if the elements are exactly the opposite, it is possible to create a different new connection by taking the golden mean and fusing both elements.
A new idea is a new connection. The new bond becomes the critical of the old bond. Therefore, it is important to find different elements that have nothing to do with each other, and that alone will inspire new connections, that is, new ideas.
物語や小説のアクションに当たる部分を建築ではアクティビティというだろう。アクションは多過ぎてはダメらしい。建築もアクティビティが多くなり過ぎると建築ではなく工作物あるいは装置になってしまう。
アクティビティはあくまでも「何がどのように起こるか」の「どのように起こるか」の部分であるから「何が」の部分が必要であり、工作物や装置には「何が」に当たる部分が無い。正解に言うと「何が」の部分が工作物や装置にもあるのだが、アクティビティの割合が多くて、「何が」の部分の存在が希薄になり、「何が」が無くてもアクティビティだけで成立している。
故に「何が」の部分の存在によって建築のアクティビティとして成立することができる。
"What you need for architectural activities"
In architecture, the part that corresponds to the action of a story or novel is called an activity. It seems that too many actions are useless. If there are too many activities in architecture, it will become a work or device instead of architecture.
Since the activity is only the "how" part of "what happens and how", the "what" part is necessary, and there is no "what" part in the work or equipment. .. The correct answer is that there is a "what" part in the work and equipment, but the percentage of activities is high, the existence of the "what" part is diluted, and even if there is no "what", the activity It is established only by.
Therefore, the existence of the "what" part can be established as an architectural activity.
たくさんの要素をどのようにつなげ、どのようなストーリーを描くのかを考えていて、プロットが大事だと思うが、出だしも大事だと思い、建築の話に置き換えて、登場人物が要素だとすると、要素に性格を割り当てて、アクションを起こし、要素の物語を形成していく。
建築では物語性は拒絶される傾向にあるが、一旦物語を紡ぎ、その物語に対してクリティカルな対応することで、要素同士につながりに新しい可能性を見出せるのではないかと考えている。
"Spinning a story"
I'm thinking about how to connect many elements and what kind of story to draw, I think that the plot is important, but I think that the beginning is also important, so if you replace it with the story of architecture and the characters are the elements, the elements Assign a personality to, take action, and form a story of elements.
Narratives tend to be rejected in architecture, but I think that by spinning a story once and taking a critical response to that story, we can discover new possibilities in connecting the elements.
課題と関心事を結びつけ言い換えることで、新しい方向性が見えてくる。そして、その新しい方向性と真逆のことを考えてみる。そして、新しい方向性と真逆のことを結びつけ言い換えてみる。そうすると、つながりを辿ってきただけなのに、はじめとは違うことになっている。それが全く違う訳ではなく、考えてみれば、それが一番進みたい方向だったりするから面白い。
"Connect"
By connecting issues and concerns and paraphrasing them, new directions can be seen. And think about the exact opposite of that new direction. Then, in other words, connect the new direction and the opposite. Then, even though I just followed the connection, it is supposed to be different from the beginning. It's not completely different, and when you think about it, it's interesting because it's the direction you want to go the most.
抽象化を決める方法を考えている。抽象化は削ぎ落とす過程があり、何をどのくらい削ぎ落としていくのかをあらかじめルールとして考えることができる。まず抽象化する実体を把握するところからはじめる。そのためには様々な要素のつながりを解明する必要がある。ルールとしてはただ単に削ぎ落としていくのでは無くて、不必要な様々な要素のつながりを切っていくように抽象化を行う。つながりの解明には様々な角度から実体を捉える必要があり、その時に抱えている課題を通して捉えると、よりつながりが鮮明になる。
"Method of abstraction"
I'm thinking about how to determine the abstraction. Abstraction has a process of scraping off, and you can think in advance what and how much to scrape off as a rule. Start by understanding the entity to be abstracted. For that purpose, it is necessary to clarify the connection of various elements. As a rule, we do not simply scrape off, but abstract so as to break the connection of various unnecessary elements. In order to clarify the connection, it is necessary to grasp the entity from various angles, and if you grasp it through the problems you are having at that time, the connection becomes clearer.
抽象化と洗練は削ぎ落とすという過程は同じだが、削ぎ落とし方が違う。削ぎ落とすためのルールが違うと言っても良いかもしれない。例えるならば、抽象化は枝葉の余分な末端を切り落として、木が持つ本質を鮮明にするが、洗練は枝葉の末端を整えることにより、木が持つ本来の姿を鮮明にする。だから、削ぎ落とし方によっては抽象化されたものも洗練されたものも同じに見えし、抽象化して洗練させることもできるから、抽象化と洗練は太古の昔から様々な所で何かを象徴したり、主張する際の手法として用いられてきたのだろう。
"Abstract and sophistication as a method"
The process of scraping off abstraction and sophistication is the same, but the scraping method is different. It may be said that the rules for scraping off are different. For example, abstraction cuts off the extra ends of the branches and leaves to clarify the essence of the tree, while refinement sharpens the ends of the branches and leaves to clarify the original appearance of the tree. So, depending on how you scrape it off, the abstracted and the refined look the same, and you can abstract and refine it, so abstraction and sophistication have symbolized something in various places since ancient times. It may have been used as a method for abstracting and asserting.
抽象化されたものは洗練されているように見える。本来、抽象化と洗練は全く別の行為で、抽象化は拡散させ、洗練は集中するようなイメージがあるが、抽象化は拡散させるために余分なものを削ぎ落とす過程があり、洗練も集中するために余分なものを削ぎ落とす過程があり、どちらも同じ過程を辿るからだろう。
"Abstract and sophistication"
The abstraction looks sophisticated. Originally, abstraction and sophistication are completely different acts, and there is an image that abstraction is diffused and refinement is concentrated, but abstraction has a process of scraping off extra things to diffuse, and sophistication is also concentrated. There is a process of scraping off excess things to do, and both follow the same process.
抽象化されることによりルールが浮かび上がる。抽象化する際にルールという枠に当てはめて整理し、余計なものを省いていく。はじめにルールが存在し、そのルールに束ねていくイメージだろうか。だから、抽象化されたものを注意深く観察すると、ルールの輪郭が表現として現れてくる。そのルールの現れがその抽象化されたものの特色ともいえる。その特色が類型になり作品性を出す。
"Rules of abstraction"
The rules emerge by being abstracted. When abstracting, apply it to the frame of rules and organize it, and omit unnecessary things. Is it an image that there are rules at the beginning and they are bundled into those rules? So, if you look carefully at the abstraction, the outline of the rule will appear as an expression. It can be said that the appearance of the rule is a feature of the abstraction. Its characteristics become a type and give a work.
抽象化されたものは、元の抽象化される前のものがわからないと理解できないものだろうかと考える機会があった。
正直に言えば、抽象化されたものがよく理解できなかったのである。
ただ、元のものがわかる時は、抽象化されたものは手に取るように理解でき、その素晴らしさに感銘を受けた。だから余計にその差があるので、元の抽象化される前のものの理解の必要性を感じてしまった。
"Abstracted"
I had the opportunity to wonder if what was abstracted could not be understood without knowing what was before the original abstraction.
To be honest, I couldn't understand the abstraction well.
However, when I knew the original, I could understand the abstracted one as if I were picking it up, and I was impressed by its wonderfulness. So there is an extra difference, and I felt the need to understand what was before the original abstraction.
間違いをしたくないから最初から確実なアイデアを出そうとすると大抵どこかで見かけたようなものになる。間違いをすることを極端に嫌がる人は多い。どこかで見かけたようなものを選択してしまうのもエビデンスがあって安心できるからだろうが、つまらない。まだ正解あるものだとそれでも良いが、正解がないものでは真逆の結果が出る行為で、つまらないは一番求められていない結果である。そういう人はその時だけ別人格になれば良い。
"Boring results"
I don't want to make mistakes, so when I try to come up with a solid idea from the beginning, it's usually something I've seen somewhere. Many people are extremely reluctant to make mistakes. It's boring to choose something that you see somewhere, probably because there is evidence and you can rest assured. It's okay if there is still a correct answer, but if there is no correct answer, the opposite result will be obtained, and boring is the least sought after result. Such a person only needs to have a different personality at that time.
ついいろいろと着飾ってしまい、何がしたかったのかがブレてわからなくなり、後になってはじめに考えていたこととは違うことをしていて困ることがある。困るのは、途中でつけ加えることは良いことでも本質がブレては意味がないとは思っているからだが、つけ加える必要があるならば本質がブレても構わない、周りは困るだろうが、結果的に良い方向に持っていけばいいだけだとして見渡してみたら、まだまだ足りない、たくさんつけ加えて、ダメならばやればいいができるのがつけ加えるの良いところ。
"Add"
I've been dressed up in various ways, and I don't know what I wanted to do, and sometimes I'm having trouble doing something different from what I was thinking at the beginning. The problem is that it is good to add in the middle, but I think that it is meaningless if the essence is blurred, but if it is necessary to add it, the essence can be blurred, the surroundings will be troubled, but the result If you look around as you just have to take it in the right direction, it's still not enough, add a lot, and if it doesn't work, you can do it.
足の裏で感じることを考えていて思い出した。お能で面をつけて登場するシテ方は面の視野が狭いので足の裏で今舞台上のどこにいるかを感じながら演じているそうで、舞台の床の板の感触の変わり目を感じながら歩いているという。
きいた話によるとお能は余計な所作と言葉を全て削ぎ落とし、必要かつ最低限の所作と言葉で表現するとのことで、まさにそれは抽象化であり、演者が抽象化に没頭できるように視野の狭い面を装着するとも考えられるのではないかと思い、抽象化して本質的なものだけを残す過程で足の裏で感じることが寄与しているとも考えられる。
抽象化して本質を今一度掘り返すようなことをしてみようと思う。
"Abstract and meet the essence"
I remembered thinking about what I felt on the soles of my feet. Since the field of view of the shite who appears with a face on Noh is narrow, he seems to be performing while feeling where he is on the stage with the soles of his feet, and he walks while feeling the change in the feel of the board on the stage floor. It is said that it is.
According to the story I heard, Noh cuts off all unnecessary actions and words and expresses them with the necessary and minimum actions and words, which is exactly the abstraction, and the perspective is to allow the performer to immerse himself in the abstraction. I think that it may be possible to wear a narrow surface, and it is also thought that the feeling on the sole of the foot in the process of abstracting and leaving only the essential things contributes.
I will try to abstract it and dig up the essence again.
蓄積された足からの情報だけがその人にとって信じるに足る情報だと考えた。きっと人は知らないうちに目からの情報に頼り過ぎているのかもしれない。
もし目からの情報が得られなければ、何も感じられないと思うことだろう。もし感じられなければ、情報も得られないし、何もわからないと思うのだろう。
目からの情報は詳細にわかるから具体性を帯びており、足からの情報は目からの情報ほど詳細にはわからないので抽象性が強くなるかもしれない。具体的に何でもわかれば良いとは限らない。抽象性が強い中で本質が浮かび上がることもある。
もしかしたら、足からの情報の方が本質をつくには良いかもしれない。
"Foot to make the essence"
I thought that the accumulated information from the feet was the only information that the person could believe. Perhaps people are relying too much on information from their eyes without their knowledge.
If you don't get the information from your eyes, you'll think you can't feel anything. If you don't feel it, you won't get any information and you probably don't know anything.
The information from the eyes is concrete because it can be understood in detail, and the information from the feet is not as detailed as the information from the eyes, so it may be more abstract. It is not always necessary to know anything concretely. The essence may emerge in a strong abstraction.
Perhaps the information from the feet is better for the essence.
山や森を歩いている時、目では木や緑や風景を追っているが、身体のどこの部分で一番山や森を感じているかというと足であり、特に靴底を通して足の裏で感じている。
足の裏の感じと目から入る視覚情報が相まり、今いる場所である山や森を認識している。だから実際に感じている身体の部位は足だけである。
目をつぶった状態でそのままで何かを感じることができるのは足だけであり、このことは歩くことで建築や様々なものを感じることにもつながる。
もしかしたら、情報量としても足は目に匹敵するかもしれない。ならば、モダニズムが目からの情報に頼っていたこと、ポストモダニズムも相変わらず目からの情報で差異を出そうとしていたことを考えれば、足からの情報に頼る建築は昔からあったけれど、まだまだ未開拓な部分があるのではないかと思ってしまう。
"Information from the feet"
When I am walking in the mountains and forests, my eyes are chasing trees, greenery and landscapes, but what part of my body I feel the most mountains and forests is my feet, especially through the soles of my feet. There is.
The feeling of the soles of the feet and the visual information that comes from the eyes combine to recognize the mountains and forests where we are. Therefore, the only part of the body that I actually feel is the legs.
Only the feet can feel something with their eyes closed, which also leads to the feeling of architecture and various things by walking.
Perhaps the amount of information is comparable to the eyes. Then, considering that modernism relied on information from the eyes, and postmodernism was still trying to make a difference with information from the eyes, architecture that relied on information from the feet has been around for a long time, but there is still more. I wonder if there are some undeveloped parts.
質感を触れずに感じるには視覚を頼ることになるが、それ以外の方法はないものかと思案中。
もうしかしたら、触れてはいるが触れている感じがない場合は視覚に頼ることなしに質感を感じることができている場合かもしれない。
それは足の裏、すなわち、床の質感は触れる意識が無く感じている。そう言えば、コルビュジエの建築は足の裏で感じていた。
"I feel it on the soles of my feet"
You have to rely on your eyes to feel the texture without touching it, but I'm wondering if there is any other way.
Perhaps if you are touching but not feeling touching, you may be able to feel the texture without relying on your eyesight.
It feels like the soles of the feet, that is, the texture of the floor, without being conscious of touching it. By the way, I felt the architecture of Le Corbusier on the soles of my feet.
質感にはイメージが刷り込まれている。逆に言えば、イメージから質感を連想し素材を決めることがある。
昔、20代の頃、イタリアンレストランの内装を設計施工した時に、イタリアには行ったことはあったが遊び半分だったので質感に意識が無く、素材選びには苦労した。
内装だけでイタリアンレストランの雰囲気を出すことは簡単だったが、いかにもイタリアという内装にはしたくはなかったので、雰囲気を言葉で言い換えながら、連想ゲームのようにイメージし、そこから思考して内装を決めていった。
イタリアンレストランに求められる内装デザインがあり、オーナーの要望があり、そこに自分のイメージを重ね合わせて中庸を取り、1つのイメージにしていった。
質感に刷り込まれているイメージは、誰にでもわかりやすく何かを伝えるには都合がいいが、都合がいいだけでは汎用な空間にしかならず、それだけは避けたかった。
"Image of texture"
The image is imprinted on the texture. To put it the other way around, the material may be decided by associating the texture with the image.
A long time ago, when I was in my twenties, when I designed and constructed the interior of an Italian restaurant, I had been to Italy, but I was playful, so I was not conscious of the texture and had a hard time choosing materials.
It was easy to create the atmosphere of an Italian restaurant with just the interior, but I didn't really want the interior to be Italian, so while paraphrasing the atmosphere in words, I imagined it as an associative game, and thought about it from there. I decided.
There was an interior design required for an Italian restaurant, and there was a request from the owner, and I overlaid my own image on it and took the middle ground to make it one image.
The image imprinted on the texture is convenient for telling something in an easy-to-understand manner to anyone, but just because it is convenient is only a general-purpose space, and I wanted to avoid that.
なかなか進まない状況にイライラしたり、気にしたりしていると気がつかないうちに時間だけが過ぎていて、その間何もしていないことに気づいて余計にイライラ、気にしたり。
どこかで進まない状況を知らないうちに一所懸命に人のせいにして、そのことすら気がつかずに、上手くいかないと嘆き、誤魔化すために美味しいものを食べたり。
時間読みが正解にできればいいのだが、人はそもそも未来を楽観的に考える生き物らしいので、ルーティンワークは別として、正解な時間を予測できないらしい。ならばそもそも予測しなくてもいい状況にすればいいと思った。
"Time cannot be predicted"
I was frustrated by the slow progress, and before I knew I was worried about it, only time had passed, and I realized that I wasn't doing anything during that time, which made me even more frustrated and worried.
Without knowing the situation where things aren't going on somewhere, I blame people so hard that I don't even realize it, lament that it doesn't work, and eat delicious food to deceive.
It would be nice if the time reading could be the correct answer, but since people seem to be creatures who are optimistic about the future in the first place, apart from routine work, it seems that the correct time cannot be predicted. Then I thought that I should make the situation so that I don't have to predict it in the first place.
質感についての質問を受けたので、簡潔に仕上げの表面の感じです、と答えた。たぶん的外れではないと思うのだが何故かしっくりとはこなかった。
質感は感じだから、あくまでも受け手の感じ方によるので正解は無いことになるが、それでは質感を完全にはコントロールできないので、「感じ」ではない何か違う言葉に置き換えたいと思った。
物質の質感は、物質を触る前に最初にどうしても目で追ってしまうので、触感よりも視覚が優位になる。だから、「感じ」という触らなくても言える言葉になり、それで丁度良いのかもしれないが。
では視覚に全く頼らない物質の質感は存在するのだろうか。存在すれば、物質の質感を「感じ」ではない言葉で表現できる糸口が見つかるかもしれないと思い、ずっと考えてはいるのだが、少なくともそれは写真には写らないものとしか思いつかない。
"Words that express texture"
When asked about the texture, he replied that it was a simple finish surface feel. I don't think it's off the mark, but for some reason it didn't quite fit.
Since the texture is a feeling, there is no correct answer because it depends on how the recipient feels, but since it is not possible to completely control the texture, I wanted to replace it with something different than "feeling".
The texture of a substance is inevitably followed by the eye before touching the substance, so the visual sense is superior to the tactile sensation. Therefore, it becomes a word that can be said without touching "feeling", and that may be just right.
Then, is there a texture of matter that does not rely on vision at all? If it exists, I think that I may find a clue that can express the texture of a substance in words other than "feeling", and I have been thinking about it for a long time, but at least I can only think of it as something that does not appear in photographs.
何か考え事をしていると、思い込みというバイアスに引きずり込まれ、あたかもそれが当たり前のように感じられ、新しい糸口に気付かずにとても後悔する時がある。
バイアスはついしてしまう。専門性が高ければ尚更で、疑うことすらしないので、だから後悔することになり、さらに自分に住み着いているように離れないので、何かきっかけがないとバイアスだと気がつかない。仮にバイアスだと気がついたとしても、排除すると違和感しかなく、排除したら何も無くなってしまうような気がする。
だから、バイアスを排除した後、一晩寝かせることにしている。時間を置くと排除した後の状態の違和感がやわらぐので、冷静に判断できるようになる。それでも違和感があれば排除しなければいい。
"Bias elimination"
When I'm thinking about something, I'm drawn into the bias of belief, and it feels like it's taken for granted, and sometimes I regret it very much without noticing a new clue.
There is a bias. It's even more so if you have a high degree of expertise, and you won't even doubt it, so you'll regret it, and you won't leave as if you're living in yourself, so you won't notice that it's a bias unless you have a chance. Even if I notice that it is a bias, I feel that if I eliminate it, I feel uncomfortable, and if I eliminate it, nothing disappears.
That's why I decided to let it rest overnight after eliminating the bias. After a while, the discomfort of the state after elimination will be softened, so you will be able to make a calm judgment. If you still feel uncomfortable, don't eliminate it.
昨日ダラダラしたから今日頑張ろうとすると、また同じようにダラダラしてしまって、いろいろ言い訳をして、また明日は頑張ろうなど思いつつ夜になる。
いろいろ言い訳して、言い訳がうまくなるだけで、ちっとも進まないから気分も優れないので、このままではいかんと明日の計画だけは立てて、よしこれならばと安心安心と眠りにつく。
もしかしたら、ダラダラしているのは何か歯車がズレはじめていておかしいからで、決して怠け心に勝てなかった訳ではないと考えると、明日の計画を立てるより今やっていることを見直した方がいいかもしれない。
"Sign of slapstick"
I was messing around yesterday, so if I try to do my best today, I'll be messing around again, making various excuses, and tomorrow I'll do my best again at night.
I make a lot of excuses, and I just get better excuses, and I don't feel good because I can't make any progress.
Perhaps it's because the gears are starting to shift and it's not that I couldn't beat my laziness, so it's better to review what I'm doing than to plan for tomorrow. It may be good.
イメージをするだけならば誰でもできるから、誰にでもできないようなイメージをしようとすると、つい行き過ぎて脱線し、全く違うことを考えていたりして、また戻ろうとするとまた脱線してしまう。
不思議なものでイメージなんだから、何をイメージしてもいいのだから、脱線しても、脱線した方が面白いからいいのに、ついつい脱線することに罪悪感を覚えてイヤな気分になることがある。
脱線したイメージは決して的外れではないが、当初に進もうとしていた方向とはズレている。ただ、ズレを修正する時に思いも寄らないことを考えつくことがあり、結果的にそれがイメージを推進する原動力になることがある。だから、脱線しても戻れば良いと思うようにしてイメージを転がすような感じでいつもいる。
"Rolling image"
Anyone can do it just by making an image, so if you try to make an image that no one can do, you will go too far and derail, thinking about something completely different, and if you try to return again, you will derail again.
It's a mysterious image, so you can imagine anything, even if you derail, it's better to derail, but you may feel guilty and unpleasant about derailing. be.
The derailed image is by no means off the mark, but it is not in the direction it was originally trying to move. However, when correcting a gap, you may come up with something unexpected, and as a result, it may become the driving force that promotes the image. Therefore, I always feel like rolling the image as if I should return even if I derail.
ものをつくる時に自然に頭の中で勝手に自分に都合のいいストーリーを流しまくっていて、ニヤニヤアブナイ奴になっているかもしれない。
まあ、しょうがないとあきらめながら、できそうもないことを考えているのが超楽しかったりする。
ただ、都合のいいストーリーも全く役に立たない無駄なことでもなく、そのストーリーには普段から気になっていることや問題意識が上手く溶け合って入り込んでいるので、そのストーリーの前提を考えたり、分解してみたり、言い換えたりしていると、これからつくろうとしているものに対してきちんとしたアプローチになり、いいアウトプットに結びつく結果になる。
"Leverage a convenient story"
When I make things, I naturally tell a story that suits me in my head, and I may be a grinning abnai guy.
Well, it's super fun to think about things that are unlikely to be possible while giving up if there is no help for it.
However, a convenient story is not a useless and useless thing at all, and since the story is well integrated with the things that you are usually worried about and the awareness of problems, you can think about the premise of the story and disassemble it. If you try or paraphrase it, you will have a decent approach to what you are trying to make, and the result will be good output.
真っ新な所から何かを考えはじめることが苦手なので、とりあえず何か仮のものをつくることにしている。
とりあえず何かあれば精神的に常に余裕を持ってその後を進めることができるので、何をやるのでも楽しく面白く、何事もハッピーになりやすい。
とりあえず何かをつくり、その後はそれに対してクリティカルに考えることを繰り返す。クリティカルに考えることでどんとん視点を変えていき、一番面白そうな方向へ展開していく。
リノベーションはそもそも最初からあるものに対して何かを付け加え変えていくことなので結果的にクリティカルになりやすい。新築の場合でもリノベーション的な思考は有効だと考えており、いつもとりあえず何かをイメージでつくり上げてから、それに対してクリティカルに考えるようにしている。
"Come one by one"
I'm not good at starting thinking about something from a brand new place, so I'm going to make something temporary for the time being.
For the time being, if there is something, I can always move forward mentally with a margin, so whatever I do is fun and interesting, and everything tends to be happy.
Make something for the time being, and then repeat thinking critically about it. By thinking critically, we will change our perspective and develop in the direction that seems to be the most interesting.
Renovation tends to be critical as a result because something is added and changed from the beginning. I think that renovation-like thinking is effective even in the case of new construction, and I always try to create something with an image and then think critically about it.
人の手が加わった自然の中に、すでにそれは自然とは言わないかもしれないが、身を置いているとよりリアルに自然を感じることができるような気がした。
不思議なもので全く人の手が入っていない自然に触れると、自然そのものを感じる前に、まず畏敬の念を抱き、自身の身の安全の確保を優先して、結局全く人の手が入らない自然に人の手を加えてから自然を感じることをする。
人も自然の一部だとしたら、それでも構わないと思うが、自然の本来の姿を知らずにそれを自然だと思い込み感じているようで、結局は全くの自然、真の自然は知ることができないものだと思った。
"True nature"
It may not be said that it is natural in the nature that has been modified by humans, but I felt that I could feel nature more realistically when I was in it.
When you come into contact with nature, which is strange and completely untouched by humans, before you feel the nature itself, first take awe, prioritize ensuring your own safety, and in the end, completely untouched by humans. Do not feel nature after modifying it naturally.
If people are also a part of nature, it's okay, but they seem to think that it is natural without knowing the true nature of nature, and in the end, it is possible to know the complete nature, the true nature. I thought it was impossible.
つくるためにあれこれ考えていると、必ず不確定なことにぶつかる。いつも同じことの繰り返しやいつも同じ人やいつものやり方の中にいればそのようなことは無いだろうが、必ず毎回新しい要素を入れるので、時には何十年も使い慣れた道具としてのCADを全く未知のものに変える時もあるので、定量的に作業が進まないこともある。
ただ、新しい要素を毎回入れていかいないと、過去に上手くいったやり方や思考を無意識に繰り返してしまい、そうすると、本来は毎回起こることが違うはずなのに、それに向き合わずに過去のやり方に固執して無理矢理当てはめるようなことをしてしまい、結果的にどこかに歪みが出る、大概は自分の中に歪みが出る。
だから、毎回真っ新に向き合い、その時最善の手段を取ろうとするから毎回変える。先日、10年以上ご無沙汰していた方と一緒に仕事をしたいと思い、その方に直接連絡した。久しぶりに声を聞いて時の経過を感じたが、かっちりと今回のプロジェクトにはまるような気がした。
"Change every time"
When I think about it to make it, I always run into uncertainties. It wouldn't happen if you were always repeating the same thing, always in the same person, or in the usual way, but because you always add new elements, sometimes CAD as a tool you've been used to for decades is completely unknown. Since there are times when it is changed to something else, the work may not proceed quantitatively.
However, if you do not add new elements every time, you will unknowingly repeat the methods and thoughts that worked well in the past, and if you do so, what will happen each time will be different, but instead of facing it, stick to the past methods I do something that I force myself to apply, and as a result, there is some distortion, usually in myself.
That's why I face new things every time and try to take the best measures at that time, so I change every time. The other day, I wanted to work with a person who had been absent for more than 10 years, so I contacted him directly. When I heard the voice for the first time in a long time, I felt the passage of time, but I felt like I was completely absorbed in this project.
自然に生成された空間を建築化したくなることがある。
人工的に生成する空間は必ずあるモデルを構築する必要があり、それは自然に生成された空間でも大体同じようことなのだが、モデルの精度、複雑さが人工的に生成されたものより自然に生成されたものの方が圧倒的に精度が高く、複雑さの度合いもケタが違う。
人工の空間は自然の空間の足元にも及ばないから、素晴らしい自然の空間に畏敬の念を抱くのかもしれない。ただ、つくり手としてはそこで終わらせたくなく、建築化したくなる。
"Architecture of nature"
Sometimes you want to build a naturally created space.
It is necessary to build a certain model for the artificially generated space, which is almost the same in the naturally generated space, but the accuracy and complexity of the model are generated more naturally than the artificially generated one. The ones that have been made are overwhelmingly more accurate, and the degree of complexity is also different.
Since the artificial space does not reach the foot of the natural space, you may be in awe of the wonderful natural space. However, as a creator, I don't want to end there, I want to build it.
今まで見たことがないような建築や空間を生み出したいと思う一方で、これを建築化したら素晴らしいものになるというものにも出会うこともある。
勝沼のワイナリー巡りをした際に、ワイナリーには葡萄畑が併設されており、その葡萄の房が棚状に実る下の空間が構築的にみたらとても面白い空間であり、ただこれを建築化するのは難しいが、是非建築化してみたいと思った。
写真では上手く表現できないのだが、一見不規則に見え、実際は規則的に並ぶ人工物が木の幹と枝の自然物を上手くコントロールして空間を構築しており、天井面の枝と葉が空隙を不規則につくり、そのため木漏れ日が空間に複雑性を足す。棚にテンションをかけるための斜めの柱の配置も面白い。
意図して建築化した訳ではないのに面白い空間になっている、特に自然による造形や空間にはまだまだ建築の世界では発見されていない、まだ見ぬ新しい世界がたくさん存在していることだろう。
"Undiscovered space"
While I want to create architecture and spaces that I have never seen before, I also come across things that would be wonderful if they were built.
When I visited Katsunuma's winery, a vineyard was attached to the winery, and the space underneath where the bunches of grapes grow like shelves is a very interesting space when viewed constructively, just to build it. It's difficult, but I definitely wanted to build it.
Although it cannot be expressed well in the photograph, it looks irregular at first glance, and in reality, the regularly arranged artificial objects control the natural objects of the tree trunk and branches to create a space, and the branches and leaves on the ceiling surface create gaps. Created irregularly, so sunbeams add complexity to the space. The arrangement of diagonal pillars to apply tension to the shelves is also interesting.
It is an interesting space even though it was not intentionally constructed, especially in the natural modeling and space, there are many new worlds that have not been discovered in the architectural world yet. ..
都市との関係性、変わりゆく景観との関係性をもっとチャンクダウンしていく必要を感じる。
どこにでもあり気づいていない中に関係性を物語るものがあり、それに触れるだけで一気に関係性が浮き彫りになり、関係性を左右することになるものを探す。
それをもっとわかりやすく、もっと平易に、もっと引っ掛かりがないような言葉で表現することが重要で、それができてはじめて建築という形にする準備ができる。
"Preparation for architecture"
I feel the need to further chunk down the relationship with the city and the changing landscape.
There are things that are ubiquitous and unnoticed that tell the relationship, and just by touching it, the relationship becomes apparent at once, and we look for something that influences the relationship.
It is important to express it in words that are easier to understand, simpler, and less entangled, and only then can we be ready to take the form of architecture.
意識して都市の変わりゆく景観とつながりを持ちながら建築を考えることは、建築に建築以外の他者性を取り入れることになり、一個の建築について考えていただけでは到達できないようなものを出現させる原動力になる。
変わりゆく景観の中から何を抽出するのか、その景観やその場所の何が異所、異空間だと思うのか、過去現在未来とつなぐ時間軸の中でどこに焦点を当てるのか、または時間の流れに対して何ができるのか、などを考えていく過程で一個の建築計画に幅と奥行きが与えられる。
"Landscape as another person"
Thinking about architecture while consciously connecting with the changing landscape of the city means incorporating otherness other than architecture into the architecture, and is the driving force for the emergence of things that cannot be reached by just thinking about one architecture. become.
What to extract from the changing landscape, what to think of the landscape and its place as a different place, a different space, where to focus on the time axis connecting the past, present and future, or the flow of time In the process of thinking about what can be done for one building plan, width and depth are given.
目が疲れるくらいに都市と視覚でつながっているので、様々な広告や情報に晒され、知らないうちに翻弄され、制御できれば良いのだが大概は制御することなどできず、制御する術を知らず、さらに目が疲れクラクラしてくることがある。
視覚で都市とつながろうとしなければ、目が疲れることもないが、視覚以外の感覚で都市とつながる術を知らない人がほとんどかもしれない。
都市とのつながり方で視覚ではなく触覚でつながることは可能性であり、その場合、建築が貢献できることはたくさんある。
触覚とは、例えば歩くことで足の裏で都市の起伏を感じたりすることである。視覚を通して触覚を感じることもできるが、視覚を除去して直に触覚で感じた方が翻弄するような情報をカットできる。その時、建築は歩くというアクティビティを通して都市とつながることを容易にする。
"Architecture that connects with the city"
Since I am visually connected to the city so much that my eyes get tired, I am exposed to various advertisements and information, and I wish I could control it without knowing it, but most of the time I can not control it, I do not know how to control it. In addition, my eyes may get tired and irritated.
If you don't try to connect to the city visually, your eyes won't get tired, but most people may not know how to connect to the city with a sense other than vision.
It is possible to connect with the city by touch rather than by sight, and in that case, architecture can contribute a lot.
Tactile sensation means, for example, walking to feel the undulations of the city on the soles of the feet. It is possible to feel the sense of touch through the sense of sight, but it is possible to cut out information that is tossed by the person who feels the sense of touch directly by removing the sense of sight. At that time, architecture facilitates connection with the city through the activity of walking.
利便性は視覚に訴えてくる。目まぐるしく利便性が駆り立ててくる。利便性と適当な距離を取りたいのに、何が効率的で何が早いかを勝手に知らせてくる。都市には利便性の良さを訴えるものに溢れている。すでに麻痺して気づいていないものもたくさんある。
利便性が都市を特徴づけるならば、視覚と利便性がつながることは、視覚と都市がつながっていることでもあり、その関係性が行き過ぎると人は何かに駆り立てられるように都市に居づらくなる。
視覚で都市とつながることを遮断し、視覚以外の感覚で都市とつながることを考えてみる。そのためにはまず視覚に訴えてくる利便性との遮断が必要であり、それは日々の生活の中での影響が大きいかもしれないが、視覚以外の感覚で都市につながることに建築は貢献できるかもしれない。
"Connecting to the city other than vision"
Convenience is visually appealing. Convenience is driven at a dizzying pace. You want to be convenient and at a reasonable distance, but you will be informed of what is efficient and what is fast. The city is full of things that appeal to convenience. There are many things that are already paralyzed and unnoticed.
If convenience characterizes a city, the connection between vision and convenience is also the connection between vision and city, and if the relationship goes too far, it becomes difficult for people to stay in the city so that they can be driven by something. ..
Think about connecting to the city with a sense other than the visual sense, blocking the connection with the city visually. For that purpose, it is first necessary to cut off from the convenience that appeals to the eyes, which may have a great influence on daily life, but architecture may contribute to connecting to the city with a sense other than the eyes. unknown.
都市の利便性を象徴するものはやはり交通網だろう。鉄道網に道路網と今だに公共工事で日本全国で少しでも便利になるように拡張が行われており、人と物の移動をいかに容易にするかが今だに問題になり、それが全て揃っているのが都市である。
利便性は大事だが行き過ぎた利便性は人を物として扱うようなもので、少しも人のためにならないのだが、利便性は加速するばかりで人はどんどん置いていかれ着いていけなくなっている。
それを回避するには利便性とある程度の距離を取り、利便性を人が自ら上手に調整できようにすれば良く、そのためにはひとつは交通網との関係性を見直すことが大事であり、その見直しの過程で建築が貢献できることがたくさんあるような気がしている。
"Convenience and distance"
The transportation network will symbolize the convenience of the city. The railroad network, the road network, and public works projects have been expanded to make it even a little more convenient throughout Japan, and how easy it is to move people and things is still a problem. The city has everything.
Convenience is important, but excessive convenience is like treating a person as a thing, and it does not benefit people at all, but convenience is only accelerating and people are being left behind and unable to reach it.
To avoid this, it is only necessary to keep a certain distance from the convenience so that people can adjust the convenience well, and for that purpose, it is important to review the relationship with the transportation network. I feel that there are many things that architecture can contribute to in the process of reviewing it.
利便性が無く効率的でない都市を想像してみる。そもそも利便性が悪く効率的でない場所を都市というかは疑問が残るが、実際に存在する可能性があるかどうかは別にして想像してみる。
上手くなかなか想像できないのが面白い。
あえてクネクネした道、あえて水辺に降りて行く、あえてアップダウンをそのままに、あえて低くく低密度で、あえて偏りをつくったり、そうかと思うとバラバラにシャフルして関係性を切ってみる。
せっかく出来上がった高効率高密度な都市、利便性の高い都市に向き合うと、関係性を一度切り、新たな関係性を築くことで行き過ぎた利便性から離れて、都市に居たいと思わせるものを築くことができるような気がして、その過程で今まで気づいていなかった都市の魅力がわかるかもしれないと思った。
"Cut the relationship once"
Imagine a city that is inconvenient and inefficient. It is doubtful that a city is a place that is inconvenient and inefficient in the first place, but let's imagine whether it may actually exist.
It's interesting that I can't imagine it well.
I dare to go down to the waterside, dare to go down to the waterside, dare to keep the ups and downs, dare to create a bias with low and low density, and when I think so, shuffle them apart and cut the relationship.
When you face a highly efficient, high-density city or a highly convenient city, you can break the relationship once and build a new relationship to get away from the excessive convenience and make you want to stay in the city. I felt like I could build it, and in the process I thought I might discover the charm of a city that I hadn't noticed before.
都市の利便性は都市のルールと結びついている。利便性は何か単体では実現することはできず、相互に関連づけられたつながりから生まれる。その関連づけられたつながりを相対的にみれば都市のルールといえる。
ルールがひとつでもは破綻したら利便性が損なわれるような状態では都市としては脆弱だが、案外どこの都市も、東京も脆弱なような、雪が降ったら機能麻痺を起こすし、それ程都市は、都市の利便性は薄氷だが、利便性は損なわれない、むしろこれからもっと便利になり利便性が上がる前提で都市は成り立っている。
大きな全体としての都市の部分としての建築を考える時はこの前提に抗えないし、自然と染まってしまう。それも都市のルールなのだが、ルールから外れることで利便性とは一線を画した建築ができないかと考えている。
"Out of the rules"
City convenience is tied to city rules. Convenience cannot be achieved by itself, but comes from interconnected connections. If you look at the related connections relatively, it can be said that it is a rule of the city.
It is vulnerable as a city in a state where even one rule breaks down and convenience is impaired, but unexpectedly every city and Tokyo are vulnerable, and when it snows, it causes functional paralysis. Convenience is thin ice, but convenience is not impaired, but rather the city is built on the premise that it will become more convenient and more convenient in the future.
When considering architecture as a part of a large city as a whole, this premise cannot be resisted and it is naturally dyed. That is also a rule of the city, but I am wondering if it is possible to build a building that is different from convenience by deviating from the rule.
都市から利便性が無くなったらと考えてみると、都市としての魅力が半減するかどうかという考えが思い浮かんだ。そのくらい、都市の魅力は利便性にあると考えている。もちろん都市の魅力は利便性だけではないが、全ての魅力が利便性に集約されるのではないかと思ってしまう。
利便性のひとつは交通網かもしれない。特に鉄道の恩恵は日々感じる。勝手なイメージだが、地下鉄も含め鉄道による移動だけである程度済ますことできる街が都市と呼べるような気がする。
人も物も移動に関わる労力とコストは膨大であり、それが軽減できる場所が都市だから人も物も集中するのだろう。
利便性を手放すのは無理かもしれないが、すでに私たちの生活は利便性という指標で常に、見えないところでも、測られているので、しかし、利便性が無くても都市に居たいと思わせる何かがあるのは確かなような気がするので、それが文化とは安直にはいわないが、それを建築化してみたい。
"Make me want to stay in the city"
When I thought about the loss of convenience from the city, I came up with the idea of whether the attractiveness of the city would be halved. I think that the attraction of the city lies in its convenience. Of course, the charm of the city is not only convenience, but I think that all the charms are concentrated in convenience.
One of the conveniences may be the transportation network. In particular, I feel the benefits of railways every day. It's a selfish image, but I feel that a city that can be moved to some extent by rail, including the subway, can be called a city.
The labor and cost involved in moving people and goods is enormous, and since the place where it can be reduced is a city, people and goods will be concentrated.
It may not be possible to let go of convenience, but already our lives are always measured in the invisible area by the index of convenience, but we want to stay in the city even if it is not convenient. I'm sure there's something to do, so I'm not saying it's a culture, but I want to build it.
都市に階層性は様々あるが、交通インフラが先にできて優先される状況はある意味ではどこの都市でも起こり得る代表的な階層性ではないだろうか。
都市の都市たる所以は交通インフラが整備されていることであった。ビジネスにしても、学業にしても、生活をするにしても頻繁に移動が伴うので、交通インフラが整備されている方が便利で効率良く広範囲に動けて、そのおかげで成果が出るから都市に人が集まり、人が集まると自然と文化が生まれるという相乗効果も都市にはあり、だから人が今までは都市に集中する結果となった。
しかし、ビジネスも学業も生活も同じ場所に留まり全てがまかなえ、頻繁に移動しなくて済む状況に変化すると、今までのような交通インフラは必要では無くなった。そうすると、都市の都市たる所以が無力化してしまい、もはや人が都市にいる意味は他に行き場が無いだけの理由になってしまったかもしれない。
それこそ、ドローンで人流も物流もまかなえるならば、交通インフラそのものが必要無い。あまりにも極端な話かもしれないが、その時仮に住む場所を自由に選択できるならば、もしかしたらその時点で「都市」という存在自体、「都市」という言葉自体が消滅しているかもしれないが、それでも都市にいるだろうか、都市に魅力を感じるだろうか。
魅力を感じるとしたら、すでに今あるもの、あるいは過去への郷愁に対してだけであり、その時点では未来に対しては何もないかもしれない。どこかで交通インフラが優先される都市構造から脱する必要があるのだろうが、それでも成り立つ都市、人が集まる都市が存在しているとしたら、人を都市につなぎ止めるものは何だろうかと考えてみる。
人はそんなに簡単には変われないので、答えがあるならば、きっとその答えの種はすでに今あり、ただ何も効力を発揮していなくて、気づかれてもいないものだろう。探し出すにはとりあえず都市をメタ的に見て、ムダではあるが、地方には無いものを探してみる。
"Attractiveness of a city that gathers people"
There are various hierarchies in cities, but in a sense, the situation where transportation infrastructure is created first and prioritized is a typical hierarchy that can occur in any city.
The reason for being a city is that the transportation infrastructure is in place. Whether it's business, school, or living, you often move around, so it's more convenient and efficient to move over a wide area if you have a well-developed transportation infrastructure. Cities also have the synergistic effect of gathering people and creating culture naturally when people gather, which has resulted in people concentrating on the city until now.
However, when business, school, and life stayed in the same place and everything was covered, and the situation changed so that people did not have to move frequently, the transportation infrastructure that they used to have became unnecessary. Then, the reason why the city is a city is incapacitated, and the meaning of people being in the city may have become the reason that there is no other place to go.
That's why if a drone can handle both human flow and logistics, there is no need for transportation infrastructure itself. It may be a very extreme story, but if you can freely choose the place to live at that time, the existence of "city" itself and the word "city" itself may have disappeared at that time. Are you still in the city or are you attracted to the city?
The only attraction you may find is for what you already have, or for nostalgia for the past, and at that point there may be nothing for the future. It may be necessary to break away from the urban structure where transportation infrastructure is prioritized somewhere, but if there is a city that still holds, and a city where people gather, wondering what keeps people in the city. View.
People don't change so easily, so if there's an answer, I'm sure the seeds of that answer are already there, just ineffective and unnoticed. To find out, look at the city meta-wise, and look for something that is wasteful but not found in rural areas.
建築が建つかどうかは法規的には土地が道路に接しているかによるので、都市部では建築と道路はセットで考える場合が多い。大体が土地に対して道路がどの方位で接しているかが計画に結構大きく影響を与える。
鉄道の高架化により風景が変わる時、事業の進捗具合によっては立ち退きによる道路付け替えよりも先に建築物ができる場合がある。道路の位置は決まっているが雑草生い茂る場所を道路に見立てて計画をする。何ともイメージしづらいが、この状況で良い環境を実現するには何をしたら良いのかを考えている。
"Looking at the weedy place"
Whether or not a building is built depends on whether the land is in contact with the road, so in urban areas, the building and the road are often considered as a set. In general, the direction in which the road touches the land has a considerable effect on the plan.
When the landscape changes due to the elevated railway, depending on the progress of the project, the building may be built before the road replacement due to eviction. The location of the road is fixed, but the place where weeds grow is likened to a road when planning. It's hard to imagine, but I'm thinking about what to do to realize a good environment in this situation.
都市の形成にはざっくりした順序があり、まずは大きな通り、道や鉄道が敷かれ、さらに細分化するように道がつくられ、通りと道に囲まれた場所を公共施設用地や私有地にしていき、最終的にはそこに建築物ができる。
まず交通インフラが先に出来上がる。都市は単独では成り立たず、人流にしても、物流にしても、他の都市とのつながりが重要であり、人流や物流は人で例えたら血液であり、血液が流れるから人は生きられるように、人も物も流れないと都市は生きられない。
だから、都市の形成ではまず流れを確保する。だが、時としてその順序が逆になる。建築物が先にでき、あとから道がつくられることがある。流れるところは決まっているのだが、流れができる前に建築物ができる。
建築は道という流れが存在しなくても成り立つのだろうか、その時の建築は流れがある場合と比べて何が違うのか、などと考えていると都市と建築の関係性で固定されてた部分が動き出す。
"Architecture first"
There is a rough order in the formation of cities, first large streets, roads and railroads are laid, roads are made to be further subdivided, and the places surrounded by streets and roads are made into public facility land or private land. , Eventually there will be a building there.
First, the transportation infrastructure is completed first. A city cannot be established by itself, and it is important to connect with other cities regardless of whether it is human flow or physical distribution. The city cannot live without the flow of people and things.
Therefore, in the formation of a city, first secure the flow. But sometimes the order is reversed. Buildings may be built first and roads may be built later. The place where it flows is decided, but the building is built before the flow is made.
When thinking about whether architecture can be established without the flow of roads, and what is the difference between architecture at that time compared to the case where there is a flow, the part fixed by the relationship between the city and architecture. Starts to move.
自由に創作するためにわざと制約を設ける。全くの自由では次にすることは制約を求めることだから創作に向かわなくなる。制約から自由になるために創作に意識が向く。創作のコツは制約を設定することであり、制約を別の言い方をすれば、常識、慣習、課題かもしれない。要するに全くの自由な創作というのはそもそも成り得ないということであり、それを逆の状況から言えば、常に創作の種となる制約は身近にある訳だから、捉え方しだいで創作がいつでもできるということである。
"Create"
Constraints are intentionally set to create freely. With total freedom, the next thing to do is to seek constraints, so you will not be able to create. Being conscious of creation to be free from restrictions. The knack of creation is to set constraints, which in other words may be common sense, customs, or challenges. In short, completely free creation is impossible in the first place, and from the opposite situation, there are always restrictions that are the seeds of creation, so you can always create depending on how you think about it. That is.
出どころが見えない、ブラックボックス化されたものは自然と人の想像力を喚起する。ブラックボックスの内部に興味があればある程知りたくなる。
見せないということもデザインのうちかもしれない。デザインの発露がわからないだけで興味が湧く。そもそも建築はできあがったものの結果で判断をされるので、発露がわからなくても良いのだが、人は想像を超えたものを見せられた時、自分の中で辻褄を合わせるために自然となぜそうなるのかを知りたくなり、納得せずにはいられない。その時に知りたいことがブラックボックス化されていたら、余計に印象に残る。故に見せないことも大事になる。
"Black box"
The black-boxed ones, whose source is invisible, naturally arouse the imagination of people. The more you are interested in the inside of a black box, the more you want to know.
Not showing it may be part of the design. I am interested just because I do not understand the appearance of the design. In the first place, the architecture is judged based on the result of the finished product, so it is not necessary to know the dew, but when a person is shown something beyond imagination, why so naturally to match the tsuji in himself. I want to know if it will be, and I can't help but be convinced. If what I wanted to know at that time was black-boxed, it would be even more impressive. Therefore, it is important not to show it.
あまりに小さい部分は消滅してしまうかもしれない危険性があるが、たくさん集まれば強固な全体をつくることができるはずであり、全体をつくることができれば、あまりに小さい部分が故にフレキシブルな動きや対応が可能になる。
部分と全体という分け方の中で階層性を設けないようにするならば、並列に分ければ良いのだが、並列でも分けた部分のスケールによって方向性や積層性が生まれ、それが階層性につながる場合がある。
全く階層性がなく部分に分けるには、部分を極端に小さくし、スケールの差に意味が無くなるようにすれば良いが、その場合はあまりに部分が小さくなり過ぎるので、部分の扱いが煩雑になり、全体をつくる難易度が上がる。
いずれにせよ、部分を極端に小さくすれば良いとなると建築の規模の大小に関係無く、独立した部分が機能を担保し、その部分が並列に並び、その並列に並ぶ部分の集合した様を建築として形づくることができる。
"The part is extremely small"
There is a risk that too small parts may disappear, but if you gather a lot, you should be able to make a strong whole, and if you can make the whole, flexible movement and correspondence because of too small parts It will be possible.
If you do not want to create a hierarchy in the division of parts and the whole, you can divide it in parallel, but even in parallel, the scale of the divided parts creates directionality and stackability, which leads to hierarchy. In some cases.
In order to divide the parts into parts without any hierarchy, it is sufficient to make the parts extremely small so that the difference in scale becomes meaningless, but in that case, the parts become too small and the handling of the parts becomes complicated. , The difficulty of making the whole goes up.
In any case, if the part should be made extremely small, regardless of the scale of the building, the independent part guarantees the function, the part is lined up in parallel, and the part that is lined up in parallel is assembled. Can be shaped as.
機能が階層構造になっていて全体がつくられる建築よりも独立した部分が機能を担保し、その部分が並列に並び、その並列に並ぶ部分の集合した様が建築として形づくられる方が面白いと考えているが、そのような建築はある程度の規模がないと難しいかもしれない。
しかし、部分の捉え方などにより規模とは関係なしに実現できないかと考えてみる。
規模が小さいということは部分も自ずと小さくなる。部分が小さい故に、部分に当てはまりそうな規模をヒントに部分を捉え直してみる。そうして部分を捉えることができれば、全体としての建築が自ずと見えてくる。
"Small part and whole"
I think that it is more interesting to form an architecture as an independent part that guarantees the function, and that part is lined up in parallel, and a collection of the parts that are lined up in parallel is formed as an architecture, rather than an architecture in which the function is hierarchical and the whole is made. However, such architecture may be difficult without a certain scale.
However, let's think about whether it can be realized regardless of the scale, depending on how to grasp the part.
The fact that the scale is small naturally means that the part is also small. Since the part is small, I will recapture the part with a hint of the scale that seems to apply to the part. If you can grasp the part in that way, you can see the architecture as a whole.
誰にでも想いがあり、それを背負う部分が必ずあり、それをどのように扱い建築化やデザイン化していくのかが毎回工夫のしどころであり、その時恣意的に想い入れに促して対処するのがもしかしたら普通には一般的には受け入られやすいのかもしれないが、それでは建築としてデザインとしては何も表現できていないことと等しいので、もう少しメタ的に考えて一般解として通用するような解決策を模索する。
想いも元を辿れば共通認識につながり、今度はその共通認識の直接的な解決策を用いて建築がつくられる場合が多いが、その時に共通認識自体を疑うことをする人はほとんどいない。疑いの中にまだ見たことがない建築のヒントがあり、それは次の時代の建築の可能性につながり、同時にそれは想いを最大限に受け止めることにもつながる。
"Solution of feelings"
Everyone has a feeling, and there is always a part to carry it on their backs, and how to handle it and build and design it is the point of ingenuity every time, and at that time it is necessary to arbitrarily encourage the feelings and deal with it. Perhaps it is usually easy to accept, but that is equivalent to not being able to express anything as a design as an architecture, so a solution that can be considered as a general solution with a little more meta-thinking. Seeking a plan.
If you trace the origin of your thoughts, it will lead to a common understanding, and in many cases, architecture will be created using the direct solution of that common recognition, but at that time, few people doubt the common recognition itself. In doubt, there are architectural hints that I haven't seen yet, which leads to the possibilities of architecture in the next era, and at the same time, it also leads to the maximum acceptance of thoughts.
「暮らし」の中から何かを抽出して建築化する場合、抽出したものはとても小さく、断片的なことかもしれず、とても建築全体を形成するには物足りず、それはただの部分に過ぎないかもしれない。いや、あくまでも「暮らし」の中から何かを抽出して建築化する場合は抽出したものは部分に留めておく必要があり、部分だとして、決してそれで建築全体を形成してはいけない。
「暮らし」の中から抽出したものだけで建築全体を形成してしまうと、建築は単なる生活用品でしかなくなる。確かに、生活用品たる建築に溢れていて、建築は生活用品だとする方が大勢かもしれないが、建築が生活用品では中で暮らしている人は生活用品の一部としての振る舞いしかできないし、生活用品という物が中心の生活になる。
物が中心より、そこで起こる出来事を中心にした建築の方が、今この不自由な生活の中で何が困るかと言うと、物は何でも手に入るが、起こるはずの出来事が起こらないことであり、出来事を通して生まれるはずのコミニケーションが生まれないことであり、それは人を疲弊させる。
今この瞬間に求められる建築は出来事をつくり出す建築であり、それは「暮らし」以外のところと建築が結びついてはじめて実現可能となるだろう。
"Architecture that creates events"
When you extract something from "living" and build it, the extraction is very small and may be fragmentary, very unsatisfactory to form the whole architecture, it is just a part. Maybe. No, if you want to extract something from "living" and build it, you need to keep the extracted part in the part, and even if it is a part, you should never form the whole architecture with it.
If the entire architecture is formed only from the "living", the architecture is nothing more than a daily necessities. Certainly, there are many people who think that architecture is a daily necessities because it is full of daily necessities, but people who live in architecture can only act as a part of daily necessities. , Living goods will be the main life.
The problem with architecture centered on the events that occur there rather than the center of things is that you can get anything, but the events that should happen do not occur. Yes, there is no communication that should be born through events, which exhausts people.
The architecture required at this moment is the one that creates the event, and it will be feasible only when the architecture is connected with the place other than "living".
建築が建築以外のことと結びついて存在したら建築としての価値は半減するのだろうか。
例えば、住宅の場合だと、建築とは関係がないことで満載であり、それを一言で言えば「暮らし」かもしれないが、建築は単なる箱、容れ物で、中身は建築とは関係がない「暮らし」で満たされていると考えた場合、「暮らし」に合わせた建築が登場する。
その場合の建築は純粋な意味での建築ではなく、「暮らし」の一部、「暮らし」に括られたものになる。その時の建築は純粋な意味での建築の価値を越えるだろうか。それは「暮らし」の中から何を抽出して建築化するかによるだろう。
"Architecture of living"
Will the value of architecture be halved if it exists in connection with something other than architecture?
For example, in the case of a house, it is full of things that have nothing to do with architecture, and in a word, it may be "living", but architecture is just a box, a container, and the contents are related to architecture. If you think that you are filled with "living" that does not exist, architecture that matches "living" will appear.
The architecture in that case is not a pure architecture, but a part of "living", "living". Will the architecture at that time exceed the value of architecture in the pure sense? It will depend on what is extracted from "living" and built.
輪郭は建築の外形をなぞるが、人の意識に浮かぶ形もなぞる。両方が一致する場合は輪郭が人の意識にそのまま思い浮かぶ。輪郭を創造する側は一致させようとする。それは当たり前だが、はじめから一致させるのを止め、人の意識に現れる形を輪郭とは別の形、その形はコントロールしない、人の意識に任せてしまうようなやり方をしてみる。
意識に思い浮かぶ形までコントロールするのがデザインだとしたら、デザインすることを放棄することになるかもしれない。
"Design abandonment"
The outline traces the outer shape of the building, but it also traces the shape that comes to human consciousness. When both match, the outline comes to mind as it is in human consciousness. The side that creates the contour tries to match. It is natural, but I will stop matching from the beginning and try to make the shape that appears in human consciousness different from the outline, do not control the shape, and leave it to human consciousness.
If design is about controlling the shape that comes to mind, you may abandon designing.
建築の輪郭自体は、建築そのものがつくり出すので、他からの影響は無く、建築自体の形がどうあるかが重要であり、それだけのような気がするが、もし建築の輪郭が他からの影響で変わることがあるとしたら何があるだろうかと考えてみた。
ひとつは輪郭自体は変わらないが、それを見る人の認識が様々に変化して、受け取る輪郭の像に変化が起こることは考えられる。意識が様々に変化するのは、まず人によって受け取り方が違うからであり、それはそもそもどのようにでも受け取れるからである。
ではそのような建築が今まで存在したことがあったかというと、歴史を紐解けば、有機的な輪郭、動植物的な輪郭などをした建築は存在した。その場合、受け取る側の見方や意識によって輪郭はいろいろな見え方をしただろう。
"The contour changes"
Since the outline of the architecture itself is created by the architecture itself, there is no influence from others, and it is important how the shape of the architecture itself is, and I feel that it is the only thing, but if the outline of the architecture is influenced by others. I wondered what would happen if it could change.
One is that the contour itself does not change, but it is conceivable that the perception of the viewer will change in various ways, and the image of the contour received will change. The reason why consciousness changes variously is that each person receives it differently, because it can be received in any way in the first place.
Then, if such architecture has ever existed, if we look at history, there were architectures with organic contours, animal and plant contours, and so on. In that case, the outline would look different depending on the perspective and consciousness of the recipient.
屋根は間近では見えないが、離れた所からは良く見える。離れれば細部はボヤけ、空との境界線である輪郭が際立つ。輪郭は頂部の形であり、屋根がつくり出す。屋根はアイコンのように、その輪郭が建築の種類を表す。屋根が無い建築もあるが、頂部の輪郭は存在する。建築ばかりではない、高速道路も、鉄道の軌道も地上を走っていれば輪郭はある。
意外と輪郭に無頓着なのではないだろうか。
外観の仕上げにはこだわるかもしれないが、輪郭にはこだわらない。仕上げなどの細部は離れればわからないのに、輪郭は離れていてもわかるのに大事にしない。色や高さや緑など景観を良くするためのコードはあるのに、輪郭についてのコードはない。
敷地境界線を越えて影響力を与えようとしたら、離れたところから価値判断をするものに注視すれば良く、輪郭はひとつの価値判断をする指標になるだろう。
"Outline crosses the boundary"
The roof cannot be seen up close, but it can be seen well from a distance. If you move away, the details will be blurred, and the outline that is the boundary with the sky will stand out. The contour is in the shape of the top, created by the roof. The outline of the roof, like an icon, represents the type of architecture. Some buildings do not have a roof, but the contours of the top are present. Not only architecture, but also highways and railroad tracks have contours if they run on the ground.
Isn't it surprisingly indifferent to the contours?
You may be particular about the finish of the appearance, but not the outline. I don't care about the details such as the finish, even if they are separated, even if they are separated. There are codes for improving the landscape such as color, height and green, but there is no code for contours.
If you want to influence beyond the boundaries of the site, you can look at the ones that make value judgments from a distance, and the outline will be an index for making one value judgment.
スカイラインの中にそっと挿入するようなイメージをいつも抱く。都市の中では既存の建築によって出来上がっているスカイラインが存在し、それは日常の風景であり、ある日突然建造物が立ち上がった時の違和感は見慣れたスカイラインが変わったことによる。
空が塞がれたり、風景を遮断したり、何か建築が立ち上がる時は同時に何かの障害になる場合がある。
しかし、新たに建築をスカイラインにそっと挿入することにより、違和感の後にくる新しさが風景をアップグレードさせることになるように考え計画している。
"New skyline"
I always have the image of gently inserting it into the skyline. In the city, there is a skyline created by existing architecture, which is an everyday landscape, and one day when a building suddenly stands up, the feeling of strangeness is due to the change in the familiar skyline.
When the sky is blocked, the landscape is blocked, or when some architecture stands up, it can be an obstacle at the same time.
However, by gently inserting the new architecture into the skyline, we are planning to think that the newness that comes after the discomfort will upgrade the landscape.
圧倒的にスケールが大きい都市計画に対して、圧倒的にスケールが小さい建築計画で何がてきるかを考えてみると、少なくとも大きいものに飲み込まれてしまうのではなく、波紋が広がるように敷地境界線を越えて影響を与えることかもしれないと思った。
小さなひとつの建築が影響を持って周辺環境の雰囲気を変えることは良い例か悪い例かは別にしてある。その時の建築はやはり自律した強度が強い建築である場合が多い。つまり、主張が強く、何かを単独で強く表現している。
ただ、そういう自律した建築は段々と疲弊をしてくることも事実である。主張の強さ、表現の強さはいずれ慣れるか時代にそぐわなくなる。その時の建築の強さは違和感しかなく、むしろ主張の強さ、表現の強さが行き詰まり感を出す。
敷地境界線を超えて与える影響力の源は自律の強さだけだろうか。影響力など無くても良いとなるとまた別の話だが、自律以外、それは他律で自律以上の影響力を出すことを考えてみると、周辺環境との関係性でまた別の視点が持て、新たな関係性が生まれるような気がする。
"Influence of small architecture"
Considering what will come from an overwhelmingly small-scale architectural plan as opposed to an overwhelmingly large-scale city plan, at least the site will spread ripples rather than being swallowed by the larger ones. I thought it might affect me beyond the boundaries.
It is a good example or a bad example that one small building has an influence and changes the atmosphere of the surrounding environment. The architecture at that time is often autonomous and strong. In other words, he has a strong assertion and expresses something strongly by himself.
However, it is also a fact that such autonomous architecture is gradually exhausted. The strength of assertion and the strength of expression will eventually become unsuitable for the times. The strength of the architecture at that time was only uncomfortable, but rather the strength of assertion and the strength of expression gave a sense of impasse.
Is the strength of autonomy the only source of influence beyond the boundaries of the site? It is a different story when it is not necessary to have influence, but when considering that it exerts more influence than autonomy by heteronomy, it has a different perspective in relation to the surrounding environment. I feel like a new relationship will be born.
延々と続く雑草が生えた緑の地面とアスファルトに、脇の線路、そして続く頭上の空がすでに風景として慣れ親しんだものになっているが、ここから今の風景の面影もないくらいに変わる。
その変わる局面のまだまだ初期の段階で新しい建築を挿入する。変わる領域と残る領域の境目に、そして、時間の境目に割り込むように挿入する。
変わらずに強い強度で建ち続けるか、変わりゆく風景の中で順応していくか。生物の進化の過程を紐解けば順応になるので、なるべく息長く建ち続けてもらうには順応しかない。
"Adapt"
The endless weedy green ground and asphalt, the railroad tracks on the sides, and the sky above us are already familiar to us as a landscape, but from here it changes to the point where there is no sign of the current landscape.
Insert new architecture in the early stages of that changing phase. Insert it so that it interrupts the boundary between the changing area and the remaining area, and the boundary of time.
Whether to continue to build with strong strength without change, or to adapt in the changing landscape. If you unravel the evolutionary process of living things, you will become acclimatized, so there is no choice but to adapt to have them continue to build for as long as possible.
枠の中にある枠の中のように段々と限定され狭まることにより、周りからより切り離され、そこだけが浮かび上がり、ただそこは奥の奥、人の目にはつきづらい所にある。一瞬は見え、残像が残り、次の瞬間にはまた別の角度から見ると違う。
印象に残るかどうか、全ての人に何かを働きかけるかもしれないが、全ての人の意識に上る訳ではないかもしれない。
ふとした時に思い出してくれるような建築を目指すくらいが都市の中では馴染み、街並みを形成し、記憶として刻まれ、ちょうど良いような気がする。
"Cut in the city"
By being gradually limited and narrowed like in the frame inside the frame, it is separated from the surroundings, and only that part emerges, but it is in the back, a place that is hard for human eyes to see. You can see it for a moment, an afterimage remains, and the next moment it looks different from another angle.
It may work on everyone to make an impression, but it may not be conscious of everyone.
I feel that it is just right for me to aim for an architecture that will remind me when I happen to be, as it becomes familiar in the city, forms the cityscape, and is engraved as a memory.
地と図という考え方があるが、敷地境界線を枠と見立てれば、枠があるからその枠の中で起こることに価値を見出すことができると考えることもできる。
敷地境界線は結界のように超えることができない線であり、そこには何も価値につながるような線引きの方法がない。ただ単に建築とは別のところで決まり、線引きが行われる。だから、敷地境界線は厄介なものだが、その結界たる敷地境界線を枠として捉えて、枠があるから価値が生まれると考えれば面白い。
敷地境界線は窮屈なもので、超えることもできなくて、そこに新たな価値を生むものでもないが、枠と捉えた瞬間に可能性を感じた。
"Border as a frame"
There is the idea of the ground and the figure, but if you think of the boundary line of the site as a frame, you can think that you can find value in what happens within that frame because there is a frame.
The site boundary is a line that cannot be crossed like a barrier, and there is no way to draw a line that leads to value. It is simply decided in a place other than architecture, and the line is drawn. Therefore, the boundary line of the site is troublesome, but it is interesting to think that the boundary line of the site, which is the boundary, is regarded as a frame and that the value is created because there is a frame.
The boundary of the site is cramped, cannot be crossed, and does not create new value, but the moment I saw it as a frame, I felt the possibility.
突然意識に上がってくるものはどこか見て印象に残っているものだろう。普段は気にならない、見えないものが急に意識しだす。
フレームの中を覗くと見えるものはフレームで縁取られている分、周りから切り離され、その部分だけが意識に残りやすい。何かのきっかけでその部分だけ意識に上がってくるかもしれない。
わざと枠、額縁、フレームをつくることにより周りとは切り離して個別の価値をつくる。そして次にできあがった価値を隠す。隠すことにより残像が残り意識に刻まれる。
"Inside the frame"
Something that suddenly comes to your consciousness will leave an impression on you. I suddenly start to notice what I can't see, which I don't usually care about.
What you can see when you look inside the frame is separated from the surroundings because it is bordered by the frame, and only that part is easy to remain in consciousness. Something may trigger that part to become conscious.
By intentionally creating frames, picture frames, and frames, we create individual values by separating them from the surroundings. And then hide the resulting value. By hiding, an afterimage remains and is engraved in the consciousness.
最大の開口部を設けようとしている。お店の中をより見せたいという意図からで、なるべく大きな窓にしようとしている。
より中を見せたければ、窓では無くて全面ガラスにすればいいと思うかもしれないが、透明なガラスだけでできた壁は、不透明な壁と同じだと考えている。透明か不透明かの違いだけで、例え透明で中が丸見えでも、不透明の仕上げと同じ扱いで壁としか認識されず、中が見えるという意識が起こらない。
より中を見せたいということは枠が必要なのだ。窓枠というフレームが中身につながる装置であり、窓の中に見えるものは中身と自動的に認識する。
ガラスの仕上げが欲しければ透明ガラスだけで壁をつくれば良いが、より中を見せたいのであれば大きな窓をつくるのが良い。
"The window you want to see inside"
We are trying to provide the largest opening. I am trying to make the windows as large as possible with the intention of showing the inside of the store more.
If you want to see more inside, you might think that you should use full glass instead of windows, but I think that a wall made of transparent glass is the same as an opaque wall. Only the difference between transparent and opaque, even if it is transparent and the inside is completely visible, it is treated the same as an opaque finish and is only recognized as a wall, and there is no awareness that the inside can be seen.
If you want to see more inside, you need a frame. A frame called a window frame is a device that connects to the contents, and what you see inside the window is automatically recognized as the contents.
If you want a glass finish, you can make a wall with only transparent glass, but if you want to see more inside, you can make a large window.
材料の耐久性が上がるとまた別の表現方法が思いつく。耐久性を確保するには2通りあり、材料の表面にコーティングをするか、材料自体の耐久性を上げるかで、前者が圧倒的に多いような気がする。その方が楽で安上がりだからである。
しかし、表面にコーティングをする場合は選べるコーティング材が限られ、案外バリエーションが無く、材料自体の耐久性が上がれば、選択できる表面のコーティング材すなわち仕上げはかなり増え、表現方法の幅が広がる。
今現在、開口部の材料に対して検討中で、コストとの兼ね合いだが、今までにない表現が可能かもしれない。
"Width of expression method"
When the durability of the material increases, another expression method comes to mind. There are two ways to ensure durability, and I feel that the former is overwhelmingly large, depending on whether the surface of the material is coated or the durability of the material itself is increased. This is because it is easier and cheaper.
However, when coating the surface, the coating materials that can be selected are limited, there is no unexpected variation, and if the durability of the material itself is improved, the coating materials that can be selected, that is, the finish, will increase considerably, and the range of expression methods will expand.
Currently, we are considering the material for the opening, which is a trade-off with cost, but it may be possible to express it like never before.
情報量が多いということが複雑とは限らない。シンプルな中に複雑なことや混沌とした情報量が多いことが包み隠されている場合があり、そういう場合は一見シンプルで、包み隠されている分情報量が程よく制御されていて、情報量が多くても複雑にはならない。モダニズム建築に多いことかもしれない。
情報量という点で考えていけば、良い建築は皆情報量が多い。あとはその情報量の多さをどのように表現するかであり、情報量の多さを隠すのか、前面に出して表現するのか、チラ見せか、それは時代によっても、風潮によっても違うところである。
"A lot of information"
A large amount of information is not always complicated. There are cases where complicated things and a lot of chaotic information are hidden in the simple, and in such cases it is seemingly simple, the amount of information is moderately controlled by the amount of hidden information, and the amount of information is large. But it doesn't get complicated. It may be common in modernist architecture.
In terms of the amount of information, all good architecture has a lot of information. The rest is how to express the large amount of information, whether to hide the large amount of information, to express it in the foreground, to show a flickering, it depends on the times and trends. ..
関心を惹くには情報量を増やすしかない。情報量が人のアクティビティを即す。これは仕上げの話で、遠目から見て外観の仕上げに予想がつき、近づいて見て確認して同じでは情報量が少ない。遠景も近景も同じような仕上げに見えるということは、外観が人に与える情報量としては限りなくゼロに近く、人がわざわざ近づこうとするアクティビティが誘発されない。
情報量の多い外観は、遠景と近景で見え方が違うか、近景にはまた別の表情がある。単に遠景と近景で見え方が違うだけでも人のアクティビティは誘発される。建築は見るもの、使うものだけではなく、人を誘惑するものでもある。
"Tempting architecture"
The only way to get attention is to increase the amount of information. The amount of information matches a person's activity. This is a finishing story, and you can expect the finish of the appearance from a distance, and if you look closely and check it, the amount of information is small. The fact that the distant view and the near view look the same means that the amount of information that the appearance gives to a person is infinitely close to zero, and the activity that the person bothers to approach is not induced.
The appearance with a lot of information may look different between the distant view and the near view, or the near view has a different expression. People's activities are triggered simply by the difference in appearance between the distant view and the near view. Architecture is not only what you see and use, but also what tempts people.
関係性の中でデザインを考えると新たな影響力があるものが生まれないと思う。そもそも関係性がある前提のものづくりははじめから影響を加味したものであり、答えを考えて問題をつくるようなもので、影響力に新鮮味が全く無い。
ただ、関係性の中で現れるものは全ての調整が済んだ後なので、安心感、安定感はあるだろう。
関係性が深くなればなるほど、その関係性の枠にはまっていく。それから逃れるためには常に関係性の外に目を向けておく必要があり、それが意識上のことでも構わないが、既存の関係性とは完全に切り離されたものである必要がある。
"Relationship design"
I don't think there will be any new influence when considering design in relationships. In the first place, manufacturing on the premise that there is a relationship is something that takes into account the influence from the beginning, and it is like creating a problem by thinking about the answer, and the influence has no freshness at all.
However, what appears in the relationship is after all the adjustments have been made, so there will be a sense of security and stability.
The deeper the relationship, the more it fits into the frame of the relationship. To escape from it, one must always look outside the relationship, which can be conscious, but it must be completely separate from the existing relationship.
外向きに意識を向けると周りが見えてくるのではなくて、内向きに意識を向けると周りが自然と関係してくる。自閉するように内部空間に籠ろうとすると周りとの距離を自然に意識してしまう。意識する時点で関係ができる。
周辺環境と関係を築くためには完結した内部空間、すなわち、独りになれる空間で良い。そこにいると人は自然と頭の中で今目の前に無い不足のものを補おうとする。不足し、不完全な状態、状況をつくり出すことが意識の上で周辺環境とつながる源になる。都市の中では必要な必要なことかもしれない。
"Creating a shortage"
If you turn your consciousness outward, you will not be able to see your surroundings, but if you turn your consciousness inward, your surroundings will be related to nature. If you try to stay in the internal space so that it closes, you will naturally be aware of the distance to the surroundings. You can have a relationship when you are conscious.
In order to build a relationship with the surrounding environment, a complete interior space, that is, a space where you can be alone, is sufficient. When there, people naturally try to make up for the shortages that are not in front of them in their heads. Creating a shortage, incomplete state, or situation is a source of conscious connection with the surrounding environment. It may be necessary in the city.
人の内面が現れるような場をつくりたいと常に思っており、それが内部空間ならば、人の内面の発露を誘発するようなものをデザインしたいと考える。
それは外部空間でも同じだが、外部空間の場合は周辺環境への影響、周辺環境からの影響を考慮する必要もあるので、人の内面の発露を誘発するより、周辺環境に働きかけ、周辺環境が人の内面の発露を誘発するようにしたい。
"Inner dew"
I always want to create a place where the inside of a person appears, and if it is an interior space, I want to design something that induces the exposure of the inside of a person.
The same is true for the external space, but in the case of the external space, it is necessary to consider the influence on the surrounding environment and the influence from the surrounding environment. I want to induce the dew on the inside of the.
地形に委ねてみる面白さもありそうだと、それは自己から離れて全く別のものの中にヒントを得ようとする試みであり、またそれは直接的な要望のプログラムでも無いので、縛られることも無く、好きに加工ができるものだから扱いやすく、それでいてその土地に建つという個別性は担保されるので、他律でありながら自律でもある状態をつくることができるのは面白い。
願わくば、建築が先にあり、後から地形ができあがるようなプロセスならば、建築を地形化することも視野に入るので、地形を後からつくる方法がないか、それは単なる外構ではないものをつくりたい。
BIMならば、地形までもオブジェクト化して、建築のモデルの延長として捉えることができるので、あとは現実世界でどうするかである。
"Leave it to the terrain"
If it seems interesting to leave it to the terrain, it is an attempt to get a hint in something completely different from the self, and since it is not a program of direct request, it is not tied up. It is easy to handle because it can be processed as you like, and yet the individuality of being built on the land is guaranteed, so it is interesting to be able to create a state that is both heteronomous and autonomous.
Hopefully, if the process is such that the architecture comes first and the terrain is created later, then there is a way to create the terrain later, because it is also possible to make the terrain into a terrain. I want to make.
With BIM, even the terrain can be made into an object and can be regarded as an extension of the architectural model, so the rest is what to do in the real world.
地形の複雑さをどれほど建築に取り込めるかを考えていると、地形を建築化しようとしてしまう。本当は建築を地形化したいのだが、地形が持つ複雑で変化に富んだ形状がまず存在するので、それと建築を同化させるようなことをすると、先に存在している地形を手がかりにしてしまう。
一旦イメージで、地形を建築化した上で、次にその建築を地形化してみる。まず先に建築がある状態をつくり出し、次にその建築の形式を壊し、一旦廃虚にしてから、次の建築のイメージを考えるのがよいかもしれない。
"Architectural terrain"
When thinking about how much the complexity of the terrain can be incorporated into architecture, we try to build the terrain. I really want to make architecture into terrain, but since there are complex and varied shapes that terrain has, if you try to assimilate it with architecture, you will use the terrain that already exists as a clue.
After building the terrain with an image, then try to build the terrain. It may be better to first create a state of architecture, then destroy the form of that architecture, ruin it once, and then think of the image of the next architecture.
関係性の中から生まれたものは、その関係性の文脈を理解していないとわからない。だから、その関係性の中にいる人たちだけのものになるか、自身で関係性の文脈を理解するか、関係性の文脈を誰にでも理解できるように語れる人が側にいる必要がある。
関係性というつながりをつくればつくる程、元まで遡らないとつながりがよく理解できない。だから、関係性の中から生まれるものがあれば、同時につながり自体も別に生まれる。
関係性からの産物とつながりが視覚化されたものが同じならばわかりやすいが、別々の場合もあり、その場合はその違いや捩れがまた新たなものを生み出すだろう。
"Product of connection"
What is born out of a relationship cannot be understood without understanding the context of that relationship. So you need to have someone on your side who can only be for those who are in the relationship, understand the context of the relationship on their own, or speak to anyone to understand the context of the relationship. ..
The more you make a connection called a relationship, the more you can't understand the connection unless you go back to the original. Therefore, if there is something that is born from the relationship, the connection itself is also born at the same time.
It is easy to understand if the product from the relationship and the visualization of the connection are the same, but in some cases they are different, in which case the differences and twists will create new things.
関係性の中から生まれるものは齟齬がなく、漏れがなく、全てが一様に満たされており、それは関係性が築かれるまでにある程度の合意があるからだが、すでに予定調和的な、わざわざ生み出さなくてもいいようなもの、生み出された瞬間に抜け殻のような中身が無いものになっており、ただ単に関係性を視覚化しただけのものが現れる。
視覚化された関係性がふわふわと軽く一人歩きをして、様々なことに影響を与える。それも軽いが故に受け入れやすいので、広範囲に影響が及ぶ可能性もある。
しかし、中身が無いだけに影響はすぐに消し去る。その軽さと跡の残らなさが、何が正しいのか、何が良いのか、とまた人を惑わせる。そして、誰かにききたくなり、ネットに、SNSに向かわせる。そこでまた違う関係性が生まれる。関係性の連鎖がはじまる。
"Chain of relationships"
What comes out of a relationship is consistent, complete, and uniformly filled, because there is some consensus before the relationship is established, but it's already harmonious and purposely created. Something that doesn't have to be, something that has no contents like a shell at the moment it is created, and something that simply visualizes the relationship appears.
The visualized relationships are fluffy and light, walking alone and affecting various things. It is also light and easy to accept, so it can have widespread effects.
However, the effect disappears immediately because there is no content. Its lightness and traces make people confused about what is right and what is good. Then, I want to ask someone, and I send them to SNS on the Internet. Then another relationship is born. The chain of relationships begins.
交換を即す、橋渡しするような存在があれば、別々の解釈や価値がつながる、それが味変。お互いを結びつける可能性をお膳立てするものを探してみると、各々にとって受け入れられる物であり、尚且つ、各々にとって異物になる。
全く別の異なる種の物だから、交換や移動が即される。お互いに誘引するのだろう。大事なのは交換するというアクティビティが起こることで、異物と同化してしまっては元の解釈や価値が濁るだけである。
案外、異物はそこら中に身近に存在しているが同化して交換することができないでいる場合が多い。交換した価値に気づくと異物は宝物になる。異物は蜜の味なのである。だから味変に使えるのである。
"Exchange is a dense taste"
If there is something that can be exchanged or bridged, different interpretations and values will be connected, which is a taste change. If you look for something that sets the possibility of connecting each other, it will be acceptable to each and will be a foreign body to each.
It's a completely different kind of thing, so it can be exchanged and moved quickly. Will attract each other. The important thing is that the activity of exchanging occurs, and if it is assimilated with a foreign substance, the original interpretation and value will only be obscured.
Unexpectedly, foreign substances are present all over the place, but in many cases they cannot be assimilated and replaced. When you realize the value of the exchange, the foreign matter becomes a treasure. Foreign matter is the taste of honey. Therefore, it can be used to change the taste.
様々な解釈が成り立つ物や建築に惹かれる。実際はひとつの解釈だけが存在を許されるのだが、状況や見る人、使う人によって解釈が違い、各々でひとつの解釈が成り立つ。
解釈の存在は物や建築がそれらしく振る舞うために必要であり、解釈が共通言語となり広まり、誰でも関係が持てるようになる。
ただ、その解釈は人の数だけ存在できるので、解釈が交換可能な物にまでなれば、ひとつの解釈に拘らなくても良くなる。では交換可能な解釈が生成されるにはどうしたら良いのか、味変のようなことをするのだろう。
"Exchangeable interpretation"
I am attracted to things and architecture that can be interpreted in various ways. In reality, only one interpretation is allowed to exist, but the interpretation differs depending on the situation, the viewer, and the user, and one interpretation holds for each.
The existence of interpretation is necessary for things and architecture to behave like that, and interpretation becomes a common language and spreads, and anyone can have a relationship.
However, there can be as many interpretations as there are people, so if the interpretations are exchangeable, it is not necessary to stick to one interpretation. So what should we do to generate an exchangeable interpretation, something like a taste change?
目の前にある物をただ見ているだけならば、良し悪しや評価は存在しない。そこに存在しているということだけである。しかし、見ているだけでは済まされない。勝手に評価をはじめ、ものさしは自分の思考になる。
思考には正解があるようで無いと思っているので、常に揺れ動き、ある瞬間だけ定まると、また動き出す、厄介なものだと思う、のもまた思考。
ただ見ているだけ、そして、評価という流れで進むならば、ただ見ているだけという状態はいらないのではないかと思うが、ただ見ているだけという状態が物を物だと認識するには必要なのかもしれない。
"I'm just looking"
If you are just looking at what is in front of you, there is no good or bad or evaluation. It just exists there. However, just looking at it is not enough. Beginning with evaluation without permission, the ruler becomes your own thought.
I don't think there seems to be a correct answer to my thoughts, so I think it's awkward to always shake, and once it's decided for a certain moment, it starts moving again.
If you just look and proceed in the flow of evaluation, I think that you do not need the state of just looking, but it is necessary to recognize that the state of just looking is a thing. It may be.
物の良し悪しに、それクオリティが高いですか、と思いたくなるものが、たくさんの人から支持されている、あるいは、支持されているように見える中に多い。結局この場合、クオリティは関係が無く、受け手とつくり手の関係性で決まる。
悩ましいところだと今までは思っていただろう。クオリティが高いものがつくれるならば、好きにつくればいい。ただ、今あるもののクオリティが低い場合、クオリティとは関係が無いところでデザインはしたくないので、今あるものを捨てるか、クオリティのアンバランスを活かすデザインをするしかない。
"If the quality is low"
There are many things that make you want to wonder if the quality of things is good or bad, while many people support or seem to support them. After all, in this case, quality is irrelevant and is determined by the relationship between the recipient and the creator.
Until now, you would have thought it was annoying. If you can make something of high quality, you can make it as you like. However, if the quality of the existing one is low, I don't want to design it in a place that has nothing to do with the quality, so I have no choice but to throw away the existing one or design to take advantage of the quality imbalance.
人の意識は安易にわかりやすいものに流されやすいので、全体像がすぐにはっきりとわかるものが受け入れられやすい。しかし、人に印象を残すことを考えたならば、全てがすぐにわかりやすい方がよいとは必ずしも言えない。
少しのわかりにくさが引っ掛かりとなり、かえって人の意識を刺激することもある。引っ掛かりやフックをデザインが担うのかもしれない。
デザインは形にした後の伝わり方までも範疇なのが当たり前だけれども、伝わった後にまた違った展開が、当初には思いも付かなかったことがはじまるようなことが起きる可能性を残したいと考える。
"Leave the possibility"
Since people's consciousness is easily swept away by something that is easy to understand, it is easy to accept something that gives a clear overview. However, when considering leaving an impression on people, it is not always better to understand everything immediately.
A little confusing can get caught and even stimulate people's consciousness. The design may be responsible for catching and hooking.
It is natural that the design is also in the category of how it is transmitted after it is formed, but I would like to leave the possibility that a different development will start after it is transmitted, something that was not initially thought of. ..
極端なものを内包することで一見普通に見せるが、どこか一部分だけでも極端なものが見えると、その普通さがかえって異常に見える。
極端なものを隠蔽することで成り立つ普通さは、すでに普通ではなく異常だが、完全に隠蔽できていれば普通にしか見えない。しかし、どこか一部分でも隠蔽が解けた場合、一見普通に見える分、一部分の極端さが異常性を孕む。ただ、その異常性を孕んだ極端なものは大部分が隠蔽されて全体像がはっきりとしないおかげで受け入れやすくはなっている。
"Extreme ordinary"
By including extreme things, it looks normal at first glance, but if you can see extreme things even in a part of it, the normality looks rather abnormal.
The normality that comes from concealing extreme things is already unusual and unusual, but if it can be completely concealed, it can only be seen as normal. However, if the concealment is released even in a part of it, the extreme of the part is abnormal because it looks normal at first glance. However, most of the extremes that contain the anomaly are hidden and the whole picture is not clear, which makes it easier to accept.
一般解を求めようとすると中庸なものになりやすい。極端ではすぐには一般的なものにはなりにくく、中庸だと一般的なものになり得る可能性が広がり、解釈のレンジも広がるからであるが、中庸だと中途半端、曖昧、はっきりしないなどあまりいいイメージは無いかもしれない。
本来、中庸はいい所取り、弁証法のジンテーゼのような存在で、妥協の産物ではないが、上手く中庸なものを生み出すのも難しい。
解釈のレンジが広く極端なものができれば、それが本来の意味の中庸かもしれない。
"Medium things"
When trying to find a general solution, it tends to be moderate. In the extreme, it is difficult to become general immediately, and in the middle, the possibility of becoming general increases and the range of interpretation expands, but in the middle, it is halfway, ambiguous, unclear, etc. You may not have a very good image.
Originally, the golden mean is a good point, like a dialectic gintese, and although it is not a compromise, it is difficult to produce a good moderate one.
If the range of interpretation is wide and extreme, it may be the middle of the original meaning.
遠くから見てみると、視界の中に入ってくるものの総量が増えるが、どこかに焦点を合わせない限り、たくさんのものが視界の中でただ浮遊しているようにしか見えない。
近くから見てみると、視界の中に入ってくるものは部分になる場合が多いが、全体の把握をせずにはいられない気分になるかもしれない。
全体が部分の総和だけならば、全体がボヤけていても、部分しかハッキリしてなくても問題が無いが、全体と部分が全く違う様相ならば、遠くでも無く、近くでも無い、中間の視界が必要になり、その中間の視界でしか全体も部分も把握できない。そして、その中間の視界は極端では無く中庸なものになるので、見ようによっては一番求めやすい視界かもしれない。
"Intermediate view"
Seen from a distance, the total amount of things that come into view increases, but unless you focus somewhere, many things just appear to be floating in your field of view.
Seen from a close distance, what comes into view is often a part, but you may feel compelled to grasp the whole thing.
If the whole is only the sum of the parts, there is no problem even if the whole is blurred or only the parts are clear, but if the whole and the parts are completely different, the middle view is neither far nor near. Is required, and the whole and part can be grasped only in the middle field of view. And since the field of view in the middle is not extreme but moderate, it may be the most sought-after field of view depending on how you look at it.
色は自律のために存在していると思ってしまう。色に着目する時、色は常にまわりからの影響を受けて相対的に存在をしているのだけれども、その色は時に自己主張をしてくる。その自己主張もまわりからの影響によるが、自己主張の瞬間は自律している。きっとこの感じは広告と同じかもしれない。何気ない日常の中の至る所に広告は存在しており、それが何かの瞬間に浮かび上って訴えかけてくる。広告もまわりとの相対関係の中で効力を発揮させようとするものであるが、時に強い自己主張が刺さるように迫ってくる。
"Approaching colors and advertisements"
I think that color exists for autonomy. When we focus on color, it is always influenced by the surroundings and exists relatively, but that color sometimes asserts itself. The self-assertion is also influenced by the surroundings, but the moment of self-assertion is autonomous. I'm sure this feeling may be the same as advertising. Advertisements are everywhere in casual everyday life, and they emerge and appeal at some moment. Advertising also tries to be effective in the relative relationship with the surroundings, but sometimes it urges a strong self-assertion.
その色にしようとすると、すでに色は別の意味を持ちはじめる。物質の表面色は相対的に決まる。今そこにその物質が必然的に存在しているのならば、その物質の表面色は今そこに存在しているための色をしている。すでに色には何かしらの存在の意味が付着している。そこでデザインをする時に色を考える。相対的にデザインを際立たせるために色を決める。その時色には元々付着していた意味にさらに別の意味を重ね合わせることになる。その重ね合わせは物質本来の色とは関係ないところで行われるので、物質本来の色に影響を与えない。物質の表面色を決める時点で表面色だけが独り歩きをはじめる。その独り歩きが今度はまわりを巻き込みはじめる。自律から他律へ変わるのである。
"Color goes to heteronomy"
When you try to make that color, the color already begins to have a different meaning. The surface color of a substance is relatively determined. If the substance is inevitably present there now, the surface color of the substance is the color that is present there. The meaning of some kind of existence is already attached to the color. So when designing, think about colors. Choose colors to make the design stand out relatively. At that time, another meaning is superimposed on the meaning originally attached to the color. Since the superposition is performed in a place that has nothing to do with the original color of the substance, it does not affect the original color of the substance. At the time of determining the surface color of a substance, only the surface color begins to walk alone. The walking alone now begins to involve the surroundings. It changes from autonomy to heteronomy.
今見ている世界を今見ている色ではない色で表現することができる。今見ている色は物質の表面色なので物質本来の色とは違う。そう考えると、表面色にあまり意味がなくなってくる。表面色は相対的にたまたまその色になったのではないかと思ったりもしてしまう。
相対的に見て物質が今そこに存在していることを表現する場合、表面色は別に何色でもよくなる。あくまでも相対的なので、例えば、元々の表面色が白だとしても、赤で白の表面色と同じ効果、同じ見え方にすることはできる。
そうすると、色とは、特に物質の表面色とは何だとなる。その表面色にデザインとしての表現を重ね合わせるのに、あまりにもうつろうものではないかと思ったりする。
ただ、そう思うのは物質に絶対的な何かを求めているからで、そもそもこの世界を形成している物質が相対的に決まるものだと考えるならば、うつろう表面色が当たり前のことになる。
"Depressed color"
You can express the world you are looking at in a color other than the color you are looking at. The color you are looking at is the surface color of the substance, so it is different from the original color of the substance. With that in mind, the surface color becomes less meaningful. I wonder if the surface color happened to be that color.
When expressing that a substance is present there in relative terms, the surface color can be any number of colors. Since it is relative to the last, for example, even if the original surface color is white, it is possible to obtain the same effect and appearance as the white surface color with red.
Then, what is the color, especially the surface color of the substance? I think it's too difficult to superimpose the expression as a design on the surface color.
However, I think so because I want something absolute from the substance, and if I think that the substance that forms this world is relatively determined in the first place, the depressive surface color is natural. ..
色彩心理学ではないが、色だけでたくさんのことが表現できる。それをしようとしないのは色だけが存在することがないからである。必ずと言ってよいほど、色は何らかの物質の色として存在しているので、色だけに着目せずに、物質に着目し、次に色をどうするか、あるいは、物質と色を同時に考える、というように色だけではない。
色は光の反射があってはじめて判別できるので、実際は色だけでは存在できず、また光の反射が四方に拡散すれば空間を染めることもある。
だから、色だけを取り出して認識するようなことをそもそも普通の人はしない。色は見た目の色以外の色として認識できることを普通の人は知らない。
"Only color"
It's not color psychology, but you can express a lot with colors alone. I don't try to do that because only color can't exist. It is almost always the case that color exists as the color of some substance, so instead of focusing only on the color, focus on the substance and then what to do with the color, or think about the substance and the color at the same time. It's not just about color.
Since colors can only be identified by the reflection of light, they cannot actually exist by themselves, and if the reflection of light diffuses in all directions, the space may be dyed.
Therefore, ordinary people do not take out and recognize only colors in the first place. The average person does not know that a color can be recognized as a color other than the apparent color.
色は不思議な存在で、色によって物質感まで表すこともできるけれど、色自体が物質だから、上手く使えば色単体で成立してしまう。
木目の物質感を表すのに茶色を使えばいいし、金属の物質感を表したければシルバーを使えばいい。近寄れば、本物との違いは一目瞭然だが、少し離れてしまえばわからないかもしれない。それはとても雑な表現として色を使う場合だが、その雑さが丁度いい場合もある。
既視感のある物質感は色のみで再現できる。それは見る方が勝手に想像力を働かせるからである。ただ、それでは本物との違いで見劣りする。
色単体でしか表現できない物質感があると思っている。その色の物質感には既視感がないはずである。なぜなら、既視感は物質に抱くのでは無く、過去の体験や記憶に抱くから、色はあまりにも日常的にある存在過ぎて体験や記憶の網目に引っ掛かってこない。
だから、色単体で成立させようとする場合は、相対的に成り立たせるように、既視感を抱く物質と組み合わせて配置すれば容易に表現できる。
"Expression of a single color"
Color is a mysterious existence, and it is possible to express a sense of substance by color, but since color itself is a substance, if used properly, it will be established by itself.
You can use brown to express the texture of wood, and silver to express the texture of metal. The difference from the real thing is obvious when you get closer, but you may not know it when you get a little further away. That's when you use color as a very crude expression, but sometimes it's just right.
The material feeling with déjà vu can be reproduced only by color. The reason is that the person who sees it uses his imagination without permission. However, it is inferior to the real thing.
I think there is a sense of substance that can only be expressed by color alone. There should be no déjà vu in the materiality of that color. Because déjà vu is not embraced by matter, but by past experiences and memories, colors are too everyday to be caught in the mesh of experiences and memories.
Therefore, when trying to establish a color by itself, it can be easily expressed by arranging it in combination with a substance having a déjà vu so that it can be established relatively.
物質の空隙に人が漂う状況を建築だとするならば、物質の空隙のつくり出し方が今までの建築とは違ってくるかもしれない。
木造や鉄骨造などは線状部材の組み合わせで建築を築き上げるので、出来上がった建築は物質の空隙とは呼べるようなものではない。鉄筋コンクリート造は物質の空隙風に構築できるが、木造や鉄骨造などと同様に線状部材で建築を築き上げていく場合もあり、なかなか空隙に漂う感じとはいかない。
イメージに近いのは洞窟かなと思った。塊の中から空隙をくり抜くイメージになる。そうなるとそもそも建築のつくり方ではない。
"Floating in the void"
If the situation where people float in the voids of matter is architecture, the way of creating voids of matter may be different from the conventional architecture.
Since wooden structures and steel structures are constructed by combining linear members, the completed architecture cannot be called a void of material. Reinforced concrete construction can be constructed in the style of material voids, but as with wooden structures and steel structures, there are cases where the building is built with linear members, so it does not feel like floating in the voids.
I thought it was a cave that was close to the image. The image is that the void is hollowed out from the mass. In that case, it is not a way to make architecture in the first place.
自然素材が持っている物質感が空間を消失してくれると考えた。
例えば、たくさんの石が集まることにより、ひとつの造形をつくり出し、その造形は空間が持つ空虚を埋めて、尚且つ、物質感だけが持ち合わせているスケール感へと引きづりこむ。それは物質感の強度に関係なく、造形が生み出すスケールを感覚的に増幅させる。
この増幅された感覚的なスケールが空間にとって代わることにより空間が消失する。
"Space disappearance"
I thought that the materiality of natural materials would eliminate the space.
For example, by gathering a lot of stones, one model is created, and the model fills the emptiness of the space and draws it into a sense of scale that only the physical feeling has. It sensuously amplifies the scale produced by modeling, regardless of the intensity of the material feeling.
Space disappears when this amplified sensory scale replaces space.
空間を満たす物質は誰でも妥当性を感じるものにしたい。いくらでも物質は存在し選び放題だが、妥当性を獲得するものは案外少なく、さらに、その物質に可能性を感じ、採用したくなるものも案外少ない。
さらに言うと物質感が空間を消失してくれるようなものがいい。建築のつくり方は必然的に空間を発生させてしまうので、その空間を否定をする訳ではないが、空間が優位になりやすい。それは空間至上主義にもつながり、例えば、わざと天井を低くくしたりなど、空間のボリュームを過度にデザインするようなことをしだす。
平衡なデザイン感覚の上に成り立つ建築でないと空間も活かされないので、今は空間を消失させるような物質感を求める感覚が必然的になってしまう。
"Substances that make space disappear"
We want everyone to feel the validity of the substance that fills the space. There are as many substances as there are, and you can choose as many as you like, but there are surprisingly few that acquire validity, and there are also surprisingly few that feel the potential of the substance and want to adopt it.
Furthermore, it is good that the material feeling disappears the space. The way of building architecture inevitably creates space, so I do not deny that space, but space tends to be superior. It also leads to the principle of space supremacy, for example, by intentionally lowering the ceiling, and over-designing the volume of the space.
Space cannot be utilized unless the architecture is built on a balanced design sense, so now it is inevitable to have a sense of materiality that makes the space disappear.
共通の物質感があるだろうと仮定して、それを探るようなことをしている。そもそも決められた空間が存在しているので、あえてまたそこで空間性を持ち出してきて違う空間を求めるよりは、今ある空間は受け入れて、それに対して何ができるかを考える方が妥当性があり、可能性があると考えた。
空間はすでに存在しているのだから、実体としての物質性を持ち込み、その物質感によって空間を満たすことが一番素直な解答のような気がしている。
"Fill with material feeling"
I'm trying to explore it, assuming that there will be a common sense of materiality. Since there is a fixed space in the first place, it is more appropriate to accept the existing space and think about what can be done for it, rather than dare to bring out the spatiality there and seek a different space. , I thought there was a possibility.
Since space already exists, I feel that the most straightforward answer is to bring in materiality as an entity and fill the space with that material feeling.
壁だけがある空間と屋根だけがある空間、どちらの場合も空間がそこにあることを認識できるが、決して同じような感じを抱かないだろう。
空間にそれほど期待しないが、今いる場所が少しでも雰囲気よく気持ちよくなればいいと思い、さらに、壁だけがある空間では、屋根だけの空間より物質性も容易に感じることができるのではないか、むしろ壁だけだと空間性より物質性の方が優位になるかもしれない。
物質性がアクティビティを誘発することは、空間性に頼らずに建築とアクティビティがつながることであり、空間を否定する訳ではないが、かと言って過度な空間信奉には違和感があるので、余計に壁に興味を持ってしまう。
"Matter from space"
In both cases, a space with only walls and a space with only roofs, you can recognize that the space is there, but you will never feel the same.
I don't expect much from the space, but I hope that the place I'm in now feels good and comfortable, and in a space with only walls, I think it's easier to feel the materiality than in a space with only a roof. Rather, if it is only a wall, materiality may be superior to spatiality.
The fact that materiality induces activity means that architecture and activity are connected without relying on spatiality, and it does not mean that space is denied. I'm interested in the wall.
屋根が誘発するアクティビティがあるとしたならば、屋根の形態や位置でアクティビティが決まる。そうすると屋根の細部はアクティビティにどれ程の影響を与えるのだろうか。
屋根とって細部は主に端部になり、人の目に一番触れるところでもある。屋根を主体に建築を考えたならば、屋根から下の部分は端部になり、細部になる。屋根にとっての細部は屋根の形態や位置などで決まるアクティビティにまた違った変化を与えるだろう。
だから、建築を屋根と屋根から下の部分で分解して考えることにより、建築が誘発するアクティビティを複雑化することができると考えてみた。
"The part below the roof"
If there is a roof-induced activity, the shape and position of the roof will determine the activity. So how much does the roof detail affect the activity?
The details of the roof are mainly the edges, which is also the most visible to the human eye. If you think about architecture mainly on the roof, the part below the roof will be the end and the details. The details for the roof will make a different difference to the activity, which depends on the shape and position of the roof.
Therefore, I thought that it would be possible to complicate the activities that the architecture induces by disassembling the architecture into the roof and the part below the roof.
暑いとつい日陰を探し、歩いている時も建物の影を踏みながら、少しでも涼しいようにと、暑いと思う気分がそうさせる。だから、庭園の中などにある四阿(あずまや)は屋根だけで構成されていて日陰ができるので、木陰に腰掛けるような感覚で佇む気分にさせてくれる。
この暑い時期は涼みたいという欲求がきっかけになり日陰を探す行動をし、そこに日陰があればすっぽりとおさまる。その日陰は何でもいいが、日陰を探す行動を取る時に日陰自体を探すのではなくて、日陰ができそうな所を探している。今までの経験上、日陰ができる仕組みから日陰ができそうな所を予測して探している。
だから、四阿を見かけただけで、涼しく休憩できる、と瞬時に思い、そこで佇む。これは四阿という建築形態がアクティビティを誘発するひとつのパターンだが、建築形態とアクティビティの間に予測が存在しており、その予測は人の経験値から割り出されるが、一般的なものなので万人に通用する。この万人に通用することが一般解につながり、四阿が休憩する場所として成り立つ。
"It works as a place"
Looking for the shade when it's hot, and stepping on the shadow of the building while walking, it makes me feel like it's hot, trying to be as cool as possible. Therefore, Azumaya in the garden is made up of only the roof and can be shaded, so it makes you feel like you are sitting in the shade of a tree.
In this hot season, the desire to be cool triggers the action of searching for a shade, and if there is a shade there, it will be completely settled. The shade can be anything, but when you take action to look for the shade, you are not looking for the shade itself, but looking for a place where you can have a shade. Based on my experience so far, I'm looking for a place that is likely to be shaded from a mechanism that can be shaded.
Therefore, I instantly thought that I could take a cool break just by seeing Shia, and I stood there. This is one pattern in which the architectural form of Shia induces activity, but there is a prediction between the building form and the activity, and the prediction is calculated from the experience value of a person, but since it is a general one, everyone It works for. This universal solution leads to a general solution, and it is established as a place for Shia to take a break.
屋根がどこまでも続けば、その下は移動可能な空間だと思い、屋根が点在していれば、その下は立ち止まり休憩できる空間だと思うかもしれない。屋根の大きさや長さ、位置より判断して、アクティビティを誘発し制限する。
この場合、細部はアクティビティの決定に影響を与えないので、細部に別の何かを、機能であったり、デザインや装飾を施して誘発するアクティビティにまた違った変化を与えることも可能になる。
アクティビティを誘発し制限するような屋根は、単に雨風を防ぎ、暑さ寒さを凌ぐだけの存在から別の存在へと昇華する。
"Existence of roof"
If the roof continues forever, you may think that the space underneath is a movable space, and if the roofs are scattered, you may think that the space underneath is a space where you can stop and rest. Judging from the size, length and position of the roof, it induces and limits activities.
In this case, the details do not affect the decision of the activity, so it is possible to give something else to the details, a function, or a different change in the activity triggered by designing or decorating.
A roof that induces and limits activity simply prevents rain and wind, and sublimates from being one that survives the heat and cold to another.
屋根は普通、手が届かない所にあるので、見るもので触るものではないが、もし身体性との関わりで考えることができたならば何があるだろうかと考えた。
見るという行為は視覚という感覚を誘発するが、感覚は身体の部位を通して気づくものなので、屋根を見るという行為だけでも身体性との関わりは生まれ、視覚を通して様々な情報を認知させる。だから、屋根が象徴性、帰属性、権威性を表す効果があるといえるのだろう。
さらに視覚を通して認知させることにより様々なアクティビティを誘発することができれば、まさに身体性をリニアに感じることになる。
屋根がアクティビティを誘発するケースを考えることができるか、その場合のアクティビティとは何か、また、その時の屋根の形状は、などと考えてみることにした。
"Activity by roof"
The roof is usually out of reach, so I can't touch it with what I see, but I wondered what would happen if I could think about it in relation to physicality.
The act of seeing induces the sensation of vision, but since the sensation is noticed through parts of the body, the act of seeing the roof alone creates a relationship with physicality and makes various information recognized through vision. Therefore, it can be said that the roof has the effect of expressing symbolism, attribution, and authority.
Furthermore, if various activities can be induced by visually recognizing them, the physicality will be felt linearly.
I decided to think about the case where the roof induces activity, what the activity is in that case, and the shape of the roof at that time.
屋根は雨風を防ぎ、暑さ寒さを凌ぐのが環境から問われる機能だが、屋根の意匠自体が何かを表すこともあり、屋根の形、素材、装飾などがその建築の象徴性、帰属性、権威性を表す効果もある。
遠くから見た時の屋根は周りとの相対効果で大きさと形を表すことができ、近寄れば様々な細部が見える。
大きさや形、細部のつくりでその建築の象徴性、帰属性、権威性を表現できる。
屋根には環境機能と意匠効果の他に何かあるだろかと考えいる。屋根単体には無いかもしれないが、屋根と他のことが結びつけば何か生まれるかもしれない。
"Other things on the roof"
The roof is a function that is required by the environment to prevent rain and wind and to survive the heat and cold, but the design of the roof itself may represent something, and the shape, material, decoration, etc. of the roof are the symbolism and attribution of the architecture. , It also has the effect of expressing authority.
The size and shape of the roof when viewed from a distance can be expressed by the relative effect with the surroundings, and various details can be seen when approaching.
The symbolism, attribution, and authority of the architecture can be expressed by the size, shape, and details.
I wonder if there is anything else on the roof besides environmental functions and design effects. It may not be on the roof alone, but something may be born if the roof is combined with other things.
つながりの中にある捩れを探し、捩れていない状態にすることをデザインが担うことで物の美しさや人に優しい物が出現すると考えている。
デザインは最終的に必ずしも物に帰結する必要は無いと考えてはいるが、デザインが人に何らかの良い影響を与えようとするならば、物として表現された美しい物や優しい物が周りにあった方がわかりやすくて良いと思う。
物の美しさは気付かないとわからない、優しい物は触れないとわらからない、だから、形にして物にして、その手段がデザインということである。
"Make things"
We believe that the beauty of things and people-friendly things will emerge if the design is responsible for finding the twist in the connection and making it untwisted.
I think that design does not necessarily have to result in things in the end, but if design wants to have some positive effect on people, there are beautiful things and gentle things expressed as things around. I think it's easier to understand.
You can't understand the beauty of things unless you notice them, and you can't understand them unless you touch gentle things.
じーっと眺めていると目が慣れてくるのか、いろいろと思いはじめる。どうでもいいことがたくさん現れては消えるが段々と収斂していく。このサイクルを無意識のうちに場所を変えながら繰り返すことにより、知らないうちに段々と深まる。
何も考えないようで、人は結構日常的に考えている。やはり、そうしないと生き残れないから、脳が自然と働くのだろう。だから、ふとした瞬間に思いつくことがある。
ならば、意図的に眺めるものが変化する場所にいる方がいろいろなことを思いつくかもしれない。
今いるのは地下鉄のコンコースにあるカフェ。変化するのは通り過ぎる人のみ。完全にコントロールされた環境が暑い日には助かるが、変化するものが少ない分思いつきが乏しくなるかもしれない。
"Inspiration"
When I stare at it, I start to wonder if my eyes get used to it. A lot of things that don't matter appear and disappear, but they gradually converge. By repeating this cycle unknowingly while changing places, it gradually deepens without knowing it.
People don't seem to think about anything, and people think about it on a daily basis. After all, if you don't do that, you won't survive, so your brain will work naturally. Therefore, I have something to come up with in a moment.
Then, you may come up with various things if you are in a place where what you see intentionally changes.
I'm at a cafe in the subway concourse. Only those who pass by change. A fully controlled environment can help on hot days, but less change may make you less imaginative.
今見えていないことを意識させたり自覚するにはどうしたら良いのか、などと考える機会があった。
よく言われるように、自分のことはわかっているようでわからないものだと、たぶん人は誰でもそうは思いつつ、自分も、どこかでこれはこうだと決めつけている。
そうしないと何も先には進まないし、何も上手くいかないと思っていて、ただそれが思い込みで、その陰にある見えてないことに気づき、自覚できる人だけがつくれるものを自分で見てみたい。
怖いが今の考えの前提部分を真逆にした時のたった一言、ワンフレーズを投げかけてみると、時に状況が一変することがある。状況が一変するということは今までが思い込みで、そのワンフレーズが陰にあり見えていなかったことである。
"What you can't see"
I had the opportunity to think about what I should do to make people aware of what they are not seeing now.
As is often said, everyone probably thinks that they know and don't know about themselves, but somewhere they decide that this is the case.
If you don't do that, nothing will go on and nothing will work, but you just realize that it's a belief and you can't see it behind it, and see for yourself what only people who can be aware of can make. want to see.
I'm scared, but when I throw a single phrase when I reverse the premise of my current thinking, sometimes the situation changes completely. Until now, it was a belief that the situation would change completely, and that one phrase was hidden behind the scenes.
見られることを意識する時点で他者性が入り込み、純粋で自律したものでは無くなる。決して純粋で自律したものが良い悪いでは無く、見られることを意識するかしないかでつくられるものに違いが出ることが面白いと思った。
車窓は夏の郊外の景色、雑草が生い茂る土地の多さに目がいく。しかし、駅周辺だけは立派なマンションが立ち並ぶ。そして、また雑草生い茂る土地ばかり、その中に所々同じような住宅がまた立ち並ぶ。そして、またその繰り返し、どこまで行っても同じ、そこには見られることの意識はあるようで無い。
"What you can see"
At the time of being aware of being seen, otherness enters and it is no longer pure and autonomous. I found it interesting that pure and autonomous things are not good or bad, and that there is a difference in what is made depending on whether or not you are aware of what you see.
From the train window, you can see the scenery of the suburbs in summer and the large amount of weedy land. However, only the area around the station is lined with fine condominiums. And again, there are only weedy lands, and similar houses are lined up in some places. And again, it seems that there is no consciousness of being seen there, which is the same no matter how far you go.
近寄ると見え方が変わる、見えたものが違う時がある。ガッカリする場合もあるし、意外な発見をする場合もある。どちらにせよ、遠くから見た場合と違う方が面白い。
近視眼的な見え方にたえることができる建築を考えることがある。遠くから眺めた時に粗く詳細には見えないが、立体として要所を押さえた造形ならば、それだけで建築として成立する。
しかし、遠くから眺めた時の粗さの中には近視眼的な別な見え方が潜んでいる、いや、潜ましている。その近視眼的な別の見せ方は、よく見ると建築とは関係が無いところで、単なる思いつきの場合もあるが、そのおかげで全く別の見せ方を実現できる。
"Look closer"
When you get closer, the appearance changes, and sometimes what you see is different. Sometimes it's disappointing, and sometimes it's a surprising discovery. Either way, it's more interesting to see it from a distance.
I sometimes think of architecture that can be seen with a short-sighted view. When viewed from a distance, it does not look rough and detailed, but if it is a three-dimensional model that holds down the key points, it will be an architecture by itself.
However, there is another short-sighted view lurking in the roughness when viewed from a distance, no, it is lurking. If you look closely, the other short-sighted way of showing is not related to architecture, and it may be just an idea, but thanks to that, you can realize a completely different way of showing.
捩れ捩れと呟きながら眺めていると案外何でも普通に見えてくる。
捩れが意識を喚起することがあるかもしれないと思った。捩れていない状態ならば、それは普通なことで、日常的なことなので誰も気にも止めないが、捩れている状態のものがあれば、それは普通なことでは無く、日常的なことでもないので、違和感と共に記憶に残ったり、意識したりすることになるだろう。だから、何かを意識させたい時は意図して捩れた状態をつくると良い。
だがしかし、それは普通のやり方では無いので、単に捩れているだけでは、その捩れに慣れてしまえば普通になり違和感は無くなり意識しなくなる。
"Twist and twist"
When you look at it while muttering and twisting, anything unexpectedly looks normal.
I thought the twist might be arousing consciousness. If it's not twisted, it's normal and everyday, so no one cares, but if it's twisted, it's neither normal nor everyday. Therefore, it will be memorable and conscious with a sense of discomfort. Therefore, when you want to be aware of something, you should intentionally create a twisted state.
However, it is not a normal method, so if you just twist it, it will become normal once you get used to the twist, and you will not feel any discomfort and you will not be conscious of it.
小さな所をクローズアップさせて全体をイメージさせるやり方は、部分と全体の関係性で考えるとわかりやすい。部分と全体に関連があるのは当たり前だが、その関係性が部分から全体へと連動していくのか、部分と全体が相似の関係なのかによってちがう。部分から全体へと連動していく場合は、部分と全体が両方とも必要であり、不可分の関係である。それに対して相似の関係は部分が無くて、極端な話、全体が無くても成り立つ。ならば、相似の関係で考えればフレキシブルに部分と全体を考えることができる。
"Part and whole"
The method of making a small part close up and making the whole image is easy to understand when considering the relationship between the part and the whole. It is natural that the part and the whole are related, but it depends on whether the relationship is linked from the part to the whole or whether the part and the whole are similar. When linking from part to whole, both part and whole are necessary, and it is an inseparable relationship. On the other hand, the similar relationship has no part, and it holds even if there is no extreme story or the whole. Then, if we think in a similar relationship, we can flexibly think about the part and the whole.
わかりやすいことは何と建築をつまらなくすることか。
小さい建築故に、遠くからも見渡せる敷地故に、建築全体を瞬時に識別しようと思えばできてしまう。その建築が自ら主張するようなものならば、これ程わかりやすいことはない。思いがままに伝わるように表現できる。
ただ、何でも可視化できてしまう状況は建築をつまらなくする。すぐに全体がわからない、近寄らないとわからないことが必要になる。
"Boring architecture"
What is easy to understand is how to make architecture boring.
Because it is a small building, it can be seen from a distance, so if you want to instantly identify the entire building, you can do it. If the architecture is self-assertive, it's not as easy to understand. It can be expressed as you wish.
However, the situation where anything can be visualized makes architecture boring. You need to know the whole thing right away, and you need to get close to it.
結局、一周して最初の案に戻ることもある。いろいろ試したが、最初の案にインパクトがあったのか、そこに戻って欲しいという話もあり、やはり、一番最初の案は、とにかくいろいろと考えるよりもプレゼンすることで話が先に進むかもしれないので、少しコンセプチュアルな案で印象づけた。
ただ、それはそれでそこからがまた発展させたり、違う展開に持っていこうとして、実際プランは結構変わったが、外観のイメージは残りそうだ。
結構、言葉では説明できない部分も多分に含んでいるので、その時と今の違いを、また設計段階を経て変わったことを盛り込むと、やはり最初の案にはそのままでは違和感があるから、今度はその違和感をうまくデザインに結びつけて、最初の案の延長線にあるものを探り出す。
"First plan"
In the end, it may go around and return to the first plan. I tried various things, but there is also a story that I want you to return to the first plan because it had an impact, so after all, the first plan may go ahead by presenting rather than thinking about it anyway. I couldn't do it, so I impressed with a slightly conceptual idea.
However, that's why the plan has changed quite a bit, trying to develop it again or take it to a different development, but the image of the appearance seems to remain.
There are a lot of parts that can not be explained in words, so if you include the difference between that time and now, and what has changed through the design stage, the first plan still feels strange as it is, so this time Find out what is an extension of the first plan by successfully linking the sense of incongruity to the design.
何かに誘惑されて感情が動けば、誰でも誘惑されたものに関心を持ち意識するだろう。何かのつくり手ならば、その時の誘惑された感情を投影し何かつくるかもしれない。
感情と建築の関わりでいうと、つくり手の感情を建築へどのように投影するかが問われ、その建築がさらに人を魅惑する。そうして感情の連鎖が起こり、建築がつくり手の感情が発端で印象的に広まる。
受け手の感情が発端になることはあるだろうか。あるとしたら、つくり手の感情は存在しない。仮に存在しても建築に投影されることはない。
"Emotions are the beginning"
If something tempts you to move your emotions, everyone will be interested in and aware of what you are tempted to do. If you are a creator of something, you may create something by projecting the tempted emotions at that time.
In terms of the relationship between emotions and architecture, the question is how to project the emotions of the creator onto architecture, and that architecture is even more fascinating. Then, a chain of emotions occurs, and the emotions of the creator of the architecture spread impressively at the beginning.
Can the emotions of the recipient be the starting point? If so, there is no emotion of the creator. Even if it exists, it will not be projected on the architecture.
きっかけがある訳でもないのに、遠くに見えている、ぼんやりだけれども、何かそこにある、段々と近づくにつれてハッキリと輪郭が立ってくる。はじめからそこにあると意識していたようにピンポイントで見つけたような、まわりはボヤけてピントが合っていないけれど、そこにあるのは遠くからピントが合ってわかっていた。
きっとこれらは自分の何かが対象物と結びついた結果で起こる現象だろう。もともと関心があること、探していたもの、興味があったものであれば、結びつきはわかりやすい。その結びつきを予測して、そこにそっと置くだけで良い。ただ、そうすると、もともとの関心や興味などが無ければ何も起こらない。
何も無いところに何かが起こることもあると仮定してみると、そこに置くものはどのようなものが良いのだろうか。目立つものか、奇抜なものか、これらは一瞬は意識するかもしれないが、見慣れたらただ普通に風景に溶け込み、結果何も起こらないような気がする。
もしかしたら、はじめの見え方としては引っ掛かりも無く、意識することも無く、ただそこにある位からはじまるのが良いのかもしれない。
"How to see at the beginning"
It's not a trigger, but it's visible in the distance, it's vague, but something is there, and as it gets closer and closer, the outline becomes clearer. I found it pinpoint as if I was aware that it was there from the beginning, but the surroundings were out of focus, but I knew that it was in focus from a distance.
I'm sure these are phenomena that occur as a result of something of your own being associated with an object. If you're originally interested in, what you're looking for, or what you're interested in, the connection is easy to understand. All you have to do is predict the connection and gently place it there. However, if you do so, nothing will happen if you do not have the original interests and interests.
Assuming that something can happen where there is nothing, what is the best thing to put there? Whether it's conspicuous or wacky, you may be conscious of these for a moment, but once you get used to it, it just blends into the landscape normally, and as a result, nothing happens.
Perhaps the first appearance is that there is no catch, no consciousness, and it is better to just start from there.
たのしいな、面白いな、ワクワクするかもがデザインで実現できたら、できることだと、それは感情を動かすことで、理屈は感情を補うために考えだすことがいい。
ただ目立つことや、派手なことや、奇抜なことや、変わったことだけでは感情は大きく揺れ動くだけ、瞬時に動いたものは瞬時に終わる。
それもいいが、余韻が長くつづくように、例えば、静かな水面に小石をひとつだけポーンと投げ込むことにより、弱い波が立ち、波紋となり伝播していくような感情の動かし方がいい。その小石と投げ込むタイミングを用意するのがデザインの役目かもしれない。
"Make weak emotions"
If a design can realize something fun, interesting, or exciting, then what you can do is move your emotions, and the theory should come up to supplement your emotions.
Just by being conspicuous, flashy, eccentric, or changing, emotions sway greatly, and things that move instantly end instantly.
That's fine, but it's better to move your emotions so that the lingering sound lasts for a long time, for example, by throwing only one pebble on a quiet surface of the water, a weak wave rises and becomes ripples and propagates. It may be the role of the design to prepare the pebbles and the timing to throw them.
まあ、できれば意識されたいし、目立ちたいし、見られたいと思った時にどうすればいいかと、そもそもぼんやりと眺めているものがはっきりと意識の俎上に上がってくる瞬間は何がきっかけで起こるのだろうかと考えてみた。
普段、意識して何かを見ることは案外少ないかもしれない。意外かもしれないが、無意識や惰性で目の前のものを見ていることも多く、いちいち何でも見ることを意識していたら脳がパンクするだろうから、習慣などにして自動で見るようにしていることも多い。
だから、改めて何かを見ることを意識してみると、人が何をきっかけに意識して見るようになるかが気になる。
"The opportunity for consciousness"
Well, if possible, I want to be conscious, I want to stand out, what to do when I want to be seen, what will happen at the moment when what I am vaguely looking at in the first place clearly rises to the height of consciousness? I thought about it.
It may be unexpectedly rare to consciously see something. It may be surprising, but I often look at things in front of me unconsciously or by inertia, and if I was conscious of seeing anything, my brain would puncture, so make it a habit and look at it automatically. Often there are.
Therefore, when I try to be conscious of seeing something again, I am wondering what causes people to be conscious of seeing something.
長い開会式をずっと見てはいられないので、所々は見るというよりは聴いていて、場面が変わりそうになるとまた見て、パフォーマンスは食い入るように、入場行進はぼんやり、はっきりが波のようにくり返される感じなど、その時々で開会式という時間空間の中で思い思いに過ごすのは普段TVを見ないけれど心地良かった。
開会式という枠の中で見たり見なかったり、意識したりしなかったりのくり返しによってつなぎ合わされた映像だけが自分のものとして記憶に残り、自分だけの時間と空間が形成されていく。それは良くも悪くも記録よりも尊く、その積み重ねでしか見られない風景があるような気がする。
"Memory rather than record"
I can't watch the long opening ceremony all the time, so I listen to it rather than see it in places, and when the scene is about to change, I see it again. I don't usually watch TV, but it was comfortable to spend my time in the time space of the opening ceremony, such as the feeling of being returned.
Only the images that are connected by repeating seeing, not seeing, and not being aware of it within the frame of the opening ceremony remain in my memory as my own, and my own time and space are formed. It is more precious than the record, for better or for worse, and I feel that there are landscapes that can only be seen by stacking them.
古い物は良い物だとは簡単には言えないけれど、時代が古い物に触れるだけで時間の感覚の幅が広がるようで面白い。
今この瞬間に生きているのに目の前には何百年も前の物がある。ということは、その間の時間分を自分が吸収して今ここにいるように思える。
実際は目の前にある物が何百年の時を経て存在しているのだが、自分がそれまでの時間分の叡智を持って何百年も前まで遡り、その当時のつくり手に共鳴しようとするので、その間の時間分を吸収しているように思える。だから、時代が古い物に触れるだけで、時間の感覚の幅が広がるし、よりたくさんの試行錯誤をしたような感覚にもなれる。
"Just touch old things"
It's not easy to say that old things are good, but it's interesting that the time can be broadened just by touching old things.
Even though I am alive at this moment, there is something hundreds of years old in front of me. So it seems like I'm here now, absorbing the time in between.
In reality, the thing in front of us has existed for hundreds of years, but with the wisdom of that time, we go back hundreds of years and try to resonate with the creator at that time. So it seems that it is absorbing the time in between. Therefore, just by touching something that is old, you can broaden your sense of time and feel like you have done more trial and error.
デザインの違いを150年間位のクロニクルでみる機会があり、現代に近くなる程デザインに求められているものが段々と重なり合ってくるのがわかった。
はじめの方は対象物と直接的に相対してデザインすることと、その対象物の属性に向けてデザインすることの2つは同時に存在し、その優劣がデザインの良し悪しを決めていたのが、そこに全く違うものを加味して重ね合わせることでデザインの独自性をより出すことをするようになる。
ところが、そのデザインの独自性自体が一昔前のデザインのようにみえてくる。それは独自性に小慣れてきたからかもしれないが、さらに違うものを重ね合わせる必要性を感じさせてしまう。
"Overlapping by the times"
I had the opportunity to see the difference in design in a chronicle for about 150 years, and I found that the closer to the present age, the more the demands for design overlap.
At the beginning, designing directly relative to the object and designing for the attributes of the object existed at the same time, and the superiority or inferiority of the design determined the quality of the design. By adding something completely different to it and superimposing it, the uniqueness of the design will be further enhanced.
However, the uniqueness of the design itself looks like the design of a long time ago. It may be because I've become accustomed to uniqueness, but it makes me feel the need to layer different things.
絶対が無いように、完璧も無く、世の中の全てのことには代替案があると考えてみることにする。
例えば、京都の龍安寺の有名な石庭は足すものが無く、引くものも無いくらいに完成された庭とされているが、もしそこに何かを足すことが求められたら、完成されたものだから何もイメージできないだろうか。
たぶん、ほとんどの人が何か足すことを、それの良し悪しは別として、思い描くことができるだろう。有名で評価が確定されているものだから完成されたと思い込んでいるだけで、何かをして別のものや代わりのものにする余地はあり、それも複数の違うものを思い描くことができるだろう。
だから、何かで頭が凝り固まってしまった時、引くより足す方が建設的な意識に向きやすいので、何か足すことを考えると現状に対して批判的で建設的な考えが浮かびやすい。
"Add something"
Just as there is absolutely, there is no perfection, and I think that everything in the world has alternatives.
For example, the famous stone garden of Ryoanji Temple in Kyoto is said to be a complete garden with nothing to add and nothing to draw, but if something is required to add to it, it is completed. Can't you imagine anything?
Maybe most people can imagine adding something, good or bad. Just believing that it's complete because it's well-known and well-established, there's room for something else or alternative, and you'll be able to envision several different things. ..
Therefore, when something makes my head stiff, adding something is more likely to lead to a constructive consciousness than pulling it, so when I think about adding something, it is easy to come up with a critical and constructive idea about the current situation.
いつも同じじゃつまらない。何か違うことと思いながらいつも同じになるのを避けたいと思う。
それには全てを肯定しながら別視点を持つように、意図的に別の角度から見るように、ただ別の角度を探すには一旦全てを否定しないとなかなか別の角度の存在に気がつかないだろう。
ところが、一旦全てを否定することが簡単にできそうでなかなかできない。全てだから何もかもになるが、何事にも対しても全てを否定することに抵抗感を覚える。万が一や、もったいないなどの感覚が湧いてくるのだろう。
だから、否定することを容易にするために、疑問に思うことにした。疑問に思うだけならば、いささか抵抗感が薄れるし、疑問にも思えないような場合は行っていることに対してきちんと準備や段取りなどができていない時かもしれないと思った。
"doubt"
It's always the same and boring. I want to avoid being the same all the time, thinking something different.
To do that, just like looking at another angle while affirming everything, intentionally looking at it from another angle, you will not notice the existence of another angle unless you deny everything once to look for another angle. ..
However, it seems easy to deny everything once, and it is difficult to do so. It's all, so everything becomes everything, but I feel reluctant to deny everything. In the unlikely event, you will feel a sense of waste.
So I decided to wonder to make it easier to deny. If I just wonder, I feel a little less reluctant, and if I don't think I'm wondering, I thought it might be a time when I wasn't properly prepared and set up for what I was doing.
何かついてデザインしようとした時に、その対象物との直接的なやり取りの中から何かヒントになることを見つけようとする場合と、その対象物の属性のようなものを抽出し、その属性に対応したデザインを考える場合とがある。
デザインが与える影響を考えるならば、なるべく多くの人に、なるべく深くを理想とするだろう。なるべく多くを目指す場合は属性に対応した方が目的を果たしやすく、なるべく深くを考えるならば直接的に対象物に対してデザインをしていく方が良いかもしれない。
では、なるべく多く深くに影響を与えたいとするならば、属性と直接的に対象物に対してデザインすることの両方を満たすことを考えるのでは無くて、両方を否定しつつ、完全否定するのでは無く、両方とのつながりは保ちつつ、全く違う別角度を探さなくてはならない。
"Do not completely deny"
When trying to design something, if you try to find some hints from the direct interaction with the object, or if you extract something like the attribute of the object and that attribute There are times when we think of a design that corresponds to.
Given the impact of design, the ideal would be as deep as possible for as many people as possible. When aiming for as many as possible, it is easier to achieve the purpose by corresponding to the attributes, and if you think as deeply as possible, it may be better to design directly for the object.
So, if you want to influence as much and deeply as possible, instead of thinking about satisfying both attributes and designing directly for the object, you should deny both and completely deny them. Instead, we have to find a completely different angle while maintaining a connection with both.
見ているようで見てないものが急に意識するようになる時に何がきっかけになるのかと考えてみると、2つのきっかけが思い浮かんだ。
ひとつ目は対象物との関係性に気づく時で、最初は関係性などわからずに見ているのか見ていないのかがはっきりとしない状態なのだが、何か細い糸くらいかもしれないが、関係性が見つかると急に自分のことのように意識し出す。
ふたつ目も関係性ではあるのだが、直接的な関係ではなく、その対象物と自分が属している社会や集団などとの関係性があらわになった時で、自分が属する社会や集団の中でその対象物の存在が円滑さをや阻害を招くかもしれない時に意識せざるを得ない。
現実的にはふたつ目の方が多いような気がする。何かを意識する時は意外と自分以外からの影響を受けているのかもしれない。
"Be aware"
When I thought about what triggered me when I suddenly became aware of what I was seeing but not seeing, I came up with two triggers.
The first is when you notice the relationship with the object, and at first it is not clear whether you are looking at it or not, but it may be something thin, but the relationship is When I find it, I suddenly start to think of myself.
The second is also a relationship, but it is not a direct relationship, but when the relationship between the object and the society or group to which you belong becomes apparent, within the society or group to which you belong. I have to be aware of this when the existence of the object may hinder smoothness or hindrance.
In reality, I feel that there are more second ones. When I am conscious of something, I may be influenced by something other than myself.
考えて言葉にすることと現実に出来上がるものとのギャップはどうするか。たぶん言葉は希望的観測を後から付け足す。おかしな話だが、人は過去も未来もバラ色に描くから仕方がないがガッカリするのは避けない。
わかる、わかる、そう言いたくなるのはわかる。でもそれ後付けでしょと言いたくなる。ただ、初めに全てが決まっている必要はない。段々と決まっていけばいい。何かを初めに期待し過ぎるのかもしれない。
全てが今、完結させる必要がないと考えるならば、きっとものづくりが変わるだろう。
"No need to complete"
What is the gap between thinking and putting it into words and what is actually produced? Maybe words add wishful thinking later. It's a funny story, but people can't help but be disappointed because they draw the past and the future in rosy colors.
I understand, I understand, I understand that I want to say that. But I want to say that it is a retrofit. However, it is not necessary that everything is decided at the beginning. It should be decided gradually. You may be expecting something too much at the beginning.
If you think that everything does not need to be completed now, manufacturing will surely change.
気持ちよかったな、と後から没頭していた時を振り返り思ったりもするが、その没頭している最中は何も考えてはいないだろう。没頭している時は没頭している物と一体感があり、没頭している物が自分自身の身体とつながり、身体の延長にあるような感覚にすらなる。
いつも思うのはデザインが対象物であることで、自分自身とは対峙するように存在している。もしデザインが自身に纏わりつくように存在するならば、自分自身の身体の一部として機能するだろう。その時のデザインはもはや「デザイン」とは言わずに皮膚に近い存在、新たな「スキン」かもしれない。
それは「服」が実現し担っているようにも思えるが、「服」の場合、身体と服との間に空間が存在する。その空間があるが故に、「服」が身体に纏わりついているとはいえず、ただ単に「身体」と「服」という二項に分かれている状態に過ぎなくなる。服は身体だとの間の空間をデザインしているともいえる。
"Design that clings together"
I sometimes think back to the time when I was absorbed in it, but I don't think I was thinking about anything while I was absorbed in it. When you are absorbed, you have a sense of unity with the things you are immersed in, and the things you are immersed in are connected to your own body, even feeling like an extension of your body.
I always think that design is an object, and it exists to confront myself. If the design exists to cling to itself, it will function as part of its own body. The design at that time is no longer called "design", but it may be a new "skin" that is close to the skin.
It seems that "clothes" are realized and responsible, but in the case of "clothes", there is a space between the body and the clothes. Because of that space, it cannot be said that "clothes" are tied to the body, but simply divided into two terms, "body" and "clothes." It can be said that clothes design the space between the body.
ワンシーンが頭をよぎったら、その時ひとは今ここにはいない。
ワンシーンを思い浮かべてもらえれば、その人との関係性が生まれる。ワンシーンに特化したデザインが持つ可能性はこの関係性の構築だろう。
ただし、そのための準備にデザインをまず受け入れることができる感情が必要である。その感情の部分までもデザインが担う時にはじめてかけがえの無いものが生まれるような気がする。
"Making irreplaceable things"
If one scene crosses my head, then no one is here now.
If you think of a scene, you will have a relationship with that person. The possibility of a one-scene-specific design would be to build this relationship.
However, the preparation for that requires the feeling of being able to accept the design first. I feel that irreplaceable things are born only when the design takes charge of even the emotional part.
穴があったら入りたい、と同じ気持ちなのだろうか。
穴も空間の一種、素材の空隙だと考えるならば、空間は素材の違いを色濃く反映するだろう。
例えば、大きな木の塊をくり抜いた穴の空間は、同じく大きな石の中をくり抜いた穴の空間と空間の大きさや形が同じでも受ける印象が全く違うものになるだろう。
さらに、同じ木でも棒のような木材を組み上げて穴ような空隙をつくる場合と、平らな板状の木材を立て掛けるようにつくった穴のような空隙もまた違う印象になるだろう。
同じ素材でも、素材自体の形が変われば、空間の印象も変わる。それは単純でミニマムな空間ほど顕著であり、より素材の違いを反映する。
だから、ミニマムな空間をつくる時、まず最初に考えるのは、何でつくるか、素材が頭に浮かび、次に素材に合わせたデザインを考える、穴があったら入りたくなるように。
"If there is a hole"
Is it the same feeling that I want to enter if there is a hole?
If you think of a hole as a kind of space, a void in the material, the space will strongly reflect the difference in the material.
For example, the space of a hole hollowed out from a large block of wood will give a completely different impression even if the size and shape of the space are the same as the space of a hole hollowed out in the same large stone.
Furthermore, even if the same wood is used, the impression of a hole-like void made by assembling stick-like wood and a hole-like void made by leaning a flat plate-shaped wood will give a different impression.
Even with the same material, if the shape of the material itself changes, the impression of the space will also change. It is more noticeable in a simple and minimal space, and more reflects the difference in materials.
Therefore, when creating a minimal space, the first thing to think about is what to make, the material comes to mind, then the design that matches the material, so that if there is a hole, you will want to enter.
つながりができれば、必ず感情が揺さぶられてしまう。人は誰でも、子供でも大人でも、感情の発露を欲している。どうでもいいとはつながりが無いこと。どうでもよければ、何の関心も無く、感情も湧いてこない。ただ、必ずしもプラスの感情とは限らず、マイナスの感情が湧いてくる場合もあるが、それでも感情が振れることには変わりがなく、振れ幅が大事になり、振れ幅の大きさが印象の度合いに比例する。
簡単に強い印象を残したいならば、第一印象で好かれるよりも嫌われることをしてマイナスの感情を引き出す方がいいかもしれない。何をすれば好かれるかは人によって違うが、何をすれば嫌われるかは大体皆同じだから。
それでもできれば好かれることによって深い印象を残したい、できれば大勢の人に対してと考えてしまうが、そのままでは無理なのである、何をすれば好かれるかは人によって違うから。なのに建築は大勢の人に対して好かれようとする。ならば、人によって好かれることとデザインを結びつけて間を取るような中庸的なことを考えればよいのだが、好かれるか、嫌われるかのどちらかにしか向かない場合が多い。
"Is it liked or disliked?"
If you can make a connection, your emotions will surely be shaken. Everyone, children and adults, wants to express their emotions. It doesn't matter that there is no connection. If it doesn't matter, I have no interest and no emotions. However, it is not always a positive emotion, and there are cases where negative emotions arise, but even so, the emotions still swing, the swing width is important, and the magnitude of the swing width is the degree of impression. Is proportional to.
If you want to easily leave a strong impression, it may be better to dislike it and elicit negative emotions than to be liked by the first impression. What you do is different for each person, but what you do is generally the same.
Even so, if possible, I would like to leave a deep impression by being liked, and if possible, I would think that it would be for a large number of people, but it is impossible as it is, because what you like is different for each person. Yet architecture is going to be liked by a lot of people. If so, you can think of a moderate thing that connects the design with what people like, but in many cases it is only suitable for either being liked or disliked.
つながりがないデザインは美しくても引っ掛かりがないので印象に残らない。
デザインしたもの自体がそれを見たり使ったりする人と何もつながりが無ければ、例え先鋭的なものでも、その人にとっては価値が無いものになってしまう。
ならば、つながりをつくることができれば、どのようなデザインでも受け入れる。デザインとはつながりをつくることだといえる。
"Make a connection"
Even if the design is beautiful, it doesn't get caught, so it doesn't leave an impression.
If the design itself has no connection to the person who sees or uses it, even a sharp one will be of no value to that person.
Then, if you can make a connection, accept any design. It can be said that design is to make a connection.
意識させるにはどうするか。全く何にも引っ掛からない、何も思わない、何も惹かないものを、決して悪くはないのに、むしろ良いぐらいなのに、なぜか意識に残らないものをどうしたら、何をすれば意識に残させることができるのか。それは建築を意識することが無い人に何をすればいいのか、もっと言うと、偏った建築観を持つ一般の人に何をすれば偏りが無くなるのかに通じる。
誰でも絶対にそれは正しいという見方をしてしまいがちだが、大概は勘違いであり、意識が狭くなる。狭い意識を広げるには、他のこととたくさんのつながりを持ち、関係性を築いていくしかない。
"Make consciousness"
How do you make them aware? Things that don't get caught in anything, don't think, don't attract anything, things that aren't bad, but rather good, but somehow unconscious, what should I do to keep them in consciousness? Can you do it? It leads to what to do for people who are not conscious of architecture, and more specifically, what to do for ordinary people who have a biased view of architecture.
Everyone tends to think that it is absolutely correct, but most of the time it is a misunderstanding and narrows consciousness. The only way to broaden your narrow consciousness is to have many connections and relationships with other things.
何をやっても人に深い印象を残したい、何かをつくるならば、建築以外でも、料理でも、本でも、記事でも、つくり手はそう考えてしまう。何かを発信したら受け手に好印象を与えたいとつくり手は自然に意識するでしょう。
その時つくり手はつくるものの精度を上げようとする。しかし、精度と印象は全く関係が無い。このことを誰もが勘違いをする、良いものをつくればいいと。
ものの良し悪しは前提であり、つくり手として良いものをつくるのは当たり前のことである。深い好印象を与えるには、受け手とどのような関係性を築くが大事であり、つくることが良い関係性を築くことになる場合が一番いい。だから、デザインすることは関係性を築くことだと考えている。
"To make an impression"
If you want to leave a deep impression on people no matter what you do, if you want to make something, the creator will think so, whether it is architecture, cooking, books, articles. The creator will naturally be aware that he wants to give a good impression to the recipient when he sends something.
At that time, the creator tries to improve the accuracy of what he makes. However, accuracy and impression have nothing to do with each other. Everyone should misunderstand this and make a good one.
Good or bad things are a premise, and it is natural to make good things as a maker. In order to give a deep impression, it is important to build a relationship with the recipient, and it is best to build a good relationship. So I think designing is about building relationships.
見てるようで見てないのです。1日にどのくらいの数の建築を見ますか、通勤や通学、外出をすれば、その数は無数に近い。しかし、夜に振り返って思い出せますか、昼間見た建築を。見てはいるけれど意識に上がってこない状態です。
建築は何気ない風景の一部であり、大きな変化でもない限り印象に残らないのが現実でしょう。だから、その印象を深いものにしたい。
人に印象を残すことは建築以外でも実はなかなか難しいことかもしれません。きっと印象に残す手法があるようでハッキリとわからない人が多いから、全ての人に満遍なく好印象を与えようとし過ぎるからです。
"did not see"
It seems to be watching, but not watching. How many buildings do you see in a day? If you commute to work, go to school, or go out, the number is close to innumerable. But can you recall the architecture you saw in the daytime? I'm watching it, but I'm not conscious of it.
Architecture is part of a casual landscape, and the reality is that it won't leave an impression unless it's a big change. Therefore, I want to deepen that impression.
It may be quite difficult to leave an impression on people other than architecture. There seems to be a method to leave an impression on many people, and many people don't understand it clearly, so they try to give a good impression to everyone.
代わりがきかないものを代わりがきくものに変える行為がデザインだと考えている。メタボリズム建築は代わりがきくものと代わりがきかないものを選別し、その選別した様をそのままデザインとして表現したから、その選別に意味が無くなるとメダボリズムの考え方と共に建築自体も存続できなくなる。代わりがきかないものをまず弱め、別視点から代わりがきくものに変える。それはもの自体を入れ替えるというよりは扱いを変えることであり、建築のようにスケールが大きいものだからできることである。
"Change the treatment"
I think design is the act of changing something that cannot be replaced into something that can be replaced. Metabolism architecture selects irreplaceable and irreplaceable ones and expresses the selected as it is as a design, so if the selection becomes meaningless, the architecture itself cannot survive along with the idea of medabolism. Weak things that cannot be replaced first, and then change them from a different perspective to something that can be replaced. It's more about changing the treatment than replacing the things themselves, and it's possible because it's a large scale thing like architecture.
もし入れ替わったらなど思うことはないだろうか。あるとしたら、同じ種別同士で考えるだろう。例えば、人と人などで、入れ替えるということは比べることができるもの同士となる。
ここでもし、比べることができないもの同士を入れ替えることを考えた場合はどうなるだろうか。例がなかなか浮かばないが、映画『猿の惑星』のように人と猿の立場を入れ替えるようなことをしただけで物語はできあがる位に、比べることができないもの同士を入れ替えることが持つ力は大きい。
"Replace"
Wouldn't it be great if they were replaced? If so, we would think of the same type. For example, exchanging between people is something that can be compared.
What if we think about swapping things that can't be compared? It's hard to come up with an example, but the power of exchanging incomparable things is great, as the story can be completed just by exchanging the positions of people and monkeys like in the movie "Planet of the Apes". ..
括弧の中の括弧の中の括弧の中にあるものは、括弧の外にあるものと何がちがうのだろうか。括弧を様々なものに見立てることができるが、括弧自体の存在がどうなのか、その括弧は誰がつくったのか、誰のものか、本当にあるのかなど、括弧自体を問うことが大事だが、実際には括弧があることは前提で、あとは括弧の構成を見抜き、括弧に対してどのような扱いをするのかが優劣を決める。そこに少し括弧を別なものに見せる要素を加えたい、そうすれば括弧自体を問うことになるし、括弧の外側も巻き込むことができるかもしれない。ちなみに、括弧は固定されておらず、代替可能で仮のものだとイメージしており、括弧に当たる部分を見つけだすことがものづくりの最初の一歩だと考えている。
"Outside the parentheses"
What is inside the parentheses inside the parentheses and what is inside the parentheses is different from what is outside the parentheses? You can think of parentheses as various things, but it is important to ask the parentheses themselves, such as what the parentheses themselves are, who made them, who they belong to, and whether they really exist. It is premised that there are parentheses, and after that, the structure of the parentheses is determined, and the superiority or inferiority of how to treat the parentheses is decided. I want to add an element that makes the parentheses look a little different, so that I'm asking the parentheses themselves, and maybe I can involve the outside of the parentheses as well. By the way, the parentheses are not fixed, and I imagine that they are substitutable and temporary, and I think that finding the part corresponding to the parentheses is the first step in manufacturing.
なかなか手強いし、なかなか上手くいかないが、ちょっとのことがトリガーになり、徐々に変化してきた。誰もやっていないから最初はできないと思ったが、面白いものである時突然に、もしかしたら、と思ってしまって、いろいろ調べたら、なんとできる方法が見つかった。
ただそうなると、今やりたいことが倍になってしまった。没頭できる時間を増やしたいのに増やせないのが一番辛いので、知恵を貸してくれる人は本当に有り難い。おかげで解決できたことがたくさんあり、肝心なことに取り組める時間を確保できたが、より深遠な所まで求めるようになってしまった。
いい材料は探せば結構ある。しかし、大事なのは使い方で、いい材料と使い方がセットにされていることに意味がある。そこが肝心なのだが、人はいい材料ばかり求めてしまい、使い方が大事だと思わない。いい材料があればそれで良しは正解ではないのに。
"Wisdom and time, good materials and usage"
It's tough and it doesn't work, but a little thing triggered it and it gradually changed. At first I thought I couldn't do it because nobody was doing it, but when it was interesting, I suddenly thought it might be possible, and after a lot of research, I found a way to do it.
But then, what I wanted to do now doubled. I want to increase the amount of time I can immerse myself in, but it's hardest not to increase it, so I'm really grateful to anyone who lends me wisdom. Thanks to that, I was able to solve many things, and I was able to secure time to work on the important things, but I began to seek deeper places.
There are quite a few good materials to look for. However, the important thing is how to use it, and it makes sense that good materials and how to use it are set. That's the point, but people just want good materials, and I don't think it's important to use them. If there is good material, that is not the correct answer.
ガタン、ゴトンと毎日毎日うるさいし、揺れる。近くの解体工事現場の音と揺れ、お互いさまでも日中家にいるとちょっとイライラ、それに近くを通るとカビ臭いから現場の前は通らない。
やっとしなくなったので、久しぶりに前を通ると景色が一変、当たり前だが何も無い。なんか新鮮というか、こんなに広い空き地というか、空き地は何かを建てる前提だから、すぐに変わるし、なかなか見ないから、いつもこのまま何も無ければいいのに。
結局、空き地は何かの空間で埋まる。どうせ埋めるならば、周りが喜ぶもので埋めて欲しい。せめてデザインはよくして欲しい。
"Filling vacant lot"
It is noisy and shakes every day with rattling and goton. The sound and shaking of the nearby demolition work site made me feel a little annoyed when I was at home during the day, and when I passed near it, I couldn't pass in front of the site because of the musty smell.
It's finally gone, so when I pass in front of me for the first time in a while, the scenery changes completely, and it's natural, but nothing. It's kind of fresh, it's such a large vacant lot, it's a premise to build something, so it changes quickly and it's hard to see, so I wish I had nothing as it is.
After all, the vacant lot is filled with some space. If you want to fill it anyway, please fill it with something that makes people happy. I want you to at least improve the design.
自分の声には3種類あるらしい。ひとつは自分の耳で聞く自分の声、もうひとつは他人が耳で聞く自分の声、そして最後がレコーディングした自分の声で、それぞれみな違うらしい。らしいというのは、他人が耳で聞く自分の声だけはわからないからで、今まではレコーディングした自分の声を他人が耳で聞く自分の声だと思っていた。
声という自分が発する分身のような存在にも自分では把握できない部分があることが面白く、声には言葉がのり、他人に対して説得や伝達などを行うためにコントロールする必要があると思っていたが、そもそも全てをコントロールできないかもしれない。
自分の声なのに他人に委ねる部分があり、それに気づかず説得や伝達を試みていたら上手くいく確率が下がるかもしれないと思ったが、全ての人がそうであるならば、他人に委ねている部分をつくること、すなわち、自分の声を発するだけでコミニケーションがはじまることになるとも思った。
"My voice"
It seems that there are three types of voices. One is your own voice that you hear with your own ears, the other is your own voice that others hear, and the last is your own voice that you recorded. It seems to be because I don't know only my own voice that others hear, so I used to think that it was my own voice that others heard.
It is interesting that there is a part of the voice that is like an alter ego that I can not grasp, and I think that it is necessary to control the voice in order to persuade and communicate with others. However, you may not be able to control everything in the first place.
There is a part that I entrust to others even though it is my own voice, and I thought that if I tried to persuade and communicate without noticing it, the probability of success would decrease, but if everyone is so, the part that I entrust to others I also thought that communication would start just by making a voice, that is, by uttering one's own voice.
「見える」と「見る」について、案外やりがちで大丈夫かなと心配になることについて考えてみた。建築設計をしている時の視点は俯瞰であり鳥瞰なので、意識して建築を見ることになる。意識することにより「見る」が審美眼になり、規律や秩序を保とうとする。この場合の規律や秩序には技術的なことや意匠的なことも含むので、「見る」が一定の水準を保つことに役立つ。それは建築以外のことでも同じだろう。「見る」ことかあると厳しく洗練される。
しかし、「見る」ことを意識するのは当事者だけなので、本当は「見える」ことを意識する必要がある。「見る」ことで抜け落ちたことが「見える」ことになり、当事者以外は「見える」しか意識しない。
一定の水準を保つ「見る」にプラスして「見える」ことを意識できるのが一番良いのだが、それができる人はほとんどいないから「見える」視点を持つ人が最強かもしれない。
"The strongest theory of" visible "people"
Regarding "seeing" and "seeing", I thought about the unexpected tendency to worry about whether it would be okay. When designing an architecture, the viewpoint is a bird's-eye view and a bird's-eye view, so you will be conscious of looking at the architecture. By being conscious, "seeing" becomes an aesthetic eye and tries to maintain discipline and order. Since the discipline and order in this case include technical and design matters, "seeing" helps to maintain a certain level. It would be the same for things other than architecture. When there is something to "see", it is severely refined.
However, since only the parties are conscious of "seeing", it is necessary to be conscious of "seeing" in reality. By "seeing", what is missing becomes "visible", and only "visible" is conscious of other than the parties concerned.
It is best to be aware of "seeing" in addition to "seeing" that maintains a certain level, but since few people can do that, those who have a "visible" perspective may be the strongest.
高い所から見下ろす東京は一面見渡す限り建築に覆われていて、一部皇居や代々木公園などの緑はあっても、地面を見ることができないくらい建築だらけである。
その光景は地上にいる時とは違う感覚を抱かせる。地上では確かに建築に囲まれている感じはあるが、道路があり空が一面に広がるから、そこまで建築に覆われている感じがない。その違いは単に見る視点の違いだけだろうか。それならば簡単な話だが、視点によって見える建築の部位が違う影響はないだろうか。
高い所から見下ろす時は屋根がよく見える。地上にいる時は屋根はほとんど見えない。都市との関係で建築を考える時は屋根が重要な要素になるのではないか。もしそうならば、建築=屋根として考えてみると面白いかもしれない。
"Tokyo full of roofs"
Looking down from a high place, Tokyo is covered with architecture as far as the eye can see, and even though there is some greenery such as the Imperial Palace and Yoyogi Park, it is so full of architecture that you cannot see the ground.
The scene gives a different feeling than when you are on the ground. On the ground, it certainly feels like it's surrounded by architecture, but because there are roads and the sky spreads all over, it doesn't feel like it's covered with architecture. Is the difference just the difference in the viewpoint of viewing? That's a simple story, but isn't there an effect that the parts of the building that can be seen differ depending on the viewpoint?
When looking down from a high place, you can see the roof well. You can hardly see the roof when you are on the ground. The roof may be an important factor when considering architecture in relation to the city. If so, it may be interesting to think of architecture as roof.
関係性について考えてしまう。建築を考える時に都市の中にどのように置くか、都市との関係をどうするか、いろいろな手法があるが、そのどれでもない手法はないものかと建築のプランと絡めながら考える。その過程は楽しいものでいろいろと巡る思考遊びのようだが、そもそも正解がある訳ではなく、一般的な所で理解されるように落とし込み、調整をし、伝える必要があるので結構考え込む。最近は屋根について、隣り合う建築同士を関係づけるアイテムとして考えている。屋根の可能性みたいことを問い直そうとしているが、知っているようで案外知らないアイテムかもしれない。屋根の機能を抜いたところでも存在する価値を探している。
"Existence of roof"
I think about the relationship. When thinking about architecture, there are various methods such as how to put them in the city and how to relate to the city, but I think that there is no method that is none of them in connection with the architectural plan. The process is fun and seems to be a play of thinking around various things, but there is no correct answer in the first place, and it is necessary to make adjustments and convey it so that it can be understood in general places, so I think about it quite a bit. Recently, I've been thinking about roofs as an item that connects adjacent buildings. I'm trying to re-question the possibilities of the roof, but it may be an item that seems to be known but unexpectedly unknown. We are looking for value that exists even if the function of the roof is removed.
敷地に対して建築面積の余裕があるから、屋根の形状をプランの平面形状とは関係無しに構築しでみようと考えてみた。
屋根はプランの平面形状を覆うイメージから、屋根の平面形状はプランに従う。しかし、屋根に求められる機能はプランとは関連性が無いので、屋根の平面形状がプランに従う必要性は全く無い。
屋根とプランを別々にデザインしてみようと考えている。その時にプラン上で何か変化が起きるか、屋根の存在が変わるかを見てみたい。
"Roof and plan separately"
Since there is room in the building area for the site, I thought about constructing the roof shape regardless of the plan shape.
From the image that the roof covers the plan shape, the plan shape of the roof follows the plan. However, since the functions required for the roof are not related to the plan, there is no need for the plan shape of the roof to follow the plan.
I'm thinking of designing the roof and the plan separately. I would like to see if something changes on the plan at that time or if the existence of the roof changes.
勝手に決めつけていることは本人にはその意識がないのでわからない。その場合、根拠を求めていくと大概は曖昧になり、結局は思い込みだったりするのだが、意識がないので根拠も求めない。厄介なものでなかなか気がつかない。さらに厄介なのは過小評価してしまうことだ、相手に対しても、自分に対しても。どこかで修正しないとズレるばかり、自然に戻ることは無いが、一旦気がつけば瞬時に全てが解ける。思い込みということだけに気がつきさえすれば良いのだが、なかなか手強いものである。
"Tough things"
I don't know what I'm deciding on my own because I don't have that consciousness. In that case, when you ask for the grounds, it usually becomes ambiguous, and in the end it is a belief, but since you are not conscious, you do not ask for the grounds either. It's awkward and hard to notice. Even more troublesome is to underestimate, both to the other person and to yourself. If you don't fix it somewhere, it will just shift and will not return to nature, but once you notice it, everything can be solved instantly. All you have to do is realize that it's a belief, but it's quite tough.
なかなか上手くまとまらなかったので、思い切って根底から変えてみようと試みたら、案外簡単に収まりよくまとまった。今までの慣習に囚われているとなかなかできないが、少しだけ適当に曖昧になると囚われていたものがわかる。
何か特別なことをしようとすると全てが普通に見える。普通に収まる時点で特別なことかもしれないのに、収まることが簡単に思えて普通に見える。もう少しだけ解像度を上げて見てみると普通では無いところが見つかるかもしれない。見方しだいで特別にも普通にも見えるのかもしれない。
"Depending on the viewpoint"
It didn't come together very well, so I took the plunge and tried to change it from the ground up, but it was unexpectedly easy and well organized. It's hard to do if you're trapped in the customs of the past, but if you get a little vague, you'll find out what you've been trapped in.
Everything looks normal when you try to do something special. It may be special when it fits normally, but it seems easy to fit and looks normal. If you raise the resolution a little more and look at it, you may find something unusual. Depending on how you look at it, it may look special or normal.
建ち方に屋根はどのような影響を与えるのかを考えてみた。プランを考える時は鳥瞰的に見るので、屋根も真上から俯瞰し考えるが実際はそのような見え方はしない。
屋根の連なりに地域性が現れることもある。例えば、合掌造りの民家は単体の外観だけでも特徴的だが、たくさんの合掌造りの民家が建った集落は独自の風景を生み出す。また、旧街道の昔は宿場町だったような場所では、長屋のように連続して密着して建ち、低い軒と竪格子の連なりがやはり独特の景観をつくり出す。
これらの例は建ち方に地域性が現れ、その地域性を表現するアイテムとして屋根が用いられている。いわば屋根はアイコンの一部を成している。
"Roof as an icon"
I thought about how the roof would affect how it was built. When thinking about a plan, I look at it from a bird's-eye view, so I think about the roof from directly above, but in reality it doesn't look like that.
Regionality may appear in the series of roofs. For example, a gassho-style private house is unique in its appearance, but a village with many gassho-style private houses creates a unique landscape. Also, in places that used to be post towns on the old highway, they are built in close contact with each other like a Nagaya, and the low eaves and vertical lattices create a unique landscape.
In these examples, regionality appears in the way of construction, and the roof is used as an item to express that regionality. So to speak, the roof forms part of the icon
建ち方に地形の要素も加えれば、よりその場でしか成り立たない建築になると考えた。地形は唯一の変わらない要素として、その土地固有の時間の流れを継承しており、地形以外の要素はほとんどが時間の経過とともに無くなる。
建築もまた時間の経過とともに無くなる存在だが、地形を反映したものであれば、時間の流れの一部になり得るかもしれない。地形を反映しないその時だけのハリボテ建築では風景の一部にすらならないので、地形を反映した建ち方を模索している。
"Terrain, time and how to build"
I thought that if we added topographical elements to the way the building was built, it would be a building that could only be built on the spot. The terrain is the only unchanging element that inherits the land's unique flow of time, with most non-terrain elements disappearing over time.
Architecture also disappears over time, but if it reflects the terrain, it could become part of the flow of time. Since the Haribote architecture that does not reflect the terrain is not even a part of the landscape, we are looking for a way to build it that reflects the terrain.
建築の建ち方を隣りとのつながりをつくるために考えている。建築面積に対して敷地面積に余裕がある建築はなかなか無いので、建ち方は敷地形状に影響を受けることが多い。
もし余裕がある場合はどうするだろうか。もちろん、日当たりを考えて方位を意識するだろうが、隣りとのつながりをつくるために方位は役に立たない。余裕があれば、上から俯瞰した時にある程度建つ位置や角度も自由になる。お互いに共通した特有の角度を持つこともでき、その角度が周辺環境に存在しない場合は、その角度を揃えるだけでつながりがあると見なせる。
"Connection by how to build"
I am thinking about how to build an architecture in order to make a connection with the neighbor. Since it is difficult to find a building that has a sufficient site area for the building area, the construction method is often affected by the site shape.
What if you can afford it? Of course, you will be aware of the orientation in consideration of the sunlight, but the orientation is useless to make a connection with the neighbor. If you can afford it, you can freely set the position and angle to some extent when you look down from above. They can have unique angles that are common to each other, and if that angle does not exist in the surrounding environment, it can be considered that there is a connection simply by aligning the angles.
隣り合うビルディングタイプの異なる建築が間を空けて建っている場合にどのようにすれば関係性があるように見えるかを考えてみた。
建築同士の間には敷地境界線が存在するので、越境してつながることはできないから、隣り合う建築に何かデザイン上で共通するものがあれば良いと考えるのが一番簡単かもしれない。
外壁の仕上げ、屋根の形や高さなどの外観上の特徴に共通点があれば一目でわかりやすいが、それではよくある建売の連なりのようでよろしくない。
外観上の特徴ではなく、建築自体の建ち方で関係性をつくれないかと考えている。
"Searching for relationships"
I thought about how it would seem to be related when adjacent buildings of different building types were built at intervals.
Since there is a site boundary between buildings, it is not possible to cross the border and connect, so it may be easiest to think that it would be good if there was something in common in the design of adjacent buildings.
It's easy to understand at a glance if there are similarities in appearance features such as the finish of the outer wall and the shape and height of the roof, but that doesn't seem to be a series of common construction sales.
I'm wondering if it's possible to create a relationship based on how the architecture itself is built, rather than on the appearance.
分棟配置にするには、1つの敷地に1つの建築という原則があるので、敷地内に境界線を設定する必要がある。境界線をつくり明確に区切りをつけるのに、その境界線は分棟配置というお互い何らかのつながりをつくるために用いられる。
越境目的の境界線だから目には見えなく実体もないから、無いようなものだ。分棟という建築の配置による作用が境界線としての特徴を全て消し去ることが面白い。分棟を拡大解釈すれば、都市の中で個々に分かれて建つ建築とみなすことはできないだろうか。隣りの建築とつながりたいと思えば境界線が消失するなんて素敵だ。
"Boundary disappearance"
In order to arrange the buildings in separate buildings, there is a principle of one building on one site, so it is necessary to set a boundary line on the site. Boundaries are used to create a clear delimiter, and the boundaries are used to create some kind of connection with each other, which is a branch layout.
It's a borderline for cross-border purposes, so it's invisible and insubstantial, so it's like nothing. It is interesting that the action of the layout of the building, which is a branch building, erases all the characteristics as a boundary line. If the branch building is expanded and interpreted, can it be regarded as an individual building in the city? It's nice that the boundaries disappear if you want to connect with the next building.
ビルディングタイプが違う建築を並列に並べる計画をしているが、その間には敷地境界線が設定されるので、境界線を越えてつなげることができない。つなげることができれば面白い計画になると当初から考えているので、越境ができなくてもつながる方法を模索しているが、そもそもつなげたいと思う衝動はどこから来るのかと考えてみた。
同じクライアントで同時期に計画をするから、何か関連性を持たせたいと自然に考えるが、その根底には境界線といういわば結界のような存在に対して普段から不自由さを抱いていて、単体の建築を超えて都市的な目線で考えた時に、より周辺環境に影響を与える建築をつくりたいと考えるからだろう。
"Impulse to connect"
We are planning to arrange buildings of different building types in parallel, but since the site boundary is set between them, it is not possible to connect across the boundary. From the beginning, I thought that it would be an interesting plan if I could connect, so I'm looking for a way to connect even if I can't cross the border, but I wondered where the urge to connect comes from.
Since the same client plans at the same time, I naturally think that I want to have something to do with it, but at the root of it, I usually have inconvenience for the existence of a boundary, which is like a barrier. This is probably because he wants to create an architecture that has a greater impact on the surrounding environment when he thinks from an urban perspective beyond a single architecture.
1つの敷地に1つの建築という原則があるので、分棟配置をする時に境界線が設定される場合がある。分棟配置をすると分棟間に「間」ができ、その「間」がすなわち境界線を表すのだが、分棟配置の時点で「間」が前提なので、「間」が不自然ではなく、境界線の存在に気がつかない。
通常ならば境界線を越えて建築行為はできないので、境界線が結界のような働きをするが、分棟配置ならば境界線を越えて建築同士がつながりを築くことができるので、さらに境界線の存在が曖昧になり、結界ではなくなる。
"Arrangement that is not a barrier"
Since there is a principle of one building on one site, boundaries may be set when arranging separate buildings. When the branch building is arranged, there is a "between" between the branch buildings, and that "between" represents the boundary line, but since the "between" is premised at the time of the branch layout, the "between" is not unnatural. I don't notice the existence of the boundary.
Normally, it is not possible to build beyond the boundary line, so the boundary line acts like a barrier, but if it is a branch layout, the buildings can cross the boundary line and build a connection, so the boundary line is further The existence of is ambiguous, and it is no longer a barrier.
同じクライアントだがビルディングタイプが違う建築同士が並ぶ。1つの敷地に1つの建築という原則のために境界線が設定される。土地はつながっており、1つの地形を成しているので、境界線は目には見えない結界として存在している。
決して越えることができない結界だから、2つの建築を隔てる「間」ができる。間は結界があることを示しているので、間の取り方で結界の強度を調整でき、もしかしたら、結界自体を緩く曖昧にできないかと考えている。
"Adjustment of barriers"
Buildings with the same client but different building types are lined up. Boundaries are set due to the principle of one building on one site. Since the lands are connected and form a single terrain, the boundaries exist as invisible barriers.
Because it is a barrier that can never be crossed, there is a "between" that separates the two buildings. Since the gap indicates that there is a barrier, I am wondering if the strength of the barrier can be adjusted by adjusting the gap, and perhaps the barrier itself can be loosely ambiguous.
俯瞰して都市のスケールを見渡してみると、様々なスケールが存在する。建築のスケールと一口に言っても、これも様々なスケールが存在する。しかし、人一人のスケールは大体同じである。大人と子供、身体の大小の差はあるが、都市や建築のスケールの違いと比べたら微細な誤差の範囲だろう。人のスケールが変化する時は人の数が変化する時である。人の数が増えれば、建築のスケールを超えることもあり、都市のスケールに匹敵することも可能だろう。
これはスケールの話だけにとどまらない。単純に大きいものはそれだけで影響力を持つので、スケールの大小は影響力にも関わる。例えば 環境に与える影響力は人の数に左右される。集めて人の数を増すだけで影響を与えることもできるが、個々人にダイレクトに影響を与えて、影響を受けた人が増えるという構図もあるだろうし、それならば建築にも可能である。
"Influencing architecture"
Looking at the scale of the city from a bird's-eye view, there are various scales. There are various scales, even if it is said to be the scale of architecture. However, the scale of each person is about the same. There is a difference in size between adults and children, and the size of the body, but it is within the margin of error when compared with the difference in the scale of cities and architecture. When the scale of people changes, it is when the number of people changes. If the number of people increases, it may exceed the scale of architecture and may be comparable to the scale of cities.
This isn't just about scale. The size of the scale is also related to the influence, because the one that is simply large has an influence by itself. For example, the influence on the environment depends on the number of people. It is possible to influence by simply collecting and increasing the number of people, but there may be a composition that directly affects each individual and the number of people affected increases, and if so, it is also possible for architecture.
不特定多数の人に影響を与え、影響を受けた人が多くなれば、大きな建築が周辺環境に与える影響力と同等かそれ以上になるかもしれないとしたが、その場合、より小さい建築の方が不特定多数の人に影響を与えやすいのではないかと考えた。
人の視野は案外狭く、意識をしないとゲシュタルト的に広い視野は保てない。一度に見える範囲を考えれば、小さい建築の方が有利かもしれない。
そうすると、不特定多数の人が集まる小さなお店に可能性があるかもしれないと思った。確かに、ひとつの小さなお店が周辺環境に影響を与える様はよく見る。しかし、その影響は必ずしも良いものとは限らない。それを建築的に紐解き、いかしたいと考えている。
"Potential of a small shop"
He said that if an unspecified number of people were affected and more people were affected, a large building might have an impact on the surrounding environment or more, but in that case, a smaller building I thought that it would be easier to affect an unspecified number of people.
People's field of vision is unexpectedly narrow, and unless they are conscious, they cannot maintain a wide field of view like Gestalt. Considering the range that can be seen at one time, a small building may be more advantageous.
Then, I thought that there might be a possibility in a small shop where an unspecified number of people gather. Certainly, I often see how one small shop affects the surrounding environment. However, the impact is not always good. I want to unravel it architecturally and make good use of it.
周辺環境に影響を与えるような建築はある程度の大きさが必要だと考えてしまうが、見え方や建ち方で小さい建築でも、あるいは、小さい建築の方がより周辺環境に影響を与えることがあるのではないかと考えてみた。
大きい建築の方がより影響を与えると考えてしまう理由は、単純に大きくて見える面積が多いからで、都市の中でより目立つからより何かしらの影響を与えやすいと考える。要するに、建築の見え方や建ち方が周辺環境に影響を与えることが前提になっている。
小さい建築は都市の中での見え方や建ち方で周辺環境に影響を与えるのは小さい故に難しいかもしれないが、もっと限定して都市の中にいる不特定多数の個々人に影響を与えることを考えるならば、建築の大きさは関係なくなるかもしれない。小さい建築でも影響を受けた人が多くなれば、それは大きな建築が周辺環境に与える影響力と同等かそれ以上になるかもしれない。
都市の中での見え方や建ち方で直接的に人とつながり影響を与えることは、大きい建築よりむしろ小さい建築の方が向いているかもしれないと考えた。
"Small architecture is better"
I think that a building that affects the surrounding environment needs a certain size, but even a small building in terms of appearance and construction, or a small building may have a greater impact on the surrounding environment. I thought it might be.
The reason why I think that a large building has more influence is simply because there is a large area that looks large, and because it stands out more in the city, I think that it is more likely to have some influence. In short, it is premised that the appearance and construction of architecture affect the surrounding environment.
It may be difficult for a small building to affect the surrounding environment in terms of how it looks and is built in the city, but it is more limited to affect an unspecified number of individuals in the city. If you think about it, the size of the building may not matter. If more people are affected by a small building, it may be as much or more than the impact of a large building on the surrounding environment.
I thought that it might be better for small buildings to connect and influence people directly in terms of how they look and build in the city, rather than large ones.
敷地境界線という目には見えない結界に阻まれて建築と都市が分断され、まとまりがなく、つながりもない風景が繰り返し、増殖していく。境界線の中だけは別世界なので何でもあり、夢の世界である。夢に現実を重ね合わせて、ほどほどの物がほどほどの佇まいをしているから、ほどほどの風景が連続し、どこにいてもほどほどの同じ風景を見ることができる。
結界は目には見えないのだから無視をして勝手につなげて、それも好き勝手につなげてみれば、結界があるが故につながり方に歪みができる。その歪みを扱い昇華させるのが建築デザインの役目になる。
"Connecting barriers"
The architecture and the city are separated by the invisible barrier of the site boundary, and the uncoordinated and unconnected landscape repeats and proliferates. Only inside the boundary is another world, so anything is there, and it is a dream world. By superimposing reality on dreams, moderate things have a moderate appearance, so moderate scenery is continuous, and you can see the same scenery wherever you are.
Since the barrier is invisible to the eye, you can ignore it and connect it as you like, and if you connect it as you like, the connection will be distorted because of the barrier. It is the role of architectural design to handle and sublimate the distortion.
建築が土地につくのは当たり前だが、土地を基準に考えれば、都市も建築も同じ土地の上である。上物が変わろうが、土地そのものがそこに存在することに変わりがない。建築を建てる時や都市を形成する時に地表面をいじり、元の土地を乱すこともあるが、周辺も含めた地形までが変わることは再開発レベルの規模でもない限り起きない。
敷地周辺のコンテクストを考えた時に地形は必ず参照することになる。地形から周辺環境生成の根拠を読み取ることができ、その根拠は現在から未来へと必ず受け継がれるものだから、その根拠に対する建築の建ち方のような態度を定める必要はあるだろう。
"Attitude toward terrain"
It is natural for architecture to land on land, but based on land, cities and architecture are on the same land. Even if the quality changes, the land itself still exists there. When building a building or forming a city, the ground surface may be tampered with and the original land may be disturbed, but the terrain including the surrounding area will not change unless it is on a redevelopment level.
When considering the context around the site, the terrain will always be referred to. Since the grounds for the creation of the surrounding environment can be read from the terrain, and the grounds are always passed down from the present to the future, it will be necessary to establish an attitude such as how to build an architecture for the grounds.
全ての道具が手作りで、自分の手や癖に馴染むように工夫がしてある。70年分のほんの一部、倉庫の奥から引っ張り出して、昔の大工の道具箱を並べてみたら、今は使わないものばかり、今は手作りしなくても安易に手に入る道具と比べたら融通が効かない。
今の道具は1つでマルチな対応ができるようになっているが、並べた道具箱にはこの場面ではこれ、あの場面ではあれ、その場面ではそれ、というように道具を見れば建築の中のどこの部分で、どのような作業をするのか、そして、どのような納め方をするのかがわかる。
道具ひとつで人と建築を想起させる。
まるで古道具市、気になるものだけをピックアップした。祖父か父親のものと、形や大きさがいいもの、自分は大工ではないから、実際の使い方や希少性より、デザインが気になるものだけを、ものとして魅力があるものだけを残すことにした。
道具としては1つでマルチタスクをこなせた方が効率がよいのだろうが、シングルタスクで対応する道具の方が特化した形や大きさの美しさがあり、ものとしての魅力を発している。
"Charm of tools"
All the tools are handmade and devised to fit your hands and habits. I pulled out a small part of 70 years' worth from the back of the warehouse and lined up the old carpenter's tool boxes. Inflexible.
Today's tools can be used for multiple purposes with one tool, but if you look at the tools in the tool box, you can see this in this scene, that scene, that scene, and so on. You can see where, what kind of work, and how to pay.
Reminiscent of people and architecture with a single tool.
It's like an old tool market, I picked up only the things I was interested in. I'm not a carpenter, I'm not a carpenter, and I'm not a carpenter. did.
It would be more efficient to be able to multitask with one tool, but the tool that supports single tasking has a more specialized shape and size, which makes it attractive as a tool. There is.
計画道路や鉄道の高架化などを都市のリノベーションとして捉えると、関係する建築も都市のリノベーションの対象となる。計画に触れる建築は大体が壊され、新しい土地区画の元に建て替わる。その場合、単なる建て替えで済ますのではなく、元があり、元に対するリノベーションとなるように、建築は元の要素を含む必要があるだろう。
"Architecture including the original"
If we consider the elevation of planned roads and railways as urban renovation, related buildings will also be subject to urban renovation. Most of the buildings that touch the plan will be destroyed and rebuilt under new parcels. In that case, the architecture would need to include the original elements so that it is not just a rebuild, but a yuan and a renovation to the yuan.
計画道路や鉄道の高架化などにより元がわからない位に風景が変わることがある。これを都市のリノベーションだとすると、都市をリノベーションするために、そこにあった建築も変える必要が出てくる。その場合、変わった後の建築は都市のリノベーション前後の時の経過を分断せずに、そのままでないにしても、何かに変換をしてでも、元を残す必要があるのではないかと考えた。
風景が変わる中で、それでも変わらないものを探した。計画道路や鉄道の高架化などは土地の区画を変えるが故に建築が存続できなくなる。更地になり、区画も変われば、ほぼ何も残らないが、元々の地形は変わらない場合がある。
変わらない地形に対して、その地形を活かすように都市のリノベーション後の建築を構築できれば、地形を通して時の経過を建築に変換して残すことができる。
"Leave the passage of time"
The scenery may change to the extent that the origin is unknown due to the elevated roads and railways. If this is a city renovation, it will be necessary to change the architecture that was there in order to renovate the city. In that case, I thought that it would be necessary to keep the original architecture after the change without dividing the passage of time before and after the renovation of the city, even if it is not as it is or if it is converted to something. ..
As the landscape changed, I searched for something that wouldn't change. Elevation of planned roads and railroads will change the lots of land, so construction will not be able to survive. If the land becomes vacant and the plot changes, almost nothing remains, but the original terrain may not change.
If the renovated architecture of the city can be constructed so as to make the best use of the terrain that does not change, the passage of time can be converted into architecture and left through the terrain.
集合住宅は概ね各住戸が均一で連続と積層が効率性を高め事業性を担保しているので、仕上げなどの違いはあるにしても、均一で効率性が現れた外観でその建物が集合住宅だと誰でもわかる。
住人は均一ではないだろうから、中身になる生活は決して均一にはならない。
建築のビルディングタイプとして集合住宅は一戸建ての住宅の次に、事務所ビルと同じ位に多いかもしれないが、事務所ビル同様、外観の均一性と中身の不均一性の違いが外観と中身を別々に存在させていることに対する違和感を建築デザインで無くしたいと考えている。
"Uncomfortable appearance"
In a multi-dwelling house, each dwelling unit is generally uniform, and continuous and stacking enhances efficiency and ensures business feasibility, so even if there are differences in finishing etc., the building has a uniform and efficient appearance. Anyone can understand that.
Residents will not be uniform, so the life inside will never be uniform.
As a building type of architecture, multiple dwellings may be as many as office buildings next to single-family homes, but like office buildings, the difference between appearance uniformity and content non-uniformity is the difference between appearance and content. I would like to eliminate the discomfort of having them exist separately in the architectural design.
決めないということは判断を保留にすることだが、判断を保留にできる状況を上手くつくり出しているとも言える。ギリギリまで判断を保留にできるから、その間に別のアイデアや可能性や視点を持つことができ、試す時間が生まれる。結果の良し悪しも重要だが、試行錯誤の時間が生み出す別視点の方が結果以上に面白いし、気持ちよい。ギリギリまで判断しなくても最後は上手くまとめられる技術は必要になる。
"A different perspective feels good"
Not deciding means putting the decision on hold, but it can be said that it has created a situation where the decision can be put on hold. You can put your judgment on hold until the last minute, so you can have other ideas, possibilities, and perspectives in the meantime, and you will have time to try it. Good or bad results are important, but a different perspective that creates time for trial and error is more interesting and pleasant than the results. At the end, we need a technology that can be put together well without making a judgment to the last minute.
決めないでいる状態は別の言い方をすると、ずっと別の可能性を探っている状態かもしれない。決めてしまったら、他を排除することになるので、別の可能性が消える。ただつくるだけならば、即断即決即行動すれば大概のことはできるが、面白いものができるかどうかは別である。普通なものをつくるだけならば面白くはないのでやる必要がなく、普通じゃないものができる可能性を残すために決めない状態をつくる。
"Undecided state"
In other words, the undecided state may be the state of exploring another possibility. Once you've decided, you're excluding others, and another possibility disappears. If you just want to make it, you can do most things if you make a quick decision and act immediately, but it is different whether you can make something interesting. If you just make ordinary things, you don't have to do it because it's not interesting, and you create an undecided state to leave the possibility of making unusual things.
いつまでも決めないことは良くなく、即断即決即行動が良いようなことを聞く時があるが、決めない状態をどこまで保てるか、決めないということは決めてなくても成り立つ状況であり、ならばそもそも決める必要がないことかもしれない。
決めないで判断を保留にしていくと、いつまでもケリがつかず終わらない状況が続き、保留がまた別の保留を生み、段々と保留事が膨れ上がり硬直し停滞してくるので、即断即決即行動をして溜め込まずに効率的に処理しようとするのだろう。溜め込みは時間の無駄ということになる。
無駄な時間を無くすことが目的ならばそれで良いが、新しい活路を見出したり、人とは違った見方や考え方をすることが目的ならば、即断即決即行動をするより、ギリギリまで決めずに溜め込み、膨れ上がり硬直した保留事を一気に全て解決できるひとつの事を見つける方が良いが、ただ膨れ上がり硬直した保留事に対する不安と上手く付き合う必要がある。
"I can't decide until the last minute"
It is not good not to decide forever, and I sometimes hear that prompt decision and immediate action are good, but it is a situation that can be established even if you do not decide how long you can keep the undecided state, in the first place. It may not be necessary to decide.
If you put the decision on hold without making a decision, the situation will continue to be unfinished, and the hold will create another hold, and the hold will gradually swell and become rigid and stagnant. It will try to process efficiently without accumulating. Accumulation is a waste of time.
If the purpose is to eliminate wasted time, that's fine, but if the purpose is to find a new way of life or to have a different perspective or way of thinking from other people, rather than taking immediate action, it is possible to accumulate without making a decision. It's better to find one thing that can solve all the bulging and rigid holdings at once, but you just have to deal with the anxiety about the bulging and rigid holdings.
曖昧であれば序列が無くなる。順序があり序列が発生してしまうと硬直して動かせなくなる。硬直を解き動かすためには、序列を解除すればよいが、そもそも序列があるから秩序が保たれているので、序列を解除し無秩序にしてしまっては意味が無く、曖昧と無秩序は意味が違うので、曖昧な秩序がある状態にしたい。
決め過ぎないことが曖昧さを生むためのひとつの方法かもしれないが、建築の場合、細かく決めることを最終目的地にしているので、決めた上での曖昧さを生み出す必要がある。
ならば、決めることを遅くするのはどうだろうか。決めない状態が続くことにより、決まらない曖昧な状態が続く。この時の曖昧な状態を最終目的地にし、曖昧な状態を定着させるのである。
"Ambiguity fixation"
If it is ambiguous, there will be no order. If there is an order and an order occurs, it becomes rigid and cannot be moved. In order to release the rigidity, it is sufficient to cancel the order, but since there is an order in the first place, there is no point in removing the order and making it disorderly, and ambiguity and disorder have different meanings. So I want to have an ambiguous order.
Not over-deciding may be one way to create ambiguity, but in the case of architecture, the final destination is to make detailed decisions, so it is necessary to create ambiguity after deciding.
So why not slow down your decision? As the undecided state continues, the undecided ambiguous state continues. The ambiguous state at this time is set as the final destination, and the ambiguous state is fixed.
決めつけを無意識のうちに行い、過去の経験からか、想像からか、蓄積された自身のものから判断し、自分に有害か無害かを瞬時に判断する能力を皆誰でも持っているから安全に道を歩くことができるのだろう。
判断に曖昧は無い。必ず白黒はっきりと無意識ではつけている。そこに漬け込むのが扇動の常套手段だが、とにかく、瞬時に判断できない物は印象に残る確率が高い。
曖昧であることが判断を保留にさせ、いつまでも頭の片隅に留まりさせる。曖昧であることを切り離そうとすればするほど留まる。実は曖昧であることを好んで受け入れてしまうのである。
曖昧の持つ可能性は至る所で使われているし、これからも有効だろう。なぜなら、曖昧には正解がない上に、曖昧には中毒性があるからで、曖昧な状態は心地良くなるのである。
"Possibilities of ambiguity"
It's safe because everyone has the ability to unknowingly make decisions, judge from past experience, imagination, or accumulated own things, and instantly judge whether they are harmful or harmless to them. You can walk on the road.
There is no ambiguity in the judgment. Be sure to wear black and white clearly and unconsciously. Immersing yourself in it is the usual way to incite, but anyway, things that cannot be judged instantly are likely to leave an impression.
Ambiguity puts the decision on hold and keeps it in the corner of the head forever. The more you try to separate the ambiguity, the more you stay. In fact, they like to accept ambiguity.
The possibilities of ambiguity are used and will continue to be valid. Because there is no correct answer to ambiguity, and ambiguity is addictive, ambiguity becomes comfortable.
曖昧な境界に建つ建築は曖昧になるのではないかと考えた。曖昧な境界は一見曖昧に見えるだけだが、どこに境界があるのかがわからず、また、建築が境界の形状を表していなければ、余計に境界がはっきりとせず、線引きができなくなる。
どこまでが敷地かわからない場所に建築が建つならば、建築もどこまでかがわからない方が余計に曖昧になる。
さらに、ビルディングタイプも曖昧にできたならば、余計に曖昧になる。そのためにはある程度の規模が必要になる。
"To make it ambiguous"
I thought that the architecture built on the ambiguous boundary would be ambiguous. Ambiguous boundaries only seem ambiguous at first glance, but if you don't know where the boundaries are, and if the architecture doesn't represent the shape of the boundaries, the boundaries will be unclear and you won't be able to draw lines.
If a building is built in a place where you do not know how far the site is, it becomes more ambiguous if you do not know how far the building is.
Moreover, if the building type can be ambiguous, it becomes even more ambiguous. For that purpose, a certain scale is required.
「曖昧な建築」という表現はあるだろうか、建築に携わる人は「曖昧」という言葉が嫌いなような気がする。建築はその時その時の過程で、一時的に決定しないことはするが、決めていきながら積み上げていくのが一般的であり、曖昧な状態を極力無くすような方向に思考を巡らす。だから、決定しない、あるいは、決定することを極力保留にする態度は新しいことに気づかせ、新しい別の視点を与える可能性を秘めてはいる。
ただ「曖昧な建築」となると最終的な結果としての建築が曖昧なのである。決定していった挙句に曖昧なのである。それは「弱い」とは違うし、何も持たない建築とも違う。「曖昧」という状態を纏っている建築なのであり、願わくば「曖昧」という言葉が良い意味や良い印象を与えて欲しいのである。
もしかしたら、「曖昧な建築」は建築単体で考えていては出現不可能かもしれない。建築を取り巻く環境まで含めて考えた時にはじめて、その建築の存在が良い意味での曖昧さを纏うことができるのかもしれないが、それはひとつの可能性に過ぎないだろう。
"Existence of ambiguous architecture"
Is there an expression of "ambiguous architecture"? I feel that people involved in architecture dislike the word "ambiguous". At that time, in the process of that time, architecture is not decided temporarily, but it is common to build up while deciding, and think in a direction that eliminates the ambiguous state as much as possible. Therefore, the attitude of not making a decision or putting it on hold as much as possible has the potential to make us aware of new things and give us a new perspective.
However, when it comes to "ambiguous architecture," the final resulting architecture is ambiguous. It is ambiguous after the decision was made. It's not "weak" and it's not like architecture with nothing. It is an architecture that has a state of "ambiguity", and hopefully the word "ambiguity" gives a good meaning and a good impression.
Perhaps "ambiguous architecture" may not appear if you think of it as a single building. It may be possible for the existence of an architecture to be ambiguous in a good sense only when the environment surrounding the architecture is considered, but that is only one possibility.
これから整備される土地に、整備される前に建築が出現し、その後に道路ができる。本来ならば道路が先で順序が逆になる。建築は道路との関係性で成り立つので、道路は設計する上での大きな手掛かりである。もちろん道路境界ははっきりとしているのだが、実際には道路は存在せず、ただの草が生えた土地があるだけである。
序列が逆転する。好きな所に建築を建てて、それに合わせて道路ができるように、道路の位置など関係無しに建築を考えたらどうなるだろかと考えてみた。
今のところ、目には見えない境界線よりは目に見える草の生えた土地の方がリアリティがある。絶対的な境界線だが目に見えないだけで曖昧になる。境界線が曖昧になるだけで別の視点が生まれる。
"Ambiguous boundaries are created"
Buildings will appear on the land to be constructed before they are constructed, and then roads will be created. Normally, the road comes first and the order is reversed. Roads are a great clue in designing, as architecture is built on relationships with roads. Of course, the road boundaries are clear, but in reality there are no roads, just grassy lands.
The order is reversed. I wondered what would happen if I built an architecture wherever I wanted and thought about the architecture regardless of the position of the road so that the road could be created accordingly.
For now, visible grassy lands are more realistic than invisible boundaries. It's an absolute border, but it's just invisible and ambiguous. Just blurring the boundaries creates another perspective.
鉄道の高架化により変わる風景には当然のように序列がある。高架が優先され、高架の脇に付け替え道路ができ、あとの残りが立ち退いた住民用の土地として利用される。
土地が整備される順番も序列に従う。故に、この序列が根本的な風景を決めてしまうことになり、交通手段優位の都市風景ができ上がる。
これが都市風景形成のルールだが、そこに事業期間の違いによる整備までの時間差が生まれる。
この時間差を利用し、土地整備の順番を変えることで、交通手段優位の都市風景を少しでも変化させることはできないかと目論んでいる。
"Changes in urban landscape"
Naturally, there is a hierarchy in the landscape that changes due to the elevated railways. The elevated road will be given priority, and a replacement road will be created beside the elevated road, and the rest will be used as land for evacuated residents.
The order in which the land is maintained also follows the order. Therefore, this order will determine the fundamental landscape, and a cityscape with superior transportation will be created.
This is the rule for forming the cityscape, but there is a time lag until maintenance due to the difference in the project period.
By using this time difference and changing the order of land development, we are planning to change the urban landscape, which is superior in terms of transportation, as much as possible.
野原の中に存在する建築がやがて、都市の中に埋没するまで風景が変わり続けるので、風景が定着した後を想像し、そこに焦点を合わせて設計するのが普通かもしれない。
ただ、風景が定着するまでの間の野原が魅力的に見えるのだ。意味もなく雑草が馴染むように建築を設計したくなる。
何故だろうと考えてみると、雑草生い茂る野原が都市の中では存在が許されていないから、一時的なものだから、一方で建築は少なくとも恒久的な存在とみなされるから、お互いに寿命が違うもの同士をどのようにつなげるかをやってみたいのだろう。
"Things with different lifespans"
The landscape will continue to change until the architecture in the field is buried in the city, so it may be normal to imagine after the landscape has settled and focus on that.
However, the fields until the landscape is settled look attractive. I want to design the architecture so that weeds fit in without meaning.
If you think about why, weedy fields are temporary because they are not allowed to exist in the city, while architecture is considered to be at least permanent, so they have different lives. I would like to try how to connect them.
不確かなことは明確にして積み上げていくことが仕事でも何かのプロジェクトでも何でも進め方としては常套手段だろう。不確かなことは誰でも無くしたいと思うし、明確にできなければ、不確かなことが意味無くなるくらいの強度を持ったもので覆い隠してしまえば良い。
ただ、不確かなことと対峙して、不確かなままで進み、不確かなままで、不確かなことに対して対峙する様がそのまま解答なり、最終形なり、成果物になることもあり得る。
もしかしたら、不確かなことをそのままにして、無理に明確にせずに、不確かなことを利用するなり、不確かによる可変性を取り込むなどした方が思いも寄らない成果につながるかもしれない。
"Leave uncertain"
Clarifying and accumulating uncertainties is a common way to proceed with work, any project, or whatever. Everyone wants to get rid of uncertainties, and if they can't be clarified, they can be covered with something strong enough to make uncertainties meaningless.
However, confronting uncertainties, proceeding with uncertainties, remaining uncertainties, and confronting uncertainties can be the answer, the final form, and the deliverable.
Perhaps it may lead to unexpected results if the uncertainties are left as they are and the uncertainties are used or the variability due to the uncertainties is incorporated without forcibly clarifying them.
「日常が大事」だという考えはいつからはじまったのだろうかと思った。建築を学びはじめた頃はバブル期だったこともあり、「日常が大事」どころか「日常」すら意識されていなかったような気がする。
デザインも今のように普通に日常の中に存在してはおらず、社会に出た時にはまだ「デザイン住宅」という言葉は無く、デザインはほんの一部のプロのものだった。
ずっと以前から普通に日常の中にデザインは存在していたが気がつかなかった。「日常が大事」で日常に価値を見出したのも最初は経済的理由からだったかもしれない。価値はいつでも本来の見出され方をしない。失って気づくか、仕方なく気づくか、いずれにせよ今を誤魔化すから何に価値があるのかわからない。
"Value to notice"
I wondered when the idea that "everyday is important" began. When she started studying architecture, she was in the bubble era, so I feel that she wasn't even aware of "everyday", let alone "everyday is important".
Design does not exist in everyday life as it does now, and when it came out to society, the word "design house" did not exist yet, and design was only for some professionals.
Designs have existed in everyday life for a long time, but I didn't notice them. It may have been for economic reasons at first that he found value in everyday life because "everyday is important". Value is not always found in its original way. Whether you lose it or notice it, you don't know what it's worth because it's deceiving the present.
例え良くても素晴らしくても、すでにある物、王道の物を真似るか、その流れを去就することには興味が無く、今までに無い物、クリティカルな物に興味が湧き、そのような物をつくりたくなる。
すでに評価が定まっている物ややり方は、そこに新しいものを付加して、全く別の物を生み出す試みをするか、一度廃墟のように扱い、すでにその物ややり方が必要無い所からスタートして、全く別の必要な物を生み出す試みをするならば、先々も残る可能性があり、残す価値がある。
知らず知らずのうちに人は、素晴らしくて評価が定まっている物に近寄ることで、自身に別の価値を纏わせようとする。ただ、その価値は蜃気楼みたいに実体が無く、ただ単に思考停止状態をつくり出すだけで、無意識にその価値を常に渇望し続けることになり満足できることが無い。
"I'm not interested in the royal road"
Even if it is good or wonderful, I am not interested in imitating existing things, royal road things, or leaving the flow, I am interested in new things, critical things, and such things I want to make it.
For things and methods that have already been evaluated, add new ones and try to create something completely different, or treat it like a ruin once and start from a place where you do not need that thing or method already. And if you try to create something completely different, it may remain and is worth it.
Unknowingly, one tries to bring another value to oneself by approaching something that is wonderful and well-regarded. However, its value is insubstantial like a mirage, and simply creating a state of thoughtlessness unconsciously keeps craving for its value and is not satisfying.
飲みに行けないのは、日常の延長なのか、日常の延長ならば家で済むから、飲みに行けないのは辛くない。非日常の体験を求めている場合は、家では済まない。非日常性はたまにはいいが、毎日続くと日常になるから意味が無いし、人は完全に振り切った非日常体験まで行う勇気がないので、実際は非日常と日常の間の少し非日常よりの辺りを求める人が多そうな気がする。非日常にも幅がある。
"Extraordinary width"
Is it an extension of my daily life that I can't go drinking? It's not painful that I can't go drinking because I can do it at home if it's an extension of my daily life. If you're looking for an extraordinary experience, you can't go home. Extraordinary is sometimes good, but if it continues every day, it becomes everyday, so it is meaningless, and people do not have the courage to completely shake off the extraordinary experience, so in reality it is a little more than extraordinary between extraordinary and everyday I feel that there are many people who want. There is a range of extraordinary things.
どうしたら記憶に残る物になるだろうかと考えてみた。一番簡単なのは体験と物が結びついた時で、物に付加される体験が記憶になり、その記憶の中に物が残る。ならば逆も真なりで、物が体験を誘発することにより、物が記憶として定着する。ただ、これらは普通にあることである。
物自体が直に記憶になることはあるのだろうか。あるとしたら、物が物としての存在を超えている時だろう。
"Memory of things"
I wondered how it would be memorable. The easiest thing is when an experience and an object are connected, and the experience added to the object becomes a memory, and the object remains in that memory. If so, the opposite is also true, and when an object induces an experience, the object becomes established as a memory. However, these are normal.
Can the thing itself become a direct memory? If so, it would be when things go beyond their existence as things.
集まって住む場所を建築化する時には何故か効率性を一番重要視する。事業性を考えた時に限られたスペースの中で少しでも多く住む場所にできた方が収益が上がると考えるからで、もちろん賃貸という事業の中での話だが、賃貸以外でもより多くの人を収容できることが一番重要になる。
その場合は建築の連続性、積層性、均一性が効率性を上げる手助けになるが、いろいろな人が同じようなパターンで繰り返され空間に押し込める違和感は素朴に感じる。
建築の連続性、積層性、均一性の効率は構造計画による骨組みと、その骨組みに入る設備や仕上げで担保される。だから、そこに人の違いが入り込む余地は無く、それが近代から続く伝統のようだ。
"Tradition of a place to gather and live"
For some reason, efficiency is of the utmost importance when building a place to gather and live. When considering business feasibility, I think that it would be more profitable to live in a place where you can live as much as possible in a limited space. Being able to accommodate is of utmost importance.
In that case, the continuity, stacking, and uniformity of the architecture will help improve efficiency, but the sense of incongruity that various people repeatedly push into the space in a similar pattern feels simple.
The efficiency of building continuity, stackability, and uniformity is guaranteed by the framework of the structural plan and the equipment and finishes that fit into the framework. Therefore, there is no room for differences between people, and it seems to be a tradition that has continued since modern times.
ひとつの繋がりができる様を人の想像力に委ねるならば、繋がりを喚起するような仕掛けを考えればよい。その場合、簡単に考えると2通りの方法があり、ひとつは大きな領域で囲ってしまうこと、もうひとつは個々の要素を近づけることである。
建築的に考えると、前者は例えば、全てを覆う大きな屋根を架けるや全てを壁で囲うことなどであり、後者は単に距離的に近づけてしまうことだが、相対的に考えれば、繋げたくない要素を遠ざけるというやり方もある。
"Awaken the connection"
If you leave it to the imagination of a person to make one connection, you can think of a mechanism that evokes the connection. In that case, there are two ways to think briefly, one is to enclose it in a large area, and the other is to bring individual elements closer together.
From an architectural point of view, the former is, for example, to build a large roof that covers everything or to surround everything with a wall, and the latter is simply to bring them closer in distance, but from a relative point of view, elements that you do not want to connect. There is also a way to keep away.
隣り同士だからといって繋がりがある訳ではない。近所づき合いでも同じである。近いからといって接点ができる訳でもない。繋がりをつくるのに距離は関係無いが、距離が近いと繋がりをつくりたくなる。
繋がりをつくりたければ、まずは真似るのが簡単かもしれない。何を真似るかにも依るが、見た感じを真似てみれば、似ているということで繋がりができる。
建築でいえば、外観のデザインを真似る、外観の素材を真似る、外観の高さを真似るなど、歴史的な景観を保存する地区でよく用いられる手法がある。
"Imitate and make a connection"
Just because they are next to each other does not mean that they are connected. The same is true for neighbors. Just because they are close does not mean that they can make contact. Distance doesn't matter to make a connection, but when the distance is short, you want to make a connection.
If you want to make a connection, it may be easy to imitate first. It depends on what you imitate, but if you try to imitate what you see, you can connect by being similar.
In terms of architecture, there are techniques often used in areas that preserve historic landscapes, such as imitating exterior designs, imitating exterior materials, and imitating exterior heights.
初めての感覚に打合せ後なった。提案がすんなりと通るような打合せでは無かったが、提案そのものには可能性を感じていたので、その可能性を伝えることとその可能性を残すことに終始した。隣り合う2つの別々なプロジェクトをひとつの関連したものとして再設定し提案するための打合せだが、建主も違うので、続けて打合せをして擦り合わせる。今まで建築の範疇だとしていた領域がさらに拡大しているので、今までに無いところまで思考を迫られるが、打合せによりまだ掘り起こしていない可能性を感じ、さらに建築の領域を広げる必要性が出てきた。今まで建築のデザイン要素そのものに着目してきたが、デザイン要素の前提となる建築の領域をどこまで広げることができるか、そこを含めて建築の設計をしていることが自然で違和感が無く心地良く、打合せ後は他のことを何もしたくなかった。
"The feeling that the realm of architecture expands"
It was after a meeting for the first time. It wasn't a meeting where the proposal went smoothly, but I felt the possibility of the proposal itself, so I decided to convey the possibility and leave it. It is a meeting to reset and propose two adjacent projects as one related project, but since the owners are different, we will continue to have a meeting and rub them together. Since the area that was considered to be the category of architecture has expanded further, it is necessary to think to a place that has never existed before, but I feel that it is possible that I have not dug up yet at the meeting, and it is necessary to further expand the area of architecture. I came. Until now, we have focused on the architectural design elements themselves, but it is natural and comfortable to design the architecture including the extent to which the architectural area that is the premise of the design elements can be expanded. , I didn't want to do anything else after the meeting.
建築は小さくても周りの環境に影響を与えるので都市スケールで考えることもする。現在2つの隣り合うプロジェクトが同時に進行しているが、全く違うビルディングタイプなので、当初は別々に考えていた。決して大きくはない敷地だが細長く、両端で1m位の高低差がある。もし2つの隣り合うプロジェクトを敷地の高低差を利用して関連づけることができたならば、どうなるだろうかと考えてみた。全く違うビルディングタイプ故に、機能上の相乗効果は無いだろうが、都市スケールで考えた場合、連続する建築の見え方は各々のプロジェクトが単体で存在する場合よりも周りの環境に与える影響は大きくなるので、それだけでも2つのプロジェクトを関連づけて考えることに価値があると思った。
"More affects the surrounding environment"
Even if the architecture is small, it affects the surrounding environment, so we also consider it on an urban scale. Currently, two adjacent projects are in progress at the same time, but since they are completely different building types, I initially thought about them separately. The site is not large, but it is long and narrow, and there is a height difference of about 1m at both ends. I wondered what would happen if two adjacent projects could be linked using the height difference of the site. Since it is a completely different building type, there will be no functional synergistic effect, but on an urban scale, the appearance of continuous architecture will have a greater impact on the surrounding environment than if each project exists alone. So, I thought it was worthwhile to think about the two projects in relation to each other.
厨房機器の特徴はステンレスの素材感、明快な機能、無駄が無いなどがあるが、厨房機器を建築デザインの要素として見做すことはない。オープンキッチンであれば厨房機器は丸見えで、見えているステンレスの素材感の機器はモダンな印象を受け、空間の印象に大きく寄与はするが、それでも厨房での作業に応じて機器を並べているだけに過ぎず、かろうじてステンレスの素材感だけが建築デザインの要素に通じるだけである。
ならば、厨房機器の存在を建築要素として扱うためには、他の建築要素と等価に扱えるようにするか、他の建築要素が厨房機器の建築的特徴に近づくしかない。
普通にいけば、厨房機器はそれ以外の建築要素とは相容れないので、プランやセクションでは分断が起こり、溶け合うことが無く、結果的にホールと厨房は分かれる。
ならば、分断せずに溶け合うことができれば、厨房機器が他の建築要素と等価な扱いになっていることになる。
道具としと厨房機器を見れば、すでに完成されていて汎用性が高いので、余計なものを付け加えたりする必要は無いし、付け加えたくも無い。だから、分断しないためには、厨房機器以外の建築要素が厨房機器の建築的特徴、例えば、ステンレスの素材感で全てが構成されている、などに近づく必要がある。
いかにして建築要素として見做していなかったモノを取り込んで空間に変化を生むかの試みである。
"Attempt to make kitchen equipment an architectural element"
The characteristics of kitchen equipment include the texture of stainless steel, clear functions, and no waste, but kitchen equipment is not regarded as an element of architectural design. In an open kitchen, the kitchen equipment is completely visible, and the visible stainless steel material gives a modern impression, which greatly contributes to the impression of the space, but even so, the equipment is only arranged according to the work in the kitchen. Only the texture of stainless steel barely leads to the elements of architectural design.
Then, in order to treat the existence of kitchen equipment as an architectural element, there is no choice but to treat it as equivalent to other architectural elements, or to make other architectural elements approach the architectural features of kitchen equipment.
Normally, kitchen equipment is incompatible with other architectural elements, so plans and sections are divided and do not merge, resulting in a separation between the hall and the kitchen.
Then, if they can be fused without being divided, the kitchen equipment is treated as equivalent to other architectural elements.
If you look at the tools and kitchen equipment, it's already completed and versatile, so you don't need to add anything extra, and you don't want to add it. Therefore, in order not to divide, it is necessary for the architectural elements other than the kitchen equipment to approach the architectural characteristics of the kitchen equipment, for example, that all are composed of the texture of stainless steel.
This is an attempt to create a change in space by incorporating things that were not regarded as architectural elements.
時は3日ある、十分すぎるぐらい、全く別視点の計画案を出すには時間がありすぎて困るくらい。さて、どうするか、元があるから、それに対してクリティカルに考えるだけだが、新しい要素を加えようと考えている。そもそも制限時間があり、終わりを意識すれば、まとめることが必要になり、新しい要素が入りづらいが、まとめる早さに自信があれば、よりギリギリまで時間を使い、たくさんの別視点を試すことができる。結局、答えを見つけるより、たくさん試すことが面白い。
"Fun to try a lot"
There are three days, more than enough, and too much time to come up with a plan from a completely different perspective. Well, there is a source for what to do, so I just think critically about it, but I am thinking of adding a new element. In the first place, there is a time limit, and if you are aware of the end, it will be necessary to put together, and it will be difficult for new elements to enter, but if you are confident in the speed of putting together, you can spend more time and try many different perspectives. it can. After all, it's more interesting to try a lot than to find the answer.
建築の要素とは見做していなかったモノをいかに取り込むかによって空間に変化が生まれる。空間の中でどのように見えるか、建築の要素とは見做していなかったから、その場所にあり、そのように見せていたものを建築の要素として意識をすれば扱いが変わり、それに伴い見え方も変わるだろう。
今までの形式やその場所や時代の様式を崩し、そこから離れるには、今までの範疇の中には無い要素を取り込むのもひとつの方法である。
"Incorporate elements outside the category"
The space changes depending on how we take in things that were not considered to be architectural elements. I didn't think of what it would look like in space as an element of architecture, so if I was conscious of what it looked like as an element of architecture, it would look different. The person will change too.
One way to break the traditional form, its place, and the style of the times and move away from it is to incorporate elements that are not in the conventional category.
周辺環境がこれから劇的に変わる中に、容易に変わることができない建築を置こうとした時に、変化した後に焦点を合わせるのが常套手段かもしれないが、それまでにも時は流れ、それまでにも建築は存在するので、変化の過程での建築の在り方も考えなくてはならない。
その時に、周辺環境の変化を全て受け止めてしまい、そして、それを跳ね返してしまうような強い強度を持った建築を置こうとする態度は新しい建築の形式や見え方を求めることになり、それはそれで面白いが、それは今までよくあることであり、そうではなくて、全てを受け止めてしまうのだけれども、その時々の変化には対応して溶け合い、ただ、次の変化には別に対応するような、最終的には建築は周辺環境には対応してきたのだけれども、その時々の痕跡は残り、その痕跡がデザインとして、新しい風景になり得るようなことを考えている。
"Architecture in the process of changing the surrounding environment"
It may be customary to focus after a change when trying to place an architecture that cannot be easily changed as the surrounding environment changes dramatically, but time has passed and by then. There is also architecture, so we must consider how architecture should be in the process of change.
At that time, the attitude of trying to place a building with strong strength that accepts all the changes in the surrounding environment and repels it will demand a new form and appearance of architecture, which is why. Interestingly, it's always the case, and it's not, it accepts everything, but it blends in with the changes of the moment, but it's just like responding to the next change separately. In the end, architecture has adapted to the surrounding environment, but the traces of that time remain, and I am thinking that the traces can become a new landscape as a design.
前から動きはあったプロジェクトが本格的に動き出しはじめたら、隣の敷地まで計画することになり、それでは別々に構想しようと、BIM上で2つの敷地モデルをつくり、様々な方向から眺めていたら、あるアングルになった瞬間、別々にイメージしていたものがひとつに、一体的につながった。
それまでは上から俯瞰するように、平面的な配置をスタディしていたのだが、敷地モデルをぐるぐると回転させ、様々なアングルから眺めてみたら、計画するものが一直線につながるアングルがあり、別々なものを一体的にプランニングする可能性に気がついた。
アングルだけで建築が決まるかもしれないと、改めて思った瞬間だった。
"Architecture determined by angles"
When a project that had been moving from before started to move in earnest, I had to plan to the next site, so I made two site models on BIM and looked at them from various directions, trying to plan them separately. At the moment when it became a certain angle, what I had imagined separately became one and connected together.
Until then, I had been studying the flat layout so that I could see it from above, but when I turned the site model around and looked at it from various angles, there was an angle where what I planned was connected in a straight line. I realized the possibility of planning different things together.
It was a moment when I thought again that the architecture might be decided only by the angle.
傾斜している土地はそれ自体で面白い。3Dプリンタで敷地模型をつくろうとして、BIM上でモデルを作成しているのだが、レベルを追ってできた敷地は急ではなく適度に緩やかに捻れて傾斜しており、土地自体が描く造形が面白くて、興味深い。
土地が描く造形を何とかうまく建築化できないかと考えている。
土地の上に建つ建築はすでに土地に依存しているにもかかわらず、無理して整地して土地からの影響を最小限にしようとする場合が多く、それは常々無理があると思っている。
土地なりに建築するというやり方もあるが、それは建築化とは言わない。土地の造形と建築の造形が関連し合うような、又は土地の造形が建築を生み出すようなことができないか、うまくできれば敷地内において建築の範囲が広がる。
"Architecture of land"
The sloping land is interesting in itself. I am trying to make a site model with a 3D printer, and I am making a model on BIM, but the site created by following the level is not steep but moderately gently twisted and inclined, and the modeling drawn by the land itself is interesting. ,Interesting.
I'm wondering if I can manage to build the modeling that the land draws.
Even though the buildings built on the land are already dependent on the land, they often try to forcibly level the land to minimize the impact from the land, which I always think is impossible.
There is also a way to build on land, but that is not called building. The scope of architecture will be expanded on the premises if the formation of land and the formation of architecture are related to each other, or if the formation of land cannot produce architecture, or if it is successful.
外部と内部のつながりを考える時、外部と内部はつなげるのが良いということが前提になるが、それは同時に、外観だけ、内部空間だけを重要視することが良くないということも前提になる。
外観だけ、あるいは内部空間だけでは建築として成立しないと考えるからだが、外観が何かを喚起し、周辺環境や内部空間に何か影響を与えるならば、あるいは内部空間から外へ広がり何か影響を与えるならば、その影響が「つながり」と呼べるような双方向で無くて、一方通行的な影響であったとしても、その場合は、外観だけ、あるいは内部空間だけでも建築として成立するだろう。
もしくは、外部でもない、内部でもないような、あるいは、外部と内部の両方の要素を併せ持ったようなハイブリッドな空間を創出できれば、「つながり」などと考える必要すらなくなる。
"Neither outside nor inside"
When considering the connection between the outside and the inside, it is premised that it is good to connect the outside and the inside, but at the same time, it is also premised that it is not good to emphasize only the appearance and the internal space.
This is because I think that the exterior alone or the interior space alone cannot be established as an architecture, but if the exterior evokes something and has any effect on the surrounding environment or interior space, or if it spreads out from the interior space and has some effect. If given, even if the effect is a one-way effect rather than a two-way effect that can be called a "connection," in that case, the exterior alone or the interior space alone will be established as an architecture.
Or, if we can create a hybrid space that is neither external nor internal, or that has both external and internal elements, we do not even have to think of it as a "connection."
アクティビティを喚起するような外観はあるのだろうか、それは建築として成立するのだろかと考えてみた。
アクティビティを喚起する外観と考えて最初にイメージするのは広告である。広告はそもそもアクティビティを喚起するためのものだから、全面広告のビルディングは正にアクティビティを喚起する外観をしている、しかし、それを建築とは言わない。
そうすると、外観のデザインが広告性を帯びればよいとなるが、広告の持つ時間が建築の持つ時間と相容れない。時間で比較すれば、建築の寿命に対して広告の寿命が圧倒的に短い。寿命が短い広告だから、建築よりもアクティビティを喚起する仕掛けができるとも言える。
ただ、それは時間で比較した場合である。広告が持つアクティビティを喚起する仕掛けを建築に転用した場合に何ができるかを考える余地はまだあると思った。
"Room for diversion of advertising"
I wondered if there was an appearance that evoked activity, or if it would be an architecture.
Advertising is the first thing that you think of as an activity-inspiring appearance. Since advertising is meant to evoke activity in the first place, a full-page advertising building has a very activity-inspiring look, but it's not called architecture.
In that case, it would be good if the design of the exterior had an advertising property, but the time of the advertisement was incompatible with the time of the architecture. When compared in terms of time, the life of advertisements is overwhelmingly shorter than the life of buildings. Since the advertisement has a short life, it can be said that it can be a mechanism to evoke activity rather than architecture.
However, that is the case when compared by time. I thought there was still room to think about what could be done if the device that evoked the activity of advertising was diverted to architecture.
狭い場所で距離感を調節するためにはどうするか。
平面的には調節できる程の距離が無い。ならば、上下に距離を取るしかない。
あるいは、実際の距離は近いが互いに向いている方向が違えば、互いに意識することは無く、距離感ではいえば遠のく。
上下の距離と向きの違いを上手に組み合わせれば、狭い場所でも離れた距離感を獲得することはできる。
"Adjustment of sense of distance"
How to adjust the sense of distance in a narrow place.
There is no adjustable distance on the plane. Then, there is no choice but to keep a distance up and down.
Alternatively, if the actual distances are close but the directions facing each other are different, they will not be aware of each other, and the sense of distance will be far.
By properly combining the vertical distance and the difference in orientation, it is possible to obtain a sense of distance even in a narrow space.
服を纏うように建築を考えた時に、人と建築の間にできる隙間をどうするか、本来であれば、建築の内部空間に人が滞在するという構図だが、人と建築の間に空間が存在し、その空間が隙間だと考えを置き換えてみると、急に壁や天井や床との距離感が気になり、服でいうとサイズ感、建築でいうとスケール感が浮き彫りになる。
隙間として見える壁、天井や床は、単に遠いか近いかだけの違いでしかなくなり、隙間の中に身を寄せる人は壁、天井や床との距離感だけを測り、ちょうど良い距離を選択して佇む。
"A sense of distance in the gap"
When thinking about architecture as if wearing clothes, what to do with the gap between people and architecture is originally a composition in which people stay in the interior space of architecture, but there is a space between people and architecture. However, when I replace the idea that the space is a gap, I suddenly become concerned about the sense of distance from the walls, ceiling, and floor, and the sense of size in terms of clothes and the sense of scale in terms of architecture become apparent.
The walls, ceilings and floors that appear as gaps are only different depending on whether they are far or near, and those who move into the gaps only measure the sense of distance to the walls, ceilings and floors and select the right distance. Standing.
建築を服のように纏うことを考えてみた。服にはサイズ感というものがあり、それは建築のスケール感と似ているかもしれない。ここ最近の流行りの服はオーバーサイズ気味で、身体との間に隙間ができる。服にはシルエットという見え方の良し悪しを図る言葉があるが、それは建築のプロポーションに対応する。
シルエットが綺麗に見えるようにデザイナーは、服と身体との間にできる隙間をデザインするだろう。
服の見え掛かりの形を直接的に綺麗に見せようとしても、服は人が着て動き回るものだから、形が定まらずに、シルエットを綺麗に見せることができないと思う。
それよりも、隙間を人の動きも考慮してデザインすれば、動きの中でシルエットを綺麗に見せることができるはずであり、それが服本来のシルエットの綺麗さにつながると思う。
では建築では、その隙間を内部空間として捉えて、シルエットにあたるプロポーションが綺麗に見えるように考えてみようと思う。
"Gap design"
I thought about wearing architecture like clothes. Clothes have a sense of size, which may resemble the scale of architecture. The clothes that are popular these days are oversized, and there is a gap between them and the body. There is a word in clothes that looks good or bad, which is called a silhouette, but it corresponds to the proportions of architecture.
Designers will design the gap between the clothes and the body so that the silhouette looks beautiful.
Even if you try to make the apparent shape of clothes look beautiful directly, you can't make the silhouette look beautiful because the clothes are worn by people and move around.
Rather, if you design the gaps in consideration of the movement of people, you should be able to make the silhouette look beautiful in the movement, which will lead to the beauty of the original silhouette of the clothes.
Then, in architecture, I would like to think of the gap as an internal space so that the proportions that correspond to the silhouette look beautiful.
人と人が佇み繋がるだけでよければ建築はいらない。別に建築がなくてもコミニケーションは取れるし、そこにいていくらでも寛ぐことはできるし、楽しむことができる。
別に建築は空気のような存在で何でもよい状態がむしろ多いかもしれないが、建築を感じることなく、人と人をつなぐ存在として建築があるのが望ましい。
建築を感じることはないが、建築によってコミニケーションの質が変わるようなことを考えている。それは、人がそこにいる時に建築がどのように関わるかが問われることであり、大多数の建築はそれを考えているようで実は的外れの考えをしていることが多い。
人と建築が対峙してしまっており、それは建築を自分から離した対象物としてみているからで、同じ物でも身に纏うような、服のような見方ができれば、また違った建築空間の在り方があるだろう。
"Wearing architecture"
You don't need architecture if you just need to connect people. Communication can be taken even if there is no separate architecture, and you can relax and enjoy yourself as much as you want.
Apart from that, architecture may be like an air and may be in a state where anything is fine, but it is desirable that architecture exists as an entity that connects people without feeling it.
I don't feel the architecture, but I think that the quality of communication will change depending on the architecture. The question is how architecture is involved when people are there, and the vast majority of architecture seems to be thinking about it, and in fact it is often off the mark.
People and architecture are confronting each other, because we see architecture as an object away from ourselves, and if we can see the same thing as clothes, it will be a different way of building space. There will be.
狭い中に人が佇む場所をつくろうとするとお互いの距離感が気になる。そこで、実際の距離は変わらないが、視線が交差しないように向きを変えたり、目線が合わないように高さを変えたりなど工夫をするのだが、それは単に人と人との関係にしか目を向けていない。
人と人の関係の間に建築を挟み込むことにより、お互いの距離感に変化が起こるようなことを考えてみる。
"Put the architecture in between"
When trying to create a place where people can stand in a small space, I'm worried about the sense of distance between them. Therefore, although the actual distance does not change, we try to change the direction so that the eyes do not intersect, or change the height so that the eyes do not match, but that is only the relationship between people. Not aimed at.
Consider that by sandwiching architecture between people, the sense of distance between them changes.
どこに佇むかと考えていくと、ひとつの視点として、同化できる場所を探して佇む場所とすることが考えられた。
同化とは、周りに順応し存在を消すことができることとするならば、建築では、人が周りの建築デザインに順応して存在を消すこととなる。そうすると、それは人と建築が一体となることだろうか。
人と建築の関係を考える中で同化は今まで考えたことがなかった。
"Assimilation of people and architecture"
When thinking about where to stand, one idea was to find a place that could be assimilated and use it as a place to stand.
Assimilation means that in architecture, a person adapts to the surrounding architectural design and disappears, if it can adapt to the surroundings and disappear. Then, does it mean that people and architecture become one?
I have never thought about assimilation while thinking about the relationship between people and architecture.
見渡す限りの広い野原があったとして、その広い野原の中で佇むとしたら、どこを選ぶだろうかと考えてみた。
別に野原でも何でもよいのだが、人が自分の居場所を選ぶ時に根源的に何を基準とするかを考えてみたかったので、とりあえず、そもそもの場所にあまり特徴が無い、なるべくニュートラルな場所を思い浮かべみた。どうして野原がニュートラルな場所かという話もあるが、それはとりあえず置いておく。
ちょっとでも窪んだ所を探すかもしれない。それとも穴を掘るか。とにかく身を隠せそうな場所、木があれば、その根元を居場所とするかもしれない。
あまりにも広くてオープンな場所では落ち着かないので、周りから目立たない場所、あるいは同化できる場所を探して佇む場所とするだろう。
"Where do you stand?"
Even if there was a wide field as far as the eye could see, I wondered where to choose if I were to stand in that wide field.
It doesn't matter if it's a field or anything, but I wanted to think about what the basic criteria should be when people choose their place of residence, so for the time being, I think of a place that is as neutral as possible and has few characteristics in the first place. saw. There is talk of why the fields are neutral, but I'll leave that for now.
You may look for a dented place. Or do you dig a hole? Anyway, if there is a place where you can hide yourself, a tree, you may use the root as your place of residence.
It's too big and open to settle down, so you'll probably want to find a place that doesn't stand out or can be assimilated.
建築的要素が直接的に人の居場所を決めることはよくある。それ以外で考えていくと、例えば、人の感情や気分がまずあり、その人の感情や気分が居場所を決めることがある。人は感情の動物だから、この感情や気分で居場所を決めることは多いだろうし、自然なことだろうが、そこに直接的に建築的要素が絡んでくるようにするには、建築的要素が人の感情や気分を誘発する図式がひとつ思い浮かぶ。
ただ、この図式は人の感情や気分が建築的要素と居場所を媒介するような役目となるので、人の感情や気分を省いてしまって、建築的要素が直接的に人の居場所を決める場合と大差がないと考える。
人の感情や気分が建築と居場所を媒介となる図式ではなくて、人の感情や気分が建築的要素に影響を与えることにより居場所が決まるような図式にすれば良い。
そのためには、人の感情や気分によって建築的要素に変化が起きるようなデザインを考える必要がある。
"Architecture determined by mood"
Architectural factors often directly determine a person's whereabouts. Other than that, for example, a person's emotions and moods may first be present, and that person's emotions and moods may determine whereabouts. Since human beings are emotional animals, it is likely that this emotion and mood will determine where we are, and it may be natural, but in order for architectural elements to be directly involved in them, architectural elements are necessary. I can think of one scheme that induces human emotions and moods.
However, in this scheme, the emotions and moods of a person act as an intermediary between the architectural elements and the whereabouts, so if the emotions and moods of the person are omitted and the architectural elements directly determine the whereabouts of the person. I think that there is no big difference.
Instead of a scheme in which a person's emotions and moods mediate between architecture and whereabouts, a scheme in which a person's emotions and moods influence architectural elements to determine whereabouts should be used.
For that purpose, it is necessary to think of a design in which architectural elements change depending on the emotions and moods of people.
なぜ人はその場所を選ぶのか、なぜ人はそこに居るのかの理由を建築から考えてみた。そこに居たいと思わせる空間であり、雰囲気があるのだろう。その雰囲気をさらに紐解いていくと、スケール感、見え方、その見え方には色や明るさ、壁や天井などの建築要素の質感などが関係してきて、これらのバランスで雰囲気が決まる。
普通はこのスケール感、見え方の色や明るさ、壁や天井などの建築要素の質感などのバランスをデザインしていく。
これら以外で人の居場所を決める要因が建築的にあるだろうか。そこを考えることが何かにつながる。
"Think about something other than normal balance"
I thought about the reason why people choose the place and why people are there from the architecture. It's a space that makes you want to be there, and it has an atmosphere. Further unraveling the atmosphere, the sense of scale, the way it looks, the color and brightness, and the texture of architectural elements such as walls and ceilings are related to the way it looks, and the balance determines the atmosphere.
Normally, we design the balance of this sense of scale, the color and brightness of the appearance, and the texture of architectural elements such as walls and ceilings.
Are there other architectural factors that determine the whereabouts of people? Thinking about it leads to something.
建築の中で人のいる場所が機能からくる要求で決まることが普通に思えてつまらない。
例えば、飲食店ならば、ホールにテーブルとイスが並び、どこのテーブルのどこのイスに座るかは、その飲食店でのルールによって決まる。そして、そのルールは飲食というお店の用途からくる建築の機能で決まる。この当たり前のことが普通に思えてつまらない。
その建築、その空間、その場所だから、その居場所がお店の用途や機能とは関係がないところで決まるデザインを考えている。
"How to decide where to stay"
It seems normal and boring that the place where people are in architecture is determined by the demands of function.
For example, in the case of a restaurant, tables and chairs are lined up in the hall, and which table and which chair to sit on is determined by the rules at that restaurant. And the rules are determined by the architectural function that comes from the purpose of the store, which is eating and drinking. This obvious thing seems normal and boring.
Because of the architecture, the space, and the place, I am thinking of a design where the place is determined where it has nothing to do with the purpose or function of the store.
小さい建築になれば、ひとつの空間だけで満たされることが多いかもしれない。小さい建築の小さい空間をいくつにも分割したら、より小さい空間ができあがるだけである。
これは小さい空間は狭苦しくて良くなく、大きい空間、広い空間は小さくて狭苦しい空間より良いという考えが元になっているが、より小さくて狭い空間の方がより大きくて、より広い空間より良いことがあれば簡単に覆ることである。
"Small and narrow is better"
In a small building, it may often be filled with just one space. If you divide a small space in a small building into several pieces, you will only have a smaller space.
This is based on the idea that a small space is not good because it is cramped, and a large space is better than a small and cramped space, but a smaller and narrower space is larger and better than a wider space. If there is, it is easy to cover.
つくり方を変えれば、見え方が変わると考えてみた。
見え方を操作するには、目に見えるものを操作することになり、それは設計やデザインすることだが、設計やデザインの後にくるつくる行為が変われば、設計やデザインが同じでも、見え方が変わるのではないかと考えた。
つくり方に疑問を持つことは設計やデザインの段階ではほとんど無い。設計やデザインではでき上がりの結果に着目し、つくり方は過程だから設計やデザインの範疇ではない。
設計やデザインの段階でつくり方も設計やデザインしたら、結果と過程の重要度が入れ替わり、過程が重視され、結果に執着しなくなる。そうなれば、状況や場面によって結果が変わり、結果が定かではなくなる。
結果が定かでない状況が見え方に変化を与えるのだろう。
"The result is uncertain"
I thought that if you change the way you make it, the way it looks will change.
To manipulate the appearance, you are manipulating what you can see, which is designing and designing, but if the design and the act of making things after the design change, the appearance will change even if the design and design are the same. I thought it might be.
There are few doubts about how to make it at the design or design stage. In design and design, we pay attention to the result of the finished product, and since the method of making is a process, it is not in the category of design or design.
If you design and design how to make at the design and design stage, the importance of the result and the process will be exchanged, the process will be emphasized, and you will not be obsessed with the result. If that happens, the results will change depending on the situation and situation, and the results will be uncertain.
The situation where the result is uncertain will change the appearance.
建築とは内部に空隙があり、そこに人が滞在できる程の大きさがあるものだと定義してみる。
内部の空隙を何かでいっぱいに満たせば、空隙ではなくなるから、それは建築にはならない。しかし、最初は空隙があったのだから、はじめは建築だった。
その満たす何かが空気ならば以前として建築である。ならば、いっぱいに満たすものしだいで建築かどうかが決まり、建築ではないのに建築になる状態をつくれるかもしれない。空隙をつくり、またそこを何かで埋める、埋めるものしだいで建築か建築じゃないかが決まる。
例えば、すぐ壊せるもので埋めてしまい、必要に応じて後で空隙をつくる。建築→建築じゃない→建築と変化した時に空間の見え方に何か変化が起こるだろうか。建築のつくり方の前提に対する疑問である。
"For the premise of how to make"
Let's define architecture as something that has a void inside and is large enough for people to stay there.
If you fill the internal void with something, it will not be an architecture because it will not be a void. However, at first there was a gap, so it was architecture at first.
If something that fills it is air, it is still architecture. Then, depending on what is filled up, it may be decided whether or not it is an architecture, and it may be possible to create a state where it becomes an architecture even though it is not an architecture. It is decided whether it is architecture or not depending on what creates a gap and fills it with something.
For example, fill it with something that can be broken immediately, and create a gap later if necessary. Will there be any change in the appearance of space when it changes from architecture to not architecture to architecture? It is a question about the premise of how to make architecture.
建築から色や質感を切り離そうと考えたのは、色や質感を選択できない状況でも建築が成り立つようにできると考えたからで、色や質感を切り離してしまえば、建築には形と空間が残る。
形は主に外形をイメージし、外形によって空間は存在するから、形と空間は切り離せなく、どちらかというと空間にとっては形は無くてはならない存在だが、形は空間無しでも存在する。
空間が無い形は中身が詰まったものだが、それを建築ということはできるのだろうか、単なる物体に過ぎないものになってしまうのではないかと思うが、空間が無い形が建築として成立することがあるならば、新しい見え方につながる可能性があるだろう。
"Shape without space"
I thought about separating colors and textures from architecture because I thought that it would be possible to make architecture even in situations where I couldn't select colors and textures. Remain.
The shape mainly imagines the outer shape, and the space exists depending on the outer shape, so the shape and the space cannot be separated. If anything, the shape is indispensable for the space, but the shape exists even without the space.
A shape without space is full of contents, but I wonder if it can be called an architecture, or it may be just an object, but a shape without space is established as an architecture. If so, it could lead to a new look.
普通は建築の範疇になり得るものを見つけ出し、建築の範疇として捉えるものを増やす、要素をつけ足すものだが、建築の範疇としているものの中にはこじつけ、むしろ建築から切り離してしまった方が良いものもある。
例えば、色や質感はどうだろうか、建築の範疇から切り離し、デザインとしてもニュートラル、中途半端、曖昧、中庸なものとして捉え直したらどうだろうか。
きっと設計する時の思考回路が変わるだろう。
"Separate colors and textures"
Usually, it is to find out what can be a category of architecture, increase what is regarded as a category of architecture, add elements, but it is better to pry some of the categories of architecture and rather separate it from architecture. There is also.
For example, what about colors and textures? How about separating them from the category of architecture and reconsidering them as neutral, half-finished, ambiguous, and moderate in design?
I'm sure the thinking circuit when designing will change.
建築を存在させるためには、全てを建築の範疇で考える必要があった。周辺の環境や建主の要望や個々の材料に至るまで全てが建築の範疇として、建築することを中心にして捉えていく。それはある意味、当たり前のことだが、中には無理矢理、建築の範疇にしている場合もあるし、無意識のうちに建築と結びつけて決めつけている場合もある。
ひとつひとつ解きほぐすように、建築の範疇にあるものの中から不自然なものを取り除こうとしている。結果的にその行為が創造やデザインにつながる。
"Remove from the category of architecture"
In order for architecture to exist, it was necessary to consider everything in the category of architecture. Everything from the surrounding environment to the needs of the owner and individual materials is considered as a category of architecture, focusing on construction. In a sense, it is a matter of course, but in some cases it is forced into the category of architecture, and in other cases it is unknowingly linked to architecture.
I'm trying to remove the unnatural things from the things in the category of architecture, as if to unravel them one by one. As a result, the act leads to creation and design.
時間と人のアクティビティを掛け合わせると何が起こるのかと考えてみた。
アクティビティが時間に左右されることは日常的にあり、いつも忙しいと言っている人はその典型であり、それは喜ばしいことではないが、時間がアクティビティに左右されることは時間を操っていることになり、時間管理が上手な人である。
建築では人のアクティビティも時間もデザイン要素として扱えて、掛け合わせで空間を決めることができ、その空間にいる人は時間やアクティビティを忘れて佇む。
"Time and activity"
I wondered what would happen if time was multiplied by human activity.
Activity is time-dependent, and people who say they're always busy are typical, which isn't a pleasure, but time-dependent activity is about manipulating time. He is a person who is good at managing time.
In architecture, people's activities and time can be treated as design elements, and the space can be decided by multiplying them, and people in that space forget about time and activity.
設計する時は今この時だから、必ず未来を考えることになり、未来を考えるために過去に遡ることもある。まだ何もない未来のことを考えるのだから当然想像力がないとできないが、過去に遡ることも全てがわかっている訳ではないから想像力かいる。
今この時を基準に未来や過去は、両方とも想像力がいるのだから、今この時だけ想像力なしに目に見える現実だけが全てということはないだろう。
"Imagination of time"
Since it is this time to design, we always think about the future, and sometimes we go back to the past to think about the future. Of course, I can't do it without imagination because I think about the future when there is nothing yet, but I have imagination because I don't know everything going back to the past.
Since both the future and the past have imagination based on this time, it is unlikely that the reality that can be seen without imagination is all.
時間の経過を建築デザインで表現するものだろうかと素直に疑問に思った。記憶としての時間経過を建築デザインに生かす試みは素晴らしい事例もたくさんあるのだが、その場合の記憶は誰もが印象的に思うことであり、そもそも特徴的である場合が多い。
日常的で普通なこと、そして、普通に起きる時間の経過を記憶として建築デザインに生かすを考えていた時に、それが当たり前過ぎていたことに疑問を持った。
"I doubt the expression of the passage of time"
I honestly wondered if the passage of time would be expressed in architectural design. There are many wonderful examples of attempts to utilize the passage of time as a memory in architectural design, but the memory in that case is something that everyone thinks impressively, and it is often characteristic in the first place.
I was skeptical that it was too commonplace when I was thinking about using everyday and ordinary things and the passage of time that normally occurs in architectural design as a memory.
今まで建築とは全く関連性がないことで成り立つ建築を想像してみる。人以外で建築と関連性があることは何があるだろうかと考えてみる。そうしたら、ふと思い浮かんだ建築があった、カーンのインド経営大学である。25年くらい前に訪れた時、よく理解できなくて、未だによくわからない建築だが、感じるのは人とは関係なしに建築そのものに宿る何かがあることで、その何かが説明できないし、わからないのだが、それを25年経った今この時の言葉で表現を試みれば、これまでとは違う建築との関わり方ができそうな気がする。
"Different ways of getting involved"
Imagine an architecture that has nothing to do with architecture until now. Think about what is related to architecture other than humans. Then, there was an architecture that came to my mind, Khan's Indian Institute of Management. When I visited about 25 years ago, I couldn't understand the architecture well, and I still don't understand it, but what I feel is that there is something in the architecture itself that has nothing to do with people, and I can't explain or understand that. However, 25 years later, if I try to express it in the words of this time, I feel that I will be able to relate to architecture differently than before.
建築は人が使うものだから、人なしで建築は成立しないだろうとずっと考えてきた。人と建築の関わりの中で建築空間を思考することに慣れ親しんできた。人との関わりの中で建築を見るのが面白い、好きな建築を見つけ出すのも人との関わり合いからだったが、人なしで建築が成立する可能性を全く考えてなく、また、建築を思考する範疇でずっと考えてきたので、建築という大枠の外と、全く関連性がないことと結びつけてこなかったし、結びつけ方がわからなかった。
"Architecture outside the category"
I've always thought that architecture wouldn't be possible without people because it's something that people use. He has become accustomed to thinking about architectural space in the relationship between people and architecture. It is interesting to see architecture in the relationship with people, and it was from the relationship with people that I found my favorite architecture, but I did not think about the possibility that architecture could be established without people, and I did not think about architecture. I've been thinking in the category of thinking for a long time, so I haven't linked it to something that has nothing to do with the outside of architecture, and I didn't know how to connect it.
人によって強度が上がった建築は、人とは関係なしに建築単体で成り立つようになる。
初期の段階では建築は人に依存するが、人によって建築が持つ可能性が最大限に引き出された後には建築だけで存在ができる程、強い存在感を出すようになり、美術工芸品とは違う人と関係ないところで成り立つ建築が生まれる。
人が単体で成り立つ建築に昇華させる。
"Architecture that people sublimate"
Buildings that have been strengthened by people will be built on their own, regardless of people.
In the early stages, architecture depends on people, but after people have maximized the potential of architecture, it has become so strong that it can exist alone, and what is an arts and crafts? An architecture that can be established in a place that has nothing to do with different people is born.
Sublimate into an architecture that consists of a single person.
人と関係ないところで建築が成り立つ様をイメージしてみる。そうすると今まで人が登場しない建築を想像したことが無いことに気がついた。
人が登場しないということは、人がいなくても建築が成り立つということだが、その昔、インドで見たタージマハルを思い出す。観光客はたくさんいたが、建築自体は贅の限りを尽くしたもので、建築というよりは美術工芸品で鑑賞するためのもので、そこに人がいる必要もなく、ただ眺めるだけのもので、建築というには違和感があった。
今度は、美術工芸品となる建築以外で、人が登場しない建築が成り立つだろうかと考えてみる。
"Architecture without people"
Imagine that architecture is established in a place that has nothing to do with people. Then I realized that I had never imagined an architecture in which no one appeared.
The fact that no one appears means that architecture can be established without people, but I remember the Taj Mahal I saw in India a long time ago. There were a lot of tourists, but the architecture itself was a luxury, it was more for arts and crafts than architecture, there was no need for people to be there, it was just for viewing. There was a sense of discomfort in architecture.
Next time, I wonder if there will be an architecture in which no one appears, other than the architecture that becomes an arts and crafts.
人の動きと空間が連動する様がいいと考えている。空間は止まっているもので、人は動くものだが、空間が人の動きを喚起する、または人の動きが空間に寄与する。
その前提は何かというと、建築は人との関わり合いで成立するものだと考えているからで、建築単体では成り立たない。
しかし、その前提が崩れたら、とも考えている。
"Architecture alone"
I think it is good that the movement of people and the space are linked. Space is stationary and people move, but space evokes the movement of people, or the movement of people contributes to space.
The premise is that architecture is established by the relationship with people, so it cannot be established by architecture alone.
However, I also think that if that premise breaks down.
川の土手のような傾斜しているところに腰を下ろして眺めることが好きだった。普通にベンチへ座ればいいのに土手を選ぶ。子供の頃、よく多摩川の土手に行ったもので、土手は恰好の観覧席だった。
ヨーロッパへ行くと傾斜している広場がある。ヨーロッパには日本とは違い広場の文化があるから、あちらこちらに有名無名な広場がたくさんあり、広場が生活に根ざしている。パリのポンピドゥセンターの前庭も傾斜した広場になっていて、たくさんの人が腰を下ろしていた。
面白いのは平らな広場では腰を下ろしている人がいないということ。別に傾斜しているからと言って腰を下ろす必要もないのだが、傾斜していると腰を下ろしている人がいても不自然ではない。傾斜と人の意識のつがりが面白い。
"Sit down on the slope"
I liked to sit down and look at the slopes like the banks of a river. I choose a bank even though I can sit on the bench normally. As a kid, he used to go to the banks of the Tama River, which was a great bleacher.
When you go to Europe, there is a sloping square. Unlike Japan, Europe has a culture of plazas, so there are many famous and unknown plazas here and there, and the plazas are rooted in our daily lives. The front yard of the Pompidou Center in Paris was also a sloping square, and many people were sitting there.
What's interesting is that no one is sitting on a flat square. You don't have to sit down just because you're tilted, but it's not unnatural for some people to sit down if you're tilted. The inclination and the connection of people's consciousness are interesting.
地面との接触面を意識して見え方を考えている。
建築は地面の上に載り、必ず地面との接触面ができるので、土地とのつながりが必然的にできてしまい、土地に縛られる、土着的な、リージョナルな建築を生み出すことになる。そこで、モダニズム建築では意識的に地面から離すことで、建築をインターナショナルなものにしようとした。その代表的な手法がピロティであり、地面から持ち上げ、切り離すことで土地とのつながりを断ち、土地と建築の間に新たな空間を差し込んだ。コルビュジエはそのピロティを多用し、新たなにできた空間を都市に寄与する交通空間として捉えていた。
地面から建築を切り離す行為は、建築をインターナショナルかリージョナルかの両極端で考えようとした時の副産物であるので、ピロティにはある種の清さを感じるが、同時にピロティには古臭さも感じるので、建築をインターナショナルかリージョナルかの両極端で考えること自体が現代では古臭く、的外れなのだろう。
接触でも無く、切り離しでも無い状態をつくり出すことができれば、新たな見え方が獲得できる。
"Connection with the land"
I am thinking about how to see it, paying attention to the contact surface with the ground.
Since the architecture rests on the ground and always has a contact surface with the ground, it inevitably creates a connection with the land, creating an indigenous, regional architecture that is tied to the land. Therefore, in modernist architecture, I tried to make the architecture international by consciously moving it away from the ground. A typical method is piloti, which breaks the connection with the land by lifting it from the ground and separating it, and inserts a new space between the land and the building. Le Corbusier made heavy use of the piloti and regarded the newly created space as a transportation space that contributes to the city.
The act of separating architecture from the ground is a by-product of trying to think of architecture at the extremes of international and regional, so the piloti feels some kind of cleanliness, but at the same time, the piloti also feels old-fashioned, so architecture. It seems that thinking at the extremes of international and regional is old-fashioned and irrelevant in modern times.
If we can create a state that is neither contact nor separation, we can acquire a new appearance.
敷地のコンテクストからレベル差を抽出し、そこに別の意味や状況を重ね合わせて、別の価値観を生み出す。意味や状況は何と関連付けるのかと考えてみる。
敷地とは全く関連が無いことを考える。飲食店の建築だから厨房設備があるので、敷地のレベル差と厨房設備を関連付けてみる。
厨房設備は機能的に動けることが要求されるので、床にレベル差があると困るかもしれないが、レベル差があることがむしろ良くなることを考えてみる。
"Not related"
Extract level differences from the context of the site and superimpose different meanings and situations on them to create different values. Think about what you relate to meaning and situation.
Consider that it has nothing to do with the site. Since it is a restaurant building, there are kitchen facilities, so let's associate the level difference of the site with the kitchen facilities.
Since kitchen equipment is required to be able to move functionally, it may be a problem if there is a level difference on the floor, but consider that the level difference is rather better.
敷地の高低差を吸収して建築するのではなくて、高低差をプランニングに活かしたいと常々考える。
見た目以上に敷地の高低差はプランニングに影響を与え、捉え方によってはコンテクストとして活かすこともある。
すでに緩やかな傾斜がある敷地で、傾斜を無視して建築することもできるが、傾斜をプランニングに活かし、レベル差をデザインした。
"Context of the site"
Instead of absorbing the height difference of the site and building it, I always want to utilize the height difference for planning.
The height difference of the site affects the planning more than it looks, and depending on how it is perceived, it may be used as a context.
It is possible to build a site that already has a gentle slope, ignoring the slope, but the slope was used for planning to design the level difference.
平らな土地というのは、意外かもしれないが、案外無い。正確にいうと平らな土地とは、道路との段差が無く、尚且つ、土地にレベル差が無く平らということであり、もちろん道路も平らである。全てが平らということは珍しい。
建築する時は平らであることが前提だから、平らでない土地に平らなレベルをどこかに設定する。その設定の仕方にもセオリーはあるのだが、その設定の仕方からデザインははじまる。
前に、渋谷駅の近く、桜の木が目の前に見える斜面地で設計をしたことがある。目の前だから平らなレベルをどこに設定しても桜の木は見える。ただ疑問に思う、平らなレベルが必要かと。斜面なりに床をつくれば、桜の木が全て見える。
結局アンビルトになったが時々思い出す。設計にはセオリーも、クライアントに対する正解も存在するが、周辺環境の特殊さを生かし一般解にまで昇華する視点などあらゆる視点から一度は考えてみることも必要だろう。
"All perspectives"
Flat land may be surprising, but not surprising. To be precise, a flat land means that there is no step with the road and the land is flat with no level difference, and of course the road is also flat. It is unusual for everything to be flat.
Since it is assumed that the building is flat, set a flat level somewhere on the uneven land. There is a theory in how to set it, but the design starts from how to set it.
Before, I designed it on a slope near Shibuya station where cherry blossom trees can be seen in front of me. Because it is right in front of you, you can see the cherry blossom trees no matter where you set the flat level. I just wonder if I need a flat level. If you make a floor on the slope, you can see all the cherry trees.
It turned out to be unbuilt, but I remember it from time to time. There are theories and correct answers for clients in the design, but it is also necessary to think once from all perspectives, such as the perspective of sublimating to a general solution by taking advantage of the peculiarities of the surrounding environment.
建築空間においてスケールによる心地良さというのがある。ただ、それも「心地良いスケール」として刷り込まれているのかもしれない。これが「心地良いスケール」ですよというパッケージを示されて、ブランド品を購入するように無条件で受け入れているのかもしれない。
大体「心地良いスケール」として示されているものはヒューマンスケールである。スケールを感じるようとする時は天井や壁までの距離を意識してみるといい。天井が低くくて圧迫感があるのに、それを人のスケールに合った落ち着く空間と解釈したりもする。
人ではない、違う尺度で建築空間のスケールを考えてみたいと思う。スケールの扱いを変えるだけでそれまでとは全く違う空間をつくり出すことができるはずである。
"Handling of scales"
There is comfort due to scale in the architectural space. However, it may also be imprinted as a "comfortable scale". They may be shown a package that says this is a "comfortable scale" and unconditionally accept them to buy branded products.
What is generally described as a "comfortable scale" is the human scale. When you want to feel the scale, you should be aware of the distance to the ceiling and walls. Even though the ceiling is low and there is a feeling of oppression, it is sometimes interpreted as a calm space that fits the scale of a person.
I would like to think about the scale of architectural space on a different scale than people. You should be able to create a completely different space just by changing the treatment of scales.
建築空間においてスケールは人の大きさを基準にするのが普通である。人が空間を使うのだから、人の大きさを基準にするのは理に適っている。
建築空間には、どのように使うか以外に、どのように見えるかもあるだろう。見え方を考える時のスケールは人を基準にする必然性は無い。ならば何を基準にスケールを決めるのか。
見え方で空間を考える時のポイントはスケールの設定基準かもしれない。
"Scale standard"
In an architectural space, the scale is usually based on the size of a person. Since people use space, it makes sense to base them on the size of the person.
In addition to how it is used, it may look like it in an architectural space. The scale when thinking about how to look does not have to be based on people. Then what is the basis for deciding the scale?
The point when thinking about space in terms of appearance may be the scale setting standard.
モノの代わりにヒトを据えてみる。ヒトが媒体となり気分や感情と空間をつなげてみる。
ヒトの見え方が空間を決める。ヒトが見た時の空間が気分によって変わる。気分によって空間の見え方が変わる。気分によって人が移動した時に移動した先ごとに空間の見え方が変わる。
人が移動するというアクティビティと気分や感情がリンクして、空間の形が非対称あるいは場所によって空間の形が違うならば、気分によって空間が決まる状況が生み出せる。
"Space created by mood"
Try to set humans instead of things. Humans serve as a medium to connect moods, emotions, and space.
The way humans see determines the space. The space when humans see it changes depending on their mood. The appearance of the space changes depending on the mood. When a person moves, the appearance of the space changes depending on the mood.
If the activity of moving people is linked to moods and emotions, and the shape of the space is asymmetrical or the shape of the space differs depending on the location, a situation can be created in which the space is determined by the mood.
モノから離れるから気分や感情を空間の要素として扱える。モノからも気分や感情を扱うことができるが、空間の要素としては相入れない。
モノの良し悪しが気分や感情を誘発するが、空間とは何も関係が無く、単に物欲と同じである。
空間の要素としての気分や感情は人の欲望とは関係が無いところで成立するはずである。
"Mood and space"
You can treat your mood and emotions as elements of space because you are away from things. You can handle moods and emotions from things, but they are incompatible as elements of space.
Good or bad things provoke moods and emotions, but they have nothing to do with space and are just like greed.
Moods and emotions as elements of space should be established where they have nothing to do with human desires.
建築は「ものづくり」ではないと考えている。
図面では「もの」の仕様を明記し、モノを決めるために図面を描き、模型はその図面を元にしてモノの積み上げを三次元で見せているが、建築空間を直接的に表記している訳では無く、モノを決めることを通して建築空間を表現しようとしている。
対してVR、ARは建築空間を直接的に表現できるツールであり、VR、ARにはモノは存在しない。現実的には図面無しでは建築をつくることはできないので、図面化の作業は残るし、現段階だとVR、AR空間をつくるために図面が必要である。
現実的には「もの」を介さずに建築空間をつくることはできないが、もし建築空間を直接的につくることができればモノは必要で無くなるし、少なくとも思考上では建築空間をつくるための「もの」は無くすことができるだろう。そうすればモノの優劣やモノをつくることから離れることができ、より制限が無く建築空間を思考できる。
"Not manufacturing"
I don't think architecture is "manufacturing."
In the drawing, the specifications of "things" are specified, a drawing is drawn to determine the thing, and the model shows the stacking of things in three dimensions based on the drawing, but it directly describes the architectural space. I am trying to express the architectural space by deciding things.
On the other hand, VR and AR are tools that can directly express the architectural space, and there are no things in VR and AR. In reality, it is not possible to create an architecture without drawings, so the work of drawing remains, and at this stage, drawings are required to create VR and AR spaces.
In reality, it is not possible to create an architectural space without going through "things", but if you can create an architectural space directly, you will not need things, and at least in terms of thinking, "things" to create an architectural space. "Will be eliminated. By doing so, you can move away from the superiority and inferiority of things and making things, and you can think about the architectural space without any restrictions.
ギチギチに遊びも無くモノが詰め込まれている状態ではうまく空間の中で立ち振る舞うことはできないだろう。モノとモノの組み合わせには完璧さを求める。その完璧さの中に美しさが宿るだろうと考えるからである。仮に完璧な組み合わせでモノがあったとして、そのモノは素晴らしいだろうが、完璧なモノで埋め尽くされた空間までも素晴らしいのだろうか。そこには断絶が存在していて、空間には空間なりのモノとは関係が無い作法が存在すると思う。
"The manner of space"
If there is no play and things are packed tightly, you will not be able to behave well in the space. We seek perfection in the combination of things. I think that beauty will dwell in that perfection. If there was a thing in the perfect combination, that thing would be wonderful, but is the space filled with perfect things also wonderful? There is a disconnection there, and I think there is a way of doing things in space that has nothing to do with things that are spaces.
窓から見える景色、窓を通して見える内部空間に惹かれる。直接景色を見るよりも、直接内部空間を見るよりも、窓の枠で切り取られ他の部分が削除されることにより、削除された部分に想像力が働き、窓越しに見えるものに見る人なりのものが入り込む余地が生まれる。この余地は解釈しだいでどうにでもなる。そもそも建築にどうにでもなる余地が無さ過ぎると思う。つくる側はその余地を想定するが、その余地を超えることは許さないので、つくる側からは余地だが、受ける側からしたら余地にはならない。受ける側の余地はつくる側からしたら何になるのだろうか。
"margin"
I am attracted to the view from the window and the interior space that can be seen through the window. Rather than seeing the scenery directly, rather than seeing the interior space directly, by cutting out with the frame of the window and deleting other parts, the imagination works on the deleted part, and it is a person who sees what can be seen through the window. There is a margin for things to enter. This margin can be anything depending on the interpretation. In the first place, I think there is too little blank space in architecture. The making side assumes that margin, but since it is not allowed to exceed that margin, it is a margin from the making side, but not from the receiving side. What will the margin on the receiving side be from the side of making?
モノを相対的に見るのが改めて面白いと思った。どうしても、モノの良し悪しを絶対的な尺度で判断してしまう。確かに、絶対的に良いモノ、悪いモノは存在するので、絶対的な良し悪しは判断できないと、いわゆる目利きである必要はあるが、そのモノ自体の見え方は相対的にならざるを得ない。モノ自体がまわりとの関係性が全く無く存在することは無いので、だから正確にいうと、モノ自体が存在している時点で絶対的な判断はできないのかもしれない。ならば、モノのまわりに存在しているモノをコントロールすることで相対的な価値を得る方が直接的にモノを扱うより新たな価値を見つける可能性が高いかもしれない。
"How to find"
I found it interesting to see things relatively. By all means, the quality of things is judged on an absolute scale. Certainly, there are absolutely good and bad things, so if you can't judge whether they are absolutely good or bad, you need to be a so-called connoisseur, but the appearance of the things themselves must be relative. .. Since the thing itself has no relationship with the surroundings and does not exist, to be precise, it may not be possible to make an absolute judgment when the thing itself exists. If so, it may be more likely to find new value by gaining relative value by controlling the things that exist around the thing, rather than directly dealing with the thing.
雑音の中に澄んだ音があるように、雑音が澄んだ音をあぶり出してくれるように、雑音は様々な場所で様々な形で存在しているから、なかなか気がつかないが、澄んだ音を探してみる耳さえあれば聞こえる。
無音の場所など無いのだから、雑音を取り込んで考えれば良く、雑などうでもいいことが実は一番多く、その扱い次第で真に見せたいことをあぶり出すことができ、意図的に直に真に見せたことを扱うわけではないので、悪い意味での恣意的にもならない。
"invisible ink"
Just as there is a clear sound in the noise, just as the noise makes a clear sound, the noise exists in various forms in various places, so it is hard to notice, but look for a clear sound. You can hear it if you have ears.
Since there is no silent place, you can think about it by taking in noise, and in fact, there are many things that don't matter, and depending on how you handle it, you can reveal what you really want to show, and intentionally it is true. It doesn't deal with what you've shown, so it's not arbitrary in a bad way.
誰も疑問に思わないこと、例えば、壁の厚さは部材の厚さで決まっている。部材の厚さに関連することは、見た目の仕上げの意匠や構造、設備の配管、断熱であるが、壁が厚くなる程、その分実際に使える空間が狭くなるので、壁はなるべく薄くしたいという前提がある。
極限まで壁を薄くする手法は今までも見られた。例えば、鉄板で壁をつくり、設備の配管は露出にし、断熱は壁に断熱塗料を塗り、もちろん構造は壁を鉄板にすることで担保されるので、壁の厚みは構造上の耐力で決まる。見た目の仕上げの意匠は鉄板の質感で十分である。
壁の厚さが部材の厚さで決らない場合があるだろうかと考えた。その場合は壁の厚さ自体に意匠上重要な意味がある場合であり、壁の厚さがデザイン要素となる場合である。
"Rethinking wall thickness"
No one wonders, for example, the thickness of the wall is determined by the thickness of the member. The things related to the thickness of the members are the design and structure of the appearance, the piping of the equipment, and the heat insulation, but the thicker the wall, the smaller the space that can actually be used, so the wall should be as thin as possible. There is a premise.
Techniques for thinning walls to the utmost have been seen. For example, the thickness of the wall is determined by the structural strength because the wall is made of iron plate, the piping of the equipment is exposed, the heat insulation is applied to the wall with heat insulating paint, and of course the structure is secured by making the wall an iron plate. The texture of the iron plate is sufficient for the visual finish.
I wondered if the wall thickness might not be determined by the thickness of the members. In that case, the wall thickness itself has an important design meaning, and the wall thickness is a design element.
見えないところに可能性があるならば、どこだろうと考えた、建築の場合である、設計図で表現されていないところである。
設計図で表現されていないとは、全く記載がないか、慣例や当たり前のことで何も考えずにいつでもどこでも同じことが記載されているかである。
前提条件が固定され疑いの余地が無い場合に起こることが考えないことであり、誰も疑問に思わない。そこにクリティカルな可能性があると思うし、それがデザインの素になる。
"Elementary"
I wondered where there was a possibility in the invisible place, in the case of architecture, where it is not represented in the blueprint.
What is not expressed in the blueprint is that there is no description at all, or that the same thing is described anytime and anywhere without thinking about customs or commonplace.
No one wonders what happens when the preconditions are fixed and unquestionable. I think there is a critical possibility, and that is the basis of design.
見えないところまで手を抜かないようにつくる、というのは何か、建築以外でも、料理や陶芸などのものをつくることならば、当てはまることだろう。手を抜かないのは当たり前だから、この場合、見えないところまで意識することが大事ということになる。
意識をすれば関心を持ち、見えないところに可能性を見出すかもしれない。普通は見えるところだけを考える。
建築の場合、見えるところは設計図で表現されているところだから、見えるところだけを考えていれば事は足りてしまい、見えないところまで意識をし可能性を見出さなくても完了する。
だから、見えないところまで意識するということは、はじめから意図して可能性を見出す目的がないとできない。
"Invisible place"
What does it mean to make things that you can't see without cutting corners? If you're making something other than architecture, such as cooking or ceramics, that's true. It is natural not to cut corners, so in this case, it is important to be aware of what you cannot see.
If you are conscious, you may be interested and find possibilities in the dark. Normally, only think about what you can see.
In the case of architecture, the visible part is represented by the blueprint, so it is enough to think only about the visible part, and it is completed without consciousness of the invisible part and finding the possibility.
Therefore, it is impossible to be conscious of the invisible part without the purpose of intentionally discovering the possibility from the beginning.
刻み、剥ぎ取り、また刻むを繰り返して生まれる空間には多彩な輪郭があると思う。主にリノベーションをイメージしたが、もしはじめから、新築の時から多彩な輪郭を表現できたならば、時間を味方につけたことになる。
何かが軽くもの足りない、薄っぺらい空間に感じる時はリアリティがないのだろう。リアリティにも種類があるが、実生活や暮らしではなくて、空間が今ここに存在しているリアリティであり、建築が存在していなければ何も起こらない渇望感のようなものである。
"No reality"
I think there are various contours in the space created by repeating chopping, peeling, and chopping. I mainly imagined renovation, but if I could express various contours from the beginning when it was newly built, I would have given time to my side.
When something feels light and lacking in a thin space, there may be no reality. There are different types of reality, but it's not real life or living, it's the reality that space exists here now, and it's like a thirst for nothing to happen without architecture.
空間に「重ねる」ことを考えていたら何か腑に落ちた。ずっと抱えていた違和感は、そこにつくろうとしていた空間がひとつの空間だけでできあがっていたからだ。
あまりにも軽薄で内容がないように思えた。全てを充足していながら、なのに何かが足りない感じがずっとしていた。単調で全てがわかりやすいが、そのわかりやすさが安直だった。
"Monotonous and easy"
When I was thinking of "overlapping" in the space, I fell in love with it. The discomfort he had had for a long time was that the space he was trying to create was created by only one space.
She seemed too frivolous and empty. Even though I was satisfied with everything, I always felt that something was missing. It was monotonous and easy to understand, but it was easy to understand.
レイヤーを重ねるようにひとつの空間に幾重にも他の空間の輪郭のようなものを重ねていくことはすぐに思いつくことで、そもそも「レイヤー」という言葉が古臭く感じる。
重ねた部分と重なりがずれた部分が交互に現れて見えるか、ランダムに出現するかすれば、また違った意味で「レイヤー」に価値が出るかもしれず、リノベーションでは入れ子のように構成し、新築ではあらかじめ複数の空間を想定して重ねる。
"Stack"
It's easy to come up with the idea of layering layers in one space, like the contours of another space, and the word "layer" feels old-fashioned in the first place.
If overlapping parts and non-overlapping parts appear to appear alternately, or if they appear randomly, the "layer" may be valuable in a different sense. In renovation, it is configured like a nest, and in new construction. Overlay by assuming multiple spaces in advance.
場所を選ぶようなことを、狭いながら、一歩違えば空間の見え方も違うような、そのくらい密度が濃い空間に仕上げてみたいと考えた。
上下左右の移動で空間が変わる、見え方が変わる。
ひとつの空間に、狭いから、幾重にも重ねて密度の濃さを出そうと考えると、重ねるものが何かが見えてくる。
"Overlay in space"
I wanted to create a space with such a high density that the appearance of the space would be different if one step was different, even though it was small, like choosing a place.
The space changes and the appearance changes by moving up, down, left and right.
Since it is small in one space, if you try to create a high density by stacking multiple layers, you can see what is layered.
目線を縦にズラすことにより、意識の上で距離感をつくり出そうとしたが、さらに目線の高さが変わることにより、空間の見え方も変わるように考えた。
ただ目線の高さを変えただけでは空間の見え方に変化は起こらないので、仕掛けなり、形の工夫が必要であり、見え方を誘導し、さらには見え方の変化がより距離感をつくり出し、狭い空間の中で結界をつくるような作用が起きないかと思案中である。
"Action to create a barrier"
I tried to create a sense of distance consciously by shifting the line of sight vertically, but I thought that the appearance of the space would change as the height of the line of sight changed.
Just changing the height of the line of sight does not change the appearance of the space, so it is necessary to devise a mechanism and shape, guide the appearance, and further change the appearance creates a sense of distance. I'm wondering if there will be an action that creates a barrier in a small space.
狭くて平面的な距離が取れないことは良くも悪くもあるが、人との関係でいうと、より密接になるか、より煩わしくなるか、願わくば距離感を自ら調節したい。
飲食店の話でいえば、隣とは適度な距離感が欲しくもなる。近い密接がいい場合もあるが、ある程度ゆっくり静かに食事をしたければ離れたい。
離れたくても離れられない、広さには限界がある。ならば、目線をタテにズラす。平行な目線が交わるのは同じテーブルにいるもの同士で、隣との距離感は目線が交わらないので少し隔たりができる。この隔たり感をつくり出す行為は距離感を取る行為よりも空間の見え方に変化をもたらす。
"Looking at the vertical"
It is good or bad that you cannot get a narrow and flat distance, but in terms of relationships with people, you want to adjust the sense of distance yourself, whether it will be closer or more troublesome.
Speaking of restaurants, you also want a sense of distance from your neighbors. Sometimes it's good to be close, but if you want to eat slowly and quietly, you want to leave.
There is a limit to the size that you cannot leave even if you want to leave. Then, shift your eyes vertically. The parallel lines of sight intersect with each other at the same table, and the sense of distance from the neighbors does not intersect, so there can be a slight gap. The act of creating this sense of separation brings about a change in the appearance of space rather than the act of taking a sense of distance.
何者かになりたいことと、何者でもないことのギャップに苦しむ人が多いと最近思った。
意外と誰でも何者かになりたいと思うのだろう、FacebookなどのSNSを見ているとよくわかる、何者かになりたいと思う時点で残念なのだが、何者にもなれない。
この瞬間に、手を動かして、誰かの、自分の、隣の人を喜ばせればいいのに、それをしない。それが一番難しいことで、誰も簡単にできない。
"The most difficult thing"
I recently thought that many people suffer from the gap between wanting to be someone and being nothing.
Surprisingly everyone wants to be someone, you can see well by looking at SNS such as Facebook, unfortunately when you want to be someone, but you can not be anyone.
At this moment, you can move your hand to please someone, your own, or your neighbor, but you don't. That's the most difficult thing, and no one can easily do it.
オープンかクローズか、その境目がどこからか、などと思いながら、21時少し前に繁華街にいた。何か食べようととしたが、どこも入れずに、もしかしたらなどと思い覗いてみてもダメそうな雰囲気、花見帰りか人出はそれなりにあったが、帰りの電車はガラガラ、家まで持ち堪えた。
今の特殊な状況と微妙な時間帯がつくり出した、開いているのかいないのか、人がいるのかいないのか、という中途半端さが心地よくなるには、お腹が満たされる以外に何が必要なのだろうか。
"Comfortable halfway"
I was in the downtown area a little before 21:00, wondering if it was open or closed, and where the boundary was. I tried to eat something, but I couldn't put it anywhere, and even if I looked into it, it seemed like it wouldn't work. ..
What is needed other than filling the stomach to make the half-hearted feeling of being open or not, and whether there are people or not, created by the current special situation and delicate time zone?
一見全く繋がりが無いもの同士を繋げてみるときっと面白いことになるだろうと考える。
今朝、現場へ行く前に井の頭公園を通り抜けた。7分咲きの桜が水面近くを這う。水平な視界の中には桜と水面と対岸の人の動きが重なり、虚実入り乱れる。
もし、ここが公園では無かったらと想像してみる。公園とは真逆の、公園が癒され佇む場所だとしたら、身体を動かしストレスフルで、水面がある所は、と考えて、労働する場所だとすぐに浮かんだが、労働は消費とセットになれば苦楽は無いと、アレントの『人間の条件』の勝手な解釈から思い込んでいるので、案外そういう場所は無いものだと思った。
"The opposite place"
I think it will be interesting to connect things that seem to have no connection at all.
I passed through Inokashira Park this morning before going to the scene. The cherry blossoms that bloom for 7 minutes crawl near the surface of the water. In the horizontal field of view, the movements of the cherry blossoms, the surface of the water, and the people on the opposite bank overlap, and the truth is mixed up.
Imagine if this wasn't in the park. If the park is the opposite of the park, where it is healed and standing, I immediately thought that it was a place to work, thinking that it was a place where I could move my body, be stressful, and have a water surface, but labor was a set with consumption. I thought that there would be no pain if it happened, because I thought from the arbitrary interpretation of Arendt's "The Human Condition", so I thought that there was no such place unexpectedly.
建築をモノとして扱わない場合はどうなるだろうかと考えてみた。建築はモノであることが大前提だから、モノでない建築は空間という領域のような囲まれた状況があるだけの認識になるのだろうか。
モノでないならば、モノの優劣は存在しない。モノの良し悪しが関係なくなる。もちろん、モノの良さで判断するようなこと、例えば、仕上げに大理石を使うなど、はどうでもいいことになる。
"If not a thing"
I wondered what would happen if architecture was not treated as a thing. Since architecture is based on the premise that it is a thing, is it just a recognition that architecture that is not a thing has an enclosed situation like the area of space?
If it is not a thing, there is no superiority or inferiority of the thing. It doesn't matter whether things are good or bad. Of course, it doesn't matter what you judge by the goodness of things, such as using marble for finishing.
人の姿勢が変われば、目線の高さが変わり、それだけで空間の見え方が変わる。座って見る空間と立って見る空間は同じ空間でも違う印象になるだろう。
人の姿勢は空間のスケールを表す。人は天井が低いと感じたならば自然と屈むように、空間のスケールを感じ取り姿勢で表現する。
要するに、空間の見え方は人の姿勢と空間のスケールでコントロールできることになる。
"Control of appearance"
When a person's posture changes, the height of the line of sight changes, and that alone changes the way the space looks. The space where you sit and see and the space where you stand will give different impressions even in the same space.
The posture of a person represents the scale of space. If a person feels that the ceiling is low, he naturally bends down, expressing the scale of the space in a perceptible posture.
In short, the appearance of space can be controlled by the posture of the person and the scale of the space.
不確実なことの連続が重なり合い、実体が炙り出されてわかるようなことを考えている。
気分や感情といった曖昧で不確実なことが居場所を選択する時の基準になり、居場所によって建築の内部空間の見え方が変われば、まるでCT画像の連続で身体を表現するように、見え方の連続を辿れば建築という実体が現れる。
すぐにわからないが、自分の気分や感情が建築像を表すことにつながるとなれば、モノに左右されない建築ができる。
"Architecture that does not depend on things"
I am thinking that a series of uncertainties will overlap and the substance will be exposed and understood.
Ambiguous and uncertainties such as moods and emotions are the criteria for choosing a location, and if the appearance of the interior space of an architecture changes depending on the location, it looks as if the body is expressed by a series of CT images. If you follow the continuation, the substance of architecture will appear.
I don't know right away, but if my mood and emotions lead to an architectural image, I can build an architecture that is not influenced by things.
気分や感情を建築に持ち込むと、曖昧で掴みどころが無く、不確実性が増し、確かなものが無くなっていく。
気分や感情自体が実体として目に見えないから曖昧だと考えるのだろう。ただ、不確実性が増すのは悪いことではない。予測可能な範囲の中で建築はつくられるもので、全てをコントロールし、全てがはじめの想定通りになるように進み、そして想定通りに完成し運用されるのを良しとするが、そこにコントロールができないものが入ると想定を超える多様性が生まれる。
真の多様性とははじめに想定できないことだろう。はじめから想定してつくられた多様性は多様にならない。
"Uncertainty that creates diversity"
Bringing moods and emotions into architecture is vague and elusive, increasing uncertainty and losing certainty.
You might think that the mood and emotions themselves are ambiguous because they are invisible as an entity. However, increasing uncertainty is not a bad thing. Architecture is built within a predictable range, and it is good to control everything, proceed so that everything is as expected at the beginning, and complete and operate as expected, but there is control there. When something that cannot be done is included, diversity beyond expectations is created.
True diversity cannot be imagined at first. Diversity created from the beginning does not become diverse.
死角があり、いる場所によって見え方が違い、いる場所は気分によって選ぶ。建築や空間の成り立ちの根源の部分が人の気分や感情で決まるのであれば、建築をモノの世界から抜け出たところで考えられると思った。
建築はモノだから、モノとしての建築は避けられないが、建築を考察したり、考えたり、デザインをする時にはモノから離れたところでできたならば、モノとしての建築の違った側面、つまり、モノでない建築を表現できる。
"Non-thing architecture"
There is a blind spot, the appearance differs depending on where you are, and you choose where you are depending on your mood. If the root of the formation of architecture and space is determined by the mood and emotions of people, I thought that it would be possible to think of architecture as a place out of the world of things.
Since architecture is a thing, architecture as a thing is inevitable, but when considering, thinking, and designing architecture, if it can be done away from things, another aspect of architecture as a thing, that is, things Can express architecture that is not.
オープンな空間の中に所々、死角になるような場所をつくろうと考えている。全てを見せるためにオープンにしているのだが、少し、ほんの少しだけ見えない所があることによって、よりオープンさが際立つと考えている。
ほの少しの死角があるのも必要かもしれないと思ったのは、段ボールの山に囲まれたから。30年分の資料と事務所で格闘している時、ふと辺りを見回したら、いつもと違う空間に見え、段ボールの素材感が異質だけれども、かえって天井の高さや部屋の広さを感じられた。
"Create the necessary blind spot"
I'm thinking of creating a blind spot in an open space. I'm opening it to show everything, but I think it's more open because there are a few things that I can't see.
I thought it might be necessary to have a few blind spots because I was surrounded by piles of cardboard. When I was struggling with materials for 30 years in the office, when I looked around, it looked like a different space than usual, and although the texture of the cardboard was different, I could feel the height of the ceiling and the size of the room. ..
モノだらけは断捨離とは真逆で捨てられずに貯めるだけ貯めて整理もできていない状況で何かと弊害があるように思うが、先人が何を大事にしていたかがよくわかる。
捨てられないとはいえ、その人にとって不要なモノは捨ててはいるはずだから、残っているモノはその人なりに偏る。
古い地図と古い名簿がたくさん残されていた。地図好きは知っていたが、伊能忠敬に興味を持っていたから、今は用をなさない名簿にはいろいろな繋がりを感じる。
断捨離をするとしたら、真っ先に捨てられるモノばかりである。ただ、捨てて捨てて最小限の暮らしと、偏った不要なモノに囲まれた暮らしと、どちらが、いやどちらかを選択する話ではないと思った。
"Throw away, don't throw away"
It's the opposite of decluttering, and it seems that there is something wrong with the situation where you can't just store and organize things without throwing them away, but you can see what the ancestors valued.
Although it cannot be thrown away, things that are unnecessary for that person should have been thrown away, so the remaining things are biased toward that person.
A lot of old maps and old rosters were left behind. I knew that I liked maps, but I was interested in Ino Tadataka, so I feel various connections to the now useless list.
If you want to cut it off, it's all the things that are thrown away first. However, I thought that it was not a matter of choosing between a minimal life that was thrown away and thrown away, and a life that was surrounded by unbalanced and unnecessary things.
時は様々なものを蓄積させる。記憶としての思い出の蓄積だけでなく、もの自体も勝手に蓄積する。
30年使用した事務所を退去し移転することになった。普段は見えない所に過去の仕事の痕跡がたくさんあり、自分も含めて誰も整理をしてこなかったので、ここ2、3ヶ月は30年分の仕事の痕跡を取捨選択し、何を残すのか、何を捨てるのかがずっと頭の片隅にあった。
結局、過去の仕事は自分が生み出した分身のようなものだと思い、すでに自分の手からは離れているが、生み出すまでの過程が記された線一本までが愛おしく、ほとんど捨てることができなかった。自分が生きている間は伴にするものだと覚悟してパッケージした。
今までものに溢れていた事務所が空になった。事務所の空間自体には特に思い入れはなく、郷愁に駆られることはないが、ものが溢れていた状態から空になった状態への変化が全てを表しているような気がしてスマホで写真を撮った。
自分好みに制作した建具越しに2部屋を撮影した。この事務所の空間に自分が手を加えたのはこの建具だけであり、この建具で自分が実現したい見え方をつくり出した。
"When moving out"
Time accumulates various things. Not only the accumulation of memories as memories, but also the things themselves are accumulated without permission.
It was decided to move out of the office that had been used for 30 years. There are many traces of past work in places that are not normally visible, and no one, including myself, has organized them, so for the past few months, I have selected the traces of work for 30 years and left what to leave. I was always in the corner of my head about what to throw away.
After all, I think his past work is like an alter ego that he created, and although he is already out of his hands, he loves even one line that describes the process of creating it, and almost throws it away. I couldn't. She was prepared to accompany her for the rest of her life and packaged it.
The office, which was full of things, has been emptied. I don't have any particular feelings about the office space itself, and I'm not driven by nostalgia, but I feel that the change from an overflowing state to an empty state represents everything on my smartphone. I took a picture.
She photographed two rooms through the fittings she made to her liking. This fitting was the only one I modified in the space of this office, and I created the look I wanted to achieve with this fitting.
狭い空間に興味が湧く。広々とした空間の良さもあり、広いから様々なことが考えられる可能性の面白さもあるが、狭い空間の重なり合う様に面白さを感じる。
何も作用しない、何も起こさない、ただそこに必要だから存在している空間よりは、空間から何かを感じたり、空間が何かを起こすきっかけになる方が面白く、それは勿論広い空間でも可能だが、狭い空間でそれを考えているとその狭さ故にひとつに空間に幾重にも作用やきっかけがある状態をつくらざるを得ず、それがかえって濃密な空間を生み出すことにつながる。
"Because it is narrow"
I am interested in a small space. There is also the goodness of a spacious space, and there is also the fun of being able to think of various things because it is wide, but I feel the fun of overlapping narrow spaces.
It's more interesting to feel something from the space or to cause something to happen, rather than the space that exists because nothing works, nothing happens, just because it is necessary there, and of course it is possible even in a large space. However, when thinking about it in a narrow space, there is no choice but to create a state in which there are multiple actions and triggers in the space due to the narrow space, which in turn leads to the creation of a dense space.
隠して見せたくないのと、オープンにして全てを見せるのと、どちらが良いのだろうという話になった。
結論を求めてというより、どちらがより自分に合うかを考えて、中間の見せ方を探っているようだった。厨房の話である。オープンキッチンにするかどうかについて、どのように見られたいのか、そして、そこで何をしたいのかを深く考えるキッカケになった。
見る見られることにはたくさんの情報が含まれるので、同時に様々なことを考えざるを得ない状況に自然となるのだろう。
"What you see and see"
I was wondering which is better, I don't want to hide it or show it all open.
Rather than seeking a conclusion, he seemed to be looking for an intermediate way of showing, thinking about which one suits him better. It's a story about the kitchen. It was a good idea to think deeply about what you want to see and what you want to do there, whether or not to make it an open kitchen.
What you see and see contains a lot of information, so it will be natural for you to think about various things at the same time.
窓を通して外と繋がろうとすると余計に窓が壁のように感じる。そもそも壁があるから外と繋がろうと考える訳で、繋がるために窓を設けたら、かえって壁があることを強調してしまう。
外と繋がりたいと考えたらば、窓は設けない方が良く、そもそも壁を無くすことが外と繋がるための最善の方法だと考える
"To connect with the outside"
When I try to connect to the outside through the window, the window feels more like a wall. In the first place, there is a wall, so I'm thinking of connecting to the outside, so if I set up a window to connect, I would rather emphasize that there is a wall.
If you want to connect with the outside, it is better not to install windows, and I think that eliminating the wall is the best way to connect with the outside.
周辺環境の風景を映し出すことで骨組みが消失しないかと考えている。それを簡単に表現するならば、鏡やステンレスの鏡面を使えば良いが、ちょっと古臭く感じる。
変わりゆく風景がそのまま刻まれ、風景と同調するような外観がつくることができれば、変わりゆくものとして建築の存在感や構築感を無くすことができる。
だだ、それにはガラスという素材では不十分であり、もっと反射の強さが必要で鏡にたどりついた。
"Disappeared in the mirror"
I am thinking that the skeleton will disappear by projecting the scenery of the surrounding environment. To express it simply, you can use a mirror or a stainless steel mirror surface, but it feels a bit old-fashioned.
If the changing landscape is carved as it is and an appearance that is in harmony with the landscape can be created, the presence and construction of the architecture can be eliminated as a changing landscape.
However, the material of glass was not enough for that, and I needed more reflection strength and arrived at the mirror.
虚実が入り交じるような見え方を考えている。ちょっと古くさい感じもするが、実の中に虚が散りばめられているような、その虚が変化して実をより実にするようなイメージが湧き、そのような見え方をどうやったら実際につくれるかを考えている。
周辺環境が変化していく中で、今現在見ている風景は実だが、同時に変化が決まった時点で今見ているのは虚になる。
虚と実に境が無くなると、あとはどちらに焦点を当てるか、選択するかになる。そうなると、虚実が建築化できると考えた。
"False architecture"
I'm thinking of a way of looking like a mixture of truth and truth. It may seem a little old-fashioned, but the image of the emptiness being scattered in the fruit, which changes and makes the fruit more fruitful, is created, and how can we actually create such an appearance? I'm thinking.
As the surrounding environment changes, the scenery we are seeing now is real, but at the same time, when the changes are decided, what we are seeing now becomes imaginary.
When the boundary between the imaginary and the real thing disappears, the rest is to choose which one to focus on. In that case, I thought that the truth could be built.
変わらない部分があるから変わることがわかる。これから風景が変化していく場所に建築を挿入する場合に見え方が変わらない部分と見え方が変わる部分をひとつの建築の中に同時に存在するようにつくる。
ずっと見え方が変わらない屋根がある。しかし、その屋根を支える部分の見え方は周りの環境に依存する、そのような建築を構想中である。
"No change"
You can see that it changes because there are parts that do not change. When inserting an architecture into a place where the landscape will change from now on, we will create a part that does not change the appearance and a part that changes the appearance at the same time in one architecture.
There is a roof that looks the same all the time. However, the appearance of the part that supports the roof depends on the surrounding environment, and we are planning such an architecture.
風景の変化を刻むことができないかと考えた。現在と2年後、5年後、10年後と周辺環境が変わるだろう。それに対して普通は変化に耐えられるような強度を持った建築を考えるだろうが、変化によって変わりながらも立ち続けるような建築はできないものだろうかと考えた。
実際には建築は動かないから、建築そのものに風景の変化を刻むような仕掛けを考えることにした。
"Architecture that carves change"
I wondered if it would be possible to carve changes in the landscape. The surrounding environment will change now, two years later, five years later, and ten years later. On the other hand, I would normally think of an architecture that is strong enough to withstand changes, but I wondered if it would be possible to create an architecture that would continue to stand while changing due to changes.
In reality, architecture doesn't move, so I decided to think of a mechanism that would engrave changes in the landscape in the architecture itself.
まわりに存在するものをまじまじと見てみる。別に取り止めもない風景である。見慣れているからだろうか、子供の頃から見ているので、なぜか立ち退きによる更地の連続に違和感が無く、その程度では印象に変化が起きない。
更地の連続は結構な違和感をつくり出してくれるはずなのに、何故か前からずっと更地で何も無かったと思える。
たぶん、鉄道の高架ができ、空が塞がれたら違和感を覚えるだろう。
"Scenery discomfort"
Take a closer look at what's around you. It is an unstoppable landscape. Perhaps because I'm used to it, I've been watching it since I was a kid, so for some reason there is no sense of discomfort in the continuation of vacant lots due to eviction, and that degree does not change the impression.
The series of vacant lots should create a sense of incongruity, but for some reason it seems that there has been nothing in the vacant lots for some reason.
Perhaps it will feel strange if the railroad is elevated and the sky is blocked.
「どのように見せたいか」と考える時、形や色が最初に思い浮かぶだろう。その時は理由よりも、言葉よりも、イメージがはじめに出てくる。ただ、その時のイメージはどこかで見たようなものである。それは多分、「どのように見せたいか」と考える時、自分が何かを見ている瞬間を思い浮かべるからだろう。
だから、「どのように見せたいか」と考えると既視感のあるものばかりになってしまう。
"What I saw somewhere"
When you think about "how you want it to look," the shapes and colors come to mind first. At that time, the image comes out first, rather than the reason, rather than the words. However, the image at that time is like what I saw somewhere. Perhaps it's because when you think about what you want to look like, you think of the moment you're looking at something.
Therefore, when you think about "how you want to look", all of them have a sense of déjà vu.
敷地境界線を越えて影響を与える建築はどのようなものだろうかと考えてみた。ハッとする建築に出会う。歩いていて、車を運転していて、電車に乗っていて、見え方が何か違う建築に出会う。その時点で影響を受けている。
どのように見えるかだけかもしれない。見ることは離れていても、遠くからでもできる。では、どのように見えるかだから、つくり手側に回れば「どのように見せたいか」になるのか。
"Beyond the border"
I wondered what kind of architecture would affect beyond the boundary of the site. Encounter a stunning architecture. I'm walking, driving a car, riding a train, and encountering something different in appearance. At that point it is affected.
It may just look like it. You can see it from a distance or from a distance. Then, because it looks like, if you turn to the creator side, it will be "how you want to look".
ずっとそこにあったような建築にできないかと考えてみる。鉄道の高架化により景色が変わるけれど、その建築だけは変わらずに昔からそこにあったような体にできないものか。
単に、古めかしく、歴史的建造物のような見え方になれば良い訳ではなくて、それならばむしろ簡単で、何とかランドなどのハリボテ建築やエイジング処理した素材を使えばいいだけであり、昔からそこにあったような体になるには、見え方に違和感が無いのであり、違和感を無くすには周辺環境のコンテクストの変化と呼応するか、コンテクストそのものを形成する建築になるかである。
"No discomfort"
I wonder if it would be possible to create an architecture that has been there for a long time. The scenery changes due to the elevated railway, but isn't it possible to make the body look like it has been there for a long time without changing the architecture?
It's not just about looking like an old-fashioned, historic building, it's rather easy, and you can manage to use haribote architecture such as lands or aged materials, which has been around for a long time. In order to have a body that looks like it is, there is no sense of discomfort in the appearance, and in order to eliminate the sense of discomfort, it is necessary to respond to changes in the context of the surrounding environment, or to create an architecture that forms the context itself.
敷地が高い塀で囲まれ、周辺環境から遮断される状況を想定して、自閉する建築を考えていた。自閉するとは自らの敷地環境や内部空間をコンテクストとして考え、それに対して計画することである。
ところが一転、遮断するものが何も無い、ずっと先まで見通せる状況になった。想定とは全く真逆の状況である。真逆ということは自閉の真逆にすれば良いのか。自閉する建築はそのようにせざるを得ない状況だったからだが、そこに閉じながらも周辺環境との関係性を上手く調整する術のようなものの可能性を感じていた。
"Relationship between autism and surroundings"
Assuming that the site is surrounded by a high wall and is cut off from the surrounding environment, I was thinking of a self-closing building. Autism is to think of your own site environment and interior space as a context and plan for it.
However, there was nothing to block, and I could see for a long time. The situation is exactly the opposite of what was expected. Should the exact opposite be the exact opposite of autism? I had no choice but to do so in a self-closing architecture, but I felt the possibility of something like a way to adjust the relationship with the surrounding environment while closing it.
周辺環境が変化することに対して、最終的にどのようになるかがわかっていれば、その最終的な状態に合わせて計画するのが常套手段だが、それではある一点の時に焦点を合わせた建築になり、現在を含み未来までの時の幅を持たない建築になってしまう。
周辺環境が変化する前の計画を元にして変化した後の計画を考えれば、その建築には時の流れが蓄積されて、それはまさに周辺環境のコンテクストに呼応するだろう。
"Accumulating the flow of time"
If you know what the final situation will be in response to changes in the surrounding environment, it is a common practice to plan for the final state, but then it is a building that focuses on one point. It becomes an architecture that does not have the width of time to the future including the present.
Considering the plan after the change based on the plan before the change of the surrounding environment, the passage of time is accumulated in the architecture, and it will correspond exactly to the context of the surrounding environment.
不完全な「美」もあると思う。美を感じる時、人は自分の完全性の基準に照らし合わせて、完全だと感じる時に美を感じる。それだけ美には崇高さを求め、そもそも「美」は完全なものだけに宿るものと思い込んでいる。
だが、不完全なものから完全にいたる途中の「美」、あるいは、完全なものから不完全なものになった時の「美」も存在するだろう。どちらも完全なものに宿る美とは違うかもしれないが、何かが足りない、何かが抜け落ちているものを人は想像力を働かせて補い見て「美」を感じることができるはずである。
"Imperfect beauty"
I think there is also imperfect "beauty". When one feels beauty, one feels beauty when one feels perfect, according to one's standards of perfection. It demands sublime from beauty, and believes that "beauty" resides only in perfection.
However, there will be "beauty" on the way from imperfect to complete, or "beauty" when it goes from perfect to imperfect. Both may be different from the beauty of perfection, but one should be able to use his imagination to supplement what is missing or missing and feel "beauty". ..
閉ざされた環境の中の閉ざされた空間で成立する建築を考える時の手掛かりは、その空間で必要とされている「機能」にするのが一番簡単である。機能にはその空間での要望や人の動きなどが現れるので、機能をプランに置き換えれば、とりあえず建築になる。
とても分かりやすい建築になる。「分かりやすい」は褒め言葉である。分かりにくい建築は人を思考停止にする。人が使うための建築ならば分かりやすい方が良い。
ただ「分かりやすい」だけでは駄目だとは薄々誰でも気がついているはずである。人が建築に求めることで「分かりやすい」は一番重要ではないだろう。
一言でいうならば「美」である。美に惹かれて欲しいと思う。美は完全性を伴う。これが厄介で、完全性を否定した不完全性を纏う建築をつくりたくなる。
"Easy to understand and incomplete"
The easiest clue when considering an architecture that can be established in a closed space in a closed environment is to make it the "function" required in that space. Requests in the space and movements of people appear in the function, so if you replace the function with a plan, it will be an architecture for the time being.
The architecture will be very easy to understand. "Easy to understand" is a compliment. Incomprehensible architecture makes people stop thinking. If it is an architecture for people to use, it should be easy to understand.
Everyone should be aware that "easy to understand" is not enough. "Easy to understand" is probably not the most important thing that people want from architecture.
In a word, it is "beauty". I want you to be attracted to beauty. Beauty comes with perfection. This is awkward and makes me want to create an architecture with imperfections that deny perfection.
窓は外の世界と内の世界をつなぐ役目だとすると、窓の大きさが変化すれば外と内のつながり方も変化する。壁面いっぱいの窓ならば、外と内はシームレスにつながり、窓の大きさが極端に小さければ、外と内のつながりはほとんど無くなる。窓の大きさの度合いに応じて外と内のつながり具合を調整できる。逆に言えば、外と内のつながり具合で窓の大きさが決まる。
窓を単なる開口部だとすれば、外の世界に向けられるだけでなく、内の世界同士のつながりの形成にも用いることができる。開口部が大きくなり壁面いっぱいになれば、壁が無い状態であり、開口部が極端に小さくなれば、単なる小窓になり、装飾か空気を通すためか、大きさにより開口部の意味合いも変わる。
窓や開口部のつながりや意味合いは、それ自体が建築の一部や物として起こす現象だが、その現象を体現する人がいてさらにつながりや意味合いが深まったり、拡散されたりする場合がとても面白いと思う。
"Connection between windows and people"
Assuming that the window serves to connect the outside world and the inside world, the way the outside and the inside are connected changes as the size of the window changes. If the window is full of walls, the outside and the inside are seamlessly connected, and if the size of the window is extremely small, the connection between the outside and the inside is almost eliminated. The connection between the outside and the inside can be adjusted according to the size of the window. Conversely, the size of the window is determined by the connection between the outside and the inside.
If a window is just an opening, it can be used not only to point to the outside world, but also to form a connection between the inside worlds. If the opening becomes large and the wall is full, there is no wall, and if the opening becomes extremely small, it becomes a mere small window, and the meaning of the opening changes depending on the size, whether it is decoration or air passage. ..
The connection and meaning of windows and openings is a phenomenon that itself occurs as a part of architecture or an object, but I think it is very interesting if there are people who embody that phenomenon and the connection and meaning are deepened or diffused. ..
目線の高さによって距離感は変わる。同じ物を見ていても高低が変われば距離が変わる。スケール感は距離感に依存することが多いから、距離をデザイン要素に取り込むことでスケール感を扱うことができる。
人の姿勢が変化することで目線の高さが変わり、対象物までの距離感も変わる。人の姿勢をデザイン要素に取り入れることで距離をデザインでき、スケール感を扱える。スケール感は人が持つ感覚で、その直接的な源はデザインされた空間だが、そのデザインが人の姿勢から派生するならば空間の親和性が高まり、人にとって心地良い空間になるだろう。
"Space with high affinity"
The sense of distance changes depending on the height of the line of sight. Even if you are looking at the same thing, the distance will change if the height changes. Since the sense of scale often depends on the sense of distance, it is possible to handle the sense of scale by incorporating the distance into the design element.
As the posture of a person changes, the height of the line of sight changes, and the sense of distance to the object also changes. By incorporating the human posture into the design elements, the distance can be designed and a sense of scale can be handled. The sense of scale is a feeling that a person has, and its direct source is the designed space, but if the design is derived from the attitude of the person, the affinity of the space will increase and it will be a comfortable space for the person.
建築は動かないから、人が動く時々で見え方を変化させて、空間に動きを与えたいと常々考えている。
建築自体は物だから、物としての建築、例えば、壁の仕上げをどうするかなど、建築の素材に焦点を当てて綺麗に見せることも面白いけれど、物だから、その物を取り巻く現象に興味があり、そこに人が絡み、人がどのように感じるのかの総和が建築だと思う。
"Because it's a thing"
Since architecture does not move, I always want to give movement to space by changing the way people look when they move.
Since architecture itself is a thing, it is interesting to focus on the material of the building and make it look beautiful, such as how to finish the wall, but because it is a thing, I am interested in the phenomenon surrounding the thing. I think architecture is the sum of how people get involved and how people feel.
住宅ならば特定の人に向けた設えをするが、店舗ならば不特定の人に向けて設えをすることを考え、日常的に慣れたアクティビティの繰り返しを考慮しないで、一期一会で空間の見え方が変わるようなデザインを考える。
空間に留まることを考えると、アクティビティの到着点が人の姿勢になる。最終的に立つ、腰掛ける、座る、寝るなどの姿勢で空間と対峙し、その時々で空間の見え方が違えば、より空間体験が一時的なものになり、新鮮さが失われず、毎回違うものになる。
"Freshness of space"
If it is a house, it will be set up for a specific person, but if it is a store, it will be set up for an unspecified person, and the appearance of the space will be seen once in a while without considering the repetition of activities that are accustomed to daily life. Think of a design that will change.
Considering staying in space, the arrival point of the activity becomes the posture of the person. In the end, if you confront the space in a posture such as standing, sitting, sitting, sleeping, etc., and the appearance of the space is different from time to time, the space experience will be more temporary, freshness will not be lost, and it will be different every time. become.
敷地形状が細長く、短手の長さは車1台分しかない。単純に敷地形状なりに計画すると、奥行きの長い建築になる。出入口を短手につくれば、内部空間は奥行き方向に長く、幾重にも重なる何かがつくれる。
奥行き方向に長ければ、移動距離も長くなり、人のアクティビティがデザイン要素になる。
人の姿勢の違いで空間を分節してみようと考えた。姿勢の違いはスケール感の違い、空間の見え方の違いを生み出せる。
"Something that overlaps"
The shape of the site is long and narrow, and the short length is only one car. If you simply plan the site shape, it will be a long-depth building. If you make the doorway short, the internal space is long in the depth direction, and you can create something that overlaps in layers.
The longer it is in the depth direction, the longer the distance traveled, and human activity becomes a design element.
I thought about segmenting the space according to the difference in human posture. Differences in posture can create differences in the sense of scale and the appearance of space.
スケール感は人の姿勢を誘発すると考えている。実際に、頭は当たらないが天井が低い場所に入り込むと人は無意識に身をかがめる。スケール感は人が感じるものだから、無意識に自分の身を守るために動作と連動するのだろう。
だから、スケール感を操作することにより、人の動作や姿勢をコントロールできる。
スケール感は見え方による。どのように空間が見えるかを感じ取ることによって生じる。そうすると、人の動作や姿勢が変化することで空間の見え方が変われば、同じ空間でもスケール感が変わることになる。
意図的にスケール感を操作することは今までもよくあった。しかし、同じ空間でスケール感がいくつも重なっていて、任意の選択ができるような状態は見たことがない。人の動作や姿勢をスケール感以外でコントロールできれば、それが可能だろう。
"A state where the sense of scale overlaps"
I think that the sense of scale induces a person's posture. In fact, people unknowingly bend down when they enter a place where the ceiling does not hit but the ceiling is low. Since the sense of scale is something that people feel, it may be linked to movements to unknowingly protect themselves.
Therefore, by manipulating the sense of scale, the movement and posture of a person can be controlled.
The feeling of scale depends on how you see it. It is caused by feeling how the space looks. Then, if the appearance of the space changes due to changes in the movements and postures of people, the sense of scale will change even in the same space.
It has always been common to intentionally manipulate the sense of scale. However, I have never seen a state in which a number of scales overlap in the same space and any choice can be made. It would be possible if we could control the movements and postures of people other than the sense of scale.
窓を開口部という。窓というとそこから人が出入りをする訳ではなくて、内部から外部を眺めるためにあるもので、開口部は壁という塞がれたものに対して開いている部分という意味であり、人が出入りすることもあり、そういう意味でいうと開口部は壁に開いている部分の総称であり、窓の上位概念である。たがら、開口部が先に存在する訳ではなくて、まず壁があり、その壁をくり抜くことで開口部をつくる。
壁には開口部の他に、境界や音熱環境や構造、設備などの要素、さらに人と人、人と空間をつなぐものとしての可能性があり、初期のスケッチでは全ての要素、全ての可能性を含みながら単線で壁を描くことが多い。
この初期のスケッチの段階で壁を単線で描くことを止めて、線に厚みを持たせてみようと考えた。壁を単線で描くことは壁が持つ全ての要素、全ての可能性に目を向けないことであり、厚みを持たせることにより空間とのつながりをより意識できると考えた。
"Make the wall thicker"
A window is called an opening. A window does not mean that people come and go from there, but it is for looking at the outside from the inside, and the opening means the part that is open to the closed thing called the wall, and people In that sense, an opening is a general term for a part that is open to a wall, and is a superordinate concept of a window. However, the opening does not exist first, but there is a wall first, and the opening is created by hollowing out the wall.
In addition to openings, walls have the potential to connect boundaries, sound-heat environments, structures, equipment, and even people-to-people, people-to-spaces, and in early sketches all elements, all. Often draws a wall with a single line, including possibilities.
At this early sketching stage, I decided to stop drawing the wall with a single line and try to make the line thicker. Drawing a wall with a single line means not paying attention to all the elements and possibilities of the wall, and I thought that by making it thicker, I could be more aware of the connection with the space.
敷地境界線の中に留まって建築を考えることが有効になる前提を考える場合、外からと内からの両面の可能性がある。外からは環境との遮断、周辺環境との関係性が全く途切れてしまうことで、内からは建築内部の空間が圧倒的に優位になることで、外と内の両面が同時に存在していなくても良く、どちらか片方だけで良いだろう。
周辺環境との遮断は視覚的に見えない状況がつくられただけでも起きる。また、建築内部の空間が圧倒的に優位になる状況は外皮を必要としない状況であり、内部空間だけが存在すれば建築が成り立つ状況だろう。
視覚的に見えない状況は周辺環境の要因にも左右されるので自らだけで完結してつくり出すことはできないが、外皮を必要としない状況は自ら完結してつくり出すことができるので前提とするにはより向いている。
"Premise that does not require exodermis"
When considering the premise that it is effective to stay within the boundary of the site and think about architecture, there is a possibility of both from the outside and from the inside. The space inside the building becomes overwhelmingly superior from the outside because it is cut off from the environment and the relationship with the surrounding environment is completely cut off, so both the outside and the inside do not exist at the same time. You can do it, and only one of them will do.
Isolation from the surrounding environment occurs even if a situation that is not visually visible is created. In addition, the situation where the space inside the building is overwhelmingly superior is the situation where the outer skin is not required, and the situation where the building can be established if only the interior space exists.
Since the situation that cannot be seen visually depends on the factors of the surrounding environment, it cannot be created by itself, but the situation that does not require the exodermis can be created by itself, so it is a prerequisite. It is more suitable.
敷地境界線を超えて街につなげようという試みは、建築が敷地境界線からはみ出ることができないから生じる衝動で、と同時に周辺環境のコンテクストからの影響も考えざるを得ない産物である。
それに対して敷地境界線の中だけで建築を考えることは真逆の試みであり、建築のスケールの大きさを考えると周辺環境に与える影響は大きいので、敷地境界線の中だけで建築を考えることには消極的になる。
ただ、そこで敷地境界線の中に留まって建築を考えることが有効になる前提が存在するならば、とても興味深いことになる。
"Stay in the border"
Attempts to connect to the city beyond the boundary of the site are impulsive because the architecture cannot extend beyond the boundary of the site, and at the same time, the influence of the context of the surrounding environment must be considered.
On the other hand, thinking about architecture only within the boundary of the site is the opposite attempt, and considering the scale of the architecture, it has a large impact on the surrounding environment, so consider architecture only within the boundary of the site. Be reluctant to do that.
However, it would be very interesting if there was a premise that it would be effective to stay within the boundary of the site and think about architecture.
狭小の敷地が高さ3mの塀で囲まれていたら、その敷地に立った時にどのように感じるだろうか。見えるのは塀と空だけだろう。外界から全く孤立して、その場所だけが唯一の手掛かり、周辺環境が存在しない。
ならば、自らの場所をコンテクストとして設計をするしかない。コンテクストを扱うが周辺環境のコンテクストは扱わない。
実際にはなかなか高さ3mの塀で囲まれることはないだろうが、視界が遮られるだけでコンテクストの扱いが変わる可能性があることが面白いと思った。
"The treatment of context changes"
If a small site is surrounded by a 3m high wall, how would you feel when you stood on that site? You can only see the fence and the sky. Totally isolated from the outside world, that place is the only clue, and there is no surrounding environment.
Then, there is no choice but to design your own place as a context. It deals with the context, but not the context of the surrounding environment.
In reality, it wouldn't be surrounded by a wall with a height of 3m, but I found it interesting that the treatment of the context could change just by blocking the view.
周辺環境のコンテクストから切り離して建築は成り立つのだろうか、普通に考えれば成り立たないと考える。それでも成り立つと考えたならば、何がどうなるのだろうか。
ひとつ建築は周辺環境から自律して成り立つことができるだろうかと考えてみる。答えは「できる」である。別に周りの環境に遠慮する必要はない、好き勝手にやればいい。その昔、随分前のテレビの映像が頭に浮かんだ、吉祥寺での赤白の外観の家の映像だ。好き勝手に建てたら皆んなが迷惑すると盛んに放映していた。確かにその家は周りから浮いていた。ただ、良し悪しは別として自ら定めたルールに従って建っているという意味で自律していた。どうしても自律というと悪いイメージを引きずってしまい、多少の違和感を覚えるのは私だけだろうか。本来、自律とは自ら定めたルールに従って行動することだから、そのルールしだいで良くも悪くもなる。
だから、良いルールで周辺環境から自律をすれば、周辺環境のコンテクストから切り離して建築は成り立つことができ、尚かつ、違和感もないはずである。
"Separate from the context"
I wonder if architecture can be established by separating it from the context of the surrounding environment. What would happen if we thought it would still hold?
I wonder if one architecture can be built autonomously from the surrounding environment. The answer is "can". You don't have to hesitate about the surrounding environment, just do whatever you want. A long time ago, a video of a house with a red-white appearance at Kichijoji came to my mind from a TV image from a long time ago. If you build it as you like, it will be broadcast actively if everyone is inconvenienced. Certainly the house was floating around. However, regardless of whether it was good or bad, it was autonomous in the sense that it was built according to the rules it had set. Is it only me who feels a little uncomfortable because it drags a bad image when it comes to autonomy? Originally, autonomy is to act according to the rules that you set yourself, so depending on the rules, it can be good or bad.
Therefore, if you are autonomous from the surrounding environment according to good rules, you should be able to establish the architecture separately from the context of the surrounding environment, and you should not feel any discomfort.
コンテクストとどのように対峙するかを考えざるを得ない、この風景を見たらそう考えてしまう。延々と続く更地、立ち退きによってできたスペース、必ず変わることが決まっている風景、そこに置く建築、周辺環境のコンテクストを無視しては何も考えられない。
だから、この状況でコンテクストを無視しても成り立つ建築は有り得るのだろうかと考えてみる。たぶん、その答えはそう簡単には見つからないかもしれないが、様々な可能性は考えてみる。
単純に周辺環境のコンテクストを無視するならば、自らをコンテクストにして内部空間を再構築する方法はあり、それはリノベーションで使う手法である。一旦周辺環境のコンテクストより構築し、タイムラグ無く次の段階でその構築されたものをコンテクストとして読み取り、その上で内部空間を再構築する。こうすると結果的にでき上がる建築は当初の周辺環境のコンテクストとは関係がない様に見える。
"Rebuilding yourself in the context"
I have to think about how to confront the context, and when I see this landscape, I think so. I can't think of anything if I ignore the endless vacant lots, the space created by evictions, the landscape that is sure to change, the architecture that is placed there, and the context of the surrounding environment.
Therefore, I wonder if there is an architecture that can be established even if the context is ignored in this situation. Perhaps the answer may not be so easy to find, but consider the various possibilities.
If you simply ignore the context of the surrounding environment, there is a way to make yourself a context and reconstruct the interior space, which is the method used in renovation. It is constructed from the context of the surrounding environment once, and the constructed one is read as the context at the next stage without a time lag, and then the internal space is reconstructed. The resulting architecture does not appear to have anything to do with the original context of the surrounding environment.
周辺環境のコンテクストを設計する時の手掛かりとする前提は、建築は動かないのでその場所に存在する必然性が必要ということだが、もし前提が変わりその場所に存在する必然性が必要ないとしたらどうなるだろうかと考えた。
コンテクストを全く手掛かりにしないだろうか。建築を周りから分断された敷地内だけの行為と考え全くコンテクストを必要としないだろうか。
コンテクストは、例え周りから分断された敷地だとしても、その敷地についてまわるものではないだろうか。ならば、建築が地面から切り離されない限り、建築はコンテクストの影響を受け続けるのではないだろうか。前提が変わりその場所に存在する必然性が必要ないとしても影響を受ける以上、コンテクストとどのように対峙するかは問われるのではないだろうか。
もしコンテクストと対峙することすら必要がない前提が構築できればどうなるだろうか。その時建築は地面から切り離されたものになるのだろうか。
"Necessity of context"
The premise when designing the context of the surrounding environment is that the architecture does not move and needs to be in that place, but what if the premise changes and it is not necessary to be in that place? Thought.
Wouldn't it be a clue to the context at all? Wouldn't it be necessary to think of architecture as an act only on the site separated from the surroundings and need no context at all?
The context may be about the site, even if it is separated from the surroundings. Then, unless the architecture is separated from the ground, the architecture will continue to be influenced by the context. Even if the premise changes and the necessity of being in the place is not necessary, it will be affected, so how to confront the context may be questioned.
What if we could build a premise that doesn't even have to confront the context? Will the architecture then be separated from the ground?
周辺環境のコンテクストを設計する時の手掛かりとするのはなぜかとふと思った。別にコンテクストを無視することもできるし、一旦受け入れてから無視することもできる。大概の建築は無視していると言ってもいいかもしれない、考慮するのは道路付けと日当り位で、これらもコンテクストではあるが、これらをコンテクストとして意識している訳ではない。
建築は動かないし、動けないので、その場所に存在する必然性が必要だと考える。存在の必然性を担保するために周辺環境のコンテクストに目を向け、抽出したコンテクストを設計の手掛かりにする。
だから、コンテクストに関係なく、建築がその場所に存在する必然性が表現できれば、コンテクストを設計の手掛かりにする必要もないのだが。
"Inevitability to exist in that place"
I wondered why it was a clue when designing the context of the surrounding environment. You can ignore the context separately, or you can accept it and then ignore it. It can be said that most architecture is ignored, considering road attachment and sunlight, which are also contexts, but they are not conscious of them as contexts.
Architecture does not move and cannot move, so I think it is necessary to exist in that place. In order to ensure the inevitability of existence, we look at the context of the surrounding environment and use the extracted context as a clue for design.
So, regardless of the context, if you can express the necessity that the architecture exists in that place, you don't need to use the context as a design clue.
屈折して、屈曲して対比をつくり出す。周辺環境のコンテクストから抽出した延々と続く様に対する内部空間は、壁が屈することにより凹み窪みができ人の居場所が形成される。
風景の延々と続く様には引っ掛かりがない。その引っ掛かりのなさに違和感を感じる。その引っ掛かりのなさに非人間的な構築感がある。
人の居場所をつくることが目的だから、内部空間では延々と続く様を見せる風景、外部空間とは対照的にする。
"Contrast interior space"
Refract and bend to create a contrast. The interior space, which is extracted from the context of the surrounding environment and continues endlessly, is dented by the bending of the wall, and a place for people is formed.
There is no catch in the endless landscape. I feel uncomfortable with the lack of catching. There is an inhuman sense of construction in the lack of catching.
Since the purpose is to create a place for people, it contrasts with the landscape that seems to continue endlessly in the interior space and the exterior space.
延々と続く更地の風景を都市部では見かけない。そもそもそのような広い更地を見かけることがない。更地があれば何かの事業用地で、いつのまにか何かの建築で埋まる。
子供の頃の西新宿、まだ都庁どころか今の超高層ビル群が無かった頃の広い空き地が記憶にある。超高層ビルを下から見上げるのも、上に上がるのも好きな子供だった。今は当たり前の超高層建築の設計に携わると現実的な見方しかしなくなる。
人間的なスケールを逸脱している更地には、ヒューマン的な人間性は感じられず、人間のためとしつつ、より効率良くからより速く、より高くが導き出され実行される。だから非人間的だと思ったけれど、よく考えたら、より効率良くも人間の欲望の果てだとしたら、とても人間的であり、その効率の中にいるから人間であると思った。
"Human vacant lot"
You can't see the endless landscape of vacant lots in urban areas. In the first place, I do not see such a large vacant lot. If there is a vacant lot, it will be a business site, and it will be filled with some kind of construction before you know it.
I remember Nishi-Shinjuku when I was a kid, and a large vacant lot when there were no skyscrapers today, let alone the Tokyo Metropolitan Government Building. He was a kid who liked looking up at skyscrapers from below and going up. Nowadays, when I am involved in the design of skyscrapers, which is commonplace, I have only a realistic view.
Human nature is not felt in the vacant lots that deviate from the human scale, and while doing it for human beings, more efficient, faster, and higher are derived and executed. So I thought it was inhuman, but when I thought about it, if it was the end of human desires more efficiently, I thought it was very human and I was human because I was in that efficiency.
建築することを意識して浮かび上がる周辺環境のコンテクストに影響された建築が、今度はその内部空間のコンテクストとして影響を与えることは、周辺環境のコンテクストを書き換えることになると考えた。
鉄道高架のための立ち退きでできた細長い変形地は、見渡す限り延々と続く更地の一部を形成しており、この延々と続く様は、今後風景が変わっても残り続けることので、現在から未来への時間のコンテクストとして抽出できる。
この延々と続く様を建築的に表現し、その内部空間では延々と続く様の対比が繰り広げられる。なぜ対比か、それはこの非人間的な論理で構築された風景への違和感から、抽出したコンテクストを一欠片も残したくない、ただしかし抽出したコンテクストと関連づけて時間的連続性は担保して、この内部空間が恣意的なものではないと表明したいからである。
"Contrast of context"
I thought that if an architecture influenced by the context of the surrounding environment that emerges with the consciousness of building influences as the context of its internal space, it would rewrite the context of the surrounding environment.
The elongated deformed land created by the eviction for the elevated railway forms a part of the vacant lot that continues endlessly as far as the eye can see, and this endless appearance will continue even if the landscape changes in the future, so from the present It can be extracted as the context of time to the future.
This endless appearance is architecturally expressed, and the contrast of endless continuation is unfolded in the internal space. Why contrast, because of the discomfort with the landscape constructed by this inhuman logic, I do not want to leave a single piece of the extracted context, but I guarantee the temporal continuity in relation to the extracted context, this This is because I want to state that the interior space is not arbitrary.
コンテクストに従い、コンテクストを書き換える。今ある周辺環境に対しては全てが対象であり、その対象を全て建築と結びつける。結びつけられたコンテクストは建築と相対化されることにより浮かび上がる。建築に向かわなければコンテクストはただの一般的な呼称に過ぎない。
建築により浮かび上ったコンテクストを今度は建築自身が内部空間に対するコンテクストになるように組み替える。コンテクストはそもそも建築と結びついたものだから、単純に組み替えるだけで建築と親和性がある。組み替えたコンテクストに影響される内部空間は、元の周辺環境のコンテクストの影響が書き換えられた様が表現される。
"The context that emerged from architecture"
Rewrite the context according to the context. Everything is about the existing surrounding environment, and all the objects are connected with architecture. The associated context emerges by being relativized with architecture. If you don't go to architecture, the context is just a general name.
The context that emerged from the architecture is now rearranged so that the architecture itself becomes the context for the interior space. Since the context is related to architecture in the first place, it has an affinity with architecture simply by rearranging it. The interior space affected by the rearranged context is expressed as if the influence of the context of the original surrounding environment was rewritten.
境界としての建築の壁を考えてみると、内外をつなぐものならば開口部は必要になり、人が通るかどうかで窓か戸に分かれ、人が通ることはそこにアクティビティが存在し、開口部の位置により人の姿勢が変化し、同時にそれはスケール感を醸し出し、壁面が室内か室外かで見た目の仕上げが違う。
図面で表現すれば壁は二重線で描かれるだけだが、様々な受容体としての側面を壁は持つ。
"Wall as a receptor"
Considering the architectural wall as a boundary, if it connects the inside and the outside, an opening is necessary, and it is divided into a window or a door depending on whether or not a person passes through, and when a person passes through, there is an activity and an opening The posture of the person changes depending on the position of the part, and at the same time, it creates a sense of scale, and the appearance finish differs depending on whether the wall surface is indoors or outdoors.
In the drawing, the wall is only drawn with double lines, but the wall has various sides as receptors.
周辺環境のコンテクストに対して少しでも能動的な対応をとるためにはどうしたらよいかと考えるきっかけは、隣地が事業用地で鋼板の目隠しで仮囲いされることになり、そのために新しく建てる建築が周りからほとんど見えなくなってしまうことだった。
建築が周りからほとんど見えなくなることは、周辺環境に埋没し存在していないことと同じであり、同時に建築側から見れば、周辺環境との断絶が起こっており、コンテクストの影響が無いことであり、受動的にコンテクストを受け入れることもできない状況である。
ただそれでも周辺環境のコンテクストは現に存在する訳だから、コンテクストに接続するための能動的な対応を考える必要がある。そうしないとその敷地にその建築が存在する必要すら無くなってしまう。
"Connect to the context"
The reason for thinking about how to take an active response to the context of the surrounding environment is that the adjacent land will be temporarily enclosed by a steel plate blindfold at the business site, and for that reason the newly built building will be around. It was almost invisible.
The fact that the building is almost invisible from the surroundings is the same as being buried in the surrounding environment and does not exist, and at the same time, from the perspective of the building, there is a disconnection from the surrounding environment and there is no influence of the context. , It is a situation that cannot passively accept the context.
However, since the context of the surrounding environment still exists, it is necessary to consider an active response to connect to the context. Otherwise, the building wouldn't even have to exist on the site.
周辺環境のコンテクストの何に焦点を当てるのか、例えば、歴史なのか、それとも現在から未来なのか、時間軸で考えることは必要になる。コンテクストを意識しなくても、設計する時に建築を時間軸で考えるが、時間軸で何を考慮するかというと「変化」であり、建築の耐久性からくる劣化などの経年変化はもちろんだが、住宅でいえば家族構成の変化、もっと大局的に観て社会情勢の変化などがある。
周辺環境の変化は、コンテクストとして、設計する時に考慮すべき最重要事項である。変化に対応できるようにプラン上で工夫をする。それは受動的な対応であり、周辺環境のコンテクストを受け入れざるをえない建築の宿命でもある。それをもう少し能動的に対応できるようにすることはできないかと考えている。
"Responding to changes in context"
It is necessary to think about what to focus on in the context of the surrounding environment, for example, history or the present to the future, on the time axis. Even if you are not conscious of the context, you think about architecture on the time axis when designing, but what you consider on the time axis is "change", not to mention aging such as deterioration due to the durability of the building. Speaking of housing, there are changes in family composition and changes in social conditions from a broader perspective.
Changes in the surrounding environment are the most important considerations to consider when designing as a context. Devise a plan so that you can respond to changes. It is a passive response and the fate of architecture that has to accept the context of the surrounding environment. I'm wondering if we can make it a little more active.
コンテクストを書き換えようとするならば、建築と周辺環境との接触面でのデザインが重要になる。具体的には接触面は外壁とその内壁を含めた壁になる。
コンテクストを人が認知する時に最初に活躍する感覚器官は目だろう。視覚からの情報でコンテクストを把握し、様々に考察する。コンテクストを書き換えるならば、まず視覚的変化を外壁面とその内壁面でつくる。
外壁面は周辺環境のコンテクストから導き出し、内壁面は自らを指針としたコンテクストから導き出し、あとは外壁面と内壁面をつなぐ要素を混える。
"How to rewrite the context"
If you want to rewrite the context, the design of the contact surface between the architecture and the surrounding environment becomes important. Specifically, the contact surface is a wall including the outer wall and its inner wall.
The eye is probably the first sensory organ to play an active role when a person recognizes a context. Grasp the context from visual information and consider various things. To rewrite the context, first make a visual change on the outer and inner walls.
The outer wall surface is derived from the context of the surrounding environment, the inner wall surface is derived from the context based on itself, and the elements that connect the outer wall surface and the inner wall surface are mixed.
建築は自ら周辺環境のコンテクストをつくっていくものだと思うようになってきた。ただ、それは建築が強いコンテクストを発動するようなことではなく、元々存在する周辺環境のコンテクストを、それが良かろうと悪かろうと、書き換えるようなことであり、書き換える時の指針を自らに求めることがコンテクストを自らつくっていくことになると考えた。
敷地境界線を超えて建築は存在することができないので、周辺環境に影響を与えることはあっても、直接周辺環境を変えることはできない。故に、計画の初めには、元々ある周辺環境のコンテクストからの影響を考慮しなくてはならない。それが設計をする上での手掛かりにもなるが、どうしてもコンテクストに引きずられて迎合してしまう場合もあるのではないか。
コンテクストを書き換えることは、自由に建築をつくることにつながるかもしれないが、建築くらいの大きなスケールだから可能なことではないかと考えている。
"Create your own context"
I have come to think that architecture creates the context of the surrounding environment. However, it is not like building a strong context, but rewriting the original context of the surrounding environment, whether it is good or bad, and asking oneself for guidelines when rewriting. I thought that I would create the context myself.
Since architecture cannot exist beyond the boundary of the site, it may affect the surrounding environment, but it cannot directly change the surrounding environment. Therefore, at the beginning of the plan, the influence of the context of the original surrounding environment must be considered. It can be a clue in designing, but it may be dragged by the context and accepted.
Rewriting the context may lead to the creation of architecture freely, but I think it is possible because it is a large scale of architecture.
もともと立ち退きで整理された後の細長い変形地なので、今見える周りの風景は更地の連なりと、更地に沿って連なる外壁と、線路のみであり、これから風景が劇変していく仮の風景の中に建築を挿入する。
今見える風景は、現実だけど仮の状態、過程の一コマに過ぎず、道路も新たにつくられるので、設計において手かがりになるコンテクストは何もないに等しいかもしれない。しかし、このような変化の過程の一コマのタイミングで設計をすることはなかなかないので、逆にコンテクストに対して考える良い機会だと思っている。
"For an empty context"
Since it was originally a long and narrow deformed land after being organized by eviction, the surrounding scenery that can be seen now is only a series of vacant lots, an outer wall that runs along the vacant lot, and a railroad track, and the landscape is a temporary landscape that will change dramatically from now on. Insert the architecture inside.
The scenery we see now is a real but tentative state, just one frame of the process, and new roads are created, so there may be almost no context in the design. However, it is difficult to design at the timing of one frame in the process of such changes, so I think it is a good opportunity to think about the context.
建築が自閉することはどうやらダメらしい。何かと繋がりがある方がいいようだ。何かとは、周辺の環境であったり、社会であったり、勿論、一般の人などであり、その「繋がり」をデザインするのだという。
今、建築雑誌を開くと公共建築が多い。今というか、バブルがはじけた後からだからもう30年位になるのだが、それまでは公共建築が建築雑誌に掲載されることはほとんど無かった。バブルがはじけ、経済状況が一気に悪くなり、民間から公共に建築家の守備範囲が一斉にスライドし、今ではそれが当たり前になった。
公共建築ではその意義が問われるので、その「繋がり」が大事になり、公共建築の登場が増えるにつれ、建築を考える上で「繋がり」が主流になっていった。
ただ、その「繋がり」は大事だが、その「繋がり」を大事にし過ぎて、建築本来の独自性が弱くなったような気がする。だから、自閉である。建築が独自性を発揮しはじめる事はバブルの頃のようになる事ではない。むしろ、自閉した建築の独自性の強さが社会の指針になるような気がしている。
今この時この社会では簡単に「繋がり」が消える。新型コロナの影響もあるが、それはトリガーに過ぎず、あまりにも「繋がり」を大事にし過ぎた反動だと考えると、自閉して建築本来の独自性の強度に向き合うことは意味がある。
"Autism in architecture"
It seems that the architecture is not self-closing. It seems better to have a connection with something. It is said that something is the surrounding environment, society, of course, ordinary people, etc., and designs the "connection".
Now, when I open an architectural magazine, there are many public buildings. It's been about 30 years since the bubble burst, but until then, public buildings were rarely published in architectural magazines. The bubble burst, the economic situation suddenly deteriorated, and the architect's defensive range slid from the private sector to the public all at once, which is now commonplace.
Since the significance of public architecture is questioned, the "connection" became important, and as the appearance of public architecture increased, the "connection" became the mainstream when thinking about architecture.
However, the "connection" is important, but I feel that the original uniqueness of the architecture has weakened because the "connection" is too important. Therefore, it is autistic. It's not like the time of the bubble when architecture began to show its uniqueness. Rather, I feel that the strength of the uniqueness of self-closing architecture is a guideline for society.
At this time, "connection" easily disappears in this society. There is also the influence of the new corona, but considering that it is just a trigger and a reaction that values "connection" too much, it makes sense to self-close and face the strength of the original uniqueness of the architecture.
敷地の周辺環境のコンテクストには簡単に影響されてしまうもので、建築は動かず敷地の範囲内にとどまるだけにコンテクストの影響から逃げることができない。ならば、コンテクストの書き換えができないものかと考えた。
実際には敷地を超えてコンテクストに直接に物理的影響を与えることはできないので、自身の敷地の中でのコンテクストの解釈を組み換えることによって、コンテクストの書き換えを試みようとした。
コンテクストが一番端的に現れるのは建築の部位でいうとどこかと考えた時に、まず壁が思い浮かんだ。コンテクストにより空間配置が決まるとしたら、その空間配置が視覚的に一番わかりやすく現れているのが壁であり、その壁によって人のアクティビティも決まるので、壁に対して何らかの組み替えを行えばコンテクストの書き換えにつながるだろうと考えた。
"Recombining walls"
It is easily influenced by the context of the surrounding environment of the site, and the architecture does not move and stays within the range of the site, so it cannot escape from the influence of the context. Then, I wondered if the context could be rewritten.
In reality, it is not possible to directly affect the context beyond the site, so I tried to rewrite the context by rearranging the interpretation of the context within my own site.
When I thought about where the context would appear most clearly in terms of architectural parts, the wall first came to my mind. If the spatial arrangement is determined by the context, the wall is the one where the spatial arrangement is most visually understandable, and the activity of the person is also determined by the wall, so if some kind of rearrangement is performed on the wall, the context I thought it would lead to rewriting.
壁の厚みが極端に厚くなれば、それはひとつの空間をつくるのではないかと考えてみた。極端に厚い壁に開口部をあければ、それが窓でもドアでも良いが、一度に床壁天井ができ、開口部の大きさがある程度以上ならば空間になるし、その空間に人が入り込むこともできる。
そもそも壁が人に相対しているだけというのはつまらない。壁だか空間だか曖昧な存在にして、そこに人が絡んでくることを考えた方が面白い。
"Wall or space"
I thought that if the wall became extremely thick, it would create a space. If you make an opening in an extremely thick wall, it can be a window or a door, but if you can create a floor wall ceiling at once and the size of the opening is larger than a certain size, it becomes a space and people can enter the space. You can also.
It's boring that the wall is just facing people in the first place. It's more interesting to think about making people entwined in a wall or space that is ambiguous.
椅子、テーブル、カウンターと高さが段々と変わることで人の姿勢や位置が変わり、そこに窓の大きさと高さ、壁の厚みの違いを加えて、各々の相関関係で空間の一部をつくろうと考えている。
空間の一部というのは、普通は全部を つくろうとするだろうが、今抱えている案件で共通のプラットフォームのようなものをつくり、あとは各々の案件で全体の空間に仕上げていけばよいと考えた。用途も違う空間でも成り立つものを構想することによって、拡張性のある一般解を求め、そこから個別なものでデコレーションして多様性を獲得したいと考えた。
それは標準プラン、標準仕様などという陳腐なものではなくて、建築の原形に近いものを構想してみたいという考えからだった。
"Similar to the original form"
As the height of chairs, tables, and counters gradually changes, the posture and position of people change, and by adding differences in the size and height of windows and the thickness of walls, a part of the space is created by each correlation. I'm thinking of making it.
He would normally try to create a part of the space, but he should create something like a common platform for the projects he has now, and then finish the entire space for each project. I thought it would be good. By envisioning something that can be used in spaces with different uses, I wanted to find an expandable general solution, and then decorate it with individual things to gain diversity.
It was because I wanted to envision something close to the original form of architecture, rather than the clichés of standard plans and specifications.
極小さな建築、周りは囲いに迫られて、建築自体が何も見えないかもしれない。周りから何も見えなければ、周りから存在しないのと同じである。ならば、すでにその建築は自律することが決まっている、自律せざるを得ない。
周りから見えないのだから、何をしても許されるかもしれない。ただ内部においての都合だけを考えればよいから不都合はない。
細長い敷地なので、建築の平面形状も細長くなる。敷地の形状と同じ平面形状になるので、それだけで周りの環境のコンテクストには準拠しているとして、あとは許されるだろう。
敷地の中で1枚の壁を考える。その壁は当然周りからは見えない。その壁は外と内を隔てる役目があるが外面は見えないので、存在は内側からのみわかる。片面だけ考えれば壁が成立し、その壁が連続すれば建築という領域ができてしまうことが面白いと思った。
"One-sided wall"
Very small architecture, the surroundings are pressed by the enclosure, and the architecture itself may not be visible. If nothing can be seen from the surroundings, it is the same as if it does not exist from the surroundings. If so, the architecture has already been decided to be autonomous, and there is no choice but to be autonomous.
You may be allowed to do anything because you cannot see it from your surroundings. There is no inconvenience because it is only necessary to consider the internal convenience.
Since the site is long and narrow, the plan shape of the building is also elongated. Since it has the same flat shape as the site, it will be allowed as it conforms to the context of the surrounding environment.
Consider a wall in the site. Of course, the wall cannot be seen from the surroundings. The wall serves to separate the outside from the inside, but the outside is invisible, so its existence can only be seen from the inside. I thought it was interesting that a wall would be formed if only one side was considered, and if the walls were continuous, an area of architecture would be created.
敷地の周辺環境のコンテクストは無視できないが無いものにはできるのではないかと考えた。コンテクストは敷地まで迫ってくる、それに対して素直に従えばコンテクストの一部に含まれてしまうが、うまく書き換えてしまえば自ら独自のコンテクストをつくることができる。
接点は壁である。外側は外壁として、内側には内壁がある。外壁と内壁の組み合わせが建築をつくり上げるが、同時に外壁と内壁の組み合わせは敷地の周辺環境のコンテクストを表現している。
この外壁と内壁の組み合わせを変化させることによってコンテクストを書き換え、自ら独自のコンテクストをつくる。それは敷地の周辺環境のコンテクストに左右されない状況で建築をつくり出すことでもある。
"Independent of context"
The context of the surrounding environment of the site cannot be ignored, but I thought that it could be done without it. The context approaches the site, and if you obediently follow it, it will be included in a part of the context, but if you rewrite it well, you can create your own context.
The point of contact is a wall. The outside is the outer wall and the inside is the inner wall. The combination of the outer wall and the inner wall creates the architecture, but at the same time, the combination of the outer wall and the inner wall expresses the context of the surrounding environment of the site.
By changing the combination of the outer wall and the inner wall, the context is rewritten and the own context is created. It is also to create architecture in a situation that is not influenced by the context of the surrounding environment of the site.
敷地の周辺環境のコンテクストを顕著化するために建築があると考えてみる。建築を設計する上での手掛かりとしてコンテクストを反映し利用しようとするが、そのコンテクスト自体は読み取らなくてはならず、普段は意識化されていないことが多い。建築ができてはじめてコンテクストが意識される。建築をつくることが先にあるからコンテクストを読み取る必要があるのだが、コンテクストは建築をつくる以前からそこに存在している。ならば、できあがる建築は最終的にはコンテクストの一部に組み込まれることになる。それは風景の一部になることであり、自律した建築にはならないだろう。そうなると、もし自律した建築を目指すならば、コンテクストは無視するしかないが、無視をしてはただ奇抜な建築を演じるだけにもなる。だから、コンテクストを書き換えてみようと考えた。
"Context that cannot be ignored"
Consider that there is architecture to make the context of the surrounding environment of the site prominent. I try to reflect and use the context as a clue in designing the architecture, but the context itself must be read, and it is often not conscious. The context is conscious only after the construction is completed. It is necessary to read the context because building the architecture comes first, but the context has existed there even before the building was built. If so, the resulting architecture will eventually be incorporated into part of the context. It will be part of the landscape, not autonomous architecture. Then, if you aim for autonomous architecture, you have no choice but to ignore the context, but if you ignore it, you will just play a strange architecture. So I decided to rewrite the context.
コンテクストに左右される建築、と昔から考えていた。その土地、その場所でなければ実現できない建築というのが理想だろうとも考えてきた。その土地の周辺環境のコンテクストを読み取り設計に反映させるのが当たり前だとも考えてきた。
コンテクストに左右されることは建築が自律できなくて他律になることではあるが、建築を左右するような影響力があるコンテクストを読み取る必要があり、その読み取りで差異が生まれ、もしかしたら、コンテクストを設計に反映させることが自律につながることもあるのではないかと考えている。
"The context is self-reliant"
I've always thought that architecture depends on the context. He has also thought that the ideal would be the land, the architecture that can only be realized in that place. He has also taken it for granted that the context of the surrounding environment of the land is read and reflected in the design.
Being influenced by the context means that the architecture cannot be autonomous and becomes heteronomous, but it is necessary to read the context that has the influence that influences the architecture, and that reading makes a difference, and maybe the context. I think that reflecting this in the design may lead to autonomy.
敷地の周辺環境のコンテクストを読み取り設計に反映させる手法は当たり前のように行われていて、その場所特有の建築を生み出すためには必須の手法となっている。コンテクストを読み取るにあたり、周辺環境が良い方がいいかもしれないが、例えば、眺望が良い、公園や緑が目の前にある、水辺の近くなど、しかし、ネガティブな環境や一見平凡な環境でも関係が無く、周辺環境のコンテクストの優劣に関係が無く、コンテクストを読み取り設計に反映させる。それは建築が動かない物で、その土地の状況に依存せざるを得ないので、否応なしにコンテクストと対峙せざるを得ないからである。もちろん、全く対峙しないと選択もあり得るがそれもコンテクストを読み取った結果のことであるならば許されるだろう。
"Reflection of context"
The method of reading the context of the surrounding environment of the site and reflecting it in the design is taken for granted, and it is an indispensable method for creating the architecture peculiar to the place. In reading the context, it may be better to have a good surrounding environment, for example, a good view, a park or greenery in front of you, near the water, etc., but it also matters in a negative environment or a seemingly mediocre environment. There is no relation to the superiority or inferiority of the context of the surrounding environment, and the context is read and reflected in the design. This is because architecture does not move and it has to depend on the situation of the land, so it has to confront the context inevitably. Of course, if you don't confront at all, you may have a choice, but that would be acceptable if it was the result of reading the context.
外壁と内壁の違いは周りの環境のコンテクストを表しているので、見た目にも外壁と内壁には違いが出る。時には外壁と内壁の違いが今いる場所の手掛かりになる。
ならば、擬似的に外壁と内壁の区別を変化させることにより、周りの環境のコンテクストを書き換えてみる。書き換えるための指針は自らをコンテクストにすることで、それは自律的建築へとつながる。
最初に周りの環境のコンテクスト通りに外壁と内壁をプランニングし、次の段階で自らのコンテクストによって外壁と内壁の区別を変化させ、周りの環境のコンテクストを書き換える。
これにより、周りの環境の中に新たな環境を入れ子状に築くことになり、それは周りの環境のコンテクストに影響を受けるという他律的な状況から自律的な建築を生み出すことができ、周りの環境の中で、都市の中で、違和感がなく自律的建築が納まることになる。
"Rewrite the context"
Since the difference between the outer wall and the inner wall represents the context of the surrounding environment, there is a difference in appearance between the outer wall and the inner wall. Sometimes the difference between the outer and inner walls is a clue as to where you are.
Then, try rewriting the context of the surrounding environment by changing the distinction between the outer wall and the inner wall in a pseudo manner. The guideline for rewriting is to make oneself a context, which leads to autonomous architecture.
First, plan the outer wall and inner wall according to the context of the surrounding environment, and in the next stage, change the distinction between the outer wall and inner wall according to your own context, and rewrite the context of the surrounding environment.
This creates a new environment nested within the surrounding environment, which can create autonomous architecture from the heteronomous situation of being influenced by the context of the surrounding environment. In the environment, in the city, autonomous architecture will be settled without any discomfort.
常にどこかで完結した建築をイメージしており、クライアントからの要望もそのイメージの中では他の建築的要素のうちのひとつであり、ひとつのループの中で数珠つなぎに物事が関連し展開して、また元に戻り、その運動が日々繰り返され生活をつくる。
建築はどこか、ちょっと古い言い方をすれば、生産工場のようであり、繰り返し日常が生産され、クライアントの要望は原材料に過ぎず、どのように加工し生産するかは工場の能力に依存する。
工場ときくと無機質のような感じを受け、抵抗感を感じる人もいるかもしれないが、建築では実際に生活が営まれ、その営みは自然発生的に現れるのではなく、意図した先に現れるので、その様は意図的に何かがつくられるという意味で工場に例えるのは理にかなっていると考える。
"Architecture is a factory"
I always imagine a building that is completed somewhere, and the request from the client is also one of the other architectural elements in that image, and things are related and developed in a string of beads in one loop. Then, it returns to its original state, and the exercise is repeated every day to create a life.
Architecture is somewhere, in a little old way, like a production factory, where everyday production is repeated, the client's request is nothing more than raw materials, and how to process and produce depends on the capacity of the factory.
Some people may feel resistance when it comes to factories, but in architecture, people actually live their lives, and their activities do not appear spontaneously, but appear ahead of their intentions. So, I think it makes sense to compare it to a factory in the sense that something is intentionally made.
対立するものがうまく溶け合うような解決策を探している。設計をしていると終始解決策を探しているようだ。
頭に浮かぶイメージには必ず実現困難なことが纏っている。最初から何もかも無理が無くすんなりと実現するようなことは無い。そもそも焼き回しのようなことはしないから、その都度新しい要素を加える分、不確実なことも増える。
不確実であるから、わからないから、興味も湧き、様々な事に関心を持つようになる。
実は空間の不確実性は必要かどうかを考えていた。何もかもが手に取るようにわかる空間は果たして魅力的かどうか。優等生的には確実性の産物が建築なのだろうが、建築を使う人が建築の全てを把握することはないので、確実性に富んだ建築にしたところで意味が無い。
では魅力的な建築や空間ではどうだろうか、「魅力的」という言葉も曖昧で不確実だが、少なくとも設計する側は不確実性を無くそうとする。それが設計だと言わんばかりに曖昧さを無くそうとする。だから、解決策を考える。ただ、ふと不確実な様には惹かれ心動かされてしまう。その惹かれる心と魅力的な空間に魅了される心は同じような気もする、根が同じような。
結果的には不確実だった、確実性を高めた結果の産物が、そうでなければ、ただいい加減な建築が増えるだけである。意図して不確実な建築をつくる、それが良さそうだと考えた。
"Uncertainty"
I'm looking for a solution that blends well with the conflict. It seems that he is always looking for a solution when he is designing.
The image that comes to mind always has something that is difficult to realize. From the beginning, everything is not unreasonable and can be realized smoothly. In the first place, we don't do things like burning, so adding new elements each time increases uncertainties.
Because it is uncertain, I don't know, so I get interested and become interested in various things.
Actually, I was wondering if spatial uncertainty was necessary. Is the space where you can grasp everything in your hands really attractive? As an honor student, the product of certainty is probably architecture, but since the person who uses the architecture does not know everything about the architecture, it is meaningless to make it a highly reliable architecture.
What about attractive architecture and spaces? The word "attractive" is vague and uncertain, but at least the designers try to eliminate the uncertainty. It tries to disambiguate as if it were a design. So think of a solution. However, I am attracted and moved by the uncertainties. The fascinated heart and the fascinated heart of the attractive space feel the same, the roots are the same.
The result is uncertain, the result of increased certainty, otherwise there will only be more sloppy architecture. I thought it would be good to intentionally create an uncertain architecture.
最近、在宅のお供にステッパーを購入した。運動不足ではないが、足踏みしていると眠くならないし、ウォーキングや階段昇降と同じ位の効果になると思うが、その場で単純な足踏みをしているだけなので、階段昇降やウォーキングではできない、携帯で様々な作業もできるし、本も読めて、マルチタスクにもならないので、集中力が途切れると踏み踏みして足を動かしている。
じっとしていると景色は同じだが、不思議なものでその場で踏み踏みしているだけで移動しているような気分にもなる。
足を動かすことで血流が良くなり脳への血の巡りも良くなるそうだ。きっと人はじっとしていられないのだろう。集中するとは絶えず様々なことに意識を張り巡らすことになるから、ひとつのことに集中していても周りの様子は手に取るようにわかる。
きっと動きの中に網目があり、その網目の細かさは人や状況によって違うだろうが、集中とは様々な出来事が網目に引っ掛かるように振る舞うことなのだろう。
ならば、空間把握の場合にも、その網目の引っ掛かりを助ける何かを用意する必要があり、その用意する行為が設計ともいえる。
"Stepping on and grasping the space"
Recently, I bought a stepper to accompany me at home. It's not a lack of exercise, but I don't feel sleepy when I step on it, and I think it's as effective as walking or climbing stairs, but since I'm just stepping on the spot, I can't go up and down stairs or walk I can do various tasks, read books, and do not multitask, so when I lose my concentration, I step on and move my legs.
The scenery is the same when you are still, but it is strange and you feel like you are moving just by stepping on the spot.
By moving your legs, blood flow improves and blood circulation to the brain also improves. I'm sure people can't stay still. When you concentrate, you are constantly conscious of various things, so even if you concentrate on one thing, you can understand the surroundings.
I'm sure there is a mesh in the movement, and the fineness of the mesh will vary depending on the person and situation, but concentration is probably the act of various events getting caught in the mesh.
Then, even in the case of grasping the space, it is necessary to prepare something that helps the mesh to be caught, and the act of preparing it can be said to be design.
スケールの違いが引力になり、人を惹きつけるようなイメージを持っている。囲われ感が好きな人は自分の身体の延長になるようなスケールを好み、開放的な感じが好きな人はスケールアウトしたような、どこか雄大な自然を好むように、人の手の及ばないようなスケール感を欲する。
スケール感は目には見えないが、そこに磁力線のような影響力を人に与えているので、知らず知らずのうちに意図せずに人は動かされているかもしれない。
建築が人に与える影響で一番大きく、一番効果的なものがスケール感だと考えているので、今までは人の手が届く細部でスケール感を表現してきた。今考えているにはもっと大きく、スケール感を重層させ、複雑なものを複雑なままに表現することである。
"Effect of scale"
The difference in scale is attractive and has an image that attracts people. People who like the feeling of being surrounded prefer a scale that is an extension of their body, and those who like the feeling of openness prefer a scale-out, somehow magnificent nature. I want a sense of scale that does not exist.
The sense of scale is invisible to the eye, but it gives a person an influence like a magnetic field line, so the person may be moved unintentionally without knowing it.
I think that the greatest and most effective effect of architecture on people is the sense of scale, so until now I have expressed the sense of scale with details that people can reach. What I'm thinking about now is to make things bigger, layer a sense of scale, and express complex things as they are.
連続して変化するような中に身を置いていれば、自分がいる場所と周りの場所との相関関係に気づくようになる。それは常に変化する可能性がある動きの中にいて、自分も動く可能性があるので、周りの動きに意識が向くためであり、常に動的な感覚で過ごすことになる。
空間に置き換えれば、人のアクティビティが常に起こるような状況や誘発する状況があることであり、その時に人は自分だけでなく周りも意識するようになる。
この周りを意識する感覚が空間把握につながるが、人のアクティビティが存在するか否かで空間把握の感覚に違いが出る。空間を動的に、すなわち、自ら把握している感覚になるためにはアクティビティの存在が必要である。
そのアクティビティの存在をスケールを操作することによって導き出そうとしている。
"Existence of activity"
If you are in a state of continuous change, you will notice the correlation between where you are and where you are. It's because I'm in a movement that can change all the time, and I can move myself, so I'm more conscious of the movements around me, and I always spend my time with a dynamic sensation.
If you replace it with a space, there are situations in which a person's activity always occurs or induces, and at that time, the person becomes aware not only of himself but also of his surroundings.
This sense of being aware of the surroundings leads to grasping the space, but the sense of grasping the space differs depending on whether or not there is a person's activity. The existence of activity is necessary in order to dynamically grasp the space, that is, to have a sense of grasping oneself.
I am trying to derive the existence of that activity by manipulating the scale.
居る場所によって印象が変われば、その建築は他律的といって良いだろう。どこに居ようと、何をしていようと建築から受ける印象が同じならば自律的な建築になる。自律的な建築は空間の強度が高く、何をしても空間に変化が起きない。
ただ、何をしても受け入れてしまい何も変わらない建築もある。一見それは自律的な建築のようだが、むしろそれは多様性がある建築といった方がしっくりくる。何でも許容できてしまう強度がある。
空間の強度が高い自律的な建築は見ていて美しく、惹かれるものがある。THE建築と思わせる。だが、社会の中で建築を考えた場合は、何をしても受け入れてしまう、何でも許容できてしまう強度が必要になる。だから、自律的多様性がある建築をつくりたいといつも考えている。
"Autonomous diversity"
If the impression changes depending on where you are, you can say that the architecture is heteronomous. No matter where you are or what you are doing, if the impression you get from architecture is the same, it will be an autonomous architecture. In autonomous architecture, the strength of the space is high, and no matter what you do, the space does not change.
However, there are some architectures that accept whatever you do and nothing changes. At first glance, it looks like an autonomous architecture, but it's more like a diverse architecture. It has the strength to tolerate anything.
Autonomous architecture with high strength of space is beautiful to see and attractive. It makes me think of THE architecture. However, when considering architecture in society, it is necessary to have the strength to accept anything and tolerate anything. Therefore, I always want to create an architecture with autonomous diversity.
自らの中にコンテクストを見つける行為は改修の場においてみられる。周辺のコンテクストに相対する既存の建築があり、その既存の建築を残しながら何かを変える時、今度は既存の建築の中にコンテクストを見出すことになる。
周辺のコンテクストの中に別のコンテクストを見つけ出し設定する行為は入れ子状態であり、コンテクストが重層し、それに対応するだけで建築の自律性が高まると考えられる。
ならば、自らの中に見つけ出すコンテクストは他律性の高いものにすれば、自律と他律の両方の性質を兼ね備えた建築になり、建築がどのような場面でも魅力的に見えるようになるのではないかと考えた。
"Nested context"
The act of finding the context within oneself can be seen in the field of renovation. When you have an existing building that is opposed to the surrounding context and you want to change something while keeping the existing building, you will now find the context in the existing building.
The act of finding and setting another context in the surrounding context is a nested state, and it is thought that the autonomy of the building is enhanced simply by layering the contexts and responding to them.
Then, if the context found in oneself is highly heteronomous, it will be an architecture that has both autonomous and heteronomous properties, and the architecture will look attractive in any situation. I thought it might be.
周りを囲まれた場所ではほとんど何も見えない。何も見えなければ外観は存在しないのも同じである。外壁は存在するが外観にはならない。見えるのは外壁の室内側だけである。
そうなると、外壁も内壁も見た目の区別が無くなる。見えるのは外も内も無く、ただ『壁』だけである。
建築的には外壁と内壁は区別される。外壁は雨露をしのぎ、断熱性が求められ、内壁には無い機能がプラスされ、見た目にも外壁と内壁は違いが出る。時には外壁と内壁の違いが今いる場所の手掛かりになる。
そうなると、今度は外壁と内壁の違いが無いことをコンテクストにする。
外壁と内壁の違いは周りの環境のコンテクストを表しているので、外壁と内壁の違いが無いことはもはや参照すべき周りの環境のコンテクストが無いことと同じである。
したがって、自らの外壁と内壁の違いが無いことをコンテクストとして空間を組み立てるしかなくなる。
"Make yourself a context"
Almost nothing can be seen in the surrounding area. It is the same that the appearance does not exist if nothing is seen. The outer wall exists, but it does not look like it. Only the indoor side of the outer wall can be seen.
In that case, there is no distinction between the appearance of the outer wall and the inner wall. There is no outside or inside, only the "wall".
Architecturally, the outer wall and the inner wall are distinguished. The outer wall is required to withstand rain and dew, and has a function that the inner wall does not have, and the outer wall and the inner wall are different in appearance. Sometimes the difference between the outer and inner walls is a clue as to where you are.
In that case, the context is that there is no difference between the outer wall and the inner wall.
Since the difference between the outer wall and the inner wall represents the context of the surrounding environment, no difference between the outer wall and the inner wall is the same as no longer having the context of the surrounding environment to be referred to.
Therefore, there is no choice but to assemble the space with the context that there is no difference between its own outer wall and inner wall.
たった1枚の壁が整流板のように流れをつくることもある、誘発することもある。何もない、動きもない所に壁が立ち上がり、そこに人が集い、スケール感が与えられ、様々なアクティビティと呼応しながら、人がいる範囲が空間として規定されていく。
実際には敷地境界線という目には見えない線が規定されていく空間に制限を与えるが、敷地境界線を超えて空間として取り込むこと、それは意識上の話だが、借景のような境界線の超え方は誰でも意識できる。
都市の中で建築を考えた場合、敷地境界線ほど強い制限はないかもしれない。絶対に実際に超えられない線である。しかし、何らかの方法で超えたように思わせたいといつも考えを巡らせる。
"Cross the border"
A single wall can create or induce a flow like a baffle. A wall rises in a place where there is nothing and no movement, people gather there, a sense of scale is given, and the range where people are present is defined as a space while responding to various activities.
Actually, it limits the space where the invisible line called the site boundary line is defined, but it is a conscious story to take in as a space beyond the site boundary line, but the boundary line like a borrowed landscape Anyone can be aware of how to overcome it.
When considering architecture in a city, there may not be as strong a limit as the site boundary. It is a line that can never actually be crossed. However, I always think about how I want to make it seem like I've exceeded it in some way.
空間を発生させる物は何かと考えている。水面に石を投げれば波紋が広がるように、何かがあれば伝播するように空間が発生するというか、特定の空間として感じられるようにするには何が必要かと考えている。
建築的には空間は発生するものとは考えない。空間は構築するもので、意図的にはじめに範囲を定めて空間を規定する。空間は発生するものだと考えれば、構築的に建築を考えないようになり、発生させる物は何かと、物の持つ個体としての魅力や性質や本質に目が行くようになる。
建築を物として捉えようとするならば、空間は発生するものだと考えた方が自然であり、水面の波紋のように広がるのであれば、敷地境界線を超えて空間として影響を与えることができる。
"Space is what happens"
I am wondering what creates space. I'm thinking about what is needed to make a space feel like a specific space, such as a space that spreads when a stone is thrown on the surface of the water and propagates if something happens.
Architecturally, I don't think that space will occur. Space is to be constructed, and the space is intentionally defined by first defining the range. If you think that space is something that occurs, you will not think about architecture constructively, and you will be able to see what you generate and the attractiveness, nature, and essence of the individual thing.
If you want to think of architecture as an object, it is more natural to think that space is generated, and if it spreads like ripples on the surface of the water, it can affect the space beyond the boundary of the site. it can.
壁と窓と床が人の姿勢に沿うように織りなして存在すれば、そこにはひとつの囲われた空間ができる。天井や屋根で蓋をしないと空間にならないような気もするが、無くても、壁があれば人は囲われ感を抱き、高い天井のホールなどのように空間を感じる。
大地があれば床もいらないような気がするが、人の姿勢に沿うためには「立つ」「椅子に座る」「床に座る」のこの三段階の人の姿勢に対応する床面は必要になる。壁と窓を利用して「椅子に座る」姿勢に対応すれば、壁と窓と床で空間になる。
壁と窓と床の関係性の見直しになるのかもしれないが、壁と窓と床の違いがはっきりとしない曖昧な様をイメージしている。
"Walls, windows and floors"
If the walls, windows, and floor are woven together to match the posture of a person, there will be an enclosed space. I feel that it wouldn't be possible to create a space without a lid on the ceiling or roof, but even without it, people would feel surrounded by the walls and feel the space like a hall with a high ceiling.
I feel that if there is earth, I don't need a floor, but in order to follow the posture of a person, it is necessary to have a floor surface that corresponds to the three stages of "standing", "sitting on a chair", and "sitting on the floor". become. If you use the walls and windows to support the "sitting on a chair" posture, the walls, windows, and floor become a space.
It may be a review of the relationship between walls, windows and floors, but I imagine that the difference between walls, windows and floors is not clear and ambiguous.
室内の温熱環境を考えていると窓に振り回られる。窓が無いと日射が入らないので暗いし寒いし、しかし、窓が有るとそこから熱が逃げる。これはあくまでも冬の場合で、夏は逆に窓が有ると日射が入り暑くなり、窓が無いと影になり暑さがやわらぐが風が入らない。全館空調を1日中行えば、窓の存在に左右されないが省エネでは無い。
今の冬の時期の晴天の昼間に窓際が寒いのは、窓の断熱性が脆弱だからである。南面以外の窓は断熱性の高いサッシと室内側に断熱性の高い付属部材を設置しないと、ブラインドやレースカーテンでは不十分、窓際にストーブを置いても熱は外に逃げる。ところが、今の時期、晴天だと南面の窓には電気ストーブ1台分の熱量があるので、レースカーテンも開けて熱を室内に取り入れたい。
ただ、このような簡単なことがわかっている専門家が実は少ない。
"The utility of windows"
When thinking about the thermal environment in the room, it is swung around by the window. Without windows, it's dark and cold because sunlight doesn't enter, but with windows, heat escapes from there. This is only the case of winter, and on the contrary, in summer, if there is a window, sunlight enters and it becomes hot, and if there is no window, it becomes a shadow and the heat softens, but the wind does not enter. If the entire building is air-conditioned all day long, it will not be energy-saving, although it does not depend on the presence of windows.
The reason why the windows are cold during the sunny day of this winter is that the heat insulation of the windows is weak. For windows other than the south side, blinds and lace curtains are not enough unless a highly heat-insulating sash and highly heat-insulating accessories are installed inside the room, and even if a stove is placed near the window, heat escapes to the outside. However, at this time of year, when the weather is fine, the window on the south side has the amount of heat for one electric stove, so I would like to open the lace curtain to take in the heat indoors.
However, there are actually few experts who know such a simple thing.
窓と壁の関係性を考えてみると、カーテンウォールは壁が透明又は半透明になり光を通すから、壁が窓になったものといえるだろう。では窓が壁になることはあるだろうか。そもそもカーテンウォールの場合を除けば、窓と壁は全く別物として扱われることが多い。
壁に空けられるのが窓であり、窓があり周りに壁がつくられるようには考えない。
では、どのような窓にするかが先にあり、その延長線上で窓が変化して壁になるようなイメージをしてみるとどうなるだろうかとわざと考えてみる。
"From the window to the wall"
Considering the relationship between windows and walls, curtain walls can be said to be windows because the walls are transparent or translucent and allow light to pass through. So can windows become walls? Except for curtain walls in the first place, windows and walls are often treated as completely different things.
It is a window that can be opened in the wall, and I do not think that there is a window and a wall is created around it.
Then, what kind of window should be used first, and I wonder what would happen if I imagined that the window would change to become a wall on the extension line.
人の姿勢からのスケールと窓と壁を合わせて何かまとまらないかと考えている。窓は壁の一種として、窓がフレームの役目では無く、壁の違う見せ方として、窓と壁の関係性をつくり、人の姿勢によるスケール感の違いに寄り添うように窓が存在するならば、人と窓の関係性ができ、その結果、人と窓と壁の関係性ができ上がる。
人と窓と壁の関係性で空間が成り立つならば、アクティビティを持つ人が可変要素になり、空間の見え方が変化する。
"Change in appearance"
I'm thinking about how to put together the scale from the human posture and the windows and walls. A window is a kind of wall, and the window is not a frame, but a different way of showing the wall. A person-window relationship is created, and as a result, a person-window-wall relationship is created.
If the space is made up of the relationship between people, windows, and walls, the person with the activity becomes a variable element, and the appearance of the space changes.
コルビュジエは人のスケールを基本にして空間のスケールを決めていた。空間のスケールを感覚的に感じるのは人であるから、人自身の大きさや手足の長さを基準にするのは理にかなっている。そこで人の姿勢を空間のスケールの基準にしてみようと考えた。
立つ、椅子に座る、床に座るのこの三段階の人の姿勢を基準にして空間のスケールを建築的に表現しようと思う。「立つ」はアクティビティを追加して「歩く」でもいいかもしれない。
建築要素との関連でいえば、「立つ」あるいは「歩く」は床と壁、「椅子に座る」は建築化された椅子になる壁か床、「床に座る」はもちろん床が対象になり、三段階の人の姿勢のスケールを持ち込んで各部位をデザインしてみる。
今現在、店舗を計画中なので、住宅よりはシンプルに三段階の人の姿勢のスケールをデザインに持ち込みやすいかもしれない。
"Bring a posture scale"
Le Corbusier decided the scale of space based on the scale of human beings. Since it is the person who feels the scale of space sensuously, it makes sense to base it on the size of the person and the length of the limbs. So he decided to use the posture of a person as a reference for the scale of space.
I would like to architecturally express the scale of space based on the postures of people in these three stages: standing, sitting on a chair, and sitting on the floor. "Standing" may be "walking" with additional activities.
In relation to architectural elements, "standing" or "walking" is the floor and walls, "sitting on a chair" is the wall or floor that becomes an architectural chair, and "sitting on the floor" is of course the floor. Let's design each part by bringing in a scale of human posture in three stages.
Currently, we are planning a store, so it may be easier to bring a scale of three levels of human posture into the design rather than a house.
壁は構造耐力、断熱、防音、遮音などの機能が満たせれば、なるべく薄くしたいと考える。壁が厚くなれば、厚くなった分だけ部屋が狭くなるからである。
普段の生活の中で壁の厚みなど意識しないだろう。設計していても壁の厚みは仕上げの工法や断熱材の厚みや柱梁の大きさ、厚みでほぼ自動的に決まることが多い。
壁の厚みをデザイン要素として扱う場合も、壁の厚みをできるだけ薄くしたい。極端に壁の厚みを薄くすることにより、外と内の仕切りになっている壁の存在が希薄になり、壁があるけれど外が身近に感じられる錯覚をつくり出すことはできる。
もし壁の厚みがひとつの空間の中で変化していくとどうなるだろうか。空間の中で壁の厚みがわかるのは主に窓のところだから、窓と壁の関係性が変化していくのだろう。ひとつの空間の中で壁の厚みが変化していくことは普通は無いので妥当性も必要だが、壁の厚みが変化してその結果得られるものが空間を決定づけるものであったり、空間のスケールを担うものであれば、壁の厚みを恣意的に変化させることもあるだろう。
"When the thickness of the wall changes"
We would like to make the wall as thin as possible if it can satisfy the functions such as structural strength, heat insulation, soundproofing, and sound insulation. This is because the thicker the wall, the smaller the room.
You will not be aware of the thickness of the wall in your daily life. Even if it is designed, the wall thickness is often determined almost automatically by the finishing method, the thickness of the heat insulating material, the size and thickness of the columns and beams.
Even when treating the wall thickness as a design element, we want to make the wall thickness as thin as possible. By making the wall extremely thin, the existence of the wall that separates the outside and the inside becomes thin, and it is possible to create the illusion that there is a wall but the outside feels close to us.
What if the wall thickness changes in one space? Since it is mainly the windows that show the thickness of the walls in the space, the relationship between the windows and the walls will change. Since the wall thickness does not usually change in one space, validity is also necessary, but what is obtained as a result of changing the wall thickness is what determines the space, or the scale of the space. If it is responsible for this, the wall thickness may be changed arbitrarily.
千利久作の茶室「待庵」の窓をメタ認知的に見て「窓は壁の違う見せ方」と考えたので、具体的に実際のデザインに応用することを試みる。
例えば、象嵌という手法がある。壁の中にガラスかアクリルのような透明な物質を仕込むことだが、見た目は壁の中に透明な部分ができ、ひとつの壁の仕上げとなるが「窓は壁の違う見せ方」という様相ではない。もっと窓としての存在は欲しい。
待庵の窓を素材や工法から考えれば、壁と同じ素材や工法からつくられており、壁をつくる過程で違うルートに至った結果に出現したような様相である。壁をつくりながら、途中で何か違うことをすると窓として現れるようなイメージになる。
いま一度、素材や工法から壁と窓の有り様を考え直してみると「窓は壁の違う見せ方」に至る可能性がありそうな気がしている。
"Beginning to consider how windows look different on walls"
Looking at the windows of the tea room "Machian" by Senrihisa, I thought that "windows look different from the walls", so I will try to apply them to the actual design.
For example, there is a technique called inlay. It is to put a transparent substance such as glass or acrylic in the wall, but it looks like a transparent part is created in the wall and it is a finish of one wall, but in the aspect that "windows look different from the wall" Absent. I want more windows.
Considering the materials and construction methods of the windows of Machian, they are made from the same materials and construction methods as the walls, and it seems that they appeared as a result of reaching a different route in the process of making the walls. If you do something different on the way while making a wall, it will appear as a window.
When I reconsider the appearance of walls and windows from the materials and construction methods, I feel that there is a possibility that "windows look different from walls".
前に展覧会で再現された千利久作の茶室「待庵」を見た時に「窓を残して壁をつくる」との記載を見つけた。
待庵の窓は単に土壁が無い所であり、四角状に土壁を塗らないで残しただけであり、窓をつくる手法に特別なことは無く、窓と壁の違いは土壁が有るか無いかだけであり、考え方によっては「窓は壁の一部」あるいは「壁は窓の一部」となり、窓と壁のどちらに焦点を当てるかによって違うだけで、待庵の場合、面積比でいえば壁の方が多いから「窓は壁の一部」になるだろうが、メタ認知的に見れば「窓も壁も同じ」「窓は壁の違う見せ方」「窓は壁の一種」としてもいいだろう。
待庵の窓にはフレームの意味合いが無いので、外の風景を切り取るような額縁の役目は無く、壁に外の移ろいだけを投影して厳選した自然を取り入れる装置になっており、壁の一種としての窓足らんとし、茶室に施される設えと同化する。
待庵の窓だが窓ではない様には惹かれるものがあり、窓と壁を機能的に分けて考えがちな現代建築には無い様相が見られて面白い。
"Window is a wall"
When I saw the tea room "Machian" by Senrihisa, which was reproduced at the exhibition before, I found a description that "I will leave the window and make a wall".
The window of Machian is simply a place without a clay wall, it is left without painting the clay wall in a square shape, there is nothing special about the method of making a window, and the difference between a window and a wall is that there is a clay wall. Depending on the way of thinking, "window is a part of the wall" or "wall is a part of the window", and it depends on whether you focus on the window or the wall. In the case of waiting hermitage, the area In terms of ratio, there are more walls, so "windows are part of the wall", but from a meta-cognitive perspective, "windows and walls are the same", "windows look different from walls", and "windows are walls". It may be a kind of "a kind of".
Since the window of the waiting hermitage has no meaning of a frame, it does not serve as a frame to cut out the outside scenery, and it is a device that projects only the outside transition on the wall and takes in the carefully selected nature, which is a kind of wall. Assimilate with the setting given to the tea room.
Although it is a window of Machian, there is something that attracts me as if it is not a window, and it is interesting to see the appearance that is not found in modern architecture, which tends to think of windows and walls as functionally separate.
外観に開口部、いわゆる窓の大きさと位置をランダムにして設置することはすでにスタンダードになった。窓の大きさや位置からプランが推測できたり、窓が室内の特定の様子を映し出したり、逆に室内から特定の風景を良く見せたりなどの、窓に窓以外の意味を持たせないためにランダムに行うのだろう。あと、外観の見た目のデザインした感もあるだろう。
すでに窓をランダムに配置することはひとつの形式になったので、いちいち詮索しない、詳細に見ない、そういうものだと見た目だけで判断してスルーしてしまう。
最近面白いと思うのは、外観がない状態、外壁を剥がし取ってしまい、窓というものの存在感がなく、内部の様子が外部に溢れ出たような見え方をしている状態である。もしかしたら工事途中の状態、あるいは既存の建物の解体工事途中の状態に似ているかもしれない。
窓というものが内部と外部をつなげることを唯一の役目としたならば、窓というフレームで切り取る必要は無く、そもそも窓というもの自体が無くても内部と外部をつなげることはできるはずである。
「窓が無く内部と外部がつながる外観を持つ建築」と言葉で記述してみたが、そこを目指すとして、実現可能かどうか、むしろ矛盾や不明なことを含んだ言葉の方が創造力が働く。
"Appearance without windows"
Random installation of openings, so-called windows, in the exterior has already become a standard. Random because the window has no meaning other than the window, such as the plan can be inferred from the size and position of the window, the window reflects a specific state of the room, and conversely, a specific landscape is shown well from the room. Will do it. Also, there will be a feeling of designing the appearance.
Randomly arranging windows has already become one form, so don't snoop, don't look at it in detail, and just look at it and let it through.
What I find interesting these days is that there is no exterior, the outer wall has been peeled off, there is no presence of a window, and the inside looks like it has overflowed to the outside. Maybe it's in the middle of construction, or similar to the state of an existing building being demolished.
If the sole role of a window is to connect the inside and the outside, there is no need to cut it out with a frame called a window, and it should be possible to connect the inside and the outside without the window itself in the first place.
I tried to describe it in words, "architecture with an exterior that connects the inside and the outside without windows", but when aiming for that, creativity works more in words that include contradictions and uncertainties, whether it is feasible or not. ..
窓を見ると部屋がわかる。道路から見た時の外観の窓の位置、大きさ、形で建築のプランは大体わかる。別に決まり事がある訳でもなく、窓の位置、大きさ、形を先に決めてからプランを考える訳でもないが、この部屋にはこのくらいの窓という暗黙の了解みたいなものは存在しており、それに沿う設計者がほとんどだから、見る人が見ればわかってしまう。
外観の窓でプランがわかることが良いのか悪いのかは別として、窓とプランが対になっており、そこに明快なわかりやすさがあることは良いことだとされている。混乱がないからで、人は周りの環境をいちいち個別に判断していたら、脳の容量がすぐにパンクしてしまうので、型式で物事を把握することは多分にあるだろう。
形式で把握すること自体は日常生活の中にもたくさんあり、そのおかげで人の脳は大事なことだけに集中できる。しかし、形式把握はどうでもよい扱いにも通じることであり、詳細に把握することを省いているのであり、そこから享受できることは何もない。
然らば、何か影響を与えたいと考えるならば、形式で把握されないような、形式から逃れる工夫が必要になる。
"Escape from form"
You can see the room by looking at the window. You can roughly understand the architectural plan by the position, size, and shape of the windows that look like when viewed from the road. There is no rule, and I don't think about the plan after deciding the position, size, and shape of the window first, but there is a tacit understanding of such a window in this room. Most of the designers follow it, so the viewer can understand it.
Regardless of whether it is good or bad to see the plan from the exterior window, it is said that it is good that the window and the plan are paired and that there is clear clarity. Because there is no confusion, if a person judges the surrounding environment individually, the capacity of the brain will be punctured quickly, so it is likely that you will grasp things by model.
There are many things to grasp in form in daily life, which allows the human brain to concentrate on what is important. However, grasping the format also leads to insignificant treatment, omitting grasping in detail, and there is nothing that can be enjoyed from it.
Then, if you want to influence something, you need to devise a way to escape from the form so that it is not grasped by the form.
建築空間の中で形となってスケールを表すものは、窓を含む壁になるかもしれないと考えた。空間の中で建築の構成要素になっているものがよく、例えば、家具などの建築から切り離されても存在できるものは違うと考え、尚且つ、人と同じように直立して存在しているものとなると、壁あるいは窓、当然柱は壁に含まれる。
前々から窓を含む壁にはまだまだ表現的な可能性があると考えている。壁はどうしても骨組みとしての構造的要素か空間を分節するための機能的要素とみなしてしまうが、これらの2つの要素だけでなく、人が空間を把握するための認知的要素にもなっていて、把握の仕方を壁の表現として上手く使えば、また違った壁の見え方が表現できるのではないかと考える。
"Potential of the wall"
I thought that what was shaped and represented the scale in the architectural space might be a wall including windows. It is often the one that is a component of architecture in the space, for example, I think that what can exist even if it is separated from the architecture such as furniture is different, and it exists upright like a person. When it comes to things, walls or windows, and of course pillars, are included in the walls.
I have always thought that the walls including windows have more expressive potential. The wall is inevitably regarded as a structural element as a framework or a functional element for segmenting space, but it is not only these two elements but also a cognitive element for human beings to grasp the space. I think that if we use the method of grasping well as an expression of the wall, we can express a different way of seeing the wall.
スケール感は自分の身体の大きさを物差しとする感覚だから人によって違う。空間の中に複数のスケールが存在していたら、自分に合うスケールに自然と近寄っていくだろう、もしくはその時の体調や感情で選ぶスケールが違うかもしれない。
スケールは形となって空間の中に目で見える存在としてあり、異なるスケールが同時に複数存在していたら、空間の中に異なる形が複数存在していることになる。
空間の中に異なる形がどのように配置されるかはその時々によって違うだろう。空間の用途、機能性によって違い、違いが唯一無二の空間を生む。その時、スケールを選ぶ人の空間の見え方はその人だけのものになる。
"How only that person can see"
The sense of scale varies from person to person because it is a sense of measuring the size of one's body. If there are multiple scales in the space, you will naturally approach the scale that suits you, or the scale you choose may differ depending on your physical condition and emotions.
The scale becomes a shape and is visible in the space, and if there are multiple different scales at the same time, there are multiple different shapes in the space.
How different shapes are arranged in space will vary from time to time. It depends on the purpose and functionality of the space, and the difference creates a unique space. At that time, the appearance of the space of the person who chooses the scale is only for that person.
小さい空間は、狭くて窮屈で息苦しいイメージがあるかもしれないが、大きさが適切だと心地良い囲われ感があり、大きい空間の中に置かれるよりも落ち着く場合があり、大きさが適切かどうかの指標が「スケール感」になる。
スケール感は感覚的なので、厳密な寸法で表せないことでもあり、人によって感じ方が異なるが、空間の中にいる人にとって狭すぎず広すぎず丁度よく、尚且つ心地よいことを「スケール感が良い」といい、褒め言葉であり、スケール感が悪いものはつくりたくないと考える。
小さいことをデメリットと考える傾向から、小さい空間だと窮屈にならずなるべく広く見せたいという思いが働き、仕切りをつくらずに一室空間を目指すことが多いが、そうすると与えられるスケールは1つになる。「与られる」という表現は、空間のタテヨコ高さの組み合わせが無限に存在する中から設計者が1つを選択するからであり、空間のタテヨコ高さの組み合わせによってスケール感が決まるからである。
小さい空間はその小ささ故に1つのスケール感の良し悪しで、成否が決まることがある。もし、スケールが複数存在したらどうなるだろうか、小さい空間に複数のスケールが存在したら狭くて窮屈で息苦しいものになってしまうだろうか、人によって感じ方が違うスケール感ならば、複数のスケールが存在した方が様々な人に適応しやすい空間ができるのではないだろうかと考えてみる。
"If there are multiple scales"
A small space may have the image of being narrow, cramped and stuffy, but if it is the right size, it feels comfortable to be surrounded, and it may be more calm than being placed in a large space. The index is "a feeling of scale".
Since the sense of scale is sensuous, it cannot be expressed in exact dimensions, and the way it feels differs depending on the person, but for the person in the space, it is not too narrow and not too wide, and it is just right and comfortable. "Good" is a compliment, and I don't want to make something with a bad sense of scale.
From the tendency to think that small space is a disadvantage, there is a desire to make it look as wide as possible without becoming cramped in a small space, and in many cases we aim for a single room space without creating partitions, but then the given scale will be one. .. The expression "given" is because the designer selects one from an infinite number of combinations of vertical and horizontal heights in the space, and the sense of scale is determined by the combination of vertical and horizontal heights in the space.
Because of its small size, a small space may be successful or unsuccessful depending on the quality of one scale feeling. What if there are multiple scales, if there are multiple scales in a small space, it will be narrow, cramped and stuffy, if the feeling of scale is different for each person, there were multiple scales I wonder if it would be possible to create a space that is easier to adapt to various people.
人は目には見えないものにも想像力を働かせて対処できるとわかった2020年だったかもしれない。実際に人は目で見ていることだけで判断はしない。
建築でも人の無意識へ訴えかけるものがたくさんあり、それは「美しい」「綺麗な」「素晴らしい」などの形容詞で曖昧に語られることが多く、上手く言葉を当てはめることができない時に曖昧な形容詞が出てくる。
スケール感についても同じである。建築空間の感じの良さを表現する時に「スケール感がいい」などと使う。スケール感も形容詞と同じで曖昧な言葉であり、本来であれば「スケール感がいい」理由をプロならば言葉で説明できなくてはいけない。
スケール感には曖昧で掴みどころが無いイメージがあるが、もしかしたら、その位に曖昧だから、人の感覚を掴み取れるのかもしれないと思うと、スケール感を意図的に操作することにより人の感覚に影響を与える術を考えたくなる。
"Intentional scale"
It may have been 2020 when people realized that they could use their imagination to deal with invisible things. Actually, people do not judge only by seeing with their eyes.
Even in architecture, there are many things that appeal to the unconscious of people, which are often vaguely spoken with adjectives such as "beautiful," "beautiful," and "wonderful," and when words cannot be applied well, vague adjectives appear. come.
The same applies to the sense of scale. When expressing the good feeling of an architectural space, it is used as "a feeling of scale is good". The sense of scale is the same as an adjective and is an ambiguous word, and if you are a professional, you must be able to explain in words the reason why "the sense of scale is good".
There is an image that the sense of scale is ambiguous and elusive, but maybe because it is so ambiguous, I think that it may be possible to grasp the sense of people, so by intentionally manipulating the sense of scale, people I want to think of ways to affect the senses.
2020年は今見ている風景が全てではないと思い知らされ、2021年は今見ている風景がさらにもっと全てではないと思うかもしれない。
いろいろな価値観が変わったが、自分が移動することで直に見ていたものを、移動せずに目の前で、しかしデバイスを通して見るようになった。きっと直に見ることで無意識に感じとっていたことが、デバイス越しにはカットされ無意識には届いていないだろうと思いながら、そうせざるを得ない状況に可能性を見出すならば、直が大事なことなど案外少ないとわかったことかもしれない。
今この時を少しでもポジティブに考えるならば、2021年はより大事なことだけが明確になるだろう。その時どうするか、他を捨てる心構えをしておく。
"2020 → 2021"
You may realize that 2020 isn't everything you're looking at, and 2021 isn't all that you're looking at.
Many values have changed, but now I can see what I was seeing directly as I moved, in front of me, but through the device, without moving. If you think that what you felt unconsciously by looking directly at it will be cut through the device and not reach you unconsciously, but you find the possibility in a situation where you have to do so, then Nao is important. You may have found that there are few things unexpectedly.
If you think about this time a little positively, 2021 will only clarify what is more important. At that time, be prepared to throw away the others.
東京タワーの足元を見ていて、人工と自然の対比などということではなく、スケールという括りで見た場合の多様性が面白いと思った。
突出した東京タワーの大きさを感じ、沿うように相似した紅葉の木々が存在し、地面を埋めつくす落ち葉とその間を縫う人々がいる。明らかにスケールが違い、ただ相互に関係し合う物同士が、どこに焦点を合わせるのかの違いで、様々なつながりをつくり出し、多様な風景を見せてくれる。
目に見えないものに翻弄された一年だった。まだまだ続く翻弄される状況の中で、唯一確かに感じられるのは目で見えるもののはずなのだが、その確かに目で見えるものでさえ、見る人によって存在が翻弄されはじめている。
きっとそれは見る側の人が見える風景をつくり出しているからだろう。いずれにせよ、翻弄されるのは仕方がないとしても、目で見えるものの存在にまで影響させないようにしたい。
"What you can see and what you can't see"
Looking at the footsteps of Tokyo Tower, I found it interesting to see the diversity when viewed in terms of scale, not the contrast between artificial and natural.
Feeling the size of the protruding Tokyo Tower, there are similar autumnal trees along it, and there are people who sew between the fallen leaves that fill the ground. Obviously the scales are different, and the things that are related to each other create various connections and show various landscapes depending on where they focus.
It was a year when I was at the mercy of something invisible. In the ongoing tossed situation, the only thing that can be surely felt is the one that can be seen, but even the one that is certainly visible is beginning to be tossed by the viewer.
I'm sure it's because it creates a landscape that the viewer can see. In any case, even if it is unavoidable to be at the mercy, I want to make sure that it does not affect the existence of what is visible.
多様性が生まれるには、最低3つの異なったものが同時に存在し、3つの相互の掛け合わせが必要になるが、多様性を判断する人はこの3つには含まれない。
昨日、東京タワーの近くにいた。窓から直近に東京タワーを眺めていたのだが、突出して東京タワーの足が見え、沿うように紅葉した木々があり、地面を埋めつくす落ち葉が季節感を表し、その間を縫う人々が何かを想う。
人はこの環境の中で多様性を感じ、この環境の中で記憶と照らし合わせて何かを見出すのか、投影するのか、それとも、違った何かを構成するのか、いずれにせよ、何かここだけの特別な想いを抱くだろう。
多様性は人の意識を動かすのであり、多様性をつくる元になったものに対して人は何か別のものを重ね合わせるのである。
"Diversity that moves consciousness"
At least three different things exist at the same time for diversity to be born, and it is necessary to multiply the three with each other, but the person who judges diversity is not included in these three.
I was near Tokyo Tower yesterday. I was looking at Tokyo Tower from the window, but I could see the legs of Tokyo Tower protruding, there were trees with colored leaves along it, and the fallen leaves that filled the ground expressed a sense of the season, and the people who sew between them showed something. think.
People feel diversity in this environment, and whether they find something in this environment in the light of their memory, project it, or compose something different, something here. Will have a special feeling only.
Diversity moves people's consciousness, and people superimpose something else on what created diversity.
建築が人から比べたら大き過ぎると感じてしまう時がある。そもそも建築は人を内包する物だから、人と比べたら大きくなるのは当たり前ではあるが、大き過ぎないと感じる建築もあるので、その違いはどこにあるのだろうかと考える。
建築が大きくなればなるほど、人が一目で把握することが難しくなる。その時人は建築の大きさを実感するのだろうが、大き過ぎると感じる時は把握することを諦めた時である。
建築が人を内包する物であるならば、人との関係性が必ず生まれる。把握することを諦めた時は関係性が断絶された時であり、それは避けなければならない。できれば、建築と人は親和的な関係でありたい。
親和的な関係を築くためには、ひとつには建築が人から把握しやすくする必要がある。大き過ぎると感じるならば、スケール感の問題であり、人にとって親和的なスケールにする。親和的なスケールとは、例えば、人のスケールから生み出されるサイズ感を人が触れるところ、人がよく目にするところに配置する。インテリアをよく見せたい時にも有効だろう。
"Affinity relationship"
Sometimes people feel that architecture is too big. In the first place, architecture is something that involves people, so it is natural that it will be larger than people, but there are also architectures that feel that it is not too large, so I wonder where the difference lies.
The larger the building, the harder it is for people to grasp at a glance. At that time, people may realize the size of the architecture, but when they feel it is too large, it is when they give up grasping it.
If architecture is something that embraces people, then a relationship with people is inevitable. When you give up on grasping, it is when the relationship is broken and you must avoid it. If possible, I want architecture and people to have an affinity relationship.
In order to build an affinity relationship, it is necessary to make architecture easier for people to understand. If you feel that it is too big, it is a matter of scale, and make it a scale that is friendly to people. An affinity scale is, for example, placed in a place where a person touches a feeling of size created from a person's scale and where a person often sees it. It is also effective when you want to make the interior look good.
形から動きを表現することは建築の場合、スケール的に大きくなるので、全体のスケールと部分のスケールと2種類のスケールを設けて、部分のスケール、それは人のスケールと言い換えてもいいが、に動きが誘発される形を施すのがいいだろう。
スケールは細部に宿るともいわれるが、スケールは作者が自由に設定できるもののひとつであり、もちろんそこに優劣は存在するが、上手くスケールを使えばそれだけで人を魅了できる。
スケールに形を施すとは、形が先にあるのではなくて、スケール感が先にあり、スケール感に沿うように形をつくることであり、スケールを上手く設定できれば形から動きを表現しやすくなる。
"Shaping the scale"
In the case of architecture, expressing movement from shape is large in scale, so we have two types of scales, the overall scale and the partial scale, which can be rephrased as the partial scale, which is the human scale. It would be nice to give it a movement-inducing form.
It is said that the scale is in the details, but the scale is one of the things that the author can set freely, and of course there are superiority and inferiority, but if you use the scale well, you can attract people by itself.
To give a shape to a scale means to create a shape that has a sense of scale first and that fits the sense of scale, not the shape first.If the scale can be set well, it will be easier to express movement from the shape. Become.
不安定で均衡の取れていないものが安定して均衡が取れている状態になろうとして動きが生じることは、力学的にあることであり、人の意識の中でも起こり得ることであり、むしろ目には見えないかもしれない人の意識の中で起こることの方が様々なイメージの決起になりやすい。
不安定で均衡が取れないから安定して均衡が取れる状態になることは形として建築的な解釈ができる。そもそも形自体が美学的には動きのある時点を捉えなたものとされている。
形に対して意識的になることで「動き」が表現できる。形しだいでその「動き」をコントロールできる。形にもっと注視して、形の生成から「動き」をつくり出そうと考えている。
"Move from shape"
It is mechanical, it can happen in human consciousness, rather it is an eye, that an unstable and unbalanced thing moves in an attempt to become a stable and balanced state. What happens in the consciousness of a person who may not be visible is more likely to cause various images.
Since it is unstable and unbalanced, it can be architecturally interpreted as a form of stable equilibrium. In the first place, the shape itself is aesthetically considered to capture a certain point of movement.
"Movement" can be expressed by becoming conscious of the shape. You can control the "movement" depending on the shape. I will pay more attention to the shape and try to create "movement" from the generation of the shape.
建築を意識の中で動かすことを考えている。人が影響を与え建築が動く。建築が可動するには物理的な限界があるので、建築が動いたように思わせるためには、ここでの動きには言葉上で「変化する」も同義と考え、建築が変化したように思わせるにはどうしたらいいのかを考えている。
岡倉天心が『茶の本』で茶室の不完全性を説いた。茶室は、茶事ごとに亭主が設えをするために、普段は設えが無い不完全な状態である。茶室は不完全な状態から茶事での完全な状態へ変化する建築ともいえる。この場合、亭主が設えを加わることで建築が変化するので、人が影響を与え建築が動くことに相当すると考えた。
「不完全性」は動く建築を考える時のキーワードのひとつになり得るし、不完全性が動きを誘発する。
"Induction of imperfections"
I am thinking of moving architecture in my consciousness. People influence and architecture moves. Since there is a physical limit to the movement of architecture, in order to make it seem that the architecture has moved, the movement here is synonymous with "changing", as if the architecture had changed. I'm thinking about how to make it remind me.
Tenshin Okakura explained the imperfections of the tea room in "The Book of Tea". The tea room is in an incomplete state, which is usually not set up because the owner sets it up for each tea ceremony. It can be said that the tea room is an architecture that changes from an incomplete state to a perfect state in the tea ceremony. In this case, the architecture changes when the owner adds the setting, so I thought that it was equivalent to the influence of people and the movement of the architecture.
"Imperfections" can be one of the keywords when thinking about moving architecture, and imperfections induce movement.
建築が不動であることは当たり前であり、不動を前提として様々なことが行われる。時々、もし建築が動けばどうなるかと考えることがある。
動きにもいろいろとあるだろうが、例えば、建築全体を持ってクルクルと回すことができれば、どうなるだろうか。建築の向きを簡単に変えることができるから、冬には常に南に大きな窓を向けて日射を取り入れて室温を上げたり、夏には常に北に大きな窓を向けて日射をなるべく取り入れないで室温が上がるのを抑えたりなどでき環境面で役立つことがはできる。
他にも動くことでできることはあるだろう。よく可動間仕切りを室内に設置することがある。間仕切りをいろいろと動かして部屋の広さを調整するものだが、これも建築が動くことの一種ではあるが、物理的に動く建築はどうしてもこの程度が限界だろう。
物理的に動く以外の動きがあるのかといえば、意識の中で動かすことも可能だろうとは考えている。
"From immovable to moving architecture"
It is natural that architecture is immovable, and various things are done on the premise of immobility. From time to time, I wonder what would happen if the architecture moved.
There will be various movements, but what if, for example, you can take the entire building and rotate it around? Since the direction of the building can be easily changed, in winter, the large windows are always directed to the south to take in sunlight to raise the room temperature, and in summer, the large windows are always directed to the north to take in as little sunlight as possible. It can be useful in terms of the environment by suppressing the rise of the temperature.
There are other things you can do by moving. Movable partitions are often installed indoors. The size of the room is adjusted by moving the partitions in various ways. This is also a type of movement of architecture, but this is the limit for physically moving architecture.
Speaking of movements other than physical movements, I think it is possible to move them in consciousness.
人が持つ何が建築に影響を与えるのだろうか。いくつか考えられるが、これだと決めればよいのだろう。直接的に建築との関係性がわからなくても、つなぐ何かを考えることがまだ見ぬ空間につながる。
やはり形がないものがいい、建築は形があるから、その形に影響を与えるものとして、形がないもの方が解釈しだいでいろいろな展開ができそうだ。
「気分屋」はあまりいい意味では使われないが、「気分」という言葉の持つイメージは悪くなく、誰でも持ち合わせているものなので一般解につながりやすく、「気分」を建築で扱うことをきいたことがない。
"Let's feel"
What influences human beings on architecture? There are several possibilities, but I wonder if this is the case. Even if you don't know the direct relationship with architecture, thinking about something to connect leads to a space you haven't seen yet.
After all, it is better to have no shape, and since architecture has a shape, it seems that the one without a shape can develop various things depending on the interpretation as something that affects the shape.
"Mood shop" is not used in a very good sense, but the image of the word "mood" is not bad, and since everyone has it, it is easy to connect to a general solution, and I heard that "mood" is treated in architecture. Never.
物だけで成り立つ建築も人だけで成り立つ建築もいいのだが不自然であり、物と人の関係性から成り立つ建築が自然である。人を内包してはじめて建築と呼べるので、建築が人に影響を与える、人が建築に影響を与える、人と建築が相互に影響を与え合う、これらの状態がしっくりくる。
建築と人の関係性で考えれば、建築の全ての形に人との関係性を持たせることができ、双方が影響し合うが、主に人が建築に影響を与えることを考えてみたい。建築が人に影響を与えることはよくあることで、建築を見て感動するのが一番端的であり、その時は物主体で建築を考えることができ、構築的に建築を扱えるので誰でも取り掛かりやすいだろう。
人が建築に影響を与える場合は、人が持つ何かが建築に影響を与えると考えられるので、その何かを定めるところからはじめる。
"People influence architecture"
Architecture that consists only of things and architecture that consists only of people are good, but it is unnatural, and architecture that consists of the relationship between things and people is natural. Since it can be called architecture only when it includes people, these conditions, in which architecture influences people, people influence architecture, and people and architecture influence each other, fit perfectly.
Considering the relationship between architecture and people, it is possible to have relationships with people in all forms of architecture, and both influence each other, but I would like to consider that people mainly influence architecture. It is common for architecture to affect people, and it is most straightforward to be impressed by seeing it. At that time, anyone can start thinking about architecture based on things and can handle architecture constructively. It will be easy.
When a person influences architecture, something that the person has is considered to affect architecture, so start by defining something.
建築は人を内包するから、全ての形に人との関係性を持たせることができる。だから、スケール感の違いを表現するために目でみえるようにした形も人との関係性で決めることができる。
スケール感の違いを形にした連続的な連なりで領域を表現でき、その領域は「空間」と言い換えることは可能だから、人との関係性が空間を決める。
"Relationship with people determines space"
Since architecture involves people, all forms can have relationships with people. Therefore, the shape that is visible to express the difference in scale can also be determined by the relationship with people.
An area can be expressed by a continuous sequence of different scales, and that area can be rephrased as "space", so the relationship with people determines the space.
目で見えるように与えた形がスケール感の違いを表現し、その形の連続が領域をつくり、空間をつくるならば、形を与える段階で、様々な作用が考えられる。
人がスケール感を感じ、その違いを感じ、そこに領域を見出すならば、与えた形も人との関係性の中で考えた方が自然で、人の状態の変化と形が呼応したら、まさにそれは人を内包することが特徴の建築にしかできないことだろう。
"People's changes and shapes respond"
If the shape given to the eye expresses the difference in the sense of scale, and the continuity of the shape creates an area and a space, various actions can be considered at the stage of giving the shape.
If a person feels a sense of scale, feels the difference, and finds an area there, it is more natural to think about the given shape in relation to the person, and if the change in the person's state and the shape correspond, Exactly that can only be done in architecture that is characterized by the inclusion of people.
スケール感の違いを意図的につくり出す。例えば、2つのスケール感を存在させ、明確に違いがわかるように、2つのスケール感を接して配置する。2つのスケール感を目で見えるようにするために形を与え、形がスケール感の違いを表現し、その形が連続することにより、スケール感の違いが境界となりスケール毎の領域が決まり、形の連続が他の役目を纏い、建築としての機能を担保する。
領域はスケール感が形になったものの連続でによって決まるので、形が領域すなわち空間を決める。
"Shape determines space"
Intentionally create a difference in scale. For example, two scale feelings exist, and the two scale feelings are placed in contact with each other so that the difference can be clearly seen. A shape is given to make the two scale feelings visible, and the shape expresses the difference in scale feeling, and by continuing the shapes, the difference in scale feeling becomes the boundary and the area for each scale is determined, and the shape The continuation of the above takes on other roles and secures the function as an architecture.
Since the area is determined by the continuity of the scale feeling, the shape determines the area, that is, the space.
スケール感は字義通り感覚なので目には見えないが、スケール感の違いは見た目の違いによって表現できる。注目をしているのはスケール感の違う物同士の接点であり、それは接線となるかもしれないが、そこにはスケール感の違いが感覚的にあり、その感覚は違和感であり、その違和感のつながりが境界となっていて、そのスケール感の違いの連なりも見た目に表現されており、その境界で囲まれた部分はひとつの領域として認識されることになる。
つまり、スケールがひとつの領域をつくり出す。そこには壁は無く、見た目にはつながっており、しかし、感覚的には境界がはっきりとあるのがわかる状態をつくり出せる。
そうすると、どのようなスケールをつくり出すかが、どのような領域をつくるかにつながり、壁をつくることが領域、それを空間と言い換えることができると考えてるので、空間を決めることにならない。
"The wall does not determine the space"
The sense of scale is literally invisible to the eye, but the difference in sense of scale can be expressed by the difference in appearance. What we are paying attention to is the point of contact between objects with different scale feelings, which may be tangent, but there is a sensuous difference in scale feeling, and that feeling is strange, and that feeling of strangeness. The connection is a boundary, and the series of differences in the sense of scale is also visually expressed, and the part surrounded by the boundary is recognized as one area.
In other words, the scale creates one area. There are no walls there, they are visually connected, but you can create a state where you can feel the boundaries clearly.
Then, what kind of scale is created leads to what kind of area is created, and I think that creating a wall can be rephrased as an area, which can be rephrased as a space, so the space is not decided.
建築は物だから物としてどうあるべきかが問われる。物として美的にどうなのか、物として社会の中でどのような位置づけになるのか、物として思考の中でどのような解釈になるのか、物として自然環境の中でどうあるべき、などなど建築以外の物と同じように様々な側面を持ち合わせていて、建築をつくる時には、その中から何を選択するかというよりは、何に重点を置くか、全ては万遍なく必要でどれかだけというのでは不完全な物になるので、バランスよくだだ比重を変えて大事な所を強調する。
どうしても切っても切れない、建築は人が中にいる物、という想いがある。これは建築以外の物とは違うことであり、建築にとっての一番の特徴であり、建築たる所以であり、人がいなければ工作物である。
人がいるということは、人は感情を持ち合わせているので、その感情と建築との関わり合いが生まれる。物としての建築では、この人の感情との関わりが無いものとされる。それは不自然だと考えるので、人の感情と建築の関係性を大事にし強調することを目論む。
"Aiming for a relationship with emotions"
Since architecture is a thing, what it should be as a thing is asked. Other than architecture, such as what it is aesthetically as a thing, what kind of position it is in society as a thing, what kind of interpretation it is in thinking as a thing, what it should be in the natural environment as a thing, etc. It has various aspects like the ones in the world, and when building an architecture, what to focus on rather than what to choose from them, everything is necessary and only how much. Then, it becomes an imperfect object, so change the specific gravity in a well-balanced manner to emphasize the important points.
There is a feeling that architecture is something that people are inside, which cannot be cut by any means. This is different from non-architectural objects, and it is the most characteristic feature of architecture, the reason for architecture, and it is a work without people.
When there is a person, people have emotions, and the relationship between those emotions and architecture is born. In architecture as a thing, it is assumed that there is no relation to this person's emotions. I think it is unnatural, so I aim to cherish and emphasize the relationship between human emotions and architecture.
細長い敷地、周りも更地、連続した空地、私鉄の高架化に伴う立ち退きでできた地形に小さな建築を挿入する。
単一用途、1室空間、平屋で小さい、もはや地形に屋根を架けるだけで成立するのではないかとさえ考えてしまう。全てが手に取れる、手が届く、手に収まる大きさである。
規模が大きなると、あれやこれやと様々な試みが可能なような気がして、規模が小さくなると、制約ばかりに目が行き、様々な試みが不可能のような気がする。
実際は小さいからできることがたくさんあるのだが、そのためには的を絞る必要があり、あれやこれやでは無く、確信的なひとつのことに収斂させる。
"Target"
Insert a small building into a long and narrow site, surrounding vacant lots, continuous open spaces, and terrain created by eviction due to the elevation of private railways.
It's a single purpose, one room space, a small one-story building, and I even wonder if it can be achieved simply by putting a roof on the terrain. Everything is accessible, accessible, and fitable.
When the scale is large, I feel that various attempts are possible, and when the scale is small, I feel that various attempts are impossible because of the restrictions.
In reality, there are many things that can be done because it is small, but to do so, it is necessary to focus on one thing that is convincing, not this or that.
もしも建築がぐにゃぐにゃと動くならば、その日の気分に合わせて動かしたいと思う。変身ロボのように戦況によって形を変えるようなことができれば楽しいだろう。
ぐにゃぐにゃに見える建築はかつて一時期だけ流行った。まるで地震で崩れかかっているような外観の建築、そのような建築をデ・コンストラクティブ、脱構築主義建築と呼んで、崩れ行く動きを一瞬止めたような外観の建築だった。
建築は動かないのが大前提だから、そこに動きを求めることにより、新たな空間を創出しようとする試みはモダニズムの初期からあり、現代でも有効なアプローチであり、建築のスケールを操作することに動きと領域をつくり出したいと考えている。
"In search of movement in architecture"
If the architecture moves squishy, I want to move it according to the mood of the day. It would be fun if we could change the shape depending on the battle situation like a transformation robot.
Architecture that looks squishy was once popular for a period of time. The appearance of the building was about to collapse due to an earthquake, and such a building was called deconstructivist or deconstructivist architecture, and the appearance of the building stopped the collapse for a moment ..
Since it is a major premise that architecture does not move, attempts to create a new space by seeking movement there have been from the early days of modernism, and it is an effective approach even in modern times, to manipulate the scale of architecture. want to create movement and territory.
気分の良い時と悪い時で見える世界が違うことはよく経験するだろう。気分が良ければ意味もなく空を見上げたりして、その空を隅々まで見たり、周りの景色が自然と目に飛び込んできて、いろんなことに気づいたりするが、気分の悪い時は同じものを見ていたとしても何も気づかない、それどころか、かえって周りから悪い影響を受けてしまう。
気分や感情が自分を取り巻く環境を変えてしまう。実際は何も変わらないのだが、気分や感情が自分を取り巻く環境の解釈や受け取り方を決めてしまう。
建築が物としてのみ存在するならば、気分や感情は全く関係なく、いつでも同じであるが、人が使うものとして建築が存在するならば、気分や感情で建築の解釈や受け取り方が変わるのは自然なことである。
建築の解釈や受け取り方が変わるということは、すなわち先にも触れたように、建築自体は物としてだけ存在していても良く、あとは建築を解釈する側や受け取る側の問題とすることは可能だから、今まで建築で気分や感情を直に扱うことは稀だった。
もし仮に人が使う物としての建築を重視するとなると、気分や感情を無視できず、気分や感情を解釈や受け取り方の発露にだけに留めておくには無理があり、気分や感情によって建築の見え方自体が変わるようにするのが自然だと考えた。
"Depends on mood and emotion"
You will often experience the difference in the world you see when you feel good and when you feel bad. If you feel good, you can look up at the sky for no reason, look at every corner of the sky, and the scenery around you naturally jumps into your eyes and notices various things, but when you feel sick, the same thing Even if I look at it, I don't notice anything, and on the contrary, I get a bad influence from the people around me.
Moods and emotions change the environment around you. In reality, nothing changes, but moods and emotions determine how to interpret and receive the environment surrounding you.
If architecture exists only as an object, it is always the same regardless of mood or emotion, but if architecture exists as something that people use, mood or emotion changes the interpretation or reception of architecture. It's natural.
The change in the interpretation and reception of architecture means that, as mentioned earlier, the architecture itself may exist only as an object, and the rest is a matter for the interpreter and recipient of the architecture. Until now, it has been rare for architecture to deal directly with moods and emotions because it is possible.
If we focus on architecture as something that people use, we cannot ignore moods and emotions, and it is impossible to keep moods and emotions only in the interpretation and manifestation of how we receive them. I thought it was natural to change the way it looks.
スケールで建築を考えれば、まず都市のスケールの中に建築のスケールが存在し、都市と建築のスケール同士は異質なので、水面にできる波紋のように都市の中に建築の領域が現れる。
領域を目で見える形にするために建築の外皮が存在し、外皮がスケールを感じさせてくれるが、仮に外皮を剥ぎ取ったとしても中身がスケールを表現する。
外皮が無い建築をなかなか見たことはないが、もし外皮が無い、あるいは外皮が無いように見せることができれば、建築の見え方としては新しいかもしれない。
外皮が無い建築とは中身がそのまま都市に剥き出しになっている状態であり、そのままで成立すれば中身と都市が直結することになり、外皮が無いことよりも建築として面白い。
"The contents are exposed"
If you think about architecture on a scale, first of all, the scale of architecture exists in the scale of the city, and since the scales of the city and the architecture are different, the area of architecture appears in the city like ripples on the surface of the water.
The exodermis of the building exists to make the area visible, and the exodermis makes you feel the scale, but even if the exodermis is peeled off, the contents express the scale.
I haven't seen architecture without exodermis, but if it can be seen as having no exodermis or without exodermis, it may be a new way of looking at architecture.
Architecture without an exodermis is a state in which the contents are exposed to the city as it is, and if it is established as it is, the contents and the city will be directly connected, which is more interesting as an architecture than without an exodermis.
スケールが連続的に変化する建築をつくろうとすると、一番単純なやり方は斜めの線を入れることであり、その斜めの線を壁や床、天井で使う。それはとてもわかりやすい、目で見てすぐわかる変化であり、形においても斜めの線はデザイン性を高めるためにも有効でなのでよくある手法だが、斜めによるスケールの連続的な変化は単調になりやすく、似たような体験や感覚は普通の階段でもできる場合があるので、結果的にデザイン性のみが特徴として残る。
斜めを用いてスケールを連続的に変化させるならば、途中でスケールの変化量を変えてみるか、スケールの変化を一度断絶させてみると単調さを回避でき、変化量の変え方や断絶の仕方は建築のプランと上手く呼応させやすいので、そこに建築的な特徴も持たせることができる。
なぜスケールの連続的な変化を必要とするかというと、スケールの連続的変化が生み出す目には見えないが、意識として感じとることができる隔たりのようなをものをつくりたいからであり、その隔たりの連続が領域として空間を感じさせる。
"Distance due to continuous changes in scale"
When trying to create an architecture with continuously changing scale, the simplest way is to put diagonal lines and use those diagonal lines on walls, floors, and ceilings. It is a very easy-to-understand, visually recognizable change, and it is a common technique because diagonal lines are also effective for improving design, but continuous changes in scale due to diagonal tend to be monotonous. Similar experiences and sensations can sometimes be achieved on ordinary stairs, and as a result, only design remains a feature.
If you change the scale continuously using diagonal, you can avoid monotony by changing the amount of change of the scale in the middle or by cutting off the change of the scale once, and how to change the amount of change and the disconnection Since the method is easy to correspond well with the architectural plan, it can also have architectural characteristics.
The reason why continuous change of scale is necessary is that we want to create something like a gap that is invisible to the eye but can be felt as consciousness, and that gap. The continuation of is made to feel the space as an area.
スケールと領域について考えているのは、素材と形、機能と形態という関係性とは別のところで建築を考えて、建築に素材や機能の要素を持ち込むことを極力少なくして、今までとは違った見え方をする建築ができる上がる可能性を高めるためである。
どうしても素材がまず思い浮かび、コンクリート打放しやスチールや木など、それで既視感が無い建築を考えるのもひとつの方法だが、どうしても必要される機能をまず考えてしまい、建築は人が使う物だから、人の使い方を機能であらかじめ設定するのもひとつの方法だが、素材と機能を建築の創作の発露にすること自体に可能性を感じられない。
スケールと領域の組合せでは各々明確な実体はなく、設定しだいで変化する曖昧さを持ち合わせていて、それが建築の輪郭や構造から細部形態まで決めることになれば、今までとは違った見え方で、少なくとも形は変わり、建築が立ち上がるかもしれない。
"Exposure other than materials and functions"
I'm thinking about scale and domain, thinking about architecture in a place other than the relationship between material and shape, function and form, and bringing materials and functional elements into architecture as little as possible. This is to increase the possibility of building a building that looks different.
One way is to think of an architecture that doesn't have a sense of déjà vu, such as exposed concrete, steel, or wood, because the material comes to mind first, but the functions that are absolutely necessary are first considered, and architecture is something that people use. One method is to preset how people use it with functions, but I don't feel the possibility of using materials and functions as a manifestation of architectural creation.
There is no clear substance in each combination of scale and area, and it has ambiguity that changes depending on the setting, and if it decides from the outline and structure of the architecture to the detailed form, it will look different from the past. So, at least the shape may change and the architecture may stand up.
領域は意識の中で存在し、スケールは感じ取るものであるならば感覚の中で存在し、ともに目には見えないが、領域もスケールも建築という物を通して目に見えるようにできる。
スケールは物が纏い、そのスケールの変わり目が領域をなぞることになる、それは複数のスケールが重なり合い同時に存在することで可能になる。
物がそこに成り立ち存在する理由は様々だが、物が纏うスケールが存在を決める、あるいは物同士のスケールの関係性が存在を決めることはでき、その時、スケールを表現する物の形は機能の影響を受けず、またスケールの変わり目が示す領域も機能の影響を受けない。
"Area, scale and function"
Areas exist in consciousness, scales exist in sensations if they are perceived, and both are invisible, but both areas and scales can be made visible through architecture.
A scale is made up of objects, and the transition of the scale traces an area, which is possible when multiple scales overlap and exist at the same time.
There are various reasons why an object exists there, but the scale that an object wears determines its existence, or the relationship between the scales of objects determines its existence. At that time, the shape of the object that expresses the scale is influenced by its function. It is not affected, and the area indicated by the scale transition is not affected by the function.
中間にいてどちらにでもなるような状態が面白いと思い、それを建築としてプランに落とし込むと、様々な領域が重なり合っているような空間になる。
領域とは、壁などの仕切りがあり境界がはっきりとした状態というよりは、もっと曖昧で仕切りの壁が見えなくてもよく、意識の中で境界が存在しているような状態だが、プランでそれを表現するのは難しく、どうしても仕切りがないと領域とみなせない。
そうすると、領域を他の方法で表現する必要が出てくる。他の方法とはスケールである。領域の違いをスケールの違いで表現し、プラン上で様々な領域が重なり合っているような空間は様々なスケールが同時に存在し、より複雑なスケールになっていく。
"The difference in scale is the difference in area"
I think it's interesting to be in the middle and be in either direction, and when I put it into a plan as an architecture, it becomes a space where various areas overlap.
An area is not a state where there is a partition such as a wall and the boundary is clear, but it is a state where it is more ambiguous and the partition wall does not have to be seen, and the boundary exists in consciousness, but in the plan It is difficult to express it, and it cannot be regarded as an area without a partition.
Then, the area needs to be represented in other ways. The other method is scale. The difference in the area is expressed by the difference in the scale, and in the space where various areas overlap on the plan, various scales exist at the same time, and the scale becomes more complicated.
素材それ自体は形を持たないから、スケールもない。素材に形を与えることを「ものづくり」というが、建築でも家具でも陶磁器でも何でも皆それは同じだろう、そうすると「ものづくり」とは素材にスケールを与えることともいえる。
素材がスケールを持つことは、そこに人との関係性が生まれることである。素材が形を持てばスケールを纏うが、そのスケールを認識するのは人であるから、形になっただけでそこに人がいなければ、スケールも存在しないことになる。
そうすると、素材と人がいてはじめてスケールが生まれ、そのスケールは素材が形を纏った時にわかり、その形をつくるのは人である、という相互に密接な関係性があることがわかる。
"Materials, people and scales"
Since the material itself has no shape, there is no scale. Giving shape to a material is called "manufacturing," but it is the same for architecture, furniture, and ceramics, so it can be said that "manufacturing" gives a scale to a material.
When a material has a scale, it creates a relationship with people. If the material has a shape, it wears a scale, but since it is the person who recognizes the scale, if there is no person there, the scale does not exist.
Then, the scale is born only when there is a material and a person, and the scale is known when the material takes a shape, and it is understood that the person who makes the shape has a close relationship with each other.
建築が内包しているものは人、素材、時間、スケール、空間などがあるが、それは単体だけでなく、相互に関係し合いながら存在している。人も建築の中では素材やスケール、時間などと同じ扱いになり、建築が成立するための要素のひとつである。
建築が内包しているものはたくさんあるが、ただたくさんあるだけではもちろん意味がなく、相互の関係性を操作することで、どのような建築にするのが決まる。
目で見てわかりやすいのは素材であり、その素材が経年変化を起こせば、そこで時間を表現でき、素材が形を持てば、そこでスケールが生まれ、その形で人との関係性を表現でき、それは空間の構成要素となる。
様々な関係性を内包する建築にはまたまだできそうなことがたくさんある。
"Including relationships"
What architecture contains is people, materials, time, scale, space, etc., but they exist not only alone but also in relation to each other. People are treated the same as materials, scales, and time in architecture, and are one of the factors for building to be established.
There are many things that architecture contains, but of course there is no point in just having many, and by manipulating the mutual relationships, what kind of architecture will be decided.
What is easy to understand with the eyes is the material, and if the material changes over time, time can be expressed there, and if the material has a shape, a scale is born there, and the relationship with people can be expressed in that form. It becomes a component of space.
There are still many things that can be done in architecture that involves various relationships.
遥かに大きい建築のスケールの中に人と同じくらいのスケールが内在している。人と同じ位のスケールはひとつではなくて、いくつものスケールが混在している。この場合のスケールの違いは物で表現され、人がそこにいることで違いがわかる。
スケール感は人がそこにいることによって感じられることだが、当然人がいなくても物はスケールを纏う。スケールが適切ならば物として建築として人に良く見え、それだけで完成度が高くなる。
たくさん混在している人と同じ位のスケールをまとめるのは遥かに大きい建築のスケールであるが、人と建築のスケールの差が大きければ、間にもうひとつの違うスケールを挟み込む余地が生まれ、その間に生まれるスケールの扱いによって規模の大きな建築の成否が決まる。
"Scale born in between"
There is a scale as large as a human being in a much larger architectural scale. There is not one scale as much as a person, but several scales are mixed. The difference in scale in this case is expressed by an object, and the difference can be seen when a person is there.
The feeling of scale is felt by the presence of people, but of course things wear scale even if there are no people. If the scale is appropriate, it will look good to people as an architecture as an object, and that alone will increase the degree of perfection.
It is a much larger architectural scale to put together the same scale as a lot of mixed people, but if the difference between the human and architectural scales is large, there is room to put another different scale in between. The success or failure of a large-scale building is determined by the treatment of the scale that is born in.
人より遥かに大きいスケールの建築があり、建築は人と同じくらいのスケールを内包し、人は建築に内包された同じくらいのスケールとだけ対峙できる。遥かに大きいスケールは感じ取ることしかできず、同じくらいのスケールから想像するしかなく、建築のスケールは人と同じくらいから遥かに大きいものまで連続的に変化していることが前提になる。
もし連続的に変化せずに、断絶したり、不連続に変化をしたら、どうなるのだろうか、感じ取り方が変わるのだろうか。
建築において人がいることが前提ならば、スケールの操作だけで違う建築になるかもしれない。
"Scale operation"
There are buildings on a much larger scale than humans, and architecture contains the same scale as humans, and humans can only confront the same scale contained in architecture. A much larger scale can only be perceived and can only be imagined from a similar scale, assuming that the architectural scale is continuously changing from about the same size as a person to much larger.
What will happen if there is a break or a discontinuous change without continuous change, and will the way of feeling change?
If it is assumed that there are people in the architecture, it may be a different architecture just by operating the scale.
感情や気持ちに居場所を与えるようなことを考えている。建築があって物としては成立し、それで過不足なく、人と建築の関係性から人を中心に考えることでも建築は成立し、それでも過不足はない。
もっと細分化して物としての建築にも素材から考えるのか、形から考えるのか、さらに表層の仕上げに特化するのか、あと見え方も物の範疇になる。
人を中心にすれば、建築は物本来の在り方を変えて人に内在する尺度で考えられる。例えば、ただそこにある建築に対して「美しい建築」と人の判断が加われば、その判断を前提に建築を考えはじめることになり、もはやただそこにある建築ではなくなるというように、人がいることで建築の在り方が決まっていく。
感情や気持ちは人が抱くものであるから、人を中心に考えて判断していく建築の在り方の範疇になるが、人の思考は感情や気持ちに左右されるので、思考より先に抱く感情や気持ちだけを先に露わにして取り出すことは可能だと考え、感情や気持ちだけを独立させて、感情や気持ちが建築と直接関係性を築くような居場所を与えてやることができれば、より建築が身近な存在になり、建築という物が消費される財からストックされる財に変わっていくキッカケにならないかと考えている。
"From consumption to stock"
I'm thinking of giving a place to my emotions and feelings. There is architecture and it is established as a thing, so there is no excess or deficiency, and architecture is established by thinking mainly about people from the relationship between people and architecture, but there is still no excess or deficiency.
Whether to think more subdivided into architecture as a thing from the material, from the shape, or to specialize in the finishing of the surface layer, the appearance also falls into the category of things.
If we focus on people, architecture can be thought of as a scale that is inherent in people by changing the way things are originally. For example, if a person's judgment is added to the architecture that is there, it will start to think about the architecture based on that judgment, and there are people who are no longer just the architecture that is there. This will determine the way architecture should be.
Since emotions and feelings are things that people have, they fall into the category of architecture that thinks and makes decisions centered on people, but since people's thoughts are influenced by emotions and feelings, emotions that they hold before thinking. I think that it is possible to expose only the feelings and feelings first, and if it is possible to make only the feelings and feelings independent and give a place where the feelings and feelings have a direct relationship with architecture, it will be better. I am wondering if architecture will become a familiar presence, and it will be a chance for architecture to change from consumed goods to stocked goods.
買った服はそのまま着られないそうで、仕立てる場合を除き、そもそも服がピッタリと自分のサイズに合うわけがないので、SMLなどのサイズに全ての人が振り分けられる訳がないから、自分のサイズに合わせるために様々な方法で「着こなし」をするのだそうだ。
普段の食事にしても、外食でも、自分の好みに味を自ら調整することはあり、出された物をそのまま食べる機会の方が少ないかもしれない。中には元の味がわからなくなるぐらいに自分好みに味を調整する人もいて「着こなし」ならぬ「味こなし」をしている。
衣食ときたので、次は住だが、住まいでも「着こなし」にあたることは「住みこなし」だろう。住まいを自分たちの生活の中に違和感なく取り入れるには、特に新しく建てた時などは、私物を広げることだ。今まで使っていた私物が違和感なく収まるように位置を変えたり、置く物を変えたり、そうしているうちに住まいが自分たちのものになっていく。
それに対して建築家は、どのような私物が持ち込まれても負けないくらいの強い強度を持った空間をつくるか、柔軟に何でも受け入れてしまうことによって強度が増していく空間をつくるか、いずれにせよ私物に空間の良し悪しを左右されないようにするだろう。
"Living"
It seems that you can't wear the clothes you bought as they are, and unless you're tailoring them, the clothes don't fit your size exactly, so there's no way everyone can be assigned to a size such as SML, so your size. It is said that they "dress" in various ways to match the situation.
Whether it's a regular meal or eating out, you may adjust the taste to your liking, and you may have less chance to eat what you serve. Some people adjust the taste to their liking so that they don't understand the original taste, and they are doing "taste" instead of "dressing".
Since I was eating clothes, I will live next time, but even if I live, it would be "living" to be "dressing". In order to incorporate a home into our lives without any discomfort, we need to expand our personal belongings, especially when we build a new one. You can change the position of your personal belongings so that they fit comfortably, change the things you put on them, and while doing so, your home will become your own.
Architects, on the other hand, either create a space that is strong enough to withstand whatever personal belongings are brought in, or create a space that increases in strength by flexibly accepting anything. At any rate, personal belongings will not affect the quality of the space.
2つの正反対のものを比較しながら進む考え方は一般的で、その間をつなぐものに興味があるのだが、はじめからつなぐものを露わにすることはできないので、まず2つのものを用意する。
できれば正反対の2つのものが良く、その方が間をつなぐもののバリエーションも増える。つなぐものは1つとは限らず、たくさんのバリエーションがある。
自分に合わなければ変えることができ、必ず自分に合うもの、つなぐものがある。様々なバリエーションがたくさんの人をつなぐものに巻き込む。そうすることで重層的につなぐものが成り立つ。
建築に例えると、人と人を内包する建築があり、その間をつなぐものが空間に様々なバリエーションとして存在しており、その時、その状態に応じて人がつなぐものを選択することにより、人と建築の関係性が決まるようなことである。
"Connecting things"
The general idea is to compare two opposites and proceed, and I'm interested in what connects them, but I can't reveal what connects from the beginning, so I'll prepare two first.
If possible, the two opposites are good, and the variation of the one that connects them will increase. There is not only one thing to connect, but there are many variations.
If it doesn't suit you, you can change it, and there are always things that suit you and things that connect. Various variations involve many people in what connects them. By doing so, a multi-layered connection is established.
If you compare it to architecture, there is an architecture that contains people, and there are various variations in the space that connect between them. At that time, by selecting the one that connects people according to the state, It's like determining the relationship between architecture.
スケールという言葉は実に曖昧である。スケールの良し悪しという価値判断があり、スケールという言葉は本来数値に置き換えられるはずだが、良いスケール、悪いスケールに数値の基準はなく、感覚的なのだ。
誰か、例えば、高名な建築家が「スケールが良い」と言えば、そういうものかと納得せざるを得ないが、感覚的なスケールの良し悪しは確かに存在するので余計に困るし、感覚的なのでスケールの良し悪しを言葉で表現するのも難しい。
スケールの曖昧さを良いことと捉えるならば、建築を見る人、体験する人が感覚的に違う受け取り方をするようにできる可能性があることかもしれない。スケールが感覚的なものであるが故に人それぞれ固有のスケール感覚を持ち合わせていると考えられるので、建築に様々なスケールを仕込むことにより、人によって違う建築の見え方、感じ方ができるようになる。
"Good scale ambiguity"
The word scale is really ambiguous. There is a value judgment that the scale is good or bad, and the word scale should be replaced with a numerical value, but there is no numerical standard for good scale and bad scale, and it is sensuous.
If someone, for example, a well-known architect says "the scale is good", I have to convince them that it is, but there are certainly good and bad sensuous scales, so it is more troublesome and sensuous. Therefore, it is difficult to express the quality of scale in words.
If we take the ambiguity of scale as a good thing, it may be possible to make people who see and experience architecture perceive it differently. Since the scale is sensuous, it is thought that each person has a unique sense of scale, so by adding various scales to the architecture, it becomes possible for each person to see and feel the architecture differently. ..
建築が成り立つスケールは、骨組みであり、人を内包するためにあり、人のスケールと同じにはならず、人のスケールより大きくなる。
人のスケールは人の身体性の延長になるようなスケールであり、建築のスケールから切り離して独立して存在させることもできる。
建築として人を内包することは、人のスケールを内包することであり、建築の中に人のスケールで建築がある状況をつくり出し、その断面をファサードとして見せることにより2つのスケールが共存し、2つのスケールをつなぐ物で空間が満たされている様がわかり、つなぐ物の変化が空間の多様性を生み、建築と人の関係性に複雑性を加える。
"Show as a cross section"
The scale on which architecture is built is a skeleton, to contain people, not the same as the scale of people, but larger than the scale of people.
The human scale is a scale that is an extension of the human physicality, and can be separated from the architectural scale and exist independently.
Including a person as an architecture is to include a person's scale, creating a situation where the architecture is on the scale of a person in the architecture, and by showing the cross section as a façade, the two scales coexist, 2 It turns out that the space is filled with the objects that connect the two scales, and the changes in the objects create diversity in the space and add complexity to the relationship between architecture and people.
建築の良し悪しは最後はスケールが決めるといつも思う。デザインが良くてもスケールがおかしいと良く見えなく、デザインが普通でもスケールが適正だと良く見えてくる。
人の気分が建築と関係を築くことをスケールの面から考えてみると、建築のスケールは人のスケールよりはるかに大きくなり、人の気分を包括して希薄にして何もないことにしてしまうことがあるので、建築と人のスケールは同じくらいにしたい。
建築の成り立ち、すなわち、建築の骨組みをスケールの面から考えてみると、建築のスケールは人を内包するために人のスケールより大きくならざるを得ない。
したいスケールとならざるを得ないスケールがあり、どちらかに寄せることができないとしたら、2つのスケールが同時に存在することになり、2つのスケールをどのように扱うかが大事になり、さらに、この2つのスケールをつなぐものが存在するのではないかと考える。
"Two scales"
I always think that the scale decides the quality of architecture at the end. Even if the design is good, it does not look good if the scale is strange, and even if the design is normal, it looks good if the scale is appropriate.
Considering that the mood of a person builds a relationship with architecture, the scale of architecture is much larger than the scale of a person, and the mood of the person is comprehensively diluted and nothing is left. I want to make the scale of architecture and people the same because there are times.
Considering the origin of architecture, that is, the framework of architecture in terms of scale, the scale of architecture must be larger than the scale of human beings in order to include people.
If you have a scale that you have no choice but to move to one of them, then you have two scales at the same time, and how you handle the two scales is important. I think there is something that connects the two scales.
人の感情を建築で扱うことは昔からあり、建築を見ることによって人の気分を高揚させたり、行動につなげたり、様々な感情が建築の着想につながったりしていた。
今考えていることは、人は良くも悪くも感情に左右されることを直にデザインと結びつけることはできないか、気分によって形や見え方が変わらないかということ。
建築は動かないし、簡単には変われないが、気分によってその都度、形や見え方が変わったようになれば、人と建築の関係性がより密接になるのではないかと考えている。
"Depending on your mood"
It has been a long time since people's emotions were treated in architecture, and by seeing architecture, people's moods were raised, they were connected to actions, and various emotions led to the idea of architecture.
What I'm thinking about now is whether people can directly connect emotional influences to design, for better or for worse, and whether their shape and appearance will change depending on their mood.
Architecture doesn't move and doesn't change easily, but I think that if the shape and appearance change each time depending on the mood, the relationship between people and architecture will become closer.
解剖学にも「形態は機能に従う」という言葉があると教えていただいた。臓器の形態が機能に従うことなのだろうか、いずれにしても面白い。
建築は人との関係性で成り立つ部分があり、建築と人が内なる形態と機能、この場合は空間と臓器になるのか、で相同的であるのはそもそもの相性が良いということになる。
「形態は機能に従う」という言葉には少し使い古された感があるが、やはり吸い寄せられ呪縛されるなりの理由があるということだろうか。
"Homology of space and organs"
I was told that anatomy also has the phrase "form follows function." Whether the morphology of the organ follows its function, it is interesting anyway.
Architecture has a part that is made up of relationships with people, and the fact that architecture and people are homologous in terms of their inner form and function, in this case space and organs, is a good match in the first place.
The word "form follows function" seems to be a little worn out, but is there a reason for it to be sucked and cursed?
「形態は機能に従う」という言葉がある。サリヴァンの言葉だが、モダニズムの簡素な形態と相まって、無意識に呪縛の言葉になっている。
ポストモダニズムの後遺症か、意味の無い、意図の無い、付加的な形態には嫌悪感があり、特に意識している訳ではないのだが、「形態は機能に従う」流れに吸い寄せられ、建築計画学も加勢し、形態的には不自由を感じることも多い。
リノベーションにはあまり興味が無かった。0から何かを生み出すことに興味があり、元々ある物に対して手を加えることは創造性に制約が掛かるような気がしていた。先日、学会のシンポジウムでコンバージョンがテーマになっていた。コンバージョンとは機能などを転用することでリノベーションの一種と理解していたので、同じくあまり興味が無かったが、シンポジウムでのたくさんの事例が興味深かった。
コンバージョンの例ですぐに思いつくのがイギリスのテート・モダンであり、発電所を美術館に機能転用したもので、広いタービン室などは大きな美術作品を展示するには最適だろう。前から知ってはいたが、形態は発電所、機能は美術館となり、転用を設定することで「形態は機能に従う」という壁を楽々と越えてしまう。
一度転用を設定してから新しい建築を構想する建築家もいて、「コンバージョン」はエコロジーと結びつき、今の時代の主要なテーマのひとつなのだろうし、形態と機能の関係性を揺さぶる刺激的な言葉である。
"Convert form and function"
There is a word "form follows function". Sullivan's words, combined with the simple form of modernism, are unknowingly cursed.
I have a dislike for the aftereffects of postmodernism, meaningless, unintentional, and additional forms, and although I am not particularly conscious of them, I am attracted to the flow of "forms follow function" and architectural planning. Also, they often feel inconvenient in form.
I wasn't very interested in renovation. I was interested in creating something from scratch, and I felt that modifying something that was originally there would limit my creativity. The other day, conversion was the theme at a symposium of an academic society. I understood that conversion is a kind of renovation by diverting functions, so I was not very interested in it, but many cases at the symposium were interesting.
An example of conversion that immediately comes to mind is the Tate Modern in England, which is a power plant converted into a museum, and a large turbine room is ideal for displaying large works of art. As I knew from before, the form becomes a power plant and the function becomes a museum, and by setting the diversion, it easily overcomes the wall of "form follows function".
Some architects set up a diversion once and then conceive a new architecture, and "conversion" is linked to ecology and is probably one of the main themes of this era, and it is an exciting word that shakes the relationship between form and function. Is.
不完全なものは何かを足すことによって完全なものになるということで創造性を喚起し、完全なものは創造性を喚起しないが完全度の高さが何かを教示する。
ギリシャのパルテノン神殿を見て何だかわからないし、廃墟にしか見えないが、建築的には幾何学の極致で、輪郭と構造と細部の形態は完全なものであり、お手本であるという。お手本とは目指すところであり、いつでも立ち返られるところであり、存在するだけで意味がある。
不完全なものは存在するだけでは何にもならない。何かを足される状況ではじめて意味が出る。建築において何かを足してくれる存在は人しかいないので、人と建築の関係性の中で建築をどうするかと考えるならば、不完全なものにすることには妥当性がある。
不完全なものは完全なものから何かを引いた状態であり、何かを引くという行為はシンプルで必要最小限なものを目指すことにつながるから、ミニマムなものと不完全なものは相性がよさそうだ。
結果としてミニマムなものをつくることは人の創造性を喚起するだろうし、その果てにはパルテノン神殿があり、この一連の流れは時間軸を遡ることになる。時間は未来から過去に流れるとは哲学者のどなたかが唱えていたが、実際の建築行為は時間を遡ることに逆行する。
建築で時間を扱うならば、創造性の時間の流れと実際の建築行為の時間の流れの違いを埋める必要があり、不完全なものと完全なものの相違を考えることが建築の時間性を炙り出してくれて、建築で時間そのものを扱えるようにしてつくれるのだろうが、時間の経過にいまひとつ興味が湧かない理由もわかった。
"How to handle time in architecture"
The imperfect one evokes creativity by adding something to make it perfect, and the perfect one does not evoke creativity but teaches what a perfect fifth is.
Looking at the Parthenon in Greece, I don't know what it is, and it looks like a ruin, but it is architecturally the culmination of geometry, and the outline, structure, and form of details are perfect and model. A model is a goal, a place where you can always return, and it makes sense just to exist.
The existence of imperfections is nothing. It only makes sense when something is added. Since there are only people who can add something in architecture, it is reasonable to make it incomplete when considering what to do with architecture in the relationship between people and architecture.
The imperfect one is the state of pulling something from the perfect one, and the act of pulling something leads to aiming for the simple and minimum necessary, so the minimum and the imperfect are compatible It looks good.
As a result, creating something minimal will arouse human creativity, and at the end is the Parthenon, a series of steps that goes back in time. Some philosophers have argued that time flows from the future to the past, but the actual building practice goes against going back in time.
When dealing with time in architecture, it is necessary to bridge the difference between the flow of time of creativity and the flow of time of actual building act, and thinking about the difference between imperfect and perfect reveals the time of architecture. I think it's possible to make it so that architecture can handle time itself, but I also understand why I'm not interested in the passage of time.
素材のことを考え、仕上げを考えている。装飾的な仕上げには抵抗を感じるので、素材と仕上げが一致するように考える。
素材と仕上げが一致しない例としては、今はあまり見なくなったが、擬木のようなコンクリートやモルタルで木の表面の木目だけを再現したもので、ならば本物の木を使えばよいと思うし、木が使えないのならば無理に木に似せる必要もなく、違うデザインを考えればよいと、そもそも擬木を使うということはコンクリートやモルタルより木目の方がよいと判断しているところがおかしく、素材で優劣をつけることに違和感がある。
仕上げを考える時、素材をどのように扱うか、わざと素材と仕上げを不一致にするならば、そこには見た目以上の意図がないと虚飾の張りぼてと同じである。
"Material and finish"
I'm thinking about the material and thinking about the finish. I feel resistance to decorative finishes, so think about matching the material and finish.
As an example where the material and finish do not match, I rarely see it now, but if it is a reproduction of only the grain of the surface of the wood with concrete or mortar like artificial wood, I think that you should use real wood. If you can't use wood, you don't have to force it to look like wood, and if you think about a different design, it's strange that using artificial wood is better than concrete or mortar. There is a sense of incongruity in giving superiority or inferiority.
When thinking about the finish, how to handle the material, if the material and the finish are intentionally inconsistent, it is the same as a vanity if there is no intention beyond the appearance.
いい年の取り方をしている人を見るだけで、こちらもいい気分になるもので、人となりがわからなくても表情に現れている。
記憶は誰にでもあり、記憶が刻まれた物もあり、記憶を継承していることが積み重なり深遠につながる。記憶は時間の経過が前提になるから、深遠を目指すならば、時間の経過とどう向き合うか、時間の経過をどのように扱うかが考えるところとなるだろう。
3年位前に京都で漆器を制作して貰った。いくつかの木地の型の中から選び、塗りは色も塗り方もデザインし、白漆に銀漆を一部纏わせてみた。制作した当時は何度か使ったが、久しぶりに引っ張り出してみたら、銀漆がいい具合に枯れていて、白漆とうまく馴染んでいるように思い、益々愛着が増した。
もしかしたら、銀漆の素材が粗悪で経年劣化をしてしまったのかもしれないが、白漆の色との相性を考えたら、粗悪だとしても銀漆の色の変化に嬉しくなった。
時間を銀漆の色変化によって目に見えるようにしたように感じ、素材が持つ力を垣間見たように思った。素材も人も変化した後にどう見えるか、きっと先のことはよくわからない様もあり、意外性もあり、ただそこに時間の経過を仕込む行為が大事なのだろう。
"Prepare the passage of time"
Just looking at a person who is getting a good age makes me feel good, and even if I don't know who I am, I can see it in my facial expression.
Everyone has memories, some of which are engraved with memories, and the inheritance of memories accumulates and leads to profoundness. Since memory is premised on the passage of time, if you aim for profoundness, you will have to think about how to deal with the passage of time and how to handle the passage of time.
I got a lacquer ware made in Kyoto about 3 years ago. I chose from several types of wood, designed the color and method of painting, and put some silver lacquer on white lacquer. I used it several times when I made it, but when I pulled it out for the first time in a while, I thought that the silver lacquer had withered well and that it blended well with the white lacquer, and I became more and more attached to it.
Perhaps the material of silver lacquer was inferior and deteriorated over time, but considering the compatibility with the color of white lacquer, I was happy with the change in the color of silver lacquer even if it was inferior.
I felt that time was made visible by the color change of silver lacquer, and I felt that I had a glimpse of the power of the material. It seems that we don't know what the future will look like after the materials and people have changed, and there are some surprises, so it is important to just put the passage of time into it.
時を経て変わった、景色もこれから変わる敷地があり、そこに新たな建築を建てるならば、周辺のコンテクストの変化を何らかの形で新たな建築に反映させたいと考える。
そこは私鉄の高架化による用地買収の末に残った敷地で、あたり一面が緑の更地になっている。これから高架ができ、更地の緑も無くなり、無規則に建築が並びはじめる。
まだ何も無いから、新たな建築が水面に石を投げてできる波紋のように周辺へ影響を与えることもできる。周辺のコンテクストの変化を受けて消化し加工して、また周辺のコンテクストへ投げ返すようなことをイメージしており、時間の経過を何らかの形でデザインとして残したい。
"Leave the passage of time"
There is a site that has changed over time and the scenery will change from now on, and if we build a new building there, we would like to reflect the changes in the surrounding context in the new building in some way.
There is a site left after the land acquisition due to the elevated private railway, and one side is a green vacant lot. From now on, the building will be elevated, the greenery of the vacant lot will disappear, and the buildings will begin to line up irregularly.
Since there is nothing yet, new architecture can affect the surroundings like ripples created by throwing stones on the surface of the water. I imagine that it will be digested and processed in response to changes in the surrounding context, and then thrown back to the surrounding context, and I want to leave the passage of time as a design in some way.
何気なく触り手に馴染ませると、指が側面の窪みにちょうど良くおさまる抹茶茶碗を手から放して見ると、窪みは茶碗に形の変化と趣きを与える。茶碗自体が変化する訳ではなく、人が触れて近づくか、離れて遠去かるかによって、窪みの意味合いが変わり、茶碗自体を扱うのか、茶碗を拝見するのかの違いに窪みが対応する。
茶碗は小さく動かすことができるから、茶碗自体が動くことにより、窪みの意味合いを変化させることができるが、建築は大きく動かすことができないから、人自身が動いて意味合いを変化させる。
人と動きと意味合いの変化の組合せによって、茶碗の窪みのようなものを建築で表現することは可能になり、窪みのようなものだけで建築が成り立ちはしないかと考えている。
"Dents and dents"
When you casually familiarize yourself with the touch, when you release the matcha bowl from your hand, the finger fits in the recess on the side, the depression gives the bowl a change of shape and taste. The bowl itself does not change, but the meaning of the dent changes depending on whether a person touches it or moves away from it, and the dent corresponds to the difference between handling the bowl itself and seeing the bowl.
Since the bowl can be moved small, the meaning of the depression can be changed by moving the bowl itself, but since the architecture cannot be moved greatly, the person himself moves to change the meaning.
By combining people, movements, and changes in meaning, it is possible to express something like a dent in a bowl in architecture, and I think that architecture can be made only with something like a dent.
精度を上げていけば叙情的になると仮定してみた。
精度を上げることは精密、精緻なものをつくり出すことになり、叙情的なものには精密、精緻とは対極の曖昧さがあるのではないかと考えてしまうが、むしろ叙情的になることを邪魔する余分なものを削ぎ落とすことが精度を上げることによってできるので、より叙情的になるのではないか。
叙情的ということを物質で考えた時に、叙情さを物質そのもので表現するのであり、精度を上げることにより物質以外で叙情さを表現してしまうことを取り除くことができる。
"Become lyrical to improve accuracy"
I assumed that if you increase the accuracy, it will become lyrical.
Increasing precision means creating precision and precision, and I think that lyrical things have ambiguity opposite to precision and precision, but rather hindering becoming lyrical. It may be more lyrical because it is possible to scrape off the excess things to be done by increasing the accuracy.
When we think of lyricism as a substance, we express lyricism with the substance itself, and by increasing the accuracy, we can eliminate the expression of lyricism other than the substance.
雰囲気が馴染み、心に引っ掛かり、気分が動かされることを叙情的だとして、叙情的なものをつくりたいと常に頭の片隅で想っている。
できあがる物は建築でも、家具でも、器でも何でもよく、種別ではなくて、叙情的であるかどうかが大事で、叙情的であるためには何をどこまで意識してつくるのか、全てを意識してつくり、叙情的である様を装うことは案外と簡単で、叙情的なデザインの見せ方をすればよい。
つくり手自身が叙情的でいるべきかも疑わしい。
意図や意識の外れたところで見える叙情さのような、自然の中にはたくさんあり、今ならば紅葉の叙情さか、意図や意識は存在しない。
叙情的であるために叙情さを纏わない。叙情的とは別の働きが結果的には叙情さを生み出すようなことを物をつくることを通して行えればと思う。
"Create lyricism"
I always think in the corner of my head that I want to make something lyrical, saying that it is lyrical that the atmosphere is familiar, that it catches my heart, and that my mood is moved.
The finished product can be architecture, furniture, vessels, whatever, it is not the type, it is important whether it is lyrical or not, and in order to be lyrical, what and how much you are conscious of making it is all conscious. It's surprisingly easy to make and pretend to be lyrical, just show the lyrical design.
It is doubtful that the creator himself should be lyrical.
There are many things in nature, such as the lyricism that can be seen outside the intention and consciousness, and now there is no intention or consciousness, such as the lyricism of autumn leaves.
Do not wear lyricism because it is lyrical. I hope that something other than lyrical work can eventually produce lyrical things through making things.
建築を規模の大小で価値判断しないが、規模が極端に小さくなると、仕切りが無くなり一室空間になり、設備や構造も簡素で最低限のものでよく、後から置かれる物も少ないので、建築単体の素性が素直に表に出てくる。
小さいから、余分な物は省き、必要最低限な物で構成するしかなく、付加物としての装飾は自然と無くなり、装飾をしたければ、人の皮膚と服が一体となるように、必要最低限の物が昇華して身に纏うしかない。
建築を構成する素材は皮膚であり、人が後から手を加える部分が服であり、皮膚と服が一体となった姿が建築単体の素性そのものになると考え、皮膚である素材の使い方を工夫し創造して、服である後から手を加える部分と区別できなく一体となるようにする。
"Building features"
We do not judge the value of architecture based on its scale, but when the scale becomes extremely small, there are no partitions and it becomes a single room space, the equipment and structure are simple and minimal, and there are few things to be placed afterwards, so architecture The identity of a single unit comes out obediently.
Because it is small, there is no choice but to omit extra things and compose it with the minimum necessary things, the decoration as an additive will disappear naturally, and if you want to decorate, the minimum necessary so that human skin and clothes are integrated There is no choice but to sublimate the limited items and wear them.
The material that makes up the building is the skin, and the part that people modify later is the clothes, and we think that the appearance of the skin and clothes integrated is the very nature of the building itself, so we devised how to use the material that is the skin. Create and make it indistinguishable from the part of the clothing that will be modified later.
いつもの材料でも組合せしだいで違って見えることはあり、違って見えれば、それは新しい空間体験になるだろう。
材料の使い方には大体セオリーがあり、それに沿っていれば間違いは無く、そのセオリーをたくさん知ることが経験を積むことかもしれないし、たくさんセオリーを知ることで技術力が上がり、材料の使い方に対する引き出しが増えるかもしれない。
ただ、そのことと違った見え方をつくることは全く関係が無いことだと考えている。ある見え方があり、それに対する材料の使い方でありセオリーであるから、見え方が変われば材料の使い方もセオリーも違う。すなわち、経験が役立たなくなる。
だから、違った見え方をつくるということは材料の使い方から考えることであり、セオリーという経験が役に立たない場合もあるからリスクもあるが、初心の楽しみというか、初源的なことから考える面白さがあり、そこに創造性を込めることができる。
"Fun of the beginning"
Even the usual materials can look different depending on the combination, and if they look different, it will be a new spatial experience.
There is generally a theory in how to use materials, and if you follow it, there is no mistake, and knowing a lot of theories may give you experience, and knowing a lot of theories will improve your technical skills and draw out how to use materials. May increase.
However, I think it has nothing to do with creating a different look. There is a certain way of looking, and it is the theory of how to use the material for it, so if the way of looking changes, the way of using the material and the theory will be different. That is, the experience becomes useless.
Therefore, creating a different look is to think from the usage of materials, and there is a risk because the experience of theory may not be useful, but it is fun to think from the beginning or the original. There is, and creativity can be put into it.
本当に小さい建築を、今までで一番小さいかもしれない建築を考えている。建築の大小を気にすることはほとんどなかったが、これだけ小さく、単一用途で、不特定多数が利用するとなると、「小さい」ということを建築デザインで考えてみる面白さを感じた。
小さいと全体的に把握がしやすいので、物としての建築を前面に押し出したくなる。それは形を幾何学にし、素材を即物的にして、建築が持っている物としての魅力を見せたいと考えることである。
それは設計していても楽しい。やはり建築は物としてどうあるべきかを問わないと単に容れ物で終わってしまうだろう。
"Architecture as a thing"
I'm thinking of a really small building, one that may be the smallest ever. I didn't really care about the size of the building, but when it was so small and used by an unspecified number of people for a single purpose, I found it interesting to think about "small" in architectural design.
If it is small, it is easy to grasp as a whole, so you want to push the architecture as a thing to the front. It is to make the shape geometric, to make the material real, and to show the attractiveness of architecture as an object.
It's fun to design. After all, architecture will simply end up as a container regardless of what it should be as a thing.
建築という物に身体性を溶け込ませたいと考えている。
本当に建築が小さくなると、人が物と同等に扱われ、建築は使っている状態でも物だけの存在になるが、それは人の身体性のようなものが建築という物の中に乗り移るというか、変換され痕跡が無くなったような状態であり、その状態を意図してつくろうとしたら、人の身体性を建築という物で捉える、表現する必要がある。
そのために、うまく染み渡るように人の身体性を建築の範疇から発露したいと考える。
"Physicality in architecture"
I want to blend my physicality into the thing of architecture.
When architecture becomes really small, people are treated the same as things, and even when they are in use, they are only things, but it means that things like human physicality are transferred into things called architecture. It is a state that has been transformed and has no traces, and if you want to create that state intentionally, you need to capture and express the physicality of a person as an architecture.
To that end, I would like to expose the physicality of human beings from the category of architecture so that they can permeate well.
本当に建築が小さくなると、その建築の中で一番場所を占める物は人になるだろう。人が物と同等に扱われる。そうなると建築は使っている状態でも物だけの存在になる。
建築を物としてだけ扱う、人との関係を無視できる。そうなると物自体の物質感が空間の質を決める。ただ、そうなるとその場所を空間というのか、空間が空間であるためには人が必要、あるいは人がいる前提が必要だと考えてしまう。
20世紀に発見された言葉である「空間」を何気なく毎日使っているが、そのように考えると「空間」という言葉に別の言葉を当てはめたくなる。
"Words other than space"
When an architecture really gets smaller, people will be the ones that occupy the most space in the architecture. People are treated the same as things. In that case, architecture becomes only a thing even when it is in use.
You can ignore the relationship with people who treat architecture only as a thing. In that case, the material feeling of the thing itself determines the quality of the space. However, in that case, I think that the place is a space, or that a space needs people or a premise that there are people.
I casually use the word "space" discovered in the 20th century every day, but when I think about it that way, I want to apply another word to the word "space".
人は時を超えて愛着あるものを存続させたいと思う心が必ずどこかに存在するのだろう、断捨離とは真逆である。
そもそも断捨離が良いとは、物を無くすことが目的になっていて、ミニマムに暮らすことはそれだけシンプルに生活と向き合えるから、迷うことなく的確に自分の進みたい方向がわかりやすくなるが、ミニマムと断捨離は全く違い、ミニマムは物を捨てる無くすことではなく、もっと身体的に意識をシンプルにすることで、それは物の有無に関係がない。
愛着ある物を増やすということは消費から遠ざかることを意味しており、生産して消費して、また再生産されるサイクルの外に出ることであり、サイクルの外にいる人だけが価値ある物を手にできるとアレントは言った。
"Valuable things"
There must be somewhere in the heart that a person wants to keep something that he is attached to over time, which is the opposite of decluttering.
In the first place, good decluttering is aimed at eliminating things, and living in the minimum makes it easier to face life, so it is easier to understand the direction you want to go without hesitation, but the minimum Decluttering is completely different, and the minimum is not to throw away things, but to make consciousness more physically simple, regardless of the presence or absence of things.
Increasing attachments means moving away from consumption, going out of the cycle of producing, consuming, and reproducing, and only those who are outside the cycle are valuable. Arendt said he could get it.
「形がない」建築をつくるのは難しくはない。正確には「形がない」ように見せる建築であり、「形がない」とした時点で「形がある」建築と一緒で、形を扱っていることに変わりはない。
形とは素材をあるルールに従って手を加えた結果現れたその時点での状態なので、形は時間の経過と密接に関係がある。だから「形がない」建築は時間がデザイン要素になったものであり、形が完成する前の時点で止めてやれば良い。
一旦「形がない」状態になり、そこからどうするかでも良く、形を扱うが、形以外の要素を重要視する場合は時間の経過を意識すると形が目立たなくなる。
"Shape and time"
It's not difficult to create "shapeless" architecture. To be precise, it is an architecture that makes it look like it has no shape, and when it is said that it has no shape, it is still dealing with shape, just like an architecture that has a shape.
The shape is closely related to the passage of time because the shape is the state at that time when the material is modified according to a certain rule. So "shapeless" architecture is a design element of time, and you can stop it before the shape is complete.
Once it becomes "shapeless", it doesn't matter what you do from there, and you deal with the shape, but if you place importance on elements other than the shape, the shape becomes inconspicuous if you are aware of the passage of time.
形に目がいき、形を見てしまう、建築を見る時の話で、その形が今まで見てきた建築の形の残像と比べてどうなのかを自然と考えている。
だから、創作の時にまず最初に自然と形をイメージしてしまう。ただ、そうすると今までに見たり、考えたり、自分のクセのような形が出てきて、それは既視感があり、どうしてもつまらないと思ってしまう。
言葉からまず考えて、その言葉を頼りに形を手繰り寄せるようなことを最近している。言葉だと、例えば「丸くて四角いもの」などのように実際の形をすぐにイメージできないようなこと、矛盾するようなことも記述でき、それは物質感にしても同じで「硬くて軟らかいもの」などのように記述できるので、そこからまた違う方向に、既視感のない方向に行ける。
今は「形がない」建築を考えている。
"Rely on words"
It's a story when you look at an architecture, where you look at the shape, and you naturally think about how that shape compares to the afterimage of the shape of the architecture you've seen so far.
Therefore, when I create it, I first imagine the shape naturally. However, if you do so, you will see, think, and form your own habit, which gives you a sense of déjà vu and makes you wonder why it is boring.
Recently, I've been thinking about words first, and then relying on those words to draw shapes. In terms of words, it is possible to describe things that cannot be immediately imagined in actual shape, such as "round and square", and things that are inconsistent, and it is the same in terms of materiality as "hard and soft". Since it can be described as such, you can go in a different direction from there, in a direction without déjà vu.
Now I'm thinking of "shapeless" architecture.
柱や壁は一見するとそれが何かの荷重、例えば、上の階や屋根の重さに耐えたり、水平の地震や風圧の力に耐えたりしているのかどうなのかがわからない。柱や壁がダミーというか、デザインとして組み込まれている場合もあるからである。
例えば、デザインとして柱や壁があった場合、それが自然に見えるように、自然に見えるとは構造上不可欠な物として見えるようにするか、わざと不自然にダミーですよとサインを送っているように見せるか。
わざとダミーだとわかる場合は他に意図があることも多い。わざとダミーだと気づかせて、そこから先の意図を考えさせることをする。
ミースの「バルセロナ・パビリオン」ではそれを行っている。そして、それがその建築でとても強いメッセージ性を帯びていて、もしそれが感じとれたならば、新しい時代の秩序に出会えることになったのだろう。
"Intention to notice unnaturalness"
At first glance, columns and walls do not know whether they are bearing some load, such as the weight of upper floors or roofs, or the forces of horizontal earthquakes and wind pressures. This is because the pillars and walls may be dummy or incorporated as a design.
For example, if there is a pillar or wall in the design, make it look natural, make it look natural as a structurally essential thing, or intentionally send a sign that it is a dummy. Do you show it like that?
If it turns out to be a dummy on purpose, there are often other intentions. Make them realize that it is a dummy on purpose, and make them think about their intentions from there.
Mies's "Barcelona Pavilion" does that. And it had a very strong message in the architecture, and if it could be felt, it would have met the order of a new era.
建築の構造が持つ重力に逆らうための秩序は、人が空間で過ごすために適した秩序とは限らない。それは空間が建築という構築物として成り立つための秩序と人がその空間で居心地良いと感じるための秩序が違うことと言い換えても同じである。
それは合致することが無いのだろうか、というか、合致させる必要があるのだろうか。建築と人の関係性に焦点を当てるならば、合致させたいし、合致して欲しいとなるだろうが、建築を物としてのみ扱うということならば、合致するかどうかはどうでもいいというか、建築が構築物として成り立つための秩序だけを考えれば良いだろう。
その結論のみは普通に行われていることだが、それでは普通過ぎて何も考えていないのと同じ過程になり、結果的にできあがる建築も普通である。
ミースの「バルセロナ・パビリオン」では、建築の構造が持つ重力に逆らうための秩序と人が空間で過ごすために適した秩序が合致していた。もっと正確に言うと、融合し、溶け合っていて、双方の秩序がひとつになっていた。
やはり、秩序はひとつの方が建築として説得力がある。違う秩序は融合させ、ひとつにしてしまえば、建築としてシンプルな複雑性を獲得できるか。
"Fusion of order"
The order of the structure of architecture to resist gravity is not always the order that people spend in space. It is the same in other words that the order for a space to be established as a structure of architecture is different from the order for people to feel comfortable in that space.
Does it never match, or does it need to match? If you focus on the relationship between architecture and people, you want to match and want to match, but if you treat architecture only as an object, it doesn't matter whether it matches or not. You only have to think about the order in which architecture works as a structure.
Only the conclusion is normal, but that is too normal and the process is the same as thinking nothing, and the resulting architecture is also normal.
At Mies' Barcelona Pavilion, the order of the architectural structure against gravity was in line with the order in which people were able to spend time in space. To be more precise, they were fused and fused, and the order of both sides was united.
After all, one person is more persuasive as an architecture. Is it possible to acquire simple complexity as an architecture by fusing different orders and combining them into one?
機能とは関係が無いところで人の動きを即すことを考えたならば、きっとプランや仕上げの素材だけでなく、様々な部位、例えば、柱や壁、開口部、階段なども捉え方を変える必要があるのではないかと思った。
柱や壁、開口部、階段などの部位はそれぞれの役割が、それを機能と呼んでもいいと思うが、あるので、その役割の秩序に則り配置されている。それらの配置は人の動きを即すことを考えて決められている訳ではないが、確実に人の動きに影響を与える。
ただ、その影響は「即す」ところまではいかずに、整流板のように「整える」、人の動きをその空間で秩序立てる程度であり、それは当たり前で、柱や壁、開口部、階段などの部位がそれぞれの役割に沿った秩序しか持ち合わせていないからである。
機能とは関係が無いところで人の動きを即すには、柱や壁、開口部、階段などの部位に別の秩序、それは人の動きを「即す」という役割を与え、その役割の秩序に則り配置してやらなければならず、それが捉え方を変えるということである。
"Give the role of" matching "people's movements"
If you think about adapting people's movements in places that have nothing to do with function, you will surely change the way you think about not only the plan and finishing materials, but also various parts such as columns, walls, openings, and stairs. I thought it was necessary.
Parts such as pillars, walls, openings, and stairs have their own roles, which can be called functions, but they are arranged according to the order of their roles. Their arrangement is not decided in consideration of the movement of people, but it certainly affects the movement of people.
However, the effect does not go to the point of "improving", but "arranging" like a rectifying plate and ordering the movement of people in the space, which is natural, such as pillars, walls, openings, stairs, etc. This is because each part of the body has only the order according to each role.
In order to adjust the movement of a person in a place that has nothing to do with the function, another order is given to parts such as pillars, walls, openings, and stairs, which gives the role of "according to" the movement of the person, and the order of that role. It must be arranged according to the above, which changes the way of thinking.
空間で動的と静的の混ざり合う濃度の違いをつくり出すためには、人と建築の関係性からなる部分を動的、建築の素の部分、それは骨組みであったり、人の影響を受けない部分を静的として、動的と静的の区別がつかなくなるぐらいに混ざり合い、その違いをわかるためには人の動きが必要で、人の動きの頻度や重複度、密集度の度合いが濃度を表す。
「バルセロナ・パビリオン」でも空間を人が歩き回ることを考え、壁や柱の配置し、ガラスの種類を変え、大理石も肌理の違うものが使われており、プランや空間配置だけではなく、様々な工夫がされていた。
歩き回ることを即す、そのためには機能は関係が無いのかもしれない。「バルセロナ・パビリオン」には機能が存在しない、故に明確なモダニズムの理念を表現できるのだが、歩き回ることを即すためにはプランや仕上げの素材の工夫で良いということだろう。
"Fit the movement of people"
In order to create a difference in concentration where dynamic and static are mixed in space, the part consisting of the relationship between people and architecture is dynamic, the elemental part of architecture, which is the skeleton or is not influenced by people. The parts are static, and they are mixed to the extent that it is difficult to distinguish between dynamic and static, and it is necessary for people to move in order to understand the difference. Represents.
In the "Barcelona Pavilion", considering that people walk around the space, the walls and pillars are arranged, the type of glass is changed, and marble with different texture is used, not only in the plan and space arrangement, but also in various ways. It was devised.
The function may not be relevant for walking around. The "Barcelona Pavilion" has no function, so it can express a clear idea of modernism, but it seems that it is sufficient to devise plans and finishing materials in order to make it easier to walk around.
人と建築の関係性からなる部分を動的、建築の素の部分、それは骨組みであったり、人の影響を受けない部分を静的として、動的と静的がスケルトン・インフィルの状態ではなくて、混ざり合う濃度の違いのようなプランを探している。
先日、地元の映画館でミースの「バルセロナ・パビリオン」の映画を見た。それは去年上映されたバウハウス100年映画祭の5本のうちの1本だったが、20年前に実物を見た時のことが蘇り、そして、そこに新たな解釈も加わり、今現在でも新鮮な感情を持たせてくらるし、現存しているのは復元だが、オリジナルの完成時期は同潤会アパートと同じくらいというから、その先鋭性に驚きもした。
そこに、大理石の壁の近い位置に鏡面仕上げの十字の柱がある。一般的には柱があれば屋根や上階を支えるものだが、あまりにも壁に近く、壁で屋根を支えることができるし、壁が水平方向の力にも耐えることができるので、構造上柱はいらない。
20年前にはそこまで気がつかなかったが、中庭には女性像の彫刻があり、このモダニズム建築とは相容れないものであるが、映画の中では十字の柱と女性像を対峙させ、十字の柱はモダニズムが廃した装飾、それも性的な装飾としていて、ミースはそこで動的なものと静的なものの混ざり合いの濃度を柱とその位置で表現し、それが見事にモダニズム建築として完結している様に改めてこの「バルセロナ・パビリオン」の素晴らしさを感じた。
"Expressing concentration with pillars"
Dynamic and static are not the state of skeleton infill, where the part consisting of the relationship between people and architecture is dynamic, the elemental part of architecture is the skeleton or the part that is not influenced by people is static. I'm looking for a plan like the difference in the concentration of mixing.
The other day, I watched a movie of Meath's "Barcelona Pavilion" at a local movie theater. It was one of the five Bauhaus 100th Anniversary Film Festivals that screened last year, but it revives when I saw it 20 years ago, and with a new interpretation, it's still fresh. I was surprised at the sharpness of the original, as the original was completed at the same time as the Dojunkai apartment, although it has been restored.
There is a mirror-finished cross pillar near the marble wall. Generally, pillars support the roof and upper floors, but they are structurally pillars because they are so close to the wall that the roof can be supported by the wall and the wall can withstand horizontal forces. I don't need it.
Twenty years ago, I didn't notice that much, but there is a sculpture of a female statue in the courtyard, which is incompatible with this modernist architecture, but in the movie, the pillar of the cross and the statue of the woman are confronted, and the pillar of the cross Is a decoration that modernism has abolished, which is also a sexual decoration, where Mies expresses the concentration of a mixture of dynamic and static in pillars and their positions, which is perfectly completed as modernist architecture. I felt the splendor of this "Barcelona Pavilion" again.
人と建築の関係性からなる部分を動的として、建築の素の部分、それは骨組みであったり、人の影響を受けない部分で静的として、動的と静的が両方同時に成り立ち、補完し合う状態をつくる。
ただ、それは動的と静的に分けると全く水と油のように混ざり合うことが無く、はっきりと分離するのではなくて、イメージとしては小さい動的と静的な微粒子が同時に存在していて、場所によって微粒子の割合が違うような、濃度が違うような状態であり、その濃度の違いで建築の見え方が決まる。
動的と静的に分けるとスケルトン・インフィルのような状態を想像してしまうが、濃度の違いと考えれば、また違った展開も現れてきそうな気がした。
"Difference between dynamic and static concentration"
Dynamic and static are both established and complemented at the same time, with the part consisting of the relationship between people and architecture as dynamic, and the basic part of architecture, which is the skeleton or the part that is not influenced by people, as static. Create a fit.
However, when it is divided into dynamic and static, it does not mix like water and oil at all, and it does not separate clearly, but as an image, small dynamic and static fine particles exist at the same time. , The ratio of fine particles differs depending on the location, and the concentration is different, and the appearance of the building is determined by the difference in the concentration.
If you divide it into dynamic and static, you can imagine a state like a skeleton infill, but considering the difference in concentration, I felt that a different development would appear.
人の数あるアクティビティの中でも「歩く」は建築と相性が良い。コルビュジエ もミースも歩くことによる空間のシーンの変化を建築に取り入れている。
歩くことで空間の中を移動し、その都度目に見える空間のシーンが変わる。この見えるものの変化が動かない建築に様々な動きを与える。
今、この建築空間の中を「歩く」という動きに、人の感情も加味することにより、建築空間の中での自分の居場所を見つけることをプランニングしている。
感情を扱うことで、より人の内面が反映され、人と建築の関係性が生まれる。それは現代建築における主要なテーマのひとつだと考えている。
"Emotions in activity"
Among the many activities of people, "walking" goes well with architecture. Le Corbusier Incorporates the changes in the spatial scene of his walking and Mies into his architecture.
By walking, you move through the space, and the scene of the visible space changes each time. This change in what you see gives various movements to architecture that does not move.
Now, I am planning to find my place in the architectural space by adding human emotions to the movement of "walking" in this architectural space.
By dealing with emotions, the inner side of the person is reflected more, and the relationship between the person and the architecture is created. I consider it one of the main themes in modern architecture.
「選択する」というアクティビティが人と建築をつなぐ。その時に選択するものは何か、それは「感情」を選択することにしようと考えている。
人の感情は目に見えるものではないので、それを目で見える形に置き換えてやる必要がある。その置き換えを建築的に考えると、感情によって居場所を選ぶことにする。
はじめは居場所を選ぶというアクティビティが人と建築をつなぐ。居場所を選ぶ時の基準が感情であり、それを繰り返していくと居場所に感情が紐づけられて、居場所を選ぶことが感情を選ぶことに変化する。
例えば、「嬉しい」気分になりたいからあそこへ行こうなど、感情を引き出したり、コントロールしたりするようになり、それによって居場所が決まるから建築の見え方もそれによって変化する。
「感情的になる」という言葉があるように、感情によって左右されることは良くないように思われるかもしれないが、人は理性で行動しているようで、実はその理性が感情に支配されていることが多く、社会を見渡しても個人の感情を現実の中で受け止めるような受け皿がない。その受け皿に建築がなるのは「衣食住」という言葉があるように人の基本的な拠り所に建築がなるので必然的だと考えている。
"Choose emotions"
The activity of "selecting" connects people and architecture. What to choose at that time, I'm thinking of choosing "emotion".
Human emotions are not visible, so we need to replace them with visible ones. Architecturally considering the replacement, I decide to choose a place based on emotions.
At first, the activity of choosing a place connects people and architecture. Emotions are the standard when choosing a place of residence, and by repeating this, emotions are linked to the place of residence, and choosing a place of residence changes to choosing emotions.
For example, if you want to feel "happy" and want to go there, you will be able to elicit and control your emotions, which will determine your whereabouts and thus change the way you look at architecture.
It may seem that it is not good to be influenced by emotions, as the word "become emotional" is, but it seems that people are acting with reason, and that reason is actually dominated by emotions. Even if you look around the society, there is no saucer that can accept individual feelings in reality. I think that it is inevitable that architecture will be built on the saucer because it will be built on the basic basis of people as the word "clothing, food and housing" is used.
人の感情を形にしたいと考えている。建築において感情を形にする、それは感情を具現化することになるが、その表現のひとつとして考えられるのが感情に応じて居場所があるということであり、感情を判断基準にして居場所を選ぶことである。
ただ、最初は感情によって居場所を選んでいたのが、段々と居場所に感情が定着してきて、その感情になりたくて、居場所に紐付けされた感情を選ぶようになるだろう。
そうすると、それは感情を形にしたことにはならないかもしれないが、感情と関係性ができた居場所が感情を具現化したものとしてもいいような気がしている。
"Emotional realization"
I want to give shape to people's emotions. Forming emotions in architecture, which embodies emotions, can be thought of as one of the expressions that there is a place to stay according to the feelings, and to choose a place based on the feelings. Is.
However, at first, the emotions were used to select the place of residence, but the emotions gradually became established in the place of residence, and I wanted to become those emotions, so I would choose the emotions associated with the location.
Then, it may not be a form of emotion, but I feel that the place where the emotion can be related can be the embodiment of emotion.
選択することを建築的に考えてみると、人は空間の中で常に何かを選択していると思った。そして、その選択には建築が起因しないものも当然あるが、空間の中で行われているならば全く建築の影響を受けないことは無いだろうとも思った。
空間の中にある選択肢から人が選択するという構図になるのが一般的だと思うが、人がその選択をする時の基準には何があるのだろうかと考えてみると、大概はその人の中にある基準が優先され、建築側には基準がない場合が多いだろうと思い、ただ、それは当たり前かもしれないが、そうすると、建築は何でもよく、建築は箱でよく、容れ物でよく、ただの箱で嫌ならばカッコいい箱にすればよく、人によって決まることになる。
それでも、人間主義の建築でいいのだが、人の中に選択の基準があるにせよ、その時に建築が応答できれば、人と建築の関係性から建築を紡ぎ出すことができ、そうすれば、建築は何でもよくなく、唯一無二のものになる。
「応答」というと建築を擬人化しているようだが、実際には建築は動くことができないので、その時に人が建築から影響を受けるということである。だから、建築が人に与える影響を手法も含めて考えることが何でもよくない建築をつくることになる。
"If the architecture can respond"
Architecturally thinking about making choices, I thought that people were always choosing something in space. And, of course, there are some choices that are not attributed to architecture, but I also thought that if they were done in space, they would not be completely unaffected by architecture.
I think it's common for people to choose from the choices in space, but when you think about what the criteria are for people to make that choice, it's usually that person. I think that the standards inside are prioritized and there are often no standards on the building side, but that may be obvious, but then the building can be anything, the building can be a box, a container, If you don't like a simple box, you can make it a cool box, and it depends on the person.
Still, humanistic architecture is fine, but even if there are criteria for selection in people, if architecture can respond at that time, it can be spun out from the relationship between people and architecture, and then architecture. Is not good at all, it will be unique.
"Response" seems to be anthropomorphic to architecture, but in reality, architecture cannot move, so people are influenced by architecture at that time. Therefore, it is not good to think about the influence of architecture on people, including methods.
人と建築の関係性において、その接点では何が媒介をしているのかを考えていた。
すぐに思いついたのは「機能」であり、建築が持ち合わせている機能を人が利用するという構図である。そもそも建築は人が内部に入り込み使うことが前提ならば、そこに使える機能が用意されている訳で、その機能を使うことで人と建築の関係が築かれる。
ただそれでは、建築は単なる装置や機械と一緒ではないかと思い、人が関わらなくても建築である、ともいえないような気がする。
ならばと、媒介するものを人の「気分」や「感情」を含めた「気持ち」とするとどうだろうか。本当にそれが媒介になるのであれば、建築が装置や機械と一緒になることはないだろう。
"If the mediator feels"
In the relationship between people and architecture, I was thinking about what mediates at that point of contact.
Immediately I came up with the "function", which is a composition in which people use the functions that architecture has. In the first place, if it is premised that people go inside and use architecture, there are functions that can be used there, and by using those functions, a relationship between people and architecture can be built.
However, I think that architecture is just like equipment and machines, and I feel that it cannot be said that it is architecture without human involvement.
Then, what if the mediator is "feeling" including "mood" and "emotion" of a person? If it really acts as an intermediary, architecture will not be associated with equipment or machinery.
言葉は段々と細分化し、言葉でギリギリ辿り着けそうな目的地を探しながら進む。
「人と建築の関係性からなる部分は同じ位のスケールで考える」という言葉からは、建築の各部位が切り離され人のスケールで立ち上げるイメージが湧き、「人と建築の関係性からなる部分」は建築の中での人と関わる機能だけを抽出して、それらを分別したものである。
さらに「分別」は、その時その場所で必要に応じて分けられ配されることで、その時の分別の基準は人の気持ちであり、「人と関わる機能だけを抽出」は建築の中での衣食住に関わる全ての機能が人との関わりの度合いの違いでグルーピングされることで、それが分別され、人のスケールで構築される。
そして、その「人のスケールで構築」されたものが建築として人と直に呼応し合い、自律と他律が同時に起こる状態が生まれ、ひとつの建築の一部となる。
"Subdivision of words is going to be realized"
The words are gradually subdivided, and we proceed while searching for a destination that we can reach at the last minute.
The phrase "think about the relationship between people and architecture on the same scale" gives the impression that each part of the building is separated and started up on the scale of people. "The part that consists of the relationship between people and architecture. "" Is an extraction of only the functions related to people in architecture and sorting them.
Furthermore, "separation" is divided and distributed as needed at that time, and the standard of separation at that time is the feelings of people, and "extracting only the functions related to people" is clothing, food and housing in the architecture. By grouping all the functions related to the above according to the degree of involvement with people, it is sorted and constructed on the scale of people.
Then, what is "constructed on a human scale" directly interacts with people as an architecture, creating a state in which autonomy and heteronomy occur at the same time, and become part of one architecture.
言葉から建築を考える場合、その言葉に形につながる情報が含意されていないと建築にはならない。それはその言葉を聴いた時に、ぼんやりでもいいから形なり、プランなり、建築がイメージできることである。
「人と建築の関係性からなる部分と、建築の骨格というか建築の素の部分を切り離せば良いと思った」という言葉には形、プランにつながる情報があると思い、はっきりではないが実際の建築がぼんやりイメージできた。
「人と建築の関係性からなる部分は同じ位のスケールで考える」という言葉からは、建築の各部位が切り離され人のスケールで立ち上げるイメージが湧き、 「建築の素の部分は人から切り離されて、人からの影響を受けず、普遍、不変に近い状態」という言葉からは、建築の物としての側面が強調され、そこでは素材と形と重力に逆らう構造による初源的にも近い構築物が凛とした姿で建つイメージが湧いた。
"Can you imagine from words?"
When thinking about architecture from words, it cannot be architecture unless the words imply information that leads to form. That is, when you hear the words, you can imagine the shape, the plan, and the architecture, even if it is vague.
I think that the phrase "I thought it would be better to separate the part consisting of the relationship between people and architecture from the skeleton of architecture or the elemental part of architecture" has information that leads to shapes and plans, but it is not clear, but in reality. I could have a vague image of the architecture of.
From the phrase, "Think about the relationship between people and architecture on the same scale," the image of each part of architecture being separated and starting up on the scale of people emerges. "The basic part of architecture is separated from people. The phrase "a state that is almost universal and almost immutable without being influenced by humans" emphasizes the aspect of architecture, where it is close to the original due to the material, shape, and structure that opposes gravity. I got the image that the structure was built with a dignified appearance.
人と建築の関係性からなる部分と、建築の骨格というか建築の素の部分を切り離せば良いと思った。人と建築の関係性からなる部分は同じ位のスケールで考える。それは建築が容れ物になるのではなくて、人と建築が並列になることによって関係性がヒエラルキーなくフラットになり、より人と建築が直に呼応し合う関係性が生まれる。
そして、建築の素の部分は人から切り離されて、人からの影響を受けず、普遍、不変に近い状態、別の言い方をすれば静的状態になる。それでいうと、人と建築の関係性からなる部分は動的状態になる。
静的な部分は動的な部分に足りないスケールを担保する。動的な部分は静的な部分が受けつけない人の内面である感情などを反映する。静的と動的の双方が補完し合い建築全体が構成される。それは自律と他律が同時に成り立ち建築が形成されることでもある。静的も動的も自律しながら、同時に他律も加味しないと建築として成立しない。
"Static and dynamic complementation"
I thought it would be good to separate the part that consists of the relationship between people and architecture from the skeleton of architecture or the basic part of architecture. Think of the relationship between people and architecture on the same scale. It is not that architecture becomes a container, but that the relationship between people and architecture becomes flat without hierarchy, and a relationship in which people and architecture directly interact with each other is created.
And the basic part of architecture is separated from people, unaffected by people, and becomes a universal, near-immutable state, or in other words, a static state. In that sense, the part consisting of the relationship between people and architecture becomes a dynamic state.
The static part guarantees a scale that is insufficient for the dynamic part. The dynamic part reflects the emotions inside the person that the static part does not accept. Both static and dynamic complement each other to form the entire architecture. It also means that autonomy and heteronomy are established at the same time and architecture is formed. It cannot be established as an architecture unless both static and dynamic are autonomous, and at the same time heteronomy is taken into consideration.
人が建築に包み込まれるのは、人と建築のスケールの差が大きいからであり、建築が容れ物であったり、内部に入り込めるのは人よりスケールを大きくしているからであり、そもそも建築は人よりスケールが大きいのが当たり前で、プランのはじめからそこを疑いようもなく容れ物をつくっている。
人と建築のスケールが同じ位になれば、容れ物ではなく、人と建築が並列になり、建築はその他の物と同じように要らなければ使われないだけの、そして、消費されるだけの存在になってしまうかもしれないが、より人と建築の関係性がヒエラルキーなくフラットになり、人と建築の関係性で成り立つ考えをするならば、劇的に建築の見え方が変わるだろうし、人と建築がお互いより近い存在になる。
"If the scale of people and architecture is about the same"
People are surrounded by architecture because there is a large difference in scale between people and architecture, and architecture is a container, and it is because it is larger than people that it can enter inside, and architecture is in the first place. It is natural that the scale is larger than that of people, and from the beginning of the plan, there is no doubt that they are making containers.
When the scale of people and architecture is about the same, people and architecture are parallel, not containers, and architecture is not used and consumed as much as other things. It may become an existence, but if the relationship between people and architecture becomes flatter without hierarchy, and if we think about the relationship between people and architecture, the appearance of architecture will change dramatically. People and architecture will be closer to each other.
人と建築の距離を縮めるには建築の成り立ちから考える必要があり、容れ物では人は建築と距離を詰められない。人が建築と直に対峙するには、人が建築に包み込まれるのではなくて、人と建築が並列になり、人は動く物、建築は動かない物として関係性を築く。
建築を人から切り離して考えることもできるが、むしろその方が建築という物を直に考えやすいかもしれないが、動く人はやはり不確定要素に満ちているし、純粋に建築という構築物だけの方が美しい物ができるだろう。
人の動きに動かない建築が呼応し、動かない建築が人の動きを制御する。容れ物ではなく、包み込まれる訳でもないから、並列な人と建築は各々別々に成り立つと同時に相互依存でもある。自律と他律が同時に成り立つ様をまず言葉で考え、次にプランにする。
"Moving people and non-moving architecture are in parallel"
In order to shorten the distance between people and architecture, it is necessary to think from the origin of architecture, and people cannot close the distance from architecture with containers. In order for people to confront architecture directly, people are not wrapped in architecture, but people and architecture are parallel, and people build relationships as moving things and architecture as immovable things.
It is possible to think of architecture separately from people, but it may be easier to think of architecture directly, but moving people are still full of uncertainties, and those who are purely architecture. Will make beautiful things.
Architecture that does not move responds to the movement of people, and architecture that does not move controls the movement of people. Since it is neither a container nor an envelopment, parallel people and architecture are both independent and interdependent. First think in words how autonomy and heteronomy hold at the same time, and then make a plan.
建築は容れ物であり、人はそこに入り込み、そこには人以外の物もたくさん置かれる。考えようによっては、人と建築の間に物があり、人と建築の距離が遠い。
距離が遠いと感じるならば、人と建築の距離を縮めたい。
建築を容れ物と考えるの止めてみる、そして、人と建築を直に並べて、人以外の物はその先に置く。人以外の物よりも、人と建築の距離が近くなる。
それはどうことか。建築が容れ物でないならば、雨露を凌ぐ、例えば傘だと思い、今ならば寒さから守る、例えば毛布だと思い、傘と毛布を組み合わせて、そこに設備をつなぐ。つなぎ方は人と建築の距離感の邪魔にならない所で、人以外の物としておく。
そんな人と建築の距離を縮めることをぼんやりと考えていたら、それはなんとなくキャンプの発想だなと思った。
"If it's not a container"
Architecture is a container, and people get in there, and many non-human things are placed there. Depending on how you think about it, there is something between people and architecture, and the distance between people and architecture is long.
If you feel that the distance is far, you want to shorten the distance between people and architecture.
Stop thinking of architecture as a container, and put people and architecture side by side, and put non-human things ahead. The distance between people and architecture is closer than that of non-human objects.
How is that? If the architecture is not a container, surpass the rain and dew, think of it as an umbrella, and now protect it from the cold, think of it as a blanket, combine an umbrella and a blanket, and connect the equipment there. The way of connecting should be something other than people, where it does not interfere with the sense of distance between people and architecture.
When I was vaguely thinking about shortening the distance between such people and architecture, I thought it was a camp idea.
集合住宅を計画中で資料をいろいろと読んでいると、集合住宅という形式のはじまりは19世紀半ばくらいで、20世紀前半までにかけて労働者のユートピアを目指して建設され、その社会的な要請とモダニズムという建築理念が一緒に隆盛した様子がわかる。
モダニストのコルビュジエの作品にも労働者住宅はあり、集合住宅はマルセイユのユニテ・ダビタシオンぐらいしか見たことはないが、しかしそれは労働者住宅ではないので、資料や展覧会などで図面や写真などを見ると、モダニズムの幾何学的な形態の建築に目を惹かれるが、そこにはその時代の社会性が反映されている端正な佇まいを感じていた。
その当時の資料を見ていると、時代背景から求められる社会的な要請と建築がリニアに対応して、社会問題の解決に建築が直に用いられていた。現代から比べれば、その当時起きていた社会問題が明確で理解しやすかったから、生活に直結する建築だけで解決できることが多かったし、建築をつくる側も目標を立てやすかったのだろう。
だからか、その当時の建築を見るとつくる側から見てもユートピアに見える。現代では起きている社会問題が複雑過ぎて建築だけでは対応できないし、できていない。
"When architecture was utopia"
When I was planning an apartment house and reading various materials, the form of an apartment house started in the middle of the 19th century, and it was built by the first half of the 20th century aiming at the utopia of workers, and its social demands and modernism. You can see how the architectural philosophy of "" has prospered together.
There is also a worker's house in the work of modernist Le Corbusier, and I have only seen apartment houses like Unite d'Habitation in Marseille, but since it is not a worker's house, I will show drawings and photographs in materials and exhibitions. When I saw it, I was attracted to the architecture of the geometrical form of modernism, but I felt a neat appearance that reflected the sociality of that era.
Looking at the materials at that time, architecture was directly used to solve social problems, as the social demands of the times and architecture responded linearly. Compared to the present day, the social problems that were occurring at that time were clear and easy to understand, so in many cases it could be solved only by architecture that is directly connected to daily life, and it would have been easier for the building side to set goals.
That's why, when you look at the architecture at that time, it looks like utopia from the perspective of the creator. The social problems that are occurring in modern times are too complicated to be dealt with by architecture alone.
人は空間に入った時にまず何をするか、初めて入った時を想定してみる。繰り返し入ったことがある空間では学習して同じような行動パターンをするかもしれないが、それも初めて入った時の行動パターンが元になる。
空間に入って感動することを想像してみる。初めはあらかじめ空間の様子がわからないから、いわばサプライズ効果で感動するかもしれないが、二度三度と入るたびに慣れてしまい感動しなくなるという話を聴くと、本当にいい空間であれば何度でも感動すると思うので、感動しない場合は人の感度の問題か、そもそも本当にいい空間かとなる。
人は初めての空間では身の置き所、すなわち、居場所を探す。まずどこに居るか、そこが安全地帯となり、それが定まってから様々な機能や用途が目に入る。
感動における人の感度は、初めての空間での居場所探しにも役立ち、共通のアンテナとして使え、それは空間を認識する際のその人固有の感性である。
"Unique sensibility"
Imagine what a person would do when he first entered the space, the first time he entered. In a space where you have entered repeatedly, you may learn and follow similar behavior patterns, but that is also based on the behavior patterns when you first enter.
Imagine entering a space and being impressed. At first, you don't know the state of the space in advance, so you may be impressed by the surprise effect, but when you hear the story that you get used to it every time you enter it and you will not be impressed, you can do it as many times as you like if it is a really good space. I think I'm impressed, so if I'm not impressed, it's a matter of human sensitivity, or it's a really good space in the first place.
In the first space, a person searches for a place to put himself, that is, a place to stay. First of all, where you are, it becomes a safe zone, and after it is decided, you can see various functions and uses.
The sensitivity of a person in impression is also useful for finding a place in the space for the first time, and can be used as a common antenna, which is the person's unique sensibility when recognizing the space.
機能を組み替えただけの空間は面白くない。例えば、水回りという機能が突然出現しても困惑するだけだし、それでは人が機能に従うことで空間が成り立つことを良しとすることになる。
何よってプランが決まるのか、その正解はひとつではないが、人と建築の関係性の範疇で考えたいと思う。建築は人が使う物だから、それが当たり前のように思われるかもしれないが、人を廃することで成り立つ建築もある。
今考えているのは、人が自身の気持ちによって自律的に建築と向き合い、それに応答する建築から他律的に影響を受けることにより、建築や空間の見え方が決まるというものであり、人と建築の関係性に気分や感情を含めた「気持ち」を持ち込むことである。
そして、その「気持ち」が建築として可視化されるようなことである。
"Visualization of feelings"
The space where the functions are just rearranged is not interesting. For example, even if the function of water circulation suddenly appears, it will only be confusing, and it will be good if a person follows the function to establish a space.
There is more than one correct answer as to why the plan is decided, but I would like to think in the category of the relationship between people and architecture. It may seem natural because architecture is something that people use, but there are also architectures that consist of abolishing people.
What I am thinking now is that people autonomously face architecture according to their own feelings, and the appearance of architecture and space is determined by being heteronomously influenced by the architecture that responds to it. It is to bring "feelings" including moods and feelings into the relationship of architecture.
And that "feeling" is visualized as architecture.
今までに見たことが無いような仕上げにしようと考えた時に、コストとの兼ね合いもあるが、それの良し悪し、受け入れられるかどうかなどを考えなければ、案外今までに見たことが無いような仕上げにすることは簡単である。
さらに設計者が考えれば、その建築に対して的外れなことをする可能性は少ないだろう。実現するとなればコストはクリア、良し悪しは精度を上げるしかない。
あとは違和感との兼ね合いだけになる。何か新しいことをしようとすれば違和感があるのは当然だと思われるかもしれないが、実は新しいと感じる物を見た時に違和感は全く無い。むしろ、新しいけれど、それがどのように新しいかを説明できる、この説明できるということがそれまでの既成の延長で考えることができるからで、それができない時に違和感が生じる。
だから、逆にいうと違和感を感じる時、人はそれに対して新しいとは考えない、ではなんと、奇抜と考える。違和感をたくさん生めば奇抜になる。違和感は生むより無くす方が難しいし、新しい。
"What is new"
When I think about finishing it like I've never seen before, there is a trade-off with cost, but if I don't think about whether it's good or bad and whether it's acceptable or not, I've never seen it before. It is easy to make such a finish.
Moreover, if the designer thinks, it is unlikely that he will do anything wrong with the architecture. If it is realized, the cost will be cleared, and the quality will have to be improved.
The only thing left is to balance the feeling of strangeness. It may seem natural that you feel uncomfortable when you try to do something new, but in reality, when you see something that feels new, you don't feel any discomfort at all. Rather, it is new, but it can explain how it is new, because this explanation can be thought of as an extension of the existing ones, and when that is not possible, a sense of discomfort arises.
So, conversely, when you feel something is wrong, people don't think it's new, but it's strange. If you create a lot of discomfort, you will be eccentric. It's harder to get rid of the discomfort than it is, and it's new.
見慣れた風景に安心することもある。それが落ち着くこともあり、見慣れた風景に引き寄せられてしまう。安心感は大事、そこにいるだけで安心できることはこの上ない喜びだろうと思う、消費する側は。
消費はどこまで行っても消費でしかなく、それはやがて短命に終わる。
ものをつくっていると消費側には回りたくない。生産する側でいたいし、それが単なる労働であることも望まない。
結局、見慣れた風景から既視感の無い風景に移るしかなく、それは既視感のある風景の延長線に存在するのだが、確実に違う何かを纏っている。
"Moving from a familiar landscape"
You may feel relieved at the familiar scenery. Sometimes it calms down and you are drawn to the familiar scenery. A sense of security is important, and I think it would be a great pleasure to be relieved just by being there, on the consumer side.
Consumption is nothing more than consumption no matter how far it goes, and it will soon end in a short life.
When I make things, I don't want to go to the consumer side. I want to be on the producer side, and I don't want it to be just labor.
In the end, there is no choice but to move from a familiar landscape to a landscape without déjà vu, which exists as an extension of the landscape with déjà vu, but is definitely wearing something different.
人よりも大きいスケールの建築は直接触れることができる部分が限られているので、離れたところから見て得られる情報から様々な判断をしており、居場所を決める時もその場所が滞在できる場所かを様々な情報から判断している。
その情報の中には慣習からくるものもあれば、その場のルールなどもあり、建築以外の社会性や倫理性などといった規範性も含まれるので、純粋に建築のみで決まることはないかもしれないが、建築はそのプランや形に社会性や倫理性を反映させるのが前提にはなっているので、しかし、今はその社会性や倫理性が明確ではなくプランや形につながる情報が無いように思われるが、建築が様々な情報を与えることにより人が居場所を選択するという図式が成り立つと考えることにする。
建築とは素材がある形になった物であり、そこに人がいなくても物としては存在する。しかし、建築は人が使う物であり、人が使わない物は工作物か廃墟であるから、そこに人との関係で建築を考える必要性が出てくる。そうすると、人が建築をどのように知覚し認識するかも含めてプランや形に人と建築の関係性を表現したい。
"Architecture gives information"
Buildings on a scale larger than humans have a limited number of parts that can be touched directly, so we make various judgments from information that can be seen from a distance, and when deciding where to stay, the place where we can stay. It is judged from various information.
Some of the information comes from customs, there are rules on the spot, and it also includes normatives such as sociality and ethics other than architecture, so it may not be decided purely by architecture alone. No, but architecture is premised on reflecting sociality and ethics in its plans and shapes, but now its sociality and ethics are not clear and there is no information that leads to plans and shapes. It seems, but I think that the scheme that a person chooses a place of residence is established by giving various information by architecture.
Architecture is a form of material that exists as a thing even if there are no people there. However, since architecture is something that people use, and things that people do not use are works or ruins, it becomes necessary to think about architecture in relation to people. Then, I would like to express the relationship between people and architecture in plans and shapes, including how people perceive and recognize architecture.
「気持ち」という言葉を「選択する」という動きのある言葉に変換した。それは「気持ち」が判断基準になる前提であり、気持ちによって何かを判断し選択した結果が形やプランになるようなことを思い描いた。
「気持ち」を分解すると「気分」と「感情」になる。どちらも人の心に関することだが、自分の心のあり様が「気分」で、他人の心のあり様が「感情」になるという。
人が主体的に建築や空間と関わりを持とうとすることを目指しているので「気分」が判断基準になり、何かを選択することにより建築や空間の形やプランが形成される。
そうすると、形やプランはいわば二次的な産物となり、人が主体的になる。それは人がいなければ、建築や空間は完成では無いということでもある。
"Architecture completed with people"
I converted the word "feeling" into a moving word "select". It is a premise that "feelings" are the criteria for judgment, and I envisioned that the result of judging and selecting something based on feelings would be the shape and plan.
When "feeling" is decomposed, it becomes "mood" and "emotion". Both are related to the human mind, but it is said that the state of one's mind becomes the "mood" and the state of the mind of another person becomes the "emotion".
Since people are aiming to independently relate to architecture and space, "mood" is the criterion, and by selecting something, the shape and plan of architecture and space are formed.
Then, the shape and plan become so-called secondary products, and people become independent. It also means that architecture and space are not complete without people.
様々な気持ちを抱く人が建築や空間とどのようにつながるのか、それをプランや形で表現する。その場合「気持ち」には直接的に形になる情報が無いが、形とはその生成過程での動的な瞬間を捉えたものとされるから、「気持ち」という言葉を動きのある言葉に置き換えてやることができれば、「気持ち」から形に結びつく情報を抽出できるかもしれない。
「気持ち」には様々な側面があるから、どこにフォーカスしてやるかによって、置き換えたり、関連させる動きのある言葉が違ってくるかもしれない。だから、それだけ「気持ち」をプランや形に結びつける自由度があり、可能性があるということもいえるだろう。
「気持ち」は人の主観であり、その人のその時における固有のものであるから、人はその「気持ち」を判断基準に使うことがあり、そうすると「気持ち」が判断した結果に現れる。このことを動きのある言葉に置き換えるならば、例えば「選択する」になるだろうか。
「選択する」という動きのある言葉から形やプランに結びつける。それは「気持ち」という言葉よりは結びつきそうな気がする。
"Transforming the word" feeling "in architecture"
Express in plans and forms how people with various feelings connect with architecture and space. In that case, "feeling" does not have information that can be directly formed, but since shape is considered to capture the dynamic moments in the process of its formation, the word "feeling" is changed to a moving word. If we can replace it, we may be able to extract information that leads to form from "feelings."
Since there are various aspects to "feeling", the words that move to replace or relate may differ depending on where you focus. Therefore, it can be said that there is a degree of freedom and possibility to connect "feelings" to plans and shapes.
Since "feeling" is a person's subjectivity and is unique to that person at that time, one may use that "feeling" as a criterion, and then the "feeling" appears in the judgment result. If we replace this with a moving word, would it be, for example, "choose"?
Connect the moving word "select" to the shape and plan. I feel that it is more connected than the word "feeling".
気分や感情も含めて「気持ち」とするが、建築においてプランや形と直接的に結びつかないところで「気持ち」を問うても意味がない。それはどうにでもなるからで、別にこれは「気持ちの良いものです」とすれば、後は好みでどうにでもなる。
では「気持ち」を建築でどう扱うかと考えてみると、気持ちの良い空間をつくる方法をまず考えようとしてしまう。「気持ち」は人によって違うし、「気持ちの良い」というフレーズや同じような意味の「居心地の良い」というフレーズは実態がよくわからずはっきりとしないが、何となくでも良い意味だとは誰でも思うので、それをつくり出すことが、例えば住宅ならば、家づくりに直結させやすい。ただそうすると、最初の話と同じだが「これが気持ちの良い家です」と一言で済み、同意しなければそれで終わりである。
建築で「気持ち」を扱うならば、特定の気持ちにフォーカスするのでは無くて、気持ちを持っている人と建築や空間をつなげることにフォーカスするのが良いだろう。気持ちの良い家や空間をつくることを直接的に目指すのではなくて、様々な気持ちを抱く人が家や空間とどのようにつながるのか、それを建築におけるプランや形で表現する。あくまでも実態として「気持ち」が建築の中でプランや形を成す。それは「気持ち」に直接的な形になる情報が無いから難しいかもしれないが、「気持ち」を含めた感性が重視される時ならば求められることだろう。
"How to handle" feelings "in architecture"
The term "feeling" includes mood and emotion, but there is no point in asking "feeling" where it is not directly related to the plan or shape in architecture. It can be anything, and if you say that this is "comfortable", then you can do whatever you like.
Then, when thinking about how to handle "feelings" in architecture, I first try to think of ways to create a comfortable space. "Feelings" vary from person to person, and the phrase "comfortable" and the phrase "comfortable" with the same meaning are not clear and unclear, but everyone thinks that they have a good meaning. Therefore, if it is a house, for example, it is easy to directly connect it to the house building. However, if you do so, it is the same as the first story, but you can just say "This is a comfortable house", and if you do not agree, that is the end.
When dealing with "feelings" in architecture, it is better to focus on connecting people who have feelings with architecture and space, rather than focusing on specific feelings. Rather than directly aiming to create a comfortable house or space, we will express how people with various feelings connect with the house or space in the plan or form of architecture. As a matter of fact, "feelings" form plans and shapes in architecture. It may be difficult because there is no information that directly forms "feelings", but it will be required when sensitivity including "feelings" is emphasized.
気分と感情は別ものとされるが、人の気持ちを扱うことでは同じと考えると、建築では人の気持ちを直に扱い、その気持ちが直に形になることがない。気持ちは一時的な場合もあるから、その瞬間を捉えて形にすることに意味がないのかもしれないし、気持ち自体に建築として形になる情報が無いから、それができないのかもしれない。
建築で人の気持ちを扱う例としてよくあるのは「居心地の良さ」をうたうことで、「居心地の良さ」は気持ちが良い様だから、居心地の良い空間を目指しましょう、それは良いことですとなる。ただ、それはある意味当たり前で、誰も気持ちが悪い建築などつくりたくは無い。
気持ちという人によって違い、実態が無く、故に直接的には形につながらないものをプランに結びつける術を探している。
"Make your feelings a plan"
Moods and emotions are different, but if you think that dealing with people's feelings is the same, architecture treats people's feelings directly, and those feelings do not take shape directly. Feelings may be temporary, so it may be meaningless to capture the moment and shape it, or it may not be possible because the feelings themselves do not have information that can be shaped as architecture.
A common example of dealing with people's feelings in architecture is to sing "comfort", and "comfort" seems to be comfortable, so let's aim for a cozy space, which is good. .. However, that is natural in a sense, and no one wants to make an unpleasant architecture.
I'm looking for a way to connect things that are different depending on the person's feelings, have no reality, and therefore do not directly form a form, to the plan.
昔、今から20年ぐらい前にアルヴァ・アアルトの建築を見た。それは北欧のフィンランドにあり、とても美しい国に建つ魅力的なモダニズム建築たちだった。
まだフィルムカメラ全盛の時代、デジカメは出始め、とても写真映りの良い建築ばかりでたくさんシャッターを切ったが、その瞬間は動きを止め、目の前の建築から目をそらすのが勿体なかった。
フィンランドの自然が投影されているかのような形と素材感、そして、そこにモダニズムの端正さを兼ね備えている空間では、じっとなどしてはいられず、動き回ることによって身体で空間を感じとり、この建築を理解しようとした。
アアルトの建築を語る言葉はたくさんあるだろうが、フィンランドの大自然と同じで、まずそれを体験しなければ何も理解できないし言葉にもできないと考え、またアアルトの建築が人のアクティビティを喚起するような、それはまるで森の中のような、光の差し込み方や素材の使い方がそのような仕掛けをしているようにも思え、歩き回ることでアアルトの建築の写真では表現されない部分が理解できるかもしれないと考えた。
モダニズムの建築というと自律した建築というイメージをすぐに持つが、アアルトの建築は自然と人工の対概念に両掛かりして、人の感受によって見え方が変わるような半自律半他律のような建築だった。
"Semi-autonomous and semi-heteronomy architecture"
A long time ago, I saw the architecture of Alvar Aalto about 20 years ago. It was a fascinating modernist architecture in a very beautiful country in Northern Europe Finland.
In the heyday of film cameras, digital cameras began to appear, and I released a lot of shutters with only very good-looking architecture, but at that moment I stopped moving and it was a waste to look away from the architecture in front of me.
In a space that combines the shape and texture of Finnish nature as if it were projected, and the neatness of modernism, you can't stay still, and you can feel the space with your body by moving around. I tried to understand.
There are many words that describe Aalto's architecture, but like the wilderness of Finland, I think that I can not understand anything or put it into words without first experiencing it, and Aalto's architecture evokes human activity. It seems like in the woods, how to insert light and how to use materials is such a mechanism, and by walking around you can understand the parts that are not expressed in Aalto's architectural photographs. I thought it might be.
Modernist architecture immediately has the image of autonomous architecture, but Aalto's architecture is like a semi-autonomous semi-heteronomy in which the appearance changes depending on the perception of human beings, which is a combination of natural and artificial concepts. It was architecture.
建築という物と感情を結びつけることができている建築は無い。あくまでも建築の形式の中で感情を恣意的に扱っているか、二次的に感情を絡めてくるだけである。
これ程建築の歴史が長いのにできないのは、人の感情を主題として建築家が扱ってこなかったからで、ところが感情に訴えかける試みは住宅にはあるが、それが建築という形に帰結できないでいる。
建築以外に関わる人は建築を通して自分の感情が満たされることを望んでいるにも関わらず、それに応えることをする建築家も、それに応えることができる建築に携わる人もいない、それが現状である。
"Architecture that connects with emotions"
There is no architecture that can connect emotions with architecture. To the last, emotions are treated arbitrarily in the form of architecture, or emotions are entwined secondarily.
The reason why architecture has such a long history cannot be done because architects have not dealt with human emotions as the subject, but there are attempts to appeal to emotions in houses, but it cannot be concluded in the form of architecture. ..
People who are not involved in architecture want their emotions to be satisfied through architecture, but there are no architects who can respond to it, and no one who is involved in architecture who can respond to it. ..
空間の中で居場所を選ぶ場合、あらかじめ何かしらのルールが設定されており、そのルールに従って選ぶことになる。そのルールは建築の範疇である場合もあるし、そうではない場合もある。
建築がそのルールを決めることができる場合は、形として居場所を選ぶことが許されている場合であり、選ぶことがデザインと結びついている場合である。また、選ぶのは人なのて、人と建築との結びつきも生まれている場合である。
形とはその生成過程での動的な瞬間を捉えたものだという。ならば、形は動的なこととして、居場所を選ぶことも動的なことになるので、どちらも動的であるから、居場所を選ぶことと形をつなげることはできることになる。
"Because it is dynamic, it connects"
When choosing a place to stay in a space, some rules are set in advance, and you will choose according to those rules. The rule may or may not be an architectural category.
If architecture can determine its rules, it is when it is allowed to choose whereabouts as a form, and when choosing is tied to design. Also, since people are the ones to choose, there is also a connection between people and architecture.
The shape is said to capture the dynamic moments in the process of its formation. Then, since the shape is dynamic and the choice of whereabouts is also dynamic, both are dynamic, so it is possible to connect the choice of whereabouts with the shape.
形の情報が無い言葉を建築にすることはできない。例えば、エコロジーという言葉も直接的には形の情報を持たないので、エコ住宅といっても、エコロジーという言葉を形にした訳ではなくて、エコロジーという言葉から環境に配慮した住宅というものを考え、例えば、省エネになるように一次エネルギーを削減できる仕組みを導入したり、太陽光発電を載せたりなどをして、建築として形にしていく。
だから、形の情報が無い言葉を建築にしようとする場合は、一旦、形の情報を持つ言葉に変換をするか、形につながる物を間に挟むかしかない。
"Words that do not lead to shape"
Words without shape information cannot be made into architecture. For example, the word ecology does not have direct form information, so even if we say eco-house, we do not think of the word ecology as a form, but rather an environment-friendly house from the word ecology. For example, we will introduce a mechanism that can reduce primary energy to save energy, install solar power generation, etc., and shape it as a building.
Therefore, if you want to make a word without shape information into an architecture, you have to convert it to a word with shape information or put something that leads to the shape in between.
ひとつの空間の中で居場所を見つけようとしたら、何を基準に決めるだろうか。それは、どうのような空間なのか、何のためにそこにいるのか、といった自分の外側にある要因にもよるのかもしれないが、そうした場合は簡単であり、そこでのルールに従うか、目的を満たす居場所を見つければ良い。
それならば、空間の方も簡単であり、ルールを設定するか、目的が満たされるような仕掛けを施せば良い。大概の建築はこれで済む。
ただ、人が住む空間はそうはいかないかもしれない。人の内側に要因がある場合も出てくるだろう。例えば、気分や感情で居場所を決めることの比重が高くなるかもしれない。
建築としては要因を外側に見つける場合がわかりやすいし、それは建築計画学として成り立っている。しかし、要因を内側に見つける場合は、例えば、気分や感情には形につながる直接的な情報が無いので、気分や感情を直接的に扱い形にした建築を今までに見たことが無い。
"Architecture of mood and emotion"
If you try to find a place in one space, what are your criteria? It may depend on factors outside of you, such as what kind of space you are in and what you are there for, but in that case it is easy and you should follow the rules there or aim for it. All you have to do is find a place to meet.
In that case, the space is easier, and you can set rules or make a mechanism to satisfy the purpose. This is all that is needed for most architecture.
However, the space where people live may not be so. There will be cases where there is a factor inside the person. For example, deciding where to stay based on mood and emotions may become more important.
It is easy to understand when the factors are found outside in architecture, and it is established as architectural planning. However, when finding factors inside, for example, moods and emotions do not have direct information that leads to shapes, so I have never seen an architecture that directly deals with moods and emotions.
壁が動く訳でもないのに迫ってくるように感じるのは圧迫感があるからで、その圧迫感は単に壁が目の前にあるからだけでなくて、その壁を見た時の印象が大きく関わり、その印象は壁の表面の仕上げの色や質感や感触といった物質感を感じとり生成される。
これは壁だけでなくて、物全般にいえることだと思うが、建築以外だと手で容易に触れることができる場合が多いから、見た目の印象も関わるが、まず手で触れて確かようとして、その物を把握しようとする。
建築は人よりスケールが大きいから、人が手で触ることができる部分が限られる。それが事前にわかるから見た目の印象による把握を優先してしまいがちであり、だから、建築は他の物より、まずどのように見えるかが重要になってくる。
建築ぐらいではないだろうか、遠景を意識して、それを見せようとするのは。他の物では遠目に見えることをあまり意識しないだろうし、意識をする必要もないだろう。
"What it looks like"
The reason why I feel that the wall is not moving but it is approaching is because there is a feeling of oppression, and the feeling of oppression is not only because the wall is in front of me, but also the impression when I see the wall. It has a lot to do with it, and the impression is created by feeling the material feeling such as the color, texture and feel of the finish on the surface of the wall.
I think this applies not only to walls, but to things in general, but since it is often easy to touch with hands other than architecture, the impression of appearance is also relevant, but first try to touch it with your hands. , Try to figure out the thing.
Since architecture is larger than humans, the parts that humans can touch are limited. Since it is known in advance, it is easy to give priority to grasping by the impression of appearance, so it is more important to see what architecture looks like than other things.
Perhaps it's about architecture, but I'm conscious of the distant view and trying to show it. You wouldn't be too conscious of what you see in the distance with other things, and you wouldn't have to.
輪島塗のフリーカップは、形式が先で、形式で内容を構成しているので、形式と内容が不可分ではあるが、形式が強過ぎて、対概念である内容が無いことになっている。だから、内容としての素材であるその漆塗りが決まらない、決めようがない。
形式で形が決まり、そこには内容に当たる素材が元々存在しないから、その漆塗りが決まらない。その形式とは、飲み口の厚みを変えて、その日の気分で飲み口を選ぶと、フリーカップの見え方も変わるということと、輪島塗ということ。
形式の中に内容を、物質を含めてしまえば良いが、輪島塗にする理由は布着せがあるから口当たりが軟らかい、手で持った時に熱くないなど、ただ、そうすると漆の色は形式とは何も関係が無いので、何色でも良いことになる。
"The content is undecided"
Wajima-nuri's free cup has the format first, and the content is composed by the format, so the format and content are inseparable, but the format is too strong and there is no content that is the opposite concept. Therefore, the lacquer coating, which is the material of the content, is undecided and cannot be decided.
The shape is decided by the form, and since there is no material that corresponds to the content, the lacquer coating is not decided. The format is that if you change the thickness of the mouthpiece and choose the mouthpiece according to the mood of the day, the appearance of the free cup will also change, and Wajima lacquer.
It is good to include the substance in the form, but the reason for using Wajima lacquer is that it has a soft texture because it is clothed, and it is not hot when held by hand. However, what is the color of lacquer? It doesn't matter, so any color will do.
音楽は形式が内容を構成するそうで、形式と内容は対概念だが、不可分なものになっており、音楽には全く詳しくないが、建築のモダニズムでは形式が何とかイズムとして自律していて、その何とかイズムが内容に覆い被さるようにして成り立っており、音楽と建築は一見似ているようだけれども、建築のモダニズムの方が形式が強く自律しているように思う。その後、建築は何とかイズムによる自律性に反発する形でよりコンセプチュアルな物、あるいは、より社会的な物を指向するようになるのだが、形式がまずはじめにあることには変わりがなかった。
その状況は、はじめて建築を勉強していた時から変わりがないので、形式から入り考えはじめることが染み付いていて、仕組みや枠組みをまず決めようとしてしまい、それが設計やデザインのお決まりのパターンで、その仕組みや枠組みは別の言い方ではコンセプトであり、全体計画であり、理念であり、形式から入りはじめることにより、様々な建築を成り立たせている領域と馴染みがよくなり、反発が無くなるのだろう。
内容は別の言い方では素材であり、質料であり、物の性質的なことになるので、形式を決めた後からどうにでもなるという暗黙の了解もある。建築は形式が先ということから逃れられないのだろうか。逃れる必要が無いのかもしれないが、物の性質的なことから形式が決まることがあるならば、その形式はより建築にしやすいはずである。
"Format first, content first"
It seems that form constitutes the content of music, and form and content are opposite concepts, but they are inseparable, and although I am not familiar with music at all, in architectural modernism, form is somehow autonomous as an ism, and that It is made up of isms that somehow cover the content, and although music and architecture seem to be similar at first glance, modernism in architecture seems to be more formally autonomous. After that, architecture somehow turned to more conceptual or more social things in a way that repelled the autonomy of ism, but the form remained in the first place.
The situation hasn't changed since I was studying architecture for the first time, so it's so ingrained that I start thinking from the form, and I try to decide the mechanism and framework first, which is the usual pattern of design and design. In other words, the mechanism and framework are a concept, an overall plan, an idea, and by starting from the form, it will become familiar with the areas that make up various architectures, and there will be no repulsion. ..
In other words, the content is a material, a material, and a property of the thing, so there is a tacit understanding that it will be irrelevant after the format is decided. Can architecture escape from the fact that form comes first? It may not be necessary to escape, but if the nature of the object determines the form, the form should be easier to build.
ある感触があり、それに触れる前からその感触が想像できるならば、その感触は特有の、固有の形を持って物として現れていると、今まで考えていた。
だから、作品としての特殊解を求めるならば、その感触と特有の形とのマッチングをズラす必要があり、一般解を求めるならば、その感触と特有の形とのマッチングを合わせ、誰からも共感を得られるようにする必要があった。
ここでいう感触は別の言い方では素材であり、素材が持つなりたい形を特有の、固有の形とした。
ただ、もかしたら、形が先かもしれないと思いはじめた。素材と形は対概念として認識をされているが、素材と形は不可分であり、音楽などは形に当たる形式が素材に当たる内容を構成している。
形が感触を構成する。感触に当たる部分は質料や物質感、内容などに置き換えても良いし、形は形式と読み替えても良い。形式が内容を構成する。
形式が先に来るのはモダニズムのようだが、モダニズムは内容と結び付けない。ならば、結びつける内容としての感触などの物質感がモダニズムとの違いをつくり出してくれるだろう。そして、形式が先ならば、実際の建築として形にはしやすい、そのように訓練を受けてきたから。だだ、形式が先だと窮屈な形になりそうな気がしてしまうから、構成するものとして感触が良さそうな気がしている。
"Feel and shape"
Until now, I have thought that if there is a certain feeling and the feeling can be imagined before touching it, the feeling appears as an object with a peculiar and peculiar shape.
Therefore, if you want a special solution as a work, you need to shift the matching between the feel and the peculiar shape, and if you want a general solution, you can match the feel and the peculiar shape and everyone I needed to be able to empathize.
In other words, the feel here is a material, and the shape that the material wants to be is a unique and unique shape.
However, I began to think that the shape might come first. The material and the shape are recognized as a counter-concept, but the material and the shape are inseparable, and in music etc., the form corresponding to the shape constitutes the content corresponding to the material.
The shape constitutes the feel. The part that corresponds to the feel may be replaced with a material, material feeling, content, etc., and the shape may be read as a form. The format constitutes the content.
It seems that modernism comes first in form, but modernism is not associated with content. If so, the material feeling such as the feeling as the content to be connected will make a difference from modernism. And if the form comes first, it is easy to form it as an actual architecture, because I have been trained in that way. However, if the format comes first, I feel that it will be cramped, so I feel that it feels good as a composition.
使う素材はなるべく自然素材かその加工品にしようとする。それは見た目で感触がわかりやすいからであり、例えば、内装仕上げにビニールクロスやできればオイルペイントやエマルジョンペイントも使いたくないし、もっといえば、石膏ボードも使いたくない。
コンクリートやモルタルも自然の素地の範疇として、それからベニヤも、あと鉄やステンレスやアルミ、ガリバリウム鋼板などの金属加工品もそれは金属としての各々の感触があり、サイディングには無いから使いたくないし、タイルはその感触に好き嫌いがあるかもしれないが良いだろう。
木の屑を固めたような、それは加工品かもしれないが擬きは使いたくないし、左官の仕上げは概ね予算が許せば、どうしても使いやすくて仕事が楽になりそうな建材は躊躇する、おもちゃの家になりそうで。
やはり、選ぶのは風合いや感触が脳裏に刻まれている物であり、それが想像でき、なおかつ、経年変化して魅力が増す物ばかりで、そこにシンプルさの好みを加える。
そして、そのような素材には形が潜在していると思い、その形をどのようにして見つけ、デザインにいかすかがまた面白い。
"If you choose the material"
I try to use natural materials or processed products as much as possible. That's because it's easy to see and feel, for example, I don't want to use vinyl cloth, preferably oil paint or emulsion paint to finish the interior, or even gypsum board.
Concrete and mortar are also included in the category of natural bases, and veneers and metal processed products such as iron, stainless steel, aluminum, and gallibarium steel plates have their own feels as metals, and I do not want to use them because they are not in siding, and tiles. May have likes and dislikes in its feel, but it's good.
It may be a processed product, but I don't want to use imitations, and if the budget allows for plastering, I hesitate to use building materials that are easy to use and work. It's going to be home.
After all, the ones that have the texture and feel engraved in their minds are the ones that can be imagined, and the ones that change over time and become more attractive, and add a taste of simplicity to them.
And I think that the shape is latent in such a material, and it is also interesting how to find the shape and use it in the design.
物の中に人をみる。物と人の関係性で建築を考えれば、空間は勝手に生成されていくから、物としての物質感や質料性を人を媒介にして表現していく。
人が触れる、もしくは建築は人のスケールよりも大きいので、実際に触れることができる場所は限られ、むしろ触れられない部分の方が多いから、その場合、人は見ることでも感触を感じることができる。
前提として、人が認識をする物としての物質感や質料性の総和が建築だとしている。だから、物質感や質料性を感触で表現し、その感触は人が享受する物であり、その享受の仕方で人の認識が変わり、建築も変わる。
"Architecture for people"
I see people in things. If we think about architecture based on the relationship between things and people, space will be created without permission, so we will express the materiality and materiality of things through people.
Since people can touch or the architecture is larger than the scale of people, the places where they can actually touch are limited, and rather there are many parts that cannot be touched, so in that case, people can feel the touch even by looking at it. it can.
As a premise, architecture is the sum of materiality and materiality as things that people recognize. Therefore, the material feeling and the materiality are expressed by the touch, and the feeling is something that people enjoy, and the way people enjoy it changes the perception of people and the architecture.
建築と建築以外の物との違いは内部に人が入れるかどうか、内部に人が入り込める空隙があるかどうか、その空隙を空間と呼ぶが、その違い、当たり前のような違いだけれども、その違いが大きい。内部に人が入り込める空間があることによりスケールが違う、大きい、建築はそれ以外の物と比べて大きくなる。この大きさが人の手の中で扱えるか、人が足を使って動くのかの差になる。
したがって、建築という物は人との関わり合いの中で存在することになる。建築以外の物であれば、人との関わり合いがなくても、例えば、石、木、茶碗でも、茶碗は人が使う物だが、人がいなくても茶碗はそこに存在できる、その時はもしかしたら茶碗という使われ方はしないかもしれないが、鑑賞用としては存在できる。だから、建築も廃墟になれば、建築の用をなさないから、人との関わりがなくても存在できる。しかし、廃墟は建築か、という問いは残る、同様にギリシャのパルテノン神殿も。
純粋に人との関わり合いがなく、物としてのみ存在する建築はあり得るのだろうか。それは事業としての出発点では人の介在は当然あるにせよ、それはさて置いて、人との関わりがない物としての建築がイメージできない。もし物としてのみの建築があるならば、その建築を使う人がいない、すなわち、ピラミッドやタージマハルのような巨大なお墓ぐらいだろうか。ならば、人との関わり合いの中で建築を考える方が素直で自然のような気がする。
"Architecture as a thing"
The difference between architecture and non-architectural things is whether or not people can enter inside, whether or not there is a space inside, and that space is called a space. The difference is a natural difference, but the difference. Is big. The scale is different due to the space inside, which is large, and the architecture is larger than other things. This size makes a difference whether it can be handled in the hands of a person or whether a person moves with his or her feet.
Therefore, architecture exists in the relationship with people. If it is something other than architecture, even if there is no relationship with people, for example, stones, wood, bowls, bowls are used by people, but even if there are no people, bowls can exist there, at that time If so, it may not be used as a bowl, but it can exist for viewing. Therefore, if architecture is abandoned, it will not be used for architecture, so it can exist without any involvement with people. However, the question remains whether the ruins are architecture, as well as the Parthenon in Greece.
Is it possible for architecture to exist only as a thing without having a pure relationship with people? It is natural that there is human intervention at the starting point as a business, but aside from that, I cannot imagine architecture as a thing that has nothing to do with people. If there is an architecture only as a thing, then no one uses it, that is, a huge tomb like the Pyramid or the Taj Mahal. If so, I feel that it is more straightforward and natural to think about architecture in relation to people.
建築の内容が気になり、どうしても建築は素材があって形になると考えてしまうが、形は空間の輪郭で、その空間にある「内容」に興味がある。
内容となると物から離れていくように感じるが、建築は物そのものの代表的な存在だから、それだけ物としては強度があるから、内容に焦点を合わせても物としての建築の部分は必ず残る。
この場合、内容とは建築を使う人が織りなすことで、人の感情や気分などが建築に作用することであり、素材と形という対概念において、両方を上手くとりなし、人の感情や気分がその都度、空間をつくるものである。
"Material, shape and content"
I'm curious about the contents of architecture, and I think that architecture has materials and forms, but the shape is the outline of the space, and I'm interested in the "contents" in that space.
When it comes to content, it feels like it's moving away from things, but since architecture is a representative of the thing itself, it's strong as a thing, so even if you focus on the content, the part of architecture as a thing always remains.
In this case, the content is weaved by the person who uses the architecture, and the emotions and moods of the person act on the architecture. In the opposite concept of material and shape, both are well handled, and the emotions and moods of the person It creates a space each time.
アクティビティの発露に建築という物が作用することがあるだろうかと考えてみた。あるとしたら外からの作用であり、建築がアクティビティの決起を促すことになる。それはまるで建築が人になったようでもある。建築は元々人が使う物だが、時としてその建築に感動する、その建築から感動させられる。感動することもアクティビティならば、その建築は人を感動させるためにうまく仕込まれているのかもしれない。
だから、受け身でそのような建築に当たれば、簡単に意のままに翻弄される。それはそれで楽しいことだが、あとが怖い、他の建築では物足りなくなる。
"Prepare architecture"
I wondered if architecture could affect the manifestation of activities. If there is, it is an action from the outside, and architecture will encourage the activity to take place. It's as if architecture has become a person. Architecture is originally used by people, but sometimes it impresses me, and I am impressed by it. If impressing is also an activity, the architecture may be well-crafted to impress people.
So, if you passively hit such an architecture, you can easily be at the mercy of it. That's fun, but scary, and other architecture isn't enough.
人のアクティビティの発露には内からと外からの2種類の作用があり、内とは自分の内面で、感情や気分などであり、外とは社会や環境で、そこに慣習や倫理上の規範のようなものも含まれ、これらが単体で作用することもあれば、複雑に絡み合い作用することもある。
だから、本来は人のアクティビティは人の数だけ存在するようなもので、把握することはできないが、そこに様々な前提条件や設定や環境などを与えることにより把握可能にする。
その様々な前提条件や設定や環境などを構築することを設計といったり、デザインと表現したり、その様々な前提条件や設定や環境などを角度を変えて考えることが哲学であったり、社会学であったり、そうすると何かいろいろなことが繋がるようで面白いと今更ながらにふと思った。
"Understanding activity"
There are two types of actions in the manifestation of human activities, from the inside and the outside. The inside is one's inner side, emotions and moods, and the outside is social and environmental, and there are customs and ethics. It also includes things like norms, which can act alone or intricately intertwined.
Therefore, it seems that there are as many human activities as there are people, and it is not possible to grasp them, but by giving them various preconditions, settings, environments, etc., it is possible to grasp them.
It is a philosophy or sociology to think about the various preconditions, settings, environment, etc. from different angles, such as designing or expressing the construction of the various preconditions, settings, environment, etc. However, I suddenly thought that it would be interesting to connect something with it.
制作中のフリーカップは飲み口の厚みを変え、その日の気分によって飲み口の位置を選ぶことにより、フリーカップの見え方がその都度変わるようにした。
飲み口の位置を厚みによって選ぶということは、自分の口に当たるフリーカップの飲み口の感触を選んでいることになる。厚みの違いは、フリーカップとしての形の違い、形の変化になる。
感触そのものには形の情報が無いが、その感触を味わう人のアクティビティ、このフリーカップの場合でいうと飲み口に唇を当てること、を介すれば、感触と形が結びつく。さらにいえば、その感触を選ぶ時の判断基準を人の気分にすれば、気分と形が結びつく。
何事も形に結びつけることができれば建築になる、といつも考えているので、気分と建築を結びつけることを試みている。
"Connect with shape"
The thickness of the free cup under construction was changed, and the position of the mouth was selected according to the mood of the day so that the appearance of the free cup would change each time.
Choosing the position of the mouthpiece according to the thickness means choosing the feel of the mouthpiece of the free cup that hits your mouth. The difference in thickness is the difference in shape as a free cup and the change in shape.
There is no shape information in the feel itself, but the feel and shape are linked through the activity of the person who tastes the feel, in the case of this free cup, putting the lips on the mouth. Furthermore, if the criteria for choosing the feel is the mood of a person, the mood and shape are linked.
I always think that if everything can be connected to the shape, it will be architecture, so I am trying to connect mood and architecture.
建築や空間は人が都合よく解釈をしていて、人によって受け取る印象が違うとしたら、建築や空間は物として自律することはできなくて、建築や空間は物だが、自律した完全な物ではなく、常に不完全な物ということになり、そこに何を足してあげれば完全な物になるのか、あるいは、何かを足せる余地を意図的に残すことを考えるのが設計ということになるだろう。
何を足すか、何が足りないかは人にどのような印象を与えることを意図するかで決まるが、そもそも人に様々な印象を与え、その中からでも、どのような印象を受け取るかを人の方で選択できるようにすることも考えられる。
他律的な建築を所望するならば、後者の方が可能性を感じる。
"Architecture of choice"
If people interpret architecture and space conveniently, and the impression they receive differs from person to person, then architecture and space cannot be autonomous as objects, and architecture and space are objects, but they are imperfect and autonomous. Instead, it is always imperfect, and the design is to think about what to add to it to make it perfect, or to intentionally leave room for something to be added. Let's do it.
What you add and what you lack depends on what kind of impression you intend to give to people, but in the first place you give various impressions to people and what kind of impression you receive from them. It is also conceivable to allow people to make choices.
If you want heteronomous architecture, the latter is more likely.
どこかに座ろうとした時に、平で、できればお尻が痛くないような、軟らかい場所を探そうとするだろう。その時の判断材料はお尻と接するところの感触であり、その感触は実際に座る前に想像で、その想像は過去の経験や似たような感触から推測している。
だから、人は物に実際に触れなくても、その物の感触を感じることができる。このことは物をつくる際にはとても重要で、特に建築は人のスケールよりかなり大きい場合がほとんどだろうから、建築の部位で日常的に人が実際に触れることができる部分はかなり限られるので、建築という物を全体的に把握しようとする場合はほとんどが非接触であり、ただ、それは日常的に触れる場所と意識的に区別されることはなく、連続的で一体の物として頭の中で合成されるだろう。
そして、その把握は人のアクティビティに影響を与えることになる。その把握によって何かを選択し、その選択によりアクティビティが決まる。さらに、その人の気分や感情が介在することにより、そのアクティビティはその時その場所限定のものになる。
"Architecture and feel"
When you try to sit somewhere, you'll try to find a soft place that's flat and preferably doesn't hurt your butt. The judgment material at that time is the feeling of contact with the buttocks, and that feeling is imagined before actually sitting, and that imagination is inferred from past experience and similar feelings.
Therefore, a person can feel the object without actually touching it. This is very important when making things, especially since architecture is often much larger than a person's scale, so the parts of the building that people can actually touch on a daily basis are quite limited. Most of the time when trying to grasp the whole thing of architecture, it is non-contact, but it is not consciously distinguished from the place where it is touched on a daily basis, and it is in my head as a continuous and one thing Will be synthesized in.
And that grasp will affect the activity of people. The grasp determines something, and that selection determines the activity. In addition, the intervening mood and emotions of the person make the activity then and locally limited.
建築という物が空間をつくる、この当たり前のことの物と空間の間に人を挟む。そして、挟むものは人の感覚であったり、感情であったり、目には見えなくうつろうもので、そのうつろいが建築の見え方や空間の見え方に影響を与える。
なぜ建築や空間の見え方であり、感じ方ではないのかというと、建築や空間をあくまでも物として扱いたいからで、見え方は実体が目の前にないと成り立たないが、感じ方だと実体が目の前になくても成り立ち、それは感じ方に物としての実体は関係ないことを意味している。
さらに、建築や空間の見え方にしたのは、建築や空間が人のスケールに比べてとても大きい割に、実際に手で触れる部分は案外少ないので、人は見ることによって触らなくもその感触を感じたり、理解したり、想像することができ、見ることによって物としての質感や感触が人に、人のアクティビティに影響を与え、人のアクティビティにより建築や空間の見え方がその都度変わり、決まるようにするためである。
"There is a person between things and space"
Architecture creates a space, and people are sandwiched between this natural thing and the space. And what is sandwiched is human senses, emotions, and invisible movements, and the movements affect the appearance of architecture and the appearance of space.
The reason why architecture and space are seen and not felt is because we want to treat architecture and space as objects, and the way of seeing is not possible unless the substance is in front of us, but the way of feeling is the substance. It holds even if it is not in front of you, which means that the substance as an object has nothing to do with how you feel.
Furthermore, the way the architecture and space look is because the architecture and space are very large compared to the scale of human beings, but the parts that are actually touched by hands are unexpectedly small, so people can feel the feeling without touching it. You can feel, understand, and imagine, and by seeing it, the texture and feel of the object affect people's activities, and the appearance of architecture and space changes and is determined each time. To do so.
ここのところ温熱環境について知識を蓄えている。来年から省エネ基準が義務化されるから、それに備えるためでもあるが、簡単にいうと、太陽の日射しは熱を持っているので、冬はその熱を利用し、夏はその熱を遮断し、快適な室温を効率良く保つための方法で、熱という目には見えない物を扱っている。
ちなみに、高気密高断熱だけでは一年を通して快適な室温を保つことはできない。その辺をプロでもわかっている人が少ない。
住宅という物を目には見えない熱に焦点を当てて、その快適性を室温で表現して設計しようという試みだが、もちろん、室温だけで快適な住宅にはならないが、目には見えない物が目の前に実物として存在している住宅という物に何らかの影響を与えるというところが面白く、それはデザインでも同じである。
デザインは目に見える形だけで表現されているように思われるかもしれないが、目には見えない何らかの影響を与えることを意図していて、少なくとも作者はそう考えているだろう。
だから、熱もデザインの範疇として扱えると考えれば、何らかの熱によるデザインも出現するだろうし、あと目には見えないが何らかの影響を与えるものは、建築の中だけでもまだまだたくさんあるから、例えば、感触などで、それをうまくデザインに取り入れることによって、まだ見ぬ新しい建築の姿がそこに隠されているかもしれない。
"Invisible but affecting architecture"
I have been accumulating knowledge about the thermal environment recently. Since energy saving standards will be mandatory from next year, it is also to prepare for it, but simply put, since the sun's sunlight has heat, we will use that heat in winter and block it in summer. It is a method for efficiently maintaining a comfortable room temperature, and deals with the invisible thing called heat.
By the way, it is not possible to maintain a comfortable room temperature throughout the year with only high airtightness and high heat insulation. There are few people who know that area even if they are professionals.
It is an attempt to design a house by focusing on invisible heat and expressing its comfort at room temperature, but of course, room temperature alone does not make a comfortable house, but it is invisible. It is interesting that there is some influence on the real house that exists in front of you, and it is the same in design.
The design may seem to be expressed only in a visible form, but it is intended to have some invisible effect, at least the author would think so.
Therefore, if we think that heat can be treated as a category of design, some kind of heat-induced design will appear, and there are still many things that are invisible but have some influence in architecture alone, so for example, feel. By incorporating it into the design well, the appearance of a new architecture that has not yet been seen may be hidden there.
建築の中で感触を味わうものがあるだろうか。人と建築が常に接している部位は床であるから、足の裏を介して床の感触を常に味わうことにはなっている。
昔、床の仕上げとしてシナベニヤを使用したことがある。その住宅の家族は完成後、スリッパではなく、靴下で生活をはじめた。そうすると、設計時にはそこまで意識が及んでいなかったが、シナベニヤの表面の仕上げの軟らかさを靴下越しに感じて、大げさではなくて本当に木の絨毯の上を歩いているようだった。
そうすると不思議なもので、その時は壁や天井にもシナベニヤの仕上げを施したのだが、壁や天井に直接触れること無しに見た目で、軟らかな感触が伝わってきて、空間全体が軟らかくまろやかに感じられた。
"A space where you can feel the touch"
Is there anything in the architecture that gives you a feel? Since the part where people and architecture are always in contact is the floor, the feel of the floor is always felt through the soles of the feet.
Once upon a time, I used cinnavenia to finish the floor. After completion, the family in the house began living in socks instead of slippers. Then, although I wasn't so conscious at the time of designing, I felt the softness of the surface finish of the cinnavenia through the socks, and it seemed that I was really walking on a wooden carpet rather than exaggerating.
Then, it was strange, and at that time, the walls and ceiling were also finished with cinnavenia, but without touching the walls and ceiling directly, the soft feel was transmitted, and the entire space felt soft and mellow. It was.
物と人がつながることに関心があり、フリーカップの制作では人の気分とつなげてみた。フリーカップの飲み口の厚みが不連続に変化しており、その日の気分で飲み口を選ぶと、厚みが違うから口当たりも違い、その口当たりの感触を唇に感じながら、その時の気分としっくりと合う所を選ぶと、不整形なカップ故に、飲み口の場所によりフリーカップの形が変わり、それはひとつとして同じ形の見え方になることはなく、気分によってフリーカップの見え方が決まるという物と人のつなげ方をした。
それと同じようなことを建築で考えているのだが、フリーカップと違い建築は動かない、だから、建築の中で動く要素を選択の対象とすることにした。ただもうひとつ、人は動くことができるので、人の動き、すなわち、アクティビティによって選択するということもできる。
人が気分によって居場所を選択すると、不整形なプラン故に建築の見え方がその都度変わるというルールで建築という物と人をつなげることはできる。あとは、気分で何をどのように選択するのか、そして、それが居場所を選択することになるのか、ここをもっと詳細に具体的にしているところである。
"Choice to connect things and people"
I was interested in connecting things and people, so I tried to connect with people's mood in the production of free cups. The thickness of the mouthpiece of the free cup changes discontinuously, and if you choose the mouthpiece according to the mood of the day, the mouthfeel will be different because the thickness is different, and while feeling the feel of the mouthfeel on your lips, you will feel at that time. If you choose a suitable place, the shape of the free cup will change depending on the location of the mouthpiece because of the irregular cup, and it will not look the same as one, but the appearance of the free cup will be determined by your mood. How to connect people.
I'm thinking about the same thing in architecture, but unlike the free cup, architecture doesn't move, so I decided to select the elements that move in architecture. However, since people can move, it is possible to make a choice according to the movement of the person, that is, the activity.
When a person chooses a place to stay according to his or her mood, it is possible to connect people with architecture by the rule that the appearance of architecture changes each time due to an irregular plan. The rest is more specific about what to choose and how to choose it in the mood, and what it means to choose where to go.
人の気分と建築をつなげてみようと思い、建築は物だから人がいなくても存在することはできるが、建築は人が使い、なおかつ入り込む物だから、人がいてはじめて建築としての価値が出る部分もあり、そこを気分を媒介にして人と建築をつなぐという観点で構築してみようと思う。
その時に人と建築をつなぐルールを設定してみた。それは、その時の気分によって人が自分の居場所を選択し、そうすることによって建築の見え方が決まる、というもので、気分によってその都度ちがう見え方の建築が出現する。
このルールによって、人の気分と建築の見え方がダイレクトにつながり、それは人と建築をダイレクトにつなげることになる。
では、もっと具体的に言うと、人が気分によって自分の居場所を選択した場合、プランが不整形ならば、居場所によって建築の見え方は変わる。ただ単にプランを不整形にするのは誰にでもできることなので、肝心なのは、気分による居場所の選択の仕方であり、それには気分と同じように変化するものを用いることになる。
"Rules that directly connect people and architecture"
I wanted to connect people's moods with architecture, and since architecture is a thing, it can exist without people, but since architecture is something that people use and enter, the part where the value of architecture comes out only when there are people. There is also, and I will try to build it from the perspective of connecting people and architecture through mood.
At that time, I set a rule that connects people and architecture. That is, a person chooses his or her place of residence according to the mood at that time, and the appearance of the architecture is determined by doing so, and an architecture with a different appearance appears each time depending on the mood.
By this rule, the mood of the person and the appearance of the architecture are directly connected, which directly connects the person and the architecture.
So, more specifically, if a person chooses his or her location according to his or her mood, and if the plan is irregular, the appearance of the architecture will change depending on the location. Anyone can simply make a plan irregular, so the point is how to choose a place to stay according to your mood, and you will use something that changes in the same way as your mood.
汎用性のあるルールをつくり、それを可視化すること、それが設計であり、デザインであるとした場合、整合性をとるためにルールは出現した建築によってカスタマイズされ、またさらに新たに出現した建築によりカスタマイズされることを繰り返さない建築はとても傲慢で嫌らしく見える。
それは、それさえすればいいというのが滲み出ており、それはつまらなく、新鮮さに欠ける。それは自身のスタイルを持つこととは正反対で、むしろ没個性へとつながる。
設計に正解を求めるようなことを意識的にしたことはないが、集合住宅の計画をしていると無意識に正解を探しているような気になる時があり、その都度改めようとする。集合住宅の効率性や集積性を意識すると、建築計画上、そこに正解が漂っているかの如く錯覚を起こしてしまい、そこから今度は外れようとすると、効率性や集積性が蔑ろになり、それに違和感を覚える。
汎用性のあるルールは、一般的に共通理解がある枠組み、例えば、集合住宅の効率性や集積性、の上に成り立つことになると考えているが、そうすると、それを可視化した場合、その集合住宅の効率性や集積性が邪魔になることがあるかもしれないと考えられる。
だから、設計のプロセスで架空の建築を立ち上げ、ルールをカスタマイズすることを繰り返してみようと考えている。
"Customize rules"
Creating a versatile rule and visualizing it, if it is a design and a design, the rule is customized by the emerging architecture for consistency, and also by the newly emerging architecture Architecture that is not repeatedly customized looks very arrogant and disgusting.
It's exuding that all you have to do is that it's boring and lacking in freshness. It's the opposite of having your own style, but rather leads to personality.
I have never consciously asked for the correct answer in the design, but when I am planning an apartment house, I sometimes feel like I am unconsciously searching for the correct answer, and I try to change it each time. If you are conscious of the efficiency and agglomeration of an apartment house, you will get the illusion that there is a correct answer in the architectural plan, and if you try to deviate from it this time, the efficiency and agglomeration will be despised. It makes me feel uncomfortable.
We believe that versatile rules will generally be built on a framework that has a common understanding, such as the efficiency and agglomeration of apartments, but then, when visualized, that apartment. It is thought that the efficiency and agglomeration of the house may be an obstacle.
That's why I'm thinking of launching a fictitious building in the design process and repeating customizing the rules.
汎用性のあるルールをつくり、それを可視化すること、それが設計であり、デザインであるとした場合、ルールはコンセプトや理念などとは違い、もっと実際に即したことであり、コンセプトや理念はその中に含まれ、溶けてなくなり旨味だけになっているような状態で、そのルールがあれば、どこでも誰でもいつでも建築として形にできるものである。
そして、そのルールは人を巻き込む、人がいてはじめて成り立つ、ただし、そのルールの発端は物になり、物の有り様がルールをつくる上で一番重要となる。
今までそのルールは建築家の頭の中にあり、そのルールがわかる瞬間があるとすれば、それは事後、建築として形になった後だった。だから、本当にそのルールが有効かどうかは形となって出現した建築で証明していた。
だから、整合性をとるためにルールは出現した建築によってカスタマイズされ、カスタマイズされたルールを知ることになる。
"Rules in my head"
Creating a versatile rule and visualizing it, if it is a design and a design, the rule is different from the concept or idea, it is more practical, and the concept or idea is If there is a rule in it, it can be formed as an architecture anytime, anywhere, in a state where it is contained in it and is not melted and has only umami.
And, the rule is established only when there is a person who involves people, but the beginning of the rule becomes a thing, and the state of the thing is the most important in making a rule.
Until now, the rule was in the mind of the architect, and if there was a moment when the rule was understood, it was after the fact, after it was formed as an architecture. Therefore, whether the rule was really valid was proved by the architecture that appeared in the form.
So, for consistency, the rules are customized by the architecture that emerged, and you will know the customized rules.
フリーカップの制作で、飲み口の厚みを選択することによって形の見え方が変わるという、いわばルールなようなものを先に思いつき、そのルールに肉付けをしていった。
そのルールはフリーカップの最終形態の方向性を示すものだが、かと言ってひとつの最終形態に収斂するものではないから、そのルールによって導き出される最終形態は人によって違うだろう、例えば、形が四角でも何でもいい、という意味で、そのルールには汎用性がある。
これをきっかけに、汎用性のあるルールをつくり、それを可視化すること、それが設計であり、デザインであり、汎用性がない、特殊なルールをつくり、それを可視化するような設計やデザインには魅力を感じないことがわかった。
"Creating versatile rules"
In the production of free cups, I first came up with something like a rule that the appearance of the shape changes depending on the thickness of the mouthpiece, and I fleshed out that rule.
The rule indicates the direction of the final form of the free cup, but it does not converge to one final form, so the final form derived by the rule will differ from person to person, for example, the shape is square. But the rule is versatile in the sense that it can be anything.
With this as a trigger, create a versatile rule and visualize it, that is design, design, non-universal, special rule, and design or design that visualizes it. Turned out to be unattractive.
集合住宅の計画をしているので、集合住宅の不完全性のようなことを考えていて、それは不特定多数の人のために用意された空間は人が入ってはじめて完全になるから、その手前の人というピースが無い状態が集合住宅の建築としての姿で、それは不完全な状態であり、そこを目指して設計するということだが、実際の設計では空間には部屋名がつき、そこに置かれる物もはじめに想定をするので、例えば、ベッドの位置やテーブルの位置などで、それらに合わせてコンセントの位置などの設備も決めたりして、そうすると、それはもはや不完全な状態ではないのではないかと思いはじめた。
同じように人が関与してはじめて成り立つものとして茶室の床の間がある。そこに人の手により掛軸やお花を設えて季節感や叙情を表現する。だから、その空間は普段何も無い時は不完全な状態であり、ただ、掛軸やお花を設えることははじめに想定されている。
集合住宅と茶室の床の間を比較すると、茶室の床の間は、はじめから想定されていることがあるにせよ、不完全な状態だと思え、それは想定されている完全な状態に至るまでの過程での選択の自由と創造性の度合いの違いがあると考えられた。
"Incomplete difference"
Since I am planning an apartment house, I am thinking about things like imperfections in an apartment house, because the space prepared for an unspecified number of people will be complete only when people enter. The state where there is no piece of the person in the foreground is the appearance as an apartment building, which is an incomplete state, and it is designed aiming for that, but in the actual design, the space has a room name, and there Since the things to be placed are also assumed first, for example, the position of the bed and the position of the table, and the equipment such as the position of the outlet are decided according to them, and then it is not in an incomplete state anymore. I began to wonder if it was there.
In the same way, there is a tea room alcove that can only be realized when people are involved. A hanging scroll and flowers are set up there by human hands to express a sense of the season and lyricism. Therefore, the space is usually in an incomplete state when there is nothing, but it is initially assumed that hanging scrolls and flowers can be placed.
Comparing the alcove between the apartment house and the alcove of the tea room, the alcove of the tea room seems to be incomplete, even if it was supposed from the beginning, and it is in the process of reaching the expected perfect state. It was thought that there was a difference in the degree of freedom of choice and the degree of creativity.
集合住宅の計画をしている。そこでアクティビティについて考えてみた。人のアクティビティは不完全な物を完全にするために発生するとするならば、そもそも集合住宅は不完全性を纏うビルディングタイプであり、不完全性に度合いがあるならば、専用住宅よりも不完全性の度合いが高い。専用住宅も人がいて完全なものになるが、そもそもその住宅を使う人に合わせた仕様になっているので、その人と行動を共にする物たちと一緒にその空間に入り込むだけでその人なりの空間になる、すなわち、不完全な部分が少ない。集合住宅は誰が入るかわからないから、不完全な部分が多く、それを別の言い方をすると汎用性が高く、誰にでも合わせることができ、人を選ばない。しかし、従来は人がそこに入った場合、そもそも想定されている使い方に添うようになり、例えばそれは、ベッドの位置、ソファの位置、家電の位置など、万人がするだろうと推測できる行動を抽出し、それを元にプランニングをする。それは専用住宅よりも不完全性の度合いが低いかもしれない。
"Degree of imperfections in apartment buildings"
I am planning an apartment house. So I thought about the activity. If human activity occurs to perfect imperfections, apartments are a building type with imperfections in the first place, and if there is a degree of imperfections, they are more incomplete than private homes. The degree of sex is high. The private house will be complete with people, but since the specifications are tailored to the person who uses the house, you can just enter the space with the people who act with that person. That is, there are few imperfections. Since we do not know who will enter the housing complex, there are many imperfections, and in other words, it is highly versatile, can be adapted to anyone, and can be used by anyone. However, in the past, when a person entered there, it came to follow the intended usage in the first place, for example, the position of the bed, the position of the sofa, the position of the home appliances, and other actions that everyone could guess. Extract and plan based on it. It may be less imperfect than a private home.
以前に考えたフリーカップでは気分という物を形にできたとするならば、今度はそのフリーカップが建築だとして考えてみる。
そうすると違いはがりに目がいく。フリーカップは簡単に動き、回転できるが、建築は動かない。フリーカップは人が手で操ることができるが、建築は人が内部に入り込み使う。やはり、スケールの違いが全く違う物を生み出しているように思える。
ただ、手だけにせよ、人が何かのアクティビティを起こす余地があり、そのアクティビティには人の感情を絡めることができそうなのはフリーカップも建築も同じである。
例えば、人がいなくてもフリーカップも建築も物として実在できるが、あくまでも人が使う物だから、人がいなければ不完全な物である。『茶の本』で岡倉天心は茶室の不完全性を説いていたが、それと同じで人がいてフリーカップも建築も完全な物になる。
そう考えると、人のアクティビティは不完全な物を完全にするために発生するともいえ、人が完全な物にするための余地を残した不完全性を纏うことが気分と物をつなぐことになるともいえる。
"Mood and things that imperfections connect"
If the free cup you thought about before could give shape to your mood, then think of it as architecture.
Then you will notice the difference. Free cups move and rotate easily, but architecture doesn't. Free cups can be manipulated by humans, but architecture is used by people inside. After all, it seems that the difference in scale produces something completely different.
However, it is the same in free cups and architecture that there is room for a person to perform some activity, even if only by hand, and that activity can involve human emotions.
For example, free cups and architecture can actually exist as objects without people, but since they are used by people, they are incomplete without people. In "The Book of Tea", Tenshin Okakura explained the imperfections of the tea room, but in the same way, there are people and the free cup and architecture are perfect.
Given that, even though human activity occurs to perfect imperfections, wearing imperfections that leaves room for humans to perfect is what connects mood and things. It can be said that it becomes.
感情や心の動きも物として、そうすると気分も物として 「気分という感情そのものを物とする」ことの解像度を上げて、もっと露わにして、実際に建築として、空間として表現することを試みる。
気分には元々の形、大きさ、重さはないが物だから、物として形や大きさや重さを表現することはできるが、そこに何か物にする要素を加えてあげないと実際に物として出現しないだろう。
そもそも物はある特定の条件のもとでしか表現できないし、成立しない。だから、物にするには条件を与えてやらないといけない。
例えば、以前、気分によって見え方が変わるフリーカップを考えてみた。それは不整形で飲み口の厚みが違う。その日の気分で飲み口を選ぶとフリーカップ自体の形も変化し、気分と呼応してフリーカップの見え方が決まる。だから、これは物としてフリーカップだが、これを物として「フリーカップという名の気分」ということもできるだろう。
当然これは、物は言いようではない。なぜなら、物として気分を表現して実在しているから、言葉だけで終わっていないからである。
さて、これを建築や空間で行うことを考えていて、その表現の部位として「壁」を考えてはいるのだが、フリーカップとは違い、建築や空間自体は動かないから、人のアクティビティも結びつける必要がある。そうすると、気分という感情と物とアクティビティの3つをつなげるための何か条件を与える必要がある。
"Connecting mood, things and activities"
Emotions and movements of the mind are also objects, and then moods are also objects. We will raise the resolution of "taking the emotions of moods themselves" to make them more exposed, and try to actually express them as architecture and space.
The mood does not have the original shape, size, and weight, but since it is a thing, it is possible to express the shape, size, and weight as an object, but if you do not add something to it, it will actually be It will not appear as a thing.
In the first place, things can only be expressed under certain specific conditions, and they do not hold. Therefore, you have to give conditions to make things.
For example, I used to think of a free cup whose appearance changes depending on the mood. It is irregular and the thickness of the mouthpiece is different. If you choose a mouthpiece according to the mood of the day, the shape of the free cup itself will change, and the appearance of the free cup will be determined in response to your mood. So, this is a free cup as a thing, but you can also call it a "feeling called a free cup".
Of course, this is not something to say. This is because it expresses the mood as a thing and exists, so it does not end with words.
Well, I'm thinking of doing this in architecture and space, and I'm thinking of "walls" as a part of that expression, but unlike free cups, architecture and space itself do not move, so people's activities are also Need to tie. Then, it is necessary to give some condition to connect the feeling of mood, the thing and the activity.
今まで気分によって変わる建築や空間を考えてきたが、それは気分という感情が建築や空間という物に対して何かの影響を与えると考えた結果だが、その気分という感情でさえ発露が物だとしたら、建築や空間として何かを表現するにせよ、一旦、気分という感情が影響を与えるというプロセスを踏むこと無しに、気分という感情そのものを物として、建築として、空間として表現すれば良いとなるが、そのようなことが実際にあり得るのか、言葉上は言えてしまうが、プランに落とし込むには「気分という感情そのものを物とする」ことの解像度を上げて、もっと露わにしないとできない。
"To make things"
Until now, I have been thinking about architecture and space that change depending on my mood, but that is the result of thinking that feelings of mood have some influence on things such as architecture and space, but even those feelings are manifestations. Then, even if you express something as architecture or space, you should express the emotion of mood as a thing, as architecture, as a space, without going through the process that the emotion of mood influences. However, I can say in words whether such a thing is actually possible, but in order to incorporate it into the plan, it is necessary to raise the resolution of "taking the feeling of mood itself as a thing" and reveal it more. ..
人と物を分けて考える時、人は精神の塊のような扱いをして、感情や心の動きを対象にし、もちろん、人のアクティビティも念頭にはあるが、そのアクティビティは感情や心の動きから引き起こされるので、感情や心の動きに含めて一緒に考えしまうから、物と相対する人という構図になってしまうが、よく考えたら人もあらゆる物質から出来上がっているので、改めて物だと思うと、人の精神は物に左右されるということに気づく。
だから、最初に物があり、そこから人の感情や心の動きとして派生していく。そうすると、人と物という分け方より、物と物、いや、全てが物とした方が自然であり、ならば、感情や心の動きも物かとなる。
感情や心の動きが物ならば、形があり、大きさがあり、重さもあることになり、それは目に見える物として表現が可能になるはずである。
では、感情や心の動きが物で目に見えるようになるならば、その物の扱い方しだいでそれを建築や空間やプロダクトとして表現できる、などと考えてみた。
"Emotions and emotional movements are things"
When we think of things separately from people, we treat them like a mass of mind, targeting emotions and emotional movements, and of course, we also have human activities in mind, but those activities are emotional and emotional. Since it is caused by movement, it is considered together with emotions and movements of the mind, so it becomes a composition of a person facing an object, but if you think about it carefully, people are also made of all substances, so it is a thing again. When I think about it, I realize that the human spirit depends on things.
Therefore, there is something first, and it is derived from it as human emotions and emotional movements. Then, rather than separating people and things, it is more natural to make things and things, no, everything as things, and if so, emotions and emotional movements also become things.
If emotions and movements of the mind are things, then they have shape, size, and weight, which should be able to be expressed as visible things.
Then, if emotions and movements of the mind become visible in an object, I thought that it could be expressed as architecture, space, or a product depending on how the object was handled.
2つに1つ的な選択は白黒がはっきりとついてわかりやすいので、それで満たそうすれば目標は立てやすく、誰にでもわかりやすいが、数値の目標も同じで、ただ、何事も捨てられない性格なもので、白も黒も両方共存し成り立つ方法はないものかとまずは考えてしまう。
ただ、そうすると目標は立てにくく、わかりにくく、数値で表すのも難しい。そもそも矛盾したモノ同士が交わることなく、同時に成り立ち、共存することがあり得るのだろうかとなる。
だから、白も黒も色のバリエーションだと考えることにすれば、ただ場所を変えて、塗り分けがしてあるだけだと思えばよく、さらに無彩色だけでなく、有彩色もあり、様々な色が塗り分けられているパレットを考え出せば、矛盾したモノ同士が交わることなく、同時に成り立ち、共存することがあり得るかもしれない。
"Making a palette"
One in two choices is easy to understand because black and white are clearly attached, so if you meet it, it is easy to set goals and it is easy for anyone to understand, but the numerical goals are the same, but it is a personality that can not throw away anything So, first of all, I wonder if there is a way to make both white and black coexist.
However, doing so makes it difficult to set goals, understand them, and express them numerically. In the first place, it is possible that contradictory things can be established and coexist at the same time without intersecting each other.
So, if you think of white and black as color variations, you can just think that they are painted in different places, and there are not only achromatic colors but also chromatic colors. If we come up with a palette with different colors, it may be possible for contradictory objects to stand together and coexist without intersecting each other.
正確で曖昧なモノ、開いていて閉じているモノ、暗くて明るいものモノなど、相対するものが共存して同時に成り立っている状態に惹かれる。それは例えば、ヒーローとヒールが一時休戦して手を組むようなことで、例えば、映画「ルパン三世 カリオストロの城」でルパンと銭形警部がカリオストロの城から脱出する時に手を組むようなことで、それは特別なことだから惹かれるのと、それが自然に何も抵抗なく行われていることに惹かれる。
ただ、それを言葉で表現することは簡単だが、実際のモノとしてそのような相対するモノが共存して同時に成り立っている状態をつくり出すことは容易ではない。
だから、もう少し実際のモノに寄せて考えていくと、絶対的な存在としてあるモノ、それを常識的なモノというかもしれないし、その時の時代性に合ったモノというかもしれないが、それを崩しそこに相対するモノ、それはもっと恣意的で、自分の手だけでは負えないようなモノを持って来ることによって、相対するモノが共存して同時に成り立っている状態をつくる。
恣意的であることを持ち込むことに抵抗はあるが、共存して同時に成り立つにはその位のことが必要なのではないだろうか。
"Bringing arbitrary things"
I am attracted to the state in which opposing objects coexist and are established at the same time, such as accurate and ambiguous objects, open and closed objects, and dark and bright objects. For example, the hero and Heal temporarily take a break and join hands, for example, in the movie "Lupin III Cagliostro's Castle", Lupine and Zenigata police join hands when they escape from Cagliostro's castle. I'm attracted because it's a special thing, and I'm attracted to the fact that it's done naturally and without any resistance.
However, although it is easy to express it in words, it is not easy to create a state in which such opposing objects coexist and are simultaneously established as actual objects.
So, if you think about the actual thing a little more, it may be a thing that is an absolute existence, it may be a common sense thing, or it may be a thing that suits the times at that time, but it breaks it down. By bringing in things that are opposite to each other, which are more arbitrary and that cannot be handled by one's own hands, the opposite things coexist and are established at the same time.
I'm reluctant to bring in arbitrary things, but I think it's necessary to have that much to coexist and hold at the same time.
空間が相対的なのは、私が見ているモノ、それはすなわち絶対的なモノ、だけで成り立っているのではなくて、私が持っているイメージ、それが相対的なモノ、からも構成されているからで、少しでも相対的なモノが含まれれば、それは絶対的なモノではなくて、相対的なモノになる
相対的であるから、人によって違うモノになる。
絶対的に美しいモノ、絶対的に素晴らしいモノは尊く、なくてはならない存在であり、その美しいという事実、素晴らしいという事実には時間の概念は無く、永遠でいいのだが、それと同時に変わるモノ、無くなるモノにも価値を見出す、それを日本文化特有のモノという人もいるが、ことで成り立つモノをつくるとしたらどうなるか。
絶対的であったり、相対的であったりするのは人に対してだから、人にとって変わるモノ、相対的なモノを持ち込めばいい。それはいろいろとあるかもしれないが、気分というのはどうだろうか、人の気分ほどコロコロ変わるモノはないし、その気分ほど人に影響を与えるモノもないだろう。
気分によって見ているもののイメージが変わる。イメージが変われば、その見ているモノの捉え方も変わる。捉え方が変われば、そのモノに対する人の行動が変わり、その見ているモノが建築や空間ならば、その建築や空間は今までとはちがうモノにならざるを得ない。
では、気分を誘発するモノを建築や空間に持ち込むか。
"Bring in"
Space is not relative to what I see, that is, to what is absolute, but to what I have and what it is. So, if there is any relative thing, it becomes a relative thing, not an absolute thing.
Because it is relative, it will be different for each person.
Absolutely beautiful things, absolutely wonderful things are precious and indispensable beings, and the fact that they are beautiful and wonderful does not have the concept of time, it is forever, but at the same time, the things that change are gone. Some people find value in things, which is unique to Japanese culture, but what happens if we make things that are made up of things?
It is to the person that it is absolute or relative, so it suffices to bring in something that changes for the person, something that is relative. There may be various things, but how do you feel about it? Nothing changes like a person's mood, and nothing affects it as much as that mood.
The image of what you see changes depending on your mood. If the image changes, the way we perceive what we are seeing also changes. If the way of thinking changes, the behavior of people for the thing will change, and if the thing you are looking at is an architecture or a space, that architecture or space will inevitably be a different thing.
Then, do you bring things that induce mood into architecture or space?
人が空間を認識する時には相対的な尺度を持ち込むので、設計する側もそのための、それを助ける何がしらのものを用意する必要があるだろうとしたが、それをもう少し詳しくいうと、その相対的な尺度とは、空間同士のつながりの強度のようなものであったり、過去の空間体験からくる差異のようなものを感じ取ることだったりするので、その相対的な尺度を判断するためのものが元々存在していることになり、そこを意識的に変えることが設計することだと考えていて、ただそのまま表したのではとてもわかりにくいので、それを理解しやすくするための何がしらの助けを用意する必要があるだろうということです。
そして、その相対的な尺度を判断するために元々存在しているものとは、慣習であったり、倫理であったりすると考えている。
"Original things that exist"
When people perceive a space, they bring in a relative scale, so the designers would have to have something for that purpose, but to explain it in more detail, the relative -Like scales are used to judge relative scales, because they are like the strength of the connections between spaces, or they are like feeling the differences from past spatial experiences. Was originally present, and I think that consciously changing it is a design, and it is very difficult to understand it just by expressing it as it is, so what is the purpose of making it easy to understand? It means that you will need to provide help.
And I think that what exists originally to judge the relative scale is custom or ethics.
空間と空間の相対的な関係性に人は影響を受けて、それらの空間を認識していく。それは絶対的な空間を感じているのではなくて、目の前にある空間同士を見比べたり、過去の空間体験と目の前の空間を重ね合わせたりする。
どうしても設計する方は絶対的な空間を目指してしまう。過去と断絶し、未来に向けて、絶対的で固有のものにしようとする。それを間違いとは思わないが、人が空間を認識する時には相対的な尺度を持ち込むので、設計する側もそのための、それを助ける何がしらのものを用意する必要があるだろう。
"Something to help"
People are influenced by the relative relationship between spaces and recognize those spaces. It doesn't feel like an absolute space, but it's comparing the spaces in front of you and superimposing past space experiences with the space in front of you.
Those who design by all means aim for an absolute space. Trying to be absolute and unique towards the future, breaking from the past. I don't think it's a mistake, but when people perceive a space, they bring in relative measures, so designers will need to have something for that to help.
空間と空間の関係性に興味があり、それは人と空間の関係性に興味があるからで、人は空間を認識する時に、同時に空間から影響を受けていて、その空間は単独で存在することはなく、空間と空間のつながりや、外部空間と内部空間のような対比など、相対的に存在し、人はその空間の相対性からの影響を受けることが多い。
だから、空間をどのように配置するのかを空間と空間の関係性から考えて決めていこうとするのだが、その時に詳細にみるのが空間と空間の接点であり、その接点となるのが多くの場合は壁である。
初期の段階でプランニングする時には壁を単線で表現する。壁は当初から厚みの無い線として扱う。空間を厚みの無い線で囲いながらプランニングする。そこに壁の厚みを持ち込み、空間を意識してみる。厚みのある線でプランニングしてみる。壁の厚みが空間と空間の関係性に影響を与えることになるだろう。
"Planning with thick lines"
I'm interested in the relationship between spaces, because I'm interested in the relationship between people and spaces, and when people perceive a space, they are also influenced by the space at the same time, and that space exists alone. Rather, there is a relative relationship such as the connection between spaces and the contrast between external space and internal space, and people are often affected by the relativity of that space.
Therefore, I try to decide how to arrange the space by considering the relationship between the spaces, but at that time it is the points of contact between the spaces that are often the points of contact. If it is a wall.
When planning at an early stage, the wall is represented by a single line. The wall is treated as a thin line from the beginning. Plan while enclosing the space with thick lines. Bring the wall thickness there, and try to be aware of the space. Try planning with thick lines. The wall thickness will affect the relationship between spaces.
壁の配置を今までは境界の位置を決めることだと考えてきた。部屋と部屋の境界、外と内の境界など、その境界が決まれば、領域を確定できるから、次はもっと細部の部分を詰めることができるようになる。
それを空間だと認識するために壁を配置するようにしている。もっというと、空間と空間の関係性を決めるために壁があると考えている。
そうすると、壁の位置だけでなく、壁の構造や壁の在り方が重要になってきて、そこで壁の厚みに注目している。
"Relationship between spaces"
Until now, we have considered that the placement of walls is to determine the position of boundaries. Once the boundaries, such as room-to-room boundaries and outside-to-inside boundaries, are defined, the area can be defined, so that it becomes possible to narrow down the details.
The walls are arranged to recognize it as a space. More specifically, I think that there are walls to determine the relationship between spaces.
Then, not only the position of the wall, but also the structure of the wall and the way the wall should be are becoming important, and we are paying attention to the thickness of the wall.
先日のプレゼンは建主がとても喜んでくれて実現に向けて動き出しそうでちょっと安堵した。なかなか直接お会いできなかったので、A3シート1枚に計画案をまとめ、それに自筆の言葉を添えて、あと3Dプリンターの模型も一緒にお届けした。
今ここで、この環境で何を実現したらいいのか、設計する側の考えや想いをきちんと込めて、それを簡潔に伝えようとしたが、それがどのような反応になって返ってくるのか、その反応でしか評価できないから安堵した。
ここのところ、いくつかの計画案の素案をSNSにあげてみている。その中で反応をみて、自分でも気に入っているものをA3シート1枚にまとめて提出した。
SNSの反応が全てでは無いし、むしろSNSの役割は情報伝達でそれ以上でもそれ以下でも無く、現実を超えようとするべきでは無く、超えようと考えると現実が壊れていくと考えていて、だから、実現する前のそれも素案に近い計画案という現実では無い情報をさらすにはちょうどいいと思っている。別にそれがダメでもまた考えればいいし、ただアウトプットにはなるから、頭のモヤモヤは整理される。それを見せられる方は迷惑な時もあるかもしれないが、それがSNSの情報の作法だと心得ていれば気にもならないだろうし、気になってもすておける。
"Information that is not the reality of drafts"
The other day's presentation was a little relieved because the owner was very pleased and seemed to move toward realization. I couldn't meet him directly, so I put together a plan on one A3 sheet, added my own words, and delivered a 3D printer model together.
Now, I tried to convey what I should achieve in this environment, the thoughts and feelings of the designer properly, and briefly convey it, but what kind of reaction will it return? I was relieved because I could only evaluate the reaction.
I've been posting some draft plans for SNS recently. After seeing the reaction, I submitted the ones I liked as a single A3 sheet.
The reaction of SNS is not all, and rather the role of SNS is not more than or less than information transmission, and we should not try to exceed the reality, and thinking that it will break the reality, Therefore, I think that it is just right to expose unrealistic information such as a plan that is close to the draft before it is realized. Even if it's useless, it's good to think about it, and it's just an output, so the stuffy mind is organized. It may be annoying for those who can show it, but if you know that it is the manner of information on SNS, it will not bother you, and you can save it.
壁の厚みの違いによる外と内の繋がり具合の濃淡を検証してみようと、計画中の集合住宅にそれを当てはめてみたが、集合住宅のように建築計画のお手本のようなビルディングタイプに斜めの壁面を挿入すると、その斜めの線があるだけで不自然に見えてきて、まとまらない。
あまりに集合住宅は効率を重視するので、そうすると斜めの線は敬遠されるということか、あるいは、計画する側が効率や集積積層できることを重視し過ぎているからか。
いずれにせよ、壁の厚みを変化させることをもう少し違った形で表現する必要がある。
"Expression of change in thickness"
In order to verify the shade of the connection between the inside and outside due to the difference in the thickness of the wall, I applied it to a planned condominium, but it is diagonal to a building type like an apartment plan like a condominium. When I insert the wall surface of, the diagonal line makes it look unnatural and does not fit together.
Maybe the housing is too important for efficiency, and then the diagonal lines are shunned, or the planners place too much importance on efficiency and stacking.
In any case, changing the wall thickness needs to be expressed in a slightly different way.
壁の厚みが連続的に変化する中に設えを仕込む。壁の厚みも場所を取るが、そこにできる空間を利用すれば厚みの選択の自由度が上がり、厚みを大きくすることができ、より壁の厚みの差を強調できる。
空間と空間の隔たりや繋がりに壁の厚みが関係すると考えており、厚ければ隔たり、薄ければ繋がり、連続的に壁の厚みが変化して、繋がりと隔たりとその中間の隔たりだか、繋がりだかがわからないような状態まで実現できれば、空間と空間の関係性がより複雑になり、当然そこに人との関係性もより絡んでくる。
そのためにも、より壁の厚みの差があった方が良いので、そうすると、壁の厚みを厚くすることによってできる空間状な場所に設えを仕込むのは至極当然なことになるだろう。
"Preparation for thickness"
Set up the fixture while the wall thickness changes continuously. Although the thickness of the wall also takes up space, if the space created there is used, the degree of freedom in selecting the thickness is increased, the thickness can be increased, and the difference in wall thickness can be further emphasized.
We think that the thickness of the wall is related to the distance and connection between spaces, if it is thick, it will be separated, if it is thin, it will be connected, the thickness of the wall will change continuously, the distance between the connection and the distance between them, the connection If it is possible to realize a situation in which people do not understand, relationships between spaces will become more complicated, and naturally relationships with people will become more involved.
For that reason as well, it is better that there is a difference in the wall thickness, and then it would be quite natural to install equipment in a space-like place that can be created by increasing the wall thickness.
集合住宅のような効率的な配置やプラン、積層性が求められるようなビルディングタイプでは外と内の関係性が単調になりやすい。例え、開口部が面する方位が違い、見える景色が変わったとしても、そもそもの外と内の関係性に変わりがない。
ただ、各戸を全くちがうプランで構成する集合住宅もあり、外と内の関係性の単調さから逃れて複雑性を獲得し、まるで一戸建て住宅が集まり積層しているようにみえるものもある。そのような集合住宅は確かに、外と内の関係性の単調さは緩和されることになるが、それでも外と内の位置関係に複雑さが増しただけで、そもそもの外と内の関係性には大した変化をもたらさない。
外と内の関係性に変化をもたらすためには、外と内をつなぐものである開口部廻りが単調ではなく、そこに複雑性をそなえなくてはならない。その複雑性は場所によって、人によって受け取るものが変化すること。
壁の厚みが連続的に変化し、その厚みの変化は開口部を通して知ることになり、開口部の大きさが同じでもその厚みが厚ければ外と内に隔たりがあり、薄ければ繋がりがある。そのような壁が連続し、時には折れ曲がり、渦巻き、プランを形づくる。
そうすることで、外と内の関係性が場所や人によって変化し、あとはその場所に合わせるようにプランニングをしていけばよいのではないか。
"Changes in the relationship between the outside and the inside"
The relationship between outside and inside tends to be monotonous in a building type that requires efficient layout, plans, and stackability, such as an apartment house. Even if the direction in which the opening faces is different and the view you see changes, the relationship between the outside and the inside does not change.
However, there are also apartment houses that consist of completely different plans for each house, and there are also those that escape from the monotonous relationship between the outside and the inside and gain complexity, and it seems that single-family houses are gathered and stacked. Such apartments will certainly ease the monotony of the relationship between the outside and the inside, but nevertheless, the complexity of the positional relationship between the outside and the inside only increases the relationship between the outside and the inside. It doesn't make a big difference in sex.
In order to bring about a change in the relationship between the outside and the inside, the area around the opening, which connects the outside and the inside, is not monotonous and must be complicated. The complexity is that what a person receives varies from place to place.
The thickness of the wall changes continuously, and the change in the thickness is known through the opening. If the thickness of the opening is the same, there is a gap between the outside and the inside, and if it is thin, there is no connection. is there. Such walls are continuous and sometimes bend, swirl, and form a plan.
By doing so, the relationship between the outside and the inside will change depending on the place and person, and after that, it may be better to plan so as to match that place.
プランを考える時に昔からよくやることがある。壁を絞るように配置する。空間に何か変化をつけたいと思うのか、それとも単なる落書き程度のことかもしれないが無意識のうちに線を描いてしまう。
壁は建築的には面白い存在で、いくつもの役割をこなす。構造体としての壁、環境性能としての壁、意匠としての壁、設備としての壁、収納としての壁、そして、窓や開口部も壁の一部である。
それらは一定の壁の厚みがあって相互に成り立つ。だから、プランを考えている時に、その相互の成り立つを断ち切り、新たな成り立ちなり、秩序を考えようとするからか、壁の厚みを一定に変化させるように壁を絞る線を描き入れてしまうのかもしれない。
"Throttle wall"
There are a lot of things to do from old times when thinking about a plan. Arrange to squeeze the wall. Do you want to change the space, or maybe it's just graffiti, but unconsciously draw a line.
Walls are architecturally entertaining and play a number of roles. A wall as a structure, a wall as environmental performance, a wall as a design, a wall as equipment, a wall as storage, and windows and openings are also part of the wall.
They have a certain wall thickness and are mutually compatible. Therefore, when I am thinking about a plan, I will draw a line that narrows down the wall so that the mutual thickness is cut off, the new formation and the order are considered. It may be.
連続的に厚みが変化する壁など見たことが無い、それはその必要性が無いからだろう。構造体としての壁や環境性能としての壁では一定の厚みが求められる。それは厚みに変化があると容易に計算が成り立たないからである。だから、厚みを変えるとしたら、それは意匠的な要因としての付加物になる。
付加物となると忌み嫌われる。モダニズムの倫理観では付加物は許されない。シンプルで余分な物が無い様が尊い。それがポストモダンになり、アイロニーとして付加物が利用され、ポストモダンの後は付加物の造形だけがテクノロジーの発達により構造体そのものとして実現可能になったが、一般的にはまだモダニズムの倫理観が残っている。
だから、壁の厚みの変化を付加物ではなくて、構造体そのものとして扱えば良いとなるが、それが一般的では無く、またシンプルで余分な物が無い様が求められるので、一定の厚みの壁ばかりになる。
空間の隔たりや繋がりに壁の厚みが関係すると考えており、その壁の厚みの変化が不連続に所々で発生するよりは、連続的に壁の厚みが変化して、繋がりと隔たりとその中間の隔たりだか、繋がりだかがわからないような状態まで実現する方が空間としては複雑で面白くなるはずである。
"Continuously changing thickness"
I have never seen a wall whose thickness changes continuously, probably because there is no need for it. A certain thickness is required for the wall as a structural body and the wall as environmental performance. This is because the calculation cannot be easily established if the thickness changes. Therefore, if the thickness is changed, it becomes an additive as a design factor.
It is disliked when it comes to additions. Additions are not allowed in modernist ethics. It is precious that it is simple and there are no extra items. It became post-modern, the additive was used as irony, and after the post-modern, only the modeling of the additive became feasible as a structure itself due to the development of technology, but in general, the ethics of modernism is still common. Is left.
Therefore, it is sufficient to handle the change in wall thickness as the structure itself, not as an additive, but that is not common, and it is required to be simple and free of excess, so a certain thickness Only walls.
We think that the wall thickness is related to the space separation and connection, and rather than the wall thickness changes occurring discontinuously in some places, the wall thickness changes continuously and the connection and separation between It would be more complicated and interesting as a space to realize a state in which it is difficult to understand whether there is a gap or a connection.
壁に同じ大きさの開口部が空いていても、そこを通り抜ける時に、ぶ厚い壁を通るのと、極薄な壁を通るのでは印象がちがうだろう。
分厚い壁は隔たりを感じ、極薄な壁は有って無いようなもので空間がひとつながりに感じるかもしれない。
それは壁の厚みが人の感情に影響を与えていることであり、その瞬間、建築と人が繋がり、その積み重ねが建築空間を認識することになる。
"Relationship and connection"
Even if there is an opening of the same size in the wall, when you pass through it, you will get the impression that it goes through a thick wall and an extremely thin wall.
Thick walls may feel a gap, and thin walls may seem like there isn't, so the space may feel a connection.
It is that the thickness of the wall influences people's emotions, and at that moment, people are connected to the architecture, and the stacks recognize the architectural space.
壁の厚みが連続的に変化することによって、繋がりと遮断が連続的に反転する状況をつくり出すことができる。
壁の厚みが厚ければ遮断、薄ければ繋がり、この単純なやり取りがわかるような開口部の開け方をし、空間を切り取る壁の厚みを変えてみる。
それだけで、空間の認識に変化が生まれる。あとはその変化を操作すれば良い、たったそれだけで違う空間が生まれる。
"Change of space"
By continuously changing the thickness of the wall, it is possible to create a situation in which the connection and the interruption are continuously reversed.
If the wall is thick, it will be blocked, if it is thin, it will be connected. Open the opening so that you can understand this simple interaction, and try changing the thickness of the wall that cuts out the space.
That alone changes the perception of space. After that, you can operate the change, and a different space is born with just that.
外壁の壁が薄いとわかれば、その空間は外と連続的に認識できるかもしれないし、外壁の壁が厚ければ、その空間は外と遮断されていると認識するだろう。要するに、壁が薄ければ繋がり、厚ければ遮断される。
しかし、今まで壁の厚みは構造体としての壁と環境性能としての壁が厚みを決めてきて、そこに空間を認識する要素としての意識は欠落していた。
ということは、壁が有るのに外と繋がり、壁が無いのに遮断されている状況がつくれるということである。
ただ、壁を厚くすればその分空間が狭くなり、壁の薄さにも限度がある。だから、壁は厚くするが、その厚みの中に設えを仕込み、厚い壁との対比で薄く壁を見せる。
"Thick and thin walls"
If the outer wall is known to be thin, the space may be continuously recognized as the outside, and if the outer wall is thick, the space may be recognized as being cut off from the outside. In short, if the wall is thin, it is connected, and if it is thick, it is blocked.
However, until now, the thickness of the wall has been determined by the wall as the structural body and the wall as the environmental performance, and the consciousness as an element for recognizing the space there has been lacking.
This means that it is possible to create a situation where there is a wall that connects to the outside, and there is no wall that blocks the environment.
However, if the wall is made thicker, the space becomes narrower by that amount, and there is a limit to the thinness of the wall. Therefore, the wall is made thicker, but a device is installed in the thickness to make the wall look thinner in comparison with a thick wall.
壁の厚みを普段の何気ない生活の中で意識することは無いだろう。そもそも壁の厚みを意識する必要も無いですし、壁の厚みが見えることを意識することも無い。
壁の厚みの違いが空間を認識する時に違いを生むと考えている。だから、壁の厚みで仕切られているように見える立ち上がりを考えてみた。
この厚みがそのまま見える立ち上がり壁が、とても薄ければ、その空間は軽快で希薄なものと認識するだろうし、逆に、とても分厚い立ち上がり壁であれば、その空間は重厚で、荒々しく、濃密なものと認識するかもしれない。
このことは、壁の厚みだけで空間の認識を操作できるということであり、壁の厚みが仕上げや平面形状など、空間を認識するものと同等の価値があるということであり、それは壁の厚みだけのデザインで空間を十分に成り立たせることができることでもある。
"Only wall thickness"
You will not be aware of the thickness of the wall in your everyday life. In the first place, there is no need to be aware of the thickness of the wall, nor is it aware of the thickness of the wall.
I think that the difference in wall thickness makes a difference when recognizing a space. So I thought about the rising that seems to be partitioned by the wall thickness.
If the rising wall where this thickness can be seen as it is is very thin, you will recognize that the space is light and thin, and conversely, if it is a very thick rising wall, the space is heavy, rough and dense. You may recognize it as something.
This means that it is possible to operate the space recognition only by the wall thickness, and the wall thickness has the same value as that for recognizing the space, such as finish or planar shape. It is also possible to fully establish the space with just the design.
人は物を介して空間を認識するということ。空間は空気みたいもので、それ自体を直に感じることはできない。しかし、壁や床や天井があり、それらに囲まれることによって空間を感じる取ることができる。
だから、物で空間を感じ取ってもらうために建築をつくる。では、その物は壁や床や天井だけだろうか、他に空間を認識させる物はあるだろうか。
ずっと考えているのが壁の厚みである。壁は空間を認識させるものだから、その厚みも当然そこに含まれてしまうし、そもそも壁の厚みを意識することがほとんどないだろうし、あるとしても設計と工事の時ぐらいだけかもしれない。
だけれども、壁の厚みが違うことで影響があるのではないだろうか。床や天井では厚い薄いはいわないが、壁だけが「壁が薄い」「壁が厚い」などという、それは大体音の問題があった時だが、音は壁からだけ伝わってくる訳では無いから、壁だけを特別視し、その厚みの違いを識別し、それが引き起こす状況を認識しようとする意識が人の中にあるのだろう。ならば、壁の厚みの違いで空間の認識に差が出るはずである。
壁の厚みの違いと空間の認識の関係を探るのも設計のうちである。
"Differences in space due to differences in wall thickness"
People recognize space through things. Space is like air, and you can't feel it directly. However, there are walls, floors, and ceilings, and you can feel the space by being surrounded by them.
Therefore, we create architecture so that people can feel the space. Then, is that thing only a wall, floor, or ceiling, or is there another thing that makes us recognize the space?
I have been thinking about wall thickness for a long time. Since the wall recognizes the space, its thickness is naturally included in it, and there is almost no awareness of the thickness of the wall in the first place, and even if there is, it may be only at the time of design and construction.
However, it may be affected by the different wall thickness. I don't say it's thick or thin on the floor or ceiling, but when there is a problem with sound, such as only the wall being "thin wall" or "wall thick", the sound is not only transmitted from the wall. Perhaps there is a consciousness in the person who pays special attention to the wall, identifies the difference in thickness, and recognizes the situation caused by it. If so, the difference in wall thickness should make a difference in the perception of space.
It is also part of the design to explore the relationship between the difference in wall thickness and the perception of space.
壁の厚みも場所を占有している。だから、壁の厚みはできれば薄くしたいと考えるかもしれない。少しでも部屋を広くしたいならばそうするだろ。
壁の厚みが増して変化し、それが低くなれば、壁がカウンターの役目をする。高さを低くくしただけで、役目が変わり、しかし、部屋を仕切る役目は変わらない。
このように壁の解釈を変えていくと、人と建築の関わりも変わっていく。
"The role of the wall changes"
The wall thickness also takes up space. So you might want to make the wall as thin as possible. If you want to make your room a little bigger, you will.
When the wall thickness increases and changes, and when it decreases, the wall acts as a counter. The role is changed only by lowering the height, but the role of partitioning the room does not change.
By changing the interpretation of the wall in this way, the relationship between people and architecture also changes.
斜めの境界を曖昧にしようと考えた。キッチリと分けることにより、空間の細分化ができ、尚且つ、そこに動きが生まれると考えていたが、もう少し空間の分節が曖昧になり、その分節する壁に厚みを持たせることによって、空間を細分化しながらも、新たな領域が生まれるようなことをイメージしている。
その新たな領域には何か設えを仕込み、曖昧な領域と相まって人に何か影響を与えることを目指す。
そして、その影響が人の内面と呼応するならば、その空間はその人特有のものになると考えている。
"Ambiguous wall"
I thought to blur the diagonal boundaries. I thought that the space could be subdivided and the movement would be created by dividing the space tightly, but the segmentation of the space became a little more ambiguous, and by making the wall that segmented it thicker While subdividing, I imagine that new areas will be created.
Something is set up in the new area, and we aim to influence something in combination with the ambiguous area.
And if the influence corresponds to the inside of the person, I think that the space will be unique to that person.
斜めの壁をプランに挿入することにより、人の動きをつくりだそうとした。確かに斜めの壁はその空間に没入した時に、その人に動きを与えるだろうが、視覚的には狭窄か拡散していく壁面が見えるだけであり、二次元の展開図に書き起こしたらただの面である。
そのただの面を見て狭窄か拡散かが瞬時にわかる訳だから、人の目から入る情報を素材として瞬時に判断している脳は素晴らしいと思うが、もう少し複雑なことを判断してもろうと思い、垂直壁面にも斜めの線を入れ、開口を三角形にした。
その垂直壁面の三角形の開口は、定量的に段々と開口の大きさが変化するので、人によって、場所によって開口から受ける印象が違い、その人、その場所だけの印象になり、そこだけの関係性やつながりが生まれる。
空間を細分化していった後に、新たなつながりができて、より空間の自由度が増すようなことを考えていたが、斜めの線を水平垂直に使い組み合わせることにより、それが少し実現可能になりそうな気がする。
"Combination of horizontal and vertical diagonal lines"
He tried to create human movement by inserting diagonal walls into the plan. Certainly, a slanted wall will give movement to the person when it is immersed in that space, but visually only the wall that narrows or spreads can be seen, and if you transcribe it in a two-dimensional development view Is the aspect of.
Since it is possible to instantly see whether it is stenosis or diffusion by seeing just that aspect, I think that the brain that instantly judges from the information entered from the human eye is wonderful, but I think that it may be a little more complicated to judge. Thinking about it, I also added diagonal lines to the vertical wall to make the opening triangular.
Since the size of the triangular openings on the vertical wall changes quantitatively and gradually, the impression from the opening varies from person to person depending on the location. Gender and connection are born.
After subdividing the space, I thought that new connections could be made and the degree of freedom of the space would increase, but by using diagonal lines horizontally and vertically, it can be realized a little. I feel like it will happen.
絶対に見ることができない、ドローンでも無理なアングルから、そもそもプランニングのスケッチでさえ、あり得ない巨人の視点だから、ちょっと視点を変えて、やはりこのプランももう少し大きな建築でないと、倍くらいの床面積がないと狭すぎるかもしれない。
本当に小さな建築を細分化していく場合の斜めの線は有効だと思うが、斜めの線以外の線では小さな建築を細分化した場合、どうしても狭くなりすぎてしまう。
本当に小さな建築は細分化せず、大きく使うのが常套手段だが、それでも細分化しようと考えているのは、本当に小さな建築なりの細分化の方法があり、それがより建築と人をつなぐ可能性があると考えているからです。
"Connecting subdivision"
From an angle that can never be seen, even with a drone, even a sketch of a planning is impossible from the perspective of a giant in the first place, so if you change the perspective a little, this plan also has a floor space that is about double Without it might be too narrow.
I think that diagonal lines are effective for subdividing really small buildings, but lines other than diagonal lines will inevitably become too narrow when subdividing small buildings.
It is a common practice not to subdivide a really small building, but to use it in a large way. I think there is.
斜めに分割すると角ができ、その角がデットスペースになるから、三角形のプランは敬遠されるが、斜めの定量的な変化は空間に動きを与えるので、その角が生かせる分割かプランを考えてみることにした。
斜めが大きく空間を分割するようにしてできた2つの三角形のうち1つをさらに細分化してみる。外との関わりにバリエーションを持たせるために適宜外部空間も挿入、細分化された空間は三角形としてグルーピングができていて、片方の三角形はそのままなので、細分化された空間は相互に置換できる。
細分化された空間は状況に応じて役割を当てはめればよい。まだまだ粗いが、細分化しつつ自由度が上がる空間ができそうである。
"Increase the degree of freedom by utilizing the diagonal in the plan"
If you divide diagonally, a corner will be created and that corner will become a dead space, so a triangular plan is shunned, but since a diagonal quantitative change gives a movement to the space, think of a plan that can make use of that corner. I decided to see it.
Let's further subdivide one of the two triangles created by dividing the space with a large diagonal. An external space is appropriately inserted to give variation to the relationship with the outside, and the subdivided spaces can be grouped as triangles, and one of the triangles remains the same, so the subdivided spaces can be replaced with each other.
A role may be applied to the subdivided space depending on the situation. Although it is still rough, it seems that there will be spaces that increase the degree of freedom while subdividing.
プランに1本の斜めの線を入れてみた。斜めに向かい合うのは空間だが、その空間に意味を与えるのは人なので、人と空間が、人と人が斜めに向かい合う。
空間を細分化していくと、空間の意味や使い道が限定されていく。それをプランニングと呼び、空間の名前や部屋名が決まっていくのだが、同時に空間の自由度が奪われる。
だから、プランニングをして煮詰めても、それでもいろいろな要素を持ち合わせている空間をつくりたいといつも考えていて、そういう空間はそこにいる人によって意味や使い道が自由にコロコロ変わる。
そして、そういう空間を単純な方法でつくりたいといつも思う。例えば、それが斜めの線を入れることで、斜めは空間や人に動きを与え、動きが生まれれば、ある特定の意味や使い道に収斂することを避けることができるのではないか。しかし、斜めは扱いが難しい。
"Slanting is free"
I put a diagonal line in my plan. It is a space that faces diagonally, but it is people who give meaning to the space, so people and spaces face each other diagonally.
As the space is subdivided, the meaning and use of the space are limited. This is called planning, and the name of the space and the room name are decided, but at the same time, the freedom of space is lost.
Therefore, even if I plan and boil down, I always want to create a space that has various elements, and the meaning and use of such a space freely change depending on the person there.
And I always want to create such a space in a simple way. For example, by inserting diagonal lines, it may give a movement to a space or a person, and if movement is created, it may be possible to avoid converging on a certain meaning or purpose. However, it is difficult to handle diagonally.
プランを細分化していくことは通常段々と空間の使い道を決めていくことになる。それは段々と空間の自由度が無くなることを意味する。
建築のビルディングタイプによってはそれが良い場合もあるけれど、小さな飲食店では何かと何かを兼ねるようなことがよくあるので、できるだけ空間の自由度が高い方が気が利いている。でも、細分化していくことが佇める場所をつくり出すとするならば、細分化しても自由度が変わらないようにするしかない。
自由度を別の言い方をすれば、置換可能度かもしれない。細分化した空間がある程度置換可能であれば、自由度が高いといえるだろう。
それでは、空間を細分化しながら置換の可能性を高めるにはどうしたらいいのか。それは、細分化していった空間を単体で考えるのでは無くて、大きさに変化をつけてグルーピングするのである。
あくまでもグルーピングした中での置換可能性になるが、それでもそのグループの中での自由度は高くなるだろう。
"Subdivision and degree of freedom"
The subdivision of the plan usually determines the usage of the space gradually. It means that the degree of freedom of space gradually disappears.
Depending on the building type of architecture, it may be good, but small restaurants often serve as something, so it is better to have as much space as possible. However, if we want to create a place where subdivision can stand, we have no choice but to keep the degree of freedom unchanged.
In other words, the degree of freedom may be the degree of substitution. If the subdivided space can be replaced to some extent, it can be said that the degree of freedom is high.
Then, how can we increase the possibility of replacement while subdividing the space? It is not to consider the subdivided spaces as a single unit, but to change the size and group them.
Although it will be possible to substitute in the grouping, the degree of freedom within the group will still be high.
人が人と一緒に佇むことができる最小の大きさは二畳だと考えている。だから、二畳単位でプランを考ることがある。それで二畳単位で並べていたら、その中に連続する二畳単位の連なりが見えたので、それを手掛かりにプランを構築してみた。
小さな建築では空間を細分化することは無理があると感じていたが、ズレながら連続する配置にすれば、何か可能性が生まれるのではないかと思えた。
その可能性とは、佇める空間が流動的に連続して、それ自体が建築になれば、建築の大小に関係無く、プランが成立し、尚且つ、空間に様々な変化がもたらされて複雑さが出て、その複雑さは利用の仕方しだいで、建築と人のギャップを埋めてくれるようなことである。
"Continuously shifting"
We believe that the smallest size a person can stand with is a tatami mat. Therefore, we may consider the plan in units of two tatami mats. Then, when I arranged them in units of 2 tatami mats, I could see a series of consecutive 2 tatami mats in them, so I tried to build a plan with that as a clue.
I felt that it was impossible to subdivide the space in a small building, but I thought that there would be some possibility if they were arranged consecutively while shifting.
The possibility is that if the standing space is fluidly continuous and becomes an architecture itself, the plan will be established regardless of the size of the architecture, and various changes will be brought to the space. And complexity, depending on how it is used, is such that it bridges the gap between architecture and people.
佇める場所はなかなかあるものでもなくて、それは家か、自宅かといわれれば、自宅でわざわざ佇むという表現も使わないような、どこか佇む場所というのは非日常な、でもそこは静寂が支配し、清らかなイメージがある。
佇める場所を外でとなると、なかなか思い浮かばないというか、個人的には京都の寺院を思い出したりして、それもやはり場所であったり、建築であったりする物が佇める感覚を与えてくれる。
では物として何がその佇める感覚を与えてくれるのだろうか、その答えを形や大きさといったスケールに求めてみたいと考えた。
すぐに思いついたのが囲われ感で、壁や天井、緑などといったものにヒューマンスケールで囲われている場所にいる時は、佇めるという感覚が起こりそうな気がする。それは建築の用途を問わずにあり得るかもしれない。
しかし、本当に小さな建築、飲食店兼料理教室では、囲われ感を出すために、さらに平面的に空間を細分化することには無理がありそうだ。
"Creating a place to stand"
There is no place to stand, and if it is said that it is a home or a home, it is unusual to stand there somewhere, but there is a quiet place. Dominates and has a pure image.
When I'm outside the place where I stand, it's hard to think of it, or I personally remember the temples in Kyoto, and I feel that it's a place or an architectural thing. Give me.
Then, I wanted to find the answer to what scale gives shape, size, and so on.
I immediately thought of being surrounded, and when I was in a place surrounded by human scales such as walls, ceilings, greens, etc., I felt like I could stand. It may be possible regardless of the architectural use.
However, in a really small building, restaurant/cooking class, it seems impossible to subdivide the space further in order to create a feeling of being enclosed.
本当は大きなテーブルを真ん中に外まではみ出るように置きたい、けれど、細長い変形狭小地ゆえに、建物規模もそれを許さないようだ。
物があるゆえに、人は何かを感じとり、何かに影響を受けて、何か行動をする。それは建築が存在することで起こることであり、建築が存在する意義でもあると思う。
なぜ大きなテーブルか、なぜ真ん中か。本当に小さな建築で、ひと目で全てが見渡せて、存在もはっきりとわかる。見る人によって違う建築が立ち上がるであろうが、ひと目で存在がわかることには変わりがない。
だから、単純で明確に伝わる物をそこに置きたい。飲食店兼料理教室ならば、人と料理をつなぐことが建築の役目であり、それをテーブルに、それも大きな1つのテーブルで表現し、テーブルという物により、つながりを人に感じとってもらいたかった。
外まではみ出すのは、その場所が鉄道高架の立ち退きによってできた変形地で、これから街が変わる、風景が変わる場所だから、何かの手掛かりとして、何かとはやはりつなぐこと、新しい環境と建築をつなぎ、それが風景の一部になり、馴染み、こなれていくようなことを想ってみた。
しかし、その大きなテーブルが入らない、ならばと反転してみることにした。内部空間ではテーブルと人の位置関係を反転させて、敷地境界線よりはみ出す部分はカット、そうすれば、大きなテーブルの痕跡は残しつつ、飲食店兼料理教室としての用途を満たすことができ、尚且つ、外とは反転したテーブルの痕跡が真ん中にでき、その痕跡が人の位置関係を決めるという、大きなテーブルが真ん中に置かれた場合と同じ状況をつくり出すことができる。
そして、反転した結果、人の意識は外へと向かう。この建築が変わりゆく風景の先駆けとなり、つながりが伝播するように外へ向かって影響が出れば嬉しい。
"Reversal and outward connection"
Actually, I would like to place a large table in the middle so that it protrudes to the outside, but it seems that the building scale does not allow it because of the narrow and deformed narrow land.
Because there are things, people feel something, are influenced by something, and do something. That is what happens when architecture exists, and I think that it also means the existence of architecture.
Why big table, why middle? It's a really small building, you can see everything at a glance, and you can see its existence clearly. Different architectures will start up depending on the viewer, but it is still possible to see their existence at a glance.
So I want to put something that is simple and clear. In a restaurant/cooking class, the role of architecture is to connect people and cooking, and I wanted to express that on a table, which is also one big table, and to let people feel the connection with the table. ..
The area outside is a deformed area created by the eviction of the elevated railway, and it is a place where the city will change and the landscape will change. I thought that it would become a part of the landscape, become familiar with, and become familiar with.
However, I decided to flip it if the big table wouldn't fit. In the internal space, the positional relationship between the table and the person is reversed, and the part that protrudes from the site boundary is cut, so that it can be used as a restaurant and cooking class while leaving the trace of a large table. On the other hand, a trace of the table that is reversed from the outside is created in the middle, and the trace determines the positional relationship of people, which can create the same situation as when a large table is placed in the middle.
And as a result of the reversal, the consciousness of the person goes out. It would be great if this architecture would be a precursor to the ever-changing landscape and would have an outward impact as the connections spread.
プランを考える時は巨人になって俯瞰してみるから、全体像はわかりやすいが、普通の人目線とは違うところを意識しないと、人の内面まで届かなくなる。
物を介して、この場合は建築だけれども、人の内面にどのような影響を及ぼすかに興味があり、それは物が人に影響を与えることが前提になるが、建築は内部に人が入り込める空間をつくり出し、外部環境という空間を形成する一要素にもなるので、十分に人に影響を与える存在といえる。
そういう存在の建築で、もっと詳細に人に影響を与える物をみていくと、形や大きさ、色や素材などがある。それらはどれも、視覚や触覚など、人の感覚に作用する物であり、人の内面に影響を与える時の入り口で、介在する物である。
そのお店は小さな飲食店兼料理教室、最低限の設備を仕込み、人の居場所をつくる、その時に空間の中に置き、外部と内部をつなぎ、建築と人をつなぎ、人と人をつなぐ役目としてテーブルという物に注目した。
大きなテーブルを3つ、真ん中のテーブルだけ高くし、2つのテーブルは外まではみ出している。その形は楕円、大きなテーブルは人を集め、人と人をつなぎ、楕円のカーブは人と人の距離を緩やかに調整し、外のテーブルは周辺環境にもこのお店の何かを伝えるためにあり、そして、立ち上がる壁には、テーブルの形と呼応した開口があり、建築を引っ掛かりがあるアイコンのような存在として、外に向かって建築と人をつなげる。
このように様々なつながりをつくり出す建築という物があってはじめて、人の内面に影響を及ぼすことができる。そして、その影響が今度は建築にかえってきて、建築の見え方が決まる。
"Connect, influence, and view"
When I think of a plan, I'm a giant and I'm going to take a bird's-eye view, so it's easy to understand the whole picture, but if I don't pay attention to what is different from ordinary eyesight, I cannot reach the inside of people.
Through things, in this case architecture, I'm interested in how it affects the inside of a person, which presupposes that things affect people, but architecture allows people to enter inside. It is one of the elements that create a space and form a space called the external environment, so it can be said that it has enough influence on people.
If you look at the objects that affect people in more detail in such existing architecture, there are shapes, sizes, colors and materials. All of them are objects that affect human senses such as visual sense and tactile sense, and are objects that intervene at the entrance when they affect the inside of a person.
The store is a small restaurant and cooking class, equipped with the minimum equipment to create a place for people, put in the space at that time, connecting the outside and the inside, connecting the architecture and people, connecting people to people I paid attention to the table.
Three large tables, only the middle table is raised, and the two tables stick out. Its shape is elliptical, the large table gathers people, connects people, the elliptic curve gently adjusts the distance between people, and the outer table conveys something of this shop to the surrounding environment. There is an opening corresponding to the shape of a table on the rising wall, and it connects the architecture and people to the outside as an icon-like entity that catches the architecture.
It is only when there is an architecture that creates various connections in this way can it influence the inside of a person. Then, the influence will change back to architecture, and the appearance of architecture will be determined.
見ている人によって同じお店でも違うものが立ち上がる。それは人の意識の中に物が介在すること。だから、どのように物を介在させるかが設計の範疇になる。
きっと人は物をいちいち見ない。何から何まで見ていたら、頭の中がパンクするから、過去の経験に当てはめて安全な物は排除する。だから、そもそも害の無い物、危険が無い物は見ない。
ところが、害があり過ぎたり、危険が大きい場合は防衛本能が働き、自分を守ろうとして関わらないようにする。
だから、少し微妙に何だか、安全そうだけど、引っ掛かるぐらいが丁度良く、興味がそそられる。
垂直面に注目してみた。目で見てわかりやすいから、そして、建築として何か意味を持たせたり、存在を誇示したり、印象的にするための最低限の操作をする場合の参照面になるから。
鉄道高架の立ち退きによってできた変形地、これから街が変わる、風景が変わる。この四角に区画整理される何も特徴が無い地に、無造作にランダムに開けられたアーチ状の開口部や出入口が違和感や引っ掛かりをつくり出し、物として人の意識の中に介在する。
ではなぜアーチか、それは物と人をつなぐ様を形として表現してみて、人の意識の中での物としての介在の仕方を少しコントロールしてみようとした結果である。
"Vertical plane for connecting control"
Different people will start up at the same shop depending on the viewer. That is that things intervene in human consciousness. Therefore, how to make things intervene is a category of design.
Surely people don't look at things one by one. No matter what you look at, you'll have a flat inside your head, so apply to your past experience and eliminate safe things. Therefore, I don't see anything harmless or dangerous.
However, if it is too harmful or too dangerous, the defense instinct works and keeps you from trying to protect yourself.
So, it seems a little subtle and safe, but just getting caught is intriguing and intriguing.
I focused on the vertical plane. It's easy to see, and it's the reference plane for the minimal manipulation to make something meaningful, show off its existence, or make an impression.
The transformed area created by the eviction of the elevated railway, the city will change, and the landscape will change. Randomly opened arch-shaped openings and doorways create a sense of discomfort and catches in this square, which has no special features, and intervenes in people's consciousness.
Then why is it an arch, which is the result of trying to control the way of intervention as an object in the consciousness of a person by expressing the shape of connecting an object and a person as a form.
そのお店を遠くから見ている人がいて、また、そのお店を電車から見ている人がいて、また、そのお店を裏から見ている人がいて、また、そのお店を中から見ている人がいて、もしかしたら、そのお店を上から見ている人もいる。
どれも同じお店だが、見ている人によって違うお店が立ち上がり、それらが同時に起こるならば、同じお店でありながら、違うお店がたくさん存在する。
そうすると、どこに合わせればいいのか、誰に合わせればいいのか、デザインをする以上は一応ターゲットが必要になるだろう、どうしたものかと。
ただそこに、そうすると、そのお店を設計する側から見ている人も加わるので、また違うお店が出現する。
もう際限ない、結局はそれがひとつのそのお店ということだろう。
"The store"
Some people are looking at the shop from a distance, some people are looking at the shop from the train, and some people are looking at the shop from the back. Some people are looking at it, and maybe others are looking at the shop from above.
Although they are all the same store, if different stores are opened depending on the viewer and they occur at the same time, there are many different stores even though they are the same store.
Then, where should I match it, who should I match it with, and beyond designing, I would need a target for the time being.
However, if you do so, people who are looking from the side designing the shop will also join, so another shop will appear again.
It's endless, it's just one store in the end.
知らないうちに様々な制約を勝手に意識しているもので、例えば、エコロジーに関することで、住宅でいえばQ値やUa値などの指標を持ち出してきて、断熱性能を比較したりなど、それが良いことで、当たり前のことで、それを満たすことがウリになり、それが全てのような、建築や住宅の本質とは関係が無いことなのに、計算すれば誰でもできることなのに、ちなみに、そこから住宅全体の窓面積を割り出すことができて、その方が余程重要だということを言う人も行う人もほとんどいないが、いつの間にかエコロジーが無条件で善になっていることに違和感しかない。
声高にエコを持ち出してくることによって、何かを見えなくしていることに気がつかないのだろうかと住宅の計画をしながらいつも思う。
周辺環境と今いるところが重なり合い、境界線が混じり合って曖昧な領域が生まれ、そこが人の集まる場所になれば、周辺環境とのつながりができ、そこでしか実現できない空間が生まれる。
これは環境を生かし、その環境に建築を溶け込まして、その場所特有の建築や空間をつくるためのよくあるひとつの手法だが、今回はそれを少し応用して、人の集まる場所をもっと詳細なアイテム、今回は大きなひとつながりのカウンター、として目で見てわかりやすく表し、また、そのカウンターが建築の特徴となるように計画している。
人が集まることがなかなかできない時だから、離れていてもつながりを感じることができることと、またいつでも集まることができることを大きなひとつながりのカウンターとして表すことを意図している。
建築を考える時に外皮と中身を別々に考えてしまう。建築は重力に逆らって下から積み上げていくので、一部違うつくり方もありますが、基本的には、建築の構造と呼ばれる骨組みの部分は外皮も中身も同時に組み上がる。
だから、外皮と中身はつながっており、別々に考える方が不自然なのだが、仕上げ材の求められる性能が違うからか、別々なものと捉えてしまう。
仮に、東京ドームのような天候に左右されない広い空間の中に家を建てるとしたら、外皮と中身を分ける必要があるだろうか。天候に左右されない空間だから外皮としての性能が必要無く、そうすると外皮と中身を分ける必要も無く、そもそも外皮と中身などという考え自体をしないだろう。
そうすると、温熱環境や環境負荷を考慮する存在としての外皮とその中身以外に、外皮と中身について別の意味合いがあるとしたら、そこが面白いし、そこに興味が湧くし、建築のデザインとしての本質的部分がそこにあるだろう、いくつか思い浮かぶ。
何からの影響かはわからないけれども、開放的な外皮の中に、不自由で動かせないもの、それは密実で塊で本質的なもの、を内包するイメージが常にある。
建築は基本的には動かないもの、動かせないもので、自由にできそうで、実は不自由なことが多く、制約が多く、その中でどうするかが問われているようにいつも感じていて、それをそのまま表現することもあるけれども、それに一旦開放的な外皮を纏わせることで、それが対象化され、より建築の本質のようなものが露わになるようなことを考えてしまう。
その開放的な外皮は存在として実体として目の前に無くてもよく、むしら感じられる、目には見えないけれど認識できるようなことの方がより内包するものを際立たせるだろう。
だから、建築を取り巻くものに、建築以上に興味が湧く。そして、それは日本的空間の得意とするところだろう。
人と人がランダムに距離を空けて居場所を確保しようとすると、その軌跡は段々と流動的になる。広場にいる人に向かって上から呼びかけたら、整然と前後左右にまっすぐに並ぶことはないだろう、人によって距離感が違うし、目線の高さも違うし、身体の大きさも違うから、何か目印や目安がないと整然とはいかない。
そして、曲がりはじめる、蛇行しはじめる。身体の向きが揃わない限り、まっすぐにはいかないもので、その身体の向きも微妙にズレるから。
むしろ、曲がったり、蛇行したりする方が自然なのかもしろない、川の流れのように。川の水は流れやすいところを流れるから、まっすぐにはいかず、曲がり蛇行する。それが極端になると三日月湖となり、また川の水が流れやすいところを流れる。
人同士が多数の中で自分の居場所を確保しようとする時も同じではないかと考え、曲がり、蛇行する軌跡をカウンターとして考えてみた。
どこまでも永遠に続く空間がもし存在したら、それは建築というだろうかと考えた。
例えば、コルビュジエの「無限発展の美術館」という構想があり、その実現例が上野の西洋美術館だが、それは渦巻状の動線空間になっていて、無限にぐるぐると渦巻状に拡張していくことを想定していた。だだ、実際には終わりがあり、そこで壁ができて終わるのだが、そもそも、渦巻き状の空間を想定している時点で建築だった。
もし、ただ広い、あるいは、ただ長い、それも永遠に続きそうなくらいの規模の空間であったなら、もはやそれは「自然」と読んでもいいのではないかと思う。
ということは、建築である証拠は、終わりがある壁で囲まれていていることであり、それも人の営みが行われる範囲である必要がある。
建築でできることは何があるのかと考えながら設計する。当たり前のことだけど、特に何も考えなくてもプランはできる。そして、その違いはわかる。
そこに人がいると感じられるか、人間がいると感じるか。ある特定の人でも、不特定多数の人でも、人が使うと考えているのか、人を社会の中で定量的に扱ったのが人間ならば、人間が使うと考えているのか。
人が使うと考えた時、ムダやブレ、揺らぎなどが生じる、決して完璧ではない、だから、偶発的な面白さを演出するような設計になる。
人間が使うと考えた時、ムダやブレ、揺らぎは無く、全てが計画通りに進み、その場合の効果が期待できるような設計になる。
どちらかが良いという訳ではないが、偶発的な面白さが生きることや生活することには必要だと考えるならば、人を感じられる設計をすることなるだろう、実際それしかしたことがないが。
天井の高さに変化を付けたく、それも居る場所によって全て高さが違うようにしたくて、ただ、天井だけを装飾として扱い、高さを変化させることもできるが、それでは構造を持った建築でわざわざ行う必要が無く、構造を持たない内装設計でいくらでも見ることはできるので、構造と一体となった、その天井の高さの変化がそのまま外観のフォルムになるように考えている。
どうも木造で小さな建築となると三角屋根を最初にイメージしてしまい、そのフォルムは単純でアイコンとして「ホーム」をイメージさせるが、ただ、それだけにそのフォルムでは引っ掛かりも無く、印象に残りにくい。
三角屋根の屋根裏の形状は天井を設けなければ、屋根なりの形がそのまま室内に露出するので、天井の高さは変化する、しかし、居る場所によって全て高さが違うようにはならない。
ならば、三角屋根自体を傾斜させようと考えた。そうすれば、居る場所によって全ての天井高さが違うようになる。
そして、そのフォルムは、三角屋根という昔からあるアイテムでの安心感が、室内での天井の高さの変化が居る場所によって全て違うという慣れない状況を上手く緩和してくれて、ことをうまく馴染ませてくれるだろう。
風景を切り取る窓のことをピクチャーウインドウというが、それは逆に考えれば、外から見たら室内の風景をも切り取る。
壁一枚隔てただけで、外と内という全く違う世界がそこに展開されているが、その壁の性能が低かった頃は、壁の性能とは断熱性や遮音性などであるが、外と内の差はほとんどなくて、外も内も大して違いがなかったのではないかと思う。
それは温熱環境や音環境だけのことではなくても、内にいても雨風を凌げるだけで外と変わらないような状況であり、結果的に外と内の違いが曖昧だった。
ところが、壁の性能が高まると外と内はキッチリと分かれ、全く違う世界が誕生することなった。温熱環境や音環境だけのことを考えた場合でも、それは内だけが静かで、夏涼しく、冬暖かい場となり、外とは全く関連性の無い内が存在し、曖昧さが無い。
この曖昧さが無い様、この外と内のキッチリと分かれた関係性には違和感を覚える。それは中から見ればピクチャーウインドウだが、それは同時に外からも中を切り取る関係性に似て、外と内が一対であるにもかかわらず、外と内が断絶している。
理想は壁の性能が高く、そのおかげで温熱環境や音環境が良く、それでいて外と内の関係性が曖昧である状況なのだが、壁だけでなく屋根も含めて外皮の性能を高めていくと、普通に考えれば、どうしてもピクチャーウインドウ的な窓ばかりになるが、ちょっと視点を変えて、風も利用してみる、その風のことを卓越風というが、地域特有の風向きを持つもので、それを利用すれば、そもそも外と内が曖昧にならざるを得ない。
外皮の性能を高めて魔法瓶のような住宅をつくっても夏が暑くなり、冷房効率が悪くなるだけだから、風を利用するのが良いだろう。
まずプロトタイプをつくり、その物から考えるようにしてみる。とりあえず、手を動かして、思いつくままに、こうかな、ああかなとやってみる。そして、出来上がった物を解説してみる、無理矢理、突然プレゼンをしなくてはならない体で、あるいは、文章にしてみる。そうすると、大概、意味不明で、辻褄が合わない、矛盾したり、支離滅裂になる、きっと人がパッと思いつくことなど、その程度のことなのだろうか。
ただ、そこに辿り着きたい部分の種があったりするような気がするし、そうあって欲しいと思う。
そこで、今計画中の10坪平屋の飲食店兼料理教室をそうしてみた。そうしたら、案外、言葉は自由だなと思って、あれこれ書いていたら、途中から言葉が追いつかず、そうすると、そろそろ数値で表そうかなと思いはじめた。
距離を取るには折りたたむしかない。10坪の中に納めるためには丁寧に折りたたんで、角を取って丸くして、周長をできるだけ長くしてより席数を稼ぎ、それで複雑な席配置にし、様々な方向に顔が向き、相対する事なく、距離感を調整でき、天井高さの変化がより席同士の違いを生み出し、ひとつとして同じ条件の席は存在しない。
そのことは、席の領域の決め方で、そこで起こる状況を決めることができ、コントロールすることができるので、ソーシャルディスタンスの有無に左右されずに済むと考えている。

この状況化に対応することで、今まで手を付けなかったことに目を向けて、新たな何かが芽生える可能性だけでも感じることができたら、後から振り返った時に肯定的に思えるかもしれない。
直線的に近づいたり離れたりしていると閉じないから絵にはならないけれど、それが回転していたり、湾曲していたりして、最初と終わりが合い閉じれば、何かしらの形を成し、ソーシャルディスタンスが絵になるような何か、カウンターか何かをイメージして一日中スケッチをしているが、どうもしっくりとこない。
距離を取ることと空間を形成することは相性がいいはずで、間を空けることは距離を取ることだから、ソーシャルディスタンスを空間形成の発露にするのは妥当性があると思うのですが、どうもうまくまとまらない。
やはり、ソーシャルディスタンスという言葉自体がネガティブな響きになっているからか、たがら、いいイメージにつながらないのか。
素直に距離をデザインすると考えれば、もっと様々なバリエーションが存在するはずだから、少しは方向性が見えてくるかもしれない。
わざと天井を低くくすることもある。どうも天井は高い方が良いと思われているようで、世間一般的には、天井が低いことは狭くて、よくマンションは天井が低いから、という会話を聴いたことがある。確かに、マンションは少しでも階高を低くして、それで少しでも多く戸数が稼ごうとするが、天井が低いということは悪いことではない。
空間の大きさの決め方には違いがあり、物を置く空間などはその物の大きさによって、その物が収納できる大きさで決まるが、人がいる空間は人の大きさが基準になる。例えば、物を置く空間としては美術館や博物館などがあり、展示する美術品の大きさにより展示室の大きさが決まる。人がいる空間の住宅やマンションなどでは、人の大きさが基準になるので、人の大きさに近ければ、それはヒューマンスケールと呼ばれ、人にとって親和性があり、適切な大きさということになる。
だから、天井の低さもヒューマンスケールと捉えれば、人にとって心地よい高さとなるかもしれないし、吹き抜けのような天井の高い空間はヒューマンスケールを逸脱しているので、人によっては落ち着きのない、居心地が悪い空間となるかもしれない。
このように、天井の高さの違いより、人に与える影響にも違いが出るので、天井の高さをデザイン要素として扱うことで、人と建築の関係性をつくり出すことができる。
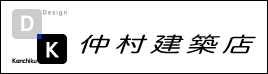
人が距離感を保ちながら繋がるにはどうしたらいいのだろうかと考えることが、このウィズコロナの中で計画案を考える時に、その建築のパブリック性が増せば増すほど、必要なことになってきた。
簡単に言えば、住宅のパブリック性は0で、プライベート性が100%だから、住宅ではその必要性は無いが、飲食店や店舗、次いで、学校や病院、美術館、博物館などの順にパブリック性が増していくと、何らかの対応が必要になり、既存の美術館などは事前予約制にし、入館日時を指定してチケットを購入することで入館人数や密度をコントロールしている。
また、既存の飲食店は人と人の距離感を取るために、客席を1つ飛ばしにしたり、テーブルの数を減らしたりして、やはり人数と密度をコントロールしている。既存の施設で、人数や密度をコントロールするにはその方法しかないのかもしれないが、それは売上にも影響する。
だから、それがわかっていて、これから計画する飲食店や店舗で今までと同じようなことはできないと考えている。ならばどうするか、人と人が適切な距離感が保ちながらも、人と人が繋がることを建築の課題としてあげ、それをデザインで解決していくことが求められている。
予算からすると10坪が限界のようだ。どのようなお店でも10坪以上あれば何とかなるだろう、10坪未満のお店だってたくさんある。飲食店兼料理教室で10坪平屋の建築、家ならば10坪は狭いが、お店ならば、ただ厨房の割合が大きくなる。
10坪の中で厨房とホールをキッチリと分けたら、例え、オープンキッチンでもどうだろうか、せせこましくなるのではないだろうか。それに中途半端な、厨房も、ホールも、広さになりそう。ホールも狭かったり、席数がとれなけば、カウンターだけにするが、ラーメン屋さんのように、何かもったいない、せっかくの10坪をテナントとして入るのではなくて、平屋で建てるのだから、他にやりようがある気がした。
例えば、10坪全てが厨房というのはどうだろうか。お店として考えたら10坪は中途半端な広さ、特色もないように思えるが、厨房として考えたら10坪は広い、料理教室も兼ねるならば、厨房は広い方がいい。
厨房の中にお客さんがいて、厨房の中で料理教室をして、全てがシェフズテーブルになる。
ただ、保健所で問題になりそうな気がするが、厨房とホールは明確に分かれていないといけないから、小まめに分けて、何とか方法はありそうな気がするが、手洗いだらけになったり、このご時世それでも構わない気もする。
そして、厨房の中には大きなひとつながりのカウンターをつくり、その中に厨房機器、設備を仕込む。カウンター上で料理がつくられ、お客さんに供され、料理教室が開かれる。
屋根はそのカウンターを雨露からしのぐためにつくられる。
その大きなカウンターが人と人、人と料理、料理と料理をつなぐ。
気分でどこで食べてもいい、どこで料理をしてもいい、そのカウンターは外まではみ出してつながっていて、外の人や街の風景もつなぐ、鉄道高架の立ち退きによってできた変形地、これから街が変わる、風景が変わる、その時に何かつなぐ役目が飲食店のカウンターというのも悪くないし、結構、食べ物につられて、だから、カウンターは変形している、変形していれば周長が長くなり、人がより集えるし、直線だらけの風景に味が出る。
こういう計画もまたよしだと思った。
考えてもみたら自然界の中で人間が知覚できることは結構限られていて、光にしても全てが見えている訳ではないし、音にしても全てが聴こえている訳ではないし、見えない色もあるし、目にはそのように見えないが、写真ならば見える象もある。
人間が知覚できる範囲が基準で表現をしているから、それが一部だということに気がつかない。そして、それが全てで、それは良いことだと思い込まされているかもしれない。
建築はどんなにデジタル化されても、つくり方はある意味ローテクで、人間が知覚できる範囲しか扱うことができないから、知覚できないことが存在していようと関係がないかもしれないが、それは人間主体で建築を考えた場合で、あくまでも人間の知覚を基準にしているからで、例えば、単なる物体が先にあって、その単なる物体から触発されて人間が使いはじめ、その物体が人間を内包できたならば、そこに空間が存在し、それは建築であり、ただ、最初は建築には見えない単なる物体だから、人間が建築として知覚していることをその単なる物体は持っていないことになる、なのに建築である。
そのような建築として知覚されない単なる物体の建築をつくりたいとふと思った。
人の住む場所と人の住まない場所で、建築として何が違ってくるのだろうかと考えてみた。
困った時は事務所として申請すれば良いと聞いたことがあるが、人が住まない場所としてまず思い浮かぶのが事務所であり、設備のことをいえば、便所と簡単な流し以外は無い、例えば、浴室があると事務所としては用途上認められないだろう。
ただそれは、人が住む住まないを機能的なハード面から見ただけであり、ここで取り上げたいのは、人との関係においての違いであり、人と建築との関係において住む住まないができあがる建築にどのような影響を与えるかということ。
人が住む場所であれば、人と建築との関係は1対1の対応になり、より人に合わせた濃密な関係性になるだろうし、人が住まない場所であれば、人と建築との関係はより希薄になるというか、建築はむしろ環境や外部空間といった人を包み込む部分との関係性がより強くなると思う。
そうすると明らかに、人が住む住まないによって、求められる建築が違ってきて、そこでできることもかなり違ってくる。
感情や気分をそのまま受け止めるような建築を考えようとしている。やはり、建築は人を包み込むようにできているもので、もしそうでなければ、工作物、土木構築物だから、それでは建築ではないから、ならば、人と建築の関わりの中で考えると、主体は人になり、それに合わせて建築が変化する方が自然のような気がする。
そうすると、人は日々の生活の中で何に一番左右されるのか、良くも悪くも感情や気分だと思う。少なくとも、感情や気分の変化無しに1日を過ごすことはないだろう。
だから、建築を計画する上で、人の感情や気分を扱うことには妥当性がある。程度の差こそあれ、感情や気分に左右される人を包み込む建築はどうあるべきかは重要な問いだと思う。
一方で、そのような言葉による問いから導き出された建築は本当に妥当性があるのだろうかとも考えてしまう。ちょっと窮屈な思いもある。
何もしなくても湧き上がってくる感情や気分があり、それが意図せずとも見方に影響を与え、その影響が何も介することなしに建築化されたようなものにしたく、それは何か固定化されたイメージの建築ではないことだけは確かなので、つくりながら、後追いでできあがったものに言葉をつけてみようと思う。それが例え的外れだとしても、できあがったものにはその時の感情や気分がダイレクトに反映されるだろうし、少なくとも窮屈な思いはない。
感情や気分が何かをきっかけに湧き上がり、それがさまざまな見方に影響を与え、その都度違う状況をつくり出す。その状況は言葉で表現するには複雑でまどろっこしく、イメージで表現するには単純すぎてつまらない。
何かを表現するというプロセスを介すると、そこで表現手段に合わせて変換しなくてはならないから、必ず抜け落ちる部分があり、それを踏まえて伝えなければならないのだが、伝えるという動作をひとつ入れないでわかるようになれば、できあがるものも違ってくるだろうと思う。
よくあるように記号化してしまえば、伝える動作を入れないで、表現というプロセスを介さないで、瞬時にわかってもらえるが、それで感情や気分によって変わる見方までわかるのだろうか、それこそ、もっとわからなくなるような気がする。
たくさんの記号が散りばめられていて、その中から選ぶようにすれば、その選ぶ基準が感情や気分であればいいのかもしれない。建築が記号の集合体になればいいのかもしれない。
と考えたところで、すでによくある「木の家」は記号化された建築だと思い、だから、「温もり」や「優しさ」などという固定された良いイメージがある一方で、感情や気分の入り込む余地がないくらい変わらないイメージになっており、それに息苦しさを感じる。
どこかでコロコロ変わる感情や気分を受け止める部分がないと人を包み込む建築で日常を送るのは辛いかもしれない。
何かをつくろうとした時に、つくろうと想定されているものがあり、自分が考えているものがあり、他人が考えているものがあり、それらが一致して同じということはほとんどない。
ということは、ひとつのものに対して、同じものなのに、さまざまなものがあるということ。
普通はこれを上手く調整して、誰もが納得するひとつのものにするのだろうけれど、せっかくだから、このさまざまなものをそのままに合体して仕上げてみるとどうなるのだろうか。納得するひとつのものと、さまざまなものをそのままに合体したものと何が違ってくるのだろうか。
さまざまなものをそのままに合体しても全ての考えや想定は盛り込まれているのだから、納得されるはずだから、上手く調整するよりも面白いものになりそうな気がするのです。
何でもかんでも平面的に捉えてしまう。昔、村上隆がスーパーフラットということをいっていたけれど、東山魁夷の絵が好きで、一番最初に絵を見て感化されたのはウォーホールのキャンベルスープなので、陰影がなく、空気遠近法でもなく、画面という二次元に三次元を描くためになるべく平面的にしようという、変化球を投げようとしたら、結局直球になり、ただ、その直球が何ともいえないシンプルな味があるような、ややこしい捻くれ者の表現が心にささる。
だから、建築という三次元の代表のような存在を表現する時にも、平面的に、フラットに、イメージでは陰影がなく、その場面場面は建築をスライスした断面という二次元を見ているような感じです。
だから、そこにいる人も厚みがなくペラペラでひらひらした存在、人間とはそういうもので、人間は社会の中で存在する人なので、その社会の在り方によって人はどのようにも人間として変わるし、変われる、人間には厚みは必要ではないかもしれない。
そのような見方だから、柔軟に人間としてウィズコロナに合わせ、ひらひらと変わればいいし、後で振り返ったら、今のこのややこしい時があったから、人として厚みが増したと思いたい。
設計とは、何でもありな多様性に枠をはめて限定的な多様性にする行為だとしたが、その枠のはめ方を人間中心に考えたいと思います。
人間中心以外では、素材や形といった物中心に考えたり、暑い寒いなどの温熱環境から派生して、また別の物中心の考えがあったりなどしますが、人間が使い、人間との関係性があるから建築として成立しているのであり、人間とは関係が無いところで成立していれば、それは単なる工作物であり、建築とは明確に違います。
だから、設計として建築を取り扱う以上、人間中心に考えるのが自然であり、そうすると、予算も物中心の範疇に入りますので、物の良し悪しとは関係が無いところで、建築の良し悪しを考えることができるようになります。
全体としてのひとつの意味づけではなくて、たくさんの意味づけが存在しており、そのどこを取り入れるかは人によって違い、その取り入れ方によってその都度意味が変わり、見え方も変わる、そのような建築をつくりたいといつも思う。
ひとつの意味で成り立つものはどこかで無理矢理その意味に合わせていて、そうすることにより存在意義を見出しているのかもしれないが、それは何とも不自然であり、別の見方や別の人が見れば、いろいろな意味がつけられる。それを簡単に言えば、多様性があるということだけれど、単なる多様性では何でもありであり、それは何でもありの建築になり、何でもありならば、あえて設計者はいらなくなる。
設計とは、何でもありな多様性に枠をはめて限定的な多様性にする行為であり、その枠のはめ方がデザインであり、デザイナーの姿勢が表れるところだろう。
本当に小さい商業施設に対して、その大きさに対する認識を建築デザインと結びつけて考えることは有効だとしたが、その大きさ故に、小さいから全てを一望でき、そうすると、本来ならば、ひとつひとつ、それは無意識に、これは何、これは何と意味を確認しながら、その存在を段々と認識していくところを、瞬時に確認と認識のズレもほとんど無く、意味づけをしてしまうことになる。
この意味づけを印象とか、イメージという言葉で置き換えるならば、その大きさ故に、第一印象を瞬時に決められてしまう。
人も同じだが、第一印象で8割ぐらいは成否は決まるかもしれないので、商業施設で、しかも小さい建築ならば、尚更、その大きさをデザイン要素として活かしコントロールしなければならないだろう。
いま、本当に小さい商業施設の計画案を考えている。一般的な家より小さく、屋台や移動販売車や露店よりは大きいくらいのスケールです。
普段、建築を用途で振り分けているところがあり、ここは家、ここは飲食店、ここはスーパー、ここはコンビニ、ここは病院、ここは、などのように、そして、勝手に大きさもこのくらいだと決めつけていて、だから、あの家は大きい、この飲食店は広い、このコンビニは狭い、などと思ったりする。
用途と大きさは結びついていて、違和感なく人に認識され伝わるための用途に対する大きさがあるような気がします。そうすると、明らかに、今計画中の商業施設はその違和感なく人に認識され伝わる大きさから外れている。
その大きさの認識に対してどうするか、それを建築のデザインとしてどのように考えるか、どのような建築のデザインに結びつけるかは、十二分にこの計画案の主題として成り立つ問いだろう。
3年に1度の一級建築士の定期講習の日、新型コロナで3回延期になり、今年度中に受講すればいいのですが、またいつ第2波の新型コロナで受講できなくなるかもしれないから、早めに、できるうちに、朝から5コマのビデオ講義と効果測定のための修了考査と1日がかりでした。
一応、修了考査に合格しないと、また定期講習を受講し直しで、今年度中に定期講習を修了しないと、修了するまで設計できなくなるのですが、たぶん修了考査で不合格になるような人はいないくらいの問題の難易度であり、ビデオ講義で使用するテキストを見て解答してもよいので、全く何も問題なく合格でき、それは全然大したことでは無いのですが、ただ、いつも思うのは、いつまでマークシート方式で解答するのだろうかということ。
マークシート方式の○✖️問題を解くのも3年に一度、この定期講習の時だけで、3年ぶりに○か✖️かを考える問題をやり、それは単なる間違い探しをしているだけで、そして、出た○か✖️かの解答をマークシートに塗り絵していく。
こういう定期講習の場合、間違い探しをする問題になるのは仕方が無いとしても、このマークシートの塗り絵をしている時にいつも思います、この時間が勿体ないな、塗り絵をしている時間で他の問題がいくつも解答できるし、学生の時にはマークシート方式がありましたから、いつまで経っても進歩しないというか、パソコンもスマホも無い時代からあるマークシート方式を今だに採用しているのは不思議だし、なんかとてもアナログだなと、アナログ好きには貴重な時間でしたが、塗り絵はなんとか別の、デジタルな方式に、その方が受ける方も管理する方も楽で時間の無駄もなく良いと思うのですが、何かマークシート方式で行う理由があるのでしょう。
線路際の敷地での設計や工事の経験は何度もあります。一番最初は前に在籍していた設計事務所ではじめて担当した集合住宅の設計で、敷地が東海道新幹線を見下ろす場所だったので、事前協議の書類を提出するためにJR東海の大井車両基地へ何度か行って、止まっているたくさんの新幹線車両を間近で見たりもしました。
他の鉄道会社でも、設計段階で事前協議をし、別にそれは大変なことではないですが、一番気を使うのは施工段階の実際に工事をする時であり、設計事務所にいた時はゼネコン任せでよかったですが、自社で設計施工をするようになると、もし万が一何か事故があれば大変なことになるかもしれないという心配がいつもありました。
ただ、実際に工事がはじまれば、心配は最初の方だけで、きちんと安全対策を取るのだから問題は無いので、段々と慣れてきて気にもならなくなり、むしろ間近で電車が見られることを楽しんだりもしていました。
そうやって余裕ができると、いつもふと思うことがあります。すごく近くを電車が通り、時には車両の中の乗客と目が合ったりして、実際の距離がとても近くても、お互いのいる場所は全く違う空間であり、その空間同士は断絶しているから、お互いに近かろうが、目が合おうが、全く気にならない、この関係性をうまく同一の建築の中におさめることができたならば、高い公共性やプライバシーが要求される建築での有効な空間構成が発見できるのではないだろうか。
実際にずーっと線路際の土地に住んでいる人にとっては、近くを電車が通っていても、気にしないどころか、無いも同然なので、それはただ単に慣れ以上の何かがあるとして考えてみるのがいいかもしれない。
毎日毎日、建築ばかり見ている、それは誰でも同じで、街を歩けば誰でも建築を見ます、どこにでも、そこらじゅうに建築は建っているから、でも後で振り返った時に、例えば、1日を振り返ってみて、覚えている建築はいくつあるだろうか、いや、いくつどころじゃなくて、ほとんど覚えていないだろう。建築をやっている私でさえ、ほとんど覚えていない、覚えているのは利用した建築ぐらいで、見てはいるけれど覚えていない。
ほとんどの人が目の前を通り過ぎる建築を覚えていない、見ていない、それはそこに建築が存在していないのと同じです。その証拠に、今まであった建築がある日突然取り壊されて無くなってはじめて、そこに今まであった建築のことを気にするが、ほとんどの場合、そこにどのような建築が建っていたかを思い出すことができない。それは意識の上でそこに建築が存在していなかったからです。
だけど、いちいち見た建築を全部覚えていたら、頭の記憶容量がパンクしてしまうから、そのくらいでいいのだろうけど、それでも覚えている建築もある訳だから、その差はどこにあるのだろうか、気になるところです。
電車の車内から窓越しに外を見ていると、流れるように風景が通り過ぎていきますが、その中でも、特に意識せずにいても、パッと目に止まる建築があります。他とは何かが違うから目に止まる訳ですが、大概そういう時は建築家の作品である場合が多いです。
それは私がそういう建築を求めているからというのも当然ありますが、ずーっと同じトーンで流れているのが突然乱れるような、ノイズのような、別の言い方をすれば、引っ掛かりがあり、そのせいで突然意識上に現れてくるようです。
その引っ掛かりが何か、私がいつも考えるのは「精度」であり、明らかに他より精度が高い、それはデザインの精度であり、そして、つくりの精度です。逆に言うと、他が粗く、雑に見えてしまうのです。
だから、建築を意識させるために必要なことのひとつとして「精度」は必ず入ってくると考えています。
変形地の建築計画を考えるのは何故だかわからないですが、宝探しをしているような楽しさがあります。
高架の用地買収の結果できた細長い変形地は、まさに切り取った後に残った余白のような土地であり、また、違う見方をすれば、元の状態の断片であるともいえる。
きっとそのような余白であり、断片である土地があちらこちらに出現しているだろう。今は空き地だが、それが段々と埋まり、何かが立ち現れた時に、これらの余白で断片な土地はどのように扱われているのだろうか。
細長い変形地であるから、利用の仕方は限られるかもしれない。実際に今計画中の土地も、前は駐車場とする計画だった。いやむしろ、駐車場として利用できるような土地の残し方をしたのかもしれない。
このような事例はきっとよくあることだろう、それ故に、これから建つかもしれない建築が何かのヒントになったり、何かを誘導するような役割に、その何かは景色の中でその建築がそこに存在することで獲得できるたくさんの人にとって良いこと、それがお宝であり、それを探り当てることが目標であり、それをこの建築計画における環境面の課題として考えています。
斜めが気になりながら、どうしてだろうと頭の片隅に残しながら、はじめて能楽を鑑賞してました。
いつもお世話になっている先生が能のシテを演じる機会にお声を掛けていただき、シテとは主役のことだとはじめて知りましたが、このようなキッカケでもなければ能楽を鑑賞することなど無いかもしれないと思い、予備知識もそこそこに宝生能楽堂へ。
非対称の客席にどこに座ろうかと迷いながら、能舞台正面に対して左斜め45度の後ろの方の席に、そこが客席も含めて全体を見渡せるかと思い、とにかくはじめてなので、舞台上だけでなく、お客の反応も見られるところが良いだろうと思いながら、その後は2回客席を移動して、舞台正面、舞台側面と座ってみました。
演者出入口と能舞台をつなぐ導入路を「橋掛り(はしかがり)」というそうで、能楽堂によりその長さは違っていても能舞台に対しては斜めに取り付いていて、何故か、どうしても建築的に見てしまうのか、それがどうして斜めなのかが気になった。
後で先生にお伺いしたら、遠近感がわかるためだと教えていただき、それが日本的、東洋的で面白く、斜めを入れることにより遠近感を出そうとするのが、西洋絵画に比べて平面的な日本画や水墨画、襖絵、屏風絵、浮世絵などの特徴と同じだと思い、それらは決して西洋絵画のように写実的ではないけれど、絵画を幾何学的に扱い、斜めの線で遠近感を実際より誇張し、写実的な西洋絵画より、より絵画的で、むしろデザインされた図案のような印象を与えてくれる。
さらに能楽はそこに実際の人の動きが加味されるので、隠れた斜めの線もあり、より幾何学な動く図案として立ち現れるような気がして、ただ、それは後から気がついたので、また機会があれば、今度はそこを意識して見てみたいと思います。
それにしても、つい建築と関連づけて考えてしまいますが、もしかしたら「斜め」を入れることを、それは過去の建築を思い返してもたくさんあるのですが、今後はまた違った見方で考えることになるような気がします。
これから景色が変わる土地にできた細長い小さな変形地、三面が道路に接する、線路際、これから高架になる、たぶん、全く雰囲気が変わるだろう。
そこに予想される建築は本当に小さい、小さな飲食兼料理教室で平屋、それだけに建築全体の形がわかりやすい。周辺の環境が変化していく中で、この小さな建築は変化に流されず、その変化を利用して、存在感を出さなくてはならない。住宅ならば、その変化に対応して住環境を整える必要があるが、飲食店ならば、まずここにお店らしきものがある形をしていないと、誰の関心も引かない。
派手で目立つのではなく、周りは住宅だから、住宅のスケール感は去就しつつ、飲食店としての外しやズレを挿入しようと考えている。
外観が基壇、中段、頂部の構成の場合、古典的なイメージになり、モダニズム建築は頂部を無くすことにより、新しい建築の見え方をつくろとした。それはモダニズムの考え方を伝えようとする時の手段として、建築の見え方を選択したのであり、新しさや考えを理解してもらうためには視覚に訴える、見え方を変えることがわかりやすい。
そして、その変え方も極端ではかえってわからなくなる。モダニズムの場合も、外観の構成を扱うということは同じであり、その中で変える、ちょっと変えることにより、変わったことがわかる、この変わったことがわかることが重要で、「あの建築は何か違う」と思わせないと。
わかりやすくもあり、同時にちょっと変わったわかりにくい部分がちょっぴり存在するような建築がいい、それが建築をつくる時の塩梅としてちょうどいい。
基壇、中段、頂部という分け方をする。建築を外から見た時に、基壇と呼ばれる基礎部分があり、頂部と呼ばれる屋根や飾りがあり、その基壇と頂部の間を中段とする。洋の東西を問わず、日本の寺院建築、ギリシャの神殿もこの基壇、中段、頂部の構成になっていて、建築の外観の構成の基本として古来よりあります。
だから、外観が基壇、中段、頂部の構成になっているのがハッキリとわかる場合、その建築は古典的なイメージを纏うことになります。
なので、モダニズム建築は前時代からのこの基本の外観の構成を去就せず、頂部を無くか、より目立たなくして、基壇と中段だけの構成を取ることによって、古典的なイメージから脱却し、新しい建築の見え方をつくろとし、それは今でも引き継がれています。
建築を外観の構成で見ていくと、基壇、中段、頂部の構成になっているか、頂部があるのか無いのかと、外観のイメージとの相関関係が面白いです。
らしさを形にする時、どこにでもあるような、特徴のない形になってしまうことは避けたい。たぶん、らしさを形にする時、そこが一番抵抗を感じるところだと思います。誰も見たことが無いものをつくりたい、新しいものをつくりたいと考える。その考え自体は良いと思います、そうでないと新しいものは生まれないから。
ただしかし、新しいかどうか、誰も見たことが無いかどうかは誰が判断して、誰のためになるのでしょうか。新しくて、誰も見たことが無いものをつくるのは案外簡単なのです。人に受け入れられることを考えなくても良ければ、誰でもできる。
らしさを形にする最大の目的は、人に受け入れられやすくするためです。独創とは、人の上に成り立ち、尚且つ、滅私したところに存在すると思うのです。滅私、すなわち、それはらしさを纏うこと、その上で、誰にもできないものをつくり出す、精度を高めて、外しズラして。
だから、外すズラし方の指南は「人に受け入れやすくするために行う」です。それだけでイメージが湧いてくるはず、難解に見せる、面白く見せるためでは無くて、外しズラした方がより人が良いと思い受け入れる、そして、それが独創になる。この場合の人は、特定の個人、クライアントでもいいですし、不特定多数の人、社会に生きる全ての人でもいい、用途により、それは違うでしょう。
らしさを形にすることが、実は独創につながる、これを理解できている人は案外少ないかもしれないです。
らしさを形にする時、どこにでもあるような、特徴のない形になってしまう可能性があり、だから、同時にその形が特徴にもなることを考えなくてはならない。
これは建築だけのことではなくて、デザイン全般、あるいは、ものづくり全般に、料理にもいえることだと思います。
そのための手法は2つあると考えていて、ひとつは外すズラす、もうひとつは精度を上げる。
外すズラすは、そこにほんの少しの違和感を挿入することです。「らしさ」はそのものではなく、どこにでもあるような特徴のない形はそのものか、そのものを真似た形であり、そこに僅かな、本当に少しの変化や、異物や、異形などを施すことにより、らしいもの、「らしさ」を纏ったものにする。
もっと付け加えますと、その外しズラした部分が見る者の意識に引っ掛かりを与え、見る者の想像力を掻き立てるので、より印象に残りやすい。
もうひとつの精度を上げるは、簡単にいうとクオリティを上げることです。形は同じでも、精度が高いだけで特徴になります。「らしさ」を追求した結果、どこにでもあるような特徴のない形になったとしても、そこから細部にわたって形のつくりの精度を上げていけば、その形の完成度が高くなり、結果的にそれが特徴になります。
ただ、精度を上げるためには、高い意識と高度な技術が必要になり、それだけに誰にでもできることではなくて、だから、特徴になります。
反対に、外すズラすは、高度な技術が無くてもできます。なぜならば、外すズラすは、精度を落とす行為と同じことをするからで、それだけに誰にでもできることですが、今度は外し方、ズラし方が重要になってきて、そこが直接特徴になる訳ですから、外すズラすための高い能力が要求されます。
どちらの手法でも特徴ある「らしさ」を形にしたものをつくることはできるので、あとはどちらを選択するかですが、できれば、精度高く外しズラした形をつくりたいと考えています。
らしさを形で出そうと考えています。素材もあると思いますが、瞬時の印象で一番残るのは形だろうと思います。
本当に小さな建築になる、だから、外形を一目で把握できてしまう。その形に好き嫌いの感情が伴うこともあるでしょう。全く好き嫌いの感情を外して成り立つことは考えにくいので、好き嫌いを超えた形をつくりたいと考えています。
好き嫌いを超越するには、やはり「らしさ」が必要になるのではないでしょうか。誰もが連想できる形、それが「らしさ」だとしたら、「らしさ」があれば、好き嫌いの感情がそもそも起きにくいのではないかと思います。
「らしさ」を別の言い方をすれば「馴染みやすさ」になるかもしれません。それが安心感を呼び、その安心感がその形を受け入れやすくする。ただそうなると、案外、どこにでもあるような、特徴のない形になってしまう可能性もあります。それが「らしさ」を形にする時に注意をしなくてはいけないところでしょう。
だから、「らしさ」を形にしながら、それが特徴にもなることを同時に考えなくてはなりません。
線路際、よく見える場所、線路に沿って細長い変形地、そこで平屋、飲食兼料理教室を行う小さな建築を考えている。
お話をいただいて、実際に行うかどうかもまだわからない、影も形もない現状で、現地を見て、これは面白そうな仕事になる予感がして「是非」と思い、それから「らしさ」をずっと考えていた。
敷地の形や大きさと、平屋との希望から、本当に小さな建築になる予定で、そうなると、必然的に建築全体を一目で判断することとなり、それで建築としての印象が、イメージが決まってしまう。要するに、建築のデザインが印象と直結するのである。
だから「らしさ」が必要かというところから考えて、使い古された言葉だが、アイコンのような、その建築を見ただけで、飲食店のような、料理教室のような「らしさ」を醸し出している方がよいのかどうなのか。
むしろ「らしさ」を外すのは簡単なので、何々に見えないようにするのは案外簡単なので、「らしさ」を醸し出すデザインを、それも建築のデザインとして成り立つものを、そちらの方が遥かに難しいので、「らしさ」を醸し出し纏う建築を考えている。
あとここが良くなればいいのに、あとここがこうなっていれば手に入れようと思うのに、ということがよくある。そういう時は大抵、自分の中でははっきりとはしていないが、なんとなくこういう物が欲しいことはわかっていて、でも具体的なイメージをまだ考えていない。
違和感を感じている状態ともいえるが、そこからよく考えると、あとここがという部分になかなか答えが見つからない、それはわかっていないからか、知識がないからか、技術がないから。
それと、その違和感は同時に、普通すぎて、よく見かけるし、ありきたりで、つまらないから、何とかした方がもっと良くなるという想いも伴う。
だから、あとここが良くなればいいのに、あとここがこうなっていれば、という想いをたくさん拾い集めるだけでも、コロナで家にいてはできない体験だなと思っていた。
人は「らしさ」を無意識のうちに求めている。
家らしさ、建築家らしさ、飲食店らしさ、などなど、究極は人間らしさか、「らしさ」を求めているというよりは、「らしさ」があるとわかりやすいから、人はわかりやすいものに惹かれるのだろう。
「らしさ」は厄介だなと思う。無視はできないし、でも無視したいし、らしいものをつくるより、らしくないものをつくりたくなる。誰も見たことがないものをつくりたくなる。
世の中で一番多いのは、斬新だけど売れないものらしい。だから、売れないと困るから「らしさ」が気になる。
精度高く、クオリティ高く、「らしく」なく、誰も見たことがないものをつくったら、どうなるのだろうか。それが斬新だけど売れないものなのだろうか。精度が高ければ、売れると思うのだが、精度が高いものは誰でもつくれるものではないから。
らしさは建築には必要なのか、物全般にいえることかもしれないが、「らしさ」がないと人はどうしていいのかがわからないのかもしれない。
建築以外だと「らしさ」から人は使い方を推測するので、「らしさ」は残しつつ、余計な物は削ぎ落として、シンプルに機能性重視のデザインでつくるか、もしくは「らしさ」にデコレーションして、「らしさ」に付加価値をつけるか。
付加価値をつける場合は気をつけないと、やり過ぎると「らしさ」が消えて何だかわからなくなる。それがアート作品であれば、それはそれでいいのだが、使い道や用途があるならば、道具としての、物としての「らしさ」が無くなると価値も無くなる。そのことがわからずに、よく勘違いしている物を見かける。
使い道や用途がはっきりしているならば、やはり「らしさ」は必要なのかもしれない。ならば、建築にも当然「らしさ」は必要になるはずだが、なぜか同意しつつ違和感がある。
「らしさ」はデザインの範疇なのかと考えた。家らしさ、飲食店らしさ、工場らしさ、遠くから見て、その外形や外観でその建築が何の用途なのかがわかることは大事なのかとも考えた。
「形態は機能に従う」ではないが、その建築が何のためにそこに存在しているのかを外観が一目で教えてくれることはよくあるし、そういう外観の判断を実際の手掛かりによくする。
駅らしさ、交番らしくさ、病院らしさ、学校らしさ、こうやって「らしさ」を並べていくと、言葉では上手く言い表せなくても、何となく「らしさ」の違いを感じることはできるだろう。そういう感じの違いを頼りに目的地を探し当てたりしている。
設計する時に意識して「らしさ」を演出することは、そうはないとは思うが、結果的に「らしさ」の範疇に落ち着くことが多いのは、建築計画学における建築の用途の違いが結果的に「らしさ」の演出になっているからだろう。だから、「らしさ」を意識しなくても、自然と「らしさ」の範疇におさまることになる。
建築以外のデザインの世界では「らしさ」やシズル感が重要視されているが、デジタル化に伴い、その「らしさ」やシズル感の演出に苦労している。それはデジタル化によって「形態は機能に従う」ではなくなってきたからで、形態は単なる「装飾」として存在するだけで、機能は形態を必要としなくなったから。
そして、「装飾としての形態」はユーザーとの関係構築のためだけにつくられる。要するに、「らしさ」という装飾で物と人をつなげるだけが形態の役目で、はじめの第一印象を決める役目を形態が担う。ということは、やはり「らしさ」はデザインの範疇になるのだろう。
では、建築にとって「らしさ」は大事なのか、そもそも必要なのか、それはまた次回、ここに書きます。あと、「らしさ」には使用との関連もあります。
自分でつくる、といっても、自分でつくるわけではなくて、人につくってもらう。自分で構想して、人につくってもらっても、自分でつくるという。つくる、ということに対して、自分の手を実際に動かすかどうかはあまり関係がないと思っている。
だから、自作といっても、構想はするけれど、実際に手を動かしてつくるのは専門の職人かプロに任せる。趣味程度でよければ、自分の手を実際に動かしてつくるが、それでは、出来上がったものに、その精度に満足できないのがわかっているから、自分では手を出さないし、そもそも趣味程度のものをつくるために構想はしない。
今までに建築において、実際に自分の手を動かして自作したことは何度かある。その時は予算が無かったのと、ちょっとやってみようかなという気持ちになったからで、ただ、精度を求めてつくり方を考えたが、やはり、その道の専門の職人では無いので、引き出しが無いというか、自分ができる範疇でしか考えられないので、出来上がったものは、それはそれで良いのだが、何かもの足りなかった。
ただ、精度を求めなければ、つくること自体は楽しいので、上手に楽しさと精度のバランスが取れるならば、自分の手を実際に動かしてつくりたい。しかし、常に出来上がりの精度が気になるし、その精度も求めているデザインの範疇だから、高い精度でないと満足できない。
自分の手を実際に動かしてつくることは、精度の曖昧さがデザインの特徴になる場合でしか成り立たないのかもしれない。
木の仕上げが施された空間にいると、他の仕上げ、例えば、コンクリート打放しの空間にいるより、癒されたり、落ち着いたりするのだろうか。
よく木をたくさん室内の仕上げに使うことを特徴とする住宅や商品化住宅がある。木をたくさん使う目的は、癒しであったり、木が自然を象徴し、自然を取り入れているというイメージの良さがあったり、また、それを望んでいる人も多いからだろう。
ただ、別の見方をして、木の表面の木目だけを取り出して考えてみることもできる。木目という装飾であり、木目という記号であり、無垢の木とは別もので、表面の木目だけを独立して考えてみる見方である。そうなれば、木もクロスやペンキや金属などの表面の仕上げの種類のひとつでしかなく、木の仕上げに特別な意味がなくなる。
装飾とは外の世界との調整をはかるためのものであり、装飾をして、自分の立ち位置を明確にするというお約束がある一種の記号のようなものでもある。
だから、クロスでもない、ペンキでもない、金属でもない、木目という装飾を施すことを選択する時点で、外の世界との調整がはじまり、立ち位置がはっきりしてくる。その調整や立ち位置の取り方を別の言い方で表現すればデザインになる。
その木目のデザインの範疇には、当然、癒しや落ち着きなどの感情も含まれるだろうが、そこで止まってしまっては木目の持つデザインの可能性を活かし切れていないと考えており、木目を装飾として意識して、何かとそれを取り巻く世界や環境との折り合いをつけるために、選択肢のひとつとして木目を利用する。そうしてはじめて、木が癒しや落ち着きなどの感情を与えるだけのものから離れて、素材として、もっと自由に、もっと創造性豊かに扱えるようになる。
建築ならば、建築で自然の中にいる心地よさや気持ちよさを表現する、それは決して自然を再現することではなくて、建築のデザインとして表現する。
フィンランドの建築家、20世紀の巨匠、アアルトの話を出した。造形、素材、光でフィンランドの自然を建築として表現し、心地よさや気持ちよさを体験させてくれる。
ここまで、素材と造形について書いた。それは素材や造形を通して建築と自然の関係性をまず書いた方がわかりやすいと考えたからで、光はそのものが自然であり、太陽の光は一様にどこにでも降り注ぐから、フィンランドの自然という地域性を出すことはできないと考えてしまう。
ところが、アアルトの自然を表現するデザイン要素として光を出した。アアルトは光も造形の一種、目に見える形を光に与えていた。だから、光は造形の下位属性になるかもしれないが、その造形としての光の扱い方がアアルトの建築の特徴だったので、造形と同等にした。
光を造形として扱う具体的な手法は、窓と呼ぶ開口部に造形を与えることだった。開口部は光の取り入れ口だから、そこが造形的になれば光を造形として表現できる、唯一光に形を与えることができる建築の部位は窓と呼ばれる開口部だけかもしれない。
冬のフィンランドは雪に閉ざされ、太陽が見えない日が続き、直接光が室内に差し込まない状況では光を感じることもできない。そこで、きっとアアルトは光を造形的に扱い、光に形を与えることにより、冬のフィンランドで光という自然を象徴的に表現したのだろう。
建築ならば、建築で自然の中にいる心地よさや気持ちよさを表現する、それは決して自然を再現することではなくて、建築のデザインとして表現する。
アアルトの造形は決して自然の形ではないが、自然を想起させる形をしている。結局、人は目から入る自然の景色を自分が判断できるものに還元して認識している。
なので、自然そのものの形もそこに規則性を探し出して見ようとし、アアルトはその規則性を抽出して造形しているような気がする、だから、自然を想起させるのだろう。
アアルトの建築をスケッチすると、アアルトの建築に使われている丸味は結構きつい、丸味が強く、自然の丸味を誇張しているような気がする。それはデザインをする上で意図的に丸味を強調しているのかと考えることもできるが、そうではなくて、より強い丸味は余韻みたいなものを残し、それが伝播していき、自然を想起させることになる。
それは丸味だけでなく、アアルトの建築に関する造形の全てにいえることで、自然を想起させるために、より人工的に形を際立たせることをしている。
建築ならば、建築で自然の中にいる心地よさや気持ちよさを表現する、それは決して自然を再現することではなくて、建築のデザインとして表現する。
フィンランドの建築家、20世紀の巨匠、アアルトの話を出した。造形、素材、光でフィンランドの自然を建築として表現し、心地よさや気持ちよさを体験させてくれる、ただ、それはフィンランドでの自然であり、フィンランドでの心地よさや気持ちよさだと思い、そこから学び、日本では日本なりの自然を建築に取り込み、心地よさや気持ちよさを表現する仕方があると考えている。
やはり、建築のデザインには地方性を取り込みたい、その地方性が日本で建築をつくることの意味につながる。
アアルトの素材は、フィンランドで手に入る自然素材を使うのが前提だった。それは時代背景もあり、第二次大戦後、フィンランドはソビエトに賠償をする立場にあり、国として貧困になり、産業らしい産業もなく、使える素材は粗悪な木材しかなく、ならばそれをデザインで生かすことをやりはじめた。
だから、その素材をデザインに利用した建築や家具などは、それを使うだけでフィンランドの森や湖をイメージできたし、それが心地よさや気持ちよさのデザインの源になった。
この季節、梅雨の晴れ間の適度な湿気がある風が心地よくて、緑の中を散歩したくなります。現場からの帰りに井の頭公園の水辺を歩くと、ほんとうに気持ちがいい。誰もがベンチでくつろぎ、思い思いに過ごしている。
こういう心地よさや気持ちよさを建築でどうやって表現するか、実現するか、そのままの緑や水辺をつくることができれば一番よいのかもしれないですが、敷地が狭かったり、そもそも庭がつくれないとどうしようもない。
建築家のアアルトはフィンランドの豊かな自然を造形、素材、光で建築の中に表現した。自然の中にいるような心地よさや気持ちよさを人工の建築で実現しようとすれば、自然をそのまま再現しても、それはどこまでいってもギミックであり、人の深層心理である心地よさや気持ちよさはそのような作為を見抜き拒絶反応を起こす。
ならば、人工である建築で自然の中いるような心地よさや気持ちよさを実現するには、それにふさわしいデザインが必要になる。そのデザイン要素がアアルトの場合、造形、素材、光だった。
では、造形、素材、光とは何なのか、それはまた次回、心地よさや気持ちよさを表現する建築デザインの話として、ここに書きます。
何かの問題や課題があり、それに対して建築のデザインで回答していく、これが建築の設計の本質だと考えています。もちろん、無理矢理に問題や課題をつくり出す必要はないですが、必ずといっていい程、問題や課題が存在するものです。
そして、家であれば、その問題や課題は、そこに住む人特有の問題や課題である場合が多い。だから、その問題や課題を建築のデザインで解決していけば、自然とそこに住む人にとって最適な建築のデザインが生まれ、住んでいて気持ちいい家になる。
だから、家に無理矢理、自分を合わせなくてもよくなる。案外、自分を合わせて住んでいて、それは慣れてくると違和感を感じなくなり、「住めば都」となるかもしれないけれど、スーツで例えたら、オーダーメイドのスーツの着心地の良さにはかなわないでしょう。
それに「住めば都」状態におちいると違和感を感じないから、課題や問題にも自分では気づかなくなる。設計のプロセスで問題や課題を意識してみるだけでも、今後の日常や暮らしを考える上で価値のあることだと思います。
何かの問題や課題があり、それに対して建築のデザインで回答していく、これが建築の設計の本質だと考えています。もちろん、無理矢理に問題や課題をつくり出す必要はないですが、必ずといっていい程、問題や課題が存在するものです。
まず周辺環境に対する問題や課題が出てくることが多いです。どのような場所に建てようとしているのか、例えば、住宅街の中に家を建てようするとプライバシーの確保が課題になることもあります。
プライバシーの確保は他人の視線が気になるもので、ところが、他人が自分とは違う状態や行動をしていたら、案外間近にいても気にならないものです。そのいい例が通りに面したオープンカフェ。カフェでお茶をしている姿は通りから丸見えでも、通りを歩いている人とカフェでお茶をしている人は全く違う行動をしているので、お互いに気にならない。
ところが、住宅街ではお隣り同士が私生活をその場で行っているので、お互いに違う生活パターンで日常を送っていたとしても、私生活を送るという状態は同じなので、お互いが気になる時が出てくる。
そうすると、後から家を建てる方が隣りの家の窓の位置を気にして配慮をする必要が出てきます。案外これが設計のプロセスにおいて重要なことになる時があります。
「つながり」を意識することが設計プロセスでは多いかもしれない。
窓がつながりを表現しているものならば(『窓はつなぐもの』を参照)、他にも見えるもの、見えないもの、建築には実にたくさんの「つながり」が表現されている。
人の動きでいえば、家事動線もつながりだが(『つながりで家事も考える』を参照)、人が動き回ることをイメージし、その時の視線の動き、それによって見える風景が連続的に変化する様を「つながり」と捉えて、変化する様をデザインのテーマにし、空間を連続的に配置して考えていく設計もあり、また逆に、空間の連続的な配置から「つながり」を設計し、人の動きをデザインするやり方もある。
「つながり」に着目すると、まだまだ様々な事柄が設計プロセスに関係してくる。
「つながり」を意識することが設計プロセスでは多いかもしれない。
窓がつながりを表現しているものならば(『窓はつなぐもの』を参照)、他にも見えるもの、見えないもの、建築には実にたくさんの「つながり」が表現されている。
例えば、「家事動線」という言葉がある。家事がしやすいように、家事をする場所や器機がどのように配置されているかを実際の人の動きを想定して線で結び、その線が短ければ短い程、家事が効率的に行え、時間もかからずに、疲れにくいという指標で、これも家事をする際の人の動作のつながりを表現したものである。
ただ、この場合の「つながり」は、お手伝いさんや将来家事ロボットなるものが存在したら、ありがたいことかもしれないが、家事を面倒なもの、効率的にさっさと終わらせて、他に楽しいことをしようよ、という裏の意味が込められているので、どうにも「家事動線」という言葉を設計プロセスで使いたくない。
家事も日常の一部であり、仕事と同じで1日のうちでかなりの時間を使うことだから、家事を家づくりに巻き込むならば、家事が楽しくなる、したくなるようにするのが本来の設計プロセスではないかと思い、その場合の「つながり」は家事だけでは完結せずに、例えば、外部空間の庭やテラス、人がくつろぐ時の気分や感情までもつなげて、その場所でしかつくることができない「つながり」を創作することになるだろう。
何とかの窓や何とかの窓口のように「窓」という言葉は外界とのつながりを含意する。建築においては「窓」というと、光や風や熱を取り入れるためにあるものとされるが、設計時にはやはり「つながり」を強く意識する。
窓はどこにあり、それがどのぐらいの大きさかによって、「つながり」を自由にコントロールしている。
例えば、リビングでテラスに面して窓を設けようとした時、その窓の幅が大きくて、高さも床から天井近くまであれば、窓を開け放して、リビングとテラスを、室内と屋外を1つのつながりとして考えようとする設計の意図が見られるし、大きさが小さい窓をいくつも並べていたら、プライバシーに配慮して、室内と屋外のつながりを制限しているのか、あるいは、外の景色を額縁のある絵のように室内で見せようとしているのかなとも、それもひとつのつながり方になる。
窓をつながりとしてみていくと、空間と空間のつながり、そのつながりの基点は人で、そうすると、窓は人と人をつなげるために存在しているものだとわかる。
人は普段、実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせて、目の前に広がる空間を感じでいる。意識の中にある空間とは、過去にどこかで経験している記憶の中の空間で、それを実際に見ている空間に重ね合わせ、自分用に空間を合成をして感じている。
だから、人は自分に都合よく空間を感じ取り、好き嫌いも合わせて、意識の中にある空間に先導される。昔、気持ちがいい体験をした場所と似ていたら自然と気持ちがほぐれて、嫌な体験をした所に似ていたら、その時の嫌な気持ちが蘇ってくる。
理性的に空間を感じるより先に、感情的に空間を判断してしまう。
でも、ならば簡単だろう、自分にとって居心地が良い空間をつくるのは。自分が自然と気持ちいいと思える空間を寄せ集めれば良い、それで少なくともハズレはない。
ところが、面白いもので、普通の人には、自分が自然と気持ちいいと思える空間がわからない、普段、そのように空間を感じようとすることが無いから。そうすると、何をするか、他人が気持ちいいと思う空間をネットや雑誌で拾い集めだす、あるいは、展示場やショールームへ行く、自分ではわからないから、気持ちいい空間の正解を求めて、挙げ句の果てに、他人の気持ち良さを自分の気持ち良さと錯覚しはじめる。それでは勘違いしたまま、自分が気持ちいい空間を知らぬまま、完成してしまう、こんなものかなと。
設計のプロセスをもう少し大事にするだけでいいのにとつい思ってしまう。
人は普段、実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせて、目の前に広がる空間を感じでいる。意識の中にある空間とは、過去にどこかで経験している記憶の中の空間で、それを実際に見ている空間に重ね合わせ、自分用に空間を合成をして感じている。
だから、同じ空間でも人によって感じ方が違う。どのように感じるかは自由なのだが、先入観や知識に感じ方を歪められてしまうこともある。他の人が良いというと、良く感じられるように、影響されてしまい、空間の感じ方など簡単に変わってしまう。
だから、知識や人の意見から入らないこと、簡単にお手軽にネットや雑誌で調べないこと、空間などそこら中に、それこそ今いる場所も空間なのだから、感じることぐらい簡単にできる。感じ方に良し悪しは無く、感じ方に正解は無い。ただし、その人特有の感じ方はあり、それは誰にでもあり、それに影響を与えるのが意識の中にある空間のみである。
意識の中にある空間は、ネットや雑誌で調べてもわからない、それをわかるためには、自分で断片を拾い集めるがごとく、空間を意識の中から引っ張り出してこなくてはならない、そのサポートをするのが設計者の役目である。
人は普段、実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせて、目の前に広がる空間を感じでいる。意識の中にある空間とは、過去にどこかで経験している記憶の中の空間で、それを実際に見ている空間に重ね合わせ、自分用に空間を合成をして感じている。
だから、意識の中にある空間がわからないと、自分が欲している、気持ち良いと思う、居心地が良い空間に辿り着けない。
しかし、普通の人に、その意識の中にある空間がわかる人はいない。そもそも、そういうことを考えたことが無いから。
はじめて家を建てる人で熱心な人は情報収集をする。しかし、これらの情報は、その意識の中にある空間には触れてこない。当たり前である、情報というのは意識の外にある事柄で、誰でも扱えるものでないと価値が無いからで、だから、いくら情報を収集をして知識を得ても、例えば、高気密高断熱、何とかソーラー、エコなんとか、無垢の木の家、これからだと、抗菌、抗ウイルスの材料などを知ったところで、自分にとって居心地が良い空間を求めているならば、そもそも辿り着けない。
その意識の中にある空間をわかるには、そういうものが存在していて、それを設計のプロセスに活かさないと、自分にとっての居心地が良い空間にはならないと知っている人が必要なのだが、プロでも情報収集で得られる知識が全てだと考えている人がほとんどだから、自分にとって居心地が良い空間に辿り着ける人はほんの一握りとなる。
人は普段、実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせて、目の前に広がる空間を感じでいる。
意識の中にある空間とは、過去にどこかで経験している記憶の中の空間で、例えば、子どもの頃に住んでいた家の部屋であったり、たまたま訪れた旅行先の宿であったり、日常的に利用する商業施設であったりなどするが、原風景と呼ばれるような強く意識に刻まれている記憶も含まれる。
子供の頃に遊んでいた公園を訪れたとしたら、実際に目の前に広がる公園に、子供の頃の記憶に残る公園を重ね合わせて見ている。それを意識せずに無意識にやっており、子供の頃の記憶だから人によって皆違うので、同じ公園を隣り同士で見ていたとしても、隣りの人とは違う公園空間を感じ取っていることになる。
このような、実際のものと意識の中にあるものの2つを同時に重ね合わせて感じ取ることは、空間だけでなく、全てのものについてもいえるかもしれない。
だから、意識の中にある空間であったり、ものであったり、それに付随する言葉も含めて、そこまで対象としてつくろうとする精神が人と空間、人とものをつなぐことになると思う。
空間を感じる瞬間というのがあると思うのです。それは壁や天井で囲まれていればいいという訳ではなくて、それでは単に室内にいるという感じだから、空間を感じさせる何かに出会うといった方がわかりやすいかもしれない。
空間を感じさせる何か、それはいろいろあるかもしれない、もしかしたら、人によっても違うかもしれない。
そこに人がいれば、あるいは、椅子のような物が置いてあれば、その比較によって空間を感じるかもしれない。ただ、それは空間の大きさを感じるのであって、空間そのものを感じている訳ではない。
そう考えていくと、私が今思いつくのは光しかない。
光は太陽からの自然光と照明による人工光に分けられるが、どちらの光でも、光が当たっているから空間を認識して、空間そのものを感じることができる。真っ暗ならば空間を感じるだろうか。
ただ、ふと思った、真っ暗でも、もしかしたら空間を感じるかもしれない。そうすると、空間を感じることには2通りあるかもしれない。
実際の空間を感じることと、人の意識の中にある空間、それは過去にどこかで経験している記憶の中の空間ともいえるが、真っ暗になった時に人の意識の中にある空間を感じるようになるかもしれない。
ということは、普段、空間を感じている時、人は実際の空間と意識の中にある空間の2つを同時に重ね合わせているのかもしれないと思った。
そして、それは建築を建て替える時に、その時、その場所、その人特有の空間の感じ方をつくることができると思えた。
真っ新な土地にして、まず基礎工事からはじめるのが実際の住宅の工事手順ですが、その前にどのような家にするのか、どのような家にしたいのかを工事ができるように具体的なものにするのが設計です。
その設計をまず最初から家の性能や指標や数値で考えていくやり方があります。例えば、高気密高断熱の家などのように、年間を通して快適な室内温度を保つことを目的に、具体的な計算式を使い、間取りから材料の選定や設備機器までを決めていく。
他に材料にこだわり、家づくりを進めていくやり方もあります。例えば、木の家であることを強調し、無垢の木を室内にたくさん使うことを大事にするなど。
最初にどのような家にしたいかのイメージが無い場合やどのような家にしたいかがわからない場合は、性能や指標や数値で考えたり、材料にこだわりを持つところから家づくりに入る方がわかりやすいかもしれませんが、流行りすたりがあります。
材料や設備などはどんどん進化しますが、家は一度建てたら、簡単に材料や設備を更新できません。だから、材料や設備などは年月が経ても価値が変わらない定番をおさえれば良いと考えています。
家の性能や指標や数値は計算式を知っていれば、誰でも年間を通して快適な室内温度を保つ設計はできます。
ただ、本来どのような家が良いかは住人によって一人一人ちがいます。材料や設備だけでは決まりません。その一人一人のちがいを考え、イメージし、合わせていき、家として具体的な形にして、工事ができるようにするのが本来の設計で、一人一人がイメージしやすいように手助けするのが設計者だと思います。
設計も工事も実際の家が完成するためのプロセスですが、工事は設計したものを実際の家にすることですから、その前の設計段階でどのような家かが決まります。
その設計を何度も経験する住人はいないでしょう。ならば、わからないことが多いけれど、その設計というプロセスを楽しみながら、今一度、一生に一度かもしれませんが、自分はどういう家に住みたいのかを想ってみるのもいいかもしれません。設計というプロセスは楽しいですよ。
服も化粧も、自分が身につけるものや着飾るものは、自分と社会との関係性を表現したり、関係性を調整したりするものであり、TPOに合わせた服選びもその一種であり、それは建築でも同じであるという。
建築でいえば、棟飾りや玄関周りの装飾がそれに当たるかもしれない。今では見られなくなったが、その集落の長の家には特別な装飾が施されていた。
それをもっと発展させて考えると、建築の外観も社会との関係性を表現しているものといえるだろう。外観全体を考えると、その地域で突出したものというより、違和感なく馴染むものが求められ、地域によっては街づくりガイドラインなるものがあり、外観の仕様や色などが条例などで定められていて、それも主旨としては突出したものよりは馴染むものをつくらせるためにある。
例えば、昔からの宿場街のような古い街並みの意匠を守り、街並みの統一感を保とうとする場合は、馴染むものの方が良いだろうし、社会との関係性を表現する上でも、その地域においては古い街並みを維持することに社会的意義を見つけることができるだろうが、そのような場合では無い時、例えば、どこにでもある普通の住宅街ならば、馴染むだけが外観として、社会との関係性を表現することにはならず、反対に突出するという表現も社会との関係性を考えて許される表現であるはずであり、突出することにより、その建築を基点として、周辺環境に良い影響が沁み渡るような外観になったならば、それはそれで素晴らしいと考えている。
私の場合、大体、外観に関してはクライアントから要望を言われることがほとんど無く、逆に、私の方から提案して、それが採用される場合がほとんどである。
提案する際には、馴染むと突出するを使い分けて、地域での見え方、あと、クライアントの人柄とイメージが合うようなものや、馴染む場合でも、突出する場合でも、全体全部を馴染むか突出するかに振る訳ではなくて、割合として、馴染むを多めにするか、突出するを多めにするか、バランスを考えて、大体、どちらかが微妙な、ほんの僅かな差で多くなるようにミックスして外観のデザインを決めていく。
今日は久しぶりに過去に建てた住宅にお邪魔した。ちょっとした不具合を見に行って、その場で処置して、すぐに帰ってきたが、やはり今は、ちょっと上がってお茶でも、という感じにはならない。
私たちは何もない真っ新なところからはじめて、形にして、完成し、クライアントに引き渡す。それが住宅ならば、そこでの日常や暮らしを想像しながらつくり上げていくが、なのに一度たりとも住むことはなく、そこでの日常や暮らしを体感することもない。
だから、クライアントが羨ましい、そこでの日常や暮らしはきっと楽しいだろうなと思えるものを設計し、つくっているから。
時には、こちらの想像を超えるような暮らし方をしているクライアントもいて、たまに、これからクライアントになるかもしれない人を連れて行って説明すると、そこにリアリティを感じ、それが決め手になることがある。
建築自体のアカデミックなことはとりあえず置いておいて、クライアント目線で考えると、どうもこちらが意図したこととは違うことが行われているということは、カスタマイズしながら積極的に自分たちの日常や暮らしを送ることができると解釈するようだ。
そのようなことは当たり前ではないかと思ったりするが、どうも自分たちの家を、それも新築の家を、カスタマイズしながら住むという発想がないのか、できても模様替えレベルと思うのか、とりあえず、我慢して家に自分たちを合わせるしかないと思うのか。
その人に合わせて、その人用につくったとしても、それはその時点のもので、いくら想像力を働かさせて将来予測をしても限界がある。それを補うために、カスタマイズできる余地、余白のようなものも予め仕込んでおく。
どうもその余地、余白が、確かにあまり他では見ないから、かえってリアリティを感じ、説得力があるのかもしれない。
最初の打合せで「商店街に住むのは本当は嫌なの」というクライアントの奥さんの一言がずっと設計をしている時の課題だった。
どうしたら安心してここで暮らせるか、おまけに面してる商店街の反対側は小学校の校舎の廊下であり、そのことも嫌な理由のようだ、プライバシーが侵されそうな気がするのだろう。
1,2階をテンナントに貸し出すので、住居は3階になる。その時点で商店街とは高さ方向にズレるし、小学校とも間に商店街をはさんでいるので距離がある、それは打合せでも説明したが、先の言葉である。今まで住んでいたところが住宅街の中だから、変わりように差があり過ぎるのかもしれない。
とはいえ、敷地を変更することはできないので、どうしたものかと思案して、商店街や小学校の側は方角としては南だから、明かり取りのためにも開口部は必要であるが、商店街や小学校の方角を見ること無しにほぼ暮らしが成り立てば、商店街や小学校を意識すること無しに暮らせるかもしれないと考えた。
そこで、屋上をつくり、住居がある3階とトップサイドライトを通して視覚的につなげ、そのトップサイドライトは明かり取りにもなり、お孫さんが遊びに来た時は屋上が庭がわり、そのトップサイドライトを通してお孫さんが見え、コミニケーションができるようにし、むしろ、商店街や小学校の方角とは反対にはなるが、室内空間からしてみれば、そちらの方角がメインのような扱いにし、全く商店街や小学校を意識すること無しに暮らせるようにした。
もちろん、クライアントの奥さんは毎日熟睡している。
可動間仕切りをよく使う。大体、そういう時は、クライアントがどういう日常を送りたいか、どういう暮らしをしたいかがはっきりしており、それに対応するために部屋の方を変化させる。
一般的には、可動間仕切りを使う時は、可変することにより、どのような部屋の使われ方をしても構わないように、より曖昧で、はっきりと決められない場合である。だから、可動間仕切りを設置することは一種の設計の手抜きのような印象があるかもしれない。
しかし、きちんとクライアントの日常や暮らしを把握した上で設置する可動間仕切りは、クライアントの要望がいくつも折り重なって1つの部屋に表現されている証しであり、より濃く、より深く、限られたスペースの中で日常や暮らしを送るための手段である。
階段の構造は、足をのせる段板があり、その段板を支える側板があれば最低限成り立つ。洗面の構造は、洗面器をはめ込む天板があり、その天板を支える脚があれば最低限成り立つ。
共通するのは板であり、階段の段板と洗面の天板は水平であることも共通する。
ただ、階段と洗面は、全く関係がない機能同士である。
少しでも効率よく水回りをまとめたい、それも階段下のスペースが空いているが、そこに壁をつくり部屋にしてしまうと狭くなるし、せっかくの階段の開放性が損なわれてしまう。
ならば、階段と洗面の共通点を頼りに、階段の段板が延びて洗面の天板となり、そこに洗面器を設置し、洗面周りの小物を置く場所として、同じく階段の段板が少しだけ延びて棚状になり、そこに家族分の歯ブラシなどを置くようにした。
クライアントの本来の要望はこの階段に滑り台をつくりたいだった。その要望通りに、さらに、洗面の機能を加えた、階段×洗面×滑り台が完成した。
きっと朝などは大忙しだろう、この階段×滑り台×洗面によって、より家族の営みをお互いに感じることとなり、そうしたら、朝がより家族にとって楽しめるでしょ。
暗い家よりは明るい家の方がいいですよね、暗い家にして欲しいという要望は今までに聴いたことがないです。明るい家にして欲しいという要望もあまりないというか、「明るい家になりますか」という問いかけは何度かありました。
奥に引っ込んだような敷地で、その分静かだけれども、周りを建物に囲まれていて太陽の光が入ってこないかもしれないという心配から。
そういう時はいつも決まって「日当たりはどうにでもなります」と答える。
確かに、敷地の周りを四方建物に囲まれていて、しかも狭小地ともなれば日当たりは厳しいので、よくあるのは日当たりが欲しい部屋、例えばリビングダイニングを2階に持ってきて、日当たりがあまり関係がない部屋、例えば寝室、水回りなどを1階に持ってくるというもの。
ただ、1階はせっかく外の庭などの外部空間と内部空間を連続させることにより広く感じさせることができるので、狭小地に建つ家ならば、尚更、1階にリビングダイニングを持ってきて広く感じさせたいだろう。
そこで、日当たりが厳しい時の対処法は、太陽の光を入れることと部屋を明るくすることを別々に行えばよい。
狭小地で周りを建物に囲まれていたら、太陽の光が1階まで差し込む時間は、季節にもよりますが、1日のうちで多くても3時間くらい、これでは太陽からの直接光だけで1階を明るくするのは不可能です。ただ、2階だと1日中太陽からの直接光で部屋を明るくすることができます。
だから、そういう時は階段を利用して、1階の部屋を明るくする。階段を1階から2階までの吹き抜けだと考え、階段室という部屋に見立てて、2階から太陽の直接光を階段室に放り込み、階段室の中を光が反射し拡散して、1階の部屋まで太陽の光を届ける。
その際、階段室と1階の部屋との境の壁は必ず半透明の壁にして、光を通すことが必要になる。これによって、昼間は半透明の壁が光っているようにも見えて、部屋を明るくする。2階からは1日中太陽の光が階段室に供給されので、1階の部屋も1日中明るくすることができ、入ってくる火は間接光になるので、熱をほとんど1階の部屋には伝えないから、夏などは明るくても暑くはならない。
建物が完成してクライアントに引き渡す時、大概、お子さんが走り回っている。子供にしてみれば家は遊び場、家は遊具なんだなと思う瞬間です。
そんな姿を何度も見ているので、設計している時からクライアントのお子さんに合わせて、それは結構クライアントには内緒で、勝手に盛り込んでいたりする場合もありますが、遊具となるような仕掛けを考えている。
子供の頃の記憶にはよくその当時住んでいた家の情景が入り込んできて、その時の体験と一緒に焼き付いています。きっとお子さんが成長していく上で家が果たす役割ははかりしれないと、結構、その後の成長や人生に影響を与えるのではないかなと思っています。
だから、ほんのちょっとなことなのですが、そこに腰掛けて本を読んだり、皆んなが見渡せるような所をつくったり、扉を開けると視界が開けて、その先にチラッと見える家族を感じたり。
クライアントのために離れをつくったことがあります。離れといっても別の建物になっている訳ではなくて、ひとつの屋根の下にテラスからしか出入りができない3帖くらいの部屋、茶室くらいの広さです、ほんとに狭い、でも、クライアントがひとりになれる部屋をつくりました。
ただ、その部屋は、出入りはテラスから一旦外に出る必要があるのですが、室内に向かって2つの窓があり、開けると1つはリビング、1つは寝室につながっていて、そんなに勝手にひとりにはなれないようにしてあり、結局はひとりいながら、ちょっと寂しくなるとどちらかの扉を開ければ、家族と、お子さんとつながることができるようにしました。
それは、大人にとっても家は遊び場、家は遊具で、子供の頃の家の原体験の延長に今の家があり、ただ大人になって求めるものは子供の頃の家ではなくて、今の自分が満たされるためのもの、それはお子さんを見ているとわかります、お子さんは親の真似をしますので、だから、打合せではお子さんをよく観察して、クライアントにたくさん尋ねます。
敷地に建てれるだけ目一杯に建物を建ててしまうと、どうしても満足に庭が取れないし、防犯のことも考えて、子供を遊ばせたり、洗濯物を干すために、屋上が欲しいという要望がクライアントから出ることがよくある。
子供の頃、屋上のある家に住みたいと思ったものです。なぜか高いところに上がるとテンションも上がるし、遠くまで見渡せるのは気持ちがいい。そういえば、学校の屋上へ行くのも好きだった。屋上へ出る扉を開ける瞬間がなんかワクワクしたことを覚えている。
屋上へ通じる階段は、自治体や確認検査機関の判断にもよりますが、建築基準法の住宅の階段の規定を受けないので、省スペース化させるために、急な階段にすることもある。
ただ、階段は廊下と同じように通路なので、人が通る場所として常に空けておく必要がある。廊下ならば、廊下も部屋という考え方をすれば無くすこともできますが、階段はそうはいかない、どうしても場所を占領してしまう。階段下の空間を便所や収納にすることもありますが、今回は2階を大きなワンルームとして、そこを必要に応じて可動間仕切りで仕切り、個室をつくるというプランなので、階段はできるだけ省スペースに、それも視線を遮らないようにして、クライアントの希望である大きなワンルームであることを邪魔したくはなかった。
だから、段違い階段にし、段板のみで構成することにした。段違い階段とは、段板が右、左と半段ずつズレて設置されており、人の足の動作に沿った段板の位置になっているもので、階段をより省スペース化できるのですが、自治体や確認検査機関の判断にもよりますが、建築基準法の住宅の階段としては認められていない。今回は屋上へ通じる階段でしたが、一応、事前に確認検査機関へ相談し了解を取り実現しました。
この階段ならば、透け透けで、屋上へ出る扉をガラス扉にしたので、太陽の光が屋上から拡散されて2階の空間にまで降りてきて明るくしてくれますし、階段の存在感自体もより無い方向に、視線もなるべく遮らないように、クライアントの望むワンルーム感が出て、不思議なことに階段が造付けの家具のように見えなくもない。
時には建築でも1本の木からはじまることもある。
クライアントとの初回打合せでは、要望を一通り傾聴し、何でもいいから話をしてもらおうとする。様々な問いかけをしたり、ご自宅にお伺いしたならば、室内にあるものに関心を持って尋ねたり、思い入れやこれだけは絶対のようなことも、特にマニュアルがある訳でもなく、その場の即興で、事前に準備もしないようにしている。
何かが情報として事前に頭に入っていると、自分にとって都合がよい言葉や話をクライアントから引き出そうとしてしまい、本来そこでしか聴くことができなかったことに辿り着けないような気がするからで、その場で聴きたいのはクライアントが本当に欲している心の声、それがわからなければ打合せをしている意味がなく、時間のムダで、メールやメッセージでやり取りすれば事足りる。
不思議なことを突然クライアントが言い出した。
「この木は父親が亡くなってから突然生えてきたのです」
「だから、建て替えする時にこの木は切らないで欲しい」
だだ、古い家を解体する時にその木が邪魔になり、解体業者が勝手に敷地の北西の角に植え替えてしまった、こちらが全く意図しない場所に。だから、その木をまた移動することもできた。でも、しなかった。
突然生えてきて、また意図しない場所に移動して、その状況をそのまま活かして設計することがクライアントが欲していることではないか、その木に父親を重ね合わせているのがわかった。
木を活かすならば、その木がある場所を庭として、外に出られる場所とし、室内の空間と連続させたい、その空間はリビングやダイニングなどの家族が集まる所で、その空間のどこからでもその木が見えるようにしてあげたかった。
料理をしてキッチンに立っている時も顔を上げると視線の先にはその木が見え、ダイニングからリビング、リビングからダイニングへと移動する時もその木が自然と視界に入るように。
その木から派生して空間の用途を順に決めていった、普通はそのようなことをしないが、この住宅ではそれが最善の設計プロセスだと考え、そして、そのように実現した。
建築の部位の中で階段は面白い存在であり、設計する時の腕の見せ所でもある。
建築家の村野藤吾は階段そのものを如何に美しく魅せるのかを突き詰めているようであり、その曲線の優雅さは一度見たら忘れられない。また、フィンランドの建築家のアルヴァ・アアルトは階段に機能的な端正さを出しながら、素材に木や鉄や煉瓦などを使い、自然な柔らかさを纏わせ、北欧モダンの空間にナチュラルに馴染ませていく。
いずれも階段をひとつの見せ場だと考えていたのだろう。それは普通に住宅でも同じであり、日常の暮らしの中で階段に様々な役割や活用の仕方や魅せ方をさせる。
空間の広さにはどうしても限界があり、効率的に広さを有効活用しようとして、時に階段の下に便所を配置したりする。便所は腰掛ける所であり、また法規上は居室ではないので、天井の高さに規定がないこともあり、天井が段々と低くなる階段下の空間を有効活用する際にはもってこいである。
ただ、便所にいる時でさえ、それは日常の暮らしの大事な時間でもあるので、いかに心地よく過ごせるかをデザインで考えたいところで、また階段下にあることを何かに活かしたいと考えた。
階段には「蹴上げ」という部分がある。段板と段板をつなぐ縦の部材で板状のものだが、階段のデザインによっては無い場合もあるが、階段下の空間を利用する場合には必要になる。
蹴上げがある場合、通常は板で塞がれているが、そこに乳白色の「ツインカーボ」という名の二重のポリカーボネート板を嵌め込んだ。この板は光を通すが、乳白色で二重になっているので、中は見えない。
便所という暗くて狭いイメージの空間に明るさを取り入れたかった。あと、階段という動線の下にあるので、階段を通る人の動きと便所を関連づけしたかった。
昼間は階段に差し込んだ太陽の光が蹴上げの乳白色のポリカーボネート板を透して便所の中まで柔らかく入ってくる。逆に、夜間は便所の照明の灯りが階段の足元灯の役目をするので、便所の灯りだけを頼りに階段の昇り降りもできる。
階段とその下の便所の相互関係をデザインし、便所に入り込んでくる太陽の光はその日の天気をも反映する。階段という存在が日常の暮らしの中で様々な事柄をつなぐ役目をする。そのつなぐ役目にはまたまだたくさんある。
将来予測をして、なるべく不用な個室はつくりたくないと考え、そもそも広さに限界がある場合にはできるだけ細かく部屋を区切りたくはなく、大きく空間を使う方が広く感じる。
ただ、そうすると、どうしても部屋を分けたい時に困る。例えば、お子さんが男女の組合せの場合は、ある程度の年齢になったら部屋を分けたいが、小さな時は別々に部屋にこもられるのも親としては心配だから、一緒の部屋の方がよく、ところが大人になってもずっと家にいる訳ではないから、部屋を分けた後に大人になって家を出たら、残った部屋は物置きになるケースも考えられる。物置きならまだいいが、単に空き部屋になったら勿体ない。
それは2世帯住宅の2階でのこと、息子さんが将来結婚した時用の空間を用意することになった。
ただ、まだ予定がない、そこで、洗面所と便所を1つの箱状の空間に納め、それだけを固定にし、あとは移動できる同じく箱状の収納家具をいくつか用意した。
それ以外は小屋裏収納と壁一面の収納のみで何もない、間仕切り壁のない広い空間だけをつくり、移動できる箱状の収納家具を使って、部屋を2つに分けたり、その場合は想定して出入り口の扉を2つあらかじめつくったが、他にも、その移動できる箱状の収納家具の置く位置によっては、寝室コーナーなどのプライベートスペースをつくり、残りは団欒スペースにするなど、その時の必要に応じて、可変できる空間とした。
箱状の収納家具を置く位置もある程度何通りも想定して、それに合うように箱状の収納家具の大きさも決めていったが、今伺うと想定外のところに置かれていて、その意外性が面白くて、収納家具は中身を入れたまま移動できるので、模様替えも楽に楽しめるのだろう。
きっとこう建って欲しいのだろうなとおもんばかることも必要だと思う。
広い土地が相続によって小さく分割され、何ヶ月後かにいくつもの建売住宅が出現し、それまでの街並みが変わることがよくある。前の風景を知っている者にとってはその変わりように違和感を覚えるが、なぜ違和感を覚えるかというと、不自然な建ち方をしているからである。
当然、事業なので、建売住宅を建てるために、広い土地を少しでも効率よく分割して、より多くの建売住宅を建てようとする。だから、そこでどのように建ったら、人同士の交流が生まれ、周りの環境とも馴染みが良いかという意識そのものが無いので、周りからしたら不自然に見える。
クライアントのお母さんが住んでいた土地を分割し、兄妹で2棟の二世帯住宅を建てる計画があった。土地を分割するところから設計をしていったのだが、お母さんからの条件が道路に対して手前と奥という土地の分割の仕方はしないで欲しい要望があった。奥になった方が不利になると考えたようだ、あくまでも兄妹でなるべく差が出ないような分割の仕方を望んでいるように感じた。
だから道路に対して、手前と奥では無くて、右と左という分割の仕方にした。ただ、そうすると土地の形が不自然に長辺が長い長方形になってしまう。
ならば、それを利点として、2棟の住宅の間に共用の長い通路を取り、お互いにその通路に面して玄関を設けて、日常の暮らしの中で自然と行き来したり、交流したり、お互いのリビングにある窓も高さを半階ずらして配置し、視線が交差することは無いが、お互いの賑わいや存在が何となくわかるようにした。
それは敷地内の親族同士の交流だが、その交流が自然と周辺環境にも伝播して、何気に人が立ち止まって話込んでいるのをよく見るようになった。
別々にいるのが嫌なのだろうと思った。
最初の打合せで敷地図を見せてもらうと、敷地の形状がほぼ真四角に近かったので、一瞬、コルビュジエの「成長する美術館」が頭に浮かんだ。コルビュジエは3つの美術館を設計し、そのうちの2つがインドにあり、あと1つが世界遺産にもなった上野の国立西洋美術館である。プランは3つともほとんど同じで、真四角の建物の中心部分にエントランスがあり、そこから2階の展示室へ階段でアプローチしていく。展示室は真四角の建物の中を渦巻状に回遊するように配置されており、仕切りがなく展示するための壁が連続しているので、閲覧する方は建物の中を一筆書きに一回りするだけでいい。
打合せでは家族の普段の生活や行動を、特に家にいる時のお互いの距離感を測ろうとつとめる。それは、その距離感がそのままプランに変換できる場合が多いからである。
お話を伺うとクライアントのご主人も奥さんもそれぞれ違う趣味を持っており、休日など家にいてもお互い別々の場所で別々のことをしているらしい。それ自体は普通にあることだし、ではそのお互いの趣味が成り立つように空間を設計すればいいだけだが、問題はその距離感であり、もっというと、その距離感がいつでも同じということだった。
建て替えだから同じ敷地なのだが、それまで住んでいた家は増改築を繰り返したせいか、壁が不自然なところにあり、別々な趣味をするための場所が近くてお互いに干渉していた。そのため、どちらかが先にその場所にいると片方は自分の趣味ができないようだった。
普通ならば、全く違う場所で自分の趣味ができるようにすればいいだろうにと思いのだが、それはしないらしい。要するに、家族がそれぞれ別々なことをしていても同じ空間の中に一緒にいたいのだろうと考えた。
同じ空間の中だが、お互いに干渉することになし自分の趣味ができて、必要な時にはその距離感を縮めて一緒にいることもできるような、お互いの距離感が調整できて、一番離れている時は姿形は見えないが、気配だけは感じるような空間をつくろうとした。
敷地の形状なりに設計すると、ほぼ真四角の建物になるので、真四角の真ん中に2階へ上がる階段を配置して、1階をその階段を中心にキッチン、ダイニング、リビング、玄関と配置して、ぐるぐると回遊できるようにし、お互いの距離感を自由に調整できるようにした。
その距離感の調整に一役買ったのが真四角の中心に配置した階段である。階段と1階の空間は透明のアクリル板で空調の仕切りをつくったが、場所によって階段の下の部分の壁の高さが違うので、階段越しにお互いが見える範囲も違ってきて、同じ空間にいながら、お互いが見える見えないの調整が少し移動するだけで容易にでき、一番見えないところでも気配はお互い感じることができる。
だから、空間の使い方しだいでお互いの距離感を自由に設定できるので、何年か毎に少し模様替えするだけで、全く違った空間体験もできるだろう。
真上から光が差し込んでキラキラと波打つ水面に辿り着くまで、階段を何段も降りていく。それはストリートレベルから地下鉄の入り口のような階段を降りて行った一番深いところに緑色の水面がある。
インドの階段井戸の話である。井戸の水面は地中の深いところにあるが、その水面まで地上から真っ直ぐの階段で降りていけるようになっている。地中の深いところにあるから水面の辺りは暗いと思っていたが、水面の真上は真っ直ぐ地上までつながっていて、トップライトのように光が井戸の側壁に反射しながら降り注いでいて結構明るい。
ちなみに、トップライトとは天井に開いている明かり取りの窓のことだが、壁に開いている窓と比べて3倍の光量がある。だから、同じ大きさの窓ならば、壁よりも天井にあった方が空間を3倍明るくする。
「昼間に電気をつけないで生活がしたい」
それがクライアントの奥さんの要望だった。しかも、家族が集まり、奥さんが1日のうちで1番居る場所であるキッチン、ダイニング、リビングは1階にしたいという要望もあった。
その敷地は周りを建物に囲まれていて、狭くはないが、太陽の光が1階に差し込む時間帯はわずかであった。昼間はずっと電気をつけなくてもよい明るさが求められていたが、仮に吹抜けを設けて、2階の天井にトップライトを設置し、1階まで光が差し込むようにしたくても、そうすると、2階に必要な部屋が必要な大きさで取れない。
吹抜けをつくらずに、それでも1階まで光を落としてこなくてはいけない、床が邪魔をする、ならば、光を通す床にすれば良い。
1階のダイニングテーブルの真上、そこは2階の廊下の床であり、ガラスの床であり、その真上にトップライトがある。1階のダイニングテーブルから見上げると空が見える。
お互いに別々なことをしていて、それは同じ時間帯に、同じ空間で、それが当たり前の家族は結構多くて、今まで携わってきた住宅のクライアントにも結構多くて、ただ、家族だから個室に篭って別々になるのは避けたという話は打合せでよく出る。
「だから個室はいらない」
「でも完全にオープンにはできない、娘二人だから」
ある住宅のクライアントから出た要望で、3LDKとか、4LDKなどのプランに慣れ親しんだ人には、空間的に矛盾をしていることになるだろう。
従来のnLDKのプランでは、個人の空間をつくるためには壁で囲うという発想だった。それが必要無いとなると発想を全く変えるしかない。ちなみに、声や物音がしても、気配を感じても良いそうだ。
ならば、個人の空間をつくるということではなくて、必要な時に隠れることができる場所、すなわち、死角をつくり出すことができれば良いのではないかと考えた。
1階全部をキッチンやリビング、ダイニングスペースと水回りに当て、2階の壁を全部無くして、全て可動間仕切りにし、可動間仕切りを全て閉めれば4つのスペースに区切られるが、開け放しても可動間仕切りの扉が残るので隠れるための死角ができる。
それが、個室はいらないが、完全にオープンにはできない空間への提案であり、採用され実現した。
どこに居ても気配を感じるように、壁で仕切られた場所はあるが、移動すれば必ずどこにいても気配を感じる。つながりたくなれば扉を開ければよい、お互いに顔が見えるし、何をしているのかわかる。それぞれの場所でそれぞれが違うことをしていても、何かがつながっている。
これは前に設計した住宅の構想段階で、クライアントの話を聴きながら、頭の中で思い浮かべたこと。
家族が好きなように好きなことをして好きな場所にいるのだけれども、ひとつ屋根の下でチラッと見えたり、音が聞こえたり、足音に気づいたり、もちろん一緒に居れば、様々な空間のつながりから、光や風が人に優しく届く。
きっとクライアントの家族がみんな家に居るのが好きだったので、ならば家の中にたくさんの居場所をつくり出し、その居場所はお互いにちょっとずつ空間的なつながりがあるから、その都度好きな居場所を選んでも、お互いにお互いを感じられる、そういう住宅をつくろうした。
具体的なプランに入る前のこういう漠然としたイメージが最後の完成へと導く道しるべになる。
"The first image becomes a guide"
There are places that are partitioned by walls so that you can feel the sign wherever you are, but when you move, you will always feel the sign. If you want to be connected, just open the door, you can see each other's faces and you can see what you are doing. Something is connected even though each place does different things.
This was the idea of the house I designed earlier, which I had in mind while listening to the client.
They do what they want and do whatever they want, but they can see a glimpse under one roof, hear a sound, notice footsteps, and of course, various spaces if they are together. Because of the connection, light and wind reach people gently.
I'm sure that all the client's families loved staying at home, so I created a lot of places in the house, and those places have a little spatial connection with each other, so I choose the place I like each time. But I tried to make such a house where we can feel each other.
Such a vague image before entering a concrete plan is a guide to the final completion.
建築物の大きさの限界は敷地の大きさで決まる。広い敷地には大きな建築物が建ち、狭い敷地には小さな建築物が建つ。それは当たり前のことだが、建築物の大きさの違いの意味はこれだけであり、大きさの違いが建築物そのものの優劣を示すものでは無い。
どこに建つか、都心であろうと、郊外であろうと、地方であろうと、山や海に近くても、それは建築物の建つ場所がどこかを選ぶだけのことであり、建つ場所で建築物そのものの優劣は決まらない。
建築物を建てる予算が有ろうが無かろうが、できあがるのは建築物であるのだがら、予算の有る無しが建築物そのもの優劣には直接関係が無い。
そうやって、ひとつひとつ紐解いていくと、まだまだ解き明かしていくことはたくさんあるが、クライアントにとっての王道、定番となる建築物が出現してくる。
"First, go to the classic road"
The size limit of a building is determined by the size of the site. Large buildings are built on large sites, and small buildings are built on narrow sites. That is obvious, but this is the only meaning of the difference in the size of the building, and the difference in size does not indicate the superiority or inferiority of the building itself.
No matter where you build it, in the city, in the suburbs, in the rural areas, or near mountains or the sea, it just means you choose where to build the building, and the building itself The superiority or inferiority is not decided.
Whether or not there is a budget to build a building, but the result is a building, but without a budget, there is no direct relation to the superiority or inferiority of the building itself.
By unraveling each one in this way, there are still many things to unravel, but a royal road for clients, a classic building will emerge.
暮らしが変わるのだろうか、大きく変わるという人もいて、今まで変えようとして変えることができなかったこと、リモートワークや電子認証などのデジタル変革がたった2ヵ月で起こり、働き方改革も一気に進むから、東京から地方へ、多拠点生活に、都市生活を補完するような地方暮らしをする人が増えるという見方がある一方で、世界的には来年には今年起こったこと、新型コロナ渦は無かったことになるだろうという人もいるし、今この混乱期にいち早く動いて、周りが止まっている間にシェアを拡大した大企業もある。
全く暮らしが変わらないということは今さら無いだろうが、どのくらい変わるのか。時代を振り子に例える人は、大きく揺れれば、振幅は大きくなり、小さければ、振幅も小さいという。
今回の新型コロナが及ぼした影響は、たくさんの死者を出し、経済的にも大きなダメージをもたらしたので、とても甚大ではあったが、暮らしに関しては巣篭もりするという、今も続く初めての経験をしていても、そのための手段はリモートワークにしても、今までSkypeやテレビ電話で行ってはいたし、日用品の配送はAmazonフレッシュ、フードデリバリーはUber Eatsなど既存のサービスを使うことで解決でき、なかなか思うように外出できないなどの不自由な思いをしながらも、慣れてくれば以前とさほど変わらず、むしろ新たな発見や試みにより、今回の新型コロナ渦を暮らしの精度を上げるために利用している人さえもいて、影響と被害は甚大だが、暮らしに対する振り子の振れ幅は小さく済んでいるような気がする。
だから今は、暮らしが大きく変わるようには思えず、ウィズコロナ用の対策がワクチンができるまでプラスされ、その期間が長く続くというぐらいの変わりようなのかなと思ってしまう。
"How much will life change?"
Some people will change their lifestyles, and it will change drastically.Because they could not change it until now, digital transformation such as remote work and electronic authentication will occur in just two months, and work style reform will progress at once. While there is a view that more people will live in rural areas that complement urban life from Tokyo to rural areas, there is no new corona whirlpool next year next year. Some would say this would be the case, and some large companies have been quick to move into this turmoil and have increased their shares while the environment has stopped.
It's unlikely that your life will change at all, but how much will it change? People who compare the times to pendulums say that if it shakes greatly, the amplitude will increase, and if it is small, the amplitude will be small.
The impact of the new Corona this time caused a lot of deaths and caused great financial damage, so it was extremely huge, but I had a bird's-eye-like experience in my life. However, even if remote work is used as a means for that, I have been using Skype or videophone until now, I can solve the problem by using existing services such as Amazon Fresh for daily necessities and Uber Eats for food delivery, which is quite easy. Even though I feel like I can not go out as I want, if I get used to it, it does not change much as before, but rather by new discoveries and trials, I am using this new corona vortex to improve the accuracy of life There are even some people, and the impact and damage are great, but I feel that the swing range of the pendulum with respect to life is small.
So now, I don't think my life will change significantly, and I wonder if the measures for Wiscorona will be added until a vaccine can be made, and that period will last for a long time.
家にいる時間が長いと、いつもよりやることが決まってきてパターン化してくるから、段々と何事もムダなく、効率的に行うようになり、本来ならば、そこに変化を加えたくて外に出たくなるのだが、それもままならないから、余計に効率的で機能性が高い暮らしになっていくが、それがかえってストレスや飽きにつながるような気がする。
だから、ちょっと緩く、主に時間にゆとりを持たせて、
どうせ仕事は思うようには進まないから、すき間が生まれるようにすると、なぜか勿体ないような気がして、今度は余計なことをしてしまう。
何かをたくさん詰め込んで効率的で機能性が高いことは良いが、本来何がしたかったのかがわからなくなってしまう。
本当はもっと日常や暮らしを楽しみたいのだが、時間に追われる羽目にならないようにする術が今ほしい。
"In a highly packed life with high functionality"
If you stay at home for a long time, you will have to decide what to do more than usual and it will become a pattern, so you will be able to do things gradually and efficiently, and if you want to make changes there, outside I want to get out of it, but I can't do that anymore, so I'm living a more efficient and highly functional life, but I feel that it leads to stress and tiredness.
So, let's relax a little, mainly to allow time
I can't do my job anyway, so if I try to create a gap, I feel like it's wasteful for some reason, and I'm doing extra things this time.
It's good that it's packed with a lot of things and efficient and highly functional, but you don't know what you originally wanted to do.
I really want to enjoy my daily life and life more, but now I want a way to prevent you from having to spend time.
「機能性」という言葉がある。よく使う言葉、よく考える言葉、衣食住に出てくる言葉。機能性の衣類は、例えば、機能性肌着のヒートテック、機能性表示食品は、例えば、トクホの食品であり、住における機能性は「効率性」と言い換えた方がわかりやすいかもしれない。
機能がまずあり、それに対応したプランが決まり、部屋の役割が決まる。その時にムダな動きは無いか、ムダなスペースは無いか、要するに、そこに与えられた機能を余すところ無くプランに反映しているか、効率良く機能を発揮できるプランになっているか、それができていれば「機能性が高い」となる。
よって、機能性は客観的な数値で表現できる。だから、クライアントを説得する材料として機能性は最良であり、数値で表現できるから、誰でも扱うことができる。
衣食住がテクノロジーの成果だとしたら、機能性のように客観的な数値で表現できることは当たり前であり、それでクライアントに納得してもらうことは必要なことではあるが、テクノロジーだけで衣食住が成り立っている訳ではない。
テクノロジー偏重になり過ぎると、テクノロジーだけで、客観的な数値だけで、住を満たそうと普通にする。それに対してクライアントも何も疑問を抱かずに、それが当たり前だと思っている。
しかし、よく考えれば、自分たちの暮らしを全て客観的な数値だけで表現できる訳が無く、主観的な感情なども入り交じってくるのに、そのような主観的な感情などを受け止めるようなことは機能性の中には含まれない。ならば、機能性以外の他の何かが必要になってくるだろうに。
"I need something other than functionality"
There is a word "functionality". Frequently used words, thoughtful words, words that appear in food, clothing and shelter. Functional clothing is, for example, heat tech for functional underwear, and functional labeling food is, for example, food from Tokuho, and it may be easier to understand that the functionality in living is "efficiency".
There is a function first, the plan corresponding to it is decided, and the role of the room is decided. At that time, there is no useless movement, there is no useless space, in short, whether the functions given there are reflected in the plan completely, or whether it is a plan that can efficiently perform the function, If so, it is "highly functional".
Therefore, the functionality can be expressed by an objective numerical value. Therefore, the functionality is the best as a material to persuade the client, and since it can be expressed by a numerical value, anyone can handle it.
If food, clothing and housing are the result of technology, it is natural to be able to express them with objective numerical values like functionality, and it is necessary to convince the client with that, but technology alone is the basis for food and clothing. Not a translation.
If technology becomes too weighted, it will be normal to fill housing with only technology and objective numbers. Clients don't question anything about it, and they take it for granted.
However, if you think carefully, there is no reason to be able to express all of your life with only objective numbers, and even if subjective feelings are mixed in, you should accept such subjective feelings. Is not included in the functionality. Then I would need something other than functionality.
建築をどうやって認識してもらうか、クライアントに。
光に感動してもらいたいと考え設計するのは、建築を評価する指標が予算やプラン、敷地の場所や周辺環境などの優劣だけでは無いことを知ってもらいたいからである。
そして、更には、日常の中で建築をどのように認識するかが大事で、その認識の仕方しだいで、例えば光の話でいえば、朝陽が室内で拡散し光の粒で充満されたように感じたならば、それは爽やかで気持ちいいことであり、それはその空間でしか体験できないことだと思えれば、朝陽を毎日感じ取ることにより、爽やかな気持ち良さと一緒にその空間をも感じ取ることになり、それが日常の中で毎日起こるならば、その爽やかな気持ち良さは建築や空間があるおかげとなり、朝陽を毎日感じ取ることが、予算が潤沢にあることよりも、敷地の場所や周辺環境が良いことよりも優先されるようになる。
そのように、建築を評価する指標において、予算や敷地の場所や周辺環境などの優劣に左右されない指標があり、その指標が予算や敷地の場所や周辺環境などの優劣よりも優先された方が、より多様で人に寄り添う建築を生み出す可能性につながる。
"To create more diverse and close-to-people architecture"
Ask clients how to recognize architecture.
The reason why we design with the impression of light is that we want to know that the indicators for evaluating a building are not limited to the superiority or inferiority of budgets, plans, site locations and surrounding environments.
Furthermore, how to recognize architecture in everyday life is important. Depending on the way of recognizing it, for example, in the case of light, the Chaoyang diffused indoors and was filled with particles of light. If you feel that it is refreshing and comfortable, and if you think that it can only be experienced in that space, by feeling the morning sun every day, you will also feel that space with refreshing comfort, it If it happens every day in everyday life, the refreshing comfort is thanks to the architecture and space, and feeling the morning sun every day is better than having a rich budget rather than having a good place and surrounding environment Will also be prioritized.
As such, there are indicators that do not depend on superiority or inferiority such as the budget, location of the site, surrounding environment, etc. in the indicators for evaluating the building, and it is better if that indicator is given priority over superiority or inferiority such as the budget, location of the site or surrounding environment. , Will lead to the possibility of creating architecture that is more diverse and closer to people.
光を意識するようになったのは建築を勉強しはじめてからだ。建築家の作品を見学する場合の見るべきポイントのひとつとして光の入り方があり、最初はそういうものかと思いつつ、自分なりに光の入り方を意識して観察し、どういうものか、どのように感じるかを積み重ねていった。
どうして光の入り方が見るべきポイントなのかというと、建築をどのように美しく見せるかと考えていった場合、そのまま見せるよりは何か演出をしたいとなり、建築は変化せずに動かないもの、光は時刻に応じて変化していくもの、そういう意味では建築と光はものの性質上、全く正反対のものであるから、かえってその差が演出上とても効果があると考えたのだろう。
ただ、光を意識することは、人から植え付けられた見方であり、自発的に気づいた見方では無かったので、光を意識していれば建築を理解できるのだから、という程度の興味しかなかった。
その後、より光を形として意識し、デザイン要素として考えはじめるようになったのは、北欧とインドの建築を訪れてからだ。
北欧で見た光は拡散した間接光であり、室内空間を淡い光が全体的に包むような感じがあり、光を形としてデザインしたというよりは、光を粒状にして空間全体にばらまいたような感じだった。
逆に、インドで見た光は鋭く指すような光で、同時に影をつくり出していたが、その時に感じたのはむしろ影が先に存在していて、その影と影の隙間に明暗をはっきりさせながら、鋭い光が割って入ってくるような感じだった。
そもそも北欧とインドでは気候が違い過ぎて 本来ならば、そのように建築を環境の面から比べるのは無理があるが、光を意識することにより、各々の建築の違いを比べて目で見て感じ取ることができ、光がむしろ建築に地域性という要素を与えていることに気がつき、では、より光を美しくみせて、それが室内空間への演出になり、クライアントが感動するにはどうしたらいいのだろうと自然に考えるようになった。
"The story of light in architecture"
I became aware of light only after I started to study architecture. One of the points to watch when observing the work of an architect is how to enter the light. Thinking that it is that kind of thing at first, but observing the way how the light enters, and wondering what it is. I accumulated what I felt.
The reason why the way of entering light is the point to see is that when I was thinking about how to make the architecture look beautiful, I wanted to do something rather than show it as it is, the architecture does not change without changing, the light Is something that changes with time, and in that sense architecture and light are the exact opposite of each other in nature, so I think that the difference would be very effective in terms of performance.
However, being conscious of light was a perspective that was planted by people and was not a spontaneously recognizable perspective, so I was only interested in the fact that I could understand architecture if I was conscious of light. .
After that, I began to think more about light as a form and to think about it as a design element only after I visited the architecture of Northern Europe and India.
The light seen in Scandinavia is diffused indirect light, and there is a feeling that the interior space is totally surrounded by faint light, rather than being designed as a shape of light, it seems that the light is granular and scattered throughout the space. It was like that.
On the contrary, the light I saw in India was sharply pointing light, and at the same time, it was creating a shadow, but what I felt at that time was that the shadow existed first and the light and darkness was clearly visible in the gap between the shadow and the shadow. While letting it go, it felt like a sharp light was breaking in.
In the first place, because the climate is too different between Northern Europe and India, it would be impossible to compare architecture in terms of the environment, but by conscious of the light, we can compare the differences between the architectures and see them visually. I could feel it and realized that the light rather gives the architecture an element of locality, so what should I do to make the light more beautiful and to create an indoor space and to impress the client? I came to think naturally.
一番最初の建築体験は光に魅せられた時だった。どうして人は光に魅せられるのだろうか、毎日毎日、太陽の光を浴びているのに、その都度感動はしない。
その時、建築は光の形をデザインするのだと思った。光量も含めて、時間に沿わせて刻々と変わる光に形を与えることにより、人に光を特別な存在に思わせているのではないか。
例えば、教会のステンドグラスはガラス自体に装飾や物語が施されているが、そのステンドグラスを通した光にも装飾や物語といった形を与えることになり、ステンドグラスと共に光も特別な存在となしている。
やはり、光が特別な存在になり得るのは、ひとつは天から全てに一様に降り注ぐためであり、もうひとつは万物に恩恵をもたらすからだろう。「一筋の光」という言葉があるように、人は光にメタファーとして希望を感じ取っている。
要するに、「一筋の光」もそうした人、すなわち、光にメタファーとしての希望を抱く人が無意識のうちに形をデザインしたようなものであり、建築はその手段となり得る存在であり、その光に魅せられた人が光と共に建築に対しても特別な感情を抱くのであり、それが素晴らしい建築体験として記憶されるのだろう。
"Memory of light, architectural experience"
The first architectural experience was when I was fascinated by light. I wonder why people are fascinated by the light, and even though I am exposed to the sunshine every day, I am not impressed each time.
At that time, I thought architecture designed the shape of light. By giving shape to the light that changes with time, including the amount of light, it may make people think of light as a special existence.
For example, church stained glass has decorations and stories on the glass itself, but the light passing through the stained glass also gives shapes such as decoration and story, and together with the stained glass, the light is also a special existence. ing.
After all, light can be a special existence, partly because it pours evenly from heaven to all, and partly because it benefits all things. As the word "a ray of light" implies, people perceive light as a metaphor.
In short, "a line of light" is like that person, that is, a person who has a hope as a metaphor for light unconsciously designed a shape, and architecture is a means that can be the means, The fascinated person will have a special feeling for the architecture with the light, and it will be remembered as a wonderful architectural experience.
コーヒーのマグカップを眺めながら、繊細さはどうやって認識するのだろうと考えていた。
まず形だろう。形がシャープならば繊細に感じる。例えば、樽型よりは糸巻き型の方が繊細に感じそうだ。やはり、樽型では野暮ったく、無骨になるだろう。
次に、厚み。厚みは端部に現れる。端部の処理が細かったり、薄かったりすると繊細さが出て、厚いと繊細には見えない。
あと、色もあるだろう。膨張色である暖色系よりは収縮色である寒色系や、黒やグレーや白のような無彩色の方が繊細に感じそうだ。
そして、精度。もしかしたら精度が一番大事かもしれない。精度とは全体のつくりの精密さであり、きっちりとしていて狂いがない様で、精度が高い方が繊細に見える。もしかしたら、形が樽型でも、厚みが厚くても、色が暖色系でも、精度が高ければ、それだけで繊細に見えるはずだ。
"Accurate?"
Looking at the coffee mug, I wondered how to recognize the delicacy.
First of all If the shape is sharp, it feels delicate. For example, the wound type seems to be more delicate than the barrel type. After all, the barrel type will be dull and clunky.
Next, thickness. Thickness appears at the edges. If the edge treatment is thin or thin, delicateness appears, and if it is thick, it does not look delicate.
There will also be colors. It seems that cold colors, which are contracted colors, and achromatic colors, such as black, gray, and white, are more delicate than warm colors, which are expanded colors.
And precision. Perhaps accuracy is the most important thing. Precision is the precision of the whole construction, it seems to be tight and there is no deviation, and the higher precision looks delicate. Maybe even if the shape is barrel-shaped, thick, or warm-colored, if it has high accuracy, it will look delicate by itself.
普通に認識していた空間が違って見える瞬間を考えていた。
認識する側、すなわち自分が立ち止まっているか、動いているか、動いていれば場面が転換していくので、その転換ごとに場面を認識するだろう。それはまるで舞台の上のセットのように、それはわかりやすい、セットが転換すればストーリーも変わる。この場合、ストーリーは日常の暮らしに言い換えてもいいだろう。動くごとに日常の暮らしが場面転換し、その都度、空間を含めた日常を認識していく。
では、立ち止まっている時はどのように認識しているか、自分は動かない、でも何かを決起に認識していく、その何かはもしかしたら日常の暮らしそのものかもしれない。ならば、立ち止まった自分を中心に据えて空間を構築してみると、日常の暮らしが直に空間に現れてくるような気がした。
"When you put yourself in the center"
I was thinking of the moment when the space that I normally recognized looks different.
The recognizing side, that is, whether you are stationary, moving, or if you are moving, the scene changes, so you will recognize the scene at each change. It's like a set on the stage, it's easy to understand, and when the set changes, the story changes. In this case, the story could be translated into everyday life. Every time you move, your daily life changes scenes, and each time you recognize your everyday life, including space.
Then, when I'm stopped, I don't move, I recognize something when I stop, but I think that something is the everyday life itself. Then, when I tried to build a space centered on myself who stopped, I felt that everyday life would immediately appear in the space.
普通のことや当たり前のことをちょっとだけ変えながら人の営みは過去から未来へと繋がっていくのだろう。それはある日突然急激に変化することでは無くて、過去に得た知識や感情などを素にして、未来へと過去からの延長線で繋ぐ。
あまりにある日突然急激に変化することは、戸惑うだけで誰もついて来れないし、そもそも急激に変化することを誰も望んで無く、徐々に緩やかに変化していかないと誰も順応できない。
人の営みによる日常は、何があろうとも、それ程簡単には大きく変わらない。今の状況での在宅ワークやリモートワークにしても、そもそも元々ある技術を使い、働き方改革の延長で捉えることができるから誰でもそれなりに順応できていて、尚且つ、新鮮で新しくも思える。
だから、必ずしも新しいことでなくても、今まで蓄積してきたモノやコトをちょっとだけ上手く活かしてやれば、乗り切れることはたくさんあるだろう。あとはそれをどう活かすか、その方向性を誰がどのように決めるかだけかもしれない。
"You can make use of the things and things you have accumulated"
It seems that people's activities will be connected from the past to the future while slightly changing the ordinary and ordinary things. It is not something that changes suddenly one day, but it connects to the future with an extension of the past, based on the knowledge and emotions acquired in the past.
Sudden sudden changes in one day can be confusing, and no one can bring them. In the first place, no one wants to change suddenly, and no one can adapt unless they change gradually.
No matter what happens, the daily life of people does not change so easily. Even in the case of home work or remote work in the current situation, it is possible to use the existing technology in the first place, and it can be understood as an extension of work style reform, so anyone can adapt as it is, and it seems fresh and new.
Therefore, even if it is not necessarily new, if you make good use of the things and things that you have accumulated so far, there will be many things you can survive. All that may be left is how to use it, and who decides the direction.
ずっと家にいる、飽きるぐらい家にいる、普段から在宅ワークなので、この状況になっても何も変わらずに生活をしていても、やはり自由に外出できないと、最初はストレスかな、疲れかなと思っていたけれど、どうも違うようで、場面が展開しない、循環しないことへ違和感のような感じがずっと続いている。
どういうことかというと、以前は、家にいる、そして、外出する、また家にいるが繰り返されることによって、自分が置かれる環境が変わり、それに応じて準備をしたり順応したりして、その都度、心身ともに変化があり、違う環境を認識して、心身や環境の違いを認識して、それが心身ともに活性化になり、良い循環をしていたのだろう。
その良い循環が無くなったので、ずっと同じ心身の状態で止まっているように感じる。たぶん、それは散歩をしたり、ジョギングをしたり、生活必需品を買いに出たくらいでは大して変わらない。
早く自由に外出できるようになってもらいたいのだが、ずっと家にいることで良い循環が途切れてしまうことを家の、建築の課題として捉えることができないだろうか、いい機会だから自ら実験台になって考えてみたいと思った。ただ、個人的な認識が先行するかもしれないけれど。
どうも身体を動かすことによって、環境や建築や空間の違いを認識しているようで、ただそこに立ち止まっていてはごく一部しか認識しておらず、たぶんそれはその必要性か無いから、別に環境や建築や空間の違いを認識しなくてもその場にはいられるからで、そこが課題のひとつのポイントかもしれないが、この状況では本来、家は安全地帯になり、そこにいるだけ気が休まり、良い循環が途切れてしまうことは別に問題にならないはずだが、そうでは無い。
つまり、人は身体を動かし続ける、あるいは、身体を動かす自由が存在しないと、いくら家という安全地帯にいても気が休まったり、心身ともに正常な状態を保つことができないようである。
ならば、その課題を建築的に解決しようとしたら、アクティビティの問題であり、アクティビティによって環境や建築や空間を認識できるようなプランニングなり、設えなり、状況なり状態をつくれば良いと一応安易に大枠の考えには及んだ。
"Considering an architecture where people can relax now"
I'm always at home, tired of being at home, and I usually work from home, so even if I'm living in this situation without any change, if I still can't go out freely, at first I feel stressed or tired. As I thought, it seems that it is different, and the feeling that something is wrong with the scene does not develop and that it does not circulate.
What I mean is that when I was at home, going out, and staying at home repeatedly, my environment changed, and I prepared and adapted accordingly. Each time there was a change in mind and body, recognizing a different environment, recognizing the difference between mind and body and the environment, and activating it both mentally and physically, which would have been a good cycle.
Since that good cycle has disappeared, I feel like I'm still staying in the same state of mind and body. Maybe that's not much different than taking a walk, jogging, or shopping for essentials.
I would like people to be able to go out freely as soon as possible.Isn't it possible to regard the fact that staying at home for a long time disrupts the good cycle as an architectural issue for homes? I wanted to think about it. However, personal recognition may come first.
Apparently, by exercising your body, you seem to recognize the differences in the environment, architecture, and space, and when you are just standing there, you are recognizing only a small part of it. Maybe it is not necessary, so another environment It may be one point of the issue because you can enter the place without recognizing the difference in architecture and space, but in this situation, the house originally becomes a safe zone, and I feel like being there. It shouldn't be a problem that rest and breaks in a good cycle, but it's not.
In other words, a person seems to be unable to maintain a normal state of mind and body no matter how much he or she is in the safety zone of the home, unless he or she continues to move or does not have the freedom to move the body.
Then, if you try to solve the problem architecturally, it is a problem of the activity, and it is easy to roughly plan if it is necessary to plan, set up, and create a situation that can recognize the environment, architecture and space by the activity. Came to the idea.
今年は花粉症にならなかった。正確に言うと、新型コロナ騒動がまだ静かだった頃、2月初め位にいつものように目が痒くなって市販の目薬を購入したが、隣国で新型コロナが大流行しだして都市封鎖が行われたら、全く痒くなくなり、いつしか花粉症のことなどすっかり忘れてしまい、新型コロナでそれどころでは無かったので、実はスギ花粉のアレルギーではなくて、大気汚染が原因だったのかもしれない。新型コロナのおかげで空気が綺麗になった。
人間の弱いところにつけ込む。家に篭っていればいいが、それでは息が詰まり、我慢できない弱みに付着してくる。ほんとイヤらしい位に人間の心理を巧みに利用して広がろうとする。
なんか新型コロナに翻弄される。空気が綺麗という意外な恩恵を受けながら、一方で亡くなる方もいるという怖さを感じ、かつてない程の振れ幅にさらされて、この振れ幅の大きさに人間が全然対応できておらず、追いついたと思ったら変異しているような感じ。
いずれも社会を営む人間の歪んだところ、ほころび、脆弱なところ、行き過ぎたところを上手く利用されているような感じで、それに対して場当たり的な対応しかできず、それは新型コロナのことがまだよくわからないから仕方がないが、空気が綺麗になって花粉症にならなかったように、後から振り返ったら、あの時があるから、今こうして良くなっていると言いたい。
ところで、今のこの状況、Stay Homeが何か建築に影響を与えるのだろうか。素直に考えれば、家にいることに関心が出て、家自体に注目が集まるはずなのだが、どうもそうではなくて、むしろ家にずっといてストレスが溜まると、それはまるで会社にいるように、だから、何か対策をしないといけない、例えば、読書をしてみては、お料理なんかはどうですかと、それは個人的には大賛成で、今までしてこなかったことを新たにはじめるのは素晴らしいことなのだが、もっと根本的に家の問題、住宅の問題として考えたい。そして、新型コロナ対応でいうところの空気が綺麗になったような結果を出したい。
"Make sure the air is clean in architecture"
I didn't have hay fever this year. To be precise, when the new Corona turmoil was still quiet, I got itchy eyes as usual in the beginning of February and purchased eye drops as usual, but the new Corona was very popular in neighboring countries and the city blockade was If it was done, it would not itch at all, and I forgot about hay fever all the time, and it was not the case with the new corona, so it may be because it was not allergic to cedar pollen, but air pollution. The clean air thanks to the new Corona.
Take advantage of where humans are weak. I just need to keep it in my house, but then I am suffocating and attach to weaknesses I can't stand. It tries to spread by making good use of human psychology to the extent that it is really unpleasant.
Somehow the new Corona is at the mercy. While receiving the unexpected benefit of clean air, on the other hand, I felt the fear that some people would die, and I was exposed to an unprecedented swing range, and human beings could not respond to this swing range at all, If you think you've caught up, it feels like you're mutated.
All of them seem to be used well in distorted places, fragile places, vulnerable places, and excessive places of people who run society, and they can only respond ad hocly, and that is why the new Corona is still good. I can't help it because I don't know, but when I look back later, as if the air didn't become hay fever and the air became clean, I want to say that it's getting better now because I have that time.
By the way, will this situation, Stay Home, have any impact on architecture? To be honest, I should be interested in staying at home and paying attention to the house itself, but that's not the case, and if you stay at home and get stressed, it's just like being at a company. , I have to do something, for example, reading, how about cooking? I personally agree with it, and it's great to start something new that I haven't done before. However, I would like to think more fundamentally as a home issue and a housing issue. And I would like to get the result that the air in the new Corona is clean.
今の状況がずっと続くようならば、早期に終息してまた同じような日常が送れないならば、人と人との関係性やつき合い方にも変化が起こるだろう。
まだリモートワークには不慣れだと皆承知の上で行い、その不慣れな分は従来のSNSやメールなどで補うことで許されているが、今後は今よりももっと言葉や文字がコミュニケーションを取る上で重要になってくる。
通常のコミニケーションでは、言葉以外に、表情の変化や声の感じや雰囲気などを加味して、何かを伝えようとするが、5Gが当たり前になるまでは、リモートでリアルタイムに詳細に相手に言葉以外の表情や声や雰囲気の違いを伝えるのは難しく、言葉や文字だけで全てを伝える必要が出てくる。
そうなると問われるのは国語力である。国語力が無いと言葉や文字だけで、表情や声や雰囲気の違いで加味できる部分を表現できない。外に出ないで、おうちで読書をしている人も多いと思うが、くしくも、それがアフターコロナの国語力養成にもなっている。
"What you need for aftercorona is your national language ability"
If the current situation continues for a long time, and if we end it early and cannot live a similar daily life, the relationships and relationships between people will change.
Everyone is aware that they are still unfamiliar with remote work, and it is permissible to supplement the unfamiliarity with conventional SNS and email, but in the future more words and characters will be communicated than now. Will become important.
In ordinary communication, in addition to words, we try to convey something by taking into account changes in facial expressions, feeling of voice, atmosphere, etc., but until 5G becomes commonplace, we can remotely communicate in detail to the other party in real time. It is difficult to convey the differences in facial expressions, voices, and moods except for, and it becomes necessary to convey everything with only words and letters.
In that case, the national language ability is asked. Without Japanese language ability, it is not possible to express the part that can be added by the difference in facial expression, voice, and mood only with words and letters. I think there are many people who do not go out and read at home, but it is also the training of the after-corona Japanese language.
まだ幼い頃、幼稚園にあがる前から遊び場は建築現場だった。大工の父親の後にくっついて、軽トラに乗り、現場で打合せをする父親の目の届く範囲で、現場の中に入って遊んでいた。おが屑を撒き散らしたり、木の切れっ端を拾い集めて積み木のようにしたり、現場だから当然刃物があり、危ないからノミには絶対に近づけなかった。きっと現場の大工さんには邪魔だったと思う。今では考えらない子供が現場の中で遊ぶなんて、でも自分にとって建築現場は遊具だった。
だから、その時の建築体験が身体に記憶として残っているので、自分にとっての建築のはじまりはいつも論理からではなくて感覚からだった。
建築をはじめ感覚で捉えて、自分が受けた印象であったり、見え方であったり、感触であったりなどがまずあり、それから自分が受けたその感覚を自分で自分に説明するように言葉に置き換えて、建築を理解しようとしていた。
だから、建築の全て、デザインからディテールまで全てを言葉に置き換えて表現でき説明できると考えている。
感覚、それを情熱と言い換えてもいいと思うが、建築を何も無いところから情熱を頼りにはじめて、実作として結実させるには論理が必要になり、その論理を使いこなしてつくるには、言葉で曖昧なところ無く示さなければ誰にも伝わらないし、説明できないし、説得できない。
だから、建築は全て言葉で表現できるのである。
"All architecture can be expressed in words"
When I was little, even before I went to kindergarten, the playground was a construction site. I was playing with the light tiger, sticking after the carpenter's father, within the sight of the father who was on the light tiger and had a meeting at the scene. I scattered the sawdust, picked up scraps of the tree and made it like a building block. Naturally, there were blades at the site, so I never approached the fleas because it was dangerous. I think it was a hindrance to the carpenter on site. It's playground equipment for me, but it's a playground for children that I don't think about now.
Therefore, the experience of architecture at that time is remembered in my body, so the beginning of architecture for me was not always logic but sense.
First of all, there is an impression, a way of seeing, and a feeling that I have received from an architectural sense, and then I should explain the feeling that I received to myself. Trying to replace it and try to understand architecture.
Therefore, I think that it is possible to express and explain everything about architecture, everything from design to detail by words.
It may be called a sense, but it can be rephrased as a passion, but it is necessary to use logic to build a real work by relying on passion from the place where there is nothing in the architecture, and to use that logic to make words, If it is not shown unambiguously, it cannot be communicated to anyone, cannot be explained, and cannot be persuaded.
Therefore, architecture can be expressed in words.
ずっと家に篭っていると、今いる場所しか安全地帯が無いと意識すると、今までの自分の家に対するイメージが段々と変わってくる。
アフターコロナには一度全てをリセットした方がいいかもしれない。シェルターとは思いたくはなかったけれど、どうしても自分の家をシェルターだと意識せずにはいられない。
シェルターとしての安全性は、今までは当たり前だと思っていた、自分の家なのだから。だけど、もっと外に出られなくなったら、安全であることが唯一絶対の条件になってしまう、自分の家なのだから。
どうしても、作り手としてはそれは避けたい。家に幻想や希望を抱くわけではないし、そうした情緒を前面に出して訴えるようなものづくりはしたくないのだが、ただ、アフターコロナではシェルターに変わる言葉を見つけないと、デザインで誰も説得できないだろうと考えてしまう。
"I have to find a word that changes to a shelter in design"
If you stay in your house for a long time, and you realize that there is a safe zone only where you are now, the image of your own home will gradually change.
It might be better to reset everything after corona once. I didn't want to think of a shelter, but I couldn't help thinking of my house as a shelter.
I used to think that safety as a shelter was commonplace, because it is my own home. But if you can't go out further, being safe is the only absolute requirement for your home.
As a creator, I definitely want to avoid it. I don't have illusions or hopes in my house, and I don't want to make things that bring out such emotions to the forefront, but in the after-corona, I can't convince anyone in the design unless I find a word that turns into a shelter. I think about it.
建築が建築として成立するためには、建築性と諸条件を満たすことが必要になる。建築性とは、歴史的蓄積や時代背景などの流行や社会的動向、哲学的思考、審美的見方などであり、諸条件とは、建主の要望や予算、法規、敷地や周辺環境の状況などである。
建築が事業として成立するためだけならば、諸条件を満たすだけでいいが、それではただの建物であり、建物を建築にまで昇華させるには建築性が必要になり、さらには、建築性と諸条件のバランスが重要になる。
それでは、建築性と諸条件のバランスをどのように取ればいいのか。その目安は割合で考え、建築性を7、諸条件を3とする。
ではどうして、その割合なのか。建築性を諸条件に比べて多くする理由は、諸条件の良し悪しに建築の優劣が左右されないためである。どうしても諸条件には良し悪しがでる。予算の有る無し、環境の良し悪しなどは仕方がないことであり、それを後から変えることはなかなか難しい。
しかし建築性は、極端な言い方をすれば、どうにでもなる。どのような建築性を持って建築と向き合うかは設計者しだいであるから、その建築性の割合を多くしておいた方がいい建築ができる可能性が高くなり、諸条件の良し悪しを上手く利用することもできるようになる。
"The balance between architectural quality and various conditions is 7: 3"
In order for an architecture to be established as an architecture, it is necessary to meet the architectural characteristics and various conditions. Architectural property refers to trends and social trends such as historical accumulation and historical background, social trends, philosophical thinking, aesthetic perspectives, etc., and various conditions include the request of the owner, budget, laws, conditions of the site and surrounding environment. And so on.
If the architecture is only to be established as a business, it is enough to satisfy the various conditions, but it is just a building, and to sublimate the building into the architecture requires architectability. The balance of conditions becomes important.
Then, how should we balance the architectural property and various conditions? Consider the ratio as a ratio, and the architectural property is 7, and the various conditions are 3.
So why is that ratio? The reason why the architectural property is increased compared to the various conditions is that the superiority or inferiority of the architectural condition is not influenced by the goodness and badness of the various conditions. There are good and bad conditions. There is no way to have a budget and the environment is bad, and it is difficult to change it later.
But, in an extreme way, architectural qualities do not matter. It is up to the designer to decide what kind of architectivity to face with the architect. Therefore, it is more likely that good architects will be able to build architects, and the good and bad conditions will be improved. You can also use it.
諸条件だけでできている建物ばかりである。建築がその時に存在するためには建築性が必要になるはずなのに、それがはじめから無いか、無視されている。それは諸条件が、それを事業性と言い換えてもいいが、優先されているということであり、それは経済性のみが判断材料になっていると言っても過言ではない。
では、建築デザインは諸条件と建築性のどちらに属するのか、本来は建築性のはずなのだが、どうも諸条件に含まれてしまう現状がある。
その時の建築デザインを決めるには、歴史的蓄積や時代背景などの流行や社会的動向や哲学的思考、審美的見方などの建築性が複雑に絡み合い、何をどのように扱うのか、どのように判断するのかを設計者が考え、建築デザインに反映させるのだが、そもそも建築性が無いか、無視をされている現状で、ただ建築デザインという行為は存在しているので、建築性なき建築デザインが諸条件に属していることになる。だから、程度の差はあるがラブホみたいな建築がたくさん存在することになる。
ではなぜ、無くても建物は建つのに、建築性が必要かというと、人間に例えるとわかりやすいかもしれないが、建築性とは人間性に当たる。人間といった場合、それは社会の中での一般的な量的な人を差す、だから誰でもいいが、そこに人間性が加わると特定の個性がある人になる。
すなわち、建築性が無ければ、どこにでもあるただの建物と同じであり、それではその建物を使う建主の個性を反映することは無く、満足させることはできない。だから建築性が必要になる。
"If there is no architectural property, it is just a building"
All the buildings are made up of only the conditions. Architecturality must be required for architecture to exist at that time, but it is missing or ignored from the beginning. It can be said that the terms are prioritized, even though it may be rephrased as businessability, and it is no exaggeration to say that only economic efficiency is a criterion.
Then, whether the architectural design belongs to the various conditions or the architectural property, which should be the architectural property originally, but there is the current situation that it is included in the various conditions.
In order to decide the architectural design at that time, how to handle what is handled and how to deal with the complicatedness of architectural characteristics such as historical accumulation and trend of the times, social trends, philosophical thinking, aesthetic perspective, etc. The designer thinks whether to make a judgment and reflects it in the architectural design, but in the first place there is no architectural property or it is ignored, there is only an act of architectural design, so an architectural design without architectural property is It belongs to various conditions. Therefore, there are a lot of architectures such as love ho, though to varying degrees.
The reason why it is easy to understand that human beings need to be built to build a building even if it isn't necessary is similar to humanity. When it comes to humans, it refers to the general quantitative person in society, so anyone can do it, but when humanity is added to it, it becomes a person with a specific personality.
In other words, if there is no architectural property, it is the same as any other building that is ubiquitous, and it does not reflect the individuality of the owner who uses the building and cannot be satisfied. That is why architecture is needed.
建築は、空間と物のバランスで成り立っているが、別の見方をすれば、建築性と諸条件のバランスで成り立っているとも言える。
空間と物のバランスが建築のそれ自体に関することならば、建築性と諸条件のバランスは建築の存在に関することである。
諸条件には、建主の要望や予算、法規、敷地の状況、周辺環境の状況などがあり、建築が事業として成り立つために必要なことである。これに対して建築性とは、建築の歴史的蓄積や社会的動向や哲学的思考や審美的見方や時代背景などの建築がその時に成り立つために要求されることである。
ただ、ほとんどの建築には建築性が無い、諸条件のみで存在している建築ばかりである。それでは建築とは言えず、単なる建物に過ぎず、それでは建主を感動させることはできないだろうと考えている。
"Architecture without architecture is not architecture"
Architecture is based on the balance between space and objects, but from another perspective, it can be said that it is based on the balance between architectural properties and various conditions.
If the balance of space and things is about the architecture itself, the balance of architecturalness and conditions is about the existence of architecture.
The various conditions include the owner's request, budget, laws, site conditions, surrounding environment conditions, etc., which are necessary for the construction to be successful as a business. On the other hand, architectural property is required for the construction of the historical accumulation of buildings, social trends, philosophical thoughts, aesthetic perspectives, historical backgrounds, etc. to be established at that time.
However, most of the architecture has no architectural properties, and only the architecture that exists only under various conditions. It cannot be said that it is architecture, it is just a building, and I think that it will not impress the owner.
建築のはじまりはいつも建主からであり、建主の要望がまずあり、その要望を満たすのが最低限になる。
ところで、空間は20世紀の発明であり、それまで建築は物としてだけの存在だったのが、そこに空間という見方が加わった。
物であれば人と相対することになるが、空間だと人は包括される。建築を自分の外に置き、その物の存在自体を、全体の有り様を意識するのに対し、空間の中に身を置き、全てを把握することはできないが、指向性を持って、ある断片のみに意識を及ぼして、建築を意識する見方ができた。
建主の要望は大抵空間に関することが多い。日常生活の中ではほとんどの時間を空間の中に身を置くことに費やすので、ある断片のみに意識した要望であることが多い。だから、建主の要望は空間をどうにかすることで解決できることが多い。
そこで、物としての建築が建主には意識されないから、建売住宅も市場では成立するのだろうし、趣味的な建築もできるのだろう。
しかし、建築は物と空間のバランスであり、どちらもそこには論理があり、気分よい日常生活を構築するためには、要望をバランスよく建築に仕立てなければならず、そこにも論理が存在する、そこはセンスではない。
"Architecture is a balance between space and things, not logic but logic"
The beginning of construction is always from the owner, and there is a request from the owner first, and it is the minimum to satisfy that request.
By the way, space was an invention of the 20th century, and until then architecture was only as a thing, but the view of space was added to it.
If it is a thing, it will face people, but if it is a space, people will be included. You can put the architecture outside yourself and be aware of the existence of the thing as a whole, but you cannot put yourself in the space and grasp everything. I was able to give a consciousness to only one person, and to have a viewpoint to be conscious of architecture.
The owner's request is often related to space. In my daily life, most of my time is spent putting myself in space, so it is often a request that only considers certain fragments. Therefore, the owner's request can often be solved by managing the space.
Therefore, since the building as a thing is not noticed by the owner, it seems that a house for sale can be established in the market, or a hobby can be built.
However, architecture is a balance between things and space, and there is logic in both, and in order to build a pleasant daily life, it is necessary to tailor requests to architecture in a well-balanced manner, and there is also logic there. Yes, that is not a sense.
毎日毎日、壁を見て暮らしているような感じがする。普段から在宅ワークだが、今までこんなに壁を意識したことは無い。Stay Homeだからか、このような状況だからだろうか、外との境界である壁を妙に意識してしまう。
そこに壁があるだけで安心してしまうのだが、朝日を浴びたり、夕日が差し込んだりすると、それだけで気分が良くなり、それは壁のどこの位置に、どのくらいの大きさの窓があるか、窓も壁の一部、壁が気分を左右するとも言える。
今までは、太陽の位置と周辺環境から、室内に、どの時間帯に、どこまで太陽の光が差し込むかが計算できるので、ここに窓を開ければ気持ちの良い光が差し込むだろう、簡単に言うと、差し込む光の量を設計して、あとはそこにいる人は気持ち良いと思うのが前提だった。
それは、光を取り入れるやり方を設計していただけであり、そこにいる人の気持ち良さを実現することを直に設計していた訳では無かった。そして、そのことに毎日毎日、壁を見て暮らしていて気がついた。
壁があり、そこに窓を開ける、それだけで外ともつながり、差し込む光は当たり前に気持ちが良い、それでは足りなかった、人の気分を受け止めるにはやり方の設計では無くて、人の気分そのものを直に反映できる建築デザインが必要だった。
"I saw the walls every day, and noticed the architectural gap"
Every day, I feel like I am living by looking at the walls. I usually work from home, but I have never been so conscious of walls. Perhaps because it's Stay Home or this situation, I strangely think about the wall that is the boundary with the outside.
I feel relieved just because there is a wall there, but when the sun rises or the sunset comes in, it makes me feel better, that is where the wall is, how big the window is, It can be said that a part of the wall, the wall affects the mood.
Up until now, it is possible to calculate from the position of the sun and the surrounding environment how much time the sun will shine into the room, so if you open a window here, you will be able to immerse yourself in pleasant light. The idea was to design the amount of light coming in and think that the rest of the people would feel comfortable.
It was only a way of designing a way to take in light, not a direct design of the comfort of the people there. And I noticed that I was living by looking at the wall every day.
There is a wall, there is a window there, it connects to the outside only, and the light that comes in is naturally pleasant, it was not enough, it was not a design of a way to catch the mood of a person I needed an architectural design that could be reflected in.
せっかく購入したスプリングコートを着ていく機会がなくなった、そもそもマスクをして着るのもと思ってしまう、そんなことを言っている場合ではないのに。
意外と平気、ずっと家に篭っていても外へ行きたいとは思わないし、おかげではかどる、目先の仕事も、その先の道筋をつけることも。
家の中にいて、どう感じるのだろうか。ずっと見ている壁が今は自分が行動できる範囲、それが今の自分が身体で感じることができる世界の全て、すなわち、建築=自分の世界。これは今だけだろう、この状況が終わった時、壁の外に解き放たれて、無限に自分の世界を、以前のように広げていくことができるはず。
ただ、以前と同じではない、自分にとって建築の意味合いが変わるだろう。一度でも建築によって自分の世界が制限されたならば、制限される前と同じようにはできない。改めて、建築が自身の身を守ってくれることに、シェルターとして、ありがたいと思うと同時に、建築はシェルターではない、身を守るのは当たり前であり、その先の部分を、建築として実現できる日常を、それによってどのような感情を人に抱かせるかを、シェルターに代わる言葉を見つけて、その日常や感情を直に提示することが求められる。
そして、きっと今とは違う気分で来年スプリングコートを着ていることだろう。
"Wearing a spring coat next year outside the architecture"
I didn't have the chance to wear the spring coat I bought, so I thought that I would wear it with a mask in the first place, even though I'm not saying that.
Surprisingly, I don't want to go out even if I stay home for a long time, and thanks to that, I can get the job done at hand and the path ahead.
How do you feel when you are inside the house? The wall that I'm looking at for a long time is the range where I can act now, that is all the world I can feel now, that is, architecture = my world. This will be the only time now, when this situation is over, you should be able to unleash yourself out of the wall and infinitely expand your world as before.
However, the meaning of architecture will change for me, which is not the same as before. Once architecture limits your world, you cannot do the same as before. Once again, I am grateful for the fact that architecture protects ourselves as a shelter, but at the same time, architecture is not a shelter. , It is required to find out alternative words for shelter and to directly present the daily life and feelings, as to what kind of feelings the person should have.
And I'm sure I'm wearing a spring coat next year with a different feeling.
いつか必ず過ぎ去るから、家に篭りながら、過ぎ去った後のことを考えている。また、いつもと変わらない日常が来るのか、たぶん来るけれど、前とは同じではいられない、また、来年同じような状況にならないとは言えないだろうから。
リセットされる人もいるだろうし、防御態勢を取るために自らリセットする人もいるだろう。いい機会かもしれない、何かを変えるタイミングとしては悪くはない、ほぼ全ての機能が止まっている状況だから、再始動するタイミングで変えれば、何事もやりやすい。
アップデートもある。ただ、それは最低限強いられるだろう、社会から、様々なことから、前と同じという訳にはいかない、また同じ状況にならないようにしないといけないから。
建築に対しても変わるだろう。建築に対する考えがリセットされてもおかしくないが、最低限以前のような論理は通用しなくなるだろう。そもそも社会から望まれる建築が変わるだろうし、経済と密接に関係する建築だから、過ぎ去った後、アフターコロナの建築は一時的かはわからないが経済の落ち込みに影響を受ける。その時建築は、自らの社会での立ち位置が問われる、それはバブル崩壊を経ているから、いやここで、バブル崩壊以降の建築の軌道修正もできるかもしれないし、また違った建築の側面が重要視されるようになるかもしれない、バブル崩壊後の建築の開閉のように。
"Architecture after passing"
I'll always pass by someday, so I'm thinking about what I've done after I've been staying in my house. Also, I wonder if there will be the same everyday as usual, but maybe it will not be the same as before, and I can not say that it will not be the same next year.
Some will be reset, others will reset themselves to take defensive posture. It may be a good opportunity, but it's not a bad time to change something, because almost all functions are stopped, so if you change it at the timing of restarting, it is easy to do anything.
There are also updates. However, it will be enforced at the very least, because of various things from society, it cannot be said that it is the same as before, and it is necessary to prevent the same situation.
It will change for architecture. It wouldn't be strange if the idea of architecture was reset, but at least the old logic would no longer work. In the first place, the architecture desired by society will change, and since it is closely related to the economy, after-corona architecture will be affected by the economic downturn after passing, although it is unknown whether it is temporary or not. At that time, the position of the building in the society is questioned, because it has undergone the bubble burst, so no, it may be possible to correct the trajectory of the building after the bubble burst, and another aspect of the building is important. Like the opening and closing of buildings after the collapse of the bubble, which may come to be.
在宅ワーク、家に篭る毎日、ただ外界とは様々な手段でつながっている、SNS、Skype、使ったことは無いがZOOMでつながる人もいるだろう、目の前にいなくても、とりあえずの意思疎通はできるから、つながっている感覚にはなれる、身体感覚は有るような無いような、人の脳は優秀だから、補ってくれるのだろう足りない部分を、ZOOMで飲み会なんて聞くと、なんか楽しそう、案外、居酒屋で呑んでるのと大して変わらないかもと思ってしまう。
これを社会とつながっていると言えるならば、つながっている人がいる場所、すなわち、その人がいる建築は社会に対して開かれた建築ということになる。きっと今、建築はシェルター化していて、社会に対して防御態勢にあるはずなのに、人はそのようなこととは関係無しに社会とつながることができる。
現代建築を考える時、建築が社会や市民に対して、開いているのか、閉じているのかは根本的な問題であり、特に建築が社会や市民に対して寄与する物だと考えるならば、開かれているのが当然なのだが、現実を見ると、そのようなことを考えること自体が無意味だと思える程、的外れな考えをしているのではないかと、昨今の状況から思ってしまう。
またまた建築が根本から揺れ動く時が来たようだ、バブル崩壊、9・11、3・11の時と同じように。
"Swaying Architecture"
Work at home, every day at home, just connected to the outside world by various means, SNS, Skype, people who have never used but will be connected by ZOOM, even if you are not in front of you, for the time being Because you can communicate, you can become a connected feeling, there is no physical sensation, because the human brain is excellent, so if you listen to the ZOOM drinking party, you will hear the missing parts that will supplement you, It looks like it's fun, and unexpectedly, I think it's not much different from drinking at a pub.
If it can be said that this is connected to society, the place where there is a connected person, that is, the architecture where the person is, is an architecture open to society. Surely, architecture is now sheltering and should be in a state of defense against society, but people can connect with society regardless of such things.
When thinking about modern architecture, whether architecture is open or closed to society and citizens is a fundamental issue, especially if you think that architecture contributes to society and citizens, It is natural that it is open, but in reality, I think from the recent situation that I am thinking so inappropriate that thinking about such a thing is meaningless itself .
It seems the time has come for the architecture to shake from the ground up, just as it did at the burst of the bubble, 9/11, 3/11.
家にずっといることになるだろうと、最低2週間は外に出なくても大丈夫ではあり、キングカズが「パーソナルロックダウン」という言葉を使って家族にもそれを徹底させているようで、それならばそれで、このような機会も今後なかなか無いだろうし、もちろん経験したことも無いので、中途半端に外出などせずに、自分もパーソナルロックダウン、ずっと家にいることで自分にどういう変化が起こるのかを見てみたい、ストレスフルになるのか、それとも逆にアップデートできるのか。
これがずっとホテル暮らしならば、ストレスフルにもなるのかもしれないが、自宅にいる訳だから快適だし、そもそも普段から在宅ワークなので変わりが無く、あとはずっと外に出ないようにすることで、どのような影響があるのか、それを建築的に考えてみたい、きっと後になって貴重な体験だったと思うだろう。
バブルが崩壊して、経済的に低迷した後、建築家が公共建築を手掛けることが急に増えた。公共建築は市民のものであるから、市民に対して開かれた建築でなければならない、それは建築全般にも言えることとなり、建築は段々と社会や市民に対して開かれた存在になっていき、それが当たり前になった。
ところが、今回の新型コロナの影響で今、建築は閉じた状態が求められている。密閉空間を避けるという意味では人がいれば換気のために物理的に開くことが求められるが、それまで人の流れや経済活動をストップさせるため、また感染させないために建築は閉じることになった、それは物理的にも、精神的にも安心感を得るために閉じた。
一時的かもしれないが、ずっと開く様を見せ続けていた建築が、社会から閉じることを要求され一斉に閉じた。建築と社会の関係性、建築と市民の関係性はこのようにいとも簡単に逆転するのか、家に篭りながら、この状況でも今後も同じように建築を開こうとするのか、開く意味があるのかを考えてみる。
"Close architecture"
If you're going to be at home all the time, you don't have to go outside for at least two weeks, and King Kaz seems to be using it with their family using the word `` personal lockdown, '' So, it is unlikely that there will be such an opportunity in the future, and of course I have never experienced it, so I will not go out halfway, personal lockdown, what kind of change will happen to me by staying at home all the time Want to see, is it stressful or can it be updated?
If you live in a hotel for a long time, it may be stressful, but it is comfortable because you are at home, and since you work at home from the beginning, there is no change, and by leaving it out all the time, I would like to think about these effects architecturally, and it would have been a valuable experience later.
After the collapse of the bubble and the economic downturn, architects have suddenly started working on public buildings. Since public buildings belong to citizens, they must be open to citizens, and this is true for architecture in general, and architecture is gradually becoming open to society and citizens. , That became the norm.
However, due to the influence of this new corona, the building is now required to be closed. In the sense of avoiding enclosed spaces, if people are present, they must be physically opened for ventilation, but until then the architecture has been closed to stop the flow of people and economic activities and to prevent infection. , It closed for physical and mental security.
Although it may be temporary, the architecture, which had been open all the time, was closed all at once as society required it to be closed. Is the relationship between architecture and society, or the relationship between architecture and citizens, easily reversed in this way? While staying in a house, will it continue to open in the same way in this situation, or will it make sense to open it? Consider
元々在宅で仕事をしているので、外に出る間隔が延びただけで普段と何も変わらない生活をしていて、それでいつもそう思うのだが、家にいると外の喧騒とは切り離された所にいるので、社会や外界の生の感じ、ライブ感のようなものが伝わってこない。
普段から外出する時は予定をまとめて、その日に全てこなすようにしているので、都内をあちこちと移動し、その時に外界のライブ感を肌身で感じ、夜の感じとか、それが新鮮な時もあり、普段では無いことに気づいたりするのだが、今はそれだけが無い。
無いならば、別のことで補えば良いと頭を切り替えて、普段やらないことを取り入れれば、そこに新鮮味があり、外出した時のような普段では無いことに気づいたりもするし、面白いもので、外出した時のライブ感のようなものは、確かに刺激的で何か影響を与えてくれて、それが気晴らしにもなるのだろうが、それは一方的なものだとわかり、こうして家の中で普段とは違うことをしているとイチイチ応答しながら考えてしまう。
今日はなぜ大きな模型が必要なのか、必要ないのではないか、いや、むしろ大きな模型はつくらない方が良いのではないかなどと延々と考えていた。
"in house"
I'm originally working from home, so I'm living the same as usual just because I've been away from home longer, so I always think so, but when I'm at home I'm separated from the hustle and bustle outside Because it is in a place, the feeling of life in society and the outside world, the feeling of live, etc. are not transmitted.
When I usually go out, I keep my schedule together and do everything on that day, so I move around in Tokyo and at that time I feel the live feeling of the outside world with my skin, at night, even when it is fresh Yes, I notice that it is not usual, but now it is not.
If you don't have it, switch your mind to supplement it with something else, and if you take in things you don't usually do, you will find that there is a fresh taste there and it is not as usual when you go out and it is interesting Things like a live feeling when you go out are definitely exciting and inspiring, and it can be a distraction, but it turns out to be a one-sided thing, thus I think that I am doing something different from my usual in the house while responding to it.
Today I was wondering why a large model is needed, why it is not necessary, or rather, why it is better not to make a large model.
知らず知らずのうちに慣習の中で行うことが当たり前になっているから、そこから外れることができず、外れてしまうのが怖く、外れないようにしてしまう。
慣習とは便利なもので、それを守っていれば、その範疇の中にいれば、いちいち説明する必要も無く、立ち位置は守られ、暗黙の了解も通るから楽である。
慣習以外のことを行ったところで評価の対象にならないから関係が無い。いかに慣習の中で新しいことを見つけ発展させるかが問われる。慣習自体を疑うこともできるが、それをやるのは効率が悪く賢いやり方では無いので、誰もやりたがらない。
結局、慣習も所属が問われるのと同じで、前提条件みたいなものだから、それは素直に受け入れて、そこから先を新しく構築することに頭を使うことが、やはり、慣習のようだ。
ただ、慣習を都合よく扱うこともできて、それは、慣習から先の部分を最初に新しく構築し、それに合わせて慣習の解釈を都合良く変えることもできると考えている。そうすれば、慣習を都合良くカスタマイズあるいはアップデートできて、それを前提にできるから、それはそれで素晴らしいはずなどと夜な夜な考えているしだい。
"Premise customs"
Because it is natural to do it in a custom without knowing it, it is impossible to get out of there, and I am afraid that it will come off, so I will not let it go off.
Customs are convenient, and if you follow them, you do not need to explain each time you are in that category.
There is no relationship since doing something other than customary will not be evaluated. The question is how to find and develop new things in custom. You can doubt the custom itself, but doing so is inefficient and not a clever way, so nobody wants to do it.
After all, custom is the same as asking for affiliation, it's like a prerequisite, so it's customary to accept it straightforwardly and use your head to build new things from there.
However, we can also treat customs conveniently, and believe that it is also possible to construct new parts of customs first, and to change the interpretation of customs accordingly. That way, you can conveniently customize or update the conventions and assume that, so it's a good night to think it should be great.
シンプルに捉えようと、難しく考えたり、複雑に考えたりすることはいくらでもできるけれど、案外、シンプルに要点だけを掴める人は少ないので、それだけで貴重な能力だと思う。
型を用意しておき、その型に当てはめることによってシンプルに捉えようとする試みはよくある。だから、型を用意をしておけば、シンプルに捉えること自体は案外簡単にできるので、あとは柔軟性をどうやって担保するか。
柔軟性とは、物事自体はそんなにわかりやすい構造をしていないので、型に上手く当てはめるには技術が必要だが、高度な技術が必要では誰も上手く型を使いこなせないので、誰でも使いやすくすること。
そのためには2通りあり、型自体を緩く遊びがある物にしておくか、複数の型を用意しておくか。どちらでも良いが、複数の型を用意しておいた方が状況に応じて型を選択すれば良いだけだから、とりあえず、高度な技術は必要無く、誰でも簡単に迅速にシンプルに捉えることができるようになる。
だから、複数の型を用意しておけば、物事をシンプルに捉えやすくなり、そうすれば、道筋がはっきりするので、より良い結果が出やすくなると思うのだが、多くはどうも型自体に緩く遊びがあるようだ。
"Multiple types"
You can think of it as difficult or complicated to capture it simply, but surprisingly few people can simply grasp the gist, so I think that alone is a valuable ability.
There are many attempts to keep a simple type by preparing a type and applying it to the type. Therefore, if you prepare a type, it is surprisingly easy to grasp it simply, and how to ensure flexibility after that.
Flexibility means that things do not have such a straightforward structure, so technology is necessary to apply them properly, but if advanced technology is required, no one can use them successfully, so making it easy for everyone to use.
There are two ways to do this, whether the mold itself should be loose and playful or have multiple molds available. Either way is fine, but if you prepare multiple types, you only have to select the type according to the situation, so for the time being, there is no need for advanced technology, anyone can easily catch it quickly and simply Become like
I think that if you prepare multiple types, it will be easier to catch things simple, and that way will be clearer, and it will be easier to get better results, but in many cases the type itself is loosely playable There seems to be.
生活必需品とは何だろうと考えてみると、どうしても最低限の物と考えてしまう。無くなったらその必要最低限の物を補充をするために外に出る。人によって必要最低限の物が違う場合もあるだろう、お酒だって飲む人には生活必需品だし、間食用のお菓子もなくてはならない人もいるだろう。食べ物は栄養だけを考えれば、お酒もお菓子もいらないが、精神的な安定をもたらす物だと考えれば、お酒もお菓子も必要になる。
では、デザインはどうだろうか、必要だろうか、生活必需品だろうか。この非常時に、この不安定な状況の時に、やはりお酒やお菓子と同じように、精神的な安定をもたらす物として考えることができるのではないだろうか。
デザインは生活必需品である。もしかしたら、殺伐として、ささくれ立ちそうな場所にいても、自分が好きな物、好きなデザインに囲まれていたら、少しは心が晴れて、精神的に安定してくるのではないだろうか。こういう時だからこそ、目に見えない物と対峙しなければならない時だからこそ、目に見える所に安心できる物を置きたい、今こそ、デザインが必要な時、デザインの力を発揮する時ではないだろうか。
"Design is a daily necessity"
When we think about what we need for daily necessities, we always consider it a minimum. When it is gone, go outside to replenish the minimum required. The minimum requirements may be different for different people, and even those who drink alcohol will be a necessity of life, and some will have to have snacks for snacks. Food does not require alcohol or sweets when it comes to nutrition alone, but when it comes to mental stability, alcohol and sweets are needed.
So what about design, whether it's necessary or necessities of life? In this emergency, in this unstable situation, it can be considered as a thing that brings mental stability, just like alcohol and sweets.
Design is a necessity of life. Perhaps, even if you are in a place that seems to be upset as a killing, if you are surrounded by your favorite things and favorite designs, your mind will be a little clearer and mentally stable. This is the time when you have to confront an invisible object, so you want to put something that can be seen where you can see it.Now, when you need design, isn't it time to use the power of design? .
北欧でデザインが盛んなのは、冬の間、雪に閉ざされて外出ができず家の中で過ごすため、どうしたら快適に暮らすことができるだろうかと工夫をした結果だという。
フィンランド、スウェーデン、デンマークと雰囲気はそれぞれ全く違う国だけど、街を歩いていると、何気ない窓の中に見える室内の様子が綺麗にデザインされているのがわかる。それもこなれている、生活とデザインが密着している感じがする。
ずっと家にいて、それが居心地が良く快適であれば、外に行きたいとも思わないし、家にいるだけで楽しい。
いつも、その時自分が好き物を部屋の真ん中に置いている、一番目に入るところ、部屋の真ん中に飾り棚を置き、好みの物をたくさん並べて、どこからでも見えるように。見ているだけで楽しいし、気分が華やかになる。
断捨離とは真逆で、好みの物が増える一方で、でも飾り棚のスペースには限界があるから、ローテーションでぐるぐると部屋の中の置き場を移動する。部屋の真ん中の飾り棚がメインで、その時の気分で、その時一番好きな物がその場所にくる。ずっと置かれている物もあるし、すぐにローテーションする物もあるし。
結局は、自分の居場所を快適にできないのに、外で快適な居場所を見つけようなんて無理だと思う。
北欧デザインの良さは、一言でいうと、洗練された親しみやすさ、だから、日常の生活に取り入れやすく、そのデザインされた物があるだけで、生活がお洒落に見える、それは、冬の間、人々の心を癒す。
"Everyday with design"
The reason why the design is thriving in Scandinavia is that it is the result of devising how to live comfortably in winter because it is closed in the snow and cannot go out and spends time in the house.
The atmosphere is completely different from Finland, Sweden, and Denmark, but when you walk around the city, you can see that the interior is clearly designed through casual windows. It feels good that life and design are in close contact.
If you stay at home and it's cozy and comfortable, you don't want to go outside and just stay home and have fun.
I always put my favorite things in the middle of the room at the time. The first place is to place a cabinet in the middle of the room and arrange a lot of favorite things so that they can be seen from anywhere. It's fun just watching and it makes me feel gorgeous.
It's the exact opposite of discarding, and while there are more things to like, there is a limit to the space in the cabinet, so you can move around in the room as you rotate around. The cabinet in the middle of the room is the main one, and at that time, my favorite thing comes to that place at that time. Some things have been around for a while, others rotate quickly.
After all, if you can't comfortably be where you are, you won't be able to find a comfortable place outside.
The good point of Scandinavian design is, in a nutshell, refined friendliness, so it is easy to incorporate into everyday life, and just by having the designed thing, life looks fashionable. Heal people's hearts.
何気ない日常は人によって違うだろうが、朝起きてから夜寝るまで、その人にとっての一番心地よい事やリズムで過ごしたいと思い、いろいろと工夫をしたり、こだわったりして、そこにその人の個性や資質が現れたりもするが、明日からもっと規制をされる可能性もあるが、この段々と不自由になっていく中で、どうしたら心地よく過ごせるか、そのようなことは無理だから、今はとにかく我慢をしてというのでは面白くない。
狭小住宅というカテゴリーがある。狭い土地、例えば、10坪位の土地に建てる住宅のことをそう呼ぶ。狭い土地でも広い土地でも法規は一様にかかるから、土地の広さに応じて住宅の広さも決まる。だから、狭小住宅の広さは数値で表したら狭い。
でも、意欲のある設計者はそこに抗う。狭い土地だから、そこの土地に建つ住宅が狭いのは仕方がないことだとは考えない。数値で表したら確かに狭いが、広く見えるような、広く感じるような工夫を考え、そして、狭小住宅だから実現できる居心地良さを見出す。
今この状況だから、人にうつさないために家にこもる時だから実現できる自分に合った居心地良さを見つけるのも良いものだと思う。
"Comfort now"
The casual daily life will vary from person to person, but from waking up in the morning to going to bed at night, I want to spend the most comfortable things and rhythms for that person, and devised and stuck in various ways. Although personality and qualities may appear, there is a possibility that it will be more restricted from tomorrow, but in this increasingly inconvenience, how can you feel comfortable, it is impossible to do such things, so now It is not fun to be patient anyway.
There is a category of small houses. A house built on a small land, for example, a land of about 10 tsubos, is so called. Laws apply uniformly on small and large lands, so the size of a house determines the size of a house. Therefore, the size of a small house is small if it is expressed by a numerical value.
But motivated designers resist it. Because it is a small land, I do not think that it is inevitable that the houses built there are narrow. The numerical value is certainly small, but we think of a device that looks wide and feels wide, and finds the comfort that can be realized because it is a small house.
In this situation, I think it's good to find the comfort that suits me when I'm staying at home to keep people out.
手元に蓋物がある。誰でも好みがあるだろう、その蓋物の形は好みではなかった。今までに何度もその蓋物の前を通り過ぎた。その度に目をやるが好みではないから興味が湧かない。
ある時、別のところで、その蓋物と同じものに出会した。遠目からその蓋物があることはわかっていたが、好みではないから近づかなかった。別のものを手に取りたくて、その蓋物の近くまで行き、顔を上げると、目の前にその蓋物が出現した。以前から目にしている蓋物と同じものだが、微妙に何かが違う。形は似ているから好みではない、色も同じようだと思うのだが、無性に手を伸ばして触りたくなった。その膨らみが、その色が艶やかに感じ、一瞬で惹かれてしまい、今は毎日眺めながら、それでも触れたくて仕方がない衝動を毎日抱く。
だが、相変わらず形は好みではない、なのに触れたくて仕方がない、説明がつかないこの衝動が湧く毎日である。きっと、何か別の扉が一瞬のうちに開いてしまったのだろう、そうしたら、中から好みとは別の何かが溢れ出てきたのかもしれない、その何かは今はわからないが、無理に詮索もしないが、なかなか外に出られない毎日のちょっとした悩ましい楽しみになっている。
"Annoying Lid"
There is a lid at hand. Everyone would have a preference, the shape of the lid was not a preference. I've passed the lid many times before. I look up each time, but I don't like it because I don't like it.
One day, I met the same thing elsewhere. I knew from a distance I had the lid, but I didn't like it because I didn't like it. I wanted to pick up another thing, approached the lid, raised my face, and the lid appeared in front of my eyes. It's the same as the lid you've seen before, but something slightly different. I don't like it because the shapes are similar, and I think the colors are the same, but I felt like reaching out to touch asexually. The bulge makes the color lustrous and fascinates in an instant. Now I look at it every day and still have the impulse that I still want to touch.
However, as always, I don't like the shape, I can't help touching it, it's every day that this unexplained impulse springs up. Perhaps something else has opened in an instant, and then something different from your taste may have overflowed from within, but I don't know that now However, I do not forcibly pry, but it is a little annoying fun every day I can not easily go out.
なぜ建築をやっているかと言うと、何気ない陽の光にハッとして感動して印象に残ったり、日常生活の中でホッとして心地よい場所に腰掛けてボーっとして眠くなったり、そんな見え方するのかなどと新しい空間に驚嘆したりして、今度は反対に自分がそのような建築や空間をつくり、誰かにその感覚を味わって欲しい、それはきっと豊かにする人も社会も心もと考えたから。
それが今までにできているかどうかは自分では判断しないが、そもそも、そのように建築のことを考え、何かをしたいと考えるのも、自分自身が元気でいることが前提になっていて、それが当たり前だからできることである。
長期戦は覚悟している、そのための準備もできている、今の空白が今後の更なる我慢を強いる可能性もあるが、建築でできることは粛々と行うしかない。しかし、何か落ち着かない。
マズローの欲求5段階説に準えれば、食事などの生理的欲求や身の安全などの安全欲求が満たされないと、その上位欲求になる貢献などの社会的欲求が湧いてこない。
今回の新型コロナウイルスによる経済的なダメージは世界的にも大きいが、それ以上に精神的なダメージ、精神的な空白がもたらすダメージの方が今後に影響を与えると思う。
"Mental blank"
The reason why I am doing architecture is that I am impressed by the casual sunlight and am impressed, or I feel like I am sitting in a comfortable place in my daily life and become sleepy as a bow, etc. I was surprised at the new space, and on the contrary, I wanted to create such an architecture and space, and I want someone to taste that feeling, because I thought that the people who enriched it and the society would have heart.
I do not judge whether it has been done by myself, but in the first place, thinking about architecture and wanting to do something on the assumption that I am fine, This is something that can be done because it is natural.
We're prepared for the long run, we're ready for it, and the current void may force us to be more patient in the future, but we can only do what architecture can do. But something restless.
According to Maslow's five-stage theory, if the physiological needs such as meals and the safety needs such as personal safety are not satisfied, social needs such as contributions to higher ranks will not emerge.
Although the economic damage caused by the new coronavirus is large worldwide, I think that the mental damage and the damage caused by the mental void will have a greater effect on the future.
完成美より不完全な様、それは、その時点では何も定まっておらず、その後、時間がそうさせるのか、作為的にそうなるのか、自然になるのか、ある時点で定まる、その時、その瞬間だけの完成美が出現し、また不完全な様へと戻っていき、また違った完成美が出現し、また、の繰り返しに、そのような不完全な様に惹かれる。
その時々で見せる完成美は、完全な物でも無く、完全とは違い、ただその瞬間だけの姿、あるいは、時間軸でのある断面を見ているだけで、金太郎飴のように、どこを切っても金太郎だが、その金太郎は全て微妙に違い、どの金太郎が完全とは言えないのと同じで、その時々での違いが見られる、それは不完全ゆえの余白のような、どうにでも解釈できる部分があるからで、その余白の部分が曖昧さを生み、様々な物や事を反映できる面白さが不完全な様にはある。
完全美は何もかも全てが揃っていて、それを全て見せて、見えている物が美しい様であり、不完全な様はその時点では全ては揃っていないが、全てを揃えるためのスペースは用意されており、そのスペースは自由に使って良い状態なので、その時々でスペースの使い方も変わるから、美しさも変わる。
今、建築で実現したいことは、このような不完全な様であり、それは容れ物だけを用意して、あとは使う人が自由にすることでは無くて、建築そのものがこのような不完全な様を表現しているようにしたいと考えている。
"Incomplete"
As imperfect than perfect beauty, it is not fixed at that time, then it is determined at a certain time, whether time will be, artificially, natural, at that time, only at that moment The perfect beauty emerges and returns to an imperfect appearance, and another perfect beauty emerges, and is repeatedly attracted to such an imperfect appearance.
The perfect beauty that is shown at that time is not perfect, unlike perfection, just looking at the figure at that moment or cross section with the time axis, like Kintaro candy, where It is Kintaro even if it is cut, but all Kintaro are slightly different, the same as which Kintaro is not perfect, and there are differences from time to time, such as margins due to imperfection, Because there is a part that can be interpreted even in, there is a case where the margin part produces ambiguity and the fun that can reflect various things and things is incomplete.
Perfect beauty has everything in it, show it all, the things you see are beautiful, and the imperfect ones are not all in place at the time, but there is space for everything The space can be used freely, and the use of the space changes from time to time, so the beauty changes.
What we want to realize in architecture now is such an imperfect state. It is not just a matter of preparing containers and leaving the user free, but the architecture itself is such an imperfect one. We want to be able to express the state.
輪郭や境界がハッキリとしていて独立した存在感を醸し出している物が良いと思っていた。それは絶対的に美しく、絶対的に素晴らしいと形容するような物で、それ自体で完成された物、例えば、美術工芸品のような、うかつに触ることができずにガラスケースの中に入っているような物である。
そうした完成された絶対的に美しい物は魅力的に見え、所有したくなるが、使うことは考えない。当たり前である、はじめから使うことは考えておらず、そもそも使う物ではない。だから、見ることで、そこに存在していることで完結しており、その完成美が全てであり、それ故に強さがあり、そこに惹かれるのかもしれない。
一方で、使う物、使われる物の良さ、美しさ、素晴らしさもあるだろう。例えば、民藝の物は、日常の生活の中で使われることを念頭につくられ、使用に耐える強さを持ち、同時にその物が日常で使われることによって、人に情緒的な豊かをもたらす。その物は人が使うことによって完結するから、その物単体での良さ、美しさ、素晴らしさはまだ完成されていないように思え、その不完全さに惹かれてしまう。
故に、完成美としての魅力は物に対して抱き、使われる物の不完全さとしての魅力は、物に対してでは無くて、人と物との関係性に対して抱く。どちらが良いということでは無いが、人と物との関係性の方に興味が湧き、そういう物、不完全性を纏う物に惹かれる。
"The imperfection of things used"
I thought it would be good if the outlines and boundaries were clear and had an independent presence. It is an absolutely beautiful and absolutely wonderful thing that can be described as a finished product, such as a piece of art and craft, in a glass case without being touched It's like
Such completed absolutely beautiful things look attractive and you want to own them, but don't consider using them. It's natural, I don't think about using it from the beginning, and it's not something I use in the first place. So, by looking at it, it is complete by being there, its complete beauty is everything, and therefore it has strength and might be drawn to it.
On the other hand, there will be things to use, good things to use, beauty, and splendor. For example, folk art objects are designed to be used in daily life, have the strength to withstand use, and at the same time bring emotional richness to people by using them in everyday life . Because the object is completed by human use, the goodness, beauty, and splendor of the object alone seem not to be completed yet, and I am attracted to its imperfection.
Therefore, the beauty as perfect beauty embraces the thing, and the charm as the imperfection of the used thing embraces not the thing but the relationship between the person and the thing. It doesn't mean which is better, but I'm interested in the relationship between people and things, and I'm attracted to those things and those that wear imperfections.
同じ用途、同じ見た目でも、形がほんのわずかでも違えば、それは別物だと考えている。その差はもしかしたら、1mmもないかもしれない。ただ、1mmは大きな誤差だ。1mm違えば、戸は閉まらない、触れば、その差はわかり、見た目にもわかる。
その物を見て、比べる物があれば、別物だと判断し、比べる物が無ければ、印象に残らない。その物自体の形、スケールが良ければ問題無く、すぐにそれが良いと判断するが、どこかバランスが悪い、何か形が良くないなどとなると、あとその物がどうなれば良いのかと自然に考えてしまい、だから、ほんのわずかな違いに気がつき、売り物ならば、別に欲しくないとなる。
正解の形は無いから、厳密に言うと、規範となる形はあるだろうが、それとそのまま同じ形の物をつくっても別物だと判断されるだろう。おかしなものだが、同じではだめで、その規範となる形より、触ってもわかるかわからないか位の違い、例えば、細い所はわからない位に微妙に細く、太い所はわからない位に微妙に太く、よりわずかだがメリハリをつけて繊細にすることでちょうど良く同じ物に見える。
だから、先の話で言えば、数値としては同じ形の物かもしれないが、感じ方は別物だと判断してしまうということ。あくまでも人が使う物ならば、その物を見て触れた時の印象が全てということで、その時に精巧さがあらわれる。
"Another"
For the same uses, the same look, and the slightest difference in shape, we consider them different. The difference may be less than 1mm. However, 1mm is a big error. If it is 1mm different, the door will not close, if you touch it, you will see the difference and you can see it.
Looking at the thing, if there is something to compare, it is judged to be another thing, and if there is no thing to compare, it does not remain in the impression. If the shape and scale of the object itself are good, there is no problem and it is immediately judged that it is good, but if somewhere the balance is poor or something is not good, etc., it will be natural what to do with the object So, you'll notice the slightest difference, and if you're selling something, you don't want it.
There is no form of the correct answer, so strictly speaking, there will be a normative form, but if you make a thing of the same form as it is, it will be judged different. It's weird, but it's not the same, it's not the same as the normative form. Slightly sharp and delicate, it looks just the same.
So, speaking earlier, the numbers may have the same shape, but the way they feel is different. If the object is used by a person, the impression of seeing and touching the object is everything, and so elaborateness appears at that time.
パッと見た時に認識しやすいのは、部分的でも良いから、ヒエラルキーがある状態で、そのヒエラルキーのつき方がわかりやすい時である。
例えば、はじめて入ったお店でトイレを探そうとした時に、そのお店の考え方にもよるが、まずバックヤードと思われる辺りを探そうとする。それはトイレがメインの空間からは見えにくい所にあるだろうからと当りをつけるからで、時々、トイレのドアかなと思うとスタッフルームのドアだったりする。
メインからサブへ、表から裏へと明確に違いがわかれば、あるいは、トイレへの案内があれば良いが、無ければ尋ねるしかない。
人にまず認識をされなければ、何も伝わらないので、関係性を持ちたければ、認識しやすさ、あるいは、認識される構造を把握することが伝える内容と同じ位に重要だとなり、もしかしたら、伝える内容が普通でも認識のされ方が良ければ、伝える内容がより良く思われるかもしれず、そうすると、認識のされ方、伝え方により重きを置くのが良いかもしれない。
"Recognized"
What is easy to recognize at a glance is when there is a hierarchy and it is easy to understand how to attach the hierarchy because it may be partial.
For example, the first time you try to find a toilet in a store you enter, depending on the way the store thinks, you first try to find a place that seems to be a backyard. It's a hit because the toilet may be hard to see from the main space, so sometimes it's a staff room door if you think it's a toilet door.
If you can clearly see the difference from the main to the sub, from the front to the back, or if there is a guide to the toilet, you have to ask if there is no guide.
If you don't recognize it first, nothing will be transmitted, so if you want to have a relationship, it is as important to understand as possible or to understand the structure to be recognized as much as what you tell, If the content to be conveyed is ordinary but well recognized, the content to be conveyed may seem better, and then it may be better to give more weight to the way of recognition and communication.
こんな時だから、時間があるから、普段できないこと、しなかったことをやる、でも、その「普段できないこと」「しなかったこと」は今この普通ではない状況でなければやろうとしなかった訳だから、そもそも一生やる必要が無いことだ。
そのようなことにせっかくできた時間を使うのは勿体ないので、日常の中で普段やっていることを、今この普通ではない状況でも同じようにやるためにはどうすれば良いかと考えてやることに時間を使うことにした。
それができれば、どのような状況に置かれても普段通りに日常を送れるし、それは精神衛生上も良いし、少しは落ち着く。
案外、日常の行動はパターン化され、ルーティン化されているので、一番困るのは、そのパターン化された行動が制限され、ルーティンできないことで、これからもっと制限されるかもしれない。制限を無視するのは簡単かもしれないが、それでは、今この普通ではない状況にさらされていることを活かせない。ならば、制限される行動をしなくても済むようにすれば良いと皆思うから、買い占めがはじまる。
行動のパターン自体は中々変えることができないし、パターン化された行動が日常の中でルーティンするおかげで、日常を送るという推進力が生まれるので、制限されると推進力を失い、日常に支障をきたす。
ただ、簡単に言ってしまえば、日常の中でルーティンしていれば推進力は生まれるので、今この普通ではない状況でもルーティン化できるパターンを再構築すれば良いことになり、そこには新しい発見があるかもしれない。
"Rebuilding routines"
I have time to do things that I can't usually do and things that I didn't do, but I wasn't going to do what I couldn't do or things I didn't do in this unusual situation right now That's why you don't have to work for a lifetime.
It's inevitable to spend the time you have done in such a way, so it's time to think about what you usually do in your daily life and how to do the same in this unusual situation now. I decided to use.
If you can do it, you will be able to send your everyday as usual in any situation, it will be good for mental health, and it will calm down a little.
Surprisingly, everyday behavior is patterned and routine, so the worst thing is that the patterned behavior is restricted and can't be routed, so it may be more restricted. It may be easy to ignore the restrictions, but that doesn't take advantage of the now unusual situation. In that case, we all want to avoid having to be restricted, so we start to buy.
The pattern of behavior itself cannot be changed easily, and the routine of patterned behavior in everyday life creates the driving force to send everyday, so if it is restricted, it loses the driving force and interferes with everyday life Come.
However, to put it simply, routines in everyday life can generate impetus, so we just need to reconstruct patterns that can be routinely used in this unusual situation. There may be.
どの分野でも同じだと思うが、その分野での暗黙の了解のような事は存在し、それが慣習化し疑いようもないものになっていて、それは時代によって変わるが、何事もまずそこからスタートする。
何も知らない者がまず手始めに行うことは、その慣習を知り学ぶことで、それは疑いようもないことだから、いちいちそこを疑っていては何も前には進まないから、とりあえず、その慣習を覚えていき、やがて、その慣習の先が創意工夫するところとなる。
慣習の部分を「知識」や「知恵」や「メカニズム」などに置き換えても良いが、その慣習の部分に対する違和感は何も知らない者にとっては「変だな」と思うか、「そんなものか」と思うかの2通り、やがて大部分は消えていくが、それでもその違和感が残っていたり、復活してきた違和感に対しては、新ためて今度は詮索しないと先に進まなくなる。それは今までを疑うことになるから、それまで身に付けたものが必要で無くなるかもしれないが、それでも一度は行う価値があると考えている。
目的が結果を出すことだけならば、結果を出すこと自体も大変な事だから、慣習の部分に違和感を覚え疑うなど時間の無駄でしかないことだが、そこを詮索することが面白そうだなと思えてしまうならば行うのもありだと思う、そうすればアップデートできる。
"Peeking into customs"
I think it's the same in every field, but there are things like tacit understanding in that field, it's customary and undeniable, it changes with the times, but everything starts from there I do.
The first thing a stranger does first is to know and learn the custom, and that is undoubtedly impossible, so if you doubt it there, nothing will go forward. Remember, and eventually, the end of that custom is where you devise.
The custom part may be replaced with "knowledge", "wisdom", "mechanism", etc., but for those who do not know anything about the unusual part of the custom, it seems "weird" or "Is that something like that?" In the two ways, most will eventually disappear, but even if the discomfort still remains or the discomfort is resurrected, you will not be able to proceed unless you pry anew. That would make you doubt what you've been doing, so you may not need what you've learned, but I think it's still worth it.
If the only purpose is to produce a result, producing the result itself is also difficult, so it is only a waste of time, such as feeling strange and uncomfortable in customs, but it seems interesting to snoop on it If you do, I think you can do it, so you can update.
装飾とは「飾る」ことだが、「飾る」という行為以外にも、モノとしての装飾という意味合いもある。建築では主に「装飾」というモノとしての意味合いの方が強いが、「飾る」という行為にも興味が湧く。
装飾が外の世界との関係を調整するものであるならば、モノとしてよりは「飾る」という行為の方が重要である。飾ることによって、自分のいる場所や自分自身を外の世界に向かって特徴づけしようとする。関係性を築きたいのであれば、まずは自分が何物なのかを示さなくてはならない、そのための特徴づけが装飾であり、「飾る」行為である。
この場合の「飾る」行為の対象には、建築や空間も含まれるし、人間自身も含まれ、その手段には建築空間のデザイン以外にも、服などのファッションも用いられる。
ならば、建築空間デザインとファッションデザインを同じ舞台に上げて、同じ様に扱ってみるのも面白い、建築空間ではもちろんスケールの違いがデザインになるが、それはファッションデザインでも同じ、サイズがあり、ファッションデザインでも建築空間デザインと同じように、サイズもデザインの内である。
建築空間デザインでは、当たり前だが、そこに建築性という規範があり、その範疇で捉えようとする。それは現実実際の複雑な状況を建築空間デザインで扱えるように単純化するためのものであるが、その建築性の部分にファッションデザインの考えや見方を移植してみると、同じように単純化しても、また違った見え方になり、それはもしかしたら、現実実際の複雑な状況が複雑なままに建築空間として立ち現れてくるのではないかと考えている。
"Decorating"
Decoration is "decorating", but in addition to the act of "decorating", it also has the meaning of decoration as a thing. In architecture, the meaning of "decoration" is mainly stronger, but I am also interested in the act of "decorating".
If decoration adjusts the relationship with the outside world, the act of "decorating" is more important than as an object. By decorating, you try to characterize your location and yourself towards the outside world. If you want to build a relationship, you must first show what you are, and the decoration is the act of "decorating".
In this case, the act of "decorating" includes architecture and space as well as human beings, and means of clothing and fashion is used in addition to the design of architectural space.
Then, it is interesting to put the architectural space design and fashion design on the same stage and treat them in the same way. Of course, in architectural space, the difference in scale will be the design, but that is the same in fashion design, there is the same size, fashion In design, as in architectural space design, size is within design.
It is natural in architectural space design, but there is a norm called architectural property, and I try to capture it in that category. It is intended to simplify real-world complex situations so that they can be handled by architectural space design.However, when porting ideas and perspectives of fashion design to the architectural part, it is similarly simplified. However, I also think that it will be a different way of seeing, and that it is likely that real and complex situations will emerge as architectural spaces with complex complexity.
複雑なことを単純にして見せる、凝縮か、還元か、間引くのかなど、手法は様々だけれども、単純でシンプルだけど、そこにたくさんの意味合いがあり、奥深さや趣深さがあると、今、頭の中では長谷川等伯の「松林図屏風」が思い浮かんでいるが、素直に感銘してしまう。
単純化しシンプルにしていくと、今までの余韻や場所を感じる間や余白が生まれ、その間や余白は一見すると何も無く、何も意味が無く、無駄のように思えるが、その間や余白に様々な心象を投影できるし、勝手に投影してしまう。
きっと人の脳は足りない何かを想像力を駆使して、勝手に創造するのだろう、その間や余白に様々なものを足し加え、様々な想いを勝手に抱かせる。その表現は決して一次的で直接的では無いから分かりやすくは無いが、それ故に、解釈しだいで様々な情景を見ることができ、一次的で直接的な表現よりも豊かで、奥深さや趣深さが生まれる、そのような二次的で間接的な表現をつくり出したいといつも考えている。
"Secondary expression"
There are various methods, such as condensing, reducing, thinning, etc. that show complicated things in a simple way, but it is simple and simple, but there are many meanings there, and if there is deepness or fancy, now, I think that Among them, Tohaku Hasegawa's "Pine forest figure screen" comes to mind, but I am impressed with it.
If you keep it simple and simple, there will be gaps and spaces that you feel the lingering and place of the past, and the gaps and margins at first glance are nothing, nothing meaningless and seem to be useless You can project a great image, and project it without permission.
Surely, the human brain will use imagination to create something that is missing, and will add various things to the space and margins to bring various thoughts to themselves. The expression is not easy to understand because it is not primary and direct, but it is possible to see various scenes depending on the interpretation, and it is richer, deeper and deeper than the primary and direct expression I always want to create such a secondary and indirect expression that can be born.
装飾が無いという装飾が成り立つならば、この世は全て装飾に満たされている、ならば、後はどの装飾を選択するかだとしたら、何を選択するか、自分の気分によって選択したいし、ファッションのように流行はあるだろうが、それを踏まえながら、より最適なものを選択したいと思う、それは損得勘定ではなくて、自分にとって最適なもの、心象としてそう思い、そして、後から事象を考える。
人と人がつながることと装飾は関係があるのか、答えは、あるだろう。人と何かしらつながりたいから、服を着るし、ファッションの流行を追う。
装飾は人とつながるためにある、ならば、建築も同じだろう、建築と人の関係性を考えるならば、装飾を考えない訳にはいかない。
"Decoration in architecture"
If the decoration without decoration is valid, the whole world is full of decorations, so if you decide which decoration to choose, what you want to choose, you want to choose according to your mood, fashion There is a trend like this, but I would like to select the most optimal one based on that, it is not a profit and loss account, but it is the most suitable for myself, I think as an image, and think about the event later .
The answer may be whether the connection between people and decoration is related. I want to connect with people, so I wear clothes and follow fashion trends.
Decoration is to connect with people, if so, architecture is the same. Considering the relationship between architecture and people, it is inevitable to consider decoration.
装飾は外の世界との関係性を示すもので、京都大学柳沢研究室『装飾と住居』によると「装飾は秩序」だという。
モダニズム建築は、装飾に限って言えば、装飾を無くすことで、装飾を余計なもの、装飾を悪のように扱い、削ぎ落とすことにより成立していた。ただ、装飾を外の世界との関係性を示すものとするならば、モダニズム建築は、装飾が無いという装飾をつくり出して、外の世界、すなわち、社会に対して関係性をつくろうとしたとも考えることができる。
しかし、人は太古の昔から、装飾性を身にまとい、外の世界との関係性を築いてきたと言える。それは建築にも現れるが、民族衣装や祭事にも現れる。だから、装飾が無いという装飾性には、人の精神衛生上、どこかに無理があり、かと言って、全くモダニズムからは離れることもできずという状況が現代だと考えている。
"Relationship of decoration"
Decoration shows its relationship with the outside world, and according to Yanagisawa Lab at Kyoto University's "Decoration and Housing", "decoration is order".
Modernist architecture, in terms of decoration, was realized by eliminating decorations, treating decorations as extras, treating decorations as evil, and scraping them off. However, if decoration is to show a relationship with the outside world, modernist architecture would also create a decoration without decoration and try to create a relationship with the outside world, that is, society. be able to.
However, it can be said that since ancient times, people have been dressed in ornaments and built relationships with the outside world. It appears in architecture, but also in national costumes and festivals. For this reason, I think that the modern situation is that the decoration without decoration is impossible somewhere in terms of human mental health, and it is impossible to leave modernism at all.
そのものズバリと何かを表現する事には抵抗を覚える。そこに何かを読み取る部分があり、そこは読み取る側が自由に創造できるのがいい、それは創造であって、正解探しではなくて、つくり手がこうですと細部まで、こう解釈して、こう考えてとすると、つくり手の思惑通りの状況をつくり上げることができるだろうが、そうしたら、読み取る側は誰でもいいことになり、別に自分でなくてもいいことに誰も興味を持たないし、誰もそのようなことに魅力を感じないし、それを作品とはそういうものとみなすかもしれないが、それはガラスケースの中の美術品のようだが、読み取る側によって作品の解釈が自由に変化し、定まっておらず、人によってその時々で違う作品が出現したら、それには、そのものズバリというよりは、二次的に何かが現れることかもしれないが、不完全な部分が垣間見え、その部分に読み取る側が反応し自由に創造できる表現の方が良いと考えている。
"Incomplete reaction"
I feel reluctant to express something. There is a part to read something, and it is good that the reader can create freely. It is creation, not the search for the correct answer, the creator is like this. By doing so, it will be possible to create the situation as the creator's intention, but then everyone will be good for the reader, and no one is interested in not being myself, Nobody is attracted to such things, and you may think of it as a work, but it seems to be a work in a glass case, but the reading side freely changes the interpretation of the work, If it is not fixed, and different works appear from time to time depending on the person, it may be that something appears secondarily, rather than by itself, but there is a glimpse of the incomplete part. , Who represented the side that read in that portion can be freely creative reaction is considered to be good.
境界を線として扱うのではなくて、そこに厚みを持たせて、境界自体に太さや意味や中身が与えられたならば、ハッキリとした境目ではなくて、ゆるやかであったり、その境界自体に注目するよになったりして、全体を俯瞰した場合に、境界としての役目は以前として残るが、その境界にまた別の領域が発生することになるだろう。
境界は見えても見えなくても消せないが、境界を乗り越えて影響を与えたいと思う。だから、境界が空間同士の境目ならば、境界にも空間を与え、空間が空間同士を分け隔てるようにすれば、境界とは言え、空間同士のつながりとして考え、境界を乗り越えて何かの影響を表現できる余地が生まれる。
境界としての壁の厚みに注目し、厚みを拡大解釈して空間として考えてみる。その過程で、境界自体にバッファゾーンも含めて、空間を与えてしまうことも考えたが、現実には境界が壁として立ち現れることが多いので、より一般解を得られやすい事を考えてみた。
そうすると、壁自体の見え方に変化は無いが、境界自体が今までとは違う意味合い、例えば、ただ境界を受け入れることしかできなかったが、壁の厚みが空間として立ち現れるならば、その厚みはもしかしたら装飾のように扱えて、人の何かを表現するようになるのではないか、そうすると、装飾が空間として立ち現れて、人の何かと呼応するようになるのではないか、それは見てみたいと思えた。
"Thickness like decoration"
Instead of treating the boundary as a line, if you give it a thickness and give the boundary itself a thickness, meaning and content, it is not a clear boundary but a loose one, If you start to pay attention and look down on the whole, the role as the boundary will remain as before, but another area will be generated at that boundary.
The boundaries can't be erased by seeing or not seeing them, but I want to overcome and influence them. So, if the boundary is a boundary between spaces, if the space is given to the boundary and the space is separated from the space, it can be said that it is a boundary, but it can be considered as a connection between spaces, and some influence over the boundary The room to express is born.
Focusing on the thickness of the wall as the boundary, we will interpret the thickness as a space by expanding it. In the process, we considered giving a space including the buffer zone to the boundary itself, but in reality, the boundary often appears as a wall, so we thought that it was easier to obtain a general solution. .
Then, there is no change in the appearance of the wall itself, but the boundary itself has a different meaning than before, for example, you could only accept the boundary, but if the wall thickness appears as a space, the thickness will be Perhaps it can be treated like a decoration and express something of a person, and then the decoration appears as a space and responds to something of a person. I thought like
境界が重なり合う様に興味があり、その様を壁で表現できないかと考えている。その重なり合う部分は、境界が曖昧になり、境界が不完全なものになり、ひと手間加えないとハッキリとしない。だから、そこに人の何かしらの行為を誘発する状態が生まれる。
壁=境界なのか。そもそも境界をつくるために壁は存在し、境界が必要でなければ壁はつくらないだろうし、境界が必要でも壁をつくらない場合はありそうだから、全ての壁は境界ではあるが、全ての境界に壁は必要ではないというところか。
境界とすると線のようなイメージだが、壁には厚みがあるから、その厚みが厚くなればなるほど、境界としての存在は薄れていき、別の存在として重要になってくるような気がするが、以前として境界の役目は果たすだろう。
ならば、壁の厚みが厚く、そこに境界として別の役目が与えられた時、それは境界が重なり合う様と同じように、境界が曖昧になり、境界が不完全なものになり、ひと手間加えないとハッキリとしない、そこに人の何かしらの行為を誘発する状態が生まれる状況になるだろうと考えてみた。
"Thick wall"
I am interested in overlapping boundaries, and I'm thinking if I can express that with walls. In the overlapping part, the boundary becomes ambiguous, the boundary becomes incomplete, and it will not be clear unless it takes time. Therefore, a state is created that triggers some sort of human action.
Is the wall the boundary? Walls exist to create a boundary in the first place, and if a boundary is not needed, a wall will not be created, and even if a boundary is needed, it is unlikely that a wall will be created, so all walls are boundaries, but all boundaries are Is there no need for walls?
The boundary is an image like a line, but the wall is thicker, so the thicker the wall, the less the boundary will be, and it feels more important as another. As before, it will serve as a border.
Then, when the wall is thick and given another role as a boundary, it becomes vague and incomplete, as if the boundaries overlap, and takes extra effort I thought that it would be a situation that would not be clear without it, and that would create a state that would trigger some sort of human action.
装飾だけの空間をつくると、それは見た目では、その空間が何をするための場所か、そこで何をしたら良いのか、すぐに判別できなく、理解できない空間になるかもしれないが、それは、空間ではそもそも何かをする目的があって人工的につくられているからで、すぐに理解できず、判別できないならば、人の脳は足りない部分を補うために、過去の経験から想像したり、こうではないかと推察して、その空間での立ち振る舞い方を瞬時に決めるだろう。
きっとモダニズムの空間はこの理解ができず、判別できない状態を無くす方向に進展して来たように思う、曖昧な部分が無い、ある意味では違いや境界をハッキリとさせてきた。
そして、次の段階として、このハッキリとした違いや境界を残しつつ、その違いや境界に幅をもたせり、形を与えたりして、その違いや境界自体がより意味のあるものになっていき、そして、その違いや境界が変異していく。
そこで、改めて装飾が問わられることになる。その時の装飾は付加物では無くて、そこに構造や機能も包括され、さらには、人の関係性がより濃密になると考えている。
"Space just for decoration"
If you create a space just for decoration, it may be a space that you can not immediately understand and understand what the space is to do and what to do there, but it is a space In the first place, because it is artificially made for the purpose of doing something, if you can not understand immediately and can not distinguish it, the human brain can imagine from past experience to compensate for the missing part, I guessed this and would instantly decide how to behave in that space.
Surely, the space of modernism seems to have evolved in a direction that does not understand this and loses the indistinguishable state, has no ambiguous parts, and in a sense, makes the differences and boundaries clear.
Then, as the next stage, while leaving these distinct differences and boundaries, the differences and boundaries are given width and shape, and the differences and boundaries themselves become more meaningful. , And the differences and boundaries mutate.
Therefore, the decoration is asked again. The decoration at that time is not an addendum, but the structure and function are also included in it, and we believe that the relationship between humans will be deeper.
一文として、一言では無く、一言が連なり文章となるように空間を考えてみれば、そこに様々な展開を考えることができる。
ひとつの文章を叙情豊かにすることもできれば、説明や解説をするような文章や、翻訳のような文章にもできるように、空間も同じ、言葉を扱うように考えてみる。
ただ事実を説明するだけの文章ならば、簡単そうに思えるが、事実のどこに焦点を当てて文章を構成するかにより違いが出るから、それはそれで事実の見方が問われるし、叙情豊かな文章にするには、いくつか方法はあるだろうが、形容詞などの修飾語の選択や使い方が重要になる。
それを空間にも適用できると考えてみると面白い。文章だと形容詞などの修飾語と修飾される語の違いがはっきりとわかり、分解することもできて、当たり前だが取り替えも容易で、取り替えると全く違う印象の文章になるが、空間では、修飾語は装飾、装飾される語は骨組みとしたら、それらは一体で分解することはできず、容易に取り替えられないし、違いもプロならばわかるが、一般の人にはわからないだろう。なのに、建築を文章技法に例えて説明することがある。
例えば、修飾語だけ残して文章は成り立つだろうか、もしかしたら、意味は伝わるかもしれないし、会話ではしばしば、修飾語だけしか使わない場合があるけれど、やはり、文章としては曖昧な表現になり、正確な意味は伝わらないかもしれない。しかし、空間ではどうだろうか、修飾語だけ、装飾だけの空間が成り立つのではないだろうか、特に、店舗デザインの世界では、会話のような空間が成り立つだろうなどと考えてみた。
"Space like conversation"
If one considers a space so that one sentence is a series of sentences, not a single sentence, various developments can be considered there.
Think of words as having the same space, so that one sentence can be lyrical, one can explain or explain, or it can be a translation.
It may seem easy to just explain the facts, but it depends on where to focus the facts and compose the text. There are several ways to do this, but the choice and usage of modifiers such as adjectives is important.
It is interesting to think that it can be applied to space. If it is a sentence, the difference between a modifier such as an adjective and the word to be modified can be clearly understood, it can be disassembled, it is natural, but it is easy to replace, and if you replace it, it will be a sentence with a completely different impression, but in space, the modifier is If the decoration and the words to be decorated are a skeleton, they cannot be disassembled in one piece, cannot be easily replaced, and the difference can be understood by professionals, but the general public will not know. Nevertheless, architecture is often described as a writing technique.
For example, does the sentence hold with the qualifier alone, or perhaps the meaning can be conveyed, and in conversations, sometimes only the qualifier is used, but again, the sentence is vague, Meaning may not be transmitted. However, I wondered what would be the space, whether it would be a space consisting only of modifiers and decorations, especially in the store design world, where a space like conversation would be realized.
日常の様々な出来事が、良いことも悪いことも、雑多なことも、毎日描かれていく中で、ひとつの空間で捉えてしまうのは無理があると自然に思う。
それは、日常の様々な出来事を一言で言い表すようなもので、一言で言い表し、済ませようとしたら、その一言の抽象度を上げないと、その一言の範疇に日常の様々な出来事が含まれてこないが、抽象度を上げたら、その日常の様々な出来事をつくり出す人の個別性が無くなってしまい、その一言の具体度を上げていくと、日常の様々な出来事がこぼれ落ちていく。
その一言は空間にも例えることができて、ひとつの空間だけで、この場合、その空間が目指しているところも含むが、日常の様々な出来事を受け止めるには無理があり、無理があるのに、ひとつの空間で成り立っている理由は、人が空間に合わせているからで、人の個別性もねじ曲げられている。
ひとつの空間とは、ある指向性や趣向性を持った空間のことであり、そこには思想も含まれるが、一言では無くて、一言が連なり一文になっていれば、抽象度を上げる必要も無く、人が空間に合わせる必要も無く、日常の様々な出来事を受け止める空間、それは一文が一言より指向性や趣向性が弱くなり、その弱さ故に、一言の抽象度が上がるのと同じ効果が出て、人が空間に合わせなくても済むようなにできるのではないかと考えてみた。
"One sentence space"
It is natural to think that it is impossible to capture various events in everyday life, good or bad, miscellaneous things, in a single space as they are drawn every day.
It is like describing various everyday events in a single word.If you want to express it in one word and finish it, you need to raise the abstraction of that one word. Although it is not included, if you increase the level of abstraction, the individuality of the person who creates the various daily events will be lost, and if you increase the specificity of the word, various events of the everyday will fall down .
One word can be compared to a space, and there is only one space, in this case, the place that the space is aiming for, but it is impossible and impossible to catch various everyday events. In addition, the reason that one space is formed is that people are adapted to the space, and the individuality of the person is also twisted.
A space is a space with a certain directivity or taste, and it includes thoughts, but it is not a single word. There is no need to raise it, and there is no need for people to adjust to the space, a space that catches various everyday events. I wondered if this would have the same effect as above, so that people would not have to adjust to the space.
装飾がそのままの形のみで現れるから抵抗感がある。装飾とは付加物であり、京都大学柳沢研究室『装飾と住居』によると「装飾は秩序」だという。
外の世界との調整をはかるために装飾をして、自分の立ち位置を明確にする、そこで秩序立てる。この場合、目につきやすいのは装飾の見た目だが、そこには見た目だけでは部外者にはわからない、仲間うちの意味を持つ、一種の記号のように、約束事とも言える。例えば、服のファッションもそうだろ。
見た目だけの装飾では単なる形や色や柄のお披露目だけ、そこに興味は無く、その装飾が何と何を結びつけているのかなど、結果どうなるかの二次的な事、それが装飾としてデザインされている様が面白いと考えている。
今まで装飾もデザインの一種と考えて来たが、デザインが装飾の一種だと考えた方が自然のような気がして、そして、装飾をもっと拡大解釈し、機能をも取り込みたいと考え、それが成り立つ装飾の在り方を模索している。
"The way of decoration"
There is a sense of resistance because the decoration appears only in its original form. Decoration is an additive, and according to Kyoto University's Yanagisawa Laboratory "Decoration and Housing", "decoration is order".
Decorate to coordinate with the outside world, clarify where you stand, and order there. In this case, it is easy to see the decoration's appearance, but it is a promise like a sign that has the meaning of fellows who can not be understood by outsiders only by appearance. For example, the fashion of clothes.
In appearance decoration, it is just a presentation of shape, color and pattern, not interested in it, secondary things such as what is connected to the decoration, what is the result, it is designed as decoration I think that it is interesting.
Until now, we have considered decoration as a kind of design, but I think that it is more natural to think that design is a kind of decoration, and we also want to expand the interpretation of decoration and incorporate functions. We are exploring the way in which decoration can be achieved.
モダニズムは機能を発見し、分割し、配置することだとしたら、配置を変えたり、分割を変えたり、機能を見直したりすれば、モダニズムの延長で語ることができるし、変えたり、見直したりした事もすんなりと新しい事として受け入れやすいが、今まで気がつかなかった建築と人の関係性を築くことによって、機能が意味を持たない、重要ではないことにならないか、そうすると、見た目はモダニズムだが、中身はまるで違うものにならないかと考えている。
機能とは建築と人をつなぐ役目があり、機能が存在するから、人は建築の中でアクティビティを起こす、その場合、機能は人が人のことを考えて決めているように思うが、実際は建築が成立するように人にとって都合が良い機能を選択しているだけであり、建築の用途が先にある。
だから、機能は人を反映していないし、人は定められた機能に合わせているだけである。
この機能を意味が無いものにできれば、建築と人の新たな関係性が築ける。そこで、機能の対極にある「装飾」を使って空間を構成しようと考えている。それも装飾が建築と人をつなぐ役目をすることによって、新たな装飾の役割が二次的に登場しないかと、その可能性を視野に入れて考えている。
"Function and decoration"
If modernism is to discover, divide and arrange functions, if you change the arrangement, change the division, and review the functions, you can talk about, extend, and review modernism as an extension of modernism It's easy to accept things as new, but building relationships between architecture and people you didn't even realize would make the functions meaningless or insignificant. I'm thinking if it will be different.
Functions have the role of connecting architecture and people, and because functions exist, people initiate activities in architecture.In that case, it seems that functions are determined by thinking of people, but in reality, Only the functions that are convenient for human beings are selected so that the construction is realized, and the purpose of the construction is first.
So the function doesn't reflect the person, and the person just fits the defined function.
If this function can be made meaningless, a new relationship between architecture and people can be established. Therefore, we are trying to construct a space using "decoration" at the opposite end of the function. In addition, we are considering the possibility that a new role of decoration will appear secondarily by the role of decoration connecting architecture and people.
モダニズムのシャープなデザインが重なり合っていくと、それはシャープさを残したまま、野暮ったくならず、叙情豊かな、様々な解釈が可能な、複雑性を帯びたデザインになるのではないかと考えている。
重なり合い、混ざり合う状況は、純度の高いものが、段々とその純度を落としていく、シャープなデザインはそのシャープが失われていく。ただ、元々シャープであれば、その余韻を残したまま、純度が落ちていく。
そうすると、重なり合い、混ざり合う状況を上手くコントロールできれば、どのような表現もモダニズムのシャープを残したまま、モダニズムの延長線で可能になる。
野暮ったくない、シャープな重なり、さらに、直線の分割ではなく、入り乱れた分割にすれば、それはモダニズムを超えた新たなモダニズムの世界ではないかと考えてしまう。
"Modernism with reduced purity"
I believe that if the sharp designs of Modernism overlap, it will become a lyrical, multi-interpretable, complex design that retains sharpness, does not want to go wild.
In the situation of overlapping and mixing, those with high purity gradually lose their purity, and sharp designs lose their sharpness. However, if it is originally sharp, its purity will decrease while retaining its lingering sound.
Then, if we can control the situation of overlapping and mixing, any expression can be made an extension of Modernism, while keeping the sharpness of Modernism.
If you do not want to be sloppy, sharp overlap, and if you do not divide a straight line but make a complicated division, you will think that it is a new world of modernism that goes beyond modernism.
そのものよりも、何かを経て垣間見えるものに興味がある。装飾ならば、表に見える色や形や柄よりも、それが形成される過程に興味が湧くし、装飾の存在の仕方がまだ完全では無くて、何か足りなくて、何かが加われば成立するような不完全な状態に興味が湧く。
そのものズバリで完成された状態は、それはそれで完全無欠な様の完璧さに憧れと羨望感はあるが、例えば建築で言えば、インドのタージマハルは建築自体が最高峰の美術工芸品であるから、それ自体の美しさは素晴らしいのだが、一瞬で飽きる、あとは関心が無い。
あと少しその場で人が何かを加えると真の姿が現れるような事に惹かれる。
"Something is missing"
I'm more interested in something glimpsed through something than in itself. If it's a decoration, I'm more interested in the process by which it is formed than in the colors, shapes, and patterns that can be seen on the table, and the way the decoration is not yet complete, if something is missing and something is added I am interested in the imperfect state that holds.
The state completed in Zubari itself has a longing and envy of perfection of completeness. The beauty in itself is wonderful, but I get tired of it in a moment, and I have no interest.
I am attracted to the fact that when a person adds something on the spot, the true appearance appears.
装飾が装飾のまま現れる姿が一番わかりやすく、その見え方が装飾の価値を決めるのだろうが、建築の場合、装飾が装飾のまま現れると違和感があり、それは建築において装飾を排除したモダニズムが今でも根底にあるからだろう、いや、勝手にそう思い込んでいるだけかもしれないが、刷り込まれているだけかもしれないが。
ただ、そこで違和感がない装飾の仕方を見つけてみようとすると、装飾の見せ方も一次的な装飾そのものではなくて、二次的な装飾、それは一次の何か、形態なのか、何なのかの、そのもの同士の重なりの中に生まれる装飾、そこに確かに形態としての装飾はあるが、その装飾の受取り様は受け手によって皆違う、例えば、一次は普通によく見るモダニズムのデザインだが、その重なりが、制御可能ではあるけれども予測不可能な状態で存在する、それは重なりの境界を曖昧にすることかもしれないが、装飾と呼べてしまう状態をつくり出していれば、モダニズムのデザインに慣れ親しんだ者でも受け入れやすく、またそれは何か新しい装飾を纏わり付かせているようにも考えられるし、それは新しい見え方にもつながる。
"Secondary decoration"
The appearance of decorations as decorations is the easiest to understand, and how they look will determine the value of decorations, but in the case of architecture, if decorations appear as decorations, there is a sense of incongruity, which is a modernism that eliminated decorations in architecture Maybe it's still at the root, no, maybe it's just a self-assured thought, but maybe it's just imprinted.
However, if you try to find a way of decorating that does not make you feel uncomfortable, the way of showing the decoration is not the primary decoration itself, but the secondary decoration, which is something primary, form, or what. The decoration that is born in the overlap of the objects themselves, there is certainly a decoration as a form, but the way of receiving the decoration differs depending on the recipient, for example, the primary is a commonly seen modernist design, but the overlap is Exist in a controllable but unpredictable state, which may blur the boundaries of overlap, but create a state that can be called decoration, even if you are familiar with modernist design It's easy, and it also seems to have some new decorations around it, which leads to a new look.
見て所有して良いと思う物と、使って良いと思う物は、必ずしも一致しない。
使って良いのは、使いやすいという意味では無くて、見て所有して良いには、ブランドだから、評価されているからも含むが、視覚から得た情報が好みでも、手などの触覚から得た情報が好みで無いとか、その逆もあり、一致することの方が珍しいかもしれない。
物欲は、時として見た目の視覚からの情報に左右される。だから、どうでも良いと思っている物には、そもそも目もくれないから、物欲も起こらない。そして、物欲が起こると「痘痕(あばた)も靨(えくぼ)」状態になり、所有する喜びが先に来て、使っても良いと錯覚してしまい、自分の審美眼でさえも書き換えてしまう、困ったものだ。
だから、所有する喜びを捨ててみて、使う喜びに重点を置いて、使うところを想像して、そこに喜びや高揚感があれば良しとしている、最近の物欲まみれから離れるために。
"Pleasure to use rather than desire"
The things you see and possess and the ones you use are not always the same.
It does not mean that it is easy to use, but it is also a brand that is good to see and own because it is evaluated, but even if you like the information obtained from the eyes, you can get it from the tactile sense of your hands. It may be rare for the information to match because there is no preference for the information and vice versa.
Desire sometimes depends on visual information. Therefore, I don't have any lust because I don't have an eye for anything I don't care about. Then, when a desire arises, it becomes "pox (dimples)", and the joy of owning it comes first, making me illusion that I can use it, and even rewriting my own aesthetic sense. I'm in trouble.
So, let's throw away the joy of owning, focus on the joy of using it, imagine the place to use it, and if there is joy and elation, it would be nice to get away from the recent desires.
オーバーラップのところに装飾がある、それがデザインの考えどころか、オーバーラップとは日常と建築の接点であり、そこに装飾がある。
服にしても、建築にしても、日常との関係を表現するために装飾があり、装飾が関係性を表現している。どのように装飾するかは、どのように自分を取り巻く世界を見ているか、その世界に対する態度表明でもある。
装飾が無いという装飾も成り立つから、装飾があるのが当たり前、全てに装飾があり、この世界は装飾で満たされていると考えると、装飾自体が機能やアクティビティを担保する可能性もあり、そうすると、装飾だけで建築をつくることも可能になるのではないかと考えている。
"Make only with decorations"
There is decoration at the overlap, which is not a design idea. Overlap is the contact point between everyday life and architecture, and there is decoration there.
In clothes and architecture, there are decorations to express the relationship with everyday life, and the decoration expresses the relationship. How to decorate is also an expression of how you look at the world around you and your attitude toward that world.
It is natural that there is no decoration, so it is natural that there is decoration, everything has decoration, and if you think that this world is filled with decoration, decoration itself may secure functions and activities, I think that it will be possible to make architecture only by decoration.
装飾は不可欠なもの、必ず存在する。装飾が無く、シンプルにしているようで、それは「装飾しない」という装飾の一種だから、そう考えると世の中は装飾に溢れている、それを自然な形で見せるのがいいなと思ってしまう。
装飾はデザインか、デザインと装飾の違いは何とか考えていたら、区別は無いなと。
普段デザインを考えているようで、実際は装飾を考えているのか、それならば装飾として、装飾を意識をして、装飾を考えるようでいいのだとしたらどうなるだろうか、その方が人と建築をつなげることができるのではないか、それで良いとして考えてみる。
今まで気づいているようでスルーしていたことに気がついたら、それが装飾だった、それがまた良い、どうしようと頭をずっと悩ましていた、今日一日、もういたたまれない気持ち、今日は心象に浸った日だった。
"How to decorate"
Decoration is indispensable and always exists. It seems that there is no decoration and it is simple. It is a kind of decoration that "does not decorate", so when you think about it, the world is full of decorations and I think it is better to show it in a natural form.
If you think about the decoration as a design or the difference between a design and a decoration, there is no distinction.
It seems that you are usually thinking about design and you are actually thinking about decoration, so if it is good to think about decoration as decoration, what if it is OK to think about decoration? Let's think that it can be connected, and that's good.
When I realized that I was aware of it and I was through it, it was a decoration, it was good again, I was struggling my head all the time, I felt irresistible one day today, I was immersed in the image today It was a day.
身近なところで「装飾」というと、着飾るための服がある。京都大学柳沢研究室『装飾と住居』によると「装飾は秩序」だという。
身に付ける服は、自分と外の世界を繋げて調整してくれるのもののひとつで、自分がこれから行こうとする場所に合わせて洋服を選択する行為は、すでに服が調整役であり、繋げ役であり、服そのものが外の世界での秩序をもたらすものになっている。
また「装飾」が自分と外の世界を繋げて調整してくれる存在ならば、日常とどのような関係性を築くかが装飾になる。だから、装飾には日常が現れる、その装飾で空間ができあがれば、その空間は日常を反映する。日常が人の気分や感情で成り立っているならば、その空間は人の気分や感情を反映するだろう。
などと考えていくと「装飾」にはまだまだ可能性があると思ってしまう。

"Possibility in decoration"
When you say "decoration" in your immediate surroundings, there are clothes to dress. According to the Yanagisawa Laboratory of Kyoto University "Decoration and Housing", "decoration is order".
Wearing clothes is one of the things that connects and coordinates the world with the outside world. It's a role, and the clothes themselves bring order to the outside world.
Also, if "decoration" exists to connect and coordinate with the outside world, what kind of relationship with everyday life is decoration. Therefore, everyday life appears in the decoration. If the space is created by the decoration, the space reflects the daily life. If everyday life is made up of people's moods and feelings, the space will reflect people's moods and feelings.
I think that "decoration" has more possibilities.
建築空間は機能から自由になれないと、人の気分や感情を反映することはできない。それは、機能には人の気分や感情が含まれないから、機能によって決められた建築空間では人の気分や感情を反映できない。
別に気分や感情を反映できなくても良いが、建築を人との関係性の中で考えようとしたならば、どうしても気分や感情が絡んでくる。人は当たり前のように日々、気分や感情の振幅の中で生きているから、それに対しての建築の在り方は問われる部分だろう。
ところが、機能と切っても切れない関係性の建築空間では、人の気分や感情の扱いは疎かになるというか、登場して来なくなるし、そもそも扱えない、言説だけで扱ったような気分にはなれるが。
だから、建築空間と機能を切り離すために「装飾」に目をつけた。
"Feature ≠ Feeling"
If the architectural space cannot be freed from its functions, it cannot reflect people's moods and emotions. Because functions do not include human moods and emotions, the architectural space determined by the functions cannot reflect human moods and emotions.
You don't have to be able to reflect your mood and emotions, but if you try to think about architecture in a relationship with people, you will inevitably have moods and emotions involved. People live in the amplitude of mood and emotions every day, so it is a matter of course how architecture should be addressed.
However, in an architectural space that has an inseparable relationship with function, people's moods and emotions are treated sparsely, or they do not appear, and they can not handle them in the first place. I can peel off.
Therefore, I focused on "decoration" to separate the function from the architectural space.
空間と機能が切り離せないならば、空間がどうなれば機能と切り離すことができるかと考えてみる。そうなると、空間又は建築と関連性があり、尚且つ、機能とは関連性が無いことを探してみる。ひとつ思い浮かんだのが「装飾」、装飾ならば空間又は建築と関連性があり、尚且つ、機能とは関連性が無いとすることができる。
装飾と機能ならば切り離すことができる、そうすると、空間=装飾として扱えば良くなる。
装飾は本来、元があっての付加物のように考えてしまうので、装飾そのものが空間になるようなイメージが湧きにくいが、例えば、コルビュジエ のロンシャンは装飾そのものが空間を成していると言えなくもないような気がし、その空間がたまたま教会だったと、勝手な解釈をしても許されそうな気がする。ならば、装飾そのものが空間になるようなイメージもできなくはない。
装飾ならば、機能性どころか、建築計画学的な効率性からも離れることができるかもしれない。次は装飾の内容について考察してみる。
"Space = decoration"
If space and function cannot be separated, think about how space can be separated from function. Then, look for something that is relevant to space or architecture, but not functional. One thing that came to mind was "decoration". If it was a decoration, it could be related to space or architecture, and not related to function.
If decoration and function can be separated, then it can be treated as space = decoration.
Originally, decoration is considered as an addition to the original, so it is difficult to imagine that the decoration itself is a space.For example, Corbusier's Longchamp can be said that the decoration itself forms a space. I feel like there is no end, and if the space happened to be a church, I feel it would be forgiven even if I interpreted it without permission. Then, it is not impossible to imagine the decoration itself as a space.
With decoration, it may be possible to move away from functionality as well as architectural efficiency. Next, let's consider the contents of the decoration.
空間を考える時に機能を優先してしまう、それは当たり前なのかもしれない、その空間は何のために存在するのか、事業であれば尚更、そうでも無くても、例えば森でテントを張って空間をつくる時でさえ、その場所での滞在中に行うことを考えてテントを張るだろうから、その考えることはそこでの機能性を高めること、すなわち、その場所で行う機能は何かを考え優先することになるから、どのような場合でも空間と機能は切り離しはできない。
ならば、空間と機能を切り離して、もし仮に考えることができたならば、また違った空間を創出できる、少なくとも言葉上はその可能性がある。
ただ、イメージが追いつかない、空間と機能を切り離すことがどういうことか、例えば、機能を定めていない空間をつくろうとすると、すでにそれは「機能を定めない」という機能性を持った空間になってしまうので本末転倒になる。
先程のテントの話で言えば、自然の森は機能とは無縁の存在で成り立っているが、人工の森は「機能を定めない」という機能性を持った空間になってしまう、人の手が入るとはそういうことか、機能も無く何かを創出できないということか、などと外出したくない日の戯れこと。
"Is it an inseparable function?"
When thinking about space, giving priority to functions, it may be natural, what is the space for, even if it is a business, even if it is not, for example, setting up a tent in a forest and setting up a space Even when you make it, you will put up a tent to think about what you do during your stay in the place, so that thinking enhances its functionality, that is, gives priority to what the function you do in the place Therefore, space and function cannot be separated in any case.
Then, we can separate space and function, and if we can think about it, we can create another space again, at least in words.
However, what does it mean to separate the space from the function that the image can not catch up with? For example, if you try to create a space where the function is not defined, it will already be a space with the functionality of "undefined function" So it will fall.
Speaking of the tent I mentioned earlier, natural forests are made up of nothing to do with functions, but artificial forests become spaces with functionality that does not define functions. Entering is that kind of thing, or that you can't create something without functions, and that you don't want to go out.
形はキライなのに、大きさ、スケールが変わると良いと思ったり、キライな形だけれどもある一部が良くて、そこが引き立て役になり、それを良いと思ってしまう。
物欲との戦いで、ひとり考えながら、自分にとって何が良いのかを捏ねくり回しながら探っている行為自体が一番デザインの学習になるかもしれない。
自分でつくり出す以外に完璧だと思う形や物はなかなか無いし、例え自分でつくり出そうとしても完璧な形には、制約や理解不足で辿り着けないかもしれないが、与えられた知識や見聞で優劣を判断したくは無いから、自分で試行錯誤するしかない、当たり前だとしていることも時にははじめから構築することもしないと、それは時間もかかり、厄介だが、そうしないと丸腰でも戦える気がしない。
などと1日考えていたら歯医者の予約をすっぽかしてしまったが、物の良し悪しの尺度は変わるもので、ちょっとした見方の違いに気づいたり、気づかされたりしただけで、キライな物まで好きになってしまうようだ。
"Dislike favorite things"
I hate the shape, but I think it would be nice to change the size and scale, or I don't like the shape, but some of the shape is good, and that helps me, and I think it's good.
In the fight against greed, the act of thinking and thinking about what is good for me while searching for it may be the best way to learn design.
There are few shapes and things that I think are perfect other than my own, and even if I try to create my own, I may not be able to reach the perfect shape due to constraints or lack of understanding, but given the knowledge and hearing I do not want to judge the superiority, so I have to do trial and error myself, if I do not make it obvious or sometimes from the beginning, it will be time-consuming and troublesome, but otherwise I feel like I can fight even if I am not do not do.
If I thought about it for a day, I made a reservation at the dentist, but the scale of good and bad things changes, and I just noticed a slight difference in viewpoint and noticed it, I like things I dislike It seems to be.
人の気分や感情など、内にあり一見外からはわからないようなことが影響して、見え方やデザインが変われば、それが人との関係を築く上で一番良いデザインだと考えている。
内在しているものが、何かを介して、外に現れてくる。その何かが建築であったり、デザインであったりすれば良い。
建築やデザインが人に影響を及ぼして、人の気分や感情が変わることはよくある。素敵なデザインやお洒落な空間に身を置けば、気分も晴れやかになるだろう。
その逆はほとんど見ない。日常の中では素敵なデザインやお洒落な空間の方が圧倒的に少なく、内なる人の気分や感情は日常的に起こる。ならば、その内なる人の気分や感情に焦点を当てて、それが影響を与えることによって変わる建築やデザインを見てみたいものだと素直に思った。
"Focus on mood and emotions"
If the appearance or design changes due to things that are inside and seemingly invisible from the outside, such as the mood and emotions of the person, I think that it is the best design to build a relationship with people .
What is inside comes out through something. It just needs to be architecture or design.
Architecture and design often affect people and change their moods and emotions. If you put yourself in a nice design and a stylish space, you will feel refreshed.
The opposite is rarely seen. In everyday life, there are overwhelmingly few nice designs and stylish spaces, and the mood and emotions of the inner people occur on a daily basis. Then I thought I would like to focus on the mood and emotions of those people and see the architecture and design that change as they affect it.
外と内で、すでに重なりがあり、そこでは当然、内と外でちがう様相を呈しており、仕上材ひとつとっても違い、そこで要求される性能も違い、当然意匠も違う、壁の話である。
例外はコンクリート打放しの壁、外も内も区別が無い。だが、建築家の安藤忠雄はコンクリート打放しの壁だけれども、その壁を外だとみなした場合はPコンの穴を埋め、内だとみなした場合はPコンの穴を埋めないことをしていた。確か、時には内だけどPコンの穴を埋めている場合があり、その空間を安藤忠雄は内だけど外だとみなすこともしており、その逆の場合も目撃したことがある。
コンクリート打放しの壁は内外同じ様相の意匠にできるので、ミニマムな空間や、シンプルな空間や、空間という場を重視する時の意匠、あるいは型枠をつくり成型するので、塊としての造形的な意匠には適しているが、別の見方をすると、成型して塊にした壁を内外の境界としてつくるだけなので、その塊に壁以上の意味や解釈を仕込むことは難しい気がする。
幾重にも重なり様々な解釈や意味を投影できる壁をつくるには、その構法的な成り立ちもデザインの範疇となりそうだ。
"Construction is also a category"
There is already an overlap between the outside and the inside, and there is, of course, a different appearance between the inside and the outside. This is a story of a wall where the finishing material is different, the required performance is different, and the design is naturally different.
The exception is bare concrete walls, where there is no distinction between inside and outside. However, Tadao Ando, an architect, is a concrete bare wall, but fills the hole of P-con if it considers the wall to be outside, and does not fill the hole of P-con if it considers it to be inside. Was. Certainly, sometimes it is inside, but sometimes it fills the hole in P-con, and Tadao Ando considers that space to be inside but outside, and has witnessed the opposite case.
Since the exposed concrete wall can be made the same design inside and outside, it is a minimal space, a simple space, a design that emphasizes the space, or a formwork that is molded and molded, so it is a solid design as a lump From a different point of view, it seems that it is difficult to add meaning and interpretation beyond the wall to the block, because it only creates the wall formed into a block as the inside and outside boundaries.
In order to create a wall that can overlap and project various interpretations and meanings, its constitutional structure is likely to fall into the category of design.
コルビュジエの初期の作品では、ピュリスムの絵画の特徴であるモチーフの重なりの要素は無いように思えるが、後期の作品、特に、ラトゥーレット修道院では重なりの要素を感じる。
一言では、一見しただけでは理解し難い建築だった。その建築を理解しようとする姿勢もどうかと思うが、あまりにもわかりそうでわかりにくい、でも、何かわかりたい衝動みたいなものがあり、それはラトゥーレット修道院に宿泊したからだろうか、あの暗闇の恐怖を経験したからだろうか、朝になり全体像が見えた時のあちらこちら問いかけてくる、投げかけてくるデザインの波に押し流されないように必死で抵抗しつつ、その一つ一つを全てを理解しようとしていた。
今から振り返れば、たくさんの重なりが、それが絵画のモチーフのような様々な造形が、様々な要素が見え隠れしながら、今そこにいる自分の立ち位置によって受ける印象が違うくらいに複雑な建築空間だった。
それがモダニズム建築とピュリスム絵画の融合の果てだと考えると妙に納得してしまう。
"End of fusion"
Corbusier's early works seem to lack the overlapping elements of the motifs that are characteristic of Purism's paintings, but in later works, especially the La Tourette monastery, they do.
In short, the architecture was hard to understand at first glance. I don't know how to try to understand the architecture, but it seems too obvious and difficult to understand, but there is something like an impulse to understand, probably because I stayed at La Tourette Monastery, that fear of darkness Perhaps because of the experience, I asked everywhere when the whole picture was seen in the morning, I understood each and every one of them while desperately resisting being washed away by the waves of the design that was thrown I was trying.
Looking back now, there is a lot of overlap, a variety of forms such as painting motifs, various elements can be seen and hidden, and the architectural space is complex enough to give a different impression depending on where you are right now was.
It is strangely convinced that this is the end of the fusion of modernist architecture and purism painting.
午後は近代建築五原則を唱えてモダニズム建築を設計し、午前はピュリスムの絵画を描く、コルビュジエはピュリスムの絵画を描きながら、それは新たな建築空間の習作であり、それは絵画の世界から建築の世界を見つめ直して、午後に新たなモダニズム建築を構想していたのであろう。
コルビュジエの頭の中ではピュリスムからモダニズムへという流れができており、それは一見すると相違しているように思ってしまうが、仮に同一、あるいは同一の部分が多いとして考えてみると面白い。
ピュリスムの絵画の特徴である、モチーフが重なり、そのモチーフの輪郭線だけが強調されたり、意味を持ってくる様と呼応する部分がモダニズム建築にはあるのだろうかと考えてしまう。
モダニズム建築は確かに、水平垂直や外観の輪郭は強調されるが、そこに重なりの要素は無いように思う。そこは未だに気づかない部分があるのかもしれない。
"See the overlap"
In the afternoon, we design modernist architecture by advocating the five principles of modern architecture, and in the morning, we draw a painting of Purism. It was likely that he had reconsidered and planned a new modernist architecture in the afternoon.
In Corbusier's head, there is a transition from purism to modernism, which at first glance seems to be different, but it is interesting to think that it is the same or that there are many identical parts.
I wonder if there is a part of modernism architecture that overlaps with the motifs that are the characteristic of the painting of Purism, and emphasizes only the outlines of the motifs, or responds to bringing meaning.
The modernist architecture certainly emphasizes the horizontal and vertical and the outline of the appearance, but I think there is no overlapping element there. There may be parts that have not yet been noticed.
デザインが幾重にも折り重なる姿はあまり見たことが無いので、なかなかイメージができないが、コラージュの技法を使った絵画を思い浮かべて、その一つ一つがデザインされたものだとしたらイメージがしやすい。
ピュリスムの絵画も、例えばコルビジェの絵画も、モチーフの重なり具合で画面を構成し、そのモチーフの重なりの輪郭線だけを抜き出して、そのモチーフ自体もそもそも平面化されており、輪郭線だけがまた別のモチーフになっていたり、別の意味をつくり出していたりするので、このモチーフもデザインされたものだとしたら、またコラージュとは違った折り重なり具合をイメージできる。
コラージュもピュリスムも平面化された画面構成をしており、それは簡単に言うと、陰影がはっきりとした立体感を出す絵画に対する新しい試みだった。モチーフに陰影をつけて奥行き感を出すのでは無くて、モチーフ自体を幾重にも折り重ねてモチーフの存在に意味合いという奥行きを付けていった。
コルビュジエは、ピュリスムの表現技法を建築に用いて、内部空間を構成していた。午前はアトリエで絵を描き、午後は事務所で建築の設計をしていたというコルビュジエ にとって、午前のピュリスムの絵を描く時間は建築の実験をしていたのだろう。
重なりの輪郭だけが浮き出たような内部空間を有するコルビュジエ設計のパリのラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸は、その内部空間に身を置くと、その輪郭に沿うようなアクティビティが自然に起こるような感じがした。それは、その輪郭と人の関係性が密接だからであろう。
ただ、そのラ・ロッシュ=ジャンヌレ邸を体験しているからこそ、きっと実現したい内部空間は輪郭という線では無くて、壁という面を用いて、もっと建築と人が呼応し合うものにならないかと考えてしまう。
"Resonate with each other"
I haven't seen any of the designs that fold over and over, so I can't easily imagine the image. However, if I think of paintings that use collage techniques, and if each of them is designed, it's easy to imagine.
Both the paintings of Purism and, for example, the paintings of Corbigier, compose the screen based on the degree of overlap of the motifs, extract only the outline of the overlap of the motif, and the motif itself is originally flattened, and only the outline is another Motifs or create different meanings, so if this motif is also designed, you can imagine how it folds differently from a collage.
Both the collage and the purism have a flattened screen composition, which, in short, was a new attempt at painting with clear shadows and a three-dimensional effect. Instead of shading the motif to give it a sense of depth, the motif itself was folded over and over to add depth to the existence of the motif.
Corbusier used purism expression techniques in architecture to compose the interior space. For Corbusier, who painted in the atelier in the morning and architectural design in the office in the afternoon, the time of painting the Purism in the morning would have been an architectural experiment.
La Corcheier-designed La Roche Jeannelet's house in Paris, which has an interior space where only the outline of the overlap emerges, when you put yourself in that interior space, it seems that activities along the outline occur naturally. did. The reason is that the relationship between the contour and the person is close.
However, just because I experienced La Roche-Jeanneret's house, I wondered if the interior space I wanted to realize would not be a line of contour, but a wall that would make architecture and people interact more Would.
空間がストラクチャー以外の要素で成り立つならば、そこは厳密に言うと、ストラクチャーがないと空間は成り立たないが、ストラクチャー以上の強度を持って空間を成り立たせる要素が存在するならば、ストラクチャーの存在を消すことができるので、その状態はストラクチャー以外の要素で空間が成り立つとしても良いだろう。
そのストラクチャー以上の強度を確保するために、人との密接な関係を築く。要するに、空間を認識する側の人との関係性で成り立つ空間になると、その空間ではストラクチャーの存在が消える。
それでは、ストラクチャー以上の強度を持って空間を成り立たせる要素を何にするか、今考えているのは「壁」及び「壁に付随するもの」である。壁ならば、物理的に消すことができないストラクチャーをも包括することができ、その包括の仕方に、空間を認識する側の人との関係性を折り込むこともでき、空間を人が自身の手中で扱えるデザインとして構成できる可能性が生まれるからである。
"Folding relationships into walls"
If space consists of elements other than structure, strictly speaking, space does not hold without structure, but if there is an element that makes space more strong than structure, the existence of structure exists. Since it can be erased, its state may be good if space is made up of elements other than structure.
Establish a close relationship with people to ensure the strength of the structure. In short, when a space is established based on the relationship with the person who recognizes the space, the existence of the structure disappears in that space.
Now, what are the elements that make up space with more strength than the structure is what we are thinking about, "walls" and "things attached to walls." Walls can include structures that cannot be physically erased, and can include relationships with people who recognize the space in the way they are included. This is because there is a possibility that it can be configured as a design that can be handled by.
ストラクチャーを消すけれど、そこに現れるのは装飾ではなくて真の姿となるように。
建築を人が自身の手中で扱えるデザインで構成しようとすると、ストラクチャーの存在を消す、あるいは、ストラクチャーをデザイン要素として扱わないようにする。
それは、人が自身の手中で扱えるデザインと、建築のように人のスケールを超えて存在するデザインの違いで、一番大きいのがストラクチャーの有無だから。
ただ、ストラクチャーは建築が建築として存在するためにはなくてはならないものでもあるし、ストラクチャー自体が現実にそこに建築があることの証明にもなっているので、その存在を消すと残るのは建築と称してストラクチャーに纏わりついていた装飾だけになる。
その装飾は、建築の真の姿を表現していないし、すでに建築では無い。それは単なる造形遊びの成れの果てである。
それを回避するためには、ストラクチャーを消した後に残るものが人と密接に関係を有していれば良く、さらに、それが空間の構成要素であれば、それを「建築」だと強引にしてしまえば良い。そして、人と密接な関係があるのだがら、それを「真の姿」だと、あるいは、今まで気がついていなかった別の「真の姿」だとしてしまえば良い。
"True figure"
Eliminate the structure, but make it appear as a true figure, not a decoration.
When trying to construct an architecture with a design that can be handled by one's own hands, the existence of the structure is erased, or the structure is not treated as a design element.
The difference between a design that people can handle in their own hands and a design that exists beyond the scale of people, such as architecture, is the biggest thing because of the presence or absence of structure.
However, the structure is indispensable for architecture to exist as architecture, and the structure itself is also a proof that there is actually architecture, so if you erase that existence, it will remain It is just the decoration that was tied to the structure, called architecture.
The decoration does not represent the true form of architecture and is no longer architecture. It is the end of mere modeling play.
In order to avoid this, it is only necessary that what remains after the structure is erased has a close relationship with people, and if it is a component of space, it must be forcibly called "architecture". Just do it. And if you have a close relationship with a person, you can call it a "true figure" or another "true figure" you haven't noticed before.
他の分野からデザインのヒントを探そうとしている。人が自身の手中で扱えるデザインと、建築のように人のスケールを超えて存在するデザインでは全く違う。建築を人が自身の手中で扱えるデザインで構成したいと考えている。
それができれば、より建築が人と密接に関係してくるだろうから。
まず最初に考えたことはストラクチャー、人が自身の手中で扱えるデザインと、建築のように人のスケールを超えて存在するデザインの違いで、一番大きいのがストラクチャーの有無、建築は明確にストラクチャーが存在する、もっと言うと、ストラクチャー自体がデザイン要素として重要である。
だから、人が自身の手中で扱えるデザインとするために、ストラクチャーの存在を消す、ストラクチャーをデザイン要素として扱わないように考えている。
"Erase the structure"
I'm trying to find design tips from other fields. A design that people can handle with their own hands is completely different from a design that exists beyond the scale of people like architecture. I want to construct the architecture with designs that people can handle with their own hands.
If we can do that, architecture will be more closely related to people.
The first thing I thought about was the difference between structure, a design that people can handle with their own hands, and a design that exists beyond the scale of people like architecture, the biggest thing is whether there is a structure, the architecture is clearly a structure The structure itself is important as a design element.
Therefore, in order to make a design that people can handle with their own hands, we try to eliminate the existence of structures and do not treat structures as design elements.
フリーカップを制作中、毎朝、豆から挽いてコーヒーを淹れる際に、その日の気分でコーヒーカップを選ぶので、その選択肢のひとつにしようと思って。気分で選ぶ、その楽しさ、身勝手さみたいなものをデザインできたら面白いと。
飲み口の厚みを不連続に変化させ、その日の気分で飲み口を選ぶと、非対称のカップだから、カップの見え方も変わる。気分が直接カップの見え方まで左右する。そして、その非対称な形故に、カップに液体が注がれてはじめて安定して鎮座する。
そのフリーカップ自体は常に不完全であり、使われてはじめて完全な姿を成す。そこでは、物と人の関係性をデザインに取り込みたかった。そうすることが物単体の価値を超えた、人にとっての価値ある物をつくることにつながると考えたから。
さて、それを建築で実現しようと考えている。しかし、人が自身の手中で扱えるデザインと、人のスケールを超えて存在するデザインで、これほど相容れないものかと、建築ではさらに何かが必要だと考えあぐねる。
"Thinking"
While making a free cup, every morning when I grind from beans and brew coffee, I choose a coffee cup according to the mood of the day, so I decided to make it one of the options. It would be interesting if you could design something that was fun, selfish, and so on.
If you change the thickness of the spout discontinuously and select the spout according to the mood of the day, the appearance of the cup changes because it is an asymmetric cup. The mood directly affects how the cup looks. And, because of its asymmetric shape, the liquid is poured into the cup, and the liquid is stably settled.
The free cup itself is always imperfect, and will only be complete when used. There, I wanted to incorporate the relationship between things and people into the design. I thought that doing so would lead to creating something valuable for people, beyond the value of the substance alone.
Well, I'm thinking about realizing that with architecture. However, he argues that there is something more needed in architecture, whether designs that people can handle in their own hands and designs that exist beyond the scale of humans are so incompatible.
ルイス・サリヴァンが「形態は機能に従う」と説いた。今だに有効な言説だと思うが、それをそのまま言われると違和感がある。
たくさんの機能が折り重なり、同時に存在し、その中から、その時々で必要な機能を選択するように発見していき、その選択が建築の見え方に影響を与えるような不均質空間をつくろうとする時、「形態は機能に従う」よりは「機能は形態に従う」方がしっくりくるように思う。
もうその形態ならば、そう行動するしかないじゃないか、機能はアクティビティを誘発するものだから、形態=機能でアクティビティが起こるが、人は視覚情報にまず反応する、要するに見た目、そうすると、見た目で分かりやすいのは機能より形態、だから、見た目の形態で機能を判断し、アクティビティを起こす。
見た目のアフォーダンスが機能を瞬時に理解させることもあるが、そのアフォーダンスも形態の一種だと考えている。
したがって、たくさんの機能の折り重なりは、形態によって表現し、その形態の中からか、又は、その形態そのものを選択するから、その時々で建築の見え方が変わり、その様はどう考えても均質空間では生まれないから、不均質空間と成す。
"Function follows form"
Louis Sullivan stated, "Form follows function." I think it is still a valid discourse, but if you say it as it is, it feels strange.
Many functions overlap and exist at the same time, and we try to find the necessary function from time to time, and try to create an inhomogeneous space where the selection affects the appearance of architecture. When I do, I think that "function follows form" is better than "form follows function".
If it is already in that form, it is necessary to act so, because the function induces the activity, the activity occurs in the form = function, but the person reacts first to the visual information, in other words, it looks like, so it can be understood by the appearance Because it is easier to form than function, it is easy to judge the function in the form of appearance and activate the activity.
Affordances can make a function understandable instantly, but I think that affordance is a form of form.
Therefore, the overlapping of many functions is expressed by the form, and from among the forms or the form itself is selected, the appearance of the architecture changes from time to time, and even if you think about it like that, Since it is not born in space, it is a heterogeneous space.
たくさんの解釈が折り重なり、同時に存在し、その中から選択するように発見していく不均質空間をつくろうとすると、その場合、解釈は1対1の対応では無くて、そこに重なり、それも前後に奥行きのある複数の解釈が重なり合っている状況をつくり出すことになる。
とりあえず「解釈」を別の言い方にしてみて「機能」とすると、たくさんの機能が折り重なり、同時に存在し、その中から、その時々で必要な機能を選択するように発見していき、その選択が建築の見え方に影響を与える。
そうすると今度は「選択」について考察したくなる。
"Selection of functions"
If you try to create an inhomogeneous space where many interpretations overlap, exist at the same time, and discover to choose from among them, then the interpretations are not a one-to-one correspondence, but overlap, It creates a situation where multiple interpretations with depth before and after overlap.
For the moment, if you try to interpret "interpretation" in another way and say "function", many functions overlap and exist at the same time, and from among them, discover that you need to select the function you need at each time Affects the appearance of architecture.
Then, I want to consider "selection".
日常の出来事が様々に形を変えて出現する空間をつくるとすると、壁から様々なものが飛び出してくるような、壁が開き中から様々なものが移動してくるような空間をすぐに思い浮かべてしまうが、それは確かに建築的な解釈に沿ってはいるが、メタボリズム的な匂いもするが、それは事象として可変することに重きが置かれており、可変した様が今までの建築の見え方と同じならば、単なるサーカスやマジックに過ぎず、ショーとしては面白いかもしれないが、空間としてはつまらないというか、何も新しいものを生み出せてはいないので、わざわざやるようなこととは思えない。
可変するよりも、心象によって事象が変化したように見えることの方が建築らしいような気がする。きっとその建築らしさのようなことは、可変する装置のような建築に対する刷り込まれた違和感から来るのだろう。
"Variably uncomfortable"
If you create a space where everyday events change shape and appear, you can immediately imagine a space where various things jump out from the wall, and various things move from inside the wall. Although it certainly conforms to the architectural interpretation, it also has a metabolic smell, but the emphasis is on changing as an event, and the appearance of the change is the If it's the same, it's just a circus or magic, and it might be interesting as a show, but it's boring as a space, or it doesn't seem to bother you because it doesn't create anything new. .
It feels more like architecture that the phenomenon seems to have changed depending on the image than it can change. Surely, the architectural nature comes from imprinted strangeness to the architecture, such as a variable device.
たくさんの解釈が前後に折り重なり、重層し、どの解釈を選択するかにより、意味が変わり、その選択は作者では無く、使う側が行う。よって、そこで実現される日常は作者の意図の範疇でありながら、様々なバリエーションが存在し、そこに使う側のアクティビティや心象が加われば、唯一無二の空間ができ上がる。
前後に折り重なる様には空間性が内在しているから、これらの言葉を空間化できる。
それは決して特異な空間ではなく、日常が様々に形を変えて出現する空間になるだろう。だから、その日常をどのように設定するかによって、特定の個人に対しても、不特定の多数にも対応できる。
"Fold back and forth"
Many interpretations wrap around and stack, and the meaning depends on which interpretation you choose, and the choice is made by the user, not the author. Therefore, although the daily life realized there is in the category of the author's intention, there are various variations, and if activities and images of the user are added to it, a unique space is created.
These words can be spatialized because there is an inherent spatiality that folds back and forth.
It will never be an unusual space, but a space where daily life will appear in various forms. Therefore, depending on how the daily life is set, it is possible to deal with a specific individual or an unspecified large number.
たくさんの解釈が折り重なり、同時に存在し、その中から選択するように発見していく不均質空間をつくるとすると、最初に思いついたのが最小限住宅である。
最小限のスペースしかないから、そこにたくさんの機能を効率良く配置し、建築家の清家清、池辺陽などが、あと、安藤忠雄も思い浮かぶが、必要な機能がキュッと凝縮されて詰め込まれているイメージがある。
ただ、それでは、たくさんの中から選択していく感じにはならない。スペースが最小限であるから効率性を高めるために機能をたくさん折り重ねるかと考えたが、そうではなくて、機能のムダを省いて最小限のスペースを実現しているようだった。
たぶん、スペースがあるかないかは関係が無いのだろう。
"Space doesn't matter"
If we create a heterogeneous space where many interpretations overlap, exist at the same time, and discover to choose from among them, the first thing we came up with is a minimal house.
Since there is only minimal space, many functions are efficiently arranged there, and architects Kiyoshi Seike and Yo Ikebe, and Tadao Ando also come to mind, but the necessary functions are packed tightly and packed. There is an image that is.
But that doesn't make me feel like choosing from many. The space was minimal, so I thought I'd fold a lot of features to increase efficiency, but instead, it seemed that the feature was wasted to minimize space.
Maybe it doesn't matter if there is space.
予め何をするかが決まっていない空間を設計してみようと考えてみると、簡単そうで案外難しい。
ユニバーサル・スペースのような空間の設計をすることは一般的によくある。限定せずに自由に使えるスペースとして、建築家のミースの空間を例にあげて、均質空間と称して、オフィスビルをイメージしてもらうとわかりやすいが、どのようなテナントにも対応可能な空間を指すが、予め何をするかが決まっていない空間とは、限定せずに自由に使える均質空間を目指すのではなくて、居心地の良い場所を自分が発見するように見つけていく空間で、その場所の解釈は人によって違い、まるで自然の中のような、森のような、均質ではなく、不均質な空間で、その時々で空間の受け止め方が変わる、違う空間、だから、予め何をするかが決まっていないということになる。
要するに、たくさんの解釈が折り重なり、同時に存在し、その中から選択するように発見していく空間である。
"Inhomogeneous space"
If you try to design a space where you don't know what to do beforehand, it seems easy and unexpectedly difficult.
It is common to design a space such as a universal space. As a space that can be used freely without limitation, taking the example of the architect's Mies space as a homogeneous space, it is easy to understand if you imagine an office building, but a space that can accommodate any tenant Pointing out, a space where you do not decide what to do beforehand is a space where you find a comfortable place to find a comfortable place, rather than aiming for a homogeneous space that can be used freely without limitation. Interpretation of the place differs from person to person. It is a heterogeneous space that is not homogeneous, like a forest, like nature, and the way of accepting the space changes from time to time. That means that it has not been decided.
In short, it is a space where many interpretations overlap, exist at the same time, and discover to choose from among them.
『予め決まりがない』
居心地の良い場所を探すように選択できたら、自然の中ではそれを当たり前のようにやっている。
きっとここは平らだからテントを張るには良いなとか、この木の根元で休憩しようとか、見晴らしの良い場所でご飯を食べようとか、そこは元々、その行為専用につくられている訳ではなく、むしろ、その場所を自分が発見するように見つけていく。
予め何をするかが決まっている空間や場所には興味が持てないのかもしれない。
選択できるということは、決まりや縛りの強度のようなものがほとんどないことかもしれない。それは例えば、室名のない部屋のような。
予め何をするかが決まっていない空間を設計してみよう。
"No pre-determined"
If you can choose to find a cozy place, you do it in nature.
Surely this place is flat, so it is good to set up a tent, to take a break at the root of this tree, to eat rice at a place with a good view, it is not originally made exclusively for that act, but rather , Find the place as you discover it.
You may not be interested in the space or place where you decide what to do in advance.
Being able to choose may mean that there is little like a rule or stiffness. For example, like a room without a room name.
Design a space where you do not know what to do beforehand.
人の手が届く範囲から建築デザインをはじめて、それが同心円状に段々と広がっていき、人と建築との接点、それはプラン的には壁で、その壁が人の日常の暮らしを反映するように、その時々の気分で何か変わる、その何かが変わる時、人と建築との間に密接な関係性が生まれる。
その関係性は人の数だけ違った種類が存在するだろう。そこは自然発生的に関係性が生まれれば良いから、デザインによって関係性を規制はしたくない。
だから、デザインでは、気分で何か変わる、その何か、その変わり方を扱う。
人と建築の接点というか、接面は壁として、気分で壁が変わる、その変わり方、実際には壁が可変する訳がないから、複数の違った壁を気分で選択すること、その選択の仕方をデザインする。
"Interface design"
Starting with architectural design within the reach of humans, it gradually expands concentrically, and the point of contact between people and architecture, which is a plan, is a wall, and the wall reflects the daily life of a person. In addition, something changes depending on the mood at the time, and when that something changes, a close relationship is created between people and architecture.
There may be as many different kinds of relationships as there are people. There is only a need to spontaneously establish the relationship, so we do not want to restrict the relationship by design.
So, design deals with something that changes with mood, something that changes.
The contact point between people and architecture, or the contact surface as a wall, the wall changes with mood, the way it changes, in fact there is no reason that the wall does not change, so select multiple different walls with mood, that choice How to design.
日常の暮らしの中で建築を考えていくと、どこか使い手に迎合してしまう印象がつきまとう。
使いやすさとか、趣味とか、居心地良さとか、気持ち良さとか、それは人それぞれ違うから、それを追い求めると使い手に合わせることになるし、建築は設計者自らの自由裁量でとはいかず、事業として成り立つようにクライアントがいて、設計者はそこではじめて登場するから、建築のことだけを考える訳にもいかず、だから、上手いこと暮らしと建築を切り離して、暮らしは取り扱わず、それは見て見ぬ振りをして、建築のことだけを語る方が作品になる。
ところが、面白いことに、建築のことだけを取り扱っているのは設計者だけで、設計者以外は建築と暮らしを区別していない、というか区別できない、だから、暮らしの中で交わされる言葉を使って設計者とクライアントはコミニケーションをするので、結局は迎合してしまう。
ならば、建築と暮らしを区別せず、日常として一緒に扱えば良いと普通に思うと、今度は日常と非日常の区別をするようになる。その区別はわかりやすく、利用しやすい。
結局、区別して、範囲を限定することによって、その範囲内で自由にやろうということで、建築を担保しているのだなと思う。
"Limited distinction"
When you think about architecture in your daily life, you will always get the impression that it will suit you.
Ease of use, hobbies, comfort, comfort, etc., are different for each person, so pursuing them will suit the user, and architecture will not be at the designer's own discretion, but will be a business. Because there is a client and the designer appears there for the first time, it is impossible to think only about architecture, so it is a good thing to separate living and architecture, living is not handled, it is pretended to see And the one who talks only about architecture becomes a work.
Interestingly, however, only architects deal exclusively with architecture, and non-designers do not distinguish between architecture and living, or indistinguishable, so we use the words exchanged in our lives. The designer and the client communicate, so they end up being compliant.
Then, if you normally think that it should be treated as everyday without distinguishing between architecture and living, then you will distinguish between everyday and extraordinary. The distinction is easy to understand and easy to use.
In the end, by limiting and limiting the scope, I think that the architect is secured by trying to be free within that range.
連続的に、床から丸味を帯びて壁になり、壁が丸味を帯びて天井になる、それは床が反転して天井になる、そのデザインをはじめて見た時、一種の発明に近い驚きがあった。
それは、オランダのユトレヒトにあるレム・コールハースとOMAが設計した『エデュカトリアム』で、ユトレヒト大学の施設である。
床、壁、天井が分節されずに、連続的に繋がっている様は、たぶんおそらく、自然界には存在せず、人がつくり出すイメージでのみ存在することで、ただ、そのイメージすら、今まで無かったので、だから発明的だと思った。
これ以降、発明的な建築に出会った記憶が無い、もちろん、素晴らしい建築にはたくさん出会ったが、なかなか発明的なものは生まれるものでもないのだろう。
ただ、床、壁、天井の関係性には、まだまだ可能性があると考えている。とりわけ壁には発明的な何かを見出したいと考えている。
"Inventive"
Continuously, the floor is rounded to a wall, the wall is rounded to a ceiling, and the floor is inverted to a ceiling. Was.
It is an Educatorium designed by Rem Koolhaas and OMA in Utrecht, the Netherlands, a facility of Utrecht University.
The fact that floors, walls, and ceilings are continuous without being segmented is probably because they do not exist in nature but exist only in images created by humans, and even that image has never existed. So I thought it was inventive.
Since then, I have no memories of encountering inventive architecture, and of course, I have met many wonderful architectures, but it is unlikely that anything innovative will be born.
However, we believe that the relationship between floors, walls, and ceilings still has potential. Especially, I want to find something inventive on the wall.
ヤコブセンのエッグチェアをコペンハーゲンのSASロイヤルホテルのロビーではじめて座った時、椅子が身体を包み込み、ロビーの中にプライベートな空間が出来上がることを感じたと同時に、人はそのような極小の自分だけの空間を潜在的に欲しているのではないかと思った。だから、エッグチェアに座ろうとする時は、休息というよりは、自分だけの空間に入り込む感じだった。
それは、自分と外界との距離感を調整することであるように思う。人はいつでも距離感を測る。人同士でも、物とでも、建築とでも、その距離感が丁度良いと居心地良さを感じる。
ヤコブセンのエッグチェアは、外界を遮断し、自分と外界を遠ざけてくれる装置になっている。だから、自分だけになりたい人が寄ってくる。
逆に、距離感を近づけてくれるものもある。例えば、同じく椅子で言えば、ベンチシート。自分以外の空間があり、そこが余白となり、そこに誰が座っても許されるし、外界との距離感を緩やかに調整し、馴染ませて、近づけてくれる、あるいは、強制的に近づけてしまう。強制的な場合は、通勤電車の長椅子が思い浮かぶ。
例えに椅子を持ち出したのは、人の身体に密着するものだから、距離感の話がわかりやすいと考えたのと、それがデザインできるものだから。
すなわち、距離感はデザインの対象にすることができるということである。
"A sense of distance is design"
When I first sat down with Jacobsen's egg chair in the lobby of the SAS Royal Hotel in Copenhagen, I felt that the chair wrapped up and created a private space in the lobby, and at the same time, people were such a tiny personal space I thought I might have a potential. So when I was sitting on an egg chair, I felt like I was going into my own space rather than resting.
I think it's about adjusting the sense of distance between me and the outside world. People always measure distance. I feel comfortable when the distance between people, objects, and architecture is just right.
Jacobsen's egg chair is a device that blocks the outside world and keeps you away from the outside world. That's why people who want to be alone come.
On the other hand, there are things that make the sense of distance closer. For example, in a chair, bench seats. There is a space other than myself, and it becomes a blank space, anyone can sit there, and the sense of distance to the outside world is adjusted slowly, familiarizing, approaching, or forcibly approaching. In compulsory cases, a commuter train chaise comes to mind.
For example, we took out the chair because it was close to the human body, so we thought it was easy to understand the sense of distance, and because we could design it.
In other words, the sense of distance can be an object of design.
人の領域をどこまで拡大するか、その原動力を人の気分にしようと考えている。気分によって左右されることが、今まで建築の領域だと見なされていたところに切り込む、その切り込み方をデザインしてみようと。
それによって、今までの建築の見え方が少しでも変われば、それは人にとっても影響を与える範囲が増えるので良いし、建築では新たな空間が生まれるかもしれない。
壁に切り込む。領域をプラン的に考えれば、最初に人の領域が切り込むべき建築の領域は壁だろう。
壁が人の気分によって左右される状況をつくり出す。そのつくり出された空間は新しい見え方になるはずだとして。だから、壁に取り付くものの見方を変えて検討する、その中で建具に行き着いた。
"Cut into the wall"
He wants to expand his territory and make him feel the driving force behind it. I try to design a way to cut into what was once considered to be an architectural domain, depending on my mood.
If the appearance of the architecture changes a little, it will increase the range of influence on people, and architecture may create a new space.
Cut into the wall. Considering the area in terms of planning, the architectural area that the human area should cut first is the wall.
The wall creates a situation that depends on the mood of the person. The created space should be a new look. Therefore, I changed the perspective of what was attached to the wall and examined it.
建具を服のように、身に纏い、着飾る、それは人と建築の関係性において、人を中心に据え、どこまでが人の領域で、どこからが建築の領域になるのかのせめぎ合いのようなことをイメージしている。
日常の生活の中でいろいろとコーディネートでできることは人の領域で、変えられないことは建築の領域で、その境界は明確にあるように思われているが、その境界自体が揺らげば、今まで見たことがない空間に出会える。
その場合は、人の領域が拡大していくのか、建築の領域が拡大していくのか、両方あり得るとは思うが、今までの建築の歴史的な流れは、建築の領域が拡大していく方向であり、その建築の領域の在り方が問われてきた。
今、興味があるのは、人の領域がどこまで拡大するか、そして、それによって、建築の領域の在り方がどう変わるかということであり、それは日常の生活や暮らしの場で起こることであるとし、それは建築を日常の生活や暮らしの中で考えるということである。
"Human domain, architectural domain"
Wearing and fitting fittings like clothes, it is like a battle between the human and the architectural relationship in the relationship between people and the building, focusing on the human sphere and from the architectural sphere. The image is.
What can be coordinated in everyday life is the domain of human beings, what cannot be changed is the domain of architecture, and it seems that the boundaries are clear, but if the boundaries themselves fluctuate, now You can meet a space you have never seen before.
In that case, it is possible that the area of people will expand or the area of architecture will expand, but I think that the historical flow of architecture so far is that the area of architecture has expanded The direction of the architectural domain has been asked.
Now I am interested in how far the human territory expands and how it changes the architectural territory, which happens in everyday life and living places. That means thinking about architecture in everyday life and daily life.
壁を建築の付属物と考えず、人の付属物と考えれば、服を着飾るように、そこにもう1枚のレイヤーを用意して、気分で選択し、装飾することができる。
壁に服を着せるように、もう1枚のレイヤーを着飾る。
外装では、外皮のことをスキンと称して、ダブルスキンなど、レイヤーを用意することはよくあり、カーテンウォールも同じ。
それを内装で考えている。外装では水密性を要求されるから、気分で選択するようなことは難しいかもしれないが、内装ならば可能かもしれないし、外装よりも日常の生活に、暮らしに密着したことが可能になるのではないか。
その内部の被覆は、壁に取り付く建具も含む。もしかしたら、その被覆は建具そのもの、建具と同義かもしれない。建具が本来の機能、出入り口や収納などから逸脱して存在するようになれば、被覆としての可能性が広がるかもしれないと考えている。
"Fittings are covered"
If you don't think of the wall as an architectural accessory, but a human accessory, you can choose another layer and decorate it, just like dressing up.
Decorate another layer to dress the wall.
On the exterior, the outer skin is called a skin, and layers such as double skins are often prepared, and the same applies to curtain walls.
I think it in the interior. The exterior needs to be watertight, so it may be difficult to choose by mood, but it may be possible for the interior, and it will be possible to adhere more closely to everyday life and living than exterior. Isn't it?
The interior coating also includes the fittings that attach to the wall. Perhaps the covering may be synonymous with the fitting itself. We believe that if fittings deviate from their original functions, doorways, storage, etc., the potential for covering may be expanded.
普段の生活の中に実用としての屏風が家にある人は少ないだろう。屏風と言えば、鑑賞用として、美術品としてのイメージが強いが、普段の生活の中で実用として使われることがある。
昔の日本家屋では、6畳や8畳などの和室が襖で仕切るだけで続いており、広く使いたい時はその襖を外して使うことができ、逆に小さく使いたい時には、屏風を立てて、その場所だけを仕切っていた。
日本家屋の続きの和室には、洋室のようなドアは無く、襖や障子で仕切り、壁は4面のうち1面しかない場合が多く、視覚上、明確な出入り口が存在しない。だから、襖や障子を外したりして、洋室よりフレキシブルに使うことができ、さらに、小さく仕切る、出入り口を明確にする、出入り口を隠すなど、細かな対応をするために屏風を使う。
屏風は、昔の日本家屋では、生活に無くてはならない小道具であり、簡単に移動もでき、空間要素のひとつだった。
その屏風に代わるものとして、和室が無くなり洋室ばかりの家では、移動に制限があるが、可動間仕切りとしての機能を持った木製の建具を使うことがある。その可動間仕切りを襖や障子の代わりとみなすこともできなくないが、洋室に障子を使うこともあるので、屏風の代わりと考えた方が素直だろう。
洋室に和の要素を取り入れた結果、木製の可動間仕切りを使うことはよくあるが、やはり屏風よりはフレキシブルではない。それは、移動に制限があるだけではなく、可動間仕切りは建築の付属物であり、屏風は人の付属物であり、その違いによるような気がする。
だから、屏風には仕切りとしての実用の役目の他に、鑑賞や美術品としての役目も負う、それは人が着飾るように。
そう考えてみると、今、建築の付属物と見なされている物を、見方を変えて、人の付属物とすれば、また違ったデザインが見えてくるかもしれない。
"Human accessories"
Few people will find a practical folding screen at home in their daily lives. Speaking of folding screens, they have a strong image as an art object for appreciation, but they are sometimes used in everyday life as practical.
In old Japanese houses, Japanese-style rooms such as 6 tatami mats and 8 tatami mats are just separated by sliding doors.If you want to use it widely, you can remove the sliding door and use it. , Only that place was partitioned.
The Japanese-style room following the Japanese house does not have a door like a Western-style room, but is divided by sliding doors and sliding doors, and often has only one of the four walls, and there is no visually clear entrance. Therefore, you can remove the fusuma or shoji and use it more flexibly than in the Western-style room, and use folding screens to provide small measures such as partitioning small, clarifying the entrance, and hiding the entrance.
Folding screens were an indispensable prop in everyday life in old Japanese houses, and they were easy to move around and were one of the spatial elements.
As an alternative to the folding screen, in a house where there are no Japanese-style rooms and only Western-style rooms, movement is restricted, but wooden fittings that function as movable partitions may be used. Although the movable partition cannot be considered as a substitute for a sliding door or a sliding screen, it may be more straightforward to think of it as a substitute for a folding screen because a Western screen may be used as a sliding screen.
As a result of incorporating Japanese elements into the Western-style rooms, wooden movable partitions are often used, but still less flexible than folding screens. Not only is there a restriction on movement, but the movable partition is an accessory of the architecture, and the folding screen is an accessory of the person, and I feel like the difference.
Therefore, in addition to the practical role as a partition, the folding screen also has a role as appreciation and art work, as if people are dressed up.
If you think so, if you change what you see now as an accessory of architecture and make it an accessory of people, you may see a different design again.
数寄屋造の建築からお庭を眺めていた。内部と外部を仕切るガラス戸は、透明度が高く、存在が感じられなかった。
ガラスを建具に使うようになったのは、たぶん、近代以降だから、数寄屋造の建築が確立された時代には、そこに建具は無く、広縁は外部で、和室と広縁の境に障子があるだけだっただろう。
だから、その障子に雨が当たらないように、数寄屋造の建築の屋根の軒が低く深く垂れ込めているのだろう。そして、雨が降れば、その屋根の軒先から雨が滴り落ちる。
今は軒先に雨を受ける樋が取り付けられているが、それは下水道が整備されたので、雨を集める必要があり取り付けられたもので、それ以前は無く、雨が滴り落ちる辺りの地面を砂利敷にして、土の泥跳ねを防ぎ、地面に浸透しやすくしていた。
その砂利敷が数寄屋造の建築を取り囲む、その様は屋根の形と建物の形の写し絵のように、ならば、そこに少しの遊び心を求めるのも数寄者のさがか、その砂利敷をお庭の構成要素のひとつにし、人が歩く所とすることにより、建築と人とお庭に関係性が生まれ、混在し、構成要素は単純ながら、複雑な空間が着物の色を引き立てる。
などと、お庭を眺めながら、適当に、自分が今いる所から外へと想いを巡らせてみた。
"Connect to the outside"
I was looking at the garden from a Sukiya-style building. The glass door, which separates the interior and exterior, was highly transparent and could not be felt.
The use of glass for fittings was probably from the modern era, so in the era when Sukiya-style architecture was established, there were no fittings, the wide rim was outside, and there was a shoji on the border between the Japanese-style room and the wide rim. Would have only been.
Therefore, the roof eaves of the Sukiya-style building may be low and deeply hung so that the shoji is not exposed to rain. And when it rains, it drips from the roof eaves.
Currently, a gutter receiving rain is attached to the eaves, but it was installed because it was necessary to collect rain because the sewer was prepared, and before that there was no gravel, and the ground around the area where the rain dripped was dropped. In order to prevent mud splashing of the soil, it was easy to penetrate the ground.
The gravel floor surrounds the Sukiya-style building, as if it were a copy of the roof shape and the shape of the building. Is a component of the garden and a place where people walk, creating a relationship between architecture and people and the garden, mixed, and the simple but complex space enhances the color of the kimono.
While looking at the garden, I thought about myself from where I am now to the outside.
建具には、その建築の精度と、その建築での暮らしが垣間見える。
建具とは、扉や戸のことであり、外部建具と内部建具があり、外部建具は木製の場合もあるが、主に鋼製かアルミニウム製で、サッシやドアと呼ばれ、内部建具は木製主体で、障子や襖も含まれる。
建具を単に仕切りとだと考えれば、雨風を凌ぐためや空調をコントロールするための、環境の仕切りとしての建具と、防犯や目隠しをするための、プライバシーの仕切りとしての建具が必要になり、それ以外の建具は必要が無いと考えているが、さらに言うと、防犯や目隠しの必要性が無ければ、プライバシーの仕切りとしての建具も必要が無くなり、建築にとって必要な建具は、環境の仕切りとしての建具のみになる。
プライバシーの仕切りが必要無い状況は、そこでの暮らしが影響するから、その影響はプランにも現れるだろう。
だから、環境の仕切りとしての建具のみの建築は、それだけでプランにも建築自体にも特色が出てることになる。それは、ぼんやりと曖昧で、特に何もない建築では起きないことであり、より細かく精緻なプランニングが必要になる。
もしかしたら、仕切りとしての建具から建築を考えはじめる可能性もあり得るのではないかと考えてみた。
"Start thinking from joinery"
The fittings provide a glimpse of the accuracy of the architecture and the life in the architecture.
Fittings are doors and doors, there are external fittings and internal fittings, and external fittings may be wooden, but they are mainly made of steel or aluminum, and are called sashes and doors, and internal fittings are wooden. Mainly includes shoji and fusuma.
If we consider the fittings simply as partitions, we need fittings as environmental partitions to overcome rain and wind and control air conditioning, and fittings as privacy partitions for crime prevention and blindfold. We believe that there is no need for other fittings, but furthermore, if there is no need for crime prevention or blindfolding, there is no need for a privacy partition, and fittings required for construction are environmental partitions. Only fittings.
In situations where privacy barriers are not needed, the impact of living there will be reflected in the plan.
Therefore, a building with only fittings as a partition of the environment will have its own characteristics in both the plan and the building itself. It is vague and ambiguous, especially in empty buildings, and requires more detailed and detailed planning.
I wondered if it might be possible to start thinking about architecture from the fittings as partitions.
建築的創造は、型を守り、その型を基にして、その先へ発展させて行くのか、それとも、型自体を疑い、新たな型をつくろうとするのか、どちらなのだろうかと考えてしまう。
単に、創造するということであれば、どちらの場合も有り得る。どちらの場合も、結果的には、新しいものが生まれるから。
だから、どちらでも構わないのだろう、あとはどちらの態度を選択するだけか、無難に行くならば、型は守った方が良いし、そちらの方が賢いやり方のような気がするし、そちらの方が新しいものができた時に抵抗なく受け入れやすく、わかりやすく、評価を受けやすいが、無性に新たな型をつくることがやりたくなるし、既存の型を疑いたくなる。
はっきりと、これは新しいと、見たことが無いと、でも良いと、なるように。
"I doubt the type"
In architectural creation, one wonders whether to follow the pattern and develop it on the basis of the pattern, or to doubt the pattern itself and create a new pattern.
Either way, it just happens to be creative. In both cases, the end result is something new.
So, it doesn't matter which one you choose, then you just have to choose which one, or if you're going to be safe, it's better to keep the pattern and it's a wiser way, It is easy to accept, understand, and evaluate without difficulty when a new one is created, but it makes it difficult to create new types asexually and to doubt existing ones.
Clearly, this is new, never seen, but good.
デザインされた物は使いにくいという迷信は今でもあるのだろうか。確かに、そういうことはあるかもしれないが、使いにくい物はデザインに関係無く存在する訳だから、デザインされた物を揶揄する決まり文句だと考えている。
民藝の「用の美」というものがある。民芸運動の中心的役割をした柳宗越が提唱したものだが、日用品の中に真の美があるというもので、日用品は使うために存在しており、美術品のように鑑賞目的では無く、使うことが目的の道具だからこそ、形や色などが美しいという。
20代のはじめ、ニューヨーク近代美術館で1脚のスツールにはじめて出会った。そのスツールの形の美しさに目を惹かれ見入ってしまった。そのスツールは座らなくても、ただそこにあるだけでも良かった。後に他で座る機会を得たが、その座り易さ、その感触に感動すら覚えた。そのスツールのキャプションにはデザイナーとして「SORI YANAGI」とあった。後に民芸運動の柳宗悦の息子さんだと知った。はじめて柳宗理の作品に触れた瞬間だった。
それ以来、使い易さと美は車の両輪、だと考えるようになった。
使い易さは、身体感覚として、日常の生活の中で、無意識のうちに訓練しているような所があるから誰でもわかりやすい。
美には、もしかしたら、意識付けのようなことが必要なのかもしれない。何が美しいかは、時と場合によって変わることもあるだろうし、永遠に美しいものも存在するが、それが美しいかどうかをはじめて知る時は、何かの導きが必要になってくるのではないだろうか。
だからと言って、すぐにでも美術館や博物館へ行けば良いとは言いたくない。
何が美しいかは、自身の中に美の基準をつくることであり、その美の基準が自身特有のものでないと日常の生活にも生かせないし、日用品の中にある真の美を見出すこともできないし、そもそも、美しいものに気が付かないだろう。知識として「用の美」を知っていても意味が無い。
もしかしたら、美に気付かせてくれる機会は、ある日突然訪れるのかもしれない。それは、知らない美、意識したことがない美を抱えている人にしか起こらない。だから、無理に美を知ろうとしない方がたくさんの美に気付くことになるかもしれないが、そうすると、感度が高い人ほど、美に気付いた時の衝撃が大きくて、それに耐えるのは大変かもしれない。見える世界が変わる代償か、でも、その方が確実に面白いし、自身特有の美の基準を得ることになると考えている。
"Notice the beauty"
Is there still a myth that designed things are hard to use? Certainly, there may be such a thing, but since there are things that are not easy to use regardless of design, I think that it is a cliche to mock the designed thing.
There is a folk art "beauty for you". It was proposed by Munekoshi Yanagi, who played a central role in the folk art movement, but there was a real beauty in daily necessities, and daily necessities exist to be used, and must not be used for appreciation like art objects. It is said that the shape and color are beautiful because it is the intended tool.
In my early 20s, I first met a stool at the Museum of Modern Art, New York. I was attracted to the beauty of the shape of the stool and watched it. It didn't matter if the stool wasn't sitting or just sitting there. Later, I had the opportunity to sit elsewhere, but I was impressed by its ease of sitting and its feel. The stool caption was "SORI YANAGI" as a designer. Later I learned that he was the son of Muneyoshi Yanagi of the folk art movement. It was the moment I first touched Sori Yanagi's work.
Since then, I have come to think that ease of use and beauty are two wheels of a car.
Ease of use is easy for anyone to understand because there are places where you are training unconsciously in your daily life as a bodily sensation.
Beauty may need something like awareness. What is beautiful can change from time to time, and there is something forever beautiful, but the first time you know if it is beautiful, you do not need any guidance I wonder.
I don't want to say that it's good to go to a museum or museum right away.
What is beautiful is to create a standard of beauty in one's own, and if the standard of beauty is not unique to oneself, it cannot be used in everyday life, and it is also possible to find the true beauty in daily necessities You can't, and you won't notice anything beautiful in the first place. There is no point in knowing the "beauty of utility" as knowledge.
Perhaps the chance to remind you of beauty comes suddenly one day. It only happens to those who have beauty that they don't know or have never conscious of. Therefore, those who do not try to know beauty may notice a lot of beauty, but then the more sensitive people are, the greater the impact when they notice beauty, and it may be difficult to withstand it Absent. At the cost of changing the world we see, we believe that it will definitely be more interesting and will give you a unique standard of beauty.
建築らしさ、というものがあるような気がする。例えば、街を歩いていて、これは建築家の作品ではないかと見当がつき、後から調べると大体間違いがない、あるいは、知っている建築家の作品は、たまたま出会しても瞬時にわかる。
それは、デザインされた建物ではなく、建築家が手掛けた建物だという「建築らしさ」が漂っている。
その違いを上手く説明できない。精度や密度などの質の差では無い、もちろん、質として一定の水準は超えているが、大きさや高さなどの量も関係が無い。
その建築らしさが厄介だ。それはたぶん、今まで見てきた建築家の作品の蓄積により、勝手に自分の中に形成されたものであり、それが基準になっており、その基準に合致しないと違和感を感じる。
別に、勝手に自分の中に形成された基準だから、それを無視しようと誰からも責められることは無いが、その基準から外れることは質が下がるような気がして躊躇する。だが、その建築らしさから外れないと、自分が今イメージしている建築ができないならば、解決案として、建築らしさを漂わせながら、少しだけ外れてみようかと考えている。
"Floating architecture"
I feel like there is architectural quality. For example, while walking in a city, I guess that this is an architect's work, and when I examine it later, there is almost no mistake, or the work of an architect I know is instantly known even if I happen to meet .
It is not an architectural design, but a building designed by an architect.
The difference cannot be explained well. There is no difference in quality such as accuracy or density. Of course, the quality exceeds a certain level, but the quantity such as size or height has no relation.
The architectural nature is troublesome. Probably, it was formed in myself by the accumulation of the architect's works that I have seen so far, and it is the standard, and I feel uncomfortable if it does not meet the standard.
On the other hand, nobody is blamed for ignoring it because it is a standard that has been formed in myself, but I feel hesitant to deviate from that standard because it seems to be degraded. However, if I can't do the architecture I'm imagining without deviating from the architectural characteristics, I'm thinking of trying to deviate a little while keeping the architectural characteristics as a solution.
気分はその人特有のものであり、その気分をデザイン要素として取り扱うことができたならば、人とそのデザインされた物との間に直接的な関係性が生まれる。そのような関係性をつくりたいと日々考えている。
コロコロ変わる気分を捕まえるのは難しいけれども、コロコロ変わる気分に応じることはできそうな気がする。
「これもアリだよね」「これもアリだよね」の繰り返し、様々な角度から選択が可能な状況が散りばめられているようなことになれば、コロコロ変わる気分に応じることができる。
それを建築空間として表現するならば、壁の在り方に取り入れてみると面白いと考えている。
"According to mood"
Mood is unique to a person, and if he could be treated as a design element, there would be a direct relationship between the person and the designed thing. I want to create such a relationship every day.
It's hard to catch the changing mood, but I feel like I can respond to the changing mood.
Repeating "This is an ant" and "This is an ant" as well, you can respond to the changing mood if you are stuck with situations where you can select from various angles.
If we express it as an architectural space, we think it would be interesting to incorporate it into the way the walls should be.
気分で変わることに何故か興味が湧く。気分で変わることは何事もあまり良いこととは思われないかもしれないが、気分ほど、その人らしさを表現しているものはないように考えている。
気分自体は目に見えるものではないから、気分が何かに反映した時に、その気分がわかる。
顔に気分が出たり、態度に気分が出たりするが、その気分を読み取る側の気分もあるから、気分を取り扱うことは、人の内なるものを扱うことになり、また、その気分が反映されたものが、具体的な物ならば、それをデザインの範疇として扱うこともできるのではないか、気分をデザインの範疇に組み込むことができるのではないかと考えている。
"Mood design"
For some reason I am interested in changing with my mood. It may not seem like anything good to change with your mood, but we try to make sure that nothing expresses that personality as much as we do.
The mood itself is not visible, so when the mood reflects on something, you know it.
Mood appears on the face and attitude, but there is also a mood on the side that reads that mood, so handling mood is dealing with inner things of people, and that mood is reflected If what is done is a concrete thing, I think that it can be treated as a category of design, or mood can be incorporated into the category of design.
壁の造形が作者の自由で好きなように成り立つためには、その壁が最低限、アフォーダンスとして成立していれば良いのではないかと考えてみた。
アフォーダンスとは手掛かりである。人のアクティビティの発露になるものである。作者が好き勝手に、自由に、恣意的に振る舞って、造形が決まっていたとしても、最低限、このアフォーダンスが成り立っていれば、その壁はデザインされたものとして受け入れられるだろう。
アフォーダンスが成り立っていなければ、ただの奇抜な壁である。それがデザインされた壁として受け入れられるかどうかは好み次第か、その壁がその造形である必要性が客観的では無いから、その壁がただの恣意的ということだろう。
恣意的な造形にはしたくないのが前提なので、ただ、造形は一見恣意的なように自由で好きなようにしたい、この矛盾を上手くつなぎ合わせるためにアフォーダンスとして成立させることは有効だろう。
"Affordance is a bridge"
In order for the author to be free and likable to shape the wall, I wondered if the wall should be at least as affordable.
Affordance is a clue. It is a manifestation of human activity. Even if the author freely, arbitrarily and arbitrarily shaped the form, if at least this affordance holds, the wall will be accepted as a design.
If affordance does not hold, it is just a strange wall. Whether it's acceptable as a designed wall is up to you, or it's just arbitrary, because the need for that wall to be shaped isn't objective.
It is premised that we do not want to make it arbitrary, but we want to make it seemingly arbitrary and free, and it would be effective to establish it as an affordance in order to connect these contradictions well.
壁を凹凸で認識するとどうなるのだろうかと考えている。
知らない空間へ行った時、まず最初に振る舞いの方向性を与えてくれるのは、壁のアフォーダンスである。アフォーダンスとは、簡単に言うと、手掛かりであり、どう扱えば良いのか、その空間でどう振る舞えば良いのかを壁が教えてくれる。
例えば、壁にドアがあれば、そのドアが開くかどうかがわからなくても、少なくとも、そのドアは何かの出入り口であり、そのドアが奥の引っ込んだ所にあれば、もしかしたら、そのドアの先がお手洗いかもしれないと推測がつく。この奥に引っ込んだドアがアフォーダンスである。
このアフォーダンスを簡略化していくと、壁の凹凸で、人の振る舞いが決まるようになるのではないか、その凹凸を空間デザインとすれば、デザインすることにより、人の振る舞いも同時に決まるようなことが起こるのではないか、そして、そのデザインは自律して存在していながら、人の振る舞いにも影響を与えるという意味で他律的でもあるという状況がつくれるのではないかと考えている。
"Affordance on the Wall"
I wonder what would happen if I recognized the wall with irregularities.
When you go to a space you don't know, the first thing that gives you the direction of behavior is affordance on the wall. Affordance is simply a clue, and the wall tells you how to handle it and how to behave in that space.
For example, if you have a door on a wall, you don't know if the door will open, at least if it's a doorway to something, and if the door is in a deep recess, maybe that door I guess that may be the restroom. The door retracted into this back is affordance.
If this affordance is simplified, people's behavior will be determined by the unevenness of the wall.If the unevenness is a space design, the behavior will be determined at the same time by designing I suppose that we can create a situation in which the design is autonomous, but also autonomous in the sense that it also affects human behavior.
形を考える時、その発露は何かあり、それを手掛かりに進めていき、その中で様々な理論、理屈、理由を、先に考えるにしても、後付けにするにしても、伴わせる。そうしないと観念的で恣意的な表現になってしまうからと強迫観念が走る。
自由に線を引いてもいいし、自由に曲線を描いてもいい。
ただ、線が引かれた途端に、たった1本の線でも、そこに建築的には意味が立ち上がる。たった1本の線で空間を感じる。
だから、その線が引かれる必然性のようなものを求めてしまう。建築が立ち上がる時、それはデザインだけで成り立つことは無く、法規や構造、設備など、デザイン以外のことがたくさん絡んでくるので、デザイン以外の意味で1本の線は引ける。
ただ、その1本の線は建築が立ち上がる時の本質を突いていないように考えてしまう。
観念的で恣意的な表現ではなく、建築の本質を突いた1本の線、その最初の線を描くことが尊いと思ってしまう。
"The first line"
When you think of a form, there is something that manifests itself, and you can use it as a clue, and in it, you can accompany various theories, theories, and reasons, whether you think first or later. Otherwise, the obsession runs because the expression is ideological and arbitrary.
You can freely draw lines or freely draw curves.
However, as soon as the line is drawn, even a single line has an architectural meaning. Feel the space with just one line.
So we want something like the necessity of drawing that line. When an architecture starts up, it does not consist solely of design. It involves many things other than design, such as regulations, structures, and facilities, so a single line can be drawn in a non-design sense.
However, it seems that the one line does not deviate from the essence of the building when it stands up.
I think it is precious to draw a single line that projects the essence of architecture rather than an idiosyncratic and arbitrary expression.
設計をしている時の複雑に絡み合った問題を整理し、単純化した後の、捨てた訳ではないが、単純化してしまったことによりに、表から消えてしまったことに興味が湧く。
それが裏付けにはなっているのだろうけれど、表から消すことなく、そのまま見えるようにしたらどうだろうか。例えば、壁が裂けて中から裏が盛り上がってくるような造形と表から消してしまったことが上手く呼応するようにする。
ところが、建築では、そのようなイメージの仕方をして、それをそのまま造形要素にするやり方は、恣意的で観念的だとして、敬遠される。
単純化して引いていく場合はまだ良いが、複雑なことをそのまま、あるいは、足してより複雑にしていく場合は、それが良いデザインでも敬遠される傾向にある。
要するに、理屈が伴わない造形は恣意的で観念的だと、それもまた良しだと思えるようにすれば良いが。
"It's also good"
It is not an abandonment after sorting out and simplifying the complicated intertwined problems when designing, but it is interesting that the simplification has made it disappear from the table.
Perhaps that is the backing, but what if you don't erase it from the table and keep it visible? For example, make sure that the wall is torn and the back is raised from the inside, and that it has disappeared from the front.
However, in architecture, it is shunned that the way of doing such an image and transforming it into a sculptural element as it is arbitrary and idiomatic.
It is still good to simplify and draw, but when it comes to adding more complexity or adding more complexity, even a good design tends to be avoided.
In essence, let's make it seem that it's also good that non-reasonable modeling is arbitrary and idiomatic.
整えないとどうなるだろうか、いつも何かを整えることばかりしてきたように思う。設計をしていると、複雑に絡み合った問題を整理し、単純化し、その単純化したものをモデルとして、建築空間を組み立てる。
そう、そこに何か解決策を見つけようとしてしまう、それがひとつの使命のように。それは正しい建築設計の在り方だが、必ずしも人に沿っていない場合もある。
人の問題などは、もしかしたら、建築で解決策が見つかるほど単純なことではないかもしれない。むしろ、解決策を見つけようとするより、複雑に絡み合った問題をそのまま提示することの方が建築の役割のような気がする。
あとは、整えるのではなくて、観察して、選択できる状況をつくる、選択が唯一の解決策になるように。
"Do not simplify"
I guess I've always been trying to fix things, what will happen if I don't. When designing, we organize and simplify complicated and intertwined problems, and assemble architectural spaces using the simplifications as models.
Yes, they try to find a solution there, like a mission. That's the right way of architectural design, but it doesn't always follow people.
Human problems may not be as simple as finding a solution in architecture. Rather, it seems like the role of architecture is to present complex and intertwined problems as they are, rather than trying to find a solution.
The rest is to make a situation where you can observe and make choices, rather than trimming, so that choice is the only solution.
人の営みの複雑さ、日常の生活の煩雑さを整理して単純化する役目が建築にはあると考えている。それが建築のプランに反映され、様々なプランがクライアントの数だけ存在するようになる。
人の営みの複雑さ、日常の生活の煩雑さを整理しつつも、単純化せずに、複雑なまま、煩雑なままに見せるプランは存在しないのだろうかと考えてしまう。
その複雑さや煩雑さは、単純化した場合と同じように、クライアントの数だけ存在する。だから、ある程度は整理しつつも、その複雑さや煩雑さをそのまま見せてしまった方が、より人の営みや日常の生活との親和性が良いような気がするし、その方が人と建築の関係において自然のような気がする。
ただ、単純化せずに複雑さや煩雑さをそのまま見せるには、別の解法を、それを建築性と呼ぶかもしれないが、用意してあげる必要がある。そして、その答えは別の分野にあるかもしれない。
"Another solution"
I believe that architecture has the role of organizing and simplifying the complexity of human operations and the complexity of everyday life. That is reflected in the architectural plans, and various plans exist as many as the number of clients.
While arranging the complexity of human activities and the complexity of everyday life, I wonder if there is a plan that does not simplify, but remains complex and complicated.
The complexity and complexity are as many as the number of clients, as in the case of simplification. Therefore, it seems that it is better to show the complexity and complexity as it is, while organizing it to some extent, it is more compatible with people's work and everyday life, and that people and architecture I feel like nature in the relationship.
However, in order to show complexity and complexity without simplification, another solution, which may be called architectural, must be prepared. And the answer may be in another area.
連続した壁が不規則に変化する様に興味がある。それは建築の壁だけでなく、壁状になった自然の地形でも同じように興味がある。
建築の場合は、単体の建築での、外壁でも、内壁でも、どちらでも、連続した壁の不規則性に興味があり、さらには、都市での単体の建築の連なりがつくり出す、連続した壁の不規則性にも興味があり、街並みなども、例えば、町家の連なりや、宿場町の街並みも綺麗で美しいが、それよりも繁華街の猥雑さの方に惹かれる。
建築でも都市でも同じだが、人のアクティビティは壁に誘発されると考えている、床や地面ではなくて。
「壁を伝っていけば、あの建築は理解できる」という話を前に聴いた覚えがあるが、人は無意識のうちに日常生活の中で壁を頼りに行動していると考えている。それは、全てのアクティビティを誘発するものが壁にあると言っても過言ではないから。出入り口、窓、キッチンや棚など、日常生活に関わるものはほぼ全て壁にある。
だから、その壁が整然としていれば、日常生活も整然となり、煩雑ならば、日常生活も煩雑になる。それは、設計する側から考えてみると、日常生活をどう捉えるか、その捉える様が壁に現れるとも言える。
日常生活をどう捉えるか、整然として単純よりは、煩雑で、複雑で、猥雑なものと捉えてしまう。日常生活は人の営みであり、人はそんなに整然として単純ではいられないから、人はそれぞれ特徴があり、考え方も違うから。
だから、それが壁に現れ、不規則に変化する様をつくりたくなる。
"The Irregular Wall"
I am interested in the continuous walls changing irregularly. It is not only interesting for architectural walls, but also for walled natural terrain.
In the case of architecture, we are interested in the irregularity of continuous walls, both exterior and interior walls, in a single building, and furthermore, the continuous wall construction of a single building in a city creates I am also interested in irregularities, and the streets, for example, the series of town houses and the post town are beautiful and beautiful, but I am more drawn to the obsceneness of downtown.
The same is true for architecture and cities, but we believe that human activities are induced by walls, not the floor or the ground.
I have heard before that you can understand that architecture if you travel along the wall, but think that people are acting unconsciously relying on the wall in their daily lives. It's no exaggeration to say that there is something on the wall that triggers all activities. Almost everything related to daily life, such as doorways, windows, kitchens and shelves, is on the wall.
Therefore, if the wall is tidy, the daily life will be tidy, and if it is complicated, the daily life will also be complicated. From a designer's point of view, it can be said that how to perceive everyday life appears on the wall.
How to perceive everyday life is more tidy, complicated, complicated and obscene than simple. Everyday life is a human activity, and people cannot be so orderly and simple, so each person has its own characteristics and different ways of thinking.
So I want to make it appear on the wall and change irregularly.
集合住宅のプランを考えている時、いつも、nLDKの形式にはならないようにしたいと思う。もちろん、それは注文住宅でも同じだが、注文住宅では、それほど意識しなくても、nLDKの形式にならないことが多い。
集合住宅では、住戸の積層と反復による効率の良さによって、事業計画上、最大住戸数、最大専有面積を取ることを求められることが一般的で、その効率の良さと住戸プランのnLDKが相性が良いのか、一般的にわかりやすいのか、建築計画上もnLDKの形式に落ちつくことが多い。
ただ、nLDKという形式だけで、日常の生活活動が規定されてしまうことが多く、それが一般的なわかりやすさにつながるのだろうけれど、確かに、nLDKの形式が欧米の生活様式を象徴する時代はあったかもしれないけれど、プランが日常の生活活動を規定してしまうことに違和感がある。
プランに日常の生活活動を合わせるのではなくて、日常の生活活動にプランを合わせるようにしたく、注文住宅では特定のクライアントがいるので、それが可能だが、集合住宅では不特定多数の住人が相手になるので、それが容易にできない。だから、それもあってnLDKの形式の一般的にわかりやすいプランに至ってしまうのだろう。
だから、集合住宅のプランでnLDKの形式を取らないならは、それに代わる他の形式を考える必要があり、それは決して、nLDKの派生ではなく、日常の生活活動から派生する形式にする必要がある。
"Not a derivative of nLDK"
When thinking about a multi-family apartment plan, I always want to make sure it doesn't come in nLDK format. Of course, the same is true for custom-built homes, but custom-built homes often don't go into nLDK format without much awareness.
In a multi-family housing, it is common practice in business plans to take the maximum number of dwelling units and the maximum occupied area due to the efficiency of stacking and repetition of dwelling units, and the efficiency and nLDK of the dwelling unit plan are compatible. Whether it is good or generally easy to understand, architectural plans often settle down in nLDK format.
However, daily living activities are often defined only by the nLDK format, which may lead to general intelligibility, but indeed, in the era when the nLDK format symbolizes Western lifestyles It may have happened, but I feel uncomfortable that the plan regulates daily living activities.
I want to match my plan to my daily life activities instead of my daily life activities.I can do this because there are specific clients in a custom-built house, but an unspecified number of residents in an apartment house It can not be done easily. So, that will lead to a generally straightforward plan in the form of nLDK.
So, if you don't take the form of nLDK in a multi-family plan, you need to think about other alternatives, which should never be derived from nLDK, but derived from daily living activities.
ぼんやりと視点を合わせず空間を見てやれば、物体の陰影だけが見えてくる。視点を合わせれば、それが何であるのかは過去の記憶からわかるが、視点を合わせなければ、ただの出っこみ引っ込みであり、その出っこみ引っ込みに特徴があるだけである。
人が空間を認識する時、瞬時に視点を合わせて、その場の状況を判断するのだろうけれど、その前の0.何秒かは視点の合わない状態、物体の陰影だけが見え、その出っこみ引っ込みしか見えない状況がある。
その状況は、空間が本来あるべき姿として認識されていない状態ではあるが、空間の骨格というか、余計な装飾が剥ぎ取れた素の状態でもある。
その素の状態はむしろ、デザインとして、つくり出したい状態でもあるのではないか、その状態で空間が成り立つのならば、その後は、どの様にでも、素だから、変容できる空間ということになるのかと考えてみた。
"Transforming elementary space"
If you look at the space without blurring the viewpoint, only the shadow of the object will be visible. If you match the viewpoint, you can understand what it is from the past memory, but if you do not match the viewpoint, it is just a depression and retraction, and the depression and retraction is only characteristic.
When a person perceives a space, he or she will instantly adjust the viewpoint and judge the situation at that moment, but in the 0 second before that, the viewpoint is not aligned, only the shadow of the object can be seen, There are situations in which you can only see in and out.
The situation is that the space is not recognized as it should be, but it is also the skeleton of the space, or the elementary state where extra decorations have been stripped off.
Isn't that elementary state rather a state that we want to create as a design, and if space can be established in that state, then, after all, it will be a space that can be transformed because it is elementary. I thought.
あくまでも机上での話だが、建築が立ち上がる時、確信めいたものが芽生えるが、そのためには何かに裏打ちされていなければならず、その何かとは、今まで経験したことや、見聞きしたことや、得た知識など、裏付けや後ろ盾になるもので、それが無いと確信が持て無い。
ところが、その確信はやはり、何処かで見たり、経験したりしたことの延長線にあるので、その延長線にあるということに対しての安心感からの確信でしかない。
全く脈絡が無いことを人は思い付くが、それを上手く今までの繋がりの中に納めていくことになるので、当初の思い付きが上手く生まれ変わる。
その上手さがセンスかもしれないが、全く脈絡が無いことを考えている楽しみは無くなる。案外、この楽しみが新しいことを生み出す、それは生まれ変わらせることでは無くて、原動力なのではないか。だから、そのまま形にすれば、それが今までの繋がりから離れた新しいものになるが、ただ、それが受け入れられるかどうかはわかない。
"Is it acceptable?"
It's just a story on the desk, but when architecture starts up, things that I'm convinced will sprout. It provides support and backing for the acquired knowledge, and I cannot be convinced that it does not exist.
However, that conviction is still an extension of what you have seen or experienced somewhere, so it is only a conviction from a sense of security that you are on that extension.
People come up with the idea that there is no context at all, but they will be able to put it into their existing connections, so their initial ideas will be reborn.
The skill may be good, but the fun of thinking that there is no context disappears. Surprisingly, this pleasure creates something new, not a reincarnation, but a driving force. So, if you take it as it is, it will be a new thing that is far from the connection, but it is not clear whether it will be accepted.
そこで立ち上がる建築がどうなりたがっているのか、などと考えてみることにした。
それはクライアントの要望などから類推する話ではなくて、その場所に建築が立ち上がるならば、その建築はどのようなものになりたがっているのか、まるで人のように、それに対して、接する側は優しく。
何をつくるか、考えられる事はたくさんあり、やってみたい事もたくさんあるが、それが建築として成り立つか、成り立つとはこなれているか、しっくりいっているか、などと抽象的な表現になってしまうが、どうも、やり過ぎてしまったり、考えだけが先走ってしまったりして、まとまりが悪くなるようなことは避けたくて。
きっと、どうなりたがっているか、というのは、無理がないというか、肩の力が抜けているというか、必然であり、妥当であり、調和されたような状態なのかと。
ただ、それは決して、今までの焼き直しのような建築ではないのは確かなことだし、それは望んでいない。
ちょっと自分から離れて、客観的に見るために、まるで人のように接してみるのも良いかと思い。
"Like a person"
So I decided to think about what kind of building I wanted to stand up to.
It is not a story that is inferred from the client's request, etc. If an architecture stands in that place, what kind of architecture it wants to be like, as if it is a person, the contact side is gentle .
There are a lot of things you can think of, and a lot of things you want to do.However, it becomes an abstract expression that it can be realized as an architecture, that it is not well-formed, or that it fits nicely. But, I don't want to be too overkill or just thinking ahead, so that things don't get cohesive.
I guess what I want to do is whether it's easy, my shoulders are loose, or it's inevitable, appropriate, and harmonious.
But it's certainly not the kind of architecture that we've ever done, and we don't want it.
I think it's a good idea to get away from yourself and see it objectively, as if you were like a person.
壁が梃子の支点の役割をするように、村上春樹の「梃子」の話が頭から離れない、それを今、自分が考えている空間に当て嵌めると、どうなるか。
空間がそこにいる人しだいで見え方が変われば、それが人と建築の関係性においては良いことだろうと考えていて、それも人の気分しだいで、何か作用して見え方が変われば良い、壁を梃子にして、気分という推進力を得て、建築を増幅させる。
そう考えていると、空間は様々な物が寄せ集まってできているが、ずっと前から、建築を学びはじめた頃から、空間は実体があるけれど、目で見ることはできず、感じることしかできない、空気のような存在だと、何故か思っていて、そうなると、空間自体にはあまり興味が無く、その様々な物が寄せ集まってできている状態に興味が湧くのだと改めて思った。
だから、建築の中にある物、全てに興味があり、家具、食器やカトラリー 、調理道具などなど、それらも建築の範疇だと考えている。
ただ、例えば、住宅ならば、自邸はともかく、住人がいて、設計者がいる、という関係性の中で、どこまで関わることができるかという想いが常にあり、全てをコントロールをしたいと思いつつ、それでは、何か予想外のことが起こらないからつまらない、という想いもあり、それでどうするかが設計の際の常に中心にある考えのひとつだった。
"Various collections"
Just as the wall plays the role of a lever, the story of Haruki Murakami's "Lever" will not be left out of my mind.
I think that if the appearance changes depending on the people in the space, it will be a good thing in the relationship between people and architecture, and if that also depends on the mood of the person, if something acts and the appearance changes Good, leverage the walls, get the driving force of mood and amplify the architecture.
If you think so, the space is made up of various things, but since long ago when you started studying architecture, the space has substance, but you can not see it with your eyes, you can only feel For some reason, I thought that it was impossible, like an air, and I realized again that I was not interested in the space itself, and that I was interested in the state that various things gathered together.
Therefore, I am interested in everything in the architecture, including furniture, tableware, cutlery, cooking utensils, etc., and consider them to be in the category of architecture.
However, for example, if it is a house, there is always a feeling of how much you can be involved in the relationship that there is a resident, a designer, aside from your own residence, and you want to control everything, There was also the idea that something unexpected was boring because nothing unexpected happened, and what to do with it was one of the always central ideas in design.
学生の頃から建築を見続けてきて、自分なりのこれが良い建築という基準のようなものが、感覚的にも、思考的にも出来上がっている中で、それとは違う建築が自分の意識の中で立ち上がりつつあり、ただそれは、そのままでは、自分なりの基準に照らし合わせた時に、良い建築とはなかなか判断されない。
少し建築に対する興味の対象が、今までとはズレてきているように思う。人と建築の関係性がまずあって、それはとても些細なことで、日常的なことで、どこでも起こり得ることで、その関係性を構築することをまず考えて、それを展開していった結果、総体として建築が出来上がる。
はじめに建築がある訳ではなくて、あるのは人との関係性だけであり、人との関係性を構築するものが建築以外ならば、それを展開していった結果、総体として出来上がるものは建築以外になる。
今まで見てきた建築は、建築として、建築単体として、とても強度があり、建築のみで成り立つ、全てを規定してしまうような力があった。それは魅力的で惹かれ、自分なりの基準を築く礎になった。
しかし、建築は、人が空間の中に入り、アクティビティが展開されることで、建築としての本来の姿になるとすると、そこでは、人と建築の関係性のみが重要であり、そこから展開していった結果、総体としての建築の姿は、唯一ひとつに決まるものでもなくなり、必ずしもひとつである必要もなくなる。それの方が面白いではないかと思ってしまった。
"Architecture"
I have been looking at architecture since I was a student, and while my own standards of good architecture are being made both intuitively and intuitively, different architectures are in my consciousness. However, it is not easy to judge a good architecture as it is when compared to your own standards.
I think that my interest in architecture has shifted slightly from before. There is a relationship between people and architecture first, it is very trivial, everyday, it can happen anywhere, the result of thinking first about building that relationship and developing it As a whole, construction is completed.
At first, there is no architecture, but only the relationship with people.If the thing that builds the relationship with people is something other than architecture, as a result of developing it, Beyond architecture.
The architecture we have seen so far is very strong as an architecture or as a building alone, and has the power to regulate everything that can be realized only by architecture. It was fascinating and fascinating and laid the foundation for setting your own standards.
However, in architecture, if people enter the space and activities are developed, it will become the original form as architecture, where only the relationship between people and architecture is important, As a result, the appearance of architecture as a whole is no longer the only one, and it does not have to be one. I thought it would be more interesting.
創作の態度として、村上春樹の『職業としての小説家』からよく考えさせられることがあるのだが、その中で「梃子」という表現が二度出てくる。
『もともとあったかたちと、そこから生じた新しいかたちの間の「落差」を通して、その落差のダイナミズムを梃子のように利用して、何かを語ろうとするわけです』
『架空の「僕」を梃子の支点にして小説世界を立ち上げ、広げていくことをひとつの目的としていた』
村上春樹は創作に梃子の役割をするものが必要だと考えているようだ。梃子は小さな力を大きな力に変えてくれるもの、素のものを増幅させてくれるもの、それは別の言い方をすれば「作品化」かもしれない。
何でもない日常の出来事を小説という作品に変えるために梃子を利用する。その梃子をどのように使うかが作者の力量ということか。
"lever"
Haruki Murakami's "Fictionalist as an Occupation" is often thought of as a creative attitude, but the expression "leverage" appears twice.
"Through the 'head' between the original form and the new form arising from it, we try to leverage the dynamism of the head like a lever and speak something."
"One purpose was to launch and expand the novel world with the fictional" me "as the leverage point."
Haruki Murakami seems to think that something is needed to play a role in creation. Leverage is what transforms a small force into a great force, and amplifies the elementary one, which, in other words, may be a "work of art".
Leverage leverage to turn anything but everyday events into novels. How to use the lever is the ability of the author.
なるべくふわっとした感じで、最初は捉えるようにして、分析的に見るのは楽しくないのと、分析的につくりたくはないので、何故そうなるのかは、わからないか、後づけで良いではないかと考えている。
いろいろと考えを巡らせたり、イメージをしたりするのは、分析をするためではなくて、坐りの良い場所を探すため、納まりの良い位置に置くため、それを決めるのは分析の結果ではなくて、しっくりくるかどうかの感覚的なこと。
だから、意外と根拠がない、あったとしても後づけ、それに自信が持てないと分析したくなるのだろう。そうすれば、頭では理解される。そういうものがつくりたい人はそれで良いが、そういうものは心に響かない、印象に残らない。
ただ、全く分析的ではないかというと、そうではなくて、自分勝手に分析的に展開している時もあるが、それは分析的というより、何かを試行錯誤するための自分勝手な思い込みを整理しているに過ぎない。
まあ、ちょっとばかり、辻褄が合わず、抜けているくらいが、より魅力的に見えるようなもの。
"One who does not analyze"
As soft as possible, try to catch it at first, and it is not fun to see analytically, and I do not want to make it analytically, so I do not know why it is so, I think that it is good to add it later ing.
It's not about analysis, but about finding ideas and thinking about images, not about doing analysis. The sensation of whether or not it will come nicely.
So, it is surprisingly unfounded, and if you do, you will want to analyze it later if you are not confident. Then you can understand in your head. That's fine for those who want to make such things, but those things don't resonate and don't leave an impression.
However, sometimes it is not analytical at all, but sometimes it is developing analytically on its own, but rather than analytical, it is a self-assured assumption to try and error something. It is just organizing.
Well, a bit, inconsistent and missing, something that looks more attractive.
極限までに簡素にした時、捨てられる部分が豊潤であり、複雑であり、その部分に興味が湧く。それは、あくまでも簡素化を経た後に捨てられた部分であり、はじめから豊潤で複雑なものには興味が無い。
要するに、捨てられた豊潤で複雑な部分は、捨てられる段階で、余分なものを切り離し、より洗練される。
この一見まどろっこしい生成の仕方が建築に合うような気がする。三次元で、実際に内部に入ることができて、体験ができる、そして、表現物である建築は、人と接している面も大きく、時間も長いから、様々なやり取りが人と建築の間で可能になる。
だから、より深く広がりを持って何かを建築から人に伝えようとすることが可能であり、その時の手段として、いくつもの段階を経ることも可能であり、それは長編小説と読者の関係性に似ているのかもしれない。
"Madoshy generation"
When simplified to the utmost extent, the discarded parts are abundant, complex, and interesting. It is a part that has been abandoned after simplification, and I am not interested in things that are rich and complex from the beginning.
In short, the abundant and complex parts that are discarded become more sophisticated when they are discarded, cutting off the excess.
I feel that this seemingly sloppy way of generation fits in with architecture. In three dimensions, you can actually enter the interior and experience it.Because the architecture, which is an expression, has a large surface in contact with people and a long time, various exchanges between people and architecture Is possible.
Therefore, it is possible to spread something deeply from architecture to humans, and at that time it is possible to go through a number of stages, depending on the relationship between the novel and the reader. It may be similar.
極限までに簡素にしながら、そこで表現されていることをある角度から見ると豊潤で複雑に見えるには、どうしたら良いのだろうかと考えてみる。
矛盾したことが同時に成り立つには、並列では無くて、どちらかが包括的で、その中にもう一方が存在する形しかないだろう。
極限までに簡素にするということは、捨てる部分がたくさんあり、尚且つ、その捨てる部分の存在が明確にわかるから、対比して簡素さが際立つ。
だから、今度は、その捨てる部分に焦点を当ててやれば、豊潤で複雑に見えるようになるのではないかと考えを進めてみる。
"Abundant and complicated"
Let's consider how to make the expression expressed in a certain angle look rich and complex, while keeping it as simple as possible.
In order for the contradictions to hold at the same time, there is no parallel, only one form that is inclusive and the other in it.
Simplifying to the utmost limit means that there are many parts to be discarded, and the existence of the discarded parts is clearly understood.
So I'm going to think that if we focus on that discarded part, it might look rich and complex.
人の感情や気分を単純化して捉えようとすれば、それは誰か自分とは違う人の感情や気分を推し量ろうとする時に、まずは単純化して、わかりやすく捉えようとするのと同じように、枝葉の部分を切り落として、太い幹の部分だけ把握するようにはできるが、それでは本来の姿を捉えきれないから、枝葉の部分を切り落とさずに、ありのまま、そのままに捉えようとすると、それはすでに単純化ではなく、複雑なことを複雑のままに捉えることになる。
ただ、それができれば良いが、人はたぶん、自分なりのフィルターを持っていて、そのフィルターを通して、自分にわるように単純化をして物事を捉えるだろうから、それと同じことを何にでもするだろうから、単純化自体をしないことはできない。
ただ、他人のフィルターは自分とは違うから、人は単純化してるいるつもりでも、側から見たら複雑怪奇に見えるかもしれない。
それを利用すれば、単純化しているのに、複雑なことを複雑のままに見せることができる。要するに、定説的なフィルターでは無い、新たなフィルターを用意して単純化してやれば良い。
"A new simplification"
If you try to capture the emotions and moods of a person in a simplified way, it's the same as trying to guess the emotions and moods of someone different from you first, just like trying to simplify and understand them easily. It is possible to cut off the branches and leaves so that only the thick trunk can be grasped, but it is not possible to capture the original shape, so if you try to capture the branches and leaves as they are, it is already simple It's not about becoming complex, but about complicated things as they are.
I just want to be able to do it, but people will probably have their own filters, and through those filters, they will do things the same way, simplifying them as if they were, and doing the same thing So simplification itself cannot be avoided.
However, because others' filters are different from yours, people may seem simplistic, but they may seem complicated when viewed from the side.
With it, you can make complicated things look complicated, while they are simplified. In essence, you can prepare a new filter that is not a conventional one and simplify it.
日常の中での気分や感情が、その人特有の物語を生むのだろうと想像している。ならば、その気分や感情を受け止める建築をつくることができれば、その建築はその人特有の建築になる。
それは、建売などの住宅に自分を合わせていき、自分だけの建築にするのとは訳が違い、建築自体が人の気分や感情が無いとそもそも成り立たない、人の気分や感情が建築の構成要素のひとつになっている、それが、今、構想している建築の辿り着きたいところ。
それを成り立たせるためには、具体的な仕組みが必要になるだろう。そうで無いと、単なる観念的な建築になってしまう。
人の気分や感情が反映された建築の断片が集合して、ひとつの建築になるが、その集合の仕方に、『職業としての小説家』で村上春樹が書いている、何か特別なマジックというか、物語性のようなものが必要になる。その何か特別なマジックというか、物語性のようなものが建築家の建築性であり、そこで新たな建築性を獲得できれば、既視感の無い建築が生まれるだろう。
"Assembly-based assembly"
I imagine that the moods and emotions in everyday life will create a unique story. Then, if you can create an architecture that captures the mood and emotions, the architecture will be unique to that person.
It is different from building your own house in a house for sale, etc., and making it your own architecture, the building itself does not work if there is no mood or emotion of people, the mood and emotion of people is the composition of architecture It is one of the elements, that is where I want to reach the architectural concept that I am currently envisioning.
To make that work, a concrete mechanism will be needed. Otherwise, it will be just an idealistic architecture.
Fragments of architecture that reflect people's moods and emotions are assembled into one architecture, but the way of assembly is something special Magic Haruki Murakami wrote in "Fictionalist as a profession" Rather, something like narrative is needed. The architect's architectural property is something special or narrative, and if we can acquire a new architectural property, an architecture without a sense of sight will be born.
ここが見せ所という部分を意識的につくり、写真写りの良い所をつくり、そのワンカットという断片が流布するような状況は、ネットが当然無い、写真しか無い近代建築では、建築作品を世界中に広めるための手段で、それに批判がありつつも、現代建築は近代建築が素になっているから、現代建築でも同じような状況であり、ネットが当然の状況では尚更、断片的な見せ方でどのように伝えるかが重要になり、無意識のうちに、断片を重要視しているように思う。
断片という細部で全体を暗示するやり方も当然あるが、建築や空間は、人よりも規模が大きいから、わざわざ細部で全体を暗示してやらなくても、実際に体験をすれば全体を把握できる。
そこで乖離が起きる、ネットで流布された断片から暗示される全体と、体験した場合の全体とで。それは当然そういうこともあるのだが、大概は、断片をネットで見る方が先で、体験が後になり、断片を見て良いなと思ったから体験したくなるので、その乖離はガッカリになる。
断片から全体を暗示させることはできるが、その断片の集合だけで全体を構成している場合にガッカリするようだ。
断片の集合に、何か特別なマジックというか、物語性のようなものがないと、実際の体験では見劣りしてしまう。そのマジックや物語性の構築が建築家の能力の見せ所だと思う。
"A collection of fragments"
In this situation, where the consciousness of creating a part called a show place, creating a place where photos are good, and the fragment of one cut are circulating, in modern architecture without a net and only photographs, the architectural works are all over the world. Although modern architecture is based on modern architecture, it is the same situation in modern architecture, even though there is criticism for it. I think it's important how to convey it, and I'm consciously thinking about fragments.
Of course, there is a way of suggesting the whole with the details of fragments, but architecture and space are larger than people, so even if you do not bother with the details in detail, you can grasp the whole by actually experiencing it.
There is a divergence between the whole that is implied from the fragments spread on the net and the whole that you experience. Of course, that's the case, but in general, it's better to watch the fragments on the net first, and later to experience it, and because it's good to see the fragments, you'll want to experience it.
Fragments can be used to suggest the whole thing, but it seems disappointing if the whole set is composed of just that set of fragments.
Without a special magic or narrative in a set of fragments, the actual experience is inferior. I think that the construction of magic and narrative is a highlight of the architect's ability.
三人称の視点で設計してみる。それは建築計画学上は当たり前のような気がするが、それでは、誰が設計しても同じような建築しかできないような気がするので、一人称の視点の割合が多くなるが、それではどうしても局所的なデザインしか生まれないような気がして、小説の視点の違いから思いを巡らせてみた。
三人称の視点の方が小説においては、より複雑な物語が描けるらしいが、その分、難易度も上がるらしい。物語に俯瞰したような広がりと、さらに細かいところまでも対象にできる奥行きが出るからだろう。作者の想像力しだいで、描けない世界が無くなるような気がする。
建築では、不特定多数の人が使用する公共施設などでは、否応なしに三人称の視点が必要になるだろうし、それが当たり前のこととして行われているが、三人称の視点が建築に、より広がりやより奥行きを与えているようには思えない。どちらかと言えば、過不足無い建築が出来上がるために使われているように思える。
それは、小説のように、建築を広がりと奥行きのあるものにしょうという意図で三人称の視点を必要としていないからだろう。だから、余計に三人称の視点による設計に可能性を感じる。
"Differences in viewpoints"
Design from a third person perspective. It seems natural in architectural planning, but it seems that no matter who designs it, only the same architecture can be done, so the percentage of first-person perspectives increases, but then it is absolutely local I felt that only design was born, so I thought about it from the viewpoint of the novel.
It seems that a third-person viewpoint can draw more complicated stories in a novel, but it also seems to be more difficult. Probably because the story looks like a bird's-eye view and the depth that can be targeted at even smaller details. Depending on the imagination of the author, I feel that the world that cannot be drawn disappears.
In architecture, in public facilities used by an unspecified number of people, a third-person perspective will be necessary without necessity, and this is done as a matter of course, but the third-person perspective spreads to architecture more widely It doesn't seem to add any depth. If anything, it seems that it is being used to create an architecture that is perfect.
That's because, like a novel, it doesn't require a third-person perspective with the intention of making the architecture more spacious and deep. Therefore, I feel the possibility of designing from a third person perspective.
ずっと一人称で設計してきたような気がする。クライアントの要望を聴いて、時にはその人格になりきって、空間を体験していくように設計をしていく。
だから、要望を聴いていく中で、すでに頭の中に空間が出来上がっていることも多く、計画案をまとめる時は、その頭の中に出来上がった空間をトレースするように、あとは諸条件に合わせてやれば良いだけである。
なぜか、頭で考えたことではなく、体感したことでしか空間はつくれない、と思い込んでいるところがあり、自身が空間を頭の中で、まず擬似的に体験し、それが過去に自分が体験した空間と比較して良いことが判断基準となる。だから、ならばクライアントの人格になりきって、擬似体験をするのが良いだろうと自然になってくる。
それは、自分にしかつくれない空間をつくろとすると、どうしても自分が今までに経験した空間を超えたいという欲が出てくるので、どうしても一人称でいろいろと思索して、まず自分がその空間を良いと判断しないと先に進まないからでもあるだろう。
そこで、三人称で考えてみると、どうなるだろうと思った。すぐに思ったのは、客観的になるだろうと、そして、頭で考えたことと体感したことがミックスされて、今までつくってきた作品とは違うものになるかもしれないと、そして、それは作品がスケールアップするように感じ、試してみる価値はありそうだと思った。
"Designing in Third Person"
I feel like I've been designing for the first person. I listen to the client's requests and sometimes design my personality to experience the space.
Therefore, while listening to the request, there are many cases where space has already been created in the head, so when compiling the plan, trace the completed space in the head, It just needs to be done.
For some reason, some people think that space can be created only by experiencing it, not by thinking with their heads. A good criterion is to compare with the space you have experienced. So it's natural to become a client and to have a simulated experience.
That is, if you try to create a space that can only be created by yourself, you will inevitably want to exceed the space that you have experienced so far. It will be because you cannot proceed unless you judge.
So, in the third person, I wondered what would happen. I immediately thought that it would be objective, and that what I thought and felt in my head would be mixed, and that it might be different from the work I had made so far. I felt the work scaled up and thought it was worth trying.
銀座松屋で開催されている「利久のかたち」展の起こし絵を立体的に空間化した利久作の茶室「待庵」の再現にて、「窓を残して壁をつくる」との記載を見つけ、その言葉に感覚的に反応してしまった。
待庵の窓は、土壁を四角状に塗り残しただけで、小舞と呼ばれる格子状の塗り壁下地がそのまま見える。だから、窓と壁の違いは、土壁があるかないかだけであり、そうすると、窓は壁の一種であり、窓は壁の派生であり、窓は壁の装飾だと見ることもできるだろう。
窓と壁は分離した要素であり、窓には採光や換気や眺望などの機能があり、壁には構造や断熱などの機能があり、それらの機能を満たした上でのデザイン上の窓配置を決めるのが近代建築以降の窓と壁の関係性であり、そこでは窓は独立した建築要素だった。
ところが、待庵では窓が壁に対して従属的な扱いになり、窓は土壁を四角状に塗り残しただけだから、壁に対して窓配置がどこでも良いことになる。
そのことは、今そこに窓がある必然性が無くなることであり、それは窓として不完全な状態を保有し続けることになり、その不完全な状態の窓を補う何かが必要になってくる。
その補う何かが、その空間が茶室であることにつながってくるのだろうと想像した。
"The window of Taian"
In the reproduction of the tea room "Taian" of Rikyu-saku, which is a three-dimensional spatialization of the drawing of the "Shape of Rikyu" exhibition held at Ginza Matsuya, I find a description that "I will leave the window and make a wall" , And responded intuitively to the words.
In the window of Taian, the basement of the lattice-shaped painted wall called Komai can be seen as it is, just leaving the clay wall in a square shape. So the only difference between a window and a wall is whether or not there is a mud wall, and then you can see that the window is a type of wall, the window is a derivative of the wall, and the window is a wall decoration .
Windows and walls are separate elements, windows have functions such as daylighting, ventilation and views, and walls have functions such as structure and heat insulation, and the window arrangement in the design after satisfying those functions It is the relationship between windows and walls since modern architecture, in which windows were independent architectural elements.
However, in Taian, the windows are treated subordinate to the walls, and the windows are simply painted on the earthen walls in a square shape, so the windows can be placed anywhere on the walls.
That means that there is no longer any need to have a window there, which will continue to have an imperfect state as a window, and will need something to compensate for the imperfect window.
I imagined that the supplement would lead to the space being a tea room.
黒豆を煮ている。お正月が過ぎたのに、今年すでに2回目、年末に1回煮たので、今季3回目である。150gずつ少量だが、2種類の丹波の黒豆を、新豆と古豆を使い分けて味比べ、そもそも豆を煮るのが好きで、煮ている時の豆の匂いが家中に充満して、昔は窓ガラスが結露したりして、その匂いが子供の頃の記憶と結びついて、いろいろな情景が蘇る。その匂いを嗅ぎたくて、豆を煮ている雰囲気を味わいたくて、キッチンで仕事をしているくらいだ。そして、もっと好きなのが、豆を戻すこと。鍋に水をはり、豆を入れて、一晩以上かけて戻すのだが、翌朝、鍋の蓋を開けるのが楽しみでしょうがない。毎回、豆の増え方に驚いて感心する。とにかく時間がかかる。他の人は知らないが、黒豆を煮るのに2日をかける。1日かけて戻し、3〜4時間煮て、1日おく。豆を煮るのにもっと簡単なやり方があるのは知っているが、圧力鍋やポットを使う方法など、それでは満たされない、豆を煮たい気持ちが、大豆ならば水煮がスーパーで売られているから、そのまま煮る必要がなく使えるし、煮豆だってわざわざを作らなくても、かえって自前でつくった方が少量だったらコストがかかるし、味だって、自分好みに調整はできるが、素人がつくる訳だから商品より美味しいということはない。ただ、つくりたくて、できた黒豆は自分だけの愛しい黒い宝石のように輝いて見える。
全く同じことである。自分だけの空間になる、それも、つくりたい気分のような単純な動機で、自分が反映された空間や建築になる、水煮の大豆や市販の煮豆のような空間や建築に自分を合わせるのではなくて、自分好みの黒豆をつくるように空間や建築に仕立てる、それを日常の中で行う、今、スケッチしながら、黒豆を煮ながら、その仕組みを考えているところ。
"While boiling black beans"
Boiled black beans. This is the third time this season since the new year has passed, but it has been boiled for the second time this year and once at the end of the year. It is a small amount of 150 g each, but I compare the taste of two types of Tamba black beans, using new beans and old beans, I like to boil beans in the first place, the smell of beans when boiling is filled in the house, The dew condensation on the window glass and the smell of the window are linked to the memories of childhood, and various scenes are revived. I want to smell the smell, taste the atmosphere of boiling beans, and work in the kitchen. And my favorite thing is to return the beans. Fill the pot with water, add the beans, and let it return over more than one night. The next morning, I'm not looking forward to opening the pot lid. Every time, I am amazed and impressed at how beans increase. It takes time anyway. Others don't know, but take two days to boil black beans. Return over 1 day, boil for 3-4 hours, leave for 1 day. I know there are easier ways to boil beans, but the pressure cooker and pot methods are not enough, so if you want to boil beans, soybeans have boiled water sold at supermarkets Therefore, you can use it without having to boil it as it is, even if you do not make boiled beans, it will cost more if you make a small amount on your own, and you can adjust the taste as you like, but it can be adjusted to your liking, but it is made by an amateur Nothing is better than a product. However, I want to make it and the resulting black beans look like my own beloved black jewel.
Exactly the same. Become a space of your own, with a simple motivation to feel like creating a space or architecture that reflects you, or adapt yourself to a space or architecture like boiled soybeans or commercially available boiled beans Instead of creating black beans that you like, you make it into space and architecture, do it in your daily life, and now you are thinking about the mechanism while sketching and boiling black beans.
建築の特徴のひとつに人のアクティビティが内部で起こることがある。逆に言えば、内部で人のアクティビティが起こらなければ建築とは言えない。
人のアクティビティは様々な方向に、自由に起こすことができる、しかし、その方向は建築に左右される。だから、人のアクティビティが建築デザインの対象になるとも言えるが、これが何とも不自由である。
当然だが、建築は人のアクティビティのみで決まる訳ではない。その他の要素、例えば、建築の構造、法規、予算など、まだまだたくさんあるが、およそそれらのほとんどが人のアクティビティを制限するものばかりと言っても過言ではない。
建築の中で、日常生活に直結するのは、人のアクティビティであり、それが制限されるということは、日常生活が制限されることでもある。
だから、余計に人のアクティビティがいつの時代でも建築のデザインの対象として扱われ、そこでどのような折り合いをつけるのか、強引に引き寄せるのか、他を無視するのかなど、様々なアプローチが存在する。
いずれにしても、この不自由さから逃れるためにスケッチをしているといつも思ってしまい、大半の時間を自由への道を探すために使っているように思う。
"Free search for activities"
One of the architectural features is that human activities occur inside. Conversely, if there is no human activity inside, it cannot be called architecture.
Human activities can occur freely in various directions, but the direction depends on the architecture. Therefore, it can be said that human activities are subject to architectural design, but this is inconvenient.
Naturally, architecture is not determined solely by human activity. There are still many other factors, such as architectural structures, regulations, budgets, etc., but it's no exaggeration to say that most of them only limit human activities.
In architecture, what is directly connected to daily life is human activity, and limiting it means limiting daily life.
Therefore, there is a variety of approaches to human activities that are always treated as an object of architectural design at any time, such as how to make arrangements, forcibly attract, or ignore others.
Either way, I always think that I'm sketching to escape this inconvenience, and I spend most of my time looking for a way to freedom.
不整形に閉じた箱がある。箱は人が入ることができるから空間と呼ばれる。
なぜ不整形かは、壁の厚みが一定ではないからだ。では、なぜ壁の厚みが一定ではないのか、壁の中に設えが仕込まれているから、その設えは日常の人の営みに必要なもの、それはあらゆるものが対象になる、基準が日常に必要なものだから、何でも良い、設えの種類を選ばない。
それは、観念的なことと構造が一体となった様がそこにある。どういうことか、壁の厚みは日常の人の営みの違いを現している、それは観念的に人が頭の中で考えること、だから、いちいち壁の厚みに仕込まれているものを確認せずに近づく、それはもはや情景反射のようになっている、そのこと自体がここの空間での仕組みであり、ここの空間が成り立つための構造になっており、まさにそれは、ここの空間に日常的にいる人にだけ起こること。
そして、不整形な箱だけに、人がいる場所により、空間の見え方が違う、それは日常の中で人の営みが行われる度に起こること。
だから、この空間がつながり、重なり合って建築になれば、その建築は日常の人の営みによって見え方が変わる。
ところで、日常の人の営みは何によって支配されているのだろうか、理性か、それとも感情か、どちらか一方ではないだろうが、どちらが勝るか、どちらでも良いが、この空間ではどちらか勝った方が建築の見え方を支配する。
いずれにせよ、日常の人の営みにより建築の見え方が決まる、願わくば、感情、それも気分で見え方が変われば、日常の生活により潤いが出るような気がする。
"What Architecture Can Do Everyday"
There is an irregularly closed box. Boxes are called spaces because people can enter them.
The reason for the irregularity is that the wall thickness is not constant. Then, why the thickness of the wall is not constant, because the installation is installed in the wall, the installation is necessary for everyday people's work, it is for everything, the standard is necessary on a daily basis Whatever it is, it doesn't matter what type of installation it is.
It is there that the idea and the structure are united. What that means is that the thickness of the wall shows the difference in the daily activities of people, that is, the idea that people think in their minds, so without having to check what is being built into the wall thickness each time Approaching, it is no longer like a scene reflection, it is a mechanism in this space itself, it is a structure for this space to be established, exactly it is everyday in this space What happens only to people.
And the appearance of the space differs depending on the place where people are located only in the irregular box, which happens every time human activities are performed in daily life.
Therefore, if these spaces are connected and overlap to form an architecture, the appearance of that architecture will change depending on the daily activities of people.
By the way, what is governed by the daily activities of human beings, whether it is reason or emotion, it is not one of them, but whichever is better, whichever is better, but either won in this space The one who controls the appearance of architecture.
In any case, the appearance of architecture is determined by the activities of everyday people. Hopefully, emotions, and if the appearance changes depending on the mood, it feels more moist in everyday life.
動くわけではないが、建築が人にアジャストして、それによって建築の見え方が変われば、素敵な建築になるかもしれない。
アジャストするとは、人の営み、あるいは、人の営みを決める想いや気分によって、建築の見え方が変わること。
何か、ゆらぎのようなものがあって、ひらひらと風によって形を変えるような、ゆらぎのようなものが建築で、風が人の営み、そのようなイメージ、確か、昔、建築家の伊東豊雄が自身の建築のことを「風の変容体」と称していたと思うが、そこまで強い全体像というか、強い形態を持たず、もっと部分的で、もっとありふれたどこにでもある形で、しかし、誰もそのことに気づいていないような存在のもの。
この建築に対する観念的なことを実現可能なところまでに持っていくためには、構造に目を向けるしかないと考えた。
この場合の「構造」とは、別の言い方をすると「成り立ち」や「仕組み」であり、その成り立つや仕組みだけに目を向けても何だかわからないが、その成り立つや仕組みを積み上げていくと、ひとつの形として完成する。
まるでそれはレゴ(LEGO)のようである。気分でひとつひとつレゴのブロックを積み上げていけば、それは何かしらの形になり、気分で積み上げ方を変えれば、また別の形になる。
そのようなことが、日常の建築空間の中でできないものかと思案中である。
"Like LEGO"
It doesn't move, but if the architecture adjusts to people, which changes the way the architecture looks, it might be a nice architecture.
Adjusting means that the appearance of architecture changes depending on people's activities or the feelings and moods that determine people's operations.
There is something like a fluctuation, and the shape that fluctuates due to the wind fluttering is the architecture, the wind is the work of people, such an image, surely, in the past, the architect Ito I think that Toyoo called his architecture "transformation of the wind", but it was not so strong a whole image, or a strong form, more partial and more ubiquitous, but , Something that no one is aware of.
In order to bring this idea of architecture to the point where it can be realized, I thought that I had to look at the structure.
In other words, the term "structure" is, in other words, "composition" or "mechanism", and it is not clear what the focus is on the composition or mechanism. Completed as a shape.
It's like LEGO. If you pile up the LEGO blocks one by one with your mood, it will take on some form, and if you change the way you pile up with mood, it will take on another form.
I am wondering if such a thing can not be done in everyday architectural space.
人の営みは複雑だから、人の営みの部分を複雑のままに表現すればよく、それが複雑だとわかるためには、単純な所から眺めなければならない。この関係性を建築に置き換えればよく、あとは人の営みの複雑さを反映する仕組みを組み込めばよい。
それこそ、複雑なことを受け止めるものが単純な仕組みでないと、複雑さがわからないし、かえって煩雑になる。
その単純な仕組みは、選択できる状態であり、人の営みの複雑さを包括的に受け止めて表現できることが求められる。
だから、人の営みの複雑さを複雑なままに見せるが、そのまま見せるのではなくて、何かに置き換えて見せることになる。その何かが建築の一部分になり、人の営みの複雑さを反映した建築になる。
そして、人の営みには様々な種類があるが、全ての営みに影響を与える、人の「気分」によって選択できる状態を単純な仕組みで形にすることを目論んでいる。
"Simple mechanism"
Because human activities are complicated, it is only necessary to express the complexities of human activities, and to see that it is complicated, we must look at it from a simple point of view. You can replace this relationship with architecture, and then incorporate a mechanism that reflects the complexity of human activities.
That is, unless something that accepts the complexity is a simple mechanism, the complexity will not be known and rather complicated.
The simple mechanism must be selectable, and must be able to comprehensively capture and express the complexity of human activities.
Therefore, the complexity of human activities is shown as complicated, but instead of being shown as it is, it is replaced with something. Something becomes a part of architecture, and it becomes an architecture that reflects the complexity of human activities.
There are various types of human activities, and we are aiming to use a simple mechanism to create a state that can be selected according to the "mood" of a person, which affects all activities.
複雑なことを複雑なままに理解するためには、それを単純な所から見ていなければ、単純な立ち位置からでないと理解できないかもしれない。それは、複雑なことと単純なことが入り組んだ空間、あるいは、単純な空間の中に入れ子状の複雑な空間があることかもしれない。
ずっと建築とは、複雑なことを単純化する作業だと考えてきた。単純化のために様々な論理や技術が存在していて、単純化の深さみたいなものを深めるためにも様々な論理や技術が存在している。
高度な単純化を成し遂げるためには、高度な論理と技術が必要で、ただ、それが建築の優劣に直結しないのも、建築としての面白さのひとつだが、それは位置エネルギーのようなもので、より高度な論理や技術からスタートした方が、より良い建築にたどり着く可能性が高いようにも感じていた。
だが、複雑なことを複雑なまま見せる建築が気になり出す。複雑なことを単純化した建築は、単純化の過程で何かを捨てることになり、その捨てた中にというか、捨てずに全てを包括的に抱き込んだ建築の方が、人に訴えかけるものがあるのではないかと、複雑なことを単純化した建築も人に訴えかけるものがあるが、それは多くの場合、単純化の洗練さに惹かれるのであって、だから、建築家の能力の見せ所にもなるが、そうではない、建築という物自体が持つ魅力のようなもので人を惹きつけるような、そのために、複雑なことを複雑なままにとどめておける状態をつくり出したいと考えている。
"It remains complicated"
In order to understand a complex matter as it is, it may not be possible to understand it from a simple standpoint unless it is seen from a simple point. It may be a space where complexity and simplicity are mixed, or a nested complex space within a simple space.
I've always thought that architecture is the task of simplifying complex things. There are various logics and technologies for simplification, and there are various logics and technologies for deepening the simplification.
Achieving a high degree of simplification requires advanced logic and technology, and one of the interesting things about architecture that does not directly relate to the architectural quality is that it is like potential energy, I also felt that starting with more advanced logic and technology was likely to lead to better architecture.
However, I am worried about architecture that shows complicated things as complex. Architecture that simplifies complicated things means throwing away something in the process of simplification, and architecture that embraces everything comprehensively without throwing it away appeals to people. Simplifying complicated things can appeal to people, but there are many things that appeal to people, but it is often attracted to the sophistication of simplification, so the ability of the architect But it's not like it, but it's like attracting people with the charm of architecture itself, so we want to create a state where we can keep complex things complicated. thinking.
軽快な空間を求めている訳ではないが、かと言って、重厚な空間を求めている訳でもない。現代建築では、軽快さも、重厚さも、極限のものまですでに存在していると言っても過言ではなく、もちろん、イマジネーションを補完する技術の進歩により、あるいは、技術の進歩がイマジネーションを触発することにより、より軽快な、より重厚な空間が出現するだろうし、それは是非見てみたいものだが、より大きく、より高い建築を求めていくのと同じで、量的な尺度の違いのような気がして、そこには興味が持てない。
また、空間の軽快さも、重厚さも建築的な修辞として、そのように表現することと捉えることもでき、そのために素材やディテールなどをどうするかを考えるが、それは軽快さや重厚さに意味があるという態度だから、それが重要なことではなく、別にどうでもよいという態度ならば、軽快でも重厚でも建築の修辞上は大差がなくなる。
もし、建築の修辞上の軽快さや重厚さに興味を持てるとしたら、それをどのようにコンビネーションするか、建築的修辞を単なる機能的なツールとして扱うこと、ただそれはポストモダンのように、表層的に扱うのではなくて、人の内面と呼応するように扱った場合に限る。
"Lightness and solidness"
It doesn't mean that you want a light space, but that doesn't mean you want a solid space. In modern architecture, it is no exaggeration to say that both lightness and heavyness already exist to the extremes, of course, due to technological advances that complement imagination, or that technological advances inspire imagination. A lighter, heavier space will emerge, and it's something we'd like to see, but it feels like a difference in quantitative scale, just as we want bigger, higher architecture. I'm not interested there.
Also, the lightness and depth of space can be regarded as expressing it as such as architectural rhetoric, and we think about how to use materials and details for that purpose, but it is said that lightness and depth are meaningful Attitudes that aren't important, and don't matter, will make no difference in their rhetoric, whether light or heavy.
If you're interested in the lightness and weight of architectural rhetorism, how to combine it, treat architectural rhetorical as a mere functional tool, just like a postmodern, superficial It is limited to the case where it is handled not in the same way but in correspondence with the inner part of the person.
人のアクティビティによって決まる他律的な建築を可変以外の手法でつくろうとすると、何があるのだろうか。
すぐに思いつくのは、人の意識を利用することだが、気をつけないと、あまりにも観念的になり過ぎるような気がして躊躇してしまう。それでなくても、設計者は観念的になりやすい。頭の中だけで全体的なつながりを考えて、それをそのまま構築してしまい、おかしなことになっている建築がたまにある。それは設計者の姿勢としては悪いことではないと思うが、具体的現実との折り合いがもう少し必要になる。
可変でなければ、選択できるということもある。選択には人のアクティビティが伴う。人が選択することによって建築が決まる、それは他律的な建築になる。その場合は、建築が選択できる状態にあることをつくれば良い。
選択ということは、少なくとも1つの動線という指向性のアクティビティではなくて、複数の動線による無指向性に近いアクティビティが必要になる。
複数の動線による無指向性の空間はイメージできる、あとは具体的現実との折り合いであり、今回は集合住宅である。
"Selectable state"
What would happen if we tried to create a heterogeneous architecture determined by human activities by means other than variable?
The immediate idea is to use human consciousness, but if you are not careful, you may feel hesitant to be too ideological and hesitate. Even so, designers tend to be ideological. Sometimes thinking about the whole connection only in my head and building it as it is, there are some architectures that are going wrong. I don't think that's a bad thing for a designer, but it requires a bit more work with concrete reality.
If it is not variable, it may be possible to select. Selection involves human activity. Architecture is determined by people's choices, and it becomes a heterogeneous architecture. In that case, you just need to make sure that you can choose the architecture.
The selection does not require the directional activity of at least one flow line, but requires an omnidirectional activity with a plurality of flow lines.
An omnidirectional space with multiple traffic lines can be imagined, and the rest is a compromise with concrete reality.
人のアクティビティによって決まる他律的な建築をつくる手法のひとつとして、人のアクティビティに応答して建築自体が可変する手法がある。例えば、可動間仕切りによって部屋の広さを変えることによって、その時々の使い方に建築を調整することである。
ただ、それは確かに建築が他律的になることだが、別の見方をすると、建築が装置化することであり、それを良しとする考えもあるだろうが、建築デザインの精神性のようなことに興味を持っていて、人の内面にまで影響を及ぼす建築をつくりたいので、そうすると、装置化した建築には精神性を投影することができず、興味が持てない。
今まで見た建築で装置化の傾向があるものは、リートフェルトが設計した住宅で世界遺産にもなった「シュレーダー邸」で、この住宅は間仕切りだけではなく、様々なものが可変した。ただ、この住宅の特色は多色使いであり、壁や天井といった要素ごとに色を塗り分けて、それぞれの要素の自律性を高めており、それはむしろ人のアクティビティに左右されない自律的な建築を目指した結果だと考えて、その多色使いに精神性を投影できる可能性は感じたが、この住宅にそれ以上の興味は持てなかった。
だから、可変以外の手法で、人のアクティビティによって決まる他律的な建築をつくろうとしている。
"Not variable"
As one of the techniques for creating a heterogeneous architecture determined by human activities, there is a technique in which the architecture itself changes in response to human activities. For example, by changing the size of a room with a movable partition, the architecture can be adjusted to the usage at that time.
However, it is certainly that architecture will be heterogeneous, but from another point of view, it is that the architecture is computerized, and there are thoughts to make it good, but like the spirit of architectural design I am interested in things and want to create an architecture that affects the inside of a person, so I can not project the spirituality on the computerized architecture and am not interested.
The architectural trend we have seen so far is the Riedfeld-designed house, which became a World Heritage Site, the Schroeder House. This house is not only a partition, but various things can be changed. However, the feature of this house is multi-colored, and the color of each element such as walls and ceilings is painted differently to enhance the autonomy of each element, which is rather an autonomous architecture that is not affected by human activities I thought that it was the intended result, and felt the possibility of projecting spirituality to the multicolored use, but I could not have any more interest in this house.
Therefore, we are trying to create a heterogeneous architecture that depends on human activities, using a technique other than variable.
プロダクトは動かすことができるから、動かすことで見方を変えることができるが、建築は動かすことができないから、自ら動いて見方を変えるしかない。そこに、建築のデザインとして、人のアクティビティが入り込む余地が生まれ、それを活かすことが建築デザインの特徴のひとつだと考えている。
人のアクティビティには2種類あり、能動的か受動的か。能動的は自ら進んで動くことに建築が応答してくれるか、受動的は建築に用意されているアクティビティのルールに自らが応答するか。
別の見方をすると、能動的な人のアクティビティで成り立つ建築は、人のアクティビティによって決まるという意味で他律的であり、受動的な人のアクティビティで成り立つ建築は、人のアクティビティには左右されないという意味で自律的とも言える。
モダニズム以降で考えると、受動的な人のアクティビティで成り立つ自律的な建築が主流だった。
要するに、建築がまずあって、その建築に人は合わせる、と言うこと。例えば、病院を思い浮かべるとわかりやすい。病院という建築がまずあって、受診したい人は、その病院の受診ルールに従って、決められたルート通りに動くだけ、それは効率良く受診できるルールを考えた結果である。
自律的な建築は、行き過ぎると、効率性だけが重要視されるようになり、その結果、人は置き去りになる。だから、人のアクティビティによって決まる他律的な建築はできないものかと日々考えている。
"By activity"
Products can be moved, so you can change your perspective by moving them, but you can't move architecture, so you have to move and change your perspective. There is room for human activity as an architectural design, and I think that utilizing this is one of the features of architectural design.
There are two types of human activity, active or passive. Whether the active responds to the willingness of the building to move, or the passive responds to the rules of the activity provided in the building.
From another perspective, architecture consisting of active human activities is heterogeneous in the sense that it depends on human activities, and architecture consisting of passive human activities is not affected by human activities. In a sense, it can be said to be autonomous.
After modernism, autonomous architecture consisting of passive human activities prevailed.
In short, it means that there is architecture first and people adjust to it. For example, it is easy to understand if you think of a hospital. There is a building called a hospital, and the person who wants to consult only needs to move according to the determined route according to the hospital's consulting rules.
When autonomous architecture goes too far, only efficiency becomes important, and as a result, people are left behind. That's why I'm thinking everyday that I can't do other disciplined architecture that depends on people's activities.
断片的につなぎ合わせたデザインだと、何故か、ポストモダンの建築を思い出す。学生の頃だった、歴史的なデザインをモチーフにして、断片的に、装飾としてつなぎ合わせていた。それでも、学生の頃、参照していた建築はモダニズムの建築だったので、ポストモダンの建築を見る度に違和感しかなかった。
デザインを表層的に捉えて、その操作が建築のデザインの全てあるかのような態度にポストモダンの建築は映り、それがかえって建築デザインに対して、窮屈な想いと、嫌な感じしかなかった。
学生の頃は、建築デザインの精神性のようなことに興味を持っていたし、人の内面にまで影響を及ぼす建築とはどういうものかを考えていたので、表層的にデザインを扱うことはしたくなかった。
それは今も変わらないが、断片的なデザインのつなぎ合わせには興味がある。そもそもデザインは建築と人をつなぐためにあり、人は、人の精神性は、常に一定ではなくて、不規則に変化をするので、その不規則な変化に、動かない建築が応答しようとするならば、ひとつの可能性として、断片的につなぎ合わされたデザインが、その不規則な変化にシンクロするという回答もありうると考える。
ただ、それは決して表層的にデザインを扱うことでは無いので、断片的にせよ、デザインには人の精神性とのつながりや関係性が必要になる。
"Fragments of Design"
The piece-by-piece design reminds me of postmodern architecture for some reason. He used to be a motif of a historical design when he was a student, and pieced it together in pieces and as decorations. Still, when I was a student, the architecture I was referring to was a modernist one, so every time I saw postmodern architecture, I felt uncomfortable.
The post-modern architecture was reflected in the attitude as if the operation were all in the architectural design, taking the design in a superficial manner. .
When I was a student, I was interested in the spirituality of architectural design, and I was thinking about what kind of architecture would affect the inside of a person. I didn't want to.
It remains the same, but I am interested in splicing fragmented designs. In the first place, design is to connect architecture with people, and people tend to change their spirituality irregularly, because they are not always constant, and the immovable architecture responds to the irregular changes. Then, I think that one possibility is that a piece of stitched design can synchronize with the irregular changes.
However, since it is not a surface treatment of design, design requires a connection or relationship with human spirituality, even if it is fragmentary.
今はより小さな物に興味が向き、それは形のある物で、さらには、形の無い物、それはすでに物では無くて、人の気分や感情、関係性などにも興味が移り、それらの形の無い事が形のある物に対して、どのように影響を及ぼすかを考えていることが多い。
形の無い事、気分や感情、関係性などを建築で扱おうとすると、それ自体には形につながる情報が無いので、それ自体を直接的に形にすることは難しいから、形のある物との連続的なつながりとして扱うことによって、建築でも形として扱えるのではないかと考えている。
建築を説明する言葉として、形の無い事、気分や感情、関係性などを語ることは意外と簡単にできるが、やはり、建築として、形のある物として表現したい。
それはまだ、建築より小さな物、それ自体が動かせる物の方が表現しやすいかもしれない。簡単に言えば、取り替えることもできるし、形を容易に変えることもできるから、気分や感情を反映しやすい。建築は動かないし、形も容易には変えられないから、そのような反映の仕方は難しい。
それだけに、形の無い事、気分や感情、関係性などを建築として、形のある物として表現することには意味があると考えている。
ひとつは、動かず、形も変わらないけれど、「〜のように見える」と想えることかもしれないと、それは形を扱うことにつながるのではないかと考えていて、それを建築として、形のある物として表現しようとしている。
"Expressing intangible things"
Now I am interested in smaller things, which are tangible things, and even shapeless things, which are not already things, but also interest in people's moods, emotions, relationships, etc. I often think about how the absence of something has an effect on things with shape.
If you try to deal with things without form, moods, emotions, relationships, etc. in architecture, it is difficult to directly form itself because there is no information that leads to form itself. By treating it as a continuous connection, I think that it can be treated as a form in architecture.
It is surprisingly easy to describe things without form, moods, feelings, relationships, etc. as words to describe architecture, but I still want to express it as something with form as architecture.
It may still be easier to express things that are smaller than architecture and that can move themselves. Simply put, they can be replaced and easily reshaped, making it easier to reflect mood and emotions. Such a reflection is difficult because architecture does not move and its shape cannot be easily changed.
For that reason, I think it is meaningful to express things without form, moods, emotions, relationships, etc. as architecture and forms.
One is that it doesn't move and its shape doesn't change, but thinking that it may be "looks like" might lead to dealing with shape. Trying to express it as an object.
日常の中で誰でも何かしらのルーティンを持っているだろう。例えば、朝のルーティンと称して、起きてから仕事をはじめるまで、決まった段取りで、決まった行動をする。
ただ、毎日同じように決まった行動をするかもしれないが、その行動をする時の気分は毎日違うだろう。
となると、もしかしたら、ルーティンの中に毎日違う気分に合わせる何かを含めている人もいるかもしれない。例えば、毎朝飲むコーヒーのカップは気分で毎日変えているなど。
建築はルーティンを形成する上で、動線や設えなどを担保する。そこで、建築が毎日変わる気分にも対応するというか、呼応して、同じルーティンの繰り返しの日常の中に、何か変化をもたらすことができたならば、それは人と建築がリニアにつながる瞬間だと思う。
具体的には、人の気分によって、建築の何かが変わる、とうことであり、人が気分によって何かを選択することにより、それに呼応して建築の何かが変わるか、変わったように見えることである。
その何かを今、壁に求めて試行錯誤をしている。
"Mood in the routine"
In everyday life everybody will have some sort of routine. For example, you call a morning routine and take a fixed action in a certain arrangement from waking up to starting work.
You may do the same thing every day, but you will feel different every day.
Perhaps some of your routines include something that adapts to different moods every day. For example, the cup of coffee you drink every morning changes every day depending on your mood.
In building the architecture, the flow lines and installations are secured in forming the routine. So, if we can respond to the mood that architecture changes every day, and if we can make something change in the repetitive daily routine of the same routine, that is the moment when people and architecture will be linearly connected. I think.
Specifically, something in the architecture changes depending on the mood of the person, and if the person chooses something according to the mood, something in the architecture changes in response to it. It is visible.
I'm trying and trying to find something on the wall now.
何か、それでいいんじゃないの、それもあるよね、そこに注目するのか、と思わせてくれるもの、それは今まで見聞きしなかったもの、考えてもみなかったこと、思いもしなかったことに気づいた時にそうなるが、人にそう思わせるものをつくりたいといつも思っている。
それは奇をてらう訳ではなくて、日常的にいつも見てはいるけれど、そこを意識して見ることが無かった、見る必要もなかったことに、ある違う意味付けや理由付けがされることにより、とても掛け替えのないものになるようなことで、何でもないことが実は重要なんだと思わせたい。
だから、それは既存の枠組みの中だけを見ていたら、自分が気がづかないから、まず自分が気がつかないと人に伝えられないから、その種はほんの些細な、身近なことからはじめて、それはものづくりとは関係が無い時もあるけれど、何でも結局はものづくりに繋げられるので、そこにはお手本は無く、何でもはじめから構築して、結果そうすると、勝手に枠組みから外れてくれるので、そこで何かに自分が気づき、今度はそれを人にわかる言葉に置き換えて伝える、その置き換える作業がデザインだと考えている。
そして、今、その置き換え作業中、なかなか人にわかってもらえるデザインが見つからない、そういう時は、またはじめに戻って、種からはじめる。
"Replacement in progress"
Something that doesn't matter, it's there, it's there, it's something that makes me wonder if I pay attention to it, I've realized that I've never seen or heard, never thought, never thought When I do, I always want to make something that makes people think so.
It is not a strange thing, but I always look at it on a daily basis, but I did not see it consciously, I did not need to see it, but by giving a different meaning and reasoning I want you to think that it is really important that nothing is so irreplaceable.
So, if you look only in the existing framework, you will not notice yourself, you will not be able to tell people unless you first notice, so the seeds are only trivial, familiar, There are times when it has nothing to do with it, but in the end everything can be connected to manufacturing, so there is no example there, build anything from scratch, and as a result you will come out of the framework without permission. I realized that design was the task of replacing it with words that people could understand.
And now, during the replacement work, it is difficult to find a design that people can easily understand. In such a case, return to the beginning and start with the seed.
建築は取っ替え引っ替えが容易にできない。ならば、建築自体が人に呼応しなければならない。
そもそも建築はモノとして存在することが成り立つように体系があるが、そこでの高いクオリティはあった上での話として、人との関係性がどうあるかに興味がある。建築以外の全てのモノに対しても同じ、人との関係性に興味がある。それをコトとして言い表してきた。
だから、例えば、バカラのグラスとか、単体でのモノとしての興味は無く、そのバカラが良いと思う人との関係性に興味がある。その前提条件として、バカラのモノとしての精度などのクオリティの高さがある。
よって、人とどのような関係性が築けるかがデザインのポイントになる。
そして、人と建築をつなぐ役目を気分に負わせようと考えている。建築に人の気分を反映させるのである。
それは、人と建築のリアルな関係性を築きたいから。
"Relationship between people and architecture"
Architecture cannot be easily replaced. Then, the architecture itself must respond to people.
In the first place, architecture has a system so that it can exist as a thing, but there is a high quality there, but as a story, I am interested in how there is a relationship with people. I am interested in the same relationship with people for all things except architecture. It has been expressed as a thing.
So, for example, I am not interested in baccarat glasses or as a single item, but I am interested in the relationship with people who think that baccarat is good. As a prerequisite, there is high quality such as the accuracy of baccarat.
Therefore, what kind of relationship can be built with people is the key to design.
And I'm thinking of giving the role of connecting people and architecture. It reflects people's mood in architecture.
Because I want to build a real relationship between people and architecture.
型は何のためにあるのかを考えていて、昨日聴いた言葉を思い出した、それは「コミニケーションのツール」。
型があることによって、何者かがはっきりとわかる、態度を表明していることだし、その型に合わせて意思疎通を図れば良いことになるからだろう。型があると何かと外に向かってわかりやすくなる。
ただ、型をつくろうとする時は、どうしても独り善がりになりそうな気がする。そもそも型をつくりたい衝動は、自分とは何者かを発信したい時だから、他者のことより自分のことを優先したくなる。
だから、独り善がりの型にならないために、型が「コミニケーションのツール」であるという意識を持つことは非常に大事だと、これはわかってはいるけれど疎かになってしまうことで、なぜならば、型は、やはり自分だけのものだから、どうしても排他的になる。
もう少し考えを進めてみると、何かが洗練されたものが型であるならば、それは「コミニケーションのツール」としての型が排他的でもあるという、この相反することが高い次元で同時に成り立っている状態が型になる。
結局、最終的には型をつくる上げることに全て行き着くような気がする。
"Making a mold"
Thinking about what the mold is for, and remembering what I heard yesterday, it's a "communication tool."
The presence of a type clearly indicates someone's attitude and makes it easy to communicate with that type. If there is a type, it becomes easy to understand something outside.
However, when I try to make a mold, I feel like I'm going to be self-righteous. In the first place, the urge to make a pattern is when you want to send out who you are, so you want to prioritize yourself over others.
So it's very important to be aware that a type is a "communication tool" so that it doesn't become a self-righteous type. Is, by itself, exclusive, so it is absolutely exclusive.
Looking a little further, if something is a refined type, then it is at the same time a higher dimension that this type of "communication tool" is also exclusive. The state becomes a type.
In the end, I feel like I end up with making the mold.
自然と型のようなものができて、この空間だったら、あの人が設計しているだろうと想像がつくことがある。
似たような空間も現れるが、やはり、真似にしか見えず、真似をする所からはじまるかもしれないが、真似はどこまでいっても真似なので、良くても新鮮味は無く、それにやはり、型なので、比較が出来てしまうから、微妙な形の違いが気になる。
どんなに美味しい食べ物でも、毎日食べたら飽きる。ならば、間隔を空ければ飽きないかというと、1ヵ月、3ヵ月、半年、1年と間隔を空けても、途中で変化が無く、毎回同じ味ならば飽きる。空間も同じか、だから、模様替えをしたり、何かを加えたり、何かを捨てたくなる。
ところが、型のようなものが出来上がると、飽きない。毎回同じでも、同じように良いし、美味しい。
きっと型とは、昇華した形であり、そこまで行くと、飽きることは無く、簡単に真似できることでは無くなるのだろう。
"Type"
You can imagine that if this space is made of nature and a type, it would be designed by that person.
A similar space also appears, but after all it looks only imitated and may start from the place where it is imitated, but since imitation is imitated no matter how far it is, it has no freshness at best, and it is also a type, I'm worried about subtle differences in shape because I can make comparisons.
No matter how delicious food you eat, you get tired of eating it every day. Then, if you do not get tired if you leave an interval, even if you have an interval of one month, three months, half a year, one year, there is no change on the way, and you will get tired of the same taste every time. The space is the same, so I want to make up, add something, or throw away something.
However, once something like a mold is completed, I will never get bored. Every time the same, just as good and delicious.
Surely, a mold is a sublimated form, and when you reach that point, you will not get tired and will not be able to imitate easily.
土鍋を探していて、画像にある小さい土鍋は1人用で、以前に散々探して、やっと手に入れたものだが、もっと大きめの、ちょっとモダンな空間に合う土鍋をと思い、それがなかなか無い。
正確に言うとあるのだが、モダンな空間に合わせることを狙った、デザインされた土鍋として売られているものは結構あるのだが、それはもはや土鍋では無くなっている。
冬だから鍋料理を、炊飯用の土鍋は普段から使っているが、それは白米専用にしたくて、他の煮炊きに使うと土鍋に匂いや味が移り、白米を炊飯した時に美味しくできないと思い、鍋料理や混ぜ御飯をつくる時などに使うための土鍋を探していて、ただ、お鍋で熱燗なんて時は、よくある土鍋が雰囲気もあるし、良いかもしれないが、モダンで繊細な空間には、よくある土鍋は合わない。
ただテーブル上のコーディネートしだいで、よくある土鍋でも、モダンで繊細な空間に合うように、どうにでもなるような気はするが、土鍋単体で、土鍋としての和の感じは残しつつ、モダンで繊細な空間に合うようにデザインされた土鍋を手に入れたい。
例え、レベルの高いデザインが施されていても、土鍋としての和の感じが無ければ、それはただのオシャレな鍋に過ぎず、それならば、土鍋以外でいくらでもあるし、わざわざ土鍋と名を打つ必要も無いし、何よりお鍋で熱燗に合わない。
熱燗に合う土鍋としての和の感じは残しつつ、デザインされていて、そのおかげで、モダンで繊細な空間の中でも映えるものが良い。
画像にある土鍋は、小ぶりだから成り立つかもしれないが、手づくりの不均一さも合わさって、形で、土鍋感とでも言うような、土鍋としての和の感じは残しつつ、よくある土鍋の形とは違い、底面の丸味が無く、シルエットが四角に近く、それが形としてモダンな要素を生んでいるようで、モダンで繊細な空間に対しても合い映える。
要するに形なんだと、土鍋の和の感じを形として残し表現しつつ、モダンで繊細な空間の中でも映える形になっているか、これが案外難しいのだろう。
"Clay pot search"
I'm looking for a clay pot, and the small one in the image is for one person. I searched for it before and finally got it, but I don't think it's a bigger, more modern one that fits a little more modern space.
To be precise, there are quite a few pots that are sold as designed clay pots that aim to fit into a modern space, but they are no longer clay pots.
I use pot dishes for cooking because of winter, but I usually use clay pots for cooking rice, but I want to use it only for white rice, and if I use it for other boiling cooking, the smell and taste will move to the clay pot and I think that it can not be delicious when cooking white rice, I'm looking for an earthen pot to use when cooking or mixing rice, but when it is hot to cook with a pot, the common earthen pot has an atmosphere and it may be good, but in a modern and delicate space, Common clay pots do not fit.
However, depending on the coordination on the table, even a common earthenware pot seems to be in any way to fit into a modern and delicate space, but it is modern and delicate while leaving the feeling of Japanese as a clay pot alone Want to get a clay pot that is designed to fit the natural space.
Even if a high level design is applied, if there is no sense of Japanese as a clay pot, it is just a fashionable pot, so there are many other things than a clay pot, and it is necessary to name it as a clay pot There is nothing, and above all, it does not go well with hot pot.
It is designed while retaining the feeling of Japanese as a hot pot that is suitable for hot sake. Thanks to that, something that shines in a modern and delicate space is good.
The earthen pot in the image may be made because it is small, but the unevenness of handmade is also combined, and the shape of the earthen pot, such as the earthen pot feeling, while leaving the feeling of Japanese as a earthen pot, is a common earthen pot shape The difference is that there is no roundness on the bottom, the silhouette is close to a square, and it seems to be creating a modern element as a shape, and it fits in a modern and delicate space.
In short, if it is a shape, it is surprisingly difficult to express whether it is a shape that shines in a modern and delicate space while retaining and expressing the Japanese feeling of a clay pot.
揺らぎがありながら、納まる所はきちんと納まっていると、何か心をくすぐられたような気になる。
カトラリーの話、物の話。
縦横、垂直水平の線と面がきちんと出ていることは、精度の証だから、それがきちんとできる技術は必要で、まず高い技術があっての話だが、それだけでは人の心を打つ物はできない。
ここで2通り考えられる。1つは、縦横、垂直水平の線と面がきちんと通っている幾何学形態のバランスの緊張感で見せる方法と、もう1つは、縦横、垂直水平の線と面の交わる所はしっかりと押さえ、それで幾何学形態のバランスは担保しつつ、交わる所に至るまでに心に響く揺らぎを与える方法である。
もちろん、どちらも難しい、緊張感ある幾何学形態のバランスを生み出すことも、心に響く揺らぎを生み出すことも。緊張感が無く、だらけた幾何学形態になるか、心に何も響かない、何ともだらしが無い揺らぎになるか、どちらもつくり出すには相当な能力が必要になる。
どちらが良いということは無いが、好みの問題か、物によって使い分けしても良いが、今日、食卓で使うスプーンを探していた。
前々から探している形があり、それはある料理屋さんで使われていたスプーンを目にして、いつもならば、その場でお店の人に尋ねるのだが、その時はたぶんと当てがあったので、自分で探せばわかるだろうと、それがなかなか無く、結局思い違いをしていた。
今朝、ふと思い立ち、もしかしたらと探し、たぶんこれだというスプーンを見つけ、それは手づくりの跡がある、ひとつとして同じものが無い、揺らぎがある物、その揺らぎの様を選んで、心に響く物を購入した。
画像のスプーンは代替の物として普段使っているもので、似ているが、揺らぎが無い。手元に届いたら比べてみるつもりだけれども、意図せずに生まれる揺らぎもデザインの範疇だと改めて思うだろう。
"Fluctuating Design"
If there is a fluctuation and the place where it fits is properly settled, it feels like something has been tickled.
Story of cutlery, story of thing.
The fact that the vertical and horizontal lines and the vertical and horizontal lines and planes are properly exhibited is proof of accuracy, so it is necessary to have a technology that can do it properly.First of all, there is a high technology, but it can not be a thing that strikes the heart of humans alone .
There are two possibilities here. One is to show the tension of the geometrical form that the vertical, horizontal, vertical and horizontal lines and the surface pass properly.The other is to hold the intersection of the vertical, horizontal, vertical and horizontal lines and the surface firmly. This is a way to maintain the balance of the geometrical forms and to give the emotional fluctuations to the intersection.
Of course, both can create a balance of difficult, tense geometrical forms, and create fluctuations that affect the heart. It requires a great deal of ability to create either a loose geometry with no tension, nothing to affect the mind, no sloppy fluctuations.
There's nothing better than that, but it's a matter of taste or things, but today I was looking for a spoon to use at the table.
There's a form I've been looking for before, and when I see a spoon used at a restaurant, I usually ask the shop's people on the spot, but at that time I was probably guessing So, if I could find it by myself, I couldn't find it easily, and ended up making a mistake.
This morning, I suddenly thought, looked for it, and found a spoon that was probably this, there was a trace of handmade, there was no one thing as a thing, there was a fluctuation, I chose something that fluctuates, something that touches my heart Purchased.
The spoon in the image is something I usually use as a substitute, similar but without fluctuations. I'm going to compare it when it arrives, but I think that the unintentional fluctuations are another category of design.
幾何学形態を組合せていけばいく程、個別性が高くなり、それはある意味、完全で完璧な形に近づいていくことであり、そうすると、汎用性は無くなり、より洗練された表現になる。
その代わり、そこに何かを付け足すことは不可能になり、そういう意味では自由度が無くなるから、ただその幾何学形態を受け入れるしかないことになる。
たくさんの幾何学形態で組合せられたもの、それを幾何学模様として見ることはあるが、それは完成度が高く、それはひとつの作品として、そのまま受け入れるしかない。
それはそれで素晴らしいことだが、見る側、使う側の自由度は無い。見る側、使う側によって何も変えることができない。見る側、使う側にとっては、幾何学形態に自分を合わせるだけ、それで合わせていて、幾何学形態の持つより高い次元のものを手に入れることはできるかもしれないが、それは自分では無い。
日常の中での幾何学形態の個別性は程々、7:3くらい、がちょうど良いかもしれない。
"Individuality of geometric forms"
The more geometrical forms are combined, the more individuality is, in a sense, approaching a perfect and perfect shape, which is less versatile and results in a more sophisticated expression.
Instead, it becomes impossible to add anything to it, and in that sense there is no freedom, so you have to just accept the geometric form.
There are many combinations of geometrical forms, which we sometimes see as geometric patterns, but they have a high degree of perfection and can only be accepted as a single work.
That's great, but there is no freedom for the viewer or the user. Nothing can be changed by the viewer or the user. For the observer and the user, it may be possible to get the higher dimensional of the geometric form by just adjusting himself to the geometric form, but that is not myself.
The individuality of geometric forms in everyday life is about 7: 3, which may be just right.
立面が三角形や四角形や円に見える立体である幾何学形態は、単純で、それ自体で完成された完璧な形だと考えるのだが、どうしても、いや、まだ、そこに何かを足せるような気がして、不完全なものに思える。
その幾何学形態を組合せた幾何学模様は、その組合せの仕方で、無限とも言えるくらいの模様を生み出すことができるから、そういう意味では、幾何学形態は汎用性が高い。
様々な自由な形態を単純化していく時には、単純な幾何学形態の組合せに分解していくから、世の中にあるほとんどの形は単純な幾何学形態だけでは成り立っていない。だからか、単純な幾何学形態を見ると物足りず、何かを足したくなる、不完全な形に思える。
完成度は高いが不完全だと、モダニズム建築の幾何学形態を見るといつも思う。
"Geometric forms are imperfect"
I think that a geometric form whose elevation is a solid that looks like a triangle, square or circle is a simple, perfect form that is completed by itself. It feels imperfect.
A geometric pattern obtained by combining the geometric forms can produce an infinite number of patterns in the manner of the combination. In this sense, the geometric forms are highly versatile.
When simplifying various free forms, they are broken down into combinations of simple geometric forms, so most forms in the world cannot be made up of simple geometric forms alone. That's why looking at simple geometric forms seems incomplete, making you want to add something.
When you look at the geometrical forms of modernist architecture, I always think it is perfect but incomplete.
仏師は何を込めるのでしょうか、建築家のコルビュジエは自然の中に幾何学形態を見つける目を持っていた、一見この結びつかない事柄に接点があるとして考えてみたら、それは何かの答えになるかもしれない。
仏像と建築は、物体と空間として捉えたら違うけれども、空間を形として認識すれば、仏像と建築を比較することは可能であり、仏像のお顔が見る時々によって受ける印象が違う理由がわかれば、それは建築でも、例えば、気分によって見え方が違うように思えることができるのではないかと考えた。
わからないが、観念とは無縁のところに仏師はいて、ただ彫る、これは聴いた話だが、木の塊の中から仏様を探し出すように、それも仏様を彫り出すというよりは、ただ形を彫り出すように、それは仏様をつくるという意識が無いのだろう。
コルビュジエは自然の風景を中から幾何学形態を抽出し、例えば、外観の水平垂直の線は、大海の水平線や林立する岩から発想されていた。コルビュジエは、後に「人間と自然との調和」をはかりはじめたのではなくて、初期から「人間と自然との調和」をめざしていたと考えている。
仏師も木の塊の中から仏様をつくるという意識が無いのならば、木の塊の中に単に幾何学形態を見出しているのかもしれない。
幾何学形態が、それ自体には意味は無く、見る側が勝手に意味づけできるものであるならば、仏像にも建築にも共通点はある。
"Buddha statue and architecture"
What can a Buddhist clerk do? The architect Corbusier had the eye to find geometric forms in nature. Might be.
Buddha statues and architecture are different if you consider them as objects and space, but if you recognize space as a form, it is possible to compare Buddha statues with architecture, and if you understand why the impression of the face of the Buddha statue is different depending on the time you see it I thought that in architecture, for example, it might seem different depending on the mood.
I do not know, but there is a Buddhist sculptor in a place that is not related to the idea, just carving, this is a story I heard, but like searching for a Buddha from a lump of wood, it is just a form rather than carving a Buddha It seems that there is no consciousness to make a Buddha like carving a sculpture.
Corbusier extracts geometric forms from natural landscapes, for example, where the horizontal and vertical lines of the exterior were inspired by the ocean's horizon and forested rocks. Corbusier believes that he did not begin to pursue "harmony between man and nature" but to aim at "harmony between man and nature" from the beginning.
If a Buddhist priest does not have the consciousness of making a Buddha from a lump of wood, he may simply find a geometric form in the lump of wood.
If the geometrical form has no meaning in itself and can be defined by the viewer, the Buddha statue and the architecture have something in common.
なぜ仏像のお顔が、例えば、大日如来像のお顔が、見る時々によって受ける印象が違うのかを考えている。きっとそれを考えていると、変化はしないけれど、その時々で建築の見え方が違うように思えることができるのではないか、その答えが見つかるかもしれない。
以前に考えた時は、確か、不完全性と汎用性があるからかもしれないと思った。
不完全性は、仏像のお顔はそこに何か見る人が足すことができる余地があり、それはちょうど建築で言うと、床の間のような存在であり、床の間は一見それ自体で完成しているが、そこに掛け軸やお花や器を足すことで、季節感や想いなどを表現でき、その床の間は見る人によって受ける印象が違う。
仏像のお顔に実際に何か物を足すことは無いが、見る人が勝手に想像力を駆使して、お顔の表情に足してしまう。それは、むしろ見る人が足すことによって仏像のお顔が成立するという意味で不完全性を纏っている。
汎用性は、その仏像のお顔がどのようにでも解釈できるということである。想像力を駆使して表情に何か足してしまう時に制限が無い、どのようにでも変化して見える、喜怒哀楽のどのようにでも、また、その境目も無い、笑っているようでも、哀しんでいるようでも、その両方の要素も併せ持つような表情にも見える。
どうして、このような不完全性と汎用性を備えることができるのだろう。例えば、明確な表情を持ったお顔ならば、そうはならない。例えば、明確な視線がある、目の動きがある、口角や眉の角度で何かを表現してしまっているなど、はっきりと何かを主張している訳ではないからか。
ここで、頭を過ぎるのは幾何学形態、一見完成されているように見えるが、その単純な形態の組合せには、何か別の幾何学形態を足すことも可能であるという意味で不完全性があり、その単純な形態の組合せはどのような建築にも対応ができるという意味で汎用性があり、そして、その足す部分は装飾にもなり、例えば、それは縄文式土器のように、その時々の表現が可能でもある。
ならば、仏像のお顔を幾何学形態として捉えて、それはデッサンのはじめのように、構造的に物体を捉えて、幾何学形態に分解して見ていくと、この不完全性と汎用性の正体がわかるのか。
"Face of Buddha statue and geometric form"
I'm thinking about why the face of a Buddha statue, for example, the face of a Dainichi Nyorai statue, has a different impression depending on when you look at it. If you think about it, it doesn't change, but you may be able to find the answer to how architecture may look different at different times.
When I thought about it earlier, I thought it might be because of incompleteness and versatility.
Imperfection is that the face of the Buddha statue has room for the viewer to add something to it, just as in architecture, between the floors, and between the floors is seemingly completed by itself However, by adding scrolls, flowers, and vessels, you can express the feeling of the season and your feelings.
Nothing is actually added to the face of the Buddha statue, but the viewer uses his or her imagination to add it to the facial expression. It is imperfect in the sense that the face of a Buddha statue is formed by the addition of a viewer.
Versatility means that the face of the Buddha statue can be interpreted in any way. There is no limit when I use my imagination to add something to my expression, it looks like it changes in any way, no way of emotions and sorrows, no boundaries, no laughing, no pity It looks like it has a combination of both elements.
How can such imperfection and versatility be provided? For example, if your face has a clear expression, this is not the case. For example, they do not clearly state something, such as having a clear gaze, eye movement, or expressing something with the angle of the mouth or eyebrow.
Here, beyond the head is a geometric form, which appears to be complete, but the combination of its simple forms is incomplete in the sense that it is possible to add some other geometric form The simple combination of forms is versatile in the sense that it can be adapted to any architecture, and its addition is also a decoration, for example, it is like a Jomon pottery, Sometimes expression is possible.
Then, the face of the Buddha statue is regarded as a geometrical form, and as at the beginning of the drawing, the object is structurally captured and decomposed into a geometrical form. Do you know the identity of?
建築のことを考えていくと、段々と構造や構法から離れていく場合があり、それは建築の幾何学的形態に反発していることに気がつくが、さらには、建築を、輪郭だけの、薄い面だけの、表面上の存在だけで考えていることに気がつくが、そうすると、イメージでは建築を、構造や構法が無い、形だけで考えていて、そこに結びつく、形を決めるための何かをシンプルに考えることができる。
時々、京都の東寺の講堂にある立体曼陀羅の大日如来像のお顔を思い出す。何度その大日如来像のお顔を拝見しても、その都度、受ける印象が違う。当たり前だが、大日如来像のお顔が変化する訳では無い。ただ、温和であったり、厳しくもあったり、怒っていたり、笑顔に見えたり、哀しげにも見える。
きっとそれは見る側の何かと大日如来像のお顔の形を勝手に結びつけて、勝手に都合よく解釈しているに過ぎないかもしれないが、見る人によって受ける印象が違うということは、それは、見る人が主体で、見る人の何かをきちんと大日如来像のお顔が反映していることになる。
そのような関係性が成り立つ建築がつくれないものかとずっと考えている。
"Relationship between shapes"
When you think about architecture, you may gradually move away from the structure and construction method, and you will notice that it is repelling the geometric form of the architecture. I realize that I only think about the existence of only the surface, the existence on the surface, but then, in the image, I think about architecture, there is no structure or construction, only the form, and there is something to decide the shape that is connected there You can think simple.
Occasionally, I recall the face of the statue of Dainichi Nyorai of the three-dimensional mandala in the auditorium at Toji Temple in Kyoto. No matter how many times you see the face of the statue of Dainichi Nyorai, you will get a different impression each time. Obviously, the face of the statue of Dainichi Nyorai does not change. However, it looks mild, harsh, angry, looks like a smile, and looks sad.
Surely, it may be simply interpreting the image of Dainichi Nyorai's face in a way that is arbitrarily interpreted by the viewer, but the impression received by the viewer is different. The person who sees it is the subject, and the face of the statue is reflected in the face of the statue.
I've always been thinking that I can't make an architecture that has such a relationship.
建築のことを考えていくと、建築の構造や構法などの技術的なことは段々と置き去りになり、後付けになってしまうが、実際に見て、良いな、素晴らしいな、綺麗だなと思う建築はよく考えると、構造や構法に惹かれている。
モダニズムの建築は素晴らしくて美しいと、建築をはじめる時から刷り込まれているからかもしれないが、そのせいで構造や構法に惹かれてしまうのかもしれないが、もっと考えを巡らせてみると、モダニズムの幾何学性に惹かれているのかもしれない。
さらにもっと言うと、幾何学的なものの純粋性みたいなものに惹かれるのかもしれない。その純粋性は一見すると、完全に完成された形態に見えるが、その純粋性には、同時に汎用性も伴い、その汎用性は、その後にあらゆるものに変化、転用も可能だと思わせてくれる不完全性をも纏う。
純粋でありながら、不完全である、もしかしたら、これほど魅惑的な形態はないかもしれない、だから惹かれる。
"Pure and imperfect"
When thinking about architecture, technical things such as architectural structure and construction method are gradually left behind and become a retrofit, but in fact, I think that it is good, wonderful, beautiful When you think about architecture, you are attracted to its structure and construction.
If modern architecture is wonderful and beautiful, it may be because it was imprinted from the beginning of construction, but it may be attracted to structure and construction, but if you think more about it, modernism You may be attracted by the geometry of
Even more so, you might be attracted to things like the purity of geometric things. At first glance, its purity seems to be a completely completed form, but its purity is also accompanied by versatility, and that versatility can be changed and diverted to anything after that. Also wear imperfections.
Being pure, but imperfect, perhaps not so fascinating.
もし無限大に空間が広ければ、そのようなことは無いが、例えば、海を想像してみると、船で航行するルートはGPSなどを使って、なるべく最短ルートで効率的に無駄なく行けるように考えるだろう、燃料の消費量も違ってくるだろうから。
海と比べれば、建築の範囲など限られているのに、やはり、人の動きなどの効率性が大事になる。空間の中にあれもこれも押し込めようとするからか、そういう意識が無くても、効率性をつい考えてしまう。
効率性以外の尺度で空間を決めていくことができれば、きっとその尺度は人の動きとは関係が無く、人の動きが尺度になると「動線」などの効率性が問題になってくるから、結果的に人の動きが伴うことにはなるが、そうでないもの、日常の中にあることで考えてみる。
"Scale of space"
If the space is infinite, there is no such thing, but if you imagine the ocean, for example, the route you navigate by boat can be as efficient as possible with the shortest possible route using GPS etc. Because you will think that the fuel consumption will be different.
Compared to the sea, the range of architecture is limited, but efficiency of human movement is still important. Even if you don't have that kind of consciousness because you are trying to push it into the space, you will think about efficiency.
If you can determine the space on a scale other than efficiency, it will surely have nothing to do with human movement, and if human movement becomes a scale, efficiency such as "traffic lines" becomes a problem. As a result, it will be accompanied by human movement, but if it is not, consider it in everyday life.
空間の指向性が無くなれば、効率という尺度から無縁になることができ、より人の営みを反映した空間とすることができる。そのためには、空間の指向性を生む壁と設えをランダムに配置にすればよいが、他にも空間の指向性を無くす方法として、空間の大きさに着目してみたい。
例えば、人が動き回れない位の小さな空間だとしたら、そこに人の動きの効率性は求められないし、「動線」などという考えも必要無い。
ならば、小さな空間の積み重ねで、空間全体を構成してみるという考えもあるが、今度は小さな空間の並びに効率性が求められるので、小さな空間をランダムに配置して指向性を無くす。
そのランダムに配置された小さな空間が設えであり、壁になり、人の営みを反映し、それは、人の営みによって、空間の形の見え方が変わることを目指す。
"Stacking of small spaces"
If the directionality of the space disappears, it can be made free from the scale of efficiency, and the space can be made more reflective of human activities. To that end, it is only necessary to randomly arrange the walls and installations that give rise to the directivity of the space, but I would like to pay attention to the size of the space as another method of eliminating the directivity of the space.
For example, if it is a small space where people cannot move around, the efficiency of human movement is not required, and the idea of "traffic lines" is not necessary.
Then, there is an idea that the whole space is configured by stacking small spaces, but this time, the efficiency of small spaces is required, so the small spaces are randomly arranged to eliminate directivity.
The randomly placed small space is a setting, becomes a wall, and reflects the human activities, which aims to change the appearance of the space depending on the human activities.
空間に指向性が無くなれば、効率性から無縁になれる。
空間における指向性は壁と設えが生むので、無指向性の空間は、その指向性を生む設えと壁がランダムに配置されていれば、人の動きはあるが、そこに指向性は生まれないかもしれない。
要するに、空間に指向性が無くなれば、動線などという考えは無意味になり、故に、人の動きに関する効率性の尺度から無縁になる。
そうなれば、空間を構成する上での自由度が格段に増し、それをどう利用するかもプランニングの範疇、デザインの範疇だが、より人の営みを反映しやすくなる、それはクライアントの日常により添えることになる。
「生活動線」という考えがクライアントの日常を反映しているように、一見思えてしまうが、実際は人の動きを効率性で判断しているだけであり、日常の人の営みに添えているとは前から考えていなかった。
これで少しは日常をより扱えるようになるかと考えている。
"Non-directional space"
If the directivity in the space is lost, efficiency can be eliminated.
Since directivity in space is created by walls and fixtures, in a non-directional space, if the fixtures and walls that produce the directivity are randomly arranged, there is human movement, but there is no directivity there. It may be.
In short, the idea of a flow line becomes meaningless if the directionality of the space is lost, and therefore it becomes irrelevant from the efficiency measure regarding human movement.
If that happens, the degree of freedom in constructing the space will be greatly increased, and how to use it will be in the category of planning and design, but it will be easier to reflect human activities, which will be added to the daily life of the client. become.
Although it seems like the idea of a "live activity line" reflects the daily life of the client, it actually only judges the movement of the person with efficiency, and is attached to the daily life of the person. I hadn't thought about it before.
I am thinking that this will allow me to handle my daily life a little more.
人は移動するから「動線」という考えが生まれ、少しでも余分な動きが無いようにと、効率性が大事になる。
それは、クロード・パラン『斜めにのびる建築』によれば、斜めの移動でも、暗に効率性の良さを大事にしていて、逆に言えば、効率性の良さを求めた結果、斜めの移動が生まれた。だから、移動する方向を決めることは、そもそも効率性を求めることと同義である。
人の営みもまた、人が移動することで生まれる。でも、イメージとして、人の営みは効率性の良さが大事ということにはならない。もちろん、効率性が悪いよりは良い方がいいかもしれないが、それよりは、人の営みでは、豊かさや満足感といったことの方が大事で、効率性を大事にして、豊かさや満足感を損なうことは避けたい。
たぶん、効率は良くないが、その分、豊かさや満足感が得られますという説明ならば、納得してくれる人は多いだろう。ただ、豊かさや満足感といった言葉は抽象度が高いので、具体的な何かをもって、豊かさや満足感を表現しないといけない、それがデザインの範疇になるのだろうし、建築で言えば、プランニングで示すことだろう。
効率の良さを豊かさや満足感に変換して説明し、納得してもらうことはよくやる手法であり、誰でも行うだろうが、効率は良くないが、という時点で効率性を相手にしまっているから、たぶん、この文脈のままでは無理がある。
だから、そもそも、効率性を扱わない、ということは、移動する方向を決める必要が無いか、移動する方向を決めないことでプランニングを考えてみる。
"Do not handle efficiency"
Since people move, the idea of a "flow line" is born, and efficiency is important so that there is no extra movement.
According to Claude Palan's "Anti-Landing Architecture", even when moving diagonally, the efficiency of darkness is cherished, and conversely, as a result of seeking efficiency, diagonal movement is was born. Therefore, determining the direction of movement is synonymous with seeking efficiency in the first place.
Human activities are also born from the movement of people. However, as an image, efficiency is not important for human activities. Of course, it may be better to be better than to be less efficient, but it is more important to have richness and satisfaction in human activities. I want to avoid losing.
Probably, the efficiency is not good, but if you explain that you can get richness and satisfaction, there will be many people who agree. However, words such as richness and satisfaction are highly abstract, so we have to express richness and satisfaction with something concrete, and that will be the category of design. Will show.
It is a technique that is often done to explain efficiency by converting efficiency into richness and satisfaction, and anyone will do it, but it is not efficient, but at that point it is not efficient. Maybe it is impossible in this context.
So, in the first place, if you don't deal with efficiency, you need to decide on the direction of movement, or think about planning by not determining the direction of movement.
建築において「動線」とは、「家事動線」という言葉をクライアントが使うくらい、一般的な言葉であり、文字通り、人の動きを線として捉えて、様々な比較検討の材料になるものであるが、大体「動線」という言葉を使う時は、人の動きの効率性の良さが求められる。
建築空間に様々な設えを納めようとすると、建築全体の大きさには制限があるから、設えの納め方の効率性の良さが大事になってくる。だから、まさに「家事動線」という言葉は、設えを少しでも効率良くコンパクトにまとめるための判断材料になる。
だから、設計者側も効率性の良さやコンパクトであることが良いとして、それをクライアントへの説明材料にもする。
これは人の動きに関することだが、建築のプランニングには、この「動線」に象徴されるように効率性が重視される傾向があり、効率性が良いプラニングが、イコール良い建築とされる傾向が強い。
もちろん、効率が悪いよりは良い方が良いかもしれないが、建築が人の営みを形にしたものであるならば、それは人の営みに効率性を当てはめることになり、そこには何かと無理が生じ、結果的にうまく当てはめるために人の営みを歪めてしまうような気がするし、「動線」を考える時は常にその効率性の呪縛から逃れられず、自由な発想を阻害するおそれもある。
だから、既存の効率性の良さでは無い効率性の良さはないものかと、呪縛から解き放たれるために、いつも考えていて、それがデザインの発露にもなる。
"Flow line curse"
In architecture, "traffic flow" is a general term that allows the client to use the word "housework flow line". It literally captures human movement as a line and is used as a material for various comparative studies. However, when using the term "flow line", good efficiency of human movement is required.
When trying to store various setups in an architectural space, the size of the entire building is limited, so the efficiency of how to store the setup is important. Therefore, the word "housework flow line" can be used as a basis for making the installations as compact and efficient as possible.
Therefore, the designers should also be efficient and compact, and use it as explanatory material to clients.
This is related to human movement, but there is a tendency for efficiency to be emphasized in the planning of architecture, as symbolized by this "flow line". Is strong.
Of course, better may be better than inefficient, but if architecture is in the shape of human activity, it will apply efficiency to human activity, and there is something unreasonable. As a result, I feel like distorting people's activities to fit them well, and when thinking about `` flow lines '', I can not always escape from the efficiency's curse, and there is a risk of hindering free thinking is there.
So, I always think about what is better than existing efficiency, so that I can be freed from the curse, and that's also the emergence of the design.
なんてことを考えていたら朝になった、できないこととできることを整理して、できることをして、できないことはできるように努力して、そんな、言うのは簡単だけどできない、自分の部屋を見ればわかる。
どうして自分が頑張らないと、部屋はいつも同じ、自分の気分に応えてくれないの。
それは当たり前か、部屋は人ではないから、でも、人でも自分の気分になんかに応えてくれるのか。
部屋は誰のものなの、誰のためにあるの、どこでも同じだけど、せめて、今だけは気分に応えて、そうすれば。
ものには頼りたくはないけれど、ものにしか頼れない時もある、それは正しい、健全、だから、そうして欲しいと思うのが本音。
きっと自分でつくれたら、こんなものはつくらない、絶対に。
"What I thought one morning"
If you were thinking about it, in the morning, you could sort out what you can and cannot do, do what you can, try to do what you can't do, it's easy to say, but you can't say it. Understand.
If I don't do my best, the room is always the same, it doesn't respond to my feelings.
Is it natural, or the room is not a person, but can a person respond to his / her feelings?
Who the room belongs to, for whom it is, everywhere is the same, but at least now, just respond to your mood and do it.
I don't want to rely on things, but sometimes I can only rely on things. That's right and healthy, so I really want you to do it.
If you can make it yourself, you will never make such a thing.
いつもの代わり映えのしない部屋を眺めながら起きる、昨日と今日とで何も変わらないのに、気分はちがう、なのに自分以外は同じ、毎朝、同じ、どうして同じなのだろうか、今日はどんより曇った気分なのに、昨日の晴れやかな気分と同じことをしなくては、どうして自分の部屋なのに、気分に応えてくるないの。
苦手だから、できないのに、そんなにうまくいかないから、でも応えて、そうしたら、今日一日、もしかしたら、うまくごまかせるかも。
なのに、どこでも同じ、いつでも同じ、小綺麗だけど、友達が来たら、皆、羨ましがるけど、その時は気分いいけど、普段はつまらない。
自分でうまくできる人は羨ましいけれど、うまくできない人に救いはないの。
それが、それを、せめてはじめに考えてくれたら、少しはちがうのに。
"Morning space"
Waking up while looking at a room that doesn't look normal, nothing changes between yesterday and today, but it feels different, but it's the same except for me, every morning, the same, why it's the same, today it's a little cloudy I have to do the same as yesterday's radiant feeling, why isn't my room responding to my mood?
I'm not good at it, so I can't do it, but it doesn't work so well.
However, it is the same everywhere, always the same, beautiful, but when friends come, everyone feels jealous, but at that time it feels good, but it is usually boring.
People who can do it themselves can be envied, but people who can't do it are not saved.
It would be a little different if you thought about it for the first time.
きっと今、無性に水が飲みたいのに、手前の壁に手を掛けてしまう、何でだろう、きっと、喉の渇きより癒したいことがそこにあるから、そこに行った時の気分を味わいたいから、そこでの気分に浸りたいから、そこにいると落ち着くから、それはその場所が居心地が良いから、それはその場所だけ、他にはまた別の良さがあるから。
今、無性に眠い、どこかに潜り込んで寝てしまいたい、どこかの穴蔵に入り込むように囲われた場所に、隙間でもいい、そこだけの場所の心地よさ、寝るとはそれを味わうため。
雨音がする、最初はかすかに、段々と強く。背中越しに感じるのは音以外、かすかな雨の匂いだけ。雨の日には大抵ここにいる、振り返りる、開ける、水滴がガラスに、やはり雨だと確かめて、また座る。
そういつも違う場面に遭遇する、同じ空間の中なのに、自分が動くから、自分に合わせて、壁は動かないが、形が変わる、そして、気分も変わる。
"Delusion of a time"
I'm sure I want to drink water now, but I'll put my hand on the wall in front of me. What's the reason, I'm sure there is something I want to heal from thirst, so I want to taste the feeling when I went there Because I want to immerse myself there, I feel calm when I'm there, because it's a cozy place, it's just that place, and there are other good things.
Now, I sleeplessly, I want to sneak somewhere and sleep, in a place surrounded so as to enter somewhere in the warehouse, a gap is also possible, the comfort of that place, so that I can enjoy it when I sleep.
There is a sound of rain. All I feel over the back is the faint rainy scent except the sound. I usually stay here on a rainy day, look back, open, make sure water drops are still on the glass, and sit down again.
So I always encounter different scenes in the same space, but I move, so the wall doesn't move, but the shape changes and my mood changes.
寒い寒い、冷たい雨から逃れ玄関に飛び込む、すぐに手を温めたい、壁づたいに洗面所へ。
途中、階段に腰掛けパンツの裾拭く、気になるから、少し座りたかったから、見上げた窓に水滴、ここは空気が交差、寒いが見渡せる。
お湯の蒸気上がる、鏡曇る、眼鏡も曇った。いつも手洗う、ベンチシートに座る、顔洗う。しばらく動きたくない。
着替えるか、食べるか。着替えるから壁づたいに、眠い、疲れた、動きたくない、その場にくじれ落ち、ふわふわな上のもふもふに顔擦りつけ、壁見つめ、さっきとはちがう壁。
壁の隙間、棚に灯りともる。暖かそうな色が吸い寄せ、壁越え、開けた所にテーブル、手をつき辺りを見渡す、その場にあるのは美味しそうな匂いだけ、ただ、気分が安らぐから、ここにしよう。
振り返る、通った壁はみなちがう。これから通る壁もちがう。
"Tonight's delusion"
Get out of the cold, cold rain, jump into the entrance, immediately warm your hands, go to the washroom to wall.
On the way, I sat down on the stairs and wiped the bottom of the pants, so I wanted to sit down a little, so water drops on the window I looked up, here the air crossed, overlooking the cold.
Steam of hot water rose, the mirror clouded, and the glasses clouded. Always wash your hands, sit on a bench seat, wash your face. I don't want to move for a while.
Change clothes or eat. I want to change the wall because I change clothes, sleepy, tired, I don't want to move, I get stuck on the spot, rub my face against the fluffy top, stare at the wall, a wall that is different from the previous one.
Lights on walls and shelves. The warm color sucks, crosses the wall, opens the table, looks around and looks around, only the delicious smell is there, but I feel relaxed here.
Looking back, the walls you pass through are different. Different walls will be passed.
出入り口から入る、そうすると、行き先が分かれる、どこに進もうが構わない、好きな方へ気分で進めば良い。
気分の行き先にはちょうど良いスペースがある。そこで何をしようか、あるいは、そこで何かをするために来た。
そのスペースには設えがある。何かをするために必要なものは全て揃っているはず、揃っていなければ、別のスペースに移動すれば良い、必要な設えがあるスペースに。
途中途中で見渡す。全体を見通すことはできないが、その都度、見える形が変わる。ここまで気分で進んで来た、この後も気分で進む。
所々で外の景色が見えると気分が変わる。気分が変わった所で、また見渡すと、見える形が変わっていることに気がつく。
何かをするためにまた別のスペースに来た。ここには必要な設えが全て揃っていた。またここでも形が変わって見える。
ここにいると気分が安らぐから、ここにしよう。
ここまで、気分で、設えを渡り歩くために、壁づたいに来た。壁にはいろいろな装飾があるが、よく見ると全て違う。まるで気分で装飾を選んでいたら、ここに来たようだ。
"Today's delusion"
Enter from the doorway, and then you will be divided into destinations, wherever you want to go, or just go ahead and feel like you want.
There is just the right space for feeling. I came here to do what to do there or to do something there.
There is a setting in that space. You should have everything you need to do something. If you don't have it, you can move to another space, where you have the necessary equipment.
Look around on the way. You can't see the whole thing, but the shape you see changes each time. I 've been feeling so far, and I 'll continue to feel better.
Feeling changes when you see the scenery outside. When you change your mood, and look around again, you will notice that the shape you see changes.
I came to another space to do something. It had all the necessary equipment here. Again, the shape appears to change.
I feel at ease here so let's go here.
So far, I've come to the wall to feel like I'm walking across the setting. There are various decorations on the wall, but if you look closely, everything is different. If you were choosing the decorations as if you were feeling, you seem to have come here.
今までずっと当たり前のようにあったことと、自分の意識の中にずっとあったこととの間に、かなりのギャップ、すぐには埋められない溝があるとして、そうすると、その溝を埋めるための手立てを考えて、うまく調整しようと試みるか、自分の意識の中にあることを殺して、当たり前のことをするか、当たり前を無視して、自分の意識の中にあることだけを行うか、3パターンあるとして、どれが良いか悪いかはとりあえず置いておいて、一番面白そうだと思うのは、溝を埋めるための手立てを考えて調整することをもっと発展させたことだと思う。
当たり前のことと自分の意識の中にあることにギャップがあることはよくあることで、それを調整することが上手い人は、世渡り上手であったり、もしかしたら、仕事ができる人かもしれない。
ただ、調整してしまうのは、せっかく自分の意識の中に芽生えた、もしかしたら、それはとても素晴らしい大発見かもしれない可能性を摘むことになるかもしれないから、できることならば、調整しない選択肢も持ちたいと思う。
だから、ギャップをむしろ利用して、ただ、それをそのまま利用しては、自分の意識の中にあるものを生で出すようで、それは受け止める方も戸惑うだろうから、ギャップ自体を何か別のもので置き換えて、それ自体を話の骨子に据えて、物語を展開していくようなイメージで表現すれば、当たり前のことと、自分の意識の中にあることの双方の要素を含んだ何か、それが新たな表現なり、新たなことになると思う。
そして、そのギャップや、そのギャップ自体を置き換えたものは、ほんの些細なことで、特別なことでは無くても、それは日常的によく目にしていて、ただ意識しないと気がつかないことでも良くて、あとは物語の展開のさせ方しだいで、どうにでもなることだろうと予測している。
"Use the gap"
There is a significant gap between what has been taken for granted and what has been in my consciousness, and there is a gap that cannot be filled immediately. Think about the tricks, try to adjust well, kill what is in your consciousness, do what you take for granted, ignore the obvious and just do what is in your consciousness, Assuming there are three patterns, let's leave which one is good or bad for the time being, and what seems to be the most interesting is that we have further developed to adjust the way to fill the gap.
There is often a gap between what is natural and what is in your consciousness, and those who are good at coordinating it may be world-class or maybe work.
However, the only thing that can be adjusted is that it has sprung up in my consciousness, maybe it can be a very great discovery, so if I can, I have the option of not adjusting it. I want to have it.
So, rather use the gap, but just using it as it is, it seems to produce something in your consciousness, and it will be confusing for those who take it. If you replace it with something and express it as an image that develops the story by setting itself as the gist of the story, what includes both elements that are natural and what is in your consciousness. I think that is a new expression and a new thing.
And the gap, or the one that replaced the gap itself, is a trivial thing, even if it is not special, it is often seen on a daily basis, and it can be noticed only by not being aware, After that, I predict that it will become a matter of course depending on how the story develops.
触っていて愛おしくなるもの、そのようなもので囲まれる生活がしたくて、そのようなものが無ければ、見つかるまで待って無いままで生活するか、自分でつくるか。
見つかるまで待つ場合は、別の言い方をすると、偶然の出会いによって、自分では気づいていなかったが、自分が前から愛おしいと感じる可能性があったものに気がつくことかもしれない。
自分でつくる場合は、自分が何を愛おしいと思っているのか、明確では無くても、ぼんやりとでもわかってはいて、でもそれが確実にこの世には存在しないから、自分でつくるしかない時である。
自分で手を掛けたものは何でも愛おしいかもしれないが、ただ、そこに精度を求めてしまう、それは自分が建築を生業としているから、ものづくりをしているから、中途半端なものでは心が動かないから。
だから、趣味でつくることは無く、自分でつくる場合も技術が一流の職人にお願いをする。そのような職人と接している時間もまた貴重で、新たな何か、新たな愛おしさに気づかせていただくことが多々ある。
"Lovely things"
If you want to live a life surrounded by things that you will love by touching them, if you don't have such things, you can either live without waiting until you find them, or make your own.
If you wait until you find it, another way of saying it is that by chance meeting you might have noticed something that you hadn't noticed before, but that you might have loved before.
When you make it yourself, you know what you love, even if it's not clear or vaguely understood, but it certainly doesn't exist in this world, so you have to make it yourself It is.
You may love anything you have done yourself, but you just want accuracy, because you are building, you are making things, and you are halfway. Because it doesn't move.
That's why I don't make it as a hobby. The time spent in contact with such craftsmen is also valuable, and I often find myself aware of something new and new love.
装飾というと、柄や色や形など、装飾的というと、それらの程度を表すが、その装飾自体、求められる装飾は時によって、時代によって変わる。だから、装飾の価値は相対的なものであり、絶対的に変わらずに永遠に同じ装飾が良いということは無いだろう。
ただし、そこに骨董的な価値、時代性の違いによる価値、それが古い新しいの価値判断では無いものが存在するならば、全ての装飾に価値があることになる。
時代性は、流行や社会からの要請などから判断されるから、相対的に判断される装飾の価値は、流行や社会が決めているとも言え、装飾を新しく生み出そうとする時は、その時代性が重要になってくるが、それでも突然、全く新しい装飾が出現することは無く、過去の古い装飾からの繋がりで少しずつ変化して、その変化の様は流行や社会と呼応する。それは今までの装飾の歴史を見れば明らかだろう。
だから、全ての装飾に価値があるとする骨董的な見方は、新しく装飾を生み出そうとする時には、とても参考になり、装飾の時代性による変化を予測することができ、また、その新しい装飾の時代や社会での受け入れられ方もコントロールしようと試みることができる。
しかし、現代建築における装飾では、この骨董的な見方が無く、常にその時代における新しい装飾を追い求める。
それは、現代建築の素となる近代建築が、簡単に言えば、装飾を否定するところからはじまっているので、装飾の時代的な連続性を認めずに、骨董的な見方を否定することになるだろうし、また、近現代建築が欧米由来だからであり、日本建築には、そもそも、そうした装飾の骨董的な見方は存在するので、現代建築が自国の建築、日本建築にまで範疇を広げて考察されるならば、また今とは違った装飾の在り様に出会えるかもしれない。
"The value of decoration"
Ornamental, such as patterns, colors, shapes, and so on, expresses the degree of them, but the decoration itself, the required decoration, varies from time to time. So the value of decoration is relative, and it will never change and the same decoration will never be good.
However, if there is an antique value, a value due to a difference in age, or something that is not an old new value judgment, all decorations are worth it.
Since the period is judged from the fashion and social demands, it can be said that the value of the decoration, which is relatively judged, is determined by the fashion and society. However, suddenly no new decorations appear suddenly, and the connection from the old decorations changes little by little, and the changes correspond to trends and society. It will be clear from the history of decoration so far.
Therefore, the antique view that all decorations are valuable can be very helpful when trying to create new decorations, and can predict changes due to the age of the decorations, and the new era of decorations You can also try to control how it is accepted in society.
However, decorations in modern architecture do not have this antique view and always seek new decorations in that era.
That is, modern architecture, which is the basis of modern architecture, starts with denying decoration, so it rejects an antique view without adhering to the continuity of decoration. And because modern architecture is derived from Europe and the United States, there is an antique view of such decoration in the first place in Japanese architecture, so contemporary architecture expands its category to home and Japanese architecture. If you do, you may encounter a different way of decorating.
空間の形を「人の営み」で直に決めたい、そのための方法論を考えていると「へり」が気になる。「縁」と言い換えてもよいが、「端」とか「先端」とか、そこにまず目がいく。
人が瞬時に認識をしたり、感じ取れる範囲は限られていると考えていて、それは小さなものでも、例えば、器でも、全体を見ることはできても、それで全てを把握できないと考えていて、それは建築ならば尚更で、全体を見通すことができないから、ただ、それは見る人の能力にも依存をすることだけれども、建築ならば、空間に入った瞬間に感じ取れることも大事だが、つくり手としては、ここを見てもらうと、ここを触ってもらうと、ここを感じ取ってもらうと、という所を用意して、少しでも作品の意図や作品に込めた想いなどをくみ取って欲しくて、それが、デザインと同義だったりする。
どれほど大きくても、どれほど小さくても、作品の良し悪しは「へり」で決まる。だから、「厚み」に興味が湧く。
"Heri"
I want to decide the shape of the space directly with "people's activities". It may be paraphrased as "edge", but "edge" or "tip" is the first thing to see.
I think that the range that people can recognize and feel instantly is limited, even if it is small, for example, a vessel, I can see the whole, but I can not grasp everything, It is much more so if it is architecture, and it is impossible to see the whole thing. However, it depends on the ability of the viewer, but if it is architecture, it is important to feel it as soon as it enters the space. If you have a look here, touch here, get a feel here, prepare a place where you want to capture the intention of the work and the thoughts embedded in the work, Or synonymous with design.
No matter how big or how small, the quality of the work is determined by the "edge". Therefore, I am interested in "thickness".
建築は人との関係性の中でしか存在できないものだと考えているから、人の営み以外で空間の形を決めることに抵抗がある。
建築やインテリアなどの空間以外のデザインならば、人の営み自体がデザインのキッカケになるから、それが自然だが、建築もそうなるようにしたい。
建築に用途上の区分があるから、例えば、住宅や事務所、美術館など、その用途が人の営みを表していて、それがデザインのキッカケになるように思われるが、それもあるが、しかし、人の営みでは決まらない。
人の営みで決めていると思いがちだが、そこにはその前に、モジュールと言った構造的制約や、法規や予算と言った制限があり、それにまず従う、それをボリュームチェックと言う。
建築行為は事業である以上、それは仕方が無いが、それでも最終的には「人の営み」で直に決めたい、そのための方法論を考える。
"Determine by human activities"
I think that architecture can only exist in relation to people, so there is resistance to determining the shape of the space other than human activities.
If it is a design other than a space such as architecture or interior, people's work itself will be a part of the design, so it is natural, but I want to make it so.
Because there is a division in use in architecture, for example, it seems that the use expresses people's activities such as houses, offices, museums, etc., but it seems to be a kick of design, but there are also, , It is not determined by human activities.
People tend to think that it is determined by human activities, but before that, there are structural restrictions such as modules, restrictions such as regulations and budgets, which are followed first, and this is called volume check.
Since building act is a business, it can't be helped, but in the end, we want to decide on a methodology for that purpose, which we want to decide directly on "human activities."
建築のデザインとフリーカップのデザインを同時に考えていると、明らかに違うことに気がつく。
フリーカップは手の中に納まり、そのデザインの全体性を瞬時に目にすることができ、手の中で自由に動かすことができるし、移動も簡単だから、他のフリーカップに替えることも簡単にできるし、自然と選択の自由がある。
今、輪島塗のフリーカップを制作中で、飲み口の厚みを変化させ、その日の気分で飲み口の位置を変えると、それに応じてフリーカップの形の見え方も変わる。気分がフリーカップの在り方を最終的に、直に、決めるように考えている。
しかし、建築はそうはいかない。建築は中に空隙があり、そこに入り込むから、そのデザインの全体性を瞬時に目にすることができない、建築の規模が大きくなればなるほど、余計無理である。そして、これが一番の違いだが、建築は動かすことができない、動かない。
だから、気分に応じて、そのままでは何も変わらない、変わったように錯覚させることはできるのだが、何かが気分に応じて変化して、見え方が変わる、そして、建築の在り方が変わるようにしたい。
それができてはじめて建築と人との関係性が成り立つと考えていて、建築は人との関係性の中でしか存在できないものだと考えているから。
"Architecture and Free Cup"
If you think about the design of the architecture and the design of the free cup at the same time, you will notice a difference.
The free cup fits in your hand, you can see the completeness of the design instantly, you can move it freely in your hand, and it's easy to move, so you can easily switch to another free cup And you have the freedom to choose naturally.
Right now, if you are making a free cup of Wajima Lacquer, changing the thickness of the mouth and changing the position of the mouth according to the mood of the day, the appearance of the shape of the free cup will change accordingly. I am thinking that my mood will eventually and directly determine how the free cup should be.
But architecture doesn't. Since there is a void in the building and it gets into it, you cannot see the completeness of the design instantly. The larger the building, the more impossible it is. And this is the biggest difference, but architecture cannot move, it does not move.
So, depending on the mood, nothing will change as it is, you can make the illusion that it has changed, but something changes according to the mood, the appearance changes, and the way of architecture changes I want to.
I think that the relationship between architecture and people can be established only when it is possible, and that architecture can only exist in relationships with people.
物語が空間の形を描くことを考えている。
物語とは、日常の中での「人の営み」、あるいは「人の営み」から端を発したその人固有のもの、例えば、気分や感情や想いや習慣など、どちらかというと、形の情報が無く、形にしにくく、複雑で、捉え所が無いもの、人に纏わり付くものから紡ぎ出されたもの。
「暮らし」とは、そもそも、そのような物語が日常的に繰り返され、物語は意図しても、意図しなくても存在する。
その雑多な物語が空間の形を直に決めるようになれば、もう少し自由な「暮らし」ができるのではないか、空間の形に合わせるような「暮らし」は不自由だと考えているから。
ただ、建築は、空間は、形をつくる所からはじまるから、形の情報が無く、形にしにくいものは扱えない。だから、その雑多な物語を受け止める何かものが必要で、そのもので建築を、空間を、形づくれば良い。
そこまでは、頭の中でつながっていて、その受け止める何かは、壁の厚みの中に省スペース化して入れ込まれた設えであり、受け止め方は壁の厚みを選択することで、雑多な物語を受け止めることを簡略化し、空間の形として反映しやすくしているのだが、だから、ここで、あとは手を動かそうと考えるのだが、まだ、物語が空間の形を描き出す上で、物語の捉え方として何かが足りないような気がして、ここから先になかなか進まない。
"Story and Space Shape"
The story is about drawing the shape of the space.
A story is a person's activities in daily life, or something unique to the person that originated from a person's activities, such as feelings, emotions, feelings, and habits. There is no information, it is difficult to shape, it is complicated, it doesn't have a catch point, and it is spun out of things that cling to people.
In the first place, "living" means that such a story is repeated on a daily basis, and the story exists whether it is intended or not.
If that miscellaneous story comes to determine the shape of the space directly, I think that a more free "living" can be achieved, or that "living" that matches the shape of the space is inconvenient.
However, since architecture begins with the place where the shape is created, there is no information about the shape, and it is difficult to handle things that are difficult to shape. Therefore, we need something to catch that miscellaneous story, and it is only necessary to shape architecture and space by itself.
Up to that point, it is connected in my head, and something that is received is a setup that is inserted into the wall thickness in a space-saving manner. It is easier to capture the story and reflect it as the shape of the space, so I'm thinking of moving my hands here, but the story still has to draw the shape of the space. I feel that something is missing as a way of catching, and I can't really go ahead from here.
「人の営み」そのもので、直に空間の形を決めていけばよい。
空間には形がある。建築空間は日常生活のアウトラインであり、アウトラインだけを取り出せば、形として認識できる。
日常生活とは「人の営み」がつくり出すもので、「人の営み」が反映されたものだとしたら、「人の営み」の形が空間と言える。
しかし、実際にはそうでは無い。空間の形は、法規や予算や建築の構造などの制限を元に決めており、「人の営み」をその中に入れ込むだけである。
あと、広い意味での数々の建築論も、空間の形を決める要因になるが、そこには「人の営み」は入らない、「人の営み」を別の言い方にすると「暮らし」、「暮らし」は建築論の外にある。
だから、「人の営み」や「暮らし」」とは別の要因で決められた空間の形では、日常生活とはマッチせずに、とても不自由な、引っ掛かりがある状況が生まれる。
ただ、「人の営み」や「暮らし」には直接、空間の形につながる情報、すなわち、形に直接つながる要因が無いから、「人の営み」や「暮らし」と空間の形を結びつける具体的なものが必要になってくる。
それが、「設え」だと考えている、「設え」がきっかけで人の営みが発生するのだから。空間の形を「設え」を備えることで生み出すのである。
"Create a shape of space"
It is only necessary to determine the shape of the space directly with "human activities".
There is shape in space. Architectural space is an outline of daily life, and if only the outline is taken out, it can be recognized as a shape.
Everyday life is created by "people's activities", and if "people's activities" are reflected, the form of "people's activities" can be said to be a space.
However, this is not the case. The shape of the space is determined based on restrictions such as regulations, budgets, and architectural structures, and only "people's activities" are included in it.
In addition, many architectural theories in a broad sense also determine the shape of the space, but there is no "people's activities", and "people's activities" is another way of saying "living", " "Living" is outside the theory of architecture.
Therefore, in the form of the space determined by factors other than "people's activities" and "living", it does not match with daily life, and a very inconvenient and catching situation arises.
However, since there is no information that directly relates to the shape of space, that is, "people's activities" and "living", that is, there are no factors that directly relate to shapes, so the specifics that link "people's activities" and "living" with the shape of the space. Something is needed.
I think that is "setting", because "setting" triggers human activities. The shape of the space is created by providing "setting".
どうしても複雑で多様な状態をつくりたいとなる。
多様性の在り方はつくり手の数だけあるとは考えているけれど、できれば、使い手の数だけ多様性の在り方があるとしたい。この場合「使い手」を「受け手」と読み替えても良いだろう。
つくり手の数だけ多様性の在り方があれば、それは作品には無限のバリエーションが存在することになるかもしれないが、その作品の無限のバリエーションに対して、その作品の使い手のバリエーションが1つであると、それでは作品に多様性があるとは言えないのではないかと考えている。
どのように多様性を表現するかにもよるが、可変性とか、選択性によって、多様性を表現することもできるだろうが、それが使い手側に委ねられて、使い手側のバリエーションが増えてはじめて、作品の多様性が獲得できるように思う。
もちろん、バリエーションを増やすことだけが作品の多様性を獲得する手段ではないが、使い手側にとっては、割とそれがわかりやすい多様性で、わかりやすさは多様性を表現する場合には必須なことだと、そうでないと多様性が伝わらないと考えている。
だから、使い手側に端を発することで、作品の見え方なり、佇まいなりが変わり、それが使い手の数だけバリエーションがあるのがいいなと思う。
日常の中で、常に、使い手側が持つ多様性に端を発している方が良いが、では、使い手側が持つ日常の中の多様性とは何か、感情とか、心のあり様であったり、気分であったりなどか。
ただ、感情とか、心のあり様であったり、気分などは無形で、形につながる直接的な情報も持たないから、感情とか、心のあり様であったり、気分などを反映する多様性を用意しないといけない。
それが、建築の場合は「壁」だと考えている。
"Acquisition of diversity"
I want to create a complex and diverse state.
I think that there are as many ways of diversity as there are creators, but if possible, I would say that there are as many ways of diversity as there are users. In this case, "user" may be read as "receiver".
If there are as many ways of diversity as there are creators, there may be infinite variations in the work, but there is one variation of the user of the work for the infinite variation of the work. If that is the case, then I think that the work may be diverse.
Depending on how the diversity is expressed, it may be possible to express diversity by variability or selectivity, but it is left to the user side and the variation on the user side increases. For the first time, I think I can acquire a variety of works.
Of course, increasing the number of variations is not the only way to acquire the diversity of the work, but for the user, it is relatively easy to understand, and it is indispensable to express diversity. Otherwise, we believe that diversity cannot be communicated.
So, starting from the user side, the way the work looks and looks changes, and I think there should be as many variations as there are users.
In daily life, it is always better to start with the diversity of the user side, but what is the daily diversity of the user side, emotions, Is it feeling?
However, since emotions, feelings, and moods are intangible and there is no direct information that leads to shapes, it is necessary to create a diversity that reflects feelings, feelings, and moods. I have to prepare.
In the case of architecture, it is considered a "wall".
民藝の筆立付水滴と香水瓶の形が似ている不思議さ。
陶器の筆立付水滴は、鳥取民藝美術館に展示してある物で、その形のバランスの良さに一目惚れをしてしまった。その2日後、鳥取の倉吉にあるショップで偶然見つけたガラスの香水瓶、見た瞬間、陶器の筆立付水滴を思い出し、思わず購入してしまった。
ガラスの香水瓶は岡山の現代作家の物なので、民藝の筆立付水滴の形を参考にした可能性も全く無くは無いが、こうして写真で見比べてみると、細部は違うが、外形としての全体の印象は似ており、全体の大きさも同じくらいである。
この全体の大きさが同じくらいというのが良いというか、不思議だ。全体の大きさ、すなわち、スケール感はとても大事で、同じ形でも、全体の大きさが違うだけで全く別物に見える。時には、外形は良いけれど、全体の大きさがあと少し小さかったら良かったのに、あと少し大きかったら良かったのに、がある。
だから、外形が似ているだけでなく、全体の大きさも同じくらいということは、この外形には、この全体の大きさがしっくりくるということが、作者も違うし、素材も違うし、使用用途も違うけれど、共通認識として根底にあるということであり、それは、スケール感を含めた外形だけを取り出して、良し悪しを論ずることができるということで、それは、外形がある物全般に対して言えることである。
すなわち、作者も、素材も、使用用途も超えて、スケール感を含めた外形だけを、形だけを独立して論ずることができるということになる。
そして、その中には建築も含まれるだろう。
建築の場合は、スケール感を含めた形だけを論ずることはよくあることで、ただ、それは従来のお決まりの建築的表現の中ではよくあるということであり、この表現をしておけば、とりあえず、間違いは無いようなことがあるので、そこから少しでも離れるために、建築以外の形から、それもスケール感を含めた建築以外の形から、建築の形を概観してみようと昨今は考えている。
建築以外の形には、ここにあげた例のように、陶磁器やガラスの器なども含まれるが、洋服や小物なども含まれると考えている、それにもスケール感を含んだ外形があるから。
"Common shape"
The wonder of the water drops with folk brushes and the shape of the perfume bottle are similar.
The water drops with pottery brushes are on display at the Tottori Folk Art Museum, and I fell in love with the balance of the shapes. Two days later, I remembered the glass perfume bottle I found by chance at a shop in Kurayoshi, Tottori, the moment I saw it, and the water drops with ceramic brushes, I bought it unintentionally.
Since the glass perfume bottle belongs to a contemporary artist in Okayama, there is no possibility of referring to the shape of water drops with folk songs. The overall impression of is similar and the overall size is about the same.
It is strange that the size of this whole should be the same. The overall size, that is, the sense of scale, is very important, even if the shape is the same. Sometimes the outer shape is good, but it would have been better if the overall size was a little smaller, but it would have been better if it was a little bigger.
So, not only the external shape is similar, but the overall size is also the same, the fact that this overall size fits perfectly, the author is different, the material is different, and the usage Although it is different, it means that it is fundamental as a common recognition, and that it is possible to take out only the outline including the sense of scale and discuss good or bad, and it can be said for all things with an outline That is.
In other words, it is possible to discuss only the shape, including the scale, independently of the author, the material, and the intended use.
And that would include architecture.
In the case of architecture, it is often the case that only the form including the sense of scale is discussed, but that is often the case in the traditional architectural expression. There are times when there is no mistake, so in order to get away from it as much as possible, I'm thinking about taking an overview of the form of architecture from a form other than architecture, and also from a form other than architecture including a sense of scale. ing.
Shapes other than architecture include ceramics and glassware, as in the example given here, but we think that clothes and accessories are also included. .
日常の物語を形づくるのが、建築の設計であり、空間は日常の生活のアウトラインを描き出すと考えている。
空間にはそれだけの影響力があるだろう。
建築は内部に空隙とも呼べる空間があり、そこに人が入り込むことができるから建築となる。入り込んだ時に見える範囲で日常の生活が行われるから、建築の空間の範囲が、日常の生活の行動の範囲、すなわち、アウトラインとなる。
そのようなことは当たり前だが、アウトラインということは、それを形として認識することもできる。
日常の生活とは人の営みであるから、人の営みを形として認識することができ、それは、人の営みを形として表現できることでもある。
すなわち、空間を形として認識することができ、空間を形として表現できることでもある。
今まで空間を形として認識したことは無いかもしれない。形として認識するものは中身が詰まったものか、全体を俯瞰的に見ることができるもの、だから、建築を外から見た場合は、形として、それを審美的に見ることになるが、入り込んだ空隙の中で、その空隙を、その空間を、形として、審美的に見ることは無かったし、そもそも、そのような視点は無かった。
だから、空間を形として意識してみると、そして、その形が人の営みだと考えてみると、床、壁、天井の面としての境界のあり方や存在の仕方が、今までとは違う意味合いで見え、随分と、不自由な形の中に人は押し込められて日常の生活を送っているのではないか、などと考えてしまう。
ただ、それは当たり前のことで、空間の形は、人の営みがまず先にあって、それを元に決めているように見えて、ほとんどの場合は、人の営みとは関係が無い、法規や予算や建築の構造などの制限を元に決めているのである。
そうなると、今まで空間の形を決めてきた要因以外のもので、空間の形を決めていけば、この不自由な形から抜け出すことができる、それも、「人の営み」そのもので、直に空間の形を決めていけばよい。
ただ、「人の営み」ではあまりにも抽象的であり、それをそのまま空間の形の決定要因にすると、それは言葉上のレトリックを使い、これが「人の営み」から直に生まれた空間ですなどと、どうにでも言葉で補完できてしまうものにしかならないから、「人の営み」をもっと建築的に、ただ、従来のお決まりの建築的表現ではないもので、具体的にもっと限定した表現にしていく必要があり、それがつくり手独自の表現にもなる。
なので、ずっと人の「気分」に焦点を当てて、空間の形を考察している。
"Shape of space"
It is architectural design that forms everyday stories, and space is considered to outline daily life.
Space will have that much influence.
Architecture has a space that can be called a void inside, and people can enter it. Since everyday life is performed in the range that can be seen when entering, the range of the space of the architecture becomes the range of behavior of daily life, that is, the outline.
That's natural, but an outline can be recognized as a shape.
Since everyday life is human activity, we can recognize human activity as a form, and it can also express human activity as a form.
In other words, space can be recognized as a shape, and space can be expressed as a shape.
You may not have ever recognized space as a shape. What is recognized as a shape is something that is packed or can be seen from a bird's-eye view, so if you look at the architecture from the outside, you will see it aesthetically as a shape, but get in However, in the gap, the gap, the space, and the shape were not seen aesthetically, and there was no such viewpoint in the first place.
So, when you think about space as a form, and think that form is a human activity, the way of boundary and presence of floors, walls, and ceilings is different from the past It looks like a meaning, and I think that people are forced into a crippled shape and lead their daily lives.
However, it is natural, and the shape of the space seems to be determined based on human activities first, and in most cases it is not related to human activities. It is determined based on restrictions such as budget and construction structure.
Then, if you decide on the shape of the space with factors other than the factors that have determined the shape of the space so far, you can get out of this inconvenient shape. You just have to decide the shape of the space.
However, it is too abstract in "people's activities", and if it is used as a determinant of the shape of the space as it is, it uses a verbal rhetoric and this is a space that was born directly from "people's activities". Because it can only be supplemented with words, the "people's work" is more architecturally, but it is not a traditional architectural expression, but a more specific expression. It is necessary to go and it becomes the original expression of the creator.
So, I have been focusing on the "feeling" of people and studying the shape of space.
たくさんの物が目の前にある。お目当ての物はすぐ手の届くところにある、そこにしかない。その前に気になる物もある。ちょっと前に存在を知った。できれば両方手に入れたい。
ただ、両手を目一杯伸ばしても、両方を同時に手にすることはできない、となると、どちらかを先に、どちらかを後に、そこにはたくさんの人がいる、誰かが同じ物を欲しがるかもしれない、先に手にしないと、どちらがより欲しいか、それはお目当ての物だが、その前に気になる物の方が近くにある。
全ての物を360度俯瞰して把握する。全ての物を1つ1つ詳細にじっくりと理解する時間は無いから、その中から気になる物に焦点を当てる。気になるのは、瞬間的に引っ掛かりがあるからで、その引っ掛かりの正体は焦点を当ててからわかる。
近づく、引っ掛かりの正体に惹かれるか、惹かれ度合いのレベルが高いか、とにかく引っ掛かりの正体が何だかわからないが、とにかく惹かれてしまうのか、その時は考えるまでもない、素直に手におさまる。
きっとそれは自分に必要な物だから、気になり、惹かれるのだと、そもそも気がつかない物は、どんなに素晴らしい物でも、見えないのと同じ、存在しないのと同じ、だから、自分が気づいて、手におさめた物はずっと大切にしたい。
"I notice because I need it"
There are many things in front of you. The item you are looking for is within easy reach. There are also things to worry about before that. I knew that there was a while ago. I want to get both if possible.
However, even if both hands are stretched out, you cannot have both at the same time. Then, there is a lot of people there, one after the other, someone wants the same thing. Maybe, if you don't get it first, which one you want is the one you want, but there is something closer to you before that.
Get a 360-degree overview of everything. I don't have time to understand all the details in detail one by one, so I will focus on the ones I care about. I'm worried because there is a momentary catch, and I can tell the identity of the catch after focusing.
I am attracted to the nature of the approach, the degree of attraction, or the level of the degree of attraction is high, or I do not know what the identity of the catch is anyway, but I do not have to think about whether it is attracted anyway.
Surely it's something that you need, and you're bothered and attracted. What you don't notice is the same as you can't see, it's the same as it doesn't exist. I want to cherish the things I put in.
精度を高めると矛盾したことができるようになる。
厚いけど薄い、太いけど細い、丈夫だけど儚いなど、ものとして実現しようとすると、一見矛盾していて不可能なように思うが、技術があり、意識を高め、ものの精度を上げて高めていくと、実現可能になる。
例えば、「厚いけど薄い」ならば、もの自体の厚みを厚くしても、先端の処理で厚みを絞るように、先端の形状を尖らせるようにすれば、薄く見えるのだが、それだけでも高い技術が必要だが、作者に薄く見せよう、そうすれば、作品全体の形のバランスが良くなるなどの、形に対する意識の高さも問われ、ただ単に厚みを絞り、先端を尖らせれば良いという訳では無い。
「太いけど細い」「丈夫だけど儚い」も同様で、簡単に言うと、先端などの端部の処理をどうするか、端部の形状の精度が重要になる。
仮に端部の形状が良くても、精度が悪いと台無しになってしまう。折角、もの自体の全体の形が良くなる端部の形状ができても、精度が悪いと、形にバラツキが出て、もの自体の全体の形のバランスが崩れ、かえって悪く見える。
わざと精度を落とし、バラツキを見せて、それを作品ですと言う場合もあるが、それは意図してバラツキを出した場合と、精度が悪くてバラツキが出た場合とでは全く異なり、それを行うならば、意図して精度良くバラツキを出さないと、ただ単に下手にしか見えない。これも一見矛盾することだが、精度の高さがあってはじめて、ものとしてバラツキを良く見せることができるのである。
だから、いずれにせよ、精度の高さはものづくりの基本だと考えているのだが、案外、これが一番疎かにしやすいことで、ある程度技術や意識が高いと、小手先で誤魔化す事ができてしまうので、それも精度良く誤魔化すことができてしまうから、気をつけないと、いつの間にか精度が落ちることがあり、それは後から振り返らないと気がつかなかったりするから、余計に、今の精度の高さが大事になる。
"Accuracy to ensure contradiction"
Increasing accuracy allows you to do contradictions.
If you try to realize it as thick, thin, thick but thin, strong but ugly, it seems contradictory at first glance. Become feasible.
For example, if it is "thick but thin", even if the thickness of the object itself is increased, it looks thin if the shape of the tip is sharpened so that the thickness is reduced by processing the tip, but that alone is a high technology Although it is necessary to show it thin to the author, so that the balance of the shape of the whole work is improved, the height of the consciousness to the shape is also questioned, so it is not necessary to just narrow the thickness and sharpen the tip No.
The same applies to "thick but thin" and "durable but ugly". To put it simply, the accuracy of the shape of the end is important, as to how to treat the end such as the tip.
Even if the shape of the end portion is good, it will be ruined if the accuracy is low. Even if the shape of the end that makes the overall shape of the object itself is improved, if the accuracy is poor, the shape will vary, and the balance of the entire shape of the object will be lost, and it will appear worse.
You may deliberately reduce accuracy, show variation, and say that it is a work, but that is completely different from intentional variation and poor accuracy and variation, if you do it For example, if you do not intentionally produce a precise variation, you can only see it. At first glance, this is a contradiction, but only when there is a high degree of accuracy can it show a good variation.
So, in any case, I think that high accuracy is the basis of manufacturing, but unexpectedly, this is the most easy to neglect, so if you have a certain level of technology and consciousness, you can be deceived by your hands. , It can also be accurately deceived, so if you are not careful, the accuracy may drop without notice, and you will not notice it unless you look back later. It will be important.
省スペース化する時の手掛かりは精度である。
人と建築の関係性をより単純で簡素にし、より密にするために設えを省スペース化し、壁の厚みの中に納めてしまえば、それは飛行機のトイレのように、匿名性が生まれ、設えの差異が壁の厚みだけになり、人は壁の厚みを選べば、それも気分次第で選べば、日常の営みがはじまる。
すなわち、それは「壁の厚み」を通して、人と建築の関係性がより直になり、また、日常の営みとより直結するので、より人と建築の関係性が濃密になる。
ただ、単に設えを小さくし、壁の厚みの中に納めれば良いという訳では無くて、狭いのと省スペースは違う。
飛行機のトイレを思い浮かべると、狭くてもその狭さを感じことは案外少ないが、実際はとても狭く、しかし、その狭さを感じないことが、そこでの営みの快適性につながる。
ではなぜ、その狭さを感じないか、それは限られたスペースの中で、余計なものが存在せず、適切な場所に適切なものが精度よく納められていて、そこでの営みが疎外されずに快適で、特に何も意識しないでも、普段通りの営みを送ることができるから。
だから、精度ほど、日常の営みに直結し、快適性につながるものはない。
"Accuracy is a clue"
The key to saving space is accuracy.
To make the relationship between people and architecture simpler, simpler, and more dense, save space and fit it in the wall thickness, it becomes anonymity, like an airplane toilet. The difference is only the thickness of the wall, and if a person chooses the thickness of the wall, it also depends on the mood, and everyday activities begin.
In other words, through "thickness of the wall", the relationship between people and architecture becomes more straightforward, and since it is more directly linked to daily activities, the relationship between people and architecture becomes more dense.
However, it does not mean that it is only necessary to reduce the size of the installation and fit it within the wall thickness.
When you think of an airplane toilet, it is surprisingly rare to feel the narrowness of a plane, but in fact it is very narrow, but not feeling the narrowness leads to the comfort of operation there.
So why don't you feel the narrowness of it? There is no extra space in a limited space, and the right things are accurately stored in the right places, and the activities there are not excluded. Because it is comfortable and you can send your daily work without being conscious of anything.
Therefore, there is nothing that is directly related to daily activities and leads to comfort as much as accuracy.
ものを選ぶ時の決めては精度になる。「もの」には食べ物も含まれるし、建築以外のインテリアも、「もの」と付くもの全ての最初の判断基準になる。
精度には2つのことが反映されていると考えている。ひとつは技術の高さ、もうひとつはつくり手の真面目さ。
そもそもの技術が低ければ、精度が落ちるだけでなく、どのように見た目を繕っても、デザインをセンスよく施しても、大したものはつくれない。
そして、こちらの方が大事かもしれないが、どんなに技術が高くても、真面目さがないと、良いものを作り続けていくことができない。
人の能力には差があるが、その能力は点では無くて、ある程度の幅があり、その時の条件や環境によって、1回であれば、1発であれば、能力差を凌駕できる結果を出すことができる。
ただ、本当に良いものは1発では無く、常に良い。
何も無い所から立ち上げる時、実績も何も無いから、自分ができる最大限のことをして、結果を出し続けないと、次が無い、その時はそのようなことを考える余裕が無いかもしれないし、ただ無我夢中なのかもしれないし、計算できないかもしれないが、その後ある程度の余裕ができると、評価されると、自分は何も変えていないつもりで、むしろ向上心は何も変わらないと考えているのに、側から見ると、大事なところを蔑ろにしていると判断される。
案外それは正しかったりするから困る、本人には自覚が無いし、自覚ができないから、余計に困る、ただ、そもそも、技術があり、真面目であれば問題は無いのだが。
最近、ここ何日間で、両極端の経験をした。自分のことも重ね合わせて考えると、とても恐い。
ずっと同じでもダメ、かと言って、変え過ぎてもダメ、それまでの良さを残して、進化する、言葉で言うのは簡単だが、それが難しくて、それができない。
ならば、人がどうなるのか、どう経過していくのかを観察することによってしか、今の自分を的確に判断することができないかもしれないと、そのために2年に一度、鳥取に来て、謙虚になろうとつとめるのだが。
"Accuracy is important"
Deciding when choosing a thing is precision. "Things" include food, and interiors other than architecture are the first criteria for all things that have "things" attached.
I believe that the accuracy reflects two things. One is high technology, and the other is the seriousness of the manufacturer.
In the first place, if the technology is low, not only will the accuracy be reduced, but even if the appearance is modified and the design is applied with a sense, a great deal cannot be made.
And this may be more important, but no matter how sophisticated it is, you can't continue to make good things without seriousness.
Although there is a difference in human ability, the ability is not a point, but there is a certain range, depending on the conditions and environment at that time, if it is one time, if it is one shot, the result can surpass the ability difference Can be put out.
However, what is really good is not always one, but it is always good.
When starting up from a place where there is nothing, there is no track record, so if you do as much as you can and do not continue to produce results, there is no next, you may not be able to think about such things It may not be, it may just be selfish, it may not be able to calculate, but if it is evaluated that it can afford to some extent after that, I am not going to change anything, rather the improvement will not change anything Even though I am thinking, from the side, it is judged that I am neglecting important points.
Unexpectedly, it is troublesome because it is correct, the person himself has no awareness and cannot be aware of it, so it is troublesome, but there is no problem if the technology is serious and serious.
In recent days, I have experienced both extremes. It's very scary when you think about yourself.
It 's easy to say in words, but it 's difficult, you ca n't do that.
Then, only by observing what the person will be and how it will progress, I may be able to judge myself accurately now, so I come to Tottori once every two years and be humble I will try to become.
設えを省スペース化することにより、匿名性が生まれ、設えの差異が壁の厚みだけになった時、人と建築の関係性がより単純で簡素になるが、より密になる。
壁の厚みの中に設えを全て納めてしまえば良い、そのために省スペース化をして、そうすると、壁の厚みだけが設えの区分を表現するようになり、人は壁の厚みだけで設えを判断するようになる。
そうなると、人と建築の関係性は、壁の厚みのみでつがることになるから、人と建築の関係性がより単純な仕組みになり、より簡素化され、誰でも、万人にわかりやすく、受け入れやすくなりつつ、気分で壁の厚みを選択するようにもなることから、気分というより複雑なことが単純な仕組みの中で、建築として扱えるようになり、気分という複雑で雑多なことが、よりそのまま、複雑なままで、建築を通して、日常生活の中で表現され、それが日常生活の豊かさになる。
"Enriching everyday life"
By saving space in the setting, anonymity is born, and when the only difference in setting is the wall thickness, the relationship between people and architecture becomes simpler and simpler, but more dense.
It is only necessary to store all the setups in the wall thickness. For this reason, space is saved, and only the thickness of the wall expresses the setup classification. Come to judge.
In that case, the relationship between people and architecture is linked only by the thickness of the wall, so the relationship between people and architecture becomes a simpler mechanism, is simplified, and anyone can understand and accept. Since it becomes easier to select the wall thickness according to the mood, it becomes possible to handle more complicated things like mood as architecture in a simple mechanism, more complicated and miscellaneous things like mood, As it is, it remains complex and is expressed in daily life through architecture, and it becomes the richness of daily life.
壁の厚みの見せ方を考えていて、省スペース化が壁の厚みの中に設えを閉じ込め、余地、余白をつくり、壁の厚みに変化を与えるのではないかと、飛行機に乗りボーッとしながら考えていた。
設えを省スペースにすれば、当然、壁の厚みの中に納まりやすいが、ただ単にスペースを省くだけだと、それが壁の厚みの中である必要が無い。
飛行機でトイレを探す時、とりあえず、近くの壁の出っ張りを目指して進む。大概、そこには何かが仕込まれており、何かの機能がある、ただ、それが何かはなかなかわからない、わからないようになっているように思う、少なくとも日常生活の中でのわかりやすさとは違う。
だから、目安は「壁」で、その壁の大きさ、厚みである、それ以外に手掛かりが無いから、それは壁の見え方の違いであり、そして、同じ機能が分散して壁の厚みの中に仕込まれていたら、飛行機ではトイレは複数あるので、その時の気分で選択することも可能だろう。
省スペース化することにより、何の機能だかわからない匿名性が生まれ、壁の見え方だけが頼りとなり、気分によって壁を選択していくことで「暮らし」が成り立つのも面白いかもしれない。
"Anonymity in life"
Thinking about how to show the thickness of the wall, thinking that space saving will confine the setting within the thickness of the wall, create room and margins, and change the thickness of the wall while riding on an airplane It was.
If the installation is made space-saving, it will naturally fit within the wall thickness, but if the space is simply omitted, it need not be in the wall thickness.
When searching for a toilet on an airplane, for the time being, aim for a bulge on a nearby wall. Generally, there is something built in and there is a function, but I don't know what it is, I don't know what it is, at least how easy it is to understand in daily life Wrong.
Therefore, the standard is "wall", which is the size and thickness of the wall, and there are no other clues. That is the difference in the appearance of the wall. If you are in charge, there are multiple toilets on an airplane, so you can choose according to your mood.
By saving space, anonymity that does not know what function is born, it depends only on the appearance of the wall, it may be interesting that "living" is realized by selecting the wall according to the mood.
どんなに美味しいものを食べていても、毎回同じだと飽きる。それが飛び切り上等でも飽きる。だから、つくる側は飽きさせない工夫というか、人の味覚の特性まで熟知してつくるのだろう。
それは単に美味しいものをつくれば良いという訳では無いのだろう、それ自体も難しいのだが、人の味覚の特性まで意識が及ぶかどうかも能力のうち、味のうちという訳か。
それは他のものづくりでも同じ。かっちり、きっちりと決められていて、それはそれで、とてもハイクオリティであり、誰も真似できないが飽きる。
よく良いものをつくれば必ず評価されるというのがあるが、確かにその通りだが、しかし、本当に良いものは飽きられない、風化しない、むしろ、時が経つほど評価が上がる、だから、飽きられる時点で、本当に良いものでは無い。
その差はどこにあるのだろうか。
それは毎回同じでは無いということ、日々変化しているということ、だから、同じように見えても同じでは無く、常に新しいものが目の前にある、だから、飽きられない、ただし、受け取る側は同じに見える。
同じに見えるけれど新しい、この一見矛盾するようなことをやり続けるのがものづくりで、同じと新しいの間にある一致しない、ねじれている、そのおかげで隙間ができる、その隙間と呼べる位の何ともかっちり、きっちりと定まらない部分が飽きさせない部分になる。
"Do not get bored"
No matter how delicious you eat, you get tired of being the same every time. I get bored even when it jumps up. Therefore, the side of the creation will be a device that will not get bored, or it will be made with familiarity with the characteristics of human taste.
It may not be just to make delicious food, but it is difficult in itself, but whether the consciousness reaches the characteristics of human taste is also a part of the ability.
The same applies to other manufacturing. It is tight and well defined, so it is very high quality and no one can imitate, but you get bored.
It is said that if you make a good one, it will always be evaluated, but that's certainly true, but you can't get tired of it, it won't weather, rather, the evaluation goes up over time, so when you get bored It's not really good.
Where is the difference?
It is not the same every time, it is changing every day, so even if it looks the same, it is not the same, there is always a new thing in front of you, so you can not get bored, but the receiving side is the same Looks like.
It seems to be the same, but it is manufacturing that keeps doing this new and seemingly contradictory thing, it is inconsistent and twisted between the same and new, and thanks to that, there is a gap, it is something that can be called the gap The part which is not fixed exactly becomes the part which does not get tired.
本当に複雑なものは、それ自体が複雑ではなくて、複雑なことを受け止めて、複雑なままに応答するもので、応答する時に複雑だと認識される。
それ自体が複雑なものは、そういうデザインで、そういうものとしか受け止められず、単にたくさんのものを見せる見本市になってしまう。
だから、本当に複雑なものは、一見して、複雑に見えないかもしれない。
そして、本当に複雑なものは、余地や余白を含んでいる。応答する時にキツキツのみちみちだと、一塊りに見え、複雑さに欠ける。
適度に余地、余白を含んでおり、そのおかげで複雑なものだと認識される。
それは日本人が得意とするところだ。
"Really complex"
Really complex is not complex in itself, it accepts complex things and responds in a complex manner, and is recognized as complex when responding.
Things that are complex in themselves are such a design and can only be taken as such, and it becomes a trade show that simply shows many things.
So something that is really complex may not seem complicated at first glance.
And really complicated things include room and margins. When you respond, it looks like a lump and lacks in complexity.
It has a moderate amount of room and margins, which makes it perceived as complicated.
That is what Japanese people are good at.
連続的に変化する壁の厚みの中に全ての設えが入り込む様子をずっと考えている、頭の中で創造して、どういうイメージが可能かを探っている。
手を動かさないのは、手を動かした瞬間からまとめに入るから。そもそも手を動かしてスケッチをする目的は、現状のイメージを留め、それを元に結論に向かって収束させる作業をすることだから、手を動かしはじめたら、手を動かす直前のイメージのクオリティを超えることができない。
要するに、まだまだ手を動かすには不十分だから、いや、今すぐにでもまとめろと言われれば、形にすることはいつでも可能だが、締切りがあるにせよ、そのような中途半端なことをするために設計をしている訳ではないから、まだ考える。
ぼんやりとこんな感じはあるのだが、そこにうまい具合にイメージがはまらない。きっと何かのキッカケで、いつもそうだが、一気に雪崩をうったようにイメージが広がるとは思うのだが、その直前にいるような気がするのだが。
「森」の中に設えがあるイメージが浮かんでいて、それがもっと建築的に具体的なイメージにならないかとも考えながら、他のことも同時に浮かんでは消えて携帯にメモする。
普通に、日常生活の中で、暮らしの中で起こり得る出来事との相関関係が馴染むように感じられたならば、そうイメージできると感じたならば、手を動かそうかと、手を動かしたいとは考えているのだが。
"Do not move your hands"
I'm always thinking about how all the equipment gets into the continuously changing wall thickness. I'm exploring what I can imagine by creating in my head.
The reason why I don't move my hand is that I'll start from the moment I move my hand. In the first place, the purpose of sketching by moving the hand is to keep the current image and to converge toward the conclusion based on it, so if you start moving your hand, exceed the quality of the image just before moving your hand I can't.
In short, it is still not enough to move your hands, no, if you are told to put it together now, you can always make it into shape, but to do such a halfway thing, even if there is a deadline I'm still thinking because I'm not designing.
There is a feeling like this, but there is no good image. I'm sure it's always like something, but I think the image will spread like an avalanche at a stretch, but I feel like I'm just before that.
While thinking about whether there is an image in the "forest" that could become a more architecturally specific image, other things will also disappear at the same time and take notes on your phone.
Ordinarily, if you feel that the correlation with events that can occur in your daily life is familiar, if you feel that you can imagine that, you want to move your hand Is thinking.
連続的に変化する壁の厚みの中に全ての設えが入り込むとしたら、その壁の厚みの変化の度合い自体が暮らしそのものを反映するようになるし、壁の厚みを連続的に変化させるためには自然発生的に、そこに、余地や余白を生み出す。
設えが密集していれば、壁の厚みの変化は激しく、それは暮らしの営みの密度が濃いことになるし、それはより私的な空間であることを表現している。だから、人はリラックスして余地や余白に気分を投影しやすいし、そうすると、人はそこに独自の物語を紡ぎ出す。
建築と人の関係性を考える時、そこに、誰にも理解されはしないが、その人独自の物語が必ず存在するようになると考えている。
そして、その物語の方向性を意図的に導くようにするのが建築のデザインであり、だから、その建築の作者の表現としてのデザインは人によって違い、そこには合う合わない、好き嫌いが存在するようになる。
"Varies by author"
If all installations enter into the continuously changing wall thickness, the degree of change in the wall thickness will reflect the living itself, and the wall thickness will change continuously. Spontaneously creates space and margins there.
If the installation is dense, the change in the wall thickness will be drastic, which means that the living activities are denser and it represents a more private space. So people can relax and easily project their mood in the room and margins, and then people spin their own stories there.
When thinking about the relationship between architecture and people, no one understands it, but I believe that there will always be a story unique to that person.
And it is the design of the architecture that deliberately guides the direction of the story, so the design as the expression of the author of the architecture varies from person to person, and there are likes and dislikes that do not fit there It becomes like this.
壁の厚みの違いを選択することによって、建築の見え方が変わり、そこに余地、余白が生まれる。設えの違いが壁の厚みの違いを生み、選択は気分によってなされて、余地、余白はその時に物語を生み出すかもしれない。
人が連続した壁を身に纏うように暮らしていると考えている。壁との距離感は心理的作用により、気分を介して決まる。
壁だけで、床と天井、屋根は空間を整える存在となると、スキップフロアなどの段差や、意図的に天井高さを低くするなど必要が無く、壁の連続性だけを考えればよいから、より簡素でシンプルになり、そこに設えによる厚みの要素のみを加えればよい。
建築を形成してまとめて表現する手順を簡素化し、複雑で雑多なものはそのままに、壁の厚みに還元して抽象化することによって、複雑で雑多なことと、簡素でシンプルなことが、一見矛盾するが、同時に存在する状態をつくり出したいと考えている。
"Complex and simple"
By selecting the difference in wall thickness, the appearance of the architecture changes, and there is room for it. The difference in the setting causes the difference in the thickness of the wall, the choice is made by the mood, and the room, the margin, may produce a story at that time.
I believe that people live like wearing continuous walls. The sense of distance from the wall is determined through mood by psychological effects.
If only floors, floors, ceilings, and roofs are used to adjust the space, there is no need for steps such as skip floors or intentionally lowering the ceiling height. It becomes simple and simple, and only the thickness element is required.
By simplifying the procedure to form and collectively represent the architecture, the complex and miscellaneous things are left as they are, and by reducing to the wall thickness and abstracting, the complex and miscellaneous things and the simple and simple things are At first glance, I want to create a state that exists at the same time, but contradicts.
建築と人の関係性を、壁と暮らしの関係性にまで絞り込んで、自らの手を動かす前に、概念的に考えると、違いは壁の厚みだけであり、その厚みの違いが、設えの違い、性能の違いになり、人は暮らしの中で、その設えの違い、性能の違いを選択するために壁の厚みを選択する。そして、そのことによって建築の見え方が変わる。
その選択の根拠は気分であり、生理現象も気分に含めてしまう。
その壁に囲まれた場所が暮らしの場所であり、床や天井、屋根はその暮らしの場所を整えるために存在する。
壁の厚みという連続的な連なりが暮らしの場所としての時間的な連なりも担保し、ひとつのまとまりを形成する。
暮らしの営みの複雑で雑多なことを壁の厚みの中に閉じ込め、その複雑で雑多な様を壁の厚みの複雑な違いで表現することにより、一旦、抽象化し、簡素化し、全ては壁の連続的な連なりに見せる。
その壁の厚みの複雑な違いの表現は装飾だが、単なる壁の連続に過ぎず、一見して装飾には見えないが、その厚みの表現が独自の建築の見え方と物語を生み出す。
そして、壁の厚みの違いに意識的な建築と、そうでない建築との間にある落差を梃子のように利用して、建築と人の関係性をつくろうとする。
"Creating relationships between architecture and people"
Before moving your hand, focusing on the relationship between architecture and people to the relationship between walls and living, the only difference is the thickness of the wall. Differences in performance and performance, people choose the thickness of the wall to choose the difference in their setting and performance in their lives. And that changes the way architecture looks.
The basis for the choice is mood, and physiological phenomena are also included in the mood.
The place surrounded by the wall is the place of living, and the floor, ceiling, and roof exist to arrange the place of living.
The continuous chain of wall thickness also secures the chain of time as a place of living and forms a unity.
By confining the complex and miscellaneous things of daily life within the thickness of the wall and expressing the complicated and miscellaneous aspects with complicated differences in the thickness of the wall, it is once abstracted and simplified. Show in a continuous sequence.
The complicated expression of the wall thickness is a decoration, but it is just a continuation of the wall and at first glance it does not look like a decoration, but the expression of the thickness creates a unique architectural view and story.
And he tries to create a relationship between architecture and people by using the difference between architecture that is conscious of the difference in wall thickness and architecture that is not.
壁と暮らしの関係性の中で、何を考えたいかというと日常的な「気分」である。
人は気分の生き物であり、気分次第で今の感じ方が変わる。それをそのまま日常の中で表してしまうかどうかはその人の問題だが、気分でコロコロ変わる、気分を日常の暮らしの中でどのように意識するかが大事だと思うならば、建築と人の関係性に想いを馳せるねらば、コロコロと変わる気分に対して、どのような建築があり得るのか、そのコロコロと変わる気分をどのように捕まえるかを建築の主題にすることは、今まで、それを考えた人はいないかもしれないが、必要なことだと思う。
気分はコロコロ変わる、それを受け止めるには、受け止め側もそれに合わせてコロコロ変わることができれば良いのだが、建築はそうはいかない。建築は動くことができない、ただ、可動間仕切りなどを使って可変することはできるが、バリエーションが限られてしまう。気分にバリエーションは無い、そんなに気分は単純ではなく、複雑で厄介なものだから、可変程度のことでは対応できない。
ならば、コロコロ変わる気分を持つ人が選択するしかない。その単純ではなく、複雑で厄介な選択を受け止めて、受け入れる、それも言葉上のレトリックでは無い建築をつくり出すしかない。
ただ、あまりにも複雑で厄介な選択だから、どこかにこちら側で、建築側で、リードするような、この範疇でならば、というデザインをしないと誰も理解できない、結果的に何も気分を受け止められないような建築になりそうな気がする。
そして、今、その可能性があるとしたら「壁の厚み」だと考えている。
"Make a mood"
What you want to think about in the relationship between the wall and your life is a daily "feeling".
People are living creatures, and the way they feel now depends on how they feel. Whether it is expressed in daily life as it is is a problem for the person, but if it is important to change how it feels in daily life, it is important If you want to think about the relationship, it has been until now that the theme of architecture is what kind of architecture is possible for the mood that changes with the heart, and how to capture the mood that changes with the heart. I don't think anyone thinks of it, but I think it's necessary.
The mood will change, and in order to catch it, the receiving side needs to be able to change accordingly, but architecture is not. Architecture cannot move, but it can be varied using movable partitions, but variations are limited. There is no variation in the mood, the mood is not so simple, it is complicated and troublesome, so it can not be handled with a variable degree.
Then, there is no choice but to choose a person with a mood that changes. Accepting and accepting that simple, complex and cumbersome choice is the only way to create an architecture that is not a verbal rhetoric.
However, because it is an overly complicated and troublesome choice, no one can understand unless it is designed to be in this category that leads somewhere on this side, on the construction side, and as a result, it feels nothing. I feel like it would be an unacceptable architecture.
And now, if there is such a possibility, I think that it is "wall thickness".
壁を図面上に表記する時、二重線を使う。二重線で壁を描き、内と外を分ける、部屋を分ける、領域を分ける。
あくまでも二重線は壁であるという意味しか持たない。だから、簡単なスケッチだと単線で表記することもある。
壁で分けられた領域が問題であり、壁は境界でしかない。
その壁には、耐力壁と非耐力壁という分け方もある。耐力壁は、建築の構造上、地震や風圧力に対抗するために必要な壁である。それは計画した建築を構造計算することによって決まる。その時に耐力壁として必要な長さ、厚みが決まる。耐力壁以外の壁は全て非耐力壁。
詳細な図面を描く時は、耐力壁の大きさを詳細に書き込みして表記するが、それ以外では、耐力壁も非耐力壁も、ただの二重線で連続的に表記する。
実際に完成した建築でも耐力壁と非耐力壁の区別は見た目では分からない。だから、耐力壁でも、非耐力壁でも、壁で分けられる領域だけが問題であり、壁は境界でしかない。
その壁に様々な物が取り付く、キッチンや水回り、エアコンや照明などの設備。壁に、その内部も含めて、日常生活に必要なものがほとんど全て取り付くと考えてもよい。
今まで、壁と暮らしの関係性を考えたことが無かった。それはインテリアデザインの範疇に含まれるようにも思うが、ここではその範疇外のことを考えている。
壁と暮らしの関係性は、言い換えれば、建築と人の関係性である。「壁」は建築というシステムの象徴であり縮図、「暮らし」は人の営みだから。
建築と人の関係性を、壁と暮らしの関係性というところまで絞り込んで考えることによって、抽象的でぼんやりしていたことが、具体的で実現可能なことになると考えている。
"The relationship between walls and living"
Use double lines when marking walls on drawings. Draw a wall with double lines, separate inside and outside, divide rooms, divide areas.
The double line only means that it is a wall. Therefore, a simple sketch is sometimes written as a single line.
The area divided by walls is a problem, and walls are only boundaries.
The walls can be divided into bearing walls and non-bearing walls. The bearing wall is a wall necessary for resisting earthquakes and wind pressure due to the structure of the building. It depends on the structural calculation of the planned architecture. At that time, the length and thickness necessary for the bearing wall are determined. All walls other than the bearing walls are non-bearing walls.
When drawing a detailed drawing, the size of the load-bearing wall is written in detail, but otherwise, the load-bearing wall and the non-bearing wall are written continuously with just a double line.
Even in an actually completed building, the distinction between bearing walls and non-bearing walls is not apparent. So, whether it is a bearing wall or a non-bearing wall, only the area divided by the wall is a problem, and the wall is only a boundary.
Various facilities on the wall, such as kitchen, water, air conditioner and lighting. You may think that almost everything you need for your daily life, including the interior, is attached to the wall.
Until now, I never thought about the relationship between walls and living. I think that it is included in the category of interior design, but here I am thinking outside that category.
In other words, the relationship between walls and living is the relationship between architecture and people. "Wall" is a symbol of architecture and a microcosm, and "living" is human activity.
By focusing on the relationship between architecture and people to the relationship between walls and living, I think that abstract and vagueness will be concrete and feasible.
微細な違いに気づく前に、それまでの認識で判断をしてしまうから、その微細な違い自体に気づくところまで行かないのだが、何か違和感が残る。
それは認識とのズレで、良い方にズレれば意外性があり、サプライズとして受け止められ、好印象になるが、悪い方にズレれば、なぜだと違和感が残る。
その違和感は、それまでの認識には無いことだから、理解ができないし、そうで無い方が良いのではと思ってしまうが、違和感は期待感の裏返しであり、そもそも駄目ならば違和感も無く、否定するのみである。
だから、その違和感を感じつつ、ただ、理解ができないから、その違和感はそのまま放っておくしかない。
ところが、その違和感がそのうち感じなくなる。その違和感自体に慣れて感じなくなったのかもしれないが、もしかしたら、その違和感が何かを整える、土台をつくる、リセットする役目を担っており、その先のことを積み重ねていくと、いつしか違和感が無くなる、それは役目を終えて、次の段階に移乗したことかもしれない。
そのような違和感、認識とのズレをわざと計算してつくり出して、自分の世界に引きずり込み、様々な表現を見せつけていき、人を魅了する、その職人は日常的にそこにいる。
"The craftsman's extreme"
Before you notice a subtle difference, you'll make a decision based on your previous recognition, so you won't go to the point where you notice the subtle difference, but you still feel something wrong.
It is a deviation from recognition. If it is shifted to the better one, it is surprising, and it is accepted as a surprise, and it makes a good impression.
The sense of incongruity is something that hasn't been recognized before, so I can't understand it, and I don't think it's better to do it, but the sense of incongruity is the reverse of my expectation. Only deny.
So, while feeling the sense of incongruity, you can't understand it.
However, the feeling of discomfort disappears soon. It may have become unfamiliar with the sense of incongruity itself, but perhaps the sense of incongruity is responsible for arranging something, creating a foundation, and resetting, and when you accumulate things beyond that, you will feel discomfort sometime It may be that it has finished its role and moved to the next stage.
Such a sense of incongruity and discrepancies between recognition and calculation are purposely calculated and dragged into your own world, showing various expressions and attracting people.
床、壁、屋根があれば建築になる。それで内と外を分け隔てるから、意識するのは大概、内部空間か外部環境である。だから、床、壁、屋根には境界としての性能が要求されるだけだ。
その性能の中には境界としての強度、単に地震や障害から強いことや、雨風を凌げるとか、暑さ寒さを和らげるとか、長い年月でもびくともしない丈夫さなどが含まれる。そして、その性能の中にはデザインも含まれてしまう。
床、壁、屋根は境界として、そこに、目の前にあり、人を、自分を当たり前のように守ってくれる存在になっている。それは、床、壁、屋根で囲まれた場所を安全地帯にしてくれる。
それ以上の意識を床、壁、屋根に持つことがないだろう、それ以上のことは必要としていないから、それでとりあえず十分だからだし、それを満たすだけでも、昨今の異常気象が度々発生する状況ではありがたく思ってしまう。
ただ、日常的に目にする床、壁、屋根が、別の言い方をすれば、シェルターとしての機能を満たしてくれれば十分では勿体ないような気がする。そこには、こちら側の、使う側の、暮らし側の意識次第で、どのような見え方にもなるような気がして、今そこを考えている。
"Exceeding consciousness as a boundary"
If there are floors, walls, and roofs, it becomes an architecture. Because it separates the inside and the outside, it is usually the internal space or the external environment that is conscious. That's why floors, walls, and roofs only require boundary performance.
Its performance includes strength as a boundary, simply being strong from earthquakes and obstacles, surpassing rain and wind, relieving heat and cold, and being strong enough not to be overwhelmed even for many years. And its performance includes design.
The floor, walls, and roof are the boundaries, and they are in front of you, protecting you as you take it for granted. It makes a place surrounded by floors, walls and roofs a safe zone.
There will be no more consciousness on the floor, walls, and roof, and no more is needed, so that's enough for the time being. I'm grateful.
However, the floors, walls, and roofs that I see on a daily basis, in other words, feel that it is not enough if it fulfills the function as a shelter. I feel that it will look like anything depending on the consciousness of this side, the user, and the living side.
茶室に入ると壁に注目してしまう、だから、茶室は内部空間だけで成り立っているように思えてしまう。
目線の先は常に壁に行き、そこから違う所に焦点が合わさるようなイメージがする。
その壁に様々な設えがしてある。そこにお茶会の主題が亭主によって散りばめられており、それを読み取るのもお茶会の楽しみであろうから、尚更、壁に意識が行く。
日常の中でこれほど、壁を意識することがあるだろうか。
壁に取り付くものは全て壁だとするならば、開口部もキッチンも収納も壁となる。そうすると、ほとんどのものが壁として扱えるし、壁になる。日常の生活は壁とともにある、壁を通して行われる、となる。お茶会での壁への意識も日常での延長として、うなずける。
もう少し日常の生活で壁に意識を持って行くとどうなるだろか、と考えてみる。壁として、開口部も、キッチンも、収納も考えてみる。それはただ単に、造り付けのものとしてではなくて、壁のバリエーションとして考えてみる。
床があって、壁があって、天井ないし屋根があれば、空間になる。開口部も、キッチンも、収納も、壁として扱うならば、その空間はどんどん抽象的になるだろう、開口部として、キッチンとして、収納としての機能は残るが、存在がどんどん薄れていくから。
もっと言えば、開口部も、キッチンも、収納も、壁として扱えば、抽象と具象のバランスをコントロールできる。
抽象と具象のバランスがコントロールできれば、日常の雑多なモノやコトと相性が良くなる気がする。雑多だと感じるのは、その空間の抽象度と合わないから。逆に言えば、雑多ではないのに、見た目上だけでも雑多に見せることができる、バランスをコントロールできれば、それをしているのがお茶会での茶室かもしれない。
壁に可能性ありかもしれない。
"Possibility of walls"
When you enter the tea room, you pay attention to the walls, so it seems that the tea room is made up of only the interior space.
The image of the point of sight always goes to the wall and then focuses on a different place.
There are various settings on the wall. The theme of the tea party is scattered by the host, and it will be fun for the tea party to read it.
Have you ever been so conscious of the walls in your daily life?
If everything that attaches to a wall is a wall, the opening, kitchen, and storage are walls. Then, most things can be treated as walls and become walls. Everyday life is with the wall and is done through the wall. The awareness of the wall at the tea party can be nodded as an extension of everyday life.
Think about what will happen if you bring your consciousness to the wall in everyday life a little more. As a wall, consider opening, kitchen, and storage. Think of it as a wall variation, not just a built-in one.
If there is a floor, walls, ceilings or roofs, it becomes a space. If the opening, the kitchen, and the storage are treated as walls, the space will become more and more abstract. The opening will function as a storage as a kitchen, but its existence will fade away.
More specifically, the balance between abstraction and concreteness can be controlled by treating the opening, kitchen, and storage as walls.
If you can control the balance between abstraction and concreteness, I feel that it will be compatible with everyday things and things. I feel miscellaneous because it doesn't match the abstraction of the space. To put it the other way around, if you can control the balance, you can show it just by looking at it, but if you can control the balance, you might be in the tea room at the tea party.
May be on the wall.
茶室という形式の強さの向こう側にある本質的な日常と気分と設えの関係性について考察している。
茶室と単なる和室の違いは何だろうか?
床の間はある、無いのは躙口と水屋と、炉が切ってあることくらいか。別に無くても、無いなりにお茶を立てることはできるだろう。あと、躙口以外の開口部も違うが、それは演出効果には影響があるだろうが、機能上、お茶を立てるのには問題が無い。特に必要な何かは無いかもしれない。もしかしたら、畳さえも、和室でなくても。
そう、単にお茶を立てるだけならば、どこでも良いのだが、茶室でなければならないことがあるのだろう。それは設えができること、その設えが重要で、その設えがお茶会には大事で、それが茶室でなければならない理由であるならば、単なる和室と茶室との違い、その落差を拡張して表現することによって、お茶会の主題や季節感などを抽象的に、暗喩的に表現している。
単なる和室に設えをしてしまったら、それは掛け軸やお花などの単なる見本市になってしまう。単なる和室と茶室という空間の落差があるから、設えをしても、その落差によって、特別な意味合いや物語が生まれる。そして、その意味合いや物語は、設える側の気分でも変わるし、受け止める側の気分でも変わる。
お茶会は非日常な出来事であるかもしれないが、お茶会の主題や季節感は日常を扱っている。だから、日常に応用できるだろう。
単なる和室と茶室の違い、でなければならない理由が見えてきたので、あと少し考察すると形につながるとは思うのだが、それで、用意している建築家の建築性とは違う建築性を用いればよいだろうとは思うのだが。
"Relationship between daily life, mood and setting"
It examines the relationship between essential daily life, mood, and setting beyond the strength of the tearoom.
What is the difference between a tea room and a simple Japanese room?
There is a space between the floors, but the only thing that is missing is the shed, water shop, and the furnace being cut. Even without it, you could make tea without it. Also, the opening other than the shed is different, but it will affect the production effect, but there is no problem in making tea functionally. There may not be anything necessary. Maybe even tatami mats are not Japanese-style rooms.
Yes, if you just want to make tea, it may be anywhere, but it may have to be a tearoom. If that setting is important, that setting is important, and that setting is important to the tea party, and that is why it must be a tea room, simply express the difference between the Japanese-style room and the tea room, and expand the gap. In this way, the theme of the tea party and the sense of the season are expressed abstractly and metaphorically.
If you set up a simple Japanese-style room, it becomes a mere trade fair for hanging scrolls and flowers. Because there is a mere gap between the Japanese-style room and the tea room, even if it is set up, a special meaning or story is born by the drop. And the meanings and stories will change depending on the mood of the person making it and the mood of the person receiving it.
The tea party may be an extraordinary event, but the theme and sense of season of the tea party deal with everyday life. So it can be applied in everyday life.
The difference between simple Japanese-style room and tea room has become apparent, so I think that it will lead to form if you consider a little more, but if you use an architecture that is different from the architecture of the architect you are preparing, I think it would be good.
「気分」を受け止める建築の例として茶室を出したが、茶室を思い浮かべる時、内部空間しか出てこない。
外観があるはずで、躙口は思い浮かぶのだが、それだけである。離れになっていれば外観はあるはずで、しかし、茶室の場合、母屋に附属した部屋であったり、単に室内の一部が茶室のような設えになっていることもあるので、明確な外観が無い場合もあるからかもしれないが、露地は思い浮かぶ。
ただ、露地は外部空間だが、内部空間の延長にある、待合の意味合いに近いような気がするので、どうしても内部空間に含めて連続的に解釈をしたくなる。
非日常を日常のように味わう工夫があると思う。それは、茶室での体験は特別で非日常なのだが、日常の中で感じることや想うことや、それこそ気分などを、より先鋭させ、意識的にさせてくれるから、素は日常にあるから、茶室で感じたり、想ったりすることに親近感があるというか、そこに誰でも自分の解釈で読み取る余地、余白があり、自分なりの物語を紡ぎ出すことができるので、お茶会に一方的に参加させられている感は無く、その場をつくり出す一員になっている気にさせてくれるからかもしれない。
茶室の建築は、それこそ教科書に出てくるような、今さら目新しさもなく、素晴らしいのはわかっているのだが、「気分」を持ち出して考えれば、また違った見え方や「気分」を受け止める建築のヒントになるのではないかと考えている。特に内部空間の設えの有る無しの差が気になる。
ただ、いわゆる茶室という形式の強さみたいなものが前面にあり、その本質の、日常と気分と設えの関係性がなかなか見えてこない。もう少し意識して考えてみたい。
"Daily life in extraordinary life"
As an example of architecture that catches "feeling", a tea room was set up, but when you think of the tea room, only the internal space comes out.
There should be an appearance, and Higuchi comes to mind, but that's it. If it is separated, it should have an appearance, but in the case of a tea room, it may be a room attached to the main house, or just a part of the room may be set up like a tea room, so a clear appearance It may be because there are cases where there is no, but the open ground comes to mind.
However, the open space is an external space, but I feel that it is close to the meaning of waiting, which is an extension of the internal space, so I definitely want to include it in the internal space and interpret it continuously.
I think there is a device to taste the extraordinary like everyday. The experience in the tearoom is special and unusual, but it makes you feel and think in everyday life, and make you feel more sharp and conscious. There is a sense of intimacy in feeling and thinking in the tea room, or there is room for anyone to read in their interpretation, there is a margin, and you can spin your own story, so you can unilaterally attend the tea party It may be because there is no feeling of participation, and it makes me feel like I am a member who creates the place.
The architecture of the tea house is just as it appears in textbooks, and it is not so novel now, but I know that it is wonderful, but if you bring out "feeling" and think about it, it will take a different view and "feeling" I think it might be a hint. In particular, I'm worried about the difference in whether there is an internal space.
However, there is something like the strength of the so-called tearoom in the foreground, and it is difficult to see the essence of the relationship between daily life, mood and setting. I want to think more consciously.
「気分」を受け止める建築と考えて、まず最初に思い浮かんだのが茶室。茶会の度に、亭主がその茶会に込める想いを設えていく。茶室はその亭主の想いを受け止める建築になっている。
想いの範疇に「気分」も含まれるだろう、むしろ、想いを日常の中に刻み込んだものが「気分」かもしれない。
催しがない時の茶室には、床の間にも、その前の待合にも、何もない、空っぽである。茶会に合わせて、亭主がその日の主題を象徴するもの、季節感などを表現するために、掛け軸やお花などを設えていく。茶室には、設えをする場所が用意されており、そこで亭主は想像性を発揮し、自分の想いを込めて、物語をつくり出す。
茶室の設え、というルール、形式の元、亭主が自由に創造性を発揮する。
それを受ける側は、その場に身を置き、何もない空っぽの茶室と、設えられた茶室との落差を感じ、そこにこの茶会の主題や、亭主の想いをくみ取る。
くみ取るとは、目の前にある設えから直接的に何かを得ようとするのではなく、設えに何か、自分なりのものを重ね合わせ、自分なりの解釈で、茶会の主題や、亭主の想いを理解すること。
そのために、設えには、余地というか余白、どのようにでも解釈できる部分があるように思い、その部分が、何もない空っぽの茶室と、設えられた茶室との落差を感じさせてくれて、掛け軸やお花や器や絵画などの設えの単なる見本市となるのを避け、そこに自分なりの物語をつくり出すことができる。
ならば、「気分」を受け止める建築とは、「気分」を込めることができる、設えができる場が用意されている建築のことで、何もない空っぽの建築と、自分なりの解釈ができる余地や余白がある設えられた建築との落差から自分なりの物語を紡ぎ出すことができる建築となる。
"Architecture that catches your mood"
The tearoom was the first thing that came to my mind when thinking of an architecture that accepts "feeling". Every time a tea party is held, the hoster sets up the feelings for the tea party. The tea room is an architecture that accepts the thoughts of the host.
The category of feelings may include "mood", but rather, the "feeling" may be something that engraves the feelings in daily life.
The tea room when there is no event is empty, with nothing between the floor and the waiting room in front of it. In line with the tea party, the host will set up hanging scrolls and flowers to represent the theme of the day and the seasons. In the tea room, there is a place to set up, where the hoster demonstrates his imagination and creates a story with his own thoughts.
The rules and form of the tea room setting, the owner of the tea ceremony is free to demonstrate creativity.
The person who receives it sits on the spot and feels the difference between the empty tea room and the tea room that has been set up, and captures the theme of the tea party and the thoughts of the host.
Rather than trying to get something directly from the setting in front of you, Kumitake is something that you put on your setting, and your own things, To understand the thoughts of
For that reason, the setting seems to have room or margin, which can be interpreted in any way, and that part makes me feel the difference between the empty tea room and the tea room that was set up. You can avoid the mere trade show of hanging scrolls, flowers, bowls, and paintings, and create your own story there.
Then, architecture that accepts "mood" is an architecture that has a place where you can put in "mood" and can be set up, and there is room for empty interpretation and your own interpretation. It becomes an architecture that can spun out its own story from the head of the building with margins.
複雑で雑多なものが存在していて、漂っていて、それが普通にあって、その中から、あとはどこにフォーカスをするか、そうすると、それがクローズアップされて、メインになり、ただ、次の瞬間、また違うものにフォーカスし、今度はそれがクローズアップされる、それは決して、整理整頓されてはおらず、思いつきや気分で変わる、それが日常の生活だと思う。
だから、日常に、生活に、そこに携わる人を建築に引き込むために「気分」を扱う。
「気分」をどうしたら建築として掴むことができるのだろうかと、ずっと考えている。
これが小物だったら、器だったら、カップだったら、服だったら、と考えると、気分によって選択すればよく、良し悪しは別として、それで「気分」を掴むことができる。
では、建築も同じように、変えれば良い、場所を変えれば良い、となるが、家は、たくさんあちこちに家がある人、別宅がある人、ならば良いが、あるいは、都市の中に居場所を気分で見立てれば良いかもしれないが、それはちょっとしんどい、行き着く先は定住したくなるし、それは安全地帯が欲しくなるから。
ならば、ひとつの場所で、「気分」という掴み所がなく、複雑で、雑多で、得体の知れない、変わりやすいことが反映された、「気分」を掴む、あるいは、「気分」を誘発する建築をつくりたいと思っている。
ただ、そうすると、相容れないのが建築計画になる。
建築計画とは大雑把に言えば、効率性や経済性を求めている。建築には多額の資金が必要だから、事業性が大事になり、その事業性を担保するには効率性や経済性が不可欠だ。「気分」は効率性や経済性の範疇には入ってこない。
どうやって折り合いをつけるかと考えている。
いや、もしかしたら、折り合いをつけようとしている時点で無理があるのかもしれない。
そもそも、「気分」を建築に引き込もうとしているのに、それが建築計画とは折り合いが悪いとはわかっているのに、尚も、建築計画にこだわる、効率性や経済性にこだわる、手放さないのがおかしいのかもしれない。
なかなか、今までの積み重ねがあるから、手放せない。
ただ、考えてもみたら、複雑で雑多なものが存在していて、漂っていて、それが普通にあって、整理整頓されていない状態を日常の生活の中で許容できるものなんて、建築くらい大きなスケールがないとできないことだから、整理整頓などして単純化してしまうのは勿体ないし、自ら建築の可能性を捨てているようなものだろうと考えて、どうするかな、となる。
"Mood and architectural plan"
There is a complex and miscellaneous thing, drifting, it is normal, and from there, the focus is the rest, and then it closes up and becomes the main, just the next At the moment, I focus on something different, and this time it is close-up, it is never organized, I think that it is a daily life that changes with thoughts and moods.
Therefore, we treat "mood" in order to draw people involved in daily life into daily life.
I've always wondered how I can grasp "feeling" as architecture.
If this is an accessory, a bowl, a cup, or a clothes, you can select it according to your mood, and whether it is good or bad, you can get a feeling.
In the same way, you can change the architecture in the same way, you can change the place, but if you have a lot of homes, people with separate homes, or a place in the city It might be a little tricky, but it's a bit tedious, because you want to settle down where you want to go, and you want a safety zone.
Then, in one place, there is no place of "mood", and it is complicated, miscellaneous, unfamiliar and variable, reflecting "moe" or triggering "moe" I want to make architecture.
However, if you do so, what is incompatible is the architectural plan.
Roughly speaking, an architectural plan calls for efficiency and economy. Since a large amount of money is required for construction, business efficiency is important, and efficiency and economic efficiency are indispensable to secure the business efficiency. "Mood" does not fall into the category of efficiency and economy.
I'm thinking about how to come to terms.
No, maybe it may be impossible when trying to make a compromise.
In the first place, we are trying to bring "feeling" into architecture, but we know that it is not well-balanced with the architectural plan, but still stick to the architectural plan. It may be strange.
It 's hard to let go because there 's a lot to date.
However, if you think about it, it is as big as architecture that something complex and miscellaneous exists, drifts, is normal, and can tolerate an unorganized state in everyday life. Since it is impossible to do without a scale, there is no need to simplify things by organizing them, and it will be a matter of thinking that it is like throwing away the possibilities of architecture.
気分を形にして建築にしようとすると、何かしらの枠組みや受け皿がいる。それは気分が直接的に建築の形につながるものを含んでいないから、例えば、気分が影響を与える何か、その何かは建築の形に直接的につながるものを含んでいるか、あるいは、気分自体を誘発するもので建築を形づくればよいのかもしれない。
いずれにせよ、何かしらの枠組みや受け皿がいる。それを別の言い方にすると、形式、ルール、メソッドになるか。
その形式、ルール、メソッドは、気分という掴み所がなく、複雑で、雑多で、得体の知れない、変わりやすいことを扱うので、整理したり、制御したりすることに長けている、十二分に許容できるものか、全く整理も制御もせずに、それでも成り立つものでないと、気分を扱えないだろう。
ただ、整理や制御も、歴史があり、積み上げてきた形式、ルール、メソッド、それをあえて建築家の建築性と言うことにするが、それで行うことであり、全く違う建築性で整理や制御をすれば、建築家の建築性側から見れば、それは整理や制御されているようには見えず、むしろ、気分という掴み所がなく、複雑で、雑多で、得体の知れない、変わりやすいことがそのままの状態で維持されているように見えるのではないだろうか。
なぜ、そのようなことを考えるかというと、既存の枠組みや受け皿からして、気分をそもそも扱えるものでは無く、むしろ、気分のような掴み所がなく、複雑で、雑多で、得体の知れない、変わりやすいことを排除するように存在している印象があるから、そして、それは効率性が優先され、気分をわざわざ扱わなくても存在できてしまうし、それが一般的で、でも、気分を排除したら、人がそこに存在しないと思うから。
"Mood saucer"
There is some kind of framework or saucer when you try to build in a mood. It doesn't include things that directly affect the shape of the architecture, for example, something that affects the mood, something that directly relates to the shape of the architecture, or the mood itself It may be necessary to shape the architecture with something that triggers.
In any case, there is some kind of framework and saucer. In other words, is it a form, a rule, or a method?
Its format, rules, and methods are complex, miscellaneous, unfamiliar, and easy to change because they don't have a sense of mood, so they are good at organizing and controlling. If you don't have to organize or control it at all, and it doesn't hold, you won't be able to handle your mood.
However, organizing and controlling has a history, and the accumulated forms, rules, methods, and dare to call it the architect's architecture. From an architect's perspective, it doesn't seem to be organized or controlled, but rather has no sense of mood, complex, miscellaneous, unfamiliar, and variable. It may seem that it is maintained as it is.
The reason why we think about it is that it doesn't handle the mood in the first place based on the existing framework and saucer. There is an impression that it exists to exclude things that are easy to change, and that gives priority to efficiency and can exist without bothering the mood, it is common, but it makes you feel If you eliminate it, you do n't think there 's a person there.
複雑なものは複雑なままでいいと思うのだが、なぜか、整理され、わかりやすくなっていることが良しとされているのが不思議だ。
断捨離がまさにそれで、片付けて、要らないものは捨てて、持ち物は少なく厳選されているのが良しとされていることが昔から不思議だった、なぜと。
自分の周りにあるものは、自分を体現しているものだから、年を重ねてくれば、様々ことを経験するから、自分にも、良し悪しは別として、降り積もったものがあり、それがその人の味とか、個性になるのに、周りにあるものを整理整頓して、今要らないものを捨てることは、降り積もった足元にあるものを捨てるようなもので、そうしたら、ガラガラとくずれて、また最初に戻って、余程、何もなかった自分が好きなのか、後悔しているのか、捨てることが好きな人が多い、そのくらい抱え込んでも大したことではないし、断捨離した位で性根は変わらないから、捨てたことを逆に後で後悔するだけなのに。
複雑で単純ではない様が面白くて、そのままでいいのに、整理して味気ない街をよく見る。代替えすれば、致し方ない場合もあるけれど、複雑なままでもいいじゃないの、という価値観が浸透すれば、少しは社会や街も艶というか、のり代というか、余白というか、隙間というか、余分なものを抱え込む余裕が生まれかな。
整理なんかしなくても良いとは言わないけれど、いや、整理する方が簡単なんだと、複雑なものを複雑なまま抱え込む方が余程、労力がいるし、それをよく見せようとしたら、もっと能力が問われるよね、だからか、人は整理したがる、別に整理したい訳ではなくて、整理されていないことを問われるのが嫌なようだ、それにしても、そのままで良いとわかっているだろうに、不思議だ。
"Even though it is complicated"
I think complex things can remain complex, but for some reason it is strange that they are well organized and easy to understand.
That's exactly why it has been mysterious that it is good to get rid of things you don't need, throw away things you don't need, and have a small selection of belongings.
The things around me are those that embody me, so as I get older, I experience various things, so I have something that has accumulated, aside from good or bad. Organizing the surroundings and throwing away the things you don't need now is like throwing away the things you have piled up, and then it will be messed up. Also, when I go back to the beginning, there are a lot of people who like myself, I regret it, I regret it, I like to throw it away. And because my sexual roots don't change, I just regret what I gave up later.
It's interesting that it's not complicated and simple, but you can keep it as it is. If you substitute it, you may not be able to do it, but if the value that you can leave it complicated is permeated, the society and the city are a little glossy, it is a margin, a margin, a gap, a gap I wonder if I can afford to carry extra things.
I don't say I don't need to organize, but no, it's easier to organize, there is more labor to hold complex things in complexity, and if you try to show it well, I think more ability is asked, that's why people don't want to be organized, they don't want to organize it separately, they don't want to be asked that they aren't organized, but they know that It 's strange.
様々な気分を誘発してくれる建築には仕掛けが必要だ。
人は気分に左右される。それを否定的に捉えずに、積極的に肯定すれば、日常が楽しくなる。だから、気分を建築として形にする、建築が日常の中で多様な人の気分を誘発し、そこから様々な物語をつくり出す。その物語は人に愛着や慣れを生み、今そこに居る場所が、建築が、自分だけの、自分特有のものになる、離れられなくなる。
その仕掛けは、建築に散りばめられる。それは、小物、素材、ディテール、型、色などの質料だ。その質料の散りばめ方から、気分の誘発度が決まる。誘発度が高ければ高いほど、人にとってより親密感が増し、自分だけの空間になるが、それは同時に他人を排除してしまう。
その度合いは、その建築が誰に向けられたものかで決めれば良い。一般的には、美術館のような公共性の高い空間ならば、気分の誘発度は下げる、住宅のような私的性の高い空間ならば、気分の誘発度を上げる。ただし、これはあくまでも一般的な目安で、美術館でも気分の誘発度を上げて、建築自体が一種の美術作品のように仕立てても良いし、住宅でも気分の誘発度を下げて、あまりにも私的な空間になり過ぎるのを避けても良い。
いずれにせよ、人の気分がつくり出す物語が日常の建築を決める。
その気分を誘発する建築に散りばめられる仕掛けとしての小物、素材、ディテール、型、色などの質料が、複雑に変形した空間で、床や壁、天井の仕上げが極端に凹凸で派手な有彩色になればなるほど、仕掛けの質料が多ければ多いほど、気分の誘発度が高い。すなわち、より多くの、より複雑な物語をつくり出し、より私的で、より親密感が増し、より自分だけの空間や建築になる。
そして、それは建築の形式とは関係が無い、気分だけの問題であり、日常の問題だから、好きに形式を選択すれば良い。
この場合の形式は、過去の積み重ねから来る建築性でもあるし、そうではなくて、注文住宅か建売住宅か、でもある。要するに、形式は関係が無いから、汎用性が高い。汎用性が高ければ、地域や人種も関係が無い。
気分は誰でも日常的に持つことだから、形式とは無関係にしないと、その汎用性の高さについていけない。様々な気分を誘発してくれる建築は、実は汎用性が高く、誰でも受け入れることができて、人と密接に関係したものになる。
"Relationship between mood and quality"
A mechanism is necessary for architecture that induces various moods.
People depend on their mood. If you positively affirm it instead of negatively, you will enjoy your daily life. Therefore, the mood is shaped as an architecture, and the architecture induces various moods in daily life, and various stories are created from it. The story gives people attachment and familiarity, and the place where they are now becomes architecture that is unique to you and unique to you.
The mechanism is scattered throughout the architecture. It is a quality fee such as accessories, materials, details, molds, and colors. The degree of the induction of mood is determined by the manner in which the quality charges are scattered. The higher the degree of triggering, the more intimate for the person and the space of their own, but at the same time it excludes others.
The degree can be determined by who the architecture is directed to. In general, if the space is highly public such as an art museum, the degree of mood is lowered. If the space is highly private such as a house, the degree of mood is raised. However, this is just a general guideline. You can raise the mood level in the museum and make the architecture itself like a kind of art work. You can avoid becoming too much space.
In any case, a story created by a person's mood determines everyday architecture.
Small materials, materials, details, molds, colors, and other qualities that are scattered in the architecture that induces that mood are complexly deformed spaces, and floors, walls, and ceiling finishes are extremely uneven and showy chromatic colors. The higher the quality fee for the device, the higher the degree of mood induction. That means creating more and more complex stories, more private, more intimate, and more personal space and architecture.
And it's just a mood problem that has nothing to do with the form of architecture, and it's a daily problem, so you can choose the form you like.
The form in this case is the architecturality that comes from the past stacks, but it is also a custom house or a built house. In short, since the format is not related, it is highly versatile. If the versatility is high, there is no relation with the region and race.
Since everyone has a mood on a daily basis, unless they are independent of the format, they cannot keep up with their versatility. The architecture that induces various moods is actually highly versatile, can be accepted by anyone, and is closely related to people.
建築の方から気分を強要してくる、「気分」を建築として形にしたいと考えても。
本やコーヒーカップなどの小さな持ち運べるようなものだったら、気分に合わなければ、取り換えれば良いが、建築はそうはいかない、そう簡単に取り替えることができない。それははじめから分かっているから、気分を合わせに行く、それは結局、建築が強要してくる気分に合わせざるを得なくなる。
例えば、朝日が差し込む場所にダイニングテーブルがあったとしたら、そこでコーヒーを飲んだり、朝食を食べたりして、気持ち良い朝を迎えて下さい、と暗黙の了解の如くだと、誰でもわかるから、それに乗らないと損をしたような気分にさせられから、そこで朝食を食べて、気持ち良い気分に浸ろうとする。
それが良いことなのだろうか?良い気分に浸ろうとしている時点で不自然に気分をつくろうとしていると思う。気分は意識してつくるというよりは、自然発生的に現れることだろう。
では、建築は何の気分も強要しないニュートラルなものに徹した方が良いのだろうか?それも違うような気がする、それは単なる味気ない建築でしかない。
では、そもそも強要してくる気分が陳腐過ぎるということか?それもあるが、陳腐でありきたりでも、それが良い場合もある。
要するに、気分に多様性が無いことが問題で、様々な気分ができる、様々な気分を誘発してくれる、すなわち、それは気分が素となった様々な物語を展開してくれる空間になっていなければならない、いくつもの物語が同時に成り立つように。
では、そのような建築をどうやってつくるのか?
簡単に考えれば、様々な気分を誘発してくれる仕掛けを散りばめれば良く、それによって発生した「気分」は多様性を帯びるので、様々な物語が展開されるようになるのだが、もっと具体的に建築としての形に落とし込まないと話にならない。
"How to make a mood in architecture"
Even if you want to make "mood" form as an architecture, you will be compelled by the architect.
If it's a small portable thing like a book or a coffee cup, if you don't feel like it, you can replace it, but architecture doesn't, it's not easy. Since we know it from the beginning, we go to the mood, and eventually we have to adapt to the mood that architecture is forcing.
For example, if there is a dining table in the place where the morning sun comes in, everyone can know that it seems like an implicit understanding that you should have a pleasant morning by drinking coffee or eating breakfast there, so you can get on it. Otherwise, it makes you feel like you've lost, so eat breakfast and try to immerse yourself in a pleasant mood.
Is that a good thing? I think I'm trying to feel unnatural when I'm trying to get in good mood. The mood will appear spontaneously rather than consciously.
Is it better to focus on neutral things that don't impose any mood? I feel that it is also different, it is just a tasteless architecture.
So, do you mean that the feeling of coercion is too stale? Sometimes it is, but even if it is obsolete, it may be good.
In short, the lack of diversity in the mood is a problem, it can be a variety of moods, induces a variety of moods, that is, it must be a space that develops various stories that make you feel good. There must be several stories at the same time.
So how do you make such an architecture?
In simple terms, it is only necessary to stir up various devices that induce various moods, and the resulting "mood" is diverse, so various stories will be developed, but more specific It will not be a story unless it is put into the form of architecture.
「気分」を建築として形にしたいと考えている。使う人が日常の中で行う行為も建築の範疇とするならば、行為に何らかの影響を与える「気分」も建築の範疇としても良いだろう。
「気分」には直接的に建築の形につながる要素は無いから、「気分」に影響を受ける行為を通して建築の形を模索する。
なぜ「気分」を形にしたいのか。それは、人が日常の中で普通に「気分」をいつでもどこでも持ち合わせていて、その「気分」がモノやコトに様々な影響を与えているから、「気分」を建築として形にできれば、これほど日常の中で、使う人と密接な関係を築ける建築はないだろうと考えた。
「気分」に影響を受けた行為は、日常の中で様々な物語をつくり出すだろう。その「気分」はひとつではないだろうから、複数の「気分」の組み合わせと手間をかけて、想像力を発揮し、影響を受けた行為から物語をつくる。
その物語を建築として置き換えて、もともとからある建築の形式との間の落差を利用して、「気分」を建築として表現していく。
その建築は自分特有の「気分」が素だから、自分特有の居場所となる。
"The mood is whereabouts"
I want to make "feeling" form as an architecture. If the act that the user uses in daily life also falls within the category of architecture, the "mood" that has some influence on the act may be the category of architecture.
Since "mood" has no elements that directly lead to the form of architecture, it seeks the form of architecture through actions that are influenced by "mood".
Why do you want to make "feeling" form? The reason is that people usually have a "mood" anywhere in their daily life, and that "mood" has various effects on things and things. In my daily life, I thought there would be no architecture that could build a close relationship with the people who use it.
Actions influenced by "mood" will create various stories in everyday life. Since that "mood" may not be one, it takes time and effort to combine multiple "mood" to demonstrate imagination and create a story from the act that was influenced.
The story is replaced with architecture, and the "feeling" is expressed as architecture using the difference between the original architectural form.
The architecture is a unique place because it has a unique mood.
よーく観察してみることにする、身の回りにあるものを。視界には入っているはずだが、意識して見たことが無かったものや、そのものがつくり出す何かがあるかもしれない。
そこにあっても、意識して見てないと、見えないのと一緒だ。そこで何か日々日常的に起こっていても、意識してわかっていないと、わかっていないのと一緒だ。
特別な何かを探しに出掛けなくても、非日常を味わいに行かなくても、目の前にある普通で日常的な風景の中に、まだ気づいていない大切なものや、それがつくり出す大切な何かがあるかもしれない。
それは他の人には気がつかない、その人特有の感覚でしか見つけることができないから。
建築はその感覚を研ぎ澄ます役目をする。ある特定の感覚に合わせる場合もあるし、そのレンジを広げて、たくさんの人の感覚に合わせる場合もあるだろう。それが、プライベートな空間とパブリックな空間の建築デザイン上の違いになる。
そう建築は、どこまでも、単なる容れ物では無くて、何か影響を与え続けるものである。だから、何でも良いということは無い。
"Nothing is good"
Things that are around you that you will be observing. There should be something in the field of sight that you have never consciously seen, or something that you create.
Even if you are there, you can't see it unless you look at it consciously. So, even if something happens every day, if it is not consciously understood, it is the same as not knowing.
Even if you don't go out to find something special, you don't have to go out to taste the extraordinary, you can create important things that you haven't noticed in the ordinary and everyday scenery in front of you. There may be something.
It isn't noticeable to other people, because it can only be found with a particular sense.
Architecture serves to sharpen that sense. It may be tailored to a specific sense, or it may be expanded to match the feelings of many people. That is the architectural design difference between private and public spaces.
So architecture is not just a container, but something that continues to influence. So there is nothing that can be done.
安全地帯であることをただ構築すると、それはシェルターになる。誰もシェルターには住みたいとは思わないだろう。非常事態の時には致し方ないが、日常的にはそこに居たいとは思わない。
それに安全地帯かどうかは、丈夫さとか、頑丈さとか、備えがあるからとか、では決まらないように思う。心の問題、そこが自分にとって巣とも呼べるような安心感が得られる場所であるかどうか。
それを建築的に表現すると、どうなるだろうか。
ひとつのやり方として、巣と巣以外の場所の違いを明確にして、その違いを拡張する。
例えば、棋士の羽生善治さんは対局でホテルや旅館などに滞在する時は、まず、部屋に自分の私物をたくさん置いて、精神的に落ち着く空間にするらしい。
寝食や身支度は自分の家以外でもできるが、そこの空間にあるものは仮初のもの、見慣れないもの、それが安心感を奪うのかもしれない。
だから、慣れというのもあるだろう。
私の亡くなった祖母は、最期の方は特養に入居していて、たまに一時帰宅をしていたが、特養へ戻ることを「帰る」と言っていた。特養がすでに自分の家と同等のもの、巣のような感覚になっていたのだと思う。
時間が巣にしてくれる、住めば都だとしたら、建築的には何もする必要がないのか、それでも建築的に何か表現できる可能性があるのか。
慣れを紐解いてみる。慣れとはどういうことか、それは空間や空間にある物に時間をかけてその人なりの物語ができることだろう、それは誰にもわからないその人だけの文字通り「物」が「語」る何かがあるのだろう。
しかし、建築にはその物語自体を設計の段階からつくることはできない。なぜなら、その物語は建築が完成後に、その建築に身を置く人がつくる物だからだし、その物語自体を設計の段階で予想して仕向けてしまうのは、あらゆる物語の可能性がある段階でその芽を摘む行為に思える。
ならば、建築にできることは、その「物」が「語」ることを誘発するだけかもしれない。それも陳腐な物語ではなくて、しかし、高尚である必要もなく、日常に即した、誰にでも理解できて、誰でも持つことができる物語、それは見過ごしてしまう位微かなことかもしれない、特別ではなく普通だから、だが、その位のことでないと毎日毎日、物語を紡ぐことはできず、その人に浸透しないだろう。
決して特別なことでは無くて、普通に今そこにある「物」が「語」ることに気がつく日常を建築が誘発する、それは想像させること、それが安心感を与え、その場所が安全地帯になる。
"What you can do in architecture"
If you just build a safety zone, it becomes a shelter. No one will want to live in a shelter. I don't want to be there in an emergency, but I don't want to be there on a daily basis.
And I don't think whether it's a safe zone depends on whether it is strong, sturdy, or prepared. Whether it is a place where you can get a peace of mind that can be called a nest for you.
What happens when we express it architecturally?
One way is to clarify the difference between the nest and the place other than the nest and extend the difference.
For example, when you stay at a hotel or ryokan in a game, Mr. Zenji Hanyu, you seem to have a lot of personal belongings in the room to make it a spiritually calm space.
You can sleep and eat outside your own home, but what is in the space is a temporary one, something you are unfamiliar with, and it may deprive you of security.
So there will be some familiarity.
My deceased grandmother, who was at the end of the period, was in Toyo, and occasionally returned home, but said that returning to Toyo was "going home." I think that the special treatment was already the same as my house, like a nest.
If time is a nest, or if you live in a city, is there anything you need to do architecturally, or can you still express something architecturally?
Try to get used to it. What does it mean to be used to it? It will be that you can take time to space and things in space, and you will be able to tell the story of that person, that is something that only "things" literally "speak" to that person that no one knows There will be.
However, in architecture, the story itself cannot be created from the design stage. This is because the story is created by the person who puts it in the building after the construction is complete, and the story itself is predicted at the design stage and directed at the stage where all the stories are possible. It seems to be the act of picking buds.
So what can be built may only trigger that "thing" "talks". It's not a stale story, but it doesn't have to be lofty, it's a daily story that anyone can understand and have, and it may be a little overlooked, It's normal, not special, but if it's not that much, you won't be able to spin the story every day, and it won't penetrate the person.
It's never a special thing, and it's an architecture that induces everyday life when you notice that "things" there are "speaking". It makes you imagine, it gives you a sense of security, and the place becomes a safe zone. Become.
先日の台風19号のことを時々思い出す。あの時ほど、自分の家が安全地帯だと思ったことはなかった。
仮にあの時に、自分の家以外に居て、例え身が安全だったとしても、何か落ち着かない、不安や心配とはまた違う感情を持っていただろう。
動物には帰巣本能があるように、巣と呼べる安全地帯がまずあって、そこから外界に出ていく。外界で何があろうとも、傷つこうとも、良いことがあっても、巣に戻ってくる。
その本能を差し置いて、家という場所を語ることはできない。もっと言えば、都市の中での自分の家という巣を位置づけることはできない。
ならば、巣としての家の在り方を建築の空間やデザインとして、あるいは、そこにどのような建築性を見出だすかが、日常の「暮らし」そのものを建築に落とし込むキッカケになると考える。
「暮らし」を主題にすると、建築を語れないという人がいる。それは「暮らし」を面倒臭いものと捉えて、そこに新たな違う建築性を見出だすことができず、「暮らし」を排除した既存の建築性でしか語れない人。
これからの建築のキーワードは「暮らし」「日常」「普通」だと考えている。
"Keyword of Architecture"
I sometimes recall the typhoon No. 19 of the other day. I never thought that my house was a safe zone like that.
Even if I was outside my home and I was safe, I would have had a different emotion from anxiety and anxiety.
In order for animals to have a homing instinct, there is a safety zone that can be called a nest. Regardless of what happens in the outside world, whether it is hurt or good, it returns to the nest.
With that instinct, you can't talk about the place of home. More specifically, you can't position your home in the city.
Then, I think that the way to find a house as a nest as an architectural space and design, or what kind of architecture is found there, will be a chance to drop everyday "living" itself into architecture.
There is a person who cannot talk about architecture when the theme is "living." It is a person who regards "living" as a nuisance, can not find a new and different architecturality there, and can only talk about existing architectural characteristics that exclude "living".
I think that the keywords of architecture in the future are "living", "daily life", and "normal".
波紋、砂紋、枯山水の庭園でよく見る波の見立て、石を島に見立て、そこから同心円状に広がっていく。
大海原にぽんと島を投げ込めば、波が立ち、広がっていく。水だから波が立つ。空間に何かを投げ込めば、波は立たないが、空気感が広がっていく。
ものが持つ影響力は時として、空間を決定づける。
そのものがあるだけで、空間に特徴が生まれる。
そう考えていくと、空間は海にも例えることができる。
海の水が充満している中に空間という領域をつくる。
重力があっても、浮力があるから、難なく立つことができるが、海流に負けないためにガッチリつくるか、海流に身を任せて、流されるままに、ユラユラと漂うように柔らかくつくるか。
せっかくだから、ユラユラと漂ってみる。
多少、ブレても、それよりは漂いの中で、居場所がはっきりとはしないが、この辺りがそう、という適当加減がよい。海の水はつながっているから、自分だけの領域を決めたところで、意味が無いし。
海水で満たされていたら、領域なんて意味が無いものになるのか、それは海は誰かのものでは無いからな。
誰かの所有では無い、所有の概念が無くなれば、領域が無くなる。実際には所有の概念を無くすことはできないが、意識としては無くすことができる。
ユラユラと漂うような空間ができれば、所有が揺らぐ、所有が揺らげば、人が居る場所が定まらない。定まらないことは曖昧さを生み、曖昧さの度合いが基準になる。
どれだけ曖昧で定まらないかが重要なんて、素晴らしい空間ができそうだが、似たような建築空間体験がすでに頭に浮かんでいる。
ならば、海は誰かものかと言えば、そんなことはないから、ちがう空間が存在するはず、そう考えていくと、まだ誰も気づいていない空間があるような気がする。
"A space that you have not noticed"
Ripples, sand crests, and the waves that are often seen in the garden of dry mountain water, the stones look like islands, and then spread concentrically.
If you throw an island into the ocean, the waves will rise and spread. Waves stand because it is water. If you throw something into the space, the waves will not rise, but the air will spread.
The influence of things sometimes determines the space.
A feature is born in space just by having it.
Thinking so, space can be compared to the sea.
Create an area called space while the sea water is full.
Even if there is gravity, you can stand without difficulty because it has buoyancy, but you can make it tight so that you can not lose to the ocean current, or you can leave it to the ocean current and make it soft so that it drifts away.
Because it 's a lot of trouble, I 'll try to drift away.
Even if it blurs somewhat, it is more drifting than it is, but the place is not clear, but it is good to adjust appropriately. Because the sea water is connected, there is no point in deciding your own area.
If it is filled with seawater, the territory becomes meaningless because the sea is not someone's.
If the concept of ownership that is not owned by someone disappears, then the territory disappears. Actually, the concept of ownership cannot be lost, but it can be lost as a consciousness.
If you can create a space that drifts, you will lose ownership, and if your ownership fluctuates, you will not be able to determine where people are. Undefined causes ambiguity, and the degree of ambiguity is the standard.
It's important to see how vague and uncertain it is, but it seems like a wonderful space, but a similar architectural space experience has already come to mind.
So, if you say someone in the sea, there is no such thing, so there should be a different space. If you think so, you will feel that there is a space that no one has noticed yet.
歴史があって、積み重ねてきたものがあって、それが体系的になり、今、身に付いているとしたら、どの世界でも、その範囲で通用する言葉を使い、その範囲でのものの見方やその範囲でのルールに従って考え、正解、不正解を出し、あるいは、ものづくりをするだろうが、あるいは、学校なり会社なり社会で教えるだろうが、人はそれよりももっと自由にいろいろ考えられるような気がして、ただ、体系的に身に付いたことがそれを邪魔をしたり、体系的に身に付いたことで判断すると、自由に考えたことが間違っていたり、恥ずかしいことであったりして、途中で自由に考えることを止めてしまう。
別に新しいことを何か発見したり、画期的ことを思いついたりする必要は無いけれど、自由に考える機会が失われてしまうのは勿体ないと思うから、せめて断片だけでも残しておいて、それが積み上がれば、それこそそれが新たに体系的な何かを生み出してくれるはずで、そうやって、自分の中に生み出したものを元にして、今まであったものとの差を最大限に拡張してやれば、それが自分だけの表現になると考えている。
京都の東福寺に行ってみた、お庭を見るために。すこし雨混じりの空だったので、街歩きをするより、こういう時の京都ではお庭を見た方が良いと勧められ、作庭家・重森三玲(1896〜1975)による「八相の庭」を見てきた。
「八相の庭」とは簡単に言うと、八つのテーマでつくられた庭のことであり、その庭が東西南北に配置され、方丈を囲っている。八つの庭の中には、現代的な幾何学模様になっているものもあり、他の日本庭園では見ないその作庭に見入ってしまった。
なぜ見入ってしまったのだろうか、良いと思ったから、では、なぜ良いと思ったのだろうか、庭を見ながら考えてみた。そもそも専門家でも無いから庭の良し悪しなどわからないし、知らない。建築に関係することと考えられなくもなく、ものづくりやデザインをしていれば、同じ尺度で良し悪しを自動的に無意識に判断してしまう、そして、良し悪しを決めてしまう。
簡単に言えば、お庭を建築的に見ていて、建築の歴史を踏まえた建築性を判断基準にして良し悪しを決めている。そこに違和感があって、その判断基準自体がある限られた範囲でしか通用していないにも関わらず、それが全てのような、それが絶対的に正しく、それが当たり前のような思考になっていて、ただ、このような高明な作庭などを見る時には自動的に無意識にそれが出てしまう。
だから、そもそもある程度評価がはっきりしたものや、高明高尚なものからは、新しい思考の発露は生まれないような気がしていて、何だかわからない、ごく普通にどこにでもあり、よく見ているような、日常的にあるものからしか、新しい思考の発露は生まれないのではないかと考えている。
"Exposure of thought"
If there is something that has history and has been accumulated, it has become systematic, and now you are wearing it, in any world, use words that are valid in that range, Thinking according to the rules within that scope, giving correct answers, incorrect answers, or making things, or teaching at school, company or society, but people can think more freely than that I just felt that what I learned systematically interfered with it, or that I learned it systematically, that it was wrong or embarrassing And stop thinking freely on the way.
There's no need to discover anything new or come up with groundbreaking things, but I don't think it's unavoidable to lose the opportunity to think freely. If it accumulates, it should be something that will create something new systematically, and based on what you have created in that way, maximize the difference from what you have ever had I think that if you expand it, it will be your own expression.
I went to Tofukuji Temple in Kyoto to see the garden. Because it was a little rainy sky, it is recommended that you look at the garden in Kyoto at this time, rather than walking around the city. I have seen.
In simple terms, the "Hachino-no-garden" is a garden created with eight themes. Some of the eight gardens have a modern geometric pattern, and I have looked into the garden that I cannot see in other Japanese gardens.
Since I thought it was good why I saw it, I wondered why I thought it was good while looking at the garden. I'm not an expert at all, so I don't know if the garden is good or bad. If you are not considered to be related to architecture, and you are making and designing, you will automatically and unconsciously judge good or bad on the same scale, and decide good or bad.
Simply put, you look at the garden architecturally and decide whether it is good or bad based on the building quality based on the history of architecture. Although there is a sense of incongruity, and the judgment criteria itself is only valid within a limited range, it is like everything, it is absolutely correct, and it is a natural thought. However, when you see such a high-light garden, it automatically appears unconsciously.
So, from the first place with a clear evaluation and a noble and high-class thing, I feel that there is no emergence of new thoughts, I do not know what it is, it is everywhere in the ordinary, I often see, I believe that new ideas can only come out of something that happens on a daily basis.
プライベートとパブリックのバランスを考えている。空間の公私混同のバランス、自分の家でも、ワンルームでも、例えば、人に見せられる部分と見せられない部分があるだろう。それを設えで分けるより、建築で空間化できないかという試み。空間の二面性の扱い方であり、それは本質的には人の二面性にまで及ぶことで、はっきりくっきりと分けるよりも、公私混同、公私が曖昧な空間をつくることを目論む。
さらに、公私のバランスだけでは、空間にも、建築にも特徴が出ない。それは個性かもしれないし、それが、〜らしさ、かもしれないが、バランスだけでは空間や建築として形にならない。
特徴を出すためにはアイテムを使う。アイテムとは空間や建築を彩る全ての物の総称であり、例えば、窓であったり、キッチン、家具など、照明器具も入る。
アイテムが無く、床と壁と天井だけに囲まれた空間や建築はパブリック度が高い。それが、立方体の空間で、床や壁、天井の仕上げが平滑で色が白ならば、パブリック度が1番高くなる。
変形が無く立方体で、何も無く平滑で真っ白な空間、それは何の特徴も無いが、それだけに全ての人や出来事に対して可能性が開かれている。
それが変形をして立方体の空間が直方体、さらには楕円、円、あるいは、もっと複雑な形になるか、または、床や壁、天井の色が白などの無彩色から有彩色に変化するか、あるいは、床や壁、天井の仕上げが平滑から凹凸が現れてくると、プライベート度が増していき、そこにアイテムが1つ、また1つと加わると、さらに、プライベート度が増していく。
複雑に変形した空間で、床や壁、天井の仕上げが極端に凹凸で派手な有彩色になればなるほど、アイテムが多ければ多いほど、プライベート度が高い。すなわち、特徴的になり、個性が出て、〜らしい空間や建築になっていく。
以上の公私のバランス調整を重ね合わせたり、連続させたりして、公私混同の曖昧な空間や建築をつくっていく。
"How to create a public / private mixed space"
Think of a balance between private and public. The balance between public and private spaces in the space, whether in your own home or one room, for example, there will be a part that can be seen and a part that cannot be seen. Rather than divide it by setting, it is an attempt to make space by architecture. It is a way of dealing with the duality of space, which essentially extends to the duality of human beings, and aims to create a vague space between public and private, rather than a clear distinction.
Furthermore, there is no special feature in space or architecture just by the balance between public and private. It may be individuality, or it may be ~ likeness, but balance alone does not form a space or architecture.
Use items to bring out features. An item is a general term for all objects that color space and architecture, and includes, for example, windows, lighting equipment such as kitchens and furniture.
There are no items and the space and architecture surrounded only by the floor, walls and ceiling are highly public. If it is a cubic space, the floor, walls, and ceiling are smooth and the color is white, the publicness is the highest.
Cubic, untransformed, smooth and pure white space, which has no features, but that opens up possibilities for all people and events.
If it is deformed and the cubic space becomes a rectangular parallelepiped, further an ellipse, a circle, or a more complicated shape, or the color of the floor, wall, or ceiling changes from achromatic such as white to chromatic, Or, when the floor, wall, and ceiling finish appear smooth and uneven, the degree of privateness increases, and when one item is added to it, the degree of privateness further increases.
In a complex deformed space, the floor, walls, and ceiling finishes are extremely uneven and flashy, and the more items, the more private. In other words, it becomes characteristic, individuality comes out, and becomes a space and architecture that seems to be.
The above-mentioned balance adjustment of public and private is overlapped or continued to create an ambiguous space and architecture that is confused between public and private.
食べている時の空間はプライベートかパブリックか、食べるという行為はとてもプライベートなことのように思えて、よく考えてみると、食べている時は無防備だし、それを人に見られるのは、結構恥ずかしいことかもしれない。
まあ、好き好んで間近で人の食べている姿をジーッと見ることもないだろうし、見られることもないから、普段はあまり感じないけれど。
ひとりで食べていたら、家でも、お店でも、プライベートな時間で、その場所は周りから切り取られたプライベートな空間になるが、誰かと一緒にいたら、一緒にいる相手によって、プライベートかパブリックかが分かれる。
ならば、それに合わせて、その時々で、時間帯とお店を選べばよいだけだが、場所を変えることができない家ではどうするか、一緒に食べる相手によって設えを変えることもあるだろう。
変化する設え、建築にとっては一番苦手なことだ、建築は変化しないからし、できないから、変化に対応できない。本来ならば、調整できればよいのだが、バランスを、プライベートかパブリックかの。
"Balance adjustment"
The space when eating is private or public, the act of eating seems like a very private thing, if you think carefully, it is defenseless when you eat and it is quite common for people to see it It may be embarrassing.
Well, I don't really like it because I don't really like watching people eating and eating up close.
If you eat alone, at home, in a shop, in private time, the place becomes a private space cut out from the surroundings, but if you are with someone, whether you are private or public depending on who you are with Divided.
If so, you only have to choose the time and shop from time to time, but what to do in a house where you can't change the place, you might change the setting depending on the person you eat together.
Changing settings, the worst thing for architecture, because architecture doesn't change and can't respond to change. Originally, it should be adjustable, but the balance is private or public.
キッチンで暮らすならば、と考えていたら、急に火鉢が思い浮かんだ。
そう言えば、子供の頃、家には火鉢があり、そこで煮炊きをしたり、暖を取ったりしていた。もちろん、メインの火種ではないが、風情もあるが、火鉢がある場所が調理場であったり、ダイニングであったり、リビングだった。
キッチンかキッチンでないか、キッチンか洗面所か、の違いは火が有るか無いかの違いだけ、IHでもよく、ポータブルのIHならば、コンセントがあればどこでもよい。
そう言えば、山やキャンプへ行けば、どこでもキッチンになる。
別にキッチンを固定する必要がなくなると、どうなるだろうか?キッチンで暮らさなくても、暮らしている所がキッチンでもある。
キッチンを隠したいという人がいる。キッチンがなければ、たぶん、住宅とはならず、建築基準法上は事務所扱いになってしまうかもしれない。食を司るキッチンがあるかないかは結構、住宅としては、いや、生活していく上では大事なことになるが、建築としては、キッチンは1つの機能を指す言葉に過ぎないから、機能を満たす器具だけあれば良いと考えれば、場所はどこでも良いので、そうなると、建築の空間や形態はどうやって決まるのだろうか、というより、どうやって決めてもよいのだと、自由だと言える。
"Kitchen is free"
When I was thinking of living in the kitchen, I suddenly thought of a brazier.
Speaking of that, when I was a child, there was a brazier in my house, where I cooked and warmed up. Of course, although it is not the main fire type, there is a taste, but the place with the brazier was a kitchen, a dining room, or a living room.
The only difference between a kitchen or non-kitchen or a kitchen or washroom is whether there is a fire or not. IH may be used.
Speaking of which, if you go to the mountains and camping, it will be a kitchen everywhere.
What happens if there is no need to fix the kitchen separately? Even if you do not live in the kitchen, the place where you live is also the kitchen.
Some people want to hide the kitchen. If there is no kitchen, it will probably not be a house and may be treated as an office under the Building Standards Act. Whether or not there is a kitchen that controls food, it is quite important as a house, but it is important for living, but as an architecture, kitchen is only a term for one function, so it satisfies the function If you think that all you need is equipment, then you can place it anywhere, and if so, you can say that you can decide rather than how the space and form of the architecture are decided.
料理を自分でつくって食べることは自分の家でしかできない、この際の自分の家は別荘、別宅を含み、キャンプは入れない。
だから、料理をつくり、それを食べることは、自分の家での主要な生活活動になる。よく考えてみると、その他の生活活動は、別に自分の家でなくても、寝ること、お風呂に入ること、家族と一緒に過ごすことでさえも、できる。
では、自分で料理をつくらない人は、自分の家はいらないのかというと、別になくても、それこそ、余計にお金はかかるかもしれないが、ホテル暮らしをしている方が良いかもしれない。ただ、それで安全地帯にいるような安心感が得られるかどうかは別の話だが。
お腹が空くのは生理現象だから、そのために何か食べ物を用意しなければならないことは誰でも同じ、ならば、極端なことを言えば、自分でつくる人にとって、自分の家=キッチン、と言っても差し支えないだろう。
私は家で仕事をしているが、寝る時以外は、ダイニングにずっといる。仕事部屋はあるのだが、今や資料や本の置き場で、ダイニングテーブルで仕事をする。
大した料理をする訳ではないが、このスタイルになったのは、豆を煮るようになってから、途中経過が気になって仕方がなかったのと、豆を煮ている時の匂いが大好きだったので、近くで仕事をするようになり、今ではキッチンの真横が定位置、冷蔵庫も近いし、コーヒーも豆から挽いていれるから、都合がよくて。
だから、1日の家での居場所の分布図をつくったら、とても狭い範囲におさまるだろう。ならば、規模を小さくして、キッチンで暮らせば良いと思っていて、その分空いた所は庭か何かにして、隣家との距離をより多く取り、窓からより多く陽の光を取り入れたいと考える。
"Kitchen life"
You can only cook and eat your own food at your own home. Your home includes villas and homes, and you cannot enter camp.
So cooking and eating is a major activity at home. If you think about it, you can do other life activities, even if you are not in your own home, sleeping, taking a bath, or even spending time with your family.
So if you don't cook yourself, you don't need your own house, even if you don't need it, it might cost more, but you might want to live in a hotel . However, it is a different story whether it will give you a sense of security as if you were in a safe zone.
Hungry is a physiological phenomenon, so everyone has to prepare food for that, so if you say the extreme, for those who make it, your home = kitchen It would be safe.
I work from home but stay in the dining room except when I sleep. Although there is a work room, I now work at a dining table in the storage of documents and books.
I didn't cook a lot, but this style was because I started cooking boiled beans, and I couldn't help thinking about the progress, and the smell of cooking beans I loved it, so I started working nearby, and now it is convenient because the kitchen is in place, the refrigerator is close, and coffee can be ground from beans.
So, if you make a map of whereabouts at home in a day, it will fit in a very narrow area. If so, I thought it would be nice to make it smaller and live in the kitchen, and make that space a garden or something, take more distance from the neighbor and take in more sunlight from the windows I want to.
「さてと、何をつくればいいのか?」と考えてみる。
何かポーンっと、お題を与えられれば、案外自動的に、ポーンっと出てくるのだが、そればかりではつまらないから、その自動的な中身をよくよく見つめ直してみようと試みる。
そこで、2つの分かれ道に出会う。
1つは行き先を決めないで、その時、その時を積み上げていく道と、もう1つは行き先を決め、ただひたすら、そこに向かって進む道と。
どちらかの道が正解で、どちらかの道が不正確、ということは無く、ただ、道によって、辿り着く場所は違う。
ちょっと、行き先を決めて進むやり方はずっとしてきたし、仕事ならば尚更で、行き先を決めないと何も計画通りには進まないので、ただ、何ができれば満足するのだろうかと考えてみると、まず行き先を決めてしまうと、重い道のりになり、それは、できあがるものに良い影響を与えないだろうから、行き先を決めるのは止めて、進む道中のことを、如何にしたら、道中が楽しみになるかな、そのためには、どうするかなと考えてみる。
つくりたいものの理想は持ちつつ、毎日、何をつくろうかな、どうやってつくろかな、と考えること自体から楽しい状況がいい。
そうすると、つくり方が楽しいものでないと、ただ、つくり方ほど、決まっているものは無い。その都度、つくり方が変わっていたら、広まらないし、効率が悪いから、ただ、楽しむためには。
ということで、つくり方から考え直す試みをはじめていて、久しぶりに夜のKinko'sに来たのでした。
"Rethink"
Think about "What should we make?"
If you are given a pawn and a title, it will come out automatically, but it will not be enough, so I will try to take a good look at its automatic contents.
So we meet two forks.
One is to decide where to go, and then to build up that time, and the other is to decide where you want to go and just go to that.
Neither road is correct or one is incorrect, but the place to reach depends on the road.
I've been doing a lot of ways to decide where to go, and if it's a job, it's much more so if I don't decide where to go, nothing will go according to plan. First of all, if you decide where to go, it will be a heavy road, and it won't have a positive effect on what you'll get, so stop deciding where you want to go, and how you look forward Kana, think about what to do for that.
Having the ideal of what you want to make, it's a fun situation to think about what to make and how to make it every day.
Then, if the method of making is not fun, there is nothing as fixed as the method of making. If the way of making changes each time, it won't spread and it's inefficient, so just enjoy it.
So, I started an attempt to reconsider how to make it and came to Kinko's at night after a long time.
光の移り変わり具合をずっと眺めたことがあるだろうか。影でも同じ、ひとつの所に留まって、じっと何時間も光や影を眺めたことがあるだろうか。
やろうと思えばできなくはない。簡単にやるならば、自分の家でできる。窓から差し込む光の軌跡を追えばよい。ただ、ボーッとして眺めているだけでいい。
でもやる人はいないだろう。そこまで暇な人がいないし、そもそも飽きてしまって見ていられない。
名建築といわれる所に泊まることができても、朝日を浴びるくらいしかできない。1日中いることはできない。
ただ、設計する側はその光の移り変わり具合を計算していたりする。どこに開口部を取るかを考える時に想像している光を。
はじめて見学した建築家の作品は安藤忠雄「光の教会」である。建築の俗名にもあるように、光の十字架が特徴的な建築で、コンクリート打放しの壁に十字状にスリットが入っている。その時に、その十字架の光の移り変わり具合を午前中から夕方、暗くなるまで眺めていた。打放しの壁に十字状にスリットが入っているだけのシンプルな建築なのに、その光の移り変わり具合の豊かさに感動し、それが設計をはじめるキッカケだった。
光は誰にでも平等に手に入る。その光に十字架の形を与えてしまうのは建築家の力量だと、その時素直に思い、こういう仕事がしたいと思った。そして、その時にいつも目にしている光の可能性に気づき、それ以降も光を意識するようになった。
今まで意識していなかったことを意識付けされ、しかもそれに感動したから、建築というものが強く印象付けられてしまった。
"light"
Have you ever watched the transition of light? Have you ever stayed in the same place with shadows and looked at light and shadows for hours?
If you want to do it, you can't do it. If you do it easily, you can do it in your own home. What is necessary is just to follow the trace of the light which injects from a window. You just have to watch it.
But no one will do it. There aren't many people out there, and I'm tired in the first place.
Even if you can stay in a place that is said to be a famous building, you can only take the sun. I can't stay all day.
However, the designing side calculates the degree of change of the light. The light you are imagining when you think about where to take openings.
The first architect to visit is Tadao Ando's "Church of Light". As is known in the name of architecture, it is a structure with a cross of light, and there are slits in the shape of a cross on the concrete wall. At that time, I watched the light transition of the cross from morning till evening until it became dark. Even though it was a simple structure with slits on the wall, it was impressed by the richness of the light transition, and that was the beginning of the design.
Light is available to everyone equally. I thought that it was the architect's ability to give the light a cross shape, and at that time I wanted to do this kind of work. At that time, I realized the possibility of the light that I was always seeing, and after that I became aware of the light.
I was impressed with what I hadn't been aware of before, and I was impressed with it, so I was impressed with architecture.
軽井沢にある篠原一男のTanikawa Houseでのお茶会後、名残惜しく、その地を離れる前に、もう一度、建物の周りを巡って、斜面を登り、南側から見た時だった、今までの様相とは違う表情が見え、ハッとし、思わず「いい」と呟いてしまった。
その時すぐに写真に納めたが、それをお見せできないのは残念だが、それまで強い建築の形式故に、その形式の強さが先導して、この建築はこう理解するのがよろしいという指示の元、確かにそれが素晴らしく、感動してはいたので、満足していたが、その瞬間、形式を超え、建築が周りの空気と同化したような、一瞬建築が消えたような、周りの自然と同化したような、考えてみれば、自然ほどそのルールに則った形式の強いものは無く、その自然の形式に建築の形式が同化した、いや、そのものになったような錯覚が起こった。
そのような感覚を覚えたのはじめだった。この感覚を味わっただけでもここに来て良かったと思ったが、それも一瞬だった。
建築の形式が強いことが時には権威的と批判されることもあり、いかに弱めるかがデザインの暗黙の了解である時もあるが、いや、もしかしたら、形式の強さには別の可能性があるのかもしれない、何故なら、やはり形式の強さには惹かれてしまうから。
"Illusion of the moment"
After the tea party at Tanikawa House by Shinohara Kazuo in Karuizawa, before leaving the place, once again around the building, climbing the slope and looking from the south side, the situation until now I saw a different expression, and was relieved and unintentionally screamed "good".
I immediately put it in the photograph at that time, but I am sorry that I can't show it, but because of the strong form of architecture until then, the strength of that form leads, and I am instructed to understand this architecture like this Sure, it was wonderful and impressed, so I was satisfied, but at that moment, beyond the form, the architecture was assimilated with the surrounding air, the architecture disappeared for a moment, the surrounding nature and If you think of it assimilated, there are no strong forms that follow the rules of nature, and there is an illusion that the form of architecture has become assimilated into that natural form.
It was the beginning of learning such a feeling. I thought it would be good to come here just by tasting this feeling, but it was also an instant.
The strong form of architecture is sometimes criticized as authoritative, and how to weaken it is sometimes an implicit understanding of the design, but maybe there is another possibility for the strength of the form It may be because it is attracted by the strength of the form.
軽井沢にある篠原一男のTanikawa Houseでのお茶会に参加した後、軽井沢千住博美術館に行った。
くしくも、両建築とも、時代は違うが、斜面地をそのまま利用した傾斜する土間を持つという共通点がある。だが、受ける印象は全く違う。
Tanikawa Houseは、斜面という地形を建築という形式に取り込み、跡形もなく建築化している。だから、建物周りの斜面と連続してはいるものの、土間に立った時に地形を感じることは無い。
軽井沢千住博美術館は、地形そのものを空間化しているようで、ガラスや屋根といった内と外を区切る輪郭があるから辛うじて建築だとわかるような、土間に立つと、土間=地形だと感じる。
Tanikawa Houseは、建築の形式の強度が強く、建築の姿や佇まいが自然と相対している。
軽井沢千住博美術館は、地形を空間化し、建築は輪郭だけ、建築の形式の強度は弱く、建築の姿や佇まいが無く、建築と自然が同化しているが、それを形式と考え、自然と同化できる位に強い形式を有しているとも言えなくもないが、Tanikawa Houseが持つ強い建築形式とは全く真逆の形式なので、両建築を比較した場合は、軽井沢千住博美術館の建築形式の強度は弱いとなるだろう。
どちらも世界的な建築で、感動してしまう位に素晴らしい建築体験をもたらしてくれるが、個人的には何故だか、建築形式の強度が強く、建築の姿や佇まいがはっきりと現れているものに惹かれてしまう。
"Inclined soil"
After attending a tea party at Tanikawa House by Shinohara Kazuo in Karuizawa, I went to the Karuizawa Senju Museum.
In addition, both architectures have a common point that they have sloping soils that use sloped land as they are, although the times are different. However, the impression I receive is completely different.
Tanikawa House incorporates the terrain of slopes into the form of architecture, and is built without a trace. Therefore, although it is continuous with the slopes around the building, it does not feel the terrain when standing in the dirt.
The Karuizawa Senju Museum of Art seems to make the terrain itself spatial, and because it has a contour that separates the inside and the outside, such as glass and roof, when you stand in the dirt, you can feel that it is a terrain = terrain.
Tanikawa House is strong in the form of architecture, and the appearance and appearance of architecture are relative to nature.
The Karuizawa Senju Museum of Art has spatialized the terrain, the architecture is only outline, the strength of the architectural form is weak, there is no form or appearance of the architecture, the architecture and nature are assimilated, but it is considered as a form, Although it can be said that it has a strong form that can be assimilated, it is completely opposite to the strong architectural form that Tanikawa House has, so when comparing the two architectures, the architectural form of Karuizawa Senju Museum of Art The strength will be weak.
Both are world-class architectures that bring amazing architectural experiences to the touch, but for personal reasons, the strength of the architectural style is strong and the appearance and appearance of the architecture is clearly visible I will be attracted.
その建築は森の中で凛々しく光り輝いていた。
軽井沢にある篠原一男のTanikawa Houseでのお茶会に参加した。個人の邸宅ということもあり、長らく未公開の建築で、一般公開されたのは竣工以来今回がはじめてらしく、あまり使われていない時期もあり、竣工当時のそのままの姿で現存しているという。
説明によると、Tanikawa Houseとは、1974年、谷川俊太郎氏が一編の詩を建築家篠原一男氏に託して建てられた北軽井沢の別宅、とのこと。
この住宅の特徴は、斜面地に建築され、その斜面がそのまま住宅内に連続して現れたような傾斜した土間を持っていること。その土間は、南北に9mの幅で、1.2mの落差を持ち、火山灰が一面敷き詰められている。この土間で谷川俊太郎は様々なイベントを行うことを想定していたらしい。
さらに、その土間には、45度の方杖が付いた太い柱が、存在を強調するように配されていた。
また、屋根が地面から1m位の高さから45度の角度ではじまるので、斜面に屋根だけが載っている印象になり、外観の印象は全てが屋根で、その屋根の材質がシルバーに着色された亜鉛鉄板なので、森の中で光り輝き、その輝きは鈍く、時として、落ち葉なのか、錆なのか、わからない経年劣化が周りの木立と絶妙な調和をはかっていた。
全体の印象としては、斜面地にシルバーの屋根が架り、それを太い柱が支え、壁が外部と内部を仕切り、斜面がそのまま室内の土間に露出して、これらの建築の架構要素が強調されることによって、建築の形式が強く打ち出され、建築が初源的な姿で、凛々しく自然の中に鎮座していた。
ところが不思議なもので、その強い建築の形式が自然の中で存在感を出しながら、うまく自然と馴染んでいた。
何故だかわからないが、その強い建築形式にとても惹かれた。
(その場での写真撮影は可でしたが、SNS等での建築写真の投稿は不可でした)
"Tanikawa House Autumn Tea Party"
The architecture shone brilliantly in the forest.
I participated in a tea party at Tanikawa House by Kazuo Shinohara in Karuizawa. It may be a private mansion, and it has been unpublished for a long time, and it has been open to the public since it was first completed, and there are times when it has not been used so much.
According to the explanation, Tanikawa House is a separate house in Kita Karuizawa, built in 1974 by Shuntaro Tanikawa entrusting a single poem to architect Kazuo Shinohara.
The feature of this house is that it is built on a sloping ground and has a sloping soil where the slope appears continuously in the house. The soil is 9m wide from north to south, has a drop of 1.2m, and is covered with volcanic ash. It seems that Shuntaro Tanikawa was supposed to hold various events in the space.
In addition, a thick pillar with a 45-degree cane was placed between them to emphasize its existence.
Also, since the roof starts at an angle of 45 degrees from a height of about 1 m from the ground, it becomes the impression that only the roof is on the slope, all the appearance impression is the roof, the material of the roof is colored silver Because it was a galvanized iron plate, it shone in the woods, and its brightness was slow.
The overall impression is that a silver roof is built on the slope, a thick pillar supports it, the wall partitions the exterior and interior, and the slope is exposed as it is between the indoor soils, emphasizing the structural elements of these buildings As a result, the form of the architecture was strongly launched, and the architecture was in its original form and was majestically settled in nature.
However, it was mysterious, and its strong architectural form made a presence in nature, and it was well adapted to nature.
I don't know why, but I was very attracted to its strong architectural style.
(Photographing on the spot was allowed, but posting of architectural photos on SNS etc. was not possible)
設計をしていると、いろいろな断片が頭に浮かぶ。
その断片は本当に些細なことだ。村上春樹はその断片を「説明しない」ということに心がけて、小説という容れ物の中にどんどん放り込んで、立体的に組み合わせていき、その組み合わせは世間的ロジックや文芸的イディオムとは関わりがないところでおこなわれ、それが基本的スキームになるとのことだった。
受け止めた断片を「説明しない」とは、イマイチよくわからなかったが、断片の個々の意味はどうでもよくて、断片同士の関係性が重要で、断片同士を立体的に組み合わせることによって、全く違う意味合いのものをつくりだそうとしていると解釈した。
それは建築でも可能であり、断片を「説明しない」ことは、思い浮かんだ断片、例えば、何かの問題であれば、それにイチイチ回答しない、という態度であり、問題にイチイチ回答するよりは、問題を立体的に組み合わせることによって、新たな、問い掛けている角度が全く違う問題をつくり出してしまうような試み、新たな問題をつくり出すことができれば、今まで見たこともないような答えに遭遇できる可能性があり、それは新たな建築につながる。
受け止めた断片をどう処理するのか、そのヒントを与えられたような気がする。
"Process not explained"
As you design, various fragments come to mind.
That piece is really trivial. Haruki Murakami keeps in mind not to explain the fragment, throws it into the container of novels and combines them three-dimensionally, where the combination has nothing to do with public logic or literary idioms It was done and it became a basic scheme.
I didn't really understand that I didn't explain the fragments I received, but I didn't care about the individual meanings of the fragments, the relationship between the fragments was important, and it was completely different by combining the fragments three-dimensionally. I interpreted it as trying to create something meaningful.
It is also possible in architecture, and "not explaining" a fragment is a fragment that comes to mind, for example, the attitude of not responding to it if it is a problem, rather than just answering the issue. By combining the three-dimensionally, you can try to create a new problem with a completely different angle, and if you can create a new problem, you can encounter answers that you have never seen before There is a nature, which leads to new architecture.
I feel like I was given a hint about how to handle the pieces that I received.
設計をしていると、いろいろな断片が頭に浮かぶ。
建築をする場所の環境やクライアントの要望はもちろんのこと、この場合、咀嚼され、重要だと考えたり、印象に残ったり、理解できなかったり、変だな、おかしいなと、別にまとめられている訳では無くて、系統だっている訳ではなくて、逆に、うまく設計に組み込めないようなことが断片で浮遊している感じ、あと、過去の記憶から、似たような場面、参考になりそうな建築を訪れた時や、本の言葉、建築家の話など、建築以外でも、訪れたレストランの料理やその時の会話、旅や遠出した時の日常とは違う場面、子供の頃の思い出などなど、ありとあらゆることが、細切れの断片となって出てくる。
ほとんどが直接に関係が無いことのように思い、浮かんでは消えて、浮かんでは消えてを繰り返すのだが、では全く関係が無いかと言えば、そうでも無くて、どこかが多少なりとも引っ掛かりがあるから、頭に思い浮かぶのだろう。
だから、考えようによっては、こちら側が、その思い浮かぶものを処理する能力に欠けているから、せっかく思い浮かんだのに、取り逃がしているとも言えなくもない。
こちら側の意識とは関係無しに思い浮かぶものを、厳密に言うと、こちら側の何らかの意識に反応して思い浮かぶのだろうが、それをコントロールができないので、もし、コントロールをするとしたら、その意識の部分だが、人は単一の意識だけで成り立つほど単純では無いので難しく、そうなると、あとは思い浮かんだものをどのように受け止めるか、という戦略なり、戦術なり、技術、それを論理という人もいるだろうが、論理になってくると、結果的に出来上がるものが、自分から出てきたものとしては不自然なものになるような気がして、もっと自分的な、言葉がおかしいが、もっと自然な受け止め方ができないか、そうすれば、創作がより個性的になるような気がして、あとは、受け止めたものを建築化するだけだが。
では、自然な受け止め方とは、それは端的に言うと、専門性を切り離した態度から生まれるのではないだろうか。
"Processing fragments"
As you design, various fragments come to mind.
In addition to the environment of the construction site and the client's request, in this case, it is chewed, it is thought that it is important, it is impressed, it is not understandable, strange, funny, it is summarized separately It is not a translation, it is not a system, and conversely, things that cannot be incorporated well into the design feel floating in fragments, and similar scenes from the past memories are likely to be helpful Other than architecture, such as when visiting a new architecture, the words of a book, the story of an architect, etc., the cuisine of the restaurant you visited, the conversation at that time, different scenes from everyday life when traveling or traveling, memories of childhood, etc. Everything comes out in small pieces.
Most of them seem to have nothing to do with it, it disappears when it floats, and disappears when it floats, but if it says nothing at all, it is not so, and there is some kind of catch Will probably come to mind.
So, depending on your thoughts, this side lacks the ability to process what comes to mind, so it's hard to say that you've missed it.
Strictly speaking, what comes to mind without regard to consciousness on this side will come to mind in response to some consciousness on this side, but it cannot be controlled, so if you control it, Although it is a part of consciousness, people are difficult because it is not so simple that it can be realized only by a single consciousness, and then it will be a strategy, tactics, technology, logic that how to accept what you thought of There will be, but when it comes to logic, I feel that what will be done as a result will be unnatural as something that came out of me, but my language is stranger I don't think I can do it more naturally, or I feel like my creation is more personal, and then I just build what I received.
So, in a nutshell, the natural perception is born from an attitude that separates expertise.
何かをつくっている時が一番楽しいとしたら、その時は頭の中で何を考えているかな、何かがないとつくれないから、いつも何かないかな、何か手がかりがないかな、と考えているようだ。
その手がかり探しも楽しいのだが、ふと、手がかりは必要なのかと。
よくよく考えてみれば、手がかりなどなくても、つくれるなと、それが良いものか悪いものかは別にして、つくれてしまう。
そもそも建築なんて単純なんだと、日本的に考えれば、柱を建てて、屋根を架けて、壁で覆えば良い。ただそれだけで建築になる。神社やお寺は正にそれだけのことでできている、初源的な建築、立派に建築になる。
では、それで良いかと言えば、よくない。
そのよくない理由を、せっせと、あれこれと考えていたのが、どうも、初源的な建築の前では太刀打ちできない。
困ったものだ、だって「そんなことしなくても別にいいんじゃないの」なんてことを言われたら、その一言で吹き飛びかねない。
実際には、クライアントがいて、そのクライアントの要望を聞いた上でプレゼンをし、きちんと言葉で何故こうなるのかを説明をするし、それは当然要望に沿ったものだから、「そんなことしなくても別にいいんじゃないの」なんて一言で終わることはないけれど、ただ、それはプレゼンのテクニックに依存していることであり、今ここで考えていたことは、そもそも建築をつくる時にどうするか、というプレゼン以前、要望以前のことで、もちろん、それは技術的なことではなくて、要するに設計論になる。
例えば、モデリングと称して、いろいろな建築家の設計論を持ってきたとしても、初源的な建築の前ではどうでも良いことになる。それが、歴史的や学術的な側面が強くなれば、その設計論に一定の説得力が出てくるのだが、その歴史的や学術的な側面すら別になくても良い場面など、むしろそちらの方が多い。
ならば、今考えているのは、もっと偏屈になって、その偏屈さの強度で、初源的な建築に対抗しようかと、人が何かをつくる時、拠り所にするのは、結局はそこ、すなわち、初源的な建築との違いを強調することしかできない。
"The reason why it is not good"
If you are having fun making something, what do you think in your mind at that time, you can't make something without something, so there's always something or a clue? It seems to be.
Searching for clues is fun, but suddenly, I need clues.
If you think carefully, if you can't make it without clues, you can make it, whether it's good or bad.
In the first place, if you think in Japan that architecture is simple, you can build a pillar, build a roof, and cover it with walls. It just becomes architecture. Shinto shrines and temples are truly original architectures that are made of that much.
So, that 's not good.
I've always thought about the bad reason, but I can't beat it in front of the original architecture.
It's a problem, because if you were told that you didn't have to do that, you could blow it away.
Actually, there is a client, and after making a presentation after listening to the client's request, explain exactly why this happens in words. It doesn't end in a word, but it just depends on the technique of the presentation, and what I was thinking about now is what to do when building architecture in the first place. Before the request, of course, it is, of course, not a technical thing, but a design theory.
For example, even if you bring the design theory of various architects called modeling, it doesn't matter before the original architecture. If the historical and academic aspects become stronger, a certain persuasive power will appear in the design theory, but there are situations where it is not necessary to separate even the historical and academic aspects. There are more.
So, what I'm thinking about now is that it becomes more biased, and the strength of that bias makes it a base when people make something, whether they want to compete with the original architecture. In other words, we can only emphasize the difference from the original architecture.
「〜らしい」とか、「〜らしく」とか、「〜風」は結局、「〜」では無いということなのに、それは当たり前だけれども、「〜」だと勘違いをついしてしまう。
例えば、「建築家らしい」振る舞いとか、「建築家らしく」行動するとか、何の職業や肩書きでも良いが、その人はその職業や肩書きでは無いから、あるいは、無いと思うから、そう考えるのだろう。
例えば、「和風」料理は、和食風味の料理ということであり、和食では無いし、「欧風」料理も、かなりアバウトだが、フランス料理っぽいとか、イタリア料理っぽいもので、フランス料理でも、イタリア料理でも無い。
「自分らしい」とか「自分らしく」も同じ、そう言っている時点で、自分では無い。
そもそも「〜らしい」「〜らしく」「〜風」などとなると、曖昧になり、その曖昧さを求めているならば良いのだが、案外言っている本人はその曖昧さを求めてはおらず、しっかりカッチリしたものをイメージしていて、ただ、そのものズバリを言い当てる言葉を持ち合わせていないか、頭の中がクリアでは無いのか、自信が無いのかもしれない。
それに「〜らしい」「〜らしく」「〜風」などは全て、外からの決めつけみたいなもの、慣習であったり、常識と言われて範囲のことであったりして、社会的な識別には役に立つかもしれないが、その人であったり、そのもの自体は、それとは別に存在していて、それとは別に成り立ちがあるのだから、何か中身のなる人なりものなりにしたければ、どうでも良いようなことだと思う。
なんて、当たり前のことだろう、なのに自分に対して「〜らしい」とか、「〜らしく」とか、普通に思ってしまうから、それを取り除いた先をイメージしてみようと。
"Like"
Although it seems to be "~", "~ like", or "~ wind" is not "~", it is natural, but it is misunderstood.
For example, you may behave as an "architect" or "behave as an architect", any occupation or title, but because that person is not or does not have that occupation or title, think so. Let 's go.
For example, "Japanese-style" cuisine is a Japanese-flavored dish, not Japanese, and "European-style" dishes are quite about, but they look like French or Italian food. It's not cooking.
The same is true of "Like me" or "Like me".
In the first place, when it becomes "~", "~" or "~", it becomes ambiguous and it is good if you are seeking the ambiguity, but the person who says unexpectedly does not seek that ambiguity, firmly You may be imagining something that is cluttered, but you may not be confident that you don't have words to tell you exactly, or that your head is not clear.
In addition, "~", "~" and "~ wind" are all things that seem to be determined from the outside, such as customary or common sense, and range. It may be useful, but the person itself, or itself, exists separately from it, and it has a separate origin, so if you want to be something inside you don't care I think that's true.
I don't think it's normal, but I usually think of myself as "~" or "~", so I'd like to imagine where it was removed.
最近出会って、ハッとした文章から、
『考えてみれば、とくに自己表現なんかしなくたって人は普通に、当たり前に生きていけます。しかし、にもかかわらず、あなたは何かを表現したいと願う。そういう「にもかかわらず」という自然な文脈の中で、僕らは意外に自分の本来の姿を目にするかもしれません。』
ある人から、だいぶ前に、村上春樹の『職業としての小説家』は面白いから、文章だけでは無く、何かをつくる人は読んだ方が良いから、と言われた。前に『走ることについて語るときに僕が語ること』は読んだことがあり、ただ実は、村上春樹の小説を読んだことが無く、興味も無かったので、人から言われてもすぐには読まなかった。
そうしたら、また最近、ちがう人から、同じことを言われたので、それならばと読みはじめ、冒頭の文章に出会った。
普通につくれば、人はそれだけで喜んでくれるし、感謝もしてくれる、それで生活もできる訳だから、こんな良いことはないとは思うし、それで当たり前に生きていけるけれど、つくっている本人は、出来上がったものに物足りなさを感じる、出来上がったものがつまらないと感じる、「にもかかわらず」そう思うから、だから、何かをしたくなる、何かを変えたくなる。
そう思うことの中身を抽出して、そう思わないようにしてやれば良い。とてもシンプルで単純な話だ。
ところが、そこをあれこれやり過ぎて、結局は不自然な方向へ行き、不自然なことをしはじめる。今度は、そのとてもシンプルで単純なことをやることに物足りなさを感じるから、何か自分なりの表現を意図して持たないといけないと考えてしまうから、それが作家性であり、作品性につながると考えてしまうから。
「にもかかわらず」という問いかけは、自己表現することが、とてもシンプルで単純な話であることを思い出させてくれた。
"in spite of"
Recently met, from a surprised sentence,
"If you think about it, people can live normally, especially if they don't do self-expression. But nevertheless you want to express something. In such a natural context of "in spite of that", we may be surprised to see our original appearance. ]
A long time ago, Haruki Murakami's "Novel as a profession" was interesting, so it was better to read not only the text but also the person who made something. I've read "What I say when I talk about running" before, but in fact, I've never read a novel by Haruki Murakami and I wasn't interested in it. I didn't read it.
Then, recently, another person told me the same thing, so I started reading and met the first sentence.
If you make it normally, people will be pleased with it alone, thank you, and you can live with it, so I think that there is no such good thing, so you can live naturally, but the person who is making it, I feel unsatisfactory with what I'm finished with, I feel like it's boring, I think "even though", so I want to do something, I want to change something.
You can extract the contents of what you think so that you do not think so. It's a very simple and simple story.
However, if you do too much, you will eventually go in an unnatural direction and begin to do unnatural things. This time, I feel unsatisfactory in doing that very simple and simple thing, and I think that I have to have something of my own expression. Because it thinks that it is connected.
The question "Despite" reminded me that expressing myself was a very simple and simple story.
台風が去った後、翌朝の澄んだ青空を気持ち良く迎えることができ、雨戸を開け、家の周りを点検し、本当に幸いにも何も被害が無く、また普段の生活に戻ることができたが、被害に遭われた方々のことを思うと胸が痛く、Facebook上では、ラグビーの歓喜と、被害の状況が、交互に映り出されて、そうなると、自分からそれらの事実がどんどん遠ざかるような気がして、どちらも現実で、どちらも大変なことだが、あまりにも両極端な出来事過ぎて、現実感が追いついていかない。
その現実感が追いついていかない様は、あの強烈な台風の最中にも感じていて、あまりにも雨風が酷くて、でも何もできない、ただじっと耐えるしかない状況で、ことさら不安にならないようにするためには、これは現実では無く、フィクションで、映画のセットの中に迷い込んでしまった位に思わないと、対応できない位だった。
だから、それが翌朝の青空でリセットされ、喉元過ぎれば熱さ忘れる、になるかと思ったが、そうは簡単には行かずに、続きがあり、あまりにも自分の状況とは違う被害状況に戸惑い、それは同じ台風に自分も晒されたからで、なぜか落ち着かない、ソワソワ感が止まらない。
ただ、それでも、明日はどうしようかな、何をしなくてはいけないのかなと考えるのだから、それは今日と明日を違うものにしようという意欲ととらえれば、きっと、その、落ち着きの無さやソワソワ感は、現実を脳か身体か心が消化しようとしているサインかもしれないと受け止めることにした。
"Reality"
After the typhoon left, I was able to greet the clear blue sky comfortably the next morning, opened the shutters, inspected the house, and fortunately there was no damage and I was able to return to my normal life. When I think about the victims, my heart hurts, and on Facebook, the joy of rugby and the situation of the damage are reflected alternately, and then I feel that those facts are moving away from me. However, both are real and both are tough, but both extreme events are too much to keep up with reality.
I don't want to be overwhelmed by the fact that the strong typhoon feels that the reality is not catching up, the rain and wind are too severe, but I can't do anything, I just have to endure it. For this reason, this was not a reality, it was a fiction that could only be dealt with if you didn't think you got lost in the movie set.
So, I thought that it would be reset in the blue sky the next morning and forget about the heat if it is too close to my throat, but it will not go so easily, there is a continuation, and I am confused by the damage situation that is different from my situation, That was because I was also exposed to the same typhoon, so I couldn't calm down.
However, I still think what I should do tomorrow and what I have to do, so if I think that it is a willingness to make today and tomorrow different, I'm sure the calmness and feeling of sorrow I decided to take reality as a sign that my brain, body, or mind is trying to digest it.
先の台風でもそうでしたが、被害に遭われた方々のことを想うと胸が痛みます。例え、対策をし尽くしたとしても、それを上回る自然の力の前にはなす術がない。きっと大昔の人は、特に日本人は、抗うより、受け入れることで、こういう状況を乗り越えてきたのでしょう。だから、昔よりは、それでも治水に関しては良くなったと、子供の頃はよく神田川が氾濫していたのが無くなったり、賛否があってもダムが今回の台風による被害を軽減させたらしい。
水と食料が当たり前にあるから、それが無くなることを想像できない、できても想像力が及ぶ範囲が狭い。今回、自分がいる地域は断水も停電もしなかったが、それはたまたまで、あの強烈な雨風の中、家にいて、いつ停電しても、いつ断水しても、おかしくない状況だと思っていた。
対策はしていて、バッテリー、ソーラーパネル、カセットコンロ、食料、水は貯められるだけ貯めて、ただ、実際に停電や断水になった場合、これで何日持つか、何日持たせれば復旧するかもわからないのに、対策をするのは難しかった。
当たり前の物だから、余計に実感が湧かない、無くなることを、それは豊かの代償かもしれないが、対策をして電源、食料、水が十分にあったとしても、いざ停電や断水になったら不安は消えないだろう。
強烈な雨風の中で一番思っていたのは、普段通りに生活を、時間を、送ること。特別に対策をし過ぎると、かえって不安が消えないし、疲れてしまう。
だから、今、停電や断水を経験している方々には、電源、食料、水がもちろん大事だが、早く普段通りの生活や時間の送り方ができるようになって欲しい。ライフラインや住む所の復旧には時間がかかるかもしれないが、それでも、生活や時間のリズムが普段通りに戻すことができれば、精神的にはだいぶ落ち着き、疲れなくなるだろうし、そのためには自然の力は受け入れて対応するしかできない。
"Power of nature"
As with the previous typhoon, my chest hurts when I think of the people who have suffered the damage. Even if you take all the measures, there is no way to do it before the power of nature that exceeds it. Surely people in the past, especially Japanese, have overcome this situation by accepting rather than resisting. Therefore, it seems that the flood control has improved from the past, and it seems that the Kanda River was often flooded when I was a child, and even if there were pros and cons, the dam reduced the damage caused by this typhoon.
Since water and food are commonplace, we cannot imagine that it will be lost, but if possible, the range of imagination is narrow. This time, the area I was in had no water outages or power outages, but it just happened that I was at home in the intense rain and wind, and I thought it would be a strange situation even if there was a power outage or a water outage. .
Measures are taken, batteries, solar panels, cassette stoves, food and water are stored as much as they can be stored, but if there is actually a power outage or water outage, how many days will it last, and how many days it will recover I didn't know, but it was difficult to take measures.
Because it is a natural thing, it may be a price for richness that it will not feel real or disappear, but it may be a price for richness, but even if there is enough power, food, water, it will be uneasy if it becomes a power outage or water cut Will not disappear.
What I thought most about the intense wind and rain was to spend my life and time as usual. If you take too many special measures, your anxiety will not disappear and you will get tired.
So, for people who are experiencing power outages and water outages, it is important to have power, food, and water, but I want them to be able to live and live as usual as soon as possible. It may take some time to restore your lifeline and place of residence, but if you can restore your life and time rhythms to normal, you will be much more calm and tired. Power can only accept and respond.
家はつくづく、シェルター、だと思う。
台風の対策を、ここまでしたのははじめて、全部の雨戸を、閉めたのもはじめて、3日前から、対策したのもはじめて。
今回は事前から、恐いくらいに、台風の影響を気にして、はじめて、停電した、断水した、その後どうするとして準備した。
今までは、何とかなる、だった。仮に、停電しても、断水しても、何とかる、何とかしてくれる、だった。
千葉の人たちが、大変な思いを、されているのもあるし、それを自分に、置き換えて、水と食料、いつも食べているものを、蓄えた。
で、最後は、家である。いくら、水と食料があっても、家が持たないと、何の意味も無い。
しかし、対策は限られる。簡単に言えば、窓をどうするかだけ、その他は、そもそもの家の、ポテンシャルの問題。
だから、頑丈に、つくりましょう、と言いたいのではなくて、この台風の機会に、余裕がない機会に、家は、シェルター、それも、心のシェルター、だとつくづく思う。
家のつくり、がどうのこうのでは無くて、家という囲われた安全地帯のありがたさ、中では、外とは、全く関係なしに、過ごせるありがたさ、それがある安心感、家がもし必要だとしたら、それが一番だと。
乱暴に言えば、家で行う機能は、全て、外で賄える。食べることも、寝ることも、その他のことも、全て、賄えないのが、安心感。安全地帯という、心の持ちよう。
それを、心底経験すると、家に対する想い、が変わる。
"Shelter of the heart"
I think the house is a shelter.
This is the first time I have taken countermeasures against a typhoon, the first time that all shutters have been closed, and the first three days before that.
This time, I was prepared for the first time because I was worried about the effects of the typhoon, and after a power outage, water cut off, and then what to do.
Until now, it was going to be somehow. Even if there was a power outage or water outage, it managed to manage it.
Some people in Chiba had a great feeling, replaced it with themselves, and stored water and food, what they always eat.
And the last is a house. No matter how much water and food you have, if you don't have a house, it has no meaning.
However, measures are limited. Simply put, what to do with the windows, the other is the potential problem of the house.
So, I don't want to say that I should make it sturdy, but I think that the house is a shelter, a heart shelter.
It's not like how a house is built, but the appreciation of the enclosed safety zone of the house, inside, thank you for being able to spend it without having anything to do with the outside, if there is a sense of security, if the house needs it, Is the best.
Roughly speaking, everything you do at home can be done outside. I can't afford to eat, sleep, or anything else. Let's have a safety zone.
If you experience it, your feelings for the house will change.
前に何度か行った本屋の前をたまたま通りかかり、目的地に行く途中、後で時間があったらと思いながら、前に行った時はどうだったかと思い返し、デザインや建築の書籍専門で、何だったか前に購入したようなと思いつつ、思い出せない。
そこは1年1度くらいしかいかない通り、近くに役所があるからそこら辺にはよく行くけれど、なかなか雰囲気のある通りで、地元の商店ばかり、肉屋、魚屋、八百屋があり、スーパーがない、夕方には惣菜目当ての買い物客が溢れはしないが適度にいて、触れ合いもありつつ、若い人が好きなようにお店をしている、飲食だけでなく、雑貨屋なども、ちょっと裏通りに入ったら、前によく見たドラマの舞台になったお店も発見、表の通りのお店のバリエーションがおしゃれから下町風まで、車もあまり通らないし、住みたい街、その通り沿いにある本屋へ用事の帰りに寄った。
本が綺麗に飾ってあり、雰囲気からしてデザイン本を扱っているのがわかる。規模は小さいので、たくさんは無いがチョイスに特徴がある本が並ぶ。
ただ、自分の趣味とは合わなかったし、建築に関する本もあまり無かった。ひと回り、適当に手に取り、パラパラと、またパラパラと、だけど、この時間は結構楽しい、大型書店とはまた別の、人の趣味をのぞき見しているような、それでいて、そう共感できるものがあると、妙に親近感がわく。
赤い函に入った大冊2冊組が目に止まる。パウル・クレーの『造形の思考』、上下巻あり、クレーのことはあまり知らず、バウハウスで教鞭を取っていたことぐらいで、もちろん、作品もその本のことも知らなかった。
手に取ったのはタイトルに惹かれたから、「造形」しかも「思考」と来たら何が書いてあるのかな、けど、そこまで期待せず、赤い函に黒いタイトル文字が何となくカッコよかったし、それまで、パラパラと流しながら本を眺めていたので、ちょっとじっくりと目を通してみようかなと。
クレーのこと、この『造形の思考』のことは、人からも聴いたことが無かったし、私の周りで話題にのぼることも無かった、それがどうしてと不思議に思うくらい、パッと適当に広げたページから引き込まれた。
造形に関することが言葉と図解で論理的に展開されている、その一つ一つを見て行くと、造形の初源的なことの成り立ちを解説していて、これほど造形に関することをわかりやすく、それも的確に教えているテキストに初めて出会った。
そこに出るくるワードが普段自分が設計する時に念頭に置く言葉であったり、ただ、そこまでストレートに図解に組み込み説明しているテキストには今まで出会わなかった。もう当然気になるし、もっとじっくり読みたくなる。Amazonばかりだけど、本屋へ行くのはこれがあるから、もう当然手に、となるのは必然でした。
"The book I met"
I happened to pass in front of a bookstore that I had visited several times before, and I thought that there was time later on my way to my destination, but I thought back how I was before, specializing in design and architecture books, I can't remember what I thought it was before.
There is a government office nearby because it only goes about once a year, but it is a street with a lot of atmosphere, there are only local shops, butchers, fish shops, greengrocers, there is no supermarket, In the evening, shoppers for sugar beets are not overflowing, but they are moderate, there is also a touch, and shops are opened as young people like. Then, I found a shop that was the stage of the drama I saw before, the variations of the shop as shown in the table, from fashionable to downtown style, not much cars, and the city where you want to live, to the bookstore along that street I stopped by the errand.
The book is beautifully decorated, and you can see that it handles the design book from the atmosphere. Since the scale is small, there aren't many books, but there are many books that are unique to choice.
However, it did not match my hobby and there were not many books on architecture. I picked up and picked it up a little, and it was a lot of fun, but this time was quite fun, something different from a large bookstore, like looking at people's hobbies, yet something that I can sympathize with There is strangely a sense of affinity.
Two large books in a red box catch your eyes. Paul Klee's "Thinking of modeling" has upper and lower volumes, and I didn't know much about Clay, I was teaching at Bauhaus, and of course I didn't know the work or the book.
I was attracted to the title because I was attracted by the title, so what was written if it came to `` modeling '' and `` thinking '', but I did not expect so much, the black title letter was somewhat cool in the red box, Until then, I was watching the book while playing with it, so I would like to take a closer look.
I didn't even hear about Clay and this "Thinking of Thinking", and I did n't get to talk about anything around me. I was drawn from the page that I expanded.
When you look at each of the things that are logically developed in terms of words and illustrations, it explains the origins of modeling, and it's so easy to understand It was the first time I met a text that taught me exactly.
The words that come out there are words that I usually keep in mind when I design, but I have never met texts that are straightforwardly embedded in illustrations. Naturally, I'm curious and I want to read more carefully. Although it is only Amazon, there is this to go to the bookstore, so it was inevitable that it was already in hand.
今読んでいる本に、日々の生活の中でそれまで当たり前だと思っていたささいなことに気を止めてみて、それを問い直し、自分なりの言葉にしてみる、それが正しいか間違いかはどうでもよくて、そのプロセス自体を無償で愛することが「哲学する」ことだと書いてある。
自分が当たり前だと思って、特に気にも止めていなかったことが、ある日突然、たまたま目にした、耳にした、言葉や映像などによって、気になり出すと同時に、そのことについてもっと深く知りたくて仕方がなくなり、いつしかその当たり前の意識だったものが大きく変わってしまう、そのようなことを起こす言葉や映像などを投げかけることができたら、それが建築でできたら面白いと常々思っている。
日々の生活の中にはまだ気づいていない宝物がたくさんあると思っていて、ただ、それを自分の力だけで気づくのは難しく、自分以外からの手助けも必要で、設計はその手助けをすることだと昔から考えており、それを「宝物探し」に例え、自分はトレジャーハンターだと、探し出したお宝を、それを見せることによって、それまで気づかなかった、当たり前だと思っていた意識が変わってくれれば、動き出したらいいなと、昔ある人にそのことを言ったら失笑されたけれど、今でも同じように考えていて、では宝物とは何だと、その本には
「本当の宝物は、誰でも見えるところに落ちているから、むしろ見つけにくい。そして誰にでも手に入れられるから、自分だけの所有にすることはできない。」(堀畑裕之『言葉の服』より)
とあり、宝物だと思うと、特別なもの、見えないところにあるもの、自分だけのものと思っていたが、自分の目で見ているものと、そのもの自体の性質は違う時があるから、なるほどと宝物に対する意識が変わった。
自分なりの言葉にしようと、宝物とは何だと、一所懸命に考えたのに、この本の言葉に出会って、すーっと腑に落ちた、そして、自分が建築でやっていることを逆の立場から経験した。
「哲学する」その無償に愛するプロセスに浸りながら、自分以外からの手助けも受け、また「哲学する」、この入れ子状のプロセスが心地よく、この入れ子がたくさんできればできるほど、日常が豊かに、自分なりの日常を獲得できるような気がした。
"Philosophy"
In the book you are reading now, stop thinking about the trivial thoughts you have taken for granted in your daily life, re-question it, and try your own words. It doesn't matter, and it is written to love the process itself for free.
What I thought was taken for granted and that I didn't care about suddenly one day suddenly happened to happen, I heard it, heard it, words and images, etc. If you can throw a word or video that causes such things to change, something that is the natural consciousness will change greatly, I always think that it will be interesting if it can be done in architecture .
I think that there are a lot of treasures that I haven't noticed in my daily life, but it is difficult to notice it with my own power, and I need help from other than myself, and design helps I have thought of it for a long time, and compared it to "treasure hunting", and if I was a treasure hunter, showing the treasure that I found out changed my consciousness that I had never noticed before. If you tell me that I should start moving, I was laughed if I told a person in the past, but I still think the same way, so what is a treasure,
"The real treasure is so easy to find that anyone can see it, and it's hard to find it, and anyone can get it, so you can't make it your own." (From Hiroyuki Horibata's "Language Clothes" )
When I thought it was a treasure, I thought it was a special thing, something that was invisible, or something that was unique to me, but there were times when the nature of the thing itself was different from what I was seeing with my own eyes. I see, my awareness of treasure has changed.
I thought hard about what the treasure was, whether it was my own words, but I met the words in this book and fell into a trap quickly, and I reversed what I was doing in architecture Experienced from the standpoint of.
"Philosophy" Soak yourself in the process of loving yourself and receive help from other than yourself. Also, "Philosophy", this nesting process is comfortable, the more you can make this nesting, the more everyday you will be I felt like I could acquire everyday life.
そーっと、仕舞い込んでおくことにして、大事かどうだかはわからないけれど、いつか役に立つかもしれないし、何より面白い話だったから。
頭の片隅にその時感じたこと、その時考えたことと一緒に、そう村上春樹が言うところの頭の中の抽斗に仕舞っておこう。
久しぶりに楽しくて、興味深い話だった。普段から見て、いろいろと考えたり、感じたりしていることを科学的検知と歴史的認識と設計的思考で、いろいろな角度から論じた話は、今までにない思考を生んで、頭の中に新たな回路ができたような感じだった。
はじめから人に教えてもらう方が楽だし、自分自身が考えることはすでにわかっていることの先からで良いとするならば、本を読み、人にきき、ネットなどで調べて、それから考えはじめれば良いけれど、それではつまらない、もしかしたら、はじめから人とは違うことが思い付いたりして、そうしたら絶対にその方が良いし、その方が楽しい。
だから、今日のことは頭の中の抽斗に仕舞っておいて、結論を出さずに仕舞っておいて、いつか必要な場面が来たら抽斗を開けて、また考えることにしよう。その時には今とは違う自分がいるから、また違った展開が待っているかもしれないし、それを楽しみにして。
"drawer"
Softly, I don't know if it's important or not, but it might be useful someday and it was an interesting story.
Along with what you felt at that time in the corner of your head and what you thought of at that time, let's finish the drawing in the head that Haruki Murakami says.
It was a fun and interesting story after a long time. Talking from a variety of perspectives, using scientific detection, historical recognition, and design thinking to think about and feel various things from a normal perspective, gives rise to unprecedented thoughts, It felt like a new circuit was created inside.
If it's easier to get people to teach from the beginning, and if you want to think beyond what you already know, you can read a book, ask people, search on the net, and then start thinking It's good, but it's boring, or maybe you've come up with something different from a person from the beginning, and that's definitely better and it's more fun.
So, for today, let's finish the drawer in my head, finish it without making any conclusions, open the drawer when someday comes, and think again. At that time, I have a different myself, so I may be waiting for a different development, and look forward to it.
出かける時の服選びで色使いを一番最初に気をつける。出かける先がどこかによって、ドレスコードがあれば別だけれども、これから会う相手によっても、どこまでのドレス度で良いか、もちろん、ジャケットやスラックスなどのアイテムでもドレス度を調整するけれども、ジャケットは脱ぐ場合もあるし、そこでいつもファッションアドバイザーのMB氏による「ドレスとカジュアルのバランス理論」を参考にさせてもらっている。その理論によると、ジャケットでも明るめの色になるとドレス度が下がるので、場所によってはカジュアルになり過ぎて場違いになる場合もあるとのこと。
亡くなったAppleの創業者スティーブ・ジョブズが、パンツは通年ジーンズだったが、冬になると黒のタートルネックで過ごしていた。ファッションアドバイザーのMB氏による「ドレスとカジュアルのバランス理論」によると、黒は一番ドレス度が高い色、冠婚葬祭で使われる黒や白が一番ドレス度が高く、濃いグレー、濃紺などの黒に近い濃い色がそれに続き、赤や黄色などの鮮やかな有彩色が一番カジュアルに見え、それとタートルネックは襟の部分も高く、襟がある方がドレス度が高く、襟が無いTシャツはカジュアルに見えるとのこと。
だから、一見すると、スティーブ・ジョブズはいつもジーンズで、スーツなどと比べたらカジュアルで普段着のように思ってしまうが、それなりにドレス度が高く、かと言って、スーツほどでは無く、ドレスとカジュアルのバランスが適度に取れていたので、スーツだと入りづらいような所にも行けて、ほとんどの場所で出入りに不都合が無いとても合理的な服装をしていたことになる。
それは服選びに時間を割きたく無い、計算した上での服の組み合わせだろうが、アイテムとして一番ドレス度が高いセットアップでも、色が鮮やかな有彩色になるとカジュアルに見えてしまうので、たくさん服を持っていれば別だが、色でドレス度を調整して場違いにならないようにするのが一番手堅いかなと考えてしまう。
建築では今でもモダニズムの影響を受けているので白が多い。モダニズムにおいて建築は、それまでの物語性の強い建築から自律するために、仕上げに白を塗り込めて、白は色というより、それまでのものを消し自律性を高める役目として扱われていた。
建築の場合、白は自律性が高い色、自律性が高いと排他的で親しみやすさが薄れる、それを服の場合で例えると、やはりそれはドレス度が高いことになる。
モダニズムにおいても、多色を用いた形式、例えば、オランダのデ・ステイル運動などもあり、作品としてはリートフェルトが設計した住宅で世界遺産の「シュレーダー邸」や同じくリートフェルトがデザインした「赤と青のいす」が有名だが、実際に見てみると、多色を住宅ならば壁や天井、椅子ならば座面と背板や肘掛けといった要素ごとに色を塗り分けて、それぞれの要素の自律性を高めるために使用していた。ここでも多色は色というより、それまでのものを消し自律性を高める役目として扱われていた。
建築において色は面白い存在である。歴史的に見れば色はどちらかというと主役では無く、モダニズム建築において自律を手助ける役目を担っている。しかし、今、街を歩けば色だらけである。服でいうところのジャケットやスラックスと言ったアイテム毎の違いよりも、まず色の方が先に目に飛び込んで来て、それも有彩色でカジュアル度が高いものばかり、生活ではカジュアル度の高い建築空間に囲まれる機会の方が多い。しかし、そのカジュアル度の高い色は建築においては意識の外に置かれている。
出かける時の服選びで一番最初に気をつけるのは色使いだが、次に気をつけるのはドレスとカジュアルのバランス。これもおかしいと場違いになる。
ドレスとカジュアルのバランスを建築に置き換えて考えてみると、もしかしたら、何かが抜け落ちているかもしれないし、そのことによってかえって不自由で場違いな状況を招いているような気がする。そうなると、色は主役になってくる。
"A balance between casual and dress of architecture"
The first thing to be aware of is the use of color when choosing clothes when going out. Depending on where you want to go, it is different if there is a dress code, but depending on the person you are going to meet, how much dressing is good, of course, even if you adjust the dress degree with items such as jackets and slacks, if you take off the jacket There is always a reference to the "dress and casual balance theory" by fashion advisor MB. According to the theory, even if it becomes a bright color even with a jacket, the degree of dress will decrease, so depending on the location it may become too casual and out of place.
Apple founder Steve Jobs, who died, was wearing jeans throughout the year, but spent the winter in a black turtleneck. According to the fashion adviser MB's "Theory of Dress-Casual Balance", black is the most dressed color, black and white used in ceremonial occasions are the most dressed, dark gray, dark blue, etc. A dark color close to black follows, and vivid chromatic colors such as red and yellow look the most casual, and the turtleneck has a higher collar part, the one with a collar has a higher dressing degree, and the T-shirt without a collar It looks casual.
So, at first glance, Steve Jobs is always jeans, and when compared to a suit, it seems to be casual and casual, but the dress is rather high, so it's not like a suit, the balance between dress and casual I was able to go to places where it was difficult to enter with suits, and I was wearing very reasonable clothes without inconvenience in going out and entering in most places.
It is a combination of calculated clothes that do not take time to choose clothes, but even the setup with the highest dress degree as an item will appear casual when the color becomes bright chromatic, so many clothes I think that it is the most robust to adjust the degree of dress by color so that it does not get out of place.
The architecture is still influenced by modernism, so it is white. In modernism, architecture has been treated as a role that enhances autonomy by erasing the previous ones, rather than color, by applying white to the finish in order to be autonomous from the highly narrative architecture.
In the case of architecture, white is a color with high autonomy, and when it is autonomy, it is exclusive and less familiar. In the case of clothes, it is also a high degree of dressing.
In modernism, there are also multicolored forms, such as the Dutch De Steil movement, and the work is a house designed by Rietveld, a world heritage "Schrader House" and also "Red" The blue chair is famous, but if you look at it, you can paint different colors for each element, such as walls and ceilings for a house, seats and backboards and armrests for a chair. Used to increase autonomy. Here too, multicolor was treated as a role to enhance the autonomy by erasing the previous ones rather than colors.
Color is an interesting thing in architecture. Historically, color is rather the leading role, but plays a role in helping autonomy in modernist architecture. But now, walking around the city is full of colors. Rather than the differences between items such as jackets and slacks in terms of clothes, the color first jumps into the eyes first, and it is also chromatic and highly casual, with a high degree of casualness in life There are more opportunities to be surrounded by architectural space. However, the casual color is left out of consciousness in architecture.
When choosing clothes when going out, the first thing to notice is the use of color, but the next thing to watch out for is the balance between dress and casual. If this is also wrong, it will be out of place.
If you think about replacing the balance between dress and casual with architecture, it may be that something is missing, which in turn leads to inconvenient and out of place situations. When that happens, the color becomes the leading role.
形が歪んだ、緑の彩色が施された器を見ると織部焼か、織部焼を真似た作品だとわかるくらい特徴的な器、作者の古田織部は最期、切腹させれた。そうすると、罪人の作品は一斉に無くなる、消えて無かったことになるらしい。
それまで端正で大振りだった茶碗が歪みはじめた。歪みや丸味を排し、黒々とした、無骨で武士が好みそうな姿をしていた茶碗から、丸味を帯び、歪み、彩色を施されたものが生まれた。
黒くて無骨で大振りな、きっと武士にふさわしい茶碗が大勢を占めると、それは権威と同等の価値が与えられるようになったのだろう。
そうなると、創造性豊かな人物ほど、その権威的なものを壊したくなる、それまで捨てられて相手にされなかったものの価値に気づき、注目する。
丸味や歪みの中に、端正で無骨以上の茶碗としての価値、茶の湯の道に沿い、より際立たせる姿を見出したのだろう。
その道程を計り知ることは難しいが、今現在も見ることができるその時代の織部焼は、ただ単に形が歪んで面白いとは違い、その形や彩色の中に見え隠れする端正で無骨なものから生まれた強さを感じるし、温和で柔らかいな印象の中にも黒くて大振りなものをも飲み込んでしまう海のような深さ、怖くもあるが、をも感じる。
器ひとつで人が亡くなる時代から残っていた物の凄み、それを今見て、そこに美とは何たるか、作品性とは、と振り返ることによって、今の人の意識を揺さぶることが素晴らしい。
"Workability"
The distorted shape of the vessel with a green color, and the distinctive vessel that can be seen as a work imitating Oribe Yaki or Oribe Yaki, the author's Furuta Oribe, was finally cut off. Then, it seems that sinner's works disappeared all at once, and disappeared.
Bowl it was up to a neat roundhouse began distortion. From a bowl that is black, rugged, and samurai-like, with distortion and roundness removed, it was born rounded, distorted and colored.
Black rustic, a roundhouse, when surely accounts for the many bowl worthy of the samurai, it probably came to be given the equivalent of the value and authority.
Sonaruto, as the rich person creativity, and want to break the authoritarian ones, aware of the value of those not in discarded opponent until then, attention.
In the rounded or distortion, value of as rugged more bowl neat, along the way of the tea ceremony, probably it found a more accentuate appearance.
It is difficult to measure and know the path, but the Oribe ware of that era, which can still be seen today, is not just distorted and interesting, but from the neat and rugged thing that appears and hides in its shape and color. I feel the strength that I was born in, and the depth and depth of the ocean that swallows black and big things in a mild and soft impression.
It is wonderful to shake the consciousness of the present person by looking at the amazing things left from the time when people died in one vessel, looking at it now, what is beauty there, and what is workability.
つくられる物には流行りすたりがあり、当たり前のように、時代によって変遷していく。
ファッションにしても、美術の世界でも、建築でも、時代によって変わる。それはもちろん、時代によって求められるものが違うし、考え方や価値基準、生活や習慣も変わるだろうから、社会が変われば、つくる物も影響を受けて、生活に密接であればあるほど、変化に敏感になる。
しかし、変化の仕方というか、作法というか、変化の流れ方は似ているように思う。
要するに、それまで捨ていた部分、無視をしていた部分、相手にしなかった部分が段々と注目を浴びてきて、それが主役へと変遷していく。急激に変化する訳では無く、徐々に徐々に、変遷していく。
瀬戸黒茶碗を時代によって見比べる試みがあった。武士が好みそうな無骨で端正で大振りな黒茶碗が、歪みはじめる。端正で無骨さを出すために歪みや曲線の波打ちは排除されていたが、その時代、目新しさや人とは違うものを求めて、歪みの中に端正さを見い出す試みがはじまったのか、丸味を帯びる。やがて、武士から町人の時代になり、大振りのものから小振りなものへ、より丸味を帯びて温和な印象の茶碗へと至ったとのこと。
建築の場合も、モダニズムにおいて自律するために、視覚性に重点を置き、それまでの建築が有していた物語性に込められていた場所性や物質性といった装飾を排除し、幾何学的な形態になり、空間を重視し、世界中どこでも同じような建築ができることを目指した。そのモダニズムも変遷していく。モダニズムの行き着く先に空間による権威的な風潮や、地域性の重要さに気づくなどがあり、排除していた場所性や物質性に注目が集まるようになり、ポストモダニズムへと変遷していった。
このように、ジャンルが違っても変化の仕方は似ており、排除していたものに注目が集まり、主役へと、またそれも交代していく。振り子のように、時代に応じて行ったり来たり、急激に変わることは無いので、同時代的に並列することもあるだろうが、基本的にどちらかが流れていく。
両義性、両方の流れを受け止めて同時に存在させ、その複雑な様をそのまま表現できないものかと考えてしまう。急激に変わることが無いのだから、その時代に求められていることをそのまま表現すると、両義的意味合いの複雑なものになるのが自然のような気がする。ただし、そのものの物の価値の寿命は短いかもしれない、その時代の流れの瞬間を捕らえるから、しかし、そのものの時代性の価値は高い、それで良いのではないかと考える。
"How to capture changes"
There is a trend in the things that are made, and as it goes without saying, it changes with the times.
Whether it is fashion, the world of art, or architecture, it changes with the times. Of course, what is required by the times will be different, and the way of thinking, value standards, life and customs will change, so if society changes, the things you make will be affected and the closer you are to life, the more it will change. Become sensitive.
However, it seems that the way of change, the manner of change, and the flow of change are similar.
In short, the part that had been thrown away, the part that had been ignored, and the part that had not been dealt with gradually became the focus of attention, and it turned into a leading role. It does not change suddenly, but gradually changes gradually.
There was an attempt to compare the Seto Black Tea Bowl according to the times. The rustic, neat and large black tea bowl that Samurai likes is beginning to distort. Distortion and curving of the curve were eliminated in order to bring out neatness and ruggedness. Tinged. Eventually, from the time of Samurai to the time of the townspeople, it became a tea bowl with a rounder and milder impression, from a large one to a small one.
In the case of architecture as well, in order to become autonomous in modernism, the emphasis is placed on visuality, and the decorations such as place and materiality that were included in the narrative nature that architecture had so far have been removed, It became a form, focused on space, and aimed to be able to build similar structures anywhere in the world. The modernism also changes. At the destination of modernism, there is an authoritative climate by space and the importance of regionality, etc., and attention has been focused on the excluded place nature and materiality, and it changed to post-modernism .
In this way, even if the genre is different, the way of change is similar, and attention is drawn to what was excluded, and it also changes to the leading role. Like a pendulum, it doesn't come and go according to the times, and it doesn't change suddenly, so it may be paralleled in the same time, but basically one of them will flow.
I am confident that I will be able to express both the ambiguity and the flow of both at the same time and express the complex state as it is. It doesn't change abruptly, so if you just express what you're looking for in that era, you will feel like it's natural to have a complex sense of ambiguity. However, the lifetime of the value of the thing itself may be short, because it captures the moment of the time, but the value of the era is high, so I think that it may be good.
乾山の蓋物の器の箱書きに添えられた言葉「身補う」に触れた。
どこまでを作品というのか、どこまでが作家性なのか、考えてしまう蓋物、市場価値を決める場合は作家性に意味があり、作品としてはその作家が全てを手掛けるのが前提なような気がしていたから意外だった。
ちょっとした欠けや割れを直す金継ぎはよく見る。その金継ぎの継ぎ方、補い方に作品性があり、わざと更に割って継ぎ、その継ぎ方を綺麗に見せることもある。
この蓋物、底の部分と蓋だけが乾山の作、底からお椀の縁までを補ってある。まさに「身補う」で、半分以上を補っている。
たぶん、お椀の割れた部分を綺麗に整形して底だけを残して、あとの部分を付け足して補い、その部分に蓋の絵柄を施し、形は元のお椀と同じで、絵柄は元のものとは違う可能性もあるとのこと。そうなると、明らかに復元では無くて、更なる作品性を求めて手を加えていることになる。
なぜか、その制作風景を想像してしまう。どういう想いで補っていたのかと考えを巡らせてしまう。たぶん、頼まれ仕事だったのではないかとのこと。作家性や作品性や市場価値もあるが、今、目の前にある、この蓋物の姿に不思議と惹かれた。
縁が、民藝の好きな窯元、因州中井窯を思わせるような、平らに厚みを強調するように仕上げられていて、ただ、それは蓋の受けの形状とは合わないような。
その場で、もしかしたら、元々の底から新たなに補ったお椀の縁までの形が、元々のお椀の形とは違うのではないかと感じた。なぜだかわからないが、かなり手を加えているような気がした。
家に帰り、その蓋物の写真を眺めていて、やはり、横から見ると、蓋の形とお椀の形が合わないような、蓋の形が丸味を帯びているのに、お椀にはその痕跡が無く、更に、元々の底の部分は補った部分と角度が違い、底の角度に合わせて補うともっと形が丸くなるようにも思えた。
想像が膨らむ蓋物である。「身補う」にも創造性を掻き立てられたのかもしれない。
もしかしたら、蓋と底は別ものだったり、絵柄が違うし、2つのものを1つに、更に補い、ただ、謙遜して「身補う」という言葉を残した。
古美術の世界はもっと型にはまったものだと思っていたが、なんて自由なんだと、型があるからかもしれないが、創作を振り返り想像する面白さは、1から創作する面白さと同じように感じた。
"Supplement"
I touched the word "supplement" attached to the box writings on the dry mountain lid.
What is the work, what is the writer's nature, the lid to think about, when deciding market value, the writer's character is meaningful, and as a work I felt that the writer would handle everything It was unexpected.
I often see gold splices that repair a little chipping or cracking. There is a workability in how to join and make up the splicing.
Only this lid, the bottom and the lid, make up the dry mountain, from the bottom to the edge of the bowl. It is exactly "supplement", and more than half is supplemented.
Perhaps the cracked part of the bowl is neatly shaped, leaving only the bottom, and the other part is added to make up, and the pattern of the lid is applied to the part, the shape is the same as the original bowl, and the pattern is the original one It may be different from that. In that case, it is clearly not a restoration, but a work for further work.
Somehow, I imagine the production landscape. It makes me think about what kind of feelings I made up for. Perhaps it was a job that was asked. Although it has writer characteristics, work characteristics, and market value, it was mysteriously attracted to the appearance of this lid in front of me.
The edges are flattened to emphasize the thickness, reminiscent of the folk song favorite potter, Inju Nakai Kiln, but it does not match the shape of the lid holder.
On the spot, I felt that the shape from the original bottom to the newly complemented porridge was different from the original porridge shape. I don't know why, but I felt like I was doing a lot of work.
I came home and looked at the picture of the lid, and when I looked from the side, the shape of the lid and the shape of the bowl do not match, but the shape of the lid is rounded, but there are traces in the bowl In addition, the angle of the original bottom part was different from the compensated part, and it seemed that the shape would become more rounded when supplemented to the angle of the bottom.
It is a lid that imaginates. "Supplement" may have stimulated creativity.
Perhaps the lid and the bottom were different, the picture was different, the two things were combined into one, and the word "supplement" was left behind.
I thought that the world of antiquities was more of a type, but it might be because there is a type that is free, but the fun to imagine looking back on the creation is the same as the fun to create from scratch I felt it.
創作の進め方は人それぞれだなと改めて思う。建築ならば、建築に対する自分の考え方があって、プロジェクトが発生した時点で、その考え方をプロジェクトの条件に合わせて形にしていくやり方をとる人が多い。
自分の考えが全く無い人はいないだろう、はじめに建築の教育を受けて、何かしらの影響を受けるから、程度の差こそあれ、建築に対する自分の考え方は育まれる。
人それぞれだなと思うのは、その建築に対する自分の考え方に強度というか、濃度の差があること。
プロジェクトの進め方には標準的なものがあり、クライアントの要望や条件の整理、敷地調査、計画検討、基本計画、実施計画、工事などという流れで進むが、濃度が薄い人は、プロジェクトの進行に合わせて浸透させる。濃度が薄いから浸透しやすく、抵抗感が無い。濃度が薄くても決められた量を打てば効くことには変わりが無い。
濃度が濃い人は、建築に対する自分の考え方にプロジェクトを当てはめていく。濃度の濃さにうまく合わせないと、プロジェクト自体がうまく進まないから、プロジェクトが標準的な進め方で流れていかない時もあり、その場合、プロジェクトの舵取りをしっかりやらないと結果に影響する。
どちらが良い悪いのではないが、結果的に出来上がる建築を見ると、濃度が濃い人の方が建築として際立った特徴が出るから、そちらに惹かれる。
"concentration"
I think that each person has a different way of creating. In the case of architecture, there are many people who have their own way of thinking about architecture, and when a project occurs, they take the way of thinking that conforms to the project conditions.
There will be no one who doesn't have any thoughts at all. First of all, after receiving an education in architecture and being influenced by something, my ideas about architecture are nurtured to some extent.
I think each person has different strengths or differences in their way of thinking about the architecture.
There are standard ways to proceed with the project, and it progresses in the order of client requests and conditions, site survey, plan review, basic plan, implementation plan, construction, etc. Infiltrate together. Since the concentration is low, it easily penetrates and there is no resistance. Even if the concentration is low, there is no change in the effect if you hit a fixed amount.
People with a high concentration will apply the project to their own way of thinking about architecture. If the density is not matched well, the project itself will not proceed well, and the project may not flow in the standard way. In that case, if the project is not steered firmly, the results will be affected.
Neither is good or bad, but when you look at the resulting architecture, people with a high concentration will be attracted to it, as it will have distinctive features as architecture.
知りたいことを調べるのはほんと簡単で、スマホですぐに手に入る。だからか、知っていることが当たり前というか、知っていて当然というか、知らないと恥ずかしいと思う人が多いような気がする。
スマホで手に入る情報が本当に価値があるかはどうかは別として、それが知識なのかは別にして、例えば、財布を忘れるより、スマホを忘れた方が困るくらい、スマホは今や肌身離さずに持っているのが当たり前になった。
だから逆に思うのは、スマホで調べられる情報は、必要な時に必要なだけすぐに調べてわかることができるから、スマホで調べられる情報は、知らなくてもよいと、知らない方がよいと。
かなりのことがスマホで調べようと思えばできるはずで、そうすると、かなりのことを知らなくてもよい。
スマホではわからない、それでいて自分にとってはとても大事な知識だけ、それだけに集中して日常を送ることができる環境が今あると考えることができる。スマホやインターネットが無かった時代には考えられないくらい、自分にとって大事で、重要で、好きなことだけに集中できる環境が今ある。
今だに知っていることに価値を見出している人は、もしかしたら、情報の内容には関心が無くて、ただカタログを集めて遠くから眺めていることが好きな人なのかもしれない。それはそれで楽しいが、スマホでは手に入らない情報に直に触れようとした方が、日常がより豊かになると思うのだが。
"You don't have to know"
Finding what you want to know is really easy and you can get it right on your smartphone. That's why there are many people who know that it is natural to know, that it is natural to know, or that it is embarrassing if they do not know.
Regardless of whether the information you get on your smartphone is really worth it or not, whether it's knowledge, for example, it's harder to forget your smartphone than to forget your wallet. It has become natural to have.
So, conversely, the information that can be checked with a smartphone can be understood as soon as necessary when you need it, so if you do not need to know the information that you can check with a smartphone .
You should be able to do a lot of things on your smartphone, and then you don't have to know a lot.
It can be thought that there is now an environment that you can't understand on your smartphone, and that you can concentrate on your daily life with only knowledge that is very important to you. There is now an environment where you can concentrate only on what you like, important and important to you as you wouldn't have thought before in the days when there was no smartphone or internet.
People who still find value in what they know may be those who are not interested in the content of the information and just like collecting catalogs and looking at them from a distance. That's fun, but I think it would be richer to try to touch information that isn't available on a smartphone.
複雑に入り組んだことにようやく糸口が見えて、その方向に進めば解決ができそうなので準備をしていたら、はじめのところで勘違いをしていて、また振り出しに戻る。
複雑なことも型に当てはめて整理をすれば、誰にでもわかりやすく、結果も見通しも簡単につくのだが、それでは望んでいた結果にはならないとすると、その型自体から考え直さなければならず、時間と手間がかかり、より複雑になってしまうこともあり、妙に上手くいったなと思っていたら、はじめで勘違いしていた。
そうなると、気持ちが萎えてくるが、かといって型に当てはめても望む結果にはならないから、また1から考え直すために、資料を引っ張り出してきた。
他の方法を考えるが、なかなか、要するに、単純化してしまえば簡単なのだが、今回の場合は、単純化することによって捨ててしまう部分に可能性がとても大きくあるような気がして、今まであまり考えることがなかった部分にも焦点を当てようとしている。
そうすると、複雑なことが整理されるどころかもっと複雑になり、簡単な間違いに気がつきにくくなる。単なる言い訳だけど、ここまで来ると、さらに細かく拾っていなかいと解決の糸口も見つからないだろう、時間との兼ね合いも出てくる。
"Misleading"
Finally, you can see the clues to the complexities, and if you go ahead, you will be able to solve the problem, so if you are preparing, make a mistake at the beginning and return to the beginning.
If complicated things are applied to a type and organized, it will be easy for everyone to understand and the results and outlook will be easy, but if that does not give the desired result, we will have to rethink from the type itself. It took a lot of time and effort, and sometimes it became more complicated, so if I thought it was strange, I misunderstood it at the beginning.
When that happens, my feelings get worse, but if I apply it to the mold, it doesn't produce the desired result, and I have pulled out the material to rethink it from scratch.
I think of other methods, but in short, it is easy if it is simplified, but in this case, I feel that there is a great possibility in the part that is discarded by simplification, so far I'm trying to focus on the parts I hadn't thought about.
This makes it more complicated than organizing complex things, making it difficult to notice simple mistakes. It's just an excuse, but if you come to this point, you'll find a clue to solving it unless you pick it up further.
複雑なことを複雑なままにしておけるということは、同時に存在することが許されていること、それを別の言い方をすると、多様性が認められていること。
多様な状態は、一歩引いて俯瞰して見ると、違いだけが、差異だけが乱立している状態で、その差異に特徴があり、その差異に価値があり、その差異を表現しても良い状況ができている。
だから、多様な状態では、その差異で優劣が決まるから、元々の出自は関係が無くなる。実際には、出自が土台としてあって差異が生まれるから、出自は重要だが、多様な状態では差異に焦点が当たり、出自が見えなくなるから関係が無くなる。
単純な状態はその逆で、差異はむしろ余計なもので、出自で優劣が決まり、差異は関係が無い。そもそも、単純な状態は全てが可視化できていないと単純とはみなされないから、差異に焦点が当たると、複雑になり過ぎて全てが可視化できなくなるから、差異には焦点を当てずに、出自でグルーピングして優劣を判断する、その方が簡単でわかりやすく、管理がしやすいから。
多様な状態でも、単純な状態でも、どちらでも良いのかもしれないけれど、差異に価値がある方が創造性があるというか、工夫のしがいがあるから、ものづくりをしている人は多様な状態の方に興味が湧くと思うのだが、意外とそうでも無い。
"Diversified states"
Being able to leave a complex thing complicated means that it is allowed to exist at the same time, and in other words, diversity is recognized.
A variety of states, when viewed from a bird's-eye view, only the difference is a state where only the difference is random, the difference is characteristic, the difference is valuable, and the difference may be expressed The situation is ready.
Therefore, in various states, the difference is determined by superiority or inferiority, so the original origin disappears. Actually, the origin is important because it is based on the origin, but the origin is important, but in various situations, the difference is focused on and the relationship disappears because the origin is invisible.
The simple state is the opposite, the difference is rather superfluous, the superiority and inferiority are determined by the origin, and the difference is irrelevant. In the first place, simple states are not considered simple unless they are all visible, so when focusing on differences, they become too complex to be fully visualized. Group and judge superiority or inferiority because it is easier, easier to understand, and easier to manage.
It may be either a variety of situations or a simple situation, but people who are making things are in a variety of situations because the difference is worth the creativity or the ingenuity I think it will be interesting to you, but not surprisingly.
やったらダメと言われると余計にやりたくなり、さらにダメと言われるとやってしまう。やったらダメだとわかっていても、やっても大丈夫、問題無いと思うのと両方天秤にかけて、行ったり来たりしながら、2つの相反することが個人の中で同居している。
料理研究家の土井善晴さんの記事を読んだ。朝食に赤福と味噌汁で「これでええやん」と「家の中の多様性」を大事に、急速に多様化では無く単純化していく社会を嘆いていた。
人は皆違うと頭ではわかっていても、その違いを容認できずに、自分との違いを攻撃してしまう人をFacebookでもよく見かける。他人どころか自分でさえも一貫した考え方などできずに揺れ動いて違いが生まれるのだから、むしろ、揺れ動き、定まらず、今何をしたら良いのだろうかと考えてしまうことがある自分に気がついて、それで良いと自分に理解があれば、他人との違いなど気にならないし、寛容にもなれる、それが「多様化」の第一歩かな。
そもそも今の自分に理解があり認めている人は、他人との違いをむしろ面白く興味深く見ていて、そちらの方が良ければサッサと自分の考えなんて変えてしまうのだから、何事も流転する、だから、今の自分と未来の自分は違うと考えられると思っているようで。
そうなると、多様性とは物事を流転させる原動力になり、未来を明るくするには、どのような多様性を持ち得るか、多様性の質が鍵になるということか。
やっぱり、赤福に味噌汁は、毎日食べたいとは思わないけれど、赤福をお土産に貰ったら一度は試してみたい、たぶん、合うと思うし、それが朝食でも別にいいし。
"Sweet and miso soup"
If you say no, you will want to do more, and if you say no, you will. Even if you know that it's not good, you can do it. It's okay to do it, and you'll have no problem.
I read an article by cooking researcher Yoshiharu Doi. He was lamenting the society that rapidly simplified, not diversified, with the importance of "this is Eyan" and "diversity in the house" with Akafuku and miso soup for breakfast.
Even if you know that people are different, you can't tolerate the difference, and people often attack Facebook on Facebook. Rather than someone else, even myself can not make a consistent way of thinking and shakes to make a difference, but rather, I am aware of myself who sometimes thinks what to do now without shaking, uncertain, and that is OK If you understand yourself, you will not be concerned about the differences with others and you will be tolerant. This is the first step in "diversification".
In the first place, people who understand and acknowledge themselves now look at the differences from others rather interesting and interesting, and if they are better, Sassa and their thoughts will change, so everything will flow. It seems that I think that I am different from myself in the future.
In that case, diversity is the driving force for diverting things, and what kind of diversity can be possessed and the quality of diversity is the key to brightening the future.
After all, I don't want to eat miso soup for Akafuku every day, but if I buy Akafuku as a souvenir, I would like to try it once.
複雑なことを整理して単純に見せることは、とてもわかりやすくなり、複雑なことを人に伝えやすくなるから、それはとても大事だと思うが、複雑なことをそのまま複雑に見せても、そこに良さがあれば、複雑なままでも良いのではないか、むしろ、複雑なことをそのまま複雑に見せることができたならば、より複雑さが理解しやすく良いのでは、あとはどのようにわかりやすく伝えるかを考えれば良いだけ。
複雑なことを単純にして提示することを専門性と呼ぶ。建築ならば、建築性。建築性を駆使することが設計者には求められる。逆に建築性を発揮するから設計者とも言える。
建築性という手段を使って、複雑な条件や要望などを整理し、そこに何らかの解法を与え、単純でわかりやすく提示することが設計である。
となると、設計者の建築性がクライアントとの共通言語にならないとプロジェクト自体がはじめから上手くいかない。
ところが、そもそも建築性とは、設計者が設計する対象を客観視して発揮されるものであり、クライアントは設計する対象に対して主観的にしか見ることができないから、設計者とクライアントとの間にボタンのかけ違い、時には大きな断絶が生じることもある。
ならば、どうするか、クライアントに頑張ってもらって、設計する対象を客観視して、設計者と同じ土俵に立ち、設計者が発揮する建築性を理解してもらうか、設計者が建築性を捨てて、クライアントと同じ土俵に立つか、設計者がクライアントとの共通言語になるものを新たに構築するかしかない。
理解あるクライアントに巡り会える場合もあるが、それを期待するよりも、設計者が建築性を捨て、新たにクライアントとの共通言語を構築する方が汎用性があり、可能性があることのように思う。
建築性を捨てる、ならば複雑なことはそのまま複雑に見せることになり、その見え方が良く、より何かを、日常を豊かにする解法を見つけ、あとはそれをわかりやすくクライアントに提示する、それが設計になる。
"Remain complex''
I think it is very important to organize complex things and show them simply because it is very easy to understand and it is easy to convey complex things to people. If it is good, it may not be complicated. Rather, if you can show the complex things as they are, the complexity will be easier to understand. Just think about what to tell.
To present complicated things simply is called expertise. If it is architecture, it is architectural. Designers are required to make full use of architecture. On the contrary, it can be said that it is a designer because it exhibits architectural properties.
The design is to organize complex conditions and demands using the means of architecture, give them some solution, and present them simply and clearly.
Then, if the architect's architecture does not become a common language with the client, the project itself will not work.
In the first place, however, architecture is achieved by objectively viewing the object designed by the designer, and the client can only see subjectively against the object being designed. In some cases, the buttons may be misplaced, sometimes causing a major break.
If so, ask the client to do their best, objectively look at the object to be designed, stand on the same ground as the designer, and understand the architectural ability exhibited by the designer, or the designer throws away the architectural ability The only way to do this is to stand on the same ground as the client, or to build a new one that allows the designer to become a common language with the client.
In some cases, you can meet an understanding client, but rather than expecting it, it is more versatile and possible for the designer to abandon the architecture and build a new common language with the client. think.
If you abandon architecture, complex things will look complicated as they are, they will look better, find a solution that enriches your daily life, and then present it to the client in an easy-to-understand manner, That is the design.
単純であることと複雑であることが同時に成り立つことは矛盾しているが、単純に見えて実は複雑、複雑に見えて実は単純、となれば同時に成り立つことは可能になる。
複雑に見えて実は単純より、単純に見えて実は複雑の方に惹かれる。質素で、シンプルで、でも本質はとても豊かであり、趣深いものが良いと思ってしまう。
それは日本人だからだろうか、日本の文化、例えば、料理にしても、建築にしても、和食にしても、数寄屋建築にしても、素材を大事にして、一見、質素で、シンプルだが、でも味わうと、とても滋味深く、豊潤で、奥深さに感心してしまう。
それは海外から見た日本のイメージでもあるかもしれない。日本人のデザイナーが海外で仕事をする時に、暗黙的に求められることらしく、ただ、意識しなくても、シンプルだが奥深い、単純に見えて実は複雑なデザインに見えるらしい。
複雑に見えて実は単純の場合は、見た目はデザインされ綺麗に見えるけれど、実は中身が無く、内容が無いということもあるが、複雑なことを複雑なまま見せている、とも言える。
複雑なことを整理して、何らかの解法を与えて、単純に見せれば、それが、単純に見えて実は複雑だが、複雑なことをそのままではなくて、複雑なまま成り立つような解法を与えて、複雑に見せれば、複雑に見えて実は単純になる。
それが、複雑に見えて実は複雑、とならないのは、実は何とは差分だから、最初からどのくらい変化したかの量が少なければ単純、多ければ複雑、となる。
ただ、複雑なことを複雑なまま見せる、ということに可能性を感じる。それは、何も無いところから1から何かをつくろうとした場合は、単純に見えて実は複雑、な状態を作りやすいが、何かあらかじめすでに存在している状態があった場合、すでにその時点で複雑になっている可能性があり、それを単純にするのは難しく、むしろ、複雑なものを整理して複雑なまま表現した方がやり易く、元々の状態とも馴染みが良いはずだから。
都市計画で失敗する例はまさに、複雑なことを無理矢理単純にしてしまうから、元々の状態と馴染めず違和感が出ることが原因で、複雑なことをそのまま複雑に解ければ、失敗する確率も減るだろう。
都市計画以外にも、建築でも、複雑なことを複雑なまま見せることで、日常がより豊かになるならば、その方が汎用性があり、可能性があるのではないかと思っている。
"Simple and complex"
There is a contradiction between being simple and complicated at the same time, but it looks simple and actually complex, and when it looks complicated and simple, it is possible to hold at the same time.
It looks more complex and actually attracts people who look simple and actually more complex than simple. It is simple, simple, but very rich in essence, and I think it is good.
I wonder if it is Japanese, or Japanese culture, such as cooking, architecture, Japanese food, sukiya architecture, cherish the material, seemingly simple, simple, but taste I am impressed by the depth and depth of the food.
It may also be a Japanese image seen from abroad. When Japanese designers work overseas, it seems that they are required implicitly. However, even if they are not conscious, they seem to be simple but profound, simple and actually look complex.
If it looks complicated and actually simple, it looks and looks beautiful, but in fact it may not have any content and may not have any content, but it can be said that it shows complex things as complex.
If you sort out complicated things, give some solution, and show it simply, it looks simple and it is actually complicated, but it does not leave the complicated things as they are, but gives a solution that can remain complex, If it looks complicated, it looks complicated and actually simple.
The reason why it looks complicated and does not become complicated is actually what is the difference, so it is simple if the amount of change from the beginning is small and complex if it is large.
However, I feel the possibility to show complicated things as they are. If you try to make something from scratch from scratch, it's easy to create a complex state that looks simple, but if something already exists, It may be complicated, and it is difficult to simplify it. Rather, it is easier to organize and express complex things as they are, and it should be familiar with the original state.
The example of failing in urban planning is simply complicating the complicated things, and because it is unfamiliar with the original state, if you solve the complicated things as they are, the probability of failure will also decrease right.
In addition to city planning, I think that in architecture, if the daily life becomes richer by showing complex things as they are, it will be more versatile and possible.
つながりがデザインの要素になっているものはいいなと素直に思ってしまう。
1つでは意味を成さないが、つながることによって、何ものかの意味が出てきて、そのつなっがている様が装飾であり、そのつながりが機能を担う。そして、そのつながり自体は自由、どのようにでもつながりは変化する。何もはじめに決められてはいないが、つながりをデザインすれば、何にでも変化する。
イメージとして、デザインされたものは、そのもの自体の形に特徴があり、見た目で瞬時にデザインを伝えてくる単純なものが多い。わざわざデザインするのだからか、デザイン自体が前面に出てくるように、そこで優劣がわかるように、絶対的で自律的で、変化を許さないものばかり。
デザインされたものの面白さ、見る楽しさ、所有する喜びは、絶対的で自律的で、変化を許さない様から生まれると言っても過言ではないので、唯一無二の存在のデザインになればなるほど、その傾向は強いように思う。
イタリア文化会館で開催中のアンジェロ・マンジャロッティ「構築のリアリティ」展へ、マンジャロッティは好きなデザイナーで、建築も手掛けるので興味があり、『Secticon(セクティコン)』という置き時計も所有しているくらい。
『Giogali(ジョーガリ)』という小さなガラスのオーナメントが規則的につながって作品になっていた。1つの単体では何も意味を成さないが、規則性を持たせたつながりをデザインすることによって照明器具やスクリーンになる、簡単に行ってしまえば、ガラスのパーツである。
そのつながり方は小さなガラスのパーツを上下に引っ掛けるだけ、その引っ掛け方をデザインしている。とても単純なことだが、そこに重力があってはじめて成り立つデザインであり、単純なことの積み重ねが、いろいろなものに変化する可能性があるという複雑性も同時に兼ね備えている。
小さなガラスのパーツは単体で存在し自律していて、ある規則性を与えると他律的に何かになり、その何かはそれで自律して存在するようになるが、またそこに違った規則性を他律的に加えることもできる。
ガラスでできているから、照明器具にすれば、昼と夜、電球の種類によっても、スクリーンにしても、昼と夜、ガラスのある所と無い所の透け具合など、加わる他律によってさらに変化する。
自律と他律を行ったり来たりできるつながりを、マンジャロッティはデザインしたのだろう、モノは、人間のように、細胞というパーツの寄せ集めであり、パーツのつながり方をデザインするだけでよいと、それはマンジャロッティの建築からも感じられた。
"Connection design"
I think it's nice to have a connection that is a design element.
It doesn't make sense in one, but by connecting, some meaning comes out, the connection is decoration, and that connection plays a function. And the connection itself is free, and the connection changes in any way. Nothing is decided at the beginning, but if you design a connection, it changes to anything.
Images designed as images are characterized by their own shape, and many of them are simple things that convey the design instantly. This is because it is bothered to design, so that the design itself comes out to the fore, so that you can see the superiority and inferiority there, everything that is absolute and autonomous and does not allow change.
It is no exaggeration to say that the fun of design, the enjoyment of viewing, and the joy of owning it are absolute and autonomous, and it is born from not allowing change, so the more unique the design is I think the trend is strong.
Angelo Manjarotti's "Reality of Construction" exhibition at the Cultural Center of Italy, Mangiarotti is a favorite designer and interested in architecture, and also owns a clock called "Secticon".
A small glass ornament called "Giogali" was regularly connected into a work. A single unit doesn't make any sense, but by designing connections with regularity, it becomes a lighting fixture or a screen.
The connection is designed by hooking small glass parts up and down. It's very simple, but it's a design that only happens when there is gravity, and it also has the complexity of being able to change the stack of simple things into many things.
A small glass part exists alone and is autonomous, and given a certain regularity, it becomes something else, and that something will exist autonomously there, but there are also different rules there Sex can be added in other ways.
Because it is made of glass, if it is made into a lighting fixture, it changes further according to other rules such as day and night, the type of light bulb, even if it is a screen, day and night, the transparency of the place with and without glass, etc. To do.
Manjarotti may have designed a connection that can go back and forth between autonomy and other rules, and things are a collection of parts called cells, just like humans, and it is only necessary to design how to connect the parts. It was felt from the Mangiarotti architecture.
専門性を出さずにはいられない。それがある故に、立ち位置が決まるというか、その立ち位置にいるためには必要というか、暗黙の了解的なことで、誰か決めた訳でも無く、ただ、当然のような態度で、その立ち位置で流通している言葉を使い、素材を使い、進め方も無論、暗黙的にある。
いつも相対している人が専門外の人だと、それではコミニケーションが上手くとれないから、専門性を上手く別の言葉に置き換えて説明するように心掛けてきた。
それでもコミニケーションが上手くとれない時は、相性が悪いから仕方がないと諦めていた。
それはコミニケーションをとることも仕事のうちで、それが仕事の成否を左右する場合もあるが、全ての仕事が、全ての人と、上手くコミニケーションをとるのは不可能だから、上手くいかない時もたまにはあるからと、それで納得していた。
コミニケーションの上手くいくいかないに関しては、それで良いとは思っているけれど、そもそも専門性を持つというはじめの時点で専門外の人とボタンの掛け違いがあるのではないか。
専門外の人から求められる専門性と、自分が有して離そうしない専門性は同じなのだろうか。
そもそも自分が有している専門性は自分の立ち位置を確保するための専門性であり、専門外の人が求めていることが、その範疇に入っているのだろうか。
全く同じである必要は無いけれど、自分の有している専門性の中心の部分からかなりの距離があるのではないだろうか。
そんなことが急に気になった。
"Specialist"
You can't help but show your expertise. Because of that, the standing position is decided, it is necessary to be in that standing position, or it is implicitly comprehensible, no one has decided, just the standing attitude with a natural attitude Of course, using words circulated in the position, using materials, and of course, there is an implicit way.
If the person who is always opposed is a non-professional person, then communication will not be successful, so I have tried to explain it by substituting the expertise with other words.
Still, when communication was not successful, I gave up because it was incompatible.
It takes communication and it is part of the work, and it may affect the success or failure of the work, but because it is impossible for all work to communicate well with everyone, sometimes it does not work well I was convinced that there was.
I don't think that communication is going well, but I think that's fine, but at the beginning of having expertise in the first place, there might be a difference between buttons and non-specialists.
Is the expertise required by non-specialists the same as the expertise I have and will not release?
In the first place, the expertise I have is the expertise to secure my position, and what does the non-professional person want in the category?
It doesn't have to be exactly the same, but it might be a considerable distance from the center of expertise you have.
That suddenly worried me.
禅宗の修行で「夜坐」と呼ばれる夕食後に寝るまでの間で行う坐禅があると聞いたことがある。
1日を振り返る時間なのか、心を静かに落ち着ける時間なのか、いずれにせよ、日が落ちた後は行動的にならず、心身共に休める時間にするということだろう。
人は一日のうちでいつが一番活動的になるのかが遺伝で決まっているようで、朝の人、昼の人、夜、夜中とタイプがあるらしく、自分は朝から昼にかけての時間帯が一番活動的で集中力が増す。
なので、大半の仕事や大事な活動は朝から昼にかけて行い、夕方以降はおまけの時間、大事なことはしないで、静かに過ごすように、また明日、日が昇ってスイッチが入るまでの休憩時間だと思っている。
だだ、もちろん、夜に仕事をする時もあるし、人と会ったり、外食したりする時もあるが、それでも寝るまでの間をどう過ごすか、大事なことはしないが、明日のためには一番大事な時間帯で、家にいる時は、朝から昼の時間帯は特に意識しなくても良いが、寝るまでの間の時間帯は意識して、深い眠りができるような工夫をしないと、明日が気持ち良く過ごせないので、一日のうちで一番過ごし方を大事にしている時間帯になる。
だから、「夜坐」の心の有り様に興味があり、たぶん、収束するように心を落ち着かせるのだろうが、そうすると眠くならないのか、坐禅中に寝ることはできないので、どうするのか、眠たいのに寝られない状況程辛いことはないから、それが修行ということか、ならば、修行ではないから、もう寝よう。
"An important time"
I have heard that there is a Zen zazen called "Yoza" in Zen training, which is performed after dinner until sleeping.
Whether it's time to look back on the day or calm down, it's time to rest after both the day and the day.
It seems that people are genetically determined when it becomes most active during the day, and there are types of people in the morning, noon, night, midnight, and I am the time from morning to noon The belt is the most active and the concentration is increased.
So, most of the work and important activities are done from morning to noon, and after that evening, extra time, don't do anything important, be quiet, and tomorrow, rest time until the sun rises and switches on I think.
Of course, there are times when I work at night, sometimes I meet people and eat out, but it doesn't matter how I spend my time until I go to bed, but for tomorrow Is the most important time zone. When you are at home, you do not need to be aware of the time zone from morning to noon, but you should be aware of the time zone until you go to sleep so that you can sleep deeply. If you don't, you won't be able to spend tomorrow comfortably, so it will be a time of day when you spend most of your day.
So I'm interested in the way of the night-sitting mind, maybe calming my mind to converge, but if I don't get sleepy then I can't sleep during zazen, so I want to sleep It 's not as painful as a situation where you ca n't sleep, so it 's training.
モノとコトに分けて考えるのはちょっと古めかしいような気がしてしまうが、直にものづくりに関わっていると、ついついモノとコトを混同して逆転させてしまう。
どうしても直接モノに触れるから、モノが持つそれ自体の状態や価値が気になってしまう。より質の良いモノ、より状態の良いモノというように、モノが良ければ全てが良いような錯覚におちいる。
そうすると、コトを考える順番が後に、モノから先に、モノがはじめにあり、そのモノを生かすためにコトを組立ててしまう。
何かを創作する時はモノよりコトが先にきた方が自由度が上がり、自由であればあるほど、創作する時の思考を遊ばせることができ、結果的に新しいモノが生まれる可能性が高まる。
例えば、何か料理をつくる時に、モノから考えるのは食材から考えること、コトから考えるのはメニューから考えること。
食材から考えた場合、当然、その食材をメインにした料理を考え、メニュー構成を考える。食材によってはつくれない料理も出てきて、それはメニュー構成にも影響を与える。
メニューから考えた場合、つくりたい料理、食べたい料理から考えることができ、それに合わせて食料選びをするから、つくれない料理は無く、メニュー構成にも制限は無い。良いモノを求めるならば、料理を決めてから、良い食材を探せば良い。
実現したいことが、自分が今つくりたい料理、自分が今食べたい料理をつくることならば、メニューから考えた方が実現の可能性が高まる。
なんてことは当たり前なのに、ものづくりをしている人は、モノに対して偏愛の趣向があるから、どうしてもモノそのものに意識が行ってしまい、可能性を狭めてしまうことも、モノからという戦略を意識して行っている場合は良いが、そうでないと、いつまでたっても実現しない。
"Previous things"
It seems a bit old-fashioned to divide things into things and things, but if you are directly involved in manufacturing, you will confuse things and things and reverse them.
I always touch things directly, so I'm curious about the state and value of things. There is an illusion that everything is better if things are better, such as things of better quality and things in better condition.
Then, after the order of thinking about things, there is things first, things first, and things are assembled to make use of those things.
When creating something, the degree of freedom is higher when things come first than things, the more freedom, the more you can play thinking when you create, and the possibility of creating new things as a result Rise.
For example, when making a dish, thinking from the thing is thinking from the ingredients, thinking from the menu is thinking from the menu.
When thinking from the ingredients, of course, consider the dishes that are mainly made from the ingredients, and consider the menu structure. Some dishes cannot be made depending on the ingredients, which also affects the menu structure.
When you think from the menu, you can think about the food you want to make and the food you want to eat, and choose food according to it, so there are no dishes that cannot be made, and there are no restrictions on the menu structure. If you want good things, you can decide what you want to cook and then look for good ingredients.
If you want to realize what you want to cook and what you want to eat now, you can think more from the menu.
Even though it is natural, people who make things have a tendency to be prejudiced towards things, so they are conscious of things themselves, and the possibility of narrowing the possibilities is also conscious of the strategy from things If it is done, it is good, but otherwise it will not be realized.
決められた時間割があって、それに従って動くのは学校みたいだが、時間という総量は、1日24時間で、決められているから、あとはそれをどう割り振るかを考えたら、自然と学校みたいに、1日の時間割が決まってしまう。あとは割り振る時の所要時間の読みの精度が問題になるだけ、読みの精度が甘くなると時間割が破綻する。
その読みは経験値もさることながら、読みの内容をよくよく考えてみると、遊びが無いというか、ギリギリぴったりで、ただ余裕をみすぎてもダメ、いつも同じことの繰り返しならばわかるがそこが難しい。
建築も量で考えれば、総量が決められている、それが法規か予算か様々な事情かによる違いで、当たり前だが無限に広がることはない。
そういえば、コルビュジエが「無限成長美術館」という渦巻き状の美術館を構想し、世界に3つだけつくった、その1つが上野の西洋美術館、あと2つはインドにある。
総量が決められていれば、それを割り振るのだが、建築が割り振るとしたら壁を建て部屋にすることを考えるが、無限成長美術館は部屋というより、渦巻き状の細長い空間が永遠に続くことを構想し、割り振るとかではない。
美術館の特徴を考えれば、作品を飾る壁が長く途切れることなくあった方が良いから、渦巻き状の空間には妥当性がある。それは、美術館の空間は人の動きによっても決まるという考えもあっただろうし、「建築的プロムナード」というコンセプトでコルビュジエはサヴォア邸という住宅をつくり、内外の境界を人に動きに応じて再構成するようなことをしていたので、空間を割り振るという考えは元々無かったのだろう。
時間も割り振るというより、途切れることなく、つながりで考えたら、1日24時間という総量は決まっていても、相乗効果で、全く関係がない時間同士がつながり、新たな価値が生まれないだろうかと、そんなことを夢想してみると、それはたぶん、切りの良い所で止める発想は捨てて、常に中途半端にしておいて、また再開なんてことを繰り返した場合に起こるのかな。
"Timetable"
There is a set timetable, and it is like a school that moves according to it, but the total amount of time is decided at 24 hours a day, so if you think about how to allocate it, it will naturally look like a school The daily timetable will be decided. After that, the accuracy of reading the required time when allocating becomes a problem, and if the reading accuracy becomes poor, the timetable breaks down.
The reading is not just experience, but if you think carefully about the content of the reading, it is said that there is no play or it is just perfect, but you can not understand even if you leave too much, but you can understand if you always repeat the same thing Is difficult.
If you think about architecture in terms of quantity, the total quantity is determined. Depending on whether it is a law, a budget, or various circumstances, it is natural, but it does not spread indefinitely.
Speaking of which, Corbusier envisioned a spiral art museum called "Infinite Growth Museum" and created only three in the world, one of which is Ueno's Western Art Museum and the other two are in India.
If the total amount is decided, it will be allocated, but if the architecture allocates, we will consider making the wall into a building room, but the infinite growth museum is not a room but a concept that a spiral elongated space will last forever And it 's not like allocating.
Considering the characteristics of the museum, it is better that the walls that decorate the work should be long and unbroken, so the spiral space is valid. It may have been thought that the museum space is also determined by the movement of people, and Corbusier creates a house called Savoie House with the concept of "architectural promenade" and reconfigures the inner and outer boundaries according to the movement of people. I thought that there was no idea of allocating space because I was doing something.
Rather than allocating time, if you think with connections without interruption, even if the total amount of 24 hours a day is decided, synergistic effects will connect hours that are not related at all, and new value will be born When I dream about it, it probably happens when I leave the idea of stopping at a well-cut place, always leave it halfway, and repeat it again.
川の流れの中に関をつくれば、流れが乱れ、関によって流れの影響が多少弱まる所ができる。
人の動きを流れに例え、関を建築の壁だとしたら、壁によって人の動きに影響が出て、立ち止まらなくていけない所に椅子やテーブルを置けば、そこが居場所かもしれない。
時間の経過を流れに例え、関を予定だとしたら、予定によって時間の経過に影響が出て、時間を費やさなければならない時に向き合えば、それが経験かもしれない。
空間の移ろいを流れに例え、関を人だとしたら、人の動きによって空間の移ろいに影響が出て、空間の移ろいがゆっくりとなる所を定めれば、そこが人が集まる場所かもしれない。
空間の移ろいは、例えば、車窓の景色かもしれない。それが、ゆっくりとなる場所は、そこに留まっている時、そして、そこに時間を費やしている時、そして、そこに壁をつくれば居場所になる。
人、時間、空間が相互に関係し合いながら、自然と居場所は決まるものなのだろう。そう考えると、居場所をつくることは、流れの中にいながら、流れを乱す行為、ただし、乱し過ぎて、流れが変わってしまったら元も子もない、そのバランス加減が技術かな。
"Technology for creating a place to stay"
If you relate to the flow of the river, the flow will be disturbed, and there will be a place where the influence of the flow will be somewhat weakened.
If you compare the movement of people to the flow, and Seki is an architectural wall, if you place a chair or table in a place where the movement of the person is affected by the wall and you have to stop, that may be your place.
If the passage of time is compared to the flow, and Seki is scheduled, it may be an experience if the schedule affects the passage of time and faces time when time must be spent.
If the movement of the space is compared to the flow, and Seki is a person, if the movement of the space is influenced by the movement of the person and the place of the movement of the space is determined slowly, that may be the place where people gather. .
The transition of the space may be, for example, the scenery of the car window. The place where it slows down becomes a place when you stay there, spend time there, and make a wall there.
People, time, and space are interrelated and nature and whereabouts are determined. When thinking so, creating a place is an act of disturbing the flow while in the flow, but if the flow changes too much, there is no original or child, and the balance adjustment is technology.
芽がたくさん、昨日までがわからないほど、毎日かわる。
ここから、あちらから、芽が出るところは決まっているのだろうが、予測がつかないところから、予測がつかない出方で、予測がつかない方向に向かう。
そもそも小枝を水につけているだけだから、規則正しい並びではないなけれども、そこから、さらに不規則に、成長スピードもバラバラ、不均一。
カオスそのもの、カオスはその状態を誘引する物が必要で、この場合は、とりあえず入れている透明なプラスチックの桶か。
バラバラ、不均一な成長状態が共存し、個々に見てみると規則性は無いが、全体を引いて見ると、桶という大枠の中でカオスという状態をつくり上げている。それは決して野放しでは無く、かと言って、徹底的に管理されている訳でも無い。
その中で、枝の出やすいところから芽が出る、そこには何かしらの秩序があり、それに従っているのだろうが、こちらにはうかがい知る余地も無く、ただ、自由に好きなところから芽を出しているようにしか見えない。
それをこちらは傍観しているだけ、ただし、桶の中の話なので、どうなろうと構わない。ただ、どんどん成長して欲しいだけ。
桶が置かれた環境の中で、桶という大枠の中で、そこから先は、枝なりに自由に成長し、それは予測のつかない様相を示す。
ただ、自由ではあるけれど、環境や桶とは全くの無関係では無くて、むしろ、日当たりなど直接的に関係性があるし、無いと成長もできない。
この当たり障りのないカオスの様を楽しむのも植物を育てる楽しみのひとつかもしれないが、常に成長し、様相が変化し、終わりがない、今の状態は常に不完全で、常に不安定で、成長とはそういうものか、このような変化は建築には無い、建築は動かないから、ただ、このカオスの楽しみはどこか建築的だと思える、それは、成長が構築とも言えなくもない、この成長する状況をつくり出す過程は建築と似ていて、それに成長する植物を建築中の建物と見立てることもできなくはないから。
建築はカオスを誘引する物になり得るのは過去の事例からわかるが、その時に、建築はカオスをつくり出す秩序にまで関与できるのだろうか、その手前までで、あとはご自由に、という以上のことをするところまで、動かない建築が関与できたらと想像してみる。
"Sprouting"
There are so many buds that I change every day that I don't know until yesterday.
From here, the place where buds will come out is decided from here, but from the place where the prediction is not possible, the direction where the prediction is not possible and the direction where the prediction cannot be made is headed.
In the first place, the twigs are just submerged in the water, so it's not a regular arrangement, but from there on, it is more irregular and the growth speed is also uneven and uneven.
Chaos itself, chaos needs something that attracts the state, in this case, is it a transparent plastic bottle for now?
Distinct and uneven growth conditions coexist and there is no regularity when viewed individually, but when looking at the whole, it creates a state of chaos within a large frame of cocoons. It's not open-ended, but it's not strictly managed.
Among them, the buds come out from the place where the branches easily come out, and there is some sort of order there, and it will be followed, but here there is no room to know, just shoot from the place you like freely It only looks like it is out.
This is just a side-by-side look, but it's a story in the cage, so it doesn't matter what happens. I just want you to grow.
In the environment where the kites are placed, in the framework of the kites, from there on, the branches grow freely like branches, which shows an unpredictable aspect.
However, although it is free, it is not completely unrelated to the environment and traps. Rather, it is directly related to the sun and cannot grow without it.
Enjoying this bland chaos may be one of the fun of growing plants, but it always grows, changes its appearance, never ends, the current state is always imperfect, always unstable, growing This is the kind of change, there is no such change in architecture, because architecture does not move, but it seems that the fun of this chaos is somehow architectural. The process of creating a situation is similar to architecture, and the growing plant cannot be regarded as a building under construction.
It can be seen from past cases that architecture can attract chaos, but at that time, can architecture be involved in the order that creates chaos? Imagine if you can get involved with non-moving architecture.
建築をいつも、ものをつくることをいつも、自分の内面との対話から発想することが多いというか、それしかないかもしれない。
直接的に関係してくるクライアントの要望や予算などは自分の外側からくるものだが、それはもちろん、それによって決まることもあるけれども、それだけで建築はつくれない。
例えば、法規にしても、それも自分の外側のことだが、法規に対する扱い方というか、対応の仕方には建築を設計する側の考えが入り込む余地があり、その部分は自分の内面との関わり合いになる。
と、では時代性は、社会性は、となる。
この時代に、この社会に生きていることで、何か影響を受け、何かを考え、何かを得ているならば、それが内面に浸透するはずだと考えてきた。
だから、内面との対話のみでもと考えてきた、が、それだけでは物足りない、いや、もっと意識的にならないと、内面から発することが実は外からの要請で規定されていることがたくさんあるように考えられるキッカケがあり、限定した狭い領域の、片手間落ちの領域のみに居たような気がしている。
自分の外側に新たに建築を規定する領域を意識できたことは、今まで断片同士だったものに繋がりがあることがわかり、その繋がりが見えてきたようで、そうなると、自分の内面との対話と同じくらい、面白いことが起こりそうな気がする。
"My inner and outer"
Perhaps it's just that you always come up with the idea of building and making things from your inner dialogue.
Client requests and budgets that are directly related come from outside of me, but of course it may be determined by that, but that alone does not make an architecture.
For example, even if it is a regulation, it is also outside of me, but there is room for the idea of the side who designs the architecture to handle the law or how to handle it, and that part is related to my inner side Get along.
And then, age is sociality.
In this era, I have thought that living in this society is influenced, thought about, and gained something that would penetrate inside.
So, I thought that it was just a dialogue with the inside, but that alone is not enough, no, I think that there are many things that are stipulated by the request from the outside if it is not more conscious I feel like I was in only a narrow, limited area with one hand missing.
The fact that I was able to be aware of the area that newly defines architecture outside of me was able to see that there was a connection to what was fragmented so far, and it seems that the connection has been seen, and when that happens, dialogue with my inside I feel like something interesting will happen.
建築をずっとやってきているから、建築性が強い、別の言い方をすれば、作品性が強い建築に興味が湧く。
それは普通ではつまらない、街中によくあるもの、よく見るものなんて論外、何も考えていないし、綺麗に見せるだけならば誰でもできるし、もっと未知なもの、もっと既視感の無いものが見たい欲求があるからだが、建築に関わりが無い人からすれば、違和感があるというか、ちょっと理解ができない可能性もあり、それは建築をつくる側と使う側のズレ、というか、そこに断層が存在するような感じもある。
そもそも建築空間単体では成り立たないと思うが、人がいなければ成り立たないと思うが、建築空間単体で成り立つ自律性を欲してしまう、そこが作品性につながるのだが、それは人が無用という問題をはらんでいて、さらには、建築空間と認識するのは人ではないかという問題も含んでいる。
人が建築空間と認識するから、建築空間として存在しているのであって、人がいなければ、そもそも建築空間自体が存在しないことになるとハイデッカーは唱え、人自体が無用とされれば、建築は単に芸術作品としての価値のみしかなくなるが、それでも良いから、建築性が強い建築をつくりたいし、見てみたい。
ところが、そのような建築性の強い建築が日常を豊かにすると夢見ている。
日常は人がつくり出すものなのに、人自体を無用とした建築が日常を豊かにすると、本気で考えている。
この一見矛盾するつながりを解くことが今の課題であり、次への足掛かり、なぜか、それを考えるのがまた楽しい。
"Everyday and Architecture"
Since I've been doing architecture for a long time, I am interested in architecture with strong workability.
It's usually boring, things that are common in the city, things that you see often are out of the question, anyone can do it if you don't think about it, just show it cleanly, and you want to see something that is unknown or that is less visible However, if you are a person who is not involved in architecture, you may feel uncomfortable, or you may not be able to understand it a little. There is a fault between the side that makes the architecture and the side that uses it. There is also a feeling.
In the first place I think that it does not hold in a single building space, but I do not think that it does not hold if there is no person, but I want the autonomy that stands in a building space alone, that leads to workability, but that is the problem that people are useless In addition, there is a problem that it is human beings who recognize it as an architectural space.
Since people recognize it as an architectural space, it exists as an architectural space, and if there are no people, Hydecker advocates that the architectural space itself does not exist in the first place. It's just a value as a work of art, but it's still good, so I want to make a building with a strong architecture and see it.
However, I dream that such a strong architecture will enrich my daily life.
Even though everyday life is something that people create, I am seriously thinking that architecture that makes people useless will enrich their daily life.
Solving this seemingly contradictory connection is the current challenge, and it is fun to think about it as a foothold for the next.
答えが溢れている、何かわからないことや疑問など、もうすでに世の中には存在しないくらいに、誰かが考え、その答えを用意していてくれて、また、その答えも誰かが出したものを元にしたものだったりするから、調べればわからないことなど無いと言える。
答えは時代とともに変わり、常に更新されていき、その状況は昔と、例えば、30年前と変わらないかもしれないが、昔、30年前のネットが無い時代は、その答えになかなかアクセスできなかったので、今ほど答えが溢れている感覚は無く、もしろ、もっと答えに飢えていて、どうやったら答えに辿り着けるのか、まず調べる手段を考えるところからはじめていたような気がする。
その調べる手段の1つが本を読むだった。簡単なことでも、尋ねる人が見つからない時など、とりあえず、近くの本屋へ、Amazonも当然無いし、昔は近所に本屋がたくさんあったから、本を探すのも、どの本を見れば答えを導き出すことができるのだろうかと、その時点で答えへ至る思考がはじまっていたように思う。
だから、答えを得た時も、そこまでに徐々に思考の積み重ねがあったから、そのまますぐに受け取るよりも、すでに少しは自分色に染まった答えになっていて、自分のものとして遜色なく、すぐに使えたような気がする。
前に聞いた話で、元プロ野球選手のイチローは本を一切読まないらしい。目に悪いからという理由の他に、本には必ず答えがあるから、それが嫌だと。何か自分に問われた時、本を読んで答えを得ても、知ったような気になっているだけで、その答えは自分で切磋琢磨して出したものではないから使えないし、意味が無いと。
思考すること無く、すぐに答えを得ることができる。それは、すでに明白な答えが存在するのに、いちいちそのことについて思考するだけ時間の無駄であり、わかっていることの先にある未知なる部分に早く取り掛かった方が効率的だという考えからすれば便利なことだろう。
しかし、その明白な答えをはじめから導き出すことと、未知なる部分の答えを導き出すことは、同じ思考能力を必要とするはず、ならば、その明白かもしれない答えを導き出すところから自分で切磋琢磨して、自分なりの思考能力を身に付けることが大事で、そうしないと、未知なる部分の答えも導き出すことはできないだろう。
だから、時には遮断、ネットを遮断、本を遮断、人の考えを遮断、答え探しをやめて、バカになって、ゆっくり自分なりに考えや思いを巡らすだけでも、休みの日には楽しいかも。
"answer"
Someone thinks and prepares the answer to the extent that the answers are overflowing, something unknown or questions no longer exist in the world, and the answer is based on something that someone gave It can be said that there is nothing that you do not understand if you examine it.
Answers change with the times and are constantly updated, and the situation may be the same as in the past, for example, 30 years ago, but in the past, when there was no internet 30 years ago, it is difficult to access the answer So, I don't feel like I'm full of answers, and I feel like I was starting to think about how to find out how to get to the answers.
One way to find out was to read a book. Even if it's simple, if you can't find the person you want to ask, for the time being, there are no Amazons in the vicinity, there is no Amazon, and there used to be a lot of bookstores in the neighborhood. I think that I could start thinking at that point in time.
So, when I got the answer, there was a gradual accumulation of thought so far, rather than receiving it as it is, it is already an answer that is a little dyed in my own color, and it is not inferior as my own, immediately I feel like I was able to use it.
As I heard before, former professional baseball player Ichiro seems not to read any books. I don't like it because it's bad for my eyes. When you ask yourself something, even if you read a book and get an answer, you just feel like you know it. Without it.
Get answers quickly without thinking. That is because there is already an obvious answer, but it is a waste of time to think about that one by one, and it is more efficient to start with the unknown part ahead of what you already know. It will be convenient.
However, deriving the obvious answer from the beginning and deriving the unknown part of the answer should require the same thinking ability. It is important to acquire your own thinking ability, otherwise you will not be able to derive answers to the unknown.
So, sometimes it's fun on a day off, just blocking, blocking the net, blocking books, blocking people's thoughts, stopping looking for answers, becoming stupid and slowly thinking and thinking.
物のある一部に焦点を当て、それがその物以外とつながりや関係性ができて、別の意味合いをつくり出し、その意味合いから再度、元の物を構築する。
その物が建築でも、何かのプロダクトでも、何でもよいが、物のある一部、構成要素を取り出してきて、その要素だけが独立して、新たな関係性を生み出し、その関係性から再構築する。
物単体で突き詰めて創作していくことに限界や行き詰まり感はないが、その物のみで、その物の価値や造形や経済性だけで、全てが完結してしまうことに違和感を感じる。
飲み口の厚みが連続的に変化する。飲み口の厚みによって唇をつけた時の感触が違う。唇をつける位置を、飲み物の種類や、それこそ、その日の気分で自由に変えれば、感触が変わる。
飲み口と気分に関係性が生まれた。ならば、気分によって飲み口を変えた場合、全体の形の見え方も呼応して変われば、気分とカップが結びつく、気分の自由さを生かす非対称のデザインにする、それが発端だった。
"Connect"
Focus on a certain part of a thing, it can be connected and related to other things, create another meaning, and build the original thing again from that meaning.
It can be anything, whether it is an architecture or a product, but it takes out a part of a thing and its components, and only that element independently creates a new relationship and reconstructs it from that relationship. To do.
There is no limit or a sense of stagnation in creating a single object, but I feel uncomfortable that everything is completed with only that object, just the value, modeling, and economics of the object.
The thickness of the mouth changes continuously. The feel when putting on the lips is different depending on the thickness of the mouth. If you change the position where you put your lips freely according to the type of drink and the mood of the day, the feel will change.
A relationship was born in the mouth and mood. Then, when the mouth was changed depending on the mood, the appearance of the whole shape changed accordingly, and the mood and the cup were connected, and the asymmetric design that utilized the freedom of the mood was the origin.
何かがちょっとだけ変わるような出来事につながればよいと思い、想い描ければ。
直接的に物と関わり合うので、建築は、どうしても物の価値だとか、物の良し悪しだとか、物の金額が最初にきて、それが中心になってしまう傾向が強いが、並列して、それまでの慣習や思い込みや生活パターンなどがちょっとだけ良い方へ動くようなことも必要ではないかと思う。
新しく建築することが、それまでのことを新しく生まれ変わらせる、刷新するようなことに思ってしまうかもしれないが、どうしても、それまでの延長線でしたか考えられないと、結局、ただ建物が新しくなるだけで終わることも多い。
変化させたくない、保守的になる気持ちはわかるし、無理して変える必要も無いし、それまでと同じでも構わないと思うが、「もしよかったら」という形で、なるべく、接した中でこうすると、ちょっとだけ日常が豊かになるようなことをクライアントへの提案の際に添えるようにしている。
そうして7年前に添えたことを今実らせて、新しい壁を挿入中、7年前に目一杯想像力を発揮して、その想像の範囲内には今のところはおさまっているが、これからは想像の範囲外、どうなるか楽しみがまた1つ増える。
"If it's fine"
I hope it will lead to an event that changes something a little, and I want to draw my thoughts.
Because it is directly related to things, architecture is inevitably the value of things, the quality of things, the amount of goods comes first, and it tends to be the center, but in parallel , I think that it is necessary that the conventional customs, assumptions, and life patterns move slightly better.
You may think that building a new building will reinvent and renovate it, but if you can't think it was an extension of it, it will be just a new building. It often ends just as it is.
I don't want to change it, I understand the feeling of being conservative, I don't have to change it forcibly, I don't mind changing it as before, In doing so, I try to add something that makes my life a little richer when making proposals to clients.
So, now that I've added it seven years ago, while inserting a new wall, I showed my imagination to the fullest seven years ago. From now on, it's out of the imagination, and one more pleasure will happen.
ふるいの目、ざるの目、網の目、ふるいにかける物によって目の密度が決まっているようで、そこまで詳しくないが、料理でも、建築だと左官屋さんが使っている。
必要な物を選別したり、不要な物を残したり、精製するためにふるいにかけるから、目的に応じて目の密度の違うふるいを用意するのだが、その目の違いを使い分けるのにも技があるような気がする。
別の言い方をすると、フィルターにかける。物だけでなく、事柄にも言える話で、どの目を使い選別するのか、精製するのかによって、最初は同じ状態、状況でも、ふるいにかけた後は違ってくる。
このふるいにかける作業は人によって違うはずで、このふるいのかけ方が個性であり、それによって状態、状況が各人違ってくるはず。
ただ、このふるいのかけ方に一定のルールがあるものもあるかもしれない。それは例えば、学問とか、学術的なこと、それは歴史が重なってつくられたふるいのかけ方だから、個人のふるいのかけ方を優先はできないが、そこの差異を埋めるのが研究することなのかもしれないが、その差異を把握して上手く研究に結びつけるのにも、ふるいのかけ方同様、技が必要な気がする。
どちらかというと、ふるい自体に興味があり、どのようなふるいが世の中に存在するのか、料理するより料理道具が好きで、料理道具を使いたいから料理をするようなものだが、たくさんのふるい集めをしたくなる。
"sieve"
The density of the eyes seems to be determined by the sieving eyes, the squirrel eyes, the mesh eyes, and the objects to be sifted.
Screening for necessary items, leaving unnecessary items, and sifting for purification, we prepare sieves with different eye densities according to the purpose. I feel like there is.
In other words, it filters. It can be said not only for things but also for matters, depending on which eye is used for selection or purification, even in the same state and situation, it will differ after sieving.
The process of sieving should be different for each person, and the way of sieving is individuality, and the state and situation should be different for each person.
However, there may be some rules for how to apply this sieve. That is, for example, academic or academic, because it is a way of sieving created by overlapping history, it is not possible to prioritize personal sieving, but it may be researching to fill in the differences I don't think, but I feel that skill is necessary to grasp the difference and to connect it well to research, as well as how to sift.
If anything, I'm interested in the sieve itself, what kind of sieves exist in the world, I like cooking utensils rather than cooking, I like cooking utensils, but it is like cooking, but collecting a lot of sieves I want to
日々、芽が出てくる、新芽がまるで枯木に花咲くように出てくる。
自宅の塀を覆っていた蔦をだいぶ整理してリセット、一部を室内で育てはじめ、最初は枝の切れ端を水につけ、植物活力素も投入、まずは新しい気根が出て長く伸びるまでと思っていたが、白い気根が何本か見えた途端に新芽がムクムクと。
朝と夕で違いがわかるくらい、伸びるのが早い、生命力が強いのか、環境に慣れてきたのか、蔦は何か絡みつくものがあってはじめて取り付くように伸びていくそうなので、室内だと横に広がるだけらしい。
ただ、その伸びる様を見ているのが面白くて、キッチンに置いているのだが、キッチンに立つ度に見入ってしまう。成長していく様が楽しい。植物を育てる楽しみとはこういうものかと、この歳にして初めて思うなんて。
枯らすのが得意だったから小学生の頃、朝顔も何も花が咲いたことがなく、興味もなかったのに。
日々変わるものは見ていて楽しいし、飽きないな、そこは建築に似ている。工事中は当然毎日出来上がっていくから、その様を見ているのは設計者として至福の時だし、完成してから、そう設計者は一所懸命に心血注いでつくっても、自分では住めない、使うことはない、それが、きっと楽しいんだろな、いいんだろうな、なんて思いながら引き渡すのだが、その後見に行くと、住む人色、使う人色に染まって、自分の想像していた変化とは違っていたりすると、またそれが、その様を見るのが楽しい。
自分の想像では、部屋中、蔦だらけになり、蔦に埋もれて、蔦の間で寝て、蔦からひょっこりと顔を出す予定なのだが、どうなることやら。
"Salmon, Mukumuku, Sprout"
Every day, buds come out, and new shoots come out like flowers in dead trees.
Organize and reset the cocoons that covered the cocoons at home, start growing some of them indoors, first put a piece of branch into the water, add plant vitality, first think that new air roots will come out and grow long However, as soon as some white air roots were seen, the shoots were muffled.
As you can see the difference between morning and evening, it grows fast, it is strong life force, whether you have become accustomed to the environment, it seems that it grows as if it is tangled up for the first time, so it is next to the room It just seems to spread.
However, it is interesting to see how it grows, and I put it in the kitchen, but I see it every time I stand in the kitchen. It 's fun to grow up. It 's the first time I 've ever thought that plant fun is like this.
I was good at withering, so when I was in elementary school, I had no flower in the morning glory and I was not interested.
It's fun to see things that change every day, and I'm never bored. It's like architecture. Of course, it is completed every day during the construction, so it's blissful as a designer who sees it like that, and even after it is completed, the designer can not live on his own even if he works hard and makes it I don't use it, but I'm sure it's fun, I'm glad I hand it over, but when I went to see it, I was dyed by the color of the people who lived and the people I used, I imagined If it is different from change, it is fun to see it again.
In my imagination, I'm going to be full of cocoons in my room, buried in cocoons, sleep between cocoons, and sneak out of my niece, but what happens.
目に見えるものは不思議だ。視野の範囲にはたくさんのものがあっても、そのうち覚えられるのはいくつもない、意識がそこに向いていないと正確には覚えられない。
何となくぼんやりと眺めていると、何となくしか覚えていないし、何となくしか記憶に残らない。
ただたぶん、目から入る情報は脳には全て残っていて、意識を向けていようが、何となく見ていようが、そのようなことには関係がなく、情報量としては同じだけはあり、例えば、写真のようにフレームにおさまっているものは全て写るように、あとはその情報に対して、どのように扱うのか、どのようにアプローチするのか、何もしなければ、残ってはいるが、永遠に陽の目を見ることはない、もしそうならば、脳は相当な容量があることになる、一生分の情報を貯めておけるのだから。
意識して覚えようとしても記憶に残らないのに、大したことでもないのに、何となくずっと覚えていることもある。
衝撃的なことがあった時はもちろん、それを覚えているが、サプライズもそう、忘れない、忘れられないが、日常で思い出すことは、どうでもよかったりすることも多い。
どちらかというと、たまに思い出すことより、日常的に思い出すことの方が大切というか、日常を豊かにしてくるように思う。
もしかしたら、それは毎日見る風景が元の情報になっていて、そこから感情や行動が結びついて、ふと思い出すのではないか。
そう考えると、日常的に毎日見る風景がどれ程大切さかがわかる。
"Daily scenery"
What is visible is strange. Even if there are many things in the field of vision, there aren't many that can be remembered, and it can't be remembered accurately if consciousness is not there.
If you look vaguely somehow, you will only remember and you will remember it.
However, all the information that enters from the eyes remains in the brain, whether it is conscious or whether it is seen somehow, it has nothing to do with such things, there is only the same amount of information, for example, It looks like everything in the frame like a photo, and after that, how to handle that information, how to approach it, if nothing is done, it remains, but forever You don't see the sun's eyes, if so, your brain will have a lot of capacity, because you can store information for a lifetime.
Even if you try to remember it, you don't remember it, but it's not a big deal, but you somehow remember it.
Of course, I remember that when there was a shocking thing, but I do not forget, I can't forget about surprises, but remembering in everyday life is often irrelevant.
If anything, I think that it is more important to remember on a daily basis than to remember occasionally, or to enrich the daily life.
Perhaps it seems that the scenery you see every day is the original information, and emotions and actions are linked from there, and you suddenly remember it.
When you think so, you can see how important the scenery you see every day is important.
暗黙のルールなるものは様々に存在していて、それを把握することが空気を読むことだったり、雰囲気を察知することだったりするが、それが社会のルール、ある特定の範囲内での常識であったりするが、そして、革新的なこと、創造的なことはその暗黙のルールを逸脱したところに存在するが、ただそれだけでは単に一過性のブーム、流行に過ぎず、真に革新的なこと、創造的なことはその暗黙のルールを書き換えてしまう。
例えば、Amazon、本は書店のみで買うものだった。25年位前、まだ日本でAmazonのサービスがはじまっていない頃、知人が洋書をアメリカのAmazonで購入したのを知り、その「Amazon」という本とは全く結びつかないネーミングが余計に印象に残った。
今では「本は書店のみで買うもの」なんて暗黙のルールは存在しない。それどころか「本はAmazonで買うもの」と暗黙のルールを書き換えてしまったと言っても過言ではない。
そのようなことは建築でも起こる、というか、建築で創造性を発揮しようとしたら、この暗黙のルールを書き換えようとすることになる。
例えば、金沢に21世紀美術館という建築がある。それまでの美術館は、美術作品を展示するためのスペースだから、美術作品を紫外線から守り、劣化を防ぐために外光はいれない、人工照明で管理し美術作品を見やすくするために、閉鎖的で、どこか薄暗いイメージがあり、ただ、それが暗黙のルールだった。
それを、箱型の展示室1つ1つを隙間を開けてバラバラに配置し、その展示室同士の隙間を開放的にし、そこに外光も取り入れ、明るくて開放的な美術館として、それまでの暗黙のルールを刷新してしまった。
まだまだ建築には暗黙のルールがたくさん存在しており、顕在化できていないものもたくさんあるような気がする。それを1つでも刷新していくことが建築やものづくりをする意味になる。
"Renewal of implicit rules"
There are various types of implicit rules, and grasping them is to read the air or to sense the atmosphere, but that is social rules, common sense within a certain range. Although innovative and creative exist beyond the implied rules, it is merely a transient boom, a trend, and truly innovative. What is creative is that it rewrites its implicit rules.
Amazon, for example, bought books only at bookstores. About 25 years ago, when Amazon's service was not yet started in Japan, I knew that an acquaintance purchased a foreign book on Amazon in the United States, and the naming that was not tied to the book `` Amazon '' was impressed .
There is no implicit rule that "books are only bought at bookstores". On the contrary, it is no exaggeration to say that the implicit rules were rewritten as "books are for Amazon".
That kind of thing happens in architecture, or if you try to show your creativity in architecture, you will try to rewrite this implicit rule.
For example, there is an architecture called the 21st Century Museum of Art in Kanazawa. Until then, the museum was a space for exhibiting artworks, so it was closed to protect the artworks from ultraviolet rays and to avoid external light to prevent deterioration. There was a dim image somewhere, but it was an implicit rule.
Each of the box-type exhibition rooms is arranged with a gap between them, making the gaps between the exhibition rooms open, and taking in outside light, making it a bright and open museum. The tacit rules have been renewed.
There are still a lot of implicit rules in architecture, and there seems to be many things that have not been revealed. Renewing even one of them means building and manufacturing.
物が場を規定してしまう、確か、ハイデッカーがそのようなことを言っていたような気がするが、その物が持つ暗黙のイメージみたいなことが、その物の見方だけでなく、その物を扱う人の印象、その物が置かれた場所の雰囲気まで決めてしまう。
前にお願いしていた輪島塗のカップ&ソーサーが届いた。同じ塗師さんの所で、フリーカップを木地から製作中だが、塗りを決めるための参考として、普段使いしようと思い、前に塗師さんの所にお伺いした時に、その場にあったカップ&ソーサーを購入、その色違いを注文していた。
塗りの色は一般的な黒と朱だが、色を反転させ、塗りにも、ぼかしや、艶を出すために油が混ぜてあったり、艶が無かったりと、1つのカップ&ソーサーにいくつもの塗りの技法が使われているので、日常の中で使いながら、フリーカップに使う塗りをどうするか、考えるつもり。
形は至ってシンプル、よくある形、だが綺麗な形、色も漆らしい色、だがきちんと工程を踏み、きちんとした材料を使った本物の塗り物、物は木地でできているから軽いが、見た目には、謂わゆる漆物、重厚なイメージになるかもしれない。
まだ、カップ&ソーサーだから、御重などに比べたら、漆物として日常使いしやすいし、受け入れやすい。
そう、漆物には受け入れにくいイメージ、それはもしかしたら高級なイメージもあり、だから、相反するイメージで受け入れにくい、扱いが難しいイメージもあるかもしれない。
もしかしたら、先のように、漆物があるだけで場が規定されてしまうかもしれない。それを上手く利用できれば良いのだが、後継者がいないらしい、後継者がいないということは、その産業が衰退していること、暗黙のイメージを上手く利用できていない証、万年筆の仕上げにしたり、箸は昔からあるが、漆物の良さを生かしきれていない。
もっと、今までとは違った、漆だから、漆物だから実現できる日常の生活の一部を、漆物は製品として万能で優秀、特に輪島塗は丈夫で普段使いにはとても良く、使えば使うほど味が出る。しかし、それは前の時代の価値観、その価値観だと他のものにとって代わられる、別に漆物でなくても良いとなる。
漆の特性、漆物の特性に特化した、それでいて技術が無いとつくれないような物をつくれば、後継者も育つのだが、その答えを形にできるのは人だから、やはり、物より人が先で、人が物や場を規定することに気がつくと、糸口が見つかるような気がする。
"People first"
The thing defines the place. Certainly, I feel like a high decker said such a thing, but the thing that the thing has an implicit image is not only how to see the thing, but the thing The impression of the person who handles it, and the atmosphere of the place where the thing is placed.
I received the Wajima Lacquer Cup & Saucer I had requested before. A free cup is being made from the wood at the same painter's place, but as a reference for deciding the paint, I would like to use it everyday, and when I visited the painter's place before, the cup & that was there I bought a saucer and ordered a different color.
The colors of the painting are common black and vermilion, but the colors are reversed, the paint is also blurred, oil is mixed to give luster, and there is no luster, many in one cup & saucer Since the painting technique is used, I will think about what to use for the free cup while using it in my daily life.
The shape is very simple, common shape, but beautiful shape, the color is also lacquered color, but the process is neat and the real coating using the proper material, the material is made of wood, it is light, but it looks May become a so-called loose lacquer, profound image.
Because it is still a cup and saucer, it is easy to use and accept as a lacquer everyday compared to Megumi.
Yes, there are images that are difficult to accept in lacquer, and possibly high-quality images, so there may be images that are difficult to accept and difficult to handle with conflicting images.
Perhaps, as before, the place may be defined only by the presence of lacquer. It would be good if you could use it well, but it seems that there is no successor, that there is no successor, that the industry has declined, proof that the implicit image has not been used well, fountain pen finishing, chopsticks Although it has been around for a long time, it does not take full advantage of the goodness of lacquer.
In addition, unlike lacquer, lacquer is a versatile and excellent product, especially Wajima Lacquer is durable and very good for everyday use. Taste comes out. However, it is not necessary to use lacquer separately, because it replaces the values of the previous period and those values.
Successor grows up if we make thing which we cannot make without technical skill that we specialized in characteristic of lacquer, characteristic of lacquer, but person can shape the answer, but after all person But first, if you notice that people define things and places, you will find clues.
マチスのダンスだったり、アンディ・ウォーホールのキャンベルスープ缶だったり、リキテンシュタインの漫画チックな絵だったり、ジャクソン・ポラックのアクションペイントだったり、時代もイズムも全く違うけれども、平面的な絵が好きでそればかりを見ていて、あと、ジャスパー・ジョーンズのフラッグ、東山魁夷の絵は全部好きで、展覧会があると必ず、前は国立近代美術館で常設されていたし、唐招提寺の襖絵は圧巻だった。
作品自体が好きな場合もあるし、作家自体が好きな場合もあるけれど、総じて、大きな括りとしては「平面性」を感じる絵画に惹かれた。
初めて平面的な絵画に触れたのはMOMAで常設されていた、先にも出たウォーホールのキャンベルスープ缶で、最初の印象が「これが絵なの、作品なの」というサプライズに、人はサプライズに弱い、記憶や印象の深い所に残る、だから、虜になる。
そうなると、不思議なことに、平面性を獲得するために排除したはずの精神性が見る側に芽生えてくる。
建築と絵画はよく比較されて、現代では建築と絵画は別々で、多種多様なイズムや思想が成り立っているが、元々は現代の建築も絵画も「モダニズム」運動とも呼べるイズムが発端で、その後の動きは相同的であり、建築を通して絵画を見たり、絵画を通して建築を見たりすると、より時代やイズムや思想を把握しやすくなる。
だからではなく、たまたまだったが、最初にモダニズムに触れたのは建築よりも絵画が先で、先のキャンベルスープ缶で、だから「平面性」の虜になった者からしてみれば、順当にモダニズム建築にも惹かれることになる。
ただ、モダニズム建築は平面的というよりは幾何学的な印象ではあるけれども、装飾を排除し、装飾に伴う精神性も排除し、純粋に自律を目指した点では建築と絵画は同じであり、平面的や幾何学的な元にある、その「純粋性」に惹かれて虜になっていたのかもしれない。
"Pure Prisoner"
It 's a Mathis dance, Andy Warhol 's Campbell soup can, Richenstein 's cartoon chic painting, Jackson Pollack 's action paint, even though it 's completely different in age and ism, but I like flat paintings I liked all of Jasper Jones's flag and Higashiyama Kaoru, and there was always a permanent exhibition at the National Museum of Modern Art. Was a masterpiece.
Sometimes I like the work itself, and sometimes I like the artist itself, but as a whole, I was attracted to paintings that feel "flatness" as a big conclusion.
The first time I touched a two-dimensional painting was a Campbell soup can from Warhol that was permanently installed at MOMA. The first impression was a surprise that "This is a picture, a work", and people are vulnerable to surprise It will remain in a place with a deep memory and impression, so you will be captivated.
Then, mysteriously, the spirituality that should have been excluded to acquire flatness will start to grow.
Architecture and paintings are often compared, and in modern times architecture and paintings are different, and a wide variety of isms and thoughts have been established. Originally, modern architecture and paintings originated from an ism that can be called the "modernism" movement, and then The movements are homologous, and if you look at paintings through architecture, or see architecture through paintings, it will be easier to understand the times, isms, and thoughts.
It wasn't, but it was still happening, but the first thing that touched modernism was the painting before the architecture, and the previous Campbell soup can, so if you were a prisoner of "flatness" Attracted to modernist architecture.
However, although modernist architecture is a geometrical impression rather than flat, architecture and painting are the same in terms of eliminating decoration, eliminating the spirituality associated with decoration, and pursuing pure autonomy. It may have been captivated by the "pureness" of the original and geometrical origin.
雨のやんだ空のような青さが青磁の色としては素晴らしいらしい、青磁の極み、浙江省龍泉窯のものを見せていただく機会があった。
青磁の良し悪しは色で決まるらしい、色の綺麗さ、くすみがなく、澄んだ青さが良く、また、塗りもぼてっというくらいに厚い方が良いとのこと。勝手な青磁のイメージだと薄塗りで繊細なものだが、この青磁の器はそうではなくて、物として重厚な存在感があった。
日常使いされていたかどうかは定かではないが、使われていたらしい。使われていた状況を想像すると、物としての存在感が波紋のように広がっていくようで、それにより、いろいろなことが明らかになるような気がした。
この青磁の器に何を盛るのか、それによって、盛った物がどのように見えて、どのように感じるのか。
この青磁の器をどこに置くか、それによって、その置いた辺りの空間がどのように変わり、どのような雰囲気になるのか。
この青磁の器を誰が扱うのか、それによって、扱う人の心や感情や意識がどのようになるのか、どのように変化するのか。
そして、もう1つ、この青磁の器がそこから無くなったら、どのようになるのか、何が変わるのか。
物に注釈して、極みまで行き、そこから引き返してくる時には、きっと違う風景が見えていることが、物の醍醐味だと思う。
"Ripple-like presence"
There was an opportunity to show me the extreme of celadon porcelain, the one of Longquan in Zhejiang Province.
The quality of the celadon seems to be determined by the color. The color is beautiful, there is no dullness, clear blue is good, and it is better to thicken the paint. The image of a celadon porcelain is thin and delicate, but this celadon porcelain was not so and had a profound presence as an object.
I'm not sure if it was used everyday, but it seems to have been used. Imagine the situation that was being used, and the presence as a thing seemed to spread like a ripple, and I felt that various things became clear.
What is put on this celadon porcelain, how does it appear and how does it feel?
Where will this celadon vessel be placed, how will the surrounding space change and what will it feel like?
Who will handle this celadon porcelain, and how will it change the mind, emotions and consciousness of the person who handles it?
And one more thing, what will change if this celadon vessel disappears from it?
Annotating things, going to the extreme, and returning from there, I think that the best part of things is that you can see a different landscape.
何かのメカニズムを解くとする、それは全体像がわかっていて、そのことについて精通していないとできず、メカニズムを解くということは、全体を要素に分解して、その各要素毎に解明し、各要素同士の関係性、つながりを明らかにすること。
きっとメカニズムを解く目的は、再現性にあると思われ、解くことによって、各要素を細かく分類し、さらに各要素よりも小さく分解して、はじめの初源まで立ち返り、そこから、くるりと反転して、元に戻っていく。初源まで行って、メカニズムの正当性を確認できたら、後は元に戻るだけ、来た道を戻る。
だができれば、戻る途中で違う道を見つけて、戻り方は同じだが、本来戻る場所とは違う所にも行ける可能性を持ちたい、再現性に創造性をプラスしたい、だから、メカニズムを解こうと考える。
答えから問題をつくり、その問題をまた解く時には、できれば、最初の答えより良いもの、創造的な答えにしたいし、また同じ答えでは意味がない。
だから、メカニズムを解こうとする時は、戻る時のために道しるべを残して、確実に帰れるようにしつつ、違う道も探りながら行く、すなわち、メカニズムを解く時に、目的は再現性だけれども、1本道を見つけるためではなくて、複数の道が存在していて、多様な結果になる可能性があることを示したい。
そう考えると、メカニズムを解くということは、ある決まっていることを分解して説明するだけでなくて、新たなメカニズムを構築することにもつながる。
"Building a mechanism"
To solve some mechanism, it is necessary to know the whole picture and not to be familiar with it, and to solve the mechanism is to break down the whole into elements and solve each element. To clarify the relationship and connection between each element.
The purpose of solving the mechanism seems to be reproducibility, and by solving it, each element is subdivided into smaller parts, further decomposed smaller than each element, returned to the first source, and then reversed. And go back. After going to the first source and confirming the correctness of the mechanism, the only way to return to it is to return to the original path.
But if you can, find a different way on the way back, the way to return is the same, but you want to be able to go to a place other than the place where you originally returned, want to add creativity to reproducibility, so think about solving the mechanism .
When you create a problem from an answer and solve it again, if possible, you want a better, creative answer than the first answer, and the same answer is meaningless.
So, when trying to solve the mechanism, there is a way to go back and make sure you can go home and explore different ways, that is, when you solve the mechanism, the purpose is reproducible, but 1 I'd like to show that there are multiple ways, not for finding the main road, and that it can have diverse results.
When thinking so, solving a mechanism not only breaks down and explains a certain thing, but also leads to the construction of a new mechanism.
うーん、気分がどうも優れないなー、天気が優れないからかなー、曇っているからかなー、なんて思うと、どんどん、天気に左右される、曇りの方が涼しい時もあるから、別に構わないのだけれども、ようするに、気分なんだなと。
建築は動くことができないから外部環境に左右される、というか、外部環境によってほぼ全てが決まると言って過言ではない。
例えば、規模は、敷地の大きさと、その場所の法規、建ぺい率や容積率、高さ制限で決まる、もちろん、予算もあり、あまりにも広い敷地の場合は目一杯の規模まで建てることはないが、都市部ではそのような広い敷地はなかなかないので、大体、目一杯の規模まで利用することになる。
用途も外部環境に左右される。繁華街のど真ん中に専用住宅をつくることはほぼないし、郊外にオフィスビルをわざわざつくることもない。
また、外部環境によって室内環境も左右される。周りが建物に囲まれている、幹線道路に面している、隣が公園、閑静な住宅街など、外部環境に対して何か対策をしたり、逆に外部環境を生かして室内環境を良くしたりする。
ただ、これだけ外部環境に左右されても、建築の優劣が外部環境で決まることはない。
規模が大きければ良い訳ではないし、建築にとって用途は何が良いかはもちろんないし、室内環境は対策や生かし方しだいでどうにでもなる。
だから、天気が曇りでも雨でも晴れでも、それで気分が変わっても、別にいいなと、曇りだからできることをしようと。
"Because it is cloudy"
Well, I do n't feel good, maybe because the weather is n't good, maybe because it 's cloudy, it 's more and more depending on the weather. However, I feel like I do.
It is not an exaggeration to say that architecture depends on the external environment because it cannot move, and that almost everything is determined by the external environment.
For example, the scale is determined by the size of the site, the regulations of the site, the building coverage ratio, floor area ratio, and height restrictions. Of course, there is also a budget, and if the site is too large, it will not be built to the full scale. In urban areas, there are not many such large sites, so they will be used to the fullest.
Applications are also affected by the external environment. There is almost no private housing in the middle of the downtown area, and there is no need to create an office building in the suburbs.
Also, the indoor environment depends on the external environment. Take measures against the outside environment, such as the surroundings surrounded by buildings, facing the main road, the park next to the park, and a quiet residential area, or conversely improve the indoor environment by taking advantage of the outside environment To do.
However, even if it depends on the external environment, the superiority or inferiority of the architecture is not determined by the external environment.
It doesn't mean that the scale is large, not to mention what the purpose is good for architecture, and the indoor environment depends on measures and how to make use of it.
So, even if the weather is cloudy, rainy or sunny, even if you change your mood, it's fine to try something you can do because it is cloudy.
繊細さというのは何かと比べないとわからないのか、繊細じゃない部分があるから、繊細さがわかるのか、だから、繊細さは相対的な価値基準になるのか。
細いものが林立する空間があったとする、例えば、自然の中でいえば竹林、竹が林立する風景は誰でも見たことがあるだろうが、その竹林を見て、繊細な空間が広がっているとはなかなか思わないかもしれない。
竹1本1本は、やはりよく見れば細い、節があるから余計に細く見えるかもしれない、特に竹林には他の木が生えているのを見ることはほとんど無いから、比べるものが無く、しかし竹は細いという認識が、松や杉に比べれば細いという認識があるから、植物のことをよく知らない人でも、竹は細いとなる。
では、竹には繊細という認識があるか、いや、要するに、認識があれば、比べるものが無くても繊細ということになる。
ただ、人の認識がつくられる時は、何かと比べた時になるから、竹が細い、という認識は、すでに比べられた結果に過ぎず、その認識が独り歩きして、絶対的な価値基準になり、それを利用して、例えば、数寄屋建築の床柱に竹を用いて、比べられる対象として、細いという認識があるものを置き、あとから付け足す、この場合、人ならば、人に比べれば竹など極細、繊細さが際立つから、数寄屋建築がより人がいることで繊細に見える、という仕掛けと考えたら、やはり、認識も、認識後の利用の段階でも、相対性が価値を決めることになるか。
そうなると、絶対的な繊細さというのは、存在するのだろうか、また、どうしたら存在するのだろうか。
数寄屋建築にしても、民家という比べる対象が存在するから、細く繊細に見える。もし、数寄屋建築だけしか存在しなければ、繊細さに気づかないかもしれない。
建築のディテールを考える時、最終的には全てを寸法に落とし込むが、その時によくあるのは、名建築を実測した結果、その建築に繊細さなイメージがあると、その建築のディテールの寸法を根拠に繊細さを出そうとすること、その建築をエビデンス代わりにするのか、どこどこ所属と一緒で、全く別の建築なので、全く根拠にもならない。その建築にとってはその寸法が繊細に見えただけのこと。
だから、名建築の実測はほとんどしなかった、もちろん、それは繊細さのこと以外にも理由があり、名建築を数値で理解しようとする行為は、その建築のその空間を理解することと本質的にずれているというか、押さえの寸法ありきで、建築空間がつくられているのではなくて、寸法は二次的に決まったものだからと考えていたので、その時は、もちろん、コルビュジエがモデュロールを使って設計した建築、例えば、ユニテダビタシオンやラ・トゥーレット修道院は宿泊して、一晩中寝ないで実測していたが、それでも、それはモデュロールを確かめるためで、名建築を数値で覚えようとしていなくて、自分の感覚で覚えようとしており、この場合、感覚は相対的で、過去に経験した建築と比べてどうかだが、自分の中に蓄積されていく感覚は絶対的なものになり、それが認識になる。
周りに比べるものがなければ、繊細さを表現することはできない、でも、繊細さを出したい時は、自分の過去の引き出しの中から、繊細さを引っ張りだして来てつくる、認識でつくる、それが絶対的な価値基準でつくるということ。
ただ、結局それは、別の表現になってしまう。比べるものが無いから、繊細さとは思われず、でも、作者がそこで繊細さに拘ると、間抜けなものしかできない、一見繊細だと、絶対的な繊細さだと表現しても、比べるものが無いから、繊細だとは認識されず、ただ細いもの、不恰好なものとなる場合がある。
ところが、この不恰好なものが、比べるものがあった場合にも起こる、明らかに、比べたら細く、材質も変えて繊細に見せようとしても起こる。
それは、そもそも、そのものが繊細では無い時、すなわち、相対的に繊細さを表現することはできても、絶対的に繊細で無いと、結局は繊細では無く不恰好になる。それは、当たり前といえばそうだが意外と多い事例のような気がする。
結局、絶対的な価値基準を持つ作者しだいだが、かといって、相対性も必要になるから、絶対と相対のバランス、出し入れが繊細さを決め、そのバランスをどうするかが設計であり、そのバランスを決めるのが設計者で、そのバランスの良し悪しは設計者の絶対的な価値基準の質というかレベルしだいということになる。
"Absolute, relative, recognition and design"
Do you not understand the sensitivity unless you compare it with something, or do you know the sensitivity because there are parts that are not delicate, so is the sensitivity a relative value standard?
Suppose that there was a space where thin objects stand, for example, in the nature, anyone would have seen a bamboo forest, the scenery where bamboo stands, but when you saw the bamboo forest, a delicate space spread out You may not feel like you are.
Each bamboo is thin, if you look closely, it may look extra thin because there are knots, especially because there are few other trees growing in the bamboo forest, so there is no comparison. However, there is a perception that bamboo is thin compared to pine and cedar, so even if you are not familiar with plants, bamboo is thin.
So, there is a perception that bamboo is delicate, or in short, if there is recognition, it means that even if there is nothing to compare, it is delicate.
However, since the recognition of human beings is when it is compared to something, the recognition that bamboo is thin is just the result of the comparison, and that recognition walks alone and becomes an absolute value standard, Using it, for example, using bamboo on the floor pillar of a Sukiya building, put something that is recognized as thin as a target to be compared, and add it later. In this case, if it is a person, it is extremely fine, such as bamboo, compared to a person However, if you think that the sukiya architecture looks more delicate because there are more people because the subtlety stands out, will the relativity determine the value at the recognition and use stage after recognition?
Then, does absolute delicacy exist and how does it exist?
Even if it is a sukiya building, it looks thin and delicate because there is an object to compare as a private house. If there is only Sukiya architecture, you may not notice the delicacy.
When thinking about the details of an architecture, eventually all of them are reduced to dimensions, but it is often the case that when measuring the famous architecture, if there is a delicate image of the architecture, the dimensions of the details of the architecture are reduced. There is no basis for trying to give subtlety to the grounds, whether the architecture should be replaced by evidence, where it belongs, where it belongs, and completely different architecture. For the architecture, the dimensions just looked delicate.
So, I did not actually measure a famous building. Of course, there was a reason other than delicacy, and the act of trying to understand a famous building numerically is essentially understanding that space of that building. I thought that the dimensions were determined in a secondary way, rather than the construction space being created with the dimensions of the press, and of course, Corbusier was of course Modroll. For example, the unite dabitacion and the La Tourette monastery stayed overnight and measured without sleeping all night, but it is still to confirm the modularity, so let's memorize the famous architecture numerically I am trying to remember it with my own sense. In this case, the sense is relative, compared to the architecture I experienced in the past, but the feeling that is accumulated in me. Becomes a thing is absolute, it comes to recognition.
You can't express delicacy if you don't have something to compare to the surroundings, but when you want to bring out delicacy, you draw out the delicacy from your past drawers. That means creating on an absolute value basis.
But in the end it becomes a different expression. Because there is nothing to compare, it does not seem to be delicate, but if the author is concerned with the sensitivity there, only the goofy thing can be done, but if it is delicate at first glance, there is nothing to compare even if expressed as absolute delicacy , It may not be recognized as delicate, it may be just thin or ugly.
However, this unpleasant thing happens even when there is something to compare. Obviously, it is thin when compared, and even when trying to make it look delicate by changing the material.
In the first place, when it is not delicate, that is, although it can express relatively delicate, if it is not absolutely delicate, it will eventually become dull and ugly. That seems to be the case, but it seems like a surprising number of cases.
After all, it is up to the author who has an absolute value standard, but since relativity is also necessary, the balance between absolute and relative, the in and out determines the delicateness, the design is what to do with that balance, the balance The designer decides the balance, and the balance is determined by the quality or level of the designer's absolute value standards.
「あるじゃん」今朝の第一声、「なんだよ」今朝の第二声、声に出した感情が今朝のはじまり、今日からまた新しいプロジェクトがはじまり、そのための段取りを1ヶ月くらい前から具体的にやりはじめた結果の今朝の声。
結構綿密に段取りして、3日前にはほぼほぼ段取りが完了し、初日の朝を迎えたはずが、人に言われて、そういえば、と思い見てみたら、在庫があり、購入する必要が無いものを一所懸命に揃え、まあ、これは新しいものを使った方が良いからと自ら慰めたのだが、さすがに数量を間違えたのには、指摘されるまで全く気付かなかったことが、指摘されたらすぐにわかるという、ここの所で記憶に無いくらいの落ち込みよう、さすがに嫌になり、ちょっと逃避行でもして気分転換するかと頭によぎったが、そうもいかず、いつも通りの行動をこなしていたら、平常には戻ったが、もうなんで間違えたかわからない。
結局、段取りが甘いということだろうが、これがまた、初日にこうことも起きるだろうというパターンに対しても、一応段取りはしており、だから、自分が落ち込んだだけで、プロジェクト自体は何も問題が無く、順調に進んだ1日だったので、そうすると、結果的には段取りの成果かなと自らに甘く、自らを慰め、これで良いだろうとした。しかし、また在庫が増えた増えた。
"Don't get depressed"
"There is" the first voice of this morning, "What 's the second voice of this morning", the emotions in the voice started this morning, a new project started again today, and the preparations for that will be done from about a month ago This morning's voice of the results I started.
It was quite carefully set up, almost 3 days ago it was almost completed, and it should have reached the morning of the first day, but people told me that if I think so, it is in stock and it is necessary to purchase I tried hard to arrange the ones that were not there, and I comforted myself because it was better to use the new ones, but I did not notice at all until I pointed out that I mistaken the quantity as expected As soon as I was pointed out, I knew that I couldn't remember this place, so I couldn't remember it. If you did, you returned to normal, but you don't know why you made a mistake.
After all, it may be that the setup is sweet, but this is also happening for the pattern that this will happen on the first day as well, so I'm just depressed and the project itself is nothing There was no problem, and it was a smooth day. So, as a result, it was sweet to myself that it was the result of the setup, and comforted myself, and I thought it would be good. But again the stock increased.
つながりの妙みたいなものがあって、決して強いつながりではないけれど、かと言って弱くもない、そんなつながりからいろいろと生まれたりする。
これは人の話で、ただネット上の話では無くて、直に触れ合う人間関係の時のみで、ネット上のつながりだと、ほんとに弱すぎて、それでもつながっているのが不思議なくらい、ところが、それが心地良い時もあるからまた不思議で、家族のような強いつながり、ネットのようなごく弱いつながり、その中間に2つくらい強さの違うつながりがあるような気がする。
今まで仕事をしたり、仕事を紹介してくれたりした人で圧倒的に多いのは、その中間くらいの強さのつながりの人で、それは人によって違うかもしれないが、最初はごく弱いつながりがはじまり、そのまま、ごく弱いままだと何も起こらないが、それが少し強くなると、もちろん、全員ではないが、仕事の話になる場合がある。
ただ、強くなり過ぎると何も起こらない。もちろん、これも人によって違うはずで、だから、仕事の場合の人とのつながりの強さはいつも気を使うところで、強くなり過ぎてはダメだと思うが、そこは難しくて苦手なところ。
"connection"
There is something strange about the connection, and it is not a strong connection, but it is not weak.
This is a story about people, not just a story on the internet, but only when people are in direct contact with each other. A connection on the internet is so weak that it is still strange that it is still connected. It is also strange because it is sometimes comfortable, and I feel that there is a strong connection like a family, a very weak connection like a net, and two connections with different strengths between them.
The overwhelming majority of people who have worked or introduced their work so far are those with intermediate strength, which may vary from person to person, but at first it is a very weak connection It starts and nothing happens if it remains very weak, but if it becomes a little stronger, of course, it may be a story about work, not everyone.
However, nothing happens when it gets too strong. Of course, this should be different from person to person, so the strength of the connection with people in the case of work is always a concern, and I think that it should not be too strong, but it is difficult and weak.
もっと早くそこを教えて、とか、はじめからそれがわかっていればな、なんて、誰にでもあるのかはわからないけれど、子供の頃から、全体を俯瞰して把握するのは苦手で、そもそも、わからないことをわかるようにすること自体が上手くできなくて、今ならば、手軽にネットを使えばわかってしまうが、その信憑性は置いておいても、その差は大きいというか、だから、それが自分でわかっていたから、設計事務所に入社した頃は、当時、パソコンもネット無い、今この目の前のわからないことに対して、どうやって答えを出せば、仕事として問題が無いのか、ばかりを考えていた。
入社して1年目位は、まだ入ったばかりだし、わからないこどが多くても、なんて言っていられるような状況ではなかったし、パンクしていた。
それがちょっとだけ楽になったのが、担当者として1つの仕事を初期段階の打合せから設計、工事監理、完成までを通しで行なった後から、よく1年目の新人を担当者にするものだなと思ったけれど、図面も、先輩が手伝ってくれて、とりあえず納めて、現場も先輩にききながら、なんとか納めて、1通りやると、つながりが見えてくる、そうすると、仕事の内容が変わっても応用が効くから、どのような内容の仕事にも対応ができるようになった。
このつながりが、わかる人にはすぐわかるらしい、それを認知力と言うのだろうが、このつながりがわからない。
どこと、どこが、こうつながるから、のどこは、それがどういうことかはよくわかるのだが、というか、調べれば誰でもわかると思うが、つながり、要するに、関係性を把握するのが苦手かもしれないと、最近また思うようになった。
で、昔習ったノートの取り方で、マインドマップをまた使いはじめた。昔は何か面倒くさいなと思ったのが、その階層構造のおかげで全体の関係性がわかりやすくなり、認知力がアップした感じで、昔面倒だなと思ったことが今はジャストフィットということは、と思いながら、スマホでマインドマップを描く日々。
"Cognitive power of connection"
I don't know if anyone can know it from the beginning, or if I knew it from the beginning, but since I was a child, I'm not good at understanding the whole, and I don't know it in the first place. I couldn't do it well, so now I can easily understand it by using the Internet, but the difference is large even if I put the credibility, so that is Because I knew it myself, when I joined the design office, I was only thinking about how to give an answer to what I didn't know right before I had no personal computer at the time. It was.
In the first year after joining the company, I had just entered, and even if there were many children I didn't understand, I wasn't in a situation to say, and I was punctured.
What made it a little easier is that after a job as a person in charge, from initial meetings to design, construction supervision, and completion, the first year's newcomer is often in charge. I thought it was, but my senior helped me, and I paid it for the time being. Can be applied to any kind of work.
Those who understand this connection seem to know it right away. This is called cognitive power, but I do not understand this connection.
Everyone knows what it is and what it is because it is connected to where and where it is, but I think anyone can understand if you examine it, but it may be weak at grasping the connection, in short, the relationship I haven't had it recently.
So I started using Mind Maps again with the notes I learned a long time ago. In the past, I thought that something was troublesome, but thanks to its hierarchical structure, the overall relationship became easier to understand, the feeling of improved cognitive power, what I thought was troublesome in the past is now just fit Thinking of a day, I draw mind maps on my smartphone.
赤いというか、今より黄色を強く感じ、もっとオレンジ色をしていたような、たぶん、気のせいかもしれない、もう40年位前の記憶だから、初めて東京タワーに行ったのは、確か、事務のおばさんに連れて行ってもらった。
天気が良い日で、青空の中に、たぶん春かな、見上げて映えるオレンジ色の格子状の鉄塔が、その頃は東京タワーより高い建物は無かったから、鮮明に残っている。
今は珍しくないというか、当たり前だが、子供の頃、高い、超高層な建物は東京タワーか霞ヶ関ビルか西新宿、まだ都庁ができる前、くらいしかなく、わざわざ見に行って、高所恐怖症なのに、展望台へ行ったりして、何だかしらないけれど、そこに行くと、神聖な気持ちになるというか、日常では見られない風景があるから、きっとそれは、ずば抜けて大きなものだから、巨大だから、自分の想像力では手に余るものだったから、惹かれたのかもしれない。
遠くから見えたりすると、そう、富士山がチラッとでも見えたりしてハッとするのと同じような感じで、気持ちがそちらに引っ張られる。
とても良い言い方をすると「崇高」かな、今、超高層ビルを見ても何とも思わないが、子供の頃は、高くて巨大というだけで価値があり、目が離せなくなるものだった。
きっとその裏には、すごい技術だな、どうやってつくるのだろうか、想像がつかない、人は想像がつかなくて、それが自分では到底できることではない時、何も考えられなくなり、無条件にそれを受け入れてしまうのかもしれない。
巨大、あるいは、すごい力感のあるものに惹かれる、子供の頃ならば良いが、もしかしたら、それはキケンなことで、ただそれだけで納得感を得てしまうのは、でも、それは日常に溢れているような気がする。
"Sublime"
It was red, or it felt more yellow than it is now, and it was more orange. Maybe it 's because I remembered about 40 years ago, so I went to Tokyo Tower for the first time. I was taken to a clerical aunt.
It was a nice day, and in the blue sky, it was probably spring, and the orange grid-like steel towers that looked up and shined still remain clear because there were no buildings higher than Tokyo Tower at that time.
It's not unusual now, but as a child, the tallest skyscraper is Tokyo Tower, Kasumigaseki Building or Nishi-Shinjuku. However, if you go to the observatory, you will not do anything, but if you go there you will feel sacred, or there is a landscape that you can not see in everyday life, so it is definitely huge and it is huge, Perhaps I was attracted because my imagination was too much for me.
If you can see it from a distance, you can see Mt. Fuji at a glance.
To put it in a very good way, it's "sublime", but now I don't think of seeing a skyscraper, but when I was a kid, it was expensive and worth it, and I could not take my eyes off.
Surely behind it, it's amazing technology, how to make it, can't imagine it, people can't imagine it, and it's not something you can do at all, you can't think of anything, unconditionally May be accepted.
It is good if you are a child, attracted to something huge or with a great sense of power, but maybe it's a quirk, but it just gets you convinced, but it's full of everyday I feel like that.
アリストテレスがね、古代の哲学者がね、物とは何ぞやと言って、自ら問いを立てて、自ら物はね、4つに分解して考えるのだよ、と言っているのですよ。
それは、物をつくるための素材と、物の形と、それをつくる人と技術、それをつくる目的だと。
物がね、どのようにしてそこにあるか、と考えたならば、素材があって、その素材を使って形をつくる、その形は、つくる目的があるから、その目的にそって、それをつくることができる技術を持った人が、それを形つくるのだけれども、古代では、なぜか、つくられた後のことはどうでもよいらしい。
古代では物は完成した時点で終わりを迎えるらしい。
それはそれで清い、物は完成した瞬間が、つくった人、この場合、つくる技術を持った人が1番満足できる状態で、1番気持ちよく、1番美しい、だから、さあ、次のことと考えられるのかもしれない。
今日行った料理屋さんで、締めに2種類のご飯と3種類のおかずの組合せ、計6種類のご飯を食べた、おかわりしたから8杯食べた。
料理も物、料理をつくる人は完成したフォトジェニックを求めているのではなく、
「いやー、そんな締めに、そんな美味しそうな物を出さないでよ、それまで散々食べたのに、呑んだのに、お腹いっぱいで入らないよ、もう」
というセリフと顔を楽しみにしているにちがいない。なんて、なんて、それにあがらい、8杯食べる、でも、まだ腹八分目。
物の終わりは消費してなくなる時、もしかしたら、消費という言葉にはあまり良いイメージはないかもしれないけれど、次の物を創作するには、今あるものを無くさないと、手放さないと、消費しないと、できないと思う、それこそ、消費より嫌いな言葉、断捨離か。
きっと古代には美味しい物が無かったのだろう、だから、アリストテレスは8杯のご飯なんて、そんなことより、「このものをこのものとしてかく有らしめているのは何か?」なんて問うて、四原因か答えはうふふ、なんて、腹の足しにもならない。
"8 cups of rice"
Aristotle, an ancient philosopher, asks what the thing is, asks himself, says that he thinks that the thing is broken down into four.
It is the material for making things, the shape of the thing, the people and technology that make it, and the purpose of making it.
If you think about how things are there, there is a material, and you use that material to make a shape. The shape has the purpose of making it. The person who has the technology that can make it forms it, but in ancient times, it seems that it doesn't matter what it was after.
In ancient times, things seem to end when they are completed.
It is clean and the moment when the product is completed, the person who made it, in this case, the person who has the skill to make it is the most satisfied, the most comfortable and the most beautiful, so it seems that Maybe.
At the restaurant we went to today, we had a combination of 2 types of rice and 3 types of side dishes, a total of 6 types of rice.
Cooking is a thing, people who make dishes are not looking for a finished photogenic,
"No, don't bring out such a tasty food to the end of it, I've eaten up until then, but I'm confused but I'm not full."
You must be looking forward to the line and the face. How, why don't you just eat it and eat 8 cups?
When the end of a thing is no longer consumed, perhaps the word "consumption" may not have a very good image, but to create the next thing, you have to lose what you have, If you don't, you think you can't do that.
Surely there were no delicious foods in the ancient times, so Aristotle said, "What is it that makes this thing like this?" The cause or answer is Ufufu.
今この瞬間を生きていることをなかなか意識できないのに、明日とか、来週の予定を考える、それは明日も来週も生きていることを意識していることになるのが何ともな話。
時代は変化するし、社会も変わるから、極端な話、過去には1日で変わった事もあったから、明日も、来週も、何も保証されていないのに、何故か、全てがこのまま、良いことも悪いことも変わらないことが前提になる。
普遍的な真理など、そうは無く、太陽は東から昇って西に沈む的な絶対的に普遍な真理など、そうは無いのに、思い込みも含めて、普遍的で本質的な事柄を追い求めてしまう。
時代性や社会性と絡めて普遍的な真理を説こうとすれば、必ずボロが出るから、そのまま放っておけばよいが、時代や社会は変化する、でも、そのようなこととは別に普遍的な法則は存在する、それが科学かもしれないし、哲学かもしれないが、必ず存在するとなると厄介だ、どう考えても、時代によって科学も哲学も変化してきたと思うし、対象を分析することには変わりが無いが、分析結果は常に時代や社会を反映してしまい、変化してきたと思うが、だから、あるのはポジショニングで、どの立場を取るのかを選択するだけだと思うのだが。
もし、そうならば、論理よりも実践が大事で、その立場において、どのように実践して、どのような結果になったのかだけが重要ということになると思うのだが、そう論理は必要だが、実践の手段にすぎない。
なかなか社会や時代の枠組みが定まりにくい現代だけれども、それでもモデルを仮定して、枠組みを定めれば、社会的な問題も浮き彫りになり、その解決策がその時代の論理であり、実践の手段、ただ、モデルは常に変化するのではないか、そう考えると、この時代や社会を根底から成立させている本質的で普遍的なことなど無いことになるのだが、あるとしたら思い込みか。
"Logic and Practice"
Even though I am not conscious of being alive at this moment, I am thinking of tomorrow or next week's schedule, and that is conscious of being alive tomorrow and next week.
Because times have changed, societies have changed, extreme talks, and in the past, things have changed in a day, so tomorrow and next week, nothing is guaranteed, but why everything is as it is The premise is that things will not change.
There is no such thing as a universal truth, but there is no such thing as an absolute universal truth that the sun rises from the east and sinks into the west, but it pursues universal and essential things, including assumptions. End up.
If you try to explain universal truths in relation to the times and societies, you will always get out of touch, so you can leave them as they are, but the times and societies will change, but apart from that, universal There is a general law, it may be science, it may be philosophy, but it will be troublesome if it always exists. I think that both science and philosophy have changed with the times, and to analyze the object Although there is no change, I think that the results of analysis have always changed, reflecting the times and society, so I think that there is only a choice of the position to be taken in positioning.
If so, I think that practice is more important than logic, and in that position, I think that it is only important how it is practiced and what kind of result is achieved, but such logic is necessary, It is only a means of practice.
Although it is difficult to determine the framework of society and the times, it is still difficult to determine the framework, and if the framework is defined, social issues will be highlighted, and the solution is the logic of that era, the means of practice, However, if the model is constantly changing, there will be no essential and universal things that have fundamentally established this era and society.
日常の何でもない、ごくありふれた、いつも行っていることがちょっとだけ、単純なことをしただけで、何かよくなって、そうしたら、今までとは、たったこれだけのことで、違った感情になったり、違った気分になったり、違った風景が見えたりして、日常が豊かになる、あくまでも日常の中の出来事が大事というか、非日常をつくりだすのは案外たやすいことで、ただ、その中にずっとはいられないし、非日常は楽しいかもしれないけれど、本当に満足したい場所は日常の中にあるのでは、日常の中にしかないのでは、で、これは氷山の一角であり、それを実現するための裾野は海面の下にあり、そこは日常からは見えないし、見せないが、そこには様々な技術や様々な考えがあり、それを磨きつつ、実践と論理のせめぎ合いをし、そのバランスにいつも気を使い、複雑で絡まったならば、解き、単純にわかりやすく、誰にでもすぐに理解できる論理を構築し、実践へと進むようなイメージでいつもものづくりをしている。
で結果、出来上がった物に対して相手が、この場合、相手は不特定多数の場合もあるし、個人の場合もあるが、愛着を持ってくれるのか、共感をしてくれるのかが大事で、それは物としての対外的な評価よりも上回り、相手が愛着を持ち、共感をしてくれたならば、それがつくる側から言えば、極上の喜びになる。
ポリシーについて考える機会があったので、今までと現在進行形の仕事を俯瞰して、そこから共通して言えることだけを抽出し、まとめてみたら、その時々は、その場面場面に合わせて、結構いろいろと考えているのに、普段自分が何気なく自分のためにしようとしていることだった。
"What is a policy?"
Everything you do in everyday life, something that is common, just doing something simple, just doing something simple, something better, and then you're just feeling this different feeling It makes you feel different, feel different scenery, enrich your daily life, it's easy to create an extraordinary life, or it's unexpected. I can't stay in it for a long time, and the extraordinary life may be fun, but the place I really want to be satisfied is in the daily life, only in the daily life, so this is the tip of the iceberg, The base for realizing it is under the sea surface, which is not visible or visible from everyday life, but there are various technologies and various ideas, and while practicing it, it is a struggle between practice and logic. ,That Lance to always use care, if tangled complex, solved, simply understandable, who built a logic that can be immediately understood even in, are always making things in images, such as the process goes to practice.
As a result, the other party may be unspecified number of people or individuals, but it is important whether you have attachment or sympathy. That exceeds the external evaluation as a thing, and if the other party has attachment and sympathy, it will be the supreme pleasure from the side of the creation.
I had an opportunity to think about the policy, so I looked down on the current and ongoing work, extracted only what I could say in common, and put it together. Even though I was thinking a lot, I was casually trying to do it for myself.
「流れるプール」と一声かかると一斉に同じ方向に動き出す群れ、そのうち、水の流れができて、その流れが全身に纏わりつき、その流れがある間は、流れのままに流されていく、泳げなかった自分はその時だけ泳げたような気分になり、中学になり泳げるになったのも、その時の感覚を身体が覚えていたから。
よく思い出すことで、一旦流れができてしまえば、あとはそれに乗るだけ、だけど、1人では流れができないから、はて、どうしたものかと。これは他人を巻き込んだり、何かを利用したりすれば、流れができるが、自分で動き出し、継続しなければいけなかいから、この場合、流れを習慣と言い換えてみて、他の言葉でも良いけれど、それが、流れができるまでの間で、止めてしまい流れができないことがよくある。
一旦流れができてしまえば、もう何も意識して動く必要が無いから、流れができるまでの我慢と思っても、我慢と思った瞬間に続かなくなるから、それは自分だけかもしれないけれど、きちんとした大人は我慢するのだろうが、だから、我慢しないでできることだけ、我慢と思ったら止めて、我慢しないやり方を考えて、そうすると、なかなか進まない、片付かないが、一旦我慢しないでできるようになると、それが習慣になり、例え、その習慣を後に止めたり、変えたりしても、その習慣になるまでの考え方や感覚は共有できるかなと思い、流れをつくるために、本当は動くのは好きではないのだけれども、その時点で我慢だから、流れができるまではいつも我慢とのせめぎ合い。
なんて、片付かない部屋を見て、あれこれ考えて、片付け本読んで利用しようとしても、だから、最近は究極の片付けを、もう片付けない、にしようかと、その時間で他のことをするという流れをつくろうかと、あとは片付かない部屋に我慢しないで済むかどうか。
"I can not stand it"
Swarms that start to move in the same direction when you say a `` flowing pool '', of which water flows, the flow gathers all over the body, and while it is flowing, it keeps flowing while flowing, swim I did not feel like I was able to swim only at that time, and I became junior high school so I could swim because my body remembered the feeling at that time.
Remember, once you have a flow, you can just ride it, but you can't do it alone. This can flow if you involve other people or use something, but you have to move and continue on your own, so in this case, try to rephrase the flow as a habit and use other words. Often, it stops and cannot flow until it can flow.
Once the flow has been made, there is no need to move consciously anymore, so even if it is patience until the flow is made, it will not continue to the moment when it was thought, so it may be only myself, but it is Adults will endure, but only stop what you can do without patience, stop if you think patience, think about how to endure, and then do not progress, do not clear up, but once you can do without patience , It becomes a habit, even if you stop or change the habit later, I think I can share the way of thinking and feeling until it becomes habit, and I do not really like to move to create a flow However, because I am patient at that time, I always fight with patience until I can flow.
How about looking at a room that is not cleaned up, thinking about everything, reading and using a cleanup book, so recently, the flow of doing other things at that time, whether to make the ultimate cleanup no longer cleanup Whether to make it or not to put up with a room that doesn't get cleaned up.
7年経つとさすがに人は変わるだろうか、7年前から今でも続いていることがもちろんあるけれど、その何倍も、7年前にはしていた、あったことが今は無い。
それが当たり前かもしれないが、逆に7年前と全てが同じだっだら、そちらの方がおかしいというか、それは進歩も退歩も無いことで、実際、肉体は変わるから、成長か老化かが、それだけで必ず変化があるはず、それに本人が気づいていない、周りは案外変わったな、なんて思っていて、老けたなんて、でも中身は変わらないな、とか。
建築は完成した段階から、成長と老化が同時にはじまる。完成した時はまだ、借り物の服を着ているような、自分たちに馴染んでいない、人に例えると、赤ん坊、それが住んでいくと、段々と自分たちの生活色に染まって、完成した当時の建築に彩りが加わる、それが成長。
ところが、建築を物としてみた場合、完成した当時が1番綺麗で、段々と劣化していく、劣化のスピードは物の材質によるが、劣化するのは止められない、これが老化。
ただ、劣化が上手くできれば味になり、完成した当時の建築に彩りと、さらに味が加わり、完成した当時の建築よりも良くなる、本来内在していたポテンシャルが解放されたような、建築として成熟した姿は実に素晴らしく、完成した当時よりも、少し年月を重ねた方が良い、というか、そうなるように設計している。
今、7年前に完成した住宅に関わっている。完成した当時赤ん坊だったお子さんが小学生になり、兄妹で使用していた部屋に間仕切壁をつくり、部屋を分ける工事、同時に劣化した部分を修復する。
人と建築の成長がシンクロし、7年経って彩りと味が加わった姿を見ているのは何とも楽しいもので、今回をきっかけに久しぶりにお会いする人もいて、見た目が変わってもあいかわらずだな、なんて内心お互い思いながら、また仕事をするようになるかもしれず、それはそれで、進歩だか退歩だか現状維持だかはわからないが、そういうこととは違う尺度でものづくりができていることが、7年前とは1番違うことかもしれない。
"7 years ago and now"
People will change over the course of 7 years, but of course there are things that have continued since 7 years ago, but many times that has been done 7 years ago.
It may be natural, but conversely, if everything is the same as 7 years ago, it is stranger, that is, there is no progress or retreat, in fact the body changes, whether it is growth or aging, There should be a change, and the person himself / herself is unaware of it, the surroundings have changed unexpectedly, and they think they are old, but the contents are not changed.
From the stage of construction completion, growth and aging begin at the same time. When it is completed, it is still unfamiliar to them, such as wearing clothes for rent, like a baby, when it lives, it is dyed gradually to their life color and completed Color is added to the architecture at that time, and it grows.
However, when looking at architecture as an object, it was the most beautiful when it was completed, and gradually deteriorated. The speed of deterioration depends on the material of the object, but the deterioration cannot be stopped.
However, if the deterioration can be made well, it will become a taste, and it will be colored, and the taste will be added, and the taste will be added, and it will be better than the architecture at the time when it was completed. The appearance is really wonderful, and it is better to spend a little more time than when it was completed.
I am involved in a house that was completed seven years ago. The child, who was a baby at the time of completion, becomes an elementary school student, creates a partition wall in the room used by his brother and sister, works to divide the room, and simultaneously repairs the deteriorated part.
It's a lot of fun to see the growth of people and architecture synchronize, and the addition of color and taste after seven years. Some people have met for the first time in a while after this time, even if the appearance changes I think I may start working again while thinking inside my heart, and I don't know if it's progressing, stepping back, or maintaining the status quo, but it's been 7 years that we have been able to make things on a different scale. It may be the most different from the previous one.
子供の頃から4色ボールペンをよく使っていて、いつからか、たぶん、中学くらいからか、使いはじめたのは、アンダーラインを引くために、色分けして、周りも結構使っていて、なぜかレポート提出で、色にもマイルールがあり、赤は重要、青は最重要、緑は余談、黒は普通としていて、人に聞くとやはりその人なりのルールがあって運用しているようだった。
前に、3色ボールペンを使った読書法の本が出版された時、パラパラと見て、同じと思い、前から本にも4色で、爪痕を残すような感じで、4色以外にも大事なページには付箋紙を貼り、その付箋紙も4色にし、ただ黒の代わりに黄で、黄の意味は青より重要な時、あとページの角を折ったり、その本を読み解くためにしていたのだが、本はノート、という教えも聞いたことがあったので、紙の本にいろいろしていた。
ただ、それは手段で、目的は本やノートの内容を頭に入れることなのに、4色を使い分けることがいつしか目的になっており、それはノートも同じで、いつしかノートを取ることが目的になっていた。
それに気づいたのは、今年になって手書きのノートを止めて、全てiPad にApple Pencilで記述するようになってから。やっていることは手書きのノートと変わらないけれど、デジタルノートには自分で制御できないルールがあり、例えば、色を変えるにも、その操作法は決められていで、手書きならば、ある程度自由に、4色ボールペンを使おうが、色鉛筆を使おうが、マーカーでも選べて、その使い方、運用の仕方も自分しだいだが、その不自由さが、それが手段ならば、そこまで感じないだろうが、目的だからとても不自由に感じた。
では止めればいい、デジタルノートを、と思うかもしれないが、同期していろいろなデバイスで見ることができ、修正も同期により反映できると、繰り返し見たりするのが便利になり、より頭に入りやすく、そのために4色を使い分けていたと、繰り返し見ないと頭に入らないと、認知の問題だけれども、それは手段だと再認識するためにデジタルノートにしたような状況に。
"4 colors"
I have been using four-color ballpoint pens a lot since I was a kid, and I started using them sometime, perhaps from junior high school. In the submission, there are also my rules in color, red is important, blue is the most important, green is a digression, black is normal, and when you ask people, it seems that they have their own rules and they are operating .
Before, when a book on reading methods using a three-color ballpoint pen was published, I thought that it was the same as a flip book, with four colors on the book from the front, feeling like leaving a nail mark, other than four colors Place sticky notes on important pages, and make the sticky notes four colors, just yellow instead of black, and when the meaning of yellow is more important than blue, you can fold the corner of the page or read the book I had heard that the book was a notebook, so I used it as a paper book.
However, it was a means, and the purpose was to put the contents of books and notebooks in mind, but the purpose was to use the four colors differently.
I noticed that this year, I stopped writing notes and started writing everything in Apple Pencil on the iPad. What you are doing is not different from handwritten notes, but digital notes have rules that you cannot control yourself, for example, even if you change the color, the operation method is decided, and if you are handwritten, you can freely to some extent, Whether you use a 4-color ballpoint pen or a colored pencil, you can choose a marker, and how you use it, how you use it, but you can't feel that inconvenience if it is a means. I felt very inconvenient.
You may think that you should stop, but you can think of digital notes, but if you can see them on various devices in sync, and you can also reflect your corrections in sync, it will be convenient to see them repeatedly, and it will be more clever. It was easy, and if you used the four colors properly, it would be a problem of cognition if you didn't come to mind unless you look at it repeatedly.
最近、時間が長く感じる。時間があっという間に過ぎるのは、楽しいことをしていたり、自分が好きなことをしている時にそうなるか、あとは、焦っていたりする時で、長く感じるのはつまらない時や、ただ、何かに没頭している時には2通りあるような気がする。
時間が、気がついたら、いつのまにかすごく経っていた、あるいは、集中して没頭して何かをして、かなりの量をこなしたのに、大して時間が掛からなかった、の2通りで、時間が進むスピード感が早いか遅いか。
実際に、時間の進むスピードが変わることは無いので、そう感じるだけだが、できれば、時間の進むスピードが遅く、時間が長く感じられる方が良く、ただ、つまらないのは嫌だな、となると、どうやって時間を使えば、スピードが遅く、時間が長く感じられるのかと考えてみたら、自分が好きなことや、やりたいことをたくさん用意し、制限時間を決めて、たくさんこなしてみると、好きなことをしているから、時間が早く経つような気がするけれども、制限時間より多くの時間を使うことが無く、それでいて、好きことをたくさんできるので良いのでは。
結局、好きことを効率良くたくさんやれば、時間を長くゆっくり使える感じになる、というなんか当たり前のことに落ち着いた。
"Long and slow"
Recently I feel that time is long. Time passes quickly when you are doing fun things, when you are doing what you like, or when you are impatient, and when it feels boring for a long time, just When I'm immersed in something, I feel that there are two ways.
When I noticed the time, I went through a lot of time, or I was focused and absorbed, did something, did a lot, but it didn't take much time. Is it fast or slow?
Actually, the speed of time does not change, so it just feels like that, but if possible, it is better that the speed of time is slow and it feels longer, but I don't want to be boring. If you think that if you use time, the speed is slow and you feel that time is long, prepare a lot of things you like and want to do, decide the time limit and do a lot, what you like I feel like it's going to be early, but I don't spend more time than the time limit, and I can do many things I like.
In the end, I settled on the natural idea that if I did a lot of things I liked efficiently, I felt that I could use my time slowly and slowly.
道具の話ですが、道具に何を求めるか、やはり、その道具を使うことによって、自分がどうなるか、を求めてしまう。
求めるものは2つで、どちらかが満たされていれば、その道具を使います。それは、自分の気分を高揚させてくれるものか、自分の時間をつくり出してくれるもの。
気分を高揚させてくれるものは人によって違うでしょうから、ただ、なかなか無いので、この時にとりあえずは無し、見つからないからとか、面倒だからとか、この程度でいいやは無し、その程度のものしかできません、その道具では。その道具を使いながら、自分の気分が高揚したら、そんな楽しい時間はないし、きっと良い時間になるでしょ。
例えば、車を移動するための道具だとしたら、動けば何でも良いよりは、気に入ったものに、ただ移動するだけで気分が高揚したら、それだけで素晴らしい時間に。
よく聞く話で、1日24時間は誰でも一緒、同じ、だから、自分の時間をつくり出してくれる道具は有り難い。例えば、ルンバ、掃除から解放されて、他のことをする時間をつくってくれる、ただ、うちのルンバは古いのか、家具に結構強く当たる、それが、家具は収納道具なので、お気に入りの家具しか置きたくないので、それにガンガン当たるのは、最新のものはそんなことはないのでしょうか。
もう模型つくりから解放されて、何でも自分でやりたいので、ただ、模型をつくる時間があったら、その分、プロジェクトを深める時間に使いたい、3Dプリンタがフル稼動です。
最初のスタディ模型はバリエーションを多く、とにかくたくさんつくりたいので、3Dプリンタで模型をつくっている間に、前の模型を検討し、新たな模型作成用データをつくり、模型ができあがってきたら、またそのデータを3Dプリンタにかけ、できあがった模型をまた検討し、新たにまた模型作成用データをつくる、これの繰り返しができるのが心地よく、楽しい時間。
そう考えると、どちらも、つくり出すのはもちろん、高揚させるのも、道具というのは時間を扱うものだと改めて思う。
"Time with tools"
It's a story about tools, but what you want from a tool is what you want to do by using that tool.
There are two things you want, and if either is satisfied, use that tool. It's something that raises your mood or creates your own time.
The things that make you feel uplifted will vary from person to person, so there aren't many, so at this time there is nothing for the time being, it can not be found, it is troublesome, this level is okay, there is only that level With that tool. If you feel better while using these tools, you will not have such a good time and it will be a good time.
For example, if it 's a tool for moving a car, it 's a great time if you just move and feel better than just moving.
The story I often hear is that everyone is the same 24 hours a day, so I appreciate a tool that can create my time. For example, rumba frees you from cleaning and takes time to do other things, but your rumba is old or hits the furniture quite a bit, because it is a storage tool, so you only place your favorite furniture I don't want it, so isn't the latest one that hits it?
Now that I'm free from modeling, I want to do everything myself, so if I have time to make a model, the 3D printer that I want to use to deepen my project is fully operational.
The first study model has many variations, and I want to make a lot anyway. So, while making a model with a 3D printer, consider the previous model, create new model creation data, and when the model is completed, It is a pleasant and fun time to repeat the process of applying the data to a 3D printer, examining the completed model again, and creating new model creation data.
When thinking so, I think again that both tools are not only made up, but also uplifting, tools are things that deal with time.
『全体と部分』
大きな視点から、その一点を見ると、相互の位置関係や様子がわかりやすく、大体、どの辺にいるのかがわかりやすいが、その一点から大きな視点を見ようとすると、そもそも全体像が把握できないから、その一点が全てであるような錯覚にとらわれることがある。
最近、知りたいことがあり、2つの講習を受けてみた。どちらの講習も、受講者同士のディスカッションの時間があったり、質問を元に講習が進めらたりと、話し手と受け手という関係性だけでは無い講習の形をとっていた。
ただ、受講者の知識にレベル差があるから、その差を埋めなかければ、ディスカッションは成り立たないし、質問も噛み合わない。そのため、片方の講習は受講前に、事前動画と称して、基礎的な知識を習得するための動画を自ら前もって見て、アウトプットをすることが要求され、そのアウトプットが参加証代わりになっていて、実際の講習では、最初から質問ではじまり、質問に答える形で講習が進む。
もう片方は講習の中で基礎的な知識を網羅して、それを受けてディスカッションし、自ら行いたいことを明確にしていく。
どちらの講習も、基礎的な知識の全体像を把握してから進むのは同じだが、片方は事前動画を別の日に自ら前もって見るから、講習当日の質問は、どうしても事前動画の内容とはあまり関係が無いというか、今その時の自分の問題にだけ収斂して、質問内容だけが独り歩きし、それが全体を表しているかのような錯覚におちいる。
もう片方はその場での基礎的な知識を網羅してから、自らの考えをまとめるので、全体の中での立ち位置が理解しやすく、より正確に何をするべきかがわかる。
どちらの講習のやり方が良いか、というのは無いとは思うし、目的によって使い分ければ良いと思うが、実際に、講習の内容が記憶に残り続け、忘れないのは、事前動画を見た方で、講習が完結するまで長い時間がかかり、それなのに、講習当日は全体性が無い質問ばかりで、事前動画を想起しながら質問や回答を理解しなければならず、それが頭に残るのだろう。
"Whole and part"
If you look at one point from a large viewpoint, it is easy to understand the mutual positional relationship and appearance, and it is easy to understand which side you are in, but if you try to look at a large viewpoint from that one point, you cannot grasp the whole picture in the first place. You may be caught in the illusion that one point is everything.
Recently, there was something I wanted to know and I took two courses. Both courses took the form of courses that were not just about the relationship between the speaker and the receiver, such as having time for discussion between students, or proceeding with the course based on questions.
However, since there is a difference in the level of knowledge of the students, if the difference is not filled, the discussion will not be possible and the questions will not engage. Therefore, before taking the course, one class is called a pre-video, and it is required to look at the video to acquire basic knowledge in advance and output it. In the actual course, the course starts from the beginning and answers the questions.
The other covers the basic knowledge in the course, discusses it, and clarifies what you want to do.
In both classes, it is the same to proceed after grasping the whole picture of basic knowledge, but one side sees the advance video in advance on another day, so the question on the day of the course is inevitably the content of the advance video It seems that there is not much relation, or it converges only on my problem at that time, and only the content of the question walks alone, and it feels as if it represents the whole.
The other side covers basic knowledge on the spot and then summarizes its thoughts, so it is easy to understand the standing position in the whole and know what to do more accurately.
I don't think there's a better way to do the course, and I think it's better to use it properly depending on the purpose. On the other hand, it takes a long time to complete the course, but on the day of the course, there are only incomplete questions, and you have to understand the questions and answers while recalling the pre-video, which remains in mind Let's go.
この世界には質料は無限にあるように思えるし、思ってしまうのだけれども、いざ建築の世界になると、それが、質料が極端に限定される。
それは建築の規模が大きく、その大きさ故に社会的な影響が大きいから、むやみに使えない、耐久性だけでなく、耐火・防火性も必要だし、やはり、経済性が、経済性以外は、性能的な問題になる、たがら、使えるか使えないかは、必要とされる性能で決まるが、経済性は一概に線引きできない。
経済性を持ち出してくれば、それは、お金がある人が得をして、お金がない人はそれなり、という構図が元になるが、そこにデザイン性を絡めると、ちと複雑になる。
料理に例えると、質料は料理の素材になる。良い素材を使えば、料理は美味しくなり、悪い素材を使えば、料理は不味くなる、これは当たり前、誰が料理をしようとも、悪い素材、それは例えば、腐った素材は誰が料理しても不味くなる。
では、値段が高い素材を使えば、料理は美味しくなり、値段が安い素材を使えば、料理は不味くなるのだろうか。そんなことはない、この場合、デザイン性とは料理人の技量であり、素材をどのように料理するか、料理人しだいで、値段が安い素材でも美味しくなるし、値段が高い素材でも不味くなる。
それは建築でも同じであり、経済性に唯一抵抗できる手段がデザイン性で、建築の素材の値段が高いからと言って良い建築になる訳では無く、値段が安いからと言って悪い建築になる訳でも無く、そこはデザインしだいでどうにでもなる余地があるから、建築家は頑張る。
しかし、性能で決まることははっきりと線引きされ、その線引きを乗り越えることもできるが、そこではまた経済性が必要とされ、デザイン性だけでは乗り越えることができない。
だから、建築の世界になると、質料が極端に限定される、だから、建築は経済性から逃れられない。この構図に建築家は無力であり、関われないが、それでも新しい建築は生まれるのだから、デザイン性に可能性を感じる、もしかしたら、経済性に余地があるのかもしれない、ちがう見方を試みてみようか。
"Economics of quality materials"
There seems to be an infinite amount of quality fees in this world, and I think, but when it comes to the world of architecture, it is extremely limited.
Because it is a large-scale building and its social impact is large, it can not be used unnecessarily, it needs not only durability but also fire resistance and fire resistance. Whether it can be used or not is determined by the required performance, but the economics cannot be drawn.
If you bring out economics, it is based on the composition that people who have money will get profits and people who do not have money will do it.
If you compare it to cooking, the quality is the material of cooking. If you use good ingredients, your dishes will be delicious. If you use bad ingredients, your dishes will be bad. This is no matter who you cook, bad ingredients, for example, rotten ingredients will be bad for anyone.
So, if you use high-priced materials, the dishes will be delicious, and if you use low-priced materials, the dishes will be delicious. In this case, design is the skill of the chef, depending on how the ingredients are cooked, and the chef, depending on the chef.
It is the same in architecture, and the only way to resist economics is design, not because the price of architectural materials is high, but not because it is good, but because it is cheap, it becomes bad. But there is room for it to be designed, so the architects do their best.
However, what is determined by performance is clearly delineated and can be overcome, but there is also a need for economy, and design alone cannot be overcome.
So, in the world of architecture, quality fees are extremely limited, so architecture cannot escape from economics. Architects are powerless and uninvolved in this composition, but new architecture is still born, so you can feel the possibility of design, maybe there is room for economy, try a different view Or?
そっと口をつけても熱くない、この季節、エアコンをつけない室内に置いてあるだけでも、何でも熱くなり、陶磁器でも、何も注いでいないのに熱い。
手で触るもの、口につけるもの、その手触り、口の感触、そこまで、どうしようかな、この触り心地、触れるだけで心地よい、など、今の季節だと、冷んやりしているとありがたい。
感触の中でも、温度には、案外気がつかないうちに敏感になる。きっと触り心地より、まず温度で判断して、不思議なもので、肌にかかったら大火傷をするような熱湯でも、口の中に、冷ましながらだが、入れることができてしまう。
だから、案外、温度に対しては、無意識に反応して、対応するから、その温度について鈍感になるというか、いちいち気に止めることがない、しかし、冷ましながら、とかしている訳だから、何らかの影響を人に与えていて、料理では、その温度や温度差が美味しさのうちというのは当たり前なのに、それを入れる器は温度に鈍感で、器に接触するものの温度をそのまま伝えるしか能がなく、温度を全く持って器自身のデザインに生かせていない。
その温度と人を媒介するのが器なのに、器はただボーっとしているだけ、そこに一工夫、そこにデザインが関与すれば、その体験がより素晴らしくなるのでは。
だから、飲み口の厚みを変えてみた、温度に器が対応するように、人の好みや気分によって飲み口の位置を変える、そうすると、器の形も変わって見える、いつでも、毎日、気分で。
温度をデザインに取り入れたかった、そのためには熱湯を注いでも、程良く、人肌くらいの温度になる器でないと、熱くて持てない器では、そもそも温度をデザインに取り入れた使いこなしができない、それでいて、まるで口づけをしているような感触が欲しかった。
それが唯一できる素材は、陶磁器ではない、硝子の器でもない、もちろん金属の器でもない、漆器だけだった。まだ漆塗のサンプルができあがってこない、木地を眺めながら、納める箱をデザインしている。
"The vessel that can do that"
It's not hot even if you put your mouth softly. Even if it's left in a room without an air conditioner this season, everything will be hot, and even if it's ceramic, it's still hot.
I feel grateful that it is cool in this season, such as touching by hand, touching by mouth, touching by touch, touching by mouth, how to do it, this touching comfort, just touching.
Even in the touch, it becomes sensitive to the temperature without notice. Surely, it's a strange thing to touch, rather than touch, so even hot water that can cause severe burns when applied to the skin can be put into the mouth, although it cools.
So, unexpectedly, it reacts unconsciously to the temperature and responds, so it will not be insensitive about that temperature, but it will not stop at all, but because it is cooling down, it has some influence In cooking, it is natural that the temperature and temperature difference are delicious, but the vessel that puts it in is insensitive to temperature, and it can only communicate the temperature of what touches the vessel as it is, It has no temperature and is not used in the design of the vessel itself.
Even though it is a vessel that mediates the temperature and the person, the vessel is just a buzz, but if it is devised there and the design is involved there, the experience will be more wonderful.
So, when I changed the thickness of the mouth, I changed the position of the mouth according to the taste and mood of the person so that the container responded to the temperature, and then the shape of the container changed, every day, every day.
I wanted to incorporate the temperature into the design.To that end, even if I poured hot water, it was not a device that would be moderately warmer than human skin. I wanted the feeling of kissing.
The only material that could do that was lacquerware, not ceramic, glass, or of course, metal. I am designing a box to put in a lacquered sample while looking at the wood.
誤魔化していると、それなりに満足感が得られるから、ついつい同じことを繰り返し、それがクセになり、今度は誤魔化している自覚さえも、そもそも誤魔化していると思っていないから、それで満足感が得られるから、ドーピングをしているようなもの、結果に満足してしまうと、それが大事か誤魔化しているのか、脳はそこまで区別できないらしい、だから、自己暗示もできるし、誤魔化しも止められなくなり、何とか欲は、例えば、物欲や食欲や性欲などは、誤魔化す元をオブラートに包んでいるだけで、今が一番大事、がキーワードらしい。
一昨年、福井の永平寺で少しだけ坐禅体験をした。永平寺は曹洞宗の大本山であり、曹洞宗の坐禅は壁に向かって行うのたが、雲水と呼ばれる修行僧が行う坐禅の真似事を、そこだけ、まるで、パラシュートでいきなり中心地に降り立つような感じでやってみた。
それは、大阪から北陸へ行く用事があり、途中の福井で下車し、日本酒の黒龍を楽しんだ翌朝の出来事、前々から、永平寺で坐禅修行をしたい希望があったが、その時の季節は真冬、たまたま大雪が降った直後、とりあえず、早朝に向かったが、驚くほど移動手段が限られ、結局坐禅の時間に僧堂にいたのは私一人だけ、案内役の雲水さんとマンツーマン、座るだけのためにここまで来たかと思うと、とても貴重な時間に思えたが、坐禅をしながら、なぜここにいるのか、と考えていたことも思い出した。
別に、その時に答えが出た訳ではないが、何か一枚一枚剥ぎ取り、その時はすでに誤魔化すのが上手くなっていたから、欲が身体の外へ出ていくような感じがした。
ほんとは誤魔化さない方が良いのに誤魔化すのは、ほんとは食べてはいけないのに食べるようなもので、その方が気持ち良く、満足してしまうからだが、その満足感が虚しいと思いはじめていた時の坐禅は、静寂で誤魔化しようが無い、誤魔化すことができない張り詰めた空気を感じるための時間だったような気がする、おかさまで。
"I can't be deceived"
If you are deceived, you will get satisfaction as it is, so you repeat the same thing, it becomes a habit, and even now, even the awareness of being deceived does not think that you are deceiving in the first place, so you get satisfaction So, if you are satisfied with the result of doping, or if you are satisfied with the result, it seems that the brain can not distinguish so much whether it is important or misleading, so you can also suggest self-implied and it will not stop Somehow, for example, greed, appetite, sexual desire, etc. are the keywords that are the most important now, just by wrapping the elements that become deceptive in oblates.
Last year, I had a little zazen experience at Eiheiji Temple in Fukui. Eiheiji Temple is the main head of the Soto sect, and the zazen of the Soto sect is directed toward the wall, but the imitation of the zazen performed by a monk called Unsui is just like a parachute and suddenly descends to the center. I tried it.
There was a business going from Osaka to Hokuriku, getting off at Fukui on the way, enjoying the sake dragon of the next morning, there was a hope to practice Zazen at Eiheiji Temple, but the season at that time was midwinter, Immediately after the heavy snowfall, I headed early in the morning, but surprisingly the means of transportation were limited, and I was the only one who was in the monastery at the time of zazen, as a guide, Unsui-san and one-on-one, just to sit It seemed like a precious time when I came here, but I also remembered why I was here while doing zazen.
Apart from that, I didn't get an answer at that time, but I felt like my greed was going out of my body because I had already peeled something off one by one and at that time I was already good at becoming a demon.
It's better not to be deceptive, but it's like eating when you really shouldn't eat it, because it makes you feel more comfortable and satisfied, but when you start thinking that the satisfaction is empty Zazen is quiet and can't be deceived, it feels like it was time to feel the tight air that can't be deceived.
おわぁ、何、何、これ、ちょっと間があって、わかった新聞の切り抜き、Amazonで古書を購入したら挟まっていた。
昭和61年の切り抜き、この本の初版が昭和60年だから、新品で購入した前の所有者が挟み、そのまま、装丁も綺麗なので、本棚にあったか、書店にあったか、黄ばんではいるが、のり掛けしたようにピシッとした紙面、天声人語だから、朝日新聞か、そう言えば昔、毎日、天声人語を読まさられたことを、なぜか辛い思い出。
同じ本で、紙か電子かを選べるならば、必ず電子書籍を選ぶ、紙の書籍を購入する時は電子版が無いから仕方がない時で、知り合いの作家さんならば別だけれども、好んで紙の書籍を収集するような、全集を欲しがるような趣味は元々無いので、すぐに携帯で読めて、すぐに知りたい内容がわかり、どこへでも何冊でも持ち歩けて、見たい時にどこでも見られるから、いつでも読み返したい本や重要な内容の本や建築雑誌、座右の書なんてもう一冊購入して、背表紙を裁断し、自らスキャンしてでも、携帯に取り込んで持ち歩いている。
昔は本の間に新聞の切り抜き、その本が掲載されていた新聞広告を切り抜いて書店で探したりして、それを栞がわりに、昔はAmazonどころかネットすらない訳だから、もしかしたら、その当時の切り抜きがうちの書棚の本にもあるかもしれない。
この感覚、前の所有者はこの本を大事だと思っていたのかもしれない、切り抜きも几帳面に挟んである、内容ももちろん大事だが、本は単なる印刷物を超えて、本自体を大事にする感覚が昔はあった、今でもあるだろうが、紙としての実体の無い方が都合が良く、寿命の短い本が多くなってしまった。
単なるデータ、単なる文字情報の集合体が本と言えばそれまでだが、執筆途中はそれこそ今はデータだが、昔の作家の原稿が売られていたり、旧家の蔵から昔の原稿用紙が出て来たりなど聞くと、建築でも今は図面はデータだが、昔の手書きの図面が美術館の収蔵品になっているくらい、制作途中にも作家の痕跡があり、その痕跡自体が作品の一部であり、それが感じられたから、本を、紙の本を所有する喜びもあったのかもしれない。
断捨離なんて言わずに、一度大事にした本は一生持っていたいものだ、紙の本として、それが生きる喜びだと思う。
"An important book"
Wow, what, what, this was a little bit, I found out a newspaper clipping, and I got stuck when I bought an old book on Amazon.
The cut-out of 1986, the first edition of this book was 1985, so the owner before buying it with a new one was sandwiched, and the binding was also beautiful, so it was on the bookshelf, in the bookstore, it was yellow, but it was glued Because it 's so crisp, the Asahi Shimbun, the Asahi Shimbun, or so to speak, once a day, every day, I read the Tenshin Mandoku for a long time.
If you can choose between paper and electronic for the same book, be sure to choose an electronic book. When you buy a paper book, there is no way because there is no electronic version. There are no hobbies like collecting paper books or wanting the whole collection, so you can read it right away on your mobile phone, know what you want to know, take it with you wherever you want it, and take it anywhere you want to see it. Because I can see it, I buy another book I want to read back at any time, a book with important contents, an architectural magazine, and a book on the right, cut the back cover, scan it myself, and carry it on my phone.
I used to cut out newspapers between books, cut out newspaper advertisements where the books were published, and look for them in bookstores. There may also be a cutout in my bookcase book.
This feeling, the previous owner may have thought this book is important, the clipping is sandwiched between notebooks, the content is of course important, but the book goes beyond mere printed matter and takes care of the book itself Although there was a sense in the past, it will still exist, but it is more convenient to have no physical substance as paper, and there are many books with short lives.
Speaking of books, a collection of mere data and simple text information is up to that point, but in the middle of writing it is now data, but old writers of old authors are sold, old manuscript papers come out from old storehouses When you ask, the drawings are now data even in architecture, but there are traces of the artist in the middle of the production so that old handwritten drawings are a collection of museums, and the traces themselves are part of the work Yes, it may have been a pleasure to own a book, a paper book because it was felt.
I don't say that I don't want to divide the book, but once I have cherished it, I want to have it for a lifetime. As a paper book, I think it's a pleasure to live.
こういうものが欲しいのだけれども、どこを探しても無い、そもそも見ない、全てを知っている訳では無いし、全てを探し切った訳でも無いけれど、そうなると、全く知らない世界のことなのに、つくりたくなる、それは十二分な動機で、つくりたい時には無知ゆえの無謀な過信もあり、例えば、ツテがあったり、知り合いがもしかしたら関係者かも、関係しているかもしれない、そうしたら、つくるのはもしかしたら簡単になるかもしれないけれど、それは利用しない。
今、頭の中にあるモヤモヤとした形にならない、でも形にしたいものをつくろうとした時に、それをつくっている専門家や専門の職人と直に繋がりたく、間に専門外の人を介在させたくなく、そして、その専門家や専門の職人と一期一会で、点と点のような初めの接点があり、お互いがお互いのことを全く知らず、こちらはもうそれを形にしたくて仕方がなく、この訳のわからない、どこのどいつだかわからない奴をものをつくるという一点だけで受け入れてくれて、真剣に話を聴いてくれて、真剣につくってくれる人に出会わないと、こちらも本気でものづくりができないし、本物ができないような気がしているので、いつも無防備で、何も持たずに現地へ行き、1から関係をつくり、本当にこういうのを「類は友を呼ぶ」というのだと思う、似たような考えの人と出会い、そうすると、その人が実は、ということになり、いつしかクオリティが高いことがやれている、建築の職人も似たような感じで出会う、そういう運は昔からあるようだ。
いつも点と点、それが線や面にはならないのだが、大概、皆んな、難題を喜ぶ人ばかり、喜んでいるように見える人ばかり、点の存在、類は友を呼ぶ。
"Points and points"
I want something like this, but I can't find it anywhere, I don't see it in the first place, I don't know everything, I don't know everything, but it's a world that I don't know at all. If you want to make it, there is also a reckless overconfidence due to ignorance, for example, there may be a fool, a person you know may be related, or you may be involved, if you make it It might be easier, but don't use it.
Now, when you try to make something that you don't want to have in your head, but want to make it into a shape, you want to connect directly with the experts and craftsmen who make it. I don't want to do it, and I meet with the experts and professional craftsmen, and there is a point-to-point initial contact. They don't know each other at all, and I can't help making it anymore. If you don't know this translation, accept who you don't know where and when, just make a thing, listen seriously and meet someone who makes it seriously. I can't, and I feel like I can't do the real thing, so I'm always defenseless, go to the local area without anything, make a relationship from scratch, and really say this kind of thing is called "friends" think I met a person with a similar idea, and then, that person was actually, and I was able to do something of high quality sometime, and the craftsmen of the architecture also met with a similar feeling, such luck has long been There seems to be.
The point, the point, it doesn't always become a line or a face, but in general, all the people who are pleased with the difficult problem, the people who seem to be happy, the existence of the point, the kind calls friends.
一度ほどいたら、元に戻らなくなってしまった、たぶんそうなるだろと思って、ほどく前の写真を撮っておいたのけれど、諦めた。
桐箱の紐の結び目をほどく、躊躇したのだけれど、中身が見たい衝動を抑え切れず、紐の折り目のクセを頼りに、試行錯誤、その折り目の向きだと、いや反対になる、輪にならない、何をしてるのかと、紐と戯れただけの時間だった。
目がショボショボとしてきたので、立って歩きながら、難しい本は難しいことが難しく書いてあるから、座って読んでいると、眠くなるから、動きながら、運動しながら読むことにしていて、リビングの中をグルグル、ぐるぐる、決して外では危なくて難しい本は読めない体質になってしまった。
ただ、難しい本が助かるのは、案外、論文チックに、起承転結がはっきりしているから、結論がすぐにどこに書いてあるかがわかる、だから、そこしか読まないのだが、眠くて眠くて、さすがに歩きながらは寝ないので、言葉がわからなくても、参照文献を知らなくても、どんどん読み進めると、突然、視界がひらける、パキッと目が覚める、モヤモヤした謎がほどけた瞬間、その難しい本を開いてよかったと思う。
ほどけたものは、また結ぶ必要が無いので、そのままにして、また次の本を読み進める、その喜びや面白さは格別だが、結びが難しい姿は案外美しくて、手が届かない存在として、そのままにしておくのも良かったかもしれない。
"Knot"
Once I had unwound it, I couldn't get it back. I thought it would be so, I took a picture of it before, but I gave up.
The knot of the paulownia box was untied and hesitated, but the impulse that the contents wanted to see could not be suppressed, relying on the habit of the fold of the string, trial and error, the direction of the fold would be the opposite, It was just time I had fun playing with the strings and what I was doing.
Since my eyes have been changed, it is difficult to read difficult books while standing and walking, so when I sit and read, I get sleepy, so I decided to read while exercising while moving, in the living room The book has become a constitution that can never read books that are dangerous and difficult outside.
However, the difficult book is saved, unexpectedly, because the paper tic is clear, the settlement is clear, so you can see where the conclusion is written immediately, so you can only read there, but it is sleepy and sleepy, as expected Even if you do not sleep while walking, even if you do not understand the language, even if you do not know the reference literature, as you read more and more, suddenly the view opens, suddenly wakes up, the moment when the mysterious mystery has unraveled, it is difficult I'm glad I opened the book.
There is no need to tie the unraveled thing again, so continue reading the next book, its joy and fun are exceptional, but the figure that is difficult to tie is unexpectedly beautiful and unreachable It may have been good to leave.
静かにしていられない、立ち止まっていられない、動きたくて動きたくて仕方がない、カッカする、身体がアツイ、じっとしていられない。
無農薬のにんにくをいただいたのでペペロンチーノを作りつつ、にんにくのオリーブオイル漬けをつくりつつ、ひとかけら、ほんのひとかけらを口に含んで噛む、なんてことはない身体は正直だな、汗が止まらない、エアコンの風を浴びていても汗、汗、汗。
聞いた話によると、にんにくは生のままだとカビやすく、農薬の溜まりにポトンするらしい市販の物は、だから、いただいた無農薬のにんにくも乾燥をさせてあるらしいのだが、普段にんにくを食べも何ともないのに、それを使ったペペロンチーノは絶品、自分で言うのも何だけど、だから余計、汗が、汗が、汗が。
いや動きたくて動きたくて、じっとしていられないのは建築で慣れているのだけれども、普通、建築はじっとして見るものだと思われているけど、違うのですよ建築は動いて見るもの、動いて止まり、また動く、ストップアンドゴー、で、適当な所でとぐろを巻く、動かずにはいられないパワーをくれるもの、建築家は結構そういう想像をしながら設計している。さながら無農薬のにんにくですな、無農薬のにんにくをつくって食べた人をじっとしていられないようにする。
市販のにんにくは、よく見る建築は、何てことはない、じっとしていられるのですよ。
"Pesticide-free"
I can't keep quiet, I can't stop, I want to move and I can't help it, I can't help it, I can't stay still.
I received pesticide-free garlic, so I made peperoncino, made garlic soaked in olive oil, chewed with a single piece, just a single piece in my mouth, my body is honest, sweat doesn't stop, Sweat, sweat, sweat even in the wind of an air conditioner.
According to the story I heard, garlic is easy to mold when it is raw, and it seems that the pesticide-free garlic is dried, so I usually eat garlic. Even though there is nothing, Peperoncino using it is exquisite, what you say by yourself, so extra sweat, sweat, sweat.
I'm used to architecture because I want to move and want to move, but I'm accustomed to architecture, but it is usually thought that architecture is something to see, but it's different. Architects are imagining things like things that move, stop, move, stop and go, wind up the appropriate places, and give you the power you can't move. It 's like pesticide-free garlic, so make sure you ca n't keep people who ate and eat pesticide-free garlic.
On the market garlic, the architecture you often look at is nothing but still standing still.
掃除するのは苦手ではないけれど、片付けるのは苦手かもしれない。掃除は回数を重ねれば、やることは同じになってくるから、大した労力も使わないように、パターン化していて、時間も読めるし、やらないとホコリが溜まるし、汚れるから、ルーティン化してやれば良いだけだが、片付けの基本は元に戻すこと、だから、元に戻すのは掃除と一緒にやるから良いのだが、そもそも元に戻しても、なんか片付いたように感じない。
設計打合せで必ずと言って良いほど、話題に上がるのは収納のこと、収納を多くして欲しいという人に限って、なぜか、部屋を広くして欲しいと矛盾したことを言う。
そもそも収納や部屋の広さが一番重要になることは無く、どういう考え方で設計したかを提案して、そこで収納や部屋の広さの話になるので、ちょっとでも多く広くという人に対しては、何をどこにどれ位収納するのか、1日の行動パターンから活動範囲がどれ位か、など事細かに聴き、大概、必要十分な量と広さを確保でき、尚かつ、そこにピタリと納まるようになる。
今住んでいる所はリノベーションした家だが、収納に関しては元からあった物を再利用して、それでは足りない場合も考えて増やした。さらに、移り住む前に使っていた収納家具と移り住んでから購入した収納家具も置けるようにして、収納が結構たくさんある。
もちろん、何をどこにどれ位収納するかを一応考えたが、確かに、そこに全て納まるのだが、そもそも、片付けるのが苦手なのに、片付けるための収納が多過ぎた。
片付けるのが苦手だから、収納を増やせば、何とかなる、隠せるし、部屋の広さを犠牲にしてでも、収納を多く取れば、その分、部屋はすっきりするだろうが間違いだった。
かえって片付ける手間が増えることになる。いくら見えないからと言って、片付けして整理整頓しておかないと、いざ使う時に探したりして時間がかかり、そうならないためには片付けをしなくてはならず、収納が多いと、片付けがさらに多くなり、それが苦手なのだから、元も子もない。
本来は片付けを一度もしないで済むのが理想なので、収納が無ければ、片付けなくて済む、ならば、収納を全部無くそう、収納が無くても生活できるようにしよう、でも、捨てる物などはじめから無い、全部大事、ならば、収納を極力使わないようにして、物を出して飾ろう、飾ってある物を掃除するのは苦手ではないから、飾れない物だけ収納して、それで片付けしない。
"Do not clean up"
I'm not good at cleaning, but I'm not good at cleaning up. If you do a lot of cleaning, the work will be the same, so you do not use much effort, it is patterned, you can read the time, otherwise dust will accumulate and it will become dirty, so it will be a routine It's all you need to do, but the basics of tidying up is to restore it, so it's good to do it with cleaning, but even if you put it back to the original, it doesn't feel like it was tidy up.
The only thing that can be said in a design meeting is that storage is the only topic of discussion, and only people who want more storage say that they contradicted that they wanted a larger room.
In the first place, storage and the size of the room are not the most important, so we suggest what kind of idea you designed and then talk about the size of the storage and room, so for those who are a little larger Can listen to details such as what is stored where and how much, the range of activities from the daily behavior pattern, and in general, it can secure the necessary and sufficient amount and space, but it fits in there It becomes like this.
The place where I live now is a renovated house, but with regard to storage, I reused the original thing and increased it considering that it was not enough. In addition, there is quite a lot of storage so that the storage furniture used before moving and the storage furniture purchased after moving can also be placed.
Of course, I thought about where and how much to store, but it certainly fits in there, but in the first place I was not good at cleaning up, but there was too much storage for cleaning up.
It's not easy to get rid of, so if you add more storage, you can manage to hide it. Even if you sacrifice the space of the room, if you take a lot of storage, the room will be cleaner.
On the other hand, the time and effort to clear up will increase. Just because you can't see it, if you don't clean it up and keep it organized, it takes time to search for it when you use it. If you don't, you have to clean it up. Since there are more and it is not good at it, there is neither a former nor a child.
Originally, it is ideal that you do not need to clean up, so if you do not have storage, you do not need to clean up, so if you do not have all storage, you can live without storage, but things to throw away etc. If everything is important, if you don't use the storage as much as possible, let's put out and decorate things, and it's not a good idea to clean the things that are decorated, so store only the things you can't decorate and don't put away .
結構家にいると独り言を言っていて、それを自覚している、というか、誰かと想定の会話をしていて、それは側から見たらアブナイ人かも、今は亡き猫とは、まだ生きていた時も、亡くなってからも話し掛けているから、ほんとヤバイ人かも、もちろん、外では声に出して言わないが、 頭の中では常に何か会話をしているかもしれない。
昔、大学生の頃、友達と旅行をしていて、一緒に泊まった時に、シャワーを浴びて出てきたら大笑いされたことがあり、どうもずっとシャワーを浴びながら何かをしゃべっていたらしく、誰かが他にいるように、その時、確か手紙を出そうとして、その文面を考えいて、その文面を唱えていた。
今考えていることを、独りでいる時に、家や車の中では、普通に声に出してしゃべっていて、想定問答をしたり、自分で自分に向かって実況中継したり、例えば、計画中の建築のコンセプトをクライアントに伝えるという設定で、その場面を一人二役で演じて、コンセプトの良し悪しを考えたり、ダメ出ししたり、読んだ本の内容を自分で自分に向かって討論したり、自分なりの勝手な解釈で解説したり、別にもっと他のことでも、些細なことでも声に出してしゃべっている。
良く言えば、自分なりに腑に落ちやすいように、自分の言葉に変換して、それを頭だけでなく、口と耳を使って、自分のものにしようとしている、悪く言えば、いつまでも頭が切り替わらずに、ずっと頭に留めておくから、黙っていられずに、何かしゃべって外に出さないと、頭がパンクする寸前とも。
ただ、そうやって独り言を言って、口と耳と頭が連動した場合の事は結構記憶に残っていて、また、そういう状況が来て、独り言の通りにしゃべる事は結構ある。
"Solo Word"
I'm telling myself that I'm quite at home, and I'm aware of it, or I'm talking to someone and it's an Abnai from the side, but now the dead cat is still alive I'm talking to him even when he died, so he's really a bad guy. Of course, he doesn't say aloud outside, but he might always have a conversation in his head.
When I was a college student, I used to travel with friends, stayed together, and when I came out taking a shower, I was laughed out. At that time, he was surely trying to write a letter, thinking about the text, and chanting the text.
When you are alone, when you are alone, at home or in the car, you are speaking out normally, answering assumptions, relaying yourself to yourself, for example, planning In a setting to convey the architectural concept of the client to the client, play the scene in one and two roles, think about the quality of the concept, put out a bad idea, discuss the contents of the book you read to yourself , I explain it with my own interpretation, and speak aloud other things and even minor things.
In other words, I am trying to convert it into my own words so that I can easily fall into the trap and make it my own not only with my head but also with my mouth and ears. I will keep it in my head without switching, so I can't be silent, just talk and do not go out, just before my head punctures.
However, if you speak to yourself and the mouth, ears, and head work together, you still have a lot of memories, and it is quite possible that such a situation will come and you will speak as you say.
どうしよう、どうしよう、どうしようかな、なんていう状況に追い込まれるのは、大概は想定外のことが起こった時で、それが日常の些細な事でも、仕事でも、程度の差こそあれ、困る時で、それは時間を管理して、スケジュールをこなす場合は極力無くしたい。
だから、最大限の想像力を発揮して、これから起こる事を予測して、スムーズに進行するように準備をするのだが、まあ未来の状況を全て把握できる訳が無いから、その対策としてバッファを持たせて、これなら大丈夫だろうと、万全、なんて時ほど、斜め後方の死角からパンチが来るような、それは衝撃的な、やはり、人との関わりの中で、人って、ほんと多種多様で、自分も含めて、他人には理解できない部分が必ずあるから、でも、そこを理解し合えると関係性が良くなるので、とにかく聴く、傾聴しかないと、言いたい衝動を1/3位に抑えて聴くと、これがなかなか、自分ではわからない所で上手く作用する場合があり、人が何に反応するかも、また、わからない、謎な部分なので、そうなると、返しはカウンターパンチしかなく、あの一言が残ることは自分でも思い返せばあるので、何かの一言が作用して上手く行くか行かないかが決まる。
人は感情の動物だから、理性を発揮していても、その一言で決まる。では、どうやったら上手くいくカウンターパンチ、一言を出せるのか、ヒントはいつも相手の言葉使いの中にあると思っている。
"A word"
What happens, how, what to do is usually driven when something unexpected happens, whether it's a trivial thing in everyday life or a job, to some degree Sometimes it's time to keep track of time and to lose as much as you can to schedule.
So, make the best use of your imagination, predict what will happen, and prepare to proceed smoothly, but since there is no reason to understand all future situations, it has a buffer as a countermeasure. Let 's say that it 's okay, it 's perfect. How about a punch coming from behind the blind spot. It 's shocking. After all, in the relationship with people, people are really diverse. There is always a part that other people can't understand, including myself, but if you can understand it, the relationship will be better, so if you listen to it, there is only listening, if you listen to the impulse you want to say to 1/3 , This may work well in places that I do not understand, it is a mysterious part that I do not know what the person reacts to, so when it happens, the return is only a counter punch, Since that word is left in there if I recall myself, or something of a word is not going go work in action is determined.
Because people are emotional animals, even if they are demonstrating reason, they are determined by that word. Then, I always think that there is a hint in the opponent's vocabulary about how to make counter punches and how to make a word.
伸び縮みするような時間の感覚が人の感情と結びついて面白いと思う時に、何をしているのかなと考えると、大体、何かに追われて焦っているか、楽しくて仕方がない時か、今この時を何とかしたい時か、だったりする。よくあることに、楽しいことをしていて、あっという間に時間が過ぎる時があるかと思うと、締切が決まっていて、あっという間にその時間になってしまう時や、逆に、なかなか進まない時間をなんとか自分の手で秒針を動かしたくなるような講義や研修などは座っているだけでも辛い時で、基本的には時間の量は同じだとしたら、気分次第で時間は伸びたり縮んだりするように感じ、ならば、時間を有効活用できる術がそこにはあるのではないかと考えてしまう。
自分の感情をコントロールしてしまえば、時間をコントロールできる、時間を制することができるのではないか、と考えてみる。
例えば、常に楽しいことばかりで、あるいは、楽しい感情に包まれていたら、時間はあっという間に過ぎてしまうので、楽しいから良いが、その時間の使い方は有効活用しているとは言えずに、浪費しているとも言える。
何かに追われて焦っている時も、時間はあっという間に過ぎてしまうが、まだ追われている分だけ、その時に何かを一所懸命にやっているので、効率的ではないかもしれないが、時間を有効活用している部類に入るかもしれない。ただ、焦るのは精神衛生上、良くは無いので、何とかしたいとなる。
辛い時は本当に何とかしたくなるが、考えようによっては、余りある時間がそこには存在していることにはなるので、ただ、辛さを楽しさに変えてしまうと、せっかくの余りある時間が颯爽とスピードアップをして逃げて行ってしまうので、辛さはそのままいじらずに、辛いまま、辛い時にしかできない時間の有効活用をすれば良い。
少し時間が経てば、人には「慣れる」という特技があるので、辛いまま、辛い感情に慣れてしまえば、じっくりと、余りある時間に向き合えるのではないかと考えてみて、「慣れる」の「慣」は習慣の「慣」でもあると気がつくと、だから、トップアスリートは気分に左右されて成績がブレないように、ルーティン化を習慣としているのかと至った。
"Get used to"
When the feeling of time that stretches and shrinks is connected with human emotions and is interesting, when you think about what you are doing, it is roughly when you are chased by something or when you have fun and can not help , Or when I want to manage this time now. Often, if you're doing something fun and you think there's a time when it's too much time, the deadline is fixed and it's time to go, or on the contrary Lectures and training that make you want to move the second hand somehow with your own hands are difficult when you are sitting, basically if the amount of time is the same, the time will grow or shrink depending on your mood If it feels like it's going to happen, then I think that there is a way to make the most of time.
If you control your feelings, think that you can control time and control time.
For example, if you always have fun, or if you are wrapped in fun emotions, the time will pass in no time, so it 's fun, but you ca n't say that you 're using it effectively. It can be said that it is wasted.
Even if you are chased by something, the time will pass quickly, but because you are still chased, you are doing something hard at that time, so it may not be efficient It may not be, but it may enter into the category using time effectively. However, it is not good for mental health to be impatient, so I want to do something.
When you have a hard time, you really want to do something, but depending on your thoughts, there will be a lot of time there, but if you change the hotness into fun, you have a lot of time. However, you can speed up and run away, so you don't need to change the spiciness.
After a little time, people have a special skill of "getting used", so if you get used to painful emotions while staying painful, think carefully that you can face a certain amount of time. I realized that "Inertia" is also the "Industry" of habits, so I came to the question that top athletes are routinely employed so that their performance is not affected by their mood.
知らず知らずのうちにできてしまう、なんてことがあったりする、それは何でも、別に結果を出そうとしていた訳でも無く、何かを意識していた訳でも無く、目の前のことに一所懸命になっていたら、できるようになった、などという経験は誰にでもあるだろう。
知識に関してはどうだろうか。知らず知らずのうちにできるようになることは、どちらかというと、身体を動かしたり、経験をして身につけるようなことだと考えてしまい、知識に関してはそのようなことは無いだろうと思ってしまう。
身体が覚えるように、無意識の動作で何かが、知らず知らずのうちにできてしまう、としたら、知識は頭で覚えることで、頭は身体の一部だから、無意識に知識を得てしまうこともあるのではないか。
本から得られる知識は、その本が専門的であればあるほど、その本自体を読まないと得られないと考えてしまう。確かに、その通りだと思うが、その本自体を読まなくても、もちろん、その本についての解説を読まなくても、いつのまにか、その専門的な本の内容を知っている場合がある。
それは、その専門的な本を発展させたり、派生させたりした本を読んだ時で、元となった本の内容をベースとして書かれているから、元の本の内容まで知ることになる。もちろん、発展させたり、派生させたりした本は著者のフィルターを一度通しているので、元の本の印象が操作される可能性があるが、元の本の根幹の内容はそのままわかるだろう。
このことは、本以外のことでも、デザインとか、アイデアでも同じで、元ネタからの発展、派生を見ていたら、元ネタの考え方まで自然に頭に入っていた、もちろん、元ネタに直接接触することが大事で、時には深く遡ることも必要だが、研究者でない限り、そこまでする必要もない場合もあり、しない方が良い場合もあり、その見極めも必要になる。
"I get"
There is something that can happen without you knowing, it is not something that you were trying to produce a result, and you weren't conscious of anything. Anyone will have the experience of being able to do it.
What about knowledge? I think that something that can be done without knowing is rather like moving the body or gaining experience, and I think that there will be no such thing about knowledge End up.
As if the body remembers, something can be done unknowingly without knowing, if knowledge is remembered with the head, because the head is part of the body, the knowledge is obtained unconsciously There may be.
The more specialized a book is, the more knowledge it can get from a book. Certainly, I think that is true, but without knowing the book itself, of course, without reading the explanation of the book, you may know the contents of the specialized book.
That is, when you read a book that was developed or derived from that specialized book, it is written based on the content of the original book, so you will know the content of the original book. Of course, books that have been developed or derived have passed the author's filter once, so the impression of the original book may be manipulated, but you will still understand the basic content of the original book.
This is the same for things other than books, design, and ideas. If you were looking at the development and derivation of the original material, you naturally came up with the idea of the original material. Of course, you were in direct contact with the original material. It is important to do this, and sometimes it is necessary to go back deeply. However, unless you are a researcher, you may or may not need to go that far.
結果から逆算して今何をするのか、今何が問題かを考えるなんて、当たり前のことで誰でも行っていると思うのだけれども、その時に、解像度というか、どこまで細かく予測できるかで全然違うようだ。
クライアントとの打合せの時に感じることがある、その解像度の違いを、ただそれは、 その違いが生業としている人の所以でもあるのだが、そこに違いがあるということがわかっている人と、わかっていない人では、打合せの深度が違ってくる、なかなか深まらずに、浅いところでウロウロしてしまう。
本当はもっと詰めたところまで、そこより深いところに侵入したいのに、そこに行くまでに時間がかかってしまう。
反対の立場だったら、まず、要望、疑問、問題を伝えるだろう、それで青写真なり、方向性なり、全体像がはっきりしてくるから、そこまでどうやって行くかは詳しい人が考えればよいのでは、そもそも、そのようにできる人に依頼をするのでは、なんて思うのだが、深くない知識や自意識のために、それが粗い解像度の原因なのだが、引っ掛かりが多くなってしまって、何とも勿体ない。
そこにヒントが隠されている場合もあるから、そこを上手くやるのも建築の範囲としているのだけれども、何とも勿体ない。解像度が粗いならば、思いっきり粗くしてしまえばよいのに、自覚が無いと中途半端だと、と我が身を振り返る。
"resolution"
I think that everyone is doing what is right now, thinking what to do now and what to do now by calculating backwards from the results, but at that time it is completely different depending on resolution or how much you can predict It seems.
The difference in resolution that you may feel when meeting with a client is just because you know that there is a difference, but that is also the reason for the person who is doing business. If you don't have it, the depth of the meeting will be different.
I really want to go deeper and deeper, but it takes time to get there.
If you are in the opposite position, you will first convey your requests, questions, and problems, so the blueprint, direction, and overall picture will be clear, so a detailed person should consider how to get there. In the first place, I don't want to ask someone who can do that, but because of my deep knowledge and self-consciousness, it's the cause of the poor resolution, but there are so many catches that I can't help it.
There are cases where hints are hidden there, so doing it well is also within the scope of architecture, but it's useless. If the resolution is rough, you can make it rough. However, if you don't realize it, you're halfway.
合わせるのか、へり下るのか、主張するのか、意外と判断が難しい、相手が何かにもよるから、一概には言えないが、当たり前の回答だろう。
これはデザインの話。注文していたコーヒーカップが届いた。出来合いの輪島塗のコーヒーカップを以前購入したのだが、使い勝手がよかったので、もう1客注文したら在庫切れで、新たなに製作をするというので、ならば、今の黒と朱色の組み合わせを反転して欲しいとお願いしていたもの。
コーヒーカップだが、同型で湯呑もあり、取っ手があるか無いかだけの違い、まず湯呑をつくり、その後に取っ手をつけコーヒーカップにしたのだろう。
元があって、そこに付け足す、建築で言えば、増築みたいなものか。新たに注文していたカップは色違い、だから取っ手は同じ形状のはずが、届いたカップは違う、取っ手の形状が違っていた、付け足すものが変わっていた。
もしはじめからコーヒーカップをデザインするならば、当然、取っ手だけを後から付け足すようなことはしない。取っ手を含めて全体でどうデザインをするのかと考える。ただ、コーヒーカップをデザインすることを想像してみると、取っ手は厄介な存在、無い方がデザインとしては完成度が高くなるような気がする、それか片方だけではなく、両側に付けるか、それもおかしいが、スープカップになってしまうが、非対称の形は良いのだが、取っ手の存在感が大きいので、取っ手の形状が全体のデザインに与える影響が大きい。
それで取っ手を意識しすぎると、カップ全体のデザインがおかしくなる。今までコーヒーカップを見て綺麗なデザインだなと思ったことがほとんどなく、取っ手が無い方がよいのに、取っ手の形状がな、と思うことが多い。それだけコーヒーカップのデザインは難しいのだろう。
毎朝コーヒーを飲むので、コーヒーカップをいくつか所有しているが、無い、無いに等しい、いいデザインのものが、だから、つくりたくなる。
"Handle"
It's hard to judge whether to match, hail down, or argue. The answer depends on what the other party is.
This is a story about design. I received the coffee cup I had ordered. I bought a freshly made Wajima-painted coffee cup in the past, but it was easy to use, so if I ordered another customer, it would be out of stock and a new one would be made. What I had asked for.
It was a coffee cup, but it was the same type and had a tea cup. The only difference was whether or not there was a handle.
Is there something like an extension in terms of architecture? The newly ordered cups were different in color, so the handle should have the same shape, but the cup that arrived was different, the shape of the handle was different, and the additions had changed.
If you're designing a coffee cup from the beginning, of course, don't just add the handle later. Think about how to design the entire design including the handle. However, if you imagine designing a coffee cup, the handle is a nuisance, and if you don't have the feeling that it will be more complete as a design, you can attach it to both sides, Although it is strange, it becomes a soup cup, but the asymmetric shape is good, but the presence of the handle is large, so the shape of the handle has a great influence on the overall design.
So if you are too conscious of the handle, the whole cup design will go wrong. I have never thought that it was a beautiful design by looking at a coffee cup until now, and I often think that the shape of the handle is good, even though it is better not to have a handle. That's how difficult it is to design a coffee cup.
I drink coffee every morning, so I have a few coffee cups, but none, no, good design, so I want to make one.
なんか夏休み、気分は、暑いし、事務所にこもる日々だからいいけれど、今週夏休みの人もいるだろから、やっと動き出したプロジェクトが、動き出す時はなぜか同時に複数だったりして、盆休み前にとりあえず青写真は描けそう。
まったくの王道から外れた、というか、今までカップのデザインはしてこなかった、というか、建築以外はほとんどデザインをしたことがなく、昔、飲食店の設計をした時に、お品書き、箸袋、楊枝入れなどなど、をデザインしたことはあったが、ほぼ素人に近く、塗りを一から調べたり、古い文献にあたったり、カップは昔から好きなので、陶磁器、硝子、それこそ、塗り物も家にはあり、造形に関しては博物館へ縄文式土器を見に行ったりもした。
輪島塗のフリーカップをつくろうとしたキッカケは置いておいても、何回輪島に通っても、いろいろと輪島塗について深掘りをして知り、デザインを考えても、自分で素人感が否めない。
建築の打合せをしていて、クライアントが自分で描いたプランを持ってくることがある、手書きでも、プリンとアウトしたものでも、それはどこまで行っても出来は素人であり、それだったら変な先入観ができるから、要望を伝えて、あとはプロに任せればいいのに、自分では上手くできていると思っていそうだと、無碍にもできなくて、つらい。
それは料理でも同じで、素人が死ぬほど頑張ってもプロの料理人には敵わないだろう、例え、同じレシピで、設備も場所も同じでも素人はプロには敵わない、知識、技術、感覚の全てが足元にも及ばない、その違いがプロたる所以、建築も同じ。
それをプロ側で経験しているから、塗師にスケッチを見せて、フリーカップについて説明する時は、素人感満載なんだろうなと思っていた。
ただ、この素人感満載でものづくりを、デザインを考えているのが実に楽しい、楽しくて仕方がない。ましてや、職人集団は日本で最高レベル、漆器で日本で最高ならば、世界的にも最高レベルだろう。
自分でデザインしたものを最高の職人集団が形にしてくれる、建築でも同じだが、これほど楽しいことは無く、ましてや、この素人感がのびのびとして楽しくさせてくれる、何かに縛られることもなく、何かに忖度することもなく、考えてみれば、建築をやりはじめた時も同じだった。
何か歴史の中でポジションが決まっていて、そのポジションは複数あるが、外れた所には無く、そのポジションを得るために勉強し、知識を得て、実務を経験し、素人からプロに成長し、そのポジションの枠の中でのみ、プロとして全うする。
その大変さと難しさと、当然面白さ、楽しさもあるだろうが、ものづくりの楽しさは、そのポジショニングとは別次元の所に存在していて、ポジショニングとは全く関係が無い。だから、ものづくりの楽しさを得るために、プロも素人も関係が無く、純粋にデザインだけに向き合えるし、そもそも建築以外のことなので、素直にプロ感を捨てられた。
確かに、素人はプロには敵わないが、素人がプロには思いつかない価値を生み出すことは可能だと思う。ただそれは先の話のポジションの枠の外になるから、プロの世界では相手にもされない。しかし、確実に新しい可能性がそこにはあり、新しい楽しさもそこにはある。
"amateur"
Somehow summer vacation, mood is hot and it's hot days in the office, but there are people who are summer vacation this week, so when the project finally started moving, there were several simultaneously at the same time, for the time being before the Bon vacation I can draw a blueprint.
I haven't designed the cup until now, or I haven't designed a cup until now, I have never designed anything other than architecture. I have designed, such as toothpick holders, but it is almost like an amateur, I studied paint from scratch, hit old literature, I like cups from a long time ago, ceramics, glass, that is also the paint home I went to the museum to see the Jomon pottery.
No matter how many times you go to Wajima Lacquer, you can't deny the feeling of an amateur by yourself, no matter how many times you visit Wajima Lacquer.
I have an architectural meeting and the client may come up with a plan that I drew, whether it is handwritten or printed out, it can be an amateur no matter how far it goes, and then a strange preconception I can tell you what I want to do and then leave it to a professional, but if you think that you are doing well, you can't make it instinctively.
It's the same in cooking, even if you do your best to the extent that an amateur dies, it won't match a professional chef, for example, with the same recipe, the same equipment and location, but an amateur is not comparable to a professional, knowledge, technology, The architecture is the same because all of the sensations do not reach the feet and the differences are professional.
I experienced it on the professional side, so when I showed my sketch to the painter and explained about the free cup, I thought it was full of amateurism.
However, it is really fun, fun, and unavoidable to think about design with this amateur-packed design. Moreover, if the craftsman group is the highest level in Japan, and the highest level of lacquerware in Japan, it will be the highest level in the world.
The best craftsman group forms what you designed yourself, the same with architecture, but there is nothing so much fun, let alone this amateur feeling freely and fun, without being bound by anything, If you think about it, it was the same when you started building.
There are several positions in history, and there are multiple positions, but they are not out of place, studying to acquire that position, gaining knowledge, experiencing business, growing from amateur to professional However, I will be a professional only within the frame of that position.
The difficulty and difficulty, and of course, the fun and the fun, but the fun of manufacturing exists in a different dimension from the positioning and has nothing to do with the positioning. So, in order to get the fun of manufacturing, there is no relationship between professionals and amateurs, they can face purely design, and since it is something other than architecture in the first place, I was abandoned professionally.
Certainly, amateurs are not competitive with professionals, but I think it is possible for amateurs to create value that professionals cannot think of. However, since it falls outside the frame of the position of the previous story, it is not made a partner in the professional world. But there are certainly new possibilities and new fun there.
「またやったか」なんてことは、人の性根なんて、なかなか変わるものではないから、他の人にとってはどうでもよいことに、いや、他の人にとってはどうでもよいことだから、ひとりのめり込むことがあり、そうなると気づくまで、いや、気づいても急には止まれない。
誰でも、そう、誰でもと思いたいから、他の人も同じだろうと、何かを集めたり、何かに執着したり、何かに拘ったりするだろう、大体、そういう時は自分なりの理由がある、言い訳、それも自分にとって都合の良い後付けの言い訳とも言えるが、これが厄介で、最もらしく、これが精神安定剤代わりになるから、これが無いと、何でもないことで、それは拘りでも何でもないから、すぐにおさまるのに、やめられなくなる。
15年前、写真撮影を趣味にしていた、フィルムで。きっかけは父親の古いフィルムカメラを見つけたこと、キヤノンのキヤノネット。50年位前に発売されたカメラで動かなかったが、修理して、撮影できるように。
道具を使う喜び、もうこれに尽きるぐらい、このカメラが好きになり、この道具を使うために写真撮影を趣味にし、出来上がってくる写真の良し悪し、上手い下手は関係なく、自分で好きなように絞りとシャッタースピードを設定して撮影していた。
道具は道具を呼ぶのか、当然の流れか、他のカメラに興味を持ち出す、ただ、キヤノンネットがそうだったから、電池が無くても動くカメラが欲しくなり、当時、思い切って、結構悩んで、CONTAX S2を手に入れた、チタン合金製で、道具としての魅力があった、しかも初一眼レフ、しかもレンズはツァイス。
いやー、難なく決壊するものです、購入してすぐにCONTAXの事業をしていた京セラが撤退発表、ツァイスレンズが、カメラボディが、手に入らなくてなる、いつかはあのレンズが手に入らなくなる、当時、新品も中古も潮が引くように市場から一斉に無くなりました。
当然、お店に行くと目の前で無くなっていく、隣の、後から来た、お客が買って行く、今買うか買わないか、ツァイスのレンズなんて、趣味程度の人がそうそう買うもんでもないです、これが俗に言う沼、レンズ沼でした、あとボディ沼もありました。
それでも理由があったから、いよいよと自覚したのは、アクセサリーというのも、フードとか、フードもレンズによって違う、これももう手に入らないからと買うと、そうだ失くした時用の予備、予備の予備なんてはじまった時ようやく、薄々は気づいていたのですがね、崖の際にいるかな、いや、フードが花が見えた、崖際の花、それを摘んで、崖から落ちずに生還、ちょっと手足は切り傷だらけで血が滲んでいましたけど、いつか役に立つだろうと、防湿庫の肥やしにしてます。
崖際の花、誰からか聞いた話で、上手いこと言うなと、おかげで今は際まで行かずに引き返せるようになりました。
"The flower which blooms to the last minute"
"Do you do it again?" Doesn't change the human sex roots very easily, so it's good for other people, no, it's good for other people, so it's possible that you're stuck with one person No, I can not stop suddenly even if I notice it until I notice it.
Everyone, yes, everyone wants to think that if others are the same, it will collect something, stick to something, stick to something, generally, it's just your own time There is a reason, an excuse, it can be said that it is a convenient retrofit excuse for me, but this is bothersome and plausible, and since it is a substitute for a tranquilizer, it is nothing, without it, it is neither matter nor anything From now on, I can't stop trying to stop soon.
15 years ago, I was interested in photography, on film. The chance was that I found my father's old film camera, Canon's Canon Net. It did not move with the camera released about 50 years ago, but it can be repaired and taken.
The pleasure of using tools, I love this camera to this end, I make photography as a hobby to use this tool, good and bad of coming photos, good and bad, regardless of yourself, as you like I was shooting with the aperture and shutter speed set.
The tool calls a tool, a natural flow, or brings interest in other cameras, but just because the Canon net is, I want a camera that can move even without a battery, and at that time, I was completely troubled, CONTAX S2 was obtained, made of titanium alloy, attractive as a tool, and the first single-lens reflex camera, and the lens is Zeiss.
No, it's breaking without difficulty, Kyocera who was doing the business of CONTAX immediately after purchasing and announced withdrawal, Zeiss lens, the camera body will not be able to get it, someday that lens will not be obtained, At that time, both new and second-hand goods were removed from the market at the same time as the tides dropped.
Naturally, if you go to a store, you will disappear in front of you, next door, you will come later, your customers will buy, buy now or not buy now, even if the lens of Zeiss, people with hobbies so much buy it There is no, this was a swamp to say, it was a lens swamp, there was also a post body swamp.
Still there was a reason, so I finally realized that the accessories, the hood, and the hood also differ depending on the lens. At the beginning of the reserve, I was aware of the thinness, but I wondered if I was on the cliff, no, I could see the flower on the hood, the flower on the cliff, I picked it up, returned it without falling from the cliff, The limbs were a bit full of cuts and blood was bleeding, but someday they will be useful to fertilize the moisture-proof store.
A flower on the cliff, a story I heard from someone, and now I can return without going to the end, if I do not say good things.
ひとにとってはどーでもよいことでも、本人はいたってまじめに取り組んでいて、いつも同じことをしていて、意味不明で、まわりの人は同じものがたくさんあっても仕方ないじゃない、本人はひとつひとつのちがいが、違うでしょ、と思いながら、どうでもいいことには価値を見出さないかと、
お店の人も、それは全部イギリスのアンティークです、毎回説明してくれるけど、毎回新鮮におどろく、毎回聞いていないのだな、どこのものか、年代が古いとか、価値基準がはっきりしていて、値札も相応なのか、ただ、欲する側はそこを見ていなくて、形とか、大きさとか、厚みや小口の手触り、材質が醸し出す雰囲気なんかを頼りに選り分けて、
今日は何本ですね、と言われながら所望し、目黒と恵比寿の間に1,2ヶ月毎に3回ばかり通っている中華屋さんへと続く道の途中に誘惑されるアンティークショップがあり、カトラリー好きのスプーンフェチなので、まっすぐそこへ、スプーンめがけて行くのははばかるから、好きものは一番最後に食べるので、他のものが気になりつつ、たまたまスプーンを見つけて見入ってます体なのだが、3回目ともなると、この前もスプーンでしたねとバレバレなので、次回はまっすぐスプーンめがけて、ただ、そこのスプーンは全て穴が空くぐらい見てしまったので新鮮味がもうないかも。
たぶん縄文人も木のスプーンを使っていただろうぐらいに、原始的な道具、変わりばえしない機能、だから、何でもあり、どうにでもなるからか、意外と形も大きさも厚みなどにバリエーションがあり、バリエーションをつくりやすいのか、
1番のフェチポイントは柄の厚み、ここの厚みが変化していたり、薄く一定だったり、微妙に曲がっていたり、カトラリーをつくる時はわざと微妙に柄の部分を曲げてみようかな、何の意味もなく、ただ、こういうのは曲げれば、意味は後付けで見つけるもので、それが道具として手放せないものになるところだったり、こういう製作時の自然な、許せる、有りなブレみたいところが今のカトラリーには無い、道具に愛着は必要なのに、そこが愛着ポイントになるのに。
"attachment"
For the people, whatever they are, they are always working seriously, always doing the same thing, meaningless, and it is no wonder if there are many same people around them, each one is one person While thinking that they are different, they may not find value in any kind of thing,
The shop staff are all British antiques, but I will explain them every time, but I am always fresh and shocking, I have not heard each time, where are they, what is the age, and the value standard is clear The price tag is also appropriate, but only the side that wants it is not looking there, depending on the shape, the size, the thickness, the texture of the small part, the atmosphere that the material brings out, and so on,
There is an antique shop that is seduced on the way to the Chinese restaurant, which goes about 3 times every 1 to 2 months between Meguro and Ebisu. Because it is a spoon fetish like a cutlery, it is not good to go straight there or to go with a spoon, so the last thing you like is, so while you care about other things, it happens that you find a spoon and you're on the body As it was the third time, I used to use a spoon last time, so I took a straight spoon on the next time, but I just saw all the spoons there are holes, so there may be no fresh taste.
Perhaps as much as the Jomon people would use a wooden spoon, there are variations in shapes, sizes, thickness, etc., surprisingly, because they are primitive tools, functions that do not change, and so anything, because they do anything. Is it easy to make variations?
The first fetish point is the thickness of the handle, the thickness here is changing, it is thin and constant, or it is slightly bent, or when making the cutlery, let's try to slightly bend the portion of the handle intentionally, what it means No, but if this is bent, the meaning will be found later, and it will be something that can not be released as a tool, or such a natural, forgiving, kind of blurry place like this at the time of production will be the cutlery of today There is no need to attach to a tool, but it becomes an attachment point.
あーあ、とか、どうしようかな、とか、いやになるな、なんて時は何もする気が起きないな、でも、やることはたくさんあるし、困るな、という時でもお腹が空くから、やる気はないくせに、お腹いっぱいご飯を、また食べたら気分も変わるだろうと思うのだけれど、気分も変わらずに、あーあ、どうしようかな、いやになるなの連発を、どうやったら、気分が落ち込んでいる時は、でも、気分が良い時はこの逆だから、結局気分しだいなんだよな、ご飯たくさん食べられるし。
何をつくるか、今しかつくれないものをつくる、ならば、全ての気分をひっくるめて、つくることに生かそうと考えて。
気分であそこにしよう、ここにしようと、自分が身体を動かして選択することはよくあるから、何かをつくるプロセスには気分が関わっていることが当たり前だと思うのだけれども、気分で変わることがネガティブに捉えられる時も。
だから、使う人の気分も拝借してしまえば、プロセスに気分が入り込もうが良いだろうと考え、気分つながりということで、よくわからないが、飲み物があって、飲む人がいて、飲む人の気分が揃ってはじめて成り立つデザインを考えたのが輪島塗のフリーカップ、ようやく塗りのサンプルが出来上がってくるメドがついた。
"As you feel"
Oh, I do, I don't care, I don't feel like doing anything at all, but I have a lot of things to do, and I'm hungry because I'm hungry, so I'm not motivated I think I will change my mind if I eat a lot of rice and eat it again, but I feel the same, oh yeah, how to do it, how I do a barrage of irritating, how I do, when I feel depressed But, when I feel good, the opposite is true, so I feel like I can eat a lot of food.
What to make, to make something that will not be done now, if it is, enliven all the mood, thinking that it will be useful for making.
Because there is a feeling that it is natural to move the body to make a choice, let's feel it here or there, so I think that it is natural that the mood is involved in the process of creating something, but it changes with the mood Even when it is caught in the negative.
So, if you borrow the mood of the person who uses it, I think that it would be better to get in the process, and I'm not sure about the mood connection, but there is a drink, there are people who drink, and the people who drink Wajima-Nuri's free cup was the first to think of a design that could only hold true, and a med's finally came with a sample of the paint.
何年か前、週に一度早朝に臨済宗の僧侶の指導の元、坐禅をしていた。臨済宗の坐禅の特徴は、最中に禅問答のお題を与えられ、その答えを考えながら坐禅をし、坐禅の後、禅問答をする。その時に教えてもらった禅語で
応無所住 而生其心
(おうむじょじゅう にしょうごしん)
がある。「応(まさ)に住(じゅう)する所無くして、而(しか)も其の心を生ずべし」と読みくだすらしい。
住する所とは、自分が留まる所、執着する所で、それが無いから、「応無所住」とは執着しないこと。其の心とは、自分の心で、生ずべしとは、自由自在に働かせることなので、「而生其心」とは自分の心を自由自在に働かせること。
「応無所住而生其心」とは、自分の心を自由自在に働かせるためには、何事にも執着しないこと。
ただ、何事にも執着しない方が良いからと言って、何もしないのではなくて、何かをして執着することがたくさんある方が、その執着の振れ幅が大きい方が人生は豊かになるから、どんどんたくさん執着をすれば良いのだが、どんなにブレても必ず元に戻るということ、執着した心をそのままにしない、元の何事にも執着しない心に戻りなさい、ということ。そうすれば、心を自由自在に働かせることができる。
要するに、何があろうとも、心を常にニュートラルな状態を保つことで、様々なことに対して、自分も含めて、心の機微に触れることができ、本来の自分でいられるということ。
執着することの方が、執着する誘惑が多いから簡単だし、執着している状態は満足感が得られるから、ついついそこが自分の居場所だと勘違いしてしまうが、元に戻りましょう、本来の自分が居るべき場所はどこですか、という気づきの禅語でした。
"Do not attach"
Several years ago, once a week early in the morning, under the guidance of the priests of the Rinzai sect, he was sitting. The feature of the Rinzai sect's zodiac is given the title of a torture question in the midst, and the zodiac is considered while thinking the answer, and the torture question is made after the zodiac. In the shame language taught at that time
Non-Resident Housing
(Study in English)
There is. It says, "If there is no place to live in Masaki, Shiro also produces the heart of Sagi."
A place where you live is a place where you stay, where you attach, and because there is no such thing, don't attach to "non-residential residence". Since the heart of a wolf is one's own mind, and the birth is to work freely, the "Gyusei's heart" is to work one's mind freely.
In order to make your mind work freely, you must not stick to anything.
However, saying that it is better not to attach to anything, it does not do anything, but if there is a lot of attachment to attach something, life is richer if the amplitude of attachment is larger Therefore, it is good to attach a lot more and more, but be sure to return to the original no matter how much the blur, not to leave the obsessed mind as it is, to return to the mind that does not attach to anything of the original. Then you can work your mind freely.
In short, no matter what, by always keeping the mind in a neutral state, you can touch the subtleties of the mind, including yourself, to various things, and be able to be yourself.
Attaching is easy because there is a lot of temptation to attach, and the state of attachment gives you a sense of satisfaction, so you may misunderstand that it is your own place, but let's go back to the original, originally It was a jargon of awareness that where I should be.
眠いと頭が働かなくなる、ボーっとしてもうろうとしてくると、寝落ちしかける寸前あたりで、何かしらのイメージが頭に広がる時がある。
それは、それまで考えたり、思ったりしていたことの延長線である場合もあるし、全く関係が無い場合もあるが、現実とイメージ、それは夢かもしれないが、区別がつかず、連続的に展開される時があり、それも変な、ありえないような、面白いものであったり。
夢と現実の境界が無くなる、無意識と顕在意識の境の扉が開いた状態になるのだろう。
イメージとしては理路整然として秩序だった顕在意識に、無秩序でごちゃまぜになっている無意識が扉から進入して来て掻き乱すような、寝ている時に見る夢が荒唐無稽なのは、この顕在意識と無意識の境が無くなっている状態で、顕在意識よりも膨大な量の無意識が顕在意識を侵食して、無意識ワールドを展開しているから。
だから、眠くて眠くて仕方が無く、でも寝ることが許されない状態の寝落ち寸前の時に、例えば、ただ聞くだけのつまらない講義の時などは、面白い映像がたくさん見られると思うことにしている。
"Interesting picture"
When I'm sleepy, my head stops working, and I'm trying to get down, there's a time when an image of something comes to my head just before I fall asleep.
It may be an extension of what you have been thinking or thinking before, and there may be no connection at all, but reality and image, it may be a dream, but it is indistinguishable, continuous There is a time when it is deployed, and it is strange, impossible, and interesting.
The boundary between the dream and the reality disappears, and the door of the border between the unconscious and the conscious mind will be open.
As the image, in a sense that orderly and orderly in a logical way, an unconscious that is disordered and messed up comes in from the door and comes to a stir, the dream that you see while sleeping is insane, this unconscious In the state where the border of the unconscious is gone, a huge amount of unconscious that is more obvious than the unconscious consciously erodes the unconscious and develops the unconscious world.
So, when I am just asleep in a state of being sleepy, sleepy, unavoidable but I can not sleep, I think that, for example, in the case of a boring lecture that I just listen, I can see many interesting images.
目をつぶってじっとしていて、でも眠らない状態を維持するのは案外難しい。
目をつぶってじっとしていること自体、人によっては苦痛で、何もイメージしない、何も考えたりしないことができず、何かしらイメージしたり、何かしら考えたりしてしまう。その時に暗闇に慣れていない人は、変なイメージや考え、思いが頭をめぐり、目をつぶってじっとしていることができない。
仮に、何もイメージしない、何も考えたりしないことができても、眠気が襲ってくる。眠いのに寝てはいけない状況ほど辛いものは無い。
何年か前、週に一度早朝に坐禅をある所でしていた。ある所とはお寺ではないが、臨済宗の僧侶が出張して約1時間くらい座禅をし、警策もあり、時間は20分ずつ2回で短めだが、場所以外は本格的な坐禅だった。
臨済宗の坐禅の特徴は、最中に禅問答の公案を思索するところ。公案とは問題のことで、禅問答のお題を与えられ、その答えを考えながら坐禅をする。
だから、目をつぶってじっとしていることができる。答えを考えることに意識を集中することになるから、眠くはならないし、変なイメージや考え、思いが頭をめぐることは無いし、余計な雑念も排除しやすく、それでいて、目をつぶって視覚情報が入らないから、頭の中ではかなりクリアに考え事ができる。
今でも時々、坐禅の真似事を自宅でも、椅子に座りながらでもするが、お題を自分に出して、何でも、何食べようかなでも、こういうことは慣れだから、瞬時にスイッチが入って頭が回り出す感じが面白く、実際の公案の答えには正解があるようだが、何よりも自分なりの答えが愛おしく、尊く思えてくる。
"Kouan"
It is surprisingly difficult to keep your eyes closed and still sleepless.
Being blinded and standing still is painful for some people, can not imagine anything, can not think of anything, can imagine something or think about something. Those who are not accustomed to darkness at that time can not have strange images, thoughts, thoughts moving around their heads and closing their eyes.
Even if you can not think of anything or think about anything, you may feel sleepy. There is nothing as painful as it is not to sleep in a sleepy situation.
Some years ago, once a week, I had a sitting area early in the morning. A certain place is not a temple, but a Buddhist priest from Rinzai sects on a business trip for about an hour, and there is a security measure, and although the time is twice as short as 20 minutes each, it was a full-fledged zazen other than the place.
The feature of the Rinzai sect's Zazen is where you think about the torture and answer plan during the process. A public draft is a problem, given the title of torture, and sitting down while thinking about the answer.
So you can close your eyes and stay still. You will not be sleepy, you will not be weird images and thoughts, your mind will not go around your mind, and it will be easy to eliminate extra clutter, because you will concentrate on thinking the answers I can think about things fairly clearly in my head because no information is included.
Even now, sometimes I do imitations of zazen at home or while sitting in a chair, but I give myself the subject, whatever I am, whatever I eat, these things get used to it, so the switch turns on and the head turns The feeling of going out is interesting, and it seems that there is a correct answer in the actual answer of the draft, but more than anything, the answer of one's own love and seems to be precious.
最近知った言葉を思い出した。
「冷え枯れる」
室町中期の茶人、村田珠光の言葉、名言を残した人。
ひえかれる、年を重ねて成熟してくること、と知った時は解釈した。「枯れる」から成熟はあまりイメージできなかったので、だから印象に残っていたのかもしれない。
ひえかれる、には一言でいうと、衰退のイメージしかない。ただ、それは反対の言葉、例えば「熱し盛る」などが豪華絢爛で、それが良いということが前提でのイメージであり、珠光は「冷え枯れる」を良いこと、そこに美意識がある、としてこの言葉を残したのだろうから、改めて「冷え枯れる」を読み味わってみる。
ひえかれる、澄んで凛とした冷たい空気が張り詰めて、そこには豪奢なものは何も無く、あるものは必然的に存在するものだけ、そこにあることが定めのようなものだけ。
ひえかれる、真の成熟の姿が一言で表されているような気がした。
"Mature"
I remembered the words I learned recently.
"Cold and dry"
A man from the middle of the Muromachi tea ceremony, the words of Murata Tamaki, and quotes.
When I learned that it would be held, matured by age, I interpreted it. Because I could not imagine much maturity from "withered", it may have left an impression.
In a nutshell, there is only an image of decline. However, it is an image based on the premise that the opposite term, for example, "Heat up" is luxurious, and that it is good, and the light is "cold and dry" is good, there is a sense of beauty, and this word I will read and taste "Cold and dry" again.
There is a clear, cool, cold air filled, there is nothing arrogant, there is only a certain thing that is necessarily present, only something that is there to be.
I felt as if the figure of true maturity to be held is expressed in one word.
最近知った言葉を思い出した。
「我が心を師にするな、心は師に導かれる」
室町中期の茶人、村田珠光の言葉、名言を残した人。
いろいろな解釈ができそうだが、規範は自分の中には置かず、外に求めるとも読め、その規範は自分の都合とは関係が無く、時には自分とは真逆のことも。
思い込みを捨てよ。思い込みを解くには自分の外に耳を傾けて、素直に従うこととも。
自分がわかる範囲などたかが知れている。外に向かって自分を解放し、広い視野を求めなさいとも。
師は我が心がつくるのではなく、師が我が心をつくるとも。
いずれにせよ、自分という者に重きを置くな、自分を疑え、自分の間違いに気づけ、そして、自分を常に空っぽにしておくことが大事だと解釈をした。
"empty"
I remembered the words I learned recently.
"Do not master my heart, my heart will be guided by him"
A man from the middle of the Muromachi tea ceremony, the words of Murata Tamaki, and quotes.
Although it seems that various interpretations can be made, the norm does not exist in oneself, and it can be read as it seeks out, and the norm has nothing to do with one's convenience, and sometimes it is the opposite of oneself.
Discard your beliefs. You can listen outside of yourself and follow obediently to get rid of your assumptions.
It is known how much I can understand. Free yourself out and seek a broad vision.
The teacher does not make my heart, but the teacher makes my heart.
Anyway, I did not put a weight on the person I called, I doubted myself, noticed my mistakes, and interpreted that it was important to keep myself empty.
意識をして何かに取り込むことは、ああ、楽しいな、面白いな、きっと、見ているだけとか、食べているだけとか、よりも良いと思ってしまう。
だから、何でも自分でやろうとしてしまい、余計に時間がかかってしまい、どうしたらいいかな、と悩む時もあるけれど、そこがまた楽しかったりする。
結局、そこの部分が無いと毎日の生活が楽しくない、日常の出来事に満足できないのだと思うが、よくよく振り返ったり、細かく見ていくと、そのものズバリ、今取り組むべきことよりも、その周辺の整理することが多かったり、そこに気をとられていたりして、そこから抜け出せないでいることも多い。
前は、その周辺のことにヒントや学ぶことも多く、そこも大事というか、そこの方が大事だと思っていたけれど、それは、そのものズバリ、今取り組むべきことから逃避しているに過ぎないので、最近は気にも止めないようにしているが、なかなか、素直に向き合うのも、いろいろ試行錯誤があって、変化があって、ヒントも学ぶこともある。
"Facing"
Being conscious and taking something into something is a lot more fun, interesting, surely, better than just looking, eating, and so on.
So I try to do everything myself, it takes extra time, and sometimes I wonder how to do it, but I enjoy it again.
After all, I think I can not enjoy my daily life without my part, but I am not satisfied with my daily events, but if I look back on it carefully or look in detail, it's better than things I should work on now. There are a lot of things to be organized and taken care of there, and in many cases they can not get out of there.
I used to think that there were a lot of hints and lessons in the surrounding area, and that was important, but I thought that there was more important, but it is only a escape from things that should be tackled now. So, I try not to stop my mind these days, but there are many trials and errors in facing honestly, there are changes, and there are also hints and lessons.
なかなかできないことをどうしてできないのだろうか、と考えていたら、まず、できることはどうしてできるのだろかと考えてみた、行き着いた答えは、全てをパターン化できて、ルーティン化していることだった。
単純な作業や簡単な家事は全てパターン化していて、ルーティン化している、それは特にそうしようと思った訳ではなくて、毎日のことだから自然とパターン化され、ルーティン化した、意識した訳ではない、だからか、自分の都合の良いように、楽なように、何も考えないでできるように、やりながら他のことを考えることができるようにそうしただけ。
できなかったことを意識してパターン化してルーティン化してみようと思う。本当にそれだけで、今まで上手くできなかったことが、上手くできるようになるのだろうか。
そのためには、全てに正解があると意識して、全てに制限時間を設ける必要があるかもしれない、それは日々の単純な作業や簡単な家事をこなすのと一緒と思えば大したことはないか、それで余白が頭の中にたくさんできればいい。
"Patterning routineization"
If I was wondering why I could not do something I could not do, I thought first of all I could do what I could do, the answer I came to was that I could pattern everything and make it routine.
Simple tasks and simple chores are all patterned and routine, not specifically intended to be so daily, so they are naturally patterned, routine, not conscious So, as it is convenient for me, just as easy, as I can think without doing anything, just as I can think of other things while doing.
I will try to make it into a routine and make it conscious of what I could not do. Does it really make it possible to do things that could not be done well until now?
To that end, you need to be aware that everything has the correct answer, and you need to set a time limit for everything, which is not a big deal with daily simple tasks and simple chores. Or, I wish I could make a lot of margins in my head.
どこまで想像力を働かせるかが重要だと、想像力の使い道は様々で、例えば、リスクヘッジも想像力が重要で、起こりうるリスクをどこまで想像できるか、よく想定という言葉を使うが、「想定内」など、それも要するに、想像力の範囲がどこまで及ぶかの問題で、範囲が広くないとリスクヘッジにもならない。
子供の頃に遊んだ缶蹴りと一緒で、缶を守るのか、缶をどこからどのタイミングで蹴りに行くのかと、ありったけの想像力を働かせて遊ぶのとリスクヘッジの想像力の働かせ方は同じ、大人になってからでも缶蹴りで遊ぶと楽しいと思うのだけれど。
きっと想像力は豊かの方が良いというのは誰しも思うところで、否定する人はいないと思うが、何でもそうだが、練度が上がってくると、それまで気がつかなかったことに気づくようになる。こなすことで精一杯だったことが慣れてくると、それまで当たり前にそうだとしていたことに疑問を持ちはじめ、試行錯誤をしはじめるが、それを当たり前だとして、そのまま疑問を持ってもスルーする人もいる。
気づくことは想像力を働かせることだから良いことだが、もっと想像力が働くと、気づいた先にある結果がどうなるかがわかる。スルー人はその想像力が働いているのかもしれないと想像力を働かせてみる。
"Range of imagination"
If it is important how much imagination is used, there are various uses of imagination. For example, risk hedge is also important in imagination, how far can you imagine possible risks, often using the term "assuming", etc. In short, it is a matter of how far the scope of imagination extends, and it is neither a hedge nor a risk hedge if the scope is not wide.
With the cans that I played in my childhood, protect the cans, from where and when to kick the cans, and the same way of working with the imagination that you used to work and the imagination of the risk hedge the same for adults I think it would be fun to play with can kicks even after that.
Surely nobody thinks that imaginative power is better if anyone thinks, but no one thinks anything like that, but when the level of practice rises, you will notice that you have not noticed until then. When you get used to doing the things you get used to, you begin to ask questions about what you used to do, and then you start trial and error, but it's a matter of course, people who pass through as they are There is also.
It is a good thing to notice because it works your imagination, but if you have more imagination, you will see what happens at the end of the notice. Through people try to use their imagination that they may be working.
間違った方向に進んでしまうのは地図を持たずに行動してしまうからで、そんなことをする訳がないだろうと思うが、案外そういう人は多いような気がする。だって、普通に、とりあえず即行動しよう、なんてことを言う人が多いし、そのようなことをうたっている本も多いし、とりあえず即行動して、行動することは良いことで、あとは動きながら考えれば良い、考える前に直感を信じて行動しなさい、そうしないと機会を失う、なんて具合に。
地図の効用は、目的地までのルートがわかることで、ルートがわかるから、きちんと目的地に着ける。
では、地図を手にするには、まずその前に、目的地がそこで良いのかの方が重要で、そこを直感で決めている時点で、根拠のないギャンブルをしているようで、ギャンブルだから当たることもあるかもしれないが、1度きりでリスクの無いことならば良いが、この先何度もあり、リスクもあることならば、きちんと根拠は必要だし、それも論理的な根拠で、根拠があるならば直感に頼る必要もない。
目的地を決め、地図を手にするにも、事前の情報収集や検討に時間を割かないと、それも徹底的にやらないと、リスクにも対応できない。
地図を持たずに即行動なんて、例えると、東京駅に着いて新宿駅が目的地だとして、どのルートで新宿駅まで行ったら良いのかわからないから、片っ端から東京駅に着いた電車に乗るようなもの、たまたま偶然、中央線や山手線に乗ることができれば良いが、そもそも、そのようなことはしないだろうに、路線図を見るか、人に尋ねるだろうに、直感で行動しないでしょう。
即行動をして良い場合は、目的地がはっきりしていて、地図を持っている時だけ、逆に言えば、目的地がはっきりして、地図があれば、行動するなど容易いこと、自戒を込めて。
"Do not act immediately"
I'm going to go wrong because I'm acting without a map, so I think I'm not going to do that, but I feel like there are a lot of people like that. Because there are many people who usually say, let's act immediately and for the time being, there are many books that sing such a thing, and it is good to act immediately and act for the time being, and while it is moving If you think about it, act on your intuition before thinking about it, otherwise you lose the opportunity.
The utility of the map is that if you know the route to the destination, you can know the route, so you can reach the destination properly.
So, first of all, to get a map, it is more important that the destination is good there, and it seems that you are doing gambling without base at the time you are deciding with that intuition, and gambling It may be hit, but it is good if there is no risk at one time only, but if there are many more and there are risks in the future, a proper basis is necessary, and it is a rational basis, it is a basis There is no need to rely on intuition if there is.
Even if you decide on a destination and get a map, you have to spend time in advance gathering and examining information, or you can not cope with risks unless you do it thoroughly.
If you take immediate action without having a map, for example, if you arrive at Tokyo Station and Shinjuku Station is the destination, you do not know which route to go to Shinjuku Station, so take a train that arrived at Tokyo Station from the other end It would be nice if I could get on the Chuo Line or Yamanote Line by accident, but I would not act with intuition to see the route map or ask people if I would not do such things in the first place.
If you are willing to act immediately, only when the destination is clear and have a map, conversely, if the destination is clear, if there is a map, it is easy to act, and self discipline Please.
結局、同じパターンの繰り返しでしかない。
案件によって、仕事の手順を変えることは無く、着手から完了まで、流れは一緒で、パターン化され、自動的に作業をしていることも多い。
作業と呼べることは、単純なことや繰り返しのことで、特に作業中に何かを決断する必要も無いことなので、1人で複数の仕事を全てこなそうとすると、意外とこの作業と呼べることの量が多いから、パターン化し自動的に行い、考えたり、決断したりすることに時間を多く割り当てようとする。
作業と呼べることのパターン化は、何でもそうだから、プライベートでも、掃除にして、考えてみると、案外同じことを繰り返しているので、朝起きてから家を出るまで、大体同じパターンだったりするから、もちろん、パターン化にコツはあり、選択しないようにするとかはあるけれど、意外と簡単にできるが、考えたり、決断したりすることもパターン化、というか、よくよく思い返してみると、そういう時も大体同じ行動をしているから、できそうだが、時間が読めない。
パターン化の1番のメリットは時間が読めることだから、時間が読めないとパターン化する意味が無い。
考えたり、決断したりすることをパターン化するには、同じ時間で結果が出るようにしなければならない。それをやろうとすると、試験と同じで、制限時間内に答えを出すことに、何ごとにも締め切りはあるので、制限時間を設けるのは当たり前のことだから、仕方がないと、まず、時間設定をして最適解を出す、それをパターン化する、結局、当たり前のように、ここに行き着く。
時間をかければ良い物ができる、締め切りよりも良い物、納得できる物ができないと意味が無い、良い物をつくるためには多少時間をオーバーしても良いだろう、とのせめぎ合い、それもパターン化の前では霞む。
"Reading time"
After all, it is only a repetition of the same pattern.
Depending on the case, there will be no change in the work procedure, and the flow will often be together, patterned and working automatically from start to finish.
Being able to call work is simple and repetitive, and there is no need to make a decision on anything in particular, so if you try to do all the work by one person, you can surprisingly call this work Because there is a lot of amount of time, we try to allocate more time to make patterns, automatically, think and make decisions.
The pattern of what can be called work can be anything, so even if it's private, it's pretty much the same pattern from waking up to leaving the house, because it's unexpectedly repeating the same thing if you think about it. Of course, there is a knack for patterning, and there is a way to avoid selection, but it is surprisingly easy, but thinking and making decisions is also patterned, or if you try to reflect on it well, I think I can do it because I do the same thing, but I can not read the time.
The first merit of patterning is that you can read time, so if you can not read time, there is no point in patterning.
To pattern thinking and making decisions, we need to get the results in the same time. If you try to do that, there is a deadline for making an answer within the same time limit as in the test, so it is only natural to set a time limit, so there is no choice but to set the time first Then you get an optimal solution, pattern it, and you end up here, as you would expect.
It takes time to do something good, something better than a deadline, something that can not be convinced is meaningless, it may be more than a little time to make a good thing I hate it before patterning.
ルーティンでこなすようにしている。
建築の設計ははじめから最後のアウトプットまでやることは同じ、そのやり方が建築の内容によって変化することは無い。極端なことを言えば、大学の設計演習の時と大して変わらない。違いがあるとしたら、私にとっては、手書きがCADに変わったくらい。
ただ、もっと細かく言うと、そのルーティンの質が変わった。簡単に言うと、作業の負担が減り、頭の中にできる余白領域がより増えてきた。
手書きの時代は、今はもう全く想像もできないし、その時代を知らない人の方が多いかもしれないが、図面を一枚一枚、最初から、手で描くということは相当な仕事量で負担であり、そのおかげで毎日終電に乗っていた。
それがCADが導入され、最初から図面を描くことはほとんどなくなり、過去の仕事で作成した図面データも利用でき、もちろん、全く違うディテール、全く違う建築になるのだが、図面作成に限って言えば、この過去の図面データを利用できることで、図面作成作業の負担がかなり軽減された。
負担軽減はそのまま時間短縮と頭の中に余白を、考える余裕をより与えてくれた。
そして、今、全てがデジタル化され、タブレットでスケッチし、そのスケッチデータからBIMを使い、3Dのモデルデータをつくり、そこから必要な図面やパースを取り出したり、3DモデルデータをVRで確認したり、3Dプリンターで模型にする。
もはや、この一連の流れをルーティンでこなすことにより、作業自体に関しては何も考える必要がなく、それでいて、設計の成果品としての質は担保され、なおかつ、頭の中に自由に使える余白領域がより増えたので、より設計の質を上げることに時間と頭を使えるようになった。
"Change of routine"
I will do my routine.
The design of the building is the same from the beginning to the final output, and the way does not change depending on the content of the building. Extremely speaking, it is no different from the university design exercises. If there is a difference, for me, handwriting has changed to CAD.
But more precisely, the quality of the routine has changed. Simply put, the work load has been reduced and the margin area in the head has been increased.
I can not imagine the age of handwriting now, and there may be many people who do not know the age, but drawing drawings by hand, one by one, from the beginning with a considerable amount of work It was a burden and thanks to that I was riding the last train every day.
That's why CAD was introduced, drawing almost nothing from the beginning, drawing data created in past work are also available, and of course, completely different details, completely different architecture, but speaking of drawing creation only By using this past drawing data, the burden of drawing creation work was considerably reduced.
The burden reduction gave me more time to think about the time saving and the margin in my head.
And now, everything is digitized, sketched with a tablet, using BIM from the sketch data, create 3D model data, extract necessary drawings and perspectives from there, or check 3D model data with VR Make a model with a 3D printer.
By doing this routine routinely, there is no need to think about the work itself, yet the quality as a design product is secured, and there is more free space available in the head. With the increase, I can use time and mind to improve the quality of the design.
見ることが優先しすぎていて、感じることが疎かになっているような気がする。
以前、お店で、デジカメを使い料理を撮影してはSNSに投稿し、スマホ片手に料理を食べながら、その投稿の反応を確認している人を見た、結局、料理は食べ残し。
その人が、料理は食べてどう感じるかより、この料理を見ていることの方が大事で、意義あることだと普通に考えているから、食べることを疎かにしてでも、写真をSNSに投稿するのだろう。
見ることで全てを感じている、全てを理解していると勘違いをしているのかもしれない。SNSに投稿することで注目をされたいとか、食べることに興味が無いのかもしれないが、それならば、料理で無くても投稿内容がいいのでは。
この人は極端な例かもしれないが、程度の差こそあれ、見ることで全てを感じ、理解していると勘違いをしてしまうことはよくあるだろう。
映像や画像の世界はまさにそこがポイントで、見ることだけで、どれだけ多くのことを感じ、どれだけ多くの情報量を得ることができるか、ただ、視覚以外の感覚は全て擬似体験でしかないのだが、見る側はそこの見るだけで全てを擬似体験として感じる訓練を毎日のようにさせられている。
だから、感じることが疎かになっても仕方がなく、だから、感じることを求めて、無意識に、身体を動かしたくなるのかもしれないし、運動したり、自然の中に行ったりとしたくなるのかもしれない、とふと思った。
"Simulated experience"
I feel that it is too high priority to see, and it feels like I am not feeling well.
Before, I used a digital camera to shoot food and post it on SNS, and while eating food with a smartphone, I saw people who confirmed the response to that post, and after all, I left the food.
Because the person thinks that it is important to look at this dish rather than how to eat it and thinks that it is significant that it is meaningful, even if it is neglected to eat, the photograph to SNS Will post.
Feeling everything by looking, it may be misunderstood as understanding everything. You may want to get attention by posting to SNS, or you may not be interested in eating, but if that is the case, it would be nice to post content even if you are not cooking.
This person may be an extreme example, but it is often the case that, to a greater or lesser extent, you look at everything to feel and understand and you misunderstand.
The world of images and images is just the point, and just seeing, how much you feel and how much information can be obtained, but all senses other than visual are only simulated experiences There is no, but the viewer is made to do training that feels everything as a simulated experience just by looking there, every day.
So there is no way it feels even if you feel insane, so you may want to unconsciously move your body, to seek to feel, to exercise or to go into nature. I thought that I might.
常に全身で体感するし、してしまう、建築は人のスケールよりも大きく、建築は空間を内包する、そもそも、その空間をつくるために建築行為は存在するから、体感が前提になる。
しかし、人は体感することよりも、視覚が先行する。視覚も五感の一部だから、視覚も体感の一部と考えるかもしれないが、モダニズム建築以降、視覚だけが分離した。
20世紀初頭、写真の発達により、その写真に建築をどのように載せるか、写真に載せることができる建築の部分は一部だけ、全てを載せることはできない、その建築の一部が写真として広まる。
体感すること無しに、その建築の一部の写真を見て、その建築の全てを把握できるようにしなければならない、それも写真はその場にとどまることはない、建築はその場所から動くことはできないが、写真となった建築は自由に動き回ることができるから、時間的余裕がない、だから、瞬時に全てを把握できるようにしなくてはならない。
視覚優位に建築が展開されていく、瞬時の視覚を経て、体感へと移行する建築が優位になる。
もちろん、モダニズム建築は変遷していくのだが、そもそも現代の建築や都市はモダニズム建築を下敷きにしているので、視覚が優位になりやすい。それが人の感覚器官にまで影響を与えていると言っても過言ではないだろう、人は日々、建築や都市に内包されているのだから、影響を受けないはずがない、インスタ映えを欲しがるのもうなずける。
体感が前提で建築行為は存在する、しかし、体感の前に視覚がくる、この認知のズレというか、感じる前に見てしまうことが起こるということが、建築デザインをする上で肝になることで、どう見せるか、どう見えるか、建築雑誌をパラパラと見ていて、そもそもここでも見るから入るのだが、止まるのは既視感がない建築になる、すでに見慣れ光景には興味がわかない、「既視感がない」ということにその建築の全てが凝縮されている。
"I see first"
You always experience the whole body and you feel, building is bigger than human scale, and building includes space. Because building act exists to create the space from the beginning, the sense of living is a premise.
However, the vision precedes the human being to feel. Since vision is also part of the five senses, vision may be considered part of bodily sensation, but since modernism architecture, only vision has separated.
At the beginning of the twentieth century, with the development of photography, how to put architecture in the photograph, only a part of the architecture that can be put in the photograph, but not all, part of the architecture spreads as a photograph .
You must be able to look at some of the photos of the architecture and make it possible to grasp all of the architecture without experiencing it, and the photos will not stay there, the architecture will move from that location Although it can not be done, since the architecture which became a photograph can move freely, it can not afford time, so it must be able to grasp all in an instant.
As architecture is developed in a visual superiority, through instantaneous vision, an architecture that shifts to a bodily sensation becomes superior.
Of course, modernist architecture is changing, but since modern architecture and cities are based on modernist architecture, vision tends to be dominant. It is no exaggeration to say that it affects even human sense organs, because people are included daily in architecture and in the city, they can not be influenced, wanting insta light I can't make it worse.
Building act is premised on bodily sensation, but there is a gap in this cognition when vision comes before bodily sensation, or that it happens to be seen before feeling it, and it becomes a key point in doing architectural design So, I wonder how to see it and how to see it, because I look at architectural magazines as flip-flops, and I'm going to see it from the first place, but the stop will be an architecture with no sense of sight, I'm not interested in sights already familiar, All the buildings are condensed in the sense that there is no sense of sight.
真の想像力を働かせるためには、目を閉じるしかない。目の前で起こることを見てしまったら、その範囲でしか頭が働かないから。
目で見ることで情報源の8割を把握する、すなわち、視覚で8割が決まる、仮に、視覚以外の感覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚を全て遮断したとしても、裁量の部分は2割しかなく、8割決まれば、大概はその印象になる。
だから、目を閉じることで、8割の情報を遮断し、聴覚、味覚、嗅覚、触覚を使い2割の情報を取得し、8割を裁量の部分に回せば良いとなる、単純な計算ならば。
目を閉じればわかるが、見ることを遮断しても、人は目で見ようとしてしまう。ただ単に、シャッターが閉まっているが如く、瞼が閉じているだけで、シャッターの中では、目の中では視神経が働いている。
すなわち、目を閉じても、五感の割合は変わらず、視覚が0になる訳ではなく、視覚以外の感覚が2割以上になることもない。
8割の視覚情報が真っ暗、真っ暗なスクリーンがそこにあるだけ、ただ、その状態になってはじめて、その真っ暗なスクリーンに、それまで経験した過去の出来事が素となって発揮される想像力が映像を映し出してくれる。
だから、いずれにせよ、人は視覚に左右されており、それはあまりにも今まで目で見てきた映像や画像の蓄積が脳にたくさんある証拠というか、すでに人が視覚優位から逃れられない証拠になる。
"The dark screen"
The only way to make your true imagination work is to close your eyes. If you see what happens in front of you, your head only works in that range.
80% of the information source can be grasped by visual observation, that is, 80% can be determined visually, even if all senses other than visual sense, hearing, taste, smell and touch are cut off, the discretionary part is 20% There is only one, and if it is 8 percent, it will usually be the impression.
So, by closing your eyes, you can block 80% of information, use hearing, taste, smell and touch to acquire 20% of information, and turn 80% into the discretionary part. If
I know if I close my eyes, but even if I stop seeing, people try to look at my eyes. Just like the shutter is closed, the eyelids are just closed, and in the shutter, the optic nerve is working in the eyes.
That is, even if the eyes are closed, the ratio of the five senses does not change, and the sense of sight does not become zero, and the sense other than the sense of sight does not become more than twenty percent.
As long as 80% of the visual information is completely dark and there is a very dark screen, it is only when it is in that state that the imagination of the past events experienced so far is displayed on the very dark screen. Will be projected.
So, in any case, people are affected by vision, which is evidence that there is a lot of accumulation of images and images that have been seen so far in the brain, or evidence that people can not escape from visual superiority already. Become.
写真だとスケール感がわからない時がある。
先日、手に入れたアンジェロ・マンジャロッティがデザインした置時計「セクティコン」がそうだった。実物を今まで見たことがなく、写真でしか知らなかった。写真でどのような形をしていて、色や細部のデザインは知っていたが、大きさを数値で把握していた訳ではなく、大きさは写真から勝手にこのぐらいだろうと想像して決めつけて、特にそのことに気も止めてもいなかった。
セクティコンの実物をはじめて見て持った時の印象は「意外と大きくて重いな」で、それがデザインの印象より先だった。
重さは数値で知ったとしても、あまり実感がわかないかもしれない。普段から物の重さを扱っているならば、数値で言われても感覚的に重さがわかるだろうが、大きさならば感覚的にわかるが、今回はなぜかはじめから勝手に決めつけていた。
よく考えてみれば、セクティコンは船室用置時計としてデザインされたものだから、船の揺れに耐えるためにも、ある程度の重さが必要だろうし、視認性を考えれば、文字盤の大きさはこのくらいは必要だから、全体の形状をこのデザインにするならば、大きさは当然このようになる。そこで、もしかしたら、外装にプラスティックを使い、見た目で少しでも軽快さを出そうとしたのかもしれない。
ただ、なぜか、写真で見たセクティコンの形状ではもっと小さいものになる、というか、もっと小さいものを求めてしまう。自分がもしセクティコンと同じ形状のものをつくろうとしたら、もっと小さくするだろう。それは好みかもしれないし、もしかしたら、実際に小さくつくったら、やはりこの大きさの方が良いとなるかもしれない。
重さは素材を変えれば自由にコントロールできるが、後は視認性の問題、そこから大きさが決まるだろうが、ただやはり、この形状のデザインに対して大きさが合っていないように思う、それをスケール感と呼ぶならば、スケール感が合っていないように思う。
セクティコンを見ていて、デザインとスケール感には相関関係がある、言い換えれば、暗黙のルールがある、と改めて思った。
"Implicit rules"
There are times when I do not understand the sense of scale with photos.
The table clock "Secticon" designed by Angelo Manjarotti, which I got the other day, was so. I have never seen the real thing, I only knew in the picture. I was in the shape of the picture, I knew the design of the color and details, but I did not know the size numerically, I decided that I imagined that the size is about this from the photo I was not particularly worried about it.
The impression when I first saw and held the real of the secticon was "It's unexpectedly large and heavy", which was ahead of the impression of design.
Even if you know the weight numerically, you may not realize much. If you usually deal with the weight of things, weight will be understood sensibly even if it is said numerically, but if it is size, it will be felt sensibly The
If you think about it carefully, because secticon is designed as a table clock for the cabin, it will need a certain amount of weight to withstand the ship's shaking, and considering the visibility, the size of the dial is this much Is necessary, so if you make the whole shape this design, the size will naturally be like this. So maybe I used plastic for the exterior and tried to put out some lightness in appearance.
However, for some reason, the shape of the secticon seen in the photograph will be smaller, or something smaller will be sought. If you try to make it the same shape as the secticon, you will make it smaller. It may be a preference, and if it actually gets smaller, it may still be better for this size.
The weight can be controlled freely by changing the material, but after that the problem of visibility, the size will be decided from that, but still it seems that the size does not match the design of this shape, If you call it a sense of scale, it does not seem like a sense of scale.
Looking at the secticon, I thought again that there is a correlation between design and sense of scale, in other words, there is an implicit rule.
どんどん大きくなったり、どんどん小さくなったりできるとすると、スケールなんてあってないようなものになる。
大きさが変わらないから、スケール感が大事になるのであって、こちらが自由に大きさを変えることができれば、多少スケール感がズレていようが大した問題ではない。
あとひと回り小さければ良いのにとか、大き過ぎなんだよなとか、はどうでも良いことになる。
スケール感だけが唯一のデザイン要素だとしても、そのスケール感を適切というか、合ったものにするだけで良く見えるし、その反対に、形は綺麗なのだが、スケール感が、あとちょっとだけ大きい方がいいとか、スケール感が合わないと、スケール感だけの話でせっかくの綺麗な形が台無しになることもある。
そのくらいスケール感は重要で、ただ、具体的に何センチがいいとか、何ミリがいいとかは無いので、感覚的なものを養う必要がある。
そのスケール感が無力化するとしたら、スケール感に変わるデザイン要素は何になるだろうか、また、それでも残るスケール感はあるはずで、その時に何を頼りにスケール感を決めれば良いのか、ただ感覚だけの話では無いような気もするが。
仮定の話で、スケール感が無力化する状況で考えてみると、全体の大きさが決まらない。それこそ何を頼りに決めれば良いのか、わからなくなってしまう。そして、全体の大きさが決まらないと何も進まない。
部分をつくることはできるが、その大きさも全体の大きさに依存するから、やはり、何もできなくなる。
きっと世の中に大きさを自由に変えることができる生物がいないのは、このような理由からだったりして。
"Inactivation of the sense of scale"
If you can get bigger and smaller and get smaller, it will be like you don't have a scale.
Since the size does not change, the sense of scale is important, and if this can freely change the size, it is not a big problem that the sense of scale may be somewhat off.
It would be fine if it would be better if it was a little smaller, or if it was too big.
Even if only the sense of scale is the only design element, it looks good if the sense of scale is appropriate or appropriate. On the contrary, the shape is beautiful but the sense of scale is slightly larger If you don't like it, or if it doesn't match the scale, the story of the scale may ruin the beautiful shape.
The sense of scale is so important, however, it is necessary to cultivate sensory ones, because there is no specific thing about how many centimeters are good or how many millimeters are good.
If the sense of scale becomes ineffective, what will be the design elements that will change to a sense of scale, and there should still be a sense of scale that remains, and what should be used to determine the scale sense at that time, just the sense I do not feel like it's a story.
If you think about the situation where the sense of scale is incapacitated in the story of assumption, the size of the whole can not be decided. You will not know what to do with it. And nothing happens if the size of the whole is not decided.
You can create parts, but the size also depends on the size of the whole, so nothing can be done.
It is probably because of this reason that there is no living thing in the world that can freely change its size.
毎朝コーヒーを飲む時に、今日はどれにしようかな、とカップを選ぶのが楽しみのひとつ、最近、ずっと気に入って使っているカップが因州中井窯のもの。
因州中井窯は、鳥取にあり、民藝を代表する窯元で、柳宗理ディレクションの器もつくっている。特徴は染め分けで、緑と黒、緑と白に半々に染め分けする器が代表的なもの。
うちには同じ種類のカップが2つあり、最近、ずっと気に入って使っているカップはそのうちの1つ、いつも同じ、パッと見はほとんど違いはないが、僅かに違う。
胴の部分の曲線が違い、その差は1mm以内だが口径が僅かに違い、縁の厚みも微妙に違う。
焼き物ならばよくある話で、個体差、同じ種類のカップでもつくり手が違えば、微妙に形は違うし、焼き物は焼く時に窯の中で収縮をするので、窯の中での位置の違いにより温度も違うので、収縮率も違う。
だだ、2つを比べてみて、はじめて分かるくらいの微妙な違いなのだが、同じ種類のカップなのだが、いつも使うのはそのうちの1つ、いつも同じ。
見た目にはほとんど違いはないから2つとも気に入っているが、コーヒーを飲んで使うところまで含めると、その飲んで使う感覚まで含めると、明らかにそのうちの1つの方が良い。
その微妙な形の違いが、実際に使う時には増幅されて、大きな違いとなって使う側の感覚に訴えてくる。
もちろん、それが良いか悪いかは好みの問題だから、良し悪しはどうでもよいのだけれども、微妙な形の違いが使う時に増幅されるのが面白く、それは使わなければ分からないことで、こういう微細な形の違いが有る無しは、1つ1つ手でつくるから起こることで、それが人の感覚に影響を与えることが素晴らしく、それが正しくものづくりの真髄だと感心した。
"The essence of manufacturing"
One of the pleasures of choosing a cup when drinking coffee every morning is one of my favorite cups.
Inshu Nakai is located in Tottori, and is a representative of folk songs, and is also making pots for the direction of the Sori Yanagi. Distinctive features are dyed, green and black, green and white dyed in half and half.
There are two cups of the same kind in my house, and recently I have always liked and used one of them, which is always the same.
The curve of the body part is different, and the difference is less than 1 mm, but the aperture is slightly different, and the thickness of the edge is also slightly different.
It is a common story about grilled dishes. Individual differences, even if the same kind of cups are made differently, the shape is slightly different, and the grilled foods shrink in the cocoon during baking, so the difference in the position in the cocoon Because the temperature is different depending on the shrinkage rate is also different.
Well, it's a subtle difference that you can see for the first time by comparing the two, but it's the same kind of cup, but always using one of them, always the same.
There is almost no difference in appearance, but I like both of them, but if you include coffee and use it, obviously one of them is better if you include the feeling of using it.
The difference in the subtle form is amplified when actually used, and it makes a big difference and appeals to the sense of the user.
Of course, whether it is good or bad is a matter of taste, so it doesn't matter whether it is good or bad, but it is interesting that the difference in subtle form is amplified when it is used, and that it is impossible to know it There was a difference in the form because it was created by hand one by one, and it was wonderful that it affects human senses, and I admired that it is the essence of making things right.
見る者と見られる者がいるという関係性が成り立つのが普通のことだと仮定したら、それが、見る者と見られる物でも良いのだが、その関係性自体が近代以降のことかもしれないが、外形には何かしらの意味を持たせることになるだろう。
外形とは、人ならば外身、物ならば外観で、もっと簡略化すれば、双方とも輪郭といえる。
その輪郭の意味を、見られる側は意図してつくるだろうし、見る側は都合よくつくるだろう。
別に意味など無くても良いと思うのだが、見る側が勝手に意味づけをしてしまう、それはたぶん、人の脳の構造の問題だと思うのだが、意味づけ、すなわち、認知することで、自分の周りの環境を把握し、自分の身の安全を保つのだろう。
だから、見られる側はその脳の構造を利用して、意図した意味づけをする、もちろん、その意図通りに見る側が意味をくみ取ってくるないこともあるだろうが、よくある話で、それが成り立つのも、見る者と見られる者がいるという関係性が前提になるから、要するに、見る側見られる側の関係性と輪郭の意味づけは共謀関係になる。
輪郭は様々な分野にあるが、最近、アンジェロ・マンジャロッティがデザインした置時計「セクティコン」を手に入れた。6年程前に復刻されたものではなく、60年前に船室用置時計としてデザイン・製造されたプラスチックの一体成型のオリジナルのもの。
その赤い丸みを帯びたフォルムは見る者に様々な想像を強いる。見られる側、すなわち、デザインした方の意図は計り知れないが、人を模したように、頭があり身体があるように見えなくもなく、水面からひょっこり顔を出したタコのようにも見えたり、もちろん、そのフォルムからミッドセンチュリーの雰囲気が漂ってきて、この時計を部屋に置いておくだけでもいい。
もし、見る側に誰もいなかったら、この時計自体の存在価値はあるのだろうかとさえ思ってしまう。
だから、見られると思って、見られることを意識してデザインする、当たり前だが、逆に言えば、見る側がいて、見る行為が無かったら、デザイン自体が無くても良いことになる。
デザインもまた、見る側見られる側の関係と共謀関係にあり、だから、見る側の目も引きたくなる。
などと、セクティコンを手にして思いながら、だから、既視感が無いことが重要だと改めて思う。
"Secticon"
Assuming that it is usual that the relationship between the viewer and the viewer is satisfied, it may be the one seen by the viewer, but the relationship itself may be after modern times , The external form will have some meaning.
The outer shape is the appearance of a person if it is a person and the appearance if it is a thing, and if it is more simplified, both of them can be said to be a contour.
The meaning of the contour will be purposefully created by the visible side, and conveniently by the viewing side.
I think it doesn't matter if I have no other meaning, but I think that the viewers make their own meaning, maybe it's a problem with the structure of the human brain, but by making meaning, that is, recognizing, Understand the environment around and keep your own safety.
So, the side to be seen uses the structure of the brain to make the intended meaning, and of course the side that looks as intended may not come to understand the meaning, but it is a common story. Since it is premised that there is a relationship between the viewer and the viewer, the relationship between the viewer and the viewer and the meaning of the contour become conspiracy, in short.
The outline is in various fields, but recently I got a table clock "Secticon" designed by Angelo Manjarotti. It is not reprinted about six years ago, but is an original plastic integrally molded and designed and manufactured as a cabinet clock 60 years ago.
The red rounded form forces the viewer to imagine various things. The side that can be seen, that is, the intention of the person who designed it, is immeasurable, but as a person imitating, it looks like a octopus with a head and a body, not as invisible as a head, and a face coming out of the water surface Or, of course, the atmosphere of mid-century comes from the form, and it is good to leave this watch in the room.
If there is no one on the side of the viewer, it even wonders if the watch itself is worthwhile.
So, I think that I can see it and design it consciously to be seen. It is a matter of course, but on the contrary, if there is no act to see, there is no need for the design itself.
The design is also in contradiction with the relationship between the viewer and the viewer, so the viewer's eyes also want to pull.
And while thinking about having a secticon, I think that it is important that there is no sense of sight.
絵画だけでなく、建築にも「作品化」はあるだろう。作品化とは作家性を出すこと。
どうしてもそうしたかったのだろう、その考え方だったら、そうはしないはずという見え方に出会う時があり、それは一貫性がないことになるのだが、それが建築を見ていて楽しい時でもある。
今まで見たことはなかったし、知らなかったけれども、もかしたら、この建築はあの人の作品かもしれない、という出会いもある。
それは明確には、こうだから、という特徴を言えないことも多いのだが、何とくそうではないかな、という程度だが、案外、それが当たっていたりする。
最近は、でも、あまりそういう作家性だとか、作品性を見るような建築に出会わなくなったような気がする。それは建築がモノとしての量感みたいなものよりも前に、言葉が先に出てくるから、自制心が働くのかもしれない。
何だか知らないけれど、これいいな、この建築いいな、と街を歩いていて思うのは、モノに対する強い引きがある時が多く、そこには匿名の作家性があるような気がして、より楽しい。
"Writing is from things"
Not only paintings, but also architecture, there will be work creation. To work is to put out a writer.
There is a time when I meet the way of thinking that I would not have done it if it was the way of thinking, it would be inconsistent, but it is also a fun time to look at architecture.
I have never seen it before, and I didn't know, but sometimes I met this architecture as the work of that person.
It is clear that, in many cases, it can not be said that this is the feature, but somehow it may not be, but it is unexpected or it is hit.
Recently, I feel that I have not been able to meet such an artist-like or architecture that looks like a work-type. It may be that self-control works because the words come first, before the architecture is like a volume.
I don't know what it is, but it's a good idea to walk around the city that this architecture is good, because there are times when there is a strong drag on things, it feels like there is an anonymous authorship, More fun.
見えてしまう話。お盆だからとは関係が無い話。
それっぽいものに見えてしまう、装えば、それなりに見えてしまう、見えるように取り繕える。
「作品化」という言葉をはじめて聞いたのは20代、美術学校へ少しだけ通っていた時、先生から。絵を仕上げるというか、まとめるというか、そういう意味で捉えていた。
例えば、「花」をそのまま描いても、それはスケッチをしただけであり、絵画という作品では無い。勿論、スケッチをしただけでも、その人なりのものは、そのスケッチに現れるのだが、あくまでもスケッチはスケッチ、絵画とは違う。
絵画とスケッチの違いは「作品化」を経ているかどうか、「作品化」に作家性を発揮して、その作家性が絵画を作品にする。
では「作品化」とはどうすることか。作家性を発揮することを20代の頃は単純に個性やセンスを発揮することだと思っていた。
だから、モチーフの陰影を無くして二次元化したり、色を実物のものとは変えたり、二次元化のさせた方や色の選択や配色に個性を出そうとしていた。
それも「作品化」の1つだとは思うけれど、今考えると、なんて稚拙なことをしていたか。個性やセンスを意識して、それを発揮しようとすればする程、それっぽいものにしようとして、それっぽいものになっていった。
それっぽいものとは、いわゆる絵画のようなもの、どこかで誰かがやっていそうなこと、その枠から外れないようにしようとすることが「作品化」だと思っていて、それが個性だと、今ならば違うと考えるのだが、「作品化」とは既視感が無いものを描くことだと。
そのための作業をする必要がある、と言われていたのだと。きっと、あの作家のように、と分類にされないようにしろよと。
"Working"
A story that you can see. It has nothing to do with it because it is the Bon festival.
It looks like it, if it is dressed, it looks like it, it can be managed to look like.
The first time I heard the word "making a work" was from my teacher when I was in the art school a little while in my twenties. I thought that I finished the picture or put it together, in that sense.
For example, if you draw "flower" as it is, it is only a sketch, not a painting. Of course, even if I just sketched, the personal thing appears in that sketch, but sketches are different from sketches and paintings.
Whether the difference between painting and sketching is "work-making", the artist's character is shown in "work-making", and the artist's nature makes the painting a work.
So what do you do with "making work"? When I was in my twenties, I thought it was about simply demonstrating individuality and sense to demonstrate writership.
Therefore, I was trying to show individuality in the two-dimensionalization, the choice of colors, and the color arrangement, by eliminating the shading of the motif and converting it to two-dimensional, changing the color from the real thing.
I think that is one of the "work-making", but how are you naive when you think about it now? The more I was conscious of my personality and sense, and the more I tried to make it, the more I wanted it to be.
What is like that is what is called painting, something that someone seems to be doing somewhere, and I think that trying to keep it out of that frame is "production", and that's an individuality So, I think that it would be different now, but "to work" is to draw something that has no sense of sight.
It was said that it was necessary to do the work for that. Surely not to be classified as being such a writer.
プランから「既視感が無い」ことがわかるか。
プランとは、この場合、平面図のこと。ありとあらゆる平面図を見ているが、確かに、今まで見たことが無いプランというものに時々遭遇するが、実際に建ち上がった空間を見ると、どこかで見たような空間であったり、別に新しくも無く、既視感が無い訳ではないことが多い。
プランでは空間の全てを表現できないので、そういうこともあるだろうが、そもそも「既視感が無い」ことはプランでは表現できないことなのだろう。
実際に空間を見た時にどう感じるかなので、その部分を判断するにはプランから想像するしかない。だから、「既視感が無い」かどうかもプランから知覚できる範囲を超えた所に存在することなのだろう。
"Exist in a place beyond the plan"
Do you understand from the plan that there is no feeling of being seen?
A plan is a plan view in this case. I'm looking at all sorts of floor plans, but I certainly encounter plans that I have never seen before, but when I look at the space actually erected, it looks like I saw it somewhere, There is nothing new, and often there is no sense of visual appearance.
The plan can not express all of the space, so that may be the case, but in the first place, "no sense of sight" may not be expressed in the plan.
Because it is how you feel when you actually see the space, you can only guess from the plan to judge that part. Therefore, it may be that it exists in the place beyond the range which can be perceived from a plan whether "there is no feeling of seeing".
真っ暗な中を歩いた。
慣れるまでは何も見えない、想像するしかない。
その時想像できるのは今まで見た光景のみ、それを手掛かりに手足を動かして進むしかない。
しだいに目が暗闇に慣れてきて、ぼんやりと辺りがわかるようになるがはっきりしない、その時も手掛かりは想像できる光景だ。
真っ暗であるから、これ以上ははっきりしない、結局、頼りは想像である。
想像で足を出し、手を広げ、探りながら進む。
突如、明るくなる。
目が明るさについていけず、眩しくて辺りがわからず、立ち止まる。
明るさに慣れ、見えてきた光景は、いつもとは違う見慣れない光景だった。
今いる場所はいつもの場所なのに、進む間に想像よりズレていた。
ズレが既視感を奪った。
"Imagination"
I walked in the dark.
I can not see anything until I get used, I can only imagine.
At that time, I can only imagine the sights I have seen so far, I have to move the limbs with it as a clue.
The eyes gradually get used to the dark, and it becomes vague to understand the surroundings, but it is unclear, and even then the clue is a sight that can be imagined.
Because it is dark, it is not clear anymore, after all, reliance is imagination.
I'm out with my imagination, spread out my hands, and explore.
Suddenly, it gets brighter.
I can't keep my eyes bright and dazzling, I don't know where I am, I stop.
The sight I used to see and used to be bright was an unfamiliar sight different from usual.
The place where I was now was the usual place, but I was shifted from my imagination as I went.
The gap deprived a sense of sight.
「見たことが無い」ものに出会った時、本当に全く見たことが無いものだと理解ができず、何が何だか分からなくなる。
「見たことが無い」ものをつくろうとするのは、新しいものをつくりたいと思い、その見た目について考えている時に起きる衝動である。
しかし、本当に全く見たことが無ければ、理解もできないのだから、新しいとも思われない。
本当に全く見たことが無いものをつくる、又は、本当に全く見たことが無いことをすることを「奇抜」と言う。「奇抜」なことをする時は、新しいことをしようとする時だが、本当に全く見たことが無い「奇抜」は理解がされないから、新しいとも思われず、変なことをしていると思われるだけ。
「奇抜」に関しては、どの分野でも言えることで、この単純な理屈が案外分からずに、よくあることだったりする。
「奇抜」が悪い訳ではないが、新しいことをしようとする時は注意が必要で、どこかで、何かがそれまでの文脈とつながっていないと、新しいとは思われない。
ここが面白いところで、実際に新しいことと、新しいと思われることは違う。本当に全く見たことが無いものであれば、それは新しいはずなのに、新しいとは理解されない。
それが新しいと思わせるためには、どこかで見たような感じがありながら、でも探してもどこにも無い状態、すなわち、それが「既視感が無い」ということである。
"It is different from stranger"
When you meet something that you have never seen, you can not understand what you have never seen at all and you will not know what it is.
Trying to create something that has never been seen is an impulse that occurs when you want to create something new and think about its appearance.
However, since I can not understand it without really seeing it at all, I do not think that it is new.
Making something that you have never seen at all, or doing something that you have never seen at all, is called "wandering". When doing something "wandering", when trying to do something new, "wandering" that you have never seen at all is not understood, so it seems that you are doing something strange without thinking it is new Only.
As for "wandering", what can be said in any field is that this simple logic is a matter of fact, not surprisingly.
Although "wandering" isn't bad, you need to be careful when trying to do something new, and it doesn't seem new unless something is connected to the context so far.
Where this is interesting, what's really new is different from what you think is new. If you have never seen it at all, it should be new, but not understood as new.
In order to make it seem new, there is a feeling that we have seen somewhere, but there is nowhere in the search, that is, it has no sense of sight.
ここのところずっと「既視感が無い」とはどういうことかを考えている。簡単に言えば「見たことが無い」ということだが、単純に見たことが無いだけならば、知らないものに出会えば、全て「既視感が無い」ものになる。
今まで知らなかったもの、見たことが無かったものを見たからと言って「既視感が無い」とは思わないだろう。
「既視感」とは「以前に見たはずも無いのに、いつか既に見ていると感ずる、その感じ」とある。それが無いということは、既に見ているはずが無い、と感じることか。
ならば「既視感が無い」とは、既にどこかで見ている可能性があるかなと自身を探りながら、最後にはそれを否定する、それが瞬時に行われることか。
ということは「既視感が無い」状態をつくり出すには、既にどこかにはありそうな感じが最初にあり、ただ、よく見ていくと違うと、最後に「無い」とすることだろうか。
"" There is no sense of sight "state"
I've been thinking about what it means to have no sense of sight all the time. To put it simply, "I have never seen it", but if I have never seen it simply, if I encounter something I do not know, it will be "I have no sense of sight".
You probably won't think that you have no sense of sight just because you saw something you didn't know or saw before.
"The visceral feeling" is "It feels like you're already seeing it someday, even though you've never seen it before." If you don't have it, feel that you can't see it already.
Then, "does not have a feeling of sight" means searching for itself as if it may already be seen somewhere, and denying it at the end, is it done in an instant?
That means that in order to create a state of "no sense of sight", it seems that there is already a feeling that is likely to be somewhere, but if you look closely, you may end up with "no" .
ラワンベニヤを鍋ビスで留める、壁天井を全て、前に連続して住宅で使ったら、最近、ホームページの作品を見て、その仕上げをオーダーされることが多い。
基本的には、その住宅に対して考えたデザインは二度と他では使わないようにしている。それは、そのデザインにした理由が当然あり、その時にしか成り立たないことだから、他で使えば、それは単にデザインだけが独り歩きをし、何も考えていないような気がするので、その時連続して使ったのは隣り合う兄弟の家で連作だったから。
ただ、このラワンベニヤを鍋ビスで留める仕上げは気に入ってしまった。
離れて見ると、ラワンベニヤの質感が部屋全体に溢れ、その木目があまりにも多いので、見ようによっては何か別の木では無い質感に見え、また、近づくと、今度は鍋ビスの存在が急に目に飛び込んで来て、ラワンベニヤの質感にまた違ったアクセントを加え、違った見え方をする。
離れて見た時と近づいて見た時で、仕上げの見え方が違い、人の動きに呼応するように建築が表情を変えるところが良かった。
その時は、ラワンベニヤの留め方をどうするかを考えていて、よく見かけるのは接着剤とフィニッシュと呼ばれる細い釘の併用だが、それではラワンベニヤの経年の反りに対して脆弱なような気がして、留めるのにビスを使いたい、ただそれだと、ラワンベニヤの面に余計な物が見え、折角、壁天井をラワンベニヤだけで仕上げるという、統一感の良さが無くなるような気がした。
そこで、使うビスは施工性を考えて、比較的手に入りやすい物を使うが、ビスの頭の形状、色、ピッチを検討して、ラワンベニヤとビスが合わさることにより、より綺麗な仕上げに見え、離れて見た時と近づいて見た時で、仕上げの見え方が違うことを意識して、現場で何度も試作しながらデザインした。
この仕上げは、ベニヤを鍋ビスで留める、という単純な仕組みながら、その見え方の変化は複雑で、あと、竣工後、クライアントが住む中で、その鍋ビスを少し緩めフックとして使い、時計やハンガーを掛けるなど、実用にも優れたところがあり、単純な仕組みで尚且つ比較的手に入りやすい材料を使うので汎用性が高く、また他でも使うことにした。
ちなみに、住宅1棟で、1万本以上2万本近い数の鍋ビスを使い、それを全部大工さんは1本1本、インパクトと呼ばれる電動工具を使い留めていったので、そのひたすらの繰り返し作業による狂気にも似た仕上げの様は圧巻である。
"Nabe Bis Madness"
If all the wall ceilings are used continuously in front of the house, it is often seen the work on the home page and the finish is ordered recently.
Basically, the design for the house is never used elsewhere. It is natural that the reason for the design, it is only that time, so if you use it elsewhere, it will feel like you are just thinking about design alone, and then use it continuously Because it was continuous production in the house of an adjacent brother.
However, I liked the finish which fastens this Rawan veneer with a pan screw.
Looking away, the texture of Ravan veneer fills the whole room and there are too many wood grain, so it looks like it is not a different wood depending on what you look at, and when it approaches, the presence of the pot screw suddenly becomes I dive into my eyes and add different accents to the texture of Ravan veneer to look different.
When I saw it when I was away and when I was approaching it, it was good for the architecture to change the expression so as to respond to the movement of people, the way of seeing the finish was different.
At that time, I was thinking about how to fasten the Lauan veneer, and it is common to use a combination of adhesive and a thin nail called finish, but then I feel like it is vulnerable to the warping of the Lawan veneer, and fasten. But I wanted to use a screw, just that, I saw an extra thing on the surface of Rawan veneer, and I felt that the goodness of unity would be lost, with the wall ceiling finished with only Rawan veneer.
Therefore, considering the ease of use, we will use relatively easy-to-use screws, but by examining the shape, color, and pitch of the screw head, it looks like a cleaner finish by combining Lawan veneer and the screw. When I saw it when I looked away, I realized that the appearance of the finish was different, and I designed it while making a trial on the site many times.
This finish is a simple mechanism to fix the veneer with a pan screw, but the change in appearance is complicated, and after the completion, the client lives in a house, and the pan screw is used as a loose hook, watch or hanger There are places that are good for practical use, such as putting in place, and because they use materials that are simple and yet relatively easy to obtain, they have high versatility and are also used elsewhere.
By the way, in one house, more than 10,000 pot screws are used as many as 10,000 or more, and all the carpenters used it one by one, electric tools called impact, so that repeated repetition The finish similar to the madness by work is a masterpiece.
モダニズムでの絵画は、モチーフの陰影が消え、そのモチーフ自体も輪郭線だけになり、二次元化する。それは一目見るだけで、全体を把握しやすくし、視覚以外の感覚は排除して、本質に迫ろうとした。実際には絵画に触れることができないが、質感としてあるのは、キャンバスと絵の具だけだった。
この絵画は、モダニズムより前の時代の反動だが、一方、日本には、岩絵具を使い、陰影など無い二次元化された絵画があった。
そこには、岩絵具としての質感は勿論あるし、和紙の質感もあるのだが、それらの質感が前面に感じることは無く、モチーフとなるものに沿うように発色し、しっとりとした印象を与えることに寄与していた。二次元化が決してモチーフを視覚で捉えやすくするためでは無く、むしろ、視覚以外の感覚を誘発し、それを岩絵具の顔料としての質感と発色が後押しし、見る側に様々な事を想起させ、モチーフをよりリアルに感じさせた。
いわゆる洋画は表現された事を、見る側はそのまま受け取るだけに設定され、その設定がモダニズムであったり、時代性だったりした。
いわゆる日本画は何かが不足しているか、何かが実物の見た目と違う、それが二次元化、そこを補うことを、見る側が想起する、無意識のうちに、その想起する余地が、同じ二次元化された絵画でも違う所で、感じるリアルさが違う所で、概念より目の前に全てがあり、それをどう感じるか、時代の反動では無い方が絵画として、モチーフの本質に迫ることができるだろうし、破綻もしないし、絵画としてだけ相対することができるから、それは素晴らしいことではないか、この文化圏に目を向けることが。
"Recollection"
In modernism paintings, the shade of the motif disappears, and the motif itself becomes only an outline, and it becomes two-dimensional. At a glance it made it easy to grasp the whole, excluding senses other than vision and trying to approach the essence. Actually I can not touch the painting, but only the canvas and the paint have the texture.
This painting is a reaction of the days before modernism, while in Japan there was a two-dimensionalized painting that used rock paint and had no shadows.
There is, of course, the texture as a rock paint and the texture of Japanese paper, but the texture does not feel on the front, and it colors in accordance with the motif and gives a moist impression Contributed to the Two-dimensionalization is by no means to make the motif easy to see visually, but rather, it induces a sense other than visual sense, and it is inspired by the texture and color of the paint as a pigment, and evokes various things on the viewing side , I made the motif feel more realistic.
The so-called foreign film was set to just receive what was expressed, and the viewer was set to just receive it, and the setting was modernism or it was historical.
The so-called Japanese paintings lack something or something is different from the real appearance, it is two-dimensional, making up for that, the viewer recalls, unconsciously, the same room for recalling the same Even in a two-dimensionalized picture, in a different place, in a place where the feeling is different, there is everything in front of the concept and how it feels, one who is not a reaction of the times approaches the essence of the motif as a painting You will be able to do it, you will not fall apart, and you will only be able to confront each other as a painting, so it's not a great thing to look at this culture.
とても乱暴に大雑把に言えば、モダニズムとは他の感覚を全部削ぎ落として視覚に特化し、触れること無しに本質に迫ろうとしたことで、モダニズム以後はその反動でしかない。
モダニズムでは、他の感覚、触覚や嗅覚、味覚、聴覚で把握できる情報を全て視覚に変換し、それが可能なのは、人間の知覚構造の特色かもしれない、視覚から8割の情報を得ているからで、一目で本質を把握できるようにし、それを写真に収め、ネットの無い時代に写真という身軽な伝達方法に載せた。
だから、視覚以外の感覚に関連することは全部消えていく。
絵画では、モチーフの陰影は消え、そのモチーフ自体も輪郭線だけになり、やがてモチーフ自体も消える。建築でも形自体に意味があると、空間を視覚的に一目で把握できなくなるから、意味を持たせないように余分な線は消え、根源的な幾何学形態になり、それは仕上げについても同じで、白くなり、絵画同様、空間も輪郭線だけになり、やがて空間自体もどこまでが空間かわからなくなる。
そこでは人間も必要で無くなる、人間を意識してしまうと、触覚や嗅覚、味覚、聴覚が現れてくるから。だから、建築では生活感が必要では無くなった。
モダニズム以後はその反動、視覚以外の感覚が復活し、触れることで得られる感覚も通して、本質に迫り、人もそこに介在する。写真以外の伝達方法も発達したから、生活感も必要になり、それが現代まで続くが、人がやることだから、人が介在するのが当たり前なのだが、そのモダニズムも、モダニズム以前の反動でしかない。
古美術の茶碗を触れる機会があった。なかなか滅多に見られるものでは無いから、箱や箱書きから茶碗まで、写真を撮りまくった。それは記録に残して後から見返すこともできるためだが、自分の手の中に留めておきたいという衝動にかられ、そのためにはまず、写真を撮ろうとしてしまう、ただ触らずにはいられない。
見るだけで、感触までわかろうと思えばわかるが、触ることでしか得られない情報があるだろうし、耳から入る知識も重要だが、一番大事なのは持った時の感触、持って見て触った時に自分がどう思うか。
だから、ひとつひとつ丹念に触った。散々触った後に、ふと、モダニズムはあったのだろうか茶碗に、と思った。
"touch"
Roughly speaking roughly, modernism is nothing more than repercussions after modernism, as it attempts to immerse itself in the essence without scraping it and touching all other senses.
In modernism, information that can be grasped by other senses, tactile sense, olfactory sense, taste sense, and auditory sense is all converted into vision, and it is possible to obtain features of 80% of information from vision, which may be characteristic of human perceptual structure So I made it possible to grasp the essence at a glance, put it in a picture, and put it in a light communication method called a picture when there was no internet.
So everything related to senses other than visual disappears.
In paintings, the shade of the motif disappears, the motif itself becomes only the outline, and eventually the motif disappears. Even in architecture, when the form itself makes sense, the space can not be grasped visually at a glance, so the extra lines disappear so as not to make sense, and it becomes the basic geometric form, which is the same for finishing as well. It becomes white, and like paintings, the space is only an outline, and eventually the space itself does not know how far it is.
There is no need for human beings, because when you are conscious of human beings, touch, smell, taste and hearing will appear. So, in architecture, a sense of life was not necessary.
After modernism, its reaction, the senses other than vision revives, and through the senses obtained by touching, the essence approaches and the person also intervenes there. Since communication methods other than photography have also been developed, a sense of life is also required, and so does the present, but because people do it, it is natural for people to intervene, but its modernism is only a reaction before modernism. Absent.
I had the opportunity to touch the teacup of the old art. It is not something that is rarely seen, so I took pictures from boxes and boxes to teacups. It is possible to leave it in the record and to look back later, but because of the urge to keep it in your own hands, you can not help but just try to take a picture first.
If you just look, you will understand if you feel the touch, but there will be information that can only be obtained by touching and knowledge that can be heard from the ear is important, but the most important thing is the feel when holding it, holding it and touching it What do you think sometimes?
So I touched it one by one. After touching it a bit, I thought it was a teacup, probably there was modernism.
建築に対する考え方やアプローチの仕方やコンセプトは素晴らしいのに、どこかで見たような、既視感に襲われるようなことがある。
建築を言葉からイメージしようとすると、言葉から実際の建築や空間に変換する時の能力が問われる。引き出しがたくさんあるのか、レシピをいっぱい知っているのか、どこまで知覚できるのか、などなど。どうしても、今まで見てきた建築や空間が頭を過る、それは意識して先人の建築から何か学ぼうとすればする程、そうなる。
よく聞くのが、後付けでコンセプトを考えること。与条件に対応して設計した建築に対して、後から考えを整理してまとめること。案外多く、後付けだから、コンセプトに対して実際に出来上がった建築や空間が破綻していない、当たり前だけど。案外その方が既視感も無かったりする。
だから、はじめから既視感が無いものをつくろうとし、後からそこに至る考え方をまとめても良いだろうし、その方が、既視感が無いことは新しいことでもあるので、言葉より建築空間生成が先になり良いのではないだろうか。
"Before words"
Though the way of thinking and approach to architecture and the concept and concept are wonderful, there are times when they are struck by a sense of devil as seen elsewhere.
When trying to image architecture from words, the ability to convert words into actual architecture and space is questioned. Whether you have a lot of drawers, you know a lot of recipes, how far you can perceive, etc. Anyway, the architecture and space I have seen so far have a head, which is the more I consciously try to learn something from my predecessor architecture.
I often ask you to think about the concept later. Organize and organize your ideas later for the buildings designed in response to the conditions. Unexpectedly, because it is retrofit, it is natural that the architecture and space actually completed for the concept have not collapsed. Unexpectedly there is also no sense of sight.
Therefore, it is possible to try to create something that has no sense of sight from the beginning, and to organize ideas that lead to that later, and it is also a new thing that there is no sense of sight, so building space generation rather than words Aren't you good at first?
しみじみいいな、と、パッと見いいな、は両立するのかな、と考えていた。
人は視覚からの情報が8割、だから、第一印象が大事で、綺麗な人や清潔に見える人は好印象になる。頭が良さそうは必ずしも好印象とはならないらしい。
要するに、視覚が優位に働き、何かを意識してやらないとそこから逃れられない。見た瞬間に表象化がはじまり、これは条件反射なので、無意識に行い、様々な情報を勝手に取得してしまう。この情報を元に様々な思い込みや決めつけをする、とてもニュートラルや平等に見ることなどできない。
だから、パッと見いいなは、第一印象が良いということになり、しみじみいいなは、後から来る、視覚とは離れたところで、視覚とは関係が無い、視覚以外の感覚が優位に働いた時に感じることだろう。
そうすると、パッと見よくて、しみじみよいのは、人に例えると、第一印象が良くて、更に内面も良いみたいな、非の打ち所がない人ということになる。なかなかいないだろう。
建築も視覚優位になりやすく、そこから逃れるための手段として言葉を使い、その言葉の使い方は建築学だけではなく、哲学や社会学なども範疇に入り、最初から視覚が働かないようにし、それがデザインであったりするのだが、よくよく考えると、いいなと思う建築は、最初から最後まで連続的にずっとよいので、視覚以外の要素で、視覚と同じ位の影響力を持たせているのだろう。
"Other than visual superiority"
I thought that it was a good idea, and good looking, would be compatible.
Eighty percent of the information from people is visual, so the first impression is important, and people who look beautiful and look clean are good impressions. It seems that a smart head is not always a good impression.
In short, vision works in a dominant way, and you can not escape from it unless you are conscious of something. At the moment when you look at it, representation starts, and this is a conditional reflection, so it is unconsciously acquired and various information is acquired without permission. Based on this information, I can not make various assumptions or decisions, nor can I look very neutral or equal.
So, it looks like the first impression is good, the first impression is good, the second is good, it comes later, it has nothing to do with vision, it has nothing to do with vision, and senses other than vision work dominates You will feel when you
In that case, it is a person who has a good impression and a good feeling, if compared to a person, a person who has a good first impression and a good inside, and no fault. It will not be easy.
Architecture also tends to become a visual advantage, and words are used as a means to escape from it, and the usage of the words is not only in architecture but also in philosophy and sociology, so that vision does not work from the beginning, Is a design, but if you think carefully about it, the architecture that I think is good is continuous from the beginning to the end, so it has the same influence as visual with elements other than visual It will be.
既視感が襲ってくるのは、見た瞬間の表象化の段階、いろいろなこと、見た目では無い、隠れた部分を感じ取る過程でのこと、そこで見たことがあるかどうか。
「既視感が無い」状態が人間の知覚において、どこで起こるのかを考えていた。
今は当たり前になったが、コンクリート打放しにモルタル薄塗りをかけ、コンクリート打放しはすでによくある仕上げで見慣れているので、同じような色味、同じような質感、でも違う、既視感が無い仕上げに、コンクリート打放しの上に更にモルタルを塗り、それを仕上げにすることは無かったので、コンクリート打放しを何か別の仕上げにするためにモルタルを下地として塗ることは普通に行うが、それを見た時にはじめて既視感ということを意識した。
どうしても、新しい建築、新しく見える建築に惹かれるので、「既視感が無い」とそれだけで新しい建築に思えたので、既視感とはどういうことかを考えたくなった。
"Opportunity to explore the feeling of the sight"
A sense of prejudice comes at the stage of the rendition of the moment of seeing, various things, things that are not visible, in the process of feeling hidden parts, and whether they have been seen there.
I was thinking where in the human perception, the "no sense of sight" condition would occur.
Now it has become commonplace, but put a thin coat of mortar on concrete release, and concrete release is already familiar with a common finish, so similar colors, similar texture, but different, no visible finish It was common practice to paint the mortar as a foundation to make the concrete release some other finish, as there was no need to further coat the mortar on top of the concrete release and finish it. It was the first time I was aware of the feeling of being visible.
I was attracted to new architecture and new-looking architecture, so I thought it was a new architecture with only "no sense of sight", so I wanted to think about what it was like.
ひとつひとつバラバラなものをそのままバラバラなままの状態で表すにはどうしたらよいか。
大きな容れ物の中に、ひとつひとつバラバラのまま、そのままの状態で納める。大きな容れ物が環境を守る役目をし、ひとつひとつバラバラなものの関係性は維持され、バラバラなままの状態で表すことができる。そして、大きな容れ物という、そのバラバラなままの状態で納める容れ物が、そのバラバラな状態を表す名称になる。
例えば、美術館や博物館がそうだろう。大きな美術館や博物館といった容れ物の中に、作品や展示物がバラバラなままの状態で納められ、ひとつひとつバラバラなものの関係性は維持され、バラバラなままの状態で表しており、その状態が、まさに美術館や博物館と呼ぶ。よくある手法だ。
他には、ひとつひとつバラバラなものを、ひとつひとつバラバラな関係性はそのまま維持して、別の事で新しく表すこと。この場合は、その関係性が、そのバラバラな状態を表す名称になる。
例えば、先程の美術館や博物館だとすると、ひとつひとつバラバラなものは、作品や展示物であり、その作品や展示物中から、あるいは、他の美術館や博物館から借りてきた作品や展示物を加えて、新たな関係性をくくり、展覧会をする。その展覧会の名称が、新たなにくくった関係性であり、それが「〜展」になる。
だから、ひとつひとつバラバラなものをそのままバラバラなままの状態で表す方法は、大まかに分けて2通りあり、1つは大きな容れ物を用意する、もう1つは新たなくくるための関係性を用意する。
前者は建築的な解釈にもなり親和性があるが、興味があるのは後者、言わば、関係性をデザインすることであり、それは建築以外でも役立つ手法であり、関係性を建築で実際の空間としてつくりたい。
"Relationships in space"
What should I do to represent things separately one by one as they are separately?
In a big container, put it as it is, one by one. Large containers serve to protect the environment, and the relationships of disjointed things are maintained and can be represented in disjointed states. And, the big container, the container which is stored in the broken state, is the name representing the broken state.
For example, museums and so on. Works and exhibits are stored in pieces in a large museum or museum space, and the relationship between pieces is kept one by one, and they are represented in a broken state, and that state is I call it a museum or a museum. It is a common technique.
The other thing is to keep things broken apart one by one, keep the broken relationships one by one, and express new things in another. In this case, the relationship is a name representing the disjointed state.
For example, in the case of the previous art museums and museums, things that fall apart one by one are works and exhibits, and by adding works and exhibits borrowed from those works and exhibits or borrowed from other art museums and museums, new items Hold a relationship and exhibit. The name of the exhibition is a new difficult relationship, which becomes "-exhibition".
Therefore, there are roughly two ways to represent things separately one by one as they are separately, one is to prepare a big container, the other is to prepare a new connection .
The former is also an architectural interpretation and has an affinity, but the latter is interesting, so to say, to design relationships, which is a useful method other than architecture, and to build relationships with actual space I want to make it.
内部でもよいし、外部にもなる、それは場面場面で変えることもできるし、ずっと外部でもよいし、時々気分でそうしてもよいし、普通にずっと内部でもよい。そのような空間ができたならば、きっと見た目も、その選択、内部か外部かで違うだろうし、そこを使う人、住む人によって、全く違った空間が出現するかもしれない。
それが集合住宅だったら、住む人の数だけ、空間の選択に違いができるし、それがそのまま外観に現れる。まさに、集合住宅でしか実現できないことになる。
そのようなプランにたどり着き、ただそのプランはとても単純で、決して言葉だけが先行した空間ではなくて、実空間として、使い方として成立をしている。
答えを探さずに、ずっと解明したかったことに対して、情報収集して、整理して、丹念につながりを解きほぐすことを繰り返し行っていた。そうすると、誰も手を付けていない領域がわかり、そこが本来自分が建築の中心に据えたいことだと理解できた。
ただ、あまりにも単純すぎて、それはよいことだと思いつつ、何か付け足ししたくなるし、何かがまだ足りないので、さらに、要するに、問題を設定したくなる、終わり時に迷う。
"End time"
It can be internal or external, it can be changed in the scene, it can be external, sometimes it can be in the mood sometimes, it can be internal as usual. If such a space is made, the appearance will be different depending on the choice, whether it is inside or outside, and a completely different space may appear depending on the person who uses it or the person who lives there.
If it is a collective housing, the choice of space can differ by the number of people living, and it will appear in the appearance as it is. Indeed, it can only be realized in an apartment complex.
Having reached such a plan, the plan is so simple that it is not a space where only words first preceded, but is established as a usage as a real space.
Without searching for an answer, I have been collecting information, organizing it, and breaking up connections carefully in order to solve what I wanted to clarify. Then I understood the area that no one had put in hand, and I understood that I would like to put it at the center of the architecture.
But it's too simple, I think it's a good thing, I want to add something, and I'm still missing something, I mean, I want to set a problem, I get lost at the end.
中途半端なんだよね、何でも中途半端に見えてしまう、中途半端って良くないイメージがあるけれど、結構本気で「類は友を呼ぶ」ということわざが大事で、自分の周りにいる人を見れば、本当の自分、心の奥底にいる自分がわかると考えていて、たがら、何でも中途半端に、人が見えてしまうのは、自分が中途半端な人なのかなと考えてしまう。
まだまだ詰められる余地がある、よくある話だが、どうしたらできるかではなくて、こうだからできないと、できない理由ばかりを説明する人に出会うとげんなりする。
そんな人、本当にいるのかと言われそうだけど、で、ところで、本題に入ろうか、どうしたらいいの、ここがこうなったら、全てが上手くいき、皆んながとりあえずハッピーになれるから、話は単純、そこを何とか実現できる方法を考えよう、それは専門の人が絞り込むことなのに、専門外の人が簡単にトリガーポイントを指摘したらまずい、職務怠慢だよね、プロでしょ、とまでは言わないし、言いたくはないので、そこに気づいて欲しいのだけれども、言葉が通じない、おかしな日本語同士でしゃべっているよね、こんな時、昔は現場でも怒鳴り散らしていたような気がするけれど、それは誰のためにもならないから、最近はそういうことが無いように、まず自分が怒鳴り散らすことが無い人と仕事をするようにしている、「類は友を呼ぶ」だから。
"Incomplete"
It's half-baked, there's an image of something half-baked and bad, but everything looks like it's halfway, but if you look at the people around you, it's important to say that the kind "calls kind" is serious. I think that I know that I am true, I am in my heart, and I think that I can see someone who is half-hearted, if only I am a half-hearted person.
It's a common story that still has room to be packed, but it's not how you can do it, and if you can't do it this way, you will meet people who just explain why you can't do it.
Such a person seems to be really there, but, by the way, how to get into the main subject, what should I do, if all this goes, everything goes well and everyone can be happy anyway, so the story is simple, there Let's think of a way to somehow realize that it is a narrowing down of specialists, but it would be bad if a non-specialist could easily point out a trigger point, it would be a delusion of duty, not to say professional, not to say So I want you to be aware of it, but you can't speak words, you're talking with strange Japanese people, At this time, it feels like you used to scream at the scene, but it's for everyone In order not to have such a thing recently, I am trying to work with a person who never screams, "kinds call "So.
なぜ建築をやりはじめたのか。父親は大工、神社仏閣もやっていたから、皆んなは宮大工と呼んでいた。祖父も大工、父親と一緒に千葉から戦後東京に出てきて、商売を、工務店をはじめた。だから、3代目、子供の記憶では、まだ、幼稚園に上がる前、父親の軽トラに乗って現場回りをしていた。もうひとり、住み込みの大工さん見習いがいた、その人と一緒に3人、なぜ、幼稚園に上がる前の自分がそこにいるのかわからないけれど、たぶん、連れて行けとただをこねたのだらう。
大昔は、建築現場で出るゴミは埋めていた、確か記憶が正しければ、多摩川を越えた川崎の山の中に行ったような、そこに一緒にトラックに乗っていたんだよね、そうそう、昔は現場で出たおがくずなんかは、区の清掃工場に捨てに行き、まだ子供ながらにして、こわいんだよ、清掃工事の中に入ったこと無いでしょ、大きな、大きな、ゴミを捨てる穴があって、そこに荷台からスコップで捨てるのだけど、まだ子供だから、危ないから、トラックの外に出してもらえず、車内の窓越しに見るしかなかったが、その底なし沼のような清掃工事の穴の恐怖心は忘れられない。
なぜそんな怖い場面がありながら、父親について行ったかと言うと、その後の唯一の楽しみが有り、多摩川の土手で、昔は売店があり、そこで好きなパンを買ってもらい、父親と住み込みの見習いと一緒に食べるのが楽しみだった、それは姉には内緒で、母親は薄々勘付いていたけれど、しょうがないと見逃してくれていたこと。
そこには、建築のケの字も、デザインのデの字もないけれど、幼い頃から刷り込まれた建築がある訳で、それは学校や社会で教えてもらった建築とは違う訳で、それはそれを経験した人にしかわからない世界がある訳で、後発の建築経験と合わせて、自分にしかできない建築を表現したいし、表現しないと死に切れないと思うのは、この歳になり、豊かな社会を見て、余計に思うこと。
"Permanently to do"
Why did you start building? His father also worked as a carpenter and shrine and temple, so everyone was called a shrine carpenter. My grandfather also came out of Chiba from postwar Tokyo with my carpenter and my father, and started to work as a builder. So, in my third generation, in my memory of my child, I was still riding around my father's light tiger before going to kindergarten. There was another carpenter apprentice who lived in, three with him, I don't know why I was there before I went to kindergarten, but maybe I got rid of them and take them alone.
A long time ago, the garbage from the construction site was buried, and if I remember correctly, I went to the mountain of Kawasaki over the Tama River, and I was on the track together there, yes, in the old days I went to the district's cleaning plant to throw away the sawdust that came out on the site, and I was scared as a child, and I'm scared, I've never entered the cleaning work, big, big, there is a hole to throw away trash , But there is a scoop from the loading platform, but because it is still a child, because it is dangerous, I could not get it out of the truck and had to look over the window inside the car, but the fear of the hole of the cleaning work like a bottomless swamp I can not forget my heart.
If you say why you went to the father while having such a scary scene, there is only one pleasure after that, there is a shop on the banks of the Tama River in the old days, you have bought the bread you like there, and the father and the resident apprenticeship I was looking forward to eating it together, which was secret to my sister, and my mother was thinly aware, but missed it.
There are no architectural characters or design characters, but there is an architecture that has been imprinted from an early age, which is different from an architecture taught in schools and in society. There is a world that is understood only by those who have experienced, and together with the late-stage construction experience, I want to express architecture that can only be done by myself, and I think that I can not die without expression, it is this age, rich society Looking at and thinking extra.
建築は、全てを規定しなければならないから、哲学や社会学などに規範を求めるのだろう。
建築を規定するために使う言語は、哲学や社会学だけではない、人の感覚も使う、しかし、感覚だから言葉にならない、言葉で説明できないこともある。それでもなお、規定しようと試みる。
言葉で全てを規定しようとする人のことを理論家と呼ぶのだろう。言葉で規定てきない所は無い、だから、何でも言葉が必要だ。この場合の言葉は知識と言い換えることができる。
知識で目の前に出現した空間を規定する、それがどういう態度でも関係がない、的を得ていても、的外れでも、こじつけでも、規定することが大事だから。
実現をしたいのは、人の心を揺さぶる未知の空間であり、知識で規定するとかしないとかとは、全く関係がない所に浮遊している事柄に思えるのだが、では、人の心を揺さぶる所まで、未知の所まで、空間を求めて行く乗り物は何か、感覚か、才能か、経験か、諦めないことか、それともやはり知識か、または、これら全てか、そこは誰も教えてくれないし、誰も教えられない、なぜなら、未知だから。
盲目になれば、たやすく未知も、心を揺さぶることも手に入る、ただ、それは求めている未知ではない。しかし、全てを知り尽くした上での未知を求める姿勢は、砂漠の中で一杯の水を求めているようなもので、心が揺さぶられない。だから、知識がある、知っている、わかっている先に、心が揺さぶられる未知はない。
知らないことへの恐怖心からくる知識には価値がなく、それを素とした空間には、未知もなく、心も揺さぶられないのではないか。今、思い出すのは、過去に心を揺さぶれた未知の建築空間、その時は未熟な時だった。
今が成熟しているかどうかは別として、未熟と盲目は同じか違うのか。書きながら考えて、考えながら書いている、これが未熟で、そもそも書かない、考えないのが盲目かな。
だから、知識を受けようとして動いていては、人の心を揺さぶる未知の空間をつくることはできず、自分で試行錯誤することでしか、人の心を揺さぶることはできないし、未知に到達しないのではないか、それが的外れでも、未知だから、それが的外れかどうかも判断てきないし、ただ、やはり、そうなると、諦めないことが重要だけど、今度はそれができる人はなかなかいない、知識を受ける方が無知の恐怖心が和らぐし、誰も無知だと思われたくはないだろうから。
"Unknown wall shaking hearts"
Since architecture must define everything, it will seek norms from philosophy, sociology, etc.
The language used to define architecture is not only philosophical or sociological; it also uses human senses, but sometimes it can not be words because senses can not be explained in words. Still, I try to define it.
People who try to define everything in words will be called theorists. There is no place where there is no provision in words, so everything needs words. The words in this case can be reworded as knowledge.
It is important to define the space that appears in front of the eyes with knowledge, regardless of attitude, whether it is a target, a target, a target, a target or a stigma.
What we want to realize is an unknown space that shakes people's mind, and it seems that it is a matter floating in a place that has nothing to do with whether or not it is defined by knowledge, but then it shakes the mind of people To the place, to the unknown, the vehicle that seeks space, sense, talent, experience, not giving up, or even knowledge, or all these, there is no one to tell me No, no one can teach, because it is unknown.
If you get blind, you can easily get the unknown and the heart shaking, but it's not the unknown you're looking for. However, the attitude of seeking unknown after knowing everything is like seeking full water in the desert, and the mind can not be shaken. So there is no unknown that the mind is shaken before you know, know and know.
There is no value in the knowledge that comes from fear of unknown things, and in the space that is based on that, there is no unknown, and the heart may not be shaken. What I remember now is an unknown architectural space that has shaken my mind in the past, and that time was immature.
Aside from whether they are now mature, are immature and blind the same or different? I think while writing, I write while thinking, this is immature, not write in the first place, it is blind not to think.
Therefore, if you are moving to receive knowledge, you can not create an unknown space that shakes the mind of a person, you can only shake the mind of a person by trial and error yourself, and you reach an unknown Even if it is out of place, it is unknown, but it is not determined whether it is out of place, but it is important not to give up if it is so, but there are not many people who can do it this time. But the fear of ignorance will be relieved, and no one will want to be considered ignorant.
建築は決まり事の集積で成り立っているので、偶然にそうなるとか、結果的にそうなった、ということは基本的には無い。
基本的には、と付けたのは、新築ならば、更地から計画をしていくので、土地に何か、例えば、地盤が軟弱であったり、地中に何か埋まっていたり、文化財など、があったとしても、それを含めての計画になるのだが、リフォームの場合は、手を付ける部分が限定されるので、手を付ける部分以外の所が影響して予想外の出来事が起こることもある。
だから、新築の場合に限って言えば、偶然や予想外は無い。
そうなると、余白としての空間をつくる場合も、その余白で起こることを全て予想してコントロールした上での余白としての空間が成り立たないといけない。
余白となると、どうにでもなる、何が起こるかはその時にならないとわからない、気分で変わる、などの要素を加味したいのだが、そうもいかないのか。
そこが、言葉だけが先行した建築とそうでない建築の分かれ道か。
"Diversion"
Since architecture consists of a collection of routine things, there is basically no such thing that happens by accident or as a result.
Basically, if it is a new construction, we will start from a land area, so something on the land, for example, the ground is soft, something is buried in the ground, or a cultural property And so, even if there is, it will be a plan including it, but in the case of renovation, the part to be touched is limited, so the unexpected event is affected by the parts other than the part to be touched It can happen.
So, just in case of new construction, there is no chance or unexpected.
In that case, even when creating a space as a margin, it is necessary to have a space as a margin with anticipation and control of everything that happens in that margin.
When it comes to the margins, I would like to add elements such as how to do anything, I don't know what will happen at that time, the mood changes, etc.
Is there a branch between the architecture where only words preceded and the architecture where not so?
余白を余白としてつくるのではなくて、プリントアウトする時の余白の設定のように数値でここから余白と決めるのではなくて、気がついたら、それが余白とか、じわりじわり余白になっていくとか、気分で今日は余白とか、現れたり消えたり、または、感じる時と感じない時があるとか、余白が何かと何かをつなぐものだとしても、常に見える必要はない。
建築は空間の範囲を規定しなければならない。その際は、壁であったり、床や天井であったり、敷地境界線かもしれないし、地面かもしれない、解釈によっては空もあり得るかもしれないが、かならず、範囲が決まる。だから、余白として建築空間をつくることは、どうやって範囲を決めるか、その際はどうなるのかを決めること。
ただ、何となく余白は範囲が決まっているようで決まっていない感じがあるので、そこの自分の中での認識の差をどうやって埋めるのか、どうしたものか、余白を考えながらプランをつくること自体に何か違和感がある。
"Plan called margin"
Instead of creating a margin as a margin, instead of using this as a numerical setting for setting a margin when printing out, you decide not to use it as a margin, but if you notice it, it will become a margin, a beginning margin, etc. So today you don't have to always see the margin, even if it appears or disappears, or if you feel or don't feel it, or if the margin connects something to something.
Architecture must define the scope of space. In that case, it may be a wall, a floor or a ceiling, a site boundary, a ground, and depending on the interpretation, it may be empty, but the scope is definitely determined. So, to create an architectural space as a margin is to decide how to determine the scope and what to do in that case.
However, there is a feeling that the margin seems to be fixed and the range is somehow decided, so how to fill in the difference in recognition in oneself there and what to do, it is in making the plan while thinking about the margin itself I have something wrong.
空間を使う側の気分を反映できるような余白をデザインすることに今は興味があり、その余白がどう展開するかに関心がある。
余白は単に何も無いところではなく、余白があることによって、余白以外の部分も引き立つ。
地と図の関係も含み、もっと多様な可能性や、何かと何かをつなぐ役割も担うのではないかと考えている。
余白があることによって、今まで特に関係が無かったもの同士がつながるのも面白いし、そこで関係性をデザインとして扱えるのが、さらに面白い。
では、余白とは何か、ときかれても、よくわからない。実体が無いもので、存在が希薄で曖昧なもので、だから、なかなかつながりを明確に意図しようとすると上手くいかない、しかし、つながりがわかると視覚的にもはっきりと見えてくる、それを空間にしようとする試み、まるでスイカパンの白い部分のように、見立てか。
"Space in space"
I'm interested in designing margins that can reflect the mood of the space users, and I'm interested in how the margins expand.
The margins are not just empty places, but the presence of the margins also makes the other areas more prominent.
Including the relationship between the earth and the figure, I think that it may play a role that connects more diverse possibilities and something.
It is also interesting that there is a margin, so that things that have not been particularly connected are connected, and that the relation can be treated as a design there.
Well, I don't really know what the margins are, sometimes. There is no substance, existence is weak and ambiguous, so it is difficult to try to clarify the connection clearly, but when the connection is understood, it can be clearly seen visually. Try to try, like a white piece of watermelon bread, do you think?
つい選択できることに価値があると考えてしまう、その方が楽しいし。
ここ2,3ヶ月のうちに2回行った飲食店への道の途中にアンティークショップがあり、覗くとつい銀のスプーンに目が行ってしまう。カトラリーが大好きで、スプーン、ホーク、ナイフなど、いいなと思うものを見つけると、つい購入し、バターナイフも、セットではなくてバラバラでも、引き出しをあけると、カトラリー専用、見てるだけでも楽しい気分になるけれど、何か食事をする度に、どれにしようかな、と選ぶ楽しさ、コーヒーカップも毎朝選ぶ楽しさがある。
別に大したスプーンではないけれど、自分が気に入って、そこには自分の審美眼も入ってくるし、それを毎日、その時の気分でも、その時の器に合うものは、その時の料理に合うものは、と選ぶことが生活する上でとても大事、今生きていることを大事にしているような気がして、毎日変化するし、毎日自分は変化していくし、それが成長かもしれないし、老いかもしれないけれど、そこに沿うためには選択肢がある状態の方が良いだろうと。
選択肢がたくさんある、たくさん用意されている状態は、結局何ひとつ決まっておらず、全てが流動的で、どうにでもなる状態であり、ひとつのことに決めれば、他の選択肢は必要無くなるので、無駄やその無駄を容認できる余地、余白を抱えている状態とも言える。
だから、余白に価値があり、余白に可能性を感じ、余白をどうやったらつくり出すことができるだろうか、と自然に考えてしまう。
それは建築に対しても同じで、きっちりと決められた建築家の審美眼による空間は素晴らしいし、そこに建築としての価値があるのだけれども、その空間を使う側の気分みたいな流動的な部分を引き受ける余白にも同じくらいの価値があり、そこもデザインの範疇だと考え、今はその余白が極まるとどうなるのだろうかに関心がある。
"Margins of choice"
I think it's worthwhile to be able to make choices, it's more fun.
There is an antique shop on the way to the restaurant that I visited twice in the past couple of months, and when I look around my eyes go to the silver spoon. I love cutlery, find something that I like like spoons, hawks, knives, etc., I just buy, buy butter knives, even if it's not a set, even if it's loose, open drawers, cutlery only, it's fun just looking However, every time you eat something, it's fun to choose which to use, and coffee cups every morning.
It's not a big spoon, but I like it and my beauty goes into it, and every day, even if it feels like that, what suits the vessel at that time, what suits the cuisine at that time, I think it's very important to choose life, I feel like I take care of being alive now, I change every day, I change myself every day, it may grow, I am old It might be, but it would be better to have a choice to follow along.
There are a lot of options, a lot of prepared states, after all there is no decision, everything is fluid, it is a state that can be done, and if you decide on one thing, the other options will not be necessary. It can be said that there is a room where the waste and the waste can be tolerated, and a margin.
So it is natural to think that there is value in the margin, the possibility of the margin, and how you can create the margin.
The same is true for architecture, and the well-defined space of the architect's aesthetics is wonderful, and although there is architectural value there, a fluid part like the mood of the side using that space Undertaking margins is equally valuable, and I think that it is a category of design, and now I'm interested in what happens when the margins are full.
最近、余白のことを考えている。余地とか、遊びとかと言うかもしれない。余分なもの、どうでもよいもの、ただ、無いと困るもの、なくてはならないもの。
きりきりで、きれきれで、きつきつで、きっちりしている完全なものに憧れたりする。美しいものや綺麗
なものは大抵完全なものを備えていて、そこに惹かれる。
ただ、完全なものはあまりにも完璧すぎてなじまなく、触れると、拒みたくなる。
余白が主役の長谷川等伯の松林図屏風、これは余白を描いていて、その余白が見るものの感受性を刺激し、あらゆる創造を意識の中で強いる。たがら、見ていると松林の余白の中に、霧や風やその先の景色を感じ、松林が浮かび上がってくる。
余白には何も描かれていない。人によっては未完成に見えるかもしれない。そういう意味で言うと不完全である、この長谷川等伯の松林図屏風は。
ただ、その不完全さがこの松林図屏風に動きや情景を与える。
等伯は松林を墨で描きながら、余白を丹念にあぶり出したように見えた。
"See the margins"
Recently, I'm thinking about margins. It may be called room or play. Extra things, things you don't care, just things you don't need, things you have to do.
I'm drowning in perfect things that are crisp, clean, tight and tight. Beautiful things and beautiful
Things are usually complete and are attracted to it.
However, perfect things are too perfect and unfriendly, and touching them makes them want to refuse.
The margin is the leading figure of Matsubayashi Hasegawa, which draws the margin, stimulates the sensitivity of what the margin sees, and forces all creation in consciousness. When I look at it, in the margin of the pine forest, I feel the mist, the wind, and the scenery beyond that, and the pine forest comes up.
Nothing is drawn in the margin. Some people may seem unfinished. In that sense, it is incomplete, this Hasegawa and other pine forest sketch screen.
However, the imperfection gives movement and a scene to this Matsubayashi maple wind.
It appears that Togashi has carefully drawn out the margin while drawing Matsubayashi with ink.
暑いのか、肌寒いのか、最近よくわからない。寒暖の感覚がおかしくなっているようで、夜暑いと思って窓を開けたら、そのうち肌寒くなって、かと思うと、昼間の風は涼しくないから、エアコンをかけると肌寒くて喉が痛くなったり、寝る時は朝方肌寒くなるかもしれないと思い、着込んで寝ると、無意識に暑かったのだろう、いつの間か脱いでいるし。
そんな感覚なんかいい加減なものだなと、それに付き合って振り回されているのも結構面白い。
感覚に言葉をつけたり、言葉を感覚で表現したり、感覚と言葉の間を行ったり来たり、そこに造形が入ってくるから、ややこしく、さらに、経験が幅を利かせてくるから、悪魔のささやきが聞こえてくるから、もうその辺が落とし所じゃないのと。
そう何事にも〆切があるから、まとめることが大事、ただ、まとめることはいつでもできるからと、そうすると相手に伝えることが疎かになる、一番自分にストレスが無いバランスをその都度見つけるのが苦手だなと、いつも思う。
"Not good"
I do not know well lately whether it is hot or chilly. When I open the window when I think it's hot at night, it feels chilly when I think it's hot in the daytime, so the wind in the daytime doesn't cool, so it's chilly and throat hurts when I turn on the air conditioner, I think it might get chilly in the morning when I go to bed, and when I got in and go to bed, I might have been unconsciously hot, and I'm taking off for some time.
It is also quite interesting that it is being swayed along with it that such feeling is kind of sloppy.
Because words are added to the senses, words are expressed with the senses, and back and forth between the senses and the words, there are shapes coming in there, so it is complicated, and because the experience brings in the width, the devil's I hear a whisper, so that area is no longer a dropout place.
So there is a limit to everything, so it's important to put it together, just because you can always put it together and you don't know how to tell it to others, it's not good to find the most stress free balance for yourself each time I always think.
考え続けていると、突然「ひらめき」があるもので、点と点が繋がり、それもここに線ができるのか、となる。
単純なことなのに気がつかない、でも、気がつくと納得して、腑に落ち、そうそう、それをやりたかった、となるから面白い。
ただ、困ることに、それは追い込まれないと、そうはならない、と思っているだけで、もともと考える量が足りていなくて、量が満たされれば、自然と「ひらめき」に行くのではないかと思い、「ひらめき」を形にするのに、また労力を要するし、時間もかかるので、また〆切間際の慌てぶりを晒すことになる。
準備だけはしていて、バックアップ体制は万全だから、もうちょっと余裕があればと思うのだが、その余裕すらも使い考え尽くそうとする。どうしたものだろうか。
"In the corner"
If you keep thinking, there is a sudden "inspiration", and the points and points are connected, which will also be a line here.
I do not notice it is simple, but I am convinced when I notice it and I fall into the trap, so I want to do it, so it is interesting.
However, it is thought that it will not be forced if it is not driven in to be troubled, and the quantity to think originally is not enough, and if the quantity is satisfied, it will naturally go to "inspiration" Because it takes time and effort to form "inspiration", it will also expose the blazing just before the deadline.
I'm just preparing and I have a backup system, so I think I'll have a little more room, but I'll try to use up even the room. What is it?
言葉をイメージより先にしている、それはイメージは既知のものしかできないような気がして。
どうしても、無意識のうちに、過去に見た建築に類型化してしまう。
「これは、あの建築の考え方の延長にあるな」
「この建築は面白いけれど、プランはあの建築にそっくりだな」
「明らかに、真似しているよね」
などなど、結構、類型化するのは案外簡単なこと。
ただ、そのおかげで、自分で計画中に真似を意識してしまう。
建築の設計をしている最大の理由は、未知の空間を見たいから、瞬時にあの建築と同じはできない。
そのイメージを乗り越える手段として言葉を利用している。言葉はイメージを伴わなくても表現できると勝手に思い込んでいるのと、言葉に引っ張られてイメージが出てくると考えているから。
ただ、ここに来て、言葉に引っ張られてイメージは出てくるのだが、現実が伴わない。イメージ通りの空間に到達しないのだ、未知だから仕方がないのかもしれないが、どうしたものか。
"Let's pull out the unknown with words"
I have words before the image, it feels like the image can only be known.
By any means, they unknowingly typify the architecture seen in the past.
"This is an extension of that architectural idea."
"This architecture is interesting, but the plan is just like that."
"Obviously, you are imitating"
And so on, it is quite easy to type out.
However, thanks to that, you will be aware of imitation while planning on your own.
The biggest reason I'm designing architecture is because I want to see an unknown space, so I can't do the same with that architecture in an instant.
I use words as a means to overcome that image. I believe that words can be expressed without an image, and I think that an image will be drawn by the words.
However, I came here, pulled by words, and an image came out, but reality does not accompany it. It does not reach the space as the image, it may not be possible because it is unknown, but what happened?
思考が行き詰まったときには、本来どうあるべきかをもう一度問い直してみることが大切、今日一日、何度も唱えた言葉。
はじめに戻って、そもそも何を考えてはじめたか、いつのまにか違う所を歩いていたりするので、軌道修正をする。
変な先入観や知識がズレを生むのかもしれない。
明確な道筋を立ててはじめていても、はじめの問いが後にブレたりする。意外とそれがあり、何度も本来どうあるべきかを問い直している。
難しいのは、本来どうあるべきかを指向しながら、でも途中で、未だに空白の部分、誰も答えを出していない部分を見つけると、それを行いたくなり、最初の指向とうまく調和調整できないかと試みて、なかなか難解なことになってくるのでブレる。
いずれにせよ、はじめの問いに対しては面白く、そこは未開の地なので、解くことに熱中している。
"question"
When thinking gets stuck, it's important to ask again what it should have been, a word that you have recited several times a day today.
I will go back to the beginning, what I started thinking about, I will walk around a different place before long, so I will correct the trajectory.
A strange preconception or knowledge may cause a gap.
Even if you are starting to make a clear path, the first question will be blurred later. Unexpectedly, there is it, and it is asking again how many things should be.
The hard part is pointing to what it should be, but if you find a blank part, a part where nobody gives an answer, along the way, you will want to do it, and it will not be harmoniously adjusted with the first one. I try, it blurs because it becomes quite difficult.
Anyway, it is interesting for the first question, and it's an unexplored land, so I'm passionate about solving it.
自分の感覚を建築化することの難しさに直面している。今まで、建築を言葉で説明する、言葉を元に建築にする、どちかが難しいか、建築を言葉で説明する方が難しいと考えていた。
建築は言葉だけでは説明できない感覚まで含めたことを形にしているので、そこまで、いくら言葉を駆使しても説明するのは無理だろう、逆に、言葉で表せることは、その時点で咀嚼され曖昧さがかなり無くなってきたものだろうから、それを建築にすることは十二分に可能だろうと。
だから、自分の感覚を言葉で表せれば、十二分に建築化することは可能だろうと考え、言葉を用意した。
ところが、そもそも、そのような建築は見たことが無いので途方に暮れる。安易にイメージしようと思えば、過去の建築に当てはめて、いくらでもできるのだが、これが何らかの試験で、制限時間内に解答を求められていたら、そうするのだが、無限に時間がある訳では無いけれど、自分の感覚をきちんと建築化したいので、だからどうしようとなる。ほんとどうしようか。
"Architecturalization"
I am faced with the difficulties of building my senses. Until now, I thought it was more difficult to explain architecture in words, to explain architecture in words, to build on the basis of words, or which one is difficult.
Architecture is a form that includes the sense that can not be explained by words alone, so it may be impossible to explain even if you make full use of words, and conversely, being able to express in words is at that time And because the ambiguity would be quite gone, it would be possible enough to make it architectural.
So I thought that it would be possible to build enough if I could express my senses in words, and prepared the words.
However, since such an architecture has never been seen in the first place, it is overwhelmed. If you want to imagine easily, you can apply it to the past architecture, and you can do as many as you like, but if this is a test and you are asked for an answer within the time limit, you do, but it does not mean that you have infinite time Because I want to build my own sense properly, so what to do. What should I do?
着地点がかすかに見えてきたのに、そこに行くまでの手段もたぶんこれかなとあるのに、全体のイメージがはっきりしない、霧がかかったよう。
見たことが無いので、見聞きしたことは全て排除して、残されているであろう、目指したい空白部分に向かってダイブをしているのだが、そこに床がたぶんあるはず、もしかしたら透明なガラスの床だから、まだ見えないのかも、光が当たれば反射してわかるはずだけれども。
トライアンドエラーの繰り返しで、時間がもうそんなに残されてはいないから、中途半端でも良ければ、いつでもまとめ上げる自信はあるけれど、それはできないので、自分で良しと思える所まで行けるかどうか、では無く、ここで書きながら、もう一度意識をし直す、着地点を。
"Destination point"
The landing point was faintly visible, but the means to get there were probably mist, although the whole image was unclear.
As I have never seen it, I have removed everything I saw and heard, and I'm going to dive, I'm diving towards the blank area I want to aim, but there should probably be a floor there, maybe transparent Because it's a glass floor, you can see if it's still visible if it's exposed to light.
I don't have much time left by repeated trial and error, so I'm confident I will always put it together if I can be halfway, but I can't do it, so I can't go to a place where I feel good. While writing here, I re-conscious again, the landing point.
片廊下を広くした位では何も起こらない。片廊下型の限界は、それが集合住宅特有の形式で、それが人々に認知をされているから、外観で集合住宅とわかってしまい、そこから意識の発展が起こらないこと。いくら内部の住戸パターンにバリエーションがあっても、外からはわからないし、伝わらない。
昔、設計施工した1戸建ての住宅が上棟してすぐに不動産屋から連絡があった、部屋を紹介して欲しいと。その住宅は間口に対して奥行きがかなり長かった、敷地形状に合わせたのだが、というか、敷地を分割するところから設計をしていて、あえてそのような形の敷地にしたのだが、間口に対して奥行きがかなり長い建物は集合住宅しかないと不動産は判断したのだろう。片廊下型の集合住宅の特徴は間口に対して奥行きがかなり長い、だから、そのくらい片廊下型の形式は認知されている。
それを利用してわざと片廊下型を採用し集合住宅を装う設計者もいるが、大概の設計者は効率を求め、最大住戸面積を確保するために片廊下型を容易に採用する。認知のされ方として、片廊下型は効率が良く最大住戸面積が取れる、という盲信があるから、中には片廊下型を採用しておけば無難と考える人もいる、非難はできない、一級建築士の設計製図試験の課題で集合住宅が出題される時の模範解答が片廊下型だから。
簡単に考えれば、最大住戸面積が確保できれば、形式は何でもありだから、片廊下型をわざわざ考える必要もない、ただそれだけのこと。
"Apartment one-way corridor"
Nothing happens when the one-way corridor is wide. The limitation of the single corridor type is that it is recognized as people in a form unique to a collective housing, so that it can be seen as a collective housing in appearance, and the development of consciousness does not occur from there. Even if there are variations in the interior unit pattern, it can not be understood from the outside and it can not be transmitted.
Once, a single-family house was designed and constructed, and soon after it was contacted by a real estate agent, I would like you to introduce a room. The house was quite long in depth to the frontage, but it was adapted to the shape of the site, or rather it was designed from the place where the site was divided, and it was made into a site of such a shape, but in the frontage On the other hand, real estate might have determined that a building with a very long depth is only an apartment complex. The characteristic of a single corridor type apartment house is that the depth is considerably long with respect to the front door, so that the single corridor type format is recognized as such.
Some designers use it to deliberately adopt a single corridor type and dress it as a housing complex, but most designers demand efficiency and easily adopt a single corridor type to secure the maximum dwelling unit area. As there is a blind belief that one corridor type can be efficiently taken and the maximum housing area can be taken as a way of being recognized, some people think that it will be safe if adopting one corridor type, can not be criticized, and is a first class building Because the model solution is one hallway type when the apartment complex is presented on the subject of the designer's design drafting test.
In simple terms, if you can secure the maximum dwelling unit area, the format is anything, so there is no need to think about a single corridor type, just that.
ある事が気になり、面白いと思って、それはどういうことなのか、それを建築的に表現しようとしたら、どうなるだろうかと考え、関連しそうな情報を集め、その情報を読み込んで、整理をし、気になることや関連することはメモをしている。
メモが少したまってきたので、読み返してみると、そもそも、情報整理が目的で、答えを探している訳ではないから、メモを取る際にも一貫性や整合性などを気にせずにしているのだが、似たような、繋がりそうなキーワードが並ぶ。
情報集めはあくまでも、関連しそうな、という程度の勘を働かせて行っているに過ぎないので、集めた情報を読み込んだら、的外れなものも中にはあるし、逆に、全く関係なさそうな情報が一緒に手に入り、それが何か関係ありそうな気がして、そうすると、自分が知りたいことを元にして情報集めをしているのだが、そもそもの本当に自分が知りたいことが実はちょっと違うのではないかなど、何かと面白い。
"Information gathering"
I think that something is interesting, I think it is interesting, what kind of thing it is, if I try to express it architecturally, I think what will happen, collect information that seems to be related, import that information, and organize it, Anxious things and related things are making notes.
Memos have accumulated a little, so if you read it back, it's just for the purpose of organizing information and not looking for answers, so when you take notes you don't care about consistency or integrity etc. However, similar, similar keywords are displayed.
Information collection is only performed with a hint that it is likely to be related, so if you read the collected information, there are some out-of-targets, and conversely, information that seems completely unrelated I feel that it seems that there is something to do with it, and then I gather information based on what I want to know, but in the first place what I really want to know Something interesting, like a little different.
とても小さな種に気づくところからはじめて、空間はそこら中にあるので、というか、ただ街を歩いていても、そこは都市空間なので、そもそも空間から逃れることができないので、電車で立って外を見ているだけでも、あれとこれ何だろうと思う。
そんな小さな種がずっと頭から離れなかったり、そのうち忘れるのだが、何かのきっかけで、また頭に浮かんだり、そうすると、携帯にメモをして、ブログのネタにする時もあるし、創作のヒントのヒントになったり、そこから新たなことが頭に浮かんで来たり。
電車に乗って外を眺めていると、時々電車がすれ違う、その時、すれ違う電車に乗っている人が見える、出入口のドア付近に立っていたならば、とても近くに、その人のディテールまでがよく見えるくらいに、そばにいるように、ただ、とても遠い人であり、お互い全く意識もしていないし、気にもならないし、見えてもいないし、記憶にも残らない。
空間の中で、とても近い人なのに、全く存在感が無い、この状態は何だろう、が小さな種で、そこからはじめてみたいと何となく思った。
"Small seeds"
You can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space because you can not escape from the space from the beginning. I think that's what it would be like.
Such a small seed will not leave the head for a long time, but I will forget it later, but when something happens or floats in my mind, then I sometimes make notes on my cell phone and use it as a material for blogs. Become a hint of, or something new comes to mind.
When I look at the outside of the train, sometimes the train passes by. At that time, people on the passing train can be seen. If I was standing near the door of the entrance, very close to that person's details. As you can see, as you are by your side, you are just a very distant person, and you are not conscious of each other at all, do not care, do not see, and do not remain in memory.
In the space, although it is a very close person, there is no presence at all, what is this state, but it is a small species and I somehow thought that I would like to start from there.
周囲に比べてひときわ大きな敷地だと、周囲に比べてひときわ大きな建物が建つ。当たり前だけれども、周囲から突出して違和感を醸し出す。それを消すためにデザイン上の工夫をするだが、ボリューム感を抑えるのはなかなかむすがしい。
違和感があっても良いが、違和感があると何が良くないか、集合住宅の場合だと、長く住んでくれないらしい、長く住んでもらわないと困るらしい。
どういう部屋かも重要だが、どういう所に建つか、どういう街に住むかも同じくらい重要で、毎日のことだから、気持ち良く住みたいとしたら、街並みも重要で、せっかく、いい住宅地の街並みの中に、突出したボリュームの建物があり、そこに住むのは多少抵抗を覚えるのだろうか。
そういう場合は、一棟の塊では無く、分棟にするか、長屋にするか、敷地分割して、ボリュームを抑えつつ、デザインにバリエーションを持たせるか、などなど。
長く住んでもらうための工夫は事業性にも関わることなので、そこにデザイン性を見出すと面白い。
"I will live for a long time"
If the site is quite large compared to the surrounding area, a very large building will be built compared to the surrounding area. Though it is natural, it protrudes from the surroundings and exudes a sense of discomfort. We will devise design in order to eliminate it, but it is quite difficult to suppress the sense of volume.
You may feel uncomfortable, but if you feel uncomfortable you may not be good, in the case of a multi-family dwelling, you may not live for a long time, it may be a problem if you do not live for a long time.
Any room is important, but it is important to live in any place, in any city, it is also important every day, so if you want to live comfortably, the cityscape is also important, so you can see out in the city of a good residential area There is a large volume of buildings, and will there be some resistance to living there?
In such a case, it is not a block of one building, but it should be divided into buildings, a long house, or divided into sites, with a reduced volume, and a variation in design, etc.
It is interesting to find design in it because the device to live for a long time is also related to business.
「分かっていること」と「分かっていないこと」を書き出してメモしてみると、「分かっていないこと」がほとんど出てこない。「分かっていること」を「分かること」、「分かっていないこと」を「分からないこと」と変えても同じ、「分かっていないこと」が何かが分からないのだ。
スタート地点に戻した、今計画中のプロジェクトの話。
「本来どうあるべきか」をもう一度問い直してみようと、着想の記憶に立ち返り、収集した情報をもう一度見返し、読み返し、もう一度自分なりの言葉でメモをしているのだが、「分かっていないこと」がほとんど出てこないということは、別の見方をすると、今計画中のプロジェクトに新しさがほとんど無いということで、既存の、今ある考えを組み合わせているに過ぎないということ。
だから、計画中のプロジェクトに対して、しっくりきておらず、何かが違う、何かが足りない、と思うのだろう。
「分かっていないこと」を明確に意識して分かるためにはどうするか、もう少し収集した情報を読み込んでみるしかないのか。
「分かっていないこと」が分かり、それを解くことにより、計画中のプロジェクトに新しさが加わり、それでどうかを見たいところだが。
"I do not know what I do not understand"
When I write out and write down "I know" and "I don't know", I hardly see "I don't understand." If you change "understood" to "understood" or "ununderstood" to "ununderstood", you do not understand something the same as "ununderstood".
The story of the project currently being planned that has returned to the starting point.
I'm going back to the idea's memory, looking back at the information I've collected, reading it back and making notes in my own words, but I'm "I don't know." The fact that it hardly comes out means, from another point of view, that the project being planned is hardly new, so it is merely combining existing ideas.
So for the project you are planning, you think that something is not right, something is different, something is missing.
What can you do to clearly and consciously understand what you do not understand, or do you have to read in a little more collected information?
You know what you don't know, and solving it adds newness to the project you're planning, and that's where you want to see.
箱の話、と言っても建築では無くて古美術。レクチャーで教わったのだが、陶器の茶碗を入れる箱を作る場合、茶碗は箱に裸で入れ、箱と茶碗との隙間が四方2mm位、上方1.5cm位の空きができる大きさが、茶碗に対する箱の大きさとしては丁度良いとのこと。だから、茶碗に対する箱の大きさを見れば、箱がその茶碗専用のものかどうかが分かる。
箱の材質も貰い物か、そうでないかで違うらしく、貰い物は樅(もみ)で、貰い物では無いということは、その茶碗専用に制作された箱の場合は桐とのこと。樅の方が安く、少し価値が下がるので、中身の茶碗も貰い物には価値があるものは無いだろうと推測するのか、例えば、旧家の持ち物の処分依頼を受けて鑑定する時は、まず箱の材質だけを見て、貰い物か、そうでないかで選り分けをするとのこと。
箱の蓋にもいろいろと種類があり、真ん中が盛り上がっている蓋は、箱のつくりとしても良いらしく高価。ただ、箱を制作するのは茶碗の制作者が行うらしいのだが、箱の丁度良い大きさがわかっていない人も中にはいて、箱の材質を桐、蓋も真ん中を盛り上げなどと、箱のつくりを良くするのだが、茶碗に対する箱の大きさが合っていない、大き過ぎたりして、布などに包んで茶碗を納めたりすることもあるらしく、それで鑑定評価が下がる場合も。
と、ここまで箱だけでもいろいろと話があり、まだ箱についてあるのだが、古美術の世界もまた、様々な見方があり面白い。
"box"
The story of the box, not architecture but old art. Although I was taught in the lecture, when making a box for putting a pottery in a bowl, the bowl is put in a box, the gap between the box and the bowl is about 2 mm in all directions, and the size of 1.5 cm above is enough for the bowl. The size of the box is just right. So if you look at the size of the box for the bowl, you can see if the box is dedicated to that bowl.
The material of the box is different depending on whether it is ugly or not, and the ugly thing is a rice husk (momi), and that it is not an ugly thing means that it is a rice husk in the case of a box specially produced for the tea bowl. Since it is cheaper and the price is lower a little, it is assumed that there will be nothing worthwhile in the bowl of the contents inside, so for example, when you ask for disposal request of the property of the old house, first identify the box Seeing only the material, it will be classified according to whether it is ugly or not.
There are various types of lids for the box, and the lid in the middle rises, so it may be good as a box and expensive. However, it seems that the maker of the bowl makes the box, but there are people who do not know the size of the box just right, the box material is covered, the lid is raised in the middle, etc. Although the size of the box for the teacup is not suitable, the size of the box for the teacup is not fit, it is too large, it may be wrapped in cloth etc. and the teacup may be put, so even if the appraisal rating falls.
And so far, there are many talks in the box alone, and there is still about the box, but the world of old art also has various views and is interesting.
白い箱は、建築では何か象徴的な存在。なぜか、ファッションでは、黒と並んで、ドレス度が高い色。
白い箱は建築的には、抽象度が高い色、白は何色にでも染まる色、だから、建築家は具体的に暮らしとか、生活とかを嫌うから、みんな白にすることにより、住宅なのに、暮らし関係ない、生活関係ないと主張している、潔くないが、それで作品性を確保しようとする。要するに、抽象度を高くして、建築性、建築家としての主張を確保したいのだ。
本当はもっと主義主張があり、そこを理解して欲しいのだが、なかなか、理解されないし、そこはまた別の訓練が必要だし、そこを頑張っても営業には繋がるが、生活していくために必要なのだが、そこに注力を躊躇する、うん、建築家のさがかもしれない。
ただ、今の建築家は暮らしや生活を包括して、自分の主張をできる人ばかりだから、希望をこめて、脱白い箱の人が多い。
白い箱はバリア、建築家が建築家らしくいるための隠蓑が白色、最近はグレー。
建築家がもっと社会的に認められる存在になるならば、それはクライアントの要望を全て受け入れて、クライアント色に染まり、それでも尚且つ、建築家としての主義主張をできる場合、それは高度、それをできる人を日本では見たことが無い。
"White"
The white box is something symbolic in architecture. For some reason, in fashion, along with black, the color with high degree of dress.
White boxes are architecturally high color abstract, white is dyed in any color, so architects specifically hate living and living, so everyone is white by making it a house, It does not relate to living, claims that it does not relate to living, and innocence, but it tries to secure the work property with it. In short, I want to increase the level of abstraction and secure the claim of architecturalness and architect.
There is really a principle claim, I want you to understand there, but it is not understood easily, there is another training required, and if you try there you will be connected to sales, but it is necessary for you to live However, there is a possibility that there is no architect who is focusing on that.
However, since now architects are only people who can comprehend living and living, and can make their own claims, there are many people with white boxes with hope.
White boxes are barriers, metaphors for architects to be architects white, and recently gray.
If the architect becomes a more socially recognized entity, it accepts all of the client's needs and becomes client-colored, yet, if it is able to claim the principle as an architect, it is a person who can do it I have never seen in Japan.
スタート地点に戻した、今計画中のプロジェクトの話。ずっと、ある程度まで完成していたが、これでいいのかと考えていた。考えていたということは、しっくりきておらず、何かが違う、何かが足りない、でもそれが分かっていないから、分からないから、しまいには、何が分からないのかが分からなくなってきたので、最初に戻した。
「本来どうあるべきか」をもう一度問い直してみようと、着想の記憶に立ち返り、収集した情報を見返す所からはじめた。もう一度見返し、読み返し、もう一度自分なりの言葉でメモしている。
メモの整理の仕方を変えた。面白いもので、何か違和感がある、ということは、まだ、もっと違った何かが出てくるかもしれない。
"Return"
The story of the project currently being planned that has returned to the starting point. It had been completed to some extent, but I was thinking that this would be fine. I didn't know what I was thinking about because I wasn't quite right, something was wrong, something wasn't good, but I didn't understand it, so I didn't know, so in the end I didn't know what I didn't know So back to the beginning.
I started from the place where I went back to the memory of the idea, and looked back at the collected information, in order to re-examine the question "what should I do?" I look back again, read back, and write down my own words again.
I changed the way of organizing notes. If something is interesting and something is wrong, there may still be something different.
記録に残すかどうかと考える時がある。
知識として使いたい時は記録を残すことにしており、知恵として使いたい時は記録を取らないことにしてきた。
知識として使いたい場合は、見聞きした内容をそのまま使えば良い場合が多いので記録して、何度も再利用するつもりで、ただ、知識の賞味期限もあるから、そのうち使えなくなり、記録もどこかに無くなってしまう。
知恵として使いたい場合は、見聞きした内容をそのまま使うことは無く、応用させたり、変形させたり、エッセンスだけを生かしたりするし、それは頭の中で無意識に行っていたりする場合が多いから、かえって頭の中以外に記録してしまうと、それができなくなるような気がして、記録をはじめから取らずに、頭だけで覚えようとする。当然、時間が経つと忘れることもあるのだが、どんなに時間が経っても忘れないことはあり、それが知恵として生かせるので、時間が経って忘れることが良い選別になっているように思う。
知識はネットでその都度調べれば良いとすれば、記録を取って残す必要が無くなるし、知恵として使う場合は記録すら取らないので、はじめから記録すること自体が必要無くなる。
だから、最近は紙ベースの記録媒体を持ち歩くことは無いのだが、それでも記録したい、メモしたいことがあれば、それが今の自分にとって本当に必要なことだと判断がつくし、今それを行えば良いという行動規範にもなる。
では建築を見に行った場合はどうするか。
知識と知恵を見分けて、知識の部分はネット調べることが可能だが、折角目の前にあるのだから、写真やスケッチを残し、知恵の部分は、写真撮影やスケッチをしたことで無意識に建築が印象付けられているので、ただ目の前の建築を考えながら感じるだけにしている。
"Do you want to record?"
Sometimes I wonder if I keep it in the record.
When we want to use it as knowledge we keep records, and when we want to use it as wisdom we keep no records.
If you want to use it as knowledge, there are many cases where you just need to use what you see and hear as it is, so I will record it and try to reuse it many times. It will be lost.
If you want to use it as wisdom, you will not use what you have heard or heard as it is, and you may apply or deform it, or use only the essence, which is often performed unconsciously in your head. I feel that I will not be able to do this if I record in my head, and I will try to learn with my head, not taking the record from the beginning. Of course, I sometimes forget as time goes by, but I do not forget how much time goes by, and I can use it as wisdom, so I think that it is a good sort to forget over time.
If knowledge should be checked each time on the Internet, there is no need to keep a record, and if it is used as wisdom it will not even take a record, so there is no need to record from the beginning itself.
So I don't carry paper-based recording media these days, but I still want to record, if I want to make notes, I can judge that it is really necessary for me now and I should do it now It also becomes a code of conduct.
But what if you go to see architecture?
Although it is possible to identify knowledge and wisdom, the part of knowledge can be searched on the net, but because it is in front of a corner, leaving a picture or a sketch, the part of wisdom unconsciously architecture by having taken a picture or sketch As I am impressed, I only feel while thinking about the architecture in front of my eyes.
好きな物に囲まれて生活がしたいから、家の中は物で溢れている。好きな物だから、捨てるなんてとんでもない。一生使うものとして、大事にしているものばかり。
捨てる、断捨離と聞くと、その言葉が一般的には、暗黙の了解として、良い意味で使われているのがわかる。どんどん不要な物は捨てて、物は少ない方が良いと、世間的には当たり前のように思われている。
だから、断捨離と言うと良い行いであり、断捨離ができないとダメ人間なような印象もある。
よくあることだと思うのだが、断捨離はあくまでも手段であり、断捨離をした結果、日常生活が豊かにならなければ意味が無い。断捨離をして、物が無くなり、スッキリするだろうが、それは一過性のことで、頭の中がスッキリ、すなわち、整理整頓され、次の行いにつながらなくては、また結局は元通りになり、断捨離した意味が無くなる。断捨離が目的になっているから。
日常生活を豊かにする方法はいくらでもあると思うが、自分の好きな物で、案外それが無くても困らない物だったりするのだが、囲まれている状態、やっぱり、普段ものづくりをしているから、お気に入りの食器がたくさんあって毎日気分で使う食器を選びたいし、お気に入りの椅子がたくさんあって毎日気分で座る椅子を選びたいし、などと考えてしまう。
頭の中が、思考がスッキリして、整理整頓されていれば良いだけの話で、頭の中を断捨離すれば良いだけで、考えが明解で、自分の感性を刺激してくれる物に、不要な物も含めて、たくさん囲まれていた方が日常生活が楽しくて、豊かになる。
仕事、生活ともに、スケジュールも、情報も、メモも、スマホとタブレットとPCで同期させながら、本もデジタル化で、管理し、終われば、必要が無くなれば、データを捨てる、消して、必要なことだけを残し頭に入れて考える。
程度は別として、考え続けることが多いから、考えるための材料はいつでもすぐに簡単に見られるようにしておきたいし、手ぶらで行動することも多いので、スマホに集約させている。断捨離はそれだけで必要十分。
"I do not want to abandon"
I want to live surrounded by my favorite things, so the house is full of things. It's a favorite thing, so it's not ridiculous to throw it away. As something to be used for the rest of my life, I only use what I cherish.
When you throw it away and ask for it, you can see that the word is generally used in a good sense as an implicit consent. It seems that it is natural for the world to throw away unnecessary things and keep things small.
So it's a good thing to say that it's an end, and there's an impression that you're not good if you can't.
I think that it is a common practice, but abandonment is a means to the last, as a result of abandonment, there is no meaning unless everyday life becomes rich. You will get rid of it, you will lose things, and it will be refreshing, but it is transient, and your mind will be clean, that is, it will be organized and you should be connected to the next thing, and eventually it will be the original It becomes a street and there is no sense of abandonment. Because the purpose is to break away.
I think that there are many ways to enrich my daily life, but I like what I like and I can't be bothered by the surprise, but I am always making things in an enclosed state. I think there are a lot of favorite dishes and I want to choose dishes that I use every day, and I have a lot of favorite chairs and I want to choose a chair that I can sit every day.
It is only a good story if the mind is clean and organized, and all you have to do is just throw away your mind, it's a clear mind and something that stimulates your sensibility. However, people who are surrounded a lot, including unnecessary things, will enjoy and enrich their daily lives.
Work, life, schedule, information, memos, while syncing with smartphones, tablets, and PCs, books are also digitalized, managed, and when finished, if there is no need, throw away data, delete it, need it I just leave things and think in my head.
Aside from the degree, I often keep thinking, so I want to make it easy to see the materials for thinking immediately and always, so I often make them act by hand, so I'm concentrating them on my smartphone. Necessity alone is sufficient enough.
あらゆる無限の事柄の中から何を選択するか、一方、あらゆる無限の事柄の中から何が正解かを見つけ出す、どちらも最終的には1つのことに絞るのだが、プロセスが全く違う。
前提として、何か問題があり、その問題を解決しなければならない。
はじめの態度として、その問題を解決するための方法はたくさんあるだろうと予測して、そのたくさんある解決方法の中から何を選択すれば良いかと考え出すか、一方、その問題を解決するための方法は1つしかなく、そのたった1つの正解を導き出そうとして考え出すか。
たった1つの正解を導き出そうとするのは、いわゆる学校の試験勉強や資格試験の勉強で、たくさんある解決方法の中から何を選択するかは、創造的なことをする時に使う。
この、たった1つの正解を導き出す考え方が苦手で、これは訓練で養うものなのだが、その訓練をすること自体が苦痛だった。
今はもう、そのような訓練をする必要が無し、若い時にサボって、いろいろと妄想していたことが今役立つから良いが、このたった1つの正解を導き出す考え方は今だに苦手で、正解という言葉自体も嫌いだ。
"No correct"
The idea is to choose what out of all infinite things, while finding out what is the correct answer out of all infinite things, both ultimately narrow to one thing, but the process is completely different.
As a premise, there is something wrong, and you have to solve it.
As a starting point, predict that there will be many ways to solve the problem, and figure out what to choose from among the many solutions, while ways to solve the problem There is only one, do you come up with the idea of trying to derive that only one correct answer?
It is the study of the so-called school exams and qualification exams that seeks to derive only one correct answer, and it is used when doing creative things what to choose among many solutions.
I'm not good at thinking about this one single correct answer, and although this is what I cultivate by training, it was painful for me to do the training itself.
Now, there is no need to do such training, and it is good because it is useful to have been variously delusions when I was young, but the way of thinking to derive this single correct answer is still poor and it is said that it is correct I also dislike the words themselves.
言葉が先か、感じることが先か。
感じて、それを言葉にする、のが順序としては正しいような気がするが、そもそも感じる時に、先入観として言葉があるような気もする。
全く先入観無しに感じることなど、不可能のような気がするから、言葉が先のように思うが、ならば、感じることが全て言葉に支配されているか、コントロールされているかというと、どうだろうか。
要は、言葉が先でも、感じることが先でも、どちらが先でも良いのだが、ただ、どちらか一方が、どちらかを制限することになると困る。
だが、考えようによっては、言葉によって制限された感じ方、感じ方によって制限された言葉は、それだけで簡潔に物事を多面的に表現していることになり、深い読み解きになっていたりする。
"Feeding with words"
Is the word ahead, or is it the first to feel?
I feel that I make it into words, but I feel that the order is correct, but when I feel in the first place, I feel that I have words as a preconception.
It feels like it is impossible to feel without prejudice at all, so I think the words are ahead, but if you feel that everything is controlled by the words, how is it? Hm?
The point is that the words may come first, the words may come first, or both may go first, but it will be a problem if one or the other restricts one or the other.
However, depending on the idea, the feeling limited by words and the words limited by feelings may be expressed simply and multilaterally by itself, resulting in deep reading and interpretation.
全く違う場面だが、人が、高い技術でつくり出した、一切の余地をはさむことができない、極めて完成度が高く、極めて繊細なもの、それは、何かしらのものづくりに携わる人ならば、一応に目指すところかもしれないが、それが本当に良いものなのだろうか、と最近よく考える。
ものをつくるということで、もの単体に焦点を当てて考えるならば、完成度と繊細さを極めることは良いことに決まっている。
つくる人がいれば、それを受ける人もいる。もの単体に焦点を当てることに、受ける人は入っていない。
極めて高い完成度、繊細さの極地が、受ける人にどう伝わるかは関係ないのだろうか。
受ける人に、完成度と繊細さの極地を伝えようとした時、もしかしたら、もの単体で極地をつくりだすのとは、何か、プロセスか、完成度か、繊細さが違うのではないだろうか。
一切の余地をはさむことができない、極めて完成度が高く、極めて繊細なものよりは、受ける人の想像力や感受性や能力に委ねる部分、もしかしたら、それは完成度や繊細さの度合いが下がることかもしれないが、余白のような不完全な部分があった方が、かえって完成度の高さや繊細さの極地であることが伝わるのではないだろうか。
そのようなことを考えながら、庭園を、欧米のものと日本のもので比べながら、欧米の庭園は繊細さを完成度高くつくり出すのに対して、日本の庭園はうつろいゆく自然の中に繊細さを見つけ出すことに思いを馳せた。
"The degree of perfection and delicacy"
It's a completely different scene, but when people bring in high technology, they can not cut any room, they are extremely complete and extremely fine, and if they are involved in the manufacturing of something, it is intended for a while I don't know when or when, but I think it's really good nowadays.
In terms of making things, it is good to have perfection and delicacy if you focus on single things.
If there is a person who makes it, there are those who receive it. There are no recipients in focusing on a single entity.
It does not matter how the extremely high degree of perfection and delicacy pole is transmitted to the recipient.
When trying to convey the pole of perfection and delicacy to the recipient, what if it were to create a pole by itself alone would it be different in something, process, perfection or delicacy? .
More than perfection, extremely delicate things that can not be divided into any room, parts that delegate to the recipient's imagination, sensitivity and ability, etc., but it does not decrease the degree of perfection and delicacy If there is an incomplete part such as a blank space, it might rather be transmitted that it is a pole of high degree of completion and delicacy.
While thinking about such things, comparing gardens with those of Western and Japanese ones, while Western gardens create delicacy to a high degree of perfection, Japanese gardens delicacy in the beautiful nature I felt lost in finding it.
技巧を尽くし完成度と繊細さを極めて、その極地まで来たとする。その場所はとても素晴らしく、全ては完全で完璧であり、全く隙も無い。感嘆の声がもれる。溜息が出る。
頭の中はさぞ脳内物質が分泌されて、恍惚の極み、気持ち良くて仕方がないだろう。この世の極みである。この時を待っていました。
しかし、実際は頭の中が混乱し、素晴らしさはわかるが、気持ち良いどころか、楽しめない。これでもか、これでもかと繊細で完全完璧なものが迫ってくる。どうしたら良いのか、わからなくなる。
すなわち、辿り着いた極地は未知の場所であり、すでに極めた既知の場所では無い。既知の場所であれば、それはすでに到達している場所であるから、極みとは思わず、単なる通過点にしか思わないだろう。
未知の場所だから、混乱し、楽しむ余裕など無く、どうしたら良いのか、わからなくなるのが当たり前であり、それは受け手の問題では無い。
そこで、2つの選択肢がある。
受け手が混乱しても、完成度と繊細さを極めて、その極地を提供するのか、受け手の感度にあわせて、完成度と繊細さを調整、すなわち、バランスをとるのか、中庸とも言うかもしれない。
一番難易度が高いのは、技巧を尽くし完成度と繊細さを極めて、その極地まで行き、それが中庸であるとも言えることか。一見、この矛盾することが解けた時、次の新しい扉が開くような気がする。
そのためには、自律だけではなく、他律でもいる必要があり、自律と他律のバランスが中庸であれば良いと思う。
"Moderate"
It is said that it has done its craftsmanship and has achieved perfection and delicacy, and that it has reached its extreme. The place is very nice, everything is perfect, perfect and completely free. There is a voice of exclamation. I get a sigh.
The substance in the brain is secreted in the head, and the limit of the acupuncture, it will be pleasant and can not be helped. It is the limit of this world. I was waiting for this time.
However, in reality, my mind is confused and I know the splendor, but I can not enjoy it. Even here, something delicate and completely perfect is approaching. I don't know what to do.
That is, the polar land reached is an unknown place, not a well-known place already. If it is a known place, it is a place that has already been reached, so it will not be considered as extreme, but only as a passing point.
Because it is an unknown place, it is confusing, there is no time to enjoy it, it is natural to lose track of what to do, and it is not a problem of the receiver.
So there are two options.
Even if the recipient is confused, it may be said that the perfection and delicacy are adjusted, that is, whether the perfection and delicacy are adjusted according to the sensitivity of the recipient, that is, whether it provides a pole or perfection. .
The highest level of difficulty is that you must be skilled and extremely complete and delicate, and go to that extreme and say that it is a middle class. At first glance, when this contradiction is solved, it feels like the next new door opens.
For that purpose, it is necessary to be not only autonomy but also other laws, and I think that it is good if the balance between autonomy and other laws is moderate.
京都近代美術館で開催されている「陶工・河井寛次郎」展の河井寛次郎の言葉より、
「一度も見た事のない私が沢山ゐる」
「すきなものの中には必ず私はゐる」
「私は習慣から身をねじる、未だ見ぬ私が見度いから」
の部分に惹かれた。自分の好きなものを自分で作ってみる、それは、まだ見たことがない自分、新しい自分を見たいから、と言っているのではないかと解釈した。
まだまだ未知の自分が存在し、それを仕事を通して見つけ出す、そのためには「習慣から身をねじる」、それは日常の中で少し見方を変えてやることか。
新しい自分と出会いたい、だから仕事する。
"I have not seen it yet"
From the words of Kawai Hirojiro at the "Poster / Kawai Hirojiro" exhibition held at the Museum of Modern Art Kyoto,
"A lot of me who I have never seen before"
"I always sing in my favorite things"
"I twist myself from the habit, because I have not seen it yet"
I was attracted to the part. I tried to make something that I liked, I interpreted it as saying that I had never seen it, I wanted to see a new one.
There is still an unknown self, who finds it through work, for that purpose, "twists from habits", does it change the way of thinking a little in everyday life?
I want to meet new myself, so I work.
京都近代美術館で開催されている「陶工・河井寛次郎」展では、河井寛次郎の言葉にも惹かれた。河井寛次郎が言葉を紡ぎ出す人とは思ってもいなかったので、その中でも
「表現されるぎりぎりの自分が、同時に、他人のもの」
「ぎりぎりの我に到達した時に初めて、ぎりぎりの他にも到達」
「自他のない世界が、ほんとうの仕事の世界」
の部分に惹かれた。自分の好きなものを自分で作ってみようとすると、独りよがりになり、結果、自分以外の他を排除するものしかできないように思ってしまうが、河井はそうではなくて、自分の好きなものをとことん突き詰めて、自分で作り得る最上級のぎりぎりのものは、自分以外の他にとっても最上級のぎりぎりのものであり、それは自分とか他とかを超越したところに存在するものであり、それが本当の仕事だという。
ぎりぎりの我について、その後、思いを巡らしたのは言うまでもない。
"I at last"
At the "Poster / Kawai Kanjiro" exhibition held at the Museum of Modern Art, Kyoto, I was also attracted by Kawai Kanjiro's words. As Kawai Kanjiro did not think that he was the person who spun words,
"At the same time, the only thing being expressed is that of others"
"The first time you get to the last thing, the last to reach the last"
"The world without oneself is the real world of work"
I was attracted to the part. If you try to make your own favorite thing, you become selfish and, as a result, you think that you can only exclude something other than yourself, but Kawai is not so, it is your own favorite thing The best stuff that you can make yourself, in a nutshell, is the best stuff you have for others, and it is something that transcends you, or something else, that's true It is a job of
It is needless to say that I went over the mind about the last of me.
京都近代美術館で開催されている「陶工・河井寛次郎」展を見た。河井寛次郎というと、民藝の人というイメージしかなく、特に詳しい訳ではないが、知り合いの投稿を見て、行ってみようと決めた。
河井寛次郎の作品を今までに何度か目にしたことがあり、典型的な民藝の作家と思っていたが、今回は初期から晩年までの作品を時系列で見ることができ、そうすると、印象がだいぶ違うものになった。
形にかなりのバリエーションがあり、それは決して民藝のような保守的というか、日常の生活に根差したものでは無いように思えた。
河井の大正時代の初期の作品が素晴らしく、民藝に関わる前の朝鮮やその他の陶器を手本にしたらしいが、すでに完成度が非常に高く、技巧とセンスの繊細さが天才的とすら思えた。きっと、このような仕事は河井にとっては難なくできることであり、だから、その後、民藝運動を提唱する最初のメンバーになり、自分の仕事に芯となるものが欲しかったのではないだろうか。
ただ、初期から晩年までの作品を通しで見てみると、明らかに、民藝運動に関わり出してから、作品に変化が出る。
民藝運動に関わる前は、繊細で聡明で、釉薬の色も鮮やかだったのに対して、民藝運動に関わるようになると、繊細さは消え、色使いがくすむようになって来た。それはそれで、もちろん良いのだが、初期の、民藝運動に関わる前の作品がとても素晴らしいだけに、民藝運動に関わることによって、その初期の作品が持っていた良さが消えてしまい、全体的にくすんでしまったような印象だ。
河井寛次郎がもし民藝運動に関わらなかったら、初期の作品からどのように展開されただろうか、と想像してみると、ちょっとだけ惜しいような気がした。
"Kusumu"
I saw the "Poster, Kawai Hirojiro" exhibition held at the Museum of Modern Art, Kyoto. Kawai Kanjiro has only an image of a folk song. It is not particularly detailed, but I decided to go and see the posts of acquaintances.
I have seen Kawai Kanjiro's works several times before and thought that I was a typical folk artist, but this time I can see works from early to late years in chronological order, and then, The impression was quite different.
There was considerable variation in shape, and it did not seem to be as conservative as a folk song or rooted in everyday life.
Kawai's early works in the Taisho era are wonderful, and they seem to have modeled on the former Korean and other pottery involved in folk songs, but their degree of completion is already very high, and the subtleties of skill and sense seem even genius . Surely such work is something that can be done without difficulty for Kawai, so it might be that I wanted to become the first member to advocate the folk song movement and to be the core of my work.
However, when you look through the works from the early to the late years, obviously, the works will change after they get involved in the folk song movement.
Before being involved in the folk song movement, it was delicate and bright, and while the color of the glaze was bright, when it came to be involved in the folk movement, the delicacy disappeared and the use of colors began to get worse. So it is of course good, but because the early works of the folk song movement were so wonderful, the goodness of the early work disappeared by being involved with the folk movement, and overall It looks like it has become dull.
I imagined that it was a bit lonely when I imagined that Kawai Kanjiro had not been involved in the folk song movement, and how it would be developed from the early works.
その土地の建築を見れば、標準語の浸透度がわかるような気がするし、その土地の人たちの言葉を聞けば、建築の地域性の度合いがわかるような気がする、とした。
数寄屋建築は、数寄屋風を合わせても、京都は多く、日本料理屋さんの中には、元々、数寄屋建築としてあった邸宅を改装しているお店もあり、そういう場所では、京都の言葉が聞けることが多い。
それが、そのお店の売りなのかもしれないけれど、建築と言葉のマッチングは、料理の味を引き立てる。
"Matching of architecture and words"
If you look at the construction of the area, you feel that you can understand the degree of penetration of the standard language, and if you hear the words of the people of that land, you feel that you can understand the degree of regionality of the construction.
Even if the Sukiya architecture is combined with the Sukiya style, there are many Kyotos, and some Japanese restaurants have renovated houses that were originally made as Sukiya architecture. I can often hear you.
That may be the selling point of the shop, but matching of architecture and words brings out the taste of the dish.
建築が言葉に与える影響もあり得るだろうと、普段、東京にいる時は当たり前の風景すぎて気がつかないし、考えることが無いけれども、大阪のような大都市にくると、どこも同じだなと思い、どこにいるのかわからない、言葉も標準語で話す人ばかりだし、地域性を感じない。
きっと地元の友達同士の会話ならば、訛りも出るし、方言も普通に話すだろうけど、大都市の、どこにいるのかがわからない風景、地域性の無さが方言や訛りを話させないのではないか。
方言や訛りはその地方の気候風土、生活様式を反映しているので、例えば、寒い地域では、口をあまり開けないでしゃべるから、独特の訛りが生まれたときいたことがある。
その土地の建築を見れば、標準語の浸透度がわかるような気がするし、その土地の人たちの言葉を聞けば、建築の地域性の度合いがわかるような気がする。
"Architecture, language and locality"
I think that when I am in Tokyo, I usually don't notice it because it is natural for me to think that architecture may have an influence on the language, but when I come to a big city like Osaka, I think that everything is the same, I do not know where I am, I only speak people who speak in standard language, and I do not feel locality.
If it is a conversation between local friends, it will make me angry and dialects will speak normally, but the scenery of a big city where I do not know where I am, the lack of locality will not make me speak dialects or angry ?
Dialects and insults reflect the climate and lifestyle of the region, so in cold areas, for example, you may have a unique insult because you speak with little opening.
If you look at the architecture of the area, you feel that you can understand the degree of penetration of the standard language, and if you hear the words of the people of that area, you feel that you can understand the degree of regionality of the architecture.
短時間で、勝手にイメージしている、コテコテの大阪に触れたくて、梅田の食堂街の中にある、老舗の串揚げ屋、そこは立ち飲み、でサクッと、昼間だし、軽くと思いつつ、10本以上に2杯、いい感じ、コレコレと思いつつ。
大阪駅周辺、日本中のどこの大都市も一緒だけれど、建築だけを見ていたら、案外どこがどこだかわからない。
行き交う人々も、ユ○○ロのおかげか、いい意味で、服装も地域によって変わりなく、海外の方は服の色合いの好みが違うからわかるが、それは日本の中だったら、どこでもあまり変わらない。
飛び交う言葉、方言、訛りだけが、音として耳に残り、「ああ、ここは」と思い出すが、それも、それ程でも無く、標準語しか聞かないことが多いような、そう、だから、串揚げ屋でも、雰囲気はイメージしている大阪、でも何か足りないな、と後で思い、そういえば、大阪弁を聞いていない、お客はもしかしたら、大阪の方で無い人も多いのかもしれないけれど、お店の人も結構標準語だったし。それは、大きく雰囲気を損なうかな、お店のつくりは真似ができるから、今、東京でも、大阪の串揚げ屋がたくさんあるし。ただ、ちょっとだけ言葉尻に大阪弁が出るような気がして、ああ大阪、の雰囲気はあった。
建築を言葉で表現する時もある。だから、訛りのような地域の違いが、建築にもある。例えば、合掌造りのような建築は、その地方の気候風土、生活様式を反映している、訛りもその地方の気候風土、生活様式を反映している。
だから、日本中のどこの大都市も建築だけを見ていたら、どこがどこだかわからなくなっている、標準語しか聞かない、は同じようなことなのか、どちらが先かはわからないけれど。
"Architecture and resentment"
In a short time, I want to touch the image of Kotekote Osaka, which I imagined for myself, and in the cafeteria town of Umeda, there is a long-established salmon fried restaurant, there is a standing drink, it is quick, it is daytime, I think lightly , 2 cups over 10, feeling good, while thinking that it is korekore.
Around Osaka Station and any major city in Japan are the same, but if you look only at the architecture, you can not know where to go.
People come and go, thanks to Yu ○ ○ R, in a good sense, clothes are the same in different regions, foreign people are different from the preference of the color of clothes is different, but it is not much change anywhere in Japan.
Only words that fly around, dialects and indignations remain in the ear as sounds, and I remember "Oh, here", but it's not that much, and often I only listen to standard words, yes, so, so, 串However, I think that the atmosphere is Osaka, but I think that something is missing later, speaking of it, I have not heard the Osaka dialect, but the customers may be that there are many who are not Osaka , People in the shop were also quite standard language. It's a big loss of atmosphere, and you can imitate the making of shops, so now there are a lot of fried salmon shops in Osaka, also in Tokyo. However, I felt like I could have an Osaka dialect in the bottom of the words, there was an atmosphere of Osaka, oh.
There are also times when words are used to express architecture. So, there is a difference in the area like resentment, also in architecture. For example, an architecture such as "Gashi" is reflecting the climate and lifestyle of the region, and the reflection also reflects the climate and lifestyle of the region.
So if you're looking at architecture in any big city in Japan, you don't know where it's gone, you're just asking the standard language, or something like that, but you don't know which one goes first.
今日一日、集合住宅計画、共用部分をまとめると比較的大きな空間になるから、バルコニー、外廊下、階段などとバラバラの要素をまとめて配置できないかと、スタディを繰り返す。
より高効率なプランにはなるが、建築計画上、集合住宅としての秩序は崩れてしまうので、見慣れない空間が出現する。
そうなると、住人が使いこなせるか、住人のポテンシャルや集合住宅の運営方法にも関わってきて、建築計画上も、そこでの暮らしも、難易度が上がる、住みこなすことができるのか。
建築計画上のセオリーが一番良い訳ではないのは想像がつくだろうが、セオリー通りは管理運営しやすい。ただ、暮らしは楽しくなる、住みこなすことができれば、秩序が崩れた方が。
"Can I live better?"
Today, the collective housing plan and the common areas will be relatively large space, so I will repeat the study whether it is possible to arrange the elements of the balcony, the outside corridor, the stairs and so on together.
It will be a more efficient plan, but in the architectural plan, the order as an apartment complex will collapse, so an unfamiliar space will appear.
Then, the resident can use it well, or it can be related to the potential of the resident and the management method of the housing complex, and in terms of architectural planning and living there, can it be made more difficult and live?
It can be imagined that the theory for architectural planning is not the best translation, but Theory Avenue is easy to manage and operate. However, if life can be enjoyable, if you can live, you will lose order.
もっとニュートラルに物事を見てみたい。
自分の都合の良いように世の中を見る、都合の悪いものは目に入らない、嫌だと思うものが気になるのは、嫌だと思うものが自分にとって都合が良いから。
車で大通りを流していて、ビルとビルの間の僅かな隙間から一瞬、良いなあの建築、と見えたものが、何ヶ月後かに建築雑誌に掲載されていたり。
隔たる、ともいうべきか、それが個性かもしれないけれど、たくさんの可能性を捨てているようにも思うし、そこに気がつくと、今、とにかく行動するなんてことはマイナスしか無いと思えてくる。
物事にはタイミングがあると思う。タイミングを見計らうには、ニュートラルな状態でいないと、そして、タイミングを合わせるためには、静止状態からではすぐに動き出せないから、予備動作というか、細かな動きは常にして、その細かな動きが知見を深めることにもなると思っている。
"Fine movement"
I would like to see things more neutral.
Seeing the world as it is convenient, inconvenient things do not come into your eyes, and things that you do not like are bothered because things that you dislike are convenient for you.
You're driving along a boulevard, and from what appears to be a good building, for a moment from the slight gap between buildings, it will be published in architectural magazines in months.
Though it may be different, it may be an individuality, but I think it seems to throw away a lot of possibilities, and if you notice it, it seems that there is only a negative thing to act now anyway .
I think things have timing. In order to look at the timing, if you are not in neutral state, and you are not able to move out immediately from the state of rest in order to adjust the timing, the preliminary movement or fine movement will always be that fine movement I think that will also deepen the knowledge.
外壁や外観だけを取り出して考えることなど、前には無かった。建築は様々な部位でできていて、外壁の他にも、外からわかるもので、屋根、基礎、窓、ドア、外階段、外廊下などなど、ただそれらは単独で存在している訳では無くて、当たり前だが、それらは全て相互に関係があり、結びついて、1つの建築になっている。
だから、その中のどれか1つの部位だけを取り出してきて考えることはおかしなことだし、意味が無いと思っていた。仮に、外階段のデザインをするにしても、建築全体のデザインの方向性に合わせて、階段形式も、螺旋階段や直階段やU字などや、部材も鉄や木、コンクリートにも、仕上げも素地、塗装とか、壁の仕上げと同じにするとか、などなど、相互の関係性の中で決めていた。
それは外観のデザインも同じで、外観だけを取り出して、他との関係性を断ち切って、その部位だけをデザインすることは可能だが、それはあまり意味が無いことで、外観だけで建築は存在しないので、ただ、クライアントは見た目が良い方が、この「良い」というのも、いかにも重厚なタイル張りのレンガ調な、例えばですが、人に自慢できるとか、そうなってくると、敷地という線引きの中で好みに応じてつくられる、周辺環境とか、街並みとかを無視した行為、外観だけの建築、外観だけの街並みになる、テーマパークのように、それだけは避けたい。
今、外壁にいろいろな意味合いを重ね合わせようと考えている。パッシブデザインをする上での全体の窓面積の調整も、言わば、外壁の要素なので、他にも、不完全性を表現して、アクティビティーを発生させる仕掛けを仕込んだり、色が与える影響も外壁にはあるだろう、などなど、外壁だけを取り出して、外壁に厚みを持たせるような思考を重ねている。それは今までとはちょっと違うアプローチの仕方、そうすることで、外壁が、周辺環境や内部プランと同等に扱われるようにならないだろうかと、そうすることで、建築の存在感が少し変わるのではないか、それが既視感の変化に繋がれば嬉しいのだが。
"outer wall"
There was never before such as taking out and thinking only the outer wall and the appearance. The building is made of various parts, and it can be seen from the outside as well as the outer wall, such as a roof, foundation, windows, doors, outside stairs, outside corridors, etc., and they are not solely present alone. It is natural, but they are all related to each other, linked, and become one building.
So it was strange to think about taking out only one of the parts in it, and I thought it would be meaningless. Temporarily, even if you design the outer stairs, according to the directionality of the design of the whole building, also the stairs type, spiral stairs, straight stairs, U-shaped, etc., the members are also iron, wood, concrete, finish, etc. It was decided in relation to each other such as the substrate, painting, and the same as finishing of the wall.
It is possible to design the appearance as well, take out only the appearance, cut off the relationship with others, and design only that part, but it is meaningless and there is no architecture, only the appearance. However, if the client looks better, this "good" is also like a tiled brick wall, for example, but if you can show off to people, it will be in the line of the site. I want to avoid it, like the theme park, which will be created according to my taste, the act of ignoring the surrounding environment, the cityscape, etc., the architecture of the appearance only, the cityscape of the appearance only.
Now, I am thinking of putting various meanings on the outer wall. The adjustment of the total window area in the passive design is also an element of the outer wall, so to say, other elements that represent imperfections and have mechanisms for generating activities, and the influence of colors on the outer wall There will be, etc., etc., only the outer wall is taken out, and it is repeated thinking to give thickness to the outer wall. It is the way of the approach which is a little different from the past, and if doing so, it will not change the sense of existence of the architecture a little if the exterior wall will be treated as equal to the surrounding environment and the internal plan Or it would be nice if that led to a change in the feeling of sight.
バッファーゾーン、緩衝地帯を広く広く拡張していくと、もはやそれは部屋のような、そうで無いような、中途半端な空間ができる。
バッファーゾーンは主役ではないから緩衝地帯なので、広くなれば、だた面積が広くなるだけで、不思議なもので、別の意味が出てくる。部屋もそうだが、部屋の中でもメイン使いの空間になる。
「広い」というだけで別の意味が出てくるのは面白い。
狭小住宅は広く見せることは出来ても、実際は狭いから、狭い中から優先順位をつけて割り振るようなところがあるけれど、元々広く取れる状況ならば、広さをコントロールするだけのデザインでいろいろな意味合いの空間を出現させることができるかもしれない。
ただシンプルに、広さだけを考えて、広さを扱うことは、距離も扱うことになる。
様々な距離をデザインすることになる。もしかしたら、そうした距離感だけをただデザインすることによって、もっと人の根源的な部分に影響を及ぼすことになるかもしれない。人と人の関係とか、人と建築の関係とか。
バッファーゾーンも別の見方をすると距離の話だし、もっと広さとか、距離とかを意識してみよう。
"Area or distance"
Buffer zone, buffer zone wide and wide expansion, it will no longer be half-space like room, not so long.
Because the buffer zone is not a leading part, it is a buffer zone, so if it gets wider, it will only be a large area, and it will be strange and have other meanings. Like the room, it becomes the main user space in the room.
It is interesting that another meaning comes out just by saying "broad".
Although small houses can be widely viewed, in fact they are narrow, so there is a place to prioritize and allocate from narrow, but if the situation can be originally taken from a wide range, the design only controls the size, which means It may be possible to make space appear.
Simply dealing with the area simply by considering the area is also dealing with the distance.
I will design various distances. In some cases, just designing such sense of distance may affect more fundamental parts of people. The relationship between people and people, and the relationship between people and architecture.
The buffer zone is a story of distance from another point of view, and let's be aware of more space and distance.
建築におけるバッファーゾーンについて考えていた。バッファーゾーンとは緩衝地帯のこと、どのようにバッファーゾーンをつくるか、それは、外部と内部の間に、外部と内部をつなぐように、外部と内部の違いを調整するように。
集合住宅計画では、そのバッファーゾーンに、バルコニーや廊下や階段の機能や、パッシブデザインをする上での温熱環境の調整機能を持たせたり、アクティビティーを発生させる仕掛けを仕込んだり、構造の要素として利用したり、それが外観のデザインになるなど、バッファーゾーンに二重三重の意味を持たせようと考えたり。
だから、バッファーゾーンの大きさというか、奥行きというか、深さというか、それは普通のバルコニーや廊下のものより大きくしようと考えていて、それはバッファーゾーンを外部や内部と等価に扱おうと考えているからで、外部、バッファーゾーン、内部という構成を、境目をどうするか、境界ができるのか、グラデーションにするのか、グラデーションが面白そうだから、よりグラデーションになるように様々な機能化された、それはレイヤーというとちょっと古い気もするので、構成要素を重ね合わせてみようと、ただ、生活感が溢れ出すように見せたいから、オープンさを調整する機能も持たせようと考えたり。
Buffer zone
I was thinking about buffer zones in architecture. A buffer zone is a buffer zone, how to create a buffer zone, as it connects the outside and the inside, between the outside and the inside, so as to adjust the difference between the outside and the inside.
In multi-family housing planning, the buffer zone is equipped with the function of balcony and corridor or stairs, the function of adjusting the thermal environment in passive design, and the mechanism for generating activity, or use as an element of structure Or, I think that the buffer zone has the meaning of double triple, such as it becomes the design of the appearance.
So the size of the buffer zone, the depth or the depth is considered to be larger than that of an ordinary balcony or corridor, and it is considered to treat the buffer zone as equivalent to the outside or the inside Because, from the external, buffer zone, internal configuration, what to do the border, whether it can be a border, whether to make a gradient, so that the gradation looks interesting, various functionalization to be more gradation, it is called a layer Because I feel a little old, I try to superimpose the components, just because I want to make my sense of life overflow, so I think that I will have the function to adjust the openness.
周辺環境から影響されたり、周辺環境と一体的であったり、周辺環境に応じて変化する、それは、その建築が自律しているのでは無くて、むしろ他律している状態で、ただ、明確にその建築でしか表現できないものがある、それは自律になるので、自律と他律が両方同時に存在して、行ったり来たりしている様をつくりだしたい。
そのようなことを思い描き、ずっとスケッチをしているのだが、集合住宅として建築計画上要求されることと、集合住宅として事業計画上要求されることを最低限でも満たそうとすると、もうそれだけで、ガチガチにプランがある程度決まってしまう。
だから、それを避けるために、すぐに図面化せずに、図面化をするのは簡単なので、イメージスケッチを繰り返して行う。それは楽しい時間だけれども、ここで上手くいかないと、方向性も決まらず、つまらないものになってしまうので、でも、なかなか。
"Image sketch"
Affected by the surrounding environment, integrated with the surrounding environment, or changed according to the surrounding environment, it is clear that the building is not self-sustaining, but rather self-disciplined There is something that can only be expressed in that architecture, and it becomes an autonomy, so I want to create a state where both autonomy and other laws exist simultaneously and come and go back and forth.
I have been thinking about such things and have been sketching all the time, but if I try to meet at least the requirements of the building plan as a collective housing and the requirements of a business plan as a collective housing, The plan will be decided to some extent.
So, to avoid that, it is easy to draw drawings without drawing them immediately, so repeat image sketching. It's a fun time, but if it doesn't work here, the direction will not be decided, and it will be boring.
「他律する建築」は、違う言い方で表現すると、「弱い建築」「負ける建築」「社会に迎合する建築」などとなるかもしれない。いずれも、あまり良いイメージには聞こえない言葉だし、ネガティブな印象すらある。
「他律」という言葉も辞書を引けば、「自分の意志ではなくて、他人に支配されること」とある。
まあ、それもいいけど、譲って譲って、尚も他律でいながら、自律でもいる、そのような矛盾を孕んだ状態が形成できれば、いいな。
いいなこの建築、素直に素晴らしいと思える建築には、それを感じる、歳かな、20代、30代、40代の頃は、とにかく既知の空間には興味がなく、未知を追いかけていたけど、既知の中に未知の部分があるとわかると、そこに惹かれる、もう頭から離れない、女性も一緒かな、とにかく、その素晴らしいと思う物を仕事ではなくて、趣味とか、遊びではなくて、本気で生み出したい、だから、毎日、プランを描くし、輪島にも通うよ。
"We make seriously"
"Architectural architecture" may be expressed as "weak architecture", "defeating architecture", "society-compliant architecture", etc. Both are words that can not be heard as very good images, or even negative impressions.
If the word "others" is also read in the dictionary, it is "not being your own will, but being ruled by others."
Well, that's fine, but it would be nice if we could form such a contradiction that is selfish, still selfish, and selfish.
This good architecture, an architecture that seems to be honestly wonderful, feels that, when I was in the 20s, 30s and 40s, I was not interested in the known space anyway, but I was chasing the unknown, If you find out that there is an unknown part in the known, you will be attracted, there will be no head away, women together, anyway, things that I think that is not a job, not a hobby or play I really want to create it, so I will draw a plan every day and attend Wajima.
その敷地に対して、法規を当てはめ、どのくらいの規模の建築ができるかを検討する、それをボリュームチェックというが、最初それを行う。
そうすると、大体の建築の大きさ、限界などがわかるのだが、CADあるいはBIMのオプションのソフトを使って「逆日影」という計算をすると、ある程度自動でボリュームチェックができ、モニター上で視覚化される。
何も考えなければ、ボリュームチェックで算出された最大規模の塊に対して、後は用途に合わせて、内部を仕切るだけ、街を見渡すと、ほとんどの建築がそうしてできていると言っても過言ではない。
事業性を考えれば、最大規模のボリュームは欲しいところだろう。そこからスタートして、デザインは外観や内部の目立つところの装飾をする程度。
それが当たり前の計画の仕方だという場所もあるが、それでは貧相で下品な建築ばかりが世の中に溢れそうな気がするので、はじめからそのような計画の仕方を行なわないとすると、ボリュームチェックはただ単に建築計画にお墨付きを与えるだけのものでしかないことに気がつく。
当然、法規は順守だが、ボリュームの限界を超えたように見せるのも建築デザインの範疇だと思うので、ボリュームチェックを行うことで、建築デザインが行うべき範疇の領域を放棄することもできるようになる。
"Volume check"
For the site, apply the regulations and consider how large the building can be built, which is called volume check, but do it first.
In this way, you can find the size and limits of most buildings, but if you use the CAD or BIM option software to calculate "back shadows", you can check the volume automatically to some extent, and it will be visualized on the monitor Ru.
If you don't think about it, for the largest block calculated by the volume check, you can just divide the interior according to the application and then look around the city and say that most buildings are done so Not too much.
In terms of business, I would like the largest volume. Starting from there, the design is about decorating the appearance and the prominent part of the interior.
There is also a place where it is a common way of planning, but it seems that only poor and vulgar construction seems to be overflowing in the world, so if you do not do such planning from the beginning, the volume check will You will notice that it is only to mark the architectural plan with a seal.
Naturally, although the laws and regulations are adhered to, it seems that it is a category of architectural design to make it appear that the volume limit is exceeded, so by performing the volume check, it is possible to abandon the domain of the category of architectural design Become.
バルコニーや外廊下を道に例え、集合住宅全体を立体的な街のように考えることがある。それは、集合住宅でなくても、商業施設でもよくある手法で、戸建ての住宅でも、敷地周辺の街並みや街路のアクティビティーに似せて、内部空間のプランニングを考えることがある。
敷地周辺の環境との連続性が確保でき、集合住宅て言えば、たくさんの人が集まって住む、ということに焦点を当てれば、それは街そのものなので、自然と馴染む考え方だし、それをコンセプトにした作品にはよくお目にかかる。
ただ、街の一部としての役割にはならないのかな、といつも思う。
建築としては、敷地内で自律して、自己完結する。それは建築基準法でも、1つの敷地に1つの建物、と決められているし、建築家としても、自律した建築を作品としてつくりたいだろうから、必然的にそうなる。
自律した自己完結の建築だけでは街は成り立たない。
街には他律した建築も必要で、この場合、他律とは自らの意志だけでは完結しないこと、であり、例えば、季節や時間によって、人が集まる場所が変わったり、建築の使われ方が変わったりすること。
他律が全く無い街が住宅街で、単一の用途の建築で形成されている場合が多く、住宅街だとお互いのプライバシーを気にして何かと閉鎖的になりがちであり、それは建築自体が自律して、自己完結しているから、排他的になるためである。
だから、集合住宅でも、戸建ての住宅でも、他律する建築を目指せば、それはすなわち、周辺環境と良好な関係が築け、街に対して影響力を持つ建築をつくることができるし、その方が街の一部としての役割も担い、街並みを形成する上でも積極的に関与できるのではないかと考えている。
"Architectural architecture"
The entire apartment complex can be considered as a three-dimensional city, even if the balcony and the outside corridor are like roads. It is a method common to commercial facilities, even if it is not a collective housing, and even in single-family homes, planning of interior space may be considered similar to the cityscape and street activities around the site.
Focusing on the fact that continuity with the environment around the site can be secured, and speaking of collective housing as a lot of people gather, it is a city itself, so it's a concept that naturally blends in with it, and that's a concept I often see your work.
However, I always think that it does not play a role as a part of the city.
As architecture, it is autonomous on site and self-completes. Because it is decided that it is one building on one site, even if it is building standard law, and you will want to create an autonomous architecture as a work as an architect, it will inevitably be so.
The city can not be built with self-contained architecture alone.
The city also needs a self-designed architecture, and in this case, the self-indulgence is not complete by its own will. For example, depending on the season or time, the place where people gather changes, how the architecture is used Change.
The town where there is no other rule at all is a residential area, and it is often formed of a single-use architecture, and in the case of a residential area, it tends to be closed with something concerned about each other's privacy. Because it is autonomous and self-contained, it is exclusive.
So, if you aim at an architecture that is equal to an apartment house or a detached house, it means that a good relationship with the surrounding environment can be built, and an architecture with an influence on the city can be created, which is I also play a role as a part of and think that I can be actively involved in forming cityscapes.
住むこと自体がアクティビティーだから、集まって住むことは異なるアクティビティーが生まれるから、その間に、オープンなパーソナルスペースができる、と考えたので、ずっとプランニングをしていた。
住む部分を何戸か集めて塊にし、複数の塊を敷地に配置し、塊の形はとりあえず四角形、複雑な形にすることもできるが、塊と塊の間のつくられ方が見たいので、単純な形でとりあえず計画していた。
そうして計画していると、塊の間が細長くなった場合などは、団地の空き地のようになり、確かにオープンなパーソナルスペースかもしれないが、イメージしているものとは違うような気がした。
団地の空き地は子供の遊び場であったり、人が集まる場所、よく言えば、イタリアの街中にあるような広場みたいな場所として機能するかもしれないが、その空き地に対して住む側は閉鎖的だった。それはまるで住宅街のように。
だから、住むこと自体はアクティビティーだが、集まって住んだ場合、個々のアクティビティーは異なっておらず、同じであり、だから、お互いのアクティビティーが気になり、空き地に対して開くことができずに閉鎖的になる。
この閉鎖的な感じを無くしたい、何とかしたく、そのためにアクティビティーを利用しようと考えているのだが、そもそもアクティビティーが同じか異なるかを見分ける段階で間違っていた。もっと言えば、オープンなパーソナルスペースは屋内につくりたいのだが。
"Identify activities"
Since living itself is an activity, gathering and living will create different activities, and in the meantime, I thought that I could have an open personal space, so I was planning for a long time.
You can gather some parts of the house into clumps, place several clumps on the site, and you can make the clumps into square shapes or complex shapes for now, but you want to see how they are made between clumps and clumps , Had planned for the moment in a simple way.
If you plan on doing so, it will become like a vacant lot in the housing complex if, for example, the space between the lumps becomes elongated, and it may be an open personal space, but it is different from what you imagined It was over.
The vacant lot of the housing complex may be a playground for children or a place where people gather, often speaking like a square like the one in the Italian town, but the side that lives against the vacant land is closed. The It's like a residential area.
So living in itself is an activity, but when gathered together, the individual activities are not different and are the same, so they are interested in each other's activities and closed without being able to open to the open space become.
I want to get rid of this closed feeling, somehow want to do it, and I'm thinking of using the activity for that purpose, but it was wrong at the stage of discerning whether the activities are the same or different. More specifically, I would like to create an open personal space indoors.
集まって住むからには、集まって住むなりの良さを出したい。ただ、集まって住むとなると、それなりのボリュームになる。
高層建築物が見当たらない住宅地では、あまり大きな塊のような建築は、街並みを分断し、そぐわないかもしれない。
事業性を加味しなければならないが、ひとつの大きな塊にするより、分けた方が1つの塊が小さくなるので、街並みと齟齬を起こさなくなる。
どうしても事業性から考えると、ちょっとでも大きく、高くとなるのは仕方ないが、事業性だけで建築は決まる訳ではないし、街並みと齟齬を起こした建築には人が違和感を覚え、人が集まらなくなるかもしれない。
そうなると、分け方にはかなりのパターンが存在し、決め手に欠くので、また他の要素を入れることになる。
"Separately small"
As we gather and live, we want to bring out the goodness of gathering and living. However, when it comes to gather and live, it becomes a certain volume.
In residential areas where high-rise buildings can not be found, too large chunks of architecture may disrupt the cityscape and make it inconsistent.
Business must be taken into consideration, but it will not cause cityscapes and hiccups as one chunk will be smaller if divided than one big chunk.
If it thinks from business nature, it will be a little big and it can not be high, but architecture is not decided by business nature alone, people feel discomfort in the city and the architecture which caused the problem, people are not gathered It may be.
In that case, there are considerable patterns in the division, which is lacking in the decisive factor, so other elements will be included.
オープンカフェもアクティビティーのひとつ。オープンカフェって、人前でお茶を飲んでいるし、大概は丸見えだし、プライバシーも何も関係無いのに、なぜか安らぐし、気が休まったりする、考えてみれば不思議なものだ。
パブリックな場所であれば、丸見えだろうとプライバシーは勝手に確保されていると思い込むのか、気が緩むのか、案外平気、パーソナルな空間がそこにできてしまう。
ただ、そこにはアクティビティーが作用しているように思う。オープンカフェで自分以外の人もそこにいて、お茶を飲んでいるから、お互い違うアクティビティーをしているから、お互い意識することもない。
もし誰もいなくて、自分だけがお茶を飲んでいたら、オープンカフェという場所が設えられているから平気かもしれないが、居心地に差が出るだろう。
複数のアクティビティーの中に埋没している時が一番見えない状況をつくり出すのかもしれない。
"Burning into activities"
Open cafe is one of the activities. An open cafe is a cup of tea in front of the public, it is almost completely visible, and it has nothing to do with privacy, but for some reason it feels soothing and restful.
If it's a public place, you may think that your privacy is secured by itself if you can see it, or if you feel relaxed, there will be an unexpected, personal space there.
However, I think that activities are working there. Because there are people other than myself at the open cafe and drinking tea, they are doing different activities, so they don't have to be aware of each other.
If nobody is there and only you are drinking tea, it may be safe because there is a place called Open Cafe, but you will feel more comfortable.
It may create a situation where you can not see the time when you are buried in multiple activities.
チラチラと動きがあったら、その奥の存在はあまり気にならないというか、手前のチラチラに気を取られて、奥に意識がいかない。見えていない訳ではないが、手品師も似たような手法を使うが、見る者の意識を他にそらすことによって、見えていない状況をつくる。
見えないのではなくて、意識しないから、見えていないのだ。だから、プライバシーの守り方にも2通りあることになる。
1つは、完全に見えなくしてしまう、カーテンを閉める、ブラインドを下ろす、そもそも壁にしてしまう、などなど、2つ目は、見る者の意識を他にそらすことによって、見えていない状況をつくり出す。
その意識を他にそらすために利用するのがアクティビティーであると考えている。
"Awakening activities"
If there is a movement with the chill, the presence of the back is not bothered too much, or the chiller in the front is distracted and the back does not get conscious. Although not invisible, magicians use a similar method, but create an invisible situation by diverting the viewer's awareness to others.
It can not be seen because it is not visible, not conscious. So there are two ways to protect privacy.
One creates the invisible situation by distracting the viewer's consciousness from others, such as making it completely invisible, closing the curtain, lowering the blinds, making it a wall, etc. .
We think that it is activity to use to divert the consciousness to others.
2階の窓から道路までは20mくらい離れている、敷地が奥まっている、いわゆる、旗竿地だから。
その窓は素通しのガラスで、内側に障子があり、カーテンは無い。元和室、今洋室、だから、窓の高さが低く、腰の高さも低い。見下ろすような目線で外を眺めるが、いつも障子は開けっ放し、中からも外からも素通しのガラスだけ、丸見え、ただ、外からだと見上げで角度があるので、天井あたりがよく見えるだけ。
この状態、素通しのガラスが入った窓をカーテンも障子も閉めずにいるのだから、生活感が溢れ出してもよいはずだが、ただ、ガラス越しに中の様子、家具やキッチンが少し見えるだけ、とても生活感が溢れ出ているとは言えない。
素通しのガラス1枚ではオープンとは言えず、それはガラスという、ある意味、透明な仕上げの外壁材が嵌め込まれているに過ぎず、それは外壁材の仕上げのパターンの1つに過ぎない。
外壁材としてのガラスでは無くて、生活感が溢れ出すオープンなガラスになるには、ただ単に素通しのガラスを入れれば良い訳ではなくて、工夫が必要になる。
その工夫しだいで、オープンでありながら、プライバシーが確保されている状態がつくれるだろう。
"Open glass"
It is about 20 meters from the window on the second floor to the road, and it is a so-called flag fence where the site is deep.
The window is made of pure glass, with a shoji inside and no curtain. A former Japanese-style room, a now-western room, so the height of the window is low and the height of the waist is low. I look at the outside with a glimpse of eyes, but always open the shoji, only the transparent glass from inside and outside, just look round, but if you look from the outside, there is an angle at the top, so only the ceiling can be seen well.
In this state, since the window with pure glass is closed without closing the curtain or shoji, it may be possible to overflow the sense of life, but only the appearance of the inside of the glass, only a little furniture and kitchen can be seen, It can not be said that the sense of living overflows very much.
A single transparent glass is not open, it is in a sense a glass, in a sense a transparent finish of the exterior wall material, which is only one of the patterns of the exterior wall material finish.
It is not a good idea to simply add pure glass, but it is necessary to devise a glass that is not an exterior wall material, but to be an open glass that overflows with a sense of lifestyle.
Depending on the device, it will be possible to create a state of privacy while being open.
ただ単に生活感が丸見えの風景には興味が無く、生活感が溢れ出た感じに興味がある、何が違うのか。
生活感が丸見えは、ただ単にオープンにされ、プライバシーに配慮されている訳でも無い。
生活感が溢れ出た感じは、オープンなのだが、生活感の端々がはみ出てきたような、余分というか、どうしようもなく、というか、肝心な所は隠されていて、守られていて、プライバシーに配慮されていて、端々だけど、そこに生活感のエッセンスが垣間見えるような。
だから、オープンにするにしても、生活感がどの程度までわかるようにするか、生活感の見え方の編集作業が必要になり、それがデザインの範疇になる。
"Design to edit the way of feeling of life"
However, I am not interested in the scenery where the sense of life is completely visible and is interested in the feeling that the feeling of life overflows, what is the difference?
A sense of life is a mere sight, not just open and privacy conscious.
Feeling that the sense of life overflows is open, but the end of the sense of life has come out, whether it is extra or no way, the important point is hidden and protected, The privacy is taken care of, and it is the end, but the essence of the sense of life can be seen a glimpse there.
So, even if it is open, it will be necessary to edit how the sense of life is seen, to what extent the sense of life can be understood, and this becomes a category of design.
GWは亡父の姉の葬儀に参列するために、何年かぶりに亡父の生まれ故郷に行った。
千葉の外れ、周りは田んぼや畑、街道沿いだけはどこにでもあるチェーン店の街並み、赤紫の○○○モールの看板、それでも夜は真っ暗なのにコンビ二のまわりはだけは青白い。
昔の銀座通りはシャッター街、駅は綺麗に建て替わって、道も整備されているが、コーヒー1杯飲むお店も無く、賑わいも無く、同じ賑わいが無くても、なぜかシャッター街の方は郷愁を誘い、ちょっと離れれば、家の1区画が比較的大きく、高い建物も無く、心地よい風が吹きわたる。
最近ずっと、自閉しないで生活感がオープンになる建築ばかりを考えているせいか、目が行くのは、生活感の伝わり方がどうかということ。
賑わいが無ければ、家の1区画が大きければ、高い建物が無ければ、周りが田畑ならば、誰の目も気にする必要が無いのだから、オープンに、生活感が溢れ出ても良さそうだろうに、自閉している、それは都市よりも強固。
そういう姿を見ると、建築だけでは解決できない、人の心理や人間関係が影響を与えている、もちろん、それは当たり前だが、都市にいると意外と思い違いをしてしまう、そういう心理や人間関係の上に社会が形成され、その社会を建築が反映してしまうことを、その逆の、都市は賑わいに慣れ、人間関係が希薄だから、建築が社会を規定できると、その思い違いから計画がスタートする。
ただ、建築の歴史を辿ると、建築が社会を規定できるというところからスタートするから新しい建築が生まても来た。建築が社会を反映するならば、そのスタートは社会を追認することだから、そこでは見慣れた風景の建築は生まれても、新しさは生まれない。
そう考えると、若い人が都会に出たがるのもわかる気がした。
"Strong more self-confident"
GW went to the hometown of his late father for the first time in several years to attend the funeral of his late father's sister.
Outside of Chiba, around rice fields and fields, the streets of chain stores where there is only along the highway, the signboard of the red-purple ○○○ mall, but it is still dark at night, but only around Combi is pale.
The old Ginza Street is a shutter town, the station is beautifully rebuilt, and the road is well maintained, but there is no shop to drink a cup of coffee, there is no bustling, and even if there is no bustling, people in shutter town somehow Nostalgic, inviting a little away, a section of the house is relatively large, there are no tall buildings, and a pleasant wind blows.
The reason why people are thinking about architecture that will open their sense of life without having a sense of autism all the time has come to see how the sense of life is transmitted.
If there is no bustling, if one section of the house is large, if there is no tall building, if there is a surrounding field, there is no need to worry about anyone's eyes, so it seems good to have a sense of openness It is self-closing, it is stronger than the city.
If you look at such a figure, it can not be solved only by architecture, but it is natural that people's psychology and human relationships are influenced, but it is natural, but if you are in a city, you unexpectedly misunderstand, such psychology or human relationships The opposite is that cities are used to the bustle and that human relationships are weak, and that planning can start from that misconception that architecture can define society, as a society is formed and that architecture reflects that society.
However, since the history of architecture starts from the point where architecture can define society, new architecture has come to be born. If architecture reflects society, the start is to recognize society, so there will be no newness, although architecture of familiar landscapes will be born.
When I thought so, I felt that I also wanted to see young people going to the city.
遠く離れていれば、オープンにできるのか、いやそれは違う、遠く離れていても、オープンにできない場合はあり、それは、ただ離れている場合。
ただ離れているとは、その間に何もない状況。その間に何もない状況とは、隔てるものが何もないだけでは無くて、空間が透明なような、かえって、よく見えてしまう状況。
離れていて、その間にアクティビティーを挟み込めれば、空間に層ができるように、空間が霞むといか、見え方に幕がかかったような、丸見えでは無い状況がつくれるのではないか、オープンにできるのではないか、そう状況が安心感を与え、生活感が溢れ出すのではないかと仮説を立てて検証してみる。
"It is not enough just to be away"
If it is far away, it can be open, no, it may be different, even if it is far away, it may not be open, if it is just away.
Just being away is a situation where there is nothing in between. In the meantime, the situation where there is nothing is not only the thing that separates nothing, but the situation where the space is transparent and looks better.
If you are separated and you can put activities between them, you can create a situation where the space is stagnant or the way you see it, and you can create a non-overview situation so that you can create a layer in the space. Let's do it, let's make a hypothesis and test that the situation gives a sense of security and a sense of life may overflow.
生活感が溢れ出た方が街としては活気があり、楽しいし、防犯にもなる。
歴史的街並みならば、極力、生活感が溢れ出ない方が良い、生活感とはかけ離れた所で元々街並みが成立しているので、生活感は不用だから。
しかし、なかなか生活感が溢れ出す状況にはならない。生活感が溢れ出すとは、違った見方をすると、プライバシーをさらす訳だから、心理的には嫌、障壁がある。その障壁を無くすのは、デザインでの方向性と技術であり、決して、クライアントの趣味趣向でも、我慢でもない。
さらに、特殊な条件が積み重なって生活感が溢れ出すオープンさが成立するよりも、一般解として、どうしたらオープンにできるのか、または、一般解として展開可能なことをやらないと、他の場所での再現性がなく、街並みには発展しない。
だから、もしかしたら、どこにでもありそうだけど、どこにもないような見え方が理想かもしれない。
"To overflow the sense of life"
People who have a sense of life are lively, enjoyable, and burglar-free as the city.
If it is a historical cityscape, it is better if the feeling of life does not overflow as much as possible, because the cityscape is originally established at a place far from the feeling of life, so the feeling of life is unnecessary.
However, it does not come to a situation where the sense of living overflows. There is a psychologically disgusting and barrier, as the sense of life overflows, as viewed from a different perspective, exposes privacy. It is the direction and technology in design that eliminates that barrier, and it is neither a client's taste preference nor a patience.
Furthermore, rather than creating an open that overflows a sense of living by accumulating special conditions, it is possible to open it as a general solution or to do something that can be expanded as a general solution in other places Does not develop into the city.
So, maybe it's likely to be everywhere, but it might be ideal to look like there is nowhere.
距離があって離れていれば、遠くにしか見えなければ、きっと窓を全開にして、太陽の光と空気を思いっきり取り入れようと、自然にするだろうな。
でも都市では、距離があって離れる状況はなかなか無い。その建築だけが突出して高ければ、上階でそういう状況になるだろうが、それもなかなか無い。
以前にも書いたが、電車のすれ違いざま同士は全くお互いに見えていない状況になり、それはお互いに動いているからで、建築は動かないので、動けないので、その状況を、お互いに見えていない状況をつくり出すには、距離を空けて離れるしかない。
そこで、距離を取ることができないので、距離があって離れている状況と同じ状況をつくり出せないかと考えてみる。
レベル差があれば、例えば、道路に対して2階ならば、無理に見ようとしない限り見えないはず、しかし、なかなかオープンにする人もいない。
要するに、中身にいる人の心理的問題もあって、レベル差だけでは安心してオープンにはできないのだろう。
ならば、もう1つの別の何かを追加してあげれば、安心してオープンにしてはくれないか、それがアクティビティーかもしれないと、いろいろとスケッチをしてみたものの、ただ、ちょっと面白い題材なので、もっといろいろと考えてみることにした。
"To make the same situation"
If you are far away and only look far, you will probably open the window and let it naturally take in sunlight and air as much as possible.
But in the city, there is no distance from the distance. If only that building stands out and is high, such a situation will occur on the upper floor, but it is not quite there.
As I wrote before, the passing trains are in a situation where they can not see each other at all, because they are moving with each other, and since the architecture does not move, they can not see each other because they can not move. The only way to create a situation that does not exist is to leave a distance.
Therefore, we can not take the distance, so we will consider whether it is possible to create the same situation as there is a distance.
If there is a level difference, for example, if it is the second floor to the road, it should not be visible unless it is forced to look at it, but there is no one who makes it quite open.
In short, due to the psychological problems of the people inside, it may not be safe and open only with the level difference.
So if I add another one, I can not open it with peace of mind, or if it might be an activity, I tried sketching in various ways, but it's just a funny subject I decided to think more and more.
すれ違う電車同士、お互い近くに乗客が見える、案外近い、しかし、距離の近さとは逆に、当たり前だが接点は無く、もう二度会うことが無い人たち、実際はもうしかしたら、どこかで会っているかもしれないが、元々関心が無いので覚えていない、お互いに丸見えなのに見ていない、見えていない状態。
こちらの電車も向こうの電車も違う活動をしているから、全く別世界にいるように接点が無い。だから、違う電車に対しては意識もしない。
これが同じ電車内ならば、例え、もう二度会うことが無い人たちでも、とりあえず、同じ空間にいるので意識はしてしまう。
同じ電車内ではオープンにできないが、違う電車に対してはオープンにできる気がする。
さらに、違う電車同士に挟まれた場所ならば、誰も関心を持たない、誰も意識しない、空白地帯が出現する。電車ならば、人を乗せたまま電車自体が動き、活動するので、この空白地帯をつくり出すのは容易だが、動かない建築では、この空白地帯はオープンなパーソナルスペースにできるのだが、なかなか難しい。
まず、活動すなわちアクティビティーを建築で発生させなければならない。このアクティビティーは人がする。不完全性を利用して、完全になろうとする働き、この場合は心の働きになるだろう、を発生させる、これが建築でのアクティビティー、このアクティビティーを複数、異なるものを発生させれば、その間に空白地帯ができ、そこがオープンなパーソナルスペースになる。
この考えのもと、スタディを延々と繰り返すも、いつでもまとめようと思えばできそうなのだが、時間があるせいか、余計なことまでしてしまう。
"Blank zone"
Trains passing each other, passengers can be seen near each other, unexpectedly close, but, contrary to the closeness of the distance, people who have no contact but have never met again, in fact, probably met somewhere It may be, but I do not remember because I am not interested in originally, I can not see each other even though I can see each other, I can not see it.
Because this train and the other train are doing different activities, there is no contact as if you were in another world. So I am not conscious of different trains.
If this is in the same train, even people who never meet again will be conscious because they are in the same space for the time being.
I can not open it on the same train, but I can open it to another train.
Furthermore, if it is a place between different trains, a blank zone will appear where nobody is interested or conscious. If it is a train, it will be easy to create this blank area, as the train itself will move with activity and it will be easy to create this blank zone, but in a static architecture this blank zone can be an open personal space, but it is quite difficult.
First, the activity or activity must be generated in the building. This activity is done by people. Taking advantage of imperfections to create a work that will try to be complete, in this case it will be a work of the mind, if this is an architectural activity, and if this activity generates several different ones, There is a blank zone in the area, which will be an open personal space.
Based on this idea, it is possible to repeat the study endlessly, but if you try to put it together all the time, it will do more than necessary because of the time.
接点の無い異なる複数のアクティビティー同士に囲まれた空間がオープンなパーソナルスペースになり、表層の不完全性により、アクティビティーは表層の外、建築の外で発生させるとし、表層の不完全性は敷地のコンテクスト/文脈からつくる、とした。
以前にも書いたが、不完全性のつくり方には、何かを足せる状態か、完全性が乱れたり崩れた状態の2つある。何かを足せる状態とは、例えると、茶会の度に設えを整える前の茶室であり、それは空っぽの状態と言っても良く、完全性が乱れたり崩れた状態とは、同じく茶室で例えると、シンメトリーが崩れた違い棚てあり、その崩れ方、乱れ方が見る者の心に働きかけてくる、心を動かす。
どちらの不完全性もアクティビティーが発生するので、2つの方法を使い分けたり、組合せることも可能だと思うが、見る者の心に働きかける方に興味がそそられ、シンメトリーが崩れり乱れた状態をつくり出すデザインをすることになるだろうが、デザインの完成が目的では無くて、その先の人の心に働きかけることが目的であるという所が、本来、デザインとはそういうもので、デザインが手段であるのがいい。
"Design of means"
The space surrounded by different activities without contact becomes an open personal space, and the imperfection of the surface causes the activity to occur outside the surface and outside the building, and the imperfection of the surface is the site It was made from context / context.
As I wrote before, there are two ways of creating imperfections: adding something, or breaking or breaking integrity. A state in which something can be added is, for example, a tea room before setting up for a tea ceremony, which may be said to be empty, and a state in which the integrity is broken or broken is similarly compared in the tea room The symmetry is broken into a different shelf, and how it collapses and disturbs works on the mind of the viewer, moving the mind.
Since both imperfections generate activity, I think it is possible to use or combine the two methods, but it is intriguing to work on the mind of the viewer and the symmetry is broken down The design will be created, but the place where the goal is not to finish the design but to work on the mind of the person ahead is basically such design, and the design is the means I hope there is.
接点の無い異なる複数のアクティビティー同士に囲まれた空間がオープンなパーソナルスペースになる、とした。
狭小空間に単一なアクティビティーを押し込めることはできるが、複数となると、さらに求めているのは異なるアクティビティー同士に囲まれた空間だから、やはり、ある程度の規模が必要になるのか。
アクティビティーを中身で発生させようとすると、どうしてもある程度の規模が必要になる。しかし、アクティビティーを中身では無くて、表層の不完全性により発生させようとすれば、中身の規模は関係無くなり、アクティビティーは表層の外、建築の外で発生させることになる。
だから、表層に不完全性をつくり、その不完全性は敷地のコンテクスト/文脈からつくれば良い。
"Incompleteness in the surface"
The space surrounded by different activities without contact points is said to be an open personal space.
It is possible to push a single activity in a small space, but if it is more than one, it is still a space surrounded by different activities that you are looking for, so is it still necessary to have a certain size?
If you try to generate an activity in the content, you will need some size. However, if the activity is generated not by the content but by the imperfection of the surface, the scale of the content is irrelevant, and the activity is generated outside the surface and outside the building.
Therefore, it is sufficient to create imperfections in the surface, and the imperfections can be made from the site context / context.
アクティビティーを利用する計画には、ある程度の規模が必要ではないかと考えていた。
アクティビティーとは大体、人間活動であり、その場を計画するのだが、流動的で、線のような空間をイメージする。
簡単に言うと、人間が動き回るのである。だから、あまり狭い空間では、動き回るという人間活動ができないのではないかと考えてしまい、どうしても、頭の中では広い敷地で計画するイメージをしてしまうが、線のような空間を折り畳むように、狭小の空間の中に押し込めれば可能であり、ただ、それだと、異なる複数のアクティビティーを押し込めるのは無理のような気がする。
計画したいのは、アクティビティーそのものでは無くて、接点の無い異なる複数のアクティビティー同士に囲まれた空間であり、そこがオープンなパーソナルスペースになると推測しているから。
やはり、ある程度の規模が必要になるのか。
"Activity in a small space"
It was thought that a certain size was necessary to plan using activity.
Activities are roughly human activities, and we plan for the place, but they image a fluid, line-like space.
Simply put, people move around. So, in a very small space, I think that I might not be able to move around, and I think in my head I have the image of planning on a large site, but I narrow it so as to fold a space like a line It is possible if it is possible to squeeze into the space of, but it seems that it is impossible to squeeze different activities.
What I want to plan is not the activity itself, but a space surrounded by different activities without contacts, and I guess that it will be an open personal space.
After all, do we need a certain size?
オープンなパーソナルスペースをつくり、住む人が自由にオープン度を選択し、生活や暮らしが溢れ出すようなイメージをしており、そのオープンなパーソナルスペースは異なるアクティビティーを発生させてつくる。
表層と中身の話で言えば、表層が異なるアクティビティーを発生させ、中身のパーソナルスペースの存在が見えているようで見えない状態をつくり出すことによって、中身のパーソナルスペースをオープンにでき、そのオープン度を中身の住人が自由に選択できる。
表層は不完全性を表現することにより、完全なものになろうとする、または、完全なものと比較する心の動き、働きを起こさせ、アクティビティーを発生させる。異なるアクティビティーは異なる不完全性によってつくり出される。
表層の不完全性をどうつくるかはデザインの範疇になってきて、その時に、敷地のコンテクスト/文脈や見立てを用いる。
接点の無い異なるアクティビティーを発生させて、その間に、オープンなパーソナルスペースができるという計画だが、ある程度の規模が必要ではある。
"Plan to create an open personal"
It creates an open personal space, people who freely choose the degree of openness, and has an image that life and life overflow, and the open personal space is created by generating different activities.
Speaking of the surface and the contents, the surface can generate different activities, making it possible to open the contents personal space by creating an invisible state where the presence of the contents personal space is visible, and the degree of opening Residents of the content can choose freely.
By expressing imperfections, the surface causes mind movement, action, and activity to try to be perfect or to compare with perfect ones. Different activities are created by different imperfections.
How to create surface imperfections becomes a category of design, and at that time, use the site context / context and remarks.
The plan is to create different activities without contact, and in the meantime, open personal space, but it needs some scale.
開口部を厳選してオープンにしていくのは敷地の欠点を補う対処療法である、とした。
パッシブデザインを行う時は開口部の位置を方位と周辺環境から決定し、開口部の総面積を計算で求める。温熱環境を考えての結果だが、パッシブデザインという括りで敷地を、周辺環境を見ている、言わば、コンテクスチュアリズムの一種、派生ということができるかもしれないが、温熱環境を主として計画を進めていくと、開口部の取り方で実際の生活や暮らしと齟齬を起こすことがあり、それはパッシブデザインが生活や暮らしとは別のところで計算により決まるからで、一見、敷地を生かしているようで、実は生活や暮らしの面から見ると、窮屈で、自由度が少なく感じ、住む人が建築に合わせているように感じる。
オープンなパーソナルスペースを異なるアクティビティーを発生させてつくろうとすることは、住む人が自由にオープン度を選択できるイメージであり、それが生活や暮らしを反映することだと考えている。
"Openness reflecting life and living"
It is said that it is the coping therapy that compensates for the fault of the site that carefully select and open the opening.
When performing passive design, the position of the opening is determined from the orientation and the surrounding environment, and the total area of the opening is calculated. It is the result of thinking about thermal environment, but it may be possible to say that it is a kind of contextualism and derivative, so to speak, looking at the site around the environment by a group of passive design In some cases, how to take the opening may cause a conflict with actual life and living, because passive design is determined by calculation at a place different from living and living, seemingly taking advantage of the site, Actually, from the aspect of life and living, I feel cramped, I feel less freedom, and I feel like the people who live fit the architecture.
I think that creating an open personal space by generating different activities is an image that allows people to choose the degree of opening freely, and that is to reflect life and living.
「表層と中身」の話をした。
中身に制限は無いが、プライバシーを守るために閉じたくなる、中身を見られたくない、という心理が働くのは当たり前だが、その閉じたくなる心理をなんとかしたい、無くしたい。
オープンにできた方が気持ちがいいだろう、天気が良い日には窓を開け放って青空をのぞみたいし、ふんだんに心地よい風を取り込みたい、
そういう生活がしたいが、なかなか、自然の中ならば可能だが、都会の中では難しい、というか、心の中で勝手に無理だと決めつけてしまう。
その障壁みたいなものを昔から、それこそ、建築を学びはじめた学生の頃から取り除きたいと考えている。
住み手が特殊な人で、自分みたいに、周りは何も無かったことにできる人ならば、人に見られようと、どうしようと関係ないから、開け放つことは可能だが、普通はそれは無理だから、周りと干渉しないように、太陽の位置を時刻によって計算し、あと、クライアントの生活習慣を考慮しながら、開口部を厳選してオープンにしていくのだが、その行為は言わば、敷地の欠点を何とか補う行為で、対処療法であるから、本来持っている敷地のポテンシャルを発揮しているとは言えず、でも、暮らしの中で、自閉せず、開いていくのだが、根本的には、それは不健康なような気がして、異なるアクティビティーを発生させ、オープンなパーソナルスペースをつくろうと、どうしても考えたくなる。
"I want to solve autism"
We talked about "surface and content".
There is no limit to the contents, but it is natural that the mind works like closing to protect the privacy and not wanting to see the contents works, but I want to manage or eliminate that closing mind.
It would be nice if you could do it openly, open the window to see the blue sky when the weather is fine, and want to take in plenty of pleasant wind,
I want to live that kind of life, but it is possible if it is in nature, but it is difficult in a city, or rather it is decided that it is impossible in the heart.
I would like to remove something like the barrier from the old days, that is when I was a student who started to learn architecture.
If a person is a special person who can do something like himself and nothing around it, it is possible to open it up regardless of how it is seen by people, but it is usually impossible. The position of the sun is calculated according to the time so as not to interfere with the surroundings, and after taking into account the client's lifestyle habits, the opening is carefully selected and opened, but the act is, as it were, a fault of the site. Because it is a coping therapy, it can not be said that it actually exerts the potential of the site that it has originally, but it will not open itself in the living without being closed, but it is fundamentally It feels like it's unhealthy, generates different activities, and wants to think about creating an open personal space.
「表層と中身」という話をした。
表層というと、極薄ペラい、ヒラヒラな感じで、厚みがあまり無いようなイメージがするかもしれないが、もっと厚みというか、奥行きがある表層をイメージしている、相当厚いかもしれない。
その厚みの中で不完全性をつくり出す工夫をしようと考えている。
その厚みはもしかしたら、バルコニーくらいの奥行きかもしれない、バルコニーになるかもしれない。
バルコニーという機能を帯びた場所になるかどうかは、中身との関連性で決まる。中身との関連性が希薄なば、それはバルコニーのような場所をした別の何かであり、でも、見た目はバルコニーだから、見る人はバルコニーだと思い想像するが、そうでは無いところで、心が動き出すかな、これが不完全性を利用したアクティビティーの発生の仕方、そのバルコニーのような場所にバルコニーには無いものが見えたり、あったりしたら、余計、心に働きかける、それが生活感が溢れ出すキッカケになるだろう。
"Place like a balcony"
We talked about "surface and content".
Speaking of the surface, it may be an image that is very thin, flat, and not thick enough, but it may be quite thick, which is an image of a thick or deep surface.
We intend to devise to create imperfections in the thickness.
Its thickness may be a balcony, which may be as deep as a balcony.
Whether it will be a balcony or not will depend on the relationship with the contents. If the relevance to the contents is weak, it is something else that made the place like a balcony, but because the appearance is a balcony, I think that the viewer thinks it to be a balcony, but where it is not, the mind is I wonder if it makes a move, how does this cause the activity to take advantage of the imperfection, something like that on the balcony that is not visible on the balcony, or if it is, it works on the mind, it overflows the sense of life. It will be.
建築の表層と中身を分けて考えるようになった。
表層と中身を分けて考えることに、ずっと違和感があり、外観だけを取り出してデザインすることに、そういう時は大抵そこしかデザインする所が無いからだったりしたから、建築は表層も中身も一体であり、全てが1つの塊としてデザインしたいと思っていた。
なぜ、表層と中身を分けて考えるようになったか、それは、表層だけが持つことができて、中身には無いことに気がついたから。
それは、周りの環境への影響。
表層のつくり方、デザインの仕方で、影響が全然違う、何をいまさら、と言わそうだし、表層だけを扱って構築した建築は昔からたくさんあり、たくさん見てきたかが、観点を変えたら、それが面白いことに気がついた。
不完全性から心を動かすアクティビティーをつくりたいと考えていたら、表層だけで、表層だけを扱えば良いのでは、そうすれば、その背後にある中身がオープンにできるのではないか、というイメージスケッチができた。
いま少し、そこを掘り下げてみるつもり。
"Separating the surface and the content"
I came to think separately from the surface and contents of the architecture.
There is a sense of incongruity in thinking about the surface and contents separately, and it is because there is usually only a place where there is only a design when it comes to taking out and designing only the appearance. Yes, I wanted to design everything as a single block.
Why did you come to think about the surface and content separately, because I realized that only the surface could have, not the content.
That is the impact on the surrounding environment.
How to make the surface, how to design, the influence is completely different, what seems to say now, there are a lot of architecture built to handle only the surface, and if you have seen a lot, change the point of view, it I noticed something interesting.
If you want to create an activity that moves your mind from imperfections, if you only have to deal with the surface and only the surface, then you may be able to open up the content behind it. It was possible.
I'm going to dig in a little bit now.
心の働きや動きを発生させるために「見立て」による不完全性を使えば良いだろうとは、すぐに思いつくのはつくのだが、としたのは、確証が持てなかったから。
「見立て」の代表例として、日本庭園をあげたが、枯山水や石庭を見て、自分が心動くのか、心の働きが発生するのか、疑問だった。
つくられた自然にどうしても興味が持てなかった。「見立て」に対する違和感はここから来る。つくることを普段行っているのに、つくらた自然にはしっくりこない。どうしたものか。
"Natural created"
Although it is obvious that it will come to mind immediately that it would be better to use the imperfection of "look up" to generate the work and movement of the mind, but it was because it could not be confirmed.
I gave a Japanese garden as a representative example of "Makeshi", but I was wondering whether I would move myself or cause my heart to see if I saw Shisui or Ishihara.
I was not really interested in the created nature. The sense of incongruity with "Make up" comes from here. Although I usually do making things, I am not comfortable with the nature I created. What should I do?
心の働きや動きが起こる、これもアクティビティーとし、不完全性が発生の源とした。
日本庭園では「見立て」を手法としている。背後の山や自然などを想起させるように、植栽の形や石の置く位置や形、砂紋の向きなどを決めて、その植栽や石や砂を山や水面に例える、このことを「見立て」という。
「見立て」はそれ自体では完全ではなくて、見る人の想起、連想があって、はじめて成り立つ。だから、日本庭園そのものには、常に不完全性があり、その不完全性をつくり出す手法が「見立て」である。よって、日本庭園の美は未完の美、とも言える。
この「見立て」を手法とした場合の、見る人の想起、連想が心の働きや動きであり、アクティビティーである。
だから、心の働きや動きを発生させるために「見立て」による不完全性を使えば良いだろうとは、すぐに思いつくのはつくのだが。
"I move my heart in my mind"
The work and movement of the mind takes place, which is also an activity, and imperfection is the source of the occurrence.
In the Japanese garden, it uses "look-up" as a method. In order to recall the mountains and nature behind it, decide the shape and position of the planting, the position and shape of the stone, the direction of the sand pattern, etc. and compare this planting and stone or sand to the mountain or water surface. It is called "Mutee".
"Make up" is not perfect by itself, but it only takes place with the viewer's recall and association. Therefore, the Japanese garden itself is always imperfect, and the method of creating that imperfection is "Make it back". Therefore, the beauty of the Japanese garden can be said to be unfinished beauty.
When this "appearance" is used as a method, the memories and associations of the viewer are the functions and movements of the mind, and the activities.
So it's easy to come to mind that it would be better to use the imperfection of "look-up" to generate the work and movement of the mind.
生活が溢れ出すようなオープンなパーソナルスペースをつくりたいとした。
そのためには、接点の無い異なるアクティビティーを複数発生させて、そのアクティビティー同士の間がオープンなパーソナルスペースになる。
アクティビティーとは活動という意味だが、そこにもしかしたら、心の働き、心の動きも入るのではないかとふと思い、今日一日考えていた。
不完全性がアクティビティーを誘発させると考えている。
不完全性には2種類あって、空っぽで何も無く、そこに足りない何かを足すことができる状態の不完全性と、完全なものが崩れ、乱れている状態の不完全性。
どちらも、完全になろうとしてアクティビティーが発生する、実際に人間活動が起こる。ただ、実際に活動が起こる前に、心の働き、心の動きが起こるだろう、その時点でアクティビティーが発生しているとしても良いのではないかと考えた。
ならば、目に見えて人間活動が起こる必要性も無くなり、心の働きや動きに焦点を当てるだけでも良いかもしれない。
それは、それが、未完の美、のようだと、今日の時点では結論に至った。
"Work of mind"
I wanted to create an open personal space that overflows my life.
For this purpose, a plurality of different activities without contact are generated to make an open personal space between the activities.
Activity means activity, but I thought about it all day, thinking that it might be the work of mind and movement of mind.
We believe that imperfections trigger activities.
There are two types of imperfections: nothing is empty and nothing can be added to it, and imperfections in which things are completely broken or disordered.
In both cases, activities occur in an attempt to become complete, and human activities actually occur. However, before activity actually occurred, it was thought that working of mind and mind movement would occur, and it might be good if activity occurred at that time.
So there is no need for visible human activity, and it may be better to focus on the actions and movements of the mind.
It came to a conclusion as of today, as it seems to be an unfinished beauty.
異なるアクティビティー同士の間にオープンなパーソナルスペースができると考えている。ちょうどそこが空白地帯というか、真空状態というか、誰も関心を持たない、誰にも干渉されないスペースができると考えている。
例えば、行き交う電車と電車の間とか、そこに普通はいないから、わからないと思うかもしれないが、電車に乗っている人はそこに目もくれない。
だから、オープンにできる。
オープンにできれば、生活が溢れ出すじゃないか。
都市がつまらない時は、街がつまらない時は、肩肘張って、虚勢を張って、繕って、虚飾にまみれている時、生活が溢れ出し、日常まみれの場所は、親近感が湧くし、ほっとするし、自分が素になれて、ストレスが無く、精神衛生上良く、楽しい、長生きするよ。
だから、オープンなパーソナルスペースのつくり方を一般解として解きたい。そのような空間を意図的につくりたい、そのような意図的な空間を見たことないが無いでしょ。
だから、考える意味があるし、トライする意味がある。
"Let's overflow the life"
I think that there is an open personal space between different activities. I think that there is a space where there is no gap with nobody, or nobody's interested, or just a vacuum zone.
For example, you may think that you don't know because you are not in the usual place, such as between trains that go and go, but those on the train will not see you there.
So you can be open.
Life would overflow if it could be open.
When the city is boring, when the city is boring, shoulders, elbows, vignettes, crawling, when covered in a vanity, life overflows, everyday places are covered with a sense of closeness and a sense of intimacy I will be a part of myself, stress free, good in mental health, enjoyable, live longer.
So I want to solve the way of creating an open personal space as a general solution. I would like to create such a space intentionally, I have never seen such an intentional space.
So it makes sense to think and to make a try.
建築を1から構想する時は、何か手がかりのようなものがあってはじめる。全く何も無く、プランが出来上がることは無い。
その手がかりは、建築論であったり、自身の建築に対する想いであったり、クライアントの要望であったり、周辺環境からもあるだろうし、建築性能としての温熱環境を満たすことであったりなど、あと、これらが複合する場合もあるだろう。
いずれにせよ、何を手がかりにするのかを選択し、構想を進めていくのだが、まず手がかりを考えるのが面白いし、悩むところ、最初の方向性だから、面白い場面や、やり甲斐を感じる時や、達成感がある場面はこの後に何度もあるが、全体の方向性を考える時は最初だけで、あとはその都度確認をするが、この方向性を間違うと、後で修正もできないし、途中をいくら頑張っても、報われない結果になる、建築としてのレベルの高さがここで決まるといか。
だから、時間をかけたくなるし、安易に決められないし、ともなるが、面白いもので、大体一番最初に思い付いたことや手がかりが、結局それを出発点として、時間をかけてそれで良いという証明を自分にしながら、構想を進めていったりする。
"clue"
When I envision building from scratch, I begin to have something like a clue. There is nothing at all and there is no plan coming up.
The clue is architecture theory, thought of one's own architecture, the request of the client, there is also from the surrounding environment, it is to meet the thermal environment as the building performance, etc. There may be cases where these are combined.
In any case, we choose what to use as a clue, and proceed with the concept, but it is interesting to think of a clue first, and to be troubled, because it is the first directionality, when you feel an interesting scene or practice There are many occasions after which there is a sense of accomplishment, but when thinking about the overall directionality, it is only the first and every time after that, it is confirmed each time, but if this directionality is wrong, correction can not be made later, No matter how hard you work on the way, it will result in no reward, if the height of the architectural level is decided here.
So it's tempting to spend time, not easy to decide, but it's also fun, and it's mostly about the first things you come up with and clues that prove it's good over time, taking it as a starting point While promoting the concept.
箱や包装も考えた方が良い、と言われた。
輪島塗のフリーカップを製作中だが、そのことを先日お会いした京都の古美術店の店主の方に話をしたら、そう言われた。
箱が良いか、包装が良いか、何か別のやり方もあるかもしれないが、どう見せるか、どう見せたいか、相手に手渡す時のことも考えないと。
そこまでは考えていなかった、フリーカップをつくることしか頭に無く、人に手渡す時のことまで考えていなかった。
店主に言わせると、そこまで考えるのが当たり前のことで、それがものをつくるということだと伝えたかったのかもしれない。
"When handing to people"
It was said that it would be better to think about boxes and packaging.
I was making a free cup of Wajima-Nuri, but when I talked to the shopkeeper of the old art shop in Kyoto that I met the other day, I was told that.
There may be other ways, such as whether the box is good, the packaging is good, but I don't think about how to show it or how I want to show it or when handing it to the other party.
I had not thought about it until then, I was only thinking about making a free cup, and I was not thinking about handing it to people.
If you ask the storekeeper, you might have wanted to tell that thinking so far is a matter of course and making things.
人の日常や生活感が溢れ出す感じに興味がある。
建築でいえば、高い塀に囲まれた中の綺麗な洋館よりは、様々な日常や生活の営みが直に目の前にある雑踏を生み出す建築、例えると、今は無い香港の九龍城、に惹かれる。
都市も同じ、セキュリティのしっかりしたゲートシティよりは、猥雑な環境でも、様々な生活感が混在する、あるいは、夜になるとあやしく出現する街、例えると、歌舞伎町や昔のニューヨーク、に惹かれる。
外壁という皮に包まれて中を伺い知ることができない建築が普通かもしれない。だから、その皮をいかにつくるか、それはデザインだけではなくて、皮としての性能、例えば、断熱性や光をいかに中に通すか、などが重要にもなる。
例えると、餃子ならば、皮は重要で、中の餡も大事だが、餃子を分類すると麺類になるらしいから、皮の食感や厚みや味が一番重要なのかもしれないし、皮が破れて中の餡が飛び出していたら、商品としてもダメだろう。
建築は雨風を凌ぐために皮が必要で、だから、断熱性や採光性を考える必要が出てくる訳だが、逆に言えば、雨風が凌げて、断熱性と採光性が確保されていれば、皮に包まれていなくても良い、中の餡が見えても良い、餡が見えた方が、餡の見せ方をデザインできるのが建築デザインの面白さかもしれない、属性も麺類では無いし。
"How to show firewood is architectural design"
I am interested in the feeling that people's everyday life and sense of life overflow.
In terms of architecture, it is more like Kowloon Castle in Hong Kong, which is not a building that produces various crowds of daily life and daily life directly in front of the beautiful Western-style building surrounded by high walls. I am attracted to
The city is also the same, with a more secure security than in the gate city, in a mixed environment or with a mix of lifestyles, or a city that pops up at night, like Kabukicho or old-fashioned New York.
It may be common to have an architecture surrounded by a skin called outer wall that can not be seen inside. So, it is important not only how to make the skin, but also the performance as a skin, such as how to insulate heat and light, etc.
For example, if it is dumplings, the skin is important, but the inside is also important, but if you classify the dumplings it will become noodles, so the texture, thickness and taste of the skin may be the most important, and the skin is broken It would be no good as a product if the spear inside was popping out.
Architecture needs skin to overwhelm the rain wind, so it is necessary to think about the heat insulation and daylighting, but conversely, if the rain and wind are secured and the heat insulation and daylighting are secured, Even if it is not necessary to be wrapped in skin, it may be possible to see the inside of the bag. If you can see the bag, the design of how to display the bag may be interesting for architectural design. Attributes are not noodles. .
『使うということ』
器は使ってなんぼ、とう言葉を何度も使っていた、古美術店の店主の方とお話ししている時に。
魯山人のお椀、博物館級のもの、それも料理を盛った形跡がある。魯山人は使うために器を、料理を盛るために器を、観賞用では無く。
使う、盛るが最初にあるから、器の形、厚みなどが決まる、それは民藝と同じなのだが、なぜか民藝は丈夫さが優先され、分厚くなる、武骨になる。
使う、盛るが最初にあるからと言って、壊れない、丈夫である必要は無い、それはまた別の話。普段使いだから、壊れない、丈夫さが必要だと、だから分厚くても良い、分厚い方が良いという考えは、使うということがわかっていない人の考え。
使うということは、自分の手先になって、自分の分身のように、自分の性質がそこに出る、美意識も。そうすると、壊れない丈夫で分厚い美意識もあるという人がいるが、それは意図して分厚くしているのでは無くて、単に丈夫さを求めた結果として分厚くなったに過ぎず、そこには美意識のかけらも無い。
使うということは、自分の美意識もセンスも生活レベルも問われているということ。
例えば、細く薄く繊細に見せるために、わざと、太く厚く武骨な部分をつくり、対比によって細く薄く繊細に見せる場合もあり、それはその武骨な部分が必要で、丈夫さを求めた結果では無くて、結果的に丈夫にはなるかもしれないが、たった1回使ったら終わりでも良い訳で、大事なのは器を使った時に、料理を盛った時に、どのように料理と調和を図るかということで、丈夫さを求めるのは単に効率、コストを優先しているに過ぎず、民藝はその意識が強いから民藝になるとも言え、民藝にするために丈夫さを求めるとも言えてしまい、それだと民藝の素の部分が現代の何事も効率を求める精神と同じになり、均一化された工業製品と相対する民藝の精神が、実は均一化された工業製品と素は一緒という、何とも皮肉な、そこに気が付かない民藝の器に料理を盛っても、というか、盛りたくない。
"Use"
When we are talking with the old art shop owner who used the bowl and used the language many times.
There is a trace of a dish of Mioyama-san, a museum-like one, and that also contains a dish. Aoi Yamato is not used for cooking, but for cooking.
Because it is used first, the shape and thickness of the bowl are decided because it is the same as the folk song, but somehow the folk song has strength and becomes thick, it becomes a samurai bone.
It doesn't have to be broken or durable just because you use it first, but it's another story. It's a regular use, so it's not broken, it needs to be strong, so it's good to be thick, the idea that thick is better is the idea of people who don't know to use it.
To use it is your own hand, like your own self, your nature comes out there, also the sense of beauty. Then, there are those who are strong and have a thick aesthetic sense that does not break, but it is not intended to be thick as intended, but merely thick as a result of seeking for toughness, and there is a fragment of aesthetics There is also no.
To use it means that one's sense of beauty, sense and life level are also questioned.
For example, in order to make it look thin, thin and delicate, it is possible to make thick, thick and thick parts intentionally, and to make it look thin, thin and thin by contrast. As a result, it may become strong, but it is good if you use it only once, but the important thing is how to keep the dish in harmony with the dish when you use it. Therefore, seeking robustness is merely giving priority to efficiency and cost, and it can be said that a folk song will be a folk song because its awareness is strong, and it can be said that it seeks robustness to become a folk song. Then, the original part of the folk song will be the same as the modern day's spirit for efficiency, and the spirit of the folk song against the uniformed industrial products and the opposite, but in fact the uniformed industrial products and the element are together Of course, ironically, you notice it Even if the dishes are served in the bowl of a good folk song, I do not want to do it.
京都の古美術店で店主の方と話し込んだ、前にカトラリーを購入したお店。
伊万里焼を見ていたら、久しぶりに伊万里を取り扱っている、と話し掛けられた。父親の代までは伊万里の専門店だったが止めたと。
今でも東京で一度は行ったり、見聞きしたことのあるお料理屋さんに器を下ろしていて、ただ、誰かに言われた訳では無いが、自分で気づいたそうで、
伊万里焼の器はお料理屋さんでは使わない。
当然理由を聞いてみたくなり、その他にも、魯山人の漆器、博物館級のものを触りながら、今ここでは書けない話などを聞いた、随分と長いことお話しをさせてもらった、掛け軸の話も、熊谷守一の、これはまだだれにも見せてない、来年のお茶会の待ち合いで、これもまだここには書けない、そんな話ばかり。
伊万里は武骨だから、お料理に合わない。その理由を聞いて、実はずっと思っていたことがあり、やっぱりと納得した、民藝の話で。
"Judging judgment"
A shop where I bought a cutlery before, talking with the shop owner at an old art shop in Kyoto.
When I watched Imari, I was told that Imari was handled after a long time. It was an Imari specialty store until his father's day, but he stopped.
Even now, I went to a restaurant in Tokyo once and dropped the dish to a restaurant that I had seen and heard, but it wasn't that he was told by someone, but I noticed that I myself.
Imari pottery is not used in the restaurant.
Naturally, I would like to ask why, and while touching the lacquerware of the Sasayama people and museum-class things, I heard a story that I can not write here, etc., a story of a long time, let me talk about the axis Well, that's not yet shown to anyone, Kumagai Moriichi's next year's tea ceremony meeting, this can not be written here yet, such a story.
As Imari is a bone, it doesn't suit you. Hearing the reason, in fact I had always thought, after all I was convinced, in the story of the folk song.
「暮らし」と「建築論」は相対することなのだろうか。先日のオープンハウスで立ち聞きした、一般紙に建築を紹介する時、建築家は建築論を展開できない、素人受けしないから、暮らしとかの話をする、本当はそこに建築論があり、それを元に実体の建築があるのに。
建築論の素は哲学であることが多い。哲学は言わば、人やこの世界を理解するための学問。暮らしは、この世界での人の営みの総称か。ならば、「暮らし」と「哲学」は相対するというよりかは、「暮らし」を哲学的に紐解いたものが建築論の一部を形成するのではないか。
たがら、「建築論」として「暮らし」を語ることができるだろうし、耳障りの良い美句麗句ではないかもしれないが、普段聞かないような言葉で、自分たちの生活を語ることが、もしかしたら、一生に一度の建築の機会には必要かもしれないと考えるがいかがだろうか。
"Architectural theory to talk about life"
Is "life" and "architectural theory" opposite to each other? When introducing the architecture to the general paper that I overheard at the open house the other day, the architect can not develop the theory of architecture, because he does not accept the amateur, talk about living and so on, there is really the theory of architecture there, Even though there is a real architecture.
The foundation of architectural theory is often philosophy. Philosophy is, in other words, learning to understand people and this world. Is living a collective term for the work of people in this world? Then, rather than "life" and "philosophical" being opposite, what philosophically deciphered "life" might form a part of architectural theory.
Therefore, you may be able to talk about "life" as "architectural theory", and it may not be a good-looking phrase, but talking about their lives with words that you would not normally hear, maybe How about thinking that it may be necessary for the opportunity of construction once in a lifetime?
最近興味があることは、創作のキッカケとなった建築論が、そこでの暮らしや生活の営みを自動的に昇華し、勝手に極上な生活に仕立て上げてくれること。
極上というと語弊があるかもしれないが、普段の生活が、そうそうは変わるはずがなく、人もそんなに簡単に変われないけれど、3つの間、人間・時間・空間のうち、1つでも変えれば何かが変わるが、一番変えやすいのが空間で、別の言い方をすれば、環境で、住んでいる場所を変える、部屋を模様替えする、職場を変えるなどが考えられるが、一番効果があるのは、住空間を全く新しくしてしまうこと、やはり、日常生活に直結するから。
変え方も人に委ねる方が案外自分の気付かないことを拾ってくれるので、だから、人自体は変わらなくても、人から見たら今の生活よりよく見えたりする意味で極上と使ってみたが、それを実現するために建築論から考えるのが面白いような気がする。
"If you change the space"
What I'm interested in recently is that the architectural theory, which has become a key to creation, automatically sublimes life and the activities of life there, and make it into an excellent life on its own.
There may be misunderstandings, but everyday life can not be changed that way, and people can not change so easily, but if one changes among human, time, and space between three, what if Although it may change, the most easy to change is space, in other words, in the environment, it is possible to change the place where you live, to change the room, to change the place of work, etc. Because it makes living space completely new, too, because it is directly connected to everyday life.
Because it is possible to pick up things that change is left unnoticipated by people, so I tried to use it in a sense that even if the people themselves did not change, they would look better than the current life when viewed from people. I think it is interesting to think from the architectural theory to realize it.
先日のオープンハウスでのこと、積極的に何か得よう、この空間をつかもう、この建築を理解しようと最初はこころみるが、ふと気がつくと、自分の作品と比べて自分より劣っている所を発見しようとしている自分がいる。
それはきっと、今見ている作品に対して対抗しようとしている心の表れかもしれないが、それが悪いこととは思わないが、そのために何か大事なことを見落としているのではないかと思って我にかえる。
そのような時はもう一度、頭の中で、今目の前で見ている建築をいろいろな角度から反芻して、その作品の良さや影響力みたいなものを重ね合わせて、今、自分がここにいる意味みたいなものを再認識して、さらに深く目の前の作品を理解しようとする。
"I hate it."
Let's get something actively in the other day's open house, grab this space, and first try to understand this architecture, but if you notice it, you will be inferior to your own work I am trying to find one.
It may be a manifestation of the mind that is trying to counter the work you are looking at now, but I do not think that it is bad, but I think that I have overlooked something important for that. Give up.
At such times, again, in my head, I rebut the architecture I am looking at in front of my eyes from various angles, superimpose things like the goodness and influence of the work, and now I am here Re-recognize the meaning of being in and try to understand the work in front of you more deeply.
建築家の手のかけ方の密度みたいなものを感じることができるのがオープンハウスの良いところ、とした。
先日のオープンハウスでは、普段の自分の仕事と比較して見ていた。その建築家の方は名の知れた、哲学者のように哲学を愛し、海外との交流も積極的で、教育者としての側面も持ち、私の好きな建築をつくる方で、自分の中では高尚な建築性と美意識が高い建築を見ることができる機会と思っていた。だから、非常に楽しみにしていた。
内部の密度というか精度が自分と違い、空間構成は元々、今までのその建築家の方の作品を写真で見ると私の好みなので、狭小な空間の中に上手く身体のスペースにジャストフィットしながら展開し、所々、その建築家の方の作品性が出ていて、軽快で、でも濃密で、巧みに内壁を傾斜させたり、開口部を空間の動きに呼応するように空けてみたりしていて、まだ誰も住んではいないのに、そこでの生活行為が見えてくる。
ただそれはそこでの暮らしを住人の特殊な趣向に合わせているのではなくて、一般解としての建築性があり、そこでの暮らしが昇華して建築と一体となるような空間構成だった。
それは正しく、そこで創作のキッカケとなった建築論が、そこでの暮らしや生活の営みを自動的に昇華し、勝手に極上な生活に仕立て上げてくれるような感じだった。
なぜそうなるのか。
建築論を創作のキッカケにすることは、レベルの高い低いはあるが、誰にでもできることだが、違うもっと簡単な言い方をすると、こなれていて、オートクチュールの服を、それを感じさせないくらいに普段着として着ているような感じ。
そこには、素材感やその使い方、細部のディテールの扱い方の工夫もあるが、そこまで昇華させるスタディの濃さと深さの違いがあると感じた。
その感じを体感できたことが、このオープンハウスに行った最大の収穫だった。
"Architecture that sublimes life"
The good thing about Open House is that you can feel something like the density of the architects' approach.
The other day at the open house, I was looking at it compared to my usual work. The architect loves philosophy like a philosopher who is famous, is also active in exchanges with foreign countries, has an aspect as an educator, and is a person who creates my favorite architecture, Then I thought that it was an opportunity to see high-rise architecture and aesthetics. So I was very looking forward to it.
Internal density or accuracy is different from myself, and the space composition is originally my favorite when looking at the picture of the architect until now, so it fits in the space of the body well in a narrow space While developing, in some places, the work of the architect is out, light, but dense, skillfully tilting the inner wall, try to open the opening to correspond to the movement of the space Even though nobody lives yet, life acts are visible there.
However, it did not match the living there with the special tastes of the residents, but it had a building solution as a general solution, and the space configuration was such that the living there sublimed and integrated with the building.
It was correct that the theory of architecture, which was the starting point of the creation, was such that life and living activities there were automatically sublimated and made into an excellent life without permission.
Why is it so?
Although it is possible to make architectural theory a starting point for creation at a high level, but anyone can do it, but in a different, simpler way, to wear a haute couture dress, it does not make you feel it. It feels like you're wearing it.
There are some ideas about how to use the material, how to use it, and how to handle the details, but I felt that there is a difference in the depth and depth of the study that you want to sublimate there.
Being able to experience that feeling was the biggest harvest I went to this open house.
先日、ある建築家のオープンハウスに行って来た。オープンハウスとは完成お披露目会であり、完成した建築を世に問う最初の機会である。
建築家によって建築に対する考え方が違うし、ある一定レベル以上の建築だから、良し悪しを見る訳では無い。
それは、例えば、星付きのレストランに行けば、美味しいの当たり前であり、シェフによって個性というか違いはあるので、そこは自分の好みに合うかもあるが、完成度とか、手のかけ方とか、変態度というか、よくそんなことするな、普通そんなことするか的な所を楽しみに行くのだが、建築も同じ。
ただ、建築の場合は自分もつくるから、その建築に対する建築家の手のかけ方の密度みたいものはすぐに手にとるようにわかるので、そこが一番刺激になる。
納め方や材料やその使い方、仕様は今まで知らなかったことがあったりすると勉強にもなるが、昔、私が20代の頃、設計事務所に入った頃はネットもパソコンも無かったので、そういう生の情報が貴重だったが、今はネットなどで調べれば、自分が欲しい情報、例えば材料や器具など、納め方まで、簡単に手に入るので、ネットで手に入らない情報、今はそれが生の情報、例えば、先程の建築家の手のかけ方の密度みたいなものを感じることができるのがオープンハウスの良いところだと思っている。
"Knowing how to use an architect"
The other day, I went to an architect's open house. The open house is a completion show, and it is the first opportunity to ask the world about the completed architecture.
Different architects have different ideas about architecture, and because they have more than a certain level of architecture, it is not a good idea to see good or bad.
For example, if you go to a restaurant with a star, it is natural for you to be delicious, and there is a difference depending on the chef's individuality, so it may suit your taste, but the degree of perfection, how to put it on hand, transformation I'm going to look forward to a place I usually do, but I do not want to do that well, but the architecture is the same.
However, in the case of architecture, I also create my own, so I know that the density of how to put the architect's hand on the architecture will be taken immediately.
I will study if I do not know how to pay, materials, how to use them, and specifications until now, but since I used to be in my twenties, when I entered the design office, I did not have a net or PC. Such raw information was valuable, but if you look at the net now, you can easily get the information you want, such as materials and equipment, how to pay, so the information that can not be obtained on the net, now Believes that it is a good part of the Open House that you can feel the raw information, such as the density of the architect's hand, for example.
建築論があるから暮らしが良くなる、建築論からはじめるから素晴らし住宅ができる、とした。
大まかに言えば、建築論には2つある。
建築の歴史の中での位置付けのための建築論と現代に存在するための建築論。
長い建築の歴史の中で今の建築が突然現れたのでは無くて、ちょっとずつちょっとずつ積み重ね、変化し、その変化が歴史の長いスパン中でその時代の建築表現として、その都度定着していった。だから、この建築の歴史の文脈に沿って、そこから外れないように建築を構築する建築論になる。
一方、建築は建築の歴史の中だけで成立するには、あまりにも規模が大きくて、社会的影響も大きいので、その時代その時代、すなわち、現代の様々な影響を拾う。簡単に言うと、その時代その時代で暮らしは変わる、暮らしが変われば建築も変わる。明治大正の暮らしと、平成令和の暮らしは違う。だから、当然求められる建築も違う。そこに建築論が存在する。ただ、その建築論は建築の歴史の中での位置付けの建築論とは齟齬をきたすかもしれない。しかし、現代を生きる人には違和感は無い。
建築論からはじめるから素晴らしい住宅ができる、としたのは、現代に存在するための建築論に焦点を当てることをいう。
"Architectural theory to exist in the present age"
It is said that living will be improved because there is an architectural theory, and a wonderful house can be created because it starts from an architectural theory.
Roughly speaking, there are two in the theory of architecture.
Architectural theory for positioning in the history of architecture and architectural theory for existing in the present.
The present architecture did not suddenly appear in the long history of architecture, but gradually piled up little by little and changed, and the change became established each time as the architectural expression of that era in the long span of history. The So, in line with the context of the history of this architecture, it becomes an architectural theory that builds architecture so as not to deviate from it.
On the other hand, architecture is too large and societal influence to be established only in the history of architecture, so we pick up various influences of that era, that is, the present age. Simply put, life changes during that time, and when life changes, architecture changes. The Meiji Taisho life is different from the Heisei Oriha life. So, naturally, the architecture required is also different. Architectural theory exists there. However, the theory of architecture may be contradictory to the theory of architecture positioned in the history of architecture. However, people living in the present age have no discomfort.
The idea of having a great house since starting with an architectural theory is to focus on the architectural theory that exists in the present age.
実体の建築が必要無くなるくらいにバーチャルの建築で建築論を展開する。
なぜか、バーチャルの建築はだれでも体験することができるから、建築論と建築の体験がリンクすることを誰にでも理解させることができる。
一般紙に建築を紹介する時、建築家は建築論を展開できない、素人受けしないから、暮らしとかの話をする、本当はそこに建築論があり、それを元に実体の建築があるのに。そこからズレているから、建築家の社会的地位があまり日本では高くない気がする。
建築論があるから暮らしが良くなる、建築論からはじめるから素晴らし住宅ができるのが当たり前なのだが、それが素人の間でも当たり前のことになれば、それが建築家にとっても創作しやすい環境になる。
"Life will be improved from the theory of architecture"
Expand the theory of architecture with virtual architecture to the extent that the actual architecture is not needed.
Because virtual architecture can be experienced by anyone, anyone can understand that architectural theory and architectural experience are linked.
When introducing architecture to general paper, architects can not develop architecture theory, they don't accept amateurs, so they talk about living and so on, although there is actually architecture theory there, even though there is an entity architecture based on that. Since it deviates from that, I think that the social status of the architect is not so high in Japan.
It makes sense to live better because there is an architectural theory, but it is natural to be able to make a wonderful house because it starts from an architectural theory, but if it becomes a natural thing even for amateurs, it will be an easy environment for architects to create .
バーチャルの建築にも価値を見出す。
実体では無いからこそ、住めるかどうかや事業性とは関係が無くなり、コンセプトやデザインがより浮き彫りになり、コンセプトやデザインがより価値あるものになる。
バーチャルの建築の現状は、実体の建築の生成過程の検討用かプレゼン用であり、そのもの自体には経済的な価値は無いが、そこに経済的な価値を見出せれば、より建築家のデザインやコンセプトが直接事業性を持ちはじめ、土地や建物の価値だけでは無い所で事業性が決まることもあるようになる。要するに、建築家の社会的存在価値が高まる。
欧米ならば、建築家の社会的地位が確立されているから、その必要は無いかもしれないが、日本での建築家が社会的な地位をより確立するには、このくらいはしないとダメではないだろうか。
では、そのためには、まずバーチャルの建築が先走り独り歩きしなくてはならない、それだけで実体の建築が必要無くなるくらいに、それは今すぐにでもできることで、もっとバーチャルの建築を通して建築論を闘わせれば良いだけだと思う。
"Architectural theory in virtual architecture"
Find value in virtual architecture.
Because it is not an entity, there is no relationship with living or business, and the concept and design become more prominent, and the concept and design become more valuable.
The present state of virtual architecture is for examination or presentation of the process of generation of the actual architecture, and itself has no economic value, but if it finds economic value there, it is more architect design The concept starts to have business directly, and business can be decided not only by the value of land and buildings. In short, the social existence value of architects increases.
In the West, the social status of architects has been established, so that may not be necessary, but for architects in Japan to establish social status more than this, it would not be Is not it?
So, in order to do so, virtual architecture has to go ahead alone, it is enough that it can be done right away, so it is better to let architectural theory fight through more virtual architecture I think only.
デジタル化されたものは作品にはならないのか。
絵画も書もキャンバスや半紙に描くから、絵画や書として価値があり、モニター上でソフトを使って同じような作品をつくり、データでやり取りしたら、誰もそれに絵画や書としての価値を見出さない、他の、デジタル作品としての価値はあるだろうが。
建築も同じで、バーチャルの中で建築を構築することができで、その中に入って体験することができても、そこに建築としての価値は無い。
何が違うのか、実体かデータの違いにどこまで意味があるのかと考えてみても、よくわからない。
キャンバスや半紙だろうと、デジタルデータであろうと、作者の作品性は出るし、それは建築も同じ。作者の作品性があっても、実体で無ければ価値が無いのか。
ただ、建築の場合は実体でないと、そこに住めないし、事業性が無い。だから、絵画や書よりも余計に実体でないと価値を見出せないかもしれない。
そうなると、建築にとって価値を決めるのは、まず実体であることで、実体足り得るには、とりあえず、そこに住めるかどうかと事業性を満たせば良いならば、そこに住めるかどうかと事業性を満たせば、あとはどうでも良い、という解釈も成り立つ。
そうなると、他のことには価値は無く、デザインは単なる建築家の自己満足か付け足しか、それは違うから、バーチャルの中の建築にも価値を見出した方が良いし、それは近い将来にそうなりそうな気がする。
"Value in Virtual Architecture"
Aren't digitalized things a work?
Both paintings and writings are drawn on canvas and semi-paper, so they are valuable as paintings and writings, and when you use software on a monitor to create similar works and exchange data, no one finds the value of paintings and writings in it Although it may be worth other digital works.
Architecture is the same, and you can build architecture in a virtual way, and even if you can get inside and experience it, there is no architectural value.
It is not clear if you think about what is different and how much the difference in substance or data means.
Whether it is canvas or paper, or digital data, the author's work comes out, and so is architecture. Even if the author's work has something to do with it, is it worthless without it?
However, in the case of architecture, it can not live there unless it is an entity, and there is no business. So you may not find value unless it is more tangible than paintings and books.
In that case, it is the first thing to decide the value for the construction, it is the first thing, to be substantive, for the time being, if it is possible to live there and if it is sufficient to satisfy the business, then fulfill the business and whether it can live there. For example, the interpretation that it does not matter afterward is also valid.
Then there is nothing worthwhile in other things, and the design is nothing more than a mere satisfaction of the architect, or it is different, so it is better to find value in the architecture in the virtual, which is likely to be in the near future I feel that.
全ては無くなるもの。
建築も同じ。でも、終わりが決まっていない、決めない。いずれ耐用年数は来るが、それよりは何十年かは建ち続ける前提で事業性が回るだけ、その終わりの時が決まっているだけで、建築の終わりは曖昧で、事業性に合わせるだけ。
土地も建物も所有しないで、期間が限定されていて、終わりがあれば、どうなるだろうか。
時期が来たら終了、はい、また次、となったら、建築に対する考え方が変わるだろうか?
土地も建物も財産にはならないから、価値がなくなり、地価が下がり、建築コストも下がる、というか、コストをかけなくなるかな、そうすると、建築の概念も変わりそう、遠くない未来にそうなりそうな気もするが。
"Don't own"
Everything is gone.
Architecture is the same. But I do not decide the end has not been decided. Although the useful life will eventually come, it will only be for business to turn on the premise that it will continue to be built for several decades, only the time of its end will be decided, the end of construction will be vague, and will only match with the business.
Do not own land or buildings, the time is limited, what will happen if there is an end.
If time comes to an end, yes, next time, will the way of thinking about architecture change?
Land and buildings will not be property, so there will be no value, lower land prices, lower construction costs, or no cost, and if you do, you will change the concept of architecture, it will likely be a distant future I will.
全ては無くなるもの。
人はいずれ死ぬし、世の中で永遠のものなど無いのに、人は何でも自分の足跡を残そうとする。そもそもそれが無理なことだから、だから、無理が生じる。
ほぼすでに手書きは無いのだが、スケッチだけは手で紙に描かないと、と思っていたが、それもデジタル化し、ノートを持たず、iPhoneやiPad などのデバイスで記録は残るが、実体が無い状態にし、そもそもはじめから過程が有るのか無いのかわからないようにしておけば、建築は実体だから、より実体として残すものが明確になるような気がして、ただ、その建築もいつかは無くなる。
今見ている現実も実は夢で、まだ朝が来ていないだけかもしれない、となったら、それはそれで現実に執着しなくなるから、ノートが無くても良いなと思うし、夢ならばそれが自然な行為であり、だから夢ならばデジタル化は自然に起こること。
人間が発明したバーチャルの世界はまさに夢の世界で、夢なのか現実なのかわからない。人間がたどり着いた世界が実は毎日見る夢に一番近いなんて、なんか面白いし、1周半ぐらいして、ようやく、元に戻る人間の先を考えない様がちょっとおかしい。
現実と夢の境目が曖昧になれば、デジタル化が起こるのは自然なことだから、今、まさに夢の中にいるのかもしれない、朝はまだかな。
"Digitization is natural"
Everything is gone.
People die in one day and no one is eternal in the world, but people try to leave their own footprints. Because it is impossible in the first place, it causes unreasonableness.
I almost thought that I would not write handwriting, but I thought that I would only draw sketches on paper by hand, but it was also digitized, had no notes, and records were kept on devices such as the iPhone and iPad, but there was no substance If you leave it in the state and don't know if there is any process from the beginning, because architecture is a real entity, it feels like it becomes clear what you will leave as a real entity, but that architecture will also disappear someday.
The reality I'm seeing now is actually a dream, and it may only be that morning hasn't come, because it won't cling to reality, so I think it's okay if there's no notebook, and it's a nature if it's a dream It is an act, so if it is a dream, digitization will happen naturally.
The virtual world invented by humans is a dream world, and we do not know whether it is a dream or a reality. It's interesting that the world the human came to actually is closest to the dream you see every day, and it's funny for a week and a half that you finally don't think of the point of the human back.
If the boundary between reality and dream is obscured, it is natural that digitization will occur, so it may be right in the dream now, it is still morning.
生活臭というか、生活感が向き出しになっている建築や都市に惹かれてしまう。
都市で言えば、ニューヨークのマンハッタンの下の方や、香港や、東京の下町などか。
建築で言えば、今は無いが香港の九龍城、治安が悪そうでも、整っているよりも、何かゴチャゴチャしている方が面白いと思ってしまう。
九龍城も外観は洗濯物が唯一、生活感を表しているとしか言えないかもしれないが、内部は、そこも都市の一部と思えるぐらい、パブリックでゴチャゴチャしていて、惹かれてしまう。
なぜ、そんなに惹かれるのか。人でも同じだが、整った体裁を装うよりも、生活感向き出しの本心で訴えかけてくる人の方が面倒くさいが心に響くのと同じ感じかもしれない。
ただ、そこでは、プライバシーには気を配らなくてはならない。それができないと人は心を開いてくれないし、見える生活臭に活き活きさが無くなる。
"The smell of life is lively"
I will be attracted to the architecture and the city where the sense of life is starting to be said to be a smell of life.
Speaking in the city, people under Manhattan in New York, Hong Kong, and downtown Tokyo.
As far as architecture is concerned, it is not at the moment, but it seems that it is more interesting to have something messy than being in order, even though the Kowloon Castle in Hong Kong is insecure.
In Kowloon Castle, the appearance may be described as the only laundry that expresses a sense of life, but the inside is sloppyly public and so attractive that it seems to be a part of the city.
Why are you so attracted? The same is true for people, but it may be the same as having a person who complains with a genuine feeling of life, rather than posing in a well-shaped manner, but it is the same thing that bothers me.
However, there is a need to pay attention to privacy. If you can not do that, people will not open their minds, and the life smell they see will be alive.
パーソナルスペースが外に向き出しになる様を見たことがあるだろうか。私物が外から丸見え、でも、それこそが生活臭で、生活そのもので、人の顔が皆違うように多様性があり、それが外に向き出しになれば、それだけで、まさに多様性を兼ね備えた建築になり、そのような建築が集まれば、多様性がある都市が生まれる。
多様性があることが良いことが前提だが、単一性が強い建築、代表例は住宅、その住宅が集まった場所が住宅街、単一性の都市の代表例だが、多様性の都市の代表例は繁華街、イメージは新宿の歌舞伎町、どちらが都市として魅力的か、都市に何を求めるかにもよるが、歌舞伎町の方が防犯上、問題があるような気がするが、歌舞伎町の方が都市として見る分には、いろいろな出来事が発生し、いろいろな人間模様が繰り広げられ、複雑に様々なことが入り組んで、面白いと思う。
確かに、歌舞伎町には防犯上問題あるかもしれないが、住宅街とて、ひと昔前は、今でもか、世田谷の住宅街は空き巣被害が酷かった地域で、防犯上の問題はどこでも、種類は違うかもしれないが付いて回る。
だから、多様性のある都市の方が面白いから、多様性を求めてしまう、都市も建築も。
プライバシーを意識するし、見られたく無いという意識も当然あるから、生活そのものが外から見られるのには抵抗があるのはよくわかるし、実際に、ガラス張りの建築を作ったとしても、カーテンやブラインドを設置し、外から見られないように、実際に住む時はしてしまい、ガラス張りの意味が住みはじめた途端になくなる、よく建築家がやりそうなこと。
レトリックとして、外から見た時に、生活が丸見えのように見えれば良く、ただ、全くのフィクションでは、テーマパーク、ディズニーランドと一緒で、それは建築としてつまらないので、やりたくない。
レトリックを使えば、ガラス張りのカーテンのようなな、実際の生活になったら、なんてならないで済むだろう、ガラス張りでも気にしないでいる住人もいるとは聞いたことがあるが、住人のポテンシャルに頼る建築では無くて、建築自体が持つ建築性で多様性を兼ね備えた建築を実現したい。
"From diverse architecture to city"
Have you ever seen your personal space turn out? Private goods can be seen from the outside, but that is the smell of life, life itself, there is diversity as people's faces are all different, and when it comes out, it just combines diversity. Architecture, and gathering such buildings will create a diverse city.
It is premised that there is good diversity, but it has a strong unity architecture, a typical example is a house, a residential area where the houses are gathered, a representative of a unitary city, but a representative of a diverse city An example is downtown, the image is Kabukicho in Shinjuku, which is attractive as a city, depending on what you seek in the city, but Kabukicho feels like there is a problem in crime prevention, but Kabukicho As the city sees as a city, various events occur, various human patterns are unfolded, and various things are complicated and I think it is interesting.
Certainly Kabukicho may have a problem with crime prevention, but as a residential area, a long time ago, or still, residential areas in Setagaya are areas where severe damage was caused by vulture, problems with crime everywhere, types It may be different, but it turns around.
So, because cities with diversity are more interesting, they seek diversity, both cities and buildings.
It is natural to be conscious of privacy and not wanting to be seen, so it is clear that there is resistance against seeing life itself from the outside, and even if you actually create a glass-covered architecture, you They set up blinds and do not actually see them from the outside, they actually do when they actually live, and the meaning of the glazing disappears as soon as they begin to live, something that architects are likely to do.
As a rhetoric, it would be nice if life looked as if it were seen from the outside, but in a whole fiction, with theme park, Disneyland, it is boring as it is architecture, so I don't want to do it.
If you use rhetoric, like a glass curtain, you won't get it in real life, I've heard that some residents don't care even if they are glazed, but the potential of the residents Rather than relying on architecture, I would like to realize a diverse and diverse architecture that the architecture itself has.
集まって住むから可能になることを見つけ出し実現することを目的に集合住宅計画を進めている。
ただ、それは、集まって住むから可能になることは、個々の住人のパーソナルスペースであれば一番良いとはじめから考えており、集合住宅のメインスペースは、やはり、個々の住人のパーソナルスペースなので、よく見かける集合住宅は効率良く積層させることが一番大事で、なるべく多くの住戸を確保するために、ただ、それは、集まって住むから可能になるパーソナルスペースでは無く、ただ単に、一戸建ての個室に水回りが付いただけのものをコピペしているようなものなので、そこが建築を学びはじめた時からずっと何とかならないかと思っていた。
集合住宅の場合、収益性を確保することが大事なので、なるべく多く、できれば可能な限り最大戸数を確保して、尚且つ、集まって住むからこそ可能になる、集まって住むからこそ、そのパーソナルスペースに価値が出るようにしたく、ただ、それは住人やテナントの能力に頼るのでは無くて、建築自体が有する建築性で実現したい。
では、建築性とは、デザインの範疇でもあるが、それだけでは無いことだと、もっと違う側面があるのではないかと頭の中では考えていて、いろいろと巡らせている。
"Aim for a personal space that is not copy"
We are proceeding with multi-family housing plans with the purpose of finding and realizing what is possible from gathering and living.
However, I think that it is best from the beginning if it is possible to gather and live from the personal space of each resident, and the main space of the collective housing is still the personal space of each resident. The most important thing to do is to build a common apartment house efficiently, and to secure as many dwellings as possible, it is not a personal space that is possible because you gather and live, it is simply water in a single-family private room It's like copying things around, so I thought it would have been a while since I started learning architecture.
In the case of collective housing, it is important to ensure profitability, so it is necessary to secure as many homes as possible, if possible, the maximum number of homes, and it is possible because it is possible to gather and live, because the personal space However, it is not to rely on the abilities of residents and tenants, but to realize the architectural nature that the architecture itself has.
So, architectural is also a category of design, but it is not only that, I think in my head that there may be more different aspects, and I have a variety of trips.
以前、集まって住むから、はじめて可能になるパーソナルスペースをつくること、を集合住宅計画の目指す所とした。
そのパーソナルスペースを建築が本来持つことができる建築性で実現したいと考えている。
例えば、住人が、あるいは、テナントでもよいが、個々の特有の能力によって、そこでしかないパーソナルスペースが生み出されるのではなくて、そもそも、建築自体がその持っている特性によって、そこでしかないパーソナルスペースが生み出されるようにしたい。
個性豊かな住人を連れてくれば、自分で自分の生活空間を好きなようにカスタマイズして、パーソナルスペースをつくるだろう、特徴あるテナントを入れれば、それだけで、特有のパーソナルスペースをつくるだろう、特に建築性を必要としなくても。
そうではなくて、建築性によって、誰でも、そこでしかないパーソナルスペースをつくれるようにしたい、それがその建築の魅力になるだろう。
"Appealing to the architectural nature"
In the past, it was the aim of collective housing planning to create a personal space that would be possible for the first time, as it would gather and live.
We want to realize that personal space with the architectural features that the building can originally have.
For example, a resident may be a tenant, but individual specific abilities do not create a personal space that is only there, but in the first place, the personal space that is only there because of the characteristics that the building itself has I want to be produced.
If you bring a distinctive resident, you will customize your own living space as you like and create a personal space, if you include a distinctive tenant, it will only create a unique personal space Especially if you don't need to be architectural.
Rather, by virtue of its architectural nature, it would be an attraction of its architecture that would allow anyone to create a personal space that is only there.
変化する建築をいつも考えている、とした。
以前にも書いたが、建築は装置では無いので、パタパタと動くのは建具ぐらいで、それによって得られる可変性は面白く、それはそれで行う価値はあるのだが、ここでイメージしている変化する建築は、建築自体が可変する訳では無くて、簡単に言うと、変化したように見える、視覚に訴えるもの。
前から、その日の気分で建築の見え方が変わるようなことが起きないか、ずっと考えている。
建築以外の小さな物であれば、それは可能で、今製作中の輪島塗のフリーカップもそう、その日の気分で見え方が変わる。
「気分」をデザイン上のキーワードにしたい。
"Keyword is feeling"
He always thinks about changing architecture.
As I wrote before, since building is not a device, it is only about fixtures that moves with patters, and the variability obtained by it is interesting, and it is worthwhile to do with it, but the changing architecture I imagine here The architecture itself does not change, and simply speaking, it looks like it has changed, appealing to the eye.
I have always been wondering if things would change the way we look at architecture in the mood of the day.
If it is a small thing other than architecture, that is possible, and so is the free cup of Wajima-bura currently being produced, and the appearance changes with the mood of the day.
I want to make "feel" a keyword on the design.
集合住宅を考えている、その建築性を考えている、集まって住むことでしかつくることができない空間や建築をつくりたいと思っている、とした。
建築は周辺の環境に左右される。20世紀の建築が目指した姿は環境に左右されない不変の建築、それがモダニズムの建築、ただ、それは破綻する、それが蔓延すると、世界中どこに行っても同じ建築が建ち、同じ都市が出現する、そんなことはちょっと想像力があれば、おかしいこととわかるはずが、時の最先端を走る人たちは盲目でわからない、今も同じだと思う。
人が不変でないように、人が使う建築が不変であるはずが無い。
だから、変化する建築をいつも考えている。
その変化は経年変化では無くて、経年変化で例えば、木が良い具合にグレーになって行くのは確かに綺麗だが、そうでは無くて、建築自体の完成した時の強度の強さが、人が段々と年を取る毎に弱くなって行くように、弱く朽ち果ていくような、やがて寿命を迎えるように、まっとうして消えて無くなるような、今のモダニズム建築が目指している方向はこれだと。
例えば、伊勢神宮は20年に一度建て替える。それは技術の継承という目的もあるが、何事も不変では無いと、戒める意味合いがあると思う。
「変化する建築」は、ある意味、不変のテーマだ。
"Changed architecture"
I think that I want to create a space and architecture that can only be created by gathering and living, thinking about its collectiveness, thinking about collective housing.
Architecture depends on the surrounding environment. The aim of the 20th century architecture is an environment-invariant architecture, it is a modernist architecture, but it simply breaks down, when it spreads, the same architecture will be built and the same city will appear everywhere in the world If you have some imagination, you should find it funny, but those who are at the cutting edge of the time are blind and don't think so, I think it is still the same.
As people are not invariant, the architecture they use can not be invariant.
So I always think about changing architecture.
The change is not a secular change, but it is certainly beautiful that the tree goes gray in a good condition, for example, but it is not so, the strength of strength when the construction itself is completed, This is the direction that modernist architecture is aiming for, as it gradually weakens as it gets older, weakly decays, and eventually reaches its end of life, completely disappears and disappears.
For example, Ise Shrine will be rebuilt once every 20 years. It also has the purpose of inheritance of technology, but I think that there is a sense of discipline that if nothing is invariable, there is a sense of discipline.
"Moving architecture" is, in a sense, a constant theme.
集合住宅を考えている、その建築性を考えている、集まって住むことでしかつくることができない空間や建築をつくりたいと思っている、と以前にも書いたが、ずっと続いている。
外から考え、段々と内に入ってきて、細部まで行って、細部から段々と広げて、外を考える、順で思考が推移している。
外とは環境で、周辺の環境から、その敷地に建つ建築を考えはじめ、コンテクチュアリズム、建築の内部空間に至り、ディテールの細部まで煮詰め、そこから返って、内部空間を見渡し、建築全体にイメージを広げ、その建築が周辺の環境に与える影響を考える。
それを考える人間は階段下の囲われた空間のソファに座って妄想している。
何とも建築は壮大な可能性があることか、環境を宇宙まで広げることもできるのだから。
"Architecture starts with a grand delusion"
I have previously written that I think of collective housing, I think of the architectural aspect, and want to create a space and architecture that can only be created by gathering and living, but it has been continuing for a long time.
Thinking from the outside, coming in gradually inside, going to the details, gradually expanding from the details, thinking outside, thinking goes in order.
The outside is the environment, and from the surrounding environment, start thinking about the architecture built on the site, and get to the interior space of the architectural architecture, getting to the details of the details, then return, look over the interior space, the whole architecture Expand the image and consider the impact of the architecture on the surrounding environment.
A man who thinks of it sits in a sofa in the enclosed space under the stairs and is delusional.
It is also possible that architecture has a grand potential, or it can also extend the environment to space.
なぜか、階段に都市性を感じてしまう。
なぜか、階段は昇降するためのものというより、座るものと思ってしまう。
都市の中で階段があると座りたくなる、日本では座らないけれど、ローマのスペイン広場の階段には皆座っている。
椅子の座面の高さは標準で40cm。
階段の1段の高さは標準で20cm。
だから、階段の2段分を使えば、椅子になる。
だから、見た目で階段が椅子に見えても不思議ではないか。
階段もスケールを大きくしていけば、椅子に見えるし、観客席にもなる。階段だか、観客席だか、わからなくなる。
ただ、スケールが大きくないとダメだから、住宅規模では難しいと思うが、考えてみれば、階段がスケールアウトした構成がスキップフロアと考えられなくもなく、階段に都市性を感じるのであれば、スキップフロアの住宅にも都市性や広場みたいなものを持ち込みたいと考えていた。
"I can see the city at the end of the stairs"
For some reason, I feel urbanity on the stairs.
For some reason, the stairs are more likely to sit than to move up and down.
I would like to sit down with stairs in the city, I can not sit in Japan, but I sit on the stairs in the Spanish square in Rome.
The height of the seat of the chair is 40 cm in standard.
The height of one step is 20 cm in standard.
So, if you use two steps of stairs, it becomes a chair.
So it's no wonder if the stairs look like a chair.
If the stairs are scaled up, they look like chairs, and they become audience seats. I don't know if it's a stairs or a spectator seat.
However, I think it is difficult on the scale of the house because it is useless if the scale is not large, but if you think about it, the configuration where the stairs are scaled out is not unthinkable as a skip floor, and if you feel urbanity in the stairs, skip I wanted to bring something like an urbanity or an open space to the houses on the floor.
住宅設計の中で上下階の移動手段はひとつの見せ場で、階段を吹抜けとし、光や風の通り道とした。
ただ、できれば階段を無くしたいといつも思っている。平屋が良いという訳では無くて、勝手なイメージだが、階段は権威的な匂いがするから。
階段にはメタファーとして階層を感じる。
時の権力者が階段や段の上から声高に語る、階段の上から主役が登場するなどのイメージがそうさせているのかもしれないが、階段は扱い方によって昇降の機能とは別に意味や役割を持たせることができる。
住宅には権威的な匂いは必要無いから、階段はひとつの見せ場だが、いつもはデザイン的な工夫はするが、目立たないというか、威張らないといか、階段自体が持つ元々の「繋ぐ」という機能を強調するようにしてデザインをしている。
ただ、時には階段を権威的に扱いたくなる。それは階段を昇降する様を主役にして空間を構成する時、その階段があるからその空間が成り立つ時、階段があるからその空間がその住宅がまとまる時。
それがクライアントの話からイメージできた時。
"Stairs are authoritative"
The moving means of the upper and lower floors in the house design was one show place, and the stairs were made to be a through hole, and it was made the path of light and wind.
However, I always want to eliminate the stairs if possible. A flattery is not good, but it is a selfish image, but the stairs have an authoritative smell.
I feel the hierarchy as a metaphor on the stairs.
It may be that the image that the person in charge of the time speaks loudly from above the stairs and steps, and the protagonist appears from above the stairs, but the stairs have different meanings and functions from lifting and lowering depending on how they are handled I can have a role.
There is no need to have an authoritative smell in the house, so the stairs are a place to show off, but they are usually designed in a design way, but they are either unremarkable or intimidating, or the original "connect" function of the stairs itself The design is to emphasize.
However, sometimes I want to treat the stairs authoritatively. It is when making up the stairs to go up and down the stairs as the main part, when there is the stairs, when the space holds, when there is the stairs, when the space is put together.
When it can be imagined from the client's story.
国立西洋美術館でル・コルビュジエ展が開催されているが、すでに2回行って、その展示の中にサヴォア邸のスロープを上って屋上庭園に出る人を撮影したビデオが流れている。
スロープは階段より広い面積を必要とするし、サヴォア邸は1階部分の外壁に沿って自動車が周回するようにもなっているので、意外と大きい住宅であり、実際に実物を見てもそう思うが、その大きさはビデオからもわかる。ただ、写真だとなぜか小さく見える、不思議だ。
そのビデオを見ていて、改めて気がついたが、実際に見ているのだが、スロープを上がりきった屋上庭園の壁にピクチャーウィンドウが設けられている。
ピクチャーウィンドウとは、外の景色を見るための窓で、窓の大きさ、窓の枠によって、外の景色が1枚の絵のように切り取られている窓のこと。意図的に見せたい景色だけを見せ、見せたくない景色は切る時につくる。
都市の中で住宅をつくる時は、結構見たくない景色が多かったりして、でも、見せたい景色も無い時などは、壁の通常より高い位置に窓を設けたりして、空しか見えないようにする。空しか見えないから、空模様が1枚の絵のように見え、光と風はよく入るし、外から室内を見られることも無く、窓が高い位置にあるから、その下は普通に壁に囲われた落ち着いた空間になる。
"Picture window"
The Le Corbusier exhibition has been held at the National Museum of Western Art, but there have already been two videos showing videos of people on the roof garden rising up the slopes of the House of Savoie.
The slope needs a larger area than the stairs, and the Savoie House is a surprisingly large house, as the car also goes along the outer wall of the first floor part, so I think so if you look at it actually But the size can be seen from the video. However, it is strange that it looks small somehow in the picture.
I watched the video and noticed again, but as I actually saw, there is a picture window on the wall of the roof garden which has climbed the slope.
A picture window is a window for viewing the outside scenery, the size of the window, the window frame, the outside window is cut out like a picture. Show only the scenery you want to show intentionally, and create the scenery you do not want to show when you cut it.
When I make a house in a city, there are a lot of scenery that I do not want to see quite, but when there is no scenery that I want to show, I install windows in a higher position than usual on the wall and see only the sky Let's do it. Because only the sky is visible, the sky pattern looks like a single picture, light and wind enter well, there is no indoor view from the outside, and the window is at a high position, so the bottom is usually on the wall It becomes a calm and calm space.
住宅設計の中で上下階の移動手段はひとつの見せ場とした。
スロープを住宅に使った事例として、すぐに思い付くのがコルビュジエのサヴォア邸で、以前、スロープは20世紀のモータリゼーションとともに主体的に扱われるようになったとしたが、このサヴォア邸はまさにモータリゼーションを体現したような住宅で、広い敷地内を自動車で運転して来て、住宅の1階の平面形状に沿って乗り入れ、そのまま住宅の中に駐車し、スロープで上階へ歩いて移動する。
スロープはもともと自動車あるいは馬車の昇降のために設けられたものだろうが、ここでは自動車を降りた人間の昇降にも使われる。
階段はスロープよりも、同じレベルの高さを上がる場合、急勾配にできるので、スロープは水平性を強調し、階段は垂直性を強調する。
たがら、住宅を設計する場合、階段は吹抜けだと考えて、光と風の通り道、特に狭小住宅では、より階段面積を小さくしたいし、光や風も取り入れたいので、螺旋階段にし、上部に光や風を取り入れる開口部を設け、段板を透かしたりもする。
"Stairs are blowouts"
The moving means of the upper and lower floors in the house design was one of the highlight.
As an example of using a slope for a house, I immediately come up with the Savoir House in Corbusier, which used to be treated mainly with motorization in the twentieth century, but this Savoir house truly embodies motorization In such a house, drive by car in a large site, ride along the flat shape of the first floor of the house, park in the house as it is, and walk to the upper floor on the slope.
Slopes may be originally provided for the lifting of cars or carriages, but they are also used here for lifting of people who got off the car.
The stairs emphasize the horizontality, and the stairs emphasize the verticality, as the stairs can be steeper if they rise the same level higher than the slope.
Therefore, when designing a house, the stairs are considered to be open-air paths, and in light and wind paths, especially in narrow houses, we want to make the stairs area smaller and to incorporate light and wind, so we make spiral stairs and light at the top Or provide an opening to take in the wind, and even see through the steps.
スロープを室内につくることは住宅ではあまりやらない。理由は階段より広い面積が必要だから、住宅ではなかなかスロープをつくる広さを確保するのが難しい。
スロープを使うことによって低い所から高い所に移動するのだが、車いすを押して上がることができるようにすると、1/12以下の勾配、角度にすると5度以下にしなくてはならない。
そうすると、1mの高さを上がるのに、水平距離で12mの長さが必要になり、住宅の1階の床から2階の床までの高さを3mとすると、水平距離で36mの長さが必要になる。
スロープで車いすを利用することを考えないならば、もっと急勾配でも構わないが、階段ならば、水平距離で約3.6mの長さで済むので、差は歴然。
ちなみに、階段には、直線やL字やU字などの平面形状があるが、一番床面積が少なくて済む階段は螺旋、だから、螺旋階段はよくつくった。
住宅設計の中で上下階の移動手段は、ひとつの見せ場だと、いつも思っていた。
"Moving means show off"
Making a slope indoors is not a common practice at home. The reason is that the area needs to be larger than the stairs, so it is difficult for a house to easily secure the area to make a slope.
By using the slope, you can move from low to high, but if you are able to push the wheelchair up, you must have a slope of 1/12 or less, and an angle of 5 degrees or less.
In this case, it takes 12m in horizontal distance to raise the height of 1m, and the height from the first floor of the house to the second floor is 3m, 36m in horizontal distance Is required.
If you don't think of using a wheelchair on the slope, you can use a steeper slope, but if you're on the stairs, the horizontal distance is only about 3.6m, so the difference is clear.
By the way, the stairs have flat shapes such as straight lines, L-shapes and U-shapes, but the stairs with the smallest floor area are spirals, so the spiral stairs were well formed.
I always thought that the means of transportation on the upper and lower floors was one of the best spots in housing design.
スロープが動線空間として主体的に扱われている建築として、真っ先に思いつくのが、ニューヨークにあるライトのグッゲンハイム美術館。
真ん中に吹抜けがある螺旋状のスロープが展示空間になっており、エレベーターで最上階まで行き、そこからスロープを降りながら作品を鑑賞する。動線としての空間がそのまま展示空間になっている。
ちなみに、このグッゲンハイム美術館は画家には不評だった。吹抜けの天井はトップライトになっており、太陽の光が直接入ってくるので、知り合いのニューヨークの画家の方に言わせると、時間帯によって光の入り具合が違うから、明るい所と暗い所の差が激しく、その時によって明るさも変わるから、作品が見づらいし、作者の意図した見え方とは違うように見えてしまう可能性がある、とのことだった。
ただ、私はこの建築が大好きで、外観も螺旋状のスロープの形がそのまま現れており、空間の特徴がそのまま他の要素を決めることになり、その考え方は単純だが、出来上がる建築は複雑に見える、というのがいい。
"Simple Complexity of Slope Architecture"
The Guggenheim Museum of Light in New York is first to come to mind as an architecture in which the slope is mainly treated as a flow line space.
A spiral slope with a blowout in the middle is the exhibition space, and the elevator takes you to the top floor, from which you can admire the work while getting off the slope. The space as a flow line is the exhibition space as it is.
By the way, this Guggenheim Museum was unpopular with the painter. The ceiling of the brow is a top light, and the light of the sun comes directly into it. If you ask an acquaintance's New York painter, the lighting conditions will differ depending on the time of day, so it will be bright and dark Because the difference is intense, and the brightness also changes depending on the time, it may be difficult to see the work, and it may appear to be different from the author's intention.
However, I love this architecture, and the appearance of the shape of a spiral slope appears as it is, the feature of the space decides the other elements as it is, and the idea is simple, but the completed architecture looks complicated It is good.
動線空間が建築の中で主体的に扱われるようになったのが20世紀以降、とした。
なかでもスロープは20世紀のモータリゼーションとともに主体的に扱われるようになったのではないか。
例えば、イタリアのトリノにあったフィアットのリンゴット自動車工場は、今は改修されショッピングモールやホテル、劇場からなる複合施設になっているが、自動車の生産ラインが螺旋状のスロープを上っており、5階建ての最上階で自動車が組み上がり、そのスロープの続きで屋上に楕円形のテストコースが設けられていた。
最初は自動車の昇降のために設けられていたスロープが、人間の昇降にも使われるようになったのだろう。
スロープは階段と違って連続的にレベルが変化していく、階段だと多少の上下動を伴ってレベルが変化していく。これは視線が階段よりスロープの方がよりスムーズに変化していくことであり、20世紀は今と違ってネットなど無い時代なので、建築を伝えるためには写真しかなく、その写真を出版物で見せるしかなく、たった1枚の写真にその建築で伝えたいこと全てを盛り込もうとした時に、どう見えるか、視線の動きが正確に計算できる方が良かったから、スロープが動線空間として主体的に扱われるようになったのではないだろうか。
"Emergence of slopes"
It is assumed that the movement line space has been dealt with predominantly in architecture since the 20th century.
Above all, slopes have come to be treated independently with motorization in the 20th century.
For example, Fiat's Lingotto Car Factory, located in Turin, Italy, is now refurbished into a complex consisting of shopping malls, hotels and theaters, but the car production line is on a spiral slope, A car was assembled on the top floor of 5 floors, and an oval test course was provided on the roof on the continuation of the slope.
The slope, which was originally provided for the lifting and lowering of the car, would have been used for lifting and lowering of humans.
Unlike the stairs, the slope changes level continuously, and in the case of the stairs the level changes with some vertical movement. This is that the line of sight changes more smoothly in the slope than in the stairs, and since the twentieth century is an age when there is no net etc. unlike now, there is only a picture to convey architecture, and that picture is a publication Because it was better to be able to accurately calculate the movement of the line of sight when trying to incorporate everything that you want to convey in that single building with only one picture to show, the slope is the dominant flow line space Isn't it coming to be treated?
20世紀以降、人間のアクティビティーが建築を支配している、とした。
人間のアクティビティーの中で一番単純で、初歩的で、誰でも行うことが「歩く」こと。「歩く」ことを建築化すると、廊下、階段、スロープなど動線空間と呼ばれる空間になる。
この動線空間が建築の中で主体的に扱われるようになったのが20世紀以降ではないだろうか。昔の宮殿や伽藍には回廊と呼ばれる動線空間があったが、それはあくまでも主要な空間を結ぶためのもので、それが主体的な空間として扱われることはなかった、それは階段やスロープもしかり。
20世紀になり人間のアクティビティーが元となった機能主義の建築になると、アクティビティーそのものが建築空間になっていく。
会津にささえ堂という建築がある。複雑な二重らせんスロープで一方通行で上がり下がりをする。中にはたくさんの観音様があり、上がって下がったて一周してくるだけで、たくさんのご利益が得られることを目的にして18世紀に建てられた。これはまさに動線空間が主体的に扱われた事例で、20世紀より前だが、これはむしろ特殊な事例で、日常の中で動線空間が主体的に扱われた事例に出会うようになったのは、やはり20世紀以降ではないだろうか。
"Occurrence of flow line space"
Human activities have dominated architecture since the 20th century.
The simplest, rudimentary, and "walking" thing anyone can do in human activity. When we build "walking", it becomes a space called traffic line space, such as corridors, stairs, and slopes.
This movement line space became to be treated independently in architecture probably after the 20th century. In the old palaces and forts, there was a flow line space called a corridor, but it was only for connecting the main spaces, and it was not treated as a dominant space, it was a staircase or slope. .
When the 20th century becomes functionalist architecture based on human activities, activities themselves become architectural spaces.
Aizu has an architecture called a temple. Up and down in one way with a complex double helix slope. There are many kannons inside, and it was built in the 18th century for the purpose of obtaining a lot of benefits just by going up and down and going around. This is a case in which the flow line space is treated in a dominant manner, and it is before 20th century, but this is rather a special case, and a case in which the flow line space is dealt in the daily life is to be encountered Is it not after the twentieth century?
建築は人のアクティビティーから出来ていて、人のアクティビティーに可能性を感じる、とした。
アクティビティーを考える上で、20世紀はアクティビティーの時代だと思っていて、空間が流動的になり、アクティビティーをそのまま形どったような空間も現れた。
これは、サリヴァンの「形態は機能に従う」から機能という言葉が意識して建築に持ち込まれるようになり、機能を考える上で、人間に必要なアクティビティーが元になったからと推測される。
もともと「形態は機能に従う」は、それまでの様式建築に見られる装飾的な建築から自由になるための言葉で、建築の形態は、装飾で決まるのでは無くて、イメージはヨーロッパの石造りの神殿や教会、必然的な人間のアクティビティーが元になった機能により決まる、イメージはガラス張りのオフィスビル、ということ。
だから、20世紀以降、人間のアクティビティーが建築を支配していると言っても過言ではなく、だから、アクティビティーについて深く考えたくなる。
"The 20th Century is an age of activity"
The architecture was made up of human activities and felt the possibility of human activities.
When thinking about activities, I think that the twentieth century is the age of activities, and the space has become fluid, and a space that has shaped activities has also appeared.
It is speculated that this is because the word "function follows function" comes to architecture with the word "function follows function" consciously, and in order to consider the function, the activity necessary for humans is the origin.
Originally "form conforms to the function" is a term to be free from decorative architecture seen in the style architecture until then, the form of the architecture is not determined by the decoration, the image is a European stone temple The image is a glass office building, which is determined by functions derived from human activities and churches.
So it's no exaggeration to say that human activities dominate architecture since the 20th century, so it's tempting to think deeply about activities.
建築の可変性に焦点を当てて、人を外的要因として扱うには、意識的にならないと難しい、とした。
人はアクティビティーを発生し、そのアクティビティーに沿って建築は構成されると言っても過言では無い。
生活動線なんかは、まさにアクティビティーで、クライアントでさえ動線という言葉を普通に使うようになった。だから、建築はアクティビティーから出来ている、アクティビティーを形にした、アクティビティーから形どったもの、という認識は普通のことになった、もっと正確に言うと、アクティビティーが建築に及ぼす影響などさして考えてもいないで、動線というアクティビティーから建築がつくられていると普通に思うようになった。
ただ、ここで言う動線は、単に、日常の家事がやりやすく、軽減される、疲労が少ないなどの効用を期待して言っているに過ぎず、そのための解決方法はもうすでに出尽くしているし、さほど難しいことでも無いから、本や雑誌やネットなどで、生活動線や家事動線などの解決方法を解説できるのであって、本来、生活動線や家事動線は、人の顔が皆違うのと同じで、人によって全く違うから、人のアクティビティーを見つめ直して、突き詰めて空間構成を考えるだけで、その人特有の建築ができる、それをやらないのが建売住宅、それをやるのが注文住宅。
この話ひとつでも、人のアクティビティーを扱うことに可能性を感じてしまうが。
"Possibility of activity"
In order to focus on the variability of architecture and treat people as external factors, it was difficult, if not conscious.
It is no exaggeration to say that people generate activities and that architecture is structured along those activities.
Livelines are just activities, and even clients have come to use the word flow normally. So, the idea that architecture is made up of activities, activity-shaped, activities-shaped, etc. has become commonplace, or more precisely, even considering the impact of activities on architecture Not, I came to think normally that architecture was made from activity called flow line.
However, the line of flow here is merely to say that it is expected to be useful for everyday household chores, eased, reduced in fatigue, etc., and solutions for that are already available. Because it is not so difficult, it is possible to explain solutions such as live activity lines and housework lines with books, magazines and the net etc. Naturally, live activity lines and housework lines are different for all human faces Because it is completely different depending on the person, the person's activity can be reconsidered, the space structure can be considered, and the building unique to the person can be made. Order housing.
Even with this story, I feel the possibility of dealing with human activities.
建築の外的要因による可変性にかなり可能性を感じている、とした。
外的要因にはいろいろあるが、例として、光、他に具体的な建築部分として、可動間仕切りを挙げた。
光は、そもそも時間により変化するので、光の取り入れ方を工夫すれば良く、単純にトップライトを設けるだけでも可変性は出る。
外的要因で一番取り上げたいのは、人。
人によって建築や空間に可変性が生まれる様が一番しっくりくるような、建築として一番自然な姿のような気がする。
人は、光と同じように、動きがあり、可変性がもともとあるので、取り入れやすいはずだが、建築はそもそも人が使うものとして設計するから、可変性に焦点を当てて、人を外的要因として扱うには、意識的にならないと難しい。
"Human variability"
It is quite possible that it is possible to change the building external factors.
There are a variety of external factors, but as an example, we have mentioned moving partitions as light and other concrete building parts.
Since light changes with time in the first place, it is sufficient to devise how to take in light, and simply providing a top light can bring about variability.
The most important factor in external factors is people.
I feel that it looks like the most natural form of architecture in which people are most likely to be able to create variability in architecture and space.
People, like light, should be easy to adopt because there is movement and variability originally, but since architecture is originally designed for human use, focusing on variability, external factors for people It is difficult to be conscious if you treat it as
可変とか、リバースブルなんて言葉が好きで、変化する可能性があることに価値があると思ってしまう。
変化にも2種類あって、そのもの自体が変化するのと、そのもの自体は変化しないが外的要因で変化したように見えるのと。
そのもの自体が変化する、リバースブルの服なんてまさにそうで、リバースブルのコートやストールなんかはとても便利で、1つあれば、その時の気分で変えることができるから嬉しいし、楽しい。
ただ、そのもの自体が変化するのはあまりにも単純というか、直すぎて、ちょっとつまらないので、趣があって、いろいろと考えを巡らすことができて、深みも感じられるから、どちらかというと、外的要因でそのもの自体は変化しないが、変化したように見える方に興味が惹かれる、建築もそうだから、そのもの自体が変化すると装置だから。
だから、どうしても建築に可変性を持ち込みたくなり、私の建築作品にはよく可動間仕切りが登場する。
可動間仕切り自体は、言わば装置だが、外的要因として、空間が仕切られる、仕切られない以上に違った見え方や違った趣になることを意図する。
建築の外的要因による可変性に、光もそうだが、かなり可能性を感じている。
"Possibilities of variability"
I like variable and reverse bullying, and I think that it is worthwhile to be able to change.
There are also two types of change, and it changes itself and it looks like it has not changed, but has changed due to external factors.
It's a change of itself, it's just like a Rebel Bull's clothes, it's very useful to have a coat or a stall on a Rebel Bull, and with one you can change it depending on the mood.
However, it is too simple or too straight to change itself, so it's a bit boring, so it's tasteful, you can go around various ideas, and you can feel the depth. It does not change in itself, but is interested in people who look like it changes, and so is architecture, because it changes itself.
So I really want to bring variability into architecture, and my architectural works often have moving partitions.
The movable partition itself is, so to speak, a device, but as an external factor, it is intended that the space is divided, and the way it looks different or more different than it is divided is to be different.
The variability of the building's external factors, like the light, feels quite possible.
すぐにイメージや具体的な事が思い付かない問いを立てることができるかどうかが鍵だ、とした。
おもしろもので、言葉だから、現実には起こり得ないだろうと思ったり、起こる気がしないことでも書けてしまうので、こうなったら良いなとか、こういう建築ってあるのか、という言えば妄想に近い、でも、そんな建築があったいいな、と心底思うことを書いたりしていると、案外、こうすればできるな、と自分の頭の中だけだけれど、やり方や方法や方向性が掴めたりして、頭の中でわかれば、大概は実行に移せるので、それが本当に良いか悪いか、技術的にできるかどうかは別にして、ただ、人の頭の中で思い付く程度のことは大概は技術的にも解決できるので、あとは予算が付いてくるかどうかくらいか、見積りしたら倍になる程度ならばまだ良い方らしい。
"A delusion is also a question"
It is the key whether you can ask questions that you can not immediately think of an image or concrete thing.
It's interesting, because it's a word, I think that it won't happen in reality, or I can write something that doesn't happen, so it's a good idea if it's like this, or if it's an architecture like this, it's close to a delusion, However, when I write something that I truly feel that there was such an architecture, I was able to grasp the way, the way and the direction, though it was only unexpectedly that I could do it this way. If you know it in your head, you can usually put it into action, so it's just about what you can think of in a person's mind, apart from whether it's really good or bad or technically feasible. It can be technically solved, so it seems that it is still better if it comes with a budget, or if it can be doubled if estimated.
ずっと言葉を頼りに考えている。考えている時は頭の中にイメージが浮かぶ、空間であったり、今まで見て来た建築であったり、ディテールであったり、建築以外も、器だったり、カトラリーであったり、ものだけでなく、出来事も、それもデザインの内だから、ただ、それらは今までに見たり聞いたりした事、既知なことばかりで、すぐに、とりあえず、パッと頭の中に広がるイメージは、取捨選択の捨てるために思い浮かべているようで、
とりあえず、パッと、具体的に建築やその部分が浮かぶ時は、絶対にどこかで誰かがやっていることだから、そのままはやらず、そこから展開していき、最終的には最初のイメージ、思い付きの痕跡がほぼ無いところまで辿り着くが、
それは誰でもできる事で、小手先の器用な人ならば、尚更、上手く見せることができるから、それで良いのだけれど、それでは満足しないから、言葉を先行させて、イメージが、具体的な事が追いついて来ないことばかりをしようとする。
例えば、集まって住むことでしかつくることができない空間や建築をめざすとしたら、1つの問いとして、住人の数だけ建築が違って見えれば、集まって住むことでしか実現できない多様で複雑な建築ができるから、そのためにはどうすれば良いか、ができる。
すぐにイメージや具体的な事が思い付かない問いができれば、あとはそれを解けば良いだけだから、実現はできる。
すぐにイメージや具体的な事が思い付かない問いを立てることができるかどうかが鍵だと思う。
"Ask a question"
I have always thought in terms of words. When thinking, the image floats in the head, it is space, it is the architecture which I have seen so far, it is the detail, it is the vessel other than the architecture, it is the cutlery, etc. Not even events, but because they are within the design, they are just what we have seen and heard, only known things, and for the time being, for the time being, the images that spread in the head and head will be discarded It seems that I think to throw it away,
First of all, when there is a package, specifically, the architecture and its parts, it is absolutely something that someone is doing somewhere, so we will not do it as it is, we will develop from there and finally think about the first image, You reach a point where there is almost no trace of
It can be done by anyone who can do it well, and it is good because it can be shown better even if it is a dexterous person at the tip of the hand, but it is not satisfactory with that, so the words precede and the image catches up with concrete things I just try to do things that I do not want.
For example, when aiming at a space or architecture that can only be created by gathering and living, one question is that if the architecture looks different depending on the number of residents, various complex architecture can be realized only by gathering and living Because you can, you can do what to do for that.
If you can immediately ask questions that do not come up with an image or concrete thing, you can do it because all you have to do is solve it.
I think the key is whether you can immediately ask questions that you do not think of an image or concrete thing.
国立西洋美術館で開催中のコルビュジエ展にて、一番最後の展示に、エスプリヌーヴォー館完成の頃か、エスプリヌーボーの最終号に掲載した、たぶん、コルビュジエの言葉だと、もう一度行って確かないと、
「人は自然の混沌な形は見えない、見ることができない。しかし、大海の水平線や林立する岩などの単純な形には魅力を感じ、すぐに見入るし、わかりやすいから、わかる」
というような趣旨の文章があり、ちょっと驚愕した。
コルビュジエの初期の作品、例えば、サヴォア邸は近代建築の五原則の1つにもある、水平連続窓が示すように、水平垂直の線が強調された外観をしており、室内に入ると、浴室の寝椅子に見られるような自然から発想したような自由曲線の形態が現れてくる。
ピュリスムの絵画に表現されている複数のモチーフが重なった輪郭線が外観に現れて、モチーフの形態自体が、それが自然の中にあるものをモチーフとして、内部の至るところに現れてくるのだと、今まで考えていたけれど、
外観の水平垂直の線は、大海の水平線や林立する岩から発想されていた、すなわち、コルビュジエは後に「人間と自然との調和」をはかりはじめたのではなくて、初期から「人間と自然との調和」をめざしていたことになるのではないか。
これは自分の中では大発見であり、コルビュジエへの見方、建築の造形を考える上での思考のめぐり方にかなり影響を与えることになるかもしれない。
"Change to Corbusier's view"
At the Corbusier exhibition being held at the National Museum of Western Art, the last exhibition, whether it was the completion of the Esprinouvaux, or in the last issue of Esprinouw, maybe Corbusier's words, I'm not sure I'll go again ,
"People do not see or can see the chaotic form of nature. However, simple forms such as the horizon of the ocean and forested rocks are attractive, readily visible, and easy to understand."
There was a sentence of purpose, and I was a little surprised.
Corbusier's early works, for example, the House of Savoie, have one of the five principles of modern architecture, as the horizontal windows show, have an appearance where horizontal and vertical lines are emphasized, and entering the room, The form of a free curve appears from the nature that can be seen in a bathroom chaise longue.
The contour line where the multiple motifs expressed in the picture of Purism are overlapped appears in the appearance, and the form of the motif itself appears in the inside of the inside with the one in nature as the motif. Although I was thinking so far,
The horizontal and vertical lines of the appearance were conceived from the horizon of the ocean and the rocks that stand in the forest, that is, Corbusier did not start to "harmonize human and nature" later, but from the beginning "human and natural The goal is to achieve "harmony".
This is a great discovery within me and may have a significant impact on the way he views Corbusier and the way he thinks in terms of architectural shapes.
コルビュジエは絵画上で「幾何学的な秩序」と「人間と自然の調和」をはかっていたのか、いや、「幾何学的な秩序」が人間のことで、「幾何学的な秩序」と「自然の調和」をはかっていたのかもしれない、とした。
人は不変ではない、いつか死ぬし、老いるし。
ただ、20世紀の「人間」という概念は不変と規定し、コルビュジエは「人間」を「幾何学的な秩序」の一部として表現していた、それがモデュロール。
人間を幾何学的な秩序とすることで建築の中に人間を取り込み、空間と一体化することをめざした、それは不変を標榜したモダニズム建築と折り合いをつけるために。
結局、人間も空間も建築も不変であるはずが無く、歪みが出るのだが、人はみな不変をなぜか求めてしまう、アンチエイジングもそう、絶対的で不変なものが好きな心理があるのか、それとも、モダニズム的な建築のデザインがやりやすいのか、今だにモダニズム建築の系譜は続いており、何かと折り合いをつけることになる。
モダニズム建築が近現代建築の基礎的なデザインなので、その系譜から逃れることはできないのかもしれないが、建築関係者の中だけで暗黙の了解的なデザインが存在するのも確かだから、全く違うデザインをイメージしたく、それはイメージの中にいたら難しいから、言葉に頼ることになる。
"Start with words"
Corbusier did "geometrical order" and "harmony of human beings and nature" in the picture, or "geometrical order" means human being, "geometrical order" and "geometrical order" It may be that he was trying to harmonize nature.
People are not constant, someday die and they grow old.
However, the concept of "human" in the 20th century is defined as immutable, and Corbusier expressed "human" as part of "geometrical order", which is modulol.
In order to bring human into architecture and unite with space by making human geometrically ordered, it is in order to reconcile with modernist architecture which insisted on invariance.
After all, human beings and space and architecture can not be invariant, and distortions occur, but all people seek for invariance somehow, like anti-aging, do they have a mind that likes absolute and invariant things Or is it easy to design modernist architecture, the genealogy of modernist architecture still continues, and we will get along with something.
Because modernist architecture is a basic design of modern and contemporary architecture, it may not be possible to escape from its genealogy, but it is also true that there is an implicit intelligible design within the building personnel alone, so a totally different design Because it is difficult if it is in the image, it will rely on words.
コルビュジエの絵を年代順に追って見ていったら、初期の建築の形態がシンプルで後の建築の形態とどうして違うのかがよくわかる、とした。
コルビュジエの晩年のピュリスムの絵には陰影が現れる。初期のピュリスムの絵はオブジェの2視点からの重なりとその輪郭線で構成されており、それが絵の構図上の幾何学的な秩序であり、その秩序はどの絵にも共通しており、それがコルビュジエの初期の絵画および建築のテーマだった。
実際、パリのラ・ロッシュ邸はその幾何学的な秩序で内部空間の見え方は構成されており、まさにピュリスムの建築だった。
晩年、コルビュジエは「人間と自然との調和」をテーマにする。「幾何学的な秩序」はどのような状況でも不変であるのに対して、「人間と自然との調和」は状況に応じて変化する、自然の変化に呼応する。
そのコルビュジエのテーマの変化が絵画に現れていて、晩年のピュリスムの絵には陰影が現れている。
陰影は光を暗示しており、光は状況によって変化する自然で、コルビュジエはピュリスムの絵の中で自然を表現していた。
コルビュジエは絵画上で「幾何学的な秩序」と「人間と自然の調和」をはかっていたのか、いや、「幾何学的な秩序」が人間のことで、「幾何学的な秩序」と「自然の調和」をはかっていたのかもしれない。
"Humans are geometric order"
When I looked at the picture of Corbusier in chronological order, I understood that the form of the initial architecture is simple and I can understand why it is different from the form of the later architecture.
Shadows appear in Picturesque paintings of Corbusier's later years. Early Pyrism paintings consisted of overlapping objects from two viewpoints and their contours, which is the geometric order on the composition of the picture, its order is in common with any picture, That was the theme of Corbusier's early painting and architecture.
Indeed, La Roche's residence in Paris was built with its geometric order and the way the inner space looks, it was exactly the architecture of Purris.
Later year, Corbusier's theme is "Harmony between man and nature". "Geometric order" is invariant under all circumstances, while "harmony between man and nature" responds to the change of nature, which changes according to the situation.
Changes in the theme of the Corbusier have appeared in the paintings, and shadows appear in the paintings of Purismu in later years.
The shadow implies light, the light is natural that changes according to circumstances, Corbusier was expressing nature in the picture of Purrism.
Did Corbusier understand "geometric order" and "harmony between man and nature" on paintings? No, "geometric order" is about human beings, "geometric order" and " Harmony of nature "might have been investigated.
光をものとして扱うのは、光を媒介にして、その日の気分の変化を建築で感じて欲しく、それで建築の見え方も変わる、とした。
建築の不変性を可変性に変えたいから、ただ、建築自体が変化してしまうと、もちろん、それも可能だし、その事例はたくさんあるけれど、建築が単に装置と化すだけのような気がして、それは建築の範疇では無いような、
それこそ、コルビュジエの「住宅は住むための機械である」の言葉でパッとイメージしてしまうような機械になってしまうような気がする。
ちなみに、「住宅は住むための機械である」は20世紀初頭の言葉であり、それまでのヨーロッパの石造りの装飾に満ちた建築に対して、新しい時代の建築をめざして唱えられた言葉で、「機械」という言葉に船や飛行機のようなイメージを重ね、未来の住宅は機能的でシンプルな形態をしたものという意味が込められている。
今、国立西洋美術館でコルビュジエの展覧会が開催されているが、今まであまり興味がなかったコルビュジエの絵を年代順に追って見ていったら、初期の建築の形態がシンプルで後の建築の形態とどうして違うのかがよくわかり勉強になった。
"Building is not a device"
Treatment of light as thing, I want you to feel the change of the mood of the day through architecture with light, so that the appearance of the architecture will change as well.
Because we want to change the invariance of construction to variable, but if the building itself changes, of course, it is also possible and there are many cases, but I feel that construction is just a device It seems that it is not in the category of architecture,
It seems that it is becoming a machine that will be imagined by Corbusier's words "House is a machine for living".
By the way, "Housing is a machine to live" is the early 20th century words, words that were chanted for the architecture of a new era against the architecture filled with European stone decoration, The word "machine" is overlaid with images like boats and planes, meaning that the future housing is a functional and simple form.
At the National Museum of Western Art, an exhibition of Corbusier is being held, but when I look at the picture of Corbusier, which I have not been interested so far, chronologically, the initial form of architecture is simple, I learned a lot about how they were different.
光をものとして扱うために粒としてイメージし、その粒の集め方、扱い方が建築の造形のヒントになる、とした。
集合住宅を考えている。その建築性を考えている。
集まって住むことでしかつくることができない空間や建築をつくりたいと思っている。
光をものとして扱おうとしているのは、光を媒介にして、その日の気分の変化を建築で感じて欲しいから。そうすれば、その日の気分によって建築の見え方も変わるだろうから。
それが住人の数だけ起これば、その建築はなんて多様で複雑で、ちょっとだけ浪漫が、と妄想するも、そこに集まって住むから、という理由づけしたいのだが、なかなか上手いこといがず、ここ数日ずっと考えている。
"Because we gather and live"
In order to treat light as a grain, it was imagined as a grain, and how to collect and handle the grains is a hint for building the architecture.
I am considering multi-family houses. I am considering its architectural nature.
I would like to create space and architecture that can only be created by gathering and living.
I 'm trying to treat light as things because I want you to feel the change in the mood of the day through architecture through light. That way, the appearance of the building will change according to the mood of the day.
If it happens as many as the number of residents, I'd like to rationalize that the architecture is so diverse and complicated, a little bit romantic, but also live and gather there, but it is quite something good, I have been thinking over the last few days.
光を造形することをイメージした時、一番最初に浮かんだのは、子供の頃、レゴブロックで遊んだ記憶。
レゴブロックは箱に描かれている絵の通りのものをつくることができるパーツがバラバラで箱に入っていて、その絵の通りのものをつくっていくのだが、私は箱の絵には全く興味が無く、バラバラのパーツから好きものだけ、使いたいものだけ取り出して、全く別のものをつくっていた。パーツ取りをして、バラバラのパーツから、例えば、蝶番の付いた扉は、飛行機の可変翼に流用したり、そのまま使うのではなくて、全く別のものに転用していた。
バラバラのパーツをひとつの大きな箱に集めて、そこからパーツを1個ずつ取り出して造形していた。
同じように、光も粒みたいなものを寄せ集めて造形していくイメージが最初に浮かんだ。
粒のようなイメージ、それは正しく、光をものとして扱うことになるので、まずは光を粒として、どのように取り入れるか、そして、その粒をどのように集めるのか、光の扱い方が段々と具体化してきた、それは光を扱うための建築の造形を考えるヒントになる。
"Treat light as grain"
When I imagined shaping light, the first thing I came up with was memories that I played with the Lego block as a child.
The LEGO block is a box that contains parts that can make street stuff depicted in a box, and it is in the box and I will make something just like that picture, but I do not like the box picture at all I was not interested, only the things I wanted to use, from the disjointed parts, I took out something completely different. For example, a door with a hinge was diverted to a variable wing of an airplane or was not used as it was, but it was diverted to a completely different thing from the disjoint parts, taking parts.
I gathered the parts in pieces in one large box, I picked up parts one by one and made it.
In the same way, an image that first gathers and shapes something that looks like grain comes first.
As it is an image like grain, it will handle light properly, so first of all let's see how light is taken as grains, how to incorporate that grain and how to grain that grain, how to handle light is step by step It has become a hint to think about the architectural formulation for handling light.
建築を造形することにより、光をものとして扱うことを試みるために、開口部、空間を考え、周りの環境に対してどう建てるかを考え、コンテクスチュアリズムとは逆の思考順序で考える、とした。
光には質量を感じないから、ものとしての意識など無く、ただ視覚のみに頼って造形していく。
具体的には、幾重にも光が差し込み、時間帯によって形づくられる光が違う、光と陰のコントラストがつくる形が違うようなイメージか。
そこに人や生活の営みも時間帯によっては光の造形に加われば、尚面白い。
同じ光の形を見ても、人によって感じ方が違うだろうし、そこにその日の気分を投影できて、その日の気分によって、光の形を含めた空間全体、その空間をつくる建築全体が違って見えるようにならないだろうか。
そのためには、ガラス張りのような一様な光が降り注ぐ建築ではないのは確かだ。
"Model light"
In order to attempt to treat light as things by modeling the architecture, think about opening, space, think about how to build against the surrounding environment, think in a thought order opposite to contrastist rhythm did.
Since we do not feel the mass in the light, we do not have consciousness as things, just rely on visual perception to shape.
Specifically, the light is inserted many times, the light formed by the time zone is different, the image that the contrast of light and shadow creates is different.
It is still interesting if people and the lives of life also participate in the shaping of light depending on the time zone.
Even if you look at the shape of the same light, you will feel different from person to person, you can project the mood of the day there, the mood of the day, the whole space including the shape of light, the whole building that creates that space is different Will not it seem to be visible?
To that end, it is certain that it is not a homogeneous light like a glass.
外の光は全体的に明るいか暗いかしかわからない。
内の光になってはじめて形がわかる。
建築は光に形を与える。
仏師が仏像を造形するように、建築家が光を造形する。
光をものとして扱い、造形することにより、仏像のお顔のように、見る人の気分によって見え方が変わるようにしたい。建築の中にある光が金堂の中にある仏像に相当する。
光をものとして扱い、造形するためには、建築を造形することになる、開口部、空間をどうするのか、周りの環境に対してどう建てるか、コンテクスチュアリズムとは逆の思考順序になる、それは面白い。
そもそも、光をものとして扱いのが面白い。光には質量を感じないから、ものとしての意識など無いから、ものとして意識したら、どうなるのだろうか。
"Treat light as thing"
I can only see whether the outside light is bright or dark overall.
Only when it turns into light inside it will be the shape.
Architecture gives shape to light.
As a Buddhist teaches a Buddha image, an architect shapes light.
I want to make light appearance change by the mood of the viewer, like the face of the statue of Buddha, by treating the light as things and shaping. The light in the architecture is equivalent to the Buddha image in Kanpo.
In order to treat light as a thing and to shape it, it is going to shape the building, how to open the opening, how to build the environment, how to build it against the surrounding environment, the order of thinking is contrary to contrastist rhythm, That's interesting.
In the first place, it is interesting to treat light as a thing. Since light does not feel mass, there is no consciousness as things, so what will happen if you are conscious as things?
建築には空間に差し込む光を利用でき、光はゼンマイ仕掛けのように変化し、そこに差異を見出せる気がする、とした。
ずっと、建築が見る人の気分によって見え方が変わるにはどうすれば良いのかを考えている。
なぜか、建築は今まで不変と考えられて来たから。当たり前だが、建築物が変化しないから不変という訳ではなくて、建築は時代や社会によって捉えられ方が変化してきた、デザインも、流行があるということ。しかし、それを受け止める建築自体は確かなもので変わらないものだから、そこに時代性や社会性を投影できた、建築自体は常にブレが無く不変が前提だった。それは経済的にも重要で、不変だから、不動産と称する事業性を含んだ建築が生まれた。
ただ、建築もものならば、不変という捉え方には無理があるだろう、もちろん、耐久性の話ではなくて、建築以外のものは、簡単に動かすことができ、使う側が取捨選択できることもあるが、ものとしてそこに気分や感情を投影することが容易にでき、それがそのものの存在価値と直結している。
例えば、毎朝飲むコーヒーを淹れるカップを気分で選ぶ、など、その日の気分がコーヒーカップの存在価値を決め、それがそのコーヒーカップのその日の見え方を決める。
だから、建築にもそのようなことが起こる、不変ではないものにしたく、そうすれば、その建築での日常は楽しいことになるのではないか、という考え方のつながり。
"Aiming for Constancy Not Constant"
In the building we can use the light to be inserted into the space, the light changed like a springmaking gimmick, and it seems to be able to find a difference there.
I'm thinking about how to see how the appearance changes depending on the mood of the building.
For some reason, architecture has been considered immutable until now. Naturally, it is not a change that the building does not change so it is not a change, the way that architecture is caught by the times and society has changed, the design also has a fashion. However, since the architecture itself which accepts this is a sure thing, it does not change, so we could project periodicity and sociality there, the building itself was always premised without blurring. Since it is economically important and unchanged, a construction including a business property called real estate was born.
However, if construction is also things, it seems impossible to understand that it is immutable, of course, it is not a story of durability, but things other than buildings can be easily moved, sometimes the use side can sort it out However, it is easy to project moods and emotions there as things, which is directly linked to the existence value of itself.
For example, the mood of the day decides the existence value of the coffee cup, such as choosing a cup to make a drink coffee every morning, which determines how to see that coffee cup that day.
So, if you want to make such things happen in architecture, do not make it immutable, so that the daily life in that architecture will be fun.
仏像も建築もものだから、大日如来像のお顔のように見る側のその日の気分を投影できる、とした。
つくり手と見る側の意識の差異をつくり出したい、そこに気分を投影できる、仏師が想う大日如来像のお顔と見る人が想う大日如来像のお顔に微妙な差異があるから、人は無意識にその差異を確かめたくなる、ただ、確かめる手段を知らないから、その時の感覚で見てしまう、感覚は瞬間的にはその時の気分に左右される、気分が良ければ、どのような景色も、ゴミ箱でさえ綺麗に見えるし、気分が悪ければ、どんな美人も醜く見えるか、たぶん見える、それだけ人は気分に左右されるし、それを日常的に受け入れているし、それを本質だと勘違いして、墓穴を掘る、仏像のお顔が笑ったり、哀しそうにする訳が無く、変化する訳が無いのに、冷静に考えれば、当たり前なのに、お顔がどう見えたかに左右される、そういう人はいい人かもしれないけれど。
仏像や建築をものとして見た場合、建築には仏像のお顔のようなこと、造形物を掘り出して、そこにつくり手の想いを込めて、見る側も想いを込める関係性を築くのは難しいかもしれないが、
仏像には扱えなくて、建築には扱えるものがある、光。
仏像はソリッド、建築はボイドと対称的に言うこともできるかもしれないが、建築には空間として、そこに差し込む光を利用することができる、しかも、その光はゼンマイ仕掛けのように変化してくれる、そこに差異を見出せる気がする。
"There is light in architecture"
Because Buddha statue and architecture are things, it is possible to project the mood of that day on the viewer side like the face of the Dainichijo statue.
I want to create a difference in consciousness between the making hand and the viewer, I can project the mood there, there is a subtle difference in the face of the Dainichi Nagai statue that the Buddha thinks and the face of the Dainichi Nagai statue that the viewer thinks, People unwittingly want to see the difference, just do not know the means to make sure, so you will see with the feeling at that time, the sensation is instantaneously dependent on the mood at that moment, if what you feel is good Even the landscape, even the garbage can be seen beautifully, and if the mood is bad, any beautiful person looks ugly, perhaps, you can see, perhaps the person depends on the mood, that is accepting on a daily basis, that is essence Misunderstanding and digging the grave, there is no reason to smile or make sorrowful the face of the Buddha statue, there is no change to change, but if you think calmly, it depends on how you looked at the face That kind of person is a nice person But no.
When seeing Buddha statues and architecture as things, it is not easy to build a relationship that allows the viewer to embrace the thought of the creator there, digging up the objects, like the face of the statue of Buddha in the architecture Although it may be difficult,
There is something that can be handled in Buddha images, architecture has light, light.
Although it may be possible to say that the Buddha statue is a solid and the architecture is symmetrical with the void, in the building space can be used the light to be inserted there, and the light changes like a spring fence I feel like I will find a difference there.
建築はものだから、そこに気分を投影できる。
ものだから、つくり手がいて、構想する人がいて、設計する人がいて、人によって差異が出る。
きっとその差異、微妙な違い、つくり手と見る側の違いによる差異が気分を投影できる部分になるのかもしれない。
大日如来像のお顔が、笑って見えたり、怒ってみえたり、穏やかに見えたり、厳しくみえたり、哀しそうに見えたりするのは、仏像のつくり手は喜怒哀楽を表情で現そうとしていなくても、見る側が勝手に仏像のお顔に、自分を重ね合わせて見てしまう、その時の自分の感情や気分を無意識に重ね合わせるのだろう。
ならば、仏像はものだから、建築もものなので、同じことが起こるはずだろう。
"Architecture and Buddha statues"
Architecture is things, so you can project mood there.
There is a creator, there is a person to conceive, there are people who design, people will make a difference.
Perhaps the difference, subtle differences, differences due to the difference between the making hands and the looking side may become a part that can project the mood.
The face of the Dainichi Nagai statue appears to be laughing, looking angry, looking calm, looking sternly, looking sadly, the making hands of Buddha statues will express emotions and emotions with expression Even if it is not, the viewer will unconsciously superimpose his emotions and mood at that time, without seeing himself superimposed on the face of a Buddha statue.
Then, the Buddha statue is things, so the same thing will happen because the building is also things.
端が、先が、もっと繊細ならば良いのに、というのは民藝だけでなく建築をにも言えることで、ものとしてどう見えるか、手先、足先を大事にしていない建築を結構見る。
わざと意図的に厚く見せているのと、何も意識せずに厚くなってしまった、では同じ厚みでも全く違って見える。
もっと言えば、繊細であれば良いのか、というのもあり、厚みがあることを意図することもあり、
さらに、もっと言えば、繊細であることは薄く、細くすることか、厚みがあって、太くても繊細になることもある。
ただ、いずれにしても、端々、先々まで意識して、1mm、0.5mm、0.3mmを出し入れする。
それは、単にディテールに凝るということだけでは無くて、建築のものという側面に対して、どう意識しているのかという話で、結構おざなりにされているのを見るし、その度に、建築はものなんだと再確認する。
"Consciousness as a thing"
Even if the end is more delicate, it seems that not only the folk art but also the architecture can be said, it seems pretty to see the architecture which does not take care of the hands and the toes.
It looks deliberately intentionally thick and it got thicker without consciousness, but it looks quite different at the same thickness.
In other words, whether it is delicious is good, sometimes it is intended to be thick,
Furthermore, to be more specific, it is thin, thin, thick, sometimes delicate even if it is thick.
However, whichever way, consciously conscious from one side to the other, take in and out 1 mm, 0.5 mm, 0.3 mm.
It is not just about sticking to detail, but we talk about how we are conscious about aspects of architecture, we see that it is quite saddened, and each time the building is a thing Reconfirm what it is.
民藝には繊細さが無い、とした。
その辺、柳宗理ディレクションは民藝に繊細な部分を持ち込もうとした痕跡があり、端々に厚みを消す処理を施しているように思える。
繊細さは美術品のようであり、民藝品は美術品の対極にあり、繊細さを求めることは美術品を目指すことであり、民藝にとってはタブーなのだろう。
厚みの厚さは民藝の象徴であり、そこに、丈夫で、毎日の生活の中での使用に何十年と耐える、そこにものとしての価値と美がある、ことを現している。
だから、民藝品の美と美術品の美は違う、という解釈が、民藝に携わる人には成り立つし、成り立たないと都合が悪いのだろう、使う我々にとっては関係ないところで。
美は美で、美の根本は同じで、民藝品とか、美術品とか、の違いは一部のつくり手と売り手が意識しているだけの話。
あとちょっと、ほんのちょっと繊細ならば完璧、端が、先が、あと1mm、いやあと、0.5mm薄ければ、細ければ、言うことないものばかり。
それを学んだのは、柳宗理の作品を見て、日常使いしているからなんだけどなと、場末の呑み屋でホッピー呑みながら想う。
"Delicacy in folk art"
It is said that folk art has no delicacy.
In that area, Yanagi Sorihi has traces of trying to bring delicate parts into folk arts, and seems to be applying treatment to eliminate the thickness.
Delicateness seems to be a work of art, folk art is on the opposite side of artworks, seeking delicacy is aiming at art objects, and for folk arts it is taboo.
The thickness of the thickness is a symbol of folk art, and it is strong, it shows that there are values and beauty there as it can withstand decades for use in everyday life.
Therefore, the interpretation that the beauty of a folk art and the beauty of a work article are different for a person engaged in folk arts, and it is not convenient if it does not make it, it is not related to us.
Beauty is beauty, the fundamentals of beauty are the same, the difference between folk art items and art goods is only the story of some making mind and seller conscious.
After a while, perfect if slightly delicate, end, tip, 1 mm afterward, no more, 0.5 mm thin, if it is thin, nothing to say.
I learned it because I see Mr. Yoshinori's works and I use it everyday, but I think while swallowing Hoppy at the sweet shop at the end.
手づくりでも、手仕事の痕跡を残さずにものをつくることは可能だろう。繊細なものをつくろとすればする程、手仕事の痕跡は消したくなる。痕跡があると、そこに意識の引っ掛かりができ、繊細に見せたいのに、仕上げに余計な意味が生まれ、さらりと流れなくなる。
厚みが無いところには痕跡は残せないし、繊細に薄く見せたいとしたら、表面の仕上げに凹凸が無い方が良い。
そうなると、手仕事の痕跡を残すと繊細なものにはならないし、
そうすると、繊細なものには、その日の気分を投影できるような余地は無いことになる。
勝手なイメージだが、民藝品は、厚くて、凹凸があり、繊細では無い。
繊細だけれども、余地・余白があり、中庸であり、その日の気分を投影できるものは、やはり、仏像のお顔がすぐに思い浮かぶ。
ちょっと民藝とは違うところに、可能性が眠っているような気がしてきた。
"Feeling of delicacy"
Even with handmade it would be possible to make things without leaving traces of manual work. The more you make the delicate things, the more you want to erase the trace of handwork. If there is a trace, you can get stuck with consciousness there, and you want to show it delicately, an extra meaning is born in the finish, it will not flow any further.
Traces can not be left in places without thickness, and if you want to show delicately thinly, it is better that the surface finish has no irregularities.
Then, leaving traces of handicrafts will not be delicate,
Then, there is no room for delicate things to be able to project the mood of the day.
Though it is a selfish image, folk art is thick, has irregularities, it is not delicate.
Though it is delicate, there is room / margin, moderate, those that can project the mood of the day, the face of the Buddha statue immediately comes to mind.
In a place a bit different from folk art, the possibility seems to be asleep.
民藝に新たな可能性を感じる、とした。
ずっと玉子焼き器を眺めている、なぜこれが良いのか。ずっとコーヒーカップを眺めている、なぜこれにその日の気分を投影できるのか。
不揃いで、一定ではなく、たぶん意味があるのだろうが、それが装飾になる処理など、そのきちんとしていない様に惹かれるからか。
京都の北村一男さん作の銅製の玉子焼き器が良いのは、形と大きさ、スケールという幾何学的な秩序に、デザインと民藝の手仕事の痕跡があるから、もっと突き詰めると、形の比率、縦横の比率のバランスの良さ、全体の大きさがこれよりも大きくてもダメ、小さくてめダメ、絶妙な大きさで、縁の補強?リベット?のデザインが、シルバーと銅色のコントラストがアクセントで良く、持ち手が丸鋼で細くて良いが、もう少し幅が狭い方が全体の形が綺麗になるし、使いやすいのではと思うが、これはもしかしたら、実際に狭くしたら、わからない、これで良いのかもしれない。
この玉子焼き器に手仕事の痕跡が無くて、角とか、端々がきちんと綺麗に整形されていても良いと感じるのだろうか、手仕事の痕跡が無くても、その日の気分を投影できるのか。
手仕事の痕跡が無くても、大まかな幾何学的な秩序やデザインは変わらない、手仕事の痕跡もデザインの内と捉えることもできるが、手仕事の痕跡のみが幾何学的な秩序をほんのちょっとだけ乱し、この乱し具合が絶妙で、そこがその日の気分を投影できる余地かもしれない。
計算して手仕事の痕跡をつくることはできないかもしれないが、全く無くても成り立たないとしたら、ものづくりとは厄介なものだと、改めて思う。
"Traces of handicrafts"
He felt new possibilities for folk art.
I have been looking at the egg oven for a long time, why is this good? I am looking at a coffee cup all the time, why can I project the mood of the day to this?
It is irregular, not constant, probably meaningful, because it is attracted to not being properly decorated, such as processing to become decorative?
Kimoto's Kitamura Kazuo's worked egg baked goods is good because there are signs of design and folk handicrafts in the geometric order of shape and size, scale, so if you make a further break, shape Ratio, good balance of vertical and horizontal ratio, even if the size of the whole is larger than this, it is not good, it is not small, is not it exaggerated size, reinforcing the edge? rivet? Although the design of silver, copper contrast is good with accent, the handle can be thin with round steel, but the one with a slightly narrower width will make the whole shape beautiful and I think that it is easy to use, but this Perhaps, if actually narrowing down, I do not know, perhaps this is fine.
Is there any trace of handwork on this egg grill and does it feel that the corners or the edges are shaped properly neatly? Even if there is no trace of handwork, can you project the mood of the day?
Even without the trace of manual work, rough geometric order and design does not change, traces of manual work can be regarded as design, but only the trace of handicraft is merely a geometrical order It is just a bit disturbed, this disturbance is exquisite, and there may be room to be able to project the mood of that day.
Although it may not be possible to calculate and make traces of handicrafts, if it does not exist at all even without it, I think again that manufacturing is troublesome.
その人の気分を投影する余地をつくるには、ちょっとだけ幾何学的な秩序をつくり手が、無意識にでも、いじれば良い、それは民藝的なつくり方、とした。
毎朝、豆から挽いてコーヒーを淹れるのが日課で、コーヒーカップをその日の気分で選んでいる。
きっかけは、柳宗理がディレクションした因州中井窯と出西窯のコーヒーカップを複数手に入れたこと。色や形が違うカップだけれども、同じ色・形でも、微妙に大きさが違ったり、釉薬の乗りの違いから来る微妙な色の差に、その日の自分の気分を乗せて、毎朝、どれにしようかと楽しみながら選んでいる。
そして、偶然にも、この因州中井窯と出西窯は民藝を代表する陶器の窯元である。
その日の気分によって違って見える建築をつくれないかと考えはじめるきっかけは、この毎朝のコーヒーカップ選び、
そして、民藝は、以前話題にしたブリコラージュにもつながる。はじめと終わりが見事につながり、新たに民藝に興味が湧いた。
今、民藝品を見ようとするならば、まずは駒場にある日本民藝館に行くが、ガラスケースに入った民藝品は美術品のようで、なんかしっくりとこない。
日本民藝館で前に、あまりにも形と大きさが秀逸だったので、銅製の玉子焼き器を購入したことがあるが、それはいわゆる民藝品の域を超えた、しかし、美術品では無く実用品としての美しさがあった。
今、民藝に可能性を感じるのは、そもそも当たり前のことかもしれないけれど、まだまだ掘り下げる余地があることがわかった。
"I feel new possibilities in folk art"
In order to create room for projecting the mood of that person, we made a little geometric order, hands, unconsciously, even if we do not know how to make it a folk artistic way.
Every morning, it is the daily routine to grind coffee from the beans and chose a coffee cup for the day 's mood.
The trigger was that you got multiple coffee cups of Genju Nakai kiln and Izuno kiln that Mr. Yanagi directed. Even though it is a cup with different colors and shapes, even in the same color and shape, it is slightly different in size and slight difference in color that comes from the difference in riding glaze, putting your own mood on the day, every morning I am picking it while having fun.
And, by chance, this Nazu Nakai kiln and Izune kiln are pottery pottery representing the folk art.
The chance to start thinking about whether you can create a building that looks different by the mood of the day is to choose this morning coffee cup,
And folk art also leads to bricolage which was talked about before. Beginning and end were connected beautifully, and new interests appeared in folk art.
Now, if you are going to see the folk art, I will go to the Japanese art museum in Komaba first, but the items in the glass case are like works of art, they do not come nicely.
Before the Nippon Municipal Hall, the form and size were too excellent, I purchased a copper egg oven, which is beyond the area of so-called folk art, but it is not a work of art There was beauty as a practical item.
Now, feeling the possibility of folk art may be a matter of course in the first place, but I found that there is still room to dig down.
数値以外で表現できる幾何学的な秩序もあり、それはつくり手に委ねられており、つくり手によって微妙にその秩序を変えて、あるいは無意識に変わって、表現することができ、その微妙な違いが見る人にとって気分を投影できる余地になるのかもしれない、とした。
ならば、人によって意図的に数値以外で表現できる幾何学的な秩序ができるならば、様々な可能性が出てくる。
簡単に考えるならば、ちょっとだけ幾何学的な秩序をつくり手がいじれば良い。それは無意識にそうなる方が良いかもしれない。それを違う言い方をすると、民藝的なつくり方か。
前から、民藝にはとても興味がある。好きな陶器の窯元も民藝と関わりがある。
民藝をまた深掘りしたくなってきた。
"Geometric non-ordinary folk art"
There is also a geometric order that can be expressed with values other than numerical values, which is entrusted to the making hands and can be expressed subtlely by changing the order, or unconsciously, expressing it, and its subtle difference It might be a room for the viewer to be able to project the mood.
Then, if you can intentionally create a geometric order that can be represented non-numerically by a person, various possibilities come out.
If you think briefly, you only need to create a little geometric order and tamper with your hands. It may be better to do so unconsciously. Way of saying it differently, how to make it a folk art?
From the front, I am very interested in folk art. The pottery kiln of your choice also has something to do with the folk art.
I want to dig deep into the folk art.
人が意識の中で何か足せる状態が気分を投影できる状態とし、それは、幾何学的な秩序を持った状態では無く、秩序が不完全な所に何か足せる、そこに気分が投影できる。とした。
気分とは実に曖昧なもので、気分で何かをする、気分で何かを選ぶ、気分でどうするかを決める、などと言うと、大抵、あまり良い印象ではなく、何となくいい加減でだらしない印象かもしれず、それは気分というものが曖昧だから、当てにならないから、そういう印象なのかもしれないが、
そういう曖昧で不確かで、何となく泡のような、霧のような、捉えどころがない、形がないものを、建築に取り込み、気分によって違って見える、その人の気分によって捉え方が違う、何か人によって変わる、不変でない空間なり、建築ができたら、それはそれで良いな、と思っていた。20世紀のモダニズム建築は排除していたが。
幾何学的な秩序は数値によってもたらされ、黄金比などが有名だが、数値以外で表現できる幾何学的な秩序もあるのではないだろうか。
先に例を出した大日如来像のお顔も、幾何学的な秩序という観点で捉えれば、古来より受け継がれている形だから、そこには幾何学的な規則性があり、数値ではなく仏師が目で見て受け継いでいる秩序があるだろう。だから、仏師によって同じ大日如来像でも微妙にその秩序を変えて、あるいは無意識に変わって、表現することができる。
その微妙な違いが見る人にとって気分を投影できる余地になるのかもしれない。
"Geometric order other than numbers"
A state where someone can add something in consciousness makes it possible to project a mood, it is not a state with a geometric order but something can be added to an incomplete place, mood can be projected there. Respectively.
Feeling is really ambiguous, you do something in a mood, choose something with a mood, decide what to do with your mood, and so on, mostly it's not a very good impression, but somewhat irresponsible and sloppy maybe something It is not impressive because it is unreliable because mood is ambiguous because it is not it,
It is somewhat different in how to catch something like ambiguous, uncertain, somehow frosty, misty, clueless, unshaped, into the architecture, looking differently depending on the mood of that person I thought that it would be good if the space changed by people, unchanged, and building was possible. Although we were excluding the modernism architecture of the 20th century.
The geometric order is brought about by numerical values, and golden ratios are famous, but there may be geometric order that can be represented by values other than numerical values.
If you grasp the face of the Dainichi Nagisa who gave an example earlier, from the viewpoint of geometric order, it is a form inherited from ancient times, there is geometric regularity, not a numerical value There will be an order that Buddhist teachers inherit and inherit. Therefore, even with the same Dainichi Nagai statue by a Buddhist subtly change its order, or unconsciously change, can express.
That subtle difference may make room for the mood to be projected to the viewer.
その日の気分によって違って見える建築ができるポイントは余地、余白よりも、中庸で何か足せる状態、とした。
建築で意図的に、中庸で何か足せる状態をつくるにはどうすればいいのだろうか。
ただ、何か足せる状態といっても、例えば、茶室のように、茶会の度に、掛け軸やお花などを足すことができるようにすることでは無くて、人が意識の中で何か足せる状態、気分を投影できる状態。
だから、むしろそれは、完璧な秩序を持った状態では無くて、それは、言い換えると、幾何学的な秩序を持った状態では無いのかもしれない。
秩序が不完全な所に何か足せる、そこに気分が投影できる。
20世紀のモダニズム建築は、幾何学的な秩序により、不変を表現し、場所や時間を超越しようと試みた。ただ、その不変が故に気分の入り込む余地が無い。
すなわち、もしかしたら、モダニズム建築は人の曖昧な所を排除する形で成立していたのかもしれない。
"Immutation eliminates ambiguity"
According to the mood of the day, the point at which building that can be seen differently is roomable, more moderate than the margin, and a state where anything can be added.
How can we make a condition that can be added intentionally, moderately in architecture?
However, even if it is said that some state can be added, for example, it is not like to be able to add hanging scrolls and flowers, etc. every time a tea ceremony, like a tea room, so that people can add something in consciousness A state where mood can be projected.
So, rather, it is not in a state with a perfect order, in other words, it may not be in a state with a geometric order.
Add something to the place where order is incomplete, you can project mood there.
The modernism architecture of the 20th century tried to express invariance and transcend place and time by geometric order. However, because of that immutability there is no room for mood to enter.
In other words, it may be that modernism architecture was established in the form of eliminating ambiguous places of people.
その物自体は動かないけれど、そこに気分を投影できる余白があれば、その日の気分によって違って見える建築ができるかもしれない、とし、その例として、奈良の大仏の大日如来像のお顔をあげた。
気分を投影できる余白があるとは、そのもの自体は完全で不変なものでは無く、空きがあるというか、何か足りないというか、物足りないくらいなのかもしれない。
何か足りない、だから、そこに自分で何か足すことができる、自分で勝手に何か足してしまう。
大日如来像のお顔も、何か足す余地があるということか、確かに、はっきりしない顔立ち、とても魅力的な顔立ちで、ずっと見ていても飽きないのだが、喜怒哀楽がはっきりしない中庸な顔立ち、あとちょっとそこに何かを足せば、例えば、目じりの角度が変わる、目が大きくなる、口角の角度が変わるなど、あとほんのちょっと変われば、その差は本当に微妙で変化がわからない位かもしれないが、喜怒哀楽が現れてくるような気がする。
その位微妙ならば、見ようによっては、角度によっても、ちょっとした目の錯覚でも、だから、その日の気分でも、喜怒哀楽がその時々で現れるかもしれない。
ポイントは余地、余白よりも、中庸で何か足せる状態か、それは余地、余白とはちょっと違うような気がする。
建築で意図的に、中庸で何か足せる状態をつくるにはどうすればいいのだろうか。
"Because it is moderate"
Although the thing itself does not move, if there is a margin where mood can be projected there, it may be possible to make a building that looks different depending on the mood of the day, as an example, the face of the Dainichi Naruha statue of the Buddha of Nara .
To have a margin where the mood can be projected itself is not perfect and immutable, it may be vacant, something missing, it may be unsatisfactory.
Something is missing, so you can add something by yourself, you add something by yourself.
The face of the Dainichi Nagai statue also has room for something, indeed, it is an unclear face, a very attractive face, I will not get tired of watching it all the time, but moderate joy and sadness If you add something to it later, for example, if the angle of eyes changes, the eyes get bigger, the angle of the mouth corner changes, and only a little change, the difference may be truly subtle and you may not know the change Although it may be, it seems that emotions and pleasures are coming up.
If it is subtle, it may appear depending on the angle, even with a slight eye illusion, so even for that day's mood, emotions and pleasures may appear at that time.
The point seems to be slightly different from the margin, the margin, the state that you can add anything with moderate, it is room and the margin.
How can we make a condition that can be added intentionally, moderately in architecture?
建築自体が、建築そのものが動かないのだけれども、その日の気分によって違って見えるように、以前に「気分に追従する建築」としたが、それは動かない建築を扱って、気分を持ち込む考え方を示し、その時は「差異」を用いて「気分に追従する建築」を実現しようとした。
仏像のお顔が、例えば、奈良の大仏の大日如来像のお顔が、見る側のこちらの気分というか、気の持ちようで、笑って見えたり、怒って見えたり、哀しそうに見えたりする。
当然、大仏のお顔が変化する訳では無く、見る側の受け取りようなのだが、こちらの気分をお顔に投影しているようなことかもしれない。
大日如来像のお顔がはっきりと喜怒哀楽を表情で出していないからで、中庸というか、喜怒哀楽のどのようにでも見て取れるお顔をしている。不動明王像のお顔の表情が明らかに怒っているように見えるのとは、ある意味対称的かもしれない。
自分の気分を投影できるということは、投影できる余地があるということで、お顔が中庸的な顔立ちをしているから、例えば、楽しそうなお顔をしているな、と思ってしまうと、大日如来像のお顔が段々と笑っているように見えてくるのかもしれない。
その物自体は動かないけれど、そこに気分を投影できる余地というか、余白があれば、その日の気分によって違って見える建築ができるかもしれないが、その余地、余白をつくるのは案外むずかしいことのような気が今はする。
"Margin to project mood"
As for the building itself, although the construction itself does not move, although it was said to be "a building that follows the mood" beforehand so that it can be seen differently according to the mood of the day, it deals with the architecture that does not move and shows the way to bring mood , At that time it tried to realize "architecture that follows the mood" using "difference".
The face of the statue of Buddha, for example, the face of the Dainichi Nagami statue of the Buddha of Nara is like the viewer's mood, I feel like having a feeling, it looks laughing, it looks angry, it looks sad I do.
Of course, the face of Big Buddha does not change, it seems to be the reception side of the viewer, but it may be like projecting this mood on your face.
Because the face of the Dainichi Nagai statue clearly expresses emotions and emotions with expression, we have a face that can be seen anything by moderate or emotional pleasure. It may be symmetrical in some ways that the face expression of Fudo statue seems to be clearly angry.
To be able to project your mood means that there is room for projection and your face has a moderate face so if you think that you have a fun looking face, Perhaps it seems that the face of Dainichi Nairi statue seems to be smiling one after another.
Although the thing itself does not move, if there is room to be able to project the mood there, if there is a margin, it may be possible to build a building that looks different depending on the mood of the day, but it is unexpectedly difficult to make room and margins I feel like I am now.
気分は7割の方、決してクライアントを感動させるためのものでは無くて、建築が建築らしく、建築の持つポテンシャルを最大限に引き出すための建築性の部分だから、とした。
その日の気分によって居場所を選ぶことができるようにする、その日の気分によって窓の開閉を変える、その日の気分によって可動間仕切りの位置を変えてみるなど、居場所を選ぶは、例えば、朝食を食べる場所を気分によって外のテラスにする、などがすぐに思いつく。
気分を持ち込む場合、その物が容易に、移動できたり、変化できたり、気分によってその物が何か変わる必要がある。
だから、建築自体は容易には移動できないので、変化する部分をたくさんつくって、建築が実体、変化が属性、例化として変化する部分、となるのか、その日の気分の変化に対応するのがよくあるやり方で一般的だろう。
それも良いが、それだと建築は単なる装置化するだけで、建売によく見られるが、それは建築が持つポテンシャルのごく一部しか示せてないよいな気がして、つまらないし、勿体ない。
建築自体が、建築そのものが動かないのだけれども、その日の気分によって違って見えるようにしたい。
以前に「気分に追従する建築」としたが、それは動かない建築を扱って、気分を持ち込む考え方を示したが、今一歩進めて考えてみたい。
"Building is not a device"
70% of people, never to impress the client never, the architecture seems to be architectural, so it is part of the architectural nature to bring out the potential of the construction to the maximum.
Choose whereabouts by choosing whereabouts according to the mood of the day, changing the opening and closing of windows according to the mood of the day, try changing the position of the movable partition by the mood of the day, for example, You will come up with a terrace on the outside by mood, and soon.
When bringing in a mood, it is necessary for the thing to be easily moved, changeable, or something change depending on the mood.
So, because the building itself can not move easily, it is better to correspond to changes in the mood of the day, whether buildings change, entities change, property changes, instantiation, etc. by creating lots of changes It will be general in some way.
It is good, but it is common for equipment to be built simply because it is a device, but it seems good to show only a small part of the potential possessed by the building, it is boring, it is objectionable.
Although the building itself, the building itself does not move, I want to make it look different by the mood of the day.
It used to be "a building that follows the mood" before, but it handled the architecture that does not move and showed a way of bringing the mood, but I would like to think forward one step further.
理屈っぽい建築性のみでなく、建築として成立させるには、7割を建築性に、3割をクライアントが感動することに費やす、名建築を見てきた結論の割合が7:3である、とした。
では、気分はどちらに入るのだろうか。使う人、見る人のその日の気分で建築が違って見えたり、使い方が変われば、より人と建築が交わり合う、というか融合するというか。
人と建築が相対する関係性は、建築を商品として消費する対象と見た場合にそうなるような気がして、それは悪い訳ではなく、商業建築ではそれは当たり前のことで、日々、我々もその恩恵に預かっているが、
例えば、終の住処であれば、そのような、人と建築が相対する関係性では、せっかく、そこでの生活を心行くまで楽しもうとしているのに、相対する関係性は建築を箱物と見なしているのと同じで、ただ建築に携わっていない人はそれが当たり前だと思っているかもしれませんが、建築に携わっている人は、人と建築の関係性はそれだけでは無いと知っているので、もっと建築を日々の生活の中に溶け込ますには、気分を持ち込むのが良いだろうと考えている。
そうすれば、建築が人の暮らしや生活に密着するような、追従するような、決して箱物では無い、雨露をしのぐだけのものでは無い、人にとってなくてはならないものになるような気が、とりあえずする。
だから、気分は7割の方、決してクライアントを感動させるためのものでは無くて、建築が建築らしく、建築の持つポテンシャルを最大限に引き出すための建築性の部分だから。
"Feeling is architectural"
In addition to the reasonable building property, the ratio of the conclusion that we saw the name architecture, which accounts for 70% for building ability, 30% for the client's impression, to be established as construction, was 7: 3 .
Then, which mood goes into? If the people who use it and the viewers feel like that day, if the architecture looks different, if the way of use changes, more people and architecture will get together or will it merge?
It seems that it seems that it will happen when you look at the relationship between people and architecture as objects to be consumed as a product, which is not a bad translation, it is commonplace in commercial construction, I am keeping with that benefit,
For example, if it is the last residence, such a relationship between people and architecture is trying to enjoy the life there as far as it is concerned, but the relative relationship is to consider architecture as a box object People who are not engaged in architecture may think that it is natural, but the person engaged in architecture knows that the relationship between people and architecture is not the only one So I think that it would be better to bring in a mood to blend more buildings into our daily lives.
Doing so would make architecture more closely related to people's lives and lives, to follow up, never to be box objects, not just to overcome rain exposure, to feel like becoming indispensable to people , I tentatively decide.
So, the mood is 70%, it is not a thing to impress the client never, the architecture seems to be architectural, it is a part of the architectural nature to maximize the potential of the building.
属性を一般的なものとするならば、属性が同じであれば、実体は例化として等価になり、ヒエラルキーが無くなるのではないか、という問いは面白く、表面の感触のみを属性として扱えば良いので、理論上はそれで、内外のヒエラルキーが無くなり、内外の境目がオープンになれば、全てが等価に扱えて、内外で空間の切れ目が無い連続したオープンスペースができるかもしれない、とした。
感触が直に空間を、感触でしかつくることができない空間ができるかもしれない。
さらに、そこに異なるアクティビティーを重ね合わせることができれば、その接点にパーソナルスペースをつくることができるだろう。
異なるアクティビティーは、敷地のコンテクスト/文脈から導き出せばよい。
そこにさらに、他のコンテクストも重ね合わせる。
ただ、このままでは理屈っぽい建築性のみになってしまい、実際に建つ建築としては成り立たないので、3割をクライアントが感動してもらうことに使い、喜ばせたい。
7割を建築性に、3割を感動に、3割は少ないと思われるかもしれないが、建築性に7割を使わないと、この3割を感動に生かせない、使えないと思っている。たくさん名建築を見てきた私なりの結論の割合が7:3である。
"Percentage of Building Property"
If the attribute is general, if the attributes are the same, the entity becomes equivalent as an example, the question of whether the hierarchy disappears is interesting, it is only necessary to treat only the feel of the surface as an attribute So, in theory, it was said that if internal and external hierarchy disappeared and the boundaries of the inside and outside were open, everything could be handled equally, and a continuous open space with no space breaks in and out could be made.
It may be possible to create a space where the feeling can be made with space, touch.
Furthermore, if you can overlay different activities there, you will be able to create a personal space at that point of contact.
Different activities can be derived from the context / context of the site.
Furthermore, another context is superimposed.
However, as it is, as it is only the reasonable building property, it will not be realized as a building to be built, so we want to please 30% to use the client to impress.
Although 70% may be thought to be less building, 30% being impressed, 30% is less, but if we do not use 70% for building property, I think that this 30% can not be used impressed, can not be used . The ratio of my conclusion that I have seen many names architecture is 7: 3.
建築における全ての実体にあり得る属性として感触に焦点を当てる、例えば、全てふわふわという感触でつくれば、建築という入れ物があって、その中身のインテリア、というようなヒエラルキーが無いものが出来上がる、とした。
ただ、ちょっと哲学すぎるし、実際問題、同じ感触で建築や家具、ソファや椅子、テーブル、ベッド、食器などができるか、できないこともないか。
属性を一般的なものとするならば、属性が同じならば、実体は例化として等価になり、ヒエラルキーが無くなるのではないか、という問いは面白い。
鉄筋コンクリートの打放しで内外をつくり、インテリアも鉄筋コンクリートの打放しにすれば、内外のヒエラルキーは無くなるが、そのようなことができる素材は、構造体にできる素材は、鉄筋コンクリートしか無く、あと鉄板もあるが、それはすでに行われている。
属性を例えば、色で、グレーとすれば、内外をグレーにすれば、実体として内外を等価にできて、ヒエラルキーが無くなるという解釈もある。
表面の仕上げのみを属性として扱えば良いので、この考え方は応用が効くだろう。
それで、内外のヒエラルキーが無くなり、内外の境目がオープンになれば、全てが等価に扱えて、内外で空間の切れ目が無い連続したオープンスペースができるかもしれない。それがオープンなパーソナルスペースだと尚面白い。
"Possibility of attributes"
Focusing on the feel as a possible attribute for all entities in the construction, for example, if it is all made with the feeling of fluffy, it is said that there is a container called architecture and there is no hierarchy such as interior of the contents .
However, it is a little philosophy, and it is not possible to make buildings and furniture, a sofa and a chair, a table, a bed, dishes etc, with the same problem with the actual problem, is not it possible?
If attributes are general, if the attributes are the same, the entity becomes equivalent as an example, and the question of whether the hierarchy disappears is interesting.
If inside and outside are made by the release of the reinforced concrete and the interior is made to release reinforced concrete, the hierarchy inside and outside will be gone but the material that can do such things is only the reinforced concrete, there are also iron plates, It has already been done.
For example, if the attribute is gray, for example, if the inside and outside are made gray, there is interpretation that the hierarchy disappears as the entity can be made equivalent to inside and outside as an entity.
Since it suffices to treat only the finish of the surface as an attribute, this way of thinking will be effective.
So, if the internal and external hierarchy disappears and the boundary between the inside and the outside becomes open, everything can be handled equally, and a continuous open space with no break in the space may be made inside and outside. It is still interesting that it is an open personal space.
建築で感触に焦点を当てると、直に人が触るというアクティビティーが発生し、空間構成に何らかの影響を与える可能性がある、とした。
別の見方で、建築という実体があり、感触はその属性という考え方もある。
属性が一般的なものであるとしたならば、属性としての感触の例化として、建築がある訳で、そうすると、属性として同じ感触ならば、家具、ソファや椅子、テーブル、ベッド、食器など、建築の中にある全てのものが、建築と同じ感触という属性の例化になる。
すなわち、感触そのものに焦点を当てることにより、家具、ソファや椅子、テーブル、ベッド、食器なども建築と並列に等価に実体として扱える、ということ。
それは面白いと思う。もっと徹底させるために、例えば、全てふわふわという感触で、建築も家具、ソファや椅子、テーブル、ベッド、食器などを仕立てたならば、全てが実体として同じに、並列に、等価に扱えて、例えば、建築という入れ物があって、その中身のインテリア、というようなヒエラルキーが無いものが出来上がる。それは、ちょっと何か可能性を感じてしまう。
それができるのも、建築における全ての実体にあり得る属性として感触に焦点を当てるからだろう。
"Feeling as an attribute"
Focusing on the feeling in architecture, it was said that there was the possibility that some activity would be exerted on the space composition due to the direct activity of people touching.
In another way, there is the entity of architecture, the feeling has its idea of its attribute.
Assuming that the attribute is general, there is architecture as an example of the feeling as an attribute, so if it has the same feeling as an attribute, it will be useful for furniture, sofa, chair, table, bed, Everything in the building is an example of the attribute of the same feel as construction.
In other words, by focusing on the feeling itself, furniture, sofas and chairs, tables, beds, tableware and the like can be treated equivalently in parallel with buildings as entities.
I think that is interesting. In order to make thoroughly more, for example, if it is all feeling fluffy, building also furniture, sofa and chair, table, bed, dishes etc, if everything is tailored, everything can be handled equally in parallel, equivalently, as entities There is a container called architecture, and there is no hierarchy like interior of its contents, but it is completed. It feels a bit of a possibility.
It can be done because it will focus on the feel as an attribute that can be found in all entities in architecture.
建築も新築当初は視覚が優位で、段々と生活をして慣れてくると感触優位になるのではないか、ならば、感触を第一に考えて建築をつくっても破綻したり、企画倒れしたり、独りよがりや建築家のエゴにはならないだろう。
建築で実際に触る場所は案外限られている。大まかに言えば、水回り以外は、床とドアノブくらいだ。家具が、ソファや椅子、テーブル、ベッドなどが、家の中で一番触るかもしれないが、家具は建築の範疇には入らない、造り付けの家具は別だが。
だから、建築の中で感触を味わえるものは、家具、食器、洋服など、ほとんどが建築の一般的な範疇では無い。
ただ、建築だって、そのもの自体には感触は存在するので、まるで写真を見るように、感触を無視することは本来できないはずである。
例えば、壁は、その仕上げにどのような素材を使うかによって、触った時の感触が全然違うし、それによって見た目の壁の質感も違う。ザラついた感触とサラッとした感触では光の反射が違うから、壁が違って見える。そういう尺度で壁の仕上げを扱ってきたが、感触そのものをはじめから扱うことはして来なかったし、その必要も無かった。
もしかしたら、感触に焦点を当てると、今までとは違う空間構成を思いつくかもしれない。
なぜならば、当たり前だが、感触を味わうには、直に人が触らないといけないし、それは新たにアクティビティーが発生することで、アクティビティーは空間構成に何らかの影響を与える可能性があるから。
"Feeling affects space composition"
Early in the construction of the newly built building, if vision is dominant at the beginning, it will become advantageous feeling when you get accustomed to living one by one, then, even if building a building with the feel first, failure or planning collapse I will not be alone or architect's ego.
The place to actually touch buildings is unexpectedly limited. Roughly speaking, except about the water, it's about the floor and the door knob. Furniture, sofas, chairs, tables, beds, etc. may touch the most in the house, but furniture does not fall within the category of building, but built furniture is different.
Therefore, most of the buildings, such as furniture, dishes, and clothes, which can be felt in the building feeling are not the general categories of architecture.
However, even buildings themselves have a feeling, as it looks like a picture, neglecting the feeling should not be possible.
For example, depending on the material used for the finishing, the feeling when touching is totally different, the appearance of the texture of the wall is also different. Because the reflection of light is different in the touch feeling and the smooth feeling, the wall looks different. I have dealt with the finishing of the wall on such a scale, but I did not handle the feeling itself from the beginning, and that was not necessary either.
Perhaps if you focus on the feel, you may come up with a different spatial configuration.
Because it is commonplace, in order to taste the feeling, it is necessary for people to touch it directly, because the activity may have some influence on the space composition as new activities occur.
今一番興味がある感触は人肌なので、これを建築で実現できるといい。
もし、人肌の感触で建築ができるならば、人が直に触れる所が、例えば、床の感触が人肌だったら、ちょっと暖かくて、素足で歩いたら気持ち良さそうだし、人に触れているようで、赤ん坊がお母さんに抱っこされていると安心するような、心の安らぎみたいなものが、それだけで、床の上を歩くだけで得られたら、ちょっと素晴らしいかもしれない。
感触は直に心を揺さぶることができるから、もしかしたら、視覚で得る情報より、量では敵わないが、質というか、深く心に浸透する情報を与えることができるかもしれない。
建築やデザインは実存するものを相手にするから、どうしてもまず視覚に左右されてしまうが、実際に生活や使用していくと、視覚より感触の方が影響を与えるようになる気が、いつも毎朝コーヒーを飲む時に思う。
毎朝コーヒーカップを選ぶ時に最初使いはじめは、気分で見た目を思うが、何回も使っていると、手に持った時の感触や唇に押し当てた時の感触をパッと思い出す。
建築も新築当初は視覚が優位で、段々と生活をして慣れてくると感触優位になるのではないかと考えてしまう。
"From vision to feel"
The most interesting feeling now is human skin, so I hope that this can be realized in architecture.
If the building can be built with the feel of the human skin, if the place where the person touches directly, for example, the feel of the floor is human skin, it is slightly warm, it will be comfortable when walking with bare feet, and it is touching the person It seems a bit wonderful if you can get it just by walking on the floor, just like that which seems to be a peace of mind that seems to be relieved when the baby is hugged in your mother.
Since feeling can shake your heart directly, perhaps it may be able to give information that infiltrates deeply into the mind, although it is not enemy by quantity, but quality, rather than information obtained visually.
Since architecture and design are opposed to existing ones, they are inevitably influenced by vision, but the feeling that feeling comes to influence more than the visual sense, whenever they actually use their lives or use, always change every morning I think when I drink coffee.
Every morning when choosing a cup of coffee the first thing to use is thought of in appearance, but when I use it many times, I remember feeling when I was holding it in my hand and the feeling when I pressed it against my lip.
At the beginning of building a new building, vision is dominant, and I think that it will become a feeling advantage when coming to life by gradually getting used.
どのような感触が欲しいかを考えて、決めれば、それに適応した機能や空間ができるかもしれないとして、感触を考えてみる。
先に出した例は、ふわふわ。
今制作中の輪島塗のフリーカップは人肌の感触を出そうとして、漆塗を石目乾漆で人肌の感触に近づけようと職人の方にお願いして、見本塗を制作中である。
だから、今一番興味がある感触は人肌なので、これを建築でも実現できるといい。
乾漆とは、乾いた粉状の漆を漆塗の上に振り掛けて仕上げる技法で、ちょっとざらついた感触になるが、石目乾漆はさらに、たぶん、乾いた粉状の漆の振り掛ける量をもっと増やして、不均一にし、さらに乾いた粉状の漆が載ったところを平らに均していく。そうすると、乾いた粉状の漆が載った所が島状になり、載っていない所が筋状になり、ちょうど肌の表面を拡大して見た時と同じような仕上げになる。これで石目乾漆の表面を触ると人肌の感触になるはずだろうという憶測で、今、見本を制作中。
ただ、石目乾漆の仕上げは、建築で言えば、吹付けタイルの仕上げに似ているような気がするし、もっと言えば、コンクリートに細かく砕いた大理石などを混ぜて、不均一に吹付けて、コテで均せば、できそうな気がするし、さらに、もっと言えば、コンクリート打放しの表面の仕上げを、型枠の仕上げ面を工夫するのか、型枠を脱型した後に手を加えるのかはわからないが、人肌の感触にすることももしかしたら可能かもしれない。そうしたら、構造体として使えるから、人肌の感触だけで建築ができるかもしれない。ただし、コンクリート打放しの表面の仕上げの技法を新たに考える必要はあるだろうが。
"Building on the feel of human skin"
Consider what kind of feeling you want, decide, if you decide, you may think that the function or space adapted to it may be made and think about the feel.
The example given earlier is fluffy.
A free cup of Wajima coat under construction now is preparing a sample painting, asking the craftsman to bring the lacquer coat closer to the human skin feeling with the stone eye lacquer, in order to bring out the human skin feeling.
So, the most interesting feeling now is human skin, so we hope that this can be realized even in architecture.
Dry lacquer is a technique that finishes dry lacquer lacquer on the lacquer finish, giving a slight gritty feel, but the stone eye lacquer is probably more dry, powdery lacquer sprinkled over more Increase it, make it nonuniform, and flatten the place where dried powdery lacquer was put on. Then, the place where dried powdery lacquer is placed becomes island-like, the place where it is not placed becomes streaky, just like looking at the surface of the skin enlarged. It is speculation now that touching the surface of the stone eye dry lacquer should be a feeling of human skin, I am producing a sample now.
However, the finish of the stone eye lacquer is like the finishing of the spray tile if it says in the construction, more speaking, mixing the finely crushed marble etc. in concrete, spraying non-uniformly Then, if you do it with the iron, you will feel like it will be possible, and more to say, whether finishing the surface of the concrete release is to devise the finished surface of the formwork or after removing the mold I do not know, but maybe it is possible to feel human skin. If you do, you can use it as a structure, so you may be able to build with only the feel of human skin. However, although it will be necessary to newly consider the technique of finishing the concrete release surface.
感触そのものが空間をつくり、機能をつくり出すことはありそうで、例えば、ふわふわな感触、ならば、ふわふわな感触から寝る機能が出てきて、その感触に包まれば空間になり、ベッドルームになりそうな気がした。
で、連想したのは、雪のかまくら、雪の感触そのものが空間になり、機能をつくり出している。
要するに、単一素材のソリッドな物であれば、その感触に応じて機能や空間をつくり出すことが可能かもしれない、とりあえず。
ならば、鉄筋コンクリートが思いつく。そうなると、構造体として使えるので、固いコンクリートの感触そのもので空間と機能をつくり出せる、打放しコンクリートの建築、とよくあるところに納まってしまう。
ソリッドの鉄板のみの建築も、鉄板は構造体として使えるので、鉄板の感触が空間と機能をつくり出すこともあったが、それも納まりの良いことに。
感触が構造という機能を担ってしまうと、実現性が極端に下がるような気がする。感触が構造としての機能まで担うことができれば、それが一番良いが、それが一番大事なことでは無いので、感触が構造という機能まで担うことは、とりあえず、置いておく。
そうすると、まず、どのような感触が欲しいかを考えて、決めれば、それに適応した機能や空間ができるかもしれないとして、感触を考えてみる。
"To determine the feel first"
The feeling itself seems to create a space and create a function, for example, with a fluffy feeling, if the function of sleeping from fluffy feel comes out, if it is wrapped in the feeling, it becomes a space, becomes a bedroom I felt that way.
So, what I associate is that the feeling of snow, the feeling of snow itself becomes space, creating a function.
In short, if it is a solid material of a single material, it may be possible to create a function and space according to its feeling, for the time being.
Then reinforced concrete can come up with. Then, since it can be used as a structure, it fits in a place where it often goes to the construction of an outgoing concrete, which can create space and function with the feel of a hard concrete itself.
Because the steel plate can be used only as a solid iron plate, the steel plate can be used as a structure, the feel of the iron plate sometimes created space and function, but that is also acceptable.
Feeling seems to decrease extremely if feels play a role of structure. If the feel can bear up to the function as a structure, that is the best, but that is not the most important thing, so let's leave that feeling will carry up to the function of the structure for the time being.
Then, first of all, thinking what kind of feeling you want, decide, if you decide, you think that the function and space adapted to it may be made, and think about the feel.
感触そのものが空間をつくり、機能をつくり出すことはあるのか。建築は空間と機能だけでできている訳では無いが、空間とは、空間はどのようになったら、空間になるのだろうか。床壁天井で囲われれば空間か。
例えば、ふわふわな感触の大きなものがあるとして、それで包まれて、中に入ることができたならば、ベッドルームになるかもしれない。ふわふわな感触だから、寝るという機能には適するのではと思い、それで包まれていれば、ベッドルームになるかもしれないという考え方。
この一例だけでも、感触から機能がつくり出せる、生まれことはありそうで、その感触に包まれれば空間にはなる。
これを展開や応用していけば、建築として成り立つ可能性もありそうな気はするが、いかがなものだろうか。
"Feeling from function to function and space"
Is the feeling itself creating a space and creating a function? Architecture is not only made up of space and function, but what does space mean when space becomes space? Floor wall Is it a space if surrounded by the ceiling?
For example, if there is a big fluffy feeling, if it could be wrapped in it and go inside it might be a bedroom. Because it is fluffy feeling, thinking that it is suitable for the function of sleeping, thinking that it may become a bedroom if wrapped with it.
Even with this example alone, it is likely that a function can be created from feel, birth is likely to occur, and if it is wrapped in the feeling it becomes a space.
I think that there is a possibility that it may be established as architecture if it develops and applies it, but what is it like?
感触を主題にしたら、テーブルウェアのデザインにも、建築にも、まだ見ぬ地平があるような気がする、としたが、やはり、機能とか、諸条件に引きづられる。
ただ、それは感触を仕上げの話と捉えているから、その前に、そのテーブルウェアにしろ、建築にしろ、成立させるための諸条件や機能や要求があるだろうと、段階的に考えてしまうからで、そのようなもののつくり方をしてきたし、そう刷り込まれているからで、ちょっと思考の順序を組み替えてみれば、それこそ違う地平が見えないかな。
以前に、建築に感触を取り込もうとした時に、見立ての手法を使う、とした。それは触ること無しに、感触をイメージさせるには、頭の中で見る人が素材感を構築してもらう必要があり、その時に見立てが持つ不完全性が感触を意識的によりイメージさせることになると考えた。
ただ、これとて、感触が仕上げの域を脱していないような気がする。
感触そのものが空間をつくり、機能をつくり出すことはないのだろうか。
"Do you feel that you can create space?"
If the theme is feeling, it seems that there is still unseen horizon both in the design of tableware and in architecture, but again, it is attracted to functions and conditions.
However, since it perceives the feel as a finishing story, before that, before that, we think that there will be various conditions, functions, and demands for establishment, whether it is tableware or construction, because it thinks step by step So, I've been working on how to make things like that, so it is being imprinted, so if I rearrange the order of thinking, I can not see a different horizon.
Previously, when trying to incorporate the feeling into architecture, he said that he used a method of interpretation. Without touching, in order to make the image feel, it is necessary for the viewer in the head to build a texture of the texture, and at that time imperfections of the view will cause the feeling to be consciously imaged Thought.
However, it seems that feeling does not get out of the area of finishing with this.
Will not the feeling itself create a space and create a function?
ずっと感触のことを考えている。
感触がデザインの一部ならば、触らないと良し悪しがわからないが、実物が目の前に無ければ、どうしようもない。
20世紀の建築家は自分の作品を世界中に広めるために、写真のワンカットを大事にして、神経を注いだ、今のようなネットが無い時代では、手段は写真しかなかったから。
だから、極端に言えば、その頃の建築のデザインは写真映えするにはどうしたら良いかが暗黙の命題でもあったし、写真で事足りた。実際に触らないとわからないことは排除されていたし、その頃のモダニズム建築にはそれで都合が良かった。
物事は何でも反動、すなわち、現状とは反対の方向へ流れていくもので、モダニズム建築が排除していた感触や実際に触らないとわからないことが主題にもなっていく。
ただ、写真がネットや動画配信、SNSに置き換わったとは言え、相変わらず、実物に触ることができないことには変わりが無いので、感触を直に伝える手段は実物に触るしかない。当たり前のことだが、これが物とか建築とかのデザインを大枠で規定してしまっているように思う。
昨日見たテーブルウェアのコンテストでも、中には仕上げの質感をデザインの一部として、デザインの副産物的に、二次的に扱っているものもあったが、質感や感触そのものをデザインの主要素にしているものは無かった、伝えるのが難しいし、それはコンテスト向きでは無いからだろうが、展示に触らずに確かめようが無いが、感触を主題にしたら、テーブルウェアのデザインにも、建築にも、まだ見ぬ地平があるような気がするのは私だけだろうか。
"Fundamentals of design"
I'm thinking about feeling all the time.
If the feel is part of the design, I do not know if I do not touch, but if the real thing is not in front of me, I can not help it.
Architects of the 20th century cherished the one-cut of the photographs, spread the nerve to spread their work all over the world, because in the era when there is no net like the present there was only a means.
So, to put it in extreme, it was an implicit proposition as to how to design the architecture of that time to photograph, and it was enough with pictures. What I did not know without actually touching was excluded, and it was convenient for that modernism architecture at that time.
Everything is recoiled, that is, it flows in the direction opposite to the present situation, so that the feeling that Modernism architecture had eliminated and the fact that you do not know without actually touching will become the subject.
However, although photos are replaced with net, movie distribution, SNS, there is no difference that things can not be touched as usual, so the only means to communicate the feeling is to touch the real thing. As a matter of course, I think that this has largely stipulated the design of objects and architecture.
Even in the tableware contest I saw yesterday, some of the designs handled the finish texture as part of the design, as a byproduct of design, secondarily, but the texture and the feeling themselves were chosen as the main elements of the design There was nothing to do, it is difficult to tell, because it is not for the contest, it can not be confirmed without touching the exhibition, but if the theme is feeling, tableware design, architecture as well Is it only me that feels like there are still unseen horizons?
道路の隅切りが面白く見えた。道路の隅切りをミラー反転させて建築の形状とすると、もしかしたら、隅切りが隅切りのように見えなくて、建築の一部に見えるかもしれない。
交通の安全のことを考えれば、当然、道路の隅切りが必要だ。交差点で見通しが悪いと事故につながるから、その点では必ずあった方が良い。
しかし、街並みの美観を考えると、道路の隅切りほど醜いものは無い。道の雰囲気を台無しにしてくれる。街並みや道の連続性を隅切りは分断する。だから、本当は道幅を広くして、隅切りを無くすことができればいいのだが、そうもいかない。
ふと、スケッチをしていて、隅切りの斜めが違って見えて、ミラー反転して建築になれば、隅切りも面白いかもしれない、道なんだか、建築なんだか、どっちつかずになり、隅切りが街並みや道を分断するどころか、街並みと道と建築を調和させはじめた。結構良いかもしれない。
"Corner cutting is ugly"
The corner cutting of the road looked interesting. If the corner cutting of the road is mirror reversed to the shape of the building, perhaps the corner cutting may not look like a corner cut and may look like a part of the building.
Given the safety of traffic, obviously it is necessary to cut corners of the road. Since it leads to an accident if the line of sight at the intersection is bad, it is better to have it always at that point.
However, considering the aesthetic appearance of the cityscape, there is nothing ugly as a corner cut of the road. It ruins the atmosphere of the road. Cut corners cutting the continuity of the cityscape and the road. So, in fact, it would be nice if we could widen the road width and eliminate corner cutting, but it does not work.
Suddenly, sketching, looking diagonally in the corner cut, if the mirror reverses and becomes the architecture, the corner cutting may be interesting, the road, it is not like anything, the corner cut becomes Far from dividing the cityscape and the road, I began to harmonize the cityscape with the roads and the architecture. It may be quite good.
ちょっと気になる言葉がある「建築性」。それが建築たる所以みたいなものと捉えているが、ついその「建築性」が疎かになってしまうような気がする。
おかしな話だが、建築性が無くても建築は成り立つ。極端に言えば、機能を満たし、法規を守れば、建築はできてしまう、そのような建築がほとんどだ。
例えば、建築性とは「不完全性とアクティビティー」「気分と感触」がいま、あるのではないかと考えている。
無くても良いとは思えず、あった方が良いの当たり前のことと捉えている、それが人にとって。
この建築性を磨き、建築として実存させることにいま一番時間を割いている。
"Time now"
There is a word which is a bit a little "Building property". It seems that it is like the thing that it is built, but it seems that its "architecturality" becomes unclear.
Although it is a funny story, building is established even if there is no building ability. In extreme terms, buildings can be built if they satisfy the function and keeping the regulations, such constructions are mostly.
For example, I believe that "building imperfections" have "imperfections and activities", "moods and feelings", and so on.
I do not think that it is not necessary, and I think that there was better being a good one, that is for people.
I am taking the most time to refine this architectural nature and make it exist as a building.
ボリュームチェックをする。それはその敷地にどのくらいの規模のものが建築できるのかを確認するためだが、同時にそれは集合住宅の場合、最大戸数を確認する、収支計画を立案する、ための元資料にもなる。
昔いた設計事務所では、もう25年くらい前の話だが、不動産屋から敷地図がfaxで送られてくると、社長がボリュームチェックをして、その敷地に対する計画案を作成し、それは収支計画用の計画案なので、最大戸数を確保したものをまた送り返していた。
その場合、建築基準法や条例などを法規を満たすのは当たり前のことだが、とにかく知りたい情報はその敷地にどれだけの規模の、戸数の集合住宅ができるか、だったので、デザインは二の次、付け足すもの扱いで、とりあえず、平面図だけあればよく、それで収支計画が立案できるので、実際に計画がスタートして外観を考える時にデザインが入ってくるようだった。
そのデザインや計画案作成の態度にはなじめず、でも大概の設計事務所はそうなのだろうと想像しながら、私が設計担当した最初の建築は、その社長が作成した計画案からはじまった集合住宅だった。だから、私が担当としてデザインできる範疇は外観くらいしかなく、それはそれで重要なのだが、プランから考えなければ、外観だけ考えても意味は無いのでは、と思いながら仕事をしていたのを思い出した。
なぜ思い出したかというと、今、そうだから、とりあえず、収支計画用の最大戸数を確保した計画案を作成し、これからどう進めていくかと考えているところだから。
ただ違うのは、この計画案はあくまでも収支計画用で、ボリュームチェック用で、アタリの図面で、ここから全く違うものをはじめからデザインしはじめる。
ところが、この計画案が結構強力で、引きづられてしまう、自分で作成したのだが、厄介なしろものだ。
"Volume check"
Perform volume check. It is to confirm how much can be built on the premises, but at the same time it is also the original source for planning the income and expenditure plan to confirm the maximum number of houses in the case of multi-family houses.
In the former design office, about 25 years ago, when the real estate agent sent the site map at fax, the president made a volume check and created a plan for the site, which is a balance plan It was a plan for use, so I sent back the one that secured the maximum number.
In that case, it is natural to satisfy the Building Standards Law and ordinances etc, but since the information that you want to know is just how large, multi-united housing can be built on the premises, design is secondary, It is treated as a thing to add, in the meantime, it is only necessary to have a plan view, so you can plan the income and expenditure plan, so it seems that the design will come in when you plan the actual planning and consider the appearance.
While imagining the design and the planning draft attitude, but imagining that most of the design office would be, the first building I was in charge of designing was a collective housing that started with the plan drafted by the president was. So, the category that I can design as a responsible person is only about the appearance, which is important, so I thought that if I did not think about it from the plan, I thought that it was meaningless to think only about the exterior, I remembered that I was working .
I remember why I remember now that I am thinking about how to proceed from now on, because I am planning a plan that secures the maximum number of households for income and expenditure planning.
The only difference is that this plan is for balance planning only, for volume checks, Atari's drawings, beginning to design completely different things from here.
However, this plan was quite powerful and attracted, created by myself, but a troublesome one.
以前に、建築に感触を取り込みために「見立て」を考え、建築に気分を取り込むために「追従する」建築で差異を考えた。いずれも、納得して建築に取り込める手法だと考えていたが、違う角度から再度、感触や気分を建築に取り込む方法を考えてみたいと思った。
そのきっかけは、今制作中の輪島塗のフリーカップ。もの自体が感触と気分を取り込む媒介になるのならば、建築でも可能なのではないか、と思ったから。
建築を空間として扱うから全体のボリュームが最重要になるが、建築を細部のものの集合体として扱えば、まず細部のもの自体がどうあるか、からはじまるので、感触やその時の人の気分を反映しやすく、その感触や気分を伴ったまま、最終的に空間が出来上がるのではないか、と考えた。
人を中心に据えて、人に密着した周辺からはじまり、その時々の人の気分を反映することが可能なものを細部から感触を含めつくり出しながら、どんどん同心円状に広がっていき、空間に仕立てていくイメージ。
イメージがまずできないと、実際のものづくりはできない、全てのイメージでなくても良いが、はじめの取っ掛かりや、大まかで良いから骨子みたいなものは欲しいが、それが段々と揃ってきたような気がする。
"Image to tailor the space"
In the past, I thought about differences in architecture "to follow" in order to capture the mood in buildings, considering "looking" to incorporate the feeling into architecture. Both thought that it was a method that I could consent to incorporate into architecture, but from another angle I wanted to think about a way to incorporate feel and mood into architecture again.
The trigger is a free cup of Wajima coat under construction now. Because I thought that it might be possible in architecture as long as things themselves become intermediaries for taking in feel and mood.
The whole volume becomes the most important because it treats architecture as space, but when treating the building as a collection of details, it first starts from how the detail itself is, so reflects the feel and the mood of the person at that time I thought that it would be easy to do, with the feel and mood accompanied, the space would eventually be finished.
Starting from the periphery that is close to people, starting from the surroundings close to people, reflecting the feeling of the people from time to time, create things including details from the details, spread more and more concentrically and tailor it to the space Some image.
If you can not do an image first, you can not make actual manufacturing, not all images, but I want something like a gist of a first bargain, because it is rough and good, but it seems that it has gotten step by step I will do.
内側からボコボコと必要な場所を広げていく感じで、人を中心に、人の周辺からはじめていくという空間のつくり方があると思う。
今日行ったオープンハウスでの説明によると、2階建ての2階の個室の天井の形を決めて、その形のまま屋根したとのこと。屋根を決めて天井が決めるのでは無くて、室内の天井の形を先にデザインし決めてから、その形の裏返しが屋根の形になる。外から見ると屋根の形で室内の天井の形がわかる。室内の天井をデザインしたら、同時に外観の屋根と室内空間もデザインされる、室内天井をデザインする時は当然、人から派生する事柄を手掛りにするだろうから、そこに人も絡んでくる、とても秀逸だと思った。
ボリュームチェックがあり、そこから細部に向かっていくやり方、ボリュームを決めれば、同時に空間や細部まで決まり、人が絡んでくる手法もあるだろうし、それはそれで素晴らしいと思うが、どうしても人が最後というか、例え最後ではなく途中に人が絡んでくることもあるが、人からはじまる感じが、人の周辺からはじめていく空間のつくり方よりは薄いような気がする。
どうして、人を中心に、人の周辺からはじめていく空間のつくり方が気になるのかと言うと、建築にもっと感触とか、気分とかを取り込みたいから。人を中心に据えてはじめた方がより感触や気分を建築に取り込めるのではないか、という勘からです。
"There are people, I feel, I have a feel"
I think that there is a way to create a space where people start from the periphery of people, with the feeling of spreading the necessary places with Bocoboko from the inside.
According to the explanation in the open house that I went today, I decided the shape of the ceiling of the 2nd floor upstairs private room, and said that he roofed in that shape. It is not to decide the roof and the ceiling to be decided, after designing and determining the shape of the ceiling in the room, the flip of that shape becomes the shape of the roof. When seen from the outside, you can see the shape of the ceiling in the room in the form of a roof. When designing the ceiling in the room, the roof of the exterior and the interior space are also designed at the same time, when designing the indoor ceiling, naturally it will clue the things derived from people, so people will also get involved there I thought it was excellent.
There is a volume check, there is a way that people decide at the same time as much as space and details, if there is a way to go to the details from there, deciding the volume, there is also a method involving people, and that is wonderful, but I guess the person is the last Even though some people are involved on the way instead of the last one, I feel that the feeling that people start with is thinner than the way I start from people's surroundings.
Why do you care about how to create a space to start from people's surroundings, mainly because people want to capture more feel and feelings in architecture. It is from the intuition that people who started putting them mainly can get more feel and mood in building.
以前に、人がいて、体を覆う衣服があり、体を支える椅子があり、食事をするためのテーブルがあり、テーブルの上には人が使う食器やカトラリーがあり、そのテーブルを照らす灯りがあり、そのテーブルや椅子や人を囲むように、床や壁や天井があり空間ができ、それが部屋と呼ばれ、部屋がいくつも連なり、家という建築ができる、ようなつくり方がしてみたい、とした。
たぶん、今の設計に対する違和感は全てここに集約されるような気がする。そう思うと、とてもすっきりとした気分になった。
ただ、果たして、このようなつくり方が現実実際にできるのだろうか。
どうしても、実際に敷地に建築を設計しはじめる時にはボリュームチェックから入る。ボリュームチェックとは、その敷地にかかる法規を調査し、どのくらいの規模まで建築可能かをみること。
ボリューム、イコール、空間では無いが、空間の大枠を決めることから考えはじめてしまうし、そこが無いと最初の事業計画が立案できないだろう。
だから、ボリュームチェックまではして、そこから、人の周辺から広げていくやり方をすれば良いのかもしれないが、その時に結局、最終的にはボリュームチェックの結果に引きづられてしまうような気がして、はじめの一歩が踏み出せないでいる。
"Hajime no Ippo"
There used to be people, there are clothes that cover the body, there is a chair that supports the body, there is a table to eat, there are tableware and cutlery used by people on the table, the light that illuminates the table There is a floor, a wall and a ceiling so that it surrounds the table, the chair, and the person, and a space is made, it is called a room, a number of rooms are connected, we want to try to make such a way that we can build a house did.
Perhaps, I feel that all the discomfort to the current design is concentrated here. I thought so, I felt very refreshing.
But I wonder if we can actually do this in reality.
By all means, when you actually start to design the building on the premises, you enter through the volume check. Volume check is to investigate the laws concerning the premises and see how big it can be built.
Although it is not volume, equal, space, I will start thinking about deciding on the space of space and if there is not there, I can not plan the first business plan.
So it may be good to do a volume check and then spread from people's surroundings, but at the time it will eventually end up with the result of the volume check I feel like I can not take the first steps.
デザインするのが好きで、ものをつくるのが好きだから、それを死ぬまでやり続けたいと、その環境づくりも含めて、今、奔走しているところで、輪島塗のフリーカップづくりは、塗りの見本待ちで、それが楽しみでしょうがなく、ここまで来ると、何をデザインするか、何をつくりたいか、また、どうしたら出来上がるのか、が明確になっているので楽しくて、待ち遠しくて、早くそのカップでコーヒーが飲みたくて仕方がない。
建築ももちろん、ものづくりなのだが、建築と建築以外では同じものづくりでも違うような感覚がある。
端的に言うと、ものそのものをつくるのか、空間をつくるのか、の違いか。建築でも細部に至る時はものそのものに向き合い、ものそのものをつくるが、最初は空間から考えるのが一般的で、大きな入れ物から考えはじめて、段々と中身に何を入れようか、中身のつくりをどうしようかと考えて細部に至る。それはインテリアデザインでも同じだが、建築はそのインテリアデザインをする空間そのものも一から考えるので、より空間をつくる思考が強くなる。
もっと違う言い方をすると、人がデザインされたものを全て操れるのか、人がデザインの一部なのか、の違いか。建築では、空間は人を包み込み、人はその空間の一部という扱いになるが、建築以外では、人から離れたところにものが実存し、そのものを人が全て操るようにデザインされる。
輪島塗のフリーカップづくりをはじめてから、この当たり前のような違いが、とても大きな違いのように感じるようになっており、それは、もしかしたら自分が指向している建築のつくり方は、空間からはじめるのでは無くて、ものそのものからはじめることではないか、とちょっとどこかで思うようになっている。
人がいて、体を覆う衣服があり、体を支える椅子があり、食事をするためのテーブルがあり、テーブルの上には人が使う食器やカトラリーがあり、そのテーブルを照らす灯りがあり、そのテーブルや椅子や人を囲むように、床や壁や天井があり空間ができ、それが部屋と呼ばれ、部屋がいくつも連なり、家という建築ができる、ようなつくり方がしてみたい。
考えてみれば、衣服以外は今すぐにでもつくることができる。
"How to make architecture"
I like to design and I like to make things, so I want to keep doing it until I die, and now I'm busy making the environment, Wajima painted free cup making is waiting for samples of paint So, it can not be helped fun, and as soon as you come this far, it's fun to see what you design, what you want to make, and how to make it, so it's fun, I can hardly wait, in that cup There is no point in wanting to drink coffee.
Not only building but also manufacturing, but there is a different feeling in building the same thing outside of architecture and architecture.
To put it briefly, is it the difference between making things themselves or creating space? Even in architecture, when it reaches the details, it faces the thing itself and makes things themselves, but at first it is common to think from the space, starting with thinking from a big container, what should we put in contents, and how to make contents I think to it and it comes down to details. Although it is the same in interior design, architecture thinks space itself to do its interior design from scratch, so thinking to create more space becomes stronger.
Writing in a different way of speaking, is it different whether people can manipulate everything that was designed or whether people are parts of design. In architecture, space envelops people, treats a person as a part of the space, but outside the building, things are existed far away from people and designed to manipulate them all.
The difference like this is beginning to feel like a very big difference since I started making a free cup of Wajima coat, which is probably how I'm pointing my way of building a building from the space It is not at all, it is supposed to start somewhere somewhere, starting with things themselves.
There are people, there are clothes that cover the body, there is a chair that supports the body, there is a table to eat, there are tableware and cutlery for people to use on the table, there is a light that illuminates the table There is a floor, a wall, a ceiling and surrounding a table, a chair and a person, a space is made, it is called a room, a number of rooms are connected, we want to try to make such a construction that a house can be done.
If I think about it, I can make anything but clothes right now.
建築という目には見えない共通認識があり、それが敷地の文脈/コンテストからくるもの、コンテクチュアリズムにつながるかもしれない、とした。
違うとしたら、何が手掛りになるのか。社会学、哲学、生物学、、、などなど、いろいろと思い浮かぶが、あとは自分が何を、どこを選択するのか、ということかもしれない。
どこを選択するかというのは、自分がどういう建築をつくりたいか。
先日ある方から言われたことがちょっと気にかかっている。
「あなたは、自分が良いというものをつくりたいのか、人が良いと言ってくれるものをつくりたいのか」
その時は「自分が良いと思うものをつくり、それで人が良いと言ってくれたらいいです」と答えが、それはそうなのだが、なぜかスッキリとしない。
もちろん「自分が良くないと思っても、人が良いと言ってくれれば、それでいいです」とは思えないが、
誤解を恐れずに言えば、人が良いと言ってくれるものをつくる自信はあるが、
スッキリしない理由は、自分が良いと思うものが、自分が良いと思うものを疑うことをここ数ヶ月行っているからかもしれない。
"doubt"
There is a common awareness that is invisible to the eyes of architecture and it is said that it may come from the context / contest of the site, leading to contextualism.
If so, what is going to be a clue? Sociology, philosophy, biology, etc, come up with various things, but after that it may be what you choose and where you choose.
Where to choose depends on what kind of architecture you want to create.
What I said from someone the other day is a bit of a concern.
"Do you want to make something good for you, do you want to make something that people say is good?"
At that time, the answer is "I want to make something that I think is good and that people are good" so it seems, but why is not it refreshing.
Of course I do not think that "It is OK if people say that people are good, even though I think that I am not good,
Speaking without fear of misunderstandings, I am confident that people will make something to say good,
The reason for not refreshing may be because what I think is good is going on doubting what I think is good for the last few months.
以前に、カオスの運動自体は、それを引き寄せる建築という目には見えない共通認識みたいなものが無ければ、そこに何も形成しない、とした。
カオスの運動は、人のアクティビティーと見立てることができるだろうから、人のアクティビティーがカオスの形態や構造を形成する訳では無いということ。
もしかしたら、これはカオスの運動の場合だけに限られないかもしれない。
もしかしたら、人のアクティビティーが形態や構造を、建築を形成する訳では無いのかもしれない。
建築計画は人のアクティビティーの完全で安定的な秩序を目指すが、そもそも完全で安定的な人のアクティビティーなど存在しない、個々により微細でも違いはあるはずで、人の振る舞いは人の数だけ種類が存在するはずで、実際には常に人のアクティビティーは不完全で不安定な秩序であり、それを元に建築を構築しようと考えてきたが、そもそも、それが違うかもしれない。
建築という目には見えない共通認識みたいなものに、人のアクティビティーが絡みついてきて、実存の建築の形態や構造が形成されるようなイメージか。
だとしたら、建築という目には見えない共通認識とは、まず第一に、場所に手掛りがあるのか。
そうしたら、それは敷地の文脈/コンテストからくるもの、コンテクチュアリズムにつながるのか。
そうだとしたら、延々と考えてきて、一周して、ほの少しだけ上昇した感じであって欲しいな。
"Contextualism after a round?"
Previously, the movement itself of chaos said that if there was not such thing as common recognition that can not be seen in the eyes of building attracting it, we will not form anything there.
Since the movement of chaos can be regarded as human activity, it means that human activity does not form the form or structure of chaos.
Perhaps this may not be limited to the case of chaos movement.
Perhaps, it may be that human activity does not constitute architecture, form or structure.
Although the architectural plan aims for a complete and stable order of human activities, there is no complete and stable human activity in the first place, there should be a difference even if it is finer than an individual, and the behavior of a person is as many as the number of people In fact, always human activity is incomplete and unstable order, I have thought about building architecture based on that, but in the first place it may be different.
Is it an image that human activities are intertwined with things like common recognition that can not be seen in the eyes of architecture and forms and structures of existential buildings are formed?
If so, is there a common recognition that is invisible to the eyes of architecture, first of all, is there a clue in place?
If so, will it come from the context / contest of the site, leading to contextualism?
If so, I'd like you to consider it all the while and feel it has gone a little just after going around.
建築は単なる物では無くて、秩序という運動の安定性を不安定にしたものの集合体であり、それは不安定な秩序という複数のアクティビティーから形態や構造が成り立っている、と言うこともできるかもしれない。
また、その不安定な複数のアクティビティーは元々個々に違っていて、その不安定で違っている様は、建築があるから認識される、ということも言える。
以前に、現代物理学ではカオスを運動として捉えているとしたが、カオスの形態や構造は、建築のようなカオスの運動を引き寄せたりするものがあってはじめて形成されるのかもしれない。この場合、建築とは、実存としての建築では無くて、その場所で構築する意志みたいな、目には見えない共通認識みたいなものか。
香港の九龍城は、カオスの運動が、あの場所だから、あの形態で現れたのかもしれない。まだ九龍城がある時に見に行ったが、同様のカオスの運動自体は香港中至るところで発生しているはずたが、他の場所では、そこに同様のカオスの形態を形成する建築という目には見えない共通認識みたいなもの、構築する意志みたいなものが無かったから、九龍城のような形態が形成されなかったのだろう。
だから、カオスの運動自体は、それを引き寄せる建築という目には見えない共通認識みたいなものが無ければ、そこに何も形成しないと思う。
そうすると、今度は、その建築という目には見えない共通認識みたいなものとは具体的に何か、と気になる。
"Attracting architecture"
Architecture is not just a thing, it is an assembly of things that instability of the movement of order, which is unstable, it can also be said that forms and structures are formed from multiple activities of unstable order Absent.
Also, the unstable activities are originally different from each other, so it seems that it is different from the instability and it seems to be recognized because of the architecture.
Previously, in modern physics it was thought that chaos was regarded as motion, but the form and structure of chaos may be formed only when there is something attracting chaotic movements like architecture. In this case, the architecture is not an existing building, is it like a willingness to build at that place, like a common recognition that is invisible to the eyes?
In Kowloong Castle of Hong Kong, the movement of chaos is that place, so it may have appeared in that form. Although I went to see it when there was Kowloon Castle, the same chaos movement itself was supposed to have occurred everywhere in Hong Kong, but in other places, in the eyes of architecture which forms similar chaos form there There was no such thing as a common recognition, there was nothing like a will to build, so it seems that the form like Kowloon castle was not formed.
So, the movement itself of chaos does not form anything there unless there is something like common recognition that can not be seen in the eyes of building attracting it.
Then, I will be concerned about what concrete things are like common recognition which can not be seen in the eyes of the building this time.
「カオスとは、力学系の不安定な非周期運動、または、それを含む状態をいう。(中略)カオスは自然の普遍的な運動形態といえる。このようなカオスの特徴は、無限個の不安定な周期軌道が共存し、それらの周期軌道群がカオスの形態と構造を特徴づけていることである。」(「散逸構造とカオス」森肇 蔵本由紀著より)
カオスは、秩序が無く、入り乱れている状態やその形態や構造そのものを指すのだと考えていたが、現代物理学では運動と捉えている。面白いのは、不安定な周期運動の軌道が共存することによって、カオスの形態と構造をつくっていること。
複数の異なる運動が共存し、カオスという形をつくる。形に先立って運動があるのか。
カオスの形、すなわち、秩序も無く、入り乱れている状態をつくり出すのが運動だとするならば、秩序もカオスという運動の一部と捉えることが可能かもしれない。秩序とは安定的な周期運動として。
そもそも建築計画は、この安定的な周期運動を目指すことになる。秩序も運動、すなわち、それはアクティビティーだから、そのように秩序を捉え直すと面白い。
以前、人間にとって理想的な空間を実現するための建築計画と、個人にとって良い空間を実現するための考え方が、同じでは無くて、「完全」と「不完全」とむしろ真逆であることが面白い、とした。そして、なぜか、その人、個人にとって良い空間を模索する時に、全て不完全性とアクティビティーに辿り着いた。
それは結局、建築とは、秩序をどう扱うか、どうつくり出すか、すなわち、秩序という運動の安定性をどのように不安定にするかを考え、実行することだから、そこに辿り着いたという訳か。
"Order is an exercise"
"Chaos is an unstable aperiodic motion of a dynamical system, or a state including it. (It is said that chaos is a universal motion form of nature.) Characteristics of such chaos are infinite number of Unstable periodic orbits coexist and their periodic orbit groups characterize the morphology and structure of chaos. "(" Dissipative structure and chaos "by Mori Satoshi Kuramoto Yukinori)
I thought that chaos refers to a state with no order, a state in which it is confused, its form and structure itself, but in modern physics it is regarded as motion. The interesting thing is to create the form and structure of chaos by coexistence of unstable cyclic motion trajectory.
Multiple different movements coexist, creating a form of chaos. Are there exercises before the shape?
If it is exercise to create a state of chaos, that is, there is no order and a state in which it is in a state of disorder, the order may also be regarded as part of the movement called chaos. Order is a stable periodic motion.
In the first place, the building plan aims at this stable periodic movement. Order is an exercise, that is, it is an activity, so it is interesting to recollect the order like that.
Before, it was not true that the building plan to realize an ideal space for human beings and the idea for realizing a good space for individuals are not the same, but rather opposite to "complete" and "incomplete" It was funny. And, for some reason, when seeking a good space for that person, individuals all arrived at imperfection and activity.
In the end, after all, because architecture is about thinking about how to deal with the order and how to create it, how to make stability of the movement of ordering instable, and to carry it out .
猥雑の秩序をつくり出すためには、どうやって、どのくらい秩序を乱せばよいのだろうか。
秩序をそのまま取り込み、何か手を加えることができるという点での不完全性の例は茶室。茶会の度に亭主が客のために設えをする。
今計画中の集合住宅では、集合住宅の建築計画を完全な秩序として扱い、それを崩して乱して取り込み不完全性をつくり、猥雑の秩序にするのがよさそうだ。
秩序を乱さないと猥雑にはならない。秩序では無いものを乱しても、それは単なる見た目のデザインでしかなく、表層的で面白くない。ましてや、集合住宅は秩序の塊のようなもの、そこで、だから「猥雑の秩序」をやる意味がある。
集合住宅の建築計画が持つ完全な秩序とは、積層性と連続性の効率の良さか。
猥雑の秩序が異なるアクティビティーを誘発するので、その異なるアクティビティー同士の接点でオープンなパーソナルスペースができる。それはもしかしたら、森の中にいるような。そうか、猥雑の秩序は、森の秩序と一緒かもしれない、ふとそう思った。
そうなると、秩序とはそもそも何だ、もっと深く知りたくなる。
"What is ordering in the first place"
How can we disturb the order in order to create a complicated order?
An example of incompleteness in that it can incorporate the order as it is and add something is a tea room. Each time a tea ceremony is held the host will set up for the customer.
In the collective housing under planning now, it seems to be better to treat the building plan of the apartment building as perfect order, disrupt it, disturb it, create incomplete incorporation, and make the order of obstruction.
It must not be complicated unless the order is disturbed. Even if you disturb things that are not orderly, it is only a visual design, it's superficial and not funny. Much more, apartment houses are like chunks of order, so there is a meaning to do "order of confusion".
Is the complete order of the building plan of multi-family housing good efficiency of laminating and continuity?
Since the complicated order induces activities that are different, open personal space is created at the points of contact between the different activities. Perhaps it is like being in the forest. That's right. Ordinance of turmoil may be with the order of the forest, I think so.
In that case, what is ordering in the first place, you want to know more deeply.
猥雑の秩序はあるのか。猥雑というと秩序が無い状態と考えてしまう。秩序が乱れている状態がひどくなれば猥雑になるかもしれないが、それは秩序の範疇にとどまっているから、そうかそれが猥雑の秩序か。
そうならば、秩序を乱すことは簡単だが、ただ乱しただけでは猥雑な感じにはならないような気がするから、どこまで乱せば猥雑になるのだろうか。猥雑とそうでない境目は、バロメーターは、と考えてしまう。
猥雑には不完全性はあるのか。猥雑それ自体は完全で、自立して実存している感じがする。香港に昔あった九龍城のように、猥雑な集合体が塊としてはじめからそこにあったような感じか。
以前、秩序に関しては、不完全性をつくる方法として2通りある、とした。ひとつは、秩序をそのまま取り込み、何か手を加えることができるという点での不完全性と、もうひとつは、完全な秩序として扱い、それを崩して乱して取り込み不完全性をつくる。
猥雑はこの2つの不完全性が入っているような気がする。
猥雑の秩序をそのまま取り込み、そこにまだ手を加えることができるという点での不完全性と、秩序を乱すことで猥雑となり、それがすでに不完全性を獲得している、すなわち猥雑=不完全性。
猥雑には2重の不完全性が潜んでいる。
以前、不完全性がアクティビティーを誘発するとした。ならば、猥雑の秩序は2つのアクティビティー、それも異なる種類のアクティビティーを発生させる。
さらに、その猥雑の秩序が複数存在すれば、さらに、複数の異なるアクティビティーも発生するだろう。
建築とは、どのような秩序をつくり出すか、としたが、猥雑の秩序をつくり出すことができたら、インテリアから都市まで、面白い状況がつくれるような気がする。
"Order of clutter"
Is there a disorderly order? If it is dirty then I think it is in a state without order. If the state in which the order is disturbed becomes terrible, it may be clumsy, but since it remains within the category of order, is it so obscure order?
If so, it is easy to disorder the order, but since it seems that it does not make you feel dysfunctional just by being disturbed, how far will it get clogged? The barometer thinks that the obstruction and the boundary that is not so.
Are there any imperfections in a disorderly situation? The obstruction itself is perfect, feeling independent and independent of existence. Like Kowloon Castle in Hong Kong, it seems that a dirty aggregate was there from the beginning as a mass.
Previously, regarding order, there were two ways to create imperfections. One is imperfection in that it takes in the order as it is, it can handle something, and the other imposes it as a complete order, breaks it and disturbs it and creates incomplete incorporation.
Troubles seem to have these two imperfections.
Incompleteness in incorporating intact orders as it is, still being able to add hands there, and being disturbed by disordering the order, that has already acquired imperfections, that is, it is complicated = incomplete sex.
Twisted imperfections are hiding behind the scenes.
Previously, incompleteness was supposed to induce activities. Then, the complicated order generates two activities, which also produce different kinds of activities.
In addition, if there are two or more of these complicated orders, more different activities will also occur.
I decided what kind of order is to be built, but if I can create a complicated order, I feel like creating an interesting situation from the interior to the city.
人は秩序が整っていなかったり、秩序が無いことに惹かれる。違う言い方をすると、猥雑に惹かれる。
自分が猥雑にはしないけれど、猥雑なものを眺めたり、猥雑な場所へ行ったり、猥雑な所で呑んだり、が楽しかったりする。
でも、猥雑な場所は、はじめから猥雑では無くて、最初は秩序が整っていて、きちんとしていて、きれいだったはずで、段々と猥雑になっていったはず。
つい秩序を整えてしまう。はじめから猥雑にしようとしてもできない。子供の頃から秩序を整えることは教わってきたが、猥雑にすることは教わっていないというか、叱られた。
大人になると、皆んな、あんなに猥雑が大好きなのに、子供には叱るんだよな。
子供の頃から猥雑にすることを教えた方がいいんじゃないかな。そしたら、大人になって、より楽しい毎日が過ごせるかも、わざわざ猥雑を求めてフラフラしなくていいし。
はじめから猥雑にできて、その猥雑のままでいられる状態はきっと、とても豊かなような気がする。
秩序を一回かませれば猥雑にできるし、そのやり方もわかるが、はじめから猥雑にできないか。
はじめから猥雑をつくり出そうとしても、つくり出す過程で秩序が必要になる、数値という秩序が。
ならば、つくり出す過程が猥雑のままならば、はじめから猥雑で、最後まで猥雑のままで出来あがるか。
つくり出す過程が猥雑ということは、良く言えば、何、ブリコラか。ただ、建築では一貫して最初から最後まで猥雑につくり上げるの無理かな、どうしても数値という秩序を使う。完成した後に時間をかけて猥雑するしかないか。仕上げだけ猥雑にするのは簡単だけれども、それでは単なる装飾か、装飾が悪い訳では無いが、それではつまらない。
結局のところ、建築とは、どのような秩序をつくり出すかを延々と行うことか。
"Can you make obscurity from the beginning?"
People are attracted by the lack of order and lack of order. In other words, it is attracted by clumsiness.
I do not do anything wrong, but I look for obscene things, go to a disorderly place, drink in a dirty place, or have fun.
However, the dirty place was not obnoxious from the beginning, at first it was supposed to be orderly, neat and beautiful, it should have gradually become dirty.
I will arrange the order. Even if I try to make it obscure from the beginning, I can not do it. I was taught to arrange order from childhood, but I was scolded as if I was not taught to be obscene.
Everyone, like adults, I love such a lot of confusion, but children scold me.
I guess it would be better to teach things to be obnoxious from childhood. Then, becoming an adult, you can spend more enjoyable everyday, you do not have to bother to search for obstacles.
From the very beginning you can get dirty and the state where you can stay in that disorder surely seems to be very rich.
If you order the order once, you can do it sloppily and you can understand how to do it, but can not you do it from scratch from the beginning?
Even if you try to create obscenities from the beginning, order is necessary in the process of creating, the order of numbers.
Then, if the process of creating it is obscene, will it be obscene from the start, will it be completed without being clogged up to the end?
What is it, Bruicola, to say that the process of creation is obscene? However, in architecture, it is impossible to consistently create from scratch to the end, use the order of numbers absolutely. Is it only obstructing over time after completion? Although it is easy to make only the finishing obscure, it is not mere decoration or decoration is not bad, but that is boring.
After all, is architecture and what kind of order to create endlessly?
その人に焦点を当てて、その人が住む特殊な建築をつくることは案外容易で、特殊になればなるほど、もっと違う言い方で、奇抜になればなるほど、考える方は楽だったりする。手掛りがあるし、暴走しても良いし、その人が良ければそれで良い訳で。きっとつくる方も楽しいかもしれない。
ただ、それをしないのは、建築は外に置かれて、周知にさらされ、周辺環境に影響を与えるから、ただ単に特殊なだけ、ただ単に奇抜なだけは許されないと考えるのと、どうしてもそこに、その建築に、一般解というか、その場限りでは無い、全ての建築に影響を与える何かを盛り込みたいと考えてしまうから。
だから、その人に焦点を当てても、そこから抽出するのは一般解に通じる特殊なもの、矛盾するような言い回しだが、最終的には一般解を内包した特殊解を導き出す行為が建築だと思っている。
そのためには、何が一般解で、何が特殊解になるのかがわかっていないと、それが共通理解につながるから、それが無いと、完成した建築を見ても誰も理解できないし、独りよがりの建築になり、やはりそれは良くないとしておかないと、何でも有りの状態になり、それは一見すると自由にものづくりができるのだけれども、建築として過去から未来に向けて積み上がっていくものが何も無くなるから、良くないだろう。
ただ、この何が一般解で、何が特殊解かは、それを理解するために建築を学んでしまうと、はじめから答えを探すことが目的の思考になり、思考は練度を重ねると、いちいち考え無くても、勝手に頭が答えを決めつけに行くから、これが厄介で、自分では創造しているつもりが、単に答えに当てはめて問題をつくっているようになる。
きっと、乱暴に言うと、一般解も特殊解も自分がそうだと決めつけてしまえば良いというか、そのくらいの勢いで思考しないと、創造していることにはならないかも、と思うくらい、容易に答えという情報が手に入る。進歩しないで、退歩すれば、目と耳を塞ぐとか、進歩することが良い訳でないと決めつければ良いのだから。
"Retreat"
It is unexpectedly easy to create a special architecture where that person lives, focusing on that person, the more special it is, the more different way of saying, the worse the more it is, the easier it is to think. There is clue and you can run away, and if that person is okay it is a good translation. It may be fun to create one.
However, it does not do it because architecture is put outside, it is exposed to public knowledge and affects the surrounding environment, so just thinking that it is unusual for just a special one, Because I think that it wants to incorporate something that affects all the buildings, that construction is not a general solution or it is not limited to that.
So even if we focus on that person, extracting from that is a special thing that leads to general solutions, a contradictory phrase, but in the end it is said that the act of deriving a special solution containing a general solution is architecture thinking.
Therefore, if you do not know what is a general solution and what becomes a special solution, it will lead to a common understanding, so if you do not have it, no one can understand it even if you look at the completed architecture, If it is not the case, it will be in a state with anything, it can be done freely if at first glance, but there is nothing that builds up from the past to the future as a building It will not be good.
However, what is this general solution and what is a special solution, if you learn the architecture to understand it, searching for answers from the beginning becomes a goal thinking, thinking repeatedly, every one Even without thinking, since the head goes to decide answers without permission, this is troublesome, and the intention of creating oneself by itself applies merely to answers and makes problems.
Surely, roughly speaking, either general solutions or special solutions should be decided to be themselves, or if we do not think about with that momentum, it seems that they may not be creating things as easily as they think Information on answer is available. Do not make progress, if you go down, you have to decide that it is not a good translation to block eyes and ears, or progress.
以前から「気分に追従する」や「感触そのもので成り立つ」や「オープンなパーソナルスペース」などと言った人間の個人的な領域に踏み込んで行く時には、「完全なアクティビティー」は分断され、それぞれが展開しはじめて、「不完全性」と「アクティビティー」が決定要因になると考えており、
人間にとって理想的な空間を実現するための建築計画と、個人にとって良い空間を実現するための考え方が、同じでは無くて、「完全」と「不完全」とむしろ真逆であることが面白いと考えていた。
秩序で言えば、「完全」が整っている状態で、「不完全」が乱れているか、無い状態。
人間にとって理想的な空間をつくるには秩序を整え、個人にとって良い空間をつくるには秩序を乱すか、秩序を無くす。
「人間」という言葉は、20世紀に生まれた、社会の中で人を位置付けするための言葉ときいたことがある。人が社会性を纏い、人間になるには整った秩序が必要というか。
その人に焦点を当てて、社会とは関係が無くなれば、整った秩序より、秩序が整っていない方が、乱れていた方が、無い方が良いはずか。ただ、乱れていようが、無かろうが、秩序を扱っていることになるので、その時点で社会性を纏っていることになる。
現代を生きる以上、やはり、社会とは無縁で生きることは不可能なので、秩序が乱れている、無い位でちょうど良いのかもしれない。
最近「混沌」という言葉が気になっている。「混沌」とは秩序が無い状態だと思ってしまうが、そうでは無くて、「秩序が無い」と言った時点で、先程も出たが、秩序を扱っていることに、秩序がある状態が元となってしまうので、それは違う。
秩序が生まれる前の、まだ何だかわからない、でもそこに何かある状態が「混沌」らしい。「混沌」に何か可能性を感じ、「混沌」を自分なりに紐解ければ、その人個人にとって良い空間をつくる術の一端を見つけることができるかもしれないと今考えている。
"Chaos and Chaos"
When you step into a personal area of human who told you such as "Following a mood", "It will be made of feeling itself", "Open personal space", etc., "complete activity" has been divided and each developed Initially, I believe that "incompleteness" and "activity" will be determinants,
It is interesting that it is not the same as the architectural plan to realize an ideal space for human beings and the idea for realizing a good space for individuals, rather than "complete" and "incomplete" I was thinking.
Speaking in order, in a state where "complete" is in place, "incomplete" is disturbed or not.
In order to create an ideal space for human beings, arrange the order, disturb the order to make good space for individuals, eliminate order.
The word "human" is something I've heard about words to position people in society, born in the 20th century. Is it necessary for a person to socialize in society and have a well-ordered order to become a human being?
Focusing on that person, if relationship with society disappears, it would be better for people who were not disordered, more disordered than ordered, more disordered. However, as it will be dealing with order, whether disordered or not, it means that society is wearing at that time.
As it is impossible to live without society, it is impossible to live in modern times, so the order may be disordered, perhaps in no place.
Recently the word "chaos" is anxious. I think that "chaos" is a state without order, but it is not so, at the time when I said "There is no order", although it came out a while ago, in dealing with the order, there is an order Because it becomes the original, it is different.
I do not know yet what the condition before the order is born, but there seems to be something in there that is "chaotic". I feel that if you feel something in "chaos" and understand "chaos" for themselves, you may be able to find a part of the technique to create a good space for that person.
ある標準的な人間が完璧に立ち振る舞いができる空間は完全な秩序を備えているだろう。その秩序が建築計画である。完璧に秩序が整っているから、安全性や機能性などが担保される。
安全性や機能性は当たり前のこととして、ただ本当に秩序が完璧に整っているのが良いのかどうか。
「気分に追従する」や「感触そのもので成り立つ」や「オープンなパーソナルスペース」などと言った人間の個人的な領域に踏み込んで行く時には、その完璧に整った状態の秩序が邪魔になる。
秩序を整えていく方が簡単だ。それができるかどうかは別として、目標が立てやすいし、秩序という規範を絶対にして、経験値で押し切れるからだ。
秩序を整える行為以外のことをしようとすると、面倒なことになることが多い。
その面倒なことを丹念に拾い集めて経験者に立ち向かうことを若い頃はやっていたが、それでは説得力が無い。
秩序が無い状態が良いのだと掲げて人間の個人的な領域に踏み込んで行くことでしか、秩序が整っている状態を上回る術はないだろう。
"Order is key"
The space where a standard human being can perfectly behave will have a complete order. That order is a building plan. Since perfect order is in place, safety and functionality etc are guaranteed.
Safety and functionality are commonplace, just whether it is good that the order is truly perfect.
When stepping into the personal area of a human who said "Following a mood" or "It will be made of feeling itself" or "Open personal space" etc, the perfectly ordered state becomes an obstacle.
It is easier to keep order. Apart from whether it can be done, it is easier to set goals and absolute standards of order, it will be overwhelmed by experience value.
Trying to do things other than arranging order is often troublesome.
It was a young age to collect the troublesome carefully and to face experienced people, but that is not convincing.
There is no way to surpass the state where the order is in place only by stepping into the personal area of human being as a state that there is no order is good.
最近ずっと集合住宅の計画を考えている。集合住宅は建築計画学を生かすお手本のようなビルディングタイプで、ある標準的な人間が完璧に立ち振る舞いができる空間を目指す。集合住宅では効率的で完全な計画性が要求されるので、建築計画を学ぶ時の教材としてもとても良く、だからか、一級建築士の設計製図試験の課題としても定期的に出題される。
建築のビルディングタイプはまず、住宅か非住宅に分かれる。この分け方は別の見方をすると、人にとってプライベート空間かパブリック空間か。集合住宅はもちろんプライベート空間に入るが、非住宅のビルディングタイプの方が種類は多い。オフィスビルや美術館・博物館、病院などなど。
ただ、建築数はたぶん住宅の方が多いだろう。東京の都心部の超高層ビルの上階から見渡したりすると、一面に低層の住宅がビッシリと地面に張り付いているように見えて、ちょっと気持ちが悪くなるくらいに異様に見える。
住宅は人のプライベート、日常の空間を担うビルディングタイプとして、不特定多数の人を相手にする訳では無いからか、建築計画としての決まり事は案外少ない。非住宅の方が不特定多数の人を相手にするので安全性などから決まり事が多いが、集合住宅は非住宅では無いが、特定の多数が積層して住み、それがプライベートの空間で、赤ん坊から老人までが日常的に長時間滞在する可能性があるビルディングタイプなので、非住宅と同じ位か、それ以上に建築計画としての決まり事が多い。
誤解を恐れずに言えば、世の中に存在するほとんどの集合住宅が建築計画としての決まり事と法規を満たすことで成り立っている。それで、あとは事業性を考慮して最大ボリュームを効率的につくり出せば良い。違って見えるのは外壁の仕上げが違うだけ。
それを「気分に追従する」や「感触そのもので成り立つ」や「オープンなパーソナルスペース」などと言った人間の個人的な領域に踏み込んで計画している。
"Beyond the Building Plan"
I have been thinking about planning multi-family houses all along recently. Apartment houses are a building type like model to make use of architectural planning studies, aiming at a space where a standard person can stand perfectly. Since efficient and complete planning is required in multi-family houses, it is also very good as a teaching material when learning the building plan, so it is also quizzed regularly as a task of a first-class architect's design and drafting test.
The building type of the building is divided into houses or non-housing first. In another way of looking at this way of dividing, is private space or public space for people? Apartment houses, of course, enter private space, but non-residential building types are more common. Office buildings, museums, museums, hospitals, etc.
However, the number of buildings probably is more for houses. Looking down from the upper floor of the skyscraper in the center of Tokyo, it seems that low-rise residential buildings are sticking to the ground and on one side, it looks odd to the extent that it feels a little uncomfortable.
It is unexpected that the plan as a building plan is unexpected because houses are not intended to be an unspecified number of people as a building type that is responsible for human private and everyday space. There are many decisions from non-residential counterparts to unspecified large numbers of people, but apartment houses are not non-residential, but a certain number of them live and live, and that is a private space, Since there is a possibility that babies and old people can stay for a long time on a daily basis, there are many decisions as building plans as much as or more than non-housing.
Without being afraid of misunderstanding, most aggregate houses existing in the world are made up of satisfying rules and regulations as a building plan. So, afterwards you can create maximum volumes efficiently in consideration of business. It only looks different the finish of the outer wall is different.
I am planning to step into a personal area of human being who said it "follows the mood", "it is made of the feeling itself" and "an open personal space" etc.
「不完全」とは、足りなかったり、ムラがあったり、均一でなかったり、余白があったり、ズレていたり、乱れていたり、まとまりがなかったり、崩れていたり、隙間があったり、遊びがあったり、真円でなかったり、完全な状態が秩序が整っている状態ならば、秩序が無い状態が不完全な状態。
「見立て」は、形から連想をしていき、見る人がいて、はじめて成り立つ。故に、見立てとしてつくられたもの、それ自体は常に不完全。
磯崎新の「見立ての手法」より、見立ては永遠に連想を繰り返す、それをどこかの瞬間で止めるために、焼き付けるために「好み」、日本庭園に「利休好み」や「遠州好み」などがあるとのこと。
日本庭園、例えば、龍安寺の石庭は、それ自体は不完全であり、眺める場所として方丈があり、そこから眺める人がいて、はじめて完全と成す。ものだけで言えば、石庭と方丈は一対である。だから、龍安寺の石庭は廊下からでは無くて、方丈から眺めるの本来の見方であり、方丈から眺めないと意図された石庭の本来の姿は見えない。何度も龍安寺の石庭には訪れたが、未だに見えていない。
見立てを手法とすると、その不完全性故に、自由に連想が繰り返され、連想が正しいか正しくないか、質が高いか低いか、など関係無しに、どうにでもデザインされたものとして見えてしまう。それが「見立て」の特徴で、見る側に解釈の自由があり、連想の自由がある。だから、良くも悪くも見る側の技量次第で成立するのだが、あくまでも作者の主体性を確保したいから「好み」が必要なのだろう。
ただ、主体性を言い出したら「見立て」を手法とする意味が半減するような気がする。
「見立て」は、連想させる不完全性が魅力であり、連想された先にあるものが見る人によって違う、その時々で違うことが「見立て」の良さであり、その方が表現の幅が広がるだろう。
違う見方をすれば、「見立て」が基点となって様々な連想による解釈がなされる訳だから、その時点で「見立て」を仕掛ける側に主体性があることにもなるので、主体性など意識せずに、主体性などから離れたところで「見立て」を見てみたい。
だから、日本庭園には魅力を感じないのかもしれない。
"Impossible as imperfect"
"Imperfect" means that there are missing, uneven, uneven, marginless, misaligned, disturbed, unbalanced, collapsed, gaps, play If there is not, it is not a perfect circle, or the complete state is in a well-ordered state, the state with no order is incomplete.
"Association" is association from the shape, there is a viewer, it will be established for the first time. Therefore, what was made as a perspective, itself is always incomplete.
From Isozaki 's "new way of thinking", the definition repeats association forever, in order to stop it at some moment, "preference" to burn, "Rikyu favorite" in Japan garden and " It is said that there is.
Japanese gardens, for example the rock garden of Ryoanji, are themselves incomplete, there is a hill as a place to look at, there is someone who can see from there, and it will be complete for the first time. In terms of things alone, the rock garden and Hodogyo are a pair. So, the rock garden at Ryoanji is not the corridor, it is the original view from which you can watch from Honjo, you can not see the original appearance of the stone garden that was intended if you do not watch from the direction. Although I visited the rock garden of Ryoanji many times, I still can not see it.
If it is a method of thinking, because of its imperfection, association is freely repeated and it seems as if it were designed anything, regardless of whether the association is right or wrong, whether the quality is high or low, etc. . It is a feature of "look", the viewer has freedom of interpretation, and there is freedom of association. So, it depends on the skill of the viewer whether it is good or bad, but since we want to secure the autonomy of the author to the last, "preference" is necessary.
However, when I say the subjectivity, I feel that the meaning of "approach" as a method is halved.
The "imposition" is incomplete association, attraction is different, it depends on who sees what is associated, the difference being different from time to time is the merit of "looking", that is broadening the range of expression right.
As a different way of thinking, interpretation is made based on "association" as a base point, so at that point it is also the subjectivity of the "placement" side, so consciousness such as identity I would like to see "distinction" away from the subjectivity and so on.
Therefore, it may not be attractive to the Japanese garden.
気分に追従する建築、感触そのもので成り立つ建築、そして、オープンなパーソナルスペース、これらを実現するためにはどうするかと考えた時に、今までの思考の軌跡を振り返ると、根の部分は同じなのか、何故かいずれも不完全性とアクティビティーに辿り着く。
不完全性がアクティビティーを生み出すのか、アクティビティーがあるから不完全性がわかるのか、どちらが先か、卵が先か、ニワトリが先か、と同じような状態で、お互い補完関係にある。
建築計画の考え方は、ある標準的な人間が完璧に立ち振る舞いができる空間を目指す。言わば、アクティビティーの完全さを目指すこと。だから、アクティビティーは完全であることが理想であり、そこに補完関係などそもそも無く、1つの「完全なアクティビティー」であるだけ。
ところが、「気分に追従する」や「感触そのもので成り立つ」や「オープンなパーソナルスペース」などと言った人間の個人的な領域に踏み込んで行く時には、「完全なアクティビティー」は分断され、それぞれが展開しはじめて、「不完全性」と「アクティビティー」が決定要因になる。
人間にとって理想的な空間を実現するための建築計画と、個人にとって良い空間を実現するための考え方が、同じでは無くて、「完全」と「不完全」とむしろ真逆であることが面白い。
"Complete and incomplete"
When looking back on the trajectory of thinking so far when looking at what to do in order to realize these, the architecture that follows the mood, the architecture made up of the feeling itself, and the open personal space, the root part is the same, Why do they all come to imperfections and activities.
There is a complementary relationship between each other, in the same way as incompleteness creates activities, whether there is activity or incompleteness, which is the first, eggs first, chicken ahead.
The idea of building plan aims at a space where a standard human being can perfectly behave. To the extent, aim for activity integrity. So it is ideal that the activity is perfect, there is no complementary relationship there, and there is only one "complete activity" in the first place.
However, when stepping into the personal area of human beings such as "Following the mood", "Built with the feeling itself", "Open personal space", etc., the "complete activity" is divided and each Beginning, "incompleteness" and "activity" become the determinants.
It is interesting that the building plan to realize an ideal space for human beings and the way of thinking to realize a good space for individuals are not the same, but rather opposite to "complete" and "incomplete".
アクティビティーがあって、差異がある、差異が浮き彫りになる。ここで、今までを振り返る。
不完全性がアクティビティーを生み出す。その不完全性は秩序を乱すことでつくり出す。その秩序は、敷地の文脈/コンテクストを読み取ることで探し出す。
気分に追従する建築は、人が思い描く空間と実際の空間との間に差異があり、その差異が余白として受け取られ、その余白が気分で様々に解釈できる部分となり、その時の気分とともに記憶を形成する。
だから、差異がアクティビティーを生み出している。
差異がある状態は、言わば、不完全な状態、だから、アクティビティーを生み出す。
感触そのもので成り立つ建築は、見立てを手法とし、見立てには不完全性が常に伴う。
その見立ての不完全性が見る側に実際に触れるのと同じ位の想像力を起こさせるのかもしれないし、もしかしたら、見立ての方がより深くそのもののことを、感触を知ろうとするようになるのかもしれない。
だから、見立てがアクティビティーを生み出している。
これを異なる用途を併設した集合住宅の計画に当てはめると、集合住宅という完全な形式があり、その形式を、実体として、概念として、敷地の文脈/コンテクストからの道や空の秩序の不完全性や、感触からの見立てによる不完全性を使い、乱し、崩し、そこに異なる用途が入ってくることにより、集合住宅の形式を完全なものにしようとする心の動きが生じ、接点の無い異なるアクティビティーが発生し、パーソナルスペースがその接点の無い異なるアクティビティー同士の間にオープンな状態で形成でき、そのオープンな状態が敷地周辺によい雰囲気を醸し出すようになればいい。
気分、感触、オープンなパーソナルスペース、と異なることを建築に持ち込もうとした、今までの軌跡を振り返ると、不完全性とアクティビティーにいずれも行き着く。そこに秩序が絡んでくるか。
"Imperfections and Activities"
There are activities, there are differences, the differences are highlighted. Here, I look back to the past.
Imperfection creates activities. The imperfections are created by disturbing the order. The order is found by reading the context / context of the site.
In the architecture that follows the mood, there is a difference between the space envisioned by a person and the actual space, the difference is received as a margin, the margin becomes a part that can be interpreted variously by the mood, forming a memory with the mood at that time .
So, the difference creates the activity.
A state with a difference is, so to speak, an incomplete state, so it creates an activity.
Buildings that consist of feeling themselves have a method of looking at, and imperfections always accompany each other.
Perhaps imperfections in its appearance may cause imagination as much as it actually touches the viewer, and perhaps the perspective will more deeply try to find out about itself It might be.
That's why the creation is creating an activity.
When this is applied to the plan of multi-family housing with different uses, there is a complete form called collective housing, and as its concept, as a concept, as concept, the imperfections of the context of the site / context from the context and the sky And using the incompleteness from the feel of touch, disturbing and breaking up, different applications entering there, the movements of the mind to make the form of the apartment complex complete, there is no point of contact Different activities occur and personal space can be formed open between different activities with no contacts, so that the open state can create a good atmosphere around the site.
Looking back on the past trajectory which tried to bring things different from mood, feel, open personal space, to architecture, both arrive at imperfection and activity. Order comes about there.
意図的につくり出す差異の特徴は、一見ではわからない位のことで、不自然には見えない。ただ、よく観察すると不自然というか、あまり有り得ない差異だったりする。
気分に追従する建築は、人が思い描く空間と実際の空間との間に差異があり、その差異が余白として受け取られ、その余白が気分で様々に解釈できる部分となり、その時の気分とともに記憶を形成する。
だから、意図的に差異をつくり出すことができれば良いが、差異ならば何でも良い訳では無い。
その判断基準は、もしかしたら、人のアクティビティーと関係があるのかもしれない。
先に出した差異の例、窓の高さや部屋のつながり方も、人のアクティビティーが当然絡む。それは人が使う空間なのだから当たり前のように思うかもしれないが、もし人のアクティビティーと関係が無い差異であるならば、それは単なる、良ければデザイン、例えば、デ・コンストラクションの建築、悪ければいい加減なものである。人のアクティビティーと関係が無ければ、それは単に表層的なものや形だけをいじっただけのものに過ぎず、人が差異とは読み取れないだろう。
人は動く中で、連続的に風景が変わっていく空間の中で、その差異を感じ取る。
だから、差異を意図的につくり出すための前提条件として、下地として、人のアクティビティーが必要。そのアクティビティーがあってはじめて差異が浮き彫りにされるのだから。
"There is activity and there is a difference"
Characteristics of deliberately created differences are about to be understood at a glance, not looking unnatural. However, if you observe frequently, it is unnatural, or it is not much difference.
In the architecture that follows the mood, there is a difference between the space envisioned by a person and the actual space, the difference is received as a margin, the margin becomes a part that can be interpreted variously by the mood, forming a memory with the mood at that time .
So it is only necessary to deliberately create a difference, but nothing is good if it differs.
The criterion may be related to human activities, perhaps.
Examples of the differences that we issued earlier, the height of the windows and the way the rooms are connected, the activities of people naturally involve. If it is a difference that does not relate to a human activity, it is merely a good design, for example, a construction of de Construction, a sloppy if it is bad . If it has nothing to do with the activity of a person, it is merely a thing that only touches superficial things and shapes, people will not be able to read as a difference.
People are moving, and feel the difference in the space where the landscape changes continuously.
Therefore, as a prerequisite for intentionally creating the difference, human activity is necessary as a base. The difference is highlighted for the first time with that activity.
差異が記憶になる、と言えば、子供の頃、夏休みに母方の田舎へ行くと、夕暮れの西日が差し込む部屋があり、その差し込み方が普段住んでいた家とは何か違っており、その部屋のことが、その時の切なさみたいな気分とともに、大好きな場所にいると夕暮れは楽しいことの終わりを象徴するものだから、今でも妙に記憶に残っている。
今は無いその部屋は、別に特別変わっていた訳でもなく、一見普通なのだが、ただ普段住んでいた家の部屋とは何かが違い、その差異を明確に言うこともできないが、夏休みのその田舎の情景を思い出す時には必ずその部屋が出てくる。
その部屋は夕暮れの西日が差し込む時間に、切ない気分に合わせるかのように、違って見えた。
その時の気分を受け止める何か、余白みたいなものがあったのだろう。もしその部屋が無かったら、夏休みの思い出の記憶も全然違うものになっていたはずだ。
このことをもっと意図的につくり出せないか。記憶になる差異をもっと明確に理解しながらつくり出せないか。
この夕暮れの西日の差し込む部屋の窓の高さは、今から思えば、低い。肘掛け窓だが、室内から見ても、屋外から見ても低い。そう、この部屋は後から増築したのかもしれない。そう言えば、その部屋と他の部分とのつながり方がちょっとおかしい。今となっては確かめる術は無いが、その家の中で、その部屋だけが廊下のどん詰まりにあった。もしかすると、昔は物入れか納戸だったところを広げて部屋にした可能性が高い。
そうたがら、その部屋と他の部分とのつながり方が差異だった。普段住んでいた家には無かった。
何かその差異を子供ながらに感じとり、その部屋自体は普通であるにもかかわらず、何か特別な場所に仕立て上げたのかもしれない。もちろん、夕暮れの西日があってのことだが。
気分に追従する建築は、丹念に紐解けをしないとわからないくらいの差異が必要なのかもしれない。
ただ、その差異を余白と捉えて、そこにその時の気分が入り込む余地があるということだが、差異ならば何でも良いという訳では無いような気がする。
"Make a difference intentionally"
Speaking of differences becoming memorable, when I was a child, when I go to the maternal countryside during the summer vacation, there is a room where the sunset at dusk is inserted, the way of inserting it is different from the house I usually live in, When the room is in a favorite place with the mood like that at that time it is symbolic of the end of fun at dusk, so even now it is strangely remembered.
The room that is not present is not a special change at all, but it seems normal at first glance, but something is different from the room of the house that I usually live in, but I can not say clearly the difference, but that during summer vacation When I recall the scenes of the country, that room certainly comes out.
The room looked different like the dusk of the evening sunny day, as if it fits a pleasant mood.
I guess there was something like a margin to catch the mood at that time. If that room did not exist, memories of memories of summer vacation would have been completely different.
Can you make this more intentionally? Can you make it while understanding the difference that becomes memorized more clearly?
The height of the windows of the rooms of the dusk of the evening in the western sun is low from now. Although it is an armrest window, it is low even when looking from the inside or from the outside. Yes, this room may have been expanded afterwards. By the way, how to connect the room and other parts is somewhat strange. There is no technique to confirm now, but in that house only that room was clogged in the hallway. Possibly, there is a high possibility that it used to be a room spreading out the place where it was a storey or a store in the past.
That being so, the connection between the room and the other part was a difference. I did not live in the house I usually lived in.
I felt something like that while I was a kid, and the room itself may have been tailored to something special, even though it is normal. Of course, there was a sunset in the evening.
The architecture that follows the mood may need a difference that you do not understand unless you carefully understand it.
However, although I think that difference is a margin, there is room for mood of that time to enter there, but it seems that there is no reason why anything is not good.
気分に追従する建築は、人が思い描く空間と実際の空間との間に差異があり、その差異が余白として受け取られ、その余白が気分で様々に解釈できる部分となるもの。
その差異は、見てすぐにはわからないかもしれないが、よく観察するとわかるくらいなもの、あるいは空間全体に及ぶものだと、全てを見渡すことができずに、部分だけを見たら、差異に気がつかないことであったりして、だから、一見して不自然ではなく、普通にどこにでもありそうなこと。
今まで見たり、つくってきた建築の中で、差異に当たることを思い返してみると、
窓の高さが何か低い、一見して最初は気がつかなかったが、でも何かが違って感じて。この場合だけではなくて、窓の高さは空間デザイン上とても大事な要素で、窓は太陽の光を取り入れたり、外の風を取り入れたりするためにあるが、人が室内から外を見るためにもあるから、窓の高さが人の背の高さを暗に示すことにもなる。
だから、その空間をどう見せたいか、どう感じさせたいかと考える時に、窓の位置や大きさも重要だが、窓の高さが一番重要で、空間をヒューマンスケールにしたい時は窓の高さをクライアントの背の高さより少し、ほんの数センチ低くしたり、狭い部屋だが空間を広々と感じさせたい時は窓の高さを高くしたり、窓自体を大きくできない場合は上の方に配置したりする。
その窓が、不自然に低くはないが、でも低い、それもその高さを測ると普段自分が設計の中では絶対に使わない数値だった。そこの壁にその大きさの窓が存在すること自体は普通にあり得ることだが、窓の高さが普通に思い描く高さと実際とで差異があり、妙にそこが気になる、たぶん、その家で生活すると、その窓の高さが記憶に残りそうな気がした、それもその時々の感情や気分と紐付けられて。
"Differences are memorized"
A building that follows the mood has a difference between the space envisaged by a person and the actual space, and the difference is received as a margin, and the margin becomes a part that can be interpreted variously in a mood.
The difference may not be understood immediately, but if you look at only the part, you will not notice the difference if you can not look at everything if you observe well if you observe well, or it spans the entire space There is no thing, so it is not unnatural at first glance, it is likely to be anywhere in the usual way.
Looking back on the fact that it hits the difference in the architecture that I have ever seen or made,
The height of the window was somewhat low, at first glance I did not notice, but something feels wrong. Not only in this case, the height of the window is a very important element in the space design, the window is for taking in the sunlight and taking in the outside wind, but for a person to see the outside from the room Also, the height of the window implies the height of the person's back.
So when you consider how you want to show the space and how you want it to be, the position and size of the window are also important, but the height of the window is the most important, and when you want to make space a human scale, It is a little less than the height of the client's back, when it is a small room, but when you want to make the space feel spacious, you can raise the height of the window or place it on the upper side if you can not enlarge the window itself .
The window is not unnaturally low but it is low, but it is a value that you never normally use in your designs when you measure its height. The fact that there is a window of that size on the wall there can be as usual, but there is a difference between the actual height and the actual height of the height of the window, it is strangely worrisome about it, maybe When I lived at home, I felt that the height of the window seemed to be in memory, that was also tied to the emotions and moods of the times.
余白のある状態、茶室の床の間であったり、仏様のお顔であったり、それは何も無い状態ではなく、そこに確固としたものが有りながら、手を加えることができたり、こちらの都合でいかようにも解釈できる状態で、汎用性が高いのか、曖昧なのか、中庸なのか。
気分に追従する建築ならば、仏様のお顔のように、こちらの気分でいかようにも解釈できる空間をつくりたい。
仏様が例えば、大日如来ならば、どういうお顔かは決まっているが、作者によって少しずつ違っているはずで、顔の輪郭に膨らみがあるとか、目が細いとか、顔の角度も違うかもしれない。そのような差異が積み重なって、こちらの気分次第でいかようにも解釈できるお顔になっているのかもしれない。
それは、標準的な大日如来のお顔があるとしたら、その標準的なお顔より何かちょっと、不自然まではいかないが、微妙に違っていたり、ズレていたり、間延びしていたりして、人が思い描く大日如来のお顔とは、それも人それぞれ違うかもしれないが、何か違うように思えるから、その差異の部分が気分によって、笑って見えたり、怒って見えたり、悲しんで見えたり、いかようにも解釈できる所になるのかもしれない。
その差異のつくりは作者自身に委ねられている所であり、その差異が余白なのだろう。
ならば、気分に追従する建築は、人が思い描く空間と実際の空間との間に差異をつくり出し、その差異のつくり方次第というか、その差異をデザインすることで実現可能になるのではないか。
"Design the difference"
There is a margin condition, between the floor of the tea room and the face of the Buddha, it is not a state without anything, there is a certain thing there, while you can add a hand, this convenience In a way that can be interpreted in such a way, whether versatility is high, ambiguous or moderate?
If you follow the mood, you want to create a space where you can interpret how you feel like this, like the face of the Buddha.
For example, if the Buddha is Dainichi Asa, it is decided what kind of face it is, but it is different by the author little by little, the outline of the face has a bulge, the eye is thin, the angle of the face is different It might be. Such differences may accumulate and it may be a face that can be interpreted in any way depending on this mood.
If there is a standard Dainichi Nagami's face, it is somewhat less unnatural than its standard face, but it is slightly different, slippery, stretched, It may seem that something is different from the face of the Dainichi Nyorai who the person envisions is, but since it seems like something different, the part of the difference seems to be laughing, depending on the mood, it looks angry, sadly It might be a place where you can see it or interpret it in the same way.
The difference is left to the author himself, and the difference is the margin.
Then, the architecture that follows the mood may be made feasible by creating a difference between the space envisaged by the person and the actual space, depending on how to make the difference, or by designing the difference .
言葉とは不思議な力を持っているもので、
「気分が建築を変えさせる」としていた時には、イメージが全くと言ってよい程膨らまなかったのに
「気分に追従する建築」と言い換えた途端に、イメージが頭の中をクルクルと回りはじめた。
その時の気分によって、同じ風景でも、切なく見えたり、華やかに見えたりすれば良い。そうすると、やはり、動かない茶室か、その茶室のからっぽの空間だから設えによっていくらでもコロコロ変わるのか。
もしかしたら、からっぽと言うより余白があるから、そこに自分の気分が入る込む余地があるから、同じ風景でも気分によって違って見えるのかもしれない。
ここまで考えて、ふと思い浮かんだ。京都や奈良へ行って神社仏閣を訪ねるのが好きで、前に人から聞いたことがあるからかもしれないけれど、そこにある動かない仏像の表情が、その時の感情によって、笑っていたり、怒っていたり、見える。特に、大日如来に、奈良の大仏や、京都の東寺の金堂の大日如来などはそう見える。
ちなみに、今日聞いた話で、日本の三大大仏は、奈良と鎌倉と、ここまでは誰でも知っていますよね、もう一つは、高岡の大仏らしいです。富山県の高岡、今度輪島に行く時に途中下車して見に行こうかな。
それは、その大仏に喜怒哀楽の区別が無い表情だから、見る側の都合でどのようにでも見える。だけど、その大仏は秀作であり、決してクオリティの低いものでは無い。
ここを解明すると、もうしかしたら「気分に追従する建築」が実現できるかもしれない予感を今日やっと得た。
"I finally got a feeling"
Words and words have strange power,
When I was saying "Feeling to change the architecture", the image did not inflate enough to say that it was totally
As soon as paraphrasing the phrase "architecture to follow the mood", the image began circling in the head around her head.
Depending on the mood at that time, even in the same landscape, you can see it look painful or look gorgeous. Then, after all, because it is an empty space in the tea room that does not move, how much will it change depending on the setting?
Perhaps there is more room than empty, so there is room to get in there for yourself, so even the same landscape may seem different depending on your mood.
Thinking so far, I misunderstood. I like going to Kyoto and Nara to visit shrines and temples, maybe because I've heard from someone before, but the expression of the Buddha statue that is not moving is smiling or getting angry due to the emotions at that time You can see it. Especially in Dainichi Nyoro, the Great Buddha of Nara and Dainichigiri in Higashiji Temple in Kyoto seem to be seen.
Incidentally, by the way I heard today, the three biggest Buddhas in Japan, Nara and Kamakura, everyone knows so far, the other is the Big Buddha of Takaoka. Takaoka in Toyama Prefecture, I will go to see it when I go to Wajima this time.
Because it is a facial expression that there is no distinction between emotions and emotions in the Big Buddha, it can be seen anything at the convenience of the viewer. However, the Big Buddha is a good work, it is by no means a low quality one.
When I clarified this, I got a feeling that I could finally realize "a building that follows the mood" only now, I got a premonition today.
建築が気分をコロコロ変えさせるのはあるだろう。
「あるだろう」というのは、建築を主体的に考えた場合、設計者も建築家も建築に携わる全ての人は建築を主体的に扱い、建築を中心にして考えるので、当然、「建築が〜させる」という思考になるので、建築が人の気分を変化させるキッカケになるにはと考えるので。
だから、気分を変化させるために、いろいろな仕掛けやシークエンスなどという歩きながら見える風景が連続的に変わるなどの演出を考えたりする。
だから、建築が気分を変えさせる、となる。
あくまでも建築が主体で、それは建築が持つ存在感の強さとは無関係、強固な建築だろうと、弱い建築だろうと、建築が気分を変えさせる。
建築を主体的に扱うのは、建築に携わる全ての人にとっては当たり前のことだから、主体的で無いと自分たちの職能が成り立たないから、それで良いと思うが、建築の主体性の成り立ち方みたいなものは、まだまだ考える余地があるのではないか。
もっと建築が受け身の状態でも、むしろ、気分によってコロコロ変わる建築、気分が建築を変えさせる、となった方が建築自体が持つ存在感や社会性がより柔軟になり、より建築が持っている人に何らかの影響を与える能力を発揮できるようになるのではないか。
荘子は言う「受け身こそ最高の主体性」と、受け身だけれども、建築が主体の状況に変わりは無い。
受け身とは没個性では無く、むしろ個性的であるから受け身になることができる、個性があり、特徴があるから、流されること無く、受け身でいられる。
だから、コロコロ変わる気分に対して建築はどう対応するのか、これは動かない、動けない建築にとっては最高に難しいことかもしれない、気分が建築を変えさせるにはどうするか。
「気分に追従する建築」言い換えるとこうなるか。
追従という状況には可能性を感じるが。
"Following architecture"
There will be something that makes architecture change the mood.
"There will be" is that when there is a subjective thinking of architecture, as both designers and architects deal with architecture as a subject, everyone involved in architecture will focus on architecture and, of course, Because it is thought that "let's do ~", because it thinks that the architecture is to make people feel better.
So, in order to change the mood, I think about the production such as changing the landscape visible while walking such as various tricks and sequences.
So, the architecture will change the mood, and will be.
It is mainly building, it is independent of the strength of the existence of the building, whether strong construction or weak architecture makes the building change its mood.
Since it is natural for everyone involved in construction to treat the building as subjective, it seems that it is good to have their own functions if it is not subjective, but it seems to be how the building of the building is established There is room for thinking still more things.
Even in the more passive state of construction, rather the building that changes depending on the mood and the mood that makes mood change the building makes the presence and social nature of the building more flexible, more people who have the architecture It will be able to demonstrate the ability to exert some influence on it.
Although Rosoko says "Passive is the best individuality", although it is passive, there is no change in the situation where building is the subject.
Passive is not deceiving personality, rather it is individuality, so it can become passive, there is personality and features, so you can be passive without being shed.
So, how does architecture respond to the mood changing, it may be the most difficult for an immovable architecture that does not move, how do you feel to change the architecture?
"Building that follows the mood" In other words, it becomes like this.
I feel the possibility in the situation of following up.
建築は気分の変化を受け止めてくれる存在なのか。あまりにも強固で融通がきかないから、コロコロ変わる、ある意味軽薄な気分なんてものを相手にもしてくれない。
どっしりと構えて、私の色はあなたの気分くらいでは変わりませんよ、って感じ。見ようによっては感じわるい。
最近、ずっと気になっていることが、画像を見ただけで、これ誰の作品がわかることが、その人の作風が確立されていて認知されていることだから、スタイルがあることだから、それは良いことだと暗黙のうちに了解になっているのは、それを外から眺めている人の、ギャラリーの、オーディエンスの、ほとんどの人がそうだが、その作品を理解した、だから良い、ということでしか無く、そこに曖昧なことが入り込む余地も無く、窮屈で息がつまりそうになり、せっかく素晴らしい作品なのに、何かそれは損をしているように思う。
せめて、その日の気分で変わるくらいの曖昧さを持ち込みたいのだが、やはり、その作品性が頑な過ぎて、どうなのか。
ただ、そもそも気分の変化を持ち込めるのか。気分の変化にどう対応して欲しいのか。建築ならでは対応の仕方があるか。こちらの気分の変化にリニアに対応してくれるのか、それとも、その変化を何でも包み込むように受け止めてくれるのか。建築は動かないし、動けないから、何でも包み込むように受け止めるしかないか。
ならば、建築は強固な作品性があった方が気分の変化に対応しやすいのか。
"Is architecture too strong?"
Is architecture that accepts the change of mood? Because it is too strong and inflexible, it does not make any sense of frivolity that changes the corner.
I have a solid massage, my color does not change with your mood. I feel bad by seeing it.
Recently, what I have been watching for a long time is that it is a style that there is a stylistic existence because that person's style is established and that it is only knowing the image of who this is interested, It is implicitly understandable that it is a good thing that most people of the audience of the gallery, who are looking at it from the outside, understand the work, so that it is good There is no room for ambiguous things to enter there, it is cramped and my breath seems to be like that and it is such a wonderful work that I think that it is losing something.
At the very least, I'd like to bring ambiguity that will change with the mood of the day, but again, how is that work's stubborn and how is it?
But can you bring in changes in the first place? How do you want us to respond to changes in mood? Is there a way of responding unique to architecture? Does it correspond linearly to changes in my mood, or will you accept any changes in that change? As the building does not move and can not move, can you accept as if you wrap everything?
Then, is it easier for architects to respond to changes in mood if there was strong workability?
感触そのもので成り立つ建築をつくるには、見立てを手法とすればよい。
見立てという手法が不完全性を備えているから、見る側が自身で補おうとする心の動きが生じ、そのものに触れてもいないのに、感触まで意識してしまう。まさにこれはアクティビティーが発生することでもある。
また、敷地の文脈/コンテクストの読み取りから、道を完全な秩序を持った存在とみなし、その道をからっぽな空間として扱うことにより、見立てと同様に、そこに不完全性を見出し取り入れ、
その場所の空の広さを天空率として表し、それを道と同様に、完全な秩序を持った存在とみなし、空の広さ、すなわち天空率は去就するが、建築は前とは異なるという秩序の完全性を欠落させることにより不完全性をつくる。
これらの道や空の秩序の不完全性が、見立てと同様に、アクティビティーを発生させる要因になる。
これを異なる用途を併設した集合住宅の計画に当てはめると、集合住宅という完全な形式があり、その形式を、実体として、概念として、敷地の文脈/コンテクストからの道や空の秩序の不完全性や、感触からの見立てによる不完全性を使い、乱し、崩し、そこに異なる用途が入ってくることにより、集合住宅の形式を完全なものにしようとする心の動きが生じ、接点の無い異なるアクティビティーが発生し、パーソナルスペースがその接点の無い異なるアクティビティー同士の間にオープンな状態で形成でき、そのオープンな状態が敷地周辺によい雰囲気を醸し出すようになればいい。
これが今回の集合住宅計画の考え方の骨子になるだろう。目指す所は、集まって住むから、はじめて可能になるパーソナルスペースをつくること。この骨子を素にして肉づけをしていく。
"Outline of multi-family housing project"
To create a building that consists of feeling itself, you can use a method of approach.
Since the method of viewing has imperfections, the viewer side is trying to supplement itself with the movement of the mind, and even though it does not touch itself, he is conscious of the feeling. This is precisely the fact that the activity occurs.
Also, by reading the context / context of the premises, considering the road as a completely ordered entity and treating that road as an empty space, we find imperfections there as well,
The sky size of the place is expressed as a sky factor and it is regarded as a perfectly ordered existence like a road, the size of the sky, that is, the sky factor is removed, but the architecture is different from the previous Creating imperfections by lacking order integrity.
The incompleteness of these roads and the sky order becomes a factor that generates the activity as well as the observation.
When this is applied to the plan of a multi-family housing with different uses, there is a complete form called a multi-family house, and as a concept, as a concept, as a concept, imperfections of the context of the site / context from the context and the sky And using the incompleteness from the feel of touch, disturbing, breaking down, different applications entering there, movements of the mind to make the form of the apartment complex complete, there is no point of contact Different activities occur and personal space can be formed open between different activities without contacts, so that the open state can create a good atmosphere around the site.
This will be the main point of the way of thinking of this multi-family housing plan. The aim is to collect and live, so make a personal space that will be possible for the first time. I will flesh out this skeleton.
見立てという構造が、触れないのに見た目で感触まで意識する状態を意図的につくり出しているのかもしれない。
見立てはそのモノ自体では完結しないで、見る側が自分の中で想いを巡らせ補うことによって成立するもので、だから見る側によって受け取り方も様々になる可能性があるし、受け取り方をコントロールすることもできない。故に、見立てには不完全性が常に伴う。
その見立ての不完全性が見る側に実際に触れるのと同じ位の想像力を起こさせるのかもしれないし、もしかしたら、見立ての方がより深くそのもののことを、感触を知ろうとするようになるのかもしれない。
だから、見立ての方が、そのものを直に見るより、より深く感触までわかるということか。
見立ては意図的であるから、見ようによっては人為による不自然さがあるが、それがかえって、自然の佇まいを炙り出し、自然を想起させる。
見立てを用いずに、自然の佇まいをつくり出そうとしても、人為である以上、それを超えて自然そのものになることは無い。
むしろ、人為として、より自然を想起してもらう手法として見立てがあり、それが茶室の中の一輪の花であり、露地の苔である。
茶道のお茶会は、亭主と客の共同作業ときくが、まさにそのための手法が見立てなのだろう。
"Feel of architecture vol.6"
It may be that the structure of looking out intentionally creates a state that is conscious of the appearance and feeling though it does not touch.
The viewpoint is not completed by the thing itself, it is established by supplementing the viewer's side with the thought in the inside, so there are possibilities that the viewing side can be variously received depending on the viewer side, and also controlling the receiving way Can not. Therefore, incompleteness always accompanies the view.
The imperfections of that appearance may cause the same imagination as to actually touch the viewer, and perhaps the viewer would like to know more about itself, its feel It might be.
Therefore, rather than looking at itself directly, you can understand the feel more deeply.
Since the way of thinking is intentional, there are unnaturalness due to artificial, depending on what you see, but it rather burns out the appearance of nature and recalls nature.
Even if it is tried to create a natural appearance without using a viewpoint, as it is artificial, beyond that it will never become natural itself.
Rather, as a human being, there is a view as a method of recalling more nature, which is a flower in a tearoom and a moss of open field.
The tea ceremony in the tea ceremony will make it easier for the host and guests to collaborate, but what exactly is a method for that is probably.
触れないのに見た目で感触まで意識する状態を意図的につくり出すには、どうするのか。
茶室に向かう露地の苔はなぜ、見た目でふわふわの感触まで意識するのだろうか、茶室の中で見る花はなぜ、花弁の感触まで意識してしまうのか。いずれも、意図的につくり出している。
感触まで意識してしまう構造というか、メカニズムがわからないと意図的にはつくり出せない。
苔の感触を意識してしまうのは、苔が大事に育てられていて、その苔に価値があり、絶対に触ってはいけない、踏んではいけないと思っているから、逆に踏んでしまった時はどうなるのだろうと、やわらかくて、ふわふわしていそうだから、苔が足型にへこむかな、などと想像してしまう。
花弁も愛でるもので、触れないから、また、茶室という非日常の空間の中にいると、花以外にも、そこにあるもの、差し込む光さえも畳に当たった所の感触というか、質感みたいなものを意識してしまう。閉ざされた空間の中で限定的に設えられたモノたちが自然としてクローズアップされてくる。それはきっと茶室が、岡倉天心が「茶の本」で言う所の、からっぽの空間で、一期一会のための設えをするための存在だからか。
それとも、茶道が、茶室が、そのような感触まで意識することだと刷り込まれているからか、あるいは、それが日本の美意識の一端のようなことをどこかで自身で思っているからか。
ただ、苔にしろ、花にしろ、いずれも人が意図的につくり出した、自然の見立てである。
見立てという構造が、触れないのに見た目で感触まで意識する状態を意図的につくり出しているとしたら、それはとても面白い、がどうだろうか。
"Feel of architecture vol.5"
How to deliberately create a state that is to the point of being conscious of the feeling to the touch though not touching.
Why is the moss on the open ground heading for the tea room conscious of the appearance and fluffy feeling? Why are flowers seen in the tea room conscious of the feel of petals? Both are intentionally created.
I can not make it intentionally if I do not know the mechanism, whether it is a structure that consciously feels like a feeling.
It is conscious of the feel of moss that moss is raised carefully and that moss is worthy and you should never touch it, I think that you should not step on it, so when you step on the other way As it will be soft and fluffy what will happen, I imagine that moss will not sink into the foot type.
Because I love petal and it does not touch, Also, when I am in an unusual space like a tea room, besides flowers, the things that exist there, the feeling of the place I hit the tatami, even the light that I insert is like the texture It conscious of something. Things limitedly set in the closed space will be close up in nature. It is certainly because the tea room is an empty space where Okakura Tenshin says in the "tea book" because it is for existence to set aside for a long time.
Or is it because the tea ceremony is being imprinted that the tea room is conscious of such a feeling, or because it thinks somewhere of itself somewhat like a part of Japanese aesthetic sense?
However, both moss and flowers, both of which are intentionally created by human beings, is a natural way of thinking.
If it is intentionally created a structure that is conscious of a structure that is not touched but conscious of the feeling to the touch, it is very interesting, is not it?
見た目の感触に既視感が無い状態とは、見た目の感触と実際に触った時の感触との間に違和感がある状態では無く、そのモノの過去の経験から推測する感触とは違うように見えることでも無いような気がする。
見た目の感触に既視感が無いことと、見た目に既視感が無いことは、同じか、違うのか。
見た目に既視感が無い状態は、例えば、一見するとコンクリート打放しのような壁に見えるが、そこにモルタルの薄塗りがかけてあり、よく見るとコンクリート打放しでは無いということ。
モルタルが仕上げの壁をあまり見ることが無いから、既視感が無いとなる訳だが、それはコンクリート打放しのように見えるから既視感が無いことにつながる。この場合、コンクリートとモルタルの感触に大した差は無いし、感触の違いまで範疇に入っていない。
感触とは、そのモノの性質によるから、見た目で受け取る情報の中に含まれていて、無意識にどのような感触かを判断しているはずだが、まずは見ることで、触れるかどうか定かでは無い状態では、感触が意識に上がって来ないのかもしれない。
だから、見た目の感触に既視感が無い状態は、感触が意識に上がって来ているので、その点で言えば、見た目に既視感が無い状態とは違うことになる。
では、触れないのに見た目で感触まで意識する状態とは、どのようなコトなのだろうか。
思い付いた例は、茶室に向かう露地の苔を見た時、ふわふわの感触を意識して、踏んではいけないと思う。また、茶室の中で見る花は、花弁の感触まで意識してしまう。いずれも触れてはいけないから、見た目で感触まで意識していることになる。
どうしてだろうか、非日常的な行為だからか、そもそも茶道がそのような感触までを意識するように設えてあるからか。
触れないのに見た目で感触まで意識する状態を意図的につくり出すことができれば、それに対して既視感が無いようにすれば良いのだが。
"Feel of architecture vol.4"
A state where there is no sense of visual impression on the appearance feeling is not a state in which there is a feeling of strangeness between the appearance feel and the feel at the time of actually touching, different from the feeling estimated from the past experience of the thing I feel that it is not even visible.
Is there a feeling of visual appearance in the appearance feeling is not the same as or difference in appearance is not the same as it looks?
For example, at first glance it looks like a wall like a concrete release, but a thin coating of mortar is put on it, and it is not concrete release as you look closely.
Since the mortar does not see much of the wall of the finish, it is a case that there is no sense of deja vu, but since it looks like a concrete release, it leads to lack of a sense of deceit. In this case, the feel of concrete and mortar is not much different, and it does not belong to the range of feel to the touch.
Since the feeling is based on the nature of the thing, it is included in the information received in the appearance, and it should be judged what kind of feeling unconsciously is, but first it is not clear whether to touch or not Then, the feel may not come up to consciousness.
So, in a state where there is no sense of visual impression on the appearance feeling, since the feeling has come up to consciousness, in that respect, it will be different from the state where there is no pre-existing sense of appearance.
So, what kind of condition is it that you are aware of your appearance and feel, without touching it?
When thinking of an example that I saw the moss on the open ground towards the tea room, I think that I should not be stepping on with the feeling of fluffy. Also, the flowers seen in the tea room conscious of the feel of petals. Since neither can be touched, it will be conscious of the appearance and the feeling.
Is it because of what it is, because it is an extraordinary act, or because the tea ceremony has been set up to be aware of such a feeling in the first place?
If it is possible to intentionally create a state that is conscious of the appearance and feel until it is not touched, it should be done so that there is no sense of deceit.
見た目の感触に既視感が無いモノをつくり出す。そうすると、人は確かめたくて触らずにいられないだろう。
また、既視感が無いということは、その人の中で完結していない不完全な状態か。
その不完全な状態がアクティビティーを生むのではないか。
では、見た目の感触に既視感が無いモノとは何があるのだろうか、どういう状態なのだろうか。
例えば、目の前にソファがある、明らかにソファの形、ソファの様子をしている。ソファだから革張りにしろ、布張りにしろ、体を包み込むようにやわらかい感触があるだろうと思うが、見た目が全て木できているように見えたら、それは何だ、と違和感を覚え、今度は木だから、固いはずだと思い、その固さを確かめたくて、座ろうとすると、やっぱりやわらかい、何、と違和感が増幅する、ソファが木に見える布張りだったということ。
実存として、ソファだから木でできていたら、ソファとしての用はなさない。しかし、ベンチシートであれば木でできていてもよいから、ソファの形をした木でできたベンチシートならば用をなすが、それはソファでは無くなる。
見た目の感触の既視感とは、今までの経験が元となったものだから、その既視感に違和感自体を起こすことは難しいことでは無い気がするが、どのように違和感を起こすかは重要で、違和感を起こすこと自体が目的になってしまうと、感触からは離れて、単なるトリックアートのようになる危険性がある。
"Feel of architecture vol.3"
Create a thing with no sense of vision in the appearance feel. Then people will not be able to keep touching themselves to see it.
Also, the fact that there is no sense of deja vu is an incomplete state that is not completed within that person.
Is not the incomplete state an activity?
Then, what is the condition that there is no sense of visual impression on the appearance feeling, what is the state?
For example, there is a sofa in front of my eyes, obviously the shape of the sofa, the state of the sofa. Because it is a sofa, leather or upholstered, I think there will be a soft feel like wrapping the body, but if it looks like everything looks like a tree, that is what it is, it is a sense of incongruity, so this time it is a tree I thought that it should be hard, when I wanted to sit down, I tried to check its firmness, after all it was soft, what made me feel uncomfortable, the sofa was upholstered by the tree.
As an existence, if it is made of wood because it is a sofa, it will not be used as a sofa. However, if it is a bench seat it can be made of wood, so if the bench seat made of a sofa shaped wooden bench sheet is used, it will not be a sofa.
Although the feeling of visual sense of the appearance feeling is based on the experience so far, it seems that it is not difficult to cause the sense of incompatibility in the sense of deja vu, but how to feel uncomfortable is If it is important and it makes sense to cause discomfort itself, there is a danger that it will be like a simple trick art, away from feel.
感触は人によって感じ方が違うこともあるだろうから、モノ自体が持つ感触だけではなく、人が介在するコトにより得られる感触もあるだろう。だから、感触を直に扱うことによって人のアクティビティーにも関与できることになる。
それが食器や家具などでは、もともと人が直に使い触れるモノであるので、そこには何か目的がありアクティビティーがあって使い触れる訳だから、特に意識しなくても、感触があるのが当たり前のことだが、建築ではそれが当たり前では無い。
食器や家具と同じように建築も人が使うモノで、そこにアクティビティーが発生はするが、食器や家具と違って直に触れる所は限られている。
建築の場合、感触は触れるのではなくて、見た目で判断するコトなのだ。
人は実際に何かモノに触れる前に、そのモノの感触を過去の経験から推測する。その推測と実際の感触が合っていれば、感触自体が印象に残ることは少ないだろうが、違っていると、感触そのものに注意が行き、そのある種の違和感がそのモノの印象まで左右する。よって、感触もデザインの要素として扱える。
だから、人のアクティビティーにも関与でき、デザインの要素として扱える感触を建築に取り入れたいのだが、というか、感触で成り立つ建築を構想してみたいのだが。
触れること無く、見た目で感触を扱い、それで成り立つ建築を構想するとなると、先程の経験値からの推測と実際の感触との違和感を利用するしかないか。それでも触れないとだめだが、逆に、見た目の感触に経験値からくる既視感が無ければ、人は触らずにはいられないのではないか。
推測と見た目の感触が一致していそうならば安心で安全、不一致していそうならば、今までに経験したことが無く、見たことも無いから不安で安全かどうかを確かめたくはならないか、そこでアクティビティーが発生するのでは。
だとしたら、実際に触れるかどうかは関係無く、感触をデザインの要素として扱えるかもしれない。
"Feel of architecture vol.2"
Since feeling may be different depending on the person, there may be not only the feel of the thing itself but also the feeling obtained by the person intervening. Therefore, by directly treating the feel, it will be able to participate in human activities as well.
Since it is a thing that people can use directly in dishes and furniture in the dishes and furniture, there is something purposeful, there is activity and there is a touch to use, so it is natural that there is feeling without special consciousness As for that, in architecture it is not commonplace.
Like dishes and furniture, architecture is a thing that people use, and activities occur there, but places to touch directly unlike dishes and furniture are limited.
In the case of architecture, the feel is not touched, it is a judgment to judge by appearance.
Before a person actually touches something, he / she deduces from the past experience the feel of the item. If the guess is in agreement with the actual feeling, it is unlikely that the feeling itself will remain in the impression, but if it is wrong, attention is paid to the feeling itself, and that kind of sense of incompatibility also affects the impression of the thing . Therefore, the touch can also be treated as an element of design.
Therefore, although I would like to incorporate the feeling that can be involved in human activities and can be treated as elements of design into architecture, I would like to conceive a building that is made up of a feel.
If we treat the appearance and feel as if it is not touched, and plan to build with that, we only have to use the feeling of incompatibility between the speculation from the previous experiential value and the actual feeling. Even so, it is useless to touch them, but on the contrary, if there is no sense of dementia coming from the experience value in the appearance feeling, people can not stop being touched.
If it seems that the feelings of inference and appearance seem to be consistent, if you feel secure, safe, unmatched, you have never experienced before and you have not seen it, so you do not want to check whether it is anxious and safe, So the activity will occur.
If so, regardless of whether it actually touches or not, perhaps the feel may be treated as an element of design.
建築に感触みたいなものを取り込みたいとしたら、どうするか。感触とは字の如く「触って感じる」こと。
「触る」とは、まず「手で触れる」ことだとしたら、建築に「手で触れる」機会は建具だけか、キッチンや便器や電気のスイッチなどの設備機器もあるが、それらは除いて、建築本体に手で触れる機会は、例えば、ドアのドアノブとか、建具ぐらいだろう。
「足で触れる」ということであれば床しかない。床も素足で歩いたり、スリッパを履かないで靴下でいると、手よりもいろいろと感じる。かたい、やわらかい、つめたい、あたたかい、ふわふわする、傾いている、などなど。
前にシナベニヤを床の仕上げに使ったことがあり、クライアントは普段の生活でスリッパを履かないので、訪ねて行った時に、そのやわらかい感触に驚いたことがある。工事中は汚さないために養生シートを敷いていたし、完成後もクライアントに引き渡すまでは綺麗なスリッパで歩いていたので気がつかなかった。
そう考えると、普段の生活の中で建築に触れる機会は案外少なかったりする。家具や食器などの方が日常生活の中では触れる機会が多いだろう。
だから、家具や食器などは直に感触を味わうことになるし、それがつくる方にとってはデザインの主題になることもあるし、使う側、選ぶ側は「この箸、持った時の感触がいいの」などと言ったりして、感触が決め手になったりもする。
しかし、やはり触れる機会が少ないからか「この建築、感触がいいの」などという言葉はあまり聴いたことが無い。
我々は勉強のために建築を見学したりする時などは、設計者がたぶんここにチカラを入れていそうな所を見つけると、例えば、階段の手すりなどを、わざわざ念入りに触ったりするけれど、普段の生活の中では特別意識でもしない限り、触ったりしないだろう、階段の手すりくらいは無意識に握ったりするかもしれないが、感触までは意識していない人が多いのでは。
では設計する側は、全く感触のことなど考えていないかと言うと、そのようなことは無い。
「この部屋の壁は、ちょっとザラついた感じの壁にしたいな」など普通に考える。ザラついた感じは、まさに感触だが、触れて本当にザラついているかどうかでは無くて、見た目でザラついた感じ、光があまり反射しないで落ち着いた感じにしたいな、ということを実現したいのだ。
言葉やイメージでは感触を言っているのに、扱っているのは見た目なのである。
建築の場合は、案外これが多い。
触れることが少ないから、見た目でどのような感触を想起させることができるかを設計しているのだ。
見た目の仕上げとそこから想起される感触に違和感が無ければ、わざわざ触ることも無いし、そこで違和感を出すことも設計の内で、そうデザインすることは可能だが、そのワザとらしさみたいなものがいやらしい時もある。
家具が触れるものならば、建築を家具化するという考えもある。その一番簡単なことが造り付けの収納であったり、テーブルであったり、ベンチシートだったりする。建築を家具化すれば、直接建築に触れる機会も増えるので、感触を直に考える機会が多くなる。
ただそれらは、見た目であったり、家具化であったり、何らかの結果で感触があるに過ぎないので、感触自体が建築を決めることにならない。そうでは無くて、感触そのもので成り立つ建築はできないものかと考えているのだ。
"Feel of architecture vol.1"
What would you do if you wanted to capture what you feel like buildings? Feeling is "touching and feeling" like a letter.
"Touching" means that if you first touch it with your hands, there are opportunities for building "touching by hands" only with fittings, equipment such as kitchens, toilet bowls and electric switches, but excluding them, The opportunity to touch the building itself with hands would be, for example, the door knob of the door or the fittings.
There is only the floor if it says "touch by feet". When walking on the bare feet on the floor, wearing socks without wearing slippers, I feel more than hands. Firm, soft, cold, warm, fluffy, leaning, etc.
Before I used the sinavena for the finish of the floor, the client does not wear slippers in my normal life, so when I visited, I was surprised by the soft feel. While under construction I was laying curing sheets to keep it from getting dirty and I did not notice it because I was walking with beautiful slippers until delivery to client even after completion.
If you think so, the opportunity to touch architecture in my normal life is unexpectedly low. There are many opportunities for furniture and tableware to be touched in everyday life.
So, furniture and tableware will taste directly, and for those who make it, it may be the subject of design, and the side to use and the side to choose are "This chopsticks, the feeling when holding it And saying that 's feeling is also decisive.
However, I have never heard the word "This architecture, feeling is nice" because I have less opportunity to touch.
When we visit the architecture for studying, if we find the place where the designer probably is going to put the power here probably, for example, they carefully touch the railings of the stairs etc, I would not touch it unless special consciousness in my life, may unconsciously grasp the railings of the stairs, but there are many people not conscious of the feeling.
In the designer, if you say that you do not think about the feeling at all, there is no such thing.
I think as usual, "I want the wall of this room to be a wall that feels a little rough." The touch feeling is exactly the touch, but I'd like to realize that I do not care whether it really touches me by touching it, I feel rough with the appearance, I want to feel calm without reflecting much light.
Words and images tell the feel, but what we are dealing with is apparent.
In the case of architecture, this is surprisingly large.
Since I do not touch much, I am designing what kind of feeling can be remembered with the appearance.
If there is no sense of incongruity in appearance finish and the feeling recalled from there, there is no way to touch it and it is possible to design so that it gives a sense of incompatibility in the design, so it is possible to design so There are times when it is nasty.
If the furniture is touchable, there is also the idea of building furniture. The easiest thing to do is build-in storage, tables, bench sheets. As buildings are furnitureed, opportunities to contact construction directly increase, so there are many opportunities to think directly at the feel.
However, since they are just looks, furniture, and there is only a feeling with some result, the feeling itself does not determine the building. It is not so, I think that it can not be constructed with the feeling itself.
道と空の秩序を敷地の文脈/コンテクストとして扱い、取り込む。
道と空はどこでもある。そこに一般性と特殊性の両方の秩序を見出し、取り込むことができ、それが良好な住環境やまだ見ぬ新たな建築を生み出すきっかけになるならば、それは良いことだろう。
さしたる特徴も無い住宅街である。ただ、今のところ、建築の規模は案外バラバラ、敷地は細分化され、売買しやすい大きさに段々と変わってきているが、それでも結構マチマチ。昔からの建築と新しい建売の建築群が混在して、見渡す風景に何かその地域特有の意匠がある訳でも無い。むしろ、新しい建売の建築群の統一感ある意匠が、はじめは浮いていたが、見慣れてくると、緑も豊富で、その地域の混在した雰囲気をうまく調整しているようにも見えてくるから不思議だ。
この状況で敷地の文脈/コンテクストとして何かを見つけるのは相当難易度が高いような気がする。どこにでもあるような住宅街でもあるので、このような状況になることは常だが、いつも悩ましい。
道と空以外に、空を扱うことで建築の規模を扱うことになるので、住宅街での規模の相対性はその時に、全体の意匠や事業計画と合わせて考えるとして、今の段階で何か見落としていないか、コンテクストとして考えることができる可能性があるものを全て検討する。
"Context of site / context reading vol.5"
We treat and incorporate the order of the road and sky as the context / context of the site.
The way and the sky are everywhere. It would be a good idea if we could find and incorporate both the generality and the special order there, which will trigger a good living environment and a new architecture that is not yet seen.
It is a residential area with no signature features. However, as of now, the size of the building is unexpectedly disjointed, the premises are subdivided and gradually changing to a size that makes it easy to buy and sell, but it is still quite satisfactory. There is a mixture of old building and building of new building, and there is not anything specific to that area in the landscape you see. Rather, the unified design of the newly built buildings floats at the beginning, but as you get used to, you will find plenty of greenery that seems to be adjusting well the mixed atmosphere of the area It's strange.
In this situation it seems to be quite difficult to find something as the context / context of the site. Because it is also a residential area where you can find it anywhere, this is always the case, but it is always annoying.
Apart from the road and the sky, we will deal with the size of the building by dealing with the sky, so at the time the relative size of the scale in the residential area will be considered together with the overall design and business plan at the present stage Do not overlook or consider anything that might be considered as a context.
道をコンテクストとして扱うならば、ひとまずこれで十分として、他のコンテクストを探してみる。
道のコンテクストをさらに計画に落としていく時には、これではまだまだ不十分だが、道というコンテクストだけで成り立つほど単純なことではないと思うので、とりあえず、この程度で他を探さないと、うまくバランスが取れないような気がする。
道はどこの敷地でも切っても切れない存在なので、それを扱うことは、規模にもよるが、どこの敷地でも成り立つ一般性を獲得できる点で良いかもしれない。
道という一般性を帯びたコンテクストを取り込んだので、できれば、この敷地特有の特殊性を帯びたコンテクストを次に扱いたいのだが、それが、何か批判性みたいなものも同時に帯びると良いような気がするが。
空は特殊性を帯びたコンテクストになり得るか。空が広く感じる、それは相対的に前面道路が広いから、そして、今、平屋だから。
そうか、天空率だ。天空率はそもそも空の見える割合。空が広く感じるならば、現況の天空率を、空が広く感じる場所での天空率を、去就すれば良い。その天空率はその敷地特有の、固有の、特殊性を帯びたコンテクストと言えるのではないか。
天空率、すなわち、空の見える割合は同じだけれども、当然次に違う建築ができる訳で、元々の空の見え方が広く感じて良いということは、それを完全な秩序とみなして、そこから、天空率は同じで、ただ建築が違うとなると、秩序を乱すことになるから、そこで不完全性が成り立つ。
天空率を斜線制限の緩和処置として使うだけでなく、空がより広く見えるならば環境はよくなるだろう、本来斜線制限も空を塞がないためとも考えられるから、天空率を敷地周辺の現状の環境の物差しとして使い、それを敷地周辺の秩序とし、それに対して次どうするか、と考えれば、それまでの敷地周辺の環境と関連性ができ、法的規制が決起となるボリューム形成とは違う、現状の環境との連続性、関連性が生まれ、新たな建築による現状の環境を悪化させるような違和感が少しでも無くなる方向に行くのではないだろうか、それが天空率によれば、経済性や事業収益性も担保でき両立できる結果にはならないだろうか。
"Context of site / context reading vol.4"
If you treat the road as a context, for now it seems enough, try looking for other contexts.
When dropping the context of the road further into the plan, this is still insufficient yet, but I think that it is not as simple as to be made with only the context of the road, so for now, if you do not look for others with this level, you will be well balanced I do not feel like it.
Since the road is incomparable at any site, handling it may be good in terms of being able to acquire the generality established at any site, depending on the scale.
Since we took in the context with the generality of roads, we would like to treat the context with the peculiarity peculiar to this site next if possible, but it seems like it should take something like criticism at the same time I feel that.
Can the sky be a specialized context? The sky feels wide, because it's relatively wide front road, and now it's a flat shop.
I see, it is the sky ratio. The sky percentage is the proportion that looks sky in the first place. If the sky feels wide, you can leave the sky rate at the place where the sky feels widely, with the sky rate of the present condition. It can be said that the sky factor is a unique, unique, context specific to the site.
The sky ratio, that is, the percentage of the sky that looks the same is the same, but of course it is possible to create a different building next, so that the way the original sky looks widely can be considered as a perfect order, from there , The sky ratio is the same, but if the construction is different, we will disturb the order, so incompleteness will be established there.
In addition to using the sky percentage as a relief procedure for diagonal limitation, the environment will be better if the sky looks wider, because it can be considered that the oblique line limit is not to block the sky as it is originally, Considering it as a measure of the environment, considering it as the order around the site, and thinking about what to do next, it is related to the environment around the premises so far, it is different from volume formation where the legal regulation is determined , The continuity and relevance with the current environment will be born and will not go unnoticed so that there will be no sense of incompatibility that will deteriorate the current environment due to new construction, according to the sky ratio, economic And business profitability can be guaranteed and it will result in being compatible.
道もそうだが、コンテクストとして取り込もうとした時、秩序に関しては、不完全性をつくる方法として2通りある。
ひとつは、秩序をそのまま取り込み、何か手を加えることができるという点での不完全性と、もうひとつは、完全な秩序として扱い、それを崩して乱して取り込み不完全性をつくる。
道をコンテクストと扱った場合は、どちらでも可能だが、道の道たる所以として、どこまでも続く連続性みたいなものは想起させたいので、道の秩序をそのまま取り込み、からっぽの空間として表現し、後で何か手を加えなくては、という不完全性にする。
道というコンテクストだけでは無いが、これで敷地とその周辺をつなぐことは最低限できそうなので、とりあえず、これはこのままにする。
道はからっぽの空間でも、敷地の外の公道である限り、何も手を出すことができないという点で完全だが、その道が敷地内に入って来た途端に、そのからっぽの空間に対して何かできるようになり、からっぽの空間が何も描かれていない真っ白なキャンバスのような不完全性を帯びるところが面白く、この考え方の気に入っているところで、また、このコンテクストの取り込み方は敷地の規模として、ある程度の大きさを必要とするだろうから、それも今回の計画にも合っている。
道というからっぽの空間が不完全性を帯び、そこに異なるアクティビティーが発生すれば、オープンなパーソナルスペースが可能になり、道というからっぽ空間がオープン性も担保してくれるので、そこに、道とパーソナルスペース、からっぽとオープン、という相互作用が生まれるところがまたいい気がする。
"Context of site / Context reading vol.3"
As with the road, when trying to incorporate it as a context, there are two ways to create imperfection with regard to order.
One is imperfections that take in order as it is and can add something, and the other as treating it as perfect order, disturbing it by disturbing it and creating incomplete incorporation.
Either way is possible when dealing with the context as a context, because we want to recall something like continuity that continues as far as the way of the way, take in the way of the way as it is, express it as an empty space, later I make imperfections without having to do something.
Not only the context of a road, but it seems that it is possible to connect the site and its surroundings to a minimum with this, so let's leave this as it is.
The road is perfect in that it can not handle anything as long as it is an empty space as long as it is a public road outside the premises, but as soon as that road entered the premises, Where it is possible to do something, where the empty space is not drawn anything but imperfectness like a pure white canvas is interesting, I like this way of thinking, and how to take in this context depends on the size of the site As it will require a certain size, it also fits this plan.
When the empty space of a road becomes incomplete and different activities occur there, an open personal space becomes possible and an empty space called a road guarantees the openness so there are roads and personal I feel that the place where the interaction of space, empty and open is born again.
道はからっぽの空間として、手をつけることができないという点で完全である。そして、そこにアクティビティーが存在する。
そもそも道はアクティビティーのためにある。人が歩き、車が通り、今いる場所とどこかをつなげてくれる。
そう考えると、道は交通空間として、そして、都市空間として、また情緒的なことを含む空間としても扱うことができるだろう。
道路は土木の分野だが、からっぽの空間として捉えれば建築行為の一部に十分に組み入れることができるはず。
だが、道はからっぽの空間で異なるアクティビティーが発生するが、建築行為を計画する側からは何も手を加えることができないという点で完全な存在とみなすことができる、完全な秩序を持った存在である。
だから、道をコンテクストとして扱うならば、その完全な秩序を崩し、乱し、不完全にして取り込めば良い。そうすることによって、敷地内に異なるアクティビティーを発生させる種になるかもしれない。
からっぽであり、何か手を加えることができる、それで不完全性を担保し、前面道路と同じ秩序、例えば、幅やレベル、隅切りなど、を持ち、前面道路と連続性がある道空間を敷地内につくることも、コンテクストを取り込むひとつの手であるかもしれない。
"Site context / context reading vol.2"
The road is complete in that it can not hold hands as an empty space. And, there are activities.
In the first place there is a way for the activity. People walk, cars connect with streets, where they are and somewhere.
If so, the road could be treated as a transportation space, as an urban space, and as a space containing emotional things.
Although the road is the field of civil engineering, it should be able to fully incorporate it into a part of building action if it is regarded as an empty space.
However, while the road generates different activities in the empty space, there is perfect order that can be regarded as complete existence in that it can not add anything from the planning side of the building action .
So, if you deal with the way as a context, you can destroy its complete order, disturb, incompletely capture it. By doing so, it may become a species that generates different activities in the premises.
It's empty and you can add something with it, so guarantee imperfections, and have the same order as the front road, such as width, level, corner cutting, etc., with a road space that is continuous with the front road Making it on the premises may be one way to capture the context.
道はコンテクストか。直接道を扱うのは気が引ける。
法規制も敷地のコンテクストならば、すでにボリュームチェックで道を直接的に扱っているから、ただ、道はまず永遠に道のままだろう、そこには惹かれる。
空地ということであれば、道も空地、子供の頃、空地がたくさんあり、勝手に入って遊び場としていたが、ある日突然に柵ができ入れなくてなり、子供ながらにそんなことは予測していて、ここがだめになったから、あっちの空地とか、今日はここで、ちょっと遠征してあそことか、流れのように転々とするのが遊びのセンスみたいなことだったから、ある日突然使えなくなっても何とも思わなかったが、常に空いていること、隙間、子供は隙間好きだから、が無性に惹かれた。
だから、道は延々と続く遊び場だった。あの道、この道、あそこの道と道の違いが遊びの違いだった、この遊びをするならば、この広さが無いと、車があまり来ない所でないと、あそこの道は疲れたら居心地のいい階段があるとか。
道をコンテクストと扱いたい。扱うとしたらどうするか、空か、空間か、坂道の方が角度があるから特長があるな、とか。
そもそも建築を行う敷地は道路に接していなければならない。これを改めて考えてみると面白いかもしれない。敷地単体では存在できないということ、必ず道路とセットになる、その道路には手をつけることができない。そして、その道路は延々と続き、常にからっぽの空間のままである。
道は上を塞いだら道でなくなるのか、道たる所以の逆がパーソナルスペースか。道の上を木の枝で塞いだだけで素敵な空間にはなるけれど。
"Way is attracted"
Is the road a context? It is not easy to handle direct roads.
If the regulation is also the context of the premises, we already deal directly with the road by volume check, so the road will remain forever for the first time, we will be attracted to it.
If it is an open space, the road was also open space, when I was a child, there were plenty of open spaces, and I decided to make it a playground without permission, but one day I suddenly did not have a fence, and while I am a kid I predicted such a thing So, as this place was useless, it was like a sense of play to topple like flowing over there a little expedition here and today, sometimes it is not possible to use it suddenly I also did not think anything, but I was always attracted because it is always vacant, gaps, children like gaps.
That's why the road was an endless playground. That road, the road, the difference between the road and the road there was a difference in play, if you play this, if there is not this area, if the car does not come so often, if the road over there is comfortable There are good stairs of the place.
I want to treat the road as a context. If it is dealt with, what to do, sky, space, on the slope are angles, so there are features, for example.
In the first place the site to be built must be in contact with the road. It may be fun to think about this again. It can not exist on the site alone, it will definitely become a set with the road, you can not put a hand on that road. And the road continues indefinitely, always being an empty space.
Will the road get out of the way after closing the top, or the reverse of the way is a personal space? Although it becomes a nice space just by closing the top of the way with branches of trees.
直接的にコンテクストを扱うことにはもちろん全く興味が無い。
例えば、古い街道沿い、宿場町に見られるような、縦格子の風景をそのままコンテクストとして、デザインに直接取り入れて、縦格子のファサードなんかはつくりたくない。
縦格子のピッチや密度、あと縦格子の隙間の空隙率とでも言うのか、隙間の見え方みたいなものを去就して、縦のラインでは無い連続性があるデザインのファサードを生み出そうと試みだろう。
ただ、こういうある意味特殊なコンテクストは珍しく、まず無い。住宅街の中で、マンションや戸建てが並ぶ風景にさしたる特長など無いのが多い。
少し木や緑などあれば、それを直接的に扱うのは、例えば、古い桜の木があるなどは、桜の季節に焦点を合わせて、コンテクスト見つけたとばかりに大きな開口部をそちらに向けるなどは短略すぎる。
もし桜の木が切られたら目も当てられない、設計者が浅はかすぎるが、そうしたくなる気持ちもわかるが、そうやりたくない。
目には直接に見えないコンテクストに気がつけと言い聞かせてながら、目が充血するくらい見開いて敷地を見渡すが、そう簡単にはコンテクストの存在に気がつかない。
ただ段々と、ここにしかない地理的条件というのもあるだろう、という地名がヒントの歴史に目を向けると、大昔は川で、今は広い道ということを思い出すと、空が他より大きく感じることに気がついた。
"Context of site / context reading vol.1"
Of course I am not interested in directly handling contexts.
For example, along the old road, taking the vertical grid landscape as it is in the post office town directly as design, I do not want to make vertical grid façade something.
We are trying to create a facade with a design with continuity that is not a vertical line, leaving behind the pitch and density of the vertical grid or the porosity of the gap between the vertical grids and the appearance of the gap .
However, such a certain meaning special context is unusual, first of all. In the residential area, there are not many features such as a lot of landscapes lined with condominiums and detached houses.
If you have a little trees and greenery, directly handling it, for example, if you have an old cherry tree, focusing on the season of cherry blossoms, focusing on the context and directing a large opening to that side as you find the context is short Too near.
If the cherry tree is cut, the designer is too shallow, but I understand the feeling that I want to do, but I do not want to do that.
While watching the context invisible to the eyes, while looking over the premises as if the eyes are congested, it is not so easy to notice the existence of the context.
However, when the place name that there will be only geographical conditions that are only here and there, it turns to the history of hints, when I remember that it is a river in the past and a wide road now, the sky feels larger than the others I noticed that.
茶道という完全な形式があるから、その形式の中で、茶室のからっぽの状態が不完全性を浮かび上がせて、その不完全性に対して、茶会の度に完全にしようとアクティビティーが発生する。
これを異なる用途を併設した集合住宅の計画に当てはめると、集合住宅という完全な形式があり、その形式の中で、実体として、概念として、欠けているから、不完全性が浮かび上がり、そこに異なる用途が入れば、完全にしようとして、接点の無い異なるアクティビティーが発生して、その接点が無い所にオープンなパーソナルスペースが形成でき、そのオープンさが敷地周辺に良い雰囲気を醸し出していくようになればいい。
完全な形式とは、秩序が完全に整っていること。不完全性とは、秩序が乱れていること。
その乱れ方が実体としてだけならば、単なるそういうデザインとなるから、そこに敷地周辺から抽出したコンテクストとしての秩序を乱したものを規範として集合住宅の形式を乱してやれば、実体としての不完全性に集合住宅の形式としての不完全性と敷地周辺のコンテクストとしての秩序の乱れによる不完全性という2つの概念としての不完全性も加味されるので、そうなってはじめて不完全性が人に認識され、アクティビティーが発生するのではないか。
不完全性をつくり出してアクティビティーを発生させることが目的でなければ、完全から乱して不完全性をつくるだけでなくて、不完全性をはじめからつくり出していくようなやり方、ブリコラージュもある。
敷地周辺の文脈/コンテクストの読み取りにも、読む側のセンスとか、どこまで読み取ることができるかという能力も必要で、できれば特殊なコンテクストよりも一般的なコンテクストを見つけ出して取り入れる方が、やり方としてどこの土地でも通用して汎用性が高いので、その方が良いと思うが、一般的なコンテクストを見つけ出して、さらに深く掘り下げて考えることは、特殊なコンテクストを扱うよりも読み取り側の知見などの能力が問われる。
"Handle disturbances of context"
Because there is a complete form of a tea ceremony, in that form, the empty state of the tea room emerges imperfections, and activity is generated to make it imperfect at every tea ceremony for its imperfection .
When this is applied to the plan of multi-family housing with different uses, there is a complete form called apartment house, and in that form, as an entity, as a concept, it is missing, incompleteness emerges If you use different applications, trying perfectly, different activities without contacts occurred, an open personal space can be formed where there is no point of contact, so that its openness creates a good atmosphere around the premises It is good.
The complete form means that the order is perfect. Imperfection is that the order is disturbed.
If that disturbance only serves as a substance, it is just such a design, so if you disturb the format of the apartment housing by disturbing the order as a context extracted from the area around the site, imperfectness as an entity Incompleteness as a form of apartment house and incompleteness due to disorder of order as a context around the site are also taken into consideration, so imperfections are recognized only by human beings for the first time It is not that activity will occur.
Unless it is the purpose of creating imperfections and generating activities, there is also a way to not only create imperfections from perfection to perfection but also create incompleteness from the beginning, bricolage.
In reading context / context around the premises, you also need the ability to read the sense of the reader, how far you can read it, and possibly if you find a more general context than a special context and adopt it as a way It seems that it is better because the general purpose is also valid in the land, but finding out the general context and thinking deeper into the deeper means that the ability of the reader's knowledge and so on is better than dealing with a special context To be questioned.
敷地の文脈/コンテクストとして、敷地周辺の秩序を取り出して考えたいとしたら、秩序とは何なのか?
周辺の建物の高さ、外壁の色、窓の位置、屋根の形、建物の向き、敷地の大きさ、建物の大きさ、混沌具合、玄関の位置、匂い、法規制など、目で見て確認できるものや五感で感じることなどか。
これらは長年、敷地周辺の地域で形成されてきた暗黙のコード、ルールみたいなものか。
これらのコンテクストと呼ばれる秩序の中から、不完全性をつくるために、実体としても、概念としても、必要なものを都合よく抽出してきて、組み合わせるのか、秩序を明示し、ただそれは、その敷地周辺の地域で完全に整っている秩序だと思われるものでないと。
まず完全なものがあり、それを崩すことで不完全性を得ようとするならば、その敷地周辺の地域で完全に整っている秩序を抽出しないといけない。
そうすれば、実体としての不完全性を獲得するのは容易にできそうな気がする。完全な秩序と対比して目で見てはっきりと不完全とわかるようにすれば良いのだから。
概念としての不完全性は、人が頭の中で想うこと、感じることだとして、それは、その敷地周辺の完全な秩序を頭の中でわかっていることが前提、暗黙知と言うべきものか、なので、誰もが認識している秩序を抽出しないと、これがこじつけで、わかりづらいとだめかもしれない、アクティビティーを生むことができないかもしれない。
いまひとつスッキリしないのは、まず完全なものがあり、それを崩すことで不完全性を得ることで、本当にアクティビティーが発生するかということ。
まず完全なものから入るのは、わかりやすくて、やりやすいのだが、不完全なものをはじめからつくり出していくことができるのではないか、その方がアクティビティーがより発生しやすいのではないか、と頭の片隅で思ってしまう。
"Perfect Order"
If we wanted to consider the order around the site as the context / context of the site, what is order?
The height of the surrounding building, the color of the exterior wall, the position of the window, the shape of the roof, the direction of the building, the size of the site, the size of the building, the state of chaotic, the position of the entrance, the smell, regulations etc Do you know what you can check and feel with five senses?
These are like an implicit code or rule that has been formed in the area around the site for many years.
From the order called these contexts, in order to create incompleteness, as an entity as well as a concept, we conveniently extract what we need and combine, explicitly state the order, but that is only around the site I think that it seems to be an order that is perfectly arranged in the region of.
First of all, if there is perfect thing and trying to get imperfections by breaking it, we need to extract the order that is perfectly arranged in the area around the site.
Then, it seems easy to obtain incompleteness as entity. Because it is good to see clearly incomplete by visually contrasting with perfect order.
As incompleteness as a concept is what people think and feel in their minds, it is based on the premise that the complete order around the site is known in the mind, is it to say as tacit knowledge , So if you do not extract the order that everyone is aware of, this may be difficult to understand, it may not be easy to understand, it may not be able to produce an activity.
The thing that is not refreshing at first is that there is perfect thing first, and getting incompleteness by breaking it is really how the activity will occur.
It is easy to understand and easy to enter from the perfect one, but it seems that whether incomplete things can be created from the beginning, that the activity is more likely to occur, I think at one corner of my head.
そもそも不完全性はアクティビティーを発生させるため、異なる用途を挿入すれば、接点の無い異なるアクティビティーが発生して、オープンなパーソナルスペースができ、そのオープンさが寛容でゆるやかさを醸し出し、敷地周辺に何かよい雰囲気を与えるのが目的であり、そのよい雰囲気は自然の中では味わえない、都市の中だから味わえること。
ただオープンにするだけではパーソナルスペースにならず、人がいない寒々しい空間、ビルの足元の誰も座らないベンチ、のようになる。接点の無い異なるアクティビティーが発生してはじめて、オープンなパーソナルスペースとして成り立つ。
そして、それは集まって住むから可能になることではないか。
完全なもの、完全な形式は、言い換えれば、秩序が整っている状態で、その秩序を扱い、変え、秩序が崩れている状態になれば、不完全性を獲得できる。
例えば、対称の形は秩序が整っているが、非対称の形は秩序が崩れているとも言える。対称の形は完全だが、非対称の形は不完全とも言える。
それは、例えば、集合住宅で言えば、窓の高さが違う、住戸の高さがズレている、バルコニーが連続していないなどなど。
ただ、これは実体としての不完全性で、これだけでは単にそういうデザインです、そういう装飾です、で終わってしまい、アクティビティーは発生しないだろう。
その秩序が敷地周辺の秩序と関連性がないと、これは概念としての秩序、とも言うべきか、敷地周辺の秩序は、良く悪くも、そこでは完全と見なせるだろう。その秩序は知らずに形成された暗黙知かもしれないが、かえってそれが強度を持って迫ってくる。
新宿の繁華街しかり、郊外の分譲地しかり。
その完全な秩序に対して、相対的にズレた時、崩れた時、不完全性を獲得できるのではないか、それが概念としての不完全性。
実体として、概念として、両方の不完全性を獲得してはじめて、不完全性によるアクティビティーが発生するのではないか。
実体としての不完全性はわかりやすい。
では、概念としての不完全性の素となる、そもそもの敷地周辺の秩序とは、何であろうか。もちろん、それは文脈/コンテクストなのだが、どこを、何を、どのようにして、秩序とみなすのか、抽出するのか。
"Imperfections in order"
In the first place incompleteness generates activities, so if you insert different applications, different activities without contacts will occur, an open personal space will be created, its openness will be tolerant and gentle, the surroundings The purpose is to give a good atmosphere, its good atmosphere can not be tasted in nature, it can be tasted because it is in the city.
Just opening it will not be a personal space, it will be like a cold space with no people, a bench without anyone sitting at the feet of the building. Only when different activities without contacts occur, it is established as an open personal space.
And it will not be possible as it gathers and lives.
In complete, complete form, in other words, in an orderly state, treating and changing that order, and becoming in a condition where the order is broken, we can acquire imperfections.
For example, symmetrical shapes are well-ordered, but asymmetric shapes are said to be disordered. The shape of symmetry is complete, but the shape of asymmetry is incomplete.
For example, in a multi-family housing, the height of the window is different, the height of the dwelling unit is misaligned, the balcony is not continuous, and so on.
However, this is an imperfection as an entity, and this alone is simply such a design, it is such an ornament, it will end with an activity, and no activity will occur.
If the order is not related to the order around the site, this should be said as a conceptual order, or the order around the site is bad, but it would be perfect there. That order may be tacit knowledge formed unknowingly, but rather it comes closer with strength.
Downtown of Shinjuku, suburban selling place.
It is imperfect as a concept, whether it can acquire incompleteness when it is displaced relative to its complete order, when it collapses.
As an entity, it is not until the concept of both imperfections is acquired that activities due to incompleteness may occur.
The imperfection as substance is easy to understand.
Then, what is the order around the site in the first place that becomes the source of incompleteness as a concept? Of course, it is a context / context, but do you extract where you think, what, how and how to treat it as order?
今、集合住宅の計画を考えている。
接点の無い異なるアクティビティーを発生させることで、オープンなパーソナルスペースができないか、とずっと考えている。
岡倉天心は「茶の本」の中で「虚」を説いた。「虚」とは、何もない、からっぽの状態、そこに何かを入れる、起こすことでアクティビティーが発生する。
このからっぽの状態を不完全性と説いていた。
不完全であるからアクティビティーが発生する。
そして、茶室は「虚」であると、茶会の度にしつらえをする。からっぽであり、不完全だから、しつらえをすることができると。
ならば、不完全性をまとった集合住宅を計画できれば、アクティビティーを発生させることができることになる。異なるアクティビティーになるかどうかは不完全性のつくられ次第か。
茶室の不完全性は、茶道という完全な形式があってこと浮き彫りになるのではないか。茶道という完全な形式を茶会で実現するために、その時々で対応できるよいに、からっぽの茶室が必要なのだろう。
集合住宅も完全な形式が存在していると言ってもよいだろう。ならば、集合住宅という完全な形式の中から不完全性を生み出せばよい。
集合住宅という完全な形式がまずあって、それに不完全性をまとわせるから、人は完全な形式と比較して不完全だと思い、アクティビティーを生み出すのではないか。
そうであるならば、集合住宅という完全な塊がまずあって、それを不完全にしていく、戸数は減らさずに、規模は変えずに。
集合住宅という見慣れた完全な形式があり、敷地の文脈/コンテクストとは関係無しに、法的規制に準拠した最大ボリュームから考えたものをつくり、そこから敷地の文脈/コンテクストに合わせて、不完全なものに仕立てていく、崩していく。
人は見慣れているものが少し崩れている位が、全く痕跡なく崩れているより、不完全性を感じるのではないか。
集合住宅という完全な塊があり、それを敷地のコンテクストに沿って不完全にしていく、規模は変えずに。その時に敷地のコンテクストを都合よく使えば良い。
普通は逆で、敷地のコンテクストから集合住宅の計画が決まるが、集合住宅の規模から考えれば、敷地のコンテクストが直接形を決めることになる。その逆な加減が余計にアンバランスさ、不完全性を生むかもしれない。
前提条件は、規模を変えない、最大規模、それを敷地のコンテクストに沿って不完全にしていくのだから、どこでも可能で、かつ、敷地によって不完全さが違ってくる。それは敷地ごとで違うアクティビティーを誘発、発生させることになるし、それは敷地の文脈/コンテクストをきちんと生かした計画にもなる。
"Creating imperfections"
I am thinking about the plan of multi-family housing now.
By thinking about generating different activities without contact points, I think that I can not open an open personal space.
Okakura Tenshin preached "imaginary" in "tea book". "Imaginary" means nothing, an empty state, putting something there, causing an activity.
He was preaching this empty state as imperfection.
Activity occurs because it is incomplete.
And, tea room is "imaginary", it makes a tea ceremony every time tea ceremony. It's empty and incomplete so you can make it.
Then, if you can plan an apartment complex with incompleteness, you will be able to generate activities. Whether or not it will be different activities depends on imperfections.
Is not the imperfection of the tea room highlight that there is a complete form of tea ceremony? In order to realize the complete form of tea ceremony in a tea ceremony, it would be necessary to have an empty tea room to be able to respond from time to time.
It can be said that apartment houses also have a complete form. Then, you can create imperfections from the complete form of collective housing.
Since there is a complete form called apartment house and put together imperfections in it, we think that people are incomplete compared to the complete form and create activities.
If so, there is a complete chunk of collective housing, making it imperfect, do not change the size without reducing the number of houses.
There is a complete format that is familiar to apartment houses, regardless of the context / context of the premises, making what they thought from the maximum volume conforming to the legal regulation, from there based on the context / context of the site incomplete Tailor it to something, it will collapse.
People seem to feel imperfections rather than being crumbled at all with the trace that the familiar things are a little collapsed.
There is a complete chunk of collective housing, making it incomplete along the context of the site, without changing the scale. You can conveniently use the context of the site at that time.
Normally it is the opposite, the plan of the apartment house is decided from the context of the premises, but from the scale of the apartment building, the context of the site will decide the form directly. The opposite adjustment may unbalance extra, may cause incompleteness.
The prerequisite is that it does not change its scale, it is the largest scale, it makes it incomplete along the context of the premises, so it is possible anywhere and incompleteness differs depending on the premises. It will trigger and generate different activities for each site, which will also be a plan to make the best use of the context / context of the site.
電車同士のような接点の無い異なるアクティビティー自体を生み出すことは、建築にはできない。
建築自体は動けないから。
建築にできることは異なるアクティビティーを誘発させるだけ、建築に誘発された人々がアクティビティーを生み出す。
老子は「無」が運動の源だと説く。
それを岡倉天心は「茶の本」の中で「虚」という。
「無」だから「有」になるために運動が起こる。
「虚」とは、何もない、からっぽの状態、そこに何かを入れる、起こすというアクティビティーが発生する。
何もないのに運動が起こる訳がないと思ってしまうが、何もないから、そこに何かを満たすために運動がはじまる。
全てが満たされている状態を「有」という。
「有」だと飽和状態で動きが起きない。
「茶の本」の例えで、水差しはからっぽだから水を入れることができる、からっぽだから水差しとして役に立つ。からっぽの状態こそが水差しの本質だと。
このからっぽの状態を不完全性と説いていた。
不完全であるからアクティビティーが発生する。
不完全であるから、完全になろうとしてアクティビティーが発生するのか、あるいは、不完全であるが故にアクティビティーを誘発するのか。
建築は電車のように動くことで、アクティビティー自体を発生させることはできないので、この不完全であるから、アクティビティーを誘発して、発生させるという考え方がしっくりくる。
その不完全なさまが、敷地の文脈/コンテクストと関連し、複合用途を持ち込むことによって、接点の無い異なるアクティビティーを発生させることができ、その結果、パーソナルスペースをオープンにすることができる。
この図式でとりあえず、しっくり来るので、次に建築の不完全なさまとは何かを考えてみる。
不完全なさまといっても
実体として不完全に見えるのか、
概念として不完全をつくるのか、
ということになろうか。
たぶん、両方が必要なのだろう、と勘は働くが。
"Imperfection triggers activities"
It is impossible to build different activities themselves without contact points like trains.
Because the building itself can not move.
What you can do for construction triggers different activities, people induced by architecture create activities.
Lao prefers that "absence" is the source of exercise.
Okakura Tenshin is said to be "imaginary" in "the book of tea".
Movement occurs to become "yes" because "no".
"Imaginary" means that there is nothing, an empty state, an activity of putting something in it, causing it to happen.
I think that there is no reason for movement but there is nothing, but exercise starts to fill something there.
The state where all is satisfied is called "yes".
If "yes", no movement occurs in the saturated state.
In the "tea book" example, the jug is empty so you can put water in, so it's empty, so it serves as a jug. The empty state is the essence of a jug.
He was preaching this empty state as imperfection.
Activity occurs because it is incomplete.
Since it is incomplete, does the activity occur to become complete, or will it induce the activity because it is incomplete?
Buildings can not generate activities themselves by moving like a train, so this imperfection is triggered by the idea of inducing and generating activities.
The incomplete matter can be associated with the context / context of the premises, bringing in composite applications, thereby generating different activities without contacts, so that personal spaces can be opened.
In this tutorial, I'm going to be right, so I will think about what is incomplete construction next.
Even if it is incomplete
Does it look incomplete as an entity?
Whether it is imperfect as a concept,
Shall I say that?
Perhaps, I will work, that both will be necessary.
ずっと、集まって住むことと、敷地の文脈/コンテクストと、アクティビティーと、秩序と、パーソナルスペースについて考えている。
ひとりでは無くて、家族だけでは無くて、シェアする訳でも無くて、ただ集まって住む、要するに、集合住宅が良いところや、その暮らしの方が楽しいと思えることや、事業者側のメリットではなくて、住む側からのメリットというべきことなのか、
それが敷地の文脈/コンテクストと関連して、そこでしかできない集住の仕方や、敷地の文脈のありようみたいなものが直接集住の仕方を決めてしまうようなことが起きて、
その時に自然発生的にアクティビティーが生まれ、そのアクティビティーに複雑さがあるから、
そのおかげでオープンなパーソナルスペースが容易にあちこちに形成され、
そのオープンな感じが、ゆるやかで、おおらかな秩序を建築に与え、
その建築があるおかげで、その周りが何となくいい雰囲気になる、
ようなことになるためには、
とここまで書いて、ひとつの建築が思い浮かんだ。
やはり、あの建築は名作だ。
"Architectural aiming aim aim vol.1"
I'm thinking about living and living together, the context / context of the site, activities, order and personal space.
It is not alone, it is not just a family, it is not a reason to share it, I just gather and live, in short, it is not a merit of the business side that things that collective houses are good and those who think that their living is fun Whether it is a merit from the living side,
As it relates to the context / context of the premises, what kind of collections can only be done there and things like what seems to be the context of the premises decide how to collect dwells,
At that time spontaneous activity is born and its activity is complex,
Thanks to that, an open personal space is easily formed here and there,
The open feeling gives the building a gentle and extraordinary order,
Thanks to its architecture, its surroundings become somewhat nice atmosphere,
In order to be like this,
And I wrote so far, one architecture came to mind.
After all, that architecture is a masterpiece.
多地域移動居住が可能になると、住宅の概念、定住という概念も変わるかもしれない。
たくさんの居場所ができる訳だから、選択肢が増えれば、定住する必要が無くなるし、いや、考え方によってはたくさんの定住場所ができるとも言える。
本宅と別荘という二地域居住は昔からあるが、もっと気軽に、たくさんの居場所で居住ができるイメージが多地域移動居住。
日本は南北に長く、四季がある気候だから、日本中にたくさんの居場所があった方がその所々で特徴ある暮らしができる。
少子化で市場が縮小しても、人の流動化でそれを補うことができる。多地域移動居住でお金を落とす所を増やすのも少子化対策のひとつ。
その時に家はどうなるのだろうか?まず必要か?30年以上のローンを組むのか?
家には物としての側面もあり、宝飾品や車や洋服、小物のように、所有する喜びというのもあるから、無くなることは無いと思うが、移動しやすくするために、物は少なくなるだろう、そもそも生活用品は買わないで全てレンタルとか、そうなると、輸送の形態も変わるかもしれない。人の移動と物資の輸送が別である必要も無く、ひとつになれば、新しい業態ができるかもしれない。
暮らしが変われば、それに比例して、変わらない暮らしが炙りだされる。それは、日本の伝統的なものだったり、昔からある季節の節目の行事であったり、今はないがしろにされ、すたれそうになっていることに再び焦点があたるかもしれない。
日本人は農耕民族で、欧米人のように狩猟民族では無いから、多地域移動居住は性に合わないかもしれないが、現代では日本中どこへ行くにでも日帰りができるくらいの移動時間で済むので、それほど移動に負担がかからないから、日本を1つの自分の土地だと考えることもできる。
むしろ、現代を生きる人には、その短時間で済む移動手段を生かした暮らしは性に合うはず。自動車の自動運転が可能になる時代なれば尚更、移動の負担が減るので。
もし多地域移動居住が可能になった時、住宅や建築はどうなるのだろうか。20世紀のモータリゼーションがもたらした暮らしの変化以上のことが起これば、住宅や建築も影響を受けざるを得ないだろうから。
"The mobilization of people changes their lives"
Multilateral movement When residence becomes possible, the concept of housing, concept of settlement may change.
Because there are plenty of places to go, as options increase, you do not have to settle down, or no, depending on your way of thinking, you can say that there are plenty of settlement places.
There are two areas of residence, home and cottage, long time ago, but the image that allows people to live in plenty of whereabouts is easily accommodated in multiple areas.
Because Japan is long in the north and south and has a climate with four seasons, people who have lots of places in Japan can live distinctive lives in that place.
Even if the market shrinks due to the declining birthrate, it can compensate for it by mobilizing people. It is also one of countermeasures to declining birthrate to increase the place to drop money with multi-region moving residence.
What will happen to the house at that time? Is it necessary first? Do you make loans for over 30 years?
There are aspects as things in the home, there are things such as jewelry, cars and clothes, accessories owned pleasure, so it will not go away, but things become less to make it easier to move Probably not all of the living supplies are bought without rental, so the form of transport may change. It is unnecessary for people's movement and goods transport to be separate, and if one becomes one, a new business situation may be possible.
If life changes, proportionately, unchanged living will be broiled. It may be focused on what is traditional in Japan, an event of a seasonal occasion that is long ago, now being underestimated and becoming disappointing.
As Japanese people are agricultural races, not hunting people like Westerners, multi-region moving residence may not match sexuality, but in modern times traveling time enough to make a day trip anywhere in Japan is enough Because it does not put too much burden on the movement, I can think that Japan is one land of my own.
Rather, for people who live in modern times, the living that made use of the means of travel that is completed in a short time should suit sex. Even in the era when automatic driving of cars becomes possible, the burden of movement will be reduced.
If multilateral migration is possible, what will happen to housing and architecture? Changes in living brought by motorization in the 20th century If more than happens, housing and architecture will have to be influenced.
なるほど、混在した街、カオスの方が賑わうは、ただ単にたくさんのアクティビティーが発生するだけでなく、オープンなパーソナルスペースが形成できるからにもよる。
そうすると、治安やゴミやインフラなどの問題が解決できれば、カオス状態の都市の方がいろいろなアクティビティーがあって楽しいだろう。
ただ、そういう都市は自然とは対極になるので、いくら公園などをつくり自然を持ち込んでも、それはつくられた自然だから、人工物と大差無い。
そうしたカオス状態の都市は面白いかもしれないが、私などは自然の中にいるよりも落ち着くと思うが、やはり、自然の真っ只中に行きたい人もいるだろう。
都市が一極集中してカオス状態になれば、当然その反動で、自然の中に行きたくなる。その時は、過疎化した地域をうまく利用すれば良い。
過疎化した地域は、すなわち、人がいないということ、都市から抜け出して行きたい場所はそういう人がいない所だと思うから、そういう場所へ、例えば、週末だけとか、仕事が許せば、週単位で行けるといいな。
移動手段と通信インフラと滞在できる場所さえ確保できればいいのだから、都市の一極集中化と地方の過疎化をセットで考えれば、費用面でも解決策がありそう。
要は、一極集中化した都市に無い所と、過疎化した地域に足りない物を補い合えば良いだけ。過疎化した地域も移動手段が増えれば喜ぶし。
そうなれば、都市の一極集中化も地方の過疎化も決して悪いことでは無く、むしろその方がお互い都合が良くなる。
人生100年時代を迎え、元気な中高年が増えるのだから、自分もそうだけど、そういう人たちの行動欲を手軽に満たしてあげれば、少子化して市場自体が縮小しても、人が流動的になり、あちこちでお金も落とすしね。
多地域移動居住。
そうなると、生活自体も、家族といても、ひとりでいても、楽しそう。やはり、たくさんのアクティビティーが用意されていて、それを手軽に選択することが可能な状態がいい、精神衛生的にもいい。
こういうことを考えている人はたくさんいるだろうけど、そこに税金を投入すれば、割と簡単に解決しそうだと思うのだが、それで、みんなが楽しく暮らせそうだと思うのだが、いかがなものか。
"Multilateral moving residence"
Indeed, mixed cities and chaos are crowded, not only because there are so many activities but also because of the ability to form an open personal space.
Then, if problems such as security, garbage and infrastructure can be solved, the city in chaotic state will be more fun with various activities.
However, since such cities will be opposite to nature, no matter how much they make parks and bring in nature, it is the natural nature created, so it is not much different from artifacts.
Such a chaotic city may be interesting, but I think that I will settle down rather than being in nature, but again, some people would like to go in the midst of nature.
If the city concentrates and becomes chaotic, of course it will be a reaction and it makes me want to go to nature. At that time, you can use the depopulated area well.
I think that the depopulated area, that is, that there is no person, the place where I want to get out of the city is such a place where there are no such people, so to such a place, for example only on the weekend, if the work allows weekly I hope to go.
It would be nice if we could secure transportation means and communication infrastructure and even a place where we could stay, so it seems to be a solution in terms of cost, considering the centralization of urban areas and depopulation of rural areas.
In short, it is only necessary to complement a place that is not in a centralized city and a missing one in a depopulated area. It will be pleased if the means of transportation also increases in depopulated areas.
If so, city centralization and local depopulation is not a bad thing, rather it will be more convenient for you.
As the longevity of a century celebrates the era of energetic and lively mature age, even if I am also so, if I can easily satisfy those behaviors of those people, even if the birthrate declines and the market itself shrinks, Then, I also drop money here and there.
Multiple area moving residence.
In that case, it seems fun to live itself, family, or alone. After all, a lot of activities are prepared, it is good to select it easily, it is good for mental hygiene.
There seems to be a lot of people thinking about this, but I think that it would be easy to solve it if you put in taxes there, but I think that everyone seems to be able to live happily, but what is it like .
異なるアクティビティー同士が同時に同じ空間に存在しているならば、それぞれに全く違う世界が広がっていて、全く接点が無いから、お互いに全く見えていない状態をつくり出せるのではないか。
お互いに全く見えていない状態になれば、容易にパーソナルスペースをつくることができる。
都市のスケールで考えるならば、いろいろなアクティビティー、これを建築に置き換えると、いろいろな用途の建築か、商店、オフィス、住宅、役所、工場などなどが混在している方が、パーソナルスペースをよりオープンにつくり出すことができ、都市全体がよりオープンな方向にいき、そのオープンさは様々な交流をつくり出し、賑わいを生むかもしれない。
それとは逆に、単一のアクティビティーで構成された都市、例えば、住宅街などは、お互いが同じ生活活動の中にいるので接点が生まれ、パーソナルスペースを確保しようとすると、隔てて、個々に分断するしかなく、閉鎖的な都市の構成に成らざるを得ないのではないか、ゲートシティのように。それが悪い訳ではないが、隔てて、個々に分断をしてしまうと、地域性や土地の文脈/コンテクストの入り込む余地が無くなり、都市としては特色を出せないものになりはしないか。
異なるアクティビティー同士がつくり出すパーソナルスペースは、都市スケールだけでなく、単体の住宅や賃貸住宅のスケールでも同様に可能だと思うのだが、スケールが小さくなる分、異なるアクティビティーを盛り込めるのか、オープンなパーソナルスペースをつくれるくらいのアクティビティーが発生するのか、そこに敷地の文脈/コンテクストも取り込める余地があるのかが、まだ疑問だ。
"Personal space should be vol.2"
If different activities exist in the same space at the same time, since completely different worlds are spreading in each and there is no contact at all, it is not possible to create a state where mutual invisibility is not seen at all.
If you do not see each other at all, you can easily create a personal space.
If you think on the scale of the city, if you replace various activities, this with architecture, people with different uses, shops, offices, houses, government offices, factories, etc. are mixed, more personal space is opened , The whole city will go to a more open direction, its openness will create various exchanges and create bustling.
On the other hand, cities composed of a single activity, such as residential streets and the like are in the same living activities, so that contacts are born, and when trying to secure personal space, they are separated individually There is no choice but to become a closed city, like a gate city. Although it is not a bad translation, separating individually separately, there will be no room for regionality and the context / context of the land to enter, and will not be a city that can not feature.
I think that personal spaces created by different activities are similarly possible not only in the city scale but also in the scale of a single house or rental housing, but as the scale becomes smaller, can you include different activities, open personal space It is still doubtful whether there will be enough activity to create, and there is room for incorporating the context / context of the site there as well.
自宅で仕事をしていることが多いので、たまにしか電車には乗らないが、乗るとよく思うことがある。
外の景色が流れていく様が好きだから、大体車窓の外ばかり見ているのだが、駅に着いた時や、駅で隣に電車がいた時など、車窓越しに駅のホームにいる人や電車の中にいる人は、よく見えるし、すごく近い場所にいるのに、ものすごく遠い存在というか、もう一生会うことが無い人かもしれないし、お互い丸見えのはずなのに、全く接触することは無いし、存在感も希薄。
当たり前と言えばそうだが、近くにて丸見えなのに、別に存在感が無いし、意識もしない、見ているようで、何も見ていない、覚えていない。
物質感としてはガラス越しに全てが見えていても、存在感としては全く見えていない、という状態。
この状態が意図的につくり出せたならば、ガラス張りの住宅が実現可能になる。
ガラス張りの住宅はいくらでもあるが、そのほとんどがカーテンかブラインド、ミラーガラスなどを使用して、内と外を視覚的に分断する。そうやって分断するならば、透過するガラスを使う意味がない。ならばガラス張りにしなければいいと思う。
意図的に、デザイン的に、ガラス張りの外観をつくり、ただ普段はプライバシーを守るためにブラインドやカーテンをしているならば、そのデザインは単なる自己満足に過ぎないし、破錠している。
物質として透明で透過するガラスを使えば、当然全てが見えてしまう、なのに、見えていない、覚えていない、感心がない、意識しないのは、ガラスを隔てて、それぞれに全く違う世界が広がっていて、全く接点が無いから。
電車の中と駅のホーム、行き先が反対方向の電車同士の中など、同じ時間にそこにいても、隔たれていて、異なるアクティビティーならば、お互いに全く見えていない状態をつくりだせるのではないか。
住宅街の中で、ガラス張りにすれば、お互いが生活活動の中にいる訳だから、透明で透過していて丸見えだと、無意識でも見てしまう、見えてしまうし、見られる感じもしてしまい、プライバシーを隠すことに気がいく。
ただ異なるアクティビティー同士にすれば、ただ住宅で、賃貸住宅で、どのようにすればいいのか。
"If between different activities"
Because I often work at home, I occupy the train only occasionally, but sometimes I think when I get on the train.
People who are at the station's home through the train window, such as when you arrive at the station, when there is a train next to the station, and so on, because you like the way the outside scenery flows, People who are in the train can see it well and they are in a very close place, they may be far away or they may never meet the other again, but they should not be touched at all, , The presence is also thin.
Although it seems normal, although it is visible in the vicinity, there is no separate presence, no consciousness, no look, seems to be watching, I do not see anything, I do not remember.
As a substance feeling, even if everything can be seen through the glass, the state that it is completely invisible as a presence.
If this condition could be deliberately created, glass-housed houses will be feasible.
There are as many glass-housed houses, but most of them use curtains, blinds, mirror glass, etc. to visually divide the inside and the outside. If you divide it in that way, there is no point in using transparent glass. Then I think that I do not have to glass it.
Designing intentionally, designing a glassed appearance, but if you are doing blinds and curtains to protect your privacy normally, the design is only mere self-satisfaction and locking.
If you use glass that is transparent and transparent as a substance, you can see everything, of course, it is not visible, I do not remember, I do not have an impression, I am not conscious that the completely different world spreads apart from the glass Because there is no contact at all.
Even if you are there at the same time, such as in the train and the station home, the train in the opposite direction in the opposite direction, if you are separated from each other, if different activities, you can not create a state where you can not see each other at all .
In the residential area, if it is glassed, since it is a translation that each other is in daily activities, it is transparent, transparent and it seems like it is visible, even if you are unconscious, you will see it, you will see it, you will feel seen, I am interested in hiding privacy.
Just different activities, just in the house, in the rental housing, how to do?
建築計画の向かう先、辿り着く先を、完璧な秩序を持った場所か、少なくともそこを目指してしまう。
病院とか、刑務所とかは、建築計画として、絶対に破綻せずに、完璧さ、完璧な秩序が求められる。
ただ、全ての建築計画が完璧な秩序を持っている必要は無く、標準的な人間を想定して、その人間が完璧に立ち振る舞いができる空間を目指すのが建築計画だから、最初の標準的な人間の想定が変われば、完璧な秩序でなくても良いはずになる。
そこに、個別の人を介在させる余地が生まれ、また秩序には、街並みの、地域の、敷地の秩序があるから、秩序を媒介にして、地域と個人を結びつけることができる。
この場合の個人は、特定でもいいし、不特定でもいい。
秩序をコントロールすることにより、地域と個人を結びつけ、建築そのものの計画をそこでしかできないものにする可能性があるのではないか。
地域の秩序は、その土地の文脈/コンテクストとして読み取ることになるから、個人から読み取る秩序も同じように文脈/コンテクストと扱えばよいか。
そうすると、扱える秩序の幅みたいなものは相当広がる。秩序をコントロールすることがその建築の成否を決める可能性があるのではないか。
"If you control the order"
I will aim at at least that place where the building plan is going to be reached, where I will reach the place with perfect order.
Hospitals, prisons, etc., as construction plans, absolutely not failing, perfection, perfect order is required.
However, it is not necessary for all the building plans to have a perfect order, and it is the building plan that aims at a space where the human being can perfectly behave, assuming a standard human being, so the first standard If human assumption changes, it will not be necessary for perfect order to be good.
There is room to intervene individuals there, and order has the order of the townscape, regional, site, so that you can connect the area and individual with the intermediacy of order.
Individuals in this case may be specific or unspecified.
By controlling the order, there is a possibility of linking the region and the individual, making the plan of the building itself possible only there.
Since the order of the area will be read as the context / context of the land, should the order to be read from the individual be treated as context / context in the same way?
Then, things like the range of usable order spread considerably. There is a possibility that controlling the order will determine the success or failure of the building.
街並みには秩序みないなものがあって、それの良し悪しもあるが、それに対してどうするのか、というのも建築計画のうちである。
ただ秩序とは不思議なもので、例えば、飲み屋街の横丁やガード下などの街並みというか、通りの風景は雑然としていて、決して秩序があるとは言えないし、建築的には褒められたものではないが、夜になると、なぜか郷愁を誘ったり、魅力的に見え、その通りに漂っている秩序とは言えない秩序が良かったりする。
とは逆に、都市計画をきちんと考えて形成された街並みは秩序が取れていて、お手本にもなるが、魅力がなかったりする。
確かに、街並みの無秩序は魅力的に見える。例えば、昔の香港の九龍城などは決してその中に入りたいとは思わないが、あの雑然とした無秩序な感じは、はじめからあれを計画した訳では無くて、ただ単に人間の都合で増殖をしていったものだからか、人智を超えた構築物としての魅力があった。
無秩序を人がつくり出すのは無理だろう。それは人の思考が無秩序では無くて、何らしかの秩序、例えば、倫理や道徳や思想など、を必ず持つから。無秩序に見える秩序をつくり出すことは可能だろうけど。
だから、秩序だけを考えるならば、無秩序にはできないが、かと言って完璧な秩序である必要もない。
例えば、街並みが雑然としていて、秩序らしいものが無い場合、それに対して、同調するのか、新たな秩序を与えるのか、それとも、その街並みならではの秩序を見つけ出し、それを取り入れるのか。もちろん、街並みの秩序などはじめから無視をしている場合が一番多いが。
きっと、同調したり、新たな秩序を与えるのは誰にでもできそうで、その街並みならではの秩序を見つけ出し、それを取り入れ表現するのは建築家しかやらないだろう。
ならではの秩序に魅力があり、それが重要だと思うのは、そこに何かをつくり出さなければ、それも、そこにつくる意味が無いものでは駄目だと思う人でないと感じないことだから。
ところで、秩序は人に安心感を与えるのではないか。
どのような秩序にもよるが、人の思考は秩序が無いと成り立たないので、求められる秩序を実現できた時には満足感を与え、クライアントや関わる全ての人に安心感を与えることができるのではないか、それは建築に限らず。
"Handle order"
There are things that are not orderly in the streets, and there are good or bad of it, but it is part of the building plan, what to do about it.
Just ordered is mysterious, for example, the streets of the street such as the street of a bar street and under the guard, the street scenery is cluttered, it can not be said that there is no order, never been praised in architectural terms There is no, but at night, somehow invites nostalgia, it looks attractive, and the order that is not the order that is drifting in that street is good.
On the contrary, the townscape formed by properly considering urban planning is orderly, it also serves as a model, but it has no charm.
Certainly, the disorder of the city looks attractive. For example, I do not think that I would like to enter Kowloon Castle in Hong Kong in the past, but the chaotic and disorderly feeling is not the plan that I planned from the beginning, Because it was what I did, there was charm as a construct beyond humanity.
It is impossible for people to create disorder. That is because human thought is not disorderly, and surely has some order, such as ethics, morality and thought. It would be possible to create a disorderly order.
So, if you consider only order, you can not do disorderly, but you do not have to be perfect order to say.
For example, if the townscape is cluttered and there is nothing that seems to be orderly, why do you want to synchronize, give a new order, or find an order unique to that city skyline and incorporate it? Of course, it is the case that ignoring from the beginning, such as the order of the streets, is the most frequent.
Surely, it can be done by anyone to synchronize and give a new order, it will only be an architect to find out the unique order of the city skyline and express it by incorporating it.
It is attractive to the unique order and I think it is important because if you do not create something there, that does not feel like you are not useless if there is no meaning to make there.
By the way, is the order giving people a sense of security?
What it depends on the order, because the people of thinking does not hold that there is no order, given the satisfaction is when you can achieve the order sought, as it can be given a sense of security to all the people that client Ya involved is Not, it is not limited to architecture.
その場所でしか実現できない空間をつくること。
その場所で無くてもいい空間ではなくて、
その場所だからいい空間になるとしたい。
場所性を意識するから、いい空間が生まれる、
という図式に魅力を感じる。
場所性を意識することを宝探しに例え、
建築家はトレジャーハンター。
良くも悪くも、その場所には、何か眠っている。
それに気づき、それを活かすのは建築家しだい。
ほとんどの建築が、場所性よりも経済性を重んじていて、決して経済性を重んじることが悪い訳では無く、建築行為は経済活動そのものという側面もあるから、
ただ、場所性がないがしろにされているならば、建築の持つ魅力や素晴らしさや、それを引き出すことができる建築家の能力が必要とされていないということになるので、それでは現代の建築が、風景が荒廃していく。
自分たちの住む街が、街の風景が、他の街と、他の都市と同じで、どこかで見たような、どこでも見るような風景で、安心したくはない。
"What is important is placeability"
To create a space that can only be realized at that place.
It is not a space you do not need in that place,
I'd like to be a nice place because it's that place.
Because we are conscious about the location, good space is born,
I feel charm in the scheme.
Comparing the awareness of the place to a treasure hunt,
The architect is a treasure hunter.
Between good and bad, in that place, I sleep something.
It is up to the architect to realize it and make use of it.
Most of the buildings place importance on economy rather than placeability, it is not a bad thing to value economic efficiency, and building acts are aspects of economic activity itself,
However, if the place is undestroyed, it means that the charm and excellence of the architecture and the ability of the architect who can draw it out are not required, so then the modern architecture is a landscape It is devastating.
I do not want to worry about the city where I live, the landscape of the city is the same as other cities and other cities, as if I saw it anywhere, anywhere.
太陽の光は敷地の文脈/コンテクストになりえるのか。
そもそも、その土地の文脈/コンテクストを読み取ることが重視されるようになったきっかけは脱近代建築だった。近代建築は、世界中のどこででも成り立つ建築を目指して、地域性や土着の物を排除して、新しい建築像を築こうとした。
その結果、都市では、世界中のどこに行っても同じような建築を目にすることになり、それは次第に、近代建築の荒廃を招くことになっていった。
地域性を大事に、土着の物に目を向けて建築を計画することが近代建築の次の建築を模索する手がかりとなり、そのための手法がその土地の文脈/コンテクストを読み取ることだった。
太陽の光は世界中のどこに行っても同じようにある。
北の国と南の国では、日照時間や日射量に違いはあるだろうが、ひとつの地域の中では大差無いだろう。
だから、太陽の光が敷地の文脈/コンテクストにはならないような気がしてしまうし、陽当たりが良いことはどこでも求められるから、そこに特性や特徴を見い出すのは難しく思えてしまう。
ところが、料理と同じで、同じ食材を使っても、その食材を調理する人によって全然味が違うように、太陽の光を敷地の文脈/コンテクストと扱い、素晴らしい建築に仕上げてしまうこともあるのではないか。
それを大学生の時に「光の教会」で学んだ。
"Light is a material"
Can the sunshine be the context / context of the site?
In the first place, the reason why importance of reading the context / context of the land became more important was deconstruction of architecture. Modern architecture aimed at building which can be done anywhere in the world, trying to build a new architectural image by excluding regionality and indigenous things.
As a result, in the cities, wherever we go all over the world we see similar constructions, which gradually lead to the devastation of modern architecture.
To cherish the regionality, planning the architecture with the attention of the indigenous thing became a clue to explore the next architecture of modern architecture, and the method for that was to read the context / context of the land.
The sunshine goes the same way wherever you go in the world.
In northern countries and south countries there will be differences in sunshine hours and solar radiation, but in one area it will not be much different.
So, it seems that the light of the sun does not become the context / context of the premises, and it is hard to find out the characteristics and features there because it is required everywhere that the sunny place is good.
However, the same as cooking, even using the same ingredients, we treat the light of the sun as a context / context of the premises and finish it into a wonderful architecture so that the taste is different at all by the person who cooks the food Is not it?
When I was a college student I learned it at "Light Church".
敷地の文脈/コンテクストがお宝だといつから思っていたのだろうか。
一番最初の建築設計は大学の設計演習の時、課題が「大学のキャンパス内に教会をつくる」だった。
その時、計画地周辺の人の流れを観察していたら、計画地の中に道をつくれば、校舎間の移動の時に必ず人が通ると思った。
だから、計画地の真ん中を貫くように道をつくり、その道の両側に礼拝堂や大小の所用室を配置して、道にも屋根をかけ、道という半屋外空間がつなぐ教会を設計した。
その道は、礼拝堂や所用室と言った教会にとって必要な空間をつなぐ役目を果たすが、同時にキャンパス内の校舎という主要な空間もつなぐ役目を担ったので、この教会があることによって、人の流れが新たにでき、様々な交流が誘発されるかもしれない所が非常に気に入っていた。
その頃は、文脈/コンテクストなんて言葉は知らなかったけれど、敷地にどういう特性があるのかを考えて設計に活かすことは、最初から当たり前のようにやっていた。

"Take advantage of characteristics"
When did the context / context of the site think that it was a treasure?
The first architectural design was when design exercises of the university, the assignment was "to create a church in the university campus".
At that time, if you were observing the flow of people around the planned area, if you make a way in the planned area, you think that people will surely pass when moving between school buildings.
Therefore, we made a way to penetrate the center of the planned place, chapels on both sides of the road, and large and small working room, we also designed a church that connects the semi-outdoor space called a road by placing a roof on the road.
That road serves the purpose of connecting the necessary space for the chapel called the chapel and the serving room, but at the same time it also played the role of connecting the main space called the school building on the campus, so this church allows people's flow I liked the place where new exchange and various exchanges might be induced.
At that time, I did not know the context / context words, but I thought about the characteristics of the premises and made use of it in the design as it is normally done from the beginning.
宝探し。
敷地の文脈/コンテクストを読み取ることを、ずっと前から宝探しだと思っている。
その敷地に眠っている文脈/コンテクストというお宝を探し出し、それを建築計画にのせて提示するお仕事。
だから、私はトレジャーハンター。
お宝はそう簡単には見つかりません。なかなかわからないように、巧妙に隠してあったりします。時には、わかりやすくお宝があったりしますが、それはダミーでその奥に本当のお宝が隠れていたりします。
お宝を探し出すためには、もちろん知識と経験が必要ですが、一番大事なのは、そこに必ずお宝はある、という強い信念。これが無いとお宝は見つかりません。
はじめから宝探しをしないこともできますが、そこにお宝が必ずあるならば、宝探しをした方がいいですよね。
"treasure hunter"
Treasure hunt.
I think that it is a treasure hunt for a long time to read the context / context of the site.
A task to find the treasure that is sleeping on the site / context and present it on the building plan.
So, I am treasure hunter.
Treasures can not be found so easily. I hide it carefully so as not to understand easily. Sometimes, there are treasures easy to understand, but it is a dummy and real treasure is hiding behind it.
Of course knowledge and experience are necessary to find treasure, but the most important thing is the strong belief that treasure is certainly there. If this is not found treasure can not be found.
You can also skip treasure hunting from the beginning, but if there is treasure there surely, you should do a treasure hunt.
桜の木がある。
道路の反対側の小さな公園にある。
春になると満開の花が舞う。
北側だから日中は陽を浴びて浮かび上がる綺麗な桜が部屋から見られるだろう。
今計画中の敷地の文脈/コンテクストを読み取ろうとすると、最初にその桜の木が目に入る。その敷地の良い所、特徴的な所、生かしたい所はどこかとまず探してしまう。
ちょうど敷地に対して、道路の反対側の正面にあるから、設計者ならば誰でもそれを室内から愛でるようにする計画をパッと思い描くだろう。
1年のうちで桜を楽しめるのはせいぜい2週間位、その2週間を楽しむための計画。敷地の道路に面する以外の3面は隣家に囲まれているから、余計に桜の木に目が行く。
桜が部屋からよく見えるように、桜に向かって大開口を設けるのが常套手段か。大開口を開けても北側で道路側だから、日射もプライバシーも問題無いだろう。
この敷地はまだ良い方なのか、敷地周辺が混沌としていたり、例えば、分譲地だったり、都市のど真ん中だったりすると、尊重すべき文脈が無い場合もある。
ただね、桜の木に注目して、それを愛でる計画でいいのだろうか。桜の木が枯れてしまったら、桜の木が切られてしまったら、どうするんだ。それでも建築計画が成り立つ強度があるのか。
桜の木に焦点を当てて、敷地の文脈を読み取ったと思うのが甘いのではないか。
桜の木があるということは、そこに都市のスケールとしては空地、空間が存在するということではないか、その桜の木はその空間に変化を与えるパラメーターとして扱えば良い、だって1年の内で2週間しか影響を与えないのだから。
その空間に対して、何ができるのが設計者の優劣が問われる所か。
桜の木が見えるように大開口を設ければ、その後にどうなろうとも保身ははかれるのに、それでは納得がいかない。
どうする。
それは建築家として、技量が問われるところだ。
"Sakura blooms"
There is a cherry tree.
It is in a small park on the other side of the road.
Flowers in full bloom will dance in the spring.
Because it is on the north side, beautiful cherry blossoms that will emerge in the sun during the day will be seen from the room.
When trying to read the context / context of the site under planning, the cherry tree comes first to the eyes. I will first find something where the good place, the characteristic place, the place I want to make use of that site.
Just in front of the premises in front of the other side of the road, we will imagine a plan to make everyone as a designer to love it from the room.
We can enjoy cherry blossoms within a year for at most two weeks, plan to enjoy the two weeks. Three sides other than facing the road on the premises are surrounded by the neighboring house, so the eyes go unnecessarily to the cherry blossoms.
Is it a usual way to set up a large opening towards the cherry blossoms so that cherry blossoms can be seen well from the room? Even if you open a large opening, you will not have solar radiation and privacy as it is on the roadside in the north.
Does this site is still better, such of, or has been the site around the chaos, for example, or was a subdivision, and or was right in the middle of the city, in some cases context should respect there is no.
But I wonder if you can pay attention to cherry trees and plan to love it. If the cherry tree withers, what will you do if the cherry tree is cut. Still there is the strength that the building plan is established?
Is not it sweet to think that reading the context of the site, focusing on cherry trees?
The fact that there is a cherry tree, there in open areas as the scale of the city, or does not mean that space is present, the tree of the cherry blossoms may be handled as a parameter that changes in the space, because of the year 2 It only affects weeks.
What can be done about the space where the superiority or inferiority of the designer is questioned.
If you set up a large opening so that the cherry blossoms can be seen, then whatever you do can protect you from anything, then it is not convincing.
what will you do.
As an architect, the skill is questioned.
全く同じ条件でも、建築する敷地が違うと、例えば、何も無い野山、郊外の分譲地、都市のど真ん中、などのように違うと、当然出来上がる建築は違うはずと、考える前から当たり前のように思ってしまう。
それは、その敷地の文脈/コンテクストを読み取り、それに対してどのように構想するかが、建築設計の第1歩だと自然に思っているからだろう。いわゆるコンテクスチュアリズムという考え方。
この考え方には賛否があるが、それは読み取った文脈をどう扱うか、読み取った後の構想の末に出来上がった建築に賛否が起こるだけで、建築が土地の上に建ち、そこから動けない以上、その土地の素性を読み取るところからはじめるのは当たり前のことで、むしろそれは、建築という行為に対する設計者の誠意だと思う。だって、建売には、そのような考えは存在しないから、野山も分譲地も都市のど真ん中でも同じ物を建てるのだから、部屋数、nLDKを満たすだけだから。
読み取った文脈をどう扱うかという設計者の態度が、敷地をどう読み取るかということにつながる。
この場合、文脈とは、例えば、その敷地や周辺の土地の歴史的背景であったり、街並み、地理的状況、周辺環境、お隣さん、気候気象、敷地の形状や高低、地盤の強弱なども入るかもしれない。
この文脈の中には良いものも悪いものもある。その判断も含めて読み取りだが、その文脈に対して、設計者はどういう態度を取るのか。そのまま受け入れるのか、手を加えるのか、迎合するのか、問題解決するのか、理想に当て嵌めるのか、などなど。
その態度に応じて都合良くその敷地の文脈を読み取ることになる。
この都合良くとは、誰にとって都合が良いのかでも違う。設計者にとって都合が良いのか、特定の個人に対して都合が良いのか、不特定の個人に対してか、不特定の大多数なのか。
住宅などの比較的小規模な建築ならば、そこに住むことになる住人に向けて都合が良くなるように、あるいは、住人をもっと一般化した不特定の個人に向けて都合が良くなるように、集合住宅はこれかな。
美術館や役所などの公共性の高い建築ならば、不特定の大多数にとって都合が良くなるように。
設計者にとって都合が良いということもある。それが作品性につながり、その人が設計する価値が出てくるから。
いずれにしよ、敷地の文脈を読み取る時点で設計がはじまっていることになり、そこからすでに設計者の優劣や、これから建つ建築の良し悪しも決まってくることになる。
"Read Context / Context"
Even under exactly the same conditions, if the site to be built is different, for example, if it is different like Noyama with nothing, suburban selling place, in the middle of a city, etc., the architecture that will be completed will naturally be different, I think.
It seems that it is natural to think that it is the first step in architectural design to read the context / context of the premises and how to conceive it. The idea of what is called Contextualism.
Although there are pros and cons, there is a pros and cons, but this is because the architecture is built on the land and can not move from there just because pros and cons of the finished architecture is done at the end of the concept after reading, It is commonplace to start from reading the identity of the land, rather it is the designer's sincerity to the act of building. Because there is no such idea in the sale, because Noyama and the selling district build the same thing in the middle of the city, it only satisfies the number of rooms, nLDK.
The attitude of the designer as to how to handle the read context leads to how to read the site.
In this case, the context means, for example, the historical background of the site or the surrounding land, the cityscape, the geographical situation, the surrounding environment, the neighbor, the climate weather, the shape and height of the site, the strength of the ground, etc. It might be.
There are good and bad in this context. Reading including that judgment is read, but what kind of attitude will the designer take for that context? Whether to accept as it is, whether to add a hand, to meet, to solve the problem, to fit the ideal, and so on.
It will conveniently read the context of the site according to its attitude.
What is convenient for this is different for everyone. Is it convenient for the designer, whether it is convenient for a specific individual, for an unspecified individual, or an unspecified majority?
For relatively small-scale buildings such as houses, so that it will be more convenient for residents who will live there, or to become more convenient for unspecified individuals who have more generalized residents , This is the apartment house.
If public buildings such as art museums and government offices are constructed, it will be convenient for the majority of unspecified people.
Sometimes it is convenient for the designer. Because it leads to workability and the person worth designing comes out.
In any case, the design is starting at the time of reading the context of the premises, from which the superiority of the designer and the good or bad of the architecture to be built will be decided.
とにかく建築を見る時は歩き回る。立ち止まるのは、全体を歩き回った後。
建築の外を歩き回りながら、どういう環境の中に建っているのだろうか、この環境の中での建築の建ち方は、などと考えながら。
知らない街に行っても同じ。とにかく歩き回る。地図で大体の位置を頭に入れながら、とにかく歩く。どこか観光名所と言っても、行かなくても想像がついてしまうことも多く、あるいは、一目見れば気が済む所が大体観光名所なので、余程行きたい名所がたくさんない限り時間を持て余してしまう。
ましてや2度3度も行ったことがあるような場所だと余計に時間が余る。間に何か美味しい食べ物や物欲を刺激するような物を挟まない限り、意外としんどい、帰りたくなる。
となるのは、その街自体が自分にとって、そもそもつまらないからだろう。
大学生の頃は、夏休みや春休みが長く、友達の知り合いがニューヨークのソーホーに住んでいて、都合が合えば、泊めてもらえたので、1ドルのホットドッグばかり食べていればいいや、と思い、一番安いエアチケット、その頃は往復で5万円台だったような、を買いよく行っていた。
その泊めてくれた人は画家で、ニューヨーク中の美術館やギャラリーを全て見られるフリーパスを持っていたので、行くとそのパスを借りて、マンハッタン中を歩いて、地下鉄にも乗ったか、美術館やギャラリーをたくさん回り美術作品を見まくっていた。
飽きることが無かった。その頃のニューヨークは治安が悪かったので、地下鉄に乗っている日本人なんかいなかったし、大通りはいいけど、近道なんて言って、1本裏通りに入ったら、雰囲気が危ないなんて当たり前だったが、それでも1ブロック違うごとに景色や雰囲気や人種が変わったりして、歩いているのが楽しくて仕方がなかった。
マンハッタンの超高層ビルの足元には時々、広場みたいになっていたり、階段があったりして、歩き疲れた時に腰掛ける場所としては丁度良かった。
特に、ミースのシーグラムビルの足元の広場状のスペースは大のお気に入りで、よく腰掛けて煙草を吸い、ひと休みしていた。そこでホームレスに煙草を無理矢理奪われたこともあったけれど、なぜかその場所に座っていると落ち着く。
周りは超高層ビルに囲まれていていて、街の喧騒のど真ん中にいるのに、そこに腰掛けた途端にパーソナルスペースができ、別に何をしていようが構わない、ような雰囲気に包まれる。
どうしてだろう、といつも考えていた。自分の周りに壁が無くオープンなのに、周りからは断絶されている感じがする。旅行者だからだろうか、生活者だったら違うのかな、いや、そもそも、この広場状の空間がそう雰囲気を持った場所だからかな、それもあるかもしれないが、他のビルの足元でも同じような。
このパーソナルスペースを住宅と見なしても良いならば、住宅は最もパーソナルなスペースだと思うから、都市の中で壁ひとつ無くオープンな住宅が成り立つことになる。
そう言えば、ミースのファンズワース邸の透明ガラスを不透明な石と同じ、と言った解釈があったことを思い出した。
ある環境の中で断絶することと、壁が有るか無いか、透明か不透明か、オープンかクローズドかは、関係が無いんだとその時に学んだような気がする。
"Personal space should be vol.1"
Anyway walking around when I see architecture. Stopping is after walking around the whole.
While walking around the outside of the building, what kind of environment are you building, how to build the building in this environment, etc.
It is the same even if you go to a city you do not know. Walk around anyway. Walk anyway while putting the approximate position on the map in mind. Even if you mention sightseeing spots somewhere, there are many things you can imagine even if you do not go, or the place where you feel comfortable is a sightseeing spot at first sight, so long as you have plenty of sights to go to, .
In addition, it's extra time if you are in a place you've been doing twice or three times. I want to go home unexpectedly and frightfully as long as there is nothing something that stimulates something delicious food or greed.
It will be because the city itself is boring for me.
When I was a college student, I had a long summer vacation or spring break, my friend's friend lived in Soho, New York, and if convenience was convenient, I was able to stay over, so I thought that I should eat only 1 dollar hot dogs, I bought a lot of cheapest air tickets, at that time it seemed like 50,000 yen round trip.
The painter who stayed at it was a painter and had a free pass to see all the museums and galleries in New York, so I decided to take that path and walk in Manhattan, ride the subway, museums and I went around a lot of galleries and saw art works.
I did not get tired. Because the security was bad at that time in New York, there was no Japanese on the subway, and the main street was fine, but it was natural to say that the atmosphere was dangerous when going into the back street saying a short cut, but even so The scenery, atmosphere and race changed every time one block differed, It was fun to walk and it could not be helped.
Sometimes at the foot of a skyscraper in Manhattan, it looks like a plaza and there are stairs, just right as a place to sit when you are tired.
Especially, the plaza-like space at the feet of the Seagram Building of Mies was a big favorite, sitting well and sucking cigarette and was taking a break. There were also cases where homeless people were forcibly taken tobacco, but somehow they settled down sitting in that place.
It is surrounded by skyscrapers and is in the middle of the hustle and bustle of the city, but as soon as you sit there you will have a personal space and you will not be afraid to do anything else. .
I always thought of why. Although there is no wall around me, it is open, I feel that it is cut off from the surroundings. Is it because it is a traveler, if it is a living person, is it different? No, in the first place, this plaza-like space seems to be a place with an atmosphere, maybe it may be, but even at the feet of other buildings .
If it is okay to consider this personal space as a house, it seems that the housing is the most personal space, so an open house will be established in the city without one wall.
By the way, I remembered that there was an interpretation saying that the transparent glass of Mrs. Fawsworth's house was the same as the opaque stone.
There seems to be learning at that time that there is no relationship between disconnection in an environment and whether there is a wall or not, transparent or opaque, open or closed.
歩き回る、とにかく歩き回る。
この建築いいな、知りたいな、や
その建築を見に行くことが目的の時は
その建築をまず体験したいと思う。
建築に対して見る点はたくさんある。
周辺の環境に対してどのように建っているか、
外観のデザイン、建築周囲の外構デザイン、
建築内部に入れるならば、エントランス、空間構成、
室内に入れるならば、内装のデザインなど。
さらに、もっと細かく見ていけば、
周辺の環境に対して、
この建築は何か調和をはかろうとしているのか、
周辺環境の問題点を解決しようとしているのか、
周辺環境から影響を受けていることは、
逆に影響を与えていることは、
なぜその建ち方をしているのか、
法的規制に対する解決方法は、
などなど、きりが無い。他の点も同じ。
最後は可能ならば実測してスケッチまでする。
が、まず体験したいと思う。
きっとそれは、学生の時に、何も無いから、知識も経験も無いから、目の前の建築から何かを得ようとした時に、とにかく、この建築はどうなっているのか、事前に資料に当たっていたとしても、自分で確かめないとはじまらない。そのためにはまず、その建築の周囲を歩き回り、建築の中に入っていき、さらに歩き回り、その建築を体験して、それで何かを感じ、考え、言葉にするしかないし、それしかできなかったから。今まで数え切れないくらいの建築を見て来たが、はじめの見方が染み付いてしまい、見たい建築の前に立つと、スイッチが入ったように突然歩き回りはじめる。
学生や20代、30代前半の頃は、写真をよく撮った。スケッチもしたが、短時間でその建築から何かを得ようとした時には、写真のフレームが有効のような気がしていたから。
なぜ短時間か?海外へ建築を見に行く時は大体、建築ツアーを利用し、ツアー終了後、そのまま日本に帰らずに延泊して、時には1ヶ月位いて、さらに見て回った。自分で見て回る時はそんなに短時間な制限は無いが、ツアーだと1ヶ所15〜30分で見学なんてこともよくあった。ツアーを利用したのは、その方が効率良く、短い期間で多くの建築が見られるから。だから、1ヶ所の滞在時間が短いのは仕方がないことだが、15〜30分は短すぎる。
建築家が長い時間を掛けて設計し、施工したものを、例え、規模が小さくても、15〜30分で理解するのは難しい、大した建築でなければ一瞬で終わるが。
だから、最初の頃は、後でも見ることができるように写真をたくさん撮って、滞在時間の短さを補っていた。
学生や20代、30代前半の頃にはすでにデジカメはあったが、画質が今ほど良くなく、メモリ容量も少なくて枚数が多く撮れないこともあり、まだフィルムカメラ全盛だった。1ヶ月位海外へ行く時にはフィルムを100本位持参し、ほとんど使っていた。
今と違って、20世紀には、建築を世の中に広めようとしたら、写真しかなかった。1枚の写真が世界中飛び回る。だから、建築家は1枚の写真でその建築の全てがわかるようにする。ここから見れば、その建築の全てがわかる場所をつくる。
その場所を探し出すのにも写真を撮る意味があった。すなわち、20世紀の建築家はイメージの中に写真のフレームがあり、常にそのフレームを意識しているのではないかと、段々と思うようになっていたから、写真を撮ることでその建築の理解が深まると考えていた。
そして、短期間でたくさんの建築を見て、たくさん写真を撮っていると、建築家や建築の規模や用途や立地条件、国や地域が違っても、写真のフレームにおさめて見るという行為で、1つの絶対的な基準ができ、それによって対等に比較することが可能になるので、これは建築の良し悪しを見て判断する時に非常に役立ち、とても勉強になった。建築の視覚情報に対する扱い方はこれで随分鍛えられた。
"Viewpoint of architecture vol.1"
Walk around, walk around anyhow.
This building is nice, I want to know,
When it is the purpose of going to see that architecture
I would like to experience the architecture first.
There are many points of view to architecture.
How it is built against the surrounding environment,
Exterior design, external design around the building,
If you put it inside the building, entrance, space composition,
If you put it in the room, interior design etc.
Furthermore, if you look more closely,
For the surrounding environment,
Is this building trying to harmonize something?
Is it trying to solve the problem of the surrounding environment,
It is affected by the surrounding environment,
On the other hand,
Why are they doing that way,
As a solution to legal restrictions,
There are no scratches, such as. The other points are the same.
Finally, measure if possible and sketch.
But first I want to experience.
Surely it is because there is nothing at the time of a student because there is nothing, knowledge and experience, so when we tried to get something from the architecture in front of us, anyway, I was hitting the materials in advance as to what is going on with this architecture Even if you do not check it yourself it will not start. To do that, we first wandered around the architecture, entered into the architecture, further walked around, experienced the architecture, so we had to do something, think, and make it, so we could only do it. Although I have looked at countless constructions until now, the first view gets stuck and I stand before the architecture I want to see, it suddenly begins to walk like a switch enters.
Students, 20s, early 30s, I took a lot of pictures. I did sketching, but when I tried to get something from that architecture in a short time, I felt that the frame of the photo was valid.
Why for a short time? When I go abroad to go to see the architecture, I usually use a construction tour, staying overnight without going home as it is after the tour, occasionally around a month and watched further. There is no such a short time when looking around by oneself, but on a tour it often happened that visiting in 15 to 30 minutes at one place. We used the tour because it is more efficient, because many buildings can be seen in a short period of time. So it is unavoidable to have a short stay in one place, but 15 to 30 minutes is too short.
Even if the scale is small, it is difficult for an architect to design and implement it for a long time, it is difficult to understand in 15 to 30 minutes, but if it is not a large construction it ends in a moment.
So at the beginning, I took a lot of photos to make it possible to see it later, and compensated for the short staying time.
Students, 20s, early 30s already had digital cameras, but the picture quality was not as good as it is now, memory capacity is too small to take many pictures, and still film cameras were at its best. When I go overseas for one month I brought 100 films and used mostly.
Unlike now, in the 20th century, when trying to spread architecture to the world, there were only pictures. One photo fly around the world. So, the architect makes a single picture to show you all of the building. From here, I will make a place to understand all of the building.
It was meaningful to take pictures to find the place. In other words, architects of the 20th century had a frame of photograph in the image, and it seemed to me that it was always conscious of the frame, taking photographs deepens the understanding of the architecture I thought.
And if you look at a lot of architecture in a short period and take a lot of pictures, even if the size and use of the architect and the building, the location conditions, the country and the region are different, the act of seeing in the frame of the picture , One absolute standard can be made, which makes it possible to compare equally, so this was very helpful for judging by looking at the good or bad of the architecture and it was a great learning experience. This way of handling the visual information of the architecture has been trained considerably with this.
冬と夏の両方を快適に暮らすためには、高気密高断熱の家にしないこと、ちょっと意外に思う人がもいるかもしれません。
高気密高断熱の家は夏により暑くなり、冷房をかけ続けていないといけないので、電気代が余計にかかります。これが魔法瓶効果。
冷房をかけ続けてもいいように、その電気をまかなうことを目的にソーラーパネルを屋根に載せる、それで売電もできるので、ソーラーパネルの設置費用はまかなえる、という考え方もあります。
ただし、都内23区内では無理、屋根の面積が取れなくて、ソーラーパネルをたくさん載せられないから。
ただ、仮にソーラーパネルをたくさん載せることができたとしても、不自然ですよね、おかしな話。
意図的に高気密高断熱にして、そのために夏の室温が上昇するから、それを抑えるために冷房を人工的に掛け続け、その冷房の電気を補うためにソーラーパネルを設置する。
全てが余分なこと。高気密高断熱にしなければ、そのために夏の室温が上昇することは無いから、室温上昇を抑えるための冷房がいらなくなり、その冷房の電気を補うためのソーラーパネルも設置する必要が無くなる。
ただし、冬を考えるとある程度の断熱性と気密性は必要で、それに自然の力を利用しないといけません。
自然の力とは、日射と通風です。
冬の晴れた日の日中の南側の窓には、ストーブ1台分と同じ量の太陽エネルギーがあります。それは日中ずっとストーブをつけているのと同じことです。これを利用しない手はない。
ただ、窓ガラスの断熱性は、外壁と比較して著しく低いので、南側にとにかく大開口を開ければ良いという話ではない。逆に、断熱性が低いから、外の熱が伝わりやすいので、太陽エネルギーを利用できるとも言えますが。
目標とする室温から住宅全体の断熱性能が決まり、その断熱性能から窓の総面積の上限が決まります。その窓の総面積の範囲内でどれだけ南側に窓を振り分けることができるのかが、日射利用のポイントです。
夏は、全ての窓に日除けを設け、屋根の断熱性能を高め、外の熱が侵入して室温を上げるのをなるべく防ぎ、その上で、室温より外気温が下がる夜間などに窓を開け通風し、排熱して、室温を下げる、のが基本的な考え方です。
通風もただ単に窓を開ければ風が通る訳では無くて、風向と窓の開け方がポイントになります。
冬も夏もなるべく暖冷房に頼らない生活の方が、光熱費もかからないし、快適だと思いませんか。そのためには、単純に高気密高断熱の家にすれば良い、という訳では無い所が面白いですね。
"How to make a warm summer cool house in winter vol.3"
In order to live comfortably both in winter and summer, there may be people who do not make it a high airtight, highly insulated home, some people surprisingly surprised.
High airtight and highly insulated houses get hotter in the summer, so you have to keep on cooling and electricity costs extra. This is a thermos bottle effect.
There is also the idea that solar panel installation costs can be covered so that solar panels can be placed on the roof to solve the electricity so that they can continue cooling, so it can also sell power.
However, it is impossible in the 23 wards of Tokyo, because the area of the roof can not be taken, so many solar panels can not be placed.
However, even if I could put a lot of solar panels, it's unnatural, is not it strange?
Intentionally high airtight and highly insulated, so the room temperature of summer will rise, so keep air conditioning hung artificially to curb it, and install solar panels to supplement the electricity of the air conditioning.
All is extra thing. If it is not highly airtight and highly insulated, therefore, the room temperature of summer never rises, so cooling for suppressing rise in room temperature is unnecessary, eliminating the need to install a solar panel for supplementing the electricity of the cooling.
However, considering winter, some degree of heat insulation and airtightness are necessary, and we have to use the power of nature for it.
The power of nature is solar radiation and draft.
There is the same amount of solar energy as the one stove in the southern window of the day during the sunny day of winter. It is the same as wearing a stove all day long. There is no hand that does not use this.
However, the insulation property of the window glass is significantly lower than the outer wall, so it is not a story that it is enough to open a large opening in the south anyway. On the contrary, since insulation is low, outside heat is easy to transmit, so it can be said that solar energy can be used.
The adiabatic performance of the entire house is determined from the targeted room temperature, and the upper limit of the total area of the window is determined from its heat insulation performance. The point of use of solar radiation is how far the window can be distributed to the south within the total area of the window.
In the summer, a shade is installed in all the windows to increase the heat insulation performance of the roof, to prevent as much as possible from raising the room temperature by the invasion of outside heat, and then open the window at night or the like where the outside temperature drops below room temperature, It is a basic idea to exhaust the heat and lower the room temperature.
Ventilation is not just a way for wind to pass if you open the window, the direction of the wind and how to open the window is a point.
Do not you think that living without relying on heating and cooling as much as possible in winter and summer, does not cost utilities and is comfortable. For that reason, it is interesting that there is no place simply to be a house with high airtightness and high insulation.
スーッと閉まる感じがよくて、毎朝、珈琲缶を開け閉めするのが楽しくて、使いたくなる、触りたくなる茶筒。外蓋が載せただけで、精巧なつくりゆえに、自然にスーッとゆっくり落ちて、ピッタリと寸分狂わずに閉まる。その感じがたまらなくよいのである。
京都の開化堂の茶筒を使いはじめて1年が過ぎた頃、京都に行く用事があり、Kaikado Caféに立ち寄った。三十三間堂に行った帰り、夕方の新幹線に乗るまでの間、コーヒーが飲みたくて。
少し疲れていたので、コーヒー1杯で長居をしてしまい、そろそろお店を出ようかと、その前にトイレでも、と思い帰ってきたら、
「今からTVの取材が入りますが、いいですか?」と店主に言われ、あまりに突然でいいも悪いもなく「は、はい」と答えたら、すぐにどばどばと人やカメラが入ってきて、目の前で取材がはじまった。
あまりにも目の前で、映るのは構わないが、顔を上げて取材の様子を見ていたら、もろに映りそうだったので、さすがにうつむき加減で、耳だけで取材の様子を伺っていた。
タレントの方が茶筒について質問をしているらしく、何を質問したかは聞き取れなかったが、店主の答えだけが聞こえてきて、
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
ちょっと意外だった。音を意識することが無かったから。確かに、茶筒を開けた時の感触は、毎朝のことだから覚えていて、とても気持ちのいいものだとわかるが、音は、まあ、音も感触のうちのような。
と同時に、この店主の答えを聞いて、自分の中ではハッとするものがあった。音が良ければ大切な物を入れてくれるかもしれない、なんて、なんて素敵なんだと。確かにそうだな、感触がいいとそれを大事にしなくてはと思うよな。
てっきり開化堂の茶筒は、外蓋が載せただけ自然にスーッと閉まるのを売りにしているのかと思っていた。その精巧さは海外でも有名らしく、私がお店に行った時も中国の方が1人で買いに来ていて「中国でも有名だ」と店員と英語で話していた。
だから、私が購入したもの中に外蓋が自然に閉まらないものがあり、手直ししてもらったこともあった。後で考えてみれば、茶筒は金属だから、冬と夏で伸び縮みするだろう。冬に製作したら、夏には、例え0.1ミリでも伸びたら、閉まらなくなるはず、製作時にどうしているのだろう、とききたくなった。
取材中、もう帰ろうかと思っていたので、コーヒーも無く、水も無く、30分くらい、あまりにも目の前なので席を立つ訳にもいかず、どうしたものかと思っていたけれど、店主の
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
という話が聞けて、京都に来た甲斐があったと思った。大切な物を入れてもらうために茶筒をつくる、そのために音、すなわち感触を良くするために自分たちの技術と知識を使う。
音が良ければ大切な物を入れてくれるだろう、なんて本当に素敵な考え方だ、素晴らしい。
建築に例えるとどうなるのだろう、帰りの新幹線でずっと考えていた。
"Lovely way of thinking"
It feels good to close with Su, and every morning, it is fun to open and close the coffee can, and you want to use it, you want to touch it. Just by placing the outer lid, because it is elaborate making, it falls naturally and suddenly, it closes perfectly and not crazy. That feeling is unbearably good.
I used a tea ceremony in Kyoto's Kaidokudo for the first time after a year, I had something to go to Kyoto, stopped by Kaikado Café. I went to Sanjusangendo on the way home and wanted to drink coffee until I got on the Shinkansen in the evening.
Because I was a bit tired, I made a long cookie with a cup of coffee, so I decided to leave the shop soon, I thought of going to the restroom before that,
The shopkeeper told me that "TV interviews are coming in from now," but the shopkeeper told me that, if it is too sudden and there is neither good nor bad, and answering "Yes, yes", people and cameras will soon I came in and interview started in front of my eyes.
I do not mind seeing it in front of my eyes, but as I looked at the state of the interview with raising my face, it seemed to be revealed as well, so I was asking about the state of the interview with just my ears .
The talent seemed to be asking questions about the tea ceremony, I could not catch what you asked, but I heard only the shopkeeper's answer,
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
It was a bit surprising. Because I was not conscious of the sound. Certainly, as I remember the feeling when I opened the tea chestnut, as I remember it every morning, I remember it is a very pleasant feeling, but the sound, well, the sound is like a feeling.
At the same time, there was something that made me feel relieved in listening to this shopkeeper's answer. It is wonderful how wonderful it might be to put important things if sound is good. Sure it is, I think that you must take care of it if the feel is nice.
I definitely thought that the tea ceremony of the Kanjido is selling that it closes naturally only with the outer lid on it. Its elaborateness is famous abroad, and when I went to a shop, the Chinese came to buy alone and was talking to a clerk in English with a clerk, "It is famous in China."
So, there were things that I did not close naturally in what I bought, and there were things I had to rework. After considering it, the tea ceremony is metal, so it will expand and shrink in winter and summer. If I make it in winter, in the summer, if it grows even by 0.1 mm, it will not close, I want to hear what you are doing in the making.
Because I thought that I would go home already, I did not have any coffee, there was no water, about 30 minutes or so, because I was in front of my eyes so I could not translate into a seat and I thought what was wrong,
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
I thought that it was worth to come to Kyoto to hear the story. To make precious things to be put in, make a tea ceremony pipe, therefore use their skills and knowledge to improve the sound, that is, feel.
If sound is good it will put important things, what a really wonderful way of thinking is wonderful.
I wonder what happens if you compare it to architecture, I have been thinking about it on the returning Shinkansen.
「音を大事にしているんです、開けた時の音。この開けた時の音が良ければ、中に大切な物を入れてくれるんじゃないかと思って」
京都へ行くと必ず寄るカフェがあり、そこでの出来事。三十三間堂を見て、東京へ帰る前に、どこかでお茶でもと思い、少し歩いて「Kaikado Café」に来た。
ここは京都で長年、茶筒を制作している「開化堂」が出しているカフェ。京都で路面電車が走っていた時の車両基地だった所を改装したらしく、洋風な建物で、室内は天井が高く明るくて、とても居心地が良いので、京都へ来ると1度は立ち寄る場所。
ちなみに、うちには開化堂の茶筒が大小7つある。ブリキ製4つ、真鍮製3つ、うち1つは毎朝飲むコーヒーの豆を入れる真鍮の珈琲缶。ここの茶筒が好きで、ちょっとずつ買い足していった。一番最初に真鍮製の珈琲缶を買い、やっぱりブリキ製も欲しくなり、違う大きさも必要だなとなり。
なぜここの茶筒か、経年変化するのが面白くて。ブリキ製は真っ黒になるし、真鍮製は赤味か黄味を帯びてくる。あと、私は持っていないが銅製の茶筒もあり、こちらは渋く茶色になっていく。
購入した時はピカピカ、ブリキ製は光沢のあるシルバー、真鍮製も光沢のあるゴールド。共に、塗装を施していない生地だから、使い込むうちに、擦れたり、手の油などが付着して、自然と色が変わるそうです。
買った時にお店の人から「最初の1週間はよく手で全体をまんべんなく触って下さい。そうすると色の変化が綺麗に早く出るようになりますよ」と言われたので、毎朝愛おしくスリスリしていた。
銅製は買わなかった。銅製が一番早く色が変わるそうで、早く経年変化を楽しみたいならば、銅製かもしれないので、それも良かったが、買ったのは真鍮製とブリキ製。
真鍮製は使う人の手の油によって、その人が普段何を食べいるのか、肉なのか魚なのかで、赤味を帯びるか、黄味を帯びるか、が違ってくるらしく、人によって経年変化した結果が違うところが面白いと思った。ただ少なくともその結果がわかるのは10年後、段々と変化していくので、赤味か黄味かは2、3年したらわかるかもしれないけれど、まだ1年なのでわからない。
ブリキ製はもっとかかる。ピカピカのシルバーが真っ黒になるには40年、私はもう生きていないかもしれない。それでも、次の世代になってもその茶筒が受け継がれ、真っ黒になった茶筒が日常生活で使われていたなら、なんて素敵なことなんだろう、と思い、そのためには今買わないと。
塗装で擬似的にその風合いを出すことは可能かもしれないが、本物の生地が変化した風合いには敵わないだろう。時間かかるのだよ本物は、がいい、ブリキ製はそこがいい。次の世代に受け継ぐ物ができた。
経年変化にはとても興味をそそられた。経年変化することは、もしかしたら現代では製品として否定的に捉えられてしまうことかもしれないが、自然の素材や生地の物を使えば、経年変化するのは当たり前のことで、それを手入れをしながら使い、また、自然の素材や生地だから手直しもできるので、長い年月に渡って、次の世代にも受け継ぐことができる。
使い捨てでは無い、物としての本来の在り方がそこにあるような気がした。
それでもうひとつ、この茶筒いいなと毎朝楽しみにしていることがある。
"Real things change"
"I treasure the sound, the sound when I opened it, thinking that if the sound of this opening is good, I will put some important things inside."
There is a cafe where you will go to Kyoto without fail, and there happens there. When I saw Sanjusangen-do, before I came back to Tokyo, I thought that it was tea somewhere, came a little "Kaikado Café".
This is a cafe that Kyoto has been producing "tea ceremony" for many years. It seems that it was refurbished where the tram was running in Kyoto, it is a western style building, the ceiling is bright and the interior is bright and very comfortable, so when you come to Kyoto it is a place to stop by once.
By the way, there are seven large and small tea cranes in the Kaiden-do. Four tinplate, three brass, one of which is a brass coffee can that puts coffee beans to drink every morning. I liked the tea ceremony here, and I bought it a little at a time. I bought a brass coffee can at the very beginning, I wanted a tinplate as well, and it became necessary to have a different size.
Why is it a tea ceremony here, it's fun to change over time. Tinplate will be black and brass will be reddish or yellowish. Also, although I do not have a copper tea cupboard, it is browned with astringency.
Shiny when purchasing, glossy silver in tinplate, shiny gold in brass. Both of them are fabrics that have not been painted, so it rubs, oils of hands adhere, and so on, it seems that the color changes with nature, as it is used.
When I bought it I was told from the store people "Please touch the whole thoroughly with your hand well in the first week, so that color changes will come out cleanly and quickly" It was.
I did not buy copper. It seems that copper changes most quickly, so if you want to enjoy secular change quickly, it may be made of copper, so it was also good, but I bought it made of brass and tin.
The brass made by the oil of the person who uses it, seems to be reddish or yellow depending on what you usually eat usually, fish or meat, it seems different, I thought that the difference between the changed results is interesting. However, at least the result will be known 10 years later, so it will gradually change, so it may be known in a couple of years whether red or yellow taste, but I do not know as it is still a year.
Tinplate takes more. It has been 40 years for shiny silver to become black, I may not be alive anymore. Even then, even if it comes to the next generation, if the tea ceremony was handed down and it was used in everyday life, it seems that it is a wonderful thing if a black tea chestnut was used in daily life, and for that I have to buy it.
Although it may be possible to produce the texture in a pseudo manner by painting, it will not be enemy to the texture where real fabrics have changed. It is time consuming, genuine article is good, Tin tin is good there. There was a thing to hand down to the next generation.
I was intrigued by the secular change. It is likely that it will be caught negatively as a product in modern times, but it is commonplace to change over time if you use natural materials or fabric items, so that it will change over time While using it, because it is also natural materials and fabrics can be reworked, over the years can be passed down to the next generation.
I felt there was the original way of things, not disposable.
And another thing, I have looked forward to this morning that this tea cup is nice.
夏の暑さは嫌いな方ではなくて、汗かきなのですが、わざと暑い日中に散歩をしたりします。季節の匂いみたいなものが好きで、特に季節の変わり目には敏感になるのか、今なら冬の匂いですかね、どういう匂いかを言葉で説明するのは難しいのですが、枯れ草のような、夜になると冷たい空気の乾いた匂いというか、感覚的で上手く説明できないですが、夏も季節の匂いを嗅ぎに外へ出ます。
ただ、今年の夏だけは違って、外へ出ることに身の危険を感じましたね。暑過ぎて外出を止めよう、陽が落ちてから出かけようと、はじめて思いました。ちょっと外に出ただけで熱中症になりそうで、水分を取っても追いつかず、身体がどんどん熱くなって沸騰してくる感じ、その状態が一番危ないらしいです。
だから、今年の夏は屋内にいることが多かった、常にエアコンがかかった部屋の中。電気代も結構かかりました。ただ、エアコンをかけないと室内にいても熱中症になりますから仕方がないですが、エアコンの風があまり好きではないので、寝る時には苦労しました。
そもそも、外の気温が高くても、室内の温度が上がらなければエアコンをかける必要は無いですよね。エアコンをかけなければ電気代が安くて済みますが、エアコンをかけないで済むということは、それだけ室内が快適だということ。春や秋の中間期は冷暖房をかけずに過ごせて気持ちいいですよね、夏にそこまでの快適性を得られなくても、エアコンをかけずに過ごせたら、その快適性に近づきますよね。
住宅の断熱性能は冬を基準に決めます。冬の目標室温を達成するために必要な断熱性能が数値で厳密に決まります。ただ、ここで問題になるのは、冬を基準に決めた断熱性能だと、夏はより暑くなるということ。
冬は外の寒さが室内に伝わらないように高い断熱性能が要求されます。いわゆる高断熱ですね。そこに隙間風などか入って寒くならないように気密性の高さも必要となります。高気密高断熱、それを行うことは難しくないです。
魔法瓶を思い浮かべ下さい。それがまさに高気密高断熱の家です。中に熱い飲み物を入れれば1日中熱い、冷めない。冬は一度暖まれば、その暖かさが持続して、1日中暖かい、だから、暖房器具をずっとつけておく必要が無いので光熱費も安くて済む。
中に冷たい飲み物を入れても1日中冷たい、氷も溶けない。だから、夏もエアコンで室内を冷やせば、1日中冷えている、だから高気密高断熱がいいと思いますよね、ところがです、魔法瓶と実際の家は違うのです。
実際の家はそれでも外の熱が室内に入ってくる、窓から、太陽の日差しが。あと生活熱というのもあります、キッチンのコンロなど。あと人も発熱しています。冬夏関係無しに、暖房も冷房もかけなくても、高気密高断熱であっても無くても、日中の室温は放っておいても上がります。
それでも冬はいいです、暖かくなるのだから。問題は夏です。何もしないで放っておくと日中はどんどん室温が上がります。大体午後になると外気温より高くなる。そして、その熱は高気密高断熱の家だと外に逃げないので、よりどんどん室温が上がることになる。これを先程も例えましたが「魔法瓶効果」と言います。
室温がより上がるのを冷房で冷やし続ける。高気密高断熱の家にしてしまうと、夏の冷房負荷が大きくなり、光熱費が余計にかかります。
ではどうすれば良いのか?
高気密高断熱にしないことです。ただし、そうするためには冬の対策が不可欠です。もちろん、夏だってそれだけでは快適に暮らせません。
冬と夏の両方を快適に暮らすためには、自然の力を利用しないといけません。その話は、ここまで長くなりましたので、また次回に。
"How to make a warm summer cool house in winter vol.2"
I do not dislike the heat of summer, I am sweating, but I will walk for a while on purpose on purpose. I like something like the seasonal smell, especially whether it becomes sensitive to the change of the season, now it is a smell of winter, it is difficult to explain what kind of smell it is, but like a dead grass, at night I can not explain it sensibly well that it is a dry smell of cold air, but in the summer I will go out to sniff the season's smell.
However, unlike the summer of this year, I felt the danger of getting outside. Let's stop going out because it was too hot, I thought for the first time to go out after the sun went down. It seems to become a heat stroke just by going out for a moment, feeling that the body gets hotter and steams more quickly, taking that moisture, it seems that the condition is the most dangerous.
So, this summer I often stay indoors, in the room where air conditioning always took place. Electricity bills took quite a while. However, there is no choice because it will be a heat stroke even if you are indoors in the room, but you do not like the air conditioner's wind so much, so it was a hard time to sleep.
In the first place, even if the outside temperature is high, you do not have to turn on the air conditioner unless the room temperature rises. If you do not apply air-conditioner it will cost less electricity, but not having to wear air-conditioner means that the interior is comfortable as much. It is comfortable to spend the mid-season of spring and autumn without putting on air-conditioning and heating, even if you can not get the comfort that much in summer, if you can spend without air conditioning, you will be comfortable with that comfort.
The insulation performance of the house is decided on the basis of winter. Winter goal The adiabatic performance necessary to achieve room temperature is strictly determined by numerical value. However, the problem here is that if the insulation performance decided on the basis of winter, the summer will get hotter.
In winter, high insulation performance is required so that outside coldness will not be transmitted indoors. It is so-called high insulation. A high level of airtightness is also required so that there will be no draft winds entering there and getting cold. High airtight high insulation, it is not difficult to do.
Please think of a thermos bottle. That is exactly a high airtight, highly insulated house. If you put hot beverages inside, it will be hot, not cool all day. Once it warms up in winter, its warmth continues, it is warm all day, so you do not need to keep the heating equipment all the time, so the utility costs are cheap.
Even if you put a cold drink in it is cold all day, ice will not melt. So, if you cool the interior with an air conditioner in the summer, it is cold all day, so I think that a high airtight high insulation is good, but it is, the thermos bottle and the actual house are different.
Actually, the outside still enters the room, the outside sunlight from the window. Another thing is life heat, kitchen stoves and so on. People also have a fever. Even if you do not need heating or cooling without winter or summer relationship, even if it is highly airtight and highly insulated, room temperature will rise even during the day.
Still winter is nice, it will be warm. The problem is summer. If you do not do anything, the room temperature rises steadily during the day. It gets higher than the outside temperature in the afternoon. And since that heat does not escape outside if it is a high airtight, highly insulated house, the room temperature rises more and more. As I mentioned earlier, we call it "Thermos bottle effect".
Continue to cool down the room temperature rises in the air conditioning. If it becomes a high airtight and highly insulated house, the cooling load of the summer becomes large, and the utility cost increases unnecessarily.
So what should I do?
It is not to be highly airtight and highly insulated. However, in winter measures are indispensable to do so. Of course, summer alone can not live comfortably alone.
In order to live comfortably in both winter and summer, we must use the power of nature. That story has been long so far, so next time.
段々と寒くなってきましたね。今日から12月、冬だから寒いのが当たり前ですけれども、今年はいつもの年よりは暖かいですね。
だから、まだあまり暖房器具を使う必要も無いし、朝起きる時に寒くてベッドから出たくないなんて、まだそんなに思わないです、東京では。
毎年こうだとありがたいですが、気候のことは何ともわからない、外気温はコントロールできませんからね。
ただ、室内の気温はコントロールできますから、とても寒い冬の年でも今年のように暖房器具をあまり使うこと無しに、朝起きる時に寒くてベッドから出たくないと思うこと無しに、過ごすことができるようになります。
朝起きる時の寝室で、暖房器具を使わずに、室温が何度になれば、ベッドから出る時につらくないですか?
昼間リビングで、暖房器具を使わずに過ごすには、室温を何度にすれば良いですか?
夜中、寝室からトイレに行く時の廊下の室温、浴室の脱衣所の室温は?
ヒートショック防止には、廊下や脱衣所と言った主要な生活空間をつなぐ所の室温が大事で、暖かくして主要な生活空間との温度差を無くさないといけない。
主要な生活空間は窓もあり、場合によっては暖房器具を使うことで暖かくすることができますが、廊下や脱衣所と言った場所はそうもいかない時もある。
住宅全体を24時間常にどこにいても暖かくなるように暖房すれば良いですが、イニシャルコストとランニングコストがかかりますし、1次エネルギーを相当使い環境負荷を上げることになり、地球環境にも良くない。
暖房器具を使わない場合の冬の室温を各部屋で何度にすれば良いのか、まず目標とする室温を決めます。これは暖房器具を使わないので光熱費を下げることにもつながります。
目標とする室温が決まらないと住宅の断熱性能が決まりません。
断熱は住宅の中で快適に過ごすために行うので、その快適性を客観的に数値で表すには室温しかありません。
目標とする室温が決まれば、それを達成するための必要な住宅の断熱性能が決まります。
必要な住宅の断熱性能が決まれば、断熱材の種類や厚さなどの仕様や、住宅全体の窓の総面積と窓の断熱性能、南側の窓の大きさが決まります。
ただ単に断熱性能の良い断熱材を厚く使えば良いのかもしれませんが、その分コストもかかる、窓も同様。それに、それで本当に快適な室温になるのかわからない。
また窓に使うガラスは、外壁に比べて断熱性能が著しく劣るので、窓がたくさんあって、窓が大きければ良いというわけでも無く、かえって室温を下げることにもなりますので、必要な断熱性能から住宅全体の窓の総面積を数値で厳密に決めます。
目標の室温から必要な断熱性能を決め、その断熱性能を達成するために断熱材の仕様を決めますが、それだけでは目標の室温を達成できません。冷めない入れ物はできましたが、そこに火種がないと、入れ物は暖まりません。
火種になるのが、晴れた日の日中の南側の窓です。その時の南側の窓にはストーブ1台分と同じ量の太陽エネルギーがあります。それは日中ずっとストーブをつけているのと同じことです。
だから、南側のどこの位置にどのくらいの大きさの窓をどれだけ設けるが重要で、それも目標の室温から決めた断熱性能から割り出して厳密に数値で決まります。
全てを簡単に言うと、日中に窓から取得した暖かい太陽のエネルギーをなるべく減らさないようにして、目標の室温を翌朝まで維持する、ということです。
ですから、取得した暖かい太陽のエネルギーをできれば貯めておきたいですよね、蓄熱しておきたい。そうすれば、日中に蓄熱したものを夜に放出して室温が下がりにくくなる。
蓄熱するにも、南側の窓の位置と大きさが重要で、さらには蓄熱する場所をどこにするか、これも目標の室温から決めた断熱性能で決めます。さらには蓄熱する場所の材質や仕上げも重要になる。
全ての基準は、目標とする室温です。室温を決めないと断熱材の仕様が決まりませんし、本当に快適に暮らせるかどうかもわかりません。
今年の夏は異常に暑かったですね。その夏をエアコン無しで快適に暮らすためにはどうするのか、もちろん室温を決めることが重要であることには変わりありませんが、その他にも重要なことがあり、それは長くなりましたので、また次回に。
"How to make a warm summer cool house in winter vol.1"
It is getting colder and fatter. Today is December, because winter is cold, it is natural to be cold, but this year it is warmer than the usual year.
So, I do not need to use much heating equipment yet, I do not think that I do not want to leave the bed because it is cold when I wake up in the morning, in Tokyo.
I appreciate it every year, but I do not understand the climate at all, I can not control the outside temperature.
However, since the temperature in the room can be controlled, it is possible to spend without thinking that it is cold and not wanting to leave the bed when getting up in the morning without much use of heating equipment as in this year even in the very cold winter years It will be like.
In the bedroom when you wake up in the morning, if you do not use heating equipment, how many degrees the room temperature is, is not it hard to get out of bed?
How many degrees of room temperature do I have to spend without using heating equipment in daytime living room?
In the middle of the night, the room temperature in the corridor when going to the toilet from the bedroom, the room temperature of the bathroom clothing room?
To prevent heat shock, the room temperature connecting the main living space such as a corridor and a dressing room is important, and it is necessary to warm the temperature difference from the main living space to be warm.
There are windows in the main living space, and in some cases you can make it warm by using heating equipment, but there are times when the place called the corridor and the dressing room does not do so either.
It is only necessary to heat the entire house 24 hours a day to keep it warm anywhere, but it costs initial cost and running cost, it uses the primary energy considerably and increases the environmental load, which is not good for the global environment .
First of all, we decide the target room temperature to determine the number of times of room temperature in each room in the winter when not using the heating equipment. This leads to lower utility costs as it does not use heating equipment.
If the target room temperature is not decided, the heat insulation performance of the house will not be decided.
Since insulation is done to stay comfortably in the house, there is only room temperature to objectively express its comfort in numerical values.
If the target room temperature is decided, the necessary heat insulation performance of the housing to achieve it will be decided.
Once the necessary heat insulation performance of the house is decided, the specifications such as the type and thickness of the insulation, the total area of the window of the entire house, the heat insulation performance of the window, the size of the window on the south are decided.
Although it may be good simply to use thick insulation material with good heat insulation performance, it costs much, corresponding to the window as well. Besides, I do not know whether it will be a really comfortable room temperature.
Also, the glass used for windows has significantly poorer insulation performance than the outer wall, so there are many windows and it is not good if the window is large, it will also lower the room temperature, so from the necessary thermal insulation performance We will strictly determine the total area of the window of the entire house by numerical value.
We decide the required insulation performance from the target room temperature and decide the specification of the insulation to achieve its insulation performance, but by doing so we can not achieve the target room temperature. I could have a container that will not cool, but if there is no fire in there, the container will not warm.
It is the window on the south side of the day during sunny days to become an ignition. The southern window at that time has the same amount of solar energy as the one stove. It is the same as wearing a stove all day long.
Therefore, it is important to set how many windows in what size on the south side, and it is also determined from the adiabatic performance decided from the target room temperature and it is strictly determined by numerical value.
To put it all in brief, it means that the warm sun energy acquired from the window during the day should not be reduced as much as possible, and the target room temperature will be maintained until the next morning.
So, I would like to store the energy of the warm sun that I acquired, if possible, I want to store the heat. Doing so will release heat stored during the day at night, making room temperature less likely to fall.
In order to store heat, the position and size of the south side window are important, and furthermore, where to place the heat storage, this is also decided by the insulation performance decided from the target room temperature. Furthermore, the material and finish of the place where the heat is stored become important.
All standards are the target room temperature. If we do not decide the room temperature, the specification of the insulation is not decided and I do not know whether I can really live comfortably.
It was unusually hot this summer. Of course it is important that it is important to decide the room temperature, what to do in order to live comfortably in the summer without an air conditioner, but of course there are other important things too, so it got longer, so next time .
先日「仲村さんのところは、3DプリンタとかVR機材とか夢の機材がありますので、アジトみたいで楽しいです」と言われたり、事務所へ行きたいという人が増えた。普段、事務所にはいないので、それに合わせて事務所にいるようにして、来る人拒まず、大歓迎、話し込んでしまう。
そう言えば「どこに向かっているんですか」とも言われた。意外では無いけれど、気恥ずかしくて一瞬間を置いて小声で「自作自演」と思わず言ってしまった。
VRもBIMも3Dプリンターも自作自演を支えるためのツール。VRからはじまり、最初はただVRでの建築の見え方が凄い、これを設計に使いたいと思っただけ、そこから、BIMに興味を持ち、25年近く使用したCADからRevitに変え、Revitのモデルには拡張性があるので、人から勧められてCGソフトを入れ、リアルなパースや動画をつくりはじめ、前から欲しかった3Dプリンターでモデルを出力して模型や部材もつくるようになり、気がつくと、設計だけでなく施工の領域にまで踏み込んで自作自演できる環境が整ってしまった。
別にこれらのツールが無くても自作自演はできるが、意識せずに、これをはじめたからこれもできるようになるな、とか、これがあるからこれもできないかな、とか、前からこれに興味があったのだけれどもできるかな、と人にきいたりして、気がついたら自分で何でも自らの手で簡単に対してそんなに労力なしに生み出せるようになっていた。根底には、道具は大事、道具しだいで変わることがたくさんある、と思っているからだろうけど、意識せずに整ってしまったことが本当は求めていたことなのかもしれない。
自作自演とは、自分の思考だけで完結でき、その評価を誰に求めるのでも無く、自分で自分に評価を下すことで、好きなことをするよりも、楽しいことをするよりも、自作自演を大事にしている。好きや楽しくても、自分の判断だけで決定できないと、どこかで迎合することになり、精神衛生上よくない。仕事として建築デザインを行いつつ、自作自演できる場があると、自分の能力を確認し、鍛え、高めることができ、相乗作用があれば、いずれ自作自演だけになるかもしれない。
このように設計環境を再構築したおかげで、どこにいても設計ができ、1人でやりくりして完結できるようになったので、もっとひとつのことに対して思考を深めることができるようになり、それが自作自演の場で自分の能力を高めることに繋がっている。
例えば、輪島塗のフリーカップづくり。これは完全に自作自演、しかし、自分から出て来たとは信じられないようなデザインに発展しており、自分の能力を確認し、鍛え、高めることができていると思う。
これからもっと自作自演をしていくことになるだろう。それを継続してずっと行っていく環境が今整いつつある。
"Self-made performances"
The other day, "Nakamura's place has 3D printers, VR equipment and dream equipment, so it's fun like an honor" and more people said they wanted to go to the office. I usually do not stay in the office, so I will stay in the office accordingly, I will not refuse to come, welcome, I will talk.
As I said, 'Where are you heading?' Although it is not surprising, I was embarrassed and sprang one moment and in a low voice I said without thinking "self-made performance".
Both VR, BIM and 3D printers are tools to support self-made performances. Beginning with VR, at first it is just how VR's architecture looks awesome, I just wanted to use it for design, from there I got interested in BIM, changed from CAD used for nearly 25 years to Revit, from Revit's As the model has extensibility, I recommend CG software from people, start making realistic perspectives and animations, outputting models with a 3D printer I wanted from before to make models and members, I noticed And, not only the design, but also the environment where we can stepping in to the field of construction and making self-made performances has been set up.
Apart from these tools I can do my own self-performance but without consciousness, since I started this I can also do this, I can not do this because there is this, I've been interested in this for some time I listened to someone that he could do it, but when I realized I could create whatever I could with my own hands without much effort by my own hands. Basically, tools are important, because they think that there are lots of things to change depending on the tool, but it may be that what you really wanted is that you did not realize it without being conscious.
Self-made performances are self-made performances rather than doing something more fun than doing anything they like by doing self-evaluation on themselves without asking anyone to evaluate themselves, being able to complete with their own thoughts alone I am cherished. Even if you like or have fun, if you can not decide just by your own judgment, you will be somewhere to meet up and it is not good for mental health. If you have a place to do your own self-made work while doing architectural design as a work, you can check your ability, train and enhance, if there is a synergistic effect, it may be only your own self-made performance.
Thanks to the rebuilding of the design environment like this, I can design anywhere, I can finish it by one person, so I can deepen my thought on one more thing, It leads to enhancing my skills at home for self-made performances.
For example, making a free cup of Wajima coat. This is completely self-made, but I am developing into a design that I can not believe that I came out of myself, I think that I have been able to confirm my skills, train and enhance.
I will be doing more self-made performances from now. The environment where we continue to do it all the time is coming.
ゲーミングPCを導入してVRをはじめた。BIMをはじめるにも同性能のPCが必要で、何が違うのかというとグラフィック性能。Macではグラフィック性能が追いつかなかったし、VRとBIMではPCにそれだけのグラフィック性能が要求されていた。
それでも新しいMacBook Proを導入してまだ半年だったので、Boot CampでWindowsを動かし、Autodesk社のRevit(レビット)をインストールして、ゲーミングPCとMacの2台体制でBIMをはじめることにはした。
簡単なモデルをつくる時はMacで十分なので、軽いから持ち歩き、詳細なモデルやプレゼン資料やCG、VRデータを作成する時はゲーミングPCと使い分けた。
VRの操作は難しいことではないので、すんなりとできるようになり、Revitは市販の教本を一通りやって基本的なことを覚え、あとはわからない度に人にきいた。
CADを使ったことがある人ならば、Revit特有のクセはあるが、問題なくできるだろう。レイヤーという概念が無いので、そもそも実際の建築にはレイヤーなど存在しないから、Revit内で実際の建物に当たるモデルを作成しようとした時にレイヤーなど使わない。
実際の建築をつくるように、床は床、壁は壁、天井は天井、下地は下地としてモデルをつくる。前に使っていたVectorworks(ベクターワークス)というCADも同じように床は床、壁は壁と作れたが、レイヤーがあり、もっと汎用性が高く、オブジェクトとして四角い床がつくれたが、Revitでは作図はできるが、そこまで汎用性が高くなく、BIMだと床など部位別にきちんと情報が整理されていないと使えないからそうなっているのだろうが、操作しだいで自由に形をつくることもできた。
ゲーミングPCはノートにした。VR装備一式を持ち運びすることができたので、ノートにすればゲーミングPCも持ち運びができ、どこでもVRができる。これは建主のお宅に持ち込んで、これから建てる予定の住宅をVRで一足先に体験してもらい打合せをすることを想定していたが、私はそれにプラスして、設計している場所の傍らに設置して、いつでもVRで設計途中の建築を検討したかったから。
この後、初期の段階でゲーミングPCを導入したおかげで、この時には想像もしていなかったことが展開できるようになり、それが新たな機会を生むことにもなった。
"I introduced a gaming PC"
Introducing gaming PC and starting VR. In order to start BIM, PC with the same performance is necessary, what is different is graphic performance. On Mac, the graphic performance did not catch up, and VR and BIM required PC for that much graphic performance.
Still it was half a year since I introduced the new MacBook Pro, so I decided to start Windows with Boot Camp, install Autodesk's Revit and start a BIM with two gaming PCs and Macs.
When creating a simple model, Mac is enough, because it is light, I carry around, carrying out detailed models, presentation materials, CG, VR data when using gaming PC differently.
Operation of VR is not a difficult thing, so we can do it smoothly, Revit learned basic things through a commercially available textbook, and he asked people whenever I do not understand it.
If you've used CAD, there are certain peculiarities of Revit, but you can do it without problems. Since there is no concept of a layer, there is no layer etc. in the actual construction in the first place, so do not use layers when you try to create a model that corresponds to an actual building in Revit.
To create the actual building, the floor is a floor, the wall is a wall, the ceiling is a ceiling, and the base is a base as a base. Similarly, CAD called Vectorworks (VectorWorks) which I used before was able to make the floor as the floor and the wall as the wall, but there is a layer, it has more general versatility, a square floor could be made as an object, but in Revit a construction Although it is possible to do so, its versatility is not high so far, it seems that it is because it can not be used unless the information is properly sorted by floor and so on with BIM, but it can also be shaped freely according to the operation It was.
I made the gaming PC a notebook. Since I was able to carry a complete set of VR equipments, I could carry a gaming PC as a notebook, and I could do VR anywhere. This was brought to the owner's house and was supposed to have a meeting to have the VR plan to build a house to be built ahead of the other, but I plans to make a meeting and places it in the place I am designing Because I wanted to set up by my side and want to consider architectures under design at any time by VR.
After that, thanks to the introduction of the gaming PC in the early stages, what was not imagined at this time could be expanded, which also resulted in new opportunities.
VRを建築設計途中の検討用ツールとして使いたいならば、BIM(ビム)とは関係無しに、現状Autndesk社のRevit(レビット)を導入するしかない。ならば、BIMにもっと興味を持ってみよう、がBIMをはじめるキッカケだった。
VRの説明会では最初にBIMの話から入った。BIMの基本概念からはじまり、BIMが今後主流になるだろう、特に施工現場ではすでに導入され機能しているなど。その中で特に興味を持った話は、Revitを導入してBIMをはじめた場合の拡張性だった。
建築設計する場合、今までは2次元の図面をつくり、それを元に3次元のパースや模型を制作していたが、Revitを導入してBIMをはじめると、最初から3次元のモデルと称する実際の建物をソフト内で構築し、必要な情報、例えば、図面などを後でモデルから取り出すことになる。
このRevitのモデルには拡張性があり、VRはそのモデルデータを変換して使用するのだけれども、このモデルを構造設計事務所に渡すと、建物の骨組みをモデルに入力して返してくれるので、Revit上で意匠設計と構造設計の整合性を見ることができ、確認申請機関にはRevitのモデルをそのまま提出すれば、ペーパーレスで確認申請の審査を受けることができ、このモデルデータはそのままで他のCGソフトに読み込ますこともできるので、よりリアルなパース画像や動画も簡単に作成することができ、また、このモデルデータを変換して使用すれば3Dプリンタで出力でき、スチレンボードで白い模型をつくる必要が無くなる。
私は1人で設計から施工管理まで行うので、設計時にRevitでモデルデータを作成することが、自分が実際に動くことによる労力や時間を大幅に削減でき、設計を大幅にサポートするだけでなく、1人だからよりRevitのモデルから拡張されたこれらのことを上手く連携させ、レスポンスよく進めることができ、設計の質を直接高めていくことができるのではないかと考えるようになった。
また、この拡張性のおかげで、どこでも場所を選ばずに、動くことなく、ノートPCとネットの環境があれば設計ができるようになる。VR装備一式も持ち運べ、最低2m角位の場所があれば良い。3Dプリンタを置く場所だけは限定されるが、一度プリントアウトの作業をすればずっとその場にいなくてよく、モデルデータだけを送信してその作業だけを誰かに頼むこともできるだろう。そうすると、事務所もいらなくなる。
BIMとは、最低限ここまで拡張性があってはじめて成り立つのではないだろうか。
そう考えると、メインのOSをMacからWindowsに変えることも、より拡張性を高め、よりクリエィティブな建築を生む可能性も高めることになる。また、Autodesk社のRevitはBIMソフトとして世界中でメインで使われるようになるので、モデルを作成すれば、それが共通言語となり、モデルを渡すだけでプレゼンから施工までできてしまう可能性も秘めていた。
ここまで順に考えてきてやっと、25年近く使用して習熟しているCADソフトを捨て、愛着のあるOSも変え、Revitを導入してBIMをはじめることに決心がついた。
これは、この先まだ15年以上は設計をして、よりいい建築を生む出したいと考えていたので、そのためには、今、設計環境を再構築する必要があるのでは、という想いもどこかにあったから決断できたのかもしれない。
"Bim's silence"
If you would like to use VR as a tool for examination in the middle of building design, you can only introduce Revit (Revit) from Autndesk, regardless of BIM (Bim). Let's be more interested in BIM, but it was a challenge to start BIM.
At the briefing session of VR, we entered from the story of BIM for the first time. Starting with the basic concept of BIM, BIM will be mainstream in the future, especially already installed and functioning at the construction site. Among them, the story that was particularly interesting was the extensibility when I introduced Revit and started BIM.
In the case of architectural design, until now, we have created a two-dimensional drawing, and based on that we created a three-dimensional perspective or a model, but if we introduce Revit and start BIM, we will call it a three-dimensional model from the beginning We will build the actual building in software and retrieve the necessary information, such as drawings etc later from the model.
This Revit's model is extensible, and VR converts its model data and uses it, but if you pass this model to the Structural Design Office, you will enter and return the framework of the building to the model , You can see the consistency of design design and structural design on Revit and you can receive the examination of confirmation application paperless if you submit Revit's model as it is to the confirmation application agency and keep this model data as it is Since it can also be loaded into other CG software, more realistic perspective images and moving images can be easily created, and if this model data is converted and used, it can be outputted with a 3D printer, and it is white with a styrene board There is no need to make a model.
Since I do it from design to construction control, creating revit model data at design time can greatly reduce labor and time due to my actual movement, not only to greatly support the design Since I was one, I began to think that I could collaborate these things extended from the model of Revit well and proceed with a good response, so that the quality of design can be improved directly.
Also, thanks to this extensibility, designing will be possible if there are laptop and net environments, without moving anywhere, without moving anywhere. You can also carry a complete set of VR equipment, as long as there is a place at least 2 m square. Although only the place to place the 3D printer is limited, once you print out, you do not have to stay there for a long time, you can send only the model data and ask someone to do just that work. Then you will not need an office.
Will not it be possible to have BIM for the first time with scalability so far?
If you think so, changing the main OS from Mac to Windows will also increase the possibilities of increasing scalability and creating more creative architecture. Also, Autodesk's Revit will be used mainly as a BIM software all over the world, so if you create a model, it will become a common language and you can also possibly be able to do from presentation to construction simply by passing a model It was.
After considering it so far, I decided to throw away the CAD software that I've been using and using for nearly 25 years, changed the OS with attachment, introduce Revit and start BIM.
This is because I was thinking that I wanted to design more than 15 years and to produce better buildings, so for that I think that it is now necessary to reconstruct the design environment somewhere It may have been decided because it was in.
VRを使ったから何かが変わるとも特に思ってはいなかったが、建主に設計内容を説明する時には役に立つかもしれないと、VRの説明会で話を聴きながら思っていた。
それまで建主には、平面図、立面図、断面図などの図面と外観、内観などのパース、スチレンボードでつくる白い模型で設計内容を説明していたが、私自身が感じたこととして、パースで説明している時が一番建主の理解度が高い。
2次元の図面から建物の全体像や室内の様子を理解するのは、慣れが必要なようで、なかなか細部やスケール感などが伝わらない時がある。白い模型は3次元なので、見てすぐに外観の形や間仕切りなどのプランは理解しやすいようだが、白い模型から実際の建物をイメージするには、やはり訓練が必要なようで、私たちは白い模型に仕上げの素材や色のが付いたものをイメージできるが、やはりそれが難しいらしく、なかなか伝わらない時がある。
なので、設計打合せの最終局面になってくると、パースを多用するようになる。ゲームや携帯コンテンツが3次元のものを2次元の画面で見るので、パースも同じだから、日常的に3次元のものを2次元に変換して理解する訓練をしているようなものになり、そのためパースが一番理解しやすいのではないかと思う。
VRは仮想ではあるが3次元空間に没入するので、頭の中で2次元に変換する必要が無いから余計に理解しやすいはずで、それはもちろん実際の建物を体験しているのと同じになるので、だから、建主に設計内容を説明する時には役に立つのではないかと思っていた。
説明会のVR体験で、VRのゴーグルをかけると、すでに目の前にはVR空間が広がっていた。コントロール・スティックがVR空間の中に浮かんでおり、それを手で掴む。説明会の会場にセッティングされたVR空間は、位置センサーが対角線状に置かれた3.5m位四方の空間で、その広さがVRのゴーグルをかけて実際に歩いて移動できるVR空間になる。もう一つの移動手段は、コントロール・スティックを使用し、ボタンを押して行きたい場所にビームを照射すると瞬時にその場所に移動できる。
あらかじめVR空間には住宅が建っており、それを空から俯瞰することもできるし、近づいて見ることもできるし、当然室内に入り歩き回ることもできる。3.5m四方のVR空間の外へ出そうになると網目状の壁が現れるので、ゴーグルを付けて部屋の様子がわからずに歩き回っても壁などにぶつかったりする危険性も無く安全だ。
説明会ではキッチンに行き、システムキッチンの天板の高さや背面の食器棚との位置関係や使いやすさ、キッチンに立った時に室内の様子がどう見えるのか、ダイニングテーブルまでの距離などが実感できた。説明会の趣旨から、たぶん主催者はこれを体験させて「ほらモデルハウスのようでしょ」と思わせたかったのだろう。
庭に出た時だった、振り返って建物を見上げて驚いた。
空から俯瞰で建物を見るのは模型でできる。模型をぐるぐる回せば、いろいろな角度から建物の外観を見ることができる。室内も模型が各階毎に分離するならば、上から俯瞰して見ることができる。室内の様子も模型にCCDカメラのような小型カメラを入れれば、画面越しには把握できる。だだし、これらは全て巨人の視点で、等身大の人間の視点では無い。たがら、スケール感を把握する時に間違えやすくなる。
庭から建物を見上げた時「この見え方ははじめてだ、これは実際に建物が立ち上がって完成した時にしか感じることができない見え方だ」と思い驚いた。キッチンに行った時も、もちろん実際に建物が完成しないと厳密にはわからないが、ある程度はキッチンのショールームなどに行けば擬似体験はできる。しかし、この庭からの見上げはVR以外では擬似体験もできないだろう。
私はこの瞬間にVRを導入することを決めた。もちろん建主への説明用ツールでもあるが、設計に使おう、設計の検討段階でVR空間に没入し、スケール感や見え方を確かめるツールとして、スケール感は建築のデザインをする上で重要なことのひとつなので、それを実際の建物が立ち上がった時と同じように確認できることは素晴らしい。
設計中にVR空間に没入し、歩き回り、立ち止まり、見上げたりして、空間のつながり方や見え方、部屋の広さや天井の高さ、開口部の位置や大きさ、光の入り方や、室内から外の見え方、またその逆など、等身大の人間の視点で確認する。考えただけでも楽しくなる。
ゴーグルを外して、その場で説明会の主催者にVRを導入することを伝えた。
"VR introduction"
Although I did not particularly speculate that something will change because I used VR, I thought it might be useful when explaining the design content to the owner, listening to the story at the VR briefing session.
Until then, the building owner explained the design contents with a drawing such as a plan view, an elevation view, a sectional view and the like, a perspective such as appearance and internal view, a white model made of a styrene board, but as I felt , Perth understands most when the time explains in Perth.
Understanding the overall image of the building and the state of the room from the two-dimensional drawing seems to require familiarity, and there are times when the details and scale feeling etc. are not transmitted easily. As the white model is 3 dimensional, it seems easy to understand the plan of appearance shape and partitions etc. as soon as you see it, but in order to image the actual building from the white model, it seems that training is still necessary, we are white I can imagine a model with a finished material or color, but it seems difficult to do, and there are times when it is hard to convey.
So, when it comes to the final stage of the design meeting, it will start to use a lot of Perth. Since games and portable contents view 3-dimensional objects on 2-dimensional screens, since the same is true for Perth, it is like being training to understand three-dimensional things to 2 dimensions on a daily basis, So I think Perth is easiest to understand.
VR is virtual, but immerses in 3-dimensional space, it should be easy to understand because it is not necessary to convert it into 2 dimensions in the head, which is of course the same as experiencing the actual building So, so I thought that it would be useful when explaining the design content to the owner.
In the VR experience of the briefing, when VR goggles were applied, the VR space had already spread before my eyes. A control stick is floating in the VR space and grips it with the hand. The VR space set at the briefing venue is a VR space that can move by actually walking and walking with VR goggles in a space of about 3.5 m in which the position sensor is placed diagonally. Another means of movement is to use the control stick and press the button to irradiate the beam to the place where you want to go, you can instantly move to that place.
Houses are built in the VR space beforehand, you can see the overhead from the sky, you can see it as you approach, you can even walk around and enter the room. Since mesh-like walls appear when going out of a 3.5 m square VR space, there is no danger of hitting a wall or the like even if walking around without wearing goggles without knowing the state of the room and it is safe.
At the briefing session, I went to the kitchen, I realized the height of the top board of the system kitchen, the positional relationship and ease of use with the cupboard on the back, how the inside of the room can be seen when standing in the kitchen, the distance to the dining table It was. Perhaps because of the purpose of the briefing session, the organizer would have liked to think that "it looks like a model house," as the organizer has experienced this.
It was when I got into the garden, I turned around and was surprised to look up at the building.
You can look at the building from the sky in an overhead view with a model. If you turn around the model, you can see the building's appearance from various angles. If the model separates for each floor also in the room, you can see it from the top down. If you insert a compact camera such as a CCD camera in the interior as a model, you can grasp it through the screen. However, these are all giant's point of view, not a life-sized human being's point of view. However, it is easy to make mistakes when grasping the sense of scale.
When I looked up at the building from the garden, I was surprised to see that this is how it looks, this is how it looks like it can only be felt only when the building is up and finished. Even when I go to the kitchen, of course, I do not know exactly that the building is not completed, but to a certain extent you can do a simulated experience if going to a kitchen showroom etc. However, looking up from this garden will not be able to simulate anything other than VR.
I decided to introduce VR at this moment. Of course, it is also a tool for explanation to the owner, but as a tool for designing it, immersing in the VR space at the stage of design consideration, and ascertaining the sense of scale and appearance, scale feeling is important in designing the building As it is one of the things, it is wonderful to be able to see it as it was when the real building stood up.
Immersed in the VR space during designing, walking around, stopping, looking up, how to connect and see the space, the size of the room and the height of the ceiling, the position and size of the opening, how to enter the light, Check out from the perspective of a life-size human being such as how to see from outside, and vice versa. Just thinking makes fun.
I told them to remove the goggle and introduce the VR to the organizer of the briefing on the spot.
呂色職人の工房では、現在制作中の石目乾漆や様々な漆塗りの仕上げや製品を見ることができた。
輪島塗のフリーカップ制作の塗りの打合せのために呂色職人の工房へ来たのだけれども、本題に入る前に塗りというか輪島塗の可能性みたいな話になって、輪島塗を万年筆に施したり、他に乾漆途中の漆器や制作完成間際のフリーカップなどを見せて貰った。
中でも、これは呂色職人の方が自分用に制作しているらしいが、1号サイズの大きさの板に自分で好きなように好きな色の漆を塗り、それに対して好きなように絵柄を描いてと蒔絵職人や沈金職人に渡して制作したものが良く、絵柄の繊細さ、精緻さに加え、その絵柄の図案的処理が古臭くなく、現代的で素晴らしかった。輪島塗は全ての工程が分業体制で、それぞれの工程に専門の職人がいるが、それぞれの職人の質の高さと文化的意識の高さと好奇心に輪島塗の奥深さと底力を見たようだった。
ただ残念なのは、これらの職人に後継者がいないこと。これらの技術を生かす場がないのだ。後継者を育てるためには、その技術を生かす場をつくらないといけなくて、そのためには職人の技術を最大限に生かす無理難題な仕事を持ち込まないといけないし、それだけでは仕事の絶対数が少ないかもしれないから、職人の技術を最大限に生かすものを現代的なセンスで勇気を持ってこれですとつくり出す人が必要、会社や組織では無くて、人でないと。「類は友を呼ぶ」という言葉があるが、「類」すなわち「集まり」の元は人で、会社や組織では当然利害が生まれ、無理難題な仕事を職人に持ち込むことを躊躇するようになるから、無理難題な仕事を持ち込む人に人が集まり類になると、友を呼べて、共感が得られ、輪が広がり、職人の技術を最大限に生かす場ができる。
輪島で現代的なセンスで漆器をつくるお店を訪れたが、輪島の職人の技術を全然生かしていないし、老舗を訪れると職人の技術を最大限に生かしたものがあるが古臭い。漆器以外の伝統工芸にも言えることだが、後継者が育たないのは、伝統技術を生かした仕事が産業として成り立っていないため、産業として成り立たないのは、宣伝やブランディングが足りないという人もいるけれど、単につくっているものが受け入られていないだけ、何をつくれば良いのかがわかっている人がいないから。
呂色職人が自分用に制作したものに銀色の漆塗りのものがあり、一緒に行った塗師の方もひと目見て「これいいじゃない」と言ったもので、私も気に入った。呂色職人にきくと、その銀色は錫だそうで、錫を焼いて色粉にしたもので、焼かないで錫を使うと臭いらしい。他に、その錫と銀の漆を塗り分けたお箸があり見せてもらうと、錫と銀では微妙に色が違う。比べると銀の方が少しだけ茶色い、これは銀が酸化するためだと呂色職人は教えてくれた。私の色の好みは錫の方だった。
輪島塗のフリーカップの漆塗りの色については、特に何色にしようという構想はなく、人肌の感触にすることだけが決まっていて、その人肌の感触をつくる上で色が決まるのであれば、その色でよかった。
カップの漆塗りの打合せになると、とにかく私は人肌の感触にすることが第一で、色に関しては二の次だと呂色職人と塗師の方に再度はっきりと伝えた。ここがブレるときちんと見本ができて来ないだろうと思ったから。呂色職人の方は私よりもたぶん10歳位は年上の方だが、
「私の肌と若い人の肌は違うからな、若い人の潤いのある肌を参考にしないと」
と言いながら、塗りの艶はどうしますか、と私にきいてきた。
私「艶も人肌の感触を出すための大事な要素だと思うので、人肌の感触を出すことを優先して、艶はあっても無くてもいいです」と伝えた。
とにかく、人肌の感触を出すためには呂色職人の伝統技術に裏打ちされた技にかかっているので、呂色職人が迷わないように、この打合せで私は交通整理に徹していた。だから、色にはこだわりがないが、色が意味性を持つのも嫌だったし、カップなので中に入れる飲み物が不味そうに見える色は避けたかったので、無彩色、これならば意味性も特に無いだろうし、飲み物を入れるのに無難な色だと思い、黒、白、それと先程の焼き錫の三色を指定し、この三色で石目乾漆の技法を元に人肌の感触をつくり出した漆塗りの見本を制作してもらうことになった。
ここまで輪島の塗師の方、椀木地職人、朴(ほう)木地職人、呂色職人の方は親身になって、私が考えたことがどうやったら実現できるのかを真剣に考えてくれました。本当に感謝の言葉しかありません。
漆塗りの見本ができ上がったら東京に送ってもらうことになり、それで木地と見本を見ながら、再度どうするかを考えて、必要ならば再度来輪する予定。見本が送られて来るのが本当に楽しみでしょうがない。
"Leverage traditional techniques"
In the workshop of Lu color craftsman, I could see the finest products and products of stone-eyed lacquer and various lacquer coatings under construction.
Although I came to the workshop of Lu color craftworker for the meeting of painting of Wajima coat free cup production, before it goes into the main subject, it is said to be painting or a story like the possibility of Wajima coat, applying Wajima coat to a fountain pen, Other than that I got the lacquerware in the middle of the lacquer and the free cup just before completion of production.
Among them, this seems to be produced by Lu color craftsman for myself, but paint the lacquer of the color of your choice on your board of size 1 size yourself as you like, as you like against it Writing a picture and passing it to a lacquer craftworker or a deposit craftworker (image one) was good, in addition to the delicacy and precision of the picture, the design process of the picture was not old-fashioned, it was wonderful contemporary. Wajima coat seemed to see the depth and bottom power of Wajima coat for high quality and cultural awareness of each craftworker and curiosity, although all processes are division of labor and each process has specialized craftsmen.
The only regret is that these craftsmen have no successor. There is no place to make use of these techniques. In order to nurture the successor, we need to create a place to make use of that technology, and to do so we have to bring in an unreasonable task to take full advantage of the craftsmen's skills, and that alone means that the absolute number of jobs Because it may be few, people who make the utmost use of craftsmanship technology are needed with a courage to do this with modern sense, this is not a company or organization, not a person. There is a word "kind calls a friend", but the origin of "kind" or "gathering" is a person, a company or organization naturally has interests, he / she will hesitate to bring unreasonable tasks to craftsmen When a person gathers into a person bringing in an impossible task, you can call friends, gain empathy, spread the circle, and have a place to make full use of craftsmanship techniques.
Although I visited a shop that makes lacquerware with modern sense in Wajima, I do not make full use of the technique of Wajima's craftsmen, and there are things that made full use of craftsmanship techniques when visiting long-established stores, but old-fashioned. Although it can be said to traditional crafts other than lacquer ware, successors do not grow up because there is no business that makes use of traditional technology as an industry, so there are people who are not satisfied with industry as advertisements and branding are insufficient But, as there is no one who knows what to create just because it is not accepted what you are making.
There is a silver lacquered lacquer (thing of the image) which Lu color artisan made for myself, and the painter who went with it also saw at a glance and said that "This is not good", and I favorite. When I heard the Lu color craftsman, the silver color seems to be tin, I baked tin to make it a color powder, and when I use tin without baking it seems to smell. Besides, if you have chopsticks (image one) that painted the tin and silver lacquer, it is slightly different in color between tin and silver. Lu color artisan taught that silver is a little brown in comparison, this is because silver oxidizes. My preference for color was towards Tin.
Regarding the lacquered color of Wajima-covered free cup, there is no specific idea of what color it is made, only what to make it to the human skin is decided and if the color is decided in order to create the feel of the human skin It was good with that color.
Anyway, I got to tell Lu color craftsman and painter again that color was about to be secondary in terms of making the feel of human skin the first time when it was a lacquering meeting for cups. Because I thought that a sample would not come out properly when this was brought down. Lu color craftsman is probably older as I am about 10 years old than me,
"My skin and the skin of young people are different, I have to refer to the skin with young people 's moisture"
While saying that, I asked me what to do with the gloss of the paint.
"I think that gloss is also an important element for giving the feel of human skin, so it is good to give a feel of human skin, gloss may or may not exist."
Anyway, in order to bring out the feel of human skin, it depends on the technique backed up by the traditional technique of Lu color craftsman, so Lu color craftworker did not get lost, I was thoroughly handling traffic control at this meeting. So, although there is no particular attention to the color, I also disliked the color to have meaning, because it was a cup, I wanted to avoid the color that the drink put in would look unfavorable, achromatic, in this case semantic Also, I thought that it was a safe color to put in drinks, I specified the three colors of black, white, and the above-mentioned grilled tin, and based on the technique of the stone eye dry lacquer in these three colors the feel of human skin It was decided to have a lacquered painting sample produced.
Have you been a Wakajima painter, a bowl of woodland craftworker, a craftsman of Park, a craftsman, Lu color craftsman so far, seriously think about how I can realize what I thought It was. I really only have words of gratitude.
When the sample of lacquer finish is finished it will be sent to Tokyo, so while watching the wood and swatches, I will think about what to do again and plan to come back if necessary. It is really fun to be able to send a sample.
呂色職人は塗師屋の所に別の用事があり、来ることになっていたらしい。別の用事とは座卓の傷直し。
輪島塗のフリーカップの塗りの人肌感触の打合せの続きは、呂色職人の工房にて行うことになったので、おもむろに傷直しの作業をしはじめた。塗師が言う、滅多に見られないよ、と。
見本場の打合せテーブルの横に布を掛けられて置かれていた座卓には、すでに傷の部分に同色の漆が塗られていて、乾くのを待っていたようだ。呂色職人により磨く作業がはじまった。
先程までの打合せの中で呂色職人の方が
「漆塗りの工程の中で何が一番重要だかわかりますか?」と私に問うてきた。
私「塗り、上塗りですかね。最終的な仕上げだから」
職人「皆さん、そう言いますね。確かに、上塗りは重要ですよ。それに花形というか、華々しい部分ですからね。でも、違うんですよ。磨きなんです」
呂色職人曰く、磨きという工程は、下塗り、中塗り、上塗りの全ての工程にあり、磨きが下手だと上手く塗れないらしい。確かに、磨いて下地が平滑でないと綺麗には塗れないだろう。自分の工程が一番重要だと言いたいだけかな、という気もしたが、ただそれも一理あるなと思った。
その磨きの作業がこれから見られる。職人は呂色粉と呼ばれる白い粉を取り出して、自分の手に付けはじめた。磨くと聞いたから、何か道具を使って行うのかと思っていたが、手の平が道具だった。
手の平の感触だけを頼りに、あらかじめ傷の部分に塗られた漆を磨いていく。元々の座卓は相当艶がある仕上げなのに、呂色粉を付けた手の平だけで段々と艶のある仕上げになっていく。素人からすれば、これだけ艶のある仕上げだと、かえって手の平にある掌紋の凹凸が細かい傷になり目立つのではないかと考えてしまうが、見事に傷の部分がわからなくなり、座卓の他の部分の艶と全く同じように仕上がった。その間わずか10分足らず、正に職人技の極致を見たようで圧倒された。
"Craftsmanship"
Lu color craftsman seems to have another business at the paint shop, and was to come. Another errand is to repair the seat.
The continuation of the discussion of the human skin feeling of the Wajima-coat free cup painting was to be done at the workshop of Lu color craftworker, so I started to do the work of rewriting in good faith. The painter says, it rarely can not be seen.
The seat table which was put on cloth next to the meeting table of the exhibition ground already had lacquer of the same color painted in the part of the wound and seems to have been waiting for drying. Work started to polish by Lu color craftsmen.
Lu color craftworker in the meeting until the previous
I asked myself "What is the most important thing in the lacquering process?"
I "paint, top coat, because it's the final finish"
Craftsman "Everyone, that's true, it is true that the top coat is important, and it's a spectacular part, because it's a flower form, but it's different, it's a polish."
Lu color craftsman said that the process of polishing is in all processes of undercoat, middle coat, top coat and if it is poor in polishing, it can not be painted well. Certainly, it will not be cleanly painted unless the surface is polished and the smoothness is not smooth. I thought that I just wanted to say that my process was the most important, but I just thought that there was a way too.
The polishing work can be seen from now. The craftsman took out the white powder called Lu color powder and began to put it in his hand. I was told that I would polish, so I was wondering if I would do it using some tools, but my palm was a tool.
Depending on only the feeling of the palm, I will polish the lacquer painted on the scratches in advance. Although the original seat table has a finished glossy finish, it gradually becomes a glossy finish with only the palm with lustrous powder. From an amateur, if this is only a shiny finish, I think that the unevenness of the palm print in the palm is a fine scratch and stands out, but it is not surprising that the part of the scratch becomes obscure, the other part of the seat table It was finished in exactly the same way as the gloss of. Meanwhile, it was less than 10 minutes and I was overwhelmed as if I saw the extreme of craftsmanship right.
「鯖あるけど」
カウンターにいたもう1人の客が帰ってすぐに大将が唐突に声を掛けてきた。
私「えっ」
大将「鯖があるけど」
間髪入れず、被せ気味に
私「ください」
大将はニコニコしながら急に話し掛けてきた。
昼間、塗師の方がそのお店のおススメを教えてくれた。今だったら香箱蟹、鱈の白子。それに加えて、輪島のふぐ刺し、白海老の天ぷら、酢牡蠣も注文、生ビールを少し呑んでから、輪島の地酒も。
香箱蟹の内子、外子で地酒をゆっくりとなんて思ったが、その旨さにかぶりつき、最後は甲羅に地酒を入れて、きれいに食べていたのを見ていたのかもしれない、全然話し掛ける雰囲気が無い大将が何の前ぶれもなく「鯖あるけど」だったので。
鱈の子付け、のどくろ、それとメニューになかった鯖の刺身を食べ比べながら、鯖が一番旨く、大将にお礼をと思い、
「鯖美味いですね」と言ったら
ニコッとしながら
「鯖はね」と一言、また黙々と大根の皮むき、仕込みか、この無理のない、ほっとかれ感がちょうど良い。
この大将に塗師の方を紹介してもらったから、輪島塗のフリーカップ制作がはじまった。
「仕事?」また唐突に一言、
私「いや、仕事というか、漆器をつくりたくて、というか、以前大将に塗師の方の連絡先をきいて、それから、以前に木地をつくり、今日塗りの打合せをしてきたんですよ」
カウンターの入口近くの端の席を指して
大将「あこの席にいたよな」
やはり、覚えていてくれたらしい。何か嬉しかった。
それから、どんなカップをつくっているのか、携帯の画像を見せながら、木地はこうしてあーして、塗りはこんな感じにしたくて、それで今日、こんなことがあって、こーなったなどと、大将に話したら、作業中の手を止めて、店で使っているカップの漆器を出してくれて、これいいだろという感じでカウンターに並べはじめた。そこから漆器談義、はじめてこのお店に来た時もそうだった。
漆器の話からはじまって旅行の話まで、大将が人懐っこく話し掛けてくる間でゆったりとしていたら4時間位いたかな、大将の言葉で一番印象に残っているのは、
「儲ける商売の仕方は客が離れるが、儲かった商売の仕方は客が支えてくれる」
輪島の塗師や職人は皆なこの「儲かった商売の仕方」で、まずは技術的な話、お金の話は二の次という様子で、だから、こちらも実現したいことをどういう技術を使って、どうつくるかの話に専念しやすい、だから、打合せをしていて楽しい、実現していく実感が直に得られるから。
最後に釜飯まで食べて、気持ちよく、お腹パンパンで、真っ暗な中、月を見ながらホテルまで、カウンター越しにしか見送らない大将がわざわざ出てきてくれて、ニコニコしながら、また来年来ますと告げて帰った輪島の夜でした。
"Reunion"
"There are mackerels"
As soon as the first customer returned to the counter, the general came suddenly.
I "Eh"
Admiral "There are mackerels"
Do not put on your hair,
I "Please"
The general suddenly spoke to us while smiling.
In the daytime, the painter taught me the recommendation of the shop. If it is now, it is a barakaba crab, cod white matter. Besides that, we also ordered Wajima's blowfish, tempura of white shrimp, vinegar oysters, drinking a bit of draft beer, also local sake from Wajima.
I thought slowly the sake as a baby crab crab and a foreign boy, but I hung on to that effect and at last it might have been seeing the local sake in the shell and eating cleanly, the atmosphere of speaking at all Because no generals were "no sausagi" without any precaution.
Mackerel was the most satisfactory while thinking of eating the cod attachment, the skull and the mackerel of the mackerel which was not in the menu, mackerel was the best,
When saying "Mackerel is delicious"
While making it nice
One word saying "Mackerel", silently peeled the radish, put it in, it is reasonable, feeling relieved is just right.
Since this general was introduced to the Painter, the Wajima-coat free cup production began.
"Work?" In addition,
I: "No, I wanted to make a lacquerware, I asked the general of the contact address of the Painter before, I made a woodland before and we had a meeting of painting today."
Point at the end seat near the entrance of the counter
Admiral "You were in the seat of ako"
After all, it seems that he remembered. I was pleased.
Then, while showing the picture of the cell, what kind of cups are making, the woodlands do like this and I want to paint like this, so today, this is the case, Talking to, I stopped the work in operation, put out the lacquerware of the cup used in the shop, and started to line up at the counter with feeling like this. It was also when I came to this shop for the first time about lacquer ware handling.
From the story of lacquerware to the story of the trip, it seems that if I was relaxing while the general caught friendly and spoken, it would have been around 4 hours, the most impressive thing in the generals'
"The way customers make money, how to make money is profitable, but customers will support the way of profitable business"
Wajima's painter and craftsman are all "how to make a profitable business", first of all technical story, the story of money is a secondary story, so the situation is like secondary story, so what kind of technology will be used for what we want to realize and how to make it Because it is easy to concentrate on the story, so that you can get a sense of fulfillment, realizing that you are having fun meeting.
Finally eating up to Kamoro, feeling good, with a stomach bumper, while looking at the moon, while seeing the moon, the general who only watches over the counter comes out of their way, noticing that I will come next year, while smiling next year It was the night of Wajima that I returned.
カップの飲み口の厚みが不連続に変化しており、その日の気分で飲み口の位置を変えることができ、また、カップに入れる液体によっても、熱いもの、冷たいもので飲み口を変えてもおもしろい。カップ自体の形が非対称なので、飲み口の位置を変えれば見え方も変わる。だから、その日の気分でカップの見え方も違う。
輪島塗のフリーカップの木地について、その日の気分とカップに入れる飲み物があってはじめて成り立つデザインを考え出した時、はじめて木地の形にしっくりきた。そこにはカップのデザインの範疇がどんどん広がり、人の営みが直にカップのデザインを決める要素になり、また気分というころころと変わるものに合わせて、デザインもころころ変わるところが、このカップはこれですというものがはっきりしない、曖昧で、でも使う人次第で見え方、すなわち存在感みたいなものまで変わり、それが特定の人だけでなく、万人に対して起こるところがいいと思った。
使う人を選ばない汎用性がありながら、使う人によって変化する特殊性を兼ね備えているのがとてもいい気がする。
普通はどちらかだけ、汎用性が高くなると誰でも使えて便利だか、そういうものは誰でも使えるようにするために、好みに左右されないように、ありきたりな、どこにでもあるものであり、それは悪いことではないが、あえてそれを使う意味もない。例えれば、100均の食器だろうか。100均の食器はよくできている、100円であのクオリティには驚くが、特徴は安いだけで、あえてそれを使う必要もない。
逆に、特殊性が高くなると、誰でも使えなくなったり、好みに左右されるようになるが、それが気に入った人にとってはかけがえのないものであり、大切なものであり、あえてそれを使う意味があるものになる。輪島塗の蒔絵の漆器などはこちらの特殊性が高い印象がある。
汎用性も特殊性も大事で両方あれば良いが、両方を求めたデザインは大抵中途半端なものになる。だから、どちらかに重きを置きつつ、片方もある程度満たすようになれば良い。やはり、大切にして欲しいし、それをあえて使う意味がある方がものの在り方としては健全というか良いことだと思うので、特殊性が強くあるけれども、汎用性も同時に満たしているのが良い、それは輪島塗の漆器の目指す方向性としても良さそうだった。
漆器でないとできないことがあると今回気づいた。日常生活の中で漆器が登場する場面はどんどん減ってきていて、むしろ日常生活とは乖離した美術工芸品として存在し、そのために伝統技術が残されている感すらあるような気がする。ただ、それだと量が少ないので産業として成り立たず、伝統技術の後継者が育たないだろう。
漆器としての特殊性は残さないと伝統技術が廃れてしまうので必要だが、同時に漆器でしか出せない汎用性もある、それは陶磁器やガラスではできないことなので、そこに気づいて焦点をあてれば汎用性を獲得できる。ただ技術水準は絶対に落とさない、価格が安いからと木地制作を他に頼まない、技術水準を落として漆器を安く制作して量をさばく汎用性を獲得しても、それは100均がすでにやっていることだし、伝統技術の担い手がすることではない。
木地の断熱性や、漆器の軽さや、漆塗りの感触などにもっと焦点を当てれば、陶磁器やガラスにはない汎用性や、さらには新たな特殊性、陶磁器の釉薬も伝統技術だが、そこに新たな試みをしている人達もいて、新しい陶磁器の感触などをつくりだしているので、漆塗りもまだまだ新たな試みをする余地が十二分にあると今回気づいた。
"The way of the previous one"
The thickness of the drinking mouth of the cup is changing discontinuously, the mood of the day can change the position of the drinking mouth, and also depending on the liquid put in the cup, hot or cold one to change the drinking mouth Interesting. Since the shape of the cup itself is asymmetrical, how it looks changes when you change the position of the drinking mouth. So, the appearance of the cup is different depending on the mood of the day.
About Wajima-covered free cup wood land, when I came up with a feeling of the day and a drink to be put in a cup for the first time, I came up with the shape of the woodland for the first time. There, the category of cup design gradually expanded, the design of the cup is changed, the design of the cup is changed, the design of the cup is changed directly according to the thing which changes with the thing which turns into the feeling directly, Things are not clear, ambiguous, but depending on who uses it, it changes to what it looks like a thing like presence, I thought that it was good not only for a specific person but also for everyone.
I have a versatility that does not depend on who I use, but I feel that it is very good to have special characteristics that change depending on who uses it.
Normally only one of them is convenient for anyone to use if the versatility is high, so that anyone can use it, so that it will not be influenced by taste, there are ordinary, everywhere, that is bad Although it is not a thing, there is no point in dare to use it. For example, is there a hundred equal tableware? 100 uniform tableware is well done, it is surprising at that quality at 100 yen, but the feature is cheap, there is no need to dare use it.
On the contrary, when the specialty becomes high, it becomes usable by everyone or becomes dependent on taste, but for those who like it it is irreplaceable, it is important, it means dare to use it There will be something there. The lacquerware of Makie of Wajima coat etc. has a high impression of this particularity.
Both general versatility and specialty are both important, but both designs are somewhat halved. So, with one's emphasis on one, one can satisfy some to a certain extent. After all, I want you to cherish it, I think that it is healthy or a good thing as a person who has a meaning to use it dare to use it, so it is good to satisfy versatility at the same time though it has strong specialty It seemed to be good as a direction for the lacquerware of Wajima coat.
I noticed this time I can not do it unless it is lacquer ware. The scene where lacquerware appears in everyday life is decreasing rapidly and it exists rather as art craft which diverged from everyday life and it seems that there is even the feeling that traditional technology is left for that reason. However, because it is small amount, it will not be established as an industry and the successor of traditional technology will not grow up.
If you do not leave any specialty as a lacquer ware, traditional techniques are obsolete, but there is also versatility that you can only do with lacquer ware, at the same time there is versatility that can not be done with ceramics or glass, so if you notice there and focus on versatility You can earn. Just do not drop the technical level absolutely, because the price is cheap, do not ask the other woodland production, even if you lower the technology level and cheaply produce the lacquerware and gain versatility to judge the quantity, it is 100 It is what I am doing, and it is not a thing that traditional technology carriers do.
If we focus more on the insulation properties of woodlands, the lightness of lacquerware and the feel of lacquering, general versatility not found in ceramics and glass, and even new specialty and ceramic glazes are also traditional techniques Some people are trying new things and have created a feeling of a new porcelain, so I noticed that there is more room for new lacquer painting than ever yet.
よく受け入れてくれるものだ、何の実績もないし、変なスケッチを持参したのに、嫌な顔ひとつせずによく付き合ってくれるものだ。面倒くさいとは思わないのだろうか、むしろ面倒くさい方へどんどん進んで行くのだけれど。そんな人がたくさんいるようには思えないけれど、こんな面倒くさいことを言う人に皆さん慣れているのかなと輪島にいる間は思っていたけれど、たぶん、そういうことではないのだろうと後で思った。
持っている技術が相当高いから、面倒とか、くさいとか、という感情や思いがそもそも湧き上がって来ない、精神的に左右されない。当たり前にできるから、当たり前にやるだけなのだろう。
確かに、非対称の形だから、難易度が高く、相当悩みながら答えを出しているけど、短時間に簡潔にできることとできないことを選り分けて、できる中から最善の策を出してくる感じ。だから、打合せをしていて本当に気持ちがいい。本当の職人と話をしていると、自分が考えたことが段々と実際の形になっていく実感が得られ楽しくて仕方がない。
椀木地屋さんでは断念したデザインですが、次に塗師のご主人が連れて行ってくれた所は朴(ほう)木地屋さん。朴(ほう)木地屋さんは仏具などをつくる木地屋で、御膳の猫足などのように複雑な形をつくる時に請われる木地屋さん、もしここで制作できなければ、この非対称の形をあきらめるしかない所だったかもしれないと後で思ったが、椀木地屋から朴木地屋までの移動の車中での塗師のご主人からは、何とかなるだろうという勘が働いているのか、楽観的な雰囲気が伝わってきたので、こちらはもう任せるしかないこともあり、私も能天気に車窓の景色を眺めていた。
10分位で朴木地屋さんに着くと、そこにはたくさんの工作機械が置いてあり、中には大型のものまで、うちの会社にも作業場があって、そこにも工作機械があり、達磨ストーブもあるので、見慣れた風景と似た雰囲気に親近感がわいた。帰る時に聞いた話だが、朴木地屋をする人は少なく、理由はこの工作機械を揃えるだけでもかなりの費用がかかり、尚かつ、工作機械を扱うので危険を伴うからだとか。この朴木地屋さんは代々昔から引き継いで営んでいるとのことで、ここの朴木地職人の方はたぶん私より若かった。
輪島塗の制作工程をとりあえず一通りは頭に入れて来たけれども、それぞれの工程での制作風景は当然見たいことがないから、それでも椀木地屋さんの制作の仕方は何となく想像できる範疇だったので、こうできないか、ああできないかと思いを巡らすことはできたが、朴木地屋さんについては全くどうするのかがわからず、ただ持参したスケッチを見せて、どうしたらこの非対称の形をつくり出すことができるのかを朴木地職人の方に考えてもらうしかなかった。
"Naturally"
It is a thing that accepts often, there is no track record, and although I brought a strange sketch, I often go out without attending a disagreeable face. I do not think that it is troublesome, but rather going more and more towards those who are troublesome. Although I do not think that there are many such people, I thought while everyone in the Wajima might be accustomed to those who say such a troublesome thing, but I thought later that it is not that kind of thing later.
Since the technology which it has is considerably high, feelings and thoughts such as troublesome or crispness do not rise in the first place, it is not influenced mentally. Because we can do it for granted, it is only natural to do it.
Certainly, it is an asymmetric form, it has a high degree of difficulty and answers while considerably worrying but I feel that it is best to pick out what I can and can not do briefly in a short time, So, it is really comfortable to have a meeting. If you are talking to a real craftsman, you will be able to have a sense of realizing that what you thought is gradually becoming an actual shape is fun.
It is a design that we abandoned at a bowl of a wooden store, but the place where the husband of the painter next took me is a Park wood store. Park is a wooden house that makes buddhist clothes and the like, a wooden store asked when making complicated shapes like the cat's legs of a meal, if you can not produce it here, you can only give up this asymmetric shape I thought later that it might have been, but from the husband of the painter in the car moving from the bowl wooden store to the Park Parka, whether the intuition that it will manage somehow works, the optimistic atmosphere is transmitted So, there are things that I have to leave to this one already, and I was watching the view of the car window in Noh weather too.
When arriving at Park Parker in 10 minutes, there are plenty of machine tools in it, there are also workplaces in our company, even large ones, there are machine tools there too, Takuma There was also a stove, so it got a sense of closeness to the atmosphere similar to familiar scenery. Although it is a story which I heard when going home, there are few people who do Park Parka, because the reason is that it costs considerably even just arranging this machine tool, and because it handles machine tools, it is dangerous. Park's wood store says that he has been taking over since a long time ago and the caskman of Park Park was probably younger than me.
Although the production process of Wajima coat was brought in the morning for the time being, nevertheless there was nothing I wanted to see the production scenery in each process, so still it was a category that can be imagined somewhat, Although I was able to think whether I could not do this, but I do not know what to do about Park Mokuya at all, just show sketches I brought, how can I create this asymmetric shape Park Ji There was no choice but to ask the craftworkers to think.
椀木地職人との打合せでも、やはり問題になったのが非対称の形だった。輪島塗フリーカップ制作のおいて、まずは木地の形をどうするか、これに関しては自分なりに満足のできるデザインの所までは行った。建築の場合もそうだけれど、イメージや構想を設計やデザインやスケッチとしてまとめ上げるのはかなりの労力を要するが、それで終わりではなく、むしろここからが本番で、この設計やデザインやスケッチを実現するために、誰に声を掛け、誰と話し、誰につくってもらうかを考えて、だから、こう準備して、こう伝えて、それにどう関わるかが重要になる。実現する段階でこれらひとつでも間違うと、せっかくまとめ上げた設計やデザインやスケッチ通りのものができず、残念な結果になる。
それだけは避けたかった、本当にこの木地のデザインが気に入っていたから。ただ、今回は全く誰もツテがない所からはじめて、お会いする人全てがはじめての方ばかりで、短時間で関係づくりからはじめるので、実際に実現することを全くと言ってよい程コントロールができない、ぶっつけ本番のようなものだった。
こういう場合、今までの経験上、依頼を請けてくれる職人の方の意識が高く、腕がよくないと、うまくいかない。そこはもう輪島の職人の方々を信頼するしかなかった。
椀木地制作の過程でも、全体の形が対称のもので厚みが違うだけならば、回転する木材にノミの角度を変えて入れてやればできるとのことで、実際にそれは今までに行ったことがあるそうで、見本(画像のもの)も見せてもらった。
ただ、それはあくまでも全体の形が対称ならばの話で、私が持って行ったスケッチを眺めながら、塗師のご主人、椀木地職人、私とで、どうしたらこの非対称の形をつくり出すことができるのかを一緒になって考えていた。
もともと回転する木材にノミを入れて成形するやり方だと、対称の形はつくりやすく、非対称の形は無理なのではないかと思っていた。私の木地職人の作業の仕方に対する勝手なイメージが椀木地制作の要領だったので、スケッチを描きはじめた当初から、この非対称の形が本当にできるのかどうか半信半疑だったが、それでも厚みを変えることができるのだからと、いろいろと考えて提案してみた。
例えば、2個1にするなど。左右別々に対称形のものをつくり、縦に半分にして、左右それぞれ別のものを組み合わせて1つのものをつくるなど。これは塗師のご主人も私もできるような気がしたが、椀木地職人はできることとは思わなかったようだった。
できるかもしれないという勘みたいなものが働く時は大抵、例えすんなりとはいかなくても、できるもので、できることとは思わない時には、全くと言ってよいほど、かもしれないすら思わない。それは長年の経験からくる勘だと思うが、できない時にはハッキリと「できません」と言ってくれた方がむしろありがたい。
この人ができない、やめた方がよいと言うならば、素直にやめようと思える人と一緒に仕事がしたい、といつも思っているので、塗師のご主人や椀木地職人の方には、素直にそう思えたので、椀木地職人が「うちではできないですね」と言った時には素直に従えた。
あとは塗師のご主人に任せるしかない。ご主人には他にアテがあるらしく、ここでは断念して、他の木地屋さんに行くことになった。
ただ、この椀木地職人の方には、プロとしての気構えと、意識と技術の高さを感じて、とても気持ちのいい打合せができ、この椀木地屋さんで過ごした時間は短くも楽しいものだった。
"Leave it to trust"
Even with a meeting with a bowl of woodland craftsman, what was still a problem was asymmetrical form. In Wajima coat free cup production, we first went to the place of design that can satisfy ourselves as to how to shape the wood land. Even in the case of architecture, it takes considerable effort to design images, concepts and design as a design, sketch, but it is not the end of it, rather it is real from here, in order to realize this design, design and sketch So, who is talking to, talking to whom and talking to whom, thinking about who to make it, so prepare this, tell them how it is important to know how to do that. If you mistake one of these at the stage of realization, you can not do the design, design or sketch that you gathered together, which is disappointing.
I wanted to avoid that much, because I really liked the design of this woodland. However, this time for the first time since nobody gets tired, it is only the first time for all of you to meet up, so we start with relationship creation in a short time, so we can not control as much as we actually can realize , It was like a batting turnaround.
In such cases, experience is that if the consciousness of the craftworker who undertakes the request is high and the skill is not good, it will not work. There was no other choice but to trust the artisans of Wajima.
Even in the course of producing bowls and woods, if the entire shape is symmetrical and the thicknesses are different only if you change the angle of the fleas to the rotating wood and you can do it actually I heard that there was something I had and a sample (image one) was shown.
However, that is only a story if the whole shape is symmetrical, while seeing the sketch that I brought, with the painter's owner, a bowl of woodland craftsmen, and me, how to create this asymmetric shape I was thinking about what I could do.
I thought that it is easy to make a symmetrical shape and not an asymmetrical shape if it is a way to insert fleas into rotating wood. Since the arbitrary image of how my woodland craftsman worked was the way of making bowls and woodlands, from the very beginning I began drawing sketches, I was dubious about whether this asymmetric shape could really be done, but still change the thickness Because I can do it, I thought variously and made a suggestion.
For example, 2 to 1 and so on. Make symmetrical ones separately on the left and right, half in length and combine different ones on the left and right to make one thing. Although I felt that my husband and master of a painter could do it, it seemed that bowl of woodland craftworker did not think that I could do it.
When something intrinsic that it might be possible works, most of the time, even if you do not get rushed up, you can do it, even when you do not think you can do it, I do not even think that it might be totally. I think that it is an intuition that comes from many years of experience, but it would be much appreciated by those who told me that it can not be "clear" when it can not be done.
If this person can not do, saying that it is better to quit, I always think that I want to work with someone who seems to stop obediently, so if you are a painter's owner or a bowl of woodland craftworker, So I thought obediently when a bowl of woodland craftworker said "You can not do it at home."
The rest is left to the master of the painter. Your husband seems to have other attes, so we abandoned here and decided to go to another wooden store.
However, for this bowl of woodland craftworker, feeling as professional, feeling the height of consciousness and technology, I was able to make a very pleasant meeting and the time spent at this bowl of the wooden store was short but fun It was.
輪島での木地の打合せの前夜は、頭の中でデザインがぐるぐる回ってほとんど眠れなかった。木地のデザインは頭の中では決まっており、あとはスケッチに起こすだけだったので、睡眠時間を確保することを優先して眠りにつき、スケッチは金沢行きの新幹線の中で描き上げることにしたが、ずっとどうするか考えていたので、脳が急にはクールダウンできず、眠りについても頭の中でカップが舞い、脳が勝手に考えていて、イメージが飛び交っていた。ただ、そのおかげなのか、翌朝の頭は、寝てないにもかかわらず、スッキリしていて、よく冴え渡っていた。
新幹線の中でスケッチを起こしながら、ずっと気掛かりだったのは、このスケッチの通りに木地をつくることができるのだろうか、ということ。非対称の形の漆器など見たことがなかったから。
この時は、もし輪島の木地屋さんでつくれないならば、つくれるところを日本全国捜し回ろうと考えいた。そのくらい、この木地のデザインが気に入っていたし、このカップのデザインが良いか悪いかを自分自身で見極めるためにも実際に形にして実現したかった。
輪島までは金沢からレンタカーで1時間半から2時間くらい、4月に訪れたが、天気がよく、日本海の海面がキラキラしていたのをよく覚えている。
輪島の塗師屋の家は昔から、塗師屋造りという職住同居の建築になっているのが特徴。私が通う塗師屋の家もその造りで、その特徴は平面計画にあり、職住同居は普通の町屋造りも同じですが、普通の町屋造りの場合は仕事場が道路側、住居が奥ですが、塗師屋造りはその配置が逆で、住居が道路側で、仕事場が奥。
輪島塗の背景には文化があり、その昔は輪島の塗師は行商しながら全国を周る文化の伝道師だったそうです。全国で見聞きした文化資産を輪島に持ち帰り、それを輪島塗の創作に生かす。家の中で文化的位置を占めるのが住居部分だから、毎日そこを通り仕事場へ行く、文化資産を創作に生かすための平面計画という訳です。
仕事場が奥なので、お客様用の玄関は住居部分と仕事場の境目にあり、道路から建物の側面を通りお客様用玄関へ行く。
その塗師の仕事場にはたくさんの漆器が見本として置いてあり、それだけでも一見の価値があるので、毎度そこへ行くと、塗師のご主人が席を外した隙に、ひとり見入っては「これいいな」とか「おー」とか「欲しいこれ」などと独り言を言って興奮していた。
木地屋さんとの打合せの後、塗師のご主人が大正時代から伝わる見本図録を見せてくれた。そこには今までに見たことがなく、この仕事場にある見本の中にもないような形のお椀がたくさん載っており、その素晴らしい形の数々に思わず見入ってしまった。このような見本図録の現代版はないらしい。仮にあっても、ここに出てくる形以外の物を創作するのは難しい気がするくらい、すでにお椀の形は考え抜かれている、というのが実感。むしろ現代の方が何も考えないで形を扱っている気がしてしまう。
今回、フリーカップの木地をデザインする上で、単純な恣意的形態操作にならないように気をつけていたが、この見本図録を見ていると、ふくよかな丸みを帯びた魅力的な形が多いこと、どうしたらこのような豊潤で魅惑的な丸みが出せるのだろうか、文化資産を創作に生かしてきた輪島塗の伝統の奥深さ故なのか、さんざん形を考えた後だっただけに、この見本図録に載っているお椀の形の素晴らしさや先人の叡智にただただ敬服するしかなかった。
"Predecessor's wisdom"
On the eve of the meeting of wooden plants in Wajima, the design went round about in the head and I could hardly sleep. The design of the woodlands was decided in the head, and the only thing that woke up in the sketch was to give priority to ensuring sleeping time, so we decided to sketch in the Shinkansen to Kanazawa for priority However, as I was thinking about what to do all the time, the brain could not cool down suddenly, the cup was dancing in my head asleep, the brain was thinking without permission, and the image was flying around. But, thanks to that, the head of the next morning was refreshing, despite not sleeping, was well well-kept.
While raising a sketch in the Shinkansen, I was worried for a long time, is it possible to make woodlands according to this sketch? I have never seen asymmetrical shaped lacquerware.
At this time, if I could not make it with Wajima's wooden store, I thought about looking around Japan all the time. About that, I liked the design of this woodland, I also wanted to realize in real shape to see if the design of this cup is good or bad on my own.
We reached Wajima from Kanazawa about one and a half to two hours by a rental car and visited in April, but I remember well that the sea level of the Sea of Japan was sparky with good weather.
The house of Wakajima's paint shop has long been a feature that it is a co-owner-shop building that lives together with a job place. The painter's house I go through is also made, its characteristics are in the planning plan, the living in the same place with the job is the same as in ordinary town houses, but in the case of ordinary town shop building the work place is on the road side, the residence is in the back, The painting shop building is opposite in arrangement, the residence is on the roadside, and the workplace is at the back.
There is culture in the background of Wajima coat, and in the past Wakajima 's painter was said to have been a mission evangelist of the culture which goes around the country while peddling. Take the cultural assets you have heard throughout the country to Wajima and make use of it to the creation of Wajima coat. Because it is the residence part occupying the cultural position in the house, going to the workplace every day passing there, plan plan to make use of cultural assets in creation.
Since the workplace is behind, the entrance for the customer is at the boundary between the residential area and the workplace, going from the road to the side of the building and going to the customer's entrance.
There are plenty of lacquer ware in the workplace of the painter, as it is worth a look, even just that, as you go there every time, in the gap where the husband of the painter took off his seat, I was excited to say himself as saying "Oh" or "I want it".
After the meeting with the wooden store, the master of the painter showed us a sample catalog transmitted from the Taisho era. I have never seen it before, so many bowls of shapes that are not in the sample in this workshop are on board and I have noticed a lot of its wonderful shapes. There seems to be no modern version of such a sample catalog. Even if there is, even if it seems to be difficult to create things other than the one that comes out here, I feel that the shape of the bowl has already been thought out. Rather, I feel that modern people deal with shapes without thinking anything.
Although I was careful not to become a simple arbitrary form manipulation in designing the free cup wooden place this time, looking at this sample catalog, a fascinating rounded and attractive shape It is a lot, how can we have such enriched and fascinating roundness, whether it is because of the depths of the Wajima coat tradition that we have been making use of cultural assets in our creation, after thinking about Shanzan shape I just had to admire the splendor of the shape of the bowl in the sample book and the wisdom of the predecessor.
何でもあり、何をつくってもよいし、何をしてもよい、漆器で木地からつくることができれば可能。
漆器の木地屋さんには4種類あるらしい。お椀などをつくる椀木地、お盆などをつくる曲物木地、お重などをつくる指物木地、仏具などをつくる朴(ほう)木地。
何でもありで自由につくってよい、普段、建築では与条件として要望や予算、期間などがあり、あとは大体おまかせになる。あとは「仲村さんにおまかせします、自由にやってください」とは言え、当たり前だけと、全くの自由ではなく、提案し、すり寄せ、また提案が何度かある。それでも、おまかせと言ってもらえるのはありがたいので、やりがいは感じるが、もっとこうしたい、もっとこうできればの想いは多少なりともいつも残る。
だが、この漆器づくりはクライアントは自分なので、何の制限もない、何をしてもよい。自分のためだけにやればよい。
輪島で輪島塗の漆器をつくる、決まっているのはこれだけ、自由度は最高に高い。この自由度の高さが重要で、私が一番望んでいたこと。
自分と対話し、自分が欲しているものを、自分が好きなように形にする。ずっと建築を通してものづくりをしてきたけれども、ここまで自由度が高い経験はない。この経験をしたかった。後にこの経験を生かす場面が訪れる予定もあるので。
ただ、自由が高いが故に、何を手がかりにはじめるかが重要で、迷うところ。
まず何をつくるか。用途はカップに、ほぼ毎朝、コーヒーを豆から挽いて飲むし、ビールが好きだしで、フリーカップにしようと決めた。
亡くなってしまったが柳宗理というデザイナーがいた。食器、カトラリー、調理道具、家具、駅のベンチ、高速道路の料金所までデザインしていて、私は柳宗理がデザインしたものが大好きで、普段使いに食器やカトラリー、調理道具に、家具と結構家の中にある。
私が柳宗理を好きになったきっかけがマグカップのデザインの話だった。飲む時にカップの縁と唇が当たる感触がよくなるように、何度も試作を繰り返して、マグカップのデザインを決めたという。
マグカップのデザインを決める判断基準が唇の感触だったことに、当時20代の私は衝撃を受けた。触った感触は後の話で、ものとして形があり、素材があり、見た目があり、それで完結していて、使いやすさという尺度はあるだろうけど、使っている最中の感触までデザインとして捉えるということは範疇になかったから。
このことがずっと頭の中にあったから、フリーカップをつくる時の手がかりは感触にしようと考えていたし、私なりに飲み口の唇の感触をデザインに取り込もうと考えた。
毎朝、コーヒーを淹れる時に、コーヒーカップをその日の気分で選んでいる。天気がよい気持ちいい朝だからこれかな、ちょっとお疲れ気味だからこれかな、今日はゆったりと飲みたいからこれかな、という感じで、カップ選びも楽しみのひとつ。
ならば、気分という尺度をデザインに取り込もう。
感触にプラス気分を盛り込む。人は結構気分に左右されるのに、ものづくりとしては案外気分を排除して考えているのでは。ものづくりは人に対して行われるから、対象として参照する人がコロコロ気分で変わってしまっては、気分に対応して変化できないモノは困る。
フリーカップのデザインについて、頭の中で最初に決めたことは、
飲み口の厚みを変えて、その日の気分によって、飲む位置を変えられるように、
でした。飲み口の厚みを変えれば、当然、飲んだ時の唇の感触も変わるはずだし、コーヒーやビール、お茶など、熱い冷たいによっても飲み口の厚みが違う方がよいのではないか、と考えた。感触のよさに、気分という変化を許容できるものを盛り込む。
これがができあがった木地の飲み口です。
ただ、これだけではフリーカップのデザインを決めるには足らないと考え、この飲み口の厚みの変え方がフリーカップ全体のデザインと連動して一体化していないと、それが次の課題でした。
"Include a feeling"
Everything is possible, what you can make, what you can do Anything is possible if you can make it from wood using lacquer ware.
There seem to be 4 kinds of lacquerware wooden store. Bowls making bowls and the like Birch wood lining, Bon festival curved woodlands, things to make heavyweight woodlands, Buddhist wooden buildings, etc.
Normally you can create anything freely, usually in architecture there are demands, budget, period, etc. as a prerequisite, and the rest is almost left to rest. Afterwards, "I will leave it to Mr. Nakamura, please do it freely", but it is not just freedom, just suggestions, grafting, and suggestions several times. Still, I am thankful that I can say it as Random, so I feel challenging but I want to do more, more I always have my feelings somewhat.
However, since this client is myself in making this lacquerware, there is no limitation and anything can be done. You can do it only for yourself.
The only thing that has been decided to make Wajima lacquer lacquerware in Wajima is the highest degree of freedom. The high degree of freedom is important, what I most wanted.
Dialogue with myself and shape what you want as if you like. Although I have been making things through architecture forever, I have never experienced a high degree of freedom. I wanted this experience. There are scenarios that will make use of this experience later.
However, because freedom is high, it is important to know what to start with clues, where to get lost.
First of all, what will you make? I used to drink coffee from beans and drink almost every morning in cup, I decided to make free cup because I like beer.
Although I died, there was a designer named Mr. Yanagi. I designed dishes, cutlery, cooking utensils, furniture, station benches, highway toll gates, I love what Sosaki Yan designed, and I regularly use dishes, cutlery, cooking utensils, furniture and fine house It is in.
The reason I became fond of Mr. Yori Shigeru was the story of the design of the mug. He said that he decided the design of the mug by repeating prototyping repeatedly so that the feeling of hitting the edge and lips of the cup when drinking was good.
I was shocked when I was in my twenties at the time that the judgment criteria for deciding the design of the mug was lip feeling. The touch which I touched is a later story, there is a shape as a thing, a material, an appearance, it is completed and there will be a measure of ease of use, but until the feeling while using it as a design It was not in the category to capture it.
Because this was always in my mind, I thought about making clues when making a free cup feel, and I thought that I would like to incorporate the feel of the lip of the drinking mouth into the design.
Every morning, when I brew coffee, I have chosen a cup of coffee for the day. Because the weather is nice and comfortable morning, I guess this is kind of a bit tired, so I guess this is something I want to drink relaxed today, so I feel like this, I also enjoy cup selection.
Then, let's incorporate the measure of mood in the design.
Add a positive feeling to the feel. People are pretty much affected by the mood, but as manufacturing, we are thinking about removing the unexpected mood. Monozukuri is done to people, so if people refer to them as objects, they change with moods, and things that can not be changed in response to their moods are in trouble.
About the design of the free cup, the first decision in my mind was,
Changing the thickness of the drinking mouth, so that you can change the drinking position by the mood of the day,
was. If you change the thickness of the drinking mouth, of course, the feeling of the lip when drinking should change as well, and I thought that it would be better if the thickness of the drinking mouth is different depending on hot and cold, such as coffee, beer, tea etc. . To the good feeling, incorporate what can tolerate the change of mood.
This is the drinking mouth of the woodland which was completed.
However, thinking that this alone is not enough to decide the design of a free cup, if the way of changing the thickness of this drinking mouth was not integrated with the design of the entire free cup, that was the next task.
形には良し悪しがあり、身の回りに置く物はできる限り良い物で固めたいので、何か物を購入する時は見た目の形でまず判断してしまう。
形が良くないのに、色が良いから、柄が良いから、希少だから、価値があるからなどと、他に良い所があるからと購入することはほとんどないが、唯一その形を超えるのが、スケール。
普段、朝からコーヒーを豆から挽いて淹れているので、毎日同じコーヒーカップでは飽きてしまう、だから気に入ったカップを見つけると手に入れることにしている。
今年手に入れたある陶芸家のマグカップがこれ。正直この形は良いとは思わない。
むしろ同じ陶芸家の次のカップの方が良い形、取っ手の位置と全体のバランスが形に特徴を与えている。
ところが、普段の朝のコーヒータイムで出番が多いのは1番目の写真のカップで、取っ手の形も全体のバランスも良くはないと思うがスケールが良い、言い換えれば、大きさが良い。この大きさだとこの形が良く見える。この形がこの大きさになった時、とても良い感じになる。
良い感じとは、物として存在している佇まいが良い、ということで、そういう物と一緒にいると、こちらまで楽しい気分やワクワクした感じにさせてくれる。
だからか、今朝はどのカップにしようかな、と考えた時に、パッと1番目の写真のカップが思い浮かぶことが多く、当然出番も多くなる。
(ちなみ、この2つのカップは金色に見えるけれども、釉薬に金を使っていないとのこと。この色を見ただけで、陶芸家が誰だかわかる人にはわかる)
このスケールが良いという感覚は人によってちがうと思うし、正解はないと思う。
建築の場合、良いスケール、という正解を、このスケールが良い、と教えられてきた。時には数値で。
確かに、教えられたスケールは良いけれども、正解としてしまったら、建築として存在している佇まいにまで正解があり、しいては、建築に正解がある、となってしまう。
どうしても、それはとても窮屈な感じがする。
良いスケールは人の感覚しだいで、いく通りも存在した方が良い。
感覚的なことは、慣習が何かのきっかけで変化した時、一緒に変わるものだと思うから。
例えば、ランニングが日課になったら、普段歩いている時に、周りの景色の変化が遅く感じられ、今すぐにでも走り出したい気分になる時があった。きっとその時は、周りの空間を捉える感覚が変化したのだと思う。
いく通りも人によって良いスケールが存在しているから、そのスケールによって、1枚目の写真のカップに魅せられたように、新しい見方が生まれる可能性がある。だから、自分のスケール感をいく通りも持つことが大事。
たぶん私のスケール感は、子供の頃レゴブロックで遊んでばかりいたので、自分の手を動かしながら、試行錯誤して育まれたような気がする。
人それぞれが持つスケール感を殺さずに大事にしてものづくりをすれば、必然的にその人にしかつくれないものができるはずだし、それが新しい見方を人々に提供することになるのではないのかな。
定番の正解より、新しい見方の方がおもしろいしね。
おもしろい方が可能性を感じるし、可能性は何事も原動力になる、人を動かしたり、社会を動かしたり。
"scale"
There is good or bad in shape, I want to solidify things that I put around myself as good as possible, so when I buy something, I judge first in appearance form.
Although the shape is not good, because the color is good, the handle is good, so it is rare, because there are values, etc. There are other good places, so there is little to purchase, but only the shape is exceeded ,scale.
Since I usually grind coffee from the bean from the morning and brew it, I get tired of the same coffee cup every day, so I decide to find a cup that I like and I get it.
This is one potter's mug caught this year. To be honest I do not think that this form is good.
Rather, the same pot of the same pot is better shaped, the position of the handle and the overall balance characterize the shape.
However, in the usual morning coffee time, it is the cup of the first photograph that has many turns, I think that the shape of the handle and the balance are not good, but the scale is good, in other words, the size is good. This size is good if it is this size. When this shape reaches this size, it makes me feel very good.
A good feeling means that the appearance that exists as a thing is good, so when you are with such things, it makes me feel excited and excited up to here.
So, when thinking about what cup to make this morning, cups from the first photo will often come to mind, and of course there will be more turnouts.
(Chinami: Although these two cups look gold, they say that they do not use gold for the glaze, just by looking at this color, it is understood to those who know the pottery)
I think the sense that this scale is good differs among people, I think there is no correct answer.
In the case of architecture, it was taught that this scale is good, the correct answer of good scale. Sometimes by number.
Certainly, although the scale taught is good, if it is taken as the correct answer, there is correct answer to the appearance which exists as architecture, and there is correct answer in construction.
By all means, it feels very cramped.
Good scales depend on people's senses and it is better to have as many as possible.
The sensory thing is that when customs change due to some reason, I think it will change together.
For example, when running becomes a daily routine, when you are walking normally, the change in the surrounding landscape is felt late and there was a time when you feel like wanting to run even now. At that time, I think that the sense of capturing the surrounding space has changed.
There are good scales as many people as they are, so there is a possibility that a new viewpoint may be born, depending on the scale, as fascinated by the cup of the first photo. Therefore, it is important to have your own sense of scale as much as possible.
Perhaps my sense of scale was just playing with the Lego block when I was a child, so I feel like I was nurtured by trial and error while moving my hand.
If we make crafts without killing the feeling of scale of each person, we can inevitably have something that can only be made for that person, and maybe that will provide new perspectives to people .
From a classic correct answer, a new perspective is more interesting.
The interesting one feels the possibility, the possibility becomes the driving force for everything, moving people, moving society.
高齢者の施設に行くと、いつも気になることがあった。
「この場所で最期を迎えたいだろうか?」
どれだけいいデザインの建築の中でもそれを感じてました。
建築のデザインの良し悪しとは別のところで。
「家感」
綺麗な建築、でも今まで住んでいた家とはちがう。
記憶の継承は、建築での大きなテーマだけれども、大体は2つ、大きな視点からの継承だったり、例えば、その地域の環境だとか、あるいは、設計者のフィルターを通しての継承だったりする。そこの読み取りや選択に作品性を見出したいからだろう。
でも、きめ細やかな視点からの、各個人の記憶の継承を丹念に行うことでしか、その人にとっての家感は出ない。
家感の欠如が高齢者の施設に対する違和感だった。
一般の住宅でも家感は大事。
記憶の継承を全くしない家づくりが大半だろう。
「記憶の継承」からくる家感を問い直すと新しい住宅デザインの可能性があるかもしれない。
ただ、アレグザンダーのパタン・ランゲージは設計者のフィルターを通し過ぎるので、ちがう何かが必要になる・・・。
「家の中にスベリ台が欲しいんです」
立て続けに違うお客さんから要望が出た。スベリ台流行り?!
面白いので即座に
「やりましょう!」と返事。
2階から1階への移動が楽というのが理由で、それもお子さんからではなく、大人からの要望、でも別に階段は付けて、でも狭小住宅、だから面白いかな。。。
お客さんは今マンション暮らしで階段が無い生活だから、日常的な階段の移動に違和感があるのかもしれない。
建築作品にも、公共空間にも、住宅にも斜めの空間を作ったものはたくさんあり、経験もしたが、斜めの移動空間はまだまだ可能性があると思う。
太古の昔、人は素足で野山を駆け巡り、その時はむしろ水平な地面の方が無かったハズ。
人の意識の奥底には、水平ではない地面でバランスを取りながら生活をする能力が眠っている。
その能力を呼び覚まそうと、今は亡き荒川修作さんが養老天命反転地を作り、その住宅版を三鷹に作ったけど、まだまだ可能性があるような気がする。
人の身体感覚と無意識と記憶をつなぐことで新しい空間の可能性があるハズ。
人の記憶が詰まったDNAを検査して、例えば、将来の疾病リスクから、未病のために日常生活はこういう姿勢で送るといいなど、その人の特性に合わせて家を設計することも現実的にはすぐそこまで来ているかもしれない。
建築やデザインは知覚することで判断できるものだけれども、人が知覚できる世界が極一部ならば、それ以外の所に建築やデザインの可能性はあるハズ。
それにしても、スベリ台流行り?!!
「自分の空間をつくる方法」
今住んでいる家もしくは部屋で、居心地良く暮らしたい、もっと快適に暮らしたい人にオススメのツールです。このツールは掃除や片付けの指南ではありません。整理整頓され綺麗な部屋だから居心地が良いとは限りません。ホテルの一室を思い浮かべてみてください。綺麗で清潔感がありますよね、でも居心地が良いですか?綺麗で清潔感があることは大事ですが、何か落ち着かなくないですか?ここでいう居心地の良さとは、普段の自分が活き活きと活動したくなる気分や安らぐ感覚です。何に対して感じるかは人それぞれ違いますが、それがきちんと感じられる家もしくは部屋が住人にとって居心地が良く快適な空間だと考えます。そのような空間のつくり方をお伝えします。
レイアウトを変える
今住んでいる空間を見渡してください。まず最初に言います。物は捨てません。物がたくさんある方、それら全てがあなたの分身です。そこに記憶があります。それを大切にするところからはじめます。気に入らないものがある?でもそれを手に入れたのはあなたです。その時に必要だったのだから、その必要とした自分を大切にしてください。大切にすることがこの後に役立ちます。そして、行うことはその大切な物を移動するだけ、ただレイアウトを変えるだけです。そのために特別な道具や家具も必要ありません。今あるもので充分です。要するに、今見えている風景を変えるのです。人は外部からの情報のうち8割を視覚で感じとり無意識に判断します。だから、人の見た目の第一印象が大事だとよく言われます。これを利用すると、空間がどう見えるかが人の感覚にとても影響を与えます。すなわち、快適な空間にするためには、自分にとって居心地の良い見え方に変えるだけでいいのです。
一番したいことは何ですか?
では何を基準にレイアウトを変えるか。まず質問です「あなたがその家もしくは部屋で一番したいことは何ですか?」その答えを基準にレイアウトを変えます。わからない人、思い付かない人は、家に人を呼んだ時にしてあげたいこと、あるいは自慢したいこと、気持ちがいいと感じることがあなたの答えです。例えば、料理がしたい、本が好き、食器を大切にしている、写真が好き、フィルムカメラを収集、現状ではできないけれどペットを飼いたいでも、何でも構いません。先程、物は捨てませんと言いました。その物が必要だった想いも答えになるかもしれません。それを決めてください。したいことがレイアウトを変えるという行動の軸になります。もしレイアウトを変えている時に分からなくなったら戻るための軸でもあります。したがって、したいことが決まるまでレイアウトは変えません。
真ん中に
したいことが決まったならば、それに関する物を空間の真ん中に置いてください。家の真ん中、部屋の真ん中です。料理が好きなならば、キッチンは移動できないので、料理を食べる場所を真ん中に。本が好き人は本棚を真ん中に、又は本を真ん中に積み上げる、あるいは本を読む時に座る椅子を部屋の真ん中に置く。食器が好きならば真ん中にディスプレイしてみましょう。フイルムカメラを真ん中にディスプレイしてもいいかもしれません。ペットが欲しいのに飼えない人は動物の写真を真ん中に置いたテーブルに貼る、天井に貼ってもいいかもしれません。写真が好きな人も同じです。
では、どうして真ん中か?一番したいことをしている時がその人にとって一番気持ちがいい時であるはずなので、そこに居て気持ちがいいと感じることが居心地の良さ、快適さにつながります。そして、空間の真ん中に置けば、必ずその一番したいことが常に自身に絡んでくる。したいこと=気持ちがいい=居心地が良い、という心の無意識の変化を利用する仕組みです。すなわち、したいことが常に居心地良くいるためのスイッチの役目をしているのです。
ところで、真ん中に置いたら邪魔になるかもしれません。邪魔ということは絡んでいる証拠なので、自身にとっては良いことです。でももしかしたら、真ん中に持ってきたことがしたいことではないかもしれませんね。自分のしたいことって実はなかなか分からなかったりします。一度いい機会なので試してみるのもいいかもしれません。自分の空間をつくるために、そして自分のしたいことを確かめるために。
(1,758字)
4月29日 (月) 祝日 に
「家という一生に一度のお宝を掘り当てるトレジャーハンター」家づくり
プラン相談会開催
お問い合せより要予約受付中です。
『考え方をちょっと変えれば、
住宅ローンや大金はかかりますが、でも日々の生活は変わらないのに、
ある日、家づくりがはじまる。
そして、目の前にとても大切な大事な物としての家が現れる。
これはまさに、お宝ですよ。
一生に一度、誰でも手に入れることができるお宝が家ですよ!
そして、そのお宝はあなただけが欲しいと思う物です。
私は
そんなお宝を、
あなたが欲しいお宝を、
どこまでも探しに行き、掘り当て、目の前に持って来る人です。
そうだから、
私はトレジャーハンターです。一緒にお宝を探しましょう!』
とは言いつつ・・・
先週、
出雲大社へ参拝に行ってきました。

この写真は、
出雲大社の鳥居の前に立って見た風景で、とても幻想的でした。
旧暦では、
出雲の国では、11月は神在月。
出雲大社に全国の神様がお集りになります。
そこで、
日本各地の工務店の方と一緒に
商売繁盛のご祈祷をうけてきました。

はじめて出雲大社に行きまして、
滞在時間は短かったのですが、
身が引き締まる思いでした。
ただ、
お干菓子をお出しするのでも・・・

何気ないコトです。。。
でも
それができるか、
それに気づくか、
は大きな差。
学ぶことが多い、
京都の鍵善。
黒いテーブル、
黒漆のお皿、
白いお干菓子。
色のコントラスト
と
白いお干菓子の並べ方
による
見え方や受ける印象。
ほんと、
何気ないコトです。。。

犬矢来(いぬやらい)。
有名な祇園のお茶屋さん、
一力茶屋の外壁の足元に巡らされた斜めの柵状のものです。
犬の小便を防ぐための囲いで
傷めばそこだけを取り替えることができ、
最近では、店構えで
京都らしさを演出する際のデザインコード・・・
と思ってました、先日京都に行くまで (^_^;
ところが、
京都の人に聞いたところ、
ひそひそ話を
外で盗み聞きされないためのもの、
だそうです。
京都らしい・・・
一瞬で思いました。
お茶屋さんの前を通ると、
お品書きはありませんが、
のれんが
入口の外側にかかっているところと
入口の内側にかかっているところがあります。
これは、タクシーの運転手さんから聞きました。
内側にかかっているところは、
一見さんお断り
だそうで、
外側にかかっているところは、
一見さんでもいいそうですが、
なんぼとられるかは、わかりまへん・・・
とのことでした (^_^;
らしさは、
時には、しきたり
だったりします。
面倒で窮屈だと思うか、
気持ちよく生活していくためのルールだと思うか。
ただ、
言葉ではない表現
学ぶことは多いです。。。
先日、石巻へ行った際に購入しました。
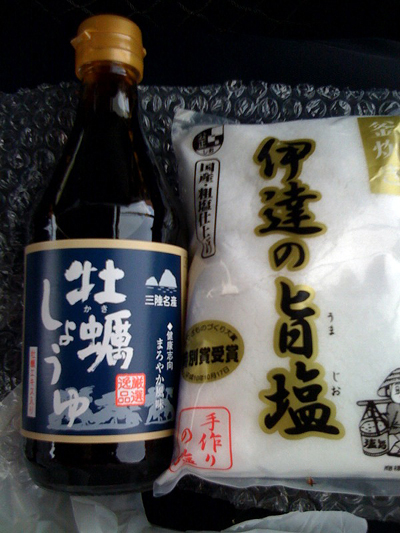
冷やしうどんに
牡蠣しょうゆ
をかけるだけで・・・ごちそうに!
いつもの料理に
伊達の旨塩
を使うだけで・・・上品な味に!
最初、試しに
茹でとうもろこしに
伊達の旨塩をかけてみました。。。
「あま〜い」
いつもの塩とも比べましたが・・・
ちがいがわかる男でした (^_^;
無くなったら、
お取り寄せしよかな、と思ってます。
欲しい方は、
『ロマン海遊21(石巻観光協会)』
をネットで検索して
問い合わせをしてみてください。
これも支援になります。
だって、
牡蠣しょうゆ
も
伊達の旨塩
も
つくってるのは、石巻の人。
たぶん、
伊達の旨塩
は当分つくれないのではないか、と思ってます。
だから、
かなり貴重な塩かもしれません。
先週末、所用で久しぶりに横浜中華街へ。。。

「ポポポッ、ポッーン」
どう思います?
おもしろいし、興味はわくけど・・・。
美味しそうじゃない、食欲わかない。
でも、自分は
持ち合わせがなかったから、、、
入るかも。。。(^_^;
これって、
意外といろいろなことに通じるかもしれません。
目的はなにか?
印象に残る
ならば、大成功です。
他にないから。。。
味は食べてもらわないと、わかりません。
食べてもらうには・・・そう、お店に入ってもらわないと。
中華街ですから、
他にお店がたくさんあります・・・。
ちなみに、
このお店・・・大盛況でした (^_^)
夕方、近くの公園へ・・・緑の中を散歩。

子供の頃よく来ました、砧公園。
いい気分転換に!

すっきりしたあ、また行こお。。。

どうして公園へ行ったか・・・
遊びに行った訳ではありません。
公共性があって、
居心地が良い、
そんな居場所をつくるには・・・
公園の形式を考えていました。
これも家づくりには大切なこと。
プランに生かします。
静岡の人はそう言うそうです。
先週2日間、ビジネスセミナーを受けに静岡へ出張。
地震による新幹線の不通で
当日の朝では間に合わないと困るので前泊。
夕食は、ホテルの近くの弁当屋に。
実は先月も静岡に出張し、目をつけておきました (^_^;
静岡弁当

『あみ焼き弁当』
ソソラレました (^_^)v
誘惑には勝てず、今回行く前から夕食は・・・。

牛タンの味噌焼きです。
けっこう、おいしい!(^_^)
セミナーで一緒の静岡の人に訊いてみました。
「なぜ静岡弁当という名前なの?有名?」
「昔から静岡弁当という名前で、あそこの店だけがやってる」
「なぜ静岡弁当かは・・・わからないなあ」
牛タンの他に、豚もありました。
その人曰く
「豚のあみ焼きは、しょう油味でおいしいよ」
来月は・・・豚!
ビジネスセミナーの内容は・・・ナイショ!!
いずれ成果をお見せします!!!
うれしいことがいっぱいの月でした。
もうすぐ4月も終わり・・・
今月は全然ブログを更新しませんでした。。。m(_ _)m
理由は2つです。
1つ目は
いまさらながら、
twitterとfacebookをはじめたから・・・
書くことがなくなってしまうんです(^_^;
大したことをつぶやく訳ではないんです。
大した書き込みする訳ではないんです。
でも、それで何か満たされてしまって・・・。
twitterは
ユーザー登録だけして、人のつぶやきを見てました。
知り合いが、、、やってるけど、つぶやくだけで、面白さがわからない、
というので、フォローしたら、自分がつぶやくのが面白くなってしまって・・・。
夜中に、、、しょうもないこと、つぶやいてます(^_^;
別の知り合いからは、うるさいと・・・。
facebookは
また別の知り合いから、やらないの?
と言われて・・・。
両方とも、
人の影響です。。。(^_^;
でも、
人の輪が広がりました。
いまさらながら、
けっこう楽しいかも。。。
3月30、31日と静岡に出張でしたが、
不測の事態に備えて、
29日の夜に静岡入り。
東京駅の新幹線ホームは明るい!


車中から見える街はどこも暗いのに、
新幹線の駅だけは日常。
その違和感が・・・
ただ、普段は気づかない
明るさ=安心感だということを思い知る。
でも限度はあるはず。。。
その限度も思い知った。
暗い街はなんとなく雰囲気があっていい。
でも、どこがどこだかわからない。。。

震災後、
はじめて東京を離れた。
東京を離れて、場所が変わって、少しホッとしている。
それだけ、毎日気が張ってて、気がかりなことが多かったのかも。
帰りの東京駅。
気を入れ直す。
早く元の生活に戻りたい。
先ほど、メールで
今度は、岩手の花巻の知り合いの工務店の方と震災後はじめて連絡がとれました。
お元気で本当に良かった。。。
ただ、その方によると
被災地の本当の現実は、ものすごく悲惨な状況で・・・、
テレビで報道されているのは、ほんの一部だそうです。
救援物資の搬送についても、全然対応が出来ていないようで、
直接現地の避難所に持ち込む方が良いみたいです。
その方も、自社で活動することを考えている、とのこと。
私自身そういう話を聞くと、とても歯痒く、無力さを感じます。
阪神淡路大震災のときも同じ感じを抱き、
それが心のどこかで引っ掛かったままでいました。
だから、今回は何かボランティアをするつもりでいます。
ただ、もう少し状況をみて、準備をしてからと思っています。
でないと、逆にまわりの人に迷惑をかけてしまうかもしれません。
いまは待機のとき、
それと、
自分の家族を守るとき、
です。
久しぶりにちょっと遠出、昨日の日曜日。
ここ2週間ほどの間に
2度もウィルス性の風邪にかかり、
相当苦しい思いをしました。
大分仕事も遅れたので、朝から一日仕事の予定でしたが、
外は暖かく、気持ち良さそうな青空に我慢できず・・・。
それに
やっと遠出できるくらいに復調、だから・・・。
午後になってから、谷中に行ってみました。
なぜ、谷中?
ゆる〜い感じが好きで。。。
時々、行きます。
もともと下町の雰囲気は好きなので
それで、ということもありますが、
それだけではない、、、感じ。
とにかく、ゆるいです、街が。
すべてがアナログ。
すべてが人まかせ。
すべてがあり。
これを都市的に考えると・・・。
わかりません (^_^;
というか、考えたくない。。。

ゆるい夕陽の風景あり。

ゆるい商店街あり。

ゆるい野良猫あり。
それでいいでしょう。
谷中は谷中。
でもひとつ・・・。
車に出会わない。
それだけで、
人が
猫が
街が
風景が
ゆるくなるのかもしれません。
でも、そんなのどうでもいいです。
あ〜あ、たのしかった。
また、明日からがんばりましょ。
たまってる仕事しなきゃ、です。

ということで、
前から買いたかった
うなぎの佃煮を
買って、家でお茶漬け食べました。
そんな日曜日。
杉並を西に向かって車で走行中に発見。。。

どこに向けて『バツ』?
誰に向けて『バツ』?
感動といっても、今度はカメラの話。
本日、夕方より
2ヶ月に一度の趣味の会。
中古カメラ好きが
毎回違うフィルムカメラを持ち寄り、
新宿のレストランでカメラ談義。 o(^^o)
このカメラ、凄いです!
はじめて存在を知りました。。。

Tessina(テッシナ)という、スイスの時計メーカーがつくったカメラ。
スイス製世界最小二眼レフ(1960年代頃)。

こんなに小さい!
でも、普通に市販されているフィルムを使うんです。
会の仲間の人が持参。
もちろん、触らせていただきました。(^^)
何に感動か?
まず、
この精巧さ、緻密さに感動!
こんなに小さいのに、
電池も無しに(当然、この会は電池無しカメラのみ許可)
自動巻き上げされる。。。
もちろん、
ちゃんと撮れます!
それと、、、デザイン、このフォルムが凄くいい!
カッコいい!!
スイス製のカメラなんてはじめて!!!
久しぶりに、、、カメラに、、、モノに
感動しました。。。
いやぁ〜、スゴい!!!!
まだ見ぬ強敵がいました。(^^;
ヒント・・・

築地市場の露店の干しイチゴ。
形が悪く出荷できず捨ててしまうイチゴを
ドライフルーツにして販売。
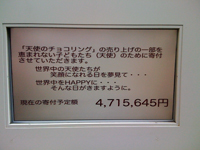
銀座の街角の壁の表示。
「天使のチョコリング」、、、チョコパンです。
買う毎に寄付になる。
干しイチゴは、二次利用。
「天使のチョコリング」は、二次効果。
どちらも『二次』がキーワード。
営業、経営、商売、、、
企画、設計、計画、、、
あらゆる場面でヒントになるキーワードでは(^^)
ちなみに、
干しイチゴも「天使のチョコリング」も購入。
このキーワードも美味しいから成り立つ!?
昨日は、
今の自分に一番欠けている所を補うための研修 part3。
銀座で受けてきました。 o(^^o)
研修内容は・・・。
別の機会にまたお話しします。
かなりパワーアップして帰ってきました。
そして、、、
いろいろなことに気づきました、、、感謝感謝です。 m(_ _)m
この研修に来ると、
昼食はいつも築地の市場まで行きます。
銀座からすぐだし、
それに行ったことがある人はわかると思いますが
食べたいもの、お店がたくさん、、、目移りします。
だから、何回でも行きたくなってしまう。。。 (^^)v
今回は、
場内まで入ってみました。

12時少し前の様子。
平日なのに結構人が。
この後、もっと行列してました。
その中の「鳥藤」というお店に。
親子丼が名物のお店。
で、
しお!?
メニューに「親子丼しお」が、、、
早速注文。

たぶん、
しょう油と砂糖のかわりに
鳥スープを使ってるのか!?
甘くなく、それでいて鳥の出汁が感じられて
今まで食べたことがない親子丼でした。
旨かったです。(^^)
わたしは甘い親子丼が苦手なので
普段は親子丼を注文しません。
でも、鳥好きなので、、、(^^;)ゞ
だから、余計おいしく感じましたよ。
そんな研修の日(?)でした。。。
昨日は、仕事関係の新年会をはしご。
新宿のホテルでの新年会を途中で抜け出して、
トステム本社の最上階にある貴賓室に行きました。 o(^^o)

じゅうたんの毛足が長い!
絵が高そう、、、3億円とか、、、ウソでしょう(^^;
トステム社員の方も入ったことない、と言ってました。
なぜここに入れたか?
社員も行けない所だから、
一般的に言えば、
我々は普通の立場では入れないですよね。。。
これからおもしろい展開があるかも・・・

たい焼きです、、、しかも羽根付き。 o(^^o)
子供の頃から食べてます。大好物のひとつ。
ただし、どこのたい焼きでもいい訳ではありません。。。
下高井戸 たつみや
のたい焼き。
これシッポがうまいんです。
皮はカリカリ。
中身のつぶあんは甘さ控えめでもなく、、、でも控えめ、、、ちょうど良い。
先日、、、
はじめて羽根付きを注文。
前々から
羽根付きを狙っていましたが、
羽根なしが通常なので、、、出来上がりのタイミングで、、、
その時にいないと出会えない、、、というか言いづらい。(^^;)ゞ
羽根を切られてしまう。
切る寸前で、意を決して
「あっ、あ〜羽根付きでぇ〜」と。。。
店員のおばちゃん2人、苦笑い。
わたしも苦笑い。。。
で、めでたく羽根つきゲット!
急いで帰宅。
たい焼きブレイク、、、喜ぶ奥さん。
ちなみに、
うちの奥さんが実家に帰る時の手土産は、ここのたい焼き。
義理の父のリクエストだそうです。。。
たい焼きほうばる、、、うまい。
羽根カリカリ、、、新しい楽しみ。
で、最後はシッポ、、、皮とつぶあんのバランス最高!
この時間、、、たい焼き以外の記憶がありません。(^^;)ゞ
食べたい人、、、並んでください。 (^-^ )
・・・でしょうか。
いろいろな所に12月は行きました。 o(^^o)
仕事や研修ですが、、、
ありがたいことに
いろいろお声が掛かります、、、感謝感謝です。
もちろん、仕事や研修ですが。。。(念押しで!)
その仕事や研修の流れで、、、(また念押しで!)
平日の昼間の築地に行ってみました、、、昼飯に。

なかなか行く機会がありませんでした、
このラーメン屋。

前から知っていて。
昔、深夜放送で店主のドキュメント番組を見ました。
それが何故か印象的で、
ずっと気になってました。。。

味はおいしかったです。
ちょっと、スープがぬるめでしたが。。。
2帖ほどの広さのお店。
立ち食いで、しかも歩道。
お店は厨房だけ。
2人で動き回らずにラーメンがつくれるように配置されてます。
つくる様を見てるだけでおもしろかったです。
やはり、
わたしの何かに触れてるみたいで、、、また行きたい、、、いや行きます。(^^;)ゞ
など、、、
新橋の夜。

銀座の夜。

もちろん、仕事や研修の流れですが、、、(またまた念押しで!)
いろいろな人に会い、
仕事につながる話、いい情報、気づき、もちろん仕事の話、、、などなど
たくさん聞けました。
今年一年の集大成とも言える月でした。
感謝感謝!
今はいろいろな意味で、
来年が楽しみです。 (^-^ )
引っ越し当日。
午前4時まで荷造りしてました。。。
眠い・・・!

でも、
引っ越し業者は来るのです。
いや〜、でも実に素早い作業に脱帽。
私には無理。

でも夜遅くまで、、、運び込みはつづくのです。
余計、私には無理。
あ〜、眠い・・・!
明日も引っ越し。
2日がかり。。。
絶対、私には無理。
一面黄色の世界。
きれいな銀杏並木。。
のはず、昼間なら。。。
神宮外苑です。。。。

夜だと、銀杏の色がよくわかりません。
暗いからというより、、、街灯のせい。
この街灯のあかりだと、
黄色の銀杏の葉が緑色に反射されてしまう。

銀杏の名所なら、
せめてそのくらい考えて、街灯を設置してほしい。
昼間見に行けばいいじゃん!
と聞こえてきそうだけど、、、
昼間行けない人もいるじゃん!
それに
夜行きたい人もいるじゃん!ね。
ひとり言。。。
きのうNHKで、
「ハーバード白熱教室@東京大学」という番組を見ました。
前々から、
一度見たかった番組でした。
内容は、
哲学的道徳観を
実際の生活の中の具体的なテーマに沿って議論する番組。
と言ってしまうと、
難しい話に思われますが、
例えば、テーマは
「イチローの年収は、オバマ大統領の年収と比べて高すぎるか?妥当か?」など。
その議論をハーバード大学のマイケル・サンデル教授という人が仕切る。
議論の内容そのものもおもしろかったけど、
一番おもしろかったことは、「ちがう」ということ。
サンデル教授は決して、議論の結論を導こうとはしない。
質問を投げかけ、
聴衆に発言させ、
意見のちがいを浮き彫りにしていくだけ。
そして、
そのちがう意見の根底にある道徳観や価値観、信念を探っていく。
人はそれぞれ
顔が違うように、道徳観や価値観、信念が違う。
それをみんなで共有することが大事で、
それは1つの結論へ向かうことよりも重要、と言いたいよう。
人によって考え方や価値観が違うということは、
案外、当たり前のようにみんな思ってはいるのでは。
でも、
いざ違う考え方に遭遇すると、
自分が否定されているような気分になり、
素直に受け入れられない。
あるいは、
自分の考え方や価値観でしか行動できない。
一番大事なことは、
国籍やコミュニティ、世代などのちがいを超えて、
価値観や信念のちがいを共有できる環境をつくれるかどうか。
「白熱教室」では哲学的道徳観を扱っていましたが、
同時に、
コミュニケーションの基本を扱っているようにも見えました。
ただ、
西洋だな、議論の行方が、、、とも思いました。
デカルト?カント?アリストテレス?だからなぁ。
(と言いたいだけ、わかりません・・・)
仕切り役が東洋の方ならば、
議論の方向性がもっと違ったものに。。。
でも、
当たり前かぁ、、、
価値観や信念がちがうんだから(^^;
今日は新宿へ。
SE構法登録施工店勉強会に参加。

『資産になる家』・・・気になりませんか?
・永く住み継げる『価値』
・高く売れる『価値』
・そして、賃貸にも転用できる『価値』
以上はすべて
SE構法だから生まれる『価値』です。
そして、
SE構法で建てるから『資産になる家』です。
ここは、
SE構法の宣伝の場所ではありませんが、
今日、勉強会に参加して
いいなぁ、と思いながら帰ってきました。
ちなみに、
宣伝といえば、
SE構法のCMが放映中です。。。
では、
どんな仕組みで『資産になる家』か?
それは、
今後、ホームページ上やメルマガで内容を紹介していきます。
早く知りたい方は、、、お問い合わせください。
説明ツールは揃ってます。
もともと、
当社がSE構法を導入した訳は、
『住宅デザインの可能性を追求できる構造システム』
だったから。
しかし、
その後のSE構法のシステムの発展により、
単なる構造システムの枠を超えて『資産になる家』の仕組みにまでなりました。
これから住宅を求める方は、
是非、SE構法を選択肢の1つに。。。
これは当社へ、、、
などとは関係なしにオススメないい仕組みだと思います。
先日、横浜の中華街へ。
まだ明るいうちに行くのは久しぶり。

昔、近くの設計事務所にいました。
大通りはその頃から様相がずいぶんと変化。
なんかキレイに、観光地らしく。
でも、いまだに変わらない、
で、とても気になる店が通り沿いに。

店名はあえて伏せます。
とにかく、、、気になる。
何が?
昔ながらの店構えの雰囲気が、、、いい。
昔ながらのステンドグラスが、、、いい。
行けばすぐわかると思います。
まわりが観光地らしくなって余計目立つ。
入りたい、、、でも外にメニューがない。
入りたい、、、でも入りづらい。。
入りたい、、、でも勇気がない。。。

結局、、、
いつも行く店で
おいしい刀削麺とあんかけチャーハンをいただきました。
2ヶ月に一度の趣味の会。
中古カメラ好きが
毎回違うフィルムカメラを持ち寄りカメラ談義。
10月は現地調査と題し、フィルムカメラを使っての撮影会。
最終週の週末に1泊で三浦海岸へ行きました。

夕方、台風が近づく中、三浦半島の剣崎灯台へ。
なかなか絵になる灯台です。

何の写真だと思いますか?
剣崎灯台下の海岸線です。
自然の力、凄い!
宿は、
メンバーが所属していた、
某大手フイルム会社の保養所。

夕食です。

別料金1,000円でこの舟盛り。
ここ保養所ですよ。
信じられない豪華さ!
さすがFフイルム。。。
お腹いっぱいいただきました(^_^)
台風が来て、
あまり撮影できなかったけど、
楽しい週末でした。
時々お参りに行きます。
先日行った時にお知らせの看板がありました。
本日、府中の大国魂神社の随神門の上棟祭がありました。
御鎮座壱千九百年記念事業としての随神門の改築だそうです。

なかなか見ることができない貴重な体験でした。
私の祖父の代から当社は神社仏閣の建築を行ってきたこともあり、
私も現代建築だけでなく、日本建築の様式にも大変興味があります。
そんなこともあり、
是非きょうは上棟祭を見てみたかったです。
普段の仕事の中で
住宅の骨組みが組み上がった時に
上棟式という形で行うことはあります。
でももっと簡略化したもので、
きょう行われた上棟祭は本格的なものでした。
言わば、正式な上棟の儀式、ということだと思います。
途中、上棟祭の起源のお話があり、
平安時代から行われている儀式だそうです。
上の写真は、
関係者が白い綱で棟木を上げる儀式(真似)をした後、
神官が棟木の所まで上がり、
合図に合わせて木槌で打ち込む様子です。
で、上棟祭の最後の儀式が餅まきです。
これを待ってる人も多そう!

足場の所に関係者が勢揃い。
さぁ、はじまります。
みんななんか、、、見上げて、、、たいへん。
ケガしないように。。。
という私もかなり夢中で、、、なんとか取ろうと。。。
成果は、、、
白いお餅を1つ取りました。
宮司さんが投げてくれたもの(写真向かって左の紋付袴の方)。

一緒に行った知人も赤いお餅を取り、
紅白並べてみました。
かなりの人だったので、
取れた方が少なかったのか、
紅白並べていたら、
写真を撮らせてください、という方が何人もいました。
上棟祭の後、
祭壇に近づいてみました。

普段の仕事の中で
このような祭壇は
例えば、地鎮祭の時に設けます。
よく見ると、
並べる供物もほとんど一緒、
でも二品くらい多いかもしれません。
帰りに、
お参りしてから、
また門の所と行くと
たぶん神社総代の方だと思いますが、
供物のお米をわけて頂きました。
家でご飯を炊く時に入れてみたいと思います。
また何時このような儀式を見られるかわからないので、
ほんとうに大変貴重な体験でした。
普段、人が意識しないコトに目を向けるのがデザイン。

関西出張最後の日は、
名古屋にいました。
気になる展覧会の2日目でした。
豊田市美術館、「石上純也展」。
開館して30分後くらいに、
メイン展示の前に。
「オープニングの前に壊れました。」
その場にいた学芸員に聞きました。
予想通りの展開だったので、特に驚きません。
学生ボランティアが修復中でした。
残骸を見るのもいい。
きっと見たかったのは、
体験したかったのは、
自分の意識を超えたコト。
ならば、
その過程の方が直に伝わってくる。
そこが狙いの展示だと。。。
それで、
冒頭の言葉。
頭ではわかっているけど、
実体として、
感覚として、
わかっていなかった。
でも、ここでつながりました。
はじめて見ました。
関西出張2日目は、
昔お世話になった人と会いました。
私がまだ建築の世界に分け入って間もない頃に、
いろいろとご指導してくれた人です。
お忙しい中、会って頂きました。
で、帰りに時計を見たら、
まだ15時。
そうだ、金閣寺に行こう!

普通、中学か高校の時に
修学旅行で京都・奈良へ行きますよね。
私は、
中学が東北、高校が南九州で
京都デビューは22才の時、
奈良デビューは32才の時でした。
で、
今まで2回京都に来てますが、
2回とも、金閣寺には縁がありませんでした。
確か、2回目は修復工事中。
それだけに、
今回、スキ(?)あれば、金閣寺
と思ってました。
なぜか?
見た事がないのも理由ですが、
金に興味がありました。
別に、金が好きな訳ではありませんが、
金箔を外観に貼った建物で、
これほど大きく、
また、
広大な風景の中に置かれているものは
世界でも現存するのは
たぶんこの金閣寺だけで、
それ故に
どう見えるのか?
どう感じるのか?
まさに究極の素材を扱っている訳ですから、
興味津々です。
それと、
三島由紀夫の「金閣寺」
を読んだことがあったので、
自分は何を感じるのか?
を体験したかったのです。
金閣寺は、
ある一面は魅惑的で
ある一面はパロディでした。
ある角度から見ると、
抱きしめたくなるほど
魅力的で誘惑されるかと思うと、
ある角度からは、
舞台のセットのように
現実感が無く、
すぐそこにあるにもかかわらず、
段ボールでできているが如くのちゃちさ。
この二面性がおもしろい。
この二面性が人を魅きつける。
私自身は、
好きな建築ではないけれど、
段ボールに金箔もどきを貼った様を
想像するだけで
行く価値はあるかも。
これは
嫌味でもなく、
本当に
私たちの大事な財産の1つだと思いました。
この金閣寺があるから、
対極に
今建築を考えることができる、
とも言えるかも。
関西出張最初の夕飯は、
京都タワーの裏の居酒屋でした。
関西的な飯を求めて駅周辺をフラフラ。
ちび餃子の看板に惹かれて。

ちび餃子は関西ですよね、東京の中華屋では見かけない。
う〜、なかなかの味。
でも、ちび?じゃなくても。この店だから?

牛すじと大根の煮込み。
牛すじも関西のイメージが。
グツグツに煮立って登場。
めちゃ旨かった。
牛すじトロトロ。
大根しみてる。
汁最高。
ハマりそうです。

地鶏のタタキ。
これは、
関西関係なし食べたかった。
脂があって、
弾力あって、
噛む程に地鶏の味がする。
かなり旨い。

で、締めのラーメン。
関西でも締めはラーメンかな、と思いつつ、
このラーメン、
メニューには「うまいラーメン」と。
余程の自信か。
でも食べたくなる。
これが悔しいかな、旨かった。
「うまいラーメン」の術中に。
牛すじと大根の煮込みの汁が入ってる感じ。
あ〜、思い出す、ハマるかも。
と、
太りそうな夕飯でした。
翌日も京都滞在。
実は、
二日続けてこの店に。。。
普段意識していない部分をデザインする。

これは、
銀座の画廊のショーウィンドウ。
たぶん、
ガラスではなく、
アクリルだと思います。
厚さを均一ではなく、
レンズ状に
不均一にしているのだと思います。
たぶん、
某建築家の
デザインだと思います。
偶然見つけました。
ショーウィンドウをつくる側は、
普段、
見せる部分をどの位の大きさ・形にするか、
それによって、耐風圧などにより
ガラス強度が決まり、
自動的にガラスの厚みを決めます。
ショーウィンドウを見る側は、
普段、
中に何が見えるか、
それによって、
興味があるかないかが決まり、
お店に入るかどうかを決めます。
ショーウィンドウは、中身をよく見せるためのもの。
そんなの当たり前ですよね。
だから、
雨風が入らないように
透明の素通しのガラスを入れる、のも当たり前。
意識するのは、
見せる中身をどうするか?
でも、
ここで
ガラスの厚みに焦点を当て、
意識してみる。
普段、
何も考えなくてもいい部分を意識してみる。
もし、
ガラスの厚みを変えてみたら。
もし、
ガラスの厚みが均一でなかったら。
もし、
ガラス以外の素材だったら。
何が変わるか?
ショーウィンドウを見る人に何か変化がおこるか?
デザインした建築家が
何を考えていたか、はわかりませんが
わたしは、
デザインする、とは
直接的に物の形や色や素材などを扱うよりも
普段意識していない部分に焦点を当てること、だと想います。
その方がたくさんの可能性があり、
きっと人の役に立つから。
週末の夜の浅草散歩。

涼しくて気持ちよかったです。
散歩の途中で見つけました。

通りに面した木製の玄関引戸の欄間部分のステンドグラス。
ちょっと粋です。
何気なく普通にあります。
昔はこういうように、
普通の家に
ちょっとステンドグラスを使う、
ことがあったのです。
ただ、今はありませんね。
何故かって?
ステンドグラスは
工業製品ではなく、手作りだから。
ハウスメーカーは使いませんよね。
(イヤミではありませんよ。。。)
ちなみに、
工務店はハウスメーカーとはちがいますよ。
だから、
工務店は粋なのです。
ガンダムの格納庫に忍び込み、
暗闇の中で足元から見上げてるようでした。

週末の夜、
東京スカイツリーの根元まで行ってみました。
周りは低い住宅。
唐突に建ち上がるタワー。
工事中だから、暗闇。
ほとんど人もいません。
工事のクレーンあり、
資材ありで、
冒頭の表現のように(ガンダム世代なもので)
現実離れした、ちょっと異様な体験でした。
なかなかこんな体験できません。
一度工事中に行かれることをオススメします。
それも夜がいい。
あまり見えすぎない方が想像力を掻き立てられるから。

プラプラと
ふらふらと
長崎ちゃんぽん食べて、
またふらふらと
またプラプラと。
ここは三軒茶屋。
いつも気になる建物。
というか、
いつも見に行く建物。
古い映画館。古い名作ばかりを上映してるよう。
その建ち方、雰囲気があります。
ただ古いだけじゃない。だから、気になる。
単純な形態、単純な色使いの外観。
でも、その見え方、雰囲気があります。
映画にはあまり興味がありませんが、
一度中に入ってみたい、、、
でも、入れない雰囲気もあります。。。
場外ですし。旨かったです。

先日の銀座での研修の際、
せっかくだからと、
研修仲間と共に、昼ご飯を食べに
築地魚市場に行きました。
週末の夜に場外のすし屋に来たことはありましたが、
平日の昼間に築地に来るのは初めて。
食後、魚市場内を散策。

平日でないと見られない光景。
朝が早い場所だけに
まだ昼過ぎですが、
商売終了でした。
それでも
普段なかなか見られない光景。
楽しくて、
あまり時間が無かったのですが、
歩き回りました。
この雑然さが魅力です。
誰もいません。
でも、、、
たくさんの人を想像します。
たくさんの声、音が聞こえてきそうです。
商売の活気が目に浮かびます。
そんな想像をする時、
人は、目の前のその場所にどっぷりと浸っています。
それは、その人にとって幸せな時間です。
しかし、
この魅力ある雑然さ
はじめから計画してつくり出すことはできません。
そこが、現代の建築計画学という学問の限界だったりします。
建築計画学とは、簡単に言うと、
数値に裏打ちされた統計学です。
統計学だから、
万人にとって機能的で支障がなく、問題ない物ができます。
そう問題ない物をつくるために建築計画学がある、
という人がいるかもしれません。
それを一生懸命、研究している方もたくさんいます。
私も建築計画学を否定するつもりはありません。
ただ、建築計画学を設計の拠り所にするのはよくない。
建築計画学は最低の基準であり、設計はその先の話だから。
設計は、
人の感覚、感情を左右する空間をどうつくるのか?
また、
その空間がどんな時間を生み出すのか?
を考える機会です。
問題ない物もつくることは、当たり前の話。
そこにフォーカスしすぎるのは、設計にとっては問題です。
先ほどの築地魚市場の場合でいうと、
あの魅力ある雑然さを誘発する空間をどうつくるのか?
自然発生的に商売の活気が産まれる空間とは?
などを考えるのが設計の仕事。
普段なかなか見られない光景だけに
私の感性も刺激を受け、たくさん誘発されました。

銀座泊。
先日、研修で銀座に行きました。
2日間の予定で、
1日目の終わりが夜遅く、
2日目の始まりが朝早かったので
初めて銀座に泊まりました。
銀座には何度も来たことがありますから、
見慣れた風景です。
でも、泊まりとなると、
なんか、銀座の街がちがって見えます。
少しの解放感も手伝ってか、
小旅行気分です。
だからか、、、
東京にいる、という感じではありません。
寝る場所が変わるだけで、、、
人というのは
ほんと、環境に左右されるものですね。
環境によって、
同じ物でも見え方、感じ方が変化する。
環境
言い換えれば、空間です。
空間が人の感覚や感情を左右する。
だから、空間を大切に。
そんなことを
あらためて実感した夜でした。

東京スカイツリー完成。
当初の予定より、
高さが低くなり
世界一高い塔ではなくなりましたが、、、
場所も
当初の予定地を変更。
五日市街道の吉祥寺〜三鷹の間の
ちょうどよいスキ間に建ち上がりました。
できあがると、
案外、小さいもんだな。。。

お昼の空です。
シュールな絵を見ているようでした。
ずっと先まで雲がなく、
空の色がグラデーション状に変化する。
文章にすると、
それだけで
写真ではわかりづらいかもしれません。
何か超現実的な風景でした。
日常の中の非日常、
一番おもしろい体験です。
昨日、今日と一日中研修を受けてきました。
電話・メールとなかなか連絡が取れなかった方、
申し訳ありませんでした。
明日からは通常通りです。
普通に連絡をしてくださって大丈夫です。
今回の研修、
来ている方は日本全国から。
それぞれの土地の事情も聞け、
また縁もでき、とても有意義でした。
明日から研修で学んだことを生かしていきます。
会いたい人がいて
今日、
横浜の桜木町に行きました。
もちろん仕事で
その人の話を聞きに。
夕方、
終わってから
中華街まで足を延ばしました。
辛い刀削麺を食べに。
関帝廟通りにうまい店があります。

帰る時に、
みなとみらい線の元町・中華街駅を利用。

写真は、
駅のホーム。
この駅、設計者は
建築家の伊東豊雄。
建築の設計をしていて知らない人はいない位の人。
私もリスペクトまではいきませんが、
作品で好きなものは多いです。
代表作に「せんだいメディアテーク」。
日本の現代建築のターニングポイント的作品。
ただ、この駅、完成度は高いけど、
デザイン的にはイマイチ。
近未来を狙ったのか。
それとも、、、
「建築家もヒトですから、ブレはある。」
と、
納得させながら帰路に。
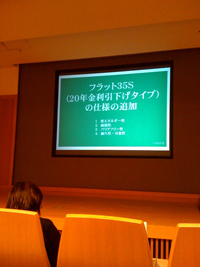
昨日、
住宅金融支援機構監修住宅工事仕様書セミナーに行きました。
改訂に伴う支援機構の仕様書の説明会。
いま、
フラット35S がかなりお得なようです。
ただし、期限付き。
説明会もかなりの人がいました。
家づくりには、
何かと不安はつきもの。
その最たるが、
資金。
まず、将来設計を考えて
ローンならば、
安心できるものを選びたいですね。
そうすれば、
家づくりの本当に楽しい部分に
没頭できます。

写真は、横浜の元町通り。
昨夜久しぶりに行きました。
昔、元町の近くの設計事務所にいましたので、
その頃はよく
ランチに行ったり、
散歩したり。
写真を見て、
他の商店街にはない
建物の特徴があります。
建物の2階部分が歩道の上にせり出しています。
これは、
元町通り街づくり協定で
通りに面する建物は、
1階部分の壁面を後退させ
空間をつくり、
それを各建物が行い、提供し
雨に濡れない歩道を連続的に確保する
と決められているそうです。
よくアーケードは見かけます、
雨に濡れない歩道確保のために。
それは便利だと思います。
ただ、、、
空が見えなくなります。
天候がわかりません。
季節感がなくなります。
どんな商売でも、
最終的には、ヒト対ヒト。
そのヒトは、案外環境に左右されます。
例えば、雨の日は憂鬱な気分になるとか。
全天候型の空間にすれば、
環境に左右されることが少なくなり、
商売がやりやすくなるかもしれません。
ただ、
商売がやりやすい、と
商売がうまくいく、はちがうと思います。
商売がうまくいくには、
ヒトを左右する環境を
味方につけた方がいい。
だって、最終的には、ヒト対ヒトですから。
なのに、環境自体を排除してしまったら、、、
シャッター通り商店街もうなづけますね。
そんなことを考えて、
元町通り街づくり協定で
決められているわけではないと思いますが、
雨に濡れない歩道があり、空もある。
いいですね。
やっぱり、夜空が見えないと。
気分がちがいます。
だって、ヒトですから。

5月のはじめに携帯サイトを立ち上げました。
それでここ3日間ほど、
サイトの内容のさらなる充実をはかりました。
携帯サイトは
PCサイトとちがって、
見える画面が小さいため、
同じ内容を伝えるにも工夫が必要です。
まして私はiPhoneを使っているために、
直接、携帯サイトを見ることができず、
どのように表現するのか、
どのように伝えるのか
を考えるのにとても苦労しました。。。
でもそれは、
画面を敷地に例えると、同じ?
計画の敷地にも大小があります。
私は計画の成否に敷地の大小は関係ない、と考えています。
工夫すればいいのだから。
ただ、
そのためには入念な敷地の読み取りが必要です。
逆に言いますと、
敷地選びの段階から計画を意識すると、
自分たちに合った敷地を見つけることができます。
敷地選びは大事です。
計画の成否、すなわち、
家づくりが成功するか否かは、土地選びで半分以上決まる、
と言っても過言ではありません。
ただ心配しないでください。
土地をすでに持っている方、工夫すればいいのですから。
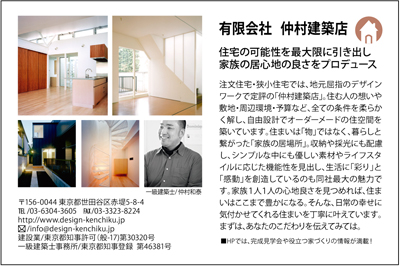
「世田谷ライフ [2010 No.33] 」誌に掲載されました。
今まで何度か雑誌に掲載されましたが、
その度になんか不思議で、おもしろいです。
見方の角度が変わると、
同じことでも違って見える。
当たり前のことかもしれませんが、
そのおもしろさは、建築にも
そして、私の趣味の写真にもあります。
それが、デザインのヒントです。

マイハウス、リノベーション中。
築40年の祖父が建てた借家に今住んでいます。
その借家から脱出するべく、
別の築30年位の家をリノベーション中です。
この家、Mホームが建てたパネル工法の家。
わかりません、なぜこの家ができるのか。
わかりません、なぜこの家がもつのか。
わかりません、なぜこのパネルでいいのか。
本当に困ります。
どうしていいのか。
どうしていいのか、が私の問題ならばいいのですが、
たぶん、将来リノベーションすることを想定していない、
と言いますか、それはどうでもいい、という感じです。
ただ、マイハウスなので
思い切って手を入れています。
計算できるところはしていますが、、、
あとは自己責任で。
家は何年も同じ状態で住みません。
大事なことです。
「可変性」。

見つけました!
葉っぱハウス。
一目惚れです。
惹かれました。
葉っぱの屋根。
白く細い柱。
単純です。
でも深い。
ただの長イスまで演出に見えます。
これは近くの病院の庭のあずまや。
きっと作者は、、、何も考えていません。
たぶん偶然の産物です。
しかし、
プロポーションとスケールがいい。
葉っぱの量。
白い柱の太さ、位置。
あずまやの高さ、大きさ。
バランスが実にいい。
少ない構成要素でも
プロポーションとスケールだけで
建築は成り立つ証明です。
建築の基本。
でも奥が深い。
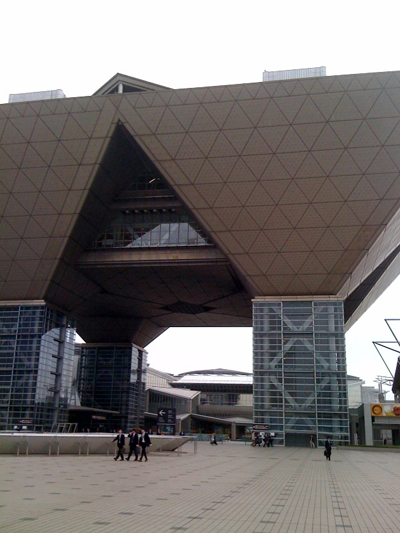
東京ビッグサイトへ久しぶりに来ました。
改正による「建築確認手続き等の運用改善に係る講習会」でした。
6/1から建築確認に関する一連の業務が少し柔軟になりそうです。
ところで、ここに来るたびに考えます。
建築と人の関係。
大きい建築は、そのスケールで人を圧倒します。
人は圧倒された後、何を想う?
すばらしい。
何だかわからない。威圧される。
奇妙だ。こわい。登りたい。
きれい。美しい。触りたい、などなど。
世界には、たくさんの大きい建築があります。
ピラミッド。
エンパイア・ステート・ビルディング。
バチカン。京都の東寺の五重塔。
サグラダ・ファミリア。
ビルバオ・グッゲンハイム美術館。
ドォオモ(大聖堂)などなど。
もうすぐ、ここに東京スカイツリーが加わるか。
これらの名建築と東京ビッグサイトを比べるつもりはありません。
ただ、圧倒して、
なおも人に「すばらしい」と想われる建築って
どうすれば。。。
何が「すばらしい」と人に想わせるのだろう。。。
東京ビッグサイトはいつも何も想いません。

見た瞬間、はっ!として、しばらく見とれてました。
まるで影絵のよう。
自宅の1階南側の硝子戸。
築40年、祖父が建てた借家。
今では見かけない、サッシではない木製の建具に
今では手に入らない曇り硝子。
今までカーテンに隠れていて気がつきませんでした。
この季節の午前中のある時間だけのショーかもしれません。
今の住宅は、
何か大切なものを犠牲にしているのかも。。。